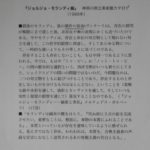読書ノート(2014年)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元のことば』 田中忠雄著 黎明書房
■一発(ほつ)菩提心を百千万発(ほつ)するなり。(正法眼蔵発菩提心)(11頁)
「しかるに、発心は一発にしてさらに発心せず、修行は無量なり、証果は一証なりとのみきくは、仏法をきくにあらず、仏法をしれるにあらず、仏法にあふにあらず」(『正法眼蔵発菩提心』)
発心は1度だけで、あとは長い修業がつづくと思うのは、仏法を傍観している者の見かた・考え方である。身をそこに投げ入れている者には、1日として新たに発心しない日はなく、1刻として新たに発心しない時はないのだ。それゆえに「百千万発」の発心なのである。最初の発心を百千万発するのだ。これを真実の修行という。(12頁)
おおよそ事をなさんとするならば、人は志を立てねばならない。(中略)
しかし、その志を貫き通すには、立志はⅠ回だけで、あとはくる日もくる日も努力あるのみと思ってはならない。初発の志を百千万発するのである。たとえば学問が成就しても、重い椅子に就任しても、事業が成功しても、なお初発の志を百千万発するのである。この百千万発がなければ、次の瞬間から学問も業務も事業も生気を失い、下降の方向をたどり、やがて頽廃におちこんでゆく。
ましてや、発心は人生の一大事にかかわるのである。発心は1どだけという姿勢では、長い修業は新鮮さを失い、マンネリズムになるほかはない。そこには喜びがない。あるのは歯をくいしばっての努力だけである。このような、いやいやながらの努力には、息抜きが必要であり、その息抜きの際に、あらぬ誘惑に引かれて初発の菩提心を失い、志を失って頽廃におちこんで行くのである。
この語は、まことに常見(常識)の徒たるわれらへの一大衝撃である。幸にして、われらに一代衝撃を受けるだけのセンスがある。これを有りがたいことと思いさだめて生涯の姿勢を正したい。(13~14頁)
■誠に夫(そ)れ無常を観ずる時、吾我の心(しん)生ぜず、名利の念起らず、時光の太(はなは)だ速かなることを恐怖(くふ)す、所以(ゆえ)に行道は頭燃を救う。身命の牢(かた)からざるを顧眄(こべん)す、所以(ゆえ)に精進は翹足(ぎょうそく)に慣(なら)う。(学道用心集、原漢文)(14~15頁頁)
そもそも、天地間の一切の事物は1つとして恒久不変なものはなく、絶えず生滅して常にあらざることを、よくよく心の眼でみるならば、利己の心が生ぜず、名声欲も利益欲も起らなくなるものである。そうして、時というものが極めて早く去ってゆくことに驚き恐れるところから、頭上にとんでくる火の粉を払うように急切に仏道を行ずるようになるのだ。わがいのちも無常生滅のなかにあり、いつ死ぬともわからないことをかえりみて、過去世の釈尊が一脚を翹(つまだ)てて7日も休みなく仏を讃歎された故事に慣って、一刻もむだにせず仏道に精進努力するようになる。
当(まさ)に無常を観ずべし(当観無常)ということが、われらをして無上の真理を求めしめる原動力であり、一大勇猛心の根源なのである。(16頁)
■道元が「故(こと)さらかくなん云はじとも」と語ったことは大切だと思う。あえてY談はせぬなどと力んで言わずとも、僧のY談はいけないと知ったら、しだいにやめなさい、というのである。じつにやわらかなお示しで、自然に頭がさがる思いである。(82頁)
■身学道といふは、身にて学道するなり。赤肉団の学道なり。
身は学道よりきたり、学道よりきたれるは、ともに身なり。(正法眼蔵心学道)(85~86頁)
ここに「身学道」というのは、身をもってする学道である。この丸裸の身体をめぐらして、直ちに仏々祖々に参ずる学道である。
そもそも「身学道」の「身」とは何ぞや。身とは学道よりきたるものであって、学道に入らざるものは、いまだ身にあらず、そこにあるものは肉であって、ただの臭皮岱にすぎない。それゆえに、学道よりきたれるものは、すべて身である。赤肉団の肉体も忽ち化して身となり、臭皮岱の肉魂も忽ち一変して身となるのである。かくのごときを身学道という。
「この身体をめぐらせして、十悪をはなれ、八戒をたもち、三宝に帰依して、捨家出家する、真実の学道なり。このゆえに真実人体といふ。後学かならず自然見(じねんけん)の外道に同ずることなかれ。」(正法眼蔵心学道)(86頁)
こうした自然見のの外道は、1度も道に向って志を立てることがない。彼らにあるものは肉体だけであり、肉欲だけである。そこには身体というものが欠如している。身学道がないからである。
身学道がなくて、観念を空転させるだけの学者、文人も、やはり自然見の外道である。頭の中で考えることと行なうことが、くいちがっている。言うことと為すことが相応しない。こうした観念の徒は、必ず自然見の外道に加担して、肉魂の世界に奉仕しているのだ。いかに高遠なことを言っても、その高遠なものが、そっくりそのまま肉魂の自然見を増長しているのである。(87頁)
近代文化というものは、自然見の外道(自然主義)が作りあげたものである。だから、近代化すればするほど、肉体がはびこり、身体が衰亡する。
1度も志を立てず、1度も道を求める気をおこさず、自然に出てくる欲望を「人間性」(ヒューマニティ)と称し、これを解放することを主義としてヒューマニズムを名乗る。近代というものの本質はこの自然見にある。
自然にわいてくる欲望を大事にしろというのが、いうところの人権尊重である。そうでないといくら弁明しても、自然見の外道は、ここまで堕落しないではおさまらないのだ。これを「肉体民主主義」というのである。(88頁)
■他は是れ吾れにあらず。(典座教訓)(89頁)
彼は私ではない。私の仕事は私の仕事、彼に代わってもらえるものではありませんぞ。
道元が天童山で修行しているとき、典座の職に慶元府出身の某用という僧がいた。典座とは一山の衆僧のために食事を管する役目である。
夏の日に、法会(ほうえ)が終って東廊をすぎ超然斎という名の堂宇に行こうとしたら、途中で年老いた典座の姿を見た。手に竹の杖を持ち、笠をかぶっていない。太陽はかんかん照りつけ、地面の敷き瓦は焼けている。典座は仏殿の前で、しきりにきのこをさらしている。流れる汗をものともせずに、懸命にきのこをさらしているが、この作務はいかにもいたましく見えるのであった。典座の背は弓のように曲り、長い眉毛は鶴のように白い。
道元は近づいて、年齢を問うたら、68になるという。
「貴僧はなぜ人を使ってこの作務をやらせないのか。」
このとき老典座いわく、
「他は是れ吾れにあらず。」(89~90頁)
この老典座との問答は、つづけてもう1つある。このとき道元は感激して、
「老僧の如法(にょほう)の(法そのままの)作務には頭がさがります。しかし、この炎暑のなかで、このように苦しい作務をやる必要がありましょうか。」
ときに老典座いわく
「さらに何の時をか待たん。」
この応答には、無常迅速なり、この時をおいて、いずれの時にか作務せん、というひびきがある。道元は、この老典座によって生活の全体について開眼(かいげん)するところがあったのである。(90~91頁)
■大道は従来一実(いちじつ)より通ず
蓬瀛(ほうえい)何ぞ必ずしも壺中に在らんや
逍遥(しょうよう)たる世外誰人(たれひと)か識(し)る
赤肉団辺(べん)に古風を振う(永平元禅師語録)(108頁)
「蓬瀛」は詳(くわ)しくは「蓬莱(ほうらい)」と「瀛洲(えいしゅう)」のこと、どちらも仙人の住む神仙境、普通に天国とか極楽とか呼ばれてるものに似ている。
「壺中」とは、むかし壺公という仙人がいて町で薬を売り、夜になるとそばにある壺のなかに入って寝た。ある日、壺公が居合わせた男に「お前も壺の中に入ったらどうだ」というので、その男が思い切って壺の中にとび込んだら、そこに蓬莱(ほうらい)といおうか瀛洲(えいしゅう)といおうか、素晴しい金殿玉楼で、その中で壺公は数十人の侍者にかしずかれて悠々としていたという。この『漢書方術伝』の伝説をふまえて「壺中」という。
「逍遥」は、あちらこちらぶらつくことであるが、ここでは遠くかけ離れた様子。
「世外」は世間のそと、つまり別天地のこと。
「赤肉団」とは、さきにも1度述べたように、赤い肉のかたまり、すなわち肉体のこと。「団」はかたまり、かたまるから団結といい、かためて作るから「団子」という。赤い肉のかたまりだから、肉体の生き生きした、なまなましさが響いてくる。(108~109頁)
「大道は従来一実より通ず。」……これこそ千古万古の金言である。人類だの、世界だのと言って、大風呂敷をひろげて、きまり文句を叫んでいる者にろくなやつはいない。
(中略)
歎くには及ばぬ。その一実こそ人間の真実の落ちつくところで、いつでもどこでも安楽境を現成するのである。
赤肉団辺に新風を競う者に、ろくなやつはいない。フーテンもゼンガクレンも、進歩的文化人も、質的には同じものである。流行を赤肉団辺に振ってゴーゴーを踊っている女と進歩的文化人とは同じもので、それ以上でもなければ、それ以下でもない。いよいよ大道はふさがって、どうにも身動きができなくなるばかりである。(110~111頁)
■いまといふ道は、行持よりさきにあるにあらず、行持現成するを、い まといふ。(正法眼蔵行持(上))(112頁)
「行持」とは「行」を持続すること、一時的な実践でなく、久しく行持てやめないこと。発心、修行、証悟を貫いて、少しのすきまもあらしめないものは行持である。
「現成」はここでは実現とか顕現の意と解してよい。(112頁)
時というものは過去、現在、未来の三時より成るというが、そのいずれも、これといってつかむことのできないものである。過去は過ぎ去ってすでに無く、未来はいまだきたらずして無く、現在すなわち「いまという道」か一瞬にして過去に呑み込まれて無に帰するものである。それゆえに過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得という。
他方、知性で表現されるときは、無眼に長い過去と無現に長い未来が、どこまでもどこまでもつながり連続していて、その中間に一刹那のいまが泡沫のようにあり、ありと思われた瞬間に消えてなくなるものである。
いまという道は不可得で、測定することはできない。いまというものは何秒間で消化、それとも何分間でしょうか、あるいは何時間でしょうかと聞いたやつがいるが、そんなことを聞くやつには、いまという道は存在しないのである。
さてまた情緒的に時をとらえると、過去にとりすがれば感傷となり、未来にとりすがれば不安となる。過去を呼び出して持ち越し苦労をする感傷の人にも、未来を思うて取り越し苦労をする人にも、いまという道はない。いまという道は過去と未来のはさみ打ちをくらって、なきものにされているのだ。いまという道は死んでいる。
(中略)
この最も重大ないまという道は、どうしたら成立するか。ここが参究の眼目である。そもそも、いまという道が、客観界のどこかに存在すると思うのが大いなる誤りである(岡野注;「全元論」ではそもそも客観界というものがない)。いまという道はそんなものではないのだ。身心を打ちこんで行じているところにのみ、いまはある。行じていないところには、いまはない。
(中略)
「行持現成するを、いまといふ」のである。このいまが、過去を背負い、未来を孕んでいる。いずれも彼方にあるがごとくであるが、「いま」に呑み込まれて、いまのなかにおさまる。これが生命になり切った時間というものの実相なのである。(112~114頁)
■公案話頭(わとう)を見て聊(いささ)か知覚ある様なりとも、それは仏祖の道にとをざかる因縁なり。無所得無所悟にて端坐して時を移さば、即(すなわち)祖道なるべし。(正法眼蔵随聞記、第五)(115頁)
「無所得、無所悟」は所得なく所悟なしの意で、道元禅の神髄を示す言葉になっている。何か代わりに得る所、悟るところあらんとアテにして修行しては仏道にとをざかる(遠ざかる)という重大な教えである。(115~116頁)
「坐禅すると、どんなよいことがありますか。」
「坐禅してもなんにもならん。」
「なんにもならんのに、なんでするんですか。」
「なんにもならんから、するのである。」
「そんなら、僕は坐禅をやめます。」
こんなことを言って下宿に帰った。佐賀の多布施川のほとりの下宿の一室がいまも目に浮ぶ。ここで私は、あの問答を何度も繰りかえした。すると、あの「なんにもならん」という一語のひびきの何とさわやかで確信にあふれていたことよ。生まれて以来、一度も味わったことのない清冽さではないか。
その魅力に惹かれて、翌日また出かけて行って、
「老師、その何にもならんのを教えてください。」
こうして老師に入門したのであった。老師の「なんにもならぬ」が道元の「無所得」であり、「無所悟」であることは、その後の参禅によって、はじめて知ったのである。老師というが、あれはまだ先師40代の頃だった。坐禅して食えなくなって餓死するなら、それもよかろうという大修行をしてまもない頃(大正11年)の老師だったので、栄養不足の顔つきが60代の人に見えたのである。
晩年の老師は次のように説かれた。「悟るとは損をすることなり」と。「さとる」の「とる」は、やはり「取る」であろうが、その「取る」が脱落し切ったとき、つまり損したとき、本当の仏法になるというのだ。和尚の「損する」とは、損得づくを脱落することだった。
仏法は、だから「途法もないもの」で、たくさんの民衆が、われもわれもとやるものではない。「こんなに大ぜい集まるのは、おかしい」と、よく老師は参禅会の壇上で言われた。(118~119頁)
■それ修証(しゅしょう)はひとつにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり。仏法には修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の弁道すなはち本証の全体なり。かかるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ、直指(じきし)の本証なるがゆえなるべし。(正法眼蔵弁道話)(125頁)
「修証」は修と証の意、修は修行、証は証悟、さとり、得道のこと。
「外道の見」とは仏法にあらざる見解のこと。
「直指の本流」とは、寄り道しない端的な本来の証(さと)りという意味。(125頁)
いま我らが坐禅するのは、証悟を向う側において、これをアテにする修行ではなくて、本来証悟の身体をめぐらしてやる修行である。これを「証上の修」というのだ。すでに証上の修である。ゆえに初心の弁道(修行、坐禅)は、直ちにこれ本来証悟の丸だしで、どこかにまだ発現していない証悟などというものは存在しない。初心の弁道も信じて打坐すれば、直ちにこれ本証の露堂々(ろどうどう)なる丸だしである。
初心の発心も仏性の全体、修行の弁道も仏性の全体、あに証悟のときをのみを仏性とせんや。道元では、草木は発芽のとき、枝葉繁茂のとき、開花のとき、結実のときを「條々の赤心なりと参学すべし。」…その1つが仏性の全体と参学すべしという。つまり過程と究極との間隙を打ち払う道元の家風を想起することが必要である。
修と証とに間隙なく、2にして実は1であるから、古仏たちが修行の心得をさずける場合にも、修のほかに証を待つ思いを持つなと教えたのである。修すなわち坐禅こそは、直ちに証(さと)りそのものであるからである。かくのごとく信じて坐るのが道元の坐禅である。(126頁)
■仏道をならふといふは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己をわすれるなり。自己をわすれるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心(しんじん)および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごしゃく)の休歇(きゅうかつ)なるあり、休歇(きゅうかつ)なる悟迹(ごしゃく)を長々出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ。(正法眼蔵現成公案)(129頁)
「万法に証せらるるなり」の「万法」とは、万物の意と解してよい。自己が「無我」で、いささかの我見も付着しないときは、自己は万法に証せられているのである。
「他己」とは自己との対になる用語であるが、「他」といえども「自」と同じく己(おのれ)であるという自他一体感から、「他」を「他己」というのである。
「脱落」とは「身心(じん)脱落」のことで、道元が天童山の如淨(にょじょう)禅師の道場で大悟したときの言葉である。道元は大悟の境地を「身心(じん)脱落せり」といい、師の如淨はこれを全面的に肯(うけが)ったのである。旧来の身と心とが共に滅して、真空無我の妙境を究めたことを身心脱落せりという。
「悟迹の休歇」の「悟迹」とは、悟りの迹(あと)という意味であるが、悟りへの経路も悟りの内容も、あとづけんとしてもその姿が見えないことを「悟迹の休歇」という。「休歇」とは、休止、つまり休(や)んでいること。
「長々出」とは、右の悟りのあとをとどめない悟りを、どこまでもどこまでも現してゆくこと。(129~130頁)
仏道を学ぶとは、よそごとを学ぶのでなく、自己自身を学ぶことである。自己自身を学ぶとは、自己を忘れて無我になることである。自己を忘れて無我になるとは、自己を運んで万物を証するのではなく、万物が進んで自己を証することである。万物が進んで自己を証するとは、自己も他己も旧来の身心を脱却し脱落して、大乗の「空」ならしめることである。ここに悟りの妙境がある。しかも、そこには悟った迹(あと)も払拭(ふつしき)されて、悟りの染汚を一点もとどめないのである。この染汚なき悟りを、どこまでもどこまでも行じつづけ、現じつづけてゆく。これが仏道の究極なのである。
学仏道は、他事の学でなく、汝自身を知ることである。しかし、自己の学とは、つまるところは自己の無我を究(きわ)め尽すことである。自己が実体であり自性(じしょう)を持っているとして自己に執著(しゅうじゃく)するかぎり自己の本質に撤することはできない。
この無我は、自己のみでなく万法の実相であるから、われと万法との2元対立を超出している。この消息を「万法に証さるるなり」という言葉で示す。自己が今日いうところの「主体性」のようなものでないことを知るべきである。
それはまた自・他の同根一体を意味する。自己・他己として共に「己(おのれ)」とする語法にもそれが現われている。自とは自己という「己(おのれ)」であり、他とは他己(万物)という「己(おのれ)」であるのだ。その一つ一つの身心が脱落するのである。一つ一つの身心は原子のごとき「実体」ではない。そのような死せる実体から脱出しなくてはならない。この脱出のときを身心脱落という。
身心脱落には悟りの迹(あと)をもとどめない。悟りが悟りにとどまって、そこにあぐらをかくとき悟りといえども染汚(しみ)となる。これを洗浄し、染汚(しみ)がなくても洗浄しもてゆくのが学仏道の極意であり、道元はこれを「行持」(行の持続)といった。(130~131頁)
■原(たず)ぬるに道本円通(えんずう)、争(いかで)か修証(しゅしょう)を仮(か)らん。宗乗自在、何ぞ功夫(くふう)を費やさん。(普勧坐禅儀、原漢文)(133頁)
「原ぬるに」とは、根源にさかのぼってつらつら思うにという意味。
「道本円通」は、道は本(もと)円満にして自在ということ。そのうち「道」とはここでは大宇宙の真理をいう。「本」とは元来、本来、本質上という意味。円通の「円」は、あまねくして到らぬところなく、欠くるところなしの意、すなわち修行と悟りのこと。
「仮らん」は、借らんと書いてもほとんど同じことで、借りる必要がどこにあろうかと訳してよいだろう。
「宗乗」の「宗」は旨(むね)とか本(もと)とかの義、すなわち第一義の真理のことであり、「乗」は元来乗りもののことで、人類を乗せて向う岸に渡して救出する大いなる法の意味。
「功夫」の「功」は功労、「夫」は扶助の義であるから、努力とか修行とかを意味する。普通の「工夫」というのは、いろいろ考案することで道元の「功夫」とは異なる。(133~134頁)
この一節なくして坐禅を説けば、おそらく結跏趺坐の坐禅は手のこんだ人為の極となる。道元の思想の根底には、かような人為を滅尽するという姿勢があった。彼はこれを「不染汙(ふぜんな)」と呼んだ。人為の付着が寸毫でも残っていれば、染汙(ぜんな)すなわち、しみであり、けがれであるのだ。
修行して得悟するなどという人為的な功夫の必要がどこにあろうか。坐禅して大悟するなどという施設の必要がどこにあろうか。元来、そのような功夫や施設は、すこしも必要ではない。必要でないところが大道であり、不染汙であり、円通自在なのである。
道元は少年の頃に、「すべての仏たちによると、人間は元来仏性そのものだとあるが、もしそうであるとすれば、なぜ彼らは発心修行して無上の真理を体得し、そうして仏とならねばならなかったのか」という困難な問題に逢着して行き詰ってしまった。元来仏性として生まれたのなら、発心も修行も証悟も不要であるはずだ。彼は時の最高学府比叡山の学匠を歴訪したが、誰ひとりとして腑におちる解答を与えてくれなかった。そこで彼は比叡山を捨てたのである。
この主題が、身心脱落し一生参学の大事を了(おわ)った道元の口から、質を変えて再び現れる。それが『普勧坐禅儀』劈頭のこの一節である。
「いかでか修証を仮らん、何ぞ功夫を費やさん」というのだ。そのような人為の主体性を容れる余地は寸毫もないというのである。
ではなぜ彼は三世の諸仏と同じように坐禅したのか、精進努力したのか、そうしてなぜ大悟したのか、大事を明(あき)らめたのか、身心脱落したのか。そもそも何がゆえにあまねく坐禅の儀を勧めるのか。ーこのような疑問をすべて打ち捨てて、道元のこの一節に耳を傾けよう。「道本円通、宗乗自在、いかでか修証功夫の要あらんや」と彼自身が言っているのだ。(134~135頁)
人為にあらず、自然にあらず、これを道元はアジアの生んだ最高巨峰のひとりとして、「道本円通、いかでか修証を仮らん」という1句によってその全体系の発想たらしめているのである。
このような人為の全面否定が確立したうえで、人間の自発的な努力やさまざまな施設がそれぞれ所を得るのである。近代の多くの思想家はこの消息にくらいので、道本円通なしに実存や主体性から出発しようとするのである。それは全宇宙から疎外された人為的主体性にすぎないのである。(136~137頁)
■諸仏如来の妙法、円通無礙自在の大道は、全宇宙にあまねきものである。ゆえに、人間もまたひとりひとり、個々にこの妙法・大道をそなえている。しかし、いかにゆたかにそなえていても、そのままほっておいて修行しないと現れない。修行して悟りをひらかないと自己のものにならないのである。ーいまだ修せざるにはあらわれず、証せざるにはうることなし。
(中略)
これを明かにするのに、最もふさわしい公案がある。私はこれ以上に適切な公案は他にないと思う。ー
唐の麻谷山宝徹(まよくさんほうてつ)禅師が扇を使っていた。僧きたりて問う、「風性は不変で且つあまねからざる処なし。」風の本性は恒久不変でかつ天地一ぱいどこにも存在する普遍的なものであります。さすれば和尚がことさらに扇を使って風を起そうとするのは可笑しいではありませんかと。
師答えていわく、そなたは風性が不変だということは知っているが、あまねからざる処なしという普遍の理が少しもわかっていないようじゃと。僧問う、しからばその普遍の理を示してもらいたいと。ときに師、扇を使うのみなり。僧、礼拝す。
道元は『正法眼蔵現成公案』最後の一節に、この公案を挙げて、「仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし」と言っている。風性とは仏性のことであり、「この法」のことである。それは天地一ぱいのもので、万人それぞれの分上にゆたかにそなわっている。だからこそ、もし人がみずから扇を使って行ずるならば、風はいつでも、どこでも、必ず生ずるのだ。いつの時点でなければならぬということもないし、どこかの一隅でなければならぬということもない。扇を使えば、風性は普遍であるから涼風が必ず生ずる。扇を使わずに涼風を得ようとするのは、風性の普遍なる所以を知らないものだ。いまだ修せざるには風は現れず、いまだ証せざるには涼風は得られないのである。(138~139頁)
■山僧、叢林を歴(ふ)ること多からず。只(ただ)是れ等閑(とうかん)に天童先師に見(まみ)えて、当下(とうげ)に眼横鼻直を認得して人にせられず。便(すなわ)ち空手にして郷(きょう)に還(かえ)る。所以(ゆえ)に一毫も仏法無し。(永平広録、巻1)(141頁)
「山僧」は「山野の僧」という意味で、一般に僧が自分を指して山僧と言う。
「叢林」とは禅の寺院のこと、「檀林」ともいう。真実の道を求める人々、すなわち僧衆が和合して一緒に住み、林のなかに樹木がたくさんあっても少しも少しも争うことがなく調和しているのと同様であるというところから来た言葉。
「等閑に」は、なおざりにということ、元来は事物を軽く見るときに使う言葉であるが、ここでは「求めずに」、「尋常に」、「当たり前の仕方で」というように、さらりとした心持を示す。
「当下に」は、すぐさまという意味で、廻り道や寄り道をせずにという心持を示す。
「一毫」の「毫」は細い毛のこと、分量の極く少いこと、髪の毛ひとすじと訳してもよい。(141~142頁)
私は大宋国に渡ったが、それほど多くの道場を歴訪して学歴を積んだわけではない。ただ学道者の常の仕方で先師、天童山如淨(にょじょう)禅師の門に入り、よそ見せずに眼は横、鼻は縦についているという道理を体得して、人にだまされないようになっただけである。
つまり私は何の御土産も持たず、すでで日本に帰ってきた。だから私には、いわゆる仏法などという特別なものは微塵もないのである。ー(142頁)
■渾身(こんしん)是れ口、虚空を判ず
居ながらに起す東西南北風(ふう)
一等に玲瓏(れいろう)として己語(こご)を談ず
滴丁東了滴丁東(てきていとうりょうてきていとう)(永平広録、巻1)(133頁)
この偈(げ)は、道元がその師、天童如浄の風鈴の偈に和して詠じたものである。そこで、まず如浄の風鈴の偈を掲げる。
渾身口に似て虚空に掛る
東西南北の風(ふう)を問わず
一等に他の与(ため)に般若を談ず
滴丁東了滴丁東
全身まるごと口みたいで虚空にぶらさがり
東西南北、風のまにまに
万物のため平等に般若空を説いている
テイ、ティン、トン、リャオ、テイ、ティン、トン
この風鈴の偈が、道元は大好きだった。若き日、如浄の会下(えか)にありしとき、師の風鈴の偈を聞いて感歎措(お)く能わず、進み出て師を排し、「和尚の風鈴の頌(じゅ)は最好中の最上なり。諸方の長老、縦(たと)い三祇劫(さんぎごう、百億万年)を経(ふ)とも、亦(また)及ぶこと能わざらん」と言い、さらに「道元何の幸ありてか、今見聞することを得て歓喜踊躍(ようやく)し、感涙衣(ころも)を湿(うる)おし、昼夜叩頭(こうとう)して頂戴す。然る所以は、端的にして而も曲調あればなり」と申しあげた。そのものずばりで、しかも曲調(ユーモア)があるからです、と言ったのである。
如浄はそのとき、ちょうどかごに乗ろうとしていたが、「笑を含んで示していわく、爾(なんじ)の道(い)うこと深く、抜群の気宇あり」と言い、つづけて「諸方賛歎すると雖(いえど)も、而も未だかって説ききたって斯(かく)の如くに非ず(おのずから出来たもので、ことさら作ったものではない)。われ天童老僧、儞(なんじ)、頌(じゅ)をつくらんと要せば、須(すべから)らく恁地(かくのごとく)つくるべし」と語った。
師弟一枚になっての、美しくもまたほほえましい光景が目に浮ぶ。道元は、後にこの偈頌(げじゅ)に唱和して、みずから一偈を成した。それが、いま揚げるところの風鈴の偈である。
全身口になり切って、虚空をよりわけ
居ながらにして東西南北の風を起す
その風の一つ一つに澄み切った声のひとりごと
チリン、チリリン、チリリン、ツン(154~155頁)
■うらむべし、山水にかくれたる声色(しょうしき)あること、又よろこぶべし、山水にあらわるる時節因縁あること。(正法眼蔵渓声山色)(165頁)
道元において、山水は人為にあらず、自然にあらず、じつに「古仏の道原成」であった。『正法眼蔵山水経』には「而近(にこん)の山水は古仏の道原成なり」とある。いま、まのあたりに見る宇治の山水は、直ちに是れ古仏の道原成、すなわち仏の成り姿である。されば渓流は間断なく古仏の道を説きつづけ、山色は仏の姿をすこしもかくすことなく露現しているのだ。
しかるに、あわれむべし、凡夫にはそれが聞こえず見えず、自然は死んで向う側の対象界に横たわっているものとなった。しかし、修行者にとっては、仏の道はただかくれているだけだ。かくて現れないことは、うらむべきことだが、努めて倦むことなくんば、現れる時節因縁がある。
宋の偉大な詩人蘇東坡は盧山に遊んだ夜、渓流の声を聞いて、仏の「八万四千偈」を聞き、たちまちに大悟した。同じく霊雲は茶店に腰かけて休息したとき村里一ぱいに咲く満開の桃の花を見て大悟した。また香厳(きょうげん)は庭の掃除をしているとき石ころが竹にあって発した声に忽然(こつねん)として真理を体得した。
むかしから渓流は声をあげて説法のしどうしだ。桃の花も太古以来、春になれば毎年満開だ。石ころがころがって竹にあたるのも、むかしから何度あったか知れない。彼らが修行の果てに仏声、仏身にふれるまで、それはかくれていたかのようである。道元はこれを「うらむべし」と言った。
しかし時節因縁によって、すなわち修行の果てに彼らは仏声を聞き仏身を見た。これを道元は「よろこぶべし」と言ったのである。
うらむべし、よろこぶべしという文章のなかに無限の思いがこめられている。道元は、じつに詩人であった。無感動の世界を禅と称するのではないのである。(167~168頁)
■ある一類おもはく、仏性は草木の種子のごとし、法雨のうるおひ、しきりにうるほすとき、芽茎(がきょう)生長し、枝葉華果(しようけか)も(茂)すことあり、果実さらに種子をはらめり。かくのごとく見解(けんげ)する、凡夫の情景なり。(正法眼蔵仏性)(173頁)
ある一群の人々は、仏性というものを草木の種と同じように考えている。種を蒔くと、雨のうるおいがしきりにやってきて、その種のなかに可能性として潜在しているものがしだいに現れ、やがて芽を出し、茎を生じ、枝や葉を茂らせ、ついに花を咲かせ、そうして実を結ばせる。かくてこの実は、また種を宿している。仏性もその通りで、一切衆生のなかに仏性の種が宿っていて、いろいろの法雨、つまり因縁がこれを育てると、ついには仏性の花が咲き実を結ぶことになる。こんなふうに思っている学者が多いけれども、これは迷える凡夫の勝手な憶測にすぎないのである。
自分の内部に仏性の種子があって、それが時間をかけてうまく育てられたら仏性の花が咲き実が結ぶと思うのは、只管打坐していない者の思いである。
そもそも道元は『涅槃経』の「一切衆生悉有仏性」を「一切衆生、悉有は仏性なり」と読んだのである。(174~175頁)
人生は芽のときも、茎のときも、枝のときも、花や実に至る単なる過程ではない。芽のときに死んだら人生は徒労だったことになるのか。ただ花と果実のときが究極目的で、他はそこへ到る手段や過程にすぎぬのなら、枝葉繁茂のところまでこじつけて死んだら、これも徒労だったことになりはしないか。
道元はこれを断乎として退ける。それは「凡夫の情景」だ。発芽(発心)は過程であると同時に究極である。枝葉(修行)も究極である。開花(小悟)も究極である。そうして果実(大悟)も究極である。究極とは何ぞや。これすなわち仏性にほかならぬ。
過程であると同時に究極の意味がないなら、人生の意味はぼやけ、生活の意義は曖昧になる。途中で無常の嵐に散らされたら、無意義だったことになる。その予感があれば、途中の一々の時期に全力を打ち込む力が抜けてしまう。
ゆえに道元は、これにつづけて、「種子および華果ともに条々の赤心なりと参究すべし」と述べた。条々とは、一つ一つということで、それぞれのときの一つ一つが赤心、すなわち仏性のまる出し、かくしようのないものと参学せよというのである。
洗面のときも究極、食事の時も究極、草むしりのときも究極、読書のときも究極、休息のときも究極であって、それらの一々は何か一つの目的に到達するための道程や過程としてのみ意義づけられるのではない。(176~177頁)
■禅宗の称は魔波旬(まはじゅん)の称するなり。魔波旬の称を称しきたらんは、魔党なるべし、仏祖の児孫にあらず。(正法眼蔵仏道)(177頁)
いまの世にも人々は禅宗の称を口にしているし、ほとんど全ての禅学徒が禅宗を自称している。しかし、道元がこれを天魔波旬のなすところと断じたことを肝に銘じなければならない。道元においては、仏祖の児孫であるかないかだけが重大なので、ことさらに宗派を立てるがごときは断じて許されることではなかった。
見よ、釈尊も迦葉の正法を伝えただけであって、いまだかって仏宗とか釈迦宗とか名乗ったことなく、宗派を名乗ったこともない。達磨にも慧可にもなく、弘忍にも慧能にもない。青原にも南獄にもない。禅宗の称を用いたのは、おそらくつまらぬ学者が仏法をこわすためにやったことであろう。なぜなら、禅宗の称は、仏祖の法以外に禅宗という特別の法があると思うところからきているからである。
宗派根性というものは、自己主張からきている。多くの宗派に伍してこれに対立しようとするところから生ずるのである。それは道元の言葉を借りていえば「慕古(ぼうこ)の志気(しいき)なく」、みずから「自立」せんとする「庸流(ようる)」のすることである。
古えを慕うことなく、いまの世にこびて、世人の気に入りそうな新味を打ち出そうとする庸流(凡庸者)が一宗一派を立てようとするのだ。もし仏法においてひとりひとりが異を立てて「自立」したら、それこそ仏法の破壊であり、そうなったら仏法は断絶して今日に伝わらなかったであろう。
「仏道におきて各々の道を自立せば、仏道いかでか今日にいたらん。迦葉も自立すべし、阿難も自立すべし。もし自立する道理を正道とせば、仏法はやく西天(インド)に滅しなまし。各々自立せん宗旨、たれかこれを慕古せん。」(正法眼蔵仏道)
古を慕うには、格外の力量と過節の志気がなくてはならない。ゆえに凡庸者は、魔王にさそわれ、一宗一派を立てて自立しようとするのである。自立した宗派は、たとえ数百万の信者を集めても、やがては消えうせるものだ。古の道を求める慕古の志の生じようがないからである。(179~180頁)
■古人云(いわ)く、百尺竿頭如何進歩(ひゃくしゃくのかんとういかんがほをすすめん)と。然(しか)あれば百尺の竿頭にのぼりて、足をはなたば死ぬべしと思ふて、つよく取りつく心のあるなり。(正法眼蔵随聞記、第三)(187頁)
百尺の竿の頂上におる人が、どうして一歩を進めることができましょうと言ったのは、一歩を進めたとたんに地に落ちて命を失うだろうと思って、竿にしがみついているからである。
師の長沙は、それを敢えて一歩を進めよと言ったのだから、師の一語「よもあしからじ」と思い切って、手足を放って一歩を進めるがよい。むろん身命はないものと覚悟せよ。
渡世のわざも捨て、わが身の暮らしも捨て、思い切って一歩を進めよ。いかに師の言葉といえ、生活の手段まで捨てては死ぬばかりだから、これだけはとても師に従えないという気があっては、いくら猛然と勉強しているようでも、道を体得することはかなわぬ。頭燃ー頭にふりかかる火の粉を打ち払うような急切さで修行に努めているようでも、わが身可愛やの一念があって、身心を放下し打ち捨てきれないかぎり、真実の道を体得することはできない。この僧には「足をはなたば死ぬべしと思ふて、つよく取(とり)つく心」がある。この取りつく心を放下するのが、まことの修行である。
すなわち、一僧の心の裏まで見通ししての一語である。懐奘をはじめ道元門下の学人たちが、いかに身をひきしめてこれを聞いたか、思いやるだに感動のきわみである。(188~189頁)
■ただわが身をも心をも、はなちわすれて、仏の居へに投げ入れて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをつひやさずして、生死をはなれ仏となる。たれの人か、こころにとどこほるべき。仏となるにいとやすきみちあり、もろもろの悪をつくらず、生死に著(じゃく)するこころなく、一切衆生のために、あわれみふかくして、かみをうやまひ、しもをあはれみ、よろづをいとふこころなく、ながふこころなくして、心におもふことなく、うれふることなき、これを仏となづく。またほかにたづぬることなかれ。(正法眼蔵生死)(194頁)
■この生死(しょうじ)は、すなはち仏の御(おん)いのちなり、これをいとひすてんとすれば、すなはち仏の御いのちをうしなはんと、するなり。これにとどまりて、生死に著(じゃく)すれば、これも仏の御いのちをうしなふなり。(正法眼蔵生死)(197頁)
生命体は母胎に宿る瞬間から刻々に無数の生と滅を繰りかえし、しばらくもとどまることがない。これを「刹那生死(しょうじ)」という。ひろげて言えば万物は「刹那生滅」して、一瞬も停止しない。有情はこの刹那生死によって身心発達し、幼、壮、老を経て一生を終えるので、これを「一期の生死」と名づける。そうして、この一期の生死を繰りかえして車輪のめぐるように一刻も停止せず六道(りくどう)に輪廻するのである。六道とは地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天で、衆生はその業によってこの六道のなかをさ迷うて、脱出できないから、「生死の苦海」という。仏法はこの苦海からの解脱を説くものと考えてよい。すなわち、生死を離れて涅槃に入ることを教える。インド仏教の元来の発想は右のごとくである。(198頁)
もし人、生死のほかにほとけをもとむれば、ながえをきたにして越(えつ)にむかひ(越はみなみの国)、おもてをみなみにして北斗をみんとするがごとし。いよいよ生死の因をあつめて、さらに解脱のみちをうしなへり。ただ生死はすなはち涅槃とこころえて、生死としていとふべきもなく、涅槃としてねがふべきもなし。このときはじめて、生死をはなるる分(ぶん)あり。
生より死にうつるとこころうるは、これはあやまりなり。生はひとときのくらいにて、すでにさきありのちあり、かるがゆえに仏法のなかには、生すなはち不生という。滅もひとときのくらいにて、またさきありのちあり、これによりて滅すなはち不滅といふ。
生といふときには、生よりほかにものなく、滅といふときは、滅のほかにものなし。かるがゆえに生きたらば、ただこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべしといふことなかれ、ねがふことなかれ。(199頁)
■又見んと 思ひし時の 秋だにも 今夜(こよひ)の月に ねられやはする(傘松道詠)(213頁)
この一首には、「御入滅之年八月十五夜、御詠歌に云」とある。御入滅の年とは建長5年(1253)で、道元54歳、その日は8月28日であるから、この一首は死の13日前に当る中秋の夜に詠まれたものである。(213頁)
■不惜(じゃく)身命なり、但惜身命なり。(正法眼蔵生死)(222頁)
「但惜身命」の「但」は「たん」と発音する。この字を「但(ただ)し」の意に解するのは大なる誤りで、但(ただ)と訓(よ)まねばならない。ほかに余念なく、ただ身命を惜しむ、これを但惜身命という。(222頁)
■いたづらに百歳いけらんは、うらむべき日月なり、かなしむべき形骸なり。たとひ百歳の日月は、声色(しょうしき)の奴婢と馳走すとも、そのなか一日の行持を行取せば、一生の百歳を行取するのみにあらず、百歳の佗生(たしょう)をも度取すべきなり。この一日の身命は、たとふべき身命なり、たとふべき形骸なり。かるがゆえに、いけらんこと一日ならんは、諸仏の機を会(え)せば、この一日を曠劫(こうごう)多生にもすぐれたりとするなり。このゆえに、いまだ決了せざらんときは一日をいたづらにつかふことなかれ。この一日はをしむべき重宝なり。(正法眼蔵行持、上)(226頁)
われらのこの一日は、惜しみてもあまりある貴重な宝である。この宝をいたずらに空費しないことを「但惜身命」ともいうのである。(227頁)
むなしく百歳を生きるとは、肉体に奉仕して五官の世界に引きずられることである。
古代インドのある都城に4人の妻をもつ億万長者がいた。第1の妻は、長者の最も愛する妻で、長者は彼女の欲しがるものは何でも与えた。欲しがる着物、首飾りを買ってやり、旅行ものりものも意のままにさせ、食物、飲みものも好きなものを与えた。
第2の妻は苦労して手に入れた妻で、多くの競争者と争って、ついに自分のものにしたのであった。長者はこの妻を第1の妻の次に愛し、いつも身近にはべらせ、お前がいるのでわしは仕合せだと言った。
第3の妻は、ときどき会って慰め合い、飽きると口論して離れることもあるが、しばらくするとまた寄りを戻すという仲であった。
第4の妻は、むしろ下女というべき女で、長者は彼女を大切にしたことは1度もなく、勝手次第にこき使った。彼女は長者に仕えて立ち働いたが、1度も愛撫されることはなかった。
さても、あるとき突然のことが生じて、長者は住みなれた都城を去って、遠い遠い国に旅立たねばならないことになった。ひとりで遠い旅路に出るのはさびしい極みである。そこで、長者は第1の妻をつれて行くことにした。「お前はわしの1ばん可愛がった妻で、お前の欲しいことは何でも叶えてあげた。さあ、旅の用意をしておくれ。」すると、第1の妻は意外にも、すげなく拒んで、「私はいやです。いくら愛してくださった人でも、一緒に遠い国へついては参りません」という。なだめても、すかしても、おどしても無駄であった。
仕方なく第2の妻をつれて行くことにした。「そなたはわしの苦労して得た掌中の玉だ。一緒に旅立ってくれるだろうね。」すると第2の妻がいうには、「あなたの1ばん溺愛した第1の夫人すら行かないというのに、私がどうして行かねばならないのですか。」こう言って、彼女は拒んだ。「あなたが遠いへ行くとき、私もついて行くという約束をしたおぼえはありません」というのが彼女の拒む理由だった。
やむを得ず、長者は第3の妻に出発を命じた。「お前とは喧嘩もしたが、また仲直りした。たがいに慰め合ってきたのだからね。」すると第3の妻が言った。「あなたの御恩は忘れませんわ。ご出発のときは、あたし都城の外までお見送りします。」「いやいや、遠い国まで一緒に行ってほしいのだよ。」「いいえ、あたしは城外までしか行きません。」
長者は憂苦し懊悩したが、ついに不本意ながら第4の妻をつれて行くことにした。「わしはお前をこき使うばかりで、すこしも大切にしてあげなかったが、お前はわしの命令に1度だってさからったことはない。」ー「はい、私はただ旦那さまだけに仕える身ですもの、楽しくても苦しくても、生きても死んでも、はい、旦那さま、わたしはついて行きます。」
『雑阿含経』にこの話があり、仏説(と)いてのたまわく、都城とは是れこの世の生の世界。遠い国とは是れ死の世界。4人の妻をもつ長者とは是れ人間の魂である。
第1の妻とは人間の肉体である。あれほど一生かかって肉体に奉仕したのに魂の出立にあたっては、無表情に床(とこ)の上に横たわって振り向きもしない。
第2の妻とは人間の財宝である。人と争って苦労のすえに得たもので、これさえあれば仕合せと思っていたが、死後も一緒についてゆくと約束したおぼえはないと言い張るのだ。
第3の妻は妻子、兄弟、姉妹、友人、親戚である。口論したり、協力したり、慰め合ったりした仲で、彼らは死別を悲しみ、城外の墓場まで涙ながらに見送る。しかし、その後は家に帰り、やがて長者のことは忘れて、おのおの自分の生きることに没頭する。
第4の妻は人間の心(しん)意識である。衆生は自分の心を大切にしないで、奴婢のごとくにこき使い、あくまで働かせ、貪欲(どんよく)に駆り立て、怒りに燃えさせ、嫉妬に狂わせる。しかるに心意識は魂と一体だから、どこまでも魂についてゆく。地獄へも、畜生界へも、どこまでもどこまでも輪廻の旅をつづけてゆく。
人々よ、愛の順序がまちがってはいないか。このまちがいこそは、生のむなしさの根源ではあるまいか。釈尊はこのように説きたまうた。(227~230頁)
(2014年1月20日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『典座教訓・赴粥飯法』 道元 講談社学術文庫
典座教訓
■『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』に、「食事を作るには、必ず仏道を求めるその心を働かせて、季節にしたがって、春夏秋冬の折々の材料を用い、食事に変化を加え、修行僧達が気持よく食べられ、身も心も安楽になるように心がけなければならない」と言っている。昔から、あの潙山(いさん)霊祐禅師や洞山守初(とうざんしゅしょ)禅師も、この典座の職をつとめられたし、そのほかにも多くのすぐれた禅僧達が、この典座職を経験してきたのである。世間一般の料理人や給仕役などと同じように考えてはならない。
私が宋(南宋)の国に留学していたころ、ひまをみては、先輩や長いあいだ役職をつとめてきた人達に尋ねてにたところ、その人達は、自分達が実際に体験し見聞きしてきたことを、少しずつ私のために説き示してくれた。このときの説明は、昔から仏道を求める深い心を持った代々の仏や祖師達が、後の世の人々にのこしてくれた、根本的な教えであった。この典座(てんぞ)の職務のあらましについては、『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』をよくよく読みなさい。そうした上で、先輩達の詳しい説明を聞かなくてはいけない。(22~23頁)
■◯斎(さい)ー梵語ウポーシャダ(身・口(く)・意の行為をつつしむこと、布薩(ふさつ)とも訳される)の訳語で、特定の日に戒律を守り功徳を積む意。在家信者が六斎日(月の8・14・15・23・29・30日)に八斎戒(殺さない、盗まない、性交しない、嘘を言わない、酒を飲まない、身を飾り歌舞を見物したりしない、高床(こうしょう)の気持ちよいベットに寝ない、正午以降は何も食べない)を守り身をつつしむこと。六斎日や故人の忌日(きじつ)などに僧を招待して食事を布施し供養する意味にも用いられる。また仏弟子の食事は、正午以前にⅠ回たべるのが正式であったことから、昼食の意に用い、禅宗寺院では、朝の粥(小食(しょうじき))に対し昼の正式な食事(中食(ちゅうじき))を意味する。日本で「とき」と訓ずるのはこのためである。(27頁)
■雪峰義存(せっぽうぎそん)和尚が洞山价(とうざんりょうかい)禅師の修行道場において、典座職をつかさどることになった。ある日、雪峰が米をといでいるときに、洞山禅師がやってきてたずねた、「砂をといで米を取り除くのか、それとも、米をといで砂を取り除くのか」と。すると雪峰は答えた、「すなも米も同時に取り除きます」と。洞山禅師がまた尋ねた、「それでは修行僧達はなにを食べるのか」と。これを聞いて雪峰は、米の入っているお盆をひっくりかえしてしまった。洞山禅師はその様子を見て言った、「お前は後日、きっと別の指導者に会ってその指導を受けることになるだろう」と。昔から、仏道の修行に志すすぐれた人達が、直接自らこの上もなく心をこめて、典座の職を実践したことは、この通りである。後のこれから修行しようとする人が、これを怠りなまけることがあってどうしてよいものか。先人達も言っている、「典座がたすきをかけて自からその職責を果たすことこそ、仏道修行する者の心構えである」と。
もし米をといでいて、砂と誤って米を捨てるようなことがあったなら、典座が自ら点検する。『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』に、「食事を作る時、典座自ら手を下してよくよく点検しなさい。そうすればおのずと調ったよい食事ができあがる」と言っている。米をといだ白水であっても、気にもとめないで捨てるようなことがあってはならない。昔から、白水をこす袋を備えておいてこれに白水を入れ、たとえ一粒の米でも無駄にしなかったのである。おかゆの米と水の分量をほどよくはかり、鍋に入れ終わったなら、これを護ることに留意して、ねずみなどが汚したり、乱したり、あるいは無用の者にのぞかせたり、さわったりさせてはならない。(34~35頁)
■○今古(こんこ)は殊劣(しゅれつ)にして、天地は懸隔(けんきゃく)す、豈(あ)に肩を斉(ひと)しくすることを得る者ならんや。ー今古と天地、殊劣と懸隔は対語で、2句は対句を構成している。仏教の見方に、釈尊の時代を下るほど機根が劣り、正法・像法としだいに、教法のみあって修行したり証悟したりする者がなくなる時期がくるとする、末法思想という下降的歴史観があり、浄土教の普及などによって広く受容された。特に日本では、社会不安の世相も反映して深刻に受けとめられ、永承7年(1052)末法元年に入ったと信じられた。また、釈尊の生まれたインドから離れた地ほど法の潤いがうすくなるとも考えられた。親鸞や日蓮を初めとする鎌倉時代の祖師達にとって、末法思想は超克されなければならない共通の時代的課題であり、浄土教や『法華経』の宣揚がこれに答える方法であった。道元の「今古云々」の文言にはこうした一般論が踏まえられているが、ただし『正法眼蔵』「弁道話」では、「とふていはく、この行(坐禅)は、いま末代悪世にも、修行せば証をうべしや。しめしていはく、教家に名相(みょうそう)をことゝせるに、なほ大乗実教(じつきょう)には、正(しょう)像末法をわくことなし。修すればみな得道すといふ。云々」といい、こうした歴史観を否定しており、『典座教訓』の次の文においてもこの主張は一貫している。(53頁)
■○一微塵ー仏教で展開する原子論では、これ以上は分割できない最小の単位を極微(ごくみ)といい、この極微を中心に上下・四方の、合計7個の極微が集まった物を一微塵という。きわめて小さなもののたとえ(『倶舍論』巻1)。ここでは、一見、仏道修行とは何の関係もないように見える典座の仕事の場所をいう。(48頁)
■○物に転ぜらるるも、能(よ)く其の物を転ずる手段なりーここで物とは、自己の心の対象となる外界の事物。「物に転ぜらるる」とは、自己を見失い外界の事物に動かされて行動すること。これに対し、「物を転ずる」とは、主体性を確立し他の影響を受けることなく、積極的に外界の事物にはたらきかけていくこと。六祖慧能が、『法華経』を学びその文義に滞っている弟子の法達を指導するために示した偈(げ)に、「心迷わば法華に転ぜられ、心悟らば法華を転ず。云々」(『景徳伝灯録』巻5)とあり、道元もこの話を『正法眼蔵』「法華転法華(てんぼっけ)」で取り上げ、さらに展開敷衍(ふえん)している。(54~55頁)
■○神通(じんずう)及び変化(へんげ)ー修行によって得られる勝れた智慧、人間の能力を超えた超自然的な力で、神足通(じんそくつう)(どこのでも自由に往来できる)・天眼通(未来を見通すことができる)・天耳(に)通(間を隔てて普通の人には聞けない音を聞くことができる)・宿命(みょう)通(人の過去世を知ることができる)・他心通(他の人が何を考えているか知ることができる)・漏尽(ろじん)通(煩悩を除くことができる)を6通という。変化は自在に姿を変える神通力。ただし禅宗では、水を運び柴を運ぶような普通の日常的行為がきわめて自然におこなわれることこそ神通とされる。(55~56頁)
■山僧(さんぞう)(岡野注;道元)、天童に在りし時、本府(ほんぶ)の用典座(ゆうてんぞ)、職に充てらる。予、斎罷(おわ)るに因(よ)り、東廊を過ぎて超然斎(ちょうねんさい)に赴(おもむ)けるの路次(ろし)、典座は仏殿の前に在りて苔(たい)を晒(さら)す。手に竹杖(ちくじょう)を携え、頭には片笠(へんりゅう)も無し。天日(てんじつ)は熱く、地甎(ちせん)も熱さも、汗流(かんりゅう)して徘徊し、力を励まして苔を晒し、稍々(やや)苦辛するをみる。背骨(はいこつ)は弓の如く、竜眉は鶴に似たり。山僧。近前(ちか)づきて、便(すなわ)ち典座の法寿を問う。座(ぞ)云う、「六十八歳なり」と。山僧云う、「如何んぞ行者(あんじゃ)・人工(にんく)を使わざる」と。座(ぞ)云う、「他(かれ)は是れ吾(わ)れにあらず」と。山僧(さんぞう)云う、「老人(にん)家(け)、如法なり。天日(てんじつ)且(か)つ恁(かく)のごとく熱(あつ)し、如何んぞ恁地(かくのごとく)にする」と。座(ぞ)云う、「更に何れの時をか待たん」と。山僧、便(すなわ)ち休す。廊を歩むの脚下、潜(ひそ)かに此の職の紀要たるを覚(さと)る。(69~70頁)
■○本府(ほんぶ)の用典座(ゆうてんぞ)ー本府は地元の寧波府(ニンポーフ)出身の意で、用は「□用」という名であるが、諱(いみな)の上字は不明。諱の下字だけで呼ぶのは禅院の礼儀で、相手に対する尊敬の意を表わす。用典座は、道元に禅の修行道場における生活の意義について眼を開かせてくれた恩人の一人。(71~72頁)
■又、嘉定(かてい)16年癸未(みずのとひつじ)5月の中(ちゅう)、慶元の舶裏(はくり)に在りて、倭使(わし)の頭(かしら)と説話する次(おり)、有る一老僧来(きた)る。年は60許(ばか)りの載(とし)なり。一直(いちじき)に便(すなわ)ち舶裏(はくり)に到り、和客(わかく)に問い、倭椹(わじん)を討(もと)め買う。山僧、他(かれ)を請(まね)きて茶を喫(きっ)せしめ、他(かれ)の所在を問えば、便(すなわ)ち阿育王山の典座なり。他(かれ)云う、「吾れは是れ西蜀(せいしょく)の人なり。郷を離れて40年を得、今、年是れ61歳なり。向来(これまで)、粗(ほぼ)諸方の叢林を歴(へ)たり。先年、権孤雲(ごんこうん)の住裏(じゅうり)に、育王を討(たず)ねて掛搭(かた)し、胡乱(こらん)に過ぐ。然(しか)るに去年、解夏(げげ)し了(おわ)りて、本寺の典座に充てらる。明日は5の日なれば、一たび供(きょう)せんとするも渾(すべ)て好喫なるもの無し。麺什を作らんと要(もと)むるも、未だ椹(じん)有らざる在り。仍(よ)りて特特として来たり、椹を討(もと)め買い、十方の雲衲(うんのう)に供養せんとするなり」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)に問う、「幾時にか彼(かしこ)を離る」と。座(ぞ)云う、「斎了(おわ)りてなり」と。山僧(さんぞう)、云う、「幾時にか寺裏(じり)に廻(かえ)り去る」と。座(ぞ)云う、「如今(いま)や、椹を買い了(おわ)れば、便(すなわ)ち行(ゆ)かん」と。山僧(さんぞう)、云う、「今日(こんにち)、期せずして相会(あいかい)し、且つ舶裏(はくり)に在りて説話す、豈(あ)に好結(けち)縁に非(あら)ざらんや。道元、典座禅師に供養せん」と。座(ぞ)云う、「可(よ)からず。明日の供養、吾れ若し管せずば、便(すなわ)ち不是になり了(おわ)らん」と。山僧(さんぞう)、云う、「寺裏(じり)何ぞ同時の者の、斎粥(さいしゅく)を理会する無からんや。典座一位在らざるも、什麽(なん)の欠闕(けつけつ)か有らん」と。座(ぞ)云う、「吾れは老年にして此の職を掌(つかさ)どる、及(すなわ)ち耄及(もうきゅう)の弁道なり。何を以(もっ)てか他(かれ)に譲るべけんや。又来たる時、未(いま)だ一夜の宿暇を請わず」と。山僧(さんぞう)、又典座に問う、「座尊年、何ぞ坐禅弁道し、古人の話頭を看せざる。煩わしく典座に充てられて、只管に作務し、甚(なん)の好事か有らん」と。座(ぞ)大笑して云う、「外国の好人、未だ弁道を了得せず、未だ文字を知得せざる有り」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)の恁地(かくのごとく)に語るを聞き、忽然として発慚(はつざん)驚心し、便(すなわ)ち他(かれ)に問う、「如何なるか是れ文字、如何なるか是れ弁道」と。座(ぞ)云う、「若し問処(もんじょ)を蹉過(しゃか)せざれば、豈に其の人に非(あら)ざらんや」と。。山僧(さんぞう)、当時、会(え)せず。座(ぞ)云う、「若し未だ了特さざれば、他事後日、育王山に到れ。一番、文字の道理を商量し去ること在らん」と。恁地(かくのごとく)に語り了(おわ)り、便(すなわ)ち座(ざ)を起(た)ちて云う。「日晏(く)れ了(おわ)れり、忙(いそ)ぎ去(ゆ)かん」と。便(すなわ)ち帰り去(ゆ)けり。(73~75頁)
■○古人の話頭――禅宗の祖師達の残されたすぐれた言行。これを記録したものを語録といい、その中の特に後代の修行者の指針・指標となるような先人の故事・逸話類は、古則・公案・話頭と呼ばれて学び研鑽され、それらを集めた『碧巌録』『無門関』『従容録』などの話頭集成本の編纂もなされた。宋代以降はこの話頭・公案の真意を究めることを修行の目的とする公案禅(一名、看話(かんな)禅)が隆盛となった。道元も留学の初めごろはこの語録・公案を学ぶことを修行と考えていたようであるが、後には公案禅を否定する「只管打坐」の禅風を確立する。話頭の頭は接尾語。(84頁)
■同年七月の間(かん)に、山僧(さんぞう)、天童に掛錫(かしゃく)す。時に彼(か)の典座来(きた)り得、相見(しょうけん)して云う、「解夏(げげ)し了(おわ)れば、典座を退きて郷(きょう)に帰り去らんとす。適々(たまたま)兄弟(ひんでい)、老子の箇裏(こり)に在りと説(い)うを聞く。如何んぞ来たり相見(しょうけん)せざらん」と。山僧(さんぞう)、喜踊(きよう)感激し、他(かれ)を接して説話するの次(おり)、前日の舶裏(はくり)に在りての、文字・弁道の因縁を説き来る。典座云う、「文字を学ぶ者は、文字の故を知らんと為すなり。弁道を務むる者は、弁道の故を肯(うけが)わんことを要(もと)むるなり」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)に問う、「如何なるか是れ文字」と。座(ぞ)云う、「一二三四五」と。又問う、「如何なるか是れ弁道」と。座云う、「徧界(へんがい)曾(かつ)て蔵(かく)さず」と。其の余の説話は、多般有りと雖(いえど)も、今は録さざるなり。山僧(さんぞう)、聊(いささ)か文字を知り、弁道を了ずるは、乃(すなわ)ち彼の典座の大恩なり。向来の一段の事(じ)を、先師全公(ぜんこう)に説似(せつじ)するに、公、甚(はなは)だ随喜するのみなり。(85頁)
■○先師全公(ぜんこう)ー建仁寺明庵栄西の弟子である、仏樹房明全(1184-1225)のことで、比叡山を下って以後の道元の本師になった。道元を伴い宋に留学したが、留学中の宝慶(ほうきょう)元年に、天童山の了然寮でで病没した。先師は、亡き本師に対する敬称で、道元は明全の遺骨を日本に持ち帰り、『舎利相伝記』を撰述して記録に留めた。(88頁)
■山僧(さんぞう)、後に、雪竇(せっちょう)の頌(じゅ)もて僧に示せることあるを看るに、云う、
一字七字、三五字
(一字や七字や、三字や五字でものごとを言いあらわすが、)
万像(まんぞう)窮(きわ)め来たるに、拠(よりどころ)を為さず。
(そのあらゆるものごとも本質を窮めてみれば、すべてよりどころとなるものではない。)
世深(ふ)け月白くして、滄溟(そうめい)に下る、
(夜も更け月はいっそう皓々と輝き、その光は大海へと下り、あたり一面月一色のせかいとなるように、)
驪樹(りじゅ)を捜(さが)し得ば、多許(たこ)有り。
(探し求めていたあの竜の顎の下のすばらしい玉も、手にいれてみれば、そこらじゅう玉でないものは何もなくなる。)
と、前年に彼の典座の云いし所と、今日(こんにち)の雪竇(せっちょう)の示す所と、自ずから相い符合す。弥々(いよいよ)知りぬ、彼の典座は、是れ真(まこと)の道人(どうにん)なりしことを。然(しか)れば則ち、従来看し所の文字は、是れ一二三四五なり、今日看る所の文字も、亦六七八九十なり。後来(こうらい)の兄弟(ひんでい)、這頭(しゃとう)より那頭(なとう)を看了(みおわ)り、那頭(なとう)より這頭(しゃとう)を看了(みおわ)りて、恁(かく)のごとき工夫を作(な)さば、便(すなわ)ち文字上に一味の禅を了得し去らん。若し是(かく)の如くならざれば、諸方の五味の禅の毒を被(こうむ)り、僧食(じき)を排便するも、未だ好手を得る能わざるなり。(89頁)
■まことにこの典座のあり方は、先人達のすぐれた言い伝えの中や、実際に私が中国で体験した中にあって、それが今も眼に見えるようであり、耳にも残っている。それを文字に記録して伝えることもあり、これをそのまま実行することもあって、これこそまさに、釈尊から正しく伝わった仏道の真髄そのものである。
もし仮りに、粥飯頭(しゅくはんとう)と呼ばれる住持職の地位について、1つの寺を統括する立場に立ったとしても、その心構えも典座と同じでなければならない。『禅苑(えん)清規』に言っている、「朝の粥と昼のご飯を支度し調えるには、十分に心を行き届かせ、豊かな内容を持ったものでなければならないし、修行僧達が生活に必要な飲食(おんじき)・衣服(えふく)・臥具・医薬の四事の供養も、事欠くようなことをさせてはならない。釈尊が100歳の寿命を20年縮めて後世に残してくれた恵みは、今の私達をおおい守ってくれており、釈尊の眉間にある白毫(びゃくごう)の光のほんの少しの恩惠も、私達には用い尽くせない」。そういうことで、「ひたすら修行僧にお仕えすることだけを考え、貧乏などを心配することはない」「物惜しみをするような小さな有限の心がなかったならば、自ずから無限の福徳がそなわってくる」とも言っている。思うに、このような配慮こそ、典座はもとより、住持職たる者が、修行僧達に対して供養し仕えるための心構えである。(94~95頁)
■修行僧に供養するための食事を支度し調える際の心構えは、材料が上等であるとか、粗末であるとかを問題にすることなく、仕事に対しては深い真心をもって当たり、食品材料に対しては、物を大切にし敬い重んずる心を起こすことが肝要である。
次のような話を知っているでしょう、ある老婆は、わずか1杯の米のとぎ汁でも、この心でお釈迦さまの供養したため、生前中にはこの上もない福楽の功徳を受け、また阿育王(アショーカ王)は、臨終のときに仏教教団に何か布施したいと願い、たった半分のマンゴーの実でもこれを差し上げようという、最後の善根の行為により、いずれも未来成仏の約束を与えられ、大きな果報を受けたということです。仏のためにする供養であっても、いつわりが多いということは、真実がないということにも及ばない。人の行ないとはこういうものである。(98頁)
■○十号―釈尊のこと。菩提を成就した釈迦牟尼仏(仏陀・覚者)には、その備わった徳相から、如来(真理の体現者)・応供(おうぐ、人間や神々から尊敬され供養を受ける資格のある者)・正遍知(しょうへんち、正しく真理を悟った人)・明行足(智慧と身体・言語行為とが完全に具わった人)・善逝(ぜんせい、悟りの境地に善く行ける者)・世間解(せけんげ、世間・出世間のことを熟知している者)・無上士(この上もない人)・調御丈夫(ちょうぎょじょうぶ、人をよく指導できる人)・天人師(てんにんし、天の神々と地上の人々の師たりうる人)・仏世尊(悟りを開き世間から尊ばれる人)という10種の称号・異名が付けられており、これを如来十号・仏十号という。ここでは仏陀・釈尊の全身心の意として用いられている。(100頁)
■◯育王の最後の大善根―釈尊と阿育王に関する故事で、マガダ国の阿育王は、釈尊の教えに基づく理想国家を築いたが、晩年には権力を失い不遇の境涯にあった。死期を悟った王は、鶏園寺(けいえんじ)の僧団に金銀を布施しようとしたが太子や大臣に反対され、自分が使用していた金・銀・鉄の食器を送り寄付し、そして最後に残った食用の半分のマンゴーの実も使いに持たせ僧衆に供養してしまった。鶏園寺(けいえんじ)の僧衆は、この半分のマンゴーの実を砕いて汁の中に入れ皆で食べ、王の布施の心を成就させた。この功徳により阿育王は、未来に成仏するという予言を与えられたという(『阿育王経』巻5、半菴摩勒施僧(はんあんもらせそう)因縁第6)(100頁)
■よく言われているように、醍醐味という御馳走を作るときも、それを決して特別上等だとはせず、菜っぱ汁を料理するときも、必ずしも粗末なものと見なしてはならない。菜っぱを手にして調理するときも、まごころ・誠実な心・清らかな心で、醍醐味を作るときと同じようにしなさい。そのわけはなぜであろうか。清らかな大海にたとえられる仏法の修行道場にいる修行僧達の中に、供養の食物が入ってしまうと、上等な醍醐味と粗末な菜っぱ汁という区別は立たず、百千の川も大海に流れ込めば、清濁の区別もなくなってしまうように、ただ1つの味だけになってしまう。ましてや、悟りを求める心をはぐくみ、仏の智慧を宿すこの肉体を養うことにおいては、上等なものであろうと粗末なものであろうと、全く同じであり、どうして別々のものがあろうか。「出家者の口はあたかもかまどのようなもので、上等なものも粗末なものも区別せず、与えられたものを好き嫌いなく、一味に食べてしまう」という経典の言葉があるが、とくと心得ておく必要がある。粗末な食べ物も、仏身であるこの肉体を十分に養い、悟りを目指す心もよく育ててくれるということを、よくよく思い返しなさい。粗末な食べ物も、いやしんだり、軽んじたりしてはいけない。人間界や天上界を導く師僧たる者は、この粗末な莆菜(ふさい)によって食事の尊さを教え、教化の効果をはかりなさい。(102~103頁)
■『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』には、「僧というものは、凡人とか聖人とかの区別に関係がなく、すべてのものごとに通ずることができる」と言っている。もし、「すべての是非の観念、得失・老少・凡聖(ぼんしょう)という区別を立てない」という意気込みがあったなら、この典座の職がどうして「そのまま悟りの世界に入りこむ」という修行でないことがあろうか。もしこれまで述べてきたところを、一歩でも踏み誤るようなことがあったなら、すぐにその場で真実とは行き違いになってしまうだろう。古からの典座職をつかさどってきた祖師方の真面目というものは、全くこのような気持で天座の仕事をしてきた点にある。後の時代において典座の職をつかさどる諸君たちも、同様にこのような心構えで典座の仕事をすれば、それでなんとかよろしいのである。百丈懐海禅師が修行道場の規則を定め、典座の職も規定したことは、どうして空しいことがあろうか。(106頁)
■◯「一切の是非、管する莫(な)し」「直(ただ)ちに無上菩提に趣く」―北宋代の居士で、『天聖広灯録』の編者としても知られる、都尉駙馬李遵勗(といふばりじゅんぎょく、?―1038)の投機の偈(げ)の中の句で、臨済宗の谷隠蘊聡(よくいんうんそう)に参じて大悟し、「学道は須(すべか)らく鉄漢(てっかん)なるべし、手を心頭に著(つ)てて便(すなわ)ち伴ぜよ。直ちに無上菩提に趣き、一切の是非を管すること莫(な)れ」という漢詩に託して自分の悟境を述べた。(『五灯会元(ごとうえげん)』巻12)。鉄漢はものに動じない大丈夫の人、不動の意志を持った修行僧。無上菩提は、梵語アヌッタラサムヤックサンボーデッヒの訳で、無上正等学(意訳)・阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい、音訳)などと訳し、この上もない最高のさとり、平等円満な仏の智慧。(107頁)
■○百丈高祖―馬祖道一の弟子、百丈懐海(749―814)のことで、江西省洪州にある百丈山大智寿聖寺の住職となり修行僧を指導したが、『百丈清規』を撰述して初めて禅宗の修行道場の規則を集大成し、それまで律寺に寄宿していた禅宗が独自の規則を有する宗派としての立場を確立したとされることから、叢林開闢の祖とされる。ただし百丈が制定した当初の古い清規(しんぎ)は失われ、『禅門規式』(景徳伝灯録』巻6)や『百丈規縄頌(きじょうじゅ)』(『禅苑清規』巻10)などが断片的に残されているにすぎない。(108頁)
■私は、中国の留学から帰国してより、2、3年間、建仁寺に留(とど)まり住んでいたことがある。この建仁寺では、深い仔細もなく典座の職を置いていたが、それはただ典座という名前があるだけで、典座という人間の実際の仕事は全くなかった。修行僧に食事を供養する仕事が、とりもなおさず仏作仏行としての実践そのものであることを知らないので、どうしてその上に仏道をわきまえることなどができよう。真実の師匠にめぐりあえず、空しく月日を過ごし、無為に仏道修行を台なしにしていることは、まったくあわれむべきである。
この建仁寺で体験した実情を述べると、昼飯と朝粥の支度については全く典座としての役目を果たしておらず、食事を作る仕事がいかに大事であるかも知らず、また考えようともしない下働きを自分の近くに置いて、大小のことをすべてこの下働きに言いつけ、その人のやったことが正しくても、正しくなくても、典座が自分で行なって監督するようなことは、かってなかった。それはあたかも、隣の家に婦人が住んでいて、そこに出掛けて行くことは僧として恥であるかのように、もし出て行って下働きの監督をするようなことがあるなら彼はそのことをまるで自分の恥であり、自分の人格に傷でもつくかのように思っている。そして寺の中に典座寮という一部屋をかまえて、寝転んだり、他人と談笑したり、お経を読んだり唱えたりして、どんなに月日が経っても、台所に出て行って仕事をするようなことはしない。いわんや、寺で使う品物を自分で買い求めたり、食事の献立や数量等について明らかにし決定したりすることは決してない。どうして典座の仕事を実際にするようなことがあろうか。ましていわんや、朝・昼の食事に際して、典座が自ら、用意した食事を庫院(くいん)の前の台の上にのせ、僧堂に望んで九拝して送り出すというような、心のこもった儀式などをすることは、夢にも知らない。典座が自ら若い修行僧達を教え導くときがきても、教えるべきことを何も知らないのである。(110~111頁)
■このように、仏道を修行しようとする心のない人が、すぐれた師僧にけっしてめぐり会うことができないということは、なげかわしいことであり、うれうべきことである。それはまるで、宝の山に入ったとしても、何も手に入れないで帰ったり、宝の海に潜(もぐ)ったとしても、何も身に得ることなく帰ってくるようなものである。典座というものは、仏道修行を目指す真実の心は起していなくても、もし悟りを開いた師匠に出会い教えを受けることができたならば、典座の役を立派に果たすことができるし、また、たとえすぐれた師匠に会うことができなくても、もし深く心に仏道を求める志を起こしていたならば、必ずや典座のつとめを仏道として成し遂げることができるということを、よく知っておくべきである。建仁寺の典座の場合は、これら2つの心が欠けているのであるから、彼が典座の職に就いたとしても、どうしてほんの少しでも自分の修行に役立つようなものがあろうか。(114頁)
■一方、私が見てきた中国の南宋時代のあちこちの寺々について言うなら、知事や頭首(ちょうしゅ)といった禅寺の役職についている人々は、1年間の任期でそれぞれのつとめにはげんでいるのだが、各自が三通りの住持と同じ心構えを踏まえて、それぞれ役職の任に当たってこれに従事し、たとえば典座の職なら修行僧を供養するというように、それぞれの職に就いたことを好い機会のめぐりあわせとして喜び、きそって仕事にはげんでいる。三通りの心構えとは、次の通りである。
1、他人のためにつとめ、そして自分自身の修行も十分に積めば、
2、修行道場をいっそう盛んにし、人間形成の場という高尚な風格も全く面目をあらたにでき、
3、古えのすぐれた人達に肩を並べ、さらに追いこし、古人の歩んだ道を継承し、その行ないの跡をしっかり保持していく。
こういうわけであるから、自分のことを他人事のようになおざりにしているおろか者がおる一方、他人のことを自分のように分け隔てせずに接するすぐれた人もいるということを、はっきり見きわめなさい。古人も言っている、「人生の3分の2は早くも過ぎてしまったが、ほんの少しの心もみがこうとしない。ただただ生をむさぼって1日Ⅰ日とあくせく日を暮らしているだけで、いくら喚びかけ反省させようとしても、一向に振り返りもしないのは、一体どうしたらよいものか」と。真実の指導者に会うことができなかったなら、俗世間的な心にひきずられてしまうということを知るべきである。金持ちの愚かな跡とり息子が、その家伝来の財物を運び出し、むなしく他人の眼前にゴミや糞尿のように捨ててしまうとは(典座という大事な職についていながら、それをむなしく見のがして無駄に時を過してしまうようなもので)、なんとなげかわしいことか。今やそうであってはならない。(117~118頁)
■◯霊台―心性・心のこと。中国禅宗5祖弘忍が後継者を決めるために、弟子達に対して悟境を提出させたところ、神秀は「身は是れ菩提樹、心は明鏡台の如し。時々に勤めて払拭(ほっしき)し、塵埃(じんあい)有らしむことなかれ」という偈(漢詩)で答え、これに対して慧能は「菩提本より樹無し、明鏡も亦台に非ず。本来無一物(いちもつ)、何れの処にか塵埃有らん」という偈を作って、これが認められ6祖となったという。神秀の偈は、万物を如実に写し出す鏡を心と見なし、これを磨き保持することを示したもので、ここで台は鏡そのもの。慧能はこれを揶揄的に批判し、後に禅の本流となった。(119頁)
■ここにいう大心(だいしん)とは、その心を大山(たいざん)のようにどっしりとさせ、大海のように広々とさせて、一方に片寄ったり固執(こしゅう)したりすることのない心である。たとえ1リョウ(金偏に兩)(約37,3g)ほどの軽いものでも、軽々しく扱わず、また逆に1鈞(いっきん、1リョウの480倍)もある重いものに対しても、特別に大げさに重々しく取り扱ったりしない。うららかな春の陽気に誘われても、それに心引かれてフラフラと春の野山にうかれ出るようなことなく、落ち葉散り布(し)く秋の景色を見ても、ことさらに物淋しい心を起さない。いうならば、春夏秋冬の四季の移り変わりも、これを自然のあるべき姿として、大きな眼で1つの景色の中に一緒にとらえ、また、軽い重いということについても、これに心迷わされることなく、差別をつけずに見るのである。このように、何物にも迷わされたり、心引かれたりしないという眼のつけ所において、大の字を書き、大の字を知り、大の字を学び、よくよく大の字を知り尽くすのである。夾山善会(かつさんぜんね)禅師の修行道場で典座をつとめていたある和尚が、もしこの大に字をよく学んでいなかったなら、思わず吹きだした一笑によって、太原孚上座(たいげんふじょうざ)を悟りにいたらしめることはできなかったであろう。潙山(いさん)霊祐禅師も、大の字をよく書いて知っていなかったら、百丈禅師のもとで修行していた折、一本の柴を取ってこれを3度吹き、百丈禅師に渡してその禅機を認められるというすばらしいはたらきはできなかったであろう。さらに、洞山守初(とうざんしゅしょ)禅師が大の字を知り尽くしていなかったら、「仏とはどういうものですか」という僧の質問に対し、「麻三斤」という見事な答えはできなかったであろう。(134~135頁)
■◯夾山(かっさん)の典座―太原孚上座(たいげんふじょうざ)を悟りに導いた僧。夾山は中国湖南省澧(れい)州石門県の東南にある霊泉禅院のことで、この典座の名前などはすべて不明であるが、太原孚上座が揚州光孝寺で『涅槃経』を講義していたところ、たまたまこの典座が雪のために行脚を阻まれて寄宿していた。孚上座が仏の法身(ほっしん、真実心)について談ずるや、典座は思わず失笑した。孚上座がこれに気づいてその訳をたずねると、「上座あなたは法身についてなにも分かってはいない」という。「それではどこが間違っているのか」と問うと、夾山(かっさん)の典座は、「上座あなたは法身の周囲だけを説いていて、肝心の法身そのものを自分に体現していない」という。そこで孚上座は虚心坦懐に典座の教えを受けて、ついに悟りを開いたという(『五灯会元』巻5、雪峯義存章)(137頁)
■○大潙(だいい)禅師……―百丈懐海とその弟子である潙山霊祐の問答で潙山が百丈の道場で修行していたころ、ある日、二人は山に入って仕事をしていた。そのとき、百丈が潙山に火を持ってこいと命じたところ、潙山は即座にハイッ持ってきましたという。百丈がどこにあるかと尋ねると、潙山は1本の枯れ枝を手に取って、フーフーフーと3度吹いて百丈に手渡した。これを見て百丈は、潙山が悟境に達したのを認めたという。(137頁)
赴粥飯法
■○法性(ほっしょう)―あらゆる存在がもっている真実にして不変なる本性。仏教の真理を指す語の1つで、真如・実相・涅槃などと異名同体である。(144頁)
■○真如―あらゆる存在がかくのごとくあること。その本体が真実にして常住なるところから真如という。(144頁)
■○法界(ほっかい)―意識の対象となるすべての存在。あらゆる現象界をいう。(144頁)
■◯理―宇宙をつらぬく根本的真理。あらゆる現象の背後にあって、そのようにあらしめている普遍的な絶対平等の真理。真如。(144頁)
■○事―一々の差別的な現象。因縁によって生じている森羅万象の相。理の対。(144頁)
■○正等覚(しょうとうがく)―仏の無常のさとりのこと。三藐三菩提(さんみゃくさんぼだい)の意訳語。(144~145頁)
■◯本末究竟等(ほんまつくきょうとう)―本末諸相の究極としての平等性。本は真如のうえからみた、あらゆるものが平等であるという立場、末は実相のうえからみた、あらゆものが異なって現われている姿、究竟は結局、とどのつまりの意。(145頁)
■○威儀(いいぎ)を具し―行・住・坐・臥(四威儀という)において、僧として正しい立居ふるまいをすること。道元の禅においては「威儀即仏法、作法是宗旨」といって、日常の正しい規律のある生活そのままが仏法であるとされる。(148頁)
■○安居(あんご)―一定期間、一寺にとどまって、ひたすら坐禅を中心とした修行にはげむこと。期間は4月15日から7月15日まで(夏安居)と、10月15日から翌年の1月15日まで(冬安居)の、それぞれ90日間がある。結制、結夏、江湖会(ごうこえ)などといい、この間、第1座として多くの修行僧を統率するのが首座である。安居の制は古くインドにおいて、雨期のあいだ外に遊行せず、一箇所に集まって坐禅修行したことに始まる。(153頁)
■○大乗菩薩僧―菩薩は菩提薩埵(ぼだいさった)の略で、上求菩提下化衆生(じょうぐぼだいげけしゅじょう)といって、無上菩薩(仏のさとり)を求めながら同時に人々を救おうと努力する修行者のこと。自己の解脱だけを目的とする声聞(仏の教えを聞いてさとる者の意)や縁覚(独覚ともいい、他の教えによらずに道をさとるが、説法教化(きょうげ)は行なわないとされる)の教えを小乗というのに対し、涅槃(さとり)に積極的な意義を認めて自利(自らを利する)と利他(他を利する)の両面をみたす菩薩の道を説く教えを大乗と呼ぶ。(176頁)
■○妙法蓮華経―略して『法華経』といい、また『大乗妙典』ともいう。『般若経』、『維摩経』、『華厳経』など大乗仏教を説く諸経典のなかでも、とくに代表的なものとして重んぜられた。全編を通じ、仏教の高い理想を揚げながら、それをむずかしい理論によらずに通俗的な因縁や譬喩(ひゆ)によって大衆にわからせようとしている点、また戯曲風な展開で興味深く読ませるようにしている点に、すぐれた特徴がある。(177~178頁)
■○文殊師利菩薩―文殊師利は略して文殊という。仏弟子のなかでとくに優れて、智慧第一といわれ、俗に「文殊の智慧」の言葉がある。普賢とともに釈迦如来像の脇士として知られ、仏の智・慧・証の徳を代表する。(178頁)
■○大乗普賢菩薩―この「大乗」のところは普通「大行(だいあん)」と唱えられている。普賢菩薩は、文殊菩薩とともに釈迦如来像の脇士として知られ、仏の理・定(じょう)・行の徳を代表する。文殊の智慧に対して普賢の行願といわれ、十種の大願をおこして仏の化導(けどう)をを助ける大乗の菩薩で、この普賢の行を大行と形容した。(178頁)
■○観世音菩薩―略して観音といわれ、大乗菩薩の中でも、智慧の文殊、願行の普賢とともに、慈悲の観音として最も名高い。『観音経』では33身に身を変えてあらゆる衆生を救済すると説かれる。観自在菩薩とも呼ばれる。(178頁)
■○摩訶般若波羅蜜―梵語の音写。偉大な完全なる智慧の意。迷いの此岸からさとりの彼岸に到るために修すべき6つの行(六波羅蜜。布施・持戒・忍辱(にんにく)・精進・禅定・智慧)のうち最も重要とされるもので、あらゆる事物や道理を見抜く深い智慧のこと。(178頁)
■○檀波羅蜜―波羅蜜は大乗の菩薩がさとりに到るために修める行のことで6つある(六波羅蜜)。すなわち、布施(完全なる施し)、持戒(戒律を完全に守ること)・忍辱(にんにく、完全なる忍耐)・精進(完全なる努力)・禅定(完全なる心の統一)・智慧(最高完全なる智慧)の6で、檀波羅蜜はこの最初の布施行のこと。(187頁)
■○貧等(とんとう)―貧(とん)と瞋(じん)と痴。貧は貧欲(とんよく)で、むさぼり執著すること、瞋(じん)は瞋恚(しんに)で、自分の心に違うものをいかり憎むこと、痴は愚痴で、ものの道理のわからぬ愚かさのこと。これらを、仏道修行の障害となることから、三毒という。心の迷いを防ぎ、身・口(く)の過(とが)を離れるには、一切の悪行の根本であるこの貧・瞋・痴をなくすのが最高の修行であるということ。ここにこの句があるのは、日ごろわれわれは美味しい物に対しては執着の心を起こし、まずい物に対しては嫌悪心を起こし、ほどほどの物に対してはもっと旨い物をと思うものであり、食事の場こそが貧・瞋・痴の三毒を離れる修行道場となりうるからである。(195頁)
■○成道(じょうどう)―仏道を成就する。さとりを得て仏になること。われわれの最大の目標である。(196頁)
■○威儀(いいぎ)―正しく法にかなった立居振る舞い。(233頁)
解説
■中国唐代における禅の興起は、インドで成立した仏教がもっとも中国的に変貌をとげる過程で行なわれた、きわめて土着性の強い思想運動そのものであった。
禅思想の大きな特徴は、天台宗や華厳宗、三論宗・浄土教などが、特定の経典や論書を拠り所とし成立したのと異なり、唐代中期に禅宗内で成立し広く宣伝された標語成句「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏(文字に絶対的な権威を措定せず、経論の教えとは別に自分の言葉で思想を語り、現在の自分のままで、自己の真実を明らかにする)」の語が示すように、自己自身が現在この場で、直接ブッダの悟りを追体験する(頓悟)ことにあった。(235頁)
■ 瓦官(がかん)、徳山にありて侍者となる。1日山に入りて木を斫(き)る。徳山、1椀の水を将(も)って官に与う。接得(うけとり)てすなわち喫却(のみほ)す。徳山云く、「会(え)すや(分かったか)」。官云く、「会(え)せず(分かりません)」。徳山、また1椀の水を将(も)って官に与う。また接して喫却(のみほ)す。徳山いわく、「会(え)すや」。官云く、「会(え)せず」。徳山云く、「何ぞ会せざるものを成持(じょうじ)取(しゅ)せざる」。官云く、「会せざるに、またこの什麽(なに)をか成持す」。徳山云く、「子(なんじ)は太(はなは)だこの鉄橛(てっけつ、優れ者)に似たり」。(『雪峰語録』巻上)
木を伐採する仕事をしている瓦官和尚に、徳山は1椀の水を与えて労をねぎらいながら、この伐採という仕事が自己の問題として受け止められているかどうか探りをいれるのである。「成持」という語は、事を計る、しっかりと守り育てることを意味するが、ここでは「分からない」ということが自己自身の問題とされつづけているかが問われている。
この会話の妙味は、二人の禅僧の間に交わされる丁々発止の禅機溢れる問答にあり、徳山は瓦官の受け止め方を最終的に認めることになるが、問答の発端そのものは、禅僧の作務にかかわる事態に対する根源的な問いかけであった。
道元も、中国留学の早々からこの禅と作務に関する大きな課題を、阿育王山広利寺で修行僧の食事の世話をしている老典座から突きつけられ、この問題を最晩年に至るまで抱きつづけ、また「道元禅」と呼ばれる独自の思想体系のなかに昇華させた、その背景には、以上のような中国禅宗の成立過程における思想的営みの大きな蓄積があったのである。(241~242頁)
■梁の武帝が問う―「私は帝位に就いて以来、多くの寺を造り経典を書写し、僧に供養してきましたが、どんな功徳があるのでしょうか」
達磨が答える―「功徳などなにもない」(中略)
武帝―「仏教の根本義(聖諦(しょうたい)第一義)とはどんなことですか」
達磨―「カラリと晴れわたった大空のようで、真理とか聖とかいったものはなにもない(廓然無聖)」
武帝―「そういうあなたは誰ですか」
達磨―「そんなことわしは知らん」
武帝は達磨の心を汲み取ることができなかった。
かくして達磨は、そのまま揚子江をわたって魏の国の嵩山(すうざん、河南省)に入ってしまったというのである。後に宝誌和尚という者が武帝に、「あの方は観音菩薩の化身で、ブッダの真の精神を伝えるためにこの国に来たのですが、あなたが後悔して、再びこの国へ迎えようとしても、もう決して帰ってはきませんぞ」と告げたという。(245頁)
■禅宗が、思想としてもまた教団ととしてもその存在が明確に人びとに認識されるようになるのは、二祖慧可・三祖僧璨(そうさん)・四祖道信・五祖弘忍とへて、弘忍のもとに神秀と慧能の二人の弟子が出て以後で、神秀は都長安に進出し、権力者則天武后の帰依を受けて世の注目を集め、その系統の禅僧も都の長安や河南省の嵩山を中心に栄え、後世北宗禅と呼ばれ、日本へは最澄によって伝えられその存在が知らされていた。
一方、これに対し慧能は、南方の曹渓(そうけい、広東省)の山中で密かに修道し、その弟子の神会(じんね、684-758)の活躍によって都にもその存在が知られるようになった。この系統は南宗禅と称されたが、同じく慧能の弟子の南嶽懐譲(なんがくえじょう、677-744)や青原行思(せいげんぎょうし、?-740)の系統の禅僧達は、おもに揚子江付近の江西・湖南・湖北などの温暖な地を拠点として修道生活をつづけ、独自の生活規範や聖典を成立させていた。
すなわち、南嶽の弟子である馬祖道一(709-788)と、青原の弟子である石頭希遷(せきとうきせん、700-790)の二師は、その思想や門人指導のあり方が、当時の人からそれぞれ、馬祖は「雑貨舗(あらゆる人びとに対応し鋭く相手の急所を突き導く修行道場)」と評されたことが伝えられている。こうした特徴ある主張や禅風は、門人や法孫達によって中国全域はもとより、朝鮮新羅にも伝えられ、平安期の日本にも伝えられた形跡がある。
さらに唐代末期から五代・宋初期にかけて禅宗は、南嶽・馬祖の系統は潙仰(いぎょう)宗・臨済宗の2系統に、青原・石頭のの系統は曹洞(そうとう)宗・雲門宗・法眼(ほうげん)宗の3系統に分かれ、臨済宗の系統はさらに黄竜慧南(おうりゅうえなん、1002-69)の系統の黄竜派と、楊岐方会(ようぎほうえ、992-1049)の系統の楊岐派の2派となり、全部で5宗7派に分かれたが、これを総称して「五家七宗」と言う。
これら禅宗の諸宗派は、それぞれ特色ある弟子の指導の仕方や思想表現、さらに坐禅観を展開させたが、臨済宗の宗風は、先人の残された語録・言行や代表的な逸話(公案)について、坐禅をしながらその真意を観察究明し、究極的意味を深く理解することを目指すという「看話(かんな)禅」を特徴とし、これに対し曹洞宗の宗風は、黙々と坐禅して自己の心奥に撤することを目指す「黙照禅」が特徴とされ、宋代禅宗の二大潮流となった。
鎌倉時代以降、栄西や道元・円爾(えんに)をはじめとする諸師によって本格的にわが国に伝えられたのが、この宋代の臨済宗・曹洞宗であり、これによって中世日本禅宗の隆盛期を迎えることになった。近世江戸期になって、隠元隆琦(いんげんりゅうき、1592-1673)によって伝えられた黄檗(おうばく)宗も臨済宗の系統であり、頭皐心越(とうこうしんえつ、1639-96)によって伝えられた寿昌(じゅしょう)派は、道元の系統とは異なるが、やはり曹洞宗の系統に属する。(246~249頁)
(2014年3月15日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵の世界』 田中忠雄著作集⑴ 浪曼
■世には、玄妙2つながら忘じきたり、慮知念覚ををなげうちきたるところに、いみじき霊力の発現を期するものがある。かような学風に対して、道元は「仏祖の挙拈(ねん)する妙は知見解会なり」と喝破した。知見解会は仏家のの調度である。これをいとい棄てんとすれば、これに取り縋る知見解会の徒と同じく、仏の御いのちを損うのである。いわゆる論理は、かくのごとき慮知念覚の知であり、知見解会である。それは即(つ)くべからず、離るべからざるものである。即すれば忽(たちま)ち経師・論師となり、離るれば忽ち棒喝の徒となる。さればと言って、殊更に不即不離すれば、驢前馬後の低迷漢となる。進歩や錯、退歩や錯。この故に、学道は必ず故実に則って、不惜身命・但惜身命底を行ずるのみである。ここから不覚不知底の覚知、不思量底の思量、山の廻途参学は現成する。『眼蔵』の論理は、まさしくかくのごとき覚知と思量と参学とをめぐらして条理を尽すものである。いわく――
「禿子(とくし)がいう無理会話、なんぢのみ無理会なり。仏祖はしかあらず。なんぢに理会せられざればとて、仏祖の理会路(りえろ)を参学せざるべからず。たとひ畢竟じて無理会なるべくば、なんぢがいまいふ理会もあたるべからず」(196頁)
■南泉が30年にわたって研ぎすました鎌をさしつけて、道の骨髄を説く大事のときに、僧はなおも道は道はと問いつづける。「現成公案」の巻にいわゆる「人はじめて法をもとむるとき、はるかに法の辺際を離卻(りきゃく)せり」とはこの有様であろうか。これが畢竟して無理会話ならば、汝が理会と思えるものは、そもそもいかなるものであるか。『那一宝』には「嗟(ああ)夫れ無理会擬議不得なるを以て禅語とせば、彼の輿台(かごかき)馬方の輩隠語ありて顧直(あたひ)の数を呼ぶ、古路里才難番堂の如き是れも亦無理会なり」とある。世の論師達のいわゆる直覚や無分別の分別などは、ほとんど例外なく、この馬方の隠語のように不可解な神秘である。知れば何ものでもない20文、30文であるが、さてその20文、30文は何ぞというに、一向に理会するところがない。隠語を20文と解いて理会せりと思うているが、その理会もあたるべからずで、この20文は、古来の脳漿をしぼって、なおかついまだに理会せざるほどの大問題である。これを理会せんとならば、汝のほしいままに立てし無理会の断見を捨てて正師に逢い、仏祖の理会路を学すべきである。――かくして、理会を道(い)うに学道の故実を以てする道元の宗風は、明らかになった。
「しかのごときのたぐい、宋朝の諸方におほし。まのあたり見聞せしところなり。あはれんべし、かれら念慮の語句なることをしらず、語句の念慮を透脱することをしらず。在宋のとき、かれらをわらふに、かれら所陳なし、無語なりしのみなり。かれらがいまの無理会の邪計(じゃけ)なるのみなり。たれかなんぢにをしふる。天真の師範なしといへども、自然(じねん)の外道児なり」
道元在宋の頃には、かような不立文字の学風が一世を風靡していた。大宋国に人なきを歎じて帰朝を決意したのも、これによるのであろう。(197頁)
■道元が天童如浄に親しく道を問うた記録『宝慶記(ほうきょうき)』にこの問題が出ている。無理会の学風は一方において断見外道であり、同時に自然の外道見すなわち天然外道である。断見外道と天然外道とは、その来所は畢竟1つであって、ともに学道の故実を紊(みだ)るものである。そういうことを如浄が諄々と説き、その要点を道元が書きとめておいたのである。
「道元拝問す、今諸方古今の長老等の云く、聞て聞かず見て見ず、直下(じきげ)一点の計較(けこう)無き、乃ち仏祖の道なりと。是を以て堅挙堅払、放喝行棒、学者をして一も卜度(ぼくたく)すること無からしめ、遂に則ち仏化の始終を問はしめ、二生の感果を期すること無からしむ。これ等是の如き等の類、仏祖の道たるべしや。和尚示して云く、若し二生無くば、実に是れ断見外道なり。仏仏祖祖、人の為めに教え設くるに、都(すべ)て外道の言説なし。若し二生無くば、乃ち今生あるべからず。此の世既に存す、何ぞ二生無からん。我が儻久しく是れ仏子なり、何ぞ外道に等しからん。又学人をして直下第二点無からしむが如きは、仏祖一方の善功方便なり、学人の為めに而も所得無きには非ず。若し所得無しと為さば、善知識に参問すべからず、諸仏も出世せざるなり。唯直下見聞して便ち了全ことを要す。更に信及無く、更に修証無くば、北州豈に仏果を得ざらんや、北州豈に見聞覚知無からんや」
この慈誨によって、道元の平素の信念はいよいよ決定(けつじょう)したのであろう。「学人の為めに所得無し」とは、明らかに無理会のことである。この見解を許せば、今生だけの断見となり、やがて一切の道徳を撥無(はつむ)する断見外道に堕ちるのみでなく、正師に参聞して修証するの要をも撥無(はつむ)する天然外道となる。北州は須弥山を囲繞する島の1つ、ここは仏の教化も及ばぬ処というが、もし正師のもとに修証することなくして仏化を得ると言わば、北州にも仏化普ねしと言わぬばならぬ。北州にも慮知念覚はあり、見聞覚知はあるから、聞いて聞かず見て見ず直下に一点の計較無きこともありうる。かような断見と自然見の所有者は、すみやかに祖道の故実を去って、北州国に帰化するがよかろう。(198~199頁)
■「山水経」の経たるゆえんは、無情説法の義にあり、「谿声便ち是れ広長舌……夜来8万4千の偈」のこころであった。山水の広長舌は直ちに経典であった。しかも、このことは、人々を誘うて典籍を離却せしめることではない。「山水経」の経が、いささかでもこの思いを誘発するならば、すでに天然外道の兆しそめた証拠である。典籍を離れることは、正師なく修証なきことと全く同じように、学道の故実を紊る天然外道である。山水を学んで道を得るのは、典籍を世界に味到するのである。「仏教」の巻に「桃華をみて悟道し竹響をききて悟道する。および見明星悟道、みなこれ経巻の知識を生長(しょうちょう)せしむるなり」とあるのは、蓋(けだ)しこの意味である。典籍に即(つ)いて徒らに文字を教える経師・論師には「而今の山水」を挙似せねばならぬ。しかも、典籍を離れてみだりに挙頭を立て払子(ほっす)あげる不立文字の徒には、或従経巻の道を示さねばならぬ。典籍に対して不即不離なる低迷漢には、山水のまさしく経巻なるゆえんを説かねばならぬ。これが道元の「山水経」である。
みだりに拳頭を立てる粗暴の学人は、典籍の外にいみじき特地を求める。そして、かような学人の腹底にも、かの無理会の見解が巣つくっているのである。故に、典籍無用の論者を斥破する「仏経」の巻の言葉を揚げて、「山水経」の参学に対する用心とする。
「しかあるに、大宋国の一二百余年の前後にあらゆる杜撰の臭皮岱(臭き革袋、人間の意ー著者)いはく、祖師の言句、なほこころにおくべからず。いはんや経教は、ながくみるべからず、もちいるべからず。ただ身心をして枯木・死灰のごとくなるべし……。かくのごとくのともがら、いたづらに外道天魔の流類(るるい)となれり。もちいるべからざるをもとめてもちいる、これによりて、仏祖の法むなしく狂癲の法となれり。あはれむべし、かなしむべし。……仏経を仏法にあらずといふは、仏祖の経をもちいし時節をうかがはず、仏祖の従経出の時節を参学せず、仏祖と仏教との親疎の量をしらざるなり。かくのごとくの杜撰のやから、稲麻竹葦(とうまちくい)のごとし。獅子の座にのぼり、人天の師として、天下に叢林をなせり」
無理会の学人は、典籍及び祖師の言句を去って、山水を師とするものである。もしかくのごとくならば、、儒教や道教との別も失われ、仏祖道は他教に習合して、ついに断絶するに至るであろう。道元は仏・儒・道三教一致の説を最も激しく斥けた。(200~201頁)
■「また水の紅海をなしつるところなれば、世界あるべからず、仏土あるべからずと学すべからず。一滴のなかにも無量の仏国土現成なり」
水を世界の一隅に擬するとき、その世界とはあらかじめ横たわれるものである。このとき、水の紅海をなすのは、既成の世界に既成の紅海一枚を添加するのみである。ともに、わが生命とはかかわりなき点景に過ぎぬ。水に世界あるべからず、仏土あるべからずという思いは、ここから生ずるのである。世界なく国土なき水は、わが生命とはなんらの繋りもない。そういう水の集積たる紅海は、いくら如実にえがいても歌うても、まことの作品とはならぬし、かような辺際にある一切の芸術的な努力は、われとわが生命を刻々に消磨するだけである。道元の道は、一茎の草にも一掬の水にも、世界すなわち仏国土の現成を学するにある。「一滴のなかにも無量の仏国土現成なり」というのは、人をしておのずからその生命の根源に立ち還らしめる言葉である。「坐禅儀」の巻に「容身の地を護持すべし」とあるのは、坐禅の作法であるが、その作法は、尺寸の地にも世界すなわち仏国土ありというところから来ている。
一滴のなかにも無量の世界は現成する。再び「現成公案」の一節を想起すれば、「水に月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる」。しかしながら、そのおのおのにやどる月は、相互に罣礙せず、また天月と弥天と罣礙することもない。天月も弥天もその全身を惜しみなく露滴にやどすけれども、それによって天月弥天ともに濡れることなく、露滴もまた破れることがない。これが露滴に世界の現成する風光である。
「しかあれば、仏土のなかにみずあるにあらず、水裏に仏土あるにあらず。水の所在、すでに三際にかゝはれず、法界にかゝはれず。しかもかくのごとくなりといへども、水現成の公按なり。仏祖のいたるところには、水かならずいたる。水のいたるところ、仏祖かならず現成するなり。これによりて、仏祖かならず水を拈じて身心とし、思量とせり。しかあればすなはち、水はかみにのぼらずといふは、内外(ないげ)の天籍(てんじゃく)にあらず。水之道(すいしどう)は、上下縦横に通達するなり」(233~234頁)
正法眼蔵山水経
■雲門匡真大師いはく、東山水上行。
この道原成の宗旨は、諸山は東山なり、一切の東山は水上行なり。このゆへに、九山迷廬(くせんめいろ)等現成せり、修証せり。これを東山といふ
しかあれども、雲門いかでか東山の皮肉骨髄・修証活計に透脱ならむ。いま現在大宋国に杜撰のやから一類あり、いまは群をなせり。小実の撃不能(ぎゃくふのう)なるところなり。かれらいはく、いまの東山水上行話、および南泉の鎌子話(けんすわ)ごときは、無理会話(むりえわ)なり。その意旨は、もろもろの念慮にかゝはれる語話は仏祖の禅話にあらず、無理会話(むりえわ)これ仏祖の語話なり。かるがゆへに、黄檗の行棒および臨済の挙喝、これら理会およびがたく、念慮にかゝはれず、これを朕兆未萌以前の大悟とするなり。先徳の方便、おほく葛藤断句をもちいるといふは、無理会(むりえ)なり。
かくのごとくいふやから、かつていまだ正師をみず、参学眼なし。いふにたらざる小ガイ(豈に犬)子(しょうがいす)なり。宋土ちかく二三百年よりこのかた、かくのごとくの魔子・六群・禿子おほし。あはれんべし、仏祖の大道の廃するなり。これらが所解、なほ小乗声聞におよばず、外道よりもおろかなり。俗にあらず僧にあらず、人にあらず天にあらず、学仏道の畜生よりもあろかなり。禿子がいふ無理会(むりえ)、なんぢのみ無理会なり、仏祖はしかあらず。なんぢに理会せられざればとて、仏祖の理会路を参学せざるべからず。たとひ畢竟じて無理会なるべくば、なんぢがいまいふ理会もあたるべからず。しかのごときのたぐひ、宋朝の諸方におほし。まのあたり見聞せしところなり。あはれんべし、かれら念慮の語句なることをしらず、語句の念慮を透脱することをしらず。在宋のとき、かれらをわらふに、かれら所陳なし、無語なりしのみなり。かれらがいまの無理会(むりえ)の邪計(じゃけ)なるのみなり。たれかなんぢにおしふる。天真の師範無しといへども、自然(じねん)の外道なり。(268~269頁)
■下地為江河(げちいこうが)。しるべし、水の下地するとき、江河をなすなり。江河の精、よく賢人となる。いま凡愚庸流(ようる)のおもはくは、水はかならず江河海川にあるとおもへり。しかにはあらず、水のなかに江海をなせり。しかあれば、紅海ならぬところにも水はあり。水の下地するとき、江海の功をなすのみなり。また水の江海をなしつるところなれば、世界あるべからず、仏土あるべからずと学すべからず。一滴のなかにも無量の仏国土現成なり。しかあれば、仏土のなかに水あるにあらず、水裏に仏土あるにあらず。水の所在、すでに三際にかゝはれず。法界にかゝはれず。しかもかくのごとくなりといへども、水現成(すいげんじょう)の公按なり。仏祖のいたるところには、水かならずいたる。水のいたるところ、仏祖かならず現成するなり。これによりて、仏祖かならず水を拈じて身心とし、思量とせり。しかあればすなはち、水はかみにのぼらずといふは、内外(ないげ)の典籍(てんじゃく)にあらず。水之道(すいしどう)は、上下縦横に通達するなり。(271頁)
(2014年3月30日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元』 坐禅ひとすじの沙門 今枝愛眞 NHKブックス
■道元は、「人はいかに生きるべきか。それをさとるためには、じぶんとはいかなるものなのか」、まずこの本来の自分というものを本当に知らなければならないと考えた。それは、どうしても見究めておかなければならない最初の大きな関門である。道元の将来を決定する重要なわかれ道でもあった。ここで、はたと行きづまったのは、天台宗の基本的なものの考え方である。それは「本来本(ほん)法性、天然自性身(じしょうしん)」という言葉についてであった。
もともと一切の人間は、誰でも仏性、つまり仏の本性をそなえ持っている。このような意味は、本覚思想ともいわれ、天台宗の最も根本的な考え方なのである。この考え方に対し、道元の心にいろいろな疑問が湧いてきた。たとえば、もしそのように、人そのものにすでに仏性がそなわっているならば、なぜわれわれは苦しい修行を実践しなければならないのであろうか。また、すでに諸仏や祖師が菩提心(悟りを求めて仏道を行じようという心)を起して修行を続ける必要があると説いたのは、どういう訳か。それにはそれだけの理由がなければならないが、果してそれは何なのか。道元は、こうした学問と修行に関する根本的な疑問を懐くにいたったのである。(30頁)
■建保2(1214)年、道元は山を下り、独自の新しい道を発見するため、園城寺長吏の公胤(こういん)僧正を訪ねた。それは、公胤も道元と同じ村上源氏の出身で、久我家や松殿家と親しいという間柄だけでなく、公胤は園城寺の座主を再度つとめた高名な学僧であり、大原問答で法然とも交流があるなど、当時の宗教界に強い影響をもつ進歩的な人物であったからではないかと思われる。
さっそく疑問を打ち明けてその教えを請うたのだが、公胤は道元の疑問には何も答えず、ただ、
「現在の中国では、達磨大師以来の祖師たちが、内面的な体験を通して伝えてきた禅宗が盛んである。あなたが求めている宗教には、それが最も適しているように思われる。大陸に渡って、その新しい宗教学んでくるのが一番よい」
と、ひたすら入宋(にっそう)を勧めるのであった。(31頁)
■こうして、公胤との出会いは、道元の一生に大きな影響を及ぼすにいたった。それは同時に、次の栄西との相見(しょうけん)にもつながっていたのである。おそらく公胤に会っていなかったならば、道元は別の道をたどったかも知れない。まことに、人と人との出会いというものは、その人の運命を左右するものである。(32頁)
■その頃のことである。さきの老典座(てんぞ)が再び道元を訪ねてやって来た。そしていうのには、
「わたしは最近、阿育王山の典座職をしりぞいて、これから故郷の西蜀に帰るところです。たまたま仲間のものから、あなたが天童山にいられると聞いたので、ぜひお目にかかりたいと思って、こうしてやって来ました」
異郷で、こういって励ましてくれた老典座の温情に、若き日の道元はどれほど感激したことであろう。以前にもまして、厳しい修行への決意を新たにしたにちがいない。
信頼と喜びで夢中になって話しているうちに、まえに船中でかわした学問や修行の問題になった。
ときにこの老僧は、
「文字を学ぶものや修行をするものは、それが何であるかをよくのみこむ必要がある」
といった。そこで道元が、
「それでは、文字とはどういうものなのですか」
と聞きかえすと、
「一、二、三、四、五、これが文字というもので、特別のものがあるわけではない」
と答えたという。そこで道元は、
「それでは修行とはどういうことですか」
と尋ねた。老僧は即座に、
「全世界すべての現象が、そのまま真理そのものであって、みな学問・修行の対象でないものはない」
と答えた。人類万物に共通な絶対の真理を見究めるのが禅の悟りであると教えられたのである。
このほかにも、道元にはいろいろ問答をかわしたが、それらを通じて、この老僧から大陸禅の手ほどきをうけた。のちになって、道元が自ら述懐し、「いささか文字を知り辨道を了ずる(真理の探究ができたこと)は、すなわち彼の典座の大恩なり」と『典座教訓』のなかで讃え、「いよいよ知る、彼の典座はこれ真の道人なることを」と、つねに老典座を追慕してやまなかったことによっても、この老僧から如何に多くを学んだかがわかるであろう。
老典座との出会いによって、道元は修行とは何であるかを知り、禅こそ自分がこれまで求めていた理想の宗教であることを、改めて確認し、いよいよ本格的な大陸禅の修行に取り組んでいったのである。(41~42頁)
■道元が天童山で修行していた夏のある日のことである。ちょうど昼食が終って廊下を歩いていく途中、仏殿のまえで用(ゆう)という典座が、これまた椎茸の話であるが、それを乾かしていた。手には竹の杖をもっているが、頭には笠もかぶっていない。太陽はさんさんと照りつけ、敷瓦は焼けつくように暑い。典座は、したたる汗もかまわず、精を出して椎茸を乾かしている。いかにも苦しそうである。その背骨は弓のように曲がり、長い眉毛は鶴のように真白い。聞けば、すでに68歳にもなるという。道元は、「そんな仕事は若い修行者にやらせればよいのに、どうしてそれをなさらないのですか」と尋ねた。すると典座は、「他はこれ吾れにあらず」――他人にやってもらったのでは、自分がしたことにはならないからですと答えた。そこで、道元はさらに、「あなたのやっている作業は、確かに法にかなっていて、実に見上げたものだと思います。けれども、こんな炎天下で、どうしてそんなに苦しんでやる必要があるのですか」と尋ねた。すると典座は、即座に、
「さらにいずれに時をか待たん」
と答えた。いまやらなければ結局やらないことになってしまう、いまやらなければ一体何時やるときがあるというのかという。この用典座の修行に対する厳しい態度を知って、道元は深く頭が下がる思いがし、ただもう沈黙のほかはなかった。道元は廊下を歩きながら、典座という役目も禅修行の大切なかなめであることを、しみじみと、ここで又悟るのであった。(44~45頁)
■また毎朝道元の隣りの席で、一人の修行僧が一日の修行を始める前に、必ず袈裟を頭の上におし戴いて、次のように高らかに唱えてから、身にまとった。
「大なるかな解脱服、無相の服田衣(え)、如来の教へを披奉(ひぶ)して、広くもろもろの衆生を度せん」(「袈裟功徳」巻)
この袈裟は、人間のあらゆる執着や煩悩をすべて取り除き、世の中に幸福をもたらすことができる法衣である。これを肩にかけ、釈尊の教えを正しく受け継ぐことによって、それを世間にひろくおしひろめ、いきとし生けるものを迷いから救済しよう。
このような教えが経典にみえたいることは、まえまえから道元も知ってはいた。しかし、その作法などについては、これまで一度も見たことも教えられたこともなかった。
「あはれむべし。郷土(日本)にありしとき、をしふる師匠なし。すすむる善友あらず。いくばくか、いたずらにすぐる光陰を、をしまざる。かなしまざらめやは。いまの見聞するところ、宿善(前世の善業)よろこぶべし。もしいたづらに郷間(日本)にあらば、いかでか、まさしく仏衣を相承着用せる僧宝(修行者)に隣肩することをえむ。非喜ひとかたならず。感涙千万行」(「袈裟功徳」巻)
道元は入宋したおかげで、いまこうして敬虔にして厳粛な作法を直接眼のあたりに見ることができ、深い感動をおぼえ、感涙にむせんだという。
「いかにしてか、われ不肖なりといふとも、仏法の嫡嗣(ちゃくし、正しい継承者)となり、正法(ぼう)を正伝して、郷土の衆生をあはれむに、仏祖正伝の衣(え)法を見聞せしめむ」(「袈裟功徳」巻)
■こうして、道元は禅修行の艱難に堪えていくうちに、釈尊の正法とはどういうものか。その核心はいったいどこにあり、どのようにして正法は伝えられてきたか。さらにまた、悟りの実体に迫るにはどうすればよいのかという、求道における真の在り方が、少しづつわかりかけてきたのだった。そして彼は、その根源をいよいよ深く探るためには、悟りを開いた証(あかし)として、師から直接弟子に授けられる嗣書(ししょ、伝法を記した相承図。血脈・宗派図ともいわれる)について、まず禅宗各派の実態を調べてみる必要があると考えた。
けれども、嗣書は禅の奥儀を示すものである上に、各派の秘事に属する大切なものであるから、容易に他見を許されないのが常である。まして24歳の若さの、しかも、外国の一修行者では、なおさらのことである。しかし、そこには道元のなみなみならぬ精進があったことはいうまでもない。道元は次々にその真剣な修行態度が認められ、禅宗各派の嗣書を直接手にとって観るという、極めて貴重な体験に恵まれた。(49頁)
■たとえ各宗派によって嗣書の形式がそれぞれ違っていても、ただ雲門宗の場合はこうだ、というように理解すべきである。なぜ釈尊が他の人にくらべて特に尊いのかといえば、それは釈尊の人物というより、釈尊が開いた悟りが尊いからなのである。それと同じように、雲門宗を開いた文偃(ぶんえん、864-949)が尊いというのも、雲門文偃の悟りが尊いからなのである。
各宗派によって嗣書の様式に相違があっても、それはそれとして認めればよい。大切なことは、悟りそのものであって、嗣書の様式ではない。こうきっぱり断言した宗月の自信にみちた言葉は、道元の心に強く響くものがあった。(50頁)
■道元は、「真の正師に指導を受けるかどうかによって、修行者が本当に悟りを開くことができるか、その悟りが偽りになってしまうかに別れる。だから、真の正師を見付けることができなければ、なにも学ばないのと同じことになってしまう。真の正師に会うことができるかどうかに、悟りの成否がかかっている」と考えていたのである。正師に会えないことに、道元はいらだちを覚えた。そして自分が本当の正師と仰ぐような理想的な禅人は、今の中国にはもういないのではないか。これ以上大陸に留まっていても所詮無駄ではないか。もしそうならば、日本に早く帰った方がよいのではなかろうか、と大陸禅に失望を感ずるようになっていた。(69頁)
■道元はこの尊い体験を「面授」の巻で次のようにのべている。
「大宋宝慶(ほうきょう)元年乙酉5月1日、道元はじめて先師天童古仏(如淨)を(天童山)妙高台に焼香礼拝す。先師古仏、はじめて道元をみる。そのとき、道元に指授面接するにいはく、仏々祖々面授の法門、現成せり(完璧な形で実現した)」(「面授」巻)
道元はさらに続けて、「このように如浄と自分との間で完璧に行なわれた面授こそ、釈尊が霊鷲山(りょうじゅせん)で説法のあと花をひねって聴衆をみたところ、摩訶迦葉一人だけがその意味を悟って微笑したという、有名な拈華微(み)笑の故事や、嵩山(すうざん)の少林寺で達磨と二祖恵可との間でとりかわされた悟りの証明の仕方、あるいは、黄梅山で五祖から六祖慧能に法衣が伝えられたときの法式、さらに雲岩曇晟(どんじょう)から洞山良价への伝法など、禅宗の伝統のなかでも特に典型的なものとされている法の伝授の仕方と全く同等の価値がある。まさしくこれは釈尊の伝法の理想的な形で、他の人は夢にも見たことがない唯一のものである」と力説している。いかに道元がこの面授の体験に強い確信をもつに至ったかがわかるであろう。
こうして如淨との対面は、道元に決定的な影響を与えた。もはや道元入宋の大目的は、ほぼ達成されたといってよかった。あとはただ、如淨から直伝された釈尊の大法を、日本に持ち帰るだけである。道元は感動し、それまでの驕慢な心はたちどころに失せ、正法を日本に伝来するためには、正師と仰ぐ如淨のもとで一層厳しい修行を積みかさね、さらに悟りを深め、真に禅の大事を学び終らなくてはならないと考えた。
そのころの心境を、道元は次のように述べている。
「いま現在、大宋国一百八十州の内外に、山寺あり。人里の寺あり。そのかず稱計すべからず。そのなかに雲水(修行者)おほし。しかあれども、先師古仏(如淨)をみざるはおほく、みたるはすくなからん。いはんや、ことばを見聞するは少分なるべし。いはんや相見(しょうけん)問訊(もんじん)のともがらおほからんや。いはんや堂奥をゆるさるゝ、いくばくにあらず。いかにいはんや先師の皮肉骨髄、眼晴面目(全人格)を礼拝することを聴許せられんや。先師古仏、たやすく僧家の討掛塔(とうかた)(そのもとに長くとどまって修行すること)をゆるさず。(中略)このくにの人なりといへども、掛塔(かた)をゆるさるゝのみにあらず、ほしきまゝに堂奥に出入して、尊儀(如淨を指す)を礼拝し、法道をきく。愚案なりといへども、むなしかるべからざる結(けち)良縁なり」(「梅花」巻)(58~59頁)
■ところが、如浄のもとに参じて間もない宝慶元年(1225)5月、師とも先輩とも仰ぐ明全が、天童山の了然寮で亡くなった。42歳であった。
はじめ師の栄西の意志をついで日本の天台宗を復興しようと考えていた明全は、その2年ほどまえに明州の天台宗景福寺を訪ねたのだった。しかし、大陸の天台宗の衰微は予想をはるかに上廻っていて、殆んど学ぶべきものがなかった。それに引き換え、江南の地一帯は、禅宗一色に塗りかえられていた。そこで明全は、改めて大陸禅を本格的に学ぶため天童山に移り住んで、この2年余り修行につとめていたのである。歳月あたかも流星のごとく、道元がはじめて建仁寺で師事してから、すでに9年の歳月が流れていた。明全は、後輩の道元が苦難を越え、いまや最高の正師にめぐり逢ったのを見て、やがて訪れるであろう日本仏教の輝かしい将来の布石を夢みながら、不運にもその実現をみないうちに、この世を去ったのである。ともに万波を乗り越えて入宋しながら、雄図むなしく異境に果てた明全の姿をみて、道元は胸中、いよいよ生死との対決を深めたにちがいない。(60頁)
■いよいよ機は熟した。翌3(1227)年、道元が昼夜をわかたず坐禅修行に熱中していた時のことである。ある朝、僧堂で坐禅中、一人の修行僧が疲労のため眠ってしまった。これをみた如浄は、一切の煩悩や執着を捨て、全身全霊を打ち込んで坐禅に専念しなければならないのに、眠ってしまうとは何事か、と大喝一声した。夢中で坐禅していた道元は、その天雷のような大音声(じょう)を聞いて、はっと吾にかえり、悟りを開くことができた。さっそく方丈に赴き、香を焼(た)いて如淨に礼拝した。その様子が只事でないのを見てとった如浄は、いったい何事があったのかと尋ねた。
このとき道元は、「肉体も精神も、一切のあらゆる煩悩や執着からのがれて、自在の境地になることができたのです。これこそ本当の悟りの境地だと確信いたします」と答えた。
これを聞いた如浄は、「そのように肉体も精神も一切のとらわれをのがれ、自由の境地になりきってこそ悟りというものである」と、道元が大悟徹底したことを、ついに認めたのである。(63~64頁)
■釈尊は6年間も坐禅し、達磨は壁に向って9年も坐禅をして仏の心を伝えた。昔の聖人たちも、このように坐禅をして修行を積んだのであるから、文字にとらわれた学問ばかりをしていないで、真実の自己を発見するために、いまの人はもっと坐禅の修行にはげむべきである。そうすれば、自然に一切のとらわれをのがれて悟りの境地を開き、真実のすがたを見究めることができるはずである。そうなるためには、まず何をおいても坐禅につとめるべきである。(『普勧坐禅儀』現代語訳)(72頁)
■坐禅には静かな部屋がよい。食事も節度が必要である。これまでの行きがかりを捨て、すべての仕事もやめ、是非善悪について一切考えてはいけない。心の働きが動くのを止め、ものを考えたり想像したりすることもやめる。もちろん仏になろうなどと考えてはいけない。まず坐禅をする場所に敷物をしき、そのうえに蒲団を置いて坐る。そして結跏趺坐、あるいは半跏趺坐する。結跏趺坐というのは、第1に右の足を左の股のうえにのせ、左の足を右の股のうえにのせる。半跏趺坐は、左の足で右の股を押すように重ねるだけである。着物や帯はゆるくしめ、きちんと整えるようにしなければならない。
つぎに、右の手を左の足のうえにのせ、左の手のひらを仰向けて、右の手のひらのうえにのせる。両手の親指はたがいに支え合うようにする。そこで姿勢を正して静かに坐り、左に片寄ったり右に傾いたり、前にかがんだり、後にそっくり返ったりしないようにする。横からみて耳と肩と真直ぐに、前からみて鼻とへそが真直ぐになるようにしなければならない。舌は上あごにつけ、唇と歯は上下ぴったりと合わせ、目はつねに開いている。身体の姿勢を正しく、呼吸もよく整えて、雑念を忘れて坐禅に打ち込むようにする。これが坐禅の要点である。(72~73頁)
■諸仏如来が代々正しく伝えてきた仏法の正門は、坐禅である。ひたすら坐禅に打ち込むことこそ、正しい仏法に入るための正門であり、最上で並ぶもののない妙術である。しかも、この法は元来誰でも備え持っているものであるから、その気になって真剣に修行をつみさえすれば、必ずその成果の証(しるし)が実際に現われてくるものである。その気になって修行しなければ、何時までたっても現われては来ない。(『弁道話』現代語訳)
このように道元は、もっぱら坐禅に打ち込むことこそ釈尊正伝の「真実(まこと)の仏法」を学びとるための正門で、唯一最高の道である、と力説した。
これは、道元が叡山時代からずっといだき続けてきた疑問、つまり、人は生まれながら仏であると説いていながら、一方では修行が必要であると教えるのは何故か、という疑問に対する答えでもあった。(76~77頁)
■そして参禅する人たちがいだくと予想される、宗教上の疑問18をかかげ、一々それに応答するという形式をとって、道元の坐禅に関する抱負と信念とを、次のようにのべた。
「これまでの説明で、坐禅の功徳が広大無辺であることは、よく承りました。しかし、おろかな人は、疑って言うでしょう。仏法には多くの入り口があります。どういうわけで、坐禅だけが真直ぐな入口だといって、坐禅だけを専らすすめるのですか」
このような質問にこたえて、道元は、
「釈尊、まさしく得道の妙術を正伝し、又、三世の如来、ともに坐禅より得道せり。このゆえに、正門なることをあひつたへるなり。しかのみにあらず、西天東地(インド・中国)の諸祖、みな坐禅より得道せるなり。ゆえに、いま正門を人天(にんでん、多くの人びと)にしめす」(『弁道話』)
「宗門の正伝にいはく、この単伝正直の仏法は、最上のなかに最上なり。参見知識のはじめより、さらに焼香・礼拝・念仏・修懺・看経(かんぎん)をもちいず。ただし、打坐して身心脱落することをえよ」(『弁道話』)(77~78頁)
■このように、道元は坐禅の心がけを説いたあと、さらに、日本に伝わっている天台宗や華厳宗は、いずれも大乗仏教の究極ともいうべきものであり、まして真言宗などは、即心是仏といって、長い期間の修行をしなくても、ひとたび万物の根源を見究めると、たちどころに正しい悟りを開くことができると説いている。これが仏法の極妙ともいってよいのに、それをさしおいて、坐禅の修行を特に勧めるのは一体なぜですか、という弟子の質問に対し、道元は次のように説いた。
(中略)
仏法を学ぶものにとっては、そのような宗派による教えの優劣や浅深が問題なのではない。それよりも、修行そのものが本物か偽物かということをよくわきまえるべきである。いろいろな言葉というものは、森羅万象以上に沢山あるものである。たとえば即心即仏という言葉は、水に映った月のようなもので、月そのものではない。また即坐成仏というのも、鏡の中の影像であって、真の悟りではない。このように、言葉の巧妙さにかかわって、仏法の真理を見誤ってはいけない。真の悟りを開くための修行こそ大切なのである。だから、いまはただその修行を勧めるために、釈尊から正伝された最もすぐれた修行である坐禅を人びとに示して、一人でも多く真実の仏法に生きる人になってもらいたいと思うのである。
また真実の仏法をうけるためには、かならず正しく悟った人を自分の指導者にえらばなければならない。ただ文字いじくりばかりしているような学者を指導者にしてはならない。かえってそれは、一人の盲人が多勢の盲人を道案内するようなものだからである。今日では釈尊の真実の仏法を正伝しているわが門流だけが、正しい悟りをひらいた人を敬い、真実の仏法を伝持している。だから、冥界の神々もやって来て帰依し、また小乗の悟りを開いた羅漢も訪れて法を問い、いずれもそれぞれ自分の心を開明する手だてを授けられたのである。他宗門では、そのようなことは全く聞かないことである。いまは万事を放擲して、釈尊正伝の仏法によって、ひたすら坐禅をすれば、かならず心の迷いや妄情の思慮分別の世界をのりこえて立派な悟りを開くことができる。
道元はこのような坐禅の効用を説き、坐禅を専修するものは、戒律を厳守しなければならない、と力説した。さらに、坐禅修行をするものが、真言宗や天台宗などの行を兼ね修することをきっぱり否定して、昔から今日にいたるまで、仏の悟りを正伝した祖師で他の修行を兼ねたという例は聞いたことがない、と如淨からも教えられたとのべ、「まことに一事をことゝせざれば、一智に達することなし」と言いきった。(80~82頁)
■また、坐禅についてはインドから各宗門でいろいろ説かれ、修行者はみな行ってきているのに、その坐禅のなかに釈尊の正法があつまっているというのは、どうしてかという問いにこたえた、次のように述べている。
「いまこの如来一大事の正法眼像無上の大法を、禅宗となづくるゆえに、この問きたれり。しるべし、この禅宗の号は、神丹(中国)以東におこれり。竺乾(じくけん、インド)にはきかず。はじめ達磨大師、嵩山の少林寺にして9年面壁(中略)のち代々の諸祖、みなつねに坐禅をもはらす。これをみるおろかなる俗家は、実をしらず、ひたゝけて坐禅宗といひき。いまのよには、坐のことばを簡して、ただ禅宗といふなり」(『弁道話』)
■ではまた、日常の行動がすべてそのまま禅でないものは、と説きながら、一方では、とくに坐禅だけをとり上げて勧めるのはなぜか、という質問には、次のように答えている。
「むかしよりの諸仏、あひつぎて修行し、証入(悟ること)せるみち、きはめしりがたし。ゆえをたづねば、ただ仏家のもちいるところをゆえとしるべし。このほかにたづぬべからず。ただし祖師ほめていはく、坐禅はすなはち安楽の法門なり」(『弁道話』)
■したがって、只管打坐という言葉を用いた道元の真意は、これまで一部でいわれてきたように公案を全面的に否定したものでは決してなく、ひたすら坐禅に撤すること、つまり専修坐禅という意味であることがわかる。釈尊が説いた根本仏教の精神に立ち還り、釈尊と同じように坐禅に撤せよという道元の叫びであったのである。(84頁)
■そこで、悟りがまだ開けないものは坐禅をするのはよいが、すでに悟りを開いたものは、その必要がないのではないか、という問いに答えて、修行と悟りの関係について、次のように説いた。
「それ、修証はひとつにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり」
「仏法には修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の弁道、すなはち本証の全体なり。かるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指(じきし)の本証(直接に究極の真理を示すこと)なるがゆえなるべし。すでに修の証なれば、証にきは(際限)なく、証の修なれば、修にはじめなし」(『弁道話』)
■しかし、これでは、修行のほかに悟りはない。いいかえれば、修行さえしていれば悟りはなどはいらない、修業さえしていればそれでよいのだ、というようにも受け取れる。そこで道元は、修業と悟りの関係について、さらに次のように説いた。
「ここをもて、釈迦如来・迦葉尊者、ともに証上の修(悟った上での修業)に受用せられ、達磨大師・大鑑高祖(六祖慧能)、おなじく証上の修に引転せらる。仏法住持のあと、みなかくのごとし。すでに証をはなれぬ修あり。われらさいはひに一分の妙修を単伝せる初心の弁道、すなはち一分の本証を無為の地にうるなり。しるべし、修をはなれぬ証を染汚(ぜんな、汚すこと)せざらしめんがために、仏祖しきりに修業のゆるくすべからざるとをしふ。妙修を放下すれば、本証手の中にみてり。本証を本証を出身(悟りの境地に入ること)すれば、妙修通身(全身)におこなはる。又、まのあたり大宋国にしてみしかば、諸方の禅院、みな坐禅堂をかまへて、五百六百および一二千僧あお安じて、日夜に坐禅をすゝめき。その席主とせる伝仏心印(仏心の確証を伝えていること)の宗師に、仏法の大意をとぶらひしかば、修証の両段にあらぬむねをきこえき。このゆえに、門下の参学のみにあらず、求法の高流(すぐれた修行者たち)、仏法のなかに真実をねがはむ人、初心(初心者)・後心(古参)をえらばず、凡人・聖人を論ぜず、仏祖のをしへにより、宗匠の道をおふて、坐禅弁道すべしとすゝむ。きかずや祖師のいはく、修証はすなはちなきにあらず、染汚することはえじ。又いはく、道をみるもの、道を修すと。しるべし、得道のなかに修行すべしといふことを」(『弁道話』)(86~87頁)
■このように道元は、修行と悟りはⅠつであるから、これを煩悩によって汚さないようにするため、きびしい修行をつまなければならないと強調した。道元はこれを「不染汚の修証」、あるいは「不染汚の行持」などともいっている。しかも、そういう本性は、もともと人間にはゆたかに備わっている。人間は煩悩具足の衆生ではなく、仏であるという解釈に立っているわけである。そこが、煩悩具足の人間こそ救われるのだという親鸞の教説と、根本的に異なる点である。
こうして、人は仏性を持っているという信の自覚に撤し、修証一如を力説したところに、道元の思想の独自性がある。それは、人は生まれながら仏性をもっているという天台宗の根本思想に対して、それならば、諸仏はなぜ修行を続けなければならないと説くのか、という道元自身の疑問に答えた最終的な結論でもあった。(68頁)
■ところがひとり道元だけは、この末法思想に同調するどころか、真向からこれに反対して、大乗仏教では正法と像法と末法の時代をわけることをしない、ときっぱり断言した。
「大乗実教(大乗の真実の教え)には、正・像・末法をわくことなし。修すれば、みな得道するといふ。いはむやこの単伝の正法には、入法出身(法に入って悟りを開くこと)、おなじく自家の財珍(宝)を愛用(活用)するなり。証の得否は、修せんもの、おのずからしらしむこと、用水の人の冷暖を、みずからわきまふるがごとし」(『弁道話』)(91頁)
■ついで8月(天福元年、1233)には「現成公案」の巻を書いて、九州にいる在家の弟子楊(よう)光秀に与えた。これは道元の思想の要点をわかりやすくのべたもので、眼にみえる諸現象のありのままの姿は、すべてそのまま仏法の現われであると考え、これをよく研究しようと主張したものである。道元はさきに『弁道話』で只管打坐を強調するなど、主として実践面を説いたのに対して、ここでは、古則とか公案を用い、見性(けんしょう、生まれながら自分に備わっている仏心を見究めること)とか、悟りということばかりに、心を奪われている当時の禅風を批判し、道元禅のの根底となる思想を、理論的に明らかにしておこうとした。(94頁)
■道元はその巻頭で、まず、
「諸法の仏法なる時節、すなはち、迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、衆生あり」
このせかいのすべてのものは、仏法が現実化されたもので、そのなかには迷いも悟りもあるし、修行があり、生も死もあり、諸仏と衆生があるとして、現実に存在するものの種々相をすべて肯定した。次に一転して、
「万法ともにわれにあらざる時節、まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし」
しかしすべてに自己という主体がなければ、そこには迷いも悟りもない。諸仏も衆生も、生も死もないわけであるといって、一切の存在を否定する空の思想を展開している。
さらに、その上で、
「仏道、もとより豊検(相対立すること)より跳出せるゆえに、生滅あり、迷悟あり、生仏あり」
といい、仏道は、もともと豊かさと慎ましさとの対立の中から出来てきたものであるから、そこには生も滅もあり、迷いも悟りも存在するし、衆生も仏もあるわけであると、さきの肯定と否定を超えた立場に立って、両者の存在を認めている。
「しかし、かくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり」
そして、そうはいっても、やはり惜しいと思う花はちり、好ましくない雑草が生い茂るのが、現実の世界というものである、と自然の在りのままの法則を是認している。
また、悟りの世界における自分の立場や考え方について、なにごとでも、自己を中心に考えて、仏道を修行し悟りを開こうとするのは誤りで、それは迷いである。それは自分を万法の外において、その観点から、万法を自分の対象物として客観的に見ようとするものだからである。仏法の世界では、万法のなかに身を置いて判断をしなければならない。この意味からすると、自己をまず忘れて、万法の方から進んで自個を修行し悟りを開こうとするとき、そこに悟りの世界が開かれるのである。このようなことをよくわきまえて、迷いを迷いとしないで大悟したのが、諸仏である。その反対に、悟りの世界に大いに迷っているのが衆生である。こういうわけで、悟りのうえに悟りを得る人もあるかわりに、反対に、迷いのなかに迷い続けている人もある。(94~96頁)
■また、仏道修行と自己との関係を次のようにのべている。
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするゝなり。自己をわするゝといふは、万法に証さるゝなり。万法に証さるゝといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(悟りの跡かた)の休歇(きゅうけつ、全く跡かたがないこと)なるあり。休歇なる悟迹を長々出ならしむ」(「現成公按」巻)(96頁)
■さらに道元は、人の生と死について、次のようにいっている。
「人のしぬるのち、さらに生とならず。しかあるを、生の死となるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆえに不生といふ、死の生にならざる、法輪(正しい仏教のおしえ)のさだまれる仏転なり。このゆへに不滅といふ。生も一時のくらいなり。死も一時のくらいなり。たとへが、冬と春のごとし。冬の春となるとおもはず。春の夏となるといはぬなり」(「現成公按」巻)(97~98頁)
■さらに、人と悟りとの関係を水に映る月に譬えて、次のように説いた。
「人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天(みてん)も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。さとりの人をやぶらざる事、月の水をうがたざるがごとし。人のさとりを罣礙(けいげ、さまたげること)せざること、滴露の天月を罣礙せざるがごとし」(「現成公按」巻)(98頁)
■さらに、悟りの条件について、道元は次のように考えていた。
「うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへども、そらのきはなし。しかあれども、うを・とり、いまだむかしよりみづ・そらをはなれず。(中略)鳥もしそらをいづれば、たちまちに死す。魚もし水をいづれば、たちまちに死す。以水為命、しりぬべし。以空為命、しりぬべし。(中略)しかあるを、水をきはめ、そらをきはめてのち、水・そらをゆかむと擬する鳥・魚あらむは、水にもそらにもみちをうべからず。ところをうべからず。このところをうれば、この行李(あんり、日常生活一般)、したがひて現成公按(参禅求道の課題が解けて、完全なすがたで実現すること)す。このみちをうれば、この行李、したがひて現成公按なり」(「現成公按」巻)(99頁)
■あるとき麻谷(まよく)山の宝徹和尚が扇を使っていたところへ、一人の僧侶がやってきて、仏教の説くところによると、風の本性は常住であって、どこにでも無いところはないということですが、なぜ和尚は扇を使っているのですか、と尋ねた。和尚はそれに答えて、貴僧は風の性質が常住だということはわかっているようだが、どこにでも無いところはないということが、まだよく判ってはいないようだ、といった。するとその僧は、それではどこにでも無いところはないというのは、どういう訳ですか、と聞き返した。ときに和尚は、ただ黙って扇をあおぐばかりであった。それを見たその僧は、はたと悟りを開いて、ただ黙って礼拝し、そこを立ち去ったという。
「仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。常住なれば、あふぎをつかふべからず。つかはぬおりも、かぜをきくべきといふは、常住もしらず、風性(風の本性)をもしらぬなり」(「現成公按」巻)
仏法の悟りのしるし、釈尊から正しく伝わってきた道は、まさにこのようでなければならない。風の本性は常住であるから、扇を使う必要などないというのは正しい。しかし、扇を使わないときも風があるであろうというのは、常住の真の意味も、風の正体もよく判っていないからである、批評を加えた。そして最後に、
「風性(仏性を指す)は常住なるがゆへに、仏家の風は、大地の黄金なるを現成(完全に実現化すること)せしめ、長河(揚子江を指す)の蘇酪(そらく、牛乳を精製した最高の飲料)を参熟せり」(「現成公按」巻)
と「現成公按」の巻を結んだ。(99~100頁)
■参禅修行によって正しい悟りを得るためには、まず正師を求めるべきで、思想と実践が相伴った正師でなければ、正しい悟りへの指導者とはいえない、と力説し、「参禅学道ハ一生ノ大事ナリ、ユルガセニスベカラズ」と言い放った。そこには、門人の教化に精根を傾けていた道元の旺盛な気魄が感じられる。
こうして、興聖寺教団の強化に没頭していた文暦元年(1234)冬、建仁寺時代に道元の門を叩いたことのある孤雲懐奘らが、深草の道元門下に正式に入門した。大和の多武峰(とうのみね)にある妙楽寺(現在の談山神社)の天台教団から新たに興聖寺教団に加わった懐奘という有力な門弟を得て、道元は門下の教化指導に一層自信を深めたにちがいない。こののち懐奘は道元門下の第1の高弟として、その教化を大いに助けたからである。(101~102頁)
■暦任元年(1238) 一顆明珠(いつかみみょうじゅ)
延応元年(1239) 即心是仏・洗浄
仁治元年(1240) 礼拝得髄・山水経・有事・袈裟功徳・伝衣(でんえ)・谿声山色・諸悪莫作
仁治二年(1241) 仏祖・嗣書(ししょ)・法華転法華・心不可得・古鏡・看経・仏性・行仏威儀・仏教・神通
仁治三年(1242) 大悟・坐禅箴(しん)・仏向上事・恁麽(いんも)・行持・海印三昧・授記・観音・阿羅漢・柏樹子・光明・身心学道・夢中説夢・道得・画餅・全機
寛元元年(1243) 都機(つき)・空華(くうげ)・古仏心・菩薩薩埵(さった)四摂法(せっぽう)・葛藤(かっとう)
■ついで翌延応元年(1239)4月には、21ヵ条からなる『重雲堂式』を著わし、修行者が集まる道場の規律を定めて、釈尊正伝の「真実の仏法」を実践するための基本的な心得を門人たちにしめした。
一、「真実の仏法を求めて真剣に修行しようという志を持ち、名誉や利欲を求めてはならない。
一、堂内の修行僧たちはよく和合し、たがいに仏道を興すことを心掛けなければならない。
一、外出を好んではならない。むかしの修行者が深山幽谷に住み、すべての世縁を断ちきって隠棲し、修行にはげんだ精神をみならわなければならない。
一、堂内で文字を読んではならない。堂内では寸陰を惜しんで修行に専念しなければならない。
一、勝手に出歩いて遊んだりしてはならない。のんびり一生を終ってしまったのでは、あとで後悔してもはじまらない。
一、他人の欠点をついたり、それにならったりしてはならない。にくしみの心をもって見てはならない。自分の徳をみがくことこそ大切である。
一、大小となく、すべて堂主に報告しなければならない。もしそれに従わないものは堂から退去させるべきである。
一、堂の中や近くで大声を出したり、大勢でガヤガヤさわいではならない。
一、堂内を勝手に歩行してもいけない。
一、堂の中で数珠を持ったり、手をたれたまま出入りしてはならない。
一、特別のとき以外は、堂内で仏名や経文を口に唱えてはいけない。
一、堂内で高い音をたてて鼻をかんだり、つばをはいたりしてはならない。
一、堂内の修行僧は、綾織りの着衣を使ってはいけない。紙や布の素衣をきていなければならない。むかしから悟りを開いた人は、みなそのようにしてきたからである。
一、もちろん酒に酔って堂内に入ってはいけない。また、酒や楡(にれ)の皮の粉を入れた漬物などを堂内に持ち込んではならない。
一、争いごとを起したものは、二人とも堂から出すべきである。自分たちの修行を妨げるだけでなく、他人の修行をも邪魔するからである。その争いを止めなかったものも同罪である。
一、堂内の規則を守らないものは、おなじように堂から出すべきである。
一、他所から僧俗を招いて、堂内の修行僧をどかせたり、近くで客人と大声で談合したりしてはならない。
一、坐禅は、僧堂の場合とおなじようにしなければならない。朝晩ともなまけてはいけない。
一、食事のとき、食器類を地面に落としたものは、禅寺の規則に従って、罰としてこらしめのために一定の燈油を納めなければならない。
一、一般の仏法の規則はもちろん、禅寺の規律は肝に銘じて厳しく守らなければならない。
一、いつでも平穏無事に修行ができるように心掛けなければならない。(抄出)(104~106頁)
■「むかし犯罪ありしとて、きらはゞ、一切菩薩をもきらふべし。もし、のちに犯罪ありぬべしとてきらはば、一切発心のぶさつをもきらふべし。如∠比きらはば、一切みなすてん。なにゝよりてか仏法現成せん。如∠是のことばゝ、仏法を知らざる癡人(ちじん)の狂言なり。かなしむべし」(「礼拝得髄」巻)(109頁)
■「浄信一現するとき、自他おなじく転ぜらるゝなり。その利益(りやく)あまねく情・非情にかうぶらしむ。その大旨は、願(ねがわく)は、われたとひ過去の悪業(ごう)おほくかさなりて、障道(仏道をさまたげること)の因縁ありとも、仏道によりて得道せりし諸仏、諸祖、われをあはれみて、業累(ごうるいを解脱せしめ、学道さはりなからしめ、その功徳法門、あまねく無尽法界(むじんほっかい、尽きることのない仏法の世界)に充満弥淪(じゅうまんみりん、あまねく行きわたらせること)せらん」(「谿声山色」巻)(110頁)
■「いま大宋国の諸山に、甲刹(かっさつ)の主人とあるもの、坐禅をしらず、学せざるおほし。あきらめしれるありといへども、すくなし。諸寺にもとより坐禅の時節さだまれり。住持より諸僧、ともに坐禅するを本分の事とせり。学者を勧誘するにも坐禅をすゝむ。しかあれども、しれる住持人はまれなり」(「坐禅箴」巻)(112頁)
■「仏祖の大道、かならず無上(最もすぐれていること)の行持(修行)あり。道環(連なり、ゆきめぐること)して断絶せず。発心(仏になろうとする心を起こすこと)・修行・菩提(迷いから目覚めて悟ること)・涅槃(完全な悟りの境地)、しばらくの間隙あらず。行持道環なり。(中略)不二曽染汚(せんな)一(煩悩などでけがれたことがない)の行持なり」(「行持」巻)(113頁)
■「仏祖の大道を行持せんには、大隠・小隠(大小の隠者)を論ずることなく、聡明鈍癡(どんち)をいとふことなかれ。たゞながく名利をなげすてゝ、万緑に繋縛せらるゝことなかれ。光陰をすごさず、頭燃(ずねん、頭髪に火がついて燃えはじめたような早急に解決を要する悩み)をはらふべし。大悟をまつことなかれ。(中略)ただまさに、家郷あらんは家郷をはなれ、恩愛あらんは恩愛をはなれ、名あらんは名をのがれ、利あらんは利をのがれ、田園あらんは田園をのがれ、親族あらんは親族をはなるべし。名利等なからんも又、はなるべし。すでに、あるをはなる。なきをもはなるべき道理、あきらかなり。それすなはち、一条の行持なり」(「行持」巻)(114頁)
■「釈迦牟尼仏、十九歳の仏寿より、深山に行持(修行)して、三十歳の仏寿にいたりて、大地有情(うじょう、一切の生きもの)同時成道の行持あり。八旬の仏寿にいたるまで、なほ山林に行持し、精藍(しょうらん、修行道場)に行持す。王宮にかへらず、国利を領せず(中略)外道の訕謗(せんぼう、そしり)を忍辱(耐え忍ぶ)す。おほよそ一化(いちけ、釈尊一代の教化)は行持なり。浄衣・乞食(こつじき、修行に必要な食を得るため食を乞い求めること)の仏儀、しかしながら行持にあらずといふことなし」(「行持」巻)
釈尊はネパールの国王淨飯王(じょうぼんのう)の王子として生まれながら、19歳で出家の道に入り、深山にこもって修行に専念した。30歳のとき悟りを開いたが、80歳の晩年にいたるまで、生涯山林を離れず、苦行(岡野注;修行の方がよい)を続けた。その間、1度も王宮に帰らず国家からの補助も一切受けず、弊衣をまとい、乞食の行によって生活するという原則的態度を変えようとせず、外道たちの謗りを甘受し、忍従し続けるのであった。
このような釈尊の姿こそ、道元の最も畏敬するところであり、修行における最高の理想像であった。
このように道元は、一貫して根本仏教の精神に立ち還ることを最高目標とした。『正法眼蔵』の最後を、「釈迦牟尼仏にひとしくして、ことなることなからん」という言葉で結んでいるのも、そのためである。道元の釈尊に対する思慕が、いかに強かったかがわかる一コマである。(115~116頁)
■達磨はインドの王国に生まれ、520年頃、釈尊の正法を伝え、広く衆生を救済するため、身命を惜まず、海路中国大陸に渡って梁の武帝に禅を説き、さらに嵩山の少林寺に入って、中国にはじめて釈尊の正法である禅を伝えた。いまや遠方のわが国の農民や村童にいたるまで、老いも若きも釈尊の正法を聞くことができるようになったのは、ひとえにそのお陰である。このように身命を惜まず、釈尊の正法を伝承したのは、実に達磨一人だけであった。
「いま正法(しょうぼう)にあふ。百千恒沙(ごうしゃ、数えきれないほど沢山)の身命をすてゝも、正法を参学すべし。(中略)しづかにおもふべし。正法よに流布せざらんときは、身命を正法のために抛捨(ほうしゃ、投げ捨てる)せんことをねがふとも、あふべからず。正法にあふ今日のわれらをねがふべし。正法にあふて身命をすてざるわれらを慚愧(ざんき)せん。はづべくは、この道理をはづべきなり。しかあれば、祖師の大恩を報謝せんことは、一日の行持(修行)なり。自己の身命をかへりみることなかれ。禽獣よりもおろかなる恩愛、をしんですてざることなかれ。たとひ愛惜(あいせき)すとも、長年のともなるべからず。あくた(ちりやごみ)のごとくなる家門、たのみてとゞまることなかれ。(中略)病雀(びょうじゃく)なほ恩をわすれず。(中略)窮亀(きゅうき、籠に入れられた亀)なほ恩をわすれず。(中略)かなしむべし。人面ながら畜類よりも愚劣ならんことは。いまの見仏門法(もんぼう、正師について仏法を聞くこと)は、仏祖面々(悟りを開いた多くの先輩たち)の行持よりきたれる慈恩なり。仏祖もし単伝せずば、いかにしてか今日にいたらん。一句(一つの言葉)の恩、なお報謝すべし。一法の恩、なほ報謝すべし。いはんや正法眼蔵無上大法の大恩、これを報謝せざらんや」(「行持」巻)(119~120頁)
■また、六祖の慧能(638-713)は、先輩の修行僧をとび越えて師法を継いだため、危害を避けて秘かに南方にかくれ、後年になってようやく世に出たと伝えられる人であるが、道元は、その慧能について、次のように説いた。
慧能は、幼くして父を失ない、老母に養育され、貧しかったので木こりで生計を立てていたが、町を歩いていたとき、『金剛経』の一句を耳にして、たちまち老母を捨てて出家してしまい、厳しい修行の末、ついに悟りを開いた。恩愛のきずなを断ち切り敢て選んだという、修行に対する厳しさを、道元はたたえたのである。(120~121頁)
■道元はこのようにのべ、世間の名利に超然とした、枯淡で脱俗的な家風を大いにたたえ、これを思慕してやまなかった。さらに「葛藤(かっとう)」の巻でも、臨済も徳山も、潙山も雲門も、趙州古仏には到底及ばないと、その禅風を高く評価したのである。(121~122頁)
■「しづかにおもふべし、一生いくばくにあらず。(中略)いたづらなる声色(しょうしき)の名利に馳騁(ちへい、感覚的な名誉や利欲にふりまわされること)することなかれ。馳騁(ちへい)せざれば、仏祖単伝の行持なるべし。すゝむらくは、大隠・小隠(修行者たち)、一箇半箇なりとも、万事万縁をなげすてゝ、行持を仏祖に行持すべし」(「行持」巻)(125頁)
■つまり、坐禅のことは『法華経』などにみえているから、知識としては一般に知られていた。しかし、坐禅だけを行なうということは、これまで殆んどなかった。さきごろ栄西が禅宗を伝えたが、これも天台宗や真言宗を兼ねるというもので、とくに禅宗の修行だけをするものではなかった。ところが、道元が深草で新しい大陸風の坐禅をするようになってから、世間の大評判になった、というのである。
その結果、道元を慕って各宗の僧侶や公家・武家などが、つぎつぎに深草の道元教団に集まってきた。そうした動きのなかで最も注目されるのは、孤雲懐奘をはじめとする旧大日派の人びとの合流である。
この大日派というのは、臨済宗大恵派の系統に屬する一派である。(129頁)
■特に、拙庵(せったん)の師である大恵に対する批判には、激烈なものがあった。
寛永2(1244)年2月、道元は大恵を評して、「大恵はもと他宗の学徒であったが、禅宗に転じ、まず宣州の理和尚について禅を修めた。しかし、それをよく理解することができなかったので、瑞州(ずいしゅう)に赴いて、曹洞宗の洞山(とうざん)道微(どうび)に参じ、悟ったという証明になる嗣書をもらいたいと願い出た。けれども、修行に未熟な点があるという理由で、嗣書を授与されなかった。そこでこんどは、臨済宗の湛堂のもとに投じ、久しく禅の指導をうけたが、そこでも、ついに嗣書を授かることができなかった。このように大恵という人は、どこまでも禅を徹底的に追究しようとしないで、嗣書ばかり早く受けようとした。その態度は、まことに道心のない浅はかな修行者というほかはない。思慮のないことは憐れというべきである」(「自証三昧」巻)と、このように大恵の無道心な修行態度と名誉欲をはげしく非難し、大恵のように禅修行に対する根本的な誤りをしないように、門人たちに警告を発している。(134頁)
■このようにみてくると、旧大日派の人びとが、道元教団に集団入門してから、大恵派に對する道元の批判が急に厳しさを加えたのは、深草教団内部における指導強化の必要上からではなかろうか。かって旧大日派がその流れをくんでいた中国大恵派の家風の欠点を、きびしく指摘することによって、道元みずからの禅の正統性を強調すると同時に、旧大日派出身の人びとに猛省をもとめ、かれらに大恵派の禅風からの脱皮を促し、これを指導矯正しようという、再教育の意図が強かったからであろうと思われる。高潔無類な道元が、ただ故なくして、大恵やその門下などに、あのような厳しい批判を浴せるはずはないであろう。(136頁)
■道元の訴えを知って、天台衆徒がそのまま黙っているはずがなかった。かれらはその反論を朝廷に奏上した、そこで朝廷は、これまでの行きがかりから、天台教団側の意向を聞き入れ、その是非について、佐(すけの)法印に判定を下させた。すると案の定、法印は、
「道元が説いている思想は、釈尊の説法をきいて悟る声聞の説どころか、師匠もなくて自分一人で悟るという縁覚(独覚)の解釈である。それは余りにも身勝手な、自己本位の解釈にすぎない。これでは多くの人びとを救おうという大乗仏教の根本理念にそむくばかりでなく、かえって護国の趣旨にも反するものである」(『渓風拾葉集』)(139頁)
■やがて道元は、釈尊正伝の「真実の(まこと)の仏法」の純粋性をまもるため、ついに一大決心をし、寛元元年(1243)7月、越前志比庄(福井県吉田郡永平寺町)へ旅立った。ときに道元、44歳のことである。(141頁)
■懐奘らをともなって、道元が越前志比庄に着いたのは、寛元元年(1243)7月の半ばすぎのことである。
新天地を得て心機一転、新宗教の宣揚に意欲を燃やしていた道元は、まだ旅の疲れも十分に癒えない閏7月1日、平泉寺に近い山奥の禅師峰(やましぶ、大野市大月町禅師峰寺)で、「三界唯心」の巻を説いた。越前における道元の第一声である。(146頁)
■やがて吉峰寺(福井県吉田郡永平寺町吉峰)に移り、ここを第二の道場とした。道元はここを古精舎とか、古寺と呼んでいるから、さきの禅師峰の道場と同様、それ以前は平泉寺などと関係がある白山天台系の古代仏教寺院ではなかったかとおもわれる。(147頁)
■寛元元年(1243)禅師峰吉峰寺 三界唯心・見仏・徧参・眼晴・家常・竜吟・仏道・蜜語・諸法実相・無常説法・洗面・面授・法性・梅華・十方・坐禅儀・説心説性・陀羅尼
寛元2年(1244)吉峰寺 大悟・優曇華・発無上心・発菩提心・如来全身・三昧王三昧・三十七品菩提分法・転法輪・自証三昧・大修行
山奥某所 祖師西来意・春秋(148頁)
■「仏道は、諸発心(ほっしん)のときも仏道なり。成正覚(じょうしょうがく、完全にさとること)のときも仏道なり。初中後、ともに仏道なり。たとへば、万里をゆくものゝ、一歩も千里のうちなり。初一歩と千里とことなれども、千里のおなじきがごとし」(「脱心脱性」巻)(149頁)
■「五宗(大陸禅の5派。雲門宗・法眼宗・潙仰宗・臨済宗・曹洞宗)を立して、各々の宗旨ありと称するは、証惑世間人のともがら、少聞薄解(教えを聞くことが少なく、理解の仕方が浅いこと)のたぐひなり」(「仏道」巻)(150頁)
■「近来、大宋国杜撰(ずさん)のともがら(中略)老子・荘子の言句を学す。これをもて、仏教の大道に一斉なりといふ。また、三教は一致なるべしといふ。あるいは、三教の鼎(かなえ)の三脚のごとし。ひとつもなければ、くつがえるべしといふ。愚癡(ものわかりが悪いこと)のはなはだしき、たとひをとるに物あらず。かくのごときのことばあるともがらも、仏法をきけりとゆるすべからず。(中略)三教一致のことば、小児子の言音におよばず、壊仏法のともがらなり」(「諸法実相」巻)(153頁)
■ところが、深草時代も後半になると、道元の考えに変化が現れるようになった。比叡山衆徒の圧迫、円爾(えんに、1201-80)による東福寺禅教団の成立などにともない、道元は教団内の指導統制をいっそう厳重にする必要が生じた。大恵派などの臨済禅に対しても、痛烈な批判を加えたのである。さらに、『護国正法義』を著わし、釈尊正伝の仏法こそ国家護持のためには、最もふさわしい宗教であることを強調し、その正統性を一段とつよく主張した。そしてついに、越前に下向する頃から、出家主義を標榜するようになったのである。(156頁)
■「いまだ出家せざるものの、仏法の正業(正しい行ない)を嗣続(継ぐこと)せることあらず、仏法の大道を正伝せることあらず。在家、わづかに近事男女の学道といへども、達道(仏道の奥義に達すること)の先蹤」(「諸法実相」巻)(153頁)
■ところが、深草時代も後半になると、道元の考えに変化が現れるようになった。比叡山衆徒の圧迫、円爾(えんに、1202-80)による東福寺禅教団の成立などにともない、道元は教団内の指導統制をいっそう厳重にする必要が生じた。大恵派などの臨済禅に対しても、痛烈な批判を加えたのである。さらに、『護国正法義』を著わし、釈尊正伝の仏法こそ国家護持のためには、最もふさわしい宗教であることを強調し、その正統性を一段とつよく主張した。そしてついに、越前に下向する頃から、出家主義を標榜するようになったのである。(156頁)
■さらに続けて、釈尊以来、出家の心と在家の心は同じだなどと、正式には一度も説かれたことはない。出家したものは、たとえ破戒・無戒の僧でも、悟りを開くことができたが、それとは反対に、在家の人は、たとえ善行をつんだ者でも、悟りを開いたというためしはない。それは在家が本当に仏道を修行する場でないからである。たしかに、仏教の諸説のなかには、在家仏教や女人成仏などの説もあるが、それらは釈尊の教えの正伝ではないのである。釈尊から正伝された真の仏教は正伝した祖師で、出家受戒をしないものは一人もなかったといえよう。(158~159頁)
■新道場も順調に整ったので、寛元三(1245)年三月春、道元は再び説法を開始した。そして、こんどこそすべての点で理想的な修行生活を実現させたいと考えた。道元はそこで、修行者はつねに根本仏教の原点に立ちかえって修行するという心がけが大切であり、日常使う袈裟や食器類なども、すべて釈尊正伝の真の仏法のいのちであると考えなければならない、と力説した。(「鉢盂」巻)(160頁)
■いよいよ鎌倉に赴いた道元は、時頼の篤い帰依をうけ、禅について説法するとともに、仏教生活をいとなむのに必要な菩薩戒を時頼に授けた。しかし、禅の修行に熱心な時頼はともかく、鎌倉の一般武士たちの信仰は、なお旧態然とした加持祈祷や密教的行事がほとんどで、道元禅による教化には限界があることは、明瞭であった。道元の期待ははずれた。時頼が禅寺を建て、その開山に迎えようとしたのを断り、宝治二(1248)年春、鎌倉武士の教化を断念して、越前の永平寺に帰ったのである。(168頁)
■やがて病状がすすむのを感じるにつけ、道元にとって最も気がかりだったのは、自分亡きあと、門弟たちに弟子たちが道元の教えをどのように伝えていくかという点であった。道元は、釈尊が入滅にあたって、最後に弟子たちに説いた先例にならい、「八大人覚」の巻を著わした。
八大人覚というのは、修行者がそれをしっかり守っていけば、仏法は永遠に滅びないと、釈尊が最後に説いた遺誡(ゆいかい)のことで、⑴欲望を少なくする⑵少しのもので満足する⑶静寂を楽しむ⑷よく精進する⑸みだらなことを考えない⑹心静かに瞑想する⑺智恵を学ぶ⑻たわむれの議論をしない、という8項目のことをいう。これは枕経(まくらぎょう)のときに読まれる『遺教経(ゆいきょうぎょう)』にみえている教えである。道元はそれに倣い、病をおして次のように説法した。
「この故に、如来(釈尊)の弟子は、かならずこれを習学したてまつる。これを修習せず、しらざらんは、仏弟子にあらず。これ如来の正法眼蔵涅槃妙心なり。しかあるに、いましらざるものはおほく、見聞せることあるものはすくなきは、魔嬈(まにょう、魔障)によりてしらざるなり。また、宿殖(しゅくじき)善根(善根功徳をつみかさねること)のすくなきもの、きかずみず。昔し正法・像法のあひだは、仏弟子みなこれをしれり。修習し参学しき。いまは、千比丘のなかに一両この、八大人覚しれる者なし。あはれむべし、澆季(末世)の陵夷(衰微)たとふるにものなし。如来の正法、いま大千(世界)に流布して、白法(びゃくほう、正法)いまだ滅せざらんとき、いそぎ習学すべきなり。緩怠(かんたい、おこたること)なることなかれ。仏法にあひたてまつること、無量劫(永久)にかたし。人身をうること、またかたし。(中略)如来の般涅槃(死)よりさきに涅槃にいり、さきだちて死せるともがらは、この八大人覚をきかず、ならはず。いまわれら見聞したてまつり、習学したてまつる。宿殖(しゅくじき)善根のちからなり。いま習学して生々(いきいきと)に増長し、かならず無上菩薩(最上の正しい悟り)にいたり、衆生のためにこれをとかんこと、釈迦牟尼仏にひとしくして、ことなることなからん」(「八大人覚」巻)(170頁)
■病状がすすんだ道元は、建長五(1253)年七月、永平寺の席を弟子懐奘に譲り、ここに懐奘は永平寺の第二世となった。
やがて療養のため、道元は永平寺を出て京都にのぼり、八月二十八日夜半、京の宿で、
「五十四年、第一天ヲ照ラス。コノ勃跳(ぼっちょう、はねまわり)ヲ打シテ、大千(世界)ヲ触破(触れて破ること)ス。咦(いい)。渾身モトムルトコロナク、活(い)キナガラ黄泉ニオツ」(原漢文)
と遺偈(ゆいげ)を記し、しずかに目を閉じたのである。行年五十四歳、それはまことに至純な求道者の一生であった。(173頁)
(2014年5月12日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元』 正法眼蔵の言語ゲーム 春日佑芳 ぺりかん社
■古人云く、「智者の辺(ほとり)にしてはまくるとも、愚人の辺にしてかつべからず」。我が身よく知りたることを、人のあしく知りたるとも、他の非を云うはまた是我が非なり。法文を云うとも、先人の愚をそしらず、また愚痴、未発心の人のうらやみ卑下しつべき所にては、よくよくこれを思うべし。(26頁)
■ふるく云く、「君子の力、牛に勝(すぐ)れたり。しかあれども、牛とあらそわず」。今の学人、我れ智恵を学人にすぐれて存ずとも、人と諍論(じょうろん)を好むことなかれ。また悪口(あっく)をもて人を云い、怒目をもて人を見ることなかれ。(27頁)
■我をはなると云うは、我が身心をすてて、我がために仏法を学すこと無きなり。ただ道のために学すべし。
学道のひとは、吾我のために仏法を学すことなかれ。ただ仏法のために仏法を学すべきなり。
仏道に入りては、仏法のために諸事を行じて、代わりに所得あらんと思うべからず。内外(ないげ)の諸教に、みな無所得なれとのみ進むるなり。(29頁)
■およそ菩提心の行願には、菩提心の発未発、行道不行道を世人にしられんことをおもはざるべし、しられざらんといとなむべし。いはんやみづから口称(くしょう)せんや。(35頁)
■人にたっとびられじと思わんこと、やすきことなり。なかなか身をすて世をそむく由獲を以てなすは、外相(げそう)ばかりの仮令(けりょう)なり。ただなにとなく世間の人のようにて、内心を調えもてゆく、これ実(まこと)の道心者なり。(35頁)
■世のすえには、まことある道心者、おほかたなし。しかあれども、しばらく心を無常にかけて、世のはかなく、人のいのちのあやふきこと、わすれざるべし。われは世のはかなきことをおもふと、しらざるべし。あひかまへて、法をおもくして、わが身、我がいのちをかろくすべし。法のためには、身のいのちもをしまざるべし。(原かた仮名)(36頁)
■広学博覧――道元はきわめて博学である。そのことは、古くは面山や黄泉による『正法眼蔵』の引用出典の研究、さらに衞藤即応(同氏校註の『正法眼蔵』の「渉典」、岩波文庫)、鏡島元隆(『道元禅師の引用経典・語録の研究』、木耳社)、水野弥穂子(同氏校註の『正法眼蔵』の脚注・補注、岩波文庫)などの先学による研究からもわかる。道元は、当時の他の祖師たちとは比較にならぬほど本を読んでいる。しかもなお、「知らず」と答えてかまわぬ、といったのである。(44頁)
■参学識(し)るべし、仏道は思慮・分別・卜度(ぼくたく)・観想・知覚・慧解(えげ)の外に在ることを。もし此らの際(あいだ)に在らば、生来つねに此らの中に在りて、つねに此らを翫(もてあそ)ぶ、何が故に今に仏道を覚せざるや。学道は、思慮・分別等のことを用いるべからず。つねに思慮等を帯して、吾が身をもって検点せば、ここに明鑑なるものなり。(70頁)
■心とは身をもってする行動にある。したがって仏に習い、仏と同じく行じていく日常の生活の中に仏心が保たれていく、このように道元は信じていました。だが、唯心論においては、まさにその肝心な生を、無視すべきものとして放擲してしまっています、その点でそれは、そもそも出発点からして、根本的に誤っているのです。道元が心常相滅論に対し、「しめしていはく、いまいふところの見、またく仏法にあらず、先尼(せんに)外道が見なり」といい、また、「この一法〔仏法〕に身と心とを分別し、生死と涅槃とをわくことあらんや。すでに仏子なり、外道の見をかたる狂人のしたのひびきをみみにふるることなかれ」(「弁道話」)と、口を極めて批判しているのは、そのためなのです。(72~73頁)
■己見を捨てるとは、ものを知る規準と思い込んでいる心意識・知見解会を離れることです。そのとき初めて、身心(しんじん)一如であり、心とは行動の現われだということがわかってくる。このことを道元は、さまざまな言葉で繰返し語っています。『正法眼蔵』は、すべてこのことを語るものであったといってもいいのです。そかし道元はこれだけ言葉を用いて語ってはいますが、自分のいおうとしていることは、言葉のうえの理解だけでは、けっして伝えることのできないものと考えていました。それは結局は、各人の日常の修行において、その実践の中でしか、実感として理解することができないものでした。
『随聞記』によれば、道元は弟子たちに対して、「経(へ)ずんが見るべし、見ずんばきくべし」という古人の言葉を引き、この言葉の意味は、「きかんよりは見るべし、見んよりは経(ふ)べし」ということだと教えています。聞くよりは見よ、見るよりは身をもって体験せよ、ということです。道元は何よりも、日常の修行が大事だと説いています。そしてその中でも、身心一如、修証一等の悟りを得る仏道の「正門」は、祗管打坐(ひたすら坐禅に打ち込むこと)だと語りました。このことも如淨のもとで、坐禅によって悟りを得た、自らの体験にもとづいているのです。(76頁)
■この身体をめぐらして、十悪をはなれ、八戒をたもち、三宝に帰依して捨家出家する、真実の学道なり。このゆえに、真実人体といふ。後学かならず自然見の外道に同ずることなかれ。(身心学道)(43頁)
■その修行の処に証が現成(転法輪)するのだから、証は時空を超えて、いかなる処においても、いかなる時にも、それを見ることができる。といってもこれは、証はどこにでもあるというわけではない、その処在は、仏道を修行するものの身体に限られている。いまの汝も、いまのわれも、証の全世界を全身に脱落(とつらく)して修行しているのだ。このことをはっきり自覚して、学道するのである。(84頁)
■道元にとって、「尽十方界は、真実人体である」とは、証の全世界は修する身体にあることをいうのであり、この言葉は、修証一等を語る、もっとも明瞭な表現のひとつなのです。(84頁)
■ 仏教はすなはち教仏なり、仏祖究尽(ぐうじん)の功徳なり。諸仏は高広にして、法教は狭少なるにあらず。まさにしるべし、仏大なるは教大なり、仏小なるは教小なり。
ここで注意すべきことは、「仏」と「教」とが分けて語られている点です。仏とは仏心(証)をもつもののこと、教とは、仏が語り、身をもって説いた行法(修)のことです。道元は、この2つは同じ概念だ、といっているのです。大意は、――仏は行ずるとは、行ずるものが仏だ、ということである。このこと(修証一等ということ)は、これまでの諸仏の究め尽してきたところである。諸仏は高広であり、行法は教少なのではない。よくわきまえよ、仏が大なら、行法も大であり、仏が小なら、行法も小なのである。――(85頁)
■ 「ただ一心を正伝して、仏教を正伝せず」といふは、仏法をしらざるなり。仏教の一心をしらず、一心の仏教をきかず。一心のほかに仏教ありといふ、なんぢが一心、いまだ一心ならず。仏教のほかに一心ありといふ、なんぢが仏教、いまだ仏教ならざらん。
大意は――「これまでの諸仏は、ただ釈迦仏の一心を以心伝心によって伝えてきたのであり、仏の教えた行法を伝えたのではない」などというのは、仏法の何たるかを知らないのだ。行法が一心であり、一心が行法である!このことがわからず、一心のほかに行法があるなどという、その汝の一心なるものは、仏の一心といえるものではない。仏の教えた行法のほかに一心ありという、その汝の仏教は、仏教といえるものでは、けっしてない!――(88頁)
■ これを妙法蓮華教ともなづく、教菩薩法なり。これを諸法となづけきたれるゆえに、法華を国土として、霊山も虚空もあり、大海もあり、大地もあり。これはすなはち実相なり、如是(にょぜ)なり。
道元にとって、諸仏によって説かれてきた仏法とは、法華経であり、菩薩に教える行法だったのです。それを道元は、「諸法」といっているのです。「法華を国土として、全世界がある」とは、この諸法(法華)に従って修行していくところに、人間の世界を見ることができるということです。その世界が実相であり、如是(証とはこれだ、と確信できる世界)なのです。ここからもわかるように、道元が「諸法実相」というのは、「一切法一心」というのと全く同様に、修するところに証の世界を見ることを意味しているのです。(92~93頁)
■「諸法」とは、「教菩薩法」としての行法です。それがまた、「仏経」「経巻」などの言葉をもって語られています。その経巻に示された教えに従って修行するところに、実相の世界がある。だから道元は、経巻は仏心・証そのものだともいうのです。「仏経」の巻にあるいくつかの文章をみておきましょう。
仏経」〔巻名〕、このなかに教菩薩法あり、教諸仏法あり。おなじくこれ大道の調度なり。調度ぬしにしたがふ、ぬし調度をつかふ。これによりて、西天東地の仏祖、かならず惑従知識、惑従経巻の正当恁麽時、おのおの発意・修行・証果かって間隙(けんぎゃく)あらざるものなり。(93頁)
■ 三界〔すべての世界〕唯一心、心外無別法。
心、仏および衆生、この三無差別。
これは『華厳経』から引かれている語句であり、これまで多くの書において、すべては心の所産であるという、唯心論の根拠として用いられてきたものです。だが、唯心論とは正反対の立場に立つ道元も、この言葉を高く評価しているのです。すれは、「いま如来道の〔如来のいう〕三界唯心は、全如来の全現成なり。全一代は全一句なり」というところにも明らかです。釈迦仏のすべてがこの一句に示されている、と道元はいうのです。では、それはなぜなのか?――この句についての解釈が、唯心論者の解釈とは、全く違うものだったからです。道元は、この句を次のように読んでいるのです。
三界は全界なり。三界はすなはち心(しん)といふにあらず。そのゆえは、三界はいく玲瓏八面も、なほ三界なり。三界にあらざらんと誤錯すといふとも、総不著(ふじゃ)なり。内外中間、初中後際、みな三界なり。三界は三界の所見のごとし、三界にあらざるものの所見は、三界を見不正(けんふしん)なり。(155~156頁)
■ 古徳云く、「作麽生(そもさん)か、これ妙浄妙心。山河大地、日月星辰」。
この言葉について道元はいいます。
あきらかにしりぬ、心とは山河(せんが)大地なり、日月星辰(にちがつしょうしん)なり。しかあれども、この道取するところ、すすめば不足あり、しりぞくればあまれり。山河大地心は、山河大地のみなり。さらに波浪なし、風煙なし。日月星辰(にちがつしょうしん)のみなり。さらにきりなし、かすみなし。(162~163頁)
■「諸悪莫作、衆善奉行」とは、これを普通に読めば、「諸悪なすことなかれ、衆善奉行すべし」ということになりますが、「諸悪莫作」の巻にみられるように、道元はこれを「諸悪は莫作なり、衆善は奉行なり」という形に読んでいるのです。これは、「悪とは私たちがやってはいけないこととして慎み、戒めていることをもって言う、また善とは、私たちがよいこととしておこなっていることをもって言う」ということです。ここで道元は、このような読み方をふまえて、悪というものも、善というものも、私たちの生と無関係に、彼方の世界に存在している事がらではなく、私たちの生の現われだといっているのです。(216~217頁)
■ 曹谿山大鑑禅師、ちなみに南嶽大慧禅師にしめすにいはく、「是什麽物(しもぶつ)、恁麽来」。
この道(どう、言葉)は、恁麽はこれ不疑なり、不会(ふうい)なるがゆえに、是什麽物なるがゆえに、万物まことにかならず什麽物なると参究すべし。一物まことにかならず什麽物なると参究すべし。什麽物は疑者にはあらざるなり、恁麽来なり。
大意は、――慧能(六祖)が、あるとき南嶽に、「ここに何が来ているのか」と語った。この言葉は、眼前に見ているもの(恁麽)が証の世界であることは疑いない、といっているのだ。なぜなら、ここにあるのは、対象的に理解することのできない「不会」のもの、すなわち、自己の修行であり、「什麽物」だからである。万物は、かならず「什麽物」(修)の現成であると考えよ。一物も、また然りである。「什麽物」という言葉は疑問を語っているのではない。ここに現成している(恁麽来している)、修をいうのだ。――
道元のいう「什麽物」とは、何かを見て、それが何であるかわからず、その正体を見定めようとしているときの言葉ではなく、問の形によって、すでに眼前に現成し、そこに恁麽来している自己の修をいうのです。(218頁)
■「什麽物、恁麽物」とは、眼前に見る世界に現成しているのは何か、という問であり、そこで問われている「「什麽物(しもぶつ、なに物)」とは、修行のことなのです。道元にとってはこの修が、証の規準でした。とすれば、もしこの問に対して、自分がいま見ている世界は、これまでの自分の修の現成であり、「ここに来ているのは修だ」と答えることができるならば、そう答えるだけの自らの修行の裏づけがあるとすれば、いまここに見ているのは、「証の世界(仏性)だ」と言い切ることができるはずです。「仏性」の巻冒頭の段における、「すなはち悉有は仏性なり」という道元の言葉は、以上のような論理の結論に当る部分なのです。この点についてみていきましょう。
ここにはまず、釈迦仏の次の言葉が示されています。
釈迦牟尼仏言く、「一切衆生、悉有仏性。如来常住、無有変易(むうへんやく)」。
道元はこの言葉こそ、これまでの一切諸仏、一切祖師の参学の眼目を語るものだといっています。これは普通に読めば、「一切衆生はことごとく仏性を有す。如来は常住にして、変易あることなし」ということになりますが、道元はそれとは違って、「悉有仏性」というところを、「悉有は仏性なり」と読んでいるのです。その読みは次の文章に示されています。
世尊道の「一切衆生、悉有仏性」は、その宗旨(そうし)いかむ。「是什麽物、恁麽物」の道転法輪なり。あるいは衆生といひ、有情といひ、群生(ぐんじょう)といひ、群類といふ。
「悉有」の言(ごん)は衆生なり、群有なり。すなはち悉有は仏性なり。悉有の一悉を衆生といふ。(221~222頁)
■ 見物聞法の最初に、難得(なんて)難問なるは「衆生無仏性」なり。或従(わくじゅう)知識、或従経巻するに、きくことのよろこぶべきは衆生無仏性なり。「一切衆生無仏性」を見聞覚知に参飽せざるものは、仏性いまだ見聞覚知せざるなり。(230~231頁)
(2014年6月10日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元禅師語録』 鏡島元隆著 講談社学術文庫
■上堂して言われた。もし人があって、一句を言い得て全世界の無限の量をなくして一真実に帰せしめても、それはなお春の夜の夢の中で吉凶を説くようなもので、何の役にも立たない。また、もし人があって、一句を言い得て一微塵を破ってその中から無限の真理を説く経をとり出しても、それはなお紅白粉(べにおしろい)で美人を塗りたくるようなもので、余計なことである。そんなことよりも、その場でただちに夢でない真実の悟りの世界を照見しおわれば、全世界といっても大きくはなく、一微塵といっても小さくないことがわかる。さて、そのように上に述べた両句がともに真実でないとき、真実の一句は何と言ったものであろう。それは、井戸の中のひき蛙が天の月を呑み尽くし、天辺の月が雲の上で自由に眠る〔井底(せいてい)の蝦蟇(虫ヘンに麻)は月を呑却(どんきゃく)し、天辺の玉兎(ぎょくと)は自(おのずか)ら雲に眠る〕と言ったらよい。(41頁)
■上堂。僧問う、「如何ならんかこれ古仏心」。答えて云(いわ)く、「鶯啼く、処処同じ」。問う、「如何ならんかこれ本来の人」。答えて云(いわ)く、「脳肢の眼(まなこ)を蓋(おお)う漢(おとこ)」。師乃(すなわ)ち云く、問(もん)有り答(とう)有るは、屎尿狼藉(しにょうろうぜき)たり。問無く答無きは、雷霆霹靂(らいていびゃくれき)す。十方大地平沈し、一切虚空迸裂(へいれつ)す。外より入(い)るを放(ゆる)さず、一槌痛く下さば、万事了畢(りょうひつ)す。依前(いぜん)として鼻孔(びくう)、大頭(だいず)垂(た)る、一対の眼晴(がんぜい)、烏(う)律律。(45頁)
■上堂して言われた。いま修行僧諸君のなかに悟りを得たものがあるかな。すると、一僧が出て礼拝した。師が云われるには、おることはおるが、ただ不十分だ、僧が聞くには、何が足りないのです。師が云うには、言うではないか、といって古人の言葉を引いていわれた。悟りを得た人を知りたいと思うか。その人は、心に人を欺(あざむ)くものがないから、顔に恥ずる色がない。(48頁)
■僧海は数少ない、道元の付法(ふほう)の弟子である(『三祖行業記』)。道元は、彼の英才を愛し、嘱望していたが、不幸、二十七歳の若さで夭逝(ようせい)した。『永平広録』では、道元は彼の死を悼(いた)んで、二回も上堂している。本録上堂の後半の二句は、本録では「底に撤して汝に方(はじ)めて見(まみ)えん、還って忌(い)む見刺(けんし)なきことを」であるが、門鶴本『広録』では「底に撤して汝に見(まみ)ゆといえども、、胸に満てる涙、湖を鏁(とぎ)す」となっている。「胸に満てる涙、湖を鏁(とぎ)す」という言葉に、道元の悲嘆がいかに深かったかがわかる。同じように、最晩年の建長4年(1252)7月17日天童忌には、道元は先師を追憶して「恩を恋うる年月、雲何ぞ綻(ほころ)びん、涙袖衣(しゅうい)を染め、紅にて斑(まだら)ならず」(『永平広録』巻7)と報恩上堂している。如淨が示寂して25年後のことである。道元を評して、「非情なモラリスト」という人(戸頃重基氏)もあるが、弟子を思い、先師を憶う道元は、むしろ多感多情な涙の人というべきであろう。(52~53頁)
■上堂して云われた。人びとすべては、夜光の珠にも比すべき明珠(めいじゅ、仏性)を本来抱いているのであり、それぞれは荊山(けいざん)の玉にもたとえるべき宝珠(仏性)を本来蔵しているのである。それなのにどうして、回光返照(えこうへんしょう)してこれを覚(さと)らないで、せっかくの宝を抱きながら、迷うて他国にレイヘイしているのであるか。古人も言っているではないか。(仏性が)耳に応ずるときは、空谷(くうこく)が大きくこだまし、小さく叫べば小さくこだまするように、声に応じて現われないものはなく、(仏性が)眼に応ずるときは、千の太陽が照らせばどんなものでも隠れる余地のないように、眼に応じて現われないものはない。このように(仏性は)歴然として眼の前の対象に明らかに現われるものであるのにこれをはずして、そのほかに仏性を求めるならば、達磨西来(せいらい)の教えを大いにゆがめるものである。(59頁)
■仏性はあらゆるはたらき、あらゆるもののうちにあって、それをしてあらしめるものである。従って、それはこのわたしのうちにも、諸君のうちにもあって、わたしと諸君の間に寸毫の隔てもない。(71頁)
■明庵千光禅師権(ごん)僧正法印大和尚ー日本臨済宗の開祖栄西禅師のこと。明庵はその字(あざな)、千光禅師(法師)は入宋(にっそう)中に得た賜号(しごう)、権僧正は帰朝後宣下を受けた僧階。栄西の示寂は建保(けんぽう)3年(1215)7月5日。
師翁ー師の師。法の祖父のこと。栄西は道元の師事した明全(1184-1225)の師であるからいう。
虚庵(きあん)ー虚庵(きあん)懐敝(えしょう)(不詳)。臨済宗黄竜派の雪庵(せったん
)従謹(じゅうきん)の法嗣。栄西の入宋時は、虚庵(きあん)は天台山万年寺に住し、後に明州天童山の住持となる。(74頁)
■上堂。海に入りて沙(いさご)を算(かず)う、空(むな)しく自(みずか)ら力を費す。塼(かわら)を磨いて鏡と作(な)す、枉(いたずら)に工夫を用(もち)う。君見ずや高高たる山上の雲、自(おのずか)ら巻き自(おのずか)ら舒(の)ぶ。滔滔たる澗下(かんか)の水、曲に随(したが)い曲に随(したが)う。衆生の日用は雲水のごとし。雲水は自由なれども人は爾(しか)らず。もし爾(しか)ることを得(え)ば、三界(さんがい)の輪廻(りんね)、何(いずれ)の処(ところ)よりか起(おこ)らん。(74~75頁)
■八月一日上堂。公案をとりあげて言われた。趙州(じょうしゅう)和尚にある僧が質問した、「道を会得した人がお目にかかりに来たときは、どうなされますか」。趙州は云った、「漆塗りの道具を呈上しよう」。これについて、師が言うには、趙州古仏は、群をとび抜けたはたらきはあるけれども、平常語で話すはたらきがない。もし誰かがわたしに、道を会得した人がお目にかかりに来たときは、どうなされますか、と訊ねるものがあれば、ただそのものに言おう。八月(陰暦)の秋ともなれば、どこにも熱さはなくなる。平生(へいぜい)そのままでお目にかかるだけだ。(82頁)
■上堂。公案をとりあげて言われた。ある僧が趙州(じょうしゅう)に質問していうには、「狗(いぬ)に仏性があるでしょうか」。趙州がいうには、「ない」。僧がいうには、「一切衆生はみな仏性があるというのに、どうして狗(いぬ)にないのでしょう」。趙州がいうには、「それは、狗にものを分け隔てる分別の働きがあるからじゃ」。これについて、師は言われた。趙州のこのような学人指導は、まことに親切である。が、山僧(わたし)はちがう。もし山僧に狗(いぬ)に仏性があるかないか問うものがあれば、彼にいうであろう。あるというも、ないというも、いずれもまちがいであると。さらに、それはどういうことかと問うものがあれば、声もろとも棒で打とう。(87頁)
■懐義尼(えぎに)が亡くなったお母さんの供養のために上堂を請うた。そこで師が云われるには、生はどこから生まれてきたか、その由(よ)って来(きた)るところはない、ちょうど、寒くなれば上衣を着るように、時節因縁によって生まれてきただけだ。死はどこへ去るか、去って留(とど)まるところはない、あたかも、暑くなれば、ももひきをぬぐように、時節因縁によって死ぬだけだ。すべてのものは、本来空で一(いつ)に帰するが、その一も帰するところはない。結局、生は徹底生、死は徹底死であって、生と死がかわることはない、罪も福もみな空であってとどまるところはないのである。(89~90頁)
■上堂して云われた。仏法は、すべてのものとピタッと一つであって、その間に裂目はなく、すべてのものに明白な事実であって、蔽(おお)い隠されているものはない。それゆえに、この仏法を釈尊が摩訶迦葉(まかかしょう)に伝えたというも嘘であり、達磨がどうして慧可にこれを授けよう。いたるところに仏法を示す言葉が現われており、人びとすべてに般若の知見が具(そな)わっているのである。だからして、虚空が仏法を説くと、あらゆるものはこれを聞くのであって、人間の口を借りずによく仏法を挙揚(こよう)しているのである。それゆえに、諸君は一日中、眼に見るところ耳に聞くところすべて仏法の中にあり、古を超え今を超えていついかなる時も仏法の中にあり、自分といわず他といわず誰もが仏法の中にあり、迷っていようが悟っていようがすべて仏法の中にある。このことがわかるか。しばらくして言われた。趙州(じょうしゅう)が師の南泉にお目にかかったかと聞かれて鎮州(ちんしゅう)では大根ができると答えたのと、青原(せいげん)が仏とは何かと聞かれて廬陵(ろりょう)の米はいくらかと答えたのと、どっちがすぐれていよう。いずれも同じ趣旨である。(91~92頁)
■中秋上堂。雲開いて胡餅(こびょう、胡麻入りの餅)天辺(てんぺん)に掛く、喚(よ)んで中秋の夜月(やげつ)円かなりと作(な)す、睡(ねむ)り覚(さ)め起き来(きた)って覔(もと)むるに処(ところ)なし、頭(こうべ)を擡(もた)げて忽地(たちまち)に晴天を見る。(98頁)
■上堂して言われた。無心ということが仏であるとは、インドから起こったことであり、心がそのまま仏であるとは、中国から言われている言葉である。しかし、これを言葉どおり受けとるならば、仏法とは天地の隔りがあるが、この言葉どおり会得できなければただの凡夫である。結局、どうかというに、春三カ月を経て菩提樹の果が熟するのであり、一夜、その花が開くと世界中が芳(かんば)しい香りの世界になるのである。(109~110頁)
■教(『金剛経』)の中に、「一切の賢聖(けんしょう)は、みな無為法を体(たい)として、差別(しゃべつ)の用(ゆう)あり」と述べられている。さて、諸君は何を呼んで差別とし、何を呼んで無為法とするか。わたしは、諸君に言おう、差別されてある当のものが、無為法である、と。このように会得すれば、一人の修行のできた衲僧(のうそう)と云えよう。もし会得できないというならば、僧堂の内に粥もあれば飯もsる、さらに工夫するがよい。
〔付記〕変化・差別(しゃべつ)する相対的事象の外に、常住・平等な絶対の真理はない。(115~116頁)
■上堂。公案をとりあげて言われた。ある僧が巌頭(がんとう)和尚に質問した。「古い帆をまだ掛けないとき、つまり、ものの成立以前の世界とは、どのような世界でしょうか」。巌頭が答えて言った。「小魚が大魚を呑むことである。大小の対立を超えることだ」。師が言われるには、この公案の趣意を会得したいと思うならば、永平(わたし)の一頌を聞くがよい。巌頭のいう小魚、大魚を呑むとは、和尚が儒書を読むことだ。仏教とか儒教の対立を超えることだ。さらに、仏教とか外道の対立を超えて、仏教に対する執われもなくしてしまうことだ。
〔付記〕巌頭と僧の問答をとりあげて、仏法の真理は、仏教とか外道の対立を超えたものであり、仏法にさえ執われてはならないものであることを示す。(146頁)
■上堂。時節因縁は仏性なり。刹那、前後円成す、但(た)だ自ら長時(ちょうじ)に退歩すれば、乳中の酪(らく)、分明なり。(147頁)
■夏安居(げあんご)開始の前の晩の説法。公案をとりあげて言われた。慈航(じこう)和尚が四明山(しめいざん)の天童山に徃持した折の結夏小参に次のように言われた。「参禅する人は、まず第一番に鼻がまっすぐで、姿勢が正しくなければならぬ。次にものを見る眼がはっきりとして、知見が正しくなければならぬ。その次には、宗旨と説法といずれにも通暁していなければならぬ。かようであって、のちに人を導くはたらきがひとしく備わり、はじめて仏界にも魔界にも自由に出入し、自分をも多人をも平等に扱えるようになる。どうしてかというと、鼻がまっすぐで、姿勢が正しければ一切がみな正しいからである。ちょうど、人が家におる場合、その家の主人公が正しければ、それに仕えるものが自然と治まるようなものだ。では、どうしたら、鼻がまっすぐに、姿勢がただしくなるか。それについては、古聖(黄檗禅師)は『断じて心を第二念(分別心)に流れないようにせよ。ここにおいてはじめて仏法に入るであろう』と言われた。この古人の言葉は、一切の対立以前の世界に仏法があることを、諸君のために表示したものではないか」。これについて、師は言われた。古人は、「断じて心を第二念(分別心)に流れないようにせよ」と言われたが、諸君に敢えて聞くが、ではどれを指して第一念(無分別心)というのであるか。永平(わたし)は今夜喋るのを惜しまず諸君に言おう。90日の安居(あんご)は明日から始まる。規格外のことを行なってはならぬ。坐蒲の上に坐ってそのほかのことを一切顧みなければ、毎日毎日が一日じゅう、寂(しず)かで天下泰平な安らかな日暮らしができるのである。(149~150頁)
■冬至の晩の説法。長いあいだの苦節を経て一陽来復の佳節を迎えた。あらゆるものはその本に帰って、はじめてその真の姿を現わすのである。だからして、宏智(わんし)禅師も言っている。「全世界はほかでもない君自身の一つの眼であり、全世界はほかでもない君自身の光明であり、全世界は一つの悟りの世界である。どんなところであれ君が仏に成れないところはなく、どんなところであれ君が説法し人を救うところでないところはない。だからして、古人も言っているではないか。『釈迦が護明(ごみょう)菩薩として兜率天(とそつてん)より降下する前に、一輪の名月が十方を照らして、一切の衆生は救われている』と」。(154頁)
■12月30日、大晦日の晩の小参に云われた。小参というのは、仏祖の家訓である。わが国では、いままでに行なわれたことのないもので、永平(わたし)が始めてこれを伝えて以来、すでに20年経っている。達磨祖師がインドから中国へ来って仏法を中国へ伝えてよりこのかた、前代の祖師は小参を家訓といってきたのである。家訓というのは、仏祖の行ないでなければ行なわず、仏祖の法服(ほうぶく)でなければ身に著(つ)けないことである。さらに言えば、名利を抛(な)げ捨て、己我を捨て去り、山谷に隠れ住んで、叢林を離れずに、さしわたし一尺もある玉(たま)も貴(たっと)ばず寸陰も惜しんで、万事も顧みず純一に修行することで、これが仏祖の家訓であり、人間界・天上界の指標となるものである。
しかしながら、立派な善知識となることは三阿僧祇劫(さんあそぎごう)という無限の長時の修行によるのでなければ不可能のことである。大衆諸君よ、この無限の長時の修行とは何か、これをみたいと思うか、といって(師は)指をポンと一度弾(はじ)いて云われた。無限の長時の修行といってもこの一弾指(いちだんじ)にある。この一弾指はもとからあるものということができようか、いまここで修行されたものということができようか。そんなことはないのだ。ここのところがわかれば、時移り年変わって、12月が終って正月がくることがわかる。これがわかれば、十方の世界はみな断ちきられてわがものとなり、過去・現在・未来の三世の世界とも知らないうちに一つになる。12月が終って正月がくるといっても、実は旧(ふる)い年が去るのでもなく、新しい年がくるのでもなく、くる年は去る年の連続ではなく、新年は新年として、旧年は旧年としてそれぞれ絶対である。それゆえに、この道理を古人は次のように示している。ある僧が石門和尚に、「一年の最終日にはどうしたらよいでしょう」と尋ねたところ、石門は「東村の王老人が夜、紙銭(しせん)を焼くことだ」(大晦日には大晦日の行事を行なう)と答えた。同じ僧が、開先(かいせん)和尚に「一年の最終日にはどうしたらよいでしょう」と尋ねたところ、開先は「いままで通り春を迎えてもあいかわらず寒い」(正月を迎えても何も変わったことはない)と答えた。今夜、もし諸君のうちに誰かが永平(わたし)に、一年の最終日にはどうしたらよいでしょう、と問うものがあれば、わたしはそのものに答えよう。前方の村々は深い雪の中にあるが、昨夜の梅の花が一枝咲いたぞ、と。寒い時候に長いあいだ立ってご苦労。(157~158頁)
■禅人に示す 近来仏道修行するものは、本ものと贋(まが)いものを弁別せず、豆と麦とを区別せずに、仏法をきわめようとしているが、それでは仏法をきわめることが、まことに困難なわけである。どうしてかというに、古者(法昌倚遇(ほうしょういぐう))は次のように言っている。「大地に雪いっぱい積もれば、春になっても依然として寒い。そのように悟りを得ても、雪が降れば寒いのは、悟らぬ前と同じである。だから、つまるところ、悟ることは易しいが、悟りの境涯を説くことはむずかしい」と。こういう誤りは、仏祖といえどもなお免(まぬか)れないところである。どうして免かれないかというと、悟ることは易しいが、悟りの境涯を説くことはむずかしいとか、悟りの境涯を説くことは易しいが、悟ることはむずかしいとか、そんなことをいう手合いの仏法の難易は、情識の上の難易を脱(まぬが)れないのだ。よくきくことではないか。ある僧が雲門に質問した。「樹が枯れ、葉が落ち尽くすとは、どういうことでしょう」。雲門は答えた。「秋風がその本性を現わすことだ」。この雲門の言葉を、仏照禅師はとりあげていうには、「さすがの雲門和尚も備えつけの品で、仏法を示す人情に堕した」と。しかし、この仏照禅師の拈提(ねんてい)は、病のないのに薬を施す余計な口だしである。
釈尊がこの世に出られた理由は、すぐれた医者となることであった。釈尊は、衆生が深く苦海に沈んでいるのを憐んで慈悲の念を起こし、種々の方便をもって一大蔵経を説法されたが、これはみな衆生の病いに応じて薬を与えたものであり、一切衆生に大安楽をもたらすために処方箋を書いて与えたものである。ところが、達磨が西来(せいらい)するにおよんで、その子孫はみな劇薬を用いるようになり、病人を一旦気絶させ、後に甦らせる手段を用いるようになった。なるほど、これは不老不死の妙薬のように、効き目は多いにちがいないが、正しい眼からみれば、立派な肉体にわざわざ傷をつけるようなものである。もし本当の手段から言えば、そうではない。処方箋も書かないし、脈もみないで、目でみただけ一目でわかり、臨機応変の処置をとるのである。よしんば相手が仏病祖病のような病いであっても、軽々しくひとにぎりで済ますようなことはしないで、そのもののすべての骨を換え腸を洗って、仏祖に対する執(とら)われを洗い流して、身も心も浄らかに爽やかにさせずにはおかないのである。従って、これ一つですべての病いを癒すのであり、あれこれの処方箋を必要としないのである。ただ、釈迦老漢自身の病いは、諸人の病いとは異なり、全身が病いで、病いのもとはどこから起こったかわからないから、衆生の病いが癒らないかぎり癒しようがないのである。不灯都正(ふとうとしょう、人名)はこのように種々の病いに処する作略をよくご存じであるから、よく眼をつけて看ていただきたい。もしこのへんのことをよく見究められれば、古の名医である扁鵲廬医(へんじゃくろい、春秋戦国の名医)も、すべて下(しも)座について仰ぎみるであろう。(163~164頁)
■諸仏のの大道は深く勝(すぐ)れて思議を超えたものであるから、仏道修行者はどうしてたやすく考えてよかろう。よくみるがよい、古人はいのちを捨て、国や妻子を捨て、これらをみること瓦や石ころ同然であったのである。そうして後、長い長いあいだ、独りで山林に住み、身心を枯木のようにして、始めて仏道と一つになったのである。このように仏道と一つになったからこそ、山川を借りて仏法を示す言葉とし、風雨をとりあげて仏法を語る言葉とし、虚空を説き破ってこの上もなくすぐれた仏法を示すことができたのである。このようであれば、どんなものでも仏法を示すに用いられないものはなく、どんなことでもいけないことはない。仏法に志すものは、このような古人のお手本に従わなければならない。
昔、ある僧が方眼(ほうげん)禅師に尋ねた。「古物とはどういうものでしょう」。法眼は言った。「いまここにあるお前、それが古物であることに何の疑いもないぞ」。僧がまた尋ねた。「ならば、一日じゅうどのように行なったらよいでしょう」。法眼はいった。「一歩一歩、踏みしめよ」と。法眼はまた言っている。「出家人たるものは、そのときどきの時節に従うがよろしい。寒いときには寒がり、暑いときには暑がるのだ。仏の言われるように、『仏性ということを知りたいならば、時節因縁を観よ』とあるとおりだ。ただ、時節を守り、時節に従うだけだ」と。子細にこの言葉の意味を参究するがよい。時節に従い、時節を守るとはどういうことかというに、それは、ものの上において、ものでないとみてはならない。かといって、ものであるとみてもならない。また、ものであってものでないとみてもならない。このようであれば、自分が古仏であることに何の疑いもなくなり、他の古仏と同じく住し、同じく行ずることは、2つの鏡が互いに照らし合うようなものである。(167~168頁)
■よくよく考えてみるに、仏道は元来すべての人にまどかに行きわたっているものであるから、どうしてあらためて修行や証(さとり)を必要としよう。仏法は誰でも自由に使いこなしているいるものであるから、どうしてさらにそれを得ようと工夫することがあろう。ましてや仏道の全体は、迷いや汚れをはるかに超えたものである。どうしてこれを払いのける手段を要しよう。すでに仏法の究極は、いまここに現われているのである。どうしてこれをめざして修行を進めることがあろう。
だが、ほんのわずかでも、そこをとりちがえると、仏道とは天地の隔たりを生むのであり、いささかでも誤まりが起こると、それからそれへと迷いが出てきて本来の心を失ってしまう。のである。だからして、たとい仏教の教えを会得して、その理解に大いに誇るべきものがあっても、わずかに悟りの境涯を垣間みる智慧を得ただけのことであり、仏道を究め心地を明らめたといっても、天をも衝(つ)く気概を揚げるだけのことである。それらは、仏道の入り口あたりをぶらつく境地を得たにしても、それはなお悟りの境地に執(とら)われて、それから脱(ぬ)け出る生きたはたらきをどれほど失ったものであることか。ましてやかの祇園精舎で説法された釈尊は、生まれながらにして悟りを得られた方であったが、なお端坐6年の修行をされたのであって、その跡かたは今日ねお見ることができる。また、達磨大師は嵩山(すうざん)の少林寺にあって、二祖慧可に仏法を伝えられたが、面壁9年、修行された名声は今日ねお言い伝えられている。釈尊・達磨のような古(いにしえ)の聖人であっても、すでにこのように修行されたのである。今の時代のわれわれがどうして修行しないでよかろう。だからして、言葉の跡を尋ねまわる探索はやめて、一歩自分に振り返って、自分を凝視(みつ)める内省をしなければならない。このような自己内省をしてゆくとき、体や心に対する執(とら)われがおのずから脱(ぬ)け落ちて、本来の面目が現われるのである。このような本来の面目を得たいと思うならば、何をおいてもそれを現前せしめる坐禅に努めなければならない。(171~172頁)
■仏道の坐禅は禅定(ぜんじょう)修行ではない。禅定修行は苦行であるが、仏道の坐禅は安楽の教えであり、禅定修行は悟りへ向っての道であるが、仏道の坐禅は悟りを究め尽くした修証である。この坐禅の上に現われる絶対の境地は、いままで自分を縛っていたあらゆる分別の網の届かない世界である。それゆえに、もしこの境地を得れば、竜が水を得るように、虎が山によるように、人は人の本来のあり方に落ちつくのであって、そこに正しい仏法がおのずから現われて、心が暗く沈んでいく動きや、明るく浮き上がる動きは、自然と消え失せてしまうのである。(177頁)
■ 大道は従来一実に通ず、蓬瀛(ほうえい)何ぞ必ずしも壺中にあらん、逍遥たる世外(せがい)誰(た)れ人(びと)か識(し)らん、赤肉団辺(しゃくにくだんぺん)に古風を振う。〔偈頌(げじゅ)、文本(ぶんぽん)官長の韻に和す〕
〔訳文〕仏祖の大道は本来、一本の真実に貫かれている。その究極の世界はどうして世間を超えた別世界にあろう。はるか彼方の世間を超えたところなど、誰も知りはしないのだ。素裸(すはだか)のこの肉身、これぞ仏祖の古風を振うところ。(196頁)
■ 西来(せいらい)の祖道我れ東(ひんがし)に伝う、月を釣り雲を耕して古風を慕う、世俗の紅塵(こうじん)飛んで到らず、深山雪夜(しんざんせつや)草庵の中(うち)。〔偈頌(げじゅ)、山居(さんご)六首(1)〕(201頁)
■ 三秋(さんしゅう)の気粛(しずか)なり清涼の候(こう)、繊月(せんげつ)叢中(そうちゅう)万感(ばんかん)の中(うち)、夜(よ)静かに更(こう)闌(た)けて北斗を看(み)れば、暁天将(まさ)に到らんとして東(ひんがし)を指す。〔偈頌(げじゅ)、山居(さんご)六首(4)〕
〔訳文〕秋三ヶ月の空気が澄んで清涼の季節。空には三日月、草むらには虫が鳴いてさまざまの思いが胸に迫る。その中を夜が静かにふけ、時が経ち、ふと北斗七星を見ると、まさに明けようととする夜空に星は東を指して落ちてゆく。(203~204頁)
(2014年8月30日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元ーその行動と思想ー』 今枝愛真著 評論社
■学問がすすむにつれて、鋭敏な道元は、天台の伝統的な教学に、反撥と疑問をいだくようになった。そして、いつしか道元の心には大きな疑問が立ちはだかった。出家してから、道元が出逢った最大の難問である。と同時に、それは道元の将来を決定する重要なわかれみちでもあった。
本来本法性(ほっしょう)、天然自性(しょう)身。
これまで、天台宗などの諸宗は、一切の衆生はもともと仏性をもっているという本覚思想、すなわち、人はもともと仏であると教えている。しかし、もしそうだとすれば、過去・現在・未来の三世の諸仏諸祖は、なぜ発心して修行する必要があると説くのであろうか。なぜ、われわれは修行を実践しなければならないのか。それにはそれ相当の理由がなければならないが、果してそれは何であろうかという、根本的な疑問が、道元の前に大きく立ちはだかったのである。(28~29頁)
■このとき道元は、かってシン(王ヘンに進)という一老僧から、長翁山の如淨こそ大宋国裏における唯一最高の具眼の道人であるから、もし仏道を本格的に学ぼうと思うならば、一度参じてみるがよい、と勧められていたことを思い出した。そこで道元は、ふたたび天童山に赴いて、同寺の31世となっていた如淨に拝謁(はいえつ)し、その刹那に、如浄から面授をうけることができたのである。道元はこのときのことを
大宋宝慶元年乙酉五月一日、道元、はじめて先師天童古仏(如淨)を(天童山)妙高台に焼香礼拝す。先師古仏、はじめて道元をみる。そのとき、道元に指授面授するにいはく、仏仏祖祖面授の法門、現成せり。(面授)
とのべている。こうして道元は、「やや堂奥を聴許せらる、わづかに身心を脱落する」ことができたのである。(67頁)
■はたして道元は、如浄と会ったその瞬間に、これこそ長年探し求めていた正師であることを発見して、無上の感激に打ちふるえた。いっぽう如淨も、初見において、道元が非凡の大器であることを看破し、仏門の法門ここに現成す、と証明を与えたのである。まさに、この相見によって、入宋の目的の大半は成就されたといってよい。こうして、この相見は日本の不世出の宗教家道元を生み出す決定的な機縁となったのである。道元は、このときの感激について、
いま現在、大宋国一百八十州の内外に、山寺あり。人里の寺あり。そのかず称計すべからず。そのなかに雲水おほし。しかあれども、先師古仏(如淨)をみざるはおほく、みたるはすくなからん。いはんや、ことばを見聞するは少分なるべし。いはんや、相見問訊(もんじん)のともがらおほからんや。堂奥をゆるさるるは、いくばくにあらず。いかにいはんや、先師の皮肉骨髄、眼晴面目を礼拝することを聴許せられんや。先師古仏、たやすく僧衆の討掛搭(かた)をゆるさずー中略ーこのくにの人なりといへども、共住ををゆるされざる。われなにのさいはひありてか、遠方外国の種子なりといへども、掛搭(かた)をゆるさるるのみにあらず、ほしきままに堂奥に出入りして、尊儀を礼拝し、法道をきく。愚暗なりといへども、むなしかるべからざる結良縁なり。(『梅華』)
とのべている。このとき、如浄は道元に対して、
仏仏祖祖面授の法門現成せり。これすなはち、霊山の拈華(ねんげ)なり、嵩山の得髄なり、黄梅の伝衣なり、洞山の面授なり。これは仏祖の眼蔵面授なり。吾屋裏のみあり。余人は夢也未見聞在なり。(『面授』)
といって、霊鷲山における釈尊と迦葉との拈華微笑、嵩山での達磨と二祖慧可の得髄、黄梅山における五祖弘忍の六祖慧能への伝衣、雲岩曇と洞山良价の面授など、禅宗でもっとも代表的な付法面授にくらべている。そこには、単なる相見(しょうけん)ではなく、釈尊から伝えられてきた仏仏祖祖の面授証契が両者の間で行なわれたことが知られるであろう。(70~71頁)
■ところが、道元が如浄に参じてまもない宝慶元年の夏安居(げあんご)中の五月二十七日、明全が天童山の了然寮で亡くなった。ときに明全は、まだ四十二歳の壮年期であった。これよりさき嘉定十六年、明全は上陸後、まず明州の天台寺院である景福寺に住持の妙雲講師を訪れている。栄西にならって、日本の天台宗を修正しようとして入宋した明全にとって、これは当然の行動であった。ところが、すでに天台宗はまったく衰えてしまっていて、ほとんど学ぶべきものがなかった。それにひきかえ、いまや禅宗が江南の地を蔽っていたのである。そこで明全は禅を本格的に学ぶために、師の栄西がかって禅を学んだことのある天童山に登り、すでに三年に及んでいたのである。建仁寺において師事してから幾星霜、しかも万波の苦難を越えて、ともに入宋しながら、雄図むなしく異国に果てた師の姿を見て、道元の心中はいかばかりであったろうか。しかしながら、師の明全からすれば、日本の生んだ希有の宗教的天才である教え子の道元が、ようやく如淨という本師にめぐり逢えたのを見て、日本仏教の輝かしい将来を夢見ながら、この世を去ることができたのは、せめてものなぐさめであったであろう。(71~72頁)
■おなじ夏安居中のことである。道元は三十三祖の変相画を拝するために、ふたたび阿育王山を訪れた。このとき道元は、西蜀出身で接客係の成桂知客と、廊下を歩きながら、いろいろ問答をかわした。しかし、変相画に関する道元の考えは成桂をはるかに超え、成桂は道元の提出する問いに充分答えることができなかった。
「這箇(しゃこ)はこれ什麽(なに)の変相ぞ」と道元が問うと、成桂は「竜樹の身、円月相を現ず」と答えた。そこで道元は、「這箇(しゃこ)はこれ一枚の変画餅に相似たり」といったが、成桂はただ大笑するのみであった。道元は、成桂が竜樹の円月相の図のなかに、画そのものを超えた形而上的なものを見ていないことを見破って、「笑裏に刀なく、画餅を破ること得ざるなり」と評している。このほか、問答数番に及んだが、なんら得るところがなかった。もちろん他の僧たちも、ほとんど道元の敵ではなかった。そこで道元は、徃持の晦岩大光に質問してみようとしたが、成桂が和尚も答えられないであろうというので、道元も思い止まったという。五山の阿育王山でさえ、このような状態であったから、宋朝の禅林においていかに人材が乏しかったかが知られよう。それにしても、阿育王山に参じて、はじめて三十三祖の変相図を見たとき領会できなかった道元が、二年たったいまは、山内に一人も具眼の達人がいないことを見破ってしまったのである。この一事によっても、いかに道元の進境が著しかったかがわかるであろう。(『仏性』)
やがて同年九月十八日、釈尊から嫡伝されてきた仏祖正伝菩薩戒脈を如淨から授けられ、道元は名実ともに、如浄の弟子となった。こうして、如浄の正式の門弟となった道元の声望は、天童山の内外にいよいよ高まっていった。(『光福寺文書』)(72~73頁)
■このように、天童山で修行していた宝慶三年のある日の早暁のこと、如淨は、坐禅の指導中に、一人の修行僧が坐睡しているのをみて、身心脱落、すなわち、一切の執着を捨てて、全身全霊を打ち込んで坐禅しなければならないのに、睡魔に犯されるままに眠ってしまうとは一体何事であるかと、大喝一声した。かたわらで坐禅に熱中していた道元は、これを聞いて、豁然と大悟し、悟脱の境地に達することができた。
さっそく道元は、方丈に赴いて、如浄に焼香礼拝した。様子がただ事でないのをみて、如浄は一体何があったのかとたずねた。これに対して道元が、身心脱落することができたので参りましたというと、これを聞いた如浄は、身心脱落、脱落身心と、道元が真に大悟徹底したことを認めたのである。ここに道元は、身心を脱落することによって、出家以来の長年の疑問を解決し、入宋の目的を達成することができたのである。しかも道元は、このような体験だけに止まらないで、いよいよ、その思索をすすめ、それを修行生活の中で実証しようとしたのである。(『永平寺三祖行業記』)
ところで、この身心脱落について、かって如浄が、
参禅ハ身心脱落ナリ。焼香・念仏・修懺(しゅせん)・看経(かんきん)ヲ用ヒズ。祗管(ひたすら)ニ打坐(たざ)スルノミ。(原漢文)
と、道元に説示した。このとき道元は、それでは身心脱落というのは一体何ですかとたずねた。すると如浄は、これに答えて、
身心脱落ハ坐禅ナリ。祗管ニ坐禅スル時、五欲ヲ離レ、五蓋(いかりなどの五つの煩悩)ヲ除クナリ。(原漢文)
といった。そこで、道元が、五欲を離れ、五蓋を除くというならば、それは禅だけではなく、禅宗以外の教宗の所説と同じではありませんか、というと、大乗だ小乗だといって、そのいずれの所説もけぎらいしてはならない、釈尊の教えにそむいて、どうして仏祖の児孫といえようか、と如浄はたしなめ、
祗管ニ打坐シテ功夫ヲ作シ、身心脱落シ来ルハ、乃チ五蓋五欲等ヲ離ルルノ術ナリ。コノ外ニスベテ別事ナシ。
と言っている。(『宝慶記』原漢文)
このようにして、道元は身心脱落を禅宗で一般にいう大悟徹底とか悟りにあたるものと把握し、その著作の中に、しばしばこれを引用している。いかに身心脱落という言葉に重きを置いていたかがわかるであろう。
ところが、身心脱落という言葉を、如浄は一度も使っていない。ただ、語録の偈の中に、一回だけであるが、「心塵脱落」という言葉が出ている。してみると、道元がしばしば用いた身心脱落という表現は、如浄の心塵脱落を道元流に解釈することによって、これに参学の大事を了畢するという、独自の深い意味を持たせたように思われるのである。(高崎直道・梅原猛『仏教の思想』十一古仏のまねび〈道元〉)(75~77頁)
■このような嗣法に対する考えは、如淨から受けついだものであろうが、道元は何から何まで如浄の思想を単純に祖述していたわけではなかった。釈尊から迦葉仏というように、「仏仏相嗣していまにいたる」という如淨の解釈に疑問をもった道元は、迦葉仏がなくなったあとに釈尊が出世成道しているのに、その間に嗣法がどうしてありえましょうか、と質問した。これに対して如浄は、
なんぢがいふところは、聴教の解なり。十聖三賢等のみちなり。仏祖嫡嫡のみちにあらず。わが仏祖相伝のみちはしかあらず(―中略―)釈迦牟尼仏は迦葉仏に嗣法すると学し、迦葉仏は釈迦牟尼仏に嗣法せりと、学するなり。かくのごとく学するとき、まさに諸仏諸祖の嗣法にてあるなり。(『嗣書』)
と教えた。如浄のいう嗣法というのは、単なる師弟間の嗣法のやりとりではなく、釈尊は迦葉仏によって嗣法し、迦葉仏も釈尊によって悟り嗣法したという解釈に立っている。そこには、過去から未来にかけて道環した法の嗣承が行なわれている。各種の嗣書を秘見し、嗣法と嗣書のあるべき姿を探究していた道元は、ここに、仏祖の嗣法の理想を見出したのである。このようにして、正師である仏仏祖祖によって脈々と伝えられてきた、仏祖の命脈である正法を、単に観念の上でなく、実証によって相嗣し、これを継承することによって、仏道の極意に達し、従来の疑問はすべて解消することができた、という自負心をもつにいたった。もはや中国にながく止まる必要はまったくなかった。あとは如浄からうけた釈尊の正法を日本に持ち帰るだけである。((79~80頁)
■如浄から仏法の神髄を学んできたという確信をもって、かれ一流の正法宣揚の意欲に燃えて、故国の土をふんだ道元は、比叡山や三井寺にはもどらないで、まず、建仁寺に身をよせた。もはや、かれは何をなすべきかを考えるまでもなかった。このころの道元は、正法宣揚と衆生済度の熱意に燃えていたからである。
それよりのち、大宋紹定のはじめ、本郷にかえりし。すなはち、弘法救生をおもひとせり。なほ、重担をかたにおけるがごとし。(『弁道話』)
という彼の述懐には、その心境がよくあらわれている。
こうして道元は、如浄から伝えてきた仏法こそ、釈尊からうけつがれてきた「仏祖単伝の正法」であるという確信をもって、かれ一流の正法禅護持の精神をつよく打ち出すにいたった。
ついで彼は、この「仏祖単伝の正法」こそ、坐禅によるものでなければならないとして、このころ『普勧坐禅儀』を著わしたのである。
したがって、この坐禅儀は、道元帰国の第一声であるとともに、道元の坐禅に対する基本的な考え方を内外に表明した、いわば、禅の独立宣言ともいうべきものであった。(83~84頁)
■さらに、坐禅は「大安楽法門」であるとのべ、その真意を会得すれば、精神爽快、竜が水を得、虎が山によるような偉大な法力が得られる、と説いている。そればかりではない。さらに注目されるのは、法然上人が本願念仏を勝なるもの易なるものとして選択したように、道元は、禅の宗を最勝最高のもの、しかも、上智下愚、利人鈍者を問わない、誰にでもひろく実践できる易行として選択したことである。
しかも、道元は坐禅儀の上に、とくに普勧という二字を冠している。あまねく勧めるというのは、出家仏教という限られた意味でなく、道俗一般にすすめる伝道宗教としての性格を表明したものにほかならない。
このように、『普勧坐禅儀』の撰述は、道元の開宗宣言であった。(86~57頁)
■ついで、さきに『普勧坐禅儀』において、坐禅の根本義を説き、坐禅は大安楽の法門だから、賢愚の差別なく、誰にでも勧めるのだといった道元は、さらに、『辨道話』において、坐禅にかんする十九の設問をかかげ、一々その疑問に答える形式で、只管打坐の仏法について、その抱負と信念を強調した。(91頁)
■仏法に入るには、多くの門があるが、坐禅こそ仏法の正門である。それは、釈尊以来の諸仏はもな坐禅によって得道したからだとして、
大師釈尊、まさしく得道の妙術を正伝し、また、三世の如来ともに、坐禅より得道せり。このゆえに、正門なることをあひつたへたるなり。しかのみにあらず。西天東地の諸祖、みな坐禅より得道せるなり。ゆえに、いま正門を人天にしめす。
とのべ、坐禅以外の諸行は、悟りにいたる一つの方便ではあっても、仏法の真の要訣ではありえないとして、世行一切をしりぞけ、もっぱらに坐禅すべきことを強く主張した。そして、坐禅は只管打坐でなければならないと説いた。(92頁)
■道元の主著である『正法眼蔵』をみると、『碧巌録』からの引用をはじめとして、いたるところで公案の論評を行なっているばかりでなく、公案の否定をしたような個所はどこにも見当たらない。したがって、道元のいう「ひとへに坐禅」とか、只管打坐というのも、従来いわれているような、公案禅・看話禅の全面的な否定を意味するわけではなく、「純一の仏法」、つまり坐禅にによる正伝の仏法を強調するあまり、宋朝風の公案禅の行過ぎを手きびしく批判しようとしたところから発したものであろう。(95頁)
■人によっては、修と証は一つではないと考えているものがあるが、それはあきらかに外道の考え方である。ほんとうは、修行そのままで証であるという修証一如の立場でなければならないとした。さらに道元は、言葉をつづけて、次のようにいっている。
いまも証上の修なるゆえに、初心の辧道、すなはち、本証の全体なり。かるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれ、とをしふ。直指の本証なるがゆえなるべし。すでに、修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。(97頁)
■魚が水を行き、ゆけども水のきは(際)なく、鳥そらをとぶに、とぶといへども、そらのきはなし。しかあれども、魚鳥いまだむかしよりみず・そらをはなれず(―中略―)鳥もしそらをいづれば、たちまちに死す。魚もし水をいづれば、たちまちに死す。以水為命、しりぬべし。以空為命、しりぬべし。
魚が水を行き、鳥が空を飛ぶという、この自然の法則にのっとって、そのところを得、みちを得れば、たちどころに悟ることができるとも説いている。
あるとき、麻谷(まよく)山の宝徹が扇子を使っているところへ僧がやってきて、仏教の説くところによると、風の性は常住であって、どこにもないところはないということですが、なぜ和尚は扇子を使っているのですか、と質問した。そこで、宝徹は言った。貴公は風性常住ということはわかったらしいが、どこにでもないところはないということは、まだ判っていないようだと。そこで僧は、それでは、どこにでもないところはないというのは、どういう訳ですか、と尋ねた。ときに、宝徹は、無言で扇子をあおぐのみであった。僧は黙して礼拝した。この話をあげて、道元は、
仏法の証験、正法の活路、それかくのごとし、常住なれば、あふぎをつかふべからず。。つかはぬをりも風をきくべきといふは、常住をもしらず、風性をもしらぬなり。(『現成公按』)(108頁)
■名利ノタメニ、仏法ヲ集スベカラズ。果報ヲ得ンガタメニ、仏法ヲ修スベカラズ。霊験ヲ得ンガタメニ、仏法ヲ修スベカラズ。タダ仏法ノタメニ仏法ヲ修ス。スナハチ、コレ道ナリ。(原漢文)
と、仏道修行の姿勢をのべ、さらに、参禅のためには正師(しょうし)を求めるべきで、もし、
正師ヲ得ザレバ、学バザルニ如カズ。ソレ正師トハ、年老耆宿ヲ問ハズ。タダ正法ヲ明ラメテ正師ノ印証ヲ得ルモノナリ(―中略―)行解(ぎょうげ)相応スル、コレスナハチ正師ナリ。(―中略―)参禅学道ハ一生ノ大事ナリ、ユルガセニスベカラズ。(原漢文)
と、思想と実践のともなった本当の正師でなければ、正しい悟りの道への指導者とはなりえない、と断言している。そこには、衆生の教化に全力を傾注しようとしている道元の旺盛な意欲が充分にうかがわれよう。(109頁)
■さらに仁治3(1242)年4月5日、求道心に燃えていた道元は、『正法眼蔵』中の最大の山の一である『行持』の巻を著わしている。
仏祖の大道、かならず無上の行持あり。道環して断絶せず。発心・修行・菩提・涅槃、しばらくの間隙あらず。行持道環なり。このゆえに、みづからの強為にあらず。佗の強為にあらず。不曾染汙の行持なり(―中略―)このゆえに、諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成し、諸仏の大道通達するなり。われらが行持によりて、諸仏の行持見成し、諸仏の大道通達するなり。われらが行持によりて、この道環の功徳あり。これによりて、仏仏祖祖、仏住し仏非し、仏心し仏成して、断絶せざるなり。(『行持』)
このように、道元の新宗教の理想は、道環して断絶しない、仏祖のもっともすぐれた行持〈不染汙の行持〉を実践すること、これを日々の行持に自然に現わすことであった。
そこで、このような仏法の理想を求めつづけた道元は、
いま、仏祖の大道を行持せんには、大隠小隠を論ずることなく、聡明鈍痴をいふことなかれ。ただ、ながく名利をなげすてて、万縁に繋縛せらるることなかれ。光陰をすごさず、頭然(ずねん)をはらふべし。大悟をまつことなかれ。大悟は家常の茶飯(さはん)なり。不悟をねがふことなかれ。不悟は髻(けい)中の宝珠なり。ただまさに、家郷あらんは家郷をはなれ、恩愛あらんは恩愛をはなれ、名あらんは名をのがれ、利あらんは利をのがれ、田園あらんは田園をのがれ、親族あらんは親族をはなるべし。名利等なからんも、また、はなるべし。すでに、あるをはなる。なきをもはなるべき道理、あきらかなり。それすなはち、一条の行持なり。生前に名利をなげすてて、一事を行持せん、仏寿長遠の行持なり。いまこの行持に行持せらるるなり。この行持あらん。身心みづからも愛すべし、みづからもうやまふべし。(『行持』)
と、名利をはじめ万縁をなげすて、自己の身命をも顧ることなく、仏祖の大道を行持することによって、はじめて大悟の域に達することができる、と説いた。(143~145頁)
■そこで道元は、このような仏祖の大道を行持するためには、日々の工夫こそもっとも肝心である、と強調している。すなわち、
仏祖の面目骨髄(―中略―)かならず一日の行持に稟受するなり。しかあれば、一日はおもかるべきなり。いたづらに百歳いけらんは、うらむべき日月なり。かなしむべき形骸なり。たとひ百歳の日月は、声色の奴婢と馳走すとも、そのなか、一日の行持を行取せば、一生の百歳を行取するのみにあらず、百歳の佗生をも度取すべきなり。この一日の身命は、たふとぶべき身命なり。たふとぶべき形骸なり。かるがゆえに、いけらんこと一日ならんは、諸仏の機を会せば、この一日を曠劫(こうごう)多生にもすぐれたりとするなり。このゆえに、いまだ決了せざれんときは、一日をいたづらにつかふことなかれ。この一日は、をしむべき重宝なり。(『行持』)
と、一日一日の行持こそ重要な意義をもっていると警告し、つづけて、一日の価値はどんな宝石にもくらべられるものではない、いったん失えば永久に取りかえしがつかないとして、
尺壁の価値に擬すべからず、驪珠にかふることなかれ。古賢をしむこと、身命よりもすぎたり。しずかにおもふべし。驪珠はもとめつべし、尺壁はうることもあらん。一生百歳のうちの一日は、ひとたびうしなはん、ふたたびうることなからん。いづれの善功方便ありてか、すぎにし一日をふたたびかへしえたる。紀事の書にしるさざるところなり。もし、いたづらにすごさざるは、日月を皮岱に包含して、もらさざるなり。しかあるを、古聖先賢は、日月ををしみ、光陰ををしむこと、眼晴よりもをしむ、国土よりもをしむ。その、いたづらに蹉過するといふは、名利の浮世に濁乱(じゅくらん)しゆくなり。いたづらに蹉過せずといふは、道にありながら、道のためにするなり。すでに決了することをえたらん。また、一日をいたづらにせざるべし。ひとへに道のために行取し、道のために説取すべし。このゆえにしりぬ。古来の仏祖、いたづらに一日の工夫をつひやさざる儀、よのつねに観想すべし。(『行持』)
と、日々寸陰を大切に過すべき心構えを繰返し説いている。
さらに、
いま正法にあふ。百千恒沙の身命をすてても、正法を参学すべし(―中略―)しづかにおもふべし。正法よに流布せざらんときは、身命を正法のために抛捨せんことをねがふとも、あふべからず。正法にあふて、身命にすてざるわれを慚愧せん。はづべくば、この道理をはづべきなり。しかあれば、祖師の大恩を報謝せんことは、一日の行持なり。自己の身命をかへりみることなかれ。禽獣よりもおろかなる恩愛、をしんですてざることなかれ。たとひ愛惜すとも、長年のともなるべからず。あくたのごとくなる家門、たのみてとどまることなかれ。たとひとどまるとも、つひの幽棲にあらず。むかし仏祖のかしこかりし、みな七宝千子をなげすて、玉殿朱樓をすみやかにすつ。テイ(口へんに弟)唾のごとくみる。糞土のごとくみる。これらみな、古来の仏祖を報謝しきれたる、知恩報恩の儀なり。病雀なほ恩をわすれず、三府の環よく報謝あり。窮亀なほ恩をわすれず、余不の印よく報謝あり。かなしむべし、人面ながら、畜類よりも愚劣ならんことは。いまの見仏聞法は、仏祖面面の行持よりきたれる慈恩なり。仏祖もし単伝せずば、いかにしてか今日にいたらん。一句の恩、なほ報謝すべし、一法の恩、なほ報謝すべし。いはんや、正法眼蔵無上大法の大恩、これを報謝せざらんや(―中略―)今日われら、正法を見聞するたぐひとなれり。祖の恩かならず報謝すべし(―中略―)ただまさに、日日の行持、その報謝の正道なるべし。いはゆるの道理は、日日の生命を等閑(なおざり)にせず、わたくしにつひやさざらんと、行持するなり。(『行持』)
といい、願ってもないこの逢いがたき仏法、正伝の仏法に逢うことができたのであるから、身命をかえりみず、万縁を抛って、仏祖単伝の無上大法の大恩に報謝するために、この正法を参究すべきである。それには、日日の行持こそ、もっとも肝要であると説いている。このようにすることによって、はじめて仏祖の大道に近づくことができるのであるとし、安逸の日をむさぼり、修行もしないで、むだに時を過ごすことを、つよく戒しめて、
しずかにおもふべし、一生いくばくにあらず(―中略―)いたづらなる声色の名利に馳騁(ちてい、狩猟すること)することなかれ。馳騁せざれば、仏祖単伝の行持なるべし。すすむらくは、一箇半箇なりとも、万事万縁をなげすてて、行持を仏祖に行持すべし。(『行持』)
と『行持』の巻を結んでいる。(153~156頁)
■十余年にわたる深草の道場を解散し、懐奘らの門徒をつれて、道元が越前志比庄に到着したのは、寛元元(1243)年七月中のことである。この月の七日に、道元は興聖寺において『葛藤』の巻を説示したあと、翌閏七月一日には、すでに越前の禅師峰(やましぶ)で『三界唯心』の巻を示衆していることによって、このことがしられる。(169頁)
■まず、『説心説性』の巻において、道元は、
仏道は、初発心(ほっしん)のときも仏道なり。成正学(じょうしょうがく)のときも仏道なり、初中後、ともに仏道なり。たとへば、万里をゆくものの、一歩も千里のうちなり。千歩も千里のうちなり。初一歩とことなれども、千里のおなじきがごとし。しかあるを、至愚のともがらはおもふらく。学仏道の時は、仏道にいたらず、果上の時のみ仏道なりと(―中略―)しかあれば、説心説性は、仏道の正直なり。杲公(大恵)、この道理に達せず。説心説性すべからずといふ。仏性の道理にあらず。いまの大宋国には、杲公におよべるもなし。
よいい、仏道においては、初発心のときも、大悟成道したときも、その途中のときも、いずれもおなじ仏道に変わりはないという、修行者の心構えについて説いている。それは、千里の道を行くのに、第一歩も最後の一歩も、その価値においてはみな変わりがないというわけである。(171~172頁)
■また、日中両国において一般に流布していた儒仏道の三教一致思想についても、『諸法実相』の巻で、
近来、大宋国杜撰(ずさん)のともがら、落処をしらず、宝所をみず。実相の言を虚説のごとくし、さらに、老子・荘子の言句を学す。これをもて、仏道の大道に一斉なりといふ。また、三教は一致なるべしといふ。あるひは、三教は鼎の三脚のごとし。ひとつもなければ、くつがへるべすといふ。愚癡のはなはだしき、たとへをとるに物あらず。かくのごときのことばあるともがらも、仏法をきけりとゆるすべからず(―中略―)三教一致のことば、小児の言音におよばず、壊仏法のともがらなり。
といい、いまの南宋には三教一致の思想を説くものが多く、そのなかには人天の導師づらをし、あるいは、帝王の師におさまっているものまでいるが、まことに仏法衰退のときというべきで、このような説をなすものは、仏法をこぼつ徒輩であるときめつけ、
みみをおほふて、三教一致の言を、きくことなかれ。邪説中の最邪説なり。(『四禅比丘』)
とまで極言している。道元がその宗教の純粋性をたっとび、安易な妥協をいかに嫌っていたかがしられるであろう。(181頁)
■こうして道元は、『正法眼蔵』の示衆を再開するにいたった。すなわち、翌寛元三(1245)年になって、三月六日『虚空』、同十二日『鉢盂』、六月十三日『安居』、七月四日『他心通』、十月二十三日『王索仙陀婆』の各巻を示衆している。この間の四月には、北越入山後はじめて、九十日間外出を禁止して坐禅修行にはげむ、結成安居がひらかれている。(『永平広録』二)
道元はまず『虚空』の巻に、如浄の風鈴の頌(しょう)を引いて、
虚空、しばらくこれを正法眼蔵涅槃妙心と参究するのみなり。
と説き、ついで『鉢盂』の巻でも、僧が食事に使う用器である鉢盂について、
これ仏仏祖祖の頂ネイ(寧に頁)面目なり。皮肉骨髄に親曾しきたれり。仏祖の眼晴頂ネイ(寧に頁)を拈来して、九月の日月とせり。安居一枚、すなはち、仏仏祖祖と喚作せるものなり。安居の頭尾、これ仏祖なり。このほか、さらに寸土なし、大地なし。
と安居の意義の重要さを強調し、『禅苑清規』から安居の章を引いて、その心得を詳しく説明している。さらに、『王索仙陀婆』の巻では、大恵と宏智正覚をくらべて、宏智こそ真の古仏であるということを悟ったのは、ただ如淨一人だけであるとして、
いま、大宋国の諸山にある長老と称するともがら、仙陀婆すべて夢也未見在なり。苦哉苦哉。祖道陵夷なり。苦学おこたらざれ。仏祖の命脈、まさに嗣続すべし(―中略―)即心是仏といふは、たれといふぞと、審細に参究すべし。
と、修行にはすすんで苦学すべきことを説いている。(184~185頁)
■永平寺という寺名は、嘉暦二(1327)年の同寺の梵鐘の銘にあるように、仏教が中国に渡来した後漢の明帝永平十一年の歴号からとったものである。仏教が中国に初めて伝わったように、日本にも、これから正伝の仏法が行なわれるということを、内外に表明しようとしたのであろう。
日本には昔から正師はなかった、自分こそ仏祖単伝の正法をはじめて伝えた正師である、真の日本仏教の創始者であるという、確固たる自負心を、道元は持っていた。したがって、永平寺と改称したとき、上堂して、
天、道アリテ以テ高清、道アリテ以テ高寧、人、道アリテ以テ安寧ナリ。所以ニ、世尊降生シテ、一手天ヲ指シ一手地ヲ指シ、周行七歩シテ曰ク、天上天下、唯我独尊ト。世尊道アリ。コレ恁麽(いんも)ナリト雖モ、永平道アリ。大家証明ス。良久シテ云ク、天上天下、当処永平。(原漢文)
と、永平寺の創立を釈尊の誕生になぞらえている。永平道あり、天上天下、当処永平という言葉には、道元の竝々ならない自信のほどがうかがわれよう。(186~187頁)
■そこで、道元の帰国第一声ともいうべき『普勧坐禅儀』をみると、そこには普勧の二字がとくに冠せられていることが注目されるであろう。これはあきらかに道俗一般に対する伝道と解すべきであろう。
つぎにまた、深草移住後まもないころの作とみられる『辨道話』の巻のなかでも、山家人は諸縁を離れているから、参禅辧道に支障がないが、世務に追われている在家のものは、どうしたら一向専修の仏道にかなうことができるであろうか、という質問に答えて、道元は、
おほよそ仏祖あはれみのあまり、広大の慈門をひらきおけり。これ一切衆生を証入せしめんがためなり。人天たれかいらざらんものや。ここをもて、むかしいまをたづぬるに、その証これおほし。しばらく代宋・順宗の帝位にして、万機いとしげかりし。坐禅辨道して仏祖の大道を会通す。李相国(翺)防相国、ともに補佐の臣位にはんべりて、一天の股肱たりし。坐禅辨道して、仏祖の大道に証入す。ただこれ、こころざしのありなしによるべし。身の在家・出家にはかかはらじ。又、ふかくことの殊劣をわきまふる人、おのづから信ずることあり。いはんや、世務は仏法をさゆとおもへるものは、ただ、世中に仏法なしとのみしりて、仏中に世法なきことをいまだしらざるなり(―中略―)大宋国には、いまのよの国王・大臣・士俗・男女、ともに心を祖道にとどめずといふことなし。武門・分家、いづれも参禅学道をこころざせり。こころざすもの、かならず心地を開明することおほし。これ、世務の仏法をさまたげざる、おのづからしられたり。国家に真実の仏法弘通すれば、諸仏諸天ひまなく衛護するがゆえに、玉化大平なり。聖化大平なれば、仏法のちからをうるものなり。(『辨道話』)
と、かれを慕って深草道場に集まってきた道俗に説いている。これによると、釈尊によって説かれた広大の慈門である仏法は、一切の衆生のために開かれており、世務は決して仏道修行の妨げにはならない。したがって、唐の代宗も順宗も、また大臣の李翺も防相国も、みな政務のかたわらそれぞれ祖師たちについて参禅辨道し、大悟することができたのである。要は、各人の心がけ如何によるものであって、もちろん在家とか出家という身分や地位の相違によるのではない、と断言している。(200~201頁)
■このように、道元の宗教は、賢愚利鈍はもとより、貴賤男女を問わず、在家・出家のくべつなくさらには、罪の有無さえ問わないという、きわめて普遍性のつよいものであった。そこには、道元一流の仏祖単伝の正法による民衆の教化救済、いわゆる、弘法救生を行なうものでなければ、真の仏法とはいえない、という立場が貫かれていたのである。
このように、深草に移った当初の道元の思想のなかには、純一な仏祖単伝の正法を鼓吹するとともに、門下の発展のために、在家成仏・女人成仏をも是認するという、きわめて包容性にとんだ積極的布教の態度がみられた。
ところが、深草の道元教団が活気を帯び、叡山側の弾圧がふたたび身辺に及ぶようになった仁治元年ころになると、道元は『護国正法義』を著わすなど、自分の伝えた仏祖単伝の正法こそ国家護持の仏法でなければならないと強調し、大恵派をはじめとする臨済禅に対して、きびしい批判を加えるとともに、自分の宗教の正法性を一段とつよく主張するようになった。
こうしてどうげんは、禅修行によって真理を体得するためには、俗塵をさけて深山幽谷に隠棲することがもっとも必要であるという、如淨の教えをうけついで、すでに深草時代の仁治元年十一月に示衆した『山水経』の巻に、
山は、超古超今より大聖の所居なり。賢人・聖人ともに山を堂奥せり、山を身心とせり。
という信念を披レキ(てへんに歴)している。
このように道元は、もっぱら山居を理想とする出家至上主義を標榜し、深山幽谷にこもって、ひたすら修行生活をまもり、その理想とする正伝の仏法を、たとえ一箇半箇のわずかな同志だけにでも伝えようという、きびしい態度にかわっていったのである。(202~203頁)
■やがて、建長四(1252)年の秋、道元の病勢は急に進んだようである。病状がすすむにつれて、道元にとって気がかりなのは、門弟たちが道元の仏法をどのように伝えてゆくかという点であったであろう。そこで、臨終の近いことを悟った道元は、修行の大原則を要約して、門人に最後の説法を試みた。これが『正法眼蔵』のなかの『八大人覚』の巻である。その説示の年月は明らかではないが、これを記したのは建長五(1253)年正月六日のことである。
八大人覚というのは、『遺教経』にみえる少欲・知足・楽寂静・観精進・不忘念・修禅定・修智恵・不戯論の八項目のことで、釈尊が入滅にあたって、この八大人覚を守ってゆけば、仏法は永遠に滅びることがないであろうと、最後に弟子達に垂示したものである。
道元は病を押して、釈尊にならって、最後に『八大人覚』の巻を説き、
このゆえに、如来の弟子は、かならずこれを習学したてまつる。これを修習せず、しらざらんは、仏弟子にあらず。これ如来の正法眼蔵涅槃妙心なり。しかあるに、いましらざるものはおほく、見聞せることあるものはすくなきは、魔嬈によりて、しらざるなり。また、宿殖善根のすくなき、きかず、みず。むかし、正法像法のあいだは、仏弟子みなこれをしれり。修習し参学しき。いまは、千比丘のなかに、一両箇の、八大人覚しれるものなし。あはれむべし、澆季の陵夷、たとふるにものなし。如来の正法、いま大千に流布して、白法いまだ滅せらんとき、いそぎ習学すべきなり。緩怠なることなかれ。仏法にあひてたてまつること、無量劫にもかたし。人身をうることも、またかたし。たとひ人身をうくといへども、三洲の人身よし。そのなかに、南洲の人身すぐれたり。見仏聞法、出家得道するゆえなり。如来の般涅槃よりさきに、さきだちて死せるともがらは、この八大人覚をきかず、ならはず。いまわれら、見聞したてまつり、習学したてまつる。宿殖善根のちからなり、いましゅうがくして、生生に増長し、かならず無上菩薩にいたり、衆生のためにこれをとかんこと、釈迦牟尼仏にひとしくして、ことなることなからん。
と、最後を結んでいる。こうして『八大人覚』は道元最後の著述となった。それは釈尊を理想とし、釈尊に等しくあるべきだという堅い決意を示したものであった。(210~212頁)
■こうして、建長五年八月二十六日夜半、道元は、
五十四年、第一天ヲ照ス
箇ノ(足へんに孛)跳(ぼっちょう)ヲ打シテ、大千ヲ触破ス、
咦(い)
渾身覔(もと)ムルトコロナク、活ナガラ黄泉ニ陥(おちい)ル、(原漢文)
という遺偈(ゆいげ)を書いて、五十四年の生涯を静かに閉じた。偶然にも、それは父通親と同年であった。
現在、東山区丸山公園鷲津町にある荼毘塔が、その荼毘の場所だといわれている。
やがて懐奘は、道元の遺骨をいだいて永平寺に帰り、同寺の西北隅に塔を建てて納めた。(213~214頁)
(2014年10月11日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『菅江真澄遊覧記(1)』 菅江真澄著 平凡社東洋文庫
伊那の中路
■腰に小さい籠のようなものをつけた女がおおぜい、野山の方に群をなして行った。これは桑の木の林にはいって、みづとよぶ、桑の芽ぐんだ若葉が花のようになったものをとり、蚕を養いそだてるためだという。みづは瑞葉のことであろうか。この蚕の種は陸奥(むつ)の商人から買いとり、このように桑の木の芽のでる時までは、早く孵化しないよう寒いところにおさめておき、またはここにある山寺というたいへん寒いところの庵の法師に預けて貯蔵しておく。四月八日、釈迦誕生の仏事にこの山に人が大ぜいのぼって、蚕の卵をつけた紙をそれぞれ持ちかえり、埋火のかたわらにおいたり、背中に負ったりして、昼夜あたためると、どうやら春になったとでも思ってか、芥子の種の芽ばえるように孵化してくるのを、雉の羽でなではらい落とし、みづという若芽のふくらんだものを食べさせ、養うということである(注)。(6~7頁)
注)この蚕の種は……養うということである
むかしは桑の若芽の伸びてくるのと、毛蚕(けご)の生まれる時期をあわせるために苦心した。今は各村に稚蚕共同飼育所ができ、村全体の蚕を二眠起きまで飼って、これを各戸にわけるようになった。(29頁)
■二十八日 医師可児(かに)永通の家を尋ねると、主人はさっそく、例の好きな道として、
五月雨のふりくらしたるこの宿にとひ来る月のかけもはつかし
と書いて、「老人のひがごとです、まあ見てください」とさしだしたので、返しに、
さみだれのふるきをしたふ宿なれはさしてとひよるかげもはつかし(15頁)
■二十五日 松本の医師沢辺某は、十年前、同じこの郷の小松有隣、吉員などと月見の席で親しく語りあった友なので、手紙を書いて、きょうそこの祭を見にいく人に託し、
月にとひ花にとはんと思ひこしあだに十とせも過ぎし春秋
という歌をおくると、夕方、返歌をもってきた。
十とせあまりわすれやはする花にめで月に遊びし春秋のそら 雲夢(16頁)
解説
■寒冷なみちのくのきびしい生活のようすはわからぬながらも、旧暦の七月にはいればやがて田畑の収穫もあろう。これならだいじょうぶ旅ができそうだと、真澄は出発を決意したにちがいない。このとき、別れをおしんで数日の同行を申しでたのが三溝政員という若者であった。政員は本洗馬のひとで、古典の学問をもとめて、真澄から「源氏物語」や「竹取物語」の講義をきき、歌などをしたしくまなんだ。その当時、政員のかいた日記が発見されて、そのようすがあきらかになった。これも美濃紙半裁二つ折りの小型本で、書き方もひじょうに真澄ににているという。それによると、政員の眼にうつった真澄の姿が次のように記されているのもまことに興味ぶかい。ここにはあくまでも真澄は国学に秀で、民間伝承にも心をとめる好学のひととなっている。おそらく政員も同じ傾向の若者だったらしい。政員はその後、手習い師匠として一生をおくり、その娘も結婚せずに村童を相手に生涯をすごして明治に至ったといわれている。
白井秀雄のぬし、二年のころまでこの里にとどまり給ふて、あたりなる古き跡ども尋ね、山の姿河の流れの行末をめでて、田草とる女の童の歌ふ一ふしまで書き集め、何くれにつけて歌をよみ、思ふかぎりの言の葉もて、あやなる文を作りて、いとあはれなる遊びをなんし給ふことのうるはしく、まぐさ刈る鎌打ちおける夕ごとに其許にとぶらひて、いにしへ紫式部の書き給へるふみの巻き々、あるは竹取物語など読み学ばひ、或はやまとの道のいとはしをも語りて、こよなう馴れむつまやかに、月日を過ぐるに、けふみな月なかのころ、越の海の深きに心を浸し、陸奥の松島名におふ嶋の、処々めでたき野山をも残りなく見廻り、古き歌の心をわきまへ、新しきをもかいもとめて、古郷に帰らまく欲りすなどのたまひて、旅衣思ひたたせぬれば、したしき友どちうち驚きて、別るることは世になきことのやうに覚え侍りしとて、ひたぶるにとどまり給へなど、袖をかかへてとどむれども、いなふねの否みにせんすベなし。こは別れにぞなるぬ。(214頁)
いかにも魅力ある真澄の人間が想像されるような文である。
このようにして政員は白糸の湯まで真澄をおくっていって、七月二日に別れた。別れぎわに政員は、もし越後が凶作で旅がつづけられないようであったら、またこの村に帰ってくるようにと、ねんごろにいったそうである。どこでも食糧ぶそくから世情がさわがしく、ひどく不安を感じたからであろう。しかし真澄はあくまでも予定どおり、奥羽めざして前進するのであった。(213~214頁)
■七月一日、白糸の湯(松本市)で備中の国玉島から来ている国仙和尚にあった。真澄は、自分の伯父のひとりが僧侶で、同門の法師としてかねてその名を聞き知っていたと、なつかしく思い、しばらく語らった。
国仙和尚は良寛上人の師にあたる人である。あるいはこのときの従僧のなかに、若き日の良寛もまじっていたかもしれない。良寛は真澄より三歳年下で、当時はたしか国仙和尚のもとに従っていたはずである。このときから47年後の天保二年(1831)、良寛は75歳で越後の島崎村(新潟県三島郡和島村)で亡くなったが、生前、すでに良寛の名声ははるか秋田までもきこえてきていた。
真澄が晩年に編んだ〔高志栞〕という雜葉集のなかに、次のように書いている。
てまり上人
手まり上人は、、出雲崎の橘屋由之がはらからなり。名を良寛といふ。国上山の五合に住ぬ。くし作り、うたよめり。手などはいといとよけく、鵬斎翁もこの書などは、いみじきよしをほめり。托鉢にありくる袖に、まり二つ三つを入れもて、児女手まりをつくところあれば、袖よりいだして、ともにうちて、小児のごとに遊びける。まことにそのこころ童もののごとし。よめるうた、
この里の宮の木下のこどもらとあそぶ春日は暮れずともよし
ただこれだけの文からは、真澄は白糸の湯の日の対面を意識していたかどうかは疑問である。(214~215頁)
(2014年10月28日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『菅江真澄遊覧記(2)』 菅江真澄著 平凡社東洋文庫
はしわの若葉
■稚蚕 蚕は卵からあえったばかりのものをケゴ、一眠を終るとチチゴという。二眠を終るとタカゴ、三眠を終ったものをフナゴ、四眠を終ったものをニワゴといい、ニワゴがやがて繭をつくるのである。(76頁)
■
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『菅江真澄遊覧記(3)』 菅江真澄著 平凡社ライブラリー
奥の浦うら
■咲いた花のなかに、まだ開いていない花もまじって山々に見えるので、春さえまだ訪れていないのではないかという思いがふかい。きょうは四月の一日(寛政五年、1793)になったが、陸奥の常として、北の浦風も身にたえがたいほど、たいそう寒く、衣服をぬぎかえるわけでもないが、年ごとに言いならわしている習慣なので、
夏はけさきならし衣かふるともまた花の香や袖にとめなん(47頁)
■六日(岡野注;5月6日) 男と女が戸外にたたずんで語りあうのを聞いていると、きのうはいちにち雨降りに暮れたので、きょうは、きのうの挨拶をしてあるくのだという男が、「その雨の晴れ間に、あなたはすきなところで、さぞや一日遊んで、どれほどたのしい思いをしたことであろう。男のならいとして、わたしは朝から雨にぬれて挨拶をして歩いて暮れた」というと、女が、「いや、わたしのような老いた身は野山にほうりだしておいても、鳥、けものさえ、口で袖ひとつひくこともあるまい。世に何のたのしみもないこの身、わたしのとしが十年も若かったならば」など
と、たわむれを言って、通り過ぎていった。(66~67頁)
牧の朝露
■七月一日(寛政5年、1793) このごろ久しく降りつづいた雨も、朝の間こやみになって、空はなおくもりがちで風がたってきた。(80頁)
■こうして大沢なで来ると、知人の亀麿が、漁師にまねて庵も海べにのぞんだ山かげにたて、この十年あまりも住んでいると、かねて聞いていたところなので、咳ばらいしてはいると、主人は机にひじをついて、『源氏物語』の明石の巻のなかばをひらいて熱心に読んでいた。文中の淡路島山の眺めをここでは尻屋の磯山(東海村)にかえて、のこるくまなくすみわたった月をおもしろがっているのであろうと訪れたのだがといえば、これはめずらしいとよろこんで迎え、今夜はここにお過しなさいというので、話しこんだ。暮れてゆくころ、海はなお荒れていたが、たくさんの舟がのり出してゆくのは、もみじいかといって鯣(するめ)にするいかをつりにでるのである。(84頁)
■優婆塞(うばそく)の某、木村だれ、胆沢郡(岩手県)水沢の宿駅に住んでいた武田氏喜の子某(なにがし)などといっしょに行く。縁むすびの石というのがあって、願いごとのある人は小石を勢いよく投げ上げた(石の上に小石がのれば願いがかなうという習俗)。坂をくだって亀麿の家につくと、戸をしめたままで、だれも人がいそうにない。主人は磯で釣り、沖にでて漁師のまねごとをしているので、どこにいったにだろうと、わたくしたちは荻の茂った崖の道にたたずんで見わたした。やがて戻った主人は、潮にぬれた衣服のまま、「おおめずらしい人たちだ」とことば少なに言い、もう筆をとって歌をつくろうとするので、さっそくわらぐつをぬいで上がった。いつ暮れるともなく夜が更けて雨が強く降ってきたが、誰もかれも歌作にばかり心をこめて、雨の音など気にもとめなかった。隣に家がないのでたいへん静かだ。やがてかもめが鳴いているのかと思ったら山がらすの声がして、夜が明けたらしい。(90頁)
■八日 ぬる湯の温泉にいってみよう、中野山の雪もおもしろかろうから、さあ見にまいろうと、恵民の家を出た。
村はずれに宝厳山法眼寺という黄檗宗の寺があった。享保年間(1720ー30ごろ)、この寺の吊鐘を、盧山と言う禅師が江戸で鋳させて、それを浪速の港へ船につんで送り、またそこから、このみちのくへ船積みして送ろうとした。とちゅう、秋田の沖に近くなったとき、大波にあって船が沈没し、釣鐘も失せてしまった。禅師は、自分の年来の願いもこれで空しくなったといって力を落とし、それから1年もたたないうちに死亡してしまった。この禅師の50年忌をしようというとしのこと、常陸の国鹿島郡上幡木村の下浜という所の地引き網に、海藻やいろいろな小貝がたくさん不着した怪しい物がかかってきた。これはなんだろうと、ついていた海藻や貝などを斧でうちくだいてみると、釣鐘だったのでおどろきあきれた。これはどこの鐘を、いつ、海におとしたのだろうと、みんなが集まってよくしらべてみると、みちのく津軽の黒石の某寺と刻みつけてあった。そこで役所にとどけてでて、船主重兵衛という人がこの津軽のくに青森の港に運ばせたのが、安永の末(1780)のことだという。盧山禅師の願望がようやくこのときになって実ったといって、この話を聞いたものは、津軽のひとはもちろん、遠いところの旅人や修行者などが、この寺の鐘を見ようと集まり、このふしぎな事実におどろき、尊いことだと話あったという。寺にはそれまで鳴らしていた釣鐘があったが、それは同じ宗派のぬる湯の寺にかけて、海から上がってきた鐘は、立派な鐘楼を建てて今も吊ってある。それをわたしもぜひ見ようと、雪をふみわけのぼっていって、その釣鐘の刻銘をみた。「……当山二代臨済正伝第三十六世嗣法沙門淨泰盧山 武陽神田鋳物師木村将監藤原安成 武江鋳調世武内彦重郎 当寺開山臨済正伝第三十五世上南下宗元頓和尚 享保八歳次癸卯天四月仏生日」というように、鐘の周囲に書きめぐらしてあった。海に沈没したものが潮波にさらわれて、遠くよその浦にいっていた例はそれほど珍らしいことではないが、その願望した禅師の50年忌をしようとした年に会ったというのは、世間にまたとあることでなかろう。その釣鐘の朝夕につく音を深い苔の下で聞いて、禅師もさぞかし、うれしいと思っておられるだろうと、しのばれた。(170~171頁)
■夕暮れて、蚊遣火をたいている炉のもとに女ばかりが集まって、釜上麻(かまげそ)《かまげそというのは、いま釜からむし上げた新しい麻、かまあげそである》というものを手ごとにとりもっている。そしてうら若い乙女がいう。「はやくこれをうんで、また(7月)7日前にひと目籠をうみ、7日からは三筋苧(みすじそ)をうんで、老いた母に布を織ってお着せしよう」と感心な子が語っている。すると、その母であろう、年老いた声で、「わたしの命が2年も3年もながらえるようにと思って言うのであろう」というのが、遠く離れたところへ、かすかに聞こえてきた《陸奥の習俗として、老いた親のある女は、Ⅰ日に苧三筋を、7月7日から次の年の7月7日まで1年間、怠らずにうみ、これで布を織り貯えて、親の亡くなったとき着せる経かたびらにし、その親が生存していれば、それをふだん着にする、だから三筋苧をいくたびもうめることを、めでたいためしとしている》。(267頁)
(2014年11月14日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元集』 日本の思想2 筑摩書房
真理の体現者 道元 玉城康四郎
■道元はこのような海印三昧をとり上げて仏祖の道をといている。ここで道元の思索の特徴について触れてみよう。通常、思索するという過程は、認識の主体と認識の対象との相対関係によって成り立っている。認識の主体が対象を認識する場合に、対象は動的なものであれ、静的なののであれ、それを認識する主体は、それ自身は認識し得ないものとして固定したものとなる。道元の場合には、このような主体と対象との相関性、したがってまた固定した主体というものを徹底的に払っていく。道元は通常の意味の認識関係をどこまでもしりぞけて、主体と対象との相関性を超えた、あるいはそれを離れた世界、いいかえれば現在即今に開示されている世界――道元のいう恁麽(いんも)――を究明して止まない。したがって究明している道元の主体そのものは、即今に開示されている世界のなかに解消し、あるいはそれに埋没し、いいかえれば主体は世界そのものとなって、その世界を究明するのである。ここに道元の独特の思索が展開する。(19頁)
■海印三昧の究明も、その代表的なものである。しばらくその跡をたどってみよう。
ここで海というのは、仏法の大海のことである。現にいま、ありとあらゆるものがこの大海に遊泳している。しかし大海が万物を包含しているのではない。いいかえれば、大海と万物が相対しているのではない。そうではなく万物のあるがままが海印三昧である。いかなる一物も、徹底徹尾、自由自在に遊泳している。道元は、このことを
「海上行(こう)の功徳、その徹底行あり、これを深深海底行なりと海上行するなり。」(『正法眼蔵』「海印三昧」)
といっている。
これは異様な世界表現であるが、その意味はつぎのごとくなるであろう。すなわち、海面を泳ぎながら、しかもその足は海底に撤しているのである。あるいは、深々と海底を行くままで海面を泳いでいるのである。(19頁)
■しかるに海印三昧における万物は、海面を泳ぎながら、足が底についているという。つまりこの世に活動しながら悟りに徹底しているのである。これはたしかに自覚の世界であるが、しかし自覚によって始めてそうなっているのではない。意識しようとしまいと、それは自覚以前の海印三昧の実情である。このことは、きわめて重要な視点であり、そしてこの点にこそ、道元にまで正伝し来たった仏祖の世界がかかっている。それは要するに、意識を離れて、いかなる一物も、何物にも疎外されることなく、徹底的にあるいは底抜けて自由に活動している三昧の事情を表わしているであろう。(19~20頁)
■では、この場合における此の身とは何を指すのであろうか。それはもとより自我ではない。そうではなく、それこそまさに法なのである。法とは、たんなるものではなく、また心でもない。それは、海印三昧、すなわち宇宙そのものの仏の世界にあり、かつその世界から見られているものである。だから、心的なものであれ、物的なものであれ、また事象であれ、ことごとく海印三昧にあり、なに一つ法でないものはない。そのような無数の法が集中して此の身が成立しており、そしてそれもまた法である。(20頁)
■道元は『維摩経』の文を引きながらつぎのように述べている。
「但、衆法(しゅぼふ)をもって此の身を合成(がふじやう)す。起る時は唯法の起るなり。滅する時は唯法の滅するなり。此の方の起る時、我起ると言はず。此の法の滅する時、我滅すと言はず。前念後念、念念相対せず。前法後法、法法相対せず。是を即ち名づけて海印三昧となす。」(「海印三昧」)
此の身は、多くの法によって合成されており、此の身が起るのは法の起るのであり、此の身が滅するのは法の滅するのである。それを自我が起ったり滅したりとはいわない、という。つまり自我という別人がいて、法の起滅を見聞しているのではない。そうではなく、無数の法によって合成されている此の身が起滅しているだけである。それは自我ではなく、無数の法の集中している全体の法が起滅している。起っている時は起っているだけ、滅する時は滅するだけである。たとえば春になった時は、春の全体が起っており、夏になった時は、夏の全体が起っており、そしてただ起っているのみである。道元はこれを、
「起はかならず時節到来なり、時は起なるがゆえに。いかならんかこれ起なる、起也なるべし。」(「海印三昧」)
したがって、起っている時はただ起っているだけであるから、何一つ隠されているものはない。「皮肉骨髄を独露せしめずといふことなし。」という。皮も肉も骨も髄も、そして臓物までもさらけ出している。一物も隠すことのない全露のすがたである。そして滅する時も同じように、このような全露の法が滅するのである。(20~21頁)
■これまで論じてきたような王三昧、あるいは海印三昧の世界を、自覚の核心から見ればどうなるのであろうか。そこには底抜けの希望と明るさと、永遠の解脱が息づいている。微塵の暗さもペシミズムもない。道元は、それを、明珠とも光明とも、あるいは仏性とも表現している。『正法眼蔵』には、「一果明珠(いっかみょうじゅ)」という巻がある。このなかに、「尽十方界、是れ一顆の明珠」という一文がある。全宇宙が一つの珠である、という。宇宙が一つの珠であるというのは、いったい何を意味しているのであろう。宇宙といえば、数かぎりのない日月星辰を思い浮べるであろうが、ここでは、外に見られた日月星辰を指すのではない。前の海印三昧においても触れたように、主体の自覚から見ているのである。主体における執着の絆が断たれて、内から外に向って門戸が開かれたときに、主体は宇宙と吹き通しになる。主体は宇宙と本質的に一体となるのである。その際の主体の自覚は、もはや自我意識にかこまれた個別的なものではない。此の身に生じている点ではまさに己の自覚ではあるが、自我意識の柵がはずされて宇宙意識となっている点では普遍的である。いわば、自己と普遍、主体と宇宙とが一つらなりになっているといえよう。そのような自覚の世界が一個の明珠というのである。(22頁)
■そうだとすれば、全存在そのものは、一物も隠すことなく、むき出しのまま(偏界不曽蔵)というほかはない。そしてこのむき出しの存在そのものには、もはや主客の対立は解消してしまっている。つまり、存在そのものを見ている主体と、見られている存在そのものとの相関性は消失している。見ているものも見られているものもなくて、全存在が同一のむき出しである。だから強いていえば、このむき出しの存在は、存在がそのまま存在であるという、存在と自覚の二重性が、同一的に拡充し尽くされている。
このような性格を道元の表現に即していうと、存在そのもののむき出しは、永遠の過去から現在刹那に貫通しており(亙(こう)古亙今)、これに一物も加える余地がなく(不受一塵)、かつその全体が完結しており(合取)、そして真理の当体であり(是什麽物恁麽来)、しかも日常生活そのままの心(平常心是道)である。したがって、あらゆる存在はそのまま、透明であり解脱している(透体脱落)、というのである。(24頁)
■生活即仏道を、かれは行持というのであるが、それは、行を続けることによって生活のなかに仏道の真実を保持していくことを指していると思われる。したがって行持は、生活者における仏道の持続的な展開であり、行持よって仏道は、始めて生活のなかに具現していくということができる。道元は、
「諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成し、われらが大道通達するなり。われらが行持によりて、諸仏の行持見成し、諸仏の大道通達するなり。」(『正法眼蔵』「行持」)
われわれの行持が実現するのは仏祖の行持によるのであり、仏祖の行持が実現するのはわれわれの行持による、という。仏祖とわれわれとは、行持によってつながっており、行持によって、仏祖正伝の大道が顕わになるのである。とすれば、行持はまさに仏祖のいのちであるということができよう。しかもかれは、
「無上の行持あり。道環して断絶せず。発心・修行・菩提・涅槃、しばらくの間隙あらず、行持道環なり。」(「行持」)
と述べている。(28頁)
■つまり、全世界は一つの透明なたまであるというのだが、その全世界についての説明である。道元は、世界をたんなる空間と見て、それを一つのたまといっているのではない。そうではなく、どこまでも自己の活動の持続として全世界をとらえ、しかもそのなかに超越的なものを体認しようとしている。右の文に即していうと、全世界というのは、間断なくつづく逐物為己・逐己為物であるという。つまり、物を追究しても結局は己以外のものではなく、逆に、己を追究しても結局は物に外ならぬ、物と己とが対立的にあるのではなく、たがいに全面的に相手を吸収し合いながら活動して止まぬ、それがすなわち全世界であるというのである。
しかもこのような実態の体認をさまたげているものは、分別の情感である。いわば認識の対象性ともいうべきものであろう。その分別が生ずると、真実の智慧が隔たるのである。しかし隔たるといっても世界の実態から離れてしまったのではない。ただ頭や顔の向きをかえただけのことである。向きが変わっただけで、実態のなかにあることには相違ない。そうはいうものの、真実の智慧が隔たっていることにはちがいないから、その隔たりを体認しなければならない。このようにして、逐物為己・逐己為物が間断なく続くのである。しかも世界の実態は、いかなる主体の認識・行為にも先立つ真理であるから、したがっていかなる主体のさばきも、なお手にあまるのである。いわば、いかなる主体をも超越する実態の道理は、かえって主体の全領域へその背後から垂幕しているといえよう。このように、主体を超え・包み・貫ぬく実態の光明こそ、一顆の明珠(一つの明るいたま)なのである。(37頁)
■では実存的思惟によってはどうか。道元が理性的立場によって理解されないことはいうまでもないが、実存的思惟は、自己の存在そのものを主題とし、思惟者と主題とが同一であるという点で特徴的である。このような思惟の主体性によって、道元的世界が無理解の状態から少なくとも理解につながる境位へ移入することは可能であろう。しかしその理解の境位とは何であろうか。それはせいぜい、道元の表明しようとする世界がおぼろげながら感知され、ある程度追経験される位のものではあるまいか。理性的立場による無理解よりはましであるとしても、この程度ではなお不徹底である。
理解をさらに推進するためには、実存的思惟に加うるに、いわば身体的思惟、すなわち行(ぎょう)が要請されるのである。道元のいわゆる只管打坐である。この打坐は、もっとも単純な形式である。この形式の日常的な繰り返し、そしてそれを長期にわたって持続することが重要である。(42頁)
■「仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の辧道すなはち本証の全体なり。かゝるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指の本証なるがゆえなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。」(辧道話)
修証一等というのは、修行と悟りとが同一であり、修行がすなわち悟りであるということを指している。悟りは、ここでは最高度の実証体験である。常識では、修行の後に悟りがあると解されやすいが、道元は明白にこれを否定する。そうではなく、悟りの上の修行であるから、最初の辧道がそのまま本来の悟りの全体である。したがって修行の後に悟りを期待する心はしりぞけられねばならぬ。修行のままが悟りであるから、悟りに終着点はなく、悟りのままが修行であるから、修行に出発点はないという。(43頁)
学道用心集
■まことに思えば、すぐれたものを愛することのできるほどの者が、当然すぐれたものを愛するのです。葉公(せつこう)が竜を愛したように、彫刻の竜ばかり喜んで、本物の竜が出てきた時気を失うようなことがあってはならないでしょう。(80頁)
■そもそも、仏道を学ぶには、最初入門の時、指導者の教えを聞いて、その教えの通りに修行します。この時、知っておくべき事があります。この時、知っておくべき事があります。よく云われる「法が我(じぶん)を転じ、我(じぶん)が法を転ずる」ということです。我(じぶん)が法を転ずる時は、我(じぶん)は強くて、法は弱いのです。反対に、法が我(じぶん)を転ずる時は、法は強くて、我は弱いのです。仏法にはもともとこの二つの時節があります。仏祖の法の正統なあとつぎでないと、このことを全く知っていません。達磨門下の禅僧でないと、その名さえ聞くことがありません。もしこの故実(ひけつ)を知らないと、仏道修行がどうしても力一杯行なわれません。修行が正しいか正しくないかの判別がどうしてつきましょう。(81頁)
■慧能禅師は、黄梅山に五祖(大満弘忍)禅師をたずねて法を求めた時、面目をなくし、二祖慧可大師は少林寺に達磨大師をたずねて法を求めては自ら臂腕(ひじ)を断ちました。こうして師の骨髄を得、自己の生き方をすっかり改めて、仏祖としての日常生活の風流(しかた)を買うのです。師を礼拝し、自己の正体を反省する坐禅をすると、そのまま仏のさとりにおちつくのです。
ではありますが、心においても身においても、住着(とどまる)ことがなく、さらさらとしていて、留帯(とどこお)るところがありません。
趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)禅師にある僧がたずねました、「狗子(いぬ)にも仏性がありますか、どうですか。」
趙州が言いました、「無。」
「無」の字の上に、おしあて、おしはかることがあり得ますか。とりつき滞(とどこお)っていられますか。全然とらえどころがないのです。
ためしに後生大事に持っているものから手を放してくれませんか、ちょっと手を放してみなさい。「身心は如何(どう)か、行李(おこない)は如何(どう)か、生死はは如何(どう)か、仏法はは如何(どう)か、世間のものごとは如何(どう)か、山河大地、人、動物、家屋は如何(どう)か。結局のところ如何(どう)なのか」と。
こうして次々に反省してゆくと、自然に、動くと静まるとの二つの相は絶えておこりません。この差別の相の全くおこらない時、しかもこれは心の働きが全くなくなったのではありません。この境地は、人間では実証することがありません。ここのところがわからずに、迷う者は実に多いのです。
参禅学道の人よ、とにかく半分迷っていればそれで充分です、全部迷っていても、しりごみしてはなりません。(ただひたすら修行するのです)わたしが祈禱(いのり)に祈禱(いのる)ところです。(83~84頁)
■右について。仏道を学ぶ丈夫(りっぱなひと)は、まず何としても道に向って修行をするのに、正しいのとただしくないのとがあることを知らなければなりません。
そもそも釈迦牟尼如来は、菩提樹のもとに端坐せられ、明星を見ることを得て忽(たちま)ちに無上の乗りものである真実の道をその場でお悟りになりました。その悟られたところの真実は、声聞とか縁覚などの到底及びもつかないところです。仏だけが自ら悟ることができるのであり、仏から仏にだけ伝えられて今に断絶(とぎれ)ることがないのです。この悟りを得た者が、どうして仏でないことがありましょう。
ここにいう「道に向う」とは、仏道の涯際(はてのはて)まで、余すところなく身につけるのです。仏の様子(ありかた)を明らかにするのです。仏道は人々(めいめい)の立っている足元にあります。道と全く一体となるので、その場で真実がすっかり明らかになるのであり、悟りとぴったり一致するので、その人が本来何不足ないその人自身になるのです。こういうわけで、よしんば最高に納得のいったところを示してみても、全体の真実の中の一部ですから、やはり「一半の悟」ということになってしまうのです。これがとりもなおさず道に向ってする修行の風流(やりかた)です。
現今仏道を学ぶ人は、道がどこで通達し、どこでふさがっているかの判断も着かず、無理にもはっきりした験(しるし)のあらわれることを好みます。これで間違わない人があるものですか。『法華経』に出て来る長者窮子のたとえ話のように、父を捨てて家を逃げ出し、自分のものである財産をすてて他国をよろめき歩いているのです。もともと長者の一人息子であるのに、長くよそ者の賤しい傭人になっているのです。まことに理由のあることです。
そもそも仏道を学ぶ者は、道そのものにならされることを求めるのです。道そのものになる者は、悟りのあとがなくなるのです。
仏道を修行する者は、まず何が何でも仏道を信じなさい。仏道を信ずる者は、何が何でも、自己が本来道(さとり)の中にあって迷惑(まよい)もせず、妄想もせず、顛倒(さかさま)な考えもなく、増(ふえ)もせず、減(へ)りもせず、悞謬(あやまり)もないということを信じなさい。このような信をおこし、このような道を明らかにして、それによって道の修行をすること、これがすなわち仏道を学ぶ基本です。
その修行の規則としては、心のはたらきのおこる根源を坐禅によって断ち切り、知識によって理解する方向に向わないようにするのです。これがとりもなおさず初心者を誘引(みちび)く方便(てだて)です。その後、身心の束縛をすっかりなくし、迷いと悟りとをさっぱり手放します。これがこれが第二段階の様子(ありかた) です。
おしなべて、自己が仏道にあることを信ずる人は特に得がたいものです。もし、自己が間違いなく道にあると信ずるなら、自然に仏祖の大道の通達するところとふさがるところとをはっきりさせ、迷いと悟りの由ってきたるもとを知るでしょう。
どなたも、ためしに心のはたらきのおこる根本を、坐禅して断ち切ってごらんなさい、十人中八人、九人までは、忽然(たちまち)に道を見ることができるでしょう。(83~87頁)
■直下承当(ちょっかじょうとう)ということ
右のついて。身心(からだぜんたい)を間違いない真実そのものにするのに、どうしても2つの面があります。師について法を聞くことと、力をつくして坐禅することとです。法を聞くことは心とそのはたらきを自在にし、坐禅は真実の修行とその実証とを手中におさめます。こういうわけで、仏道に入るには、やはり、どちらか1つを捨てても、真実をそっくり承当(うけとる)ことはできません。
そもそも、人はみな身心があります。その作(はたらき)には強い、弱いがあります。勇猛なのと、にぶくて劣っているのとです。あるいは動き、あるいは容儀をなすところ、この身心をもって直接に仏を実証する、これが承当(じょうとう)です。よく言われる、従来(これまで)の身心をどこへどう廻転(めぐら)すこともなく、ただ身心が真実を実証するに随ってゆくのを直下と名づけ、承当と名づけるのです。ただ身心の真実に随ってゆくのです、ですから、古くからもっていた見解ではありません。ただその真実をそっくり承当(うけとっ)てゆくだけです、ですから、新しくもぐりこむ巣のようなものではないのです。(88頁)
辧道話
■これらの等正覚(ほとけたち)は、さらに、反対に、目に見えないところで親しく資(たす)け合うみちが通じるので、この坐禅人は、確爾(しっかり)と身心が解脱の境地に立ち、これまでの雑(まじりけ)のある、穢れた感覚や意識や思量をたち切って、ありのままの真実である仏法にぴったりとかない、微塵の数ほどの無限に多くの諸仏如来の道場ごとにあますところなく、仏の説法教化のおこるのを助け、ひろく、仏となって仏をも立ちこえた聞法者に教えを垂れ、仏をもたちこえた法を勢いはげしく説き立てます。この時、十方のあらゆるものごとのある世界の土地・草木、牆(かきね)と壁、瓦と礫(いしころ)が、みな仏としての説法教化をするので、それらのおこすところの風や水などの利益にあずかるものどもは、みな、甚妙不可思議な仏の化導に、目に見えないところで資(たす)けられて、それ自身にそなわった最も親しいさとりをあらわします。これらの水や火を受け用いる仲間は、みな本来さとっている仏の化導を周(めぐ)り旋(めぐ)らせるので、これらの仲間といっしょに住み、話を通じ合っているものも、また残らずお互いに無窮の仏徳が備わり、次から次へと広くはたらきを及ぼして、尽きることなく、とぎれることなく、人間の思議も及ばず、はかりみることもできない仏法を、あらゆるものごとの存在する世界全体の内にも外にもゆきわたらせるのです。ではありますが、これら多くのことが、坐禅をしている本人の知覚に入ってこないようになっていることは、寂静無為の坐禅の中で、人間のしわざが全くなくなっている、直接の証(さとり)だからです。もし、世間一般の人の考えのように、修行とその実証としてのさとりを段階的なものとするならば、互いに別のものとして知覚し意識するはずです。もし、知覚や意識の範囲に入ってくるものならば、本来のさとりの大原則ではありません。さとりの大原則には、人間の分別・判断は手がとどかないのですから。(100~101頁)
■お教えしましょう――。きみが今、諸仏の正しい生き方、無上の大法(だいほう)である坐禅を、無内容にすわって何もすることがないと思うなら、これを、大乗をそしる人とするのです。迷いが実に深いことは、大海の中にいながら、水がないと言うようなものです。坐禅すれば、はや勿体なくも諸仏の自受用三昧にどっしりとおちついて坐っているのです。これが、広大の功徳をなす、ということではありませんか。気の毒にまあ、法の眼がまだ開けず、精神もひきつづき酔っぱらったままですね。
おしなべて、諸仏の境界(きょうがい)は、不可思議です。意識作用の手のとどくところではありません。ましてや、信ずることのできない、知慧の劣った人が知ることのできるものではありません。ただまっすぐに信じることのできるすぐれた聞法者だけが、入ることができるのです。信じることのできない人は、かりに教えたとしても、聞き入れることができません。『法華経』が説かれた霊鷲山(りょうじゅせん)でも、これ以上新しい教えを聞くには及ばないと言って席を立ち、釈尊から「退席するのもまあよろしい」と言われた連中(れんじゅう)がありました。おしなべて、心に正しい信仰がおこったら、修行し、師について学びなさい。そうでなければ、当分やめておいたらいいでしょう。そして、前世から法のめぐみがなかったことを自らうらむのです。(104~105頁)
■又、よく聞いてください、われわれは本来、無上の菩提(さとり)に何不足ないのです。いつにかわらず受用しているのですが、それをそっくり承当(うけと)ることができないので、むやみと頭で物を考えて概念をつくるくせがついていて、そのつくりあげた概念が実在するものとして追いかけるために、ひろびろした真実の道をわけもなく踏み誤るのです。この頭で考えた概念によって、眼病の人が空中に幻覚の花を見るように、実体のないかげがさまざまあらわれます。あるいは十二因縁で輪廻転生する身と思い、二十五有(う)という迷いの中の存在だと思い、声聞・縁覚・菩薩の三乗だとか、人天乗(にんでんじょう)・仏乗を加えて五乗だと言ったり、仏はあるとか仏はないとかいった意見は尽きることがありません。こうした概念の積みくずしをやって、仏道修行の正しい道だと思ってはなりません。
ということですのに、今はまぎれもなく仏の印形どおりに身をなして、万事を手放し、ひたすらに坐禅する時、迷いだ悟りだという人情による思慮分別の世界をとびこえて、凡夫か聖人かのあり方に関係なく、たった今、相対の世界の外に自在にあそび、無上菩提を受用するのです。あの魚とりかごや兎あみみたいな文字にかかずらっている者は、肩を並べることもできないのです。(108~109頁)
■証(さとり)と別でない修行がすでにここにあります、われわれは幸いにも、われわれ自身にそなわる不可思議の修行を自身伝えているので、初心でする坐禅修行が、そのまま自分の身にそなわる本来の証(さとり)を、人間の営みの全くないところで身につけるのです。おわかりでしょう、修行を離れてはあり得ない証(さとり)を、人間の生活で染汚(けが)されないようにするため、仏祖はしきりに修行の手をゆるめてはならないと教えられるのです。この不可思議の修行で手放しになると、本来成仏の証(さとり)は手のうち一杯になります。本来成仏の証(さとり)を一歩進めると、不可思議の修行は身(からだ)全体に行なわれます。(114~115頁)
■聞いたことがおありでしょう、祖師が言っておられます、「修行も証(さとり)もないではない。しかし、それは人間的なものとしてとらえてけがすことはできない」と。また、「真実の道(菩提)をはっきり見通した者が、真実の道を修行する」とも言っておられます。おわかりでしょう、道を得て、さとりのまっただ中で修行すべきであるということです。(115頁)
■おたずねします――。ある者は、次のようなことをいいます、「生れて死ぬことを憂い悲しむことはない。生死の苦しみからのがれ出るのにたいそう速い方法がある。世に言う心(しん)の本体が永遠不変であるという道理を知るのである。その説くところは、この身体は、生まれたからには必ず死への経過をたどるのであるが、この心(しん)の本体は決して滅することがない。生滅の法則に押し流されないですむ心の本体が自身にあることを知ってしまえば、これを本来の正体とするのであるから、今の身はこれはかりのすがたである。ここに死んではかしこに生れ、一定していない。心(しん)は、これは永遠不変である。過去、現在、未来ともに変わるはずがない。このように知るのを、生死の苦をのがれたとはいうのである。この趣旨を知る者は、これまでの生れては死に生れては死にのくり返しが全く断絶して、今生この身が終るとき、性海(しょうかい)という本体の世界に入る。この性海に流れ入る時、諸仏如来ののように不可思議の徳がまぎれもなくそなわる。現在は、たとい知ったとしても、前の世からのまよいの業によってつくられている身体であるから、諸仏とひとしくないのである。この趣旨を知らない者は、永久に生死の輪廻を続けるであろう。ということであるから、ただ急いで心(しん)の本体の永遠不変である趣旨をよくよく知るべきである。坐禅などといって、益もなくのんびり坐って、一生をすごしたところで、何の効果が期待されよう。」このように言う趣旨は、これはほんとうに諸仏諸祖の道にかなっておりますか、いかがでしょう。
お教えしましょう――。今言われた考えは、全然仏法ではありません、先尼外道の考えです。
それについて言えば、次のとおりです。先尼外道の考えは、「自分の身の中に一つの霊知(たましい)がある。その霊知(たましい)は、何かに出会うと、好き、嫌いを弁別し、是非(よしあし)を弁別する。痛い、かゆいを知り、苦か楽かを知るのは、すべてこの霊知(たましい)の力である。ところが、この霊知(たましい)の正体は、この身が死んでなくなる時、中味だけ抜けだして別の所で生れ変るから、永久になくならず、不変である」というのです。先尼外道の考えというのは、このようなものです。
そういうことであるのに、この考えを教わって仏法とするのは、瓦や石ころをつかんで黄金の宝と思うよりもなお間抜けです。おろかな迷いのはずべきこと、たとえようにもたとえるものがありません。大唐国の慧忠(えちゅう)国師がふかくいましめておいでです。今、心は不滅で、相(かたち)だけが死んでゆくという間違った考えをはじき出して、諸仏の妙法と等しいものとし、こんな生死(まよい)の根本原因をつくっておいて、それで生死の苦をのがれたと思うのは、間の抜けたことではありませんか、特にあわれむべきです。ただもうこれは外道の間違った考えだと知るのです、耳を傾けてはなりません。
話がここまできては、黙っているわけにもいけません、やむを得ず、ここに一層のあわれみをたれて、きみの間違った考えを救ってあげよう。いいですか、仏法では、本来身と心は全く一つのものであって、本体と様相とは二つでないと説きます。これは西天インドでも、東地中国でも、同じく人の知っているところです、この原則には決してはずれはしないのです。ましてや、仏法で不変を説く時には、あらゆるものすべてみな不変です。身と心とを区別することはありません。寂滅と、一瞬一瞬に消えてあとかたがないと説く時は、あらゆるものごとすべて寂滅です。本体と様相とを区別することはありません。ということであるのに、どうして、身は滅するが心は不変だなどと言えるでしょう。正しい道理にそむかないはずはないでしょう。そればかりではありません、生まれて死ぬ、この事実がそのまま涅槃(さとり)であると、よくよく自覚すべきです。仏法では、生まれて死ぬ、この事実のほかに涅槃(さとり)を説くことはないのです。ましてや、心は身と関係なく不変だなどと理解することで、生死の苦をのがれた仏の智慧だなどと考えちがいをしてみても、その理解し、分別する心は、その場でやはり浮んでは消えていって、全然不変ではありません。これはたよりないことではありませんか。
昔からいわれているところをよく観てごらんなさい、身と心とが一つであるということは、仏法がいつに変らず説くところです。それだのに、どうしてこの身が生滅するとき、心だけが身から離れていって、生滅しないということがあるでしょうか。もし、身と心が、一つである時もあり、一つでない時もあるなら、仏説はどうしてもうそいつわりになってしまうでしょう。又、生れて死ぬということは、取りのぞかなければならないことだと思っているのは、仏法をきらう罪となります。気をつけるべきです。
いいですか、仏法で「心性大総相の法門」といって説くところは、あらゆるものごとのある世界全体を含めて言うのであって、本体と様相とを分けることなく、生と滅と二つを分けて言うことはありません。菩提とか涅槃とかいわれるおさとりに至るまで、心の正体でないものはありません。あらゆるものごとすべて、宇宙に存在するすべてのもの、みなともに一つの心(しん)であって、全部中に含まれ、一つになっていないことがありません。この多くの法門(もの)は、みな平等なただ一つの心(しん)です。少しの異違(ちがい)もないと説くのが、これがすなわち仏法者がの正体を正しく知っているありさまです。ということであるのに、この唯一絶対の法において、身と心とを分けて考え、生死と涅槃とを区別することがありましょうか。われわれは仏の子なのです、外道の考えを述べる気違いが、舌をたたいて出す雑音は、耳にふれることもなりません。(116~120頁)
正法眼蔵第一 現成公按
■「現成公按」の「現成」とは、絶対の真実が今目の前に実現していることである。「公按」の「公」は平等、「按」は「分を守る」ことである(『正法眼蔵抄』の解釈による)。つまり「現成公按」とは、絶対の真実が現前していることであり、それはあらゆるものごとが平等に分を守っていることである。これが「諸法が仏法である」ということである。大乗仏教でよく言われる本来成仏ということも、つまりは一切が本来仏であったということである。
そして、この「一切が仏である」という事実は、人間のはからいと一切関係ない。このわたしではない。それが「万法われにあらざる」ということである。ここから、概念の世界をそのままにして、生きている身体をもってする修行がおこなわれる。「仏道もとより豊険(ほうけん)より超出す」とはこのことである。『正法眼蔵』では、多くの場合、開口一番に最も大切な基本原則が述べられていることに注意すべきである。(135頁)
■自己をはこんで万法を修行し、実証するのを迷とします。万法がすすんで自己を修行し、実証するのが悟りです。迷いを大悟するのは諸仏です。悟りに大迷いしているのが衆生です。さらに、悟りの上に悟りを得る漢(ひと)もあります、迷いの中でまた迷う漢(ひと)もあります。諸仏がまぎれもなく諸仏である時は、自己は諸仏であると自覚する必要はありません。ではありますが証仏です、仏を実証してゆくのです。
形あるものを見るには、身心(からだぜんたい)でもって見るのです、音あるものを聞くには、身心(からだぜんたい)でもって聞くのです、その時、たしかに対象を理解するのですが、鏡に物をうつすようなことではありません、水と月とのような関係ではありません。一方が実証されるときは、他方はかげになっているのです。
仏道を修行するということは、自己を修行することです。自己を修行するということは、自己をわすれることです。自己をわすれるということは、自己が万法に実証されることです。自己が万法に実証されるということは、自己の身心と、それに他己の身心をも解脱させることです。悟りのあとかたは全くなくなっています。全くなくなっている悟りのあとかたを、そのままどこまでも続けさせるのです。
人がはじめて法を求める時、法の辺際(あたり)をはるかに離れています。法が自分にまっすぐ伝わった時には、直ちに自己の本分におちついた人です。
人が舟に乗ってゆくのに、目を向うへ向けて岸を見ると、岸が動いてゆくように見間違えます。目をちかく自分の乗っている舟につけると、舟が進むのがわかります。そのように、身心の正体を正しく知らないで、万法を見分けようとすると、自己の正体は不変のものであるかと思い違いをします。もし自己の日常生活を深く反省して、箇裏(このところ、注;この現在の絶対のあり方)に帰して見ると、万法が我(じぶん)というものでない道理がはっきりします。(136~137頁)
■たき木が灰になります、それから逆にたき木になるはずはありません。ということであるのに、灰はあとで、たき木はその前だと見てはなりません。いいですか、たき木はたき木としてのあり方にあって、あともあれば前もあります。前後はありますが、前は前、後は後と、それぞれ別なのです。灰は灰としてのあり方にあって、後もあり、前もあります。そのたき木が灰となってしまってから、もうたき木にならないように、人が死んでから、もう生になることはありません。ということなので、生が死になると言わないのは、仏法がいつに変らず説くところです。ですからこの生を不生というのです。死が生にならないのは、仏がきまって説かれる法です。ですからこの滅を不滅というのです。生も一時(そのとき)の(全体の)あり方です。言ってみれば、冬が春になるとは思わないのです。春が夏になるとは言わないのです。
人が悟りを得るのは、水に月がやどるようなものです。月もぬれず、水もこわれされません。月はひろく大きな光ですが、尺寸(わずか)の水にやどり、月全体も天(そら)全体も、草の露にもやどり、一滴の水にもやどります。さとりが人をこわさないことは、月が水に穴をあけないのと同様です。人がさとりの罣礙(さまたげ、ケイゲ)にならないことは、一滴の露が天月をうつす罣礙(さまたげ)にならないのと同様です。月影が深いことは、月の高さを示すものでしょう。さとりの時節がいつからかということは、水に大小があるか撿点(よくしらべ、ケンテン)、天月に広い狭いあるかを考えてみたらいいでしょう。(138~140頁)
■修行によって、身心に法が充分にゆきわたらない間は、法はこれで充分だと思われます。法がもし身心に完全にゆきわたると、どこか一面に不足があるように感じられるものです。たとえば、舟にのって、岸も見えない大海のまっただ中に出て四方を見ると、あたり一面ただ丸く見えるばかりです。そのほか別な相(かたち)は見えません。ではありますが、この大海は、丸いのでもありません、方(しかく)いのでもありません。これ以外の海の徳(ありかた)は、言いつくせるものではないのです。水は、魚が見れば宮殿に見え、天人が見ると瓔珞(たまのかざり、オウラク)に見えるようなものです。ただ自分の眼で見る範囲内で、一応丸く見えるばかりです。このたとえのように、万法もまたそうなのです。世間的に、また仏法の上からも、多くの様子(ありさま)をそなえているのですが、修行の力の及ぶ範囲だけを見て、理解しているのです。万法そのもののあり方を知るには、さきの海のように、四角い、丸いと見えるほかに、残された海の徳(ありかた)、山の徳(ありかた)が多くあってしかもきわまりなく、四方のさまざまな世界があることを知らなくてはなりません。周囲だけがこのようにあるのではありません。すぐ足もとも、一滴の水も、このようであると知りなさい。(140~141頁)
■魚が水を泳いでゆきますが、泳げども泳げども水に終りがなく、鳥が空を飛びますが、飛べども飛べども空にははてしがありません。ではありますが、魚も鳥も、かって水を離れたことがなく、空を離れたことがありません。ただ大きく用いるときは使い方がおおきく、少ししかいらない時は使い方が小さいのです。このようにして、そのときそのときに全存在をつくしているのであり、その所その所に力一杯の生き方をしているのですが、鳥がもし空から飛び出せば、たちまち死んでしまいます。魚がもし水を出れば、たちまちに死んでしまいます。魚は水が命であることがわかるでしょう、鳥は空が命であることがわかるでしょう。鳥は鳥を命とするということもあります、魚は魚を命とするということもあります。命が鳥としてあったということでしょう、命が魚としてあったということでしょう。このほかさらに進んで言うことができるでしょう。生きているところに絶対の修行があり、その実証があり、そこに寿命という連続したものがあるというのは、このようなことです。ということであるのに、水を知りつくし、空を知りつくしてから、水や空をゆこうとする鳥や魚があるなら、水にも空にも、ゆくみちが得られないでしょう、生きるところが得られないでしょう。この自分の生きているところが自分のものになれば、この日常生活がすぐさま絶対の真実の実現となります。この生きてゆくみちが自分のものになれば、この日常生活がすぐさま絶対の真実の実現です。このみち、このところ、これは大でもなく小でもなく、自分でもなく自分以外のものでもなく、以前からあるのでもなく、今はじめて現われたのでもないからこのようにあるのです。(141~142頁)
■そういうように、人がもし仏道を修行し、実証するにあたっては、実証するにあたっては、一法を得て一法に通じるのです。一行に出会って一行を修行するのです。そこに、自分の生きるところがあり、そのみちは全体の事実に通達しているので、修行して知られる内容がどのあたりまでか、はっきりしないのは、この知るという事実が、仏法の究極と全く一致してしまっているのでそのようにあるのです。修行して得たところが、必ず自分の知るところとなって、自分の意識でとらえられるものと思ってはなりません。修行すれば証(さとり)の究極は直ちに現前するのですが、自己に最も親しい真実は必ずしも現前した事実ばかりではありません、現前した事実は、これこれと判断してとらえることはできないものです。(142~143頁)
■麻浴山(まよくざん)の宝徹禅師が扇を使っていたおり、僧がやって来てたずねました、「風性(ふうしょう)は常住(いつもあるもの)で、あまねくゆきわたらないところはありません、どういうわけで和尚さまはその上扇を使われるのですか。」
禅師が言われます、「おまえさん、ただ風性が常住(いつもあるもの)だということは知っているが、どこといってゆきわたらないところがない道理を知らないね」と。
僧が言います、「どこといってゆきわたらないことがない道理とはどういうことですか。」
この時、師は扇を使うばかりでした。
僧は礼拝しました。
仏法のさとりのたしかな証拠、仏から正伝された生き生きした生き方は、まさにこのとおりです。常住(いつもあるもの)なら扇を使うことはあるまい、扇を使わない時も風があるだろうというのは、常住ということもしらず、風の正体も知らないのです。風性は常住ですから、仏の家の家風は大地を黄金として現前させ、修行熟しては長河(揚子江)の水まで蘇酪(そらく)といった最高の飲みものとするのです。正法眼蔵現成公按第一
これは、天福元年(1233)八月十五日のころ、太宰府の俗弟子揚光秀に書いて与えたものです。(143~144頁)
(2014年12月14日)