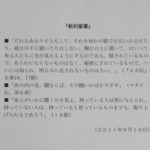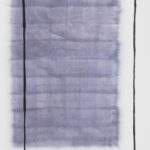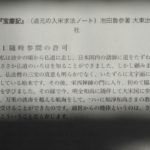『道元集』 日本の思想2 筑摩書房
真理の体現者 道元 玉城康四郎
■道元はこのような海印三昧をとり上げて仏祖の道をといている。ここで道元の思索の特徴について触れてみよう。通常、思索するという過程は、認識の主体と認識の対象との相対関係によって成り立っている。認識の主体が対象を認識する場合に、対象は動的なものであれ、静的なののであれ、それを認識する主体は、それ自身は認識し得ないものとして固定したものとなる。道元の場合には、このような主体と対象との相関性、したがってまた固定した主体というものを徹底的に払っていく。道元は通常の意味の認識関係をどこまでもしりぞけて、主体と対象との相関性を超えた、あるいはそれを離れた世界、いいかえれば現在即今に開示されている世界――道元のいう恁麽(いんも)――を究明して止まない。したがって究明している道元の主体そのものは、即今に開示されている世界のなかに解消し、あるいはそれに埋没し、いいかえれば主体は世界そのものとなって、その世界を究明するのである。ここに道元の独特の思索が展開する。(19頁)
■海印三昧の究明も、その代表的なものである。しばらくその跡をたどってみよう。
ここで海というのは、仏法の大海のことである。現にいま、ありとあらゆるものがこの大海に遊泳している。しかし大海が万物を包含しているのではない。いいかえれば、大海と万物が相対しているのではない。そうではなく万物のあるがままが海印三昧である。いかなる一物も、徹底徹尾、自由自在に遊泳している。道元は、このことを
「海上行(こう)の功徳、その徹底行あり、これを深深海底行なりと海上行するなり。」(『正法眼蔵』「海印三昧」)
といっている。
これは異様な世界表現であるが、その意味はつぎのごとくなるであろう。すなわち、海面を泳ぎながら、しかもその足は海底に撤しているのである。あるいは、深々と海底を行くままで海面を泳いでいるのである。(19頁)
■しかるに海印三昧における万物は、海面を泳ぎながら、足が底についているという。つまりこの世に活動しながら悟りに徹底しているのである。これはたしかに自覚の世界であるが、しかし自覚によって始めてそうなっているのではない。意識しようとしまいと、それは自覚以前の海印三昧の実情である。このことは、きわめて重要な視点であり、そしてこの点にこそ、道元にまで正伝し来たった仏祖の世界がかかっている。それは要するに、意識を離れて、いかなる一物も、何物にも疎外されることなく、徹底的にあるいは底抜けて自由に活動している三昧の事情を表わしているであろう。(19~20頁)
■では、この場合における此の身とは何を指すのであろうか。それはもとより自我ではない。そうではなく、それこそまさに法なのである。法とは、たんなるものではなく、また心でもない。それは、海印三昧、すなわち宇宙そのものの仏の世界にあり、かつその世界から見られているものである。だから、心的なものであれ、物的なものであれ、また事象であれ、ことごとく海印三昧にあり、なに一つ法でないものはない。そのような無数の法が集中して此の身が成立しており、そしてそれもまた法である。(20頁)
■道元は『維摩経』の文を引きながらつぎのように述べている。
「但、衆法(しゅぼふ)をもって此の身を合成(がふじやう)す。起る時は唯法の起るなり。滅する時は唯法の滅するなり。此の方の起る時、我起ると言はず。此の法の滅する時、我滅すと言はず。前念後念、念念相対せず。前法後法、法法相対せず。是を即ち名づけて海印三昧となす。」(「海印三昧」)
此の身は、多くの法によって合成されており、此の身が起るのは法の起るのであり、此の身が滅するのは法の滅するのである。それを自我が起ったり滅したりとはいわない、という。つまり自我という別人がいて、法の起滅を見聞しているのではない。そうではなく、無数の法によって合成されている此の身が起滅しているだけである。それは自我ではなく、無数の法の集中している全体の法が起滅している。起っている時は起っているだけ、滅する時は滅するだけである。たとえば春になった時は、春の全体が起っており、夏になった時は、夏の全体が起っており、そしてただ起っているのみである。道元はこれを、
「起はかならず時節到来なり、時は起なるがゆえに。いかならんかこれ起なる、起也なるべし。」(「海印三昧」)
したがって、起っている時はただ起っているだけであるから、何一つ隠されているものはない。「皮肉骨髄を独露せしめずといふことなし。」という。皮も肉も骨も髄も、そして臓物までもさらけ出している。一物も隠すことのない全露のすがたである。そして滅する時も同じように、このような全露の法が滅するのである。(20~21頁)
■これまで論じてきたような王三昧、あるいは海印三昧の世界を、自覚の核心から見ればどうなるのであろうか。そこには底抜けの希望と明るさと、永遠の解脱が息づいている。微塵の暗さもペシミズムもない。道元は、それを、明珠とも光明とも、あるいは仏性とも表現している。『正法眼蔵』には、「一果明珠(いっかみょうじゅ)」という巻がある。このなかに、「尽十方界、是れ一顆の明珠」という一文がある。全宇宙が一つの珠である、という。宇宙が一つの珠であるというのは、いったい何を意味しているのであろう。宇宙といえば、数かぎりのない日月星辰を思い浮べるであろうが、ここでは、外に見られた日月星辰を指すのではない。前の海印三昧においても触れたように、主体の自覚から見ているのである。主体における執着の絆が断たれて、内から外に向って門戸が開かれたときに、主体は宇宙と吹き通しになる。主体は宇宙と本質的に一体となるのである。その際の主体の自覚は、もはや自我意識にかこまれた個別的なものではない。此の身に生じている点ではまさに己の自覚ではあるが、自我意識の柵がはずされて宇宙意識となっている点では普遍的である。いわば、自己と普遍、主体と宇宙とが一つらなりになっているといえよう。そのような自覚の世界が一個の明珠というのである。(22頁)
■そうだとすれば、全存在そのものは、一物も隠すことなく、むき出しのまま(偏界不曽蔵)というほかはない。そしてこのむき出しの存在そのものには、もはや主客の対立は解消してしまっている。つまり、存在そのものを見ている主体と、見られている存在そのものとの相関性は消失している。見ているものも見られているものもなくて、全存在が同一のむき出しである。だから強いていえば、このむき出しの存在は、存在がそのまま存在であるという、存在と自覚の二重性が、同一的に拡充し尽くされている。
このような性格を道元の表現に即していうと、存在そのもののむき出しは、永遠の過去から現在刹那に貫通しており(亙(こう)古亙今)、これに一物も加える余地がなく(不受一塵)、かつその全体が完結しており(合取)、そして真理の当体であり(是什麽物恁麽来)、しかも日常生活そのままの心(平常心是道)である。したがって、あらゆる存在はそのまま、透明であり解脱している(透体脱落)、というのである。(24頁)
■生活即仏道を、かれは行持というのであるが、それは、行を続けることによって生活のなかに仏道の真実を保持していくことを指していると思われる。したがって行持は、生活者における仏道の持続的な展開であり、行持よって仏道は、始めて生活のなかに具現していくということができる。道元は、
「諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成し、われらが大道通達するなり。われらが行持によりて、諸仏の行持見成し、諸仏の大道通達するなり。」(『正法眼蔵』「行持」)
われわれの行持が実現するのは仏祖の行持によるのであり、仏祖の行持が実現するのはわれわれの行持による、という。仏祖とわれわれとは、行持によってつながっており、行持によって、仏祖正伝の大道が顕わになるのである。とすれば、行持はまさに仏祖のいのちであるということができよう。しかもかれは、
「無上の行持あり。道環して断絶せず。発心・修行・菩提・涅槃、しばらくの間隙あらず、行持道環なり。」(「行持」)
と述べている。(28頁)
■つまり、全世界は一つの透明なたまであるというのだが、その全世界についての説明である。道元は、世界をたんなる空間と見て、それを一つのたまといっているのではない。そうではなく、どこまでも自己の活動の持続として全世界をとらえ、しかもそのなかに超越的なものを体認しようとしている。右の文に即していうと、全世界というのは、間断なくつづく逐物為己・逐己為物であるという。つまり、物を追究しても結局は己以外のものではなく、逆に、己を追究しても結局は物に外ならぬ、物と己とが対立的にあるのではなく、たがいに全面的に相手を吸収し合いながら活動して止まぬ、それがすなわち全世界であるというのである。
しかもこのような実態の体認をさまたげているものは、分別の情感である。いわば認識の対象性ともいうべきものであろう。その分別が生ずると、真実の智慧が隔たるのである。しかし隔たるといっても世界の実態から離れてしまったのではない。ただ頭や顔の向きをかえただけのことである。向きが変わっただけで、実態のなかにあることには相違ない。そうはいうものの、真実の智慧が隔たっていることにはちがいないから、その隔たりを体認しなければならない。このようにして、逐物為己・逐己為物が間断なく続くのである。しかも世界の実態は、いかなる主体の認識・行為にも先立つ真理であるから、したがっていかなる主体のさばきも、なお手にあまるのである。いわば、いかなる主体をも超越する実態の道理は、かえって主体の全領域へその背後から垂幕しているといえよう。このように、主体を超え・包み・貫ぬく実態の光明こそ、一顆の明珠(一つの明るいたま)なのである。(37頁)
■では実存的思惟によってはどうか。道元が理性的立場によって理解されないことはいうまでもないが、実存的思惟は、自己の存在そのものを主題とし、思惟者と主題とが同一であるという点で特徴的である。このような思惟の主体性によって、道元的世界が無理解の状態から少なくとも理解につながる境位へ移入することは可能であろう。しかしその理解の境位とは何であろうか。それはせいぜい、道元の表明しようとする世界がおぼろげながら感知され、ある程度追経験される位のものではあるまいか。理性的立場による無理解よりはましであるとしても、この程度ではなお不徹底である。
理解をさらに推進するためには、実存的思惟に加うるに、いわば身体的思惟、すなわち行(ぎょう)が要請されるのである。道元のいわゆる只管打坐である。この打坐は、もっとも単純な形式である。この形式の日常的な繰り返し、そしてそれを長期にわたって持続することが重要である。(42頁)
■「仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の辧道すなはち本証の全体なり。かゝるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指の本証なるがゆえなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし。」(辧道話)
修証一等というのは、修行と悟りとが同一であり、修行がすなわち悟りであるということを指している。悟りは、ここでは最高度の実証体験である。常識では、修行の後に悟りがあると解されやすいが、道元は明白にこれを否定する。そうではなく、悟りの上の修行であるから、最初の辧道がそのまま本来の悟りの全体である。したがって修行の後に悟りを期待する心はしりぞけられねばならぬ。修行のままが悟りであるから、悟りに終着点はなく、悟りのままが修行であるから、修行に出発点はないという。(43頁)
学道用心集
■まことに思えば、すぐれたものを愛することのできるほどの者が、当然すぐれたものを愛するのです。葉公(せつこう)が竜を愛したように、彫刻の竜ばかり喜んで、本物の竜が出てきた時気を失うようなことがあってはならないでしょう。(80頁)
■そもそも、仏道を学ぶには、最初入門の時、指導者の教えを聞いて、その教えの通りに修行します。この時、知っておくべき事があります。この時、知っておくべき事があります。よく云われる「法が我(じぶん)を転じ、我(じぶん)が法を転ずる」ということです。我(じぶん)が法を転ずる時は、我(じぶん)は強くて、法は弱いのです。反対に、法が我(じぶん)を転ずる時は、法は強くて、我は弱いのです。仏法にはもともとこの二つの時節があります。仏祖の法の正統なあとつぎでないと、このことを全く知っていません。達磨門下の禅僧でないと、その名さえ聞くことがありません。もしこの故実(ひけつ)を知らないと、仏道修行がどうしても力一杯行なわれません。修行が正しいか正しくないかの判別がどうしてつきましょう。(81頁)
■慧能禅師は、黄梅山に五祖(大満弘忍)禅師をたずねて法を求めた時、面目をなくし、二祖慧可大師は少林寺に達磨大師をたずねて法を求めては自ら臂腕(ひじ)を断ちました。こうして師の骨髄を得、自己の生き方をすっかり改めて、仏祖としての日常生活の風流(しかた)を買うのです。師を礼拝し、自己の正体を反省する坐禅をすると、そのまま仏のさとりにおちつくのです。
ではありますが、心においても身においても、住着(とどまる)ことがなく、さらさらとしていて、留帯(とどこお)るところがありません。
趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)禅師にある僧がたずねました、「狗子(いぬ)にも仏性がありますか、どうですか。」
趙州が言いました、「無。」
「無」の字の上に、おしあて、おしはかることがあり得ますか。とりつき滞(とどこお)っていられますか。全然とらえどころがないのです。
ためしに後生大事に持っているものから手を放してくれませんか、ちょっと手を放してみなさい。「身心は如何(どう)か、行李(おこない)は如何(どう)か、生死はは如何(どう)か、仏法はは如何(どう)か、世間のものごとは如何(どう)か、山河大地、人、動物、家屋は如何(どう)か。結局のところ如何(どう)なのか」と。
こうして次々に反省してゆくと、自然に、動くと静まるとの二つの相は絶えておこりません。この差別の相の全くおこらない時、しかもこれは心の働きが全くなくなったのではありません。この境地は、人間では実証することがありません。ここのところがわからずに、迷う者は実に多いのです。
参禅学道の人よ、とにかく半分迷っていればそれで充分です、全部迷っていても、しりごみしてはなりません。(ただひたすら修行するのです)わたしが祈禱(いのり)に祈禱(いのる)ところです。(83~84頁)
■右について。仏道を学ぶ丈夫(りっぱなひと)は、まず何としても道に向って修行をするのに、正しいのとただしくないのとがあることを知らなければなりません。
そもそも釈迦牟尼如来は、菩提樹のもとに端坐せられ、明星を見ることを得て忽(たちま)ちに無上の乗りものである真実の道をその場でお悟りになりました。その悟られたところの真実は、声聞とか縁覚などの到底及びもつかないところです。仏だけが自ら悟ることができるのであり、仏から仏にだけ伝えられて今に断絶(とぎれ)ることがないのです。この悟りを得た者が、どうして仏でないことがありましょう。
ここにいう「道に向う」とは、仏道の涯際(はてのはて)まで、余すところなく身につけるのです。仏の様子(ありかた)を明らかにするのです。仏道は人々(めいめい)の立っている足元にあります。道と全く一体となるので、その場で真実がすっかり明らかになるのであり、悟りとぴったり一致するので、その人が本来何不足ないその人自身になるのです。こういうわけで、よしんば最高に納得のいったところを示してみても、全体の真実の中の一部ですから、やはり「一半の悟」ということになってしまうのです。これがとりもなおさず道に向ってする修行の風流(やりかた)です。
現今仏道を学ぶ人は、道がどこで通達し、どこでふさがっているかの判断も着かず、無理にもはっきりした験(しるし)のあらわれることを好みます。これで間違わない人があるものですか。『法華経』に出て来る長者窮子のたとえ話のように、父を捨てて家を逃げ出し、自分のものである財産をすてて他国をよろめき歩いているのです。もともと長者の一人息子であるのに、長くよそ者の賤しい傭人になっているのです。まことに理由のあることです。
そもそも仏道を学ぶ者は、道そのものにならされることを求めるのです。道そのものになる者は、悟りのあとがなくなるのです。
仏道を修行する者は、まず何が何でも仏道を信じなさい。仏道を信ずる者は、何が何でも、自己が本来道(さとり)の中にあって迷惑(まよい)もせず、妄想もせず、顛倒(さかさま)な考えもなく、増(ふえ)もせず、減(へ)りもせず、悞謬(あやまり)もないということを信じなさい。このような信をおこし、このような道を明らかにして、それによって道の修行をすること、これがすなわち仏道を学ぶ基本です。
その修行の規則としては、心のはたらきのおこる根源を坐禅によって断ち切り、知識によって理解する方向に向わないようにするのです。これがとりもなおさず初心者を誘引(みちび)く方便(てだて)です。その後、身心の束縛をすっかりなくし、迷いと悟りとをさっぱり手放します。これがこれが第二段階の様子(ありかた) です。
おしなべて、自己が仏道にあることを信ずる人は特に得がたいものです。もし、自己が間違いなく道にあると信ずるなら、自然に仏祖の大道の通達するところとふさがるところとをはっきりさせ、迷いと悟りの由ってきたるもとを知るでしょう。
どなたも、ためしに心のはたらきのおこる根本を、坐禅して断ち切ってごらんなさい、十人中八人、九人までは、忽然(たちまち)に道を見ることができるでしょう。(83~87頁)
■直下承当(ちょっかじょうとう)ということ
右のついて。身心(からだぜんたい)を間違いない真実そのものにするのに、どうしても2つの面があります。師について法を聞くことと、力をつくして坐禅することとです。法を聞くことは心とそのはたらきを自在にし、坐禅は真実の修行とその実証とを手中におさめます。こういうわけで、仏道に入るには、やはり、どちらか1つを捨てても、真実をそっくり承当(うけとる)ことはできません。
そもそも、人はみな身心があります。その作(はたらき)には強い、弱いがあります。勇猛なのと、にぶくて劣っているのとです。あるいは動き、あるいは容儀をなすところ、この身心をもって直接に仏を実証する、これが承当(じょうとう)です。よく言われる、従来(これまで)の身心をどこへどう廻転(めぐら)すこともなく、ただ身心が真実を実証するに随ってゆくのを直下と名づけ、承当と名づけるのです。ただ身心の真実に随ってゆくのです、ですから、古くからもっていた見解ではありません。ただその真実をそっくり承当(うけとっ)てゆくだけです、ですから、新しくもぐりこむ巣のようなものではないのです。(88頁)
辧道話
■これらの等正覚(ほとけたち)は、さらに、反対に、目に見えないところで親しく資(たす)け合うみちが通じるので、この坐禅人は、確爾(しっかり)と身心が解脱の境地に立ち、これまでの雑(まじりけ)のある、穢れた感覚や意識や思量をたち切って、ありのままの真実である仏法にぴったりとかない、微塵の数ほどの無限に多くの諸仏如来の道場ごとにあますところなく、仏の説法教化のおこるのを助け、ひろく、仏となって仏をも立ちこえた聞法者に教えを垂れ、仏をもたちこえた法を勢いはげしく説き立てます。この時、十方のあらゆるものごとのある世界の土地・草木、牆(かきね)と壁、瓦と礫(いしころ)が、みな仏としての説法教化をするので、それらのおこすところの風や水などの利益にあずかるものどもは、みな、甚妙不可思議な仏の化導に、目に見えないところで資(たす)けられて、それ自身にそなわった最も親しいさとりをあらわします。これらの水や火を受け用いる仲間は、みな本来さとっている仏の化導を周(めぐ)り旋(めぐ)らせるので、これらの仲間といっしょに住み、話を通じ合っているものも、また残らずお互いに無窮の仏徳が備わり、次から次へと広くはたらきを及ぼして、尽きることなく、とぎれることなく、人間の思議も及ばず、はかりみることもできない仏法を、あらゆるものごとの存在する世界全体の内にも外にもゆきわたらせるのです。ではありますが、これら多くのことが、坐禅をしている本人の知覚に入ってこないようになっていることは、寂静無為の坐禅の中で、人間のしわざが全くなくなっている、直接の証(さとり)だからです。もし、世間一般の人の考えのように、修行とその実証としてのさとりを段階的なものとするならば、互いに別のものとして知覚し意識するはずです。もし、知覚や意識の範囲に入ってくるものならば、本来のさとりの大原則ではありません。さとりの大原則には、人間の分別・判断は手がとどかないのですから。(100~101頁)
■お教えしましょう――。きみが今、諸仏の正しい生き方、無上の大法(だいほう)である坐禅を、無内容にすわって何もすることがないと思うなら、これを、大乗をそしる人とするのです。迷いが実に深いことは、大海の中にいながら、水がないと言うようなものです。坐禅すれば、はや勿体なくも諸仏の自受用三昧にどっしりとおちついて坐っているのです。これが、広大の功徳をなす、ということではありませんか。気の毒にまあ、法の眼がまだ開けず、精神もひきつづき酔っぱらったままですね。
おしなべて、諸仏の境界(きょうがい)は、不可思議です。意識作用の手のとどくところではありません。ましてや、信ずることのできない、知慧の劣った人が知ることのできるものではありません。ただまっすぐに信じることのできるすぐれた聞法者だけが、入ることができるのです。信じることのできない人は、かりに教えたとしても、聞き入れることができません。『法華経』が説かれた霊鷲山(りょうじゅせん)でも、これ以上新しい教えを聞くには及ばないと言って席を立ち、釈尊から「退席するのもまあよろしい」と言われた連中(れんじゅう)がありました。おしなべて、心に正しい信仰がおこったら、修行し、師について学びなさい。そうでなければ、当分やめておいたらいいでしょう。そして、前世から法のめぐみがなかったことを自らうらむのです。(104~105頁)
■又、よく聞いてください、われわれは本来、無上の菩提(さとり)に何不足ないのです。いつにかわらず受用しているのですが、それをそっくり承当(うけと)ることができないので、むやみと頭で物を考えて概念をつくるくせがついていて、そのつくりあげた概念が実在するものとして追いかけるために、ひろびろした真実の道をわけもなく踏み誤るのです。この頭で考えた概念によって、眼病の人が空中に幻覚の花を見るように、実体のないかげがさまざまあらわれます。あるいは十二因縁で輪廻転生する身と思い、二十五有(う)という迷いの中の存在だと思い、声聞・縁覚・菩薩の三乗だとか、人天乗(にんでんじょう)・仏乗を加えて五乗だと言ったり、仏はあるとか仏はないとかいった意見は尽きることがありません。こうした概念の積みくずしをやって、仏道修行の正しい道だと思ってはなりません。
ということですのに、今はまぎれもなく仏の印形どおりに身をなして、万事を手放し、ひたすらに坐禅する時、迷いだ悟りだという人情による思慮分別の世界をとびこえて、凡夫か聖人かのあり方に関係なく、たった今、相対の世界の外に自在にあそび、無上菩提を受用するのです。あの魚とりかごや兎あみみたいな文字にかかずらっている者は、肩を並べることもできないのです。(108~109頁)
■証(さとり)と別でない修行がすでにここにあります、われわれは幸いにも、われわれ自身にそなわる不可思議の修行を自身伝えているので、初心でする坐禅修行が、そのまま自分の身にそなわる本来の証(さとり)を、人間の営みの全くないところで身につけるのです。おわかりでしょう、修行を離れてはあり得ない証(さとり)を、人間の生活で染汚(けが)されないようにするため、仏祖はしきりに修行の手をゆるめてはならないと教えられるのです。この不可思議の修行で手放しになると、本来成仏の証(さとり)は手のうち一杯になります。本来成仏の証(さとり)を一歩進めると、不可思議の修行は身(からだ)全体に行なわれます。(114~115頁)
■聞いたことがおありでしょう、祖師が言っておられます、「修行も証(さとり)もないではない。しかし、それは人間的なものとしてとらえてけがすことはできない」と。また、「真実の道(菩提)をはっきり見通した者が、真実の道を修行する」とも言っておられます。おわかりでしょう、道を得て、さとりのまっただ中で修行すべきであるということです。(115頁)
■おたずねします――。ある者は、次のようなことをいいます、「生れて死ぬことを憂い悲しむことはない。生死の苦しみからのがれ出るのにたいそう速い方法がある。世に言う心(しん)の本体が永遠不変であるという道理を知るのである。その説くところは、この身体は、生まれたからには必ず死への経過をたどるのであるが、この心(しん)の本体は決して滅することがない。生滅の法則に押し流されないですむ心の本体が自身にあることを知ってしまえば、これを本来の正体とするのであるから、今の身はこれはかりのすがたである。ここに死んではかしこに生れ、一定していない。心(しん)は、これは永遠不変である。過去、現在、未来ともに変わるはずがない。このように知るのを、生死の苦をのがれたとはいうのである。この趣旨を知る者は、これまでの生れては死に生れては死にのくり返しが全く断絶して、今生この身が終るとき、性海(しょうかい)という本体の世界に入る。この性海に流れ入る時、諸仏如来ののように不可思議の徳がまぎれもなくそなわる。現在は、たとい知ったとしても、前の世からのまよいの業によってつくられている身体であるから、諸仏とひとしくないのである。この趣旨を知らない者は、永久に生死の輪廻を続けるであろう。ということであるから、ただ急いで心(しん)の本体の永遠不変である趣旨をよくよく知るべきである。坐禅などといって、益もなくのんびり坐って、一生をすごしたところで、何の効果が期待されよう。」このように言う趣旨は、これはほんとうに諸仏諸祖の道にかなっておりますか、いかがでしょう。
お教えしましょう――。今言われた考えは、全然仏法ではありません、先尼外道の考えです。
それについて言えば、次のとおりです。先尼外道の考えは、「自分の身の中に一つの霊知(たましい)がある。その霊知(たましい)は、何かに出会うと、好き、嫌いを弁別し、是非(よしあし)を弁別する。痛い、かゆいを知り、苦か楽かを知るのは、すべてこの霊知(たましい)の力である。ところが、この霊知(たましい)の正体は、この身が死んでなくなる時、中味だけ抜けだして別の所で生れ変るから、永久になくならず、不変である」というのです。先尼外道の考えというのは、このようなものです。
そういうことであるのに、この考えを教わって仏法とするのは、瓦や石ころをつかんで黄金の宝と思うよりもなお間抜けです。おろかな迷いのはずべきこと、たとえようにもたとえるものがありません。大唐国の慧忠(えちゅう)国師がふかくいましめておいでです。今、心は不滅で、相(かたち)だけが死んでゆくという間違った考えをはじき出して、諸仏の妙法と等しいものとし、こんな生死(まよい)の根本原因をつくっておいて、それで生死の苦をのがれたと思うのは、間の抜けたことではありませんか、特にあわれむべきです。ただもうこれは外道の間違った考えだと知るのです、耳を傾けてはなりません。
話がここまできては、黙っているわけにもいけません、やむを得ず、ここに一層のあわれみをたれて、きみの間違った考えを救ってあげよう。いいですか、仏法では、本来身と心は全く一つのものであって、本体と様相とは二つでないと説きます。これは西天インドでも、東地中国でも、同じく人の知っているところです、この原則には決してはずれはしないのです。ましてや、仏法で不変を説く時には、あらゆるものすべてみな不変です。身と心とを区別することはありません。寂滅と、一瞬一瞬に消えてあとかたがないと説く時は、あらゆるものごとすべて寂滅です。本体と様相とを区別することはありません。ということであるのに、どうして、身は滅するが心は不変だなどと言えるでしょう。正しい道理にそむかないはずはないでしょう。そればかりではありません、生まれて死ぬ、この事実がそのまま涅槃(さとり)であると、よくよく自覚すべきです。仏法では、生まれて死ぬ、この事実のほかに涅槃(さとり)を説くことはないのです。ましてや、心は身と関係なく不変だなどと理解することで、生死の苦をのがれた仏の智慧だなどと考えちがいをしてみても、その理解し、分別する心は、その場でやはり浮んでは消えていって、全然不変ではありません。これはたよりないことではありませんか。
昔からいわれているところをよく観てごらんなさい、身と心とが一つであるということは、仏法がいつに変らず説くところです。それだのに、どうしてこの身が生滅するとき、心だけが身から離れていって、生滅しないということがあるでしょうか。もし、身と心が、一つである時もあり、一つでない時もあるなら、仏説はどうしてもうそいつわりになってしまうでしょう。又、生れて死ぬということは、取りのぞかなければならないことだと思っているのは、仏法をきらう罪となります。気をつけるべきです。
いいですか、仏法で「心性大総相の法門」といって説くところは、あらゆるものごとのある世界全体を含めて言うのであって、本体と様相とを分けることなく、生と滅と二つを分けて言うことはありません。菩提とか涅槃とかいわれるおさとりに至るまで、心の正体でないものはありません。あらゆるものごとすべて、宇宙に存在するすべてのもの、みなともに一つの心(しん)であって、全部中に含まれ、一つになっていないことがありません。この多くの法門(もの)は、みな平等なただ一つの心(しん)です。少しの異違(ちがい)もないと説くのが、これがすなわち仏法者がの正体を正しく知っているありさまです。ということであるのに、この唯一絶対の法において、身と心とを分けて考え、生死と涅槃とを区別することがありましょうか。われわれは仏の子なのです、外道の考えを述べる気違いが、舌をたたいて出す雑音は、耳にふれることもなりません。(116~120頁)
正法眼蔵第一 現成公按
■「現成公按」の「現成」とは、絶対の真実が今目の前に実現していることである。「公按」の「公」は平等、「按」は「分を守る」ことである(『正法眼蔵抄』の解釈による)。つまり「現成公按」とは、絶対の真実が現前していることであり、それはあらゆるものごとが平等に分を守っていることである。これが「諸法が仏法である」ということである。大乗仏教でよく言われる本来成仏ということも、つまりは一切が本来仏であったということである。
そして、この「一切が仏である」という事実は、人間のはからいと一切関係ない。このわたしではない。それが「万法われにあらざる」ということである。ここから、概念の世界をそのままにして、生きている身体をもってする修行がおこなわれる。「仏道もとより豊険(ほうけん)より超出す」とはこのことである。『正法眼蔵』では、多くの場合、開口一番に最も大切な基本原則が述べられていることに注意すべきである。(135頁)
■自己をはこんで万法を修行し、実証するのを迷とします。万法がすすんで自己を修行し、実証するのが悟りです。迷いを大悟するのは諸仏です。悟りに大迷いしているのが衆生です。さらに、悟りの上に悟りを得る漢(ひと)もあります、迷いの中でまた迷う漢(ひと)もあります。諸仏がまぎれもなく諸仏である時は、自己は諸仏であると自覚する必要はありません。ではありますが証仏です、仏を実証してゆくのです。
形あるものを見るには、身心(からだぜんたい)でもって見るのです、音あるものを聞くには、身心(からだぜんたい)でもって聞くのです、その時、たしかに対象を理解するのですが、鏡に物をうつすようなことではありません、水と月とのような関係ではありません。一方が実証されるときは、他方はかげになっているのです。
仏道を修行するということは、自己を修行することです。自己を修行するということは、自己をわすれることです。自己をわすれるということは、自己が万法に実証されることです。自己が万法に実証されるということは、自己の身心と、それに他己の身心をも解脱させることです。悟りのあとかたは全くなくなっています。全くなくなっている悟りのあとかたを、そのままどこまでも続けさせるのです。
人がはじめて法を求める時、法の辺際(あたり)をはるかに離れています。法が自分にまっすぐ伝わった時には、直ちに自己の本分におちついた人です。
人が舟に乗ってゆくのに、目を向うへ向けて岸を見ると、岸が動いてゆくように見間違えます。目をちかく自分の乗っている舟につけると、舟が進むのがわかります。そのように、身心の正体を正しく知らないで、万法を見分けようとすると、自己の正体は不変のものであるかと思い違いをします。もし自己の日常生活を深く反省して、箇裏(このところ、注;この現在の絶対のあり方)に帰して見ると、万法が我(じぶん)というものでない道理がはっきりします。(136~137頁)
■たき木が灰になります、それから逆にたき木になるはずはありません。ということであるのに、灰はあとで、たき木はその前だと見てはなりません。いいですか、たき木はたき木としてのあり方にあって、あともあれば前もあります。前後はありますが、前は前、後は後と、それぞれ別なのです。灰は灰としてのあり方にあって、後もあり、前もあります。そのたき木が灰となってしまってから、もうたき木にならないように、人が死んでから、もう生になることはありません。ということなので、生が死になると言わないのは、仏法がいつに変らず説くところです。ですからこの生を不生というのです。死が生にならないのは、仏がきまって説かれる法です。ですからこの滅を不滅というのです。生も一時(そのとき)の(全体の)あり方です。言ってみれば、冬が春になるとは思わないのです。春が夏になるとは言わないのです。
人が悟りを得るのは、水に月がやどるようなものです。月もぬれず、水もこわれされません。月はひろく大きな光ですが、尺寸(わずか)の水にやどり、月全体も天(そら)全体も、草の露にもやどり、一滴の水にもやどります。さとりが人をこわさないことは、月が水に穴をあけないのと同様です。人がさとりの罣礙(さまたげ、ケイゲ)にならないことは、一滴の露が天月をうつす罣礙(さまたげ)にならないのと同様です。月影が深いことは、月の高さを示すものでしょう。さとりの時節がいつからかということは、水に大小があるか撿点(よくしらべ、ケンテン)、天月に広い狭いあるかを考えてみたらいいでしょう。(138~140頁)
■修行によって、身心に法が充分にゆきわたらない間は、法はこれで充分だと思われます。法がもし身心に完全にゆきわたると、どこか一面に不足があるように感じられるものです。たとえば、舟にのって、岸も見えない大海のまっただ中に出て四方を見ると、あたり一面ただ丸く見えるばかりです。そのほか別な相(かたち)は見えません。ではありますが、この大海は、丸いのでもありません、方(しかく)いのでもありません。これ以外の海の徳(ありかた)は、言いつくせるものではないのです。水は、魚が見れば宮殿に見え、天人が見ると瓔珞(たまのかざり、オウラク)に見えるようなものです。ただ自分の眼で見る範囲内で、一応丸く見えるばかりです。このたとえのように、万法もまたそうなのです。世間的に、また仏法の上からも、多くの様子(ありさま)をそなえているのですが、修行の力の及ぶ範囲だけを見て、理解しているのです。万法そのもののあり方を知るには、さきの海のように、四角い、丸いと見えるほかに、残された海の徳(ありかた)、山の徳(ありかた)が多くあってしかもきわまりなく、四方のさまざまな世界があることを知らなくてはなりません。周囲だけがこのようにあるのではありません。すぐ足もとも、一滴の水も、このようであると知りなさい。(140~141頁)
■魚が水を泳いでゆきますが、泳げども泳げども水に終りがなく、鳥が空を飛びますが、飛べども飛べども空にははてしがありません。ではありますが、魚も鳥も、かって水を離れたことがなく、空を離れたことがありません。ただ大きく用いるときは使い方がおおきく、少ししかいらない時は使い方が小さいのです。このようにして、そのときそのときに全存在をつくしているのであり、その所その所に力一杯の生き方をしているのですが、鳥がもし空から飛び出せば、たちまち死んでしまいます。魚がもし水を出れば、たちまちに死んでしまいます。魚は水が命であることがわかるでしょう、鳥は空が命であることがわかるでしょう。鳥は鳥を命とするということもあります、魚は魚を命とするということもあります。命が鳥としてあったということでしょう、命が魚としてあったということでしょう。このほかさらに進んで言うことができるでしょう。生きているところに絶対の修行があり、その実証があり、そこに寿命という連続したものがあるというのは、このようなことです。ということであるのに、水を知りつくし、空を知りつくしてから、水や空をゆこうとする鳥や魚があるなら、水にも空にも、ゆくみちが得られないでしょう、生きるところが得られないでしょう。この自分の生きているところが自分のものになれば、この日常生活がすぐさま絶対の真実の実現となります。この生きてゆくみちが自分のものになれば、この日常生活がすぐさま絶対の真実の実現です。このみち、このところ、これは大でもなく小でもなく、自分でもなく自分以外のものでもなく、以前からあるのでもなく、今はじめて現われたのでもないからこのようにあるのです。(141~142頁)
■そういうように、人がもし仏道を修行し、実証するにあたっては、実証するにあたっては、一法を得て一法に通じるのです。一行に出会って一行を修行するのです。そこに、自分の生きるところがあり、そのみちは全体の事実に通達しているので、修行して知られる内容がどのあたりまでか、はっきりしないのは、この知るという事実が、仏法の究極と全く一致してしまっているのでそのようにあるのです。修行して得たところが、必ず自分の知るところとなって、自分の意識でとらえられるものと思ってはなりません。修行すれば証(さとり)の究極は直ちに現前するのですが、自己に最も親しい真実は必ずしも現前した事実ばかりではありません、現前した事実は、これこれと判断してとらえることはできないものです。(142~143頁)
■麻浴山(まよくざん)の宝徹禅師が扇を使っていたおり、僧がやって来てたずねました、「風性(ふうしょう)は常住(いつもあるもの)で、あまねくゆきわたらないところはありません、どういうわけで和尚さまはその上扇を使われるのですか。」
禅師が言われます、「おまえさん、ただ風性が常住(いつもあるもの)だということは知っているが、どこといってゆきわたらないところがない道理を知らないね」と。
僧が言います、「どこといってゆきわたらないことがない道理とはどういうことですか。」
この時、師は扇を使うばかりでした。
僧は礼拝しました。
仏法のさとりのたしかな証拠、仏から正伝された生き生きした生き方は、まさにこのとおりです。常住(いつもあるもの)なら扇を使うことはあるまい、扇を使わない時も風があるだろうというのは、常住ということもしらず、風の正体も知らないのです。風性は常住ですから、仏の家の家風は大地を黄金として現前させ、修行熟しては長河(揚子江)の水まで蘇酪(そらく)といった最高の飲みものとするのです。正法眼蔵現成公按第一
これは、天福元年(1233)八月十五日のころ、太宰府の俗弟子揚光秀に書いて与えたものです。(143~144頁)
(2014年12月14日