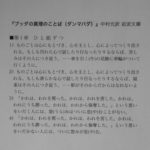『道元』 坐禅ひとすじの沙門 今枝愛眞 NHKブックス
■道元は、「人はいかに生きるべきか。それをさとるためには、じぶんとはいかなるものなのか」、まずこの本来の自分というものを本当に知らなければならないと考えた。それは、どうしても見究めておかなければならない最初の大きな関門である。道元の将来を決定する重要なわかれ道でもあった。ここで、はたと行きづまったのは、天台宗の基本的なものの考え方である。それは「本来本(ほん)法性、天然自性身(じしょうしん)」という言葉についてであった。
もともと一切の人間は、誰でも仏性、つまり仏の本性をそなえ持っている。このような意味は、本覚思想ともいわれ、天台宗の最も根本的な考え方なのである。この考え方に対し、道元の心にいろいろな疑問が湧いてきた。たとえば、もしそのように、人そのものにすでに仏性がそなわっているならば、なぜわれわれは苦しい修行を実践しなければならないのであろうか。また、すでに諸仏や祖師が菩提心(悟りを求めて仏道を行じようという心)を起して修行を続ける必要があると説いたのは、どういう訳か。それにはそれだけの理由がなければならないが、果してそれは何なのか。道元は、こうした学問と修行に関する根本的な疑問を懐くにいたったのである。(30頁)
■建保2(1214)年、道元は山を下り、独自の新しい道を発見するため、園城寺長吏の公胤(こういん)僧正を訪ねた。それは、公胤も道元と同じ村上源氏の出身で、久我家や松殿家と親しいという間柄だけでなく、公胤は園城寺の座主を再度つとめた高名な学僧であり、大原問答で法然とも交流があるなど、当時の宗教界に強い影響をもつ進歩的な人物であったからではないかと思われる。
さっそく疑問を打ち明けてその教えを請うたのだが、公胤は道元の疑問には何も答えず、ただ、
「現在の中国では、達磨大師以来の祖師たちが、内面的な体験を通して伝えてきた禅宗が盛んである。あなたが求めている宗教には、それが最も適しているように思われる。大陸に渡って、その新しい宗教学んでくるのが一番よい」
と、ひたすら入宋(にっそう)を勧めるのであった。(31頁)
■こうして、公胤との出会いは、道元の一生に大きな影響を及ぼすにいたった。それは同時に、次の栄西との相見(しょうけん)にもつながっていたのである。おそらく公胤に会っていなかったならば、道元は別の道をたどったかも知れない。まことに、人と人との出会いというものは、その人の運命を左右するものである。(32頁)
■その頃のことである。さきの老典座(てんぞ)が再び道元を訪ねてやって来た。そしていうのには、
「わたしは最近、阿育王山の典座職をしりぞいて、これから故郷の西蜀に帰るところです。たまたま仲間のものから、あなたが天童山にいられると聞いたので、ぜひお目にかかりたいと思って、こうしてやって来ました」
異郷で、こういって励ましてくれた老典座の温情に、若き日の道元はどれほど感激したことであろう。以前にもまして、厳しい修行への決意を新たにしたにちがいない。
信頼と喜びで夢中になって話しているうちに、まえに船中でかわした学問や修行の問題になった。
ときにこの老僧は、
「文字を学ぶものや修行をするものは、それが何であるかをよくのみこむ必要がある」
といった。そこで道元が、
「それでは、文字とはどういうものなのですか」
と聞きかえすと、
「一、二、三、四、五、これが文字というもので、特別のものがあるわけではない」
と答えたという。そこで道元は、
「それでは修行とはどういうことですか」
と尋ねた。老僧は即座に、
「全世界すべての現象が、そのまま真理そのものであって、みな学問・修行の対象でないものはない」
と答えた。人類万物に共通な絶対の真理を見究めるのが禅の悟りであると教えられたのである。
このほかにも、道元にはいろいろ問答をかわしたが、それらを通じて、この老僧から大陸禅の手ほどきをうけた。のちになって、道元が自ら述懐し、「いささか文字を知り辨道を了ずる(真理の探究ができたこと)は、すなわち彼の典座の大恩なり」と『典座教訓』のなかで讃え、「いよいよ知る、彼の典座はこれ真の道人なることを」と、つねに老典座を追慕してやまなかったことによっても、この老僧から如何に多くを学んだかがわかるであろう。
老典座との出会いによって、道元は修行とは何であるかを知り、禅こそ自分がこれまで求めていた理想の宗教であることを、改めて確認し、いよいよ本格的な大陸禅の修行に取り組んでいったのである。(41~42頁)
■道元が天童山で修行していた夏のある日のことである。ちょうど昼食が終って廊下を歩いていく途中、仏殿のまえで用(ゆう)という典座が、これまた椎茸の話であるが、それを乾かしていた。手には竹の杖をもっているが、頭には笠もかぶっていない。太陽はさんさんと照りつけ、敷瓦は焼けつくように暑い。典座は、したたる汗もかまわず、精を出して椎茸を乾かしている。いかにも苦しそうである。その背骨は弓のように曲がり、長い眉毛は鶴のように真白い。聞けば、すでに68歳にもなるという。道元は、「そんな仕事は若い修行者にやらせればよいのに、どうしてそれをなさらないのですか」と尋ねた。すると典座は、「他はこれ吾れにあらず」――他人にやってもらったのでは、自分がしたことにはならないからですと答えた。そこで、道元はさらに、「あなたのやっている作業は、確かに法にかなっていて、実に見上げたものだと思います。けれども、こんな炎天下で、どうしてそんなに苦しんでやる必要があるのですか」と尋ねた。すると典座は、即座に、
「さらにいずれに時をか待たん」
と答えた。いまやらなければ結局やらないことになってしまう、いまやらなければ一体何時やるときがあるというのかという。この用典座の修行に対する厳しい態度を知って、道元は深く頭が下がる思いがし、ただもう沈黙のほかはなかった。道元は廊下を歩きながら、典座という役目も禅修行の大切なかなめであることを、しみじみと、ここで又悟るのであった。(44~45頁)
■また毎朝道元の隣りの席で、一人の修行僧が一日の修行を始める前に、必ず袈裟を頭の上におし戴いて、次のように高らかに唱えてから、身にまとった。
「大なるかな解脱服、無相の服田衣(え)、如来の教へを披奉(ひぶ)して、広くもろもろの衆生を度せん」(「袈裟功徳」巻)
この袈裟は、人間のあらゆる執着や煩悩をすべて取り除き、世の中に幸福をもたらすことができる法衣である。これを肩にかけ、釈尊の教えを正しく受け継ぐことによって、それを世間にひろくおしひろめ、いきとし生けるものを迷いから救済しよう。
このような教えが経典にみえたいることは、まえまえから道元も知ってはいた。しかし、その作法などについては、これまで一度も見たことも教えられたこともなかった。
「あはれむべし。郷土(日本)にありしとき、をしふる師匠なし。すすむる善友あらず。いくばくか、いたずらにすぐる光陰を、をしまざる。かなしまざらめやは。いまの見聞するところ、宿善(前世の善業)よろこぶべし。もしいたづらに郷間(日本)にあらば、いかでか、まさしく仏衣を相承着用せる僧宝(修行者)に隣肩することをえむ。非喜ひとかたならず。感涙千万行」(「袈裟功徳」巻)
道元は入宋したおかげで、いまこうして敬虔にして厳粛な作法を直接眼のあたりに見ることができ、深い感動をおぼえ、感涙にむせんだという。
「いかにしてか、われ不肖なりといふとも、仏法の嫡嗣(ちゃくし、正しい継承者)となり、正法(ぼう)を正伝して、郷土の衆生をあはれむに、仏祖正伝の衣(え)法を見聞せしめむ」(「袈裟功徳」巻)
■こうして、道元は禅修行の艱難に堪えていくうちに、釈尊の正法とはどういうものか。その核心はいったいどこにあり、どのようにして正法は伝えられてきたか。さらにまた、悟りの実体に迫るにはどうすればよいのかという、求道における真の在り方が、少しづつわかりかけてきたのだった。そして彼は、その根源をいよいよ深く探るためには、悟りを開いた証(あかし)として、師から直接弟子に授けられる嗣書(ししょ、伝法を記した相承図。血脈・宗派図ともいわれる)について、まず禅宗各派の実態を調べてみる必要があると考えた。
けれども、嗣書は禅の奥儀を示すものである上に、各派の秘事に属する大切なものであるから、容易に他見を許されないのが常である。まして24歳の若さの、しかも、外国の一修行者では、なおさらのことである。しかし、そこには道元のなみなみならぬ精進があったことはいうまでもない。道元は次々にその真剣な修行態度が認められ、禅宗各派の嗣書を直接手にとって観るという、極めて貴重な体験に恵まれた。(49頁)
■たとえ各宗派によって嗣書の形式がそれぞれ違っていても、ただ雲門宗の場合はこうだ、というように理解すべきである。なぜ釈尊が他の人にくらべて特に尊いのかといえば、それは釈尊の人物というより、釈尊が開いた悟りが尊いからなのである。それと同じように、雲門宗を開いた文偃(ぶんえん、864-949)が尊いというのも、雲門文偃の悟りが尊いからなのである。
各宗派によって嗣書の様式に相違があっても、それはそれとして認めればよい。大切なことは、悟りそのものであって、嗣書の様式ではない。こうきっぱり断言した宗月の自信にみちた言葉は、道元の心に強く響くものがあった。(50頁)
■道元は、「真の正師に指導を受けるかどうかによって、修行者が本当に悟りを開くことができるか、その悟りが偽りになってしまうかに別れる。だから、真の正師を見付けることができなければ、なにも学ばないのと同じことになってしまう。真の正師に会うことができるかどうかに、悟りの成否がかかっている」と考えていたのである。正師に会えないことに、道元はいらだちを覚えた。そして自分が本当の正師と仰ぐような理想的な禅人は、今の中国にはもういないのではないか。これ以上大陸に留まっていても所詮無駄ではないか。もしそうならば、日本に早く帰った方がよいのではなかろうか、と大陸禅に失望を感ずるようになっていた。(69頁)
■道元はこの尊い体験を「面授」の巻で次のようにのべている。
「大宋宝慶(ほうきょう)元年乙酉5月1日、道元はじめて先師天童古仏(如淨)を(天童山)妙高台に焼香礼拝す。先師古仏、はじめて道元をみる。そのとき、道元に指授面接するにいはく、仏々祖々面授の法門、現成せり(完璧な形で実現した)」(「面授」巻)
道元はさらに続けて、「このように如浄と自分との間で完璧に行なわれた面授こそ、釈尊が霊鷲山(りょうじゅせん)で説法のあと花をひねって聴衆をみたところ、摩訶迦葉一人だけがその意味を悟って微笑したという、有名な拈華微(み)笑の故事や、嵩山(すうざん)の少林寺で達磨と二祖恵可との間でとりかわされた悟りの証明の仕方、あるいは、黄梅山で五祖から六祖慧能に法衣が伝えられたときの法式、さらに雲岩曇晟(どんじょう)から洞山良价への伝法など、禅宗の伝統のなかでも特に典型的なものとされている法の伝授の仕方と全く同等の価値がある。まさしくこれは釈尊の伝法の理想的な形で、他の人は夢にも見たことがない唯一のものである」と力説している。いかに道元がこの面授の体験に強い確信をもつに至ったかがわかるであろう。
こうして如淨との対面は、道元に決定的な影響を与えた。もはや道元入宋の大目的は、ほぼ達成されたといってよかった。あとはただ、如淨から直伝された釈尊の大法を、日本に持ち帰るだけである。道元は感動し、それまでの驕慢な心はたちどころに失せ、正法を日本に伝来するためには、正師と仰ぐ如淨のもとで一層厳しい修行を積みかさね、さらに悟りを深め、真に禅の大事を学び終らなくてはならないと考えた。
そのころの心境を、道元は次のように述べている。
「いま現在、大宋国一百八十州の内外に、山寺あり。人里の寺あり。そのかず稱計すべからず。そのなかに雲水(修行者)おほし。しかあれども、先師古仏(如淨)をみざるはおほく、みたるはすくなからん。いはんや、ことばを見聞するは少分なるべし。いはんや相見(しょうけん)問訊(もんじん)のともがらおほからんや。いはんや堂奥をゆるさるゝ、いくばくにあらず。いかにいはんや先師の皮肉骨髄、眼晴面目(全人格)を礼拝することを聴許せられんや。先師古仏、たやすく僧家の討掛塔(とうかた)(そのもとに長くとどまって修行すること)をゆるさず。(中略)このくにの人なりといへども、掛塔(かた)をゆるさるゝのみにあらず、ほしきまゝに堂奥に出入して、尊儀(如淨を指す)を礼拝し、法道をきく。愚案なりといへども、むなしかるべからざる結(けち)良縁なり」(「梅花」巻)(58~59頁)
■ところが、如浄のもとに参じて間もない宝慶元年(1225)5月、師とも先輩とも仰ぐ明全が、天童山の了然寮で亡くなった。42歳であった。
はじめ師の栄西の意志をついで日本の天台宗を復興しようと考えていた明全は、その2年ほどまえに明州の天台宗景福寺を訪ねたのだった。しかし、大陸の天台宗の衰微は予想をはるかに上廻っていて、殆んど学ぶべきものがなかった。それに引き換え、江南の地一帯は、禅宗一色に塗りかえられていた。そこで明全は、改めて大陸禅を本格的に学ぶため天童山に移り住んで、この2年余り修行につとめていたのである。歳月あたかも流星のごとく、道元がはじめて建仁寺で師事してから、すでに9年の歳月が流れていた。明全は、後輩の道元が苦難を越え、いまや最高の正師にめぐり逢ったのを見て、やがて訪れるであろう日本仏教の輝かしい将来の布石を夢みながら、不運にもその実現をみないうちに、この世を去ったのである。ともに万波を乗り越えて入宋しながら、雄図むなしく異境に果てた明全の姿をみて、道元は胸中、いよいよ生死との対決を深めたにちがいない。(60頁)
■いよいよ機は熟した。翌3(1227)年、道元が昼夜をわかたず坐禅修行に熱中していた時のことである。ある朝、僧堂で坐禅中、一人の修行僧が疲労のため眠ってしまった。これをみた如浄は、一切の煩悩や執着を捨て、全身全霊を打ち込んで坐禅に専念しなければならないのに、眠ってしまうとは何事か、と大喝一声した。夢中で坐禅していた道元は、その天雷のような大音声(じょう)を聞いて、はっと吾にかえり、悟りを開くことができた。さっそく方丈に赴き、香を焼(た)いて如淨に礼拝した。その様子が只事でないのを見てとった如浄は、いったい何事があったのかと尋ねた。
このとき道元は、「肉体も精神も、一切のあらゆる煩悩や執着からのがれて、自在の境地になることができたのです。これこそ本当の悟りの境地だと確信いたします」と答えた。
これを聞いた如浄は、「そのように肉体も精神も一切のとらわれをのがれ、自由の境地になりきってこそ悟りというものである」と、道元が大悟徹底したことを、ついに認めたのである。(63~64頁)
■釈尊は6年間も坐禅し、達磨は壁に向って9年も坐禅をして仏の心を伝えた。昔の聖人たちも、このように坐禅をして修行を積んだのであるから、文字にとらわれた学問ばかりをしていないで、真実の自己を発見するために、いまの人はもっと坐禅の修行にはげむべきである。そうすれば、自然に一切のとらわれをのがれて悟りの境地を開き、真実のすがたを見究めることができるはずである。そうなるためには、まず何をおいても坐禅につとめるべきである。(『普勧坐禅儀』現代語訳)(72頁)
■坐禅には静かな部屋がよい。食事も節度が必要である。これまでの行きがかりを捨て、すべての仕事もやめ、是非善悪について一切考えてはいけない。心の働きが動くのを止め、ものを考えたり想像したりすることもやめる。もちろん仏になろうなどと考えてはいけない。まず坐禅をする場所に敷物をしき、そのうえに蒲団を置いて坐る。そして結跏趺坐、あるいは半跏趺坐する。結跏趺坐というのは、第1に右の足を左の股のうえにのせ、左の足を右の股のうえにのせる。半跏趺坐は、左の足で右の股を押すように重ねるだけである。着物や帯はゆるくしめ、きちんと整えるようにしなければならない。
つぎに、右の手を左の足のうえにのせ、左の手のひらを仰向けて、右の手のひらのうえにのせる。両手の親指はたがいに支え合うようにする。そこで姿勢を正して静かに坐り、左に片寄ったり右に傾いたり、前にかがんだり、後にそっくり返ったりしないようにする。横からみて耳と肩と真直ぐに、前からみて鼻とへそが真直ぐになるようにしなければならない。舌は上あごにつけ、唇と歯は上下ぴったりと合わせ、目はつねに開いている。身体の姿勢を正しく、呼吸もよく整えて、雑念を忘れて坐禅に打ち込むようにする。これが坐禅の要点である。(72~73頁)
■諸仏如来が代々正しく伝えてきた仏法の正門は、坐禅である。ひたすら坐禅に打ち込むことこそ、正しい仏法に入るための正門であり、最上で並ぶもののない妙術である。しかも、この法は元来誰でも備え持っているものであるから、その気になって真剣に修行をつみさえすれば、必ずその成果の証(しるし)が実際に現われてくるものである。その気になって修行しなければ、何時までたっても現われては来ない。(『弁道話』現代語訳)
このように道元は、もっぱら坐禅に打ち込むことこそ釈尊正伝の「真実(まこと)の仏法」を学びとるための正門で、唯一最高の道である、と力説した。
これは、道元が叡山時代からずっといだき続けてきた疑問、つまり、人は生まれながら仏であると説いていながら、一方では修行が必要であると教えるのは何故か、という疑問に対する答えでもあった。(76~77頁)
■そして参禅する人たちがいだくと予想される、宗教上の疑問18をかかげ、一々それに応答するという形式をとって、道元の坐禅に関する抱負と信念とを、次のようにのべた。
「これまでの説明で、坐禅の功徳が広大無辺であることは、よく承りました。しかし、おろかな人は、疑って言うでしょう。仏法には多くの入り口があります。どういうわけで、坐禅だけが真直ぐな入口だといって、坐禅だけを専らすすめるのですか」
このような質問にこたえて、道元は、
「釈尊、まさしく得道の妙術を正伝し、又、三世の如来、ともに坐禅より得道せり。このゆえに、正門なることをあひつたへるなり。しかのみにあらず、西天東地(インド・中国)の諸祖、みな坐禅より得道せるなり。ゆえに、いま正門を人天(にんでん、多くの人びと)にしめす」(『弁道話』)
「宗門の正伝にいはく、この単伝正直の仏法は、最上のなかに最上なり。参見知識のはじめより、さらに焼香・礼拝・念仏・修懺・看経(かんぎん)をもちいず。ただし、打坐して身心脱落することをえよ」(『弁道話』)(77~78頁)
■このように、道元は坐禅の心がけを説いたあと、さらに、日本に伝わっている天台宗や華厳宗は、いずれも大乗仏教の究極ともいうべきものであり、まして真言宗などは、即心是仏といって、長い期間の修行をしなくても、ひとたび万物の根源を見究めると、たちどころに正しい悟りを開くことができると説いている。これが仏法の極妙ともいってよいのに、それをさしおいて、坐禅の修行を特に勧めるのは一体なぜですか、という弟子の質問に対し、道元は次のように説いた。
(中略)
仏法を学ぶものにとっては、そのような宗派による教えの優劣や浅深が問題なのではない。それよりも、修行そのものが本物か偽物かということをよくわきまえるべきである。いろいろな言葉というものは、森羅万象以上に沢山あるものである。たとえば即心即仏という言葉は、水に映った月のようなもので、月そのものではない。また即坐成仏というのも、鏡の中の影像であって、真の悟りではない。このように、言葉の巧妙さにかかわって、仏法の真理を見誤ってはいけない。真の悟りを開くための修行こそ大切なのである。だから、いまはただその修行を勧めるために、釈尊から正伝された最もすぐれた修行である坐禅を人びとに示して、一人でも多く真実の仏法に生きる人になってもらいたいと思うのである。
また真実の仏法をうけるためには、かならず正しく悟った人を自分の指導者にえらばなければならない。ただ文字いじくりばかりしているような学者を指導者にしてはならない。かえってそれは、一人の盲人が多勢の盲人を道案内するようなものだからである。今日では釈尊の真実の仏法を正伝しているわが門流だけが、正しい悟りをひらいた人を敬い、真実の仏法を伝持している。だから、冥界の神々もやって来て帰依し、また小乗の悟りを開いた羅漢も訪れて法を問い、いずれもそれぞれ自分の心を開明する手だてを授けられたのである。他宗門では、そのようなことは全く聞かないことである。いまは万事を放擲して、釈尊正伝の仏法によって、ひたすら坐禅をすれば、かならず心の迷いや妄情の思慮分別の世界をのりこえて立派な悟りを開くことができる。
道元はこのような坐禅の効用を説き、坐禅を専修するものは、戒律を厳守しなければならない、と力説した。さらに、坐禅修行をするものが、真言宗や天台宗などの行を兼ね修することをきっぱり否定して、昔から今日にいたるまで、仏の悟りを正伝した祖師で他の修行を兼ねたという例は聞いたことがない、と如淨からも教えられたとのべ、「まことに一事をことゝせざれば、一智に達することなし」と言いきった。(80~82頁)
■また、坐禅についてはインドから各宗門でいろいろ説かれ、修行者はみな行ってきているのに、その坐禅のなかに釈尊の正法があつまっているというのは、どうしてかという問いにこたえた、次のように述べている。
「いまこの如来一大事の正法眼像無上の大法を、禅宗となづくるゆえに、この問きたれり。しるべし、この禅宗の号は、神丹(中国)以東におこれり。竺乾(じくけん、インド)にはきかず。はじめ達磨大師、嵩山の少林寺にして9年面壁(中略)のち代々の諸祖、みなつねに坐禅をもはらす。これをみるおろかなる俗家は、実をしらず、ひたゝけて坐禅宗といひき。いまのよには、坐のことばを簡して、ただ禅宗といふなり」(『弁道話』)
■ではまた、日常の行動がすべてそのまま禅でないものは、と説きながら、一方では、とくに坐禅だけをとり上げて勧めるのはなぜか、という質問には、次のように答えている。
「むかしよりの諸仏、あひつぎて修行し、証入(悟ること)せるみち、きはめしりがたし。ゆえをたづねば、ただ仏家のもちいるところをゆえとしるべし。このほかにたづぬべからず。ただし祖師ほめていはく、坐禅はすなはち安楽の法門なり」(『弁道話』)
■したがって、只管打坐という言葉を用いた道元の真意は、これまで一部でいわれてきたように公案を全面的に否定したものでは決してなく、ひたすら坐禅に撤すること、つまり専修坐禅という意味であることがわかる。釈尊が説いた根本仏教の精神に立ち還り、釈尊と同じように坐禅に撤せよという道元の叫びであったのである。(84頁)
■そこで、悟りがまだ開けないものは坐禅をするのはよいが、すでに悟りを開いたものは、その必要がないのではないか、という問いに答えて、修行と悟りの関係について、次のように説いた。
「それ、修証はひとつにあらずとおもへる、すなはち外道の見なり」
「仏法には修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆえに、初心の弁道、すなはち本証の全体なり。かるがゆえに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指(じきし)の本証(直接に究極の真理を示すこと)なるがゆえなるべし。すでに修の証なれば、証にきは(際限)なく、証の修なれば、修にはじめなし」(『弁道話』)
■しかし、これでは、修行のほかに悟りはない。いいかえれば、修行さえしていれば悟りはなどはいらない、修業さえしていればそれでよいのだ、というようにも受け取れる。そこで道元は、修業と悟りの関係について、さらに次のように説いた。
「ここをもて、釈迦如来・迦葉尊者、ともに証上の修(悟った上での修業)に受用せられ、達磨大師・大鑑高祖(六祖慧能)、おなじく証上の修に引転せらる。仏法住持のあと、みなかくのごとし。すでに証をはなれぬ修あり。われらさいはひに一分の妙修を単伝せる初心の弁道、すなはち一分の本証を無為の地にうるなり。しるべし、修をはなれぬ証を染汚(ぜんな、汚すこと)せざらしめんがために、仏祖しきりに修業のゆるくすべからざるとをしふ。妙修を放下すれば、本証手の中にみてり。本証を本証を出身(悟りの境地に入ること)すれば、妙修通身(全身)におこなはる。又、まのあたり大宋国にしてみしかば、諸方の禅院、みな坐禅堂をかまへて、五百六百および一二千僧あお安じて、日夜に坐禅をすゝめき。その席主とせる伝仏心印(仏心の確証を伝えていること)の宗師に、仏法の大意をとぶらひしかば、修証の両段にあらぬむねをきこえき。このゆえに、門下の参学のみにあらず、求法の高流(すぐれた修行者たち)、仏法のなかに真実をねがはむ人、初心(初心者)・後心(古参)をえらばず、凡人・聖人を論ぜず、仏祖のをしへにより、宗匠の道をおふて、坐禅弁道すべしとすゝむ。きかずや祖師のいはく、修証はすなはちなきにあらず、染汚することはえじ。又いはく、道をみるもの、道を修すと。しるべし、得道のなかに修行すべしといふことを」(『弁道話』)(86~87頁)
■このように道元は、修行と悟りはⅠつであるから、これを煩悩によって汚さないようにするため、きびしい修行をつまなければならないと強調した。道元はこれを「不染汚の修証」、あるいは「不染汚の行持」などともいっている。しかも、そういう本性は、もともと人間にはゆたかに備わっている。人間は煩悩具足の衆生ではなく、仏であるという解釈に立っているわけである。そこが、煩悩具足の人間こそ救われるのだという親鸞の教説と、根本的に異なる点である。
こうして、人は仏性を持っているという信の自覚に撤し、修証一如を力説したところに、道元の思想の独自性がある。それは、人は生まれながら仏性をもっているという天台宗の根本思想に対して、それならば、諸仏はなぜ修行を続けなければならないと説くのか、という道元自身の疑問に答えた最終的な結論でもあった。(68頁)
■ところがひとり道元だけは、この末法思想に同調するどころか、真向からこれに反対して、大乗仏教では正法と像法と末法の時代をわけることをしない、ときっぱり断言した。
「大乗実教(大乗の真実の教え)には、正・像・末法をわくことなし。修すれば、みな得道するといふ。いはむやこの単伝の正法には、入法出身(法に入って悟りを開くこと)、おなじく自家の財珍(宝)を愛用(活用)するなり。証の得否は、修せんもの、おのずからしらしむこと、用水の人の冷暖を、みずからわきまふるがごとし」(『弁道話』)(91頁)
■ついで8月(天福元年、1233)には「現成公案」の巻を書いて、九州にいる在家の弟子楊(よう)光秀に与えた。これは道元の思想の要点をわかりやすくのべたもので、眼にみえる諸現象のありのままの姿は、すべてそのまま仏法の現われであると考え、これをよく研究しようと主張したものである。道元はさきに『弁道話』で只管打坐を強調するなど、主として実践面を説いたのに対して、ここでは、古則とか公案を用い、見性(けんしょう、生まれながら自分に備わっている仏心を見究めること)とか、悟りということばかりに、心を奪われている当時の禅風を批判し、道元禅のの根底となる思想を、理論的に明らかにしておこうとした。(94頁)
■道元はその巻頭で、まず、
「諸法の仏法なる時節、すなはち、迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、衆生あり」
このせかいのすべてのものは、仏法が現実化されたもので、そのなかには迷いも悟りもあるし、修行があり、生も死もあり、諸仏と衆生があるとして、現実に存在するものの種々相をすべて肯定した。次に一転して、
「万法ともにわれにあらざる時節、まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし」
しかしすべてに自己という主体がなければ、そこには迷いも悟りもない。諸仏も衆生も、生も死もないわけであるといって、一切の存在を否定する空の思想を展開している。
さらに、その上で、
「仏道、もとより豊検(相対立すること)より跳出せるゆえに、生滅あり、迷悟あり、生仏あり」
といい、仏道は、もともと豊かさと慎ましさとの対立の中から出来てきたものであるから、そこには生も滅もあり、迷いも悟りも存在するし、衆生も仏もあるわけであると、さきの肯定と否定を超えた立場に立って、両者の存在を認めている。
「しかし、かくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり」
そして、そうはいっても、やはり惜しいと思う花はちり、好ましくない雑草が生い茂るのが、現実の世界というものである、と自然の在りのままの法則を是認している。
また、悟りの世界における自分の立場や考え方について、なにごとでも、自己を中心に考えて、仏道を修行し悟りを開こうとするのは誤りで、それは迷いである。それは自分を万法の外において、その観点から、万法を自分の対象物として客観的に見ようとするものだからである。仏法の世界では、万法のなかに身を置いて判断をしなければならない。この意味からすると、自己をまず忘れて、万法の方から進んで自個を修行し悟りを開こうとするとき、そこに悟りの世界が開かれるのである。このようなことをよくわきまえて、迷いを迷いとしないで大悟したのが、諸仏である。その反対に、悟りの世界に大いに迷っているのが衆生である。こういうわけで、悟りのうえに悟りを得る人もあるかわりに、反対に、迷いのなかに迷い続けている人もある。(94~96頁)
■また、仏道修行と自己との関係を次のようにのべている。
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするゝなり。自己をわするゝといふは、万法に証さるゝなり。万法に証さるゝといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(悟りの跡かた)の休歇(きゅうけつ、全く跡かたがないこと)なるあり。休歇なる悟迹を長々出ならしむ」(「現成公按」巻)(96頁)
■さらに道元は、人の生と死について、次のようにいっている。
「人のしぬるのち、さらに生とならず。しかあるを、生の死となるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆえに不生といふ、死の生にならざる、法輪(正しい仏教のおしえ)のさだまれる仏転なり。このゆへに不滅といふ。生も一時のくらいなり。死も一時のくらいなり。たとへが、冬と春のごとし。冬の春となるとおもはず。春の夏となるといはぬなり」(「現成公按」巻)(97~98頁)
■さらに、人と悟りとの関係を水に映る月に譬えて、次のように説いた。
「人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天(みてん)も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。さとりの人をやぶらざる事、月の水をうがたざるがごとし。人のさとりを罣礙(けいげ、さまたげること)せざること、滴露の天月を罣礙せざるがごとし」(「現成公按」巻)(98頁)
■さらに、悟りの条件について、道元は次のように考えていた。
「うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへども、そらのきはなし。しかあれども、うを・とり、いまだむかしよりみづ・そらをはなれず。(中略)鳥もしそらをいづれば、たちまちに死す。魚もし水をいづれば、たちまちに死す。以水為命、しりぬべし。以空為命、しりぬべし。(中略)しかあるを、水をきはめ、そらをきはめてのち、水・そらをゆかむと擬する鳥・魚あらむは、水にもそらにもみちをうべからず。ところをうべからず。このところをうれば、この行李(あんり、日常生活一般)、したがひて現成公按(参禅求道の課題が解けて、完全なすがたで実現すること)す。このみちをうれば、この行李、したがひて現成公按なり」(「現成公按」巻)(99頁)
■あるとき麻谷(まよく)山の宝徹和尚が扇を使っていたところへ、一人の僧侶がやってきて、仏教の説くところによると、風の本性は常住であって、どこにでも無いところはないということですが、なぜ和尚は扇を使っているのですか、と尋ねた。和尚はそれに答えて、貴僧は風の性質が常住だということはわかっているようだが、どこにでも無いところはないということが、まだよく判ってはいないようだ、といった。するとその僧は、それではどこにでも無いところはないというのは、どういう訳ですか、と聞き返した。ときに和尚は、ただ黙って扇をあおぐばかりであった。それを見たその僧は、はたと悟りを開いて、ただ黙って礼拝し、そこを立ち去ったという。
「仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。常住なれば、あふぎをつかふべからず。つかはぬおりも、かぜをきくべきといふは、常住もしらず、風性(風の本性)をもしらぬなり」(「現成公按」巻)
仏法の悟りのしるし、釈尊から正しく伝わってきた道は、まさにこのようでなければならない。風の本性は常住であるから、扇を使う必要などないというのは正しい。しかし、扇を使わないときも風があるであろうというのは、常住の真の意味も、風の正体もよく判っていないからである、批評を加えた。そして最後に、
「風性(仏性を指す)は常住なるがゆへに、仏家の風は、大地の黄金なるを現成(完全に実現化すること)せしめ、長河(揚子江を指す)の蘇酪(そらく、牛乳を精製した最高の飲料)を参熟せり」(「現成公按」巻)
と「現成公按」の巻を結んだ。(99~100頁)
■参禅修行によって正しい悟りを得るためには、まず正師を求めるべきで、思想と実践が相伴った正師でなければ、正しい悟りへの指導者とはいえない、と力説し、「参禅学道ハ一生ノ大事ナリ、ユルガセニスベカラズ」と言い放った。そこには、門人の教化に精根を傾けていた道元の旺盛な気魄が感じられる。
こうして、興聖寺教団の強化に没頭していた文暦元年(1234)冬、建仁寺時代に道元の門を叩いたことのある孤雲懐奘らが、深草の道元門下に正式に入門した。大和の多武峰(とうのみね)にある妙楽寺(現在の談山神社)の天台教団から新たに興聖寺教団に加わった懐奘という有力な門弟を得て、道元は門下の教化指導に一層自信を深めたにちがいない。こののち懐奘は道元門下の第1の高弟として、その教化を大いに助けたからである。(101~102頁)
■暦任元年(1238) 一顆明珠(いつかみみょうじゅ)
延応元年(1239) 即心是仏・洗浄
仁治元年(1240) 礼拝得髄・山水経・有事・袈裟功徳・伝衣(でんえ)・谿声山色・諸悪莫作
仁治二年(1241) 仏祖・嗣書(ししょ)・法華転法華・心不可得・古鏡・看経・仏性・行仏威儀・仏教・神通
仁治三年(1242) 大悟・坐禅箴(しん)・仏向上事・恁麽(いんも)・行持・海印三昧・授記・観音・阿羅漢・柏樹子・光明・身心学道・夢中説夢・道得・画餅・全機
寛元元年(1243) 都機(つき)・空華(くうげ)・古仏心・菩薩薩埵(さった)四摂法(せっぽう)・葛藤(かっとう)
■ついで翌延応元年(1239)4月には、21ヵ条からなる『重雲堂式』を著わし、修行者が集まる道場の規律を定めて、釈尊正伝の「真実の仏法」を実践するための基本的な心得を門人たちにしめした。
一、「真実の仏法を求めて真剣に修行しようという志を持ち、名誉や利欲を求めてはならない。
一、堂内の修行僧たちはよく和合し、たがいに仏道を興すことを心掛けなければならない。
一、外出を好んではならない。むかしの修行者が深山幽谷に住み、すべての世縁を断ちきって隠棲し、修行にはげんだ精神をみならわなければならない。
一、堂内で文字を読んではならない。堂内では寸陰を惜しんで修行に専念しなければならない。
一、勝手に出歩いて遊んだりしてはならない。のんびり一生を終ってしまったのでは、あとで後悔してもはじまらない。
一、他人の欠点をついたり、それにならったりしてはならない。にくしみの心をもって見てはならない。自分の徳をみがくことこそ大切である。
一、大小となく、すべて堂主に報告しなければならない。もしそれに従わないものは堂から退去させるべきである。
一、堂の中や近くで大声を出したり、大勢でガヤガヤさわいではならない。
一、堂内を勝手に歩行してもいけない。
一、堂の中で数珠を持ったり、手をたれたまま出入りしてはならない。
一、特別のとき以外は、堂内で仏名や経文を口に唱えてはいけない。
一、堂内で高い音をたてて鼻をかんだり、つばをはいたりしてはならない。
一、堂内の修行僧は、綾織りの着衣を使ってはいけない。紙や布の素衣をきていなければならない。むかしから悟りを開いた人は、みなそのようにしてきたからである。
一、もちろん酒に酔って堂内に入ってはいけない。また、酒や楡(にれ)の皮の粉を入れた漬物などを堂内に持ち込んではならない。
一、争いごとを起したものは、二人とも堂から出すべきである。自分たちの修行を妨げるだけでなく、他人の修行をも邪魔するからである。その争いを止めなかったものも同罪である。
一、堂内の規則を守らないものは、おなじように堂から出すべきである。
一、他所から僧俗を招いて、堂内の修行僧をどかせたり、近くで客人と大声で談合したりしてはならない。
一、坐禅は、僧堂の場合とおなじようにしなければならない。朝晩ともなまけてはいけない。
一、食事のとき、食器類を地面に落としたものは、禅寺の規則に従って、罰としてこらしめのために一定の燈油を納めなければならない。
一、一般の仏法の規則はもちろん、禅寺の規律は肝に銘じて厳しく守らなければならない。
一、いつでも平穏無事に修行ができるように心掛けなければならない。(抄出)(104~106頁)
■「むかし犯罪ありしとて、きらはゞ、一切菩薩をもきらふべし。もし、のちに犯罪ありぬべしとてきらはば、一切発心のぶさつをもきらふべし。如∠比きらはば、一切みなすてん。なにゝよりてか仏法現成せん。如∠是のことばゝ、仏法を知らざる癡人(ちじん)の狂言なり。かなしむべし」(「礼拝得髄」巻)(109頁)
■「浄信一現するとき、自他おなじく転ぜらるゝなり。その利益(りやく)あまねく情・非情にかうぶらしむ。その大旨は、願(ねがわく)は、われたとひ過去の悪業(ごう)おほくかさなりて、障道(仏道をさまたげること)の因縁ありとも、仏道によりて得道せりし諸仏、諸祖、われをあはれみて、業累(ごうるいを解脱せしめ、学道さはりなからしめ、その功徳法門、あまねく無尽法界(むじんほっかい、尽きることのない仏法の世界)に充満弥淪(じゅうまんみりん、あまねく行きわたらせること)せらん」(「谿声山色」巻)(110頁)
■「いま大宋国の諸山に、甲刹(かっさつ)の主人とあるもの、坐禅をしらず、学せざるおほし。あきらめしれるありといへども、すくなし。諸寺にもとより坐禅の時節さだまれり。住持より諸僧、ともに坐禅するを本分の事とせり。学者を勧誘するにも坐禅をすゝむ。しかあれども、しれる住持人はまれなり」(「坐禅箴」巻)(112頁)
■「仏祖の大道、かならず無上(最もすぐれていること)の行持(修行)あり。道環(連なり、ゆきめぐること)して断絶せず。発心(仏になろうとする心を起こすこと)・修行・菩提(迷いから目覚めて悟ること)・涅槃(完全な悟りの境地)、しばらくの間隙あらず。行持道環なり。(中略)不二曽染汚(せんな)一(煩悩などでけがれたことがない)の行持なり」(「行持」巻)(113頁)
■「仏祖の大道を行持せんには、大隠・小隠(大小の隠者)を論ずることなく、聡明鈍癡(どんち)をいとふことなかれ。たゞながく名利をなげすてゝ、万緑に繋縛せらるゝことなかれ。光陰をすごさず、頭燃(ずねん、頭髪に火がついて燃えはじめたような早急に解決を要する悩み)をはらふべし。大悟をまつことなかれ。(中略)ただまさに、家郷あらんは家郷をはなれ、恩愛あらんは恩愛をはなれ、名あらんは名をのがれ、利あらんは利をのがれ、田園あらんは田園をのがれ、親族あらんは親族をはなるべし。名利等なからんも又、はなるべし。すでに、あるをはなる。なきをもはなるべき道理、あきらかなり。それすなはち、一条の行持なり」(「行持」巻)(114頁)
■「釈迦牟尼仏、十九歳の仏寿より、深山に行持(修行)して、三十歳の仏寿にいたりて、大地有情(うじょう、一切の生きもの)同時成道の行持あり。八旬の仏寿にいたるまで、なほ山林に行持し、精藍(しょうらん、修行道場)に行持す。王宮にかへらず、国利を領せず(中略)外道の訕謗(せんぼう、そしり)を忍辱(耐え忍ぶ)す。おほよそ一化(いちけ、釈尊一代の教化)は行持なり。浄衣・乞食(こつじき、修行に必要な食を得るため食を乞い求めること)の仏儀、しかしながら行持にあらずといふことなし」(「行持」巻)
釈尊はネパールの国王淨飯王(じょうぼんのう)の王子として生まれながら、19歳で出家の道に入り、深山にこもって修行に専念した。30歳のとき悟りを開いたが、80歳の晩年にいたるまで、生涯山林を離れず、苦行(岡野注;修行の方がよい)を続けた。その間、1度も王宮に帰らず国家からの補助も一切受けず、弊衣をまとい、乞食の行によって生活するという原則的態度を変えようとせず、外道たちの謗りを甘受し、忍従し続けるのであった。
このような釈尊の姿こそ、道元の最も畏敬するところであり、修行における最高の理想像であった。
このように道元は、一貫して根本仏教の精神に立ち還ることを最高目標とした。『正法眼蔵』の最後を、「釈迦牟尼仏にひとしくして、ことなることなからん」という言葉で結んでいるのも、そのためである。道元の釈尊に対する思慕が、いかに強かったかがわかる一コマである。(115~116頁)
■達磨はインドの王国に生まれ、520年頃、釈尊の正法を伝え、広く衆生を救済するため、身命を惜まず、海路中国大陸に渡って梁の武帝に禅を説き、さらに嵩山の少林寺に入って、中国にはじめて釈尊の正法である禅を伝えた。いまや遠方のわが国の農民や村童にいたるまで、老いも若きも釈尊の正法を聞くことができるようになったのは、ひとえにそのお陰である。このように身命を惜まず、釈尊の正法を伝承したのは、実に達磨一人だけであった。
「いま正法(しょうぼう)にあふ。百千恒沙(ごうしゃ、数えきれないほど沢山)の身命をすてゝも、正法を参学すべし。(中略)しづかにおもふべし。正法よに流布せざらんときは、身命を正法のために抛捨(ほうしゃ、投げ捨てる)せんことをねがふとも、あふべからず。正法にあふ今日のわれらをねがふべし。正法にあふて身命をすてざるわれらを慚愧(ざんき)せん。はづべくは、この道理をはづべきなり。しかあれば、祖師の大恩を報謝せんことは、一日の行持(修行)なり。自己の身命をかへりみることなかれ。禽獣よりもおろかなる恩愛、をしんですてざることなかれ。たとひ愛惜(あいせき)すとも、長年のともなるべからず。あくた(ちりやごみ)のごとくなる家門、たのみてとゞまることなかれ。(中略)病雀(びょうじゃく)なほ恩をわすれず。(中略)窮亀(きゅうき、籠に入れられた亀)なほ恩をわすれず。(中略)かなしむべし。人面ながら畜類よりも愚劣ならんことは。いまの見仏門法(もんぼう、正師について仏法を聞くこと)は、仏祖面々(悟りを開いた多くの先輩たち)の行持よりきたれる慈恩なり。仏祖もし単伝せずば、いかにしてか今日にいたらん。一句(一つの言葉)の恩、なお報謝すべし。一法の恩、なほ報謝すべし。いはんや正法眼蔵無上大法の大恩、これを報謝せざらんや」(「行持」巻)(119~120頁)
■また、六祖の慧能(638-713)は、先輩の修行僧をとび越えて師法を継いだため、危害を避けて秘かに南方にかくれ、後年になってようやく世に出たと伝えられる人であるが、道元は、その慧能について、次のように説いた。
慧能は、幼くして父を失ない、老母に養育され、貧しかったので木こりで生計を立てていたが、町を歩いていたとき、『金剛経』の一句を耳にして、たちまち老母を捨てて出家してしまい、厳しい修行の末、ついに悟りを開いた。恩愛のきずなを断ち切り敢て選んだという、修行に対する厳しさを、道元はたたえたのである。(120~121頁)
■道元はこのようにのべ、世間の名利に超然とした、枯淡で脱俗的な家風を大いにたたえ、これを思慕してやまなかった。さらに「葛藤(かっとう)」の巻でも、臨済も徳山も、潙山も雲門も、趙州古仏には到底及ばないと、その禅風を高く評価したのである。(121~122頁)
■「しづかにおもふべし、一生いくばくにあらず。(中略)いたづらなる声色(しょうしき)の名利に馳騁(ちへい、感覚的な名誉や利欲にふりまわされること)することなかれ。馳騁(ちへい)せざれば、仏祖単伝の行持なるべし。すゝむらくは、大隠・小隠(修行者たち)、一箇半箇なりとも、万事万縁をなげすてゝ、行持を仏祖に行持すべし」(「行持」巻)(125頁)
■つまり、坐禅のことは『法華経』などにみえているから、知識としては一般に知られていた。しかし、坐禅だけを行なうということは、これまで殆んどなかった。さきごろ栄西が禅宗を伝えたが、これも天台宗や真言宗を兼ねるというもので、とくに禅宗の修行だけをするものではなかった。ところが、道元が深草で新しい大陸風の坐禅をするようになってから、世間の大評判になった、というのである。
その結果、道元を慕って各宗の僧侶や公家・武家などが、つぎつぎに深草の道元教団に集まってきた。そうした動きのなかで最も注目されるのは、孤雲懐奘をはじめとする旧大日派の人びとの合流である。
この大日派というのは、臨済宗大恵派の系統に屬する一派である。(129頁)
■特に、拙庵(せったん)の師である大恵に対する批判には、激烈なものがあった。
寛永2(1244)年2月、道元は大恵を評して、「大恵はもと他宗の学徒であったが、禅宗に転じ、まず宣州の理和尚について禅を修めた。しかし、それをよく理解することができなかったので、瑞州(ずいしゅう)に赴いて、曹洞宗の洞山(とうざん)道微(どうび)に参じ、悟ったという証明になる嗣書をもらいたいと願い出た。けれども、修行に未熟な点があるという理由で、嗣書を授与されなかった。そこでこんどは、臨済宗の湛堂のもとに投じ、久しく禅の指導をうけたが、そこでも、ついに嗣書を授かることができなかった。このように大恵という人は、どこまでも禅を徹底的に追究しようとしないで、嗣書ばかり早く受けようとした。その態度は、まことに道心のない浅はかな修行者というほかはない。思慮のないことは憐れというべきである」(「自証三昧」巻)と、このように大恵の無道心な修行態度と名誉欲をはげしく非難し、大恵のように禅修行に対する根本的な誤りをしないように、門人たちに警告を発している。(134頁)
■このようにみてくると、旧大日派の人びとが、道元教団に集団入門してから、大恵派に對する道元の批判が急に厳しさを加えたのは、深草教団内部における指導強化の必要上からではなかろうか。かって旧大日派がその流れをくんでいた中国大恵派の家風の欠点を、きびしく指摘することによって、道元みずからの禅の正統性を強調すると同時に、旧大日派出身の人びとに猛省をもとめ、かれらに大恵派の禅風からの脱皮を促し、これを指導矯正しようという、再教育の意図が強かったからであろうと思われる。高潔無類な道元が、ただ故なくして、大恵やその門下などに、あのような厳しい批判を浴せるはずはないであろう。(136頁)
■道元の訴えを知って、天台衆徒がそのまま黙っているはずがなかった。かれらはその反論を朝廷に奏上した、そこで朝廷は、これまでの行きがかりから、天台教団側の意向を聞き入れ、その是非について、佐(すけの)法印に判定を下させた。すると案の定、法印は、
「道元が説いている思想は、釈尊の説法をきいて悟る声聞の説どころか、師匠もなくて自分一人で悟るという縁覚(独覚)の解釈である。それは余りにも身勝手な、自己本位の解釈にすぎない。これでは多くの人びとを救おうという大乗仏教の根本理念にそむくばかりでなく、かえって護国の趣旨にも反するものである」(『渓風拾葉集』)(139頁)
■やがて道元は、釈尊正伝の「真実の(まこと)の仏法」の純粋性をまもるため、ついに一大決心をし、寛元元年(1243)7月、越前志比庄(福井県吉田郡永平寺町)へ旅立った。ときに道元、44歳のことである。(141頁)
■懐奘らをともなって、道元が越前志比庄に着いたのは、寛元元年(1243)7月の半ばすぎのことである。
新天地を得て心機一転、新宗教の宣揚に意欲を燃やしていた道元は、まだ旅の疲れも十分に癒えない閏7月1日、平泉寺に近い山奥の禅師峰(やましぶ、大野市大月町禅師峰寺)で、「三界唯心」の巻を説いた。越前における道元の第一声である。(146頁)
■やがて吉峰寺(福井県吉田郡永平寺町吉峰)に移り、ここを第二の道場とした。道元はここを古精舎とか、古寺と呼んでいるから、さきの禅師峰の道場と同様、それ以前は平泉寺などと関係がある白山天台系の古代仏教寺院ではなかったかとおもわれる。(147頁)
■寛元元年(1243)禅師峰吉峰寺 三界唯心・見仏・徧参・眼晴・家常・竜吟・仏道・蜜語・諸法実相・無常説法・洗面・面授・法性・梅華・十方・坐禅儀・説心説性・陀羅尼
寛元2年(1244)吉峰寺 大悟・優曇華・発無上心・発菩提心・如来全身・三昧王三昧・三十七品菩提分法・転法輪・自証三昧・大修行
山奥某所 祖師西来意・春秋(148頁)
■「仏道は、諸発心(ほっしん)のときも仏道なり。成正覚(じょうしょうがく、完全にさとること)のときも仏道なり。初中後、ともに仏道なり。たとへば、万里をゆくものゝ、一歩も千里のうちなり。初一歩と千里とことなれども、千里のおなじきがごとし」(「脱心脱性」巻)(149頁)
■「五宗(大陸禅の5派。雲門宗・法眼宗・潙仰宗・臨済宗・曹洞宗)を立して、各々の宗旨ありと称するは、証惑世間人のともがら、少聞薄解(教えを聞くことが少なく、理解の仕方が浅いこと)のたぐひなり」(「仏道」巻)(150頁)
■「近来、大宋国杜撰(ずさん)のともがら(中略)老子・荘子の言句を学す。これをもて、仏教の大道に一斉なりといふ。また、三教は一致なるべしといふ。あるいは、三教の鼎(かなえ)の三脚のごとし。ひとつもなければ、くつがえるべしといふ。愚癡(ものわかりが悪いこと)のはなはだしき、たとひをとるに物あらず。かくのごときのことばあるともがらも、仏法をきけりとゆるすべからず。(中略)三教一致のことば、小児子の言音におよばず、壊仏法のともがらなり」(「諸法実相」巻)(153頁)
■ところが、深草時代も後半になると、道元の考えに変化が現れるようになった。比叡山衆徒の圧迫、円爾(えんに、1201-80)による東福寺禅教団の成立などにともない、道元は教団内の指導統制をいっそう厳重にする必要が生じた。大恵派などの臨済禅に対しても、痛烈な批判を加えたのである。さらに、『護国正法義』を著わし、釈尊正伝の仏法こそ国家護持のためには、最もふさわしい宗教であることを強調し、その正統性を一段とつよく主張した。そしてついに、越前に下向する頃から、出家主義を標榜するようになったのである。(156頁)
■「いまだ出家せざるものの、仏法の正業(正しい行ない)を嗣続(継ぐこと)せることあらず、仏法の大道を正伝せることあらず。在家、わづかに近事男女の学道といへども、達道(仏道の奥義に達すること)の先蹤」(「諸法実相」巻)(153頁)
■ところが、深草時代も後半になると、道元の考えに変化が現れるようになった。比叡山衆徒の圧迫、円爾(えんに、1202-80)による東福寺禅教団の成立などにともない、道元は教団内の指導統制をいっそう厳重にする必要が生じた。大恵派などの臨済禅に対しても、痛烈な批判を加えたのである。さらに、『護国正法義』を著わし、釈尊正伝の仏法こそ国家護持のためには、最もふさわしい宗教であることを強調し、その正統性を一段とつよく主張した。そしてついに、越前に下向する頃から、出家主義を標榜するようになったのである。(156頁)
■さらに続けて、釈尊以来、出家の心と在家の心は同じだなどと、正式には一度も説かれたことはない。出家したものは、たとえ破戒・無戒の僧でも、悟りを開くことができたが、それとは反対に、在家の人は、たとえ善行をつんだ者でも、悟りを開いたというためしはない。それは在家が本当に仏道を修行する場でないからである。たしかに、仏教の諸説のなかには、在家仏教や女人成仏などの説もあるが、それらは釈尊の教えの正伝ではないのである。釈尊から正伝された真の仏教は正伝した祖師で、出家受戒をしないものは一人もなかったといえよう。(158~159頁)
■新道場も順調に整ったので、寛元三(1245)年三月春、道元は再び説法を開始した。そして、こんどこそすべての点で理想的な修行生活を実現させたいと考えた。道元はそこで、修行者はつねに根本仏教の原点に立ちかえって修行するという心がけが大切であり、日常使う袈裟や食器類なども、すべて釈尊正伝の真の仏法のいのちであると考えなければならない、と力説した。(「鉢盂」巻)(160頁)
■いよいよ鎌倉に赴いた道元は、時頼の篤い帰依をうけ、禅について説法するとともに、仏教生活をいとなむのに必要な菩薩戒を時頼に授けた。しかし、禅の修行に熱心な時頼はともかく、鎌倉の一般武士たちの信仰は、なお旧態然とした加持祈祷や密教的行事がほとんどで、道元禅による教化には限界があることは、明瞭であった。道元の期待ははずれた。時頼が禅寺を建て、その開山に迎えようとしたのを断り、宝治二(1248)年春、鎌倉武士の教化を断念して、越前の永平寺に帰ったのである。(168頁)
■やがて病状がすすむのを感じるにつけ、道元にとって最も気がかりだったのは、自分亡きあと、門弟たちに弟子たちが道元の教えをどのように伝えていくかという点であった。道元は、釈尊が入滅にあたって、最後に弟子たちに説いた先例にならい、「八大人覚」の巻を著わした。
八大人覚というのは、修行者がそれをしっかり守っていけば、仏法は永遠に滅びないと、釈尊が最後に説いた遺誡(ゆいかい)のことで、⑴欲望を少なくする⑵少しのもので満足する⑶静寂を楽しむ⑷よく精進する⑸みだらなことを考えない⑹心静かに瞑想する⑺智恵を学ぶ⑻たわむれの議論をしない、という8項目のことをいう。これは枕経(まくらぎょう)のときに読まれる『遺教経(ゆいきょうぎょう)』にみえている教えである。道元はそれに倣い、病をおして次のように説法した。
「この故に、如来(釈尊)の弟子は、かならずこれを習学したてまつる。これを修習せず、しらざらんは、仏弟子にあらず。これ如来の正法眼蔵涅槃妙心なり。しかあるに、いましらざるものはおほく、見聞せることあるものはすくなきは、魔嬈(まにょう、魔障)によりてしらざるなり。また、宿殖(しゅくじき)善根(善根功徳をつみかさねること)のすくなきもの、きかずみず。昔し正法・像法のあひだは、仏弟子みなこれをしれり。修習し参学しき。いまは、千比丘のなかに一両この、八大人覚しれる者なし。あはれむべし、澆季(末世)の陵夷(衰微)たとふるにものなし。如来の正法、いま大千(世界)に流布して、白法(びゃくほう、正法)いまだ滅せざらんとき、いそぎ習学すべきなり。緩怠(かんたい、おこたること)なることなかれ。仏法にあひたてまつること、無量劫(永久)にかたし。人身をうること、またかたし。(中略)如来の般涅槃(死)よりさきに涅槃にいり、さきだちて死せるともがらは、この八大人覚をきかず、ならはず。いまわれら見聞したてまつり、習学したてまつる。宿殖(しゅくじき)善根のちからなり。いま習学して生々(いきいきと)に増長し、かならず無上菩薩(最上の正しい悟り)にいたり、衆生のためにこれをとかんこと、釈迦牟尼仏にひとしくして、ことなることなからん」(「八大人覚」巻)(170頁)
■病状がすすんだ道元は、建長五(1253)年七月、永平寺の席を弟子懐奘に譲り、ここに懐奘は永平寺の第二世となった。
やがて療養のため、道元は永平寺を出て京都にのぼり、八月二十八日夜半、京の宿で、
「五十四年、第一天ヲ照ラス。コノ勃跳(ぼっちょう、はねまわり)ヲ打シテ、大千(世界)ヲ触破(触れて破ること)ス。咦(いい)。渾身モトムルトコロナク、活(い)キナガラ黄泉ニオツ」(原漢文)
と遺偈(ゆいげ)を記し、しずかに目を閉じたのである。行年五十四歳、それはまことに至純な求道者の一生であった。(173頁)
(2014年5月12日)