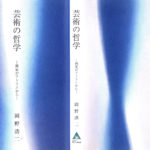| 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 |
第5章
● 記号では「時間」が捉えられない
僕はこれまで、絵だけを描いて生きてきた。「美」のベクトルだけに努力してきた。そんな僕がこれまで、この本のようなで考えで「芸術」にアプローチしてきて、こんなところに辿り着くとは思ってもいなかった。数学や、記号論理学、哲学、科学、物理学等がみな関連し、つながっているのだ。そしてそんな他分野のメダリストにもどんどん「つっこみ」がはいるのだ。そして、その「つっこみ」の「もと」が、最近、ウィトゲンシュタインに関する本(『論理哲学論考』を読む、野矢茂樹著、ちくま学芸文庫)を読んでいて気づいたのだ。まだ、それに気づいて時間もあまり経っていないので、生硬で荒っぽく見当違いなところもあってその分野の専門家には噴飯ものかもしれないが、美術も他の分野からいろいろ見当違いな意見を言われてきたので、お互いさまと思って許していただきたい。
まず、結論を先に言ってそれを順不同に説明し、最後にそのことが画家として自分にどう関係してどうするのかという、順で述べたいと思う。
⑴ この宇宙を含めて世界のすべての個物には「時間」が含まれている。
「時間」は「存在」の要素ではない。だから「時間」だけを単独に取り出せな
い。「存在」と「時間」は一体である(この後、ハイデッガーの世界=内=存在にな
らって「存在=時間」とする)
⑵ 記号では存在=時間が捉えきれない。記号では、記号そのものが「時間」を含ま
ないので連続性、無限、境界、勾配、グラデーションが捉えきれない。そのた
めに記号をツールに使う数学、記号論理学、その数学をツールに使う理数系諸科
学に昔からさまざまなパラドクスが生まれる。
⑶ 芸術と物感(形而上学的実在感)と時間性はからみあって一体である。表音文
字と表意文字が共存している日本語のすばらしさ。その記号を使って「知」を組
み上げ、世界を組み上げることのできる日本人は幸せである。
⑷ 画家として存在=時間を描写するということは、時間性の描出なしには完全な
描写にはならない。だから、これからの目標は、光と空間に加えて時間の表現を
いかに美しく描出するかだ。
リオタールが、「ポストモダンとは大きな物語の終焉なのであった」と言っているように、現代思想は民主主義と科学技術の発達による一つの帰結で、哲学も科学的社会学的になり従来からの形而上学(存在論)的哲学はウイトゲンシュタイン以来出ていない。彼はラッセルらの始めた数学的な論理、「記号論理学」で世界を明晰に言い尽くそうとした。そして、言いうることと、言いえないことの境界線を引こうとした。世界とは曖昧なものではなく、「現実に成立していることの総体」であり、論理的空間とは「可能性として成立しうることの総体」であると主張した。
ウイトゲンシュタインは、壮大なテーマで取り組んだが、最終的に成功したとは僕には思えない。要するに、記号には時間が入らないという欠陥がある。これが僕の結論だ。世界存在には時間があるのに、記号には時間が抜け落ちている。
記号では、連続性や勾配、グラデーションがしっかりと捉えられないのだ。時間が入らない記号でものごとを説明しようとするから無理がある。ものごとにはすべて時間が入り込んでいる。言語にも、最も記号的な名詞にさえも時間は入っている。しかし、数字や純粋な記号(本質)には時間が入っていない。時間が入ってない記号を用いて世界を記述しようとする時に、微細なところに進んでいくとさまざまな袋小路に入り込むことになる。そこを「つっこみ」続けていると、土台に時間が入っていないことが問題だということが分かる。
アリストテレスの説いた推論の諸原理は、ラッセルもそれを自分の論理学の第一原理とした。すなわち、
*同一律:何であろうとあるものはある。
*矛盾律:いかなるものも、あり、かつあらぬことはありえない。
*排中律:すべてのものは、あるかあらぬかの、どちらかでなければならない。
一見当たりまえでどこにもケチのつけられそうもない、ラッセルの「第一原理」も「時間」が入ると成り立たなくなる。
最も問題のないと思われている同一律は記号で記述すると「A=A」である。しかし、これは世界に存在する個物にあてはめると厳密には妥当しない。時間を入れて考えてみよう。昨日の僕と今日の僕は違う。今日のリンゴと明日のリンゴは違う。現実的に同じようなものだと言っても、では今日生きていて明日死ぬ人では、今日と明日ではまったく違うのだ。それは、「今日」と、「明日」の違いだと言われれば、では「私」とはいつの私か?という問題がででくる。数字の「2」も、世界に存在する個物にあてはめると、それはいつの「2」か?という問題がでてくる。時間をいれれば、AはAであるという同一律さえ、その法則さえ成り立たない。論理をなしているそのもの、アプリオリ(生得的)と考えられていた、ラッセルのいう「第一原理」は、場所を変えても時間を変えても変わらないはずだった。アンドロメダ銀河の星に行こうと、どこへ行っても、いつでも成り立つと思われていたが、時間を入れるとどうだろう? どこへ行っても妥当するはずの、AはAであると思っていた同一律が時間を入れると妥当しないのだ。矛盾律、排中律にはもともとさまざまなパラドクスと批判がある。
もう一つ例を挙げると、電球が二つ、Aという電球とBという電球があって、そのケースは四つに分かれるという。Aも点いている、Bも点いている。Aは点いているが、Bは点いていない。Bは点いているがAは点いていない。AもBも点いていない。……これらの四つであるが、ではこの四つにすべてが当てはまるだろうか。どっちでもない場合もある。どう捉えていいか分からない場合もある。停電になるかもしれないし、電球が切れかかって点いたり消えたりしてるかもしれない。電球は点いているか否か分かりやすいが、今度はドライアイスが二つあって、これがあるかないかを想定するとしたら、電球のようにすべての出来事を四つに記号化することは難しいだろう。記号に時間という概念を入れると違ってくる。そのようにA、Bという記号ではとらえられなくなる。論理までそうなる。
つまり、記号そのものは人間が創ったすばらしいツールなのだが、それで世界を捉まえようとすると、時間を初めとして、連続性、勾配、極小、無限などがその網の目から抜け落ちる。しかし、記号は現象界に現われない物を記号化(ゼロ、マイナス、虚数、マンデルブロー集合、フラクタル幾何学、カオス、コンピューター等々、)できれば、人間の世界の地平を大きく拡げることも確かなことなのだ。
もう少し、記号化についての欠点について書くけれども、記号化が悪いわけではない。存在=時間を、人間の「本質直観」と記号を組み合わせて、フラーの「テンセグリティー」のような構造でバインドすれば、より高度な世界像が描出できるのではないか(このことは、後で述べます)。
●飛ぶ矢は止まっている
ラッセルとウイトゲンシュタインは、数学的な真理はアプリオリなものと考えるので、それをいじる必要はないという。それらは全面的に土台である。その土台の上に論理記号を使って世界を記述しようという壮大な試みだったのだ。人間がなしてきた諸々のなかでも壮大な哲学的取り組みだったのだが、しかし「時間」が問題だった。さらに問題は「連続」。つまりアナログとデジタル、連続したものは記号では捉えきれない。
記号論理学のツールである記号そのものが、存在=時間のなかの時間性と連続を含まないものであり、ここが、世界の存在を記号で捉えきれると考えた人間の壮大な誤謬なのだ。
ゲーデルの不完全性定理は、数学的なことは門外漢の僕には解らないが、真か偽かということに勾配がついていて連続して境界がないならば、当然、真での偽でもどちらでもない問題がでてくるのは当然のことだ。ほ乳類かは虫類か、生物か無生物か、有か無か等と同じように記号でいうとAかBか、真か偽かである。しかしその二つの記号の間が連続しているものというのは、微細なところがデジタル化できないから、あるいはどんなに微細に分けても隙間ができるので、真か偽かで言い当てることはできないものがでてくるのだ。真でもない、偽でもないという命題が必ずでてくる。ゲーデルはウイーン学団の一人で、もともと論理実証主義の人だった。
時間のことで以前疑問がうかんだことがあるが、音声だけのカセットテープを止めると沈黙がくる。しかし、初期の頃のVTRのテープを止めると静止画像が写っている。違いは何だろう?VTRのテープを止めると静止画像なら、音声のテープでも「あ」で止まれば「あああ・・・」と続いていないとおかしいのではないだろうか。そこで、以前、専門家にテープの構造を聞いたことがある。音声のテープでは情報を一旦切っているそうだが、一方で画像の場合は、テープの幅での情報を斜めに繰り返し繰り返し、読み取っているのだそうだ。つまり初期の頃のVTRの静止画像は読み取るところの機械が動いている(連続している)ということだった。
ゼノンの、「飛ぶ矢は止まっている」というパラドクスと同じである。映画(今のVTRは停止ボタンを押すとテレビに切り替わるので映画にします)の場合は、ゼノンの矢と同様にパラパラ漫画のようなものだ。瞬間的なシャッターで押しても、パラパラ漫画の間を詰めても1枚1枚の画像はいつもは止まっている。そしてコマとコマの間に穴が空く。このように時間を記号で捉えようとすると、記号と記号の間に穴が空いて、どうしても、時間そのものの連続は捉えることができない。
量子力学の不確定性原理も同じで本来連続しているものをどんなにこまかく切っても、記号で計測するしかない観測者の限界で、その間が抜け落ちて量れない。確率でしか言うことができないのだ。
アキレスと亀でも同様である。位置も時間も、パラパラ漫画のように特定できない。双方が動いているし、厳密な意味では記号で表わせない。その地点も時間も厳密で微細で確実な意味で、記号では特定できない。アキレスが亀を追い抜くところを映画に撮ったとすれば、確かにアキレスは亀を追い抜いているのだが、追い抜くた瞬間の一コマは厳密には撮れないからだ。
《こんな話が、絵とどういう関係があるのかといえば、1枚の平面(静止画像)に存在=時間を錯視させようとすると、時間性をどう描写したらいいのかという問題に関わるのことなので、もう少し我慢してください。》
●シュレディンガーのネコ
数字のことは小学生のとき分数を習った時に疑問があった。そのときは先生から納得いく説明が得られなかったが、今でも疑問のママだ。1/3+1/3+1/3=1になる。しかし少数では0.3333333…+0.3333333…+0.3333333…=0.9999999…になる。では0.9999999…はイコール1といえるのだろうか。0.9999999…=1 はアプリオリな真理なのか、人間がそう決めただけのことなのか。そうすると1は点ではなくて微細に滲んでいるのか。まるで光は粒か波かという問題に似ている。これも連続を記号で描写しようとすると現出するパラドクスではないのか。
中学生のとき読んだにジョージ・ガモフの『1.2.3…無限大』という本のなかで、二つの線分中の無限の点の数を比べる方法、無限と無限の大きさの比較の方法を知ったが(1対1対応させて比べる)、驚くべきことに、線分の長短にかかわらず、線分内の無限の点の数は同じなのだ。それは、一点を合わせて任意の角度で二つの線分を開いて、もう一方の端同士を結んで、その線に平行に一方の線分内の点ともう一方の線分の点を結べば、すべての点はもう一方の線分内の点と1対1対応する。だから線分内の無限の点の数は同じ。中学生の僕はこの推論に感心したけれど、現実との整合性、つまり長い線分と短い線分の点の数が同じということに納得がいかない。長短二つの線分の、長い方の線分をどんどん無限に伸ばし、短い方の線分をどんどん無限に短くすると、そして、二つの線分内無限の点の数がおなじだとすると∞=0、「無限大はゼロに等しい」こんな奇妙なことになってしまう。(数直線を考えれば、ゼロの位置と無限大の位置が同じだとするとプラスの方向に無限に進んで行けばやがてゼロに戻り、マイナスの方向に無限に進んで行けばやがてゼロに戻る。数直線は直線ではなく、無限大の記号の∞のような形態になっているのだろうか。……僕の考えのどこがおかしいのか誰か教えて)
アキレスとカメ、飛ぶ矢は止まっている、量子力学に関するハイゼンベルグとアインシュタインの論争(神はサイコロを振らない)……、これらのテーマは、記号は「連続」と「時間」というものを捉えきれないということである。記号ではパラパラ漫画のようにしか捉えられない。存在だってそうだ。真か偽かという問題も、真と偽の間に境界がなく連続した勾配であるならば、真でも偽でもない量域あるのは当然だし、またそれを記号で描写することができないのも当然のことだ。
0.9999999…(無限個) は、1ではなくて 0.9999999(有限個) とⅠの隙間にある数で、そもそもの錯誤は1を3で割り算すると、割り切れなくて小数点以下の3が無限に続くという「無限」をむりやり記号に押し込めようとしたことが 0.9999999…=1 というこんな奇妙なパラドクスが生じた原因なのだ(と僕は思う)。ウイトゲンシュタインは彼の前期の著作である『論理哲学論考』において「およそ言い得ることは明瞭に言い得、語り得ざることについては沈黙しなくてはならない」と言ったが、そして「言い得ること」と「言い得ざること」に境界線を確定しようとしたのだが、どうもその壮大な試みはうまくいっていない。その大前提に、世界のなかに「連続」「無限」「時間」が存在のしていることへの認識が薄いからだ。これは、数学から哲学に進んだ人に多く見られる特徴で世界をデジタルに見るのでアナログの感受性が薄い。「言い得ること」「言い得ざること」といっても、まずそれらは連続している。連続して勾配がある。正しいことと誤りとの間にも勾配があって、それらの境界はフラクタルである。記号化する行為がそもそも限界のあることで、言葉や数字で処理しようというそのツールに欠陥がある。それゆえに、さまざまな所でパラドクスが生じる。だから、ウイトゲンシュタインの鬼子というべき論理実証主義が「言い得ざること」を禁止と解釈し、形而上学を否定して行き詰まったのも当然といえばと当然なことなのである。
人生もそうだ。記号でミクロの量子からマクロのネコの生死を「AならばB、BならばC、ゆえにAならばCである」の論理で結びつけたのが「シュレディンガーのネコ」のパラドクスである。量子力学を原因にして、ドミノ倒しのように、最後にネコのところに行くと、ネコは半分死んでいるということになる。ネコは死んでいるか生きているかどちらかなのに、生と死が重なりあって50%生きていて50%死んでいる状態をどう説明するか、それがパラドクスになる。
前著『芸術の杣径』に書いた「シュレーディンガーの猫」のパラドクスに対する僕の以前の解釈は以下のとおりだ。
〔僕は量子力学の「シュレーディンガーの猫」のパラドクスにはもともとの思考実験自体に欠陥があると思うのだが、誰か教えて欲しい。まず第1の疑問は、何故、一匹の猫で結果を打ち切るのか。猫を百匹集め、それをひとまとめにするのと、別々にするのとでは結果が違ってくる。別々にすれば、ふたたび確率が浮上するのではないのか。第二は、「猫」で結果を打ち切らないで、最終的に人類が破滅するような装置にまで結果を延ばすとすると、観測者も実験した人も何も知らない人も、人間の文化も「シュレーディンガーの猫」のパラドクス自体もなくなって、ナンセンスな思考実験になってしまう。第三は、これが最も僕の関心がある問題だが、論理自体に問題がないのか。A=B、B=C、ゆえにA=C、この三段論法は両辺を入れ替えても成立する円環的で完璧な論理学的定理だが、Aの原因はB、Bの原因はC、ゆえにAの原因はCである、と言う推論は成り立ち証明されているのか。この推論を定理として事象の証明に使ってもいいのか。〕
現在の僕の解釈は、そもそもネコの死も確率でしかいえないのだ。生きているか死んでいるかという境界線は、連続しているのだ。もし生が、誕生から死まで0から誕生して(遺伝子の連続を考えれば誕生する瞬間も特定できない)が死の0に向かっていくものとして肉体と精神の成長の頂点を100とすると、仮にここは死、ここは生と決めても、実際、微妙なところでは80%の生としか言えない。いつも100%の生なのか? 明日にも死にそうな人は90%死んでいる。これは天気予報の雨の確率の解釈の違いとおなじで、50%の雨の確率は雨が降るか降らないかの確率であって、雨が半分の地域に降るということではない。シュレディンガーのネコも、箱に入ったときにすでに半分は死んでいる。いつかは死ぬのだ。箱を開けても開けなくても、ネコはどっちみち何十%は死んでいると言える。だから、箱に入れられたときに確率が50%にはねあがったのだ。
●絵画における時間性
さて、やっとここまで来ました。ここからは僕がこまごまと前述した世界観、世界の認識、世界の解釈が画家としてどう関わって具体的にどういうベクトルで絵を描いていくのかという私的「判断力批判」を述べたいと思います。……ではこういう話が、絵とどう関係があるのか。ウイトゲンシュタインをはじめ他の哲学者たちは、壮大な世界を描写し読み解こうとした。「語りえる」ことは明確に語り「語りえない」ことは「語りえない」ということを示そう(記述しよう)とした。「説明しないこと!―記述すること!」はウイトゲンシュタインの日記に書かれていた言葉だ。さらに「『論理哲学論考』の写像理論」では、「命題とは何か」という問いに対して「命題とは現実の像である」と言っている。僕は画家としてはっきりとこの立ち位置で絵を描くことを宣言する。僕が独りで鼻息荒く宣言してみても、ポストモダンの美術界では「屁のつっぱり(漫画『キン肉マン』にでてくるプロレス技。北京オリンピックの柔道無差別級の金メダリストが優勝後ののインタビューで使った)」にもならないだろうが、画家は自分の絵画制作の立ち位置を明確に示すべきだ。僕の今の考えでは、シュールリアリズムや表現主義やネオダダイズムはダメ、つまり絵画は、表現(expression)ではなく「描写(impression)」なのだ。
では絵描きは「何を」「どう」描写するべきか。何人かの画家は描写しようとした。芸術家も、哲学者も、科学者も、宗教家も、世界の存在を命題とした。世界とはこういうものだと描写しようとした。それでいままで述べたように、時間性が入っている写像が一番ヒエラルキーの高い描写なのだ。当然なことで、存在=時間のその物自体はとりだせないが、その描写に肉薄すれば、絵でいえば当然「美」のヒエラルキーのトップクラスの絵になるのだ。
雪舟、モネ、セザンヌ、坂本繁二郎、ジョルジョ・モランディ(Giorgio Morandi 1890~1964年)、マチス、ド・スタール。彼らの絵には物感を感じる。物感というのは分かりにくいが、時間性をテクニカルタームにして作品を観るとよく分かる。龍安寺の石庭とか芭蕉の俳句とか、心惹かれるものは時間性を感じ、郷愁を感じるからだ。マルセル・プルースト(Marcel Proust 1871~1922年)の『失われた時を求めて』のなかで、紅茶に浸したマドレーヌの味から幼少期の記憶がありありと蘇ってくるというようすを書いていて、彼はそれを「無意識的記憶」と呼ぶが、あの感覚は時間性と関わっている。そして「紅茶に浸したマドレーヌ」に類した、いくつかの「無意識的記憶」は、プルーストを微妙な幸福感に満たす。過去の存在=時間は世界の中から消え去っているのに、自分の身体のどこかにその写像、「紅茶に浸したマドレーヌ」が息づいている。ひっそりと隠れている自分の身体の中の時間性と、芸術作品の時間性がシンクロ(共鳴)するから、そのことが鑑賞者を幸せな気持にさせるのだ。
僕が絵画制作において次にやることは、「時間性」を絵に入れようということである。二年くらい前から「物感、物感」と言ってきたが、逆説的ではあるが記号化できたことは、「時間性」を絵に入れるということである。そしてもう一つは「記号ではやっぱりダメ」ということ。記号でダメな理由は、記号でやると時間が抜け落ちるのだ。絵において、僕がいま興奮するようにして、取り組もうとしているのはその点だ。はっきりと目標とすべきことが分かった。時間を入れると、一番ヒエラルキーの高い描写になる。つまり、より美しい絵になる。
皆の目の前にリンゴを一つ置いて「このリンゴを言葉で描写しなさい」と言われたら、ある人は酸っぱそうといい、ある人は赤いと言い、ある人は丸いと言い、ある人は200円位かと言う。ランダム・ドット・ステレオグラム(3Dアート)ではランダムなドットの奥に、両眼の焦点を変えると、別のものが見える。同じように、世界もパラダイムを変えると違うものが見えてくる。ハイデッガーは、人間を見て存在とは何かを考え、存在一般(つまりリンゴの存在)についても構想(未完)していた。世界を描写しようと思ってきた僕が、抽象印象主義で「光と空間」まで来た。さらにその上の、ヒエラルキーの高い描写は何かというと、これに「時間性」を付け加えればいいのだ。
そこでセザンヌの絵を見ると、ヒントがある。セザンヌは記号で対象を見ていない。光を使って世界を描写したのがモネで、モネは対象の実体存在(記号)から光の関係存在に認識をパラダイム転換した。そこに空間を入れたのがセザンヌ。セザンヌはさらに時間をも意識していたと僕は思う。それが未来派のほうに進んだ。犬の足を何本も描くというように、記号化のほうに向かった。でもそういう絵は、時間を運動としてとらえるのだから稚拙だ。動かないリンゴにも時間は入っている。僕にも時間が入っている。運動だけに時間があるのではない。リンゴの時間を描かなければならない。そこでセザンヌは、一つの視線ごとに一つのタッチで描いた。モネは『つみわら』の連作のように光が変化するごとにキャンバスを替えて、つまり時間を微分していった。この方向はたぶん写真の影響が大きかったのだろう。セザンヌの絵には、描き始めから完成までの彼の視線の時間の厚みが画面に残っている。
ウイトゲンシュタインの話にもどるが、「リンゴがある」というのは描けるが、「リンゴがない」ということを像にできないというのがウイトゲンシュタインの論である。お皿の上にリンゴがある写真は撮れるが、お皿の上に「リンゴ」(梨ではなく)がないという写真は撮れない。組み写真にしたりレイヤーをかければ写真で表わすことができても、それは100%「リンゴがない」という像ではない。それと、赤っぽい緑はないというのだ。一つの空間に二つの状態は重なり合わないというのだ。しかし、赤っぽい緑というのを描くことはできる。絵なら描けるのだ。簡単なことで赤と緑を点描すればいい。点描は厳密には位置が違うと言うのなら、点を無限に小さくすればよい。「ない」ということも僕は描くことができる。リンゴがないというのをどうやって描くかというと、『論理哲学論考を読む』(野矢茂樹著)では、リンゴを描いてその上に×を描く方法を述べている。
〔注:言語をもち、世界の像を作り、そうして、可能性へと扉が開かれている人だけが、否定を捉えうるのである。ただひたすら現実を見るだけでは、否定に対応するいかなる要素も見出されはしない。すなわち、否定とは現実に存在する対象ではない。あるいは、否定形の考えようとしてみてもよい。「テーブルの上にパンダはいない」という絵を描こうとしてみていただきたい。どういう絵を描くだろう。パンダのいないテーブルの絵を描くだろうか。しかしそれはただのテーブルの絵でしかない。よろしい。それを「テーブルの上にアオウミガメはいない」の絵だといってもよい。フンボルトペンギンがいないでも、カボチャがないでも、金塊がないでもよい。それゆえ、あえて描くならば、テーブルの上にパンダがいる絵を描き、それにバツ印を書き加えるといったことだろう。そのとき、バツ印は絵の一部だろうか。テーブルが絵の一部であるように、バツ印も絵の一部なのだろうか。少なくとも写実的な像の一部ではない。バツ印は、描かれた絵に対してその絵を否定するといういう、絵全体に対するある態度を表わしている。こうしたことも、否定詞が名ではないことを直観的に支持してくれるだろう。(『論理哲学論考』を読む )(野矢茂樹著 ちくま学芸文庫 102~103頁〕
バツ印は、絵の中ではどうなのか。デュシャンが「泉」と題をつけて便器を出品したり、モナリザの絵に髭を描いたり、またマグリットはパイプの絵を描いて「これはパイプではない」という題名をつけた。それは、ポストモダンの多くの作品と同じく、絵画のルール違反でルールの違う競技になってしまう。まあ、デュシャンは「美」を否定しているのだからどうしようもないが。
一方で、映画なら「ない」ということを簡単に描ける。映画は時間の芸術だからそれはお手の物だ。お皿ごと外にだして、太陽の日差しで(影によって時間の経過が分かる)皿の上のリンゴを撮って次にお皿だけ撮れば、リンゴがないということを描ける。絵でも記号を使うと×(ない、の記号)を描いたり、太陽は○を描いて周りに放射状の線(太陽の記号)だし、動いている自動車は、漫画なら自動車の後ろに線を描いたりして表すが、絵は違う。絵なら、リンゴの絵を描いて、拭き消すのだ。かすかに残っている。それでリンゴがあったことが分かる。あるいは、リンゴを描いた絵を乾かしてその上におなじお皿だけの絵で覆いつくしても、リンゴのマチュエルが表面に残る。梨ではない、リンゴがなくなったのだ。リンゴがあったのだ。痕跡を残すのがセザンヌで、一瞬一瞬の視線を残していけば、あるいはズラしたり、直したりすると、輪郭線(記号)にも時間性が感じられる。「時間」が分かれば、絵において僕にはそれができそうだ。暗示させるのだが、絵はそもそもが錯視である。どんな絵も、キャンバスの上の絵具のかたまりにすぎない。絵で時間を描くことは、錯視を使えばできそうなのだ。そんなことで、、ウイトゲンシュタインを読んで、僕は興奮して記号化(意識、知、脳)と描写(身体、感覚、眼)の認識論的な違いについてあれこれと考えた続けている。
人間はナチュラルには記号で世界を編み上げているので、世界の実相を見ることができない。しかし、存在にはすべてのものに時間が関わっているから、記号化はできない。それでも、時間を記号化できれば新たな論理空間を脱構築(ディコンソトラクション)できる可能性がある。時間を加えて、新たに組み直すことはできる。組み直すというとバカバカしいような、途方もない話だが、ブロックのようにゼロから新たに積むのなら論理を組み立て直すのは難しいし、人生の残り時間も少ない。フラーの「テンセグリティー」ような形態のなかに科学と文明が積み重ねられてきたと考えれば、そこには時間がなかったのだ。だから欠陥がある。「時間」という一本の棒がなかったのだ。フラーの「テンセグリティー」に棒が一本足りなかったようなもので、だから、新たに一本を加えてもう一回組み直せば、ゼロから積み直すのでなく、今までのすべてのものをムダにしないでバインドし直すことができる。僕の絵を全部を組み直す。ただし、これまでの仕事をすべて生かして。
●存在の時間性をあらわす芸術
アインシュタインと量子力学の論争も当たり前のことだ。空間も時間も連続しているのでミクロの部分ではデジタル化するのにコマとコマに間ができてしまう。この間の部分は確率でしか言えないということで、世界の実在の問題ではなく記号化の限界の問題なのだ。マクロの世界でも、自分の睡眠と覚醒の時間を大体でしか、正確には特定できないだろう。寝入りばなと起きたばかりの状態は、睡眠と覚醒が重なりあっているので寝ているのか起きているのか特定できない。生物と無生物もそう。生物自体も、連続して進化したのだから、連続して勾配している。だからカモノハシのように卵を生む爬虫類と哺乳類の中間のような生物もいる。世界は連続しているのだ。空間も時間も切ることはできない。美術の世界も、未来派とかいろんな方法で時間を描こうとした試みは、あったかもしれないが、時間そのものを描こうとしなかった。モランディは若いころは未来派だった。同じ時間を問題にして、そのころの絵と晩年の絵の、対象の捉え方の違いをよく見比べてみると、僕が絵は描写だと強調することの意味が分ってもらえるだろう。
今、僕の目が惹かれるものはモランディ、ド・スタール、セザンヌ、マチス、ルドン、坂本繁二郎、牧谿(ルビもっけい)、等伯、雪舟、竜安寺の石庭、ブランクーシー、イサム・ノグチ。それらの人の作品は、存在=時間のアトモスフェア(雰囲気。ミニマル・アートの画家たちが嫌った単語)が色濃く錯視される。ただ対象物を描写しているだけなのに、「物感」とか「芸術」であると感じさせるのは、世界存在の描写の、ヒエラルキーの高いものである。リンゴといえばリンゴしか見えない人もいるが、坂本繁二郎やセザンヌは一生懸命に見て、一生懸命に描いている。僕の結論は、これまで僕のイズムの「抽象印象主義」において、マニフェストのように「光と空間」だと書いてきたが、さらに時間を加えるのだ。「光と空間と時間」。これが、今後の大きな目標だ。抽象印象時間主義というか新印象主義というか、やはり抽象印象主義でいいのか、呼び方は決まっていないが……。
時間は平面に対して奥行き(前後)の方向である。パラパラ漫画の紙の束の厚みのことである。モネは時間を微分していった。夕陽の当たる『積みわら』を何枚も描いたが、それらは静止したパラパラ漫画の一枚一枚だということもできる。セザンヌは存在=時間を描写する過程の、過ぎ去る時間を積分して画面に定着した。坂本繁二郎にも、モランディにも時間を感じる。坂本繁二郎は「精神」とは言ってない。前述のように繁二郎は自己などと言ってはいけないというのだ。意識的に時間を使ってはいないが、やはり存在について考えている。存在というものを考えると、すべての存在には時間がある。その感覚を日本人は、元来持っている。表音文字(デジタル)と表意文字(アナログ)の二つの文字が共存する日本語のせいなのかもしれない。
芭蕉の俳句を英語に翻訳すると言語の違いがよく分る。「古池や 蛙飛びこむ 水の音」。まずこの文の主語は英語ではカエルだろうが日本人なら芭蕉がポチャン(バチャバチャではない)というカエル(トノサマガエルかアカガエル)の音をきいている情景がイメージされるので、主語はI hearすなはち芭蕉だろう。カエルは単数か複数か、アマガエルかガマガエルかトノサマガエルか(英語ではウシガエルになりそうだ)、カエルとカワズはどうちがうのか、「古池や」の「や」をどう訳すのか、等表音文字のデジタル記号しか持たない言語でアナログ言語の極点にある芭蕉の俳句を訳するのは困難きわまりないことであろう。(閑話:僕が中学世のときに、ニワトリの鳴き声を英語では「コッカドゥードゥルドゥー」だということを授業で習い、そのときから英語に対する興味が半減した。「コケコッコー」が「コッカドゥードゥルドゥー」に聞こえるなんて、その感受性を疑う。そんな言語は努力して習うに値しないと思ったのだ。今は反省しているが。)……この「ビミョー」なアトモスフェアを平均的日本人は軽々とクリアーして芭蕉の描写した世界観を理解し共有するのだ。これはあらためて考えてみれば凄いことなのだ。セザンヌの絵画空間を一般の人が理解するのと同じことなのだから。
「諸行無常」という言葉は、この世ははかないという意味ではなく、無常すなわちすべてのものには時間があるということなのだ。万物に時間が入っているので、今日のリンゴは明日のリンゴでない。今日の私は昨日の私ではない。今日の幸福は明日の幸福ではない。昨日の不幸は今日の不幸ではない。禅宗の「不立文字、教外別伝(ルビふりゅうもんじ、きょうげべつでん)」は、悟り(成仏)にいたる過程は言葉(経典)を勉強すれば伝えられるが、悟りそのものは文字にはあらわせない、ということなので、「只管打坐(ルビしかんたざ)」ただひたすら坐禅することで釈迦の悟りを身体で体験せよ、ということをいっているのだ。このように、日本人はアナログの領域を表わす言語を駆使して、アナログとデジタルの言語を縒り合わせ世界を編み上げてきたのだ。
最近、西田幾多郎(1870~1945年)や大森荘蔵(1921~1997年)の日本人的感性の哲学者のことも気になっている。大森荘蔵 の著作は以前にほとんど揃えていたので(読んだのは1、2冊のみ)来年あたり挑戦しようと思っている。ふたり共に、時間を意識的に扱っており、時間について考えをめぐらしている。両者の本はちょっとかじった程度で言うのもおこがましいが、西田幾多郎は広く一般にも知られているのでともかく、大森荘蔵を知っている一般人は少ない。大森荘蔵は生前から現在に至るまでもっとメジャーに評価されるべきだと僕はおもうが、どうだろうか。
時間を入れるなら、時間が平面に錯視されるならば、そしてそれが存在の実相ならば美しくないはずがない。画家は、時間を画面に入れて、絵をより美しくしなければならない。「存在=時間」は、「真・善・美」は超越であると僕は確信しているわけだから、ヒエラルキーの最高の「美」は芸術美だから、絵は美しくなければならない。画家は美しさを目指さなければならない。
●これからの絵が楽しみ
絵を描き始めのころは、誰の画集を見ても自分より上手いので欠点など見つからず当然「ツッコミ」など入りようがなかった。哲学を含め他の分野も同じように、以前はただ納得し感心するばかりで、互いに相反する意見もどちらも正しく思えて反論も思いつく余地がなかった。それが、ゲーデルの不完全性定理から始まって、ここまでツッコミが入ったなんて、自分でも感心するよ。勉強は、やり続けるもんだね。それもこれも、美に対して常に真正面から取り組んできたおかげなんだろう。だって「真・善・美」は超越で同じもののちがう様相なのだから。
記号ではどうしてもパラドックスが出てくる。コンピューターは意識を持てるか。コンピューター「ハル」(HAL、映画『2001年宇宙の旅』にでてくる人工頭脳。名前の由来は当時最も進んでいたコンピューターの会社IBMのアルファベットの一つ前の文字)のように自己意識を持った人工頭脳はできるか?……それは不可能だ。それをアメリカでは一生懸命に試みているが実際はできていないしできない。記号ではできないのだ。最小の部品が無機物ならば自他の空間がフラクタルにならないのでタイムマシンと同じように不可能なのだ。チェスで世界チャンピョンとコンピューターが対戦してコンピューターが勝ったことがあったが、それはマラソンのランナーと自転車に乗った人を競わせるようなもので、無意味な戦いだ。コンピューターと人間が戦うには、コンピューター自らが電源を入れ、自らがキーボードを叩かなくてはゲームが成り立たない。チェスの世界チャンピョンはコンピューターという凶器をもったチェスのプログラマーという人間に負けたのだ。だから、同じ競技で同じルールではないので、チェスの世界チャンピョンはコンピューターに負けたわけではない。走り高跳びの選手は棒高跳びの選手に負けたわけではないのである。
内と外は連続している。では、円の線上ではどこが内なのか外なのか。僕がフラクタル幾何学やマンデンブロー集合に興味を持ったのも、同じ観点からだ。国境線の長さはものすごく変わる。線を引くときに、完全にこちらがA、こちらはBというように分けられない。ガタガタの線になるし、どんなに小さく厳密にしようとしても砂粒の一つひとつまでは決定できない。勾配しているものの端のほうでは明確に決められるが、連続しているものは極小と極大でフラクタルになる。
フラクタル幾何学では、カオスとかフラクタルの概念を記号によって近年新しく拓いてきた。その辺が「知」の重要な問題になるだろう。人間の生を、「知」で捉えようとするとどうしても避けては通れない。内か外かという問題は難しいね。飯を食う。リンゴを食う。口にあるものは、内か外か。そう考えると危うくなる。胃から腸へ続いていくが、その空間を辿っていくとそこは内か外か。
水の中を通る光は、水に対して光は外部の存在だ。では眼球の中を通る光は自己の外部か内部か。角質層は外部か内部か。水の中の魚は水とは全く異なるものだ。だけどやはり外部と内部の境界を決めようとすると同じ問題にぶつかる。だいたい内部のことでも一個一個の細胞に対して血液は外部だ。では最後に、考えること、思うこと、意識することはどうか。考える、思う、意識する、は自己の内部とみなしてしていいにしても、考えること、思うこと、意識すること、の「こと」の情報は内部か外部か。文章を書いたり、絵を描いたりすることは外部世界から情報が入って内部を通過して外部に顕現させる、という行為である。外部と内部は境界がなく連続している。そのように内と外は絡み合っている。ほとんどのものがじつは絡み合っている。有機物はすべてマンデンブロー集合の形態になっているのだ。人間は外部に対して「世界=内=存在(ハイデガーの造語)」であるが、内部に対しても「世界=内=存在」である。だから、こういう空間を創造しない限りコンピューターには単細胞生物の自己意識さえ持てないのである。
絵も人生もそうだ。小津安二郎(1903~1963年)監督の映画を見ると分かる。小津安二郎はよく自分の映画を豆腐に例えているのだが、豆腐は部分と全体が自己相似形(フラクタクル)である。小津映画では全体と部分が同じ形をしている。人生もそうするのが正解なのだ。一生と、一日の曲線を一緒にする。一瞬一瞬と一日を、同じように過す。事件を起こしたり、途中で生き方を変えることは、一生の曲線と日々の曲線が乖離してしまい、大抵は失敗する。仏教では昔からフラクタルの概念をいろいろな言葉で言い表している。「一即一切、一切即一」「一入一切、一切一入」「重々無尽」「主客一如」「相即相入」等。特に「事事無礙法界」の「インドラ網のたとえ」はマンデルブロー集合そのままである。日本人はもともと「日々の生活」ということをよく言う。あれは一日一日を、一期一会できちんと生きるということだ。
ウイトゲンシュタインはすごい。「論理で倫理がいえないか」などと壮大なテーマに取り組んだ。ところが記号という欠陥ツールでやろうとしたことが間違いだった。絵描きや芸術家のようなことをウイトゲンシュタインはやろうとしてダメだったが、やろうとしたこと自体は壮大だった。彼は、論理の第一前提に「時間」を入れていないからだ。三段論法のA=B、B=C、ゆえにA=Cというのは、時間という概念を入れて考えると危うくなる。時間を入れると、A=Aというものさえ崩れてしまう。その論理はアプリオリで、だれがやっても証明の必要のないものだった。ところが、時間を入れるとそれが崩れてしまう。パラドックスが出てしまう。
飛ぶ矢は止まっているとか、アキレスとカメとか、古典的なパラドックスはこの問題に起因している。しかし、芸術だけが時間を暗示できるのだ。これからどんな絵になるか、楽しみだ。これまで、これだけやってきたのだから。いろんな手を使うが、しかし前述のように一本釣りをする必要はない。網をかけて「ここにマグロがいますよ」というのであって、「これはマグロだ」と言って船上で挙げてみる必要はない。
時間はここにあるのだ。僕がその絵をなんとかする。絵は錯視なのだ。マグロを描くことしかできない、現実のマグロを画面に貼り付けるわけではない。ウイトゲンシュタインのように網をかけて、グッとしぼって……。ウイトゲンシュタインは人間として素晴らしい。何人かの人間はそのような概念の広い世界を相手にして人生を過すのだ。大きな網を仕掛け、論理で網を絞り込んでいったのだが、「時間」だけが抜け落ちていた。絞っても絞っても、時間だけが抜けていた。
僕は網をかけて絞っていって、確かにここにいますよと暗示できればいい。すごいだろう。壮大なことだ。岡山県の玉野市という港町の、造船所の社宅の「コウちゃん」から、ここまできたのだ。一介の卑小な実存がここまで来たのだ。絵は見た目にはそんなに変わらないかもしれないが、考え方としては大きく変わる。フラーのように、僕はこれまでこうやってきたということを「時間」を入れてバインドし直せばいいのだから。
●あとがき
最初の予定では四章で終わりで、あとはしめの文章を書くつもりでいたのだが、11月の個展の行き帰りの電車のなかで、「『論理哲学論考』を読む」(野矢茂樹著、ちくま学芸文庫)を読んでいて、大変なことに気づいて興奮し、急遽、越智氏と原田さんにお願いして、アートヴィレッジのある湯島の喫茶店で5回目のテープを録ってもらった。きっちりと「落ち」がついた、終章にふさわしい文章ができたと自負しています。だいたい、男女とも歳をとると、人の話は聞きたくないし自分の話は聞いてもらいたい聞かせたいという、はなはだはた迷惑な傾向になってくる。その傾向の人一倍つよい僕が十全に語り尽くした感があり、この本を書き終わったら数年間はおとなしくしているつもりです。(2008年師走のアトリエにて)
| 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 |