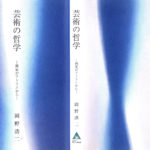| 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 |
『芸術の哲学』第2章
————————————————————————————————–
●描写か、表現か…
これは画家にとって最も重要な問題で、これを話さないと本書を出版する意味がないという大切な話。
美術史をみれば、つい百年前のセザンヌまでは、絵画は一本の大きな川だった。西洋、東洋と場所と技法は違っていても同じ一本の川だった。しかし、現在の美術の状況を見まわしてみると、なんと多くの支流に分かれてしまっているのだろう。もう、流れのないプールの中で一人一人の画家が浮かんでいる状態だ。この状態を良しとするのか、我慢できないのか。僕は、我慢できないから、こんな本を書いているのだけれど。
一本の川。ダヴィンチ、ヴェラスケス、クールベ、モネ、セザンヌ、マチス、ここまでは水流豊かに流れてきたのに、多くの支流に分岐する大きな要因のひとつは、ポストモダンの国家アメリカの、文化への台頭だろう。フランスのはぐれ画家だったマルセル・デュシャンがアメリカで開かれたヨーロッパの現代絵画展(1913年)で評判になり、本人もアメリカに渡り国籍も取って(1915年)その後のニューヨーク・ダダの中心人物となった。第一次世界大戦(1914年~1918年)後、金持になったが、歴史のないアメリカは、バーンズコレクションでわかるようにパリに絵を買いにいっていた。ここへきて漸く本家のものまねでない、自前の美術の種ができた。二十世紀の後半はまさにアメリカの時代で,美術の中心はパリからニューヨークに移ってしまう。そして、その波を戦後の日本の美術界はもろにかぶってしまった。デュシャンは画家でありながら「網膜的」な芸術への懐疑と嫌悪を明言している。こんなことを言う画家がいたり、それに追随する日本の評論家や若い画家たちに、画学生だった僕は驚き、戸惑った。「美」を否定して絵画は成り立つのか。音楽が耳の芸術なら、美術は目の芸術ではないのか。僕が考え、信じて進んでいる方向は、間違っているのか……。
ダダイズムは第一次世界大戦に対する抵抗や、時代の閉塞感、虚無感をもとに、一九一〇年代半ばに,自然発生的にヨーロッパの各地に起こった芸術運動だ。
コンセプトは,規制の秩序や常識に対する否定、攻撃、破壊。画家も参加したが、こういう美学よりも社会学的なイズムは、しゃべる人むきで、文学者が中心(ツァラ、ブルトン)だった。ダダイズムは美術史にはほとんど影響なかったけれど、詩人のブルトンがダダから分かれてつくったシュルレアリスムの運動は、フロイドの精神分析をとりいれ、ダリ、エルンスト、キリコ、マグリットなどに影響して美術史の一つの流れになった。ブルトンは第二次世界大戦の時アメリカに亡命してニューヨークの抽象表現主義の画家達に大きな影響を与えた。ヨーロッパのダダの運動はすぐに下火になったののだが、このダダが歴史のないポスト・モダンの国アメリカに、パリのはぐれ画家デュシャンによって飛び火して火種はのこり、一九五十年代半ばから、抽象表現主義にかわって台頭してきたニュヨークの若い画家達(ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ等、ポップ・アートもこの流れ)によってネオダダとして再び燃え盛った。アメリカの国力を背景にしたこの波はすぐに日本にとどき、大阪の『具体美術』、東京では『ネオ・ダダ・オルガナイザーズ』『読売アンデパンダン』と一九六〇年代の日本の美術ジャーナリズムは抽象、アバンギャルド(前衛。なつかしい言葉だなぁ……)で沸騰していた。
現在、その当時を振り返って、迷ったとき、あるいは袋小路にはいった時に、自分の目(横に丶)を信じてきて、つくづく良かったと思う。《参照文:「芸術の杣径』22~25頁》
とにかくその頃は、学生運動で学内が盛り上がっている時のノンポリ学生のように、社会と関係ない美術(美の横にだけ丶)をやっていると、画家としてのモラルを問われる雰囲気だった。特にそれまでの東京芸術大学はフランス絵画一辺倒だったので保守の牙城とみられ、その当時の社会のムードと学内からも新しく着任した改革派の教授のゴリ押しで、受験問題も授業内容もドラスティックに変わって、文化の伝統の豊かな日本の美術教育が、現在のポストモダン的状況に至っている。
時間が過ぎれば、また透徹した目で広く世界を見渡せば当たりまえで何でもないことなのに、還暦過ぎてやっとこんな事が言えるようになるんだよ。人生はやっかいだね。まあ、だから面白いとも言えるが。
で、表現か描写か、だけど。何故、表現も描写も、でないのかという理由はうまく説明できるかどうか、また理解してもらえるかどうかわからないが……とにかく、表現か描写か。
「表現か描写か」は、戦後の日本美術界でいちじ問題にされた〔「何を描くか」か「どう描くか」〕や〔「物を描くか」か「事(ルビ、こと)を描くか」〕と共通の問題意識である。〔「何を描くか」か「どう描くか」〕や〔「物を描くか」か「事を描くか」〕はマルキシズムにシンパシーを持った画家達からの問題提起で、「リンゴをどう描くか」なんてやってたってナンセンス、「リンゴはリンゴだ」ということに何の意味があるのか、というわけだ。「リンゴをどう描くか」が僕の立場だから、当然その意見に対して、反論と、自分の描画の理論武装しなくてはならない。現代の画家がどうしてこの問題を棚上げにして、きちんと総括しないで絵を描いていけるのか不思議でならない。当然、僕は画家だから、〔「何を描くか」か「どう描くか」〕や〔「物を描くか」か「事を描くか」〕のような芸術社会学的な問題提起ではなく、「表現か描写か」という美学的な問題に替えて提起したい。芸術の社会学的問題は話題にしなくてもいいが、最近絵描きがさっぱり美学的な問題を話題にしなくなったなぁ……。
まず、描写。…クールベ、モネ、セザンヌ、マチスの絵を見比べると、絵のモティーフはみんな同じものを描いている。描いているものは変わらない。世界を描写している。風景、人物、静物と誰もが目にすることができる、特別なものとか珍しくもない、どこにでもあるありふれた対象を絵にしている。画家のすぐ横にある、ありふれた対象をとらえる目がすばらしい。何が描いてあるかという「内容」は同じで、目で対象を認識する仕方、すなわち「形式」が違っている。描写だけで成り立つこのような絵画は、印象派前後と日本の花鳥風月の絵くらいしか思いつかない。印象派前後の、認識の「形式」の方を重視し、目が独立し、視覚だけで自立していった時代の方が珍しく、貴重で奇跡的なのだ。美が、芸術が、視覚が、目が、それだけが、それだけで存在し、それを感受する人は生の喜びと肯定感に満たされる。世界は美しくて、生きていくことは素晴らしい、これは各種の展覧会で僕が彼らの絵に直接出会った時の実感なのだ。絵画が超越(美)にこれほど近接した時代は無かった。目が美を味わい、解釈は後で脳が行なうのだ。
一方の、表現。絵の「内容」の方を重視する画家達がいる。いや、この言い方は間違っていて、いつに時代もほとんどの画家は「内容」、「何を描くか」を自分の表現の中心の課題として絵を描いている。これらの画家は枚挙にいとまが無い。表現は、いわばおしゃべりの事だから、カント、デカルトの近代自我意識が世界に登場して以降、アマチュアも含めて大部分の画家が「表現」しようとしている。何かを言おうとしている。画家になることを志して、最初のうちは描写の勉強をするが、初歩的な技術を身につけると、すぐに表現の方にベクトルを替えてしまう。
シュルレアリスムを例にとれば、ダリの絵を見ると、描かれている対象の「内容」が重要だということが歴然としている。柔らかい時計とかキリンの背中が燃えているとか、描写しているものは異常で変わっているが、しかしその形式はありふれている。その容器というべき空間や光は従来の当たりまえの認識、捉え方を出ていない。つまり、リアリズムの絵の中身をエキセントリックに異化すればシュルレアリスムの画になるのだ。
表現と描写はどのイズムにも分岐点になって、フォーヴィズムはブラマンクの表現とマチスの造形(日本のフォーヴィズムはブラマンクの流れ)。印象派はゴッホが描写とムンクの表現で、どちらも描写と表現の分岐点にいる。
表現は、何かを言おうとすることだから、反芸術のダダイズムやコンセプチュアルアートもこの範疇のイズムである。「何かを言おうとすること」の内容は当然言語的だから、哲学者や文学畑あがりの評論家が喜ぶのは、洋の東西を問わず当然だろう。
描写は認識、表現は内容を問題にしている。どちらのベクトルに進むのか。僕は、高校二年生の時から、生き方のポリシーを実存主義と決めていた。(参照文:『芸術の杣径』132~134頁 私は、高校二年生の時、実存主義に~標榜するに至ったのだ。)実存主義を美術史にあてはめると、ダダイズムやシュルレアリスムや表現主義になるのだ。生き方は実存主義でも、目が惹かれるのはモネ、セザンヌ、マチスの方向の絵画で表現の方向の絵画ではない。どうにも、その分裂を止揚できないでいたが、五十歳台にはいった頃、我流の哲学的思考により、実存論的世界観そのものが間違っていることに気付いた。世界の存在は、内在か超越かという問題だ。
観念論か、経験論か。実在論か、唯名論か。これらの問題はプラトン、アリストテレスのギリシャ哲学から現在まで延々と続いている。近代ではカントを代表するドイツ観念論(演繹的。知性重視)とベーコン、ヒュームを代表するイギリス経験論(帰納的、感覚重視)。
カントの有名な認識論における「コペルニクス的転回」とは、人間は物自体を認識することはできないのだから、外部にある対象を受け入れるのではなく、人間の認識が世界を構成するのだという、ドイツロマン派の芸術家達の理論的支柱になった説である。世界をどう捉えるかは、人間のほうで、自我の外側には人間には出られないし、物自体には到達できない。世界や、その歴史やその秩序は人間が構成するものだという考え方、これが観念論だ。カントはアプリオリ(先天的、生得的)や外部世界の存在そのものは否定してはいないが、第二次世界大戦後の文化、芸術にカリスマ的影響を及ぼしたサルトルの実存主義は、いっさいのアプリオリを認めない極端な自我中心の世界観だ。ちょうど僕は画学生時代で、その頃は人間を中心にするヒューマニズムやヒッピー、学生運動、紅衛兵など反体制、サブカルチャー、改革、革新、の風潮が世界中の若者を席巻した感があった。
世界の存在が人間の側にあるなら、つまり美も内在であるなら当然、美は超越でも普遍でもないわけで、人それぞれ百人百通りと考えるのは当然だろう。そういう考えの人たちからすると、単に外側を描写しても、「なんだ、そんなの、そこには何もないではないか」ということだ。実存のほうを問題にしなくてはダメだという考え。
しかし、実存主義を通過して超越的実在論者になった現在の僕の考えでは、外側に世界は実在する。「内在」ではなく、自分の自我意識の外側、つまり「超越」的に、きちんと世界は実在するのだ。そういう信念がないと描写というのは成り立たない。カントは、人間の認識は物自体にはとどかないといった。今の僕はそうは思わない。僕の考えでは、人間は自分の外には出られないのに、どうやって外側のものが認識できるのかといえば、外側の実在は人間の肉体の感覚器官にカメラや鏡のように勝手に自動的に写り込んできて、それを自我意識が解釈している、と考えれば納得いく。つまり、自我意識のバイヤスのかかった解釈の外側に無意識(自我が関係しないのだから当然)に写り込む膨大な外部世界を人間の肉体は情報処理し保存しているのだ。物自体はかってに人間の内側に写り込んできているのだ。だから、世界の存在を通底する「真・善・美」も自我に関わりなく、あまねくすでに写り込んでいるのだから、それを自我意識を意識的にエポケー(スイッチを切る)して観想、観照すれば超越(美)に届き得るし、またそれを顕現することもけっして不可能ではない。
《参照文:学生時代は、不満がなかった。自分でやればいいことだから、そのようにやってきたし、教わろうとは少しも思っていなかった。環境は大学が全部揃えてくれている。おまけに、美大生というモラトリアム状態の無責任さと、大学生ということで周りの人からも認められ、将来の自分の可能性を含めて、非常に楽しかった。(今から考えるとあたりまえなのだけれども、大学を卒業して、社会に出て裸になってみると、会社や学校や美術団体に所属していないと周りからの視線は冷たいもので、その頃にずいぶん一般社会に鍛えられた)
当時、周囲の美術状況は、世界の美術の中心がヨーロッパからアメリカに移り、アメリカの美術運動がリアルタイムに日本に紹介され激動の時代だった。互いに矛盾するコンセプトのイズムが月替りに若い画家の間を駆け巡るのだ。シュールレアリスム、抽象表現主義、アンフォルメル、壁派、反芸術、ポップ・アート、オプティカルアート、ネオ・ダダ、ミニマル・アート、シュポール・シュルファス、美術運動に留まらず風俗にまで拡がったアングラ、サイケデリック、ハプニング等々。
世の中が、政治も文化も反体制、反権力、美術もアヴァンギャルド(前衛)に向かっていると「自分の今やっていることは間違っているのかなあ」と不安になったこともあった。(当時の流行語、自己批判、サブカルチャー、カウンターカルチャー)
特にその頃は、僕の好きなマチスやピカソが、とくにマチスはむしろ否定的に捉えられていた。
かといって、美大生になっても、マチスやピカソはまだまだ理解できていない。セザンヌも理解できなかった。モネやベラスケスも、すごく惹かれるけれど、結局理解できていなかった。当時の絵の見方というのは、どうしても感傷的、文学的にみてしまう。松本竣介とか、佐伯祐三とか、モジリアニだとか、ある意味では感傷的で、青春の甘酸っぱい、ロマンチックな、そういうものに非常に反応するわけだ。しかし、造形的なものには、どうも確かに良さそうだとは理解できても、分析できない。自分がそれだけのスキル(技能)を持っていないから。
ただし、マチスを否定されると「僕はマチスに惹かれているんだけれど、間違っているのかな…」という気持ちになる。世の中全体がそんな傾向だったので、その当時の代表的な意見ではマチスは「保守反動」に見られていた。マチスは第二次世界大戦中、フランスがドイツの占領下で、自分の娘が抵抗運動の嫌疑で拘束された時も、彼の作品の上にはまったく影響しなかった。
ピカソは『ゲルニカ』を描いたり、大戦後一時共産党にはいったりと、かなり社会状況に反応していくのだけれど、マチスは唯美主義というか、芸術至上主義的で、絵はそういう周りの状況と一切関係なしにやっていた。
マチス的な唯美的世界は、時代に遊離した、女性をソファーに座らせて、ヌクヌクと心地のいい美しい絵を描いている、保守反動のきわみだと攻撃された。その風潮が当然、僕の近辺にも影響してくる。
「今の時代にまだヌードなんか描いて、そういうのはアナクロだよ…」と、ちょっと先走った同級生にいわれた。「造形とか、美とか、もうそんな時代ではないよ…」と。僕はそういう絵が好きだし、いわゆる描写の仕事だから、主観表現とか、政治的メッセージなんかは、一切絵に考えていないのだから、不安になるのは当然だ。
それからデュシャン。一時期、美術ジャーナリズムはデュシャンがいい、いいと神様みたいに言っていた。デュシャンは、目を喜ばせるための「網膜的絵画」を否定した。「…何だ、これは。美味しいものを出さない料理屋があるのか、美を目指さない絵描きがいるのか。こんな絵が本当にいいのか。僕が間違っているのか…」
今になってみれば僕のほうが正しいと自信を持っていえるが、当時は自分の進むベクトルがあやふやなのだから危なく道に迷うところだった。デュシャンの有名な『大ガラス絵』とセザンヌやマチスの絵を同時に並べて比べてみれば、絵と図の違いがよく解る。デュシャンの絵は、まるで設計図を見ているようだ。
同 36~38頁から
その時に、僕がとったそれを打開する方法は、大学の図書館で、時代、ジャンル(写真、デザイン、イラスト、漫画)、イズム等を度外視してあらゆる平面作品を、少しでも自分の眼に引っ掛かれば無作為にスライドに撮ったのだ。そのスライドをマウントして、白い模造紙に直交する二本の線を引き、交点を自分の現在の立っている位置と仮定して、スライドを一枚一枚その紙面上に置いていった。Y軸線の上の方向には無条件に感動する作品、Y軸線の下方には無条件に否定する作品、一部心惹かれる(いわゆる、面白い)作品はY軸の左右の紙面に。もちろん、すんなりと簡単には行かない。何度も並べ変えたり、また、何処に置いたらいいのか分らない作品もたくさん出て来た。そういう作業を何日かやっているうちに、現在(2005年)の自分のコンセプトをも決定する重大な糸口を見付けたのだった。
Y軸線上のスライドはほとんど動かない。動くのは、線上外の作品だ。僕のY軸線上外の作品の作者は、各々のY軸をその方向に設定して仕事をしているのだ。そのY軸のベクトルが各々の作家のコンセプトの違いなのだ。
その事に気付いた後に、僕のとった行動は、Y軸線上の作品を残して、線上外のスライドを全て一括して「判断停止」のジャンルにまとめたのです(パソコンでいえばゴミ箱フォルダー)。
僕の一生を賭けてやるべき事は、自分のY軸線上を少しでも上に這い上がるように努めるのみだ。そして、他者の作品のコメントに、「面白い」という言葉を使わない。他者の作品が僕のY軸線上にない場合は、判断停止(エポケー)、つまり見ない。エポケーした作品群はその後自分の位置が上がったら、取り出して評価し直し、評価出来ない物は又ゴミ箱に一括する。こうやって、自分の絵画制作のベクトルを定めたのです。そのようにして、その次点で、自分(原点)のすぐ上にあったのがコローとバルビゾン派、特にドービニー等の画家達。それで彼らの作品を参考にしながら、武蔵野近郊の風景を描き始めたのだ。》
●人生の処し方と美意識が、結びつかない……
僕はかって実存主義者だったから、五十歳前後までは人生の決断や生き方はすべて自分の「自我」によるのだと決めていた。自分の時間は自分が使う、自分の人生は自分が決める。人間関係や社会的な行為のきまりを、自分の外側に措定しない。アプリオリに超越「真・善・美」などが存在したりはしない、まずは自分が選択し、美意識やモラルは自分が決めていくのだ、という考えだった。
実存主義は現実の社会で生きていくには大変困難だ。僕は画家だからまだいいが、現実社会の方からの要請を受け入れないで、自分の都合ばかりを優先すれば、サラリーマンは出世しないだろうし、すぐにリストラされるだろう。就職にしのぎをけずる今の若者には考えられないだろうが、僕たちのこの時代(一九七〇年代)の若者は自分から積極的に社会からドロップアウトする人もいたくらいだ。あまり極端になると、ラスコーリニコフ(ドストフスキー作『罪と罰』1866年 の主人公)のように金貸しの老婆を殺したり、ムルソー(カミュ作『異邦人』1942年 の主人公)のように、殺人の動機を「太陽が眩しかったから」という、犯罪行為も正当化してしまう。なにしろ、モラルも外側には認めないのだから、自己に忠実に生きようとするのだから。
いっときの前衛絵画ブームや学生運動、ロマン主義から実存主義のヒッピー、ヒューマニズム、カウンターカルチャー、サブカルチャー、反体制、ドロップアウト、脱サラ、四畳半フォーク、プログレッシブ・ロック、フリー・ジャズ、アングラ、等々これらの動きに影響した、通底するイズムは実存主義だ。大まかに分ければ、自己の自由と主観の実存主義と、その反対に、外部世界の客観的実在性への信頼の上に進歩してきた科学的世界観、この二つの対比。《参照文:『アインシュタインロマン3』NHKアインシュタイン・プロジェクト 日本放送出版協会150~152頁
1930年8月十日、『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』は、一面をつぶして大きな記事を載せた。「アインシュタインとタゴール 真理の深みを探る」と題されたこの記事は、インドの詩人・哲学者のタゴールがアインシュタインの別荘を訪れたときの会話を記録している。それは詩人と科学者、東洋と西洋の深い溝を隔てながらの対話であった。――中略――
T(タゴール)「われわれの宇宙が、永遠なる人間と調和するとき、われわれはそれが真理であることを知り、美とかんずるのです」
E(アインシュタイン)「それはまったく人間的な宇宙の理解です」
T「この世界は人間的な世界です。この世界の科学的な見方というものもまた、科学者の見方です」(中略)
E「証明することはできませんが、ピタゴラスの定理において、真理は人間とはかんけいなく存在すると私は信じています」(中略)
T「私たちが真理とよぶものは、実在(リアリティ)の主観的な面と客観的な面との間の合理的な調和の中にあるのです。そして、その両面とも、個を超えた人間に属しているのです」
E「日常生活でさえ、われわれとは関わりのないことがあります。実在が心の外に、われわれとは無関係に存在することがわかります。(中略)例えば、家にだれ一人いなくても、机はその場所に存在しています」
T「そうです。机は個人の心の外にありますが、すべての人の心の外側にあるわけではないのです。机はわれわれに共通する意識によって知覚されるのです。(中略)客観的に見える机も単に現象にすぎないことを科学は証明しました。つまり、人間が机だと思うものは、もしその意識がなくなれば存在しないのです」
ー中略ー
タゴールは、客観的に正しいということは科学においても存在せず、あくまで人間という集合が正しいとしているだけである、と言う。
一方のアインシュタインの考え方は、哲学の用語では「素朴実在論」と呼ばれるものだ。ともかく日常経験から言って、人間が見ようが見まいが客観的に世界は存在している、という考え方である。》
既成の制度や体制を、自己の自由をおかすものとして否定し、すべての価値観を一度壊して(ダダイズム)、自分たちでもう一度、モラルとか美意識を再構築しようというのが、あのころの風潮。
それで、僕は人生の処し方は実存主義でやってきたのに、絵のほうは、目は、超越的な美の方向を目指す画家のほうに惹かれる。表現主義や、シュルレアリスムや、人生派、つまり「語る絵画」に比べて、モネや、セザンヌや、マチスなどの「視惟する絵画」のほうに惹かれていく。人生の後半になって、特にそうなってきた。自分の美意識と、人生の処し方とが齟齬をおこしてある期間うまく結びつかなかった。そこで、どうなの?それで、どうするの?となる。
●フラクタルとゲシュタルト
しかし、それが解決した。僕の世界観のフォーマットだった実存主義が間違っていたのだ。僕の意識より、僕の目のほうが正しかったのだ。それは心理学の「逆さメガネ」の実験のことや「夢のなかの空間」のことを考えてきて、しだいに解決してきた。要は、主観と客観、内在と超越、自分と世界……これらが、境界があってキチッと二つに分かれてはいない、ということだ。存在の根源が実体であるならば一元論がなりたつが、存在の根源が関係であれば二元論で世界観を組み上げなければならない。「関係」ならば一つでは関係できない。世界はペアーで成り立っているのだ。「有る」も「無い」とペアーで、どちらも単独では存在しないのだ。人間と世界があって、人間はこんなことを考え続けている。
自分と世界があって、現象があって、自分がこちら側にいる。あちら側には物や他人がいる。そして、それが出会った時にいろんな現象が起きる。それが事象だ。人間だけでなく、物体と物体とがぶつかったときも現象が起きる。こちら側とあちら側、世界の存在のアルケーはこちら側とあちら側とどちらに一元論化、収束していくのか。この哲学上の問題が数多くの言説を歴史の上に生み出し、互いの説が闘ってきた。あちら側は科学、数学、唯物論、構造主義、実在論、こちら側は唯名論、実存主義、ロマン主義、観念論。あちら側は実在するのか空なのか、それともこちら側がつけた名前にすぎないのか。こちら側はそもそも、自我はあるのか(仏教では無我を説く教説もある)、あるとすれば自分のどれが自我でどこにどうあるのか。原因の原因をたどっていくと、究極の原因は「1」でなければ、一神教を信じる人たちは特に「2」だとなんだかすわりが悪いのではないか。
ところが、「夢の中の空間」のことを考えたり、「逆さメガネ」を考えたりしているうちに、フラクタル幾何学に出会った。フラクタル(注:拡大しても縮小しても限り無く自己相似形の図形、例カリフラワー)とか、ゲシュタルト(注:全体性。全体の形態)とか。
フラクタルとは、部分と全体の関係が自己相似形な図形のこと。雪の結晶、雲のかたち、海岸線、木と枝と葉脈、カリフラワー等の幾何学的な形だけでなく、部分と全体の関係に解釈をひろげて、人間の存在の在りようもフラクタルをあてはめるとイメージしやすい。クローン人間は理論的には可能ということだが、部分の細胞一つから全体ができるのだから、一つ一つの細胞の中に全体のかたちの情報が詰まっている、つまり磁石のようになっていると考えていいのではないか。そうだとすると、人が芸術をなそうと思うと、この本の「磁石と人間」の章に書いたように、美の方向に全細胞をフラクタルにそろえると磁力というエネルギーが生まれるのではないか。芸術という方向に細胞を揃えることだ。なにかをなそうと思うと、磁力をもつことが必要。フラクタルに揃わないから磁力という力が出ないのだ。職業に関係なく、部分部分がバラバラになっていると、力が出ないのだ。
ゲシュタルトも耳慣れない言葉でわかりづらい概念だが、イメージがつかめれば人間の認識のメカニズムの理解に役立つ。ゲシュタルトとは全体の形態のことで、全体は要素に還元できない、つまり全体は部分の寄せ集めではない、人間は全体は全体のまま認識すべきだし、またそう認識している、というようなこと。認知心理学のゲシュタルト心理学やカウンセリングのゲシュタルト療法などで主要な概念になっている。人間や組織や世界を、要素還元的(小さく分けて原因を追及していく)でなく、全体を全体として捉え認識すると、そして部分と全体を重ね合わせてみると、ものごとがよく見えてくる。運動の練習で、分習法(ドリブルやヘディングをそれだけ分けて練習する方法)と全習法(試合形式で練習する)、分析(アナライズ)と統合(シンセサイズ)。個々の技術はうまくても本番のゲームで問われるのは結果だし、生きていく上での行動で問われるのは総合判断だ。悲しいかな現代は、文明の発達のために人間が専門化せざるをえなくて、家庭でも、仕事でも、部分としての役割だけにおわっている。自分とはゲシュタルトなのだ。人間とはゲシュタルトなのだ。世界とはゲシュタルトなのだ。超越(真・善・美)とはゲシュタルトなのだ。
●夢の現象学
夢は、自分の脳の内部で起きている現象だ。さて、「夢の中に出てくる他人は誰が話しているのか?」。
他人の出てくる夢は誰でも見るだろう。誰もが見る夢なのに、この本の『虚数』の章でも話したが、僕のこういう疑問の立て方が非凡だろ。最初の単純な疑問、それは夢の中の他人は誰かということ。他人が僕の頭の中に居着いているのか?
ところで僕は、単純な疑問があると解けるまで放っておけない。中学生の頃の疑問は「生まれつき目の見えない人は夢を見るのか?見るとすれば、どんな夢をみるのか?」ということ。こんな疑問が次々に続いて生まれ、まわりまわって結局現在の僕の絵のコンセプトにまで影響している。子供の頃から、世界は不思議なことだらけだった。そういう疑問から入っていって「動物は夢を見るのか?」「昆虫は夢を見るのか?」とサツマ芋のように疑問がずるずると連なってわいてくる。
僕が出した結論だけ言うと、夢は「見る」のではなくて、夢の空間の中で「生きている」。夢を「生きている」とすると、生まれつき目の見えない人は当然夢を見る。動物も夢を見る。昆虫も夢を見る。
夢の中の他人の話に戻ると、夢の中の他人は、誰が話しているのか。夢を、映画を見ているように見ていると仮定すると、自分が観客席で見ているとして、では映画を映している人はだれか?自分の中の一部が観客で、一部が映写している人で、では、映画を撮ったのはだれか? これも自分。
そうすると、脚本を書いて台詞を指示したのは自分だし、カメラマンも自分だし……。では俳優はだれ? 台詞を全部指示したとしても、台詞をしゃべっているのはだれ? 俳優そのものはどうするの? 俳優だけはどうこじつけても後ろに自分がくっつかない。どこかから連れてこなければならない。俳優を連れてこなければ成り立たない。すべて自作自演だとしても、夢の中の他人だけは純粋な他者だ。他人だけでなく、風景や、物も。つまり自分の中に他者が住みついている。風景や物も住みついている。起きて、生活している空間が、そっくりそのまま頭の中に映りこんでいる。これをどう考えたらいいか? そこからフラクタルという考えに入っていく。
ものごとを、こういうふうに考える。こちらに自我があってそちらに社会があって、ここに境界線があって、自分と世界、内部と外部が境界線のもとにはっきりと分け、自我の存在、世界の存在というように、これを対立させて闘わせるから矛盾が生じる。また夢の中の他人のことも、説明がつかなくなる。このようにイメージしたらどうだろう。磁石のように、外側の世界をN極自分の内側をS極だとすると、磁石を折るとまた磁石になるように、外部世界N極と自分S極の関係が、そのままスッポリと自分の内部にもあると考えると、夢の中の他人についても説明がつく。全体と部分が相似形(自己相似形)の構造、境界線のない構造、それがフラクタルなので、マンデルブロー集合の図像には境界線がない。有機物はそもそも外部空間と内部空間の境界がないので、だから水や空気や食べ物を取り込み、またはき出すことができる。外部の存在であるリンゴを自分が食べて消化吸収して一方は内部の血となり、一方は外部に便となって排泄される。この全課程で、自分がリンゴを認識した時から、食べて排泄する時までのリンゴは外部から内部に移る境い目はどこにもない。人間は肉体も精神もフラクタルになっているのではないか。つまり、自分の中に外部が開かれ、取り込まれている。人間の膨大な数の細胞の一つ一つにまで血液は供給され、時間と空間と個体の全体の情報が詰まって、全体も部分も同時に生きている。空間の概念が、外側の大きな世界の中に小さな部分の自分がいるという、こういう構造が、脳の中にもあって、細胞の一個一個がまたそういう構造になっている。ハイデガーは人間の在りようを、箱の中の石のような存在のしかたで存在していないとして、人間のことを実存(現実存在)と呼び、その様態を世界=内=存在と名付けた。
人間は実存で目一杯ではない。実存が世界を、内部に飲み込むかたちで認識(フロイドの認識)しているのではない。世界の中で自分は部分だ。同じように自分の中(脳)でも自我意識は部分なのだ。脳の中の自我意識の周りには、あらかじめ身体にインプリントされたパースペクティブが広がっている。人間だけでなく、有機物はすべて外に向かって世界=内=存在であるが、内に向かっても世界=内=存在である(内~であるに丶)。
高度な自我意識がなくても、動物や昆虫も、外部と内部がフラクタルな構造で生きている。植物や単細胞の微生物も、脳はなくても細胞の中に、外部の時間と空間のパースペクティブの情報は持っている。自我意識に近い、「今、ここ」「自他」の情報は細胞の中に入っている。
無機物は内部が世界=内=存在になっていないので、そこが有機物とは違っている。だから機械の事故は情け容赦がない。森や林の植物を見てみると、きれいに住み分けている。隣り合った木同士が生存競争しても、無機物の接触と違って、隣の木の幹を突き抜けるというようなことは無い。
犬はしゃべれないが、飼い主のしゃべる夢をみる。犬がごちそうを前にして飼い主に「待て!」と命令されてうなされる、こんな夢はきっとみるだろう。飼い主の「待て」という言葉は起きている時は外部のできごとだが、夢の中では犬の脳の内部での出来事だ。犬はしゃべれないのに、飼い主のしゃべる夢をなぜみることができるのか? それは、犬の自己意識の外側に犬の身体を通して外部が、意識に関わりなくインプリントされているからだ。飼い主(外部)の形象は、意識(犬の知性)が解釈するのではなく犬の身体が写し込むのだ。
さて、夢を見るという話の結論は、夢は見る(見る、の横にヽ)のではない、「夢の中の空間を生き(生き、の横にヽ)ている」のだ。だから目の見えない人も夢を見る。日常の覚醒時の空間が、スッポリ夢の中の空間になっている。その夢の中の自我が生きている。自我意識のない夢はない。夢の中で自分があちら側(見られる対象の方)に出てくることはめったになく、ほとんどいつもこちら側(見る主体の方)にいる。自分がライオンになったりする夢は見ない。時系列はとんだりしても、夢はビデオテープのように逆回りの時間はない。これらはすべて、夢の中の空間を「生きている」証拠。つまり、肉体は眠っていても脳の中の自我意識だけは、完全にではないが覚醒している(レム睡眠)。だから苦しい夢を見ると、夢の中でも苦しんでうなされるのだ。覚醒時は脳と身体は繋がっていて、身体は意志どおりに動くが、睡眠中は脳と身体の間のスイッチが切れていて身体が反応しない(たまにスイッチがONのままの人がいて、夢の中の動きを睡眠中にする人がいるのをテレビで見たことがある)。逆に、スイッチが切れたままなのに、脳が完全に覚醒した状態がいわゆる「金縛り」で僕も寝入りばなに時々かかる。睡眠中は覚醒時の空間が、スッポリ頭の中にあって、その頭(脳)の中の自我意識が、その夢の中の空間を生きている。「夢の中の空間を生きている」、そういう構造になっていると思う。
●「俺が、俺が……」といっても
夢の中の空間がそういう構造になっているのなら、起きて生活している時の脳の中の空間も同じようになっているにちがいない。現に朝起きる時、夢うつつから現実の空間に移る時、空間そのものの質の違いはない。そうだとすると脳の中は、自我意識の周りに身体が勝手に写し込んだ世界がとりまいている。僕の脳の中では、自我はやはり一部なのだ。
脳のない生物は多い。脳がないということは自我意識もない。植物は自我意識がない。ゾウリムシは単細胞で、だからとうぜん脳がない。(……中学生の頃、顕微鏡で覗いた微生物の世界は面白かったなぁ。身の回りにある、ありふれた世界も自分の視点を変えれば新しい世界が現れる。一滴の水の中にも生のドラマが息づいている)ゾウリムシは顕微鏡で観察すると、脳がないのにまるで意志があるかのような動きをする。好物があると「オイチィ、オイチィ」といって集まってくるし、いやな物を近づけるとサッサと逃げだす。ゾウリムシは、たかが一個の細胞なのに、脳もないのに、全体の行動はどうやって決めるの?
ハエをたたこうとすると、サッと逃げる。ハエから見たら、大きな物なんてたくさんあるのに、人がたたこうとするのが何故分かるのか。「あいつが俺をたたこうとしている」と、ハエには何故認識できるのだろう。
美大生だった頃、夜下宿で本を読んでいた時、蟻が一匹机の上にいるのを見つけた。蟻は夜も働いているのか。僕は手近にあった鉛筆を蟻の前に置いて登らせた。蟻が、右に歩いて行くと鉛筆の左端を持ち、先まで行って反転して左に歩くと右端を持つ。こうして、蟻は何度も鉛筆を往復した。蟻は近眼らしいので、僕の手の動きは見えない。いったい、この蟻はどうするのだろう。僕はかなりの時間、あとには蟻との根比べになって鉛筆を持ち替え続けた。
すると、蟻は突然鉛筆から飛び下りた。また鉛筆に誘導して同じことを繰り返すと飛び下りる時間はしだいに短くなり、終わりにはすぐに飛び下りるようになり、そこで蟻を窓の外に解放した。
蟻が飛び下りたのは、蟻の心が決断したのか。イソップ物語のように、擬人的な心が蟻の中にあるのか。心や意志が蟻にあるなら、どうして「こんなに群れのために働いてばかりではつまらないからここから出よう」なんて、思わないのだろう?
動物や昆虫は一匹ごとに自分の行動を決定する心や意志を持っている。しかし、彼らは投げ入れられた世界の中から一歩も出られない。彼らの「生きられる空間」の中では、自由意志の働く余地はない。彼らは意志で動いているのではなく、ゾウリムシを含めて、機械的というか構造的というか本能的になっている。つまり、個々の生物は、被投された世界(過去性)だけしか持っていないので自分を投企(未来性)できない。麦の種が落ちれば麦の一生が待ちかまえているので、決して米になることはない。
人間においても、生物という点では同じだが、人間は何が特別かというと、内面の世界を外部に取り出せることである。何を考えているかという内側の世界を、言語や美術や音楽で表わすことができる。だから、ボノボのカンジ君のように簡単なパソコンを使って自分の表現手段を持てば、一気に時空は広がるのだ。(参照文:「人間とは何か」岡野浩二作品集123頁)
もう一つ人間が他の生物と違う点は、これはあくまで僕の仮説だが、内部世界の中心点と、その後その中に生まれた自我意識の中心点がズレているということだ。人間が生まれ落ちてから、内部世界は時間とともに同心円状に広がっていくとすれば、その中に自我意識が中心点のズレたところに生まれて、互いに時間とともに広がっていく。中心点がズレていることと、人によって自意識と世界観の成長の差によって、年齢的には思春期の頃、世界観の外にはみだす部分が出てくる。
その部分が、「世界がそうであっても、俺はそういうのは嫌いだ」と主張できる。自殺が人間だけにあるように、世界そのものを人間は否定することもできる。人間は、人間だけ、自殺さえも投企する。人間だけが「世界がそうであるなら、世界がそうであっても俺はこっちで生きる」と言える。ドストエフスキーもそう言っている。彼は実存主義者だから、2+3が5であっても、俺はそんなの信じないといえば、そっちのほうが上だという考えだ。人間の前に2+3=5の強固な壁があっても頭をぶつける自由が人間にはある、と彼は言っている。『地下生活者の手記』(1864年)に書いてあったはずで、高校三年の時に出会って、実存主義を自分の人生のポリシーにしようと思った。
しかし今は、自分の実存の自分の世界との関係と構造が分かってきて、自分は自分で目一杯ではない、自分の実存も自分の中ではほんの一部分に過ぎないと気付いた。僕の中では自分が主人公ですべて自分が決める、と思っていたが、その自分の中に世界はかってに写り込んできて世界の時空を形成し、その世界=内の自分が「俺が、俺が……」と言っても、それは実存が自分の部分に過ぎないのなら、自分が世界の部分に過ぎないのなら、『自分とはいったい何ぼのもんじゃ?」ということ。部分なのだから、そんなところを、自分の内面とか、自分の感性とかを問題にして絵の制作をしては、とてもダメだと考えるようになった。
●100人100通りではない
そんなところを問題にしてはダメというのは、自我の、部分の話だ。つまり外部が自分の中に、全体として脳内の時空に入っていて、それは実存主義者から言えば「超越」のはずだが、それが自分の中にあるとしたら、自分を認めると同時に、世界の存在を、認めざるをえないではないか。世界の存在を認めるのなら、自分が世界に含まれるとしたら、世界の普遍性とか超越性なども、認めるしかないではないか。
実存主義は、世界の存在を人間の〈内在〉と考えるので〈超越〉やアプリオリな存在を認めない。サルトルのような極端な実存主義では特に。それを認めたら実存主義であることができなくなる。だから、この本の「人生の処し方と美意識が、結びつかない……」の章で紹介した、アインシュタインとタゴールの二つの世界観が近代の代表的な世界観で、互いに争ってきた。それが、僕の中でも50代になるまで意識の実存主義と目の超越的唯美主義が争って、論理的な答えが出せないでいた。
僕がその問題を止揚して一応の答えを出せたのは、一つは「夢の現象学」の考察と、もう一つは、〈逆さメガネ〉の実験を本で読んで、人間と世界との関係の脳の内部構造を、推論して得たおかげだ。
〈逆さメガネ〉の実験というのは、人間は逆に見える(上下と左右がある)メガネをかけて生活するとどうなるか、という実験心理学の類末(ルビ:てんまつ)の話。本で読んだだけだから、自分が試したわけではないが、本当らしい。想像しても納得がいく。最初、被験者は船酔い状態になり、何週間かうまく行動ができないのだけれど、それでもメガネをかけ続けて日常生活を送ると、あるとき、数週間後に、突然周りの風景が正立するとのことだ。(参照文:『芸術の杣径』「続・夢の中の空間」より135~136頁 いよいよ~生成されるのか。)もともと人間の眼球には対象は逆さに写っているのだけれど、正立しているように脳が認識している。その実験によると、ある時期突然正立する。それは意志の力や自我の訓練ではなく、外から飛んでくるんだ。自分の中の自我が働いているわけではない。メガネをかけても寝てばかりいて行動しなければ、日常生活をしなければ正立しないかもしれないが。そして、正立してからも、本箱の本の背表紙の文字は逆さのままだとか(これは身体の情報処理と意識の情報処理が別のルートだということなのか)、興味深い現象だ。
そうすると、実存主義ではそれぞれの実存が世界をもつわけだから、当然ながら世界は、100人100通り。しかし、僕一人が〈逆さメガネ〉をかけていて全世界の人が裸眼であっても、全世界の人に逆さメガネをかけさせて自分だけ裸眼でいても、同じように同じものを見ていることになる。それぞれの自我のフィルターやバイヤスに関係なく、身体は世界を同じように写し込んで、その後の意識の解釈のところでそれぞれの実存のバイヤスがかかるのだ。眼球は同じものを見ている。僕が特殊な感覚であるとか、視力がいいとか、そういうこととは関係ない。外側からそうさせるという構造になっている。自分がどう考えようと、そうなってしまうのだから。
では、仮に全員が、逆さメガネでなくサングラスをかけていて、自分だけがかけていなかったら、あるいは自分だけがサングラスをかけていたら、どうなるのか。しかし、世界はそんなことにお構いなしに、空間と時間の座標に写り込んでくる。「変わり者だから、あいつだけメガネをかけている」とか言っても、世界は各々の身体に共通に写り込むのだ。それは、動物や昆虫も人間と同じ世界を写し込んでいる。違うのは動物や昆虫や各々の人間の、自我意識の解釈のちがいだ。身体が写し込んだ世界は、客観的な実在する、内在から超越する世界である。世界には、有名な動物学者のローレンツが発見した〈インプリンティング〉という仕組みがある。鳥が、卵の殻をやぶって最初に見た動くものを自分の親だと思うという刷り込み、インプリンティングだ。愛情とかの実存が関わる事柄でなく、そのようにプログラムされている。動物に逆さメガネをかけさせたらどうなるか、は興味ある問題だが、たぶん人での実験結果と変わらず、しばらくすると普通通りの行動ができるだろう。世界は常に身体にインプリンティングしている。感覚器官は写り込むすべてを情報処理している。暗闇の中で、見たい物にライトを当てて見るように、見ているのではない。意識はその物にピントを合わせるが、周りの意識外の物も目はちゃんと写している。考え事をしていても目にはちゃんと眼前の風景が映っているし、意識的に注視している物の周りも目には映っている。そして、そのビデオテープは脳の中のどこかに保存されている。
自我が関与してもしなくても、感覚器官にハンデキャップを抱えていても、自我が偏向していても、そうとうバイヤスのかかった変人でも、世界はすべての人の身体に共通に同じ形象で写り込む。人間の外部の〈超越〉的実在がインプリンティングされて脳に保存されて〈内在〉に場所を移す。そして、そのように写り込んだ世界の中に、自我意識が育っていく。
●自我は排するほうがいい
経験論と観念論の違いはというと、経験論者は、人間は白紙(タブラ・ラーサ:磨いた板の意)で生まれると考える。何も描かれていない白紙に、経験によって描き込まれるという。しかし、そうだとしたら、おかしなことがある。生まれてから一度も経験していない赤ん坊が、まるですでに知っているかのように行動するのだ。一度も経験していない赤ちゃんを,高いところに、透明の大きな厚いガラス板を二つのテーブルに渡して、一方のテーブルに赤ちゃんを乗せて、もう一方にお菓子とか玩具を置いたり母親が「おいで」とよぶように設定しても、初めての経験のはずなのに、その赤ちゃんは怖がる。これは経験論からするとおかしいし、説明がつかない。これに似たような現象は多々あるが、これが経験論が観念論者から突かれる点だ。しかし実際は、子供にとって空間と時間は、生まれ落ちてからの身体に、意識の解釈なしに勝手に写り込み、脳に世界のパースペクティブが自動的に形成されているのだ。自我が解釈しようがしまいが、世界はそのように映り込んでいる。外側の世界が、人や生物の内側にフラクタルに映り込んでいる。経験論者の「人間はタブラ・ラーサだ」という比喩に僕がつけ加えれば、その板はアプリオリに鏡のようにピカピカに磨かれていて、なにも書(横に丶)き込まれていなくても、周りがかってに映り込んできて世界が描(横に丶)き込まれるのだ。その世界の上に、後から意識によって書(横に丶)き加えるのだ。
「ここと今」「自己と他者」という認識は、細胞一つ一つにさえある。ということは、細胞の一つ一つの中に全部の情報が入っていて、それぞれが時空に開かれている。クローン動物は一つの細胞から全体ができるのだから、小さな部分にすぎない一個の細胞に全体がスッポリと入っている。無機物の部分ならそのようなことは不可能だ。有機物だから可能である。(どんなに、コンピューターやテクノロジーが進歩、発達しても鉄腕アトムや、『2001年宇宙の旅』のハルのような心的意識を持つロボットは生まれないだろう。なぜなら、全体を成らしめる部分が無機物なので、空間が閉じられているために無理だと思う)。フラクタルに、磁石のN・Sと同じようにフラクタルに、生きている空間と自分というこの関係がずっと細胞の一つにまで続く。磁石を割っても割っても磁石が続くように、このフラクタルという関係が続く。
たとえば、ヘレン・ケラーがサリバン先生によって「水」という言葉と実際の水が初めて結びつくのを認識する有名なエピソードがあるが、実存主義や単純な経験主義ではこの事の説明がつかない。ヘレン・ケラーは一歳九ヶ月の時の熱病で視覚と聴覚が失われ育っているのだから、当然サリバン先生と、経験も、経験によってつくられた実存的世界観もまったく異なるはずである。世界が(サリバン先生と共通の)すでに脳や身体に、映り描(横に丶)き込まれていることを前提にしなくては、描(横に丶)き込まれた世界の形象の原型が内在していなければ、間違いに気付くことができない。文化、宗教、習慣、経験、など書(横に丶)き込まれる内容はさまざま違っても、写り描(横に丶)き込まれた世界は、ヘレン・ケラーもサリバン先生も世界中の人々も動物も昆虫も微生物も、僕もあなたも、共通な形象がそれぞれに内在するのだ。それを前提し認めなければ、他者とのコミュニケーションはなりたたないし、すべてが「独り言」になってしまう。
芸術については、この辺が一番重要なところだ。
ここのところを、是非分かってほしい。そうすると「表現と描写の違い」がよく分かる。そうすると画家は何をすべきか、人間が何をすべきかも分かる。要は、自我自我というのをやめにしましょうということ。それから100人100通りではありません。美は超越であるということ。画家が美を目ざせば、「それぞれが好きなように自由に,既存のしばりを解放して表現しましょう」などと言っていられなくなる。画家が自分の中に、超越が映り込んで内在している構造を認めれば、シュルレアリスムや表現派やダダイズム等の実存主義的画家の仕事が方向違いだということに気がつくだろう。実存主義が少し前の、ヒッピーとか紅衛兵とか学生運動とか、その時代の考え方のバックグラウンドだった。芸大でも前の章で書いたように「アカデミズムはダメだ。あなたの好きなように描きなさい」という悲しむべき考えになってしまった。
人は自分の感覚器官(身体)に外部世界が映り込んで描(横に丶)き込まれ、内在化している。
この辺が僕の、40代後半からの考えの骨子である。そのあたりから確信したし、誰と話しても「超越だ!美だ!」と声高に言ってきた。そのバックにある世界観とは、こういうことなのだ。
●リンゴに目がいくと、リンゴの存在が見えない!?
ドイツ観念論は、観念の担い手が個人であるか、個人を超えた宇宙あるいは神などとさまざまだが、世界の成り立ちを自我、自己意識、理性、精神のように精神的なものから説明する。そのため、外的な物体や自然を原理にする実在論や唯物論と対立する。カントは、カテゴリーを客観的実在の反映とはみなさず、純粋悟性の真の主要概念とみなした。しかし、人間は外界をカテゴリーに分類して認識(意識の志向性と対象性)する前に、つまり記号で認識する前に、心のない鏡に外界が映るように、自分の身体に映り込んで内在している。自己意識の外側に意識の介在しない世界が内在している。超越(真・善・美)は人間や自己に関係ない。「ピタゴラスの定理」の意味や価値は、ピタゴラス自身の生活や性格とまったく関係ない。超越(真・善・美)は人間を超えているから超越なのだけれど、自我意識に関わりなく、身体に映り込むかたちで内在する。
超越(真・善・美)は、超越というくらいだからとうぜん人間の外に実在するのだけれど、人間のどこに映り込んで内在するのかというと自我や記号を排したところにあるのだ。このことを、人間は歴史上さまざまな言葉で言ってきた。「本質直感」「純粋経験」「観想」「不立文字(ルビ、ふりゅうもんじ)」「テオリア」。日常生活ではほとんど使わないし解りにくい言葉だが、絵を描いていると分かる。絵でも文章でも何かを描写しようとするとよく分かる。
テーブルの上にリンゴがある。それを何人かの人が見ていて、目の前の物を言葉で描写しなさいと言われたとする。簡単なことだから、みんな同じような事しか書かないだろうと思うだろうが、違う。それは各人に映り込むのは同じ形象であるが、その人その人の意識が違うからだ。意識は実存だからだ。ある人は「リンゴは丸い」という。ある人は「リンゴは赤い」という。ある人は「あのリンゴはスッパそうだ」という。ある人は「あのリンゴは200円くらいかな」という。これらは全部間違いではない。だからこの部分(カテゴリー)で、お互いの見方の正しさを主張して論争しても決着がつかないし不毛だ。
ある哲学者は言った。「存在者は存在を隠蔽する」。存在者とは物。物という存在者は、「物が存(存の横に、をつける)る」ということを隠すのだ。これはハイデガーの言葉だ。人間はリンゴを見るとリンゴの表面に目が行ってしまうから、「赤い」とか「丸い」とか言う。意識が物に集中してしまって、存在ということに気付かない。普通の人はリンゴを見て、リンゴの〈存在〉などに注意を向ける人などいない。同じ世界に生きているのに、リンゴの落ちるのを見て万有引力を発見する人もいるし、〈存在〉や〈時間〉について考え続ける人もいる。こういう人は凄いね、凄いことだね。
これが、じつは坂本繁二郎の言った「物感」ということだと思う。
リンゴの実体の観察に目が行ってリンゴの光や存在を忘れる。坂本繁二郎は、馬を描いても能面を描いても月を描いても画面は常に同じテイストだ。それは個別の物を描こうとしているのではなく、世界を、存在を描こうとしている。光と空間を描こうとしている。セザンヌもそうだ。
物を描写するというのは、簡単ではない。物のイデアと存在と空間との関係、そしてそれらによって成されるゲシュタルト(全体性)。それを制作し、美として他者に提示して、客観的に美しい存在としてこれを伝えようとしたら、なんと困難なことだろう。自分というものを一冊の本にしようとか、誰かを過不足なく描写しようとしたら、作品のいい悪いや美醜の価値判断を考慮に入れなくても、単に描写という命題だけでも、対象をどう描写すればいいのか。
映画で一人の男を描写しようとすれば、その人の全過程を、60年なら60年全部を撮りつづければいいが、それは不可能だから、映画なら二時間。本なら一冊。絵ならキャンバス一枚。そういう条件で、どのように描写したらいいか……。
このように考えを進めると、あっちこっちのテーマがつながる。だから面白いのだ。絵を描いていると全部がつながる。だから毎日が面白い。そちらに家庭や生活があって、こちらで仕事として絵を描くというのとは違うのだ。人間の内部も、人生も、空間も時間も、全部がフラクタル。こういうことが、一番話したいテーマで、面白い。ここいら辺がこの本の一番のところであり、是非とも言いたいことだ。
●仕事は無限にある
今年(2008年)の正月のテレビ番組の中で、武術家が出てきて古武道の動きを解説している時に、バックミンスター・フラー(Richard Buckminster Fuller, 1895-1983年、私が中学生の時にフラーが来日して巨大なテント構造のドームを造ったことが、当時の新聞に載っていた)の名前が出て、フラーの模型を使っていた。さっそく翌日その模型を作ってみた。同じ長さの6本の棒を棒どうしはどこも接触させないで、30本のタコ紐を棒の両端に結んで、紐のテンションだけで一つの構造体を作るのである。一日がかりでやっと作ったが面白かった。ついでに、3本の棒と12本のタコ紐でも作れるだろうと思い、つごう2つの模型を作った。それをアトリエに置いて見ていると色んなことが類推できて、私の世界観に新たな示唆を与えてくれている。
フラーは非常に興味深い人物で、早速ネット検索で本を何冊か手に入れて読んでみた。そのなかの、井口和基氏の本から少し長い文章ですがそのまま引用します。
フラーのクリティカル・パス(岡野注・フラーの著書の題名)は面白い。その中で、1827年にフラーが人生で破たんし自殺の直前まで追い詰められた時、つまりフラーが「自分には身を投げるか、あるいは考えるかしかなかった。」と考えた時、フラーはやることも無く、金も無く、できることと言えば、後は自分の頭の中で考えることくらいしかなかったのである。この時、彼が何をどう考えたのかという話が、第4章の「バックミンスター・フラーの自己規律」というものに描かれているのである。大分前に私がフランクリンの自己規律というのを話題にしたことがあったのであるが、フラーの自己規律も実に示唆的であり、実にユニークである。だから、この章にもいわゆる「ためになる教訓」に満ち満ちているように感じるのである。その中でも、私が非常に気に入ったものは、フラーが言うところの「プリセッション」(物理の日本語では、歳差運動と訳されているが、ここでの内容はもっと広い。)という概念の発見である。
フラーの言うプリセッションとは、次のような物理現象のことを意味している。例えば、水を円柱形の袋に入れて底面と頂点面を同時に圧縮する(引っ張る)と逆に側面の中央部は膨張する(収縮する)というような物理的な運動のことを言うのである。あるいは、太陽と地球の引力と円運動の関係のように、太陽から地球への引力は動径(半径)方向に働くが、円運動はそれとは垂直に行われる現象である。あるいは、上から下にあがるというような現象である。こういうように、一つの運動に対してそれとは直角の方向へ運動が起こる物理現象をフラーはプリセッションと考えたのである。もちろんこの意味では普通の物理で言うコマの歳差運動もプリセッションの一つである。つまり、重力によってコマが横に倒れようとするが、運動はそれとは垂直に行なわれてコマはぐるぐる歳差運動をして回るのであるから、フラーのプリセッションの一つであると考えられるわけである。こういった自然現象のプリセッションは力の方向に垂直に行なわれるのである。この場合、仕事は行われずエネルギーは保存する。力の方向に進めば摩擦も働き、エネルギーが減少するが、直角方向の運動は摩擦なく永遠に運動可能である。まさしく、磁場中の電子はこの原理によって永久運動するのである。太陽系の中の地球もこうして太陽の周りを回っているのである。そこで30代のフラーは考えた。果して人間社会のプリセッションとは何であるのか? 確かに,人間界においても社会の人間に力が働く方向(つまり、政治力や経済力と呼ぶものが働く方向)があるのである。人は名誉に突き進み、お金にむらがろうとするものである。当然、弱い人は強い人の周りを回って生活している。これは、自然界の力の構造と同じではないだろうか? だとすれば、それと直角に、つまり90度で運動するということも可能ではないだろうか?
さらにフラーは考えた。これは人間社会ではどういうことを意味するのだろうか? 多くの人間、普通の人間は家族のために生きる。あるいは会社や自分の置かれた組織のために生きるのである。つまり、これは力の場に沿った運動である。この方向では、力に引き付けられればそれは社会の流れに沿った方向であり、反発すればそれは社会に反する方向への運動にすぎないのである。もしそうであるならば、力に90度の生き方があるのなら、それはそうしたものではないはずである。つまり、だれもしないこと。言い換えれば、地球人全体のことを考えることではないだろうか? 誰か特有の個人、組織、国,民族のためではない、そんな方向がプリセッション運動ではないだろうかとフラーは考えた。
驚くべきことに、若いフラーはこのプリセッションの効果を証明するために「自殺するのではなく、自分のエゴを殺した。」のである。そして、以後50数年に渡ってこれを実証してきたのである。そのために、多くの友人や家族や親戚から無責任な人間と非難され続けたと言う。時には忠告に従って家族のために仕事をしたこともあった。だが、そんな時は自分の計画がとん挫し、すべてがうまく行かなくなったようである。そんな時は意固地になって自分の計画を推進したのである。しかし、不思議なことに、自分が必要とする時に必要なことが決まって現れ、自分の味方をしてくれたのである。そして、今日まで生き抜いてこれたのであるとフラーは言っているのである。
フラーはこの話をみつばちの話にして例えているのである。みつばちは花の蜜を見つけると、仲間にそのことをお尻を90度に振りながら8の字歩きをして伝える。これはあくまで自分の仲間のために行う利他的な行為である。しかし、実はこれが花に花粉を付けて受粉させる働きを持つのである。こうして、みつばちは知らず知らずのうちに植物の生育を助けているのである。
人間社会もそのようになっているのではないか。これは現在我々が「共生」と呼ぶ現象の本質を突いているいるように私は思うのである。もし花と共生するためにみつばちが何か花のためになることを自ら選んで仕事するとすれば、きっとみつばちたちは疲れ切ってしまうのではないだろうか? 花から見れば一見自分勝手に見えるのかも知れないが、みつばちはみつばちの世界のために利他的に行動しているのである。この行動が実はもっとも花を助ける行動に繋がるのである。そうやって自然はうまく両者を共生させてくれるわけである。だから、決してみつばちは花の奴隷でもなく、また花もみつばちの奴隷ではないのである。
『フラーとカウフマンの世界』(114頁~116頁) 井口和基著 太陽書房
フラーは面白いことを言っている。「職業は少ないが、仕事は無限にある」。直接金を得ようとするから生きることがつまらなくなるのであって、僕と一緒だよ。僕は「オファーはなくてもやることはいくらでもある」と、昔から言ってきた。オファーによって仕事をすると、売れっ子になって忙しいか、「売れないなぁ。ちっとも注文が無いなぁ」などと嘆いたりするしかない。その方向で人生を過すと、暇か、忙しいかとどちらかになる。僕はフラーの本を読んで「そうだ、そうだ!」と思った。僕はオファーはなくても、この本の原稿書きをふくめて毎日が忙しいのだ。
●テンセグリティー
テンセグリティーとは耳慣れない単語だが、バックミンスター・フラーの本のなかにでてくる言葉だ。いろいろ調べてみたのだが、どこにも載っていないのでフラーの造語なのかもしれない。意味は、圧縮力(tension)と引張力(compression)の両方から成り立つ構造、のことのようだ。フラーの本の挿絵を参考にして自分で作った模型をみていると、いろんなことが解ってくる。個々の人間もその人間がつくった社会も、この模型をアナロジーにして透かし見ればはっきりと構造が見えてくる。社会と人間もじつは全てテンセグリティーだ。社会もある意味では個人から始まるが、そこでも僕が以前から言っている〈フラクタル〉に行き着く。
マクロの宇宙もそうなっている。月があって地球があって太陽系があって,銀河系があって大宇宙を形作っているが、個々の星はお互いに接してはいない。それが太陽系という形態を作り、銀河系という形態をつくり、宇宙という形態を作っている。
ミクロの世界もそうなっている。分子、原子、素粒子、とどこまで小さく割っていってもムクな個体(粒)に辿りつかない。どんなに微細な小宇宙もテンセグリティーによって構造化され形態をなしている。
社会も、国家や会社や地域社会や家庭などいくつものコミュニティ(共同社会)を形成しているが、その実体はない。個々の人間(コンプレッション)がテンションによってコミュニティを作っている。個々の人間をコンプレッションとすると、テンションは何かというと「愛(超越)」、「欲望(食欲、性欲、金銭欲、権力欲)」、「恐怖(暴力)」の三つ。国家、地域社会、会社、家庭などのほとんどのコミュニティが三つのうちのどれかをテンションにして成り立っている。その三つ、すぐ目につくのはそういうこと。
人間が、個々バラバラにあるものがコミュニティとして一つにカッチリと形成するには、世界中を見渡してもほとんどがお金か権力か宗教か民族のいずれかだ。テンションをかけなければきちっと形成しないのだから、ハサミで紐を切ってしまったら、もともとはバラバラなのだから、お金が結びつけたり、昔の社会なら権力者の強制力が、個々を結びつけていた。暴力が使えなくなると、自由主義社会では金の力であり、結局お金に代わるものはとりあえず見つからない。宗教や民族は世界中の紛争をみると分かるように構造態が開かれてないので他のコミュニティとの問題が多すぎる。フラーは〈エコロジー〉や〈共生〉や〈宇宙船地球号〉の概念の先駆者で、この辺のことも言及しているようなので、興味がある人はフラーの著書を読んでみればいいと思う。
この模型を作ってみて、僕に最も役立ったのは、自分自身はこうなっている、このような構造態で人間を考えなければならない、ということに気付いたことだ。僕は今まで自分を、ブロックを積むように日々を過ごし、その結果が現在のじぶんである、と考えていた。だから、もし人生の途中で間違いに気付き人生をまるごと脱構築(ディコンストラクション)しようとしたら、バラバラにしたブロックを新たに一から積み上げなければならない。今までの蓄積を捨てさる勇気と、新たに築きあげる気の遠くなる作業をしいられるので、若くないととても踏み出せない。おまけに、ブロックの脱構築の場合は今までの形態のブロックで新しく使えないかたちのブロックは捨てなければならないし、また新しく削って作らなくてはならない。幸い、僕の場合は紆余曲折して今にいたっているが、まあ幸運だった。人間の構造をブロックを積み上げた構造とみないで、引張力と圧縮力でできた構造態だと思えば、脱構築も簡単だ。この模型の紐を切り離して、新しい点に結び直して新たな構造態を作ればいいのだ。ブロックを積み直して新たな形態を作るのに比べ、棒と紐の構造態は質的に組み替え直すことは大変だが時間的には雲泥の差だ。それに、過去の経験で捨てさるものはなにもない。自分の過去の紐と棒を使って自分の全体を組み直せばいいのだから。
●年収400万の夫
前(生きられる空間、の章で)にも話したが、ネットの読売新聞の「発言小町」に載っていた話。トピ(トピックス:話題、の略?)を立ててみんながレス(レスポンス:返答、応答の略)を送る。昔の井戸端会議のパソコン版という感じで、トピを立てる方も、レスを書き込む方も女性が多い。そのコーナーに、ある30代の女性がトピを立てた。その女性は実家が裕福で結婚まではなんの不自由もなく育ったそうだが、今の生活についての悩みで、トピのタイトルは「年収400万の夫」。年収400万というのは微妙なところで、男にとっては妻から不満を言われる筋合いはないと思うのだが、とにかくその女性はこのままでは子供を産んで教育費もかかるし、将来の自分の生活に不満なわけだ。それに対してレスが多数あって、「300万でも私はやってます」といったような、ほとんどがお金の問題の切り口に終止している。しかし、僕なら「年収400万の夫」と夫をとらえる、その見方がもうダメだと言いたい。そういう見方で周囲を写し、自分の中に、お金をテンションにして「生きられる空間」を形成して人生を送れば、決して幸せな人生は送れないだろう。前章の「テンセグリティ」を家庭という共同体にたとえると、棒が家族の一人一人だとすると、何を紐とするのか。テンションをかける紐を金銭にすると、家庭は、パートタイムやアルバイトの仕事とおなじように脆くて弱い構造であろう。脆くて弱い構造態の共同体の中の個人はいつまでも孤独な存在であろう。自分の夫を「年収400万の夫」と表現するその薄情さに自分が気付き反省しなければ、どう過したって水気のない痩せた、「足るを知る」ことのない、不満だらけの不幸な人生しか送れないだろう。テンセグリティの模型の紐のテンションをお金にたとえ棒にかかるコンプレッションを人間のストレスにたとえて、恋人や友人や家庭や学校や会社の人間関係を考えればすぐに分かることだ。
生きるうえで、自分をまとめあげる紐のテンションを何に措定するかによってその人の人生の内容は大きく変わる。同じ世界に生きていて、世界を認識する時のものの見方によって「生きられる世界」は大きく変わる。昨今の異常な事件もこの「生きられる世界」の歪みが原因だろう。
「夢の現象学」の章で書いたように、夢の中の他人は他人である。自分の脳の中に他人が映り込んで住みついている。ということは、同じように他人の中の自分は、自分である。他人という鏡に映り込んだ自分の写像である。そして、他人の中に自分が住みついている。
「私の本当の姿を他人は分かってくれない」などという言説のように、自分は他人に実物より良く写して欲しいのなら、自分も他人を良く写してあげなければ不公平だ。自分の妻に「年収400万の夫」と呼ばれ、そういう姿で自分が映り込んでいるパートナーと一緒に暮らさざるを得ない夫はなんと不幸なことだろう。もっとも、夫もテンションの中身が妻と同じならば、それに子供がいなければ他人が別に言うべきことではないが。
超越(真・善・美)をテンションに措定して人生を送っている人たちの多くは、生涯独身だったり、女性関係や家庭や人間関係がうまくいかなかったりする。芸術家、哲学者……すぐに、次々と名前が浮かんでくる。人間関係がうまくいかないのは、テンションの内容の違い(自分の欲望を措定するのか超越を措定するのか)が原因なのだ。
●絵のうえで実存主義を捨てる
自分の生き方のポリシーを実存主義と考えていた頃は、とうぜん芸術は超越ではないわけで、人生のほうを優先し、内在を問題にして絵を描いていた。最初の分岐点のリアリズムからフォーヴィスムへ移る変わり目の頃が、一番迷いの時期だった。フォーヴィスムは色彩を個物の表面の属性から切り離して、色を自由に使うことから始まったのだが、造形や描写のマチスの方向と表現主義のブラマンクの方向に分岐する。僕はまだ手探りの状態で、ブラマンク風のフォーヴィスムから表現主義の方向の画も短い期間だったが描いていた時期もあった。表現主義で絵を描いていると造形上の問題が生じる。絵画上の問題と自分の表現ということを、どういうふうに融合していくか、それがよく分からなかった。目が味わう画面の美しさよりも画家の表現の内容の方にベクトルを向けて制作していくのだから当然造形は無視される。あのころ、自分でも絵画上の間違いや考えの上の間違いをしていたと思う。個性を出そうとしていた訳ではないのだが…。絵画には、科学的というか、構造的というか、数学的というか、超越的な問題がある。しかし、自分なりの表現をやっていくと、造形上の問題が解決できない。きちんと理論化できない。
実存主義は絵画史のイズムではシュルレアリスムや表現主義になるのだが、当時の僕は、人生の上では実存主義だったが、絵画制作のイズムを表現主義的フォーヴィスムでは、やってみてこのイズムでは美のベクトルから外れていることに気がついた。1983年ころ、新宿にK画廊が開廊し、開廊記念展から一、二回個展をやった頃の作品は『岡野浩二WORKS DOCUMENT(1)1974~1984』にも載せてあるけれど、その後は、生き方は実存主義でも、絵画上のベクトルは表現主義から離れていった。しかし、完全に「美とは超越だ」と思えたのは、五十歳に近くなり、「夢の中の空間」や「生きられる空間」や「逆さメガネの実験」等を推論したうえで、生きるうえでのポリシーとして永く羅針盤にしてきた実存主義的世界観を組み替えることになった。
僕は一貫して自分の感情や感覚を表現しようとしたことはないが、ムンクやエゴン・シーレやエコール・ド・パリも画家たちの絵の評価が定まらなかった。画面はそれぞれ美しいのに、内容はどれも実存主義的だ。僕の作った美術の座標系のなかで、キッチリと位置が定められない。だから、マチスもいい、ムンクもいいとなってしまい、的確に区分けができていなかった。そういう画家たちの絵の、美のあり場所が腑分けできていなかったので、座標はあってもどこにも置けなかった。Y軸のすぐ近くにあるのだけれど、どう評価するか、定まらなかった。(参照文:『芸術の杣径』37~38頁 そのときに~絵画制作のベクトルを定めたのです。)
人間は一つのことに専念して、永く生きているといいね。そんな、分からなかったことが分かってくる。だから、このような大それた題名の本も書く気にもなるんだもの。
美術史のなかのすべてのイズムに、ファインアート(純粋絵画)のすべての画家の世界観に、〈超越〉の方向と〈内在〉の方向の二つのベクトルがあって、その分岐がその後の自分の絵画を決定する。リアリズムは、〈超越〉の方向に印象派、〈内在〉の方向にシュルレアリスム。印象主義は〈超越〉の方向にセザンヌ、〈内在〉の方向にゴーギャンやムンク。フォヴィスムは、〈超越〉の方向にマチス、〈内在〉の方向にブラマンク以後の表現派。近くは、〈超越〉の方向にマチス、〈内在〉の方向にピカソ。
ピカソは実存的内容が身辺に溢れている時は画のモティーフに困らないが、ベラスケスやマネの画を主題にして多くの美しい絵を残しているのは、その時期〈内在〉の題材がなかったためだと僕は思う。実際にピカソの画はゲルニカを含めて実存的内容の過剰な大作よりも、それに至る途中のエスキースや、対象を個々に描写しながら試行錯誤していった作品のほうが僕には美しく見える。実存的内容が少なくそのぶん造形的な美に満たされているから、ベラスケスやマネの画を主題にした作品やなにげない身辺の風景や静物などの描写の作品が僕には好もしく感じられるのだと思う。
〈世界〉は、人間の外側に人間に関係なくある〈超越〉なのか、〈内在〉つまり人間が、認識する側が創造するのか。〈美〉は、人間の外側に人間に関係なくある〈超越〉なのか、〈内在〉つまり人間の内側に生まれ、認識する側が創造するのか。その世界観によって画家の描く絵が違ってくるし、当然生き方も決まってくる。この弁証法的な進歩によって世界の美術史は脈々と続いてきたのだ。
そう考えると、〈美〉は一〇〇人一〇〇通りと考えるポスト・モダンの国アメリカがリードしてきた戦後の現代美術の流れは、ゴーキーやロスコ等の少数の画家を除いて見当はずれの現象だったことが分かるだろう。人は錯誤するし、家族も錯誤する、会社も錯誤する、国家も錯誤する、時代も錯誤する。
●鏡は美しいところに持っていく
ドイツロマン主義では「自己、自己……」と主張した。イタリアルネッサンスでは、中世キリスト教神学の、日常生活から遊離し硬直した超越志向の反動で人文主義が出てきた。またニーチェは人間の欲望を肯定、自己を積極的に肯定しようというわけだ。それら一連の方向が中世のスコラ哲学を超えて、近世の文化を支える思想的バックボーンの一つとして機能してきた。近世になると〈超越〉は神から自然に替わり、科学や数学の客観的実在論と人間が主体の「生の哲学」実存主義が争う。この歴史の流れはあくまでキリスト教的世界観(あくまで一元論に集約することにこだわる)の西洋のことであって、東洋では、特に日本ではもともと自我の概念が希薄なのと多神教で神よりも自然を上位に置いてきたので世界観が異なる。中観派の祖で古代インド仏教の僧ナーガールジュナが空(ルビ:くう)の思想で言った「無我」の境地。お釈迦様は、煩悩を捨てよと言った。我執への執着が苦しみの源泉だという。禅宗などでは自己放下(ルビ:ほうげ)、自己意識を捨て去り,自己の迷いや執着を捨て去って悟りに至ると言う。
一九六〇年から一九七〇年代にかけて全世界の若者文化を捲き込んだムーブメント(前衛、反体制、アングラ、ヒッピー、、ドロップアウト、ハプニング、ポップ…等々)は科学技術が中心で人間不在の文明の進歩に対する、人間の側からの反乱と言っていいかもしれない。現にその頃、実存主義者サルトルはカリスマだった。その風潮からすると、〈美〉をベクトルにして画の制作をしている僕はある意味、保守反動だ。第2次世界大戦後マチスは、現実に反動だと言われた。マチスの有名な言葉「私は、働いた人の疲れをいやす、ソファーのような画を描きたい」に対して、「こんな大変な時代にぬくぬくとソファーに女性を坐らせて、そんなのんきな絵を画家が描いている場合か」と非難された。ピカソも当時一緒にいた女性のジローに「マチスのソファーはブルジョワジーの坐るためのものだ」と言ったという。一方でピカソは戦後、共産党に入党したり、『朝鮮の虐殺』や『戦争』や『平和』を描いたりしたが、そのてのメッセージ性の強い作品は僕にはどうも感心できない。有名な『ゲルニカ』も、僕としては、ピカソの他の作品と比べると美しさのてんで評価は低い。自分がどう考えようと自由で、まして愛とか平和とかいわれて反対すべき言葉はなにもないが、〈美〉は超越だから画家が自分の絵でそんなことを表現するのは間違っていると思う。画家の実存に関する部分は画とは別の行動で示すべきで、絵画は純粋に〈美〉を目指すべきだ。アスリートは競技中にマイクを持って、自分のことを語ったり、政治的なプロパガンダをしたりはしない。棋士が対戦中に将棋盤の前で、将棋以外のことは考えないし、しない。世の中のすべての仕事は、実存とは関係ない。世界中で一部の画家だけが、おせっかいにも自分のことを語ったり、他人の意識を変えようとしたり、しいては他人を説教したりする。そのようなことは、アスリートや棋士の競技場や将棋盤の前の行為ではないのと同じで、画家のキャンバスの前の行為ではない。それは当人が、競技場や将棋盤やキャンバスの外でするべきことである。
それでも実存はしぶとくて、人間だけは他の生物と違って被投された世界から実存が少しはみだしている。それが人間の「自由」の部分である。世界を映し込む自分の肉体をどこに持って行くかという自由と、映し込まれた世界をどう解釈するかという自由。その二つが、実存が被投された世界からはみだした部分だ。
身体という鏡をどこに持っていくのかは自分の自由意志だ。世界は勝手に映り込むが、鏡をそこに持っていくのは自分だ。金銭や権力などの人間の欲望のあり場所つまり生活に持っていくか、美しい場所つまり超越に持っていくか。人間は美しい世界を映し込むほうが幸せにきまっている。だからこそ芸術は、創作することも、鑑賞することも両方とも意味があり価値があるのだ。価値ある芸術作品に接すると、「世界は美しいし生きることは良きことだ」という人生の肯定感に充たされ、自分もただ生きるだけでもつらいけれど、頑張ろうというエネルギーが湧いてくる。その逆で、なるべく暴力とか気持の悪い感じのエキセントリックな芸術作品などは、見せるべきではないし、見るべきではない。そのような美と無縁な絵を見ることは目の毒だ。これも真実だといわれるかもしれないが、わざわざ美味しくない料理を食べにレスランにいくようなそんな物好きな人はいないし、不味い料理をだすレストランはお客が来なくて現実に存在できない。だいいち人は、不味くて身体にも悪いものを、なんでわざわざ口に入れなければいけないんだ。鏡(身体)は美しいところに持っていくべきである。
それと、実存が関わることは、そうやって映り込んだ世界をどう解釈するかというもう一つの問題がある。人間は周りの世界を「記号」として解釈している。自己の解釈以前に、世界は自分の身体に映り込んでいることを忘れている。絵画をどう捕らえるかという問題も、他者をどう捕らえるかという問題も同じで、そのときあらかじめ映っているのだが、自己がどう解釈するかという段階で、自己が記号で解釈してしまう。何かがあると目に映ったものは、目にインプリントされているのだけど記号で解釈するのだ。
「このリンゴは200円くらいかな」というのは、自己がすることだ。人間は他者を記号で見る。しかし、自分自身は記号で見られたいだろうか。映す主体であるし、映される客体でもある。やはり人間は、自分を美しく大きく映してほしいのに、他者を映しているときは記号で解釈するくせに、自分が映されるときは記号で解釈されることに不満が生じる。できるだけ美しく映す。「夢の現象学」の章で言ったように、自分の中に映り込んだ他人は他人だし、他人の中に映り込んだ自分は自分で、「映し、映され」だから、できるだけ美しく美しく映すべきだ。人間の内部世界と外部世界がフラクタクルだとすれば、世界は超越であって実在するのだから、超越の真もあり、超越の善もあり、超越の美もある。だから正しく映しさえすればいいのだ。現実にはどこでおかしくなるかというと、「真・善・美は超越ではない。内在だ」と考えるからで、それがさまざまなドグマを生み、争いや事件がたえないのだ。正しく映しさえすれば、世界は美しく平和だ。映し方がおかしいから、狂ってくるのだ。映された世界の解釈が歪んでいるから不幸になるのだ。
●自己を放下すると生きることが楽になる
坂本繁二郎の絵の柿を「この柿は腐っているの」とか、セザンヌのリンゴの絵を「このリンゴの値段はいくらくらいかしら」という見方は間違っている。ルノワールの絵を見て、「この女性、太っている!」というのも同様。見方は人それぞれねといって、大きな顔をして世の中を渡っていってはいけない。女性から「年収400万の夫」というような言い方をされたら、僕なら黙って家出するね。そんな見方で夫を解釈する人と一緒に生活していて美しい作品が描けるわけがないもの。
僕がまだ20代の頃、ラジオでこういう人生相談を聞いた。ある女性が、つきあっている男性が二人いて、一人はサラリーマンで、一人は自営。どちら男性と結婚したらいいのか迷っているという。しかし、それはおかしいだろう。人間のAかBかで悩むのなら分かるのだが、サラリーマンなら結婚し、自営なら結婚しない?そういうふうに人間を見る人がいる。見合い結婚でそう考える人はいても、恋愛でそう考えるなんておかしい。そういう見方があることにビックリした。そのことを周囲の男女に話すのだが、男性は数人僕の意見に同調する人がいるのだが、女性には100%「えっ?どこがおかしいの」と言われる。
それらは、僕の日頃考えていることとまるで違う。人間ってそんなふうに考えるの?と思う。そう言うと「あなたの見方のほうがおかしい」と言われる。「年収400万の夫」を相談している人と同じだ。もちろん男性でも、そういう僕からみれば不思議な人はたくさんいる。男女共そういう人たちが大多数なのだ。
そういう人が多い。だから僕の絵は、理解されるのが難しいかもしれない。ただ、絵は理解してくれなくてもいいが、あんまり自信を持つなと言いたい。ピタゴラスの定理を理解しなくても生きていく上でなにも困ることはないが、理解できないのならピタゴラスについてあなたは何も言うな、と言いたい。昨今の、すべてについて誰もがテレビのコメンテーターのような物言いをするのはおかしい。誰にインタビューしても、みんな、何か言おうとする。「私はこのことは知らないのでコメントできません」などと言う人は少なくて、みんな、よく知らないことでも自信をもってコメントしようとする。個人が関われることは限られている。一人の人間は、世界中のすべての事象に関われない。だからすべての人が、それぞれに自分に与えられた仕事に誇りを持ってベストをつくし、自分の分野のことは誰にも何も言わせないだけの結果をだせば世の中はうまくいくのに…。それぞれが、その分野のスペシャリストになって、自分の分野外のことはそちらの専門家に任せなさいよということだ。
自己を放下すると、ほんとうに楽になる。身のうちの欲望に動かされる小さな実存を、生き方の根拠にしたら人生はつまらない。世界のなかのほんの小さな自分、自分のなかのほんの小さな自己意識、そのちいさな自己意識のなかの欲望(食欲、性欲、金銭欲、権力欲、名誉欲)のコマンド(命令、指令)で一生を送る……それさえあきらめれば、その執着から解脱さえすれば、勉強すべきことは還暦を過ぎてもたくさんあるし、やらなければならない仕事は無限にある。金も名誉も女性も、そういうものが手に入るならやぶさか(やぶさかの横に丶)ではない。しかし、それを得ようとしてとりたてて努力はしない。若い人に時代錯誤と言われても、それで結構です。別に他人に理解されなくてもいい(理解されることにやぶさかではないが)。女性にもてなくてもいい(もてることにやぶさかではないが)。お金もそこそこ入ってくればいい(多いぶんにはやぶさかではないが)。若い時はともかく、還暦を過ぎても人間の欲望は限りがない。僕は、賞でも断りはしない。女性も、来てくれるなら大歓迎する。お金も拒みはしない。しかし、欲望の引力にそった行動はしない。そう決めたら日々の人生が楽しい。死ぬまでにやるべき仕事はたくさんあるし。……ずっと前から、数十年、延々とそうやって生きてきた。いまもずっと続いているし死ぬまで続くだろう。
この本で書いていることは、日頃僕が絵を描きながら一人で作り上げた世界観だ。その分野のプロパーに言わせると、同じような説はすでにあるかも知れないが「これは僕の新説だよ」という気持だ。哲学の本を読んでも、著者に「僕の話を聞いてほしい。世界はこうなっているのだ。なんで分からないんだ……」という気になる。そう考えると、色んな解決されないパラドックスはなんでもないことだ。内と外とが境界がなくフラクタルであると気がつけば、なんて言うことはないのだ。世界はフラクタルである、ということに気がつけば、すべて説明がつくのだ。主観も客観も、二つで一つであって、そういう世界観で世界と自我を解釈すれば、部分も全体もなんてことないじゃないか。アトリエで、一人で、みんなどうして分からないのかな、と考えている。
| 第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 |