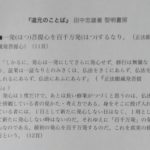『月を見つけたチャウラ』ピランデッロ短編集 光文社古典新訳文庫
■まわりに誰か人がいるとき、わたしはけっして彼女を見ることはない。しかし、彼女がわたしをみているのを感じる。彼女が見ている。一瞬たりとも視線をそらすことなく、わたしをじっと見つめている。
面と向きあって、説明してやりたい。たいした問題ではないのだと。不安になる必要はないと。この束の間の行為は、おまえ以外の相手とはできないのだからと。おまえにとってはどうでもいいことでも、わたしにとってはすべてなのだ、と。毎日わたしは好機をうかがい、誰にもしられないようこっそりと、おぞましいほどの悦びとともにその行為に至る。行為に耽ることにより、神がかった恍惚と自覚のうえの狂気を味わい、身震いする。ほんの一瞬、己を解き放ち、すべてに対する復讐をなしとげるのだ。
この行為を誰にも暴かれることはないという確信が、わたしには必要だった(そんな確信を持てる相手は、彼女以外には考えられまい)。万が一他人にしられでもしたら、もたらされる損害は――それも9、わたしにだけおよぶのではない――はかりしれないものになるだろう。そんなことになったら、わたしはおしまいだ。恐れられ、捕えられ、縛りあげられ、精神を病む者たちが入る療養所にひきずっていかれる。
わたしのこの行為を知られた場合にまわりの人びとが感じるだろう恐怖は、ちょうどいま、わたしの犠牲となる彼女の眼に浮かんでいる恐怖とおなじものだ。
数えきれないほどの人びとの人生、名誉、自由、財産が、わたしの手に委ねられている。彼らは、わたしの文書や、助言や、サポートを求め、朝から晩までつきまとうのだ。それだけではなく、公の場においてもプライベートにおいても、わたしには多大な責任が重くのしかかっている。妻もいれば子どもたちもいる。妻も子も、身の処し方を心得ていないことがしばしばで、つねにわたしの威厳ある態度によってコントロールする必要があった。わたしが、非の打ちどころなく、ありとあらゆる義務にぶれることなく従ってみせることによって、つねに模範を示しつづけなければならなかったのだ。夫として、父として、一市民として、法学教授として、弁護士として、いずれも甲乙つけがたいほど重大な義務が、わたしにはあった。そのため、万が一秘密を知られでもしたら、たいへんなことになる!
たしかに、わたしの犠牲者である彼女は喋ることができない。それにもかかわらず、数日来、わたしは以前のような確信がもてなくなり、不安にかられ、打ちひしがれていた。というのも、彼女が喋れないのは事実だが、わたしをじっと見つめるのだ。なんともいえない目でわたしを見る。その目に明らかな恐怖の色が浮かんでいるため、いまにも誰かが気づき、理由を追及しようとするのではあるまいか……。わたしはそれを恐れていた。
繰り返すが、そんなことになれば、わたしは一巻の終わりだ。わたしのその行為の真の意味を理解し評価してくれる人は、sるとき不意に人生の本質を垣間みたわたしとおなじように、人生の本質を垣間みたことのある、ごくひと握りの人間にすぎないのだ。
言葉にし、他人に理解してもらうのは容易ではないことを承知のうえで、あえて話してみることにしよう。
わたしは、出張で滞在していたペルージャから、半月ほど前に戻ってきたところだった。
わたしのもっとも重大な義務のひとつが、全身にのしかかる疲労感や、自ら課した、あるいは他人に課せられたあらゆる責任の、とてつもない重みを知覚しないよう努めることだった。そして、わたしの疲れきった意識が、折にふれて気分転換の必要があると求めてくるのに対し、頑として屈しないことであった。手ぐすねを引いて待ちかまえる煩わしい諸事から生じる疲労が臨界点に達したとき、わたしに許された唯一の対処法は、別の新たな雑事に意識をふり向けることだった。
そんなわけで、列車に乗り込むさい、わたしは読んでおくべき新しい書類をいくつか革鞄に入れておいた。そして、それらに目を通しているうちに最初に行きあたった難解な箇所で、視線をあげ、列車の窓を見た。外の景色を眺めてみた者の、意識は難解な箇所で、視線をあげ、列車の窓を見た。外の景色を眺めてみたものの、意識は難解な箇所に集中していたため、目はなにも見ていなかった。
いや、じつのところ、なにも見ていなかったというのは正確ではない。目にはたしかに映っていた。ウンブリア地方の田園風景ののどかな美しさを目にし、おそらく眼球ではそれを堪能してもいた。それでもわたしは、目に映るものには明らかに注意をはらっていなかった。
わずかずつながら、わたしをとらえている難問に対する意識がゆるむことはあっても、だからといって、わたしの眼前をかろやかに通りすぎてゆく、心安まる澄んだ田園生活をしっかりと知覚するわけではなかった。
わたしは、目にしているものについて考えていなかっただけでなく、もはやなにも考えてはいなかった。どれくらいの時間そうしていたかわからないが、曖昧で不可解であると同時に、明晰で穏やかな思考停止のような状態に、わたしはあった。それはまた、風通しのよいものだった。わたしの精神が、あたかも感覚からひきはがされ、はてしなく遠ざかってしまったようだ。そうして不思議なことに、わたしの精神のものとはとても思えない繊細さでもって、別の人生の蠢(うごめ)きをかすかに感じていた。それはわたしの人生ではないが、わたしのものとなり得たかもしれない人生だった。この場所ではなく、今という時でもなく、あの、はてしない遠い場所の、遥かに彼方の人生なのだ。それはおそらく、わたしの精神の人生だったのだ。いつのことかも、どのようにしてなのかもわからないが……。
その人生におけるさまざまな行為ではなく、様相でもなく、生じるそばから消えてしまう願望のようなものの記憶だけが、わたしの精神にまとわりついていた。そこに存在しないという苦悩とともに。それは漠然としてはいたものの、心を苛(さいな)む、烈(はげ)しい苦悩だった。おそらく、花を咲かせることのできなかった蕾(つぼみ)にも似た、そんな苦悩だった。要するに、生きるに値したはずの人生の蠢(うごめ)きなのだ。あのはるか彼方で、光が点滅し、揺れながら、その存在を誇示している。だが、それは生じなかった人生なのだ。その人生においてこそ、わたしの精神はようやく、すべて完全な形で、欠けることなく、自身の姿を見いだせるはずなのだ。その人生において、わたしの精神はただ楽しむだけでなく、苦悩も味わうのだが、その苦悩はまぎれもなくわたしの精神のものなのだ。
知らず知らずのうちに瞼(まぶた)が閉じていき、眠りのなかで、わたしはその生じなかった人生の夢のつづきを見ていた。おさらくそうだったのだろうと思う。というのも、もう少しで目的地に着くというところ、身体じゅうがしびれ、口のなかが苦く、からからに渇いた状態で目が覚めたとき、わたしは別の精神にのっとられていたから。これまでの人生に対して途轍(とてつ)もない倦怠を感じ、陰鬱でどんよりとした驚きのなかにいた。これまでの習慣だった諸事が、あらゆる意味を失ってしまったかのように見え、しかもそれがわたしの目には、おそろしく耐えがたいほど深刻に思えたのだ。
このような精神状態でわたしは駅に降りたち、出口で待っていた車に乗り込み、家へと向った。
こうしてわたしは自分のアパートメントの階段に着き、自分の家のドアの前の廊下に立っていた。
そのとき、ブロンズ色をした暗いドアの前に、ふと見たのだった。ドアには、わたしの名前が刻まれた楕円形の真鍮の表札がかかっている。名前の前には肩書きが、後にはこれまでのわたしの学術・職業上の業績が記されている。そのドアの前に、まるで外から眺めているかのように、わたし自身の姿とわたしの人生を垣間見たのだ。だがわたしは、それをわたし自身だと認めることも、わたしの人生だと認めることもできずにいた。
突如として、わたしは革の鞄を小脇に抱えてドアの前に立っている男が、その家に住んでいる男が、自分でないのだという確信を抱いて、ぎょっとした。これまでもずっと、自分ではなかったのだ。不意にわたしは、自分がその家だけでなく、その男の人生からもずっと不在だったことを思い知った。いや、いっさいの人生において、まぎれもなく、確実に不在だったのだ。わたしは、これまでけっして生きたことなどなかった。1度だって人生に存在したことはなかった。つまり、わたしのものだと認めることのできる人生、わたしが望み、わたしのものとして実感できる人生において、わたしが存在したことはなかったのだ。目の前にいきなり、そのような服装で、そのような恰好をしてあらわれたわたし自身の身体も、わたしという人物も、わたしとは無関係な人間のように思えたのだ。あたかも何者かがたくらんで、そのような人物像をわたしに押しつけたとでもいうように。わたしを他人の人生において繰るために、つねに不在だった人生に、あたかもわたしが居るような行動をとらせるために……。そして今、わたしの精神が、これまで一時たりとも、一瞬たりともそこに居なかったことに、突如として気づいたのだった!
わたしを装っているあの男を、あのように造りあげたのは誰なのか。私のように望んだのは誰なのか。あの男にあのような服を着せ、ズボンをはかせたのは誰なのか。あの男をあんなふうに動かし、喋らせているのは誰なのか。あのおとこに、ことごとく重苦しくいやらしい義務をあれほど押しつけたのは誰なのか。受勲者(コンメンダトーレ)、教授、弁護士……誰もがあの男を求め、あの男に敬意をはらい、賞賛する、誰もが競い合うようにしてあの男の文書や助言、サポートなどを欲しがり、一時たりとも安らぎを与えず、息をつかせもしない……。あの男がわたしだと?わたしだというのか?ほんとうに?そんなはずがない!あの男が朝から晩までどっぷりと浸(つ)かっていた煩わしい諸事など、わたしにいったいなんのかかわりがあるというのか。もろもろの尊敬も、彼が享受していた特別扱いも、受勲者、教授、弁護士といった地位も、そしてさまざまな義務や職務を怠ることなく、せっせと果たすことによって得た富も栄誉も、わたしにはいっさいかかわりのないことだ。
わたしの名の入った楕円形の真鍮の表札を掲げたドアの向こうには、1人の女と4人の子どもが待っていた。彼らは毎日、わたしであるはずの我慢ならないその男を――いまやわたしは、その男の姿にわたしとは別の人物を……敵を見ていた――、嫌悪感とともに眺めていた。それは、わたし自身が抱いていた嫌悪感と同種のものだったが、わたしは、そのような気持を彼らが抱くことに耐えられなかった。あの女はわたしの妻なのか?わたしの子どもたちなのか?だが、あの男がこれまでずっとわたしではなかったのなら、ドアの前に立っている我慢ならない男がわたしはないのなら(わたしは、そのことにおそろしいまでの確信を抱いていた)、あの女はいったい誰の妻なのか?あの4人の子どもたちは、いったい誰の子だというのか?わたしのではない!あの男の妻子だ。わたしの精神が、この瞬間において肉体を持つことができたなら、まがいもない肉体を持つことができたなら、まがいもない姿を持つことができたなら、すべての煩わしい諸事や義務や名誉や尊敬や富とともに、足蹴にし、つまみだし、引き裂き、めちゃめちゃにしてやったであろう男のものなのだ。妻も一緒に。そう、おそらく妻も一緒に……。
だが、子どもたちは?
わたしは両手をこめかみに持っていき、ぎゅっと頭を抱えた。
だめだ。わたしの子どもたちだと感じることはできなかった。それでも、これまで毎日まいにち顔をつきあわせ、わたしを必要とし、わたしの世話や助言や仕事を求めてきた、わたしの外の世界にあるはずの彼らの、なんとも奇妙な、重苦しい、不安に満ちた感情に押されるように、こうした感情越しに列車のなかで知覚した、やりきれない倦怠感とともに、わたしはドアの前に立っているその我慢ならない男のなかに戻ることにしたのだ。
わたしは、ポケットから鍵をとりだし、ドアを開け、その家のなかに……これまでの人生のなかに入って、いった。
これこそがわたしの悲劇だった。「わたしの」と言ったが、いったい何人の人がこうした悲劇に見舞われていることだろう。
要するに、生きている人は、生きているかぎり、己を見ているのではなく、ただ生きているのみ……。もしも己の人生が見えるとしたら、それはもう、その人生を生きていない証拠である。ただ人生を耐え忍び、ひきずっているにすぎない。あたかも、息絶えてしまったかのような人生をひきずっているだけなのだ。なぜならば、あらゆる形が、それじたい、死なのだから。
そのことを理解している者は、ごくわずかにすぎない。ほぼ全員といってもいいくらい大多数の人間が、世間一般にいわれている地位を築くために、形に到達するために、日々闘い、憔悴する。そしてひとたび形に到達すると、自分たちの人生を掌握いたと思いこむが、じっさいには死へと歩みはじめているのだ。ただし、誰もそれを知らずにいる。なぜなら、己の姿は見えないのだから。ようやく到達した瀕死の形から、もはや逃れることはできない。己が死んでしまったことに気づかずに、生きていると思いこむ。自ら与えた、あるいは他人に与えられた形や幸運、めぐりあわせ、各人が生まれついた境遇というものを見極められる者だけが、己を知ることができる。
だが、その形が見えるということは、われわれの人生がもはやそこにはないという証拠である。たしかに、人生が目の前にあれば、われわれはそれを見ることなく生きるほかはないのだから。そのなかで、正体を知りもせずに、1日いちにちと死んでいく。なぜなら、それじたいが死なのだから。つまり、われわれが目にし、知り得ることは、われわれのなかの死んだ部分だけなのだ。己を知るということは、すなわち、死を意味する。
わたしのおかれた状況は、さらに悪かった。わたしが見ていたのは、わたしのなかの死んだ部分ではなく、これまで一時(いっとき)たりともわたしは生きていなかったという事実だった。他人が――わたしではない――わたしに与えた形を目にし、わたしの人生は、わたしの本物の人生は、いちどだってその形のなかに存在していなかったことを知覚する。わたしは、どこにでもある材料のように扱われ、脳と、精神と、筋肉と、神経と、肉体とをあてがわれ、彼らの思うがままに練りあわされ、形成されたのだった。仕事をし、行動し、ひたすら義務を果たすために。
わたしは必死になってそこに自分自身の姿を探し求めるが、見つからない。そこで叫びだす。1度だってわたしのものだったことのない、この死んだ形のなかで、わたしの精神が叫びだす。いったいどういうことだ?これが、わたしだって?こんな人間が、わたしだって?そんなはずがあるものか!わたしは吐き気をもよおし、戦慄する。わたしではない、一時(いっとき)たりともわたしであったことなどない、その形に対する憎悪。わたしのものとはとうてい思えない義務ばかりが、重くのしかかる形。わたしにはかかわりのない、煩わしい諸事で抑圧された形。わたしにはどうでもよい敬意の対象となっているかたち……。
もろもろの義務も、煩わしい諸事も、このような敬意も、いっさいがわたしの外部にあり、わたしのうえを素通りする。わたしに重くのしかかり、苦しめ、押しつぶし、息さえもさせてくれない、虚しいことども。死んだことども。
そこから自分を解き放てばいいと?だが、事実が起らなかったようにすることは誰にもできない。死がわたしたちを捕えて放さないのに、それを打ち消すことは誰にもできない。
事実というものがある。人は、いったん行為をおこなったならば、たとえおこなった行為のなかに、のちのち己を感じることができなかったとしても、己の姿を見いだすことができなかったとしても、その行為が、己を捕える檻(おり)のように、そこにとどまるものだ。おして、その行為の招いた結果が、あたかもとぐろのように、蛸の足のように、己のまわりをとりまくのである。その行為と、それが招いた結果のために、望みもしないまま、予期しないまま、引き受けざるを得なくなった責任が、息もできないほど濃密な空気のように、己のまわりに重苦しくまとわりつく。そんな状態で、どうやって自己を解き放てというのだ?わたしのものではないにもかかわらず、こうしてわたしを象徴し、あらゆる人びとがわたしを見出し、わたしだと認識し、望み、尊敬している形に囚われているわたしが、どうやったら別の人生を、本物のわたしの人生を手に入れ、動かすことができるというのか?わたし自身は死んでいると感じたとしても、ほかの人たちにとっては存続しつづけなければならない、彼らがほかでもなくそのように望み、造りあげた形を成した人生ではないのか?
わたしの人生の形は、なんとしてでもこうあるべきなのだ。こうであることが、妻にとっても、子どもたちにとっても、社会にとっても、ひいては法学部の学生にとっても、わたしに人生や名誉、自由や財産を委ねる顧客たちに撮っても、必要だった。そうでなければならず、わたしにはその形を変えることも、足蹴にすることも、とりのぞくこともできない。抵抗も復讐もできない。唯一わたしに可能なのは、毎日、ほんの一瞬だけ、誰のも見られないように細心の注意をはらい、好機をうかがいながら、こっそりと例の行為に至ることだけだった。
そう。わたしは、雌の老いたシェパードを1頭、11年前から室内で飼っている。白と黒のぶちで、太っていて、背が低く、毛むくじゃらで、目は老いのせいですでにどんよりと濁っている。
わたしと彼女とは、これまでよい関係にはなかった。おそらく、彼女は当初、家のなかで音をたててはいけないというわたしの仕事を、受け入れられなかったのだろう。だが、齢をとるにしたがって、しだいにみとめていった。そして、いつまでも彼女と庭で駆けずりまわりたがる子どもたちの、気まぐれな横暴から逃げだすために、しばらく前からわたしのいるこの書斎に非難してくるようになった。
朝から晩まで、絨毯のうえで、両の前足のあいだにとがった鼻先をうずめて眠っている。ここにいれば、たくさんの書類や書物にかこまれ、守られているような安心感があるのだろう。そして、ときおり片目をうすく開け、わたしを見あげる。
まるで、「偉いはねえ。そう、その調子で働きなさい。そこから動いてはダメよ。だって、あなたがそこで仕事をしているかぎり、子どもたちは誰もここには来ないから、あたしの眠りが妨げられることもないの」とでも言いたげだ。
哀れな犬は、そんなふうに考えていたにちがいない。もう半月ほど前になるだろうか、そんな目でわたしを見あげる彼女を見ているうちに、彼女を相手に復讐をなしとげたいという欲望がこみあげてきた。
べつに痛い思いをさせるわけではない。彼女に、とくになにをするというわけではない。可能なタイミング、すなわち来客たちが一瞬わたしを一人にしてくれるような時をうかがい、わたしは物音をたてないよう、慎重に肘掛け椅子から立ちあがる。人びとがおそれ羨むわたしの学識が、法学教授であり弁護士であるわたしのすばらしい知識が、夫としての、父親としての非のうちどころのない威厳が、わずかのあいだ、この玉座のような肘掛け椅子から離れることを、誰にも知られないように。そして、爪先立ちで部屋の入り口へ向かい、誰かがとつぜんあらわれないか、廊下をこっそり偵察し、ほんのしばらくのあいだ、ドアに鍵をかける。
わたしの目は悦びに輝き、これからおこなおうとしている快楽のために両手が震える。それは、狂人になるという快楽だ。ほんの一瞬だけ、狂気に身を委ねる。ほんの一瞬だけ、牢獄のようにわたしを捕えているこの死んだ形から脱けだす。わたしを窒息させ、押しつぶすこの学識や威厳を、ほんの一瞬だけ嘲笑い、めちゃめちゃにし、否定する。わたしは彼女のもとに……絨毯のうえで眠っている雌犬のもとに走り寄る。そして、彼女の2本の後ろ足を優しくそっとつかみ、手押し車のように歩かせるのだ。後ろ足をわたしが支え、前足だけで8歩か、多くても10歩、歩かせる。
それだけのことだった。ほかになにをするわけでもない。それが済むとドアへと急ぎ、カチャリとも音を立てないように静かに鍵を開け、ふたたび玉座のような肘掛け椅子に座る。先ほどと変わらぬ、非のうちどころのない威厳とともに、わたしのすばらしい知識を充填した大砲のような状態で、次の客を迎える。
ところが、ここ半月ほど、その雌犬が、あの濁った目を恐怖のあまり見ひらいて、愕然とわたしを見つめるようになった。わたしは彼女に説明したい。先ほども言ったとおり、たいした問題ではないのだと。不安になる必要はないと。そんな目でわたしを見ないでほしいと。
だが、犬はわたしの行為のおぞましさを理解している。
もしも子どもたちの誰かが、ふざけ半分にそのようなことをするのならば、少しも問題ではない。だが、わたしがふざけるわけのないことを、彼女は知っている。そのときだけわたしがふざけているとは考えられない。だからこそ、恐怖にかられ、あのような忌まわしげな目でわたしのことを見つづけるのだ。(1915年)(118~135頁)(『手押し車』全文)
■信仰を失うには幾通りもの理由が考えられる。信仰を失った者はたいてい、少なくとも信仰のうちは、なにかしら代償を得たという確信があるものだ。せめて、それまでは信仰によって許されなかった言葉を気兼ねなく口にし、してはいけなかった行為ができる自由を得たと思うものだ。
ところが、信仰を失った原因が抑えがたい世俗的な欲求ではなく、祭壇の聖杯や聖水ではもはや満たすことのできない精神の渇望である場合、信仰を失った者が、その代償としてなにかを得たという確信を抱くことは難しい。せいぜい、とどのつまり、己にはもはやなんの価値もなくなっていたものを失くしただけのことだと思い、信仰を失ったことに対して、とりあえずは不平を口にしない程度だろう。
トンマシーノ・ウンツィオは、信仰とともにすべてを失うことになった。司祭であった亡き伯父の条件つきの遺言に従い、父親が彼に与えてやれた唯一の社会的地位までうしなったのだ。(140頁)(『使徒書簡朗誦係』)
■ところが、突如として、とあるニュースがあたかも疾風のように村じゅうを駆けめぐり、みんなを驚かせた。使徒書簡朗誦係のトンマシーノ・ウンツィオが、分遣隊の指揮官であるデ・ヴェネラ中尉から平手打ちをくらっただけでなく、決闘を挑まれたらしい。というのも、その前の晩、トンマシーノは、サンタ・マリア・ディ・ロレート教会へと続く田舎道で、中尉の婚約者であるミス・オルガ・ファネッリに、「バカヤロー!」と面と向かって叫んだことを認めながら、その理由を説明しようとしなかったというのだ。(145~146頁)(『使徒書簡朗誦係』)
■誰もが――とりわけ父や母、決闘を見守る2人の介添人、そしてデ・ヴェネラ中尉に、ミス・ファネッリ自身が――暴言の真の理由を知りたくて身悶えするなか、誰にも増して悶々としていたのは、それを打ち明けることのできないトンマシーノだった。理由が理由なだけに、たとえ話したとしても、誰も信じてはくれまいし、それどころか、明かすことのできない秘密を、戯言(ざれごと)でごまかそうとしていると思われるのが落ちだった。(147~148頁)(『使徒書簡朗誦係』)
■存在と言う不思議の、得体のしれない、途轍もない虚しさよ。小さな蟻が生れ、ショウジョウ蝿が生れ、1本の草が生える。この世界に、1匹の蟻!この世界に、1匹のショウジョウ蝿、1本の草……。1本の草が生え、生長し、花が咲き、そして枯れていく。永遠にその繰り返しだが、1本としておなじものはないのだ。そう、けっして!
こうして、1か月ほど前から、トンマシーノは来る日も来る日も、ほかでもなくそんな1本の草の短い一生を見守っていたのだった。それは、荒れはてたサンタ・マリア・ディ・ロレート教会の裏の、苔生(こけむ)した2つの灰色の岩のあいだに生えた、1本の草だった。(148~149頁)(『使徒書簡朗誦係』)
■彼は立ちどまり、近づこうとはせずに、ひとしきり休んだ彼女がその場を彼にゆずるのを待っていた。果して、しばらくすると彼女は立ちあがった。おそらく、彼がこっそり見ていることに気づいて、気分を害したにちがいない。彼女はあたりを少し見まわした。そして、なにげなく手を伸ばし、ほかでもなくその1本の草を折ると、ゆらゆらと垂れさがる穂とともに、口にくわえた。
トンマシーノ・ウンツィオは、まるで心をひきちぎられたように感じた。そして、草を口にくわえた彼女が目の前を通りすぎる瞬間、耐えきれずに、「バカヤロー!」と叫んでしまったのだ。(151頁)(『使徒書簡朗誦係』)
■瀕死の枕元で、司祭が彼に尋ねた。
「我が子よ、なぜだね?話してごらん」
すると、トンマシーノは半ば瞼を閉じたまま、吐息とも、やさしい微笑みともつかぬ息をもらしながら、消え入るような声で、たったひとこと、こう答えた。
「司祭さま、1本の草のためです……」
トンマシーノは、死ぬまぎわまでうわごとを言いつづけた……誰もが、そう思った。(1911年)(153頁)(『使徒書簡朗誦係』)
(2013年5月12日)