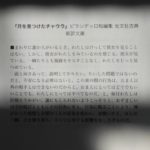『驢鞍橋』鈴木正三著 鈴木大拙校訂 岩波文庫
解説
一、略傳
鈴木正三は、参州西加茂郡足助の人、天正七年(西、1579)に生まれた。鈴木家の遠祖は紀州熊野に住み、初代に重忠なるものがあり、その十餘代の孫に重基があり、更に十餘代を經て重次があり、正三はその長子である。三河に移り住したのは重基の時で、郷邑の戦亂に際して邑人に擁せられて將となり、為めに重んぜられたといふ。重次には正三、重成の二子があった。正三は弟の重成に家を譲り、自らは高橋庄の七十騎の某の家を嗣いで九太夫と號した。七十騎といふのは官に役せず、随意に軍陣に望んで功をなす武士の一團であった如くである。徳川家康が坂東を鎭するに及んで、この七十騎を總之上にうつしたが、正三もこの一團と共に鹽子に往った。
正三は早くから生死の問題に凝滞して佛門に志し、十七歳の時に寶物集に載する涅槃經の雪山童子の因縁を覧て、頓に無常幻化を悟り、半偈を求めて軀を雪山に投げた童子の如く、道のために身命を惜しまざるの決意を堅めた。慶長五年關ケ原陣が起り、七十騎は本多佐渡守の陣に加つて戰ひ、正三もまたこれに從つたが、陣中忠義に死せんと捨身の鍛鍊をし、佛道の所謂、勇猛精進において、契得するところがあつたと云う。
戦後、暇隙(かげき)を得るに曁(およ)んでひたむきに佛門を慕ひ、下妻多寶院良尊に見(まみ)え、又宇都宮慧林寺(けいりんじ)物外を訪れ、或は關本(せきもと)最乗寺に籠って僧と交わった。物外の會下には臨済禅の宗匠たる大愚、愚堂、明關(めいかん)が居たが、何れも同参であつたものゝ如くである。
慶長十九年大坂陣が起り、正三は本多出雲守に列して出陣し、終つて岡崎城に於て軍功により新領地を賜り、越えて元和元年の再度の大坂陣には徳川秀忠の先陣をつとめて大坂に至つた。時に三十七歳であつた。
後に江戸に下り、駿河台に住止し、起(貴)雲寺萬安を訪(おとな)うて洞上の宗風、百戸の惑を理會した。萬安は興聖寺の中興開山となった洞門の大徳で、臨濟の愚堂、大愚と道交があり、共に道譽(どうよ)の高かつた人である。正三は出家、得道、嗣法という順序を踏まないで、この萬安の感化を強く受けたまゝ、法としては曹洞禪の宗風(しゅうふう)をかれより嗣(つ)ぐことになつた。(併し驢鞍橋に現れたところから見ると、正三禪には頗(すこぶ)る獨得の宗風がある。必ずしも彼を洞濟の何れかに屬させなければならぬと云ふことはない。これは別に述べることにする。)萬安の下を辭してからは八王子の山奥に入つて坐禪をして、鳩(あつま)る者のために錄語を講じたりした。
元和五年(正三、四十一歳)、高木主水正に従つて大坂城に仕え、この年同期のために〔盲安杖〕を書いた。この書は禪の境地に立つて武士の武士たる心構へを説いたもので、正三最初の著作である。
翌年にはまた江戸に還つたが、遂に家を猶子(ゆうし、甥)に譲り出家遁世をした。時に四十二歳であつた。一日出家の名を大愚に乞うたところ、大愚は
『公は道價既に重い、誰か名を安ぜよう、萑(下に曰)名で可であらう』と云つたといふことである。大愚と正三との關係は詳(つまび)らかでないが、驢鞍橋下巻末に『南泉寺大愚和尚の渡にも寮舎を構へて久しく居り給ふ』と見立てゐるから、大愚は物外下の同参であつても、正三の尊崇する宗匠の一人であつたと思はれる。
同七年、名宿を敲(たた)いて五幾に廻歩し、神社佛塔を拝し、八年には豊の雪窓、高野の玄俊と相携えて法隆寺に投じて律を綜べ、経を学び、玄俊より沙彌戒を稟(う)け、一寒暑を経てついで三河の千鳥山に入つて凝念工夫した。台嚴、本秀の二人がその時、師の道に歸(帰)して晨夕参叩(しんゆうさんこう)した。寛永元年、石平山の幽谷に居を定めて結廬(けつろ)するに諸方の雲衲、遠近の男女靡然(ひぜん)として従った。妙心寺の雲居もこの廬(いおり)を訪ねたと云はれる。同八年、京都に上つたが、眞迢(しんちょう)と云ふ台宗の法師は、師に見(まみ)えて『石平是正悟之活人、末法時中得逢叵値』(石平行業記)と歎じた。この年、大坂より紀州熊野に詣り、遠祖の故地を尋ねたが、廻って和歌山に至り、其處の加納氏の諸士のために道を説き、武士日用を著した。武士日用に『農人日用』『職人日用』『商人日用』の三章を續けて著し、合して四民日用と云つた。今日、正三の著として萬民徳用一巻があるが、この四民徳用に『修行之念願』、『三寶之徳用』を加へたものである。
翌九年、石平山に新に佛殿を創め、寺を恩眞寺と稱した。中央に観音大士、左右に徳川家康及び秀忠の碑を安置した。正三は徳川家の恩顧を謝すること極めて篤かった。
正三は石平山恩眞寺の後來住持たるべき資格を次の如くに規定してゐる。
『恩眞住僧後來莫道心之士、則俾無知之行者衛燈香。硬不得令世間之長老住位』と(石平行業記)。
正三の著作のうちには、當時の佛教界に對する革新的意見が屡〃述べられてゐるが、道心なき長老をして恩眞の後席を嗣がしめるといふことは、正三の最も排するところであったのである。
其後、正三の足跡は大和の吉野、近江の山澤にも及び、丹後の瑞巌寺に至つては萬安の請に随つて〔麓草分〕二巻を著し、轉じて江戸に下つては尼女を度して〔二人比丘尼〕一巻、〔念仏雙紙〕二巻を著した。それから數年を經て寛永十六年八月二十八日、偶〃石平山にあつたが、暁に廓然として開悟するところが有つたといふ。時に六十一歳であつた。
同十九年(正三、六十四歳)、弟重成は肥後天草に吏(り)として轉出したが、正三は悟處(ごしょ)に坐在するを欲せず、弟に随つて自ら天草に赴き、邪宗泛濫(はんらん)の地に佛宇を建立して正法の弘通を圖(はか)つた。重成は正三のために幕府に訴へて建立に要する三百輌斛(りょうこく)を賜り、三十二宇を建て、うち一宇は浄土宗として家康、秀忠の牌(はい)を安じ餘りは曹洞宗となした。正三は〈破幾利支丹〉一巻を書して寺毎に置き、邪教の永斷を誓願した。
駐錫(ちゅうしゃく)三年、ついで長崎を經て還り、慶安元年には江戸に抵つた。教禪の學者、老幼貴賤擧げて歸仰した。天徳寺長水、賢宗寺萬休、海安寺呑海・春嶺等は糀町に舎を締んで剋定し、師を講じて垂語を願つた。
同三年、森田氏は、菴(あん)を四ツ谷に建てて、師を迎へたが、正三は此處(ここ)於て〔三寶徳用〕一巻を著した。同五年、熊谷氏はまた牛込の天徳寺境内に了心菴を建て、師を聘(へい)したが、此處にあつては〔修行之念願〕一巻を書いた。〔三寶徳用〕、〔修行之念願〕は前に記した〔四民徳用〕に合巻されて萬民徳用一巻をなすものである。〔修行之念願〕は正三最後の述作である。師は恒に昏沈の坐禪、無事の工夫を斥(しりぞ)けて世法卽(そく)佛法と云ふべき、活動的で社會的な禪を主張した。なほ正三禪の特色ある性格につきては、後に少しく述べることにする。
かくて慶安元年(正三、七十歳)、江戸に至つてより凡(おおよ)そ七年、明暦元年(西、1655)春に病を發し、その六月二十五日申刻、恬然(てんぜん)として駿河台の弟重成の宅に於て、法臘(ほうろう)三十六年、七十七歳の生涯を閉ぢた。末後兩三日前に一僧あつて尚法要を示し給へといふに、師ははたと睨んで、『何と云ふぞ、我三十年云ふことをえうけずして、左様のことを云ふか。正三は死ぬよ也』(驢鞍橋下巻)、と云つたといふ。如何にも武人正三らしい最後の句である。
その寂日の夜、全身を了心菴に遷し、龕(がん)を天徳寺に送り、翌日闍維(じゃい)し、天徳の北崗に塔した。後、塔は下總吉倉松山に遷した。門人五十餘員があり、不三は衆中の長老で、師の在世中に稲田觀音院に住し、雲歩は師の滅後に豊後能仁寺、肥後天福寺を闢(ひら)き、惠中は大府の草菴に居した。惠中は〔驢鞍橋〕の筆録者であり、〔石平行業記〕の著者でもあり、このほか禪と念佛に關(かん)する著作に、〔末法成佛結斷章〕一巻があり、正三禪を祖述した〔草菴雑記〕三巻がある。
正三の著書は上記の外に〔因果物語〕がある。これは何時書いたものかわからぬが、惠中の記すところでは、『人の靈化物語を作す毎に加様のことを聞捨にするは無道心のこと也。末世の者加様のことを證據(しょうこ)と作して進まずして、何を以て進んやと云つて集め給也。殊(こと)に曰(い)はく、我集むる所は〔元亮釋書〕、〔砂石集〕の物語よりも證據正しと也と』。〔因果物語〕は幽靈話の一種であると云つてよからう。(243頁)(一、略傳おわり)
三、正三禪の特色
正三道人の禪は日本禪思想史上特異の色彩を放つものである。傳統思想に終始するものは、正三禪を異端視するかも知れぬ。又はこれを輕視して顧みないで居ようとするでもあらう。が、苟(いやしく)も一心の誠を竭(つく)して人生の大問題を解決せんと努力した人は、如何なる系統又は無系統の人であつても、その言ふ所、その經驗したところに對してして、耳を傾けるが、眞摯(しんし)な學人の爲すべきところであらう。
正三禪には幾多の特處がある。彼は誰の禪を繼承したとは云つて居ない。多くの禪匠に参じたことはあつたが、誰に對して殊に心を傾けて修禪したとは云つて居ない。彼は自分の問題の解決に忙はしくして、あの公案はわかる、この公案はわからないなどと、看話禪者のやうに公案に捉へられぬ。彼は自分の求むるところは何處(いずこ)に在るかを知つて居た。『各々は佛法好也。我は佛法を知らず。只死なぬ身となること一つを勤むるばかり也』と(驢鞍橋下、12)、彼は云ふ、又『只牙咬(はがみ)をして死ぬこと一つを窮(きわ)むること也』(同上)とも云ふ。正三禪は日日の生活の上で『死習(しになら)う』ことを體得するところに在つたのである。これが彼の修行であつた。〈驢鞍橋〉の至るところで彼は死に言及して居る。『我は死がいやなに因(よ)つて、生通(いきどお)にして死ぬ身となりたさに修行はする也』(上、81)との聲明は、正三の修禪の全部であつた。
それで、彼は此點から見て、古今の祖師達を品騭(ひんしつ)せんとする。彼は見解とか法語とか語録とか云ふものに對しては、餘り重きをおかなかった。曰はく『古(いにしえ)の祖師達のも修行熟せるは少しと見えたり。大かた小見解を是とし、經文語録を以て法語を書き、教化などして、語録等を残されたると思ふ也。云云。』(上、34)。
彼は明かに學禪の目標を自覺して得たので、所謂(いわゆる)、お悟りなるもの、又そのお悟りを特種の熟語で表現すつことには、大して關心を持たなかった。『昔も實に隙の明(あひ)たるは釋迦御一人なるべし、其外の祖師、殊に我朝の傳教、弘法、まだ佛境界には遙なるべし』(下、107)。『道元和尚などを隙の明(あい)た人のやうにこそ思はるらん。未だ境界にあらず。その自由になるものにあらず』(下、121)。『隙の明た』と云ふは正三が屡々(しばしば)用ゐる文字である。生死を超越して而(し)かも生死に生きて居る境界を實地に獲得したのを、隙があいたと云ふのである。正三も此點においては十分の自信が持てなかつたやうだが、それでも『今日まで存命(ながらへ)て修行も大略には仕上(しのぼ)せたれ』(下、13)と云つて居る。そうかと思ふと『此年まで如是されども隙得明(えあか)ぬ故に』とも云ふ。又『我も八十まで生きたれど、何の變もなし。乍去(さりながら)我は慥(たし)かに種は取た也』(下、107)とも云ふ。『種を取る』とは、『隙のあく』方向を間違へては居ないと云ふことらしい。卽ち正三は自ら佛境界を得たとは云はぬが、その方に近づきつゝある、その鍵は握って居ると云ふのであらう。
正三は普化(ふけ)の境涯を理想としたものの如くに見える。『普化の意、道ならば三町ばかり行くほどが間、慥(たし)かの移れり。是は大ひに徳になる也。我も普化ほどには世世生生において修しつけんと思ふ心強ふ起れり。普化は慥(たし)かに佛境界の人と覺えたり』と(下、13)、彼は云ふのである。又下巻の五十七及八十九にも普化に言及して、彼の境界を『中中さつさつとしたる活境界』だと云ひ、又『普化の境界が乗りたので、修行ようたらぬと云ふことを知る』とも云つて居る。
普化は、人々の知って居るやうに、臨濟録中に現はれる人物で臨濟と同時代である。臨濟の教化を助けたと云ふが、其行動は如何にも飄飄乎として風の如く捕捉すべからざる底のものがある。彼の眼中には臨濟の如きものはほとんど無かつたと云はれ得る。彼は正三の考へる如く物だの肉體だのと云ふ『實』に因へられぬ『隙の明いた』自由自在の人であった。方の外に遊んで居る人であつた。寒山、拾得を想はせる人であつた。『度人も何も有るやうの機にあらず』と(下、85)、正三は云つて居る。
正三はこのやうに、日用光裡に實際の境地を手に入るることを修行の目的として居たので、『見解などと云ふことも指して用に立たぬもの也』(下、5)として、見解卽ち思想に對しては、さして重きを置かなかった。見解は又悟りである。『悟る悟りはあぶないことぞ。我も悟らぬ悟がすきなり。法然などの念佛往生も悟らぬ悟也』(同上)と、正三は斷ずる。
見解はまた見性である。此見性を看話禪(かんなぜん)の對象として居るが、正三は見性に止まりてこの圏繪(けんかい)の外に出ることを知らぬのを嫌忌する。『見性の分ありてもなほなほ強く修することなり。まかなか隙の明くことにあらず。然るに今時は少見解あれば早や修行成就と思ひ、師家を立て、亦(また)人を印可する也。すべて大ひに差へり』と(下、16)、彼は云ふ。見解、悟人、見性など云ふ一次性のものに止まりて、これを常住に使ひこなさない限り、そんなものは大して役に立たぬのであるが、看話禪の學者は概して比弊に陥るのである。正三の警告は肯綮(こうけい)に中(かな)つて居る。『さてまた悟入すれば佛境界なりと思へり。そでもない事也。たとひ見解ありとも、自由に使ふるべからず。佛境界と云ふは格別の事也』と(上、七十七)。實にその通りである。
畢竟のところを云へば、見解は修行と相應すべきもので、修行のない見解、卽ち境界から出ない見解は、鬼の空念佛である。が、人間の意識はこの空念佛の方向に進むやうに出来て居る。それがその長處で又短處である。正三は徹底してその短處を切り捨てんとするのである。『我ヲツキリの中にも言ひ習うて道理の上手は多きなり。然れども修行するものは一人もなし。我此前石の平にて少し沙汰しければ、皆理屈佛法になるによつて、飽き果て、ふつと理を沙汰せず。ちょつとよりから一向に修し行ずる事ばかりを授(さずけ)るなり』(上、47)と云ふ正三の心持ちはよくわかる。
併し只修行すると云ふことはない。修行と云ふとき既に修して行ずべき何かがそこにあるのである。『修行』に先行して何かの見解、思想、悟りなどと云ふものがなくてはならなぬ。正三の斥(しりぞ)くるところは、見解を見解として、『それが何の用にも立ぬもの也』の位地に止まる時なのである。業障を盡くすと云ふも修行の義である。(上、45)。人間としては何かの意味で思想がなくてはならぬ。『理を沙汰せず』にはすまされぬのである。思想だけあつても、人間には濟度の機會が與へられて居る。『畜生の如くにして冥より冥に落ち入り』ることはない(上、100)。何となれば、この思想の故に修行も可能になり、業障をも盡くし能ふのである。正三も此間の消息を知らぬことはない。それで彼は『意の暗き行者』を誡(いまし)めて曰はく『其方はまず言句を錬り鍛うて意に徹すべし(中略)。なかなか意暗くしては修行はかどるべからず。」まづ其方は専(もっぱ)ら意を受け習はるべし』(上、102)と。意と云ふは思想であり、見解である、言句に現はし得べきところのものである。只無暗(むやみ)に修行すると云ふことはあり得べからざることである。正三も普化の境界において、その意を得たものであつたので、七十七歳をつくし得たのである。
正三禪に今一つの特有なるものは、念佛である。元明時代における念佛禪でもなく、浄土系を引いた念佛でもない、また白隠和尚が比較して居る念佛と云ふときの念佛でもない。正三獨自のもので、異數の念佛である。
『初心のものに悟を安く授け、暫時に隙を明さすこと大罪也。今時世間に比類多し、恐るべきことなり。我は浄土宗のやうに念佛を申し習はする位ひがすき也。其故に初心の者には先(まず)所作を授る也』
『浄土宗のやうに』と云ふが、正三のはその實そんな念佛でない。『念佛を申し佛に成んと思ふは輪廻の業也』と(上、87)云ふのであるから、彼の念佛は後世を願ふためではなくて、安楽に死ぬるためである。『然間、萬事を放下して南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛と息を引切り引切り常に死に習ひて安楽に死ぬる外なし』(同上)と云ふやうな念佛は、何の望をも持たぬ念佛、只死に習ふ念佛である。これを『只土(ただつち)になりて念佛修行する』とも云ひ(上、57)、又『虚空一枚になる』とも云ふのである(同上)。それは念佛の中に全存在を叩き込むので、一念の妄想もなく、生死の自覺もなく、我他彼此の相對感もなく、一心不亂に念佛そのものとなる、これが念佛で死に習ふのである。生死の業を申し盡くすことである。正三は何時も『死習(しになら)つて、死の隙を明る事』(上、42)を修禪の眼目とした、此に正三禪の特異性がある。
とに角、正三禪の始終を通じて強く現はれて居る思想は『此(この)糞袋を何とも思はず打捨つること也。これを仕習ふより別の佛法を知らず』と(上、13)云ふのである。『なにもなき坿(がけ)の下へたゞ落ちて死んで見るに中中張合無(なく)して飛れざる也』(同上)と云ふところに正三の面目を窺ふことが出来る。闇から突き出す鎗(やり)先に引つかかつて莞爾(かんじ)として死んで行けるやうにと、彼は修行した。これは只出来ることでなく、又俗の云ふ『犬死』とか、『死を何とも思はぬ』とか云ふ死に方ではなくて、正三の『死習ひ』には深い死生観があり、宗教的安心があり、哲學的直感がある。彼はこれを文字の上、思想の上に現はして解明することをしなかつた。僅かに普化の境界にその意を得たものと云つて居るに過ぎないのである。
正三禪は日本における禪思想史上大いに異彩を放つものと云はなくてはならぬ。なほ詳細は他日を期する。(237~254頁)
2023年6月28日了