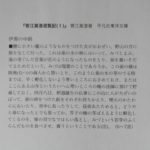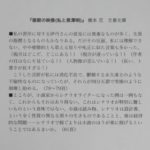『正法眼蔵(4)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
海 印 三 昧 ( かいいんざんまい )
■開 題
この一巻は、仁治三年(1242)の四月二十日、宇治県の興聖宝林寺において記されたものである。巻末の奥書には「孟夏二十日」の文字が見える。孟夏とは、夏のはじめの意をもって、陰暦四月の異称となすことばである。その好時期にあたって、道元は、さきに「行持」の大巻を脱稿したほか、この「海印三昧」の巻についでは、さらに「授記」の巻、「観音」の巻と、都合四巻をこの月うちに制作しておられる。連日の執筆であったことと察せられる。
ー中略ー
かくて、その意味するところは、大海が一切の存在をそのあるがままの相(すがた)において印写することによって、仏祖が三昧にある心境が、また一切の存在をそのあるがままの相において印象することを語っているのだと知られる。かくて、海印三昧とは、大海をもって象徴せられる仏の三昧であるとでもいうことをうるであろう。
では、そのような仏の三昧における心境とは、どのようなものであろうか。それが、いま道元のこの巻において説こうとするところである。その説くところは、おおよそ、その前半とその後半二分して受領することができるようである。
その前半には、まず『維摩詰所説教』の中巻、文殊師利問疾品(もんじゅしりもんしつぼん)における維摩詰のことばの一節があげられ、それに馬祖道一の説明が加えられている。それに依って、道元は、大海の印写する一切の存在のすがたを、いうなれば分析的に解説するのである。その一切の存在のありようは、馬祖道一によって、つぎのように語られている。
「前念後念、念念相待せず、前法後法、法法相対せず。是れ即ち名づけて海印三昧となす」
そこでは、これを時間的にいえば、前なる念(刹那)と後なる念とは、たがいになんの関係もなく、これを空間的にいえば、前なる法(存在)と後なる法は、それぞれに絶対である。それが、大海をもって象徴せられる三昧の心境に印象する一切の存在のありようであるという。
その後半では、洞山(とうざん)の法嗣(ほっす)である曹山本寂(そうざんほんじゃく)の、一人の僧の問いに答える問答があげられる。その問答の主題は『華厳経』の十字品(じゅうじぼん)にみえる「大海は死屍を宿(とど)めず」という一句である。それは、この経が説く「大海の十徳」の一句であるが、その意(こころ)をいまこの問答によって追求してゆくと、そこに、いうところの大海、もしくは、大海をもって象徴せられる仏の三昧の境地が、いうなれば全体的に打ち出されてくるのである。活潑潑地(かつぱつぱつち)として具現されてくるのである。
ここでも、道元の解説は、微にわたり細にわたり、あるいは高古(こうこ)にして綿密をきわめ、例によって難解ではあるが、読みきたり、思いめぐらした末、もう一度、冒頭の一節にいたれば、もろもろの仏祖といわれる方々は、みなかならず海印三昧という定を得ておられて、法を説くにも、証する時にも、行ずる時にも、いつもこの三昧にひたっておられる」
というのが、やっとほのぼのと判ってくるのである。(16~18頁)
■もろもろの仏祖といわれる方々は、みなかならず海印三昧すなわち大海をもって象徴せられる定(じょう)を得ておられて、法を説くにも、証するにも、行ずる時にも、たえずこの三昧にひたっている。その大海をゆくさまは、あくまでも徹底するがゆえに、これを「深々として海底を行く」と表現するのである。世の生死に流浪する衆生たちをその本源に還らしめたいと願うのも、このような心のうごきではないか。さらに、これまでに関所をこえ、煩悩のまどわしを破って解脱しきたった仏祖の面々も、もとよりことごとくこの三昧の大海に流れ入るものである。
仏はいった。
「ただ、もろもろの存在があって、結合してこの身を成すのである。その起るときにはただ存在が起るのであり、その滅するときにはただ存在が滅するのである。だから、その起るときには我が起るとはいわず、その滅するときにも我が滅するとはいわない。また、(これを時間的にみれば)前なる刹那と後なる刹那は、たがいになんの関係もなく、(これを空間的にいえば)前なる存在と後なる存在は、それぞれ絶対である。これを名づけて海印三昧というのである」
この仏のことばを、くわしく学びいたり、思いめぐらしてみるがよい。仏道をさとることは、かならずしも多くを学ぶことによるものでもなく、また多くを聞くことによるものでもない。多聞広学の人も、さらに四句を聞いて仏道を会得し、微細に学べる人も、最後には一句の偈(げ)によって悟るというものである。ましてや、いまの仏のことばは、本覚(がく)つまり人がもともと有する覚性を前提としたものでもなく、また始覚(がく)つまり教えを聞いてそれが悟りの花をひらくといったものでもない。いったい、仏祖というものは、その本覚などということを実現するものではあるが、その本覚だ始覚だという覚性を論じわかって、それで仏祖となるではないのである。
いうところの海印三昧のなる時は、それはただもろもろの存在のみの時である。だから、それを大海をもって象徴するのである。さらに、その時には、それらが結合してこの身を成すという。もろもろの存在が結びあって成れる一つの集合体、それがつまりこの身である。この身を一つの集合体だというのではない。ただ、もろもろの存在が寄り集まるのであり、寄り集まってこの身をなしている、それをこの身と表現するのみである。
「その起る時にはただ存在が起るのである」という。それは、ただ存在が起るのであって、べつになんぞ起るということがあるのではない。だから、その起るのは自分がそれと気がつくのでもなく、それを知ることもできない。これを「われ起るといわず」という。また、われ起るとはいわないからとて、別に人があって、この存在が起るのを見たり聞いたり気がついたり、あるいは、あれこれと思い量り、知りわけるわけでもない。だから、他日一歩をすすめて自己を直視する時には、おのずからあるがままなる姿を直視するには、まことに好都合というものである。
しかるところ、その起るというは、かならず時期が到来してのことである。時をほかにして起ることはありえないからである。では、その起るとはどのようなことであろうか。それはただ成るのであろう。すでにそれはある時の成立である。だから、その時にあたって皮肉・骨髄がおのずから現われたとしてもすこしも不思議ではない。だが、その成立はすでにいうがごとく結合して成るのであるから、そこに成るこの身、そこに起るわれは、「ただ、もろもろの存在をもって」成るのである。それは、見る物、聞く声といった対象であるばかりでなく、いまや、われ起るというもろもろの存在である。いや、それは、われ起るとはいえないわれが成ったのである。いえないとは、いわないということではない。いうというのは、それはただ表現であって主張ではないからである。また、その「起る時」とは、ただこの存在が起るのであって、世のいわゆる時をいうのではない。この存在そのものがその起る時なのであって、その時、意志や欲望など三界(がい)ことごとくが競い起るのではない。
かって、古仏はいった。
「忽然(ねん)として火起る」
その起ることの、なにかに関連して相対的ならぬことを、ここに「火起る」と表現しているのである。
また、古仏に問うていった者がある。
「起滅とどまらざる時いかに」
というのは、その起ると滅するとを、自分で自分が起るのだと思い、自分で自分が滅するのだと思うから、それが停(とど)まらないのを、どうすればよいかというのである。だが、その起と滅のとどまらぬのは、起滅そのものに任せておけばよいのである。むしろ、その気滅のとどまらぬを、そのままに仏祖の御いのちとして断続せしめるのである。それで古仏は、問う者を叱していった。
「それはいったい、誰が起滅するというのじゃ」
そのいう意味は、起滅は起滅にまかせて、「まさにこの身をもって得度すべし」であり、あるいは、「すなわちこの身を現ずる」のであり、そして「ために法を説く」のである。あるいは、「過去心は不可徳」であって、「汝はわが髄を得る」のであり、「汝はわが骨を得る」のである。いったい、誰が起滅するのだというのは、このことなのである。
また、「この存在の滅する時、われ滅すとはいわず」とある。まさしく「われ滅すとはいわず」の時が、それが「この存在の滅する時」である。その滅というのは存在の滅である。滅するとはいうけれども存在といってよかろう。そして、それは存在であるから、煩悩に関わらぬものである。煩悩に関わらないから清(しょう)浄である。そして、その清浄なるものが、とりも直さず諸仏であり初祖である。しかるに、「汝もまたかくのごとし」という。誰が汝でないものがあろうか。さきの刹那もあとの刹那も、みんな汝でであろう。また、「われもまたかくのごとし」という。われであらぬものが誰であろうか。あとの刹那もさきの刹那も、すべてわれだからである。
この滅には、いろいろの見方が具(そな)えられている。いわゆる最高の涅槃という見方もある。それを死というものもある。あるいは、生の執(しゅう)に対していえば断となすものもある。あるいはまた、ついに帰するところとなすものもある。そのようにいろいろの見方があるが、それらすべて滅のありようを示している。だから、その滅が自分のこととなった時にも「われ起る」とはいえないけれども、そのいえない道理は、生のときにはみな同じでも、死の場合にはけっして同じではあるまい。すでに、さきなる存在の滅があり、あとなる存在の滅があり、また、存在にはまえなる刹那があり、あとなる刹那がある。つまり、存在のありようは、前後の存在としてあり、前後の時をもつのみであって、その間になんの関連もなく、絶対であるのが、存在のありようなのである。だから、存在とは、絶対にして、なんの関係もないものだといえば、それでほぼ完全な表現だといえよう。だが、また、その滅を四大・五蘊について見れば、またいろいろことがあり、あるいは、四大・五蘊の移り変わりとして滅を見ても、また一歩をすすめて、ああそうかと思うところがあろう。しかし、そういうことになると、身体(からだ)じゅうに眼のある手があっても、なおまだとても及ばないことであろう。いそがしいことじゃ。だが、ともあれ、滅ということは、仏祖にとっての大事なもんだいである。
しかるに、いま起も滅も、絶対のものであって、たがいに相待つものではないといったが、そこには、やっぱり、物の起るには初めがあり、中があり、また後なるがある。そこは、建前は針をも容れないが、裏では車馬でもおおっぴらで通れるというところであろうか。だからといって、滅をその初・中・後に関連せしむべきではない。そこは、やっぱり絶対である。たとい、さきに滅した処に忽然として存在が生起したとしても、それは滅したものがまた生起したのではない。ただ存在が起ったのである。ただ存在の生起であるから、相待ではなく、絶対である。また、滅と滅とも、相待つものではなく、それぞれ絶対である。むろん、滅にもまた、初めなるがあり、中ごろなるがあり、後なるがあるが、そこに到ってこれが滅だと滅をつまみだそうとしても何ものもない。ただ、心に問うてみれば、やはりそれがあると知られる。また、これまで存在したものが忽然として滅したからとて、それは起が滅したのではない。ただ存在が滅したのである。ただ存在の滅であるから、相関ものではなく絶対である。かくて、たとい、これがすなわち滅というものがあり、これがすなわち起というものがあっても、ただ海印三昧をもって名づけて、それがもろもろの存在だとするのである。これが起これが滅だということが判らないわけではないが、そこをただ、ずばりと名づけて海印三昧というのである。
この三昧というのは、直観であり、その表現である。またいわば、人が夜間に手をうしろにして枕をさぐるがごときである。夜そのようにして背なかに手をやって枕をさぐることは、とおいとおい昔からのことであるが、また仏はそれを「われは海中において、ただつねに妙法華(け)経を宣べ説く」といわれた。けだし、「われ起るとはいわず」であるから「われは海中において」である。その前面も、一波わずかに動けば万波これに随って、つねに宣説するのであり、その後面も、万波わずかに動けば一波これに随っての妙法華経である。たとい千尺万尺の釣糸をのばしてみても、残念ながら、それはただまっすぐに垂れるのみである。いまここに前面といい後面というは、「われは海面において」の意であって、たとえば、前面といい後面というようなものである。前面・後面というのは、わが頭のまえ、頭のうしろということである。
いったい、海のなかには人がいる道理はない。「われ海において」では、世人の住むところでもなく、聖(しょう)者の愛するところでもない。それをいま「われひとり海中において」といい、そこでただ常に宣説するという。その海中というのは、海のなかというのでもなく、海の内だ外だというのでもなく、ただとこしえに法華経を説いているという。それは、東西南北のどこに居るわけではないけれども、船子(し)徳誠(じょう)が偈をもっていえば、「満船空しうして月明を載せて帰る」というところである。その帰るとは、まさしく帰り来るのである。それをあくまでも水に関わって考えるものは誰もないはず。それはただ仏道の関わるところにおいてのみ理解できることである。それは水をもって象徴せられる心境である。さらにいえば、空(そら)をもって象徴せられる心境であり、さらにいえば、泥をもって象徴せられる心境である。水をもって象徴せられる心境は、なおかならずしも海をもって象徴せられるそれではないけれども、さらにそれを超えてゆけば、それは海をもって象徴せられる心境にいたるであろう。これを海印という。また水印といい、泥印といい、心印ともいうのであり、その心印を直々に伝えられて、水をもって象徴し、泥をもって象徴し、また、空をもって象徴とするである。(23~29頁)
〈注解〉海印三昧;その原語は“略”である。“略”とは、大海を意味し、“略”とは、印すること、印象すること、象徴することをいい、また“略”とは、三昧と音写し、定(じょう)と意訳する。よって「大海をもって象徴せられる定」をかくいうのだと知られる。その心行が、いかなる道理によって仏祖のそれとされるかは、いま道元のつづいて精細に解説するところである。
本覚・始覚;人間の本来有する覚の可能性と、人が教法を聞いてはじめて覚の可能性を実現することとである。
但以衆法、合成此身;「ただ衆法をもって、この身を合成(ごうじょう)す」と読まれる。そこの「衆法」とあるは、いろいろな存在というほどの意で、それらが合せ結んでこの身が成立しているというのである。たとえば、この身は四大所成(しだいしょじょう)であるといった趣きである。
道得・言得;言と道は、いずれも「いう」と読むことばであるが、いま道元は、言得を主張するの意にとり、道得はただ表現するの意にもちいている。したがって、そのまえの句に「不言は不道にはあらず」とあるのは、「いえないとは、いわないということではない」となる。
前念後念;念とは、ここでは最小の時間の単位、いわゆる刹那である。
手眼;千手観音には、そのそれぞれの手に眼がある。それによって、ここでは、いろいろの見方があるというのであろう。
印;それはもと“略”の訳語であり、「しるし」とか、「印象」とかの意である。いまここでは、仏祖の心境を、「海」や「水」をもって語っているのであるから、「象徴する」の意にとってよかろうと思われる。(30~32頁)
■曹山の元証大師に、ひとりの僧が問うていった。
「承(うけたま)われば、教えには、「大海は死屍(しし)を宿(とど)めず」ということばあるとのこと。その海はどのようなものでございましょうか」
師はいった。
「万有を包含しているのだ」
僧はいった。
「いかなれば、それは死屍(しし)を宿(とど)めないのでありましょうか」
「息の絶えたものは宿めないからである」
僧はいった。
「すでに万有を包含しているというのに、どうして息の絶えたものは宿ねずとするのでありましょうか」
師はいった。
「万有は、その役をはたさなくなった時に、息が絶えるというのだ」
この曹山本寂は、雲居道膺(うんごどうよう)と同門の兄弟弟子であって、洞山良价(とうざんりょうかい)の宗(むね)とするところは、ぴたりと彼らによって受け継がれている。いま、「教えにこういうことばがある」というのは、仏祖の正しい教えであって、凡庸の聖者のいうところではなく、仏法にかこつけたつまらぬ教えではない。(36頁)
■師は答えて、「万有を包含しているのだ」といった。それは海をいっておる。その意(こころ)の表現するところは、なにか一つの物が万有を包含するというのではなく、ただ包含万有(ほうがんばんゆう)である。大海が万有を包含するというのではない。包含万有というのが大海であるとする。なにものとも判らないが、かりにそれを万有とするのである。仏祖の面々に相見(まみ)えることも、かりに万有と思ってよいのであるが、いま包含という時には、たとえば山も、ただ高き峯の頂(いただき)に立つのみではなく、たとえば水も、深々として海底を行くのみではない。それを集約していってもそうであろうし、また、拡大していってもそうである。たとえば、仏性海といい、あるいは、毗盧蔵海(びるぞうかい)というのも、すべてただ万有のことである。その海の面はどこにも見えずとも、仏祖の面々がその大海に遊泳せられることは疑いない。たとえば、多福禅師は一つの竹やぶについて語って、「一本二本は曲がっている」といい、また、「三四本は斜めだわい」といったが、それも万有を会得せしめる手だてであった。だが、そこのところは、どうして千曲万曲といわなかったのか。また、どうして千叢万叢(せんそうばんそう)もまたしかりといわなかったのか。だが、ともあれ、一むれの竹やぶもまたこうなのだという道理を忘れてはならない。そして、いま曹山が「包含万有」というのも、それもまた万有のすがたである。
そこで、僧がまた、「どうして息の絶えたものはとどめずとするのか」といったのは、ちょっと見ると疑問のようであるが、そこはもうそのような心持ちになっているのである。これまで疑問として抱いてきたものは、いつしかその疑問としたものに相見えるというものである。どんな処だから、どうして息の絶えたものはとどめないのか、どうしてそこには死屍を宿めないのか。そう疑っているうちに、いつしか、ああそれは、すでに包含万有であるから、息の絶えたものはとどめないのだなあと判ってくる。つまり、包含というのは、とどめるのではない、宿(やど)すのでもないと知られるのである。万有は、たといすべてが死屍であろうとも、けっしてそれを宿すことはしない。そんな石は、この老僧は一子も打たないのである。
すると、曹山は、「万有は、その役を果たさなく時に、息が絶えるというのだ」といった。そういう意味は、万有は、たとい生きているものでも、死んでいるものでも、そのなかに宿めるわけではない。たとい死んだ屍(しかばね)であろうとも、万有にあずかる行動のあるものは、すべて包含するであろう、いや、包含しているのであろう。万有のさきにまたあとに、その役を果しているものは、けっして息が絶えたのではない。そこでは、いわゆる一人の盲人がもろもろの盲人の手を引いているのである。その道理はまた、そのまま、一人の盲人が一人の盲人の手を引いているのであり、またもろもろのの盲人がもろもろの盲人の手を引くことである。そして、もろもろの盲人がもろもろの盲人の手を引くとき、それは、包含万有を包含するというものである。かくて、さらにどこの国のどこの世界に行ってみようとも、万有でないものはどこにも見出すことはできないのである。それを海印三昧というのである。(37~39頁)
〈注解〉明頭来明頭打……;普化和尚の鈴鐸偈文として知られる句である。なにが来ようと、その情況に応じて渋滞なきをいう。(40頁)
授 記 ( じ ゅ き )
■仏祖が一人より一人へと直々に法を伝えること、それが授記である。いまだ仏祖にまみえてまなばぬものには、夢にも見えないところである。
その授記の時期にはいろいろある。まだ仏道をまなぼうとする心を発(おこ)さないものに授記することもある。仏性なきものに授記することもあれば、仏性あるものに授記することもある。あるいは、姿あるものに授記するすることもあり、姿なきものに授記することもある。あるいはまた、もろもろの仏に授記するすることもあり、仏はすべての仏の授記を保持しているのである。だが、仏は、授記を得たのちに仏となるのだとまなんではならない。また、仏となってのちに授記を得るのだとまなぶべきでもない。まことは、授記のその時に仏となるのであり、授記のその時に修行がなるのである。だから、すべて仏には授記があるのであり、また、身心に授記を得るのである。したがって、授記がよくよく受領せらるれば、そのとき、仏道もまたよくよく受領せられるのである。だが、その授記には、また身前の授記というのがあり、身後の授記がある。つまり、自己に知ることができる授記があり、自己に知られない授記があり、また他に知らせることができる授記があり、他に知らせることのできぬ授記があるのである。
それによって判るように、授記とは自己を実現することである。あるいは、授記とは実現されたる自己なのである。だから、仏から仏、祖から祖へと、じきじきに相承(あいうけ)てきたものは、ただ授記のみである。べつになに一つとして授記ならざるものはない。ましてや、そのほかに山(せん)河大地があり、大山巨海があろうはずはなく、いわんや、その間にべつにあれこれの人々があろう道理もない。その授記というのは、やっぱり、一句を説くことであり、一句を聞くことである。それは会得できない一句であることもあり、会得せられる一句であることもある。それを行ずるのであり、それを説くのである。その時、それが退くべきことを教えてくれ、また進むべきことを教えてくれるのである。いまわたしどもが坐して衣(ころも)をまとう。それも古来からの授記によるのではなかったならば、けっして実現しないのである。それをわたしどもは合掌して頂戴(ちょうだい)する。かくしてそれが実現するのも授記なのである。
仏はいった。
「いったい、授記にはいろいろあるけれども、いまはかりにその要をとっていえば八種がある。つぎのごとし、
一には、自分だけが知って、他は知らないもの
二には、人々はみな知っていて、自分だけが知らないもの
三には、自分も、また人々も、ともに知っているもの
四には、自分も、また人々も、ともに知らないもの
五には、近い者は気がつき、遠い者は気がつかないもの
六には、遠い者は気がつき、近い者は気がつかないもの
七には、近い者も、遠い者も、ともには気がつくもの
八には、遠い者も、近い者も、ともに気がつかないもの」
このようないろいろの授記がある。だからして、いまこの人間のこころに知られないからとて、授記などあるものかと思ってはならない。あるいは、まだ悟っていない人間が、容易に授記を得るなどあるはずはないといってはいけない。世のつねの人々は、修行の功がみちて成仏のことが決定した時に、はじめて授記のことがあるのだと、そのようにまなんできているようであるが、仏道はそうではないのである。あるいは善知識にしたがって一句をきき、あるいは経巻によって一句をまなぶ。そのことのある時、それがとりも直さず授記を得るのである。それはもともと諸仏の行じたまえるところであり、それが百草の善根というものだからである。
もし授記が語られたならば、それを聞くことを得たものは、みな究極地にいたる人である。しるがよい、一塵もなお無上であるという。一塵すらもなおどこまで向上するか知れない。ましてや、授記がそうでないはずはあるまい。授記こそは大事実現の一法でなかろうはずはない。いや、それは万法であり、修(しゅ)証であり、仏祖であり、坐禅弁道であり、大悟大迷であって、そうでなかろうはずはないのである。かって黄檗が臨済に語って、「わが宗は汝にいたって大いに興(おこ)るであろう」といったのも授記である。けだし、授記とは目標であり、旗じるしであって、かならずしもこれでなくてはならぬというものではない。破顔微(み)笑もそれである。生死去(こ)来のこともそれである。この十方世界のことごとくがそれであり、また、あまねく世界がなんの蔵(かく)すところもないのも授記というものである。(46~49頁)
〈注解〉授記;それはもと“略”の訳語であって、音写して「和伽羅那(わからな)」と記す。その意味するところは、道元がいうがごとく、一般には「修行の功みちて成仏の定まれるとき」、はじめて与えられる決語として解されている。だが、道元の解釈はもっとそれを拡大して、それは「いまだ菩提心を起こさざるものにも」与えられるとする。(50頁)
■「われはいま仏にしたがって、授記の荘厳(しょうごん)のこと、および転次に決を受けるであろうことを聞きて、身心はあまねく歓喜せり」
そのいうところは、まず「授記というすばらしいこと」は、かならず「われがいま仏にしたがって聞く」ということである。わたしがいま仏にしたがって聞くところは、やがてまためぐって「転次に決を受けるであろう」というのであるから、「身心があまねく歓喜している」というのである。それがやがて、つぎつぎに巡って、このわたしが授記を受けるのであろう。それは、過去のわたしか、いまのわたしか、未来のわたしか、それとも他人のことかと思いまどうてはならない。それに「仏にしたがって聞いた」のである。他人から聞いたのではない。迷いか悟りかの問題でもない。また、それは衆生のことでもなく、草木国土のことでもなく、「仏にしたがって聞いた」授記というすばらしい事であり、そして、転次に決を受けるであろう」というのである。その転次というのは、けっして一隅にのみとどまるものではない。だからして「身心があまねく歓びにみちる」のである。その歓びは、必然、身体いっぱいに満ちあふれ、心のすみずみにまで行きわたるのである。さらにいえば、身はかならず心にゆきわたり、心はかならずに身ゆきわたるのであるから、身心にあまねしというのである。かくて、その歓びは世界にあまねく、四方にあまねく、身にあまねく、心にあまねく、まさに、特上にしてまじりけのない歓喜である。それは、疑いもなく、寝ても寤(さ)めても歓ばしめ、迷うにも悟るにも喜ばしめる歓喜であって、それぞれの人が身をもって知ることができるところであるが、それでいて、それぞれの人に関わりのない純粋な歓喜である。その故にこそ、「転次に決を受ける」という、素晴らしい授記のことがなるのである。(62~63頁)
■そこでは、一句一偈を聞いて、たちまちに歓喜の心をもよおす。そういう聞き方をするのがよいのである。さらに皮肉骨髄のことを考えているような暇はないのである。ただ、無上の智慧にいたるであろうとの授記を与えられたならば、それでわが願いはすでに満たされたのである。そう考える人がよいのである。また、それでみんなの望みも充たされるのである。そのように受領するのがよいのであろう。かっては、松の枝をもって授記したこともあり、優曇華をもって授記したこともある。あるいは、瞬目(しゅんもく)をもって授記し、破顔をもって授記したこともあるし、また、皮の鞋(くつ)を与えて授記した先例もある。そうしたことは、すべてこのことが、思量分別のよく解するところではないからであろう。さらにはまた、「わが身はこうだ」との授記もあり、「汝の身はこうだ」という授記もある。そのいう意味は、授記がよく過去・現在・未来の三世にわたるものであることを語っている。それは授記における過去・現在・未来であるから、あるいは自己の授記として実現し、また他己の授記として実現するのである。(67~68頁)
〈注解〉四部・八部;四部は四衆。比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷(うばい、女性の在家仏教者)をいう。八部は八部衆であって、さきの天・龍王以下の八種の異類である。
我身是也・汝身是也;「わが身はこれなり」「汝の身はこれなり」と読まれる。それは、六祖慧能が南嶽懐譲に「我亦如是、汝亦如是」との授記を与えたことを指しているのであろう。(68頁)
■維摩詰は、弥勒菩薩にいった。
「弥勒よ、世尊がそなたに記を授けて、一生にまさに最高の智慧を得るであろうと仰せられたのは、いったい、いずれの生をもって授記を得たというのであるか。過去であるか、未来であるか、それとも現在であるか。もし過去の生(しょう)というならば、過去の生はすでに滅した。もし未来の生というならば、未来の生はまだ至らない。またもし現在の生といわば、現在の生はとどまるところがない。仏の説きたまうところによれば、比丘よ、汝のいまの時は、あるいは生、あるいは老、あるいは滅である。もし無生(むしょう)にして授記をうるといわば、無生はすなわち正しいありかたである。だが、その正しいありかたのなかには、また授記もなく、最高の智慧を得るということもありえない。いったい、弥勒よ、そなたが一生の記を受けたというののは何であるか。真実の生によって授記を得たというのか。それとも真実の滅によって授記を得たというのであるか。もし真実の生をもって授記を得たというのであるならば、真実には生があるはずはないのであり、もし真実の滅によって授記を得たとするならば、真実の境地には滅はないのである。生きとし生きる者はみな真実であり、一切の事どももまた真実である。あるいは、もろもろの聖者賢者もまた真実であり、弥勒にいたるまでみな真実である。したがって、もし弥勒が授記を得るならば、生きとし生ける者もまた当然授記するはずである。その故いかんとなれば、真実は二つならず、異らざるゆえである。だから、もし弥勒が最高の智慧を得るならば、生きとし生ける者もみなまた最高の智慧を得るであろう。その故はいかにといわば、生きとし生ける者はみなさとりの印相(しるし)をまとうているからである」
いま維摩詰がいうところは、如来もこれを間違いとはいうまい。しかるに、弥勒が授記のことはすでに定まっている。したがって、一切衆生が授記のことも、また同じく決定(けつじょう)であろう。けだし、もし衆生の授記がなかったならば、また弥勒の授記もありえないはずだからである。すでにいうがごとく、「生きとし生ける者はみなさとりの印相(しるし)をまとうている」のである。そもそも、授記というものは、今日ここにある衆生と諸仏の智慧のいのちである。だから、一切の衆生もまた、弥勒とともに発心するのであるから、またともに授記するのであり、ともに悟りを得るのである。
だが、しかし、維摩がいうところの「正しいありかたのなかには、また授記もない」というのは、正しいありかたがすなわち授記であることを知らないようである。それは「正しいありようがすなわち悟り」だといいえないとするのと同じことではないか。また維摩は、「過去の生はすでに滅した。未来の生はまだ至らない。現在の生はとどまるところがない」などという。だが、過去はかならずしもすでに滅したのではない。未来はかならずしもいまだ至らないわけではない。あるいは、現在はまたかならずしも住(とど)まらないわけでもない。住(とど)まらないもの、まだ至らないもの、すでに滅したもの、それが現在であり、未来であり、過去あるとまなんできたのであろうが、そこは、さらに一歩をすすめて、さらに、いまだ至らない未来が、それがそのまま過去であり現在である道理もまたいいうるのでなくてはなるまい。
とするならば、生においても滅においても、ともに授記があってよい道理である。滅にあっても生にあっても、ともにさとりを得ることがあってよいはずである。そして、一切の衆生が授記をうる時、そのとき弥勒もまた授記をうるのである。では、かりに一つ維摩に問うてみよう。
「いったい、弥勒と衆生とは、同じなのか別なのか。こころみに答えてみよ」
すでにさきにいうように、もし、弥勒が授記を得るならば、生きとし生ける者もまた授記を得るだろうという。もし弥勒が衆生でないというならば、衆生は衆生ではないし、弥勒は弥勒ではないであろう。どうでござる。そして、まさにここにいたれば、維摩もまた維摩ではないであろう。もしも維摩でないのならば、そなたのいうことはなんの役にも立たないだろう。
かくいうことができるであろう。授記が一切衆生をあらしめる時、一切衆生もまた弥勒もあるのである、と。つまり、授記はよく一切をあらしめるのである。(71~73頁)
〈注解〉維摩詰;在家仏教の経典としての『維摩詰所説経』の主人公である。在家として、菩薩の行を修し、究極地をきわめた人物という想定である。
弥勒;『弥勒経』の主人公であり、「一生補処(ふしょ)」の菩薩として知られる。つまり、この一生において記をうけ、次世には釈迦仏の処を補うと信じられているが、いま維摩は、その一生を問題としているのである。
無生;生滅をはなれたありようをいう。つまり「生滅滅已」の境であって、涅槃がそれであるとする。
如;存在のあるがままのすがた。それが真実であり、実相であるとするのが仏教の真理観である。
授決;授記である。記をしばしば決と表現する。(74頁)
観 音 ( かんのん )
■開 題
この一巻が制作されたのは、仁治三年(1242)四月二十六日のこと。例によって興聖宝林寺においてしるしたものであろう。すでにいうがごとく、この年の四月には、「行持」の巻より、この「観音」の巻にいたるまで、じつに四巻が制作されているが、そのなかにおいて、この一巻のみが衆に示されているのは、なんといっても、その主題がポピュラーであることにもよるところがあったであろうか。
さて、観音とは、一応整理しておいたがよいであろうが、もと“略”(音写すれば、阿縛慮枳低湿伐羅(あばらきていしゅばら))の訳語であるが、いわゆる旧(く)訳と新訳とによって、その訳語にも、その理解にも、ややニュアンスのちがいが存している。旧訳においては、その訳語は、観世音であって、略して、また観音とする。したがって、観世音とは、よく世の人々の救いを求める声を聞いて、直ちに赴いて救済の手をのべたもう菩薩といった考え方がつよい。それに対して、新訳においては、その訳語は、観世自在、もしくは観自在である。そこでは、一切諸法の観察はいうまでもないこと、また、世の人々のありようを観察すること自在にして、そのありように応じて自由に慈悲を行じたもう菩薩という考え方が前面に出てきている。つまり、同じく大衆の救済を志向しながらも、聞(もん)より見(けん)にその重点が移ったとでもいうことができようか。
しかるに、これまで、仏祖先徳によって、観音について語られたおびただしいことばの存するなかから、いまここに道元がとりあげるものは、ただひとつ、雲巌(うんがん)と道吾(どうご)の対話である。その理由について、道元は、その奥書にはっきりといっておる。
「いま仏法の西来よりこのかた、仏祖おほく観音を道取すといへども、雲巌・道吾におよばざるゆえに、ひとりこの観音を道取す」
その二人の対話は、すでにこの一巻の冒頭にくわしく記され、かつ、この全巻にわたってくわしい注釈がほどこされているのであるから、もはや、わたしの冗舌を加える余地もないところであるが、ただ一つ、では道元は、この二人の対話が語る観音論が、どの点において余地の仏祖たちのそれに勝るとするのかというならば、それは、その対話がみごとに観音の性と相、つまり、今日の表現をもっていうなれば、観音の本質とその作用をいい得ているというのである。それを道元は、こんないい方をしている。
「たとえば、余仏のいう観音は、ただ十二面であるが、雲厳はそうはいわない。あるいは、余仏のいう観音は、おおよそ千の手眼(しゅがん)があるとするが、雲巌はそうはいわない。また、たとい余仏のいう観音が八万四千の手眼があるといったとしても、雲巌のいい方はそれともちがう」
では、どうちがうというのか。それはもう、その対話のはじめに、雲巌が、「大悲菩薩は、眼のある手をあまたもっておられるが、どうするのですか」という、その問いの構造のなかにはっきりと打ち出されているとする。
大悲の菩薩ということばは、観音の本質を表現することばである。そして、手眼の菩薩を語るときには、そのいとなみをこそ表現しておるのである。だから、雲巌はただ「許多の手眼」つまり、あまたの手眼としかいわない。それを、なにごとぞ、ただ十二面だとか、三十三身とか、千手眼だとか、そんな形状にのみとらわれている観音の考え方は、とうてい「雲巌・道吾におよばず」というのである(76~78頁)
■雲巌の無住大師が、道吾山の修一(しゅいつ)大師に問うていった。
「大悲菩薩は、眼のある手をあまたもっておられるが、どうするのですか」
道吾はいった。
「ひとが夜背なかに手をやって、枕をさぐるようなものだ」
雲巌はいった。
「ああ、わかった。わかった」
道吾がいった。
「そなた、どんな具合にわかったというのだ」
雲巌はいった。
「からだじゅうが、あまねく眼のある手なのでしょう」
道吾がいった。
「いうことは、なかなかいいよるわい。ただ、それでは八九分どおりいい得たところだ」
雲巌はいった。
「それがしは、まあ、そういうところですが、では、兄弟子は、どんな具合に仰せられる」
そこで道吾がいった。
「からだじゅうが、すべて眼のある手なのだ」
観音を語ったことばは、むかしから今まで、あれこれと沢山にあるけれども、いずれもこの雲巌と道吾の問答にまさるものはない。観音についてまなぼうと思うならば、いまの雲巌・道吾のことばを研究してみるがよい。
いまいうところの大悲菩薩というのは、観世音菩薩のことであり、また観自在菩薩ともいう。諸仏の父母ともいうべき菩薩であって、まだ得道しない、仏よりも以前の存在だと学んではならない。過去には正法明(しょうぼうみょう)如来であられたのである。(82~83頁)
■しかるに、いま、道吾が「ただいい得ること八九分のところか」ということばを聞いて、それは、十分にいわねばならぬところを、よくいい得るにいたらずして八九分どおりというのかと受取るものが多い。もし仏法がそんなものであるならば、とても今日にまでも続いているはずはない。いうところの八九分どおりというのは、百千といってもよいのである。「あまた」というところだとまなぶべきである。すでに八九分といっているのだから、それはもう八九分にはとどまらぬはずである。それが判らなければいけない。仏祖たちのことばは、そのようにまなびいたるべきものなのである。
すると雲巌は、「それがしは、まあ、そういうところですが、兄弟子は、では、どう仰せられます」よいった。道吾が「八九分どおりいい得たところだ」というのであるから、雲巌もまた「ただ、かくのごとし」というのである。それは、わが跡をとどめずというところであるが、それでいて、そのいわんとするところは、ちゃんといい得ているのである。いましがた自分のいわんとしたことを、いわないままで差し控える時には、「それがしは、ただ、かくのごとし」などとはいわない。
すると道吾は、「からだじゅうがすべて、手眼なのだ」といった。いうところの意は、手眼があそこにもあり、ここにもあって、それで「からだじゅう」というのではない。そうではなくて、「からだじゅう」がすべて手眼であるのを、「通身これ手眼」というのである。
ということは、身体がそのまま手眼であるということではない。だから、「あまたの手眼をもって」という。手と眼を用いることがさまざまであるならば、その手眼は、どうしても「通身これ手眼」でなくてはなるまい。だから、もしも、「あまたの身心(しんじん)をもって、それをどうするのだ」と問うときには、「通身これいかに」といってもよいであろう。ましてや、雲巌が「遍」といい、道吾は「通」といったが、それらはいずれも美事にいい得たるものであって、かの「あまたの手眼」をいうには、それぞれそのような表現があってよいであろう。
それなのに、釈尊の説きたまう観音は、たいてい千手眼(しゅげん)であり、十二面であり、あるいは三十三身といい、あるいは八万四千の相好(ごう)があるという。そして、いま雲巌・道吾の語る観音は「あまたの手眼」をもつという。だが、よくよく思いみれば、それらはすべて多い少ないをいったものではない。とするならば、この雲巌・道吾のいう「あまたの手眼」ある観音をまなびいたれば、すべての仏もまた、観音の三昧の境地を、ほぼ八九分どおり成就することを得るであろう。(94~95頁)
阿 羅 漢 ( あ ら か ん )
■開 題
この一巻が、制作せられ、そして衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の夏五月十五日のこと、いつもの通り、宇治の興聖宝林寺においてのことであった。五月雨(さみだれ)の季節にはいって、ようやく雨もよいの日々がつづいていたであろうと察せられる。
この一巻はごく短いものであるが、わたしには、いささか興味をそそられるものが存する。なんとなれば、阿羅漢とは、よく知られているように、いわゆる小乗仏教の聖者をいうことばである。パーリ語でいえば“arahant”,サンスクリットでは“arahat”,それを音写して阿羅漢となし、それを意訳して応供(おうぐ)となす。修学すでに成って、またまなぶべきところなく、世の供養を受くるに応(あたい)する位にいたれる者というほどの意である。つまり、世の供養に応(あたい)するから応供(おうぐ)であり、既にまなぶべきところがないから無学位とて、これを、四果すなわち仏道修行の四つの段位の最高位として揚げるのが、小乗仏教の考え方である。
それに対して、大乗仏教のよってたつ立場は、阿羅漢道を批判して、あらたに菩薩道をたてるところにあるとするのが、世のつねにいうところである。とするならば、いったい、いま道元はこの巻題を揚げて、その間のずれをいかに処理するのであろうか。あるいは、阿羅漢そのものに対して、いかなる評価を付与しようとするのであろうか。それが、わたしの、いささか興味をそそられる点であったのである。
だが、いま道元は、阿羅漢という名字をも、その考え方をも、けっして却(しりぞ)けない。それをもって、「名づけて仏地(ぶつじ)となす」のが、まさしく「仏道の通軌(つうき)」であるとする。
「阿羅漢を称して仏地とする道理をの参学すべし、仏地を称して阿羅漢とする道理をも参学すべきなり。阿羅漢果のほかに、一塵一法の乗法あらず、いはんや三藐三菩提あらんや」
そのいうとこらは、阿羅漢の実現する境地を描いて、このほかに仏教の究極とするところはないということであり、それこそが仏地すなわち仏の境地であり、それこそが阿耨多羅三藐三菩提を志求(しぐ)するゆえに」
である。まさしく仏道は無窮である。最高の智慧の追求には窮(きわ)まるところはなく、したがってまた、阿羅漢の追求にもまた窮まるところがあろうはずはないとする。
そこまでいたった時、ふるい小乗仏教の聖者としての阿羅漢の面目は、そのままにして、まったく新しい大乗仏教の光のもとに齎(もたら)されて燦(さん)として輝く存在となる。もはや、それは枯木寒巌のごとき存在ではない。いまや、それは、あくまで最高の智慧を追求し、精魂をかたむけて打坐(たざ)しているのであり、あるいはまた、いまも昔も、師と弟子とがたがいに機に投じて、破顔しまた瞬目しているのである。いま道元がその瞼のうちにえがくものは、そのような阿羅漢のすがたなのである(100~102頁)
〈注解〉漏;煩悩をいう。
第四果;小乗の修行の段階を、預流果、一来果、不還(げん)果、無学果とたてる。その第四果はその最高の段階であって、また阿羅漢果という。(105頁)
栢 樹 子 ( はくじゅし )
■開 題
この一巻が制作せられたのは、仁治三年(1242)の五月二十一日のこと。例によって興聖宝林寺において衆に示された。奥書の日付に「五月菖(しょう)節二十一日」と見えているのは、雨にぬれる菖蒲のすがたをでも眺めてであろうかと思わせられることである。
さて、巻頭にみえる「栢樹子」の栢は、柏の俗字であって、ふるい語録などには、「柏樹子」でみえている。その柏は、いうまでもない、「かしわ」であって、わたしどもにも親しみ深い木である。だが、それにも増して、わたしども仏教者にとってよく知られているのは「庭前(ていぜん)の栢樹子」の一句である。それがこの一巻の主題であることは申すまでもない。
だが、道元がまず語りいずるところは、その有名な公案のことではなくて、それを打ち出した趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)その人の行履についてである。そして、あまり長からぬこの一巻の三分の一をこえる分量を、まずその行履を語ることにあてているのである。おそらく、道元は、よほどこの仏祖に心を寄せていたものと思われる。そのなによりの証拠には、道元はそのくだりにおいて、古仏ということばを趙州のために二度まで用いている。古仏ということばは、道元が仏祖を語る場合に、その最高の表現として用いることばであって、滅多なことでは用いていないのである。
わたしも、もともと、この仏祖の自由闊達なことばに、ひそかに心を惹かれていたのであるが、いま、道元が語る趙州の行履を訳するに当たって、その心持ちのいよいよ新たなるものを感じたことである。なかでも趙州の「十二時の歌」と称されるもののうち「辰の刻」(いまの午前八時ごろ)すなわち食事のことを歌った詩を訳していて、わたしはなにか身震いするようなものを感じた。その原文は、訓読すればこう読まれる。
「烟火徒労にして四鄰を望む
饅頭(食ヘンに追)子(たいす)は前年に別れたり
今日思量して空しく津(しん)を嚥(の)む
持念すくなくして嗟歎(さたん)しきりなり」
「米なくむなしく四隣の炊煙をながむ
饅頭・団子はすでに前年に別れたり
今はただ思いいでてつばきを呑む
嗟歎しきりにして法を念(おも)うはまれなり」
それは、一見して洒脱をきわめる詩であるが、わたしはそれを訳しているうちに、これは到底、洒脱とか闊達とかといって済ませることのできないものであることを感ぜしめられた。なにか、その底には、身震いするような凄いものが蔵せられているのである。そして、趙州従諗(しん)とは、そのような古仏であったにちがいないと思う。
では「庭前の栢樹子」ということばも、「栢樹仏性」と問答も、いまはただ、古仏が古仏のことばを解説するままに、推し頂くのほかはあるまいと思う。(118~119頁)
■趙州真際(ざい)大師は、釈尊より数えて第三十七世である。六十一歳にしてはじめて発心し、出家して仏道を学んだ。その時、彼は誓うていった。
「たとい百歳であろうとも、もし彼がわたしよりも劣っているならば、わたしは彼をおしえよう。たといわずかに七歳であろうとも、もし彼がわたしよりも勝れているならば、わたしは彼におしえを乞うであろう」
そのような誓いをたてて、南のかたに旅し、道を求めているうちに、南泉にいたって普願和尚を拝した。その時、南泉は方丈にあって横になっていたが、趙州がやってきたので問うていった。
「どちらからおいでじゃ」
趙州はいった。
「瑞像(ずいぞう)院からでございます」
南泉はいった。
「では瑞像は見たかなあ」
趙州はいった。
「瑞像は見ませんでしたが、横になった如来を見ました」
そこで、 南泉は身をおこして問うていった。
「そなたは、いったい、誰ぞ師によって得度した沙弥(しゃみ)か、それとも師はないのか」
趙州は答えていった。
「師について得度いたしました」
南泉はいった。
「では、そなたの師はどなたじゃ」
趙州はいった。
「まだ春のはじめで寒うございます。伏しておもんみれば、尊体には御機嫌うるわしゅう存じあげます」
そこで南泉は、維那(いのう)をよんでいった。
「この沙弥をしかるべくとりはからえ」
そのようにして、趙州は、南泉に身を寄せることとなり、さらに余処に赴くことなく、そこで修行すること三十年におよんだ。その間、寸陰をもむなしゅうすることなく、雑事にかかわることもなかった。ついに、南泉の法を嗣いでからのちは、趙州の観音院に住すること、また三十年におよんだ。その住持としてのありようは、世のつねの諸方の住持どもとはまったくちがっていた。
ある時には、趙州はこんな偈を説いたこともあった。
「米なくむなしく四隣の炊煙をながむ
饅頭・団子はすでに前年に別れたり
今はただ思いいでてつばきを呑む
嗟歎(さたん)しきりにして法を念(おも)うはまれなり
近くの村びとにも碌なやつはなく
来る者はただ茶を飲みにきたという
茶をのんで食うものがなければまたぶつぶつとぬかす」
かわいそうに、飯をたくことも稀であり、おいしい物はむろんすくない。饅頭や団子は前年にたべたきりだという。近隣の村びとがくるのは茶をのみにくるだけである。だから、茶をもって来るもの(入門するもの)は、その辺りの者ではあるまい。彼らは賢者をもとめる雲水であるが、この趙州のなりたいと思うものはあるまい。
その趙州は、またある時、偈をなしていった。
「ひそかに天下の出家人を思いみるに
わが住持のごときはいくばくかある
土の寝(ね)台にやぶれた粗竹をしいて
楊(やなぎ)を編んだ枕には被(おお)いものもない
尊像のまえには焚(た)くべき香もなくて
牛糞のにおいのみがただようている」
この表現をみただけで、その寺の暮しがいかに貧しいかがよく判るのである。その暮しかたをよくよくまなぶがよいのである。とどまる僧たちも多くはなく、二十人に満たないというのは、このような行き方がむつかしいからである。僧堂も小さなもので、前架・後架のわかちもない。夜のあいだも灯火がなく、冬になっても炭火もない。ふとみれば、かわいそうな趙州の老後のくらしであるが、これこそ古仏のみさおというものである。
また、ある時のこと、僧堂の床几(しょうぎ)の脚がおれたことがあった。すると趙州は、もえさしの材をそえ木として、縄でしばって、いつまでもその儘にしておいた。知事の役の僧が、あれは取りかえたいと申しあげたが、趙州はそれを許さなかった。まったく世にもめずらしい事である。
日々の生活は、朝めしも昼めしもまったく米粒のみえない粥ばかり、ただ空しく窓に対して坐し、隙間風にさらされるばかりであった。時には、木の実をひろうて、自分も雲水も、それを日用の糧(かて)にあてはまることもあった。いまの後進者たちが、かの師の行履を讃(ほ)めたたえるのは、とてもその行履には及びもつかないが、せめて古をしたう心ばえをというのであろう。
また、ある時には、衆(しゅ)に示してこのように語った。
「わしは南方にあること三十年、ただ一筋に坐禅した。なんじたちも、この一大事を成しとげたいと思うならば、理を究めて坐禅してみるがよい。三年・五年・二十年・三十年とそうしたならば、道を得ないということはない。もし得なかったならば、わしの首をとり、その髑髏を柄杓にして、小便を汲むがよろしい」
趙州はそのように誓ったが、まことに坐禅によって道をもとめることこそ、仏道の直路というもの。まさに理を究めて坐禅するがよろしい。
のちに、人々は「趙州は古仏である」といったことである。(124~128頁)
〈注解〉趙州真際大師;趙州従諗(897寂、寿120)。南泉普願の法嗣(ほっす)。趙州の観音院に住した。諡して真際大師と称する。
南泉;南泉普願(834寂、寿87)。馬祖道一の法嗣(ほっす)。池陽の南泉山に住す。
沙弥;出家してまだ比丘とならぬ小僧をいう。有主・無主は師のありやなしやを問うのである。
維那;寺中にあっていろいろの事務をつかさどる役名をいう。
前架・後架;僧堂にて、前架は役僧の坐席、後架は雲水の坐席をいう。(125頁)
■趙州の真際大師に、ひとりの僧が問うていった。
「いったい、祖師が西の方から来られたのは、どういう意(こころ)でありましょうか」
趙州がいった。
「庭前の栢樹子じゃ」
僧はいった。
「和尚よ。外境をもって人にしめしてはなりませぬ」
趙州がいった。
「わしは、外境をもって人に示しはしないよ」
僧はいった。
「では、いったい、祖師が西の方から来られたのは、どんな意(こころ)でありましょうか」
趙州がいった。
「庭前の栢樹子じゃ」
この一則の公案は、趙州から始まったものであるが、突きつめてみれば、もろもろの仏たちがその全身をもって成しきたったところであって、誰のことばというべきものでもないのである。
ついては、まず知らねばならぬことは、いま「庭前の栢樹子」というのは、外境を語ったものではないということである。また、かならずしも自己を語ったものでもないのである。祖師が西来の意味は、けっして外境にもまた自己にも属するものではないのである。だから、「和尚は外境をもって人に示すべきではない」というのであり、また、「わしは外境をもって人に示しはしない」というのである。
いったい、いずれの吾だって吾であってよいのだから、吾もまた人でなかろう道理はない。だが、外境の問題となると、それはどうしても西来の意(こころ)に関わってくる。西来の意をほかにして、その外境はありえないからである。だからといって、外境があってはじめて西来の意が起こるというものでもなく、また、祖師の西来の意は、かならずしも正法の眼目とするところ、涅槃のふしぎな心というわけでもない。それはただの心でもなく、ただの仏でもなく、また、ただの物でもないのである。
いまかの僧が「祖師が西の方から来られたのは、どういう意(こころ)であろうか」といったのは、ただの問いばかりではない。だからといって、師も弟子もともに判っているというわけでもない。いったい、こういう問答の時は、向うもまだはっきりと判っていないし、こっちもまたどれほど判っているかというところである。事がめんどうであるから、ずばりと矛盾をこえて裁断するのである。「虚を承(う)けて響きに応ずる」とでもいうところであろうか。是も非もこえてずばりといってしまえば、「庭前の栢樹子」ということになる。それが外境のものでなくっては、栢樹子であろうはずはない。だが、たとい外境であっても、「わしは、外境をもって人に示しているのではない」のであり、「和尚は外境をもって人に示してはならない」のである。
思うに、その柏樹子は、古祠(こし)の栢樹子ではない。古祠のそれではないから、そのうちに枯れてゆくであろう。枯れてなくなるとすれば、またわが工夫が必要となってくる。だが、工夫がいるということは、「わしは外境をもって人に示してはいない」証拠である。では、今度はなにをもって人に示せばよいかというなれば、今度は「吾もまたかくの如し」とでもいおうか。(130~133頁)
〈注解〉境;人の認識作用の対象をいう。外界であり、外境である。
公按;もと「公布の案牘(とく)」の意のことばであるが、それによって、仏祖のことばを求道者に与えて工夫させる一定の問題をいう。さだまれる問題というほどの意であろう。
古祠;思うに古祠とは、孔子廟のことであろう。そこには、二十四株の柏があって、犯すことを禁じていたので、永年にわたって保存せられたという。いま庭前の栢樹は、そうでないとするのである。(133頁)
■趙州(じょうしゅう)の真際(ざい)大師に、またひとりの僧が問うていった。
「栢樹もまた仏性がありましょうか、どうか」
趙州はいった。
「有り」
僧はいった。
「では、栢樹はいつ仏となるのでありましょうか」
趙州はいった。
「虚空が地に落ちるのを待ってである」
僧はいった。
「では、虚空はいつ地に落ちるでありましょうか」
趙州はいった。
「栢樹子が仏になるのを待ってである」
いまの趙州のことばをよく聴き、またかの僧の問うところも捨てないがよろしい。いま趙州がいう「虚空が地に落ちる時」というのと、「栢樹が仏になる時」というのとは、たがいに関連したことをいっておるのではない。いまかの僧は栢樹を問い、仏性を問い、成仏を問い、時節を問うているのである。あるいは、虚空を問題とし、また、その地に落ちることを問題としているのである。また、趙州がかの僧に答えて、「有り」といっておるのは、「栢樹に仏性あり」というのである。そのことばをよくよく理解して、仏祖のいのちとするところに通暁(ぎょう)しなければならない。
いったい、栢樹子に仏性があるなどとは、世のつねにいい得ないことであり、いまだかっていわれたことはないのである。だが、いまやそれはぶっしょうがあるという、そのありようをはっきりと知らねばならない。では、栢樹には仏性があるとして、その仏性が果(み)をむすんだ時には、どんな仏になるのか。また、その寿命の長短や、身長の大小はいかに。あるいは、その種類もまたききたい。さらには、たくさんの栢樹がああるが、みんな同じ種族であるか、それとも別種のものもあるのか。さらにまた、仏となる栢樹のほかに、修行する栢樹もあり、発心する栢樹もあるのであろうか。それとも、栢樹には成仏の事はあっても、修行や発心のことはないのであろうか。さらにはまた、栢樹と虚空とは、どんな関係があるのか。栢樹の成仏は、かならず虚空が地に落つる時を待つというのは、栢樹の功を樹(た)てるのはかならず虚空におうてだというのであるか。とするならば、栢樹の位置すべきところは、虚空の初位なのか最上位なのか、それらのことも、審(つまび)らかに思いめぐらしてみるがよい。
そこで、わたしは、ひるがえって老いたる趙州に問うてみたい。「あなたもまた一本の枯れ栢樹でござるなれば、そのような事どもを経てこられましたか」と。いったい、栢樹に仏性があるなどとは、外道や小乗の輩(やから)の考えうるところではなく、また、経・論の研究にのみ没頭している学者などの見聞しうるところでもない。ましてや、枯木寒岩(こぼくかんがん)のやからのことばにそんな花の咲こう道理はない。ただ趙州の同類どものみが、よくこのことを学びきたり、追求しいたることができるのである。
いま趙州は栢樹に仏性があるといった。だが、栢樹といえば栢樹にこだわり、仏性といえば仏性にひっかかる。かくて、この表現は、だれでもすぐ判るといったものではない。仏法をまなぶ人々でも、かならずしもこのことばを究めつくすことはむつかしい。たといもろもろの仏たちだって、それをいい得る仏もあり、いい得ない仏もあるというものである。
そこで趙州は、「虚空が地に落つる時を待つ」といったが、それは、あり得ないことをいうのではない。栢樹子が仏となる度ごとに、虚空が地におちるのである。その響きは、百千の雷(らい)よりもはげしい。その栢樹が成仏する時は、いちおうこの世の十二時のなかのそれであるが、またそれはこの世ならぬ時でもある。その地に落ちる虚空というのも、この世の人々のみる虚空のみではない。そこには、もう一つの虚空があるが、それは余人の見ざるところ、ただ趙州ひとりの見るところである。また、虚空が落ちるところの地というのも、この世の人たちの住む地ではなくて、そこには、もう一つの地がある。それは、光も闇もいたらぬところ、ただ趙州一人の到るところである。そして、虚空が地に落ちる時には、たとい日月でも山河でも、ともに落ちざるはないであろう。
では、いったい、仏性あるものはかならず成仏するといったのは誰であるか。そもそも仏性とは、仏となって以後にい得ること。せいぜいのところ、成仏とともに生ずる仏性もある。そこは、いうなれば、なんぞ必ずしも然(しか)らんやというところであろうか。では、いったい、それをどういったらよいものか。(136~139頁)
〈注解〉初地・果位;菩薩修行の五十二位のなかで、第四十一位より五十位までを十地という。その第一位、歓喜地(かんぎち)を初地という。それに対して果位とは、さとりの位であって、これを究竟(くきょう)位とする。ただし、ここでは、栢樹が成仏するのは、虚空のどの辺でかといっているのであって、べつに五十二位に関係はあるまい。
枯木死灰;小乗の聖者の非活動的境地をいうに、枯木といい、灰心といい、滅智といい、あるいは寒巌という。いまは、枯木寒巌と訳しておいた。
仏性は成仏以後の荘厳;仏性とは、仏となって以後にいい得ることというほどの意である。その点において、道元はあきらかに、「一切衆生、悉有仏性」というところを、そのままに受けとっていない。その仏性についての道元の所見は「仏性」の巻につまびらかである。(140頁)
光 明 ( こうみょう )
■開 題
(前略)道元は、まず、その冒頭に長沙景岑(ちょうしゃけいしん)のことばをあげる。そこでは、かの師は「仏祖の光明」について語っているようである。この「十方世界のことごとく」がすべて、仏祖のまなこであり、仏祖のことばであり、仏祖の全身であり、仏祖の光明ならざるはないというのである。それは、けっして、単なる象徴的なことばではないのであるから、それをまずつぶさにまなびいたらなければならない、と道元はいう。
ついで、道元は、雲門文偃(ぶんえん)のことばをあげて語る。それによって道元がいわんとするところは、そのような光明を有するものは、けっして仏祖のみの限ったものではないということである。
「人々ことごとく光明の在るあり」
だが、
「見ようとしても見えない。なんにも判らない。では、いったい、人々に光明があるとはどういうことだ」
それは、雲門が高座から衆にむかっていったことばであった。だが、僧たちは、誰も答えるものがなかった。すると、雲門がみずから代わって答えていった。
「僧堂・仏殿・庫裡(くり)・山門じゃ」
わたしは、その雲門の一句にたいへん心を惹かれる。だが、それはどういうことかと問われるならば、むろん、わたしにも説明することはできない。かくて、道元がこの巻末にしるす奥書の一句が、ふしぎな雰囲気をまとうて生きてくるのである。
「時に、梅雨は霖々として降り、軒端の雨だれは滴々として已まぬ。いったい光明はいずこにかある。やはり人々は雲門のことばに教えられねばならないものであろうか」(143~144頁)
■いうところの仏祖の光明とは、十方の世界のことごとくがそれである。すべての仏、すべての祖がことごとく光明である。仏と仏とがすべて光明なのである。仏が光であり、光が仏である。つまり、仏祖は、仏祖を光明としているのである。この光明を修行して、仏となり、仏として坐し、仏を証(あか)しするのである。その故をもって「この光は東方の一万八千仏土を照す」というのである。このことばそのものがすでに光明である。「この光」というは仏なる光である。「東方を照す」とは、東方はすなわち光のあるところだからである。東だ西だという方角の俗論ではない。それがもろもろの存在の世界の中心なのである。拳(こぶし)の中央なのである。つまり、ことばの上では東方というけれど、まことはそれは光明の幾分の一かにすぎない。だから、この世界にも東方があり、他の世界にも東方があり、さらには東方にも東方があることを学ぶがよろしい。
また「一万八千」というのは、万とはいえど、拳の半分ぐらいのもの、心の半分ぐらいのものである。かならずしも、いくつというわけではない。そもそも、仏土というものは眼睛のなかのことことである。それを、なんぞ、東方に照すということばを聞いて、なにか一条の白絹(しろぎぬ)が東の方にずっと渡っているかのように想像するのは、ほんとうの仏教の学び方ではない。十方の世界のことごとくが、ただ東方なのである。東方をもって十方の世界のことごとくを語るのである。かくして、そこに十方の世界のことごとくがあり、また、十方の世界と語ったことばが、一万八千の仏土と聞えてくるのである。(148~149頁)
〈注解〉長沙招賢大師;長沙景岑(ちょうしゃけいしん、生没年不詳)。南泉普願の法嗣(ほっす)。(140頁)
■一つ一つの光明が、さまざまの草まのである。さまざまの草である光明は、その茎もその葉もその花もその果も、その光の色はすべて他から与えられたものではない。いろいろさまざまの光明がすでにそこにあるのに、なにをまた光(こう)と説き明(みょう)と説こうぞ。いったい、どうして山河大地が忽然として生じたというのであるか。そこのところは、長沙がいうところの「十方の世界はことごとく自己の光明である」という表現をこそ、つまびらかにまなびいたるがよろしい。光明なる自己が十方の世界のすべてであることをまなびいたるべきである。
生まれ来り死して去るのも光明の去(こ)来である。凡をこえ聖(しょう)をこえるというも光明の色どりである。仏となり祖となるというのも光明の色彩のことに過ぎない。修行する証得するということがないわけではないが、それもまた光明のいたすところである。草木といい牆壁(しょうへき)といい、あるいは皮肉といい骨髄というも、すべて光明の赤きであり白きである。山水に霞たなびき、鳥とんで天にいたるも、みな光明のめぐらすところである。自己の光明を見聞するは、仏に値(あ)えるしるしであり、仏に見(まみ)えるあかしである。けだし、十方の世界のことごとくが自己であり、この自己こそは十方世界のすべてであって、もはやそれを避(よ)けて通る余地はありえない。たとえ避けてゆく路があるとしても、それはただ差別の世界をこえて彼方にいたるだけのことである。詮ずるところは、この髑髏(どくろ)をささえる七尺の身が、とりもなおさず全世界のすがたであり形である。仏道においていうところの尽十方世界とは、この独露・形骸(ぎょうがい)・皮肉・骨髄のほかはないのである。(154頁)
身 心 学 道 ( しんじんがくどう )
■開 題
この一巻が、興聖寺において制作され、衆に示されたのは、仁治三年(1242)の秋の重陽()ちょうようの節句、つまり九月のことであった。菊花くそい咲いて天日うららかの頃とて、来ってこの師の説法に耳を傾ける者もすくなくなかったことであろう。かの『建撕記(けんぜいき)』が、
「この深草寺は、皇城(こうじょう)に近ふして、月卿雲客(げっけいうんきゃく)、花(か)族車馬、往来耐えず」
と記しているのも、このころの興聖寺の繁昌ぶりをしるしたものであろう。
だが、このころの道元の心中は、かならずしもその秋天のように静かに晴れわたったものではなかったように、わたしには思われてならない。いまもいう『建撕記(けんぜいき)』はしるしていう。
「同(仁治三)年八月五日、天童如浄和尚語録はじめて至る。同六日上堂あり」(ただし『如淨和尚語録』の後序によれば、仁治二年二月中旬とあるが、それは相弟子の瑞巌義遠が書写して道元あてに送った日付でもあろうか)
そして、その上堂のときのことばには、つぎのような一句がしるしとどめられている。
「箇是天堂打ボツ跳、踏翻東海龍魚驚」(これはこれ天堂ボツ跳を打ち、東海に踏翻(とうはん)して龍魚おどろく)
ちょうどこの『身心学道」の巻のなかにも「ボツ跳」という語がみえている。ぱっと魚のはねるさまをいうことばである。先師如浄がなくなったのは、道元が告暇(こくか)したあくる年、紹定(じょう)元年(1228)のこと。それからもう十四年の歳月をけみしているのだが、いま、その先師の語録に接するにあたって、道元の心中のおどろきというか、目覚めというか、それはまさに察するに余りありというところである。それをいま道元は、東海の龍魚のおどろきをもって語っているのである。
ここに、そのようなことを敢えて挿(さしはさ)んでいうのは他でもない。この『身心学道」の巻は、その語録到来ののちの最初の制作であるからである。むろん、この一巻のなかには、別に際立ってその影を投じているわけではない。おそらくは、この一巻の構想は、その到来の以前になっていたものにちがいあるまい。東海の龍魚の驚愕がその果を結ぶためには、なお藉(か)すにもっと時をもってしなければならぬであろう。ただ、このころより以後しだいにあらわとなってくる道元の内的展開を理解するためには、この東海の龍魚のおどろきと目覚めは、その不可欠の要素であることを、ここにはっきりと言及しておかねばなるまい。
さて、この『身心学道」の巻の構想は、きわめて簡明である。学道とは、仏道をまなぶということである。その仏道のまねびを、道元はかりに二つに分って語ろうとするのである。その二つとは、いうまでもないこと、心をもって学することと、身をもって学することである。『身心学道」とは、その二つを併せたる巻題にほかならない。
ついで道元は、まず心学道について語り、さらに身学道について説明する。それでこの一巻はつきる。その二つの部分には、それぞれ道元が心を砕いて語る核心をなす問題がある。その一つは、心である。そのもう一つは、身である。
それをもっと具体的にいえば、心学道の部分においては、「山(せん)河大地・日月星晨これ心なり」との表現について注釈するのが中心であり、また、身学道を語っては、「尽十方界是真実人体」(尽十方界、これこの真実人体)ないし、「生死去(こ)来真実人体」の句について究(ぐう)尽することが主たる課題として語られている。とすると、心をもって学道するとは、また身をもって学道するとは、詮ずるところ、心をまなぶことであり、また身をまなぶことだといってもよいのであろうか。この一巻を訳しながら、わたしの胸中には、「仏道をならふといふは、自己をならふ也」というあの「現成公案」の一句が、しきりと明滅したことであった。(166~168頁)
■仏道は、行ぜざるには得ず、学ばざるにはうたた遠い。南嶽の大慧禅師はいった、「修行証得ということはないわけではない。ただ純粋でなくてはいけない」と。もし仏道をまなばなかったならば、外道や極悪なものの道に堕ちるであろう。だから、前の仏も後(のち)の仏もかならず仏道を修行するのである。仏道をまなび習うには、いまかりにいわば二つある。心をもってまなぶことと、身をもってまなぶことがそれである。
まず、心をもってまなぶとは、あらゆる心をもってまなぶことをいう。その心というものには、質多(しった)すなわち慮(おもんばか)る心があり、汗栗駄(かりだ)すなわち心臓の心があり、また矣栗駄(いりだ)すなはち要をあつめた心要をいう場合もある。また、仏と人の気持が相通じて、さとりを求める心をおこし、仏祖の大道に帰依して、求道(ぐどう)のことを学習するということもある。その時には、たといまだ真実の求道の心はおこっていなくても、すでにさきにその道を行じたもうた仏祖のあとに倣(なら)うがよい。それが菩提心をおこすというものであり、それが赤心というものであり、古仏の心というものであり、また、いわゆる平常心というものであり、三界一心というものである。
さらにいえば、それらの心をすべて打ち忘れて仏道をまなぶものがあり、また、とくに心を取りあげて仏道をまなぶものもある。だから、思量しながらまなぶものもあれば、また思量をすててまなぶものもある。あるいは金襴の衣を正伝しまた頂戴するということもある。あるいは、礼拝して位置に就いたとき、「汝はわが髄を得たり」とのことばを頂くということもあれば、あるいは、米を碓(つ)き、衣を伝えられて、心をもって心をまなぶということもある。(171~172頁)
〈注解〉南嶽大慧禅師;南嶽懐譲(なんがくえじょう、744寂、寿68)。六祖慧能の法嗣(ほっす)。南嶽の般若寺観音院に住す。(後略)
金襴衣……;仏祖と迦葉のあいだに行われた伝衣のことをいうのである。
碓米伝衣……;五祖弘忍と六祖慧能のあいだに行われた嗣法のことをいうのである。
色にかかる・空にかかる;物質の世界で考え、抽象の世界で考えられているというほどの意。古来、六欲天といい、四(し)無色界いえるものが、道元の頭にあるのである。有形の世界と無形の世界といってもといであろう。(175~176頁)
■菩提心を発(おこ)すという。その心は生死のことにあたって得ることもある。あるいは、涅槃に入りてこれを得ることもある。あるいはまた、生死や涅槃をほかにして得らるることもある。どんな場合とかぎったものではなく、発心と境涯とは関係はない。境によって発(おこ)るものでもなく、智によって発るものでもなく、ただ菩提心が発るのであり、あるいは、ただ菩提心を発すのである。だから、菩提心を発すということは、有でもなければ、無でもないし、善でもなければ、悪でもなく、あるいは、善悪いまだ定まらぬものでもない。また、それは、業によって報いられる境遇を因由として発るものではなく、天の住みびとはけっして発さないといったものでもない。ただ時期がきさえすればきっと菩提心を発すであろう。けだし、菩提心を発すことは、その住むところになんの関係もないからである。そして、まさしく菩提心を発したその時には、存在の世界はことごとくこの心を発すにいたる。そういえば、あたかもこの心がその住むところを転ずるように思われるであろうが、そのことは、その住むところの知るところではない。ただ、身心(しんじん)・住処がともに一本の手を出すのであり、ただ、おのずからにして手を出すのである。どんな輩(やから)のなかに住んでいようとも独立独歩の道をゆくのである。たとい、地獄・餓鬼・畜生・修羅などのなかにあろうとも菩提心を発すのである。
また、赤心片々という。片々とはきれぎれなるさまをいう。そして、赤心というものはすべて片々たるものである。一きれ、二きれといったものではなく、ただ片々としているのである。蓮の葉は団々として、そのまるきこと鏡に似ているし、菱の実の角は尖々(せんせん)として、その尖(とが)れること錐に似ている。だが、鏡に似ているとはいっても片々であり、錐に似ているとはいってもやはり片々である。
また、古仏心というのは、むかし一人の僧があって、大証国師に問うていったことがある。
「いったい、古仏心とはどういうことでありましょうか」
すると、国師は答えていった。
「牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)じゃ」
それによって知るがよい。それは、古仏の心が牆壁だ瓦礫だというのではない。また、牆壁瓦礫をもって古仏心だというのでもない。ただ、古仏の心というものは、このようにまなぶべきだというのである。
また、平常心というのは、この世界と他の世界をとわず、すべて平常心なのである。昔という日はここより去り、今という日はここより来る。去るときには天もことごとく去り、来るときには地もことごとく来る。これが平常心である。その平常心は、この家の内にあって開きまた閉じる。それが、いずれの門いずれの家においても、同時にして然るのである。だから平常心なのである。思うに、いまわたしどもは一向に気がつかないけれども、この天地の全体にはなにかことばがある。地から噴(ふ)き出してくる声のようなものがある。いや、ことばといえばことばであり、心といえば心であり、あるいは、法といえば法といってもよい。それは、人の寿命やその営みの生じまた滅するものであるから、聖者の境地にいたる以前のものにはすこしも判らない。判らないけれども、発心すればかならず悟りへの道につくことができる。すでにここにあるのであるから、悟りにいたるであろうことはなんの怪しむことがあろうか。とはいっても、現に怪しむ気持は発(おこ)ってくるが、それがとりも直さず平常というものである。(179~181頁)
〈注解〉生死涅槃;ここには生死と涅槃が対照的にとりあげられている。その場合には、生死とは、生死に束縛せられた迷いの境地をいい、涅槃とは、その迷いを解脱した究極安穏の境地を指す。
無記;善悪無記である。いまだ善とも悪とも決定しないことである。
赤心;まごころ。それを片々として語るのは、何ものにも纏(おお)われ、縛せられられない心だからであろう。
大証国師;南陽慧忠(775寂、寿不詳)。六祖慧能の法嗣(ほっす)。諡して大証国師と称する。(後略)(181~182頁)
■身学道というのは、身をもって仏道をまなぶのである。肉体をもってする学道である。いったい、身というものは学道によって得られるものであって、学道によって獲得されるものもまた身である。十方世界のことごとくが、それが一箇の真実の人体というのもそのことに他ならず、あるいは、生死去(こ)来のすがたこそまことの人のありようだというのもそれである。そして、その身体をもってして、よく十悪をはなれ、八戒をたもち、仏・法・僧の三宝に帰依し、あるいは家を捨てて出家する。それがまことの学道というものである。だから、そのすがたをもって真実の人体というのである。後より来りまなぶものも、けっして自然外道(じねんげどう)どもの邪見に同じてはならない。
かって百丈大智禅師はいった。
「もし、人は本来清浄にして、もともと解脱しているのであって、それがおのずから仏であるとか、あるいは、それがおのずから禅道なのだなどという見解に執する者があったならば、それは、とりも直さず自然外道の輩(やから)というものじゃ」
そのことばは、けっして、人なき家のやぶれ道具ではなく、まさに、学道において積みかさねてきた功徳というものである。そのありようをいわば、たとえば大魚の飛ぶ跳ねて八面玲瓏(れいろう)たるがごとく、あるいは万緑ことごとく脱落してなお藤の樹に依るがごとしともいうべきか。あるいはまた、古経における仏のことばをもっていわば、あるいはその身を現じ、得度して法を説くのであり、あるいは他の身を現じ、得度して法を説くのであり、あるいはその身を現ぜずして、得度して法を説くのであり、あるいは他の身を現ぜずして、得度して法を説くのであり、乃至はまったく法を説かぬのである。
しかるところ、その身を棄つるといいその命を捨てるというのは、いかにも矛盾したことに思われるであろうが、それは音をとどめるために声を揚げるがごとく、また臂(ひじ)を断って髄を得るようなものと知るがよい。たとい威音王仏(いおんおうぶつ)よりも以前に発心し学道したものであっても、これを「わが児孫なり」ということもあるというものである。
そして、尽十方世界というのは、十方みな世界だということである。十方とは、東・西・南・北、ないし北西・南西・北東・南東、上・下をいう。その表裏と縦横をことごとく尽した時にいうことばであると思量するがよい。思量するというのは、この人体はたとい自と他とにこだわらざるをえないものではあろうが、ともかくも尽十方だとあきらめ、決定(けつじょう)するのである。それがいまだ聞かざることを聞くというものである。けだし、十方ともに等しく、もろもろの世界もすべて等しいからである。そして、人体もまた四大・五蘊(うん)にほかならないが、その四大や五蘊の対象である六塵(ろくじん)は凡夫のよく究め尽すところではなく、ただ聖者(しょうじゃ)のみがよく究めいたるところである。
また、その対象たる客体の一つ一つについて、よくよく十方世界を観察するがよい。だが、そのいう意味は、一つの客体のなかに十方世界をおしこめてしまうことではない。それは、一つの客体をまなぶことによって、僧堂・仏殿がいかにして成るかがわかり、あるいは、僧堂・仏殿がいかにして成るかがわかれば、全世界がいかにして成るかがわかるのである。すべてはそのようにして成るのであり、成るというのはそのように成るのである。そこのところの道理が、とりもなおさず、尽十方世界は真実人体なりということである。けっして自然外道などのまちがった見解をまなんではならない。それは外界の量の問題ではないのであるから、広い狭いのことではない。つまり、尽十方世界というのは、ありとあらゆる説法のことであり、それを思い定めて動かざることであり、よく憶念して忘ぜらることである。
ありとあらゆる説法は、それはすべて仏の法輪を転じたまえるものである。その法輪の転ずるところは、いずれの世界にもわたり、またいずれの時にもわたる。だからとて、それはあてどのないものではない。そのあてどというのは真実人体である。まことの人間のありようである。そして、いまこの汝、いまこのわれこそが、尽十方世界なる真実人体なる人間である。そこを間違えないように仏道をまなぶがよいのである。
古来から、三大阿僧祇劫(あそうぎこう)といい、十三大阿僧祇劫といい、あるいは、無量阿僧祇劫というが、たといどんなにながいながい時間であろうとも、あるいは身をすて、あるいは身を受けながらも、絶えず仏道をまなんでゆけば、そこにかならず一進一退の学道がある。たとえば、師を拝して問いを呈する。それがそのまま学道のすがたに他ならない。あるいは、枯木のごとき境地を意図するものもあろう。あるいは、死灰のごとくならんと努力するものもあろう。それもまた暫時の間断もない学道である。月日のすぎゆくことは迅速であるが、学道はどこまでつづくか判らない幽遠なものである。家をすてて出家せるすがたはまことに蕭条(しょうじょう)たるものであるが、それを樵夫(きこり)とまちがえてはならぬ。あるいは、その生を支えるために力をつくすこともあろうが、それを小作人と同じとしてはならぬ。そこではもう、迷いを悟りの論でもなく、善だ悪だのの議でもない。邪正・真偽のほとりはすでに遠く超えているのである。
生死去(こ)来はまことの人間のありようだという。いわゆる生死は、凡夫の流転する境地であり、大聖(だいしょう)のすでに解脱するところである。だが、いまいうところの生死とは、凡夫と聖者の区別を超えたものであるから、それでこそ真実体とするのである。なるほど古経には、あるいは二種の生死を説き、あるいは七種の生死を語る。だが、究め尽してみれば、それらもすべてみな生死にあらざるはない。とするならば、それも必ずしも恐怖すべきものではないのである。なぜかとならば、人はまだ生をすてないのに、現にすでに死をみることができるはないか。また、いまだ死をすてないのに、すでに生をみることができるであろう。生はけっして死を碍(さまた)げるものではなく、死もまた生を碍げるものではない。その生と死の真相はいずれも凡夫の知りうるところではないが、そこを、あえて喩(たと)えをもっていうなれば、生はたとうれば一本の柏の木のようなものであり、死はたとうれば一塊ノの鉄人形のようなものである。そして、たとい柏の木が柏の木にさまたげられることがあろうとも、生はけっして死に碍げられることはない。だから、どこまでも学道につとめることができる。そもそも生に、あの生この生と、あまたの生があるわけではなく、死も二つあるわけではない。あるいはまた、死は生に相対するものでもなく、生が死と相待つものでもないのである。
圜悟禅師(えんごぜんじ)はいった。
「生もまたそのからくりはすべて明らかである。死もまたその機構はすべてあらわである。それぞれ大いなる虚空にいっぱいであって、なんのまじり気もないのじゃ」
そのことばを静かに思いめぐらして、よくよく検討してみるがよろしい。圜悟禅師はかってこのようにいったというのだが、ひょっとすると、なお禅師はまだ、生死の全からくりが虚空にいっぱいどころか、さらにそれを溢れるものだということを知らなかったのではあるまいか。
ともあれ、その去来(こらい)というを考えてみると、去のも生死があり、来にも生死があり、あるいは、生にも去来があり、死にも去来がある。去来には尽十方世界をその翼として飛び去り飛び来(きた)るのであり、十方世界のことごとくをその足として一進しまた一退するのである。
また、その生死を頭となし尾となして、その尽十方世界なる真実の人間のありようは、まことに自由自在なものであって、ひらりと身を翻(ひるがえ)せば、それはどこまでも大きく、また、ひょっと頭をめぐらせば、それはどこまでも小さい。あるいはまた、坦々たる平地かと思えば、壁のごとくそびえ立つ千仭(せんじん)の山々であり、そびえ立つ千仭の山々かと思えば、坦々たる平地である。そこにこそ、かの南瞻浮洲(なんせんぶしゅう)・北倶廬洲(ほっくるしゅう)の面目がある。それをよくよく検討して学道するのである。また、それでこそ、かの学人たちの追求する極致の面目というものであって、それを取りあげて学道するのほかになにがあろうぞ。(186~190頁)
〈注解〉尽十方界是箇真実人体;『景徳伝燈録』巻二一に見える福州慧球(えきゅう)のことばに出ずる。「ただ先師のいうがごとし。尽十方世界、是真実体」とある。先師とは玄沙師備(げんしゃしび)である。
十悪;殺生・偸盗(ちゅうとう、ぬすみ)・邪淫・妄語(うそ)などの十種の悪をいう。
八戒;八斎戒(はっさいかい)という。殺生・不与取(与えられざるを取る)など、日々行ずべき八種の戒をいう。
自然見の外道;自然外道の考え方というほどの意。自然外道は仏陀のころの外道であって、自然のままなるをよしとする主張をした。
百丈大智禅師;百丈懐海(814寂、寿95)。馬祖道一の法嗣(ほっす)。
得度;修行して生死(迷い)の彼岸にわたること。
三昧・陀羅尼;三昧とは、心を一処に定めて動ぜしめざることであり、陀羅尼とは、よく聴き、理解して、忘失せしめざることをいう。
転法輪;仏の説法をいうことばである。
枯木・死灰;小乗の聖者の境地をいうことばである。
いまだ生をすてざれども……;生死の問題の究極地であって、容易に説明しがたい。いまは、ただ「生死」の巻の一節をあげて参考に資しうるのみである。
「生より死にうつるとこころうるは、これあやまりなり。生はひとときのくらゐにて、すでにさきありのちあり。かるがゆゑに仏法のなかには、生すなはち不生といふ。滅もひとときのくらゐにて、又さきありのちあり。これによりて滅すなはち不滅といふ。生といふときには、生よりほかにものなく、滅といふときには、滅のほかにものなし」(191~193頁)
夢 中 説 夢 ( むちゅうせつむ )
■開 題
この一巻が、制作され、衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の秋もようやく酣(たけ)た九月二十一日、例のごとく興聖寺においてであった。
ところで、「夢中説話」とは、誰でもお判りのとおり、夢のなかにあって夢を説くということである。そのような巻題を揚げて、いったい、道元はなにを語ろうとするのであるか。この一巻に読みいたるもののまず思うところは、そのことでなくてはなるまい。
それに対する答案は、まずこの巻の冒頭において示されている。
「諸仏諸祖出興(しゅっこう)の道、それ朕兆(ちんちょう)已然(いぜん)なるゆゑに、旧窠(きゅうか)の緒論にあらず、これによりて、仏祖辺、仏向上等の功徳あり。……はるかに凡界の測度(しきたく)にあらざるべし。……これを夢中説夢す。証中見証なるがゆゑに、夢中説夢なり」
そういうところは、いささか難解の文字をつらねているけれど、その意(こころ)は判然と受けとることができる。諸仏諸祖が世に出でて語りたまうところは、永遠のことに属するものであって、現実膠着(こうちゃく)の輩(やから)の所論とはまったく異なったものである。だからして仏祖のほとりにいたらしめ、あるいは、仏祖を超えてゆかしむるほどの力があるのであって、凡人のとうてい推して測りうるところではない。それをいま夢のなかにあって夢を説くとはいうのである。悟りのなかにあって悟りを見るのであるから、夢のなかにあって夢を説くというのである。そのようにいうのである。
したがって、道元はまた、つづいていっておる。
「この夢中説夢処、これ仏祖国なり、仏祖会(え)なり。仏国仏会・祖道祖席は、証上而(に)証、夢中説夢なり。この道取説取にあひながら、仏会にあらずとすべからず。これ仏転法輪なり」
そのいうところは、だから、夢中説夢のなされるところこそ、まさしく仏祖の世界であるというのである。しかるに、世の凡俗の輩どもは、そのような表現に出会いながらも、ぽかんとして気がつかないでいるものが多い。それではいけない。それこそ仏の転法輪というものだと、声をはげまして語っているのである。
それらによって、わたしどもは、いま道元が夢をもって語ろうとしているものが何であるかを、容易に知ることができるはずである。それは疑いもなく、悟りの世界であり、仏祖の世界なのである。しかるところ、誰しもが思うところによれば、夢とは、非現実的にして、まことに頼りがたく、不確かなものなのである。しかるを、道元は、何故をもって、その夢をもって悟りの世界を譬(たと)えようとするのであるか。さらに読み進めてゆけば、やがてその答えが与えられるのである。
そこでは、道元は、夢なることばをもって、悟りの世界の非現実性を説いているのである。悟りの世界は、けっして現実的なものではない。仏の世界は、けっして「視よここにあり、かしこにあり」というべきものではない。それは、現象界に属するものではなくて、むしろ叡智界に属するものである。叡智の世界はこの世の時間と空間とを超越して存する。その世界の遊化(ゆげ)する人格であるがゆえにこそ、道元は諸仏をもって夢中に説夢されるのだと語るのである。
だが、それが非現実の世界に属するということは、けっして「夜夢のごとく」頼りないものだということではない。頼りないというのは、むしろ現実の世界である。そこでは、すべてが刻々に移ろうている。諸行が無常であるというのは、そのことに他ならない。それに反して、かの非現実なる悟りの世界は、はるかに堅碓なる世界である。かの曇鸞(どんらん)のことばを借りていうならば、「かの世界の相を観ずるに、勝れて三界道に過ぎたり」であるが、その真相がほの見えてくる時、その人は、仏教にたいしてはじめて聴く耳をもつもの、見る眼をもてるものとなるのである。(196~198頁)
■したがって、仏道をまなぼうとしない人は、この夢のなかにあって夢を説くのに出会っても、ただ徒(いたず)らに、それはありもしないものをあるように思い、迷いに迷いをかさねるようなものだと思う。だが、そうではない。それは、たとい、迷いのなかにあってまた迷うといい、あるいは、惑いのうえに惑いをかさねるといわれようとも、そう表現する表現のなかにこそ、天空に通ずる路がある。まさにそのことを思いめぐらして究めるがよいのである。(202頁)
■ともあれ、そこにおいてはじめて、仏と仏との相見(そうけん)がある。とするならば、そこに到らんがためには、誰かその頭をも目をも髄をも脳をも、あるいは、その身その肉、その手その足をも惜しむものがあろうか。惜しまないからこそ、「金(きん)を売る人はこれすべからく金を買う人」なる道理であって、それを玄の玄といい、妙の妙といい、悟りの悟りといい、また、頭のうえに頭をのせるというのである。そして、それこそ、とりもなおさず、仏祖たちの履(ふ)みきたれるところである。しかるに、それをまなぶにあたって、頭というからには、人の頂上だとのみ思うものが多く、それを毘盧遮那仏の頂上だろうなどと考えてみるものは一向にない。ましてや、それが「明明百草頭」の頭であろうと思うものにおいてをやである。頭そのものが判ってはいないのである。(204~205頁)
〈注解〉明明なる百草;「明明百草頭」なる句による。万法のあるがままのすがたの朗然たるをいうことばであって、仏祖のしきりに語りきたった句である。
夢然;ここでは「ぼうぜん」と読む。この夢(ぼう)は、明らかならぬさまをいうことばである。
微塵;物質の最小の単位をいうことばである。
売金須是買金人;「金を売るはすべからくこれ金を買うの人」と読む。身命を愛惜せぬ者こそが身命を得るというほどの意をあらわす。
毘盧;毘盧遮那仏の略。さらに遍一切処(へんいっさいしょ)などと訳する仏であって、全宇宙を象徴する仏である。(205~206頁)
■釈迦牟尼仏はおおせられた。
「もろもろの仏のからだは金色にして、さまざまの瑞相がすばらしかった。その法を聞いて人に伝えんとするに、つねにすばらしい夢にみちていた。ついで国の王となったけれども、宮殿をも捨て眷族をもすて、またくさぐさの栄華栄耀をもすてて、仏道の修行に身を投じた。ついに菩提樹のもとにいたり、獅子の座に端座して、道を求めること七日、七日をすぎて仏智を得、最高の道を成就して、起って法輪をぞ転じた。すなわち、もろもろの人々のために、法を説いて長時をけみし、解脱のすぐれた道を説いて、数かぎりもない衆生をすくった。かくていま永遠の静寂に入るに、燈の滅するがごとくならん。汝らもしのちの悪世のなかにあって、よくこの最高の法を説かんとするならば、その人はかならずや、いまいうがごとき功徳をうることができるであろう」
いまの仏の説きたもうたところをまなんで、よくよく諸仏のつどいというものを知るがよい。それは単なる譬(たと)えではないのである。諸仏の妙(たえ)なる教えは、ただ仏と仏の世界のことであるから、夢のなかのことも、覚(さ)めてのことも、同じく真実なのである。覚めてのなかの発心・修行・正覚(がく)・涅槃があり、また夢のなかでの発心・修行・正覚(がく)・涅槃があって、そのいずれも真実である。大小のちがいもなく、いずれが勝りいずれが劣るということもないのである。
それなのに、「また夢に国王となる」などというと、昔も今も、たいてい、それは「この最高の法を説く」ちからによって、そのような夜の夢をみるのであろうと思うようであるが、そのように解釈するのは、まだ仏説をよく知らないからである。そこでは、夢も覚ももともと同じであり、一つである。いずれも真実である。仏法では、たとい譬喩であっても、それはあるがままの真実である。しかるに、ましてやここでは譬えではなく、夢に国王となったというのは、まさしく仏法の真実なのである。釈迦牟尼仏も、そのほかのすべての諸仏も諸祖も、みんな夢のなかにおいて、発心し修行し、そしてすぐれた正覚(がく)を成就したのである。だからして、いまこの娑婆世界における仏一代の教化のいとなみのごときは、とりもなおさず夢のなかのわざなのである。七日というのは仏智を得るための期間であるが、他方、法輪を転じ、衆生を救うためには、千万億劫を経たりという。夢のなかの消息は知るべからざるところである。
また、「もろもろの仏のからだは金色であって、さまざまの瑞相(ずいそう)がすばらしかった。その法を聞いて人に伝えようとしたところが、つねにすばらしい夢にみちみちていた」という。それでも明らかに知れることであるが、すばらしい夢とは、もろもろの仏にほかならないのである。「つねにあり」と如来がいっておられるのであるから、けっして百年の夢のみではないのである。けだし、その如来がいってあられるのであるから、けっして百年の夢のみではないのである。けだし、その如来が法を人のために説かれたのは、この世にその身を現じてのことであったではないか。いったい、法を聞くというが、それには、眼をもって声を聞くこともあり、心に声を聞くこともある。あるいは、この浮世で聞くこともあり、またこの世のはじまり以前に聞くということもある。
また、「もろもろの仏のからだは金色であって、さまざまの瑞相(ずいそう)がすばらしかった」という。そのよき夢はもろもろの仏身のことであるが、それは、そのまま今にいたっても疑いえないところである。この現実の世にあって仏の教化はずっと行われていることであるが、なお仏祖がさとりえたる道理は、かならず夢のなかのわざであり、夢のなかでのことである。すべからく「仏法を謗(そし)るなかれということばをまなぶがよい。法をそしるなかれということばをまなびいたれば、いまの如来のことばも、たちまちにしてよく理解できるであろう。
〈注解〉無漏妙法;無漏は煩悩のなきをいう。解脱にみちびくすぐれた法である。
発心・修行・菩提・涅槃;仏教の全道程であり、仏者の全生涯である。菩提は正覚(がく)であり、涅槃は入滅である。
道 得 ( ど う と く )
●原 文
諸仏諸祖は道得なり。このゆゑに、仏祖の仏祖を選するには、かならず道得也未と問取するなり。この問取、こころにても問取す、身にても問取す。拄杖(しゅじょう)払子(ほっす)にても問取す、露柱燈籠にても問取するなり。仏祖にあらざれば問取なし、道得なし、そのところなきがゆゑに。その道得は、他人にしたがひてうるにあらず、わがちからの能にあらず、ただまさに仏祖の究弁あれば、仏祖の道得あるなり。
かの道得のなかに、むかしも修行し証究す、いまも功夫し弁道す。仏祖の仏祖を功夫して、仏祖の道得を弁肯するとき、この道得、おのづから三年、八年、三十年、四十年の功夫となりて、尽力道得するなり。
(裏書云、三十年、二十年は、みな道得のなれる年月なり。この年月、ちからをあはせて道得せしむるなり。このときは、その何十年の間も、道得の間隙なかりけるなり。)
しかあればすなはち、証究のときの見得、それまことなるべし。かのときの見得をまこととするがゆゑに、いまの道得なることは不疑なり。ゆゑに、いまの道得、かのときの見得をそなへたるなり。かのときの見得いまの見得をそなへたり。このゆゑに、いま道得あり、いま見得あり。いまの道得とかのときの見得と、一条なり、万里なり。いまの功夫、すなはち道得と見得とに功夫されてゆくなり。
この功夫の把定の、月ふかく年おほくかさなりて、さらに従来の年月の功夫を脱落するなり。脱落せんとするとき、皮肉骨髄おなじく脱落を弁肯す、国土山河(せんが)ともに脱落を弁肯するなり。このとき、脱落を究竟(くきょう)の宝所として、いたらんと擬しゆくところに、この擬到(ぎとう)はすなはち現出にてあるゆゑに、正当脱落のとき、またざるに現成する道得あり。心(しん)のちからにあらず、身のちからにあらずといへども、おのづから道得あり。すでに道得せらるるに、めづらしくあやしくおぼえざるなり。
しかあれども、この道得を道得するとき、不道得を不道するなり。道得に道得すると認得せるも、いまだ不道得底を不道得底と証究せざるは、なほ仏祖の面目にあらず、仏祖の骨髄にあらず。しかあれば、三拝依位而立(さんぱいえいにりゅう)の道得底、いかにしてか皮肉骨髄のやからの道得底とひとしからん。皮肉骨髄のやからの道得底、さらに三拝依位而立の道得に接するにあらず、そなはれるにあらず。いまわれと他と、異類中行と相見(しょうけん)するは、いまかれと他と、異類中行と相見するまり。われに道得底あり、不道得底あり。かれに道得底あり、不道得底あり。道底に自他あり、不道底に自他あり。(223~224頁)
〈注解〉道得也未;「道得せりや、未だしや」と読まれる。「何といったか、それともまだか」というほどの意である。
功夫の把定;勇猛なる精進のゆるみなきことをいう。古註に「ゆるさず功夫するなり」とみえる。
三拝依位而立の道得底……;この一句は、その背景に、『景徳伝燈録』巻三、達磨章の一節が存する。そこでは、達磨がその門人たちに命じて、それぞれの所得を語らしめた。その一人にたいしては「汝はわが皮を得たり」といった。他の一人は「汝はわが肉を得たり」であった。さらに他の一人は「汝はわが骨を得たり」と示された。そして慧可の番になると、彼は何事も語らず、ただ「礼拝してのち位に依りて立つ」た。すると達磨は「汝はわが髄を得たり」といって、かの大法を彼に付属したという。それが慧可嗣法の消息である。いま「三拝依位而立の道得底」というはそのことである。だが、それは言語による表現ではないから、また不道得底というべきである。つづいて「「皮肉骨髄のやからの道得底」とあるのは、まことは皮と肉と骨まででよいのである。髄を得たる慧可は別格であるとしなければなるまい。
異類中行と相見;類を異にした者に相見(あいまみ)えるというほどの意であろう。なお、「われと他」というのは、前項にいうところの「慧可と他の三人」の意であり、また「かれと他」というのは「かれら三人と慧可」の意であると受けとられる。どちらからみても、慧可と彼らとは類を異にしていたというのである。(227~228頁)
画 餅 ( が び ょ う )
■開 題
この一巻は、仁治三年(1242)十一月五日、いつものように興聖宝林寺にあって制作され、かつ衆(しゅ)に示されたものと知られる。
この巻題のよってきたるところは、すぐ気付かれるように、この巻中にみえる、
「古仏言、画餅不充飢」
の句によったものである。画餅(がびょう)は飢えを充(みた)すことができないという意味の句は、二人の仏祖をすぐ思い出させる。その一人は徳山宣鑑(865寂、寿84)であって、その消息はさきの「心不可得」の両巻につぶさにしるされている。いま一人は香厳智閑(きょうげんしかん、年寿不詳)であって、その消息もまた、すでにさきの「谿声山色(けいせいさんしょく)」の巻にくわしく記すところである。しかるに、いまここには、ただ「古仏言」とのみあって、そのいずれのことばなるかを知りがたいところである。だが、古註はたいていこれを香厳智閑のことばとしている。わたしもまた、そうであろうと思う。なんとなれば、この巻のなかには、竹の声を聞いて大悟するという句もみえているし(それは香厳の故事である)、また、道元はおそらく徳山宣鑑には、「古仏」という称をもちいないであろうと思われるからである。
それにしても、この巻における道元のこの句にたいする解釈は、驚くほどに警抜(けいばつ)なものであって、まったく常識のそとに出ずるものである。まさに刮目して見るに値いする。
その第一には、「画餅」なる語にたいする解釈である。その解釈は、一見するところ、はなはだ解し難い行文をもって充たされているようであるが、ようやく読みいたってみるならば、詮ずるところ、それは一箇の概念であるといっているのだと知られる。概念といえば、御存じの通り、この道の家風として、もっとも軽蔑するところである。「画餅は飢えを充さず」というその句の意味するところも、もともとその意にほかならない。しかるに、いま道元がその語句に与える重さははなはだ重いのである。たとえば、
「いま道著(どうじゃく)する画餅といふは、一切の糊餅(こびょう)・菜餅(なもち)・乳餅・焼餅・糍餅(じびょう)等、みなこれ画図より現成するなり」
という。あるいは、
「しるべし、画等、餅等、法等なり。このゆゑに、いま現成するところの諸餅、ともに画餅なり」
という。あるいはまた、
「このほかに画餅をもとむるには、つひにいまだ相逢(そうほう)せず、未拈出(ねんしゅつ)なり」
といって憚(はばか)らない。そのいわんとするところは、あきらかに、概念と存在と、そして存在のありようである。概念なくして存在は考えられないのであり、また存在のありようも理解せられないのである。かくして、道元が画餅すなわちその概念に与える価値は、はなはだ重いものであると知られる。
その第二には、「飢(き)」の一字にたいする解釈、もしくは、「不充飢」の句にたいする解釈である。そこでは、道元は、「飢」の一字にあてるに「所求(しょぐ)の心」をもってしている。そして画餅すなわち概念化された表現が、容易に飢すなわち所求の心をみたさないことを語りいでる。だが、それは「餅に相待せらるる飢あらざるがゆゑ」であるという。それは詰まるところ、凡夫の求むるところが、いつも見当ちがいをしているからだということであろう。かくて、『随聞記』にみえる道元のことばをもっていうなれば、結局、「学道の人は人情を棄つべきなり」ということになるのであろう。
そして、その第三には、道元はついに、
「画餅にあらざれば充飢の薬なし」
といい切ってしまう。かくして、「画餅不充飢」の一句は、まったくその常識的解釈の正反対なる意味を与えられるにいたる。そこで、わたしはひそかに、解釈とは原作の包蔵する以上のものを展開することでなくてはならない、といったシュライエルマッヘルのことばを思い出さざるを得ない。
なお、この卷きにおいて道元がいわんとするところをよりよく理解するために、さきの「夢中説夢」の巻、ならびに「道得」の巻に説くところを思い出していただけるならば幸いである。(242~244頁)
●原 文
画餅不能充飢と道取するは、たとへば、諸悪莫作、衆善奉行と道取するがごとし、是(ぜ)什麼物什麼来(いんもぶついんもらい)と道取するがごとし、吾常於是切(岡野注;漢文)といふがごとし。しばらくかくのごとく参学すべし。
画餅といふ道取、かって見来せるともがらすくなし、知及(ちぎゅう)せるものまたくあらず。なにとしてか恁麼しる。従来の一枚二枚の臭皮岱を勘過するに、疑著(ぎじゃく)におよばず、親覲(しんごん)におよばず、ただ隣談に側耳せずして不管なるがごとし。(247頁)
●原 文
しるべし、画等、餅等、法等なり。このゆゑに、いま現成するところの諸餅、ともに画餅なり。このほかに画餅をもとむるには、つひにいまだ相逢う(そうほう)せず。未拈出なり。一時現なりといへども、一時不現なり。しかあれども、老少の相にあらず、去来の跡(せき)にあらざるなり。しかある這頭(しゃとう)に、画餅国土あらはれ、成立するなり。(248頁)
■いま、描ける餅は飢えを充さずというのは、たとえば、「もろもろの悪は作ることなく、もろもろの善を奉行せよ」というがごとくであり、あるいは「いったいこんな物がどこから来たのだ」というがごとくであり、あるいはまた、「わしはいつもこのことに一処懸命だよ」というようなものである。かりにそう思ってまなびいたるがよろしい。
この画餅ということばは、これまでにも、判ったものはすくなく、よく知りえたものはまったくない。どうしてそうだと判るか。これまでの人々をあれこれと勘(かんが)えてみると、疑うにも及ばず、みずから体験することもせず、まるで近隣の話に耳をそばだてず、われ関せずといった具合なのである。
そもそもこの描ける餅なるものは、よく知るがよい。それは、この世の現実のおもかげを有するとともに、また永遠のおもかげをもったものである。もともとそれは米や麦粉をもって作らるるものであるところを、さて生ずるといおうか生ぜぬものといおうか、ともあれ、いまや描ける餅なるものが現実にあり、またその表現があるのである。それは、えがいた時にはあり描かない時にはないのだと、そんな工合に考えてはならない。けだし、餅をえがく絵具は、山水を描く絵具とおなじであろう。いうところの山水をえがくには青や赤をもってするのであり、あがける餅を餅をあがくには米や麦粉をもってする。だからして、その用いかたも同じであり、また考えかたもひとしいのである。すなわち、いまいうところの画餅なるものは、すべて米の餅も、菜餅も、乳餅も、焼餅も、黍(きび)餅も、みな画図から出てくるのである。つまり、画ひとしければ、餅ひとしく、そのありようもまた等しいのである。したがって、いま造られるいろいろの餅は、すべて画餅なのである。そのほかに描ける餅をもとめたって、めぐり逢うことはできない。あるいは造り出すこともできない。つまり、餅というものは、ある時現われてくるものであるが、それはもとはといえば、一時の出現によってなるものではない。だからして、それはまた古いの新しいのというべきものでもなく、また造ったの造らないのというべきものでもないのである。とするならば、ここには画餅の世界なるものがあって、厳として存在しているということとなる。(249~250頁)
〈注解〉画等、餅等、法等;画ひとしければ、餅ひとしく、そのありようもまた等しいという。そこには、概念と存在とそんざいのありようの関係が語られているのであって、この一節の画龍点睛の一句はこれであると知られる。(岡野注;物の世界・事の世界・法の世界の三元論)(252頁)
■また、「飢えを充さず」という。その飢えは、この世の時間に支配されているものではないが、それが容易に画餅(がびょう)と相見(あいまみ)える手立てがない。画餅をくらうといえども、なかなか飢えをとどめる効果がないのである。それは、飢えにぴったりとくる餅でないからであり、あるいは、餅にぴったりとした飢えではないからである。そのゆえに、そのはたらきも伝えられず、その風情も伝わらないのである。思うに、飢えも一本の杖である。それを横に担ぎ縦に担ぎなど、千変万化がある。餅もまた一つの身心(しんじん)の現れとして、青黄赤白あるいは長い短い、あるいは円い四角いとさまざまである。たとえば、山水をえがくには、青や緑や赤などをもちい、あるいは奇巌怪石をえがき、あるいは七宝(しっぽう)や四宝などをもってえがく。そして、餅をえがく仕方もまた同じである。あるいはまた、人をえがくには四大をもってし五蘊をもってするし、仏をえがくには、泥をもって室(むろ)をつくり、土をもってその身軀(しんく)つくり、三十二相をあらわす。あるいは、一茎の草花をもって表現することもあり、あるいは、ながいながい修行をもって表現することもある。
そのようにして一幅のえがける仏をなすのであるから、すべてもろもろの仏はみな画仏であり、また、すべての画仏はみなもろもろの仏である。そこで、画仏と画餅とをよくよく比較してみるがよい。いずれが石でつくった亀であり、いずれが鉄でできた杖なのであるか。あるいは、いずれが具体的なものであり、いずれが抽象的なものであろうか。そこを仔細に思いめぐらして究めるがよろしい。そのように思いめぐらしてみると、生死(しょうじ)というも去來(こらい)というも、ことごとくえがける画図である。無上の智慧というのも、えがいた画図にほかならない。あるいは、万有といい、虚空というも、すべていずれもえがける図にあらざるはないのである。(253~254頁)
〈注解〉飢に相待せられる餅なし、餅に相待せらるる飢なし;所求の心にえがくところと、さとりの風景とのあいだに、大きなずれがあることをいうのである。
色法・心法;感覚界に属するものと、叡智界に屬するものである。いまは、具体的なものと、抽象的なものと訳しておいた。
法界;ここの“dharma”すなはち法は、存在そのものの意である。つまり、万有すなわち存在の世界である。それに対して、虚空はつまり非存在の世界である。そんなものは、誰も具体的に示すことはできないから、ただその概念があるのみであり、それをいま画図であるというのである。(254~255頁)
■古仏はいった。
「道なって白雪は村里をおおいつくした。その時一切は青山数幅の画図に入りきたった」
それは大悟の境地を語った句である。弁道工夫の成就を説いたことばである。だからして、道のなれるまさにその時を表現して、白雪といい、また青山数幅というのである。つまり画をえがいているのである。けだし、その境地においては、一動一静すべて画図ならざるはないのである。そして、いまわたしどものいとなむ修行もまた、その画図によって教えられたものである。あるいは、仏の十号といい三明(さんみょう)というも、一幅の画である。あるいはまた、五根(ごこん)といい、五力といい、七覚支(しちかくし)といい、八正道というも、おなじく一幅の画にほかならない。もしも、画は実(じつ)ではないというならば、よろずの存在もまた実ではない。もしも、よろずの存在がすべて実でないならば、仏法もまた実ではあるまい。もし仏法が真実であるならば、画餅もまたしんじつであろう。
雲門匡真大師(きょうしんだいし)に、ある時、一人の僧が問うていった。
「ひとつ仏を超え、祖を越えたところのお話を承りとう存じます」
師は答えていった。
「それは糊餅(かゆもち)だよ」
このことばを、静かに思いめぐらしてみるがよろしい。すでにこの「糊餅」という表現が実現しているから、また仏を超え祖を越えたはなしを説く祖師もあるだろう。また、それが判らぬ男もあるだろう、聞いて納得する修行者もあろう。そして、また生まれてくることばもあろうが、いまこの見事にいい得たる糊餅(かゆもち)という表現は、これもまた疑いもなく画餅(がびょう)のひとつである。そこには、仏を超え祖を越える話が打ち出されていて、仏ともなり、魔ともなるほどの力がひそんでいるのである。
また、先師如浄禅師はいったことがある。
「脩竹(しゅうちく)も芭蕉も画図に入った」
そのことばは、長い短いを超えた世界を語ったものであって、いまいうところの画図をまなぶべき表現である。
修竹とは長い竹である。それを成すものはもと陰陽のはこびではあるけれども、またその陰陽のはこびをあらしめるものは、いまいうところの画中の修竹の年月である。だが、その年月その陰陽は測ることができないのである。たとえば、大聖(だいしょう)は陰陽の運行をあきらかに見ることはできるが、なお陰陽そのものを測ることはできない。なんとなれば、陰陽はもともと存在のありように等しく、その運行にひとしく、したがってまた仏の道にひとしいからである。つまり、大聖にとって陰陽は知るべき対象ではないからである。いま外道や小乗の輩が、その心その目をもって測る陰陽とはちがうのである。ここでは、それは画中の修竹の陰陽である。その修竹の年月のはこびである。修竹の世界のなかにあるのであり、そして、その修竹のなかまとして、十方もろもろの仏があるのである。よって知るがよい。かくて天地乾坤(けんこん)は、修竹の根であり茎であり枝であり葉である。だからして、天地乾坤は悠久なることをうるのであり、大海も須弥山(しゅみせん)も十方の世界のことごとくも堅牢なることができるのであり、あるいは、老師のもちいる拄杖(つえ)も竹箆(しっぺい)もいつまでも老いざらしめることができるのである。
また、芭蕉は物質的要素である地水火風空と、精神的要素としての心意識や智慧を、その根茎とし枝葉とし花果とし光や色とするものである。そのゆえに、秋風がふけば秋風のなかに消えて、一塵ものこすところがない。奇麗さっぱりしたものである。内にしていえば、眼底に筋一つ骨一つのこすのでもなく、外にしていえば、その辺りに膠(にかわ)や緑青(とりもち)をのこすのでもなく、まさにずばりと解脱そのものである。なお、その消えゆくさまは、速い遅いのことではないから、須臾(しゅゆ)とか刹那とかいったことでもない。そして、そのような営みをなす力があってこそ、はじめて地水火風をして活溌ならしめることができ、また心意識や智慧をして静かならしめることができるのである。すなわち、芭蕉は春夏秋冬をその道具として、あるいは生じ、あるいは茂り、またあるいは実り、あるいは枯れるのだと知られる。
いま、このような修竹と芭蕉のありようは、みな画図にほかならない。だからして、竹の声を聞いて大悟するというものは、大小をえらぶこともなく、あれもこれもみな画図なのであろう。それは凡情の思いはからいではないかなどと疑ってはならない。それは、あの竹はどうしてあんなに長い、この竹はどうしてこんなに短いというにひとしく、あるいは、この竹はどうしてこんなに長い、あの竹はどうしてあんなに短いというようなものである。それらはみんな画図なのだから、長い短いがあって図はちゃんと釣合いがとれるのである。長い画があれば、また短い画があってよいではないか。そこの道理をはっきりとわきまえるがよろしい。つまるところ、この世界もこの存在もことごとく画図であるのだから、人も存在も画によってあらわとなるのであり、仏祖のまた画によって成るのである。
とするならば、すなわち、えがける餅でなかったならば、飢えを充たす効能はないのである。また、えがける飢えがなかったならば、その人に逢うことはできないのであり、画によって充たされるのでなくては、まことの力とならないのである。さらにいうなれば、飢えたる時に充し、飢えざるに充し、あるいは、飢えたるに充さず、飢えざるに充さぬことも、ただ画餅にしてはじめて能(あた)うところであって、えがける餅にあらざれば能わざるところであり、またいい得ざるところである。だから、いまはまず、それらをなしうるものは画餅であることをまなびいたるがよろしい。そして、その意味するところをまなびいたった時、その時人はいささか、物に転じ、また物に転ぜられるちからが、わが身心(しんじん)にくまもなく湓(あふ)れることを感ずるであろう。いまだその功徳の湓るるを感じないうちは、まだまだ学道の力量がでてこないのである。そして、その力量を実現せしむることは、つまるところ、その画を証することによって実現するのである。(258~262頁)
〈注解〉三明;仏の三つの通力である。宿命通・天眼通・漏尽通の三つがそれである。
根・力・覚・道;五根(信根・精進根・念根・定根・慧根)、五力(信力・精進力・念力・定力・慧力)、七覚支(択法・精進・喜・軽安・捨・定・念の七つの覚)、八正道(正見・正思・正語・正業・正命・正精進・正念・正定)をいう。
雲門匡真大師;雲門文偃(ぶんえん、949寂、寿不詳)は雪峰義存の法嗣(ほっす)。諡(おくりな)して匡(きょう)真弘明禅師と称す。
天地乾坤;乾坤というもまた天地の意にほかならない。
画餅・画飢・画充;「画餅不充飢」の句によって、画餅のほかに、さらに画飢と画充の句をなしたのである。(262~263頁)
全 機 ( ぜ ん き )
■開 題
この一巻が制作され、そして衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)のもおしつまった十二月十七日のことであった。ただ、珍しいことには、この一巻の示衆(じしゅ)は、いつもの興聖宝林寺においてでかなくて、京都東山なる六波羅蜜寺のちかくの波多野義重(よししげ)の京邸(やしき)において行われた。おそらく、興聖寺の成立以後、道元の開講が興聖寺以外の場処でおこなわれたのは、これが初めてのことと思われる。
(ー中略ー)例によって、道元はそのもっとも肝要のところを、その冒頭において端的に語り出でる。いわく、
「諸仏の大道、その究尽(ぐうじん)するところ、透脱なり、現成なり」
諸仏の大道というものは、それを究めつくしてみると、それはもう徹頭徹尾どこまでも透きとおって、いとも明らかに見渡せるものだという。だから、その大道を究めた仏祖たちにとっては、生の全体がくまもなく見通せるのである。したがって、死の全風景もまた曇るところなく見渡すことができる。そして、いま道元が「全機」なる題目のもとに語ろうとしていることも、また、その生と死の全体であり、全風景であるといってよかろうと思われる。
●原 文
諸仏の大道、その究尽(ぐうじん)するところ、透脱なり、現成なり。その透脱といふは、あるいは生も生を透脱し、死も死を透脱するなり。このゆゑに、出生死あり、入生死あり、ともに究尽の大道なり。捨生死あり、度生死あり、ともに究尽の大道なり。現成これ生なり、生これ現成なり。その現成のとき、生の全現成にあらずといふことなし、死の全現成にあらずといふことなし。この機関、よく生ならしめ、よく死ならしむ。
この機関の現成する正(しょう)当恁麼時、かならずしも大にあらず、かならずしも小にあらず。偏界にあらず、局量にあらず。長遠にあらず、短促にあらず。いまの生はこの機関にあり、この機関はいまの生にあり。生は来にあらず、生は去にあらず、生は現にあらず、生は成にあらざるなり。しかあれども、生は全機現なり、死は全機現なり。しるべし、自己に無量の法あるなかに、生あり、死あるなり。しずかに思量すべし、いまこの生、および生と同生せるところの衆(しゅ)法は、生にともなりとやせん、生にともならずとやせん。一時一法としても、生にともならざることなし。一時一心としても、生にともならざるなし。
生といふは、たとへば人のふねにのれるときのごとし。このふねは、われ帆をつかひ、われかぢをとれり、われさををさすといへども、ふねわれをのせて、ふねのほかにわれなし。われふねにのりて、このふねもふねならしむ。この正(しょう)当恁麼時は、舟の世界にあらざることなし。天も水も岸も、みな舟の時節となれり、さらに舟にあらざる時節とおなじからず。このゆゑに、生はわが生ぜしむるなり、われをば生のわれならしむるなり。舟にのれるには、身心依正(しんじんえしょう)、ともに舟の機関なり。尽大地・尽虚空、ともに舟の機関なり。生なるわれ、われなる生、それかくのごとし。(268~269頁)
■もろもろの仏の大道は、それを究め尽してみると、まったく透きとおって、明々白々なるものである。透きとおっているというのは、たとえば生についていえば、生のどこにも曇れるところがなく、また死についていえば、死のどこにも覆われたるところがない。だから、生死(しょうじ)を出ずることも自由自在であり、また生死に入ることも思うがままである。それもみな大道を究め尽しているからである。あるいはまた、生死を捨てることもあり、生死をこえることもあるが、それもみな大道を究め尽しているからである。かくて、明々白々たる生があるのであり、明々白々として生を生きるのであるが、そのことの成る時には、かならず生のすべてをあげてかくなるのであり、また死のすべてをあげてかくなるのである。そのからくりがあって、はじめてこの生があり、また死があるのである。
そのからくりの実現するまさにその時、それはかならずしも大でもなく、また小でもない。あるいは、この世界にあまねしというでもなく、一部に限られるというでもなく、あるいはまた、長いというでも、短いというでもない。ただ、いまの生はそのようなからくりによってなるのであり、そのようなからくりがこのいまの生にあるのである。もとより、生というものは、来るにもあらず、去るにもあらず、あるいは、現ずるでもなく、成るものでもない。ただ、生とはそのからくりの実現するすべてをいうのであり、死もまたそのからくりの実現するすべてに他ならない。誰でも知っているように、自己にはいろいろさまざまの事がある。そのなかに、生があり、また死がある。だが、静かに考えてみるがよろしい。いったい、このせいがあり、そして、この生とともにおこるさまざまの事があるのであるが、それらの事はこの生とともなるものであろうか、それとも別のことであろうか。いわずと知れたこと、いかなる時のいかなる事といえども、この生とともならざるはないのであり、いかなる事のいかなる思いといえども、またこの生と別なるはないのである。
生とは、たとうれば、人が舟に乗った時のようなものである。その舟は、われが帆をあやつり、われが梶(かじ)をとる、あるいは、われが棹(さお)をさすのであるが、それにもかかわらず、やっぱり、舟がわれを乗せているのであり、舟のほかにわれがあるわけではない。つまり、われが舟に乗って、舟を舟たらしめているのである。まさにその時のさまをよくよく思いめぐらしてまなぶがよい。まさにその時においては、すべてが舟の世界にあらざるはない。天も、水も、岸も、すべてがことごとく舟の時なのであって、舟ならぬ時とはまったくちがっている。それと同じように、この生はわれが生きているものであるとともに、またこの生がわれをわれならしめているのである。舟に乗った時には、わが身心(じん)もまたその環境もすべて舟のからくりである。いや、大智のことごとくも、虚空のすべても、みな舟のからくりならざるはない。この生なるわれ、われというこの生は、そのようなものなのである。(269~271頁)
〈注解〉機関;からくりと訳しておいたが、仕組み、構造、ありよう、はたらきといった意味のことばである。(271頁)
都 機 ( つ き )
■開 題
この一巻は、仁治四年(1243)の一月六日付の制作である。その仁治四年は、二月二十六日に改元せられて、寛元元年となるのであるから、仁治四年の制作はこの一本のみと知られる。
また、この一巻は、興聖宝林寺において制作されたまま、衆(しゅ)に示すことがおこなわれていないのであるが、その理由は、おそらく、この一巻が、さきに前年の十二月十七日、波多野義重(よししげ)の邸(やしき)において衆み示されたかの「全機」の巻と、その趣きをおなじうするものだからに違いあるまい。つまり、道元は、同じ趣きのものを、さきの示衆(じしゅ)ののち、もう一度、構想をあらたにして、暮れから正月にかけて、この一巻として制作したのであろう。
「全機」と「都機」。しかるに、都は すべてであるから、この二つの主題が、同じ趣きを表現するものであることは、人の容易に気付くところであろう。ところが、いま「都機」の都の字は、これを漢音で読めば「と」であるが、それを「呉音」をもって読めば「つ」である。人によっては、その「都機」を『とき」と読んでいる向きもあるようであるが、わたしには、それは「つき」と読むべきものであるように思われる。道元もまた、きった、そう読んでもらうことを期待していたにちがいない。そう思うのは、わたしには、この一巻の制作の動機は敢えて申しあげなくてはなるまいと思う。
すでにいうように、その前年の十二月十七日、さきの「全機」の巻を人々のまえにおいて披露した。だが、ふと考えてみると、それは「都機」はまた「つき」と読むことができる。そうと気がついた時、道元の心のなかには何かひらめくものがあった。それは、いまいうところの「全機」もしくは「都機」という主題の趣きを、仏祖たちはしばしば月をもって語ったものである。そのことに気がついた時、道元の胸中には、同じ主題のもとに新しい構想が生まれた。かくて道元は、同じ趣きを、新しい主題と構想のもとに、暮れから正月の怱忙(そうぼう)のなかにも、新草としてこれを執筆した。それがこの「都機」の巻であると、わたしにはそう想像するのほかはないように思われる。
かくて、この一巻における道元は、「都機」という主題をたてながら、その本文においては、いちども都機という文字をしるしていない。そこでは、いつも月である。月を語りながら、いつもその背後には都機がある。引用する仏祖のことばもまたすべてそうなのである。
まず最初には、『金光明経(みょうきょう)』から釈迦牟尼仏のことばが引かれる。それは「仏の真法身(ほっしん)」を語るに、虚空を語り、また水中の月を語っているのである。
ついで道元は、盤山宝積(ほうしゃく)のことばをもたらして語る。それはもう、ずばりと「心月孤円」とうち出されているが、それこそ「都機」そのもののありようなのである。
さらに道元は、投子(とうす)大同の月を主題とする問答を取りあげたのち、最後には『円覚(がく)経』の一節を引いて、もう一度、釈迦牟尼仏の月に関連したことばをあげて、これに詳細な解説を加えて結びとしている。
かくて、この一巻は、一見すれば、月を語り月を論ずることに終始しているのであるが、それら仏祖の語る月には、いつもその言裏(げんり)に「都機」があり、「心月」があり、「円覚」のありようが説かれているのである。まことに珍しい一巻の構想であるといってよかろう。
「全機」もしくは「都機」なることばの意味するところが何であるかについては、さきの「全機」の巻の開題において、及ばずながら、いささか記しておいたので、参照していただけるならば幸いである。(278~280頁)
■もろもろの月の円(まろ)やかであるのは、けして前後数日のことのみではない。いや、円やかとなれる月は、ただ前後数日のみ円やかなるにはあらぬ。だから、釈迦牟尼仏も仰せられたことがある。
「仏の真(まこと)なる法身(ほっしん)は、なお虚空のごとくであり、その物に応じて形を現ずるさまは、水中の月の如くである」
そこには「水中の月の如し」とある。その如しというのは、あくまでも水中の月であって、それは水がそうなのであり、月がそうなのであり、水にうつった月がそうなのである。だが、如(にょ)ということばは、よく似ていることをいうことばではない。如はあくまでもそのものでなくてはならない。いま「仏のまことの法身は、なお虚空のごとし」という。その虚空こそがそのまま仏のまことの法身なのである。仏のまことの法身であるがゆえに、あらゆる地、あらゆる世界、あらゆる物、あらゆる現象がそのまま虚空である。目のまえにみえるさまざまの草木、さまざまの物象がそのまま、すべて仏の真法身にあらざるはない。それが水中の月の如しということなのである。
いったい、月のでるのは、かならず夜にかぎったものではない。また、夜はかならず暗いというものではない。人間世界のみの小さな量見にのみ捉えられていてはならない。日月のないところにだって昼夜はあるであろう。日月はただ昼夜のためにあるものではない。日も月もいずれもあるがままにしてあるのであって、一月(ひとつき)の二月(ふたつき)のというべきものでも千月の万月のというものでもない。たとい、月そのものが一月だ二月だという考え方を保証するものであっても、それはたまたま月がそうだというだけのことであって、仏教はかならずしもそうはいわない。それは仏道の知見というものではない。だからして、たとい昨夜は月があったからとて、今夜の月は昨夜の月ではないのである。仏道では、今夜の月は、さきなる月もあとなる月も、あくまで今夜の月であると考えるがよいのである。月は月へと相嗣(あいつ)ぐものであるから、いろいろの月があっても、新しいの旧いのというべきものではないのである。(281~282頁)
■古仏もいったことがある。
「一心一切法、一切法一心」
だからして、心は一切の存在のほかにはなく、一切の存在は心のほかにはない。とするならば、心は月なのであるから、また月は月なのである。心にほかならぬ一切の存在は、すべてことごとく月であるから、またあまねく世界はすべて月なのである。心にほかならぬ一切の存在は、すべてことごとく月であるから、またあまねく世界はすべて月なのである。この身もまたすべて月なのである。たといかぎりもない年月のあいだにはいろいろの事があっても、それもまた月ならざるはない。いまわれらがこの身心(じん)を托(たく)する国土の今日も明日も、また同じく月のなかにあるのである。生死もむろん月のなかにあり、十方(じっぽう)世界のことごとくもまたその月のなかの上下であり、左右であるにすぎない。さらに、われらの日々のいとなみもまた、つまり、この月のなかにおけるあれやこれやにすぎないのである。(286頁)
〈注解〉心月孤円……;「心月孤円にして、光は万象を呑む。光は境を照らすに非ず、境もまた存するに非ず。光境ともに亡ず、またこれ何物ぞ」と読まれる。
光象;さきの「火呑万象」の上下の二字をとって、光の万象を照らすをいうのであろう。
一心一切法、一切法一心;もと『摩訶止観』にみえることばであるが、ここでは六祖慧能のことばとして『法宝壇経』の句に取意して語っているようである。かくて、「古仏いはく」の古仏は慧能のことである。(286~287頁)
■釈迦牟尼仏は、金剛菩薩につげて語りたもうた。「たとえば、目を動かせば湛(たた)うる水もゆらぐがごとく、定(じょう)に入って動かざる眼は火をも転ずるがごとく、雲はしれば月をはこび、舟ゆけば岸うつるもまた同じことである」
いま仏の説きたもう、「雲が走れば月が運び、舟が行けば岸が移ろう」というところを、よくよくまなび究めるがよい。あわただしうまなんではいけない。また凡情に準じて考えてはならない。しかるに、この仏説を仏説のとおりに受けとっているものは稀なのである。それを仏説のままに学びならうというのは、円覚(がく)というのは必ずしもこの身心のことでもなく、あるいは正覚(がく)・涅槃のことでもないことを知ることである。正覚(がく)・涅槃はかならずしも円覚ではなく、わが身心のこともまたそうではないのである。
いま仏のいう、「雲はしれば月はこび、舟ゆけば岸うつる」というのは、雲が走るときには月も動くということであり、舟が行くときには岸も移るということである。そのいう意味は、雲と月とは、時を同じうして動くということであり、歩を同じうして行くということであって、どっちが終りというでもなく、いずれが前いずれが後とするのでもない。また、舟と岸とも、時を同じうして行くということであり、歩を同じうして動くということであって、べつにいつ始まりいつ止まるというでもなく、あるいはいつまでも流転するというわけでもない。あるいはまた行(ぎょう)といえば、人間の行をまなんだものもあろうが、人間の行というものもまた、いつ始まりいつ終わるというものではなく、始まり終わりのある行は人のそれとはちがう。だが、その点をあげて、それを人間の行とならべて考えてはいけない。雲の走るも、月の動くも、舟の行くも、岸の移るも、それとはまったく別のことなのである。愚かにして小さな量見のなかに縮かんではいけない。雲の走るは東西南北を問うことなく、月の運行は昼夜古今にわたって休むことがないということ、これを忘れてはならない。また、舟の行き、岸の移ろうことは、いずれも過去現在未来の三世(ぜ)によって変わることなく、よく三世をしてあらしめるところである。これを、「直ちに如今(いま)にいたって飽(あ)いて飢えず」という。(292~293頁)
〈注解〉定眼;禅定に入って寂静に帰し、もはや対象にひかれて動揺しない眼のありようをいう。
円覚;円(まろ)やかなさとり。さとりはもとより全体性のものであり、全体性のさとりでなくてはさとりとはいえない。覚性(かくしょう)平等とはそのことである。普遍妥当なることをその性となすのである。円覚とはそのことである(294~295頁)
空 華 ( く う げ )
■開 題
この一巻は、寛元元年(1243)の三月十日、興聖宝林寺において衆(しゅ)に示されたものとある。ひそかの偲べば天地に万花の咲きいでて、まさにかの「華ひらいて世界起る」の句が思われる時節であったにちがいない。
その天地になかにあって、いま道元が語りいでるところの主題は「空華(くうげ)」とある。それは、また言葉をかえていえば、世尊の仰せられたことばをもって「虚空の華」といってもよく、あるいは「首楞(しゅりょう)厳経(ごんきょう)」の表現をもって、
「またエイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)人の空中の華を見るがごとし」
といってもよいという。道元はまずその「空華」の語を解説して、そのように説きいでたのである。
「仮令(けりょう)すらくは、空華といはんは、この清氣のなかに浮雲のごとくにして、飛華の風にふかれて東西し、および昇降するがごとくなる彩色のいできたらんずるを、空華といはんずるとおもへり」
文中にそのような一節を見出して、わたしもおのずから「ははあ」と頷いたことではある。
「エイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)人のエイというのは、眼のかすめるということばである。その眼のかすめる人が空中の華を見るがごとしといえば、それはそれは妄法すなわちありもしない華を虚空にみるようなものだということとなる。それが凡人の思わくのおのずからおちつくところであろう。だが、そこで道元は、ずばりと示していう。
「おろかにエイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)を妄法なりとして、このほかに真法ありと学するなかれ。しかあらんは、少量の見なり」
また、
「しるべし、仏道のエイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)人といふは、本覚(がく)人なり、妙覚人なり、三界(がい)人なり、仏向上人なり」(298~299頁)
■初祖達磨大師はいった。
「一華五葉を開き、結果自然(じねん)に成る」
この花のひらく時、ならびにその光輝や形相(すがた)をまなぶがよい。この花の弁は五片である。五弁のひらくとき一つの花となるのである。その花によっていわんとするところは、「われもとこの国に来れるは、法を伝えて迷える衆生を救わんがため」だということである。その光輝と形相をたずねるとは、このことを知ることである。その果の結ぶところは、その成りゆきに任せるのである。それを自然に成るというのである。
自然に成るというのは、因を修めれば果を感ずるということである。どこにも通ずる因があって、どこでも通じる果があるのである。いやしくも私(わたくし)のない因果を修して、私のない因果を感ずるのである。自というは己(おのれ)であるが、己というはまた必ず汝のことでもある。ともに四大をもってなり、五蘊によってなる人間である。そこらあたりの誰であってもよいのであるから、われでもないし、たれでもない。そして、誰でなくてはならないというものでもないから自とはいうのである。然(ねん)はゆるすというほどの意である。
つまい、時が来れば自然にしてなるというのであって、それがそのまま花ひらく時であり、果を結ぶ時である。あるいは、法を伝え、迷える衆生を救う時である。たとえば紅蓮華(げ)のひらく時ひらく処は、火のある時、火のもえる処だというようなものである。鑽(きり)の火も焔々ともえる火も、ともに紅蓮華のひらく処であり、ひらく時である。もし紅蓮華のひらく時であり、ひらくでなかったならば、一穂(いっすい)の火もはたらくことはない。それによっても知るがよい。一穂の火にも、百朶(だ)千朶の紅蓮華があって、空にひらき、地にひらき、過去にひらき、また現在にひらくのである。つまり、火のあらわれる時あらわれる処を見聞(けんもん)するには、紅蓮華を見聞すればよいのであるから、紅蓮華のひらく時と処を見遁すことなく見聞するがよいのである。
ひとりの古い先徳はいった。
「紅蓮華は火の裏(なか)にひらく」
そのいうがごとく、紅蓮華は火のなかにひらくのである。火のなかとはなにかを知りたいと思うならば、それは紅蓮華のひらくところである。この世の住みびとも見解にとらわれて、火のなかを考えてはならない。これを疑うものは、水のなかに蓮華が生ずることをも疑うであろう。枝のさきにもろもろの花の咲くことだって疑うであろう。さきに疑うならば、この世界がここに安定していることだって疑えよう。それなのに、それらは疑わずして、火のなかに花のひらくことのみを疑うというは愚かなこと。「花ひらいて世界起る」所以(ゆえん)をよく知るものは、仏祖のほかにはないのである。
「花ひらく」というのは、時と処をさだめることもなくして、森羅万象がその数かぎりもない形相を、いともうるわしく整えることである。ただに春に花あり秋に果あるのみではなく、また、時いたればかならず花あり果あることを知るがよい。花も果もともに時節をまもるのであり、時も節もすべて花果をもつのである。そのゆえに、さまざまの草にはみな花があり果があるのであり、もろもろの樹にもすべて花果があるのであり、あるいはまた、金銀銅鉄珊瑚玻璃(はり)にも、地水火風空にも、すべて花があり果があるのである。さらにいえば、また人々(にんにん)すべて花がある。若きにも花があり、老いたる人にも花がある。そして、そのようなさまざまの花のなかにあって、世尊の説きたまえるは虚空の花である。
それなのに、いまだ見聞あさきともがらは、その虚空の花が、どんな色でどんな光をおびているか、あるいはどんな葉をひろげどんな花をひらくか、そこは一向に知らずして、ただ「空華」とのみ聞き及んでいるのみである。では、はっきりと知るがよい。仏道においてのみ空華が語られるのである。外道では空華のことは語られない。ましてやそれを覚(さと)りつくすものはない。ただもろもろの仏もろもろの祖のみが、ひとり虚空の花を知り、大地の花を知り、また世界なる花の咲きまた萎(しぼ)むを知っているのである。けだし、それらの花こそは、まさしく経典にほかならず、それこそ仏道をまなぶものの依るべき規準であると心得ているからである。そして、それらもろもろの花のなかにおいても、仏祖のよってもって宗(むね)とするところは虚空の花である。それゆえに、すべて仏の世界、ならびにもろもろの仏の説きたもうところは、とりもなおさず、空華であるというのである。
しかるに、世の凡愚なる輩どもは、如来はエイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)眼(げん)すなわちかすんだ眼のみるところが空華であると仰せられたと伝え聞いて、たいてい、つぎのように思っている。つまり、ケイ眼というのは、事実をありのままに見ることができない衆生のまなこをいうのであって、病める眼は事実をありのままに見えないのであるから、なんにもない虚空にありもしない華を見るのだろうと考える。そして、その考え方にとらわれているから、あるいは三界といい六道というも、あるいは仏ありといい仏なしというも、すべてみな、ありもしないのをあやまり見るのだと心得ている。さらにいえば、そのような迷妄を見る眼も病が よこなれば、もはやありもしない華などは見えないのであるから、それを「空にはもともと華などはない」というのだと、そんな解釈もするのである。
かわいそうに、そんな輩どもは、如来の語りたもうた空華とは、いかなる時、いかなる経緯で語られたものかも知らないのである。もろもろの仏たちがかすめる眼に空華をみると説かれた道理は、けっして凡夫や外道などの考えるようなものではないのである。もろもろの仏や如来は、すべてこの空華を修行しきたって、如来の室に入り、如来の衣を著し、如来の坐にいたることを得たのであり、あるいは、それによって拈華(ねんげ)し瞬目することをえたのである。つまり、それらはみな、かすめる眼の空華という公案を解いてそこに到ったのであって、それによって、正法の眼目を蔵するところ、涅槃というふしぎな心が、いまもなお正しく伝えられて断絶することがないのであり、あるいは菩提といい、涅槃といい、あるいは法身といい、自性(しょう)というなどは、すべてその空華の花のひらける花弁のひとひら、ふたひらに他ならないのである。(303~307頁)
〈注解〉高祖道……;高祖とは菩提達磨である。「一華開五葉云々」の引用句は、『景徳伝燈録』巻三、達磨伝にみえる。
四大・五蘊;人間を構成する物質的要素と精神的要素をあげて、そこよりいえば誰でも同じ人間であるといっておるのである。(307頁)
■釈迦牟尼仏はいった。
「また眼かすめる人(エイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)人)の、空中の花を見るにひとしい。眼のかすみ(エイ(翳、の羽が目の字。眼のかすめる)病)がなくなれば、花は空(くう)において滅するであろう」
その表現をあきらかにした学者は、いまだかってない。空ということを知らないから、空の華を知らないから、眼かすめる人を知らず、眼かすめる人を見ず、眼かすめる人にあわず、ましてや眼かすめる人ではないのである。よく眼かすめる人と相見(まみ)えてこそ、はじめて空華のなんたるかをも知り、みずから空華をもみることができよう。そして、ひとたび空華をみてよりのちは、また華が空にさえるということもわかるし、さらに、空華はひとたび滅しても、それで無くなってしまうものではないこともわかる。そのように思うのは、小乗の輩(やから)の見解だと知られる。
では、空華が消えてなくなった時には、それはどうなったのであろうか。彼らは、それをただ捨てられたのだろうとのみ考えて、そののちの大事なことを知らないのである。空華にもまた下種の時があり、成熟の時があり、また解脱の時があることを知らないのである。いまの一般の学者たちはたいてい、かの月日のてらすところが空であろうと思い、星辰のかかるところが空なのであろうと思っている。だから、たとえていうならば、空華というのは、この大気のなかに浮かべる雲のようなものであって、それが吹く風のまにまに、あるいは東西にうごき、あるいは昇りくだる。その間にはいろいろ色合いをも現ずるのをば、さてこそ虚空の花とでもいうのであろうと思っている。したがって、存在の要素としての地・水・火・風とか、物質的世界のもろもろの存在のありようとか、あるいはまた本覚とか本性とか、それ等のことを空華というのだということは、まるで気もつかないのである。したがってまた、もろもろの存在の法則というものがあって、それによって地・水・火・風存の諸要素とが存在を構成するのだということも知らないし、あるいはまた、もろもろの存在の法則があって、それによってこの物質的世界がちゃんと存在のありように住しているのだということも知らないで、ただ物質的世界があって、そこにもろもろの存在があるのだとばかり考えているのである。つまり、眼にかすみがかかっているから空華が見えるのだとばかり思っていて、空華があるからこそ眼にかすみがかかるのだという道理をさとらないのである。
それによっても知られるように、仏道において眼かすめる人というのは、本覚の人であり、妙覚(みょうがく)の人であり、あるいは、諸仏にひとしい人であり、三界にひとしい人であり、三界を知る人であり、また仏を超えてゆく人である。それを愚かにも、眼かすむといえば、それは虚妄(こもう)の法をみるのであって、真実の法はそのほかにあるのだとまなぶようなことがあってはならない。そんなのは凡庸の考え方である。いったい、かすめる眼の花などはありもしないものだとするならば、それを虚妄だと主張する方もせられる方も、いずれもありもせぬ虚妄のことをいっておることとなる。それでは両方ともありもせぬことを論じているのであって、そんな議論は成立する道理がない。もしその議論が成立する道理がないならば、かすめる眼の花は虚妄だというようなことは、結局いいえないことでなくてはならない。(312~314頁)
〈注解〉本覚;本有の覚性の意。人はもともと存在のあるがままを見うるものえあるが、煩悩のさまたげるところによってそれを歪曲して見るのである。とするならば、人はそれを払拭し、本来の面目を恢復することによって、覚性に立ちかえることをうるとするのである。(317頁)
■「涅槃といい生死というは、これ空華なるのみなり」
涅槃というは、仏の最高の智慧であって、仏祖やその弟子たちの住するところ。また生死というは人間のあるがままの相(すがた)である。つまり、涅槃といい生死というは、仏祖や凡夫のあるがままの相であるが、いまそれを空華であるという。その空華の根や茎や、枝や葉や、花や果や、さてはその光輝や色彩にいたるまで、つまるところは、みなその空華の花ひらく姿である。空華はかならず空なる果をむすび、また空なる種子を蒔くのである。とするならば、いま見るところの三界は、その空華の五弁の花のひらけるものであって、かって三界にあって見し三界とはいささか異なっている。つまり、コれこそ諸法のあるがままの相であり、これこそ諸法の華のすがたである。乃至は、さらに測り知れざる諸法があろうとも、それもみな空なる華であり、空なる果であり、いうところの梅・柳・桃・李に異なるところはないとまなぶがよい。(322頁)
〈注解〉一念;一念とは一刹那というほどの意。それによって刹那刹那の想いを指さすのであろう。
不生;生滅を超越したものであることを意味する。
真如;それは仏教的真理の根基をなすものであるが、その原語は“(略)”であって、万有のあるがままの相にほかならない。それを中国人は「柳は緑、花は紅」と表現したこともあり、鈴木大拙はこれを訳して“suchness”としたことも思い出される。
諸法実相;もろもろの存在のあるがままの相であって、それが仏教でいう真理の根底であるが、それもまた空華のすがたであるという。(323~324頁)
■福州芙蓉山の霊訓禅師(れいくんぜんじ)は、はじめて帰宗寺(きすじ)の至真禅師にまみえた時、問うていった。
「仏とは、いったい、どんなものでございましょうか」
帰宗(きす)はいった。
「では、いって聞かせようが、そなたは信ずるであろうか」
霊訓はいった。
「和尚の御ことばを信ぜずしてどういたしましょう」
帰宗はいった。
「ではいうなれば、そなたがとりも直さず仏である」
霊訓はいった。
「それをどのように受領したならばよろしゅうございましょうか」
帰宗はいった。
「ちょっとでも眼が翳(かす、羽が目)めば、空華はたちまち乱れ散るであろう」
いま帰宗のいうところの「一翳(えい、羽が目)目にあらば空華乱墜(らんつい)す」とは、思うにすでに仏たるもののいうところである。よって知ることができる。かすめる眼の華が乱れ散るというは、仏を実現することである。眼において結ぶ空華のみのりは、仏たることの保証である。かすむことによってその眼が成るのである。そこのところは、「空華眼にあれば、一翳(えい、羽が目)が乱れ散る」といってもよいであろうし、また、「一眼空にあれば、さまざまの翳(かすみ、羽が目)が乱れ散るのだ」といってもよいであろう。かくて、翳(かすみ、羽が目)もまたあらゆる可能性を発現し、眼もまたあらゆる可能性を発現する。あるいは、空もまたあらゆる可能性を現わし、華もまたあらゆる可能性を現ずるのである。また、乱れ散るというのは、いうなれば観音の千眼(げん)であり、その身がすべて眼なのである。つまり、この一眼のある時ある処には、かならず空なる華があり、眼の華があるのである。眼の華を空なる華というのである。その眼華なることばを、きっと智見をもって明らかにするがよい。(327~328頁)
■石門山の慧徹禅師(えてつぜんじ)は、梁山縁観(りょうざんえんかん)の門下の長老であるが、ある時、ひとりの僧が禅師に問うていった。
「いかならんかこれ山中の宝」
この問いの意味するところは、たとえば、「いかならんかこれ仏(ぶつ)」と問うにおなじであり、あるいは、「いかならんかこれ道(どう)」と問うようなものである。
禅師は答えていった。
「空華は地より発(おこ)る。だが、国をあげて買わんとするも手立てはない」
このことばは、まったく他のことばに較べていうことができない。世のつねの諸方の老師たちのそれは、空華を論ずるにあたって、ただ、空華は空において生じ、さらに空にあって滅すると語っているのみである。そこをさらに一歩すすめて、それは「空より」発ると知っているものもいまだない。ましていわんや、それが「地より」開くものと誰が知っていよう。それはただ石門だけである。
その「地より」というのは、終始かならず地からということであり、また「発(おこ)る」というは「開く」ということである。まさにその時には、大地のいたるところより発るのであり、大地のありとあらゆるところに開くのである。それが「国をあげて買わんとするもその手立てはない」というのは、国じゅうにはそれが欲しいと思うものはないわけではないが、誰もそれを買うべき手立てはないというのである。また、地より発る空華があるという、それはまた、この大地のことごとくが華によって華ひらくということである。したがってまた、そこには、空華は地をも空をもともに華ひらかしめるという意味があると知るがよろしい。(329~330頁)
〈注解〉眼華;空華は眼にある華であるから、またかくいうのである。
空華の空華を論ずる;仏祖が空華について語るのは、つまり空華が空華を論ずるものに他ならずとするのである。(331頁)
菩 提 薩 埵 四 摂 法 ( ぼ だ い さ っ た し し ょ う ぼ う )
■開 題
この一巻の構成はいたって簡明である。それは、菩提薩埵すなわち菩薩の行ずべく定められた、「四摂法」の四つの項目をならべて、それをつぎつぎに解説したのみのものである。「四摂法」というのは、注解にもしるしておいたように「衆生を摂取するための四つの項目」というほどの意味のことばであって、「布施」と「愛語」と「利行(りぎょう)」と「同事」がその四つの項目にあたる。そして、この巻においては、その四つの項目がつぎつぎに解説されているのみである。
しかるに、その解説がそれぞれに素晴らしいのである。たとえば、その第一の項目である「布施」について、道元は、いきなり、
「その布施といふは、不貧(ふとん)なり。不貧といふは、むさぼらざるなり。むさぼらずといふは、よのなかにいふへつらはざるなり」
と示している。思うに、わたしどもは、これまでに、「布施」の説明として、いまだかって、それは「不貧」であると耳にしてこともないし、あるいは、それを「へつらはざるなり」と目にしたこともなかったのではないか。いったい、「布施」について、どこからそのような説明のことばが生まれてくるのであるか。それは、つまるところ、より深く掘りさげられた鍬(くわ)の下からのみ、はじめて新しい泉は滾々(こんこん)と湧きでてくるのだというのほかはないであろうし、省みて、わたしどもが従来の布施についての思索が、いかに平板にしてただ表面的現象をのみ撫(ぶ)するものであったかが歎かれるのである。「へつらはざるなり」の一句については、わが思いの及ばざるを恐れて、註解には古註の一節をひいておいた。参看していただければ幸いである。
またたとえば、ついで道元は、その第二の項目である「愛語」に語りいたるが、そこでは、今度は、まことに道元らしい簡潔にして、また美しい章句をつらねている。なかでも、わたしがしばしば愛吟して措かざる一節はつぎのようである。
「怨敵を降伏(ごうぶく)し、君子を和睦ならしむること、愛語を根本とするなり。むかひて愛語をきくは、おもてをよろこばしめ、こころをたのしくす。むかはずして愛語をきくは、肝に銘じ、魂に銘ず。しるべし、愛語は愛心よりおこる、愛心は慈心を種子(しゅうじ)とせり。愛語よく廻転のちからあることを学すべきなり、ただ能(のう)を賞するのみにあらず」(355~356頁)
■一つには、布施。
二つには、愛語。
三つには、利行(りぎょう)。
四つには、同事。
その布施というのは、不貧(ふとん)、すなわちむさぼらざることである。むさぼらないというのは、世の中にいう諂(へつら)いのこころなきことである。たとい全世界をすべて領していても、人々を教化して正しい道に帰せしめようとするならば、どうしても不貧でなくてはならない。それは、たとえば、捨つべき宝を見も知らぬ人に施すがごとくでなくてはならない。むかしより遠き山の花を如来に供養するということがあり、また前世のたからを衆生に施すということがあるが、教法にしても、物品にしても、いずれも布施するにふさわしい性質をもともと具えているのである。わが物ではなくっても、布施できないという道理はないのである。その物が軽少だからといって嫌ってはならない。それが本当に役立てばよいのである。道は道に打ちまかせて純一無難なるがよく、その時はじめて道が得られる。得道(とくどう)の時には、かならず、道が道に打ちまかされて、おのずからにしてそれがなるのである。そして、いま財貨もまたそれ自身に打ちまかされる時、その財貨はかならず布施となる。自分に施すべきものは自分に施し、他に施すべきものは他に施すのである。そのような布施のえにしによるちからは、とおく天界までも通じ、人間界にも通じ、また証(さとり)を得た聖者たちにも通ずるであろう。なんとなれば、その時、彼らは、あるいは布施の施し手となり、また受け手となって、たがいに縁を結ぶからである。だから、仏もかって仰せられたことがある。
「布施する人が衆人のなかにある時、諸人はまずその人を仰ぎみるであろう」
それによっても、目にみえずとも、心が通ずるということが判るではないか。だからして、一句一偈(げ)の法をも布施するがよい。さすれば、それが今生・他正のよき種をまくこととなる。あるいは一銭・一草の財(たから)をも布施するがよい。そうすれば、それがこの世あの世のよき報いの種子ともなるのである。法も財(たから)であろう。財も法であろう。願う心があればそうなるのである。
まことに、ふるくは、髭(ひげ)を施して民の心をととのえたという故事もあり、あるいは、砂を供養して王位を得るということもあったという。ただ相手の反対給付をむさぼることなく、自己のもてる力をわかつのである。渡場に舟をおき、あるいは橋を架けるのも、布施のいとなみである。もしよくよく布施をまなんでみるならば、よき身をうけて人のためとなるも布施、あるいは、この身を捨てるのも布施、治生産業(ちしょうさんごう)すべて布施にあらざるはない。花を風のふくに委(まか)せ、鳥を季のうつりかわりに委せるというも、また布施のいとなみであろう。むかし阿育(アショカ)大王は、半分のマンゴーをもってよく数百の僧たちを供養したというが、それをこそ大いなる供養なりとなす道理を、施すものもまた受来る人もよくよくまなぶがよい。ただにおのが身の力をつくして供養するのみならず、また時におよんでの布施というものも考えるがよいのである。
思うに、この身は、前世にうえた布施の徳があったればこそ、いまこの身を得ているのである。だから、仏も仰せられたことがある。
「この自分にだって、なおこれを受け用いることができる。ましていわんや、これを父母や妻子に与えずしてなんとするぞ」
それによっても知られるではないか。自分で用いるのも布施の一分である。父母や妻子にあたえるのも布施にちがいあるまい。もしまた、よく布施として塵ひとつほどのものでも捨てようとする時には、たといそれがいたらぬ自己の所作であろうとも、しずかに喜びの念をいただくがよろしい。なんとなれば、それは、もろもろの仏のつみたもうた功徳のひとつを、いまわれも正伝してつくっているのだからであり、また、それは菩薩の修したもうた法のひとつを、いまわれもはじめて修しているのだからである。
まことに転じがたいのは衆生の心である。だが、一つの財をきっかけとして、それで衆生の心が転じはじめたならば、それを得道にまで転じてゆくこともできようかと思われる。その手はじめは、かならず布施をもってすべきである。だからして、六波羅蜜のはじめに檀波羅蜜があるのである。心の大小もまたはかることはできないけれども、心が物を転ずるという時があり、また物が心を転ずるということがある。そして、布施とはそのことに他ならない。(359~362頁)
〈注解〉六波羅蜜;度と訳し、また到彼岸と訳する。それを修して菩薩がその目的に到達しうるところの行業である。それに、施・戒・忍・精進・定・慧の六つがあげられ、これを六波羅蜜というが、その第一にはつねに施波羅蜜すなわち檀波羅蜜がおかれている。檀とは檀那であって、それを訳すれば施もしくは布施である(363頁)
■愛語というのは、衆生をみていつくしみ愛する心をおこし、心にかけて愛のことばを語ることである。およそ荒々しいことばはつつしむことである。世俗にも安否を問うという礼儀があり、仏道には「お大事に」と自愛自重をすすめることばがあり、また「ご機嫌いかがでございますか」と問う礼儀がある。「衆生を慈しみ念ずること、なお赤子(せきし)のごとし」というが、そのような思いを内にたくわえてことばを語る、それが愛語である。
徳あるものは賞めるがよい。徳なきものは憐れむがよい。その愛語をこのむところから、いつとはなしに愛語は成長してくるのである。そうすれば、つね日頃は思いもかけぬような愛語もふっと現われてくるようなこともある。だから、いまのこの身命のつづくかぎりは、このんで愛語するように力(つと)めるがよい。また、世々生々(せぜしょうじょう)にも退転することのないようにと念ずるがよい。
思うに、怨敵をして降服(ごうぶく)せしめるにも、君子をして仲むつまじうせしむるにも、いつも愛語を根本とするのである。相向って愛語をきけば、おのずからにして面(おもて)によろこびがあふれ、心をたのしうするであろう。また、相向わずして愛語を聞いたならば、それは、肝に銘じ、魂をゆりうごかすであろう。けだし、愛語は愛心よりおこるものであり、愛心はまたいつくしみの心を種子としてなれるものだからである。まことに、愛語はよく天を廻(めぐ)らすほどの力あるものなることをまなばねばならない。ただ能力あるを賞するのみではいけないのである。(364~365頁)
〈注解〉珍重・不審;珍重とは、「御身お大事に」よ、自愛自重をすすめることばであり、不審とは、「ご機嫌いかがでございますか」と訊ねることばである。比丘が相わかれ、相見える時の作法のことばであって、朝起きた時には不審、夜寝(い)ぬるにあたっては珍重というのがならいである。
■利行(りぎょう)というのは、貴きと賤(いや)しきをえらばず、人々のために利益になるように手立てをめぐらすことである。たとえば、遠いまた近いさきざきのことまで見守って、他人を利するような手段を講ずるのである。窮した亀をあわれみ、病める雀をやしなうのもそれであるが、その時、彼らがその恩返しをすることを期待せず、ただひとえに利行を旨としてそれをなすのである。
しかるに、世の愚かなる人々は、他人を利することを先きとすれば、自分の利益がそれだけ駄目になるのだと思っている。だが、そうではないのである。利行とはそんな半端なものではない。あまねく自己をも他人をも利益するのである。むかしの人は、一たび沐浴するに三たび髪をゆい、一たび食事するに三たび口にいれたものを吐いたことがあった(岡野注;周公の三吐握)というが、それはひとえに他人を利せんとする心であった。よその国の者ならば教えないというのではなかった。
つまり、仇(あだ)も味方もひとしく利するべきであり、自己をも他人をもおなじく利するのである。もしこの心を会得すれば、草や木や風や水にまで、利行がおのずから及ぶというものであって、それこそまさに利行というものである。ただひたすらに愚かなることはなすまいと励むがよいのである。(366~367頁)
■同時というは、違(たが)わざることである。自己にもそむかず、他者にもたがわず、たとえば、人間界にあらわれた如来は、人間界の住みびとにまったく同(どう)じたもうたごとくである。人間界にあれば人間界に同じたもうたのであるから、如来はまた余(ほか)の世界にあれば、その世界に同じたまうであろうと知られる。つまり、同時ということを知るとき、自らもも他もまったく一如なのである。むかしから、琴(きん)・詩・酒(しゅ)においては、人は、人を友とし、天を友とし、また神を友とするという。人が琴・詩・酒を友とすれば、琴・詩・酒は琴・詩・酒を友とし、人は人を友とし、天は天を友とし、神は神を友とするということともなる。これが同事のまねびである。たとえば、事(じ)というのは、儀(ぎ)(のり)であり、威(い)(かたち)であり、態(たい)(さま)である。他者をして自己に同ぜしめることは、同時に自己をして他者に同ぜしめることであろう。自と他とは、時にしたがって、無限に交流するものである。『管子』にいわく、
「海は水を辞せず、故によくその大を成す。山は土を辞せず、故によくその高きを成す。明主は人を嫌わず、故によくその衆(しゅ)を成す」
よりて知るがよい。海は水を辞せずという。それが同事である。さらに知るがよい。水もまた海を辞せない性状を具備しているのである。だからして、よく水があつまって海となるのであり、また土が積もり重なって山となるのである。かくて、ひそかに思えば、海は海を辞さないからこそ、海を成し、その大を成すのである。また、山は山を辞せざるによりてこそ、山を成し、その高きを成すのである。さらにまた、明主は人を厭わざるがゆえにこそ、その衆をなすのである。衆というのは国である。だから、いうところの明主とは、帝王をいうのであろう。帝王は人を厭わないのである。人を厭わないからといって、賞罰のことがないわけではないが、賞罰はあっても、けっして人をきらわないのである。むかしの人は素直であったから、国にはいわゆる賞罰というものがなかった。かの時代の賞罰は、いまのそれとはちがうのである。いまも、賞せされることを期待せずして道を求める人があってよいはずであるが、それは愚かなるものの思慮のおよぶところではあるまい。だが、明主は心あきらかであるから、人を厭わないのである。いったい、人はかならず国を成し、そして明主をもとめる心がある。だが、明主が明主たるの道理をくまもなく知るものは稀である。だから、明主に厭われないことだけを喜ぶのであるが、同時にまたそれは、自己が明主を厭わないのだとは気がつかない。つまり明主にも、また愚人にも、同事の道理があるのであって、それがまた生きとし生けるものの願いであり、また行ずるところである。かくて、ただまさに、いつも和(おだやか)な顔容をもってすべての人に接するがよいというのである。(370~371頁)
葛 藤 ( か っ と う )
■いったい、もろもろの聖者たちは、たいてい、葛藤の根源を切断するという方向にのみ傾向して、どうも、葛藤をもって葛藤をきるという行き方をするものはない。あるいは、葛藤をもって葛藤にまつわるということも知らないし、ましてや、葛藤をもって葛藤に嗣ぐなどとはとても知るまい。嗣法はすなわち葛藤なのだといっても、そんなことを知ったもの、聞いたものは滅多にあるまい。ましてや、そんなことを言いえたものは、とてもあるまい。そうと証りえたものも、めったにありはすまい。
しかるに、先師なる如淨古仏は語っていったことがある。
「夕顔の蔓らしいものが夕顔にまつわりついているわい」
この示衆(じしゅ)のことばは、いまだかって古今のもろもろのご老師たちにおいて見聞しないところであり、ひとり先師如浄において語り示されたものである。夕顔の蔓にまつわっているというのは、仏祖が仏祖に参学し、仏祖が仏祖に印可を与えることをいっておる。たとえば、以心伝心というがごときである。
第二十八祖菩提達磨は門人たちに語っていった。
「時はまさに至らんとしている。そなたたちは、ひとつ、その得たるところをいってみてはどうじゃ」
そこで、門人の道副(どうふく)がいった。
「わたしのいまの所見をもうしますと、文字に執せず、文字を離れずして、大道の用をなすということでございます」
初祖はいった。
「そなたは、わが皮を得たのである」
ついで、比丘尼の総持(そうじ)がいった。
「わたしのいま理解するところを申しあげますれば、よろこび喜んで阿閦(あしゅく)仏の国土を見たけれど、一たび見しのちは、さらに再見せずというところでございます」
初祖はいった。
「そなたは、わが肉を得たのである」
つぎに、道育がいった。
「四大はもと空にして、五蘊もまた存するものにあらず。されば、わたしの見るところをいわば、一物として得べきものなしというところでございます」
初祖はいった。
「そなたは、わが骨を得たのである」
最後に、慧可は、初祖に向って礼拝すること三たびしてのち、あるべき位置によって立った。すると、初祖は彼に向っていった。
「そなたは、わが髄を得たのである」
そして、果せるかな、慧可を二祖となして、法を伝え、また衣を伝えたことであった。(382~383頁)
■しかるに、いまだ正伝を得ない輩たちが考えるところは、たいてい、その門下の四人の解するところにそれぞれ浅い深いがあったので、祖師もまた、皮・肉・骨・髄の四つの文字を、その浅深にあてて語りたもうたとするのである。つまり、皮・肉は骨・髄よりも浅いのだと思い、二祖の見解はもっとも勝れていたので、「髄を得たり」という印可を得たのだというのである。そんなふうにいうのは、いまだかって仏祖にまなんだこともなく、仏祖のじきじきのことばをいただいたこともないからである。
はっきりと知らねばならない。初祖がいうところの皮・肉・骨・髄とは、けっして見るところの浅深を語ったものではない。たとい門下の見解に優劣がありとしても、諸祖のいうところはただ「吾を得たり」のみである。その意味は、「吾が髄を得たり」というも、また「吾が骨を得たり」というも、いずれも「人のためにするときには人に接し、草を拈ずるときには草に落つ」というところであって、それでは足りた、それでは足りないというのではない。そこの呼吸は、たとえばかの拈華(ねんげ)のごとくであり、あるいは、たとえばかの伝衣(え)のようなものである。四人の門下のためにいっておることは、終始おなじである。ただ、祖師のことばはおなじであっても、四人の見解はかならずしも等しいわけではない。だが、四人の見解はいろいろであっても、祖師のいうところはあくまでひとつなのである。(384~385頁)
■もしも祖師の門下にもっと多くの門人があったならば、祖師はおそらく、「汝はわが心を得たり」とも説いたであろう。「汝はわが身を得たり」とも説いたであろう。あるいは、「汝はわが仏を得たり」と説いたかも知れない。「汝はわが眼睛(がんぜい)を得たり」とも説いたであろう。また、「汝はわが証(しょう)を得たり」とも説いたであろう。そして、そこにいうところの「汝」は、それが祖師である場合があり、また、慧可である場合もある。それには、その「得」の道理をよくよく思いめぐらしてみるがよろしい。つまり、「汝はわれを得たり」ともいえるし、「汝とわれを得たり」ともいうこともできよう。そもそも、祖師の身心を考えてみて、いかに達磨でも、その内と外とがまったく同じだということはありえないとか、あるいは、その全身がすべて等しいなどということはあり得ないなどというならば、それは仏祖の実現したまえる国土というものをまったく知らないのである。(386頁)
■皮を得たのならば、それは骨をも肉をも髄をも得たのである。骨・肉・髄を得たのは、それはまた皮肉をも面目をも得たのである。それはただ尽十方世界の真実のありようがそうだというのみではない。また、このわれや汝の皮・肉・骨・髄がすべてそうなのである。だからして、それをまた、「わが衣を得たり」というし、「汝はわが法を得たり」ともいう。そのように、師家のいい方にも、いろいろと凡俗を抜け出したところがあり、また、学人の聞くとこともさまざまと自由自在のところがあって、そこではもう師も弟子もまったく異なるところはない。その師と弟子のもはや異なるところのない道理を仏祖の葛藤とはいうのであり、その相からまりあっているところが、いまの皮・肉・骨・髄のいのちとするところである。つまり、拈華し瞬目したまえるのが、すなわち葛藤であり、あるいは、破顔微(み)笑したまえるのが、皮・肉・骨・髄にほかならないのである。そこをさらに学び究めてみるがよろしい。すなわち、その葛藤が種子(しゅうじ)となって、そこから枝葉をのべ、花を開き果を結び、それらが葛藤をめぐって、たがいに交渉しあうのであるから、そこに仏祖も実現するのであり、さとりも実現するのである。(387頁)
〈注解〉得吾如(にょ);吾が汝であり、汝が吾である境地にいたることをいうのであろう。それは、つまり、自他のわかちを超えていることに他なるまい。(388頁)
■趙州(じょうしゅう)の真際(ざい)大師は衆(しゅ)に示していった。
「迦葉(かしょう)は阿難に伝えた。では、達磨はどんな人に伝えたか、いって見よ」
すると、一人の僧が問うていった。
「かの二祖が髄を得たというが、そうではないのですか」
趙州はいった。
「二祖をそしってはいけない」
やがて、趙州はかさねていった。
「達磨はまた語って、外にある者は皮を得、内にある者は髄を得るといったという。では、いってみるがよい。さらに奥にあらん者は、いったい何を得るだろうか」
僧は問うていった。
「では、そもそも髄を得るというのは、どういうことでありましょうか」
趙州はいった。
「ただ皮をよく識るがよい。わしの内にだって、べつに髄などというものはありはしない」
僧はいった。
「その髄とは、いったい、どんなものでございましょう」
趙州はいった。
「そんなことをいっていたのでは、皮だって摸(さぐ)りあてることはできまい」
これによっても知るがよい。皮も摸りあてることができない時には、髄もまた判りっこはないのであり、よく皮を知りうる者は、また髄をも得ることができるのである。「そんなことをいっていたのでは、皮だって摸りあてることはできまい」というそこの道理を、よくよく思いめぐらしてみるがよいのである。(392~393頁)
■さきの仏祖も、古仏の讃辞をもって趙州を讃歎した。のちの仏祖もまた、古仏の讃辞をもって趙州を讃歎する。それによっても、趙州が古今のさまざまの仏祖をも抜きんでた古仏であったことが知られるのである。だからして、いま趙州がいうところの皮肉骨髄の微妙な関係は、かの古仏が語りともうた「汝われを得たり」の言句を解くべき基準である。では、その基準たるところを、よくよく思いめぐらして、学び究めるがよろしい。
また、初祖菩提達磨は、そののち西帰したという。それは正しからずとわたしは学んでいる。宋雲の見しところは、かならずしも真実ではあるまい。宋雲などがどうして祖師の進退を知るはずがあろう。ただ祖師は亡くなられたのち、熊耳山(ゆうじさん)に骨を納めたとのみしるのが、正しいまなび方である。(395頁)
〈注解〉趙州真際大師;趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん、897寂、寿120)。馬祖道一の法嗣(ほっす)。諡(おくりな)して真際大師と称する。
雪峰真覚大師;雪峰義存(ぎそん、908寂、寿87)。徳山宣鑑(とくざんせんかん)の法嗣(ほっす)。賜号あって真覚大師と称する。
宋雲;北魏の僧、勅命によって天竺に使し、葱嶺(そうれい、パミールの辺り)において達磨に遭ったという。(396頁)
(2016年2月14日)