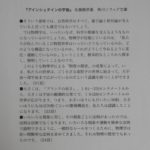『道元「永平広録 真賛•自賛•偈頌」』大谷哲夫 全訳注 講談社学術文庫
はじめに
■日本では中国の詩文芸としての絶句や律詩などの漢詩文を一般に漢詩といいます。偈頌は形態的にはこの漢詩形によりますが、その内面はあくまでも仏教的真実の世界、または仏徳や諸禅徳のさとりの行実(ぎょうじつ)を讃えたり、禅の教義や真実を詠ずる言語表象で、それは単なる情緒的な文芸詩とはその趣を全く異にします。したがって、偈頌は形式的には漢詩の範疇(はんちゅう)にはありますが、強いて表現すれば「仏教思想詩」「禅仏法の漢詩」「さとりの漢詩」ともいえるものなのです。(4頁)
■「風鈴の頌」というのは、道元自身の在宋時代の求道(ぐどう)の系譜ともいえる在宋留学記『宝慶(きょう)記』では、第一句と第三句のみ提示されますが、『正法眼蔵』「摩訶般若波羅蜜」巻には、
渾身似口掛虚空 渾身口に似て虚空に掛かる
不問東西南北風 問わず東西南北の風
一等為佗談般若 一等に他の為に般若を談ず
滴丁東了滴丁東 滴丁東了滴丁東(てきちょうとうりょうてきちょうとう)
とあります。ちなみに、『如浄語録』巻下では、「渾身似口」は「渾身是口」に、「不問東西」は「不管東西」に、「一等為侘」は「一等与渠」となり、『宝慶記』では「一等与他」となるなどの小異があります。この偈頌は、一読する限りでは、風鈴が全身を口にして虚空に掛かり、東西南北どのような風にも対応し、ちりりんちりりん、ちりりんと鳴っているという単なる風鈴の風情を詠じたもののようです。が、道元は、この風鈴の頌を風鈴がつねに般若を談じ仏の世界を顕現している風情を頌したものととらえ、この偈頌を拝読した時の感動を「歓喜踊躍(やく)、感涙衣をうるおす」と、『宝慶記』に記しています。
では、道元はなぜこの「風鈴の偈頌」に歓喜し感涙したのでしょうか。
それは道元在宋中の如浄膝下にあったある日のことに起因します。
如浄はまさに輿(こし)に乗り出かける寸前のことでしたが、道元は礼をつくして声をかけます。「たまたま、和尚の風鈴の頌を承りましたが、その第一句には『渾身口に似て虚空に掛かる』とあり、第三句に『一等に他の為に般若を談ず』とあります。この虚空は、単なる青い空をいっていないにも拘(かか)わらず、仏法をわきまえない人は、さも実体があるかのようにとらえて、必ずその虚空を紺碧の空のことだなどといいます。最近の参学者は、まだ仏法を窮めていないので、青い空を仏法の虚空と同じだととらえています。真に憐憫すべきことだと思います」
すると、如浄は慈誨(かい)していわれたのです。
「虚空というのは、広大無辺な仏法の智慧・般若をそのように表現したのである。目にみえる紺碧の空・青空のことではない。虚空というのは、般若そのものであるから、遮(さえぎ)るものがある(有礙)わけでもなければ、遮るものがない(無礙)わけでもない。また偏真(へんしん)などという真と虚とに分けて真のみの世界を空想し執着(じゃく)するものでもない。それらは虚空ではない。諸方の長老たちは、物質の存在する現実の世界(色法)が分かっていない。空と色を別のものと思っているから、空のことなど理解できるはずがない。しかし、私のいるこの場では、大宋国の仏法が衰微したなどとはいうべきではない。正伝の仏法は、今、ここに、生きて、あるのだ」
道元は、感謝の御拝をし、次のように申し上げます。
「この風鈴の頌は、私の大好きな最高の偈頌です。いまの中国の長老方では、たとえ三阿僧(そう)祇劫という無限な時間を経たとしても、とても作れるものではありません。雲水たちはそれぞれこの頌を大切にすべきです。私、道元は遠い辺地の日本からやって来て、仏法に対して寡聞にして少見ではありますが、いま、『伝灯録』の類(たぐい)および諸師方の語録を見ても、この『風鈴の頌』に匹敵するものを見たことはありません。私は、幸せにもいま、それを見聞し、歓喜し踊躍し、感涙袖を濡らす状態のなかで昼夜合掌し拝受いたしております。なぜならば、この偈頌は、虚空というものをものの見事に表現しながらも、偈頌としてその調子が真に格調高くすばらしいからです」
すると、如浄は微笑しながら次のように慈誨します。
「汝(きみ)のいうところは深く、抜群の見識がある。私は、この頌を健康府の清涼寺に住職しているときに作った。諸方の長老たちは讃歎こそすれ、いままでに一度も汝のように説き明かしたものはいなかった。私は、天童山(ざん)の住職として、汝に、仏法を見極める確かな識眼があることを認める。汝も頌を作ろうとするときは、このようにつくりなさい」
古来、禅門においては、この「虚空」をどうとらえるか、つまり己の存在にどう拘わるのかという点がある種の命題となっていて、祖師方もその参究に懸命でした。たとえば、馬祖道一(709ー788)の弟子・石鞏慧蔵(しゃっきょうえぞう、生没年不詳)と西(せい)堂智蔵(735-814)とによる虚空についての次のような問答があります。
兄弟子である石鞏が弟弟子の西堂に「虚空をつかむことができるか」と問うと、西堂は手で虚空をつかむ仕草をします。石鞏は「それでは虚空の真実をつかんでいない」といって、西堂の鼻をつかんで強く引っ張ったので、西堂は忍痛の声をあげます。石鞏は、西堂の悟道の因縁をつくったのです。
「虚空」というのは、常識的には紺碧の空であり、宇宙的な大空間です。が、道元の、「風鈴の頌」への拝問に、如浄が「般若のことを虚空と表現したのだ」と明確に慈誨するように、虚空は、一般でいう紺碧の空という意味ではなく、般若つまり仏法の無辺なる智慧が虚空なのです。「虚空つまり般若」、その果てしない無限な仏法の宇宙的な大空間、それは、すべての事象を包含しその存在を少しも妨げず、我々自身もそのなかに存在しているのです。
そうであるならば、そのただなかに存在する我々が、そのなかで、綿密に功夫(くふう)し弁道し発心(ほっしん)し修証し、生かせれてあるので、虚空こそが仏祖のいのち、あるがままの己の存在そのものとなります。そのような虚空の究極の真実を会得する決定的な視点を与えてくれた因縁の偈頌が、まさにこの如浄の「風鈴の頌」であったのです。換言しますと、中国に渡ってまで追い求めた仏法の究極、さとりの世界を原体験することを模索し続けていた道元に、この「風鈴の偈頌」は、その世界をまさに言葉という表象の世界でものの見事に表現して、その世界に決定的な示唆を与えたものであったのです。如浄の「風鈴の頌」にはそれだけの背景があり、それを如浄と道元という稀有な禅者が共有しえたからこそ、それが、先の道元の「感涙衣をうるおす」という表現になっているのです。道元の「感涙衣をうるおす」という表現は、正伝の仏法がまさに正しく伝承され眼前に展開されている現場に遭遇した場合の感動のみに限られます。したがって、この偈頌は、道元の偈頌観と作頌するときの覚悟を示唆しているので、少し長くなりましたが、提示してみました。
ですから、この偈頌への感動は、道元は終生持ち続けることになります。このは、まず、道元34歳のときの『正法眼蔵』「摩訶般若波羅蜜」巻に、さらに46歳のとき、越前に移り大仏寺の建立の翌年、寛元3年(1245)3月の『正法眼蔵』「虚空」巻でも、また、『永平広録』巻9-頌古(祖師の遺した古則に対して偈頌でその宗意を簡潔に宣揚したもの)の58では、本師如浄の「風鈴の頌」に対して、「渾身是口虚空を判ず、居起東西南北の風 一等に玲瓏として己語を談ず 滴丁東了滴丁東」と作頌しています。つまり、眼に見えない風は、東西南北どこからも吹いてきて、虚空に掛かる風鈴を鳴らすが、その響く鈴の音は、風鈴が全身、虚空となってちりりんちりりんと般若を語り、虚空そのものを現していると示した頌古はに対しての著(じゃく)語(自分自身の宗旨眼をもって祖師の頌などを短評する語)といってもいいものなのです。(7~13頁)
玄和尚真賛
侍者 詮慧(せんね)等編
■仏樹和尚(ぶつじゅおしょう)
平生の行道(ぎょうどう)徹通して親しし、寂滅より以来(このかた)面目新たなり、
且(しばらく)く道(い)え如何が今日の事(じ)、金剛焔(えん)の後(のち)真身(しんじん)を露(あらわ)す。
〈現代語訳〉
仏樹和尚
わが師仏樹和尚の仏道修行は、真に徹底を極めておられ、
ご示寂(じじゃく)後もその面目は不滅で、今日にいたっても新たに輝いておられる。
私は、いまも、今日は如何(いかが)ですかと問いかけたい。
師は、荼毘(だび)され金剛炎となられたが、その真実は今日にいたっても露堂々として現前しておられるので。
〈語義〉
○仏樹和尚 道元の師、栄西(1141-1215)の高弟。明全(1184-1225)のこと。
○金剛焔 仏身を金剛をも焼きつくす火炎のなかに投じて荼毘に付したが、明全の真身は生死去来にあずからない堅固無相の法身(ほっしん)なのである。
〈解説〉
道元の本師は天童如浄(1163-1228)であるのはいうまでもない。が、その本師とする如浄に巡り合うまでの、道元の参学の師は多く、なかでも明全は、道元が『正法眼蔵』「弁道話」巻において「予発心(ほっしん)求法(ぐほう)よりこのかた、わが朝の遍方に知識をとぶらいき。ちなみに建仁の全公(明全)をみる、あいしたがう霜華(そうけ)、すみやかに九廻(くじゅん)をへたり。いささか臨済の家風を聞く。全公は祖師西(栄西)和尚の上足(じょうそく)として、ひとり無上の仏法を正伝せり、あえて余輩のならぶべきにあらず」と述べるように、道元の十八歳から二十六歳にいたる時代の都合ほぼ九年間、道元の生涯で最も随侍された忘れがたき師の一人である。
明全は伊賀(現在の三重県)の人。八歳で出家、横川首楞厳院(よかわしゅりょうごんいん)の明融(みょうゆう)阿闍梨の弟子となって天台学を修め、十六歳で東大寺の戒壇院で具足戒を受け、延暦寺で円頓(どん)戒を受ける(『明全和尚戒牒(ちょう)奥書』による)。その後、諸方を遊学、建仁寺を開創した栄西の門下となり、一説にはその示寂後建仁寺の住職となったともいう。道元は、栄西や横川の縁で、建保五年(1217)八月、明全に投じている。貞応二年(1223)二月二十二日、明全は死の床にある師・明融阿闍梨の、今回の入宋(にっそう)を中止し、自分を看病し死を看取ってから入宋の本懐を遂げるように、との懇願を、仏法のためと意を決して(師の入宋にいたる決意経過は、『正法眼蔵随聞記』〈巻6-13〉に活写されている)、道元・廓然・亮照とともに入宋した。はじめ景福寺に参じ、次いで天童山の無際了派(1145-1224)に参ずる。在宋3年、ようやくその名が知られるようになった矢先の宝慶(きょう)元年(1225)五月二十七日、辰の刻(午前八時頃)天童山の了然寮にて示寂、享年42歳。明全はその死に臨み、衣装を整え、正身端坐のまま入寂した。荼毘に付すと、火五色に変じ、白色の舎利三顆(か)を得、拾うにつれて370余顆となったという。道元は明全の真景に賛するにあたり、その際のことも脳裏にあったものと思われる。その舎利は道元が帰国のときに持ち帰り、建仁寺開山堂の入定(にゅうじょう)塔の前には明全の五輪塔が建てられている(『明全和尚戒牒(ちょう)奥書』『舎利相伝記』)。
道元の大(だい)悟徹底は、恩師明全示寂後間もなくの夏安居も終わりに近い日のことであることを勘案すると、明全の示寂は道元に計り知れないほどの極めて強い影響を与えたことを示唆している。つまり、明全の存在は、道元の入宋求法大悟徹底の本懐を遂げさせるための先導師、つまり明全の存在こそが、道元にとっては菩薩そのものではなかったのかと思えてくる。
本真賛は、そうした道元の、先師仏樹房明全和尚への心の奥底からの報恩の賛頌である。道元はそれゆえにこそまた、『永平広録』巻6ー上堂435において仏樹和尚(明全)の27回忌(建長三年〈1251〉五月二十七日)には追善上堂して、
山僧(さんぞう)、今日、仏祖の第一義門を開演す。所生(しょしょう)の功徳、先師大和尚に廻向す。
として、阿難の七仏偈(諸悪莫作、諸善奉行、自浄其意、是諸仏教ーもろもろの悪を作さず、もろもろの善行をなし、自らその意旨を浄化する、これこそが諸仏の教えである)を説示し、最後に、
弟兄(でいひん)仏口(ぶっく)所生子(しょうし)、一偈単伝する、是(これ)、本孝(こう)。
(弟である阿難尊者も兄の迦葉(かしょう)尊者もともに、尊者の教説から生まれた真実の仏法の子らである。その子らが、そのすぐれた一偈(ことば)を仏祖から仏祖へ純粋に相伝したように単伝すること、そのことこそが真実の「孝」というものである。)
と廻向している。さらに翌年の建長四年の忌辰にも追善上堂している。(50~54頁)
自賛
■〈語義〉
○正尾正頭 頭正尾正の言い換え、最初も終わりも正しいこと。
○雲自水由 雲水とは行雲流水の略で、禅僧が何物にもよらず、尋師訪道(じんしほうどう)のために一所に止まることなく自由無礙に修行するさまを表現した語。(62頁)
■元来頂寧(ちょうねい)なり。道は也(また)丹蒦(たんかく)同じく成ず、証は也(また)暁天(ぎょうてん)一悟なり。
誰(たれ)か道(い)うべし祗這是(ししゃぜ)と。
〈現代語訳〉
仏道は、この頂相(ちんそう)のなかに絵の具で十分に表現されているし、さとりは釈尊が明けの明星を一見したところにある。
誰が、真実そのものの円(まど)かな心を言葉で表現できるのであろう。
祗(ただ)、這(これ)、是(これ)、これ以外の何物でもないという外はない。すべてがこの頂相(ちんそう)にあるとのみいっておこう、それは知りがたきわが心であるのだが。
〈語義〉
○祗這是 ただ、これ、これ。これ以外の何物でもないこと。仏法は現実即今に余すことなく我々の目の前に現成していることを指す。(69~70頁)
■〈語義〉
○附骨附随 全身すべて祖師達磨の境涯とならねばならない。達磨はその四人の弟子に付法の印として、道副に皮を、尼総持に肉を、道育に骨を、慧可に髄を与えた、といったと伝えられる。皮肉骨髄はそのすべてが人間の身体を構成する重要なぶぶんであるところから、道元は『正法眼蔵』「袈裟功徳」巻において、「三世諸仏の皮肉骨髄を正伝せるなり、正法眼蔵を正伝せるなり。この功徳、さらに人天に、問著(じゃく)すべからず、仏祖に参学すべし」という。つまり道元はいずれを得るも達磨の前面目を得たので、そこに優劣はないとする。(71頁)
■直指人心、拳頭頂寧(ねい、寧に頁)、見性成仏、鼻孔(くう)眼睛(ぜい)、
得皮得髄二三枚、微(み)笑拈花(げ)開五葉。
〈現代語訳〉
直接に人の心を指し示して、自己(おのれ)の心が仏性そのものと自覚させる、といったところで、拳(こぶし)で頭の天辺を指しても同じこと。
自己の本性が仏性にほかならないとさとったところで、自己自身の鼻も眼も具現化しているところ。
そこにこそ、達磨の皮肉骨髄を得た仏法が展開し、
その仏法は、釈尊が拈華(げ、花)し迦葉(しょう)が微(み)笑したところに始まり、達磨以後五葉に開花している。
〈語義〉
○直指人心 直指人心は、「見性成仏」と続く言葉で、人の心を直指し、自分の心が仏性にほかならないと自覚することが成仏である、とする。この言葉は、達磨が伝えたとする「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」の四句の一句で、経典が伝えるところには仏法の真実はなく、達磨が伝えたところのみに仏祖の大(だい)道がある。つまり、禅宗の綱領は、経典や文字のなかにあるのではなく、経典や文字の指し示しているところを直接端的にとらえるところにあるとする、禅宗以外の仏教、経典・文字をよりどころとしている教家に対する優位を強調する言葉でもある。
○得皮得髄 達磨大師が四人の弟子に所解を提出させ、それぞれわが皮・肉・骨・髄をえたと印証したことに始まる。この場合、文字の上では、皮を得、髄を得ることではあるが、達磨の仏法の全相続をいう。道元は『正法眼蔵』「葛藤(かっとう)」巻において「得皮得髄の殊劣(しゅれつ)によれるにあらず」といって優劣をつけず、また「骨肉髄をえたるは、皮肉面目をえたり」というように、皮・肉・骨・髄すべてが身体を構成する重要な部分であり、同時にその一つ一つが身体であるとするので、どこを得ようと達磨の全仏法を得たことになる。(79~81頁)
偈頌
■「偈頌」について
道元の「偈頌」125首は『永平広録』第十巻に集録されている。
「偈頌」の「偈」は梵語のgathaの音訳、偈または迦陀(かだ)、「頌」は中国語の詩のことで、やがて梵漢混淆(ぼんかんこんこう)した「偈頌」という漢語に表記されるようになる。いずれにしても「偈頌」は仏法の教説の一段または全分の終わりに詩句をもって陳(の)べる韻文のことである。が、とくに禅門では五言あるいは七言の漢詩形で仏徳を讃歎し、さらには教義・見解(けんげ)を説示したものを総称して「偈頌」という。つまり、禅門における「偈頌」は単なる分学的な感情を表象する一般的な所謂(いわゆる)「漢詩」とは些(いささ)か趣(おもむき)を異にし、仏法の言詮(ごんせん)を超えた悟境、自内証の世界、自分自身のとらえた仏法等々を言葉に託して表象するのが「偈頌」ということになるので、禅門の「偈頌」はとくに「禅的表現詩」といえる。したがって、広義でいえば、「真賛」「自賛」の賛、さらに「頌古」またその頌も「偈頌」の範疇ではあるが、いまは『祖山本 永平広録』の分類にしたがっておくほうが便宜であるのでそのままとした。
道元は、貞応二年(1223・宋の嘉定十六年)、二十四歳のとき、建仁寺で師事した明全(1184-1225)らとともに入宋(にっそう)し、四月上旬明州にいたり、七月天童山景徳寺に掛錫(かしゃく)し、無際了派(1145-1224)に謁(えつ)し許されたが縁契(かな)わず、その秋には尋師訪道(じんしほうどう)に出て、再び天童山に帰った。そして、本師となる天童如浄(1163-1228)に初相(しょう)見したのは宝慶(ほうきょう)元年(1225)五月一日のことである。が、同月二十七日明全示(じ)寂し、七月二日より本師如浄古仏に親しく問法し、夏安居中に大事を了畢(りょうひつ)した。以後如浄にしたがい、宝慶三年(1227)七月上旬に帰国した。時に道元二十八歳であった。
つまり、道元は宝慶元年(1225)より同三年(1227)にいたるほぼ三年間、天童山景徳寺に掛錫し、天童如浄古仏に師事したのである。が、「偈頌」として収録せられたその最初のものは、『永平広録』「偈頌」の巻頭に「師、嘗(かつ)て大宋宝慶二年丙戌(へいじゅつ)に於いて、慶元府太(たい)白名山天童景徳禅寺に寓す」と記してあるように、その掛錫された中間の年である宝慶二年(1226)に作頌されたものより始まり、以後五〇首までが在宋時代の作として収録されている。
ではなぜ『永平広録』の第十巻「偈頌』の巻頭に、この「宝慶二年」をわざわざ強調して記しているのであろうか。それは、その年以前の道元は僧堂の披位(僧が坐禅して起臥する場)にあって不眠不休の頭燃を救(はら)って坐禅弁道した時期であり、一大事を了畢してもなお、如浄古仏に随侍し拝問していた時期である。したがって、恐らくは道元自身に作頌の余裕はなく、道元の中国での作頌は、異国僧でありながら大(だい)悟徹底したした評判が聞こえるようになった時期、つまり宝慶元年の夏案居以後、幾分かの余裕のもてた宝慶二年以後のことであることを示しているのである。(96~98頁)
■元来仏祖明心の地、知見当(その)時(かみ)眼睛(ぜい)を偸(ぬす)む、
擬前退歩す金(こん)獅子、鉄蒺蔾(しつり)迸(ひん)して木馬驚く。
〈現代語訳〉
元来、仏祖の法というのは、自己の心を明瞭に認識すること。
従来からの凡夫の分別知を、仏道の的確な要所に転換する。
それには金毛の獅子が猛り狂うようにして、進んでは退く修行の功を積むことが必要。
そうすれば、鉄菱(びし)に無心の木馬も驚くように、弁道すれば天童古仏の厳しい叱声が自己の心に響く。
〈語義〉
○元来仏祖 元来、仏祖道というのは心を明らめること。
○偸眼睛 眼睛は目玉のこと、転じて眼目・要点の意、禅門ではとくに肝要の意。道元は眼睛に無量無辺の意味を持たせている。偸眼睛は仏道の要所を的確につかむこと。
○鉄蒺蔾 三角形の尖った鉄菱で、これを地上に散(ま)き敵の侵入を防ぐもの。この鉄蒺蔾(てつしつり)を撒いておいたように、無心な木馬までが驚いてしまうように心地が進みがたいのが仏地である。(126~127頁)
■従来の諸仏祖呑尽(どんじん)して、他に従わずして円通(えんずう)を証することを得(う)(卍山 他に由って証せず自ずから円通)。
〈現代語訳〉
貴殿は、釈尊をはじめ従来の諸仏祖を、腹のなかに呑み込み、わがものとして、
仏祖の力を借りずに、自分で欠けることのない境地を得ているのである(卍山 ほかの力を借りずに自ら円通する)。(129~130)
■業識(ごつしき)忙忙(卍山。茫茫)たり飽毒(ほうどく)の身(しん)、去来処(ところ)に触れて真を留(とど)めず、
今朝(こんちょう)蹈破(とうは)す紅炉子(こうろす)、全体雍容(ようよう)たり赤脚人(しゃっきゃくじん)。
〈現代語訳〉
妄想(もうぞう)が無限に広がり、貧瞋癡(とんじんち)の三毒のあふれた身であった君よ、。
生死輪廻に苛(さいな)まれ、真実を見失ったすがたをしていた君よ、
それには金毛の獅子が猛り狂うようにして、進んでは退く修行の功を積むことが必要。
ところが、今朝、君は、業識(ごつしき)も妄想もすべてを紅炉に叩き込み焼きつくし、
無礙(むげ)脱体(だったい)し、真実解脱の人となった。(131~132頁)
■一花(いちげ)開く処(ところ)処象(しゅぞう)を新(あらた)にす、万里の春風一等(卍本 直下(じきげ))に知る、
樹(き)を辞する紅花飛んで狼藉なり(卍本 門を出(いで)て逐(お)うこと莫(なか)れ紅(くれない)を尋(たずね)る客)、
擬前退歩幾(いくば)くの迷岐ぞ。
〈語義〉
○一花開 春になって一花が開くと万物が新たになるように、自己の心地が開けると世界の諸象がすべて新たに映る。
○尋紅客(卍本) 百花繚乱として咲く花を尋ねる人。そのような人は表面的な美しさのみを求めて真実を見ない。(132~133頁)
■〈語義〉
○渓声山色 渓の声、山の色は大自然の真実のすがたそのもので、仏の説法そのものであり、仏の清浄(しょうじょう)身でないものはなに一つないということ。『正法眼蔵』「渓声山色」巻に「たとい渓声山色八万四千偈を現成せしめざることは、夜来なりとも、渓山の渓山を挙似(こじ)する尽力未便ならんは、たれかなんじを渓声山色と見聞せん」とある。(146頁)
■然子が終焉(しゅうえん)の語を看る
廓然無聖硬きこと鉄の如し、試みに紅炉(こうろ)に点ず鎖(さ)ゆること雪に似たり、
更に問う今何(いずれ)の処にか帰り去る(卍本 而今何の処にか去る)、
碧波(へきは)深き処(ところ)何(いか)なる月をか看る(卍本 碧波心裡月を看ず)。
〈現代語訳〉
ああ廓然よ、君は廓然無聖の語のように、心に屈託なく求道(ぐどう)の精神は鉄のように硬かった。
それなのに、その肉体も紅炉に投ずると雪のようにはかなくも消えた。
私は問いたい、君はいまどこに帰ったのか(卍本 現在、どこにいるのか)、と。
紺碧の波の深きところで、一体どんな月を見ているのか(卍本 こころの奥には月は見えない)、と。
〈語義〉
○然子 明全と道元の渡宋に同行した廓然・亮照のうち、恐らくは明全の侍者を務めた廓然ではないかとする説が有力と思われる。
○廓然無聖 隔年無聖は、達磨が梁の武帝の質問に答えた言葉で、心が開けて何の執着(じゃく)もない大悟の境涯から見れば、凡聖(しょう)の相対区別はなく厳然たる事実のみがあることを示した言葉。(147~149頁)
■〈現代語訳〉
儒教は、天と地もない原初の世界が破れ、天・地・人が現れた、という。
が、これは天も、地も、人も、それぞれの本来のはたらきが現れたのだ。
仏法のせかいでは、人間と物質はそれぞれが解け合い通じ、二つの事象など区別しない。
それゆえに、情識(じょうしき)を超越した石女(うまずめ)に三台の区別などないのだから、三台に舞わせることはない。
(卍本 天地未だ分かれざる原初の世界に、すでに天・地・人に分かれる兆しはあった。
それゆえに、天・地・人と区別してそれぞれの本来のすがたを求めることはない。
森羅万象(ばんぞう)、区別などなくすべてが一つで、平等であるところに着眼せよ。
そうすれば、石女が三台に舞うすがたを笑って楽しめるであろう)。(155頁)
■〈現代語訳〉
ひとたび、さとりの光に照らされれば、主とか客とかの相対的区別はなくなる(卍本 忘れる)。
うちなる自己を反省して本来の自分自身を照らしてみると、存在する自己すらもない(卍本 報慈庵の身は貧にして貴く、仏道もまた清貧である)。
元来、自分は、現在も、その直前も、その直後も、何もないということに気づく。
それこそが真実の世界であることに気づかなかった過去を思うと残念で涙がこみ上げる(卍本 隔てる何ものもない)。(161頁)
(卍本 隔てる)。(155頁)
■三途(さんず)六道(りくどう)崔嵬(さいかい)峙(さきだ)てたり、来去風騒しくして意(こころ)自(おのずか)ら通ず、
正(しょう)眼当観すれば時節至れり(卍本 四生(しょう)六道遊戯(ゆげ)に当(あ)つ、去去来来意自ら空ず、正眼に諦(たい)観す通達(だつ)の者)、張三李四老年翁。
〈現代語訳〉
人は死しては三途(さんず)の川を渡り、生きては六道に輪廻するという厳しい現実がたちはだかり(卍本 人は四生六道に迷う愚かなものというが、それこそが自在無礙の境界)、
生死(しょうじ)去来の迷いに吹き付ける風は騒がしいが、そここそが無礙の三昧(ざんまい)境)。
正法(ぼう)眼をもって観れば、そここそが悟達(ごたつ)の時節(卍本 この悟達諦観の人こそが)。
あそこにいる李さん張さんであり年老いた翁。(167~168頁)
■這(こ)の外(卍本 言外)何ぞ求めん真的の所、霊機(れいき)点ずる処(卍本 霊機一転)来由(らいゆう)を失う、何人(なんびと)か此(ここ)に到って空際を脱せん、問うこと莫(なか)れ身無くして疾瘳(しっちゅう)を悟ることを(卍本 語ることを)。
〈現代語訳〉
仏法の真実以外に何を求めるのか(卍本 言語の思量を離れたところに仏法の真実を求める)。
自己の霊妙不可思議な仏性がはたらけば(卍本 霊気が一転すれば)生死去来などの迷妄は根本的になくなる。
ここにいたれば、誰が一体、空相無相を向け出せないものがいようや。
自分自身の身体を判然と自覚しないのに、生死煩悩等に悩まされる実体のない病など問題とすることはない。(173~174頁)
■未だ知らず大道本(もと)より何如(いか)ならん、鶻(髑、どく)髏(こつろう)を透脱して自都を遺(のこ)す、
彼此(ひし)伶併(れいへい)来去錯(あやま)る、一廻(ひとたび)照顧(しょうこ)すれば跡蹤(せきしょう)無し。
〈現代語訳〉
大道は、本来どのようなものなのか、人は知らない。
髑髏になって人間の情識から抜け出しても、本来の自分を遺すから、
あちらこちらと彷徨(さまよ)って行くべき道を錯(あやま)るのです。
ひとたび自己を照顧すれば、さとりの痕跡もないさとりの世界が開けるものです。(180~181頁)
■昌国県補陀舌迦山(ほだろかさん)に詣でて因(ちな)もに題す
聞思(もんし)修(しゅ)本(もと)より証心の間(卍本 三摩地に入り)、豈(あに)洞(とう)中に聖(しょう)顔を現ぜんことを覓(もとめんや(卍本 自己端厳にして聖顔を現ず)、
我告げ来る人須(すべから)く覚(さとるべし(卍本 為に来人に告げて此の意を明らかにす)、観音宝陀山に在らず。
〈現代語訳〉
仏法を聞き、思慮し、修行するのは、もとより己の心を証するため(卍本 不動の心境になるため)。
どうして洞窟のなかに観世音菩薩のお顔の現れるのを求めよう(卍本 自己のうちの端正な自己が観世音の聖顔となって現れる)。
私は、ここに参詣に来る人たちに告げよう、自己に目覚めよと(卍本 ここに参詣に来る人たちに、この意を明らめよと告げよう)。
観世音菩薩はここ宝陀山にご不在なのだ、探し求める己のなかにおられるのだから。(182~183頁)
■須(すべから)く知るべし仏法心空に到るを、人の言い説き窮める所なるべからず(卍本 是語言の説いて窮むべきにあらず)、
見色聞声(もんしょう)倶(とも)に脱落なり、東西南北自ら流通(るずう)す。
〈現代語訳〉
仏法は、心が空になること、心は実体がないことを、執着を離れて、すべてのことをありのままに見るところに到達することであることを知らねばならぬ。
これは人が言葉をもって究められるところではない(卍本 言葉の説いて究められるところではない)。
心空になれば、見るもの聞くもの、感覚にとらわれることを脱落し、自在となる。
そうなれば東西南北ありとあらゆるところに、仏法が遍在する。(186~187頁)
■磨塼作鏡(ませんさきょう)功夫(くふう)に藉(よ)る、識(し)るべし斯(こ)れ猶半途に滞る(卍本 脚下須らく知るべし半途に滞ることを)、
若し東西(卍本 西来)真的の旨(し)を問わば、噴噴(ふんぷん)地の上に觜盧都(しろと)す。
〈現代語訳〉
参禅弁道は、甎(せん)を磨いて鏡とするような無所得の功夫(くふう)を重ねるが、
これとて、まだ修行の中途半端なところに滞っていることを識(し)らねばならぬ(卍本 脚下、すなわち己自身が中途半端であることを知らねばならぬ)。
もし、達磨の伝えられた真実(卍本 西来)の仏法を問うならば、
私は、言葉など用いず、大きく息をはき口を閉じて地上に黙坐しよう、只管打坐のみが真実であるのだから。
〈語義〉
○磨塼作鏡 塼は甎とも。よく焼いた固い瓦のこと。「甎を磨いて鏡と作(な)す」というのは、南嶽懐譲(677-744)と、その弟子馬祖道一(709-788)との師資証契(しししょうかい)の問答として有名で「南嶽磨甎」といわれる公案。坐禅が、六祖慧能(638ー713)の「金剛経」を中心とした無所得に徹するから、南嶽においてもこの坐禅が継承され、何物も求めずただ行ずるものとして、南嶽は甎を磨いて馬祖に示したのである。この公案の眼目は、磨甎という行為が単なる徒労無駄骨をいうのではなく、坐禅は仏になる手段ではない(不図作仏、ふとさぶつ)ことを明確にしたもので、坐禅が有所得であってはならない実態を如実に示すものである。この磨甎作鏡は『景徳伝灯録』巻五・南嶽懐譲章に出る。『正法眼蔵』「古鏡」巻では、馬祖が南嶽に参じた故事を説いた後に「この一段の大事、むかしよりすう百歳のあいだ、人おおくおもえらくは、南嶽ひとえに馬祖を勧励せしむると。いまだかならずしもしかあらず、大聖(だいしょう)の行履、はるかに凡境を出離せるのみなり。大聖もし磨甎の法なくば、いかでか為人の方便あらん。為人のちからは仏祖の骨髄なり」と説かれている。同「坐禅箴」巻には本公案を事細かに引用しその一々に懇切な提唱が見られる。また『永平広録』では巻四ー上堂270に、さらに巻九ー頌古38にも見える。
○觜盧都 口を閉じて一言も発しない。(195~197頁)
■禅人に与う 八首
①側耳(そくじ)抬頭(たいとう)して家風(卍本 暁風)を待つ、
幾過(きか)春雨牧牛懵(もだ)ゆ(卍本 牛を牧し雨に吟じて空濛に立つ)、
誰(たれ)か知らん這箇(しゃこ)の衝天(しょうてん)の意(こころ)、只揚眉(ようび)瞬目の中(うち)に在り。
〈現代語訳〉
禅人に与える 八首
①寂莫として静まりかえった山中に、夜も眠れず、心を澄まし、耳をそばだて、頭を抬(もた)げて、家風を待つ(卍本 暁風が吹き、夜の明けるのを待つ)。
長い年月、静寂そのもののなかに牛の声を聞いたが、それはまさに修行僧たちの呻吟(卍本 小雨のそぼ降るなかに牛の鳴き声が聞こえる)。
しかし、誰が知ろう、この静寂等閑のなかに、正法を究めんとする衝天の意気があることを。
そして仏法は、日常の普段の何でもない動作、眉をあげたり、目をしばたく、そうしたなかにあることを。
〈語義〉
○揚眉瞬目 眉をあげ、瞬きをする。日常の不断の何でもない動作。(197~199頁)
②仏祖元来眼前に在り、秋深くしては覚(おぼ)え難し古船の舷(ふなばた)(卍本 前灘波動いて秋煙を鎖す)、
夜寒くしては乱れ易(やす)し鴈行の列、左右祗(ただ)斯(こ)れ空(そら)に満てる煙(けむり)(卍本 月暗くして尋ね難し古渡の舟)。
〈現代語訳〉
②仏祖はもともと目の前におられて歴々として明らかなものだ。
だが、それを見誤ると、仏祖が秋が深い霧のなかで古船が霞んでいるような状態になる(卍本 荒波に揉まれて行き先に迷うようなものだ)。
夜寒の空に迷って乱れ飛ぶ雁のように、
周囲を見渡せば、空間に煙が満ちているように仏祖の家風が満ちている(卍本 月暗くして涅槃にいたる舟を探す術もない)。(199~200頁)
③宗(しゅう)説倶(とも)に通ず瞥(べつ)地の先、誰人(たれびと)か此(ここ)に到って安然たるべき(卍本 誰か能く此に到って山玄を解せん)、
松風(しょうふう)響きに愧(は)づ(卍本 松風空しく響く)聾人(ろうじん)の耳、
竹露屢(しばしば)零(おち)て月辺に納(い)る(卍本 竹露屢零つ涼月の辺)。
〈現代語訳〉
③宗旨の根本に通じ、宗旨を説き示せても、ほんの少し先が見えただけ。
そこにいたったからといって、誰がそこに安然としていられよう(卍本 そこにいたったからといって、誰が仏道の幽玄なる奥義に参じ得たといえよう)。
松風は、耳に聞こえない人には響かず虚しいものだし(卍本 松風空しく響く)、
竹葉に宿る露にも、天空にかかる月にも解脱の風光は輝いているのに、見えない人には見えないもの。
〈語義〉
○松風 宗説倶通した松風の風情。(200~201頁)
④大機転ずる処漫天動ず(卍本 文彩を絶つ)、徹底蹤(あと)無し線路の辺(ほとり)、
孤(ひと)り楼台に詠ずれば唯(ただ)月色のみあり(卍本 五夜の楼台唯月色)、
雲に染む時雨(じう)燃煙を湿(ぬら)す(卍本 暁来の一雨残因を洗う)。
〈現代語訳〉
④信心堅固な弁道によって得たその境涯がはたらくと、天一面が開けるように迷悟是非が転じ(卍本 迷悟是非など相対的な世界がなくなり)、
見渡すかぎり、徹底してどこにも何物も残っていない。
大機の自在なすがたは、独り楼台に詠ずるとき、空に月が輝くように(卍本 暁天の楼台に月が輝く)、
雲に馴染んだ時雨が燃焼した跡の煙さえ消し去るようにさとりの痕跡さえ残さない(卍本 明け方の一雨が残煙を洗い流すようにさとりの残跡さえない)。(201~202頁)
⑤無明誰か悪(にく)まん唯(ただ)秋(卍本 草頭)の露、実相元来此の裏に真なり、
留(とど)めて(卍本 留めて得て)知り難し流水の底、結び来ては変じ易し承(じょう)当の身。
〈現代語訳〉
⑤誰が、無明の迷いを憎むことがあろう、それは秋露(卍本 草の葉に宿る露)のように消え去るもの、
そして無明の迷いもまた、あるがままの真実のすがたなのだから。
無明の迷いは、流水の流れを留めても(卍本 留め得て)、その底が見えないようなもの。
無明の迷いはそのようなものだと分かっても、変わりやすいのは、そうだと分かったと思うこの身。
〈語義〉
○承当 会得、領得すること。またこの世に人間として生まれること。(203~204頁)
⑥松風高く韻(ひび)いて夏宵(かしょう)秋なり、竹響頻(しき)りに慅(さわ)いで(卍本 竹葉の露頻りに降って)暁涙(ぎょうるい)流る、
唯途(みち)に触れて全体動ずべし、誰(たれ)か古路(ころ)を忘れて此の間(あいだ)に憂(うれ)えん。
〈現代語訳〉
⑥松風がより高く鳴り響く夏の末の宵、秋の初めのころ、
竹も響き、竹葉の露もしきりに落ちて(卍本 竹の葉の露がしきりに降って)物寂しい暁の時分、移ろいゆく気配に無常を感じて涙が頬を伝う、
そのようなときであるからこそ、松風・竹響の見聞声色にとらわれず、心を発動せねばならぬ。
誰が、古仏の辿(たど)った仏祖道を忘れ、初秋のもの悲しき無常世界に身をゆだねていられよう。
〈語義〉
○暁涙 竹露がしきりに落ちるように涙がながれる。
○古路 諸仏の開悟した仏法の大道。
○此間 無常なる世界。(204~205頁)
⑦雲晴天に断えて鶴の意(こころ)閑(しずか)なり、浪(なみ)古岸に連なって魚行謾(おそ)し(卍本 謾たり)、
誰人(たれびと)か眼(まなこ)を此の参際に著(つ)けん(卍本 設し人眼を著けて斯際に及べば)、
百尺の竿頭一進の間。
〈現代語訳〉
⑦雲一つとしてない晴天に、鶴は心静かに舞い、
浪は古岸に連なって押し寄せ、魚は広々とした海にゆったりと泳ぐ。
誰が、このあるがままの自由自在な境界(がい)に、眼をつけるだろう(卍本 もし人が任運に、自由自在のこの境にいたるには)。
それには、百尺竿頭の先にぶら下がっている自分自身を放下することなのだ。
〈語義〉
○百尺竿頭 全句のような任運自然(じねん)の道理のなかで、知解分別にわたる自己を徹底的に放下し転身自由となる。(205~206頁)
⑧玉人夢破(さ)めて暁雲忪(いそが)し、夜月霧消えて残露空し、
独り寒床を覚(し)る意(こころ)を待つに似たり(卍本 独り覚る寒床限り無き意)、
風光憶(おも)わず訪心の中(うち)(卍本 風光凄断す寂寥の中)。
〈現代語訳〉
⑦仏道修行者が迷妄の夢から覚めると、暁雲が飛び去ったような気分。
夜月にかかっていた霧も晴れ、残露もない爽快な朝景色に似て、それは一切の迷妄が消え去った境地。
独り暁天の寒床に坐していると限りない思いが駆けめぐり(卍本 独り暁天の寒床に打坐していると、種々様々な思いが駆けめぐることを覚る)、
暁雲、夜月、霧、残露、そういった風光が心を揺さぶる(卍本 この寂寥たる山中の暁天坐禅では、そうした風光さえもが断たれる)。
〈語義〉
○玉人 仏道修行者、禅者のこと。
○寒床 寒々とした禅床のこと。(206~207頁)
〈解説〉禅人に与える八首について
偈頌53~60の八首は、とくに自然の風物と仏法を照らし合わせている語句が多い。たとえば、その八首から拾い出してみると「幾過春雨牧牛懵(卍本 牧牛吟雨立空濛)ー中略ー 等々とあって、その偈頌には寂寥感が強く漂っている。それは恐らく、道元が雲遊萍記(ひょうき)し弘法(ぐほう)激揚(げきよう)の時をまつとして安養院に閑居していた時代であったからではいかと拝察される。(208頁)
■閑居の時 七(六)首
①阿誰か取舎せん悄然なりと雖(いえど)も(卍本 取舎を双忘して思い翛然たり)、
万物同時に現在前(ぜん)す、
仏法今従(よ)り心既に尽きぬ、身儀向後且(また)縁に随う。
〈現代語訳〉
閑居の時(卍本 閑居の偶作) 七(六)首
①憂いに沈むような感傷の場ではあるが、それに浸っているのではない(卍本 一切の取捨選択を忘却し、心は寂然として静寂)。
ここに端坐すれば万物すべてが、仏法そのものとして、同時に目の前に、あるがままに現れている。
正伝の仏法に、いまも、そして今後とも、わが心は動揺することなく、
わが身を処縁に処して自在無碍に生きるばかり。
〈語義〉
○閑居之時 閑居とはしずかなるたたずまいのなかの意である。が、道元の実際の閑居は寛喜二年(1230)から、山城深草安養院に閑居した三年間で道元の三十歳から三十三歳の頃である。(216~218頁)
②木人昨夜離根(卍本 離魂)し去る、露柱灯籠幾(いくば)くか恩を恋うる(卍本 旧恩を恋う)、
同道方(まさ)に知る絶境界、動著(じゃく)して乾坤を覆(おお)わしむること勿れ。
〈現代語訳〉
②昨夜、思量分別を超え迷妄の根本(卍本 魂)から離脱して無心無礙となった木人が、どこかへ去った。
今まで一緒(とも)に過ごしてきた無情なる露柱や灯籠たちは、今、彼の恩を恋い慕っている。
一緒に修行してきたあるがままに現成している木人・露柱・灯籠たちは、その絶対自在無礙の境界(がい)を知っている。
だからこそ、その無心玄妙なる境界について、心を動揺させ妄想(ぞう)を起こして知解(ちげ)をもって天地を覆うようなことをしてはならぬ。
〈語義〉
○木人 木でつくった人形。思慮分別を超えた境涯にたとえる。
○露柱灯籠 むきだしの柱と灯籠。禅門では、無情または非情なものがそのものとして現成し不断に真実を説いている相(すがた)を例示するのに用いる。同様のものに瓦礫(がりゃく)・牆壁(しょうへき)・木人などがある。
○絶境界 無心の木人がどこかへ行くと、無情な露柱灯籠がそれを恋い慕うといったような、思慮分別を超越した世界。
○覆乾坤 乾坤は天地のこと。全世界を暗黒に覆いかくす意。(218~220頁)
③触目遇縁(しょくもくぐうえん)尽(ことごと)く是親し、経行(きんひん)坐臥体(たい)全く真なり、
人有って若し箇中の意(こころを問わば、法眼(ほうげん)蔵中一点の塵(ちり)。
〈現代語訳〉
②ここでは、目に触れ縁にあうものすべてが仏法の世界そのものに親しい。
経行・坐禅・臥床(がしょう)といったごく日常的なことすべてがその真実。
人あって、この閑居の意中を問うならば、
その質問に答えたりするのは、仏法の真実、正法眼蔵中に一つの塵を舞わせるようなもの、脱落底のところにそのような質問は無用と答えよう。
〈語義〉
○触目遇縁 目に縁にあう。仏法により解脱した心境から見るもの。
○経行座臥 行・住・坐・臥の四威儀(しいぎ)。経行は動、座臥は静、日常生活の一挙一動。
○法眼蔵中 正法眼蔵のこと。正法の仏法。(220~221頁)
④大用(だいゆう)現前眼(まなこ)に当って新(あらた)なり、然(しか)りと雖(いえど)も何ぞ其(そ)の真を呈すべき(卍本 是の如くなりとも曷ぞ真を呈せん)。
愁人(しゅうじん)愁人に向かって道(い)うこと莫(なか)れ、向道愁人人を愁殺す。
〈現代語訳〉
④仏法の大きなはたらきは、つねに目の前にあって新鮮。
そうではあるのだが、その真実を表すのは容易ではない(卍本 それはそうなのだが、その真実をどのように表現したらよいであろう)。
愁いを抱く人が、愁いを抱く人に言葉をかけてはならない。
迷っている人が、迷っている人に言葉をかければ、さらに混迷を深めるようなもの。愁いを抱く人は、その愁いを自分自身の胸のうちにしまっておけばよい。
〈語義〉
○大用 仏法の大きなはたらき。
○愁人 字義どおりでは、愁い悲しんでいる人がさらに憂愁を誘うような話をする、という意であるが、この愁人は迷悟の人。(221~222頁)
⑤生死憐れむべし休して又起こる(卍本 雲変更)、迷途覚路夢中に行く、
然りと雖(いえど)も尚忘れ難き事有り(卍本 唯一事を留めて醒めて猶記す)。
深草の閑居夜雨の声。
〈現代語訳〉
⑤生死の流転は、何ともはかなく哀しきこと、それは一つの真実のすがたであるのに、忘れたかと思うとまた起きてくる(卍本 雲が流れ去りまた沸き上がるように、とりとめもない)。
迷いとかさとりというのも同じこと、それが二つ在るのではなく、一つの真実で取捨選択すべきものではなく、それは夢覚(がく)一如で、夢中に徃来したようなもの。
醒めればあとかたもないとはいうけれど、それはそのとおりなのだが、忘れがたいのは、弘法(ぐほう)救生(ぐしょう)の強き一念のみである(卍本 夢から醒めても、なおこれだけは記憶に残っている)。
それを知ってか知らずか、都を離れた深草の閑居の庵(いおり)には、夜来の雨が降りそそぐ声のみが響いている。
〈語義〉
○夢中 道元は夢の世界も仏法の世界の範疇であると説く。『正法眼蔵』「嗣書」巻に「道元、台山より天童にかえる路程に、大梅山護聖寺の丹過に宿するに、大梅祖師きたりて、開華せる一枝の梅華をさずくる霊夢を感ず。(中略)夢中と覚中と、おなじく真実なるべし。道元在宋のあいだ、帰国よりのち、いまだ人にかたらず」とある。また同「夢中説夢」巻に、「夢中の諸法、ともに実相なり。覚中の発心・修行・菩提・涅槃あり、覚中の発心・修行・菩提・涅槃あり、夢覚おのおの実相なり、大小せず、勝劣せず」とある。
(中略)この偈頌はその思いが重く肩にのしかかっていた深草の閑居の時代の作であろう。(222~224頁)
⑥涼風方(まさ)に渡って秋の響きを覚(し)る、天気爽清にして結果新(あらた)なり、
結果新たにして(卍本 新たなる時)香(こう)満界なり、廻避無き処得聞親し(卍本 疎親没し)。
〈現代語訳〉
⑥涼風が吹きわたると、あたり一面に秋の気配を感じる。
天気は清涼で、木々の実も新たに熟してくる。
木の実の新たに熟すとき(卍本 新たなるとき)、
その仏法の香りがあたりに充満するように仏果のはたらきに満たされる。
その香りは避けようにも避ける場などない、
そのように、仏法のはたらきは親疎の差別なく、あるがままにあたり一面にあふれている。
〈語義〉
○涼風 以下は秋の風情にたとえて仏道修行の孰処をいう。涼風は迷悟を超脱した風。
○没疎親(卍本) 凡聖迷悟の差別のないこと。
〈解説〉深草閑居の時について
道元は、宋から帰国し、しばらく京建仁寺に止まり、さらに深草の安養院にあって、本師天童如浄の膝下で、坐禅弁道に励み、大悟了畢(だいごりょうひつ)した正伝の仏法をどのように日本に広めるかを念頭に置きながらも、雲遊萍寄(ひょうき)、つまりまさに空にたゆとう雲のように行き場なく、浮き草のように寄るべき岸辺もない生活のなかで、まさに正伝の仏法を弘通(ぐずう)し衆生救済の激揚の時を待つ状況にあった。道元は、その心境を『正法眼蔵』「弁道話」巻に「ついに大白峰の淨禅師に参じて、一生参学の大事ここにおわりぬ。それよりのち、大宋紹定のはじめ、本郷にかえりし、すなわち弘法救生をおもいとせり、なお重担をかたにおけるがごとし。しかあるに弘通のこころを放下せん、激揚のときをまつゆえに、しばらく雲遊萍寄して、まさに先哲の風(ふう)をきこえんとす」と吐露している。
道元が「雲遊萍寄」と表現した、この深草閑居の時期は、打ち続く飢饉のなかで、後に展開する『正法眼蔵』の総論ともいうべき「弁道話」を書き著し、正伝の仏法を弘法しようとする意気軒昂な時期ではあったが、その心中は、何の寄る辺もない、まさに空に浮く雲のごとく、水に漂う浮き草のような生活のなかで、因縁の熟すのをまつ忸怩たる思いにも駆られていたのではなかったか。正伝の仏法の流布という重い荷物を肩に背負っている弘法救生(ぐほうぐしょう)の思いと、激揚の時をまつ雲遊萍寄の生活。しかし、自分が、先哲の風をならって雲遊萍寄しているとき、真の求道者は、邪師に惑わされ、伝えるべき正しい種が絶えてしまうではないか等々、様々な思いが交差していたのではなかったか。
道元の仏法は、この雲遊萍寄の時代を経て、まさに激揚の時期を迎え、弘法救生の精神が縦横無尽に展開されていくことになる。先の「禅人に与える 八種」の偈頌とこの「閑居の時 六首」は、その安養院時代の激揚の時をまつ時代の作頌ではないかと推測される。この閑居の時代こそが、道元の仏法が展開される準備期間でもあったのである。
なお、この閑居の偈頌は『祖山本』は「閑居の時 七首」とあり、『卍山本』は「閑居の偶作 七首」とある。が、実際は六首で、次の71の「春雪の夜」を入れると「七」になるが、「春雪の夜」は、次の72と連作のようであり、しかも、それは永平寺での作頌ではなかったかと思われる。また『祖山本』の78に「此れより已後(のち)、皆、越州に在って作す」とあるが、それ以前にも越州の作が混入しているところもあるようである。(225~227頁)
■春雪夜
春雪の夜
桃の花、李(すもも)の花があでやかに咲き、雪や霜がどれほど凄絶な美しさをみせようとも、それに愛着しない(卍本 どのような美しいすがたであろうとも、愛着にとらわれない)。
青々とした松、緑の竹も、流れ去る雲や煙とどれほどの違いがあろう(卍本 松や杉が雪に覆われてその緑青が隠れる、そのすがたにこそ愛着する)。
歳をとれば皮膚は衰え鶏皮のように、頭髪は鶴羽のように白くなるのに、何も染めなくてもそれはそれで良いではないか(卍本 ぶつどうに生きる人は、心が乱れ散ることも忘却の彼方にあるのだから)。
世俗の名聞利養など、とっくに投げ捨てて、もはや数十年。
〈語義〉
○名利(みょうり) 名聞利養(みょうもんりよう)。(228~229頁)
■大師釈尊在世八十年
夜半の烏児(うに)頭(こうべ)に雪を戴く、天明(めい)に唖子(あし)酌(く)んで泉と言う、
此の家の料理他国に異なり、一丈の池心一丈の蓮。
〈現代語訳〉
大師釈尊の仏法の世界は、真っ暗闇のなかに、真っ黒なカラスが頭に真っ白な雪を載せているように、黒白未分の差別の世界を絶し、
夜明けに、もの言えぬ人が、水を汲み、泉の水だよと声をあげたように、ことほど左様に、言語では表現できないところさえも超え、物の道理を絶した境界(がい)。
それゆえに、仏家の料理(家風)は、他国の料理とはまったく異なり、
一丈の池には一丈の蓮の花が咲くように、その仏法の香りは三世十方の世界に次元を超えて薫る、その仏法を私は相承(じょう)している。(232~233頁)
■八月十五夜
八月十五夜、月の前に於いて、各(おのおの)月を頌(じゅ)す。此の月心月に非ず、天月に非ず、昨月に非ず、夜月に非ず、尖月に非ず、想像(おもいや)る、是、秋の月なり。如何。
金波(きんぱ)泊(とど)まるに非ず河宿(かしゅく)なりと雖(いえど)も(卍本 止まるに非ず)、爽気高く晴れて匝地(そうち)秋なり、
渭水盧花嵩(すう)岳の雪、誰(たれ)か怨まん長夜の更に悠悠たることを。
〈語義〉
○匝地(そうち) すべての大地。
○渭水盧花嵩岳雪 渭水は二祖神光慧可(487-593)はそのほとりに生誕したといわれる。いま頃の秋の時分の渭水のあたりは、盧花が真っ白に咲き乱れ、冬の早い達磨の祖山にはすでに雪が降っているであろう。(234~236頁)
■重陽に兄弟(ひんでい)と志(こころざし)を言う
〈現代語訳〉
九月九日の重陽の節句にちなみ、修行者たちと作頌して志を示す(卍本 再会す)
重陽の節句は、昨日のこの日、わがこの地を去り、
今年の九月、またここにやって来た。
過ぎ去りまたやって来る年月日など憶(おも)うことはやめよう。
この叢林のなかにも菊の花が咲き誇っているのを歓んで看(み)るばかり(卍本 欄干によって談笑し、ふと看れば菊の花が咲き誇っている)。
〈語義〉
○兄弟(ひんでい) 法門の兄弟、雲兄水弟(うんびんすいてい)の意で、広くは大衆(だいしゅ)、同参、同学をいう。(237~238頁)
■冬夜に諸兄弟(ひんでい)志(こころざし)を言う、師見て之を和す
二千一百有余歳、笠漢(じくかん)幾(いくば)くの経法か尚(なお)残る、
仏祖の伝衣(え)縦(たと)え偏(彳)界(がい)なりとも、憐むべし冬夜水雲寒(すさま)じ。
〈語義〉
○二千一百有余歳 釈尊よりわが永平にいたる年数。
○偏(彳)界 遍界とも。全世界あまねく仏法のはたらきで満ちている。遍法界、全世界。
○冬夜水雲寒 仏の衣は世界に遍(あまね)しといっても、冬夜の雲水にはやはり寒さがこたえる、そのなかでも正伝の仏法を只管打坐のなかに伝える。(238~239頁)
■ちなみに、『傘松道詠(さんしょうどうえい)』(『曹全』「宗源」)には「宝治元年(1247)相州鎌倉にいまして最明寺道崇禅門(北条時頼)の請によりて題詠十首」として、次のような道詠(和歌)が収められている。なお、この10首の道詠は最明寺殿の北の方の所望により詠じたともいわれる。
あら磯の波もえよせぬ高巌に蠣もつくべきのりならばこそ(「教外別伝」)
いい捨てしその言の葉の外なれば筆にも跡をとどめざりけり(「不立文字」)
*波もひき風もつながぬ捨おぶね月こそ夜半のさかりなりけり(「正法眼蔵」)
いつもただ我ふる里の花なれば色もかわらず過ごし春かな(「涅槃妙心」)
*春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷(すず)しかりけり(「本来面目」)
*おし鳥やかもめともまたみえわかぬ立つる波間にうき沈むかな(「即心足仏」)
水鳥のゆくもかえるも跡たえてされども道はわすれざりけり(「応無所住而生其心」)
尋ね入る深山の奥のさとぞもと我住み馴れし都なりける(「父母所生身即証大覚位」)
*世の中にまことの人やなかるらんかぎりも見えぬ大空の色(「尽十法界真実人体」)
*春風にほころびにけり桃の花枝葉にのこるうたがいもなし(「霊雲見桃花」)(242~243頁)
■六月半(なかば)衆に示す
自家の鼻孔(くう)自家牽(ひ)く、一軸(いちじく)の画図(がず)(卍本 一片の功夫)九夏(くげ)の天、
今より後僅かに残る三十日、直(じき)に須(すべから)く精進して頭燃(卍本 頭然)を救(はら)うべし。
〈現代語訳〉
六月の半ばに、衆僧に示す
自分の修行は、自分の鼻に自分で綱をつけ自分を引っ張るように自分でするもの。
九十日間の安居(ご)は、一軸の絵画(卍本 一片の功夫)を完成させるようなもの。
今日から、残りは、わずか三十日、
頭に火が着けばすぐに消そうとするように、専一に、一瞬も懈怠(けたい)しないように功夫弁道せねばならぬ。
〈語義〉
○自家鼻孔 自分の修行は自分でするもの。
○救頭燃(卍本然) 頭に火が着けばすぐに消そうとするように、専一に、一瞬も懈怠しないように弁道功夫すること。
なお、『傘松道詠(さんしょうどうえい)』(『曹全』「宗源」)には、「坐禅」と題して、次の四首が収められている。
守るとも思わずながら小田山のいたずらならぬかがしなりけり
頂に鵲(かささぎ)の巣やつくるらん眉にかかれるささがにの糸
*濁りなき心の水にすむ月は波もくだけて光とぞなる
この心天津空にも花そなう三世の仏に奉らばや(247~248頁)
■〈語義〉
○公案 公府(役所)の安牘(あんとく)(公の条文)の意。国家の律法のごときは、天下の公道、不変の条理なりという語より転じて、禅門では仏祖が示した言動などを記して求道者に示し、参究推考すべき問題をいう。
■〈語義〉
○歯門闕 如浄が、その偈頌の最後に「笑殺す胡僧の歯門を欠く」といっているが、これは達磨が中国にやって来て、菩提流支(ぼだいるし)と光統律師(こうずりつし)と法論し、敗れた二人は仲間と達磨を追い出すために石をぶつけて迫害した。その際、達磨は、その石で前歯を欠いたといわれる伝説がある。つまり、達磨は石をぶつけられ、前歯を欠いて法が説けないようになったなどというのは笑止だというのである。葉があっても仏法を説けない人はいる。達磨大師は歯を欠くような迫害を受けても面壁という黙坐の行履によっても仏法を守持したのである。(260頁)
■〈語義〉
○虚空 果てしない無限の宇宙的な大空間で、すべての事象を包含しその存在を少しも妨げず、我々自身もそのなかに存在しているということ。(254頁)
■〈解説〉観月について
観月あるいは翫月(がんげつ)という、陰暦八月十五日は中秋の節で、世間では「お月見」の行事ではあるが、五月の端午の節と同様に重んぜられた節句で、古来観月の節とされた。所謂、「十五夜」である。叢林でもこの日には住持が上堂し、とくに道元にとっても、この観月には毎年特別の思いがあったのであろうことは、中秋の上堂が仁治元年(1240)から示(じ)寂の前年の建長四年(1252)まで九回ほどされていることがそれを証明している。
道元は、幼少の頃から培われた詩心を、自身では払拭されようとはするのであるが、その如何ともしようのない詩心を誘われる「翫月」ということがよほどお好きであったのであろう。
道元のは、仁治四年(1243)正月六日に興聖寺にて撰述したものに、『正法眼蔵』「都機(つき)」巻がある。
「都機」巻は、まさに「月」が主題として説示されてはいるが、この巻に示された「月」は単に虚空に浮かぶ美しい月をいうのではない。
道元が「月」によって説き示されたのは、仏祖たちがしばしば月に仮託して語った「諸方無我」あるいは「諸行無常」といった言葉に集約される正伝の仏法の真実義である。つまり、道元は「月」を説示されながら、その背後にはつねに「都機」(仏法のすべてのはたらき)を説かれているのである。
ところで、道元は、建長四年(1252)八月十五日の中秋に当たり、よほどの感慨をもよおされたものか、釈尊と月との因縁(『大智度論』に見られる)について、上堂(巻七ー上堂521)で長広舌をふるわれた(講談社学術文庫『道元「永平広録・上堂」選』238頁参照)。「今日の明日のその光は、釈尊その人の光である。それ故にこそ、その光を消してはならない、それこそが仏祖の児孫としてのつとめである、それこそが釈尊のお諭しであり、それを守ることこそが『伝灯』である」と。
このような何か遺誡(ゆいかい)めいた上堂、しかも本上堂のように長い中秋の上堂が、数ある中秋の上堂のなかでも本上堂のみであるのは、『訂補建撕(ぜい)記』に「今夏の比(ころ)より微疾まします」と見られるように、今夏の頃より兆した微疾(病のこと)を重大なものと感じられ、中秋の上堂は、この日が最後となることを予感されたゆえでもあろうか。人間(じんかん)の五十年はかの天の一昼夜に過ぎないとする月天子の寿命の計算などには、そうした予兆や感慨が窺(うかが)われもする。
翌、建長五年(1253)の夏、体調の秀れなかった道元は、波多野義重らの勧めに従い上洛するが、その途次、「越前路より都におもむきし時木芽山という所にて」と題して、
草の葉に首途せる身の木の目山雲に路ある心地こそすれ
さらに「無常」と題して、
朝日待つ草葉の露のほどなきにいそぎなたちそ野辺の秋風
世の中は何にたとえん水鳥のはしふる露にやどる月影
と詠じている。
そして建長五年の中秋の節は、やむを得ず療養のために滞在された京都で迎えられ、
また見んとおもいし時の秋だにも今宵の月にねられやはする
(『傘松道詠』『曹全』「宗源」下192頁)
と詠じ、その十三日後の八月二十八日には入般(はつ)涅槃なされるのである(265~267頁)
■(卍本 梅辺に白(はく)を重ねて顔を看ず、僧家三般(そうけさんぱん)の別有りと雖(いえど)も、半箇も何ぞ曾(かつ)て黒山(こくざん)に堕せん)
〈現代語訳〉
(卍本 雪の上に霜が降るようなその厳しい寒さは言葉では表現できない。白い梅花に雪が重なり、白一色で見分けがつかない。修行僧に三種ありなどというが、ここ永平寺には、只管打坐に徹し迷妄に堕するものは一人だになし)
〈語義〉
○雪上加霜 雪の上に霜を加える。通常は無用の意味を持つが、ここは白の上に白を加える意で、区別できない、言語を超越していることをいう。また、本来成仏身である釈尊が雪山に修行したことを、雪山に霜を加えるとして、上堂に「臘月の寒梅月光を含む。雪山の雪の上に更に霜を加う、如来の毫相(ごうそう)猶(なお)今在り、遠孫(そん)を利益(りやく)す、豈(あに)度量せんや」(『永平広録』(巻七ー上堂473)と説示している。
■生涯虚実(卍本 事々)是非乱れがわし、月を弄(ろう)し風を嘲(ちょう)し鳥を聴く間(卍本 物に対して真を失す虚実の間)、
多歳徒(いたずら)に看れば山に雪有り、今冬忽(たちまち)ち覚(し)る雪山を成(な)すを。
〈現代語訳〉
人の生涯は、虚と実と(卍本 色々なことに)、是と非とが入り乱れて迷走し、
月を愛でたり、風を厭(いと)ったり、鳥のさえずりに耳を傾けたりする間、花鳥風月などどうにもならぬことにも翻弄される(卍本 事物に対して、時には、虚であるのに実とし、実であるのに虚と、真実の理を失うこともある)。
多年にわたって、冬になれば、山に雪が積もるものと単純に思いこんでいたが、今年の冬、そうではない。
雪が山そのものとなり、山と雪とが何の区別もなく一体となって存在している厳然たる事実を覚(し)る。(272~273頁)
■三界十方何ぞ一色なる、誰か論ぜん天上及び人間(じんかん)、
伝うること莫(なか)れ寒苦鳥(かんくちょう)の言語、無熱悩池雪山に在り。
〈現代語訳〉
三界という時間を貫く世界も、十方という全空間の世界まで、雪の白一色(いっしき)、対立のない平等の世界。
これでは、天上の理想の世界だの人間の世界などと分けて議論はできない。
雪山の寒苦鳥のように、夜通し、寒苦、寒苦などと鳴くことはない。
熱さも悩みもないという無熱悩池は、雪の降り積もった雪山の奥地にこそある。
〈語義〉
○三界十方 三界は欲界・色界・無色界などの時間的全世界、十方は東西南北・四維(しゆい、東南・東北・西南・西北)・上下などの方角の全世界。
○寒苦鳥 雪山鳥。雪に閉じ込められ寒さに苦しむ鳥、越山中の学人。『鶯林拾葉(おうりんしゅうよう)』(第23)に「物語に云く。雪山という山に寒苦鳥あり、終夜、雌は殺我寒故(寒いから私を殺して)と説き、雄は夜明造巣(夜が明けたら巣を作ろう)と鳴く、夜が開ければ温となるゆえに巣を作らず、『何故造作巣、安穏無常身、今日不知死、明日不知死』と鳴くなり」とある。これは世の無常を語る説話として知られた。
○無熱悩池 無熱悩の池はインドの雪山にあるとされ、その池では菩薩などが龍となって住んでいるという。(273~274頁)
■〈解説〉雪の頌について
永平寺は北陸の越前にある。冬から春になっても雪は消えない。七、八尺のときも一丈あまりのときもあり、随時増減している。また、道元の師である如浄古仏に「雪裏の梅華」という言葉がある。道元はこの言葉を愛された。それゆえ、当山に住職されてから、多く「雪」を題材とされて説法された。
いうまでもなく、越前の永平寺は、まさに山奥の雪の多い地方にある。道元は、寛元元年(1243)七月、四十四歳のときに入越し、以後示寂(じじゃく)の建長五年(1253)八月、京に発(た)つ五十四歳まで、ほぼ十年間を永平寺で「山居(ご)」(後の「山居の偈頌」を尊び、その雪を仏法の友として親しみ幾多の説示をし雪にちなむ偈頌を作頌した。(276頁)
■〈解説〉冬至について
冬至は、いうまでもなく、一年のうちの昼の長さが最も短い冬の極点の日で、古来、陰が極まり陽の始まる日、「一陽来復」(冬が去り春に向かう意)として祝われた。道元は、この冬至の日の様相を仏法把握の根本的時節の問題とした。上堂で、宏智(わんし)古仏の語を「宏智古仏、天童に住せし時、冬至の上堂に云く『陰極まり陽生じ、力(つとめ)窮(きわ)まり位転ず。蒼龍は骨を退(ひ)いて驟(はせ)り、玄豹(げんぴょう)は霧を披(ひら)いて変ず。要すらくは、三世諸仏の髑髏を将(も)って、穿(うが)って数珠子(し)一穿と作(な)さんことを(今日、冬至の日は、陰の気が極まり陽の気が生じる日である。それと同じように、あらゆるものの力は限界までくるとその様相を転ずるのである。蒼き龍は骨をぬき姿形を変えて、自在に飛天し、また、玄(くろ)き豹は霧のなかでその紋様をあざやかに変えるのも、そのはたらきである。それゆえに、諸君も、万法と一体となっている三世の諸仏の髑髏に穴を開けて一連の数珠とするように、諸仏の骨髄を自分のものとし、自分自身を作りかえて諸仏としなければならない)』」と取り上げて「冬至というのは、俗世間の慶節ではあるが、実はそれはそのまま仏祖の慶事でもある。昨日はひとすじの線ほどの日の短さが最高潮となって、陰の気が行き着くところまで行き、厳しい寒さの風の声もやんだ。今朝はひとすじの線ほどの日の長さがもどり、陽の気が生れて万物が息を吹き返しざわめくようになる。すなわち、こうしたこと、大自然の営みを、禅僧としても慶事として、歌って手をうち喜び、この時に応じて、仏祖も祝福して舞うのである」と説示している(『永平広録』巻二ー上堂135)。このような冬至の説示は、冬至の上堂としては五回ほどが収録され、宏智古仏の冬至の上堂語は、『永平広録』巻二ー上堂206にも引用せられている。冬至の上堂の数が少ないのは、冬至の小参(しょうさん)が、巻八の小参の部に四回ほど収録されているように、冬至に際してはとくに小参という形でごく親しく説法されたからでもあろう。とくに『永平広録』の小参は総計二十回分が収録されているが、その内容は結夏(けつげ)・解夏・冬至・除夜に限られているのが特徴である。(282~283頁)
■仏成道(ぶつじょうどう)
明星を擒出(きんしゅつ)して世界紅なり、眼睛(ぜい)霹靂して虚空を破す、
更に拈ず成道娑婆国、委悉に春に向かう木(もく)杓の風。
〈現代語訳〉
仏成道(釈尊が成道された日)
釈尊が、明けの明星をとらえたとき、さとりの威光で世界が紅色に染まった。
釈尊の眼睛は、稲妻のように光り轟き、虚空を照破した。
同時に、迷妄の娑婆国を成道の世界へと一新され、
春に向かう風が吹くように、脱落の風が吹きわたったのだ。
〈語義〉
○擒出 とらえいだす。釈尊が十二月八日、菩提樹下(げ)にあって、暁天の明星を見て悟道されたこと。
○明星 暁天の明星、釈尊は三十歳、十二月八日の明けの明星とともに大(だい)悟された。
○娑婆国 内に煩悩を懐き、外に苦悩するなど種々の苦しみに晒される俗世間。
○委悉 つぶさにくわしく、ことごとくを。
○木杓 木製の柄杓。木杓破・破木杓という語句があり、それは無用で役にたたないところから転じて脱落した悟境の世界、身心脱落の意にたとえる。
〈解説〉仏成道について
釈尊の成道された月日については、所説があるが、禅家では、十二月八日を釈尊の成道日とし、この日に成道会を行うことが宋代頃から定着し、この風習が、現今の日本仏教の各宗派に採用されている。日本におけるそうした礎を創られたのは道元である。道元は、その経緯を、建長元年(1249)十二月八日、釈尊の成道にちなむ、所謂臘月八日の上堂で、
日本国先代、曾(かつ)て仏生会(え)・仏涅槃会を伝う。然而(しかれ)ども、未だ曾て仏成道会を伝え行わず。永平、始めて伝え已(すで)に二十年。自今已後、尽未来際、伝えて行うべし。(『永平広録』巻五ー上堂406)
と述べている。この上堂は建長二年(1250)のことで、この二十年前といえば、寛喜二年のことである。残念ながら、この年の臘八成道会の上堂語は『永平広録』に収録されていないので、その当時、臘八の上堂がどのようになされたのか、いまは知る術を持たず詳細は不明である。が、道元が「自今已後、尽未来際、伝えて行うべし」とされた慈訓は厳密に護持され、今日に伝えられているのは周知されるところである。(284~287頁)
■雪の夜、準記室の二十八字を感じて、病中に右筆す
訪道登高す深雪の夜(よ)、覆身(ふくしん)没腰(もつよう)憐むべき時なり、
頭(こうべ)を刎(き)り臂を断つ邪法なりと雖(いえど)も、藤蛇(とうだ)を跳(ちょう)脱する乃(すなわ)ち正師(しょうし)なり
(卍本 憐れむべし庭際腰を没する時、試みに看よ断臂の旧公案、藤蛇を跳脱して幾固か知らん)。
〈現代語訳〉
雪の夜、準書記の偈頌に感じて作頌、病中にあったが筆をとった(卍本 義準書記の雪夜の偈頌の韻に欠ぐ)
この深雪の夜、昔日、厳冬の深雪のなかに達磨を訪ねた慧可のことが思い出されるが、義準よ君は、同じように雪を踏み分けやって来たが、大変であったであろう。
身をも腰をも没する雪のなかを、よくぞこの永平寺まで訪ねてくれた。
仏法のために、頭を剃り、また臂を断つなどの求道の精神は邪法ではあるが、
藤蛇のごとき妄想(ぞう)を、いのちをかけて絶ちきるのが真の正師なのだ
(卍本 庭の雪は腰を没するほどあるのによくぞ来られた、臂を断ついのちがけの求道の精神を参究し、藤蛇のような妄執を断つことを知らねばならぬ)。
〈語義〉
○準記室 準は人命、義準のこと、記室は書記。生没年不詳。
○藤蛇 木にまつわる藤を蛇に見まちがうように偽を真とし、真を偽と見まちがえる。偏見して執着(しゅうじゃく)した妄見・迷妄のこと。
〈解説〉義準の雪中見舞いについて
義準は、日本達磨宗の懐鑑(えかん)の弟子で、永平寺三代徹通義介(1219-1309)と同年で、比叡山で三蔵教学を学び、後に仁治二年(1241)頃興聖寺の道元に師事する。道元の越前移住に際して、興聖寺に留まり院事を管理した。後に永平寺に移り書状侍者(住職の文書の管理や草案をつくる役)を務め、道元亡き後、永平寺二代孤雲懐奘(1198-1280)に参じて心印を受け、越前永徳寺の第一祖となる。また晩年は歓喜(ぎ)院に住し、豊(ぶん)後の永慶寺に住職したとも、また一説には、道元示寂(じじゃく)後、義能と改名し高野山金剛三昧院に学び、播磨の無量寿院開山伝統大僧都(ず)になったとも伝えられる。義準は、その師懐鑑(えかん)の忌辰(きしん)に当って、道元に上堂を請願している。『永平広録』巻七ー上堂507に「準書状、為懐鑑上人忌辰請上堂」がある。義準が雪中の永平寺に道元を訪ねたのは、建長四年(1252)十一月頃、道元示寂の前年のことで、雪漫々と積もるなかのことで、それは、まさに少室峰(しょうしつほう)の達磨に訪道した慧可の様相を連想させる。
道元は『訂補建撕(ぜい)記』の記すところによると、建長四年の夏頃から健康がすぐれず、翌年の建長五年(1253)の八月五日には京に向う。そのときの偈頌が
十年飯を喫す永平の場 七箇月来たって病床に臥す
薬を人間(じんかん)に討(たず)ねて峡を出ず 如来に手を授して医王に見せしむ
というのである。ここから、建長四年夏頃からは体調を崩され、その暮れから翌建長五年初頭には病床に臥され重篤であったことが窺える。ちなみに義準が雪中に永平寺に上山したのが十一月であれば、時節もあい、それは道元への最後の雪中見舞いであり、その際に義準が偈頌を呈したのに感じての、道元の慈愛に満ちた偈頌である。(292~293頁)
■山居 十五首
①幾ばくか悦ぶ山居尤(もっと)も寂寞なるを、斯(こ)れに因(よ)って常に法華経を読む、
専精(しょう)樹下(げ)何ぞ憎愛せん、妬(ねた)ましきかな秋深き夜(よる)の雨の声(卍本 月色は見るべし雨は聴くべし)。(293~294頁)
②西(せい)来の祖道我東に伝う、月に瑩(みが)き(卍本 釣り)雲に耕して古風を慕う、
世俗の黄塵飛んで豈(あに)到らんや(卍本 到らず)、深山の雪夜(せつや)草庵の中(うち)。
③夜坐(やざ)更闌(た)けて眠り未だ至らず(卍本 熟さず)、弥(いよいよ)(卍本 情(まこと)に)知る弁道は山林なるべし、
渓声耳に入り月穿(うが)つ眼(まなこ)を(卍本 眼に到る)、此の外(ほか)更に一念の心無し(卍本 何の用心をか須(もち)いん)。
④我山を愛する時山主を愛す、石頭大小道(どう)何ぞ休せん、
白雲黄葉時節を待つ(卍本 時節に応ず)、既(すで)に抛捨(ほうしゃ)し来(きた)る俗の九流。
⑤雲根(うんこん)を采得して水関(すいかん)を透(とお)す(卍本 雲根を透るに坐得して)、破顔して拝会(はいえ)す拈華顔(ねんげがん)(卍本 破顔拝会す拈華の顔(かんばせ))、
明らかに知りぬ久遠劫(ごう)来の契(ちぎり)(卍本 約)、山(やま)主人を愛し我山に入(い)る。
⑥山に在って漸(ようや)く覚(おぼ)ゆ山の声(しょう)色(卍本 消息)、結菓開花(げ)脱空を疑う、
且問(しょもん)何を以ってか本色(じき)と為する、青黄赤白(せいおうびゃくじゃく)画図の中(うち)。
〈現代語訳〉
山に棲み、ようやく本来の山の真実のすがた(卍本 消息)が分かる。
草木は時節に応じ、緑にしたがって実を結び花を咲かせるが、そればかりが山の本来のすがたではない。
それでは一体何が真実のすがたなのだと問えば、
山の、緑に応じて青・黄・赤・白等々に転変する、そのすがたそのものにある。
〈語義〉
○脱空 空を脱けでたものがあるかを疑うという意だが、空は、この場合は縁生をいう。すべてが縁によらぬものはないの意。雲門文偃(えん)(864-949)の「雲門録」下に「師云く、什麼(いかに)せん脱空の妄語、代って云く、事孤起せず」とある。
⑦久しく人間(じんかん)を舎(す)てて(卍本 人間に在って)愛借(じゃく)無し、文章筆硯(ひつけん)既(すで)に拋(す)て来(きた)る、
花を見(卍本 看)鳥を聞くに風情少なし、山に在り乍(なが)ら猶(なお)不才を愧(は)づ(卍本 時人の不才を笑うに一任す)。
〈語義〉
○乍在山猶愧不才(卍本 一任時人笑不才) 山居に徹しながらも、そうした花鳥風月の真髄を詩文にしえない自分の不才を恥じるばかりだ(卍本 いや、もうそのようなことは、時の人の不才を笑うに任そう)。
⑧幾(いくば)くか怜(あわ)れむ(卍本 憐れむ)潦倒(ろうとう)画図の質(すがた)、耳目時と与(とも)に明らからずと雖(いえど)も(卍本 明らかならずに似たり)、
云(こと)に拋(なげす)て難(がた)く還(また)染め易(やす)きこと有り(卍本 只此の見聞染る所無し)、
草庵の秋の雨(卍本 秋色)夜の渓(たに)の声。
⑨三秋の暮立(ぼりつ)(卍本 気粛)清涼の候、繊月(せんげつ)叢中(そうちゅう)万感の中(うち)、
夜静かに更(こう)闌(た)けて北斗を望む(卍本 看る)、暁天将(まさ)に到りなんとして東を指す。
⑩三間(さんげん)の茅屋(ぼうおく)清涼に足れり(卍本 既に風涼)、鼻孔(くう)瞞(まん)じ難(がた)し(卍本 鼻観先ず参ず)秋菊香(かんば)し、
鉄眼(げん)銅睛(ぜい)何ぞ潦倒(ろうとう)せん(卍本 誰か弁別せん)、越州にして九度(たび)重陽を見んとは。
⑫晩鐘月に鳴らして灯籠を上ぐ、雲衲(うんのう)坐堂して静かに空を観ず、
幸いに三田(さんでん)を得て今種を下す、快(こころよ)きかな孰脱一心の中(うち)。
⑬蛬(きりぎりす)の思い虫の声(卍本 蛬思蟬声(きょうしぜんせい))何ぞ切切、微風朧月(ろうげつ)両(ふたつなが)ら悠悠たり、
雲松柏(しょうはく)に封じて池台(ちたい)旧(ふ)りたり、雨梧桐(ごどう)に滴(したた)る山寺(さんじ)秋なり。
〈語義〉
○雨滴 雨の滴るは、悟道の響きか。『正法眼蔵』「行持」巻下に「漹山のそのかみの行持、しずかにおもいやるべきなり。おもいやるというは、わがいま漹山にすめらんがごとくおもうべし。深夜のあめの声、こけをうがつのみならんや、岩石を山穿却(せんきゃく)するちからもあるべし」とある。
⑭灯(ともしび)を挑(かか)げ筆を把(と)って志(こころざし)を言んと欲す、遥かに西天曩祖(さいてんのうそ)の蹤(あと)を慕う、
我仏の伝衣(え)寒谷(かんこく)の始(はじめ)、独り唯嵩嶽(すうがく)少林の冬のみならんや。
〈語義〉
○我仏伝衣 釈尊の伝えた伝衣のあとかた。
○寒谷 仏国土。
○嵩嶽少林 嵩山少林寺での神光慧可(487-593)の雪中断臂のこと。
⑮深山深谷草庵の中(うち)、観念坐禅窮(きわ)むべからず、
功徳の高峰塵(ちり)尚(なお)運ぶ、如来の弟子神通(じんずう)を願う。
〈語義〉
○神通 深山深谷草庵のなかという山居(さんご)こそが、仏法の真実のはたらきである神通(じんずう)である。『正法眼蔵』「神通」巻に、神通とは、一滴の水が大海を呑んだり吐いたり、小さな塵が高山をとらえたり放ったりすることであることを「しかあれば仏道はかならず神通より達するなり。その達する、涓滴(けんてき)の巨海を呑吐する、微塵(みじん)の高嶽(こうがく)を拈放(ねんほう)する、たれか疑著(ぎじゃく)することをえん。これすなわち神通なるのみなり」と述べている。
〈解説〉山居について
「山居(さんご)」とは、世塵のいたらない深山幽谷に身心を処して、その静寂な山水のなかに仏に出会い仏道を行ずる修行生活をいう。
道元は、除夜の小参で、僧の生活基盤は、「山居」に極まることを、釈尊の言として「山林に睡眠するは、仏、歓喜し、聚落に精進するは、仏、喜ばず」(『永平広録』巻8ー小参2)と引き、歴代の大祖師方が皆山居し、俗でも有道の士は皆深山に隠れたことを示し、結夏(けつげ)の小参では「僧家は山に居する好し」として「居山好底の道理」を偈頌で、縁にあうことこそが大事で、それであるからこそそれぞれの場で仏道に励みすべてに通ずるようになるのだとして、「松風は暁の窓辺を打ち、月光は秋水に映る。鶴を飼うものはその潔さを愛し、雲を見てはその悠々たるすがたを心に刻む。時に応じ節に応じて、季節は移ろう。夏には薫風が吹きわたり、万谿(まんけい)・万嶽(まんがく)に雨が絶え間なく降れば、山や谷は濛々と煙る。まさに、そうしたとき、どうか」といい、さらに、「端座する場は苔むして岩石は滑りやすく、吹く風は高く、多福のいう竹は群がり鳴り響いている、ということは、すべてはあるがままにある、と云うことなのだ」(『永平広録』巻8ー小参19)と言葉を継いでいる。
また、『正法眼蔵』「山水経」巻にも、その根本の精神を、山水こそは、古仏の説くところを実現したものといい、「而今(にこん)の山水は、古仏の道現成なり」と示し、さらに、山は遥かな昔より大聖・賢人たちが住まいとし、山を身心としたとして「賢人聖人ともに山を堂奥とせり、山を身心とせり、賢人聖人によりて山は現成せるなり。(中略)おおよそ山は国界に属せりといえども、山を愛する人に属するなり。山かならず主を愛するとき、聖賢高徳やまにいるなり」と説示している。そうした山居の精神の支柱となったのは、本師如浄古仏の「城邑(じょうゆう)聚楽に住することなかれ、国王大臣に近づくことなかれ。ただ深山幽谷に居りて一箇半箇を説得して断絶せしむることなかれ」という垂誡(すいかい)である。さらには、宝治二年(1248)の「鎌倉からの帰山の上堂」の帰山底の句(『永平広録』巻3ー上堂251)にも、「山僧(ぞう)出で去る半年余、猶(なお)孤輪の太虚に処するがごとし、今日山に帰れば雲喜ぶ気あり、山を愛するの愛初めより甚(はなは)だし」と見える。山居の偈頌にも、「我山を愛する時、山主を愛す」と頌しているように、道元の山居への徹底した感慨は、偈頌十五首ばかりではなく、『正法眼蔵』や『永平広録』など著作のいたるところに散見される。
そのような「山居』の精神が結実しているのが「山居」の偈頌一五首なのである。
『傘松道詠』には「草庵雑詠」として、二六首ほどの道詠が収められているので以下に記しておく。(岡野選5首)
草の庵(いお)に立ちても居ても祈ること我より先に人をわたさん
徒(いたずら)に過ごす月日はおおけれど道をもとむる時ぞすくなき
大空に心の月をながむるもやみにまよいて色にめでけり
春風に我ことの葉のちりけるを花の歌とや人のみるらん
山のはのほのめくよいの月影に光もうすくとぶほたるかな(293~316頁)
■十二時頌
鶏鳴(けいめい) 丑
②渾身(こんしん)我に似て是渾身 何ぞ渾身して孤夢(こぼう)新(あらた)ならしめんに、
仏腹祖胎都(すべ)て活計す、披毛(ひもう)戴角(たいかく)疏親(そしん)を見んや。
〈現代語訳〉
鶏鳴 丑 夜八ツ・四更、午前一時ー午前三時
②この時刻では、わが身は夢のなかにあっても、それとて自分以外のなにものでもない。
どうしてこの禅床のわが身一人が夢に迷うことがあろう。
いま、この我自身は仏祖の胎内にあって仏祖としてはたらいている。
禽獣たちの生命あるものと自分自身には親密とか疎遠とかの区別はなくすべてが平等の世界にいる。
日出(にっしゅつ) 卯(う)
④眼睛を換了して相(しょう)見し来(きた)る、自穿(じせん)の鼻孔(びくう)幾千枚ぞ、
明くるを遅(ま)つ雪の夜(よる)豈(あに)寒谷(かんこく)ならんや(卍本 海東の雪暁寒谷にあらず)、日所生頭是日胎(にっしょしょうとうこれにったい)。
〈現代語訳〉
日出 卯 明け六ツ・六更、午前五時ー午前七時
④己の眼睛に切り換えて、新たに仏と出会う。
自分自身を穿(うが)つように辛苦し、弁道功夫し自身を探究する。
慧可は大雪のなかで夜が開けるまで立ちつくしたが、仏法の嗣続(しぞく)せんとする心意気のなかでは、寒谷の厳寒も物の数ではなかった
(卍本 東海に日は昇り、雪の夜も明け、寒谷の冷気も暖気に包まれる)。
いま、太陽がその頭を覗かせたが、それこそがすべてを見通す眼睛の出現。
〈語義〉
○換了眼睛 自己の眼を仏眼に換えて。あるいは昨日の眼を今日の眼に変えて日々を新たにの意をも含むか。
○日所生 太陽が出るところ。太陽が出ると。太陽の胎内、もののはじまり。
〈現代語訳〉
食事(じきじ) 辰 明け五ツ・七更、午前七時ー午前九時
④食事のときには、大菩提心をもって、修行道場の僧堂も仏殿も、宇宙全体を呑却(どんきゃく)する気概で食事ををする。
真実を求める高き志は、あの雲や霞を愛して空腹を満たす。
インドで展鉢(てんぱつ)すれば、その飯の湿気は新羅に及ぶように、釈迦の仏法は、はるか遠くまでその功徳がいたっている、その功徳をいただく。
食の功徳の偉大さは、趙州(じょうしゅう)は学人に茶を勧めて、喫茶という日常底のなかにこそ仏法が顕現していることを示した、趙州に茶を勧められたわけではないが、趙州の示す仏祖一体の食事を十分に味わいいただく。
〈語義〉
○喫却僧堂 喫却は食べつくす。僧堂を食らい仏殿を飲み込む。食の功徳の大きさは心に万物を食するところにある。
○趙州 趙州従諗(ちょうしゅうじゅうしん、778-897)は学人に「喫茶去」と茶を勧めて、喫茶という日常底のなかにこそ仏法が顕現していることを示した故事。
禺中(ぐうちゅう) 巳(み)
〈現代語訳〉
禺中 巳 昼四ツ・八更、午前九時ー午前一一時 食事が終わり坐禅のとき
⑥坐禅三昧(ざんまい)のなかでさらに上の境涯を納得し、龍が水を得たように溌剌と絶対妙境にいたる。
身心一如(しんじんいちにょ)の安心(じん)の境涯は、草が春を迎えたのと同じ喜悦の心境(卍本 早く春に会う)。
真実に出合いたいと、皆競って努力しているが、それに出合うのはほかならぬ己自身。
ありとあらゆる物が一塵の汚れもなく、山(せん)河大地、それがありのままに仏法を顕現している。
〈語義〉
○身心倶語 身心一如の安心の境地。
○撲落縦横 撲落は打ち落とす。縦横はたてとよこ、思うままに。ありとあらゆるものが、一塵に汚れることなく脱落してそのあるがままに顕現している。
日昳(じつてつ) 未(ひつじ)
⑧日面目中円月(がち)面(卍本 日面相中円月の面)、
経を得て眼を遮(さえぎ)れば眼経と成る、産来参究竟(つい)に外無し、雲は晴天に在り水瓶(かめ)に在り。
〈現代語訳〉
日昳 未 昼八ツ・十更、午後一時ー午後三時
⑧日昳、未の刻は看経(かんきん)のときだ、変易する現象のなかにあって、太陽と月は円く何も変わらない。
看経することによって、その不変の理を学べば、眼が経となり、経が眼となる。
仏道の参来し参究すべきものは、このほかに何もない。
雲は晴天に浮かび、水は瓶にあるように、諸法実相のすがたは、あるべきところにありのままにある。
〈語義〉
○日面目(卍本 相)中円月面 日面は太陽、月(がち)面は月。変易する現象のなかにあって、太陽と月は円く何も変わらない、不変の理法を示すことを象徴的に表現する。
○雲在晴天 雲は空にあり、諸法実相ありのままのすがた。
晡時(ほじ) 申(さる)
⑨脚尖(きゃくせん)趯倒(てきとう)す海山嶽(かいせんがく)(卍本 鉄崑崙)、無孔(むく)の拳頭黒雲を興(おこ)す(卍本 拳頭を挙起して海嶽昏し)、
忽地(こつち)の風雷轟(ごう)霹靂たり、省来打(た)坐して精(しょう)魂を弄(ろう)す。
〈現代語訳〉
晡時 申 昼七ツ・十一更、午後三時ー午後五時
⑧晡時、申の刻、日傾く時刻、脚の先で大海を躍り超え、山岳を踏み倒すようにして(卍本 鉄の崑崙山)何ものにも執(とら)われず、
自在なる非思量の坐禅に打ちこめば、黒雲を呼び(卍本 拳を挙げれば海嶽昏くなり)、
たちまちにして風雷が起こり、天地に轟々(ごうごう)たる雷鳴が轟く。
そのとき、自己を徹底的に省みて、打坐に全生命を打ち込む。
〈語義〉
○脚尖趯倒 脚尖はつま先。趯倒は躍り上がり踏み倒す。脚の先で踏み倒す。物に執着(じゃく)しないこと。
○無孔拳頭 孔のない拳とは、無孔の鉄鎚と同様に手のつけようもないという意味も持つ。自在無礙な非思量の坐禅のこと。
○忽地 たちまち、にわかに。
○霹靂 激しく鳴り響く雷、雷の激しく鳴り響く音。転じて迅雷のように激しく鋭い機峰。
○弄精魂 精力的に専一に弁道功夫すること。
〈解説〉十二頌について
■道元は、『正法眼蔵』「諸悪莫作」巻で「衆生作仏作祖の時節、ひごろ所有の仏祖を罣礙(けいげ)せずといえども、作仏祖する道理を、十二時中の行住坐臥につらつら思量すべきなり」といって、その時々に自覚し弁道することを説示しているが、その実際を示したのが、この十二時頌である。(317~342頁)
(2017年11月24日)