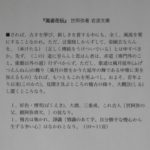『ウィトゲンシュタインの知88』野家啓一篇 新書館
■『確実性の問題』
『確実性の問題』は1949年から51年にかけて書かれたメモの集積である。外見は『哲学探究』と同様短い断章より成るものであるが、『哲学探究』が著作としての完成度をかなりの程度実現しているのに対して、これはまだ未選別未推敲のメモのまま残されている。というのも、ウィトゲンシュタインにはもうそれをまとめなおす時間が残されていなかったのである。このメモが書き始められた年に彼は前立腺ガンの告知を受けている。そして最後の第676節の日付は51年4月27日となっている。その翌日、ウィトゲンシュタインは意識を失い、次の日の朝、62歳の生涯を終える。まさに、死を受け入れつつ書かれた絶筆なのである。
きっかけはムーアの論文「常識の擁護」とそれを巡るマルコムの議論にあった。ムーアはこの論文において認識論の伝統に叛旗をひるがえした。従来の認識論においては、不確実な命題を確実な命題で基礎づける試みが繰り返され、しかも、その確実性は意識の領域に求められていたが、それに対してムーアは、自分の手や大地といった外界の存在において根拠の探求を打ち止めにしようとした。こうした意識内在主義の拒否と根拠の終端の確認は、まさにウィトゲンシュタインの方向と共通するものであり、彼はムーアに強く共感しつつ、その不備を咎め、さらなる展開を求めたのである。
ウィトゲンシュタインは、探求の主題となりそれゆえ知の対象となる確実性と、ムーアが求めた確実性の領域とを区別する。例えば、歴史の探究においては、探求されている時代に大地が存在したことはその探求における不動の枠組みとなっている。大地が存在したことは歴史的探求によって明らかにされることではなく、歴史的探求を可能にするための前提として、歴史的探求を営む者が鵜呑みにしなければならないことにほかならない。それゆえ、歴史的探求の実践に加担しつつ、大地の存在を疑うことは不可能なのである。もし大地の存在を疑うならば、そのとき歴史的探求は放棄されなけばならない。ここに、『確実性の問題』が明らかにしようとする確実性の領域がある。それは確かに根拠の終端ではあるが、他の諸命題を支える基礎としての根拠となるわけではない。「動かぬものは、それ自体がはっきりと明瞭に見て取られるがゆえに不動なのではなく、そのまわりにあるものによって固定されているのだ」(『確実性の問題』第144節)。つまり、不動の基盤があるから実践が可能になるのではなく、われわれがかく実践しているからこそ、そこに不動の枠組みが要求されるのである。
さらに『確実性の問題』の特徴は、そうした枠組みを規則ではなく、「ここに手がある」や「大地がある」といった経験命題の形をしたものに求めたことにある。そうした命題は「世界像命題」と呼ばれる。それは、われわれがこの世界で生きるために鵜呑みにしなければならない生活の枠組みにほかならない。そして、あらゆる探求はこうした枠組みをもと。それは、それ自体として絶対確実という身分をもつものではないから、実践と探求の場を変えることによって疑いの目を向けることも可能である。しかしそのときには、その疑いの枠組みとして他の経験命題が不動の位置をもたされることになる。疑うためには疑われぬものが必要とされる。「すべてを疑おうとする者は、疑うところまで行き着くこともできない」(『確実性の問題』第115節)。
それゆえ、個別の命題を単独で取り出すならば、いかなる命題であれ、疑うことは可能である。われわれは名証的な命題を個別に受け入れ、その礎石の上に知識を構築するのではない。受け入れられるものは個別の命題ではなく、体系全体である。ここには、一見クワイン的な全体論的知識観がある。だが、体系全体を受け入れることにおいて不可疑の枠組みが要請されるという洞察は、クワインの全体論とは異なる方向を示していると言うべきだろう。(野矢茂樹)(80~81頁)
■論理形式
――前略――
さて一方、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(1922年)においては、命題の有意味生は命題が現実の像であることに存する(4.01)。像とは現実のモデルとなるようないま一つの事実である(2.12,2.141)ということに留意して、この論点を検討してみよう。さて、およそ何ものかが他の何ものかの像であるためには、両者が何らかの写像形式を共有していなければならない(2.17)。たとえば空間的な像は有色的なものを写像する(2.171)。このとき、いかなる写像形式に関してであれ像と写像されるものとに共有される形式というもの、いわば最大限に抽象的な写像形式というものが考えられるはずである。ウィトゲンシュタインはそれを「論理形式」と呼ぶ(2.18)。論理形式によって写像する像は論理像であり、事実の論理像が思想である(2.181,3)。そして思想とは有意義な命題なのである(4)から、つまるところ命題はそれがしゃぞうする現実と同じ論理形式を有するのでなければならない。こうして、ラッセルにおいては判断主観が命題を理解するための与件として位置づけられていた命題の形式という観念は、『論考』においてそのような認識論的枠組みがまったく捨象された論理形式という観念へと鋳直される。
――後略――(中川大)(95頁)
■写像理論
「『論理哲学論考』の写像理論」という場合、それは、「命題とは何か」という問いに対して「命題とは現実の像である」と答える「命題の写像理論」のことを指すことも、また、「そもそも像とは何であるか」という問いに答える「写像の一般理論」のことを指すこともありうる。しかし、後者の理論は前者の理論を支えるために提示されていることが明らかであるとおもわれるので、われわれは「命題(あるいは文)とは何か」という問いがいかなる問いであったかを振り返ることから始めよう。
――中略――
ラッセルの説では、真理の対応説が保存されるものの、主観の作用から独立したところで文の有意味生を確保しようとしたフレーゲ説の眼目は失われてしまう。こうしてウィトゲンシュタインの目標は、主観の作用を排除しつつ対応説を維持する命題論となる。それが写像理論である。写像理論は、ラッセルの考えに反して、偽の命題も真の命題と同様、事実となんらかの対応関係を有すると主張する。すなはち命題の有意味性は一般に事実との対応が保証する。ただし、真の命題と偽の命題とは、それらのじじつとの対応の仕方が異なるのである。
さて、『論考』において世界(すべての現実)は諸事実からなり、事実は諸事態の存立であり、事態は諸対象の結合である(1.1,1.2,2,2.01,2.063)。そして像とはその要素が対象と対応し、現実と写像形式を共有することによって現実のモデルであるような事実である(2.12,2.13,2.17)。そして像は現実と一致するかもしないかも、真であるかも偽であるかもしれない(2.21)のであるから、像というものは、現実の写像でありながら、しかも偽でありうるものだということになる。ところで有意味な命題は事実の論理像(論理形式によって現実を写像する像)である(3,4.01)から、命題は現実の写像であるということによってその有意味性を保証され、しかもそれは命題の真偽からは独立のこととなる。
この見解において、名前と命題の対比は明確である。すなわち、名前の現実に対する関係は唯一的であり、名前は対象を名指さなければその意味を失うのに対して、命題は二肢関係的であり、真でなくても意義を失うわけではない。命題は真という仕方で現実に関係づけられることもできるという意味で方向をもち、それが命題が意義を有するということである。それにひきかえ、フレーゲは文も名前であると、ラッセルは名前(通常の固有名)も文も不完全記号であると見なすことによって、この対比を見失ったのである。(中川大)(96~97頁)
■超越論的
「超越論的」(transzendental)という言葉は『超越的(transzendent)」から派生したものであり、超越的なもの(意識を超えた対象)の妥当性と意味を認識の問題として論ずることを意味する。それを哲学的概念として洗練させたカントは『純粋理性批判』において、「私は、対象にではなく、対象を認識するわれわれの認識の仕方に、この認識の仕方がアプリオリに可能である限りにおいて、これに一般に関与する一切の認識を超越論的と称する」(B25)と述べている簡単に言えば「超越論的」とは「経験の可能性の条件」に関わる認識のことであり、ウィトゲンシュタインの用法も基本的にはこのカントによる定式化を踏まえている。
『論理哲学論考』において、「超越論的」という言葉が用いられているのは2箇所のみである。それらのうち一方は「論理」に、他方は「倫理」に関わっており、両者はともに「語り得ぬもの」の領域に属する。論理と倫理というかけ離れたものが、なぜともに「超越論的」であり「語り得ぬもの」であるのか。ここに『論考』の秘密を解く鍵が隠されている。
第一は「倫理は学説ではなく、世界の鏡像である。論理は超越論的である」(6.13)という箇所である。これは「論理の命題は同語反復命題(トートロジー)である」(6.1)という節に対する注釈であり、論理は経験科学のように世界の内容について語るものでなく、論理空間の構造という世界の形式を示すものであることが述べられている。論理はいっさいの経験的じじつに先立ち、われわれの経験の可能性をあらかじめ条件づけるものであるがゆえに、「超越論的」なのである。
第二の用例は「倫理を口にしえないことは明らかである。倫理は超越論的である」(6.421)という箇所に見ることができる。倫理の命題は「事実」ではなく「価値」を語るものである。ウィトゲンシュタインによれば、すべての出来事や状態は偶然的であり、世界の中に「価値」は存在しない。経験科学の語る「事実」が偶然的であるのに対し、世界のあるべき姿を指定する「価値」は必然的でなければならない。だが、世界の「内」に在るものが偶然的である以上、「出来事や状態を偶然的でなくするものは世界の中に在ることはできない」(6.41)のであり、それは世界の「外」に在るほかない。世界の外部にあるものをわれわれは語ることができない。「倫理の命題は存在しえない」(6.42)と結論されるゆえんだ。
だとすれば、倫理は世界の外にあるものとして、「超越論的」よりはむしろ「超越的」と称されるべきであろう。だが、倫理は世界を超越したものではなく、あくまでも「世界の限界」に接するものとして、やはりわれわれの経験の可能性の条件をなしているのである。世界の限界は言語の限界を通じて内側からのみ画定されるというのが『論考』の基本姿勢であった。いわば論理と倫理は「内部」と「外部」とから相補的に世界の「かたち」を定めているのである。
『論考』以後、ウィトゲンシュタインは「超越論的」という言葉をまったく用いていない。だが、そのことから彼の後期哲学を一種の「自然主義」と見ることは間違いである。前期・後期を問わず、経験の可能性の条件を「言語の可能性の条件」の探求を通じて解明しようとする彼の態度は一貫して揺らぐことはなかった。「言語ゲーム」の考察もまた、それが事実概念であるとともに方法概念でもあるという両義性ににおいて、経験的探求であると同時に超越論的探求であるという二重性を備えている。その意味で、ステニウスが『論考』を特徴づけるのに用いた「超越論的言語主義」という呼称は、ウィトゲンシュタインの哲学全体に対してもそのまま当てはめることができるのである。(野家啓一)(106~107頁)
■独我論
『論理哲学論考』において「独我論」は次のように登場する。
5.6 私の言語の限界は私の世界の限界を意味する。
5.61 論理は世界に満ちている。世界の限界は論理の限界でもある。
(略)
我々は考えられないことを考えることはできない。我々はまた、考えら
れないことを語ることもできない。
5.62 この考察は独我論はどの程度まで真理であるかという問いを決するための
鍵を与える。
独我論 が言わんとすることは全く正しい。ただそれは語られることで
はなく、示されることなのである。
世界が私の世界であることは、この言語(ただそれだけを私が理解する
ような言語)の限界が私の世界の限界を意味するということの内にしめさ
れている。
この箇所の「私の言語」という表現は、『論考』を読む者に唐突な印象を与えるに違いない。そのうえ、最後の命題は明らかに間違っているように見える。〈私の〉理解する言語と〈私の〉世界との間にどのような関係が成り立っていようと、そのことの内に〈世界そのもの〉が私の世界であることなどが示されるはずがないからだ。――略――(永井均)(108頁)
《私(岡野)の意見:世界そのものは勝手に身体に写り込んできて私の世界の地を作る。その世界を意識が解釈していくときに独我論が持ち上がってくる。》
■治療的分析
哲学的に考えることでどうしても陥ってしまいがちな隘路というものがある。そういった隘路にはまりこんだときの苦しみを知っていれば、ウィトゲンシュタインの次のような言葉は何らかの副因を含んでいるように聞こえてくる。
「哲学者は、病気をとりあつかうように、問いをとりあつかう」(『哲学探究』第1部255節)。
ここで「とりあつかう」と訳出されているのは英語では treatment であり、医学では「治療」と訳される言葉である。ウィトゲンシュタインの哲学は、哲学の旅路の救急病院でありたいと申し出ているかのようだ。では哲学はどんな病気に人を導きうるというのだろうか、またそこにどんな治療法を用意しておかなければならないと彼は思ったのだろうか。
上の引用の直前に、数学の場合が例として挙がっている。彼が考えていたのは、数学者が突如「数とは何か?それは実在か否か?」といった問いに取り憑かれた場合のことである。ここからはあのクリプキ流の誇張懐疑が連想される。「私が今していることは本当に加算だろうか?実は私が加算だと思っているだけで、それはクワ算だと誰かに言われたら抗弁のしようがないではないか」。それでも数学者はそのまま演算を続けるだろうが、哲学者はここで立ち止まることを余儀なくされる。
――略――(新宮一成)(156頁)
■ザラザラした大地
ウィトゲンシュタインの哲学は大きく二つの時期に分けられる。すなはち、『論理哲学論考』に代表される前期と『哲学探究』を中心とする後期とである。むろん一人の哲学者の一連の著作に連続性と非連続性があるのは当然だが、ウィトゲンシュタインの場合、その「転回」が余りにも劇的であったために、後の解釈者たちはその謎を解明しようとして腐心した。いわばこの「非連続の連続」とも言うべき事態を過不足なく捉えることが、ウィトゲンシュタイン解釈における扇の要となるのである。『探求』の序文の中で彼は「16年前ふたたび哲学に従事するようになってから、私は、自分が最初の本に書いたことのうちに重大な誤りがあることを認めねばならなかった」と述べている。最初の本とはもちろん『論考』のことである。それではそこにある「重大な誤り」とは何であったのか。それに一つの手がかりを与えてくれるのが『探求』107節の以下のような文章である。
「現実の言葉を精密に考察すればするほど、この言語とわれわれの要請との間の軋轢は強くなる。(論理の透明な純粋性は、私にとって探求の結果生じたものではなく、一つの要請であった。)この要請は今や空虚なものとなろうとしている。――われわれは摩擦のない滑らかな氷の上に迷い込んだのであり、そこでは諸条件がある意味で理想的なのだが、まさにそのためにわれわれは歩くことができない。われわれは歩きたいのであり、そのためには摩擦が必要である。ザラザラした大地に戻れ!」
ここでは「現実の言語」と透明で純粋な論理言語、すなわち「理想言語」とが氷上と大地というメタファーによって鮮やかに対比されている。『論考』においてウィトゲンシュタインが目指したのは、理想言語という氷の上に論理分析の鑿でもって透明な氷の宮殿を構築することであった。条件はすべて「理想的」にしつらえられている。だが、その宮殿で人間が生活することはできなかった。そこには応接間や広間はあっても台所はなく、寝室に備え付けられていらのはプロクルステスのベッドであったからである。
宮殿を出たウィトゲンシュタインは、氷の上には何よりも「摩擦」がないことに気づく。この「摩擦」という比喩は、カントの「軽快な鳩は自由に翼を張って空中を飛びながら、空気の抵抗を感じて、真空のなかであればもっと遥かにとく飛べるであろうにと考えるかもしれない」(『純粋理性批判』諸言)という言葉を思い起こさせる。『論考』の時期のウィトゲンシュタインが抱いたのも、この鳩と同様の錯覚であった。後に彼は理想言語に触れて「まるでそれらの言語がわれわれの日常言語よりももっと優れた、完全な言語であるかのように聞こえる」(『探求』81節)と述べて、その錯覚を訂正している。ともかく、歩いたり飛んだりするためには摩擦や抵抗が必要なのである。そこでウィトゲンシュタインは「ザラザラした大地へ戻れ!」と叫ぶ。摩擦のある大地とは、生活の文脈の中に埋め込まれた日常言語が織りなす人間的な世界のことにほかならない。
理想言語から日常言語への視座の転換は、同時に命題の論理分析から言語ゲームの記述へという方法論上の転換でもあった。ウィトゲンシュタインが「透明な純粋さという先入見は、われわれが自分たちの全考察を転回することによってのみ取り除くことができる(ただし考察の転回は、われわれ本来の必要を中心にしてなされねばならない)」(『探求』108節)と述べるゆえんである。
「ザラザラした大地」に立ち戻ったウィトゲンシュタインは、透明な氷原とはおよそ対照的な薮や泥濘に足をとられながら、困難な道を手探りで進むことになる(その歩行記録が膨大な遺稿として残されている)。しかし、ともかくもそれは人間の住む、猥雑ではあるが肥沃な大地なのである。(野家啓一)(158~159頁)
■世界像
――略――
世界像と将棋の規則との比較は、『確実性の問題』では明確に論じられていない重要な問題を提起する。将棋の規則であれば、例えば二歩禁止の規則をなくした新しいゲームを考えることもできる。あるいはまた、将棋の規則に従わずに済むもっとも抜本的な、そして唯一の方法は、将棋を指さないことである。では、世界像はどうだろうか。それは改変可能であったり、拒否可能であったりするのだろうか。
ウィトゲンシュタインが世界像の改変可能性を示唆していることはまずまちがいないところである。すなわち、いまわれわれが受け継いでいるこれらの神話と異なる神話をもっている人々は考えうる。だが、改変可能であるのもかかわらず、世界像を拒否することは不可能であるように思われる。例えば「これは私の手だ」ということをごく日常的な場面で疑うとすれば、私は私の正気をも疑わねばならないだろう。それはつまり、私には「これは私の手だ」ということは疑いえないということである。同様に、昨日の大地の存在を疑うこと、テーブルの上に置かれた3個のリンゴが見ているうちに4個になるのではないかと考えること、こうしたこともまた、正気からの離脱によってしか可能ではない。
ひとつの解釈にすぎないが、世界像はおそらく生活形式と結びついている。ウィトゲンシュタインはさまざまな議論において、しばしば異なる生活形式を想定する。しかし、われわれはこの生活形式を拒否することはできない。生活形式もまた、改変可能だが拒否不可能なのである。実際、3個のリンゴが見ているうちに4個になるのではないかと考えることは、われわれの生活形式に反しているだろう。それは将棋のように隔離されたゲームからの離脱ではなく、われわれがまともとみなす生活からの離脱にほかならない。(野矢茂樹)(171頁)
■言語論的転回
哲学史の常識といったものをあらためて眺めてみると、3つの名前がひとつの単位になるといったことが、どうも多いように思われる。だれでもすぐ思い出すのは、「デカルト・スピノザ・ライプニッツ」と、「ロック・バークリー・フューム」だろう。ほかにも、「ソクラテス・プラトン・アリストテレス」だとか、「フィヒテ・シェリング・ヘーゲル」だとかもある。こうした3つ組は、必ずしも、ヘーゲル流の「正・反・合」といった弁証法的発展過程の図式と合致するわけでもなければ、影響関係をはっきり問題にできるのは三代目までだけといった法則があるようにも思えない。結局のところ、深く考える必要はなくて、3という数が――変な言い方だが――語呂がいいだけかもしれない。
初期の分析哲学の歴史に関しても、現在の哲学史的常識は、3つの名前を返す。つまり、「フレーゲ・ラッセル・ウィトゲンシュタイン」である。そして、もうひとつの哲学史的常識によれば、3つの名前のどこかで、「言語論的転回」が生じたことになる。――中略―― こうして、ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』こそが、言語論的転回のもっとも明確な表現であるという主張に行き着くことになる。
――略―― 私のみるところ、言語論的転回後の哲学に特徴的なのは、たがいに関連しあう、つぎのような2つの認識の少なくとも一方が、そこに含まれていることである。
(1)哲学的問題の発生そのものに、言語が深く関わっていることの認識。
(2)哲学的問題の解決において、言語にかかわる問題の考察を経由することの不
可欠性の認識。
『論理哲学論考』が、この両方の認識を含んでいるという点は、まず疑いない。
――略―― (飯田隆)(182~183頁)
■分析哲学
分析哲学とは、哲学的問題を概念(あるいは言語表現)の分析により解明しようとするアプローチに対する総称だが、狭い意味では、今世紀、特に英語圏で隆盛を誇った伝統を指す。後者には、2つの学派が区別できる。
(1)論理分析 ――略――(2)日常言語分析 ――略――(古田裕清)(186~187頁)
■科学哲学
ウィトゲンシュタインは20世紀の科学哲学の成立と展開に、2重の意味で決定的な役割を果たしている。まず彼は前期の『論理哲学論考』を通じてウィーン学団の「論理実証主義」に哲学的バックボーンを与え、次に、『哲学探究』に代表される後期思想を通じて、いわゆる「新科学哲学」の勃興を促したのである。彼の前期から後期への思想的転回は、そのまま旧科学哲学から新科学哲学への潮流転換に対応していると言ってよい。
ウィーン学団は「形而上学の除去」をスローガンにして従来の哲学を批判し、哲学そのものの「科学化」、すなわち「科学的哲学」の確立を目指して出発した。彼らの宣言書『科学的世界把握』の末尾には、指導的代表者としてアインシュタイン、ラッセルと共にウィトゲンシュタインの名が掲げられている。ウィーン学団にとって、哲学の課題とは言明の明晰化であり、その方法は「論理分析」であった。これは『論考』の思想そのものにほかならず、彼らにとって本書がバイブルの位置を占めたゆえんである。
――中略――
20世紀の科学哲学はクーンの「パラダイム論」のよって決定的な転機を迎える。彼の『科学革命の構造』は科学的知識の累積生と連続的進歩という論理実証主義の基本前提に対する正面からの異議申し立てであった。クーンはパラダイムを論ずる際に、ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論を引き合いに出している。実際、「科学的探求の論理の一部として、事実上疑いの対象とされないものが確実なものである」(『確実性の問題』342節)や「改めて行なわれる実験が、それ以前の実験に偽証の罪を負わせることはできない。できるのは、われわれの見方を一変させることだけである」(同前292節)といったウィトゲンシュタインの言葉は、クーンのパラダイム転換の概念を先取りするものであった。その意味で、前期・後期を問わず、ウィトゲンシュタインの哲学を抜きに現代の科学哲学を語ることはできないのである。(野家啓一)(188~189頁)
■数学基礎論
――略―― とはいえ、この間違え方の中には彼の特異な数学観が現れており、そのために、20世紀初頭の「数学の危機」に対して、ウィトゲンシュタインは他の同時代人の誰もとることができなかったユニークな態度をとることができた。このことは強調しておきたい。
その数学観を大雑把にまとめると次のようになる。(1)数学とは規則に従った式の変形(つまり計算・証明)に尽きるのであり、それ以外はすべて数学にまつわる哲学的散文にすぎない。(2)数学的命題はその意味を計算・証明の過程からくみ取るのであり、数学的命題の意味は外部からあてがわれるのではない。(3)数学者の言説を自分が批判する場合、それは、式の変形の部分ではなく、哲学的散文の方を批判しているのだ。
――中略――
これに対し、ウィトゲンシュタインの態度はとてつもなくラディカルなものである。すなわち、数学には認識論的危機は生じていない。なぜなら、数学は式変形のゲームであり、何かを知るという営みではないから、というものだ。
「私がゲームすることができる限り、私はゲームできるのであり、すべては秩序
だっている。じっさい、事態は次のようである。計算としての計算は秩序だって
いる。矛盾について語ることはまったく意味をなさない。」(『ウィトゲンシュ
タインとウィーン学団』120頁)
「数学で矛盾が発見されたからといって、数学者たちが何百年も計算してきたも
のがすべて、突然廃棄されるだろうか。それは計算ではなかったと我々は言うだ
ろうか。断じてそうではない。」(『ウィトゲンシュタインとウィーン学団』
195~6頁)
矛盾が顕在化していないなら、支障なく数学ゲームを続行できるのだから、矛盾を気にすることはない。かりに矛盾が明らかになったとしても、規則を手直ししてゲームを続行すればよい。いずれにせよ、数学が矛盾を免れているということをあらかじめ示しておこうとする試みは迷信的恐れを動機とするにすぎない。私はこうした考え方は間違っていると思う。しかし、この間違いは彼以外の誰にもまねのできないまさしく天才的間違いだとも思うのである。(戸田山和久)(190~191)
■宗教哲学
デレク・ジャーマンも映画(『ウィトゲンシュタイン』)の中で語らせているように、ウィトゲンシュタインは「私はすべての問題を宗教的立場から見ないではいられない」と語った。また、「真に宗教的な人間にとって、悲劇的なものは何もない」という言葉も残している。論じたいことは多岐にわたるが、以下では、彼が(1)宗教を「語りえないもの」として定式化したこと、(2)宗教を「生活を統制するもの」として捉えたことに焦点をしぼって論じてみたい。
(1)ウィトゲンシュタインいわく、「私ははっきりとある宗教を思い浮かべることができる。だが、その宗教には教義がなく、それゆえ、そこでは何も語られない。明らかに、宗教の本質は語られるということとは全く関係ないのである」(『ウィトゲンシュタインとウィーン学団』)。――中略――
いずれにしろ、彼は理論的・体系的な宗教哲学なるものを構築する立場とは正反対の立場にたつ。そして、これこそが彼の「宗教哲学」である。だとすれば、彼が考えている宗教は人の行為や生き方と直結することもうなずける。
(2)同性愛者でもあったウィトゲンシュタインは、自分のおよんだ行為に対して嫌悪感を抱くのが常であり、後悔の念からか、「自分の生き方を変えたい」という旨の言葉を折にふれて残している。ひょっとしたら、同性愛者であったことは、彼が宗教を「生活を統制するもの」として強く捉えたことの要因の一つかもしれない。さらにドゥルーリーも述べているように、「自分の生活の仕方のすべてを変えようという、常にもち続けたウィトゲンシュタインの意志に対して同情や共感を感じないとすれば、彼を理解することはできない」だろう。
これは、ウィトゲンシュタインのいわば「宗教的」生を理解するうえで、重要な言葉である。彼は「懺悔は新生活の一部であるに違いない」(『断片』)と書きつけている。懺悔によってそれまでの自分と決別でき、新しい自分の生が始まる、というわけだ。また彼は、キリスト教は「〔言葉で語られる〕良い教えはすべてなんの役にもたたない、君達は暮らしぶり(あるいは暮らしの方向)を変えなければならない」(同)ことをとりわけ物語っている。とも認めている。思えば、「人生は尾根を走る一本の道に似ている」(同)。右にも左にもツルツルした斜面があるから、どの方向をとっても滑り落ちてしまう。不安定なじんせいの行路を歩んでいるとき、その歩むべき方向をはっきりと示してくれるものが、ウィトゲンシュタインの考える宗教である。こうしたことを理解すれば、冒頭に紹介した彼の二番目の言葉も納得できるだろう。(星川啓慈)(202~203頁)
2009年1月7日