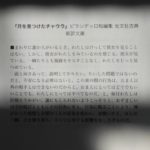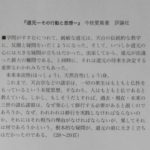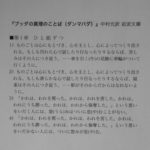『南北朝』日本歴史シリーズ7 世界文化社
■世阿弥は「諸道諸事において、幽玄なるをもて上果とせり。殊更、当芸において、幽玄の風体第一とせり。……何の物まねにしなを変へてなりとも、幽玄をば離るべからず」と、幽玄を能楽の最高の理念としている。しかしそれにしても、彼のいう幽玄とは、どのような美なのであろうか。
世阿弥の属した大和猿楽は、元来「遊楽の道は一切物まねなり」というように、物まね換言すれば写実的表現を特色としたものであった。しかし彼は余りにも写実的な表現は「俗にいやしく」なり、能楽の保護者である将軍義満ら「上つ方」「貴人高位」の好みに合わぬことを察知し、近江猿楽や田楽の特色である歌舞重視の芸風をとりいれ、芸風の革新をはかった。すなわち、せりふを歌謡化し、所作を舞踏化して表現をロマン的で非限定的なものとし、それだけ写実的表現を抑制し、幽思微情のただよう表現を主とするように改めた。そして彼は、このように歌舞を物まねに優越させることで成立する、余剰的表現様式を幽玄と称したのである。しかし彼においては、幽玄は表現の様式概念であると同時に、美の質にかかわる概念でもあった。
表現様式としての幽玄は余剰的表現のことであるが、その余剰の質は閑寂なもの、悲壮なもの、優艶なものなど、いろいろなものでありうる。ところで世阿弥の重んじた余剰の質はどのようなものであったろうか。それについて詳述している余裕はないが、彼が「何と見るも花やかなる為手(して)、是れ幽玄なり」「人の品々をみるに、公家の御たたずまひの位高く、人望余に変れる御有様、是幽玄なる位と申すべきやらん。然らば、ただ美しく柔和なる体、幽玄の本体なり」と説き、また「人においては女御(じょうご)、更衣(こうい)又は遊女、好色、美男、草木には花のたぐひ、かやうの数々は、その形、幽玄のものなり」「幽玄みやびたるふし、かかりは女体の用風より出づ」といっていることに、注意を喚起しておきたい。
それは今日人びとが一般に、この語において連想するような寂静、枯淡、冷厳の美ではなく、花やか・美し・柔和・みやび・やさしさなどの語で説明される貴族的・女性的な美、王朝貴族のあこがれた優艶の美に近いものであった。
世阿弥が能楽の理念とした幽玄は、このようにして、歌舞を物まねに優越させて余剰あふれる表現様式をとり、しかも情緒的・ロマン的・唯美的な王朝文学と緊密に結合した貴族的・女性的な優雅艶麗の美を、その余剰としてただよわせることであった。世阿弥の能楽が、将軍義満を中心とする公武の社会に大きな人気をえたのは、それがこのような意味での幽玄を理念とした歌舞劇であり、それが王朝文化憧憬の時代の好みによく投じたからにほかならない。能楽の興隆は、その意味で、北山文化の基本的性格を示すよい例証である。
しかし世阿弥は、以上のような幽玄の美を能の基本的な美とはしたが、これを究極至高の美としたのではなかった。彼が花の否定である「しほれ」の美を高く評価し、ことに『花鏡(かきょう)』の「批判之事」の一段で、はなやかな美しさを否定的に超越した「無文(むもん)の能」を至高のものとしていることを忘れてはならない。
けだし彼はここにおいて能を、「見(けん)より出でくる能、聞(もん)より出でくる能、心(しん)より出でくる能」の3段階にわけて、それぞれ説明している。ちなみに、見より出でくる能とは視覚に訴えて面白い「はではでしい能」で、「目ききは申すに及ばず、さほどに能を知らぬ人までも、みな同心に面白やと思ふ」大衆うけのする能のことであり、聞より出でくる能とは「さしより、しみじみとして、やがて音曲調子に合せて、しとやかに面白」いが、凡庸な「田舎目ききなどは、さほどとも思はぬ」向上した能のことである。
最後の心より出でくる能とは「無上の上手」名人が、すべての曲を習得した後に演ずる淡々とした能、「歌舞の二曲も物まねも儀理(戯曲の筋の面白さ)もさしてなき能」ではあるが、その『さびさびとしたる中に、何とやらん感心のある所ある」能のことで、これを「冷えたる曲」「無心の能とも、又無文の能」ともいうのである。これは「よき程の目ききも見知らぬなり、まして田舎目ききなどは思ひも寄るまじき」能で、これこそ究極至高の能だと、世阿弥はいうのである。
このようにして、はではでしく表現の多彩な能を基本としながらも、しみじみとしとやかに面白い能にいたり、さらに表現を極度におさえた象徴的な表現様式と、簡素枯淡・寡黙寂静の美、無一物の美を実現しようというのが、世阿弥の理想であった。
そして世阿弥の能のこの3段階論の構造が、公家的・浄土教的なものを基層とし、観音殿を中層とし、禅宗的なものを最上層とした金閣の構造と、きわめて類似しているのは単なる偶然であろうか。いや偶然ではなく、同じ北山時代の好みの異なる分野における表現だから類似しているのだ、と解釈すべきであろう。(『北山文化』世阿弥の幽玄 芳賀幸四郎)(146~148頁)
■四書中心と形而上学的学風とを特色とした宋学は、鎌倉中期に禅僧によって伝えられ、禅宗の布教と世俗教化の一方便として、もっぱら禅僧によって講究され、南北朝末期に義堂周信(ぎどうしゅうしん)らが出てからしだいに普及した。ついで、この時代には三教一致の思想――儒・仏・道の三教はその根本の理は一であるという思想にささえられて、岐陽方秀(ぎようほうしゅう)・大椿周亨(だいちんしゅうこう)らのように禅僧でありながら宋学の研究に専念するものが輩出し、宋学が大いに興隆した。そしてついに、漢唐訓詁(くんこ)の学の系統をひく清原家などの儒学にも、深く浸透するようになった。近世における朱子学興隆の基盤はこの時代に確立したのである。
禅宗が学問・文学の教養ゆたかな士大夫(したいふ)以上の知識階層を主たる支持者として発展した関係上、中国においてすで偈頌(げじゅ)とよばれる宗教的な詩や法語を述作する風が盛んであったが、この風潮も鎌倉末期以来、帰化僧や留学僧らによって輸入され、南北朝時代になって一段と盛んになり、その末期から北山時代にかけて、世にいう五山文学の黄金時代を現出した。(『北山文化』宋学と五山文学の興隆 芳賀幸四郎)(150頁)
■北宋から南宋をへて元にいたる時代には、北宋(ほくしゅう)画と南宋画・院体派と在野派それに非職業画人の一派などがきそいおこり、山水画・花鳥画・道釈画などが、それぞれ多彩な発展をとげ、ことに墨線と墨色とをもって対象の本質をきわめて主観的に表現する水墨画が発達した。
この水墨画は、禅の精神と深く相通ずるものがあったため、鎌倉の円覚寺蔵の『仏日庵公物目録』でその一端が察せられるように、鎌倉末期からすでに、禅僧らによって多数わが国に請来され、鑑賞されていた。ついで南北朝時代にはいるにおよんで、これら舶載の水墨画を鑑賞する趣味は、禅僧社会から上層武家社会にまで拡大するにいたった。そしてそれにともない、我が国人の間に、これらを模倣して描くものがあらわれるようになった。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(150頁)
■しかし、ここで注目すべきことは『御物御画目録』のうちで幅数の最も多いのが、103幅の牧溪の作品で、27幅の梁楷(りょうかい)をはるかに引きはなしていることである。牧溪の絵画は、元代の絵画批評家として名高い夏文彦(かぶんげん)の『図絵宝鑑』巻4に「粗悪にして古法無く、誠に雅玩に非ず」とあるように、中国では低く評価されていたのであった。
ところで、この『図絵宝鑑』は北山時代にすでにわが国に輸入されており、したがって、この牧溪評はわが国の知識人の間に知られていたはずである。しかもそれにもかかわらず、義満らが牧溪の画をきわめて高く評価していたことは、まことに興味深く、かつ示唆ゆたかな現象といわねばならない。
なぜなら、それは一つには義満らの鑑賞眼が必ずしも中国の評価にとらわれず自由独創的なものであったことを示し、二つには彼らが一方では伝統的な公家文化や優艶華麗を意味する幽玄美に心ひかれながらも、他方では禅宗的な簡素枯淡の美・清貧無一物の美に魅力を感じていたことを、よく語るものだからである。
ともあれ、この北山時代には一方では「融通念仏縁起絵巻」の筆者の一人として知られる土佐行広らによって、大和絵が復活した半面、このように宋元風水墨画が禅僧画家らの活躍で発達し、禅僧画家牧溪の作品が極度に尊重されたのであった。このことは、金閣の構造や世阿弥の美の理念の構造と一脈相通ずるもので、北山文化の性格を知る上のよい手がかりである。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(152~154頁)
■公家社会に荷担された伝統的な古典文化と、禅僧社会に荷担された新しい舶載文化とが、それぞれに独自に栄えながらも、将軍義満・義持を棟梁とする武家社会を媒介として接触し、しだいに融合の度を進めたこと、これが北山文化の基本的性格であり、またそこに日本文化史上における北山文化の歴史的意義があるのである。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(154頁)
(2012年2月15日)