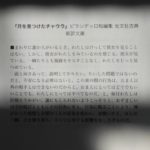| 『セザンヌとの対話』ジョアキム・ギャスケ著 成田重郎訳 東出版
■セザンヌ――(中略)わしの画布から地球の方に。重く重く。どこの空気があるか。稠密な軽快さがあるか。天下とは同一の上昇に於いて、同一の慾望に於いて、友情を、これらの外光の下にある事物すべてから、解放することであるかもしれない。世界の1分が過ぎてゆく。その現実に於いて、それを画くこと! そして、そのためにすべてを忘れること。1分、そのものに成ること。そこにやって来るのが尖鋭な種板だ。われわれの前に現れたすべてのものを忘れて、われわれの見る所のものの像を与えること。 (中略) ギャスケ――あなたは、すべてを忘れなければならないと、おっしゃる。それならば、何故、風景の前で、ああいう準備をし、あんなに瞑想するのですか。 セザンヌ――残念ながら、わしはもう無邪気でないからだ。われわれは文明人だ。われわれが嫌でも応でも、古典的な心づかいが、われわれのなかにある。わしは、絵画に於いては、明瞭に表現したいと思う。えせの無知者には、流派よりも、ずーっと憎悪すべき一種の非文明がある。つまり、今日では最早無知であり得ないということだ。人は、最早、無知ではない。われわれは生まれながら、容易なものをもたらしている。その容易なものを打ち壊さなければならない。容易さは芸術の死である。あの洞窟の天井の下に、自分達の狩猟の夢を彫り込んだ、初期の人間達のことに思い至るならば! 或いは又、善良なキリスト教徒達が、墓地の壁に壁画の天国を描いたことを、思って見るならば! それが、すべてが、彼等の実技と成り、魂と成り、印象となったのだ。 かようにして、風景の前にいることだ。風景から宗教を解放することだ。或る日々には、わしが正直に描いているようにおもわれる。わしは、わしの発見した道のプリミテフのままでいるのだ。わしは、ね。君、聴きたまえ、ちょっとでいい。わしの拙劣の信仰を以って、公式に到達したいのだが……完全に実現したいのだが……(14~15頁) ■セザンヌ――そう。抽象的実技は、涸渇しながら扮飾する自分の美辞の下に、乾き切ることでおしまいに成る。ボローニヤ人達を御覧。彼等はもう何も感ぜぬ……人が或る感覚を必要とする時には、自己圏内の観念を、思想を、言葉を、持ってはならぬ。偉大なる言葉というものは、あなたがたの思想に非ざる思想だ。写真版は芸術の癩病である。ほら、ね、神話。あれは、絵画の方では、跡をつけることが出来る。それは侵略的実技の歴史だ。終わりに女神達を描いた時には、もう人は女達を描かなかった。展覧会を廻って見たまえ。幸運な男は、葉の下の水の反映を表出するを知らない。彼は、それに水の精をくっつける。アングルの《泉》! この画は水とどんな関係があるのか……君は、文学の方では、無駄話をする。こう呼ぶ……ヴェニユース、ヅゥス、アポルロンと。君が、もう、深い情緒を以て、言い得ない時には、海の泡沫、空の雲、太陽の力と。君は、こんな希臘神の病人達を信じているのか。そこでだ、 真より美なるもの 何もなし 真のみが 愛すべきもの(16~17頁) ■セザンヌ――そんなことはない。銀色では、恐らく、あろう。青い、青味がかかっている。……決して灰色じゃない。灰色であるにしても、生まで、黄色で、騒々しくって、金平糖製よろしくだが、それ以上のことはない。それはちょうど、何も見ない観客者達が、プロヴァンスを叱責するようなものだ……さよう。土は、ここでは、いつも振動している。起伏があり光を反射し、眼瞼をしばたたかせる。だが、土はいつも差異を見せ、柔らか味があるように感ずるがいい。一つの拍子が土をうねうねさせている。 ただ遊戯と舞踏だけを愛せよ、 ただただ、拍子だけを求めよ、(20~21頁) ■セザンヌ――(中略)わしは文学的絵画を好まない。一人物を使って、彼の考え、彼の為すことを書くのは、つまり、その思想なり、或いは、その挙動なりが、デッサンや色彩に依って、表出されていないことを告白することだ。そして、ギュスタヴ・ドレのように、自然の表情を強制しようと望むこと、樹木を曲がりくねらし、岩を渋面作らせること、或いは又、ダ・ヴィンチのように洗練することさえも、それは、まだ、文学に属するのだ。全く彩られた論理がある。画家はそれに対してのほか、服従してはならぬ。頭脳の論理に対しては、決して従ってはならぬ。画家がそれに没頭すれば、おしまいだ。常に眼の論理に従え。もし画家が正しく感ずれば、彼は正しく考えるであろう。絵画は、第一に、一つの光学である。われわれの芸術の素材がそこにある。われわれの眼の考えるもののなかにある……自然の意味する所を述べるために、自然が尊重される時に、自然は常に解決させられる。(中略)(23頁) ■セザンヌ――(中略)それで、わしは、まだ知らない。百姓のことじゃ、そう、そう、わしは、時々、疑問に思ったのだが、あの人達は風景が何か、樹木が何か知っているか、というのだ。そうだ。こんなことは、君には変に思われるであろう。わしは時たま散歩をした。馬鈴薯を売りに、市場へ行く一人の小作人の荷車の後から、附いて行った。彼は、われわれが頭脳をもって、総体として、見たと呼ぶ所のものを決して見なかった。彼は決してサント・ヴィクトワールを見なかった。百姓達は道に沿うて、あちら、こちらに種が播かれたこととか、明日の天気がどうとか、また、サント・ヴィクトワールが帽子を冠るか、冠らないかを、知っている。あの人達は、それを獣のように嗅ぎわける。ちょうど、犬がただその必要に応じて、そのパンの片が何か、知っているようなものである。しかし、樹という樹は緑であり、そして、その緑が1本の樹木であり、この地が紅く、あの崩れた紅が丘陵であるということを、大部分は、自分の功利的無意識のほかで、それを感じ、それを知っているとは、わしには、ほんとに信ぜられない。わたくし自身の何ものも失わないで、わしはその本能に追い駆けなければいけないし、それから、そちこちの野原の色彩は、わしには1つの思想を意味するものでなければならぬ。ちょうど、それは百姓達にとって、1つの収穫を意味するようなものである。百姓達は黄色を前に見ると、始めなければならない収穫の所作を自然に感ずる。それは、ちょうど、わしが、その同じニュアンスを前にして、わしの画布の上に、これと対応して、方形の麦畑を波打たせる色調を、本能的に取り入れなければならない筈であったようなものである。このように一筆一筆を下ろせば、地は再び活きて来ることであろう。わしの畑を耕すおかげで、そこに立派な風景が立ち現れて来ることでもあろう……クゥルベとその薪束の話を覚えておいでか。クゥルベは、薪束だったことを知らずに、自分の色調を出した。それが何を描写しているか、と彼がたずねた。人が見に行った。すると薪束だった。宇宙だった。宏漠たる宇宙だった。本質的画家にとっては、色彩だけのなかに物体を見、それを把握し、それを自己の内部で、他の物体と結ぶあの画家の眼が無ければならぬ。自然に対しては、余りに細心に過ぎたといういうことも、余りに真面目に過ぎたということも、余りに屈従したということも、決してないのである。だが、多少、人は自己のモデェルを自由にするものである。そして、特に自己の表現方法を支配するに至る。表現方法をモチフに従わせなければならぬ。モチフをおのれに屈せしめぬがいい。それに対しては、おのれを曲げるがよい。それを内部に生まれさせ、芽生えさせるがよい。自己の前にあるものを画くこと。そして出来るだけは、最も論理的に表現しようと忍ぶこと。わしは、このほかのことは、決してやらなかった。君は、その時、君を待っている発見を想いやらないのだ。が、実現すべき進歩のためには、自然しか存在しない。そして、眼は、自然に接触して教育される。眼は眺め、且、仕事をするおかげで、同心的となる。(24~25頁) ■セザンヌ――(中略)いつかの晩、われわれはエーキスに帰りながら、カントのことを話した。わしは君の見地に立ちたいと思った。感じのある樹木達? 1本の樹と、われわれの間に、共通な何物があるのか。わしに見える通りの1本の松と、実際あるままの1本の松との間はどうか。あーん、わしが、もし、そいつを画に収めたら……そうするとだ、われわれの目の前に落ちて来て、われわれの画と成るのは、あの自然の部分の実現ではなかろうか……感じのある樹木達よ……そして、この彩画のなかには、範疇表の全部よりも、君の実在と君の現象の全部よりも、あらゆる人々の一層近づき得る外観の哲学がないのではなかろうか。それを見ると、自己との、人間との、あらゆる事物の相対性を、感ずるかもしれないのだ。わしは、独り思うたのだが、空間と時間とを描きたいのだ。どうしてかと云うと、空間と時間とが、色彩感覚の造形と成ってほしいからだ。というのは、わしは、時々、色彩を以って、実体的大実在(グラン・ザンテイテ・ヌウメナル)だ、生きた思想だ、純粋理性の存在だ、と想像するからだ。われわれは、それらとは一致し得るのでもあろう。自然は表面だけのものではない。深さを持つ。色彩は、この表面に於ける、表現である。色彩は、宇宙の根源から立ち昇る。色彩は、宇宙の生命である。宇宙の思想の生命である。その生命に対して、デッサンは全然の抽象である。それ故、決してデッサンと色彩とを分離してはならぬ。それは、ちょうど、君が言葉を使わずに、純粋の数字を以って、純粋の象徴を以って、考えようと望むようなものだ。デッサンは代数である。文字である。デッサンに生命が至れば、デッサンが感覚を意味すれば、忽ちデッサンは彩られる。色彩の充実は、いつもデッサンの充実と一致する。実際、自然のなかで、何かデッサンされたものをわしに、見せてくれたまえ。どこ? どこ? 素直にデッサンをして、建てるもの、壁とか家とか。それを見たまえ。時間や自然が、それらを、斜にたたせているのだ。自然は直線を怖れている。技師達には、馬鹿げた話だ! われわれは、道路係じゃない。技師達と来たら、色彩にはひどく悩まされている次第さ。あの連中はね……ところで、わしはだ……そう、感覚が、すべての基本だ。(30~31頁) ■セザンヌ――わしは、更に、次のように書きとめてある。(読む) 【光を与える色彩感覚は、抽象の原因であって、これらの抽象は接触点が些(さ、少ない)やかで、繊細である場合は、わしの画布に彩色することを許さぬし、また、物体の区画限定を追求することも許さない。そのために、わしの画像なり、彩画なりは、不完全であるということに成るのだ。他面に於ては、写影の遠近が相互に落ちて合う。そのために、新印象派画家の嵌込み細工が生じたのである。それは黒線で輪郭を取る。全力を尽くして打破すべき欠陥だ。然るに自然に相談すれば、この目的を達するほうほうが、われわれに与えられるのである。】 ギャスケ――で、それは? セザンヌ――写影! 色彩の写影。彩られた場所――写影の魂がここで合体する――囚われた日光7色熱、太陽に於ける写影の遭遇……わしは、わしの写影を、パレットの上のわしの色調でもって作り上げる。お解りか……写影を見なければならない……はっきりと……だが、写影を配置し、それを融合せしめることだ。それがね、廻転しなくっちゃいけない。そして、それと同時に、中にはいらなくっちゃいけない。容積(ヴォリューム)だけが大事なのだ。よく描くには物体間に少しばかりの空気がいる。ちょうど、よく考えるには、思想間に、感覚を中に入れるようなものである。瀝青(ビチューム)は平板である。論理は狭小である。写影がもうなくなっている穴倉のなかで、画をかく。直観が、もうなくなっている3段論法のなかで、緊めつけられる。ボール紙よ。膨れなくっちゃいけない。いいかい、君。諸々の色調の正しい挿入に於ける諸々の対照を、近親関係に置かなければいけない。眼の極く僅かばかりの過失でも、すべてを打倒する。それで、このわしと来たら、恐ろしいのだ。わしの眼は、幹に、土くれに、ひっついて了う。わしは、そいつを引き離そうと、悩んでいる。それだけ、何かが、わしを引き留めるわけである。 ギャスケ――そうですよ。わたくしは、そのことに気がついていました。あなたは、次の筆を下ろすのに、時々、20分というもの、じっとしていましたね? セザンヌ――そして、眼だ。ねえ。わしの家内が、そう云っていたが、わしの眼が、頭から飛び出し、充血しているのだ……一種の陶酔、恍惚といったようなものが、霧のなかにでもいるように、わしをふらふらさせるのだ。わしが、画布から立上がる時に……ねえ、わしは、ちょっと狂人じゃないか……絵画の固定観念……フランノフェル……バルタザル・イラエス……幾度も、わしはね、そのことを、われとわが身に、たずねているのだ。(32~33頁) ■セザンヌ――(中略)誠実な人間は、血のなかに自分の法典を持つ。天才は生きながら、自分自身の法典を作る。そう、それに違いはない。天才は、他人の何ものも、無視はしないが、自分自身の方法を作り出すのだ。 ギャスケ――一つの方法? セザンヌ――(中略)わしの方法は、空想の憎悪がそれだ。君。わしは決して、他の方法を持ち合わせなかった。わしはキャベツのように馬鹿でありたいのだ。わしの方法、わしの法典というのは現実主義だ。しかし、よく聴いてくれたまえ。偉大に満ち満ちた現実主義だ。真実なるものの勇壮である。クゥルベ。フロオベール、それ以上である。わしは浪漫派に属しない。物質の小さな拇指に於ける宇宙の無辺、奔流。これが不可能だと君は思うか。血で彩られた無窮よ。ルーベンスよ。(35~36頁) ■セザンヌ――アングルにも、やはり、血がない。アングルはデッサンする。復興期前派は、デッサンした。彼等は彩色した。自然の大きさで弥撒の祈祷文集の彩色をした。絵画、絵画と称されているもの、は、ヴェネツィア派と共に生まれている。テェヌの物語る所によると、フィレンツェでは、あらゆる画家達は、先ず、金銀細工師であった。彼等はデッサンをした。アングルのように……ああ、全くアングル、ラファエロ、そして、商品全体は、頗るきれいだ。わしは他の一人以上に鈍物ではない。わしは思いのままに線を楽しんでいる。だが、そこに暗誦がある。ホルバイン、クルゥエ、又は、アングルは線しか持たない。それだけじゃ充分ではないのだ。それは頗るきれいだ。が、それだけじゃ充分ではない。あの『泉』を見たまえ……純粋だ。優美だ。爽快だけれども、プラトニックだ。これは一つの画像(イマージュ)だ。空中では廻転しない。ボール紙の岩は、その湿気を少しも、あの濡れ肉の大理石とは、交換しない……周囲の滲透はどこにあるのか。(中略)。(48頁) ■セザンヌ――ドガは、画家には不足である。画家に成り切っていないのだ……ちょっと、タンペラマンがあれば、頗るつきの画家には成れる。一つの芸術感(サンス・ダール)があれば、沢山だ。そして、それは疑いもなく、ブゥルジョワの恐怖である。その感じというのは。それだから、学士院、年金、名誉なんてものは、阿呆達や、無考えの連中や、滑稽な奴等のためにしか、与えられ得ないのだ。そかし、わしの話しているのは、そういう連中のことじゃない。そいつ等は、学校へゆけ。教授連に即け。わしの知ったことじゃない。わしの心から悲しむのは、こういうことだ。君が信じて居られ、そして、わしに話してくれるあの若い人達が、いずれも、イタリアを走せ廻らず、また、ここルゥブル博物館で日を暮らさないということだ。後で、自然の懐に飛び込むだけで済ます。すべてのことは、とりわけ、芸術に於いては、自然と接触して発展させた、そして、適用した理論である。このわしの上に振りかかったようなことが、その若い人達の上に起こらないでほしいものだ。と、わしは願う。(54頁) ■セザンヌ――(中略)わしは来る途中、君に話したようなわけで、あの中世期の芸術のすべては、非常に感動せしめるものだが、それを、わしの芸術に、ルネッサンスの芸術に、対立させたのである。おわかりだろう。ああいった、中世期の礼拝式的象徴主義というようなものは、全く抽象的である。そのことを考えなければいけない。ルネッサンスの異端的な芸術は全く自然的である。一は自然を曲解して、われわれには、何か解らないが、神学的真理を表示する。他は、君がよく感じている通り、抽象を現実に連れ戻すが、現実は常に自然的であり、敢えて言うならば、肉感的な普遍的な意味を持つ。……わしの賛美するのは、林檎が復興期前派の聖母の手のなかでは、象徴的だが、ルネッサンスの聖母の手のなかでは、子供の玩具になることである。(中略)われわれ画家としては、救世主を讃える天使の渦巻きよりは、寧ろ、この葡萄樹の開花を描かねばならぬ。われわれの見ることだけ、或いは、われわれの見ることの出来ることだけを、描くことにしよう……あのジョルジォーネのように。ほれ、その……(57頁) ■セザンヌ――われわれのあらゆる空想を、大きな肉の夢を以って美しくしよう。気高いものにしよう。自然を空想から、描き出さないことにしよう。われわれに、それが出来なければ、それだけ、いけない。君、おわかりだろうが、マネは《草の上の昼飯》のなかで、何か知らないが、ここで、すべての官能を極楽入りさせるような、あの気高さの何か知らないが、顫えを加えなければ、ならなかったのだろう。(58頁) ■セザンヌ――わしは、理論的に、正しいことを望まない。だが、しかし、自然に即して、正しくありたいのだ。アングルは、その様相(ステール)にも拘らず、エーキスの噂や、彼の賛美者の話のように、頗る小さな画家に過ぎない。最も偉大なる人々と云えば、それを君はご存知だ。ヴェネツィア人達とスペイン人達だ。(63頁) ■セザンヌ――ああ、誰でも、自分の鍋のなかに、何が煮えているか位知っています。わしはあなたを知っていますよ、あなたを描いているのだから……ね、ギャスケさん。あなたには、確信というものがある。それが、わしの希望の最たるものだ。確信! わしが、一つの画に取り掛る度毎に、今度は、うまく行くのだぞ……と、自信するし、またそう思う。だが、すぐ思い出すことは、これまで毎度、いつでも、しくじったことだった。そこで、わしは、血をしぼる……あなたは知っているだろう、人生で良いもの、悪いものを。そして、あなたは、あなたの道を辿る……わしは、わしがこの手におえない画技を手に、どこへゆくのか、どこへ行ったらよいものか、決して知らないのだ。あらゆる理論は、内部的にする……これは、わしが、人生に於て、臆病であるためであろうか。実際、人に性格があれば才能がある。わしは性格があれば沢山だ、とは言わない。良く描くには、善良な人であることだけで足りる、とは言わない。そんなことなら、わけもないことであろうが……だが、道楽者が天禀を持つものと、わしは思わない。 ギャスケ――ワグネル。 セザンヌ――わしは、音楽家じゃない……それから、ね、いいか。道楽者というのは悪魔のタンペラマンを持つものでではない。常に、或るもの……一人の友達……であるためには、このタンペラマンを以って、けりがつくわけではないね。ギャスケさん。なにね、手をよごさないでおくことだ。芸術家なんてものは、多少誰でもそうだ。けれども、才能のないのは、正に、その連中なのだ。自己の芸術に就いては、変性しないものでなければならぬ。そして、自己の芸術のなかで、変化しないものであるためには、その生命に於て、そうであるべく、鍛錬されなければならぬ……うむギャスケさん、老ポワローはどう? 要するに。為すことを知るということと、知らせることとがある。為すことを知っている時には、知らせる必要はないのだ。このことは、いつでも知れ切ったことだ。(82~83頁) ■セザンヌ――わしの云いたいのは、芸術家は、個々人の極端に限られた数をしか目ざしていない、ということである。そして、実際は、芸術家がその生きている時に、余り多くの人を知るのだから、たまらない。芸術家は、そのモチフと共に、その省察と共に、そのモデルと共に、おのが場所を生きなければならぬ。特徴を与えること……そして、とりわけ、性格の聡明な観察に基かない見解を軽蔑しなければならぬ。芸術家は文学者精神を恐れなければならぬ……ギャスケさん、あなたん所の息っちゃんが、よくわしを解ってくれますよ……この精神が、よく、画家を、その真の道から離れしめ、自然の具体的研究から遠ざからしめ、そのために手に触れ難い思索のなかに、長過ぎる位、落ち込んで了うことに成ったのだ。われわれは、百遍も、このことを言った……ああ、批評家達、あのユイスマンの連中……わしは、いつも、あの人達に、わしをぐるぐる振り廻す連中に、手紙を書きたいと思っていた……画技の基本を成すものに、3つの事がある。それは、あなたがたには、決してお解りに成るまい。わしは、そのために35年来、献身して来た。3ケ条というのは、慎重、誠実、服従。思想に対して慎重。自己に対して誠実。対象に対して服従……対象への絶対の服従。(88頁) ■セザンヌ――そーら、そーら、君は夢中に成っている……わしは、のぼせないよ。はぁ……その籠(籠を描いた絵)は、わしが後々の記念に、わしの御者にやったのだ。おわかりだろうと思うが、あの男は、わしの母をひどく大事にしてくれる……そこで、あの人は満足していた。わしに大変ありがたいと云った……けれども、あれは、わしの所に、その画を置いて行った……あれは、その画を持ち帰るのを忘れたのだ……何と君に言ったらよいのだろうか……その程度には描くことだ、それが、わしの運命なのだから。 ギャスケ――画伯…… (中略) セザンヌ――わしは、画をかきながら、死ぬ、と心で誓ったのだ。《画をかきながら、死のうと、わたくしは自ら誓った》それは官能のためには、馬鹿に成って了う情熱の赴くにまかせる老人達を、脅かす耄碌のなかに、沈んで了うよりは、ましだ……神はわしのために、その事を斟酌するであろう。(97頁) ■セザンヌ――そうだ。君には、君の比喩がある。君の比較がある。われわれのデッサンが、余り眼につく時のわれわれのように、《ように》を連発するように思われるに拘らず。人の袖を引っぱり過ぎてはいけない。だが、画家のわれわれとしては、色調だけだ。眼に見えることだけだ……彼、バルザックは、御馳走の出た食卓の話をする。自分の静物をつくる。だが、ヴェロネェズ式にだ……1枚のナプキン…… セザンヌ読む。 《……降ったばかりの雪が積もったように白く、そして、その上には、小さな白パンを盛り上げた食器が、対称的な山をなしていた》 セザンヌ――わしの若い時には、絶えず、これを描きたいと思った。清々しい雪白のナプキンを。今じゃ、わしは知っている、《食器が対称的に山をなしていた》ことと、《小さな白パン》としか、描いてはならないことを。わしが、もし《盛り上げた》のを描いたら、おしまいだ。君、お解りになるか。で、わしが、ほんとに、わしの食器とわしのパンとを、自然に即したように釣合をとり、暈せば、花環も、雪も、あらゆる振動も、そこにあるべきことを確信されていい。(100頁) ■(美術館の)戸の上に、わしは、彫らせよう、《画家達入るべからず、外に太陽あり。》(103頁) ■セザンヌ――昔の人達は、どうしてか、わしは知らないが、数キロの仕事をやってのけるために、行動した。わしは、50センチのカンヴァスを塗り上げるために、自分を焼き尽くし、自分の命をつめている。構うものか。これが人生だ。わしは、画をかきながら、死のう。 セザンヌ――わしは、画をかきながら、死のう……画をかきながら、死ぬ……(104~105頁) ■ピサロはわたしを好く思っていますが、このわたしはわたしで、頗るわたし自身を良く思っています。周囲の全ての人達よりも、わたしはずっとえらいのだと思い始めています。わたしが自分の都合のよいように考えていることは、良く知っての事です。わたしはふんだんに勉強しなければなりません。これは愚鈍な奴にほめちぎられるような結末に達するためではありません。通俗的に世間で評判取るようなことは職人の工技の所業にほかなりません。そんなものは、作品を非芸術的なものとし、取柄のないものとするばかりです。一層真実となし、更に高尚にしようという悦びのため以外は、わたしは何も附け加えようなどとは、してはならないのです。 威をもって臨む時が、常にあるものですし、また、空虚な外観にいい気になって眼を細める人達よりも、遥かに熱心で一層徹底した賛美者がいるものだ、ということを信じて下さい。(1874年9月26日母への手紙)(118頁) ■わたしは、少し遅れて自然を見始めた。と言っても、それがために、興味津々たるものあることを止めはしない。(1878年12月19日、ゾラへ)(120頁) ■わたしは、理論的にわたしの試みの結果を弁護できる、と感ずるようになる日までは、黙々として仕事だけすることに決心した。 〔1889年11月25日に、セザンヌはかねてベルギィの20人界のマウス書記長から ブリュッセル展覧会に出品方を勧誘されていたので、承諾の旨答えた。1877年 以来、セザンヌは印象派展にも出品せず、ひたすら沈黙を守りながら制作にい そしんでいたのである。彼はもう50代に達していた。〕(121頁) ■光を与える彩色感覚は、抽象の原因であって、この抽象が、わたしの画を塗抹することも許さず、また、物象の限界を追窮することも許さない。これは接触点が微弱で、繊細の場合のことである。そのために、わたしの画像なり画作なりが不完全であることが目立つのである。(1905年10月23日、ベルナアルへの手紙)(123頁) 2009年2月3日 |
『セザンヌとの対話』ジョアキム・ギャスケ著 成田重郎訳 東出版
投稿日:2020-06-13 更新日:
執筆者:okanokouseki