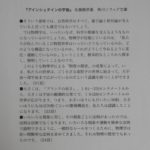| 『セザンヌ』ガスケ著 與謝野文子訳 岩波文庫
■しかし彼らにとっての最高の喜び、最終の抒情。ほとんど宗教的な饗宴といえば、それはアルク川で泳いで、ぬれたまま本を読み、柳の陰でさるまた1枚で議論することだった。川は彼らのものだった。春が終わりに近づくと、自由な日は明け方から夕暮れまで、さっそく川を占領して、自分たちの領地にしてしまい、そこでぽちゃぽちゃ泳いだり、水を浴びたり、草をさぐったり、水中の魚の生活や、反射と陰影のきらきらした動きを目で追ったり、昆虫や水滴のはかない世界の中に、消えゆく微小なるものの中の、無限大なるものの宇宙的な悲劇を発見するのだった。彼らは、ひとつの形容詞、太陽や考えのかすかなニュアンス、ちょっとした逆説的な断言がもとで、互いに髪をつかみ合い、砂の上にころげて、息長く笑いながら抱き合って立ち上がることがしばしばあった。ジプシーみたいに、じいじい焼ける葡萄の若枝の上で骨付き肉を焼き、びんは泉の水につけてひやした。彼らはキャンプ生活をした。彼らは生きた。熱を帯びた芸術家の頭脳が、これほど自然な開花を見たことはかってないだろう。彼らの想像力は、真理の真っ只中に漬かるのだった。一生を通じて、最悪の瞬間にもこの頃の異教的な勢いまたは聖なる不安を保ち続けたのである。後日セザンヌがある友人に語ったこの言葉がいかにもよくわかる。「自然にならって絵を描くことは、対象を模写することではない、いくつかの感覚を実現(レアリゼ)させることです」(35~36頁) ■セザンヌの全生涯は、大きな突進の後に来る深い失望、無我夢中に張り切った後に来るまっ暗な落胆が交互に続くというような人生の他になにものでもなかった。毎朝、起きると、世界の征服に出発した。自分の情熱と意志を、自分の芸術と等しいものに見立てるのだった。晩になって床につくときは、生きることに絶望し、絵を描いた自分を呪うのだった。一つだけ慰めがあり、それは自分の仕事だったが、その仕事が「振るわない」ときは、殉教者の苦しみを味わった。きりのない失意に落ち込んでいくのだった。ある晩、この状態の彼に出会った人に、何をそういうふうに考えているのかと聞かれて、彼は、ヴィニーの詩句の動詞を一つ入れかえて答えた。 主よ、私を孤独で強い者になさいました 大地の眠りのなかに眠らせて下さい(56頁) ■そのころゾラがバーイユに宛ててこう書いている。 「彼はひとかたまりでできた人間で、こわばっていて、手にとると硬い。何に遭っても曲げられるということもないし、彼に妥協させるなんてとても無理なことだ」(57~58頁) ■彼をさえぎるものはもはや何もない。彼の技術(メチエ)さえも思うがままに動くように見える。思索の狂躁ぶりは、ある日〔ルーヴルの〕さろん・かれの真ん中でユオに「ルーヴルに火をつけるべきだ」と、叫んだほどである。画帖の1ページに、『エミール』からの数行を書きなぐる。「肉体は魂に従うためには、たくましさをそなえていなければならない。良き従者は、頑健であらねばならない。肉体は弱ければ弱いほど命令を下す。強ければ強いほど従う。虚弱な肉体は魂を虚弱にする」その下に、太い筆跡で、念を押している。「私は頑健だ。私の魂は強い……」アトリエの壁の土に、木炭で、「幸福は仕事にあり」と書く。(72~73頁) ■それらの装飾的な下絵、情熱あふれる肉体、夢の中の重い葉むら、熱狂した閨房の中で「彼を誘惑する緋色の裸の乳房」などを前にすると、彼は懐疑にとりつかれた。ピサロに言われていたように、手で触れたり目で見たりできるもの以外に、何も発明したり描いたりしてはならない。ところが、ゆるやかに流れる川を前に、本物の枝の陰に画架を立てて、草や土隗に足をのせていると、大きな構成(コンポジシオン)がなつかしくなり、昔の巨匠たちの思い出やルーヴル美術館で見た凱旋の図やいろいろな場面が彼をおそうのだった。(78頁) ■その絵を汚しているほこりの層を私がふきとって見ると、鹿毛色で、ひびが入っていて、金槌で打たれた跡が見られたが、真新しかった。そこには、白鳥の形をした雲の上にしゃがんだ、激流のように流れ出す肉付きの女性が見られた。腹を前につき出し、乳房はふくらんでいて、ぎらぎら照り返るような鼻づらが、赤くも茶色くもある髪の毛のとび立つ下で、すばらしくもあり見るも恐ろしく、手には血のかたまり、腰には金の鎖、大きい首飾り、そして胴体はまるでダナエのように光線や金貨の雨にうたれていた。その女のまわりに、服を身につけた男や神父や将軍や老人、一人の子供、労働者や裁判官、いまわしくねじれた人の群れが、夜明けの光を浴びてわめいていた。ドーミエの描くような赤面だったが、血が頭に上がったみたいに紅色にむくんでいた。嵐のような肉体が、それに蛇のようにまといつくバロックな色彩のダンテばりの虹に咬みつかれていた。こわばった腕たちの渦巻き。――そして空の暗い一隅に一つの星の下に、目を手で被っている純白の姿が見えていた。 「――どうだね。これはミルボー好みだろうが」とセザンヌは、この黙示録の一節を鑑賞中の私をつかまえて言うなり、足で絵をけとばし屋根裏の奥へと追い払った。(80~81頁) ■「――これが私のタブローとなるよ、私が後世に残すものにね……だが中心は?中心がうまく見つからないんだ……何のまわりに女たちを全員集めればよいか?ああ、プッサンのアラベスク。あの人は隅々までそれに通じていたよ。ロンドンにあるバッコス祭や、ルーヴルにある《フローラ》の中では身体の線と風景の線がどこに始まってどこに終わるのか……一体をなしているんだ。中心がないのだ。私は、穴のようなものが、光の視線、目に見えない太陽みたいなものが私の描いた全部の身体を待ち伏せして、包んで、なでて、強烈なものにするのであってほしいんだ……真ん中でね」 そう言いながらクロッキーを1枚破いた。(89頁) ■彼は絵画の神秘主義者であったし、絵画の偉大な孤独者であった。この地上でのいろいろな利害、市民としての義務、生まれつき好きなものも絵画には負けた。その例をせめて二つだけでも紹介しよう。 ジャで、ある晩のこと、積みわらと農家が燃えていた。炎の色彩豊かな動きにうっとりして、彼はそれを眺めていた。ニュアンスをかきとめたり、色彩や影のちょっとした秘密を見つけたりしていた。すると消防士たちがやって来た。「待て!」と叫んだ。気が狂ったと思われた。相手は念を押した。彼は鉄砲をつかんだ。 「はじめに消そうとするやつは一発うってやる」それで灰になってしまうまで、火の魔術を楽しみ、火の舞う姿と反射を研究した。 それからずっと後のことだが、1897年に母親の葬儀が行われた日の午後、いつもどおりに「モチーフ」を求めて野外に出かけた。それこそが死んだ人と心を共にし祈る最善の方法だったのだ。(97~98頁) ■この人たちの誰よりも自分の芸術に取りつかれていて、自分の仕事の神秘主義者であり、絵画の修道僧であったセザンヌには、危険にさらされた祖国の叫びが一切耳に入らなかったし、何も見えはしなかった。自らの天才が彼の運命だったのだ。町が敵の手に渡り人々がわめく中で砂の上に身をかがめて問題を解き終えようとする姿で発見されたアルキメデスみたいに、セザンヌは砲弾の降る下でも画を描いていただろう。彼はパリを去った。私は彼の人生について知っている事柄を何ひとつ伏せたり飛ばしたりしたくない。警察はエックスの辺りで彼を探したと言われている。母親と一緒にレスタックに逃げていた。海を前に仕事をしているのだった。(99頁) ■ある晩、彼は私にデッサン用紙を1枚手渡してくれた。曲線や正方形や奇妙にもつれた幾何学的な図が入り組んでいる下に、彼は力の入った太い筆跡で、次の文に線を引いておいたのだった。「詩の女神の腕の中で青春を費やせ……彼女の愛は、他のすべての愛の失望から慰めてくれる」もう少し上の方に太い活字体でシニョレッリ(SIGNORELLI)、そして小さな字でルーベンス(Rubens)と彼は記しておいたのだった。正方形のうちの一つは、水彩のかすかな色合いのブルーに染まっていた。彼は私に紙を渡した。 「これはゴーティエの言葉だ……仕事だ、仕事をしなければならないのだ。」彼は言った。私に突然背を向けて口ごもるように、「芸術は生きることの慰めになる」と言った。そして紙を私から奪い取るなり小さくちぎった。私が退散するまで、一言も口をきいてくれなかった。(112頁) ■「私は自分の道のプリミティフである」この道を切り開くために、そこを通って自分が目的としているところにより確実に到達するために、彼は自分をうっとりさせる大きな主題から遠ざかった。森全体を表現できないことに苦しんで、一本の木を写すことに努力をした。ところが厖大な樹液はその輪郭を破裂させるのだった。彼はすぐにやって来る勝利や成功に伴ういろいろな喜び、気持の良い付き合いや友情さえ断念した。絶対の探求に没頭した。孤独であった。仕事をした。(116頁) ■暮らしぶりは一切変えない。すでに前から、明け方に始まって晩まで、太陽の生む一日という一日は、毎日働いていたのである。暁に起きてこれを続けてゆく。しかし秩序をもたない霊感(インスピレーション)や偶然まかせの探求というものと、意識的な労働や筋道の立った作業というものとの間や、発明と服従との間では、彼はすでに自分の選択をした。「服従はあらゆる進歩の基本である(注)」今後、彼は世界を写すことにする。地球の肖像画を描くことにする。ある顔やある家具を生きたものにしておく太陽のにぶい労働の跡を必死に追うことにする。対象に服従する。夢はもう見ないことにするのだ。 (注)シャルル・モーラスの小冊子の巻頭に引用されたオーギュスト・コントのこの文章を、私の家でセザンヌが目にしたとき、しばらく考えこんでから、「それは本当だ……なんて本当なのだろう」と言った。 ■ときどき、ヴァン・ゴッホの話をしてくれたが、つねに好感を交えてのことだった。私の家で、ゴッホの絵が2枚ほど鑑賞できるので喜んだ。ポール・ゴーガンについても同じだった。人が言い張っているように、アルルまで彼らに会いに行ったと私は思わない。ゴーガンにはタンギー爺さんのところやカフェで会ったりしたが、それもたまにだ。(125頁) ■彼と知り合いになったのは、1896年のことだ。まだ57歳でしかなかったが、心のなかの殉教にすっかり身は荒れ果てて、落胆した病身の彼はすでに老人に見えた。彼の丈夫な血筋のなかに硬くしっかりと流れる頑健な体質が再び姿を見せることがあるにはあったが、ほとんど毎晩、激しい頭痛に見舞われて、拷問のように糖尿病に悩まされていた。彼はつねに自分の力を上回っていた。神経をとがらして、目には筋が走り、頭脳は荒され、心は熱におかされ、自分の懐疑に打ちひしがれていた。喜びのうちに仕事をしていたならば、多分ティツィアーノのように100歳までは絵を描き続けたに違いない。自分のなかの動物としての部分に過労を与えすぎていたのだ。(138~139頁) ■私はなにがしの者でもなく、まだほとんど子供だった。エックスで何かの展覧会の際に、彼の風景画を見たことがあり、絵画というもののすべてが眼の中に入って来たような感じを受けた。この2枚の絵は色彩と線の世界を私に開いてくれた。それ以来1週間というもの、私は新しい世界に酔ってほっつき歩いた。父は、町じゅうから嘲弄されていたこの画家を私に紹介する約束をしてくれた。私はそこにいるのは彼だと察した。私は近づいてゆき、御尊敬申し上げています、とつぶやいた。彼は顔を赤らめて、どもり始めた。それから背を伸ばして、今度は私が顔を赤らめてしまうようなかかとの先まで焼けてしまうようなおそろしい視線を投げつけた。 「ねえ、若造の君、おれをからかうなよ」 円卓をすごい勢いの拳固で叩いてぐらつかせた。コップが鳴った。すべてが傾いた。私はかってあんなに大きな不安を抱いたことはないような気がする。セザンヌの目は涙ぐんだ。両手で私をつかまえた。「まあ、ここにお坐り……アンリ、これは君の倅か。いい子じゃないか……」と私に向かって言った。腹を立てた声は今やすっかり人が善さそうに優しくなっていた。私のほうを向いて、「君は若い……君には判るまい。私はもう絵が描きたくないんだ。私はすべてを投げた……ちょっとお聞きなさい、私はあわれなやつだ……うらまないで下さいよ……私の絵をたった2枚見かけただけで君が私の絵にだまされてしまったなんて、どうして信じられますか、一方で私について書いているものかきども(ものかきどもの横に丶)が一度としてそれがわからなかったというのに……ああ、連中には、ひどい目に遭ったよ。君は、サント・ヴィクトワールなのだね、特に気に入ってしまったのは。わかるかね。あの絵が気に入ったんだね。あした、君の家に届けさせるよ……それにサインもするよ……」 かれは他の人たちのほうを振り向いた。 「――ゆっくり話していて下さい。私は、この子とおしゃべりがしたい。連れてゆくよ……ねえ、アンリ、晩飯を一緒にどうだ?」彼はコップを飲みほして、私と腕を組んだ。私たちはまち(まちの横に丶)を囲んでいる大通りの闇のなかへ深く入っていった。彼は信じられないほどの高揚状態にあった。心を私に打ち明けて、自分の絶望や、見捨てられてくさってしまっていることや、自分の絵画と人生の苦悩、ルナンの言うあの「深い感情」、あの「統一」を語ってくれた。私はそれをうまく言い表したいのだが、あの晩は、この「深い感情」によって尊敬の念などを遠く超えて、恍惚に達するほどの戦慄を覚えさせられた。心情を通して、彼の天才に私は触れたのだった。彼というものが私にはよく感じられた。同時にあれほど偉大であれほど不幸たり得るということは、それまでの私には、絶対に信じられなかったであろう。別れたときは、彼の人間的な苦しみに対して、信仰をいだいてしまったのか、それとも彼の超自然的な画才を崇拝していたのか、どちらかわからなくなっていた。(141~143頁) ■「春を見るのは今度が初めてだ」と彼は言った。 自信もすっかりよみがえった。しまいには、自分の天才のことを私に口走った。ある晩、心からうちとけて、私に打ち明けたのである。 「私が今生きているただひとりの画家だ」 その後、彼はこぶしを固く握りしめ、暗い沈黙に浸ってしまった。人を寄せつけぬ雰囲気で帰宅した。彼の身に災難でも降りかかったかのように、。次の日、彼は来なかった。2、3日、私は重ねてたのんだが、駄目だった。そのうち、こんな一筆をもらった。 「拝啓、パリに明日出発いたします、敬具」4月の15日だった。(144~145頁) ■「親愛なるガスケ様、 今晩、並木通り(クール)の下でお目にかかりました。ガスケ夫人とご一緒でした。私の思い違いかもしれませんが、あなたは私に対してかなりお怒りになっておられるように見えました。 私の内、内なる人間、それを見ていただくことができれば、多分お怒りにならないと思います。どんな悲惨な状態に私が追いつめられているかが見えないのですか。自己(自己の横に丶)を制することもできず、存在すらしていない人間です。それなのに、哲学者でありたいというそのあなたが、私にとどめをさしたいのですか。でも私は、たかが50フランくらいの記事をでっちあげるために私の身の上に注意を引いたXやそのほかの馬鹿どもをのろいます。私は一生、生活できるようになるために働いてきました。自分の私生活に人の注意を引かずによい絵が描けると思っていました。みちろん、芸術家は知的に、より高いところに行きたがります。でも人間としては地味な存在であり続けなければなりません。楽しみは勉強のなかに宿っているべきです。私が作品を実現(レアリゼ)することに成功していれば、一緒に一杯飲みに行ったアトリエの友だち何人かとひっそり引っ込んでいたでしょう。あの時代のいい友人がまだいます。出世はしていませんよ。でもメダルや勲章ずくめのやくざな連中よりははるかに絵描きとして上です。それなのに、私の年齢になってまだ何かを信じなさいとでもおっしゃるのですか。しかも、私は死んでいるも同然です。あなたは若い。成功したいとお思っているのはよくわかります。でも私はね、私の置かれた立場では、おとなしくしていることしか残されていません。自分の故郷の地形がひじょうに好きだということがなかったらば、ここにいたりはしません。 うるさいことはこれで十分申し上げましたが、私の立場をご説明したあとは、あなたに危害を加えたかのように私を見たりなさらないだろうと存じます。どうか、私の高齢をご配慮の上、私の心からの挨拶と好意を、お受け下さいますよう」 私はさっそくジャ・ド・ブッファンへ飛んで行った。セザンヌは私を見るなり、腕を広げた。「もうあの話はやめよう。おれは年とった馬鹿だ。ここにお坐りなさい。あなたの肖像を描こう」(147~148頁) ■デュラン=リュエル画廊などで、展覧会に彼が顔を出すと、人々は場所をゆずり、彼に挨拶はするし、敬意を表して歓待する。彼は気がつかずにいる。カミーユ・ピサロやルノワールやギョーマンのように彼が認めている人たちは、彼にふさわしく、そして彼らの取ってしかるべき態度で待遇してくれる。セザンヌは、この人たちとも交際せずに、ときどきしか会わない。それでいて、孤独は重荷なのだ。生きている最大の画家として彼の尊敬するクロード・モネ、その名声の最高点に達していたモネがある日、私の目の前で、セザンヌをほとんど師呼ばわりしたばかりか、現時の絵画のなかでいかに偉大な地位を占めているか、そして彼から発生するルネッサンスのことなどを語った。セザンヌはかすかにほほ笑んで、ぶっきらぼうに握手をして、「仕事をしに行こう」とぶつぶつつぶやきながら大通り(ブルヴァール)の群衆のなかに消えて行った。(154頁) ■セリジェ氏が「セザンヌの精神主義」と呼んでいるものが、絵のなかでますます強調されてくる(注)。 (注)セリュジュ氏に言わせれば、「彼は純粋画家である。彼の様式(スティール)は画家の様式であり、彼の詩は画家の詩である。再現された物(オブジェ)の用途や概念までが、色彩を帯びた形態(フォルム)の魅力を前にして消失する。ありきたりの画家のりんごを前にすると、食べてもよいね、と言う。セザンヌのりんごのことは、美しい、と言う。恐れ多くてとてもむく(むくの横に丶)わけにはゆかない。写生したくなる。これこそがセザンヌの精神主義(スピリチュアリスム)を成している。私は意図的に、観念主義(イデアリスム)ということばを使っていない、なぜならば観念的(イデアル)なりんごというのは、〈口の〉粘膜に快感を与えるようなものであるに違いないからで、セザンヌのりんごは、眼を経て精神に語りかける……特筆すべきことは、画題(シュジュ)の不在である。彼の最初の画風(マニエール)では、主題(シュジュ)がときには幼稚で、とるに足らなかった。画風が進展したのちは、しゅだいはすっかりなくなって、ひとつのモチーフ(モチーフの横に丶)だけになる」(モーリス・ドニ氏が『理論』の244ページに引用)(155頁) ■ある日、わが家で昼食を食べているとき、彼は広鉢(ジャット)に盛られた黄桃と(あんず)と桃を見て、われわれにこう言った。 「見てごらんなさい。光はあんなに黄桃にやさしくしている、黄桃を丸ごとつかみ、果肉に入り込み、四方から照らしている!それにひきかえ、桃に対してはけちだ。その半分しか明るくしていない」 それまで誰も言わなかったような気のきいた、小さな発言をこんなふうにするのだった。またあるとき、私がカルディナル通りを彼らと連れだって歩いていると、彼は、 「芸術家というのはね、アーモンドの木が花をつけるように、かたつむりが粘液を出すように、作品をつくらなければなりません……」ともらした。 彼は付け加える。 「私はもしかすると、早く生まれすぎたのかもしれない。自分の世代よりは、君たちの世代の画家だったんだ……君は若い、君には生気がある。君は自分の芸術に、感動をひそめる人々だけが与えることのできる推進力を与えるでしょう。私は、そろそろ年を取ってきました。自分を表現する時間が足りないでしょう……さあ、仕事をしましょう……(注)」 (注)この言葉も、ここで私が老画家の口から言わせている言葉のほとんどがそうであるように、私の死後に刊行される書簡からの断片であることを、明記しておく必要があるだろうか。彼の口からしじゅう聞かされたことを完全に要約するものである。私は、それが可能だったときはつねに、自分自身の記憶やノートよりは、書かれた証言、しかもセザンヌ自身によって書かれたもののほうを重んじてきた。(162~163頁) ■ある日の、烈風(ミストラル)が吹く午後、友人グザヴィエ・ド・マガロンと私が、彼が仕事していないものと思って突然、訪ねて行ったときのことだ。岩の上で、破れて風に飛ばされる自分の絵の前で、大粒の涙をこぼしながら、こぶしを固くにぎりしめ、地団駄を踏んでいる場面に出くわした。石切り場の草むらの中になげ飛ばされた絵をわれわれが走ってひろいに行こうとすると、彼はさけんだ。 「放っておけ、放っておけ……今度こそ、うまく自分が表現できるところだった……うまくいっていた、うまくいっていた……でもそうはならない運命なんだ。いいから。あれは放っておけ」 水色めいた谷の上にサント・ヴィクトワール山が輝く大きな風景画、それはほやほやに新鮮で、やわらかく光り輝いていたが、風に押されて入ってゆく草にべとべと粘りついていた。傷だらけになりひきさかれて、絵は人間のように血がしたたるのだった。絵の赤茶色の部分や、紅に色どられた大理石や、松や、宝石細工の山や、熱烈な空などが突風に破られた姿がわれわれの目の前にあった……自然とたちうちできる一つの傑作だった。セザンヌは、顔面から眼が飛び出しそうになって、われわれと一緒にそれを見つめた。狂気というべきか、われわれにはわからない何かに彼は駆られた。絵のほうに歩み寄り、それをつかんで、引き裂いて、岩の上に投げ捨てて、靴で踏みつけて破ったのだ。それからそれにもたれかかるように倒れて、われわれにさも責任があるかのように、こちらを拳固で脅かしながら「とっとと行ってくれ、とっとと行ってくれ……」と言った。われわれは松林のなかに隠れて、彼が1時間以上も子供みたいに泣いているのを耳にした。(163~165頁) ■付き合ったことはないが、最もセザンヌをとく察した人のひとりであるエリー・フォールは、この偉大な、ひとつの倫理に忠実な人生の、人間的な面や、つねに自分に対して勝ち続けなければならないというあの一種の悲劇的な内面の勝利を、すばらしい言葉で表現した。「この世で彼を引きつけるものは光と陰影が物に対して与える色彩と造形の組み合わせのほかには何ひとつなかった。それらの組み合わせは目にたいへん緻密な法則を教えてくれるので、高度の精神の持ち主は、その法則を人生に応用して、倫理的な、形而上学的な方向づけを求めることができるのだ」(165頁) ■「感動を原理としない芸術は、芸術ではない!」と叫んだ。 進むにしたがって、ますます感動を求めるようになった。理性が整理され、厳格に、痛烈に、くるいなく働くようになればなるほど、感受性がその上に、よりみごとに感動の花を開かせた。彼の描くヴィクトワール山の強靭な土台と硬い斜面にほころびる春の微笑のように。(168~169頁) ■ある晩、詩人のレオ・ラルギエが、老大家に朗読をしてきかせようと思って、自分の詩を思い出して再現しようと、舟の水彩画にじっと目を凝らしていた。それはセザンヌがしばしば絵を描きにいったに違いない場所のなつかしい思い出で、そこにあるのを好んでいたのだろうが、「どうぞ持っていらっしゃい」と言った。なんでも人にやってしまうような人だった。後年、彼の御者から話してもらったことだが、なんべんもセザンヌはこの人に絵のうちのどれか1枚――大きな静物画や特に桃の籠――を贈ったものだが、この人も持ってゆくことをためらった。セザンヌは執拗に言った。「まあ私の記念に……あなたには、母をいつもよく世話してもらいましたし……将来、これを持っていれば楽しいですよ」食堂には、エックスの風景と静物画が1枚ずつ。それが彼にとっての贅沢のすべてだった。仕事だけを愛していたのだ。(177~178頁) ■中世の飾画師(イマジエ)たちは、画題に対して受け身の姿勢になっていた、ヴェネツィア派の画家たちにしてもそうなのだと、彼は自分に言い聞かせた。目に見えるものを描いていればよいのだ。画家は何もかもを描くのでなくてはならない。フローベールが自らの芸術で発揮したのと同じような客観性を発揮し、世界や対象物に完全に服従して、眼の持つ一種の宿命に身をまかせるのでなければならない。最もささやかな現実が、最も華やかな絵画のインスピレーションとなるかもしれない。そうだ。ヴィジォンのしゅくめいというのがある。資質(タンペラマン)によって選択がおこなわれるのであり、それを引き出して強化するものしか目には受け止めない。世界はひとつの個性を帯びる。目にするものはすべて美しい。(194~195頁) ■1902年の7月の、それと同じ頃、私に次のようなことを書いている。 「私は、モネとルノワールを除く現存の画家は皆軽蔑する。そして私は仕事することによって成功したい」1年ほどたって、1903年9月には、こう書いてきた。「描き始めた絵にはまだ6ケ月手を入れなければならない。「仏蘭西芸術家展(サロン・デ・ザルティスト・フランセ)」に出品されて、受けるべき待遇を受けにゆくであろう」(196頁) ■1人の神父が通る姿を見て、震えながら、「司祭たちは恐ろしい……はめられてしまうんですよ……」とつぶやくときがあるかと思うと、熱心なカトリック信者である友人のドゥモーランに、「先生は神を信じていらっしゃいますか」と尋ねられて、「だって君、信じていなかったら、私は絵が描けないではありませんか」というような答えをするのだった。キリスト像を描く着想を提案しようとするエミール・ベルナール氏に対して、こんな理由を挙げて断るのだった。「絶対にそんなだいそれたことは私にはできません。難しすぎます。私などよりはそれが上手にできた人たちがいます……」彼は、自分の芸術に対する誇りや尊敬というものを、自分の信仰の謙虚さや祈りというものよりも上においていたわけだ。(197~198頁) ■この霧の奥深い中にあって、すっかりこわばった彼は、ある朝、ヴィクトワール山の前に画架を立て、絵を描いていた。自分のモチーフをつかんでいたのだ。絵を描いた。今や好きになっていた灰色の天候で、世界の老年期の薄ら笑いというか、ひとつのやさしい朝だった。絵を描いた……車が迎えに来たとき、御者は、パレットを手に持ち、ずぶぬれで震えているところを見つけた。雨はやんでいた。銀色の空が田園にのどかさを与えた。悲劇の山には虹が輪光さながらにかかっていた。何も目に入らないセザンヌは、車に乗るのがせいいっぱいだった。1冊の本、彼の昔からのウェルギリウスの書が、泥のなかにころげ落ちた。 「あれは、放っておいて、私の絵も放っておいて」と喘いで言った。熱があった。譫言(うわごと)を言った。彼は寝かされた。夜通し彼は、あそこの、絵の地平線に、思索と人生の地平線に、いまだかって鑑賞したことのないようなサント・ヴィクトワール山を再び見たのだ。神々しいその姿を描くのだった。光り輝き、超自然の、そしてその本質とその永遠なる姿の真実のなかでサント・ヴィクトワールを見た。まだいまだに見ているかもしれない……彼は再び起き上がらなかった。(204~205頁) ■セザンヌ 太陽が照って、希望が心の中で笑っている。 ガスケ 今朝は、ご機嫌うるわしいですか。 セザンヌ モチーフをつかんだよ……(手を合わせる)。モチーフというのは、そうだね、こういった……。 ガスケ どういうのですか? セザンヌ まあ、こんな……(再び同じ仕草をする。10本の指を開いて両手を離したのち、ゆっくり、ゆっくり両の手を近寄せて、かたく握りしめて、こわばらせて、互いにくい込ませる)。これに達するのでなけりゃいけない……。私がもうちょっと上か、もうちょっと下を通ったら、全部が駄目になる。ゆるすぎる網の目というか、穴があって、そこから感動や光や真理が逃げ出してしまうようではいけない。絵全体を、私は、いっぺんに、総合的に押し進めてゆくんです。おわかりかな。私はちりぢりばらばらになるものを全部、同じひとつの勢い、同じひとつの信念でもって近づける……われわれの見るものは全部、散乱して、どこかに行ってしまう、そうでしょう。自然はいつも同じ自然だけれど、私たちの目にあらわれているものの中からは何も残らないでしょう。われわれの芸術は、自然が持続しているということの戦慄を人に与えるべきなのだが、それは自然のあらゆる変化の要素や外見を駆使してなのだ。永遠なものとして味わわせてくれなければならない。自然の下には何があるんでしょうね。何もないかも知れない。もしかしてすべてがあるかも知れない。すべてです、おわかりになりますか。それで私は、自然の迷える手を合せてやるのです……あっちから、こっちから、方々から、左から右から、その色調、そのニュアンスを私はつかんで、それを定着させて、それを互いに近づけます。……それは線を作ってゆくんです、物(オブジェ)や岩や木になってゆきます。私が考えないうちに。容積(ヴォリューム)を持つようになります。色価がそなわってくるんです。もしこういう容積やこういう色価が私の画布のうえで、私の感受性のなかで、目の前にある数々の平面やしみ(ターシュ)に適合したら、そうしたら、私の絵は両手を組むのだ。ぐらぐら揺れない。高すぎも低すぎもしない。真の、濃厚な、充実した絵です……ところが、私がちょっとでも気が散って、少しでも気のゆるみがあると、特にまた、ある日には解釈をしすぎるようなことがあったり、今日の理論が昨夜の理論に逆らって、私をひきずったりするようなことがあると、いわば、絵を描きながら私が思考し、私が介入すると、ぽちゃっと、全部お流れになってしまう。 ガスケ 介入なさるといいますと、どうして? セザンヌ 芸術家は、数多くの感覚を受ける器です。ひとつの受信機です……まあ、いわば、性能のよい機械、こわれやすくて複雑で、他のものに比べたら特に……ところが、芸術家が介入したりすると、翻訳しなければならないものの中で、些細な自分というものの意志をはたらかせて参加しでもすれば、自分の卑小な面をそこに持ち込むのです。そうなる作品の質は低い。 ガスケ 要するに、芸術家は自然に対して劣るというのでしょうか。 セザンヌ 私はそうは言わなかった。なに、あなたはその手にひっかかるんですか。芸術は自然に平行しているひとつの調和です。画家はいつも自然に対して劣っている、なんていうことを口走る馬鹿どもはなんと評すべきかな。平行しているのです。もちろん、意志的に介入しなければのことですが、その辺はわかって下さい。芸術家の全意志は、沈黙であらねばならない。自分の内の、偏見の声々をだまらせなければならないし、忘れて、忘れて、沈黙にひたって、完全なるひとつのこだまになる。そうすると、彼の感光板に、景色全体が記されてゆきます。画布にそれを定着させ、外に顕在させるに当たって、メチエがのちにものを言う段になりますが、それも、命令に従い、無意識に翻訳するという敬虔なメチエです。自分の言語に精通するのあまり、自分の解説する文章(テキスト)、2つの平行した文章、見たり感じたりした自然、そこにある自然(彼は、緑と青の平野を指差した)……こちらにある自然(彼はおでこをたたいた)……両方ともが持続できるために、芸の命と言う、半ば人間半ば神の命をもって生きるために、そうだ、よく聞いて下さい、神の命ですよ、それには双方が融合しなければいけません。風景は、私のなかで反射し、人間的になり自らを思考する。私は風景を客体化し、投影し、画布に定着させる……。せんだって、あなたはカントの話をして下さいました。私はとちるかもしれませんけれど、思うに、この風景の主観的認識が私だとすれば、私の絵は客観的認識のほうでしょう。私の絵、風景のどちらも両方とも私の外にあって、しかし一方は、混沌としていて、つかみどころもなく、こんがらがっていて、論理的な活動なしに、いかなる理にもはずれている。他方は、定着した、感覚界の、範疇化されたもので、表象のドラマや様相に一役買っているものです……表象の個性に個性に一役かっています。ええ、わかっています、わかっています……これは解釈にすぎません。ー後略ー(215~216頁) ■セザンヌ あなたに伝えようとしていることはもっと不思議で、存在の根源や手にとってみりわけにはゆかない感覚の源にからまっているものなのです。しかしそれこそが、私の思うに、資質(タンペラマン)をつくり上げるのだ。そして、原動力すなわち気質なるものの他には、一人の人間を、達成したい目標まで支えてくれるものはない。先ほどあなたに申し上げたが、仕事をしているとき、芸術家の、自由なる頭脳は、感光板のよう、ただの受信機のようでなくてはなりません。しかしですね、この感光板は、たいへん凝ったいろいろな液に漬かってきて、物の丹念な像が浸透することができるくらいの受容点に達しています。気長な仕事や熟考や勉強やさまざまの苦労、そして喜び、つまり人生というものが、この感光板の下準備をしてきた。巨匠たちの技法をたえず熟慮すること。そして、ふだんわれわれの動いている環境……あの太陽、ちょっと聞いて下さい……光線の偶然や、世界中にわたっての太陽の運動や浸透や化身というものをいったい誰がいつ描くのでしょうか、誰が語るのでしょうか。地球の物理的な歴史、地球の心理学のようなものでありましょう。生きものも物も、全部多かれ少なかれ、貯蔵された、組織化された、ほんの少量の太陽熱にすぎません、太陽の思い出の品というか、世界の脳味噌のなかで燃えるほんのちょっぴりの燐にすぎません。友だちのマリオン君がそういう事を語っているのは聞きごたえがありますよ。私はその本質を抽出したい。世界の脈絡のない倫理、そこに、世界の抱いている神の夢神の感情、神の概念があります。どこでもかしこでも、光線が暗い扉をたたいています。どこでもひとつの線がひとつの色調を包囲して、虜にしている。私はそれを自由にしてやりたい。われわれプロヴァンスや、私の想像するギリシャやイタリアという古典的な大国は、光明が精神性を帯びて、風景は鋭い知性のほんのりした笑みのようなものであるくに(くにの横に丶)なのです。……われわれのくに(くにの横に丶)の雰囲気(アトモスフェア)の繊細さは、われわれの精神の繊細さと通じるところがあります。互いに互いが含まれているのです。われわれの頭脳と宇宙が接する場は、色彩です。だから、真の画家たちには色彩が劇性(ドラマ)に満ち満ちて現われるのですよ。あのサント・ヴィクトワール山を見てごらんなさい。なんという勢い、なんという太陽の激しい渇望、そして晩になっておの重量が全部下りてきたときのなんというメランコリア……あの石のかたまりは火だったのだ。まだ中に火を秘めている。(中略)私は長い間、サント・ヴィクトワールが描けずに、どうして描けばよいかわからずにおりました。ものを見ることを知らない他の人たちと同じに、陰影が凹だと想像していたからです。ところが、ほら、、見なさい、陰影は凸です、その中心から逃げています。縮むかわりに、陰影は蒸発して、流体化する。真っ青になってあたりの空気の呼吸に加わります。たとえばあそこ、右のほうの、ピロン・デュ・ロワの上空では、逆に光は湿気を含んで、きらめきながら揺れています。海です……、これを表現しなければならないんだ。これを知っていなければならないんだ。敢えて言うならば、この知識の溶剤にこそ、自分の感光板を漬けなければならないのだ。風景をうまく描くには、私はまず地質学的な土台を見つけ出さなければいけない。考えてもごらんなさい、世界の歴史は、2個の原子が出会って、2つの化学的な渦巻き、2つの舞踊が組み合さったその日から始まっている。あの大きな虹たち、あの宇宙的な数々のプリズム、空無の上にあるわれわれ自身の暁、私はルクレティウスを読みながらそういうものの立ちのぼってくるのが目に見えて、自分が飽和されてゆく。この霧雨の下で、私は世界の処女性を呼吸する。ニュアンスを受けとめる鋭い感覚が私をさいなむ。無限というものにそなわったすべてのニュアンスに私は彩られる。その瞬間、私は自分の絵と一体になる。われわれは虹色に輝く一つの混沌をなすのだ。私のモチーフの前に来て、私はそのなかに迷い込んでしまう。ぼうっと、もの思いにふける。遠方の友のように、太陽は私のなかに鈍く侵入しては、私の怠惰をあたため、受胎させる。われわれ(絵と私)は発芽する。夜が再び下りてくると、ついぞ絵などは描いたことはなく今後も描くまいという気がする。夜が来ないと、土地から目が離せないのだ、私の溶け込んだこのわずかばかりの土地から。ある時あくる朝になって、地質的な土台がゆっくり見えてきて、いくつもの層が出来上がり、それは私の絵の大きな面(プラン)だが、石のその骨格を頭のなかで描く。水の下に岩が露出しているのや、空が重くのしかかるのが見える。すべてがきちっとおさまる。線的な様相が色の薄い動悸に包まれる。赤い土が深淵から出て来る。私は風景から少し離れ始め、風景が見えてくるのだ。この地質的な線、この最初のエスキスによって風景から足がぬける。地球の尺度なる幾何学。やさしい感情におそわれる。その感情の根から、樹液やさまざまの色彩がのぼってくる。一種の開放。魂の光を放つ様、地球と太陽の間に交わされる視線や外に露呈された秘儀ややりとり、理想と現実、色彩!空気のような、色のついた論理が、暗い強情な幾何学にとってかわるのだ。すべてが、木々や畑や家が、有機的にまとまる。私には見える。斑紋が。地層や準備の仕事や素描の中の世界はへっこみ、災害にでも遭ったようにくずれ落ちている。激変がそれを持ちさらって、更生させた。新しい時代が生きている。真の時代!すべてが同時に濃密で、流体的であり、そして自然である。その時代には、私の見逃すものはない。もう色彩の数々があるだけで、その内に光明があって、色彩を思考する存在と、太陽へ向っての地球の上昇と、愛へ向っての深奥からの発散がある。天才とは、この上昇というものを一瞬の平衡のなかに固定することなんでしょうね、もちろんその勢いを匂わせながら。私は、この考え、この感動の吐出、全宇宙の赤々とした炭火の上にあるこの存在の煙、それを自分のものにしたい。私の絵は重い、筆におもりがぶら下がっている。すべてが落下する。すべてが再び地平線の下に落下する。私の頭脳から私の絵の上に、私の絵から地球の上に。重々しく。空気や濃密な軽やかさはどこに行ってしまったのだ。天才は、外気のなかのこれらのあらゆるものを、同じひとつの上昇、同じひとつの欲望にたばねて、その友情を引き出すことでしょう。遷りゆく世界の一瞬がそこにある。その現実のなかでそれを描く!そしてそのためにすべてを忘れる。そのものになりきる。そのとき感光板であること。われわれ以前にあらわれたものはすべて忘れて、目に見えるもののイメージを(220~224頁) ■セザンヌ 洞窟の丸くなった天井に狩猟の夢を刻み込んだ初めての人間たちや、墓の壁面に自分んなりの天国をフレスコの手法で描いたあの善良な(初期)キリスト教徒たち、彼らは自分をつくり上げて、彼らのメチエも魂の印象も全部自分で身につけた。そんなふうにして景色の前に立つ。そのなかの宗教を引き出す。日によっては、自分が素朴(ナイフ)なふうに絵を描いているように思える。自らの道におけるプリミティフなのだ。私は無器用さの信念をもってして、定式(フォルミュール)に達したい、まあちょっと聞いてくれ、完全に実現(レアリゼ)させたいのだ。なんと言ったって、無知や素朴を装うのは、最低の退廃だ。老衰だ。今日では、ものを知らないということはできない、自分でものを覚えることも。生まれたときから、自分のメチエを吸っているんだ。悪いふうに。だから逆にそれに型をつけなければならないんだ。四方八方、社会という広大な宗教的でないひとつの学校に漬かっています。ええ、そこの生徒たちに相当する一種の古典主義(クラシシズム)があって、それが私の何よりも嫌うものなのです。だから、神様の場合と同じに、誰かが言ったように、少々の学は遠ざけ、たくさんの学は引き戻す、と私は想像します。そう、たくさんの学は自然に引き戻してくれる。ただの技巧(メチエ)だけでは不足とわかるから。 ガスケ 技巧(メチエ)で不足とは? セザンヌ そうです。抽象的な技巧(メチエ)は、しまいには人を干からびさせる、疲れてゆくに従って荘重になるその修辞法(レトリック)に押しつぶされて。ボローニア派の画家たちをごらんなさい。もう何も感じていない……感覚が必要なときには、手の届くところにひとつの考え、ひとつの思念、ひとつの言葉が絶対にあってはいけないのだ。大義名分、それは自分のものではない思念だ。型にはまったものは、芸術の癩病だ。ほら、絵画における神話、ずっとその追跡をすると、メチエが幅をきかせてゆく歴史にあたる。女神たちを描いたら、しまいには女を描かなくなったんだ。一連のサロンをひとまわりしてみなさい。やっこさんが、木の葉の下で見ずに光が反射しているのがうまく出せない、すると水の精を一人そこに置くんだ。アングルの《泉》!あれは、水とどんな関係があるっていうんだ……それで君たち、文学のほうでは、くどくどと書いては叫ぶじゃないか、ヴィーナスだ、ゼウスだ、アポロだ、それも、深い感動に駆られて、海の泡、空の雲、太陽の力というふうに言えなくなっているとき。オリュンポス山のあの古ぼけた道具立てを信じているんですか?じゃ、どうなんですか。 真実なるものの他に美しいものはなく 真実なるもののみ愛すべきなり。(225~227頁) ■セザンヌ これこそ画家だ……彼らはほんとうに異教徒だ。あのルネッサンスには、たぐいのない真実味の爆発がある。2度と見られない絵画や形態(フォルム)への愛情がある……イエズス会の人たちがやがて現われる。すべてがしゃちほこばっている。なんでも勉強し、なんでも教える。革命があってやっと自然が再発見されるし、ドラクロワがお好みのエトルタの海岸を描くし、コローがローマのあばら屋を、クールベが森の下草や海の波を描くのだ。しかもなんと苦しく、ゆっくりと、いかに段階を踏んできたか!格好をつける……(テオドール)ルソー、ドービニー、ミレー。風景画を、歴史画のように、構成(コンポゼ)するんだ。私が言いたいのは、外から、ということだ。風景の修辞法(レトリック)を作って、ひとつの文章や種々の効果、それをたらい回しする。デュプレから教わったんだとルソーが言っていた、絵画の仕掛け作り。コローだってそう。私はもっと地に足がついた絵画のほうが好きだ。自然というのは、表面よりは、奥行きのほうにあるのだということが、まだまだ発見されていない。だって、少し考えてみたまえ、表面を変更したり、飾ったり、みがきをかけることはできますよ、真理に手をつけずに、奥行きに手をつけることはできない。真実を語りたいという健全な本能に駆られるんだ。細部を発明したり、想像するくらいなら、自分の絵を投げたほうがよいというふうになる。とにかく知りたいんだよ。 ガスケ 知るとは? セザンヌ そう、私は知りたいのだ。さらによく感じるために知る、さらによく知るために感じる。自分のやっている技巧(メチエ)では私は先頭に立っている(ル・プルミエ)が、単純でありたいのだ。知の境地に達している者は単純だ。中途半端にものを知っている人たち、素人たちは中途半端なものしか実現(レアリゼ)しない。まあ、本当を言えば、ぼろい絵を描く人たちだけが素人なのだ。マネがゴーガンにそう言った。私はそういう素人の仲間にされたくないね。だから、真の、古典主義者(クラシック)になりたい、感覚を経て、自然を経て再び古典主義に戻りたい。前は考えがこんがらかっていた。生命!生命!その言葉ばかり口にしていたものだ。馬鹿なおれは、ルーヴルを焼き払いたかった!自然を経てルーヴルに行き、ルーヴルを経て自然にもう一度戻らなければならないのだ……でもゾラはなかなかうまく『作品』のなかで、私のことをつかんだよ。君はおぼえていないかも知れないが、彼がこうわめいている場面で。「ああ、生命!生命!それを感じて、その現実において表わすこと、生命をそれとして愛し、そこにのみ真の、永遠の、移りゆく唯一の美を見てとる……」 彼の記憶はためらった、そして、一気に最後まで彼は言い通した。 セザンヌ 「……それを去勢することによって高尚たらせようという馬鹿な考えを抱かぬこと、醜いものとされているものは個性の突出でしかないことを理解し、ものに生命を与えて、そして人間を作りだすこと、これは神となる唯一の方法だ」(229~231頁) ■セザンヌ まあちょっと聞いて下さい……(スイスに近い)タワロールにいたときです。温厚な部落(パトラン)といえば、これに限ります。ねずみ色といえば、わんさとある!それに、緑色も。地球図のありとあらゆる緑青。周囲の丘はなかなか高い、と私にはそう見えたがね、ところが人には低く見えるのだ、しかも雨が降って降って!……くたびれた2つの山間の道にはさまった湖があるんだ、英国夫人たちの出てきそうな湖だ。画帖の紙が一葉一葉、木々からすっかり水彩されて落ちてくる。もちろん、これもまた自然なのだが……私の見るような自然ではない。わかりますか。ねずみ色と隣り合わせのねずみ色。ねずみ色を1つも描いたことのないうちは画家じゃないんだ。あらゆる画家の敵はねずみ色だ、とドラクロワは言っている。でも違うんだ、ねずみ色を1つも描いたことのないうちは、画家じゃないんだ。 (中略) 自然は万人に語りかける。ほら、ところが、風景というものはかって1度も描かれていない。不在の人間、それでいて、風景のなかに完全に没入した人間。あの大仕掛けの仏教、涅槃だの、情念も逸話もない慰安だの、色彩!ここだったらただ蓄積して、自分が開花するがままに任せればよい。この土地は孕んでくれている……たとえば、遠く、パリにいても、その香りを私はまだ感じる。(233~235頁) ■セザンヌ 私は今日ずいぶんおしゃべりだ。芸術談義というのはほとんど無用なものなのだがね。 ガスケ 芸術家同士を近づけたりするとはお思いになりませんか。 セザンヌ 絵はその場ですぐ見えるか、それとも絶対に見えないかだ。説明は何の用もなさない。解説したってどうなる?そんなのは全部、おおよそのことだ。今しているみたいにしゃべることはしなきゃいけない。葡萄酒を1杯ひっかけるみたいに面白いからね。そのほかには、あるひとつの芸術でひとつの進歩を実現させる仕事が馬鹿どもにわかってもらえないことに対して、十分な補いをしてくれることになる。ちょっとお聞きなさい、君のような文学者は、抽象的観念で表現する、一方で画家は、素描(デッサン)と色彩を使って、自分の感覚したり、知覚したものを具体化させる。彼の画布の上にあって、他人の目にもそれが知覚できるようでなかったなら、それについていくら云々したところで、それが人に吸収されるようになるわけではないんだ。私は文学的絵画は嫌いだ。人物の下に、何を思索しているか、何をしているかを書くことは、その人物の思索や仕草が素描と色彩によって十分示し表わされていないことの告白だ。そして、ギュスターヴ・ドレみたいに自然の表現に無理をさせ、木をねじ曲げたり、岩に顰面(しかめつら)させたり、またダ・ヴィンチみたいに凝りすぎるのも、やはり文学だ。色彩的な論理があるじゃありませんか。画家はそれだけに服従すればよいのです。頭脳の論理には絶対に服従してはいけません。自分をそれにゆだねたら、破滅する。いつも目の論理。正確に感じれば、正確に考えることになりますよ。絵画はまずひとつの光学です。われわれの芸術の素材(マチエール)は、われわれの目の考えているものの中にある。自然というものは、敬意をもって接すれば、自分が何をいみしているかを、適当な工夫をしていってくれるんです。 ガスケ あなたにとって、何か意味しているのですか。あなたが自然のなかに投入しているものとは違いますか。 セザンヌ そうかもしれぬ……しかも実際には、君が正しい。自然を私は模写しようと思ったけれども、それができなかった。あっちこっち探求しては、自然を四方八方から攻めてきたが駄目だった。どこからも、降伏させられない。でも私は、たとえば太陽は再現できないものであって、たのもの……色彩でもって、再現しなければならないということを発見したとき、満足だったよ。色彩以外の、いろんな理論、それはそれなりのひとつの論理学である素描、そう、算術と幾何学と色彩を折衷したひとつの論理学、ひとつの生きていない自然〔静物〕である素描もそうだが、いろいろの観念や感覚でさえも回り道なのだ。近道をしたつもりにときどきなるが、遠回りになっている。すべてを表し、すべてを置き直すには1つしか道はない。色彩だ。敢えて言わしてもらえば、色彩は生物的なのだ。色彩は生きていて、ただ1つ、色彩だけが物に生を与え得る。事実、私は人間でしょう?どうしたって、この木は1本の木、この岩は1つの岩、この犬は1匹の犬だと言う概念から離れられない……。(236~238頁) ■セザンヌ ある種の黄色を前にして、あの人たちは自発的に、そろそろ始めなければならない刈り入れの仕草を感じとるのだ。私が熟しつつある同じそのニュアンスを目の前にして、本能的に画布にそれに相当する色調(トン)――麦畑を波打たせるような色調――を置くすべを知っていなければならないのと同じなんだ。筆をつかいつかいするうちに、土地が新たに生きてくるだろうよ……クールベと芝の束のこと話を思い出してごらんなさい。彼は色を塗っていた、芝の束だとも知らずに。ここに再現したのは何かと彼は尋ねた。人が見に行った。そうしたら、芝の束だったんだよ。世界、広い世界もそれと同じさ。その本質において描くためには、色彩のなかにだけ、物体を見て、自分のものにして捉え、自分のなかで他の物体と結びつける画家のあの目がそなわっていなければならない。自然に対しては、いくら几帳面でも、いくら率直でも、いくら従順でも、過ぎているということはないのだ。しかしだね、自分のモデルや特に表現手段が自在であると言ったって、おおよそのことだ。自分のモチーフにそれらを適応させなければならない。モチーフを曲げるのではなく、自分のほうがその前に屈する。自分のなかで生まれるがまま、発芽するがままに放っておく。目の前にあるものを描き、できる限り論理的に、もちろん自然な論理で、つとめて表現する。そういうふうにするとどんな発見があなたをまちかまえているか、想像も及ばないほどだよ。まあ、いろいろとなすべき進歩に関していえば、しぜんしかない。そして目はそれに触れて教育されるんだ。見たり、働いたりしているうちに、同心同円になるよ。 ガスケ どうして同心同円? セザンヌ 私が皮をむいているこのオレンジや、たとえば、りんごや玉や頭には、ひとつの頂点があって、その点は、光の、陰影の、色彩的諸感覚(サンサシオン・コロラント)のすさまじい効果にもかかわらず、われわれの目につねに最も接近している。私はそれを言いたい。物体の端は、あなたの地平線に位置しているもう1つの点のほうへ逃げていく。それがわかったときには……。 彼はほほ笑む。 セザンヌ まあ、絵描きじゃなきゃ、何もわからないのだ。私もずいぶん理論をでっち上げたものだ……ああ、神さま!……(239~241頁) ■セザンヌ 君の知らない画家で、私を訪ねて来た人にそう書いた。彼はずいぶん理論をでっち上げている。私は彼にこう言っている、こう書きつけたんだ、要約すると……。 彼は、ゆっくりと、おじけづいて教条主義的な声の調子で読み上げた。 セザンヌ 「自然は円筒、球体、円錐をつかって処理すること。全体にパースペクティヴがあたえられたならば、ある物体、ある面のおのおのの側面がひとつの中心点に向っていること。地平線に平行した線は広がりをつくる、すなわち自然のⅠ断面、もしくは、こういう言い方のほうがお好みなら、〈全能ナル父ニシテ永遠ナル神〉があなたの目前にくり広げる光景のⅠ断面。この地平線に直角の線は奥行きを作る。ところで、自然は、われわれ人間にとって、表面よりは奥行きに在るのだ、それゆえに、種々の赤色や黄色によって再現された(われわれの)光の振動の中に、空気を感じさせるために種々の空色を十分に取り入れる必要が生じる」 セザンヌ ええ……ものを書くより絵を描いていてよかったでしょう、どうかね?私はまだ(画家で文学者の)フロマンタンには1本取っていないな。 彼は紙を丸めて、捨てた。私はそれを拾う。彼は肩をすくめる。(242~243頁) ■セザンヌ 私だって、何を隠そう、印象主義者だった。ピサロは私に対してものすごい影響を与えた。しかし私は印象主義を、美術館の芸術のように堅固な、長続きするものにしたかったのだ。モーリス・ドニにもそう言ったよ。ルノワールはうまいやつだ。ピサロは農民だ。ルノワールは陶器の絵付職人をしていたのだよ……。彼の巨大な才能のなかになにか真珠の光沢のようなものが残ってしまっている。それにしてもたいした作品を作ったよ。私は彼の風景画を好まない。綿をかぶっているように彼は見ているんだ。シスレーか?そうだね。でもモネは1つの眼だ、絵描き始まって以来の非凡なる眼だ。私は彼に脱帽するよ。クールベのほうは、自分の眼にあらかじめ像ができていた。モネは若い頃、ほら、あっちのほう、英仏海峡で彼と付き合っている。でも、緑色の色斑(ターシュ)ひとつで、風景をわれわれに現すのに十分であるのと同じように、肉の色1つがある顔を表現してくれたり、人間の姿を現すのに足るのだ。そういうことからして、ぼくたちはもしかすると全員ピサロの流れをくんでいる。彼がアンティーユ諸島に生まれたのは運がよかった、あそこでは教師なしで素描(デッサン)を覚えた。いきさつを全部私に話してくれたんだ。1865年にすでに、黒や瀝青(ビチューム)やシェナ土やいろんなオークル色を排除した。偉業だ。彼は私にこう言っていた、3原色とそこから直接できた組合わせの色以外では絶対に絵を描くな。ええ、そうだよ、彼が1番初めの印象主義者だ。印象主義ってなんですか、視覚混合ですよ。画布の上では色調(トン)が分離していて、網膜のなかで再現される。ぼくたちはそこを通過しなければならなかった。モネの断崖は非凡な連作として世に残るだろうし、彼の絵の100枚かそのくらいは、そうだ。サロンで彼の《夏》を落選させたのだと思うと!審査員どもは皆、豚だ。今に見てなさい、彼はルーヴルに入りますよ、コンスタブルやターナーの横に並んで。いや、もっとだ、彼はもっと偉大なのだ。地球の虹色の輝きを描いた。水を描いた。覚えていますか、一緒に見たあのルーアンのカテドラルのいくつもの作品。あのとき君が、まるでジョフロワみたいに、これが、ルナンや最新の原子論の仮説や生物学的な流動や万物の運動などに相当する絵画である、なんて口ごもりながら言ってたのは、なんですか。君がそう思いたきゃね。でも、万物が逃げ去ってゆくなかで、これらのモネの絵のなかに今度は、骨組とか、頑健さを入れていかなければならないんです……ああ、あの人が絵を描いているのを君が見たらねえ。太陽が沈むとき、それをさまざまな透明さにいたるところまで追ってゆける唯一の眼、唯一の手です。それに、気に入った麦わらの山はぽんと買う羽振りのよさがあります。ちょうどいい畑の一角があれば、彼は買うのです。しかも邪魔されないように背の高い下男と犬に番をさせて。私にもそれが要るよ。そして弟子もだ。印象主義のひとつの伝統をつくる、その特徴というものを引き出すこと。流派?いや違う、ひとつの伝統だ。実物を写生してのプッサンだ。(243~245頁) ■セザンヌ この間の晩、エックスに帰る途中で、私たちはカントの話をしましたね。私は君の観点に立ってみようとした。感性のある木々?木とわれわれとの間に共通の何があるのだろうか。私に見えるような松と、実際に存しているところの松との間には、何があるか。ちょっと、これを私が描いたらどうだろう……そうすれば、われわれの目について、絵(タブロー)を与えてくれる自然のあの一部分を実現(レアリゼ)させたことになるんではなかろうか?感性をそなえた木々!……そしてその絵のなかには、範疇のあらゆる表や、君が口にする本体(ヌーメン)だの、現象だのよりはずっと万人に入ってゆきやすいひとつの外観の哲学が、存在するのではないだろうかね。それを見て、自分に対して、人間に対して、万物の相対性を感じることになるだろう。私は、こう自分に言い聞かせた。空間と時間が、色彩の感性の形相となるように描いてみたい。なぜかといえば、私はときどき、いろいろの色彩を、大きな本体的本質として、生きた観念として、純粋理性の存在者たちとして、想像することがあるのだよ。ぼくたちが通信できる相手のように。自然は表面にはない。奥行きにある。いろいろの色彩は、表面にあっての、この奥行きの表現である。世界の根から立ちのぼってくる。色彩は世界の生命だ、諸観念の生命だ。素描(デッサン)のほうは抽象なるものにつきる。だから、決して色と分離してはいけない。言葉ぬきに、純粋な数字、純粋記号(シンボル)でものを考えようとするみたいだ。素描はひとつの代数、ひとつの記述だ。生命がやってきてそれに、みなぎった瞬間、感覚を意味した瞬間、色がつくのだ。色の円熟はつねに素描の円熟に相応している。ほんとうを言えば、自然のなかにひとつだって素描されたものがあるんだったら、見せてもらいたいね。どこにだ、どこにだ。人間が真っすぐに、図に描いたように建てるもの、壁や家なんかは、時や自然がめちゃくちゃにするじゃありませんか。自然は直線を憎悪する。技師どもはくそくらえだ!われわれは、道路検査官ではないんだ。あの連中は色彩なんぞ気にしてはいないよ。それなのに私は……そう、そう、感覚がすべての基盤にある。(247~249頁) ■彼は読みあげる。 セザンヌ 「光を与える色彩的な諸感覚(サンサシオン・コロラント)は、いくつもの抽象の原因であるが、接触点が細かく、繊細なとき、それらの抽象では画布をうめることもできないし、オブジェの境界を定めつくすこともできない。そういうことのために、私の像(イマージュ)あるいは絵が不完全ということになる。また一方で、面(プラン)が互いに重なり合う、そのために輪郭を黒い線で囲う新印象主義的な嵌め込み細工となるが、これは全力をあげて一掃しなければならない欠点である。ところで、自然が相談相手となって、その目標に達するいろいろな手段を与えてくれている」 ガスケ で、それは? セザンヌ 色彩のなかの面(プラン)だ、面だよ!諸面の魂が融合する色鮮やかな場。プリズムの熱に到達する。太陽において諸面が出会う。私はパレットの上の色調(トン)をつかって面を作っている、おわかりですか……面を見なきゃいけません……はっきりと……しかしそれらを配置して、混ぜるのです。回転するものであると同時に、中間にふさがるものでなければならない。容積(ヴォリューム)だけが大事なのだ。よい絵を描くためには、物と物の間に空気が要る。よい思考をするためには、観念と観念の間に感覚が要るのと同じだ。瀝青(ビチューム)は味気ない。論理は先行きが知れている。もう面というものなどのない地下室で絵が描かれている。もはや直感がなんのはたらきもしないような3段論法なんかで身を縛っているんだ。それでは下絵(カルトン)だよ。ふくれあがってくる必要がある。目が少しでもひるんだら、おしまいだ。私の場合、大変なのは、目が幹や土塊にくっついてしまうことだよ。そこから目を引き離すのに苦しむんだよ、あまりにも何かに引きとめられるから。(250~251頁) ■セザンヌ 写す……写す、そうだ……それしかないのだ。でも資質のある人々は、どうなんだ!絵画は自分の内輪のものはちゃんと見分けますよ。私はね、私は自然のなかに没入したい、自然と一緒、自然のように再び生えてきたい、岩の頑固な色調、山の合理的な強情、空気の流動性、太陽の熱が自分にほしいのだ。ひとつの緑の色のなかに、私の頭脳全体が、木の樹液の流れと一体になって流れ出すであろう。われわれの前には、光と愛の大きな存在が立ちはだかっている、よろよろする宇宙があり、物たちにはためらいがある。私はそれらの物たちのオリュンポス山になってやるのだ。物たちの神になってやるんだ。天におわします理想が私の内で結婚なさいます。ちょっと聞いて下さい。色彩は、観念と神の煌々たる肉体です。玄義の透明、法則の虹色の輝き。色彩の真珠のような光沢ある笑みが、気を失った世界の死顔に生気を再び与えている。昨日はどこにある?私の見た平野や山はどこだ?この絵の中に、この色彩のなかにあるのだ。君のやっている詩のなかよりは、ぼくたちの絵のなかのほうに、世界の認識が永久に存続する。それは、より多くの物質化した感覚がそこには参加しているからだ。絵は「人間」の歩んだ段階の道しるべとなっている。洞窟の壁面の馴鹿(となかい)に始まって、豚肉でもうけている業者たちの家の壁にかけられるモネの断崖にいたるまで、人間のたどった道がずっと追ってゆけるよ……エジプトの地下室にいっぱいいる狩人や漁師、ポンペイの数々の甘い誘いかけ、ピサやシエナのフレスコ画、ヴェロネーゼやルーベンスの神話を題材にした絵、そういうものからひとつの証言が浮かび上がってきます。ひとつの精神が汲みとれます。それも、どこにおいても同一の精神であり、客観化された記憶なのです。彼の見ているもののなかに具体化された人間の、絵にされた記憶です。われわれは皆同じ一人の人間です。色のついたこの鎖に1個の輪を私が足してゆくことになります。私の空色の輪。真の自然がもたらしてくれるものとか、知性のなかにもう1度入り込んでゆく風景、風景の実証主義です、文明人のわれわれが、(フランク人の)サリ族の群が昔渡っていったこの風景、そういうひとつの風景を目の前にして、ダーウィンやショーペンハウアーについて雑談しながら感じること。最終の段階に来て疲れ果てたわれわれの五感には、自然の涅槃というインドから来たなぐさめがあります。雲の劇的な様子の下で、生えてくる小麦の平和……近づきがたい、目に見えぬ神なる太陽!……たくさんの体系(シシテム)、ひとつの体系……そうだ、ひとつ必要なんだ。ところがその体系が決まったら、今度は写生だ。すでにできたシステムがあれば、それを忘れて、写すのだ。巨匠たちはそこなんですよ。画家たちはそこなんだ。ヴェネツィア派の人たち。ヴェネツィアで君は見ましたか、あの巨大なティントレット、あそこには陸と海と、水陸の地球がわれわれの頭上にぶら下がっていて、移動する地平線があり、奥行きと海の遠景があり、飛翔する肉体があり、巨大な丸みが、地球儀が、ほうり出された惑星が、落下して天空をころげゆく。彼の時代にですよ!今のわれわれは彼を予言していたんだ。われわれを苛む宇宙の執念が彼にすでにあった。ところがね、私はこう確信しているんだよ、彼は絵を描きながら、まかされた天井のことや、容積(ヴォリューム)の平衡をとることや、色価を重ねてゆくこと――上手に描くこと――のほかにはきっと一切何も考えなかった。ところがね、上手に描くということは、自分自身にかかわらず、自分の時代を、その最も先端を走るものにおいて表現することであって、世界の、人間の階位の、1番上に立つことだ。言葉に、色に、意味がある。絵描きが、絵の文法を知った上で、そのセンテンスをこわさずに過剰なほど練って、目に映るものを敷き写すと、欲しようが欲しまいが、彼がその画布の上で翻訳するものは、彼の時代の最も情報をつかんでいた頭脳が構想したものや、構想しつつあるものなのだ。ジォットはダンテに対応し、ティントレットはシェークスピアに、プッサンはデカルトに、ドラクロワは、誰にだろうか。馬鹿げているのは、既製の神話体系や物体(オブジェ)についての出来あがった考えをもっていること、現実のかわりにそれを模写することなのだ。この大地よりもあれら想像の産物を。にせ絵描きは、この木やあなたの顔やこの犬が見えないのだ、一般的な木、顔、犬しか見えない。彼らには何も見えていない。同じであるものは絶対にない。連中は、固定した、霧のかかったような一種のタイプが彼らの目――ところで目があるんだろうかね――とモデルにしているものとの間にいつも浮いていて、それをたらい回ししている。そうだ、大きな法則や原理が必要だ、それに気がつくと、知的な大きな動揺や感情の状態におちいるけれども、その後は純情に自然を写生する必要がある。私は頭脳の人間ですよ。思う存分そう受けとっていいですよ。しかし私は動物のような人間でもあります。私は哲学論をぶったり、雑談したり、君と話をしたりする。絵具を前にして、筆を握ると、私は絵描き、びりっけつの絵描き、一人の幼児でしかなくなるんだ。精魂かたむけて汗水たらす。もうなんにも知らないんだ。私は絵を描いている。規則に従っているからといって、自分を正直者と思い込んでいる人たちに少し似かよっている。正直な人間は自分の規則が血のなかを流れている。天才は、自分の規則に従って生きてゆくなかに作られるのだ。そうだ、天才は他人について知らない事は何ひとつないのではありながら、自分自身の方法を編み出してゆくものだ。 ガスケ 方法ですか? セザンヌ そう、いつも同じものだ。真実。天才は方法を発見するんだけれども、つきつめれば、それはいつも同じものなのだ。私の方法は、言ってみれば、ほかに持ったためしはありませんけれども、想像力を嫌うことですよ。私は馬鹿に徹したい。私の方法、私の規準、それは写実主義(レアリスム)だ。だけど、その辺はよく理解して下さい。そうとは知らずに高貴なものに満ちたひとつのレアリスムです。現実の英雄主義。クールベ、フローベール。それよりはさらに優れて。私はロマン主義の徒ではない。世界の無限の広がり、世界の急流がほんの一寸足らずの物質のなかに。それが不可能だとお考えですか。血の色づいた永遠。ルーベンス。(252~257頁) ■セザンヌ 絵描きにとって、文学に走ってしまうことが何よりも危険なんですよ。その罠にかかると、お陀仏だ。私はそのことは身をもって知っています。ブルードンがクールベに及ぼした害、それと同じ害をゾラが私に及ぼすことだってあり得たんです。ボードレールだけですよ、まともにドラクロワやコンスタンタン・ギースのことを語ったのは。フローベールが手紙のなかで、自分が技術(テクニック)に通じていないような芸術の事は語るまいときつく自分に禁じているのですが、私はそれがたいへん気に入っている。彼らしいところが出ているよ……私は絵描きに無知であってほしいわけでは決してないんだ。逆だ。偉大な時代には、画家たちはすべてに通じていた。古い時代は、芸術家たちが群衆にものを教える先生だった。ほら、あそこにノートル・ダム寺院が見えていますね。天地創造や世界の歴史、宗教の教義、聖者の美徳と生涯、諸工芸、その頃に知られていたことはすべてノートル・ダム寺院の門やステンドグラスに教示されている。フランスじゅうのカテドラルでもそうだがね。中世は目を通して信仰を学んでいたんだ、ヴィヨンの母親みたいに……。 (中略)私は自分を古典主義者だと称している。そうでありたい。ところがそれが退屈だ。ヴェルサイユ宮殿は退屈だ、あそこの正方形の中庭も退屈だ。コンコルド広場だけだ、あれは美しい。生命!……生命!……それでいた、こういうことが全部いかに複雑かごらんなさい。生命やレアリスムは、プリミティフの延長のえのなかよりは、15世紀、16世紀にあるのだ。私はプリミティフが嫌いだ、ジォットのことはよく知らない。一度この目で見なくてはと思っている。私はルーベンス、プッサンとヴェネツィア派の人たちだけが好きだ……よく聞いて下さいね。十字架を使って神を意味させるほうが、ひとつの顔の表情で意味させるより楽なんです。(263~265頁) ■セザンヌ ちょっと、あれをごらんなさい……《サレトラケーの勝利の女神》。これはひとつの観念、総動員された国民、ひとつの国民の生活のなかの英雄的な瞬間だけれども、布はぴったり身体に付き、翼ははばたいていて、乳房はふくらもうとしている。頭部を見なくったって、私には視線が想像できるよ、なぜかといえば、脚や腰や身体全体をむち打って、駆けめぐって、歌っている血潮は全部、急流のように脳を通りぬけて、ギリシア全土の動きなのだ。頭部がはずれたとき、大理石からきっと血が出たに違いないよ……それに引きかえ、上の階では、死刑執行人の刃で、あの小さな殉教者たちの首を断ち落としてごらんなさい。鮮紅色(ヴァーミリオン)がちょっぴり垂れてくる、そんなのが血ですか……あの人たちは、もう血の気もぬけて神のなかにはばたいて行ってしまったのだ。魂は描けるものではありませんよ。それに見てごらんなさい、《勝利の女神》の翼は目にもとまらない、私の目にはもうとまらないんだ。あまりにも自然に見えるんで、気にならないんだ。肉体は、それがなくても戦勝に喜び勇んで飛び立ってゆける。自分の勢いをちゃんと持っている……ところが、キリストや聖母様や聖者たちのまわりにある後光なんかは、あれしか目につかない。あれが大きく構えている。あれが私には邪魔だ。どうしようもないでしょ。魂は描けるものじゃありません。肉体は描けます、そして肉体がうまく描けていると、畜生!魂がその肉体にそなわっていた場合には、魂が四方から輝いて、透けて見える。(267~268頁) ■セザンヌ アングルだって、まったくだ、血のかけがない。彼は素描(デッサン)をしている。プリミティフたちは素描をしていた。色を塗って、ミサ典書の塗り絵を大規模にやっていたんだ。絵画、いわゆる絵画というものは、ヴェネツィア派とともに初めて生まれる。テーヌは、フィレンツェでは絵描きは初めの頃、金の細工師だったと語っています。彼らは素描をした。アングルもそうだ……ああ、それは美しいですよ、アングル、ラファエロ、その他もろもろ。私だって人並みに感じることができます。その気になれば、私は線の快楽を味わいますよ。でもそこにはひとつの障害がある。ホルバインやクルーエあるいはアングルには、線しかない。でね、それじゃ足りません。たいへん美しいけど、それでは足りない。この《泉》を見てごらん……純粋だし、あまいし、柔らかい、だけどプラトニックなのだ。1枚の図像であって、空中のなかで回転していない。しめった、あるいはしめっているべきこの肉付きの大理石と、ボール紙でできたような岩との間に、岩石中の湿気のやりとりがまったく無なのだ。周囲の浸透がどこにあるんだ?しかもあの女は泉なんだから、水から、岩から、葉のなかから出てこなくちゃならない、なのに、それにくっついてしまっている。理想の処女を描こうとするあまり、彼は、肉体をまったく描かずにすませた。彼にそれが不可能だったわけでは決してないんだがね。彼の描いた肖像画や、私の好きな《黄金時代》を思い出したまえ。あれは自分のシステムに徹底した精神のせいだ。システムも精神も間違っている。ダヴィッドは絵画を殺した。彼らは「紋切型(ポンシフ)」を取り入れた。理想の足、理想の手、完全な顔や腹部、至高の存在者を彼らは描こうとしたんだ。特色(カラクテール)を廃止したんだ。偉大な画家をなすのはね、彼の手に触れたすべてのものに与えられる特色なのだ、突出というか、動きというか、情熱というか、情熱的な心の静けさというものもありますからね。彼らはそれがこわい、むしろそれについて考えたみたことがないんだ。彼らの時代のあの情熱や嵐や社会的な暴力に対する反動かも知れない。(269~271ページ) ■セザンヌ 奇跡が起きている、水は葡萄酒に変えられて、世界は絵画に変えられた。絵画の真実のなかを泳いでいるわけだ。よっぱらっているのだ。幸せなのだ。私の場合、色彩の風に吹き飛ばされるみたいで、顔にもろに受ける音楽みたいで、血のなかを流れている私の技巧(メチエ)そのものだ……ああ、あいつらは、恐るべき技巧を持っていたよ。われわれはそれに引きかえ何物でもないんだ、古ぼけた虫けらだよ、よく聞いておきなさい、何物でもないのだ。理解するということすらわれわれにはできなくなっている……昔は、私はこういうものに火をつけたいと思ったんだからね。発明したい、個性を発揮したいという執念からだ……ものを知らないと、知っている人たちが邪魔しているように思ってしまうんだ……ところがその逆で、付き合ってみれば、場所をふさぐどころかそういう人たちは手を取ってくれて、親切に隣りに座らせてくれて、つまらぬ話をもどかしくしゃべらせてくれたんだよ。(278~279頁) ■セザンヌ 私が残念に思っているのは、君の話によく出てくる、君の信じているあの若い人たち皆がだね、イタリアを駆けめぐったり、ここ〔ルーヴル〕で一日じゅう過すというようなことをしないことだ。後から、自然のど真ん中に飛び込んでゆくにしてもだ。すべては、ことに芸術ではそうだけど、自然に触れて発展し、応用された理論なのだ。私の身にふりかかったようなことがこの若い人たちにあって欲しくないね。わかっています、わかっていますよ、公のサロンがいつまでもあんなに劣っているのは、理由がはっきりしている。彼らはあくまでも多かれ少なかれ、いろんな方式を活用しているにすぎないんだ。画家にとっては、感覚がすべての基礎にある。これは飽きずに言い続けるつもりだ。いろいろの方式をほめたてるのではないんだ。個人的な感情や、観察や、個性をもっとたくさん用いたほうがよいだろう。ところが、ここがむずかしいところなのだ!理論は常に簡単だ。考えていることを証明する段になって、手ごわい障害物がでてくる。ここでは、結局、画家がものを考えることを覚えるのだと、私は思っている。自然に面して、画家はものを見ることを覚える。自分以前に代々の画家が続いてきたのに、突然きのこみたいに芽生えてきたと思い込んでしまうのは、こっけいだよ。これらのすべての仕事をなぜ利用しないのか、このすさまじい貢献をなぜおろそかにするのか。そうだ、ルーヴルはわれわれが読み方を習う本なのだよ。われわれは、だからといって、偉大な先達のきれいな定式(フォルミュール)だけを暗記して喜んでいてはならない。ドラクロワの言葉だがね、われわれは、すべての語が見つかる辞書を見てきたのだ。さあ外に出よう。美しい自然を学習しよう、その精神を明るみに出すように努力してみよう、自分個人の資質(タンペラマン)に合った表現をするように心がけよう。しかも時間と熟考はだんだんものの見方を変化させるんだ。そしてしまいにには、われわれに理解できてくる。神様のおぼしめしがあれば、われわれや、君の友人たちにも、これのような大仕掛けのものをでっち上げる器量が出てくるかもしれない……それにこっちの虹に対して、あっちのほうの銀色の調和を対立させることができるようになるかもしれない。(282~283頁) ■セザンヌ 絵が好きな人なら、こういう絵が好きのはずだ。絵の横に文学を求めたり、逸話や主題に興味津々となったりするようでは、これらの絵は好きになれない……一枚の絵(タブロー)は何をも再現していないのだ、まず色彩だけを再現しなければならないのだ……私は大嫌いさ、もろもろの物語だの、心理学だのそれのまつわるベラダン調のうるさったらしい事柄は。まったく、それはちゃんと絵におさまっているのだ、絵描きたちは阿呆じゃないんだ、しかしだね、それを目で、そうだ、目でだ、見るべきなのだ。絵描きはそれ以外のことを求めたわけではない。絵描きの心理学といえば、それは二つの色調の出会いなんだ。絵描きの感動はそこにある。それなのだ、絵描きの物語、絵描きの真実、絵描きの深さは。だって、そうだろう、絵描きなんだもの!(285頁) ■セザンヌ 地上の幸せの理想……それは美しい定式(フォルミュール)を持つことだ。(298頁) ■セザンヌ そう、私が言いたいのは、芸術家でごく限られた個人(アンディヴィデュ)の数だけを対象にしているということだ。しかも、芸術家は生前、結局、つねに人を多く知りすぎている。自分の隅っこで、自分のモチーフ、自分の思案、自分のモデルと一緒に暮らしてゆくのでなければならない。特徴を出すこと……そして、これをよく聞いておいて下さい、芸術家は、いろいろな特徴のかしこい観察の上に成り立つのではない意見は、軽視しなければならない。文学者くずれの精神を恐れなくてはならないんだ……アンリ、君の倅(せがれ)は私のことをわかっていてくれる……そういう精神は、あまりにもしょっちゅう、絵描きを自然の具体的な勉強という本道からはずし、雲をつかむような空論の中にあまりにも長い間、迷わせておくんだ。これは何百回と口にしてきたことだ……ああ、批評家たち!あのユイスマンのような連中たち……私はつきまとってくる連中たち皆に、いつも手紙で書いてやりたいんだ。君たちの持ち合せていないもので、35年前からそれに向って、私が努力しているものがある、それはメチエの根本をなす次の三つのものだ、良心、真心、従順さ。思考を前にしての良心、自分自身に向っての真心、対象を前にしての従順さ……対象を前にしての完全なる従順さ、これはサント=ブーヴがゴーティエについて書いた『月曜評論』のうちの一篇の中でうまく見つけた表現だよ……アンリ、この15分ばかりは、君が対象だ……モデルと表現方法とをおさえていれば、目の前にあるものを描いて、筋道通りに努力しさえすればいいのだ。誰のことをも信じずに仕事をする、力をつけてゆく。あとのことはくだらん……。(333~335頁) ■セザンヌ 感情を原理としていない芸術は芸術でない……でも感情、それはねえ、原理であり、始めと終わりなのです。真ん中には技巧(メチエ)、客観的なもの、実地とがあるんだ……アンリ、君とぼくの間に、君の個性とぼくの個性との間には、世界がある、太陽があるのだ……そこを通りすぎてゆくもの……ぼくたちが共通に見ているもの……ぼくたちの着物、ぼくたちの肉付き、光の反射……そういうものの中に材料を求めて猛勉強しなければならない……その部分のなかで、ちょっとでも筆が横にそれると、万事が曲がってしまう。ぼくが、内面だけで感動していると、目を変なふうに描いてしまう……君の視線のまわりに、その中で交わっている小さなブルーや茶色の無限な網目をちゃんと織り込んでゆけば、ぼくの画布の上でも君の視線のとおりの視線をぼくは作れるのだ……タッチを一つまた一つまた一つ……そしてぼくに熱が入っていなくて、学校でやるみたいに、素描をしたり塗ったりしたら、何も見えなくなる。(338頁) ■ガスケ父 昨日3枚目の札(トランプ)を取るときまで手に置いといた切り札のことを考えていたんだ……。 セザンヌ ほらごらんなさい……レブラントやルーベンスやティツィアーノは崇高な妥協をして、一気に自分たちの全人格と、目の前にあるこの肉体とを、融合するすべを知っていた。肉に自分たちの情熱を吹き込み、ほかの人々の顔に似せながら自らの夢や悲しみに栄光を与えた……全くそうなんだ……私にはそれができない……。 ガスケ それは、あなたが他の人に愛情を傾けすぎるからです……。 セザンヌ それは真実に従いたいからだ……フローベールみたいに……すべてのものの真実をつかみとる……自分をそれに従わせる……。 ガスケ それは不可能かもしれません。 セザンヌ ひじょうにむつかしい、君のお父さんに一部私がすり替われば、私の目指す全体像ができる……それに影や光の部分を参考に使う……私は現実にそうやって近づくだろう、現実がそっくりそのまま欲しいのだ……そうでないと、私も私の流儀で、美術学校に対して非難していることをやってしまう破目になる頭の中に既製の典型があり、真実をそれから敷き写すことになる……そうではなく、私は自分自身を真実から敷き写していきたい。私ってなんだろうか……その魂の内まで真実に達する、あるがままの真実を表現する。それで大失敗に終わったってしょうがないじゃないか。ためすだけはためしたことになる。一つの道を開いたことになる。もっと頑丈な、もっと微妙な人たちがやってくるだろう……モネが風景についてしたことを人体像できっとするだろう……その人たちは写真的に描くだろう……でも私の話によくついてきて下さいね、その人たちは魂や性格やひとりの人間というものを写真にとるように描くだろう……そしてまた他の人たちがそういう印象の中から大芸術を、色彩のある心理学を、人間のひとつの哲学を引き出すに違いない……。(340~341頁) ■彼は本棚に一冊の本を取りにゆく、読みふるしたバルザックだ、彼は『あら皮』をぱらぱらめくる。 セザンヌ そうだ、君たちには、比喩や比較が使える、もっともだね、しじゅう、「……のように」をふやして使うと、ぼくたちの場合、素描が見えすぎているのと同じだ。人のことをあまりしつこく扱っては駄目だ……でもぼくたちには、ぼくたちの色調、目に見えるものしかない……ほら……バルザックが、支度された食卓を語るとき、彼なりに静物画を作っている。でもヴェロネーゼ調だ……1枚のテーブル掛け……。 彼は読みあげる。 セザンヌ 「……降ったばかりの雪の層のように白く、その上には、小さな黄金色のパンを王冠の形に乗せた食器が、対称的に高く積み上げられていた」若い頃はずっと、私は、一面に拡がる新雪、これが描きたかったんだ。今では、「小さな黄金色のパン」と「食器が高く積み上げられていた」それしか描こうとしてはならないことがわかった。「王冠の形に乗せた」というのを私が描くと、それは駄目なんだ……おわかりですか。しかも私が、実物どおりに食器やパンに均衡やニュアンスを与えれば、王冠や雪やすべての震えがちゃんとそこに表れるものなんですよ……画家には2つのものがある、目と頭脳です。その2つは互いに助け合うべきです。その相互発展をめざして積極的に働くべきです、でもそれは画家としてだ。目は、自然を見ることによって。頭脳は、表現のいろいろの方法を提供してくれる、組織化された感覚の論理によって。(352~353頁) 2010年2月11日 |
『セザンヌ』ガスケ著 與謝野文子訳 岩波文庫
投稿日:
執筆者:okanokouseki