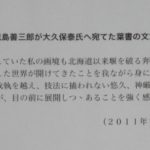『道元禅師語録』鏡島元隆著 講談社学術文庫
■あらゆる既成の枠組みを超え、勇猛果敢であり、人情俗情を超えた、家風峻厳な宗師家(しゅうしけ)でなければ、どうして修行僧の癒(いや)すことのできない病弊をなおし、枝づるの根のようにはびこった誤った知見の根を断ち切ることができようか。昔はそのような宗師家が少なくなかったが、今日においては誰があろうか。このような澆季(ぎょうき)の世にあって、太白山如浄禅師(たいはくざんにょじょうぜんじ)は奮然として一たび出でて、独り宗風を振ったのである。諸方の宗師家(しゅうしけ)はみなこれを忌み遠ざけ、修行僧はこれを畏(おそ)れ避けて、近づくものがなかった。しかるに日本の道元禅師は、遠く海を渡ってこの国に来り、ただちに如浄禅師の室に投じ、心の塵である煩悩を除き去って一生参学の大事を了えられた。その後、故国へ帰って、思慮を傾け尽くして仏法の精髄をあらわし示された。いま、禅師の弟子の義尹禅人(ぎいんぜんにん)が、禅師が説かれたその言葉を拾い集めて、自分のもとに来て、序文を作るよう求めるのである。そこで、自分はこのもののために言おう、「君の師は縦横無尽に説法されたが、その説法は一言も舌の先を動かして生まれたものではない。だからして、驢馬(ろば)の鞍(くら)をみて、これをおやじの下あごと見るのが誤りであるように、残された言葉の上に君の師の仏法があると思ってはならぬぞ」 景定5年11月1日 無外義遠(むがいぎおん)書す(16~17頁)
〔付記〕 禅僧が号と諱(いみな)を称するようになったのは、南宋のころからであって、世俗化事象である。本録に序・跋を撰した無外義遠、退耕徳寧、虚(き)堂智愚についていえば、無外、退耕、虚堂は号であって、義遠、徳寧、智愚は諱である。しかし、天童如浄、永平道元においては天童、永平は寺号であって、いわゆるの号ではない。如浄や道元が号を称しなかったのは、彼らの反俗精神を示すものである。如浄が長翁如浄、道元が希玄道元と呼ばれることがあるが、長翁は如浄のニックネームであり、希玄は晩年の道元の別称であるから、いずれも号ではない。(18頁)
■〔訳文〕上堂し説法された。山僧(わたし)は、諸方の叢林(そうりん)をあまり多く経たわけではないが、ただはからずも、先師(じ)天童如浄禅師にお目にかかり、その場で、眼は横、鼻はまっすぐであることがわかって、もはや天童如浄禅師にはだまされなくなった。そこで、何も携えずに故郷に還ってきた。だからして、山僧(わたし)には、いささかも仏法はない。ただ、なんのはからいもなく自分の思うままに、時を過しているだけだ。看よ。毎朝毎朝朝日は東に昇るし、毎夜毎よ月は西に沈む。雲がかれあがると、山肌が現われ、雨が通り過ぎると、あたりの山々は低い姿を現わす。結局、どうだというのだ。しばらくしていうには、3年ごとに閏年(うるうどし)がⅠ回やってくるし、鶏は五更(ごこう、午前4時)になると時を告げて鳴く。大衆諸君。長いあいだ立たせてご苦労であった。といって、法堂(はっとう)の座を下りた。〈謝詞(しゃし)は記録しない。〉(20~21頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。仏法とは、身や心についての執(とら)われがすっぽりなくなることだ。対境がすべて執著(しゅうちゃく)の相手でなくなることだ。ここにいたれば、悟りもないが、どこにも迷いのつけようもない。いま、この座に誰か江南の客がいるか。おれば、鷓鴣(しゃこ)(注)の声ならぬ声を聞くがよい。(28頁)
注;鷓鴣――鳩の一種。江南、揚子江の南に鳴き、その声を聞けば江南の人は故郷を憶い出すという。
〔付記〕 身心脱落は、『如浄語録』では心塵(じん)脱落と記され、本録の無外義遠の序にも「心塵(じん)脱落の処(ところ)に向(おい)て生涯を喪尽(そうじん)す」と述べられている。そこで、道元は如浄の心塵脱落を身心脱落と聞きちがえたのではないか、という説が唱えられたことがある。しかし、中国語では心塵脱落と身心脱落とは発音が異なるというから、道元が聞きちがえたはずはない。心塵脱落と身心脱落とは、身心不二の立場からしては結局、同じことに帰するが、心塵脱落は心を清めることに重点がおかれ、身心脱落は身を整えることに重点がおかれて、重点の異なるものがある。それゆえに、如浄におけるが、道元によって身心脱落へと深化されたとみるべきである。(28~29頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。釈迦牟尼な言われた。「暁の明星が現われた時、自分と大地のありとあらゆる衆生(いきもの)は同時に悟りを得た」と。さて、ここで言ってみよ、釈迦牟尼が悟った真理とは、一体、どのような真理であるか……。もし、人がこれを会得すれば、釈迦牟尼は慚愧のために身のおきどころがあるまい。どうしてそうなのか、早く言ってみよ、早く、早く。悟ってみれば、仏法の真理など、どこにもないのに、これをあるかのように、吹聴した釈迦牟尼は、恥を知らぬもの。(32頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。端的に言えば、本来無一物(もつ)である。が、本来無一物とは全世界が隠すところなく現われていることであることを誰が知ろう。といって法座を下りた。(33頁)
■〔訳文〕上堂して、公案をとり挙げて言われた。東(とう)印度の国王が、般若多羅尊者(注)を請(しょう)してお斎(とき)を供養した折、国王が質問して言うには、「ほかの人びとは、みな供養に応えてお経を読んだのに、尊者(あなた)はどうしてお経を読んでくれないのですか」と。尊者はこれに答えて言った。「貧道(わたし)は、出る息はもろもろのものの世界に吐かないし、入る息は体のどこにも吸いこまない、そのような天地いっぱいの経をいつも百千万億巻、読んでいるんです」と。師はこの公案をとり挙げおわっていうには、尊者以上に、更に一段の道理を説いてみよ、と。(35頁)
注;般若多羅――禅宗第27祖とされ、菩提達磨の師。
〔付記〕 東(とう)印度の国王と般若多羅の問答を通して、経典を読むことの真実の意味は、天地自然の道理を感得するにあることを示す。(36頁)
■〔訳文〕上堂して、公案をとり上げて言われた。昔、迦葉(かしょう)尊者(注1)が壁に塗る土を捏ねていた時、ひとりの沙弥(しゃみ)が質問した。「尊者は何でご自分でなされるのですか」。尊者は言われた。「わたしがもししなければ、誰がわたしのためにやってくれよう」。師がこれについて言うには、尊者の心は12月の扇のようなものだ(注2)。何のためのものでない。身は寒谷の雲のようなものだ。何の執(とら)われもない。もし、尊者の「我が為す」ことがわかれば、一切の人の為すことがわかる。尊者の行為は、「我」とか「誰」とかの2見にわたらないものであって、その行為は鉄壁のように切り立って、外から窺いようもない境地である。(38頁)
注1;迦葉尊者――摩訶迦葉は釈迦牟尼の弟子。禅宗の伝統だい第1祖。
注2;12月の扇云々――この季節には扇は風を起こす要がない、めざす目的のないことのたとえ。また寒い谷には雲は雨を呼ばない、寄りつくもののないことのたとえ。
〔付記〕 この沙弥と摩訶迦葉の問答の背景には、一般仏教と禅宗の勤労に対する考え方のちがいがある。仏教の伝統では、僧侶自らは生産・勤労には従事しないものとされた。勤労することは、これを禁止した釈尊の戒律に触れるからである。したがって、中国の仏教教団では、勤労は沙弥が辺り、大僧(だいそう、一人前の僧)がこれに当たることはなかった。しかし、禅宗は百丈の有名な「1日作(な)さざれば、1日食(くら)わず」の言葉が示すように、敢(あえ)て戒律を破って、勤労を僧団の規則にとり入れたのである。本録はこの1沙弥と摩訶迦葉の問答には、このような禅宗の勤労観が窺える。(39頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。もし人があって、1句を言い得て全世界の無限の量をなくして1真実に帰せしめても、それはなお春の夜の夢の中で吉凶を説くようなもので、何の役にも立たない。また、もし人があって、1句を言い得て、Ⅰ微塵を破ってその中から無限の真理を説く経をとり出しても、それはなお紅白粉(おしろい)で美人を塗りたくるようなもので、余計なことである。そんなことよりも、その場でただちに夢でない真実の悟りの世界を照見しおわれば、全世界といっても大きくはなく、1微塵と言っても小さくないことがわかる。さて、そのように上に述べた両句がともに真実でないとき、真実のⅠ句は何と言ったものだろうか。それは、井戸のひき蛙が天の月を呑み尽くし、天辺の月が雲の上で自由に眠ると言ったらよい。(41頁)
〔付記〕 真実の1句は、法界を1微塵に帰せしめした言葉でもなく、1微塵を法界に拡げた言葉でもなく、法界即Ⅰ微塵、Ⅰ微塵即法界を言い表わした言葉でなければならぬとして、それを言い表わした言葉として、「井底(せいてい)の蝦蟇、月を呑却(どんきゃく)し、天辺の玉兔(ぎょくと)、自(おのずか)ら雲に眠る」の語を示す。(42頁)
■〔付記〕 高尚な理論も、平俗な言説も駄目だが、かといって他人の口真似でも困る。心底、自分の肺腑から出た、自分の言葉を言ってみよ。(45頁)
■〔訳文〕上堂。僧が「古仏心とは何でしょうか」と問うと、師は、春がきて鶯が鳴くのは、どこでも同じである。(古仏心とは、どこにも遍満している仏のいのちである)と答えた。「では、本来の人とはなんでしょうか」と問うと、師は、大脳が眼を覆いかくした異相の男である、(見るはたらき、聞くはたらきがすべて般若の智慧としてはたらく男である)と答えた。これをさらに総括して師は言われた。古仏心・本来の人について、あれこれと問答するのは、糞や小便を撒き散らすように、古仏心・本来の人を汚すものだ。問答を交わさなくても、激しい雷がとどろき鳴りわたれば、耳をふさぐことができないように、古仏心・本来の人は隠しようがない歴然たる事実だ。この古仏心・本来の人を会得すれば、十方大地はひとしくシ沈み、一切虚空はほとばしり裂ける、悟りの世界が開ける。この悟りは、外から入るものでもなく、内から出てゆくものでもなく、一槌(いっつい)を痛く下すところに、万事落着するのである。だが、悟りの世界が開けても、従来通り鼻は大きな顔に垂れ、眼は両眼とも黒々としていることに変わりはねい。(45~46頁)
■〔訳文〕仏を外に求めて一歩を進めるときは、他国をさまよい歩くを免れない。これに反し、仏を内に求めて1歩を退くときは、祖父の田園(本来の自己)にとらわれるのを免れない。であれば、外に求めて進みもせず、内に求めて退きもしないとき、そこに解脱の道があるであろうか。そこにこそ解脱の道がある。しばらくして云うには、仏というのは方便をもって垢衣(くえ)をかけて泥にまみれるものをいうのであるが、天子の立派な衣服をまとうものは誰としよう。これもまた仏である。(50頁)
〔付記〕 仏は外に求めるも誤まり、内に求めるも誤まり、2見を超えて直下に承当するものが仏であると示す。(51頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。人びとはすべて天をも衝(つ)く志気がなければならぬ。如来がなされた跡をもとめてはならない、と言って法座を降りた。(53~54頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。仏法を会得したものは、何ものにも依存せず、一切の執(とら)われを脱して完全に真実である。かれは、あらゆるものと渾然と1つでありながら、ものとははっきり別であり、しっかりと揺るぎない境地に立ちながら、いきいきと動いている。そのさまは、月が水に映っても月自体は水に跡を留めないようなものであり、風が空を吹き抜けても空自体は風に動かされないようなものである。もし、このような境地をわがものとすることができれば、狭い路地では飾りたてた立派な馬には騎(の)らないで、帰り途(みち)には破れた衣服を着るのである。(57頁)
〔付記〕 仏法者は何ものにも依存せず、事に処して無礙自在である。かくして衆生の機根に応じた教化もできる。(58頁)
■〔訳文〕上堂して云われた。人びとすべては、夜光の珠にも比すべき明珠(めいじゅ、仏性)を本来抱いているのであり、それぞれは荊山(けいざん)の玉(注)にもたとえるべき宝珠(仏性)を本来蔵しているのである。それなのにどうして、回光返照(えこうへんしょう)してこれを覚らないで、せっかくの宝を抱きながら、迷うて他国にレイ(足ヘンに令)ヘイ(足ヘンに并)しているのであるか。古人も言っているではないか。(仏性が)眼に応ずるときは、千の太陽が照らせばどんなものでも隠れる余地のないように、眼に応じて現われないものはない。このように(仏性は)歴然として眼の前の対象に明らかに現われるものであるのにこれをはずして、そのほかに仏性を求めるならば、達磨西来の教えを大いにゆがめるものである。(59頁)
注;荊山の玉――楚(そ)人下和(べんか)が荊山において得たあらたま。下和はこれを厲(れい)王・武王に献じて罰せられ、文王に献じてはじめてその真価が見出されたという(『韓非子』)。仏性にたとえる。
■覚えていることだが、丹霞子淳(たんかしじゅん)和尚は古則ををとり挙げて、つぎのように言っている。
「徳山が衆に示していうには、『我が仏法においては、宗旨の堂奥は言葉では示されない、また何1つとして人に与えるものはない』と。徳山がこのように言うのは、草をかき分けて人を求めたもので、全身、泥水をかぶるのを知らないものである。よくよくみれば、ただ1見識を具えているだけで、完全な仏法把握とは言えない。もし丹霞(わたし)ならそうは言わぬ。わが仏法においては、宗旨の堂奥を示す言葉がある。ただその言葉は、金の刀のように堅い刃をもって切っても分別できないものであり、深く幽玄な妙旨であり、玉女(ぎょくじょ)が夜、懐胎するような思議を超えたものである」と。これについて、師は言われた。丹霞和尚がこのように言うのは、がさつな徳山を照破するものだ。ではあるが、永平(わたし)はそうは言わぬ。わが仏法においては、宗旨の堂奥は言葉では示されない。体験と言葉は一致しないからである。ではあるが、言葉を拈(ひね)李出して人に示すのは、驢馬や馬の胎(おなか)に入る慈悲行によるものである。(64頁)
■〔訳文〕結夏上堂。払子(ほっす)をもって1円相を作って云われた。結制安居(あんご)はこれ(円相)を超越している。また1円相を作って云われた。90日間の禁足安居は、これ(円相)を究明するにある。だからして、次のように言えよう。過去久遠劫(ごう)の昔の仏というも、これ(円相)を受け、仮に仏と名づけるのであり、歴代の祖師というも、これ(円相)によって人間界・天上界に仏法を弘(ひろ)めるのである。してみれば、諸君が結制安居するのは、威音王仏(いおんのうぶつ)・歴代の祖師とともに、いたるところに安居し、いつも禁足しているのである。ではあるが、これ(円相)をもって究極の道理としてはならぬ、これ(円相)をもって仏の上の境涯としてはならぬ。究極の道理をも一掃して留(とど)まらず、仏の上の境涯をも踏み倒して進まねばならぬ。永平(わたし)がいまここに結ぶ安居は、今後、諸方の叢林のために手本となることができよう。(66~67頁)
■〔訳文〕仏性はあらゆるはたらきを動かしながら、それ自身はいささかも動かないものであり、それぞれのものは仏性のまったき現われとして個々の相を示している。このあらゆるはたらき、あらゆるものの根源としての仏性は、仏の眼をもっても見ることができないし、迷悟の対立的眼をもってもとらえることができない。この仏性を具えていることにおいては、仏の鼻がこのわたしの眼であり、このわたしの眼が仏の鼻であるように、仏とわたしに何の異なることはない。この仏の眼からみれば、山を隔てて煙を見ただけで、それが火であることがわかり、垣根を隔てて角を見ただけで、それが牛であることがわかる。払子をとりあげていうには、ただこれ(仏性)においては、わたしと諸君との間に寸毫の隔てもない。畢竟、これをどう呼んだらよいのであろう。仏性は、夜が明けてくると山鳥が夜明けを知らせて鳴き、春になれば早咲きの梅が春を知らせて芳しくにおう、そのうちにある。(70頁)
〔付記〕 仏性はあらゆるはたらき、あらゆるもののうちにあって、それをしてあらしめるものである。従って、それはこのわたしのうちにも、諸君のうちにもあって、わたしと諸君との間に寸毫の隔てもない(71頁)
■〔訳文〕仏法を学ぶのに教学を究めて仏法の悟りにいたろうとするのは、海に入って沙(いさご)を数えるような空しい努力である。かといって、教学を捨てて、悟りをめあてに修行するのは、塼(かわら)を磨いて鏡とするように、これまた空しい工夫である。高い山の雲を見るがよい。雲は、何のはからいもなく、自然と縮んだり延びたりしている。滔滔と流れる谷川の水を見るがよい。水は、何のはからいもなく、曲がったところは曲がり、まっすぐなところはまっすぐに流れている。人間の日常も、雲や水のようでなければならぬ、雲や水は自由無礙であるが、人間はそうはいかない。もし雲や水のようであれば、人間が三界に流転生死することも、起こりようがないのである。(75頁)
■〔訳文〕8月1日上堂。公案をとりあげて言われた。趙州(じょうしゅう)和尚にある僧が質問した、「道を会得した人がお目にかかりに来たときは、どうなされますか」。趙州は云った、「漆塗りの道具を呈上しよう」。これについて、師が言うには、趙州古仏は、群をとび抜けたはたらきはあるけれども、平常語で話すはたらきがない。もし誰かがわたしに、道を会得した人がお目にかかりに来たときは、どうなされますか、と訪ねるものがあれば、ただそのものに言おう。8月(陰暦)の秋ともなれば、どこにも熱さはなくなる。平生(へいぜい)そのままでお目にかかるだけだ。(82頁)
〔付記〕 趙州の、道を会得した人が相見(しょうけん)に来たらどうする、という公案をとりあげて、平生(へいぜい)底以外に示すものはないと提示する。(83頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。永平(わたし)はある時は、仏法の深い道理の立場に立って説くが、それはただ諸君の心を穏やかにさせたいためである。ある時は、方便手段を用いるが、それはただ諸君をして自由無礙なはたらきをさせたいためである。ある時は、けたはずれなすばやいやり方をするが、それはただ諸君をして身心への執われを抜け出させたいためである。ある時は、坐禅三昧に入るが、それは諸君をして仏法を自由に拈提(ねんてい)させたいためである。だがもし人が出てきて、それらを超えたその上のことはどうか、と聞くものがあれば、そのものに言ってやろう。朝の風が吹いてものを洗い流すと、夕べのもやが清らかとなり、おぼろげに現われた青山は画図を述べたように美しい。(84頁)
〔付記〕 仏法を会得させたいためにさまざまの手段方法を用いて説き、示すが、究極のねらいは自然と一如して生きることにある。(84頁)
■〔訳文〕上堂。公案をとりあげて言われた。ある僧が趙州に質問していうには、「狗(いぬ)には仏性があるでしょうか」。趙州がいうには、「ない」。僧がいうには、「一切衆生はみな仏性があるというのに、どうして狗(いぬ)にはないのでしょう」。趙州がいうには、「それは、狗(いぬ)にものを分け隔てる分別の働きがあるからじゃ」。これについて、師は言われた。趙州のこのような学人指導は、まことに親切である。が、山僧(わたし)はちがう。もし山僧(わたし)に狗に仏性があるかないか問うものがあれば、彼にいうであろう。あるというも、ないというも、いずれもまちがいであると。さらに、それはどういうことかと問うものがあれば、声もろともに棒で打とう。(87頁)
■〔訳文〕上堂して云われた。仏法は、すべてのものとピタッと1つであって、その間に裂け目はなく、すべてのものに明白な事実であって、蔽い隠されているものではない。それゆえに、この仏法を釈尊が摩訶迦葉(かしょう)に伝えたというのも嘘であり、達磨がどうして慧可にこれを授けよう。いたるところに仏法を示す言葉が現われており、人びとすべてに般若の知見が具わっているのである。だからして、虚空が仏法を説くと、あらゆるものはこれを聞くのであって、人間の口を借りずによく仏法を挙揚(こおう)しているのである。それゆえに、諸君は1日中、眼に見えるところ耳に聞くところすべて仏法の中にあり、古を超えていついかなる時も仏法の中にあり、自分といわず他といわず誰もが仏法の中にあり、迷っていようが悟っていようがすべて仏法の中にある。このことがわかるか。しばらくして言われた。趙州が師の南泉にお目にかかったかと聞かれて鎮(ちん)州大根ができると答えたのと、青原(せいげん)仏とは何かと聞かれて廬陵(ろりょう)の米はいくらかと答えたのと、どっちがすぐれていよう。いずれも同じ趣旨である。(91~92頁)
■いままでもふだんのやり方に拙ないものがあっても、任に当たって努めれば、大丈夫の志気があらわれて、自ずから然るべきはたらきが出てくるのである。(94頁)
〔付記〕新旧の維那(いの)、知客(しか)が交代するに際し、その役職の任務と重要性を説いて、旧知事を慰労し新知事を激励する。『禅苑清規』が1年交代であったから、永平寺でも1年交代であったと思われる。(94頁)
■〔訳文〕上堂。公案を挙して示された。昔、(ある僧が)鵝湖(がこ)大義禅師に質問した。「欲界には禅がないのに、どうして禅定の修行をなさるのですか」。鵝湖が云うには、「お前は、欲界に禅がないことだけ知って、禅界に欲がないのを知らないな」。(僧は)何とも答えることができなかった。これに対し、師は次のように云われた。坐禅は、七顛八倒する欲界の只中でこそ行ぜられるべきものである。欲界に禅がないというのも、禅界に欲がないというのも、2つながら誤りである。真と妄、禅と欲を対立させてみるのは、2つながら誤っていることが分かって、はじめて仏法を行ずる人が見えてくるのである。(99~100頁)
■○中下は多く聞いて多く信ぜずー「上士は一決して一切了ず。中下は多く聞いて多く信ぜず」(『証道歌』)による。(102頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。ある僧が華厳休静禅師(けごんきゅうじょうぜんじ)に質問した。「大悟した人が迷うことがあるでしょうか」。休静が云うには「1度(ひとたび)大悟すれば2度と迷うことはない。それは1ぺん破れた鏡は、2度と照らすことがなく、1度地に落ちた花はふたたび枝に著けられないようなものだ」。これに対し、師は云われた。永平(わたし)は今日、華厳休静の境界に入って、華厳休静の境界のはてをさらに明らかにしよう。というのは、已むを得ず、口を開いてお喋りせざるを得ないからだ。もし誰か、大悟した人が迷うことがあるでしょうか、とわたしに聞くものがあれば、そのものに言おう。大海がもし、もう水は十分だと満足すれば、大海に注ぐ百川の川は逆流せざるを得ない、と。(103頁)
■〔訳文〕上堂し、大衆を召して言われた。ただ6祖慧能だけが仏法を会得していないだけでなく、インドにおいても、仏法をインドにおいても、仏法を会得している人はいないのである。このようにいうと、もしかしたら一人のものが出てきて、和尚がそんなことを言えば、露柱や灯籠に笑われますぞ、というものがあるかもしれないが、わたしはただそのものに言おう。これは、僧堂の長連単の上で学び得たもので、さらにその上のことはどうじゃと。しばらくして(師は)いった。胡人の鬚(ひげ)はそのように赤いと思っていたら、何のもとに、もともと赤い鬚の胡人であったわい。(114頁)
■〔訳文〕もし仏法を人間の思慮分別の立場から解すれば、眉や鬚が落ちる仏罰を受けるのを免れない。かといって、人間の思慮分別を破り除いてその上に仏法を高く掲げても、地獄に入ることは矢を射るように速い。では、永平(わたし)の学人指導はどういうものか、見たいと思うか。それはつぎのようだ。ただ雪が消えてしまえば、自然と春はやってくる。思慮分別をとくに除かなくても、修行していくところに思慮分別は自ずから消えて、仏法が現われてくるのである。(120~121頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。仏はほとけへ手ずから授け、祖師は祖師へ相い伝えたが、一体、何を相い伝え、何を手ずから授けたか。大衆諸君、その究極のところを知りたいと思うか。これについては、三世の諸仏・六代の祖師は、破れ草鞋や破れ柄杓のように、何の役にも立たぬものと知るべきである。そのことに疑いためらうならば、永平(わたし) は諸君の脚(あし)の底にある。諸君自身、自分の脚下(あしもと)をよくみるがよい。(122頁)
〔付記〕仏仏祖祖の授手し相伝する仏法の当体は、他によって教えられるものではなく、自ら工夫し、自ら究明するほかない。(122頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。世尊が言われるには、「一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、十万の虚空世界がことごとくみな消えうせる」と。五祖法演和尚が言うには、「一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、十万の虚空世界がいたるところつきあたり、ぶつかりあう」と。夾山(かつさん)の円悟禅師が言うには、「一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、十万の虚空世界が錦の上に花を添えたように光り輝く」と。仏性法泰和尚が言うには、「一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、十万の虚空世界はただ十方の虚空世界である」と。天童山の先師(じ)如淨禅師がが言うには、「一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、十万の虚空世界がことごとくみな消えうせるとは、世尊のお言葉であるが、これはなお特別すぐれた見解の提示であるのを免れない。天童(わたし)はそうは言わない。一人でも菩提心を起こして、真実に帰入すれば、乞食が飯椀をぶちこわしてしまう」と。これについて、師はいわれた。5人の尊宿(そんしゅく)はこのように言われたが、永平(わたし)はそうは言わない。一人でも菩提心を起こして真実世界に帰入すれば、十万の虚空世界が菩提心を起こして真実に帰入するのである。(124~125頁)
■〔訳文〕天童如浄禅師の忌日(きにち)に上堂して言われた。わたしは入宋(にっそう)して天童如浄和尚に仏法を学んだが、かんじんの仏法もみな忘れてしまった。ただ、眼が横に鼻がまっ直にあるのがわかっただけで、格別のことはない。だからして、天童和尚が学者(わたし)をだましたなどと言ってはならない。天童和尚がかえって永平(わたし)にだまされたのだ。(126~127頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。天下が泰平であるあるからして、いたるところに鉢盂(はつう、応量噐)で食事する人があり(出家修行ができる)、人民が安楽であるからして丸柱がいつも花開かれている(法莚が盛んである)。だからして、摩訶迦葉(かしょう)は世尊のもとに破顔微笑し、慧可は達磨のもとに礼拝得髄したのである。たとい、この境地を得ても、ここにとどまらず、さらに年長く修行しなければならぬ。だからして、「太山に登らなければ、天の高いことはわからないし、大海原を渡らなければ、海の広いのはわからぬ」と言われるのである。もし修行のできたものならば、天地を1粒の粟の中に納めることができるし、大海を1本の髪の毛の先に置くことができるし、華蔵(けぞう)世界、常寂光土(じょうじゃっこうど)をすべて眉の毛、睫(まつげ)の上におくこともできよう。さて、このような人はどこにおいて安身立命(あんじんりゅうみょう)するであろうか、といって、師は膝をいちどたたいて言われた。山川を渉(わた)り歩いて、草鞋の底をすり破るほど修行を重ねて、はじめていままでの自分が、眼にあざむかれていたことがわかるのである。(128~129頁)
〔付記〕 仏法は無限に広く、かつ深いからして、その参究もまた限りない精進の道でなければならない。(129頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。ある僧が投子(とうす)大和尚にたずねた。「仏法においていちばん究極の問題は何でしょう」。投子がいうには、「それはいま、尹司空(いんしくう)が老僧(わたし)を請(しょう)じて開堂させていることじゃ」。師がいうには、もし永平(わたし)ならばそうは言わぬ。仏法においていちばん究極の問題は何でしょう、と問うものがあれば、、ただそのものに答えて言おう。それは、早朝には粥を食べ、昼には飯を食べ、体がすこやかであれば経行(きんひん)し、疲れれば眠ることだ。(130頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。ある僧が古徳(帰宗道詮、きすどうせん)に聞いた。「深い山の切り立った崖、そんなところにも仏法はありますか」。古徳は答えた。「石の大きなのは大きいなりに、小さなのは小さいなりにある、それが仏法だ」。先師天童如浄和尚は言われた。「深い山の切り立った崖に仏法があるかの問いに、石の大きなのは大きいなりに、小さなのは小さいなりにあるとの答え。それはなお崖に執(とら)われ石に執われるものだ。崖は崩れ、石はつんざき裂かれ、虚空はガアガア騒いでいる」と。これについて、師は云われた。帰宗(きす)と天童、2人の尊宿はこのように言われたが、永平(わたし)はさらに1語を加えよう。もし誰か、深い山の切り立った崖に仏法があるかと、問うものがあれば、そのものに言おう。虚空は消え失せ、頑石はうなずいていると。しかし、このようにいうもなお仏法に執われた見方である。結局、どうなんだ、といって、払子(ほっす)を投げて、法堂の座を下りられた。(132~134頁)
■〔訳文〕元日に上堂して言われた。ものを見て心を明らめることによって、釈尊は悟りを得たのであり、声を聞いて道を悟ることによって、祖師達磨は釈尊の道を受け継いだのである。それゆえに、悟る以前の釈尊は、霊鷲山(りょうじゅせん)において月に語りかけて修行したのであり、悟った以後の達磨は、釈尊の教えをさらに世に弘めたのである。このことはしばらく措くとしても、たとえばどんな純金であっても鍛(きた)えに鍛えなければどうして光りを発しよう。また、どんな至宝であってもこれを鑑別する人がいなければどうして真贋が見分けられよう。そのように、仏法も百錬の修行によって始めて達せられるのである。万物みな改まるこの元旦を迎えて、さて諸君はどうか。しばらくして言われた。初春とはいえ、なお寒気がきびしい。伏して願うことは、大衆諸君の起居が、この上もなく幸多からんことを。(136頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。ある僧が百丈に質(たず)ねた、「この世の中で、いちばんすばらしいことは何でしょう」。百丈が言うには「わしが、この百丈山に独坐していることだ」と。今日もし永平(わたし)に、この世の中で、いちばんすばらしいことは何か、と聞くものがあれば、わたしはそのものに言おう、今日、法鼓(ほっく)を鳴らして上堂することだ。
〔付記〕この世の中でいちばんすばらしいことは、ただ平生の生活のうちにある。百丈は百丈、永平は永平、その生き方は異なるにしても。(141頁)
■〔訳文〕降誕会(ごうたんえ)上堂。釈尊の真身は兜率天より降下されたのではないし、ましてや摩耶夫人のお腹を借りて生まれたものではない。釈尊の降誕とは、無量の功徳のあつまりが肉身の姿を借りて突然現われ出たことであり、三千年に一度花開くという優曇華(うどんげ)の花が、火の中に一枝開いたようなすばらしい出来事である。こういう釈尊にもまた泣きどころがあるが、わかるか。それは、家の財産を身代かぎりにして、売るものがなくなって、あろうことか、小さな赤ん坊(誕生仏)まで売りに出したことだ(注)。(142頁)
注;小嬰孩(しょうえいがい)を売弄(まいろう)す――小さな赤ん坊を売りに出す。誕生仏をお祝いすることをこのようにいう。それが釈尊の泣きどころであるというのは、後のちのものに法要を営ませ迷惑をかけたこと、今日にいたるまで降誕を祝う盛儀を生んだことを逆説的に讃歎した言葉。(142頁)
■〔訳文〕禅僧の面目をずばりと示すものは、坐禅することだ。参禅は参ずべきものがなくなるまで修行するのが、正しい伝承である。だが、この正伝にも執われてはならない。それが、皆の人が達磨の西来を頌(たた)える正しいあり方である。(143頁)
■〔訳文〕夏安居の解制にちなむ上堂。君たち、夏安居の無事終了を見たいと思うか。一円相を描いていうには、この一円相を会得せよ。また一円相を描いていうには、この一円相に参ずれば、如来禅は君たちが会得したことは許してやるが、祖師禅を見ようと思ったなら、万里を隔つというものだ。さて、そういう永平(わたし)の意図はどこにあろう。君たちは、ただ日が東に昇ることはみな知っているが、夏安居の終りが秋のはじまりであることを誰が知っていよう。祖師禅とはこれを知ることだ。(144頁)
■〔訳文〕上堂。公案をとりあげて言われた。ある僧が巌頭(がんとう)和尚に質問した。「古い帆をまだ掛けないとき、つまり、ものの成立以前の世界とは、どのような世界でしょうか」。巌頭が答えて言った。「小魚が大魚を呑むことである。大小の対立を超えることだ」。師が言われるには、この公案の趣意を会得したいと思うならば、永平(わたし)の一頌を聴くがよい。巌頭のいう小魚、大魚を呑むとは、和尚が儒書を読むことだ。仏教とか儒教の対立を超えることだ。さらに、仏教とか外道の対立を超えて、仏教に対する執われもなくしてしまうことだ。(146頁)
■〔訳文〕上堂して言われた。仏性とは時節因縁(注)である。そのときそのときに現われ、前にも後にも完全に現われている。ただこの道理を自分自身に回光返照してよくよく参究すれば、牛乳は牛乳として、酪(らく)は酪として、それぞれ仏性であることがはっきりする。(147頁)
注;時節因縁――時節が到り因縁が熟すること。道元はこれを未来に望めず、現にいま、時節は到っており、因縁は熟しているとみる。「いわゆる仏性をしらんとおもわば、しるべし時節因縁これなり」(『正法眼蔵・仏性)(147頁)
■〔訳文〕夏案居開始の前の晩の説法。ー中略ー これについて、師は言われた。古人は、「断じて心を第二念(分別心)に流れないようにせよ」と言われたが、諸君に敢えて聞くが、ではどれを指して第一念(無分別心)というのであるか。永平(わたし)は今夜喋るのを惜しまず諸君に言おう。90日の安居(あんご)は明日から始まる。規則外のことを行なってはならぬ。坐蒲(ざふ)の上に坐ってそのほかのことを一切顧みなければ、毎日毎日がⅠ日じゅう、寂(しず)かで天下泰平な安らかな日暮らしができるのである。(149~150頁)
■〔訳文〕夏案居の解制の日の晩の説法。一円相を描いていうには、この一円相は数量を超えた仏法の根本問題である。過去・現在・未来の三世の諸仏もこの根本問題をあきらめたのであり、歴代祖師もこの根本問題を悟ったのであって、仏道修行者はすべてこの根本問題に参ずるのである。もし毎日の生活においてこの根本問題をすっかりわがものとすれば、親しく仏祖をも一段超えた境地にいたるであろう。これについて、次のような公案を知らぬことはあるまい。趙州(じょうしゅう)が大慈に尋ねた。「般若は何をもって根本とするか」。大慈がいうには、「般若は何をもって根本とするか」。きいて、趙州はからからと大笑した。翌日、趙州が地を掃いていたところへ大慈がやってきて問うには、「般若は何をもって根本とするか」。聞くや、趙州は箒をほうり出して、からからと大笑した。大衆諸君、大慈と趙州、この二人の古仏の一世一代の出会いは、すばらしいではないか。諸君は、今日解制の期に臨んで、この公案をどのように工夫するか。わたしは言おう。昨日は応量器でご飯を頂いたが、今朝は鉢盂(はつう)でお粥をいただいた。さて、わたしの言うところと、この二人の古人とは、同じことを言っているのか、別のことを言っているのか。さて、どうじゃ。しばらくして、云われた。大慈がもしももう一ぺん尋ねれば、趙州はまたもや新たに大笑するであろう。久しく立たせてしまった、諸君、ではさようなら。(152~153頁)
■〔訳文〕冬至の晩の説法。長いあいだの苦節を経て一陽来復の佳節を迎えた。あらゆるものはその本に帰って、はじめてその真の姿を現わすのである。だからして、宏智(わんし)禅師も言っている。「全世界はhpかでもない君自身の1つの眼であり、全世界はほかではない君自身であり、全世界はほかではない君自身の光明であり、全世界は1つの悟りの世界である。どんなところであれ君が説法し人を救うところでないところはない。だからして、古人も言っているではないか。『釈尊が護明菩薩として兜率天より降下しない前に、一輪の明月が十万を照らして、一切の衆生は救われている』と」。(154頁)
■〔訳文〕12月30日、大晦日の晩の小参に云われた。小参というのは、仏祖の家訓である。わが国では、いままでに行なわれたことのないもので、永平(わたし)が始てこれを伝えて以来、すでに20年経っている。達磨祖師がインドから中国に来って仏法を中国に伝えてよりこのかた、前代の祖師は小参を家訓といってきたのである。家訓というのは、仏祖の行ないでなければ行なわず、仏祖の法服(ほうぶく)
でなければ身に着けないことである。さらに言えば、名利を抛(な)げ捨て、己我を捨て去り、三谷に隠れ住んで、叢林をを離れずに、さしわたし一尺もある玉(たま)も貴ばず寸陰も惜しんで、万事も顧みず純一に修行することで、これが仏祖の家訓であり、人間界・天上界の指標となるものである。
しかしながら、立派な善知識となることは三阿僧祇劫(あそうぎごう)という無限の長時の修行によるのでなければ不可能のことである。大衆諸君よ、この無限の長時の修行とは何か、これをみたいと思うか、といって(師は)指をポンと1度弾(はじ)いて云われた。無限の長時の修行といってもこの一弾指(だんじ)にある。この一弾指はもとからあるものということができようか、いまここで修行されたものということができようか。そんなことはないのだ。ここのところがわかれば、時移り年変わって、12月が終って正月がくることがわかる。これがわかれば、十方の世界はみな断ちきられてわがものとなり、過去・現在・未来の三世の世界とも知らないうちに一つになる。12月が終わって正月がくるといっても、実は旧い年が去るのでもなく、新しい年がくるのでもなく、くる年は去る年の連続ではなく、新年は新年として、旧年は旧年としてそれぞれ絶対である。それゆえに、この道理を古人は次のように示している。ある僧が石門和尚に、「1年の最終日にはどうしたらよいでしょう」と尋ねたところ、石門は「東村の王老人が夜、紙銭を焼くことだ」(大晦日には大晦日の行事を行う)と答えた。同じ僧が、開先(かいせん)和尚に「1年の最終日にはどうしたらよいでしょう」と尋ねたところ、開先は「いままで通り春を迎えてもあいかわらず寒い」(正月を迎えても何も変わったことはない)と答えた。今夜、もし諸君のうちの誰かが永平(わたし)に、1年の最終日にはどうしたらよいでしょう、と問うものがあれば、わたしはそのものに答えよう。前方の村々は深い雪の中にあるが、昨夜梅の花が一枝咲いたぞ、と。寒い時候に長いあいだ立ってご苦労。(157~158頁)
■〔訳文〕禅人に示す 近来仏道修行するものは、本ものと贋(まが)いものを弁別せず、豆と麦とを区別せずに、仏法をきわめようとしているが、それでは仏法をきわめることがまことに困難なわけである。どうしてかというに、古者(法昌倚遇(ほうしょういぐう))は次のように言っている。「大地に雪いっぱい積もれば、春になっても依然として寒い。そのように悟りを得ても、雪が降れば寒いのは、悟らぬ前と同じである。だから、つまるところ、悟ることは易しいが、悟りの境涯を説くことはむずかしい」と。こういう誤りは、仏祖といえどもなお免れないところである。どうして免かれないかというと、悟ることは易しいが、悟りの境涯を説くことはむずかしいとか、悟りの境涯を説くことは易しいが、悟ることはむずかしいとか、そんなことをいう手合いの仏法の難易は、情識の上の難易を脱(まぬか)れないのだ。よくきくことではないか。ある僧が雲門に質問した。「樹が枯れ、葉が落ち尽くすとは、どういうことでしょう」。雲門は答えた。「秋風がその本性を現わすことだ」。この雲門の言葉を、仏照禅師はとりあげていうには、「さすがの雲門和尚も備えつけの品で、仏法を示す人情に堕した」と。しかし、この仏照禅師の拈提(ねんてい)は、病いのないのに薬を施す余計な口だしである。
釈尊がこの世に出られた理由は、すぐれた医者となることであった。釈尊は、衆生が深く苦海に沈んでいるのに憐んで慈悲の念を起こし、種々の方便をもって一大蔵経を説法されたが、これはみな衆生の病いに応じて薬を与えられたものであり、一切衆生に大安楽をもたらすために処方箋を書いて与えたものである。ところが、達磨が西来(せいらい)するにおよんで、その子孫はみな劇薬を用いるようになり、病人を一旦気絶させ、後に甦らせる手段を用いるようになった。なるほど、これは不老不死の妙薬のように、効き目は多いにちがいないが、正しい眼からみれば、立派な肉体にわざわざ傷をつけるようなものである。もし本当の手段から言えば、そうではない。処方箋も書かないし、脈もみないで、目でみただけ一目でわかり、臨機応変の処置をとるのである。よしんば相手が仏病祖病のような病いであっても、軽々しくひとにぎりで済ますようなことをしないで、そのもののすべての骨を換え腸を洗って、仏祖に対する執(とら)われを洗い流して、身も心も浄らかに爽やかにさせずにはおかないのである。従って、これ1つですべての病いを癒すのであり、あれこれの処方箋を必要としないのである。ただ釈迦老漢自身の病いは、諸人の病いとは異なり、全身が病いで、病いのもとはどこから起こったかわからないから、衆生の病いが癒らないかぎり癒しようがないのである。普灯都正(ふとうとしょう)はこのように種々の病いに処する作略をよくご存じであるから、よく眼をつけて看ていただきたい。もしこのへんのことをよく見究められれば、古の名医である扁鵲廬医(へんじゃくろい)も、すべて下座について仰ぎみるであろう。(163~164頁)
■〔訳文〕諸仏の大道は深く勝れて思議を超えたものであるから、仏道修行者はどうしてたやすく考えてよかろう。よくみるがよい、古人はいのちを捨て、国や妻子を捨て、これらをみること瓦や石ころ同然であったのである。そうして後、長い長いあいだ、独りで山林に住み、身心を枯木のようにして、始めて仏道と1つになったからこそ、山川を借りて仏法を示すことができたのである。このようであれば、どんなことでも仏法を示すに用いられないものはなく、どんなことでもいけないことはない。仏道に志すものは、このような古人のお手本に従わなければならない。
昔、ある僧が法眼(ほうがん)禅師に尋ねた。「古仏とはどういうものでしょう」。法眼は言った。「いまここにあるお前、それが古仏であることに何の疑いもないぞ」。僧がまた尋ねた。「ならば、Ⅰ日じゅうどのように行なったらよいでしょう」。法眼はいった。「一歩一歩、踏みしめよ」と。法眼はまた言っている。「出家人たるものは、そのときどきの時節に従うがよろしい。寒いときには寒がり、暑いときには暑がるのだ。仏の言われるように、『仏性ということを知りたいならば、時節因縁を観よ』とあるとおりだ。ただ、時節を守り、時節に従うだけだ」と。子細にこの言葉の意味を参究するがよい。時節に従い、時節を守るとはどういうことかというに、それは、ものの上において、ものでないないとみてはならない、かといって、ものであるとみてもならない。このようであれば、自分が古仏であることに何の疑いもなくなり、他の古仏と同じく住し、同じく行ずることは、2つの鏡が互いに照らし合うようなものである。
だからして、釈尊は言われた。「出家が村に托鉢するのは、ちょうど蜜蜂が花から蜜を吸うようなものである。ただ花の甘味だけをとって、花の色香を傷つけてはならぬ」と。どうして、この時節の教えに従わなくてよかろう。出家はⅠ日中、さまざまの縁に出会い、さまざままの境に出会うが、そのときただものの味のみとって、ものの色香を傷つけてはならない。君に言うが、さまざまの縁に出会い、さまざままの境に出会う、そのときこそ、釈尊の教える、ものの色香を傷つけてはならない、という時節である。このときを離れて、釈尊の教えがどこにあろう。そのことは、ほかでもない、あらゆるものごとが君のために証明してくれるところだ。山僧(わたし)がこのようにいうのも、事情やむを得ずしていうのである。了然(りょうねん)道者の仏道を志求する心の切実なことは、他のもののとうてい及ぶところではない。それゆえに筆をとっていささか書き示して参究の参考に供する次第である。よくよく努め励んでいただきたい。(167~169頁)
■〔訳文〕一体、坐禅するには静かな室でするのがよい。。飲食に節度を保ち、あらゆるかかわりあいを投げ捨て、すべての執(とら)われをやめて、善いの悪いの、正しいの間違っているのという判断をやめて、心があれこれと外へ動くのもやめ、あれこれと内へ動くはからいをやめるのである。その際、仏になろうとするめあてさえもってはいけないのであるから、どうして坐臥のすがたに執(とら)われることがあろう。
平常、坐禅すうところには、厚く坐褥(ざにく)を敷き、その上に坐蒲を用いるのである。これには、結跏趺坐と半跏趺坐の2通りの仕方がある。結跏趺坐というのは、まず右足を左の腿の上におき、左足を右の腿の上におくのである。半跏趺坐は、ただ左足で右の腿を押さえるだけである。ゆったりと着物をき、帯をしめて、きちんと整えるがよい。次に右手を左足の上におき、左の掌を右の掌の上において、両方の親指が向き合って互いにささえあうようにする。これがとりもなおさず、正身端坐することである。。前後左右どちらにも姿勢をくずしてはならない。それには、まずもって耳と肩とがまっすぐに、鼻と臍(ほぞ)とがまっすぐに対し合い、舌は上の腭(あざと)につけ、唇と歯とをつけ、目はかならず常に開いて、鼻息が微かに通うようにしなければならぬ。このようにして身相が整ったところで、一息にフーッと息を吐き出し、右と左に体をいちど揺って、山の動かぬように坐りこみ、思量分別を超えたところを思量するのである。思量分別を超えたところをどうして思量するかといえば、それは思量をなくすことではなくて、思量の1つ1つに思量を超えた智のはたらきを現わしていくことである。これが坐禅にとっていちばん大事な要訣である。
仏道の坐禅は禅定修行ではない。禅定修行は苦行であるが、仏道の坐禅は安楽の教えであり、禅定修行は悟りへ向かっての道であるが、仏道の坐禅は悟りを究め尽くした修証である。この坐禅の上に現われる絶対の境地は、いままで自分を縛っていたあらゆる分別の網の届かない世界である。それゆえに、もしこの境地を得れば、竜が水を得るように、虎ガ山によるように、人は人の」本来のあり方に落ちつくのであって、そこに正しい仏法がおのずから現われて、心が暗く沈んでいく動きや、明るく浮き上がる動きは、自然と消え失せてしまうのである。(176~177頁)
■〔訳文〕もし坐禅の床を起つときは、静かに身を動かし、ゆったりと起(た)ちなさい、いきなり荒々しく起ってはならない。よくよく観察するに、凡を超え聖を超えるすぐれたはたらき、また坐したまま死に、立ったまま死ぬという自由なはたらきは、すべて坐禅の力によるのである。そればかりではない、古人が旗竿を指し針をみせ鎚を下ろして学人を導くはたらきを挙げてみても、これらはすべて思慮分別で理解できることではない。どうして小乗の神通力や修行・証(さと)りの方法でわかることであろう。それは、眼や耳の感覚器官を超えた行ないである。どうして知識以前のはたらきでないことがあろう。であるからして、上根であるとか下根であるとかは問わず、利口であるとか愚鈍であるとかは択(えら)ばず、専心一意に坐禅しさえすれば、それが正しい修行である。この只管打坐は、修行や証(さと)りによって汚されない修行であり、その趣意とするところは何も変わったことのない当たり前の世界である。
一体、この娑婆世界であれ他土の世界であれ、インドであれ中国であれ、仏の正法(しょうぼう)を保持し、もっぱら仏道を宣揚するものは、ただ坐禅を務めて、山之動かないように不動の姿になりきったのである。人の機根には千人は千人、万人は万人、それぞれ相違があっても、ただ参禅弁道するがよい。どうして自分の坐禅の床を放り出して、やたらと他国の塵境をうろつくことがあろう。ここにおいて、もし一歩をふみ錯(あやま)れば、目の前の大道とすれちがうことになる。すでに受けがたい人間の大切な身を受けたものであるからには、虚しく月日を過ごしてはならない。仏道の大切ないのちを保任するものである以上、誰が石火のようにすぐ消え失せる楽しみに耽(ふ)けろう。そればかりではない、人の体は草に宿った露のようにはかないものであり、人の一生は稲妻のように瞬時のものである。あっという間に忽ちに空しくなり、すぐさま消え失せるものである。であれば、是非ともお願いしていことは、仏法を学ぶ立派な学人よ、彫竜(坐禅)を久しく習って、それが真竜(証リ)に出会う道であることを驚き怪しんではならない。ほんものをずばりと示す仏道に精進し、仏法を学び尽くして有為の世界を超えた真実の人を貴び、過去の仏仏が証してきた悟りにピタッと合致し、祖祖が伝えてきた坐禅を正しく受け継ぐ人になっていただきたい。久しくこのように精進すれば、かならずそのような人になるにちがいない。そのときは、仏の智慧はおのずから開かれ、これを受用することは思うままであろう。(180~181頁)
■〔訳文〕仏祖にとってもっとも大切なはたらき、仏の智慧は、思慮を超えて思量の世界に現われるものであり、対立を超えて対立せる物の世界に現われるものである。思慮を超えて思量の世界に現われるものであるから、その現われた思量は不思量と1つであり、対立を超えて対立せる物の世界に現われるものであるから、その現われた物は無対立と1つである。思量は不思量と1つであるから。その思量には何の汚れも留めないのであり、物は無対立と1つであるから、その物には何の対立も残さないのである。何の汚れも留めない思量であるからして、その思量はいくら思量しても思量の執(とら)われを脱(ぬ)け出ており、何の対立も残さない物であるからして、その対立はいくら物として現われても物の執われを超え出ているのである。この坐禅の境地を偈(うた)で示せば次のようである。
水はあくまで澄んで地の底にまですき透っている
その中を泳いでいる魚は、魚の動きが天地の動きで、魚の姿をとどめない
空はどこまでも広く天のはてにまですき透っている
その中を飛んでいる鳥は、鳥の動きが天地の動きで、鳥の姿をとどめない(183~184頁)
■〔訳文〕風をみ、草の根をかき分けても師をたずねて参禅すべきである。祖師が伝えた仏法は明明と明らか、その妙旨は言葉に伝えることはできぬ、山や河をいく千万里踏み破らなければならぬと恨んではならぬ、踏み破って、脚下の1つ1つが君のために仏法の幽玄な門を開いてくれよう。(192~193頁)
■〔訳文〕仏法の奥深い旨を言葉で説くのはすべてそれごと。口を槌(つち)のように、言葉を忘じ、黙々と独坐するがよい。とはいえ、仏法は説けないものと、はじめから固守し、孤絶を誇るべきものではない。あらゆるものが、それみずから仏法を発揮している。(193頁)
(2013年12月6日)