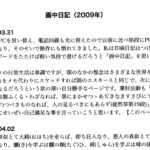『オディロン・ルドン』本江邦夫著 みすず書房
■ルドンのことば(ある若い画家にむけて)《自然とともに閉じこもりなさい》(Enfermez-vous avec la nature.) あらゆるものをその素材にしたがって描くこと。ごつごつした樹木、すべすべした肌を。(14頁)
■とはいえ、ルドンとブレスダンとの出会いの本質、それがルドンになにをもたらしたかということでいえば、先にふれた晩年の「打ち明け話」のつぎの一節いじょうにみごとな描写はないであろう。
わたくしがボルドーで彼に会ったとき、彼はひどい困窮のなかにいたのですが、そんなことは気にもとめず猛然と制作にはげんでいました。彼が住んでいた通りの名は、いまはもうちがう名前になっていますが、「獅子の穴」(Fosse-aux-Lion)通りといい、彼はそれをほほ笑みながら冗談でもいうように教えてくれたのです。その通りはシャルトルー会修道院のうつくしい墓地のちかくにあり、わたくしは幾度となく、朝早くこの墓地を横切って彼のところに通ったものです。それは春のことでした。ボルドーの春といったらそれはもう香しく甘美なのです。澄みきった空のもと、空気は暖かく湿り、光はあくまでも透明です。青春時代の印象が、時の経過によって美化されているのかもしれませんが、彼の家へとみちびく狭い歩道のついた、人気のない小さな通りを歩いていくときの、生き生きしたしなやかさをそんなにもつよく感じることができたのは、やはりその場所だけで、そんなことはそれから二度となかったのです。その一画はまだ整備の途中で、住んでいる人も少なく、木々は低い石壁や生け垣をこえて迫り出し、歩道に散っている西洋さんざしの花ばなを踏みしだきながら、わたくしはひたすら奇妙な夢想に我を忘れていたのです。(49頁)
■たとえ誤解にみちた擁護であろうとも、完全な敵よりはるかにましだ。ユイスマンの評にとまどいつつも、先に引いたインタビューのつぎの箇所は意外にルドンの本音が出ているのかもしれない。「とのかく彼は私の努力にたいして好意的でありつづけました。このことに、私は感動もし驚きもします。というのも、ここだけの話ですが、私の《夢》を非常に早くから誉めそやし勇気づけてくれた人物が、その一方で、あえて私が私の芸術と呼ぶものと対極をなすポール・セザンヌの芸術を発見し擁護したりもするのですから。」実名こそ挙げていないものの、ここでルドンが言及しているのはあきらかにエミール・ベルナールのことであろう。(122頁)
■細かく見ていけば、巨人のごとき大きさをもつはずの《奇妙な花》の、あのいかにも自然なたたずまい、そこに秘められた次元の横断を可能にしたものこそ、こうしたルドン独得の精緻な伎倆であったこと、これはどちらかというと不器用な画家とおもをれがちなルドンにあってはもっと強調されてよいものだ。彼自身のちに書いているではないか。「私の独創性のすべては、ありうるものの法則に従って、ありえない存在を人間らしく生かす、つまり目に見えるものの論理を、見えないもののために、可能なかぎり利用する点にあるのだ」と。つまりルドンはその類いまれな想像力を羽ばたかせる一方で、それほどまでに現実に肉薄し、その本質を直感しようとしていたのである。ここに彼の非凡さがあるのだ。(133~134頁)
■幻想なり空想に身をまかせてイメージを書き散らすような、そんないいかげんな画家ではないのだ、自分は。節制こそ、自分の芸術の原点である、と彼はいいたいのだ。だからこそ彼はつぎのように言葉をつづけるのである。
それは、だれがなんといおうとも、私のデッサンは真実のものだということです。それらのなかには人間の風景があるのです。じつをいいますと、これは私という人間の特別な性質なのですが、私は自然というものの微細かつ偶発的ないし刹那的な諸事物を模写したいという必要性をずうっと感じてきたし、今もそうなのです。草の一茎、小石、木の一枝、古壁の一部を細密に描く努力をとつづけたあとで、はじめて私は想像力によって創造したいという気持ちで苛まれるようになるのです。このように受け取られ調合された外部の自然は、変形されて、私の源泉、私の酵母となるのです。私の最良の作品は、こうした訓練のあとにつづく瞬間にもたらされるのです。(155~156頁)
■だからこそ、おなじ「打ち明け話」の少し手前で、彼は自分の芸術の独自性を、いくぶん誇らしく述べたててもいるのだ。
だれも私から、もっとも非現実的な創造物に生命の幻影をあたえたという功績を奪うことはできません。私の独自性のすべては、それゆえ、ありうるものの法則にしたがって、ありえない存在を人間らしく生かさしめる、つまり目に見えるものの論理を見えないもののために可能なかぎり役立たせる点にあるのです。
この主張があってこそ、いやむしろそれを補強するために、すぐあとの細密描写のくだりがあるのだとすらいえるだろう。その底に流れるのは、あくまでも「自然を源泉とすることによって、私は私によって作りだされたものが真実のものだとおもう」という信念であった。さもなければ、それらはただのまがいものでしかない。「ピカールへの手紙』とくらべてはるかに長文で、しかも入念に構想された「打ち明け話」を、ルドンはこうして、いささか弁明の調子をこめてつぎのように結ぶのである。
自分のデッサンについて、私はやはりそうおもうのです。そしておそらくは、人間が作りだしたものすべてにつきものの弱点、不均衡、不完全がその大部分を占めるにしろ、私のデッサンは(人間の表情をしているから)、もしかりにそれが、私のいうように、生命、および存在するものすべてに必要とされる精神的伝達の法則にしたがって形成され、構成され、打ち立てられていなかったとしたら、一瞬といえども見るにたえないものとなったでしょう。(156~157頁)
■とりわけ問題になるのは、「暗示的芸術」の部分である。これを「放射」と関連づけるのはルドンの年来の主張であったらしく、晩年に認めた「芸術家の打ち明け話」にもつぎのくだりがある。
暗示的な芸術とは、事物の夢への放射のごときものであり、思考もまたそこへ向うのです。退廃的であろうとなかろうと、それはそうしたものなのです。むしろこういったほうがよいでしょう。それは、私たち自身の生の最高度の飛躍をめざした芸術の生長、発展であり、その支えないし精神的維持の最高点であり、これにはどうしても精神的高揚が必要なのです。(162~163頁)
■ここでの彼の目標ははっきりしていて、それは暗示的芸術と音楽との親近性をまず述べることで、自身の芸術の曖昧さを擁護することにある。
こうした暗示的芸術は、そっくりそのまま音楽という喚起的な芸術の中に、より自由に、輝かしく存在します。私の芸術にしても、よく似たさまざまな要素、置換され変形されるいくつかの形を、偶然的なものとはいっさい関係なしに、ある論理にしたがって組み合わせることで存在するのです。私がデビューしたとき、私にかんする批評はみなつぎのような誤りをおかしていました。つまり、そうした批評には、なにひとつ定義したり、理解したり、限定したり、正確にしたりしてはいけない。なぜならば、真摯に、ひたすら新しいものはすべて――ある意味では美そのもののように――それ自身のうちに意味をもっているからだ、ということがわかっていないのです。(163頁)
■このとき、ふと思い出されるのは、知覚をめぐる古代ギリシアつまりソクラテス以前の自然哲学者による教説である。近代的な思考からするとそれはあまりに古拙におもえ馴染みにくいものかもしれないが、問題の設定そのものはきわめて原理的である。つまり、なぜ外なる事物を人間は知覚することができるのか。彼らはここけら思考をはじめ、それは物体の表面が剥離して適当な通路をとおって感覚器官の内部に入ってくるからだと結論づけたのである。たとえば、エンペドクレスはいっている。「存在するすべての物から流出するものがある」と。そして、こうした流出物が感覚器官の小孔にぴたりと当てはまる大きさのときにかぎって、その物にたいする知覚が生じるというのである。(164~165頁)
■こうした芸術至上主義的な高らかな宣言とともにオーリエは本論にはいっていくのだが、それについて詳細に論じる余裕はない。ここではただ漠然と、この夭折の作家は画家と自然との、天上的な愛を媒介とした聖なる一体化に絵画の極致をみていたとだけいっておこう。特筆すべきは、そうした一体化から彼が導きだしたつぎのような見解である。
「諸事物、すなわち抽象的にいえば、線、点、面、影、色彩がさまざまに結合したものは、神秘的ではあるが驚くほど表現力にとんだ言語の語彙を形成し、芸術家たらんとすればぜひともこれを知る必要があるのだ。この言語はあらゆる他の言語と同様、その筆跡、正書法、文法、統辞法、修辞法すら有し、これこそが様式なのである。
このように理解された芸術においては、目的はもはや事物の即物的かつ直接的な再現などにはなく、絵画言語のあらゆる要素、線、面、影、色彩は(…)抽象的な諸要素となり、その固有の表現法にしたがってそれらを組合わせ、強弱をつけ、誇張し、変形することが可能となり、その結果として芸術作品の一般的な目的、すなわちある理念、ある夢想、ある思想の表現に到達するのである。」(188~189頁)
■そのくわしい経緯は不明だが、おそらくはその当時のパリ芸術界の中枢をしめつつあった象徴主義者たちの肝煎りで、その鳴り物入りのタヒチ滞在――正確には第一次タヒチ滞在(1891-93年)を目前にしたゴーギャンの壮行会が華ばなしく開かれたのは1891年3月23日のことであった。その翌日、ゴーギャンはデンマークにいる妻のメットに誇らしげに書いている。
「昨日みんながぼくのために晩餐会を催してくれました。出席したのは45人――文筆家や画家たちで、マラルメの主催でした。いろんな詩の朗読、たび重なる乾杯そしてぼくにたいするじつに熱烈な賛美。ぼくはきみに保証します。今から3年後には、ぼくはこの闘いに勝利をおさめ、ぼくらは――きみとぼくは――難事を避けてくらすことができるようになるでしょう。きみは安らぎ、ぼくは仕事をするのです。」(232頁)
■みずから誘惑を欲しながらも、最終的にそれを拒絶する聖アントワーヌ、いやフロベールの、どこか矛盾にみちた悲壮な姿にルドンそのひとのイメージを重ねあわせてみることもできよう。聖アントワーヌ、それはすでに苦悩する近代の人間像となっているのである。にもかかわらず、このフロベール畢生の「力作」の評判は芳しいものではなかった。まったくの失敗作というのではないが、名作の誉れ高い『ボヴァリー夫人』や『感情教育』とくらべればそのあまりに風変わりな外観ゆえに欠陥作とみなされ、ヴァレリーなどは「(聖)フロベ=ルの誘惑」という皮肉っぽい題名の批判文すら書いている。とはいえ、このヴィジョンにみちた聖人伝がその深いところで19世紀末という、実証主義と神秘主義とが共存しえた時代の核心にせまるものをもっていたこと、まさにそれゆえにルドンのような本質的に内面的な画家の興味をひいたこともまた否定できない事実なのだ。(251頁)
■この疑念については、ルドン自身が晩年に記した数行が格好の応答となるであろう。
神秘の意味、それはつねに曖昧さのうちに、2重、3重の外観、つまり外観というものにたいするさまざまの疑い(イメージのなかのイメージ)のうちにあることである。生まれてくる、あるいは見る者の精神状態に応じてそのようになるさまざまな形態。あらゆるものは、それらが 現れ出るものであるだけに、よりいっそう暗示的である(1902年)。(285頁)
■ともあれ、ここで確実に言えるのはただひとつのこと――ルドンが〈黒〉の素材、すなわち木炭にたいする興味をしだいに失っていったということだ。たとえば、移行が完了しつつあった1902年に彼は書いている。
私は昔のように木炭画を描こうとおもいましたが、だめでした。それは木炭と決裂したということです。じつをいえば、私たちが生きながらえるのは、ただただ新しい素材によってなのです。それ以来、私は色彩と結婚しました。もうそれなしで過すことはできません。(モーリス・ファブル宛 1902年7月21日付け)(302~303頁)
■これにたいし、少なくとも1895年のペイルルバードでは〈黒〉はまだ死んでいなかった。オランダの収集家ポンジェに彼はこう書き送っている。
私は聖アントワーヌの誘惑の新しいシリーズに取りかかるつもりでここにやってきたのですが、自然に逆らわないためにふたたび木炭を取りあげました。ここはその源泉です。だから私は譲歩するのです。(アンドレ・ポンジュ宛 1895年8月7日付け)(303頁)
■人間存在の内なる想像力のメタファーともいうべき《黒》を渉猟しつくしたルドンが1890年代をつうじて《色彩》へと飛翔していったことは、この画家の生涯を一本の樹木にたとえるならば、なかば必然的、いやむしろ論理的なことである。大地という暗闇に根ざしつつ長い年月をかけてついに開花し、澄明な大気のもとでいまや咲き誇るこの樹木ほどに、この寡黙な画家にかんする美しいイメージはない。しかしながら、作品の価格の高騰とも結びついたこうした華麗さの一方で、この本質的にロマン主義的な画家の作品世界にどこかしら悲壮なものが漂いはじめるのもまた否定しがたい事実である。これはあの天上的な、夢幻の花ばなをいっているのではない。あれはパステルであれ油彩であれ、素材との直接性ないし交感を重んじた、この内面性にして力動的な想像力の画家であってこそ達成しえたひとつの精華ともいうべきものだ。ルドンの花ばなに集約されているのは、手つかずで存在するもの、まさにその現前の心からの賛美である。(319頁)
2010年3月28日