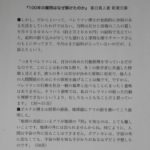『風姿花伝』 世阿弥著 岩波文庫
■されば、古きを學び、新しきを賞する中にも、全く、風流を邪にすることなかれ。ただ、言葉賤しからずして、姿幽玄ならんを、(承けたる)〔正しく傅統をうけついでいる〕とは申すべきか。先ず、(この)道に至らんと思はん者は、非道〔専門外のこと。能藝以外の道〕行ずべからず。ただし、歌道は風月延年(ふげつえんねん)の飾り〔風月の景をかりた延年の舞である申樂に美を加えるもの〕なれば、もつともこれを用ふべし。およそ、若年より以來(このかた)、見聞き及ぶところの稽古の條々、大概注(しる)し置くところなり。
1、好色・博奕(ばくえき)、大酒、三重戒、これ古人〔世阿弥の父、観阿弥清次。〕の掟なり。
1、稽古は強かれ、諍識〔情識のあて字。自分勝手な慢心から生ずる争い心〕はなかれとなり。(10~11頁)
■(五十有餘)この比(ころ)よりは、大方、せぬならでは、手立あるまじ〔「せぬ」という方法より外に方法はあるまい〕。「麒麟も老いては駑馬(とば)に劣る」と申す事あり。さりながら、誠に得たらん能者ならば、物數はみなみな失せて、善悪見所は少(すくな)しとも、花は殘るべし。
亡父〔観阿弥。至徳元年(1384)歿〕にて候ひし者は、五十二と(申しし)五月(十九日)に死去せしが、その月の四日の日、駿河の國淺間〔静岡にある浅間神社であろう〕の御前(おんまえ)にて法樂〔神社に奉納し、神慮・仏意を慰め奉る能〕仕り、その日の申樂、殊に花やかにて、見物の上下、一同に褒美せしなり。およそ、その比(ころ)、物數をば早や初心に譲りて〔年若いシテにさせて〕、やすき所を少な少なと色へて〔色どって〕せしかども、花はいや増しに見えしなり。これ、誠に得たりし〔体得した〕花なるが故に、能は枝葉も(少く)、老木(おいき)になるまで、花は散らで殘りしなり。これ、目(ま)のあたり、老骨に殘りし花の證據なり。(21~22頁)
■老人の物まね、この道の奥儀なり。能の位、やがて外目に現はるる〔演者の藝位が(老人に扮すると)すぐ見物人に見えてしまう〕事なれば、これ、第一の大事なり。
およそ、能をよきほど〔相当に〕極めたる爲手(して)も、老いたる姿は得ぬ人〔手に入っていない人〕多し。例へば、木樵、鹽汲(しほくみ)の態(わざ)(物)などの翁形(おきなかたち)をし寄せぬれば、やがて上手と申す事、これ、誤りたる批判なり。冠(かぶり)・直衣(なほし)、烏帽子・狩衣の老人の姿、得たらん人ならでは、似合ふべからず。稽古の劫(こふ)入りて〔年功を積んで〕、位上(のぼ)らでは、似合ふべからず。
また、花なくば、面白き所あるまじ。およそ、老人の立ち振舞、老いぬればとて、腰・膝(を)屈め、身を詰むれば〔體をちぢめるようにすると〕、花失せて、古様(こやう)に〔古くさく〕見ゆるるなり。さるほどに、面白き所稀なり。ただ、大方、いかにもいかにも、そぞろかで〔はしたなくならないようにつつしんで〕、しとやかに立ち振舞ふべし。殊さら、老人の舞かかり、無上の大事なり。花ありて年寄と見ゆるる公案〔工夫すべき課題〕、委(くは)しく口傅あり。習ふべし。ただ、老木に花の咲かんが如し。(26~27頁)
■(直面(ひためん)〔シテが面をつけないで、素顔のままでする能〕)これまた、大事なり。およそ、もとより俗の身なれば、やすかりぬべき事なれども〔一體(直面物は対象が大てい)俗人であるから、(俗人である役者にとって)やさしいはずであるが〕、不思議に、能の位上らねば、直面は見られぬものなり。
先ず、これは、假令(けりょう)〔大體〕、その物その物によりて學ばん事、是非なし〔勿論である〕。面色をば似すべき道理もなきを、常の顔に變へて、顔氣色(かおけしき)を繕ふ事あり。さらに見られぬものなり。振舞・風情をば、その物に似すべし。顔氣色をば、いかにもいかにも、己(おの)れなりに、繕はで直(すぐ)に持つ〔あるがままに、あたり前にしている〕べし。(28頁)
■親に別れ、子を尋ね、夫に捨てられ、(妻)に後(おく)るる、かようの思ひに狂亂しる物狂ひ、一大事なり。よきほどの爲手(して)〔相当にできる役者〕も、(ここを)心に分けずして、ただ一偏に〔どれもこれも同じように〕狂ひ働くほどに、見る人の感もなし。思ひ故の物狂ひをば、いかにも、物思ふ氣色を本意に當てて、狂ふ所を花に當てて、心を入れて狂へば、感も、面白き見所も、定めてあるべし。かやうなる手柄〔手ぎわ〕にて、人を泣かする所あらば、無上の上手と知るべし。これを、心底に、よくよく思ひ分くべし。(29頁)
■また、直面(ひためん)の物狂ひ、能を極めてならでは、十分にはあるまじきなり。顔氣色をそれになさねば、物狂ひに似ず。得たる所なくて、顔氣色を變ゆれば、見られぬ所あり。物まねの(奥義)とも申しつべし。大事の申樂などには、初心の人、斟酌すべし。直面の一大事、二色(ふたいろ)を一心になして、面白き所を花に當てん事、いかほどの大事ぞや。よくよく稽古あるべし。(30~31頁)
■問。ここに大(おおい)なる不審あり。早や劫(こう)入りたる爲手(して)の〔(相手が)年功を積んだシテで〕、しかも名人なるに、ただ今の若き爲手の立合に、(勝つ)事あり。これ、不審なり。
答。これこそ、先に申しつる、三十以前の時分の花なれ。古き爲手は早や花失せて、古様なる時分に、珍しき花にて勝つ事あり。眞實の目利きは見分くべし。さあらば、目利き・目利かず、批判の勝負〔見物人の批判力の優劣を争う勝負〕になるべきか。
さりながら、様(やう)あり〔仔細がある〕。五十以來まで花の失せざらんほどの爲手には、いかなる若き花なりとも、勝つ事はあるまじ。ただ、これ、よきほどの上手の、花の失せたる故に、負くる事あり。いかなる名木なりとも、花の咲かぬ時の木をや見ん〔木を見ようか、それとも〕、犬桜の一重なりとも、初花色々と咲けるをや見ん〔咲いているのを見るだろうか、勿論後者である〕。かやうの譬(たと)へを思ふ時は、一旦の花〔一時的な花。時分の花〕なりとも、立合に勝つは理(ことわり)なり。
されば、肝要、この道は、ただ、花が能の命なるを、花の失するをもしらず、本(もと)の名望ばかりを頼む事、古き爲手(して)の、返す返(がえ)す誤りなり。物數をば似せたりとも〔數々の物まねに通じても〕、花のあるやうを知らざらんは、花咲かぬ時の草木を集めて見んが如し。萬木千草において、花の色も皆々異なれども、面白しと見る心は、同じ花なり。物數は少くとも、一方(ひとむき)の花を取り極めたらん爲手は一體(てい)の名望〔その一體についての名望〕は久しかるべし。されば、主(ぬし)の心には、随分花ありと思へども、人の目に見ゆるる公案なからんは、田舎の花・藪梅などの、徒らに咲き匂はんが如し。
また、同じ上手なりとも、その内にて重々あるべし〔段階段階があるであろう〕。たとひ、随分極めたる上手・名人なりとも、この花の公案なからんは、上手にて(は)通るとも、花は後まではあるまじきなり。公案を極めたらん上手は、たとへ、能は下るとも、花は殘るべし。花だに殘らば、面白さは一期(ご)あるべし。されば、誠の花の殘りたる爲手には、いかなる若き爲手なりとも、勝つ事はあるまじきなり。(46~47頁)
■そもそも、風姿花傅の條々、大方。外見の憚(はばか)り、庭訓(ていきん)のため注(しる)すといへども、ただ望む所の本意とは、當世、この道の輩(ともがら)を見るに、藝の嗜(たしな)みは疎(おろそか)かにて、非道〔能藝以外の道〕のみ行じ、たまたま當藝に至る時も、ただ一夕の見證(けしょう)〔藝道上の一時的な悟り〕、一旦の名利に染みて、源を忘れて流れを失ふ事、道すでに廢(すた)る時節かと、これを歎くのみなり。しかれば、道を嗜(たしな)み、藝を重んずる所、私なくば〔私心を去ったならば〕、などかその徳〔能藝にはげむことによって得られるよい結果〕を得ざらん。殊さら、この藝、その風を継ぐ〔古来の遺風伝統を継承する〕といへども、自力より出づる振舞あれば、語にも及び難し。その風を得て、心より心に傅はる花なれば、風姿花傅と名附く。(69頁)
■およそ、能の名望を得る事、品々(しなじな)多し〔いろいろな場合がある〕。上手は、目利(き)かず〔鑑賞眼の低い人〕の心に相叶(かな)ふ事難(かた)し。下手は、目利きの眼(まなこ)に合う事なし。下手にて目利きの眼に叶はぬは、不審あるべからず。上手の、目利かずの心に合わぬ事、これは、目利かずの眼の及ばぬ所なれども、得たる上手にて、工夫あらん爲手(して)ならば、また、目利かずの眼にも面白しと見るやうに、能をすべし。この工夫と達者とを極めたらん爲手をば、花を極めたるとや申すべき。されば、この位に至りたらん爲手は、いかに年寄りたりとも、若き花〔年若いシテの持つ時分の花〕に劣る事あるべからず。されば、この位を得たらん上手こそ天下にも許され、また、遠國(おんごく)・田舎の人までも、遍(あまね)く、面白しとは見るべけれ。この工夫を得たらん爲手は、和州へも、江州へも、もしくは田樂の風體(ふうてい)までも、人の好み・望みによりて、いずれにも亙(わた)る上手なるべし。この嗜みの本意を顯(あら)はさんがため、風姿花傅を作するなり。
かやうに申せばとて、我が風體の形木(かたぎ)の疎(おろそ)かならんは、殊(こと)殊に、能の命あるべからず。これ、弱き爲手(して)なるべし。我が風體の形木を極めてこそ、遍(あまね)き風體をも知りたるにてはあるべけれ。遍き風體を心にかけんとて、我が形木に入らざらん爲手は、我風體を知らぬのみならず、他所(よそ)の風體をも、確かにはまして知るまじきなり。されば、能弱くて、久しく花はあるべからず。久しく花のなからんは、いづれの風體をも知らぬに同じかるべし。しかれば、花傅の花の段に、「物數を盡(つく)し、工夫を極めて後、花の失せぬ所をば知るべし」と云へり。(73~74頁)
■(秘)儀に云はく、「そもそも、藝能とは、諸人(しょにん)の心を和げて、上下の感をなさん事〔上下の人々を一様に感動させること〕、壽福増長〔壽命福徳を増すこと〕の基(もとい)、遐齢(かれい)・延年〔どちらも壽命をのばすこと〕の法なるべし。極め極めては、諸道悉く、壽福延長ならん」となり。殊さら、この藝、位を極めて、佳名を殘す事、これ、天下の許されなり。これ、壽福増長なり。
しかれども、この故實〔心得べきこと〕あり。上根・上智〔根機も智慧もすぐれていること〕の眼(まなこ)に見ゆるる所、長(たけ)・位の極まりたる爲手(して)におきては、相應至極なれば、是非なし。およそ、愚かなる輩(ともがら)、遠國(をんごく)・田舎の賤しき眼には、この長(たけ)・位の上れる風體、及び難し〔鑑賞することができない〕。これをいかがすべき。
この藝とは、衆人愛敬(しゆにんあいぎやう)〔見物人からあまねく愛敬されること〕をもて、一座建立〔一座が繁榮していくための〕の壽福とせり。故に、餘(あま)り及ばぬ風體のみなれば、また、諸人の褒美缺(か)けたり。このために、能に初心を忘れずして、時に應じ、所によりて、愚かなる眼にもげにもと思ふやうに能をせん事、これ、壽福なり。よくよく、この風俗の極めを見るに〔世の習わしの根本に照らして考えてみると〕、貴所・山寺・田舎・遠國・諸社の祭禮に至るまで、おしなべて、譏(そし)りを得ざらんを、壽福の達人の爲手(して)とは申すべきか。されば、いかなる上手なりとも衆人愛敬(しゆにんあいぎやう)缺けたる所あらんを、壽福増長の爲手とは申し難し。しかれば、亡父は、いかなる田舎・山里の片邊(かたほとり)にても、その心を受けて、所の風儀を一大事にかけて、藝をせしなり。(75~76頁)
■およそ、花傅の中、年來稽古より始めて、この條々を注(しる)す所、全く、自力より出づる才覺ならず。幼少より以來(このかた)、亡父の力を得て人と成りしより二十餘年が間、目に觸(ふ)れ、耳に聞き置きしまま、その風を承(う)けて、道のため、家のため、これを作する所、私あらんものか。(78~79頁)
■一、作者の思ひ分くべき事あり。ひたすら静かな本木(もとき)の音曲ばかりなると、また、舞・働きのみなるとは、一向きなれば、書きよきものなり。音曲にて働く能〔謡をもとにして所作をする能〕あるべし。これ、一大事なり。眞實面白しと感をなすは、これなり。聞く所は、耳近かに、面白き言葉にて、節のかかりよくて、文字移りの美しく續きたらんが、殊さら、風情を持ちたる詰め〔演技の面白さを伴う一曲のやま〕を嗜(たしなみ)みて書くべし。この數々相應する所にて、諸人(しょにん)一同に感するなり。
さるほどに、細かに知るべき事あり。風情を博士(はかせ)にて〔所作を基準として〕音曲をする爲手(して)は、初心の所なり。音曲より働きの生ずるは、劫(こふ)入りたる故〔年功を積んだため〕なり。音曲は聞く所、風體は見る所なり。一切の事は、謂はれを道にしてこそ、萬(よろず)の風情にはなるべき理(ことわり)なれ。謂はれを現はすは、言葉なり。さるほどに、音曲は體(たい)なり、風情は用なり〔耳に入る音曲は體で、それから生ずる、眼に見える姿は用である〕。しかれば、音曲より働きの生ずるは、順なり。働きにて音曲するは、逆なり。諸道・諸事において、順・逆とこそ下(くだ)るべけれ。逆・順とはあるべからず。返す返(がえ)す、音曲の言葉の便りをもて、風體を彩り給ふべきなり。これ、音曲・働き、一心になる稽古なり。
さるほどに、能を書く所に、また工夫あり。音曲より働きを生じさせんがため、書くところをば、風情を本(ほん)に書くべし。風情を本に書きて、さて、その言葉を謡ふ時には、風情おのづから生ずべし。しかれば、書く所をば、風情を先立てて、しかも、謡ひの節かかりよきやうに嗜むべし。さて、當座の藝能に至る時は、また、音曲を先とすべし。かように嗜みて、劫入(こふい)りぬれば、謡ふも風情、舞ふも音曲なりて、萬曲一心たる達者〔あらゆる能を、音曲・風體一心に演じ得る達者〕となるべし。これまた、作者の高名なり。(83~84頁)
■一、能に、強き・幽玄・弱き・荒きを知る事、大方は見えたる事なれば、たやすきやうなれども、眞實これを知らぬによりて、弱く、荒き爲手(して)多し。先ず、一切の物まねに、偽(いつは)る所〔眞實でない所。ほんとうの物眞似になっていない所〕にて、荒くも弱くもなると知るべし。この境、よきほどの〔いいかげんな〕工夫にては、紛(まぎ)るべし。よくよく、心底を分けて案じ納むべき事なり。
先ず、弱かるべき事を強くするは、偽りなれば、これ、荒きなり。強かるべき事に強きは、これ、強きなり。荒きにはあらず。もし、強かるべき事を、幽玄にせんとて、物まね似たらずば、幽玄にはなくて、これ、弱きなり。さるほどに、ただ、物まねに任せて、その物に成り入りて、偽りなくば、荒くも弱くもあるまじきなり。また、強かるべき理(ことわり)過ぎて強きは、殊さら荒きなり。幽玄の風體よりなほ優しくせんとせば、これ、殊さら弱きなり。
この分け目をよくよく見るに、幽玄と強きは別(べち)にあるものと心得る故に、迷うなり。この二つは、その物の體にあり。例えば、人においては、女御(にようご)・更衣、または、遊女・好色〔美女〕・美男・草木には花の類(たぐ)ひ、かやうの數々は、その形、幽玄の物なり。また、あるいは武士(もののふ)・荒夷(あらえびす)、あるいは鬼・神、草木にも松・杉、かやうの數々の類ひは、強き物と申すべきか。かやうの萬物の品々を、よくし似せたらんは、幽玄の物まねは幽玄になり、強きはおのづから強かるべし。この分け目をばあてがはずして〔考慮しないで〕、ただ幽玄にせんとばかり心得て、物まねおろそかなれば、それに似ず。似ぬをば知らで幽玄にするぞと思ふ心、これ、弱きなり。されば遊女・美男などの物まねをよく似せたらば、おのづから幽玄なるべし。ただ、似せんとばかり思ふべし。また、強き事をも、よく似せたらんは、おのづから強かるべし。(85~86頁)
■そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫(もてあそ)ぶなり。申樂も、人の心に珍しきと知るところ、卽(すなは)ち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは、同じ心なり。いづれの花か散らで殘るべき。散る故によりて、咲く比(ころ)あれば、珍しきなり。能も住(ぢゆう)する所なきを、先ず、花と知るべし。住せずして、餘(よ)の風體(ふうてい)に移れば、珍しきなり。
ただし、様(やう)あり。珍しきといへばとて、世になき風體をし出(い)だすにてはあるべからず。花傅に出だす所の條々悉(ことごと)く稽古し終りて、さて、申樂をせん時に、その物數を用々に従ひて、取り出だすべし。花と申すも、萬(よろず)の草木において、いづれか、四季(折節)の、時の花の外に、珍しき花のあるべき。その如くに、習ひ覺えつる品々を極めぬれば、時・折節の當世を心得て、時の人の好みの品によりて、その風體を取り出だす、これ、時の花の咲くを見んが如し。花と申すも、去年(こぞ)咲きし種なり。能も、もと見し風體なれども、物數を極めぬれば、その數を盡(つく)す(ほど)久しし。久しくて見れば、また珍しきなり。(92~93頁)
■物まねの鬼の段に、「鬼ばかりをよくせん者は、鬼の面白き所をも知るまじき」と申したるも、物數を盡(つく)して、鬼を珍しくし出だしたらんは、珍しき所花なるべきほどに、面白かるべし。餘の風體はなくて、鬼ばかりを(をする)上手と思はば〔(見物人が)あのシテは鬼ばかりを演ずる上手だと思っていたのでは〕、よくしたりとは見ゆるるとも、珍しき心あるまじければ、見所に花はあるべからず。「巌(いはほ)に花の咲かんが如し」と申したるも、鬼をば強く、恐ろしく、肝を消すやうにするならでは、およその風體なし。これ、巌なり。花といふは、餘の風體を残さずして、幽玄至極の上手と人の思ひ慣れたる所に、思ひの外に鬼をすれば、珍しく見ゆるる所、これ、花なり。しかれば、鬼ばかりをせんずる爲手(して)は、巌ばかりにて、花はあるべからず。(94~95頁)
■一、能に十體(じつてい)〔物まねのあらゆる風體〕を心得べき事。十體を得たらん爲手は、同じ事を、一廻り一廻りづつするとも、その一通りの間久しかるべければ、珍しかるべし。十體を得たらん人は、その内の故實・工夫にては、百色(ももいろ)にも亙(わた)るべし。先づ、五年・三年の中(うち)に一遍づつも、珍しくし替ふるやうならんずるあてがひ〔とりはからい。計畫〕を持つべし。これは、大きなる安立(あんりふ)〔安心立命の略。心頼み〕なり。または、一年の中(うち)、四季折節をも心に掛くべし。また、日を重ねたる申樂、一日の中(うち)は申すに及ばず、風體の品々を彩るべし。かやうに大がう〔大庭の晴れの演能〕より初めて、ちちとある事までも自然々々に心に掛くれば、一期、花は失せまじきなり。
また云はく、十體を知らんよりは、年々去來の花を忘るべからず。年々去來の花とは、例へば、十體とは物まねの品々なり。年々去來とは、幼かりし時の粧ひ、初心の時分の態(わざ)、手盛(てざか)り〔わざに油ののった30前後の頃〕の振舞、年寄りての風體、この時分々々の、おのれと身にありし風體を〔しぜんと身に備わっていた風體〕、皆、當藝に一度に持つ事なり。ある時は兒(ちご)、若族(にゃくぞく)の能(か)と見え、ある時は年盛りの爲手(して)かと覺え、または、いかほども臈たけて〔年劫を經て〕、劫入りたるやうに見えて、同じ主とも見えぬやうに能をすべし。これ、卽(すなは)ち、幼少の時より老後までの藝を一度に持つ理(ことわり)なり。さるほどに、(年々(としどし))去り來る花〔年齢に應じて、過去に身につけた花と、將來身にそなわるべき花〕とは云へり。(99~100頁)
■されば、初心よりの以來(このかた)の、藝能の品々を忘れずして、その時々、用々に従ひて取り出だすべし。若くては年寄の風體、年寄りては盛りの風體を殘す事、珍しきにあらずや。しかれば、藝能の位上れば、過ぎし風體をし捨てし捨て忘るる事、ひたすら、花の種を失ふなるべし。その時々にありし花のままにて、種なければ、手(た)折れる(枝の花)の如し。種あらば、年々時々の比(ころ)に、などか逢はざらん。ただ、返す返す、初心を忘るべからず。されば、常の批判〔常々聞かれる批評のことば〕にも、若き爲手(して)をば、「早く上(あが)りたる」、「劫(こふ)入りたる」なと譽め、年寄りたるをば、「若やぎたる」など、批判するなり。これ、珍しき理(ことわり)ならずや。十體の内を彩らば、百色(ももいろ)にもなるべし。その上に、年々去來の品々を、一心當藝(いつしんたうげい)に〔一身に當座の藝として〕持ちたらんは、いかほどの花ぞや。(101頁)
■一、因果の花を知る事、極め〔究極。極意〕なるべし。一切、みな因果なり。初心よりの藝能の數々は、因なり。能を極め、名を得る事は、果なり。しかれば、稽古するところの因おろそかなれば、果を果すことも(難し)。これをよくよく知るべし。また、時分〔時の運〕にも恐るべし。去年盛りあらば、今年は花なかるべき事を知るべし。時の間(ま)にも、男時(おどき)・女時(めどき)とてあるべし。いかにすれども、能にも、よき時あれば、必ず、また、わろきことあり。これ、力なき因果〔人力ではどうすることもできない因果〕なり。これを心得て、さのみ(に)大事になからん時の申樂には、立合い勝負に、それほどに我意執(がいしふ)〔我意を張ること〕を起さず、骨をも折らで、勝負に負くるとも心に懸けず、手を貯(たば)いて〔わざに餘裕を殘しておいて〕、少な少なと〔控え目に〕能をすれば、見物衆も、これはいかやうなるぞと思ひ醒めたる〔感興がうすらいでいる。興ざめしている〕所に、大事の申樂の日、手立てを變へて、得手の能をして、精勵(せいれい)を出だせば、これまた、見る人の思ひの外なる心出で來れば、肝要の立合、大事の勝負に、定めて勝つ事あり。これ珍しき大用〔珍しさの大きなはたらき〕なり。これほどわかりつる因果に、またよきなり。(106頁)
(2012年4月7日)