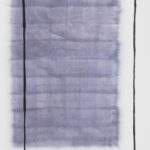読書ノート(2015年)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『釈尊のさとり』 増谷文雄著 講談社学術文庫
識 語
■この小さな著作をよんでくださる方々に、まず3つのことを申しあげておきたいと思います。
その第一には、釈尊の「さとり」は直観であるということであります。直観というものはそれを説明してみよといわれても、言葉では説明できるものではありません、むかしの禅語に、「言語(ごんご)道断」とか、「言詮(こんせん)不到」などというのはそのことであります。
わたしは、ながい間にわたって、ただ一人の人物を見詰めてまいりました。それは、ほかでもない、釈尊その人であります。そして、釈尊の生涯とその思想において、その眼目をなすものは、申すまでもなく、かの菩提樹下における大覚成就、すなわち「さとり」であります。だが、それが、どうも、はっきりと把握できない。わたしにとっては、それがじれったくてたまらなかったのであります。だが、やっと、わたしも知ることができました。その「さとり」とは、まさしく直観であったということであります。
その第二には、その直観なるものは、受動的なものだということであります。そのことについては、わたしは、道元禅師によって啓発せられました。それは、本文のなかでも述べておいたことでもありますが、かの『正法眼蔵』の第三巻、「現成公案」のなかにおいて、道元禅師は、「自己をはこびて万法を修証(しゅしょう)するを迷いとす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり」と説いておられます。ただ「あっ、そうか」と触発せられるのが直観なのであります。それを、ああであろうか、こうであろうかと、自己の思考をもって模索するは迷いであります。
だが、しかし、そのようにして与えられた直感を、こんどは思いととのえる。すなわち、知性化することは、わたしどもの悟性の役割であります。そこで、やっと気が付いてみると、かの大覚を成就した釈尊が、なおもしばらくの間、かの樹下にとどまって思索せられたのは、それがそのような知性のいとなみのためにほかならなかったのであります。釈尊の「さとり」は、そこまで到って完成したのであります。わたしが、その樹下における釈尊のさまざまの思索についても、くどくどと申しあげたのは、その故であります。
その第三には、この小さな著作のなれる因縁について申しあげておかねばなりません。これは、一昨年、昭和五十二年九月のこと、わたしは、富山県の県民大学校地方講座に出講いたしまして、そのようにして思い整えたところを、「釈尊のさとり」という演題をもって講述いたしました。それを、富山県教育委員会においては、筆録して下さったうえ、同委員会編集の「精神開発叢書」(非売品)として上梓してくださったのであります。
しかるところ、それがさらに、講談社の編集部の方のお目にとまりまして、「学術文庫」の一冊に加えていただくことになったのであります。その因縁をはぐくんで下さった方々には、ふかく感謝いたさなければなりません。
そのようにして、この「学術文庫」の一冊に加えていただくに当っては、わたしは、旧稿に、あらためて、いささか筆を加えました。たとえば、講演では正確な表現ができなかったところを、より正確に叙述をあらためるとか、あるいは、経典などからの引用は、それをより正確にし、かつ、その出処を明記するなどであります。だが、その全体としては、もともと講演の筆録でありますので、講演のままといたしました。諒としていただきたいと思います。(3~5頁)
■それから、「現成」というのは、「実現する」とか「成就する」とかいう意味のことばで、これは古くから仏教でもちいられております。たとえば、「現成正覚」というと、他でもない、釈尊その人が「さとり」を成就したことをいう荘厳なる表現であります。
しかるに、いま禅家においては、雲水や居士たちが、御老師から公案すなわち課題をいただいて、坐禅修行のなかにおいてかの「さとり」を再体験しようとする。それを、釈尊の「現成正覚」にちなんで、ここに「現成公案」と表現されているのであります。つまり、「現成公案」とは、釈尊の道をあるこうとする者におけるの実現をいうことばであると知られるのであります。(岡野注;現成公案の私の解釈は違います)
そのなかにおいて、道元禅師は、「迷(まよい)」と「悟(さとり)」を語って、つぎのような素晴しい一節をなしているのであります。いわく、
「自己をはこびて万法を修証するを迷とす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり」「自己をはこぶ」というのは、自分のほうからすすんでというほどの意であります。「万法を修証する」とは、一切の存在、ありとあらゆるものを弁別するほどの意であります。といたしますと、この第一句のいうところは、「一切の存在のありようを、自分の方からすすんで、あれはこうであろう、これはこうであろうという具合に心を動かすことは迷いなのだ」ということであります。(20~21頁)
■さらに申しますなれば、一切の存在は、いつもその真相は、わたしどもの前に明らかに露呈しておるのでありました。それを、むかしの禅家のかたがたは、よく「万法露々(ばんぽうろろ)」などと申しておられました。一切の存在は、なんの隠すところもなく、その真相を露呈しているのであります。「柳はみどり、花はくれない」であります。その露々として現じている姿を、そのままに受けとるということが大事なのであります。
つまり、「さとり」というものは直観である。直観というものは受動性そのものである。そのことをはっきりと把握していただきますと、さきに申しましたように、がその正覚成就の消息についた、なにも語りのこしておられないことの事情もまた、よく判っていただけるはずであります。
また、鈴木大拙先生がそのことを語って、「その時、釈尊の頭のなかには、大きなクェスチョン・マークがあった」などと独特の表現をなされた、そのふかい含蓄もまた、理解していただけるはずでございます。(22頁)
■「かようにわたしは聞いた。
はじめて正覚を成就したまえる世尊は、ある時、ウルヴェーラー(優楼比螺)村のランジャラー(尼連禅)河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の初分(午後8時ごろ)のころ、つぎのように、順序にしたがって、縁起の法をよくよく観じもうた。〈これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず〉すなわち、無明(無智)に縁(よ)りて行(意志、ギョウ)がある。行によりて識(意識)がある。識によりて名色(個体)がある。名色によりて六処(6つの感官、ロクショ)がある。六処がよりて触(対象との接触、ソク)がある。触によって受(感覚)がある。受によって愛(貪り)がある。愛によりて取(取着、シュヂャク)がある。取によって有(欲望的存在、ウ)がある。有によって生(迷いの生涯、ショウ)がある。生によって老死があり、愁・悲・苦・憂・悩がある。このすべての苦の生起はかくのごとしである、と。かくて、世尊は、その所得を知って、その時、このようなウダーナ(感興の偈)を唱えたもうた。
『まこと熱意をこめて思惟する聖者に、
かの万法のあらわれとなるとき
彼の疑惑はことごとく消えされり
有因の法を知れるゆえなり』」(28~29頁)
■つづいてその経(「自説経)」は、、まず、
「はじめて正覚を成就したまえる釈尊は、ウルヴェーラー村のネーランジャラー河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
と述べております。
それは、「さとり」の直後、それから七日の間、釈尊は、さきの菩提樹のもとで、ぴたりと結跏趺坐したままで、解脱の楽しみ、すなわち「さとり」の楽しみを、じっと味わっておられたというのであります。(30頁)
■さらに続いて、この経は、
「七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の初分のころ、つぎのように、順序にしたがって、縁起の法をよくよく観じたもうた」
と叙べています。
それまで、釈尊はもっぱら「さとり」の楽しみを享受することに浸っておられましたが、ここで釈尊の悟性は、はっきりと働きはじめたのであります。その与えられたる直感を素材として、いまや、その論理的関係を追究する人間の思惟が作用しはじめたのであります。7日を過ぎたのち、世尊は、「その定より起って」とあります。「定」とは、また「三昧」(concentration)という。心を一境に集注すること。その時には、心念はほぼ停止するがゆえに、それをまた「定」と訳するのであります。
それまで、釈尊は、その定中にあって「解脱のたのしみを享けつつ坐したもうた」のでありました。だが、いまは、「その定より起って」、縁起の論理的関係を追究しはじめたのであります。直観の受動態をひるがえして、悟性の能動的活動がはじめられたのであります。
そして、その悟性のいとなみとして、最初になった成果は、そこに、つぎのように語られております。
「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」
それを、漢訳をもって申しますと、「因是有是、比生則生」(これによってこれあり、これ生ずればこれ生ず)などと見えております。(31~32頁)
■それにつけても、ふと思いだすのでありますが、経典にしばしば見えていることばに、「阿耨多羅三藐三菩提」という述語がございます。仏教を学びはじめた頃には、なんとまあむずかしいことばであろうかと思ったことがありましたば、それもそのはずでありまして、これは梵語の音写でありました。
それを意訳いたしますれば、「無上正等覚」などとなることばであります。「無上」というは最高ということ、「正」というは妥当すること、そして、「等」というは普遍なることを意味するのであります。それを今日の学術的な用語をもっていうならば、最高の普遍妥当性を有する真理であることを意味することばであります。(33~34頁)
■では、その苦の問題について、釈尊はどのように考えたのでありましょうか。それは、この経が、つづいて述べているながながしい連鎖のつづきであります。いわく、
「すなわち、無明によりて行がある。行によりて識がある。識によりて名色がある。名色によりて六処がある。六処によりて触がある。触によりて受がある。受によりて愛がある。愛によりて取がある。取によりて有がある。有によりて生がある。生によりて老死があり、愁・悲・苦・憂・悩がある。このすべての苦の生起はかくのごとしである」
そこには、「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」という公式にあてて、その生起の条件を順次に思いめぐらしてゆくと、そこには、明・行(ぎょう)・識・名色・六処・触(そく)・受・愛・取・有(う)・生(しょう)・老死と、十二の条件が順次に連鎖をなしていることが考えられたのであります。
それがいうところの十二縁起、もしくは十二因縁と称せられるところのものでして、そのような条件の連鎖によって苦が生起するのだと知られたのでありました。(34~35頁)
■では、その経もまた、ごく短い経でありますので、そのままに読んでみたいと思います。
「かようにわたしは聞いた。
はじめて正覚を成就したまえる世尊は、ある時、ウルヴェーラー(優楼比螺)村のランジャラー(尼連禅)河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の中分(午前零時ごろ)のころ、つぎのように、逆次にしたがって、縁起の法をよくよく観じもうた。〈これなければこれなし、これ滅すればこれ滅す〉すなわち、無明(無智)の滅によりて行(意志、ギョウ)滅す。行の滅によりて識(意識)滅す。識の滅によりて名色(個体)滅す。名色の滅によりて六処(6つの感官、ロクショ)滅す。六処の滅によりて触(対象との接触、ソク)滅す。触の滅によりて受(感覚)滅す。受の滅によりて愛(貪り)滅す。愛の滅によりて取(取着、シュヂャク)滅す。取の滅によりて有(欲望的存在、ウ)が滅する。有が滅すれば生(迷いの生涯、ショウ)が滅する。生が滅すれば老死が滅し、愁・悲・苦・憂・悩が滅する。このすべての苦の滅はかくのごとくである、と。かくて、世尊は、その所得を知って、その時、このようなウダーナ(感興の偈)を唱えたもうた。
『まこと熱意をこめて思惟する聖者に、
かの万法のあらわれとなるとき
彼の疑惑はことごとく消えされり
諸縁の滅を知れるがゆえなり』」(36~37頁)
■この経の叙するところも、また、さきの経の叙述によく似ているようでありますが、よく読んでみると、大事なところで、二つの対照的なちがいを存しております。
その第一は、例の「縁起の公式」についてでありますが、さきの経においては、それは、
「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」
と述べられてありましたが、この経においては、それに対するところは、こんどは、
「これなければこれなし、これ滅すればこれ滅す」
と述べられてあります。それを漢訳についてみると、「比滅即滅、比無即無」(これ滅すればすなわち滅す、これ無ければすなわち無し)などとなっております。それを、さきの表現を「縁起の公式」と申しますならば、この表現は「縁滅の公式」とでもいうところでございましょう。そして、さきの 「縁起の公式」に対しまして、さらにこの「縁滅の公式」が成立することによって、釈尊の「さとり」は、はじめて完全なものとなるのであります。
なんとなれば、すでに申したように、釈尊が、その出家に際して胸奥にいだいていた課題は、他でもない、苦の問題でありました。その苦なるものはいかにして存するものであるか。いかにして苦なるものは生起するのであるか。そのことについて、「このすべての苦の生起はかくのごとくである」と、みごとにその「縁(よ)りて起る」ところを解明しえたのは、さきの「縁起の公式」によるものでありました。(37~38頁)
■だが、その生起の条件をあきらかにしただけでは、まだまだ課題は解決したわけではありません。そこにはもう一つ、ではいかにして克服するか。その方途が確立されねばなりません。その方途のよりて考えられるべき準則が、この「縁滅の公式」なのでありました。
では、その苦を滅尽するためには、釈尊はどのように考えたのでありましょうか。それを、この経もまた、ながながしい連鎖をもって、つぎのように語っております。それが、第二のちがいであります。いわく、
「すなわち、無明(無智)の滅によりて行(意志、ギョウ)滅す。行の滅によりて識(意識)滅す。識の滅によりて名色(個体)滅す。名色の滅によりて六処(6つの感官、ロクショ)滅す。六処の滅によりて触(対象との接触、ソク)滅す。触の滅によりて受(感覚)滅す。受の滅によりて愛(貪り)滅す。愛の滅によりて取(取着、シュヂャク)滅す。取の滅によりて有(欲望的存在、ウ)が滅する。有が滅すれば生(迷いの生涯、ショウ)が滅する。生が滅すれば老死が滅し、愁・悲・苦・憂・悩が滅する。このすべての苦の滅はかくのごとくである」
そこでは、「これでなければこれなし、これ滅すればこれ滅す」という、いうところの「縁滅の公式」にあてて、その滅尽の条件を、こんどは逆の順序によって思いめぐらしてゆく。すると、そこには、無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死と、さきの十二の条件が、今度は逆の順序によって連鎖をなしていることがしられたのであります。
それもまた、いうところの十二縁起、もしくは十二因縁と称せられるところのものでありまして、そのような条件の連続によって、苦の滅尽が実現せられるというのであります。
かくて、この経は、
「まこと熱意をこめて思惟する聖者に
かの万法のあらわとなれるとき
彼の疑惑はことごとく消え去れり
諸縁の滅を知れるがゆえなり」
との偈をもって結ばれているのであります。
釈尊は、かの菩提樹のもとにおいて、ついに正覚を成就なされてからも、なお、おなじ樹下にとどまられること、さらに二週間、もしくは三週間、その間には「さとり」の内容をいろいろ整理しておられました。さきに申した二つの経典の叙するところは、その間における釈尊の、貴重なる悟性のいとなみの跡でありました。(39~40頁)
■そこに「苦の聖諦」(the proposition about sufferring) というのは、苦についての聖なる命題というほどの意味のことばであります。「比丘たちよ、わたしの苦に関する命題はこれである」と、釈尊はまず、苦とは何であるかについて、この「苦の聖諦」を、はじめて釈尊の説法を聞く五人の修行者のまえに打ち出したのであります。
そこで釈尊が語られたものは、まず、生・老・病・死の四つの苦でありました。これを後代の人々はよく「四苦」と申しました。だが、それだけではない。わたしどもこの人間とてのそんざいは、なおいろいろの苦にとりかこまれています。
「怨憎するものに会うのは苦である」。それを中国の訳経者たちは「怨憎会苦」と訳しました。また、「愛するものと別離するのは苦である」。それを中国の訳経者たちは「愛別離苦」と訳しました。美しい訳語でありました。さらに、「求めて得ざるは苦である」。それは漢訳では「求不得苦(くふとっく)」と訳されました。(42頁)
■そのように追究してまいりますと、結局、「総じていえば、この人間の存在を構成するものすべて苦である」ということになります。それは漢訳においては「五蘊(陰、オン)盛苦」などと訳されております。五蘊もしくは五陰というのは、人間を構成する肉体的および精神的諸要素をあげて、人間存在のすべてを指していることばでありまして、つまり、われら人間の存在は、いずれの面よりいっても、すべて苦におおわれているのだというのであります。(42~43頁)
■それは、釈尊の弟子の比丘のサーリプッタ(舎利弗)が、マガダ(摩掲陀)の国のナーラカ(那羅迦)という剥らにとどまっている解きのことでありました。その村は、彼の故郷でありますので、帰省していたのでもあろうかと思います。そこに、かねて知り合いの外道の遊行者のジャンプカーダカ(闇浮車)なるものが訪ねてまいりまして、いろいろの質問をいたしましたが、そのなかに、つぎのような問答がしるされているのであります。
「友サーリプッタよ、苦、苦と称せられるが、友よ、いったい、苦とはなんであろうか」
「友よ、これらの三つが苦である。すなわち、苦苦性(くくしょう)、行苦性、壊苦性(えくしょう)である。友よ、これらの三つが苦である」
このサーリプッタという比丘は、後年いうところの十大弟子中の随一でありまして、その頭脳の明晰なることで知られ、智慧第一の仏弟子と称せられた方でありますが、いま、この質問にたいする応答もまた、明快なるものであります。(43~44頁)
■彼は、ここで、いわゆる苦なるものを、三つに分類して説明しております。まず、苦苦性というのは、肉体的苦痛によって引き起こされる苦であります。たとえば寒さとか、暑さとか、飢えとか、渇(かつ)とかいった肉体的苦痛によって引き起こされる苦、〝苦しいから苦しい〟といった苦であります。
つぎに、まず、壊苦性(えくしょう)から申しあげると、これは、環境もしくは身分の変化によって起こる苦であります。たとえば、いままで金持ちだったものが貧乏になるとか、高い地位にあったものが左遷されるとか、順境から逆境に転落する。つまり、〝好もしきものが壊する苦しみ〟が壊苦(えく)なのであります。
だが、もう一つの、行苦性というのは、いささか難しい。そこで行とは、古来から「遷流(せんる)」の義ありと注されております。つまり、行とは「移ろう」ということであります。万物は流れるであります。この世はすべて無常転変であるということをいっておる言葉であります。
詮(せん)ずるところ、この世のすべてのものは、一時(いっとき)としてじっとしておるものはない、すべてが絶えず変化しているのであります。だから、そのなかに住むわたしたちの場合も、生ある者はかならず死があるのであります。若きものもかならず老いるのであります。形あるものはかならずいつかは崩れるのであります。まさしく一切が無常なのであります。行苦というのは、そのような世のなかに生きて、そのような有為転変によって感ぜしめられる苦しみなのであります。(44~45頁)
■では、いったいその十二縁起の順観と逆観とが、どのようにして苦の生起を説明し、また、苦の滅尽を可能にするものでありましょうか。それは、わたしどもにとって、容易に理解し、容易に納得することのできるものではございません。それのみではありません。釈尊 が、もともと、はじめてこのことを考えられた時には、それは、このように細かいものではなくて、もっとはるかに簡単な、そして、もっと明瞭なものであったように思われます。そのことをいくつかのふるい経典が示しているのであります。
それをごく簡単なものにして申しますなれば、たとえばそれを、無明と取と苦の三つの支節をもって説明することもできましょう。そこで、まず、無明というのは、迷いの根本としての無知であります。存在と人間の真相について正しい智慧がないことであります。つづいて、取というのは、取りつくことであります。そのことを取著とか、執著といってよいでありましょう。
だが、存在のありようというものが判っていないのでありますから、いくら取りすがってみても、詮ずるところ、それは時の移ろいとともに変化してしまう、あるいは無くなってしまう。それは取りすがっている者にとっては、苦ということになるのであります。
では、それをどうすればよいのでありましょうか。それには、まず無明をなくすことから始めねばなりません。まず無明をなくするためには、まず、一切の存在の真相を正しく見ることが必要であります。無知ではなくて、知が必要であります。仏教というものは、まさしく智慧のおしえであります。かくして、まず、その無明がなくなると、こんどは取がなくなるのであります。すべては時の移ろいとともに変化します。つまり、無常なるものに執着することはなくなるのであります。そして、取がなくなれば、おのずから苦もまたなくなるのであります。といたしますと、無明・取・苦の三支の縁起もまた成立するはずでありましょう。
十二縁起というものは、もともと、そのように簡明であったものが、次第にその支節を増して、このように支節の多いものとなったのでありましょう。(50~51頁)
■かくして、釈尊は、依然としてニグローダの樹下にあって、やがて、この新しい問題のまえに置かれた自分自身を見出したのであります。一つの経(南伝・相応部経典、六、一、勧請。漢訳、増一阿含経、十九、一)は、この新しい問題のまえに置かれた釈尊の心中の思いを、つぎのように描写しているのであります。
「わたしが借りえたこの方は、はなはだ深くして、見がたく、悟りがたい。寂静微妙(じゃくじょうみみょう)にして、思惟の領域をこえ、すぐれたる智者のみのよく覚知しうるところである。しかるに、この世間の人々は、ただ欲望をたのしみ、欲望をよろこび、欲望に躍るばかりである。欲望をたのしみ、欲望をよろこび、欲望におどる人々には、この理(ことわり)はとうてい見難い。この理とは、すべては相依生にして、縁(条件)ありて起こるということであり、また、それに反して、すべての計らいをやめ、すべての所依(しょえ)を捨てされば、渇愛つき、滅しつくして、涅槃にいたるということである。しかるに、もしわたしがこの法を説いても、人々がわたしのいうことを理解しなかったならば、わたしはただ疲労し困憊(こんぱい)するばかりであろう」
そして、いまだかって聞いたことのない未曾有の偈が、釈尊の心の中に浮んできたという。
「苦労してやっと証得したものを
なぜまた人に説かねばならぬのか
貪りと怒りとに焼かれる人々には
この法をさとることは容易ではない
これは世のつねの流れにさからい
甚深(じんじん)、微妙(みみょう)、精細にして知りがたく
欲望の激情にまみれたるもの
無明に覆われしものには悟りがたい」
それら釈尊の心中の思い、ならびに、この偈の語るところは、あきらかに、釈尊が、そのはじめ、法を説くことについて消極的であったことを示しております。(65~67頁)
■だが、そこで、この経の叙述もまた一変して、突如として、神話的叙述がはじまります。こんな具合であります。
「その時、梵天は、世尊の心中の思いを知って、かように考えた。
『ああ、これでは世間は滅びるであろう。これでは世間は滅びるであろう。世尊・応供・等正覚者のゴゴロは、躊躇(ちゅうちょ)に傾きて、法を説きたもうことに傾きたまわず』
そこで梵天は、たとえば、力ある男子が、屈したる腕を伸し、また伸したる腕を屈するがごとく、たちまちに梵天界に姿を没して、世尊のまえに現われた。
そして、梵天は、上衣を一肩に掛け、右膝を大地につけ、世尊を合掌して、礼拝して、申していった。
『世尊よ、法を説きたまえ。善逝(ぜんせい)よ、法を説きたまえ。この世には眼を塵(ちり)におおわるることすくなき人々もある。彼らも、法を聞くことを得なければ堕(お)ちてゆくであろう。この世には、法を理解するものもあるであろう』」
そして梵天は、釈尊に、人間観察を奨(すす)めました。人間というのは、この世間のことであります。そこで、釈尊は、この世の人々の姿を、もう一度、よくよく観察いたしました。すると、そこには、人々の眼の曇りおおきものもあり、曇りすくなきものもありました。利根のものもあれば、鈍根のものもありました。あるいは、教えやすいものもあり、また教えがたいものもありました。そのさまざまなる人間の姿を、経の叙述は、青(しょう)蓮華・黄(おう)蓮華・白(びゃく)蓮華のきそい咲く蓮池に喩えてかたっております。
たとえば、それらの蓮華のなかには、泥の中に生え、泥の中で長じ、泥の中で花を開いているものもありました。あるいはまた、泥の中で生じ、泥の中に長じたけれども、水面をはるかに抜んでて花を開いているものもありました。
そして、人間の世界もまた、それと同じようであることを知りました。衆生のなかには、智慧の眼が煩悩の塵でひどく汚れておるものもあれば また、その汚れのすくないものもありました。それらのことを、釈尊は、よくよく観察いたしました結果、はじめて説法の決意を固められ、梵天にむかって、つぎのような偈を説いたというのであります。いわく、
「彼らに甘露の門はひらかれたり
耳あるものは聞け、ふるき信を去れ」
ここに、「甘露の門はひらかれたり」というのは、この教えの門が開かれたということ。そして、「ふるき信を去れ」というのは、いままでの考え方を一掃して聞くがよいということであります。そして、その経の叙述は、「時に、梵天は、わが説法の願いは、世尊はこれを許したまえりと、世尊を礼拝して、そこから姿を没した」と述べて、この一巻をむすんでおります。(67~70頁)
■だが、やっとそのイシパタナ・ミガダーヤ(仙人住処・鹿野苑)に着いて、彼ら五人の比丘たちを見出すことをえた釈尊は、そこでいきなり、手強い抵抗に遇わねばなりませんでした。彼らは、釈尊が、その練りに練った構想をもって、その証悟せるところを語ろうといたしましても、頑強にそれを拒絶いたしました。苦行を放棄して奢侈(しゃし)に堕(だ)したそなたに、無上の等正覚が成就できようはずはないではないか、というのが、その強硬なる拒絶の理由でありました。(75~76頁)
■そういわれてみると、いま彼らの前に坐する釈尊の顔貌はは、清らかにして輝きわたっておりました。そこで、「では」ということで、その前に坐する五人の比丘たちのまえに、まず釈尊が開陳したものは、初転法輪(しょてんぼうりん)、すなわち、最初の説法の一節は、そのプロローグをなすものでありました。一つの経(南伝・相応部経典、五六、一一、如来所説。漢訳、雑阿含経、一五の一七、転法輪)は、それを、つぎのように記しとどめています。
「比丘はちよ、出家したる者は、二つの極端に親しみ近づいてはならない。その二つとは何であろうか。
愛欲に貪著(とんぢゃく)することは、下劣にして卑しく、また、自ら苦しめることは、ただ苦しいだけであって、聖にあらず、役に立たないことである。比丘たちよ、如来は、この二つの極端を捨てて、中道を悟った。これは、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる。
比丘たちよ、では、如来が、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる中道を悟ったというのは、どのようなことであろうか。それは聖なる八つの道である。すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定である。比丘たちよ、これが、如来の悟りえたるところの中道であって、これが、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめるのである」(76~77頁)
■そこには、彼が、なにゆえに苦行を放棄したか、その所以(ゆえん)が語られています。それとともに、彼の選んだ道が、けっして「奢侈に堕した」ものでなかったことが語られています。彼がそこで選びとったものは、中道(the middle path) 以外のなにものでもありませんでした。そして、その中道こそが、人々に「眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる」ものだと語っているのであります。そして、また、その中道とは、いかなる道であるかというならば、それは聖なる八支の道、すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定がそれであるということでありました。
つまるところ、苦行を放棄してからの釈尊がとった道は、「もろもろの欲望に貪著する」という快楽主義の道でもなく、また、「みずから苦行を事とする」という禁欲主義の道でもなく、それらの二つの極端をしりぞけて、その中道に立つということでありました。
そして、その中道というのは、いったい、いかなる道であるかというならば、それは「聖なる八つの道」、すなわち、「正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定」であると、いとも具体的に示されているのであります。(78~79頁)
■釈尊の最初の説法の本論は四つの命題から成るものでありました。それを、古来から、四諦(したい)もしくは四聖諦(しょうたい)と申してまいりました。それらは、四つの命題からなる釈尊の考え方の基本的構造をなすものでありました。それを釈尊は、最初の説法において、五人の比丘たちのまえに、つぎのように開陳いたしました。
「比丘たちよ、苦の聖諦とはこれである。いわく、生は苦である。老は苦である。病は苦である。死は苦である。愁え・悲しみ・苦しみ・憂(うれ)え・悩みは苦である。怨憎(おんぞう)するものに会うは苦である。愛するものと別離するのは苦である。求めて得ざるはくである。総じていえば、この人間の存在を構成するものはすべて苦である。
比丘たちよ、苦の生起についての聖諦とはこれである。いわく、迷いの生涯を引き起こし、喜びと貪りとを伴い、あれへこれへと絡(から)まりつく渇愛がそれである。すなわち、欲の渇愛・有(う)の渇愛、無有(むう)の渇愛がそれである」
まず、これが、四つの聖諦のうちの、前半の二つの命題であります。(80~81頁)
■さて、前半の二つの命題につづいて、釈尊は、こんどは、後半の二つの命題を、つぎのように開陳いたしました。
「比丘たちよ、苦の滅尽についての聖諦はこうである。いわく、その渇愛をあますところなく離れ滅して、捨て去り、振り切り、解脱して、執着なきにいたるのである。
比丘たちよ、苦の滅尽にいたる道についての聖諦はこうである。いわく、聖なる八支の道、すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定である」(82~83頁)
■もう一度その実践項目を列挙いたしまするならば、「正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定」とあります。それを、わたしは、四つのグループに分類して考えるようにいたしております。
1 正見――正しい見方。
2 正思・正語・正業――身・口・意のいとなみを正しくすること。
3 正命――正しい生き方。
4 正精進・正念・正定――正しい修行のいとなみ。
それは、生活の全分野に渡っての「正しい」生き方のほかの何ものでもないのであります。(84頁)
■では、いったい、そこで「正しい」というのはどういうことでありましょうか。それは、たいへんむずかしい問題でありますが、いまのところは、三つの項目をあげて説明しておきたいと思います。それが、仏教で「正しい」という場合のもっとも重要な条件であります。
その一つは、〝正しい〟とは〝如〟であるということができるようであります。〝如実〟といってもよいでありましょう。〝あるがまま〟であります。それを、いろいろと空想や迷妄をもって飾りたて曲(ゆが)めてしまっては、正しいとはいいがたいでしょう。かくして、〝正しい〟の一つの条件は〝離妄想(りぼうそう)〟といってもよいでありましょう。
その第二の条件としては、〝正しい〟とは〝離辺〟であるということができるようであります。〝辺〟とは極端であります。それを離れた道はすなわち〝中道〟であります。人間が極端に立っている間は、けっして正しい道につくことはできない。正しい見方もできない。正しい修行もできない。正しい生き方もできないのであります。かくて、仏教では、「正は中なり」とするのであります。
そして、その第三には、「正は等なり」といいうるようであります。「等」とは平等ということであります。どこにも当てはまるということであります。ここには当てはまるが、あそこには妥当しないというのは、正しいとはいえないようであります。
釈尊の「さとり」を語るにあたって、仏教ではしばしば「等正覚」とか、「正等覚」といいます。そのさとりは普遍妥当なものであったからであります。したがって、〝正〟とはまた〝等〟でなくてはならないはずであります。(84~85頁)
■経典のしるすところによりますと、この初転法輪なるものは、幾日も幾日もの日数をかけての説法であったようであります。ある日には、三にんが行乞して、その得たる食によって、六人(五比丘および釈尊)が飢えをしのぎ、また、ある日には、二人が托鉢して、その得たるものによって、六人が生きたと記されてあります。これだけの大きな問題が、簡単な説法で解決できるはずはありません。
彼らは、釈尊をかこんで、幾日も幾日も、ともに論じ、ともに語りました。釈尊は彼らのためみ、ありとあらゆる面から説きました。そして、ある日、ある時、彼ら五人のなかの一人、コーンダンニャ(憍陳如)なるものに、やっと「清浄にして汚れなき法眼が開け」て、彼は、「すべて生起せるものは、また滅するものである」と知ることができました。すなわち、釈尊の説きたもうところをついに理解することができたのであります。
その時には、釈尊の喜びもまたただならぬものがあったようであります。経のことばは、その釈尊の喜びを叙して、つぎのように述べているのであります。
「その時、世尊は、歓喜の声をあげて仰せられた。
『まことにコーンダンニャ(憍陳如)は悟った。まことにコーンダンニャは悟った』
かくして、長老コーンダンニアは、〈アニャータ・コーンダンニャ〉(阿若憍陳如――悟れるコーンダンニャの意)の名を得たのである」
その釈尊の喜びは、この経の叙述からもおしはかられるところでありますが、経のことばは、さらに、また、そこで、例の神話的叙述をもって、その時、天上および地居(じこ)の神々が、一斉に大声をあげて、つぎのように言ったと述べております。
「『世尊は、バーラーナシーのイシバタナ・ミガダーヤにおいいぇ、このように無上の法輪を転じたもうた。それは、もはや、沙門・婆羅門、あるいは、天神・悪魔・梵天、もしくは、この世の何者たりとも覆(くつがえ)すことはできないであろう』」
そして、その時また、「この十千世界は、ゆれ動き、震い動き、大ゆれにゆれ動いた」とも叙しているのであります。(86~88頁)
■説法とは、それを客観的世界に打ち出すいとなみであります。そして、それをよく理解するものが出てまいりますと、そこで正法はこの世界に豎立されていないのであります。。釈尊のはじめての説法は、そのような意味をもつものであります。その最初の説法にかけた釈尊の意気ごみはたいへんなものでありました。
それにもかかわらず、最初の説法は、けっして易々として成ったものではありません。その対象として選んだ五人の比丘たちも、よういに耳を傾けようとはあいませんでした。やっと説法をはじめてからも、彼らがそれを理解するまでには、なお数日も数日もかかったようであります。
だが、ついに、やっとコーンダンニャがそれを理解し、つづいて、他の四人もこれを理解しました。その時の釈尊の喜びは異常なものであったようであります。それもそのはず、その時、仏法はこの人間世界に不動に豎立されました。それとともに、釈尊のさとりはここに完成したということができるでありましょう。(89~90頁)
(2015年1月12日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵』【真実の求め】酒井得元 大法輪閣
●先師古仏云わく、渾身口に似て虚空に掛く、東西南北の風を問わず、一等に他が為に般若を談ず、滴丁東了滴丁東(てきていとうりょうてきていとう)
これ仏祖嫡々の談般若なり。渾身般若なり、渾自(こんじ)般若なり、渾他般若なり、渾自般若なり、渾東西南北般若なり。(132頁)
■この詩は『宝慶記』の中に出ているでしょ。この詩に対して道元禅師は、大変随喜されておりますね、非常にほめておられます。昔からこの詩は東洋一だという話があります。東洋一の名詩であると。文学的にはともかくとして、私たちの宗乗(しゅうじょう)(注)から、これは素晴らしい。
「渾身口に似て虚空に掛く」ー中略ーつまり、鈴(れい)というものは、身体全体が口で、そして虚空と一体であると、こう言いたいところですね。
そして「東西南北の風を問わず」――どっちの風が吹かなければならないということはない。風が吹きさえすれば鳴る。これは方角なしだ。方角なしということは、尽十方界ということを表わしている。
「一等に他が為に般若を談ず」――一等に、みんな平等です、いつでも、ジャランジャランジャランジャラン鳴っております。あのジャランジャランジャランジャラン鳴っている音が般若の音なんですね。つまり具体的に般若を示してくれる。(132~133頁)
注1;大乗・仏乗・一乗の乗と同じ。これに乗って直に道場・如来地に至る乗り物、仏が本来乗っている乗り物。それに宗の字がつく。
■道元禅師が自己ということを一体どう取り扱っておられたか。一体、自己というのは何だろうか。私たちが普通やっている自己、「オレが、お前が」という自己を突き詰めてまいりますと、寝ている時には、自己は一服しています。やっぱり物が欲しいという時にこれが出て来る。つまりこの自我というものは、私たちの身体の生命活動の一つの表情だったのです。自我というものは、それしかないのです。だから私たちの日常生活の主体である自己というものは、自我意識であり、それは身体の生命活動の一つの表情と見たらいいのです。すなわち私たちの生活活動のすべては、身体の生命活動の表情、生命活動の景色でこの自己というものを考えなければならない。(169頁)
■ここで道元禅師の有名な「現成公案」の巻の言葉、「仏道をならふといふは、自己をならふなり」を参究してみたいと思います。この自己というものについて、道元禅師はこう言っておられます。「自己をならふといふは、自己をわするるなり」。この「わすれる」ということはどういうことでしょうか。「自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり」。これが「わすれるということだ」とあります。これは、我々の日常生活の中での忘れるという一つの精神現象ではなく、身体の生命活動そのものの事実が「わすれる」であったのです。
「万法」と言いますと、道元禅師の好きな言葉には「尽十法界の真実」という言葉があります。これは禅の独特の言葉です。この尽十法界という言葉を六祖以後で一番先に使い出したのは南泉普願(なんせんふがん)あたりからでしょう。その弟子たちが尽十法界という言葉を盛んに使っています。趙州(じょうしゅう)も使ってます。趙州になってから遂に「尽十法界真実人体(にんたい)」という言葉に結実しました。この言葉は当然、仏法にあっては、結実しなければならなくて結実したものです。
尽十法界ということは宇宙全体のことです。つまり宇宙全体が真実であったのです。考えてみると、宇宙全体とはどういうものであるか。これが道元禅師の『正法眼蔵』の中心となっています。と申しますのは、道元禅師はこの宇宙の真実というものを存在として見ないんですね。すべてのものが一時も休まず、休憩なしに生命活動をしていると、こういうふうに見ておられる。だからそのことが言葉になって「仏向上事」という語が出現した。この仏向上事という語は宇宙の真実の実態を表現したもので、これが「仏向上事」の巻という『正法眼蔵』独特の巻と現成したのです。
じつはこれを私も、どういうふうに読んだらいいかと思って苦しんだんです。そうしていたらこれは「仏は向上事なり」と読むとよいと分った。つまり宇宙のすべてのもののあり方には向下はありません。向上ばかりです。すべては絶えず、ずっと生き続けています。世の中には何一つとして若くなるものはありません。みんな毎日々々歳を取っています。コンクリートの建物も、歳取るんだそうです。私らもそうです。みなさんももう後50年たってごらん、みんなこんな顔になることでしょう。そのころの顔を見てみたいと思うけれども、仕方がない。全部ただひたすらに歳取っています。つまりこれが向上ということで、いつでも向上を続けています。宇宙全体がこのように、のべつ幕なしに生命活動を続けているのです。つまり言うと、この実態が因縁和合であったのです。すべてのものはかく一生懸命に新しく新しく生き続ける努力をしています。それと同時に新しく出来たものはすぐ壊れています。(170~171頁)
■だからすべての形というものは、それぞれ出来上がった時の姿がすべてで、それが絶えず続けられているのであったのです。だから、すべてはその時の姿が絶えず連続的に続けられているのですから、言ってみるならば、すべてのもの、形態というものは一時的なものの姿であったのです。だからその姿は「時」であったのです。「法」という概念もこのような実態を表現したものですから、私は法という概念を、ものごととか事件というように理解しています。ものごというように解してみると、すべてのものの実態がよく理解できます。すべてのものはこういうふうですから、いつも新しいのです。ですから道元禅師には有名な「有時(うじ)」の言葉がある。そしてそれによって「有時」の巻が撰述されている。これは「有は時なり」ということです。または時は有なりということです。(171~172頁)
■したがって人生で悩んだり悲しんだりして、人生の一大事とばかり大騒ぎをしても、それはあなたがただ狼狽しているだかで、事実は大したことはありません。これらはみんな向上事の風景です。その風景というものは、その時だけのもので、消えてしまったらそれまでのものです。その時だけのものだから、道元禅師は、このことを「夢中説夢」という言葉で、これを巧みに表現されておられます。(173頁)
■「自己の身心および他己の身心を脱落せしむるなり」というのは、この尽十方界真実人体の実修実証の只管打坐の実態を実践的に表現したものです。そしてこれが「自己をならふ」ということであったのです。その時、すなわち本当に自己に撤するのであり、人生を超えているのです。つまり「自己をならふ」ということは人生の中でのことではなかったのです。仏道における「自己」とは「尽中方界真実人体」のことであったのです。(175頁)
■補注
【現成公案】;『正法眼蔵抄』には「現ハ隠顕ニアラズ、成ハ作学ニアラズ、公ト云フハ平等ノ義也、按ト云ハ守分ノ義也。平不平名曰公、守分名曰按」とあり、『正法眼蔵』の現成公案の意味はこれによって解すべきである。(208頁)
【六祖と神秀上座】:六祖慧能が廬行者(ろあんじゃ、行者は得度を受けず在俗のまま寺の労務に服する者。姓が廬であるので廬行者という)として五祖弘忍の下にあって碓坊(たいぼう)で修行していた時、五祖は門人を集め、自分の意にかなう一偈(げ)を作った者があれば、衣法(えほう)を付して第六代(達磨を初祖として)の祖にしよう、と告げた。黄梅(おうばい)七百の僧中の教授師として衆望をになった神秀上座は「身は是れ菩提樹、心は明鏡台の如し、時々に勤めて払拭(ほっしき)して、塵埃(じんない)をして惹(ひ)からしむこと莫(な)かれ」という偈を作って壁上に書した。これに対し廬行者は「菩提本樹なし、明鏡も亦た台にあらず、本来無一物、何の処にか塵埃を惹かん」という偈を作った。五祖は密かに廬行者に衣鉢(いはつ)を授け六祖とした。(六祖壇経)(210頁)
【六祖】;河北省范陽(はんよう)の人、姓は廬氏。父が広東省に左遷されて新州で生まれる。幼くして父を失い、薪を売って母を養う。一日、客が『金剛経』を読むのを聞いて心が明らかになり、問えば黄梅山の五祖弘忍禅師より得たという。黄梅に至っての五祖との問答は、『伝灯録』五祖章によると、「汝何よりか来る」「嶺南(れいなん)」「何事をか須(もち)いんと欲す」「唯だ作仏(さぶつ)を求む」「嶺南人、仏性なし、若為(いかん)してか仏を得ん」「人に即ち南北有りとも、仏性豈然(あにしか)あらんや」とある。これによって五祖は異人なることを知ったが、呵して碓坊(たいぼう)に去らしめた。六祖は昼夜休まず碓(うす)を踏んで服労すること八ヶ月、五祖は時の至るを知って、門下に付法の為の偈を作らせた。六祖の偈が五祖の意にかない、衣鉢を授けられたことは前述のとおりである。この後六祖は猟人の中に隠れて十六年、上元三年(678)風動幡動の問答で法性寺(ほっしょうじ)の印宗に見出され、印宗に法を説いて来歴を明かし、祝髪(しゅくはつ)し具足戒を受けた。翌儀鳳二年、曹渓の宝林寺に移り、大いに宗風を発揚した。
六祖の門下からは青原行思と南嶽懐譲が出て、いわゆる五家(ごけ)として繁栄し、中でも曹洞宗(そうとうしゅう)・臨済宗の系統は現在に続いている。その他、南陽慧忠・永嘉玄覚(ようかげんがく)など多くのすぐれた禅者が輩出した。また、神秀の系統を北宗と言うの対して、六祖の系統は南宗と言われる。
六祖の遷化は先天二年八月三日、春秋7十六歳。憲宗より大鑑禅師と諡(おくりな)されたので大鑑慧能(だいかんえのう)といい、また六祖、曹渓等という。(210~211頁)
【毘盧舎那仏】;Vairocanaの音訳。盧舎那仏ともいう。真言宗では大日如来とする。華厳経・梵網経等に説かれる。(212頁)
【無所得】;得る所なし。『摩訶般若波羅蜜多心経』に、「舎利子よ、是の諸法は空相にして、不生不滅・不空不浄・不増不滅なり。是の故に空の中には、色も無く、眼耳鼻舌身意も無く、色声香味触法も無く、限界も無く乃至意識界も無く、無明も無く無明の尽くることも無く、乃至老死も無く老死の尽くることもなく、苦集滅道も無く、智も無く亦た得ることも無し。得る所無きを以ての故に」とある。得て自分のものにしようとしても、自分のものとして得られるものは一つもない。物的にも、認識においても、納得においても、すべて得られない。(213~214頁)
【無性闡提(むしょうせんだい)】;無性は無性有情。法相宗で説く五種姓(菩提定姓・独覚定姓・声聞定姓・無性有情)の一。仏になる種子(しゅうじ)を先天的に持っていないため成仏できないとされる。闡提(せんだい)は一闡提(せんだい)の略。断善根・信不具足と訳され、仏になる善根を断じているので成仏できないとされる。
観世音菩薩のように大悲を先にとする菩薩は、衆生を先に度して一切の衆生が成仏し終って後でないと自らは成仏しないという誓願をたてている。ところが衆生は尽きることがないので、永遠に成仏できない。故に無姓闡提(むしょうせんだい)の菩薩という。(215~216頁)
【苦集(じゅう)滅道】;四聖諦(しょうたい)、または四諦という。諦はsatyaで、現代の学者は真理と訳している。この身はすべて苦であるという真理(苦諦)。苦の生起の原因(それは渇愛である)という真理(集諦)。苦の滅尽という真理――それは渇愛を完全に離れ滅することである(滅諦)。苦の滅尽に導く道、それは八正道である、という真理(道諦)。(78頁)
【孤雲懐奘】;孤雲懐奘(こうんえじょう、1198~1280)。建久九年、京都に生まれる。比叡山の円能法印について剃髪、十八歳で菩薩戒を受ける。倶舎・成実・三論・法相を学び、摩訶止観を学すが、名利の学業の益なきことを知って叡山を下り、浄土の教門を学び、小坂の奥義を聞き、多武峰(とうのみね)の覚晏が見性の義を談ずるのを知って参じる。時に道元禅師が帰朝して建仁寺に寓するを聞いて参問し、文暦元年(1234)深草の草庵に参じ、翌年仏祖正伝の戒法を受け、更に参じて一毫衆穴を穿つの因縁を聞いて省悟し法嗣とされる。これより後二十年、影の形に随うがごとく、諸職を務めても必ず侍者を兼ね、一日も禅師の元を離れなかった。道元禅師も、懐奘禅師を重んじて永平寺の一切の仏事を行わしめ、室中の礼はあたかも師匠のごとくであった。建長五年、道元禅師の退院によって師席に住し、禅師の遺跡を継いで永平寺僧団を率いた。文永四年(1167)席を徹通義介に譲ったが、義介退院の後、再び住持して、公安三年八月二十四日示寂、八十三歳。死期も先師に同じく八月下旬を願い、遺骨は禅師塔の傍ら侍者位に安じて別に塔を立てないよう遺言した。(228~229頁)
【聞法】;◆身心を決択(けっちゃく)するに自ずから両般有り。参師門法と功夫坐禅となり(学道用心集)。
門法と坐禅は、車の両輪、鳥の両翼とされる。(230頁)
(2015年2月15日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵(1)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
摩訶般若波羅蜜(まかはんにゃはらみつ)
■開題
この「摩訶般若波羅蜜」の巻が制作され、かつ衆に示されたのは、天福(てんぷく)元年(1233)の夏安居の日のことであったと記されてある。天福元年といえば、その春、興聖寺が成立したばかりの年であることが、まず思い浮んでくる。『建撕記(けんぜいき)』によれば、「大法挙揚(こよう)の為に、宇治郡深草の極楽寺の旧跡に就れ、興聖寺を建立の発願あり。天福元年癸巳(みずのとみ)の春に落成して、興聖宝林寺と号す」とある。しかるに、この巻の奥書によれば、ただ「観音導利院にありて、衆に示す」とある。その院号はさきの極楽寺の院号をそのままに用いたもの。つまり、そこには、その院号のみが記されて、興聖寺もしくは興聖宝林寺なる寺号はなお記されていない。その事情はなお審(つまび)らかにすることをえないが、そんなところにも、なんとなく、草創のみぎりの風情が偲ばれるのである。(20頁)
■さて「摩訶般若波羅蜜」とは“――”の音写である。古来それは音写をもって語るのが習いであるが、いまもし、それを現代語をもって意訳をこころみるならば、摩訶とは大の意、般若とは智慧であり、そして、波羅蜜(新訳では波羅蜜多、旧約では波羅蜜)とは、成就・完成・到達・建立等の意のことばである。よって、「摩訶般若波羅蜜」とは、「大いなる智慧の成就」と訳したならばどうであろうかと思う。(21頁)
■あるいは、智慧の成就に十二の名目がある。六根(六つの感官)と六境(六つの対象)がそれである。また、十八の智慧がある。眼・耳・鼻・舌・身・意の六根、色・声・香・味・触・法の六境、および、それぞれの交渉によってなる眼識(げんしき)・耳識・鼻識・舌識・身識・意識がそれである。また、四つの智慧がある。苦・集(じゅ)・滅・道の四諦(したい)がそれである。また、六つの智慧がある。布施・持戒・忍辱(にんにく)・精進・静慮・智慧の六波羅蜜がそれである。また、ただ一つの智慧の成就があって、いま現に成就しておる。比すべきものもなき等正覚がそれである。また、智慧の成立に三つがある。過去・現在・未来がそれである。また、六つの智慧がある。世の常に行なわれる行・住・坐・臥がそれである。(23頁)
■阿耨多羅三藐三菩提 意訳すれば、無上等正覚となる。仏陀の正覚(さとり)の内容をなすものである。最高(阿耨多羅=無上)なる、普遍(三藐=等)にして妥当(三=正)なる智慧(菩提=覚)というほどのことばである。(24~25頁)
【岡野記、参考文献; 「また一枚の般若波羅蜜、而今現成せり、阿耨多羅三藐三菩提なり」――いままでこういうふうに般若波羅蜜を説明してまいりました、全部般若ですね。これもみな、どれもこれもが前の章を受けてのことですよ。
それから今度は「一枚の般若波羅蜜」――これ「一枚の般若波羅蜜」と申しますと、今まで六枚あった、あるいは四枚あった、十八枚あった、十二枚あった、とどういう関係だ?これは別です。そうして、ここでは「一枚の般若」――一枚というと全体のことを言っています。これより他ない。二枚目がないんだ。つまり「一枚の般若」と申しますと、尽十法界全部を一枚としたつまり尽十法界の真実をつかまえて般若波羅蜜。
「而今現成せり」――而今というは現在です。今そこにあるじゃないか。「現成」というのは、現成の「現」ということは、いままでなかったものがそこに姿を現わす意味の現ではないと、「現成公案」の巻で説明しました。つまり言うと、ありのままだ。それから「成」というのは、成仏の成で完成の意味だ。ありのまま、完成している。ありのままが完全な姿。
つまり「而今現成せり」で、今現在のこのままだ。今現在が、そのものが、これが般若波羅蜜じゃないか、こういうことですね。現実そのもの。これが般若波羅蜜じゃないか。般若波羅蜜以外何ものもない。これが阿耨多羅三藐三菩提である。
「阿耨多羅三藐三菩提」というのは、『金剛経』なんかになりますと、「法の阿耨多羅三藐三菩提を得ること有ることなし」とあるものね。「これが阿耨多羅三藐三菩提ですよ」と、つかみ取ることのできるものではない。そうでしょ、「これが本当の阿耨多羅三藐三菩提だよ」と、つかんで、みんなに見せられるようなものじゃない。つかめないよ。そのはずだ、この而今現成のもの、現実全部ですよ、これが、これ全体、つまみ食いじゃあありません、全体が阿耨多羅三藐三菩提だと、こういうことになる。それから、そこで一つ切りますよ。この言葉は特別のものですね。(『正法眼蔵』真実の求め 般若波羅蜜の巻 酒井得元 大法輪閣(87~88頁))】
現成公案
●自己をはこびて万法を修証(しゅしょう)するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。迷を大悟(だいご)するは諸仏なり、悟に大迷(だいめい)なるは衆生なり。さらに悟上に得悟する漢あり、迷中又迷(うめい)の漢あり。(42頁)
■自己をおしてよろずのことどもを計(はか)らうのは迷いである。よろずのことどもの来って自己を証(あか)しするのが悟りである。迷いを転じて大悟(だいご)するのが諸仏であり、悟りに執して迷いに迷うのが衆生である。さらにいえば、悟りのうえに悟りをかさねる者があり、迷いのなかにあってまた迷う者もある。
諸仏がまさしくまさしく諸仏となるときには、かならずしも自己は仏であると自覚するの必要はない。それでも仏を証するのである。仏とはこれかと悟りつつゆくのである。身心(しんじん)を傾けて物を見る。あるいは身心をそばだてて声を聞く。それが自分ではよく解るのであるが、鏡に物を映すようにはまいらぬ。水に映る月のようににはゆかない。一方がわかれば他方はわからないのである。(42~43頁)
■色 もと「形あるもの」の意であって、眼識によってそれと認識することのできる物的存在(色法という)をいうことばである。ただし、それにはまた「壊(え)するもの」すなはち「へんかするもの」の意があるので、現代の用語をもってするならば、「物質」ではなくて、「物象」または「現象」が適当である。(43頁)
●自己をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法に証さるるなり。万法に証さるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごせき、悟りのあと)の休歇(きゅうかつ、休はやむ、やすむ。歇はやむ)なるあり、休歇なる悟迹を長長出(ちょうちょうしゅつ、ぐんと抜け出るというほどの意)ならしむ。
人はじめて法をもとむるとき、はるかに法の辺際を離却(りきゃく)せり。法すでにおのれに正伝するとき、すみやかに本分人(自己の本来の面目に出会える人というほどの意)なり。
人、舟にのりてゆくに、めをめぐらして岸を見れば、きしのうつるとあやまる、目をしたしく舟につくれば、ふねのすすむをしるがごとく、身心を乱想して万法を弁肯(べんこう、弁はわきまえる、肯はがえんずる)するには、自心自性は常住なるかとあやまる。もし行李(あんり、行履である。仏祖たちの踏みきたった跡)をしたしくして箇裏(こり)に帰すれば、万法のわれにあらぬ道理あきらけし。(44頁)
■仏道をならうとは、自己をならうことである。自己をならうとは、自己を忘れることである。自己を忘れるとは、よろずのことどもに教えられることである。よろずのことどもに教えられるとは、自己の身心をも他己の身心をも脱ぎ捨てることである。悟りにいたったならば、そこでしばらく休むもよい。だが、やがてまたそこを大きく抜け出てゆかねばならない。
人がはじめて法を求める頃には、はるかに法のありかを離れている。すでに法がまさしく伝えられた時には、たちまち本来の人となる。
人が舟に乗って行くとき、眼をめぐらして岸を見れば、岸が移りゆくかにみえる。目を親しく舟をつければ、はじめて舟の進むのがわかる。それと同じく、わが身心をあれこれと思いめぐらしてよろずのことどもを計らう時には、わが心、わが本性は変らぬものかと思い誤る。もし仏祖先徳の足跡をつぶさに踏んでそこに到れば、よろずのことの我にあらぬ道理が明らかとなる。(44~45頁)
●たき木はひとなる、さらにかへりてたき木になるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪(たきぎ)はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位(ほうい、物のありよう)に住して、さきありのちあり。前後ありといへども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるがごとく、人のしぬるのち、さらに生とならず。
しかあるを、生(しょう)の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり、このゆゑに不生(ふしょう)といふ。死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転なり、このゆえに不滅といふ。
生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。たとへば冬と春とのごとし。冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。(46頁)
■薪は灰となる。だが、灰はもう一度もとに戻って薪とはなれむ。それなのに、灰はのち、薪はさきと見るべきではなかろう。知るがよい、薪は薪として先があり後がある。前後はあるけれども、その前後は断ち切れている。灰もまたはいとしてあり、後があり先がある。だが、かの薪は灰となったのち、もう一度薪とはならない。
それと同じく、人は死せるのち、もう一度生きることはできぬ。だからして、生が死になるといわないのが、仏法のさだまれる習いである。このゆえに不滅という。
生は一時のありようであり、死もまた一時のありようである。たとえば、冬と春とのごとくである。冬が春となるとも思わず、春が夏となるともいわないのである。(47頁)
●人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。ひろきおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天(注1)も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。さとりの人をやぶらざること、月の水をうがたざるがごとし。人のさとりを罣礙(注2)せざること、滴露の天月を罣礙せざるがごとし。ふかきことはたかき分量なるべし。時節の長短は、大水小水を撿点し、天月の広狭を弁取すべし(注3)。(48頁)
注1;弥天(みてん)ー弥はあまねし。全天というほどの意である。
注2;罣礙(けいげ)ー罣はひっかかる、礙はさまたげる。障害をなすという意である。
注3;時節の長短は……ー余情陰々として解しがたい一節であるが、おそらくは、修行の年月を云々する輩(やから)を却(しりぞ)けるの文であろう。それは、水の大小によって、映ずる月天の広狭はないと知るがよいというのであろう。(49頁)
■いまだ身心(しんじん)に法のゆきわたらぬ時には、すでに法は満てりと思う。もし法がしんしんに満ちた時には、どこかまだ足らないように思われる。
たとえば、船に乗って、陸のみえない海にいで四方を眺めると、ただ円いばかりで、どこにも違った景色はみえない。だが、大海は円いわけでもなく、四角いわけでもない。それ以上の海のさまは見えないだけのことである。海の徳は宮殿のごとく、瓔珞(ようらく)(注1)のごとしという。ただ、わが視界のおよぶところが、いちおう円く見えるのみである。
よろずのことどももまた同じである。それはこの世の内外にわたり、さまざまの様相を成しているが、人はその力量・眼力のおよぶかぎりをもって見かつ解するのである。よくよろずのことどものさまを学ぶには、ただ円い四角いと見えるところのみでなく、見えざる山海のありようのなお際限なく、さまざまの世界のあることを知らねばならぬ。自己のまわりがそうというのみではない。脚下も、一滴の水も、またそうだと知らねばならぬ。
注1;珠玉・金銀などを編んで作った装身の具である。経の説くところによれば、龍魚は水をみること、瓔珞のごとしとなし、また宮殿のごとしという。いま、海をそのようにみるものもあるというのである。(50~51頁)
●うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれども、うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。只用大のときは使大なり、要小のときは使小なり。かくのごとくして、頭頭(注1)に辺際をつくさずといふことなく、処処に蹈翻(注2)せずといふことなしといへども、鳥もしそらをいづれば、たちまちに死す、魚もし水をいづれば、たちまちに死す。以水為命いりぬべし、以空為命しりぬべし。以鳥為命あり、以魚為命あり。以命為鳥なるべし、以命為魚なるべし。このほかさらに進歩あるべし。修証あり、その寿者命者あることかくのごとし。
しかあるを、水をきはめ、そらをきはめたのち、水そらをゆかんと擬する鳥魚あらんは、水にもそらにも、みちをうべからず、ところをうべからず。このところをうれば、この行李(あんり)したがひて現成公案す。このみちをうれば、この行李したがひて現成公案なり。このみち、このところ、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、さきよりあるにあらず、いま現ずるにあらざるがゆゑに、かくのごとくあるなり。
しかあるがごとく、人もし仏道を修証するに、得一法通一法なり、遇一行修一行なり。これにところあり、みち通達(つうだつ)せるによりて、しらるるきはのしるからざるは、このしることの、仏法の究尽(ぐうじん)と同生し同参するゆゑにしかあるなり。
得処かならず自己の知見となりて、慮知にしられんずるとならふことなかれ。証究すみやかに現成すといへども、密有(注3)かならずしも見成にあらず。見成これ何必(注4)なり。(51~52頁)
注1;頭頭(ずず)ー弥はあまねし。それぞれにというところである。
注2;蹈翻(とうほん)ー蹈はふむ、足をもって地を踏むのである。翻はひるがえる、翼をもって空を飛ぶのである。。
注3;密有(みつう)ー密には、精密の意と内容の意の両方の意味がある。ここでは、内証すなわちわが証し得たる内なる所有というほどの意であろう。
注;何必ーなんぞ必ずしも必要ならんや、というほどの意である。(54~55頁)
■魚が水のなかをゆく。どこまで行っても水の際限はない。鳥が空を飛ぶ。どこまで飛んでも空に限りはない。だが、魚も鳥も、いまだかって水を離れず、空を出ない。ただ大を用うるときは大を使い、小を要するときは小を使う。そのようにして、それぞれどこまでも水をゆき、ところとして飛ばざるはない。鳥がもし空を出ずればたちまちに死に、魚がもし水を出でなばたちどころに死ぬ。水をもって命(いのち)となし、空をもって命となすとはそのことである。鳥をもって命となし、魚をもって命となすのである。いや、命をもって鳥となし、命をもって魚となすのであろう。そのほは、さらにいろいろといえようが、われらの修証(しゅしょう)といい、寿命というも、またそのようなのである。
それなのに、水を究めてのち水を行かんとする魚があり、空をきわめてのちそらをゆかんとする鳥があらば、彼らは水にも空にもその道を得ず、その処を得ることはできまい。その処を得れば、その行くところにしたがってさとりは実現し、その道を得れば、その履(ふ)むところおのずからにさとりは顕現する。その道、その処は、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、前よりあるにあらず、いま新たに現ずるにもあらず、おのずからにしてかくのごとくなるのである。
それと同じく、人の仏道をおさめんとするにも、一法を得れば一法に通ずるのであり、一行にあえば一行を修するのである。そこにもまた処があり、道が通じているのであるが、それがはっきりとは判らない。それは、仏法を究めるとともに生じ、ともに関わるからなのである。
自己の得たるところは、必ずしも、自己の知見となって自覚せられるものと思ってはならぬ。悟りはすみやかに実現しても、わが内なる所有(しょう)はかならずしも明らかではない。それを明らかにすることはかならずしも必要ではないのである。(53~54頁)
■麻谷山(まよくざん)の宝徹禅師が扇を使っていた。そこに一人の僧が来って問うていった。
「風性は常住にして、処として周(あまね)からぬはないという。それなのに、和尚はなぜまた扇を使うのであるか」
師はいった。
「なんじはただ風性は常住であるということを知っているが、まだ、、処として周(あまね)からぬはないという道理はわかっていないらしい」
僧がいった。
「でが、処として周(あまね)からぬはないというのは、どういうことでありましょうか」
その時、師はただ扇を使うのみであった。それを見て、僧は礼拝した。
仏法のあかし、正伝の自由自在なることは、かくのごとしである。つねにあるから扇を使うべきではない、扇を用いぬ時にも風はあるのだというのは、常住ということも知らず、風性というものも解っていないのである。風性は常住であるからこそ、仏教の風は、大地の黄金なることも顕現し、長河の水を乳酪たらしめる妙用をも実現することを得るのである。(56~57頁)
一顆明珠
■この「尽十法世界は、これ一顆の明珠である」という表現は、玄沙の初めて吐いたことばである。その大旨をいわば、尽十法世界とは、広大というにもあらず、微小というにもあらず、まるい四角いというにもあらず、中正なりというにもあらず、活潑潑地(かつはつはつち)というにもあらず、炯々(けいけい)として明らかというにもあらず。あるいは、生死(しょうじ)にもあらず去来(こらい)にもあらぬがゆえに、生死・去来である。そのゆえに、昨日は去り、今日は来る。つまるところ、あれだこれだと見ることもできないし、これだあれだと挙げていうこともできない。
つまるところ、尽十法というのは、客体を追うて主体となし、主体を追うて客体となし、その尽くるところを知らぬのである。情が生ずれば智は遠ざかる。これを「隔(かく)」と表現する。頭(こうべ)をめぐらして面(おもて)をかえる。その時、事を展(の)べ、機に投ずるのである。主体を追うて客体となすがゆえに、尽くるところを知らぬ尽十法なのである。いまだ機の発せざる前(さき)の道理を得れば、機のかなめを支配するにあまりあるのである。(68~69頁)
■玄沙はいった。「なんじは、とんでもないところに抜け道を知っておったぞ」と。
知るがよい。日も月も、往古(むかし)よりいまだ変わらぬ、日は日としてして出で、月は月として出ずる。それなのに、いまは六月であるから、わが名は「熱(あつし)」であるといったら不可であろう。だから、この明珠には始めがあるか無いかといえば、それはどうともいえない。ただ尽十方世界は一顆の明珠である。二顆ともいわず、三顆ともいわぬ。すべてがただ一つの正法の眼である。その全体が一つの真実体である。全身が一句であり、全身が光明であり、全身が全身なのである。全身が全身であるから、どこにも差し障るところがなく、まことに円(まろ)やかにして、円転自在である。
明珠のありようは、そのように顕然たるものであるから、現に物を見、声を聞きたもう観音・弥勒があり、現身をもって法を説きたもう古仏・新仏があって、まさに時がいたれば、あるいはそれを虚空にかかげ、あるいはそれを衣の裏につつみ、あるいは頷(おとがい)の下にひそめ、あるいは髻(もとどり)の中におさめたもう。そのすべてが尽十方世界、一顆明珠である。それを、衣の裏につつみたもうのが仏のすがたであって、表にかけるといってはならない。髻の中、頷(あざと)の下におさめつつみたもうの御姿であって、その表面にかけるものと思ってはならぬ。(74~75頁)
注1;観音・弥勒ー旧訳(くやく)に「観世音」(略して観音)といい、新訳に「観自在」となす。弥勒は未来仏として下生(げしょう)し説法する時をまっている菩薩である。いずれも、この世の衆生の姿を見、その声を聞いているのだとする。。
注2;正当麼時ーまさにこの時にあたってというほどのことば。現在、現時である。
注3;酔酒の時節……ー『法華経』巻四、五百弟子授記品(じゅきぼん)に、「譬(たと)えば人あり、親友の家にいたり、酒の酔いて臥す。この時、親友官事まさに行かんとして、無価の宝珠を以てその衣裏に繋げ、これを与えて去る。その人酔臥して都(すべて覚知せず……」とあるによる。
注3;転不転ー『大般(はつ)涅槃経』第二、寿命品(ぼん)に、人酒に酔いて、その眼のくらんだ時、山河草木、日月星辰がすべて廻転するようにみえるを譬えとして、衆生もまた、煩悩無明のゆえに顚倒心(てんどうしん)を生じ、まことは転にあらぬを転なりとの思いの生ずるを説いた一節がある。転不転の文字はそれによるものであろう。(76頁)
■すでにかくの如くであるのに、なお、われは明珠ではあるまいと思い迷うには、けっして珠ではないからではない。思い迷い、疑いをいだき、取捨にとまどうのも、ただしばらくの小さな計らいというもの。それは心せまきに似ているけれども、また愛すべきものである。明珠とは、そのように光彩きわまりないものである。その彩(いろどり)と光の一片一片がすべて尽十方界の功徳であって、何びともこれを奪うことはできない。市場で瓦石を投ずる人はない。六道の因果に落ちるか落ちないかと思い煩う必要はない。因果はもともと徹頭徹尾明らかである。それが明珠の面目であり、それが明珠の眼晴(がんぜい)である。
そうではあっても、われもなんじも、いかなるが明珠であらぬかは知らない。それをあれこれと思い煩うのは、草を結んで罠(わな)をかけるようなもの。そこを玄沙の教えにより、この身心(しんじん)の明珠なるありようを、聞き知って明らかにしたうえは、もはやこの心はわがものではあるまい。とすれば、事の起こりまた滅するは誰のことであるか。いまや、明珠であるか明珠でないかと思い煩う要はないはず。たとい思い煩ったとて、明珠でないわけではない。また、たとい明珠ならぬものがあって、それでなにか事が起こったとしても、それはわが心の関わるところではあるまい。それはまさに黒山鬼窟(ここざんきくつ)の関わるところ。それもまた一顆の明珠なるのみである。(78頁)
即心是仏
■開題
さて、この一巻のこうせいは、まずこの一句の誤れる解釈の批判から始められている。道元はまず、ブッダ在世のころの外道、セーニャ(先尼、勝軍外道)なるものの所説を挙げて詳述する。そこでは、たとい肉体は滅びても、なお肉体より抜けいでて永遠に存する霊知なるものが措定されている。もし「即心」の句をもってそのような独存の心の存在を指すものと思い誤るならば、それはすなわち「外道に零落す」るものであるという。しかも、仏教者のなかにもそのような謬見(びゅうけん)におかされているものが、今も昔もけっして少なくないことが道元の歎きであった。
――(中略)――
かくして最後に、道元は、初めて「仏祖の正伝しきたれる即心是仏」に語りいたる。「正伝しきたれる心とふは、一心一切法、一切法一心なり」と語り、「即心是仏とは、発心・修行・菩提・涅槃の諸仏なり」と語る。
それらの説示は、第一には、仏教はけっして唯心論みはあらざることを示している。「一心一切法」といい、「一切法一心」というのはそのことである。けだし、一切の存在を離れて心はなく、心をほかにして一切の存在はないからである。かくて道元はいう。
「あきらかにしりぬ。心とは、山河大地なり、日月星辰なり」
と。
その第二には、仏教はけっして自然のままにして即心是仏なりとはいわないとするのである。「即心是仏とは、発心・修行・菩提・涅槃の諸仏なり」とはそのことである。けだし、発心もなく修行もなくして、なお迷妄の雲にとざされている輩には、けっして即心是仏ということはできないのである。かくて道元はまた、いまの句を裏返していう。
「いまだ発心・修行・菩提・涅槃せざるは、即心是仏にあらず」
と。(82~83頁)
■それが外道のたぐいというのはこうである。西の方インドにセーニヤ(先尼)という外道があった。彼は説いていった。――大道(だいどう)はわれらのこの現身にある。そのありようはたやすく判るであろう。われらは苦と楽とを分別することができる。冷と煖(だん)とをおのずからにして知り、痛いかゆいをもよく知っている。何物にもさまたげられず、何物にもかかずらわぬ。存在は去来(こらい)し、対象は生滅するけれども、霊知は常恒にして変わることがない。この霊知はあまねくして、凡夫と聖者を択(えら)ばず、一切の衆生を隔てることがない。なかには、しばし虚妄(こもう)のことに迷うこともあろうが、一たび真実の智慧にぴたりと帰するにいたれば、そんざいもなく対象も滅して、ただ本性の霊知のみが瞭然としてとこしなえに存するにいたる。たといこの身は死んでも、霊知は死せずしてこの身を出ずる。たとえば、家は焼けても、その家主はいで去るがごとくである。この昭々として明らかに、霊妙にして不思議なるもの、それが覚者・知者の本性というもの。これを仏といい、悟りとも称する。それは自他の同じく具するところ、迷える者にも悟れる者にもひとしく周(あまね)きもの。一切の存在、もろもろの対象はともかくもあれ、霊知は対象と同じからず、万物とも異なって、とこしえに変わることがない。いま現存するもろもろの対象も、霊知のかかわるかぎりは、真実といってよろしい。本性に関連して存するがゆえに虚妄ではないのである。だがしかし、それも霊知のごとく不変にして存するわけではない。生じてはまた滅するからである。しかるに、霊知は生滅にかかわらず、霊妙のいとなみをなすがゆえに、霊知とはいうのである。それをまた真我(しんが)といい、覚元といい、本性といい、本体と称する。そのような本性をさとるを、また永遠に帰するといい、帰真の大士なりともいう。そして、それより後は、もはや生死を繰り返すこともなく、不生不滅の本性の大海に悟入する。そのほかに真実はない。そこに到らざるかぎりは三界・六道の流転は尽くることなしという。
――これがセーニヤ外道の所説である。(86~87頁)
〈注解〉先尼;セーニヤ」の音写。南伝『中部経典』五七、「狗行者経」に、「裸形にして狗行者(くぎょうじゃ)なるセーニヤ」として登場する。また、漢訳『雑阿含経』「先尼出家」には、先尼外道なる者あり、ブッダを訪れて、五蘊と如来の関係について問うたとある。さらに大乗の経論においては、しばしば勝軍梵志(しょうぐんぼんし、セーニヤの意訳)として登場し、本文にみるがごとき説をなしている。
三界・六道;三界とは、欲界・色界・無色界をいう。凡夫が生死往来する世界の三つの様式をあらわす。また、六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天界の六趣をいう。人がその所業によって趣(おもむ)き生まれるであろう世界の六つのありようを示したものである。いずれも輪廻の思想にもとづくものである。(88~89頁)
■唐の大証国師慧忠和尚が僧に問うていった。
「どちらの方からおいでたか」
僧がいった。
「南の方からまいりました」
和尚がいった。
「南の方にはどんな善知識があられるか」
僧がいった。
「たくさんの善知識がおられます」
和尚がいった。
「どんなことを説いておられるか」
僧がいった。
「あちらの方の知識は、ずばりと学人に即心是仏と示されます。仏とは覚の意であるが、汝らはすべて見聞覚知の性をそなえている。その性は善である。よく眉をあげてまばたき、過去と未来をかけめぐり、また身中にあまねくして、頭にふるれば頭が知り、脚にいたれば脚が知る。その故に正徧知と名づける。これを離れてほかにまた別の仏はない。この身に生滅があるが、この心性ははじめなき古(いにしえ)よりこのかたいまだかって生滅がない。この身の生滅は、龍の骨を換えるがごとく、蛇の皮を脱ぐに似ており、また人も古き家を出(い)ずると同じである。つまり、この身は無常であるけれども、その性は常恒なのであると、南方の善知識の所説はおおよそかようであります」
和尚がいった。
「もしそうだとすれば、かのセーニヤ外道と異なるところはない。かの外道はいう。―わがこの身中に一つの霊妙な性がある。この性はよく痛いかゆいを知る。この身の壊れる時には、この霊妙な性は出でて去る。家が焼ければ家の主は出でて去ると同じである。家は無常であるが、家の主には変わりがないのである――と。そのような所説は、よくよく倹(しら)べてみると、正と邪を区別せず、いずれを正、いずれを邪ともなさぬ。わたしが遊学したころにも、そのような様子がいろいろと見えていたが、近頃はいよいよ盛んであるらしい。三百五百といった人々を集め、それをずらりと見渡して、これが南方の宗のおもむきであるという。かの『六祖壇経』をとって恣(ほしい)ままに改変し、鄙(いや)しい物語をまぜ合わせ、仏祖の聖意をけずりなどして、後進の徒をまどわせている。それがどうして仏者の教えといえようか。悲しいかな、わが宗は亡びてしまったのだ。もしも見聞覚知をもって、それが仏性だというならば、かの維摩居士が――法は見聞覚知を離る。もし見聞覚知を行ずるも、そはただ見聞覚知であって、別に法を求むるにはあらず――といった言葉は成立しないではないか」(90~92頁)
〈注解〉直下;「じきげ」と読む。そのまま、ただちにの意。(93頁)
■大証国師は曹古仏の高弟である。人天の大知識である。この国師の教示のおもむきをよくよく理解して、仏道修行のかがみとするがよい。セーニヤ外道などの所説に従ってはならぬ。近代の大宋国のもろもろの禅院の主たる輩(やから)どもには、国師のような人物はない。昔から国師に肩をならべるほどの知識は一人もないのえある。それなのに、世人はあやまって、臨済・徳山は国師に比肩するであろうと思っている。そのような輩どもばかりが多い。名眼(げん)の人なきことが嘆かわしい。
いうところの仏祖の保ちきたれる即心是仏は、外道や小乗の徒の夢にも知らざるところである。ただ仏祖と仏祖のみ、即心是仏と正伝しきたり、聞きたり、行じきたり、証しきたって究め尽くすところである。
仏は百草である。それを摘みきたり、また捨て去る。だが、それが丈六の金身(こんじん)だというのではない。即は公案である。だが、その理解をもまたず、その失敗をも避けない。是(ぜ)は三界(がい)である。だが、そこを出ずるにもあらず、唯心というにもあらぬ。心(しん)は牆壁(しょうへき)である。だが、土を捏ねるにもあらず、形を造るでもない。ただ即心是仏と究明し、あるいは心即仏是と究めいたり、あるいは仏即是心と訪ねいたり、即心仏是と問いいたり、また是仏心即と参究するのである。
かくのごとく究め到るのが、まさしき即心是仏であって、そのことごとくを挙げ、それを即心是仏の句にこめて正伝するのであり、そのように正伝して今日にいたっておる。(94~95頁)
〈注解〉曹古仏;六祖慧能のこと。彼は広東省韶州府の双峯山下、曹候なる流れのほとりに曹叔良(そうしゅくりょう)なるものが建立した宝林寺に住し、そこにあって南宗禅を弘め、中国禅を大成した。よって六祖をまた曹候をもって呼ぶのである。また、古仏とは、道元がまことの師家を称するに好んで用いた最高の尊称である。(95頁)
百仏草……;道元はそこに特色のある行文をもって、即・心・是・仏の四つの文字の説明を試ている。すなわち、仏を語るに百草をもってし、即を語るに公案をもってし、是を説くに三界をもってし、そして、心を説くに牆壁(しょうへき)をもってしている。それをさきのセーニヤ外道の霊知の独存をとく所説と比べてみるがよい。ここでは、物を離れ対象を離れて、仏もなく心もないのである。詮ずるところは、一切の法(存在)に即して一心があるのであり、一心に即して一切の法があるのである。かくて、この説示を背景として、やがて「いはゆる正伝しきたれる心といふは、一心一切法、一切法一心なり」と説かれる。そこにこの巻の圧巻の文字があるといってよろしい。(96頁)
■〔一心一切法、一切法一心〕
そこにいうところの正伝しきたれる心とは、一心一切法、一切法一心である。だから、古人はいっておる。
「もし人が心を識(し)りうれば、大地には寸土もない」
つまり、心のなんたるかを知りえた時には、この世を覆う天も落ち、大地もことごとく裂け破れる。あるいは、その時、大地はさらに厚さ三寸を増すといってもよい。また古徳はいう。
「妙浄明(みょう)心とはいったい何か。山(せん)河大地であり、日月星辰である」
それによっても、心とは、山(せん)河大地であり、日月星辰であると、明らかに知られる。だが、その表現は、一歩を進むれば不足があり、一歩を退けば余りがあろう。山河大地という心は、ただ山河大地なるのみである。別に波浪もなく、風煙もないのである。日月星辰であるという心は、ただ日月星辰なるのみである。さらに霧があるのでもなく、霞みがかかっているでもない。生死去(こ)来の心は、ただ生死去来のみであって、別に迷いもなく悟りもない。牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)の心はただ牆壁瓦礫であって、さらに泥もなければ水もない。四大・五蘊にして、ほかに意馬も心猿もあるわけではない。あるいは椅子払子(ほっす)の心は椅子払子のみであって、ほかに竹があり木があるわけではない。
かくのごとくである故に、即心是仏とは世の常情に染まぬ即心是仏であり、諸仏とは人の煩悩に汚れぬ諸仏である。詮ずるところ、即心是仏とは発心・修行・菩提・涅槃の諸仏にほかならない。いまだ発心・修行・菩提・涅槃せざるには、即心是仏ではない。たとい一微塵のなかに発心・修行しても、それが即心是仏である。たといただ一度でも発心・修行すれば、それも即心是仏である。あるいは、たとい片手ほどでも発心・修行すれば、それも即心是仏である。だからといって、長い長い間にわたって修行して仏となるのは即心是仏ではないなどというのは、いまだ即心是仏を見ざるものであり、知らざるものであり、学ばざるものである。即心是仏を説く正師にめぐり遇うことをえないのである。
いうところの諸仏とは、釈迦牟尼仏である。釈迦牟尼仏はまさに即心是仏である。過去と現在と未来の諸仏はすべて、その仏となりたまう時には、かならず釈迦牟尼仏となるのである。それが即心是仏である。(98~100頁)
〈注解〉一心一切法、一切法一心;ここに法というは存在である。物であり、対象である。それを離れて別に独存する一心が存するわけではない。それをかく表現するのである。(100頁)
不染汙;「ふぜんま」と読む。「ふぜんな」ともいう。清浄の意。
刹那;「きわめて短い時間の単位。
極微;分割しつくされた最小の物質をいう。(101頁)
洗浄
■開題
この「洗浄」の巻が、宇治県の興聖寺において衆のために説かれたのは、延応元年(1239)の冬10月23日のことであった。現存の『正法眼蔵』の巻々によって知られるかぎりでは、衆に示されたものの第5晩目にあたるようである。
この巻の説くところは、いうまでもないが、僧たちがその身心(しんじん)を清浄(しょうじょう)に保つこと、もっと具体的にいえば、なによりも大小便に関することである。。それを道元はここに、まことに事細かに整々として語っているのである。わたしはひそかに想像してみるのであるが、さきには「大いなる智慧」について語り、あるいは「この世界は一顆の明珠」であると説き、あるいはまた、「即心是仏」とはこのことにこそと示してきた若き道元が、いまここに「大小便を洗い、十指の爪をきる」ことを具(つぶ)さに説きいずるに接して、あるいは思いもかけぬ思いをなした僧たちもあったのではないかと思う。もしあったとしても、それは少しも不思議なことではあるまい。さらにいうなれば、今日にしてこの『正法眼蔵』の巻々に読みいたる人々もまた、「現成公案」の巻、「一顆明珠」の巻、あるいは「即心是仏」の巻等々と読み進んで、ついにこの「洗浄」の巻に読みいたった時、いったい、どのような思いをなすことであろうか。それもまた、かならずしも想像に難からぬところであろう。
もしも、この一巻に読みいたって、いささか意想外の思いをなす方々があるならば、わたしはまず、二つのことを指摘して、そこに深い思いをいたされんことを促したいと思うのである。
その一つは、この『正法眼蔵』のなかにもう一つ、「洗面」と題せられる巻が存することである。その巻は、いまの『正法眼蔵』では、寛元元年(1243)10月20日、越前吉田県の吉峯寺にあって衆に示された際の草稿をもって集録せられているが、その初稿は、延応元年10月23日、観音導利院興聖宝林寺にあって衆に示されたものと知られる。つまり、道元は、その日、この「洗浄」の巻、ならびに、かの「洗面」の巻を相ついで示されて、僧たちのためにつぶさに「浄身の法」を説かれたものと知られる。まず、そのことに思いをいたされたいのである。
その二つには、それらの巻々において道元の説くところは、詮ずるところ、かの「洗面」の巻のことばをもっていうなれば、「内外倶淨(ないげぐじょう)」にして仏法ははじめて現成するのだということであり、あるいは、この「洗浄」の巻に繰り返される一句をもっていうなれば、まず「仏法の身心(しんじん)」が成るのでなかったならば、仏道の現成というわけにはゆかないということである。それらのことばを、じっと味わってみていただきたいのである。
いったい、仏教とは、単なる抽象的な思惟のいとなみをもって了(おわ)るものでなく、それが現実の人間の生活のうえに具体的に実現されて、それではじめて成就するものなのである。道元がいう「仏法の身心(しんじん)」ということばは、そのような重い意味をになって語られているのである。そして、その故にこそ、ここに、またかしこに、威儀作法のことが事細かに説き示されているのであり、そのことの整々といとなまれることが、まさに得道にほかならないとするのである。そのことを道元は、ここに「身心に修行を威儀せしむる正当恁麼時、すなはち久遠の本行を具足円成せり」と語り、あるいは、もっと端的には、「作法これ宗旨(そうし)なり、得道これ作法なり」と語っている。そこに深い思いをいたしていただきたいと思うのである。(104~106頁)
■仏祖のまもり来った修行がある。いわゆる清浄がそれである。
南嶽山観音院の大慧(だいえ)禅師に、ある時、慧能が問うていった。
「振り返って、なお修行によらねばならぬことがあるだろうか」
大慧がいった。
「ないわけでもありません。汚(よご)れてはいけません」
六祖がいった。
「その汚(けが)れないということだけが、もろもろの仏の心したまうところである。なんじもそうだ。わたしもそうだ。あるいは、天竺の祖師がたもそうであった」
また、『大比丘三千威儀経』にいう。
「身を浄めるとは、大小便を洗い、十指の爪を剪(き)ることである」
そういうことで、清浄とは身心にわたることであるけれども、身を浄めるの法があり、また心を浄めるの法がある。いや、ただ身心を浄めるのみではなく、国土を浄めるのである。たとい国土に塵穢(じんえ)なくとも、それを浄からしめるのが諸仏の念じたまうところである。仏の境涯にいたっても、なお怠らざるところである。その意味するところは、容易に測りつくしがたい。作法とはそのことである。得道とは作法にほかならない。
『華厳経』淨行品(じょうぎょうぼん)にいわく、
「大便小便にあたっては、まさに願わくは衆生、よく汚穢(おえ)を除いて、婬・努(ぬ)・痴をなからしめよと。すでにして水に就(つ)かば、まさに願わくは衆生、無上道に向って、出世の法を得しめよと。水をこって穢(え)をすすがば、まさに願わくは衆生、淨忍(じょうにん)を身にそなえて、あくまでも無垢ならんことをと」
水はかならずしももと浄なるにあらず、また、もと不浄なるにもあらず。この身もかならずしももと浄なのではなく、またもと不浄なのでもない。もろもろの事どももまた同じである。水に情(こころ)があるわけでもなく、また情がないわけでもない。この身が有(う)情なわけでもなく、非常なわけでもない。よろずの事もまた同じである。それが仏世尊の説きたまうところである。そうであるから、水をもって身を浄めるわけではなく、ただ、仏法によって仏法を保つためにこのことがある。それを洗浄という。それを、仏祖がしたしくその身心をもって正伝するところであり、仏祖がじきじきにそのことばをもって見聞せしめるところであり、また、仏祖がその光明をもって明らかに示したまうところである。すべて無量無辺の功徳を実現したまうところであって、身心にその作法がぴたりと具わるその瞬間に、たちまちにして久遠の修行が完全に成るのであり、そのゆえに修行の身心が現ずるのである。(108~109頁)
〈注解〉婬・怒・痴;貧(とん)・瞋(じん)・痴の三毒の旧訳(くやく)である。(110頁)
礼拝得髄
■釈尊のおおせには、――最高の智慧を説く師にめぐり遇うには、その血統をたずねてはならぬ、その顔容(かたち)をみてはならぬ、その欠点をきらうてはならぬ、またその行為を案じてはならない。ただ智慧を尊重するのゆえをもって、日々に百千両の金(こがね)をたてまつるがよく、最上の食をもって供養するがよく、天より花をふらせて尊重するがよく、日々朝・昼・夕に礼拝し恭敬(くぎょう)して、いささかも憂悩の心をあらしめてはならない。そのようにすれば、智慧の道はかならず開けてくるものである。われもまた、発心よりこのかた、そのように修行して、いまは最高の智慧を得ることができたのである――とある。
されば、樹も石もわがために説き、田も里もわがために説かんことを願うがよい。円柱にも法を問うてみるがよく、牆壁(しょうへき)にも真理を聞いてみるがよい。むかし帝釈天は、野狐を師として礼拝し、法を問うたことがあるという。よって、大菩薩の称が伝わっているが、それはその手段の尊卑によるものではない。
それなのに、世のなかの仏法を知らざる愚か者たちは、われは大比丘であるから、年少の得法者を拝するわけにはゆかぬと思う。われは久しく修行してきたのだから、後進の得法者を拝するわけにはゆかぬといい、われは法務を司(つかさど)るものであるから、ほかの得法の僧を拝してはならぬといい、われは僧正の官にあるあるのだから、俗男俗女の得法者を拝してはならぬといい、われは三賢である十聖(じっしょう)であるから、たとい得法したからとて比丘尼などを拝するわけにゆかないといい、あるいはまた、われは皇族の血筋をひくものであるから、たとい得法者であっても臣下の僧を拝することはできないという。そのような愚か者たちは、いたずらに父の許(もと)を離れて他国に流浪し、ついに仏道を見ることはできないであろう。(141~142頁)
■またもし、かって淫の犯したことがあるとて嫌うのであるならば、すべての菩薩をも嫌わねばならない。もしまた、今後罪を犯すことがあろうとて嫌うのであるならば、すべて発心の修行者も嫌わねばならぬ。そのように嫌うならば、結局はすべてみな捨てねばならない。仏法はいったい、何により誰によって実現するのであるか。そんなことばは、まだ仏法をしらぬ痴人(ちにん)の狂言である。悲しいことである。
もしなんじの願のごとくならば、釈尊およびその在世のころの諸菩薩は、みな罪を犯したことになるのか。また、彼らはなんじよりも智慧を求める心が浅かったというのか。静かに考えてみるがよい。釈尊が教法の伝統を委ねた祖師ならびに当時の菩薩たちは、その願がなかったならば、仏法を学ぶことができなかったであろうか。そう考えてみるがよいのである。また、もしその願のごとくであったならば、女人を済度することができぬのみならず、得法の女人が現われて世の人々のために法を説いても、到って聞くことができないではないか。もし到って聞かなかったならば菩薩ではない。つまり外道である。
いまの大宋国をみると、ながらく修行を続けてきたらしい僧たちが、むなしく海の砂を数えて、いつまでも迷いの海に流浪しているものがある。また、女人ではあるけれども、善知識に参じて修行し、人天(にんでん)の導師たるにいたっているものがある。餅を売らずして捨てた老婆もある。男子の僧でありながら、空しく仏海のいさごを数えて、仏法はいまだ夢にも知らぬなどというのは、まったく可哀そうなことだ。
およそ、対象に対してはそれを明晰にすることを学ぶがよい。怖じて逃げることのみ学ぶのは、小乗の聖者たちの行き方である。東を捨てて西に隠れようとすれば、そこにもまた対象がないわけではない。たとい遁げおおせたと思っても、なお明晰にしないかぎりは、遠ざけたからとてなお対象はある。それはまだ解脱というものではない。遠ざけた対象には、かえって関心がいよいよ深いというものである。(166~167頁)
谿声山色(けいせいさんしょく)
■開題
この「谿声山色」の巻が制作され、そして衆に示されたのは、延応二年(1240)の夏安居が始まって五日目のことであった。むろん宇治県の興聖宝林寺においてのことである。巻末の奥書にいうところである。
ちなみに、この年の制作は七巻、そして、そのなかから、この「谿声山色」の巻をはじめとして四巻が衆に示されている。制作と示衆(じしゅ)とは、いまや、ようやく軌道に乗って動き始めたというところであろう。
さて、この巻題の「谿声山色」なる句の出ずるところは、この巻のなかにいうがごとく、かの蘇東坡(そとうば)が常総照覚禅師(じょうそうしょうがくぜんじ)に呈した詩の一句であるが、それによっていま道元がここに語らんとするところは、つまり仏教における悟りの成るその決定的瞬間の消息についてである。
思うに、その決定的瞬間は、けっして、ただ熱心に経疏(きょうしょ)を披見(ひけん)し、あるいはその言句を解釈することに専(もっぱ)らなる者を訪れるものではない。むしろ、よくその身心(しんじん)をととのえて、渓声に仏の説法を聞き、山色に清浄身(しょうじょうしん)を見ることのできるがごとき心境をととのえる。そのとき、かの決定的瞬間がその人を訪れる。それが、道元のこの一巻をもって説くところである。
思い起こせば、道元は、さきに、かの「現成公案」の巻において、
「自己をはこびて万法を修証(しゅしょう)するを迷とす、万法ししみて自己を修証するはさとりなり」
と語った。それは、悟りの消息が具象的にして受動的なる直観によってなるものなることを道破した千古の名言であるといってよろしい。しかるに、いまここに、道元は、その間の消息をさらに具体的に、仏祖先徳の踏みきたれる足跡をもって語ろうとするのである。
かくて、道元は、まず、さきにいう蘇東坡の詩をあげて、それに釈しそれを讃えたるのち、よく知られた二人の先徳の故事を物語る。その一人は香厳智閑(きょうげんしかん)禅師であって、竹にあたった石の音を聞いた瞬間に悟ったという。もう一人は、霊雲志勤禅師であって、時春にして梅花の咲きほこるをみて、ふっとその決定的瞬間を迎えることを得たという。
だが、そのような瞬間は、花を見、竹の音を聞く誰でもを訪れるものではない。いったい、谿(たに)の声を聞き、山の色をみる心境というものは、いかにして成るのであろうか。それがこの巻の後半に語るところである。
そこで道元が強調して語るところは、まず発菩提心のすすめである。最高の智慧を欣(よろこ)び求める心を発(おこ)すことである。ついで、名利を追究する心を離れることである。しかるに、今日では、仏教者にしてなおかつ名利に心を奪われるものが少なくない。そのことを歎き論ずるくだりには、まことに辛辣きわまることばが連ねられている。
「しかあるを、おろかなる人は、たとひ道心ありといへども、はやく本志をわすれて、あやまりて人天(にんでん)の供養をまちて、仏法の功徳いたれりとよろこぶ。国王大臣の帰依しきりなれば、わがみちの現成とおもへり。これは学道の一魔なり」
わたしは、その一節が忘れられない。では、わたしどもは、いかにしてその「学道の一魔」より遁(のが)れることを得るであろうか。そこで道元が力をこめて語ることは、ここでもまた「仏祖先徳の行履」を踏むということであった。
「およそ初心の情量は、仏道をはからふことあたはず。測量(しきりょう)すといへども、あたらざるなり。初心に測量せずといへども、究竟(くきょう)に究尽(ぐうじん)なきにあらず。徹地(てつち)の堂奥(おう)は初心の浅識にあらず。ただまさに先聖(しょう)の道をふまんことを行履すべし」
それもまた、わたしにとっては、銘記して忘れがたい一節である。(180~182頁)
■また、香厳智閑(きょうげんしかん)禅師が大潙大円禅師の門に学んだころのこと、大潙(だいい)がいった。
「なんじは聡明にして博学であるが、ひとつ、注釈のなかから憶(おぼ)えたものでなく、父母のまだ生まれぬ以前(さき)から得きった一句をわがために語ってみるがよい」
そこで香厳は、いくたびもそれを試みたが、どうしてもできなかった。彼は深くわが身を恨み、年来たくわえる書籍を披見(ひけん)してみたが、なお見当もつかない。かくて彼はついに年頃集めきたった書籍を焚(や)いていった。
「画に描いた餅は飢えをいやすに足りぬ。われは誓う。この生涯において仏法を理解することは望むまい。ただ行粥飯僧(ぎょうしゅくはんそう)となろう」
かくて、粥飯を行じて幾年も経った。行粥飯僧(ぎょうしゅくはんそう)とは、衆(しゅ)僧のために飯焚きをして奉仕する僧のことであった、わが国でいう台所方のようなものである。かくして彼は大潙にいった。
「わたしは身も心も昏(くら)く、なお、道(い)うことができません。願わくは和尚、わがために教えたまえ」
だが、大潙はいった。
「わたしは汝のために説くことを辞するものではない。しかし、そうしたならば、きっと汝はのちになってわたしを恨むこととなるであろう」
そのようにして年月を経るうち、やがて大証国師の跡を訪ね、武当山に入って、国師のいおりのあとに草庵をむすんで住んだ。そこには竹を植えて友としていたが、ある日のこと、路を掃いているとき、石が跳んで竹に当たり、かっと音を立てた。それを聞いたとき、彼は豁然として大悟(だいご)した。そこで、沐浴斎戒し、大潙山に向って焼香礼拝して、はるかに大潙に向っていった。
「大潙大和尚、かってあなたがわたしのために説いたならば、どうしてこのことがありえましょう。和尚の恩の深きことは、父母よりもすぐれております」
そして最後に、一偈を賦(ぶ)した。いわく。
「一撃所知(しょち)を亡(ぼう)ず
さらに自ら修治(しゅうち)せず
道容(どうよう)を古路(ころ)に揚(あ)ぐ、
悄然の機に堕せず
処々に蹤跡(しょうせき)なし
声色(しょうしき)のほかの威儀なり
諸法の達道の者
みな上々の機といわん」
その偈を大潙に呈した時、大潙はいった。「こやつ徹底しよったわい」と。(191~192頁)
〈注解〉一撃亡所知……;漢詩であるから、一応訓読しておいたが、さらに意訳を試ておく。
「あの音ひとつで知識はふっとんだ
もはやあれこれ思い煩うことはない
ありのままの姿で仏道をあゆみ
行ないすました者にはなり申さぬ
ただ自由自在にこそ振る舞いたい
言語文字のほかに当為はある
無礙自在の道に達する者こそ
まさに上々の機というべきなり」(192~193頁)
■また、霊雲志勤(しきん)禅師は、三十年このかた修行してきた人であるが、ある時、山に遊び、山麓に休息して、はるかに人里を眺めた。時春にして桃花の盛りなるを見て、忽然として悟った。そこで一詩を賦して、大潙に呈していった。
「三十年このかた知識を訪ねて
葉落ち芽を生ずることすでに幾回ぞ
ひとたび桃花を見てよりのちは
たちまち疑いを超えて今にいたる」
大潙は、「縁より入る者は、長く退失せず」といって、ただちに印可を与えたという。だが、誰か縁より入らぬ者があろうか。また入りてはまた退失する者があろうか。それはひとり志勤のことのみではないが、彼はやがて大潙の法を嗣いだ。もしも山色が清浄(しょうじょう)身でなかったならば、どうしてこのようなことがありえようか。(194頁)
〈注解〉三十年来尋剣客;剣客は善知識を意味する。(194頁)
■かくて知らねばならぬ。山色谿声によらずんば、拈華微笑の舞台も開かれず、二祖が得髄もありえないであろう。渓声山色の功徳によって、大地と人間が同時に成道するのであり、明星のきらめくを見て悟る仏たちもありうるのである。求法(ぐほう)の志の深かった先哲たちも、われらと同じ人間であった。その先例をいまの人はかならず参考とするがよい。今日でも、名利を離れて真実に仏法を学ばんとする者は、そのような志を立てるがよい。
しかるに、近来のわが国においては、ほんとうに仏法を求める人は稀である。ないわけではないが、その縁に遇いがたいのである。たまたま僧となって俗を離れたようでも、仏道をもって名利への手段とするもののみが多い。気の毒なことであり、口惜しいことである。この月日を惜しまず、むなしく暗闇のわざに偓促(あくせく)として、いつになったらこの俗世をはなれ、悟りを開く時があろうか。たといよき師に遇うても、本物を愛することはできまい。先師はそのような人を「かわいそうな者だ」といった。さきの世の悪因によってそうなのだからである。この世に生を受けても、法のために法を求める志がないから、本物をみても本物を疑い、正法(しょうぼう)に遇うても正法に嫌われるのである。この身心(しんじん)骨肉が、かって法によって生じたものでないから、法と相応しないのであり、法を受用することができないのである。その由は、仏祖よりこのかた師資相承(ししそうじょう)してすでに久しい。いまや菩提心は昔の夢を説くに等しいものとなった。かわいそうに、宝の山に生れながら、宝をしらず、宝を見ず、いわんや法の宝を得ることをやである。
もしも菩提心を発(おこ)しさえすれば、そののちなお六道(ろくどう)・四生(ししょう)を経(へ)めぐろうとも、その輪廻のえにしがすべて菩提のいとなみとなる。であるから、たといこれまでの年月はむなしく過しても、今生の間には急ぎ願を発(おこ)すがよい。その願のありようは、われも衆生もみなともに、今生よりこのかた生々(しょうじょう)を尽くして、正法を聞くことができますようにということ。また、聞くことを得たならば、正法を疑わず、不信の念を抱かじということ。まさに正法に遇うことを得たときには、世法を疑てて仏法をたもち、ついに大地有(う)情とともに成道することを得るようにということ。そのように発願(ほつがん)すれば、おのずから正しい発心(ほっしん)の条件がととのうのである。この心映えをおろそかにしてはならぬ。(199~200頁)
〈注解〉拈華;せそんが拈華微笑し、迦葉がそれに相応じて、その時両者の間に以心伝心のことが成ったという有名な故事をいう。
得髄;二祖慧可が初祖達磨の骨髄を得てその法嗣(はつす)となった故事を指さす。(200頁)
■いったい、菩提心を行ずるには、その発心(ほつしん)や実践を世の人々に知られたいと思ってはならない。むしろ知られまいとするがよい。ましてや、みずから口に称(とな)えるようなことは不可である。いまの人は実をもとめることが稀であるから、身に行ずることもなく、心に悟るところもなくとも、ただ他人がほめたりすると、それが学解(がくげ)・実践の具足した人だと思う。迷いの中に迷いを重ねるとはそのことである。そのような間違った考えはすみやかに捨てるがよい。
仏法を学ぶにあたり、もっとも見聞しがたいのは正法の心術というものである。その心術は仏より仏へと相伝してきたもので、これを仏の光明といい、また仏心ともいい伝えておる。世尊在世の時から今日までには、名利をもとめることを学道の目的とするかに思われる人も少なくなかったが、それでもなお、正師(しょうし)の教えにめぐり遇うて、心を翻して正法を求むれば、おのずからに道を得ることができる。
いま仏道を学ぶ人々にも、またそのような病いがあることを知らねばならない。たとえば、初心にして学び始めたばかりの者でも、久しく修行して練りに練った者でも、なお伝授の時機を得ることがあり、得ぬこともある。また、古(いにしえ)を慕うてならう者もあれば、古人をそしって学ばぬ輩(やから)もあろうが、そのいずれをも愛してはならぬ、恨んでもならぬ。どうして憂えぬわけにゆこう、恨まぬわけにはまいらぬというか。それは、貧(とん)・瞋(じん)・痴を三毒と知っている者は稀なのだから、恨んではならないというのである。(202~203頁)
■大事なことは、初めて仏道を求めた時の志を忘れぬことである。けだし、初めて発心する時には、他人のために法をもとめず、名利をなげすてて到るのだから、名利を求めず、ただ一途に道を得んことを志すのであって、国王・大臣などの尊敬や供養を受けたいなどとは思ってもみないことであった。それなのに、いまもいうような事となるのは、もともと期するところではなく、求めるところではない。世人との面倒な関わりをもつことも期するところではないのである。
しかるに、愚かなる者は、たとい道心はあっても、たちまちもとの志を忘れ、あやまって世人の供養を待ち、それを仏法の功徳なりと喜ぶ。あるいは、国王・大臣の帰依を得れば、それでわが道は成れりと思う。それは仏道を学ぶ者にとっての魔障であると知らねばならなぬ。見るがよい、仏ののたまえる言葉にも、「如来の現在にもなお怨み嫉(ねた)みあり」とあるではないか。愚は賢を知らず、小人は大聖(だいしょう)を怨むというのはこのことである。
また、西の方インドの祖師がたは、しばしば外道や小乗の徒や国王などのために悩まされたことがある。それは外道たちがすぐれていたからでもなく、祖師がたに深い慮(おもんばか)りがなかったからではない。
初祖達磨はインドより渡来してのち嵩山(すうざん)にあったが、梁の武帝も魏の王も知らなかった。そのころ二匹の犬があった。菩提流支(るし)と光統律師(こうずりっし)である。虚名(こみょう)と邪利が正しき人によって妨げられることを恐れて、天日をくらまそうとするような振る舞いをしたのである。その悪業(ごう)は世尊在世のころの提婆達多にもすぎるものであった。だが、あわれむべし、彼らが深く愛する名利は、祖師が糞(くそ)よりも厭(いと)うところであった。
そのようなことは仏法の力量がまだいたらなかったからではない。よき人を吠える犬もあるということである。吠える犬を煩(わずら)うことはない。恨むこともない。それもまた導いてやらねばならぬと思うがよい。たとえば、「汝は畜生なりといえども、菩提心を発(おこ)すがよい」といってやるがよい。先哲は「人間の畜生」といったことがある。また帰依し供養する魔類もあろうというもの。だから経のことばにも、「国王・王子・大臣・宦官・婆羅門・居士に親近(しんごん)せざれ」とみえる。真に仏道を学ばんとする者の忘れてならぬ心得である。さすれば、初学の修行者の功徳も、進むにしたがって増すであろう。
また、昔から天神がきたって行者の志をためし、あるいは悪魔がきたって行者の修行を妨げるということもあった。それらはみな、名利の思いを離れない時に、そのような事が起こるのである。慈悲の思い深く、衆生済度の願い大なる時には、そんな障(さまた)げはないものである。また、修行の力によって自然に国土を得ることがあり、あるいは世運の栄えに似たようなこともある。そんな時には、さらにその人を吟味してみるがよい。目をつぶって眠っていてはならぬ。愚人はそのような栄えを喜ぶ。あたかも愚かな犬の骨をしゃぶるがごとくである。だが、賢聖(けんじょう)はこれを厭う。たとえば世人の糞穢(ふんえ)を厭うがごとくにである。(206~208頁)
〈注解〉菩提流支;北インドの人。、508年洛陽にいたって訳経のことに従事した。
光統律師;慧忠、四分律宗の祖。彼は菩提流支と相謀って、達磨を亡きものにしようとしたという。道元がここにいうのはそのことである。(208頁)
■おおよそ初心のはからいは、仏道をはからうことはできない。測ってみてもけっして当たらないのである。だが、初心で測れないからとて、究極の境地をきわめえないわけではないのである。つきつめた境地の奥深いところは、初心の浅い知識では測れないだけのこと。ただ、すべからく仏祖先徳のあるいた道を踏もうと心掛けるがよい。その時、師を訪ね道を問えば、山に攀(よ)じ、海を渡ることもできるのである。導師を訪ね、教えを乞うには、まさに天より降下し、地より湧出(ゆしゅつ)するの趣きがあって然るべきである。かくして師に相見(まみ)える時には、あるいは人が物いい、あるいは自然が物いう。それを身体(からだ)で聞き、また心で聞く。
いったい、耳をもって聴くは日常茶飯のことであるが、眼をもって聞くことは、必ずしも誰にでもできることではない。仏を見るにしても、自仏を見るものがあり、他仏を見るものがあり、また、大仏を見、小仏をも見る。だが、大仏を見ても驚くことはなく、小仏を見てもあやしむことはない。その大仏・小仏を、いまかりに山色・谿声と考えてみるもよい。そこには広長舌(こうちょうぜつ)があり、八万偈があり、それを挙げて示せばはるかに俗を脱し、それを徹見すれば独り抜きんでるのである。それが俗言にいう「いといよ高く、いよいよ堅し」というところ。また先仏は、「天にみち地にみつ」ともいった。春松に操があり、秋菊に秀気がある。すべてよきかなである。
善知識がこの境地にいたった時には、まさにこの世の大師である。いまだその境地にいたらずして、みだりに人のために説くは世の大賊である。春松も見ずして、なにをもって説かんとするか。いかにして根源を裁断せんとするのであるか。(210~211頁)
〈注解〉何必不必;「なんぞ必ずしも必せんや」というほどの句である。
自仏・他仏;自仏とは、自心に仏を見るのであり、他仏とは、他者に仏を見るのである。(211頁)
■またもし身心に懈怠(けたい)があり、不信の念が生ずるようなことがあったならば、まごころを専(もっぱ)らにして仏の前に懺悔(さんげするがよい。そうすれば、懺悔の功徳の力がわれを救い、清浄(しょうじょう)にしてくれるであろう。その功徳は自由自在に浄信を生み、精進を育てる力をもっているからである。一たび浄信が生ずれば、自他ひとしく一転して、その利益(りやく)はあまねく人間と自然の上に及ぶ。
その懺悔の大旨をいえば、――たといわが悪業(あくごう)が積もり重なって、修道の障(さまた)げとなりましょうしょうとも、もろもろの得道の仏祖に願わくは、われを愍(あわ)れんで業のわざわいを免れしめたまえ、学道のさわりをなからしめたまえ。その教えの功徳を限りなき法界にあまねからしめたまえ。その愍れみをわが上にも布(し)かせたまえ――と。思うに、仏祖もむかしはわれらにひとしく、われらも未来は仏祖となるであろう。いま仏祖を仰ぎみれば一箇の仏祖にまします。だが、その発心の時を思えばやはり一つの発心であったはずである。それは、あまねく愍れみをかけるに、結局のところ好都合というものであろう。
そこのところを龍牙(りゅうが)は、
「過去の生(しょう)においていまだ了得せずんば今すべからく了得するがよい。
この生において生々(しょうじょう)の身を度し終わるがよい。
古(いにしえ)の仏もいまだ悟らなかったならば今の人に同じ、
悟り了すれば今の人もすなわち古人である」
といっておる。静かにその道理を思い究めるがよい。それはわれらもまた仏となりうる保証である。
そのように懺悔すれば、かならず仏祖の冥々の助けがあるものである。心に思い、身にいとなみ、口にいいあらわして、仏に白(もう)すがよい。口にいいあらわすことの力が、罪悪の根元を溶かしてしまうのである。これも一種の正しい修行であり、正しい信心であり、正しい信身である。それを正しく修するときには、谿(たに)の声も谿の色も、山の色も山の声も、みな八万四千偈(げ)を惜しみはしない。自己がもし名利の身心(しんじん)を惜しまないならば、谿も山もまたそれらを惜しまないのである。たとい谿声山色が八万四千偈を実現しようと実現しまいと、あるいはそれが夜であってもなくても、谿山の谿山たることを挙げて示す力が具(そな)わらなければ、誰か谿の声を聞き、山の色を見ることを得るであろうか。(213~214頁)
〈注解〉龍牙;湖南の龍牙山にありし居遁(ことん、923寂、寿89)である。洞山良价の発嗣(ほっす)。(215頁)
諸悪莫作
■開題
この「諸悪莫作」の巻が、宇治県の興聖宝林寺において衆に示されたのは、延応庚子月夕との記されている。それは延応二年(1240)の秋もようやく酣(たけ)た八月十五日、つまり、中秋の名月の夕であったと知られる。きっと、その夜の月は殊さらにあざやかであったにちがいあるまいと思いしのばれる。
その冒頭には、まず、人のよく知るところの「七仏通戒偈」が挙げられている。この巻の題目とするところは、いうまでもなく、その偈の第一句によるものである。また、道元が、この一巻においていわんとするところも、当然、その偈のこころとするところに他ならない。
いうところの「七仏通戒偈」なるものが、過去七仏に通ずる仏教の大意の表現であることは、また人々の広く知るところである。いや、道元の口吻(こうふん)をかりていうなれば、それはまた「ただに七仏のみにあらず、まさしくこれもろもろの仏のおしえ」にほかならない。だからして、その偈の結句にも「是諸仏教(ぜしょぶっきょう)」とあるのだと知られる。
しかるに、いま道元がこの「七仏通戒偈」について釈するところに読みいたってみると、それはもはや人々のよく知るところとは遥かに遠いものであることに一驚するのである。つまり、道元がこの偈について語るところは、遠く平板の常識的所見をはるかに超えているのである。
かって、わたし自身もまた、この一巻に読みいたって間もなく、「あっ」とばかりに声をあげて、わが浅解浅慮を恥じ入ったことがある。そのことを、わたしはまず告白しておかなければならない。それは、開巻まもなくして、つぎのような一節に読みいたった時のことであった。
「この無上菩提を或従(わくじゅう)知識(あるいは知識に従い)してきき、或従経巻(あるいは経巻に従い)してきく。はじめは、諸悪莫作ときこゆるなり。諸悪莫作ときこえざるは、仏正法(ぼう)にあらず、真説なるべし。しるべし、諸悪莫作ときこゆる、これ仏正法なり」
そういわれてみると、なるほどそのとおりであろうと思う。いや、そうでなければならぬはずだと思う。それなのに、それまでのわたしは、露ほどもそうとは気がつくことができなかった。わたしは、ひそかに、わが浅解浅慮を恥じ入るとともに、また道元の思索のいかに深くしてかつ精緻なるかに、もう一度思いを新たにせざるをえなかったのである。
そして、その精にしてかつ深なる道元の思索は、むろんその一節にのみとどまるものではない。この全巻のいたるところに溢れていってよろしい。したがって、その精にしてかつ深なる思索をもってするその表現は、はなはだ微妙にして、時にはいささか晦渋のあとさえも感じせしめる。なかでも、莫作について語るくだり、ならびに、奉行について説くくだりは、なかなか難解であるといわねばならない。その思索と表現とが相俟(あいま)ってそうなのである。
だが、よくその晦渋と難解とを越えて、この一巻に味わいいたることができるならば、かの「七仏通戒偈」は、おそらく、まったく新しい面目をもって、わたしどもの前に再現するであろうことが期待せられる。(218~220頁)
■古仏いわく、「諸悪莫作、衆(しゅ)善奉行、自浄其(ご)意、是諸仏教」(もろもろの悪を作すことなく、もろもろの善を奉行して、みずからその意を浄む、これがもろもろの仏の教えなり)と。
これは七仏に通ずる教誡(きょうかい)として、前仏より後仏へと正伝し、後仏は前仏より相嗣ぎきたったものである。だが、それは、ひとり七仏のみならず、また、もろもろの仏の教えである。その道理をよく思い究めるがよい。いうところの七仏の教えは、かならずそれぞれの七仏のそれと同じである。相伝し相嗣(そうし)するがゆえにかくなるのである。だが、すでに「これもろもろの仏のおしえなり」とある。また百千万の仏たちの教(きょう)であり、行(ぎょう)であり、証なのである。
さて、ここにいうところの諸悪とは、善・悪・無記の三つの性(しょう)のなかの悪性(あくしょう)である。だが、その性にはなんの実体もない。善性・無記性もまた同じであって、また無漏(むろ)である、実相であるともいうが、この三性については、なおいろいろのことがある。
いまはまず諸悪についていえば、この世界の悪とかの世界の悪とはかならずしも同じではない。さきの時とあとの時でも違うことがある。また天上界の悪と人間界の悪も同じからず、いわんや仏道と世間とでは、悪といい、善といい、無記というも、はるかに異なるのである。つまり、善悪は時によるが、時が善悪なのではない。善悪は事によるが、事が善悪なのでもない。事がひとしければ、善がひとしく、事がひとしければ、悪がひとしいだけである。
しかるに、仏の最高の智慧を学ぼうとして、教えを聞き、修行を重ね、証(さとり)にいたることは、まことに深(じん)にして遠(おん)、かつ妙である。その最高の智慧を、あるいは善知識にしたがって聞き、あるいは経巻によって学ぶに、はじめはただ諸悪莫作、つまり、もろもろの悪を作(な)すことなかれとのみ聞こえるものである。そう聞こえないのは、仏の正法(しょうぼう)ではなく、魔説なのであろう。されば、諸悪莫作と聞こえるのが、それが仏の正法であると知るがよいのである。
その諸悪を作(な)すことなかれというのは、凡夫がみずから思いめぐらして、そのように思うのではない。仏の知慧の説かれるのを聞いていると、自然にそのように聞こえるのである。そのように聞こえるのが、最高の智慧をことばにいいあらわした表現である。すでに智慧の力にひかれて諸悪莫作と願い、諸悪莫作とおこなっているうちに、いつしか諸悪が作られないようになる。それが修行の力の表現というものである。その力の表現は、あらゆる処、あらゆる世界、あらゆる時、あらゆる事にわたって成るのであるが、その基本はいつも莫作である。
その時その人は、たとい諸悪をつくるべきところに住し、あるいは到り、あるいは諸悪をつくる条件の下におかれ、あるいは諸悪をつくる友に交わっているように見えても、けっして諸悪をつくることがないのである。莫作の力が現われるがゆえに、諸悪が諸悪とならないである。諸悪には一定の道具立てというものはない。自由自在なのである。まさにそこに到れば、悪が来って人を犯すのではない道理が解り、また人が悪を破るわけでもないことが解ってくる。(222~224頁)
〈注解〉無漏;漏(ろ)とは漏注(ろちゅう)の意。なにものかが人の感官などを通して沁み込んでくることをいう。特に煩悩を指していうことが多い。ただ、いまここでは、善悪のことを語って、それらはそのように外より漏れ注いでくるものではないとするのである。けだし、それらはなんの実体もないものであるからである。
実相;諸法実相とて存在の真相をいうことばである。しかるに、仏教の説くところによれば、一切の存在は縁起すなわち関係性のものであって、なんら、固定的な実体あるものではないとする。いまその実相のことばをもって、善悪の真相を語ることもできるとするのである。(224頁)
■しかるに、もろもろの仏祖はいまだかって教をも行をも証をも汚すことがないのであるあるから、教・行・証はまたもろもろの仏祖をはばむことがない。そのゆえ、仏祖の修行においては、過去・現在・未来を通じて、後にも先にも、その教・行・証を避けて通る仏もなく祖もない。また、衆生が仏となり祖となる時には、これまでの仏祖が邪魔になるわけではないのであるから、いまの人もよく仏となり祖となりうる道理を、四六時中の行住坐臥のうちにもよくよく考えてみるがよい。衆生が仏となり、祖となる時には、衆生を破るのでもなく、奪うのでもなく、また失うわけでもない。ただ身心を脱落するのみである。
つまり、善悪の因果そのままに修行するのであって、なにも因果を動かすでもなく、なんぞ手段を講ずるでもない。かえって因果が時に及んでわれらを修行せしめるのである。かくして、その因果の真相が明らかとなってみると、それはただ莫作である、無生であり、無常である、また不眛であり、不落である。ただ身心脱落であるからである。
そのように学んでゆくと、諸悪は一にかかって莫作であったのかと解ってくる。その理解に助けられて、さらに諸悪は莫作だとの考えが徹底し、実践もまた定まる。まさにそこに到れば、初・中・終のことごとくが諸悪莫作となってくるのであるから、そこではもはや、諸悪はなんぞ条件があって生ずるというものではなく、ただ莫作であるだけである。もし諸悪がひとしければ、諸事もまたひとしい。しかるを、諸悪は条件があって生ずるものとのみ考えて、その条件はおのずから莫作であることに気がつかないのは、あわれむべき輩(やから)たちではある。
いったい、「仏種(ぶっしゅ)は縁より起こる」というから、また、縁は仏種より起こるのであろう。諸悪はないわけではない、ただ莫作である。諸悪があるわけでもない、ただ莫作である。諸悪は空でもない、ただ莫作である。諸悪は色(現象)でもない、ただ莫作である。諸悪は「作(な)すなかれ」でもない、ただ莫作である。たとうれば春松は、無でもなく有(う)でもない、人の造ったものではない。秋菊も有(う)でもなく無でもない、人の作(な)したものではない。諸仏も有にあらず無にあらず、ただ莫作である。露柱・燈籠・払子(ほっす)・拄杖(しゅじょう)なども、あるにあらず、なきにあらず、ただ莫作である。有にあらず無にあらず、ただ莫作である。自己もまたそのように学ぶのが、あきらめられたる公案であり、また公案をあきらめるというものである。主体の側から考究し、また客体の側から工夫するのである。
ではそのようであったのに、今までは、作られえないものを作っていたのかと後悔するのも、それはほかならぬ莫作の考える力というものである。しかるに、どうせ作られえない諸悪ならば、作ってもよいではないかと考えたりするのは、北にむいて南にゆこうとするに同じである。
詮ずるところ、諸悪莫作は、驢馬(ろば)が井戸をのぞけば、井戸が驢馬をみるというのみでなく、井戸が井戸をみ、驢馬が驢馬をみるのである。人が人を見るのであり、山が山を見るのである。その相対的関係をつき破った道理を説くところが諸悪莫作なのである。
「仏のまことの法身(ほっしん)は、なお虚空のごとし。物に応じて形を現ずること、水中の月のごとし」
という、物に応じての莫作であるから、さまざまの形を現ずる莫作であって、その無礙自在なることは、なお虚空のごとくであるが、また水中の月のごとく、疑いもなく水が月を宿しているのである。そこまでゆけば、もはや莫作のありようは疑いもなく明らかであろう。(228~230頁)
〈注解〉※ここでは、莫作についての深い思索が展開せられる。「莫作」といえば「作(な)すなかれ」である。だが、それは仏の強要でもなく、わが身心を強いるものでもない。ただ、最高の智慧の説かれるところ、自然にそう聞えてくるのである。その莫作のふしぎなありようが諄々(じゅんじゅん)として説かれるのである。(230頁)
■さて、もろもろの善は、なにか条件があって生ずるというものでもなく、またなにか条件があって滅するというものでもない。
また、もろもろの善はもろもろの事ではあるけれども、もろもろの事がもろもろの善なのではない。条件と生滅ともろもろの善とは、それぞれ初めがあり終わりがある。
そのもろもろの善を奉行するというが、ここでもそれは、自にあらず他にあらず、また自他のしるところでもない。自他の知見といえば、知に自があり他があり、また見(けん)に自があり他があるのであるから、おのおのの開かれた眼が、ここにあり、またかしこにある。それが奉行である。だが、そのときの奉行は、たとい悟りが実現したとしても、その悟りはその時はじめて成るのでもなく、また、それがいつまでも続くものでもない。ましてやそれを根本の行ということはできまい。
善を作(な)すことは奉行であるからとて、人の測り知るところではない。いまの奉行は、たとい開かれたる眼があってのこととしても、測らうべきことではない。事を測ろうがために眼を開いたのではない。開かれたる眼の測度(しきど)は、余の事の測度(しきど)と同じであってはならない。
つまるところ、もろもろの善は、有(う)でも無でもない、空でも色でもない。ただ奉行である。その奉行にはかならず衆善の実現がある。その衆善の実現こそが仏者の課題であるが、だからとて、それもまた生滅のことではなく、なにかの条件によることでもない。奉行のはじめも、中ごろも、終りもまた同じである。すでに諸善のなかの一善が奉行せられるところには、一切世界の善がことごとく奉行せられる。(234~235頁)
〈注解〉※ここでは、奉行について深い思索が展開せられる。奉行とは、教えを奉じて行ずることであるが、だが、ここでもまた、衆禅がそれを強要するのでもなく、自己が強いてこれを行ずるでもない。その奉行のふしぎなありようが、また懇々と説かれるのである。
自にあらず、自にしられず、他にあらず、他にしられず;善を奉行するといえば、それを行ずる人と、行ぜられる善があるように思われる。その二者を自と他のことばで表現して、この句をなしているものと知られる。だが、その自も他も、努めているのでもなく、自覚しているのでもなく、おのずからにして衆善奉行はなるのだとするのである。(236頁)
■ただ、莫作と奉行とは、驢(ろ)いまだ去らざるに、馬(ば)すでにいたるというところである。(238頁)
〈注解〉驢事未去、馬事到来;「驢事(ろじ)いまだ去らず、馬事到来す」と読む。前者の事のいまだ終らないうちに、すでに後者の事がはじまっているというほどの意の句である。それを莫作と奉行とにあてていえば、莫作のことが完了してから、それから奉行のことが始まるのではないといっておるのである。(238頁)
■たとい諸悪が幾重にも全世界を覆い、一切を呑みつくしていようとも、それは莫作で解脱できる。衆善はもともと初・中・終の善の善であるから、それは奉行でその性(しょう)も相も体も力(りき)もそのまま実現される。居易はまだその境地を踏んだことがないから、三歳の童子もいいうるであろうなどといった。いうべきことをいう力がないのに、そういったのである。(244頁)
〈注解〉性・相・体・力;この四つの語は、仏教においてよく用いられる述語であるので、ならべて注しておきたい。性(しょう)は不易の義にして、変化することのない本質をいう。相は存在の相状であって、その本質のあらわれた姿である。また、体は本体というほどの義であって、力はその顕現した力用(はたらき)をいう。(247頁)
■童子のことばは汝に一任する。だが、童子に一任するというのではないぞということである。老翁の行じえないことも汝に一任する。だが、老翁に一任するというのではないぞというのである。仏法のことはすべて、そのように考え、そのように説き、そのように受領するのが道理というものである。(246頁)
有事(うじ)
■古仏はいった。
「ある時は高々たる峰頂(ほうちょう)に立ち、ある時は深々(しんしん)たる海底を行く。ある時は三面・八臂(はっぴ)、ある時は丈六(じょうろく)・八尺。ある時は拄杖(しゅじょう)・払子(ほっす)、ある時は露柱・燈籠。またある時は張三(ちょうさん)・李四、ある時は大地・虚空」
ここに「ある時」という。それはすでに時があるもの(有)であることを語っている。あるものはすべて時なのである。一丈六尺の金身の仏の時である。時であるがゆえに、時の装(よそお)いとしての光明がある。いまの十二時について学ぶがよい。三面八臂の仏も時である。時であるからして、いまの十二時と異なるところはなかろう。十二時の長さ短さはまだ量ってみなくても、やはり十二という。その去りかつ来ることが明らかであるから、誰もそれを疑わないのである。疑わないからとて、知っているわけではない。人はもともと、知らないことをただあれこれと疑ってみるだけで、それもいっこう定まるところがない。だから、以前の疑問がかならずしもいまの疑問と同じわけでもない。つまり、疑うこともまたしばらく時であるということである。
いったい、この世界は、自己をおしひろげて全世界となすのである。その全世界の人々(にんにん)物々(ぶつぶつ)をかりに時々(じじ)であると考えてみるがよい。すると、物と物とがたがいに相礙(あいさまた)げることがないように、時と時が相ぶつかることもない。だから、同じ時に別の発心があることもあれば、同じ発心が別の時にあるということもある。そして、修行や成道(じょうどう)についてもまた同じである。自己をおし並べて自己がそれを見るのであるから、自己もまた時だというのは、このような道理をいうのである。
そのような道理であるから、大地のいたるところに、さまざまの現象があり、いろいろの草木があるが、その現象の草木の一つ一つがそれぞれ全世界をもっていることを学ばねばならない。そのように思いめぐらしてみるのが、修行の第一歩である。そして、かの境地に到達してみると、そこにもまたさまざまの現象があり、いろいろ草木がある。そのなかには、わかる現象もわからぬ現象もあるし、また、わからぬ草木もわかる草木もある。だが、どこまでいっても、そのような時ばかりであるのだから、ある時はまたすべての時である。ある草木も、ある現象も、みな時である。そして、それぞれの時に、すべての存在、すべての世界がこめられているのである。ときには、いまの時にもれる存在や世界があるかないかと考えてみるのもよかろう。(254~255頁)
〈注解〉※まず、薬山惟儼の(やくざんいげん)の句をあげて、それを手掛りとして、存在と時間の問題に語りいたる。すべての存在は時間であり、また、すべての時間は存在である。したがって、時をほかにして一本の草木も一つの現象も考えることはできない。かくて、「時々の時に尽有(う)尽界あるなり」であって、「有時」の重さを思うべきだとするのである。(255頁)
■それなのに、まだ仏法を学ばぬ凡夫のころには、たいてい、ある時ということばを聞けば、ある時には三面・八臂であったとか、ある時には一丈六尺、もしくは八尺であったといった工合に思う。それは、たとうれば、河を過ぎ、山を過ぎたというようなものである。たとい、その山河はあったとしても、いまはもうその山河を超えきたって、われはすでに玉殿朱楼のなかにあり、山河とわれとは天と地ほどの隔たりがあると思う。だがしかし、事の道理はけっしてただそれだけではないのである。
いまもいうとおり、山を登り、河を渡った時に、われがあったのである。そのわれには時があるのであろう。そのわれはすでにここに存する。とするならば、その時は去ることはできない。もしも時に去来(こらい)する作用がなかったならば、山を登った時のある時は「いま」であろう。もしも時が去来する作用を保っているとしても、なおわれにある時の「いま」がある。そえが有時というものである。かの山を登り河を渡った時は、この玉殿朱楼の時を呑み去り、また吐き出すのであろうか。
三面・八臂はきのうの時であった。丈六・八尺は今日の時であった。だが、その昨日のことも今日のことも、真一文字に山のなかに入りきたって、いま千峰万峰を見渡している。その時はすでに去ったわけではないのである。三面・八臂もわがある時として過ぎ去った。だが、それは彼方にあるようであるが、また「いま」なのである。丈六・八尺もまたわがある時として経過した、だが、それも彼方に過ぎ去ったようであるが、また「いま」なのである。
とするなれば、松も時であり、竹も時である。時は飛び去るとのみ心得てはならない。飛び去るのが時の性質とのみ学んではならない。もし時は飛び去るものとのみすれば、そこに隙間が出てくるであろう。「ある時」ということばの道理にまだめぐり遇えないのは、時はただ過ぎゆくものとのみ学んでいるからである。(257~258頁)
〈注解〉而今;いま。今というほどの意であろう。したがって、「有時の而今」といえば、ある時にしてしてしかも「いま」なる時というほどの意であった、いま道元がここに語りいでる時間論の最大の急処がそこにあるといってよいであろう。(259頁)
■これを要約していえば、あらゆる世界のあらゆる存在は、連続する時々(じじ)である。だが、それはまたある時であるから、またわがある時である。そのある時には経めぐる作用がある。いうところの今日から明日に経めぐる。今日から今日に経めぐる。昨日から今日に経めぐる。また、今日から今日に経めぐり、明日から明日に経めぐる。その経めぐることは時のはたらきであるから、古今の時が相重なることもなく、積もるわけでもなく、ただ、青原(せいげん)も時であり、黄檗も時であり、江西(こうぜい)も石頭(せきとう)も時である。自他それぞれがすでに時であるから、また修行も時、証得(しょうとく)も時であり、泥に入り水をわたって人々のために法を説くのも、また同じく時である。
いったい、いまの一般の人々の考え方とその由来するところは、凡夫の見るところではあるけれども、かならずしもすべて凡夫の法というもののみではない。時には法が凡夫のうえに作用していることもある。ただ凡夫は、その時にもこれが法であろうなどとは露思わないから、自分が丈六の金身(こんしん)の仏であろうなどとは思ってもみないのである。だが、われは丈六の金身などとは滅想もないと思うのも、またある時の一つであって、まさに、初心にしていまだ証(さと)らざる者も「看(み)よ、看よ」というところである。
たとえば、いまこの世の中で、時に配して午(うま)・未(ひつじ)などというのも、また物のありようをもって時の上り下りにあてている。子(ねずみ)も時であり、寅も時である。そして、衆生も時であり、仏もまた時である。衆生が仏となる時には、三面・八臂にして全世界を証(さと)り、あるいは、丈六の金身となって全世界を究め尽くすのである。そもそも、全世界をもって全世界を究め尽くすのが究尽(ぐうじん)ということであり、丈六の金身となって丈六の金身を証(あか)しするのが、発心・修行・正覚(しょうがく)・涅槃というものである。そこには存在があり、また時間がある。ただ、あらゆる時間をあらゆる存在として究め尽くすだけであって、もはや剰(あま)すところはない。剰すところがあっては、まだ存在についても時間についても、究め尽くしたとはいえないのである。さらに存在の道理にうちまかせてゆけば、その間違いに気がついた前後をもふくまて、それもまたある時のありようと知られる。事のありようの活撥撥地(かつぱつぱつち)としているのが、つまりある時なのである。それを有(う)だ無だと騒ぎ立てることはいらぬことである。
また、時はただ一向に過ぎゆくものとのみ考えて、そのいまだ到らざるを理解しないものがある。理解もまた時ではあるけれども、時を待てば理解が生まれてくるわけでもない。そこで、時はただ去来(こらい)するものとのみ心得て、ある時とは物のありよう事のありようだと見透(みとお)す人はない。それではとても悟りの難関を突破する時はありえない。
また、たとい存在のありように気がついても、誰がその所得を表現することができようか。たとい「これだ」というところを得てすでに久しくとも、なお、まだ、いかにしてその面目を現すべきかを模索している者ばかりである。だからといって、凡夫のいうある時に打ちまかせていえば、正覚も涅槃も、わずかに去来のすがたのある時のこととなってしまう。(261~262頁)
〈注解〉究尽;『法華経』巻一、方便品に、「唯仏与仏、乃能究尽、諸法実相」(ただ仏と仏、すなわち能く諸法の実相を究尽す)というよく知られた一句がある。それを踏まえて、諸法の実相を究尽するというのは、「全世界をもって全世界を究め尽くすことだ」といい、それが仏にほかならないと語るのである。(264頁)
■いったい、時は鳥あみ鳥かごをもって捕らえることはできない。ただある時が成るのみである。いま彼方にあり此方にあり天界の眷族(けんぞく)たちも、いまわが力を尽くすある時である。そのほか、もろもろの衆(しゅ)たちの存在も、わがいま力を尽くして顕現するある時である。あるいはまた、あの世この世にあるいろいろの類(たぐい)の者の存在も、すべてわが尽力(じんりき)の形成するある時であり、わが尽力の経めぐるところである。わが尽力の到りおよぶにあらずしては、一物一事も実現することなく、経めぐりきたることはないと学ぶがよい。
思うに、経めぐり来るといえば、風の吹き来り、雨の降り去るように思うであろうが、そんなふうに考えるべきではない。この世界はすべて、変転せぬものはなく、去来(こらい)せざるものはなく、みな経めぐり来るのである。そのありようは、たとえば春のようなものである。春にはいろいろの様相がある。それを経めぐるというのである。春のほかには何物もないのに、ただ春がめぐり来るというのである。たとえていえば、春の推移はかならず春を経きたるのである。春の移りゆきが春ではないが、それは春の推移であるから、経めぐり来って、いま春の時にあたって、春が実現するのである。つまびらかに思いいたり、思い去るがよい。その推移経過を語るにあたって、外界の対象はこれを外にして、別になにか経めぐるものがあり、それが幾世界を過ぎゆき、幾年月を経めぐり渡るように思うのは、なお仏道をまなぶに専一ならぬからである。(265~266頁)
袈裟功徳
■開題
では、「身をもって得る」というは、どういうことであるか。起きるにも寝るにも、顔を洗うにも、食事をするにも、そのほか行住坐臥のすべてにおいて、仏のさだめたまえる律儀のままにする。その時、その身の威儀をさきとして、心もまた随うて改まるのである。道元がしきりと「仏祖の行履に随ふべし」と語るのも、結局、同じ心であるといってよいであろう。
(2015年5月8日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵(2)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
山水経
■いまの山水は、古仏のことばの顕現(岡野注;現成の方がいいと思う)である。いずれも法に則して、その功徳を究め尽したものである。それはこの世界の成立の以前の消息であって、いまもなお活きているのであり、万物のきざしもない古(いにしえ)からのことであるから、その顕現は古今をつらぬくものである。かくて、山のもろもろの功徳は高大かつ無辺であるから、あるいは雲に乗って到り、あるいは風に順(したが)ってはたらき、自由自在にして到らざるはないのである。(17頁)
●もし山の運歩を疑著(ぎじゃく)するは、自己の運歩をもいまだしらざるなり。自己の運歩なきにはあらず、自己の運歩いまだしらざるなり、あきらめざるなり。自己の運歩をしらんがごとき、まさに青山の運歩をもしるべきなり。青山すでに有情にあらず、非情にあらず。自己すでに有情にあらず、非情にあらず。いま青山の運歩を疑著(ぎじゃく)せんこと、うべからず。いく法界(ほっかい)を量局として、青山を照鑑すべしとしらず。青山の運歩および自己の運歩、あきらかに撿点すべきなり。退歩歩退、ともに撿点あるべし。未朕兆(みちんちょう)の正当時、空王那畔(くうおうなはん)より、進歩退歩に運歩しばらくもやまざること、撿点すべし。(18~19頁)
■太陽山の道楷(どうかい)和尚は衆に示していった。
「青山はつねに運歩し、石女(せきじょ)はよる児(こ)を生む」と。
山はつねにあらゆる功徳をそなえている。そのゆえに、つねに安住し、またつねに歩くのである。その運歩のいとなみをつまびらかにまなぶがよい。山が歩くといっても、それは人間が歩くのとはちがう。だが、人間が歩くのとおなじでないからとて、山の歩くことを疑ってはならない。いま仏祖の説くところも、すでに山の歩くことを語っている。それは物の根本を抑(おさ)えているからである。「つねに運歩す」とのこの垂示をよくよく思いめぐらしてみるがよい。歩くがゆえに常なのである。青山の運歩はその疾(はや)きこと風よりも速(すみ)やかであるが、山外の人もまた知らず気づかない。山を見るまなこのない人は、気づかず、知らず、見ず、聞かざるが道理というものである。
もし山の運歩を疑うならば、それは自己の運歩をもまだ知らないのである。自己にも運歩がないわけではない。まだ自己の運歩を知らないだけである。それを明らかにしないだけである。自己の運歩を知っているなら、きっと青山の運歩をも知るはずである。青山はもとより生き物であるわけでもなく、生き物でないわけでもない。自己もまた生き物であるわけでもなく、ないわけでもない。とするならば、いま青山の運歩を疑うなどとはありえないことである。いろいろの世界を基準として青山を考えてみることを知らないからである。よくよく青山の運歩、ならびに自己の運歩をしらべてみるがよい。進歩のみならず、退歩をもしらべてみるがよい。この世界のはじめのかの時から、乃至(ないし)は、まだ万物のなかったかの時から、あるいは進歩し、あるいは退歩して、その運歩のしばらくも休む時のないことを点検してみるがよいのである。
もしもその運歩の休む時があったならば、仏祖の現われることもなかったであろう。もしもその運歩に終りがあったならば、仏法は今日に到らなかったであろう。進歩はいまだ休(や)まず、退歩もまたいまだ休(や)まないのである。その進歩と退歩と撞着せず、その退歩は進歩と相反しない。そのありようを山は流れるといい、あるいは流れる山といい、またあるいは「青山は運歩する」といい、あるいはまた「東山は水上を行く」という。それをまなぶことが山をまなぶというものである。山の身心をあらためず、山の面目をそのままにして、ひるがえってまなびいたるのである。青山に運歩があるものか、東山が水の上を行くものかと謗(そし)ってはならない。それは、おのれの見解が低くちいさいから、青山があるくという句をあやしむのであり、まなぶこと少なくして拙(つたな)きがゆえに、流るる山ということばに驚くのである。いま「流るる山」といえば誰もおどろかないが、それもその道理によく通じているわけではなく、ただ矮小な見聞に沈没してのことである。
つまり、山とは、その積みきたった功徳のことごとくを挙げて、その名となし、その命となすものであって、そこには歩きがあり、流れがあり、時に及んでは、山が小児(こども)を生むこともある。また、山が仏祖をなすの道理によって、仏祖もまたそこから出現してくるのである。たとい草木・土石・牆壁(しょうへき)のみが眼のまえに現われてきても、疑ってはならぬ、驚いてはならぬ。それで山のすべてが成っているわけではない。また、それがたといすばらしい宝のように見えたとしても、それはけっして実相ではない。たとい諸仏の修行の場処のように思えても、かならずしも愛著すべきではない。たといそれが諸仏のふしぎな功徳とうなずけようとも、真実はただそれだけではないのである。
それぞれの見るところは、それぞれの主觀と対象によるものである。それを仏祖もまたそうだと思ってはならない。それらは一隅の小さな見解である。対象を転じて心(しん)となし、心を転じて対象となすことは、仏の呵(か)したまうところ。心を説き、性(しょう)を説くことは、仏の肯(うべな)わぬところである。心を見、性を見るなどというは外道のいうところである。また、言(ことば)にかかわり句にとどこおることは解脱にいたる道ではない。ここには、そのような境地を突き抜けたものがある。いまいうところの「青山はつねに運歩する」というのがそれであり、「東山は水上を行く」というのがそれである。つぶさに学び究めるがよいのである。
また「石女はよる児を生む」の句は、石女の児を生む時を夜だといっておる。いったい、世には男石があり、女石があり、そのいずれでもない石もある。それらを天に配し地に配して、天石といい地石という。俗間にいうところであるが、あまり人の知らないところである。それが子を生むというのはどういうことか、その道理を知らねばならぬ。子を生むというのは、親と子よがならび生ずるのであるか。児も親となるを子を生むこととのみ思ってよいのであろうか。また親の子となるとき、はじめて子を生むという意味が成るのではないか。そこを徹底して思いめぐらしてみるがよい。(21~24頁)
〈注解〉石女;うまずめ
量局;尺度、基準の意。局はちぢこまるの意。(24頁)
■いまの大宋国には、一群の杜撰(ずさん)のやからどもがはびこっていて、すこしばかり本当のことをいっても、いっこうに打撃をあたえることができぬ有様である。彼らは、いまの「東山水上行」の話や、南泉の「鎌子(けんす)」の話などは、無理会話(えわ)というものだという。その意味は、もろもろの思惟にかかわれる語話は、仏祖の禅語というものではなく、理解のできない話こそ仏祖の語話だというのである。さればこそ、黄檗の棒や、臨済の喝(かつ)などは、理解のおよびがたく、思惟のかかわるところではないが、これこそ無始以前の大悟というものである。先徳の手段がたいてい、煩わしき言辞を離れて、ずばりとした句をもってするのは、それが無理会だからであるというのである。
そのようなことをいう輩(やから)どもは、いまだかって正師にまみえたこともなく、仏法をまなぶ眼もなく、いうに足りない小さな愚か者である。宋国では、この二、三百年このかた、そのような不埒なにせものの仏教者がおおい。こんなことでは仏祖の大道はすたれてしまうと思うと悲しくなる。彼らの解するところは、小乗の徒にもなお及ばず、外道よりも愚かである。俗にもあらず、僧にもあらず、人間でもなく、天上の者でもなく、仏道をまなぶ畜生よりも愚かである。汝らがいうところの無理会話とは、汝らのみ理解できないのであって、仏祖はけっしてそうではない。汝らに理解できないからとて、仏祖の理路はまなばねばならないのである。もしも畢竟するところ理解できないものならば、汝のいうところの「理会」ということもありえないのである。
そのようなたぐいの輩が、いまの宋土の諸方におおく、わたしも目(ま)のあたりに見聞したことがある。かわいそうに彼らは、思惟は言語であることを知らないのであり、言語が思惟をつらぬいていることを知らないのである。わたしはかつて宗にあったころ、彼らを嘲笑(あざわら)ったことがあるが、彼らはなにごともいうことができず、ただ黙っているだけであった。彼らがいう「無理会」とは、一つの邪計にすぎないのである。誰がそんなことを彼らにおしえたのか。本物の師がなかったから、おのずからにして外道の見解におちたのであろう。
さて、この「東山は水上を行く」とは、仏祖の心底であると知らねばならぬ。もろもろの水水は諸山の脚下に現われる。だから、諸山は雲に乗って天をあゆむのである。もろもろの水の頂は諸山である。のぼるにも、くだるにも、その行歩(ぎょうほ)はともに水上である。諸山の爪先はよくもろもろの水を踏んであるき、もろもろの水はその足下にほとばしり出でる。かくてその運歩は縦横自在にして、もろもろの事が自然にして成るのである。水は強にあらず弱にあらず、湿にあらず乾にあらず、動にあらず弱にあらず、冷にあらず煖にあらず、有(う)にあらず無にあらず、迷にあらず悟にあらず。凝(こお)りては金剛よりも堅くして、よく破るものなく、融けては乳よりも柔らかにして、誰もこれを壊すことはできない。
かくて、水の成就し所有する功徳は、誰もあやしむことはできない。時に及んでは、十方の水を十方において見ることをまなぶがよい。いや、人間が水を見る時のことのみでない。水が水を見る時のことをもまなぶがよい。水が水を見究めるのであるから、水が水を表現するのである。それをまなぶのである。それによって人は、自己が自己に相逢ううべき路を見出すこともできるであろう。また、他己が他己を究める活路をも見出し、凡俗の常情を超克することもできるであろう。(28~30頁)
〈注解〉杜撰;疎漏にして誤りのおおいことをいうことば。もと杜黙(ともく)なるものの作詞がよく韻をまちがえていたという故事による。道元は宗の禅僧たちの綿密ならぬ考え方を評して、しばしばこのことばを用いている。
魔子・六群・禿子;魔子は悪魔のやから、六群は六比丘とて、しばしば戒を破った比丘たち、禿子は外形のみ僧形にして、その心事のしからざる者をいうことば。それらのことばを連ねて、仏法を毒するにせものの仏教者というほどの意を表わしている。(30~31頁)
■仏いわく、
「一切の諸方は、畢竟して解脱にして、住するところあること無し」
それによっても知られるように、自由にして繋縛(けばく)されることなくとも、もろもろの物は存在している。それなのに人が水を見る時には、ただ流れて止まらずとのみみる一途(いっと)である。その流れ方にもさまざまあって、人の見るところはその一端のみである。すなわち、地を流れ、空を流れ、上にむかって流れ,下にむかって流れる。昇っては雲をなし,下っては淵をなす。
『文子(もんし)』にいわく、
「水の道は、天にのぼりては雨露(うろ)となり、地にくだりては江河となる」
いま俗間ににいうところもなおこのようである。仏祖の弟子と称する人々が、俗人よりも無知であっては、なによりも恥かしいことではないか。いわく、水のゆくところは水のよく知覚するところではなくとも、水はよく行動するのであり、また、水のまったく知覚せざるところでなくとも、水はよく行動するのである。(37頁)
■かくて、仏祖のいたるところには、かならず水がいたり、水のいたるところところには、かならず仏祖が現われる。それによって、仏祖はかならず水をとりあげて、これを身心ととなし、これを思索の糧(かて)とする。だから、水は上にのぼらないなどとは、内外の文献にも見えない。水の道は上下に通じ、縦横に通ずるのである。
それなのに、仏教の経典には、時に、火と風は上にのぼり、地と水は下にくだるという。その上下について研究してみると、それは仏道の上り下りをいうのである。つまり、地と水のゆくところを下とするのであって、下を地と水のゆくところとするのではない。また、火と風のゆくところを上であるとするのみである。この世界のありようは、かならずしも上下・四方の基準によるものではなくて、かりに、四大(しだい)・五大・六大などの行くところによって、その方角を定めているだけである。無想天は上にあり、阿鼻獄は下にあるとするのではない。阿鼻獄はどこにもある。無想天もどこにもある。
それだから、龍魚が水を宮殿と見るのは、人が宮殿を見るようなものであろう。けっして流れ行くものとは思えないであろう。もし傍(かたわら)にあって観る者が、汝の宮殿は流れる水ではないかといったとしても、それはわたしどもが「山は流れる」ということばを聞くとおなじであって、龍魚はただびっくりして目を疑うのみであろう。あるいは、さらに宮殿楼閣の欄干はこう、円柱はこうといい張るかもしれない。そこの道理をよくよく思い来り、思い去ってみるがよい。(38~39頁)
■山ははるかなる古より大聖の居すところである。賢人(けんにん)・聖者(しょうじゃ)はともに山を住いとし、山を身心(しんじん)となした。賢人・聖者によって山はその意味を実現したのである。いったい、山にはどれほどの大聖・大賢が入ったことであろうかと思うのであるが、山に入ってからは、誰もたがいに相逢うようなことはなかった。ただ山のはたらきが現われるのみである。山に入った跡さえものこってはいないのである。
さて、世間にあって山を眺める時と、山中にあって山と相逢う時とでは、その顔つきも眼つきもはるかにちがっている。人は山は流れぬという。その憶測・知見は、すでに龍魚のそれと同じではない。人間が自分の世界にあって考えていることは、他類のものの疑うところ、あるいは疑ってもみないところであろう。だから、「山は流れる」という仏祖のことばをまなぶがよいのである。ただ驚き疑うにまかせておいてはならぬ。その一つをとれば「流れる」であり、他の一つをあぐれば「流れぬ」である。ある時は「流」であり、またある時は「不流」である。そこをまなび究めなくては、如来のおしえは判らないのである。古仏はいう、
「無間業(むげんごう)を招かざることを得んと欲せば、如来の正法輪(しょうぼうりん)を謗(ぼう)ずることなかれ」
と。このことばをふかく骨髄に銘ずるがよい。そらに銘ずるがよく、地に銘ずるがよい。それはすでに、樹に刻み石に刻み、あるいは野に説き里に説いて経としてのこされてある。(43~44頁)
■よって知るべきである、山は人間社会のものにあらず、また高き天のものでもないのであり、人の思い測りをもって山を推し測ることはできない。もしも人間社会のならいに準(なぞら)えて考えなければ、誰が「山は流れる」とか「山は流れぬ」などという表現に頭を傾(かし)げようか。(44~45頁)
■いったい、この世界に水があるというが、ただそれのみではない。また水の中にも世界があるのである。さらに、水の中がそうであるのみでなく、雲の中にも生き物の世界があり、風の中にも生き物の世界があり、火の中にも衆生の世界があり、地の中にも衆生の世界あり、全世界のなかに衆生の世界がある。あるいは、一茎の草の中にも衆生の世界があり、一振りの杖の中にも衆生の世界がある。そして、衆生の世界のあるところには、そこにまた、かならず仏祖の世界がある。そのような道理をよくよく聞いてまなぶがよい。
とするならば、水はすなはち真龍の住むところであって、それはただ流れ落ちるのみではない。流れるのみだというのは、そのことばがすでに水を謗(そし)っているのである。だから、たとえば、水は流るるにあらずと無理にもいわねばならぬのである。水は水のあるがままの姿でよいのである。水は水そのものであって、流れではないのである。一つの水の流るるを究わめ、流れざるを究むれば、あらゆる存在を究め尽くすことも、またたちまちにして成るのである。
また、山にも、宝にかくれる山があり、沢にかくれる山があり、空にかくれる山があり、山にかくれる山がある。そのかくれるところに山の山たる所以(ゆえん)があることをまなぶべきである。
古仏はいう、
「山はこれ山、水はこれ水」
と。そのいうところは、凡情の見るところの山を「これ山」というのではなく、仏祖が見るところの山を「これ山」だというのである。だからして、よく山をまなび究めるがよく、山をまなび究むれば山に教えられるところがあろう。そのような山水は、おのずからにして賢を生み、聖(しょう)を成すのである。(48~49頁)
仏祖
■開題
この「仏祖」の巻は、仁治二年(1241)の正月三日、いつものように興聖宝林寺において、書しかつ衆(しゅ)に示したものであった。だが、その日、法堂(はっとう)にのぼった道元には、いささか日頃のそれとは趣を異にした気韻がただよっていたのではあるまいかと、わたしは想像を逞しうする。
なんとなれば、その日はなお正月のはじめにおける示衆(じしゅ)のことは、この師の生涯において、他にその例をみない。しかも、その好日を選んで、衆に示すところは、他でもない、道元自身が面授伝法(ぽう)の仏祖たる自覚の開示であったからである。
したがって、この巻の内容もまた、まったく、他の巻々とその類を異にするものであった。それはまず、
「宗礼(それ)仏祖の現成は、仏祖を挙拈(こねん)して奉覲(ぶごん)するなり」
と冒頭(ぼうとう)せられる。そもそも、仏祖とはいかにして成るものであるか。それはただ、仏祖を捉えきたって見(まみ)えたてまつるのだという。つまり、仏祖を拝して仏祖となるのであり、それが面授伝法の消息である。
そして、道元は、それに僅かの説明を加えたるのち、毘婆尸仏(びばしぶつ)大和尚より如淨大和尚にいたるまでの、歴代五十七位の仏祖をあげて、ずらりと並べ記し、その終りもまた、ただ、
「道元、大宋国方慶(ほうきょう)元年乙酉(いつゆう)夏安居時、先師天童古仏大和尚に参侍して、この仏祖を礼拝頂載すること究尽(ぐうじん)せり。唯仏与仏なり」
との一句をもって結んでいる。
これを要するに、この日の説示は、歴代五十七位の仏祖の名を並べあげて、われこそはこれらの仏祖正伝の法をじきじきに嗣ぐ仏祖であるといっているのである。
それは、他に例を見ない、まことに事かわった垂示であったが、おそらくは、それを聞くなみいる大衆たちも、仏祖正伝の法をまのあたりに見るの思いに、ひとしおの緊張感をみなぎらせたことであろうと想像せられる。(52~53頁)
■そもそも仏祖となるには、仏祖を撰(えら)びきたって見(まみ)えたてまつるのである。それは過去・現在・未来の諸仏の場合のみではない。けだし、このことの何時(いつ)はじまったかは知りえないからである。ただ、まさしく仏祖の面目を保ちもてるものを得きたって、これを礼拝し、これに相見(まみ)えるのである。ただ、仏祖の功徳を示現(じげん)せしめ、それを頂載し、礼拝し、かつ体得するのである。(53~54頁)
■わたし道元は、大宋国方慶(ほうきょう)元年(1225)の夏安居の時、先師なる天童古仏大和尚に参じて侍し、この仏祖を礼拝し頂載することを究めつくした。まさに、ただ仏と仏とのあいだの相承(そうじょう)である。(61頁)
嗣書
■第二十八祖達磨大師が中国に来られてこの方、仏祖に嗣法ということのあることが、はじめて中国にも知られたのであって、それ以前にはまったく知られていなかった。西の方からきた論師(じ)・法師(ほっし)なども、聞きおよばず、知らざるところであった。また、十聖・三賢など、まだ修行中のものの聞き及ぶところではなく、ましてや、経の文字づらのみを撫でまわしている呪術師などは、そんなことがあろうとは思いもかけぬところであった。彼らは、仏法の器たる人身を受けながら、ただ徒らに教義の網にからまれて、脱出する法もしらず、跳躍する時をも期せず、まことに哀れなものである。それゆえに、学道のことはさらに精細に思いめぐらし、修行のことはさらに志気を振るい起こさねばならぬというのである。(74頁)
■人物の話のついでに、むかしからの仏祖の家風をいろいろと語り、大潙(だいい)と仰山(きょうざん)のことに及んだ時、和尚は、「わしのところの嗣書を見たことがありましょうや」といった。すると、和尚は、自分で起って行って、嗣書を捧げてきていった。
「これは、たとい親しいひとでも、たとい永年侍僧をつとめる者でもみせない。それが仏祖の訓戒である。しかるに、わたしは時々都城にでて知府(ちふ)にお目にかかるのだが、そのように都城にあった時、一夜夢をみたことがある。大梅山(だいばいざん)の法常禅師と思われる高僧が、一枝の梅花をかざしていった。〈もし海を渡ってくる本物があったならば、花を与えることを惜しんではならぬ〉と、そういって、わしに梅花を手渡した。わしは夢のなかで、思わず〈いまだ船舷(ふなばた)を跨(また)がざるに、好(よ)し、与うるに三十棒をもってせん〉と吟じた。しかるに、それからいまだ五日を経ざるに、いまそなたと相見えることをえた。しかも、そなたは海を渡って来たのである。梅花の綾もおそらくこの嗣にかけたのであろう。それを大梅が教えてくれたのにちがいあるまい。ぴたりと夢と符合するので、これを取り出して来たのである。もしもそなたが、わしの法を嗣ぎたいと思うならば、それも惜しみはしない」
わたしは感きわまって措(お)くところをしらず、嗣書をお願いするところであっただろうが、ただ焼香し、礼拝して、その嗣書を敬重し供養するのみであった。その時、焼香の侍者に法寧というものがいたが、彼もこの嗣書をはじめて見るのだといった。
わたしはひそかに思った。この一段のことは、まったく仏祖の冥々のたすけなくてはあり得ないことであって、辺地日本の愚か者が、なんの幸いがあってか、この事に遇うことができたのであろう。そう思うと、感涙しきりに落ちて袖をぬらしたことであった。その時、天台山の維摩堂や大舎堂などは、まったく人無うして静まりかえっていた。その嗣書は、地(じ)に梅をしいた白綾に書したもので、長さ九寸余、幅一丈余であった。軸は黄玉にして、表紙は錦であった。
天台山から天童山にかえる途中、わたしは、大梅山の護聖寺の宿舎に泊まったが、その夜は大梅祖師がきたって、花咲ける梅花一枝をさずける夢をみた。仏祖のみそなわすところは、まことにしるしありというべきである。その一枝はおよそ縦横一尺ばかりのものであった。その梅花はまさに優曇華ともいうべきであろうか。夢もうつつも、おなじく真実であろう。このことを、わたしは、宋にあったころも、また故国に帰ってからも、まだ人に話したことはない。(90~91頁)
■「迦葉(かしょう)仏が涅槃に入られてから、釈迦牟尼仏ははじめて世にいでて成道せられました。ましてやまた、現在刧の諸仏がどうして過去刧の諸仏に嗣法いたしましょうか。このこと、いかがな道理でありましょうか」
すると先師はいった。
「そなたのいうところは、ただ教えを聴く者の解釈である。十聖(じっしょう)・三賢(げん)など、なお究極の境地にいたらぬ者の道である。仏祖正伝の道ではない。わしが仏から仏へと相伝してきた道はそうではない。釈迦牟尼仏はまさしく迦葉仏に嗣法したと習ってきた。釈迦仏が嗣法してからのち、迦葉仏は涅槃に入ったと学んできたのである。釈迦仏がもし迦葉仏に嗣法しなかったならば、それは自然(じねん)外道と同じであろう。誰か釈迦仏を信ずる者があろう。そのようにして仏から仏へと相嗣いでいまにいたっておるから、いずれの仏も正しい法の嗣ぎ手である。連続しているか、いっしょであるかということではなく、まさにそのようにして仏と仏とが相嗣ぐのだとまなぶのである。もろもろの小乗のやからがいうところの、劫だの寿だのの尺度には関わらないにである。
もしも仏道が、ただひとり釈迦仏にはじまるというならば、まだわずかに二千年のことである。けっして古くはない。その相嗣ぐところもなおわずかに四十余代にすぎない。まだ新しいといってよかろう。この仏道の相伝はそのようにまなぶべきではない。釈迦仏は迦葉仏に嗣法するとまなび、迦葉仏は釈迦仏に嗣法したとまなぶのである。そのようにまなんでこそ、それがまさに諸仏・諸祖の嗣法というものなのである」
その時、わたしは、はじめて仏祖に嗣法ある所以(ゆえん)を領解(りょうげ)することをえたのみならず、また、それまでの旧い穴から抜け出ることができたのであった。(96~97頁)
法華転法華(ほっけてんほっけ)
■開題
「十方仏土中者(は)、法華の唯有(ゆいう)なり。これに十方三世一切諸仏、阿耨多羅三藐三菩提衆(しゅ)は、転法華あり、法華転あり。これすなはち、本行菩薩道の不退不転なり」
そのいうところは、十方の仏土はただ法の花ひらくところであるというのである。そこには、十方三世の諸仏・諸菩薩があって、あるいは法華を転じ、あるいは法華に転ぜられているのであるが、それがそのまま菩薩のかぎりもない修行の不退転のあゆみであるという。
わたしどもは、心迷えば法華に転ぜられるといえば、それを恨むべきことなし、心悟れば法華を転ずといえば、それを歓ぶべきことなりと受領してきた。だが、それは、どうやら、おろかな凡情の差別であったらしい。心迷えば法華に転ぜられるという。だが、それも法華のいとなみであるならば、結構なことではないか、と道元はいう。心悟れば法華を転ずという。だが、それもまた、突きつめて考えてみると、法華のわれらを転じてそこに到らしめるのではないかという。かくて結語がある。
「広大深(じん)遠なり、深(じん)大久遠(くおん)なり。心迷法華転なり、心悟転法華なる、実にこれ法華転法華なり」
かくして、「法華転」と「転法華」の二つの命題は、さらに広大なるところにおいて、みごとに「法華転法華」なる一つの命題に帰しているのである。そして、それこそ、道元が指さして、この一巻において開示しようとするところであったと知られる。(102~103頁)
■だから、そこに説くところは疑いもなく一仏乗であって、かならずただ仏が仏に究尽せしめる。かの七仏も諸仏もそれぞれに諸仏をして究尽せしめ、あるいは釈迦牟尼仏を成道せしめるのである。西の方天竺、東の方中国にいたるまで、十方の仏土において然るのである。第三十三祖慧能大和尚にたるまで、ただ仏tと仏がのみが一乗の法を究尽しきたったのであり、それが疑いもなくただ一仏乗の一大事なのである。
〈注解〉阿耨多羅三藐三菩提;無上等正覚と訳する。仏の最高の智慧をいうことばである。(107頁)
■この経はまたいう、「一心に仏を見んと欲す」と。それは自分のことと思うか、また他人のことと思うか。釈迦牟尼仏はかって、分身として成道したこともあり、全身をもって成道したこともある。また、「倶(とも)に霊鷲山(りょうじゅせん)に出ず」というのは、みずから身命を惜しまないからである。あるいは、、「つねにここに住して法を説く」との開示があり、「方便にして涅槃を現ず」との悟人がある。「近しといえども見ず」というが、それもわが一心のゆえであることを信ぜぬものはあるまい。まことにこの土(ど)は「天人つねに充満」するところ、すなわち、釈迦牟尼仏・毘盧遮那仏の国土にして、常寂光土にほかならない。われらはおのずから四土を具するというが、詮ずるところは、生仏一如の仏土に住するのである。
微塵を知るものは法界を知り、法界を証するものは微塵を証する。諸仏はみずから法界を証して、われらには証を与えないわけではない。その説法は「初めも中も終りも善き」がゆえである。したがって、いまもその証はあるがままの相である。驚き怖るるもまたあるがままならぬはない。ただ異なるところは、仏はその知見をもって微塵を見、微塵に安住するのである。法界に坐しても広きにあらず、微塵に坐しても狭いとはしないのである。その故は、安住せずしては坐すことがないからである。安住すれば広き狭きに驚くことがないのである。それは法華の実体とそのはたらきを究め尽しているからである。
とするならば、われらがいま具するこの相と性(しょう)は、この法界における修行であろうか、微塵における修行であろうか。ともあれ、驚くことはない、怖るることはない、ただ法華の転ずるながいながい菩薩の修行にちがいないのである。それを微塵の小とみるも、法界の大とみるも、おのが作意でも計らいでもない。計らうにも思うにも、法華の計らいをならうがよく、法華の思うところを思うがよいのである。
もし開示悟入ときくならば、それを「衆生をして開示悟入せしめんと欲す」と受けとるがよい。もし法華が「仏の知見を開く」と転じたならば、それを「仏の知見を示す」と受けとるがよく、もし法華が「仏の知見を悟る」と転じたならば、それは「仏の知見に入る」とならうがよく、あるいは法華が「仏の知見を示す」と転ずるならば、「仏の知見を悟る」と受領するがよい。そのように法華の転ずる開示悟入にもいろいろの考え方があろう。すべて諸仏如来の実現したまえる知見も、この広大無辺なる法華の転ずるところ。あるいは、成仏の予言もまた自己が仏の知見を開くことに他ならず、けっして他人の与えるものではないのである。それがとりも直さず、心迷えば法華に転ぜられるということである。(121~123頁)
〈注解〉常寂光土;四土の一つ。生滅なく(常)、煩悩なく(寂)、智慧の光のみみちあふれている国土という。それは法身の仏たる毘盧遮那の国土であるとする。ただし、ここに釈迦牟尼仏と毘盧遮那仏の二仏をあげているのは、現身の仏にとっても、法身の仏にとっても、このあるがままの世界が常寂光土であるとするのであろう。(124頁)
■また「心悟れば法華を転ず」という。ここでは法華を転ずるのである。さきにいうところの法華がわれらを転ずる力を究めつくすとき、われらは翻(ひるがえ)って自己を転ずるような力を実現するにいたる。その実現を「転法華」という。これまでの法華の転ずるはたらきは、いまもけっして休むことはないけれども、それが自然にはねかえって法華を転ずるのである。驢事(ろじ)はまだ了(おわ)らないのに馬事が到来するのである。それがこの世に現われる唯一の大事というものである。
たとえば、この今日が語るところの地より湧きいでる無数の聖衆は、久しき昔からの法華の修行者たちであるが、いまや自己を転じて湧出するのであり、また法華に転ぜられて湧出するのである。いや地より湧きいでるのみではない。虚空からも湧きいでるのである。さらにいわば、地と空とのみではない。法華より湧きいずると知るがよいのである。
いったい、法華の立場にたってみる時は、かならず父は少(わか)く子は老いているものである。子が子でないわけでもなく、父が父でないわけでもない。それでもなお、子は老い父は少(わか)しとまなぶがよい。世の不信にならって驚いてはならぬ。世の不信なるもまた法華のならいである。だから、ある時仏ましまして法華を転ずるのである。すると、仏の開示に転ぜられて地より湧き、仏の知見に転ぜられて地より湧きいずるのである。
その法華の転ずる時、法華の悟りがあり、悟られたる法華がある。たとえば、下方というのはとりも直さず空中である。この下といい空というのが、そのまま法華を転ずることである。あるいは仏の寿量を語るもまたそれである。仏寿や、法華や、法界や、一心は、いずれも下ともなり、空ともなると思い廻(めぐ)らしてみるがよい。だから、下方空というは、それがそのまま転法華の成就である。(129~130頁)
■いったい、中国にこの経が伝えられてよりこのかたすでに数百年、その間には注解義釈をつくる者おおく、またこの経によってすぐれた導師となった者もあるが、いまわれらが高祖曹谿慧能のように、法華転のおもむきをえた者はなく、また転法華のむねを説ける者はない。いまそれを聞き、その趣に遇うことをえたのは、まさに古仏の古仏に遇うを見るのであり、これこそ古仏の仏土というものであろう。歓ぶがよい。劫より劫にいたるも法華である。昼より夜にいたるも法華である。法華は劫より劫にいたるがゆえであり、昼も夜もすべて法華であるがゆえである。たとい自ら心を強くしても弱くしても、すべてそれが法華である。すべてあるがままなるが珍宝であり、光明であり、仏智の行ぜられるところである。まことに広大にして深遠である。心迷えば法華が転ずるのであり、心悟れば法華を転ずるのである。さらにいえば、これこそ法華が法華を転ずるのである。
「心迷えば法華転じ、心悟れば法華を転ず、究尽することよくかくのごとくなれば、法華法華を転ず」
そのように供養し、恭敬し、尊重し、讃歎するならば、それがまさしく法華これ法華というところであろう。(132~134頁)
〈注解〉色即是空;『般若心経』のよく知られた句であるが、いま道元はその句をもって娑婆即寂光土なることを語っているようである。(134頁)
法華是法華;道元がこの巻において、法華ということばに込める意味はまことに広大無辺である。それはただかの『法華経』のことのみではない。この世界のおのずからの展開がそれであり、また仏の教化のいとのみのことごとくがそれである。その意味のことごとくをこめて、ここに「法華これ法華なるべし」の結語が語られているのだと知られる。(135頁)
心不可得(後)
■心不可得、これが諸仏の保持するところである。諸仏はこれを最高の智慧としてその身に保持してきたのである。
『金剛経』にいう。
「過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得」
それが諸仏の保持するところの心不可得をそのままいい表わしている。諸仏は、三界は心不可得である、諸仏は心不可得であると会得してきたのである。それを明瞭に会得することは、諸仏にならわねば得られないのであり、諸仏にならわねば伝えらられないのである。諸仏にならうというのは、丈六の仏身にならうのであり、一本の草花にならうのである。諸祖にならうというのは、諸祖の皮肉骨髄にならうのであり、破顔微(み)笑にならうのである。その意味するところをいわば、正法(ぼう)の本質は仏祖と仏祖とのあいだに明瞭に正伝されてきているのであって、その心象はあたかも指さすがごとく、一人から一人へとじきじきに伝えられている。だから、師を訪れてまなべば、かならずその骨髄・面目をつたえられて、その身そのままに受けることができるというのである。したがって、仏道をならわず、仏祖の室に入らないものは、とてもそれを見聞し、会得することはできない。問うて聞くこともできない。打ち出していうなどとは夢にも思いおよばぬところである。(159~160頁)
〈注解〉三界;欲界(欲望に駆使される人間の世界)、色界(現象そのものの世界)、無色界(叡智による抽象の世界)。
諸法;もろもろの存在。
丈六身;一丈六尺の仏身。それが仏の身量であるとせられている。(161頁)
■そこで老婆が問うていった。
「わたしはあるとき「金剛経」をきいたことがございますが、そのなかに過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得という句がありました。いま和尚さんは餅を買うて、いったい、いずれの心を点じようとなさるのか。答えてくださったら餅を売りましょう。もし答えができなければ売るわけにはゆきません」
徳山(さん)はその問いをまえにしてただ茫然、答うるすべをしらなかった。そこで老婆は、つと立ちあがって、袖をはらって去り、ついに徳山に餅を売ってくれなかった。(165頁)
■この話の経緯を考えてみると、徳山はまだそのころ本当には判っていなかったことがよく判る。老婆はそのとき徳山を沈黙せしめたが、かといって彼女が実は本物であったかどうかは定めがたい。おそらくは、心不可得ということばを聞き、心などあるものではないとのみ思って、かくは問うたのであろう。徳山はなかなかの男であったから、考える力もあったのであろう。とするならば、考えてみて、かの老婆が本物であったことも、どこかで言及しているはずであるが、まだ徳山も徳山になっていない時のことであったから、老婆の本物であるかどうかも、なお判らない、見えなかったのでもあろうか。
また、そのように老婆を疑うのは、まんざら理由のないことでもない。もし徳山が答え得なかったならば、なぜ徳山にむかって、「和尚が答え得ないならば、かえって老婆に問うよい。わたしが和尚のために答えよう」といわなかったか。その時徳山の問いを迎えていったことばがあるならば、それで老婆の本当に力あることも判るはずである。もしもこの二人に、古人の骨髄や面目、あるいは古物の光明や瑞相(ずいそう)に参入する工夫があったならば、徳山をも老婆をも、可得をも不可得をも、あるいは、餅をも心をも、掴むも放すも自由自在であったであろう。
いわゆる仏心とは三世である。心と三世とは禹(う)の毛ほどのへだたりもないのであるが、また、相去り相離るることを論ずるならば、十万八千里なりといってもなお及ばないであろう。過去心とはなにかと問うものがあらば、彼にむかっていうがよい、「これ不可得」と。現在心とはなにかと問うものがあったならば、答えていうがよい、「これ不可得」と。また、未来心とは何ぞと問うものがあったならば、また「これ不可得」と答えるがよい。そのいうところの意味は、心をかりに不可得と名づける、そのような心があるというのではない。また、心は得られないというのでもなく、ただ不可得というのである。あるいは、心は得ることができるというのでもなく、ただ一途に不可得というのである。また、過去心不可得とはどういうことかと問うものがあらば、生死去(こ)来と答えるがよい。現在心不可得とはどういうことかといわば、生死去(こ)来というがよい。あるいは、未来心不可得とはいかにといわば、また生死去来というがよい。いったい、牆壁(しょうへき)瓦礫(がりゃく)にほかならぬのが仏心であって、三世の諸仏はいずれもそれを不可得であると証(さと)ってうる。また、仏心にほかならぬ牆壁瓦礫があらば、三世の諸仏はそれをも不可得であると証している。ましてや、山河大地にほかならないものは、不可得そのものである。草木風水にして不可得なるもの、それが心であるといってもよい。あるいは、「まさに住する所なくしてその心生ず」という。それもまた不可得である。あるいは、また、十方の諸仏は一代にして八万の法門を説くという。不可得の心(しん)とはかかるものなのである。(169~170頁)
■また、大証国師のころ、西の方から大耳(だいじ)三蔵なるものが京師に到着した。他心通をえた者ということであった。そこで、唐の粛宗(しゅくそう)は国師に命じて彼を試みさせた。三蔵はちらりと国師をみて、進みでて礼拝し、その右にたった。やがて国師が問うていった。
「なんじは他心通をえたというが、そうであるか」
「いうまでもない」
と三蔵は答えた。
国師はいった。
「では、いってみるがよい。わたしはいま何処におるか」
三蔵はいった。
「和尚は一国の師であられるのに、おやまあ、西川(せいせん)においでで競艇を見ておいでじゃ」
しばらくして、国師はふたたび問うていった。
「いってみるがよい。わたしはいま何処におるか」
三蔵はいった。
「和尚は一国の師であられるのに、なんとまあ、天津橋(てんしんきょう)のうえで猿まわしを見ておいでじゃ」
国師はまた問うていった。
「もう一度いってみるがよい。わたしはいま何処にあるか」
今度は、しばらく経っても、三蔵はどうしても答えることができなかった。そこで、国師は叱咤していった。
「この野狐精(やこぜい)め。なんじの他心通はいったいどこへ行った」
だが、三蔵はいぜん答うるところがなかった。
このようなことは、知らなければいけない。聞かなければおかしいと思うであろう。仏祖と三蔵とではまるでちがう、天地の差があるのである。仏祖は仏法が判っておる、三蔵はまだそれを知らない。いったい、三蔵は在俗の者でもなることができる。たとえば、文学の道に通じた者などもそうである、だがしかし、ひろくインドや中国の言語に通ずるのみならず、他心通までも修得していても、こと仏法の身心にいたっては、なお夢にも知らないのである。だから、仏祖の位を証得(しょうとく)している国師のまえにでると、たちまちに看破せられることとなる。
仏道において心(しん)をまなぶには、よろずの存在がそのまま心である。三界はただ心である。ただ心のみであるから唯心なのであろう。仏もまたそのまま心といってもよい。いや仏のみではない。自己も他人もすべてひとしくそうなのである。だからして、いたずらに西川(せいせん)までも下ってゆく必要はなく、あるいは天津橋(てんしんきょう)までも飛んでいって心をさがす必要はない。もし仏道の身心を会得したいならば、仏道の智慧をまなぶがよい。さすれば、仏道ではすべての大地がみな心である。生ずると滅するとにかかわらず、すべての存在がみな心である。すべての心がみな智慧だと学んでもよい。
三蔵にはそれが判らないから、ただ野狐のわざを弄するのみであった。だから、はじめの両度の問いにも、国師の心が判らず、国師の心に通うことができなかった。ただいたずらに、西川だの天津だの、あるいは競艇だの猿廻しなどと、人をたばかる野狐のわざを弄するばかりであった。どうして国師が判るものか。また、どこに国師がいるのか判ろうはずもなかった。「わたしはいま何処におるか」と、国師が三度まで問うても、そのことばの意味も判らなかった。もし判ったならば、国師に問うべきであった。聞く耳がないからすれ違ってしまうのである。もし三蔵が仏法をまなんだことがあったならば、国師のことばも判ったであろうし、国師の身心を見ることもできたであろう。だが、日頃から仏法をまなんでいなかったので、人天(にんでん)の導師にめぐりあいながら、いたずらに機会を逸してしまった。あわれなこと、かなしいことである。
いったい、三蔵の学者などに、どうして仏祖の足跡が判るものか。国師の在処(ありか)が知れるものか。ましてや、西方の論師(ろんじ)やインドの三蔵など、とても国師の足跡が判ろうはずはない。三蔵の知りうるところは、天帝(てんたい)も知るであろう、論師も知るであろう。論師や天帝の知りうるところぐらいは、やがて仏位にいたるべき菩薩の智力のおよばぬところではなく、また、十聖・三賢(さんげん)もけっして及びえないものではない。だが、国師の身心は、天帝も知りえざるところ、いまだ仏位にいたらぬ菩薩もまだ判らないところである。仏教において身心を論ずればこのようである。これを知り、これを信ずるがよい。(174~177頁)
■ある時、ひとりの僧が国師に問うていった。
「古仏心とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)じゃ」
これも心不可得である。
またある時、ひとりの僧が国師に問うていった。
「諸仏のつねなる心とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「幸いに、わしの参内(さんだい)に出遇ったなあ」
これも不可得の心を究明しているのである。
またある時、天帝釈が国師に問うていったことがある。
「どのようにしたならば、この無常の世界を解脱することができましょうか」
国師はいった。
「天神は道を修めて、この無常の世界を解脱するがよろしい」
天帝釈はかさねて問うていった。
「その道とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「つかのまの心、それが道である」
天帝釈がいった。
「つかのまの心とは、どのようなものでありましょうか」
国師は手をあげて指さしていった。
「これが般若の台(うてな)である。あれが真珠の網でござる」
天帝釈は頭をさげて礼拝した。
およそ仏道にあっては、仏祖たちの会座(えざ)において身心を談ずることが多い。いずれもそれをまなぶことは、凡情の思量をもってしては及ばないところである。心不可得ということを思いめぐらしてみるがよいのである。(194~195頁)
〈注解〉真珠網;この世界を指さして真珠をちりばめた網というのであろう。『華厳経』に因陀羅網とて、この世界の構造を語るに宝石をちりばめた宝網のたとえがある。推して知るべきである。(196頁)
古鏡(こきょう)
■開題
この「古鏡」の巻は、仁治二年(1241)九月九日、いつものように興聖寺において衆(しゅ)に示された。
では、その巻題のもとに道元が説こうとするものは、いったい何であるか。それについて、わたしは、ここでまず、道元がこの『正法眼蔵』の巻々において、しばしば試みている手法をあかしておきたいと思う。
道元は、まず、その冒頭の一節ににおいて、ずばりと、そのいわんとするところを凝縮して語りいでる。この巻においていうなれば、
「諸仏諸祖の受持し単伝するは、古鏡なり。同見同面なり、同像同鋳なり、同参同証す。胡来胡現、十万八千、漢来漢現、一念万年なり。古来古現し、今来今現し、祖来祖現するなり」
とあるのがそれである。道元は、この巻においていわんとするところを、すでにこの数十字のなかに凝縮して打ち出しているのである。
幾度もいうように、この『正法眼蔵』の巻々は、総じて、まことに難解である。まさに難解第一の書である。だが、その難解にめげずして、さらに幾度となく読みきたり読みさるうちに、ふと気がついてみつと、その難解さは、しばしば、その冒頭の一段において極まるのである。何故であろうかと思いめぐらしてみると、結局するところ、そこに、いまもいうように、もっとも凝縮された要旨がずばりと語りいだされているからである。
では試みに、いまここに引用した冒頭の一節を、いささか解きほぐしていうなれば、おおよそ、つぎの四点にわかっていうことを得るであろうか。
その第一には、もろもろの仏祖が伝え来るものはなにか、それは仏心ということもできよう。智慧ということもできよう。あるいは心印ということもできよう。だが、それらは、結局、抽象的な概念にしかすぎない。それを、もっと具体的にいうなれば、古鏡をもって象徴することができるとする。
その第二には、もろもろの仏祖がそれによって営むところを、古鏡に事寄せていえば、同像同鋳であるということを語っている。彼らの言行は、一見すれば不覊奔放であるが、まことは、ぴたりと一致しておるという。同参同証という所以である。
その第三には、その営むところを、さらに突きつめていえば、つねにあるがままを把握していることを特徴とするという。古鏡の、胡来胡現であり、漢来漢現であることを力説しているのは、そのことを語っているのである。
そして、その第四には、そのような仏祖のありようは、古今を通じて変わるものではないことが示されている。古来古現し、今来今現すというは、そのことである。道元が古仏ということばを愛惜していることは、この『正法眼蔵』の巻々のいたるところにみられるが、そのことばのなかには、この考え方が基底として存している。
さて、そのように凝縮した冒頭の一節を打ち出したのち、道元は、つぎつぎに、古鏡にちなむ仏祖の言行・問答をとりあげて、こんどは、嚙んで含めるような心ばえをもって、つぶさにそれぞれの解説をこころみる。
そこには、伽耶舎多尊者(がやしゃたそんじゃ)のふしぎな円鑑の物語もある。六祖慧能のよく知られた明鏡の偈(げ)も説かれている。さらに、雪峰・玄沙・三聖(しょう)などの古鏡にちなむことばが論ぜられ、最後に、南嶽が馬祖のためにしめした「瓦を磨いて鏡となす」という物語があげられている。その結びに及んで、
「塼(せん)もし鏡とならずば、人ほとけになるべからず」
という一句があるのが、わたしには忘れられない。(198~200頁)
■もろもろの仏祖が伝え受け、保持し、また伝えいたるものは古鏡である。それはいつでも、同じ面(おもて)をうつし、同じ証(さとり)をうつし出す。胡人がきたれば胡人をうつしだすこと、その数かぎりなく、漢人がきたれば漢人ををうつし出すこと、その時をえらぶことがない。古人がくれば古人を現じ、今人がくれば今人を現じ、また祖が来れば祖を現ずるのである。(200~201頁)
〈注解〉※この一段は、仏祖の一人より一人へと仏心を単伝するありようを語るに、古鏡をもって象徴するのである。古鏡とは、智慧をたとえていうのが、古来からのならいである。
胡人;胡は北方のえびず。それによって、すべての異邦人をいうのである。
漢人;漢は中国本土の称。漢人はすなはち中国人である。(201頁)
■では、心と眼がみな相似ているというはどういうことであるか。それは、心は心に相似ているいるのであり、眼は眼に相似ているのである。相似ているのは心と眼であって、たとえば、心・眼それぞれに相似ているということである。では、さらに、心が心に相似ているとはどういうことであるか。いわゆる「道眼は眼に礙(さ)えられる」ということでる。
いま、かの童子がいうところの偈の意は、そういうことであって、それが、童子のはじめて僧伽難提(そうぎゃなんだい)尊者にまみえた真の理由であった。その意味をよくよく思いめぐらして、大円鑑のうつしだす仏祖の面影をまなぶがよい。それが古鏡をかえりみることなのである。(208頁)
■第三十三祖大鑑禅師慧能は、かって黄梅山の法席にあって修行していたころ、壁に一偈を書して祖師弘忍に呈(てい)した。いわく、
「菩提はもと樹なし
明鏡もまた台に非ず
本来一物なし
いずれの処にか塵埃(じんあい)あらん」
では、その表現をまなびとってみるがよい。大鑑禅師を世の人々は古仏とよぶ。圜悟禅師も、「曹谿のまことの古仏に稽首(けいしゅ)する」といっておる。だからして、大鑑禅師が明鏡について語れば、「本来一物なし、いずれの処にか塵埃あらん」である。また、「明鏡は台に非ず」という。そこにいのちがある。思いめぐらしてみるがよい。明々なのはみな明鏡である。だから、明るいものがくれば、明るいのである。それは何処でもないから、何処にもないのである。ましてや、鏡にない塵が、この世界のどこにのこっていようか。鏡につもらぬ塵が、鏡にのこっていようはずがあるものか。かくて知るがよい、この世界はけっして「塵の世界」ではないのである。だからして古鏡のおもてである。(211~212頁)
〈注解〉第三十三祖大鑑禅師;大鑑禅師は曹谿慧能の諡号。六祖である。ここに第三十三祖というは、西天二十八祖よりつづいて数えたのである。
菩提本無樹云々;『法宝壇経』によれば、五祖弘忍のもとに神秀と慧能があったころのこと、神秀が宝林寺の南廊壁間に、その心所見を呈して、「身是菩提樹、心如明鏡台、時時勤払拭、勿使惹塵埃」と書した。それに対して、慧能もまた所見を呈して、壁間にこの偈を書したという。ただし、古来その結句は「何処惹塵埃」(いずれの処にか塵埃を惹かん)と伝えられている。(212頁)
■雪峰山の真覚(しんかく)大師は、ある時、衆(しゅ)に示していった。
「このことを会得しようとならば、わが内は一面の古鏡によう似ておる。胡人が来れば胡人がうつり、漢人が来れば漢人がうつる」
すると、玄沙師備(げんしゃしび)がすすに出て、問うていった。
「では、ひょっこり明鏡の来たるに遇ったら、どういうことになるのでしょう」
雪峰はいった。
「胡人も漢人も、ともに隠れるよ」
玄沙はいった。
「わたしはそうは思いません」
雪峰はいった。
「しからば、そなたはどう思うか」
玄沙はいった。
「では、和尚の方から問うていただきたい」
雪峰が問うていった。
「では、にわかに明鏡に来たるに遇った時にはいかに」
玄沙がいった。
「木端微塵でござる」
まず、雪峰が「このこと」といったのは、いったい何のことかと考えてみなければならぬ。だが、いまのところは、これをしばらく雪峰の古鏡論としてまなぶことにしよう。
まず、「一面の古鏡のごとし」という。一面とは、まったく際限がなく、また、内も外もないことである。そのような盤のうえを一つの球(たま)がはしる。それが自己なのである。
また、「胡人が来れば胡人が現ずる」という。胡人というは、一人の赤鬚の異邦人である。また、「漢人が来れば漢人が現ずる」という。漢人とは、開闢(びゃく)のいにしえから、かの国土に生(お)い育ってきた人であるが、いま雪峰のいうところでは、古鏡の功徳としてその漢人が現われるという。いまの漢人はその漢人ではないから、すなわち漢人が現ずるというのである。
さらに雪峰は、「胡人も漢人も、ともに隠れる」という。それは、さらにいうならば、「鏡そのものも隠れる」というところであろう。そこで、玄沙は、いや木端微塵に砕けるのだといった。いうなれば、そんなところであろうけれども、そこで今度は、玄沙が責められる番だ。では、「わしにその砕片を還(かえ)してくれ」とか、あるいは、なんでわしに明鏡を還してくれないか」と。(218~219頁)
■かって、江西の馬祖が南嶽に師事していたころ、南嶽は、ふしぎな仕方でさとりを得しめた。それが瓦を磨くということばのはじめであった。
そのころ、馬祖は伝法院に住して、世のつねのように坐禅を行ずること、ほぼ十余年のころのことであった。雨夜の草庵のたたずまいを思いやるがよい。雪にとざされて寒々とした坐牀(ざしょう)にも怠ることがなかった。その草庵を、ある時、南嶽が訪れたのである。
馬祖がかたわらに侍立していると、南嶽が問うていった。
「そなたは、この頃なにをしておるか」
馬祖はいった。
「この頃わたしは、ただ坐っておるだけでございます」
南嶽がいった。
「坐禅をして、どうしようというのか」
馬祖がいった。
「坐禅をして仏になろうとするのでございます」
すると、南嶽は、一片の瓦をひろってきて、草庵のほとりの石にあてて磨きはじめた。それを見て、馬祖は、問うていった。
「和尚は、なにをなさるのですか」
南嶽がいった。
「瓦を磨くのじゃ」
馬祖はいった。
「瓦を磨いて、それをどうなさるのですか」
南嶽がいった。
「磨いて鏡にしようというのじゃ」
馬祖はいった。
「瓦を磨いて、どうして鏡となすことができましょうぞ」
南嶽がいった。
「坐禅したからとて、どうして仏になることができようか」
この一段の対話は、昔から何百年ものあいだ、人々はたいてい、ただ南嶽が馬祖を激励したとのみ思っている。けっして、そうとのみは限らないのである。すぐれた聖者の言行は、はるかに凡人の境地をぬきん出ているのである。
いかにすぐれた聖者であろうとも、もし瓦を磨く手立てがなかったならば、どうして人のために方便をたてえようか。人のためにするというのは仏祖の本質というもの。そのために手段を講ずるのは、いうなれば手なれた家具というものである。家具であり、調度であるから、それが仏の家につたえられるのである。ましてや、いま南嶽は、それをもって、みごとに馬祖をみちびきたもうた。その指導のありようは、仏祖正伝とは直指(じきし)であることをよく示している。
まことに知る。磨いた瓦が鏡となった時、馬祖が仏となったのである。また、馬祖が仏となった時、馬祖はたちまち馬祖その人となったのである。そして、馬祖が馬祖となったその時、坐禅がたちまち坐禅となった。
だからして、瓦を磨いて鏡をなすということが、古仏の骨髄として伝えられて、いまもなお、瓦のなれる古鏡が存する。その鏡は、よくよく磨いてみると、もともと清淨(しょうじょう)なものであって、塵に汚れた瓦ではなかった。ただ瓦であったものを磨いただけである。そこに鏡が実現するというのが、とりもなおさず仏祖の工夫というものである。
もしも、磨いた瓦が鏡とならないならば、鏡を磨いても鏡となすことはできまい。誰が考えたことでもあるまいが、おなじ「作」の一字を冠して、作仏といい、また作鏡(さきょう)というではないか。
また、古鏡を磨くにあたり、あやまって瓦としてしまうことはないかと心配する者もあろうか。だが、この磨く時の消息は、他の場合をもって推し測るべきものではない。ともあれ、南嶽のことばは、まさにいうべきことをいいえているのであって、結局するところ、かならず瓦を磨いて鏡となすことをうるのである。では、いまの人もまた、その瓦をとって試みに磨いてみるがよい。きっと鏡となすことをうるのであろう。
もしも、瓦が鏡とならないものならば、人が仏となろうはずはない。もしも、瓦は泥のかたまりだと軽んずるならば、人もまた泥のかたまりと軽んじねばなるまい。人にもし心があるとならば、瓦にもまた心があるはずである。誰が知ろうぞ、瓦を磨ききたって瓦を現ずる鏡のあろうことを。また、誰ぞ知らん、鏡を磨ききたって鏡をなせる鏡の存することを。(257~259頁)
仏性(ぶっしょう)
■釈迦牟尼仏はいった。
「一切衆生、悉有(しつう)仏性、如来常住、無有変易」
それは、われらの大師釈尊のとかれた大説法であるが、また、すべての仏たち、すべての祖たちの頭(ず)頂となし、眼目となすところである。仏教者はこれをまなびきたること、すでに二千百九十年(日本の仁治二年にあたる)、その間、正嫡(しょうちゃく)をかずうればおおよそ五十代(先師天童如浄禅師に至る)、西のかた天竺において代々伝持すること二十八代、東の国において世々相承(そうじょう)すること二十三世、みなよく保ちつづけて今日にいたる。
釈尊がいうところの「一切衆生、悉有仏性」とは、その意味するところはいかに。それは、「こんな物がどうして来たのだ」といっておられるのである。あるいは衆生といい、あるいは有情(うじょう)といい、あるいは群生(しょう)といい、あるいは郡類という。悉有というのは、その衆生のことであり、その群有(う)のことである。つまり、悉有は仏性であって、その悉有の一つのありようを衆生というのである。まさにその時にいたれば、衆生はその内も外もそのまま仏性の悉有である。それは仏祖の伝える皮肉骨髄のみではない。「汝はわが皮肉骨髄を得たり」であるからである。
それによっても判るように、いま仏性に悉有せられる「有(う)」は、有りや無しやの有ではない。悉有は仏のことばであり、仏の舌であり、したがって、また仏祖の眼目であり、仏者の鼻孔である。それはけっして治有(しう)でもなく、本有(ほんぬ)でもなく、また妙有などというものでもない。ましてや、縁有や妄有(もうう)であろうはずはない。心・境・性(しょう)・相などに関わるものでもない。だからして、衆生悉有の身心と世界とは、すべて、業(ごう)の力をもって変えうるものでもない。妄情を縁として齎(もたら)されるものでもなく、あるいは自然にしてかくあるものでもなく、神通の力によって証得せられるものでもない。もしも衆生の悉有なる仏性が、業によるもの、縁によるもの、あるいは自然にしてかくあるものとするならば、もろもろの聖者のさとりも、もろもろの仏の智慧も、あるいはもろもろの祖の眼目も、また業や縁や自然にしてしかるものであろう。だが、そうではないのである。すべてこの世界にはまったく外より来るものはない。ずばりといえば、べつに第二の人があるわけではない。ただ、「直ちに根源を切断することを知らず、あれこれと妄想を逞(たくま)しゅうして休(や)む」の時がないのである。「徧界(へんかい)かって蔵(かく)さず」という。妄情によってなる存在などあろうはずもないのである。
だが、「徧界(へんかい)かって蔵(かく)さず」というのは、かならずしも「一切世界はわが有(う)」ということではない。それは外道のまちがった所見である。だからといって、また本有(ぬ)の有でもない。それは古今にわたっての存在であるからである。また、はじめて起これる有でもない。「一塵をも受けず」であるからである。また、突如として出現する有でもない。それは凡人も聖者もともに同じく有するがゆえである。あるいは、始めのない有でもない。だから「こんな物がどうして来たのだ」という。あるいは、ある時はじめて存する有でもない。だから「平常心これ道(どう)」というのである。つまるところ、悉有というのは、快(こころ)よき便の捉えどころがないようなものであって、そのように会得すれば、悉有は気持ちよく身体を脱落してゆくのである。(304~306頁)
〈注解〉什麼物恁麼来;『景徳伝燈録』巻五、南嶽伝にみえる一句。南嶽懐譲がはじめて六祖慧能に見参したときの問答であって、そこには、「乃直詣曹谿参六祖、祖問、什麼処来。曰、嵩山来。祖曰、什麼仏恁麼来」とある。「こんな物がどうして来たのだ」というほどの意であろう。
始有・本有・妙有・縁有・妄有;有という仏教の述語はもと“bhava”(=beinng)の訳語である。音写してまた烏波(うは)ともいう。あることであり、存在である。そのありようにさまざまある。ある時より始めてあるを始有(しう)という。もとよりあるを本有(ぬ)という。空にして有(う)なるを真空妙有という。また、縁(条件)あるによりてあるを縁有といい、迷妄によりてあるを妄有という。そして、仏性の悉有はそのいずれでもないとするのである。
心・境・性・相;心は内なる心、境は外なる対象、自仏の本質として易(かわ)らざるは性であり、その性のあらわれとしてのすがた・はたらきは相である。
偏界不曾蔵;「偏界曾つて蔵(かく)さず」である。『碧巌録』第五三則に、「偏界不蔵、全機独露」の句もみえる。一切の諸方はいささかもその秘密をかくし蔵することなく、その実相をそのままに露呈しているというほどの意である。
平常心是道;『無門関』の「平常心是道」のくだりに、南泉と趙州の問答がある。「趙州問、如何是道、泉曰、平常心是道」と。
快便難逢;『渉典続貂(しょうてんぞくちょう)』によれば、『談藪(だんそう)」なる文献に「下坡不走、快便難逢」の句があるという。坡(どて)でここちよく小便をする。小便はさらさらと流れてゆく。それはもう逢えない。そんな意味であろう。その句をもって、道元は、つぎの透体脱落の句にかけているのである。(306~308頁)
■その仏性ということばを、学者のなかには、先尼外道のいう「我(が)」のように思い誤っているものがすくなくない。それは、然るべき人にあわず、自己にもあわず、師にもまなばないからである。ただいたずらに、わが内に風のそよぎ火のもゆるようにゆれ動く心識をもって、それが覚知のはたらきだと思っているのである。いったい、仏性に覚知のはたらきがあるなどと、誰がいったのであろうか。なるほど、諸仏のことを覚者といい知者とはいうけれども、仏性はけっして覚知でも覚了(かくりょう)でもない。ましてや、諸仏を覚者・知者というときの覚と知とは、なんじらが云々する誤れる考えをいうのではない。風・火の二大(にだい)のうごきを覚知とするのではない。ただ、一箇両箇の仏の面目、祖の面目をなるを覚知とするのである。
漢より宋にいたるまでの間にも、あるいは西の方天竺にまで往復し、あるいは人々の教化に力をつくした古老先徳はすくなくなかったが、そのなかにも、風大・火大の動きをもって仏性のはたらきと思っていたものはすくなくなかった。あわれむべきことである。仏教のまなびかたが疎漏であったためにこの誤りをおかしたのである。いま仏教をまなぼうとする後学初心のものはそうではいけない。
たとい覚知をまなんでも、覚知とはそんな心の動きではない。たとい心の動きをまなんでも、心のはたらきはそんなものではない。もし本当の心のはたらきを会得できれば、本当の覚知もわかるはずである。「仏性とは、かれに達しこれに達す」という。仏性はかならず悉有である。悉有が仏性であるからである。悉有とはばらばらになったものではなく、また鉄のかたまりのようなものでもない。あるいは、雲水が拳骨を突きだすあれであって、大でもなく小でもない。また、すでに仏性というからには、もろもろに聖者とならべていうべきでもない。それは仏性と比すべきものではない。
ある一部の人々は、仏性は草木の種子のようなものだという。それは、法雨のきたって、しきりと潤すとき、芽を出し、茎を生じ、枝や葉をひろげ、花をひらき果(み)をむすぶにいたり、さらにその果は種子をはらむ。だが、そのように考えるには凡夫の計らいというものである。たといそのような見方をしても、その種子とその花と果(み)は、それぞれ別々の心のすがたと考えてみるがよい。果のなかに種子があったり、種子のなかには見えないけれども根や茎があったり、あるいは、どこから集めてくるわけでもないが、そこばくの枝や葉をだして繁りはびこる。そんな内か外かの問題でもなく、生ずる生じないの問題でもない。これは古今にわたって空しからぬものである。だから、たとい一応は凡夫の見解にまかせるとしても、ここでは根も茎も枝も葉も、すべてが同時に生じ同時に滅するものと知らねばならない。同じく悉有なる仏性だからである。(310~311頁)
〈注解〉※つづいて、仏性について、先人の誤れる所見三つを揚げて批判する。その一つは、自我の覚知はたらきをもってそれとする所見であり、その二つには、心意識の動きをもってそれとする所見であり、その三つには、草木の種子をもってそれを喩える所見である。
先尼外道;先尼は“Seniya” の音写であって外道の姓である。その外道の説くところは、さきの「即心是仏」の巻にくわしく紹介され、かつ、大証国師慧忠の語をもって、それに批判が加えられている。
■仏いわく、
「仏性の義を知らんと欲(おも)わば、当(まさ)に時節の因縁を観ずべし。時節もし至れば、仏性現前す」
いま仏性の義を知りたいと思うならばという。それはただ知るのみのことではない。また行じようと思うならばであり、証(あか)ししようとするならばであり、あるいは、説こうとするならばであり、忘れようとするならばである。その説も、行も、証も、忘も、あるいは錯(たが)うも、錯わざるも、すべては時の関係である。その時の関係を観察するには、時の関係をもって観ずるのである。払子(ほっす)・拄杖(しゅじょう)などをもって観ずるのである。けっして、有漏智・無漏智、もしくは本覚・始覚(しかく)・無覚・正覚(しょうがく)等の智をもってしては観察しがたいのである。当(まさ)に観ずべしというは、観るか観られるかにかかわらず、また正しく観るか誤って観るかなどということでもなく、まさに当に観ずるのであるから、自己が観るのでもなく、他が観るのでもない。時の関係そのままにして、時の関係を超絶するのである。仏性そのままにして、仏性を脱却するのである。仏は仏そのままに、性は性そのままに観ずるのである。
時節もし至ればという。その句を、昔の人も、往々にして、いつか仏性が現われる時があるだろうから、その時を待つのだと思っている。このように修行してゆけば、自然に仏性の現われる時期もあるだろう。時期が来なければ、いくら師を訪(おとな)うて法を問おうとも、分別して思いめぐらしても、なかなか現われてくるものではあるまいと、そのように考えて、なすこともなく俗塵に沈み、むなしく阿呆(あほう)な面(つら)をさらしている。そんな徒輩はおそらく自然外道の仲間なのであろう。
いまいうところの「仏性の義を知らんと欲(おも)わば」とは、いいかえれば、また「当(まさ)に仏性の義を知るべし」ということである。また「当に時節の因縁を観ずべし」というは、「当(まさ)に時節の因縁を知るべし」ということである。いわゆる仏性を知ろうと思うならば、時節の因縁がそれであると知らねばならない。時節もし至ればというのは、すでに時節がいたっておるのだ、なんの躊躇(ため)らうことやあらんというのである。疑うならば疑ってみるもよい。仏性はいつか我に還って来ているのである。
まさに知るがよい。時節もし至らばとは、寸分の時も空しく過ごしてはならぬということであり、もし至らばとは、すでに至るというに同じである。もしも時いたらばと待つならば、仏性はついに至らぬであろう。かくして、時すでに至れりとあらば、それこそ仏性の現われである。あるいは、その理(ことわり)もおのずから明らかなのである。およそ、時のいたらぬ時というものはなく、仏性の現前せざる仏性というものはないのである。(315~316頁)
〈注解〉有漏智・無漏智;漏とは煩悩のはたらきをいうことば。有漏智とは、いまだ煩悩を断たざる世俗智をいい、それに対して、無漏智とは、一切の煩悩をはなれた清浄な智慧をいう。
本学・始学;本覚とは、本有(ほんぬ)の覚性というほどの意である。それに対して、始学とは、教えを聞いてはじめて覚(めざ)めることである。だが、そのような覚める性は、突きつめてみると、もともとわが内に存するものであったはずである。それが本有の覚性である。
天然外道;また自然(じねん)外道、もしくは自然見(じねんけん)外道という。十種外道の一つである。一切の存在は因によりて生起することを認めず、自然にしてかくあるものとなすが故に、なんの人力の加うるところなしとする見解に立つのである。
三昧;“sama-dhi”の音写である。また三摩提(さんまでい)と写す。定と訳す。心を一処に集中して動せしめざるをいう。
六通;六神通である。定・慧等の力によってうる六種の自在なる力をいう。神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏人通(ろうじんつう)をいうのが常である。
神通波羅蜜;波羅蜜は“pa-ramita-”音写であって、到達、完成、成就を意味する。(318~319頁)
■中国の第六祖曹谿山大鑑禅師が、そのむかしはじめて黄梅山に詣(いた)ったとき、五祖は問うていった。
「汝はいずれの処よりきたのか」
彼はいった。
「嶺南人でございます」
五祖はいった。
「来(きた)ってなにを求めんとするか」
彼はいった。
「ただ仏となることを求めるのでございます」
五祖はいった。
「嶺南人は無仏性である。どうして仏になれようぞ」
この「嶺南人は無仏性」というのは、嶺南人には仏性がないというのでもなく、嶺南人は仏性があるというのでもない。ただ「嶺南人は無仏性」というのである。「どうして仏となれようぞ」というのは、どうして仏となろうとするのかというのである。
いったい、仏性の道理は、これを明確につかんだ先達(せんだち)はすくない。それは、もろもろの小乗の徒輩や、経師(きょうじ)や論師(ろんし)の知りうるところではない。ただ仏祖の流れを汲むもののみがそれを伝え来っておる。仏性というものは、成仏以前に身に具(そな)わっているものではなく、仏となってはじめて具わる。仏性はかならず成仏にともなう。その道理をよくまなびよく究めるがよい。二十年も三十年もかけて工夫しかつまなぶがよい。修行の途中にあるものが知りうるところではない。いま衆生に仏性ありといい、また衆生に仏性なしというは、この道理によるのであり、それは成仏以来はじめて具足するのだとまなぶのが正しいのである。そのようにまなばないのは仏法ではあるまい。でなかったならば、仏法はとうてい今日に到りえなかったであろう。もしこの道理を知らなかったならば、成仏も判るまい、聞くことも見ることもないのである。
かかるがゆえに、五祖は、彼に向かって語るに、嶺南人は無仏性だといったのである。仏法をまなぶにあたって、まず聞きうることの難きは、衆生無仏性ということである。あるいは善知識にしたがい、あるいは経巻によって、聞いてよろこぶべきことは、衆生無仏性ということでなくてはならぬ。一切衆生に仏性なしと、いやというほど聞かされ思いしらされるのでなかったならば、まだ仏性のことを聞いた判ったとはいえない。六祖はひたすらに仏とならんことをねがう。五祖は彼をしてよく作(さ)仏せしめようとする。それには他のいい方はない。ただ「嶺南人は無仏性」だというのみである。かくて、無仏性と語り、無仏性と聞く。それがまっ直ぐに作仏にいたる道だと知られるのである。とするならば、まさに無仏性のその時こそが、とりも直さず仏となるの時である。いまだ無仏性と聞かず、語らざるの時には、まだまだ仏にはなれないのである。
すると、六祖はいった。
「人に南北はあっても、仏性には南北はありません」
そのことばを取りあげて、その句のこころを思いめぐらしてみるがよい。とくに南北ということばは、心にあてて照らしてみるがよいのである。この六祖のことばには大事な意味がある。それは、人は仏となりえても、仏性は仏となりえないという一つの構えである。六祖がそれに気がついていたかどうか。
思うに、四祖五祖の語った無仏性という表現は、まことに注目をうながすに足るものであった。はるかにそれに相対して、迦葉仏や釈迦牟尼仏などの仏たちは、仏となり法を説くにあたって、悉有仏性と表現する力をもっておられた。その悉有の有から無仏性の無へと法が嗣(つ)がれてきてもすこしも不思議ではない。かくして、無仏性の語は四祖・五祖の室内より聞こえきたって、はるかに今日におよんでおる。だが、この時、六祖ほどの人であったならば、この無仏性の語をもう一歩ふみ込んだ工夫があってしかるべきであったと思う。有りや無しやはしばらく措(お)いて、いったい仏性とはいかにと問うてみるべきであった。仏性とはそもそもどのようなものかと訊(たず)ぬべきではなかったか。今の人々も、仏性と聞けば、さらに仏性とはなんぞと問うことをせず、ただ仏性の有りや無しやなどをのみ論ずる。それと同じである。迂闊(うかつ)というものである。
とするならば、しばらくいろいろの場合の無をとりあげて、無仏性の無にあてて考えてみるがよい。六祖は「人に南北あり、仏性に南北なし」といった。その表現を再三再四、ふかく沈潜して掬(すく)うてみるがよい。蝦(えび)をとるには撈波子(ろうはし)という竹具ををもってすくう。まさにそのようにして掬ってみるがよい。あるいはそれをしずかに拈(こ)ねまわしてみるもよい。しかるを愚かなる輩(やから)は、人間には物のひっかかりがあるから南北があるが、仏性は虚(きょ)にして無礙なるがゆえに南北の論におよばずと、六祖のことばをそんな工合に推し測る。それはわけもない愚蒙(ぐもう)の沙汰というもの。そんな愚かな考え方をなげすてて、まっ直ぐにまなびいたらねばならぬ。(330~333頁)
■第十四祖龍樹尊者は、梵音にはナーガルジュナ(那伽閼刺樹那)といい、訳して龍樹、龍勝、もしくは龍猛という。西の方天竺の人である。ある時、南天竺にいたってみると、その地の人々はたいてい招福の術を信じ、尊者がすぐれた法を説いても、彼らはたがいに相顧(かえり)みて、
「人は福(さいわい)のあるのがこの世でなによりのこと。仏性などと説いたって、誰も見ることはできはしない」
といった。だが、尊者は説いていった。
「汝ら仏性を見ようと思うならば、まず我(が)の慢心をさるがよい」
彼らはいった。
「仏性とは大きなものか小さなものか」
尊者はいった。
「仏性は大にあらず小にあらず、広きにもあらず狭きにもあらず、また福(さいわい)もなく報(むくい)もなく、不死にして不生である」
彼らは、その理(ことわり)のすぐれたるを聞いて、ようやく心をひるがえした。そこで尊者は、こんどは、その座において自在身を現じた。それは満月のようであった。会衆はすべてただ法を説く声のみを聞いて、尊者のすがたは見えなかった。その会衆のなかに、長者の子で迦那提婆(かなだいば)という者があって、みなにいった。
「みなさんはこの相(すがた)が判りますか」
会衆はいった。
「こんなのは、まだ見たことも聞いたこともない。あるいは、心に知るところでもなく、身に経験したこともない」
そこで提婆がいった。
「これは、尊者が仏性の姿を現じて、わたしどもに示しておられるのです。どうしてそうと判るかといえば、無相三昧はそのすがた満月のごとしとあります。仏性は廓然として虚(こ)明なものであるからです」
彼がそういい終わると、満月の輪相はたちまち消えて、尊者はまたもとの座に復し、偈を説いていった。
「身にまろき月の相を現じ
もって諸仏の本体をあらわす
法を説くにその形なく
よって声色(しょうしき)にあらざることを示す」
まさに知るがよい。真に役立つものは声や形に現われたものではなく、本当の説法というものは形がないのである。龍樹尊者はそれまでにも仏性を説くこと幾度なるかを知らない。いまはただその一つを略してあげるのみである。
そこにはまず、「汝仏性を見んと欲せば、先ず我慢を除くべし」とある。その説く意味を、素通りせずに考えてみるがよい。それは見ることができないわけではない。だが、見るためには我慢を除かねばならぬ。我(が)もひとつではない、慢(まん)ももさまざまである。それを除くにもまたさまざまの方法があろう。だが、いずれにしても、かくすれば仏性を見ることをうるのである。この眼で見るように見えるのである。
また、「仏性は大にあらず小にあらず」という。それも世のつねの凡夫や小乗のやからの例にならってはならぬ。かたくなに仏性は広大なものとのみ思うのは、かえって誤解を重ねることとなろう。もしも大にあらず小にあらずというその表現にひっかかるようならば、いままさに龍樹の前にあってそれを聴くような思いををもって思いめぐらしてみるがよい。そう思って聴いておると、尊者はやがて偈を説いて申される。「身に円月の相を現じ、もって諸仏の体を表わす」と。それは、もろもろの仏の実体を身をもって表現するのであるから、とうぜん円月の相でなくてはならない。そこでは、長いの短いの、四角いの円いのというのは、すべてその実体ではない。その身相における表現が判らなければ、円月の相が判らないばかりではなくまた諸仏の実体も判らないであろう。
すると、愚かなる者はいうのであろう。その時、尊者はかりに化身をもって円月の相を現じたのであろうと。そう思うのは、仏道を相承(そうじょう)しないやからどもの間違った考えである。何処に、また何時、尊者が自身ならぬ身を現じたというか。まさに知るがよい。そのとき尊者はただ高座に坐しておったのみである。その身のありようは誰もが坐っていると同じであった。その姿がそのまま円き月の姿を現じていたのである。その姿は四角でも円(まる)でもなく、有でも無でもなく、陰でも顕(けん)でもなく、その他なにものでもなかった。ただそのままの姿であった。それを円月相というは、そこには一体なにがあったか、どうみても、それは月であった。その姿は、まず我慢を除いたものであるから、もはや龍樹ではなくて諸仏の実体である。それでもって諸仏の実体を現じているのだから、それがそのままそれである。だから、仏の姿がどうということではない。また、仏性が満月を思わせるような虚明(こめい)なものだからといって、それで円月相をもち出したわけでもない。ましてや、そのはたらきは声色(しょうしき)でもなく、その姿は肉身でもない。あるいは、いずれの蘊(うん)・処(じょ)・界に属するものでもない。いや、一応はそれらに似ているようであるが、ただそれらをもって表現するだけのことである。それはあくまでも諸仏の実体である。それは説法の姿にほかならぬ。だから、その形はない。その形がないから、無相三昧にししてはじめてその相を現ずるのである。
いまその一座の人々は、その円月相を望見しながら、その目はそれを見ることがなかったという。それは説法の機微というものである。自在身を現じてもそれは声や形ではない。円月の相は陰顕自在であるから、座上にあって自在身を現じたその時でも、すべての会衆はただ法を説く声をきくのみにして、師の姿を見ることがなかったのである。ただ、この師の法嗣(ほうし)たる迦那提婆尊者のみは、あきらかに満月の相を知り、円月の相を見、その姿の現ずるを見、諸仏の本性を識(し)り、また諸仏の実体を識った。師の室に入ってその法を受くる者はたくさんあっても、この迦那提婆に比すべきものはあるまい。彼こそは半座の尊者である。会衆の導師として、師の坐を分かたれる者である。けだし、彼が正法眼蔵を付与せられ、無上の大法を正伝せられたことは、かって霊鷲山上の会座(えざ)において、摩訶迦葉が仏の高足(こうそく)としてそれを受けたとおなじである。
龍樹は仏教に帰する以前、すでに婆羅門の諸学に通じ、多くの弟子をもっていた。だが彼は、それらをみな謝して去らしめ、仏祖となってのちはただ一人提婆を正嫡(しょうちゃく)として、眼蔵を付与し大法を正伝した。それが無上の仏道の単伝というものである。しかるに、時として、われも龍樹菩薩の法嗣であると僣称(せんしょう)して、論を造り、説をなす者をみることがある。それらはたいてい、龍樹の名をかりたのみであって、龍樹の造(ぞう)ではない。ただ、さきに去らしめられた弟子たちが人々を迷わすだけのものである。仏弟子たるものは、ただひとすじに、迦那提婆の伝うるところのみが龍樹の所説であると知るべきである。それが正信を得たというものである。しかるに、偽作と知りながらもそれを受ける者が少なくないのは、仏法を謗(ぼう)ずる愚かなる衆生というものであって、あわれにもまた悲しむべきことである。
さて、迦那提婆はその時、龍樹菩薩のその姿を指さして、一座の人々に告げていった。「これは尊者が仏性の姿を現じて、われらに示しておられるのである。どうしてそれが判るかといえば、無相三昧はその姿満月のごとくにして、仏性は廓然として虚明(こめい)なものであるからである」と。いまこの世界にくまもなく流布する仏法をまなび来れる古今の人々にして、この姿をもって仏性なりといったものが誰があろうか。その余の人々はただ、仏性とは眼に見、耳に聴き、心に識(し)るなどのものではないと表現するのみである。この姿が仏性とは知らないからいい得ないのである。祖師が惜しむわけではないが、ただ眼も耳もふさがっているから見聞することができないのである。あるいは、それをそうと識るべき境地にいたらないから了別するころができないのである。無相三昧の姿の満月のごとくなるを望見し礼拝しながらも、なお眼はそれと見ることができないのである。
彼は、仏性は廓然(かくねん)として虚明(こめい)であるという。だから、身をもって仏性を説くにもまた虚明にして廓然である。仏性を説くために現じた姿は、諸仏の実体を顕しているのである。いずれの仏もこの姿を実体としないものがあろうか。けだし、仏の実体はその姿である。姿として現れる仏性があるのである。かつて、仏性とは四大(しだい)である、五蘊であると説いた仏祖の指標も、かえってそのかりそめの姿によるのである。すでに諸仏の本質をかたるに体(たい)という。この世界のありようがすべてそうなのである。一切のことがそれによるのである。仏の功徳というも、その姿に尽き、その姿に究極する。その数かぎりない功徳のひとつひとつが、その姿のかりそめの現われにほかならないのである。
それなのに、龍樹・提婆の師弟より以後、印度・中国・日本においてたまたま仏教をまなぶ人々があっても、まだ龍樹・提婆のように語った者はない。おおくの経師(きょうじ)・論師などが仏祖のことばを解しそこねたのである。宋国においても、むかしからこの物語をえがこうとして、身にえがき、心にえがき、空にえがき、壁にえがくこと能わずして、ただむやみに筆のさきによってえがき、かの法座のうえに鏡のような一つの輪をえがいて、それが龍樹の現じた円月相であるとした。それ以來すでに数百年の歳月を経て、ずっと人の眼をごまかしつづけけているのに、誰一人としてそれを誤りがと指摘する者もない。万事がそのように間違っているのだから、かなしいことである。もしも龍樹の現じた円月の相が、一つの輪相であったと心得るならば、それこそ本当に画餅一枚というべきもの。人を愚弄するにも程があろうというものである。
悲しいかな、大宋国の在家も出家も、誰一人として龍樹のことばを解せず、提婆のことばに通ずる者もなかった。ましてやかの尊者の姿を身をもって迫るものはなかった。円月はくらく、満月は欠けていたのである。それも古(いにしえ)をまなぶことをおろそかにし、古をしたう心のいたらぬがためである。先人も後輩も、せっかく真の仏の姿に遇うて、画餅を味わうの愚をおかしてはなるまい。
識るがよい。かの円月の相を現じたるをえがかんとならば、その法座にその姿が現われねばならない。眉を揚(あ)げ目をまたたく端正な姿がそこになくてはならない。正法眼蔵そのものの姿が、そこに高々(こうこう)として坐しているのでなくてはならぬ。あるいは、にっこりと微笑する顔がそこになくてはならない。けだし、その時こそ、仏が成り祖が成るの時だからである。その画がそのまま月の姿でなかったならば、それはいまだ到らず、説法もせず、声色(しょうしき)もなく、なんの用をもなさぬのである。もしその姿をえがこうとならば、円月相をえがくがよい。円月相をえがけば、円月の姿がえがかれるであろう。その姿が円月相であるから、円月相をえがけば満月の相がえがかれ、満月の姿が現ずるであろう。しかるに、その姿をあががず、円月をえがかず、満月の相をえがかず、したがって、諸仏の実体を表わすことをえず、説法もせず、ただいたずらに画餅一枚をえがく。それがなんの用をなそう。いそぎ見たからとて、誰も飢えを充たすことはできまい。なるほど月は円い。円きは仏の姿である。その円きをまなぶに一枚の銭のように思ってはならぬ。一枚の餅に似ているとしてはならぬ。その姿は円月の姿である。「その形満月のごとし」である。一枚の銭、一枚の餅は、その円きをまなぶがよいのである。(344~351頁)
〈注解〉那伽閼刺樹那;ナーガルジュナの音写。龍樹等と訳す。紀元二~三世紀の人。はじめ婆羅門の学をまなび、のち仏教に帰して、大乗仏教を唱導した。おびただしい著作があり、後世の仏教者によって八宗の祖師と称せられる。
無相三昧;三昧の境地に入って、空三昧を成就すれば、空なるがゆえに一切の差別なきを観ずる。その境地を無相三昧という。
天然外道;また自然(じねん)外道、もしくは自然見(じねんけん)外道という。
■おそらくは、それは描くことのできないものであろう。法はすべて描かないがよく、描くならば簡明に描くがよい。だから、円月相を身に現じた姿などは、古来から描いたものはないのである。およそ仏性とは、いまの心のはたらきであろうと思う考えが脱けないから、有(う)仏性というも、無仏性というも、いずれも理解する手がかりがないのであろう。また、それをどう表現してみようぞとまなぶものも稀である。その怠りが仏道の衰えであると知るがよい。諸方の堂頭のなかには、一生に一度もまったく仏性ということばを口にしたことのない者すらもある。ある者はいう、「教えを聴こうとする者は仏性を談ずる。参禅の雲水たちは口にすべきではない」と。そんな輩はまことに畜生である。なんという悪魔の徒党が、わが仏・如来の道にまじって、これを汚そうとするのであるか。そんな聴教(ちょうきょう)というものが仏教にあろうか。そんな参禅というものが仏教にあろうぞ。そんな聴教そんな参禅は、いまだかつて仏道にはないとしるがよいのである。(345頁)
〈注解〉堂頭;「どうちょう」と読む。禅林にて、一寺の頭すなわち住持をいう。(356頁)
■大潙山の大円和尚は、ある時、衆に示していった。
「一切衆生無仏性」
それを聞く人々のなかには、聞いてよろこぶすぐれた機根の人もあろう、また驚いてわが耳を疑うものもあろう。釈尊の説いたことばは「一切衆生悉有仏性」である。大潙の語るところは「一切衆生無仏性」である。有と無のことばの道理ははるかにことなる。そのことばの当否を疑うのも尤(もっと)もなことである。だが、「一切衆生無仏性」の表現こそもっとも勝れている。
斉安(さいあん)国師の「有仏性」の句は、古仏のそれとともに双手(もろて)をなしているようであるが、それはいわば、一本の杖を二人で舁(かつ)いでいるようなもの。いまの大潙はそうではない。一本の杖が二人を呑んでいるともいえよう。さらにいえば、斉安国師は馬祖の直弟子、大潙は馬祖の孫弟子である。いま大潙のいう趣は、一切衆生無仏性をもって理のきわまるところとなす。それは、けっして、いい加減にして桁をはずれたことばではない。仏教のなかの経典もそのように受けとっているのである。(361頁)
■つぎに大潙にむかっていいたい。たとい一切衆生無仏性とはいい得ても、なお一切仏性無衆生とはいい得まい。また一切仏性無仏性とはいうまい。ましてや、一切諸仏無仏性とは夢にもいまだ見ざるところであろう。試みにいってみるならば拝見したいものである。(362頁)
〈注解〉鳥道;鳥の道である。鳥はその道をゆくけれども、そこには跡があるわけではない。有りと無しにかかわらないのである。いまそれをもって衆生と仏性の関係にたとえるのである。
大潙山大円禅師;潙山霊祐(853寂、寿83)であり、諡(おくりな)して大円禅師という。(363頁)
■そこで南泉が、「誰ぞ長老の所見ではあるまいなあ」といった。それは、これを自分の所見とはよもやいうまいなあ、というほどのことばである。そなたの所見かときかれても、それを自分のですと頷(うなず)いてはならない。自分の考え方にぴったりだからとて、それは黄檗のものではない。黄檗の所見はかならずしも自己の所見ではない。長老たちの見るところはどこまでdも露(あら)わなるものだからである。
そこで黄檗は「不敢(ふかん)」つまり「いえ、けっして」といった。このことばは、宋土においt、おのが能(のう)について問われたとき、できることをできるという場合でも「不敢(ふかん)」というのである。だから「敢えてせず」ということばは、かならずしも敢えてしないのではない。そのことばのままとはかぎらないのである。長老の所見は、たとい長老であっても、たとい黄檗であっても、それをいうには「不敢」であろう。一頭の水牛がでで来て「もう、もう」というの類である。そういうのが物のいい方というもの、その物いう意味は、ひとつみずから試みにいうてみるがよろしい。
■趙州(じょうしゅう)真際(ざい)大師に、ひとりの僧が問うていった。
「狗子もまた仏性があるでしょうか」
その問いのこころを、まず明らかにしなければならぬ。狗子とは犬である。その犬に仏性があるかと問うのでもなく、ないかと問うのでもない。大丈夫たるものもまた学道すべきやと問うたのである。あやまってすごい老師に遇うた。その恨みはふかいけれだも、三十年ものかた、やっと半箇の聖人たることをえたという故事もある。その風流をまなぶのである。
趙州はいった。
「無」
そのことばがあって、はじめてまなぶべき方途が見えるのである。仏性そのものからいっても無である。狗子のほうからいっても無である。あるいは第三者がそばから見てもやはり同じく無である。その無にいたって、はじめて石をも融かす時がくるのである。そこでかの僧はいった。
「一切の衆生はみな仏性ありという。なんとしてか狗子にはないのでありましょうか」
そのいう意味は、もし一切衆生が無であるならば、仏性も無であろう。狗子もまた無であろうという。その意味はいったいどういうことかと問うのである。狗子の仏性のことなど、あらためて無といわなくても判っているではないかとするのである。そこで趙州がいった。
「人間には業識(ごっしき)があるからなあ」
そのことばの意味は、人間がもっているのは業識であるということ。業識があるから、人間には有りというが、狗子にはそれが無いから仏性無しという。業識ではなお狗子を理解しえないから、どうしても狗子に仏性ありといえないのである。たとい有るといおうと無いといおうと、どっちにしても、ここは業識の問題である。
また、ひとりの僧が趙州に問うていった。
「狗子もまた仏性有りや無しや」
この問答は、すでにこの僧が趙州のこころを知っていたのであろう。いったい、仏性を語り、仏性を問うというのは、仏祖の日常茶飯のことである。趙州は答えていった。
「有(う)」
その有のありようは、教家の論師などがいう有でもなく、有部にいうところの有でもない。そこはさらに一歩をすすめて仏のいう有をまなばねばならぬ。仏のいう有が趙州のいう有である。趙州の有は狗子の有であり、狗子の有は仏性の有である。
その時かの僧はいった。
「すでに有ならば、なんとしてかまたこの皮岱に入り来るのでありましょうか」
この僧のことばは、いま有るのか、むかしから有るのか、あるいはすでに有るのかと問うているのである。すでに有といえば、そえはこの世のもろもろの存在に似ているけれども、仏性のありようは玲瓏(れいろう)としてひとり明らかである。それがすでに有るというのは、いったい、外からはいってくるのか、そうでもないのか。いま「なんとしてかこの皮岱に入り来るのか」という問いは、いい加減に考えて間違えてはならない。
そこで趙州がいった。
「それは彼らが知っていて、ことさらに犯すがためである」
この語句は世俗のことばとして、ながく巷間に流布しているが、ここでは趙州のことばである。そのこころは、知りながらもことさらに犯すということであるが、いまこのことばに疑いを抱かぬものはすくなくないであろう。ことに「入り来る」という入るの一字が判りにくいが、その入るの一字もかならずしも適切ではない。いわんや、「庵中不死の人を識(し)らんと欲せば、豈(あに)ただ今のこの皮岱を離れんや」である。その不死の人が誰であろうと、いずれの時にか皮岱を離れないものがあろうか。とすると、「ことさらに犯す」というのは必ずしも「皮岱に入る」ことではなく、「皮岱に入る」とは必ずしも「知りてことさらに犯す」ことでもない。そこはどうしても、「知りて」のゆえに「ことさらに犯す」のでなくてはならない。
だから、この「ことさらに犯す」とは、つまり、なにか繋縛(けばく)を脱する過程が包み蔵(かく)されているのである。それをまた突然「入ってくる」などと説くのである。その脱する過程は、その時には、自分にも判らないし、人にも判らない。では、まだまだ完全には脱(ぬ)け切っていないのだといってはいけない。それは驢(ろ)がさきか馬があとかと論ずる輩のいうこと。ましてや雲居(うんご)高祖もいっておるではないか、「仏法のかたほとりの事をまなんでくると、たちまちあれこれと詰らぬことが気になってくるものだ」と。まさにその通りであって、いささか仏法の周辺をまなぶと、その過ちが日とともに深く、月とともに深まってくる。狗子の仏性の有無などということが気になってくるのもそれである。だが、知りて犯すのもまた仏性があるからである。(376~379頁)
〈注解〉業識(ごっしき);善悪の業によって招いた果報というほどの意味。
教家の論師;教家は禅家に対する語。仏教をまなぶに、経を説くところを分別して、文字言語によっていたろうとする学者たちというほどの意。
有部;部派仏教の一つ。“サーヴァスチヴァーダ”を音写して薩婆多(さつばた)といい、意訳して説一切有部という。それを略して有部というのである。三世実有の説を主張するのがその特色である。(380頁)
(2015年7月12日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵(3)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
行仏 威儀(ぎょうぶついぎ)
■開題
この「行仏威儀」と題する一巻が制作されたのは、仁治二年(1241)冬十月中旬、例によって興聖宝林寺においてのことであった。だが、この一巻は、別に衆(しゅ)に示すことはなかったようである。
まず、その巻題とする「行仏威儀」とは、あまり聞くことのないことばであるが、それは、いったい、どういうことであろうかと、そう思いながらこの巻に読みいたってみると果たせるかな、道元もまたその巻題の説明から始めている。
「諸仏かならず威儀を行足す。これ行仏なり」
そして、その行仏とは、報仏とか、化仏とか、自性(しょう)身仏とか、他性身仏とか、あるいは始覚(しかく)か本覚かなどと、そのような仏の概念化したものとは、まったく比肩していうべきものではないとするのである。では、いったい、行仏とはどのように理解したならばよいか。すると、続いて道元はいう。
「しるべし、諸仏の仏道にある、覚をまたざるなり。仏向上の道(どう)に行履(あんり)を通達せること、唯(ただ)行仏のみなり。自性仏等、夢也未(むやみ)見在なるところなり」
そのいうところは、こういうことであろうか。――そもそも、諸仏は、仏道を行ずるにあたっては、覚(さと)りばかりを期待しているものではないということを、まず知るべきである。もろもろの仏は、ただ一筋に仏のあゆむべき道を、一歩一歩と踏みしめて行く。それはただ行仏のみである。自性身仏がどうの、他性身仏がどうのということなどは、夢にも考えてみたことがないことだ――と。
そのような「行仏威儀」の説示を味わい読みながら、いつしか、わたしが念頭に思い浮かべていたことが二つある。その一つは、かの『正法眼蔵随聞記』(第二の四)にみえる一節のことであって、そこには、こんな一節が記しとどめられてある。
「仏道に入るには、我こころに善悪を分けて、よしと思ひあししと思ふことを捨てて、我が身よからん我が意(こころ)なにとあらんと思ふ心をわすれて、善くもあれ、悪くもあれ、仏祖の言語行履に随ひゆくなり」
まず頭で考えて納得しようとする行き方をすてて、ともあれ、「仏祖先徳の行履ならばなすべきなり」、また、「もし仏祖の行履に無からん事はなすべからず」とする。そのことを、わたしはまず思い浮かべた。
もう一つは、かの『典座教訓』に記す道元その人の体験であって、もっと具体的で、かつ、わたしにはもっと印象の深い一節である。
それは、なお若かりし道元が、宋に渡ってまもなく遇った一人の老典座との問答のことであるが、その時、道元は、その老典座に向かって、
「座(そ)尊年、何ぞ坐禅弁道し、古人の話頭を看せずして、煩はしく典座に充(み)てて只管に作務す。甚(なん)の好事かある」
と詰(なじ)った。あなたはいい年をして、台所仕事などを一処懸命にやっているが、それで何になるか。もっと坐禅をしたり、語録を見たりなさってはどうか、といった。典座とは、禅院の台所のことを司る職のことである。すると、その老いたる典座は大いに笑って、
「外国の好人いまだ弁道を了得せず、いまだ文字を知得せざること在り」
といった。外国のお若い方は、まだ仏教というものが、本当にはお解りでないらしい、といった。それが道元には骨身にこたえた。そして、それが、真の仏教とはなにかという彼の課題の焦点をなした。だから、その問答を記した結語には、
「山僧いささか文字を知り、弁道を了ずることは、乃(すなわ)ち彼の典座の大恩なり」
と記している。それを課題の焦点として、真の仏教とはなにかを了得することができたからである。
わたしは、「行仏威儀」の問題をさておいて、顧みて他を語ることに冗舌を弄(ろう)しすぎた嫌いがあるかも知れない。だが、この行仏のことは、文字や概念をもって解説しうることの遥か彼方にある。とするならば、こうした道元その人の体験や垂示を身に当てて、そこから「行仏威儀」の真相に向かって、手をのべ足をはこぶのほかはあるまいと思うのである。(16~18頁)
■もろもろの仏はかならず整々たる作法にかなった行住坐臥をいとなむ。これを行仏という。行ずる仏である。
その行仏は、報仏すなはち過去の願行によって成れる仏でもなく化仏(けぶつ)すなはち通力をもって化作(けさ)した仏でもない。あるいは、自性身仏すなはち法そのものとしての仏でもなく、他性身仏すなわち衆生のために姿を現じた仏でもない。あるいはまた、本覚(がく)すなわち衆生が本来有する覚性をいうのでもなく、始覚(しかく)すなわちその覚性の始めて目ざめたるをいうのでもなく、乃至は、性覚(しょうかく)つまり真如の本体をいうのでもなく、無覚つまり性のほかに覚(さとり)はないということでもない。そのような仏の概念は、決して行仏と並べていうべきものではないのである。
そもそも、もろもろの仏は、仏道を行じて、覚をのみ期待するものではないということを、まず知るべきである。ただ一筋に、仏に向かっての道を、一歩一歩と踏み締めてゆくのである。それはただ行仏のみである。自性身仏などということは、いまだ夢にも見ないところである。(19~20頁)
〈注解〉威儀;行住坐臥における振舞いの、ぴたりと律儀作法にかなえることをいう。
行仏;この一巻をもって行仏のなんたるかを説くのであるが、まずは、仏を行ずるのではなく、むしろ、行をもって仏となるというほどの意と心得られるがよい。
報仏;法身(じん)仏。三身仏の一。過去における願・行の報いてなれる仏というほどの意である。
化仏;化身仏。仏・菩薩がその通力をもって示現する仏身をいう。
自性身仏;法身(ほっしん)仏のことである法そのものを仏身とするのであるから、まったく無形無色な抽象的なものである。
他性身仏;また他生身仏と記す。他受用身の仏、すなわち、衆生の機根等に応じて示現する仏身である。応身仏ともいう。
化仏;化身仏。仏・菩薩がその通力をもって示現する仏身をいう。
始覚・本覚;衆生のもともと有する覚(さとり)の可能性を本覚といい、それがはじめて目覚めて現実態となることを始覚ともいう。
性覚・無覚;真理の本体は、もともと覚(めざ)めているという考え方を、性覚という。とすると、その本体をほかにして覚(さとり)はないのであるから、無覚という。(20頁)
■そこで、しばらく、その行仏の威儀について、ひとつ研究しておかなければならぬことがある。それは、そのように仏がそのまま自己であるということになると、吾もまたかくのごとし、汝もまたかくのごとしであって、すべてがただわが能力にかかっているようであるが、さらに、十方の諸仏もまた然りということになると、もはやそれだけではありえまい。だからして、古仏もまた、
「その辺のことを体得して、わが内に帰り来って行ずるがよい」
といっておる。そのように受領して、はじめてもろもろの法も、身(しん)も、行も、仏も、おのずからわが身辺に感ぜられてくる。その行・法・身・仏が、それぞれに突き当たっては、「ああ、そうか」と思えるようになる。思い当たるところがあるから、それがすっぽりと会得できるのである。
眼前に百草がきそい茂っておるのに、一つも見えない、なんにも見えないと慌ててはいけない。かしこに行き、ここに来たって、あれを摘み、これを摘んで、おなじ門を出たり入ったりしているうちに、すべてこの世界にはなんの覆い蔵(かく)すところもないのだから、やがて、世尊のことばもさとりも、あるいは、なさることも、命じたまうところも、ぴたりと解ってくるというものである。
「門を出ずればすなわちこれ草、門を入ればすなわちこれ草、万里寸草なし」という。いや、入の一字や、出の一字は、いずれもいらない。そんな捉え方は、放(ほ)っておいたほうがよいともいわないが、つまりは夢まぼろしの非現実のことである。だが、誰がそれを単なる錯誤といいうるであろうか。歩を進むるも錯(たが)い、歩を退くもまた錯(たが)う。一歩も錯(さく)、二歩も錯であるから、錯また錯ならざるはない。だが、天と地ほどの隔たりがあるからこそ、「道(どう)にいたるには難(かた)からず」である。つまり、威儀でもよい、儀威でもよい。大(だい)道は本来ゆるやかなものだと思い定めるがよい。たとえば、出生(しょう)にも道に合(がっ)して出で、入(にっ)死にも道に合うて入るのであって、その徹頭徹尾において珠玉を転ずるがごとき威儀がととのっているのだと知るがよい。
仏の威儀の一端をあらしめるものは、この天地のすべてであり、この生死去(こ)来のすべてである。あるいは、数かぎりない国土であり、世界である。その国土、その世界がその仏の威儀の一端をなすのである。
いったい、仏教を学ぶ人々は、たいてい、「尽乾坤(じんけんこん)」などというと、この閻浮提(えんぶだい)のことであろうと思い、またその四州の一つであろうと思う。あるいは、中国一国を頭にえがき、日本一国を想像したりする。また、「尽大地」といっても、ただこの三千世界を思い浮かべ、時にはわずか一州・一県を思い浮かべる。だが、この尽乾坤・尽大地などということばを学ぶには、もっと幾度も幾度も思いめぐらしてみなければならぬ。広いのであろうと思って、それで休(や)めてしまってはならない。
そのことばの意を究めてみると、極(ごく)大は小に同じく、極小は大に同じくして、仏をも祖をも超越しているのだと知られる。ただの大なる存在でもなく、また小さなる存在でもないといえば、おかしいようであるが、それが威儀を行ずる仏である。もろもろの仏祖が語ってきた「尽乾坤の威儀」といい、「尽大地の威儀」というのは、いずれも、このあるがままの、見るかぎりの世界のことだと学ぶべきである。このあまねき世界は、ただ「かつて覆蔵(ふくぞう)せず」というだけではない。またそれが行ずる仏の威儀にぴたりと中(あた)るのである。(30~32頁)
■古くから祖師たちはいう。
「釈迦牟尼仏は、迦葉仏のところで正法(ぼう)を伝えてのち、兜率天(とそつてん)界におもむいて、兜率の諸天を教化し、今もまします」
まさに知るがよい。人間の世界にあった釈尊は、かの時「大いなる死」をとりたもうて教化を布(し)かれたが、やがて天界にのぼって、いまもなお彼処(かしこ)にましまして、天界の諸天を教化しているという。仏法を学ぶものは知らねばならぬ。人間の世界にあらわれた釈尊にも、千変万化のことばがあり、行動があり、また説法があったが、それは人間世界の一隅において光を放ち、奇瑞(きずい)を現じたにすぎない。さらに天界にのぼったのちには、もっとさまざまの教化があったであろう。それを思わないのは愚かというものである。
仏祖正伝の大道の断続をはるかに超越し、無始無終の時を捨象したこの考え方は、ひとり仏道にのみ伝うるところにして、余他の輩のまったく知らざるところである。そして、いまいうところの行仏の教化を布くところにも、また四生以外のものがあり、天界でも人間界でも存在の世界などでもないところがあろうというのである。だから、行仏の作為を覗(うかが)いみようとするには、天界や人間界のまなこをもって見てはならない。あるいは、人間や諸天の心をもってしてはならぬ。それをもって推し測ろうとしてはならぬ。
それは、十聖(じっしょう)・三賢など仏道の修行者もはっきりとは知らないこと。ましてや、人間や諸天の推量の及ぶところではあるまい。人小なれば、その知るところもまた小さく、命みじかければ、その思量もまた短いという。それでどうしてか、行仏のなすところを測り知ることができようか。(40~41頁)
〈注解〉此輩罪根深重(しはいざいこんじんじゅう);『法華経』第二、「方便品」にみえる。そこでは、仏の説法を前にして、多くの在家・出家の者がその座を退いたことが記されている。それは、彼らが罪根深重、かつ増上慢にとらわれ、「未得を得といい、未証を証という」輩であったから、世尊もまた黙然ととして制止しなかったという。その経の趣をもって、この前後の文を読まなければ、理解しがたいであろう。(43頁)
■しかるに、いま行ずる仏のなすところはまったく自由自在である。たとい仏だからといっても、泥を拕(か)き水にもぐるの活路に通じているから、なんの礙(さまた)げにもならない。天界にのぼれば神々を教化し、人間界にあれば人々を教化する。花ひらけば世界起こるであって、その間にすこしも隙間がないのである。だから、はるかに自他の境を遠く超え、往(ゆ)くも来るも独徃独歩である。すなわち、兜率天に往き、兜率天より来たって、なんの間隙なく、また安楽土に到り、安楽土より来たって、常に自由自在である。あるいは、兜率天をはるかに脱し、安楽土を遠く超えるのであり、あるいは、安楽・兜率を千々に砕くのであり、あるいは、兜率・安楽を捉えてはまた放つのである。つまり、一口にして呑みつくすのである。
いったい、安楽土・兜率天などという浄土や天界は、そのいずれに赴(おもむ)くもなお輪廻なることに変わりはない。行くといえば行くのであり、悟りといえば悟りであり、また、迷いといえば迷いである。それがすべて、行仏の草鞋のなかの、かりそめの足指の動きなのである。あるいは、それはまた、一発の放屁の声といってもよく、また脱糞のかおりといってもよい。鼻の孔のあるものは嗅ぐことができる。耳があり、身があり、足があるならば、聞くこともできよう。その得るというのは、わが皮肉を得、わが骨髄を得るのであるから、別に行じて他より得来たるのではない。
かくして生死(しょうじ)を了得して、まったくこだわるところのない境地にいたれば、古くからいいきたった言葉がある。「大聖は、生死を心にまかせ、生死を身にまかせ、生死を大道にまかせ、生死を生死にまかす」と。その意味するところを実現するのは、古(いにしえ)の時でもない、今の時でもない。ただ行仏の威儀のなるとき、忽然として行じ尽くされるのである
それは、どこが始め、どこが終わりというのではないが、生死・身心の趣がすうっと肯けてくるのである。行がいたると明(みょう)がいたる。それが自然なのである。頭を撫でて鏡に向かえば、そこに頭がある。それによく似ている。反射して返照する。それと同じである。その明(みょう)の上にさらに明を重ねることも、行仏をいよいよ豊にして、行ずるにしたがって思うがままである。
その思うがままなる道理を、よく心に当てて究めるがよい。よろしく努めて思いめぐらせば、万物のありようがすっと心に浮かんできて、三界などというのは心の分かつところだと気がつく。そう気がついてみると、万法などというのもまた、おのれの故里に帰っただけのことであって、それはつまりその人のいとなみに他ならぬのである。だからして、翻(ひるがえ)ってそれを句中に求め、言外にさぐるなど、繰り返し繰り返しして深く沈潜して撈(すく)うてみるならば、把握してなお余りがあり、放念してまた余りがあるであろう。
その工夫は、生とはいかに、死とはいかに、身心(じん)とはいったい何か、あるいは、与うる奪うとはいったいどういうことか、思うにまかせるといい任(まか)せぬというはどういうことか、あるいはまた、それらのことは、同じ門を出入りしながらも相逢わないのか、一つのものが時に身を蔵(かく)し、時に角(つの)を露わすのか、それとも、大いなる煩悩にしてはじめて解しうるのか、老熟した思慮をもってはじめて知りうるのか、さらにはまた、一顆明珠というものか、一大蔵教というものであるか、あるいは、一本の拄杖(しゅじょう)なのか、一人の面目なのか、また、それが解るのは幾十年もの後のことか、時の長い短いには関係のないことかと、つぶさに思いいたり思い来るがよい。その思いをつぶさにして、はじめて眼いっぱいに声を聞くことができ、耳いっぱいに物を見ることができる。
さらに、沙門にかかる一隻眼の開けきたるとき、ただに目前の事、目前の物を見るのみならず、また、おのずからにして悠揚たる破顔があり瞬目がある。それも行仏のしばしの威儀というものである。その時、彼はもはや、物に引かれるでもなく、物を率(ひ)くでもない。事情のなるがままに任せて、無生・無作なるでもない。あるいは、本性のあるがままに任せるのでもなく、物のあるがままにゆだねるのでもなく、もとより然るにもあらず、あるがままを是とするのでもなく、ただ仏の威儀を行ずる仏としてあるのみである。
だからして、法のためにすることも、身のためにすることも、すべてよく心のままであり、生を離れ死を離れることも、しばらく仏に任せておくのである。かくて、はじめて、万法唯心といい、三界唯心ということができる。さらに一歩を進めていうなれば、ただ心のみといってもよく、それがいうところの牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)なのである。ただ心のみではないから牆壁瓦礫というのではない。それは、仏の威儀を行ずる仏のなすところが、心にまかせ物にまかせながら、おのずから物のためとなり身のためになっていることをいうのである。そこのところは、始覚(しかく)だの本覚(がく)だのと論(あげつら)うものなどの思い及ぶところではなく、ましてや、外道・小乗の輩や、三賢・十聖などの境地にあるものの、とうてい思い及びえないところである。
その振舞うところのひとつひとつは、容易に領会しがたい。なにか活き活きとはしているが、なんの統一もなくばらばらである。それは、いったい、一本のものか、別々のものか。一本のものといおうとせれば先もなく後もなく、別々のものかと思えば自他の別がない。ただそこには、「事を展(の)べ、機の投ず」るの力があり工夫があるから、その威風は万法を掩(おお)うのであり、その眼光は一世を抜きいでている。いったい、光明には、光を放つ放たぬに関係のない光明がある。いや、光を放たぬ光明がある。僧堂・仏殿・廚庫(ちゅうこ)・山門がそれである。さらに、十方に通じる眼があり、大地のことごとくを収める眼がある。それは心の前にあり、また心の後ろにある。眼・耳・鼻・舌・身・意の六根は、そのような光明の功徳の盛んなものであるが、それを知らずして身につけている三世(ぜ)もろもろの仏たちがあり、また、知って機に投ずる狐狸のたぐいもある。その鼻があり、その眼があるならば、法を説くも、法を聴くも、すべて行仏ということを得るであろう。(46~50頁)
〈注解〉拕泥滞水(たでいたいすい);『碧巌録』の第一則に、、「道箇仏字、拕泥滞水」とみえる。仏とは、俗塵を遠ざかるのみの存在ではなく、また、泥を掻き、水をもぐるのたぐいのことを辞さないのである。(50頁)
三界ただ心の大隔;三界とは、欲界(人間欲望の世界)、色界(物質・現象の世界)、無色界(叡智抽象の世界)をいう。そのような三つの世界があるなどというのも、ただ心の分かち考えるところに他ならずというのである。
本有;本来固有の意であり、外より来るものにあらざるをいう。(51頁)
■この雪峰のことばによく通達(だつ)することは、また仏の出処進退に通達することである。三世の諸仏が火焔のなかにいますというからとて、限りなき宇宙を経めぐるのでもなく、あるいは、極微(ごくび)の世界に通ずるのでもない。あるいは、大いなる法輪を転ずるというからとて、大きいであろう広いであろうと思うべきではない。あるいはまた、大いなる法輪を転ずるのは、自分のためでもなく、他のためでもなく、また、説かんがためでも、聴かんがためでもないのである。(61頁)
■釈迦牟尼仏はいった。
「もしこの経を説けば、それはとりも直さずわたしを見ることである。ただ一人のために説くことも、またはなはだ難しいことである」
とするならば、よく法を説くことは、そのまま釈迦牟尼仏の見(まみ)えることである。それがとりも直さず「わたしを見ることだ」とは、釈迦牟尼仏のことだからである。
釈迦牟尼仏は、またいった。
「わが亡きのちにおいて、この経を聴きて受持(じゅじ)し、よくその意味をたずねることも、またはなはだ難しいことである」(63頁)
■しかるに、喜ばしいかな、いまわれらは、その生を受けるところは聖者の地を去ること遠く、その生くる時もまた聖者の時を去ること遠いけれども、なおこの一天の説法を聞くことのできる時に遇うことを得たのである。仏が法を説くということは、すでにしばしば聞き及ぶところであったが、法が仏を説くということは、幾重にも無智に蔽(おお)われて、これまでまったく知らなかった。しかるに、いま圜悟のいうがごとくであるとするならば、三世のもろもろの仏たちは、三世にあって法に説かれているのであり、また、三世のもろもろの法は、三世にわたって仏に説かれているのである。それをいま、風前にあってずばりと言句のしがらみを截断(せつだん)してみるならば、そこにはただこの一天の覆うところがあるのみである。それは維摩詰(きつ)であろうとなかろうとどうでもよい。この一天を覆うところという一句が、余すところなくすべてを道破し尽くしている。
それでこそ、まさしく、法が仏を説くのであり、法が仏を行ずるのであり、法が仏を証(さと)るのであり、同時にまた、仏が法を説くのであり、仏が仏を行ずるのであり、仏が仏を作(な)るのである。そして、それらのすべてが行ずる仏の出処進退にほかならない。だから、天にわたり地にわたり、また古(いにしえ)にわたり今にわたって、得るところを軽るんずることなく、明きらむるところを大事に用いるがよいというのである。(65~66頁)
〈注解〉赤鬚胡・胡鬚赤;赤ひげの外人というも、外人のひげは赤いというも、詮ずるところは同じことであって、いずれを優れたりとも劣れりともいえないというほどの意である。
性・相;性とは、存在の本性であり、相とは、その現れとしてのすがたやはたらきである。本体論と現象論であるといってもよく、その二つの流れがこれまでの仏教学の主流をなしていた。(67頁)
仏教
■開題
この一巻が衆(しゅ)に示されたのは、仁治二年(1241)の十一月十四日、いつものように興聖宝林寺においてのことであった。道元の制作活動はこの前後よりようやく活発となり、この年の九月、十月、十一月は、それぞれ二本ずつ制作が行なわれている。
ここに仏教というのは、わたしどもがこの宗教を総体として仏教と呼ぶのとは、いささかその概念内容を異にしておる。わたしどもがこの宗教を仏教と呼ぶその概念内容にあたるものは、かの時代にあっては、仏法であり、また仏道である。いささか思想の側に傾斜していえば仏法であり、また実践の側に重きをおいていえば仏道であった。そして、それを総体として仏教というようになったのは、明治以後のことに属するのである。
では、ここに仏教というのは何か。その概念内容は、この巻の冒頭において、みごとな表現をもって、端的に示されている。「諸仏の道原成(どうげんじょう)、これ仏教なり」である。そこに「道(どう)」というのは、「いう」であり、「ことば」である。もろもろの仏のことばの実現したるもの、それが仏教であるというのである。
とするならば、その「諸仏の道(どう)」はどこに実現しているか。それは経のほかにはない。古い述語をもっていうならば、三乗十二分教がそれであり、あるいは九分教がそれである。かくて、道元はこの巻において、三乗十二分教ないし九分教につき、その概観を試みているのである。だが、道元がこの巻において語ろうとするもっとも大事なことは、そのことではなかった。それは、むしろ、仏教すなわち経に対する態度に関することであった。
そのことを説かんとするにあたって、道元はまず、教外別伝の主張を謬説(びゅうせつ)なりとして批判しておる。初めてその一節に読みいたった時には、わたしはわが眼を疑うの思いであった。だが、幾度読みいたってみても、道元の筆は明らかに、「教外別伝の謬説」と繰り返し語っているのであった。彼はまず、いわゆる「教外別伝」の故実を紹介し、その主張を再現してこれを批判する。
「かくのごとくの漢、たとひ数百千年のさきに先達と称すとも、恁麼(いんも)の説話あらば、仏法仏道はあきらめず、通ぜざりけるとしるべし」
そんなことをいう輩は、いくら先輩だといっても、仏法も仏道もわかってはいないのだという。その批判のことばは、例によってまったく歯切れがよい。
だからといって、道元は、けっして、三乗十二分教にこびりついて、ひたすらその訓詁(くんこ)注釈のことにかかずらい、あるいは法性(ほっしょう)を論じ法相(ほっそう)を証することに没頭するのが、真の仏者の道とするわけではない。それはいわゆる経師(きょうじ)・論師(ろんじ)などのたぐいのすることである。そこは、むしろ、
「十二分教をみるは仏祖をみるなり、仏祖を道取するは十二分教を道取するなり」
と心得べきであるとする。なんとなれば三乗十二分教はすべてこれ仏祖の眼晴(ぜい)であり、仏祖の骨髄であり、仏祖の光明であり、また仏祖の荘厳(しょうごん)であるからだという。
かくて、道元は、この一巻の結びの一句に示していう。
「およそしるべし、三乗十二分教は仏祖の眼晴なり。これを開眼(げん)せざらんもの、いかでか仏祖の児孫(じそん)ならん。これを拈来(ねんらい)せざらんもの、いかでか仏祖の正眼(しょうげん)を単伝せん」
ここにいたって、わたしは、明らかに、この師が遠く世の禅家の庸流(ようりゅう)の輩を抜きんでていることを感ぜざるをえないのであるが、その趣は、これより以後の制作において、いよいよ明らかに観取せられることに注目していただきたいと思う。(70~72頁)
■もろもろの仏のことばの実現したるもの、それが仏教にほかならない。それは仏祖が仏祖のために説くところであるから、また教が教のために正伝するのである。それが法輪を転ずるということである。その法輪の眼晴(ひとみ)のなかにあって、もろもろの仏祖が出現し、またもろもろの仏祖が滅してゆくのである。
そのもろもろの仏祖には、あるいはいと小さな処に出現しまた入滅するものがあり、あるいは全世界をおおうて現われまた滅するものがあり、あるいはまた、つかのまの出現があり、長年月にわたる出現もある。だが、小さな処、短い時間の出現だからといって、けっして功徳がないわけではなく、ひろい世界、ながい年月にわたる出現だからといって、まされりとするわけでもない。
だから、朝(あした)に成道して夕(ゆうべ)に入滅する仏たちも、けっして功徳がないとはいえない。もしも、一日では功徳が少ないというならば、釈尊のこの世界における八十年だって長いわけではあるまい。その八十年をもって十劫(ごう)二十劫に比したならば、それは一日と八十年のようなものであろう。その長劫(ちょうごう)にわたる寿命と八十年の寿命だけをとりあげて比ぶれば、むしろ比べものにはならない。だが、かの仏の功徳とこの仏の功徳とを比べて優劣を云々することはできない。なんとなれば、仏の教えとはとりもなおさず教える仏である。仏祖が究めつくしてきた功徳なのである。もろもろの仏は広大であるが、その教法は矮小であるというようなことはありえない。つまり、もし仏が大であれば教もまた大である。仏がもし小であれば教もまた小である。
かくて知らねばならぬ。仏と教とは大小の量をもっていうべきものでもなく、善いの悪いのとわかち語るべきものでもなく、あるいはまた、自己のための教えでもなく、他人のための教えでもないのである。(73~74頁)
〈注解〉転法輪;仏が教法を説くことを、車輪の転ずるを喩(たと)えとしていう。説法である。
仏教・教仏;仏と教との同一性を語らんとして、仏教を転置して教仏というのである。仏の教はまた教の仏にほかならずとするのである。(74頁)
■ある男がいう。釈迦はむかしその生涯にわたって教典を説示したが、その他にまたすぐれた一心の法を摩訶迦葉(かしょう)に正伝した。それを正しい嗣手(つぎて)から正しい嗣手へと相承(そうじょう)していまにいたっておる。だから、教というのは機に応じてのたわむれの論議であって、その一心こそ真実の道理である。その正伝した一心を教外別伝という。それは三乗十二分教、すなわちもろもろの教典の語るところとは、まったく別のものである、と。また、その一心こそさいじょうのものであるから、直指人心、見性成仏と説くのである、という。
そのいい方は、けっして仏教のものではない。そこには自由にいたる活路もなく、全身にそなわる修行の輝きもない。そんな男は、たとい数百数千年の先輩であろうとも、そんなことを言うようでは、仏法も仏道もまだ解っていない、通じていないのだと知るがよい。なぜかというならば、彼らはまだ、仏も知らない、心も知らない、内も知らない、外もわかってはいないからである。なぜ知らないかといえば、いまだかって仏法をきかないからである。
たとえば、いま諸仏という。その諸仏の本末がどうかも知らず、どこから来てどこに去るかも学ばないのであるから、とうてい仏弟子とはいいえないのである。あるいは、ただ一心を正伝して、仏の教えを正伝しないなどというのも、仏法を知らないからである。仏の教えが一心であることも知らず、一心がすなわち仏の教えであることも学ばないから、一心のほかに仏の教えがあるなどという。その汝がいう一心は、まだ一心ではあるまい。また仏の教えのほかに一心があるなどという、その汝がいう仏の教えとは、けっして仏の教えであるまい。たとえ教外別伝の説を相伝したのだといっても、なんじはまだ内も外も知らないのだから、言葉と道理とが符合しないのである。
いったい、仏の正法(しょうぼう)の眼晴(がんぜい)をじきじきに伝えられた仏祖が、どうして仏の教えを伝受しなかったはずがあろうか。ましてや釈尊が、なんとしてか仏教にあるべからざる教法を設けられるはずがあろうぞ。すでに釈尊に直伝(じきでん)の教法があったならば、いずれの仏祖もそれを無からしむるはずはない。かくて、上乗の一心というは、三乗十二分教がそれである。大乗の教典(でん)小乗の教典のことごとくがそれである。
かくて、知るがよい。仏心というのは、仏の眼晴である。破木杓(はもくしゃく)である、もろもろの存在である、三界であるがゆえに、山海(がい)国土・日月星辰である。つまり、仏教というは森羅万象である。外というのは、われらの住むところであり、ここから来るのである。正伝とは、自己から自己に伝えるのである。だから、正伝のなかに自己があるのであり、また、一心から一心に正伝するのであるから、正伝のなかに一心があるのである。さらにいえば、上乗の一心とは土石砂礫(どせきしゃりゃく)である。土石砂礫が一心であるから、土石砂礫は土石砂礫である。
もし上乗の一心を正伝するというならば、かくのごとくであろう。しかるに、教外別伝などという男どもは、けっしてこのような意味を知ってはいない。だからして、教外別伝の説などを信じて、仏の教えをあやまってはならない。もしも彼らがいうままに受け取るならば、教えは心外別伝ということになろうか。もしも心外別伝というならば、一句も半偈も伝わるはずはない。もし心外別伝といわなければ、教外別伝とはいえないのである。
いったい摩訶迦葉は、釈尊の法嗣(ほっす)として、法蔵をゆだねられた方であり、正法の眼蔵を正伝して仏道の統領でる。しかるに、その人が仏の教えは正伝しなかったとするならば、これほど可笑しなことはあるまい。かくて知るがよい。一句を伝授さるれば、一つの真理を正伝せられるのであり、一句を伝持すれば、また山が伝え水が伝えてくれるのである。ただ、それにはどうしても仏祖の正伝によらねばならなぬ。(77~80頁)
〈注解〉法蔵の教主;法蔵とは仏所説の教法をいうことば。禅門においては、摩訶迦葉は法蔵を付嘱せられた第一祖として尊崇せられている。また、摩訶迦葉が第一結集(けつじゅう)、すなわち最初の教法の編集にあたり、これを主宰したことも、また隠れもない歴史的事実である。(81頁)
■また、波羅蜜というのは、到(とう)彼岸である。彼岸は此処にあり彼処にありというものではないが、なお到ることができるのである。その到るというのが仏道の大事な問題である。修行のかなたの岸にいたるのであろうなどと思ってはならぬ。かなたの岸に修行があるから、修行すれば彼岸に到るのである。その修行はあやまつことなく、いかなる世界をも実現する力をそなえているからである。(90頁)
〈注解〉六波羅蜜;菩薩の行ずべき六つの大行であって、それによって修行者は彼岸に到るとするのである。その六つの大行は続いて示されている。(91頁)
■思うに、仏が法を説くというが、また、法が仏を説く。法が仏に説かれるとともに、仏が法に説かれるのである。さらにいえば、煩悩の火焔もえさかるこの世界が仏を説き、法を説くのであり、また、仏がこの世界を説き、法がこの世界を説く。かくて、この経をすでに説くという所以があり、また、この故に説くという所以がある。この経は説くまいとしても説かざるをえないのである。だからして、「その故をもってこの経を説く」というのである。
かくて、その説くところは全世界に及び、また全世界がこの経を説くのである。この仏もかの仏もすべてこの経をと称し、この世界もかの世界もともにこの経をと説く。その故にこの経を説くというのであり、この経こそ仏の教えである。かくて知らねばならぬ。数かぎりもない仏の教えが竹箆(しっぺい)であり払子(ほっす)であり、仏の教えの数かぎりもないのが拄杖(しゅじょう)であり拳頭(けんとう)である。
これを要するに、三乗十二分教などは仏祖の眼晴(がんぜい)であると知るのがよいのである。これに眼を開かないものが、どうして仏祖の門下ということができようか。これを学び来らぬものが、どうすれば仏祖の正法を伝え受けることができようぞ。正法の眼目を体得することを得ない者は、断じて七仏の法嗣(ほっす)ではありえないのである。(102~103頁)
〈注解〉竹篦(しっぺい)・払子(ほっす)・拄杖(しゅじょう)・拳頭;師家が学人を接得するに用いる道具をならべて記したのである。(81頁)
神通(じんずう)
■開題
この一巻は、仁治二年(1241)の十一月十六日、例によって興聖宝林寺にあって衆(しゅ)に示したものである。その年に制作された十一本のなかの最後のものであった。
いつものように、道元がこの巻においていわんとするところは、その冒頭においてずばりと打ち出されている。
「かくのごとくなる神通は、仏家の茶飯なり、諸仏いまに懈倦(げけん)せざるなり」
いまから語ろうとする神通は、仏教者にとって日常茶飯のことであるというのであり、もろもろの仏はそれをいつも行じているのだという。
そして、続いて示す仏祖の神通の範例は、大潙(だいい)と仰山(きょうざん)と香厳(きょうげん)の三人の師弟の間に現ぜられたそれであった。昼寝をしていた大潙がに「いま夢をみていたよ」と話すと、仰山が「一盆の水、一条の手巾(しゅきん)」をもってくる。やがて室にはいってきた香厳にそれを話すと、こんどは香厳が「一椀の茶を点来(てんらい)」する。それを大潙が「二子の神通智慧」は舎利弗(しゃりほつ)、目犍連(もっけんれん)にもまさっていると称(たた)えたという。
それが、「かくのごとくなる神通は、仏家の茶飯」という好範例である。それは、鬼面をもって人を驚かすようなものでもない。わたしどもの日常の生活では考えられないようなことでもない。まさに日常茶飯のことのほかではない。しかるに、道元は、続いて、かかる茶飯なる神通を語って大神通となし、世にいうところの摩訶不思議なるそれを談じて小神通となす。その意(こころ)を汲むことがこの一巻の急処にほかならない。
古来から、仏法に不思議なしという。その通りである。世にいうところの宗教なるものは、しばしば奇蹟を語り、神通を談ずる。そのなかにあって、仏教だけはそのようなことに心を奪われない。「いかんがこれ道(どう)」と問われるならば、「平常心これ道」と答えるのが仏教者の建前である。それにもかかわらず、いま道元は、この巻題をかかげて仏教の神通を語る。けだし諸仏の行ずるところは、それにまさる神通はないからである。
その道理を、いまこの巻に引用する臨済のことばをもっていうなれば、
「色界に入りて色の惑(まどわし)をこうむらず、声(しょう)界に入りて声の惑をこうむらず、香界に入りて香の惑をこうむらず、味界に入りて味の惑をこうむらず、触(そく)界に入りて触の惑をこうむらず、法界(ほっかい)に入りて法の惑をこうむらず」
とある。それが仏教者の六神通というものであって、その時、人は、この「繋縛(けばく)」の世にありながら全く自由であり、「五蘊の漏質」でありながら、まさに「地行の神通」をそなえるものとなるのだという。
その「五蘊の漏質」とは、その身は依然として色・受・想・行・識(それが五蘊である)の成すところであり、煩悩具足の人間であるということ。したがって、天を駆けたり、水上を歩いたりすることはできないけれども、なおかつ、この地上にあってまったく縛せられることなき自由なる存在としてある。「地行の神通」とはそのことであって、それこそ最高の神通にほかならずというのである。(106~107頁)
■五通・六通を小神通というのは、それらは修行のいかんにかかわるものであり、また、時と処とによって制限があるからである。生きている時には現ずるが、死後には現じないのであり、自己には通ずるが、他人には通じないのであり、この土(ど)においては現われるが、かの土には現われないのであり、また、常ならぬ時には現われるけれども、日常の時には現われないのである。
しかるに、この大神通はそうではない。もろもろの仏の教法も証得(さとり)も、すべてこの大神通によって実現せしめるのである。それは、もろもろの仏のまします処において実現するのみならず、また、仏のいまだいまさぬ時と処とにおいても実現する。神通力をもった仏の教化のしかたは、まったく不思議なものであって、その仏のいまだいまさぬさきにその神通力が現ずる。前か中か後かに関しないものである。仏の神通によるにあらずしては、もろもろの仏の発心(ほっしん)も修行も正覚(しょうがく)も入滅も、いまだかってないのである。
いま、このかぎりなき世界の常にして変わらざるも、みなそれは仏の神通である。「一毛が巨海を呑む」のみではない。また、一毛が巨海を保つのであり、一毛が巨海を現ずるのであり、一毛が巨海を吐くのであり、一毛が巨海ならしめるのである。そのように、一毛がすべての世界を呑みかつ吐くとき、では、世界がことごとくそうなったら、もはや世界はなくなってしまうかのように学んではならない。
一粒の芥(からし)だねがそのなかに須弥山(しゅみせん)を包蔵(ほうぞう)するなどというのも、また同じことである。芥だねの一粒が、また須弥山を吐くのであり、あるいは、限りなき海のごときこの世界を現ずるのである。一毛が巨海を吐き、一粒の芥だねが巨海を吐くには、一瞬にして吐くのであり、万劫(ばんごう)にわたって吐くのである。万劫も一瞬も、おなじく一毛一芥(かい)より吐かれるものならば、一毛一芥はいったいそれを何によって得来るのであるか。それは、とりもなおさず神通によって得るのである。その得るというのは、神通によるのでるから、まさに神通が神通を生むのである。かくて、この神通は、過去と現在と未来にわたって、存すると存せないの別はないと知るべきである。もろもろの仏は、いつもこの神通のなかに悠々自適しているのである。(118~119頁)
■なんじはいう。仏に六神通があるのは、まことに不可思議である、と。だが、一切の諸天も神仏も阿修羅も大力の鬼もまた神通を有する。それらもまた仏たるべきであろうかいかに。仏道を修する者はあやまってはならぬ。たとえば、阿修羅は天帝釈と戦い、戦いやぶれるや八万四千の部下をひきいて、一本の蓮(はす)の孔のなかに入って隠れたというが、それもまた聖(たっと)いことであろうかどうか。
世の僧たちがあげていうところは、みな業通(ごうつう)というものか依通(えつう)というものばかりである。仏の六神通というのは、まったくその類を異にするものである。現実の世界に入って現象に惑わされず、声の世界に入って声の惑わしを受けず、香の世界に入って香の惑わしを受けず、味の世界に入って味の惑わしを受けず、感触の世界に入って感触に惑わされず、思想の世界にあって思想の惑わしを被(こうむ)らない。そのゆえに、その六種の世界の真相を熟知し、そのすべて空(くう)なるを知って、何物にも捉えられざるものとなる。これが無依(むえ)の道人というものである。その身はなお五蘊の成すところにして、煩悩具足のともがらではあるけれども、それでそのまま地行(ちぎょう)の神通というものなのである。(133頁)
〈注解〉阿修羅;悪神にして、常に天帝釈と戦う神であるという。
天帝釈;帝釈天である。インド神話におけるインドラの仏教化した神である。
業通;宿業の力によって自然にそなわる神通である。
依通;呪術などによって現ずる神通をいう。(135頁)
大悟(だいご)
■開題
この一巻は、仁治三年(1242)の正月二十八日の制作。恒例によって、興聖宝林寺において衆(しゅ)に示したものであるが、奥書によれば、さらに寛元二年(1244)正月二十七日にも、越前の吉峯(よしみね)寺において「人天(にんでん)の大衆(だいしゅ)」に示したと記されている。
仁治三年から、その翌仁治四年(その二月二十六日改元して寛元元年となる)に及んで道元の制作活動はその最高潮に達したようであって、仁治三年の間に制作された『正法眼蔵』は十六巻を数える。そして、この「大悟」の巻は、その年の最初のものであった。
この「大悟」の一句は、ご承知のように、禅門において聞くことしきりにして、禅者は大悟をもって本懐とするのが常であるように見受けられる。この巻にみえる句をもっていうなれば、「悟道是本期」(道(どう)を悟るこれ本期(ほんご)なり)というのはそのことである。だが、道元はむしろ、そのような考え方に対しては批判的であって、そのようにただいたずらに「待悟」する者は、ついに「仏祖の光明にてらされる」時はないであろうとも語っている。
その意趣は、例によって、ずばりと巻の冒頭において語り出されている。
「仏仏の大道(だいどう)、つたはれて綿密なり。祖祖の功業(くごう)、あらはれて平展なり。このゆゑに大悟現成し、不悟至道し、省悟弄悟(しょうごろうご)し、失悟放行(しつごほうぎょう)す。これ仏祖家常なり」
とあるは、その趣である。したがって、詰まるところは、仏祖はかならず大悟によってそこに到るものではあるが、しかも必ずしも、大悟の渾然としてまどかなるをのみ仏祖とするのではなく、仏祖もまたしばしば大悟のほとりを跳び出して、悠々として山河大地とあそび、またわが身心(しんじん)と遊ぶのだという。
そして、道元がこの巻において力を込めて説いているのは、むしろ、悟りと迷いの問題であるように思われる。
華厳寺の宝智大師に、ひとりの僧が問うていう。「大悟底の人却(かえ)って迷う時如何」それに師が答えて、「破鏡重ねて照さず。落華樹(枝)に上り難し」という。道元が『景徳伝灯録』からその問答を引用して、綿々として注釈を施している一節は、どうやら、この一巻のなかでのもっとも興味をそそるところであって、まことに難解であるが、また示唆するところが豊かである。
「大悟も片手であり、迷うもまた片手ではないか。その二つがあって、はじめて両手が揃うと考えることもできよう。とするならば、大悟した人にも、またどうしても迷いがあるのだと、そう受け止めるのがはじめて徹底した理解といえよう。そうすれば、大悟というものは、また、迷いをいよいよ親しみ深いものにしてくれるものだと解ってくる」
そこまでくると、大悟ということばが、まったく新しい印象をもって、わが前におかれる思いがあるのは、ひとり私だけのことではあるまい。(142~143頁)
■まことに、大悟とは、始めもなく、また終わりもないものであり、迷いもまたしかるのである。したがって、大悟と差し障るような迷いなどはないのであって、むしろ、大悟三枚をひねくり廻して小迷半枚をつくるといったところ。つまり、雪山(せつせん)は雪山のために大悟するのであり、木は木のために、石は石のために大悟するのであり、また、諸仏は衆生のために大悟するのであり、衆生は諸仏の大悟を大悟するのであり、しかも、前後の関係はまったくない。だから、いまの大悟は、自分のものでも、他人のものでもない。どこから来るというのでもないが、道は坦々として通じている。また、どこに去るというのでもないから、他にしたがって探しもとめてはいけない。どうしてそうかというなれば、それはどこかに行ってしまうからである。(157~158頁)
■とするならば、仰山(きょうざん)は、「第二頭におちること」を歎きながら、悟りには第二級品などはないと、それを否定しようとしているらしい。たとい第二頭であっても、それが悟りを成じたからには、もはや本物だとしなければならない。だから、たとい第二頭であろうと、第三頭であろうとあるいは幾百幾千番目のものであろうと、悟りは悟りであろう。もし第二頭であれば、そのまえには第一頭がああるはず。それは別だとするのでもない。それは、たとえていえば、昨日のわれもわれであるから、昨日のわれからみれば、今日のわれは第二番目のわれだというようなものである。いまの悟りは、昨日のそれではないとはいわない、いまに始めたものではないからであると、そのように学びいたるがよいのである。だから、大悟の頭が黒かろうと白かろうと、なんの思い煩うことはない。(163頁)
〈注解〉第二頭;第二番目の人もしくは物をいうことばである。それは第二番目であるから、第一番目のものとは別のものということとなり、また、第一番目のものが第一級のものとすれば、それは第二級のものとなる。ここでは、その二つの意がともに含まれているようである。(164頁)
坐禅箴(ざぜんしん)
■開題
それに対して坐禅箴という時には、いうなればその内面に指向して、坐禅の心得、坐禅のいましめ、つまり坐禅のなんたるかに説きいたらんとするものということを得るであろう。その内容のことなりは、さきの「坐禅儀」に比ぶるに、この「坐禅箴」の内容をもってすれば、ほぼ明らかということを得るであろう。(167頁)
■ 薬山の弘道大師が坐っていると、ひとりの僧が問うていった。
「そのように一心不乱に坐られて、どんなことをお考えですか」
師はいった。
「あの不思量というやつを考えている」
僧がいった。
「不思量というものは、どうしたら考えられましょう」
師はいった。
「考えないのである」
薬山惟儼(やくざんいげん)がこのようにいっておるのを、わが身に当てて、よくよく坐り方を学び、正しい坐禅を伝え受けるがよい。それが仏教に伝わる坐り方というものである。ぴたりと端坐してなにを考えるか。それについて語ったのは、けっして薬山のみではないが、薬山のことばは、よくそれを言い得たものの一つである。それは、あの不思量というやつを思量するのだという。そこに、思量といえば思量の心髄があり、また不思量といえば不思量のぎりぎりのところが語られている。
しかるに、かの僧はかさねて、不思量というのはどうしたら思量できましょうかと問うた。まことに、不思量ということは、古くからいわれているが、いったい、どうしたらそれが考えられるかというのである。思うに、坐禅するときにも、まったく考えるということがないはずはない。もしそのことが無かったならば、坐禅の進境というものがどうしてありえようか。浅はかな愚人でないかぎりは、誰だってそこのところを問いたいと思うはずである。
薬山はそれに答えて、「非思量」といった。考えないことだといった。考えないということは、なんの濁りもなく、まったく透き通ったものであるが、不思量ということを考えるには、どうしてもこの非思量をもってするの他(ほか)はない。非思量にもなんらかの内容がある。そのなにかが非思量のわれをあらしめるのである。なるほどそこに端坐しているのはわれであるが、そのわれはただ思量するわれではなく、ぴたりと端坐しているのである。端坐はまさに端坐であるから、その端坐が端坐を思い量ろう道理はない。したがって、端坐して思うことは、仏のことでもなく、法のことでもなく、悟りのことでもなく、あるいはなにかの理解のことでもなく、ただ非思量である。
薬山がこのように語り伝えたのは、釈迦牟尼仏より数えれば、すでに三十六代のことであった。また、これを逆に遡(さかのぼ)っていえば、三十六代にして釈迦牟尼仏がまします。ともあれ、そのように正伝しきたって、ここに「この不思量なるものを思量する」ということばがある。(169~171頁)
〈注解〉薬山弘道大師;弘道大師とは、薬山惟儼(834寂、寿84)の諡号(しごう)である。関藤希遷の法嗣(ほっす)である。澧(れい)州の薬山に住して薬山と称された。
■しかるに、近年、愚かにして杜撰(ずさん)なる輩(やから)は、「坐禅の修行は心のうちの無事を得ればそれでよいのだ。つまり、それは平穏の境地というものだ」などといっておる。そのような見方は、小乗の学者にすら及ばず、世間の人々よりも劣れるもので、とても仏法を学ぶ者とはいえない。ところが、現在、大宋国には、そのような坐禅の修行者が多いのであるから、祖道のおとろえを歎かざるをえないのである。
また、こんなことをいう連中もある。――坐禅して道を修めるのは、初心や後進の者のすることであって、必ずしも仏祖のなすところではない。行くも禅、坐するも禅、語・黙・動・静すべておのずから安然たるべきであって、ただ坐禅の修行のみこだわってはならない。――臨済の流れを汲むと称する連中は、たいていそのような見解である。仏法の正しい命(いのち)をぴたりと伝えないから、こんないい方をすることとなるのである。
いったい、なにが初心だというのか。初心ならぬ者がどこにあるのか。初心とはどこまでだというのか。まさに知るべきである。仏道を学ぶものの生まれる修行として、坐禅して道を修するのである。その標榜するところの主旨をいえば、仏となることを求めずしてただ仏の威儀を行ずるのである。けだし、仏の威儀を行ずるのは、けっして仏とならんがためではないのであって、それは公案として明白である。その身がすでに仏であるならば、さらに仏となるの要はないのである。文字のしがらみを打ち破ってみれば、坐仏はさらに作仏するの要はあるまい。まさにそこに到ってみれば、もともと仏になる力もあれば、悪魔になる力もある。進むも退くも自由自在なのである。(173~174頁)
〈注解〉人天乗;五乗(人乗・天乗・声聞乗・縁覚乗・菩薩乗)のうち、はじめの二つをあげたのである。それらは、まだ仏教にいたらない世間の人々の道である。
身仏;ここでは、作仏・坐仏・身仏の三つが相対して語られている。身仏という述語はないようであるが、思うに、即心是仏という考え方を背景として、このことばを語っているのであろう。(174頁)
■江西(ぜい)の大寂(だいじゃく)禅師は、南嶽の大慧禅師に見(まみ)えて学び、その心印を受けてより以來、たえず坐禅していた。すると、ある時、南嶽が彼を訪ねて問うていった。
「そなたは、坐禅して、なにごとを図(はか)るのであるか」
この問いを、静かに思いめぐらして研究してみるがよい。というのは、坐禅より上になにか意図するところがあるのか、坐禅より外に別になにか意図するところがあるのか、あるいは、なんにも意図するところがあってはならないのか。いま坐禅してどんな図を心に描いているかと問うのである。そこを審(つまび)らかに考えてみるがよいのである。
彫龍を愛するより進みて真龍を愛すべしというが、彫龍にも、真龍にも、ともに雲をよび雨を降らせる力のあることを学ばねばならない。遠きを貴(たっと)しとしてはならぬ。遠きを賤(いや)しとしてはならぬ。むしろ、遠きに慣れるがよい。また、近きを賤しとしてはならぬ。近きを貴しとするもいけない。むしろ近きに習熟するがよい。目に見るところを軽んじてはいけない。目に見るところを重んじてもいけない。また、耳に聞くところを重しとしてもいけない、耳に聞くところを軽しとしてもいけない。むしろ、耳目をして聡明ならしめるがよい。
江西(ぜい)は答えていった。
「作仏を図るのでございます」
このことばを、はっきりと見定めねばならない。作仏すなわち仏となるというのであるが、それはどうなることであるか。仏によって作仏せられるのを作仏というのであるか。あるいは、自分が仏になるのを作仏というのであるか。そてとも、仏にはその能動と受動の両面があるのをひっくるめて作仏というのであるか。あるいはまた、作仏を図るには、その両面を超越するのであるから、超越して作仏するというのか。さらにいえば、作仏にはいろいろとあるけれども、それをすべて図るという一字をもって表現して、「作仏を図る」というのであるか。かくて知ることができる。江西(ぜい)の大寂(だいじゃく)がいうところは、ともあれ坐禅はかならず作仏を図るのであり、坐禅にはかならず作仏の意図があるということである。その意図は、作仏より以前にあるともいえるし、作仏よりも後だということもできるし、まさに作仏のなるその時になるのだともいえるであろう。
では、かりに問うてみるならば、そのようにして心のなかに描く図は、どのような作仏を描き出しているのであろうか。その時、言語・文字をもって描き出されるものには、さらにいろいろの煩わしい表現をまつわっているであろうが、そのことごとくが一つずつ、すべて作仏の表現として、ぴたりと的を射たものであって、その一つをも避けて通ってはならない。もしも一つでも避けて通ろうとするならば、それは生命(いのち)なきものとなるであろう。そして、その生命を失ったとき、それは単なる一箇の文字となってしまうのである。
すると、南嶽は、どこからか一片の塼(かわら)をひろってきて、石にあてて磨き始めた。大寂がそれを見て、問うていった。
「和尚はなにをなさるのですか」
誰がみても、それは塼を磨いているのだとわかる。だが、塼を磨くの道理を知るものは誰か。しかるに、いま大寂は、塼を磨いてどうするのだと問うたのである。そう問うからには、必ずや塼を磨く道理をたずねるのであろう。いったい、自己の考えるところをもって、他に考えようはないように思ってはならない。のみならず、いろいろのなす業(わざ)にもいろいろと学ぶべきろとがあると思い定めねばならない。そうしないから、仏を見ても仏を知らず、水を見ても水を知らず、山を見ても山がわからないのだと思い知るがよい。眼前にみるところのほかには、ほかに考えようはないなどと慌(あわただ)しく結論する者は、仏教を学ぶことはできない。
南嶽は、その問いに答えていった。
「磨いて鏡にしようというのじゃ」
そういう意味を明らかにしなければならない。磨いて鏡となすとは、明らかに道理のあることであって、それは公案にも明らかである。けっして根もないことではない。たとい塼は塼(かわら)であっても、また、たとい鏡は鏡であって、磨くという道理をよくよく究めてみるならば、いくらでもその手本があることが知られよう。古鏡も、明鏡も、塼を磨くことによって鏡となしうるのである。もしもろもろの鏡は塼を磨くことからきたのだと知らなかったならば、仏祖のことばを会得することもできないし、仏祖の垂示に遇うこともできないし、また、仏祖の気合にふれることもできないであろう。
すると、大寂が問うていった。
「塼を磨いて、どうして鏡となすことができましょうや」
だが、まことは、雄々しい男子が塼を磨くのであるから、たとい他の力量をかりなくとも、また、塼を磨くことと鏡をつくることは別のことであっても鏡をなすことは速(すみ)やかであろう。
そこで、南嶽がいった。
「坐禅したからとて、どうして仏となることを得ようか」
それで明らかに知ることができる。坐禅は作仏を期待するものではないという道理があり、作仏は坐禅にかかわらないという趣旨があるが、それがここに明らかに打ち出されているのである。
大寂がいった。
「では、いかがしたならば善いでありましょうか」
そのいい方は、もっぱら世間のそこら辺りで聞く問いによく似ているが、それはまた、出世間のかしこの消息をも問うているのである。たとえば、親友の親友に会った時のようなものであって、わたしの親友は、また彼にも親友である。つまり、どうしたらよいかという問いは、同時にその両方に通ずるのである。
南嶽はいった。
「人が車を御(ぎょ)する時、もし車が行かなかったならば、車を打つがよいか、牛を打つがよいか」
しばらく、「もし車が行かなかったならば」という句について考えてみるならば、車が行くというのはどういうことであろうか、また、車が行かないというのはどういうことであろうか。たとえば、水の流れるというのが、車の行くに当たるのか、それとも、水の流れないのが、車の行くに当たるのであろうか。流れるのは水の行ではないともいえよう。水の行は流れることではないとも考えられるからである。とするならば、「車がもし行かなかったならば」ということばを考えてみるならば、行かないことがあるとも考えられるし、また、行かないことはないとも考えうる。その時によってのことだからである。だから、もし行かなかったならばということばは、一概にそれがいけないと言っているわけではないのである。
続いて、「車を打つがよいか、牛を打つがよいか」という。車を打つこともあり、牛を打つこともあるであろう。だが、そこで、車を打つのと牛を打つのは、同じなのであろうか、別なのであろうか、と考えてみなければならない。すると、世間には車を打つということはないのである。凡夫には打車の法がないのに、仏道には打車の法があることが解ってくる。それが仏道を学ぶ眼目なのである。だが、仏道に打車の法があることを学んでも、それを打牛の法といっしょにしてはならない。よくよく精細に思いめぐらしてみなければならない。
また、打牛の法は、世の常に行なわれていることではあるが、仏道における打牛のことは、さらにいろいろと訊ね学ぶがよい。たとえば、水牛を打つのか、鉄牛を打つのか、泥牛を打つのかと考えてみるがよく、あるいは、鞭(むち)をもって打つか、全世界を打つか、三界唯心の心を打つか、わが骨髄をせめたてて打するかと問うてみるがよく、さらには、拳頭をあげて打つこともあろうし、拳(こぶし)と拳が火花をちらすこともあろうし、また牛が牛を打つということもあろう。
その時、大寂は対(こた)えるところがなかったというが、それをむやみに取り違えてはならない。その時、彼は、塼(かわら)をなげうって玉を得たのであり、頭(かしら)をめぐらしてその面(おもて)の向きを変えることができたのであって、その対(こた)えざるの意味は、誰も横から手を出して奪うことはできない。(179~184頁)
〈注解〉江西大寂禅師;馬祖道一(786寂、寿80)であり、世に江西の馬祖と称せられた。南嶽懐譲の法嗣である。江西(こうぜい)鐘陵(しょうりょう)の開元(げん)寺に住した。諡(おくりな)して大(だい)寂禅師と称する。
南嶽大慧禅師;南嶽懐譲(744寂、寿68)である。六祖慧能の法を嗣ぎ、南嶽の般若寺観音堂に住す。諡(おくりな)して大慧(だいえ)禅師と称する。
図;道元はここで、「図什麽」あるいは「図作仏」の図の一字について、いろいろと思索をめぐらしておる。それは、何事かをはかる、意図することであるとともに、また絵図を描くことに通ずる。しかるに、ここで描かれる図は、心のなかでのことであるから、それを今日のことばでいえばイメージ(観念)がそれにあたる。そこから、「図は作仏より前なるべし。作仏より後なるべし、作仏の正当恁麼時(しょうとういんもじ)なるべし」などという思索が展開されるのである。作仏を修行の果とみれば、そのイメージは、図としてその前にあり、仏とはこれかときがつくのは作仏ののちであるから、その図は作仏の後ともいえるし、sるいは、作仏のなるまさにその時においてこそ、そのイメージは完成するともいえるのである。(185頁)
■南嶽はまた示していった。
「なんじは坐禅を学んでいる。それは坐仏を学んでいるのだよ」
そのことばをよくよく思いめぐらして、仏祖の教えの機微を学びとるがよい。いうところの坐禅を学ぶとは、ずばりとその真相をいえば、どういうことであろうかと思っていたが、それは坐仏を学ぶことだと知ることができた。正伝につながる仏者でなかったならば、とてもとても、このように学坐禅は学坐仏なのだといい切ることはできまい。まことにや、初心の坐禅は、初めての坐禅であり、初めての坐禅は、初めての坐仏であると知るがよろしい。
さらに南嶽は、坐禅について語っていった。
「もし坐禅を学ぶならば、坐禅は座臥ではないのだよ」
そのいうところは、坐禅は坐禅であって、座臥ではないのだということである。坐禅は座臥でないと教えられてみると、自分のすべての行住坐臥が坐禅となるのであって、もはや、これは坐禅に関係が深いの、これは関係が浅いのと、思いわかつことはできない。ましてや、これは迷い、あれは悟りと論じわかつことはできまい。そのようなことを智慧をもって、裁断しうるものは、誰もあろうはずがないのである。
南嶽はまた示していった。
「もし坐仏を学ぶのならば、仏に定まった姿かたちはないのだよ」
いま、さきにいうところの学坐仏について語るならば、こういわなくはならない。そこここの仏が坐仏でましますのは、その定まった姿のない姿を、その姿であらわしているのである。いま仏には定相(じょうそう)がないというのは、それがよく仏の姿をいい得ているのである。そして、定まれる姿のない仏であるがゆえに、坐れる仏の姿もないはずはないのである。だからして、もし坐禅を学ぶならば、それはとりも直さず、坐仏を学ぶということとなる。もしも一定のかたちをとらなかったならば、誰も仏を弁別することはできまい。弁別すべき対象がないからである。それで、坐仏のすがたをとるのである。
南嶽はまたいった。
「そなたがもし坐仏すれば、それがとりもなおさず殺仏(せつぶつ)というものだ」
さらにそのいうところは、坐仏を学びいたれば、仏そのものとなるというのである。坐仏のまさにしかる時は仏そのものなのである。仏そのものの御姿やその智慧の輝きは、いったい如何(いか)ならんと訊ねいたってみると、それは坐仏のなかの何ものでもないのである。これを殺仏というのである。殺の一字は、凡夫の世界にあっては、人を殺すなどということばであるが、けっしてそれと一緒にしてはならない。そこで、坐仏は殺仏であるというのは、どういうことであろうかと、よくよく研究してみるがよろしい。坐仏の功徳に殺仏ということのある道理を、よくよく心によどめて、われらに殺人のことありやなしやと思い究めてみるがよろしい。
南嶽は続けていう。
「もし坐相を執するならば、その理に達するわけではないのだよ」
ここに、坐禅を執するというのは、坐相を捨てて、しかも坐相が目につき気にかかることである。そのゆえは、坐相するからには坐相を離れることはできない。坐相を離れることはできないから、みごとに坐相を執(と)るすがたができても、ねおそれではその道理に達するというわけにはゆかないのでる。そのところの工夫を脱落身心(じん)というのである。
いまだかって坐ったことのないものには、このような道理はありえない。それは坐った時にいえることであり、坐った人にいえることであり、坐れる仏にいえることであり、坐仏を学ぶについていえることである。坐るとはいっても、人の座臥するその坐ではない。人の坐するすがたは、おのずから坐仏に似、仏の坐するに似ているけれども、人が仏となるのであり、仏となる人があるということである。仏となる人があるとはいっても、すべての人が仏となるわけではない。仏がすべて人であるのでもなく、すべての仏がすべての人なのでもないから、人がかならず仏であるのでもなく、仏がかならず人であるのでもない。坐仏という時にもまた同じことである。
いま、南嶽と江西(ぜい)の問答をみれば、師もすぐれ、弟子もすぐれている。坐仏が作仏であることを証(あか)しているのが江西であり、作仏を坐仏として示しているのが南嶽である。南嶽の門下にはこのような追求があったし、薬山の門下にはさきのような垂示があった。よってもって、仏祖たちの要(かなめ)とするところは坐仏であったと知られるであろう。すでに仏祖たる者はみなこれを要として用いてきた。だが、いまだ仏祖にいたらぬ者には、夢にもいまだ見ざるところであるのも、詮(せん)ないことであろう。(189~192頁)
〈注解〉殺仏;古注に「殺仏とは、逆害の殺にあらず、ただ第二人なきのみにあらず、一人に逢う一人もなきなり」とある。いままでの概念としての仏は克服されてなくなることをいうのであろう。
脱落身心;身心(じん)を脱落する。あるいは、身心脱落すなわち身心が脱落するという。ぴたりと坐相をとる。その時、身心一如にして、その理屈をあげつらう心のいとなみなどは別にないのである。「若執坐相、非達其理」とは、その境地であるとするのである。(192頁)
■いったい、西のかたでも東のかたでも、仏法がつたわるというのは、かならず坐仏が伝わることなのである。それが仏法の肝心かなめだからである。だから、仏法が伝わらなければ、坐禅は伝わらないのであり、それが仏祖から仏祖へと伝えられたのは、坐禅の趣によってである。だから、その趣を正伝しないものは仏祖ではないのである。
思うに、この一つの教えが判らなければ、よろずの教えが判らないのであり、よろずの修行がわからないのである。それらの事どもを明らかにせずしては、明眼(めいげん)の人ということもできない、得道の人ともいえない。ましてや、古今の仏祖に列することはとてもできないのであろう。だから、仏祖はかならず坐禅を正伝するのだと断言されるのである。
また、仏祖の光明に照らされるというのは、この坐禅を修め学ぶことである。愚かな人々は、仏の光明というと、日月の光のごとく、あるいは、珠(たま)のひかりの輝きのようなものかと思い誤る。日月のひかり輝くところは、わずかに衆生の住するこの世界に限られ、とても仏の光明には比べものにならない。仏の光明というのは、一つの句を聴いて忘れないのがそれであり、一つの教えを保ち守るのがそれであり、坐禅を直々に伝受するのがそれである。もしも仏の光明に照らされるのでなかったならば、それらを保ちつづけることも、信じ受けることもできないのである。(198頁)
■ 坐禅箴(しん)(宏智(わんし)禅師正覚撰)
仏祖のかなめとなしたまうところは、事に触れずして知り、縁に対せずして照す。その知はおのずから微(び)であり、縁に対せずして照すがゆえに、その照はおのずから妙である。その知はおのずから微(び)であるから、まったく分別のおもいがなく、その照はおのずから妙であるから、毛筋ほどの兆(きざし)もない。まったく分別のおもいがないから、その知は類(たぐい)なくしてふしぎであり、毛筋ほどの兆(きざし)もないから、その照はまったく捉えることができない。水は清くして底に徹し、そこに魚が悠々として游いでいる。空はひろくして限りがなく、鳥ははるけくも飛んでゆく。
この坐禅箴の示すところは、坐禅の自由自在のはたらきを語っている。それは言葉やかたちを超えたところの作法であり、また、遠く今昔を越えたところの定則である。そこには、もはや世間の人々のいう仏祖のすがたはなく、そこには、もはやわが身もわが心もなく、そこには、ただ見馴れぬ異形の人があるのみである。
さて、仏々の要機(ようき)という。仏たちはかならず仏たることを肝心かなめとするのであり、その要機の実現したのが、とりもなおさず坐禅である。また、祖々の機要という。先師に別にそんな言い方があるわけではない。それが祖々たる所以である。すでに法を伝え、衣を伝えている。ちょっと頭(かしら)をめぐらして面(おもて)の向きを変えれば、それはそのまま仏々の要機である。それをまた、ちょっと面(おもて)の向きを変えて頭(かしら)をめぐらせば、それがそのまま祖々の機要とするところである。
また、事に触れずして知るという。その知はむろん感覚の知ではない。感覚の知は小さな知である。叡智(えいち)の知ではない。叡智的知は精神の能動的なはたらきである。だから、その知は事に触れないのである。事にかかわらないのがその知のありようである。だからとて、それを遍(あまね)き知だと思ってはならないし、あるいは、それを自(おのずか)らの知と限定してもいけない。その事に触れずというのは、なにものにも滞(とどこお)ることなき、身心脱落の境地にあることにほかならない。
また、縁に対せずして照らすという。その照らすというは、外に向かって何物かを照らすというのでなく、また、わがうちにおいて霊がひとり輝くというがごときでもない。ただ外境にかかわらずして照らすのである。認識の対象がおのずから輝いているのであるから、それが照らされて輝くということではないのである。つまり、この世界のすべてが、あるがままにして然るのであって、この世界が壊(こわ)れてはじめて然るというものではない。まことに微であり、妙であって、関係があって、かつ関係がないというところである。
さらに、その知はおのずから微であるから、まったく分別の思いがないという。思いという知のいとなみは、かならずしも他の力をかりない。その知には形がある。その形は山であり河である。その山河は微かではあるが、また不可思議なものであって、それを用うれば、活撥撥地(かっぱつぱつち)として生きた働きをなす。たとえば、龍は禹(う)門を越えてはじめて龍となるというが、龍をwがくものは、そんなことには少しもこだわらない。そんなちょっとしたことに用いる知も、この世界のあらゆる山河を捉えきたり、力を尽くして知るのである。わが知にそのような山河に直接した基礎がなかったならば、一知も半解もありえないのである。では、分析的思惟(ゆい)はその後において到来したのに、われらはそれに捉われているのかと歎く必要はない。仏たちもすでに曾(か)つては分別なされたが、いまはすでに仏となっておられる。「曾つて無し」とはいうが、「すでに曾つて」である。その「すでに曾つて」分別なされた方々が仏となっているのである。とするならば、「曾つて分別の思いなし」とは、そんな人には逢わないよというところなのであろう。
また、その照はおのずから妙であるから、毛筋ほどの兆(きざし)もないという。毛筋ほどといっておるが、それはこの世界のことごとくのことをいっておる。それなのに、おのずから妙であり、みずから照らすのであるから、光などはどこにもないように見える。だが、見えないとて目をあやしんではならぬ。光は見えるはずと聞いて、その耳のみを信じてはいけない。「言外に向かって直々にその本源をたずねるがよく、言中に向かってその規定をもとめてはならぬ」というが、いまいうところの照はそれである。だから類(たぐい)がないのであり、だから捉えることができないのである。それをふしぎとして伝え来たり、それをそのとおりと頂いてきたのに、わたしだけが拒んで疑っているのであろうか。
さらに、水が清らかにして底に徹し、魚が悠々として游いでいるという。水が清いというのは、空にある水は清らかな水というには差し支えがあろう。ましてや、この世界に広く行きわたっている水は、水清らかという水ではない。ただ、果てしなくして岸辺もないのが、徹底の清らかな水というものである。魚がもしこの水のなかを行くとするならば、行くとはいえ、いやその行程いく万里に及ぼうととも、その行は測ることもできず、窮(きわ)まるところもないであろう。目測する岸も無く、浮かぶ雲もなく、沈む底もないのであるから、誰も測量することはできない。測ろうとしてもただ徹底の清水のみである。坐禅のありようは、その魚の行くがごとく、千万の行程がありとも、誰も測ることはできない。その徹底透脱(とうだつ)の行程は、すべて鳥飛んで行くことなしというところである。
さらに、最後に、空は闊(ひろ)くして限りもなく、鳥ははるけくも飛んでゆくという。空が闊いというのは、天にかかっているからではない。天にかかっているような空は、闊い空とはいいがたい。ましてや、此処(ここ)にもある彼処(あそこ)にもあるというような空は、とても闊い空とはいえない。ただ、見える見えないにかかわらず、表もなく裏もない空にして、はじめて闊い空なのである。鳥がもしその空を飛べば、それが空を飛ぶというものの一つのありようである。その空を飛ぶあとを測ることができない。その飛ぶ空はこの世界のすべてにわたる。この世界のことごとくが飛ぶ空であるから、その飛ぶこと、いくばくなりと知ることはできない。測ることのできないところを表現するに、いま「杳々(ようよう)」というのである。はるかにして知りがたいというのである。まさに「足下に一糸をもとどめずして去るべし」である。けだし、空が飛び去るときには、鳥も飛び去り、鳥の飛び去るときには、空もまた飛び去るのである。その飛び去り方をいうべきことばを求むれば、「やだここに在り」というところであろう。それが坐上のいましめである。どこに行こうとも、いつでも勇躍して「ただここに在り」というがよいのである。(200~204頁)
〈注解〉※このいささか長大な一節は、詮ずるところ、宏智(わんし)禅師の坐禅箴を挙げて、それに懇切なる評釈を与えたものである。それに先立って、道元は、まず、従来の坐禅銘(めい)・坐禅儀・坐禅箴と称するものを評し、その多くが坐禅のなんたるかを知らない輩(やから)の作るところで、まったく取るに足らざるものであるとなし、ただ、この宏智禅師の坐禅箴のみが、仏祖にふさわしいものとして、その全分をあげて記し、かつ、懇切なる評釈を加えたものと知られる。
六道輪廻の業相;六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の境涯をいうことばであるが、そのいずれも、つまりは、衆生のおもむき住する世界であり、日月の輝くのは、その世界でのいとなみにすぎぬというのである。
坐禅銘・坐禅儀・坐禅箴;坐禅銘といえば、坐禅の功徳をたたえることが中心となるであろうし、坐禅儀といえば、その儀則・作法を語ることに重点がおかれ、また、坐禅箴となれば、それについての訓戒・いましめということで、坐禅のなんたるかを説くことを旨とするであろう。道元にもまた、坐禅儀ならびに坐禅箴の制作があるが、いまこの坐禅箴においては、まさしく坐禅のなんたるかを説くことに、力を尽くしていることが知られる。
十地・等覚;菩薩の修行の段階を、十信・十住・十行・十廻向・十地・等覚・妙覚の五十二位にわかつ。そのなかの十地と等覚とをあげていうのである。その完成の一歩手前の境地なのである。
宏智禅師正覚和尚;宏智(わんし)正覚(1157寂、寿67)または天童正覚(しょうがく)と称す。丹霞子淳(たんかしじゅん)の法嗣(ほっす)。晩年天童山に住すること三十年に及んだ。続いて記される「坐禅箴」は『宏智広録』巻八に見えている。
要機;もっとも大事な心のありようというほどの意。
杳杳(ようよう);はるか、くらい。
声色向上の威儀;声すなわちことばや、色すなわち目に見えるすがたを超越した作法というほどの意。
父母未生前の節目;時間の関係を超えたこと、すなわち、古今を通じてなすべき定めというほどの意
覚知・了知;覚知は感覚による知であり、了知は理解による知である。感覚は受動的であるが、理解は叡知の能動的なはたらきによる。だから、「了知は造作(ぞうさ)なり」というのである。(204~206頁)
■宏智禅師の坐禅箴は以上のごとくである。歴代の宿老(しゅくろう)のなかにも、このような坐禅箴は見ることをえない。諸方の俗物どもが、もしこの坐禅箴のような見事な表現を試みようとしても、一生や二生ではとても及ばぬところである。いま諸方を訪ねても、こんな坐禅箴は他処(よそ)のどこにもない。先師如浄は、法堂(はっとう)にお出ましの時、つねづね「宏智は古仏である」と仰せられた。ほかの者をそのようにいうことは全くなかった。人を知る眼があれば、仏祖の心を知ることができるのである。よってもって、洞山(とうざん)の門に仏祖のましますことが知られる。
いま宏智禅師を去ること八十余年であるが、わたしは、かの坐禅箴をみて、つぎのような坐禅箴を制作した。いまは仁治三年の三月十八日である。今年より紹興二十七年十月八日(宏智の没年)にいたるまでを遡(さかのぼ)って数うれば、なおわずかに八十五年である。
いま制作するところの坐禅箴はこうである。
坐禅箴
仏祖が要(かなめ)となしたまう心の動きは、思量せずして現じ、渉入(しょうにゅう)せずして成ずるにある。思量せずして現ずるがゆえに、その現ずるところはおのずからわが身心(しんじん)に親しく、渉入せずして成ずるがゆえに、その成ずるところはおのずから真実にかなう。その現ずるところがおのずから親しければ、そこにはまったく混りけがなく、その成ずるところがおのずから真実にかなっておるから、そこにはいささかの偏(かたよ)りもない。まったく混りけなくわが身心に親しいのであるから、もはや何ものをも捨てることなくして身心脱落がなるのであり、いささかの偏りもなくして真実にかなっているのであるから、もはやなんの図(はか)らうところもなくして坐禅修行がなるのである。水清らかにして地に徹し、魚行いいて魚に似たり。空闊(ひろ)うして天に透(とお)り、鳥飛んで鳥の如し。
かの宏智禅師の坐禅箴は、けっして、その表現いまだしというわけではないが、また、このように言うこともできるであろう。およそ仏祖の流れを汲む者は、かならず坐禅を一大事として学ぶがよい。それが仏祖正伝のしるしというものである。
正法眼蔵 坐禅箴
仁治三年三月十八日、興聖宝林寺にありて記す。
同四年冬十一月、越州吉田県吉峰(よしみね)精舎にありて衆に示す。(208~209頁)
仏向上事(ぶっこうじょうじ)
■開題
この一巻が記され、そして、例によって興聖寺において衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の三月二十三日とある。克明に記された奥書のいうところである。ひるがえってみると、その同じ三月中には、さきに「坐禅箴」の巻が脱稿し、この一巻に続いては、また「恁麼(いんも)」の巻が制作されている。道元の制作の意欲はいよいよ高揚しきたったもののように察せられる。
では、いったい、この巻題にいうところの「仏向上事」とは、いかなることをいうのであろうか。そのことから、まず申さねばなるまい。
それは、かならずしも一般にひろく用いられている仏教述語ではなく、洞山(とうざん)良价(りょうかい)にいたってはじめて語りいでられたことばである。道元は、この巻の冒頭に、その洞山のことばを挙げ、そしていっておる。
「いまいふところの仏向上事の道(どう)、大師その本祖なり。自余の仏祖は、大師の道を参学しきたり、仏向上事を体得するなり」
だが、その洞山のいうところがすでに、そのことは体得してのみ判ることであって、話しただけでは、「そなたたちに判らない」といっておる。つまり、凡夫の境地にうごめいていたる私どもには、聞いたって判らない、読んだって判りっこないといっている。それだけはっきりと言われると、私もまた、当然ここで解説の筆をなげうつの他はないのであある。
それにもかかわらず、いま道元は、そのことについて、なお数百言を費やして、私どものために噛んで含めるような解説をここにいとなんでいる。わたしは、いまはせめてその解説に取りすがって、この問題の責めをふさいでおきたいと思う。
さて、その道元の解説は、その最後段に及んで、ずばりとこの「仏向上事」ということばを説明してこういっておる。
「いはゆる仏向上事といふは、仏にいたりて、すすみてさらに仏をみるなり」
向上とは、わたしどもの通常いうところの、上に向かって進んでゆくことのほかではないが、では、どこからどこに向かって進んでゆくのかというと、ここにはそれは、すでに「仏にいたりて」、さらに「仏をみる」ことだと知られる。わたしどもは、人が凡夫の位からすすんで仏の境地にまでいたることしか考えないのが常である。しかるに、いま洞山が「仏向上事」という時には、仏にいたったものが、さらに進んでさらに「仏をみる」のだと知られる。とするならば、まだ凡夫の位にあってうごめいている私どもにとって、仏の境地からさらに上に向かって進んでゆくなど、いったいどういうことであるか、そのイメージさえも心に描くことができないのも、また理の当然としなければなるまい。
では、いったい洞山はどうしてそんなことを雲水たちに語ったのであろうか。道元の解説は、そこをこのように説き明しているのである。
「而今(にこん)の示衆(じしゅ)は、仏向上人となるべしとにあらず、仏向上人と相見(しょうけん)すべしとにあらず、ただしばらく仏向上人ありとしるべしとなり」
まったく到りつくした解説である。いま洞山は、すでに仏祖となって、さらに仏祖を越えてゆこうとしている方である。ひとつ山を越えてみると、さらに彼方にまた越えねばならぬ山がある。まさに仏道は無窮である。洞山はいまそのことを体得して、その目前に展開する新しい風景を「いささか話しておきたい」のだという。その発言の心は、いますぐに、「そなたたちも仏を越える人となれ」というのでもなく、あるいは、「仏を越える人に相見(まみ)えるがよい」というのでもない。ただ、しばらく、「仏を越える人というものがあると、知るがよい」というのだという。
それで、わたしはふと思い出したことがある。それは、かの「現成公案」の巻きに、
「悟迹(ごせき)の休歇(きゅうかつ)なるあり、休歇ねる悟迹を長長出ならしむ」
というふしぎな一句があったことである。それは、悟ったらそこで一休みするもよかろうということであり、また、一休みしたらそこからまた遠く抜け出てゆかめばならぬ、というほどの意であろう。ああ、その後半こそ、仏向上事ということだったのかと、いまになって気がつくのである。
ともあれ、ここには、広大無辺なる仏教の風景が打ち出されており、その道を行くものは、せめて「道(どう)は無窮」なることを、知るだけでも知っておくがよい、気がついてもらいたいというのが、このようなことをふと説きいでた洞山の心であり、また、この一巻を制作した道元の心であったと知られるのである。(212~214頁)
■黄檗和尚はいった。
「いったい、出家した人は、当然、これまで申してきたようなことがあることを知らねばならない。しかるに、たとえば、四祖のお弟子であった牛頭(ごず)法融大師のごときは、縦横自在には説くけれども、なおいまだ向上の急処を知らない。その眼目頭脳があってこそ、はじめて、いずれが正かいずれが邪かを弁別することができるのである」
いま黄檗がいうところの「これまで申してきたようなこと」というのは、昔から仏や祖たちが正しく伝えてきたことである。正法(しょうぼう)の眼目を蔵するところであり、涅槃のふしぎな心境である。それは、もともと自己にそなわるものであるけれども、まさに「知らねばならない」のであり、自己にそなわるだけでは、「なおいまだ知らない」のである。仏より仏へと正伝するのでなくては、夢にすら見ることもできないのである。
黄檗希運は、百丈懐海の法嗣(ほっす)であって、しかも百丈よりもすぐれ、馬祖道一の孫弟子にあたり、しかも馬祖よりもすぐれている。おおよそその辺りの仏祖三、四代の間において、黄檗に肩を比べる者はいない。ただひとり、その黄檗のみがあって、いまここに、牛頭山の法融といえども、いまだ弁舌と叡智の二つの角はそなえていなかったことを明かしたのである。それは、ほかの仏祖たちのいまだ知らざるところであった。(244~245頁)
〈注解〉牛頭法融;(657寂、寿64)牛頭禅の祖。四祖道信の傍系の法嗣。牛頭山に住す。その説くところは、いま道元の解説によって、その一半を知ることを得るであろう。
牛頭の両角;牛の頭には両角があるが、牛頭には両角がないといっている。つまり、彼には弁舌はあるが、真の修行による叡智はないといっているのである。
十聖三賢;まだ修行の途中にあるものというほどの意。十聖は、菩薩の十地(じゅうじ)までいたった聖者(しょうじゃ)をいい、なお十地以前の三十位にあるものを三賢という。(246~247頁)
恁麼(いんも)
■開題
この一巻が制作せられて、例によって宇治県の興聖宝林寺において衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の三月二十日のことであったと記されている。とするならば、まさに春ようやく闌(た)けて、百花きそい咲くの候であったはずである。文中に「たとへば東君(とうくん)の春にあふがごとし」という一句のあったことも、ふと思い出されるというものである。
「恁麼」という言葉は、よく知られるように、禅門の人々が好んで口にし筆にするところである。そのことばは、もと宋代の俗語にいずるところであって、また、什麼・甚麼(いんも)・怎麼(いんも)・与麼(いんも)などの文字があてられるのほか、また恁地(いんち)などというようである。
それがもと俗語として有する意味は、「このような」とか、「このとおり」とか、「そのとおり」とかいうことであり、それが形容詞にも、名詞にも、疑問詞にも用いられているようである。だから、試みに「恁麼物恁麼来(いんもぶついんもらい)」なる句を、和文でも俗語風に訳してみるならば、「こげん物がどげんして来よったのじゃ」といった具合になろうというものである。(250頁)
●原文
身すでにわたくしにあらず、いのちは光陰にうつされてしばらくもとどめがたし。紅顔いづくへかさりにし、たずねんとするに蹤跡(しょうせき)なし。つらつら観ずるところに、往時のふたたびあふべからざるおほし。赤心もとどまらず、片片として往来す。たとひまことありといふとも、吾我のほとりにとどこほるものにあらず。(253頁)
■この身がすでにわたしのものではないのである。生命は時間とともに移ろうて、しばしの程もとどまることはできない。若き日の紅顔はいったい何処にいってしまったのか。尋ねようとしても跡かたもない。つくづくと思うてはみるけれども、過ぎ去ったことにはもはやふたたび遇うことはできない。心もまたとどまらず、ただあれこれと往(ゆ)き来するばかりである。たとい、心はまことに存するものだとしても、かならずしもわが事わが物のまわりに停滞しているわけでもない。
それなのに、いつから、どこからということなしに、いつしか発心するものがある。その心が起こってからは、その人は、これまで弄(もてあそ)んでいたことはすべて投げ捨てて、ひたすら、いまだ聞かざるところを聞かんと願い、いまだ証(さと)らざるところを証らんことを求め始める。それは、けっして自己のなすところではあるまい。それはそれは恁麼の人であるがつえに、かくなるものと知られるのである。
では、なぜそれが恁麼の人であるというのであるか。それは、ほかでもない、恁麼の事を得たいと思っているから、恁麼の人であるというのである。そして、すでに恁麼の人としての面目をそなえているからには、もはや恁麼の事を思い煩うの要はないというのである。たとい思い悩んだからといって、それは恁麼の事なのであるから、けっして憂うることはないのである。また、恁麼の事はどうしてそうなのであるかと、驚き怪しむこともあるまい。たとい驚いても怪しんでも、それはやっぱりそうなのである。あるがままにあるものを驚いたり、怪しんだりしてはならないのである。
それは、ただ仏の尺度をもってのみ量るべきではない。また、心の尺度のみをもって量るべきでもない。あるいは、法則の尺度のみをもって量るべきでもなく、この世界の尺度をもってのみ量るべきでもない。ただまさに「すでに恁麼の人であるからには、いかでか恁麼の事を思い煩う要があろうか」であろう。だから、見えるもの聞こえるもののあるがままがそうなのであり、われの身や心のあるがままがそうなのであり、諸仏のあるがままがそうであるはずである。
たとえば、人が地に躓いて倒れる。その時、それをありのままに、ああ地によって倒れたと理解すると、また必ず地によって起きることができる。そうすれば、地によって倒れたことも、なんの怪しむこともなかろう。それを、古い昔から、西の方天竺でも、また天上においても、こんな具合にいっておる。
「もし地によって倒れたならば、また地によって起(た)つがよい。地を離れて起きようとしても、とても起(た)てる道理はない」
そのいうところは、地によって倒れるものは、かならず地によって起きるのであって、地によらずして起きようとしても、けっして起きることはできないというのである。それなのに、そこを拈(ひね)くりまわして、大悟(だいご)こそうるわしく、身心(しんじん)は脱け出さねばならぬかのように思っている。だからして、もし「諸仏が成道の消息はいかに」と問うならば、「地によって倒れるものは、また地によって起きる」ようなものだと語られるのである。そこのところをよく研究して、これまでのこともはっきりとするがよく、これからのこともはっきりとするがよく、また、今のこともはっきりとするがよい。悟るも悟らぬも、迷うも迷わぬも、あるいは、悟りに躓くも、迷いに妨げられるも、いずれもみな地によって倒れるものが、また地によって起つの道理である。それが天上でも地上でもいうところであり、西の方でも東の国でもいうところであり、また、古でも今でもいうところであり、古仏でも新仏でもそういうところであって、そのいい方は、まことにいい得て、見事なものだといわねばならない。
だがしかし、ただそのようにのみ理解して、さらにもっとほかの考え方ができないようでは、それはなお、そのことばをよくよく研究したものとはいえないであろう。なるほど古仏のことばはそのように伝えられているが、さらに自分が古仏として古仏のいい方を試みるならば、そこにはじめて進歩というものがあるであろう。たとえいまだ西の方天竺においても説かれず、あるいは天上においても語られたことがなくとも、さらに別のいい方があってもよいはずなのである。
では、試みにいってみるならば、
「地によって倒れるものが、もし地によって起きようとするならば、いつまで経っても、けっして起きることはできない」
と、それは、なにか一つの活路があって、はじめて起きることができるとするのである。それは、またいうなれば、
「地によって倒れるものは、かならず空(そら)によって起き、空にあって倒れるものは、かならず地によって起きるのだ」
ということである。もしそうでなかったならば、とても起きることはできないのである。もろもろの仏もまた祖も、すべてそうであったのである。
すると、人があって、このように問うたとしよう。
「空と地とは、どのくらい離れているか」
もしそのように問う者があれば、わたしは彼に向かって、このようにいうであろう。
「空と地とは、相去ること十万八千里である。もし地によって倒れるものは、かならず空によって起きる。空をはなれて起きようとしても、とても起(た)てる道理はない。また、もし空によって倒れるものは、かならず地によって起きる。地を離れて起きようとしても、とても起きられる道理はないのだ」
そのようにいうことのできない者は、まだ仏教でいうところの地と空の尺度を、聞いたことも見たこともないのであろう。(257~261頁)
〈注解〉恁麼;また什(いんも)などとしるす。禅門の用語。もと宋代の俗語にして、こんな、そんなの意をもったことばであり、また、疑問にもちいて、どんな、いかなるの意をもあらわす。だが、禅家の人々がそのことばに託するところは、なおはなはだ微妙であって、道元がいまこの一巻をもって語ろうとするところも、その微妙な意味するところである。開題をも参照せられたい。
吾我;吾も我もいずれも「われ」であるが、強いて分別していうなれば、吾は自己の存在を指さし、我は我所すなわち「われ」の所有するところをいう。(261頁)
■第十七代の祖師は、僧伽難提(そうぎゃなんだい)尊者という方で、その法嗣(ほっす)に伽耶舎多(がやしゃた)があった。ある時、尊者は、軒端(のきば)にかけた風鈴が風にふかれて鳴るのを聞いて、伽耶舎多をかえりみて問うていった。
「あれは、風が鳴るのであろうか、鈴が鳴るのであろうか」
伽耶舎多は答えていった。
「風が鳴るのでも、鈴が鳴るのでもございません。わが心が鳴るのでございます」
尊者はまた問うていった。
「その心というは、また何であるか」
伽耶舎多は答えていった。
「いずれも静かだからでございます」
尊者はいった。
「善いかな、善いかな。わが道(どう)を嗣ぐべきものは、汝のほかにはない」
かくて、尊者はついに伽耶舎多に正法(しょうぼう)の眼睛(がんぜい)を伝えた。
それは、風の鳴るにもあらざるところを、「わが心が鳴る」と学ぶのであり、また、鈴の鳴るとのでもないところを、「わが心が鳴る」と学ぶのである。だが、「わが心が鳴る」と、そうはいうけれども、まことは、すべてが静かなのである。西の方天竺から東の方にそのような問答が伝えられて、古代から今日にいたるまで、それが仏教を学ぶための一つの基準とされているのであるが、また、それを誤って解するものも少なくない。たとえば、それをこのように解するものもある。いま多伽耶舎多が、「風が鳴るのでない、鈴が鳴るのでもない、わが心が鳴るのだ」というのは、まさにその時にあたって、それを聞こうとする心のはたらきが起こる。その心のはたらきの起こるのを心というのであって、もしその心のはたらきがなかったならば、その鳴る音をきくことはありえない。その心のなたらきによって聞くということが成立するのであるから、そこに聞(もん)の根本があるということができる。だから、心が鳴るのだというのであるとする。それは正しい解釈ではない。正(しょう)師に就かないから、こういうことになるのである。それは、たとうれば、依主釈(えしゅしゃく)だの隣近(りんごん)釈だのとあげつらう学者どもの解釈のようなものであって、そんなのは仏道の至妙な学とはいえない。
それに反して、仏道の正しい嗣ぎ手である仏祖に学びいたってみると、かの最高の智慧、正法の眼睛(がんぜい)をもって、これを寂静といい、無為といい、三昧といい、あるいは陀羅尼という。その道理をいわば、一事一物が静かでありさえすれば、総(すべ)てがみな静かだというのである。風のふくこと静かなれば、鈴の鳴ることもまた静かである。だから「ともに寂静なり」というのである。「心が鳴る」というは、風が鳴るからでもない、また心が鳴るからでもない。仏祖はそのようにいうのである。わたしどもがこの身をもってよく知っているありのままの姿を、あれこれと拈(ひね)くり回すよりも、むしろ、ただ、風が鳴る、鈴が鳴る、風に吹かれて鳴る、あるいは、鳴っているから鳴っているというがよろしい。「なんぞ恁麼の事に関せん」であって、その時、ありのままなるものがありのままであるのである。(263~265頁)
〈注解〉僧伽難提;禅門にいう付法蔵の仏祖の第十七祖である。舎衞城の出身、羅睺羅多(らごらた)の法を嗣ぎ、中印度に教化を布いたという。
伽耶舎多;禅門でいう第十八祖。中印度の出身。僧伽難提の法を嗣ぎ、大月氏国に布教した。(261頁)
依主(えしゅ)・隣近(りんごん);梵語の合成語を解釈する六種の方法があり、これを六(りく)合釈もしくは六離合釈(りくりがっしゃく)などという。その六種のなかに依主釈とか隣近釈という項目があげられている。そんなスコラスティックな論議にふけっている学者のわざを嘲笑(あざわら)って、「依主・隣近の論師(じ)の釈」なる句をなしているのである。まず依主釈というのは、「所依(しょえ)為主」の意であって、たとえば「眼(げん)識」という合成語は、その識は眼に依って生ずるのであるから、眼を主として、それによって生ずる識と釈するのだという。また、隣近釈というのは、たとえば四念処(じょ)という合成語は、身・受・心・法を観ずることであって、その本体は慧であるが、その営みにつれて念の作用がつよく作用するので念処と名づけるのだという。そんなことのみに頭をつっこんでいては、「仏道の玄学」はならぬといっておるのである。
陀羅尼;訳して能持などとする。観ずるところの法をよく持して散佚(さんいつ)せしめざるをいうのであるが、ここでは特に、他人の毀誉(きよ)のことばなどによって心を動揺せしめないことをいっておるのであろう。(266~267頁)
■第三十三祖、曹谿山の大鑑禅師が、まだ出家となる以前のことであるが、広州の法性(ほっしょう)寺に泊まったことがあった。すると、そこに二人の僧があって論争しておった。一人の僧は、「旛(はた)が動くのだ」といった。もう一人の僧は、「風が動くのだよ」といった。そんな具合に、たがいに言いあらそって、とどまるところがなかった。そこで六祖(大鑑禅師)がいった。「風が動くのでもない、旛が動くのでもない。そなたがたの心が動くのである」
その二人の僧は、それを聞いてただちに信じ受けた。その二人の僧は西の方から来た者であったという。
しかるに、いまのこのいい方は、風も旛(はた)もまた動くのも、すべて心であるのだと、六祖はそういったことになる。それでは、まったく、六祖のことばを聞いても、六祖のことばを解しないこととなる。ましてや、六祖のいい得たところをよく表現するものとはいえない。どうして、そんなことをいうのであるか。それは、六祖が「そなたがたの心が動くのだ」というのを聞いて、そのことばの意味するところをいわんとして、そのことばのままに「仁者(じんしゃ)の心が動くのだ」と表現したのでは、まだ六祖に見(まみ)えたものとはいえない、六祖を解するものにあらず、六祖の遠き弟子とはいいがたい。いま六祖の弟子として、六祖のことばを表現し、六祖の身心(しんじん)を得て言表するには、このようにいうべきである。さきにいうところの「仁者(じんしゃ)の心が動く」というはともあれ、さらに「仁者が動く」ということができよう。どうしてそういうのであるか。それは、動くものが動くからであり、そなたがたはそなたがたであるからである。すでに恁麼の人であるがゆえに、あるがままにこそいうのである。
六祖慧能は以前新州のきこりであった。山のことや水のことにはよく通じていた。だが、青松のもとに心をめぐらして、その根本を切断したことはあっても、僧堂の明窓のもとにゆったりと坐して、心が照らす古き教えがあろうなどとは、知るべき道理もなかった。また、わが心をすすぎ清めるわざなども、誰にも習ったことはなかった。その彼が、ふと町にあって経を聞いた、それも自分で期待したことでもなく、また他の人がすすめたわけでもない。彼はまだ幼いころに父を喪(うしな)い、長じてからは母を養っていた。わが衣服のなかに一粒の明珠があって、それがやがて天地を照らすものとなろうとは、つゆ思いもかけぬところであった。それが、忽然(こつねん)として目をさまして、老母をすて、善知識を訪ねたのであるから、人の世にも稀なこととしなければならぬ。もとより恩愛を軽んじたのではない。ただ法を重んずるがゆえに、恩をもなお軽しとして恩愛を捨てたのである。これが、とりもなおさず、「智ある者もし聞かば、すなわちよく信解(しんげ)するであろう」という所以である。
したがってまた、智というものは、人に学んで得るものでなく、みずから造り出すものでもなく、智がよく智に伝えられるのであり、智がよく智をたずねるのである。『大唐西域(さいいき)記』にいう五百の蝙蝠(こうもり)は、経を聞いて身の焼かれることも知らず、死してのち聖者(しょうじゃ)の境地を成就したという。それは智がみずからの身をほろぼしたのであるが、智には、もともと別に身も心もないのである。また、『金光明経』の説くところによれば、乾上がった池のたくさんの魚どもが、大乗経典を聞くことを得て、天に生まれることを得たという。そこでは、智がそのまま身であるがゆえに、なんの因縁もまくとも、法を聞けばただちに信解するのである。
智はどこからか来るものでもなく、入(はい)りこむものでもない。たとえば、陽(ひ)の神が春にあうようなものである。智は、また有念でも、無念でもなく、あるいは有心でも、無心でもない。ましてや、大小にかかわるものでもなく、あるいは、迷うの悟るのといったものでもない。よいうのは、まだ仏法がどんなものであるかも知らず、以前から聞いているわけではないから、仏法を慕っていたわけでもなく、求めていたわけでもないものが、ふと法を聞くと、たちまち恩をも軽んじ、身をも忘れるというのは、つまり、「有智(うち)」の身心というものは、もともと自己のものではないから、そのようなこととなるのである。「すなわちよく信解するであろう」とは、そのことをいうのである。
思うに、わたしどもは、その智をもちながら、いくたびとなき生死を繰り返して、ただいたずらに俗塵のなかにとどまってきたことか。それは、なお、玉(ぎょく)をそのなかに包んだ石が、玉も石に包まれているとは知らず、石も玉を包んでいるとは気がつかないようなものである。人がそれを知ってこれをとるのは、玉の期待するところでもなく、石の予期するところでもない。あるいは、石の知るところでもなく、玉の思うところでもない。だが、人もまた智もそれと知らなくとも、いつかは必ず、智が道(どう)を開くときがあろうというものである。
「無智にして疑い怪しまば、すなわち永(とこし)えに失うこととなる」ということばがある。智はけっして有りというべきでもなく、また無しというべきものでもないのであるが、ある時には春松の有るがあり、また秋菊の無きときがある。もしも無智にして疑い怪しむ時には、正しき智慧もすべて疑われ、もろもろの事もすべて怪しむこととなる。そのとき、それは永久に失われてしまうのである。聞くべきことばも、証(さと)るべきことも、すべてまったく疑い怪しまれるのである。
しかるに、この世界のすべてのことは、われじゃ誰じゃにかかわることなく、なんの包み蔵(かく)すところもなく、どこまでも一本道の見通しである。たとい春が来て芽を出し枝がのびたとしても、十方の仏土のなかには、ただ一つの真実の教えがあるのみであり、たとい秋到って葉が落ちたとしても、それもまた万物は万物のありように住しているいるのであり、世間のすがたはいつも変わりがないのである。それがすでに恁麼の事なのであって、有智と無智とは、昼と夜、一日の両面にすぎない。六祖もまた、そのような恁麼の人であったから、恁麼の事にぱっと眼を開いたのである。そこですぐ黄梅山(おうばいざん)にいたって、大(だい)満禅師(弘忍)を拝したところが、行者(あんじゃ)の室に投げ込まれた。そこで来る夜も来る夜も米を碓(つ)いていたが、およそ八箇月を経たころのこと、ある夜ふけてのころ、大満禅師がみずからそっと碓房(たいぼう)にやってきて、六祖に問うていった。
「米は白くなったかな」
六祖はいった。
「白くなりましたが、まだ篩(ふる)ってはおりません」
すると、大満は杖をもって、ぽんぽんぽんと三度碓(うす)を叩いた。それを見て、六祖は箕(み)に米を入れて、三度あおりふるった。その時、この師とこの弟子の呼吸はぴたりと合ったのだという。自分でも気がつかず、相手もそうとは思わなかったのであるが、伝法(でんぽう)・伝衣(でんえ)のことは、まさしくその瞬間になったのであった。(270~275頁)
〈注解〉※ここには六祖慧能が五祖弘忍に見(まみ)えて、その法を嗣ぐものとなった消息を、よく知られた二つの物語を挙げて語っている。その間の六祖慧能の心事こそは、それこそ、「恁麼の人」がいつしか「恁麼の事」を得たる好範例とするのである。それらの物語は、いずれも『法宝壇経(ほうぼうだんきょう)』に記すところである。
東君;太陽、日輪。また春の神。東皇ともいう。
三菩提;“sanbodhi”の音写である。正覚と訳する。正しき智である。(275頁)
■無際大師はいった。
「そんなものは得られない。そんなでないものも掴まらない。そんなもの、そんなでないものも、すべてが手におえない。そなたは、いったい、どうすればよいのじゃ」
それが、つまり、無際大師が薬山に教えていったことばである。恁麼も不恁麼も総じて捕らえがたいのであるから、恁麼も得がたいのであり、不恁麼も得られないのである。恁麼はただあるがままなのであって、限りあるものをいうのでもなく、限りないものをいうのでもない。だから、恁麼はただ不得(ふとく)と学ぶがよいのであり、不得とはどういうことかとなれば、ただ恁麼に問うてみるがよいのである。恁麼も不得もそんなものであるから、それは、けっして、ただ仏教の範疇(はんちゅう)に属するものではなく、理解することができないのであり、証(さと)ることができないのである。
かって、曹谿山の大鑑禅師(慧能)は、南嶽懐譲(えじょう)に対していった。
「こりゃ、いったい、こげんなものが、どっから来たというのだ」
そのいうところは、恁麼は疑うこともできないというのである。それは理解することもできないが、また、現に「こんなもの」としてあるからである。だから、よろずの物はかならず「こんなもの」であると考えてみるがよいのであり、一物として「こんなもの」ならざるものはないと考えてみるがよいとするのである。つまり、「こんなもの」とは、疑っていうのではなく、ただ、「どこからきたのか」、現にここにあるのである。(278~279頁)
〈注解〉南嶽山無際大師;石頭希遷(790寂、寿91)である。青原行思の法嗣。
薬山;薬山惟儼(いげん)(834寂、寿84)である。石頭希遷の法嗣。澧(れい)州の薬山に住した。諡(おくりな)して弘道大師と称する。
三乗十二分教;仏教経典のすべてをいうことばである。
直指人心、見性成仏;直々にわが心に向かって尋ねいたり、そこに自己の本性をみることによって仏と成るという。禅門の主張するところである。(279~280頁)
行持(ぎょうじ)(上)
■開題
ー前略ー。以上あぐるところの仏祖たちは、すべてその名を知られた方々ばかりであるが、それらの方々が仏祖たる所以は、一つにかかってその行持によるの他(ほか)はない。とするならば、それらの方々が仏祖たる所以につき、せめて「三三両両の行持の句、それかくのごとし」と語らずにはいられないとするのが、まさに道元の心であったにちがいないのである。
かくて、この一巻は、思いもかけず、いまもいうがごとき長大の一巻をなすにいたってしまったのである。そして、古来この一巻は、上・下の二巻にわかって取り扱われることを常とするにいたっておる。だが、いうまでもなく、この一巻にこめる心はただ一つ、仏祖の大道においては、連綿として断絶せざる「無上の行持」によってのみ事が成るものとしらねばならない。
もしも、「わたしは、はや五十になった六十になった、あるいは七十・八十の高齢になったから、もうこの辺でやめておこうなどというのは、まさに至愚(しぐ)である」といわねばならないという。わたしには、その一句が、心に沁み、身に沁みる思いである。けだし、「道は無窮(むきゅう)なり」であるからである。
わたしもまた、この長大の一巻を、古来の例にしたがって、上下二巻に分かち訳することとする。(285~286頁)
■仏祖の大(だい)道には、かならず最高の行があって、連綿として断絶することがない。発心(ほっしん)・修行・正覚(しょうがく)・涅槃とつづいていささかの間隙もない。行は持続し、道(どう)はこれからあれへと巡りめぐって続いているのである。だからして、それは、自分で強いてするのでもなく、また他人に強いられてするのでもなく、ごく自然にしてなんの混じり気もない行の持続である。その行の力が、われをも支え、また他(ひと)をもささえる。その意味はいかにとなれば、わたしの続けている行が、そのまま全地全天にその功徳を及ぼしているということであって、他(ひと)もそれとは知らず、自分もそうとは気がつかなくとも、まさにしかるのである。
たとえば、諸仏や諸祖の続けたまう行があって、それではじめてわたしどもの行持も実現し、わたしどもの大道も成るのである。また、それを翻(ひるがえ)していうなれば、わたしどもの行持があることによって、諸仏の行持が明らかとなり、諸仏の大道も通達(だつ)するのだということともなる。つまり、わたしどもの行持があってはじめて、その巡りめぐって作用する力がはたらき、それによって、仏祖たちもまた、ある時には仏としてましまし、ある時には仏のすがたをとらず、またある時には、そっと仏の心を抱き、またある時には、成道の時を迎えたまい、その間にいささかの断絶することがないのである。
さらにいえば、この行持があってはじめて日月星辰があるのであり、この行持によってはじめて大地虚空(だいちこくう)があり、また、この行持によってこの世界があり、この身心(じん)があるのである。じっと行を持続するということは、かならずしも世の人々の好むところではないであろうが、詮ずるところ、すべての人はそこに帰せざるをえない。三世のもろもろの仏たちもまた、つまり、過去・現在・未来の行持によってこそ、すでに仏となり、いま仏となっているのであり、また、やがて仏となりたまうのである。(287~288頁)
〈注解〉四大・五蘊;四大は地・水・火・風、この世界を構成する要素である。五蘊は、色・受・想・行・識であって、この身心を構成する要素をいう。さきには、この世界とこの身心を、その由りて来るところにより語り、ここではそれをその構成要素をもって語っている。(288頁)
■趙州(じょうしゅう)観音院の真際(ざい)大師従諗(しん)和尚は、齢(よわい)六十一歳にして、はじめて発心し求道(ぐどう)の志しをおこした。水瓶(びょう)と錫杖をたずさえて行脚し、諸方を遍歴しながら、常にみずから戒(いまし)めていった。
「たとい七歳の童子であろうとも、もしわれに勝らば、われすなわち彼に問わん。百歳の老翁も、われに及ばざれば、われすなわち彼を教えよう」
かくして南泉普願のことばを学んで工夫すること二十年。齢八十にいたって、はじめて趙州城東の観音院に住し、人々を教化すること四十年に及んだ。
いまだかって、一封の書をもって布施をもとめたこともなく、僧堂も粗末なもので、六知事の坐する床もなく、僧たちの洗足所もなかった。あるときには、牀几(しょうぎ)の脚が折れたので、一本の焼けぼっくいを縛りつけて、いつまでもそれで凌いでいた。掛かりの役目のものが、それを取り換えたいといっても、趙州はゆるさなかった。古仏の家風というものはこんなものである。
彼が趙州に住んだのは八十歳以後のことで、法を嗣(つ)いでからこのかたのことである。まさに正法(ぼう)を正伝して、人みな古仏と称した。まだ正法(ぼう)を正伝しない者とは、その重さがまったく違っている。また齢八十にいたらぬ者は、師よりも強健であろうが、なお壮年にして軽々なるわれらは、とても師の崇重(すうじゅう)なるに遠く及ばざるところ。学道に励み、行の持続につとめなくてはならない。
寺には、四十年の間、世の財なるものを蓄えることなく、いつも米穀に事欠いていた。栗や椎の実を拾うて食にあてることもあったし、時には、今日の食を明日にのばして食事をするということもあった。まことに古聖高徳の面影であり、慕(した)よるべき徳行というものである。
ある時、衆(しゅ)に示していった。
「汝がもし、一生叢林を離れずして、物いわざること十年もしくは五年ならんには、人は汝を呼んで唖漢となすことなし。それより以後は、諸仏もまた汝をいかんともすべからず」
それは行持のことをいっておるのである。
しるがよい、十年も五年ものあいだ物いわずとも、けっして唖ではないのである。仏道というものはそんなものである。仏の説きたまうことばを聞かないものが、唖ではなくて物をいわない道理はありえない。とするならば、行持のもっとも大事なことは叢林を離れないことである。叢林を離れないからすべてのことばが脱落するのである。叢林は常に寂黙(じゃくもく)のところだからである。
しかるに、愚かなる者どもは、唖ではなくて物いわぬ道理を知らず、また師家(しけ)もこれを教えない。誰が邪魔するわけでもないが、知りえないのである。さらにいうなれば、この沈黙こそが恁麼をえたるものとも知らず、聞かないのであるから、まったく憐れな者どもである。
この叢林を離れざる行持とは、静かに行持しなければならない。東の風がふけば東にゆれ、西の風がふけば西になびいてはならない。十年五年の春風秋月には、誰も気がつくものはなくとも、澄みきった顔色と音声のことばがある。それはわれわれには知られず理解されないが、ただ、寸陰の行持をも惜しむがよいとのみ学ぶがよい。物いわずといえば空っぽなのかと思ってはならぬ。ここに入るも叢林である。ここを出るも叢林である。あるいは、鳥の行くところも叢林であり、この世界が叢林なのである。(314~316頁)
〈注解〉趙州観音院真際大師従諗;趙州従諗(897寂、寿120)。真際大師は諡号である。
叢林;禅院をいう。
■法演和尚は、また、ある時、示していったことがある。
「行は重いを越ゆることはない。思いは行を越えることはない」
このことばもまた重んずべきである。日夜にこれを思い、朝夕にこれを行じて、いたずらに東・西・南・北の風にふかれるようであってはならない。
ましてや、この日本国は、王や大臣の宮殿もなお立派な建物ではなく、わずかに通り一遍の白木造りの家にすぎない。ましてや、出家し仏道を学ぶものが、どうして立派な建物に静かに住むべきであろうぞ。もし、そんな立派な建物を得たならば、それは正しからぬ生き方によるものにちがいない。正しい生業(なりわい)によって、めったにそんなことがあるものではない。もともと有ればそれで結構である。それをあらためて造営しようなどと思ってはならない。もともと、草庵茅屋(ぼうおく)こそ、古聖(しょう)の住むべきところであり、古聖の愛するところである。後進もまたそれを慕って学ぶがよく、思い間違えてはならない。(329~330頁)
■これまでの仏祖のなかには、諸天の神々の供養を受けたというものも多い。しかるに、すでにその道を得て仏となれば、その行なうところは天衆(しゅ)の眼も及びがたく、その思うところは神々もこれを知るよしもなくなるのである。その消息を明らかに知っておかねばならない。むろん、諸天の神々も、もしよく仏祖の行履(あんり)を踏むことにつとむれば、彼らもまた仏祖に近づく道はある。だが、仏祖がはるかに諸天の神々を超えた証(さと)りを得たのでは、諸天の神々ももはや見上げるすべもなくなり、仏祖のほとりに近づくこともできなくなる。だから、かつて南泉普願はいったことがある。
「わたしはどうも修行の力がなくて、鬼神に覗(うかが)い知られるわい」
それでも判るように、まだ修行もできていない鬼神にその心をうかがい知られるというのは、まだ修行の力が足りないからなのである。(331頁)
〈注解〉天・天衆;もと“deva”を訳したことばである。神々の住む世界(天)、あるいはそこに住む神々をいうことばである。しかるに、この一段に記するところを解(げ)しがたく思う方もあろうかと思う、その不審のよってきたるところは、現代のヨーロッパ的思想では、神(単数)をもって最高かつ全智全能であるとするのに対して、仏教では、仏を最高位におき、神々はなお「欲界」(欲望の世界)の住み人にして、仏の思うところ、行うところを覗(うかが)い知りがたいことが多いとするのである。それによって、文中引用の南泉普願のふしぎなことばをも味わっていただきたいのである。(333頁)
■それによっても判るように、そのようなことは、世俗の能事であって、僧たる者の徳ではない。そもそも、仏道に入りては、初めから、はるかに三界の人事を越ゆるのである。三界の事に使役せられず、三界の考え方にかかわらざるものであることを、つまびらかに問うて知らねばならない。身(しん)・口(く)・意の三業(ごう)のこと、および、この身心(じん)およびこの世界のことを身にあてて学び考えるがよろしい。仏祖の行じたまうところは、いうまでもなく、人々を済度するという大きな利益(やく)があるけれども、人々はいっこうに仏祖の行ずるところによって助けられるなどとは気がつかないものである。
したがって、いま仏祖の大道を行じつづけるにあたっては、町に住むか(大隠)、山に入るか(小隠)を論ずべきでもなく、聡明か痴鈍かを問題にすべきでもない。ただ、いつでも、名利をなげすてて、もろもろの事に束縛されないがよろしい。時間をむだに過さず、常に頭上の火をはらうがごとくにするがよい。また、大悟(だいご)をこそと待つ思いがあってはならぬ。大悟とは仏家における日常茶飯のことである。だからとて、悟らざることを願うもよくない。それはすでに髻中(けいちゅう)の宝珠としてそなわっている。
ただ、心得べきことは、家郷にあるものは家郷を離れ、恩愛のしがらみあるものは恩愛を離れ、名あるものは名をのがれ、利あるものは利をのがれ、田園あるは田園をのがれ、親族あるは親族を離れるがよい。名利などなきものも、またその思いを離れるがよいのである。すでにあるを離るべきものならば、またなきをも離るべき道理は明らかである。それがつまり、まっすぐ筋の通った行持というものである。
もしも幸いにして、生(しょう)前に名利をなげすてて、なんぞ一事を行じつづけることもあらば、それは仏法久住(ぶっぽうくじゅう)のゆえに、仏法によって長久の行持となろう。いま、わたしどもの行持も、きっとそのような行持に支持されているにちがいない。そのような行持をそなえた身心は、自分でも大事にしなければならない。また、自分でもそれを敬うがよいのである。(336~337頁)
〈注解〉三界;欲界(人間欲望の世界)、色界(物質・現象の世界)、無色界(抽象的叡智の世界)。
■もしも行持の力いまだ到らずして、仏祖の骨髄を受けることができないのは、なお仏祖たるべき身心を尊重せず、仏祖の面目を受けることを喜ばないからである。いったい、仏祖の面目といい骨髄というものは、去るものでもなく、来るものでもないけれども、かならず一日の行持によって受けるものである。したがって、その一日こそは、まことに重かるべきものである。しかるを、ただいたずらに百歳を生きるなどとは、まったく悲しむべき月日であり、また、うらむべき人間の形骸(ぎょうがい)のような生き方をしても、そのなかのただ一日でもみごと行持を成就するならば、それは一生の百歳を成就するのみではない。また、百歳の他生をも救うことができるのである。
この一日の身命(みょう)こそは、まことに尊ぶべき身命であり、たっとぶべき姿である。そのゆえをもって、たとい生くること一日たりとも、もろもろの仏の心に会うことができるならば、この一日をもって長い長い多年にもすぐれているのだとするのである。そのような故をもって、いまだ決定(けつじょう)するにいたらぬ時には、一日をもむだにつかってはならない。その一日こそ大切にしなければならぬ宝であって、直径一尺の珠のあたいなどとは比べものにならない。黒龍がその顎(あざと)にひそめる珠といえども、それと代えてはならない。だから、古賢は一日を惜しむこと、その身命以上だった。そのことを静かに思いみなければならない。
黒龍の顎(あざと)の珠は求めることもできよう。径一尺の珠も得ることができるであろう。だが、一生百歳のうちの一日は、ひとたび失えば、また得ることはできない。どのようなすぐれた手立てをもってしても、過ぎ去った一日をかえしたということは、いずれの書にも記さざるところである。
もし、いたずらに日月を過ごすまいとするならば、その月日をわが内につつみ込んで、外に漏らさないようにするのである。だから、古来の聖賢(しょうけん)は、日月を惜しみ、時間を惜しむこと、わが眼睛(ひとみ)よりも惜しみ、わが国土よりも惜しむ。それをいたずらに過ごすというのは、名利の浮世に捲きこまれてゆくことであり、それをいたずらに過ごさぬというのは、道にあって常に道のためにすることである。
すでに、そのように決定(けつじょう)することをえたならば、また、一日をいたずらにすることはあるまい。ただ、ひたすらに道のために行じ、また道のために説くであろう。それで判ることであるが、古からの仏祖は、けっして、ただ一日も無駄なことに心を用いるものではないこと、世の人々のよく知るところであろう。されば、春日遅々として花開くの日も、明窓のもとに坐して道を思うがよく、蕭々(しょうしょう)としてもの淋しい雨の夜も、草庵に坐して道をわすれてはならぬ。
思うに、月日というものは、どうしてかくもわれらの修行工夫を盗むものであろうか。それも、一日を盗むばかりではない。また多年のあいだ積んできた功徳をすら盗み去るのである。月日とわれらとは、いったい、なんの仇敵(あだかたき)なのであろうか。だが、よくよく思うてみると、月日に咎(とが)があるわけではない。ただ、自分のよく修せざるによってかくなるのである。恨めしいことである。自分が自分と親しからず、われがわれを恨むよりほかないのである。
仏祖といえども、恩愛のことがないわけではない。だが、彼らはそのすべてを投げ捨ててきたのである。また、仏祖といえども、いろいろの縁(えにし)がないわけではない。だが、彼らはそのすべてを棄ててきたのである。たとい惜しまれる縁であっても、自他の縁はいつまでも惜しみとどめることのできるものではないのであるから、もしも自分が恩愛を投げ捨てなかったならば、かえって恩愛が自分を投げ捨てるいわれがある。恩愛をいとしいと思うならば、恩愛をいとしむがよい。恩愛をいとしむというには、恩愛を投げ捨てるのほかはないのである。(343~345頁)
〈注解〉不去・如去・如来・不来;さるものでもなく、来るものでもなく、去るようでもあり、来るようでもある、というほどの意である。
■つまり、仏法の奥に入ることができるできる者があり、またできない者があり、またいは、老師の決定的なことばを聞くことができる者があり、またできない者がある。しかるを、時は矢よりも速やかであり、命は露よりももろい。師はあっても、自分が参見することをえないこともあり、参じて学ぼうとするに師を得ないこともある。そのような憾(うら)みや悲しみも、目(ま)のあたりに見聞してきたことであった。
すぐれた善知識というものは、かならず人を知る力を具えているものだが、道を修め行を積むにあたっては、あくまでも親しみ近づくことのできる師弟の縁(えにし)というものは稀なものである。雪峰がかって洞(とう)山に登り、あるいは投子(とうす)山に登った時にも、きっといろいろと煩わしいことを忍ばねばならぬこともあったであろう。それにもかかわらず、雪峰のこの純一な行持は、まったく感歎にたえぬところであり、これを学ばないでは惜しむべきことである。(362頁)
行持(下)
■中国の初祖達磨大師が、西の方天竺(てんじく)から中国に来られたのは、般若多羅尊者の命によるものであった。航海三年の歳月の間には、その苦しみは風や雪だけではなかった。また逆巻く波濤(はとう)は、雲か煙か、どこまでも連なっていた。それを越えてまだ見も知らぬ国に入ろうとするのは、命を惜しむ世の常の人々には、思いもよらぬところであろうが、それも、ひとえに、仏法を伝えて迷える人々を救おうとする大慈悲心からきた行というものであろう。けだし、法を伝えることは自己のためであるからかくするのである。とともに、その対象は全世界であるからかくするのである。さらにいえば、この一切世界は真実の条理の行われるところであるからそうであり、その条理こそわが求むるところであるからそうであり、その一切世界こそが一切世界であるからそうなのである。とするならば、人はどこに生まれようとも、それは王宮(おうぐう)にあらざるはなく、その王宮はすべて悟りの道場にあらざるはないのである。
達磨大師はそのような故をもって西より来られたのである。迷える人々を救おうとする自己であるから、驚きもなく、怖れもなく、その対象としての全世界であるから、疑うところもなく、恐るるところもなく、生まれた国を永久に去って、大船を艤(ぎ)し、南海を航して、広州に着いた。乗船の人も少なからず、随身の僧たちもたくさんあったであろうが、記録はなにごとも記してはいない。船が岸についてからのことも、詳しく知るものはない。
着岸の日は、梁(りょう)の普通(ふつう)八年(527)の九月二十一日であった。広州の長官の蕭昂(しょうこう)なるものが賓(ひん)主の礼をもって接待した。つまり、上奏(じょうそう)の文を草して武帝に申し上げた。蕭昂(しょうこう)の律儀な処置であった。すると、武帝は上奏文を見てはなはだ喜び、使者をもって、詔(みことのり)をもたらして迎えたてまつった。そのとしの十月一日のことであった。
初祖達磨大師は、金陵(きんりょう)にいたって、梁の武帝と会見した。武帝は問うていった。
「朕は、即位よりこのかた、寺を造り、経を写し、僧を度すること、記(しる)すことができないほどである。どんな功徳があるであろうか」
達磨はいった。
「いずれも功徳はない」
武帝はいった。
「なんで功徳がないのであるか」
達磨はいった。
「それはただ人々(にんにん)の小さな果(か)というのもで、かえって煩悩の因である。影の形に従うがようなもので、有りとはいえど実(じつ)ではない」
武帝はいった。
「では、いかなるが真の功徳というものであるか」
達磨はいった。
「浄智(じょうち)はまことに円(まろ)やかにして、諸法はもともと空々寂々たるものであるが、そのような功徳は、この世に求める者はない」
武帝はまた問うていった。
「いったい、仏教の教えるもっとも大事なことは何であろうか」
達磨はいった。
「廓然無聖でござる」
武帝はいった。
「朕に対しているのは誰であるか」
達磨はいった。
「識(し)らない」
武帝はそれが解らなかった。達磨は二人のゴゴロの動きが契合(けいごう)する見込みのないことを知った。だから、おなじ月の十九日、ひそかに江(こう)を北に越えて、同じ年の十一月二十三日、洛陽にいたり、嵩山(すうざん)の少林寺に寓居し、壁に面して坐し、終日黙然としていた。
だが、魏の王もおろかであって、達磨のなんたるかを知らず、またそれを恥ずべき理(ことわり)をも知らなかった。達磨は南天竺の王族の出身であり、大国の皇子である。大国の王宮に育って、その作法にも習熟していた。小国のならわしには、大国の王者に見られては恥ずかしいことが少なくないものだが、達磨は別にそんなことには心を動かさず、国をも捨てず、人をも捨てずに魏にとどまっていた。その間には、菩提流支(ぼだいるし)の誹謗を受けたこともあったが、なんの弁解もせず、憎みもしなかったし、光統律師(こうずりつし)の邪計があっても、恨みもせず、耳にも入れなかった。(369~372頁)
〈注解〉金陵;宋の都、いまの南京。
度;出家せしめる。中国では出家にあたって度牒(どちょう)という許状を与える制度があった。
聖諦第一義諦;聖諦(しょうたい)とは、ここでは仏教の真理、そのなかでもっとも大事な真理、もしくは、それを表現する命題をいう。それを問うているのである。
廓然無聖;大空のごとく広々として、聖も非聖もない境地をいう。(374頁)
■まだそのようなすぐれた帝王の教化に遇うことをえない民どもは、君につかえるとはどんなことか、親につかえるとはどうするかも知らないのだから、君の臣としてもあわれであり、親の子としても可哀そうである。臣となっても、子となっても、大事なことも知らずに過ごし、大切な時もむなしく過ごしてしまう。そのような家柄に生れて、国の重き職を授けられた者はなく、軽い官位すらねおめったに受けることがない。国の乱れている時でもなおそうであり、平和の時にはなお見聞することが稀である。
そのような辺地に生まれ、そのような卑賤の身でありながら、なおかつ如来の正法(ぼう)を聞こうとするならば、どうしてこの卑賤の身を惜しむこころがあってよかろうか。それを惜しんで、いったい、なんのために捨てようというのであるか。たとい、その身分が重くかつ賢明な人であっても、なお法のためにその身を惜しむべきではない。ましてや、この卑賤の身命をやである。たとい身は卑賤であっても、もしも道のため法のために、惜しむところなく捨てることもあれば、それは天の神よりも貴(たっと)く、理想の王者よりもすぐれたものであろう。総じていえば、天の神、地の神、この世の誰よりも高貴であろう。(382頁)
〈注解〉楚国の至愚;『後漢書』の応劭(おうしょう)伝に、宋の愚人が燕石(玉に似て玉でない石)を宝として大事にしていた話がある。それをもって玉石の区別を知らぬことに冠したのであろう。ただし、それは楚国ではなくて、宋国の愚人となっている。他に楚国の王の愚かさを語った物語もあるが、それは玉石混淆のことに冠すべきものではない。だが、いずれにしても、これは玉石云々を形容する句にすぎない。(385頁)
■そういうことであるから、この初祖がもたらした仏祖のみちは、いかに峻険であろうとも、これを厭い嫌うて辞すべきではない。その玄妙の家風はいまもなお仰ぎ見ることを得るのに、この身命を惜しんだとても、結局なんにしようというのであるか。
香厳(きょうげん)禅師は偈(げ)をなしていう。
「よろずの思い計(はから)いは身のためであるが
身は結局、塚穴のなかの塵ではないか
白髪は物いわぬなどと思うてはならぬ
それは冥土の言伝(ことづて)をもたらすものじゃ」
だからして、この身を惜しんでよろずの思い計らいをしたからとて、ついには塚穴のなかのひと盛りの塵となるのである。ましてや、小国の王やその臣下たちに使われて、ただいたずらに東に西にと駆け回るのでは、その苦労のほども察せられるというものである。人は義によってはその身命を軽んずるものである。殉死の作法が忘れ去られないなどはそのゆえである。だが、君恩に使われる者の前途は、また目の前も判らぬ闇であって、つまらぬ臣どもにこき使われ、その辺(あた)りで身命を捨てる者が、昔からも少なくない。仏法の器となりうる身を惜しいことではないか。
しかるに、いまわれらは正法に遇うことをえた。されば、百千無数の身命を捨てても、正法にいたり学ぶべきである。つまらぬ小人(じん)と、広大深(じん)遠の仏法と、その選択は迷うべき余地もあるまい。静かに思うてもみるがよい。正法が世に行われていない時には、この身命を正法のために捨てようと思ってもかなわぬことであった。そかるに、いま幸いにして正法に遇うことをえた。そのわたしどものことをじっと考えてみるがよい。正法に遇いながら、身命を捨てなかったならば、それは恥ずかしいことである。恥ずかしいことを知るほどの者ならば、まずこの道理を恥じなければならない。(391~392頁)
■しかるに、いまわたしどもが、道のためにその身を捨てなかったならば、他日、その髑髏は、野外に捨てられた時、誰がこれを礼拝するか、誰がこれを買おうぞ。そんなことになってしまっては、この自分の魂が、やがて過去を振り返って恨まなくてはなるまい。古き経が語る譬喩にも、鬼が自分の昔の骨を打つという話があり、天の神が昔の自分の骨をおがむという話もある。むなしく塵と化し土となる時のことを思いやるならば、とてもいまの自分を愛惜(じゃく)してはおれまいし、また、のちの世を憐れまずにはおれまい。それを傍(はた)から見ている人があったとするならば、かならずや涙を催さずにはおれないであろう。とするならば、むなしく塵と化し土となって人に嫌われる髑髏の身をもって、よく仏の正法を行ずるものとなりうるならば、それこそ幸いというものでなくてはなるまい。
だから、寒さの苦しみを恐れてはならない。寒苦はなお人を損なうものではなく、また、なお道を損なうものでもない。ただ、修せざるを恐れなくてはならぬ。修せざれば、それが人を損じ、道をやぶる。また、暑さの苦しみも恐れてはならない。暑熱もなお人を損なうものではなく、また道を損なうものでもない。ただ、修せざることが、人を損じ、道をやぶるのである。かって釈尊は馬糧の麦の供養をうけ、伯夷(はくい)はわらびをとって生きたという。それは、出世間と世間におけるすぐれた先例である。血を求める餓鬼にならい、乳をもとめる畜生になろうてはならない。ただ一日の行持に励む。それがもろもろの仏たちの履(ふ)みきたった足跡である。(393~394頁)
〈注解〉香厳禅師;香厳智閑(きょうげんしかん、年寿不詳)。潙山霊祐の法を継ぐ。すでに見来ったように、よく偈(げ)をつくった人であるが、つぎに引用の偈は、その出処未詳である。(395頁)
■やっと少林寺にたどりついたけれども、入室(にっしつ)は許されなかった。達磨はまるで振り向いてもくれないようであった。その夜、慧可は、眠ることも、坐ることも、休むことすらできなかった。ただ、じっと立ち尽くして夜の明けるを待っていると、夜の雪はまことに無情であった。だんだんと積もって腰をうずめるにいたり、落ちる涙は一滴一滴と凍った。その涙をみると、また涙が出た。わが身を省(かえり)みることも幾度であったか。そのなかで彼はこうも思ったという。
「昔の人が道を求めるには、骨をたたいてその髄を取り、血をしぼって饑(う)えた者を救うということもあり、また、髪を布(し)いて泥を掩(おお)い、崖より身を投じて飢えたる虎を養ったという話もある。古人にしてなおそのようであったというのに、わたしはいったい何者であるか」
そのように思うと、志を励ます気持がふるいおこった。
そこにいう「古人にしてなおそのようであったというのに、わたしはいったい何者であるか」ということばは、後進のものの忘れてはならないところである。それを、ちょっとでも忘れていたら、そこから人はどこまでもとなく落ちてゆくのである。
それはともあれ、慧可はそのように思うと、法を求め道を求める志のいよいよ燃えるをおぼえるばかりであった。雪を浴びる苦しみを少しも苦しみとしなかったからであろう。だが、夜明けのおそい冬の夜はなかなか明けない。その間の消息は、推し測ろうとしても、ただ肝をひやし、身の毛もよだつばかりである。(402~403頁)
■静かに思いみると、たとい初祖がいくたび西より渡来しようとも、もしも二祖のこの行持がなかったならば、今日の思うがままに学ぶ雲水はありえなかったであろう。しかるに、今日わたしどもはこうして正法を見聞することができる。この仏祖の恩はかならず報いて謝さねばならない。その報謝には、ほかのことでは報いることはできない。身命をもってしても足らず、国や城をもってしてもなお不足である。国や城は、他人に奪われることもあるし、親から子にゆずることもできる。また、身命は無常にもまかさねばならぬ。時には、主君にまかせ、時には、邪道にまかせて身命を捨てる者すらもある。とするならば、それをもって報謝にあてようとするのは、道理ではあるまい。ただ、日々の行持、これこそまさにその報謝の正しい道であるとしなければなるまい。
そのありようは、日々の生命をなおざりにせず、わたくしごとに費やさないようにと、心して行ずるのである。その故はいかにとならば、この生命は、前々からの行持のおかげであり、行持の大恩である。それは急ぎ報謝しなければならない。しかるに、そのような仏祖の行持のおかげを蒙(こうむ)ってなれるこの肉体を、ただいたずらに妻子の奴僕となし、妻子の弄(もてあそ)ぶにまかせて、その零落を惜しまなかったならば、それは悲しむべきこと、恥ずべきことでなければなるまい。また、邪(よこしま)のことに狂い、身命を名利の鬼にまかせるならば、それもまた恥ずべき悲しむべきことでなければならない。名利というものは一頭の大(だい)賊である。名利を重んずるならば、名利のことをしみじみと思うてみるがよい。名利のことをしみじみと思うてみるならば、やがて、仏祖ともなりうるこの身命を、名利のことにまかせて破るようなことはなくなるのである。妻子眷(けん)族の上に思いをかけることも、また同じであると知るがよい。
そもそも、名利というものは、ただ夢まぼろしのごとく空虚なものと学ぶべきではない。むしろ、一般の人々のように考えてみるがよいのである。名利のことをしみじみと思うてみることをせず、かえって罪の報いをのみ積もらしてはならない。学びきたれる正法の眼をもって、あまねく諸方をみるにあたっては、常にその心得がなくてはならない。
世のなかの心ある人々は、金銀や珍宝のめぐみを蒙っても、なおかならず報謝する。うれしい言葉をかけてくれたよしみにすら、心あるものはみな報謝の思いに励む。ましてや、如来の説きたまえる最高の教法を見聞きすることのできる大恩は、人間たるものの誰が忘れてよかろうぞ。これを忘れなければ、それが一生の宝である。それもまた行持である。そして、この行を持して退転することのない人のむころは、その生ける時と死せる時を問わず、同じく七宝の塔におさめ、すべての人々が供養するに値するのである。そのような大恩があると知ったならば、かならずや、この果敢(はか)ない命をもいたずらに零落せしめず、かの山のような徳をも報ずるがよい。それがそのまま行持である。そして、その行持のわざを通じて、そこに祖・仏として行ずるわたしが実現するのである。
いったい、仏祖や二祖は、かって精舎を創(はじ)めたことがない。したがって、草を刈るといった煩わしいことはなかった。続いて、三祖や四祖もまたそうであった。五祖や六祖にいたっても、なおみずから寺院を創建するということはなかった。青原や南嶽もまたそうであった。
また石頭大師は、草庵を大石の上に結んで、石の上に坐禅していた。昼も夜も眠らず、ずっと坐っていた。いろいろの務めは欠かさなかったけれども、二六時中の坐禅はかならずつとめてきた。いま青原門下の流れが広く天下に流れて、多くの人々を潤(うるお)わしているのも、石頭大師の力ある行持のしからしむるところである。いまの雲門や法眼(げん)の流れも、またみな石頭大師の流れを汲むものである。(404~406頁)
〈注解〉石頭大師;また石頭和尚という。石頭希遷(せきとうきせん、790寂、寿91)。青原行思の法を嗣ぐ。(395頁)
■唐の高宗の永徽(えいき)二年(651)、閏(うるう)九月四日のこと、四祖禅師は突然、門人を集め、誡(いまし)めを説いていった。
「すべてもろもろの存在は、みなことごとく迷いを脱している。汝らはそれぞれみずからの心をうちにひそめ、仏の教えを未来に伝えるがよい」
いい了(おわ)ると、安坐したまま亡くなった。寿は七十二歳であった。本山に埋葬したが、その翌年の四月八日、塔墓(とうぼ)の戸がしぜんに開いた。そのありようは人の生くるがことくであった。それで門人たちも、あえてそれを閉じなかったという。
よって知るがよい。すべてもろもろの存在は、ことごとくみな生滅の法にしたがう。もろもろの存在はただ空であるのみではない。存在が存在でないわけではない。ただ、みなことごとく生滅の法にしたがって存する存在である。いま四祖禅師においては、なお生ける時には、生ける時の行持があった。すでに死してからは、死してからの行持があった。生きている者はかならず滅するものとのみ学ぶのは、狭い見解でである。また、すでに死せる者にはなんの知覚もないと考えるのも見識が狭いからである。仏道を学ぶものは、そのような小さな見解・見識になずんではならない。生ける者の滅してなお不滅なるものがあり、死せる者にもなお思うところがあってはずである。(410~411頁)
■彼(岡野注;玄沙師備(げんしゃしび))はもともと、雪峰義存とは法兄・法弟の間柄であったが、しかし、彼は雪峰を尊敬して親しみ、その間柄はあたかも師弟のようであった。その雪峰は、彼のその苦行ぶりをみてあれは師備の「頭陀(ずだ)」だといっておった。そして、ある日のこと、雪峰は師備に問うていった。
「頭陀袋なんかもって、どこへ往(ゆ)こうというのだ」
師備は答えていった。
「やっと人に騙されずにすみましたわい」
またある日のこと、雪峰は師備を呼んでいった。
「師備よ、頭陀袋をととのえたら、なぜ遍歴に出掛けないのだ」
師備は答えていった。
「達磨は中国にやって来たわけでもなく、また、二祖は印度にでかけて行ったわけでもありません」
雪峰はそれを深くうなずいたことであった。
やがて、雪峰が象骨山(ぞうこつざん)に登るに及んでは、師備もまたともに赴(おもむ)き、力を合わせてその建立につとめたので、たくさんの雲水が集まってきた。そこでも師備は、朝も晩もかわることなく、雪峰の室に入って、あるいは問いを呈し、あるいは裁断をもとめた。諸方から集まってくる雲水たちも、いまだ決せざるところのある者は、かならずまず師備のところにいたって指導をこうた。また、雪峰和尚もよく、あの備頭陀(びずだ)に問うがよいといった。師備はまた慈しみの深いひとであったから、そんな時には、師匠にゆずらない懇切な指導につとめた。
こんなことは、郡を抜いた行持を経てきた者でなくてはありえないことである。終日坐禅するといった行持は稀なことなのである。いたずらに眼前の事物にひかれて走りまわっている者は多いが、ひねもす坐禅につとめる人は稀なのである。いま後進としてこの道を行くものは、おのれに残された時間の少ないことを恐れて、終日の打坐(たざ)をこそこれ努めるがよい。(413~415頁)
〈注解〉玄沙宗一大師;玄沙師備(げんしゃしび、908寂、寿74)。雪峰義存の法を嗣ぐ。のち、福州の玄沙山に住した。諡して宋一(いつ)大師と号する。
具足戒;戒を受領して、出家の比丘にまることをいう。
頭陀;衣食住のむさぼりを払う行法をいう。しかるに、頭陀はまたいわゆる頭陀袋をいうことばであって、その二つの意味が、ここでは面白く用いられている。
徧参;禅僧が行脚してあまねく天下の善知識を訪ねること。また遍参とも記す。
象骨山;雪峰山のことである。雪峰が寺を開いて雪峰山と名づけたのである。(415頁)
■「……(前略)……
長慶の慧稜(えりょう)和尚は、雪峰門下の長老であって、あるいは雪峰山に参じ、あるいは玄沙山(ざん)に赴いて、学ぶことおおよそ二十九年である。その歳月(としつき)のあいだに座蒲団を坐り破ること二十枚に及んだという。いまでも坐禅に心を寄せるものは、この長慶をあげて慕うべき範例だとする。だが、慕う者はおおいが、及ぶものはすくない。しかるところ、長慶が三十年の坐禅工夫はついに空しからず、あるとき、涼風の簾(みす)をふきあげるのをみて、忽然として大いに悟るところがあった。
思うに、この人は、三十年来かって故郷にも帰らず、親族を訪れることもなく、となりの坐席のものとも談笑せず、ただ坐禅工夫に専注した。しかも、その行持は三十年。疑問をどこまでも疑問として追求すること三十年に及んだのである。まさに並々ならぬすぐれた機根の人であり、大いなる器であったといわねばならない。
そのような賢固な志のことを伝聞するのは、たいてい経巻によってであるが、そのためにはまず、疑うべきことを疑い、恥ずべきことを恥とすることを知らねばならぬ。それには、まず長慶に赴き見(まみ)えるがよいであろう。ひるがえって、現実はいかにといわば、世の人々はたいてい道を求める心がなく、その行うところもまずいので、すぐ名利のことに捉われるのである。(417頁)
〈注解〉長慶の慧稜和尚;長慶慧稜(932寂、寿79)。雪峰の法嗣。(418頁)
■潙山の大円禅師は、百丈禅師の印可のことばを得ると、ただちに潙山の峻嶮(しゅんけん)によじのぼり、鳥や獣に伍(ご)し、草庵をむすんで修練(しゅれん)にいそしんだ。風雪をもいとうことなく、橡(とち)や栗の実を食となした。堂宇(どうう)がないので、安住するところもなかったが、それでも、四十をすぎた頃から、その行持が次第にあらわれてきて、のちには、天下の名刹(めいさつ)として、すぐれた求(ぐ)道者が峻嶮を踏破して集まり来ったものである。
いったい、寺院を建立したいと思っても、人の心の動きを気にしてはならない。ただ、仏法を行じつづけることを堅固にするがよい。修練はあるが堂閣(どうかく)はないというのが、それが真の仏者の道場というものである。樹下の露地をふく風が遠く聞こえるのであり、そのような仏者のあるところが長く聖域として存するのである。つまり、一人の行持があれば、それがもろもろの仏の道場に伝わるであろうからである。
だから、末世の愚人はただいたずらに堂閣の建立に心を労するが、そんなことは不要である。仏祖はかって堂閣のことを念としたことはない。しかるに、自己のまなこはまだ開かれないのに、いたずらに堂閣を構えるなどというのは、断じて仏たちに仏堂を献じようとするのではなく、ただおのれの名利の巣窟としようがために他(ほか)ならない。潙山がその昔になし来ったところを静かに思いやるがよい。思いやるというのは、自分がいま潙山に住んでいるかのように思うてみるのである。
深夜の雨の音は、苔を洗うくらいのことではなかったであろう。きっと岩石をもつらぬくほどの激しさであったにちがいあるまい。また冬空の夜には、鳥や獣さえもめったに見かけなかったであろう。ましてや、人の気配を感ずることなど全くなかったであろう。身命を軽うし仏法を重んずる修行でなくては、とてもこんな生き方はできないところである。だから、草を刈ることも急がないし、地を平らげることもせず、ただ行を持しておのれを練り、仏道を追求して心を労するのみである。ああ、思えば、仏法を伝持しきたった仏祖たちには、このような山中の苦難に堪えてこられた方がどのくらいおられたことであろうか。
ちなもに、かの潙山のありようを伝え聞くと、そこには池があり、水があり、ある時には氷が張りつめることもあり、ある時には霧がおし包んでしまうこともあるらしい。それはとうてい人間の幽居するに堪えるところではないが、それがおのずから仏道を成じ、奥義にいたらしめる霊験(れいげん)のはなはだ顕著なるものがあるのである。
このような行持の話を見聞するには、身をやすやすとしたままで聞くべきではない。だが、そんな行持に励んで得べき報(むく)いがなんであるかを知らなければ、それも詮ないことであろう。しかし、もし志のある後進であるならば、その昔の潙山をいまわが目の前に見るように思いやって、感歎これを久しゅうしなければならないはずである。思うに、その潙山の行持の功徳によって、大地の基底もゆるがず、世界も破れることなく、天の神々の住まいも穏やかにして、人間の国土も保全することをうるのである。
わたしどもは潙山の流れを汲むものではないけれども、潙山は立派な祖師であったらしい。のちには仰山(きょうざん)がきたって随侍した。仰山はもと先師百丈のところにあって、十を問えば百を答える才気煥発の器であったが、さらに潙山に参じて、かの師を見守ること三年に及んだ。近来ではまったく絶えて、見聞することもない行持であった。だから、こんな話はまったく独特であって他には求めがたい。(420~422頁)
〈注解〉大潙山大円禅師;潙山霊祐(853寂、寿83)である。百丈の法を嗣ぎ、潙仰(いぎょう)宗の祖となる。ほかにも、潙山を号とする者があるので、特に霊祐を大潙とよぶのがならいである。
授記;未来の成仏につき予言を与えることをいうことばであるが、ここでは百丈が潙山に嘱(しょく)して、「潙山は勝境である。汝は当にこれを居(こ)して吾が宗を嗣ぎ、ひろく後学を度すべし」といったのであるから、もっと正確には付嘱というところである。
仰山;仰山慧寂(916寂、寿77)である。潙山霊祐の法嗣。潙山を助けて、その法を宣揚したので、潙仰宗の名がおこった。(422頁)
■ところで、わたしは今日、諸人の前に面をさらして家門の風(ふう)を説こうとしているが、これはどうも勝手が違って具合がわるい。ましてや、さらに上堂とか入室(にっしつ)とかいって、槌(つち)をひねり、払子(ほっす)を立てて、あるいは喝(かつ)をなし、あるいは棒をふりまわして、まるで癇癪もちがその病をおこしたようなことをするのは、ただに学人たちをないがしろにする許(ばか)りではなく、さらには先聖に背くものである。汝らも知っているであろう。達磨は西より渡来して、小室山(しょうしつざん)のふもとにいたったが、ただ面壁して坐すること九年であった。二祖が雪のなかに立ち、臂を断つにいたっては、まことに艱難を受けたことであった。だがしかし、達磨はかって一語を吐いたわけでもなく、二祖はかって一句を呈して問うたわけでもない。それでも、達磨をよんで〈人の為にせず〉となすことはできまい。あるいは、二祖を指さして〈師を求めず〉となすことはできまい。わたしは、それらの古聖のなすところを説くたびに、恥ずかしくて身の置きどころがないような思いをし、また後輩として軟弱なることを愧(は)じいるばかりである。
ましていわんや、いまの世では、いろいろの御馳走をたがいに振舞いおうて、さてそこで、これで四事もすべて整ったので、もう発心してよいなどとぬかす。そんなことでは、おそらくは手足をならすところまでも行けず、いつまで経っても仏道の遠いところに落ちてゆくばかりである。光陰は矢のごとしというのに、まことに惜しいことではある。
とはいいながらも、他人(ひと)のことはその人の得手にまかせるがよいというもの。わたしもまた強いてそなたがたを教えるわけにはゆかない。では、ひるがえって古人の偈(げ)をみてはどうか。
『山の田でつくった玄米の飯
あわい黄色の野菜の漬けもの
食べる食べぬは君にまかせる
食べねばどこへでも行くがよいわい』
伏して惟(おもん)みるに、道を同じゅうする者よ、つまるところは各自の努力でござる。では、お大事に」
これが、とりもなおさず、仏祖直伝の骨髄というものである。芙蓉高祖の行持はなおいろいろとあるが、いまは一応これをあげて示すのである。わたしども後進たるものは、この高祖が芙蓉山でおこなった行持を、とくに慕うて学ぶがよい。それはそのまま教祖釈尊の教えたまうところなのである。(429~430頁)
〈注解〉※ここには、芙蓉道楷のかなり長い垂示を漢文のままに引用している。仏々祖々にはみなすぐれた行持の事蹟が伝え残されている。だが、事細かに説きあかしたものは稀である。道元がここに、その長い垂示をそのままに引用した心組みもまた知られようというものである。その稀なるを珍重して挙げたのであろう。
芙蓉山の道楷;芙蓉道楷(1118寂、寿76)。投子義青(とうすぎせい)の法嗣(ほっす)。晩年芙蓉山の湖上に庵をむすんで住んだ。
心・念;心なるものと、そのはたらきをいう。
趙州;趙州従諗(ちょうしゅうじゅうしん、897寂、寿120)のこと。南泉普願の法嗣。
入室;弟子が師の室に入って、したしく所得を呈して問うことをいう。
上座;禅林にて、師家や学人に対して用いる二人称である。(431~432頁)
■洪州江西(ぜい)の開元寺大寂禅師は、諱(いみな)を道一という。漢州十方県のひとである。南嶽に見(まみ)えて随侍すること十余年である。そのある時のこと、郷里に帰ろうとして途中まで行ったが、そこから引き返して南嶽のもとにいたり、焼香して礼拝した。すると南嶽は偈をつくって、馬祖に与えていった。
「君に勧む、郷に帰るなかれ
郷に帰れば、道おこなわれず
隣り近処の老婆たちは
むかし名をもって汝を呼ぼう」
すると馬祖は、その垂訓ををありがたく頂いて、誓って「わたしは生々世々(しょうじょうせぜ)にも漢州にまいりませぬ」といった。そのような誓願を立ててからは、漢州に向かって一歩を勧めることもなく、ただ江西ににずっと住みつづけ、この人に見(まみ)えんとする者は、四方八方から来り集まった。その間(かん)、わずかに「即心是仏」の句を吐いたほかには、まったく人のために説くところはなかった。それでいて、なお立派に南嶽の法を嗣ぎ、世人のいのちともいうべき仏者となった。
では、その「郷に帰るなかれ」とは、どういうことであるか。郷に帰らないとは、どうあればよいというのか。それなのに、「郷に帰れば、道おこなわれず」とある。道の行われないのは、郷に帰るからだと受け取るべきか、それとも郷に帰るからではないと受領すべきか。いったい郷に帰るからだと受け取るべきか、それとも郷に帰ればなにがゆえに道が行われないこととなるのか。それは、行わないから行われないのであろうか。それとも、自分がそれを碍(さまた)げているのであろうか。
さらに、「隣り近処の老婆たち」が、「汝のむかしの名をもって呼ぶであろう」と、そういっておるのではない。そこは、二つの句を一つにして、ずばりと、「並舎老婆子、説汝旧時名」といっておるのである。南嶽はどうしてこのことばを吐いたのか。馬祖はどのようにしてこの垂誡(すいかい)を頂戴したのか。その道理をつらつら考えてみると、それは、自己が南に向かって行けば、大地もまた同じく南に向かって行くということである。南ばかりではない。他行(こう)はすべてまたそうなのである。それを、須弥山(しゅみせん)や大海を規準として、そうではあるまいと疑い、あるいは、日月や星辰を標準として首をかしげるのは、小さな量見というものである。
五祖の大(だい)満禅師は、キ州黄(おう)梅も人である。俗姓は周氏であった。母の姓を名告(なの)ったのであって、この人は父をなくして生まれたのである。ちょうど老子と同じである。七歳にして法を伝えてから、七十四歳にいたるまで、仏祖の伝える正法の眼目をよく保ち持って、ひそかに衣(え)法を慧能に伝えた。そのころ慧能はなお雑役のものであった。まことに独特のことであった。しかるに、この衣法を、上座の神秀に伝えず、慧能に伝えたからして、正法の寿命は絶えなかったのである。(434~435頁)
〈注解〉※ここには、場祖道一のこと、および五祖弘忍のことが語られている。前者は詳しく、後者は簡略であるが、五祖弘忍のことは、すでに「仏性」の巻、および、「伝衣(え)」の巻に詳しく述べたところである。
洪州江西開元寺大寂禅師;馬祖道一(786寂、寿80)である。南嶽懐(え)譲の法嗣(ほっす)。江西鐘陵の開元寺に住し、世に江西の馬祖と称せされた。諡して大寂禅師と号する。
心・念;心なるものと、そのはたらきをいう。
南嶽;南嶽懐(え)譲(744寂、寿68)のこと。六祖慧能の法嗣。
第三十二祖大満禅師;五祖の大満弘忍(716寂、寿74)である。西天の祖師につづいて算(かず)うれば三十二祖となる。四祖道信の法嗣。
慧能・神秀;二人よも五祖弘忍の弟子であるが、弘忍のあとを嗣いで、六祖となったものは、神秀上座ではなくて、慧能行(あん)者であったことがよく知られている。行者とは、いまだ得度せず、寺中の諸役のの者のもとにあって雑役に服するものをいう。(435~436頁)
■先師天童和尚は、越(えつ)のあたりの人である。十九歳にして教義をのみ学ぶことを捨てて、禅門にいたり、七十歳にいたって、なお罷(や)むことがなかった。寧宗(ねいそう)皇帝より紫衣(しえ)ならびに禅師号の御沙汰があったけれどもついに受けず、上表の文を草して拝辞した。四方の修行する僧たちは、みなこの人を崇敬し、遠近の有識のものもすべてこの人の徳をたたえた。皇帝もまたこのことを大いに悦び、お茶をたまわった。聞くものはみな世にも珍しい事と讃談した。
その故はいかにとならば、名聞を愛することは戒を犯すことよりもなお悪いからである。戒を犯すは一時の非であるが、名聞を愛するは一生の累(わずら)いである。それを捨てないのは愚かであり、それを受けるのは道理に眛(くら)いというものである。それは、受けないのが正しい出処であり、捨てるのが道理にかなう進退である。達磨より以後、六代の祖師はそれぞれ師号があるが、それらはみな没後の諡(おくりな)であって、この世にあって名聞に心をひかれたわけではない。だからして、われらもまた、生前没後の名聞をむさぼる心をすてて、ただ仏祖の行じきたった跡をふもうと念ずるがよく、それを貪り愛した鳥けだものに等しュうなってはならない。大したものでもない自分をひたすらに愛執(あいしゅう)するのは、鳥けだものもするところである。畜生だっておなじである。ひるがえって、名聞・利養を捨てることは、人々のまれとするところであるが、仏祖にしていまだそれを捨てないものはないのである。
しかるに、ある者はいう。われらは衆生を利益(やく)せんがために名聞をむさぼり、利養を愛するのである、と。それは、たいへんな間違った考え方である。仏法のなかに巣くう外道であり、正法をそしる悪魔の輩である。もしそのいうがごとくであるならば、名利を貪らなかった仏祖たちは、衆生を利益しようととの思いはなかったのであろうか。まったく嗤(わら)うべきである。また、不貧(とん)の利生(しょう)ということがあるが、どうじゃ。いったい、衆生を利益するにもいろいろとあることを知らずして、まことは衆生を利するものでもないことを衆生の利益だという。そんなのは悪魔のたぐいなのであろう。そんな輩に利益せられた衆生は、地獄に堕ちる仲間であって、暗い生涯を送らねばならぬことを悲しむがよい。そんな愚かな考え方を衆生を利するなどといってはならない。
だからして、先師天童和尚が師号を賜(たまわ)っても上表の文を草して拝辞したというのが、古来の勝れた範例となるのであり、後進たるものの学ぶべきところとされるのである。わたしは、幸にして、目のあたりに先師をみることを得たのであるが、それは、ほんとうの人物というものにめぐり会うことができたのだと思っている。
先師は十九の歳から郷をはなれ師を訪ねて、仏道を求め、禅を修すること、六十五歳にいたってもなお已(や)むところがなかった。その間、権力者に近づかず、皇帝に見(まみ)えたこともなく、宰相と親しんだこともなく、官吏に近づいたこともない。表を上(たてまつ)って紫衣(しえ)・師号を辞したばかりでなく、また生涯けっして色模様の袈裟を着たこともなかった。いつものように上堂したり、入室(にっしつ)のときにも、常に黒い袈裟ころもを用いた。
雲水たちに教訓を与える時には、よくこんなことを仰せられた。
「禅を修し、仏道を学ぶには、まず道心のあることが大切である。それが仏道を学ぶはじめでなければならぬ。いまは、この二百年このかた、祖師の道がすたれて、まことに悲しむべきことである。ましてや、一句をいいうるものは稀である。
わたしは、そのむかし、径山(きんざん)に杖をとどめていたことがあるが、そのころは仏照徳光(ぶっしょうとくこう)なるものが住持であった。法堂(はっとう)にのぼって説いていうに、『仏法とか禅堂とかいうものは、かならずしも他の人の説いた言句をもとむべきではない。ただ各自がそれぞれに会得するがよろしい』と。そういって、僧堂のなかのこともすべて監督せず、雲水たちのこともすべてわれ関せずで、ただ来客と会って付き合うばかりであった。この仏照という人は、まったく仏法のあるべきようを知らず、ただひとえに名をむさぼり利を愛するのみであった。いったい、仏法がもし各自それぞれの会得すべきものであるならば、どうして年功を積んだ修行者たちが師をたずねて道を問うことをしようか。きっと仏照徳光はいまだかって参禅したこともない人であったにちがいあるまい。
しかるに、いま諸方の長者たちも、どうやら仏照の輩にすぎないようである。そんな輩の手中に仏法があろうはずはない。まことに惜しむべきことではある」
そのように仰せられるのを、仏照の輩どももたくさん聞いていたが、腹をたてるものはなかった。
先師は、また仰せられた。
「参禅というものは、ただ身心(しんじん)脱落するのである。それには、焼香も礼拝も念仏も修懴(しゅさん)も看経(かんきん)もいらない。ただひたすれに打ち坐って、はじめて得るのである」
思うに、いま宋国の諸処方々には、参禅の名をかかげて、仏祖の流れを汲むと称する者は、百、二百にとどまらず、いたるところにあるけれども、坐禅をただ打ち坐るものとして勧める者は、まったく風のたよりにも聞き及ばない。天下にただ一人、先師天童和尚のみである。どこに行っても天童和尚をほめないものはないが、和尚はいっこうに彼らをほめない。なかにはまた、天童和尚を知らない大寺の住持もあるが、そんなのは、中国に生まれたとはいっても、鳥けだものの類(たぐい)であろう。なんとなれば、彼らは、到って学ぶべきに到らずして、いたずらに歳月を過ごしたものにちがいないからである。かわいそうに彼ら天童和尚をしらない輩は、いい加減なでたらめを口やかましく説いて、それが仏祖の家風とのみ間違えているのである。
また、先師はいつもみなにむかってかように説かれた。
「わたしは、十九歳の時よりこのかた、方々の禅院をめぐり歩いたが、人のために説く師というものはなかった。また、十九歳の時よりこのかた、一日一夜といえども坐禅の蒲団をしかなかったことはなかった。まだ住持とならぬ頃から、里の人々と話をしたこともない。時間がおしいからであった。あるいは、どこの禅院に足をとどめても、庵のなか、寮のなかを見てまわったこともない。ましてや、山水に遊ぶなどということに心をもちいる道理があろうか
また、僧堂や公界(くがい)のほか、あるいは桟道(かけはし)の上とか、垣根の内側とか、人気(げ)のないところにただ一人でいって、適宜なところで坐禅した。いつでも袖のなかに蒲団をしのばせていて、時には岩の下でも坐禅した。そして、いつでも思ったことは、お釈迦さまの樹下の座のように坐りぬきたいと思った。それがわたしの期するところであった。時には、臀(しり)の肉がただれるようなこともあったが、そんな時には、ますます坐禅にはげんだ。
わたしはもう今年六十五歳になった。老骨になって頭もよくまわらず、坐禅の理屈などはわからないが、四方から集まる兄弟の雲水たちがいとしいので、この禅院の住持として、来り参ずるものを諭(さと)し、人々のために仏道を伝えるのである。方々の長老たちは、どこにどんな仏法があるか、判ったものではないからなあ」
法堂にのぼられると、よくそのように説かれたものであった。(444~448頁)
〈注解〉先師天童和尚;天童如浄(1228寂、寿66)である。雪寶智鑑(せっちょうちかん)譲の法を嗣ぎ、曹洞(とう)の流れを汲む。天童山景徳寺に住す。先師とは亡くなった師をいうことばであって、道元にとっては、先師とは如浄のほかにはない。
看経;経を黙読すること。
径行;坐禅の合間に、運動のために、一定のところを歩くことをいう。(453~454頁)
■静かに考えてみるがよろしい。この一生はいくばくでもない。だが、たとい仏祖のことばをまなぶことわずかに二、三句であろうとも、その語句が表現しているのは仏祖そのものの表現であるはずである。なんとなれば、仏祖は身心がひとつであるから、その吐いた一句両句も、すべてみな仏祖のあたたかい血のかよう身心そのものである。したがって、それらの仏祖の語句をわが身心をもって学びとるならば、それは、かの仏祖の身心がきたってわが身心を表現しているのである。そして、まさにその会得のなる時、その時には今度は、かの仏祖のことばがわが身心を表現しているのである。しかるに、よくよく考えてみると、この生においてよくかかる会得をなしうるということは、また未来のわが身の生々(しょうじょう)のことでなくてはなるまい。つまるところ、そのとき仏となり祖となれば、さらに仏をこえ、祖をこえてゆくこととなろう。
上にあげたそこばくの行持に関する語句は、まさにかくのごとくなるものである。願わくは、つまらぬ目前の名利に惹(ひ)かれて右往左往することなかれ。右往左往することがなければ、それが仏祖のじきじきに伝える行持というものである。望みたいのは、世の中に隠れてもよい、世の外に隠れてもよい、一人でもよい、半人でもよい、どうかよろずのこと、よろずの縁をなげすてて、仏祖の行持をそのままに行持してもらいたいのである。(451~452頁)
(2015年10月31日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――