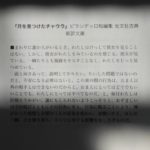読書ノート(2008年)全
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■ 四月十七日 伊東温泉伊東屋。
晴、うららかだった。
茅ヶ崎まで歩く、汽車で熱海まで、そこからまた歩く、行程七里、疲れた。
富士はほんとうに尊い、私も富士見西行の姿になった。
熱海はさすがに温泉郷らしい賑やかさだった、伊東も観光祭。
今日の道は山も海も美しかったけれど自動車がうるさかった。
山の水をぞんぶんに飲んだ、おりおりすべったりころんだりした。
旅のおもしろさ、旅のさびしさ。
・松並木がなくなると富士をまともに
・とおく富士をおいて桜まんかい
四月十八日 滞在、休養、整理
伊豆はさすがに南国情緒だ、麦が穂に出て燕が飛びこうている。
○伊豆は生きるにも死ぬるにもよいところである。
○伊豆は至るところ花が咲いて湯が湧く、どこかに私にふさわしい寝床はないかな!
大地から湧きあがる湯は有難い。
同宿同行の話がなかなか興味深い、トギヤ老人、アメヤクズレ、ルンペン、ヘンロ、ツジウラウリ。……
焼酎ひっかけてぐっすり眠った。
・なみおとのさくらほろほろ
・春の夜の近目と老眼とこんがらがって
・伊豆はあたたかく死ぬるによろしい波音
・湯の町通りぬける春風
四月十九日 雨、予想した通り。
みんな篭城して四方山話、誰も一城のいや一畳の主だ、私も一隅に陣取って読んだり書いたりする。
午后ははれた、私は行乞をやめてそこらを見物して歩く、淨の池で悠々泳いでいる毒魚。
伊東はいわゆる湯町情調が濃厚で、私のようなものには向かない。
波音、夕焼、旅情切ないものがあった。
一杯ひっかける余裕はない、寝苦しい一夜だった。
(伊東町)
・おなごやの春もにぎやかな青木の実
・まいにち風ふくからたちの芽で
・はるばるときて伊豆の山なみ夕焼くる
・こうして生きていることが、草の芽が赤い
4月二十日 快晴、下田に出立する。
川奈ゴルフ場、一碧湖、富戸の俎板岩、光の村、等々を横目で眺めつつ通りすぎる、雑木山が美しい、天城連山が尊い、山うぐいすが有難い。
風、風、強い風が吹く、吹きまくられつつ歩く、さびしい、つかれる。
赤沢あたりから海岸の風景が殊によろしくなる。茫々たる海、峨々たる巌、熱川温泉に安宿があるというので下って行ったが断られた、稲取へ暮れて着いて宿をとってほっとした、行程八里強。
・芽ぶくより若葉する湯けむりおちこち
・山路あるけば山の鴉がきてはなく
四月二十一日 谷津温泉、 一郎居。
しずかな、わびしい宿だった、花屑がそこらいちめんに散りしいていた。
昨夜のルンペン君と別れる、今生ふたたび逢うことはなかろう。
今日も晴れて風が吹く。
今井浜は伊豆舞子とよばれるだけあって海浜がうつくしい。
行程三里弱、午前中に谷津の松木一郎君を訪ねる、一郎居は春風駘蕩だ、桜の花片が坐(ママ)敷へ散り込む。
メロン、トマトを御馳走になる、それは君の手作りだ、内湯の御馳走は何より。
・うらうら石仏もねむそうな
四月二十二日
雨、ふと目覚めて耳を疑った。
ここはほんとうにあたたかい、もう牡丹が咲いて、蚊が出てくる。
温泉は湧出量が豊富で高温である、雑木山の空へ噴き上げる湯煙の勢いよさ。
△ △ △
朝湯のあつさよろしさありがたさ。
朝酒とは勿体なし。
ほんとうではない、といって、うそでもない生活、それが私の現在だ。
△洗濯、身も心も内も外も。
△花菖蒲の輸出。
△栖足寺の甕(銘は祖母懐、作は藤四郎)
四月二十二日〔続〕花時風雨多、まったくその通りの雨風だった。
熱い湯を自分で加減して何度も入浴する、奥さんが呆れて笑われる。
湯、そして酒、ああ極楽々々。
午后だんだん晴れる、一郎君といっしょに下田に向かう。
山蕗が咲きほうけている、ふきのとうが伸びて咲いて、咲きおえているのである。
○伊豆の若葉はうつくしい。
白浜の色はほんとうにうつくしかった、砂の白さ、海のみどり。
太平洋をまえに、墓をうしろに、砂丘にあぐらをかいて持参の酒を飲んだ。
至るところに鉱山、小さい金鉱があった、それも伊豆らしいと思わせた。
下田近くなると、まず玉泉寺があった、維新史の第一頁を歩いているようだ。
浜崎の兎子居に草鞋をぬぐ、そして二三子と共に食卓を囲んで話しつづける。
酔うて書きなぐる、いつもの私のように。
そして一郎君と枕をならべて熟睡。
伊豆は、湯はよいけれど水はよろしくない、温泉地のどこでもそうであるように。
伊豆に多いのは旅宿の立看板と隧道と、そしてバス。
・この木もあの木もうつくしい若葉
・別れようとして水を腹いっぱい
△天草を干しひろげる
△来の宮神社の禁酒デー!
四月二十三日 曇、 うすら寒い。
朝早く、二人で散歩する、風が落ちて波音が耳につく、前はすぐ海だ。
牡丹の花ざかり、楓の若葉が赤い。
蛙が鳴く、頬白が囀ずる。
弁天島は特異な存在である、吉田松陰の故事はなつかしい。
九時すぎ、三人で下田へ、途中、一郎君とわかれる、一郎君いろいろありがとう。
稲生沢川を渡ればまさに下田港だ、港町情調ゆたかであろう、私は通りぬけて下賀茂温泉へ。
留置の手紙は二通ありがたかった。
雑木山がよい姿と色とを見せてくれる。
下賀茂は好きな温泉場である、雑木山につつまれて、のびやかな湯けむりがそこここから立ち昇る、そこここに散在している旅館もしずかでしんみりとしている。
その一軒の二階に案内された、さっそく驚くべき熱い強温泉だ、ぽかぽかあたたまってからまた酒だ、あまりご馳走はないけれどうまいうまい。
兎子君が専子君を同伴して紹介された、三人同伴で専子居へ落ちつく、兎子君は帰宅、私と専子君とはまた入浴して、そして来訪のSさんと飲みだした。
今夜も酔うて、しゃべって、書きなぐった、湯と酒とが無何有郷に連れていってくれた、ぐっすりねむれた。……
ノンキだね、ゼイタクだね、ホガらかだね、モッタイないね!
・波音強くして葱坊主
・道は若葉の中を鉱山へ
・きょうのみちはすみれたんぽぽさきつづいて
・すみれたんぽぽこどもらとたわむれる
△黒船襲来、異人上陸で、里人は牛を連れて山へ逃げたそうな。
△黒船祭の前日。
四月二十四日 晴、后曇。
早朝、川ぶちの共同湯にはいる、底から湧きあがってくる湯のうれしさ。
湯けむりが白く雑木若葉へひろがってゆく、まことに平和な風景。
七時のバスで出発、松崎へ急ぐ。
峠のんzがめはよかった、山またやま、木という木が芽ぶいて若葉してかがやく。
バスガールと運ちゃんちの会話、お客は私一人。
九時松崎着、海岸づたいに歩く。
昨夜、飲みすぎたので、さすがの私も弱っている、すべってころんで向脛をすりむいた。
遠足の小学生がうれしそうにおべんとうを持ってゆく、私の頭陀袋にも、一郎君から貰った般若湯が一壜ある。
田子からすみれ丸に乗って沼津へ。
今夜は土肥温泉に泊る筈だったがその予定を変更したしたのである、だいたい私の旅の予定なんかあるべきでない、ゆきあたりばったり、行きたいだけ行き、留まりたいところに留まればよいのである、山頭火でたらめ道中がよろしいのである。ふさわしいのである。
凪で気楽で嬉しい海上の三時間だった。
沼津に着いたのは五時、ようやく梅軒を探しあてて客となる。
夜は句会、桃の会の方々が集まって楽しく談笑句作した。
・明けてくる若葉から炭焼くけむり
・山のみどりを分けのぼるバスのうなりつつ
・鴉さわぐしこは墓地
・水平線がうつくしい腰掛がある
・山の青さ海の青さみんな甲板に
(田子浦)
・そこらに島をばらまいて春の海
△さよなら伊豆よ
やって来ましたぞ駿河
△伊豆めぐりで
東海岸は陸から海を
西海岸は海から陸を鑑賞した
(『其中日記』抄 種田山頭火より 俳人 昭和十一年春)
『伊豆の國』第二集 温泉 木蓮社(107頁~115頁)2008年1月12日―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■フラーのプリセッション概念の意味 ~アカデミズムの真の理解~
フラーのクリティカル・パス(岡野注・フラーの著書の題名)は面白い。その中で、1827年にフラーが人生で破たんし自殺の直前まで追い詰められた時、つまりフラーが「自分には身を投げるか、あるいは考えるかしかなかった。」と考えた時、フラーはやることも無く、金も無く、できることと言えば、後は自分の頭の中で考えることくらいしかなかったのである。この時、彼が何をどう考えたのかという話が、第4章の「バックミンスター・フラーの自己規律」というものに描かれているのである。大分前に私がフランクリンの自己規律というのを話題にしたことがあったのであるが、フラーの自己規律も実に示唆的であり、実にユニークである。だから、この章にもいわゆる「ためになる教訓」に満ち満ちているように感じるのである。その中でも、私が非常に気に入ったものは、フラーが言うところの「プリセッション」(物理の日本語では、歳差運動と訳されているが、ここでの内容はもっと広い。)という概念の発見である。
フラーの言うプリセッションとは、次のような物理現象のことを意味している。例えば、水を円柱形の袋に入れて底面と頂点面を同時に圧縮する(引っ張る)と逆に側面の中央部は膨張する(収縮する)というような物理的な運動のことを言うのである。あるいは、太陽と地球の引力と円運動の関係のように、太陽から地球への引力は動径(半径)方向に働くが、円運動はそれとは垂直に行われる現象である。あるいは、上から下にあがるというような現象である。こういうように、一つの運動に対してそれとは直角の方向へ運動が起こる物理現象をフラーはプリセッションと考えたのである。もちろんこの意味では普通の物理で言うコマの歳差運動もプリセッションの一つである。つまり、重力によってコマが横に倒れようとするが、運動はそれとは垂直に行なわれてコマはぐるぐる歳差運動をして回るのであるから、フラーのプリセッションの一つであると考えられるわけである。こういった自然現象のプリセッションは力の方向に垂直に行なわれるのである。この場合、仕事は行われずエネルギーは保存する。力の方向に進めば摩擦も働き、エネルギーが減少するが、直角方向の運動は摩擦なく永遠に運動可能である。まさしく、磁場中の電子はこの原理によって永久運動するのである。太陽系の中の地球もこうして太陽の周りを回っているのである。そこで30代のフラーは考えた。果して人間社会のプリセッションとは何であるのか? 確かに,人間界においても社会の人間に力が働く方向(つまり、政治力や経済力と呼ぶものが働く方向)があるのである。人は名誉に突き進み、お金にむらがろうとするものである。当然、弱い人は強い人の周りを回って生活している。これは、自然界の力の構造と同じではないだろうか? だとすれば、それと直角に、つまり90度で運動するということも可能ではないだろうか?
さらにフラーは考えた。これは人間社会ではどういうことを意味するのだろうか? 多くの人間、普通の人間は家族のために生きる。あるいは会社や自分の置かれた組織のために生きるのである。つまり、これは力の場に沿った運動である。この方向では、力に引き付けられればそれは社会の流れに沿った方向であり、反発すればそれは社会に反する方向への運動にすぎないのである。もしそうであるならば、力に90度の生き方があるのなら、それはそうしたものではないはずである。つまり、だれもしないこと。言い換えれば、地球人全体のことを考えることではないだろうか? 誰か特有の個人、組織、国,民族のためではない、そんな方向がプリセッション運動ではないだろうかとフラーは考えた。
驚くべきことに、若いフラーはこのプリセッションの効果を証明するために「自殺するのではなく、自分のエゴを殺した。」のである。そして、以後50数年に渡ってこれを実証してきたのである。そのために、多くの友人や家族や親戚から無責任な人間と非難され続けたと言う。時には忠告に従って家族のために仕事をしたこともあった。だが、そんな時は自分の計画がとん挫し、すべてがうまく行かなくなったようである。そんな時は意固地になって自分の計画を推進したのである。しかし、不思議なことに、自分が必要とする時に必要なことが決まって現れ、自分の味方をしてくれたのである。そして、今日まで生き抜いてこれたのであるとフラーは言っているのである。
フラーはこの話をみつばちの話にして例えているのである。みつばちは花の蜜を見つけると、仲間にそのことをお尻を90度に振りながら8の字歩きをして伝える。これはあくまで自分の仲間のために行う利他的な行為である。しかし、実はこれが花に花粉を付けて受粉させる働きを持つのである。こうして、みつばちは知らず知らずのうちに植物の生育を助けているのである。
人間社会もそのようになっているのではないか。これは現在我々が「共生」と呼ぶ現象の本質を突いているいるように私は思うのである。もし花と共生するためにみつばちが何か花のためになることを自ら選んで仕事するとすれば、きっとみつばちたちは疲れ切ってしまうのではないだろうか? 花から見れば一見自分勝手に見えるのかも知れないが、みつばちはみつばちの世界のために利他的に行動しているのである。この行動が実はもっとも花を助ける行動に繋がるのである。そうやって自然はうまく両者を共生させてくれるわけである。だから、決してみつばちは花の奴隷でもなく、また花もみつばちの奴隷ではないのである。(114頁~116頁)
■包括的思考力、これが21世紀のキーワード
昨年末からフラー、カウフマンとずっと彼らの著作を見てきたが、私はだんだん物事の本質が理解できたと思うのである。つまり、我々の世界で今何が失われたかが分かってきたのである。それはフラーが言う「包括的思考力」、そして「感じる力」(感性を磨くこととも言える)が、既存の学校システム、科学教育システムにはまったくないということである。フラーやカウフマンはともに自分の感性と包括的思考に基づいて自分の世界を作り、この現実世界の謎に挑んできたのである。
しかしこれまでの科学、特に19世紀から20世紀にかけての科学というものは自分の感性を捨て去り、科学的知識と論理(ロジック)だけに基づくという還元主義的な方法で行ってきたのである。科学知識が膨大になればなるほどほじくり返す穴の数もその大きさも増えたのである。それが世に言う専門分野というものである。まあ、海の底に穴作ってそこに住む虫の類いである。そういう連中はもっと強い生き物の餌になる。つまり、体制側に住む連中の手足や餌になるのである。そして、ノーベル賞はその恩恵を賞したものと見ることもできる。
一方、フラーやカウフマン、古くはピタゴラスやソクラテス、近代ではショーペンハウエル、シュタイナー、モンテソーレ、マクレーンなどという人々は、もちろんそれぞれに自分の得意とする専門分野は持っていたのであるが、それ以外に非常に幅広く博識を持ち、包括的思考の大家でもあったのである。
それがどういうわけか、得られた科学知識の方にばかり人々の目が向き、これをもたらした大本の感性やら包括的思考力の方には目が進まなかったのである。要するに、一言で言えば物事が逆転し本末転倒になったのである。その結果、科学は一見進歩したように見えるが本質的なものを少しも解決できないという柔な科学に変質してしまったのである。
太古の昔、カルタゴのアルキメデスは博識と知恵で度重なるローマ軍の攻撃を撃退したという話がある。つまり、科学的思考がそのまま直接人々の生存に影響を与えた時代や命を救った時代があったのである。もちろん今でもそれはあることはあるのであるが、そのほとんどはどうでも良いものに変わってしまったのである。例えばハバードモデルで定理を一つ証明したところでこの世界の安定性にはまったく無関係なのである。数多くの論文が書かれたとしても、それで実生活に変革が行われるかというとそれはない。どうでもいいものであるからである。そういったものはあくまで科学者世界の就職証明書の類いに成り下がったというわけである。論文四つで博士号。論文20で助教授昇進。そういうレベルのお話であるからである。
我々は、この世界の謎を解きたい! 会社の上司のことはどうでもいい。その目的のためには何が必要か? これが問題というわけである。兼好法師も証言したように盛者も必衰の理がある。驕れるものも久しからずというものである。しかし、この目的のためには現代までの教育システムには重大な欠陥がある。それが、この包括的思考力を育む場がまったくないということである。知識は覚えたがばらばらのままである。英語も数学も覚えたがそれらは何の関係も無い。テストを受けたがそれは学校のためであり自分のためにはならない。学校の先生とてばらばらである。英語の先生にとって音楽は無関係である。数学の先生にとって社会学はどうでもいいことなのである。これでは、生徒や子供達は浮かばれない。子供にとって自分の親はどこかの会社の使い捨ての従業員でしかない。その会社を首になればそれでもう他の会社では使い物にならない。そういうことを見ていれば、子供がやる気をなくすのはあたりまえだろう。会社へ入れば学校で学んだことのほんの一部を使って夢の無い仕事をするだけとなれば、それでは、フリーター(=パートタイマー)、プー太郎の方が良く見えるのである。つまり、こういった現象のすべては還元主義に犯された脳の陥る病気なのである。心の隙間ができたかすかすの分断された脳の問題である。脳をいろんな経験で満たすのは実は非常に簡単なことである。それは自分の感性を信じて物事を包括的に考えることなのである。どうせ数学を学ぶなら英語で学んでみる。どうせ生物を理解したいなら物理学の立場で眺める。クロスリンクさせるわけである。
包括的思考を身につけさせるためには、「ゆとり」や「あそび」(遊ぶという意味のあそびではない。ここでは機械のあそびのあそびの意味だ。つまり一種のゆとり、ゆるみ、すきまの意味である)が必要なのである。どうやら世の教育関係者は頭にこの意味の「あそび」がないから文字通りの意味しか理解していないようである。「ゆとり」も「ゆっくりする」という意味であり、「あそび」も同じである。きっちりぎゅうぎゅう詰めになった状態には「ゆとり」も「あそび」もない。いくら授業時間を減らし科目を少なくしたところで、授業がぎゅうぎゅう詰めであったとしたら、「ゆとり」も「あそび」もなく包括的思考は生まれない。どんなギアもどんな精巧な機械もそれなりの「あそび」がなければうまく動かないものなのである。そのために潤滑油をつけるわけである。
フラーやカウフマンのはなしにもたくさんのエピソードが潤滑油になり散らばっている。それが「ゆとり」や「あそび」なのである。日本人の本にはそれがない。だから窮屈になり面白くなくなるというわけである。ノーベル田中さんの良さはここにある。変人ではあっても窮屈な人ではない。あそび心(何度も言うが、遊ぶという意味のあそびではない!)やゆとりの心が散見されるからである。こんな包括的思考を育む学校は生まれるのだろうか? 包括的思考を身に付けた人間しかできない相談だからかなり難しいだろう。しかしこういう人間が育たない限りこの世界の諸問題が解決しないことだけは確かなことである。そらはこの包括的思考力を日本の政治家は身につけていないから党利党則だけにこだわり国民のことまで頭がまわらない還元主義者の団体になってしまうからである。包括的思考力、これが21世紀のキーワードである。(201頁~203頁)
『フラーとカウフマンの世界』 井口和基著 太陽書房 2008年1月21日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■生きることをやめる土壇場になって、生きることを始めるのでは、時すでに遅しではないか。(12頁)(『道徳書簡集』セネカ)
■さあ家に帰ろう。そうして帰ったうえは、どうか交わりをやめ、世人との遊びを絶ちたい。世間と私とは双方からたがいに忘れ合おう。ふたたび車に乗って何を求めに行こうか。今は何の望みもない。親戚の情のこもった話を悦び、琴や書物を楽しんで憂いを消すのである。農夫は私に、もう春になったことを告げる。これから西の田に仕事が忙しくなろうとしているのだ。あるときは巾(きぬ)をかけて飾った車に命じ、あるときは一艘の舟に棹さし、うねうねとした深い谷川の奥をたずね、また高低のはげしい山路を通って丘を越えて行き、山水の美景をたのしむ。木々はよろこばしげに、枝葉がしげり花咲こうとしており、泉は滴りながら、はじめて氷がとけて流れ出ている。こんな春のいぶきを見て、万物がよい時節を得て、幸福そうな様子を、私は喜ぶのであるが、またそれに比べて私の生命がだんだん終わりになるのを思って心が動くのである。春が来て春が逝く、こうして人生は過ぎて行くのである。(14、15頁)(『陶淵明』星川清孝訳)
■青年のころから、私はこの四〇歳の時期を成功への努力の終点と決め、どんな種類のことにせよ、自分の望むことのできる限界と決めていた。この年齢になったら、そのときどんな境涯にあったとしても、そこから抜け出そうとじたばたするようなことはしないで、それからは行く末のことを心配せずに、その日その日を暮らしてゆこうと固く心に決めていた。ついにその時は来て、私はなんの苦痛も感じないで、この計画を実行に移した。(16~17頁)(『孤独な散歩社の夢想』J・J・ルソー)
■地上では、私にとってはすべては終わってしまった。善にせよ悪にせよ、人々はもう私に何もすることができない。私にはもうこの世で期待したり恐れたりすることは何一つ残っていない。……地上にある私はもと住んでいた惑星から落ちてきて別の惑星にいるようなものだ。(18頁)(『孤独な散歩社の夢想』J・J・ルソー)
■諸君は今にも死ぬかのようにすべてを恐怖するが、いつまでも死なないかのようにすべてを熱望する。(19頁)(『道徳論集』セネカ)
■自分自身の人生の利益を知るほうが、公共の穀物の利益を知るよりももっと有益なことである。最も重大な業務に最もてきしているきみの精神的な活力を、たとえ名誉はあっても幸福な人生にはなんの役にもたたない役目から呼び戻すがよい。そして考えてみるがよい。きみが若年のころから、学問研究のあらゆる修業で勉強してきたことは、巨大な量の穀物がきみの良好な管理に委ねられるためではなかったのだ。きみは何かもっと偉大でもっと崇高なものを自分に約束したはずである。(22~23頁)(『道徳論集』セネカ)
■おらゆる人間はあらゆる時代と同様に、今でもまだ奴隷と自由人とに分かれている、なぜなら、自分の一日の三分の二を自分のためにもっていない者は奴隷であるから。そのほかの点では、たとえ彼が政治家・役人・学者など何者であろうとしても同じことである。(25頁)(『人間的、あまりに人間的』ニーチェ)
■日本民族の絶滅とか人類の滅亡は大事件だけれど自分がまもなく死ぬのは大した事件ではない、と思いこんでいる人。こうした人を哲学的に分類すると「実在論者(realist)」と言えましょう。これに対して、――私のように――「自分が死ぬ」ことこそ何にもまさる大事件であり、人類の死も世界の滅亡もどこ吹く風という人々は「唯名論者(nominalist)」と称してよい。
説明すれば長くなりますが、かいつまんで言いますとこういうことです。中世以来の大論争なのですが、その論点は普遍概念に対応するもの(例えば、概念としての人間)と個物(個々の人間)とはどちらが「実在するか」という問いです。こう言うと「個々の人間が実在しているに決まっているじゃないか」と思われるかもしれませんが、それは考えを突きつめていないからです。(26頁)
〔もちろん現在の私(岡野)は実在論者です〕
■ところで、なぜ彼らが唯名論者と呼ばれるかといいますと、「普遍が実在する」と主張することが実在論だからで、この文脈で「個物のみが実在する」と主張することはすなわち「普遍はただ名だけだ」ということになり「唯名論」となるわけです。(29頁)
■ある経営学の本を書いていたときのことである。古典的業績を引用しているうちに、どうもそれにはタネ本ならぬタネ論文があるらしいことに気がついた。そこで、人気のない朝から大学の図書館の書庫に行き、お目あての論文をさがしはじめた。……棚にならんだ雑誌の背表紙を目で追いながら、ほこりをはらい、めざしている年をさがす。書架の下のほうにようやくそれを見つけて、しゃがみこんで手にとってみる。……その場で活字に目を走らせながら、ふと、私はあることに気がついて、背筋がぞくっとした。
「この論文は六五年ものあいだ、この瞬間をただひたすら待っていたんだ」
この論文はコピーをとられることはおろか、印刷されてから六五年間、一度も読まれた形跡がないのだ。……この論文はわたくしのようなような人間がどこからかやってくるのをただひたすら待っていたのである。著者はもう何十年も前に亡くなっている。……「ああ私の仕事とはこういうものだったんだ。この仕事に就いてほんとうによかった」と感慨でいっぱいになった。(105頁)(『できる社員は「やり過ごす」』高橋伸夫)
■私が専門の大家であるのは、蛭の脳髄に限るのだ。――それが私の世界なのだ!そして、それはまたれっきとした一つの世界なのだ!……なんと長いこと、私はこの一つのこと、つまり蛭の脳髄を追いかけてきたことか!ぬるぬるした真理を取り逃すまいと思って!ここに私の国があるわけだ!
――そのために私はほかのいっさいのことを投げ捨てた。そこで、私の知識のすぐ隣には、私の暗黒な無知がたむろしているということになった。私の知的良心は私が一つのことだけ知って、ほかのいっさいを知らないようにと要求する。およそ中途半端な知識の持ち主、おぼろげな者、はっきり決まらない者、のぼせて夢みごこちの者を見ると、私は嘔吐をもよおす。
私の誠実が終わるところでは、私は盲目だし、また盲目でありたいと願う。およそ知ろうとかかるかぎりは、かならず誠実でありたいと思う。つまり、過酷に厳密に狭く残酷に血も涙もなく。(107頁)(『ツァラトゥストラはこう言った』ニーチェ)
■哲学が教えるのは行なうことであって、語ることではありません。哲学が要求するのはこういうことです――各人は自己の方式にのっとって生活すること、言うことと生活が矛盾しないこと、さらに内なる生活そのものが自己のあらゆる行為と一つであって、色の違いがないことです。英知の最高の義務と証拠は、言葉と行為が調和を保つことであり、自己がどこにおいても自己自身を同等であり同一であることです。(116頁)(『道徳書簡集』セネカ)
■おもうに真に人間好きな人は、人間嫌いになるのが当然の成行きなのだろう。(131頁)(『いまなぜ青山二郎なのか』白洲正子)
■きみの意志の格律が、つねに同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ。(144頁)(『実践理性批判』カント)
■……一般的に言えば、宗教の誤りは危険であり、哲学の誤りはただ滑稽なだけである。(171頁)(『人性論』D・ヒューム)
〔芸術の誤りは、不快なだけである。岡野〕
■女性は一種類の記憶しかもたない。性的衝動や生殖に関連する記憶である。
恥を知るためには、それが意識されなければならない。羞恥心にもつねに分化は必要なのである。たんなる性的な存在である女性がなぜ非性的に見せかけることができるかといえば、性的そのものでしかないからだが(……)、それと同様につねに無恥である女性は、なぜ自分を羞恥の権化みたいに見せかけることができるかといえば、まったく彼女に羞恥心がないからである。(207、208頁)(『性と性格』O・ヴァイニンガー)
■女性は一人でいるときでもつねに他人と交際している。他人の影響を受けつづけている。女性はモナドではない。モナドならかならずやほかとの境があるはずである。女性は限界をもたない。(209頁)(『性と性格』O・ヴァイニンガー)
■……女性は存在せず、また存在を主張しようとしないから嘘を吐く。日常経験の事実だけしか言わない人間、内的判断形態をもたずに外的なものだけで判断する人間、すなわち存在しようとしない人間はかならず嘘を吐く。女性はどんなに客観的に真実を語っていてもつねに嘘を吐いている。(210、211頁)(『性と性格』O・ヴァイニンガー)
■……何かに打ち当たる迄行くという事は、学問をする人、教育を受ける人が、生涯の仕事としても、必要ぢやないでしょうか。あゝ此処におれの進むべき道があった!漸く掘り当てた!斯ういふ感投詞を心の底から叫び出される時、あなたがたは始めて心を安んずる事が出来るでせう。容易に打ち壊されない自信が、其呼び声とともにむくむく首を擡げて来るのではありませんか。既に其域に達している方も多数のうちにはあるかも知れませんが、若し途中で霧か靄のために懊悩していられる方があるならば、何んな犠牲を払っても、あゝ此所だといふ堀当てる所迄行ったら宜しからうと思ふのです。必ずしも国家の為ばかりだからといふのではありません。又あなた方の御家族の為に申し上げる次第でもありません。貴方がた自身の幸福のために、それが絶対に必要ぢやないかと思ふから申上げるのです。もし私の通つたやうな道を通り過ぎた後なら致し方もないが、もし何処かにこだわりがあるなら、それを踏潰す迄進まなければ駄目ですよ。――尤も進んだつて何う進んで好いか解らないのだから、何かに打つかる所迄行くより外に仕方がないのです。(231、232頁)(『私の個人主義』夏目漱石)
■そして、こうした無慈悲な「世間論者」の中心に親がいる。もしあなたが豊かな人生を送りたいのなら、親の言うことを一〇〇パーセント聞くことだけは避けねばなりません。親とは、(普通)子供たちが無事に人生を終えてくれることだけを願っている救いようのない人種です。英雄にならなくてもいい。警察のごやっかいにならずに健康で、きちんと定職について、できれば結婚し家庭をもって幸せに暮らしてくれればいい。つまり、幸せに死んでくれればいい。これが全国いや全世界の親(とくに母親)の願いでしょう。(236頁)
『人生を〈半分〉降りる』 中島義道著 ちくま文庫 2008年5月3日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ゲシュタルトの祈り
私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。
私はあなたの期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。
そしてあなたも、私の期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。
もしも縁があって、私たちが出会えたならそれは素晴らしいこと。
出会えなくても、それもまたすばらしいこと。
ウィキペディアの『ゲシュタルト』の項 2008年6月1日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ 1925年第一回の渡欧でヨーロッパ近代絵画から大きな刺激を受け、1928年の第二回渡欧でユトリロやスーチンの作品に深い感銘を受けた国吉は、やがて第二期に向う新しい傾向を見せはじめた。1922年にパリに戻っていたパスキンとの再開、また彼の手引きによるヨーロッパの近代絵画やエコール・ド・パリの作家たちとの接触は、国吉にとって教えられるところが多かった。それは国吉自身の後年の回想によって明らかである。
「私はフランスの近代作家から、とくに彼らのメディアムに対する理解の鋭さに感銘を受けた。あちらではほとんどの作家が対象から直接に描いている。それは当時の私の方法とは異るものであった。私はそれまではほとんど想像と過去の記憶から描いていたので、その方法を変えるのに苦心した」と、国吉は述べている。この頃より彼の作品に写実性が加わり、好んで女をモチーフにして描くようになった。(みづえ1975年10月号26頁)
ヤスオ・クニヨシ 祖国喪失と望郷 村木明 2008年8月14日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■反射機能について、いかに自分たちがうぬぼれているかを知るために、ちょっとこんなことを考えてほしい。あなたが昼飯に魚とポテトを食べたとして、これで髪をつくろう、あれで皮膚をつくろうと、それらを意識的に分けて体内に回しているわけじゃないだろう? 誰だって、自分がどうやって七ポンドから七十ポンドに育ったか、さらになったのか、そんなことを知っているやつはいない。これらはみんな、自動的におこなわれるのであって、これまでもそうしたわけだ。この地球上で、私たち全体を救ってくれているのも、こうした自動的な働きによるところがとても大きい。(44頁)
■シナジーとは、システムのなかの別々の部分、あるいはそうした部分の寄せ集めの振る舞いをバラバラに見ていても、決して予想できるような、そんなシステム全体の振る舞いを指すもので、こんなことを意味するのは私たちの言葉のなかでただひとつ、シナジーだけだ。(72頁)
■この難破船のなかの金持と評判の男の不動産、その純資産的価値の正当性などというものも、結局は「神の目から見た」正当性に戻って評価されねばならない、ということだ。どういうことかといえば、まず腕力と卑劣さと武力でもって土地の主権とかいうものが主張され、次に中身が道徳的かどうかはべつにして、とにかく主権国の武力で武装された法律というものがあって、それで守られた「合法的な」財産として、土地が合法的に再譲渡される。そしてそのあと抽象化されて、株券や債券といった紙に印刷され、ついには会社の資産になったということにすぎない。(88頁)
■富というのは、代謝的(メタボリック)、超物質的(メタフィジカル)再生に関して、物質的に規定されたある時間と空間の解放レベルを維持するために、私たちがある数の人間のために具体的に準備できた未来の日数のことだ。(89~90頁)
■シナジェティクスは富というものがなにを意味しているのか、そのことを明らかにする。富とは未来に向かってエネルギーの再生がうまくいくようにする私たちの能力であり、自分からなにかを始め、干渉されずに行動していく自由度を高めていく私たちの能力でもあり、つまりはサイバネティクス的にいえば、これらは物質的なエネルギーと超物質的(メタフィジカル)なノウハウというふたつの主要部分に分類できる。そしてこの物質的なエネルギーの方は、さらにふたつの交換可能な相に分けられる。連合と分離だ。エネルギーは連合して物質となり、分離して放射となる。(92頁)
■ところが突然、光が私たちのもとに届くには、太陽からなら八分間、太陽の向こうの最も近い恒星からなら二年半、ほかの恒星からなら何年もかかるということが発見された。この今の瞬間に存在すると考えられていた多くの星が、数千年も前に燃え尽きたものであることを、私たちはたかだか3分の二世紀前に知ったにすぎない。宇宙は同時的なものではない。(94頁)
■ほんとうの富は勘定ができないほど、容赦なくシナジー的に増えて、それを享受する人間の数もみらいの日数もつねに増え続けていったから、その結果、人類の一パーセント以下がなんとか健康で快適に生き延びられるという状態から、今世紀になって、人類の四四パーセントが、以前には経験することも夢見ることもできなかったような標準生活を生きられるようになった。このまったく予想もできなかったような成功は、たったの三分の二世紀で起こっている。しかしその間、世界の人口一人あたりの金属資源は減り続けていったにもかかわらず、だ。それはどっかの政府か企業が意識して、特別に試みて起こったことではない。人間がより少ないものでより多くのことをどんどんやっていく方法を、それと気づかずシナジー的に身につけはじめたからこそ、こんなことが起こったわけだ。(100~101頁)
■物質的な資源についていえば、つい最近まで、人間は自分たちが知っている材料からしか建築や機械やその他の製品をつくれないと思ってきた。過去にも時々、科学者たちは生産技術の展望を大きく変えるような新しい合金を発見してきた。しかし今日では航空宇宙工学の分野を見ればわかるように、科学者たちは超物質的(メタフィジカル)な能力を発達させ、ユニークな素材を完全に「注文通り」つくりだすところまできている。こうした新素材は、これまで宇宙に存在することが知られていたどんな物質にもまさって、あらかじめ指定した物理特性をまんぞくする。だからこそ、再突入に必要な円錐頭(ノーズコーン)は開発できた。人間を乗せて、ロケットで打ち上げられた人口衛星が、地球に再突入する際の円錐頭(ノーズコーン)だ。シナジーは本質に関わる。社会全体が緊急事態だと私たちが表明し、そんな圧力がかかるときのみ、今までに代わる効果的で適切な技術戦略がシナジー的にあらわれる。このとき、心は物質を支配し、主権国家の国境の地理的局所性だけにへばりついていた限界から、人類は逃れていくのだ。(103~104頁)
■「おまえ」とか「おれ」にかじりついて、生存のために闘う必要がないという意味での自由でもあり、だからお互いに信頼しあい、自発的に、また論理を重んじて、人は自由に協力していけるようになるだろう。(109頁)
■一家の生活は苦しかった。シカゴのスラムの安アパートに住み、隣りはアル・カポネのところの殺し屋だった。フラーは妻子を妻の実家に帰し、自分は自殺することを考えた。「乳飲児を抱え、もじとおり一文無しだった。私は自分に言い聞かせたんだ。最善を尽くしたのにうまくいかなかった。たぶん私の能力が足りなかったんだ。みんなそう思っているらしいし、実の母親でさえ、いつも私のことを能無し呼ばわりしていた。きっと母親の言うとおりなんだ、とね。」(ロナルド・グロス著『アメリカ流クリエイティブ・ライフ』紀田順一郎訳、TBSブリタニカ)ある晩、フラーは一人アパートを出ると、ミシガン湖畔まで歩いていった。カナダ側から激しい風が吹きつけており、波が彼の足を洗った。このまま死んでしまおうか?しかし、彼は思いとどまる。そして決心した。「人は自分自身で考えねばならない。もう一度、自分だけでこの宇宙と向かい合ってみよう。自分の言葉で、自分の経験だけを信じて、もう一度宇宙を見直してみよう」。自殺の代替案として、自分のコスモロジーの構築を思いつくとは驚きである。彼はその後二年間かけて、自分が本当に信じられる宇宙像をつくりあげていった。(156頁)
■ 私は地球で生きている。
けれども私が何者か、今も自分でわからない。
カテゴリーなんかでないことは、
それでもちゃんと知っている。
私は名詞なんかじゃない。
どうやら私は動詞のようだ。
進化していくプロセスだ。
宇宙の積分関数だ。(184~185頁)
■題名の『クリティカル・パス』とはオペレーションズ・リサーチ(OR)の用語で、作業ネットワーク中、プロジェクトの完了時間を左右する重要な作業経路のことをいう。あるプロジェクトを最短時間内でうまく達成できるかどうかは、このクリティカル・パスのデザインにかかっている。フラーはこの大著で、人類社会を一気に次のステージまで進めるためのクリティカル・パスを提案しようとしたのである。(186頁)
『宇宙船地球号操縦マニュアル』バックミンスター・フラー著 芹沢高志訳
ちくま学芸文庫 2008年10月30日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「シナジー」とは、「部分または、その部分を構成するどんな下位にある部分を考察することによっても予測できない全体として達成された機能」と定義される。「シナジー」の具体例として、フラーはクロム・ニッケル鋼という合金を好んで引用した。その合金は、合金を構成する最も弱い部分の十倍、最も強い部分の六倍の引っ張り強度を示した。合金の引っ張り強度は、各構成要素の引っ張り強度の総和よりもはるかに大きい。(107頁)
■六本の同じ長さのストラット(支柱)から、二つの三角形ができる。しかし、シナジー的な配置にすれば、同じ六本のストラットは、四つの三角形からなる一つの正四面体を形成する。そこには思いがけないシナジー効果が存在する。四面体の内部に体積(領域)が得られることによって、宇宙は、四面体の内側にある宇宙と外側にある宇宙、さらに宇宙という概念を最初に分離する二文法のシステム(ビット)という、そのどちらにも入らない部分が形成される。このような方法で結合することによって得られる莫大な利益を暗示するものは、ストラットという物質や三角形という形態にはまったく存在しない。構成要素間の関係の変化だけが、この飛躍的な効率をもたらした。フラーは、四面体が宇宙における最小限の「システム」であるとみなした。(107頁)
■テンセグリティー 「個体」は存在しない!宇宙に「物」は存在しない!ーRBF フラーは講演で、非常に力を込めた声でこう主張した。「どんな規模であれ、宇宙は、張力の海に浮かぶ圧縮力の島々によって構成されている」と強調した。恒星や惑星は、引力という孤立した島々である。断面積がゼロでありながら、その重さのない引力という「ケーブル」によって、常に要求される強度を正確に保持して、月は地球とつながっている。原子間における相互の距離は、惑星間における相互の距離と相対的に同じになる。宇宙のあらゆる事象は、他の何かと実際に接触した状態で存在していない。物質とはすべてエネルギーであり、角度と振動数によって秩序づけられている。(118~119頁)
■また、フラーはフェミニストたちをも苛立たせた。性差に関するフラーの次のような見解を認めない者もいた。「テンセグリティー構造における圧縮部材のように、男性は不連続的な存在であり、行ったり来たりひとつの場所に定まることがない。卵子を宿す女性は、生命の再生において張力部材のように連続的である。女性は、子供や老人と連れ添ってとどまる傾向がある。男性が獲物や糧をもたらすと、女性がその獲物を無駄にしないようそれを飼うのか、皮を剥ぐのか、乳を搾るのか、乗り物として利用するのか、食料とするのかといったことを決定した、女性の果たしてきた役割こそが、人類史における初の産業化だった」。(132~133頁)
■「真実」とは特別な場合(special cases)である。「真理」とは、一般化された原理を表現したものである。「神」とは、すべての「真理」をシナジェティックに統合した存在である。(134頁)
■身長をお金で調節することはできない。人間だけがお金を必要とする。自然法則の支配する物理的な成功には、お金は介在しない。ーRBF(312頁)
■「生活費を稼ぐ必要はない」。この断言に、聴衆が唖然とするであろうことはフラーにはわかっていた。それを「働く必要はない」という意味に解釈した非現実的な者もいた。フラーは、けっしてそのような意味で言ったのではなかった。職業は十分にはないのかもしれないが、仕事は常に限りなくある。(312頁)
■その解決策にはコストがかかりすぎるという異議(必ずあろ反応)には、「これを実行〈しない〉場合には、どれくらいの損失が発生するか」と訪ねるとよい(これはフラーが好んだ質問のひとつだった)。その答えが本当のコストだ。競争が起きた場合には、「自分の目標は包括することであり、独占することではない」ことを思い出すべきである。また、「効率の悪いデザインを積極的に陳腐化することは、競争原理に基づいた攻撃ではない」ということも重要である。(314頁)
■そして最後に、忍耐が必要である。プロジェクトは連鎖的に波及していく。これまでにも述べてきたように、革新的な仕事には独自の懐胎期間がある。懐胎期間でさえ加速度的である。しかしバラのつぼみをドライバーでこじ開けるようなことをしてはならない。仕事を立派に終えたならば、あなたの発見は、それが最も包括的で効果的となる状況の中でゆっくりと、しかし必然的に機能していくだろう。「正しければ、問題なく先に進むことができる。勇気づけられるのはこのときだ」とフラーは述べた。フラーにはその勇気が確かにあった。プロジェクトの妨げとなったダイマクシオン・カーの衝突やモントリオール・ドームの修復工事中の火災、そして権力の介入によるエネルギー自律型のバイオ・シェルターへの破壊行為といったものを、フラーは、ある種の不運ではなく、むしろ成功を確固たるものとする、自身の哲学に対する試金石であると見なしていた。フラーの人生は時折、旧約聖書に登場するヨブのようであるが、フラーが歩調を弛めることは決してなかった。(314~315頁)
『バックミンスター・フラーの世界』 ジェイ・ボールドウィン著 梶川泰司訳
美術出版社 2008年11月1日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■高校時代にやったことがもう一つあった。それは問題や定理を発明することだ。つまりどうせ数学をやっている以上は、これを利用できるような実際例を考えだすのである。僕は直角三角形に関する問題をひと組発明したが、このうち第三辺の長さを求める問題では、二辺の長さがわかっていることにする代わり、二辺の差がわかっていることにした。この典型的な例をあげると、まず旗竿があって、そのてっぺんから綱が下がっている。この綱を垂直に下ろすと旗竿よりも3フィート長い。今度は綱がたるまないよいに横に引っぱってみると、竿の根元から5フィート離れたところまで来るものとする。この旗竿の高さは何フィートあるか?(18~19頁)
■MIT時代、僕はいろいろないたずらをするのが好きだった。あるとき製図のクラスで、一人の学生が雲形定規(変てこな波形で、曲線を描くのに使うプラスチックの定規)を取りあげて、「この曲線に何か特別な公式でもあるのかな?」と言った。僕はちょっと考えてから「むろんだよ。その曲線は特別な曲線なんだから。そらこの通り」と雲形定規をとりあげて、ゆっくり回しはじめた。「雲形定規って奴は、どういう風に回しても、各曲線の最低点では、接線が水平になるようにできてるんだよ。」
こうなるとクラスの連中が、一人残らず自分の定規をいろいろな角度に持ち、この一番低い点に鉛筆をあてて回しはじめた。そして確かに接線が水平だということにはじめて気がついたのである。みんなこの「発見」に沸き立ったが、誰もがとっくにかなり進んだところまで微積分をやっていて、「どんな曲線についても、極小点(最低点)での導関数(接線)はゼロ(つまり水平)である」ということは知りぬいているはずなのだ。ただそれを実際に当てはめてみることができなかっただけだ。言うなれば、自分の「知っている」ことすら知らなかったということになる。(43~44頁)
■人はよく僕のことをふざけた奴だと思っているらしいが、僕はだいたい正直なのだ。ただ正直であるその在り方が人と違うおかげで、信じてもらえないことがしょっちゅうなのだ。(52頁)
■催眠術をかけられるというのはなかなか面白いものだ。僕たちは「できるけどやらないだけのことさ」といつも自分に言いきかせているわけだが、これは「できない」というのを別な言葉で言っているだけのことなのだ。(104頁)
■高等学術研究所が僕という男をそれほど買いかぶったって、それは僕の罪ではない。そんな期待に沿うなど、どだい無理な話だ。明らかにまちがいだ。向こうがまちがっていることだってありうるのだと思いついたとたんに、僕はこの考えがそっくりそのまま、職の話を持ちかけてきたほかのところにも当てはまるのに気がついた。今勤めているこの大学ですら然りだ。自分は自分以外の何者でもない。他の連中が僕をすばらしいと考えて金をくれようとしたって、それは向こうの不運というものだ。(308頁)
■僕はまた他のことも考えはじめた。前にはあんなに物理をやるのが楽しかったというのに、今はいささか食傷気味だ。なぜ昔は楽しめたのだろう? そうだ、以前は僕は物理で遊んだのだった。いつもやりたいと思ったことをやったまでで、それが核物理の発展のために重要であろうがなかろうが、そんなことは知ったことではなかった。ただ僕が面白く遊べるかどうかが決め手だったのだ。高校時代など、蛇口から出る水がだんだん先細りになっていくのを見て、そのカーブが何によって決まるのかを考え出すことができるかなと思ったことがある。これをやるのは簡単だった。僕が別にそれをやらなくたって痛くも痒くもない。もう誰かがとうにやってしまったことだし、別に科学の未来に役立つこともことでも何でもないが、そんなことはどうでもよかった。僕はただ自分で楽しむためにいろんなことを発明したり、いろいろ作ったりして遊んだだけの話だ。(309頁)
■今でも覚えているが、ハンス・ベーテのところに行って「おいハンス、面白いことに気がついたぞ。皿がこういう風に回るだろう? それでこれが2対1だという理由はだ……」とばかり僕は彼に加速の計算をして見せた。
するとハンスは「なかなか面白いじゃないか。だがそれは何の役に立つんだね? 何のためにそんな計算をやったんだい?」ときいた。
「なに別に何の役にも立たないよ。面白いからやってるだけさ。」僕は物理学を楽しむだけのために好きなことをやるんだと決心していたから、このときのベーテの反応はちっとも気にならなかった。
ー中略ー
こうなると努力なんぞというものはぜんぜん要らなかった。こういうものを相手に遊ぶのは実に楽なのだ。びんのコルク栓でも抜いたようなもので、すべてがすらすらと流れ出しはじめた。この流れを止められるものなら止めてみよと思ったぐらいだ。そのときは何の重要性もなかったことだが、結果としては非常に大切なことを僕はやっていたのだ。後でノーベル賞をもらうもとになったダイアグラム(ファインマン・ダイヤグラム)も何もかも、僕がぐらぐらする皿を見て遊び半分にやりはじめた計算がそもそもの発端だったのである。
『ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)』 R.P.ファインマン著 大貫昌子訳
岩波現代文庫 2008年11月2日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■それにしても、マッハの〈現象学〉の概念を継承したフッサールがその〈思考経済説〉を拒否したのは幾分奇異に思われましが、これには世紀転換期の特異な時代風潮が関わっているように思われます。この時期、一種の〈純粋主義〉が流行します。純粋詩・純粋小説・純粋芸術・純粋持続・純粋経験・純粋意識・純粋言語・純粋論理学・純粋経済学・純粋法学など、数えあげればきりもありません。そこにはさまざまな動機が働いていたようですが、その一つとして、H・スペンサー以来進化論と連動しはじめた功利主義・自然主義・相対主義に対する反撥がありました。これはつきつめれば生(レーベン)の生ぐささに対する反撥です。その生ぐささは、工業化都市化の進行とともに生じた都会の汚濁にも重ね合わせて感じられていたにちがいありません。そうした汚れた日常的現実を打ち破って、その底に真に〈現実的な現実〉をもとめようという志向がさまざまな〈純粋主義〉となって現われたように思われます。フッサールが思考経済説を否定して〈純粋論理学〉をもとめるその努力にも、そうした志向が働いていたにちがいありません。(92~93頁)
■1924年になってからのことですが、ウィーン大学でマッハやボルツマンの後任として〈帰納的科学の歴史と理論〉の講座の教授になっていたモーリッツ・シュリック(1882~1936年)が中心になって、哲学者と自然科学者による気軽な討論会がはじめられました。その参加者20人が1928年10月に〈エルンスト・マッハ協会〉を結成します。彼らはマッハの現象学に厳密性を与えようとして、討論の基本的テキストにウィトゲンシュタイン(1889~1951年)の『論理哲学論考』[1922年]を選びました。この会が翌年オットー・ノイラートの発案で〈ウィーン学団〉と名前を替え、ライヘンバッハを中心に同じ頃結成されたベルリンの〈経験哲学協会〉と合同で、1929年にプラハで「精密化学の認識論」を討議する会合を催し、翌30年から雑誌『エアケントニス(認識)』を刊行しはじめます。ベルリン・グループをも包摂したこの広義の〈ウィーン学団〉の思想は、『科学的世界把握ーウィーン学団』というその宣言書にうかがわれます。
「輓近(ばんきん)の経験主義および実証主義を、方向においていっそう生物学的
-心理学的であった初期の形態から区別するものは、論理分析の方法である」
(ノイラート『経験主義と社会学』[1973年]。野家啓一『無根拠からの出
発』勁草書房、1993年、21ページの引用による)。
ウィーン学団は、マッハの「生物学的-心理学的」実証主義を捨て、ラッセルとウィトゲンシュタインによって展開された〈論理的原子論〉を根底に据えた〈論理実証主義〉を採ったのです。メンバーには、ほかにルドルフ・カルナップやカール・ポパー、クルト・ゲーデルらもくわわっていました。そして1930年代にカルナップらの亡命とともに論理実証主義はアメリカに移植されます(「シカゴ学団」)。(97~98頁)
■ここでウィトゲンシュタインの念頭にある〈現象学〉が、当時すでに一派をなしていたフッサールのそれでなく、マッハのそれであることは、こんなふうに〈現象学〉と〈文法〉とを等値した上で彼か、
「マッハが思考実験と呼ぶものは、もとよりなんら実験ではない。それは結局は
文法的考察である」。
と、マッハに言及していることからも明らかです。彼の後期のいわゆる〈文法的考察〉や、結局はその具体的遂行である〈言語ゲーム理論〉もが、マッハの〈現象学〉につながるものであることは明らかです。(100頁)
■『チャンドス卿の手紙』については、ドイツ文学の松本道介さんが、この作品はホーフマンスタールにおける印象主義から表現主義への転換を指標する作品として読むべきではないかと主張した「ホーフマンスタールと表現主義」(『陽気な黙示録』中央大学人文科学研究所、1994年、所収)という刺激的な論文を書いておられます。松本さんは、ここでホーフマンスタールに起きた変化を、「世界の外にいて、あるいは世界の上にいて世界を眺める姿勢から、世界の中に身をおく人間としての姿勢、世界と一体化できる人間の姿勢への変化」といちおう規定しながらも、そうも言いきれない微妙な、だが本質的な変化だと付けくわえられています。(102~103頁)
■さらによく1907年1月12日付でフッサールがホーフマンスタールにしの訪問に対する礼状を書いているのですが、その手紙のなかでフッサールはホーフマンスタールの説く反自然主義的な詩人の美的直感と、「あらゆる実在的な態度を遮断する」自分の「純粋に現象学的な精神態度」とには深く通底するものがあると書いています。(104頁)
■「可能的なもの」は「いまだ目ざめぬ神のもくろみをたっぷり抱えこんでいるもの」だとさえ言われています。これに近い考えが、ムージルにはギムナジウム時代からあったものらしく、当時書いた愛国心をテーマにした作文のなかで、「おそらくは神もまた、この世界について可能の接続法で語るのをもっともこのむであろう。〔……〕というのも、神は世界を作りながら、この世界は別様でもありうるだろうと考えているのだから」と書いているそうです(大川勇「可能性感覚の射程」、前掲『ムージル 思惟する感覚』所収、299頁)。この大川さんも書いているように、むろんこれはライプニッツの『弁神論』を裏がえした考え方ですが、一方、ムージルのこの〈可能性感覚〉にはフッサールの〈本質直感〉に近いものも感じられます。フッサールの言う〈本質〉というのも、現実的なものが生起してくる際にのっとるべき規則のようなものであり、彼はこれを、ゆるしがたいものとされる現実を相対化するための手段として使っているのです。後期の『デカルト的省察』[1929年]においても、フッサールは自分の〈現象学〉を、「純粋な可能性(純粋な表象可能性、純粋な想像可能性)の領域のうちに身を置くア・プリオリな学、……つまり超越論的存在の現実性についてではなく、むしろそのな可能性について判断し、そうすることによって同時に、もろもろの現実にア・プリオリな規則を予示するような学」[『フッサリアーナ』第一巻、56頁]と規定しています。彼の言うア・プリオリな本質の領域とは、ムージルの言う「いまだ目ざめぬ神のもくろみ」に当たるようです。
しかし、もう一方で、ムージルの言う〈可能的なもの〉には、マッハやゲシュタルト心理学者たちの言う〈ゲシュタルト〉を思わせるところもあります。マッハの思想は実証主義とは言われるものの、かっして固定された経験的所与にぴったりと埋めこまれた、いわゆる〈くそリアリズム〉ではありません。彼の言う〈感覚的諸要素〉はさまざまな関数的連関に組みこまれ、さまざまなゲシュタルトのうちに現われることのできるものです。しかも、このゲシュタルトに必然性はありません。マッハも図と地とが交替する反転図形を話題にしています(『感覚の分析』、前掲訳書、173頁)。ゲシュタルトもまた「偶然でコンベンショナル」なものなのです。『特性のない男』の遺稿となった部分にこういう箇所があるそうです(早坂七緒「ムージルの〈可能性感覚〉の誕生」、前掲『ムージル 思惟する感覚』所収、332頁の引用による)。
「もしわれわれを現実に適応させる感性に代わって、別の感性が勢力を占めるな
らば、われわれは単に変化する世界像についてのみでなく、また別の世界につい
ても話すことがゆるされるだろう」。(111~113頁)
■ムージルはかって同級生であったヴォルフガング・ケラーの仕事に絶えず注意を向けていたらしく、ケーラーの『物理的ゲシュタルト』[1920年]が発表された直後にも、「どうしようもないヨーロッパ、もしくはあてどのない旅」というエッセイ[1922年]の一節でこれにふれています。
「現代が哲学をもっていないわけは、現代が哲学を創造できないためというよ
り、むしろ、現代は、事実に合わない申し出を拒絶するがためである。(実例の欲
しい方は控え目に自然哲学的試みと銘打たれた書物、若きベルリンの哲学者、ヴ
ォルフガング・ケラーの『静止と恒常状態における物理的ゲシュタルト』を読ま
れるとよい。そして、それを理解されるだけの知識をおもちの方なら、きっと事
実についての科学の次元から、太古の形而上学的難問の解決が暗示されているこ
とに気づかれよう)」(『ムージル著作集』第9巻、田島範男、長谷淳基訳、松籟
社、1997年、128頁)。
ムージルの創作活動が、マッハ、フッサール、ケーラー、コフカらの織りなす世紀転換期オーストリアの思想圏で営まれていたことは明らかなようです。(114~115頁)
■ジョージ・スタイナーが名著『ハイデガー』の新版[1989年](生松敬三訳、岩波同時代ライブラリー、1992年)に付した「新たな序論」(この部分だけ木田元訳)で、この時代の思想的雰囲気にふれて実に興味深いことを言っているので、それを紹介しておきたい。彼はそこで、第一次世界大戦の1928年から1927年までの10年間に、「その分量と文体の極端さから書物以上の書物とも言うべきもの」がはんダースもドイツで出版されたと、言い出すのである。
ー中略ー
スタイナーに言わせると、それはまず、これらがすべて大冊だということである。これは偶然ではない。これらの書物はすべて全体性を目指し、「利用可能なすべての洞察の集大成(スンマ)を提供しようとする企て」だからである。
次に、これらの書物はみな、ある意味で黙示録的である。つまり終末論的であり、予言的である。「この世の終わりをしるしづける最後の出来事」に訴えかけ、来たるべき新たな世界についての予言をふくんでいる。
ー中略ー
こうして、現存の世界の終末を宣言し、新たな世界を予言するこれらの著作においては、当然言語の過激な革新が企てられる。第一次世界大戦のあの惨禍のあとで、ブルジョワ社会で使い古され擦りきれた偽りの言葉で語ることなどどうしてできようか。そこでは、言語を過激なかたちで新たなものにしようと企てられるのである。ー中略ー……スタイナーはこう要約する。
「要するに、第一次世界大戦後のドイツ語は、他のいかなる言語よりもいっそう
意識的に、いっそう暴力的に、また事実上ダダの影響――時代の絶望と希望とを
表明しうる人類の新たな言語をもとめるその絶望的な呼びかけの影響――を受け
てきたそれなりの流儀で、過去との断絶をもとめているのである。特に可動的な
構文法を賦与され、語や語根をほとんど意のままに砕いたり融合させたりしうる
可能性を賦与されたドイツ語は、刷新の誘因として、過去のものとしては隠者た
ち、つまりマイスター・エックハルトやベーメやヘルダーリンを選び、現代のも
のとしては、超現実主義(シュルレアリスム)や映画のような革新運動を選んでい
るように見える。『救済の星』やブロッホのメシア信仰的著作群、バルトの聖書
解釈学、そしてなかんずく『存在と時間』は、もっとも革新的な性格の言語活動
である」(前掲訳書、7~8頁)(129~132頁)
■もともとアリストテレス研究者として出発したハイデガーは、アリストテレスのテキストや中世スコラ学者によるその注釈書を丹念に読み解き、さらにデカルト、カントら近代の哲学者のテキストを読み進むうちに、西洋哲学史にはプラトン/アリストテレス以来〈存在〉を〈被制作性〉と見る、つまり〈ある〉ということを〈作られてある〉と見る特殊な存在概念が、さまざまに変様されながらも一貫して承(う)け継がれ、これが西洋文化形成の基底にすえられているということに気づいた。
ハイデガーはこの西洋哲学の歴史を、ニーチェに教えられたもっと壮大な視野のうちに据えて相対化しようとする。プラトン/アリストテレスよりももっと早い時代の〈ソクラテス以前の思想家たち〉の書き残した断片を見ると、この時代のギリシャ人は〈存在〉を〈生成〉と、つまり〈ある〉ということを〈なる〉ことと見ていたことが分かる。それと対比して、西洋哲学を貫く」〈存在=被制作性〉という存在概念がかなり特殊なものであることを明らかにし、それを相対化しようとするのが、『存在と時間』第二部の課題であり、この本はまずこの部分から発想されたのである。
次いで、この歴史的考察の視座を確保するために、さまざまな〈存在概念〉のもつ〈時間的性格〉を解明する、つまり〈存在〉と〈時間〉の関係を問う第一部第三編が構想されたにちがいない。第一部第一、二篇での人間存在の分析はそのための準備作業として、しかも先ほど見たような敗戦後の実存哲学的雰囲気と時代の終末論的気分とに多分に促されながら、最後にあわただしく構想されたと見てよいであろう。
そして、第一部第三篇でハイデガーは、〈存在=被制作性〉と見る存在概念が、自分自身の死から眼をそらし、眼前の事物との交渉に没頭して生きる人間の〈非本来的時間性〉を場として形成されるものであり、〈存在=生成〉と見る存在概念こそ、自分の死を直視し、それに覚悟をさだめて生きる人間の〈本来的時間性〉を場として形成されるものであることを明らかにするはずであった。
しかも、これを明らかにした上での彼のねらいは、〈存在=被制作性〉という存在概念を基底に据え、自然をも制作のための無機的な材料と見る〈物質的自然観〉の上に立って形成されてきた西洋文化――いまや巨大な技術文明と化し、はっきりその行く末の見えてきた西洋文化――を転換するために、もう一度〈存在=生成〉と見、自然を生きて生成するものと見ていたかっての存在概念を復権し、文化形成の方向を転換しようとするところにあった。そのためには、人間をその非本来的な在り方から本来的な在り方に立ちかえらせる必要がある。といっても、一人や二人の人間がその生き方を変えてみたところで、どうなるものではない。だが、ひょっとして世界史を領導する一つの民族が全体として本来生に立ちかえるようなことが起これば、話は違ってくる。(136~138頁)
『木田元の最終講義』 木田元著 角川ソフィア文庫 2008年11月3日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■科学がもともと「分化の学」ないしは「百科の学」を意味する言葉として使われ始めた事実を踏まえるならば、「科学」は知識を表わすサイエンスの訳語ではなく、個別諸科学を表わす複数形のサイエンシーズ(sciences)の訳語だと言わねばならない。先に、科学はサイエンスの訳語に非ずと述べたゆえんである。(38頁)
■クーンの「パラダイム」という概念は、まさにサイエンスからサイエンシーズへの知識体系の変化、すなわち科学の専門分化と密接に関わっている。クーンによれば、個々の専門分野は「パラダイム」、すなわちその領域の研究活動を特徴づける模範例となる科学的業績を獲得することによって初めて、「科学」として自己を確立するのである。したがって、ある研究分野が「科学」であるかどうかを判定する基準は、そこに「パラダイム」が見いだせるかどうかにかかっている。クーンが「何が科学であるか」という質問に答えを出せなかったのも、個々の研究分野ににおいていつの時点で「パラダイム」が成立したかを確認するには、綿密な歴史的考察を必要とするからである。また、社会科学に「何かあやしげな感じがつきまとっている」のも、この分野における「パラダイム」の存在がいまだ不明確だからにほかならない。(38頁)
■すなわち、明治期にわが国に輸入されたのは、自然哲学を背景とした統一的な知の体系(コスモロジー)としての科学であるよりは、すでに専門分化して哲学やコスモロジーから切り離された個別諸科学であり、さらには科学とテクノロジーとが融合して産業政策に組み込まれた「産業化科学」(ラベッツ)であった。このことは日本の近代化(=工業化)を推進する大きな力となると同時に、多面で基礎科学を軽視し応用化学を重視する一般的風潮を生んだ。大学の中に「工学部」を設置したのはわが国が世界最初であった(1886)ことや、現在でも理学部と工学部学生数の比率は1対7と著しく偏っている(アメルカではほぼ1対1)という事実が、それを端的に物語っている(村上陽一郎『文明のなかの科学』1994による)。われわれにとってはありふれた「科学技術」という言い方そのものが、他の西欧語に対応する語を見つけるのが難しい日本語特有の言葉であり、わが国の科学受容のあり方が生み出した概念なのである。(40頁)
■現在では「コスモロジー」という言葉は、二つの異なった意味で使われている。一つは物理化学が探求の対象とする「宇宙論」であり、もう一つは文化人類学的な意味でのコスモロジーである。後者は大は宇宙像から小は儀礼、タブー、祭りなどわれわれの生活様式を秩序づける慣習や習俗をも含んだ、人間の生き方を統御する包括的な図式であり、むしろ「世界観」と呼ぶのがふさわしい。(45頁)
■16、17世紀に起こった大文字の科学革命は、コイレが指摘するように、この古代・中世的コスモスの大規模な解体過程であった。そのきっかけを作ったのが、天文学における地球中心説(天動説)から太陽中心説(地動説)への理論転換である。しかし、それは単なる科学理論の交代には留まらなかった。地球が宇宙の不動の中心(大地)から太陽の周りを回転する惑星となったことは、まさに「驚天動地」の出来事であり、既成の「認識の秩序」を揺るがすと同時に人々の「生存の秩序」を根底から脅かすものだったのである。
まず、地球が惑星に、月がその衛星になったことは、月上界と月下界、すなわち天上と地上の区別がなくなったことを意味する。次に、神や天使の住まう場所と考えられていた最高天球が消滅して無限の宇宙となったことは、「神―天使―人間―動物―植物―無生物」という存在のヒエラルヒー(位階秩序)の成立基盤が失われたことを意味している。さらに、アリストテレス的世界像のもとでは、地上の物体を形作る四元素にはそれぞれの故郷ともいうべき「自然な(本来の)場所」が定められていた。この自然な場所へ戻ろうとする傾向生こそ物体の自然運動(上下運動)の根拠なのである。
しかし、大地を基準に立てられた上下方向という価値の座標軸が無意味となることによって、自然な場所という概念もまた意味を失う。地上の物体は帰るべき場所とともに運動の根拠をも失ったのである(この点に、近代物理学において第一に「慣性の法則」が要請されざるをえない理由が存する。物体の等速直線運動に理由は要らないことを主張するのがこの法則だからである)。「コスモスの解体」とは、それゆえ「階層的に秩序づけられた有限の世界構造という観念、すなわち質的および存在論的に差異化された世界という観念の崩壊」(コイレ、前掲論文)にほかならない。
要するに、科学革命を通じて宇宙は質的差異のない等方等質の茫漠たる空間となったのであり、同時にそれは空間が数学(幾何学)によって記述可能な抽象的対象となったことを意味する。これがコイレの言う科学革命の第二の特質「空間の幾何学化」である。あるいは、宇宙は人間的な意味や価値によって秩序づけられた「コスモス」から、天上と地上とが物理法則によって統一された無限空間、すなわち「ユニバース」へと大きく変貌したと言うこともできる。「この無限の空間の永遠の沈黙は私を恐怖させる」(『パンセ』206)というパスカルの有名な言葉は、コスモスを前にした人間の実存的なおののきを表白したものであろう。おそらくそれは、人類が二足歩行を開始して初めて天空を振り仰いだときに感じたよるべなき不安に比すべきものであった。(45~48頁)
■この科学理論上の方向転換は、アリストテレス的な「質的秩序」からガリレオ的な「数学的秩序」への眼差しの向け変えと言うことができる。少なくともアリストテレス主義の伝統のなかでは、自然学の対象に数学を適用することは方法論上の錯誤にほかならなかった。その意味で、科学革命によってもたらされた「空間の幾何学化」は、「自然の数学化」と表裏一体をなすものなのである。近代科学の成立期にあって、その自然の数学化を強力に押し進めたのは、ほかならぬガリレオ・ガリレイであった。
哲学は、われわれの眼前にいつも開かれているこの壮大な書物(つまり宇宙です
)のなかに記されているのです。けれども、そこに書いてある言葉を学び、文字を
習得しておかなければ、理解することはできません。空しく迷宮の闇のなかをさ
まようばかりです。(『黄金計量者』第6、青木靖三訳)
これは「宇宙という書物は数学の言葉で書かれている」と簡略化してしられているガリレオの言葉である。冒頭の「哲学」はむしろ自然哲学、今日で言えば自然科学を意味する。明らかにここでは、宇宙が数学的秩序を持つのみならず、その秩序は数学を媒介としなければ人間には理解できないことが主張されている。ウィトゲンシュタイン流に言えば、ガリレオはここで数学的言語を用いた自然科学という新たな「言語ゲーム」の確立を宣言しているのである。コイレは先の論文において、この点を捉えてガリレオをプラトン主義者と見なし、彼の試みを「プラトン主義の実験的証明」と呼んだ。アリストテレス–スコラの伝統によって葬りさられたピュタゴラス–プラトンの伝統こそは、宇宙に内在する「数学的秩序」の存在を確信していたからである。(49~50頁)
■ところで、こうしたガリレオの方向転換に対して、20世紀に入ってから最も鋭い批判の矢を放ったのは、コイレの師でもある現象学の創始者フッサールであった。彼は最晩年の著書『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』(以下『危機』と略す)のなかで、「ガリレオによる自然の数学化」に一節を割いて詳しい論評を行なっている。
―中略―
フッサールによれば、科学の意味基底として存在する生活世界、すなわち「われわれの全生活が実際にそこで営まれているところの、現実に直視され、現実に経験され、また経験されうるこの世界」(『危機』第9節)を数学的シンボルと式からなるりねんの衣で覆い尽くした張本人こそガリレオにほかならなかった。ガリレオが幾何学的言語の導入によってもたらした新たな科学的経験(数量的認識)は、直接的・現実的な生活世界的経験を見失わせ、それをベールで覆い隠す役割を果たしたというのである。その何よりの証左は、われわれが色や匂いに満ちた知覚的世界を「主観的」世界として貶(おとし)め、無色無味無臭の物理的世界こそ「客観的」世界と考えることのなかに見ることができる。フッサールはそれを本末転倒として指弾する。「理念化された自然を科学以前の直感的自然にすりかえることは、ガリレオと同時に始まった」(『危機』第9節)と言われるゆえんである。(51~53頁)
■通常、われわれは高校の「世界史」の授業などで、近代の出発点は14、15世紀のイタリア・ルネッサンスおよび16世紀初頭の宗教改革にあると教えられる。バターフィールドはこの通説に対して異を立て、近代世界および近代精神のせい立を17世紀の「科学革命」に求める。なぜなら、ルネッサンス(「再生」や「復活」を意味する)はその名のとおり古代のギリシャ・ローマ分化の復興運動であり、宗教改革は原始キリスト教の精神への回帰運動であったように、両者はともに古代を模範とする復古運動にすぎないからである。それらは中世キリスト教世界を批判する運動ではあっても、古代以来のアリストテレス的世界像を否定するにはいたらなかった。それを覆したところにこそ近代世界の面目があるとすれば、その出発点は17世紀の「科学革命」まで下らなければならない。これがバターフィールドの提案である。
―中略― この科学革命を成就することによって、その後西欧諸国は世界史における覇権を確立し、近代史における「西欧の優位」はゆるがぬものとなった。日本を含むアジア・アフリカ地域の諸国にとって、「近代化」がすなわち「西欧化」にほかならなかったゆえんである。(55~56頁)
■クーンはアリストテレスの著作を読み進むうちに、そこに「質的変化一般」の記述という近代以後とまったく異なる自然の見方があることに気づいたことを回想しながら、「この種の変化は、その後すぐにハーバード・バターフィールドによって『思考の帽子のかぶり替え』として記述されることとなり、この点に関する疑問から私は即座にゲシュタルト心理学や関連する分野の書物へと向うことになった」(『本質的緊張』「自伝的序文」)と述べている。後に彼が『科学革命の構造』のなかで科学理論のパラダイム転換を知覚上の「ゲシュタルト・チェンジ」、すなわち反転図形やだまし絵に見られる図柄の変換になぞらえていうことからも、その影響の大きさを窺うことができる。バターフィールドの示唆とは、次のようなものであった。
およそ天体の物理学であれ地上の物理学であれ―この両者は科学革命全体を通じ
て戦略上の拠点となったものであるが―その改革をもたらしたのは新しい観測と
か、新事実の発見とかではなく、科学者の精神の内部に起こった意識の変化なの
であった。(中略)あらゆる精神活動の中で最もやりにくいこと、まだ柔軟性を
失っていないと考えられる若い頭脳にとってすらきわめて困難なこと、それは、
従来と同じ一連のデータを用いながら、しかもそれらに別の枠組みを当てはめて
相互の関係を新しい体系に組み替えることであると言えよう。それはつまり、い
わば別の種類の思考の帽子をかぶって今までとはまったく違った見方をしてみる
ことである。(『近代科学の誕生』第一章)
通常われわれは、コペルニクスは優れた天文学者であり、彼が収集した正確な観測データや新たな観測事実の発見こそが天動説から地動説への理論転換をもたらしたのだ、と考えがちである。しかし、当時のコペルニクスが手にしていた観測データは、プトレマイオスのそれとほとんど代わるところはなかった。天体観測の技術に関する限り、コペルニクスよりは約二世代下のティコ=ブラーエの方がはるかに優秀な天文学者であったと言ってよい。にもかかわらず、ティコ=ブラーエはコペ
ルニクス説を拒否し、地球中心説に固執したまま天動説と地動説の折衷案を提起したに留まったのである。
このコペルニクスとティコ=ブラーエの関係ほど、バターフィールドの言う「思考の帽子(thinking-cap)のかぶり替え」を如実に例証しているものはない。コペルニクスは「従来と同じ一連のデータ」を使いながら、それを「別の枠組み(a different framework)」に当てはめることによって、太陽中心説という、「新しい体系」を組み立てたのである。それに対してティコ=ブラーエは、新たな観測上の発見をなし(新星の発見や彗星の位置が月より高いこと)、火星の精密な観測データを蒐集したにもかかわらず、新たな思考の帽子をかぶることができなかった(彼の観測データは弟子のケプラーに譲り渡され、前述の「ケプラーの3法則」発見の基礎となった)。コペルニクスの場合、彼に新たな思考の帽子をもたらしたものが、彼が深く傾倒していた新プラトン主義ないしはヘルメス主義に由来する「太陽崇拝」の思想であったことは、多くの科学史家が明らかにしているところである。(57~59頁)
■通常われわれは「科学」の起源を古代ギリシャの幾何学や物理学、さらにはバビロニアの天文学にまで遡るけれども、現代的な意味での「科学」、すなわち個別諸科学とその社会的制度化が完成するのは、前章で述べたように19世紀中葉のことである。この時期にようやく科学は哲学の一分野(自然哲学)という軛から離脱し、新しい〈知〉としての自己を確立した。それゆえ、17世紀の二度にわたる科学革命は、いわば〈知〉の領域における「市民革命」と言うべき出来事であった。革命によって成立した新政権は、当然にも当然にも旧政権からおのれを区別するとともに、その正統性を外に向って明らかにせねばならない。
科学が哲学、神学、法学、歴史といった〈知〉の旧体制(アンシャン・レジーム)に対抗し、それを凌駕するためには、まずみずからの来歴を語る系図を作成し、さらにその方法論上の優位を証明してみせる必要があった。そのような使命を担って登場したのが「科学史」であり「科学哲学」にほかならない。(66頁)
■このホイッグ史観に反旗を翻し、科学史研究の水準を一挙に高めたのは、クーンが「他のどの科学史家にもまして私の師と呼ぶにふさわしい人物」(『本質的緊張』第二章)と語った先のアレクサンドル・コイレであった。彼は過去の事績を現在の高みから「後知恵」によって裁断することを排し、過去の科学者たちが直面した問題を彼ら自身が用いた概念を通じてりかいし、それを一次資料に即してあらゆる角度から内在的に再構成するという「内的科学史(internal history)」の方法論を洗練させた。内的科学史を研究する上での指針を、クーンは次のように述べている。
科学史家は、彼の知っている今日の科学をできる限り考慮の外に置くというこ
とである。彼は、彼が研究しようとしている時代の教科書や定期刊行物から、科
学を学ばなければならない。そして彼は、それとそれらが繰り広げる固有の伝統
とに精通してから、発見や発明によって科学発達の方向を変えることになる革新
者に取り組むべきである。革新者たちを扱う際には、彼は革新者たちが考えたの
と同じように考えるよう試みなければならない。(『本質的緊張』第五章)(74~
75頁)
■ヒューエルの科学哲学の特質は、ハーシェルのそれが一貫して経験主義的であるのに対し、カント哲学の影響を濃厚に受けて、事実を統括するアプリオリな概念の働きを強調するところにある。ヒューエルによれば、感覚的経験から得られた事実を概念で結びつけることを通じて、われわれは真理を獲得する。その際に行なわれる手続きが「帰納」、すなはち仮説の形成である。真理の発見にいたるまでには、おびただしい数の仮説が提起され、また淘汰される。彼は科学史上の事例を考察しながら、その過程を「言葉で表現される以上の数多くの推測が彼ら[科学者]の心を通りすぎ、諸概念のできる限り多くの結合が形作られては、まもなく却下される」(第11巻第4章)と描写している。つまり、帰納の過程ですでにさまざまな試行錯誤がなされるのである。その結果、「一連の仮説が呼び出されては素早く吟味にかけられ、やがて多様な集団のなかから仮説の選択を行なう決定がくだされる」(同前)ことになる。次に来るのは、その選択された仮説を検証する過程である。この検証をめぐるヒューエルの考察は、仮説の予測的機能を明らかにしていて興味深い。(81頁)
■ヒルベルトの見解は、19世紀も終わろうとする1899年に刊行された『幾何学の基礎』において初めて体系的に提示された。かれはユークリッド幾何学を公理主義的に再構成するというささやかな企図から出発しながらも、結果として幾何学を「空間の学」から「抽象数学」へと変貌させ、現代数学へと至るパラダイム転換をなしとげたのである。ヒルベルトはまず点、線、面、などユークリッドが定義を与えた幾何学の基本概念を「無定義述語」としてそれを空間直観から切り離し、公理をそれらの無定義述語の間の関係を定める「仮説」あるいは任意に取り決めのできる「規約」として特徴づけた。それによって、点、線、面、などの概念は実在との関係を断ち切られて一群の公理系を満足する「あるもの」にすぎなくなり、また公理系は「自明の直観的真理」ではなく、無矛盾性、完全性、独立性などの形式的性質を満足する一連の「無証明命題」となった。「点、線、面の代わりにテーブル、椅子、ビールジョッキと言い換えても幾何学ができる」というヒルベルトの言葉は、彼の幾何学観を端的に表明したものである。
明きらかに、ヒルベルトにとっては、幾何学的公理は空間直観に照らして真理性を保証されるべきものではなく、任意に選択できる仮説にすぎない。しかし、システムとしての「公理系」については、その無矛盾性が証明されなければならないのである。それに対してフレーゲは、「公理が真であることから、それらが互いに矛盾していないことが帰結します。それゆえ、さらなる証明は不必要です」と主張する。つまり、ヒルベルトにとって証明すべき無矛盾性は、フレーゲにとっては証明不要の自明な事柄であり、逆にフレーゲにとって絶対必要な公理の真理性を、ヒルベルトはまったく問題にしないのである。両者の間には、何が幾何学の「問題」であるかについて、そもそも「共通の尺度」、すなわち通約可能性が存在していない。二つの異なるパラダイム(科学研究の前提事項)の間では同じ用語を使いながらもコミュニケーションの行き違いが生じるという、クーンの言う「通約不可能性」にとって、これほど好都合な事例はまたとないであろう。ここで争われているのは、すでに真偽の問題ではなく、どちらの幾何学パラダイムを受け入れるという態度決定の問題なのである。(88~89頁)
《私(岡野)は通約は可能であると思う。世界は超越論的に実在しているのだから》
■もう一つ注目しておかねばならないのは、ヒルベルトの問題提起を通じて数学的真理の身分について根本的な考え方の変更が起こったことである。ヒルベルトがフレーゲ宛の書翰で語った言葉によれば、「任意に措定された公理がすべての帰結に関して相互に矛盾しないのであれば、その公理は真であり、それらによって定義されたものは存在する」のである。したがって、幾何学的命題は「規約」として任意に選ばれた公理系から純粋に論理的手続きのみによって導出された帰結、すなわち「条件付きの真理」にほかならない。ピタゴラスの定理といえども、公理系の選択を抜きにその真偽を論ずることはできない。「真理」という言葉は、それが属する体系的文脈(パラダイム)に依存するのである。
この真理のパラダイム依存性こそ、後にクーンのパラダイム論をめぐって非難が集中した点である。クーンが「〈科学〉殺人事件」の法廷に引き出されたのも、主たる理由は「真理の相対主義」の主唱者と目されたからであった。しかし、ヒルベルトの主張は、別に奇矯なものではない。数学的真理は、それを証明すべき形式的言語の体系に依存するということにすぎない。つまり、前提や推論規則が異なれば、証明される真理もまた異ならざるをえないということである。クーンのパラダイム論も、実質的にはこのヒルベルトの主張と変わるところはない。ただ、それを自然科学に適用したところから、科学的実在論者の強力な反発を招いたのである。(89~90頁)
《私(岡野)は科学的実在論者の意見の方に組する》
■アインシャタインが1905年にはっぴょうした論文「運動物体の電気力学」は「すべての物理法則は、いかなる慣性系を基準にとろうと同一である」という相対性原理をようせいすることによって、絶対静止系のような特別な基準系は存在しないことを明らかにした。これはニュートンの言う絶対空間が存在しないことを意味する。また彼は「真空中を伝播する光の速度は、光源の運動状態と無関係に一定値Cをとる」という光速度不変の原理を要請することによって、「同時刻」という概念が観測者の座標系に相対的であることを示した。これは「絶対時間」という概念を無意味にするとともに、空間を瞬時に伝わる万有引力のような「遠隔作用」の存在を否定するものであった。さらにアインシャタインは物体に固有の不変量と考えられてきた質量が、物体の運動速度に伴って変化するものであることを明らかにした。これら絶対空間、絶対時間、質量、遠隔作用などニュートン力学の基本概念に根本的な変更を加えたことは、古典物理学的世界像への信頼を根底から打ち砕くものであった。
クーンはこれを明白な「科学革命」の一例とかんがえる。ニュートン力学と相対性理論の間には、基本概念をめぐる「意味変化」が生じているからである。この概念上の意味変化をクーンが「通訳不可能性」として特徴づけたことから、大きな論議が巻き起こったのであるが、その詳細は第4章の叙述にゆだねよう。さらに、「エーテルに対する地球の相対速度」といった物理学の中心問題が消滅したことも「科学革命」の特徴と言える。パラダイム転換は何が解決されるべき「問題」であるかに関する共通了解を根本的に変更するものだからである。(93~94頁)
《私(岡野)は、基本概念をめぐる「意味変化」と捉えない。世界のゲシュタルトの空間と時間の量の変化による、B・フラーのテンセグリティのテンションの紐の組み替えだと思う》
■それと同時にノイラートとカルナップが作成してシュリックに捧げたウィーン学団の綱領文書『科学的世界把握―ウィーン学団』が刊行された。これは学団の成立過程やその哲学的主張を高らかに謳い上げた宣言文であり、末尾には「科学的世界把握の指導的代表者」としてアインシャタイン、ラッセル、ウィトゲンシュタインの名前が掲げられている。それぞれ物理学、論理学、哲学の分野に新たな期を画した3人を先達と仰いでいるところに、彼らの目指すべき方向が端的にしめされている。その一節を見てみることにしよう。
科学には「深層」といったものは存在しない。存在しているものは、すべて表
象である。複雑で常にすべてを見通すことができず、しばしば個的な形でしか理
解できない網を構成しているものは、すべて体験である。すべてのものが人間に
とって近づきうる。人間はあらゆるものの尺度である。(中略)科学的世界把握
は、解くことができない謎はないことを認める。伝統的哲学の問題を明晰にする
こと、その結果一部では、それは疑似問題としてその正体が明らかにされ、また
一部では経験的問題へと変形させられ、そうして経験科学の判断にゆだねられる
ことになる。このような問題と言明の明晰化に哲学の仕事の課題が存するのであ
り、固有な「哲学的」言明を打ち立てることにその課題があるのではない。明晰
化の方法とは論理分析の方法のことである。(Wissenshaftliche Weltauf-fassung
: Der Wiener Kreis,寺中平治訳)(98~99頁)
■論理学は19世紀後半にフレーゲの『概念記法』(1879)が出現することによって飛躍的な発展をとげた。すなわち、アリストテレス以来の名辞を単位とする伝統的論理学に代わって、命題を単位とし、その内部構造を解析する記号論理学が登場したにのである。その体系はホワイトヘッドとラッセルの『数学原理』全3巻(1910-13)によって形式的に整備され、さらにウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(1922)によった哲学的意味を与えられた。ウィーン学団の指導的代表者としてラッセルとウィトゲンシュタインの名が挙げられていたのは、こうした理由による。彼らが研ぎ上げた記号論理学という剣は、旧来の形而上学に立ち向かう何よりの武器となったのである。
ウィーン学団は彼らの科学哲学を「科学論理学(Wissenshaftslogik)」と呼んだ。(100頁)
■仮説演繹法を非合理な当て推量であると神秘的に解釈することは、発見の文脈と正当化の文脈とを混同することから生まれる。物事を発見するという行為は、論理的分析のできない事柄であり、天才の創造的機能に代置しうるような〈発見機械〉を論理規則にのっとって製作することは不可能なのである。しかし、この科学的発見を説明することは、論理学者の仕事ではない。論理学者のなしうるすべては、ある事実を説明しうると称される理論と、その与えられた事実との関係を分析することである。言い換えれば、論理学は正当化の文脈のみを取り扱うのである。(ライヘンバッハ『科学哲学の形成』市井三郎訳)(101頁)
■仮説演繹法のプロセスを簡単にまとめておけば以下のようになる。
⑴ 観察による科学的データの収集
⑵ 帰納法に基づく仮説の提起
⑶ 仮説からのテスト可能命題の演繹
⑷ 実験によるテスト可能命題の検証および反証
⑸ 検証された仮説に基づく理論の形成
このうち⑵の仮説の提起が発見の文脈に、また⑶の論理的演繹および⑷の検証と反証の過程が正当化の文脈にそれぞれ対応する。それゆえ、正当化の手続きは科学的仮説の論理分析とテスト可能命題の経験的実証とからなる。科学哲学の役割を正当化の文脈に限定したウィーン学団の思想が「論理実証主義」と呼ばれるゆえんである。(102頁)
■論理実証主義の今一つの目標は、科学理論の耕造を公理に基づく演繹的体系として論理的に整備するとともに、すべての経験科学を唯一の理論言語によって統一することであった。これが「統一科学」のりねんである。統一科学の構想そのものは、マッハの要素一元論にまで遡る。彼はこの世界を構成する基本要素は原子や分子ではなく「色、音、熱、圧、時間、空間……」などの感性的諸要素であると考え、これら諸要素の関数的依属関係を「思考経済の法則」に則って縮約的に記述することが科学の目標であると主張した。それゆえ、物理学と心理学の違いは、物と心という研究対象の違いではなく、諸要素の関連態を記述する視点の違いにすぎない。すべての科学は、諸要素の関数関係の記述に帰着するのであり、その観点から統一されるべきなのである。
ウィーン学団はこの統一科学の構想を引き継ぎ、マッハが科学の存在論的統一を目指したとすれば、その言語論的統一を目指したのである。それは、すべての科学を唯一の理論言語によって記述することに帰着する。その理論言語のモデルとなったのは、基本的には物理学の言語であった。物理学こそは実在の耕造を厳密な概念構成によって法則的に記述する「科学のなかの科学」と考えられたからである。したがって、社会学は心理学へ、心理学は生物学へ、生物学は科学へと順次論理分析を通じて還元されていくことになる。自然科学のみならず社会科学の基本概念と法則もまた、それが科学である以上、最終的には物理学の基本概念と法則によって定義され、定式化されねばならないのである。「ただ一つのかがくのなかに、すべての認識は根本的に同じ種類の認識として自己の位置を見いだす」(カルナップ)という統一科学の理念は、その意味で物理学的還元主義の別名であった。(105~106頁)
《私(岡野)の考え:物理学的還元主義は美術では、ミニマルアートになるので私のコンセプトと違うけれど、科学が物の還元主義だとしたら物理学は関係の還元主義だといえて、その点はおおいに認めるべきものがある。いずれにしても還元主義は対概念であるフラーのいうシナジェティクスを欠いているので、美術家としては方法論として一部認めても、全面的には容認できない》
■しかし、クーンはアリストテレスの『自然学』が彼の理解を拒絶した地点で立ち止まり、考え直した。その理由は別にこみいったものではない。いわば「コロンブスの卵」のようなものである。アリストテレスは生物学の分野では鋭い博物学的観察眼の持ち主であり、また論理学者としては三段論法の体系を集大成した伝統的論理学の創始者であった。さらに、倫理学や政治学におけるアリストテレスの洞察は今日なお生きており、ときには論争の的とすらなっている。このような万学に通じた希有の学者が、物理学の分野だけに限ってとんでもない間違いを犯すなどということがありうるだろうか。クーンはこう考えたのである。
―中略―
忘れられない(非常に暑かった)ある夏の日、突然これらの困惑が消え失せ
た。それかで格闘していたテクストのもう一つの読み方を与える一貫した基本原
理を、私はたちまちのうちに悟ったのである。はじめて私ハ、アリストテレスの
研究テーマは質的変化一般なのであって、石の落下も子供から大人への成長も共
に含むのだという事実に正当な重点を置いた。後に力学になるはずの主題は、彼
の自然学においてはせいぜいのところまだ十分に分離されない特殊事例なので
あった。いっそう重要だったのは、私が次のことに気づいたことであった。それ
は、アリストテレスの宇宙の永久的な構成要素、つまり存在論的に第一に不滅な
諸元素とは、物体というよりも質なのであって、遍在する中性の質量の一部に質
が押しつけられると個々の物体や実体が構成されるということである。(中略)
きわめて不十分で乱暴な言い方ではあるが、アリストテレスの営みに対する私の
新しい理解のこれらの諸側面は、一連のテクストの新しい読み方の発見というこ
とで私が意味していたところを示すに違いない。それを成し遂げて以来、それま
で不自然な比喩と思えていたことがしばしば写実的な描写に見えてきて、見かけ
上の不自然さも消え失せた。その結果として、私はアリストテレス主義者になっ
たというわけではないにせよ、ある程度までは彼らのように考えることを学んだ
のであった。(『本質的緊張』「自伝的序文」)(115~116頁)
■それが同時に、パラダイム論の形成にいたる第一歩でもあったことは言うまでもない。そのことはクーンが「私によるアリストテレスの読み方が明らかにしたとことは、人が自然を見た見方および自然へ言語を適用した仕方における全面的な変化なのであって、それは知識をふかするとか、僅かづつ誤りを正すとかから成るものとして記述することのできない性格のものなのである」と述べていることからも明らかであろう。自然に対する見方の「全面的な変化」こそパラダイム転換、すなわち「科学哲学」にほかならないからである。彼自身が「科学史を発見する一方において、私は私自身の最初の科学革命を発見していた」と述べるゆえんである。(119頁)
■『コペルニクス革命』の冒頭は、「コペルニクス革命は観念上の革命、すなわち宇宙および宇宙に対する人間自身の関係についてわれわれ人間がもっている概念体系の転換であった」という一文で始まっている。この観念や概念を整合的に組織化したものが「概念図式」にほかならない。古代人のそれは、地球と恒星天球という二つの球から成る宇宙というものであった。概念図式は「理論」であると同時に「世界感」でもある。
一方でそれは観測資料の秩序だった要約であり、概念上の「思考経済」すなわち最小限の思考の出費で事実をできるだけ完全に記述することに寄与する。それがなければ、科学は複雑な自然現象についての膨大な情報を蓄積し、それを説明することはできないであろう。他方でそれは「創造された世界における人間の位置を定義し、人間と神との関係に物理的意味を与える」働きをする。その限りで、概念図式は想像力の産物でもある。この二つの側面、すなわち具体的な研究の指針であるとともに知識を組織化する世界観的枠組みでもあるという両義性は、後のパラダイム概念にも引き継がれるものである。(124頁)
■科学理論はその中心をなす主要仮説のみならず、補助仮説や背景的知識をも含んだ複合的な体系であり、その中の単一の命題が反証されたからといって理論全体が直ちに放棄されることはありえない、ということである。したがって、理論転換の問題は、単純な論理的過程に還元することはできない。クーンの言葉を借りれば「論理的矛盾を強調することは本質的問題を覆い隠してしまう」のである。むしろ、究明されるべきは「見かけの一時的な不一致を逃れがたい矛盾へと変えるものは何か。一時代には明晰で柔軟で緻密なものと賞賛された概念図式が、次の時代には単に不明瞭で曖昧で面倒なものとなるのはどうしてなのか。科学者はなぜ不一致にも拘わらず理論にしがみつき、それに固執し続けるのか。科学者はどのような理由で理論を放棄するに至るのか」といった諸問題である。(126~127頁)
■クーンが「科学的信念の解剖学」を転回するに当たって鋭利なメスを入れたのは、伝統と革新のパラドキシカルな関係についてであった。この主題はクーンの科学論を通底する主調低音であり、それがすでに処女作において明瞭な響きをもって奏でられていることは指摘しておくに値する。彼はコペルニクスの『天球回転論』が「革命的なテクストというよりは革命を引き起こしたテクスト」であったことを述べ、さらに次のように続けている。
革命を引き起こす著作は過去の伝統の頂点であると同時に将来の新たな伝統の
源泉でもある。全体として『天球回転論』は、古代の天文学的および宇宙論的伝
統の内部にほとんどすっぽり収まっている。だが、その概して古典的な枠組みの
中には、当の著者すら予見できないような仕方で科学思想の方向を転換する少数
の新奇性が見いだされるのであり、それが古代の伝統との急速で完全な断絶をも
たらしたのである。天文学の歴史が用意する視座から見ると、『天球回転論』は
二重の性格をもっている。それは古代的であると同時に近代的であり、保守的で
あると同時に急進的である。したがって、その著作の意義は、その過去と未来、
すなわちそれを生み出した伝統とそれが生み出した伝統とを同時に見渡すことに
よってのみ見いだすことができる。(第5章)(127~128頁)
■会議の趣旨は、科学的そうぞうせいの基盤となる「逸脱的思考(divergent thinking)」の構造を解明し、それを実現する才能をいかにして見つけ出すかを論ずる、というものであった。逸脱的思考とは、古い解答を拒否して新しい方向へと出発する、基礎科学者に求められる幅広く自由な思考のことである。主催者側はそれを、科学者は「最も(自明な)事実や概念であってもそれを必ずしも受け入れることはなく、逆に最もありそうにない可能性について想像力を発揮するまでに偏見から解放されていなければならない」(セリエ)と特徴づけている。明らかに、ここに揚げられているのは、われわれがアインシュタインなどをモデルに思い描く「理想的科学者像」とでも言うべきものである。(131~131頁)
■それとは逆に、通常研究はその最良のものすらが、科学教育の中で習得され、それに続く専門家集団内での生活の中で補強された安定的合意の上に固く基礎づけられた高度に求心的な活動なのです。典型的には確かに、この求心的で合意によって束縛された研究こそが最終的には革命をもたらすのです。しかし、科学的伝統の革命的転換というものは比較的まれなことであり、求心的研究の長い期間がこの転換に対する必然的な前提となります。以下で示すように、その時代の科学的伝統に固く基礎づけられた研究だけが、その伝統を打ち壊し新しい伝統を招来しうるのです。(『本質的緊張』第9章)(134頁)
■つまり、科学者が用いる「力」「質量」「化合物」といった基礎的な用語の定義に関して何らかの一致が存在し、それが通常科学の研究を支えていると考えたのである。
しかし、その試みは見事に失敗に帰した。クーン自身の述懐によれば、「明らかに、私が探していたような合意は存在していなかった」のであり、「1959年の初めになってようやくわかったことは、実際にはこのような合意はまったく必要ないということ」であった。この点に気づいたことこそ、「パラダイム」概念の形成にとって決定的な一歩であったということができる。ウィトゲンシュタインは言語における人間の一致を「それは意見の一致ではなく、生活形式の一致である」(『哲学探究』第1部241節)と述べているが、その言い方を借りるならば「パラダイム」は科学者たちの「意見の一致」ではなく「生活形式の一致」を表現するための概念なのである。(139頁)
■この講演は「生産的な科学者は、ゲームを形作る新しい規則と新しい駒とを発見する成功した革新者であるためには、前もって設定された規則に従って複雑なゲームを楽しむ伝統主義者でなければなりません」と締め括られている。これがウィトゲンシュタインの言語ゲーム論を下敷きにした発言であることはいうまでもないが、この科学者像は、クーンが処女作においてコペルニクスのなかに見いだしたものであったことは注目されてよい。まさに「伝統と革新の弁証法」を生きる科学というイメージこそは、彼の科学観を貫く一本の赤い糸だからである。これはクーンの主著『科学革命の構造』においても、明瞭な主調低音として鳴り響いている。(142頁)
■『科学革命の構造』を書いた目的を、クーンは「研究活動それ自体の歴史的記録から浮かび上がる、科学のまったく異なった描像を描き出すこと」に求めている。それは、科学の複雑に入り組んだ地層を考古学者の眼差しをもって探求する一種の「科学のアルケオロジー(考古学)」の試みであったと言ってよい。フーコが『言語と物』において目指したのが「人文科学の考古学」であったとすれば、クーンが『科学革命の構造』において目指したのは、いわば「自然科学の考古学」と言うべきものであった。その意味で、フーコの「エスピテーメ」とクーンの「パラダイム」が、ともに〈歴史的アプリオリ〉という性格を共有し、〈知〉の連続的進歩という通念を痛撃したのは単なる偶然の一致に留まるものではない。(142頁)
《私(岡野)の意見:〈知〉すなわち〈解釈〉は連続的に進まないかもしれないが、〈存在(時間を含む)〉は時に分岐はするけれど常に連続的だと思う》
■しかし、すでにN・R・ハンソンが『科学的発見のパターン』(1958)において指摘したように、科学的事実は「理論負荷的」なのであり、理論的背景を離れた「裸の事実」なるものはありえなあい。たとえば、1枚の顕微鏡写真のなかに染色体を見いだし、霧箱写真から素粒子の種類を同定することは高度な理論的作業であり、生物学や物理学の理論を知らない素人にできることではない。観察とは単なる「感覚与件」の受容にとどまるものではなく、理論的文脈のなかで「事実」を構成する作業なのである。
―中略― だが、事実と理論が分離できないとすれば、観察事実は科学理論を検証ないしは反証する際の中立的な基盤ではありえず、事実は理論を打ち倒せないことになろう。そのとおりである。理論を打ち倒すのは事実ではなく、それに代わる新たな理論にほかならない。このことこそ、クーンの「科学革命」あるいは「パラダイム転換」が示唆するものであった。(150頁)
《私(岡野)の意見:〈知〉すなわち〈解釈〉の問題と、肉体に写る外部の〈存在(時間を含む)〉は、つまり目に写った写像は中立的な基盤であると思う》
■ところで、イアン・ハッキングは彼が編集した優れたアンソロジー『科学革命』(オックスフォード大学出版局)の序文において、論理実証主義的科学観の要点を以下の九ヵ条にまとめている。すなはち、⑴科学的実在論、⑵科学と非科学との境界設定、⑶科学的知識の累積生、⑷観察と理論の区別、⑸科学の経験的基盤、⑹科学理論の演繹的構造、⑺科学的概念の厳密性、⑻正当化の文脈と発見の文脈のくべつ、⑼物理学による科学の統一(還元主義)、の九項目である。すでに見たように、クーンが提起した論理実証主義的科学観への疑念は、このうち⑶、⑷および⑻に関わっている。これらの基本テーゼは相互に依存しあっているものであり、とりわけクーンが問題にした⑶と⑷の条項は、論理実証主義的科学観のアキレス腱とも言うべきものであった。クーンがウィーン学団という巨人に向って投げた石は、そのアキレス腱を断ち切ったのである。(152頁)
■科学の歴史のほとんどは「通常科学」の期間であると言ってよい。パラダイム転換が起こるのは、「異常科学」の一時期に属する稀な出来事にすぎない。時代に先駆けた天才の悲劇がしばしば科学史のエピソードを飾るのも、異常科学の才能を持った科学者が折悪しく通常科学の時期に生まれ合わせたという理由によるものであろう。(158頁)
■危機に陥ったパラダイムがたどる道は3通りに分かれる。第一は変則事例が通常科学に吸収されて見かけ上の危機が克服されること、第二は問題が手強すぎるため、その解決が次の世代に委ねられること、そして第三は新たなパラダイム候補が現われ、その受容をめぐる闘いを経て危機が終結へ向かうことである。この第三の場合が、いわゆる「科学革命」あるいは「パラダイム転換」と呼ばれる事態にほかならない。(164頁)
■科学理論上のパラダイム転換という事態を「革命」と名づけたことについて、クーンは科学革命と政治革命との類似性を指摘している。ともに既成の制度が問題を解決しえなくなって機能不全に陥り、危機の感覚が醸成されることから革命が始まるからである。さらにクーンは「対立する政治制度の間の選択と同様に、対立するパラダイムの間の選択は、共同体の生活をめぐる両立不可能な流儀の間の選択にほかならないことがわかる」と述べている。だとすれば、パラダイムの選択の問題は、論理分析や決定実験といった、一義的な基準ではきめられないことになろう。そこからクーンは「政治革命におけると同様に、パラダイムの選択においても、関連する共同体の同意を上回る高い基準は存在しない」と結論するのである。(166頁)
■しかしながら、基準の通訳不可能性以上のものがそこには含まれている。新しいパラダイムはふつう古いパラダイムからうまれるのだから、新しいパラダイムはふつう、概念的であると操作的であるとを問わず、伝統的パラダイムがこれまで採用してきたパラダイムがこれまで採用してきた語彙や装置の多くを取り入れる。しかし、新しいパラダイムがこれら借用した要素をほかならぬ伝統的な仕方で用いることは稀である。新しいパラダイムの内部では、古い用語、概念および実験はお互いに新たな関係を取り結ぶ。その不可避的結果として、適切な言葉ではないかもしれないが、二つの競合する学派の間の誤解と呼ぶべきものが生ずるのである。(中略)アインシュタインの宇宙に移行するためには、空間、時間、物質、力、等々といった糸からなる概念的織物の全体を作り変え、もう一度自然全体にかぶせ直さねばならない。(『科学革命の構造』第12章)(170頁)
■しかしながら、他方で彼は「パラダイムのようなものが知覚自体の前提条件ではないかと推測される」と述べており、パラダイム概念が日常的知覚の次元にまで拡張可能であるかのように示唆している。そのため、パラダイム転換が科学的世界のみならず日常的世界をも全面的に変化させるかのような誤解を招いたのである。(178頁)
■科学の進歩に関する通俗的イメージは、無限の彼方にある「進歩の殿堂」へ向って、科学者たちが一致協力しあいながら一歩一歩階段を登るように確実に近づいていく、というものであろう。つまり、クーンの要約によれば「自然に関する一つの完全で客観的で真なる説明が存在し、科学的業績の正しい尺度は、それがわれわれをかの究極目標へ近づける度合いにほかならない」という科学像である。これは明らかに、「真理」という究極目標を設定している点において、目的論的な描像と言うことができる。この目的論の背景にあるのは、一種の神学といって悪ければ、パトナムの言う「形而上学的実在論」の信念である。正当化の文脈を発見の文脈から切り離し、科学を完全に合理的な方法論あるいは論理的アルゴリズムに還元しようとした論理実証主義の科学観を支えてきたのは、この根拠なき「形而上学的実在論」の信念であったといってよい。(188~189頁)
《私(岡野)の意見:論理実証主義の限界は、論理をなりたたせる原理そのものと、その道具である記号では、存在の時間性と存在の勾配はとらえきれないというところにあるので、「形而上学的実在論」は正しい信念だと思う》
■クーンが科学革命を政治革命とアナロジカルに捉えていたことも、彼の意図とは別に1960年代末の「正治の季節」と共鳴現象を引き起こすもととなったと言えよう。(196頁)
■以上のような論理実証主義の基本前提に対する批判という点では、ポパーとクーンは問題意識を共有する。しかし、ポパーは「検証可能性」や「帰納主義」を拒絶しながらも、「境界設定の基準」「発見の文脈と正当化の文脈の峻別」および「科学の進歩」を擁護することにおいては論理実証主義と軌を一にしている。クーンと見解が分かれるのはその点である。それゆえクーんは、先のシンポジウムにおける基調報告のなかで、ポパーと自分が科学に関する同じデータを取り上げ、実質的に同じ答えを与えている場合でも、その意図はしばしばまったく異なっていることを指摘する。彼らは同じ論文の同じ行を論じても、そこから描き出される科学像は異なっているのであり、それゆえクーンは「われわれを隔てているのは不一致であるよりも、むしろゲシュタルト変換である」と述べ、「彼がアヒルと呼んでいるものをウサギと見ることもできるということを、どうやって説得したらよいのか」と反問している。ここでクーンがポパーと自分の科学観の違いを「ゲシュタルト変換」になぞらえていることは興味深い。それというのも、彼らの間に戦わされた論争は、まさに旧科学哲学から新科学哲学への「パラダイム転換」をめぐる問題だったからである。(206頁)
■科学者が自分の「誤り」から学ぶことができるのも、何が「誤り」であるかの基準が明示されている通常研究の領域においてでしかない。その点をクーンは次のように説明している。
個人が自分の誤りから学ぶことができる唯一の理由は、実践によってこれらの
規則[論理規則、言語規則、論理や言語と経験との間の関係についての規則]を
体現しているグループが、規則を適用する際に個人が犯す誤りを分離できるから
にほかならない。要するに、カール卿の命法が最も明瞭に当てはまる種類の誤り
は、あらかじめ確立された規則に支配された活動の内部において、個人が犯す理
解や認識の失敗である。科学の中でこのような誤りが最も頻繁に生じるのは、通
常のパズル解き研究の実践の内部においてであり、またおそらくはその内部にお
いてのみである。(『批判と知識の成長』)(208頁)
《私(岡野)の意見:人間は外に向っても、内に向っても世界=内=存在なのだから、世界と自己との関係からダイレクトに自分の誤りを学ぶことができる》
■だがポパーによれば、そのような回避策は科学者が取るべき公正な態度ではない。科学者はすべからく反証例が挙げられれば自説を清く撤回すべきなのである。ポパーはそれゆえにこそ、研究に携わる科学者が順守すべき「規則」あるいは「規範」を確立すべきことを提案する。だとすれば、ポパーが求めているのは、科学的発見の「論理」であるよりは、むしろ「倫理」だと言うべきであろう。(209頁)
■ここにはポパーとクーンの科学像の違いが端的に現われており、興味深い。ポパーが念頭に置いているのは、アインシュタインやハイゼンベルグらが個人の才能のみを頼りにして発見や発明をなしえた20世紀前半の「古きよき時代」の科学である。そこにでは確かに「純粋科学」が成立する余地があった。それに対して、クーンは第二次世界大戦における科学者の戦時動員を体験し、戦後の共同研究による巨大科学のプロジェクトを目の当たりにした世代である。すでに純粋科学と応用科学の境界線は曖昧になり、高価な実験施設を備えるためには、まず膨大な申請書類を書いて予算を獲得せねばならない。科学者はもはや実験室のなかで孤高を保つことはできず、世俗の社会制度のしがらみのなかで研究をすすめざるをえないのである。クーンはそうした科学研究の現状を、いわば文化人類学の眼差しで捉えようとしたにすぎない。そのようにして描かれた科学者が、ポパーの目には「科学の堕落」と映るのである。(216頁)
■しかし彼(岡野注:クーン)は、意味論的真理概念に「絶対的」や「客観的」といった王冠を戴かせ、それを認識論的真理概念とすり替えることを拒否するのである。しかも、ポパーがこの絶対的真理概念に依拠して、科学の目的は「批判的議論の光に照らして、真理により近い理論を見いだすことである」として究極の真理へと向う「科学の進歩」を語るとき、クーンはやはりそれを拒否せざるをえない。それはパトナムの言う『形而上学的実在論」を前提することなしには語りえない事柄だからである。(217~218頁)
■マートンはこの論文で、後に「マートン・テーゼ」と呼ばれることになる2つの命題を提起した。第一は、17世紀イギリスにおける科学研究を方向づけたのは、経済的・技術的要求であったというテーゼである。前者の命題は明らかに、マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で提起した基本テーゼを近代化学の起源をめぐる考察に適用したものであることが見てとれる。このマートン・テーゼに対しては否定的議論も少なくなかったが、その後、科学社会学が自立した学問分野として確立されるに当たって、研究上の「模範例」としての役割を果たしていった。いわゆる「マートン学派」が形作られたのである。(264~265頁)
■そのなかで最もよく知られているのは、「マートン・ノルム」と呼ばれる科学者を律する行動規範に関する分析である。彼はそれを『社会理論と社会構造』(1949、邦訳みすず書房)第16章「科学と民主的社会構造」のなかで四つの規範に定式化している。
第一は、「普遍主義」であり、「科学のリストに入ってくる真理要求を受け入れるか拒否するかは、要求主体の個人的、社会的属性に左右されるべきでない」というものである。つまり、科学理論の妥当性の判断はそれを提出した科学者の人種、国籍、宗教などに影響されるべきでなく、その内容が「観察とすでに確認ずみの知識とに一致する」か否かという基準のみによって判断されるべきだ、ということである。この普遍主義は、さらに「学者としての経験は才能ある者に開放されているべきだという要求」と密接に結びついている。
第二は、「公有性」であり、「科学の実質的な知見は社会的恊働の所産であり、共同体に帰属する」という規範である。ここから秘密主義が否定され、研究成果は学会や学術雑誌を通じて公表されねばならない、という公開制の要求が導かれる。またこの規範は科学的知識を「私有財産」とすることを禁じる。科学的発見に対して科学者が受け取る唯一の褒賞は「世間から認められ尊厳を受けること」に尽きるのである。(205~206頁)
■たとえば、飛行機事故が起こったとする。そのときには、直ちに事故調査委員会が組織され、事故(失敗)の原因が徹底的に究明されることであろう。しかし、飛行機が問題なく飛んでいるときには、その順調な飛行(成功)の原因を究明する委員会が組織されることはありえない。それに対して、成功も失敗と同様にその原因が究明されるべきだと主張するのがストロング・プログラムの要点である。したがって、真なる信念や合理性は、偽なる信念や非合理生とまったく同様に、科学社会学によって因果的に説明されるべき事柄だということになる。言い換えれば、普遍妥当的な真理と認められてきた数学や論理学の知識も、科学社会学的説明を免れることはできないのである。(271頁)
■これは近代初頭にベーコンとデカルトによって彼らの科学的方法論の核に据えられた考えであり、知識は疑いえない堅固な基盤の上に築き上げられねばならない、というテーゼを指す。その基盤をデカルトは「アルキメデスノ支点」にたとえている。ただし、ベーコンはその基礎を「経験的なもの」に求め、デカルトはそれを「生得的なもの」に求めた。また、基礎から知識へと上昇する手続きとして、前者は「帰納法」を、後者は「演繹法」を要請した。この基礎づけ主義の二つの流れは、科学的知識の「実証的」側面と「論理的」側面を特徴づけるものとして、伝統的科学哲学(論理実証主義)のなかへと流れ込んだ。すなはち、クーンの言う「経験的基礎づけ主義」と「演繹的正当化主義」とである。(277~278頁)
■伝統的科学哲学が想像したように、理論間の選択に関わるすべての個人が、合理的に同一の証拠のもとでは同一の決定をなすべく強いられると仮定してみましょう。長期間定着していた理論が新しく提示された代替理論によって置き換えられるにはどれほど強力な証拠が必要でしょうか。もし要求が高く設定されれば、新たに提出された理論はその力を立証する余地を与えられないでしょうし、低く設定されれば、既成の理論は新理論の攻撃から身を守る機会を得られないでしょう。独我論的方法は科学の前進の息の根を止めてしまうでしょう。判断による決定的手続きは共同体に、生活形式のいかなる選択にも伴う危険を分散させることを可能にしているのです。(『思想』1986年8月号、佐々木力・羽片俊夫訳)(280頁)
■『科学革命の構造』中山茂訳、みすず書房、1971年(1962)
言うまでもなく、科学史・科学哲学の分野を震撼させたクーンの主著である。初版は全13章からなり、ウィーン=シカゴ学派のメンバーを編集委員とする「統一科学国際百科全書」の第2巻第2号として1962年に刊行された。しかし、本書の役割は、ウィーン学団が築き上げてきた論理実証主義的な科学観を完膚なきまでに打ち砕くことにあった。その意味で本書は、論理実証主義の牙城に送り込まれた「トロイの木馬」にたとえらることができる。それは累積的科学観とホイッグ史観(進歩史観)に対して突きつけられた大胆な挑戦状であった。その結果、20世紀の科学観は大きな「パラダイム転換」を経験したのである。
―中略―
本書が与えた衝撃は、何よりも、科学理論は検証や反証という合理的手続きを通じて客観的知識を確立し、唯一の真理へ向って連続的に進歩する、という従来の常識的な科学観を根本から否定したことにあった。それに代えてクーンは、科学理論パラダイム転換を通じて断続的に転換する、という新たな科学像を提起する。科学研究の具体的指針である「パラダイム」に支えられたルーティン・ワークとしての研究活動をクーンは「通常科学」と呼ぶ。通常科学は、明確な目標とルールをもつことで「パズル解き」に類比される。しかし、通常科学はその枠組みのなかでは解決できない「変則事例」を不可避的に生み出し、その結果パラダイムへの信頼が崩れて「危機」の状況が訪れる。危機の時期には複数の代替パラダイムが競合するが、やがて一つのパラダイムが勝利を収め、新たな通常科学の活動が開始される。以上がクーンの科学革命論の概要である。
このクーンの問題提起は、科学革命期の理論選択に当たっては論理的アルゴリズムが存在しないこと、また新旧のパラダイムの間にはコミュニケーションの断絶をもたらす「通約不可能性」が存在することを主張するに及んで、科学哲学者からの猛烈な反発と批判を招いた。いわゆる「パラダイム論争」である。むろん、専門の哲学者でないクーンの論述には哲学的な杜撰さが各所に見られる。しかし、本書は細部にわたる論理的整合性よりは、全体として描き出された科学像の斬新さによって評価されるべき著作である。われわれはむしろ、クーンが提示する科学史上の具体的な事例分析がもつ説得力にこそ目を向けるべきであろう。(307~309頁)
■『科学革命における本質的緊張』我孫子誠也・佐野正博訳、みすず書房、1998年(1977)
とりわけ、1947年に起こった「回心」体験の叙述は興味深い。クーンは科学史の講義を準備するためアリストテレスの『自然学』に取り組んだが、その運動論の記述は誤謬の集積であった。ある夏の日、アリストテレスの研究テーマは質的変化一般であることに気づき、その困惑は突然消え失せた。それは彼にとってテクストの読み方の「発見」であると同時に、科学史という学問への「開眼」でもあった。この体験を通じて、クーンは「科学革命」の構想をえるのである。
『パラダイムとは何か』 野家啓一著 講談社学術文庫 2008年12月1日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■どうだろうきみ、ひどく怖い気がするんだけれど、わたしたちは、わたしたちを知らぬ多くのものによってつくられているのではないかしら。だからこそ、わたしたちはわたしたち自身を知らないのだ。もし、そういうものが無限にあるとしたら、いかなる思索も空しいね……(47~48頁)
■きっとあのひとの魂は、自然の掟に反して葉ではなく根のほうが明るいほうへと伸びてゆく奇異な植物にでもなってしまうのでしょう!(75頁)
■神父さまはわたくしにこうおっしゃいました。「あのかたは恐ろしいまでに善から身をひきはなしておいでだが、幸いなことに悪からも身をひきはなしておいでだ…… あのかたのなかには、なにかしらぞっとするような純粋さ、なにかしれぬ超然たるところ、なにかしら議論の余地のない力と光とがある。深く磨きぬかれた知力のなかに、あれほど混乱も疑惑も不在だという例を、わたしはいまだかって見たことがありません。あのかたの静かなことといったら恐ろしいほどです!魂の不安という言葉も、内面の影という言葉も、なにひとつあのかたにはあてはまらない、――それに恐怖や渇望への本能から由来するようなところは、まったくない…… だがまた、「神の愛」へと向うようななにものも。(85~86頁)
■――「神なき神秘家!……光かがやく無意味! おや、口がすべった、言うは易しだ! いつわりの明晰…… 神なき神秘家、いや奥さん、それなりの方向も意味ももたぬ動き、結局どこのも行きつかぬ動き、そんなものは考えられぬのですぞ!……神なき神秘家!……イッポグリフォだ、ケンタウロスだ、と言ってはどうしていけないんだ!」
――「スフィンクスではいけないんですの、神父さま?」(87頁)
■そしてそれが何であれ切断してしまう、あの突然の自己への回帰、そしてあれらの二股にわかれた視力、あれらの三叉にわかれた注意力、ある事象群がそれらの世界ではばらばらに分割されているのを、別の世界で触れあわせるあの接触……それこそは自己だ。(110頁)
■『自分ひとりでやるゲーム』
ゲームの規則
もしも、みずから賞讃に値いする思えば、この勝負は勝ちだ。
もしも、勝ちの勝負が計算により、意志と一貫性と明晰さをともなって勝ったものならば、――儲けは最大限に大きい。(110頁)
■わたしは(可見の)世界から、ただ力しか借りたくない――形態ではなく、形態をつくるのに必要なものを借りたいのだ。
物語はいらない――「装飾」はいらない――岩とか空気とか水とか植物的素材といった物質そのものの感覚――それから、それらの基本的な力の感覚。
そしてさまざまな行為と位相――個人とその記憶ではなく。(143頁)
『ムッシュー・テスト』 ポール・ヴァレリー 清水徹訳 岩波文庫
2008年12月2日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■本書が全体としてもつ意義は、おおむねつぎのように要約されよう。およそ語られうることは明晰に語らえうる。そして、論じえないことについては、ひとは沈黙せねばならない。(1-4)(25頁)
■7 語りえぬものについては、沈黙せねばならない。
これが、『論考』の最後のことばである。――中略――
われわれは何かを語るとき、論理に従う。論理は有意味に語るための条件である。それゆえ、論理それ自体について語ろうとすることには根本的におかしなところがある。つまり、論理は「語りえない」のである。論理は、われわれが論理に従いつつ他の何ごとかを語るとき、そこにおいて「示される」ものでしかない。
もうひとつ、論理と並ぶ、あるいは論理以上に重要視されるもの、それは倫理である。倫理もまた、語りえず示されるしかない。そして語りえぬとして却下されるのではなく、語りえぬがゆえに語りうるものよりもいっそう重要とされる。そうして、善、悪、幸福、価値、生の意義、こうした話題がそっくり語りえぬ沈黙の内に位置づけられる。ウィトゲンシュタインのその手つきは、あたかも「語る」ことによってそれらを卑しめてしまわないようにするかのごとくに見える。(26~27頁)
■{世界……現実に成立していることの総体 論理空間……可能性として成立しうることの総体}(29頁)
■われわれにはどれほどのことが考えられるのか。それが『論考』の根本問題である。他方、論理空間とは、可能性として成立しうることの総体、つまり、世界のあり方の可能性としてわれわれが考えられるかぎりのすべてである。とすれば、まさに論理空間のあり方を明らかにすることは、思考の限界を画定することに直接結びつくものとなるだろう。もっと単刀直入に言うならば(その分少しラフな言い方になるが)、論理空間の限界こそ、思考の限界にほかならない。(30頁)
■自分自身が定義域に含まれているときには、その結果生じる自己言及文が有意味であることは保証されている。もしその自己言及文がナンセンスならば、定義域から自分自身を排除すればよい。解明とはそういうことである。しかし、定義域に自分自身が含まれていないならば、自己言及文を作ることはできない。かくして、ラッセルのパラドクスは生じない。(96頁)
■定義域が異なれば、それはもはや同じ関数とはみなされないのである。ここに、ことがらの核心がある。
――中略――
命題関数「Xは神経質である」で考えてみよう。日常言語においてわれわれは、暗黙の内に、その定義域を人間ないしはある程度人間と生活の仕方が似ていると感じられる動物に限定しているだろう。そこでそれが暗黙の内であることに乗じて、あろトマト(トマちゃん)について、「トマちゃんは神経質だ」と言ったとする。ウィトゲンシュタインならば、それはナンセンスだと言うだろう。他方、命題関数が定義域と独立に定まっていると考えるならば(あるいはすべての個体に関して定義されていると考えるならば)、「トマちゃんは神経質だ」はナンセンスではなく、偽であるということになる。そのとき、「トマちゃんは神経質ではない」は真となる。それに対して、ウィトゲンシュタインならば、「トマちゃんは神経質ではない」もまたナンセンスとなる。(97~98頁)
■言語をもち、世界の像を作り、そうして、可能性へと扉が開かれている人だけが、否定を捉えうるのである。ただひたすら現実を見るだけでは、否定に対応するいかなる要素も見出されはしない。すなわち、否定とは現実に存在する対象ではない。あるいは、否定形の考えようとしてみてもよい。「テーブルの上にパンダはいない」という絵を描こうとしてみていただきたい。どういう絵を描くだろう。パンダのいないテーブルの絵を描くだろうか。しかしそれはただのテーブルの絵でしかない。よろしい。それを「テーブルの上にアオウミガメはいない」の絵だといってもよい。フンボルトペンギンがいないでも、カボチャがないでも、金塊がないでもよい。それゆえ、あえて描くならば、テーブルの上にパンダがいる絵を描き、それにバツ印を書き加えるといったことだろう。そのとき、バツ印は絵の一部だろうか。テーブルが絵の一部であるように、バツ印も絵の一部なのだろうか。少なくとも写実的な像の一部ではない。バツ印は、描かれた絵に対してその絵を否定するといういう、絵全体に対するある態度を表わしている。こうしたことも、否定詞が名ではないことを直観的に支持してくれるだろう。(102~103頁)
■ポチは白いという事態はあるが、ポチは白くないという、いわば否定的事態などあるはしない。これは当然とも言える論点であるが、きちんと押さえておいてほしい。事態とは対象の配列の可能性にほかならない。しかし、否定は対象ではない。それゆえ、事態はそのすみずみまで肯定的なものでしかありえない。否定命題の意味は事態の像という観点からだけでは捉えきれないのである。(104頁)
■いずれにせよ、すぐれて「像」と呼ばれるべきものは名の配列が対象の配列を表わしているものであり。それゆえ否定命題はそのような意味では像ではない。しかし、像ではないと言ってしまうことにも問題が残る。『論考』四・〇六において『命題は現実の像であることによってのみ、真か偽でありうる」と断言しているからである。この箇所はすぐ次に否定が論じられる箇所であり、ここで「命題」と呼んでいるものに否定命題も含まれていることは疑いがない。とすれば、ここまできっぱり言われてしまってはしょうがない、否定命題のように名の配列だけではないものもまた、像なのである。
だが、そうだとすれば、否定命題は何の像なのだろうか。どうも『論考』を読んでいるとこういうところが次々と気になってくるのである。私自信、これに関してはかなりあれこれ考えたのだが、結論だけ述べておこう。「Pではない」という否定命題は、事態Pの像なのである。「へ?」と思われるかもしれないが、どうもそうとしか考えようがない。「それじゃあ、肯定命題『P』も否定命題『Pではない』も、同じ事態Pの像になってしまうが、それでよいのか?」と訪ねられるかもしれないが、それでよいのである。事態の側に否定に対応する対象を認めない以上、そう結論するするしかない。ならば、肯定も否定も像として同じものなのかと言えば、それはそうではない。両者はたしかに同一の事態を写している。しかし、肯定命題と否定命題はそれぞれ異なった仕方で、それを写しとっているのである。つまり、肯定命題は事態を肯定的に写し、否定命題はそれを否定的に写す。「事態Pを否定的に写す」ということがどういうことかと言えば、つまり、その真理領域の中にPを含ませないような仕方でPを写すということにほかならない。「肯定的に写す」とは、真理領域にPを含ませる仕方でPを写すということである。像関係とは、それがどの事態の像なのかということに加えて、その事態をどのように写しとっているのかという写像の仕方をも含めて捉えられねばならない。それゆえ、像関係とは、たんにひとつの像とひとつの事態との間の対応関係を意味するものではない。あくまでも論理空間全体を背景にもちつつ、事態との間に対応関係をもつものでなければならない。そのようにしてはじめて、否定を像という観点のもとで捉えることができる。(110~112頁)
■二・〇二 対象は単純である。(128頁)
■四・一一六 およそ考えられうることはすべて明晰に考えられうる。(141頁)
■「ア・プリオリ」という伝統的な哲学用語はウィトゲンシュタインの哲学においてもキーワードとなる。それは「経験に先立つ」ものであり、「経験」とは論理空間における諸可能性の中のどれが現実として現われているかを認識することである。別の言い方をするならば、経験命題の真偽を確定するものが経験であり、「ア・プリオリ」とは、検証に先立ち、検証を可能にするために前提にされているということにほかならない。ここにおいて、「科学」と「哲学」が対比される。ウィトゲンシュタインは経験による検証を、一括して「科学」に属するものとみなす。他方哲学はただひたすらア・プリオリなものに関わる。「語りうるもの」とは科学であり、それに対して、ア・プリオリなものこそが、『論考』が明示しようとしている「語りえぬもの」たちの中核なのである。(178頁)
■五・五五二 論理を理解するためにわれわれが必要とする「経験」は何かがかくかくであるというものではなく、何かが〈ある〉というものである。しかしそれはまさにいささかも経験ではない。
論理は何かが〈このように〉あるといういかなる経験よりも〈前に〉ある。
論理は「いかに」よりも前にあるが、「何が」よりも前ではない。
「ともあれ何かが存在する」ということ、これは存在論的経験よりも原初的であり、たしかにもはや経験とは呼びえないだろう。しかし、私の前になんらかの可能性が開けているかぎり、私はどこかで現実と接触していなければならない。何かが存在することは、私は確かなものとして受けとめていなければならない。ともあれ何かが存在する。それは認識よりも、論理よりも、あらゆるものに先立つ、始原なのである。(189頁)
■五・六 私の言葉の限界が私の世界の限界を意味する。(205頁)
■こうして、ただ現われるものだけを厳格に禁欲的に受け取ることにおいて、げんしょうしゅぎは独我論へと踏み込んでいく。現象主義のもとでは、たとえば他人の頭痛などは意味を失う。他人の痛みは私には現われえない。もし私に現われたならば、それは私が痛いということであり、私の痛みでしかない。あるいはまた他人の知覚も私には現われえない。「他人の意識」あるいは「他の意識主体」、そう呼ばれうるようなものは現象主義の受け取る世界にはもはや何ひとつない。他我が消え去り、ただ自我のみが存在する。すなわち、独我論の世界が開ける。
さらに、他人の意識を抹消することによって、現象主義はその現れを「私の意識への現われ」と言うことさえできないことになる。現れはすべて私の意識への現われでしかありえず、それゆえむしろそれを「私の意識」と言い立てることにはポイントがなくなるのである。意識主体たる私ではない。その場合にも、そこで意識された私自身を意識している私がいる。意識主体たる私は意識への現れを受け散る主体であり、それはそうした現れを超越しているのでなければならない。そして他人の意識は現われえないのだから、私は現れを私への現れと他人への現れとに区別する必要もない。ただ、現れがある。これが現象主義の開く世界にほかならない。
こうした現象主義がその現われの世界を記述するとき、それはどうしたってある独特な言語にならざるをえないだろう。たとえば「彼女はひどい歯痛に悩まされている」という日常的な言い方は、それが痛みを感じる意識主体たる彼女を想定していることにおいて拒否されねばならない。あるいは、「私は少し頭が痛い」という言い方における「私」もまた、現れを受け取る主体としての自我それ自身は現れえないという理由で、消去されねばならない。(207~208頁)
■ ものは私の意志との関係によってはじめて「意味」を獲得する。
なぜならば、「すべてのものは、それがあるところのものであって、それ以外の
ものではない」からである。(『草稿』1916年10月15日)
■「言語」とは有意味な命題の総体にほかならない。そして有意味な複合命題の総体は要素命題の総体によって決定される。さらに、要素命題の総体は名の総体によって決まる。それゆえ、言語の総体を規定するものは名の総体である。また、名の総体は対象の総体に対応する。そして対象の総体は事態の総体を決め、事態の総体は論理空間を決定する。それゆえ、論理空間を規定するものは対象の総体である。
五・五五六一 経験的実在は対象の総体によって限界づけられる。限界は再び要素命題の総体において示される。(215~216頁)
■五・六二 この見解が、独我論はどの程度正しいかという問いに答える鍵とな
る。
「この見解」とはまさに五・六一の「存在論は語りえない」という議論である。この関連は現象主義的解釈には捉えがたいものであるに違いない。しかし。いまやわれわれはその関連を明らかにすることができる。五・六二の残りの部分を引用しよう。
すなわち、独我論の言わんとするところはまったく正しい。ただ、それは語られえず、示されているのである。
世界が私の世界であることは、この言語(私が理解する唯一の言語)の限界が私の世界の限界を意味することに示されている。
独我論は正しい。それは私の論理空間が外部をもたないということにほかならない。私はこの論理空間の外にある他の存在論について、それを語ることも示すこともできない。私はいかなる意味でもそれを理解することができない。
そして同時に、独我論は語られえず、示されている。それは私自身の存在論が語られえず示されうるのみであるということにほかならない。こうして、独我論についての主張は、存在論についての主張とぴったり重なることになる。(220~221頁)
■ばず、独我論は主体否定テーゼを伴って完成される。独我論は、「世界は私の世界である」と言う。しかし、主体否定テーゼに従えば、「私の世界」と言われるべき「私」は世界の内にはない。それは世界が存在するための前提であり、現れてくるのはただ世界だけである。それゆえ、独我論の「世界は私の世界である」という主張は、主体否定テーゼを経て、そこにおける「私」さえ消去されることとなり、結果として、たんに「世界はこの世界である」と主張するだけのものとなる。この点を捉えてウィトゲンシュタインは次のように主張する。
五・六四 ここにおいて、独我論を徹底すると純粋な実在論と一致することが見
てとられる。独我論の自我は広がりを欠いた点にまで縮退し、自我に対応する実
在が残される。(246頁)
■では、論理や数学の命題はなぜ必然的なものになるのだろうか。
これに対するひとつの応答が「心理主義」と呼ばれるものである。「論理とは思考の法則にほかならない」、心理主義はそう説明する。そのとき、論理学はいわば心理学の一分野となる。そしてさらにこう説明を続けるだろう。思考法則は自分の思考を反省してみるだけで分かるものであるから、その意味でそれはア・プリオリに知られる。さらに、それは思考を律する法則であるから、それに反したことをわれわれは考えることができない。その意味でそれは必然的に真となる。(252頁)
■論理実証主義は、20世紀前半、とくに1930年代にその中心的活動を為した哲学うんどうである。彼らは、フレーゲとラッセルによって開発された記号論理学を武器として携え、ラディカルな経験主義を標榜した。単純に言ってしまえば、経験に基づいたデータから論理的に展開されるもののみをまっとうな認識(科学的認識)として認め、そうでないものは悪しき形而上学として追放しようというのである。
彼らはその運動の初期において『論考』と出会った。そして決定的な影響を受けた。(255頁)
■「規約」と呼ばれうるものの典型的な例を出すならば、たとえば自動車は道路の左側を走らねばならないという日本の交通法規が挙げられる。別に右側で統一してもよかったかもしれない。しかし、われわれは「左側を走る」という規則に決めたのである。これがもし、最初から選択の余地なく、なんらかの不可思議な力によって左側しか走れないようになっていたとするならば、そもそも「取り決め」ということの意味が失われてしまうだろう。「右でも左でもよいのだが、どっちにするか」という選択肢を前にして、どちらを選ぶことも恣意的であるときにのみ、そのどちらかに取り決めるということが言える。だから、枝から離れたリンゴが下に落ちるのは、取り決めではない。(262~263頁)
■ここは、『論考』が規約主義ではないことに同意されたとしても、なお誤解されやすいところであるから、繰り返し強調しておきたい。『論考』が規約主義ではありえないのは、たしかに表面的には論理空間が唯一のものと想定されていたからである。しかし、より深い理由はそこにはない。それは、論理が操作に基づき、それゆえ強い意味でア・プリオリだからである。(264頁)
■六・一二七 論理学の命題はすべてが同じ身分である。それらの間に基本法則と派生的命題が本質的に定まっているというようなものではない。(265頁)
■まずフレーゲとラッセルの路線を簡単に紹介しよう。たとえば箱の中に10個のリンゴがある。われわれはそこで「リンゴが10個ある」と言う。ここにおいて「10個ある」と言われるには、あたりまえのことであるが、個々のリンゴではない。個々のリンゴはそれぞれ1個であり、このリンゴについて、それが10個あるという性質をもっていると言われているわけではない。それゆえ「10」という性質が与えられているのは、あくまでもそのリンゴの集合に対してである。つまり、数とは集合の性質なのである。そこでメンバーの数が10であるような集合をすべて集めてくるならば、それらが共通にもっている性質が、すなわち「10」であると考えられる。あるいは、「10」とはメンバーのかずが0であるような集合のすべてからなる集合の名前にほかならない。こうして、フレーゲとラッセルは数を集合の性質あるいは集合の集合として捉えるわけである。
これに対して『論考』における数の捉え方はこうである。
六・〇二一 数は操作のベキである。
「操作のベキ」とは、操作の反復回数のことにほかならない。ここで操作とはとりわけ真理操作を意味しているが、別に真理操作に限定する必要はないだろう。単純に言って、「何回操作したか」、それが数だというのである。それゆえ、数詞は名ではない。これは「論理語は名ではない」という主張と正確に対応している。論理語は操作を表わし、操作は対象ではない。それゆえ、操作のベキも対象ではない。こうしてウィトゲンシュタインは、数をなんらかの対象として理解することを拒否する。数は集合の性質のようなものではない。(274~275頁)
■私はただこれらの対象から、そしてこれらの対象のみから事態を構成し、それによって論理空間を張る。それゆえ、対象領域が異なれば論理空間は異なったものとなる。しかし、私はこの論理空間の内部で思考するのであり、他の論理空間なるものは端的に思考不可能なものでしかない。だとすれば、私にとっては、これらの対象が存在するということは、私がこのような思考可能性の内に生きているかぎり、選択の余地のないもの、他の選択肢を考えることのできないものとなる。対象の存在に対して、「たまたまのことだ」と言いたくなるざわめきにも似た思いを断ち切って、そのある意味で「必然的」と言わねばならない相が現れてくる。これが、「神秘」である。
六・四四 神秘とは、世界がいかにあるかではなく、世界があるというそのこと
である。(283頁)
■関連してもうひとつ問題を提起しよう。「倫理は超越論的である」と述べたそのすぐ後に、カッコの中に入れられて、次のコメントが挿入される。
六・四二一 (倫理と美はひとつである。)(289頁)
■「永遠の相のもとに世界を見る」とは論理空間とともに対象を見ることにほかならず、そして論理空間の内部には私の死だけを他人の死から区別するものは何もない、つまり論理空間の内部においてであれば私の死は存在すると考えられるからである。しかし、この点は慎重に検討しなければならない。
もしかなうならば、ウィトゲンシュタインに確かめてみたい。
「あなたの論理空間に、あなた自身の死は含まれているのでしょうか」
答えは否定的であるようにもおもわれる。なにしろ死は人生のできごとではないのだから。だが、それならばさらに尋ねたい。
「ではたとえばソクラテスの死やラッセルの死は論理空間に含まれているのでしょうか」
これに対しては肯定的な答えを期待したい。死が私の人生のできごとではないというのはあくまでも私の死についてであり、他人の死ではない。他人の死はもう死んでいる人であれば現実の事実として、まだ生きている人であれば可能的な事実として、論理空間に含まれている。では、「私は百年後には死んでいるだろう」という命題はどうなのだろうか。
あるいは別の尋ね方をしよう。
「あなたの論理空間の内部において、あなた自身は他の人にはない独自の位置を占めているのでしょうか」(294~295頁)
■この世界の苦難を避けることができないというのに、そもそもいかにしてひとは
幸福でありうるのか。(『草稿』1916年8月13日)
これは幸福に対するペシミズムではない。逆である。ここでウィトゲンシュタインは幸福についてむしろとても楽天的に考えていると言える。世俗的な意味でどれほど苦難に満ちた人生であろうとも、幸福は訪れるはずだ。この信念、この希望。
幸福の本質はいっさいの現世的な状態とは別のところにある。それゆえ、幸福な何が起ころうとも幸福であり、不幸な人は何が起ころうとも不幸である。「何が起ころうとも」というこの特徴は、これもまた正当な意味においてではないけれども、「必然的」と呼びたくなる特徴と言えるだろう。トートロジーが何が起ころうとも真であり、それゆえ必然的に真であったように、幸福な人は「必然的に」幸福なのである。
六・四一 世界の意義は世界の外になければならない。世界の中ではすべてはあ
るようにあり、すべては起こるように起こる。世界の中には価値は存在しない。
私がこのような幸福を引き受けるとすれば、それは論理空間の内部においてではありえない。論理空間の内部にあるのは事実である。そしていま考えられている幸福は世俗的なものではない。「何が起ころうと幸福である」と言いうる地点に立つためには、幸福を論理空間の内部において現れてくるような個人の境遇の一種にしてしまうわけにはいかない。ウィトゲンシュタインの言う幸福とは、論理空間がそこに根ざしている私の生におけるものであるだろう。すなわち、幸福を享受する主体は、永遠の相のもとに世界を見てとっている私にほかならない。(302~303頁)
■善と悪は主体によってはじめて登場する。そして主体は世界に属さない。それは
世界の限界である。
(ショーペンハウエルのように)こう述べることもできる。表象の世界は善でも
悪でもない。善であったり悪であったりするのは意志する主体である。
これらの命題はすべてまったく明晰さを欠いていると私は自覚している。
つまり、これまで述べたことからすれば、意志する主体が幸福か不幸かでなけれ
ばならないのだ。そして幸福も不幸も世界には属しえない。
主体が世界の一部ではなく世界の存在の前提であるように、善悪は世界の中の性
質ではなく、主体の述語なのだ。
主体の本質はまだまったくベールの向こうにある。
そうだ。私の仕事は論理の基礎から世界の本質へと広がってきている。(『草
稿』1916年8月2日)
世界の事実を事実ありのままに受けとる純粋に観想的な主体には幸福も不幸もない。幸福や不幸を生み出すのは、生きる意志である。生きる意志に満たされた世界、それが善き生であり、幸福な世界である。生きる意志を奪い取る世界、それが悪しき生であり、不幸な世界である。あるいは、ここで美との通底点を見出すならば、美とは私に生きる意志を呼び覚ます力のことであるだろう。
そして美とは、まさに幸福にするもののことだ。(『草稿』1916年10月21日)
ここにおいてこそ、「世界と生とはひとつである」と最終的に言われうる。(304~305頁)
■私の人生がかくもみじめである、あるいは満ち足りているのも、それは私の人生上の世俗的なエピソードのかめではない。ひとえに私の生きる意志にかかっている。生きようとすること。自殺ぎりぎりのところで踏み止まっていたウィトゲンシュタインの声にならない声。それこそが、『論考』の沈黙の意味するところだった。それはたんに語ることができないという沈黙ではない。示すこともできない。いっそう深いその沈黙のうちに差し出される「生の器」を、生きる意志でみたすこと。かくして『論考』全体を貫くウィトゲンシュタインのメッセージは、次の一言に集約される。
幸福に生きよ!(『草稿』1916年7月8日)(307頁)
■おそらく本書は、ここに表わされている思想――ないしはそれに類似した思想
――をすでに自ら考えたことのある人だけに理解されるだろう。
序文のこの言葉は、たんに『論考』も思想が目新しいというだけでなく、まさに『論考』の方法に触れたものになっている。『論考』は何ごとかを「説明」するものではない。その方法は「解明」であり『論考』の主張するところからしても、それは解明でしかありえなかった。日常言語の論理を説明することはできない。すでに論理になじんでいる者のみが、『論考』の解明する論理を理解することができる。さらに言えば、『論考』の全構図が私の生に根ざし、しかもそれが他の生を拒否するものである以上、『論考』を実質をもって理解できる人は、ただ一人、『論考』の著者だけであるようにさえ思われる。(308~309頁)
■ウィトゲンシュタイン自身は『論考』を独我論の脈絡に置こうとしていた。どうしてもそう感じられる。ウィトゲンシュタインは論理空間を共有しない者として他者を捉え、それを拒否することにおいて、痛切に意味の他者という力を感じていた。それはおそらくたしかなことである。はなから鈍感であればこのような独我論を提示するはずもない。『論考』全体が、意味の他者という他者性に向けてピリピリと神経を尖らせているようにさえ感じられる。いや『論考』に限らずウィトゲンシュタインの哲学全体に、たえず自らの思考の外部に潜む他者の影が射している。だがそれは、ウィトゲンシュタインにとって迎え入れるべき希望ではなく、払い除けるべき不安であったように思われる。それゆえウィトゲンシュタインは『論考』を書き、『論考』の中に自閉しようとした。私は、ウィトゲンシュタインの最大の過ちはそこにあったと言いたい。(313頁)
■かくして、ひとたび名と操作(論理語)が固定されるならば、そこから構成される全命題も固定される。予見しえないものは、可能な命題のどれが真でありどれが偽なのかという認識である。たとえば今日の天気はカーテンを開けて外を見ることによってはじめて知りうる。しかし、どんな天候が眼前に広がろうとも、それは私の思考可能性の中に用意されていたものでしかない。その意味で、思ってもいなかった天気などありはしない。世界の実情がどうであれ、それはすべて私の論理空間に用意されている。
六・一二五一 それゆえ論理においても驚きはけっして生じえない。
自然数をいくら数え続けても驚き(こんな数があったのか!)はありえないように、論理空間をいくら精査しても驚くべきことは何ひとつない。あえて「退屈」という言葉を使おう。自然数をただひたすら数え続けることが退屈でしかないように、論理空間は退屈に満たされる。固定された基底と操作の反復によって開かれる無限は、本質的に退屈なものでしかありえない。そしてウィトゲンシュタインは、その退屈を積極的に迎えいれた。
現在の中で生きる人は、恐れや希望なしに生きる。(『草稿』1916年7月14日)
――中略――
六・五 謎は存在しない。(315~317頁)
■実際の言語を詳しく見れば見るほど、この言語とわれわれの要求するものとの衝
突は激しくなる。(論理に結晶のような純粋さを見るのは、調べて分かったこと
ではなく、要求だったのだ。)この衝突は耐え難くなり、われわれの要求はもは
や空虚なものになろうとしている。――われわれはツルツルした氷の上に入り込
み、摩擦がなく、それゆえある意味では条件は理想的なのだが、まさにそのため
に歩くことができない。われわれは歩きたいのである。だから摩擦が必要なの
だ。ザラザラした大地へ戻れ!(『探求』第107節)(351頁)
■私が書くもののすべてがそれを巡っている、ひとつの大問題――世界にア・プリ
オリな秩序は存在するか。存在するのならば、それは何か。(『草稿』1915年
6月1日)(360頁)
■「語られぬ自然」が言語を支え、その言葉をもってわれわれは自然を語り出すのである。ウィトゲンシュタインは言語実践を支えるこうした自然の秩序を「自然誌」と呼ぶ。それゆえ、自然誌とは――私の考えでは――記述された自然の秩序ではありえない。私の好みで、きっとウィトゲンシュタインが嫌がるだろうカントめかした言い方をさせてもらうならば、それは、自然現象の記述が可能であるために要請される「自然それ自体」なのである。(370頁)
「『論理哲学論考』を読む」野矢茂樹 ちくま学芸文庫 2008年12月27日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■たくさんの哲学的な問題があることは間違いない。それについて考えれば考えるほど、さらにたくさんの問題を見つけることができる。それらの問題は、見渡す限り遠くまで広がっている。そしてそれらの大部分は未解決のままなのだ。今日では、強力なコンピューターや望遠鏡やクレーン等々を使えば、それらの問題がどれほどの重さのあるものなのかを計算することができるだろう。もっともそれらの問題が集められて、すべてが1カ所に置かれたとしての話だが。あるいはそれらが端から端まで並べられたなら、どれくらい遠くまで延びるかを計算することもできるだろうし、それらの問題を非常に綿密に検討すれば、それらがどのような断片から成り立っているのか正確にわかるであろう。なぜなら今日ではコンピューターとテクノロジーは、ほとんどどんな事でも、重要なことは何でも疑いがなくできるからである。恐らくは哲学の諸問題を解決すること以外は。
哲学の諸問題にとって問題なのは、それらの諸問題にはしかるべき解決法がないということなのである。(116~117頁)
■ギュゲスの指輪
表面的に見れば、ギュゲスの指輪の物語は人間の本性についての物語である。しかし、この物語の原型が見出されるプラトンの『国家』第2巻では、それは道徳と倫理的な価値についてのもっと広汎な議論の一部なのだ。この中でクラウコンは、「正義」と「不正」の起源はもっと偉大な何物よりも明らさまな自己利益の方により多くの関わりを持っているという彼の主張を説明するための方法として、この物語をソクラテスに語ったのである。正義とは単に、「不正を行いながら何の罰も受けないという最も望ましいこと」と「不正をこうむりながらそれに関して何をすることもできないという最も望ましくないこと」との間の妥協にすぎないのだ。この意味においてはギュゲスの指輪の物語は、社会契約つまり自由を安全と交換するために市民たちが署名する想像上の契約の物語でもあるのである。(159頁)
■ケーニヒスベルクの厳格な論理学および形而上学の教授であったイマーヌエル・カント(1724-1804)は、1つどころか(それだけでもたいていの哲学者たちのとっては十分な数だが)4つの新しい専門用語を考案することによって、哲学に対して最大の貢献をした。その4つというのは「分析的(analytic)」とその反対語である「総合的(synthetic)」、「先験的(アプリオリ)」とその反対語である「後験的(アポステリオリ)」である。それらの意味は極端にあいまいなものだ。(200頁)
■エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック(1715-1780)は次のような物語を述べている。深い眠りから目覚めたら自分が何人かの他の人々と一緒に迷路の中にいることに気づいたと想像してみたまえ。他の人々は外に出る方法を見つけるための一般的な原則をめぐって議論しているとする。エティエンヌが言うように、これはひどくばかげたことのように見えるかもしれない。しかし彼が言うには、それこそまさに哲学者たちがしていることなのである。「まず最初にただ単にわれわれ自身がどこにいるのかを知ることの方が、早まってもう迷路の外に出ていると信じこむことよりも、重要なことなのである」と彼は結論づける。
けれども、別のアプローチの仕方が、問題の中にそれとなく示されている。そのアプローチの仕方というのは、われわれには瞑想するよりももっと役に立つ仕事があるということなのである。今日ではわれわれは多くの事柄をしたがっており、また多くの物をつくったり、それを感性したりしたがっている。今日ではわれわれは自分たちの体よりもすぐれており、また実際のところ、われわれの精神よりもすぐれているような機械を用いることで、世界を実用的に扱っているのである。結局のところ、瞑想することによって金持になった人間は1人もいないのだ。(231~232頁)
■残念なことに、哲学の最も重要な問題のいくつかがまだ一般には解決不可能な部類に属するものと思われていることを気にかけながら、モーリッツ・シュリックは話を続ける。それらの問題は「論理」的に解答不能なのか、原則的に解答不能なのか、実際の状況のために「経験」的に解答不能なのかのいずれかなのだ、と。けれども真の質問というものは決して論理的に解答不能であってはならない。なぜなら、それは自らの意味を示すことができないということに等しいからであり、意味を持たない質問は結局のところ、質問ではないからだ。そんな質問は後ろに疑問符が置かれた「ナンセンスな言葉の連なり」にすぎないのである。
かくしてシュリック教授は厳しい結論を下して言う。哲学者が「時間の本質とは何か?」とか「われわれは絶対者(神)を知ることができるか?」というような言葉の連なりによってわれわれを面くらわせながらも、「注意深くて正確な解釈と定義によってそれらの言葉の意味を説明することを怠る」ときには、答が何一つ用意されていなくても驚いてはならない。「それはあたかも「哲学の重さはどのくらいなのか?」とわれわれに問いかけたようなものなのである。」結局のところ、それは全く質問などではなくて、単なるたわ言にすぎない。
論理実証主義者たちの研究方法は、少なくともイデオロギーの面でいくらかのものを、人気はないが賢いスコットランドの哲学者デイヴィッド・ヒュームに負っている。ヒュームこそがまさに論理実証主義よりも200年知覚前に『人間知性研究』(1748)において次のように書いた人物なのである。
例えば、神学の本や学校用の形而上学の本ならどんな本でもいいから手に取っ
て、こう自問してみよう。この本には何か量や数に関する抽象的な推論が書かれ
ているだろうか? かかれてはいない。この本には何か事実や実在の諸問題に関
して経験に基づく推論が書かれているだろうか? それも書かれてはいない。そ
れならばそんなほんは火にくべてしまいなさい。なぜならこの本には詭弁と幻覚
しか書かれていないからである。(233~234頁)
『哲学101問』マーティン・コーエン著 矢橋明郎訳 ちくま学芸文庫
2008年12月29日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――