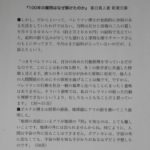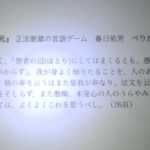『釈尊のさとり』 増谷文雄著 講談社学術文庫
識 語
■この小さな著作をよんでくださる方々に、まず3つのことを申しあげておきたいと思います。
その第一には、釈尊の「さとり」は直観であるということであります。直観というものはそれを説明してみよといわれても、言葉では説明できるものではありません、むかしの禅語に、「言語(ごんご)道断」とか、「言詮(こんせん)不到」などというのはそのことであります。
わたしは、ながい間にわたって、ただ一人の人物を見詰めてまいりました。それは、ほかでもない、釈尊その人であります。そして、釈尊の生涯とその思想において、その眼目をなすものは、申すまでもなく、かの菩提樹下における大覚成就、すなわち「さとり」であります。だが、それが、どうも、はっきりと把握できない。わたしにとっては、それがじれったくてたまらなかったのであります。だが、やっと、わたしも知ることができました。その「さとり」とは、まさしく直観であったということであります。
その第二には、その直観なるものは、受動的なものだということであります。そのことについては、わたしは、道元禅師によって啓発せられました。それは、本文のなかでも述べておいたことでもありますが、かの『正法眼蔵』の第三巻、「現成公案」のなかにおいて、道元禅師は、「自己をはこびて万法を修証(しゅしょう)するを迷いとす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり」と説いておられます。ただ「あっ、そうか」と触発せられるのが直観なのであります。それを、ああであろうか、こうであろうかと、自己の思考をもって模索するは迷いであります。
だが、しかし、そのようにして与えられた直感を、こんどは思いととのえる。すなわち、知性化することは、わたしどもの悟性の役割であります。そこで、やっと気が付いてみると、かの大覚を成就した釈尊が、なおもしばらくの間、かの樹下にとどまって思索せられたのは、それがそのような知性のいとなみのためにほかならなかったのであります。釈尊の「さとり」は、そこまで到って完成したのであります。わたしが、その樹下における釈尊のさまざまの思索についても、くどくどと申しあげたのは、その故であります。
その第三には、この小さな著作のなれる因縁について申しあげておかねばなりません。これは、一昨年、昭和五十二年九月のこと、わたしは、富山県の県民大学校地方講座に出講いたしまして、そのようにして思い整えたところを、「釈尊のさとり」という演題をもって講述いたしました。それを、富山県教育委員会においては、筆録して下さったうえ、同委員会編集の「精神開発叢書」(非売品)として上梓してくださったのであります。
しかるところ、それがさらに、講談社の編集部の方のお目にとまりまして、「学術文庫」の一冊に加えていただくことになったのであります。その因縁をはぐくんで下さった方々には、ふかく感謝いたさなければなりません。
そのようにして、この「学術文庫」の一冊に加えていただくに当っては、わたしは、旧稿に、あらためて、いささか筆を加えました。たとえば、講演では正確な表現ができなかったところを、より正確に叙述をあらためるとか、あるいは、経典などからの引用は、それをより正確にし、かつ、その出処を明記するなどであります。だが、その全体としては、もともと講演の筆録でありますので、講演のままといたしました。諒としていただきたいと思います。(3~5頁)
■それから、「現成」というのは、「実現する」とか「成就する」とかいう意味のことばで、これは古くから仏教でもちいられております。たとえば、「現成正覚」というと、他でもない、釈尊その人が「さとり」を成就したことをいう荘厳なる表現であります。
しかるに、いま禅家においては、雲水や居士たちが、御老師から公案すなわち課題をいただいて、坐禅修行のなかにおいてかの「さとり」を再体験しようとする。それを、釈尊の「現成正覚」にちなんで、ここに「現成公案」と表現されているのであります。つまり、「現成公案」とは、釈尊の道をあるこうとする者におけるの実現をいうことばであると知られるのであります。(岡野注;現成公案の私の解釈は違います)
そのなかにおいて、道元禅師は、「迷(まよい)」と「悟(さとり)」を語って、つぎのような素晴しい一節をなしているのであります。いわく、
「自己をはこびて万法を修証するを迷とす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり」「自己をはこぶ」というのは、自分のほうからすすんでというほどの意であります。「万法を修証する」とは、一切の存在、ありとあらゆるものを弁別するほどの意であります。といたしますと、この第一句のいうところは、「一切の存在のありようを、自分の方からすすんで、あれはこうであろう、これはこうであろうという具合に心を動かすことは迷いなのだ」ということであります。(20~21頁)
■さらに申しますなれば、一切の存在は、いつもその真相は、わたしどもの前に明らかに露呈しておるのでありました。それを、むかしの禅家のかたがたは、よく「万法露々(ばんぽうろろ)」などと申しておられました。一切の存在は、なんの隠すところもなく、その真相を露呈しているのであります。「柳はみどり、花はくれない」であります。その露々として現じている姿を、そのままに受けとるということが大事なのであります。
つまり、「さとり」というものは直観である。直観というものは受動性そのものである。そのことをはっきりと把握していただきますと、さきに申しましたように、がその正覚成就の消息についた、なにも語りのこしておられないことの事情もまた、よく判っていただけるはずであります。
また、鈴木大拙先生がそのことを語って、「その時、釈尊の頭のなかには、大きなクェスチョン・マークがあった」などと独特の表現をなされた、そのふかい含蓄もまた、理解していただけるはずでございます。(22頁)
■「かようにわたしは聞いた。
はじめて正覚を成就したまえる世尊は、ある時、ウルヴェーラー(優楼比螺)村のランジャラー(尼連禅)河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の初分(午後8時ごろ)のころ、つぎのように、順序にしたがって、縁起の法をよくよく観じもうた。〈これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず〉すなわち、無明(無智)に縁(よ)りて行(意志、ギョウ)がある。行によりて識(意識)がある。識によりて名色(個体)がある。名色によりて六処(6つの感官、ロクショ)がある。六処がよりて触(対象との接触、ソク)がある。触によって受(感覚)がある。受によって愛(貪り)がある。愛によりて取(取着、シュヂャク)がある。取によって有(欲望的存在、ウ)がある。有によって生(迷いの生涯、ショウ)がある。生によって老死があり、愁・悲・苦・憂・悩がある。このすべての苦の生起はかくのごとしである、と。かくて、世尊は、その所得を知って、その時、このようなウダーナ(感興の偈)を唱えたもうた。
『まこと熱意をこめて思惟する聖者に、
かの万法のあらわれとなるとき
彼の疑惑はことごとく消えされり
有因の法を知れるゆえなり』」(28~29頁)
■つづいてその経(「自説経)」は、、まず、
「はじめて正覚を成就したまえる釈尊は、ウルヴェーラー村のネーランジャラー河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
と述べております。
それは、「さとり」の直後、それから七日の間、釈尊は、さきの菩提樹のもとで、ぴたりと結跏趺坐したままで、解脱の楽しみ、すなわち「さとり」の楽しみを、じっと味わっておられたというのであります。(30頁)
■さらに続いて、この経は、
「七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の初分のころ、つぎのように、順序にしたがって、縁起の法をよくよく観じたもうた」
と叙べています。
それまで、釈尊はもっぱら「さとり」の楽しみを享受することに浸っておられましたが、ここで釈尊の悟性は、はっきりと働きはじめたのであります。その与えられたる直感を素材として、いまや、その論理的関係を追究する人間の思惟が作用しはじめたのであります。7日を過ぎたのち、世尊は、「その定より起って」とあります。「定」とは、また「三昧」(concentration)という。心を一境に集注すること。その時には、心念はほぼ停止するがゆえに、それをまた「定」と訳するのであります。
それまで、釈尊は、その定中にあって「解脱のたのしみを享けつつ坐したもうた」のでありました。だが、いまは、「その定より起って」、縁起の論理的関係を追究しはじめたのであります。直観の受動態をひるがえして、悟性の能動的活動がはじめられたのであります。
そして、その悟性のいとなみとして、最初になった成果は、そこに、つぎのように語られております。
「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」
それを、漢訳をもって申しますと、「因是有是、比生則生」(これによってこれあり、これ生ずればこれ生ず)などと見えております。(31~32頁)
■それにつけても、ふと思いだすのでありますが、経典にしばしば見えていることばに、「阿耨多羅三藐三菩提」という述語がございます。仏教を学びはじめた頃には、なんとまあむずかしいことばであろうかと思ったことがありましたば、それもそのはずでありまして、これは梵語の音写でありました。
それを意訳いたしますれば、「無上正等覚」などとなることばであります。「無上」というは最高ということ、「正」というは妥当すること、そして、「等」というは普遍なることを意味するのであります。それを今日の学術的な用語をもっていうならば、最高の普遍妥当性を有する真理であることを意味することばであります。(33~34頁)
■では、その苦の問題について、釈尊はどのように考えたのでありましょうか。それは、この経が、つづいて述べているながながしい連鎖のつづきであります。いわく、
「すなわち、無明によりて行がある。行によりて識がある。識によりて名色がある。名色によりて六処がある。六処によりて触がある。触によりて受がある。受によりて愛がある。愛によりて取がある。取によりて有がある。有によりて生がある。生によりて老死があり、愁・悲・苦・憂・悩がある。このすべての苦の生起はかくのごとしである」
そこには、「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」という公式にあてて、その生起の条件を順次に思いめぐらしてゆくと、そこには、明・行(ぎょう)・識・名色・六処・触(そく)・受・愛・取・有(う)・生(しょう)・老死と、十二の条件が順次に連鎖をなしていることが考えられたのであります。
それがいうところの十二縁起、もしくは十二因縁と称せられるところのものでして、そのような条件の連鎖によって苦が生起するのだと知られたのでありました。(34~35頁)
■では、その経もまた、ごく短い経でありますので、そのままに読んでみたいと思います。
「かようにわたしは聞いた。
はじめて正覚を成就したまえる世尊は、ある時、ウルヴェーラー(優楼比螺)村のランジャラー(尼連禅)河のほとりなる菩提樹のもとにましました。その時、世尊は、一たび結跏趺坐したままにして、七日間、解脱のたのしみを亨けつつ坐しもうた。
七日を過ぎてのち、世尊は、その定(じょう)より起って、夜の中分(午前零時ごろ)のころ、つぎのように、逆次にしたがって、縁起の法をよくよく観じもうた。〈これなければこれなし、これ滅すればこれ滅す〉すなわち、無明(無智)の滅によりて行(意志、ギョウ)滅す。行の滅によりて識(意識)滅す。識の滅によりて名色(個体)滅す。名色の滅によりて六処(6つの感官、ロクショ)滅す。六処の滅によりて触(対象との接触、ソク)滅す。触の滅によりて受(感覚)滅す。受の滅によりて愛(貪り)滅す。愛の滅によりて取(取着、シュヂャク)滅す。取の滅によりて有(欲望的存在、ウ)が滅する。有が滅すれば生(迷いの生涯、ショウ)が滅する。生が滅すれば老死が滅し、愁・悲・苦・憂・悩が滅する。このすべての苦の滅はかくのごとくである、と。かくて、世尊は、その所得を知って、その時、このようなウダーナ(感興の偈)を唱えたもうた。
『まこと熱意をこめて思惟する聖者に、
かの万法のあらわれとなるとき
彼の疑惑はことごとく消えされり
諸縁の滅を知れるがゆえなり』」(36~37頁)
■この経の叙するところも、また、さきの経の叙述によく似ているようでありますが、よく読んでみると、大事なところで、二つの対照的なちがいを存しております。
その第一は、例の「縁起の公式」についてでありますが、さきの経においては、それは、
「これあればこれあり、これ生ずればこれ生ず」
と述べられてありましたが、この経においては、それに対するところは、こんどは、
「これなければこれなし、これ滅すればこれ滅す」
と述べられてあります。それを漢訳についてみると、「比滅即滅、比無即無」(これ滅すればすなわち滅す、これ無ければすなわち無し)などとなっております。それを、さきの表現を「縁起の公式」と申しますならば、この表現は「縁滅の公式」とでもいうところでございましょう。そして、さきの 「縁起の公式」に対しまして、さらにこの「縁滅の公式」が成立することによって、釈尊の「さとり」は、はじめて完全なものとなるのであります。
なんとなれば、すでに申したように、釈尊が、その出家に際して胸奥にいだいていた課題は、他でもない、苦の問題でありました。その苦なるものはいかにして存するものであるか。いかにして苦なるものは生起するのであるか。そのことについて、「このすべての苦の生起はかくのごとくである」と、みごとにその「縁(よ)りて起る」ところを解明しえたのは、さきの「縁起の公式」によるものでありました。(37~38頁)
■だが、その生起の条件をあきらかにしただけでは、まだまだ課題は解決したわけではありません。そこにはもう一つ、ではいかにして克服するか。その方途が確立されねばなりません。その方途のよりて考えられるべき準則が、この「縁滅の公式」なのでありました。
では、その苦を滅尽するためには、釈尊はどのように考えたのでありましょうか。それを、この経もまた、ながながしい連鎖をもって、つぎのように語っております。それが、第二のちがいであります。いわく、
「すなわち、無明(無智)の滅によりて行(意志、ギョウ)滅す。行の滅によりて識(意識)滅す。識の滅によりて名色(個体)滅す。名色の滅によりて六処(6つの感官、ロクショ)滅す。六処の滅によりて触(対象との接触、ソク)滅す。触の滅によりて受(感覚)滅す。受の滅によりて愛(貪り)滅す。愛の滅によりて取(取着、シュヂャク)滅す。取の滅によりて有(欲望的存在、ウ)が滅する。有が滅すれば生(迷いの生涯、ショウ)が滅する。生が滅すれば老死が滅し、愁・悲・苦・憂・悩が滅する。このすべての苦の滅はかくのごとくである」
そこでは、「これでなければこれなし、これ滅すればこれ滅す」という、いうところの「縁滅の公式」にあてて、その滅尽の条件を、こんどは逆の順序によって思いめぐらしてゆく。すると、そこには、無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死と、さきの十二の条件が、今度は逆の順序によって連鎖をなしていることがしられたのであります。
それもまた、いうところの十二縁起、もしくは十二因縁と称せられるところのものでありまして、そのような条件の連続によって、苦の滅尽が実現せられるというのであります。
かくて、この経は、
「まこと熱意をこめて思惟する聖者に
かの万法のあらわとなれるとき
彼の疑惑はことごとく消え去れり
諸縁の滅を知れるがゆえなり」
との偈をもって結ばれているのであります。
釈尊は、かの菩提樹のもとにおいて、ついに正覚を成就なされてからも、なお、おなじ樹下にとどまられること、さらに二週間、もしくは三週間、その間には「さとり」の内容をいろいろ整理しておられました。さきに申した二つの経典の叙するところは、その間における釈尊の、貴重なる悟性のいとなみの跡でありました。(39~40頁)
■そこに「苦の聖諦」(the proposition about sufferring) というのは、苦についての聖なる命題というほどの意味のことばであります。「比丘たちよ、わたしの苦に関する命題はこれである」と、釈尊はまず、苦とは何であるかについて、この「苦の聖諦」を、はじめて釈尊の説法を聞く五人の修行者のまえに打ち出したのであります。
そこで釈尊が語られたものは、まず、生・老・病・死の四つの苦でありました。これを後代の人々はよく「四苦」と申しました。だが、それだけではない。わたしどもこの人間とてのそんざいは、なおいろいろの苦にとりかこまれています。
「怨憎するものに会うのは苦である」。それを中国の訳経者たちは「怨憎会苦」と訳しました。また、「愛するものと別離するのは苦である」。それを中国の訳経者たちは「愛別離苦」と訳しました。美しい訳語でありました。さらに、「求めて得ざるは苦である」。それは漢訳では「求不得苦(くふとっく)」と訳されました。(42頁)
■そのように追究してまいりますと、結局、「総じていえば、この人間の存在を構成するものすべて苦である」ということになります。それは漢訳においては「五蘊(陰、オン)盛苦」などと訳されております。五蘊もしくは五陰というのは、人間を構成する肉体的および精神的諸要素をあげて、人間存在のすべてを指していることばでありまして、つまり、われら人間の存在は、いずれの面よりいっても、すべて苦におおわれているのだというのであります。(42~43頁)
■それは、釈尊の弟子の比丘のサーリプッタ(舎利弗)が、マガダ(摩掲陀)の国のナーラカ(那羅迦)という剥らにとどまっている解きのことでありました。その村は、彼の故郷でありますので、帰省していたのでもあろうかと思います。そこに、かねて知り合いの外道の遊行者のジャンプカーダカ(闇浮車)なるものが訪ねてまいりまして、いろいろの質問をいたしましたが、そのなかに、つぎのような問答がしるされているのであります。
「友サーリプッタよ、苦、苦と称せられるが、友よ、いったい、苦とはなんであろうか」
「友よ、これらの三つが苦である。すなわち、苦苦性(くくしょう)、行苦性、壊苦性(えくしょう)である。友よ、これらの三つが苦である」
このサーリプッタという比丘は、後年いうところの十大弟子中の随一でありまして、その頭脳の明晰なることで知られ、智慧第一の仏弟子と称せられた方でありますが、いま、この質問にたいする応答もまた、明快なるものであります。(43~44頁)
■彼は、ここで、いわゆる苦なるものを、三つに分類して説明しております。まず、苦苦性というのは、肉体的苦痛によって引き起こされる苦であります。たとえば寒さとか、暑さとか、飢えとか、渇(かつ)とかいった肉体的苦痛によって引き起こされる苦、〝苦しいから苦しい〟といった苦であります。
つぎに、まず、壊苦性(えくしょう)から申しあげると、これは、環境もしくは身分の変化によって起こる苦であります。たとえば、いままで金持ちだったものが貧乏になるとか、高い地位にあったものが左遷されるとか、順境から逆境に転落する。つまり、〝好もしきものが壊する苦しみ〟が壊苦(えく)なのであります。
だが、もう一つの、行苦性というのは、いささか難しい。そこで行とは、古来から「遷流(せんる)」の義ありと注されております。つまり、行とは「移ろう」ということであります。万物は流れるであります。この世はすべて無常転変であるということをいっておる言葉であります。
詮(せん)ずるところ、この世のすべてのものは、一時(いっとき)としてじっとしておるものはない、すべてが絶えず変化しているのであります。だから、そのなかに住むわたしたちの場合も、生ある者はかならず死があるのであります。若きものもかならず老いるのであります。形あるものはかならずいつかは崩れるのであります。まさしく一切が無常なのであります。行苦というのは、そのような世のなかに生きて、そのような有為転変によって感ぜしめられる苦しみなのであります。(44~45頁)
■では、いったいその十二縁起の順観と逆観とが、どのようにして苦の生起を説明し、また、苦の滅尽を可能にするものでありましょうか。それは、わたしどもにとって、容易に理解し、容易に納得することのできるものではございません。それのみではありません。釈尊 が、もともと、はじめてこのことを考えられた時には、それは、このように細かいものではなくて、もっとはるかに簡単な、そして、もっと明瞭なものであったように思われます。そのことをいくつかのふるい経典が示しているのであります。
それをごく簡単なものにして申しますなれば、たとえばそれを、無明と取と苦の三つの支節をもって説明することもできましょう。そこで、まず、無明というのは、迷いの根本としての無知であります。存在と人間の真相について正しい智慧がないことであります。つづいて、取というのは、取りつくことであります。そのことを取著とか、執著といってよいでありましょう。
だが、存在のありようというものが判っていないのでありますから、いくら取りすがってみても、詮ずるところ、それは時の移ろいとともに変化してしまう、あるいは無くなってしまう。それは取りすがっている者にとっては、苦ということになるのであります。
では、それをどうすればよいのでありましょうか。それには、まず無明をなくすことから始めねばなりません。まず無明をなくするためには、まず、一切の存在の真相を正しく見ることが必要であります。無知ではなくて、知が必要であります。仏教というものは、まさしく智慧のおしえであります。かくして、まず、その無明がなくなると、こんどは取がなくなるのであります。すべては時の移ろいとともに変化します。つまり、無常なるものに執着することはなくなるのであります。そして、取がなくなれば、おのずから苦もまたなくなるのであります。といたしますと、無明・取・苦の三支の縁起もまた成立するはずでありましょう。
十二縁起というものは、もともと、そのように簡明であったものが、次第にその支節を増して、このように支節の多いものとなったのでありましょう。(50~51頁)
■かくして、釈尊は、依然としてニグローダの樹下にあって、やがて、この新しい問題のまえに置かれた自分自身を見出したのであります。一つの経(南伝・相応部経典、六、一、勧請。漢訳、増一阿含経、十九、一)は、この新しい問題のまえに置かれた釈尊の心中の思いを、つぎのように描写しているのであります。
「わたしが借りえたこの方は、はなはだ深くして、見がたく、悟りがたい。寂静微妙(じゃくじょうみみょう)にして、思惟の領域をこえ、すぐれたる智者のみのよく覚知しうるところである。しかるに、この世間の人々は、ただ欲望をたのしみ、欲望をよろこび、欲望に躍るばかりである。欲望をたのしみ、欲望をよろこび、欲望におどる人々には、この理(ことわり)はとうてい見難い。この理とは、すべては相依生にして、縁(条件)ありて起こるということであり、また、それに反して、すべての計らいをやめ、すべての所依(しょえ)を捨てされば、渇愛つき、滅しつくして、涅槃にいたるということである。しかるに、もしわたしがこの法を説いても、人々がわたしのいうことを理解しなかったならば、わたしはただ疲労し困憊(こんぱい)するばかりであろう」
そして、いまだかって聞いたことのない未曾有の偈が、釈尊の心の中に浮んできたという。
「苦労してやっと証得したものを
なぜまた人に説かねばならぬのか
貪りと怒りとに焼かれる人々には
この法をさとることは容易ではない
これは世のつねの流れにさからい
甚深(じんじん)、微妙(みみょう)、精細にして知りがたく
欲望の激情にまみれたるもの
無明に覆われしものには悟りがたい」
それら釈尊の心中の思い、ならびに、この偈の語るところは、あきらかに、釈尊が、そのはじめ、法を説くことについて消極的であったことを示しております。(65~67頁)
■だが、そこで、この経の叙述もまた一変して、突如として、神話的叙述がはじまります。こんな具合であります。
「その時、梵天は、世尊の心中の思いを知って、かように考えた。
『ああ、これでは世間は滅びるであろう。これでは世間は滅びるであろう。世尊・応供・等正覚者のゴゴロは、躊躇(ちゅうちょ)に傾きて、法を説きたもうことに傾きたまわず』
そこで梵天は、たとえば、力ある男子が、屈したる腕を伸し、また伸したる腕を屈するがごとく、たちまちに梵天界に姿を没して、世尊のまえに現われた。
そして、梵天は、上衣を一肩に掛け、右膝を大地につけ、世尊を合掌して、礼拝して、申していった。
『世尊よ、法を説きたまえ。善逝(ぜんせい)よ、法を説きたまえ。この世には眼を塵(ちり)におおわるることすくなき人々もある。彼らも、法を聞くことを得なければ堕(お)ちてゆくであろう。この世には、法を理解するものもあるであろう』」
そして梵天は、釈尊に、人間観察を奨(すす)めました。人間というのは、この世間のことであります。そこで、釈尊は、この世の人々の姿を、もう一度、よくよく観察いたしました。すると、そこには、人々の眼の曇りおおきものもあり、曇りすくなきものもありました。利根のものもあれば、鈍根のものもありました。あるいは、教えやすいものもあり、また教えがたいものもありました。そのさまざまなる人間の姿を、経の叙述は、青(しょう)蓮華・黄(おう)蓮華・白(びゃく)蓮華のきそい咲く蓮池に喩えてかたっております。
たとえば、それらの蓮華のなかには、泥の中に生え、泥の中で長じ、泥の中で花を開いているものもありました。あるいはまた、泥の中で生じ、泥の中に長じたけれども、水面をはるかに抜んでて花を開いているものもありました。
そして、人間の世界もまた、それと同じようであることを知りました。衆生のなかには、智慧の眼が煩悩の塵でひどく汚れておるものもあれば また、その汚れのすくないものもありました。それらのことを、釈尊は、よくよく観察いたしました結果、はじめて説法の決意を固められ、梵天にむかって、つぎのような偈を説いたというのであります。いわく、
「彼らに甘露の門はひらかれたり
耳あるものは聞け、ふるき信を去れ」
ここに、「甘露の門はひらかれたり」というのは、この教えの門が開かれたということ。そして、「ふるき信を去れ」というのは、いままでの考え方を一掃して聞くがよいということであります。そして、その経の叙述は、「時に、梵天は、わが説法の願いは、世尊はこれを許したまえりと、世尊を礼拝して、そこから姿を没した」と述べて、この一巻をむすんでおります。(67~70頁)
■だが、やっとそのイシパタナ・ミガダーヤ(仙人住処・鹿野苑)に着いて、彼ら五人の比丘たちを見出すことをえた釈尊は、そこでいきなり、手強い抵抗に遇わねばなりませんでした。彼らは、釈尊が、その練りに練った構想をもって、その証悟せるところを語ろうといたしましても、頑強にそれを拒絶いたしました。苦行を放棄して奢侈(しゃし)に堕(だ)したそなたに、無上の等正覚が成就できようはずはないではないか、というのが、その強硬なる拒絶の理由でありました。(75~76頁)
■そういわれてみると、いま彼らの前に坐する釈尊の顔貌はは、清らかにして輝きわたっておりました。そこで、「では」ということで、その前に坐する五人の比丘たちのまえに、まず釈尊が開陳したものは、初転法輪(しょてんぼうりん)、すなわち、最初の説法の一節は、そのプロローグをなすものでありました。一つの経(南伝・相応部経典、五六、一一、如来所説。漢訳、雑阿含経、一五の一七、転法輪)は、それを、つぎのように記しとどめています。
「比丘はちよ、出家したる者は、二つの極端に親しみ近づいてはならない。その二つとは何であろうか。
愛欲に貪著(とんぢゃく)することは、下劣にして卑しく、また、自ら苦しめることは、ただ苦しいだけであって、聖にあらず、役に立たないことである。比丘たちよ、如来は、この二つの極端を捨てて、中道を悟った。これは、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる。
比丘たちよ、では、如来が、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる中道を悟ったというのは、どのようなことであろうか。それは聖なる八つの道である。すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定である。比丘たちよ、これが、如来の悟りえたるところの中道であって、これが、眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめるのである」(76~77頁)
■そこには、彼が、なにゆえに苦行を放棄したか、その所以(ゆえん)が語られています。それとともに、彼の選んだ道が、けっして「奢侈に堕した」ものでなかったことが語られています。彼がそこで選びとったものは、中道(the middle path) 以外のなにものでもありませんでした。そして、その中道こそが、人々に「眼を与え、智を生じ、寂静・証智・等覚(がく)・涅槃にいたらしめる」ものだと語っているのであります。そして、また、その中道とは、いかなる道であるかというならば、それは聖なる八支の道、すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定がそれであるということでありました。
つまるところ、苦行を放棄してからの釈尊がとった道は、「もろもろの欲望に貪著する」という快楽主義の道でもなく、また、「みずから苦行を事とする」という禁欲主義の道でもなく、それらの二つの極端をしりぞけて、その中道に立つということでありました。
そして、その中道というのは、いったい、いかなる道であるかというならば、それは「聖なる八つの道」、すなわち、「正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定」であると、いとも具体的に示されているのであります。(78~79頁)
■釈尊の最初の説法の本論は四つの命題から成るものでありました。それを、古来から、四諦(したい)もしくは四聖諦(しょうたい)と申してまいりました。それらは、四つの命題からなる釈尊の考え方の基本的構造をなすものでありました。それを釈尊は、最初の説法において、五人の比丘たちのまえに、つぎのように開陳いたしました。
「比丘たちよ、苦の聖諦とはこれである。いわく、生は苦である。老は苦である。病は苦である。死は苦である。愁え・悲しみ・苦しみ・憂(うれ)え・悩みは苦である。怨憎(おんぞう)するものに会うは苦である。愛するものと別離するのは苦である。求めて得ざるはくである。総じていえば、この人間の存在を構成するものはすべて苦である。
比丘たちよ、苦の生起についての聖諦とはこれである。いわく、迷いの生涯を引き起こし、喜びと貪りとを伴い、あれへこれへと絡(から)まりつく渇愛がそれである。すなわち、欲の渇愛・有(う)の渇愛、無有(むう)の渇愛がそれである」
まず、これが、四つの聖諦のうちの、前半の二つの命題であります。(80~81頁)
■さて、前半の二つの命題につづいて、釈尊は、こんどは、後半の二つの命題を、つぎのように開陳いたしました。
「比丘たちよ、苦の滅尽についての聖諦はこうである。いわく、その渇愛をあますところなく離れ滅して、捨て去り、振り切り、解脱して、執着なきにいたるのである。
比丘たちよ、苦の滅尽にいたる道についての聖諦はこうである。いわく、聖なる八支の道、すなわち、正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定である」(82~83頁)
■もう一度その実践項目を列挙いたしまするならば、「正見・正思・正悟・正業・正命・正精進・正念・正定」とあります。それを、わたしは、四つのグループに分類して考えるようにいたしております。
1 正見――正しい見方。
2 正思・正語・正業――身・口・意のいとなみを正しくすること。
3 正命――正しい生き方。
4 正精進・正念・正定――正しい修行のいとなみ。
それは、生活の全分野に渡っての「正しい」生き方のほかの何ものでもないのであります。(84頁)
■では、いったい、そこで「正しい」というのはどういうことでありましょうか。それは、たいへんむずかしい問題でありますが、いまのところは、三つの項目をあげて説明しておきたいと思います。それが、仏教で「正しい」という場合のもっとも重要な条件であります。
その一つは、〝正しい〟とは〝如〟であるということができるようであります。〝如実〟といってもよいでありましょう。〝あるがまま〟であります。それを、いろいろと空想や迷妄をもって飾りたて曲(ゆが)めてしまっては、正しいとはいいがたいでしょう。かくして、〝正しい〟の一つの条件は〝離妄想(りぼうそう)〟といってもよいでありましょう。
その第二の条件としては、〝正しい〟とは〝離辺〟であるということができるようであります。〝辺〟とは極端であります。それを離れた道はすなわち〝中道〟であります。人間が極端に立っている間は、けっして正しい道につくことはできない。正しい見方もできない。正しい修行もできない。正しい生き方もできないのであります。かくて、仏教では、「正は中なり」とするのであります。
そして、その第三には、「正は等なり」といいうるようであります。「等」とは平等ということであります。どこにも当てはまるということであります。ここには当てはまるが、あそこには妥当しないというのは、正しいとはいえないようであります。
釈尊の「さとり」を語るにあたって、仏教ではしばしば「等正覚」とか、「正等覚」といいます。そのさとりは普遍妥当なものであったからであります。したがって、〝正〟とはまた〝等〟でなくてはならないはずであります。(84~85頁)
■経典のしるすところによりますと、この初転法輪なるものは、幾日も幾日もの日数をかけての説法であったようであります。ある日には、三にんが行乞して、その得たる食によって、六人(五比丘および釈尊)が飢えをしのぎ、また、ある日には、二人が托鉢して、その得たるものによって、六人が生きたと記されてあります。これだけの大きな問題が、簡単な説法で解決できるはずはありません。
彼らは、釈尊をかこんで、幾日も幾日も、ともに論じ、ともに語りました。釈尊は彼らのためみ、ありとあらゆる面から説きました。そして、ある日、ある時、彼ら五人のなかの一人、コーンダンニャ(憍陳如)なるものに、やっと「清浄にして汚れなき法眼が開け」て、彼は、「すべて生起せるものは、また滅するものである」と知ることができました。すなわち、釈尊の説きたもうところをついに理解することができたのであります。
その時には、釈尊の喜びもまたただならぬものがあったようであります。経のことばは、その釈尊の喜びを叙して、つぎのように述べているのであります。
「その時、世尊は、歓喜の声をあげて仰せられた。
『まことにコーンダンニャ(憍陳如)は悟った。まことにコーンダンニャは悟った』
かくして、長老コーンダンニアは、〈アニャータ・コーンダンニャ〉(阿若憍陳如――悟れるコーンダンニャの意)の名を得たのである」
その釈尊の喜びは、この経の叙述からもおしはかられるところでありますが、経のことばは、さらに、また、そこで、例の神話的叙述をもって、その時、天上および地居(じこ)の神々が、一斉に大声をあげて、つぎのように言ったと述べております。
「『世尊は、バーラーナシーのイシバタナ・ミガダーヤにおいいぇ、このように無上の法輪を転じたもうた。それは、もはや、沙門・婆羅門、あるいは、天神・悪魔・梵天、もしくは、この世の何者たりとも覆(くつがえ)すことはできないであろう』」
そして、その時また、「この十千世界は、ゆれ動き、震い動き、大ゆれにゆれ動いた」とも叙しているのであります。(86~88頁)
■説法とは、それを客観的世界に打ち出すいとなみであります。そして、それをよく理解するものが出てまいりますと、そこで正法はこの世界に豎立されていないのであります。。釈尊のはじめての説法は、そのような意味をもつものであります。その最初の説法にかけた釈尊の意気ごみはたいへんなものでありました。
それにもかかわらず、最初の説法は、けっして易々として成ったものではありません。その対象として選んだ五人の比丘たちも、よういに耳を傾けようとはあいませんでした。やっと説法をはじめてからも、彼らがそれを理解するまでには、なお数日も数日もかかったようであります。
だが、ついに、やっとコーンダンニャがそれを理解し、つづいて、他の四人もこれを理解しました。その時の釈尊の喜びは異常なものであったようであります。それもそのはず、その時、仏法はこの人間世界に不動に豎立されました。それとともに、釈尊のさとりはここに完成したということができるでありましょう。(89~90頁)
(2015年1月12日