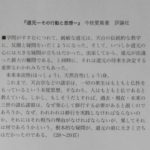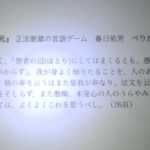読書ノート(2017年)
――――――――――――――――――――――――――――――
『道元「永平広録・頌古」』大谷哲夫 全訳注 講談社学術文庫
はじめに
■『永平広録』(十巻)は『正法眼蔵』と双璧をなす道元禅師の主著です。『正法眼蔵』の各巻の示衆(じしゅ)が、仏法参学者たちへの「信」にもとづく言語による仏法の知的「説得」の教科書とすれば、『永平広録』、とくにその「上堂」は、その仏法の本質を具現化する、知にもとづくさとりへの実践の場、「信」にもとづく「行」への転化、魂の救済の場、いのりの場で、道元が参学者たちに語り示した言(ごん)句を「語録」として文章にとどめたものです。ですから、道元の仏法は『正法眼蔵』と『永平広録』とによって完結する、といえるのです。
本書は、その『永平広録』の第九巻に収められた「頌古」九十則を分かりやすく現代語に訳し、語釈・解説をほどこすものです。
「頌古」とは、「古則を頌(じゅ)す」ことを意味します。古則というのは、とくに禅門ではそれを古則・公案と併称する場合が多いのですが、仏祖といわれる卓越した禅僧たちがさとりに至った因縁として語り伝えられてきた語話、あるいは、師資(しし、師と弟子)が相(しょう)見したときの様子やその際の問答の機縁を示すものをいいます。そして、古則・公案のいずれにしても、それらは後の修行者たちの手本や規範として、長らく伝えられてきたものです。
つまり、「頌古」というのは、そうした古則・公案を拈提(ねんてい、拈(と)りあげて学人に提示すること)し、あおのあとに、「偈頌(げじゅ)」とよばれる漢詩を添えることによって、その古則の真意を、さとりの境地を自分自身の内に判然とさせ、かつ、その古則に自身の宗意(宗教的安心)を盛り込んで歌のかたちで吐露する、言ってみれば、非言語の世界を言語によって表現することをいうのです。(3~4頁)
■なお「玄和尚」とは、道元の諱(いみな)、希玄にちなんだものです。(4頁)
1 世尊妙心附嘱 ( せそんみょうしんふしょく )
■〈現代語訳〉
釈尊は、霊鷲山(りょうじゅせん)で多くの人びとを前にして、一枝の金波羅華(こんぱらげ、優曇華、うどんげ)を御手に拈(と)られて瞬きをされた。その深意をさとった摩訶迦葉は、にっこりと微笑(ほほえ)んだ。
釈尊は、眼前の人びとに告げた。
「私の無上の正法の功徳とその真髄とを、すべて摩訶迦葉に付嘱した。この大法を将来に流布し、断絶してはならない」
そして、その証として、金糸で刺繍されたお袈裟を摩訶迦葉に与えた。
うららかな春のうたた寝からさめて、はじめて花の香りをかぎ分けるように、
その正法の真意を広く人天に示すのは摩訶迦葉のみ。
釈尊の正法眼蔵涅槃妙心とは、山に降る雨が、すべてを洗いすすぎ、雪のように清らかに、
峰にかかっていた雲が飛び散り、すべては霜のように輝く、あるがままのすがただ。
仏法を身にまとった色とりどりの魚たちが水面を波立たせ、
花が咲き乱れ鳥が断腸の想いで鳴いているのに、
霊鷲山の誰もが、その真意をはかりかねて、虚しく釈尊を仰ぐばかり、
頭陀第一の摩訶迦葉のみ、このさとりの芳香を知り、悦びとした。(18~19頁)
〈語義〉
○正法眼蔵 正法は釈尊の正しい教法。仏法の真髄。眼蔵の眼はすべてのものをうつし、蔵はすべてのものを包むの意味。したがって、「正法眼蔵」とはあらゆるものを映しだし、あらゆるものをつつむ無上の正法の功徳・仏法の真髄をいう。
○涅槃妙心 涅槃はさとりのすがたに入った安楽なすがた、妙心は言語を超越した玄妙な心のことで、ともに仏心のこと。
○迸散(ほうさん) ほとばしり散る。飛び散る。
2 仏言三界唯心( ぶつごんさんがいゆいしん )
■〈現代語訳〉
三界はただ一心のみ
山や川をたとえ雲がさえぎり、本来のすがたが見えなくても、
すべては無心なのに、それを海の砂粒をかぞえるようにして人智でわかろうとする。
その世界をわかろうと魚が三段の滝を飛び越えると龍に化すような波を待つことなどない。
釈尊が霊鷲山で示された一枝の金波羅華(こんぱらげ)がさとりの真髄を示しているではないか。
〈語義〉
○三界唯心 三界唯一心のことをいう。三界は教学的には、欲界・色界・無色界の意味で、それがすべて一心によること。
○龍門三級 兎三級浪とも。山西省黄河の上流で、瀑布をなすのを龍門という。瀑水は三段に分かれ険にしてして船を通ぜず、これを龍門三級という。江海の大魚数千その下に集まるが、それ以上上がれず、上がれば龍になるという。愚人は夜中、その魚が龍に化したのも知らずに魚を求めまわることから、禅門では、師家の拈提の落処を智解分別して方角違いをすることに用いる。(22~24頁)
5 居士覓罪懺罪( こじべきざいさんざい )
■〈現代語訳〉
二祖神光慧可大師の会下に居士(後の三祖僧璨、そうさん)がいて、二祖に尋ねて言った。
「私の身体には、病気のように罪過がまとわりついています。この罪過は何かの罪障によると思いますが、どうか和尚、その原因となった私の罪を清めてください」
二祖は答えて言った。
「その君の罪とやらをここにもってくれば、君のために罪過を浄めてあげよう」
居士はしばらくして、言った。
「罪を求めても得られず、ここにもってこられません」
二祖は答えて言った。
「私の、君のための懺悔(さんげ)は終わった。今後、この罪障は求めて得られないものであることを示す仏法僧の三宝に帰依し、生きなさい」
罪犯は天に満ちるほどに溢れているが、それを求めてみても求められるものでなく、その天に満ち溢れる罪犯こそが、仏道に入る好因縁となる。
罪犯は忽然としてさとりと重なり合って現れ、
一筋の仏道の清風がさわやかに吹き渡るとき、罪犯は消え去る。
〈語義〉
○二祖大師 中国禅宗二祖、神光慧可(487-594)。菩提達磨の法嗣(ほっす)。
○居士 三粗大師僧璨(?ー606)のこと。三祖は、四十歳まで俗人であったとされる。
○風恙(ふうよう) 風も恙も病気・やまいのこと。また、恙については、古昔、草居の時代、よく人を噛む虫のことをツツガといい、その毒を被る人が多かったところから、人に会うときは、まずツツガの憂いがあるかないかを尋ねたことから、憂いまた疾病の意味に転化したという。この場合の風恙に纏(まつら)われるというのは、とくに煩悩・罪過に纏わりつかれているという意味合いが強い。(33~34頁)
7 大満三撃三簸( だいまんさんげきさんは)
■〈現代語訳〉
中国禅宗第五祖大満弘忍禅師は、夜中、密かに米ゆき部屋を訪ねて、後の第六祖となる慧能居士に尋ねて言った。
「米が白くなるように、君の修行はすべてをぬぐい去って究極に至ったかな」
慧能は言った。
「米は白くはなったのですが、まだ糠だらけで篩(ふるい)にかけて最後の仕上げをしていません」
大満禅師は、杖で碓(うす)を三回打った。慧能は、即座に米から糠を取り除くために、米を三回篩にかけてから、大満禅師の居室に入り法を嗣いだ。
夜更けの碓坊で真実の眼を見開いて、慧能は五祖を見た、
五祖である仏は、まさに釈尊・達磨の嗣子であり、
その五祖の獅子のごとき威神力こそが、弟子慧能を仏祖の位に投げあげ、
後の慧能の象王のごとき行処には、小さな狐どものような修行者がたちどころに獅子となった。
〈語義〉
○大満禅師 中国禅宗五祖弘忍(601-674)。四祖道信(580-651)の法嗣(ほっす)。
○能居士 中国禅宗六祖慧能(638-713)のこと。本頌古の故事以降、五祖弘忍の法を衣とともに嗣いで、後に出家して諸方遍歴し、やがて曹渓山に住す。会下に青原行思(?-740)、南嶽懐譲(677-744)の二神足を出して南宗禅を形成する。
〈解説〉
(前略)この碓坊での問答に至る経緯は、『六祖壇経』や『景徳伝灯録』巻五が詳しく伝えるので今、翻案してみよう。
咸亨(かんこう)年代(670-674)、波頭山に一居士がいて、名を慧能といった。蘄(き)州から大満禅師に参じたとき、次のような問答が交わされた。
「どこから来たのか」「嶺南です」「何を求めてきたのか」「仏になるためです」「嶺南地方の人は無知蒙昧で仏にはなりえないと言われている」
すると、慧能は言った。
「確かに、人には南や北という出身地はあるでしょう。しかし、仏性に南北はないでしょう」
それを聞いた大満は慧能の非凡の才を見抜き、碓坊に行けと命じ、慧能はその言に随い、碓坊に昼夜休まず八ヵ月の間働き通した。
大満は自身の寿命と付授の時を知り、大衆に「随意に一偈(げ)を述べよ」と命ずる。すると、会下(えか)の七百余の上座であった神(じん)秀(?-706)が、大衆の期待を背負って廊壁に「身は是れ菩提樹、心は明鏡の台(うてな)の如し、時時に勤めて払拭す、遺って塵埃(じんあい)有ることなし(我が身こそがさとりの樹、こころは明鏡の台のようなもの、常に勤めて磨き上げる、ゆえに塵埃などつきようもない)」と、一偈を書した。
その偈を、大満が深く嘆賞したことを聞いた慧能は、夜になって密かに一童子に告げて神秀の偈の横に次のような一偈を書かせた。
「菩提本樹に非ず、心鏡亦台に非ず、本来無一物、何ぞ仮るて塵埃を払わん(さとりは樹ではない、心鏡も台ではない、本来なにものもないのに、塵埃など払う必要はない)」
その偈頌を見た大満は、大衆の前では「まだ本性を見せてはいない」と言明しながらも、その夜、密かに人を使わして慧能を召して告げた。
「諸仏の出世は一大事の為のゆえに、機の大小に随ってこれを引導する。(中略)釈尊の仏法は二十八世代を経て達磨に至り中国に至った。そして慧可大師を得て吾に至る。今、法宝および所伝の袈裟を汝に付す。善く自ら保ち護って断絶せしむることなかれ」
そこで、慧能はその夜半、南に逃れ、五祖大満弘忍の命を護り四年の間猟師の家に隠れ、儀鳳元年(676)三十九歳の時、南海(広東省)の法性寺(「六祖風幡心動」参照)に至り印宗について出家し具足戒を受けたと伝は伝える。
『正法眼蔵』「恁麼」の巻(岩波・上430)には次のような示衆がある。
恁麼人なるがゆゑに、六祖も発明せり。つひにすなはち黄梅山に参じて、大満禅師を拝するに、行堂に投下せしむ。尽夜に米を碓(つく)こと、わずかに八箇月をふるほどに、あるとき夜ふかく更たけて、大満みづからひそかに碓房にいりて六祖にとふ、米白也未と。六祖いはく、白也、未有篩在と。大満つゑにて臼をうつこと三下するに、六祖箕(み)にいれる米をみたび篩(ひる)、このとき師資の道あひかなふといふ。みづからもしらず、他も不会なりといへども伝法伝衣、まさしく恁麼の正当時節なり。(41~43頁)
9 古人明明百草( こじんめいめいひゃくそう)
古人云く「明明百草頭、明明祖師意」と。
結ばんと欲(ほっ)するに留(とど)まらず千万里、門内に処して未だ他明を待たず、情(こころ)無くしては失い易し動容の路、病耳(じ)猶(なお)悲しむ夜雨の声。
■〈現代語訳〉
古人は言った。
「眼前に、はっきりとある百草(森羅万象)のすがた、そこにこそ明白に祖師西来の仏法が現れている」
煩悩は結びとめようと思っても、千里も万里もはてしなく駆けめぐり、
そのすべては、常に仏法の内にあるから、その外では解決の光明をみいだせず、
怠惰なる心では、祖師西来の仏祖意すら見失いかねない。
迷妄の中にただよう耳には、夜の雨の音すらもただ悲しくのみ聞こえるのだ。
〈語義〉
○古人 龐蘊(ほうおん、?ー808)のこと。馬祖道一(709ー788)下の居士(在家の禅者)。字(あざな)は道玄。一般に龐居士と呼ばれ、その身は一生僧形は執らず居士で終わったが、独自の悟境を熟成し、震旦(しんたん、中国)の維摩居士と称される。(48~49頁)
10 船子蔵身莫蔵( せんすぞうしんまくぞう)
〈解説〉
(前略)船子徳誠は薬山に侍すること三十年にしてその法を嗣いだ。が、彼は生来山水を好み、華亭で船頭をしながら縁に随(したが)い機に応じて法を説いたところから、時の人は華亭の船子和尚と呼んだ。しかし、彼には師の薬山の法に報いるべき弟子ができない。そこで兄弟子の雲巌や道吾にたのんでいたがついに道吾円智(769-835)の慫慂(しょうよう)により、夾山善会(かっさんぜんね、805-881)を得た。そこで彼を舟に乗せ、舟から突き落とし、相対を絶し、自他の分別を超えた自在無碍(むげ)の境地すなはち没蹤跡(もっしょうせき)に徹する行履(あんり)を説き、その法を確実に伝えて後、自ら舟を踏翻(とうはん)して煙波に没したという故事である。(後略)
『正法眼蔵』「山水経」巻(岩波・上228)には、この故事をとりあげ次のような示衆がある。
むかし徳誠(じょう)和尚、たちまちに薬山をはなれて江心にすみし、すなはち華亭江(かていこう)の賢聖をえたるなり。魚をつらざらんや、人をつらざらんや、水をつらざらんや、みづからをつらざらんや。人の徳誠をみることをうるは、徳誠なり、徳誠の人を接するは、人にあふなり。世界に水ありといふのみにあらず、水界に世界あり。水中のかくのごとくあるのみにあらず、雲中にも有情世界あり、風中にも有情世界あり、火中にも有情世界あり、地中にも有情世界あり、法界中にも有情世界あり、一茎草中にも有情世界あり、一拄杖中にも有情世界あり、有情世界あるがごときは、そのところかならず仏祖世界あり、かくのごとくの道理、よくよく参学すべし。(54~55頁)
11 大安牧牛領旨( だいあんぼくぎゅうりょうし)
■〈現代語訳〉
大安禅師が、その師である百丈に質問した。
「私は、仏を知りたいと強く思っておりますが、何が仏なのでしょうか」
百丈は答えた。
「それは、牛に乗っていながら牛を探し求めるように、本来、自分に仏性がありながらそれを他に求めるようなものだよ」
大安が言った。
「そうとわかったら、その後はどうなのでしょう」
百丈は言った。
「人が牛に乗って、家に帰るようなものだよ」
大安は言った。
「まだよくわからないのですが、さとり得たそのさとりをどのように守り、どのように保っていけばよいのでしょうか」
百丈は言った。
「牛を飼う人が、杖で、植えたばかりの苗を食い荒らされないように牛を監視するごとく、仏知見の杖で己の本来のすがたを注視することだ」
大安は、この問答の後、仏道修行のありようを会得したのである。
朝霞の中を歩めば霧が深くなくても衣服が濡れるように、大安はおのずと百丈の仏法に感化され、
夕陽が沈み、山々が遠くにかすみ、安穏に一日が暮れるように自在なる安心の境を得た。
その大安と百丈の師資証契(しししょうかい)のすがたは、『雪月』や『梅化』の曲を口ずさみながら、
牧童が夕日のなかに家に帰る安穏な風景そのものを見事に描きだした絵のようだ。
〈語義〉
○大安禅師 大安頼安(793-883)。幼い時に黄檗山(おうばくさん)に出家し、百丈懐海(749-814)の法嗣(ほっす)となり、潙山霊祐(771-853)の法席を嗣ぎ、福州の長慶禅院に入り、二十余年にわたり化をしき、咸(かん)通十四年(873)に紫衣ならびに延聖大師号を賜わる。
○騎牛覓(べき)牛 さとりのなかにありながら、さとりをもとめるたとえ。
○騎牛至家 さとりを得て本来の自己のすがたに帰ること。
〈解説〉
(前略)牛と牧童を素材として、修行の階梯を物語化する『十牛図』が、道元の在世時には、梁山廓庵(りょうざんかくあん、生没年不詳)によって大成されていた。(55~58頁)
12 雲巌豎起掃帚( うんがんじゅきそうそう)
■〈現代語訳〉
雲巌が地を掃いていた時、潙山が言った。
「一生懸命なされてご苦労さま」
雲巌は言った。
「一生懸命でないものもいますよ」
潙山が言った。
「そうであれば、つまり、天空に二つの月があるように、己の中に一生懸命なものとそうでないものが二つあるということではないか」
雲巌は、二つに分かれた自分などないことを示すため一本の箒(ほうき)を立てて言った。
「それでは、この箒は、第幾番目の月だというのだ」
一体誰が、地を掃いていて、一生懸命な自分とそうでない自分などと人格の二面性など考えるのか、
月を持ち出して、人格が二つだの一つだのと言う議論も無駄ではないが、
何千何百という観念の上の月に、さらに月を積み重ね、
たとえ第二月などと言っても、己の真実のすがたはただ一つである。
〈語義〉
○雲巌 雲巌曇晟(うんがんどんじょう)(782-841)。幼時に石門に出家し、百丈懐海(749-814)に参学すること二十年、後に薬山惟儼(やくさんいげん)(751-834)に参じてその法を嗣ぎ、雲巌山に宗風を挙げた。門下に洞山良价(とうざんりょうかい)(807-869)がいる。
二十余年にわたり化をしき、咸(かん)通十四年(873)に紫衣ならびに延聖大師号を賜わる。
○潙山 潙山霊祐(771-853)。十五歳で出家し、杭州の龍興寺で経律を学び、百丈懐海に参学しその法を嗣いだ。同じ会下(えか)に黄檗希運(生没年不詳)がいて、ともに唐代の禅界に名を馳せるが、とくに霊祐は大潙山に止住し宗風を挙揚し、仰山慧寂(きょうざんえじゃく)(807-883)ら多くの龍象を世に送り出し、その法系は潙仰宗(いぎょうしゅう)と言われる。(59~61頁)
14 石霜充米頭縁( せきそうじゅうべいじゅうえん)
■〈現代語訳〉
石霜が、まだ潙山のもとで米を掌(つかさど)る役職に当てられていたときのことである。ある日、米を管理する部屋で米を篩(ふる)っていると、潙山が言った。
「施主からの供養米をまき散らして粗末にしてはならないぞ」
石霜は答えた。
「まき散らしたりして、粗末にしておりません」
すると潙山は地面から一粒の米を拾って言った。
「君は、まき散らし、粗末にしていないと言うが、この一粒はどこからやって来たのか」
石霜が答えに窮すると、潙山が、また言った。
「これはたったの一粒ではあるが、見過ごしてはいけない。この一粒から百千の米粒が生まれるのだ」
すると、石霜が言った。
「百千という米粒が、この一粒から生まれることはわかるのですが、私には、この一粒がどこから生まれたのかわかりません」
大潙は、呵々大笑して方丈に帰り、夕刻の上堂で言った。
「修行僧諸君よ、米つき部屋に大した虫(やつ)がいるぞ」
潙山は、一体どこから、あの一粒を見つけたのだろう、
あの一粒を見つけ出すように、まだ石霜のために何も説きもしないのに素晴らしい人材を得た。
もはや百千万の米粒を捜して、その中に逸材を求めることはないのだ、
ここに、すべての米粒を食い尽くすように、仏法の要諦を極めた石霜という大虫がいるのであるから。
〈語義〉
○石霜 石霜慶諸(せきそうけいしょ)(807-888)。道吾円智(769-835)の法嗣。十三歳のとき西山昭鑑に得度。二十三歳、嵩山(すうざん)で受具、戒律を学び、後に道吾に参学、その法を嗣ぐ。石霜山に止住すること二十年、修行僧とともに坐禅し横臥することがなく、そのすがたが切り株のようであったところから、世人は枯木衆(こぼくしゅ)と呼んだという。唐の光啓四年(888)示寂(じじゃく)。
○大潙 大潙(潙山)霊祐(771-853)。
○米頭(べいじゅう) 典座下で衆僧の粥飯(しゅくはん)の米を掌(つかさど)る役。(65~68頁)
15 雪峰鼇山成道( せっぽうごうさんじょうどう)
■〈現代語訳〉
雪峰と巌(がん)頭が、かって二人でともに仏道修行の途中に鼇山(ごうさん)に来たが、行く道を大雪に阻(はば)まれて滞在したときのことである。
雪峰は法兄の巌頭に質問した。
「どうしたらよいのでしょう」
巌頭は言った。
「将来、もし釈尊の仏法を宣揚しようと思うならば、一つ一つ、ことごとくが他者からの受け売りではなく、自己の胸の中から真実にほとばしり流れ出て、そのすべてが天地いっぱいに広がるものでなければならぬ」
雪峰は、この言葉を聞いて直(じき)に大悟して、すぐに巌頭に礼拝し終わるや繰り返し大声で叫んだ。
「今日、はじめて、鼇山(ごうさん)にさとったぞ。今日はじめて、鼇山(ごうさん)ににさとったぞ」
昨夜、法兄の巌頭に、弁道のすがたがまるで深村の土地神のようだと言われて、
奇岩や怪石を見てもただ怨恨のすがたにしか見えなかった理由をつかみ得、
そして、今日、あるがままの鼇山(ごうさん)と同じ心境となり、仏法を成就した。
が、それでもなお、一つの魔が亡(ほろ)んでもまた一つの魔が生ずるように、仏道修行はなお続くのだ。
〈語義〉
○雪峰 雪峰義存(せっぽうぎそん)(822-908)。徳山宣鑑(とくさんせんかん)(782?-865)の法嗣。十二歳のとき父とともに玉潤寺(ぎょくじゅんじ)の慶玄律師に参じ、一七歳で剃髪。二十四歳のとき会昌(かいしょう)(841-846)の破仏に遭い、俗服をまとい芙蓉霊訓(ふようれいくん)に学び、さらに洞(とう)山良价(807-869)の門に入り、その指示により徳山に参学してその法を嗣いだ。
○巌頭 巌頭全カツ(大に歳)(828-887)。徳山宣鑑の法嗣。霊泉寺の義公の下で出家、長安の西明寺で具戒。初め教宗に学び、後に雪峰・欽山と交友、仰(きょう)山慧寂(807-883)に参学し、徳山の会下に参じて、その法を嗣いだが、唐の光啓三年(887)四月八日、賊刃に倒れた。
○土地 土地は土地神。(69~72頁)
16 法眼不知親切( ほうげんふちしんせつ)
■〈現代語訳〉
法眼文(もん)益禅師が、かって羅漢桂琛(ちん)禅師に参じたときのこと、桂琛が法眼に尋ねた。
「君は、これからどこへいくのか」
法眼は答えた。
「前々から続けている行脚をするだけです」
桂琛が聞いた。
「行脚とは何か」
法眼が答えた。
「知りません」
すると、桂琛が言った。
「その知らないということこそが、仏法を最も切実にとらえる肝心要(かなめ)のところである」
その言葉を聞くや、法眼は豁然(かつねん)と大悟した。
きままに、そしてまた気ままに、ゆったりと、
自在な行脚がどうして種々さまざまな規準などにしばられよう、
が、しかしその不知なる行脚の世界にほんの少しでも理屈が入り込めば、
仏道の真実の知はたったの二、三升に過ぎないことになる。
〈語義〉
○法眼禅師 法眼文益(ほうげんもんえき)(885-958)。羅漢桂琛(らかんけいちん)の法嗣。法眼宗の祖。
○琛禅師 青原下。羅漢桂琛(867-928)。玄沙師備(835-908)の法嗣。羅漢桂琛は常山(じょうさん)万歳寺の無相大師に師事し、後に雲居(ご)道庸(よう)や雪峰義存(822-908)に参学し、玄沙師備の会下に参じその法を嗣いだ。後に、西石山の地蔵院、章州の羅漢院に住して宗風を振るったため地蔵桂琛あるいは羅漢桂琛と呼ばれた。天成三年(928)秋、六十二歳で示(じ)寂。
〈解説〉
道元は本語話を取り上げた後、「若し、是、興聖ならば、地蔵和尚に向かって道(い)うべし。不知、是、最親切、知るもまた、最親切なる。親切は一任ばあれ、最親切なりとも、且(しばら)く地蔵に問う、親切とは、甚麼ぞ」と説示している。つまり、行脚についての様々な束縛を一切はなれて、行脚していることすら不知となって仏道を行ずる、それが最親切なのである。だが、道元は、自分だったら、桂琛(ちん)禅師に「不知は、確かに最も切実にとらえていますが、知るということも最も切実にとらえることだと思います。親切、最親切のことですが、親切の実態はどういうことでしょうか」と質問したであろう、と拈提(ねんてい)している。(73~76頁)
17 投子呑却両三( とうすどんきゃくりょうさん)
■〈現代語訳〉
投子(す)大同に、ある時、僧が質問した。
「月がまだ円(まる)くならないときの状況は、どのように表現できますか」
投子が答えた。
「月が月を三つほど呑み込んだようなものだ」
僧が質問した。
「それでは月が円くなったときはいかがですか」
投子が答えた。
「月が月を七、八個はき出したようなものだ」
仏道は、瓦を磨き、鏡をも磨き、さらに天空をも磨くようにして、
さらに人間(じんかん)を遥かに超脱して修行するのだが、それでもいまだ円成(じょう)しない。
それにつけても想うのは、秋になったから中秋の名月があるのではなく、
月が存在するから中秋となるのが、本来のすがたであるということである。
円かろうと欠けていようと月は月、
それゆえ、月はよる輝く明珠であるなどということはない。
月が月を二、三個呑んだとか、七、八個吐き出したとか、そのようなことはどうでもよい。
ただ言えるのは、天空に晧々として円く輝く月の光は火炉の炎とはちがうということだ。
〈語義〉
○投子 投子大同(819-914)。翠微無学(すいびむがく)(生没年不詳)の法嗣。投子大同は幼時に出家し、初め『華厳経』を学び、翠微に参じて玄旨をさとり、後に周遊して桐城県で、趙州と問答し投子山に隠棲し、投子山に在ること三十余年、無畏の弁をもって徃来激発、衆僧常に室に満つといわれた。乾化(けんか)四年(914)四月六日、九十六歳にて示(じ)寂。
〈解説〉
『正法眼蔵』「都機」巻に、この公案を引いて以下のような示衆がある。
いま参求するところは、未円なり、円後なり。ともにそれ月の造次なり。月に三箇四箇あるなかに、未円の一枚あり。呑却は三箇四箇なり、このとき月未円時の見成なり。吐却は七箇八箇なり、このとき円後の見成なり。月の月を呑却するに、三箇四箇なり。呑却に月ありて現成す、月は呑却の見成なり。月の月を吐却するに七箇八箇あり、吐却に月ありて現成す、月は吐却の見成なり。このゆゑに呑却尽なり、吐却尽なり、尽地尽天吐却なり、蓋天蓋地呑却なり。呑自呑他すべし、吐自吐他すべし。(76~80頁)
18 青原拈靠払子( せいげんねんこうほっす)
〈語義〉
○青原 青原行思(?-740)。六祖慧能(638-713)の法嗣。青原は幼時に出家し、六祖慧能の法を嗣ぎ、南嶽懐譲(677-744)とともに二大弟子と称せられた。江西省の青原山静居(じょうご)寺に住して宗風をあげ、その門下から雲門宗・曹洞宗・法眼宗の法系が育つことになる。開元二十八年(740)十一月示(じ)寂。
○石頭 石頭希遷(700-790)。六祖慧能に得度するが、慧能の示(じ)寂にともない青原に参じて師事す。天宝年代(742-756)初め衡山(こうざん)の南寺に行き、寺東の石上に庵を結び常に坐禅していたために石頭和尚と呼ばれたが、広徳二年(764)梁端(りょうたん)に下り宗風を宣揚し、薬山惟儼(やくさんいげん)に法を付す。貞元六年(790)十二月示寂、九十一歳。
○承当 会得・会取、合点すること。(84~85頁)
19 青原聖諦不為( せいげんしょうたいふい)
〈語義〉
○器 道器。仏法をさとりうる力量をもった人物。
○地軸 大地を支えていると想像された心棒。地下には大地を支える地軸が一万里に三千六百軸あるといわれる。転じて大地の奥底。
○天関 天帝の宮殿。北斗七星とも。
〈解説〉
「青原聖諦不為」の「青原」は、青原行思。「聖諦不為」の「聖諦」は、聖人のさとった真理、それにすら「不為」つまり執着しないこと。この語話は古来より「聖諦不為の則:ともいわれる青原と六祖慧能との修証についての有名な公案で「青原階級」ともいわれる。元来、大乗仏教では五十二位の修行の階級があり、そこには聖諦もあったが、そこを超えた絶対境地には聖諦も俗諦も五十二位もない、真実の仏道は、そうした段階(階級)を超越し、無階級の自由を獲得するのが本来で、その分別判断を止揚し絶対の行を示したものとされる。(87~88頁)
20 薬山何不早道( やくさんかふそうどう)
〈語義〉
○薬山 薬山惟儼(748-828)。薬山は十七歳のとき、広東省の西山慧照(せいざんえしょう)に得度、二十九歳で衡岳寺(こうがくじ)帰澡(きそう)に受具、後に石頭帰遷(きせん)(700-790)に参じ、大悟してその法を嗣ぐ。石頭に侍すること十三年にして薬山(芍薬山)に住したときには四、五十人が参集したという。太和二年(828)十二月示寂。八十四歳。薬山に著作はないが、広く経論に通じ、戒律を厳守し、その端的な接化の家風は、よく一句をもって禅仏法を道破するにあり、後に弟子の雲巌・道吾の法系が栄えるにいたる。
○雲巌 雲巌曇晟(どんじょう)(782-841)。門下に洞山(とうざん)良价がいる。(90~91頁)
21 趙州東門西門( じょうしゅうとうもんせいもん)
■〈現代語訳〉
ある僧が趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)に尋ねた。
「趙州とは何ですか」
趙州は答えた。
「趙州には、東門があり、西門があり、南門があり、北門がある」
僧が言った。
「そのようなことを聞いているのではありません」
すると趙州が答えた。
「君は、趙州のことを聞いたではないか!」
ある僧が縁あって趙州に尋ねたことがあるのだが、
趙州はその境涯を趙州城の東・西・南・北の門を借りて答えとした。
四つの門があるというのは、趙州が四つの門で構成されているようだが
ではどの門が最初の門かなどいうのは趙州の本質を知らないからである。
〈語義〉
○趙州 趙州従諗(778-897)。南嶽下。趙州は南泉(784-834)に参学して開、黄檗、宝寿、塩官、夾山(かっさん)に歴参したが、真定帥王の請により、趙州(河北省西部の都市9の観音院に住し、四十年間江南の禅風とは異なる『趙州録』に見られる独自で機知に富んだ宗風を挙揚した。なお、住した地である趙州は趙州城ともいわれ、西は太行山脈を背負い前方には河北平野が広がり、南北は中国全土に通ずる大道に沿い、古くから軍事的要地とされ、随唐時代以前は覇王の地として知られたところである。趙州には示衆や問答で公案として伝えられるものが多く、趙州従諗によって河北の地にも南宗禅が盛んになったといわれる。
○乾元(けんげん) 天の道、天徳のはじめのもの。乾は天、元は大。東西南北に『易』の元亨利貞の四徳を配する、東は乾元になるところから、四方の初をいう。(92~94頁)
22 夾山水中大悟( かつさんすいちゅうだいご)
■〈現代語訳〉
華亭の船子徳誠(せんすとくじょう)和尚が言った。
「千尺も糸を垂れている意図は、深淵にあるもの、つまり、君、夾山を釣り上げるところにある。さて、釣り糸の先につけられた鉤針(かぎばり)はわずか三寸目先にある。さあ、そこで、私の言葉に囚われない君自身の真実を突き詰めた独創の一句を言ってみよ。さあ、言え。さあ、言え」
ところが、夾山が口を開こうとしたその途端、船子は持っていた竿で、夾山を突き落とした。
その瞬間、夾山は大悟(だいご)した。
京口()きょうこうの竹林寺に住した夾山の説教は、ありのままを説いてよく知られていたのだが、
それを聞いた道吾円智に失笑され、華亭の船子に投じた夾山は、言語を超脱するその宗風の難しさに翻弄され、もの言うことも憚られた。
ところがどうだ、波頭のおどるところが収まるように言語を超絶すると金鱗が飛び跳ねた。
船子の奏した魚歌一曲はなんと深みのある曲か、夾山は三度も頷いたではないか。
〈語義〉
○華亭船子徳誠 船子徳誠(生没年不詳・唐代の人)。薬山惟儼(745-828)の法嗣。
〈解説〉
「夾山水中大悟」の「夾山」は、華亭船子和尚と言われた船子徳誠の法嗣となった夾山善会(かつさんぜんね、805-881)。「水中大悟」とは、船子とその弟子夾山との開悟嗣法の因縁である。船子は薬山惟儼の法を嗣いだが、生来山水を好むために、華亭の呉江にあって一小船を浮かべ、徃来の人に時に従い縁に随(したが)って法を説いていた。しかし、薬山の恩に報いるべき嗣法の弟子ができない。そこで兄弟子の道吾円智(769-835)・雲巌曇晟(782-841)に委嘱したところ、道吾によって夾山善会を得、本文に見られる船上の問答教示の結果、夾山を大悟せしめ印可嗣(し)法して後、自らは舟を踏翻(とうほん)して煙波の中に没したという。(95~98頁)
23 玄沙脚指出血( げんしゃきゃくししゅっけつ)
■〈現代語訳〉
玄沙師備は、その師雪峰義存のように雲水行脚し尋師訪道するために嶺を越えようとしたのだが、嶺についた途端につまずき足の指から血が出た。その時忽然(こつねん)として自らのあり方についてさとるに至った。そして雪峰義存の会下に帰り、以後諸方に他の師を求めて行雲流水することはなかった。
師の雪峰のように遍参(ざん)を思いつき、せわしく嶺に至ったが石に躓(つまず)き脚指を傷つけ、
その血は流れしたたり大地を染めた、その時自己の存在を確実に知り、
水の根源を求めるような、雲を穿(うが)つような遍参の空しさを知り
象骨山の真師雪峰の下に帰り真の遍参に徹した。
〈語義〉
○玄沙 玄沙師備(835-908)。雪峰義存(822-908)の法嗣、青原下。幼年より釣りを好む。咸通(かんつう)初年の一日たちまち発心し、芙蓉山の霊訓(れいくん)に参じて出家。同五年(864)春、開元寺の道玄律師に依って具足戒を受けた。同年秋、故郷に帰り修行に勤め、同七ねんには霊訓の師、雪峰義存に参じてその法を嗣ぐ。雪峰の会下にあっては、その持戒厳格なるが故に備頭陀(びずだ)と尊称され、また、謝家の三男であるところから謝三郎ともいう。
〈解説〉
『正法眼蔵』「一顆明珠」巻の冒頭には、玄沙の経歴を述べたあとに次のような示衆がある。
あるとき、あまねく諸方を参徹せんため、嚢をたづさえて出嶺するちなみに、脚指を石に築着して、流血し痛楚(つうそ)するに、忽然として猛省していはく、是身非有、痛自何来。すなはち雪峰にかへる。雪峰とふ那箇是備頭陀。玄沙いはく、終不敢誑於人。このことばを、雪峰ことに愛していはく、たれかこのことばをもたざらん、たれかこのことばを道得せん。雪峰さらにとふ、備頭陀なんぞ遍参せざる。師いはく、達磨不来東土、二祖不徃西天といふに、雪峰ことにほめき。(中略)衣は布をもちゐ、ひとつをかへざりければ、ももつづりにつづれりけり。はだへには紙衣をもちゐけり、艾草をもきけり。雪峰に参ずるほかは、自余の知識をとぶらはざりけり。しかあれども、まさに師の法を嗣(し)するちから弁取せりき。(98~101頁)
25 宏智去来山中( わんしきょらいさんちゅう)
■〈現代語訳〉
宏智禅師が頌して言われた。
仏道に徹底して生きる山中の人々は、
識(し)っている、青山が自分の身体のひとつであることを、
青山が自分自身であり、その自分自身のほかに我という存在はない。
であるならば、感覚的な迷いなど一体どこに着くのか。
師(道元)はこの頌の韻を引き継がれた。
山中の人は山を愛する人である。(山中人可愛山人)
仏道に徹底して生きる山中の人は、(去去来来山是身)
山は自分自身でありながら、自分自身はいまだ我という存在ではない。(山是身兮身未我)
であるならば、一体どこに感覚的な迷いなどを尋ねもとめようや。(更尋何処一根塵)
〈語義〉
○宏智 宏智正覚(わんししょうがく)(1091-1157)。丹霞子淳(1064-1117)の法嗣。天童山に三十年住山し、正伝の仏法を挙揚したゆえ、天童中興の祖と称される。宏智の禅は世に黙照禅・宏智禅とされ、また文辞に巧みで、雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)(980-1052)と並んで孔門の子遊・子夏、詩壇の李白・杜甫に比せされ、禅門にあっては臨済宗の大慧宗杲(?ー1232)とともに二大甘露門とも称せされる。
〈解説〉
『正法眼蔵』「山水経」巻には、「青山常運歩」について次のような示衆がある。
青山の運歩は其疾如風よりすみやかなれども、山中人は不覚不知也。山中とは世界裏の華開なり。山外人は不覚不知なり。山をみる眼目あらざる人は、不覚、不知、不見、不聞、這箇道理なり。もし山の運歩を疑著するは、自己の運歩をもいまだしらざるなり。自己の運歩なきにはあらず、自己の運歩いまだしらざるなり、あきらめざるなり。自己の運歩をしらんがごとき、まさに最山の運歩をもしるべきなり。(105ー108頁)
26 南泉養得水牯( なんせんようとくすいこ)
〈語義〉
○南泉 南泉普願(748-834)。大歴十二年(777)、齢三十にして嵩(すう)岳会善寺の高律師によって受具す。はじめは唯識・具舎・三論を学んだが、禅の真実は経論の外にあることをさとり、ついに馬祖道一(ばそどういつ)(709-788)の法を嗣ぐ。貞元十一年(795)、普願の行脚中に南泉寺にとどまり、自らの俗姓にちなみ王老師と称し、禅院を構築、蓑笠を付け牛を飼育し、山に入って木を切り、田を耕しながら禅道を挙揚した。弟子に趙州従諗・子湖利蹤(しこりしょう)・長沙景岑(ちょうしゃけいしん)等々がいる。(110頁)
27 国師試験三蔵 (こくししけんさんぞう)
〈現代語訳〉
インドの大耳三蔵という僧が中国の都長安に来て自慢げに言った。
「私は、人の心を見抜く眼を具えている」
時の代宗皇帝は、南陽慧忠国師に大耳三蔵を試験することを命じた。
試験の場で、三蔵は、ちらっと国師を見ると礼拝して、国師の前に立った。
国師が言った。
「君は、他心通を得ているのか」
三蔵が答えた。
「いえいえ、どういたしまして」
国師が言った。
「では言ってみるがよい。老僧(わたし)は、今、どこにいるか」
三蔵が言った。
「和尚は、一国の師匠であります。それが、どうして西川で舟の競走をご覧になっておられるのでしょうか」
国師が再び聞いた。
「では言ってみるがよい。老僧(わたし)は、今、どこにいるか」
三蔵が言った。
「和尚は、一国の師匠であります。どうして、天津橋の上で猿廻しをご覧になっておられるのでしょうか」
国師は、三度目も全く同じ質問をした。
その質問に対して三蔵は、しばらく黙っていたが、今度は国師の居場所を答えることができなかった。すると、国師は叱責して言った。
「この、エセ仏者め。他心通などどこにあるというのか」
三蔵は、答えることがなかった。
琴の名手伯牙(はくが)は、その音を真に理解する知己鐘子期(しょうしき)が来ないのを恨みに思うように、国師は三蔵に真の仏法の理解を期待したのだが……。
善財童子が探し得なかった徳雲和尚は、未明から妙峰山(みょうほうざん)で善財を待っていたのに会えなかった。
それらは、あちらの谷もこちらの谷も一つのはずなのに、心の通ずる路が絶えているのに似ていて、
そうなると、気の毒にも仏の神通は狐の通力ではないか。
〈語義〉
○他心通 六神通の一。他人の心念を自由に知ることができる神通力。他は神(じん)足・天眼(げん)・天耳(じ)・宿命(みょう)・漏尽通(ろじんずう)。
○慧忠国師 南陽慧忠(?ー775)。六祖慧能(638-713)の法嗣(ほっす)。慧忠は青原行思・南嶽懐譲(えじょう)・荷沢神会(かたくじんね)・永嘉玄覚(ようかげんかく)等とともに慧能門下の五大宗匠で、禅風こそ異なるが、神会と同じく北方に禅風を挙げ、道一等が南方で唱道する禅を批判したという。その禅風は身心一如・即心是仏を主旨として無情説法を初めて唱えた。
〈解説〉
道元の同公案に対する解釈の特質すべき点は、過去の五尊宿は概ね、大耳三蔵が前二問ででは的確に南陽慧忠の在処を言い当て、第三問だけ言い当てずに慧忠国師に叱責されたと解釈するが、道元は、『正法眼蔵』「他心通」巻の末尾近くで、初めからそうした他心通はないと指摘し、仏法の心の現成として他心通を次のように示衆している。
第一度より第三度にいたるまで、おなじことばにて問著するなり。(中略)この道理をしらず、あきらめずして、国師よりのち数百歳のあひだ、諸方の長老、みだりに下語説道理するなり。(中略)いま仏法のなかに、もし他心通ありといはば、まさに他身通あるべし、他拳頭通あるべし、他眼精通あるべし。すでに恁麼ならば、まさに自心通あるべし、自身通あるべし。すでにかくのごとくならんには、自心の自拈、いまし自心通なるべし。かくのごとく道取現成せん。おのづから、心づからの他心通ならん。(111ー116頁)
28 船子垂糸千尺 (せんしすいしせんじゃく)
〈語義〉
○船子和尚 船子徳誠(せんすとくじょう、生没年不詳)。(111ー116頁)
29 長慶巻簾大悟( ちょうけいけんれんだいご)
孰(たれ)か磨(ま)する去りし日顔(かお)玉(たま)の如し、一たび老いて回(かえ)る時鬢(びん)霜(しも)に似たり、簾(れん)を巻破(けんぱ)して縦(たと)え月の色を偸(ぬす)むとも、我(わ)が纓(えい)且(しばらく)滄浪(そうろう)に濯(あろ)うべし。
〈現代語訳〉
長慶が霊雲に尋ねた。
「どのようなことが仏法の大意ですか」
霊雲は答えた。
「あれも、そしてこれもだよ」
長慶はこのようにして雪峰義存と玄沙師備のあいだを徃来していたが、三十年の間、仏法の大意をあきらかにできなかった。
ところが、ある日、いつものように何気なく簾を巻き上げた瞬間、忽然と大悟した。
去りし日の顔は。誰が磨いたわけでもないのに玉のように輝いていたのに、
一度(ひとたび)老いて振り返ってみれば三十年、鬢(びん)はすでに霜のように白くなり、
いつものように簾を巻きあげた時、玲瓏(れいろう)な月の光にも似たさとりを得ても、
冠の紐を洗うという滄浪(そうろう)のたとえのごとく、弁道に限りがないゆえに、さらに仏道に励まねばならぬ。
〈語義〉
○霊雲 霊雲志勤(れいうんしごん、生没年不詳)。唐代の人。南嶽下。潙山霊祐の下にあって一見桃華によって悟道し、偈(げ)を述べたことで有名。(120~122頁)
30 巌頭移取盧山 (がんとういしゅろざん)
〈解説〉
「巌頭移取盧山」の「巌頭」は巌頭全豁(がんとうぜんかつ)。「移取盧山」とは、ある僧が巌頭に「祖師意」とは何かという質問をしたのに対して「盧山を移してこい」と言うのだが、盧山が移動するはずがない。盧山は不動不著(じゃく)のすがたを示し、達磨が西(せい)来しようがしましが、中国にやって来ようが来まいが、真実の仏法の端的は対境の如何にかかわらず常に、各人の脚下にあることを示している。
(中略)
道元はその頌(じゅ)において「青山運歩」の語を用いる。これは青山は運歩しているという意味だが、この青山は不動の実態を表し、運歩は随縁の功徳を表すと去れ、不動の兀坐の無所得無所悟がそのまま偉大なる活動である意であることを示している。(126頁)
33 投子了然開悟( とうすりょうねんかいご)
〈現代語訳〉
投子義青和尚が、太陽警玄(たいようけいげん)に仕えて三年たったある日のこと、太陽は義青に質問した。
「仏法を信じない者が、釈尊に『仏法の真実は、言語をもって説法するのか、言葉ではしないのか』と言った。すると、釈尊はしばし無言でおられたのだが、さて、君はそれをどう思うか」
義青が答えようとする、その途端、太陽は義青の口をふさぎ何も言わせなかったその瞬間、義青ははっきりと言葉では表現し得ない仏法の真実をさとって礼拝した。
太陽が言った。
「君は、奥深い仏法のはたらきをさとったか」
義青が言った。
「たとえそのようなことがあっても、すべて吐き出してしまうことが必要です」
時に、資という侍者が傍(かたわ)らにいて言った。
「青華厳とも崇められたお人が、今日はまるで病気になって汗をかいているようだ」
そのように言われた義青は振りむいて言った。
「わかりもしないのに余計なことを言うな、口を閉じよ!」
たとえ太陽が義青の口を覆って言葉では表現できない真実のあることに導いたのは良いが、鼻までは覆えなかったように蜜語には及ぶまい。
いまだ仏法の真実を呑み込んでいなくても、口を開き言葉に出すことはわけはない。
弟子義青は師太陽に口を覆われ、仏道の究極は言葉では表現できないという真実をしらされた、そのような関係があればこそ、その流れが永く続き、今後も続くであろう。
そのさまは、晴天に雷が轟き、その雷光が仏法を象徴する旗となって激しくはためいているようだ。
〈語義〉
○投子 投子義青(とうすぎせい、1032-1083)。七歳で妙相寺にて出家、十五歳にて得度し『百度論』を修学、『華厳経』を聴く。後に聖巌寺(しょうがんじ)の浮山法遠(円鑑)(ふざんほうおん、991-1067)に参じ、その会下で頭角を現し、青華厳(せいけごん)と尊称された。(133~136頁)
35 夾山耳目不到( かつさんじもくふとう)
夾山云く「目前無法、意在目前、是(これ)、目前の法に不(あら)ず。耳目の所到(しょとう)に非(あら)ず」と。
眼睛(がんぜい)を突出す千万箇、翳(かげ)南北飛んで根締(こんてい)を絶す、
一朝(ちょう)に落ちて再び提撕(ていぜい)す、樹(き)に満てる鷓鴣(しゃこ)日裏(にちり)に啼(な)く。
〈現代語訳〉
夾山善会(かつさんぜんね)が言った。
「仏法は目の前にあって見えるというものではない。が、そのはたらきは目の前にある。仏法というのは、目や耳の感覚によって会得できるものではない」
船子(せんす)によって大悟徹底した夾山のもののとらえ方は幾万の眼をもつように多様化し、
また、世の状況も影があちこちに移動するように千変万化し、根が生えてそこにとどまるわけではない。
そのように現実は常に変動して止まないから、当然のように今日も法を説く、
それは、いつものように、樹に鈴なりになって、鷓鴣(しゃこ)が日の光のなかで鳴いているのと同じで、そうした当たり前の情景こそが仏法そのものだからなのだ。
〈語義〉
○夾山 夾山善会(805-881)。船子徳誠(せんすとくじょう)の法嗣。
36 翠微遮竿那竿( すいびしゃかんなかん)
氷を増し水を積む二つ始めに非(あら)ず、日月(にちげつ)歳時各(おのおの)余に似たり、
陌上(はくじょう)の茴香(ういきょう)多少(いくばく)の味(あじ)ぞ、西川(せいせん)の附子(ふす)自(じ)心虚(しんきょ)なり。
〈現代語訳〉
清平(せいへい)が師の翠微無学に尋ねた。
「達磨大師がインドからこの中国にやって来た、その真実の意図とは何でしょうか」
翠微が言った。
「人がいなくなるのを待て。そうしたら君のために説こう」
清平はしばらく黙っていてから言った。
「人はいません。お願いです。師よ、お説きください」
翠微は禅床から下り、清平を連れて竹林に入った。すると、清平はまた言った。
「人はいません。お願いです。師よ、法を説いてください」
翠微は竹を指さして言った。
「この竹はこのように長く、あの竹はあれほどに短い」
年々氷が厚さを増し、それが溶けて水かさが増し満々たる流れにすがたを変えるが、その最初のすがたは知るよしもなく、
日月歳時のまさにその通りで、何のはからいもなく、
畦道の茴香の味は、どのような味なのか、
西川のトリカブトも、自身が薬であるか毒であるかなどは不明なことなのだ。
〈解説〉
つまり対待(たいだい)(人智のはからいである。迷・悟、善・悪など二法が対立する、という意味)のない仏法世界である竹林で、ありとあらゆる存在はあるがままに仏法のすがたそのものであることを示したのである。(144~147頁)
37 臥龍真実人体( がりゅうしんじつにんたい)
〈現代語訳〉
臥龍が了院主(りょういんじゅ)に尋ねた。
「先師玄沙師備は『ありとあらゆるすべての世界に、そのありとあらゆる処、あらゆる時に真実の仏法が生き生きと現れている』と言われた。院主よ、君は僧堂にもそれを見るか」
院主が答えた。
「和尚、迷いごとを言ってはなりません」
臥龍が言った。
「先師は亡くなったが、真実の仏法は正確に受け嗣がれ、あたかもその肉体はなお暖かく生きておられるのです」
春が来たとか来ないとか観念的なことより花が咲き誇る現実に眼を向ければ春の香りがするではないか、
眼の裏に映ずるすがたは二つや三つなどというものではない。
冷たいのも暖かいのも、それはそれで、水は時節によって霜にも梅雨にも変化するものだし、
臥龍から院主へと親しく密々と伝えられた境涯は、言ってみれば流れる水と静かにとどまる水と表現を変えたようなものだ。
〈解説〉
中国禅宗では、さとりは自分で実践し体認するもの、つまり水を飲んだときに初めて冷たいか暖かいかが、その人にわかるという「冷暖自知」という言葉が使われた。が、道元は、仏法のありようとはおのおの独立でありながら普遍的なものであるとして、『正法眼蔵』「法性(ほっしょう)」巻で次のように示衆している。
大道は、如人飲水冷暖自知(人が水を飲んでその冷暖を自ら知るごとき)の道理にはあらざるなり。一切諸仏、および一切菩薩、一切衆生は、みな生知のちからにて、一切法性の大道をあきらむるなり。経巻知識にしたがひて、法性の大道をおきらむるを、みずから法性をあきらむるとす。(148~151頁)
38 南嶽磨塼作鏡( なんがくませんさきょう)
〈現代語訳〉
南嶽懐譲がその弟子馬祖道一に尋ねた。
「君は、何のために坐禅をしているのかね」
馬祖が言った。
「仏になるためです」
すると、南嶽は一つの塼(かわら)を取り、馬祖の庵(いおり)の前の石の上で磨き始めた。馬祖はそれを見ていたが、ついに尋ねた。
「お師匠さま、何をしておいでですか」
南嶽が言った。
「磨いて鏡にするのだ」
馬祖が言った。
「塼を磨いて、どうして鏡にすることができましょう」
南嶽が言った。
「坐禅して、どうして仏となることができよう」
馬祖が言った。
「それでは、どうすればよろしいのでしょう」
南嶽が言った。
「人が牛車(ぎっしゃ)に乗っているようなものだ。車が動かなくなったとき、車を打てば動くのか、牛を打てば動くのか」
馬祖は答えることができなかった。
すると、また南嶽が示して言った。
「君は、坐禅を学ぶといいながら、坐仏を学んでいるのだ。もし、坐禅を学んでいるのなら、そのときの禅とは坐ったり寝そべったりではないということだ。もし、坐仏を学ぶならば、そのときの仏は、一定のすがたに固執したものではない。だからこそ、融通無碍の法のもとで、仏であるとかないとか、あれこれと取捨選択してはならない。君が、もし、坐禅をして仏になろうとするなら、仏を殺すことになるから仏に執着してはならない。もし、坐禅の端坐のすがたにこだわっているのならば、仏道の真の境涯に達することはできない」
ばすは、この教えを聞いて、仏法の最高の醍醐の味を味わったのである。
塼を磨いて鏡とすることを真の功夫(くふう)という、
鏡を取り上げて塼とすることなどは分別の世界の人が思いつくことではない。
南嶽と馬祖とは奥深い真実を互いに点検し、それを明白にし、
四角い鏡、丸い鏡とすがたは違っても、師と資(弟子)一枚となっての法の相続なのだ。
たとえ、仏法と一体となり鉄のような意志を持つ人間であろうと、どうして塼を鏡にすることができようか、
仏になったという意識を消し去るには学人の坐禅功夫を超えねばならぬ、
それには坐禅し座臥し経行(きんひん)するというあたりまえのことを行ずるばかり、
南山に雲が起これば、西江(せいこう)に雨が降る、それが仏法のならいなのである。
〈語義〉
○南嶽 南嶽懐譲(677-744)。六祖慧能(638-713)の法嗣。
○馬祖 馬祖道一(709-788)。南嶽懐譲の法嗣。
〈解説〉
この公案は坐禅の根本義を明確にしたもので、その眼目は「不図作仏」であるとされる。この「磨塼作鏡」は単なる徒労無駄骨を言うのではなく、坐禅が有所得であってはならぬ、無所得・無所悟でなければならない実態を如実に示すものである。
この一段の大事、むかしより数百歳のあひだ、人おほくおもへらくは、南嶽ひとへに馬祖を勧励(かんれい)せしむると。いまだかならずしもしかあらず、大聖もし磨塼の法なくが、いかでか為人の方便あらん。為人のちからは仏祖の骨髄なり。(『正法眼蔵』「古鏡」巻)(151~159頁)
39 潙山生仏無性( いさんしょうぶつむしょう)
潙山云(いわ)く「一切衆生無仏性」。
〈語義〉
○潙山 潙山霊祐(771-853)。百丈懐海(749-814)の法嗣。南嶽下。弟子の仰山慧寂(きょうざんえじゃく、807-883)とともに大いに禅風を挙揚し、その法系は潙仰(ぎょう)宗といわれる。
〈解説〉
「潙山生仏無性」の「潙山」は、潙山霊祐。「生仏無性」とは、潙山の言った「一切衆生無仏性」のことである。この場合の「無仏性」というのは、言葉のうえでは「一切衆生悉有仏性」の対句ではあるが、字義通りに「仏性が無い」、仏になる可能性がないというのはなく、有とか無とかという対立する概念を超越したもの、つまり仏性をそなえないものは一物も存在せず、しかもそれは仏性という言葉も必要なく、そうした固定化したものでもないことを言う。(157~159頁)
41 玄沙一箇明珠( げんしゃいっこみょうじゅ)
〈現代語訳〉
玄沙の言う一箇の明珠は、時空を超えて今も昔もあまねく照らしているのだが、
こうした事実には根拠があるとは言い切れぬので、その実態は容易に知りがたい、
それは四角とか円とか長短などという単位でははかりきれず、またその辺際もなく、
さらにそのはたらきは内とか外とか中間とかの境もないのである。
〈語義〉
○玄沙 玄沙師備(835-908)。雪峰義存(822-908)の法嗣。(163~165頁)
44 黄檗従上宗乗( おうばくじゅうじょうしゅうじょう)
黄檗、嘗(かつ)て百丈に問う「従上の宗乗、如何(いかん)が人に指示する」と。百丈拠坐(こざ)す。檗(ばく)曰(いわ)く「後代(こうだい)の児孫、何を将(も)ってか伝授する」と。百丈云(いわ)く「我、将為(おもえ)らく、你(なんじ)は是、箇人」と。便(すなわ)ち方丈に帰る。
証し去り伝え来(きた)る従上の祖、一生の参学事何ぞ空(むな)しからん、
破顔せる面目霊山(りょうぜん)の昔、温至(し)得髄す少室の中(うち)。(173頁)
45 趙州庭前柏樹( じょうしゅうていぜんはくじゅ)
趙州(じょうしゅう)、因(ちな)みに僧問う「如何(いか)なるか是、祖師西(せい)来意」と。趙州云く「庭前の栢樹子」と。僧曰(いわ)く「和尚、境(きょう)を以(も)って人を示すこと莫(なか)れ」と。趙州云(いわ)く「吾(われ)、境(きょう)を以(も)って人を示さず」と。僧曰く「如何なるか是、祖師西(せい)来意」と。趙州云く「庭前の栢樹子」と。
無根の柏樹虚空に掛かり、祖意西来何の後前ぞ、
古仏株を守って枝葉(しよう)落ちぬ、他に代わる一語天然に至る。
兀地(ごつち)何を図(と)してか年歳積もれる、雪霜一骨庭前に在り、
趙州道(い)うこと莫(なか)れ西来意と、古節中才豈(あに)自然(じねん)ならんや。
僧有って道(みち)を趙州老に問う、只(ただ)道(い)う庭前の栢樹子、
端的の言は是妙なりと雖(いえど)も、但(ただ)恨む祖師の来意遅きことを。
〈現代語訳〉
趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)に、ある時、ある僧が尋ねた。
「達磨大師が、インドから中国にやって来られた真意はどこにあるのでしょうか」
趙州が答えた。
「庭前の柏の樹さ」
僧が言った。
「庭前の柏の樹などと、目の前の事物で示されるのではなく、もっと意味のある言葉で教えてください」
「いや、私は、何も目の前の事物で示したのではない」
すると、その僧が、また聞いた。
「達磨大師が、インドから中国にやって来られた真意はどこにあるのでしょうか」
趙州は答えた。
「庭前の柏の樹さ」
〈語義〉
○祖師西来意 祖師西来意というのは「中国禅宗の祖師である菩提達磨大師がインドから中国にやって来た真意とは何か」というのが原意である。が、それはしばしば「仏法の大意・真義・奥義・真髄とは何か」という禅の根底を問う意味に使われる。(176~180頁)
46 瑯揶清浄本然(ろうやしょうじょうほんねん)
僧、瑯揶(てへんではなくおうへん)に問う「清(しょう)浄本然ならんには、如何(いかん)が山(せん)河大地を忽生(こつしょう)する」と。云く「清浄本然なり、如何が山河大地を忽生せん」と。
春松秋菊時節に順(したが)う、蓋(がい)地蓋天現鏡空し、
竹影(ちくえい)掃除すれば塵(ちり)転(うた)た積る、月潭水(たんすい)を穿(うが)って各(おのおの)融通す。
〈現代語訳〉
瑯揶(てへんがおうへん)慧覚(ろうやえかく)に、弟子の長水子璿(ちょうすいしせん)が尋ねた。
「山河大地というのは、そのままが清浄無垢であるのに、なぜ分別取捨憎愛の対象としての山河大地が生まれるのでしょうか」
瑯揶が答えた。
「山河大地というのは、そのままが清浄無垢であるのに、なぜ分別取捨憎愛の対象としての山河大地が生まれるのか」
春になると常緑の松でさえ青々と冴えわたり、秋には満開の菊の香が高く薫り、その存在を示すのは時節にしたがう、
そのように世界のすべての事象は、そのあるがままのすがたが現実に鏡に映し出されるように展開している。
風にそよぐ竹影は、あたかも地上を掃除しているようだが、地上の塵は積ったままであり、
清浄な月の光は深遠な水底にもとどくが、その痕跡もとどめずに流れゆく。
〈語義〉
○僧 長水子璿(ちょうすいしせん、?ー1038)。瑯揶(おうへん)慧覚(ろうやえかく) の法嗣。教禅一致論者として知られる。
○瑯揶 瑯揶慧覚(生没年不詳)。宋代の人。汾(ふん)陽善昭(947-1024)の法嗣で臨済の宗義を挙揚した。
〈解説〉
『正法眼蔵』「谿声山色」巻には次のような示衆がある。
長沙岑禅師にある僧とふ、いかにしてか山河大地くぉ転じて自己に帰せしめん。師いはく、いかにしてか自己を転じて山河大地に帰せしめん。いまの道取は、自己のおのづから自己にてある、自己たとひ山河大地といふとも、さらに初帰に罣礙すべきにあらず。瑯揶の広昭大師慧覚和尚は、南嶽の遠孫なり。あるとき教家の講師子璿(しせん)とふ、清浄本然、云何忽生山河大地。かくのごとくとふに、和尚しめすにいはく、清浄本然、云何忽生山河大地。ここにしりぬ、清浄本然なる山河大地を、山河大地とあやまるべきにあらず。しかあるを経師、かつてゆめにもきかざれば、山河大地を山河大地としらざるなり。(181~184頁)
47 米胡還仮悟否(べいこげんけごひ)
〈語義〉
○第二頭 第二義門のこと。第一義門は言語や思惟を超えた仏法の究極の宗義を言い、第二義門はその第一義門の最奥の宗義を離れて種々の手段で衆生の迷妄を断じて成仏得悟の道を示すことを言う。「第二頭に落第」とは、宗乗の第一義から逸脱したこと。『正法眼蔵』「大悟」の巻に「落第二頭」について、「しかあるを、さとりといふは、第二頭におつるをいかんがすべきといひつれば、第二頭もさとりといふなり。第二頭といふは、さとりになりぬるといひや、さとりをうといひや、さとりきたれりといはんがごとし。なりぬといふも、きたれりといふも、さとりなりといふなり。しかあれば第二頭におつることをいたみながら、第二頭をなからしむるがごとし。さとりのなれらん第二頭は、またまことの第二頭なりともおぼゆ。しかあれば、たとえ第二頭なりとも、たとひ百千頭なりとも、さとりなるべし。第二頭あれば、これよりかみに第一頭のあるを、のこせるにはあらぬなり。たとへば昨日のわれをわれとすれども、昨日はけふを第二人といはんがごとし。而今のさとり、昨日にあらずとはいはず、いまはじめたるにあらず、かくのごとく参取するなり。しかあれば大悟頭黒なり、大悟頭白なり」と詳述されるように、第二頭も第一頭に即応することが示されている。
○将錯就錯(しょうしゃくじゅしゃく) 間違ったしまったことをその状況に応じて処理し、問題を巧妙有利に解決すること。『正法眼蔵』「即心是仏」巻には「仏仏祖祖、いまだまぬかれず保任しきたれるは、即心是仏のみなり。しかあるを、西天には即心是仏なし、震旦にはじめてきけり、学者おほくあやまるによりて、将錯就錯せず。将錯就錯さざるゆゑに、おほく外道に零落す」と示されている。また、将錯就錯するところにさとりの道が開けるゆえに古聖(しょう)先徳も将錯就錯して道を成じたことを、慧忠国師と大耳三蔵との故事を引いて「このゆゑに、いま仏道の心不可得をきかしむるなり。この一法を通ずることをえざらんともがら、自余の法を通ぜりといはんこと信じがたしといへども、古先もかくのごとく将錯就錯ありとしるべし」とはっきりと示している。
〈解説〉
「米胡還仮悟否」の「米胡」は、京兆米胡(けいちょうべいこ)。「還仮(げんけ)悟否とは、米胡がある僧をして兄弟弟子の仰(きょう)山慧寂に「今の世の人たちはさとりにいたるのか否か」と質問させたことに対して、仰山は「さとりは現実に確かにあるが、第二頭(主觀と客観の対立するところ、対象として求められるもの)に落ちて困る」と答えた。人はすぐにさとりを求めるが、求めて得られるものは対象として得たものであって、さとりはあくまでも無所得・無所悟そのものでなければならないことを示した語話である。(184~188頁)
49 青原又恁去(せいげんゆういんもこ)
〈語義〉
○祖師西(せい)来意 直接には「達磨がインドから中国に来た真意」だが、仏法の真髄を問う命題でもある。「仏仏の真髄」とか「仏法的的の大意」と同意。
50 洞山仏向上事(とうざんぶつこうじょうじ)
〈語義〉
○洞山 直接には洞山良价(807-869)。雲巌曇晟(782-841)の法嗣。青原下。南泉や潙山に参じ、雲巌に学び、再遊の時に水を過ぎんとして悟り、雲巌に嗣ぐ。後に中国曹洞宗の高祖と称される。
〈解説〉
「物向上事」とは、仏以上のことをいうのではなく、仏の真実のすがたの意味で、それを具現することが仏道修行であり、それは物向上事を体得して初めて知りうることである、と洞山が僧に教示した語話である。(195~197頁)
51 臨済悟黄檗棒(りんざいごおうばくぼう)
臨済、黄檗の会中(えちゅう)に在(あ)って三年、行業(ぎょうごう)純一なり。首座(そ)、勧励して仏法的的の大意を問わしむ。三度(たび)到問するに、三度喫棒(きつぼう)す。徃(ゆ)きて大愚(だいぐ)に有過無過(うかむか)を問う。愚云(いわ)く「黄檗、恁麼老婆、汝が為に得徹困(とくてつこん)なり。更に這裏(しゃり)に来(きた)って有過無過を問わんや」と。済、言下(ごんか)に大悟して曰く「元来、黄檗仏法多子無し」と。大愚、撮り住(とど)めて云(いわ)く「這尿(しゃにょう)牀子(じょうす)、適来(せきらい)言うには、有過無過と道(い)う。如今(にょこん)、却(また)、黄檗仏法多子無し、と道(い)う。你(なんじ)、什麼(いか)なる道理を見る。速道速道」と。済(さい)、大愚(だいぐ)の脇下(きょうか)に於いて、築(つ)くこと三築(ちく)す。大愚、拓開(たくかい)して云(いわ)く「你(なんじ)、黄檗を師とすべし。我(わ)が事に干(あず)かるに非(あら)ず」と。済、大愚を辞して、却(また)、黄檗に廻(かえ)る。
棒頭の明眼(げん)強いて相見(そうけん)す、脇下(きょうか)に児(こ)を憐れむ塊(つちくれ)未(いま)だ銷(しょう)せず、
汝が為に老婆心切切なり、風顚(てん)じ水逆(げき)して幾(いくば)くか迢迢(ちょうちょう)たる。
〈現代語訳〉
臨済義玄(りんざいぎげん)は、かって黄檗の弟子としてその会下にあって修行をつむこと三年であった。その修行態度が極めて純粋かつ綿密であったので、時の首座が臨済を督励し、仏法の根本義を師の黄檗に尋ねさせた。ところが、臨済は三度尋ねても三度とも、黄檗から同じように痛棒を喫した。そこで、臨済は、高安大愚のところに行き、自分の質問が間違っているのかどうかを尋ねると、大愚が言った。
「黄檗は、そのように、老婆のように親切に君に接して、本当に疲れてしまったろうよ。それなのに、ここに来て、まだそれが間違っているかどうかなどと、よく言うぞ」
そう言われて、臨済はたちどころに大悟して言った。
「もともと、黄檗の仏法は、それほど複雑なものではなかったのだ」
その言葉を聞くや、大愚は臨済をとっつかまえ脇の下に挟み込んで言った。
「この小便小僧めが、さっきは間違っているかどうかを聞いたのに、今度は、黄檗の仏法など複雑なものではないなどとほざく。お前に、一体何がわかったというのだ。言えるものなら、言ってみよ、さあ早く言え、早く言え」
すると、臨済は、ことばに置き換えることのできない、その瞬間に得た境地を、大愚の脇の下を三度突くということによって示した。
大愚は、臨済のその所作により、彼のさとるところを了解し押さえつけていた臨済を離して言った。
「お前の師匠は黄檗である。私に関わることではない」
そうして、臨済は、師資証契(しししょうかい)の機縁の重大さを感知し、大愚のところを辞して黄檗のもとに帰ったのである。
黄檗は、痛棒を加えることによって、臨済の迷妄に滞る眼を開かせ、
大愚は、臨済の未だ解けぬ迷妄のかたまりが残っているのを憐れみ巧みに接化(け)した。
臨済よ、君のための、黄檗の痛棒や大愚の接化は、老婆のそれのようにまことに親切きわまるもので、
黄檗の法を嗣いだ臨済の流れに逆らうような激しい法統はいまだ衰えを知らぬ。
〈語義〉
○大愚 高安大愚(生没年不詳)。唐代の人。馬祖門下の帰宗智常(きすちじょう、生没年不詳)の法嗣で、臨済義玄を接化した人として知られる。(198~201頁)
52 洞山無情説法(とうざんむじょうせつぽう)
無情説法無情会(え)す、牆壁(しょうへき)草木(そうもく)を教(し)て春ならしむこと莫(なか)れ、
凡聖(しょう)含霊己分(こぶん)に非ず、山(せん)河日月及び星辰(せいしん)。
〈現代語訳〉
無情の説法は、無情にしてはじめて理解することができるのだ、
土や壁のあるよう、草や木のいとなみは、春という時節にかかわらず仏法を説く、
凡も聖(しょう)も衆生もすべて同根で自己の裁量などの計算は無用のこと、
山(せん)河星辰すべてのいとなみが無情説法で、仏法そのものなのだ。
適丁東了適丁東(てきちょうとうりょうてきちょうとう)(202~205頁)
58 天童渾身似口(てんどうこんしんじく)
天童和尚云く「渾身口に似て虚(こ)空に掛かれり。問わず、東西南北の風。一等に他と般若を談ず。適丁東了適丁東(てきちょうとうりょうてきちょうとう)」と。
渾身是(これ)口虚空を判ず、居起(きょき)東西南北の風、
一等に玲瓏(れいろう)して己語(こご)を談ず、適丁東了適丁東(てきちょうとうりょうてきちょうとう)。
〈現代語訳〉
天童如淨和尚は、風鈴を頌(じゅ)して言った。
全身を口にして、虚空に掛かり、
東西南北どのような風にも対応し、
あらゆるところに般若の智慧を説く、
ちりりんちりりんちりりんりん。
風鈴を逆さにして、全身を口にして仏法を説く、
東西南北あらゆるところ無辺際にあらゆるところに、
何の分け隔てもなく、すべての真実を説く、
チチ、チン、トウ、リョウ、チチ、チン、トウ。
〈語義〉
○天童 天童如淨(1163-1228)。唐代の人。足庵智鑑(そくあんちかん、1105ー92)の法嗣。道元の本師。十九歳の時、教学を捨て雪寶山(せつちょうざん)の足庵智鑑に参じ、智鑑の痛棒下に庭前の栢樹子の話に悟道し、淨頭として修行したとされる。嘉定十七年(1224)、勅命により太白山天童景徳寺に住す。道元の著述には、その厳格な風貌等を伝えるが、僧伝等には不詳な面が多い。
〈解説〉
なお、道元の在宋記録でもある『宝慶記』には、道元がこの「風鈴の頌」を、
和尚の風鈴の頌は最好中の最上なり。諸方の長老は、縦(たとい)、三祇劫を経とも、亦及ぶこと能らざらむ。(中略)道元何の幸いありてか今見聞するを得て、歓喜踊躍し、感涙衣を湿(うる)ほし、昼夜叩頭(こうとう)して頂載す。然る所以は、端直にして而も曲調あればなり。
と、それは如浄がまさに輿(こし)に乗らんとする時であったが、最大限の賛辞をもって話しかけると、如浄は笑いながら、
你(なんじ)の道(い)ふこと深く抜群の気宇あり。我、清涼に在りて這箇の風鈴の頌をつくれり。諸方讃歎すと雖(いえども)、而も未だ嘗(かつ)て説き来つて斯の如きならず。我、天童老僧、你、頌をつくらむと要せば、須(すべ)く恁地につくるべし。
と答えた、といかにも楽しげに記している。(226~228頁)
59 南嶽一物不中(なんがくいちもつふちゅう)
南嶽譲(じょう)禅師(じ)、六祖に参ず。祖問うて云く「什麼(いずれ)の処(ところ)従(よ)りか来(きた)てり」と。祖云く「是、什麼物、与麼来」と。譲、措(お)くこと罔(な)し。是(ここ)に於いて執侍(しつじ)すること八年。方(まさ)に前(さき)の話(わ)を省(あき)らむ。乃(すなわ)ち祖に告げて曰(いわ)く「懐(え)譲、当初(そのかみ)、来(きた)りし時、和尚、某甲(それがし)を接せし、是什麼物与麼来を会得す」と。祖云く「你(なんじ)、作麼生(そもさん)か会(え)す」と。譲云く「説似(じ)一物即不中」と。祖云く「還(また)、修(しゅ)証を仮(か)るや、否や」と。譲云く「修(しゅ)証は即(すなわ)ち無きに不(あら)ず。染汚(ぜんな)することは即ち得じ」と。祖云く「祗(ただ)、此の不染汚、是(これ)、諸仏の護念する所。汝も亦(また)、是(かく)の如(ごと)し。吾(われ)も亦、是の如し。乃至、西天の初祖も亦、是の如し」と。
物子(ぶつし)を料理し来る、一等の箇(これ)南嶽。
風(かぜ)生(しょう)なることを弄(ろう)し雲の起るを見る、虎嘯(こしょう)を味わい龍吟(ぎん)を愛す。
一向功夫(くふう)し、八年金を練(ね)る、脱体(だつたい)脱体、委悉(いしつ)すや也(また)未(いま)だしや。
恁来恁生(さん)何物か是、父母(ぶも)未生已前(いぜん)の心。
直(じき)に如今(にょこん)に至って妙を得(う)と雖(いえど)も、毘婆尸仏(びばしぶつ)早く心を留(とど)む。
〈現代語訳〉
南嶽懐譲禅師が六祖に参じた時、六祖が尋ねて言った。
「どこから来たのか」
懐譲は答えた。
「嵩山(すうざん)の安国師(あんこくし)の所より参りました」
六祖が言った。
「何者がこのようにして来ているのか」
懐譲は答えられなかった。
そこで、以來八年間、懐譲は六祖の下で修行を励み、師の問いに対する答えを得ることができ、六祖に告げた。
「私、懐譲は、かつてこの山に来た時、師は私に課題を与えられました。その『何者がこのようにして来ているのか』との問いの意味がわかりました」
六祖が言った。
「君は、何がどのようにして意味がわかったのか」
懐譲は言った。
「そのものを言葉で表現しても表現しきれるものではなく、何を言っても、すぐさまに的はずれになってしまいます」
六祖は言った。
「それは修行した結果としてさとりえてわかったことなのか」
懐譲は言った。
「修行やさとりがないとは言いませんが、修行とさとりを個別にみるとそれぞれを汚すことになります」
六祖が言った。
「その不染汚のところこそを諸仏が護持してきたのであり、自分もまたその通りであり、君もまたその通りであり、そしてインドの祖師方もその通りなのである」
南嶽懐譲は自己を究明するために六祖のもとにやって来た。
それが龍が吟じて雲起こり、虎の嘶(いなな)くを聞いて風の生じるその風情を楽しむ六祖の情識を超越した禅風を求めたからだ。
懐譲は、その六祖の膝下でひたすらに八年、自己を練りに練った。
脱落したか、そのすべてに脱落したか、
何者がどのようにここに存在しているのか、ということについて、
この六祖の問いは、父母の未生以前の真実を問われたのだ。
懐譲は、六祖のもとで、その真意を会得したが、
それは、すでに遠い昔の毘婆尸仏(びばしぶつ)の時代に得られていた事実であったのだ。
〈語義〉
○南嶽 南嶽懐譲(677-744)。六祖慧能(638ー713)に侍すること十五年にしてその法を嗣ぐ。青原とともに六祖の二大弟子とされ、その宗風は中国禅宗の主流となった。
61 道吾智不到処(どうごちふとうしょ)
太陽の光の下では、小さな灯火の光がその光を失うように、
壺の中から宇宙を見るような視点は、薬山(さん)の仏法の前に全く光りを失ったのだ。
〈語義〉
○道吾 道吾円智(769-835)。薬山惟儼(745ー828)の法嗣。青原下。幼いときに、涅槃和尚について出家し、薬山惟儼に参学して法を嗣ぎ、諸山を遍歴の後、道吾山にて禅風を振るう。唐の太和九年(835)示(じ)寂。世寿六十七。
○雲巌 雲巌曇晟(782-841)。薬山惟儼の法嗣。青原下。幼いときに、石門について出家し、百丈懐海(749-814)に随侍すること二十年。後に薬山惟儼に参学して法を嗣ぐ。雲巌山に宗風を挙げ、弟子に洞(とう)山良价(807-869)を出す。会昌元年(一説に太和三年〈829〉)示寂。世寿六十。
○薬山 薬山惟儼。石頭希遷(700ー790)の法嗣。青原下。
○切忌(せつき) 絶対に…してはならない。
○道著(どうじゃく) 言葉で言いきること。
○智頭陀(ちずだ) 道吾円智が衣食住に厳格で簡素な生活をする(頭陀)ところからそのように呼ばれたのであろう。
62 香厳撃竹大悟(きょうげんげきちくだいご)
香厳、因(ちな)みに潙山云く「汝、生下(しょうげ)して嬰児と為(な)りし時、未だ東西南北を弁(わきま)えず。此の時に当たって、吾(わ)が為に説け、看(み)ん」と。厳、下語(あぎょ)し、并(なら)びに道理を説くに、並(なら)びに相(あい)契(かな)わず。便(すなわ)ち武当山に入って、忠国師の旧庵の基(もと)に卓庵(たくあん)す。一日(じつ)、道路を併淨(へいじょう)す。因(ちな)みに、棄礫(きれき)、竹を撃って響かす。時に、忽然と大(だい)悟す。
終日虚心にして鳳(ほう)の臻(いた)るを待つ、村(そん)僧一道却(かえ)って隣(りん)を成す、
龍吟鳳唱聞くに拍(はく)無し、瓦礫(がりゃく)言(ことば)を伝(つた)う枯木人(こぼくじん)。
〈現代語訳〉
香厳智鑑が、かって潙山霊祐に参学した時のことである。
潙山が言った。
「君が、生まれたての赤子の時には、まだ東西南北もわからなかったであろう。その時の状況を、私のために説明してみよ」
そう言われて、香厳は、言葉で道理を説こうとしたが、どれも師の潙山の意に契(かな)うような言葉がでてこなかった。そこで、武当山に入って、南陽慧忠国師が住んでいた庵の跡に自分の庵を建てて住んだ。ある日、道路を掃除していた時、掃き捨てた石ころが竹に当たった。その響くのを聞いて忽然と大悟した。
竹叢の庵の中で、香厳は虚心純一に弁道し、鳳凰の飛来する好事を待っていた、
訪れるもの一人としてなく、香厳の隣人は弁道一筋そのものであった、
舞い降りた鳳(おおとり)が吟じ、鳳が歌っても手拍子すらなかったのに、
ただ、石ころのみが竹を打って響き、枯木の人である香厳にさとりの言葉を伝えた。
〈語義〉
○香厳 香厳智閑(きょうげんちかん、?-896)。潙山霊祐の法嗣。南嶽下。
○潙山 潙山霊祐(771-853)。南嶽下。潙仰宗(いぎょうしゅう)の祖。
〈解説〉
「香厳撃竹大悟」の「香厳」は、香厳智閑。「撃竹大悟」とは、香厳智閑の開悟の語話である。香厳は、百丈懐海について出家し、後に潙山霊祐に参じてその会下(えか)にあっては多聞博記であった。が、潙山から「君の所説は、すべてが学問的な語句の中で学んだものに過ぎない。そうではなく父母(ぶも)未生已前の一句を道取せよ」と詰問されてそれに真の答えを得られず、仏道の真実は学問による文字知識の及ぶところではないことに気づき、自分の所持していた書籍を全部焼き捨て、武当山の慧忠国師の遺跡に庵居する。そして、一日、庭を掃除していたとき、箒(ほうき)にとばされた石ころが竹にぶつかる音を聞いて忽然大悟した因縁である。
『正法眼蔵』「渓声山色」巻には、次のようにまことに詳しい示衆がある。
また香厳智閑禅師、かつて大潙大円禅師の会に学道せしとき、大潙いはく、なんぢ聡明博解なり、章疏のなかより記持せず、父母未生以前にあたりて、わがために一句を道取しきたるべし。香厳いはんことをもとむること、数番すれども不得なり。ふかく身心をうらみ、年来たくはふるところの書籍を披尋(ひじん)するに、なほ茫然なり。つひに火をもちて年来のあつむる書をやきていはく、画にかけるもちひは、うゑをふさぐにたらず、われちかふ、此生に仏法を会せんことをのぞまじ、ただ行粥飯僧とならん、といひて、行粥飯して年月をふるなり。行粥飯僧といふは、衆僧に粥飯を行益するなり、このくにの陪饌役送のごときなり。かくのごとくして大潙にまうす、智閑は身心昏眛にして道不得なり、和尚わがためにいふべし。大潙のいはく、われなんぢのためにいはんことを辞せず、おそらくはのちに、なんぢわれをうらみん。かくて年月をふるに、大証国師の蹤跡(しょうせき)をたづねて、武当山にいりて、国師の庵(いおり)のあとに、くさをむすびて為庵す。竹をうゑてともとしけり。あるとき道路を併淨するちなみに、かはらほとばしりて、竹にあたりてひびきをなすをきくに、豁然として大悟す。沐浴し潔斎して、大潙山にむかひて焼香礼拝して、大潙にむかひてまうす、大潙大和尚、むかしわがためにとくことあらば、いかでかいまこの事あらん。恩のふかきこと、父母よりもすぐれたり。つひに偈をつくりていはく、一撃亡所知、更不自修治、動容揚古路、不堕悄然機、処処無蹤跡、声色外威儀、諸方達道者、咸言上上機(一撃に所知を亡ず、更に自ら修治せず、道容を古路に揚げ、悄然の機に堕せず、処処に蹤跡無し、声色外の威儀、諸方達道の者は、咸(み)な上上の機と言ふべし)。この偈を大潙に呈す。大潙いはく、此子徹也。
また『永平広録』巻六ー上堂457、巻八ー法語2、巻九ー頌古87「香厳千尺懸崖」参照。『三百則』上・17参考。(243~247頁)
63 南泉修行無力(なんせんしゅぎょうむりょく)
〈語義〉
○南泉 南泉普願(748-834)。馬祖道一(709-788)の法嗣。南嶽下。
65 長沙莫妄想縁(ちょうさまくもうぞうえん)
〈現代語訳〉
仏性を論じようとすると、分別が先立つかた、あるなしの二つが働きだす。
身体を構成するエネルギーが消滅すれば、身体は寒(ひえ)きり、そこに真実があらわれる。
生死はあるのだが、それを支配するものなどありはしないのだ。
そのように根拠のないものなどについて、いたずらに言葉で説明するなどせぬがよい。(258頁)
66 仰山高処高平(きょうざんこうじょこうへい)
仰山(きょうざん)、一日(じつ)、潙山に随(したが)って開田す。仰山問うて曰く「遮頭(しゃとう)は恁麼に低きことを得たり、那頭は恁麼に高きことを得たり」と。潙云(いわ)く「水、能(よ)く物を平(たいら)ぐ、但(ただ)、水を以(も)って平ぐべし」と。仰(きょう)云く「水も也(また)、憑(たの)み無し。和尚、但(ただ)、高処(じょ)高平、低処(じょ)低平なるべし」と。潙山、之(これ)を然(しか)りとす。
山前(さんぜん)一片の閑田地、上下高低草料(そうりょう)に任(まか)す、
方円を算(かず)え曲直を料(はか)らんと欲(おも)わば、東西南北一青苗(せいびょう)。
〈現代語訳〉
仰山慧寂が、ある日、師の潙山霊祐にお供して田で作務をした時のこと、仰山が師に尋ねて言った。
「ここは低く、あそこは高いですね」
潙山は答えて言った。
「水はいつも水平だから、水を入れればその高低はなくなるよ」
仰山は言った。
「水はいつも水平とおっしゃいますが、水など入れるまでもなく、高い所は高いままで、低い所は低いまま、それでよろしいのではありませんか」
潙山はそのように言う弟子の仰山の境涯を認めた。
大潙山の麓の誰の所有地でもない田畑、
土地の上下高低あるがままそのままに耕してそれなりに税を納める、
そこが四角か丸かなどと物差しで調べたところで、
結局のところは、東西南北どこからどこまでも植えるのは青い苗である。
〈語義〉
○仰山 仰山慧寂(807-883)。潙山霊祐の法嗣。
○潙山 潙山霊祐(771-853)。南嶽下。潙仰(いぎょう)宗の祖。
〈解説〉
『正法眼蔵』「阿羅漢」巻には次のような示衆がある。
尽諸有結は、尽十方界不曾蔵なり。心得自在の形段、これを高処自高平、低処自邸平なりと参究す。このゆゑに墻壁瓦礫(しょうへきがりゃく)あり。自在といふは、心也全機現なり。(260~263頁)
69 大潙左脇五字(だいいさきょうごじ)
〈語義〉
○大潙 潙山霊祐(771-853)。南嶽下。潙仰(いぎょう)宗の祖。
○水牯牛 去勢した水牛。その意から転じて本来の面目を行じる仏道修行者の意にも用いる。(271頁)
70 深明見人牽網(しんめいけんじんけんもう)
〈現代語訳〉
奉先深と清涼明の二人の修行者が、淮河にたどり着いたとき、漁師が網を牽いていて、その網から鯉が飛び出るのを見た。
すると奉先深が言った。
「明禅兄、あの鯉は実に機敏に、網という煩悩から飛び出して、自在無碍な淮水の世界に行きましたね。まるで禅僧みたいではありませんか」
清涼明は言った。
「確かに、それはそうだが、それならはじめから網に掛からなければよいではないか」
奉先深が言った。
「明禅兄、そう言っては、あなたは、真実を見る目に欠けると思います」
そう言われた清涼明は悩み、真夜中に至ってさとるところがあった。
淮水の流れが仏法の流れとなって、深・明二人の修行者のもとに至ったところ、
網という煩悩(まよい)を飛び出した鯉の生命がきらめいた。
その生命の躍動がなければ、
二人は、ただ悄然と淮河の流れを見るばかりであったろう。(274頁)
71 庵主渓深杓長(あんじゅけいしんしゃくちょう)
雪峰山(ざん)の畔(ほとり)に一僧有って卓庵す。多年、剃頭せず。自(みずか)ら、一柄(ぺい)の木杓(もくしゃく)を作って、渓辺(けいへん)に去(ゆ)きて水をく(爫曰)んで喫(きつ)す。時に僧有(あ)って問う「如何なるか是、祖師西(せい)来意」と。庵主(じゅ)曰(いわ)く「渓(たに)深くしては杓柄(しゃくへい)長し」と。僧、帰って雪峰に挙似(こじ)す。峰(ほう)云(いわ)く「也(また)、甚(はなはだ)奇怪なり。然(しか)も是(かく)の如くなりと雖(いえど)も、須(すべから)く是、老僧、勘過(かんか)して始得(しとく)ならん」と。峰、一日(じつ)、侍者と同じく剃刀(ていとう)を将(も)って去(ゆ)きて他(かれ)を訪(とぶら)う。纔(わず)かに相見(しょうけん)して、便(すなわ)ち問う「道得せば、即(すなわ)ち汝が頭を剃らじ」と。庵主(じゅ)、便(すなわ)ち、水を将(も)って洗頭(せんず)す。峰、便ち、他(かれ)の与(ため)に剃却(ていきゃく)す。
人有って西来意を問著(もんじゃく)す、木杓(もくしゃく)柄(へい)長くして渓(たに)転(うた)た深し、
箇中無限の意(こころ)を識(し)らんと欲(おも)わば、松風(しょうふう)一たび弄(ろう)す没絃(もつげん)の琴。
〈現代語訳〉
雪峰山(せっぽうざん)のほとりで、ある僧が庵を結び修行していた。彼は長い間剃髪しなかったが、その修行ぶりは、自分で一本の木杓を作り、渓に下りては水を汲むというように極めて簡素であった。
ある時、その評判を聞いた雪峰の侍者が質問した。
「祖師西来意とは、どういうことか」
すると、その庵主(じゅ)は答えた。
「渓(たに)が深ければ、柄杓の柄の長いものよ」
そのように答えられた侍者は、すぐに帰って雪峰義存にそのことを伝えると、雪峰は言った。
「それはまた、怪しいまでに素晴らしい言葉だ。ではあるが、私が直接、その僧に会ってその真偽を判断しよう」
ある日、雪峰は侍者に剃刀(かみそり)を持たせ、その庵主を訪問し、彼に会うやいなや言った。
「仏法の事実を十分に言い得れば、君の頭を剃ることはしない」
すると、庵主は、仏法の深奥の真実は言語をもっては示し得ないところを、水を持ってきて頭を洗い清めるという事実をもって示したので、雪峰は彼のために剃髪した。
ある僧が、長髪の僧に祖師西来意の真意について質問した。
その答えは、渓が深ければ、その水を汲む柄杓の柄も長いものだ、というものだった。
この言葉に秘められた無限の意旨を知ろうと思うならば、
かつて、陶淵明が琴の音を聞いたように、無為に仏法を説く松風の無限の音を聞かねばならぬ。
〈語義〉
○雪峰 雪峰義存(822-908)。徳山宣鑑(782-865)の法嗣。
○祖師西来意 語義的には「達磨大師がインドから中国にやってきた真意とは何か」ということだが、この語はしばしば仏法の大意を問う語として使われる。(276~278頁)
72 霊雲見桃悟道(れいうんけんとうごどう)
霊雲、因(ちな)みに桃華を見て悟道す。有頌(うじゅ)して云(いわ)く「三十年来尋剣(じんけん)の客なり。幾廻(いくたび)か葉落ち又枝を推(ぬ)きんずる、一たび桃華を見て自従(よ)り後、直(じき)に如今(にょこん)に至って更に不疑なり」と。潙山に挙似(こじ)す。山云く「縁より入(い)る者は、永(なが)く退失せず。汝、善く護持すべし」と。玄沙、聞いて云く「諦当(ていとう)、甚諦当、敢保(かんぽ)すらくは、老兄(ひん)、未だ徹せざること在り」と。
古曾(むかし)悞(あやま)って桃源に入(い)りし客、両眼(げん)華(はな)を看て一たび枝を動ず、
更に歩んで都(すべ)て忘る那畔(なはん)の事(じ)、何を将(も)ってか酬答(しゅうとう)大家(け)の疑い。
艶陽(えんよう)たる桃李(とうり)藍朱(らんしゅ)の色、百世春の時同じく本枝(ほんし)なり、
賤近(せんきん)愚(ぐ)ならずば須(すべから)く遠きを貴(たっと)ぶべし、目を軽んじて耳を重くして痴疑(ちぎ)すること莫(なか)れ。
〈現代語訳〉
霊雲志勤(れいうんしごん)は、桃の花の咲いているのを見てさとり、頌(じゅ)して言った。
三十年、なんと愚かに無駄に過ごしてきたことか、
その間幾度となく、花は咲き葉が落ち枝から芽も出ていたのに……、
しかし、今、桃の花の咲くのを見て、
真実をさとり、何の迷いもない。
これを師の潙山霊祐に示すと、師は言った。
「縁のはたらきによって、その境に至った者は、永久にそれを失うことはない。君は、それを護持するがよい」
それより一世代後の玄沙師備が言った。
「霊雲禅師の頌は、確かに良いことを言っていて真にその通りfrはあるが、あえて言わせてもらえば、まだ徹底しているとは言い難い」
昔、桃源郷に迷い込んだ人が、
両目で確実に桃の花が咲いている事実を認め、その爛漫たる桃花を歓楽したが、
故郷には、そこで見たすべてを忘却して帰った。
確かに、桃花爛漫と咲き誇る境の風光を問われても、答えることはない、その風光の痕跡もないのだから……。
晩春の候、桃李の葉が緑に、花が紅に艶(えん)を競うように彩をなし、
それは百世の昔より、春になれば繰り返す当然のことなのだ。
身近なことを軽んじ、手の届かない遠くにあるものを貴ぶのが人の習いであるが、
目の前の現実を見ずに、耳に聞こえる言葉のみを重んじ、理論にたよって変に疑いをもってはならぬ。
〈語義〉
○霊雲 霊雲志勤(生没年不詳。唐代の人)。潙山霊祐(771-853)の法嗣。南嶽下。
○尋剣客 楚の人が、舟で河を渡るとき、剣を落とし、船端に目印をつけて「ここが、私の剣の落ちた場所である」と言い、舟が止まったときに、その目印のところを探したが剣はなかったという「刻舟求剣」の故事に因み、愚かなことをする人を尋剣の客という。(281~284頁)
73 趙州狗子仏性(じょうしゅうくすぶっしょう)
趙州、因(ちな)みに僧問う「狗子に還(また)、仏性有りや、也(また)、無しや」と。州云く「有り」と。僧曰(いわ)く「既(すで)に有り。什麼(なん)と為(し)てか、却(また)、這箇(しゃこ)の皮袋に撞入(とうにゅう)する」と。州云く「他(かれ)、知って故(ことさ)らに犯(おか)すが為(ため)なり」と。僧有って問う「狗子(くす)に還(また)、仏性有りや、也(また)、無しや」。州云く「無し」と。僧曰(いわ)く「一切衆生、皆(みな)、仏性有り」、狗子、什麼(なん)と為(し)てか、「却、無し」と。州云く「伊(かれ)に業識(ごっしき)有ること在(あ)るが為なり」と。
全身狗子全身仏、箇裏に論じ難し有りや也(また)無しや、
一等に売り来って還(また)自(みずか)ら買う、憂(うれ)うること莫(なか)れ折本(せっぽん)と又偏枯と。
有無の二仏性、衆生の命に造(いた)らず、
酪(らく)の蘇(そ)と成るに似たりと雖(いえど)も、猶(なお)滅尽定(じょう)の如し。
〈現代語訳〉
趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん)に、ある僧が尋ねた。
「犬に仏性はありますか」
趙州は答えた。
「ある」
僧は言った。
「あるとおっしゃいますが、それではなぜ、仏性がありながら、どうして犬として目の前にいるのですか」
趙州が言った。
「犬は、仏性を十分に承知の上で、犬として生きているのだ」
別の機会に、ある僧が尋ねた。
「犬に仏性がありますか」
趙州は答えた。
「ない」
僧は言った。
「この世の生きとし生けるもの、ありとあらゆるものに仏性があるといのに、犬にはどうしてないのですか」
趙州は答えた。
「昔から、犬には犬のはたらきがあり、犬として生きているからだ」
犬の全身は、仏の全身である。
そこで、仏性が有るとか無いとか論ずることはできないのだ。
趙州が有るの無いのと言っているのは、自分で売って、自分で買っているように無駄なことをしているようだが、
しかし、何も心配することはない、元手をすって損をするように仏性を示せなくなったわけではなく、有仏性・無仏性にこだわって動きがとれなくなったわけではないのだから。
仏性が有るの無いのと言ったところで、
ありとあらゆる生命には何の関係もない。
有る無いということは、酪と蘇というようなもので、その元は乳であり、味が違うから別物だというのは誤りだ。
思慮分別を絶した滅尽定(じょう)の世界にはそのようなことはない。
〈語義〉
○趙州 趙州従諗(778-897)。南泉普願(748-834)の法嗣。
〈解説〉
「趙州狗子仏性」の「趙州」は、趙州従諗。「狗子仏性」とは、「趙州狗子」「趙州有無」「趙州無字」「趙州仏性」等々と称せさられる公案である。「仏性」とは、釈尊の本性・如来蔵とも同視され、仏となる種子(しゅじ)がすべてのものに具有されている意味で、『大般涅槃経』は「一切衆生悉有仏性」として、すべてのもろもろが平等にこの可能性を有するとした。
この語話で、ある僧が趙州に「犬に仏性があるか」と問うと「有る」と答え、またある僧には「無い」と答えた、その「仏性の有る無し」は、「有り」と「無し」と対立する有無ではなく、有という仏性、無という仏性、つまり存在の実体概念を超越した仏性の存在そのものについての問答である。つまり「一切衆生悉有仏性」にこだわれば有の固執になるのである。
この語話は『永平広録』巻3-上堂226、巻4ー同429にもたびたび説示されている。
道元は、「一切衆生悉有仏性」について、そのような可能性や仏教以外の教説でいう固定した変化の無い実体としての我などを仏性と見ることを避けて、仏性の真義は人間に内在する可能性などではなく、草木国土・日月星辰というすべてが現に仏であると説示する。したがって「一切衆生悉有仏性」も、道元は「一切衆生、悉有は、仏性なり」と読んでいる。(285~290頁)
74 洞山寒熱廻避(とうざんかんねつかいひ)
洞山、因(ちな)みに僧問う「時節恁麼熱。甚(いず)れの処(ところ)に向かって廻避せん」と。山云く「寒熱不到の処に向かって廻避すべし」と。僧曰(いわ)く「作麼生(そもさん)か是、寒熱不到の処」と。山云く「寒時は闍梨(じゃり)を寒殺し、熱時は闍梨を熱殺す」と。
寒熱来(きた)る時撒手(さつしゅ)して行(ゆ)く、眉目落尽して新名(めい)を殺す、
太平は本(もと)是(これ)将軍の致(ち)なり、将軍をして太平を見せしむること莫(なか)れ。
〈現代語訳〉
洞山良价(とうざんりょうかい)に、あるとき、ある僧が尋ねた。
「こんなに暑いときは、この暑さをどこに避けたらよいのでしょうか」
洞山は答えた。
「暑さ寒さの至らぬところに避ければよい」
僧が言った。
「暑さ寒さの至らぬところとはどこですか」
洞山が言った。
「寒いときには、君自身が寒さそのものに成りきり、暑いときには、暑さに成りきることだ」
寒いときには寒さに、暑いときには暑さに成りきるがよい。
そこは、自分自身の本来の面目など全くなくなった世界では、そこには寒熱とかの虚名などない。
洞山はその世界を作り出した大将軍としてそこに鎭座しているが、
大将軍たるもの、その平和な世の中に安住し執着しないのだ。
〈語義〉
○洞山 洞山良价(807-869)、雲巌曇晟(782-841)の法嗣。
○将軍…… 将軍は乱にあってこそ、その真の存在理由がある。この場合の将軍は洞山のこと。(292~294頁)
75 馬祖即心即仏(ばそそくしんそくぶつ)
馬祖云く「即心即仏」と。
忽(たちま)ちに忘る独歩来時(らいじ)の路(みち)、廻首して那(なん)ぞ能(よ)く此の中に滞(とどこお)らん、
幾度(いくたび)か売り来って還(また)自ら買う、憐むべし山竹清風を引く。
〈現代語訳〉
馬祖が言った。
「心そのものが仏である」
大梅法常は、馬祖の「即心即仏」の語を聞いて仏道の実体を理解し、自分が懸命に精進を重ねた道をたちまちに放棄した。
だが、その言葉がどれはど優れていようと、そこにうろうろと首を振り向けてまでその言葉に滞っていては、自分の仏道の真実の弁道さえも失う。
幾たびも自問自答し、仏道の真実を回光返照せねばならぬ、
山に茂る竹林に真実を伝える涼風が渡っているのであるから……。
〈語義〉
○馬祖 馬祖道一(709-788)。南嶽懐譲(677-744)の法嗣。「南嶽磨塼(せん)」によって心印を得、江西を中心に教線を張り、湖南の石頭希遷(700ー790)と並んで禅界の双璧と称せられる。その禅風は、教典などに拠らない大機大用で、百丈懐海・西堂智蔵・南泉普願等々多士済々たる龍象を輩出し、南嶽下は天下を風靡するに至る。また、南嶽下には馬祖を始めその弟子たちに語録が多く、後世の膨大な語録出現の契機となっている。
〈解説〉
「馬祖即心即仏」の「馬祖」は、馬祖道一。「即心即仏」とは、『馬祖語録』冒頭に記される大梅法常(752-839)と馬祖との問答に出るもので、大機大用の禅風を挙揚(こよう)した「平常心是道」とともに有名な語話であり、後の禅者たちの道標となった古則である。馬祖は、大梅法常の「仏とは何か」との問いに「即心即仏(心こそが仏にほかならない)」と答えた。法常はこの語によって、大梅山中での坐禅三昧の生活に入り、後年、馬祖が「非心非仏」と言っても私は「即心即仏」でよい)」と言って坐を立たなかったと伝えられる。「即心即仏」とは「即心是仏」を強調した言葉で、馬祖はこの言葉で学人を説得してきたが、「即心即仏」の言葉に執着するものが出てきたため、その執着を払底するために「非心非仏」の言葉を用いたので、「即心即仏」と「非心非仏」は異質のものではない。『永平広録』巻4ー上堂319に詳細な上堂がある。(296~298頁)
76 南泉斬却猫児(なんせんざんきゃくみょうに)
南泉、一日(じつ)、東西両堂に猫児(みょうに)を争う。泉、見て遂に提起して云く「道得せば即ち斬らず」と。衆(しゅ)、無対(むたい)。泉、猫児を斬却して両段と為す。泉、復(また)、前(さき)の話を挙(こ)して趙州に問う。州、便(すなわ)ち草鞋(そうあい)を脱いで頭上に戴(いただ)いて出ず。泉云く「子(なんじ)、若(も)し在(あらまし)かば、恰(あた)かも猫児を救得(きゅうとく)してん」と。
南泉道(どう)有り。再三の行(こう)、雲衲(うんのう)の風流霹靂の声、
惜しむべし猫児幾(いくば)くの露命、霜刀(そうとう)当たる処(ところ)に疑情を断ず。
池陽(ちよう)提起すれば猫児道す、道得猫生ずるや否や未だ生ぜらるか、
且(しばら)く道(い)え南泉聴くや也(また)未だしや、両堂の雲衲一雷の声。
〈現代語訳〉
ある日、南泉会下の僧たちが東西に別(わか)れて、猫に仏性が有るか無いかで激論していた。
そこに登場した南泉は、猫をとりあげて言った。
「議論の余地などない仏法の真実を道(い)い得れば、猫を斬らないでおく」
僧たちは一人として答えるものはなかった。
そこで南泉は、猫を一刀両断にした。
後に、南泉は、この話を趙州にし、質(ただ)したところ、趙州は、ただちに草鞋(わらじ)を脱いで頭の上に載せて出ていった。
南泉は言った。
「もし、お前があの時、あそこにおれば猫を救えたものを」
南泉は、「猫に仏性が有るか無いか」について、言葉でどう表現するか三度も示された。
僧たちが、南泉の問いかけに一声も発しなかったのは、まさに霹靂の大音声(おんじょう)なのだ。
なんともはかなき猫の命ではあるが、
しかし、冴えた刀がはかなき命を断ち切ると同時に、また僧たちの疑団を断ち切ったのだ。
南泉は猫をとりあげて言った。
が、仏性の有無を言葉で表現できたところで、猫は生きながらえたのであろうか。
それはそうと、南泉は聞いたであろうか。
両堂の僧たちの、あの無対の、沈黙した、黙したがための、あの一大雷音を……。
〈語義〉
○南泉 南泉普願(748-834)。馬祖道一(709-788)の法嗣。南嶽下。
〈解説〉
「南泉斬却猫児」の「南泉」は、南泉普願。「斬却猫児」とは、「南泉斬猫」として有名な公案である。ある日、雲水たちが東西の両堂に分れて、猫の仏性について論争していた。そこへ登場した南泉は「議論する余地などない仏法の真実を言ってみよ」と猫をとりあげて雲水たちに迫った。雲水たちは、答えることができない。そこで、南泉は本来議論の余地のない仏法の真実を議論するのは誤りであることを猫を切り捨てるという手段によって示した。後に、趙州に「君ならどうする」と問うと、趙州は頭に草鞋を載せて退室するという行動に出た。つまり、趙州は南泉の斬猫の手段すらも、草鞋は本来足に履くものであるのに、頭に草鞋を載せるように無意味なこと、仏法の絶対の真実は些少な有無などにかかわらず日常の現実にそのまま承当することを示したのである。趙州のそうした行為は、南泉によって「お前がその場におれば無益な殺生をせずに済んだものを」と言って、その熟した法味が称賛されたのである。(中略)なお、道元の「南泉斬猫」については、『正法眼蔵随聞記』で、道元と懐弉が、この時の南泉の対応について議論しているのが次のように見えるのが参考となろう。
ある時、弉、師に問ウて云ク、如何ナルカ是レ不眛因果底の道理。師云ク、不動因果ナリ。云ク、なんとしてか脱落せん。師云ク、歴然(ねん)一時見(げん)なり。云く、是ノごとクならば、果、引起すや。師云ク、惣(すべ)て是ノごとクならば、南泉猫児を截(き)ル事、大衆(だいしゅ)已(すで)に道得(いいえ)ず。即(すなわ)チ猫児を斬却シ了(おわ)りぬ。後に趙州草鞋(そうあい)ヲ脱シテ戴(いただ)キ出し、また一段の儀式なり。また云ク、我レ若シ南泉なりせば即チ道(い)フべし、「道(い)ヒ得たりとも即チ斬却せん。道不得なりとも即チ斬却せん。何人(なんびと)か猫児を争ふ、何人(なんびと)か猫児を救ふ。」ト。大衆に代ツて道(い)ハん、「既に道得す。請フ、和尚猫児ヲ斬ラン(ことを)。」ト。また大衆に代ツて道ハん、「南泉ただ一刀両段のみを知ツて一刀一段を知ラず。」ト。弉云ク、如何ナルカ是レ一刀一段。師云ク、大衆道不得、良久不対ナラバ、泉、道フべし、「大衆已に道得す」と云ツて猫児を放下せまし。古人云ク、「大用(ゆう)現前して軌則を存セず。」ト。また云ク、今の斬猫は是レ即チ仏法の大用、あるいは一転語なり。若シ一転語あらずば、山河大地妙淨明心とも云フべからず。また即心是仏とも云フべからず。また即心是仏とも云フべからず。即チこノ一転語ノ言下にて、猫児ガ躰仏身と見、またこの語を聞イて学人も頓(とん)に悟入すべし。また云ク、こノ斬猫即チ是レ仏行なり。喚(よ)ンで何とか道フべき。喚(よ)ンで斬猫とすべし。また云ク、是レ罪相なりや。云ク、罪相なり。何としてか脱落せん。云ク、別。並ビ具ス。云く、別解(げ)脱戒とハ是ノごとキヲ道ふか。云く、然なり。(300~305頁)
77 百丈野狐堕脱(ひゃくじょうやこだだつ)
〈現代語訳〉
百丈懐海の説法の席には、きまって一人の老人がいて、常に大衆(だいしゅ)とともに説法を聴き、大衆が退室すれば、老人も一諸に退室した。
ところが、ある日、説法が終わっても退室しなかったので、百丈が尋ねた。
「そこに立っているのは、どなたかな」
老人は言った。
「私は、実は人間ではありません。釈尊は以前の過去七仏の迦葉(かしょう)仏の時には、この百丈山の住職でした。が、そのおり修行僧から『大いに修行しさとった者も因果と関わりがあるのでしょうか、ないのであようか』と聞かれたので、私は、彼のために『因果とは関わりはない』と答えたのです。それからというもの、五百回にわたって狐の身となって生まれることになってしまいました。今こそ、お願いです。和尚様。私に代わり、正しい機縁の言葉を示され、私を狐の身からお救いください」
そのように告白すると老人は尋ねた。
「大いに修行しさとった者も因果と関わりがあるのでしょうか、ないのであようか」
百丈は言った。
「因果の道理はくらますことはできない」
老人は、その言葉を聞いてただちにさとり、礼をして言った。
「私は、すでに狐の身からすくわれました」
大いに修行しさとったものは因果に関わりをもたぬ、と答えたばかりに、
前百丈であった老狐の眼前には鬼窟が出現し、あたかも老狐はもとからそこの住人のようだが、そうではない。
なぜなら、その鬼窟の中からでさえも、今百丈の一転語によってそこを抜け出し、
眼前の山河こそが真実の仏法を証明していることを知りえたのであるから。
何と哀れな、過去迦葉仏の時の一尊仏であった前百丈よ、
身を野狐の身に落し五百回もの狐として過ごしてしまった。
だが今は、逆に今百丈の正しき真実の仏法を聞き、
もはや蒙昧な野狐の鳴き声など出さずにすむようになったのだ。
〈語義〉
○百丈 百丈懐海(749-814)。馬祖道一(709-788)の法嗣。
〈解説〉
「百丈野狐堕脱」の「百丈」は、百丈懐海。「野狐堕脱」とは、「百丈堕野狐身の話」とも「不落不眛の話」ともいわれる公案。野狐身に落ちた老僧は、「不落因果」「撥無因果」ともいわれる因果を否定する独断と偏見の境地に堕ちているのである。この「不落因果」「撥無因果」の反対が、「不眛因果」(因果の道理は絶対にくらますことはできない)であり、また「深信因果」(深く因果の道理を信じること)ともいわれる。大自然の法則には、人間の些少な思慮分別などは通用しないのである。それ故に、「不眛因果」の理によって老僧は自己の迷妄を払拭し、野狐身を脱することができたとされるのである。(中略)
『正法眼蔵』(深信因果)巻に、「深信因果」こそが正伝の仏法の真髄であることを、先の百丈と老人の話を引いた後に次のように示衆している。
この一段の因縁、天聖広灯録にあり。しかあるに、参学のともがら、因果の道理をあきらめず、いたずらに撥無因果のあやまりあり。あはれむべし、澆風一扇して、祖道陵替(りょうたい)せり。不落因果は、まさしくこれ撥無因果なり、これによりて悪趣に堕す。不眛因果は、あきらかにこれ深信因果なり、これによりてきくもの悪趣を脱す。あやしむべきにあらず、うたがうべきにあらず。近代参禅学道と称するともがら、おほく因果を撥無せり。なにによりてか、因果を撥無せりとしる。いはゆる不落と不眛と、一等にしてことならずとおもへり、これによりて、因果を撥無せりとしるなり。(305~310頁)
78 馬祖頭白頭黒(ばそずはくずこく)
〈現代語訳〉
馬祖道一に、あるとき僧が質問した。
「言葉で表現するちころ、すべての否定的表現などの極めて厄介な四句百非という弁証的な議論を抜きにして、お願いいたします、師匠、私に達磨大師の真実の仏法をズバリと示してください」
場祖大師が言った。
「わしは今日疲れていて、お前に説くことはできないから、智蔵のところへ尋ねて行くがよい」
僧は、西(せい)堂智蔵に尋ねた。
智蔵は僧に言った。
「どうして、師匠に尋ねないのだ」
僧が言った。
「師匠が、あなたに聞くように言ったのです」
すると智蔵が言った。
「私は、今日、頭が痛いので、お前に説くことはできない。懐海(えかい)師兄(ひん)のところへ尋ねに行きなさい」
僧は、百丈懐海に尋ねた。
「懐海が言った。
「私も、そこのところになると、わからない」
僧は、馬祖大師にそのことを伝えた。
すると、馬祖大師が言った。
「智蔵の頭は白く、懐海の頭は黒い」
仏法は、四句百非という言葉での判断論議を絶している。
ある僧の質問は、極めて精微ではあるのだが、
それに対して、禅堂での修行をした禅僧でなければ、
懐海や智蔵のようにズバリと端的に答えられようか。
〈語義〉
○馬祖 馬祖道一(709-788)。
〈解説〉
「馬祖頭白頭黒」の「馬祖」は、百馬祖道一。「頭白頭黒」とは、馬祖に、ある僧が「西来意」の意味を問うが、馬祖、そしてその弟子の西堂智蔵・百丈懐海が軽率な返答をしなかった語話に出るもので、「馬祖四句百非」あるいは「馬祖黒白」とも称される公案である。「四句」は「四句分別」のことで、インドにおける①肯定、②否定、③一部肯定一部否定、④両者の否定または懐疑、とする四句のことで思慮分別判断の一切のこと。「百非」はすべての言語の実に非ざること、つまり一切の否定のこと。仏教の真実は、「四句百非」という弁証的な論議を超越したものであるところから、四句を離れ百非を絶すという。達磨の真実の仏法の宗旨を問う僧に、馬祖は質問されたからといって答えられる問題ではないので「今日は疲れている」と答えるのである。それに対して西堂智蔵と百丈懐海という二人の馬祖の弟子は、僧に応対しているが、それは馬祖が「いずれが兄か弟か、優劣つけがたい」と賛嘆するほどに、四句を離れ百非を絶した言詮(ごんせん)によって表現できない仏法の真実を提示したものであった。(310~314頁)
79 魯祖見僧面壁(ろそけんそうめんぺき)
〈現代語訳〉
魯祖宝雲禅師は、いつも僧が来るのを見ると、面壁し坐禅した。
我が師と仰ぐ魯祖禅師は、天下に比類なく、転身自在の活路を歩まれた。
しばしば僧が来るのを見ては、只管打坐して言詮(ごんせん)を超越された。
そうした魯祖のために、かりそめにも一言でも言葉を発すれば、
面壁に徹した魯祖の功を無としてしまうのである。
〈語義〉
○魯祖 魯祖宝雲(生没年不詳)。中唐時代の人。馬祖道一(709-788)の法嗣。南嶽下。
〈解説〉
「魯祖見僧面壁」の「魯祖」は、魯祖宝雲。「見僧面壁」とは、「魯祖面壁」ともいわれ、魯祖が、面壁によって学人を説得した公案である。魯祖は参来の僧があると面壁して取り合わなかったという。魯祖の面壁はそれがそのまま学人への説得であり、人々が只管打坐の中に魯祖の示す仏法の真実を会取(えしゅ)しなければならないことを示している。が、「魯祖面壁」については、南泉は「面壁ばかりでは何年たっても一人も打出(たしゅつ)できまい」と誹謗し、以下多くの古徳が論評しているが、中でも羅山(らざん)・玄沙などは「我当時もし見ば背上(はいじょう)に五火抄(ごかしょう)を与えん」と言ったことから「古徳火抄」なる語を派生している。(314~316頁)
80 馬祖日面月面(ばそにちめんがちめん)
馬祖不安の時、僧有って問う「和尚、近日、尊位(そんい)如何(いかん)」と。祖云く「日面仏、月(がち)面仏」と。
江西(こうざい)曾(かつ)て仏有り、日月(にちげつ)を以(も)って面(おもて)と為(な)す。
何事か未(いま)だ相(あい)備(そな)わらず、囲碁敵手に逢(あ)えり。
〈現代語訳〉
馬祖道一が病床にあった時、ある僧が尋ねた。
「和尚様、このごろお具合はどうですか」
馬祖が言った。
「私は、仏の光明の中にあるよ」
江西には、かって真の古仏がいた。
馬祖は、日月をもって己の本来のすがたとし、四大不調であっても生滅去来を超えていた。
師にとっては、何の不安もなく、円満でないものは何もない。
日月をもって答えとしたのは、囲碁の好敵手に出会ったように、真の仏法を示したのである。
〈語義〉
○馬祖不安…… 馬祖は馬祖道一(709-788)。この語話は「馬祖不安」といわれ、馬祖が病床にあっての接化の公案。日面仏は千八百年の寿命を持つとされる仏、月面仏は一日一夜の寿命しかない仏とされる。仏法に徹し切っている馬祖の、寿命の長短を超越した仏法に証契(しょうかい)せんことを願っての僧への接化である。
○江西 馬祖は、六祖慧能や南嶽懐譲に師事し、多くの禅林に参師問法したが、とくに江西省の開元寺にあって禅風を鼓吹し、江西に人ありと称された。(316~318頁)
83 大随劫火洞然(だいずいごうかとうねん)
大随、因(ちな)みに僧問う「劫火(ごうか)洞然(とうねん)、大(だい)千倶壊。此箇(しこ)、還(また)、壊(え)すや、也(また)、無しや」と。随云く「壊(え)す」と。僧曰(いわ)く「恁麼(いんも)ならば、則(すなわ)ち他に随(したが)って去らん」と。随云く「随他去(こ)」と。
被毛(ひもう)戴角(たいかく)他に同じて去(も)てゆく、劫火洞然たれども転頭せず。
枯木(こぼく)死灰(かい)猶(なお)焼尽(しょうじん)す、何の面目有ってか因由(ゆう)を恨む。
〈現代語訳〉
ある時、大随法真禅師に、ある僧が尋ねた。
「とてつもない大火災がおきて、すべての世界が壊滅すると、経にあります。が、そのときには、仏法の本質、仏性もなくなるのですか」
大随は堪えた。
「なくなるさ」
僧が言った。
「劫火とともになくなるのですね」
大随が言った。
「劫火とともになくなる」
劫火がおきれば、毛におおわれたもの、角を懐いたもの、ありとあらゆるものが消え去るのだ。
そのような劫火がすべてを覆い尽くしても、なお、振り返りもしない。
枯木や死灰でさえも焼き尽くしてしまうとき、
どうして、その劫火の因縁や理由などを恨むことがあろうや。
〈語義〉
○大随 大随法真(834-919)。南嶽下。道吾円智(769-835)・雲巌曇晟(782-841)・洞(とう)山良价(かい)(807-869)に参じ、潙山霊祐(771-852)の会下で刻苦修行し、悟道し、後に大安長慶(854-932)の法を嗣ぐ。その家風は篤実で温雅の中にも禅機秀逸なものがあるとされる。(326~328頁)
85 天童祗管打坐(てんどうしかんたざ)
天童和尚云く「我が箇裏(こり)、不用焼香・礼拝・念仏・修懴(しゅうさん)・看経(かんきん)。祗管打坐、始得(しとく)」と。
自(みずか)らの手頭(しゅとう)を亀(かが)む不拈(ふねん)に非(あら)ず、之乎(しこ)者也失(やしつ)と得(とく)と、
龍蛇(りゅうだ)混雑して龍蛇に似たり、渾坐(こんざ)蟠身(はんしん)元より羽翼(うよく)。
〈現代語訳〉
天童如浄和尚が示された。
「わが道場では、仏道修行において重要視される焼香・礼拝・念仏・修懴(さん)・看経を必要としない。なぜなら、仏道の究極は只管打坐においてこそ得られるからである」
わが天童和尚は焼香・礼拝・念仏・修懴(さん)・看経などにとらわれることなく、
それらを文章の置き字のようにし、ことさらに論ずることはなかった。
龍と蛇とが混在しているように、迷・悟、凡・聖(しょう)は判じ難い。
ただ打坐するところに大空を無限に飛翔する力がそなわり、自在無碍(げ)なるはたらきがあるのだ。
〈語義〉
○天童 天童如浄(1163-1227)。足庵智鑑の法嗣。道元の本師。
〈解説〉
「天童祗管打坐」の「天童」は天童如浄。「祗管打坐」とは、「只管打坐」で、天童膝下(しっか)では、焼香・礼拝・念仏・修懴(さん)・看経、すなわち、お香を焚いて仏に供養すること、仏祖を礼拝すること、仏を念ずること、仏に罪を懺悔(さんげ)すること、経文を看読するなどは、仏道修行にとって重要なこととされるが、わがこの道場においては必要としない。仏々祖々の家風は、坐禅弁道のみである、と、天童如浄の宣言に示される。
この因縁については『永平広録』巻6-上堂432に次のように拈提(ねんてい)している。なお、『永平広録』巻9ー頌古86「天童身心脱落」も参照。
仏々祖々の家風は、坐禅弁道のみなり。先師天童云く「跏趺坐(かふざ)は、乃(すなわ)ち古仏の法なり。参禅は身心脱落なり。不要、焼香・礼拝・念仏・修懴(さん)・看経。祗管打坐、始めて得。それ坐禅は乃ち、第一に(目ヘンに盍)睡(こうすい)すること莫(な)かれ。是、刹那(せつな)須臾(しゅゆ)なりと雖(いえど)も、猛壮、先と為す」。
さらに『正法眼蔵』「弁道話」巻には次のような示衆がある。
いはく、仏法を住持せし諸祖、ならびに諸仏、ともに自受用三昧に端坐依行するを、その開悟のまさしきみちとせり。西天東地、さとりをえし人、その風にしたがえり。これ師資(しし)ひそかに妙術を正伝し、真訣を稟持せしによりてなり。
宗門の正伝にいはく、この単伝正直の仏法は、最上のなかに最上なり。参見知識のはじめより、さらに焼香・礼拝・念仏・修懴(さん)・看経をもちゐず、ただし打坐して身心脱落することをえよ。(331~334頁)
87 香厳千尺懸崖(きょうげんせんじゃくけんがい)
香厳、一日(じつ)、衆に
喪(そう)身失命(みょう)して
〈現代語訳〉
香厳智閑が、ある時、大衆(だいしゅ)に向かって言われた。
「ある人が、」
仏法のために
〈語義〉
○香厳 香厳智閑(?-896)。道元禅師の本師。潙仰(いぎょう)宗の祖潙山霊祐(771-853)の法嗣。
86 天童身心脱落(てんどうしんじんだつらく)
天童和尚云く「参禅は身心脱落」と。
木(もく)杓を弄来(ろうらい)して風波(ふうは)起こる、恩大きに徳深くして報も亦深し、
縦(たと)え海枯れて寒(かん)徹底することを見るとも、身死して心を留(とど)めざらしむこと莫(なか)れ。
〈現代語訳〉
わが師天童如浄和尚は言われた。
「参禅は身心脱落である」
わが師天童和尚は「参禅は身心脱落である」と言う、言ってみれば役にも立たない破木(もく)杓のような境涯で三千大千世界に波乱を起こされた。
が、その恩徳は極めて広大で、その偉大な恩に報いるのはただならぬことなのだ。
たとえ海が枯れ果て底を見通すような徹底した境地になろうとも、
死んで心を残すように、決して身心脱落した痕跡を留めるようなことがあってはならない。
〈語義〉
○天童 天童如浄(1163-1227)。道元禅師の本師。足庵智鑑(1105-92)の法嗣。足庵は、長盧山の真歇(けつ)清了(1089-1151)に参じた後、天童宗玨(そうかつ)(1094-1162)の法を嗣ぎ、紹興二十四年(1154)五十歳で棲真寺(せいしんじ)に初住し、以後、香山、報恩寺、雪寶山(せっちょうざん)にも移住する。(334~336頁)
87 香厳千尺懸崖(きょうげんせんじゃくけんがい)
香厳、一日(じつ)、衆(しゅ)に謂(かた)って曰(いわ)く「人の千尺(じゃく)の懸崖に在るが如き、口に樹枝(じゅし)を銜(ふく)み、脚(あし)、蹋(ふ)む所無く、手、攀(よじ)る所無(な)からんに、忽(たちま)ちに人有って問わん『如何が是、西(せい)来意』と。若し口を開いて答えれば喪身失命(みょう)せん。若し答えずば、又、他の所問(しょもん)に違(い)す。当恁麼の時、且(しばら)く、作麼生(そもさん)」と。時に、招(しょう)上座という有って出(いで)て曰く「樹(じゅ)に上(のぼ)る時は即(すなわ)ち問わず。樹に上らずの時、如何(いかん)」と。厳、笑う而已(のみ)なり。
喪(そう)身失命(みょう)して死中に活(かつ)す、猶(かつ)惜しむ嬢(じょう)生(しょう)の両片皮(ぴ)、
他に答えんと擬欲(ぎよく)すれば言(ことば)口に満つ、問来すれば也(また)是口枝を銜(ふく)む。
〈現代語訳〉
香厳智閑が、ある時、大衆(だいしゅ)に向かって言われた。
「ある人が、千尺もの切り立った崖で、手でつかみ足をかけてよじ登るところもなく、口にくわえた木の枝のみで身を支えていた時、突然、『祖師西来意』と仏法の本質を問われたとする。もし、その質問に答えたなら、千尋の谷底に落ちて死ぬであろう。しかし、答えなければ、質問した人の意思に背くことになる。さて、その時、どうすればよいか」
その時、招(しょう)という僧が言った。
「そのような非常事態の時に、そのような質問はしません。地上にある時に質問されたら、どう答えるのですか」
それに対して、香厳はただ笑うのみであった。
仏法のために身命(みょう)を投げ捨て、すべて脱落し、その大死一番のところで自在の境涯となる。
香厳は、そこのところを、自身の口を開いて説くことを惜しんでいるようだ。
尋ねたものに答えてやろうとすると、言葉が口の中にあふれてくるのに……。
だが、しかし、それは尋ねるということ自体が、すでに口に木の枝をくわえているように、祖師西来意の真意を得ているからなのだ。
〈語義〉
○香厳 香厳智閑(?-896)。道元禅師の本師。潙仰(いぎょう)宗の祖潙山霊祐(771-853)の法嗣。香厳は庭前掃除のとき、掃いた小石が竹に当たる音を聞いて忽然大悟したことはよく知られている。
〈解説〉
『正法眼蔵』「祖師西来意」巻には次のような示衆がある。
しかあればしるべし、答生来意する一切の仏祖は、みな上樹口銜樹枝の時節にあひたりて、答来するなり。雪寶(空に買)明覚禅師重顕和尚、樹上道即易、樹上道即難、老僧上樹也、致将一問来。いま致将一問来は、たとひ尽力来すとも、この問きたることおそくして、うらむらくは、答よりものちに問来せることを。あまねく古今の老古錐(こすい)にとふ、香厳呵呵大笑する、これ樹上道なりや、樹下道なりや、答西来意なりや、不答西来意なりや。試道看。(338~341頁)
88 宏智失銭遭罪(わんししっせんそうざい)
宏智禅師、初めて丹霞に参ず。霞(か)問う「如何なるか是、空劫已然(いぜんの自己」と。曰く「井底(せいてい)の蝦蟇、月を呑却す。三更に夜明(やみょう)の簾(れん)を借らず」と。霞曰く「未在、更に道(い)え」と。智、疑議す。霞、打つこと一払子(ぼっす)して云く「又、不借(じゃく)と道(い)わんや」と。智、忽(たちま)ちに悟って作礼(さらい)す。霞云く「何ぞ、一句子(くす)を道取せざる」と。智曰く「某甲(それがし)、今日(きょう)、失銭遭罪」と。霞曰く「未だ打つことを得るに暇(いとま)あらず。你(なんじ)、且去(しゃこ)すべし」と。
風流売り尽して人の買わんことを図(はか)る、夜月(やげつ)山を出(いで)て更に窓に到る、
河内(かだい)に失銭して河裏(かり)に覔(もと)む、江(こう)に在って叫ぶ者は休江に歇(けつ)す。
〈現代語訳〉
宏智正覚(わんししょうがく)禅師が、その師となる丹霞子淳にはじめて参じたとき、丹霞が尋ねた。
「空劫という父母も生まれていない、自分が全く存在しない以前の自分とは、一体何であるか」
宏智は答えた。
「井戸の底に棲んでいて他の世界を何も知らない凡愚な蝦蟇が、月を呑み込んだと思っても、月は真夜中の三更にさえ夜明簾など必要とせず、依然として月は天上に輝いているように、自己の存在というのは、そのようにあるものです」
すると、丹霞が言った。
「まだ、まだ、十分ではない。さらに言ってみよ」
宏智が、考えたすえに言おうとすると、その瞬間、丹霞は、払子(ほっす)を一振りして言った。
「お前は、また夜明簾など必要としないと言うのか」
この言葉で、宏智はさとりを得て、丹霞に作礼すると、丹霞が言った。
「わかったのであるならば、なぜ一言言わないのだ」
宏智は言った。
「私は、今日は、仏道の真実を得ましたが、今の心境は、銭を失って罰せられるように、損をした上に損を重ねた心境で、とても言葉で表現することはできません」
丹霞が言った。
「私は、もうお前を打って研鑽させる必要はないから、この場を去るがよい」
丹霞は、仏道修行の究極を風流として専売し、それを買いに来る学人を求めた。
その言葉は、月が山の端(は)を出て、真夜中になって窓に月光が差し込むように、宏智に差し込んだのだ。
河で銭を失ったならば、それを河に求めなければならぬものだし、
河の流れのなかで、喉の渇きを訴えるものは、その流れの水を飲めばよいように、自己の存在を外に求めるのは誤りなのだ。
〈語義〉
○宏智 宏智正覚(1091-1157)。道元禅師の本師。丹霞子淳の法嗣。
○丹霞 宏智の師、丹霞子淳(1064-1117)のこと。丹霞は四川省(剣州)の人で、27歳で受具し、諸師に歴参したのちに、幼くして神仙を学び辟穀(へきこく)の術を得たという大陽山の芙蓉道楷(1043-1118)に師事しその法を嗣ぐ。崇寧三年(1104)南陽の丹霞山に住して禅風を振るい、真歇清了(1089=1151)、宏智正覚などを輩出した。
○夜明簾 水晶・白玉で作った簾で夜中でも明るく輝くという。さとりの境涯にたとえられる。
○擬議 何かを考えて言おうとする。擬は、~をしようとする意。(342~344頁)
89 二祖心不可得(にそしんふかとく)
二祖大師、初祖に問う「我心(がしん)、未だ寧(ねい)ならず、乞うらくは、師、安(あん)を与えんことを」と。祖云(いわ)く「心を将(も)って来(きた)れ。汝(なんじ)に安を与えん」と。云く「心を覓(もと)むるに了(つい)に不可得なり」と。祖云く「我、汝に安心を与えオワ(立のしたに見)んむ」と。
了了として了の時了すべき無し、玄玄として玄の処(ところ)是(これ)紛紜(ふんうん)たり、
他を道畔(どうはん)に尋(たず)ぬれば錯(あやま)って己(おのれ)に逢う、水に引かされ来(きた)って稍(やや)雲に歩む。
〈現代語訳〉
二祖大師神光慧可が、かって初祖達磨大師に尋ねた。
「私の心は、まだ安らかではありません。どうか、師よ、私の心を安らかにして下さい」
初祖が言った。
「お前の心とやらを、ここに持ってくれば、その心を安らかにしてやろう」
慧可が言った。
「心を求めましたが、どこにも見つけることはできませんでした」
すると、達磨が言った。
「私は、お前の心を安らかにした」
仏道のすべてを了畢(ひつ)したところには、その上に何かを見解(けんげ)することもない、さとりすらもない。
その境地を玄妙不可思議などと表現する、そのこと自体すらが妄想(ぞう)である。
二祖慧可は、自分自身の心を不安として、初祖達磨に向かって尋ね求めたのだが、他に尋ねて自己を見いだすように、道のほとりのふとしたところで自分自身に出会ったのだ。
それはまさに、水の流れに乗っていると思ったら、いつの間にか雲の上にいる、そのように自在無碍の境地に至ったのである。
〈語義〉
○二祖大師 中国禅宗第二祖神光慧可(487-593)のこと。
○初祖 中国禅宗初祖菩提達磨のこと。
〈解説〉
「二祖心不可得」の「二祖」は、中国禅宗第二祖の神光慧可。「心不可得」とは、慧可がその師達磨との問答で安心(じん)を得た因縁で、「二祖安心」ともいわれる。安心というのは、心を安んずることであるが、心というものは対象としてとらえられるものではない、つまり不可得であり、不可得とは認識の対象ともならない。それゆえに空を体得することこそが安心への道であることを示した公案である。
(中略)
さらに、この「心不可得」という語は『金剛経』に出るものであり、心はとらえることができないものであり、そのとらえることができない実体が心であるが、それは相対するものではなく、目の前に現前している心が思量を超えてはたらいていることを「後心不可得」巻で次のように示衆(じしゅ)している。
心不可得は諸仏なり、みずから阿耨多羅三藐(みゃく)三菩提と保任しきたれり。
金剛経曰、過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得。
これすなはち諸仏なる心不可得の保任は、諸仏にならはざれば証取(しょうしゅ)せず、諸仏にならはざれば正伝せざるなり。諸仏にならふといふは、丈六身にならひ、一茎草にならふなり。諸祖にならふといふは、皮肉骨髄にならひ、破顔微笑にならふなり。この宗旨は正法眼蔵あきらかに正伝しきたりて、仏仏祖祖の心印、まさに直指(じきし)なること嫡嫡単伝せるに、とぶらひならふに、かならずその骨髄面目つたはれ、身体髪膚うくるなり。仏道をならはず、祖室にいらざらんは、見聞せず会取せず、問取の法におよばず、道取の分ゆめにもいまだみざるところなり。(346~350頁)
90 真歇豁然契悟(しんけつかつねんかいご)
真歇禅師、丹霞に参じて入室(にっしつ)す。霞問う「如何なるか是、空劫時の自己」と。喝(けつ)、対(こた)えんと擬(ぎ)す。霞曰く「你(なんじ)、鬧(いそが)わしくこと在り、且(しばら)く去れ」と。一日(じつ)、鉢盂(はつう)峰(ほう)に登るに、豁(あき)らかに契悟(かいご)す。徃帰(おうき)して霞の見(まみ)ゆ。方(まさ)に侍立(じりゅう)する次いでに、霞、掌(しょう)して曰く「将謂(しょうい)すらくは、你(なんじ)、有ることを知れり」と。師、欣然(きんぜん)として之を拝す。
臭悪(しゅうお)を相兼(あいか)ねて虚空を悩ます、地を遮(さえぎ)り天を蓋(おお)って透通(とうつう)を要す、
再び上関に向かって相(あい)架構(かこう)す、元来走馬す鉢盂(はつう)の中。
〈現代語訳〉
真歇清了禅師が、その師となる丹霞子淳に参学し、入室したとき、丹霞が尋ねた。
「空劫という、父母も生まれていない、自分も全く存在しない以前の自分とは、一体なんであるか」
真歇が答えようとすると、すかさず丹霞が言った。
「お前は、分別智がはたらきすぎ気持ちが乱れ、まだわかっていない。まあ、しばらくこの場から立ち去るがよい」
そして、ある日のこと、真歇が丹霞山中の鉢盂峰(はつうほう)に登ったとき、忽然と空劫時の自己について契悟(かいご)し、いそぎ帰って師の丹霞の側に立つと、師は手を打って言った。
「お前は、その時にも存在したことがわかったのだな」
真歇は欣然として、丹霞を礼拝した。
真実なる自己の存在への究明のためとはいえ、そこにはたらく分別智は極めて醜悪で、それは虚空を悩ますほどの大きな誤りなのだ。
真歇の弁道は、地を遮り天を覆うほどの心意気に燃えてのものであったのだが……。
真歇は、丹霞に心が乱れていると言われて、はじめて空劫の玄関に立ち返り、新たな家を造り、そこに安住の地を見いだしたのだ。
だが、しかし、それは鉢盂の中を走る馬のようなもので、鉢盂の中の自分自身と空劫時の自己とは何ら変わりはないのだ。
〈語義〉
○真歇禅師 真歇清了(1089-1151)。11歳で聖果(しょうか)寺の清俊(せいしゅん)について出家、『法華経』を学び、18歳で受具。四川省の大慈寺に入り、『円覚経』『金剛経』を学び、のちに峨嵋山(がびさん)に登り普賢(ふげん)に排し、河南省の丹霞山の子淳(1094-1117)に参じたその法を嗣ぐ。法弟に宏智正覚(わんちしょうがく、1091-1157)がいる。
○鉢盂峰(はつうほう) 丹霞山中にある峰の名前。鉢盂とは、もちろん応量噐のことだが、鉢盂は袈裟とともに禅門においては最も尊重されるものであることから、この場合の鉢盂は天地一宇を象徴するも常見を透脱した境涯をも示している。
○欣然 よろこんで……するさま。
〈解説〉
「真歇豁然契悟」の「真歇」は、真歇清了。「豁然契悟」とは、丹霞子淳に参学した真歇清了に「空劫已前の自己」を質問され、それに窮した真歇が、後日、寺の裏山に登り、丹霞の室にもどり、丹霞との問答によって契悟した因縁である。
空劫時の自己、つまり空劫時の自分の存在は、言葉をもって知ることができるものではなく、本来が不言説であることを示している。つまり、丹霞の質問に、真歇が答えようとするのを間髪を入れずにさえぎったのは、真歇が丹霞に参じた当時、真歇は本来不言説である空劫時の自己について、地をさえぎり天を覆わんほどの心意気に燃えて懸命に弁道していたが、そこには当然、分別妄想の念がしきりにはたらいているのを丹霞が見抜いての「お前は心が乱れている」という指摘である。鉢盂峰から帰った真歇が丹霞の側に黙って侍立(じりゅう)したのは、その不言の処を示しているのである。
「空劫已前の自己」については、『永平広録』「宏智失銭遭罪」に、丹霞子淳が宏智正覚に同じ質問をしていることが見える。つまり、丹霞は、その弟子、真歇清了と宏智正覚に「空劫以前の自己」という命題によって、この二人を悟道に導いたのである。
(2017年4月24日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『道元「永平広録 真賛•自賛•偈頌」』大谷哲夫 全訳注 講談社学術文庫
はじめに
■日本では中国の詩文芸としての絶句や律詩などの漢詩文を一般に漢詩といいます。偈頌は形態的にはこの漢詩形によりますが、その内面はあくまでも仏教的真実の世界、または仏徳や諸禅徳のさとりの行実(ぎょうじつ)を讃えたり、禅の教義や真実を詠ずる言語表象で、それは単なる情緒的な文芸詩とはその趣を全く異にします。したがって、偈頌は形式的には漢詩の範疇(はんちゅう)にはありますが、強いて表現すれば「仏教思想詩」「禅仏法の漢詩」「さとりの漢詩」ともいえるものなのです。(4頁)
■「風鈴の頌」というのは、道元自身の在宋時代の求道(ぐどう)の系譜ともいえる在宋留学記『宝慶(きょう)記』では、第一句と第三句のみ提示されますが、『正法眼蔵』「摩訶般若波羅蜜」巻には、
渾身似口掛虚空 渾身口に似て虚空に掛かる
不問東西南北風 問わず東西南北の風
一等為佗談般若 一等に他の為に般若を談ず
滴丁東了滴丁東 滴丁東了滴丁東(てきちょうとうりょうてきちょうとう)
とあります。ちなみに、『如浄語録』巻下では、「渾身似口」は「渾身是口」に、「不問東西」は「不管東西」に、「一等為侘」は「一等与渠」となり、『宝慶記』では「一等与他」となるなどの小異があります。この偈頌は、一読する限りでは、風鈴が全身を口にして虚空に掛かり、東西南北どのような風にも対応し、ちりりんちりりん、ちりりんと鳴っているという単なる風鈴の風情を詠じたもののようです。が、道元は、この風鈴の頌を風鈴がつねに般若を談じ仏の世界を顕現している風情を頌したものととらえ、この偈頌を拝読した時の感動を「歓喜踊躍(やく)、感涙衣をうるおす」と、『宝慶記』に記しています。
では、道元はなぜこの「風鈴の偈頌」に歓喜し感涙したのでしょうか。
それは道元在宋中の如浄膝下にあったある日のことに起因します。
如浄はまさに輿(こし)に乗り出かける寸前のことでしたが、道元は礼をつくして声をかけます。「たまたま、和尚の風鈴の頌を承りましたが、その第一句には『渾身口に似て虚空に掛かる』とあり、第三句に『一等に他の為に般若を談ず』とあります。この虚空は、単なる青い空をいっていないにも拘(かか)わらず、仏法をわきまえない人は、さも実体があるかのようにとらえて、必ずその虚空を紺碧の空のことだなどといいます。最近の参学者は、まだ仏法を窮めていないので、青い空を仏法の虚空と同じだととらえています。真に憐憫すべきことだと思います」
すると、如浄は慈誨(かい)していわれたのです。
「虚空というのは、広大無辺な仏法の智慧・般若をそのように表現したのである。目にみえる紺碧の空・青空のことではない。虚空というのは、般若そのものであるから、遮(さえぎ)るものがある(有礙)わけでもなければ、遮るものがない(無礙)わけでもない。また偏真(へんしん)などという真と虚とに分けて真のみの世界を空想し執着(じゃく)するものでもない。それらは虚空ではない。諸方の長老たちは、物質の存在する現実の世界(色法)が分かっていない。空と色を別のものと思っているから、空のことなど理解できるはずがない。しかし、私のいるこの場では、大宋国の仏法が衰微したなどとはいうべきではない。正伝の仏法は、今、ここに、生きて、あるのだ」
道元は、感謝の御拝をし、次のように申し上げます。
「この風鈴の頌は、私の大好きな最高の偈頌です。いまの中国の長老方では、たとえ三阿僧(そう)祇劫という無限な時間を経たとしても、とても作れるものではありません。雲水たちはそれぞれこの頌を大切にすべきです。私、道元は遠い辺地の日本からやって来て、仏法に対して寡聞にして少見ではありますが、いま、『伝灯録』の類(たぐい)および諸師方の語録を見ても、この『風鈴の頌』に匹敵するものを見たことはありません。私は、幸せにもいま、それを見聞し、歓喜し踊躍し、感涙袖を濡らす状態のなかで昼夜合掌し拝受いたしております。なぜならば、この偈頌は、虚空というものをものの見事に表現しながらも、偈頌としてその調子が真に格調高くすばらしいからです」
すると、如浄は微笑しながら次のように慈誨します。
「汝(きみ)のいうところは深く、抜群の見識がある。私は、この頌を健康府の清涼寺に住職しているときに作った。諸方の長老たちは讃歎こそすれ、いままでに一度も汝のように説き明かしたものはいなかった。私は、天童山(ざん)の住職として、汝に、仏法を見極める確かな識眼があることを認める。汝も頌を作ろうとするときは、このようにつくりなさい」
古来、禅門においては、この「虚空」をどうとらえるか、つまり己の存在にどう拘わるのかという点がある種の命題となっていて、祖師方もその参究に懸命でした。たとえば、馬祖道一(709ー788)の弟子・石鞏慧蔵(しゃっきょうえぞう、生没年不詳)と西(せい)堂智蔵(735-814)とによる虚空についての次のような問答があります。
兄弟子である石鞏が弟弟子の西堂に「虚空をつかむことができるか」と問うと、西堂は手で虚空をつかむ仕草をします。石鞏は「それでは虚空の真実をつかんでいない」といって、西堂の鼻をつかんで強く引っ張ったので、西堂は忍痛の声をあげます。石鞏は、西堂の悟道の因縁をつくったのです。
「虚空」というのは、常識的には紺碧の空であり、宇宙的な大空間です。が、道元の、「風鈴の頌」への拝問に、如浄が「般若のことを虚空と表現したのだ」と明確に慈誨するように、虚空は、一般でいう紺碧の空という意味ではなく、般若つまり仏法の無辺なる智慧が虚空なのです。「虚空つまり般若」、その果てしない無限な仏法の宇宙的な大空間、それは、すべての事象を包含しその存在を少しも妨げず、我々自身もそのなかに存在しているのです。
そうであるならば、そのただなかに存在する我々が、そのなかで、綿密に功夫(くふう)し弁道し発心(ほっしん)し修証し、生かせれてあるので、虚空こそが仏祖のいのち、あるがままの己の存在そのものとなります。そのような虚空の究極の真実を会得する決定的な視点を与えてくれた因縁の偈頌が、まさにこの如浄の「風鈴の頌」であったのです。換言しますと、中国に渡ってまで追い求めた仏法の究極、さとりの世界を原体験することを模索し続けていた道元に、この「風鈴の偈頌」は、その世界をまさに言葉という表象の世界でものの見事に表現して、その世界に決定的な示唆を与えたものであったのです。如浄の「風鈴の頌」にはそれだけの背景があり、それを如浄と道元という稀有な禅者が共有しえたからこそ、それが、先の道元の「感涙衣をうるおす」という表現になっているのです。道元の「感涙衣をうるおす」という表現は、正伝の仏法がまさに正しく伝承され眼前に展開されている現場に遭遇した場合の感動のみに限られます。したがって、この偈頌は、道元の偈頌観と作頌するときの覚悟を示唆しているので、少し長くなりましたが、提示してみました。
ですから、この偈頌への感動は、道元は終生持ち続けることになります。このは、まず、道元34歳のときの『正法眼蔵』「摩訶般若波羅蜜」巻に、さらに46歳のとき、越前に移り大仏寺の建立の翌年、寛元3年(1245)3月の『正法眼蔵』「虚空」巻でも、また、『永平広録』巻9-頌古(祖師の遺した古則に対して偈頌でその宗意を簡潔に宣揚したもの)の58では、本師如浄の「風鈴の頌」に対して、「渾身是口虚空を判ず、居起東西南北の風 一等に玲瓏として己語を談ず 滴丁東了滴丁東」と作頌しています。つまり、眼に見えない風は、東西南北どこからも吹いてきて、虚空に掛かる風鈴を鳴らすが、その響く鈴の音は、風鈴が全身、虚空となってちりりんちりりんと般若を語り、虚空そのものを現していると示した頌古はに対しての著(じゃく)語(自分自身の宗旨眼をもって祖師の頌などを短評する語)といってもいいものなのです。(7~13頁)
玄和尚真賛
侍者 詮慧(せんね)等編
■仏樹和尚(ぶつじゅおしょう)
平生の行道(ぎょうどう)徹通して親しし、寂滅より以来(このかた)面目新たなり、
且(しばらく)く道(い)え如何が今日の事(じ)、金剛焔(えん)の後(のち)真身(しんじん)を露(あらわ)す。
〈現代語訳〉
仏樹和尚
わが師仏樹和尚の仏道修行は、真に徹底を極めておられ、
ご示寂(じじゃく)後もその面目は不滅で、今日にいたっても新たに輝いておられる。
私は、いまも、今日は如何(いかが)ですかと問いかけたい。
師は、荼毘(だび)され金剛炎となられたが、その真実は今日にいたっても露堂々として現前しておられるので。
〈語義〉
○仏樹和尚 道元の師、栄西(1141-1215)の高弟。明全(1184-1225)のこと。
○金剛焔 仏身を金剛をも焼きつくす火炎のなかに投じて荼毘に付したが、明全の真身は生死去来にあずからない堅固無相の法身(ほっしん)なのである。
〈解説〉
道元の本師は天童如浄(1163-1228)であるのはいうまでもない。が、その本師とする如浄に巡り合うまでの、道元の参学の師は多く、なかでも明全は、道元が『正法眼蔵』「弁道話」巻において「予発心(ほっしん)求法(ぐほう)よりこのかた、わが朝の遍方に知識をとぶらいき。ちなみに建仁の全公(明全)をみる、あいしたがう霜華(そうけ)、すみやかに九廻(くじゅん)をへたり。いささか臨済の家風を聞く。全公は祖師西(栄西)和尚の上足(じょうそく)として、ひとり無上の仏法を正伝せり、あえて余輩のならぶべきにあらず」と述べるように、道元の十八歳から二十六歳にいたる時代の都合ほぼ九年間、道元の生涯で最も随侍された忘れがたき師の一人である。
明全は伊賀(現在の三重県)の人。八歳で出家、横川首楞厳院(よかわしゅりょうごんいん)の明融(みょうゆう)阿闍梨の弟子となって天台学を修め、十六歳で東大寺の戒壇院で具足戒を受け、延暦寺で円頓(どん)戒を受ける(『明全和尚戒牒(ちょう)奥書』による)。その後、諸方を遊学、建仁寺を開創した栄西の門下となり、一説にはその示寂後建仁寺の住職となったともいう。道元は、栄西や横川の縁で、建保五年(1217)八月、明全に投じている。貞応二年(1223)二月二十二日、明全は死の床にある師・明融阿闍梨の、今回の入宋(にっそう)を中止し、自分を看病し死を看取ってから入宋の本懐を遂げるように、との懇願を、仏法のためと意を決して(師の入宋にいたる決意経過は、『正法眼蔵随聞記』〈巻6-13〉に活写されている)、道元・廓然・亮照とともに入宋した。はじめ景福寺に参じ、次いで天童山の無際了派(1145-1224)に参ずる。在宋3年、ようやくその名が知られるようになった矢先の宝慶(きょう)元年(1225)五月二十七日、辰の刻(午前八時頃)天童山の了然寮にて示寂、享年42歳。明全はその死に臨み、衣装を整え、正身端坐のまま入寂した。荼毘に付すと、火五色に変じ、白色の舎利三顆(か)を得、拾うにつれて370余顆となったという。道元は明全の真景に賛するにあたり、その際のことも脳裏にあったものと思われる。その舎利は道元が帰国のときに持ち帰り、建仁寺開山堂の入定(にゅうじょう)塔の前には明全の五輪塔が建てられている(『明全和尚戒牒(ちょう)奥書』『舎利相伝記』)。
道元の大(だい)悟徹底は、恩師明全示寂後間もなくの夏安居も終わりに近い日のことであることを勘案すると、明全の示寂は道元に計り知れないほどの極めて強い影響を与えたことを示唆している。つまり、明全の存在は、道元の入宋求法大悟徹底の本懐を遂げさせるための先導師、つまり明全の存在こそが、道元にとっては菩薩そのものではなかったのかと思えてくる。
本真賛は、そうした道元の、先師仏樹房明全和尚への心の奥底からの報恩の賛頌である。道元はそれゆえにこそまた、『永平広録』巻6ー上堂435において仏樹和尚(明全)の27回忌(建長三年〈1251〉五月二十七日)には追善上堂して、
山僧(さんぞう)、今日、仏祖の第一義門を開演す。所生(しょしょう)の功徳、先師大和尚に廻向す。
として、阿難の七仏偈(諸悪莫作、諸善奉行、自浄其意、是諸仏教ーもろもろの悪を作さず、もろもろの善行をなし、自らその意旨を浄化する、これこそが諸仏の教えである)を説示し、最後に、
弟兄(でいひん)仏口(ぶっく)所生子(しょうし)、一偈単伝する、是(これ)、本孝(こう)。
(弟である阿難尊者も兄の迦葉(かしょう)尊者もともに、尊者の教説から生まれた真実の仏法の子らである。その子らが、そのすぐれた一偈(ことば)を仏祖から仏祖へ純粋に相伝したように単伝すること、そのことこそが真実の「孝」というものである。)
と廻向している。さらに翌年の建長四年の忌辰にも追善上堂している。(50~54頁)
自賛
■〈語義〉
○正尾正頭 頭正尾正の言い換え、最初も終わりも正しいこと。
○雲自水由 雲水とは行雲流水の略で、禅僧が何物にもよらず、尋師訪道(じんしほうどう)のために一所に止まることなく自由無礙に修行するさまを表現した語。(62頁)
■元来頂寧(ちょうねい)なり。道は也(また)丹蒦(たんかく)同じく成ず、証は也(また)暁天(ぎょうてん)一悟なり。
誰(たれ)か道(い)うべし祗這是(ししゃぜ)と。
〈現代語訳〉
仏道は、この頂相(ちんそう)のなかに絵の具で十分に表現されているし、さとりは釈尊が明けの明星を一見したところにある。
誰が、真実そのものの円(まど)かな心を言葉で表現できるのであろう。
祗(ただ)、這(これ)、是(これ)、これ以外の何物でもないという外はない。すべてがこの頂相(ちんそう)にあるとのみいっておこう、それは知りがたきわが心であるのだが。
〈語義〉
○祗這是 ただ、これ、これ。これ以外の何物でもないこと。仏法は現実即今に余すことなく我々の目の前に現成していることを指す。(69~70頁)
■〈語義〉
○附骨附随 全身すべて祖師達磨の境涯とならねばならない。達磨はその四人の弟子に付法の印として、道副に皮を、尼総持に肉を、道育に骨を、慧可に髄を与えた、といったと伝えられる。皮肉骨髄はそのすべてが人間の身体を構成する重要なぶぶんであるところから、道元は『正法眼蔵』「袈裟功徳」巻において、「三世諸仏の皮肉骨髄を正伝せるなり、正法眼蔵を正伝せるなり。この功徳、さらに人天に、問著(じゃく)すべからず、仏祖に参学すべし」という。つまり道元はいずれを得るも達磨の前面目を得たので、そこに優劣はないとする。(71頁)
■直指人心、拳頭頂寧(ねい、寧に頁)、見性成仏、鼻孔(くう)眼睛(ぜい)、
得皮得髄二三枚、微(み)笑拈花(げ)開五葉。
〈現代語訳〉
直接に人の心を指し示して、自己(おのれ)の心が仏性そのものと自覚させる、といったところで、拳(こぶし)で頭の天辺を指しても同じこと。
自己の本性が仏性にほかならないとさとったところで、自己自身の鼻も眼も具現化しているところ。
そこにこそ、達磨の皮肉骨髄を得た仏法が展開し、
その仏法は、釈尊が拈華(げ、花)し迦葉(しょう)が微(み)笑したところに始まり、達磨以後五葉に開花している。
〈語義〉
○直指人心 直指人心は、「見性成仏」と続く言葉で、人の心を直指し、自分の心が仏性にほかならないと自覚することが成仏である、とする。この言葉は、達磨が伝えたとする「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏」の四句の一句で、経典が伝えるところには仏法の真実はなく、達磨が伝えたところのみに仏祖の大(だい)道がある。つまり、禅宗の綱領は、経典や文字のなかにあるのではなく、経典や文字の指し示しているところを直接端的にとらえるところにあるとする、禅宗以外の仏教、経典・文字をよりどころとしている教家に対する優位を強調する言葉でもある。
○得皮得髄 達磨大師が四人の弟子に所解を提出させ、それぞれわが皮・肉・骨・髄をえたと印証したことに始まる。この場合、文字の上では、皮を得、髄を得ることではあるが、達磨の仏法の全相続をいう。道元は『正法眼蔵』「葛藤(かっとう)」巻において「得皮得髄の殊劣(しゅれつ)によれるにあらず」といって優劣をつけず、また「骨肉髄をえたるは、皮肉面目をえたり」というように、皮・肉・骨・髄すべてが身体を構成する重要な部分であり、同時にその一つ一つが身体であるとするので、どこを得ようと達磨の全仏法を得たことになる。(79~81頁)
偈頌
■「偈頌」について
道元の「偈頌」125首は『永平広録』第十巻に集録されている。
「偈頌」の「偈」は梵語のgathaの音訳、偈または迦陀(かだ)、「頌」は中国語の詩のことで、やがて梵漢混淆(ぼんかんこんこう)した「偈頌」という漢語に表記されるようになる。いずれにしても「偈頌」は仏法の教説の一段または全分の終わりに詩句をもって陳(の)べる韻文のことである。が、とくに禅門では五言あるいは七言の漢詩形で仏徳を讃歎し、さらには教義・見解(けんげ)を説示したものを総称して「偈頌」という。つまり、禅門における「偈頌」は単なる分学的な感情を表象する一般的な所謂(いわゆる)「漢詩」とは些(いささ)か趣(おもむき)を異にし、仏法の言詮(ごんせん)を超えた悟境、自内証の世界、自分自身のとらえた仏法等々を言葉に託して表象するのが「偈頌」ということになるので、禅門の「偈頌」はとくに「禅的表現詩」といえる。したがって、広義でいえば、「真賛」「自賛」の賛、さらに「頌古」またその頌も「偈頌」の範疇ではあるが、いまは『祖山本 永平広録』の分類にしたがっておくほうが便宜であるのでそのままとした。
道元は、貞応二年(1223・宋の嘉定十六年)、二十四歳のとき、建仁寺で師事した明全(1184-1225)らとともに入宋(にっそう)し、四月上旬明州にいたり、七月天童山景徳寺に掛錫(かしゃく)し、無際了派(1145-1224)に謁(えつ)し許されたが縁契(かな)わず、その秋には尋師訪道(じんしほうどう)に出て、再び天童山に帰った。そして、本師となる天童如浄(1163-1228)に初相(しょう)見したのは宝慶(ほうきょう)元年(1225)五月一日のことである。が、同月二十七日明全示(じ)寂し、七月二日より本師如浄古仏に親しく問法し、夏安居中に大事を了畢(りょうひつ)した。以後如浄にしたがい、宝慶三年(1227)七月上旬に帰国した。時に道元二十八歳であった。
つまり、道元は宝慶元年(1225)より同三年(1227)にいたるほぼ三年間、天童山景徳寺に掛錫し、天童如浄古仏に師事したのである。が、「偈頌」として収録せられたその最初のものは、『永平広録』「偈頌」の巻頭に「師、嘗(かつ)て大宋宝慶二年丙戌(へいじゅつ)に於いて、慶元府太(たい)白名山天童景徳禅寺に寓す」と記してあるように、その掛錫された中間の年である宝慶二年(1226)に作頌されたものより始まり、以後五〇首までが在宋時代の作として収録されている。
ではなぜ『永平広録』の第十巻「偈頌』の巻頭に、この「宝慶二年」をわざわざ強調して記しているのであろうか。それは、その年以前の道元は僧堂の披位(僧が坐禅して起臥する場)にあって不眠不休の頭燃を救(はら)って坐禅弁道した時期であり、一大事を了畢してもなお、如浄古仏に随侍し拝問していた時期である。したがって、恐らくは道元自身に作頌の余裕はなく、道元の中国での作頌は、異国僧でありながら大(だい)悟徹底したした評判が聞こえるようになった時期、つまり宝慶元年の夏案居以後、幾分かの余裕のもてた宝慶二年以後のことであることを示しているのである。(96~98頁)
■元来仏祖明心の地、知見当(その)時(かみ)眼睛(ぜい)を偸(ぬす)む、
擬前退歩す金(こん)獅子、鉄蒺蔾(しつり)迸(ひん)して木馬驚く。
〈現代語訳〉
元来、仏祖の法というのは、自己の心を明瞭に認識すること。
従来からの凡夫の分別知を、仏道の的確な要所に転換する。
それには金毛の獅子が猛り狂うようにして、進んでは退く修行の功を積むことが必要。
そうすれば、鉄菱(びし)に無心の木馬も驚くように、弁道すれば天童古仏の厳しい叱声が自己の心に響く。
〈語義〉
○元来仏祖 元来、仏祖道というのは心を明らめること。
○偸眼睛 眼睛は目玉のこと、転じて眼目・要点の意、禅門ではとくに肝要の意。道元は眼睛に無量無辺の意味を持たせている。偸眼睛は仏道の要所を的確につかむこと。
○鉄蒺蔾 三角形の尖った鉄菱で、これを地上に散(ま)き敵の侵入を防ぐもの。この鉄蒺蔾(てつしつり)を撒いておいたように、無心な木馬までが驚いてしまうように心地が進みがたいのが仏地である。(126~127頁)
■従来の諸仏祖呑尽(どんじん)して、他に従わずして円通(えんずう)を証することを得(う)(卍山 他に由って証せず自ずから円通)。
〈現代語訳〉
貴殿は、釈尊をはじめ従来の諸仏祖を、腹のなかに呑み込み、わがものとして、
仏祖の力を借りずに、自分で欠けることのない境地を得ているのである(卍山 ほかの力を借りずに自ら円通する)。(129~130)
■業識(ごつしき)忙忙(卍山。茫茫)たり飽毒(ほうどく)の身(しん)、去来処(ところ)に触れて真を留(とど)めず、
今朝(こんちょう)蹈破(とうは)す紅炉子(こうろす)、全体雍容(ようよう)たり赤脚人(しゃっきゃくじん)。
〈現代語訳〉
妄想(もうぞう)が無限に広がり、貧瞋癡(とんじんち)の三毒のあふれた身であった君よ、。
生死輪廻に苛(さいな)まれ、真実を見失ったすがたをしていた君よ、
それには金毛の獅子が猛り狂うようにして、進んでは退く修行の功を積むことが必要。
ところが、今朝、君は、業識(ごつしき)も妄想もすべてを紅炉に叩き込み焼きつくし、
無礙(むげ)脱体(だったい)し、真実解脱の人となった。(131~132頁)
■一花(いちげ)開く処(ところ)処象(しゅぞう)を新(あらた)にす、万里の春風一等(卍本 直下(じきげ))に知る、
樹(き)を辞する紅花飛んで狼藉なり(卍本 門を出(いで)て逐(お)うこと莫(なか)れ紅(くれない)を尋(たずね)る客)、
擬前退歩幾(いくば)くの迷岐ぞ。
〈語義〉
○一花開 春になって一花が開くと万物が新たになるように、自己の心地が開けると世界の諸象がすべて新たに映る。
○尋紅客(卍本) 百花繚乱として咲く花を尋ねる人。そのような人は表面的な美しさのみを求めて真実を見ない。(132~133頁)
■〈語義〉
○渓声山色 渓の声、山の色は大自然の真実のすがたそのもので、仏の説法そのものであり、仏の清浄(しょうじょう)身でないものはなに一つないということ。『正法眼蔵』「渓声山色」巻に「たとい渓声山色八万四千偈を現成せしめざることは、夜来なりとも、渓山の渓山を挙似(こじ)する尽力未便ならんは、たれかなんじを渓声山色と見聞せん」とある。(146頁)
■然子が終焉(しゅうえん)の語を看る
廓然無聖硬きこと鉄の如し、試みに紅炉(こうろ)に点ず鎖(さ)ゆること雪に似たり、
更に問う今何(いずれ)の処にか帰り去る(卍本 而今何の処にか去る)、
碧波(へきは)深き処(ところ)何(いか)なる月をか看る(卍本 碧波心裡月を看ず)。
〈現代語訳〉
ああ廓然よ、君は廓然無聖の語のように、心に屈託なく求道(ぐどう)の精神は鉄のように硬かった。
それなのに、その肉体も紅炉に投ずると雪のようにはかなくも消えた。
私は問いたい、君はいまどこに帰ったのか(卍本 現在、どこにいるのか)、と。
紺碧の波の深きところで、一体どんな月を見ているのか(卍本 こころの奥には月は見えない)、と。
〈語義〉
○然子 明全と道元の渡宋に同行した廓然・亮照のうち、恐らくは明全の侍者を務めた廓然ではないかとする説が有力と思われる。
○廓然無聖 隔年無聖は、達磨が梁の武帝の質問に答えた言葉で、心が開けて何の執着(じゃく)もない大悟の境涯から見れば、凡聖(しょう)の相対区別はなく厳然たる事実のみがあることを示した言葉。(147~149頁)
■〈現代語訳〉
儒教は、天と地もない原初の世界が破れ、天・地・人が現れた、という。
が、これは天も、地も、人も、それぞれの本来のはたらきが現れたのだ。
仏法のせかいでは、人間と物質はそれぞれが解け合い通じ、二つの事象など区別しない。
それゆえに、情識(じょうしき)を超越した石女(うまずめ)に三台の区別などないのだから、三台に舞わせることはない。
(卍本 天地未だ分かれざる原初の世界に、すでに天・地・人に分かれる兆しはあった。
それゆえに、天・地・人と区別してそれぞれの本来のすがたを求めることはない。
森羅万象(ばんぞう)、区別などなくすべてが一つで、平等であるところに着眼せよ。
そうすれば、石女が三台に舞うすがたを笑って楽しめるであろう)。(155頁)
■〈現代語訳〉
ひとたび、さとりの光に照らされれば、主とか客とかの相対的区別はなくなる(卍本 忘れる)。
うちなる自己を反省して本来の自分自身を照らしてみると、存在する自己すらもない(卍本 報慈庵の身は貧にして貴く、仏道もまた清貧である)。
元来、自分は、現在も、その直前も、その直後も、何もないということに気づく。
それこそが真実の世界であることに気づかなかった過去を思うと残念で涙がこみ上げる(卍本 隔てる何ものもない)。(161頁)
(卍本 隔てる)。(155頁)
■三途(さんず)六道(りくどう)崔嵬(さいかい)峙(さきだ)てたり、来去風騒しくして意(こころ)自(おのずか)ら通ず、
正(しょう)眼当観すれば時節至れり(卍本 四生(しょう)六道遊戯(ゆげ)に当(あ)つ、去去来来意自ら空ず、正眼に諦(たい)観す通達(だつ)の者)、張三李四老年翁。
〈現代語訳〉
人は死しては三途(さんず)の川を渡り、生きては六道に輪廻するという厳しい現実がたちはだかり(卍本 人は四生六道に迷う愚かなものというが、それこそが自在無礙の境界)、
生死(しょうじ)去来の迷いに吹き付ける風は騒がしいが、そここそが無礙の三昧(ざんまい)境)。
正法(ぼう)眼をもって観れば、そここそが悟達(ごたつ)の時節(卍本 この悟達諦観の人こそが)。
あそこにいる李さん張さんであり年老いた翁。(167~168頁)
■這(こ)の外(卍本 言外)何ぞ求めん真的の所、霊機(れいき)点ずる処(卍本 霊機一転)来由(らいゆう)を失う、何人(なんびと)か此(ここ)に到って空際を脱せん、問うこと莫(なか)れ身無くして疾瘳(しっちゅう)を悟ることを(卍本 語ることを)。
〈現代語訳〉
仏法の真実以外に何を求めるのか(卍本 言語の思量を離れたところに仏法の真実を求める)。
自己の霊妙不可思議な仏性がはたらけば(卍本 霊気が一転すれば)生死去来などの迷妄は根本的になくなる。
ここにいたれば、誰が一体、空相無相を向け出せないものがいようや。
自分自身の身体を判然と自覚しないのに、生死煩悩等に悩まされる実体のない病など問題とすることはない。(173~174頁)
■未だ知らず大道本(もと)より何如(いか)ならん、鶻(髑、どく)髏(こつろう)を透脱して自都を遺(のこ)す、
彼此(ひし)伶併(れいへい)来去錯(あやま)る、一廻(ひとたび)照顧(しょうこ)すれば跡蹤(せきしょう)無し。
〈現代語訳〉
大道は、本来どのようなものなのか、人は知らない。
髑髏になって人間の情識から抜け出しても、本来の自分を遺すから、
あちらこちらと彷徨(さまよ)って行くべき道を錯(あやま)るのです。
ひとたび自己を照顧すれば、さとりの痕跡もないさとりの世界が開けるものです。(180~181頁)
■昌国県補陀舌迦山(ほだろかさん)に詣でて因(ちな)もに題す
聞思(もんし)修(しゅ)本(もと)より証心の間(卍本 三摩地に入り)、豈(あに)洞(とう)中に聖(しょう)顔を現ぜんことを覓(もとめんや(卍本 自己端厳にして聖顔を現ず)、
我告げ来る人須(すべから)く覚(さとるべし(卍本 為に来人に告げて此の意を明らかにす)、観音宝陀山に在らず。
〈現代語訳〉
仏法を聞き、思慮し、修行するのは、もとより己の心を証するため(卍本 不動の心境になるため)。
どうして洞窟のなかに観世音菩薩のお顔の現れるのを求めよう(卍本 自己のうちの端正な自己が観世音の聖顔となって現れる)。
私は、ここに参詣に来る人たちに告げよう、自己に目覚めよと(卍本 ここに参詣に来る人たちに、この意を明らめよと告げよう)。
観世音菩薩はここ宝陀山にご不在なのだ、探し求める己のなかにおられるのだから。(182~183頁)
■須(すべから)く知るべし仏法心空に到るを、人の言い説き窮める所なるべからず(卍本 是語言の説いて窮むべきにあらず)、
見色聞声(もんしょう)倶(とも)に脱落なり、東西南北自ら流通(るずう)す。
〈現代語訳〉
仏法は、心が空になること、心は実体がないことを、執着を離れて、すべてのことをありのままに見るところに到達することであることを知らねばならぬ。
これは人が言葉をもって究められるところではない(卍本 言葉の説いて究められるところではない)。
心空になれば、見るもの聞くもの、感覚にとらわれることを脱落し、自在となる。
そうなれば東西南北ありとあらゆるところに、仏法が遍在する。(186~187頁)
■磨塼作鏡(ませんさきょう)功夫(くふう)に藉(よ)る、識(し)るべし斯(こ)れ猶半途に滞る(卍本 脚下須らく知るべし半途に滞ることを)、
若し東西(卍本 西来)真的の旨(し)を問わば、噴噴(ふんぷん)地の上に觜盧都(しろと)す。
〈現代語訳〉
参禅弁道は、甎(せん)を磨いて鏡とするような無所得の功夫(くふう)を重ねるが、
これとて、まだ修行の中途半端なところに滞っていることを識(し)らねばならぬ(卍本 脚下、すなわち己自身が中途半端であることを知らねばならぬ)。
もし、達磨の伝えられた真実(卍本 西来)の仏法を問うならば、
私は、言葉など用いず、大きく息をはき口を閉じて地上に黙坐しよう、只管打坐のみが真実であるのだから。
〈語義〉
○磨塼作鏡 塼は甎とも。よく焼いた固い瓦のこと。「甎を磨いて鏡と作(な)す」というのは、南嶽懐譲(677-744)と、その弟子馬祖道一(709-788)との師資証契(しししょうかい)の問答として有名で「南嶽磨甎」といわれる公案。坐禅が、六祖慧能(638ー713)の「金剛経」を中心とした無所得に徹するから、南嶽においてもこの坐禅が継承され、何物も求めずただ行ずるものとして、南嶽は甎を磨いて馬祖に示したのである。この公案の眼目は、磨甎という行為が単なる徒労無駄骨をいうのではなく、坐禅は仏になる手段ではない(不図作仏、ふとさぶつ)ことを明確にしたもので、坐禅が有所得であってはならない実態を如実に示すものである。この磨甎作鏡は『景徳伝灯録』巻五・南嶽懐譲章に出る。『正法眼蔵』「古鏡」巻では、馬祖が南嶽に参じた故事を説いた後に「この一段の大事、むかしよりすう百歳のあいだ、人おおくおもえらくは、南嶽ひとえに馬祖を勧励せしむると。いまだかならずしもしかあらず、大聖(だいしょう)の行履、はるかに凡境を出離せるのみなり。大聖もし磨甎の法なくば、いかでか為人の方便あらん。為人のちからは仏祖の骨髄なり」と説かれている。同「坐禅箴」巻には本公案を事細かに引用しその一々に懇切な提唱が見られる。また『永平広録』では巻四ー上堂270に、さらに巻九ー頌古38にも見える。
○觜盧都 口を閉じて一言も発しない。(195~197頁)
■禅人に与う 八首
①側耳(そくじ)抬頭(たいとう)して家風(卍本 暁風)を待つ、
幾過(きか)春雨牧牛懵(もだ)ゆ(卍本 牛を牧し雨に吟じて空濛に立つ)、
誰(たれ)か知らん這箇(しゃこ)の衝天(しょうてん)の意(こころ)、只揚眉(ようび)瞬目の中(うち)に在り。
〈現代語訳〉
禅人に与える 八首
①寂莫として静まりかえった山中に、夜も眠れず、心を澄まし、耳をそばだて、頭を抬(もた)げて、家風を待つ(卍本 暁風が吹き、夜の明けるのを待つ)。
長い年月、静寂そのもののなかに牛の声を聞いたが、それはまさに修行僧たちの呻吟(卍本 小雨のそぼ降るなかに牛の鳴き声が聞こえる)。
しかし、誰が知ろう、この静寂等閑のなかに、正法を究めんとする衝天の意気があることを。
そして仏法は、日常の普段の何でもない動作、眉をあげたり、目をしばたく、そうしたなかにあることを。
〈語義〉
○揚眉瞬目 眉をあげ、瞬きをする。日常の不断の何でもない動作。(197~199頁)
②仏祖元来眼前に在り、秋深くしては覚(おぼ)え難し古船の舷(ふなばた)(卍本 前灘波動いて秋煙を鎖す)、
夜寒くしては乱れ易(やす)し鴈行の列、左右祗(ただ)斯(こ)れ空(そら)に満てる煙(けむり)(卍本 月暗くして尋ね難し古渡の舟)。
〈現代語訳〉
②仏祖はもともと目の前におられて歴々として明らかなものだ。
だが、それを見誤ると、仏祖が秋が深い霧のなかで古船が霞んでいるような状態になる(卍本 荒波に揉まれて行き先に迷うようなものだ)。
夜寒の空に迷って乱れ飛ぶ雁のように、
周囲を見渡せば、空間に煙が満ちているように仏祖の家風が満ちている(卍本 月暗くして涅槃にいたる舟を探す術もない)。(199~200頁)
③宗(しゅう)説倶(とも)に通ず瞥(べつ)地の先、誰人(たれびと)か此(ここ)に到って安然たるべき(卍本 誰か能く此に到って山玄を解せん)、
松風(しょうふう)響きに愧(は)づ(卍本 松風空しく響く)聾人(ろうじん)の耳、
竹露屢(しばしば)零(おち)て月辺に納(い)る(卍本 竹露屢零つ涼月の辺)。
〈現代語訳〉
③宗旨の根本に通じ、宗旨を説き示せても、ほんの少し先が見えただけ。
そこにいたったからといって、誰がそこに安然としていられよう(卍本 そこにいたったからといって、誰が仏道の幽玄なる奥義に参じ得たといえよう)。
松風は、耳に聞こえない人には響かず虚しいものだし(卍本 松風空しく響く)、
竹葉に宿る露にも、天空にかかる月にも解脱の風光は輝いているのに、見えない人には見えないもの。
〈語義〉
○松風 宗説倶通した松風の風情。(200~201頁)
④大機転ずる処漫天動ず(卍本 文彩を絶つ)、徹底蹤(あと)無し線路の辺(ほとり)、
孤(ひと)り楼台に詠ずれば唯(ただ)月色のみあり(卍本 五夜の楼台唯月色)、
雲に染む時雨(じう)燃煙を湿(ぬら)す(卍本 暁来の一雨残因を洗う)。
〈現代語訳〉
④信心堅固な弁道によって得たその境涯がはたらくと、天一面が開けるように迷悟是非が転じ(卍本 迷悟是非など相対的な世界がなくなり)、
見渡すかぎり、徹底してどこにも何物も残っていない。
大機の自在なすがたは、独り楼台に詠ずるとき、空に月が輝くように(卍本 暁天の楼台に月が輝く)、
雲に馴染んだ時雨が燃焼した跡の煙さえ消し去るようにさとりの痕跡さえ残さない(卍本 明け方の一雨が残煙を洗い流すようにさとりの残跡さえない)。(201~202頁)
⑤無明誰か悪(にく)まん唯(ただ)秋(卍本 草頭)の露、実相元来此の裏に真なり、
留(とど)めて(卍本 留めて得て)知り難し流水の底、結び来ては変じ易し承(じょう)当の身。
〈現代語訳〉
⑤誰が、無明の迷いを憎むことがあろう、それは秋露(卍本 草の葉に宿る露)のように消え去るもの、
そして無明の迷いもまた、あるがままの真実のすがたなのだから。
無明の迷いは、流水の流れを留めても(卍本 留め得て)、その底が見えないようなもの。
無明の迷いはそのようなものだと分かっても、変わりやすいのは、そうだと分かったと思うこの身。
〈語義〉
○承当 会得、領得すること。またこの世に人間として生まれること。(203~204頁)
⑥松風高く韻(ひび)いて夏宵(かしょう)秋なり、竹響頻(しき)りに慅(さわ)いで(卍本 竹葉の露頻りに降って)暁涙(ぎょうるい)流る、
唯途(みち)に触れて全体動ずべし、誰(たれ)か古路(ころ)を忘れて此の間(あいだ)に憂(うれ)えん。
〈現代語訳〉
⑥松風がより高く鳴り響く夏の末の宵、秋の初めのころ、
竹も響き、竹葉の露もしきりに落ちて(卍本 竹の葉の露がしきりに降って)物寂しい暁の時分、移ろいゆく気配に無常を感じて涙が頬を伝う、
そのようなときであるからこそ、松風・竹響の見聞声色にとらわれず、心を発動せねばならぬ。
誰が、古仏の辿(たど)った仏祖道を忘れ、初秋のもの悲しき無常世界に身をゆだねていられよう。
〈語義〉
○暁涙 竹露がしきりに落ちるように涙がながれる。
○古路 諸仏の開悟した仏法の大道。
○此間 無常なる世界。(204~205頁)
⑦雲晴天に断えて鶴の意(こころ)閑(しずか)なり、浪(なみ)古岸に連なって魚行謾(おそ)し(卍本 謾たり)、
誰人(たれびと)か眼(まなこ)を此の参際に著(つ)けん(卍本 設し人眼を著けて斯際に及べば)、
百尺の竿頭一進の間。
〈現代語訳〉
⑦雲一つとしてない晴天に、鶴は心静かに舞い、
浪は古岸に連なって押し寄せ、魚は広々とした海にゆったりと泳ぐ。
誰が、このあるがままの自由自在な境界(がい)に、眼をつけるだろう(卍本 もし人が任運に、自由自在のこの境にいたるには)。
それには、百尺竿頭の先にぶら下がっている自分自身を放下することなのだ。
〈語義〉
○百尺竿頭 全句のような任運自然(じねん)の道理のなかで、知解分別にわたる自己を徹底的に放下し転身自由となる。(205~206頁)
⑧玉人夢破(さ)めて暁雲忪(いそが)し、夜月霧消えて残露空し、
独り寒床を覚(し)る意(こころ)を待つに似たり(卍本 独り覚る寒床限り無き意)、
風光憶(おも)わず訪心の中(うち)(卍本 風光凄断す寂寥の中)。
〈現代語訳〉
⑦仏道修行者が迷妄の夢から覚めると、暁雲が飛び去ったような気分。
夜月にかかっていた霧も晴れ、残露もない爽快な朝景色に似て、それは一切の迷妄が消え去った境地。
独り暁天の寒床に坐していると限りない思いが駆けめぐり(卍本 独り暁天の寒床に打坐していると、種々様々な思いが駆けめぐることを覚る)、
暁雲、夜月、霧、残露、そういった風光が心を揺さぶる(卍本 この寂寥たる山中の暁天坐禅では、そうした風光さえもが断たれる)。
〈語義〉
○玉人 仏道修行者、禅者のこと。
○寒床 寒々とした禅床のこと。(206~207頁)
〈解説〉禅人に与える八首について
偈頌53~60の八首は、とくに自然の風物と仏法を照らし合わせている語句が多い。たとえば、その八首から拾い出してみると「幾過春雨牧牛懵(卍本 牧牛吟雨立空濛)ー中略ー 等々とあって、その偈頌には寂寥感が強く漂っている。それは恐らく、道元が雲遊萍記(ひょうき)し弘法(ぐほう)激揚(げきよう)の時をまつとして安養院に閑居していた時代であったからではいかと拝察される。(208頁)
■閑居の時 七(六)首
①阿誰か取舎せん悄然なりと雖(いえど)も(卍本 取舎を双忘して思い翛然たり)、
万物同時に現在前(ぜん)す、
仏法今従(よ)り心既に尽きぬ、身儀向後且(また)縁に随う。
〈現代語訳〉
閑居の時(卍本 閑居の偶作) 七(六)首
①憂いに沈むような感傷の場ではあるが、それに浸っているのではない(卍本 一切の取捨選択を忘却し、心は寂然として静寂)。
ここに端坐すれば万物すべてが、仏法そのものとして、同時に目の前に、あるがままに現れている。
正伝の仏法に、いまも、そして今後とも、わが心は動揺することなく、
わが身を処縁に処して自在無碍に生きるばかり。
〈語義〉
○閑居之時 閑居とはしずかなるたたずまいのなかの意である。が、道元の実際の閑居は寛喜二年(1230)から、山城深草安養院に閑居した三年間で道元の三十歳から三十三歳の頃である。(216~218頁)
②木人昨夜離根(卍本 離魂)し去る、露柱灯籠幾(いくば)くか恩を恋うる(卍本 旧恩を恋う)、
同道方(まさ)に知る絶境界、動著(じゃく)して乾坤を覆(おお)わしむること勿れ。
〈現代語訳〉
②昨夜、思量分別を超え迷妄の根本(卍本 魂)から離脱して無心無礙となった木人が、どこかへ去った。
今まで一緒(とも)に過ごしてきた無情なる露柱や灯籠たちは、今、彼の恩を恋い慕っている。
一緒に修行してきたあるがままに現成している木人・露柱・灯籠たちは、その絶対自在無礙の境界(がい)を知っている。
だからこそ、その無心玄妙なる境界について、心を動揺させ妄想(ぞう)を起こして知解(ちげ)をもって天地を覆うようなことをしてはならぬ。
〈語義〉
○木人 木でつくった人形。思慮分別を超えた境涯にたとえる。
○露柱灯籠 むきだしの柱と灯籠。禅門では、無情または非情なものがそのものとして現成し不断に真実を説いている相(すがた)を例示するのに用いる。同様のものに瓦礫(がりゃく)・牆壁(しょうへき)・木人などがある。
○絶境界 無心の木人がどこかへ行くと、無情な露柱灯籠がそれを恋い慕うといったような、思慮分別を超越した世界。
○覆乾坤 乾坤は天地のこと。全世界を暗黒に覆いかくす意。(218~220頁)
③触目遇縁(しょくもくぐうえん)尽(ことごと)く是親し、経行(きんひん)坐臥体(たい)全く真なり、
人有って若し箇中の意(こころを問わば、法眼(ほうげん)蔵中一点の塵(ちり)。
〈現代語訳〉
②ここでは、目に触れ縁にあうものすべてが仏法の世界そのものに親しい。
経行・坐禅・臥床(がしょう)といったごく日常的なことすべてがその真実。
人あって、この閑居の意中を問うならば、
その質問に答えたりするのは、仏法の真実、正法眼蔵中に一つの塵を舞わせるようなもの、脱落底のところにそのような質問は無用と答えよう。
〈語義〉
○触目遇縁 目に縁にあう。仏法により解脱した心境から見るもの。
○経行座臥 行・住・坐・臥の四威儀(しいぎ)。経行は動、座臥は静、日常生活の一挙一動。
○法眼蔵中 正法眼蔵のこと。正法の仏法。(220~221頁)
④大用(だいゆう)現前眼(まなこ)に当って新(あらた)なり、然(しか)りと雖(いえど)も何ぞ其(そ)の真を呈すべき(卍本 是の如くなりとも曷ぞ真を呈せん)。
愁人(しゅうじん)愁人に向かって道(い)うこと莫(なか)れ、向道愁人人を愁殺す。
〈現代語訳〉
④仏法の大きなはたらきは、つねに目の前にあって新鮮。
そうではあるのだが、その真実を表すのは容易ではない(卍本 それはそうなのだが、その真実をどのように表現したらよいであろう)。
愁いを抱く人が、愁いを抱く人に言葉をかけてはならない。
迷っている人が、迷っている人に言葉をかければ、さらに混迷を深めるようなもの。愁いを抱く人は、その愁いを自分自身の胸のうちにしまっておけばよい。
〈語義〉
○大用 仏法の大きなはたらき。
○愁人 字義どおりでは、愁い悲しんでいる人がさらに憂愁を誘うような話をする、という意であるが、この愁人は迷悟の人。(221~222頁)
⑤生死憐れむべし休して又起こる(卍本 雲変更)、迷途覚路夢中に行く、
然りと雖(いえど)も尚忘れ難き事有り(卍本 唯一事を留めて醒めて猶記す)。
深草の閑居夜雨の声。
〈現代語訳〉
⑤生死の流転は、何ともはかなく哀しきこと、それは一つの真実のすがたであるのに、忘れたかと思うとまた起きてくる(卍本 雲が流れ去りまた沸き上がるように、とりとめもない)。
迷いとかさとりというのも同じこと、それが二つ在るのではなく、一つの真実で取捨選択すべきものではなく、それは夢覚(がく)一如で、夢中に徃来したようなもの。
醒めればあとかたもないとはいうけれど、それはそのとおりなのだが、忘れがたいのは、弘法(ぐほう)救生(ぐしょう)の強き一念のみである(卍本 夢から醒めても、なおこれだけは記憶に残っている)。
それを知ってか知らずか、都を離れた深草の閑居の庵(いおり)には、夜来の雨が降りそそぐ声のみが響いている。
〈語義〉
○夢中 道元は夢の世界も仏法の世界の範疇であると説く。『正法眼蔵』「嗣書」巻に「道元、台山より天童にかえる路程に、大梅山護聖寺の丹過に宿するに、大梅祖師きたりて、開華せる一枝の梅華をさずくる霊夢を感ず。(中略)夢中と覚中と、おなじく真実なるべし。道元在宋のあいだ、帰国よりのち、いまだ人にかたらず」とある。また同「夢中説夢」巻に、「夢中の諸法、ともに実相なり。覚中の発心・修行・菩提・涅槃あり、覚中の発心・修行・菩提・涅槃あり、夢覚おのおの実相なり、大小せず、勝劣せず」とある。
(中略)この偈頌はその思いが重く肩にのしかかっていた深草の閑居の時代の作であろう。(222~224頁)
⑥涼風方(まさ)に渡って秋の響きを覚(し)る、天気爽清にして結果新(あらた)なり、
結果新たにして(卍本 新たなる時)香(こう)満界なり、廻避無き処得聞親し(卍本 疎親没し)。
〈現代語訳〉
⑥涼風が吹きわたると、あたり一面に秋の気配を感じる。
天気は清涼で、木々の実も新たに熟してくる。
木の実の新たに熟すとき(卍本 新たなるとき)、
その仏法の香りがあたりに充満するように仏果のはたらきに満たされる。
その香りは避けようにも避ける場などない、
そのように、仏法のはたらきは親疎の差別なく、あるがままにあたり一面にあふれている。
〈語義〉
○涼風 以下は秋の風情にたとえて仏道修行の孰処をいう。涼風は迷悟を超脱した風。
○没疎親(卍本) 凡聖迷悟の差別のないこと。
〈解説〉深草閑居の時について
道元は、宋から帰国し、しばらく京建仁寺に止まり、さらに深草の安養院にあって、本師天童如浄の膝下で、坐禅弁道に励み、大悟了畢(だいごりょうひつ)した正伝の仏法をどのように日本に広めるかを念頭に置きながらも、雲遊萍寄(ひょうき)、つまりまさに空にたゆとう雲のように行き場なく、浮き草のように寄るべき岸辺もない生活のなかで、まさに正伝の仏法を弘通(ぐずう)し衆生救済の激揚の時を待つ状況にあった。道元は、その心境を『正法眼蔵』「弁道話」巻に「ついに大白峰の淨禅師に参じて、一生参学の大事ここにおわりぬ。それよりのち、大宋紹定のはじめ、本郷にかえりし、すなわち弘法救生をおもいとせり、なお重担をかたにおけるがごとし。しかあるに弘通のこころを放下せん、激揚のときをまつゆえに、しばらく雲遊萍寄して、まさに先哲の風(ふう)をきこえんとす」と吐露している。
道元が「雲遊萍寄」と表現した、この深草閑居の時期は、打ち続く飢饉のなかで、後に展開する『正法眼蔵』の総論ともいうべき「弁道話」を書き著し、正伝の仏法を弘法しようとする意気軒昂な時期ではあったが、その心中は、何の寄る辺もない、まさに空に浮く雲のごとく、水に漂う浮き草のような生活のなかで、因縁の熟すのをまつ忸怩たる思いにも駆られていたのではなかったか。正伝の仏法の流布という重い荷物を肩に背負っている弘法救生(ぐほうぐしょう)の思いと、激揚の時をまつ雲遊萍寄の生活。しかし、自分が、先哲の風をならって雲遊萍寄しているとき、真の求道者は、邪師に惑わされ、伝えるべき正しい種が絶えてしまうではないか等々、様々な思いが交差していたのではなかったか。
道元の仏法は、この雲遊萍寄の時代を経て、まさに激揚の時期を迎え、弘法救生の精神が縦横無尽に展開されていくことになる。先の「禅人に与える 八種」の偈頌とこの「閑居の時 六首」は、その安養院時代の激揚の時をまつ時代の作頌ではないかと推測される。この閑居の時代こそが、道元の仏法が展開される準備期間でもあったのである。
なお、この閑居の偈頌は『祖山本』は「閑居の時 七首」とあり、『卍山本』は「閑居の偶作 七首」とある。が、実際は六首で、次の71の「春雪の夜」を入れると「七」になるが、「春雪の夜」は、次の72と連作のようであり、しかも、それは永平寺での作頌ではなかったかと思われる。また『祖山本』の78に「此れより已後(のち)、皆、越州に在って作す」とあるが、それ以前にも越州の作が混入しているところもあるようである。(225~227頁)
■春雪夜
春雪の夜
桃の花、李(すもも)の花があでやかに咲き、雪や霜がどれほど凄絶な美しさをみせようとも、それに愛着しない(卍本 どのような美しいすがたであろうとも、愛着にとらわれない)。
青々とした松、緑の竹も、流れ去る雲や煙とどれほどの違いがあろう(卍本 松や杉が雪に覆われてその緑青が隠れる、そのすがたにこそ愛着する)。
歳をとれば皮膚は衰え鶏皮のように、頭髪は鶴羽のように白くなるのに、何も染めなくてもそれはそれで良いではないか(卍本 ぶつどうに生きる人は、心が乱れ散ることも忘却の彼方にあるのだから)。
世俗の名聞利養など、とっくに投げ捨てて、もはや数十年。
〈語義〉
○名利(みょうり) 名聞利養(みょうもんりよう)。(228~229頁)
■大師釈尊在世八十年
夜半の烏児(うに)頭(こうべ)に雪を戴く、天明(めい)に唖子(あし)酌(く)んで泉と言う、
此の家の料理他国に異なり、一丈の池心一丈の蓮。
〈現代語訳〉
大師釈尊の仏法の世界は、真っ暗闇のなかに、真っ黒なカラスが頭に真っ白な雪を載せているように、黒白未分の差別の世界を絶し、
夜明けに、もの言えぬ人が、水を汲み、泉の水だよと声をあげたように、ことほど左様に、言語では表現できないところさえも超え、物の道理を絶した境界(がい)。
それゆえに、仏家の料理(家風)は、他国の料理とはまったく異なり、
一丈の池には一丈の蓮の花が咲くように、その仏法の香りは三世十方の世界に次元を超えて薫る、その仏法を私は相承(じょう)している。(232~233頁)
■八月十五夜
八月十五夜、月の前に於いて、各(おのおの)月を頌(じゅ)す。此の月心月に非ず、天月に非ず、昨月に非ず、夜月に非ず、尖月に非ず、想像(おもいや)る、是、秋の月なり。如何。
金波(きんぱ)泊(とど)まるに非ず河宿(かしゅく)なりと雖(いえど)も(卍本 止まるに非ず)、爽気高く晴れて匝地(そうち)秋なり、
渭水盧花嵩(すう)岳の雪、誰(たれ)か怨まん長夜の更に悠悠たることを。
〈語義〉
○匝地(そうち) すべての大地。
○渭水盧花嵩岳雪 渭水は二祖神光慧可(487-593)はそのほとりに生誕したといわれる。いま頃の秋の時分の渭水のあたりは、盧花が真っ白に咲き乱れ、冬の早い達磨の祖山にはすでに雪が降っているであろう。(234~236頁)
■重陽に兄弟(ひんでい)と志(こころざし)を言う
〈現代語訳〉
九月九日の重陽の節句にちなみ、修行者たちと作頌して志を示す(卍本 再会す)
重陽の節句は、昨日のこの日、わがこの地を去り、
今年の九月、またここにやって来た。
過ぎ去りまたやって来る年月日など憶(おも)うことはやめよう。
この叢林のなかにも菊の花が咲き誇っているのを歓んで看(み)るばかり(卍本 欄干によって談笑し、ふと看れば菊の花が咲き誇っている)。
〈語義〉
○兄弟(ひんでい) 法門の兄弟、雲兄水弟(うんびんすいてい)の意で、広くは大衆(だいしゅ)、同参、同学をいう。(237~238頁)
■冬夜に諸兄弟(ひんでい)志(こころざし)を言う、師見て之を和す
二千一百有余歳、笠漢(じくかん)幾(いくば)くの経法か尚(なお)残る、
仏祖の伝衣(え)縦(たと)え偏(彳)界(がい)なりとも、憐むべし冬夜水雲寒(すさま)じ。
〈語義〉
○二千一百有余歳 釈尊よりわが永平にいたる年数。
○偏(彳)界 遍界とも。全世界あまねく仏法のはたらきで満ちている。遍法界、全世界。
○冬夜水雲寒 仏の衣は世界に遍(あまね)しといっても、冬夜の雲水にはやはり寒さがこたえる、そのなかでも正伝の仏法を只管打坐のなかに伝える。(238~239頁)
■ちなみに、『傘松道詠(さんしょうどうえい)』(『曹全』「宗源」)には「宝治元年(1247)相州鎌倉にいまして最明寺道崇禅門(北条時頼)の請によりて題詠十首」として、次のような道詠(和歌)が収められている。なお、この10首の道詠は最明寺殿の北の方の所望により詠じたともいわれる。
あら磯の波もえよせぬ高巌に蠣もつくべきのりならばこそ(「教外別伝」)
いい捨てしその言の葉の外なれば筆にも跡をとどめざりけり(「不立文字」)
*波もひき風もつながぬ捨おぶね月こそ夜半のさかりなりけり(「正法眼蔵」)
いつもただ我ふる里の花なれば色もかわらず過ごし春かな(「涅槃妙心」)
*春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷(すず)しかりけり(「本来面目」)
*おし鳥やかもめともまたみえわかぬ立つる波間にうき沈むかな(「即心足仏」)
水鳥のゆくもかえるも跡たえてされども道はわすれざりけり(「応無所住而生其心」)
尋ね入る深山の奥のさとぞもと我住み馴れし都なりける(「父母所生身即証大覚位」)
*世の中にまことの人やなかるらんかぎりも見えぬ大空の色(「尽十法界真実人体」)
*春風にほころびにけり桃の花枝葉にのこるうたがいもなし(「霊雲見桃花」)(242~243頁)
■六月半(なかば)衆に示す
自家の鼻孔(くう)自家牽(ひ)く、一軸(いちじく)の画図(がず)(卍本 一片の功夫)九夏(くげ)の天、
今より後僅かに残る三十日、直(じき)に須(すべから)く精進して頭燃(卍本 頭然)を救(はら)うべし。
〈現代語訳〉
六月の半ばに、衆僧に示す
自分の修行は、自分の鼻に自分で綱をつけ自分を引っ張るように自分でするもの。
九十日間の安居(ご)は、一軸の絵画(卍本 一片の功夫)を完成させるようなもの。
今日から、残りは、わずか三十日、
頭に火が着けばすぐに消そうとするように、専一に、一瞬も懈怠(けたい)しないように功夫弁道せねばならぬ。
〈語義〉
○自家鼻孔 自分の修行は自分でするもの。
○救頭燃(卍本然) 頭に火が着けばすぐに消そうとするように、専一に、一瞬も懈怠しないように弁道功夫すること。
なお、『傘松道詠(さんしょうどうえい)』(『曹全』「宗源」)には、「坐禅」と題して、次の四首が収められている。
守るとも思わずながら小田山のいたずらならぬかがしなりけり
頂に鵲(かささぎ)の巣やつくるらん眉にかかれるささがにの糸
*濁りなき心の水にすむ月は波もくだけて光とぞなる
この心天津空にも花そなう三世の仏に奉らばや(247~248頁)
■〈語義〉
○公案 公府(役所)の安牘(あんとく)(公の条文)の意。国家の律法のごときは、天下の公道、不変の条理なりという語より転じて、禅門では仏祖が示した言動などを記して求道者に示し、参究推考すべき問題をいう。
■〈語義〉
○歯門闕 如浄が、その偈頌の最後に「笑殺す胡僧の歯門を欠く」といっているが、これは達磨が中国にやって来て、菩提流支(ぼだいるし)と光統律師(こうずりつし)と法論し、敗れた二人は仲間と達磨を追い出すために石をぶつけて迫害した。その際、達磨は、その石で前歯を欠いたといわれる伝説がある。つまり、達磨は石をぶつけられ、前歯を欠いて法が説けないようになったなどというのは笑止だというのである。葉があっても仏法を説けない人はいる。達磨大師は歯を欠くような迫害を受けても面壁という黙坐の行履によっても仏法を守持したのである。(260頁)
■〈語義〉
○虚空 果てしない無限の宇宙的な大空間で、すべての事象を包含しその存在を少しも妨げず、我々自身もそのなかに存在しているということ。(254頁)
■〈解説〉観月について
観月あるいは翫月(がんげつ)という、陰暦八月十五日は中秋の節で、世間では「お月見」の行事ではあるが、五月の端午の節と同様に重んぜられた節句で、古来観月の節とされた。所謂、「十五夜」である。叢林でもこの日には住持が上堂し、とくに道元にとっても、この観月には毎年特別の思いがあったのであろうことは、中秋の上堂が仁治元年(1240)から示(じ)寂の前年の建長四年(1252)まで九回ほどされていることがそれを証明している。
道元は、幼少の頃から培われた詩心を、自身では払拭されようとはするのであるが、その如何ともしようのない詩心を誘われる「翫月」ということがよほどお好きであったのであろう。
道元のは、仁治四年(1243)正月六日に興聖寺にて撰述したものに、『正法眼蔵』「都機(つき)」巻がある。
「都機」巻は、まさに「月」が主題として説示されてはいるが、この巻に示された「月」は単に虚空に浮かぶ美しい月をいうのではない。
道元が「月」によって説き示されたのは、仏祖たちがしばしば月に仮託して語った「諸方無我」あるいは「諸行無常」といった言葉に集約される正伝の仏法の真実義である。つまり、道元は「月」を説示されながら、その背後にはつねに「都機」(仏法のすべてのはたらき)を説かれているのである。
ところで、道元は、建長四年(1252)八月十五日の中秋に当たり、よほどの感慨をもよおされたものか、釈尊と月との因縁(『大智度論』に見られる)について、上堂(巻七ー上堂521)で長広舌をふるわれた(講談社学術文庫『道元「永平広録・上堂」選』238頁参照)。「今日の明日のその光は、釈尊その人の光である。それ故にこそ、その光を消してはならない、それこそが仏祖の児孫としてのつとめである、それこそが釈尊のお諭しであり、それを守ることこそが『伝灯』である」と。
このような何か遺誡(ゆいかい)めいた上堂、しかも本上堂のように長い中秋の上堂が、数ある中秋の上堂のなかでも本上堂のみであるのは、『訂補建撕(ぜい)記』に「今夏の比(ころ)より微疾まします」と見られるように、今夏の頃より兆した微疾(病のこと)を重大なものと感じられ、中秋の上堂は、この日が最後となることを予感されたゆえでもあろうか。人間(じんかん)の五十年はかの天の一昼夜に過ぎないとする月天子の寿命の計算などには、そうした予兆や感慨が窺(うかが)われもする。
翌、建長五年(1253)の夏、体調の秀れなかった道元は、波多野義重らの勧めに従い上洛するが、その途次、「越前路より都におもむきし時木芽山という所にて」と題して、
草の葉に首途せる身の木の目山雲に路ある心地こそすれ
さらに「無常」と題して、
朝日待つ草葉の露のほどなきにいそぎなたちそ野辺の秋風
世の中は何にたとえん水鳥のはしふる露にやどる月影
と詠じている。
そして建長五年の中秋の節は、やむを得ず療養のために滞在された京都で迎えられ、
また見んとおもいし時の秋だにも今宵の月にねられやはする
(『傘松道詠』『曹全』「宗源」下192頁)
と詠じ、その十三日後の八月二十八日には入般(はつ)涅槃なされるのである(265~267頁)
■(卍本 梅辺に白(はく)を重ねて顔を看ず、僧家三般(そうけさんぱん)の別有りと雖(いえど)も、半箇も何ぞ曾(かつ)て黒山(こくざん)に堕せん)
〈現代語訳〉
(卍本 雪の上に霜が降るようなその厳しい寒さは言葉では表現できない。白い梅花に雪が重なり、白一色で見分けがつかない。修行僧に三種ありなどというが、ここ永平寺には、只管打坐に徹し迷妄に堕するものは一人だになし)
〈語義〉
○雪上加霜 雪の上に霜を加える。通常は無用の意味を持つが、ここは白の上に白を加える意で、区別できない、言語を超越していることをいう。また、本来成仏身である釈尊が雪山に修行したことを、雪山に霜を加えるとして、上堂に「臘月の寒梅月光を含む。雪山の雪の上に更に霜を加う、如来の毫相(ごうそう)猶(なお)今在り、遠孫(そん)を利益(りやく)す、豈(あに)度量せんや」(『永平広録』(巻七ー上堂473)と説示している。
■生涯虚実(卍本 事々)是非乱れがわし、月を弄(ろう)し風を嘲(ちょう)し鳥を聴く間(卍本 物に対して真を失す虚実の間)、
多歳徒(いたずら)に看れば山に雪有り、今冬忽(たちまち)ち覚(し)る雪山を成(な)すを。
〈現代語訳〉
人の生涯は、虚と実と(卍本 色々なことに)、是と非とが入り乱れて迷走し、
月を愛でたり、風を厭(いと)ったり、鳥のさえずりに耳を傾けたりする間、花鳥風月などどうにもならぬことにも翻弄される(卍本 事物に対して、時には、虚であるのに実とし、実であるのに虚と、真実の理を失うこともある)。
多年にわたって、冬になれば、山に雪が積もるものと単純に思いこんでいたが、今年の冬、そうではない。
雪が山そのものとなり、山と雪とが何の区別もなく一体となって存在している厳然たる事実を覚(し)る。(272~273頁)
■三界十方何ぞ一色なる、誰か論ぜん天上及び人間(じんかん)、
伝うること莫(なか)れ寒苦鳥(かんくちょう)の言語、無熱悩池雪山に在り。
〈現代語訳〉
三界という時間を貫く世界も、十方という全空間の世界まで、雪の白一色(いっしき)、対立のない平等の世界。
これでは、天上の理想の世界だの人間の世界などと分けて議論はできない。
雪山の寒苦鳥のように、夜通し、寒苦、寒苦などと鳴くことはない。
熱さも悩みもないという無熱悩池は、雪の降り積もった雪山の奥地にこそある。
〈語義〉
○三界十方 三界は欲界・色界・無色界などの時間的全世界、十方は東西南北・四維(しゆい、東南・東北・西南・西北)・上下などの方角の全世界。
○寒苦鳥 雪山鳥。雪に閉じ込められ寒さに苦しむ鳥、越山中の学人。『鶯林拾葉(おうりんしゅうよう)』(第23)に「物語に云く。雪山という山に寒苦鳥あり、終夜、雌は殺我寒故(寒いから私を殺して)と説き、雄は夜明造巣(夜が明けたら巣を作ろう)と鳴く、夜が開ければ温となるゆえに巣を作らず、『何故造作巣、安穏無常身、今日不知死、明日不知死』と鳴くなり」とある。これは世の無常を語る説話として知られた。
○無熱悩池 無熱悩の池はインドの雪山にあるとされ、その池では菩薩などが龍となって住んでいるという。(273~274頁)
■〈解説〉雪の頌について
永平寺は北陸の越前にある。冬から春になっても雪は消えない。七、八尺のときも一丈あまりのときもあり、随時増減している。また、道元の師である如浄古仏に「雪裏の梅華」という言葉がある。道元はこの言葉を愛された。それゆえ、当山に住職されてから、多く「雪」を題材とされて説法された。
いうまでもなく、越前の永平寺は、まさに山奥の雪の多い地方にある。道元は、寛元元年(1243)七月、四十四歳のときに入越し、以後示寂(じじゃく)の建長五年(1253)八月、京に発(た)つ五十四歳まで、ほぼ十年間を永平寺で「山居(ご)」(後の「山居の偈頌」を尊び、その雪を仏法の友として親しみ幾多の説示をし雪にちなむ偈頌を作頌した。(276頁)
■〈解説〉冬至について
冬至は、いうまでもなく、一年のうちの昼の長さが最も短い冬の極点の日で、古来、陰が極まり陽の始まる日、「一陽来復」(冬が去り春に向かう意)として祝われた。道元は、この冬至の日の様相を仏法把握の根本的時節の問題とした。上堂で、宏智(わんし)古仏の語を「宏智古仏、天童に住せし時、冬至の上堂に云く『陰極まり陽生じ、力(つとめ)窮(きわ)まり位転ず。蒼龍は骨を退(ひ)いて驟(はせ)り、玄豹(げんぴょう)は霧を披(ひら)いて変ず。要すらくは、三世諸仏の髑髏を将(も)って、穿(うが)って数珠子(し)一穿と作(な)さんことを(今日、冬至の日は、陰の気が極まり陽の気が生じる日である。それと同じように、あらゆるものの力は限界までくるとその様相を転ずるのである。蒼き龍は骨をぬき姿形を変えて、自在に飛天し、また、玄(くろ)き豹は霧のなかでその紋様をあざやかに変えるのも、そのはたらきである。それゆえに、諸君も、万法と一体となっている三世の諸仏の髑髏に穴を開けて一連の数珠とするように、諸仏の骨髄を自分のものとし、自分自身を作りかえて諸仏としなければならない)』」と取り上げて「冬至というのは、俗世間の慶節ではあるが、実はそれはそのまま仏祖の慶事でもある。昨日はひとすじの線ほどの日の短さが最高潮となって、陰の気が行き着くところまで行き、厳しい寒さの風の声もやんだ。今朝はひとすじの線ほどの日の長さがもどり、陽の気が生れて万物が息を吹き返しざわめくようになる。すなわち、こうしたこと、大自然の営みを、禅僧としても慶事として、歌って手をうち喜び、この時に応じて、仏祖も祝福して舞うのである」と説示している(『永平広録』巻二ー上堂135)。このような冬至の説示は、冬至の上堂としては五回ほどが収録され、宏智古仏の冬至の上堂語は、『永平広録』巻二ー上堂206にも引用せられている。冬至の上堂の数が少ないのは、冬至の小参(しょうさん)が、巻八の小参の部に四回ほど収録されているように、冬至に際してはとくに小参という形でごく親しく説法されたからでもあろう。とくに『永平広録』の小参は総計二十回分が収録されているが、その内容は結夏(けつげ)・解夏・冬至・除夜に限られているのが特徴である。(282~283頁)
■仏成道(ぶつじょうどう)
明星を擒出(きんしゅつ)して世界紅なり、眼睛(ぜい)霹靂して虚空を破す、
更に拈ず成道娑婆国、委悉に春に向かう木(もく)杓の風。
〈現代語訳〉
仏成道(釈尊が成道された日)
釈尊が、明けの明星をとらえたとき、さとりの威光で世界が紅色に染まった。
釈尊の眼睛は、稲妻のように光り轟き、虚空を照破した。
同時に、迷妄の娑婆国を成道の世界へと一新され、
春に向かう風が吹くように、脱落の風が吹きわたったのだ。
〈語義〉
○擒出 とらえいだす。釈尊が十二月八日、菩提樹下(げ)にあって、暁天の明星を見て悟道されたこと。
○明星 暁天の明星、釈尊は三十歳、十二月八日の明けの明星とともに大(だい)悟された。
○娑婆国 内に煩悩を懐き、外に苦悩するなど種々の苦しみに晒される俗世間。
○委悉 つぶさにくわしく、ことごとくを。
○木杓 木製の柄杓。木杓破・破木杓という語句があり、それは無用で役にたたないところから転じて脱落した悟境の世界、身心脱落の意にたとえる。
〈解説〉仏成道について
釈尊の成道された月日については、所説があるが、禅家では、十二月八日を釈尊の成道日とし、この日に成道会を行うことが宋代頃から定着し、この風習が、現今の日本仏教の各宗派に採用されている。日本におけるそうした礎を創られたのは道元である。道元は、その経緯を、建長元年(1249)十二月八日、釈尊の成道にちなむ、所謂臘月八日の上堂で、
日本国先代、曾(かつ)て仏生会(え)・仏涅槃会を伝う。然而(しかれ)ども、未だ曾て仏成道会を伝え行わず。永平、始めて伝え已(すで)に二十年。自今已後、尽未来際、伝えて行うべし。(『永平広録』巻五ー上堂406)
と述べている。この上堂は建長二年(1250)のことで、この二十年前といえば、寛喜二年のことである。残念ながら、この年の臘八成道会の上堂語は『永平広録』に収録されていないので、その当時、臘八の上堂がどのようになされたのか、いまは知る術を持たず詳細は不明である。が、道元が「自今已後、尽未来際、伝えて行うべし」とされた慈訓は厳密に護持され、今日に伝えられているのは周知されるところである。(284~287頁)
■雪の夜、準記室の二十八字を感じて、病中に右筆す
訪道登高す深雪の夜(よ)、覆身(ふくしん)没腰(もつよう)憐むべき時なり、
頭(こうべ)を刎(き)り臂を断つ邪法なりと雖(いえど)も、藤蛇(とうだ)を跳(ちょう)脱する乃(すなわ)ち正師(しょうし)なり
(卍本 憐れむべし庭際腰を没する時、試みに看よ断臂の旧公案、藤蛇を跳脱して幾固か知らん)。
〈現代語訳〉
雪の夜、準書記の偈頌に感じて作頌、病中にあったが筆をとった(卍本 義準書記の雪夜の偈頌の韻に欠ぐ)
この深雪の夜、昔日、厳冬の深雪のなかに達磨を訪ねた慧可のことが思い出されるが、義準よ君は、同じように雪を踏み分けやって来たが、大変であったであろう。
身をも腰をも没する雪のなかを、よくぞこの永平寺まで訪ねてくれた。
仏法のために、頭を剃り、また臂を断つなどの求道の精神は邪法ではあるが、
藤蛇のごとき妄想(ぞう)を、いのちをかけて絶ちきるのが真の正師なのだ
(卍本 庭の雪は腰を没するほどあるのによくぞ来られた、臂を断ついのちがけの求道の精神を参究し、藤蛇のような妄執を断つことを知らねばならぬ)。
〈語義〉
○準記室 準は人命、義準のこと、記室は書記。生没年不詳。
○藤蛇 木にまつわる藤を蛇に見まちがうように偽を真とし、真を偽と見まちがえる。偏見して執着(しゅうじゃく)した妄見・迷妄のこと。
〈解説〉義準の雪中見舞いについて
義準は、日本達磨宗の懐鑑(えかん)の弟子で、永平寺三代徹通義介(1219-1309)と同年で、比叡山で三蔵教学を学び、後に仁治二年(1241)頃興聖寺の道元に師事する。道元の越前移住に際して、興聖寺に留まり院事を管理した。後に永平寺に移り書状侍者(住職の文書の管理や草案をつくる役)を務め、道元亡き後、永平寺二代孤雲懐奘(1198-1280)に参じて心印を受け、越前永徳寺の第一祖となる。また晩年は歓喜(ぎ)院に住し、豊(ぶん)後の永慶寺に住職したとも、また一説には、道元示寂(じじゃく)後、義能と改名し高野山金剛三昧院に学び、播磨の無量寿院開山伝統大僧都(ず)になったとも伝えられる。義準は、その師懐鑑(えかん)の忌辰(きしん)に当って、道元に上堂を請願している。『永平広録』巻七ー上堂507に「準書状、為懐鑑上人忌辰請上堂」がある。義準が雪中の永平寺に道元を訪ねたのは、建長四年(1252)十一月頃、道元示寂の前年のことで、雪漫々と積もるなかのことで、それは、まさに少室峰(しょうしつほう)の達磨に訪道した慧可の様相を連想させる。
道元は『訂補建撕(ぜい)記』の記すところによると、建長四年の夏頃から健康がすぐれず、翌年の建長五年(1253)の八月五日には京に向う。そのときの偈頌が
十年飯を喫す永平の場 七箇月来たって病床に臥す
薬を人間(じんかん)に討(たず)ねて峡を出ず 如来に手を授して医王に見せしむ
というのである。ここから、建長四年夏頃からは体調を崩され、その暮れから翌建長五年初頭には病床に臥され重篤であったことが窺える。ちなみに義準が雪中に永平寺に上山したのが十一月であれば、時節もあい、それは道元への最後の雪中見舞いであり、その際に義準が偈頌を呈したのに感じての、道元の慈愛に満ちた偈頌である。(292~293頁)
■山居 十五首
①幾ばくか悦ぶ山居尤(もっと)も寂寞なるを、斯(こ)れに因(よ)って常に法華経を読む、
専精(しょう)樹下(げ)何ぞ憎愛せん、妬(ねた)ましきかな秋深き夜(よる)の雨の声(卍本 月色は見るべし雨は聴くべし)。(293~294頁)
②西(せい)来の祖道我東に伝う、月に瑩(みが)き(卍本 釣り)雲に耕して古風を慕う、
世俗の黄塵飛んで豈(あに)到らんや(卍本 到らず)、深山の雪夜(せつや)草庵の中(うち)。
③夜坐(やざ)更闌(た)けて眠り未だ至らず(卍本 熟さず)、弥(いよいよ)(卍本 情(まこと)に)知る弁道は山林なるべし、
渓声耳に入り月穿(うが)つ眼(まなこ)を(卍本 眼に到る)、此の外(ほか)更に一念の心無し(卍本 何の用心をか須(もち)いん)。
④我山を愛する時山主を愛す、石頭大小道(どう)何ぞ休せん、
白雲黄葉時節を待つ(卍本 時節に応ず)、既(すで)に抛捨(ほうしゃ)し来(きた)る俗の九流。
⑤雲根(うんこん)を采得して水関(すいかん)を透(とお)す(卍本 雲根を透るに坐得して)、破顔して拝会(はいえ)す拈華顔(ねんげがん)(卍本 破顔拝会す拈華の顔(かんばせ))、
明らかに知りぬ久遠劫(ごう)来の契(ちぎり)(卍本 約)、山(やま)主人を愛し我山に入(い)る。
⑥山に在って漸(ようや)く覚(おぼ)ゆ山の声(しょう)色(卍本 消息)、結菓開花(げ)脱空を疑う、
且問(しょもん)何を以ってか本色(じき)と為する、青黄赤白(せいおうびゃくじゃく)画図の中(うち)。
〈現代語訳〉
山に棲み、ようやく本来の山の真実のすがた(卍本 消息)が分かる。
草木は時節に応じ、緑にしたがって実を結び花を咲かせるが、そればかりが山の本来のすがたではない。
それでは一体何が真実のすがたなのだと問えば、
山の、緑に応じて青・黄・赤・白等々に転変する、そのすがたそのものにある。
〈語義〉
○脱空 空を脱けでたものがあるかを疑うという意だが、空は、この場合は縁生をいう。すべてが縁によらぬものはないの意。雲門文偃(えん)(864-949)の「雲門録」下に「師云く、什麼(いかに)せん脱空の妄語、代って云く、事孤起せず」とある。
⑦久しく人間(じんかん)を舎(す)てて(卍本 人間に在って)愛借(じゃく)無し、文章筆硯(ひつけん)既(すで)に拋(す)て来(きた)る、
花を見(卍本 看)鳥を聞くに風情少なし、山に在り乍(なが)ら猶(なお)不才を愧(は)づ(卍本 時人の不才を笑うに一任す)。
〈語義〉
○乍在山猶愧不才(卍本 一任時人笑不才) 山居に徹しながらも、そうした花鳥風月の真髄を詩文にしえない自分の不才を恥じるばかりだ(卍本 いや、もうそのようなことは、時の人の不才を笑うに任そう)。
⑧幾(いくば)くか怜(あわ)れむ(卍本 憐れむ)潦倒(ろうとう)画図の質(すがた)、耳目時と与(とも)に明らからずと雖(いえど)も(卍本 明らかならずに似たり)、
云(こと)に拋(なげす)て難(がた)く還(また)染め易(やす)きこと有り(卍本 只此の見聞染る所無し)、
草庵の秋の雨(卍本 秋色)夜の渓(たに)の声。
⑨三秋の暮立(ぼりつ)(卍本 気粛)清涼の候、繊月(せんげつ)叢中(そうちゅう)万感の中(うち)、
夜静かに更(こう)闌(た)けて北斗を望む(卍本 看る)、暁天将(まさ)に到りなんとして東を指す。
⑩三間(さんげん)の茅屋(ぼうおく)清涼に足れり(卍本 既に風涼)、鼻孔(くう)瞞(まん)じ難(がた)し(卍本 鼻観先ず参ず)秋菊香(かんば)し、
鉄眼(げん)銅睛(ぜい)何ぞ潦倒(ろうとう)せん(卍本 誰か弁別せん)、越州にして九度(たび)重陽を見んとは。
⑫晩鐘月に鳴らして灯籠を上ぐ、雲衲(うんのう)坐堂して静かに空を観ず、
幸いに三田(さんでん)を得て今種を下す、快(こころよ)きかな孰脱一心の中(うち)。
⑬蛬(きりぎりす)の思い虫の声(卍本 蛬思蟬声(きょうしぜんせい))何ぞ切切、微風朧月(ろうげつ)両(ふたつなが)ら悠悠たり、
雲松柏(しょうはく)に封じて池台(ちたい)旧(ふ)りたり、雨梧桐(ごどう)に滴(したた)る山寺(さんじ)秋なり。
〈語義〉
○雨滴 雨の滴るは、悟道の響きか。『正法眼蔵』「行持」巻下に「漹山のそのかみの行持、しずかにおもいやるべきなり。おもいやるというは、わがいま漹山にすめらんがごとくおもうべし。深夜のあめの声、こけをうがつのみならんや、岩石を山穿却(せんきゃく)するちからもあるべし」とある。
⑭灯(ともしび)を挑(かか)げ筆を把(と)って志(こころざし)を言んと欲す、遥かに西天曩祖(さいてんのうそ)の蹤(あと)を慕う、
我仏の伝衣(え)寒谷(かんこく)の始(はじめ)、独り唯嵩嶽(すうがく)少林の冬のみならんや。
〈語義〉
○我仏伝衣 釈尊の伝えた伝衣のあとかた。
○寒谷 仏国土。
○嵩嶽少林 嵩山少林寺での神光慧可(487-593)の雪中断臂のこと。
⑮深山深谷草庵の中(うち)、観念坐禅窮(きわ)むべからず、
功徳の高峰塵(ちり)尚(なお)運ぶ、如来の弟子神通(じんずう)を願う。
〈語義〉
○神通 深山深谷草庵のなかという山居(さんご)こそが、仏法の真実のはたらきである神通(じんずう)である。『正法眼蔵』「神通」巻に、神通とは、一滴の水が大海を呑んだり吐いたり、小さな塵が高山をとらえたり放ったりすることであることを「しかあれば仏道はかならず神通より達するなり。その達する、涓滴(けんてき)の巨海を呑吐する、微塵(みじん)の高嶽(こうがく)を拈放(ねんほう)する、たれか疑著(ぎじゃく)することをえん。これすなわち神通なるのみなり」と述べている。
〈解説〉山居について
「山居(さんご)」とは、世塵のいたらない深山幽谷に身心を処して、その静寂な山水のなかに仏に出会い仏道を行ずる修行生活をいう。
道元は、除夜の小参で、僧の生活基盤は、「山居」に極まることを、釈尊の言として「山林に睡眠するは、仏、歓喜し、聚落に精進するは、仏、喜ばず」(『永平広録』巻8ー小参2)と引き、歴代の大祖師方が皆山居し、俗でも有道の士は皆深山に隠れたことを示し、結夏(けつげ)の小参では「僧家は山に居する好し」として「居山好底の道理」を偈頌で、縁にあうことこそが大事で、それであるからこそそれぞれの場で仏道に励みすべてに通ずるようになるのだとして、「松風は暁の窓辺を打ち、月光は秋水に映る。鶴を飼うものはその潔さを愛し、雲を見てはその悠々たるすがたを心に刻む。時に応じ節に応じて、季節は移ろう。夏には薫風が吹きわたり、万谿(まんけい)・万嶽(まんがく)に雨が絶え間なく降れば、山や谷は濛々と煙る。まさに、そうしたとき、どうか」といい、さらに、「端座する場は苔むして岩石は滑りやすく、吹く風は高く、多福のいう竹は群がり鳴り響いている、ということは、すべてはあるがままにある、と云うことなのだ」(『永平広録』巻8ー小参19)と言葉を継いでいる。
また、『正法眼蔵』「山水経」巻にも、その根本の精神を、山水こそは、古仏の説くところを実現したものといい、「而今(にこん)の山水は、古仏の道現成なり」と示し、さらに、山は遥かな昔より大聖・賢人たちが住まいとし、山を身心としたとして「賢人聖人ともに山を堂奥とせり、山を身心とせり、賢人聖人によりて山は現成せるなり。(中略)おおよそ山は国界に属せりといえども、山を愛する人に属するなり。山かならず主を愛するとき、聖賢高徳やまにいるなり」と説示している。そうした山居の精神の支柱となったのは、本師如浄古仏の「城邑(じょうゆう)聚楽に住することなかれ、国王大臣に近づくことなかれ。ただ深山幽谷に居りて一箇半箇を説得して断絶せしむることなかれ」という垂誡(すいかい)である。さらには、宝治二年(1248)の「鎌倉からの帰山の上堂」の帰山底の句(『永平広録』巻3ー上堂251)にも、「山僧(ぞう)出で去る半年余、猶(なお)孤輪の太虚に処するがごとし、今日山に帰れば雲喜ぶ気あり、山を愛するの愛初めより甚(はなは)だし」と見える。山居の偈頌にも、「我山を愛する時、山主を愛す」と頌しているように、道元の山居への徹底した感慨は、偈頌十五首ばかりではなく、『正法眼蔵』や『永平広録』など著作のいたるところに散見される。
そのような「山居』の精神が結実しているのが「山居」の偈頌一五首なのである。
『傘松道詠』には「草庵雑詠」として、二六首ほどの道詠が収められているので以下に記しておく。(岡野選5首)
草の庵(いお)に立ちても居ても祈ること我より先に人をわたさん
徒(いたずら)に過ごす月日はおおけれど道をもとむる時ぞすくなき
大空に心の月をながむるもやみにまよいて色にめでけり
春風に我ことの葉のちりけるを花の歌とや人のみるらん
山のはのほのめくよいの月影に光もうすくとぶほたるかな(293~316頁)
■十二時頌
鶏鳴(けいめい) 丑
②渾身(こんしん)我に似て是渾身 何ぞ渾身して孤夢(こぼう)新(あらた)ならしめんに、
仏腹祖胎都(すべ)て活計す、披毛(ひもう)戴角(たいかく)疏親(そしん)を見んや。
〈現代語訳〉
鶏鳴 丑 夜八ツ・四更、午前一時ー午前三時
②この時刻では、わが身は夢のなかにあっても、それとて自分以外のなにものでもない。
どうしてこの禅床のわが身一人が夢に迷うことがあろう。
いま、この我自身は仏祖の胎内にあって仏祖としてはたらいている。
禽獣たちの生命あるものと自分自身には親密とか疎遠とかの区別はなくすべてが平等の世界にいる。
日出(にっしゅつ) 卯(う)
④眼睛を換了して相(しょう)見し来(きた)る、自穿(じせん)の鼻孔(びくう)幾千枚ぞ、
明くるを遅(ま)つ雪の夜(よる)豈(あに)寒谷(かんこく)ならんや(卍本 海東の雪暁寒谷にあらず)、日所生頭是日胎(にっしょしょうとうこれにったい)。
〈現代語訳〉
日出 卯 明け六ツ・六更、午前五時ー午前七時
④己の眼睛に切り換えて、新たに仏と出会う。
自分自身を穿(うが)つように辛苦し、弁道功夫し自身を探究する。
慧可は大雪のなかで夜が開けるまで立ちつくしたが、仏法の嗣続(しぞく)せんとする心意気のなかでは、寒谷の厳寒も物の数ではなかった
(卍本 東海に日は昇り、雪の夜も明け、寒谷の冷気も暖気に包まれる)。
いま、太陽がその頭を覗かせたが、それこそがすべてを見通す眼睛の出現。
〈語義〉
○換了眼睛 自己の眼を仏眼に換えて。あるいは昨日の眼を今日の眼に変えて日々を新たにの意をも含むか。
○日所生 太陽が出るところ。太陽が出ると。太陽の胎内、もののはじまり。
〈現代語訳〉
食事(じきじ) 辰 明け五ツ・七更、午前七時ー午前九時
④食事のときには、大菩提心をもって、修行道場の僧堂も仏殿も、宇宙全体を呑却(どんきゃく)する気概で食事ををする。
真実を求める高き志は、あの雲や霞を愛して空腹を満たす。
インドで展鉢(てんぱつ)すれば、その飯の湿気は新羅に及ぶように、釈迦の仏法は、はるか遠くまでその功徳がいたっている、その功徳をいただく。
食の功徳の偉大さは、趙州(じょうしゅう)は学人に茶を勧めて、喫茶という日常底のなかにこそ仏法が顕現していることを示した、趙州に茶を勧められたわけではないが、趙州の示す仏祖一体の食事を十分に味わいいただく。
〈語義〉
○喫却僧堂 喫却は食べつくす。僧堂を食らい仏殿を飲み込む。食の功徳の大きさは心に万物を食するところにある。
○趙州 趙州従諗(ちょうしゅうじゅうしん、778-897)は学人に「喫茶去」と茶を勧めて、喫茶という日常底のなかにこそ仏法が顕現していることを示した故事。
禺中(ぐうちゅう) 巳(み)
〈現代語訳〉
禺中 巳 昼四ツ・八更、午前九時ー午前一一時 食事が終わり坐禅のとき
⑥坐禅三昧(ざんまい)のなかでさらに上の境涯を納得し、龍が水を得たように溌剌と絶対妙境にいたる。
身心一如(しんじんいちにょ)の安心(じん)の境涯は、草が春を迎えたのと同じ喜悦の心境(卍本 早く春に会う)。
真実に出合いたいと、皆競って努力しているが、それに出合うのはほかならぬ己自身。
ありとあらゆる物が一塵の汚れもなく、山(せん)河大地、それがありのままに仏法を顕現している。
〈語義〉
○身心倶語 身心一如の安心の境地。
○撲落縦横 撲落は打ち落とす。縦横はたてとよこ、思うままに。ありとあらゆるものが、一塵に汚れることなく脱落してそのあるがままに顕現している。
日昳(じつてつ) 未(ひつじ)
⑧日面目中円月(がち)面(卍本 日面相中円月の面)、
経を得て眼を遮(さえぎ)れば眼経と成る、産来参究竟(つい)に外無し、雲は晴天に在り水瓶(かめ)に在り。
〈現代語訳〉
日昳 未 昼八ツ・十更、午後一時ー午後三時
⑧日昳、未の刻は看経(かんきん)のときだ、変易する現象のなかにあって、太陽と月は円く何も変わらない。
看経することによって、その不変の理を学べば、眼が経となり、経が眼となる。
仏道の参来し参究すべきものは、このほかに何もない。
雲は晴天に浮かび、水は瓶にあるように、諸法実相のすがたは、あるべきところにありのままにある。
〈語義〉
○日面目(卍本 相)中円月面 日面は太陽、月(がち)面は月。変易する現象のなかにあって、太陽と月は円く何も変わらない、不変の理法を示すことを象徴的に表現する。
○雲在晴天 雲は空にあり、諸法実相ありのままのすがた。
晡時(ほじ) 申(さる)
⑨脚尖(きゃくせん)趯倒(てきとう)す海山嶽(かいせんがく)(卍本 鉄崑崙)、無孔(むく)の拳頭黒雲を興(おこ)す(卍本 拳頭を挙起して海嶽昏し)、
忽地(こつち)の風雷轟(ごう)霹靂たり、省来打(た)坐して精(しょう)魂を弄(ろう)す。
〈現代語訳〉
晡時 申 昼七ツ・十一更、午後三時ー午後五時
⑧晡時、申の刻、日傾く時刻、脚の先で大海を躍り超え、山岳を踏み倒すようにして(卍本 鉄の崑崙山)何ものにも執(とら)われず、
自在なる非思量の坐禅に打ちこめば、黒雲を呼び(卍本 拳を挙げれば海嶽昏くなり)、
たちまちにして風雷が起こり、天地に轟々(ごうごう)たる雷鳴が轟く。
そのとき、自己を徹底的に省みて、打坐に全生命を打ち込む。
〈語義〉
○脚尖趯倒 脚尖はつま先。趯倒は躍り上がり踏み倒す。脚の先で踏み倒す。物に執着(じゃく)しないこと。
○無孔拳頭 孔のない拳とは、無孔の鉄鎚と同様に手のつけようもないという意味も持つ。自在無礙な非思量の坐禅のこと。
○忽地 たちまち、にわかに。
○霹靂 激しく鳴り響く雷、雷の激しく鳴り響く音。転じて迅雷のように激しく鋭い機峰。
○弄精魂 精力的に専一に弁道功夫すること。
〈解説〉十二頌について
■道元は、『正法眼蔵』「諸悪莫作」巻で「衆生作仏作祖の時節、ひごろ所有の仏祖を罣礙(けいげ)せずといえども、作仏祖する道理を、十二時中の行住坐臥につらつら思量すべきなり」といって、その時々に自覚し弁道することを説示しているが、その実際を示したのが、この十二時頌である。(317~342頁)
(2017年11月24日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――