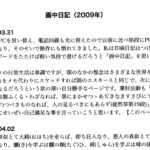■それにしても、マッハの〈現象学〉の概念を継承したフッサールがその〈思考経済説〉を拒否したのは幾分奇異に思われましが、これには世紀転換期の特異な時代風潮が関わっているように思われます。この時期、一種の〈純粋主義〉が流行します。純粋詩・純粋小説・純粋芸術・純粋持続・純粋経験・純粋意識・純粋言語・純粋論理学・純粋経済学・純粋法学など、数えあげればきりもありません。そこにはさまざまな動機が働いていたようですが、その一つとして、H・スペンサー以来進化論と連動しはじめた功利主義・自然主義・相対主義に対する反撥がありました。これはつきつめれば生(レーベン)の生ぐささに対する反撥です。その生ぐささは、工業化都市化の進行とともに生じた都会の汚濁にも重ね合わせて感じられていたにちがいありません。そうした汚れた日常的現実を打ち破って、その底に真に〈現実的な現実〉をもとめようという志向がさまざまな〈純粋主義〉となって現われたように思われます。フッサールが思考経済説を否定して〈純粋論理学〉をもとめるその努力にも、そうした志向が働いていたにちがいありません。(92~93頁)
■1924年になってからのことですが、ウィーン大学でマッハやボルツマンの後任として〈帰納的科学の歴史と理論〉の講座の教授になっていたモーリッツ・シュリック(1882~1936年)が中心になって、哲学者と自然科学者による気軽な討論会がはじめられました。その参加者20人が1928年10月に〈エルンスト・マッハ協会〉を結成します。彼らはマッハの現象学に厳密性を与えようとして、討論の基本的テキストにウィトゲンシュタイン(1889~1951年)の『論理哲学論考』[1922年]を選びました。この会が翌年オットー・ノイラートの発案で〈ウィーン学団〉と名前を替え、ライヘンバッハを中心に同じ頃結成されたベルリンの〈経験哲学協会〉と合同で、1929年にプラハで「精密化学の認識論」を討議する会合を催し、翌30年から雑誌『エアケントニス(認識)』を刊行しはじめます。ベルリン・グループをも包摂したこの広義の〈ウィーン学団〉の思想は、『科学的世界把握ーウィーン学団』というその宣言書にうかがわれます。
「輓近(ばんきん)の経験主義および実証主義を、方向においていっそう生物学的
-心理学的であった初期の形態から区別するものは、論理分析の方法である」
(ノイラート『経験主義と社会学』[1973年]。野家啓一『無根拠からの出
発』勁草書房、1993年、21ページの引用による)。
ウィーン学団は、マッハの「生物学的-心理学的」実証主義を捨て、ラッセルとウィトゲンシュタインによって展開された〈論理的原子論〉を根底に据えた〈論理実証主義〉を採ったのです。メンバーには、ほかにルドルフ・カルナップやカール・ポパー、クルト・ゲーデルらもくわわっていました。そして1930年代にカルナップらの亡命とともに論理実証主義はアメリカに移植されます(「シカゴ学団」)。(97~98頁)
■ここでウィトゲンシュタインの念頭にある〈現象学〉が、当時すでに一派をなしていたフッサールのそれでなく、マッハのそれであることは、こんなふうに〈現象学〉と〈文法〉とを等値した上で彼か、
「マッハが思考実験と呼ぶものは、もとよりなんら実験ではない。それは結局は
文法的考察である」。
と、マッハに言及していることからも明らかです。彼の後期のいわゆる〈文法的考察〉や、結局はその具体的遂行である〈言語ゲーム理論〉もが、マッハの〈現象学〉につながるものであることは明らかです。(100頁)
■『チャンドス卿の手紙』については、ドイツ文学の松本道介さんが、この作品はホーフマンスタールにおける印象主義から表現主義への転換を指標する作品として読むべきではないかと主張した「ホーフマンスタールと表現主義」(『陽気な黙示録』中央大学人文科学研究所、1994年、所収)という刺激的な論文を書いておられます。松本さんは、ここでホーフマンスタールに起きた変化を、「世界の外にいて、あるいは世界の上にいて世界を眺める姿勢から、世界の中に身をおく人間としての姿勢、世界と一体化できる人間の姿勢への変化」といちおう規定しながらも、そうも言いきれない微妙な、だが本質的な変化だと付けくわえられています。(102~103頁)
■さらによく1907年1月12日付でフッサールがホーフマンスタールにしの訪問に対する礼状を書いているのですが、その手紙のなかでフッサールはホーフマンスタールの説く反自然主義的な詩人の美的直感と、「あらゆる実在的な態度を遮断する」自分の「純粋に現象学的な精神態度」とには深く通底するものがあると書いています。(104頁)
■「可能的なもの」は「いまだ目ざめぬ神のもくろみをたっぷり抱えこんでいるもの」だとさえ言われています。これに近い考えが、ムージルにはギムナジウム時代からあったものらしく、当時書いた愛国心をテーマにした作文のなかで、「おそらくは神もまた、この世界について可能の接続法で語るのをもっともこのむであろう。〔……〕というのも、神は世界を作りながら、この世界は別様でもありうるだろうと考えているのだから」と書いているそうです(大川勇「可能性感覚の射程」、前掲『ムージル 思惟する感覚』所収、299頁)。この大川さんも書いているように、むろんこれはライプニッツの『弁神論』を裏がえした考え方ですが、一方、ムージルのこの〈可能性感覚〉にはフッサールの〈本質直感〉に近いものも感じられます。フッサールの言う〈本質〉というのも、現実的なものが生起してくる際にのっとるべき規則のようなものであり、彼はこれを、ゆるしがたいものとされる現実を相対化するための手段として使っているのです。後期の『デカルト的省察』[1929年]においても、フッサールは自分の〈現象学〉を、「純粋な可能性(純粋な表象可能性、純粋な想像可能性)の領域のうちに身を置くア・プリオリな学、……つまり超越論的存在の現実性についてではなく、むしろそのな可能性について判断し、そうすることによって同時に、もろもろの現実にア・プリオリな規則を予示するような学」[『フッサリアーナ』第一巻、56頁]と規定しています。彼の言うア・プリオリな本質の領域とは、ムージルの言う「いまだ目ざめぬ神のもくろみ」に当たるようです。
しかし、もう一方で、ムージルの言う〈可能的なもの〉には、マッハやゲシュタルト心理学者たちの言う〈ゲシュタルト〉を思わせるところもあります。マッハの思想は実証主義とは言われるものの、かっして固定された経験的所与にぴったりと埋めこまれた、いわゆる〈くそリアリズム〉ではありません。彼の言う〈感覚的諸要素〉はさまざまな関数的連関に組みこまれ、さまざまなゲシュタルトのうちに現われることのできるものです。しかも、このゲシュタルトに必然性はありません。マッハも図と地とが交替する反転図形を話題にしています(『感覚の分析』、前掲訳書、173頁)。ゲシュタルトもまた「偶然でコンベンショナル」なものなのです。『特性のない男』の遺稿となった部分にこういう箇所があるそうです(早坂七緒「ムージルの〈可能性感覚〉の誕生」、前掲『ムージル 思惟する感覚』所収、332頁の引用による)。
「もしわれわれを現実に適応させる感性に代わって、別の感性が勢力を占めるな
らば、われわれは単に変化する世界像についてのみでなく、また別の世界につい
ても話すことがゆるされるだろう」。(111~113頁)
■ムージルはかって同級生であったヴォルフガング・ケラーの仕事に絶えず注意を向けていたらしく、ケーラーの『物理的ゲシュタルト』[1920年]が発表された直後にも、「どうしようもないヨーロッパ、もしくはあてどのない旅」というエッセイ[1922年]の一節でこれにふれています。
「現代が哲学をもっていないわけは、現代が哲学を創造できないためというよ
り、むしろ、現代は、事実に合わない申し出を拒絶するがためである。(実例の欲
しい方は控え目に自然哲学的試みと銘打たれた書物、若きベルリンの哲学者、ヴ
ォルフガング・ケラーの『静止と恒常状態における物理的ゲシュタルト』を読ま
れるとよい。そして、それを理解されるだけの知識をおもちの方なら、きっと事
実についての科学の次元から、太古の形而上学的難問の解決が暗示されているこ
とに気づかれよう)」(『ムージル著作集』第9巻、田島範男、長谷淳基訳、松籟
社、1997年、128頁)。
ムージルの創作活動が、マッハ、フッサール、ケーラー、コフカらの織りなす世紀転換期オーストリアの思想圏で営まれていたことは明らかなようです。(114~115頁)
■ジョージ・スタイナーが名著『ハイデガー』の新版[1989年](生松敬三訳、岩波同時代ライブラリー、1992年)に付した「新たな序論」(この部分だけ木田元訳)で、この時代の思想的雰囲気にふれて実に興味深いことを言っているので、それを紹介しておきたい。彼はそこで、第一次世界大戦の1928年から1927年までの10年間に、「その分量と文体の極端さから書物以上の書物とも言うべきもの」がはんダースもドイツで出版されたと、言い出すのである。
ー中略ー
スタイナーに言わせると、それはまず、これらがすべて大冊だということである。これは偶然ではない。これらの書物はすべて全体性を目指し、「利用可能なすべての洞察の集大成(スンマ)を提供しようとする企て」だからである。
次に、これらの書物はみな、ある意味で黙示録的である。つまり終末論的であり、予言的である。「この世の終わりをしるしづける最後の出来事」に訴えかけ、来たるべき新たな世界についての予言をふくんでいる。
ー中略ー
こうして、現存の世界の終末を宣言し、新たな世界を予言するこれらの著作においては、当然言語の過激な革新が企てられる。第一次世界大戦のあの惨禍のあとで、ブルジョワ社会で使い古され擦りきれた偽りの言葉で語ることなどどうしてできようか。そこでは、言語を過激なかたちで新たなものにしようと企てられるのである。ー中略ー……スタイナーはこう要約する。
「要するに、第一次世界大戦後のドイツ語は、他のいかなる言語よりもいっそう
意識的に、いっそう暴力的に、また事実上ダダの影響――時代の絶望と希望とを
表明しうる人類の新たな言語をもとめるその絶望的な呼びかけの影響――を受け
てきたそれなりの流儀で、過去との断絶をもとめているのである。特に可動的な
構文法を賦与され、語や語根をほとんど意のままに砕いたり融合させたりしうる
可能性を賦与されたドイツ語は、刷新の誘因として、過去のものとしては隠者た
ち、つまりマイスター・エックハルトやベーメやヘルダーリンを選び、現代のも
のとしては、超現実主義(シュルレアリスム)や映画のような革新運動を選んでい
るように見える。『救済の星』やブロッホのメシア信仰的著作群、バルトの聖書
解釈学、そしてなかんずく『存在と時間』は、もっとも革新的な性格の言語活動
である」(前掲訳書、7~8頁)(129~132頁)
■もともとアリストテレス研究者として出発したハイデガーは、アリストテレスのテキストや中世スコラ学者によるその注釈書を丹念に読み解き、さらにデカルト、カントら近代の哲学者のテキストを読み進むうちに、西洋哲学史にはプラトン/アリストテレス以来〈存在〉を〈被制作性〉と見る、つまり〈ある〉ということを〈作られてある〉と見る特殊な存在概念が、さまざまに変様されながらも一貫して承(う)け継がれ、これが西洋文化形成の基底にすえられているということに気づいた。
ハイデガーはこの西洋哲学の歴史を、ニーチェに教えられたもっと壮大な視野のうちに据えて相対化しようとする。プラトン/アリストテレスよりももっと早い時代の〈ソクラテス以前の思想家たち〉の書き残した断片を見ると、この時代のギリシャ人は〈存在〉を〈生成〉と、つまり〈ある〉ということを〈なる〉ことと見ていたことが分かる。それと対比して、西洋哲学を貫く」〈存在=被制作性〉という存在概念がかなり特殊なものであることを明らかにし、それを相対化しようとするのが、『存在と時間』第二部の課題であり、この本はまずこの部分から発想されたのである。
次いで、この歴史的考察の視座を確保するために、さまざまな〈存在概念〉のもつ〈時間的性格〉を解明する、つまり〈存在〉と〈時間〉の関係を問う第一部第三編が構想されたにちがいない。第一部第一、二篇での人間存在の分析はそのための準備作業として、しかも先ほど見たような敗戦後の実存哲学的雰囲気と時代の終末論的気分とに多分に促されながら、最後にあわただしく構想されたと見てよいであろう。
そして、第一部第三篇でハイデガーは、〈存在=被制作性〉と見る存在概念が、自分自身の死から眼をそらし、眼前の事物との交渉に没頭して生きる人間の〈非本来的時間性〉を場として形成されるものであり、〈存在=生成〉と見る存在概念こそ、自分の死を直視し、それに覚悟をさだめて生きる人間の〈本来的時間性〉を場として形成されるものであることを明らかにするはずであった。
しかも、これを明らかにした上での彼のねらいは、〈存在=被制作性〉という存在概念を基底に据え、自然をも制作のための無機的な材料と見る〈物質的自然観〉の上に立って形成されてきた西洋文化――いまや巨大な技術文明と化し、はっきりその行く末の見えてきた西洋文化――を転換するために、もう一度〈存在=生成〉と見、自然を生きて生成するものと見ていたかっての存在概念を復権し、文化形成の方向を転換しようとするところにあった。そのためには、人間をその非本来的な在り方から本来的な在り方に立ちかえらせる必要がある。といっても、一人や二人の人間がその生き方を変えてみたところで、どうなるものではない。だが、ひょっとして世界史を領導する一つの民族が全体として本来生に立ちかえるようなことが起これば、話は違ってくる。(136~138頁)
『木田元の最終講義』 木田元著 角川ソフィア文庫 2008年11月3日