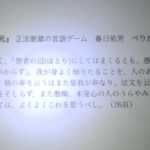『自我の哲学史』酒井潔著 講談社現代新書
■あらかじめ見通しをいえば、われわれが通常、社会生活で是とする自我概念は、基本的には西洋哲学の自我概念の上に成り立っており、日本人は近代化においてそれを受容したのである。しかし元々それは体型に合わないスーツしたいなものではなかったか。それが露(あら)わになりだしたのが今日の思想的・文化的状況なのではないだろうか。自我が主体として、自由と責任の担い手たらんと意識することが、かならずしも人間の自己解放を意味するとは断定できまい。もしかしたら自我の確立は幸福のための絶対的な条件ではないのかもしれないのだ。(6頁)
■自我を考えるといっても、自我そのものが考えられているのではなく、じつは「自我の観念」(または「自我の概念」)があれこれと考えられているのである。「観念」とはこの場合、われわれの意識作用のなかで思い浮かばれている「像」であり、「表象」である。(23頁)
■日本語訳では「フィアシュテルンク」はふつう「表象」と翻訳される。カントなどでは「表象」と「観念」はほとんど同じ意味なのである。つまり近世では「イデア」も人間の意識が自らの前に置いてこれを思惟する対象、すなわち「観念」と呼ばれるものになる。「フィアシュテルンク」はそういう事態を直截にあらわした言葉だ。カント哲学から出発しながら独自の立場を標榜したショペンハウアーの主著も『意志と表象としての世界』と題する。ちなみに現在のドイツ語でも「フィアシュテルンク」は、思惟されている内容とか考え方などといった意味で広くもちいられている。
またデカルトからライプニッツを経てカント直前までの17、8世紀では、「観念」、「表象」、「概念」は相互に置換されて用いられていたのである。「概念」が事物の、特種的ではない普遍的な概念として、「観念」から区別されるようになるのはカントとヘーゲル以後のことである。(24頁)
■そうだとすると、そうした自我の像を見て、こんどは「これが私だ」と判断するいわばもう一人の〈自我〉が区別されよう。だがこの〈自我〉自体は、もはや認知の対象たりえない。この「自我の二重化」という問題を、さすがにカントは看過しなかった。カントによれば、普通われわれが自分自身について何事かを思い浮かべ、身体に痛みを感じたり、過去の自分を想起したり、あるいは自分の夢や空想にふけったりするとき、そうした意識の活動は「内感」と呼ばれる。しかしそこで示されるのはそのつどバラバラな印象に過ぎないという。そのような内感に知覚されたかぎりの経験的心理学的な自我は連続的でも主体的でもなく、自我の同一性を基礎づけることができない。
そこでカントは、心の内で想起されている自我に対して、そういう自我像に先行しつつ、これに論理的形式を付与して、自我や世界の認識一般を可能ならしめる純粋な制約としての自我を区別する。後者の自我は、それがアプリオリに対象へ越え出ているという意味で「超越論的自我」と呼ばれる。「超越論的自我」は実体でも主体でもなく、「私は思惟する」という活動そのものである。「私は思惟する」はどんな対象認識にも伴っている。たとえば「私は何かを見る」は、「私は、私が何かを見ていることを、思惟する」という意味にほかならない。「私は思惟する」という純粋な活動としての超越論的自我は、われわれによっていつも気づかれているわけではない。しかしそれは常に機能していて、それ自体不変で同一である。それは内感の非統一的自我に対して、真の統一と同一を付与する原理として優位をもつ。やはり結局カントでも、自我の同一性や主体性という性格そのものは、位相をずらして、「超越論的自我」のそれとして堅持されているのである。(25~25頁)
■だがヴィットゲンシュタインが『論理哲学論考』などで示唆しているのは、それ自身は絶対客観化されないような自分だけの我、すなわち〈自我〉のことであろう。世界を対象的に観察し、記述する主体は、そこで現れる他の事物や人間と同じ資格で存在するとはいえないが、さりとてそれは無ではない。かくてそのような〈自我〉は「世界の境界」とか、「形而上学的な主体」などと呼ばれるのである。しかしそういう絶待に知られる側には立たないような〈自我〉もまた世界の内に存在するはずであろう。〈自我〉は世界の外部から、ある神的な視点に依拠してこの世界を傍観するというのではないだろう。それは超歴史的でも超自然的でもない。自我は〈自我〉によって「私はコレコレである」と認識されたかぎりでの自我と同様に、すでに歴史的現実の世界の内にあるところの主体なのである。(28頁)
■このようにキルケゴールにおいては、単独でかけがえのない自我は、デカルトのように思惟実体でもなく、カントのように超越論的自我、もしくは道徳的意志でもない。キルケゴールは自我を主体や主語の側にではなく、むしろ私が私に関わる関係の側に見出そうとする。自我はもはや何か有るものというよりは、そのつど「私が私へ」関係する活動自体を意味する。かくして自我は「自己」Selbstという概念のもとに考察されることになる。自我から自己への転回こそ、20世紀の実存主義の先駆とみられるのである。(31頁)
■キルケゴールにおいてにおいても、またその後の実存主義の系譜上に位置づけられるサルトル(J.-P.Sartre,1905-80)やカミユ(A.Camus,1913-60)においても、たしかに「自己」が主題であり、これは決して実体ではない。サルトルの言う意識としての自己は、「即自」(en soi 事物的存在)ではなく「対自」である。「対自」(pour soi) は、読んで地のごとく、自分が自分に対しているのであって、自分と自分のあいだにそれゆえ「無」を含み、脆弱である。いかし「対自」は他方ではそれゆえにいろいろなことを企て(「投企」)、自分を超えてゆく、そしてその意味で自由でもあると強く示唆されている。すでにキルケゴールでも、自己は、己を定立した唯一の他者すなわち神に対して立つ単独者であった。つまり自己は自らの内に緊張または分裂を含む特異な存在者でありながら、そういう自己全体の内容・性格については、近世的伝統である連続性、同一性、行為の責任主体といった性格を色濃く保っているのである。(31~32頁)
■しかし懐疑が真に徹底されるべきであるなら、そうした私の行う〈説得〉、あるいは〈思惟そのもの〉も否定されねばならなかったはずであろう。しかしデカルトの懐疑は、「私」の存在には向けられぬばかりか、意識の、疑ったり自己説得する働きそのものの明証性にもかっして向けられない。〈私が欺かれる〉とは、〈悪霊によって欺かれた者として私は自分を思惟する〉を意味するのであって、そのように想定する私の思惟自体はすこぶるクリアだということが前提されているのである。(39頁)
■デカルトは、「懐疑」を方法としながら、じつは最初から、我の存在ならびに意識(思惟、コギト)の明証性という二つの聖域を設けていたのである。(40頁)
■いうまでもなく「実体」(substantia)はギリシャ哲学における「ウーシア」以来の伝統的概念であり、「それだけで存在するもの」を意味する。デカルトもほぼ伝統に沿って、「実体」を「存在するために他のいかなるものをも必要としない、というふうに存在するもの」と定義している(「哲学原理」1-51)。たとえば色とか長さとかは単独では存在できず、かならず何かあるものの色や長さである。それにたいし自我は自我だけで存在できる。また、実体の性質のうち、それを欠いては実体が存在できないような本質的なものを「属性」という。実体は属性によって認識されることができる。そういう属性としてデカルトは自我について「思惟」を認めるのである。かくて自我は、あらゆるその変化・状態にもかかわらず、それ自身は、同一で連続している。「実体」「性質」「属性」という伝統概念に訴えてまでデカルトは、「我思惟する」という作用から「我は思惟する実体(すなわち精神)である」を帰結しようとしているのである。(44頁)
■たしかに、デカルトは、中世からそれまでの伝統的哲学のように、「心」を自存する実体として前提するかわりに、「懐疑」という革新的な方法により、彼の哲学の土台を吟味し、構築し直そうとした。そのために自分の意識に映ったものを順次ふるいにかけていった。しかしそもそも〈思惟以外の性質をまったくもたないような自我〉という観念も、〈思惟という働きの主体である思惟そのもの〉という観念も、そのような意識検証によるならば、検出されるよりは、むしろいずれも疑わしいとされかねない代物だったのである。にもかかわらず、デカルトは「思惟だけを性質とするような自我」、「精神という名の実体」という観念が真であり実在的だと断定するのである。(45頁)
■自我は連続的であり、常に同一でなければならない。そのことの形而上学的表現が「我は思惟実体である」であった。「実体」である以上、自我は連続で同一でなければならない。そのような自我を、デカルトは意識の内部に見出そうとした。(54頁)
■他方、そうした経験的心理学的自我のいわば背後にあって、これを絶えず思惟し、私はいまコレコレだと意識しているが、それ自体は絶対に対象化されない、もう一人の自我が考えられる。「いま窓から冬空を眺めている」と意識しているのは、たしかに同じじぶんではある。しかしそのように意識している当の〈自我〉は、およそ何であるともいえないような自我なのである。
この後者の〈自我〉を、カントは「我思惟す」(Ich denke)という自己意識(=統覚)の働きとして、彼の『純粋理性批判』の根本に置いた。この〈自我〉は、一切の対象認識をアプリオリに可能ならしめる論理的形式的な制約である。その意味で「我思惟す」の〈自我〉は「超越論的自我」とされる。つまり、それは対象認識を可能にする先験的制約であり、対象に認識が「超えてゆく」仕方をアプリオリに示すのである。(56頁)
■「我思惟す」は「統覚」(Apperzeption)と呼ばれる。統覚はその語源ad-perceptioの語義どおり、対象知覚に付け加わる意識作用のことである。しかし知覚にそのつど付加し、「私が何かを思惟していることに気づく」というような統覚は「経験的統覚」である。「経験的統覚」は「内感」に相当する。これに対し、「我思惟す」が対象認識をアプリオリに可能ならしめる場合、それは「超越論的統覚」といわれるのである。(57頁)
■悟性による直感の多様の結合は、単なる取り集めでないとすれば、「一」ないし「統一」という概念を要する。この「一」は「統一する」働きによる。この統一こそ、超越論的統覚たる「我思惟す」が常に対象表象に随伴していることによって実現させる。多様を結合する仕方としてのカテゴリーは統覚の統一作用に担われている。小舟という対象について何かを判断し認識するとき、そのことを「我思惟す」が知覚に伴いつつ、知覚をいわば自己にひきつけられてこれを、たとえば因果性の範疇に従って結合統一することによってのみなされると、カントは考えるのである。(59頁)
■デカルトからカントへの展開を通じて、西洋近世の同一的、連続的、主体的自我は一層内在化される。つまり自我は意識の内部に置かれる。デカルトでは自我はそれでもなお「思惟実体」と規定されたのに比し、カントでは自我は対象認識の「超越論的な制約」だとされる。それはもの(res)として有るのではなく、私が何であれ認識を行う以上、常に「我思惟す」として随伴するはずの論理的機能でしかない、というのだ。(61~62頁)
■ところで、このように経験的自我にやいして、いわばその論理的制約としての超越論的統覚がより根本であるとすれば、そこには個人性はない。超越論的統覚作用そのものは普遍的だからである。誰もがいわば無色透明な、「我思惟す」を遂行しているというだけでは自我の個別性は生じない。個人差がわれわれにそれとして認知されるのは、むしろ経験的統覚(内感)においてであるだろう。しかしラントは超越論的自我に定位し続ける。個別的な経験的統覚は、意識に対する表象でしかない、という立場をとるのである。(63頁)
■永田良昭著『人の社会性とは何か』(ミネルヴァ書房、2003)は好個の案内である。まず自己は自己であるという「同一性」について見てみよう。エリクソン、ミード、ストライカー、バークといった社会心理学者が、自己の「同一性」を論じている。その場合、(A)社会的構造と自己の関連に注目するか、(B)自己の確証の内的過程に関心を寄せるかという2つの方向に区別したうえで、このAとBを統合することが示唆される。この2つの方向の区別は心理学における対比であるが、これを形而上学の位相に移せば、Aは明らかにライプニッツ的、Bはデカルト的もしくは唯名論的な自我論――そこでは私の個性を客観的に決定するよりも、私に気づくことが主題である――ということができよう。
同一性とは、単に自己自身の不変性の感覚を意味する(B)だけではなく、自己自身と他者が共有する基本的性質をも含むもの(A)として再構成される必要があるという、この社会心理学の主張は、その経験論的アプローチを別にすれば、たしかにライプニッツを連想させる。(86~87頁)
■今日の社会心理学では、「われわれが他者との関係において存在し、自己自身の定義そのものが社会的に成立している以上は、他者と自己の関係が明らかになることがとりもなおさず自己が何物であるかを明らかにすることである」と結論される(永田、163頁)。しかしこれこそは、個体は、個々をめぐる状況や他者との行きがかり(外的規定)をも余さず含んではじめて規定されうるとしたライプニッツの意図したことではなかったか。(87頁)
■ライプニッツが、世界が神に予見されながらもあくまで「必然」ではないと主張するとき、一切は唯一実体=神の様態として必然的に産出されるのみとしたスピノザへの対抗があるだろう。とにかくライプニッツによれば、他の誰とも違うこの唯一の自我に関わる出来事や意志決定の系統は、神の創造の自由も人間の自由をも排除しない。スピノザの指示したような絶対的必然性ではなく、むしろ「仮定的必然性」と呼ばれるべきものである。(89~90頁)
■ところで、同一の葉は2枚とない、というライプニッツの言い分に反駁しようとしたある貴族が、ヘレンハウゼン城館の広い庭園を探しまわったが、同じ形状の葉を見つけることはできなかった、という当時のエピソードが残っている(「人間知性新論」Ⅱ-27-3)。(92頁)
■いずれにしても「自我とはかくかくのものである」という観念が確立されたのが、デカルトに始まる近世哲学の自我論の展開であったといえよう。カントやフィヒテでは英知的で道徳的な自我が、経験的な自我を律するという面が強く示唆された。ところが、ヘーゲル以後、19世紀中頃になると、ショーペンハウアー(A.Shopenhauer,1788-1860)やキルケゴール(S.A.Kierkegaard,1813-1855)まどのように、そういう理性的な自我の背後にあるような自我を、ある根源的な意志として見ようとする傾向が出てくる。根源的な自我といっても、もはやカントのように理性的なもの、普遍的なものではなく、むしろ個別的単独的で、実存的である。(96頁)
■キルケゴールが哲学史上にもたらした貢献は、なんといっても、「自我」(Ich)と「自己」(Selbst)を区別したことである。ここに初めて「自己」が哲学概念として明確に問われたのである。「自己」という概念の登場をもって、実存主義の開始と見ることもできる。それまでは、デカルトでもカントにおいても、主体的で主語的な「自我」が主題であった。その事情はデカルトのように思惟実体であろうと、カントのように超越論的主観であろうと基本的にはかわりはない。どちらも主体的、能動的であり、それについて述語としてさまざまな状態や作用が付与される。
これに対してキルケゴールは、主著として名高い『死にいたる病』(1849)第1編Aの冒頭で、「人間とは精神である。しかし精神とは何であるか。精神とは自己である。しかし自己とは何であるか。自己とは、ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である』(桝田啓三郎訳、中央公論社)と言明し、精神を自我でなく、最初から「自己」と定義する。(97頁)
■第1の関係の軋轢から生じる絶望は、何かについての絶望である。たとえば自分の有限性、あるいは不自由について絶望する。キルケゴールによればこれはまだ本来の意味で絶望とはいえないし、人は多くの場合、自分が絶望していることにすら気づかないでいる。
第2の関係(再帰的関係)の軋轢から生じるぜつぼうは自己逃避である。自分で自分が支えきれなくなり、自分から逃げようとする。
第3の、神への関わりあいが不透明になってしまうような軋轢から生じる絶望が、傲慢、強情、反抗であって、これが最も深い絶望である。「死にいたる病」とは、ガンでも心筋梗塞でもなく、まさにこの絶望を意味する。この3重の深まりゆく絶望の現象を克明に跡づけてゆくことが『死にいたる病』の最大のモチーフであった。(100頁)
■自我は各自の「遠近法」を遂行しつつ生きる、とニーチェは言う。自我のある数だけ、異なった遠近法が存し、またその逆でもある。(106頁)
■「遠近法」は自我が世界を見るときの見方である。その視線は主観=自我の方から放たれている。素朴な実在論や知覚因果論のように、われわれの感覚が外的対象から刺激を受けることにより知覚が生じる、というのではない。自我が、自らの作用によって世界を支配しようと意志するのである。遠近法主義の思想で主題化されるのは、主観から対象へという方向がもっぱらであって、対象から主観へという方向はほとんど見られていない。(107~108頁)
■自我と呼ばれるものが、さしあたり日常性ではどのような有り方をするかを問うのが、彼の前記の主著『存在と時間』(1927)の「現存在の準備的基礎分析」である。近代的自我の主体性、連続性、自己同一性といっても、「事実生」の諸相においては自己隠蔽は、現代の大衆社会によって助長され増幅される。カントやヒュームのように合理主義的な、あるいは自然主義的な見方では不十分である。なぜなら自我は必ずしも理性の判断を目的とはしないからであり、また動物や植物などの自然的存在者と違って、自我はそのつどの時代や地域に固有な仕方で現れるからだ。
『存在と時間』を構想・執筆した1920年代ヨーロッパの都市と技術と人間を、ハイデッガーもヤスパースに劣らず注視しつづけた。そして同書の白眉をなす現存在分析論を通じて、自我は、彼の見た日常的現実においては、近代的自我の理念とはおよそ逆の傾向を示すことが露にされる。それをふまえたうえで、ハイデッガーは現存在の実存をなおも「存在可能」としてとらえる。これは、自我を「有ることができる」という視点から、時間性でいえば「将来」の方から見ることを意味する。つまり、現存在は現実にはそういう非本来生に埋没する有り方をしていても、これに馴染まず、あえて自己を解放し、「世人」から「自己」自身にもどるように「決断」することも「できる」のである。(125~126頁)
■ここでハイデッガーが示唆する「覚悟」とは言うまでもなく、単に心構えというようなことではなく、「死への存在」としての自己の有り方、すなわち「先駆的覚悟性」を意味する。ふだんは忘却している死を、他の誰にも代わってもらえない我がこととして引き受け、そうした自分だけの存在を選びとるべく改めて決断することである。そのとき自己は本来的となり自己として常立的に自らの立つ場を確保しつつ自立する。(132頁)
■現存在は投げられて・投げる「被投的企投」の存在者であると、ハイデッガーは定式化する(134頁)
■ハイデッガーによれば、現存在の歴史性とはこういう事態である。まず、現存在が己れの死に先駆しつつ己れの存在をそのつど決断しつつ、かつ現存在がかってのそれであったところのもの、ないしわれわれが現にそうでしか有り得ないところの「伝承」ないし「遺産」(Erbe)をあらためて己れに「引き受ける」。そして、その反復のなかで、現実世界の状況にそのつど向いあい、関わ現存在のあり方が、「現存在の歴史性」である。けだし「伝承」とは「伝来の諸可能性をすでに自分自身に伝承させること」なのである。(135頁)
■戦争、迫害、災害などによって、実際におおくの「ホームレス」が生じる。また経済不況でも多くのホームレスが出る。しかし目には見えないが、一層大規模で深刻な事態が考えられる。それは、自我そのものが自己を失い、自己の居場所すなわち故郷を失うという「ホームレス」なのである。ハイデッガーも、第二次大戦後に発表した一連の講演や論文を通じて「故郷喪失」を指摘し、「馴染まれた世界」から「見も知らぬ空間」へと、現代人の地球規模の大量移住が進行中である、と警告している。(144頁)
■ディルタイはこうした「生」としての自我をとらえるために、「解釈」という新しい方法を提示した。「認識」が自然科学の方法であるのに対し、「解釈」は精神科学、なかでも歴史学の方法として重要だと主張する。「生」はどのような仕方でとらえられ得るのか。
「生」はこれを分析によって部分に分けたり、要素に還元したりすべきものではない。「生」はただその全体としてのみ理解され得る。「生」の全体とは、そこにおいては異なった諸契機がひとつの統一に向けて織り上げられているような「連関」のことである。「生の連関」は単なる生命体の身体システムでも、心理学的な統一体でもない。それは、まさに体験されたものからなる連関として、自我生活の現実を規定している。(149~150頁)
■賢治にとって、宇宙も、自我も、そのつど自分の心に映った「心象」の内容に他ならなかった。そういう意味で賢治の心象世界はまさに何でもありの世界である。そこには、一方では天台や華厳などで説く「一念三千」や「三界唯心」との、また他方では「宇宙の鏡」として全世界を表出するライプニッツの「モナド」との近さも見出される。そしてそれはそのままスケッチされ、詩作の素材にされるべきものだったのである。(162頁)
■その理由として賢治は、相互主観性の理論というようなものに訴えるのではなく、むしろ彼独自の相互浸透的な精神の共同体ともいうべきものを提示する。他人といってもそれは自分の心の中に映った他人の心象である。また私も、他人にとって、外部の絶対的な他者でなく、他人の心の内部に映った心象なのである。要するに私といっても他人といってもすべて心象内部のことである。
そのかぎりにおいて、デカルトの引いた内と外という区別は意義を失う。私と他人、他人と私、個人と個人はいわばたえず境界を自由に出入りする。境界の維持されるフッサール的な類比に基づく感情移入論ではなく、越境型の自他一元論とでもいえよう。(165頁)
■その「序論」で西田は、自己が自己を写す自覚について、「例えば英国に居て完全なる英国の地図を写すことを企図すると考えて見よ」と述べて説明する。自分のいる場所の地図を遺漏なく写そうとすれば、その地図に加え、それを写している自分をも新たに写しとらねばならない。こうしてそれは無限に続く。自己を写すとは静止的な事柄ではなく、無限に動的に発展するはたらきである、と西田は言う。(170頁)
■自覚とは、2つの同様な自己の結合ではなく、直感と反省を総合する働きである。第一期の『善の研究』では〈純粋経験の自発自展〉と〈その外でこれを反省する営み〉とが、いわばまだ分裂したままだった。別の言い方をすれば、主客未分の「純粋経験」において、自己は直接に経験可能とされるにとどまっていた。しかし、自己は反省によって論理的言語で説明され得るものでもなければならない。だが「反省」といっても自我を外から写すのではなく、自己の事実としてアプローチされねばならない。(171頁)
■自我は何である、と言った瞬間、それはもはや自我ではなくなる。だから自我は述語に置かれる以外ない。これが論理的には述語論理と呼ばれ、存在論的にみれば、無によって包まれ、無が自我に浸透するといわれる事態だ。「自我は何でもない」。西洋哲学では、存在者はかならず何らかの属性をもつ。例えば、中世哲学では「事物」ということが超越的範疇としてすべての存在者について語られた。つまり有るものは必ず何かとして有るのだ。これが「実在性」ということのもともとの意味だった。したがって無はいかなる属性も持たないのである。西田はそういう西洋哲学の概念を用いて、実体でもなく、同一、連続でもないような自我を言語化しようと試みているのである。(178頁)
■西田は亡くなる2ヶ月前の1945年4月に書き上げた長編論文「場所的論理と宗教的世界観」のなかで、われわれがそこから生まれそこへと死にゆく世界を「平常底」と呼んで強調する。しかしこの「平常」ということも、われわれの日常を無造作に肯定したものではなく、ある種の還元(エポケー)のうえに成り立つ。つまりそれは、われわれが目前の物に没入する有り方から己を転じ、世界と自我、生と死をひとつのこととして見る立場に立ってはじめてなりたつ境地である。囚われのない、述語の方向に自我を問い極めるとは、自己のうちに自己を深いところで体験するということである。自我は自己として、平常底における直接的で深い体験をとおして知られるのである。そういう体験は世界の事物に対して何か受動的であるよりは、むしろ「物となって考え、物となって行う」という境地での体験であり、そのとき自己はその真実において証明されるであろう。(180頁)
■西田はとくに1930年代以降、「歴史」の問題に向かい、歴史を、無を根底として個が相互に無尽に限定しあう絶対矛盾的自己同一としてとらえようとする。そこでは世界も自我もそういう矛盾的自己同一のいわば坩堝、大海のなかに呑み込まれていくかのようだ。自我の営みや作用は全面的に歴史の中に収容される。自我と他者、自我と世界は相互に溶解する。そうした全体が、西田によってしばしば日常的全体あるいは歴史と同一視されるのである。(181頁)
■心理学者の下條信輔氏は『サブミナル・マインド―潜在的人間観のゆくえ』(中央公論社、1996)において、大脳生理学等の知見を用いながら、人間の心が、顕在的で自覚的な過程だけでなく、潜在的で無自覚的な過程にも強く依存していると主張する。そして他者知覚と自己知覚との間には、「手がかりの与えられた方に関する過度の差こそあれ」、本質的な違いはない、という驚くべき結論を提出している。これこそ、「我の観念が最も明証的である」と断言してはばからないデカルトにはっきり対立する立場であろう。(198~199頁)
■このように近代の自我概念は主体的であるとともに、同一的であることをその重要なメルクマールにしてきた。今日ではそれが昂じて、人々は、主体性などよりも、もっぱら同一性にしか注意を払わなくなっているようにも見受けられる。それは、パスポートや保険証の偽造による詐欺、本人の声を装ったオレオレ詐欺、キャッシュカードのスキミングなどによる銀行預金の不正引出その他、個人情報がらみの犯罪が増加している状況とも関係があるのかもしれない。もしかしたら自我の実質は、ただ「ニセモノではない」という事態に還元されてゆくのであろうか。(210頁)
■プラトンの代表作『国家』第7巻冒頭部に述べられる有名な「洞窟の比喩」こそ、このギリシャ発祥の(哲学)における物の見方の基本性格を示している。
その比喩によれば、われわれの通常の認識の仕方は、ちょうど暗い洞窟の中で、奥底を見るように頭が固定されたまま、椅子に座らされている囚人達に比べられる。彼らのはるか後ろには火が燃えていて、洞窟の上方を行き交う人間や事物の影が洞窟の底に映っている。囚人たちは後ろを振り向くことができないので、影の正体、つまり真実在を見ることができない。彼らは子供のときから影しか見ていないので、この影を真実在だと思い込んでいる。もしそれに疑義をさしはさみ、光が差してくる方向を指示する人がいても容易に聞き入れず、敵意すら抱く。故にわれわれは、まず、影でなく人間や事物そのもの、すなわち真実在を見ようと努力しなければならない。次に、ひとたび真実在を見たならば、暗闇に戻ってそこに縛られ続けている人々にそうした真実を伝えなければならない。この2つが哲学者の役目なのだ。(218~219頁)
■「見る」ということが、たしかに西洋哲学の認識論の原点にはある。伝統的認識論のイデア追究的、現実世界離反的な傾向を批判したニーチェにおいてすら、彼の言う「力への意志」は同時に「光学的な見」とも言い換えられてもいた。それはフッサールでも基本的に同じだ。しかもフッサールが、見るはたらきと見られたものとの「志向性」の関係と言ったときには、見るはたらきから、矢が志向対象に向かって放たれている。科学者が対象を見る目は攻撃的である。対象は見るものに対して曝され弱々しく無防備であり、傷つきやすい。日本語には、「刺すような視線」という表現があるが、これは故なしとはしない。(224頁)
■要するに、中庸を実現できる人間は万事に心配りや気遣いのできる人なのである。そのためには自我は一定の視座に立ち続け、刻々変化する状況を持ちこたえ、かつ受け身ではなく能動的に判断できるのでなければならないであろう。つまり自我は連続的、同一的、主体的であることが要請されているのである。すでにアリストテレスにおいても、自我が自己同一的に事物や状況を己の視点から観察し続ける。換言すれば、感情の波に隷属することなく、自発的に世界の中心に立ち続け、周囲の世界の変化を冷静な絶対的観察者として「見」ている、という近代的自我モデルが早くも見出されるのである。(233頁)
■往々にしてわれわれは、外に現れた言動とは別に、他人の内面を区別してかかっているのではないか。「あの人は言ったり行なったりしていることはひどいが、芯は善人だ」というような言い方がよくなされる。だが、言動に現れたことに基づいて、その通りに判断してなぜいけないのだろうか。なぜわれわれは、現れもしない不可知の内面的自我を想定し、それが何であるかを解釈しようとするのだろうか。
よく知られているように、心理療法の一種である精神分析の臨床では、患者の深層自我を呼び出そうとする。しかし、観察し分析する者としての医師との一対一の面接は、患者の衰弱した自我にとってはあまりに重いものである。
このような精神分析の方法に対して、最近あらたに「行動福祉」という立場が注目を集めはじめている。行動福祉(行動療法)は、個人の無意識や過去も含め全人格にコミットしようとする精神分析とは違って、当面の問題になっている事柄だけを対象とする。したがってクライエントの内面に立ち入ることはしない。行動療法のほうが医師も患者も言ってみれば気が楽なのであり、しかも治療の効果ははるかに早く出る場合が多いと聞く。(244~245頁)
2010年8月7日