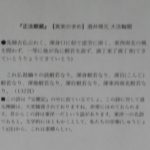『正法眼蔵(6)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
梅 華(ばいか)
■開 題
この一巻が制作されたのは、、仁治四年(1243)十一月六日とある。ただし、仁治四年はその二月二十六日をもって改元されて寛元元年となったのであるから、まことは寛元元年は仲冬(ちゅうとう)十一月六日のこととしられる。異本に寛元元年とあるのは、それを訂(ただ)して書写したものであろう。
また、この一巻には、どこにも示衆のことは記されていない。そして、奥書の日付につづいて、若干の付加せられた余録がみえる。おそらくは、示衆のことなきままに、さらに書き加えられたものであろう。
さて、この一巻を繙(ひもと)いて、まず思い出されることは、かの『如浄和尚語録』の到来のことでなくてはならない。その到来は、かの『建撕(ぜい)記』によれば、仁治三年(1242)の八月五日であったという。また、その翌六日には、法堂(はっとう)にいでまして、その語録を捧じ、香を薫じて、
「箇是天童ボッ跳、蹈翻(とうほん)東海龍魚驚」(こはこれ天童、ボッ跳を打ち、東海に蹈翻して龍魚おどろく)
という一句を中心とした法語を示したこともある。それは、いまこの『正法眼蔵』についてみても、『如浄和尚語録』上下二巻からの引用が、さきの「夢中説夢」の巻(仁治三年九月二十一日、興聖宝林寺にありて衆に示す)より以前の制作には見当たらないことによっても首肯されるところである。
(念のために申せば、『天童山景徳寺如淨禅師続語録』の巻末の跋に、道元みずから記して「今日本仁治二年歳次辛丑二月中旬、瑞巌遠公遥送此録付、頂載奉献五体投地」とあるのは、瑞巌寺の無外義遠がみずから編するところのその続語録を送ってきたものと知られる)
いま、その到来直後の法語をつくづくと案じてみると、そこにはただならぬ道元の感銘がこめられている。如浄がなくなられたのは紹定二年(1229)、道元が告暇(こくか)したした翌々年のことであった。それから指折りかぞえてみると、すでに今年は十三年目になる。その間にも、かの先師のことを思い出さぬ日とては一日もなかったであろう。だが、こうやって、この語録に接してみると、かの先師の印象はもう一度、鮮烈に蘇ってくる。それをいまここに道元は、天童山の大魚がぱっと跳(は)ねて、東海の龍魚があっと驚いているというのである。
かくて道元は、幾度となくその語録をむさぼり読んだにちがいない。そのしるしには、この『正法眼蔵』においても、それ以後、その語録からの引用がしきりと行なわれる。そして、この「梅華」の巻においては、ほとんどその全巻がその引用と解説をもってみたされているのである。
では、いったい、天童如浄という方は、どのような方であったのか。その印象は、どうやら、はなはだ摑みがたいものであったように思われる。その語録の後記にも、
「温然如天球、樸然似生鉄、只応宝愛、不堪咬嚼](温然天球のごとく、樸然生鉄に似たり、と見えている。したがって、わたしどもにはとても歯がたたない。とてもその印象を語ることなどはできないところであるが、いまその語録によってわたしにもいいうることの一つは、その方はたいへん梅華が好きであられたらしく、それがまた相応(ふさ)わしい方であったらしいからである。
そして、いま道元もまた、八たびにおよんで、先師如浄が梅華にちなんで説きたもうた垂示もしくは偈頌(げじゅ)を引用して、この一巻を構成しているのである。それによって道元が説示しようとするのは、仏祖の眼睛そのもののおもむきであるが、それはもうこの「梅華」一巻にゆだねるのほかはあるまい。(16~18頁)
■〈注解〉華開世界起;第二十七祖般若多羅の偈句であって、道元のたいへん珍重するところであったらしい。(21頁)
■先師なる如浄古仏は、また、よういに僧たちがその禅院に入ることをも許したまわなかった。つねづねに仰せには、「道心もないくせに雲水づらをした奴は、わしのところには入れるものか」と、そういって逐(お)い出したものである。逐い出してしまうと、「その分際でもないのに、いったい、どうしようとぬかすのだ。あんな犬は人さわがせするだけだ。掛搭(かた)しかるべからず」と仰せられた。
わたしは、それを目(ま)のあたりに見、また目のあたりに聞いた。そして、ひそかに思ったことは、彼らはいったい、いかなる罪根があって、この国の人に生まれながらも、この禅院にとどまることを許されないのか、ということであった。また、それなのに、わたしはなんの幸いがあってか、とおい外国の生まれでありながら、この禅院にとどまることを許されたのみならず、自由にお部屋に出入して、尊顔を礼拝し、お話を拝聴することもできる。これはいったい、どうしたことであろうか、ということであった。それは、思うに、われ暗愚なりとはいえ、なにか空しからぬよき縁(えにし)のしからしむるところがあってのことと考えるのほかはあるまい。
先師がなお世にあって宋朝の人々を教化しておられたころにも、なおそのもとに参じて道を得たものがあり、また得なかった人もあった。しかるに、先師なる古仏はすでにこの世を去りたもうた。いまやこの世は暗夜よりもくらいと申さねばなるまい。何故であるか。それは、先師なる古仏の前後には、先師のような古仏はないからである。だから、そういうのである。
だからして、いまこの先師古仏の説きたもうたところを見聞する後学は考えるがよろしい。ほかの諸方の人々も、これとおなじような教えを見聞し、参学することができるであろうと思うならば、それはとんでもない間違いである。いま先師古仏が申される雪のなかの梅華というような垂示は、まったく比類を絶した稀有の教えである。われらは日ごろ、いくたびとなく雪中に梅華のひらくを見ているけれども、それがわが仏なる釈迦牟尼如来の瞬目であろうなどとは気もつかないで、ただぼんやりと破顔の機を逸してきたことであろう。だが、いまやすでに先師古仏は雪のなかの梅華を、これぞ如来の眼睛であると正伝せられ、われらはそれを拝承した。いまや、それを思いめぐらして頂門の眼となし、眼中の瞳となすがよろしい。さらに梅華に到って梅華を究めつこせば、もはや疑う余地はまったくないであろう。ここにいたって、これを天上天下ただわれ独りたつとき眼睛、諸仏諸菩薩のなかの最尊なりと知ることをうるであろう。(25~26頁)
■まことに、かの老いたる世尊の光明は、もろもろの存在のあるがままの相(すがた)を究めつくして、もはや一微塵ほどのあますところもない。思うに人間界の住みびとと天上界の住みびととでは、その見るところに別があり、また、凡人と聖者とでは、その思うところはとおく相隔(へだ)たっているであろう。だが、大地は漫々たる雪におおわれており、雪は漫々として天地をおおいつくしている。この雪の漫々たる表裏のまろやかなるさま、それが老いたる世尊の眼睛にほかならない。
知るがよい、華も地もことごとく生滅を超えたるものである。華は生滅を超えている。華が生滅を超えているから、地もまた生滅を超えているのである。華も地もことごとく生滅を超えているから、眼睛もまた生滅を超えている。生滅を超えているというのは、無上のさとりのことである。まさにかくのごとしと知ったときには、梅華はただ一枝である。それをことばに表現していうならば、雪中に一枝の梅華がかおるとなる。その時、地生じ華もまた生ずる。
これをさらに雪漫々たりというのは、その時表も裏もことごとく雪漫々たることである。世界はことごとく心なる大地である。ことごとくの世界は華という思いである。世界がことごとく華という思いであるから、全世界は梅華にほかならぬ。全世界が梅華であるから、全世界はまた世尊の眼睛である。いまその到る処は、山(せん)河大地である。その事の到り、その時の到れば、すべて「われもとこの土に来るは、法を伝え迷情を救うにあり、一華は五葉を開き、結果は自然にして成る」というあのことばが到る処に実現するであろう。西(せい)来といい、東漸(とうぜん)ということばもあるが、それもまた梅華のいまにして到ることにほかならない。(31~32頁)
〈注解〉五眼;肉眼、天眼、慧眼、法眼、仏眼の五つをあげて五眼となす。
十 方(じっぽう)
■開 題
この「十巻」の巻が制作せられ、そして衆に示されたのは、寛元元年(1243)十一月十三日とある。それはむろん陰暦のことであるから、もう冬も酣(たけなわ)のことであるはずだと、ふと気がついて検べてみると、この一巻の示衆(じしゅ)は、この年、吉峰(よしみね)精舎において行なわれた最後のそれであった。そして、それから以後の示衆は、その翌年の二月中旬にいたるまで、禅師峰(やましぶ)山下の草庵において行なわれる。おそらくは、雪のために徃来も思うにまかせないようになったからであろうと察せられる。
さて、この一巻は、さして長いものではないが、そのなかには、おおよそつぎのような三つのことが説かれている。
その第一には、道元はまず、『法華経』方便品(ぼん)の「十方仏土中、唯有一乗法」の文をひいて、
「いはゆる十方は、仏土を把来(はらい)してこれをなせり。このゆゑに、仏土を拈来(ねんらい)せざれば、十方いまだあらざるなり」
という。では、いったい、それはどういうことであるか。静かに思いめぐらしてみると、それは、どうやら、叡智(えいち)の世界のことであり、抽象の世界のことであるといっておるのである。むろん、かの時代には、抽象という概念はない。そんな時には、道元はいつも、こんな具合に表現するのがならいである。
「有にあらず無にあらず、自にあらず他にあらず。離四句(りしく)なり、絶百非(ぜつひゃっぴ)なり。ただこれ十方なるのみなり、仏土なるのみなり」
その第二には、道元はついで、長沙景岑(ちょうしゃけいしん)禅師の有名なる垂示をあげて語る。そこには、つぎつぎと、つぎのようなことばが取りあげられ、解説が加えられている。たとえば、
「尽十法界、是沙門一隻眼」(尽十方界は、これ沙門の一隻眼なり)
とか、
「尽十法界、是自己光明」(尽十方界は、これ自己の光明なり)
とか、あるいは、
「尽十法界、無一人自己」(尽十方界は、一人として自己ならざるものなし)
というがごとき句である。おそらく、それらの句々の解説が、この巻の中心なのであろうが、それがまた難解にして容易に理解しがたい。だが、ふと気がついてみると、いまもいうように、道元は十法界とは、叡智の世界であり、抽象の世界であるといっておる。とするならば、尽十方界とは、沙門の一隻眼だといい、自己の光明にほかならずといい、あるいは、それは自己をおいてあり得ざるものだという意味が、朗然として解けてくるではないか。
そして、その第三には、玄沙師備の「尽十方界、是一顆明珠」(尽十方界は、これ一顆の明珠なり)という一句がとりあげられる。それはもうきわめて有名な句であって、古来から仏祖たちはそれを依処とし、雲水たちはそれを修行の衣糧としてきたものである。さればにや、道元もまたこの『正法眼蔵』のなかにおいて、すでにはやく「一顆明珠」の巻を制作して衆に示されたことであった。そこには、なお若かりし道元が、力をつくし心をこめてつづった詳細なる解説もある。もう一度ひるがえって披見し参照されたい。(52~54頁)
■にぎりこぶし一つ、ただそれが十方のすがたである。あるいは、一片の赤心、それが玲瓏として十方世界である。わが骨髄までしぼり出して、もはやあますところもないのである。
釈迦牟尼仏は、大衆に告げて仰せられたもうた。
「十方の仏土のなかに、ただ一乗の法がある」
いうところの十方とは、仏土をとりあげていうのである。だからして、仏土を捉えずしては、十方はまだあり得ないのである。それは仏土であるからして、仏をもってその主となす。たとえば、この娑婆世界は釈迦牟尼仏の国土であるというがごとくである。では、まずこの娑婆世界をとりあげて、それにもいろいろとあることを心にとめて、さて十方仏土もまたさまざまであることをまなぶがよろしい。
つまり、この十方は一方に帰する。あるいは、一仏に帰する。そこが十方が現ずるのである。十方が一方であり、この方であり、わが方であり、あるいは、わがいま立つ方であるがゆえに、それはまた、眼睛(がんぜい)のあるところであり、拳頭のあるところであり、露柱(ろしゅ)・燈籠のあるところである。そのような十方の仏土にすむ十方の仏たちは、いまだ大にあらず小にあらず、あるいは、なお淨でも穢(え)でもない。だから、十方の仏土の仏と仏たちは、たがいに讃(ほ)め称(たた)えて、けっして、非難しおうて、その長所短所を語り、あるいは好きだ嫌いだというようなことはない。そんなことを転法輪だの、説法だのとは思っていない。彼らはただ、たがいに諸仏となり、仏子となって、あるいは助言をあたえ、あるいは、御機嫌いかがと問い申すのである。
仏祖の国土のことを承るには、このようにまなぶのである。外道・悪魔のともがらのように、是非を批判し、そしり辱(はずか)しめるようなことはないのである。いま中国に伝わっている仏教経典を披見(ひけん)して、釈迦牟尼仏が生涯の教化のことを窺(うかが)いみるに、釈迦牟尼仏はいまだかつて、余地の仏たちの勝劣を説いたこともなく、また、余処の仏たちは仏にあらずなどと語ったこともない。おおよそ一代の説法のなかには、仏たちがたがいに是非を論ずるような仏語はどこにもみえないし、また余地の仏たちが釈迦牟尼仏を批判するようなことばもまったく伝わっていない。だからして、釈迦牟尼仏は、大衆に告げて仰せられた。
「ただわたしだけがこの相を知っている。そして十方の仏たちもまたそうなのである」
知るがよい。「ただわたしだけがこの相を知る」というその相は、いうなれば杖をもって空中に円相を描くようなものである。その円相は、この竿はどうしてこんなに長い、あの竿はどうしてあんなに短いといったところで、その形はいろいろあっても、みんなおなじである。それとおなじように、十方の仏たちのことばも、詮ずるところ、「ただわたしだけがこの相を知る」ということ。そして、釈迦牟尼仏もまたそうだという。それをいま、釈迦牟尼仏の側からいえば、「ただわれのみこの相を悟る。それぞれの仏たちもまた然り」である。つまるところ、我というも、知るというも、これというも、あるいは、一切というも、十方というも、また、娑婆世界も、釈迦牟尼仏も、みんなおなじく一円相なのである。
そのいう意味は、それがすなわち経典だとまなぶがよいというのである。諸仏と仏土とは、二つの別のものではない。さらにいえば、それは、生あるものでも、生なきものでもない。迷いでもなければ、悟りでもない。善でも、悪でも、また無記でもない。淨でもなく、穢でもない。あるいは、成(じょう)・住・壊(え)・空のいずれに属するものでもない。常でもなければ、無常でもない。有でもなければ、無でもない。自でもなくして、また他でもない。すなわち、四句の分別をはなれ、あらゆる否定(非)を絶しているのである。それはただ十方であるのみであり、仏の世界なのである。とするならば、その十方とは、頭があって尻尾のない奴らしい。(56~58頁)
見 仏(けんぶつ)
■釈迦牟尼仏は、大衆に告げて仰せられた。
「もし仏にもろもろの相あることと、仏にもろもろの相なきことを見るならば、とりもなおさず、それが如来にまみえるというものである」
いまいうところの仏の諸相を見ることと、仏の諸相にはあらぬことと、この二つがならびそろうて、それではじめてすっきりと体得できるというものである。だから、それを如来にまみえるというのだという。また、この仏を見る眼がすでにぱっと見開かれたことを見仏とするのである。あるいは、この仏を見る眼のはたらきが、それがすなわち、仏法を参学する眼にほかならない。いったい、自己なる仏をかなたに見るということと、彼方なる仏のほかに自己なる仏を見るということは、それは別々のことのように思われるけれども、いまいう見仏をまなぶことと、見仏がわかって肯(うべ)なうことと、もはや見仏を超越してしまうことと、あるいは見仏を活かしていろいろと用いることなど、それらは結局するところ、おなじことを別の光のもとで見ているだけのことである。それらは、つまり、いろいろの面から、いろいろの身、いろいろの心、いろいろの眼で見ている見仏である。いまにしてわれらが行ずる発心も、修行も、証悟も、すべてこの見仏のなかにあって、眼睛をいかし、骨髄をいかしているのにほかならない。とするならば、ここもかしこも、これもあれも、すべてが見仏のいとなみだといってよかろう。(75~76頁)
●原 文
菩薩道といふは、吾亦(えき)如是、汝亦如是なり。(83頁)
■菩薩道というは、「われもまたかくのごとし。汝もまたかくのごとし」である。(84頁)
■釈迦牟尼仏は、普賢菩薩に告げて仰せられた。
「もしこの法華経を受持し、読誦(どくじゅ)し、正(しょう)憶念し、修習し、書写する者あらば、当(まさ)に知るべし、この人はすなわち釈迦牟尼仏を見たてまつるなり、仏の御口よりこの経典を聞くが如くならん」
おおよそすべての仏たちは、釈迦牟尼仏を見、釈迦牟尼仏となるのをこそ、成仏といい、また作仏(さぶつ)というのである。そのようなことは、もとはといえば、いまいうところの七つの箇条をいとなむことによって得るのである。その七種のことを行ずる人こそ、まさにその人と知るべきであり、まさしくその当人なのである。それは、とりもなおさず、釈迦牟尼仏を見たてまつるであるから、また、したしく仏の口からこの経典を聞くようなものである。
そもそも、釈迦牟尼仏という方は、釈迦牟尼仏を見たてまつってから、はじめて釈迦牟尼仏にましまされる。だからして、その舌相(ぜっそう)は三千世界を覆い、いずれの山海も仏の経にあらざるはないけれども、ただそれを書写するその人のみが、よく釈迦牟尼仏を見たてまつる。あるいは、仏の口は万古に閉ざされることなく、いずれの時節も経典にあらぬはないけれども、ただよくそれを受持する行人(ぎょうじん)だけが、釈迦牟尼仏を見たてまつる。さらにいうなれば、目や耳や鼻など、六根のいとなむところもまたおなじであるはずであり、あるいは、日ごろかりそめのいとなみも、また同様であろう。
思えば、いまわれらはこの経典に生まれ遇うことを得たのである。だから、身心をはげまして、この法華経を受持し、独誦し、正しく憶念し、修習し、また書写するならば、それはとりもなおさず釈迦牟尼仏を見たてまつることであろう。あるいは、それは仏の御口よりこの経典を聞くがごとしという。とするならば、誰だってこれをきそうて聞こうとしないものがあろうか。もしも、これを急がず、務めざるものがあらば、それは心貧しゅうして幸福の智慧(ちえ)なき人々であろう。もしよく修習するならば、それこそ「当(まさ)に知るべし、この人はすなわち釈迦牟尼仏を見たてまつるなり」というところである。(89~91頁)
■釈迦牟尼仏はまた仰せられた。
「あらゆる功徳を修めて、柔和にして質直なる人は、かならずみな、わたしが此処にあって法を説いている姿を見ることであろう」
いまあらゆる功徳という。それはもう、わが身を忘れて努め、どこまでも努めなければなるまい。だが、それを修しきたって、はじめて「われもまたかくのごとし、汝もまたかくのごとし」といわれるような柔和にして質直なものとなる。それでこそ、はじめて、よく泥中にあっても仏にまみえ、波のまにまに漂っていても仏にまみえ、此処にあって法を説くという仏の説法にもあずかることができるというものである。(101頁)
〈注解〉頭正尾正;終始一貫していること。ここでは当然の結果と訳しておいた。(102頁)
遍 参(へんさん)
■開 題
この一巻が制作され衆に示されたのは、、寛元元年(1243)十一月二十七日とある。北越の冬もようやく極まれるころであり、さきの巻の開題でもいった禅師峰(やましぶ)の茅庵(ぼうあん)にくだってからの二番目の示衆である。
遍参とは、また徧参とも書かれる。禅僧があまねく行脚して天下の善知識に参学することをいう。この巻の冒頭に、
「仏祖の大道は、究竟参徹(くきょうさんてつ)なり、足下無糸子(そっかむしこ)なり、足下雲生(うんしょう)なり」
とあるのも、そのことをいっておるのである。仏祖の大道は、徹頭徹尾、善知識を訪ねて参学することに尽きる。そして、その行脚の仕方は、洞山良价(とうざんりょうかい)のことばをもっていえば、「足下に一糸なくして去る」がよく、あるいは、達磨伝の一節をもっていえば、その行くや、「足下に雲を生ずる」おもむきあるべしというのである。それは禅門における常套の考え方であるといって差し支えあるまい。
だが、道元がこの一巻において語らんとするところは、けっして、そのような禅門の常套語ではない。どうやらこの人は、かりそめにも常識的なことばを繰り返すことは潔(いさぎよ)しとしないらしい。そして、この一巻においても、つづいて語るところは、まったく世の凡庸の徒のいうところと、その類を異にする。
そこで道元がまず取りあげているのは、雪峰義存と玄沙師備の師弟のあいだに交された問答である。こうである。
そこでは、まず雪峰が玄沙を召していった。
「頭陀袋を用意したのに、なぜ行脚に出掛けないのじゃ」
玄沙はそれに答えていった。
「達磨も中国に来たわけではないし、二祖も天竺に出掛けたわけではありません」
すると雪峰は「うん、うん」と深くうなずいたことであったという。
ここで道元が『景徳伝燈録』巻十八から引いているのはそれだけであるが、さきの「一顆明珠」の巻の冒頭には、道元はそこのところを、もっと詳しくこんな具合に物語っている。
そこではまず玄沙が、「あまねく諸方を参徹せんために、嚢(のう)をたづさえて出嶺」しようとする。だが、山をくだる途中で、岩に脚指(あしゆび)をぶっつけて、「流血し痛楚(つうそ)するに、忽然として猛省して」雪峰山に帰った。それを見て、雪峰が問うていう。
「頭陀袋を用意して、どうしようというのだ」
玄沙はそれに答えて、
「やっと人を誑(だま)さずにすみました」
そして、他日また雪峰が玄沙を召して、さきの問答とはなったのである。
それだけ付け加えて申せば、それでいくらかの、この問答の真相がうかがえはせぬかと思うのであるが、どうやら玄沙も、はじめは、遍参とはただ天下の善知識をたずねて行脚することのみ考えていたらしい。それが、脚の指を岩にぶっつけて血を流したところで、はっとばかりに、やっと気がついたのである。
なんと気がついたか。それをいまの玄沙のことばでいえば、「達磨東土に来らず、二祖西天に往かず」である。それをいまこの巻における道元のことばで申すなれば、
「等閑の入一叢林、出一叢林を遍参とするにあらず。全眼睛の参見を遍参とす、打得徹を遍参とす。面皮厚多少を見徹する、すなはち遍参なり」
ということとなるであろう。そして、そのことをもっとも印象ふかく教えてくれるのは、いまの玄沙の問答であるとするのである。かくていう、「遍参の宗旨、ただ玄沙に参学すべし」と。よってこの一巻のおもむきを知ることをうるであろう。(116~118頁)
■仏祖の大道は、徹頭徹尾、善知識を訪ねて参学することに尽きる。その去るや、足下に一糸なくして去り、その行くや、足下に雲を生ずという。とはいうものの、はじめて菩提心の花がひらいて世界がおこるのであり、また、日常の喫茶喫飯のことを指して、わしはいつもこれを大切にしていると申された仏祖もある。だからして、甜(あま)い瓜は蔕(へた)まで甜いのであり、苦(にが)いひさごは根まで苦いのであり、あるいはさとう大根は蔕まで甜いのである。仏祖もまたみんなそのようにして参学してきたのである。
玄沙山の宗一大師は、ある時、師の雪峰から呼ばれた。雪峰はいった。
「頭陀袋を用意したのに、なぜ行脚に出掛けないのじゃ」
玄沙はいった。
「達磨も中国に来たわけではないし、二祖も天竺に出かけたわけではありません」
雪峰は深くうなずいたという。
いうところの遍参の道理は、ここではすっかりひっくり返ってしまっている。そんなことは仏の教えにも説かれてはいないし、修行のどの段階にあるというものでもあるまい。
また、南嶽の大慧禅師が、はじめて曹谿古仏を尋ねていった時、曹谿古仏はいった。
「こんな物がどうして来たのだ」(岡野注;「是甚麼物恁麼来」)
南嶽は、その泥の団子をこねまわして思いめぐらすことに終始して八年におよんだ。そのあげくに、思いめぐらした一石をもって、古仏に申していった。
「わたくし懐譲(えじょう)がはじめてこちらに参りました時、和尚にはわたくし懐譲にお会いくださって、こんな物がどうして来たのだと仰せでございました。それがやっと判りました」
すると曹谿古仏は仰せられた。
「では、そなたはそれをどう判ったというのだ」
その時、南嶽はいった。
「一物をあげて申したのでは、あたりませぬ」
それが思いめぐらした成果である。八年の成果である。
すると、曹谿古仏は問うていった。
「では、まだ修行が必要であろうか、どうであろうか」
南嶽は申していった。
「修行はいらないわけではありません。ただ純粋でなくてはいけません」
そこで、曹谿古仏は仰せられた。
「わしもそのようじゃ、そなたもそのようじゃ(岡野注;「吾亦如是(ごやくにょぜ)、汝亦如是(にょやくにょぜ)」)。そして、天竺のもろもろの仏祖たちも、みんなそのようであった」
それから南嶽は、さらに八年にわたって思いめぐらした。それでその始終を指おり数えてみると、じつに十五年の遍参である。
思うに、恁麼来すなわちどうして来たのかというのも遍参である。また、説似(じ)一物(もつ)即不中すなわち、一物をあげていったのでは中(あた)らないといって、もろもろの仏祖の扉をひらき、仏祖に参見したのも、またおなじような遍参である。この仏法の世界に入ってよりこのかた、もう幾度となく、身をひるがえして行脚してきた。だが、なおざりに禅院に入り、なおざりに禅院を出るのを遍参とするのではない。その眼睛(がんぜい)を見開いて参見するのが遍参である。どこまでも叩きあげるのが遍参である。あるいは、仏祖の面皮はどのくらい厚いかを見通すのが、すなわち遍参というものである。(119~122頁)
〈注解〉曹谿古仏;大鑑慧能(だいかんえのう、713寂、寿76)。五祖弘忍の法を嗣いで六祖となり、曹谿の宝林寺に住す。その法を嗣ぐもののうち、南嶽懐譲・青原行思の二人がもっとも知られている。(123頁)
■雪峰がいうところの遍参の主旨は、むろん山を下ることをすすめるのでもなく、あまねく天下を行脚することをすすめるものでもない。いうなれば、玄沙がいうところの「達磨も中国に来たわけではなく、二祖も天竺に出かけたわけではない」という発言をうながしたのである。
玄沙が「達磨は中国に来たわけではない」といったのは、来たのを来ないというような滅茶苦茶な発言ではない。それは大地に寸土なしの道理によるのである。それが正法の世界のありようである。そして、ここにいうところの達磨とは、その正法のいのちの先端である。たとい中国の全土が湧出してかしずいたかたとて来たというわけでもなく、またそうでないからとて来ないわけでもない。つまり、中国に来らずであるから中国に面(かお)を現わすのであり、中国がたとい仏祖の面(かお)を見たからといって、中国に来たわけではない。つまり、仏祖を捉えようとすれば、かえって鼻の孔を見失うというところである。
いったい、大地は東でも西でもない。東西ということは大地には関係ないことである。いま玄妙は「二祖は天竺に往(ゆ)かなかった」といったが、たとい彼が天竺に行脚したとしても、やはり二祖は天竺に往かなかったのである。もし二祖が天竺に往ったといったのでは、片手落ちというものである。
では、二祖はどういう訳で天竺に往かなかったか。しばらくそのことを考えてみよう。そのわけは、達磨の碧(あお)い目の眼睛に飛び込んだから、天竺に往かなかったのである。もしあの碧い目のなかに跳び込むことができなかったら、彼はきっと天竺にも赴(おもむ)いたであろう。つまり彼においては、達磨の眼睛をえぐり出すことが遍参にほかならなかったのである。天竺に往ったり、中国に来るのが、遍参ではないのである。天台や南嶽にいたり、あるいは五台山や天上にのぼるのを、遍参とするのではないのである。四海・五糊を超越してしまわなければ、遍参とはいえないのである。四海だの五糊だのを徃来しているあいだは、まだまだ四海・五糊を自由にすることはできない。それはただ、路をなめらかにし、足下をなめらかにするだけのことで、遍参のことはどこかに見失ってしまっているのである。
いったい、この十方世界のすべては、そのままあるがままなる一箇の人間のすがたにほかならない。そこにまなび徹するのが遍参というものである。だからして、達磨は東土に来らず、二祖は西天に往かずといったいい方もあろうというものである。つまり、遍参とは、石が大きければ大きいまま、石が小さければ小さいまま、石はそのままに動かさずして、大は大とまなび、小は小ときわめるのである。それを、ただあれにもこれにもと参見するのは、まだまことの遍参というものではない。遍(あまね)くとはいうものの、そのなかにいろいろの変化があるのが遍参である。地を打つときにはただ地を打つ。それが遍参である。ひとつ地を打ったかと思うと、つぎには空を打つ、さらには四方八方というのは、遍参ではない。倶胝(くてい)は天龍和尚に参見して、一指頭の垂示を得たという。それが遍参である。それからのちは、倶胝はいつもただ一指を立てたという、それが遍参である。(125~127頁)
〈注解〉倶胝;金華山の倶胝(くてい)和尚として、『景徳伝燈録』巻11にみえる。天龍和尚の法嗣(ほっす)。倶胝が天龍和尚に参じた時、和尚はただ一指をたてた。倶胝はそれによって悟り、それからは彼もまた生涯、一指をたてるのみであったという。これを倶胝の一指頭禅という。(128頁)
眼 睛(がんぜい)
■洞山悟本大師(とうざんごほんだいし)は、かって雲巌曇晟の門下にありしころ、ちょうど雲巌がわらじを作っているところに出会い、雲巌に申していった。
「わたしは、和尚によって眼睛を得たいと思っております」
雲巌はいった。
「そなたのは、誰かにやってしまったのかい」
洞山はいった。
「わたしには、眼睛はございません」
雲巌はいった。
「いや有るんだよ。だが、そなたはどっちにむけて著(つ)けているのだ」
洞山は黙っていた。すると、雲巌がまたいった。
「眼睛を得たいと思う、それがとりもなおさず眼睛ではないか」
洞山はいった。
「いや、それは眼睛ではございません」
雲巌は、「ちぇっ」といって、舌打ちしたことであった。
そういうことであるので、ずばりといえば、すべて参学は、とりもなおさず眼睛を乞うことである。僧堂で坐るのも、法堂(はっとう)にのぼるのも、また和尚のお部屋に入室するのも、すべて眼睛を乞うのである。あるいは、衆とともに来たり、衆とともに去る、そのすべてがおのずからにして眼睛をもとめることである。しかもそれは、自己がどうすることでもなく、また他人がどうしてくれるわけでもないことが明らかである。
いまも洞山はすでに、「和尚によって眼睛を得たい」とお願いした。それでも判るように、それがもし自分のものならば、人に乞われてもどうにもならないし、もしそれが他人のものだったら、それを人に乞うわけにはゆくまい。
そこで雲巌は、「そなたのは、誰かにやってしまったのか」といった。「そなたの」といってもよい時があり、また、誰にやったといい得る場合もある。
だが、洞山は、「わたしには眼睛はございません」といった。それは眼睛がみずから物言っているのである。こういうことばがどうして成るか。そこを静かに思いめぐらしてまなぶがよろしい。
すると雲巌は、「いや、有るのに、どっちをむけて著けているのだ」といった。それも眼睛のことをいっているのであって、「わたしには眼睛はない」というその無は、じつは、有るのだけれども、どこか余処(よそ)をむいているのだというのである。なるほど、どこかを向いているのは、有るからである。そこをこんな具合にいうのだと知らねばならない。
だが洞山は黙っていた。それは、いうところを知らずして、ただぼやっとしていたのではない。そこは、沈々として思いにふけっていたのである。
そこで雲巌は、彼のために示して、「眼睛を得たいと思うところ、それがとりもなおさず眼睛ではないか」といった。それは眼睛そのものを見せようとしているのであり、活きた眼睛をとり出して見せているのである。
いまいうところの雲巌のことばの主旨は、眼睛がはじめて眼睛を乞うのだといっておる。水は水を引き、山は山に連なるというところである。だから、まさしく独立独行なのであるが、だが、同時にまた人間ことごとく然りといってもよろしい。
ところが、洞山は、「いや、それは眼睛ではございません」といった。それは眼睛が自分を批判していっているのである。だから、眼睛にはあらずとする身心(じん)にも考え方にもいろいろとあるであろうが、それがとりもなおさず活きた眼睛の自己批判だと、もう一度見直すべきである。
いったい、三世の諸仏はみな、眼睛が法輪を転じ、説法をなさるのを、露地に立って聴いて三世の諸仏とはなったのである。つまり、修行していたる究極のところとはといえば、すべて眼睛のなかに跳びこんで、はじめて発心し、修行し、そして大いなる悟りを成就するのである。しかも、その眼睛はもともと自己のものでもなく、また他人のものでもないのであるから、なんの差し障るところもないから、そのような大事もすらすらと自由自在なのである。
だから、一人の古徳もいったことがる。
「まことに奇なることであるが、十方の仏はもとこれ眼中の華にまします」
そのいうところは、十方の仏というは眼睛のことだというのである。眼中の華がつまり十方の仏なのである。まだまだ進歩することもあり、退歩することもあり、あるいは打坐(たざ)するかとみれば、睡(ねむ)っていることもあろうが、それもみんな眼睛そのものの力をうけてそうあるのである。つまり、摑むも放すもすべて眼睛のなかでのことである。(147~150頁)
家 常(かじょう)
■趙州(じょうしゅう)の真際(ざい)大師は、一人の新しく来た僧に問うていった。
「かって此処に来たことがあるか」
その僧はいった。
「はい、かって来たことがございます」
師はいった。
「お茶をのんでゆきなさい」
また一人の僧に問うていった。
「かって此処に来たことがあるか」
その僧はいった。
「いえ、まだ来たことはございません」
師はいった。
「お茶をのんでゆきなさい」
院主(いんじゅ)が師に問うていった。
「いったい、かって此処に来たことのあるものにも、かって此処に来たことのないものにも、みんなお茶をのんでゆけと仰せられますのは、どういうことでありましょうか」
すると師は、「院主よ」と呼んだ。院主が「はい」と答えた。すると、師はまたいった。
「お茶をのんでゆきなさい」
いまいうところの「此処」は、頭のてっぺんでもなく、鼻の孔でもなく、あるいは趙州でもない。此処をとびこえてしまえば、かって来たことがあろうと、来たことがなかろうと差し支えはあるまい。だが、いったい、ここをなんのところだと思えば、かくもひたすらに、来たことがあるか、ないかと問うのであろうか。だからして、かって先師は仰せられたことがある。
「誰ぞ美々しき酒楼に人を迎えて、趙州の茶を汲むものがあろうぞ」
だからして、仏祖の常日ごろには、ただ喫茶喫飯(きっぱん)のみであると知るがよい。(183~185頁)
〈注解〉趙州真際大師;趙州従諗(897寂、寿120)。南泉(なんぜん)普願の法嗣(ほっす)。趙州観音院に住して趙州をもって称せらる。諡(おくりな)して真際(ざい)大師という。
院主;「いんじゅ」と読む。寺務を主宰する者である。一山の主たる住持とは別であって、また監院とか監寺とかいう。(185頁)
龍 吟(りゅうぎん)
■舒州(じょしゅう)投子山の慈済大師(じさいだいし)に、ある時、一人の僧が問うていった。
「枯木のなかにも、また龍の声があるのでございましょうか」
師はいった。
「わしにいわせれば、髑髏のなかに獅子の声があるというところじゃ」
枯木あるいは死灰をもって究極の境地を談ずるのは、もともと外道の教えるところである。だがしかし、外道がいうところの枯木と、仏祖がいうところの枯木は、まるで異なるものであろう。外道もまた枯木を談ずるけれども、ほんとうは枯木を知らないのである。ましてや、いまいう龍の声を聞き得るはずはない。つまり、外道は枯木を朽木だと思っている。だから、それはもはや春に逢うことはできないと教えられている。
それに反して、仏祖がいうところの枯木は、「海枯れて」底を見ずというあの枯である。「海枯れて」はまた「木枯れて」である。木は枯れてもまた春に逢うのである。木のそのままじっとしているのが枯である。いま冬にして、山の木も、海の木も、空の木も、みんな枯木である。また、これから芽をふく萌芽は、枯木のいぶく龍の声であるし、あるいは、いく抱えもある大木だって、枯木から生まれた児であり孫である。
つまり、枯ということの性質やその作用は、まことにさまざまであって、誰だったかさる仏祖もいわれたように、ある時には枯れぼっくいであり、またある時には枯れぼっくいではないのである。あるいはまた、それは山谷(さんこく)の木のことであり、あるいは、あた、田里(でんり)の木のことであってもよい。山谷の木というのは、世のなかでいうところの松柏(しょうはく)のことであるし、また、田里の木というのは、世のなかの人々のことである。それらはみんな、まず根があって、そこから葉がのびてくる。その根を仏祖という。また、それらはやがて、枝も葉もみんな大木にかえってゆかねばならぬ。それがとりもなおさず参学というものである。
そのようなのが、枯木のあの姿であり、この姿である。すなわち、ある時はのびのびとその身をのばした姿をあらわし、またある時はすっかり身をひそめて小さくなった姿をとる時がある。そして、もしそのような枯木でなかったならば、とても時にいたって龍のいぶきなどできるものではないであろうし、また、声をひそめて静かな境地に入ることもできないであろう。かって、一人の仏祖は、
「いくたびか春に逢うて心はかわらず」
と詠じたことがあたが、それは、この世界のすべてが、このような枯木の龍吟であることを語っている。その吟ずる声は、いうところの宮(きゅう)・商・角・羽(う)の五音のたぐいのものではないが、そこはむしろ、その五音もまたこの龍吟より生まれたものだといってよかろう。
しかるに、いま、かの一人の僧は、投子山の慈済(じさい)大師に問うて、「枯木のなかにも、また龍の声があるのでございましょうか」といった。それは、遠い遠い昔から今にいたるまで、いまだかってなかった、問いの成立である。こんな問答はいまにしてはじめての実現である。それにたいして、投子山の慈済大師は、「わしにいわせれば、髑髏のなかから獅子の声がきこえるということじゃなあ」といった。それは、「なんの掩(おお)うところやあらん」、まことにその通り、その通りじゃというところであって、「おのれを屈し、人を推して、また休(や)まず」というものであろうか。だが、これによって、髑髏の獅子吼もまた、世にあまねきこととなったといってよかろう。(191~193頁)
〈注解〉舒(じょ)州投子山慈済(さい)大師;投子大同(914寂、寿不詳)。翠微(すいみ)無学の法嗣(ほっす)。投子山に庵居して三十年なりという。諡(おくりな)して慈済(じさい)大師という。
宮・商・角・羽;中国での音楽の基音とせられる五音である。ドレミファというところである。(193~194頁)
春 秋(しゅんじゅう)
■ある時、一人の僧が洞(とう)山悟本大師に問うていった。
「寒さ暑さが到来した時には、どうしたらよろしゅうございましょう」
師はいった。
「寒さ暑さのないところにゆけばよいではないか」
僧はいった。
「いったい、寒さ暑さのないところなど、どこにゆけばあるのでございましょうか」
師はいった。
「寒い時には、そなたをうんと寒がらせるがよろしい。暑い時には、そなたをうんと暑がらせるがよろしい」
このはなしは、むかしの人々も、ああだろうこうだろうと、いろいろと考えてきたものである。いまの人々も、いろいろと思いめぐらしてみるがよろしい。仏祖もまたかならずこの道理をまなんできた。それをまなんできたものが仏祖なのである。印度においても中国においても、古今の仏祖たる方々はたいてい、この道理をちゃんと身にそなえていた。つまり、この道理をその身にそなえることが、仏祖たるものの課題なのである。
しかるに、いま、かの僧は問うて、「寒さ暑さが到来した時には、どうして廻避したらよいでしょうか」という。それをよくよく考えてみるがよろしい。というのは、そのまさしく寒さの到来した時といい、またまさしくその暑さの到来したというのは、いったいどのようなことであるか、そこを精細にしらべてみるがよいというのである。その寒さ暑さというものは、寒さは寒きさながら、寒さのほかのなにものでもないのであり、また暑さは暑ささながら、暑さのほかのなにものでもないのである。だから、寒さ暑さの到来する時には、いうなれば、それは、寒さ暑さそれ自体の頭のうえから到来するのであり、あるいは、寒さ暑さそのものの眼睛のなかから現われてくるのである。けっして、どこか余処に寒さ暑さがあって、それを誰かが持ってくるわけではない。だから、その頭のうえは、とりもなおさず無寒暑のところであり、また、その眼睛のなかには、すなわち寒暑はないのである。
しかるに、洞(とう)山悟本大師はそこで、「寒い時には、そなたをとことんまで寒がらせるがよろしい」といい、また、「暑い時には、そなたを徹底的に暑がらせるがよろしい」といった。それは、まさしく寒さ暑さが到来した時のことである。だが、その時には、たとい時寒にしてして、その寒さがどんなに寒かろうとも、なおかならずしもその寒さがそなたを震えあがらせるわけでもないし、また、たとい時暑時にあたって、その暑さがどんなにひどかろうとも、なおかならずしもその暑さがそなたを暑がらせるものとはかぎらないのである。つまり、寒さはどこまでもただ寒さである。また暑さもまたどこまでもただ暑さである。それは、かならずしもそなたには関係のないことである。それを、ただいろいろと策を講じて廻避しようなどとしても、それはなお、頭と尻尾をとりかえてみるというにすぎまい。かくて、寒さとは、とりもなおさず先徳の活きた眼睛であると承知するがよく、また暑さとは、すなわち先師のあたたかい皮であり肉であると知るがよいというのである。(207~209頁)
〈注解〉洞山悟本大師;洞(とう)山良价である。
■行(ぎょう)雲流水
■慶元府なる天童山の宏智(わんち)禅師は、丹霞和尚の法を嗣ぎ、諱(いみな)を正覚(がく)和尚という。ある時いった。
「もしこのことを喩(たと)えていうなれば、それは二人で碁を打っているのによく似ている。碁を打つときには、対手(あいて)はわが打つ著手にはなかなか応じないし、また、われは対手を胡麻化そうとばかりしているものである。もしそこのところがよくよく体得できれば、はじめて洞山(とうざん)のいう意味が判ってくるであろう。だが、それでもなお合点がゆかないというならば、わしもまたひとつ注釈でもいれておかねばなるまい。
ここに到ってみれば暑もなく寒もない
大海原だって乾(ひ)あがってしまったら
大うみがめでも苦ものう拾えるのに
なんでまあ沙のうえで釣竿をいじっているのじゃ」
まずいうなれば、碁を打つということはないわけではないが、いったい、二人で打つというのはどういうことであるか。もしも二人で碁を打つというなれば、それはどうやらへぼ碁らしい。もしへぼ碁であるならば、それはなお碁を打つとはいいがたい。どうでござる。そこは、もしいうならば、こういう具合にいうべきところであろう。――囲碁というものは一人で打つものであって、その一人、つまり、自分のなかで敵手にめぐり逢うものである――と。とはいいながらも、いま宏智禅師がいうところの、「対手はわがうつ著手にはなかなか応じない」というところは、よくよく心して思いめぐらしてにるがよろしい。いやいや、われとわが身にあててまなびきわめるがよいのである。対手はわがうつ著手にはなかなか応じてくれないということは、汝はけっして我であろうはずはないということである。また、「われは対手を胡麻化そうとばかりしている」という。そこもまたうっかりして、いい加減に通りすごしてはいけない。泥のなかにも泥がある。泥はどこまでも泥である。だから、そこに踏みこんだものは、足を洗い、また冠(かんむり)のひもまで洗わなければならない。また、珠のなかにも珠がある。珠はどこまでも珠である。だから、その光を放つにあたっては、他人(ひと)をもてらし、また自己をもてらすのである。(215~216頁)
〈注解〉天童山宏智禅師;宏智正覚(わんちしょうがく、1157寂、寿67)。丹霞子淳の法嗣(ほっす)。かって天童山にあり、住すること三十年という。(216頁)
■だいたい、諸方の代々の方々は、このようにしてべちゃくちゃと頌古(じゅこ)をこととしているが、まだまだ高祖洞山のほとりを覗うことはできないらしい。なぜならば、仏祖の日常には、寒暑をどうなされていたやら知らないものだから、ただいたずらに「寒ければ火にあたり、暑ければ涼み」などといっておる。可哀そうなものである。いったい、なんじらは、古徳のほとりにあって、なにを寒暑というのだと聞いてきたのだ。祖師の道がすっかり廃(すた)れてしまったことを、悲しまざるを得ないではないか。
願わくは、この寒暑の意味するところをも知り、この寒暑の時期をも体験し、さらにはこの寒暑を自由にもちいきたって、そこでもう一度、高祖の示したもうことばを称え、またそれを取り上げて語るがよろしい。まだまだそうは参らぬというならば、そこはむしろ、まず自覚するがよろしい。世俗の人々だって、年月のありようにつき、また万物の受け取りかたについて、聖人と賢者とではいろいろのちがいがあり、また、君子と愚夫とではさまざまの相異がある。ましていわんや、仏道でいう寒暑が、なお愚夫のいうところの寒暑とおなじだろうなどと考えたのでは、とんだ錯覚というものであろう。そこはよくよくまなび究めるがよろしい。(228~229頁)
祖 師 西 来 意(そしせいらいい)
■さて、「人の千尺の懸崖にして樹に上(のぼ)るがごとし」という。そのいい方を、まずしずかにまなびいたるがよろしい。そこで人というのはなんであるか。仏殿の大柱だって木の杙(くい)でないわけではない。破顔微(み)笑する仏や祖だって、ここに相まみえるわれやひとだって、みんその人ならざるはない。その人がいま樹にのぼるという。その場所は、この大地でもない、百尺の竿頭でもない、それは千尺の懸崖である。たといそこを脱(ぬ)け出しても、やっぱり千尺の懸崖のなかである。そのなかにも、落ちる時があり、また上る時もあるということが判るのである。
とするならば、上向きにも千尺であろう。下向きにもまた千尺であろう。左むきにも千尺であろう。右むきにもまた千尺であろう。あるいは、ここもまた千尺であり、あそこもまた千尺であろう。あるいはまた、その人も千尺であり、その樹もまたせんしゃくであろう。つまり、上にいうところの千尺はそんなものであろう。では、ちょっと聞きたいが、その千尺とはどのくらいであろうか。答えていわく、それは、かの古鏡(こきょう)ぐらいのもの、あるいは、かの火炉(かろ)ぐらいのもの、あるいはまた、かの無縫塔(ほうとう)ぐらいのものというところであろう。
また、「口に樹の枝を銜(くわ)える」というが、いったい、口とはどういうものであろうか。たとい、口のすべては知り得なくても、ここは、樹とえだということであるから、まずは枝をたずね、その葉を摘んで、だんだんと口なるもののありようを尋ね知るがよろしい。すると、いまのところは、樹の枝をつかまえているのが口だというのであるから、そこでは、口いっぱいはすべて枝であり、また、枝いっぱいはすべて口であろう。あるいは、身体じゅうが口であり、また、口じゅうが身体であるといってもよかろう。また、樹はみずから樹を踏んでいるから、だから脚は樹を踏まずという。それはまた、脚はみずから脚を踏むといってもおなじであろう。あるいはまた、枝はみずから枝に攀(よ)じているから、だから手は枝を攀じずという。それはまた、手はみずから手を攀ずるといってもおなじことであろう。だがしかし、脚のかかとには、なお進むの退くのといったことがあり、また手のさきには、なお握るの放すのということもある。だから、世の人たちはたいてい、ここのところはなにか虚空にかかっているのだなあと思うであろうが、けっしてそうではない。ここは樹の枝を銜えているというところに意味があるのである。
つづいて、「樹下にたちまち人ありて問わん。如何ならんかこれ祖師西来意」とある。そこに「樹の下にたちまち人があって」というのは、あたかも樹のなかに人があってといってもよいところであろう。つまり、そこは人か樹かというようなところであるから、また、「人の下にたちまち人があって問うた」といってもよいところであろう。だから、また、ここは、樹が樹に問うているのであり、人が人に問うているのであり、樹がすべてそのまますっかり人となって問うているのである。そして、それとおなじように、いま西来意を問うには、まず西来意を挙して問うのであるという。つまり、問う者もまた口に呪枝を銜えて問い来るのである。口に枝を銜えずしては、よく問うことを得ないのである。それでなくては、口いっぱいの言葉だでないのであり、言葉いっぱいの口が開(あ)かないのである。だから、西来意をいかにと問わんとする時には、まず西来意を口に銜えて問うというのである。(238~240頁)
■そこで、「もし口を開いてその人に答うれば、たちまち身を喪(うしな)い、命を失う」という。その「もし口を開いてその人に答うれば」ということばを、よくよく身にあてて考えてみるがよろしい。すると、口を開かないでその人に答えるということだってあり得るではないか。もしそうすれば、身も喪わず、命も全うすることができるではないかと、そういうものもあるであろう。だが、たとい、口を開くとか、口を開かないとかいうことはあり得ても、口に樹枝を銜(くわ)えるということについては、いずれでもすこしも差し支えはあるまい。開くの、閉じるのということは、それがすべての口の問題ではあるまい。口によっては、ぽかんと開いているのもあれば、きりっと閉じているのもあろう。だがしかし、樹の枝を銜えるということは、これはすべての口の日常のことであって、口を開くにも閉ざすにもなんの差し障りもないことである。
では、「口を開いてその人に答える」というのは、その樹枝を開いて人に答えることをいうのであろうか。それとも西来意を開いて人に答えるというのであろうか。そこは、もし西来意を開いてその人に答えるのでなかったならば、「いかなるか、これ祖師西来意」という問いに答えたことにはなるまい。また、もしその人に答えるのでなかったならば、それは身を全うし、命を保ったのであって、身を喪い命を失うということにはなるまい。またもし、その前から身を失い命を失っているのだったら、むろん、人に答えるなどということはあり得ないであろう。しかるに、いま香厳和尚のこころはいかにというならば、それは、人に答うることを辞せずというところにある。だから、おそらくは、身を喪い命を失うよりほかはないとの覚悟のうえであろう。
知るがよい。いまだ人に答えない時には、身をまもり命を保つのである。だが、たちまち人の問いに逢うて答えた時には、一たび喪身失命しても、また身を翻して命を得るのである。思うに、人々はみな口いっぱいに物いいたいことがある。だから、人にも答えるがよい。自分にも答えるがよい。また、人にも問うがよく、自分にも問うがよろしい。それを口にことばを銜えるという。それをいまは、口に枝を銜えているといったのである。だから、もし人に答えない時には、それは人の問うところに悖(もと)るとはいうものの、わがみずから問うところには違うものではあるまい。
ともあれ、よって知ることのできるではないか。すべてこれまで西来意の問いに答えてきた仏祖のかたがたは、みんなこの「樹に上がって口に樹の枝を銜えた」時、つまり、その決定的瞬間にあたって答えてきたのである。また、すべてこれまで西来意について問うてきた仏祖たちも、みんなその「樹に上って口に樹の枝を銜えた」その瞬間にあたって問うてきたものなのである。(242~244頁)
■雪竇(せっちょう)山の明覚禅師重顕(じゅうけん)和尚はいったことがある。
「樹上にして道(い)うはやさしく、樹下にして道うは難しい。だから、わしは樹に上がるから、一問をもって来るがよい」
いま、和尚は「一問をもって来るがよい」というが、もはやどんなに力を尽くしてみたところが、残念ながら、その問いはいつでも、答えよりも後になってしまう。でも、一つ、あまねく古今の長老たちに問うてみたい。いま香厳和尚は呵々として大笑 したというが、いったい、それは樹上にして物いうたのであろうか、それとも、樹下で物いうたのであろうか。また、それは西来意の問いに答えたのであろうか。それとも答なかったのであろうか。どうじゃ、試みにいってみるがよい。
〈注解〉聞きたることおそらく……;いま雪竇は、わしは樹に上っているから、一問をひっさげて来れという。だが、いまからいかに力んでも、残念ながら、問いよりもさきに、答えのほうができているからなあ、というのであろう。(246頁)
優 曇 華(うどんげ)
■「霊鷲山(りょうじゅせん)の百万の衆のまえにして、世尊は優曇華を手にして目を瞬きたもうた。その時、摩訶迦葉(かしょう)が顔をほころばせてほほえんだ。世尊は仰せられた。『われに正法眼蔵、涅槃妙心がある。それをいま摩訶迦葉に与える』と」
思うに、過去・現在・未来の三世の諸仏は、みなこの拈華によって出現するのである。これをもって仏に向かって修するものは、自己のさとりを実現するのであり、これをもって衆生に向かっては、その冥盲をやぶり、その心を開くのである。したがって、拈華のなかにあっては、上に向かおうが下に向かおうが、自己に向かおうが他人に向かおうが、あるいは、外に向かおうが内に向かおうが、いずれもすべて拈華ならざるはない。華も、仏も、心も、身も、すべてがおなじである。また、いくたび拈華が行なわれても、それがことごとく嗣法(じほう)であり、「これを汝に与える」のである。いま世尊が拈華して、なお手から華を放さないのに、もう華がきたって世尊の法を嗣いでいるといった具合である。つまり、拈華のことは、ある時にのみ行なわれるのではなく、あらゆる時に行なわれているのであって、そこにはいつでも世尊がおられ、おなじ拈華が行なわれているのである。
いわゆる拈華というのは、華が華を拈ずるのである。梅の華がそれであり、春の華がそれであり、雪の華がそれであり、蓮(はちす)の華がそれである。たとえば、梅華の五葉という。それは、仏一代の説法にほかならない。だから、それはまた、五千四十八巻の経巻であり、三乗十二分教の教えであり、あるいは三賢十聖(さんげんじっしょうのたどる道程である。だからして、まだ三賢十聖の階位にあるものでは、このことはよく判らないであろう。そこには、なお多くの経巻があり、おおくの不思議がある。そこのところの消息をこそ、「華開いて世界起る」とはいうのである。そこでは、「一華は五葉を開き、結果は自然にして成る」という。それは、喩(たと)えていうなれば、風鈴が虚空にかかって風のまにまにひねもす鳴っているようなものであろうか。あるいは、霊雲志勤(ごん)は桃花のさかりなるをみて目が見えなくなり、また、香厳智閑(きょうげんしかん)は翠竹(すいちく)にあたる石の音を聞いて耳がつぶれたというのも、いまの拈華である。あるいは、二祖慧可が雪に腰をうずめ臂を断って、ついに礼拝得随することを得たというのは、その華がみずからひらいたのであろうし、また、六祖慧能がただひたすらに米を碓(つ)いて、ついに夜半の伝衣(え)にいたったというのは、その華がおのれを拈じたものであろう。さすれば、それらもすべて、詮ずるところ、世尊の御手のなかの命であると申さねばなるまい。(252~253頁)
■いったい、拈華というのは、世尊の成(じょう)道よりも以前にあり、また世尊の成道と同時であり、さらに世尊の成道よりものちにある。だから、それは華の成道といってもよく、はるかに初・中・終などの時間のことを超越している。つまり、もろもろの仏もろもろの祖たちが、発心して仏道を歩きはじめ、修行し、証得してそれを保持する、それらはすべて拈華が春風をひるがえすに外ならないのである。だから、そのときゴーダマ世尊は、華のなかに身を蔵(かく)し、虚空のかなたに身を蔵しているのであるから、その鼻のあたまを捉えてみるがよい。すると、それはただ虚空を捉えているにすぎないであろうが、それこそまさしく拈華というものである。けだし、拈華とは、眼睛(ぜい)をもって拈ずるものであり、心識をもって拈ずるものであり、あるいは、鼻のあたまを拈ずるのであり、あるいは、華が華を拈ずるのである。(253~254頁)
■いったい、この山(せん)河大地、日月風雨より、人畜草木にいたるまで、みないろいろの営みをなしているが、そのそれぞれの営みが、とりもなおさず優曇華を拈ずるのである。生といい死というも、その華のいろであり、その華のひかりである。いま、わたしどもがこのようにまなびいたるのも、またその華を拈じているのである。
仏は仰せられた。
「たとえば、それは優曇華のようなものであって、一切の人々がみな愛楽(あいぎょう)する」
ここに「一切の人々」というは、すでに仏祖となれる人々のことであり、また、その可能性を蔵する人々のことである。さらには、草木昆虫にいたるまで「おのずから光明のあるあり」である。また、「みな愛楽する」とは、それらの面々が、いまもなお活撥々地(かっぱつぱっち)として生きていることであり、したがって、一切はみな優曇華にほかならない。だからして、これをすなわち稀(まれ)なりというのである。(254~255頁)
〈注解〉渾身是巳掛渾身;「渾身これすでに渾身にかかる」とでも読むべきであろうか。古注によれば、「如浄和尚語録」のなかに、「風鈴」と題する偈があり、その一句に「渾身是口掛虚空」とある。道元はそれによってこの一句をものしたのであろうといい、そのいうところは因果同時のことであろうという。わたしもその説をとる。(255頁)
■目を瞬(まばた)くというは、樹下にうち坐って、その眼睛(ぜい)を明星ととりかえてしまった時のことである。すると、そのとき摩訶迦葉が、顔をほころばせてにこっと笑った。その顔をほころばせた途端に、その顔は拈華の顔になってしまったのである。如来が瞬目した途端に、われらの眼睛は失われてしまったのである。その如来の瞬目こそ、とりもなおさず拈華である。その時、優曇華のこころがおのずからひらくのである。そして、まさしくその時におよんでは、世尊も、迦葉も、生きとし生けるものも、そしてわれらも、みなともどもに一本の手をさしのべて、おなじように華を拈ずる。そのことは、今日ただいまもなお休むことがないのである。さらにいうなれば、手のなかに身を蔵(かく)すということもあるのであるから、この身心(じん)ががそれであるということもできる。(257頁)
■また、祖師菩提達磨が西の方より来られたこと、それもまた拈華したのである。拈華はこれまた精魂を弄(ろう)するという。精魂を弄するととは、ただひたすらにうち坐って、身心を脱落することである。仏となり祖となることを弄精魂とはいう。衣を着け飯を喫することをも弄精魂というのである。いや、おおよそ仏祖がぎりぎりの定めとしてさだめたことは、かならず弄精魂である。あるいは仏殿において相見(しょうけん)し、あるいは僧堂においてまた見(まみ)える。そのたびに、華の色はいよいよ加わり、その色にはまた光がましてくる。さらに僧堂にあっては、彼方から雲板を拍(たた)く音が聞こえてき、仏殿にあっては笙(しょう)を吹く音(ね)が水底から聞こえてくる。かと思うと、おおなんとしたことか、思わぬ梅華の調(しら)べも聞こえてくる。と申すのは、かつて先師如浄古仏は歌って仰せられたことがある。
「じっと世尊が眼睛(ひとみ)つぶれば
雪の中にただ一枝の梅華ひらく
いまは到るところ茨(いばら)ばかりだが
やがて春風は繚乱として吹かん」
いま、如来の眼睛は、あやまって梅華となってしまった。その梅華もいまはただ生いしげる荊棘(けいきょく)のなかにある。如来は眼睛のなかにその身を蔵(かく)し、眼睛は梅華のなかに身をひそめ、その梅華もまたただ荊棘のなかにある。だが、やがては繚乱として春風を吹かせる。ともあれ、こんな具合であるが、やはり梅華の調べは楽しく快い。
先師如浄古仏は、また、かって仰せられたことがある。
「霊雲の見るところは桃華にらき
天童の見るところは桃華おちる」
知るがよい。桃華のひらくは霊雲志勤(れいうんしごん)の見処(けんじょ)である。それはずっといまにいたるまで、さらに疑いの余地もない。しかるに、天童如浄の見処は華桃おつるところであるという。思うに、華桃のひらくは春の風にもよおされてであり、桃華のおつるは春の風に憎まれてであろう。だが、たとい春風の華桃をにくむこと深くとも、桃華はやがて散りおちて、その身心を新たにするであろう。(259~251頁)
発 無 上 心(ほつむじょうしん)
■開 題
「おほよそ発菩提心の因縁、ほかより拈来せず、菩提心を拈来して、発心するなり。菩提心を拈来するといふは、一茎草(いつきんそう)を拈じて造仏し、無根樹を拈じて造経するねり。いさごをもて供仏し、漿(こんず)をもて供仏するなり。一摶(いったん)の食(じき)を衆生にほどこし、五茎の華を如来にたてまつるなり。他のすすめによりて片善を修し、魔に嬈(にょう)せられて礼仏する、また発菩提心なり。……造仏造搭するなり、読経念仏するなり。為衆説法するなり、尋師訪道するなり、結跏趺坐(けっかふざ)するなり。一礼三宝するなり、一称南無仏するなり。かくのごとく、八万法蘊(うん)の因縁、かならず発心なり」
わたしは、この一節がことのほかに好きであって、時に及んで愛誦するのであるが、ここに到れば、もはや、在家の発菩提心がどうの、出家の発菩提心がどうのということは、まったく無用のことに属するであろうと思う。(266頁)
■西の国の高祖はいった。
「雪山(せつさん)をもって大涅槃に喩(たと)える」
知るがよい、それは喩うべきものを喩えたというべきである。喩うべきものはというは、近しいからであり、ずばりと判るからである。ここに雪山すなわちヒマーラヤをもってきたのは、雪山をもって喩えようとするのであり、また、大いなる涅槃をもってきたのは、それに喩えようとするのである。
また、中国の初祖はいった。
「心は木石のごとし」
ここにいう心とは、心のあるがままの姿である。大地いっぱいの心である。だから、自己の心でもあり、他心の心でもある。いや、この世界じゅうの人、あるいは、あらゆる世界の仏祖や、天なる龍などをもふくめて、それらの心はみな木石にほかならないという。そのほかには、別に心などというものはないというのである。その木石は、当然ながら、有とか、無とか、空とか、色とかのありように捉われない。その木石なる心をもって、人は発心し、修行し、まら証得する。心はもともと木石だからである。その木石なる心のちからをもって、いまのこの不思量のところを思量することも成るのである。そして、その木なる心、石なる心の姿や声を見聞することによって、われらははじめて外道のともがらを超えることができる。それより以前は、けっして仏道などというものではないのである。
大証国師はいった。
「牆壁瓦礫(がりゃく)、これが古仏心である」
そのいう牆壁瓦礫とは、いったい、いずれのところにあるのかと、よくよく考えてみるがよろしい。あるいは、いったい、そんなものがどうして出来たのだと、問うてみるがよろしい。また、古仏心というのは、なにも遠い遠いむかしのことをいうのではない。いまここに普通に生活している人々のいまの境界をいっておるにすぎない。そのような人々が、ふと坐りはじめて仏となる、それが発心というものである。(268~269頁)
〈注解〉※道元はまず、仏祖の三つのことばを挙げ、それを解説することによって、心のなんたるかを語ろうとしている。発無上心、もしくは、発菩提心のことに語りいたろうとする準備であるといってよかろう。
雪山喩大涅槃;雪山はヒマーラヤ、それをもって大涅槃にたとえるのは、その不動なる姿によるものであろうか。
心如;心の真相、本質を指さしているのである。それは、そのあるがままの姿にほかならない。(260頁)
■いったい、菩提心を発(おこ)し因縁は、外からもってくるものではない。それは、ただ菩提心をもって発心(ほっしん)するものである。菩提心をもたらすというのは、一茎の草をとって仏となし、根のない樹をもたらして経となすのである。あるいは、妙をもって仏に供し、米の汁をささげて仏を供養するのである。あるいはまた、一握りの食を衆生にほどこし、五茎の花を如来にたてまつるのもそれである。さらにいえば、他(ひと)にすすめられてほんの小さな善をなし、悪魔にだまされて仏を礼拝するのも、また菩提心を発(おこ)すというものである。むろん、そのようなことのみではない。家を家にあらずと知って、家を捨てて出家するのもそれである。山に入って道を修め、信じて行じ、あるいは、法を行ずるのもそれである。仏像をつくり、寺搭をつくるのもそれである。経を読み、仏を念ずるのもそれである。人々のために法を説くのもそれであり、師を尋ねて道を訪うのもそれである。結跏趺坐するのもそれであり、一たび三宝を礼拝するのもそれであり、一たび南無仏と称するのもまたそれである。
そのように、いろいろの事がすべて、かならず発心の因縁となる。あるいは、夢のなかにして発心したものが道を得ることもある。あるいは、酔のなかに発心したものが得道するということもある。あるいは、飛花落葉のなかにあって発心し得道するというものがあり、あるいは、桃花を見、翠竹の声をきいて、発心し得道するというものもある。あるいは、天上にあって発心し得道するというものもあれば、あるいは、海中にあって発心し得道するというものもある。それらはみな、あるいは、おのれの発菩提心のなかにあってさらに菩提心を発(おこ)すのであり、あるいは、おのれの身心(じん)のなかにあって菩提心を発すのであり、あるいは、諸仏の身心のなかにあって菩提心を発すののであり、あるいはまた、諸仏の皮肉骨髄のなかにあって発菩提心するのである。
だからして、今日にして塔を造り、仏像を造るなどすることも、まさしく発菩提心であって、まっすぐに成仏にいたることを得るのであり、けっして中間において挫折することはないであろう。これを自然の功徳といい、法爾(に)の功徳という。あるいは、これを真理と見ることとなし、法の本質を知ることとなす。あるいは、これを諸仏の三昧を集むることとなし、諸仏の守護を得ることとなす。あるいはまた、これを無上の正覚を得ることとなし、聖者の境界にいたることとなし、仏を成就することとなす。このほかには、別にまた自然・法爾などということはあり得ないのである。(271~273頁)
■しかるに、小乗の愚かなるものはいう。――像を造り、塔を起こすなどということは、為にする煩悩のわざである。そんなことは捨ておいて営んではならない。思慮することを息(や)め、じっと心を凝(こ)らす、それが自然というものである。煩悩をはなれ、なんの為にするところもない、それが真実というものである。あるいは、万法のあるがままの姿をじっと観ずる、それが無為というものである。――こんな具合にいうのが、西の方でも、東の方でも、昔も今もならいとするところである。だからして、あるいは重き罪をおかし、あるいは逆賊をつくりながらも、仏像を造らず、寺塔も起こさない。あるいは煩悩・邪見にそまりながらも、念仏を申し読経することもない。これでは、ただに人間としてのよき種を台なしにしてしまうばかりではなく、また、仏たるべき可能性をも壊してしまうことになるのであろう。そんなことでは、仏法の時世にあいながら、いつしか、仏法の怨敵となってしまうであろう。あるいは、三宝の山に入りながら、なんにも得ないで帰り、あるいはまた、三宝の海に入りながら、なんの獲物をも得ないで帰るようなものであって、こんな悲しいことはないではないか。これでは、たとい千の仏、万の祖の出世にあおうとも、とても仏道に縁をむすぶ時期はなく、発心の機会にあうこともないであろう。それは、いったい、なに故であるかというと、やっぱり、それは、経巻の記すところにしたがわず、善知識のことばに耳を傾けないから、こういうことになるのである。あるいは、それはたいてい、外道や邪見の師にしたがうからのように思われる。造像造塔などは発菩提心とはいえないなどという見解は、はやく投げ捨てるがよろしい。そして、心を洗い、身を洗い、耳を洗い、目を洗うて、そのような見解はふたたび見聞しないがよろしい。ただ、仏の経巻にしたがい、善知識にしたごうて、まさしく正法に帰し、仏法を修学するがよいのである。(275~276頁)
●原 文
仏法の大道は、一塵のなかに大千の経巻あり、一塵のなかに無量の諸仏まします。一草一木ともに身心なり。万法不生(しょう)なれば一心も不生なり、諸方実相なれば一塵実相なり。しかあれば、一心は諸法なり、諸法は一心なり全身なり。(276頁)
■そもそも、仏法の大道においては、塵ほどの物のなかにも幾千の経巻があり、また、極微(ごくみ)の物のうちにも限りなき仏たちがまします。あるいは、一つの草、一本の木もまたそれぞれにその身心(じん)を有する。しかるに、万法すなわちあらゆる存在はもともと生滅を超えたものであるから、その一心もまた生滅を超えたものである。また、もろもろの存在はあるがままの姿のほかのなにものでもないのであるから、いまいうところの極微のものもまたそのあるがままの姿のほかのなにものでもないのであるから、いまいうところの極微のものもまたそのあるがままの姿のほかのなにものでもない。だからして、つまるところ、一心はもろもろの存在にほかならず、また、もろもろの存在は一心に異ならず、全身に異なるところはない。
しかるところ、造塔などのことが、もし人の計らいにいでる純粋でないものならば、仏の悟りや、仏教の真理や、人間の仏たる可能性などもまた、不純な、人間の計らいにいずるものであろう。だが、仏教の真理や、人間の仏たる可能性は、けっしてそのような純粋ならぬものではない。だから、造像起塔などのこともまた、当然そのような不純なものではない。まったく、自然なる菩提心の発露である。自然にして煩悩にゆがめられることのない功徳である。されば、造仏起塔等のことは、ただまさしく菩提心の発露であると、ぴたりと決定(けつじょう)して信ずるがよいのである。永劫にわたる身行も心願もそこから芽ばえてくるのであり、その発心はもはやいつまでもいつまでも覆(くつがえ)すことはできない。それが仏にまみえ、法を聞くということである。
かくて、知るがよろしい。あるいは木石をあつめ、あるいは泥土をかさね、あるいは金銀や七宝をあつめて、仏像を造り、堂塔を起す。それは、とりもなおさず、一心をあつめて堂塔を起こし、仏像を造るのである。だからして、経のことばにもいう。
「この思いをなす時は、十方の仏たちはみなその姿を現じたもう」
そのいうところは、一たび仏たらんと思う時には、十方の思惟(しゆい)仏はみなその姿を現じたもうというのであり、また、なんぞ一事を仏たらんとしていとなむ時には、よろずのことがことごとく作仏のいとなみとなるというのである。そのように知るがよいのである。(277~289頁)
〈注解〉作是思惟時、十方仏皆現;「この思惟をなす時、十方の仏はみな現ず」と読まれる。『法華経』方便品にみえる句である。(279頁)
●原 文
「明星出現(ノ)時、我(ト)与大地有情、同時成道」
しかあれば、発心・修行・菩提・涅槃は、同時の発心・修行・菩提・涅槃なるべし。仏道の身心(じん)は草木瓦礫(りゃく)なり、風雨水火なり。これをめぐらして仏道ならしむる、すなはち発心なり。虚空を撮得(さつとく)して造塔造仏すべし、谿水を掬搯(テヘンをトル、さくよう)して造仏造塔すべし。これ発阿耨(のく)多羅三藐(みゃく)三菩提なり、一発菩提心を百千万発するなり。修証もまたかくのごとし。(280頁)
■「かの明星が出現した時に、わたしと大地や生きとし生けるものは、みな同時に成道した」
だからして、発心することも、修行することも、正覚(がく)を成ずることも、あるいはまた涅槃に入ることも、すべてみな同時なのであろう。いったい、仏道の身心たるものは、草木であり、瓦礫(れき)であり、あるいは水や火である。それを回向しきたって仏道となすのである。それがとりもなおさず発心なのである。されば、虚空を拈じきたって造仏起塔するがよく、谿(たに)の水を掬(く)みとって造塔するがよろしい。それがすなわち無上心を発(おこ)すということである。そして、一たびその心を発したならば、さらに百たびも千たびも万たびも発すがよい。修や証についてもまたおなじである。
それなのに、発心は一たび発(おこ)せばもはや発すことなく、修行は限りないものであるが、その成果はただ一度のさとりのみであると、そのように聞くのは、仏法を聞くというものではなく、仏法をしるというものでもなく、また、仏法に遇うというものでもないのである。思うに、千たび億たびの発心も、もとはといえば、かならず、一たびの発心のおこすところであり、また、千人億人の発心も、また一人の発心の発すところである。したがって、これを翻(ひるがえ)していえば、一人一回の発心が千億の発心となるのである。修行だの、証果だの、あるいは法を転ずるについても、またおなじ道理であろう。もし、かの草木などが草木でなかったならば、どうしてこの身心があろう。もし、また、この身心が身心でなかったならば、どうしてかの草木があろう。けだし、草木は草木であるからこそ草木である、それでこんなことをいうのである。(281~282頁)
■「華厳経」にいわく、
「菩薩が生死のなかにありて、はじめて発心する時には
ひたむきに悟りを求めて、その心かたくして動かすべからず
その一念の功徳は、深くかつ広くしてはてしもあらず
如来のことわけての説明も、窮劫(ぐうこう)に説きつくすこと能わず」
はっきりと知っておくがよろしい。生死のことをとりあげて発心するのが、それがただひたむきに悟りを求めるこことなるのである。その時、その一念は、一本の草、一本の木とおなじものになっているはずである。けだし、いまやわれも彼もただ一生一死のものとなっているからである。
だがしかし、その功徳の深きことも、また広きことも、まったくはてしないものであるという。如来はそれを「窮劫(ぐうこう)」などということばをもって説明しているけれども、とてもその期を尽くすことはできるものではない。海は涸(か)れてもまだ底があり、人は死んでもなお心はのこるのであって、とてもいい尽くすことはできない。そして、かの一念の深さ広さの果てしないように、一草、一木も、あるいは、一石も、一瓦、また果てしないものである。もし一草、一石がそうであるならば、かの一念もまたそうであろうし、またかの発心もまたしかるはずである。
とするならば、深山に入りて仏の道を思惟(ゆい)することは容易であり、塔をつくり仏の像をつくることははなはだ難いであろう。それらはともに、精進にして怠ることなきによりて成就することではあるが、その一つは、心を能動的にはたらかせて得ることであり、いま一つは、心がゆり動かされて成就することであって、それとこれとでは、はるかに相異なるのである。そして、このような発菩提心がつもりつもって仏祖が実現するのである。(291~292頁)
〈注解〉窮劫;きわまれる劫ということば。それによって時の最大値をいうのである。「窮劫を言語として」とはこの窮劫ということばを言語表現として、というほどの意である。(292頁)
発 菩 提 心 ( ほつぼだいしん)
■開 題
すでにさきにもいったように、この「発菩提心」の巻は、まえの「発無上心」の巻と、いろいろの関係をもった巻である。まず第一に、この巻は、いずれも、寛元二年(1244)二月十四日、越前吉田吉峰(よしみね)精舎において衆に示されたものとある。それぞれの巻の奥付にいうところである。つまり、おなじ日に、おなじ場処で開示されたものなのである。そのうえ、さらに第二には、この二つの巻は、いずれもおなじような題目を揚げておるのである。すでに、さきにも指摘したことであるが、さきの巻の巻題は、見られるとおり「発無上心」であるが、そのいう意味は、まったく「発菩提心」にほかならない。現に、その内容には、発菩提心のおもむきのみが説かれていて、無上心などというようなことばは一度だって出てこないのである。
そこで、当然おこってくる疑問は、では、その聴衆はどうであったかということである。つまり、その日の二回の示衆(じしゅ)における聴衆は、いったい、おなじ人々であったであろうか、それとも別の人々であったろうかということである。そのことにたいするわたしの所見はこうである。
それは、結論からさきに申すなれば、この二回の示衆は、おそらく、それぞれ別の人々を対象としてなされたものであるということである。そして、その一回、つまり「発無上心」と題するところの示衆は、在家の人々を対象として発菩提心を説いたのであり、もう一回の示衆、つまり「発菩提心」と題するところのそれは、あきらかに出家の人々を対象として、おなじく発菩提心のことを説いたものと、そのように受領せられるのである。
わたしは、この度、はじめて、この2巻をつづけて精読したのであるが、それでやっと気がついたことは、この2巻の引用や叙述には、まったく重複するところがないのである。けっして、書き直したようなものではなく、まったく別の制作である。いや、別の種の人々を対象とした新しい制作なのである。つまり、一つは在家の人々、とくに工事のため集まった人々を対象として説いたものであり、もう一つは在家の人々を対象として語っている。気をつけて読んでみると、そのおもむきが、その叙述のなかにもあきらかに汲みとれるのである。
なによりも、まず、その全巻にみなぎる雰囲気が、これとそれとでは、まったく違っているのである。「発無上心」の全巻にみなぎっているものは、なによりもまず、発菩提心のすばらしさを称(たた)え、すみやかに発心すべきことのすすめであるといってよろしい。それに対して、「発菩提心」の巻のいうところは、むしろ、発菩提心の退転を警告し、いかにしてその退廃をまもるべきかというところに重点があり、最後に悪魔なるものについて語った『大智度論』からのながながとした引用があるのが印象的である。
もっと具体的なことをもって、その証(あか)しをあげようとするならば、さきの「発無上心」の巻には、すでに指摘したことであるが、特に「造仏造塔」のことが取り上げられて、それが発菩提心の因縁として強調せられている。それは、当然のこと、新寺建立(こんりゅう)のことに尽瘁(じんすい)している工事の関係者たちのことを思い出させる。それに反して、のちの「発菩提心」の巻には、「行者」とか「初心の菩薩」とかいったことばが散見せられることが、わたしにはまた印象的であった。道元がこの山中に入ってから、まだ半年あまりに過ぎない。それにもかかわらず、その門下に投じた「初心の菩薩」は、かならずしも少なくなかったように思われる。特に、それらの出家の人々をまえにし、汝の発心をよく守護するがよい。しからずんば菩提心は退転しやすいものなのだと警告する。それは僧家をまえにしての示衆であったにちがいないと思われるのである。(296~298頁)
■経にいう。
「つねに自らこの念をなす、なにをもってか衆生をして、
無上道に入りてすみやかに、仏身を成就することを得しめんと」
これがとりもなおさず如来のいのちとするところである。仏というものは、その発心より、修行、そして悟りの境地にいたっても、いつもそのようなのである。
つまり、衆生を利益するということは、衆生をして「自らいまだ度することを得ずして、まず他を度せん」とする心をおこしたからとて、その力によって自分が仏となろうと思ってはならない。たとい、それによって、仏になるほどの功徳が十分に熟したからといっても、なおそれを他に回向(えこう)して、衆生の成仏もしくは得道に資するのでなくてはならない。(308頁)
■とするならば、いま「一切の衆生たちが、これは「わがもの」と執着している草木瓦礫(りゃく)、金銀財宝などを手放して、それを菩提心のために施しする、それもまた発菩提心でなかろうはずがあろうか。いったい、心といい物というものは、自でもなく、他でもなく、あるいは共性(ぐしょう)のものでも、無因性のものでもないのであるから、それによって、もし一刹那でも菩提心をおこすならば、それによってすべての物はそれをいやます機縁となるであろう。そもそも、発心といい、得道というも、すべてはみな刹那刹那に生じてはまた滅するものなのである。もしそうでなかったならば、前の刹那の悪はなくなるわけにゆかない。前の刹那の悪がまだなくならなかったならば、後の刹那の善がいま生ずることもできない。この刹那というものがどんなものかは、ただ如来のみひとりとく知っておられる。「一刹那の心、よく一語を起こす。一刹那の語、とく一字を説く」というが、それもまた、ひとり如来のみの知るところで、余の聖者たちの知り得るところではない。
いったい、屈強の男子がひとたび指をはじくあいだに、六十五の刹那があって、その刹那刹那にも、われらを構成する物質と精神の諸要素はたえず生滅を繰り返しているが、凡夫はそれをまったく知らず、気がつかないでいる。ただ、その刹那がつもりつもって、恆河(ごうが)の砂ほどになって、やっと気がつくのである。一日一夜のあいだには、六十四億九千九百八十の刹那があって、その刹那刹那にわれらの身心の諸要素も変わってゆく。だが、凡夫はまったくそれを知らない。知らない、気がつかないからして、菩提心をおこさないのである。つまり、仏法を知らず、仏法を信じないものは、この刹那生滅の道理を信じないのである。もし如来の正法眼蔵をあきらめ、涅槃妙心を得るというほどのものは、かならずこの刹那生滅の道理を信じているのである。(309~310頁)
■ただ、もし如来の救法の力によるならば、衆生もまたよく三千世界をみることができる。そのおおよそをいえば、いまの生の存在から、生より生にいたる中間があり、そして来世の生としての存在にいたる。その間もまた刹那刹那にうつりゆくのである。それも、わが心によってではなく、業(ごう)にひかれて生死を繰り返すのであるが、かくして一刹那もとどまることがないのである。そのように生死流転するこの身心をもって、すみやかに「自らいまだ度せずして、まず他を度せん」との菩提心をおこすがよいというのである。たとい発心せずして、ひたすらこの身心を惜しんだところが、生老病死はついにまぬがれることを得ず、この身心はついにわが有(もの)となることはできないであろう。(311頁)
■ところで、菩薩がなお初心のころ、菩提心を失うというのは、たいていは、正師にあわないからであるらしい。正師にあわなければ、正法を聞くことができない。正法を聞くことができなければ、おそらくは、因果がわからなくなり、解脱がわからなくなり、三宝(ぽう)がわからなくなり、また、過去・現在・未来などのもろもろの存在もわからなくなってしまう。そして、ただいたずらに現在の五欲にばかり執著(しゅうじゃく)して、やがて得べき悟りの功徳をとり遁してしまうのである。
あるいはまた、悪魔の王などが、行者を妨げようとして、あるいは仏の姿に身を変じ、あるいは父母・師匠・乃至は親族や天の神々などの形を現じて近づいてきて、菩薩にむかって偽りすすめていう、――仏道はながくかつ遠い、ながいながい間いろいろの苦を受けねばならない。こんな辛(つら)いものはない。そんなことよりも、まず自分がはやく生死を解脱して、それからのちに衆生を救うがよろしい。――行者のなかには、そのようなことばを聞いて、それで菩提心をしぼませ、菩薩の行業をやめるものもあろう。だが、そこをはっきり知らねばならない。そんなことをいうのは、とりもなおさず悪魔のことばである。菩薩たるものは、それを見抜いて、従うようなことがあってはならない。もっぱら、「自らいまだ度することをえずして、まず他を度せん」との願いをたてて退いてはならない。この願いに反するようなものは、総て悪魔のことばであると知るがよく、あるいは外道の説だと知るがよく、あるいはまた、悪友のいうことだと知るがよろしい。けっして従ってはならない。(322~323頁)
〈注解〉常楽我淨;常とは、変わらず移ろわざること、楽とは身の病気と心の憂えのないこと、我とは、大自在なることを得たること、そして、淨とは、三惑つきて清らかなること。この四つを涅槃の四徳という。(323頁)
■(『大智度論論』にいわく、)ー略ー 魔とはもと天竺のことばである。中国では能奪命(のうだつみょう)と訳する。死魔はまさしく命を奪うに似たることをなす。たとえば智慧の命を奪うがごときである。この故にまた殺者(せっしゃ)という。
問うていわく、
『すでに五衆の魔のなかに、他の三種の魔をふくんでいる。それなのに、なにすれば別に四つの魔を説くのであろうか』
答えていわく、
『まことは、ただ一つの魔であるが、なおその意義をいろいろと分析するからして、四つの種類を立てるのである』」
以上いうところは、かの龍樹祖師の仰せである。この道の行者たるものは、かく知ってよく勤めまなぶがよろしい。いたずらに悪魔のたぶらかしを蒙(こうむ)って、菩提心を退転せしめてはならない。それが菩提心を守護するということなのである。(326頁)
如 来 全 身(にょらいぜんしん)
■開 題
ー略ー。 かくて、この一巻もまた、きわめて短い一巻であり、かつ、その内容もきわめて簡明である。いや、けっして平凡な俗言ではないけれども、その構成は単純にして、かつ明快であり、けっして複雑多岐にわたるこのではない。
わたしは、その現代語訳において、この巻の前半の小見出しとして、
「経巻は如来の全身なり」
と記しておいたが、わたしは、この一巻の趣は、結局それだといってよかろうと思っている。いや、この巻の原文をもって、もっと敷衍(ふえん)されたところをあげてみるとこうである。
「しかあれば、経巻は如来全身なり。経巻を礼拝するは、如来を礼拝したてまつるなり。経巻にあひたてまつるは、如来にまみえたてまつるなり。経巻は如来舎利(しゃり)なり」
まことに明快である。わたしはもう、それ以上のことは、なんの付け加えるものももたない。(330~331頁)
■その時、釈迦牟尼仏は、王舎城外の耆闍崛山(ぎじゃくくつせん)に住したまい、薬王菩薩に告げて仰せられた。
「薬王よ、どこであろうと、もしくは説きもしくは読み、もしくは誦(じゅ)しもしくは書き、もしくはまた経巻の存するところには、みなまさに七宝の塔を起て、できるかぎり大きく厳(いか)めしく造り営むがよく、別にまた舎利を安置しなくてもよい。その故はなんであろうか。それはそのなかにすでに如来の全身があるからである。この塔こそは、まさにあらゆる香華や瓔珞(ようらく)や幢幡(どうばん)、あるいは、伎楽や歌頌(かじゅ)をもって供養し、恭敬(くぎょう)し、尊重し、讃歎するがよろしいもし人ありて、この塔を見ることを得て、礼拝し供養するならば、まさに知るがよい。それはもう無上最高の智慧に近づいているのである」
いまいうところの経巻とは、あるいは説きあるいは読み、あるいは誦しあるいは書するところのものである。だが、この経巻のほかになんぞ実相なるものが存するわけではない。また、まさに七宝の塔を起てるがよいというが、その規準は現実の大きさである。また、その中にすでに如来の全身があるというのは、つまり、経巻が如来の全身だということである。だからして、たといそれを説こうが読もうが、誦しようが書こうが、いつでもそれは如来の全身である。さればこそ、あらゆる香華や瓔珞(ようらく)や繒蓋や幢幡(どうばん)や伎楽や歌頌(かじゅ)をもって、供養し、恭敬(くぎょう)し、尊重し、讃歎するがよろしいという。それらのなかには、天華があり、天香があり、あるいは天蓋もあろう。だが、それらはみんな現実のものである。あるいは、そのなかにはまた、人間世界のすぐれた香や花もあり、あるいは衣服もあるであろう。それらも、もちろん、みんなあるがままのものである。あるいはまた、さらに供養といい、恭敬(くぎょう)という。それも見らるるとおりのものである。しかるを、まさに塔を起すがよいといい、また、別に舎利を安置しなくてもよいという。それでこそ、経巻がとりもなおさず如来の舎利であり、如来の全身であるということが、よく判るではないか。(333~334頁)
■だからして、経巻は如来の全身である。経巻を礼拝することは、如来を礼拝したてまつることである。経巻に出会うということは、如来に見(まみ)えたてまつることである。つまり、経巻は如来の舎利であって、そのゆえに、舎利というはこの経ということなのである。また、たとい経巻とはとりもなおさず舎利であると知っていても、舎利とはつまり経巻のことと知らなかったならば、それはまだ本当の仏道というものではないのである。
かくて、思えば、いまのもろもろの存在のあるがままの姿は経巻である。人間世界のもの、天上のもの、海中や虚空のもの、あるいはこの土やかの土のものも、みんなそのままに実相であり、経巻であり、かつ舎利である。だから、舎利を受持し、読誦し、解説し、あるいは書写して悟りをひらくがよろしい。さすれば、それがそのまま「あるいは経巻に従いて」ということである。さらにいえば、古仏の舎利というがあり、古仏のしゃりというもある。あるいは辟支仏(びゃくしぶつ)の舎利があり、転輪王の舎利があり、獅子の舎利がある。あるいはまた、木仏の舎利があり、絵仏の舎利があり、また人(にん)の舎利がある。現在の大宋国にも、代々の仏祖たちが、生きておられたころ舎利を生み出したものがあり、また、荼毘(だび)ののちに舎利を生じたものもすくなくないが、それらはすべて経巻なのである。
■釈迦牟尼仏は多くの人々に告げて仰せられた。
「わたしは、前生(ぜんしょう)において菩薩の道を行じたが、その時に得た寿命は、いま今生(こんじょう)においてもなお尽きない。さらに後生(ごしょう)みおいては、またそれに倍することとなろう」
いま釈迦牟尼仏が、今生において遺されたたくさんの舎利、それもまた仏の寿命にほかならぬと仰せられるのである。そして、その過去世において菩薩道を行じたもうたのは、この世界においてのことのみではないのであるから、その間に成じたもうた寿命は、いったいいくばくになるのであろうか。そして、そのすべてが如来の全身である。また、そのすべてが経巻なのである。(338頁)
■また、智積(ちしゃく)菩薩はいった。
「わたしの見るところでは、数もしれぬ年月にわたって、難行苦行し、功徳を積んで、菩薩の道を行じたもうて、いまだかって休止されたこともない。だから、この全世界には、芥子粒ほどでも、菩薩が身を捨て命をおわられたところでないところはない。それもまた衆生のための故であって、そののちにやっと初めて悟りの道を成就することを得られたものである」
それでもよく判るではないか。この全世界もまた仏の慈悲の心のほんの一分でしかない。あるいは、虚空のほんの一部であいかない。だから、それは如来の全身にほかならないのである。そうなってくると、もはやここには如来の身を捨てたところ、ここは身を捨てないところといった問題ではなくなる。あるいは、仏となるまえとあととで、舎利がどうのこうのということもない。それはもう仏だ舎利だとならべていうべきところではない。さらにいうなれば、数かぎりもない年月にわたっての難行苦行ということも、詮ずるところは、仏の腹中のはからいのほかではなく、仏の皮肉骨髄にほかならない。また、すでにここまでにも、いまだかって休止されたことがないとある。このことは、仏になってからも休(や)む時はなく、いよいよ精進なさるということなのである。この全世界を教化したもうても、なお休止することはないのである。如来の全身の営みはかくのごとくなのである。(338~339頁)
〈注解〉智積菩薩;『法華経』にでてくる菩薩の名である。大通智勝仏の時に出家した十六王子の一人で、また、多宝如来の会下にあったという。
菩提堂;菩薩道が修行の道であるのに対して、菩提堂は悟りの道である。あるいは、前者を下化衆生の道であるとすれば、これは上求菩提の道なのである。
赤心一片;仏の慈悲心のほんの一分というところであろう。それに対して、つづいていう虚空一隻というのは、仏の虚空身すなわち虚空にあまねき仏身のほんの一部ということであろう。かくて、この世界のすべてが「如来の全身」というところなのである。(339~340頁)
三 昧 王 三 昧(さんまいおうざんまい)
■開 題
ー略ー。 さて、この巻の題目である「三昧王三昧」ねることばは、わたしどもがこの巻において初めて出遇うことばである。その出処(しゅっしょ)はといえば、それもこの巻において知ることができるように、かの龍樹の大著『大智度論』(巻七)であるらしい。そこには
「如此修習、証入三昧王三昧」(このごとく修習して、三昧王三昧に証入す)
とみえている。それが、道元が二度にわたって引用した『大智度論』からの引用文の末尾である。早速、「大正新脩大蔵経」によって、その部分を照合してみているうちに、さらにそれに続いて、つぎのような一節があることを見出して、わたしは狂喜した。
「是三昧王三昧中最第一、自在能縁無量諸法、如諸人中王第一、王中転輪聖王第一、一切天上天下仏第一。此三昧亦如是、於諸三昧中最第一」(この三昧は、もろもろの三昧中において最第一にして、自在によく無量の諸法を縁ず。もろもろの人中には王第一、王中には転輪聖(じょう)王第一、一切の天上天下には仏第一なるがごとく、この三昧もまたかくの如く、もろもろの三昧中において最第一なり)
いったい、この『大智度論』なるものは、かの龍樹が『摩訶般若波羅蜜経』を詳釈したものであって、しばしば仏教の百科事典のごとしとされるものであるが、いまここにおいては、結跏趺坐について、そのありようとその功徳を説いて、ついにこの「三昧王三昧」の句をなすにいたっているのである。道元はそれに注して、
「あきらかにしりぬ、結跏趺坐、これ三昧王三昧なり、これ証入なり」
と相応じている。道元が殊のほかにこの句を喜んだであろうことが、よく判るように思われる。その余のことは、みじかい一巻のことそて、あまり申すべきこともないようである。(342~343頁)
■まっしぐらに一切の世界を超越しきたって、仏祖の家においてもっとも尊かつ貴なるものは、結跏趺坐である。外道や悪魔のともがらの頭上をひらりと踏みこえて、ぴたりと仏祖の家の奥ふかきところにそのなかの人たらしめるものは、ただ結跏趺坐のみである。つまり、仏祖のぎりぎりのなかのぎりぎりのところを超えてゆくには、ただこのことを措(お)いて他に手だてはない。だから、仏祖たちはみなこれを営んで、また他に為すところはないのである。
まさに知るがよい。この坐の世界とその他の世界とは、まったく別の世界である。そこの道理をはっきりとつかんだうえで、仏祖たちの発心・修行・正覚(がく)・涅槃のことをまなぶがよろしい。では、いったい、ぴたりと坐った時、この世界はたてむきであるか、よこむきであるか。あるいは、その時、その坐はいったいどうなのか。それはとんぼ返りでもしているのか。それとも、ぴちぴち跳ねているのでもあろうか。あるいは、なにか考えているのか、それとも、なんにも考えていないのか。あるいは、なにごとかを作(な)しているのか、それとも、なんにも作(し)てはいないのか。あるいはまた、坐のなかに坐っているのか、身心(しんじん)のなかに坐っているのか、それとも、坐をも身心をもすべてを忘れて坐っているのか。そんな具合にいろいろさまざまに思いめぐらしてみるがよろしい。そして、身をもって結跏趺坐するがよく、心をもって結跏趺坐するがよく、さらに身心を忘れさって結跏趺坐するがよろしい。(344~345頁)
■かくて、釈迦牟尼仏は、大衆に告げて、「この故をもって結跏趺坐するのである」と仰せられた。それからまた、如来なる世尊は、もろもろの弟子たちに教えて、つぎのように仰せられた。
「なんじらはまさに、そのように坐するがよい。世の外道たちのなかには、あるいは、足をつまだてて道を求むるものがある。あるいは、いつも立ったままで道を求むるものがある。あるいは、足を肩のうえにあげて道を求めるものもある。そのような並みはずれたことでは、心はかならず邪悪の海に没するにきまっている。その身体が安らかでないからである。だから、わたしはみなに教えて、結跏趺坐するがよい、身を正しゅうして坐するがよいという。なんお故であろうか。
それは、身を正しゅうすれば心が正しゅうなりやすいからである。その身がぴたりと正坐すれば、心もまた懶(ものう)からず。心は端正にして意識もまたあきらかに、ぴたりとそこに集中されている。もしも心が散乱したり、あるいは、その身が動揺したりしても、またすぐそれを元のようにすることができる。三昧を具現したり、三昧の境地に入りたいと思うならば、いろいろと馳(は)せる思い散る心を、みなそこに摂(おさ)めてしまうがよい。よくそれを習い修むれば、三昧のなかの王三昧を実現することができるであろう」
かくて明らかに知ることができる。結跏趺坐はこれ三昧のなかの王三昧である。それによってその境地に入ることを得る。そして、その他の三昧はすべて、この王三昧の身内なのである。
その結跏趺坐は、身を正しゅうする。心を正しゅうする。身心を正しゅうするのである。かくて、そこには正しき仏祖があり、正しき修行と証得がある。さらにいえば、正しき頭脳があり、正しきいのちがある。つまり、いま、人間の皮・肉・骨・髄のことごとくをぴたりと結跏して、三昧のなかの王三昧を趺坐するのである。世尊もつねにこの結跏趺坐を保持なされて、もろもろの弟子たちにもそれを正伝なされた。また、世の人々にもそれを教えたもうた。いうところの七仏より正伝しきたったという心のありようとは、とりもなおさずこれにほかならないのである。(352~353頁)
■だからして、一生であろうと万生であろうと、ともあれ始めから終りまで、いささかも禅林をはなれることなく、昼夜ただひたむきに結跏趺坐して余事を顧みることなきもの、それが三昧のなかの王三昧というものである。(354頁)
〈注解〉三昧王三昧;ここにはじめて巻題のことばがでてくる。三昧のなかのもっとも大事な三昧というほどの意であって、『大智度論』の文にも、つづいて「是三昧於諸三昧中最第一……」(この三昧はもろもろの三昧のなかにおいて最第一……)とみえている。(354頁)
三 十 七 品 菩 提 分 法(さんじゅうしちぼんぼだいぶんぽう)
■開 題
ー略ー
仏教の行者として、正業すなわち正しき業(わざ)はなんであるか。それは、ずばりと、出家修道であり、山に入って悟りをひらくことである。出家の心と在家の心と、結局は異なるものでないなどとは、とんでもない魔子・畜生のいうことである。そこは、ぴたりと、
「いまだ出家せざるものの、仏法の正業を嗣続(しぞく)せることあらず、仏法の大道を正伝せることあらず」
と知らなければならない、という。(359頁)
■まず四念住(しねんじゅう)である。それはまた四念処(しねんじょ)ともいう。つぎのごとし。
一には、身の不浄なることを観察する。
二には、受(感受)はこれ苦なりと観察する。
三には、心は無常なりと観察する。
四には、存在はすべて我(が)なきものなることを観察する。(363頁)
■いったい、世尊には夜半に明星を見たもうて正覚(がく)を成じたという。その道理もまた身の不浄なるを観じたもうたにほかならない。それは淨か穢(え)かといったことではない。全身これ不浄なのであり、この身このままに不浄なのである。そのようにまなびいたってみると、悪魔が仏となる時には、悪魔の身をもって悪魔を降して仏になるのであり、仏が仏となるときには、仏の身をもって仏になろうとして仏になるのであり、また、人が仏となる時には、人の身をもって人を調(ととの)えて仏になるのだとわかってくる。まさしくそのままにしてというところに、大事な呼吸があることをよくよくまなびいたるがよろしい。(364頁)
〈注解〉一皮岱は尽十方界……;道元がしばしば引用する句に「生死去來、真実人体」(圜悟禅師のことば)とあり、あるいは「尽十方界、真実人体」(長沙禅師のことば)とある。一皮岱とは、この人間の皮をかぶった身をいうことばであるが、それがそのまま「尽十方界」であり、あるいは「真実体」であるというのは、そのような句を背景として語られているものと知られたい。なお、それについては、さきの「身心学道」の巻を参照されたい。(365頁)
■つぎには五根すなわち五つの能力である。つぎのごとし。
一には、信根(しんこん)すなわち信の能力である。
二には、精進根すなわち精進の能力である。
三には、念根すなわち念の能力である。
四には、定根(じょうこん)すなわち定の能力である。
五には、慧根(えこん)すなわち智慧の能力である。
まず、信根というのは、自己の能力でもなく、また他者の力でもないと知らねばならない。あるいは、自己が強いてなすところでもなく、自己が仕組んでなすわけでもなく、また、他者にひかれてなすのでもなく、自己のさだめなきさだめによるわけでもない。だからして、はじめて西天東地の仏祖たちがこの信根をこそ道の元、功徳の母としてぴたりと相伝しきたることを得たのである。思うに、全身がもはや信よりほかの何ものもないというにいたって、それを信と称するのである。だからして、信はいつでも仏の境界と相伴っているものであり、仏の境界にあらずしては信は実現しないのである。そのゆえにこそ、
「仏法の大海は、信を能入となす」
というのである。すべての信の実現するところは、かならず仏祖の実現するところなのである。
つぎに、精進根というのは、よくみずから省みきたって、ただひたすらに坐ることである。休(や)めようと思っても休めることができないのである。勤勉といえばたいへん勤勉なのであり、悠々としているといえば至極悠々たるものである。そして、勤勉といっても悠々と大してかわりはないのである。
かって、釈迦牟尼仏は仰せられた。
「わたしはつねに勤めて精進した。それでわたしはすでに最高無上の智慧を成就することを得た」
いうところの「つねに勤めて」とは、過去・現在・未来を通じて、いつもかわらず怠らなかったというのである。そして、わたしはつねに勤めて精進したから、それですでに無上にして最高の智慧を成ずることを得たという。それを翻(ひるがえ)していえば、わたしはすでに最高無上の智慧を成ずることを得たから、つねに勤めて精進するのだともいってよいはずである。もしそうでなかったならば、いったい、どうしてつねに勤めることができようか。また、そうでなかったならば、いったい、どうして智慧を成ずることを得たであろう。そういう意味は、論ばかりをひねくり、経ばかりを勉強ばかりを勉強している学僧たちでは、とても判ろうはずはない。ましてや、そんなことを師についてまなんだことのあろう道理はない。(388~389頁)
■つぎには、五力である。つぎのごとし。
一には、信の力である。
二には、精進の力である。
三には、念の力である。
四には、定(じょう)の力である。
五には、智慧の力である。
まず信の力というものは、自分じしんに騙(だま)されて、もう遁(に)げるところがないといったところであり、あるいは、仏祖に呼びかけられて、どうしても頭をむけずにはおれないといったところである。だからもう、生涯を通してもはやこれよりほかにはないのである。たとい、いくら転(ころ)んでもかまうことはない、なんど倒れてもやっぱりそれで行くのである。だからして、信は水晶の珠のごとしという。伝法といい伝衣というも信にほかならず、それによって仏を伝え、祖を伝えるのである。
つぎに、精進の力というのは、行のとどかぬところを説くことであり、また、説のおよばぬところを行ずることであるという。だからして、一寸を説きうる時には、一寸を説くに如(し)くはなく、また、一句を行じうる時には、一句を行ずるに如くはないのである。つとめてするうちに力を得る、それが精進の力というものである。
つぎに、念の力のことであるが、人の鼻かぶをとらえて引っ張ったのでは、ひどい奴だといわれるにきまっている。そこは、やはり、鼻がひっぱるのでなくてはならない。そうすれば、玉は玉をひくこととなり、瓦は瓦をひくこととなるのであろう。なに、まだそれを用いたことはないというのか、それは三十棒をくらうに値するわい。この念の力というものは、天下の人がみんな用いたって、いっこうに擦りへるような心配はないというものである。
また、定の力というものは、子がその母を得たるがごとくであり、あるいは、母がその子を得たるがごとくである。あるいはまた、子のその子を得たるがごとくであり、母のその母を得たるがごとくである。だがしかし、だからといって、頭をもって顔に換えるわけでもなく、また、金をもって金を買うわけでもない。ここはもう、唱えばいよいよ声高しというところであり、修すればいよいよ強しというところである。
最後に、智慧の力というものは、一朝一夕にして成るものではない。だが、これが成就すれば、船の渡しに遇うがごときものである。だから昔から、また渡しに船を得るがごとしという。そういう意味は渡しにはかならず船だというのである。この渡しにもかの渡しにも、船があってはじめて自由自在なることをうるのであって、智慧の光のあるところには、春の氷はおのずから消えてゆくのである。(394~396頁)
■つぎには、八正道である。それはまた八聖(しょう)道ともいう。
一には、正(しょう)見を実践することである。
二には、正思惟(しょうしゆい)を実践することである。。
三には、正(しょう)語を実践することである。。
四には、正業(しょうごう)を実践することである。。
五には、正命(しょうみょう)を実践することである。
六には、正精進を実践することである。
七には、正念を実践することである。
八には、正定(しょうじょう)を実践することである。
まず正見道支、すなわち、正見という実践の徳目であるが、それは、いうなれば、眼睛(ぜい)のなかに身を蔵(かく)すことである。だがしかし、そのためには、まず、この身が生まれるさきに遡(さかのぼ)って、この身よりさきに生まれた眼をもたねばならない。それは、いまだかって眼のまえに堂々として見えているものと別のものを見るわけではないが、それがいわゆる悟りの実現なのであり、遠いとおい昔から仏祖たちが親しく見てこられたものにほかならないのである。そして、その眼のなかにわが身を蔵(かく)したものでなくては、けっして仏祖とはいえないのである。
つぎには、正思唯道支、すなわち、正しい思惟の実践という徳目であるが、この思惟をなす時には、十方の仏たちがみな現れてくるという。だからして、これを翻(ひるがえ)していえば、十方が現じ、諸仏が現われてくる時は、とりもなおさず、まさしくこの思惟をなしている時なのである。だから、また、この思惟をいとなんでいる時、それは自己でも、他者でもないとしなければならない。だがしかし、いまやこの思惟を思惟し終わったその時には、その人はすぐ波羅奈(はらな)の郊外なる鹿野苑(ろくやおん)に赴いているのである。なんとなれば、この思惟のあるところは、それは鹿野苑であるからである。かって古仏は、仰せられたことがある。
「それは不思量のところを思量することである」
すると僧はまた、問うていった。
「その不思量のところを、どうしたら思量できましょうか」
師は仰せられた。
「それは非思量だよ」
これが正しい思量であり、正しい思惟というものである。坐して蒲団を坐りぬく。それが正しい思惟というものなのだ。
つぎには、正語道支、すなわち、正しい言語の実践という徳目である。そのありようをいわば、唖子は自分では唖子だとは思っていないというところであろうか。みんなのなかでの唖子はまだ一度だって物をいい得たことはない。だが、唖子の世界のなかではみんな唖子ではないのである。彼らは、べつに、もろもろの聖者を慕うこともなく、あるいは、おのれの霊性を重んずることもしない。ただ、ひたすらに、「口はこれ壁に掛けておく」ものなることをまなび究めるのである。一切の口を一切の壁にかけるのである。(404~406頁)
■そういうことであるので、曹谿古仏すなわち六祖慧能だって、たちまちにして親のもとを辞して師を尋ねたのである。それが正しい業である。まだかの『金剛(こんごう)経』を聞いて発(ほつ)心するにいたらなかったころには、樵夫(きこり)を生業として家にあった。だが、いまや『金剛経』を聞いて仏法の力の薫ずるところとなってからは、さらりと重き担(にな)いものを抛()ほうり出して出家したのである。それによっても判るとおり、ひとたびわが身心が仏法の薫ずるところとなってしまえば、もはや在家にとどまることはできないのである。そして、もろもろの仏祖もまたみなそうなのである。それを、出家してはならぬなどという奴は、逆罪をつくるよりもっと重い罪を犯すのであり、仏敵なり提婆達多(だいばだった)よりもさらに悪いやつだとしなければならない。あるいは、六群の比丘(びく)とか、六群の比丘尼(びくに)とか、もしくは十八群の比丘などといわれる連中よりも、もっと罪が重いということを知って、ともに相語らうことをやめるがよろしい。思えば一生の寿命などいくばくでもないものであって、そんな悪魔の子や畜生などと相語らっているような時間などありはしない。ましてや、この人間として受けた身心は、さきの世にも仏法を見聞した種子を蔵(かく)しているのであって、仏法に無縁のものではあるまい。これを悪魔のやからとなしてはなるまい。悪魔のやからに投じてはなるまい。むしろ、仏祖のふかき恩をわすれることなく、法の乳にとってはぐくまれたものをよく保護して、悪しき犬どもの叫び声を聞かしめないようにするがよい。ましていわんや、悪しき犬どもと坐をおなじゅうし、食をともにするなど、もってのほかのことである。(415~416頁)
■思うに、大師釈尊が、かたじけなくも父王の位をすてられて、これを嗣がせられなかったのは、けっして王位が貴(たっと)からぬからではなかった。それはただ、もっとも貴い仏の位を嗣がんがためであった。その仏の位とは、つまり、出家の位である。三界の天衆も人衆も、みなことごとくおし頂いて、崇敬してやむことなき位なのである。梵天王・帝釈天王といえども、坐をひとしゅうせざるところである。ましていわんや、この下界の人衆や龍衆の王たちの並ぶものであろうはずはない。それはまさしく無上の等正覚(がく)の位である。その位にあってこそ、はじめてよく法を説き、衆生を救済し、光を放ち、瑞相を現ずることができるのである。そして、出家の位にあって営むもろもろの業は、それこそその位にいたる正しき業なのであって、それはまた、七仏ならびに諸仏のつねに抱懐(ほうかい)してゆるがせにせざるところである。さらにいうなれば、それはまた、ただ仏と仏にあらざれば、究め尽くすことをえざるところである。されば、いまだ出家しないものたちは、すでに出家せるものに、よく見(まみ)えたてまつり、仕えたてまつり、頭を低うして敬礼(きょうらい)し、身命をもなげすてて供養したてまつるがよいのである。(416~417頁)
■つぎには、正念道支、すなわち正しい憶念の実践の徳目である。それは、いうなれば、自らだまされて、いつの間にか法に近づいているのである。正念がなってそこでそこから智が生じてくると、そのようにまなぶのは「父を捨てて逃げる」というものである。念が智であり、智が念なのである。またあるいは、念のなかで智がおこるのだとまなぶのも、やはり捉われた考え方である。だからといって、なんの念ずるところもない無念無想こそとりもなおさず正念だと思ってはならないし、あるいは、転倒した心や意識などを念といってはいけない。それは、まさしく、「汝はいまやわが皮肉骨髄を得たり」という時、それがとりもなおさず正念道支というものである。(434~435頁)
■最後に、正定道支、すなわち定の実践の徳目である。それは仏祖をも超越することであり、正定そのものを超越することである。よくそこに到った時、その人はすでによく自由になにごとをもなしうる器量があるのであって、たとえば、頭(ず)頂を切り裂いて鼻の孔をつくることでもできるであろう。思うに、世尊は正法眼蔵のなかにあって、優曇華(うどんげ)を拈じたもうた。優曇華のなかには百千の迦葉(かしょう)があって破顔し微(み)笑する。その話は久しく用いきたって、いまは破れ木杓にもひとしい。だからして、草枯れ葉落つること六年にして、葉開くこと一夜である。だが、劫火(ごうか)は洞然として燃えようと、大千世界はすべて崩壊しようと、すべてはなるように任せておけばよろしい。(435頁)
渓声余韻6(岡野注;増谷文雄氏のあとがき)
■それから、道元はさらに、足掛け三年かの地にとどまって、宝慶三年の冬、天童に告暇した。去るにのぞんで、如浄より芙蓉道楷の法衣などを授かり、また、
「国に帰らば化を布(し)き、広く人天を利せよ。城邑聚落に住するなかれ、国王大臣に近づくなかれ、ただ深山幽谷に居して、一箇半箇を接得し、わが宗を断絶に到さしむることなかれ云々」
との教誡を与えられて帰ってきた。国に着いたのは安貞二年(宋の紹定元年)の正月であったらしい。(442頁)
■いうまでもなく「教外別伝」とは、禅門のよってたつ根本の主張であるとされている。それを「謬説」として却ける道元の痛烈な言辞は、読む人をして唖然たらしめるのであるが、よくよく調べてみると、それは、かって道元が、如浄の方丈において問うてえた答えの花開けるものと知られる。その時、如浄は「仏祖の大道、なんぞ教内教外にかかはらんや。……世界に二種の仏法あるべからず」と道元に教えたという。(443頁)
■だが、あたかもよし、仁治二年(1241)二月中旬には、かってかの国にありしころの兄弟弟子の瑞巌義遠(ずいがんぎおん)が『天童山景徳寺如浄禅師読語録』を送ってくれた。また、その翌仁治三年(1242)八月五日には『如浄和尚語録』二巻も到来した。道元がそれらを貪るようにして読んだであろうことは、そのころ制作された『正法眼蔵』の巻々を披見しただけでもよく判る。十五年まえの師のことば、この時にいたって道元の心中にあって開花し結実したとしても、なんの不思議もないではないか。(444頁)
(2016年8月1日)