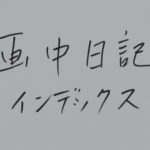『正法眼蔵(3)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
行仏 威儀(ぎょうぶついぎ)
■開題
この「行仏威儀」と題する一巻が制作されたのは、仁治二年(1241)冬十月中旬、例によって興聖宝林寺においてのことであった。だが、この一巻は、別に衆(しゅ)に示すことはなかったようである。
まず、その巻題とする「行仏威儀」とは、あまり聞くことのないことばであるが、それは、いったい、どういうことであろうかと、そう思いながらこの巻に読みいたってみると果たせるかな、道元もまたその巻題の説明から始めている。
「諸仏かならず威儀を行足す。これ行仏なり」
そして、その行仏とは、報仏とか、化仏とか、自性(しょう)身仏とか、他性身仏とか、あるいは始覚(しかく)か本覚かなどと、そのような仏の概念化したものとは、まったく比肩していうべきものではないとするのである。では、いったい、行仏とはどのように理解したならばよいか。すると、続いて道元はいう。
「しるべし、諸仏の仏道にある、覚をまたざるなり。仏向上の道(どう)に行履(あんり)を通達せること、唯(ただ)行仏のみなり。自性仏等、夢也未(むやみ)見在なるところなり」
そのいうところは、こういうことであろうか。――そもそも、諸仏は、仏道を行ずるにあたっては、覚(さと)りばかりを期待しているものではないということを、まず知るべきである。もろもろの仏は、ただ一筋に仏のあゆむべき道を、一歩一歩と踏みしめて行く。それはただ行仏のみである。自性身仏がどうの、他性身仏がどうのということなどは、夢にも考えてみたことがないことだ――と。
そのような「行仏威儀」の説示を味わい読みながら、いつしか、わたしが念頭に思い浮かべていたことが二つある。その一つは、かの『正法眼蔵随聞記』(第二の四)にみえる一節のことであって、そこには、こんな一節が記しとどめられてある。
「仏道に入るには、我こころに善悪を分けて、よしと思ひあししと思ふことを捨てて、我が身よからん我が意(こころ)なにとあらんと思ふ心をわすれて、善くもあれ、悪くもあれ、仏祖の言語行履に随ひゆくなり」
まず頭で考えて納得しようとする行き方をすてて、ともあれ、「仏祖先徳の行履ならばなすべきなり」、また、「もし仏祖の行履に無からん事はなすべからず」とする。そのことを、わたしはまず思い浮かべた。
もう一つは、かの『典座教訓』に記す道元その人の体験であって、もっと具体的で、かつ、わたしにはもっと印象の深い一節である。
それは、なお若かりし道元が、宋に渡ってまもなく遇った一人の老典座との問答のことであるが、その時、道元は、その老典座に向かって、
「座(そ)尊年、何ぞ坐禅弁道し、古人の話頭を看せずして、煩はしく典座に充(み)てて只管に作務す。甚(なん)の好事かある」
と詰(なじ)った。あなたはいい年をして、台所仕事などを一処懸命にやっているが、それで何になるか。もっと坐禅をしたり、語録を見たりなさってはどうか、といった。典座とは、禅院の台所のことを司る職のことである。すると、その老いたる典座は大いに笑って、
「外国の好人いまだ弁道を了得せず、いまだ文字を知得せざること在り」
といった。外国のお若い方は、まだ仏教というものが、本当にはお解りでないらしい、といった。それが道元には骨身にこたえた。そして、それが、真の仏教とはなにかという彼の課題の焦点をなした。だから、その問答を記した結語には、
「山僧いささか文字を知り、弁道を了ずることは、乃(すなわ)ち彼の典座の大恩なり」
と記している。それを課題の焦点として、真の仏教とはなにかを了得することができたからである。
わたしは、「行仏威儀」の問題をさておいて、顧みて他を語ることに冗舌を弄(ろう)しすぎた嫌いがあるかも知れない。だが、この行仏のことは、文字や概念をもって解説しうることの遥か彼方にある。とするならば、こうした道元その人の体験や垂示を身に当てて、そこから「行仏威儀」の真相に向かって、手をのべ足をはこぶのほかはあるまいと思うのである。(16~18頁)
■もろもろの仏はかならず整々たる作法にかなった行住坐臥をいとなむ。これを行仏という。行ずる仏である。
その行仏は、報仏すなはち過去の願行によって成れる仏でもなく化仏(けぶつ)すなはち通力をもって化作(けさ)した仏でもない。あるいは、自性身仏すなはち法そのものとしての仏でもなく、他性身仏すなわち衆生のために姿を現じた仏でもない。あるいはまた、本覚(がく)すなわち衆生が本来有する覚性をいうのでもなく、始覚(しかく)すなわちその覚性の始めて目ざめたるをいうのでもなく、乃至は、性覚(しょうかく)つまり真如の本体をいうのでもなく、無覚つまり性のほかに覚(さとり)はないということでもない。そのような仏の概念は、決して行仏と並べていうべきものではないのである。
そもそも、もろもろの仏は、仏道を行じて、覚をのみ期待するものではないということを、まず知るべきである。ただ一筋に、仏に向かっての道を、一歩一歩と踏み締めてゆくのである。それはただ行仏のみである。自性身仏などということは、いまだ夢にも見ないところである。(19~20頁)
〈注解〉威儀;行住坐臥における振舞いの、ぴたりと律儀作法にかなえることをいう。
行仏;この一巻をもって行仏のなんたるかを説くのであるが、まずは、仏を行ずるのではなく、むしろ、行をもって仏となるというほどの意と心得られるがよい。
報仏;法身(じん)仏。三身仏の一。過去における願・行の報いてなれる仏というほどの意である。
化仏;化身仏。仏・菩薩がその通力をもって示現する仏身をいう。
自性身仏;法身(ほっしん)仏のことである法そのものを仏身とするのであるから、まったく無形無色な抽象的なものである。
他性身仏;また他生身仏と記す。他受用身の仏、すなわち、衆生の機根等に応じて示現する仏身である。応身仏ともいう。
化仏;化身仏。仏・菩薩がその通力をもって示現する仏身をいう。
始覚・本覚;衆生のもともと有する覚(さとり)の可能性を本覚といい、それがはじめて目覚めて現実態となることを始覚ともいう。
性覚・無覚;真理の本体は、もともと覚(めざ)めているという考え方を、性覚という。とすると、その本体をほかにして覚(さとり)はないのであるから、無覚という。(20頁)
■そこで、しばらく、その行仏の威儀について、ひとつ研究しておかなければならぬことがある。それは、そのように仏がそのまま自己であるということになると、吾もまたかくのごとし、汝もまたかくのごとしであって、すべてがただわが能力にかかっているようであるが、さらに、十方の諸仏もまた然りということになると、もはやそれだけではありえまい。だからして、古仏もまた、
「その辺のことを体得して、わが内に帰り来って行ずるがよい」
といっておる。そのように受領して、はじめてもろもろの法も、身(しん)も、行も、仏も、おのずからわが身辺に感ぜられてくる。その行・法・身・仏が、それぞれに突き当たっては、「ああ、そうか」と思えるようになる。思い当たるところがあるから、それがすっぽりと会得できるのである。
眼前に百草がきそい茂っておるのに、一つも見えない、なんにも見えないと慌ててはいけない。かしこに行き、ここに来たって、あれを摘み、これを摘んで、おなじ門を出たり入ったりしているうちに、すべてこの世界にはなんの覆い蔵(かく)すところもないのだから、やがて、世尊のことばもさとりも、あるいは、なさることも、命じたまうところも、ぴたりと解ってくるというものである。
「門を出ずればすなわちこれ草、門を入ればすなわちこれ草、万里寸草なし」という。いや、入の一字や、出の一字は、いずれもいらない。そんな捉え方は、放(ほ)っておいたほうがよいともいわないが、つまりは夢まぼろしの非現実のことである。だが、誰がそれを単なる錯誤といいうるであろうか。歩を進むるも錯(たが)い、歩を退くもまた錯(たが)う。一歩も錯(さく)、二歩も錯であるから、錯また錯ならざるはない。だが、天と地ほどの隔たりがあるからこそ、「道(どう)にいたるには難(かた)からず」である。つまり、威儀でもよい、儀威でもよい。大(だい)道は本来ゆるやかなものだと思い定めるがよい。たとえば、出生(しょう)にも道に合(がっ)して出で、入(にっ)死にも道に合うて入るのであって、その徹頭徹尾において珠玉を転ずるがごとき威儀がととのっているのだと知るがよい。
仏の威儀の一端をあらしめるものは、この天地のすべてであり、この生死去(こ)来のすべてである。あるいは、数かぎりない国土であり、世界である。その国土、その世界がその仏の威儀の一端をなすのである。
いったい、仏教を学ぶ人々は、たいてい、「尽乾坤(じんけんこん)」などというと、この閻浮提(えんぶだい)のことであろうと思い、またその四州の一つであろうと思う。あるいは、中国一国を頭にえがき、日本一国を想像したりする。また、「尽大地」といっても、ただこの三千世界を思い浮かべ、時にはわずか一州・一県を思い浮かべる。だが、この尽乾坤・尽大地などということばを学ぶには、もっと幾度も幾度も思いめぐらしてみなければならぬ。広いのであろうと思って、それで休(や)めてしまってはならない。
そのことばの意を究めてみると、極(ごく)大は小に同じく、極小は大に同じくして、仏をも祖をも超越しているのだと知られる。ただの大なる存在でもなく、また小さなる存在でもないといえば、おかしいようであるが、それが威儀を行ずる仏である。もろもろの仏祖が語ってきた「尽乾坤の威儀」といい、「尽大地の威儀」というのは、いずれも、このあるがままの、見るかぎりの世界のことだと学ぶべきである。このあまねき世界は、ただ「かつて覆蔵(ふくぞう)せず」というだけではない。またそれが行ずる仏の威儀にぴたりと中(あた)るのである。(30~32頁)
■古くから祖師たちはいう。
「釈迦牟尼仏は、迦葉仏のところで正法(ぼう)を伝えてのち、兜率天(とそつてん)界におもむいて、兜率の諸天を教化し、今もまします」
まさに知るがよい。人間の世界にあった釈尊は、かの時「大いなる死」をとりたもうて教化を布(し)かれたが、やがて天界にのぼって、いまもなお彼処(かしこ)にましまして、天界の諸天を教化しているという。仏法を学ぶものは知らねばならぬ。人間の世界にあらわれた釈尊にも、千変万化のことばがあり、行動があり、また説法があったが、それは人間世界の一隅において光を放ち、奇瑞(きずい)を現じたにすぎない。さらに天界にのぼったのちには、もっとさまざまの教化があったであろう。それを思わないのは愚かというものである。
仏祖正伝の大道の断続をはるかに超越し、無始無終の時を捨象したこの考え方は、ひとり仏道にのみ伝うるところにして、余他の輩のまったく知らざるところである。そして、いまいうところの行仏の教化を布くところにも、また四生以外のものがあり、天界でも人間界でも存在の世界などでもないところがあろうというのである。だから、行仏の作為を覗(うかが)いみようとするには、天界や人間界のまなこをもって見てはならない。あるいは、人間や諸天の心をもってしてはならぬ。それをもって推し測ろうとしてはならぬ。
それは、十聖(じっしょう)・三賢など仏道の修行者もはっきりとは知らないこと。ましてや、人間や諸天の推量の及ぶところではあるまい。人小なれば、その知るところもまた小さく、命みじかければ、その思量もまた短いという。それでどうしてか、行仏のなすところを測り知ることができようか。(40~41頁)
〈注解〉此輩罪根深重(しはいざいこんじんじゅう);『法華経』第二、「方便品」にみえる。そこでは、仏の説法を前にして、多くの在家・出家の者がその座を退いたことが記されている。それは、彼らが罪根深重、かつ増上慢にとらわれ、「未得を得といい、未証を証という」輩であったから、世尊もまた黙然ととして制止しなかったという。その経の趣をもって、この前後の文を読まなければ、理解しがたいであろう。(43頁)
■しかるに、いま行ずる仏のなすところはまったく自由自在である。たとい仏だからといっても、泥を拕(か)き水にもぐるの活路に通じているから、なんの礙(さまた)げにもならない。天界にのぼれば神々を教化し、人間界にあれば人々を教化する。花ひらけば世界起こるであって、その間にすこしも隙間がないのである。だから、はるかに自他の境を遠く超え、往(ゆ)くも来るも独徃独歩である。すなわち、兜率天に往き、兜率天より来たって、なんの間隙なく、また安楽土に到り、安楽土より来たって、常に自由自在である。あるいは、兜率天をはるかに脱し、安楽土を遠く超えるのであり、あるいは、安楽・兜率を千々に砕くのであり、あるいは、兜率・安楽を捉えてはまた放つのである。つまり、一口にして呑みつくすのである。
いったい、安楽土・兜率天などという浄土や天界は、そのいずれに赴(おもむ)くもなお輪廻なることに変わりはない。行くといえば行くのであり、悟りといえば悟りであり、また、迷いといえば迷いである。それがすべて、行仏の草鞋のなかの、かりそめの足指の動きなのである。あるいは、それはまた、一発の放屁の声といってもよく、また脱糞のかおりといってもよい。鼻の孔のあるものは嗅ぐことができる。耳があり、身があり、足があるならば、聞くこともできよう。その得るというのは、わが皮肉を得、わが骨髄を得るのであるから、別に行じて他より得来たるのではない。
かくして生死(しょうじ)を了得して、まったくこだわるところのない境地にいたれば、古くからいいきたった言葉がある。「大聖は、生死を心にまかせ、生死を身にまかせ、生死を大道にまかせ、生死を生死にまかす」と。その意味するところを実現するのは、古(いにしえ)の時でもない、今の時でもない。ただ行仏の威儀のなるとき、忽然として行じ尽くされるのである
それは、どこが始め、どこが終わりというのではないが、生死・身心の趣がすうっと肯けてくるのである。行がいたると明(みょう)がいたる。それが自然なのである。頭を撫でて鏡に向かえば、そこに頭がある。それによく似ている。反射して返照する。それと同じである。その明(みょう)の上にさらに明を重ねることも、行仏をいよいよ豊にして、行ずるにしたがって思うがままである。
その思うがままなる道理を、よく心に当てて究めるがよい。よろしく努めて思いめぐらせば、万物のありようがすっと心に浮かんできて、三界などというのは心の分かつところだと気がつく。そう気がついてみると、万法などというのもまた、おのれの故里に帰っただけのことであって、それはつまりその人のいとなみに他ならぬのである。だからして、翻(ひるがえ)ってそれを句中に求め、言外にさぐるなど、繰り返し繰り返しして深く沈潜して撈(すく)うてみるならば、把握してなお余りがあり、放念してまた余りがあるであろう。
その工夫は、生とはいかに、死とはいかに、身心(じん)とはいったい何か、あるいは、与うる奪うとはいったいどういうことか、思うにまかせるといい任(まか)せぬというはどういうことか、あるいはまた、それらのことは、同じ門を出入りしながらも相逢わないのか、一つのものが時に身を蔵(かく)し、時に角(つの)を露わすのか、それとも、大いなる煩悩にしてはじめて解しうるのか、老熟した思慮をもってはじめて知りうるのか、さらにはまた、一顆明珠というものか、一大蔵教というものであるか、あるいは、一本の拄杖(しゅじょう)なのか、一人の面目なのか、また、それが解るのは幾十年もの後のことか、時の長い短いには関係のないことかと、つぶさに思いいたり思い来るがよい。その思いをつぶさにして、はじめて眼いっぱいに声を聞くことができ、耳いっぱいに物を見ることができる。
さらに、沙門にかかる一隻眼の開けきたるとき、ただに目前の事、目前の物を見るのみならず、また、おのずからにして悠揚たる破顔があり瞬目がある。それも行仏のしばしの威儀というものである。その時、彼はもはや、物に引かれるでもなく、物を率(ひ)くでもない。事情のなるがままに任せて、無生・無作なるでもない。あるいは、本性のあるがままに任せるのでもなく、物のあるがままにゆだねるのでもなく、もとより然るにもあらず、あるがままを是とするのでもなく、ただ仏の威儀を行ずる仏としてあるのみである。
だからして、法のためにすることも、身のためにすることも、すべてよく心のままであり、生を離れ死を離れることも、しばらく仏に任せておくのである。かくて、はじめて、万法唯心といい、三界唯心ということができる。さらに一歩を進めていうなれば、ただ心のみといってもよく、それがいうところの牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)なのである。ただ心のみではないから牆壁瓦礫というのではない。それは、仏の威儀を行ずる仏のなすところが、心にまかせ物にまかせながら、おのずから物のためとなり身のためになっていることをいうのである。そこのところは、始覚(しかく)だの本覚(がく)だのと論(あげつら)うものなどの思い及ぶところではなく、ましてや、外道・小乗の輩や、三賢・十聖などの境地にあるものの、とうてい思い及びえないところである。
その振舞うところのひとつひとつは、容易に領会しがたい。なにか活き活きとはしているが、なんの統一もなくばらばらである。それは、いったい、一本のものか、別々のものか。一本のものといおうとせれば先もなく後もなく、別々のものかと思えば自他の別がない。ただそこには、「事を展(の)べ、機の投ず」るの力があり工夫があるから、その威風は万法を掩(おお)うのであり、その眼光は一世を抜きいでている。いったい、光明には、光を放つ放たぬに関係のない光明がある。いや、光を放たぬ光明がある。僧堂・仏殿・廚庫(ちゅうこ)・山門がそれである。さらに、十方に通じる眼があり、大地のことごとくを収める眼がある。それは心の前にあり、また心の後ろにある。眼・耳・鼻・舌・身・意の六根は、そのような光明の功徳の盛んなものであるが、それを知らずして身につけている三世(ぜ)もろもろの仏たちがあり、また、知って機に投ずる狐狸のたぐいもある。その鼻があり、その眼があるならば、法を説くも、法を聴くも、すべて行仏ということを得るであろう。(46~50頁)
〈注解〉拕泥滞水(たでいたいすい);『碧巌録』の第一則に、、「道箇仏字、拕泥滞水」とみえる。仏とは、俗塵を遠ざかるのみの存在ではなく、また、泥を掻き、水をもぐるのたぐいのことを辞さないのである。(50頁)
三界ただ心の大隔;三界とは、欲界(人間欲望の世界)、色界(物質・現象の世界)、無色界(叡智抽象の世界)をいう。そのような三つの世界があるなどというのも、ただ心の分かち考えるところに他ならずというのである。
本有;本来固有の意であり、外より来るものにあらざるをいう。(51頁)
■この雪峰のことばによく通達(だつ)することは、また仏の出処進退に通達することである。三世の諸仏が火焔のなかにいますというからとて、限りなき宇宙を経めぐるのでもなく、あるいは、極微(ごくび)の世界に通ずるのでもない。あるいは、大いなる法輪を転ずるというからとて、大きいであろう広いであろうと思うべきではない。あるいはまた、大いなる法輪を転ずるのは、自分のためでもなく、他のためでもなく、また、説かんがためでも、聴かんがためでもないのである。(61頁)
■釈迦牟尼仏はいった。
「もしこの経を説けば、それはとりも直さずわたしを見ることである。ただ一人のために説くことも、またはなはだ難しいことである」
とするならば、よく法を説くことは、そのまま釈迦牟尼仏の見(まみ)えることである。それがとりも直さず「わたしを見ることだ」とは、釈迦牟尼仏のことだからである。
釈迦牟尼仏は、またいった。
「わが亡きのちにおいて、この経を聴きて受持(じゅじ)し、よくその意味をたずねることも、またはなはだ難しいことである」(63頁)
■しかるに、喜ばしいかな、いまわれらは、その生を受けるところは聖者の地を去ること遠く、その生くる時もまた聖者の時を去ること遠いけれども、なおこの一天の説法を聞くことのできる時に遇うことを得たのである。仏が法を説くということは、すでにしばしば聞き及ぶところであったが、法が仏を説くということは、幾重にも無智に蔽(おお)われて、これまでまったく知らなかった。しかるに、いま圜悟のいうがごとくであるとするならば、三世のもろもろの仏たちは、三世にあって法に説かれているのであり、また、三世のもろもろの法は、三世にわたって仏に説かれているのである。それをいま、風前にあってずばりと言句のしがらみを截断(せつだん)してみるならば、そこにはただこの一天の覆うところがあるのみである。それは維摩詰(きつ)であろうとなかろうとどうでもよい。この一天を覆うところという一句が、余すところなくすべてを道破し尽くしている。
それでこそ、まさしく、法が仏を説くのであり、法が仏を行ずるのであり、法が仏を証(さと)るのであり、同時にまた、仏が法を説くのであり、仏が仏を行ずるのであり、仏が仏を作(な)るのである。そして、それらのすべてが行ずる仏の出処進退にほかならない。だから、天にわたり地にわたり、また古(いにしえ)にわたり今にわたって、得るところを軽るんずることなく、明きらむるところを大事に用いるがよいというのである。(65~66頁)
〈注解〉赤鬚胡・胡鬚赤;赤ひげの外人というも、外人のひげは赤いというも、詮ずるところは同じことであって、いずれを優れたりとも劣れりともいえないというほどの意である。
性・相;性とは、存在の本性であり、相とは、その現れとしてのすがたやはたらきである。本体論と現象論であるといってもよく、その二つの流れがこれまでの仏教学の主流をなしていた。(67頁)
仏教
■開題
この一巻が衆(しゅ)に示されたのは、仁治二年(1241)の十一月十四日、いつものように興聖宝林寺においてのことであった。道元の制作活動はこの前後よりようやく活発となり、この年の九月、十月、十一月は、それぞれ二本ずつ制作が行なわれている。
ここに仏教というのは、わたしどもがこの宗教を総体として仏教と呼ぶのとは、いささかその概念内容を異にしておる。わたしどもがこの宗教を仏教と呼ぶその概念内容にあたるものは、かの時代にあっては、仏法であり、また仏道である。いささか思想の側に傾斜していえば仏法であり、また実践の側に重きをおいていえば仏道であった。そして、それを総体として仏教というようになったのは、明治以後のことに属するのである。
では、ここに仏教というのは何か。その概念内容は、この巻の冒頭において、みごとな表現をもって、端的に示されている。「諸仏の道原成(どうげんじょう)、これ仏教なり」である。そこに「道(どう)」というのは、「いう」であり、「ことば」である。もろもろの仏のことばの実現したるもの、それが仏教であるというのである。
とするならば、その「諸仏の道(どう)」はどこに実現しているか。それは経のほかにはない。古い述語をもっていうならば、三乗十二分教がそれであり、あるいは九分教がそれである。かくて、道元はこの巻において、三乗十二分教ないし九分教につき、その概観を試みているのである。だが、道元がこの巻において語ろうとするもっとも大事なことは、そのことではなかった。それは、むしろ、仏教すなわち経に対する態度に関することであった。
そのことを説かんとするにあたって、道元はまず、教外別伝の主張を謬説(びゅうせつ)なりとして批判しておる。初めてその一節に読みいたった時には、わたしはわが眼を疑うの思いであった。だが、幾度読みいたってみても、道元の筆は明らかに、「教外別伝の謬説」と繰り返し語っているのであった。彼はまず、いわゆる「教外別伝」の故実を紹介し、その主張を再現してこれを批判する。
「かくのごとくの漢、たとひ数百千年のさきに先達と称すとも、恁麼(いんも)の説話あらば、仏法仏道はあきらめず、通ぜざりけるとしるべし」
そんなことをいう輩は、いくら先輩だといっても、仏法も仏道もわかってはいないのだという。その批判のことばは、例によってまったく歯切れがよい。
だからといって、道元は、けっして、三乗十二分教にこびりついて、ひたすらその訓詁(くんこ)注釈のことにかかずらい、あるいは法性(ほっしょう)を論じ法相(ほっそう)を証することに没頭するのが、真の仏者の道とするわけではない。それはいわゆる経師(きょうじ)・論師(ろんじ)などのたぐいのすることである。そこは、むしろ、
「十二分教をみるは仏祖をみるなり、仏祖を道取するは十二分教を道取するなり」
と心得べきであるとする。なんとなれば三乗十二分教はすべてこれ仏祖の眼晴(ぜい)であり、仏祖の骨髄であり、仏祖の光明であり、また仏祖の荘厳(しょうごん)であるからだという。
かくて、道元は、この一巻の結びの一句に示していう。
「およそしるべし、三乗十二分教は仏祖の眼晴なり。これを開眼(げん)せざらんもの、いかでか仏祖の児孫(じそん)ならん。これを拈来(ねんらい)せざらんもの、いかでか仏祖の正眼(しょうげん)を単伝せん」
ここにいたって、わたしは、明らかに、この師が遠く世の禅家の庸流(ようりゅう)の輩を抜きんでていることを感ぜざるをえないのであるが、その趣は、これより以後の制作において、いよいよ明らかに観取せられることに注目していただきたいと思う。(70~72頁)
■もろもろの仏のことばの実現したるもの、それが仏教にほかならない。それは仏祖が仏祖のために説くところであるから、また教が教のために正伝するのである。それが法輪を転ずるということである。その法輪の眼晴(ひとみ)のなかにあって、もろもろの仏祖が出現し、またもろもろの仏祖が滅してゆくのである。
そのもろもろの仏祖には、あるいはいと小さな処に出現しまた入滅するものがあり、あるいは全世界をおおうて現われまた滅するものがあり、あるいはまた、つかのまの出現があり、長年月にわたる出現もある。だが、小さな処、短い時間の出現だからといって、けっして功徳がないわけではなく、ひろい世界、ながい年月にわたる出現だからといって、まされりとするわけでもない。
だから、朝(あした)に成道して夕(ゆうべ)に入滅する仏たちも、けっして功徳がないとはいえない。もしも、一日では功徳が少ないというならば、釈尊のこの世界における八十年だって長いわけではあるまい。その八十年をもって十劫(ごう)二十劫に比したならば、それは一日と八十年のようなものであろう。その長劫(ちょうごう)にわたる寿命と八十年の寿命だけをとりあげて比ぶれば、むしろ比べものにはならない。だが、かの仏の功徳とこの仏の功徳とを比べて優劣を云々することはできない。なんとなれば、仏の教えとはとりもなおさず教える仏である。仏祖が究めつくしてきた功徳なのである。もろもろの仏は広大であるが、その教法は矮小であるというようなことはありえない。つまり、もし仏が大であれば教もまた大である。仏がもし小であれば教もまた小である。
かくて知らねばならぬ。仏と教とは大小の量をもっていうべきものでもなく、善いの悪いのとわかち語るべきものでもなく、あるいはまた、自己のための教えでもなく、他人のための教えでもないのである。(73~74頁)
〈注解〉転法輪;仏が教法を説くことを、車輪の転ずるを喩(たと)えとしていう。説法である。
仏教・教仏;仏と教との同一性を語らんとして、仏教を転置して教仏というのである。仏の教はまた教の仏にほかならずとするのである。(74頁)
■ある男がいう。釈迦はむかしその生涯にわたって教典を説示したが、その他にまたすぐれた一心の法を摩訶迦葉(かしょう)に正伝した。それを正しい嗣手(つぎて)から正しい嗣手へと相承(そうじょう)していまにいたっておる。だから、教というのは機に応じてのたわむれの論議であって、その一心こそ真実の道理である。その正伝した一心を教外別伝という。それは三乗十二分教、すなわちもろもろの教典の語るところとは、まったく別のものである、と。また、その一心こそさいじょうのものであるから、直指人心、見性成仏と説くのである、という。
そのいい方は、けっして仏教のものではない。そこには自由にいたる活路もなく、全身にそなわる修行の輝きもない。そんな男は、たとい数百数千年の先輩であろうとも、そんなことを言うようでは、仏法も仏道もまだ解っていない、通じていないのだと知るがよい。なぜかというならば、彼らはまだ、仏も知らない、心も知らない、内も知らない、外もわかってはいないからである。なぜ知らないかといえば、いまだかって仏法をきかないからである。
たとえば、いま諸仏という。その諸仏の本末がどうかも知らず、どこから来てどこに去るかも学ばないのであるから、とうてい仏弟子とはいいえないのである。あるいは、ただ一心を正伝して、仏の教えを正伝しないなどというのも、仏法を知らないからである。仏の教えが一心であることも知らず、一心がすなわち仏の教えであることも学ばないから、一心のほかに仏の教えがあるなどという。その汝がいう一心は、まだ一心ではあるまい。また仏の教えのほかに一心があるなどという、その汝がいう仏の教えとは、けっして仏の教えであるまい。たとえ教外別伝の説を相伝したのだといっても、なんじはまだ内も外も知らないのだから、言葉と道理とが符合しないのである。
いったい、仏の正法(しょうぼう)の眼晴(がんぜい)をじきじきに伝えられた仏祖が、どうして仏の教えを伝受しなかったはずがあろうか。ましてや釈尊が、なんとしてか仏教にあるべからざる教法を設けられるはずがあろうぞ。すでに釈尊に直伝(じきでん)の教法があったならば、いずれの仏祖もそれを無からしむるはずはない。かくて、上乗の一心というは、三乗十二分教がそれである。大乗の教典(でん)小乗の教典のことごとくがそれである。
かくて、知るがよい。仏心というのは、仏の眼晴である。破木杓(はもくしゃく)である、もろもろの存在である、三界であるがゆえに、山海(がい)国土・日月星辰である。つまり、仏教というは森羅万象である。外というのは、われらの住むところであり、ここから来るのである。正伝とは、自己から自己に伝えるのである。だから、正伝のなかに自己があるのであり、また、一心から一心に正伝するのであるから、正伝のなかに一心があるのである。さらにいえば、上乗の一心とは土石砂礫(どせきしゃりゃく)である。土石砂礫が一心であるから、土石砂礫は土石砂礫である。
もし上乗の一心を正伝するというならば、かくのごとくであろう。しかるに、教外別伝などという男どもは、けっしてこのような意味を知ってはいない。だからして、教外別伝の説などを信じて、仏の教えをあやまってはならない。もしも彼らがいうままに受け取るならば、教えは心外別伝ということになろうか。もしも心外別伝というならば、一句も半偈も伝わるはずはない。もし心外別伝といわなければ、教外別伝とはいえないのである。
いったい摩訶迦葉は、釈尊の法嗣(ほっす)として、法蔵をゆだねられた方であり、正法の眼蔵を正伝して仏道の統領でる。しかるに、その人が仏の教えは正伝しなかったとするならば、これほど可笑しなことはあるまい。かくて知るがよい。一句を伝授さるれば、一つの真理を正伝せられるのであり、一句を伝持すれば、また山が伝え水が伝えてくれるのである。ただ、それにはどうしても仏祖の正伝によらねばならなぬ。(77~80頁)
〈注解〉法蔵の教主;法蔵とは仏所説の教法をいうことば。禅門においては、摩訶迦葉は法蔵を付嘱せられた第一祖として尊崇せられている。また、摩訶迦葉が第一結集(けつじゅう)、すなわち最初の教法の編集にあたり、これを主宰したことも、また隠れもない歴史的事実である。(81頁)
■また、波羅蜜というのは、到(とう)彼岸である。彼岸は此処にあり彼処にありというものではないが、なお到ることができるのである。その到るというのが仏道の大事な問題である。修行のかなたの岸にいたるのであろうなどと思ってはならぬ。かなたの岸に修行があるから、修行すれば彼岸に到るのである。その修行はあやまつことなく、いかなる世界をも実現する力をそなえているからである。(90頁)
〈注解〉六波羅蜜;菩薩の行ずべき六つの大行であって、それによって修行者は彼岸に到るとするのである。その六つの大行は続いて示されている。(91頁)
■思うに、仏が法を説くというが、また、法が仏を説く。法が仏に説かれるとともに、仏が法に説かれるのである。さらにいえば、煩悩の火焔もえさかるこの世界が仏を説き、法を説くのであり、また、仏がこの世界を説き、法がこの世界を説く。かくて、この経をすでに説くという所以があり、また、この故に説くという所以がある。この経は説くまいとしても説かざるをえないのである。だからして、「その故をもってこの経を説く」というのである。
かくて、その説くところは全世界に及び、また全世界がこの経を説くのである。この仏もかの仏もすべてこの経をと称し、この世界もかの世界もともにこの経をと説く。その故にこの経を説くというのであり、この経こそ仏の教えである。かくて知らねばならぬ。数かぎりもない仏の教えが竹箆(しっぺい)であり払子(ほっす)であり、仏の教えの数かぎりもないのが拄杖(しゅじょう)であり拳頭(けんとう)である。
これを要するに、三乗十二分教などは仏祖の眼晴(がんぜい)であると知るのがよいのである。これに眼を開かないものが、どうして仏祖の門下ということができようか。これを学び来らぬものが、どうすれば仏祖の正法を伝え受けることができようぞ。正法の眼目を体得することを得ない者は、断じて七仏の法嗣(ほっす)ではありえないのである。(102~103頁)
〈注解〉竹篦(しっぺい)・払子(ほっす)・拄杖(しゅじょう)・拳頭;師家が学人を接得するに用いる道具をならべて記したのである。(81頁)
神通(じんずう)
■開題
この一巻は、仁治二年(1241)の十一月十六日、例によって興聖宝林寺にあって衆(しゅ)に示したものである。その年に制作された十一本のなかの最後のものであった。
いつものように、道元がこの巻においていわんとするところは、その冒頭においてずばりと打ち出されている。
「かくのごとくなる神通は、仏家の茶飯なり、諸仏いまに懈倦(げけん)せざるなり」
いまから語ろうとする神通は、仏教者にとって日常茶飯のことであるというのであり、もろもろの仏はそれをいつも行じているのだという。
そして、続いて示す仏祖の神通の範例は、大潙(だいい)と仰山(きょうざん)と香厳(きょうげん)の三人の師弟の間に現ぜられたそれであった。昼寝をしていた大潙がに「いま夢をみていたよ」と話すと、仰山が「一盆の水、一条の手巾(しゅきん)」をもってくる。やがて室にはいってきた香厳にそれを話すと、こんどは香厳が「一椀の茶を点来(てんらい)」する。それを大潙が「二子の神通智慧」は舎利弗(しゃりほつ)、目犍連(もっけんれん)にもまさっていると称(たた)えたという。
それが、「かくのごとくなる神通は、仏家の茶飯」という好範例である。それは、鬼面をもって人を驚かすようなものでもない。わたしどもの日常の生活では考えられないようなことでもない。まさに日常茶飯のことのほかではない。しかるに、道元は、続いて、かかる茶飯なる神通を語って大神通となし、世にいうところの摩訶不思議なるそれを談じて小神通となす。その意(こころ)を汲むことがこの一巻の急処にほかならない。
古来から、仏法に不思議なしという。その通りである。世にいうところの宗教なるものは、しばしば奇蹟を語り、神通を談ずる。そのなかにあって、仏教だけはそのようなことに心を奪われない。「いかんがこれ道(どう)」と問われるならば、「平常心これ道」と答えるのが仏教者の建前である。それにもかかわらず、いま道元は、この巻題をかかげて仏教の神通を語る。けだし諸仏の行ずるところは、それにまさる神通はないからである。
その道理を、いまこの巻に引用する臨済のことばをもっていうなれば、
「色界に入りて色の惑(まどわし)をこうむらず、声(しょう)界に入りて声の惑をこうむらず、香界に入りて香の惑をこうむらず、味界に入りて味の惑をこうむらず、触(そく)界に入りて触の惑をこうむらず、法界(ほっかい)に入りて法の惑をこうむらず」
とある。それが仏教者の六神通というものであって、その時、人は、この「繋縛(けばく)」の世にありながら全く自由であり、「五蘊の漏質」でありながら、まさに「地行の神通」をそなえるものとなるのだという。
その「五蘊の漏質」とは、その身は依然として色・受・想・行・識(それが五蘊である)の成すところであり、煩悩具足の人間であるということ。したがって、天を駆けたり、水上を歩いたりすることはできないけれども、なおかつ、この地上にあってまったく縛せられることなき自由なる存在としてある。「地行の神通」とはそのことであって、それこそ最高の神通にほかならずというのである。(106~107頁)
■五通・六通を小神通というのは、それらは修行のいかんにかかわるものであり、また、時と処とによって制限があるからである。生きている時には現ずるが、死後には現じないのであり、自己には通ずるが、他人には通じないのであり、この土(ど)においては現われるが、かの土には現われないのであり、また、常ならぬ時には現われるけれども、日常の時には現われないのである。
しかるに、この大神通はそうではない。もろもろの仏の教法も証得(さとり)も、すべてこの大神通によって実現せしめるのである。それは、もろもろの仏のまします処において実現するのみならず、また、仏のいまだいまさぬ時と処とにおいても実現する。神通力をもった仏の教化のしかたは、まったく不思議なものであって、その仏のいまだいまさぬさきにその神通力が現ずる。前か中か後かに関しないものである。仏の神通によるにあらずしては、もろもろの仏の発心(ほっしん)も修行も正覚(しょうがく)も入滅も、いまだかってないのである。
いま、このかぎりなき世界の常にして変わらざるも、みなそれは仏の神通である。「一毛が巨海を呑む」のみではない。また、一毛が巨海を保つのであり、一毛が巨海を現ずるのであり、一毛が巨海を吐くのであり、一毛が巨海ならしめるのである。そのように、一毛がすべての世界を呑みかつ吐くとき、では、世界がことごとくそうなったら、もはや世界はなくなってしまうかのように学んではならない。
一粒の芥(からし)だねがそのなかに須弥山(しゅみせん)を包蔵(ほうぞう)するなどというのも、また同じことである。芥だねの一粒が、また須弥山を吐くのであり、あるいは、限りなき海のごときこの世界を現ずるのである。一毛が巨海を吐き、一粒の芥だねが巨海を吐くには、一瞬にして吐くのであり、万劫(ばんごう)にわたって吐くのである。万劫も一瞬も、おなじく一毛一芥(かい)より吐かれるものならば、一毛一芥はいったいそれを何によって得来るのであるか。それは、とりもなおさず神通によって得るのである。その得るというのは、神通によるのでるから、まさに神通が神通を生むのである。かくて、この神通は、過去と現在と未来にわたって、存すると存せないの別はないと知るべきである。もろもろの仏は、いつもこの神通のなかに悠々自適しているのである。(118~119頁)
■なんじはいう。仏に六神通があるのは、まことに不可思議である、と。だが、一切の諸天も神仏も阿修羅も大力の鬼もまた神通を有する。それらもまた仏たるべきであろうかいかに。仏道を修する者はあやまってはならぬ。たとえば、阿修羅は天帝釈と戦い、戦いやぶれるや八万四千の部下をひきいて、一本の蓮(はす)の孔のなかに入って隠れたというが、それもまた聖(たっと)いことであろうかどうか。
世の僧たちがあげていうところは、みな業通(ごうつう)というものか依通(えつう)というものばかりである。仏の六神通というのは、まったくその類を異にするものである。現実の世界に入って現象に惑わされず、声の世界に入って声の惑わしを受けず、香の世界に入って香の惑わしを受けず、味の世界に入って味の惑わしを受けず、感触の世界に入って感触に惑わされず、思想の世界にあって思想の惑わしを被(こうむ)らない。そのゆえに、その六種の世界の真相を熟知し、そのすべて空(くう)なるを知って、何物にも捉えられざるものとなる。これが無依(むえ)の道人というものである。その身はなお五蘊の成すところにして、煩悩具足のともがらではあるけれども、それでそのまま地行(ちぎょう)の神通というものなのである。(133頁)
〈注解〉阿修羅;悪神にして、常に天帝釈と戦う神であるという。
天帝釈;帝釈天である。インド神話におけるインドラの仏教化した神である。
業通;宿業の力によって自然にそなわる神通である。
依通;呪術などによって現ずる神通をいう。(135頁)
大悟(だいご)
■開題
この一巻は、仁治三年(1242)の正月二十八日の制作。恒例によって、興聖宝林寺において衆(しゅ)に示したものであるが、奥書によれば、さらに寛元二年(1244)正月二十七日にも、越前の吉峯(よしみね)寺において「人天(にんでん)の大衆(だいしゅ)」に示したと記されている。
仁治三年から、その翌仁治四年(その二月二十六日改元して寛元元年となる)に及んで道元の制作活動はその最高潮に達したようであって、仁治三年の間に制作された『正法眼蔵』は十六巻を数える。そして、この「大悟」の巻は、その年の最初のものであった。
この「大悟」の一句は、ご承知のように、禅門において聞くことしきりにして、禅者は大悟をもって本懐とするのが常であるように見受けられる。この巻にみえる句をもっていうなれば、「悟道是本期」(道(どう)を悟るこれ本期(ほんご)なり)というのはそのことである。だが、道元はむしろ、そのような考え方に対しては批判的であって、そのようにただいたずらに「待悟」する者は、ついに「仏祖の光明にてらされる」時はないであろうとも語っている。
その意趣は、例によって、ずばりと巻の冒頭において語り出されている。
「仏仏の大道(だいどう)、つたはれて綿密なり。祖祖の功業(くごう)、あらはれて平展なり。このゆゑに大悟現成し、不悟至道し、省悟弄悟(しょうごろうご)し、失悟放行(しつごほうぎょう)す。これ仏祖家常なり」
とあるは、その趣である。したがって、詰まるところは、仏祖はかならず大悟によってそこに到るものではあるが、しかも必ずしも、大悟の渾然としてまどかなるをのみ仏祖とするのではなく、仏祖もまたしばしば大悟のほとりを跳び出して、悠々として山河大地とあそび、またわが身心(しんじん)と遊ぶのだという。
そして、道元がこの巻において力を込めて説いているのは、むしろ、悟りと迷いの問題であるように思われる。
華厳寺の宝智大師に、ひとりの僧が問うていう。「大悟底の人却(かえ)って迷う時如何」それに師が答えて、「破鏡重ねて照さず。落華樹(枝)に上り難し」という。道元が『景徳伝灯録』からその問答を引用して、綿々として注釈を施している一節は、どうやら、この一巻のなかでのもっとも興味をそそるところであって、まことに難解であるが、また示唆するところが豊かである。
「大悟も片手であり、迷うもまた片手ではないか。その二つがあって、はじめて両手が揃うと考えることもできよう。とするならば、大悟した人にも、またどうしても迷いがあるのだと、そう受け止めるのがはじめて徹底した理解といえよう。そうすれば、大悟というものは、また、迷いをいよいよ親しみ深いものにしてくれるものだと解ってくる」
そこまでくると、大悟ということばが、まったく新しい印象をもって、わが前におかれる思いがあるのは、ひとり私だけのことではあるまい。(142~143頁)
■まことに、大悟とは、始めもなく、また終わりもないものであり、迷いもまたしかるのである。したがって、大悟と差し障るような迷いなどはないのであって、むしろ、大悟三枚をひねくり廻して小迷半枚をつくるといったところ。つまり、雪山(せつせん)は雪山のために大悟するのであり、木は木のために、石は石のために大悟するのであり、また、諸仏は衆生のために大悟するのであり、衆生は諸仏の大悟を大悟するのであり、しかも、前後の関係はまったくない。だから、いまの大悟は、自分のものでも、他人のものでもない。どこから来るというのでもないが、道は坦々として通じている。また、どこに去るというのでもないから、他にしたがって探しもとめてはいけない。どうしてそうかというなれば、それはどこかに行ってしまうからである。(157~158頁)
■とするならば、仰山(きょうざん)は、「第二頭におちること」を歎きながら、悟りには第二級品などはないと、それを否定しようとしているらしい。たとい第二頭であっても、それが悟りを成じたからには、もはや本物だとしなければならない。だから、たとい第二頭であろうと、第三頭であろうとあるいは幾百幾千番目のものであろうと、悟りは悟りであろう。もし第二頭であれば、そのまえには第一頭がああるはず。それは別だとするのでもない。それは、たとえていえば、昨日のわれもわれであるから、昨日のわれからみれば、今日のわれは第二番目のわれだというようなものである。いまの悟りは、昨日のそれではないとはいわない、いまに始めたものではないからであると、そのように学びいたるがよいのである。だから、大悟の頭が黒かろうと白かろうと、なんの思い煩うことはない。(163頁)
〈注解〉第二頭;第二番目の人もしくは物をいうことばである。それは第二番目であるから、第一番目のものとは別のものということとなり、また、第一番目のものが第一級のものとすれば、それは第二級のものとなる。ここでは、その二つの意がともに含まれているようである。(164頁)
坐禅箴(ざぜんしん)
■開題
それに対して坐禅箴という時には、いうなればその内面に指向して、坐禅の心得、坐禅のいましめ、つまり坐禅のなんたるかに説きいたらんとするものということを得るであろう。その内容のことなりは、さきの「坐禅儀」に比ぶるに、この「坐禅箴」の内容をもってすれば、ほぼ明らかということを得るであろう。(167頁)
■ 薬山の弘道大師が坐っていると、ひとりの僧が問うていった。
「そのように一心不乱に坐られて、どんなことをお考えですか」
師はいった。
「あの不思量というやつを考えている」
僧がいった。
「不思量というものは、どうしたら考えられましょう」
師はいった。
「考えないのである」
薬山惟儼(やくざんいげん)がこのようにいっておるのを、わが身に当てて、よくよく坐り方を学び、正しい坐禅を伝え受けるがよい。それが仏教に伝わる坐り方というものである。ぴたりと端坐してなにを考えるか。それについて語ったのは、けっして薬山のみではないが、薬山のことばは、よくそれを言い得たものの一つである。それは、あの不思量というやつを思量するのだという。そこに、思量といえば思量の心髄があり、また不思量といえば不思量のぎりぎりのところが語られている。
しかるに、かの僧はかさねて、不思量というのはどうしたら思量できましょうかと問うた。まことに、不思量ということは、古くからいわれているが、いったい、どうしたらそれが考えられるかというのである。思うに、坐禅するときにも、まったく考えるということがないはずはない。もしそのことが無かったならば、坐禅の進境というものがどうしてありえようか。浅はかな愚人でないかぎりは、誰だってそこのところを問いたいと思うはずである。
薬山はそれに答えて、「非思量」といった。考えないことだといった。考えないということは、なんの濁りもなく、まったく透き通ったものであるが、不思量ということを考えるには、どうしてもこの非思量をもってするの他(ほか)はない。非思量にもなんらかの内容がある。そのなにかが非思量のわれをあらしめるのである。なるほどそこに端坐しているのはわれであるが、そのわれはただ思量するわれではなく、ぴたりと端坐しているのである。端坐はまさに端坐であるから、その端坐が端坐を思い量ろう道理はない。したがって、端坐して思うことは、仏のことでもなく、法のことでもなく、悟りのことでもなく、あるいはなにかの理解のことでもなく、ただ非思量である。
薬山がこのように語り伝えたのは、釈迦牟尼仏より数えれば、すでに三十六代のことであった。また、これを逆に遡(さかのぼ)っていえば、三十六代にして釈迦牟尼仏がまします。ともあれ、そのように正伝しきたって、ここに「この不思量なるものを思量する」ということばがある。(169~171頁)
〈注解〉薬山弘道大師;弘道大師とは、薬山惟儼(834寂、寿84)の諡号(しごう)である。関藤希遷の法嗣(ほっす)である。澧(れい)州の薬山に住して薬山と称された。
■しかるに、近年、愚かにして杜撰(ずさん)なる輩(やから)は、「坐禅の修行は心のうちの無事を得ればそれでよいのだ。つまり、それは平穏の境地というものだ」などといっておる。そのような見方は、小乗の学者にすら及ばず、世間の人々よりも劣れるもので、とても仏法を学ぶ者とはいえない。ところが、現在、大宋国には、そのような坐禅の修行者が多いのであるから、祖道のおとろえを歎かざるをえないのである。
また、こんなことをいう連中もある。――坐禅して道を修めるのは、初心や後進の者のすることであって、必ずしも仏祖のなすところではない。行くも禅、坐するも禅、語・黙・動・静すべておのずから安然たるべきであって、ただ坐禅の修行のみこだわってはならない。――臨済の流れを汲むと称する連中は、たいていそのような見解である。仏法の正しい命(いのち)をぴたりと伝えないから、こんないい方をすることとなるのである。
いったい、なにが初心だというのか。初心ならぬ者がどこにあるのか。初心とはどこまでだというのか。まさに知るべきである。仏道を学ぶものの生まれる修行として、坐禅して道を修するのである。その標榜するところの主旨をいえば、仏となることを求めずしてただ仏の威儀を行ずるのである。けだし、仏の威儀を行ずるのは、けっして仏とならんがためではないのであって、それは公案として明白である。その身がすでに仏であるならば、さらに仏となるの要はないのである。文字のしがらみを打ち破ってみれば、坐仏はさらに作仏するの要はあるまい。まさにそこに到ってみれば、もともと仏になる力もあれば、悪魔になる力もある。進むも退くも自由自在なのである。(173~174頁)
〈注解〉人天乗;五乗(人乗・天乗・声聞乗・縁覚乗・菩薩乗)のうち、はじめの二つをあげたのである。それらは、まだ仏教にいたらない世間の人々の道である。
身仏;ここでは、作仏・坐仏・身仏の三つが相対して語られている。身仏という述語はないようであるが、思うに、即心是仏という考え方を背景として、このことばを語っているのであろう。(174頁)
■江西(ぜい)の大寂(だいじゃく)禅師は、南嶽の大慧禅師に見(まみ)えて学び、その心印を受けてより以來、たえず坐禅していた。すると、ある時、南嶽が彼を訪ねて問うていった。
「そなたは、坐禅して、なにごとを図(はか)るのであるか」
この問いを、静かに思いめぐらして研究してみるがよい。というのは、坐禅より上になにか意図するところがあるのか、坐禅より外に別になにか意図するところがあるのか、あるいは、なんにも意図するところがあってはならないのか。いま坐禅してどんな図を心に描いているかと問うのである。そこを審(つまび)らかに考えてみるがよいのである。
彫龍を愛するより進みて真龍を愛すべしというが、彫龍にも、真龍にも、ともに雲をよび雨を降らせる力のあることを学ばねばならない。遠きを貴(たっと)しとしてはならぬ。遠きを賤(いや)しとしてはならぬ。むしろ、遠きに慣れるがよい。また、近きを賤しとしてはならぬ。近きを貴しとするもいけない。むしろ近きに習熟するがよい。目に見るところを軽んじてはいけない。目に見るところを重んじてもいけない。また、耳に聞くところを重しとしてもいけない、耳に聞くところを軽しとしてもいけない。むしろ、耳目をして聡明ならしめるがよい。
江西(ぜい)は答えていった。
「作仏を図るのでございます」
このことばを、はっきりと見定めねばならない。作仏すなわち仏となるというのであるが、それはどうなることであるか。仏によって作仏せられるのを作仏というのであるか。あるいは、自分が仏になるのを作仏というのであるか。そてとも、仏にはその能動と受動の両面があるのをひっくるめて作仏というのであるか。あるいはまた、作仏を図るには、その両面を超越するのであるから、超越して作仏するというのか。さらにいえば、作仏にはいろいろとあるけれども、それをすべて図るという一字をもって表現して、「作仏を図る」というのであるか。かくて知ることができる。江西(ぜい)の大寂(だいじゃく)がいうところは、ともあれ坐禅はかならず作仏を図るのであり、坐禅にはかならず作仏の意図があるということである。その意図は、作仏より以前にあるともいえるし、作仏よりも後だということもできるし、まさに作仏のなるその時になるのだともいえるであろう。
では、かりに問うてみるならば、そのようにして心のなかに描く図は、どのような作仏を描き出しているのであろうか。その時、言語・文字をもって描き出されるものには、さらにいろいろの煩わしい表現をまつわっているであろうが、そのことごとくが一つずつ、すべて作仏の表現として、ぴたりと的を射たものであって、その一つをも避けて通ってはならない。もしも一つでも避けて通ろうとするならば、それは生命(いのち)なきものとなるであろう。そして、その生命を失ったとき、それは単なる一箇の文字となってしまうのである。
すると、南嶽は、どこからか一片の塼(かわら)をひろってきて、石にあてて磨き始めた。大寂がそれを見て、問うていった。
「和尚はなにをなさるのですか」
誰がみても、それは塼を磨いているのだとわかる。だが、塼を磨くの道理を知るものは誰か。しかるに、いま大寂は、塼を磨いてどうするのだと問うたのである。そう問うからには、必ずや塼を磨く道理をたずねるのであろう。いったい、自己の考えるところをもって、他に考えようはないように思ってはならない。のみならず、いろいろのなす業(わざ)にもいろいろと学ぶべきろとがあると思い定めねばならない。そうしないから、仏を見ても仏を知らず、水を見ても水を知らず、山を見ても山がわからないのだと思い知るがよい。眼前にみるところのほかには、ほかに考えようはないなどと慌(あわただ)しく結論する者は、仏教を学ぶことはできない。
南嶽は、その問いに答えていった。
「磨いて鏡にしようというのじゃ」
そういう意味を明らかにしなければならない。磨いて鏡となすとは、明らかに道理のあることであって、それは公案にも明らかである。けっして根もないことではない。たとい塼は塼(かわら)であっても、また、たとい鏡は鏡であって、磨くという道理をよくよく究めてみるならば、いくらでもその手本があることが知られよう。古鏡も、明鏡も、塼を磨くことによって鏡となしうるのである。もしもろもろの鏡は塼を磨くことからきたのだと知らなかったならば、仏祖のことばを会得することもできないし、仏祖の垂示に遇うこともできないし、また、仏祖の気合にふれることもできないであろう。
すると、大寂が問うていった。
「塼を磨いて、どうして鏡となすことができましょうや」
だが、まことは、雄々しい男子が塼を磨くのであるから、たとい他の力量をかりなくとも、また、塼を磨くことと鏡をつくることは別のことであっても鏡をなすことは速(すみ)やかであろう。
そこで、南嶽がいった。
「坐禅したからとて、どうして仏となることを得ようか」
それで明らかに知ることができる。坐禅は作仏を期待するものではないという道理があり、作仏は坐禅にかかわらないという趣旨があるが、それがここに明らかに打ち出されているのである。
大寂がいった。
「では、いかがしたならば善いでありましょうか」
そのいい方は、もっぱら世間のそこら辺りで聞く問いによく似ているが、それはまた、出世間のかしこの消息をも問うているのである。たとえば、親友の親友に会った時のようなものであって、わたしの親友は、また彼にも親友である。つまり、どうしたらよいかという問いは、同時にその両方に通ずるのである。
南嶽はいった。
「人が車を御(ぎょ)する時、もし車が行かなかったならば、車を打つがよいか、牛を打つがよいか」
しばらく、「もし車が行かなかったならば」という句について考えてみるならば、車が行くというのはどういうことであろうか、また、車が行かないというのはどういうことであろうか。たとえば、水の流れるというのが、車の行くに当たるのか、それとも、水の流れないのが、車の行くに当たるのであろうか。流れるのは水の行ではないともいえよう。水の行は流れることではないとも考えられるからである。とするならば、「車がもし行かなかったならば」ということばを考えてみるならば、行かないことがあるとも考えられるし、また、行かないことはないとも考えうる。その時によってのことだからである。だから、もし行かなかったならばということばは、一概にそれがいけないと言っているわけではないのである。
続いて、「車を打つがよいか、牛を打つがよいか」という。車を打つこともあり、牛を打つこともあるであろう。だが、そこで、車を打つのと牛を打つのは、同じなのであろうか、別なのであろうか、と考えてみなければならない。すると、世間には車を打つということはないのである。凡夫には打車の法がないのに、仏道には打車の法があることが解ってくる。それが仏道を学ぶ眼目なのである。だが、仏道に打車の法があることを学んでも、それを打牛の法といっしょにしてはならない。よくよく精細に思いめぐらしてみなければならない。
また、打牛の法は、世の常に行なわれていることではあるが、仏道における打牛のことは、さらにいろいろと訊ね学ぶがよい。たとえば、水牛を打つのか、鉄牛を打つのか、泥牛を打つのかと考えてみるがよく、あるいは、鞭(むち)をもって打つか、全世界を打つか、三界唯心の心を打つか、わが骨髄をせめたてて打するかと問うてみるがよく、さらには、拳頭をあげて打つこともあろうし、拳(こぶし)と拳が火花をちらすこともあろうし、また牛が牛を打つということもあろう。
その時、大寂は対(こた)えるところがなかったというが、それをむやみに取り違えてはならない。その時、彼は、塼(かわら)をなげうって玉を得たのであり、頭(かしら)をめぐらしてその面(おもて)の向きを変えることができたのであって、その対(こた)えざるの意味は、誰も横から手を出して奪うことはできない。(179~184頁)
〈注解〉江西大寂禅師;馬祖道一(786寂、寿80)であり、世に江西の馬祖と称せられた。南嶽懐譲の法嗣である。江西(こうぜい)鐘陵(しょうりょう)の開元(げん)寺に住した。諡(おくりな)して大(だい)寂禅師と称する。
南嶽大慧禅師;南嶽懐譲(744寂、寿68)である。六祖慧能の法を嗣ぎ、南嶽の般若寺観音堂に住す。諡(おくりな)して大慧(だいえ)禅師と称する。
図;道元はここで、「図什麽」あるいは「図作仏」の図の一字について、いろいろと思索をめぐらしておる。それは、何事かをはかる、意図することであるとともに、また絵図を描くことに通ずる。しかるに、ここで描かれる図は、心のなかでのことであるから、それを今日のことばでいえばイメージ(観念)がそれにあたる。そこから、「図は作仏より前なるべし。作仏より後なるべし、作仏の正当恁麼時(しょうとういんもじ)なるべし」などという思索が展開されるのである。作仏を修行の果とみれば、そのイメージは、図としてその前にあり、仏とはこれかときがつくのは作仏ののちであるから、その図は作仏の後ともいえるし、sるいは、作仏のなるまさにその時においてこそ、そのイメージは完成するともいえるのである。(185頁)
■南嶽はまた示していった。
「なんじは坐禅を学んでいる。それは坐仏を学んでいるのだよ」
そのことばをよくよく思いめぐらして、仏祖の教えの機微を学びとるがよい。いうところの坐禅を学ぶとは、ずばりとその真相をいえば、どういうことであろうかと思っていたが、それは坐仏を学ぶことだと知ることができた。正伝につながる仏者でなかったならば、とてもとても、このように学坐禅は学坐仏なのだといい切ることはできまい。まことにや、初心の坐禅は、初めての坐禅であり、初めての坐禅は、初めての坐仏であると知るがよろしい。
さらに南嶽は、坐禅について語っていった。
「もし坐禅を学ぶならば、坐禅は座臥ではないのだよ」
そのいうところは、坐禅は坐禅であって、座臥ではないのだということである。坐禅は座臥でないと教えられてみると、自分のすべての行住坐臥が坐禅となるのであって、もはや、これは坐禅に関係が深いの、これは関係が浅いのと、思いわかつことはできない。ましてや、これは迷い、あれは悟りと論じわかつことはできまい。そのようなことを智慧をもって、裁断しうるものは、誰もあろうはずがないのである。
南嶽はまた示していった。
「もし坐仏を学ぶのならば、仏に定まった姿かたちはないのだよ」
いま、さきにいうところの学坐仏について語るならば、こういわなくはならない。そこここの仏が坐仏でましますのは、その定まった姿のない姿を、その姿であらわしているのである。いま仏には定相(じょうそう)がないというのは、それがよく仏の姿をいい得ているのである。そして、定まれる姿のない仏であるがゆえに、坐れる仏の姿もないはずはないのである。だからして、もし坐禅を学ぶならば、それはとりも直さず、坐仏を学ぶということとなる。もしも一定のかたちをとらなかったならば、誰も仏を弁別することはできまい。弁別すべき対象がないからである。それで、坐仏のすがたをとるのである。
南嶽はまたいった。
「そなたがもし坐仏すれば、それがとりもなおさず殺仏(せつぶつ)というものだ」
さらにそのいうところは、坐仏を学びいたれば、仏そのものとなるというのである。坐仏のまさにしかる時は仏そのものなのである。仏そのものの御姿やその智慧の輝きは、いったい如何(いか)ならんと訊ねいたってみると、それは坐仏のなかの何ものでもないのである。これを殺仏というのである。殺の一字は、凡夫の世界にあっては、人を殺すなどということばであるが、けっしてそれと一緒にしてはならない。そこで、坐仏は殺仏であるというのは、どういうことであろうかと、よくよく研究してみるがよろしい。坐仏の功徳に殺仏ということのある道理を、よくよく心によどめて、われらに殺人のことありやなしやと思い究めてみるがよろしい。
南嶽は続けていう。
「もし坐相を執するならば、その理に達するわけではないのだよ」
ここに、坐禅を執するというのは、坐相を捨てて、しかも坐相が目につき気にかかることである。そのゆえは、坐相するからには坐相を離れることはできない。坐相を離れることはできないから、みごとに坐相を執(と)るすがたができても、ねおそれではその道理に達するというわけにはゆかないのでる。そのところの工夫を脱落身心(じん)というのである。
いまだかって坐ったことのないものには、このような道理はありえない。それは坐った時にいえることであり、坐った人にいえることであり、坐れる仏にいえることであり、坐仏を学ぶについていえることである。坐るとはいっても、人の座臥するその坐ではない。人の坐するすがたは、おのずから坐仏に似、仏の坐するに似ているけれども、人が仏となるのであり、仏となる人があるということである。仏となる人があるとはいっても、すべての人が仏となるわけではない。仏がすべて人であるのでもなく、すべての仏がすべての人なのでもないから、人がかならず仏であるのでもなく、仏がかならず人であるのでもない。坐仏という時にもまた同じことである。
いま、南嶽と江西(ぜい)の問答をみれば、師もすぐれ、弟子もすぐれている。坐仏が作仏であることを証(あか)しているのが江西であり、作仏を坐仏として示しているのが南嶽である。南嶽の門下にはこのような追求があったし、薬山の門下にはさきのような垂示があった。よってもって、仏祖たちの要(かなめ)とするところは坐仏であったと知られるであろう。すでに仏祖たる者はみなこれを要として用いてきた。だが、いまだ仏祖にいたらぬ者には、夢にもいまだ見ざるところであるのも、詮(せん)ないことであろう。(189~192頁)
〈注解〉殺仏;古注に「殺仏とは、逆害の殺にあらず、ただ第二人なきのみにあらず、一人に逢う一人もなきなり」とある。いままでの概念としての仏は克服されてなくなることをいうのであろう。
脱落身心;身心(じん)を脱落する。あるいは、身心脱落すなわち身心が脱落するという。ぴたりと坐相をとる。その時、身心一如にして、その理屈をあげつらう心のいとなみなどは別にないのである。「若執坐相、非達其理」とは、その境地であるとするのである。(192頁)
■いったい、西のかたでも東のかたでも、仏法がつたわるというのは、かならず坐仏が伝わることなのである。それが仏法の肝心かなめだからである。だから、仏法が伝わらなければ、坐禅は伝わらないのであり、それが仏祖から仏祖へと伝えられたのは、坐禅の趣によってである。だから、その趣を正伝しないものは仏祖ではないのである。
思うに、この一つの教えが判らなければ、よろずの教えが判らないのであり、よろずの修行がわからないのである。それらの事どもを明らかにせずしては、明眼(めいげん)の人ということもできない、得道の人ともいえない。ましてや、古今の仏祖に列することはとてもできないのであろう。だから、仏祖はかならず坐禅を正伝するのだと断言されるのである。
また、仏祖の光明に照らされるというのは、この坐禅を修め学ぶことである。愚かな人々は、仏の光明というと、日月の光のごとく、あるいは、珠(たま)のひかりの輝きのようなものかと思い誤る。日月のひかり輝くところは、わずかに衆生の住するこの世界に限られ、とても仏の光明には比べものにならない。仏の光明というのは、一つの句を聴いて忘れないのがそれであり、一つの教えを保ち守るのがそれであり、坐禅を直々に伝受するのがそれである。もしも仏の光明に照らされるのでなかったならば、それらを保ちつづけることも、信じ受けることもできないのである。(198頁)
■ 坐禅箴(しん)(宏智(わんし)禅師正覚撰)
仏祖のかなめとなしたまうところは、事に触れずして知り、縁に対せずして照す。その知はおのずから微(び)であり、縁に対せずして照すがゆえに、その照はおのずから妙である。その知はおのずから微(び)であるから、まったく分別のおもいがなく、その照はおのずから妙であるから、毛筋ほどの兆(きざし)もない。まったく分別のおもいがないから、その知は類(たぐい)なくしてふしぎであり、毛筋ほどの兆(きざし)もないから、その照はまったく捉えることができない。水は清くして底に徹し、そこに魚が悠々として游いでいる。空はひろくして限りがなく、鳥ははるけくも飛んでゆく。
この坐禅箴の示すところは、坐禅の自由自在のはたらきを語っている。それは言葉やかたちを超えたところの作法であり、また、遠く今昔を越えたところの定則である。そこには、もはや世間の人々のいう仏祖のすがたはなく、そこには、もはやわが身もわが心もなく、そこには、ただ見馴れぬ異形の人があるのみである。
さて、仏々の要機(ようき)という。仏たちはかならず仏たることを肝心かなめとするのであり、その要機の実現したのが、とりもなおさず坐禅である。また、祖々の機要という。先師に別にそんな言い方があるわけではない。それが祖々たる所以である。すでに法を伝え、衣を伝えている。ちょっと頭(かしら)をめぐらして面(おもて)の向きを変えれば、それはそのまま仏々の要機である。それをまた、ちょっと面(おもて)の向きを変えて頭(かしら)をめぐらせば、それがそのまま祖々の機要とするところである。
また、事に触れずして知るという。その知はむろん感覚の知ではない。感覚の知は小さな知である。叡智(えいち)の知ではない。叡智的知は精神の能動的なはたらきである。だから、その知は事に触れないのである。事にかかわらないのがその知のありようである。だからとて、それを遍(あまね)き知だと思ってはならないし、あるいは、それを自(おのずか)らの知と限定してもいけない。その事に触れずというのは、なにものにも滞(とどこお)ることなき、身心脱落の境地にあることにほかならない。
また、縁に対せずして照らすという。その照らすというは、外に向かって何物かを照らすというのでなく、また、わがうちにおいて霊がひとり輝くというがごときでもない。ただ外境にかかわらずして照らすのである。認識の対象がおのずから輝いているのであるから、それが照らされて輝くということではないのである。つまり、この世界のすべてが、あるがままにして然るのであって、この世界が壊(こわ)れてはじめて然るというものではない。まことに微であり、妙であって、関係があって、かつ関係がないというところである。
さらに、その知はおのずから微であるから、まったく分別の思いがないという。思いという知のいとなみは、かならずしも他の力をかりない。その知には形がある。その形は山であり河である。その山河は微かではあるが、また不可思議なものであって、それを用うれば、活撥撥地(かっぱつぱつち)として生きた働きをなす。たとえば、龍は禹(う)門を越えてはじめて龍となるというが、龍をwがくものは、そんなことには少しもこだわらない。そんなちょっとしたことに用いる知も、この世界のあらゆる山河を捉えきたり、力を尽くして知るのである。わが知にそのような山河に直接した基礎がなかったならば、一知も半解もありえないのである。では、分析的思惟(ゆい)はその後において到来したのに、われらはそれに捉われているのかと歎く必要はない。仏たちもすでに曾(か)つては分別なされたが、いまはすでに仏となっておられる。「曾つて無し」とはいうが、「すでに曾つて」である。その「すでに曾つて」分別なされた方々が仏となっているのである。とするならば、「曾つて分別の思いなし」とは、そんな人には逢わないよというところなのであろう。
また、その照はおのずから妙であるから、毛筋ほどの兆(きざし)もないという。毛筋ほどといっておるが、それはこの世界のことごとくのことをいっておる。それなのに、おのずから妙であり、みずから照らすのであるから、光などはどこにもないように見える。だが、見えないとて目をあやしんではならぬ。光は見えるはずと聞いて、その耳のみを信じてはいけない。「言外に向かって直々にその本源をたずねるがよく、言中に向かってその規定をもとめてはならぬ」というが、いまいうところの照はそれである。だから類(たぐい)がないのであり、だから捉えることができないのである。それをふしぎとして伝え来たり、それをそのとおりと頂いてきたのに、わたしだけが拒んで疑っているのであろうか。
さらに、水が清らかにして底に徹し、魚が悠々として游いでいるという。水が清いというのは、空にある水は清らかな水というには差し支えがあろう。ましてや、この世界に広く行きわたっている水は、水清らかという水ではない。ただ、果てしなくして岸辺もないのが、徹底の清らかな水というものである。魚がもしこの水のなかを行くとするならば、行くとはいえ、いやその行程いく万里に及ぼうととも、その行は測ることもできず、窮(きわ)まるところもないであろう。目測する岸も無く、浮かぶ雲もなく、沈む底もないのであるから、誰も測量することはできない。測ろうとしてもただ徹底の清水のみである。坐禅のありようは、その魚の行くがごとく、千万の行程がありとも、誰も測ることはできない。その徹底透脱(とうだつ)の行程は、すべて鳥飛んで行くことなしというところである。
さらに、最後に、空は闊(ひろ)くして限りもなく、鳥ははるけくも飛んでゆくという。空が闊いというのは、天にかかっているからではない。天にかかっているような空は、闊い空とはいいがたい。ましてや、此処(ここ)にもある彼処(あそこ)にもあるというような空は、とても闊い空とはいえない。ただ、見える見えないにかかわらず、表もなく裏もない空にして、はじめて闊い空なのである。鳥がもしその空を飛べば、それが空を飛ぶというものの一つのありようである。その空を飛ぶあとを測ることができない。その飛ぶ空はこの世界のすべてにわたる。この世界のことごとくが飛ぶ空であるから、その飛ぶこと、いくばくなりと知ることはできない。測ることのできないところを表現するに、いま「杳々(ようよう)」というのである。はるかにして知りがたいというのである。まさに「足下に一糸をもとどめずして去るべし」である。けだし、空が飛び去るときには、鳥も飛び去り、鳥の飛び去るときには、空もまた飛び去るのである。その飛び去り方をいうべきことばを求むれば、「やだここに在り」というところであろう。それが坐上のいましめである。どこに行こうとも、いつでも勇躍して「ただここに在り」というがよいのである。(200~204頁)
〈注解〉※このいささか長大な一節は、詮ずるところ、宏智(わんし)禅師の坐禅箴を挙げて、それに懇切なる評釈を与えたものである。それに先立って、道元は、まず、従来の坐禅銘(めい)・坐禅儀・坐禅箴と称するものを評し、その多くが坐禅のなんたるかを知らない輩(やから)の作るところで、まったく取るに足らざるものであるとなし、ただ、この宏智禅師の坐禅箴のみが、仏祖にふさわしいものとして、その全分をあげて記し、かつ、懇切なる評釈を加えたものと知られる。
六道輪廻の業相;六道とは、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の境涯をいうことばであるが、そのいずれも、つまりは、衆生のおもむき住する世界であり、日月の輝くのは、その世界でのいとなみにすぎぬというのである。
坐禅銘・坐禅儀・坐禅箴;坐禅銘といえば、坐禅の功徳をたたえることが中心となるであろうし、坐禅儀といえば、その儀則・作法を語ることに重点がおかれ、また、坐禅箴となれば、それについての訓戒・いましめということで、坐禅のなんたるかを説くことを旨とするであろう。道元にもまた、坐禅儀ならびに坐禅箴の制作があるが、いまこの坐禅箴においては、まさしく坐禅のなんたるかを説くことに、力を尽くしていることが知られる。
十地・等覚;菩薩の修行の段階を、十信・十住・十行・十廻向・十地・等覚・妙覚の五十二位にわかつ。そのなかの十地と等覚とをあげていうのである。その完成の一歩手前の境地なのである。
宏智禅師正覚和尚;宏智(わんし)正覚(1157寂、寿67)または天童正覚(しょうがく)と称す。丹霞子淳(たんかしじゅん)の法嗣(ほっす)。晩年天童山に住すること三十年に及んだ。続いて記される「坐禅箴」は『宏智広録』巻八に見えている。
要機;もっとも大事な心のありようというほどの意。
杳杳(ようよう);はるか、くらい。
声色向上の威儀;声すなわちことばや、色すなわち目に見えるすがたを超越した作法というほどの意。
父母未生前の節目;時間の関係を超えたこと、すなわち、古今を通じてなすべき定めというほどの意
覚知・了知;覚知は感覚による知であり、了知は理解による知である。感覚は受動的であるが、理解は叡知の能動的なはたらきによる。だから、「了知は造作(ぞうさ)なり」というのである。(204~206頁)
■宏智禅師の坐禅箴は以上のごとくである。歴代の宿老(しゅくろう)のなかにも、このような坐禅箴は見ることをえない。諸方の俗物どもが、もしこの坐禅箴のような見事な表現を試みようとしても、一生や二生ではとても及ばぬところである。いま諸方を訪ねても、こんな坐禅箴は他処(よそ)のどこにもない。先師如浄は、法堂(はっとう)にお出ましの時、つねづね「宏智は古仏である」と仰せられた。ほかの者をそのようにいうことは全くなかった。人を知る眼があれば、仏祖の心を知ることができるのである。よってもって、洞山(とうざん)の門に仏祖のましますことが知られる。
いま宏智禅師を去ること八十余年であるが、わたしは、かの坐禅箴をみて、つぎのような坐禅箴を制作した。いまは仁治三年の三月十八日である。今年より紹興二十七年十月八日(宏智の没年)にいたるまでを遡(さかのぼ)って数うれば、なおわずかに八十五年である。
いま制作するところの坐禅箴はこうである。
坐禅箴
仏祖が要(かなめ)となしたまう心の動きは、思量せずして現じ、渉入(しょうにゅう)せずして成ずるにある。思量せずして現ずるがゆえに、その現ずるところはおのずからわが身心(しんじん)に親しく、渉入せずして成ずるがゆえに、その成ずるところはおのずから真実にかなう。その現ずるところがおのずから親しければ、そこにはまったく混りけがなく、その成ずるところがおのずから真実にかなっておるから、そこにはいささかの偏(かたよ)りもない。まったく混りけなくわが身心に親しいのであるから、もはや何ものをも捨てることなくして身心脱落がなるのであり、いささかの偏りもなくして真実にかなっているのであるから、もはやなんの図(はか)らうところもなくして坐禅修行がなるのである。水清らかにして地に徹し、魚行いいて魚に似たり。空闊(ひろ)うして天に透(とお)り、鳥飛んで鳥の如し。
かの宏智禅師の坐禅箴は、けっして、その表現いまだしというわけではないが、また、このように言うこともできるであろう。およそ仏祖の流れを汲む者は、かならず坐禅を一大事として学ぶがよい。それが仏祖正伝のしるしというものである。
正法眼蔵 坐禅箴
仁治三年三月十八日、興聖宝林寺にありて記す。
同四年冬十一月、越州吉田県吉峰(よしみね)精舎にありて衆に示す。(208~209頁)
仏向上事(ぶっこうじょうじ)
■開題
この一巻が記され、そして、例によって興聖寺において衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の三月二十三日とある。克明に記された奥書のいうところである。ひるがえってみると、その同じ三月中には、さきに「坐禅箴」の巻が脱稿し、この一巻に続いては、また「恁麼(いんも)」の巻が制作されている。道元の制作の意欲はいよいよ高揚しきたったもののように察せられる。
では、いったい、この巻題にいうところの「仏向上事」とは、いかなることをいうのであろうか。そのことから、まず申さねばなるまい。
それは、かならずしも一般にひろく用いられている仏教述語ではなく、洞山(とうざん)良价(りょうかい)にいたってはじめて語りいでられたことばである。道元は、この巻の冒頭に、その洞山のことばを挙げ、そしていっておる。
「いまいふところの仏向上事の道(どう)、大師その本祖なり。自余の仏祖は、大師の道を参学しきたり、仏向上事を体得するなり」
だが、その洞山のいうところがすでに、そのことは体得してのみ判ることであって、話しただけでは、「そなたたちに判らない」といっておる。つまり、凡夫の境地にうごめいていたる私どもには、聞いたって判らない、読んだって判りっこないといっている。それだけはっきりと言われると、私もまた、当然ここで解説の筆をなげうつの他はないのであある。
それにもかかわらず、いま道元は、そのことについて、なお数百言を費やして、私どものために噛んで含めるような解説をここにいとなんでいる。わたしは、いまはせめてその解説に取りすがって、この問題の責めをふさいでおきたいと思う。
さて、その道元の解説は、その最後段に及んで、ずばりとこの「仏向上事」ということばを説明してこういっておる。
「いはゆる仏向上事といふは、仏にいたりて、すすみてさらに仏をみるなり」
向上とは、わたしどもの通常いうところの、上に向かって進んでゆくことのほかではないが、では、どこからどこに向かって進んでゆくのかというと、ここにはそれは、すでに「仏にいたりて」、さらに「仏をみる」ことだと知られる。わたしどもは、人が凡夫の位からすすんで仏の境地にまでいたることしか考えないのが常である。しかるに、いま洞山が「仏向上事」という時には、仏にいたったものが、さらに進んでさらに「仏をみる」のだと知られる。とするならば、まだ凡夫の位にあってうごめいている私どもにとって、仏の境地からさらに上に向かって進んでゆくなど、いったいどういうことであるか、そのイメージさえも心に描くことができないのも、また理の当然としなければなるまい。
では、いったい洞山はどうしてそんなことを雲水たちに語ったのであろうか。道元の解説は、そこをこのように説き明しているのである。
「而今(にこん)の示衆(じしゅ)は、仏向上人となるべしとにあらず、仏向上人と相見(しょうけん)すべしとにあらず、ただしばらく仏向上人ありとしるべしとなり」
まったく到りつくした解説である。いま洞山は、すでに仏祖となって、さらに仏祖を越えてゆこうとしている方である。ひとつ山を越えてみると、さらに彼方にまた越えねばならぬ山がある。まさに仏道は無窮である。洞山はいまそのことを体得して、その目前に展開する新しい風景を「いささか話しておきたい」のだという。その発言の心は、いますぐに、「そなたたちも仏を越える人となれ」というのでもなく、あるいは、「仏を越える人に相見(まみ)えるがよい」というのでもない。ただ、しばらく、「仏を越える人というものがあると、知るがよい」というのだという。
それで、わたしはふと思い出したことがある。それは、かの「現成公案」の巻きに、
「悟迹(ごせき)の休歇(きゅうかつ)なるあり、休歇ねる悟迹を長長出ならしむ」
というふしぎな一句があったことである。それは、悟ったらそこで一休みするもよかろうということであり、また、一休みしたらそこからまた遠く抜け出てゆかめばならぬ、というほどの意であろう。ああ、その後半こそ、仏向上事ということだったのかと、いまになって気がつくのである。
ともあれ、ここには、広大無辺なる仏教の風景が打ち出されており、その道を行くものは、せめて「道(どう)は無窮」なることを、知るだけでも知っておくがよい、気がついてもらいたいというのが、このようなことをふと説きいでた洞山の心であり、また、この一巻を制作した道元の心であったと知られるのである。(212~214頁)
■黄檗和尚はいった。
「いったい、出家した人は、当然、これまで申してきたようなことがあることを知らねばならない。しかるに、たとえば、四祖のお弟子であった牛頭(ごず)法融大師のごときは、縦横自在には説くけれども、なおいまだ向上の急処を知らない。その眼目頭脳があってこそ、はじめて、いずれが正かいずれが邪かを弁別することができるのである」
いま黄檗がいうところの「これまで申してきたようなこと」というのは、昔から仏や祖たちが正しく伝えてきたことである。正法(しょうぼう)の眼目を蔵するところであり、涅槃のふしぎな心境である。それは、もともと自己にそなわるものであるけれども、まさに「知らねばならない」のであり、自己にそなわるだけでは、「なおいまだ知らない」のである。仏より仏へと正伝するのでなくては、夢にすら見ることもできないのである。
黄檗希運は、百丈懐海の法嗣(ほっす)であって、しかも百丈よりもすぐれ、馬祖道一の孫弟子にあたり、しかも馬祖よりもすぐれている。おおよそその辺りの仏祖三、四代の間において、黄檗に肩を比べる者はいない。ただひとり、その黄檗のみがあって、いまここに、牛頭山の法融といえども、いまだ弁舌と叡智の二つの角はそなえていなかったことを明かしたのである。それは、ほかの仏祖たちのいまだ知らざるところであった。(244~245頁)
〈注解〉牛頭法融;(657寂、寿64)牛頭禅の祖。四祖道信の傍系の法嗣。牛頭山に住す。その説くところは、いま道元の解説によって、その一半を知ることを得るであろう。
牛頭の両角;牛の頭には両角があるが、牛頭には両角がないといっている。つまり、彼には弁舌はあるが、真の修行による叡智はないといっているのである。
十聖三賢;まだ修行の途中にあるものというほどの意。十聖は、菩薩の十地(じゅうじ)までいたった聖者(しょうじゃ)をいい、なお十地以前の三十位にあるものを三賢という。(246~247頁)
恁麼(いんも)
■開題
この一巻が制作せられて、例によって宇治県の興聖宝林寺において衆(しゅ)に示されたのは、仁治三年(1242)の三月二十日のことであったと記されている。とするならば、まさに春ようやく闌(た)けて、百花きそい咲くの候であったはずである。文中に「たとへば東君(とうくん)の春にあふがごとし」という一句のあったことも、ふと思い出されるというものである。
「恁麼」という言葉は、よく知られるように、禅門の人々が好んで口にし筆にするところである。そのことばは、もと宋代の俗語にいずるところであって、また、什麼・甚麼(いんも)・怎麼(いんも)・与麼(いんも)などの文字があてられるのほか、また恁地(いんち)などというようである。
それがもと俗語として有する意味は、「このような」とか、「このとおり」とか、「そのとおり」とかいうことであり、それが形容詞にも、名詞にも、疑問詞にも用いられているようである。だから、試みに「恁麼物恁麼来(いんもぶついんもらい)」なる句を、和文でも俗語風に訳してみるならば、「こげん物がどげんして来よったのじゃ」といった具合になろうというものである。(250頁)
●原文
身すでにわたくしにあらず、いのちは光陰にうつされてしばらくもとどめがたし。紅顔いづくへかさりにし、たずねんとするに蹤跡(しょうせき)なし。つらつら観ずるところに、往時のふたたびあふべからざるおほし。赤心もとどまらず、片片として往来す。たとひまことありといふとも、吾我のほとりにとどこほるものにあらず。(253頁)
■この身がすでにわたしのものではないのである。生命は時間とともに移ろうて、しばしの程もとどまることはできない。若き日の紅顔はいったい何処にいってしまったのか。尋ねようとしても跡かたもない。つくづくと思うてはみるけれども、過ぎ去ったことにはもはやふたたび遇うことはできない。心もまたとどまらず、ただあれこれと往(ゆ)き来するばかりである。たとい、心はまことに存するものだとしても、かならずしもわが事わが物のまわりに停滞しているわけでもない。
それなのに、いつから、どこからということなしに、いつしか発心するものがある。その心が起こってからは、その人は、これまで弄(もてあそ)んでいたことはすべて投げ捨てて、ひたすら、いまだ聞かざるところを聞かんと願い、いまだ証(さと)らざるところを証らんことを求め始める。それは、けっして自己のなすところではあるまい。それはそれは恁麼の人であるがつえに、かくなるものと知られるのである。
では、なぜそれが恁麼の人であるというのであるか。それは、ほかでもない、恁麼の事を得たいと思っているから、恁麼の人であるというのである。そして、すでに恁麼の人としての面目をそなえているからには、もはや恁麼の事を思い煩うの要はないというのである。たとい思い悩んだからといって、それは恁麼の事なのであるから、けっして憂うることはないのである。また、恁麼の事はどうしてそうなのであるかと、驚き怪しむこともあるまい。たとい驚いても怪しんでも、それはやっぱりそうなのである。あるがままにあるものを驚いたり、怪しんだりしてはならないのである。
それは、ただ仏の尺度をもってのみ量るべきではない。また、心の尺度のみをもって量るべきでもない。あるいは、法則の尺度のみをもって量るべきでもなく、この世界の尺度をもってのみ量るべきでもない。ただまさに「すでに恁麼の人であるからには、いかでか恁麼の事を思い煩う要があろうか」であろう。だから、見えるもの聞こえるもののあるがままがそうなのであり、われの身や心のあるがままがそうなのであり、諸仏のあるがままがそうであるはずである。
たとえば、人が地に躓いて倒れる。その時、それをありのままに、ああ地によって倒れたと理解すると、また必ず地によって起きることができる。そうすれば、地によって倒れたことも、なんの怪しむこともなかろう。それを、古い昔から、西の方天竺でも、また天上においても、こんな具合にいっておる。
「もし地によって倒れたならば、また地によって起(た)つがよい。地を離れて起きようとしても、とても起(た)てる道理はない」
そのいうところは、地によって倒れるものは、かならず地によって起きるのであって、地によらずして起きようとしても、けっして起きることはできないというのである。それなのに、そこを拈(ひね)くりまわして、大悟(だいご)こそうるわしく、身心(しんじん)は脱け出さねばならぬかのように思っている。だからして、もし「諸仏が成道の消息はいかに」と問うならば、「地によって倒れるものは、また地によって起きる」ようなものだと語られるのである。そこのところをよく研究して、これまでのこともはっきりとするがよく、これからのこともはっきりとするがよく、また、今のこともはっきりとするがよい。悟るも悟らぬも、迷うも迷わぬも、あるいは、悟りに躓くも、迷いに妨げられるも、いずれもみな地によって倒れるものが、また地によって起つの道理である。それが天上でも地上でもいうところであり、西の方でも東の国でもいうところであり、また、古でも今でもいうところであり、古仏でも新仏でもそういうところであって、そのいい方は、まことにいい得て、見事なものだといわねばならない。
だがしかし、ただそのようにのみ理解して、さらにもっとほかの考え方ができないようでは、それはなお、そのことばをよくよく研究したものとはいえないであろう。なるほど古仏のことばはそのように伝えられているが、さらに自分が古仏として古仏のいい方を試みるならば、そこにはじめて進歩というものがあるであろう。たとえいまだ西の方天竺においても説かれず、あるいは天上においても語られたことがなくとも、さらに別のいい方があってもよいはずなのである。
では、試みにいってみるならば、
「地によって倒れるものが、もし地によって起きようとするならば、いつまで経っても、けっして起きることはできない」
と、それは、なにか一つの活路があって、はじめて起きることができるとするのである。それは、またいうなれば、
「地によって倒れるものは、かならず空(そら)によって起き、空にあって倒れるものは、かならず地によって起きるのだ」
ということである。もしそうでなかったならば、とても起きることはできないのである。もろもろの仏もまた祖も、すべてそうであったのである。
すると、人があって、このように問うたとしよう。
「空と地とは、どのくらい離れているか」
もしそのように問う者があれば、わたしは彼に向かって、このようにいうであろう。
「空と地とは、相去ること十万八千里である。もし地によって倒れるものは、かならず空によって起きる。空をはなれて起きようとしても、とても起(た)てる道理はない。また、もし空によって倒れるものは、かならず地によって起きる。地を離れて起きようとしても、とても起きられる道理はないのだ」
そのようにいうことのできない者は、まだ仏教でいうところの地と空の尺度を、聞いたことも見たこともないのであろう。(257~261頁)
〈注解〉恁麼;また什(いんも)などとしるす。禅門の用語。もと宋代の俗語にして、こんな、そんなの意をもったことばであり、また、疑問にもちいて、どんな、いかなるの意をもあらわす。だが、禅家の人々がそのことばに託するところは、なおはなはだ微妙であって、道元がいまこの一巻をもって語ろうとするところも、その微妙な意味するところである。開題をも参照せられたい。
吾我;吾も我もいずれも「われ」であるが、強いて分別していうなれば、吾は自己の存在を指さし、我は我所すなわち「われ」の所有するところをいう。(261頁)
■第十七代の祖師は、僧伽難提(そうぎゃなんだい)尊者という方で、その法嗣(ほっす)に伽耶舎多(がやしゃた)があった。ある時、尊者は、軒端(のきば)にかけた風鈴が風にふかれて鳴るのを聞いて、伽耶舎多をかえりみて問うていった。
「あれは、風が鳴るのであろうか、鈴が鳴るのであろうか」
伽耶舎多は答えていった。
「風が鳴るのでも、鈴が鳴るのでもございません。わが心が鳴るのでございます」
尊者はまた問うていった。
「その心というは、また何であるか」
伽耶舎多は答えていった。
「いずれも静かだからでございます」
尊者はいった。
「善いかな、善いかな。わが道(どう)を嗣ぐべきものは、汝のほかにはない」
かくて、尊者はついに伽耶舎多に正法(しょうぼう)の眼睛(がんぜい)を伝えた。
それは、風の鳴るにもあらざるところを、「わが心が鳴る」と学ぶのであり、また、鈴の鳴るとのでもないところを、「わが心が鳴る」と学ぶのである。だが、「わが心が鳴る」と、そうはいうけれども、まことは、すべてが静かなのである。西の方天竺から東の方にそのような問答が伝えられて、古代から今日にいたるまで、それが仏教を学ぶための一つの基準とされているのであるが、また、それを誤って解するものも少なくない。たとえば、それをこのように解するものもある。いま多伽耶舎多が、「風が鳴るのでない、鈴が鳴るのでもない、わが心が鳴るのだ」というのは、まさにその時にあたって、それを聞こうとする心のはたらきが起こる。その心のはたらきの起こるのを心というのであって、もしその心のはたらきがなかったならば、その鳴る音をきくことはありえない。その心のなたらきによって聞くということが成立するのであるから、そこに聞(もん)の根本があるということができる。だから、心が鳴るのだというのであるとする。それは正しい解釈ではない。正(しょう)師に就かないから、こういうことになるのである。それは、たとうれば、依主釈(えしゅしゃく)だの隣近(りんごん)釈だのとあげつらう学者どもの解釈のようなものであって、そんなのは仏道の至妙な学とはいえない。
それに反して、仏道の正しい嗣ぎ手である仏祖に学びいたってみると、かの最高の智慧、正法の眼睛(がんぜい)をもって、これを寂静といい、無為といい、三昧といい、あるいは陀羅尼という。その道理をいわば、一事一物が静かでありさえすれば、総(すべ)てがみな静かだというのである。風のふくこと静かなれば、鈴の鳴ることもまた静かである。だから「ともに寂静なり」というのである。「心が鳴る」というは、風が鳴るからでもない、また心が鳴るからでもない。仏祖はそのようにいうのである。わたしどもがこの身をもってよく知っているありのままの姿を、あれこれと拈(ひね)くり回すよりも、むしろ、ただ、風が鳴る、鈴が鳴る、風に吹かれて鳴る、あるいは、鳴っているから鳴っているというがよろしい。「なんぞ恁麼の事に関せん」であって、その時、ありのままなるものがありのままであるのである。(263~265頁)
〈注解〉僧伽難提;禅門にいう付法蔵の仏祖の第十七祖である。舎衞城の出身、羅睺羅多(らごらた)の法を嗣ぎ、中印度に教化を布いたという。
伽耶舎多;禅門でいう第十八祖。中印度の出身。僧伽難提の法を嗣ぎ、大月氏国に布教した。(261頁)
依主(えしゅ)・隣近(りんごん);梵語の合成語を解釈する六種の方法があり、これを六(りく)合釈もしくは六離合釈(りくりがっしゃく)などという。その六種のなかに依主釈とか隣近釈という項目があげられている。そんなスコラスティックな論議にふけっている学者のわざを嘲笑(あざわら)って、「依主・隣近の論師(じ)の釈」なる句をなしているのである。まず依主釈というのは、「所依(しょえ)為主」の意であって、たとえば「眼(げん)識」という合成語は、その識は眼に依って生ずるのであるから、眼を主として、それによって生ずる識と釈するのだという。また、隣近釈というのは、たとえば四念処(じょ)という合成語は、身・受・心・法を観ずることであって、その本体は慧であるが、その営みにつれて念の作用がつよく作用するので念処と名づけるのだという。そんなことのみに頭をつっこんでいては、「仏道の玄学」はならぬといっておるのである。
陀羅尼;訳して能持などとする。観ずるところの法をよく持して散佚(さんいつ)せしめざるをいうのであるが、ここでは特に、他人の毀誉(きよ)のことばなどによって心を動揺せしめないことをいっておるのであろう。(266~267頁)
■第三十三祖、曹谿山の大鑑禅師が、まだ出家となる以前のことであるが、広州の法性(ほっしょう)寺に泊まったことがあった。すると、そこに二人の僧があって論争しておった。一人の僧は、「旛(はた)が動くのだ」といった。もう一人の僧は、「風が動くのだよ」といった。そんな具合に、たがいに言いあらそって、とどまるところがなかった。そこで六祖(大鑑禅師)がいった。「風が動くのでもない、旛が動くのでもない。そなたがたの心が動くのである」
その二人の僧は、それを聞いてただちに信じ受けた。その二人の僧は西の方から来た者であったという。
しかるに、いまのこのいい方は、風も旛(はた)もまた動くのも、すべて心であるのだと、六祖はそういったことになる。それでは、まったく、六祖のことばを聞いても、六祖のことばを解しないこととなる。ましてや、六祖のいい得たところをよく表現するものとはいえない。どうして、そんなことをいうのであるか。それは、六祖が「そなたがたの心が動くのだ」というのを聞いて、そのことばの意味するところをいわんとして、そのことばのままに「仁者(じんしゃ)の心が動くのだ」と表現したのでは、まだ六祖に見(まみ)えたものとはいえない、六祖を解するものにあらず、六祖の遠き弟子とはいいがたい。いま六祖の弟子として、六祖のことばを表現し、六祖の身心(しんじん)を得て言表するには、このようにいうべきである。さきにいうところの「仁者(じんしゃ)の心が動く」というはともあれ、さらに「仁者が動く」ということができよう。どうしてそういうのであるか。それは、動くものが動くからであり、そなたがたはそなたがたであるからである。すでに恁麼の人であるがゆえに、あるがままにこそいうのである。
六祖慧能は以前新州のきこりであった。山のことや水のことにはよく通じていた。だが、青松のもとに心をめぐらして、その根本を切断したことはあっても、僧堂の明窓のもとにゆったりと坐して、心が照らす古き教えがあろうなどとは、知るべき道理もなかった。また、わが心をすすぎ清めるわざなども、誰にも習ったことはなかった。その彼が、ふと町にあって経を聞いた、それも自分で期待したことでもなく、また他の人がすすめたわけでもない。彼はまだ幼いころに父を喪(うしな)い、長じてからは母を養っていた。わが衣服のなかに一粒の明珠があって、それがやがて天地を照らすものとなろうとは、つゆ思いもかけぬところであった。それが、忽然(こつねん)として目をさまして、老母をすて、善知識を訪ねたのであるから、人の世にも稀なこととしなければならぬ。もとより恩愛を軽んじたのではない。ただ法を重んずるがゆえに、恩をもなお軽しとして恩愛を捨てたのである。これが、とりもなおさず、「智ある者もし聞かば、すなわちよく信解(しんげ)するであろう」という所以である。
したがってまた、智というものは、人に学んで得るものでなく、みずから造り出すものでもなく、智がよく智に伝えられるのであり、智がよく智をたずねるのである。『大唐西域(さいいき)記』にいう五百の蝙蝠(こうもり)は、経を聞いて身の焼かれることも知らず、死してのち聖者(しょうじゃ)の境地を成就したという。それは智がみずからの身をほろぼしたのであるが、智には、もともと別に身も心もないのである。また、『金光明経』の説くところによれば、乾上がった池のたくさんの魚どもが、大乗経典を聞くことを得て、天に生まれることを得たという。そこでは、智がそのまま身であるがゆえに、なんの因縁もまくとも、法を聞けばただちに信解するのである。
智はどこからか来るものでもなく、入(はい)りこむものでもない。たとえば、陽(ひ)の神が春にあうようなものである。智は、また有念でも、無念でもなく、あるいは有心でも、無心でもない。ましてや、大小にかかわるものでもなく、あるいは、迷うの悟るのといったものでもない。よいうのは、まだ仏法がどんなものであるかも知らず、以前から聞いているわけではないから、仏法を慕っていたわけでもなく、求めていたわけでもないものが、ふと法を聞くと、たちまち恩をも軽んじ、身をも忘れるというのは、つまり、「有智(うち)」の身心というものは、もともと自己のものではないから、そのようなこととなるのである。「すなわちよく信解するであろう」とは、そのことをいうのである。
思うに、わたしどもは、その智をもちながら、いくたびとなき生死を繰り返して、ただいたずらに俗塵のなかにとどまってきたことか。それは、なお、玉(ぎょく)をそのなかに包んだ石が、玉も石に包まれているとは知らず、石も玉を包んでいるとは気がつかないようなものである。人がそれを知ってこれをとるのは、玉の期待するところでもなく、石の予期するところでもない。あるいは、石の知るところでもなく、玉の思うところでもない。だが、人もまた智もそれと知らなくとも、いつかは必ず、智が道(どう)を開くときがあろうというものである。
「無智にして疑い怪しまば、すなわち永(とこし)えに失うこととなる」ということばがある。智はけっして有りというべきでもなく、また無しというべきものでもないのであるが、ある時には春松の有るがあり、また秋菊の無きときがある。もしも無智にして疑い怪しむ時には、正しき智慧もすべて疑われ、もろもろの事もすべて怪しむこととなる。そのとき、それは永久に失われてしまうのである。聞くべきことばも、証(さと)るべきことも、すべてまったく疑い怪しまれるのである。
しかるに、この世界のすべてのことは、われじゃ誰じゃにかかわることなく、なんの包み蔵(かく)すところもなく、どこまでも一本道の見通しである。たとい春が来て芽を出し枝がのびたとしても、十方の仏土のなかには、ただ一つの真実の教えがあるのみであり、たとい秋到って葉が落ちたとしても、それもまた万物は万物のありように住しているいるのであり、世間のすがたはいつも変わりがないのである。それがすでに恁麼の事なのであって、有智と無智とは、昼と夜、一日の両面にすぎない。六祖もまた、そのような恁麼の人であったから、恁麼の事にぱっと眼を開いたのである。そこですぐ黄梅山(おうばいざん)にいたって、大(だい)満禅師(弘忍)を拝したところが、行者(あんじゃ)の室に投げ込まれた。そこで来る夜も来る夜も米を碓(つ)いていたが、およそ八箇月を経たころのこと、ある夜ふけてのころ、大満禅師がみずからそっと碓房(たいぼう)にやってきて、六祖に問うていった。
「米は白くなったかな」
六祖はいった。
「白くなりましたが、まだ篩(ふる)ってはおりません」
すると、大満は杖をもって、ぽんぽんぽんと三度碓(うす)を叩いた。それを見て、六祖は箕(み)に米を入れて、三度あおりふるった。その時、この師とこの弟子の呼吸はぴたりと合ったのだという。自分でも気がつかず、相手もそうとは思わなかったのであるが、伝法(でんぽう)・伝衣(でんえ)のことは、まさしくその瞬間になったのであった。(270~275頁)
〈注解〉※ここには六祖慧能が五祖弘忍に見(まみ)えて、その法を嗣ぐものとなった消息を、よく知られた二つの物語を挙げて語っている。その間の六祖慧能の心事こそは、それこそ、「恁麼の人」がいつしか「恁麼の事」を得たる好範例とするのである。それらの物語は、いずれも『法宝壇経(ほうぼうだんきょう)』に記すところである。
東君;太陽、日輪。また春の神。東皇ともいう。
三菩提;“sanbodhi”の音写である。正覚と訳する。正しき智である。(275頁)
■無際大師はいった。
「そんなものは得られない。そんなでないものも掴まらない。そんなもの、そんなでないものも、すべてが手におえない。そなたは、いったい、どうすればよいのじゃ」
それが、つまり、無際大師が薬山に教えていったことばである。恁麼も不恁麼も総じて捕らえがたいのであるから、恁麼も得がたいのであり、不恁麼も得られないのである。恁麼はただあるがままなのであって、限りあるものをいうのでもなく、限りないものをいうのでもない。だから、恁麼はただ不得(ふとく)と学ぶがよいのであり、不得とはどういうことかとなれば、ただ恁麼に問うてみるがよいのである。恁麼も不得もそんなものであるから、それは、けっして、ただ仏教の範疇(はんちゅう)に属するものではなく、理解することができないのであり、証(さと)ることができないのである。
かって、曹谿山の大鑑禅師(慧能)は、南嶽懐譲(えじょう)に対していった。
「こりゃ、いったい、こげんなものが、どっから来たというのだ」
そのいうところは、恁麼は疑うこともできないというのである。それは理解することもできないが、また、現に「こんなもの」としてあるからである。だから、よろずの物はかならず「こんなもの」であると考えてみるがよいのであり、一物として「こんなもの」ならざるものはないと考えてみるがよいとするのである。つまり、「こんなもの」とは、疑っていうのではなく、ただ、「どこからきたのか」、現にここにあるのである。(278~279頁)
〈注解〉南嶽山無際大師;石頭希遷(790寂、寿91)である。青原行思の法嗣。
薬山;薬山惟儼(いげん)(834寂、寿84)である。石頭希遷の法嗣。澧(れい)州の薬山に住した。諡(おくりな)して弘道大師と称する。
三乗十二分教;仏教経典のすべてをいうことばである。
直指人心、見性成仏;直々にわが心に向かって尋ねいたり、そこに自己の本性をみることによって仏と成るという。禅門の主張するところである。(279~280頁)
行持(ぎょうじ)(上)
■開題
ー前略ー。以上あぐるところの仏祖たちは、すべてその名を知られた方々ばかりであるが、それらの方々が仏祖たる所以は、一つにかかってその行持によるの他(ほか)はない。とするならば、それらの方々が仏祖たる所以につき、せめて「三三両両の行持の句、それかくのごとし」と語らずにはいられないとするのが、まさに道元の心であったにちがいないのである。
かくて、この一巻は、思いもかけず、いまもいうがごとき長大の一巻をなすにいたってしまったのである。そして、古来この一巻は、上・下の二巻にわかって取り扱われることを常とするにいたっておる。だが、いうまでもなく、この一巻にこめる心はただ一つ、仏祖の大道においては、連綿として断絶せざる「無上の行持」によってのみ事が成るものとしらねばならない。
もしも、「わたしは、はや五十になった六十になった、あるいは七十・八十の高齢になったから、もうこの辺でやめておこうなどというのは、まさに至愚(しぐ)である」といわねばならないという。わたしには、その一句が、心に沁み、身に沁みる思いである。けだし、「道は無窮(むきゅう)なり」であるからである。
わたしもまた、この長大の一巻を、古来の例にしたがって、上下二巻に分かち訳することとする。(285~286頁)
■仏祖の大(だい)道には、かならず最高の行があって、連綿として断絶することがない。発心(ほっしん)・修行・正覚(しょうがく)・涅槃とつづいていささかの間隙もない。行は持続し、道(どう)はこれからあれへと巡りめぐって続いているのである。だからして、それは、自分で強いてするのでもなく、また他人に強いられてするのでもなく、ごく自然にしてなんの混じり気もない行の持続である。その行の力が、われをも支え、また他(ひと)をもささえる。その意味はいかにとなれば、わたしの続けている行が、そのまま全地全天にその功徳を及ぼしているということであって、他(ひと)もそれとは知らず、自分もそうとは気がつかなくとも、まさにしかるのである。
たとえば、諸仏や諸祖の続けたまう行があって、それではじめてわたしどもの行持も実現し、わたしどもの大道も成るのである。また、それを翻(ひるがえ)していうなれば、わたしどもの行持があることによって、諸仏の行持が明らかとなり、諸仏の大道も通達(だつ)するのだということともなる。つまり、わたしどもの行持があってはじめて、その巡りめぐって作用する力がはたらき、それによって、仏祖たちもまた、ある時には仏としてましまし、ある時には仏のすがたをとらず、またある時には、そっと仏の心を抱き、またある時には、成道の時を迎えたまい、その間にいささかの断絶することがないのである。
さらにいえば、この行持があってはじめて日月星辰があるのであり、この行持によってはじめて大地虚空(だいちこくう)があり、また、この行持によってこの世界があり、この身心(じん)があるのである。じっと行を持続するということは、かならずしも世の人々の好むところではないであろうが、詮ずるところ、すべての人はそこに帰せざるをえない。三世のもろもろの仏たちもまた、つまり、過去・現在・未来の行持によってこそ、すでに仏となり、いま仏となっているのであり、また、やがて仏となりたまうのである。(287~288頁)
〈注解〉四大・五蘊;四大は地・水・火・風、この世界を構成する要素である。五蘊は、色・受・想・行・識であって、この身心を構成する要素をいう。さきには、この世界とこの身心を、その由りて来るところにより語り、ここではそれをその構成要素をもって語っている。(288頁)
■趙州(じょうしゅう)観音院の真際(ざい)大師従諗(しん)和尚は、齢(よわい)六十一歳にして、はじめて発心し求道(ぐどう)の志しをおこした。水瓶(びょう)と錫杖をたずさえて行脚し、諸方を遍歴しながら、常にみずから戒(いまし)めていった。
「たとい七歳の童子であろうとも、もしわれに勝らば、われすなわち彼に問わん。百歳の老翁も、われに及ばざれば、われすなわち彼を教えよう」
かくして南泉普願のことばを学んで工夫すること二十年。齢八十にいたって、はじめて趙州城東の観音院に住し、人々を教化すること四十年に及んだ。
いまだかって、一封の書をもって布施をもとめたこともなく、僧堂も粗末なもので、六知事の坐する床もなく、僧たちの洗足所もなかった。あるときには、牀几(しょうぎ)の脚が折れたので、一本の焼けぼっくいを縛りつけて、いつまでもそれで凌いでいた。掛かりの役目のものが、それを取り換えたいといっても、趙州はゆるさなかった。古仏の家風というものはこんなものである。
彼が趙州に住んだのは八十歳以後のことで、法を嗣(つ)いでからこのかたのことである。まさに正法(ぼう)を正伝して、人みな古仏と称した。まだ正法(ぼう)を正伝しない者とは、その重さがまったく違っている。また齢八十にいたらぬ者は、師よりも強健であろうが、なお壮年にして軽々なるわれらは、とても師の崇重(すうじゅう)なるに遠く及ばざるところ。学道に励み、行の持続につとめなくてはならない。
寺には、四十年の間、世の財なるものを蓄えることなく、いつも米穀に事欠いていた。栗や椎の実を拾うて食にあてることもあったし、時には、今日の食を明日にのばして食事をするということもあった。まことに古聖高徳の面影であり、慕(した)よるべき徳行というものである。
ある時、衆(しゅ)に示していった。
「汝がもし、一生叢林を離れずして、物いわざること十年もしくは五年ならんには、人は汝を呼んで唖漢となすことなし。それより以後は、諸仏もまた汝をいかんともすべからず」
それは行持のことをいっておるのである。
しるがよい、十年も五年ものあいだ物いわずとも、けっして唖ではないのである。仏道というものはそんなものである。仏の説きたまうことばを聞かないものが、唖ではなくて物をいわない道理はありえない。とするならば、行持のもっとも大事なことは叢林を離れないことである。叢林を離れないからすべてのことばが脱落するのである。叢林は常に寂黙(じゃくもく)のところだからである。
しかるに、愚かなる者どもは、唖ではなくて物いわぬ道理を知らず、また師家(しけ)もこれを教えない。誰が邪魔するわけでもないが、知りえないのである。さらにいうなれば、この沈黙こそが恁麼をえたるものとも知らず、聞かないのであるから、まったく憐れな者どもである。
この叢林を離れざる行持とは、静かに行持しなければならない。東の風がふけば東にゆれ、西の風がふけば西になびいてはならない。十年五年の春風秋月には、誰も気がつくものはなくとも、澄みきった顔色と音声のことばがある。それはわれわれには知られず理解されないが、ただ、寸陰の行持をも惜しむがよいとのみ学ぶがよい。物いわずといえば空っぽなのかと思ってはならぬ。ここに入るも叢林である。ここを出るも叢林である。あるいは、鳥の行くところも叢林であり、この世界が叢林なのである。(314~316頁)
〈注解〉趙州観音院真際大師従諗;趙州従諗(897寂、寿120)。真際大師は諡号である。
叢林;禅院をいう。
■法演和尚は、また、ある時、示していったことがある。
「行は重いを越ゆることはない。思いは行を越えることはない」
このことばもまた重んずべきである。日夜にこれを思い、朝夕にこれを行じて、いたずらに東・西・南・北の風にふかれるようであってはならない。
ましてや、この日本国は、王や大臣の宮殿もなお立派な建物ではなく、わずかに通り一遍の白木造りの家にすぎない。ましてや、出家し仏道を学ぶものが、どうして立派な建物に静かに住むべきであろうぞ。もし、そんな立派な建物を得たならば、それは正しからぬ生き方によるものにちがいない。正しい生業(なりわい)によって、めったにそんなことがあるものではない。もともと有ればそれで結構である。それをあらためて造営しようなどと思ってはならない。もともと、草庵茅屋(ぼうおく)こそ、古聖(しょう)の住むべきところであり、古聖の愛するところである。後進もまたそれを慕って学ぶがよく、思い間違えてはならない。(329~330頁)
■これまでの仏祖のなかには、諸天の神々の供養を受けたというものも多い。しかるに、すでにその道を得て仏となれば、その行なうところは天衆(しゅ)の眼も及びがたく、その思うところは神々もこれを知るよしもなくなるのである。その消息を明らかに知っておかねばならない。むろん、諸天の神々も、もしよく仏祖の行履(あんり)を踏むことにつとむれば、彼らもまた仏祖に近づく道はある。だが、仏祖がはるかに諸天の神々を超えた証(さと)りを得たのでは、諸天の神々ももはや見上げるすべもなくなり、仏祖のほとりに近づくこともできなくなる。だから、かつて南泉普願はいったことがある。
「わたしはどうも修行の力がなくて、鬼神に覗(うかが)い知られるわい」
それでも判るように、まだ修行もできていない鬼神にその心をうかがい知られるというのは、まだ修行の力が足りないからなのである。(331頁)
〈注解〉天・天衆;もと“deva”を訳したことばである。神々の住む世界(天)、あるいはそこに住む神々をいうことばである。しかるに、この一段に記するところを解(げ)しがたく思う方もあろうかと思う、その不審のよってきたるところは、現代のヨーロッパ的思想では、神(単数)をもって最高かつ全智全能であるとするのに対して、仏教では、仏を最高位におき、神々はなお「欲界」(欲望の世界)の住み人にして、仏の思うところ、行うところを覗(うかが)い知りがたいことが多いとするのである。それによって、文中引用の南泉普願のふしぎなことばをも味わっていただきたいのである。(333頁)
■それによっても判るように、そのようなことは、世俗の能事であって、僧たる者の徳ではない。そもそも、仏道に入りては、初めから、はるかに三界の人事を越ゆるのである。三界の事に使役せられず、三界の考え方にかかわらざるものであることを、つまびらかに問うて知らねばならない。身(しん)・口(く)・意の三業(ごう)のこと、および、この身心(じん)およびこの世界のことを身にあてて学び考えるがよろしい。仏祖の行じたまうところは、いうまでもなく、人々を済度するという大きな利益(やく)があるけれども、人々はいっこうに仏祖の行ずるところによって助けられるなどとは気がつかないものである。
したがって、いま仏祖の大道を行じつづけるにあたっては、町に住むか(大隠)、山に入るか(小隠)を論ずべきでもなく、聡明か痴鈍かを問題にすべきでもない。ただ、いつでも、名利をなげすてて、もろもろの事に束縛されないがよろしい。時間をむだに過さず、常に頭上の火をはらうがごとくにするがよい。また、大悟(だいご)をこそと待つ思いがあってはならぬ。大悟とは仏家における日常茶飯のことである。だからとて、悟らざることを願うもよくない。それはすでに髻中(けいちゅう)の宝珠としてそなわっている。
ただ、心得べきことは、家郷にあるものは家郷を離れ、恩愛のしがらみあるものは恩愛を離れ、名あるものは名をのがれ、利あるものは利をのがれ、田園あるは田園をのがれ、親族あるは親族を離れるがよい。名利などなきものも、またその思いを離れるがよいのである。すでにあるを離るべきものならば、またなきをも離るべき道理は明らかである。それがつまり、まっすぐ筋の通った行持というものである。
もしも幸いにして、生(しょう)前に名利をなげすてて、なんぞ一事を行じつづけることもあらば、それは仏法久住(ぶっぽうくじゅう)のゆえに、仏法によって長久の行持となろう。いま、わたしどもの行持も、きっとそのような行持に支持されているにちがいない。そのような行持をそなえた身心は、自分でも大事にしなければならない。また、自分でもそれを敬うがよいのである。(336~337頁)
〈注解〉三界;欲界(人間欲望の世界)、色界(物質・現象の世界)、無色界(抽象的叡智の世界)。
■もしも行持の力いまだ到らずして、仏祖の骨髄を受けることができないのは、なお仏祖たるべき身心を尊重せず、仏祖の面目を受けることを喜ばないからである。いったい、仏祖の面目といい骨髄というものは、去るものでもなく、来るものでもないけれども、かならず一日の行持によって受けるものである。したがって、その一日こそは、まことに重かるべきものである。しかるを、ただいたずらに百歳を生きるなどとは、まったく悲しむべき月日であり、また、うらむべき人間の形骸(ぎょうがい)のような生き方をしても、そのなかのただ一日でもみごと行持を成就するならば、それは一生の百歳を成就するのみではない。また、百歳の他生をも救うことができるのである。
この一日の身命(みょう)こそは、まことに尊ぶべき身命であり、たっとぶべき姿である。そのゆえをもって、たとい生くること一日たりとも、もろもろの仏の心に会うことができるならば、この一日をもって長い長い多年にもすぐれているのだとするのである。そのような故をもって、いまだ決定(けつじょう)するにいたらぬ時には、一日をもむだにつかってはならない。その一日こそ大切にしなければならぬ宝であって、直径一尺の珠のあたいなどとは比べものにならない。黒龍がその顎(あざと)にひそめる珠といえども、それと代えてはならない。だから、古賢は一日を惜しむこと、その身命以上だった。そのことを静かに思いみなければならない。
黒龍の顎(あざと)の珠は求めることもできよう。径一尺の珠も得ることができるであろう。だが、一生百歳のうちの一日は、ひとたび失えば、また得ることはできない。どのようなすぐれた手立てをもってしても、過ぎ去った一日をかえしたということは、いずれの書にも記さざるところである。
もし、いたずらに日月を過ごすまいとするならば、その月日をわが内につつみ込んで、外に漏らさないようにするのである。だから、古来の聖賢(しょうけん)は、日月を惜しみ、時間を惜しむこと、わが眼睛(ひとみ)よりも惜しみ、わが国土よりも惜しむ。それをいたずらに過ごすというのは、名利の浮世に捲きこまれてゆくことであり、それをいたずらに過ごさぬというのは、道にあって常に道のためにすることである。
すでに、そのように決定(けつじょう)することをえたならば、また、一日をいたずらにすることはあるまい。ただ、ひたすらに道のために行じ、また道のために説くであろう。それで判ることであるが、古からの仏祖は、けっして、ただ一日も無駄なことに心を用いるものではないこと、世の人々のよく知るところであろう。されば、春日遅々として花開くの日も、明窓のもとに坐して道を思うがよく、蕭々(しょうしょう)としてもの淋しい雨の夜も、草庵に坐して道をわすれてはならぬ。
思うに、月日というものは、どうしてかくもわれらの修行工夫を盗むものであろうか。それも、一日を盗むばかりではない。また多年のあいだ積んできた功徳をすら盗み去るのである。月日とわれらとは、いったい、なんの仇敵(あだかたき)なのであろうか。だが、よくよく思うてみると、月日に咎(とが)があるわけではない。ただ、自分のよく修せざるによってかくなるのである。恨めしいことである。自分が自分と親しからず、われがわれを恨むよりほかないのである。
仏祖といえども、恩愛のことがないわけではない。だが、彼らはそのすべてを投げ捨ててきたのである。また、仏祖といえども、いろいろの縁(えにし)がないわけではない。だが、彼らはそのすべてを棄ててきたのである。たとい惜しまれる縁であっても、自他の縁はいつまでも惜しみとどめることのできるものではないのであるから、もしも自分が恩愛を投げ捨てなかったならば、かえって恩愛が自分を投げ捨てるいわれがある。恩愛をいとしいと思うならば、恩愛をいとしむがよい。恩愛をいとしむというには、恩愛を投げ捨てるのほかはないのである。(343~345頁)
〈注解〉不去・如去・如来・不来;さるものでもなく、来るものでもなく、去るようでもあり、来るようでもある、というほどの意である。
■つまり、仏法の奥に入ることができるできる者があり、またできない者があり、またいは、老師の決定的なことばを聞くことができる者があり、またできない者がある。しかるを、時は矢よりも速やかであり、命は露よりももろい。師はあっても、自分が参見することをえないこともあり、参じて学ぼうとするに師を得ないこともある。そのような憾(うら)みや悲しみも、目(ま)のあたりに見聞してきたことであった。
すぐれた善知識というものは、かならず人を知る力を具えているものだが、道を修め行を積むにあたっては、あくまでも親しみ近づくことのできる師弟の縁(えにし)というものは稀なものである。雪峰がかって洞(とう)山に登り、あるいは投子(とうす)山に登った時にも、きっといろいろと煩わしいことを忍ばねばならぬこともあったであろう。それにもかかわらず、雪峰のこの純一な行持は、まったく感歎にたえぬところであり、これを学ばないでは惜しむべきことである。(362頁)
行持(下)
■中国の初祖達磨大師が、西の方天竺(てんじく)から中国に来られたのは、般若多羅尊者の命によるものであった。航海三年の歳月の間には、その苦しみは風や雪だけではなかった。また逆巻く波濤(はとう)は、雲か煙か、どこまでも連なっていた。それを越えてまだ見も知らぬ国に入ろうとするのは、命を惜しむ世の常の人々には、思いもよらぬところであろうが、それも、ひとえに、仏法を伝えて迷える人々を救おうとする大慈悲心からきた行というものであろう。けだし、法を伝えることは自己のためであるからかくするのである。とともに、その対象は全世界であるからかくするのである。さらにいえば、この一切世界は真実の条理の行われるところであるからそうであり、その条理こそわが求むるところであるからそうであり、その一切世界こそが一切世界であるからそうなのである。とするならば、人はどこに生まれようとも、それは王宮(おうぐう)にあらざるはなく、その王宮はすべて悟りの道場にあらざるはないのである。
達磨大師はそのような故をもって西より来られたのである。迷える人々を救おうとする自己であるから、驚きもなく、怖れもなく、その対象としての全世界であるから、疑うところもなく、恐るるところもなく、生まれた国を永久に去って、大船を艤(ぎ)し、南海を航して、広州に着いた。乗船の人も少なからず、随身の僧たちもたくさんあったであろうが、記録はなにごとも記してはいない。船が岸についてからのことも、詳しく知るものはない。
着岸の日は、梁(りょう)の普通(ふつう)八年(527)の九月二十一日であった。広州の長官の蕭昂(しょうこう)なるものが賓(ひん)主の礼をもって接待した。つまり、上奏(じょうそう)の文を草して武帝に申し上げた。蕭昂(しょうこう)の律儀な処置であった。すると、武帝は上奏文を見てはなはだ喜び、使者をもって、詔(みことのり)をもたらして迎えたてまつった。そのとしの十月一日のことであった。
初祖達磨大師は、金陵(きんりょう)にいたって、梁の武帝と会見した。武帝は問うていった。
「朕は、即位よりこのかた、寺を造り、経を写し、僧を度すること、記(しる)すことができないほどである。どんな功徳があるであろうか」
達磨はいった。
「いずれも功徳はない」
武帝はいった。
「なんで功徳がないのであるか」
達磨はいった。
「それはただ人々(にんにん)の小さな果(か)というのもで、かえって煩悩の因である。影の形に従うがようなもので、有りとはいえど実(じつ)ではない」
武帝はいった。
「では、いかなるが真の功徳というものであるか」
達磨はいった。
「浄智(じょうち)はまことに円(まろ)やかにして、諸法はもともと空々寂々たるものであるが、そのような功徳は、この世に求める者はない」
武帝はまた問うていった。
「いったい、仏教の教えるもっとも大事なことは何であろうか」
達磨はいった。
「廓然無聖でござる」
武帝はいった。
「朕に対しているのは誰であるか」
達磨はいった。
「識(し)らない」
武帝はそれが解らなかった。達磨は二人のゴゴロの動きが契合(けいごう)する見込みのないことを知った。だから、おなじ月の十九日、ひそかに江(こう)を北に越えて、同じ年の十一月二十三日、洛陽にいたり、嵩山(すうざん)の少林寺に寓居し、壁に面して坐し、終日黙然としていた。
だが、魏の王もおろかであって、達磨のなんたるかを知らず、またそれを恥ずべき理(ことわり)をも知らなかった。達磨は南天竺の王族の出身であり、大国の皇子である。大国の王宮に育って、その作法にも習熟していた。小国のならわしには、大国の王者に見られては恥ずかしいことが少なくないものだが、達磨は別にそんなことには心を動かさず、国をも捨てず、人をも捨てずに魏にとどまっていた。その間には、菩提流支(ぼだいるし)の誹謗を受けたこともあったが、なんの弁解もせず、憎みもしなかったし、光統律師(こうずりつし)の邪計があっても、恨みもせず、耳にも入れなかった。(369~372頁)
〈注解〉金陵;宋の都、いまの南京。
度;出家せしめる。中国では出家にあたって度牒(どちょう)という許状を与える制度があった。
聖諦第一義諦;聖諦(しょうたい)とは、ここでは仏教の真理、そのなかでもっとも大事な真理、もしくは、それを表現する命題をいう。それを問うているのである。
廓然無聖;大空のごとく広々として、聖も非聖もない境地をいう。(374頁)
■まだそのようなすぐれた帝王の教化に遇うことをえない民どもは、君につかえるとはどんなことか、親につかえるとはどうするかも知らないのだから、君の臣としてもあわれであり、親の子としても可哀そうである。臣となっても、子となっても、大事なことも知らずに過ごし、大切な時もむなしく過ごしてしまう。そのような家柄に生れて、国の重き職を授けられた者はなく、軽い官位すらねおめったに受けることがない。国の乱れている時でもなおそうであり、平和の時にはなお見聞することが稀である。
そのような辺地に生まれ、そのような卑賤の身でありながら、なおかつ如来の正法(ぼう)を聞こうとするならば、どうしてこの卑賤の身を惜しむこころがあってよかろうか。それを惜しんで、いったい、なんのために捨てようというのであるか。たとい、その身分が重くかつ賢明な人であっても、なお法のためにその身を惜しむべきではない。ましてや、この卑賤の身命をやである。たとい身は卑賤であっても、もしも道のため法のために、惜しむところなく捨てることもあれば、それは天の神よりも貴(たっと)く、理想の王者よりもすぐれたものであろう。総じていえば、天の神、地の神、この世の誰よりも高貴であろう。(382頁)
〈注解〉楚国の至愚;『後漢書』の応劭(おうしょう)伝に、宋の愚人が燕石(玉に似て玉でない石)を宝として大事にしていた話がある。それをもって玉石の区別を知らぬことに冠したのであろう。ただし、それは楚国ではなくて、宋国の愚人となっている。他に楚国の王の愚かさを語った物語もあるが、それは玉石混淆のことに冠すべきものではない。だが、いずれにしても、これは玉石云々を形容する句にすぎない。(385頁)
■そういうことであるから、この初祖がもたらした仏祖のみちは、いかに峻険であろうとも、これを厭い嫌うて辞すべきではない。その玄妙の家風はいまもなお仰ぎ見ることを得るのに、この身命を惜しんだとても、結局なんにしようというのであるか。
香厳(きょうげん)禅師は偈(げ)をなしていう。
「よろずの思い計(はから)いは身のためであるが
身は結局、塚穴のなかの塵ではないか
白髪は物いわぬなどと思うてはならぬ
それは冥土の言伝(ことづて)をもたらすものじゃ」
だからして、この身を惜しんでよろずの思い計らいをしたからとて、ついには塚穴のなかのひと盛りの塵となるのである。ましてや、小国の王やその臣下たちに使われて、ただいたずらに東に西にと駆け回るのでは、その苦労のほども察せられるというものである。人は義によってはその身命を軽んずるものである。殉死の作法が忘れ去られないなどはそのゆえである。だが、君恩に使われる者の前途は、また目の前も判らぬ闇であって、つまらぬ臣どもにこき使われ、その辺(あた)りで身命を捨てる者が、昔からも少なくない。仏法の器となりうる身を惜しいことではないか。
しかるに、いまわれらは正法に遇うことをえた。されば、百千無数の身命を捨てても、正法にいたり学ぶべきである。つまらぬ小人(じん)と、広大深(じん)遠の仏法と、その選択は迷うべき余地もあるまい。静かに思うてもみるがよい。正法が世に行われていない時には、この身命を正法のために捨てようと思ってもかなわぬことであった。そかるに、いま幸いにして正法に遇うことをえた。そのわたしどものことをじっと考えてみるがよい。正法に遇いながら、身命を捨てなかったならば、それは恥ずかしいことである。恥ずかしいことを知るほどの者ならば、まずこの道理を恥じなければならない。(391~392頁)
■しかるに、いまわたしどもが、道のためにその身を捨てなかったならば、他日、その髑髏は、野外に捨てられた時、誰がこれを礼拝するか、誰がこれを買おうぞ。そんなことになってしまっては、この自分の魂が、やがて過去を振り返って恨まなくてはなるまい。古き経が語る譬喩にも、鬼が自分の昔の骨を打つという話があり、天の神が昔の自分の骨をおがむという話もある。むなしく塵と化し土となる時のことを思いやるならば、とてもいまの自分を愛惜(じゃく)してはおれまいし、また、のちの世を憐れまずにはおれまい。それを傍(はた)から見ている人があったとするならば、かならずや涙を催さずにはおれないであろう。とするならば、むなしく塵と化し土となって人に嫌われる髑髏の身をもって、よく仏の正法を行ずるものとなりうるならば、それこそ幸いというものでなくてはなるまい。
だから、寒さの苦しみを恐れてはならない。寒苦はなお人を損なうものではなく、また、なお道を損なうものでもない。ただ、修せざるを恐れなくてはならぬ。修せざれば、それが人を損じ、道をやぶる。また、暑さの苦しみも恐れてはならない。暑熱もなお人を損なうものではなく、また道を損なうものでもない。ただ、修せざることが、人を損じ、道をやぶるのである。かって釈尊は馬糧の麦の供養をうけ、伯夷(はくい)はわらびをとって生きたという。それは、出世間と世間におけるすぐれた先例である。血を求める餓鬼にならい、乳をもとめる畜生になろうてはならない。ただ一日の行持に励む。それがもろもろの仏たちの履(ふ)みきたった足跡である。(393~394頁)
〈注解〉香厳禅師;香厳智閑(きょうげんしかん、年寿不詳)。潙山霊祐の法を継ぐ。すでに見来ったように、よく偈(げ)をつくった人であるが、つぎに引用の偈は、その出処未詳である。(395頁)
■やっと少林寺にたどりついたけれども、入室(にっしつ)は許されなかった。達磨はまるで振り向いてもくれないようであった。その夜、慧可は、眠ることも、坐ることも、休むことすらできなかった。ただ、じっと立ち尽くして夜の明けるを待っていると、夜の雪はまことに無情であった。だんだんと積もって腰をうずめるにいたり、落ちる涙は一滴一滴と凍った。その涙をみると、また涙が出た。わが身を省(かえり)みることも幾度であったか。そのなかで彼はこうも思ったという。
「昔の人が道を求めるには、骨をたたいてその髄を取り、血をしぼって饑(う)えた者を救うということもあり、また、髪を布(し)いて泥を掩(おお)い、崖より身を投じて飢えたる虎を養ったという話もある。古人にしてなおそのようであったというのに、わたしはいったい何者であるか」
そのように思うと、志を励ます気持がふるいおこった。
そこにいう「古人にしてなおそのようであったというのに、わたしはいったい何者であるか」ということばは、後進のものの忘れてはならないところである。それを、ちょっとでも忘れていたら、そこから人はどこまでもとなく落ちてゆくのである。
それはともあれ、慧可はそのように思うと、法を求め道を求める志のいよいよ燃えるをおぼえるばかりであった。雪を浴びる苦しみを少しも苦しみとしなかったからであろう。だが、夜明けのおそい冬の夜はなかなか明けない。その間の消息は、推し測ろうとしても、ただ肝をひやし、身の毛もよだつばかりである。(402~403頁)
■静かに思いみると、たとい初祖がいくたび西より渡来しようとも、もしも二祖のこの行持がなかったならば、今日の思うがままに学ぶ雲水はありえなかったであろう。しかるに、今日わたしどもはこうして正法を見聞することができる。この仏祖の恩はかならず報いて謝さねばならない。その報謝には、ほかのことでは報いることはできない。身命をもってしても足らず、国や城をもってしてもなお不足である。国や城は、他人に奪われることもあるし、親から子にゆずることもできる。また、身命は無常にもまかさねばならぬ。時には、主君にまかせ、時には、邪道にまかせて身命を捨てる者すらもある。とするならば、それをもって報謝にあてようとするのは、道理ではあるまい。ただ、日々の行持、これこそまさにその報謝の正しい道であるとしなければなるまい。
そのありようは、日々の生命をなおざりにせず、わたくしごとに費やさないようにと、心して行ずるのである。その故はいかにとならば、この生命は、前々からの行持のおかげであり、行持の大恩である。それは急ぎ報謝しなければならない。しかるに、そのような仏祖の行持のおかげを蒙(こうむ)ってなれるこの肉体を、ただいたずらに妻子の奴僕となし、妻子の弄(もてあそ)ぶにまかせて、その零落を惜しまなかったならば、それは悲しむべきこと、恥ずべきことでなければなるまい。また、邪(よこしま)のことに狂い、身命を名利の鬼にまかせるならば、それもまた恥ずべき悲しむべきことでなければならない。名利というものは一頭の大(だい)賊である。名利を重んずるならば、名利のことをしみじみと思うてみるがよい。名利のことをしみじみと思うてみるならば、やがて、仏祖ともなりうるこの身命を、名利のことにまかせて破るようなことはなくなるのである。妻子眷(けん)族の上に思いをかけることも、また同じであると知るがよい。
そもそも、名利というものは、ただ夢まぼろしのごとく空虚なものと学ぶべきではない。むしろ、一般の人々のように考えてみるがよいのである。名利のことをしみじみと思うてみることをせず、かえって罪の報いをのみ積もらしてはならない。学びきたれる正法の眼をもって、あまねく諸方をみるにあたっては、常にその心得がなくてはならない。
世のなかの心ある人々は、金銀や珍宝のめぐみを蒙っても、なおかならず報謝する。うれしい言葉をかけてくれたよしみにすら、心あるものはみな報謝の思いに励む。ましてや、如来の説きたまえる最高の教法を見聞きすることのできる大恩は、人間たるものの誰が忘れてよかろうぞ。これを忘れなければ、それが一生の宝である。それもまた行持である。そして、この行を持して退転することのない人のむころは、その生ける時と死せる時を問わず、同じく七宝の塔におさめ、すべての人々が供養するに値するのである。そのような大恩があると知ったならば、かならずや、この果敢(はか)ない命をもいたずらに零落せしめず、かの山のような徳をも報ずるがよい。それがそのまま行持である。そして、その行持のわざを通じて、そこに祖・仏として行ずるわたしが実現するのである。
いったい、仏祖や二祖は、かって精舎を創(はじ)めたことがない。したがって、草を刈るといった煩わしいことはなかった。続いて、三祖や四祖もまたそうであった。五祖や六祖にいたっても、なおみずから寺院を創建するということはなかった。青原や南嶽もまたそうであった。
また石頭大師は、草庵を大石の上に結んで、石の上に坐禅していた。昼も夜も眠らず、ずっと坐っていた。いろいろの務めは欠かさなかったけれども、二六時中の坐禅はかならずつとめてきた。いま青原門下の流れが広く天下に流れて、多くの人々を潤(うるお)わしているのも、石頭大師の力ある行持のしからしむるところである。いまの雲門や法眼(げん)の流れも、またみな石頭大師の流れを汲むものである。(404~406頁)
〈注解〉石頭大師;また石頭和尚という。石頭希遷(せきとうきせん、790寂、寿91)。青原行思の法を嗣ぐ。(395頁)
■唐の高宗の永徽(えいき)二年(651)、閏(うるう)九月四日のこと、四祖禅師は突然、門人を集め、誡(いまし)めを説いていった。
「すべてもろもろの存在は、みなことごとく迷いを脱している。汝らはそれぞれみずからの心をうちにひそめ、仏の教えを未来に伝えるがよい」
いい了(おわ)ると、安坐したまま亡くなった。寿は七十二歳であった。本山に埋葬したが、その翌年の四月八日、塔墓(とうぼ)の戸がしぜんに開いた。そのありようは人の生くるがことくであった。それで門人たちも、あえてそれを閉じなかったという。
よって知るがよい。すべてもろもろの存在は、ことごとくみな生滅の法にしたがう。もろもろの存在はただ空であるのみではない。存在が存在でないわけではない。ただ、みなことごとく生滅の法にしたがって存する存在である。いま四祖禅師においては、なお生ける時には、生ける時の行持があった。すでに死してからは、死してからの行持があった。生きている者はかならず滅するものとのみ学ぶのは、狭い見解でである。また、すでに死せる者にはなんの知覚もないと考えるのも見識が狭いからである。仏道を学ぶものは、そのような小さな見解・見識になずんではならない。生ける者の滅してなお不滅なるものがあり、死せる者にもなお思うところがあってはずである。(410~411頁)
■彼(岡野注;玄沙師備(げんしゃしび))はもともと、雪峰義存とは法兄・法弟の間柄であったが、しかし、彼は雪峰を尊敬して親しみ、その間柄はあたかも師弟のようであった。その雪峰は、彼のその苦行ぶりをみてあれは師備の「頭陀(ずだ)」だといっておった。そして、ある日のこと、雪峰は師備に問うていった。
「頭陀袋なんかもって、どこへ往(ゆ)こうというのだ」
師備は答えていった。
「やっと人に騙されずにすみましたわい」
またある日のこと、雪峰は師備を呼んでいった。
「師備よ、頭陀袋をととのえたら、なぜ遍歴に出掛けないのだ」
師備は答えていった。
「達磨は中国にやって来たわけでもなく、また、二祖は印度にでかけて行ったわけでもありません」
雪峰はそれを深くうなずいたことであった。
やがて、雪峰が象骨山(ぞうこつざん)に登るに及んでは、師備もまたともに赴(おもむ)き、力を合わせてその建立につとめたので、たくさんの雲水が集まってきた。そこでも師備は、朝も晩もかわることなく、雪峰の室に入って、あるいは問いを呈し、あるいは裁断をもとめた。諸方から集まってくる雲水たちも、いまだ決せざるところのある者は、かならずまず師備のところにいたって指導をこうた。また、雪峰和尚もよく、あの備頭陀(びずだ)に問うがよいといった。師備はまた慈しみの深いひとであったから、そんな時には、師匠にゆずらない懇切な指導につとめた。
こんなことは、郡を抜いた行持を経てきた者でなくてはありえないことである。終日坐禅するといった行持は稀なことなのである。いたずらに眼前の事物にひかれて走りまわっている者は多いが、ひねもす坐禅につとめる人は稀なのである。いま後進としてこの道を行くものは、おのれに残された時間の少ないことを恐れて、終日の打坐(たざ)をこそこれ努めるがよい。(413~415頁)
〈注解〉玄沙宗一大師;玄沙師備(げんしゃしび、908寂、寿74)。雪峰義存の法を嗣ぐ。のち、福州の玄沙山に住した。諡して宋一(いつ)大師と号する。
具足戒;戒を受領して、出家の比丘にまることをいう。
頭陀;衣食住のむさぼりを払う行法をいう。しかるに、頭陀はまたいわゆる頭陀袋をいうことばであって、その二つの意味が、ここでは面白く用いられている。
徧参;禅僧が行脚してあまねく天下の善知識を訪ねること。また遍参とも記す。
象骨山;雪峰山のことである。雪峰が寺を開いて雪峰山と名づけたのである。(415頁)
■「……(前略)……
長慶の慧稜(えりょう)和尚は、雪峰門下の長老であって、あるいは雪峰山に参じ、あるいは玄沙山(ざん)に赴いて、学ぶことおおよそ二十九年である。その歳月(としつき)のあいだに座蒲団を坐り破ること二十枚に及んだという。いまでも坐禅に心を寄せるものは、この長慶をあげて慕うべき範例だとする。だが、慕う者はおおいが、及ぶものはすくない。しかるところ、長慶が三十年の坐禅工夫はついに空しからず、あるとき、涼風の簾(みす)をふきあげるのをみて、忽然として大いに悟るところがあった。
思うに、この人は、三十年来かって故郷にも帰らず、親族を訪れることもなく、となりの坐席のものとも談笑せず、ただ坐禅工夫に専注した。しかも、その行持は三十年。疑問をどこまでも疑問として追求すること三十年に及んだのである。まさに並々ならぬすぐれた機根の人であり、大いなる器であったといわねばならない。
そのような賢固な志のことを伝聞するのは、たいてい経巻によってであるが、そのためにはまず、疑うべきことを疑い、恥ずべきことを恥とすることを知らねばならぬ。それには、まず長慶に赴き見(まみ)えるがよいであろう。ひるがえって、現実はいかにといわば、世の人々はたいてい道を求める心がなく、その行うところもまずいので、すぐ名利のことに捉われるのである。(417頁)
〈注解〉長慶の慧稜和尚;長慶慧稜(932寂、寿79)。雪峰の法嗣。(418頁)
■潙山の大円禅師は、百丈禅師の印可のことばを得ると、ただちに潙山の峻嶮(しゅんけん)によじのぼり、鳥や獣に伍(ご)し、草庵をむすんで修練(しゅれん)にいそしんだ。風雪をもいとうことなく、橡(とち)や栗の実を食となした。堂宇(どうう)がないので、安住するところもなかったが、それでも、四十をすぎた頃から、その行持が次第にあらわれてきて、のちには、天下の名刹(めいさつ)として、すぐれた求(ぐ)道者が峻嶮を踏破して集まり来ったものである。
いったい、寺院を建立したいと思っても、人の心の動きを気にしてはならない。ただ、仏法を行じつづけることを堅固にするがよい。修練はあるが堂閣(どうかく)はないというのが、それが真の仏者の道場というものである。樹下の露地をふく風が遠く聞こえるのであり、そのような仏者のあるところが長く聖域として存するのである。つまり、一人の行持があれば、それがもろもろの仏の道場に伝わるであろうからである。
だから、末世の愚人はただいたずらに堂閣の建立に心を労するが、そんなことは不要である。仏祖はかって堂閣のことを念としたことはない。しかるに、自己のまなこはまだ開かれないのに、いたずらに堂閣を構えるなどというのは、断じて仏たちに仏堂を献じようとするのではなく、ただおのれの名利の巣窟としようがために他(ほか)ならない。潙山がその昔になし来ったところを静かに思いやるがよい。思いやるというのは、自分がいま潙山に住んでいるかのように思うてみるのである。
深夜の雨の音は、苔を洗うくらいのことではなかったであろう。きっと岩石をもつらぬくほどの激しさであったにちがいあるまい。また冬空の夜には、鳥や獣さえもめったに見かけなかったであろう。ましてや、人の気配を感ずることなど全くなかったであろう。身命を軽うし仏法を重んずる修行でなくては、とてもこんな生き方はできないところである。だから、草を刈ることも急がないし、地を平らげることもせず、ただ行を持しておのれを練り、仏道を追求して心を労するのみである。ああ、思えば、仏法を伝持しきたった仏祖たちには、このような山中の苦難に堪えてこられた方がどのくらいおられたことであろうか。
ちなもに、かの潙山のありようを伝え聞くと、そこには池があり、水があり、ある時には氷が張りつめることもあり、ある時には霧がおし包んでしまうこともあるらしい。それはとうてい人間の幽居するに堪えるところではないが、それがおのずから仏道を成じ、奥義にいたらしめる霊験(れいげん)のはなはだ顕著なるものがあるのである。
このような行持の話を見聞するには、身をやすやすとしたままで聞くべきではない。だが、そんな行持に励んで得べき報(むく)いがなんであるかを知らなければ、それも詮ないことであろう。しかし、もし志のある後進であるならば、その昔の潙山をいまわが目の前に見るように思いやって、感歎これを久しゅうしなければならないはずである。思うに、その潙山の行持の功徳によって、大地の基底もゆるがず、世界も破れることなく、天の神々の住まいも穏やかにして、人間の国土も保全することをうるのである。
わたしどもは潙山の流れを汲むものではないけれども、潙山は立派な祖師であったらしい。のちには仰山(きょうざん)がきたって随侍した。仰山はもと先師百丈のところにあって、十を問えば百を答える才気煥発の器であったが、さらに潙山に参じて、かの師を見守ること三年に及んだ。近来ではまったく絶えて、見聞することもない行持であった。だから、こんな話はまったく独特であって他には求めがたい。(420~422頁)
〈注解〉大潙山大円禅師;潙山霊祐(853寂、寿83)である。百丈の法を嗣ぎ、潙仰(いぎょう)宗の祖となる。ほかにも、潙山を号とする者があるので、特に霊祐を大潙とよぶのがならいである。
授記;未来の成仏につき予言を与えることをいうことばであるが、ここでは百丈が潙山に嘱(しょく)して、「潙山は勝境である。汝は当にこれを居(こ)して吾が宗を嗣ぎ、ひろく後学を度すべし」といったのであるから、もっと正確には付嘱というところである。
仰山;仰山慧寂(916寂、寿77)である。潙山霊祐の法嗣。潙山を助けて、その法を宣揚したので、潙仰宗の名がおこった。(422頁)
■ところで、わたしは今日、諸人の前に面をさらして家門の風(ふう)を説こうとしているが、これはどうも勝手が違って具合がわるい。ましてや、さらに上堂とか入室(にっしつ)とかいって、槌(つち)をひねり、払子(ほっす)を立てて、あるいは喝(かつ)をなし、あるいは棒をふりまわして、まるで癇癪もちがその病をおこしたようなことをするのは、ただに学人たちをないがしろにする許(ばか)りではなく、さらには先聖に背くものである。汝らも知っているであろう。達磨は西より渡来して、小室山(しょうしつざん)のふもとにいたったが、ただ面壁して坐すること九年であった。二祖が雪のなかに立ち、臂を断つにいたっては、まことに艱難を受けたことであった。だがしかし、達磨はかって一語を吐いたわけでもなく、二祖はかって一句を呈して問うたわけでもない。それでも、達磨をよんで〈人の為にせず〉となすことはできまい。あるいは、二祖を指さして〈師を求めず〉となすことはできまい。わたしは、それらの古聖のなすところを説くたびに、恥ずかしくて身の置きどころがないような思いをし、また後輩として軟弱なることを愧(は)じいるばかりである。
ましていわんや、いまの世では、いろいろの御馳走をたがいに振舞いおうて、さてそこで、これで四事もすべて整ったので、もう発心してよいなどとぬかす。そんなことでは、おそらくは手足をならすところまでも行けず、いつまで経っても仏道の遠いところに落ちてゆくばかりである。光陰は矢のごとしというのに、まことに惜しいことではある。
とはいいながらも、他人(ひと)のことはその人の得手にまかせるがよいというもの。わたしもまた強いてそなたがたを教えるわけにはゆかない。では、ひるがえって古人の偈(げ)をみてはどうか。
『山の田でつくった玄米の飯
あわい黄色の野菜の漬けもの
食べる食べぬは君にまかせる
食べねばどこへでも行くがよいわい』
伏して惟(おもん)みるに、道を同じゅうする者よ、つまるところは各自の努力でござる。では、お大事に」
これが、とりもなおさず、仏祖直伝の骨髄というものである。芙蓉高祖の行持はなおいろいろとあるが、いまは一応これをあげて示すのである。わたしども後進たるものは、この高祖が芙蓉山でおこなった行持を、とくに慕うて学ぶがよい。それはそのまま教祖釈尊の教えたまうところなのである。(429~430頁)
〈注解〉※ここには、芙蓉道楷のかなり長い垂示を漢文のままに引用している。仏々祖々にはみなすぐれた行持の事蹟が伝え残されている。だが、事細かに説きあかしたものは稀である。道元がここに、その長い垂示をそのままに引用した心組みもまた知られようというものである。その稀なるを珍重して挙げたのであろう。
芙蓉山の道楷;芙蓉道楷(1118寂、寿76)。投子義青(とうすぎせい)の法嗣(ほっす)。晩年芙蓉山の湖上に庵をむすんで住んだ。
心・念;心なるものと、そのはたらきをいう。
趙州;趙州従諗(ちょうしゅうじゅうしん、897寂、寿120)のこと。南泉普願の法嗣。
入室;弟子が師の室に入って、したしく所得を呈して問うことをいう。
上座;禅林にて、師家や学人に対して用いる二人称である。(431~432頁)
■洪州江西(ぜい)の開元寺大寂禅師は、諱(いみな)を道一という。漢州十方県のひとである。南嶽に見(まみ)えて随侍すること十余年である。そのある時のこと、郷里に帰ろうとして途中まで行ったが、そこから引き返して南嶽のもとにいたり、焼香して礼拝した。すると南嶽は偈をつくって、馬祖に与えていった。
「君に勧む、郷に帰るなかれ
郷に帰れば、道おこなわれず
隣り近処の老婆たちは
むかし名をもって汝を呼ぼう」
すると馬祖は、その垂訓ををありがたく頂いて、誓って「わたしは生々世々(しょうじょうせぜ)にも漢州にまいりませぬ」といった。そのような誓願を立ててからは、漢州に向かって一歩を勧めることもなく、ただ江西ににずっと住みつづけ、この人に見(まみ)えんとする者は、四方八方から来り集まった。その間(かん)、わずかに「即心是仏」の句を吐いたほかには、まったく人のために説くところはなかった。それでいて、なお立派に南嶽の法を嗣ぎ、世人のいのちともいうべき仏者となった。
では、その「郷に帰るなかれ」とは、どういうことであるか。郷に帰らないとは、どうあればよいというのか。それなのに、「郷に帰れば、道おこなわれず」とある。道の行われないのは、郷に帰るからだと受け取るべきか、それとも郷に帰るからではないと受領すべきか。いったい郷に帰るからだと受け取るべきか、それとも郷に帰ればなにがゆえに道が行われないこととなるのか。それは、行わないから行われないのであろうか。それとも、自分がそれを碍(さまた)げているのであろうか。
さらに、「隣り近処の老婆たち」が、「汝のむかしの名をもって呼ぶであろう」と、そういっておるのではない。そこは、二つの句を一つにして、ずばりと、「並舎老婆子、説汝旧時名」といっておるのである。南嶽はどうしてこのことばを吐いたのか。馬祖はどのようにしてこの垂誡(すいかい)を頂戴したのか。その道理をつらつら考えてみると、それは、自己が南に向かって行けば、大地もまた同じく南に向かって行くということである。南ばかりではない。他行(こう)はすべてまたそうなのである。それを、須弥山(しゅみせん)や大海を規準として、そうではあるまいと疑い、あるいは、日月や星辰を標準として首をかしげるのは、小さな量見というものである。
五祖の大(だい)満禅師は、キ州黄(おう)梅も人である。俗姓は周氏であった。母の姓を名告(なの)ったのであって、この人は父をなくして生まれたのである。ちょうど老子と同じである。七歳にして法を伝えてから、七十四歳にいたるまで、仏祖の伝える正法の眼目をよく保ち持って、ひそかに衣(え)法を慧能に伝えた。そのころ慧能はなお雑役のものであった。まことに独特のことであった。しかるに、この衣法を、上座の神秀に伝えず、慧能に伝えたからして、正法の寿命は絶えなかったのである。(434~435頁)
〈注解〉※ここには、場祖道一のこと、および五祖弘忍のことが語られている。前者は詳しく、後者は簡略であるが、五祖弘忍のことは、すでに「仏性」の巻、および、「伝衣(え)」の巻に詳しく述べたところである。
洪州江西開元寺大寂禅師;馬祖道一(786寂、寿80)である。南嶽懐(え)譲の法嗣(ほっす)。江西鐘陵の開元寺に住し、世に江西の馬祖と称せされた。諡して大寂禅師と号する。
心・念;心なるものと、そのはたらきをいう。
南嶽;南嶽懐(え)譲(744寂、寿68)のこと。六祖慧能の法嗣。
第三十二祖大満禅師;五祖の大満弘忍(716寂、寿74)である。西天の祖師につづいて算(かず)うれば三十二祖となる。四祖道信の法嗣。
慧能・神秀;二人よも五祖弘忍の弟子であるが、弘忍のあとを嗣いで、六祖となったものは、神秀上座ではなくて、慧能行(あん)者であったことがよく知られている。行者とは、いまだ得度せず、寺中の諸役のの者のもとにあって雑役に服するものをいう。(435~436頁)
■先師天童和尚は、越(えつ)のあたりの人である。十九歳にして教義をのみ学ぶことを捨てて、禅門にいたり、七十歳にいたって、なお罷(や)むことがなかった。寧宗(ねいそう)皇帝より紫衣(しえ)ならびに禅師号の御沙汰があったけれどもついに受けず、上表の文を草して拝辞した。四方の修行する僧たちは、みなこの人を崇敬し、遠近の有識のものもすべてこの人の徳をたたえた。皇帝もまたこのことを大いに悦び、お茶をたまわった。聞くものはみな世にも珍しい事と讃談した。
その故はいかにとならば、名聞を愛することは戒を犯すことよりもなお悪いからである。戒を犯すは一時の非であるが、名聞を愛するは一生の累(わずら)いである。それを捨てないのは愚かであり、それを受けるのは道理に眛(くら)いというものである。それは、受けないのが正しい出処であり、捨てるのが道理にかなう進退である。達磨より以後、六代の祖師はそれぞれ師号があるが、それらはみな没後の諡(おくりな)であって、この世にあって名聞に心をひかれたわけではない。だからして、われらもまた、生前没後の名聞をむさぼる心をすてて、ただ仏祖の行じきたった跡をふもうと念ずるがよく、それを貪り愛した鳥けだものに等しュうなってはならない。大したものでもない自分をひたすらに愛執(あいしゅう)するのは、鳥けだものもするところである。畜生だっておなじである。ひるがえって、名聞・利養を捨てることは、人々のまれとするところであるが、仏祖にしていまだそれを捨てないものはないのである。
しかるに、ある者はいう。われらは衆生を利益(やく)せんがために名聞をむさぼり、利養を愛するのである、と。それは、たいへんな間違った考え方である。仏法のなかに巣くう外道であり、正法をそしる悪魔の輩である。もしそのいうがごとくであるならば、名利を貪らなかった仏祖たちは、衆生を利益しようととの思いはなかったのであろうか。まったく嗤(わら)うべきである。また、不貧(とん)の利生(しょう)ということがあるが、どうじゃ。いったい、衆生を利益するにもいろいろとあることを知らずして、まことは衆生を利するものでもないことを衆生の利益だという。そんなのは悪魔のたぐいなのであろう。そんな輩に利益せられた衆生は、地獄に堕ちる仲間であって、暗い生涯を送らねばならぬことを悲しむがよい。そんな愚かな考え方を衆生を利するなどといってはならない。
だからして、先師天童和尚が師号を賜(たまわ)っても上表の文を草して拝辞したというのが、古来の勝れた範例となるのであり、後進たるものの学ぶべきところとされるのである。わたしは、幸にして、目のあたりに先師をみることを得たのであるが、それは、ほんとうの人物というものにめぐり会うことができたのだと思っている。
先師は十九の歳から郷をはなれ師を訪ねて、仏道を求め、禅を修すること、六十五歳にいたってもなお已(や)むところがなかった。その間、権力者に近づかず、皇帝に見(まみ)えたこともなく、宰相と親しんだこともなく、官吏に近づいたこともない。表を上(たてまつ)って紫衣(しえ)・師号を辞したばかりでなく、また生涯けっして色模様の袈裟を着たこともなかった。いつものように上堂したり、入室(にっしつ)のときにも、常に黒い袈裟ころもを用いた。
雲水たちに教訓を与える時には、よくこんなことを仰せられた。
「禅を修し、仏道を学ぶには、まず道心のあることが大切である。それが仏道を学ぶはじめでなければならぬ。いまは、この二百年このかた、祖師の道がすたれて、まことに悲しむべきことである。ましてや、一句をいいうるものは稀である。
わたしは、そのむかし、径山(きんざん)に杖をとどめていたことがあるが、そのころは仏照徳光(ぶっしょうとくこう)なるものが住持であった。法堂(はっとう)にのぼって説いていうに、『仏法とか禅堂とかいうものは、かならずしも他の人の説いた言句をもとむべきではない。ただ各自がそれぞれに会得するがよろしい』と。そういって、僧堂のなかのこともすべて監督せず、雲水たちのこともすべてわれ関せずで、ただ来客と会って付き合うばかりであった。この仏照という人は、まったく仏法のあるべきようを知らず、ただひとえに名をむさぼり利を愛するのみであった。いったい、仏法がもし各自それぞれの会得すべきものであるならば、どうして年功を積んだ修行者たちが師をたずねて道を問うことをしようか。きっと仏照徳光はいまだかって参禅したこともない人であったにちがいあるまい。
しかるに、いま諸方の長者たちも、どうやら仏照の輩にすぎないようである。そんな輩の手中に仏法があろうはずはない。まことに惜しむべきことではある」
そのように仰せられるのを、仏照の輩どももたくさん聞いていたが、腹をたてるものはなかった。
先師は、また仰せられた。
「参禅というものは、ただ身心(しんじん)脱落するのである。それには、焼香も礼拝も念仏も修懴(しゅさん)も看経(かんきん)もいらない。ただひたすれに打ち坐って、はじめて得るのである」
思うに、いま宋国の諸処方々には、参禅の名をかかげて、仏祖の流れを汲むと称する者は、百、二百にとどまらず、いたるところにあるけれども、坐禅をただ打ち坐るものとして勧める者は、まったく風のたよりにも聞き及ばない。天下にただ一人、先師天童和尚のみである。どこに行っても天童和尚をほめないものはないが、和尚はいっこうに彼らをほめない。なかにはまた、天童和尚を知らない大寺の住持もあるが、そんなのは、中国に生まれたとはいっても、鳥けだものの類(たぐい)であろう。なんとなれば、彼らは、到って学ぶべきに到らずして、いたずらに歳月を過ごしたものにちがいないからである。かわいそうに彼ら天童和尚をしらない輩は、いい加減なでたらめを口やかましく説いて、それが仏祖の家風とのみ間違えているのである。
また、先師はいつもみなにむかってかように説かれた。
「わたしは、十九歳の時よりこのかた、方々の禅院をめぐり歩いたが、人のために説く師というものはなかった。また、十九歳の時よりこのかた、一日一夜といえども坐禅の蒲団をしかなかったことはなかった。まだ住持とならぬ頃から、里の人々と話をしたこともない。時間がおしいからであった。あるいは、どこの禅院に足をとどめても、庵のなか、寮のなかを見てまわったこともない。ましてや、山水に遊ぶなどということに心をもちいる道理があろうか
また、僧堂や公界(くがい)のほか、あるいは桟道(かけはし)の上とか、垣根の内側とか、人気(げ)のないところにただ一人でいって、適宜なところで坐禅した。いつでも袖のなかに蒲団をしのばせていて、時には岩の下でも坐禅した。そして、いつでも思ったことは、お釈迦さまの樹下の座のように坐りぬきたいと思った。それがわたしの期するところであった。時には、臀(しり)の肉がただれるようなこともあったが、そんな時には、ますます坐禅にはげんだ。
わたしはもう今年六十五歳になった。老骨になって頭もよくまわらず、坐禅の理屈などはわからないが、四方から集まる兄弟の雲水たちがいとしいので、この禅院の住持として、来り参ずるものを諭(さと)し、人々のために仏道を伝えるのである。方々の長老たちは、どこにどんな仏法があるか、判ったものではないからなあ」
法堂にのぼられると、よくそのように説かれたものであった。(444~448頁)
〈注解〉先師天童和尚;天童如浄(1228寂、寿66)である。雪寶智鑑(せっちょうちかん)譲の法を嗣ぎ、曹洞(とう)の流れを汲む。天童山景徳寺に住す。先師とは亡くなった師をいうことばであって、道元にとっては、先師とは如浄のほかにはない。
看経;経を黙読すること。
径行;坐禅の合間に、運動のために、一定のところを歩くことをいう。(453~454頁)
■静かに考えてみるがよろしい。この一生はいくばくでもない。だが、たとい仏祖のことばをまなぶことわずかに二、三句であろうとも、その語句が表現しているのは仏祖そのものの表現であるはずである。なんとなれば、仏祖は身心がひとつであるから、その吐いた一句両句も、すべてみな仏祖のあたたかい血のかよう身心そのものである。したがって、それらの仏祖の語句をわが身心をもって学びとるならば、それは、かの仏祖の身心がきたってわが身心を表現しているのである。そして、まさにその会得のなる時、その時には今度は、かの仏祖のことばがわが身心を表現しているのである。しかるに、よくよく考えてみると、この生においてよくかかる会得をなしうるということは、また未来のわが身の生々(しょうじょう)のことでなくてはなるまい。つまるところ、そのとき仏となり祖となれば、さらに仏をこえ、祖をこえてゆくこととなろう。
上にあげたそこばくの行持に関する語句は、まさにかくのごとくなるものである。願わくは、つまらぬ目前の名利に惹(ひ)かれて右往左往することなかれ。右往左往することがなければ、それが仏祖のじきじきに伝える行持というものである。望みたいのは、世の中に隠れてもよい、世の外に隠れてもよい、一人でもよい、半人でもよい、どうかよろずのこと、よろずの縁をなげすてて、仏祖の行持をそのままに行持してもらいたいのである。(451~452頁)
(2015年10月31日)