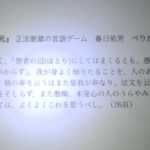『善の研究』西田幾多郎著 全注釈小坂国継 講談社学術文庫
■純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明してみたいというのは、余が大分前から有(も)っていた考えであった。初めはマッハなどを読んでみたが、どうも満足はできなかった。そのうち、個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである、個人的区別より経験が根本的であるという考えから独我論を脱することができ、また経験を能動的と考うることによってフィヒテ以後の超越哲学とも調和し得るかのように考え、ついにこの書の第2編を書いたのであるが、その不完全なることはいうまでもない。
思索などする奴は緑の野にあって枯れ草を食う動物の如しとメフィストに嘲(あざけ)らるるかも知らぬが、我は哲理を考えるように罰せられているといった哲学者(ヘーゲル)もあるように、一たび禁断の果(み)を食った人間には、かかる苦悩のあるのも已むを得ぬことであろう。(16頁)
■行為的直観(注5)の世界、ポイエシス(注6)の世界こそ真に純粋経験の世界であるのである。
(5)行為的直観 後期西田哲学の主要概念。一見すると矛盾対立的である行為と直観、働くことと見ることとの間の相即的・相補的関係を表現する用語。真の行為は深く物を見ることから生ずる。したがって、行為と直観は相互に対立的であるのではなく、むしろ行為は直観から生ずるのであり、行為即直観であると説く思想。
(6)ポイエシス 芸術的制作。西田は彼の行為的直観の思想を説明するのに、好んでポイエシスを例にとっている。(25~26頁)
■フェフィネルはある朝ライプチヒのローゼンタールの腰掛けに休らいながら、日麗らかに花薫り鳥歌い蝶舞う春の牧場を眺め、色もなく音もなき自然科学的な夜の見方に反して、ありのままが真である昼の見方に耽(ふけ)ったと自らいっている。私は何の影響によったかは知らないが、早くから実在は現実そのままのものでなければならない、いわゆる物質の世界という如きものはこれから考えられたものにすぎないという考えを有(も)っていた、まだ高等学校の学生であった頃、金沢の街を歩きながら、夢みる如くかかる考えに耽ったことが今も思い出される。その頃の考えがこの書の基ともなったかと思う。私がこの書を物せし頃、この書がかくまでに長く多くの人に読まれ、私がかくまでに生き長らえて、この書の重版を見ようとは思いもよらないことであった。この書に対して、命なりけり小夜の中山(注9)の感なきを得ない。(24頁)
(注9)西行法師『山家集』にある「年たけて又こゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山の下の句。「年とってまた越えることができるとは思わなかった、命があったればこそできたのである」との意。「小夜の中山」は静岡県掛川市にある坂路。箱根路に次ぐ東海道の難所として知られた。(28頁)
■純粋経験とは意志の要求と実現との間に少しの間隙もなく(注4)その最も自由にして、活発なる状態である。(39頁)
(注4)純粋経験においては意志の要求と実現との間に少しの間隙もないということは、意志的要求と実際の行為との間にいかなる断絶も分裂もないということである。要求がそのまま行為となり、行為がそのまま欲求の実現となるということである。もし意志の要求とその実現との間に断絶があるとすれば、その場合は、主観と客観が分裂しているということであり、もはや純粋経験の状態ではなくなっているということである。(41~42頁)
■しかし、さらにいえば、事実をあるがままに受けとるという表現自体も本当は十分ではない。というのも、そこにはまだ受けとる主体の存在が前提されているからである。そこには、なお、(事実を)受けとるものと受けとられるものとの間隙や対立がみとめられる。受けとる主体自身も消えてなくなってしまった時、はじめてそこにただ事実だけが存在することになるだろう。それで、純粋経験とは、いわゆる自己というものがなくなって、自己が物と一体となり、事実そのものとなっているような状態である。徹底して自己を否定し、空しくして、物に即し、事に即して見ていこうとする西田哲学の性格が、この冒頭の「経験」の定義によく表われている。それは、デカルトの「我思う故に我あり」(cogito ergo sum)から出発する西欧近代の主観主義の立場とは対極にある考え方である。(49頁)
■しからば、いかなる思想が真でありいかなる思想が偽であるかというに、我々はいつでも意識体系の中で最も有力なるもの、すなわち最大最深なる体系を客観的実在だと信じ、これに合った場合を偽と考えるのである。(64~65頁)
■我々は普通に思惟によりて一般的なるものを知り、経験によりて個体的なるものを知ると思うている。しかし、個体を離れて一般的なるものがあるのではない、真に一般的なるものは個体的実現の背後における潜勢力(注1)である、個体の中にありてこれを発展せしむる力である、例えば植物の種子の如きものである。もし個体より抽象せられた他の特殊と対立する如きものならば、そは真の一般ではなくして、やはり特殊である、かかる場合では一般は特殊の上に位するのではなく、これと同列にあるのである、例えば、色ある3角形について、3角形より見れば色は特殊であるであろうが、色より見れば3角は特殊である(注2)。(70頁)
(注1)潜勢力 「統一的或者」「或統一者」「潜在的統一作用」と同様、普遍的意識の別名。
(注2)例えば、3角形を基準にすれば、赤色をした3角形は3角形一般から見ると特殊であるが、反対に色を基準にすれば、3角の形をした赤色は赤色一般からすれば特殊である。(72頁)
■時間空間という如きものもかかる内容にもとづいてこれを統一する一つの形式にすぎないのである(注5)。(71頁)
(注5)時間や空間については、これをニュートンのように実在と考える考え方と、カントのように現象を秩序づける形式と考える考え方があるが、この点に関しては、西田の考えはカントのそれと一致している。(72頁)
【私(岡野)の考え;私はニュートンのように実在と考えている】
■この意味より見れば、普通に感覚あるいは知覚といっているようなものは極めて内容に乏しき一般的なるもので、深き意味に充ちたる画家の直覚の如きものが反って真に個体的といいうるであろう。(71頁)
■思惟を進行させるおはわれわれの勝手な意志ではなく、思惟は思惟自身によって自ら展開していくのである。われわれの思惟の対象と一体となった時、すなわち対象の中に没入した時、はじめて思惟本来の活動を見るのである。(77頁)
■常識では、時間空間において限定された物質的なものを個体と呼んでいる。しかし、このような規定は外面的であって、真の個体は、その外面においてではなく、その内容において個体的でなければならない。すなわち、唯一の特性をもったものでなければならない。一般的なものがその発展の極限に至ったものが個体である。そして、この点からすれば、感覚や知覚はきわめて内容の乏しい一般的なものであって、むしろ芸術家の直覚のようなものこそ真に個体的であるといえるのである。(83頁)
■ゲーテが「意欲せざる天の星は美し(注1)」といったように、いかなるものも自己運動の表象の系統に入り来らざるものは意志の目的とはならぬのである。(87頁)
(注1)ゲーテの小曲「涙の中にある慰め」の中の一節。
星を獲ろうと望みはすまい。
われらは星の光を悦び、
晴れた夜毎に空を仰いで
大きい歓喜を身に感じる。(片山敏彦訳『ゲーテ詩集』〈1〉、岩波文庫、125頁)(87~88頁)
■我々が現実と離れた高き目的を実行しようと想う場合には種々の手段を考え、これによりて一歩一歩と進まねばならぬ、しかしてかく手段を考えるのはすなわち客観に調和を求めるのである、これに従うのである。もし到底その手段を見出すことができぬならば、目的そのものを変更するより外はなかろう。これに反し、目的が極めて現実に近かった時には、飲食起臥の習慣的行為の如く、欲求はただちに実行となるのである、かかる場合には主観より働くのではなく、反って客観より働くとも見らるるのである。(90頁)
■真理は我々の作為すべきものでなく、反ってこれに従うて思惟すべきものであるというのである。しかし、我々が真理といっているものははたして全く主観を離れて存するものであろうか。(91頁)
【私(岡野)の考え;私は「真・善・美」は超越的存在と考えるので、当然主観を離れて存在するとおもう】
■いかなるものが真理であるかということについては種々の議論もあるであろうが、余は最も具体的なる経験の事実に近づいたものが真理であると思う(注3)。(97頁)
(注3)「余は最も具体的なる……あると思う」 西田は認識を主観と対象との一致とも考えなければ、主観による対象の構成作用とも考えない。具体的事実の直覚と考えている。しかも、この具体的事実はきわめて多様な側面を有するとともに無限の深さを有していると考えられている。したがって、そのもっとも根源的でもっとも深い事実を直覚することが真の認識ということになる。西田は、ここではそれを「最も具体的なる経験の事実に近づいたもの」と表現している。(98頁)
■完全なる真理は個人的であり、現実的である。それ故に、完全なる真理は言語にいい現わすべきものではない、いわゆる科学的真理の如きは完全なる真理とはいえないのである。(97頁)
【私(岡野)の考え;私は「真・善・美」は超越的存在と考えるので、科学的真理は〈完全〉なる真理とはいえないが、真理の一部であると考える】
■意志というのは普通の知識というものよりも一層根本的なる意識体系であって統一の中心となるものである(注1)。知と意との区別は意識の内容にあるのではなく、その体系内の地位によりて定まってくるのであると思う。
(注1)ここでは、意志や知識よりも一層根本的な意識体系であって統一の中心となるものである、と述べられている。ここには、知よりも意を根本的と見る西田の主意主義の立場が明確に現われている。(101頁)
■学者の新思想を得るのも、道徳家の新動機を(注6)得るのも、美術家の新思想を得るのも、宗教家の新覚醒をうるのもすべてかかる統一の発現にもとづくのである(故に、すべて神秘的直覚にもとづくのである)。(113頁)
(注6)動機 行動を決定する根拠となる目的意識を伴った欲求ないし衝動。ここでは道徳家にとっての動機が、学者にとっての思想、美術家にとっての理想、宗教家にとっての覚醒と対応するものとしてあげられている。(114頁)
■物我(もつが)相忘(ぼう)じ、物が我を動かすのでもなく、我が物を動かすのでもない、ただ一の世界、一の光景あるのみである。知的直観といえば主観的作用のように聞こえるのであるが、その実は主客を超越した状態である、主客の対立はむしろこの統一によりて成立するといってよい、芸術の神来の如きものは皆この境に達するのである。また、知的直観とは事実を離れたる抽象的一般性の直覚をいうのではない。画の精神は描かれたる個々の事物と異なれどもまたこれを離れてあるのではない。かっていったように、真の一般と個性とは相反するものでない、個性的限定によりて反って真の一般を現すことができる、芸術家の精巧なる一刀一筆は全体の真意を現わすがためである。(115頁)
■真の宗教的覚悟とは思惟にもとづける抽象的知識でもない、また単に盲目的感情でもない、知識および意志の根柢に横たわれる深遠なる統一を自得するのである、すなわち一種の知的直観である、深き生命の捕捉である。故に、いかなる論理の刃もこれに向かうことはできず、いかなる欲求もこれを動かすことはできぬ、すべての真理および満足の根本的直覚がなければならぬと思う。学問道徳の本には宗教がなければならぬ、学問道徳はこれによりて成立するのである(注2)。
(注2)宗教が学問道徳の基本があるという考えは西田の根本思想の一つであった。第4編第1章には「人智の未だ開けない時は人々反って宗教的であって、学問道徳の極致はまた宗教に入らねばならぬようになる」と述べられている。(121頁)
■世界はこのようなもの、人生はこのようなものという哲学的世界観および人生観と、人間はかくせねばならぬ、かかる処に安心せねばならぬという道徳宗教の実践的要求とは密接な関係を持っている。人は相容れない知識的確信と実践的要求とをもって満足することはできない。例えば、高尚なる精神的要求を持っている人は唯物論に満足できず、唯物論を信じている人は、いつしか高尚なる精神的要求に疑いを抱くようになる。元来、真理は1つである。知識においての真理はただちに実践上の真理であり、実践上の真理はただちに知識においての真理でなければならぬ。深く考える人、真摯なる人は必ず知識と情意との一致を求むるようになる。我々は何を為すべきか、いずこに安心すべきかの問題を論ずる前に、まず天地人生の真相はいかなるものであるか、真の実在はいかなるものなるかを明らかにせねばならぬ。
哲学と宗教を最も能く一致したのはインドの哲学、宗教である。インドの哲学、宗教では知即善で迷即悪である。宇宙の本体はブラフマンでブラフマンは吾人の心即アートマンである。このブラフマン即アートマンなることを知るのが、哲学および宗教の奥義であった。キリスト教は始め全く実践的であったが、知識的満足を求むる人心の要求は抑えがたく、ついに中世のキリスト教哲学なるものが発達した。シナの道徳には哲学的方面の発達がはなはだ乏しいが、宋代以後の思想はすこぶるこの傾向がある。これらの事実は皆人心の根柢には知識と情意との一致を求むる深き要求のあることを証明するのである。欧州の思想の発達について見ても、古代の哲学でソクラテス、プラトーを始めとし教訓の目的が主となっている。近代において知識の方が特に長足の進歩をなすとともに知識と情意との統一が困難になり、この両方面が相分かれるような傾向ができた。しかし、これは人心本来の要求に合うたものではない。(125~126頁)
■事実と認識の間に一毫の間隙がない。真に疑うに疑いようがないのである。(130頁)
■我々は意識現象と物体現象と2種の経験的事実があるように考えているが、その実はただ1種あるのみである。すなわち、意識現象あるのみである。物体現象というのはその中で各人に共通で不変的関係を有するものを抽象したのにすぎない(注2)。
(注2)いわゆる物体という実体が存在するのではなく、通常、われわれが物体と呼んでいるのは、意識現象の内で比較的に客観的で不変的な関係を有する部分を抽出して、それに名称を与えたものにすぎない。西田の考えは明らかに唯名論的である。(142頁)
【私(岡野)の考え;私の考えは実在論的で、このあたりからこの本を読み進めるのに、気がおもくなる】
■また、普通には、意識の外にある定まった性質を具えた物の本体が独立に存在し、意識現象はこれにもとづいて起こる現象にすぎないと考えられている。しかし、意識外に独立固定せる物とはいかなるものであるか。厳密に意識現象を離れて物そのものの性質を想像することはできぬ。単にある一定の現象を起こす不知的の或者というより外にない(注1)。(142~143頁)
(注1)西田は意識現象を唯一の実在と考える。したがって、意識現象から独立した物とか物の性質とかいったものの存在をみとめない。もしそのようなもの、例えばわれわれが感覚している個々の「リンゴ」ではなく、いわば「リンゴ」そのものとか「リンゴ」自体とかいったようなものが存在するとしたら、それは時間・空間という枠(直観形式)の下では、またすべてのものは因果法則に従って生ずるという前提条件の下では、われわれの感官に「赤い」とか「丸い」とか「硬い」とか「甘い」とか感じられる、しかしそれ自身はまったく不可知的な或者としかいいようがないというわけである。西田自身、直截に「我々が実際に感覚しているもの、それが物自身である」と考えている。(143~144頁)
【私(岡野)の考え;同じく、だんだん私の世界観とくい違いこの本を読み進めるのに、気がおもくなる】
■いわゆる唯物論者なる者は、物の存在ということをうたがいのない直接自明の事実であるかのように考えて、これをもって精神現象をも説明しようとしている。しかし、少しく考えてみると、こは本末を転倒しているのである(注2)。(143頁)
(注2)本来、純粋経験説は主客未分の「純粋経験」を唯一の実在と考えるたちばであるから、唯物論でも唯心論でもなく、そのような二元論を超越した立場であるが、この箇所に見られるように、『善の研究』には、唯心論に親近感を示す表現が散見される。例えば、本編第9章では「実在は精神において始めて完全なる実在となる」と述べられ、また第4編第3章では「物体によりて精神を説明しようとするのはその本末を顛倒したものといわねばならぬ」と述べられている。(144頁)
【私(岡野)の考え;人間の外側の物の世界は、人間に無関係に実存に超越して在るのだけれども、人間に写り込む形で人間の身体に内在すると考える】
――ここで私はこれ以上読み進めるのを一旦断念したのだが、全注釈を書いた編者の小坂国継氏の補論「『善の研究』について」を読んで、そのなかで「内在的超越主義」(ということは、私が外在的に超越と措定していた存在を、以前読み、この【読書ノート】の2009年8月29日のページにも記した「物の世界」、「心の世界」、「プラトン的イデア界」を三位一体とするペンローズの説と同じではないかと驚く)という言葉にであい、あらためて読み進めることにする。本のページの順序とは違いますが、私が読んだ順にしたがって以下を記していきます――
■意識現象とというと何か主観的もしくは心理的なもののように受けとられがちであるが、ここでいう意識現象とは、主観と客観の未分の状態、あるいは両者の統一的状態、つまり事物が自然現象と精神現象に分かれる以前の根源的状態を指し示す言葉である。
しかし、純粋経験という言葉自体は西田の造語ではない。純粋経験説は当時の西欧の流行思想の一つであって、アヴェナリウスやマッハの『経験批判論』やジェームスの『根本的経験論』において用いられた言葉である。経験批判論というのは、思惟による付加物を取り去った純粋な経験を回復し、主観と客観、意識と存在に分裂する以前の中立的な純粋経験によって世界を説明していこうとする思想であり、また根本的経験論というのは、主客未分の中性的な純粋経験を唯一実在と考え、経験と経験とを結ぶ関係をも一種の経験と考えて、主観と客観、意識と存在を、このような純粋経験相互の関係から生ずる同じ純粋経験の2つの機能ととして説明しようとするものである。いずれも、デカルトに始まる、主観と客観、あるいは意識と対象とを分離する2元論的な思考様式を徹底的に批判して、このような分離以前の純粋経験をもって根本的実在と考え、またそれによってすべてのものを説明していこうとする考え方である。(473~474頁)
■いずれにしても、西田のいう純粋経験の概念は主体的な体験や境位という性格が強い。純粋経験を説明する時、彼が好んで宗教家の「三昧」や芸術家の「神来」の境地を引き合いに出す所以であろう。それは、外から観察された経験というよりも、むしろ内から体験された経験であり、対象的に眺められた経験ではなく、主体的に生きられた経験である。われわれの自己が純粋経験するのであり、否むしろ純粋経験がわれわれの自己自身なのである。(479~480頁)
■さらに、西田は「厳密にいえば、すべての実在には精神があるといってよい」(第2編第9章)とか、「自然もやはり1種の自己を具えているのである」(同編第8章)とかいって、物活論的もしくは汎心論的な考え方をも示している。そして、そこから万物同性的ないしは万物一体的な考え方を提示している。例えば、「元来物と我と区別のあるのではない、客観世界は自己の反影といい得るように自己は客観世界の反影である。我が見る世界を離れて我はない。天地同根万物一体である」(第3編第11章)といっている。(501頁)
■このような誠意や至誠の強調、いいかえれば私欲や私心のなさの強調――それは「人欲を去りて天理を存する」とか「物になって見、物になって行なう」という言葉で表現されている――は陽明と西田に通底した思想である。彼らの思想は世界や物を自己に内在的なものとして、あるいは自己の内に映されたものとして見ていこうとしている点では唯心論であり、それも極端な主観的唯心論であるが、同時にその世界や物をいわゆる自己が消滅したところ、自己が自己を喪失したところから見ていこうとする点で、むしろ無心論であり、徹底した即物論ともいうべきものである。いいかえれば、この哲学は自己が自己でないものになることを要求する哲学であり、また実際に自己が自己でないものになったときに始めて理解されるような哲学である。それ故に、彼らは知よりも意を、知識よりも行為を優先する。それが知行合一の思想である。(504~505頁)
■東洋に独特な思惟様式の特徴として、第1にあげられるのはその唯心論的性格であろう。仏教も陽明学も西田哲学も、これを西洋哲学的な枠組みから見れば、いずれも唯心論に属するものとして分類することができる。(508頁)
■このように陽明においても西田においても、その思想の対象はもっぱら心であり、自己である。彼らは真の心や自己を探求し、またそのことをとおしてものの世界を明らかにしようとした。この点で両者はまったく一致している。そして、この点から見れば、彼らの思想は明らかに主観的唯心論であり、また主観的観念論でもある。(509頁)
■ けれども、普遍的なものは個物的なものに対してただ単に内在的であるだけでなく、同時に超越的でもある。ただその超越的であるというのは、外的・対象的方向に超越的であるのではなく、むしろ反対に内的・主体的方向に超越的であるのである。従来、西洋哲学は伝統的に実在を対象的・超越的方向に考えてきた。それに対して、王陽明や西田幾多郎はもっぱら実在を内在的・超越的方向にもとめている。そして、それは禅仏教でいう「廻光返照」や「脚下照顧(きゃっかしょうこ)」の精神とも符合しているといえるであろう。彼らは実在を自己の外に超越したものとして考えるのではなく、反対にどこまでも自己の内の内に、あるいは底の底に突きぬけたところにもとめようとした。外的超越的方向ではなく、むしろ内的超越的方向である。このような思惟方法は従来の西洋的思惟方法の枠組みを突破するものであるいわなければならない。筆者は東洋思想がもっているこのような内向的性格を、西洋に伝統的な「物の形而上学」に対する「心の形而上学」として特徴づけたことがある。西田自身も東洋に伝統的な論理を西洋的「物の論理」に対する「心の論理」と呼んでいる。(510頁)
■そしてこの点で、西田や王陽明の思想は「内在的超越主義」であるといえよう。(511頁)
■しかし、ここで注意すべきは、このような万物一体の思想の根柢には「否定の論理」が働いていることである。われわれが自己の内底に世界を見、物を見る。また、その意味で世界や物と一体になるということは、実は自己がいわゆる自己であることをどこまでも否定していくことである。こうして、いわゆる自己というものがなくなればなくなるほど、われわれは世界や物と一体となることができる。このように、万物一体の思想は徹底した自己否定を基礎にしている。(512頁)
■自己の内底に物を見るということは、じつは自己というものが消失して「物になりきる」(西田)ということであり、「心を尽くす」(陽明)ということである。そこには、明らかに「否定の論理」が働いている。彼らのいう万物一体の思想は、自己というものをこちら側に保持しておいて、しかる後に対象としての世界や物に対して感情移入していくものではない。つまり、万物の外側から万物と一体になるのではない。そうではなくて、万物の内側から万物と一体になるのである。どこまでも自己というものを否定し消滅させて世界や物になりきるのである。換言すれば、自己を無限に肯定して自己実現をしていくのではなく、むしろ反対に徹底して自己を否定していくことによって、反って真の自己を実現していこうとするのである。そこでは、つねに自己が自己でないものになるということが要求されている。しかも、自己が自己でないものになった時自己は真の自己になると考えられている。そして、そのように自己が真の自己になるための不可欠の要件として、「誠意」や「至誠」が力説されている。それは陽明にとっては「心を尽くす」ということと同義であり、西田にとっては「物になりきる」ということと同義であった。両者にとって共通しているのは、学問はただ知識の習得ではなく、同時に人格の陶冶であり、知と行は一体にして不離なるものであるという考え方である。このような知行合一的な考え方は、とかく知識は知識、実践は実践として両者を分けて考える傾向のある西洋的思惟方法に対して、東洋的思惟方法がもっている顕著な一特性である、といえるであろう。(513頁)
――本のページの順序に戻します――
■純粋経験においては未だ知情意の分離なく、唯一の活動であるように、また未だ主観客観の対立もない。主観客観の対立は我々の思惟の要求より出てくるので、直截経験の事実ではない。直截経験の上においてはただ独立自全の一事実あるのみである。見る主観もなければ見らるる客観もない。あたかも我々が微妙なる音楽に心を奪われ、物我(もつが)相忘れ、天地ただ嚠喨(りゅうりょう)たる一楽声のみなるが如く、この刹那いわゆる真実在が現前している。これを空気の振動であるとか、自分がこれを聴いているのかという考えは、我々がこの実在の真景を離れて反省し、思惟するによって起こってくるので、この時我々はすでに真実在を離れているのである。(155頁)
■しかし、人が情意を有するのでなく、情意が個人をつくるのである、情意は直接経験のじじつである(注1)。
(注1)個人が存在して、その個人が情意を有しているのではない。反対に情意とい
う純粋経験の事実があって、そこから個人の存在がというものが推理されるのである。この言葉は、『善の研究』の序にある「個人あって経験あるにあらず、経験あって個人あるのである、個人的区別より経験が根本的である」という言葉と対応している。(158~159頁)
■上にいったように、主客を没したる知情意合一の意識状態が真実在である。我々が独立自全の真実在を想起すればおのずからこの形において現われてくる。(163頁)
■この統一的或物が物体現象ではこれを外界に存する物力となし、精神現象ではこれを意識の統一力に帰するのであるが、前にいったように、物体現象といい精神現象というも純粋経験の上においては同一であるから、この2種の統一作用は元来、同一種に属すべきものである。我々の思惟意志の根柢における統一力と宇宙現象の根柢における統一力とはただちに同一である、例えば、我々の論理、数学の法則はただちに宇宙現象がこれによりて成立し得る原則である。(173頁)
■ヘーゲルは何でも理性的なるものは実在であって、実在は必ず理性的なるものであるといった。この語は種々の反対を受けたにもかかわらず、見方によっては動かすべからざる真理である。宇宙の現象はいかに些細なるものであっても、決して偶然に起こり前後にまったくなんらの関係をもたぬものはない。必ず起こるべき理由を具して起こるのである。我らはこれを偶然と見るのは単に知識の不足より来るのである。
普通には何か活動の主があって、これより活動が起こるものと考えている。しかし、直接経験より見れば活動そのものが実在である。この主たる物というは抽象概念である。我々は統一とその内容との対立を互いに独立の実在であるかのように思うからかくの如き考えを生ずるのである。(178頁)
■直接経験より見れば、同一内容の意識はただちに同一の意識である、真理は何人が何時代に考えても同一であるように、我々の昨日の意識と今日の意識とは同一の体系に属し同一の内容を有するが故に、ただちに結合せられて一意識と成るのである。個人の一生というものはかくの如き一体系を成せる意識の発展である。
この点より見れば、精神の根柢には常に不変的或者がある。このものが日々その発展を大きくするのである。時間の経過とはこの発展に伴う統一的中心点が変じてゆくのである、この中心点がいつでも「今」である(注3)。(183頁)
(注3)時間が経過するというのは、根源的統一力の発展において、その中心点が変移していくということである。そして、変移していくその瞬間瞬間の中心点が「今」であり、「自己」であるのである。(184頁)
■自己は認識主観であるが、この自己を認識しようとすると、われわれはこれを対象化しなければならない。しかし、対象化された自己は客観としての自己であって、もはや主観としての自己でなくなってしまう。それは「意識する意識」ではなく、「意識される意識」となる。この意味で、主観としての自己はけっして認識の対象とはならないものである。ちょうど眼は何でも見ることができるが、自分自身を見ることができないように、自己は何でも知ることができるが、自分自身を知ることはできない。(193~194頁)
■ハルトマンも無意識が活動であるといっているように、我々が主観の位置に立ち活動の状態にある時はいつも無意識である。これに飯紙、ある意識を客観的対象として意識した時には、その意識はすでに活動を失ったものである。たとえば、ある芸術の修練についても、一々の動作を意識している間は未だ真に生きた芸術ではない、無意識の状態に至って始めて生きた芸術となるのである。(196頁)
■実在はただ一つあるのみであって、その見方の異なるによりて種々の形を呈するのである。(201頁)
■我々は愛する花を見、また親しき動物を見て、ただちに全体において統一的或者を捕捉するのである。これがその物の自己、その物の本体である。美術家はかくの如き直覚の最もすぐれた人である。彼らは一見、物の真相を看破して統一的或者を捕捉するのである。彼らの現わす所のものは表面の事実でなく、深く物の根柢に潜める不変の本体である。(207頁)
■意志はただ客観的自然に従うによってのみ実現し得るのである。水を動かすのは水の性に従うのである、人を支配するのは人の性に従うのである、自分を支配するのは自分の性に従うのである、我々の意志が客観的となるだけそれだけ有力となるのである。釈迦、キリスト(基督)が千歳の後にも万人を動かす力を有するのは、実に彼らの精神が能く客観的であった故である。我なき者すなわち自己を滅せる者は最も偉大なる者である。
普通には精神現象と物体現象とを内外によりて区別し、前者は内に、後者は外にあると考えている。しかしかくの如き考えは、精神は肉体の中にあるという独断より起こるので、直接経験より見ればすべて同一の意識現象であって、内外の区別があるのではない。我々が単に内面的なる主観的精神といっているものは極めて表面的なる微弱なる精神である、すなわち個人的空想である。これに反して、大なる深き精神は宇宙の真理に合したる宇宙の活動そのものである。それで、かくの如き精神にはおのずから外界の活動を伴うのである、活動すまいと思うてもできないのである。美術家の神来(注3)の如きはその一例である。
(注3)インスピレーション、霊感。(222~223頁)
■精神は実在の統一作用であって、大なる精神は自然と一致するのであるから、我々は小なる自己をもって自己となす時には苦痛多く、自己が大きくなり客観的自然と一致するに従って幸福となるのである。(224頁)
■実在成立の根柢には歴々として動かすべからざる統一の作用が働いている。実在は実にこれによって成立するのである。例えば、3角形のすべての角の和は2直角であるというの理はどこにあるのであるか、我々は理そのものを見ることも聞くこともできない、しかもここに厳然として動かすべからざる理が存在するのではないか。また、一幅の名画に対するとせよ、我々はその全体において神韻縹渺(しんいんひょうびょう)として霊気人を襲うものあるを見る、しかもその中の一物一景についてそのしかる所以のものを見出さんとしても到底これを求むることはできない。神はこれらの意味における宇宙の統一者である。実在の根本である。ただその能く無なるが故に、有らざる所なく働かざる所がないのである。
数理を解し得ざる者には、いかに深遠なる数理もなんらの知識を与えず、美を解し得ざる者には、いかに巧妙なる名画もなんらの感動を与えぬように、平凡にして浅薄なる人間には神の存在は空想の如くに思われ、なんらの意味もないように感ぜられる、したがって宗教などを無用視している。真正の神を知らんと欲する者はぜひ自己をそれだけに修練して、これを知り得るの眼を具えねばならぬ。かくの如き人には宇宙全体の上に神の力なるものが、名画の中における画家の精神の如くに活躍し、直接経験の事実として感ぜられるのである。これを見神(注6)の事実というのである。
(注6)神の示現を心中に感得すること。(233~234頁)
■元来無限なる我々の精神は決して個人的自己の統一をもって満足するものではない。さらに、進んで一層大なる統一を求めねばならぬ。我々の大なる自己は他人と自己とを包含したものであるから、他人に同情を表わし他人と自己との一致統一を求むるようになる。我々の他愛とはかくの如くして起こってくる超個人的統一の要求である。故に、我々は他愛において、自愛におけるよりも一層大なる平安と喜悦とを感ずるのである。しかして、宇宙の統一なる神は実にかかる統一的活動の根本である。我々の愛の根本、喜びの根本である。神は無限の愛、無限の喜悦、平安である。(236頁)
■以上のような神概念は通常の神概念とは非常に異なっている。まず、それは宇宙の外にあって、外から宇宙を支配している人格的な存在者ではない。また、宇宙の創造主としての神でもない。さらには、宇宙におけるすべての目的や調和の原因としての神でもない。ましてや、」道徳的秩序の維持者としての神ではない。西田の神概念は、このような有神論的な神よりも、むしろ汎神論的な神の観念に近い。彼は神と世界との関係を、芸術家とその作品との関係としてよりも、むしろ本体とその現象との関係としてとらえているように思われる。(237~238頁)
■想像も意志も、ある一定の目的観念にしたがった観念統一の作用であるが、想像の目的は「自然の模倣」であるのに対して、意志の目的は「自己の実現」にあるから、この点で両者は本質的に異なっているように見える。しかし、想像も、例えば芸術家の「入神」すなわち霊感(インスピレーション)の域に達すれば「全く自己をその中に没し自己と物と全然一致して、物の活動がただちに自己の意志活動と感ぜらるるようにもなる」。したがって、想像と意志を明確に区別することは困難である。(249頁)
■かく考うれば、真理は単に相対的である。余はむしろこの考えを反対となし、分析よりも綜合に重きを置いて、合目的なる自然が個々の分立より綜合に進み、階段を踏んで己が真意を発揮すると見るのが至当であると思う。(254頁)
■意志が自由であるか、はたまた必然であるかは久しき以来学者の頭を悩ました問題である。この議論は道徳上大切であるのみならず、これによりて意志の哲学的性質をも明らかにすることができるのである。(259頁)
■すなわち、観念をいかに分析し、いかに綜合するかが自己の自由に属するのである。もちろん、この場合においても観念の分析綜合には動かすべからざる先天的法則なるものがあって、勝手にできるのではなく、また観念間の結合が唯一であるか、またはある結合が特に恐盛であった時には、我々はどうしてもこの結合に従わねばならぬのである。ただ観念成立の先天的法則の範囲内において、しかも観念結合に2つ以上の途があり、これらの結合の強度が脅迫的ならざる場合においてのみ、全然選択の自由を有するのである。(260頁)
■宇宙の現象は1つとして偶然に起こるものはない、極めて些細なる事柄でも、精しく研究すれば必ず相当の原因を持っている。この考えはすべて学問と称するものの根本的思想であって、かつ科学の発達とともにますますこの思想が確実となるのである。自然現象の中にて従来神秘的と思われていたものも、一々その原因結果が明瞭となって、数学的に計算ができるようにまで進んできた。今日の所でなお原因がないなどと思われているものは我々の意志くらいである。しかし意志といってもこの動かすべからざる自然の大法則の外に脱することはできまい。今日意志が自由であると思うているのは、畢竟未だ科学の発達が幼稚であって、一々この原因を説明することができぬ故である。しかのみならず、意志的動作も個々の場合においては、実に不規則であって一見定まった原因がないようであるが、多数の人の動作を統計的に考えてみると案外秩序的である、決して一定の原因結果がないとは見られない。これらの考えはますます我々の意志に原因があるという確信を強くし、我々の意志はすべての自然現象と同じく、必然なる機械的因果の法則に支配せらるるもので、別に意志という一種の神秘力はないという断案に到達するのである。(261頁)
■なんらの理由なくして全く偶然に事を決する如きことがあったならば、我々はこの時意志の自由を感じないで、反ってこれを偶然の出来事として外より働いたものと考えるのである(注1)。
(注1)何の理由も原因もなく行為を決定することができるという場合、その行為は偶然おこななわれた行為であり、その時の外界の事情によって生じた行為であるということになるであろう。いいかえれば、それは外から決定された行為であって、内から生じた自由な行為とはいえない。自由であるということの内には、それが自分の外からではなく、自分の内から決定されたという意味がなんらかの形で含まれていなければならない。(262頁)
■我々の精神には精神活動の法則がある。精神がこの己自身の法則に従うて働いた時が真に自由であるのである。自由には2つの意義がある。1つは全く原因がないすなわち偶然ということと同意義の自由であって、1つは自分が外の束縛を受けない、己自らにて働く意味の自由である。すなわち、必然的自由の意義である。意志の自由というのは、後者における意味の自由である。しかし、ここにおいて次の如き問題が起こってくるであろう。自己の性質に従うて働くのが自由であるというならば、万物皆自己の性質に従って働かぬものはない、水の流れるのも火の燃えるのも皆自己の性質に従うのである。しかるに、何故に他を必然として、独り意志のみ自由となすのであるか。(264頁)
■さらに、詳言すれば、意識には必ず一般的性質のものがある、すなわち意識は理想的要素をもっている。これでなければ意識ではない。しかして、これらの性質があるということは、現実のかかる出来事の外、さらに他の可能性を有しているというのである。現実にしてしかも理想を含み、理想的にしてしかも現実を離れぬというのが意識の特性である。(266頁)
■このように、西田は、真の自由は「内的な自由」ないしは「必然的自由」でなければならないと言うことを主張し、またこのような意味での自由には、事物に対する知的な洞察が不可欠であるということを強調している。われわれは自己の自然に従うが故に自由であり、自己の行為の理由を知るが故に自由である。「我々は知識の進むとともにますます自由の人となることができる」。この意味で、ソクラテスを裁いたアテナイ人よりもソクラテスの方が自由であり、また人間は「考える葦」であるが故に、彼を滅せんとするものよりも尊い。(270~271頁)
■すべての現象あるいは出来事を見るに2つの点よりすることができる。1はいかにして起こったか、また何故にかくあらざるべからざるかの原因もしくは理由の考究であり、1は何のために起こったかという目的の考究である(注1)。例えば、ここに1個の花ありとせよ。こはいかにしてできたかといえば、植物と外囲の事情とにより、物理および科学の法則によりて生じたものであるといわねばならず、何のためかといえば果実を結ぶためであるということとなる。前者は単に物の成立の法則を研究する理論的研究であって、後者は、物の活動の法則を研究する実践的研究である。(272頁)
(注1)前者は「動力因」ないし「作用院」、後者は「目的因」と呼ばれる。(273頁)
■なるほど我々の日常の経験について考えてみると、行為の善悪を判断するのは、かれこれ理由を考えるのではなく、たいてい直覚的に判断するのである。いわゆる良心なるものがあって、あたかも眼が物の美醜を判ずるが如く、ただちに行為の善悪を判ずることができるのである。直覚説はこの事実を根拠としたもので、最も事実に近い学説である。しかのみならず、行為の善悪は理由の説明を許さぬというのは、道徳の威厳を保つ上においてすこぶる有効である。(280頁)
■エソップの寓話の中に、ある時鹿の子が母鹿の犬の声に怖れて逃げるのを見て、お母さんは大きな体をして何故に小さい犬の声に駭(おどろ)いて逃げるのかと問うた。ところが、母鹿は何故か知らぬが、ただ犬の声が無暗にこわいから逃げるのだといったという話がある(注5)。
(注5)『イソップ寓話集』第4部351「仔牛と鹿」。西田の記憶は正確ではないようである。きわめて短い寓話なので、その全文をかかげておく。
いくら図体が大きく頑強そうに見えても、生まれつき臆病な者は、言葉で励ましても力づけはできない、ということ。
仔牛が鹿に向かって、
「君は犬より体が大きいし、足の速さでも勝っている。おまけに防御の角まである。なのにどうしてそんなに犬を怖がるのだ」と尋ねると、鹿の言うには、
「たしかに全部揃ってる。だけど犬の吠えるのを聞いたら、分別がかき曇り、頭の中は逃げることで、一杯になるのだ」(中務哲郎訳、岩波文庫、262頁)(292~293頁)
■利己的快楽説とは、自己の快楽の追究をもって人生の究極目的とするものである。この説の代表として西田はキュレネ学派のアイスティッポスの説とエピクロスの説とを紹介している。アイスティッポスは瞬間の積極的な快楽をもとめたのに対して、エピクロスは一生にわたる消極的な快楽、つまり快楽の享受よりも苦痛の欠如をもとめた。エピクロスにとっては最大の善は心の安静(アタラクシア)にあり、彼の考えは一種の隠遁主義であった。「エピクロスの園」という言葉がそれをよく示している。
また、公衆的快楽説とは、功利主義のことであり、その根本原理においては利己的快楽説と異ならないが、ただこの説は、個人の快楽をもって最上の善とは考えず、かえって社会全体の快楽をもって最高善と考える。それが公衆的快楽説と呼ばれる所以である。功利主義の究極目的は「最大多数の最大幸福」にあるのである。(320頁)
■善は何であるかの説明は意志そのものの性質に求めねばならぬことは明らかである。意志は意識の根本的統一作用であって、ただちにまた実在の根本たる統一力の発現である。意志は他のための活動ではなく、己自らのための活動である。意志の価値を定むる根本は意志そのものの中に求むるより外はないのである。意志活動の性質は、先に行為の性質を論じた時にいったように、その根柢には先天的要求(意識の素因)なるものがあって、意識の上には目的観念として現われ、これによりて意識の統一するにあるのである。この統一が完成せられた時、すなわち理想が実現せられた時我々に満足の感情を生じ、これに反した時は不満足を生ずるのである。行為の価値を定むるものは一にこの意志の根本たる先天的要求にあるので、能くこの要求すなわち吾人の理想を実現し得た時にはその行為は善として賞讃せられ、これに反した時は悪として非難せられるのである。そこで善とは我々の内面的要求すなわち理想の実現、換言すれば、意志の発展完成であるということとなる。かくの如き根本的思想にもとづく倫理学説を活動説という(注1)。(325頁)
(注1)(energetism)意志説と同義。人間精神の本質を知情意の内の意志にもとめ、意志の発展・完成を最高善とする立場。(326頁)
■真正の幸福は反って厳粛なる理想の実現によりて得らるべきものである。世人は往々自己の理想の実現または要求の満足などいえば利己主義または我儘主義と同一視している。しかし、最も深き自己の内面的要求の声は我々にとりて大なる威力を有し、人生においてこれより厳かなるものはないのである。(323頁)
■すなわち、我々の精神が種々の能力を発展し円満なる発達を遂げるのが最上の善である(アリストテレースのいわゆるenntelechie(注2)が善である)。竹は竹、松は松と各自その天賦を充分に発揮するように、人間が人間の天性自然を発揮するのが人間の善である。スピノーザも「徳とは自己固有の性質に従うて働くの謂(いい)に外ならず」といった。
(注1)(エンテレケイア)(完全現実態)。単なる可能態(デュミナス)に対する言葉で、完全におこなわれた行為とか、完成された現実性とかいった意味。(328頁)
■ここにおいて善の概念は美の概念と近接してくる。美とは物が理想の如くに実現する場合に感ぜられるのである。理想の如くに実現するというのは物が自然の本性を発揮する謂いである。それで花が花の本性を現じたる時最も美なるが如く、人間が人間の本性を現じた時は美の頂上に達するのである。善はすなわち美である。たとい行為そのものは大なる人性の要求から見てなんらの価値なきものであっても、その行為が真にその人の天性より出でたる自然の行為であった時には一種の美感を惹くように、道徳上においても一種寛容の情を生ずるのである。ギリシャ人は善と美とを同一視している。この考えは最も能くプラトーにおいて現われている。(329頁)
■いわゆる価値的判断の本(もと)である内面的欲求と実在の統一力とは1つであって2つあるのではない。存在と価値とを分けて考えるのは、知識の対象と情意の対象とを分かつ抽象的作用よりくるので、具体的真実性においてはこの両者は元来1つであるのである。すなわち、善を求め善に遷るというのは、つまり自己の真を知ることとなる。合理論者が真と善とを同一にしたのも1面の真理を含んでいる。しかし、抽象的知識と善とは必ずしも一致しない。このばあいにおける知とはいわゆる体得の意味でなければならぬ。これらの考えはギリシャにおいてプラトーまたインドにおいてウパニシャッドの根本的思想であって、善に対する最深の思想であると思う(プラトーでは善の理想が実在の根本である、また、中世哲学においても「すべての実在は善なり」という句がある)。(330頁)
■真の意識統一というのは我々を知らずして自然に現われ来る純一無雑の作用であって、知情意の分別なく主客の隔離なく独立自全なる意識本来の状態である。我々の真人格はかくの如き時にその全体を現わすのである。故に、人格は単に理性にあらず、欲望にあらず、況んや無意識的衝動にあらず、あたかも天才の神来の如く各人の内より直接に自発的に活動する無限の統一力である(古人も道は知、不知に属せずといった(注4)。(342頁)
(注4)『無門関」第19則に出てくる南泉の言葉。(343頁)
■上来論じた所を総括していえば、善とは自己の内面的要求を満足するものをいうので、自己の最大なる要求とは意識の根本的統一力すなわち人格の要求であるから、これを満足することすなわち人格の実現というのが我々にとりて絶対的善である。しかして、この人格の要求とは意識の統一力であるとともに実在の根柢における無限なる統一力の発現である、我々の人格を実現するというはこの力に合一するの謂である(注1)。善はかくの如きものであるとすれば、これより善行為とはいかなる行為であるかを定めることができると思う。(346頁)
(注1)西田の人格概念の特徴は、それが人間の内なる原理(意識の統一力)であると同時に、宇宙の根源的統一力でもあると考えられている点である。そして、前者が後者に合致するということが善行為の動機すなわち善の形式であると考えられている。すなわち、意識の統一力の発現である内面的要求が同時に宇宙の根源的統一力の発現と見なされる時、そこの人格が実現する。(347頁)
■善行為とはすべての自己の内面的必然より起こる行為でなければならぬ。先にもいったように、我々の全人格の要求は我々が未だ思慮分別せざる直接経験の状態においてのみ自覚することができる。人格とはかかる場合において心の奥底より現われ来って、徐ろに全心を包容する一種の内面的要求の声である。人格そのものを目的とする善行とはかくの如き要求に従った行為でなければならぬ。これに背けば自己の人格を否定した者である。至誠(注1)とは善行に欠くべからざる要件である。
(注1)至誠ないし誠は西田が非常に重視した徳目で、遺稿となった『場所的論理と宗教的世界観」においても説かれている。(347~348頁)
■しかし、人格の内面的必然すなわち至誠というのは知情意合一の上の要求である。知識の判断、人情の要求に反して単に盲目的衝動に従うの謂ではない。自己の知をつくし情を尽くした上において始めて真の人格的要求すなわち至誠(注4)が現われてくるのである。自己の全力を尽くしきり、ほとんど自己の意識がなくなり、自己が自己を意識せざる所に、始めて真の人格の活動を見るのである。試みに芸術の作品について見よ。画家の真の人格すなわちオリジナリティはいかなる場合に現われるか。画家が意識の上において種々の企図をなす間は未だ真に画家の人格を見ることはできない。多年苦心の結果、技芸内に熟して意至り筆おのずから随(したが)う所に至って始めてこれを見ることができるのである。道徳上における人格の発現もこれと異ならぬのである。人格を発現するのは一時の情慾に従うのではなく、最も厳粛なる内面の要求に従うのである。放縦懦弱(だじゃく)とは正反対であって、反って艱難辛苦の事業である。
(注4)至誠はもともと『中庸』の根本思想で、その20章に「誠は天の道なり。これを誠にするは人の道なり」とある。これは、そのまま西田の人格概念にあてはめることができるであろう。(349~350頁)
■自己の真摯なる内面的要求に従うということ、すなわち自己の真人格を実現するということは、客観に対して主観を立し、外物を自己に従えるという意味ではない。自己の主観的空想を消磨し尽くして全然物と一致したる処に、反って自己の真要求を満足し真の自己を見ることができるのである。一面より見れば、各自の客観的世界は各自の人格の反影であるということができる。否、各自の真の自己は各自の前に現われたる独立自全なる実在の体系そのものの外にはないのである。(350頁)
■それで、自己の最大要求を充たし自己を実現するということは、自己の客観的理想を実現するということになる、すなわち客観といっちするということである。この点より見て、善行為は必ず愛であるということができる。愛というのはすべて自他一致の感情である。主客合一の感情である。ただ人が人に対する場合のみでなく、画家が自然に対する場合も愛である。(350~351頁)
■しかし、さらに一歩を進めて考えてみると、真の善行というのは客観を主幹に従えるのでなく、また主観が客観に従うのでもない。主観相没し物我(もつが)相忘れ天地唯一実在の活動あるのみなるに至って、甫(はじ)めて善行の極致に達するのである。物が我を動かしたのでもよし、我が物を動かしたのでもよい。雪舟が自然を描いたものでもよし、自然が雪舟を通して自己を描いたものでもよい。元来、物と我と区別のあるのではない、客観世界は自己の反影といい得るように自己は客観世界の反影である。我が見る世界を離れて我はない(実在第9精神の章を参看せよ)。天地同根万物一体である。インドの古賢はこれを「それは汝である」といい、パウロは「もはや余生けるにあらずキリスト余にありて生けるなり」といい(ガラテア書第2章20)、孔子は「心の欲する所に従うて矩(のり)を踰(こ)えず」といわれたのである。(351~352頁)
■我々の肉体の本は祖先の細胞にある。我々は我々の子孫とともに同一細胞の分裂によりて生じたものである。生物の全種族を通じて同一の生物と見ることができる。生物学者は今日生物は死せずといっている。意識生活について見てもそのとおりである。人間が共同生活を営む処には必ず各人の意識を統一する社会意識なるものがある。言語、風俗、習慣、制度、法律、宗教、文学等はすべてこの社会的意識の現象である。我々の個人的意識はこの中に発生しこの中に養成せられたもので、この大なる意識を構成する一細胞にすぎない。知識も道徳も趣味もすべて社会的意義をもっている。最も普遍的なる学問すらも社会的因襲を脱しない(今日各国に学風というものがあるのはこれがためである)。いわゆる個人の特性というものはこの社会的意識なる基礎の上に現われ来る多様なる変化にすぎない、いかに奇抜なる天才でもこの社会的意識の範囲を脱することはできぬ。反って社会的意識の深大なる意義を発揮した人である。(キリストのユダヤ教に対する関係がその一例である(注2))。真に社会的意識となんらの関係なき者は狂人の意識の如きものにすぎぬ。
(注2)例えばイエスの出現は、当時のユダヤ社会、特にその支配層の堕落、ユダヤ人のなかに広まった終末論思想やメシア(救世主)の来臨への願望等と密接に連関している。(359~360頁)
■かく社会的意識なるものがあって我々の個人的意識はその一部であるから、我々の要求の大部分はすべて社会的である。もし我々の欲望の中よりその他愛的要素を去ったならば、ほとんど何物も残らないくらいである。我々の生命慾も主なる原因は他愛にあるをもってみても明らかである。(361頁)
■ここにおいて、我々はさらに大なる生命を求めねばならぬようになる、すなわち、意識中心の推移によりてさらに大なる統一を求めねばならぬようになるのである。かくの如き要求はすべて我々の協同的精神の発生の場合においてもこれを見ることができるのであるが、ただ宗教的要求はかかる要求の極点である。我々は客観的世界に対して主観的自己を立っしこれによりて前者を統一せんとする間は、その主観的自己はいかに大なるにもせよ、その統一は未だ相対的たるを免れない、絶対的統一はただ全然主観的統一を棄てて客観的統一に一致することによりて得られるのである。(382頁)
■宗教とは神と人との関係である。神とは種々の考え方もあるであろうが、これを宇宙の根本と見ておくのが最も適当であろうと思う、しかして、人とは我々の個人的意識を指すのである。この両者の関係の考え方によって種々の宗教が定まってくるのである。しからばいかなる関係が真の宗教的関係であろうか。もし神と我とはその根柢において本質を異にし、神は単に人間以上の偉大な力という如きものとするならば、我々はこれに向かって毫も宗教的動機を見出すことはできぬ。あるいはこれを恐れてその命に従うこともあろう、あるいは、これに媚びて福利を求めることもあろう。しかし、そは皆利己心より出ずるにすぎない、本質を異にせぬものの相互の関係は利己心の外になりたつことはできないのである。(389頁)
■我々が神に祈りまたは感謝するというも、自己の存在のためにするのではない、己が本文の家郷たる神に帰せんことを祈りまたこれに帰せしことを感謝するのである。また、神が人を愛するというのもこの世の幸福を与うるのではない。これをして己に帰せしめるのである。神は生命の源である、我はただ神において生く。かくありてこそ宗教は生命に充ち、真の敬虔の念も出でくるのである。単に諦めるといい、任すという如きはなお自己の臭気を脱しておらぬ、未だ真の敬虔の念とはいわれない。神において真の自己を見出すなどという語はあるいは自己の重きを置くように思われるかも知らぬが、これ反って真に己を棄てて神を崇(たっと)ぶ所以である。(390頁)
■神は宇宙の外に超越せるものであって、外より世界を支配し人に対しても外から働くように考えることもでき、また神は内在的であって、人は神の一部であり神は内より人に働くと考えることもできる。前者は有神論(注1)の考えであって、後者はいわゆる汎神論(注2)の考えである。(392頁)
(注1)有神論;広義においては、神の存在を否定する無神論に対して、神の存在を主張する立場をいうが、狭義においては、神の人格生を否定する理神論に対しては神の人格性を肯定し、また神の内在性を主張する汎神論に対してはその超越性を主張する立場をいう。
(注2)汎神論;一切万有は神であり、神は自然であるとする立場。「神即自然」の定型で表現され、神の内在性と否人格性を主張する。万有神論ともいう。(393頁)
■昨日の意識と今日の意識は同一の統一を有するがゆえに同一の精神と見ることができるように、自己の意識と他己の意識は同一の統一を有するがゆえに同一の精神と見ることができる。そして、これを自己と自己の根柢たる神との関係にまで拡大していけば、われわれの精神は神と同一体であるということになる。だとすれば、「我は神において生く」というのは単なる比喩ではなくして事実であることになるであろう。そして、これが西田の正真の信念であった。それ故、「宗教の真意はこの神人合一の意義を獲得するにあるのである。すなわち、我々は意識の根柢において自己の意識を破りて働く堂々たる宇宙的精神を実験するにあるのである」と西田は述べている。そして、ここに西田の宗教観の核心があるといえるであろう。(401頁)
■神とはこの宇宙の根本をいうのである。上に述べたように、余は神を宇宙の外に超越せる造物者とは見ずして、ただちにこの実在の根柢と考えるのである。神と宇宙との関係は芸術家とその作品との如き関係ではなく、本体と現象(注2)との関係である。宇宙は神の所作物ではなく、神の表現である。外は日月星辰の運行より、内は人心の機微に至るまでことごとく神の表現でないものはない、我々はこれらの物の根柢においていちいち神の霊光を拝することができるのである。
(注2)本体と現象;現象とは文字どおりすがた(象)となって現われたもの、われわれの五感に映ったもののことをいい、本体とは現象の奥にあると考えられる実体をいう。通常、現象は変化するものであるのに対して、本体は恒常不変であると考えられている。(402頁)
■かく実在に精神と自然との別なく、従うて2種の統一あることなく、ただ同一なる直接経験の事実その物が見方によりて種々の差別を生ずるものとすれば、余が前にいった実在の根柢たる神とは、この直接経験の事実すなわち我々の意識現象の根柢でなければならぬ。しかるに、すべて我々の意識現象は体系をなしたものである。超個人的統一によりて成れるいわゆる自然現象といえどもこの形式を離れることはできぬ。統一的或者の自己発展というのがすべての実在の形式であって、神とはかくの如き実在の統一者である。宇宙と神との関係は、我々の意識現象とその統一との関係である。思惟においても意志においても心象が1つの目的観念により統一せられ、すべてがこの統一的観念の表現と見なされる如くに、神は宇宙の統一者であり宇宙は神の表現である。この比較は単に比喩ではなくして事実である。神は我々の意識の最大最終の統一者である、否、我々の意識は神の意識の一部であって、その統一は神の統一より来るのである。小は我々の一喜一憂より大は日月星辰の運行に至るまで皆この統一によらぬものはない。ニュートンやケプレルもこの偉大なる宇宙的意識の統一に打たれたのである。(407~408頁)
■自覚とは部分的意識体系が全意識の中心において統一せられるる場合に伴う現象である。自覚は反省によって起こる、しかして、自己の反省とはかくの如く意識の中心を求むる作用である。自己とは意識の統一作用の外にない、この統一がかわれば自己もかわる。この外に自己の本体というようなものは空名にすぎぬのである。我々が内に省みて一種特別なる自己の意識を得るように思うが、そは心理学者のいう如くこの統一に伴う感情にすぎない(注6)。かくの如き意識あってこの統一がおこなわれるのではなく、この統一あってかくの如き意識を生ずるのである。(410頁)
(注6)例えば、ジェームスは、自己はけっして実体的な存在ではなく、いわば「意識の流れ」(stream of consciousness)、あるいは「主観的な生の流れ」(stream of subjective life)であり、われわれがそこに何か統一的なものを感じるのは、他の対象には感じ得ないような一種独特な「暖かさ」と「親しさ」があるからである、といっている。(ジェームス『心理学』岩波文庫、上巻、220-223頁)(412頁)
■かく神には不定的意志すなわち随意ということがないのであるから、神の愛というのも神はある人々を愛し、ある人々を憎み、ある人々を栄えしめ、ある人々を亡ぼすという如き偏狭の愛ではない。神はすべての実在の根柢として、その愛は平等普遍でなければならず、かつその自己発展そのものがただちに我々にとりて無限の愛でなければならぬ。万物自然の発展の外に特別なる神の愛はないのである。(414頁)
■すべての意識の統一は変化の上に超越して湛然不動でなければならぬ、しかも変化はこれより起こってくるのである、すなわち動いて動かざるものである。また、意識の統一は知識の対象となることはできぬ、すべての範疇を超越している、我々はこれのなんらの定形を与うることもできぬ、しかも万物はこれによりて成立するのである。それで、神の精神という如きことは、一方より見ればいかにも不可知的であるが、また一方より見れば反って我々の精神と密接しているのである。我々はこの意識統一の根柢においてただちに神の面影に接することができる。故に、ベーメも「天は到る処にあり、汝の立つ処行く処皆天あり」といい、また「最深なる内生によって神に到る」といっている。(416頁)
■しかし、ヘーゲルなどのいったように、真の個人性というのは一般性を離れて存するものではない、一般性の限定せられたものが個人性となるのである。一般的なるものは具体的なるものの精神である。個人性とは、一般性に外より他の或者を加えたのではない、一般性の発展したものが個人性となるのである。なんらの内面的統一もない単に種々の性質の偶然的結合というようなものには個人性というべきものはない。個人的人格の要素たる意志の自由ということは一般的なるものが己自身を限定する self-determination の謂である。(419頁)
■右の如き状態においては天地ただ一指(注7)、万物我と一体(注8)であるが、曩にもいったように、一方より見れば実在体系の衝突により、一方より見ればその発展の必然的過程として実在体系の分裂を来すようになる、すなわちいわゆる反省なるものが起こってこなければならぬ。これによって現実であってものが観念的となり、具体的であったものが抽象的となり、一であったものが多となる。ここにおいて、一方に神あれば一方に世界あり、一方に我あれば一方に物あり、彼此相対し物々相背くようになる。我らの祖先が知慧の樹の果を食うて神の楽園より追い出だされたというのも、この真理を意味するのであろう。人祖堕落はアダム、エヴの昔ばかりではなく、我らの心の中に時々刻々おこなわれているのである。しかし、翻って考えてみれば、分裂といい反省といい別にかかる作用があるのではない、皆これ統一の反面たる分化作用の発展にすぎないのである。分裂や反省の背後にはさらに深遠なる統一の可能性を含んでいる、反省は深き統一に達する途(みち)である(「善人なほ往生す、いかにいはんや悪人をや」という語がある)。神はその最深なる統一を現わすにはまず大いに分裂せねばならぬ。人間は一方より見ればただちに神の自覚である。キリスト教の伝説をかりていえば、アダムの堕落があってこそキリストの救いがあり、したがって無限なる神の愛が明らかとなったのである。(436頁)
(注7)一指頭禅、倶胝(くてい)の一指ともいう。『無門関』3則。
(注8)万物我と一体;僧肇(そうじょう)(?-414)の言葉。「天地与我同根、万物与我一体」。『碧巌録』第40則。もとは『荘子(そうじ)』の斉物(せいぶつ)論へん6にある「天地は我と並び生じて、万物は我と一たり」に由来する。(440頁)
■われわれはわれわれの意識内容を知ることはできるが、意識統一そのものを知ることはできないということである。意識統一そのものはけっして意識の対象とはならないからである。意識統一は文字どおり意識を統一するはたらきであるが、それがいしきされたときには、その意識統一はもはや〈意識を統一する意識〉ではなく、反対に〈意識によって統一された意識〉になってしまう。むしろ意識統一はあらゆる意識を超越するものでなければならない。黒を見て黒を意識するも心(意識統一自身)は黒であるわけではない。白を見て白を意識するも心は白であるわけではない。意識統一自身は不可知である。したがって、また、意識統一の根柢である神自身も不可知であることになる。ディオニュシオス一派の否定神学が神は肯定によってではなく否定によって知られると説き、クザーヌスは神は有にして無であるといい、ベーメは「無底」であるといった所以である。これらの言葉はいずれも神の不可思議性を表現したものと考えられる。また、神は永久であるとか、遍在であるとか、全知全能であるとかいうのも、意識統一のこのような超越的な性格を表現したものである。(446~447頁)
■万物が神の表現であるということは、必ずしも各人の自覚的独立を妨げるものではなく、部分は全体の統一の下にあるということは、必ずしも各人の意識の独立性を否定するものではない。各人はそれぞれ神の一表現でありながら、同時にその発展の担い手として目的そのものである。個人性は、それが全体の一要素として働く時真の個人性を発揮するのであり、また神の愛は無限であるがゆえに、すべての人格を自己の内に包容するとともに、すべての人格の独立を承認するのである。ここには後の「一即多・多即一」の思想の萌芽が見られる。(448~449頁)
■何故に知は主客合一であるか。我々が物の真相を知るというのは、自己の妄想臆断すなわちいわゆる主観的のものを消耗し尽くして物の真相に一致した時、すなわち純客観に一致した時始てこれを能くするのである。例えば、名月の薄黒い処のあるは兎が餅をついているのであるとか、地震は地下の大鯰が動くのであるとかいうのは主観的妄想である。しかるに、我々は天文、地質の学において全然かかる主観的妄想を棄て、純客観的なる自然法則に従うて考究し、ここに始てこれらの現象の真相を知ることができる。数千年来の学問進歩の歴史は我々人間が主観を棄て客観に従い来った道筋を示したものである。(451頁)
■我々が自己の私を棄てて純客観的すなわち無私となればなるほど愛は大きくなり深くなる。親子夫妻の愛より朋友の愛にすすむ。仏陀の愛は禽獣草木にまでも及んだのである。(452頁)
■余の考えをもって見ると、普通の知とは非人格的対象の知識である。たとい対象が人格的であっても、これを非人格的として見た時の知識である。これに反し、愛とは人格的対象の知識である、たとい対象が非人格的であってもこれを人格的として見た時の知識である。両者の差は精神作用そのものにあるのではなく、むしろ対象の種類によるといってよろしい。しかして、古来、幾多の学者哲人のいったように、宇宙実在の本体は人格的のものであるとすると、愛は実在の本体を捕捉する力である。物の最も深き知識である。分析推論の知識は物の表面的知識であって実在そのものを捕捉することはできぬ。我々はただ愛によりてのみこれに達することができる。愛は知の極点である。(454頁)
■ここで西田は、われわれが自分の主観的妄想や臆断を断って、純粋に客観的になればなるほど、われわれは物の真相に迫ることができる、と説いている。けれども、ここでいう「客観的」を自然科学でいうところの「客観的」と同一視してはならない。西田はここで自然科学的な、いわゆる客観的な見方を称揚しているわけではけっしてないのである。。というのも、自然科学でいう客観は、主観と客観の2元論の立場に立った、したがって主観と対立するものとして主観の側から見られた客観である。これに対して、西田のいう客観は、主観が自己を没し、自己を無にしたところに生じてくるような客観である。したがって、それは主観=客観としての客観であり、純粋客観である。主観と客観を対立させた上で、主観によって構成された客観ではなく、主観が自己を消耗し尽くしたところに現れてくる客観である。前者においてはどうしても主観主義的要素が残る。カントの認識論が一種の主観的観念論であるのと同様である。晩年、西田は、デカルトやカントに代表される近代西洋の物の見方を「主観主義」とか「対象論理」とか呼び、これに対して自分の考え方を「絶対的客観主義」と呼んだ。一見すると、本章の最初の部分で、あたかも西田が自然科学的な、いわゆる客観的な見方を主張しているように見えるが、真相はそうではない。(458頁)
■しかるに、宇宙の本体が人格的なものだとすれば、愛は実在の本体を把握する力であり、事物についての最も深い知識であることになろう。この意味で、「愛は知の極点」である。そして、西田はこの愛の観念を宗教に適用して、宗教の本質は神への愛にあり、「我は神を知らず我ただ神を愛す」というものが最も神をしるものであると論結している。(459頁)
2010年12月26日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――