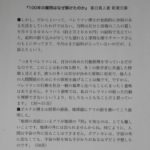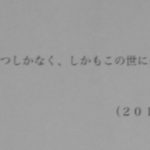『典座教訓・赴粥飯法』 道元 講談社学術文庫
典座教訓
■『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』に、「食事を作るには、必ず仏道を求めるその心を働かせて、季節にしたがって、春夏秋冬の折々の材料を用い、食事に変化を加え、修行僧達が気持よく食べられ、身も心も安楽になるように心がけなければならない」と言っている。昔から、あの潙山(いさん)霊祐禅師や洞山守初(とうざんしゅしょ)禅師も、この典座の職をつとめられたし、そのほかにも多くのすぐれた禅僧達が、この典座職を経験してきたのである。世間一般の料理人や給仕役などと同じように考えてはならない。
私が宋(南宋)の国に留学していたころ、ひまをみては、先輩や長いあいだ役職をつとめてきた人達に尋ねてにたところ、その人達は、自分達が実際に体験し見聞きしてきたことを、少しずつ私のために説き示してくれた。このときの説明は、昔から仏道を求める深い心を持った代々の仏や祖師達が、後の世の人々にのこしてくれた、根本的な教えであった。この典座(てんぞ)の職務のあらましについては、『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』をよくよく読みなさい。そうした上で、先輩達の詳しい説明を聞かなくてはいけない。(22~23頁)
■◯斎(さい)ー梵語ウポーシャダ(身・口(く)・意の行為をつつしむこと、布薩(ふさつ)とも訳される)の訳語で、特定の日に戒律を守り功徳を積む意。在家信者が六斎日(月の8・14・15・23・29・30日)に八斎戒(殺さない、盗まない、性交しない、嘘を言わない、酒を飲まない、身を飾り歌舞を見物したりしない、高床(こうしょう)の気持ちよいベットに寝ない、正午以降は何も食べない)を守り身をつつしむこと。六斎日や故人の忌日(きじつ)などに僧を招待して食事を布施し供養する意味にも用いられる。また仏弟子の食事は、正午以前にⅠ回たべるのが正式であったことから、昼食の意に用い、禅宗寺院では、朝の粥(小食(しょうじき))に対し昼の正式な食事(中食(ちゅうじき))を意味する。日本で「とき」と訓ずるのはこのためである。(27頁)
■雪峰義存(せっぽうぎそん)和尚が洞山价(とうざんりょうかい)禅師の修行道場において、典座職をつかさどることになった。ある日、雪峰が米をといでいるときに、洞山禅師がやってきてたずねた、「砂をといで米を取り除くのか、それとも、米をといで砂を取り除くのか」と。すると雪峰は答えた、「すなも米も同時に取り除きます」と。洞山禅師がまた尋ねた、「それでは修行僧達はなにを食べるのか」と。これを聞いて雪峰は、米の入っているお盆をひっくりかえしてしまった。洞山禅師はその様子を見て言った、「お前は後日、きっと別の指導者に会ってその指導を受けることになるだろう」と。昔から、仏道の修行に志すすぐれた人達が、直接自らこの上もなく心をこめて、典座の職を実践したことは、この通りである。後のこれから修行しようとする人が、これを怠りなまけることがあってどうしてよいものか。先人達も言っている、「典座がたすきをかけて自からその職責を果たすことこそ、仏道修行する者の心構えである」と。
もし米をといでいて、砂と誤って米を捨てるようなことがあったなら、典座が自ら点検する。『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』に、「食事を作る時、典座自ら手を下してよくよく点検しなさい。そうすればおのずと調ったよい食事ができあがる」と言っている。米をといだ白水であっても、気にもとめないで捨てるようなことがあってはならない。昔から、白水をこす袋を備えておいてこれに白水を入れ、たとえ一粒の米でも無駄にしなかったのである。おかゆの米と水の分量をほどよくはかり、鍋に入れ終わったなら、これを護ることに留意して、ねずみなどが汚したり、乱したり、あるいは無用の者にのぞかせたり、さわったりさせてはならない。(34~35頁)
■○今古(こんこ)は殊劣(しゅれつ)にして、天地は懸隔(けんきゃく)す、豈(あ)に肩を斉(ひと)しくすることを得る者ならんや。ー今古と天地、殊劣と懸隔は対語で、2句は対句を構成している。仏教の見方に、釈尊の時代を下るほど機根が劣り、正法・像法としだいに、教法のみあって修行したり証悟したりする者がなくなる時期がくるとする、末法思想という下降的歴史観があり、浄土教の普及などによって広く受容された。特に日本では、社会不安の世相も反映して深刻に受けとめられ、永承7年(1052)末法元年に入ったと信じられた。また、釈尊の生まれたインドから離れた地ほど法の潤いがうすくなるとも考えられた。親鸞や日蓮を初めとする鎌倉時代の祖師達にとって、末法思想は超克されなければならない共通の時代的課題であり、浄土教や『法華経』の宣揚がこれに答える方法であった。道元の「今古云々」の文言にはこうした一般論が踏まえられているが、ただし『正法眼蔵』「弁道話」では、「とふていはく、この行(坐禅)は、いま末代悪世にも、修行せば証をうべしや。しめしていはく、教家に名相(みょうそう)をことゝせるに、なほ大乗実教(じつきょう)には、正(しょう)像末法をわくことなし。修すればみな得道すといふ。云々」といい、こうした歴史観を否定しており、『典座教訓』の次の文においてもこの主張は一貫している。(53頁)
■○一微塵ー仏教で展開する原子論では、これ以上は分割できない最小の単位を極微(ごくみ)といい、この極微を中心に上下・四方の、合計7個の極微が集まった物を一微塵という。きわめて小さなもののたとえ(『倶舍論』巻1)。ここでは、一見、仏道修行とは何の関係もないように見える典座の仕事の場所をいう。(48頁)
■○物に転ぜらるるも、能(よ)く其の物を転ずる手段なりーここで物とは、自己の心の対象となる外界の事物。「物に転ぜらるる」とは、自己を見失い外界の事物に動かされて行動すること。これに対し、「物を転ずる」とは、主体性を確立し他の影響を受けることなく、積極的に外界の事物にはたらきかけていくこと。六祖慧能が、『法華経』を学びその文義に滞っている弟子の法達を指導するために示した偈(げ)に、「心迷わば法華に転ぜられ、心悟らば法華を転ず。云々」(『景徳伝灯録』巻5)とあり、道元もこの話を『正法眼蔵』「法華転法華(てんぼっけ)」で取り上げ、さらに展開敷衍(ふえん)している。(54~55頁)
■○神通(じんずう)及び変化(へんげ)ー修行によって得られる勝れた智慧、人間の能力を超えた超自然的な力で、神足通(じんそくつう)(どこのでも自由に往来できる)・天眼通(未来を見通すことができる)・天耳(に)通(間を隔てて普通の人には聞けない音を聞くことができる)・宿命(みょう)通(人の過去世を知ることができる)・他心通(他の人が何を考えているか知ることができる)・漏尽(ろじん)通(煩悩を除くことができる)を6通という。変化は自在に姿を変える神通力。ただし禅宗では、水を運び柴を運ぶような普通の日常的行為がきわめて自然におこなわれることこそ神通とされる。(55~56頁)
■山僧(さんぞう)(岡野注;道元)、天童に在りし時、本府(ほんぶ)の用典座(ゆうてんぞ)、職に充てらる。予、斎罷(おわ)るに因(よ)り、東廊を過ぎて超然斎(ちょうねんさい)に赴(おもむ)けるの路次(ろし)、典座は仏殿の前に在りて苔(たい)を晒(さら)す。手に竹杖(ちくじょう)を携え、頭には片笠(へんりゅう)も無し。天日(てんじつ)は熱く、地甎(ちせん)も熱さも、汗流(かんりゅう)して徘徊し、力を励まして苔を晒し、稍々(やや)苦辛するをみる。背骨(はいこつ)は弓の如く、竜眉は鶴に似たり。山僧。近前(ちか)づきて、便(すなわ)ち典座の法寿を問う。座(ぞ)云う、「六十八歳なり」と。山僧云う、「如何んぞ行者(あんじゃ)・人工(にんく)を使わざる」と。座(ぞ)云う、「他(かれ)は是れ吾(わ)れにあらず」と。山僧(さんぞう)云う、「老人(にん)家(け)、如法なり。天日(てんじつ)且(か)つ恁(かく)のごとく熱(あつ)し、如何んぞ恁地(かくのごとく)にする」と。座(ぞ)云う、「更に何れの時をか待たん」と。山僧、便(すなわ)ち休す。廊を歩むの脚下、潜(ひそ)かに此の職の紀要たるを覚(さと)る。(69~70頁)
■○本府(ほんぶ)の用典座(ゆうてんぞ)ー本府は地元の寧波府(ニンポーフ)出身の意で、用は「□用」という名であるが、諱(いみな)の上字は不明。諱の下字だけで呼ぶのは禅院の礼儀で、相手に対する尊敬の意を表わす。用典座は、道元に禅の修行道場における生活の意義について眼を開かせてくれた恩人の一人。(71~72頁)
■又、嘉定(かてい)16年癸未(みずのとひつじ)5月の中(ちゅう)、慶元の舶裏(はくり)に在りて、倭使(わし)の頭(かしら)と説話する次(おり)、有る一老僧来(きた)る。年は60許(ばか)りの載(とし)なり。一直(いちじき)に便(すなわ)ち舶裏(はくり)に到り、和客(わかく)に問い、倭椹(わじん)を討(もと)め買う。山僧、他(かれ)を請(まね)きて茶を喫(きっ)せしめ、他(かれ)の所在を問えば、便(すなわ)ち阿育王山の典座なり。他(かれ)云う、「吾れは是れ西蜀(せいしょく)の人なり。郷を離れて40年を得、今、年是れ61歳なり。向来(これまで)、粗(ほぼ)諸方の叢林を歴(へ)たり。先年、権孤雲(ごんこうん)の住裏(じゅうり)に、育王を討(たず)ねて掛搭(かた)し、胡乱(こらん)に過ぐ。然(しか)るに去年、解夏(げげ)し了(おわ)りて、本寺の典座に充てらる。明日は5の日なれば、一たび供(きょう)せんとするも渾(すべ)て好喫なるもの無し。麺什を作らんと要(もと)むるも、未だ椹(じん)有らざる在り。仍(よ)りて特特として来たり、椹を討(もと)め買い、十方の雲衲(うんのう)に供養せんとするなり」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)に問う、「幾時にか彼(かしこ)を離る」と。座(ぞ)云う、「斎了(おわ)りてなり」と。山僧(さんぞう)、云う、「幾時にか寺裏(じり)に廻(かえ)り去る」と。座(ぞ)云う、「如今(いま)や、椹を買い了(おわ)れば、便(すなわ)ち行(ゆ)かん」と。山僧(さんぞう)、云う、「今日(こんにち)、期せずして相会(あいかい)し、且つ舶裏(はくり)に在りて説話す、豈(あ)に好結(けち)縁に非(あら)ざらんや。道元、典座禅師に供養せん」と。座(ぞ)云う、「可(よ)からず。明日の供養、吾れ若し管せずば、便(すなわ)ち不是になり了(おわ)らん」と。山僧(さんぞう)、云う、「寺裏(じり)何ぞ同時の者の、斎粥(さいしゅく)を理会する無からんや。典座一位在らざるも、什麽(なん)の欠闕(けつけつ)か有らん」と。座(ぞ)云う、「吾れは老年にして此の職を掌(つかさ)どる、及(すなわ)ち耄及(もうきゅう)の弁道なり。何を以(もっ)てか他(かれ)に譲るべけんや。又来たる時、未(いま)だ一夜の宿暇を請わず」と。山僧(さんぞう)、又典座に問う、「座尊年、何ぞ坐禅弁道し、古人の話頭を看せざる。煩わしく典座に充てられて、只管に作務し、甚(なん)の好事か有らん」と。座(ぞ)大笑して云う、「外国の好人、未だ弁道を了得せず、未だ文字を知得せざる有り」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)の恁地(かくのごとく)に語るを聞き、忽然として発慚(はつざん)驚心し、便(すなわ)ち他(かれ)に問う、「如何なるか是れ文字、如何なるか是れ弁道」と。座(ぞ)云う、「若し問処(もんじょ)を蹉過(しゃか)せざれば、豈に其の人に非(あら)ざらんや」と。。山僧(さんぞう)、当時、会(え)せず。座(ぞ)云う、「若し未だ了特さざれば、他事後日、育王山に到れ。一番、文字の道理を商量し去ること在らん」と。恁地(かくのごとく)に語り了(おわ)り、便(すなわ)ち座(ざ)を起(た)ちて云う。「日晏(く)れ了(おわ)れり、忙(いそ)ぎ去(ゆ)かん」と。便(すなわ)ち帰り去(ゆ)けり。(73~75頁)
■○古人の話頭――禅宗の祖師達の残されたすぐれた言行。これを記録したものを語録といい、その中の特に後代の修行者の指針・指標となるような先人の故事・逸話類は、古則・公案・話頭と呼ばれて学び研鑽され、それらを集めた『碧巌録』『無門関』『従容録』などの話頭集成本の編纂もなされた。宋代以降はこの話頭・公案の真意を究めることを修行の目的とする公案禅(一名、看話(かんな)禅)が隆盛となった。道元も留学の初めごろはこの語録・公案を学ぶことを修行と考えていたようであるが、後には公案禅を否定する「只管打坐」の禅風を確立する。話頭の頭は接尾語。(84頁)
■同年七月の間(かん)に、山僧(さんぞう)、天童に掛錫(かしゃく)す。時に彼(か)の典座来(きた)り得、相見(しょうけん)して云う、「解夏(げげ)し了(おわ)れば、典座を退きて郷(きょう)に帰り去らんとす。適々(たまたま)兄弟(ひんでい)、老子の箇裏(こり)に在りと説(い)うを聞く。如何んぞ来たり相見(しょうけん)せざらん」と。山僧(さんぞう)、喜踊(きよう)感激し、他(かれ)を接して説話するの次(おり)、前日の舶裏(はくり)に在りての、文字・弁道の因縁を説き来る。典座云う、「文字を学ぶ者は、文字の故を知らんと為すなり。弁道を務むる者は、弁道の故を肯(うけが)わんことを要(もと)むるなり」と。山僧(さんぞう)、他(かれ)に問う、「如何なるか是れ文字」と。座(ぞ)云う、「一二三四五」と。又問う、「如何なるか是れ弁道」と。座云う、「徧界(へんがい)曾(かつ)て蔵(かく)さず」と。其の余の説話は、多般有りと雖(いえど)も、今は録さざるなり。山僧(さんぞう)、聊(いささ)か文字を知り、弁道を了ずるは、乃(すなわ)ち彼の典座の大恩なり。向来の一段の事(じ)を、先師全公(ぜんこう)に説似(せつじ)するに、公、甚(はなは)だ随喜するのみなり。(85頁)
■○先師全公(ぜんこう)ー建仁寺明庵栄西の弟子である、仏樹房明全(1184-1225)のことで、比叡山を下って以後の道元の本師になった。道元を伴い宋に留学したが、留学中の宝慶(ほうきょう)元年に、天童山の了然寮でで病没した。先師は、亡き本師に対する敬称で、道元は明全の遺骨を日本に持ち帰り、『舎利相伝記』を撰述して記録に留めた。(88頁)
■山僧(さんぞう)、後に、雪竇(せっちょう)の頌(じゅ)もて僧に示せることあるを看るに、云う、
一字七字、三五字
(一字や七字や、三字や五字でものごとを言いあらわすが、)
万像(まんぞう)窮(きわ)め来たるに、拠(よりどころ)を為さず。
(そのあらゆるものごとも本質を窮めてみれば、すべてよりどころとなるものではない。)
世深(ふ)け月白くして、滄溟(そうめい)に下る、
(夜も更け月はいっそう皓々と輝き、その光は大海へと下り、あたり一面月一色のせかいとなるように、)
驪樹(りじゅ)を捜(さが)し得ば、多許(たこ)有り。
(探し求めていたあの竜の顎の下のすばらしい玉も、手にいれてみれば、そこらじゅう玉でないものは何もなくなる。)
と、前年に彼の典座の云いし所と、今日(こんにち)の雪竇(せっちょう)の示す所と、自ずから相い符合す。弥々(いよいよ)知りぬ、彼の典座は、是れ真(まこと)の道人(どうにん)なりしことを。然(しか)れば則ち、従来看し所の文字は、是れ一二三四五なり、今日看る所の文字も、亦六七八九十なり。後来(こうらい)の兄弟(ひんでい)、這頭(しゃとう)より那頭(なとう)を看了(みおわ)り、那頭(なとう)より這頭(しゃとう)を看了(みおわ)りて、恁(かく)のごとき工夫を作(な)さば、便(すなわ)ち文字上に一味の禅を了得し去らん。若し是(かく)の如くならざれば、諸方の五味の禅の毒を被(こうむ)り、僧食(じき)を排便するも、未だ好手を得る能わざるなり。(89頁)
■まことにこの典座のあり方は、先人達のすぐれた言い伝えの中や、実際に私が中国で体験した中にあって、それが今も眼に見えるようであり、耳にも残っている。それを文字に記録して伝えることもあり、これをそのまま実行することもあって、これこそまさに、釈尊から正しく伝わった仏道の真髄そのものである。
もし仮りに、粥飯頭(しゅくはんとう)と呼ばれる住持職の地位について、1つの寺を統括する立場に立ったとしても、その心構えも典座と同じでなければならない。『禅苑(えん)清規』に言っている、「朝の粥と昼のご飯を支度し調えるには、十分に心を行き届かせ、豊かな内容を持ったものでなければならないし、修行僧達が生活に必要な飲食(おんじき)・衣服(えふく)・臥具・医薬の四事の供養も、事欠くようなことをさせてはならない。釈尊が100歳の寿命を20年縮めて後世に残してくれた恵みは、今の私達をおおい守ってくれており、釈尊の眉間にある白毫(びゃくごう)の光のほんの少しの恩惠も、私達には用い尽くせない」。そういうことで、「ひたすら修行僧にお仕えすることだけを考え、貧乏などを心配することはない」「物惜しみをするような小さな有限の心がなかったならば、自ずから無限の福徳がそなわってくる」とも言っている。思うに、このような配慮こそ、典座はもとより、住持職たる者が、修行僧達に対して供養し仕えるための心構えである。(94~95頁)
■修行僧に供養するための食事を支度し調える際の心構えは、材料が上等であるとか、粗末であるとかを問題にすることなく、仕事に対しては深い真心をもって当たり、食品材料に対しては、物を大切にし敬い重んずる心を起こすことが肝要である。
次のような話を知っているでしょう、ある老婆は、わずか1杯の米のとぎ汁でも、この心でお釈迦さまの供養したため、生前中にはこの上もない福楽の功徳を受け、また阿育王(アショーカ王)は、臨終のときに仏教教団に何か布施したいと願い、たった半分のマンゴーの実でもこれを差し上げようという、最後の善根の行為により、いずれも未来成仏の約束を与えられ、大きな果報を受けたということです。仏のためにする供養であっても、いつわりが多いということは、真実がないということにも及ばない。人の行ないとはこういうものである。(98頁)
■○十号―釈尊のこと。菩提を成就した釈迦牟尼仏(仏陀・覚者)には、その備わった徳相から、如来(真理の体現者)・応供(おうぐ、人間や神々から尊敬され供養を受ける資格のある者)・正遍知(しょうへんち、正しく真理を悟った人)・明行足(智慧と身体・言語行為とが完全に具わった人)・善逝(ぜんせい、悟りの境地に善く行ける者)・世間解(せけんげ、世間・出世間のことを熟知している者)・無上士(この上もない人)・調御丈夫(ちょうぎょじょうぶ、人をよく指導できる人)・天人師(てんにんし、天の神々と地上の人々の師たりうる人)・仏世尊(悟りを開き世間から尊ばれる人)という10種の称号・異名が付けられており、これを如来十号・仏十号という。ここでは仏陀・釈尊の全身心の意として用いられている。(100頁)
■◯育王の最後の大善根―釈尊と阿育王に関する故事で、マガダ国の阿育王は、釈尊の教えに基づく理想国家を築いたが、晩年には権力を失い不遇の境涯にあった。死期を悟った王は、鶏園寺(けいえんじ)の僧団に金銀を布施しようとしたが太子や大臣に反対され、自分が使用していた金・銀・鉄の食器を送り寄付し、そして最後に残った食用の半分のマンゴーの実も使いに持たせ僧衆に供養してしまった。鶏園寺(けいえんじ)の僧衆は、この半分のマンゴーの実を砕いて汁の中に入れ皆で食べ、王の布施の心を成就させた。この功徳により阿育王は、未来に成仏するという予言を与えられたという(『阿育王経』巻5、半菴摩勒施僧(はんあんもらせそう)因縁第6)(100頁)
■よく言われているように、醍醐味という御馳走を作るときも、それを決して特別上等だとはせず、菜っぱ汁を料理するときも、必ずしも粗末なものと見なしてはならない。菜っぱを手にして調理するときも、まごころ・誠実な心・清らかな心で、醍醐味を作るときと同じようにしなさい。そのわけはなぜであろうか。清らかな大海にたとえられる仏法の修行道場にいる修行僧達の中に、供養の食物が入ってしまうと、上等な醍醐味と粗末な菜っぱ汁という区別は立たず、百千の川も大海に流れ込めば、清濁の区別もなくなってしまうように、ただ1つの味だけになってしまう。ましてや、悟りを求める心をはぐくみ、仏の智慧を宿すこの肉体を養うことにおいては、上等なものであろうと粗末なものであろうと、全く同じであり、どうして別々のものがあろうか。「出家者の口はあたかもかまどのようなもので、上等なものも粗末なものも区別せず、与えられたものを好き嫌いなく、一味に食べてしまう」という経典の言葉があるが、とくと心得ておく必要がある。粗末な食べ物も、仏身であるこの肉体を十分に養い、悟りを目指す心もよく育ててくれるということを、よくよく思い返しなさい。粗末な食べ物も、いやしんだり、軽んじたりしてはいけない。人間界や天上界を導く師僧たる者は、この粗末な莆菜(ふさい)によって食事の尊さを教え、教化の効果をはかりなさい。(102~103頁)
■『禅苑清規(ぜんねんしんぎ)』には、「僧というものは、凡人とか聖人とかの区別に関係がなく、すべてのものごとに通ずることができる」と言っている。もし、「すべての是非の観念、得失・老少・凡聖(ぼんしょう)という区別を立てない」という意気込みがあったなら、この典座の職がどうして「そのまま悟りの世界に入りこむ」という修行でないことがあろうか。もしこれまで述べてきたところを、一歩でも踏み誤るようなことがあったなら、すぐにその場で真実とは行き違いになってしまうだろう。古からの典座職をつかさどってきた祖師方の真面目というものは、全くこのような気持で天座の仕事をしてきた点にある。後の時代において典座の職をつかさどる諸君たちも、同様にこのような心構えで典座の仕事をすれば、それでなんとかよろしいのである。百丈懐海禅師が修行道場の規則を定め、典座の職も規定したことは、どうして空しいことがあろうか。(106頁)
■◯「一切の是非、管する莫(な)し」「直(ただ)ちに無上菩提に趣く」―北宋代の居士で、『天聖広灯録』の編者としても知られる、都尉駙馬李遵勗(といふばりじゅんぎょく、?―1038)の投機の偈(げ)の中の句で、臨済宗の谷隠蘊聡(よくいんうんそう)に参じて大悟し、「学道は須(すべか)らく鉄漢(てっかん)なるべし、手を心頭に著(つ)てて便(すなわ)ち伴ぜよ。直ちに無上菩提に趣き、一切の是非を管すること莫(な)れ」という漢詩に託して自分の悟境を述べた。(『五灯会元(ごとうえげん)』巻12)。鉄漢はものに動じない大丈夫の人、不動の意志を持った修行僧。無上菩提は、梵語アヌッタラサムヤックサンボーデッヒの訳で、無上正等学(意訳)・阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい、音訳)などと訳し、この上もない最高のさとり、平等円満な仏の智慧。(107頁)
■○百丈高祖―馬祖道一の弟子、百丈懐海(749―814)のことで、江西省洪州にある百丈山大智寿聖寺の住職となり修行僧を指導したが、『百丈清規』を撰述して初めて禅宗の修行道場の規則を集大成し、それまで律寺に寄宿していた禅宗が独自の規則を有する宗派としての立場を確立したとされることから、叢林開闢の祖とされる。ただし百丈が制定した当初の古い清規(しんぎ)は失われ、『禅門規式』(景徳伝灯録』巻6)や『百丈規縄頌(きじょうじゅ)』(『禅苑清規』巻10)などが断片的に残されているにすぎない。(108頁)
■私は、中国の留学から帰国してより、2、3年間、建仁寺に留(とど)まり住んでいたことがある。この建仁寺では、深い仔細もなく典座の職を置いていたが、それはただ典座という名前があるだけで、典座という人間の実際の仕事は全くなかった。修行僧に食事を供養する仕事が、とりもなおさず仏作仏行としての実践そのものであることを知らないので、どうしてその上に仏道をわきまえることなどができよう。真実の師匠にめぐりあえず、空しく月日を過ごし、無為に仏道修行を台なしにしていることは、まったくあわれむべきである。
この建仁寺で体験した実情を述べると、昼飯と朝粥の支度については全く典座としての役目を果たしておらず、食事を作る仕事がいかに大事であるかも知らず、また考えようともしない下働きを自分の近くに置いて、大小のことをすべてこの下働きに言いつけ、その人のやったことが正しくても、正しくなくても、典座が自分で行なって監督するようなことは、かってなかった。それはあたかも、隣の家に婦人が住んでいて、そこに出掛けて行くことは僧として恥であるかのように、もし出て行って下働きの監督をするようなことがあるなら彼はそのことをまるで自分の恥であり、自分の人格に傷でもつくかのように思っている。そして寺の中に典座寮という一部屋をかまえて、寝転んだり、他人と談笑したり、お経を読んだり唱えたりして、どんなに月日が経っても、台所に出て行って仕事をするようなことはしない。いわんや、寺で使う品物を自分で買い求めたり、食事の献立や数量等について明らかにし決定したりすることは決してない。どうして典座の仕事を実際にするようなことがあろうか。ましていわんや、朝・昼の食事に際して、典座が自ら、用意した食事を庫院(くいん)の前の台の上にのせ、僧堂に望んで九拝して送り出すというような、心のこもった儀式などをすることは、夢にも知らない。典座が自ら若い修行僧達を教え導くときがきても、教えるべきことを何も知らないのである。(110~111頁)
■このように、仏道を修行しようとする心のない人が、すぐれた師僧にけっしてめぐり会うことができないということは、なげかわしいことであり、うれうべきことである。それはまるで、宝の山に入ったとしても、何も手に入れないで帰ったり、宝の海に潜(もぐ)ったとしても、何も身に得ることなく帰ってくるようなものである。典座というものは、仏道修行を目指す真実の心は起していなくても、もし悟りを開いた師匠に出会い教えを受けることができたならば、典座の役を立派に果たすことができるし、また、たとえすぐれた師匠に会うことができなくても、もし深く心に仏道を求める志を起こしていたならば、必ずや典座のつとめを仏道として成し遂げることができるということを、よく知っておくべきである。建仁寺の典座の場合は、これら2つの心が欠けているのであるから、彼が典座の職に就いたとしても、どうしてほんの少しでも自分の修行に役立つようなものがあろうか。(114頁)
■一方、私が見てきた中国の南宋時代のあちこちの寺々について言うなら、知事や頭首(ちょうしゅ)といった禅寺の役職についている人々は、1年間の任期でそれぞれのつとめにはげんでいるのだが、各自が三通りの住持と同じ心構えを踏まえて、それぞれ役職の任に当たってこれに従事し、たとえば典座の職なら修行僧を供養するというように、それぞれの職に就いたことを好い機会のめぐりあわせとして喜び、きそって仕事にはげんでいる。三通りの心構えとは、次の通りである。
1、他人のためにつとめ、そして自分自身の修行も十分に積めば、
2、修行道場をいっそう盛んにし、人間形成の場という高尚な風格も全く面目をあらたにでき、
3、古えのすぐれた人達に肩を並べ、さらに追いこし、古人の歩んだ道を継承し、その行ないの跡をしっかり保持していく。
こういうわけであるから、自分のことを他人事のようになおざりにしているおろか者がおる一方、他人のことを自分のように分け隔てせずに接するすぐれた人もいるということを、はっきり見きわめなさい。古人も言っている、「人生の3分の2は早くも過ぎてしまったが、ほんの少しの心もみがこうとしない。ただただ生をむさぼって1日Ⅰ日とあくせく日を暮らしているだけで、いくら喚びかけ反省させようとしても、一向に振り返りもしないのは、一体どうしたらよいものか」と。真実の指導者に会うことができなかったなら、俗世間的な心にひきずられてしまうということを知るべきである。金持ちの愚かな跡とり息子が、その家伝来の財物を運び出し、むなしく他人の眼前にゴミや糞尿のように捨ててしまうとは(典座という大事な職についていながら、それをむなしく見のがして無駄に時を過してしまうようなもので)、なんとなげかわしいことか。今やそうであってはならない。(117~118頁)
■◯霊台―心性・心のこと。中国禅宗5祖弘忍が後継者を決めるために、弟子達に対して悟境を提出させたところ、神秀は「身は是れ菩提樹、心は明鏡台の如し。時々に勤めて払拭(ほっしき)し、塵埃(じんあい)有らしむことなかれ」という偈(漢詩)で答え、これに対して慧能は「菩提本より樹無し、明鏡も亦台に非ず。本来無一物(いちもつ)、何れの処にか塵埃有らん」という偈を作って、これが認められ6祖となったという。神秀の偈は、万物を如実に写し出す鏡を心と見なし、これを磨き保持することを示したもので、ここで台は鏡そのもの。慧能はこれを揶揄的に批判し、後に禅の本流となった。(119頁)
■ここにいう大心(だいしん)とは、その心を大山(たいざん)のようにどっしりとさせ、大海のように広々とさせて、一方に片寄ったり固執(こしゅう)したりすることのない心である。たとえ1リョウ(金偏に兩)(約37,3g)ほどの軽いものでも、軽々しく扱わず、また逆に1鈞(いっきん、1リョウの480倍)もある重いものに対しても、特別に大げさに重々しく取り扱ったりしない。うららかな春の陽気に誘われても、それに心引かれてフラフラと春の野山にうかれ出るようなことなく、落ち葉散り布(し)く秋の景色を見ても、ことさらに物淋しい心を起さない。いうならば、春夏秋冬の四季の移り変わりも、これを自然のあるべき姿として、大きな眼で1つの景色の中に一緒にとらえ、また、軽い重いということについても、これに心迷わされることなく、差別をつけずに見るのである。このように、何物にも迷わされたり、心引かれたりしないという眼のつけ所において、大の字を書き、大の字を知り、大の字を学び、よくよく大の字を知り尽くすのである。夾山善会(かつさんぜんね)禅師の修行道場で典座をつとめていたある和尚が、もしこの大に字をよく学んでいなかったなら、思わず吹きだした一笑によって、太原孚上座(たいげんふじょうざ)を悟りにいたらしめることはできなかったであろう。潙山(いさん)霊祐禅師も、大の字をよく書いて知っていなかったら、百丈禅師のもとで修行していた折、一本の柴を取ってこれを3度吹き、百丈禅師に渡してその禅機を認められるというすばらしいはたらきはできなかったであろう。さらに、洞山守初(とうざんしゅしょ)禅師が大の字を知り尽くしていなかったら、「仏とはどういうものですか」という僧の質問に対し、「麻三斤」という見事な答えはできなかったであろう。(134~135頁)
■◯夾山(かっさん)の典座―太原孚上座(たいげんふじょうざ)を悟りに導いた僧。夾山は中国湖南省澧(れい)州石門県の東南にある霊泉禅院のことで、この典座の名前などはすべて不明であるが、太原孚上座が揚州光孝寺で『涅槃経』を講義していたところ、たまたまこの典座が雪のために行脚を阻まれて寄宿していた。孚上座が仏の法身(ほっしん、真実心)について談ずるや、典座は思わず失笑した。孚上座がこれに気づいてその訳をたずねると、「上座あなたは法身についてなにも分かってはいない」という。「それではどこが間違っているのか」と問うと、夾山(かっさん)の典座は、「上座あなたは法身の周囲だけを説いていて、肝心の法身そのものを自分に体現していない」という。そこで孚上座は虚心坦懐に典座の教えを受けて、ついに悟りを開いたという(『五灯会元』巻5、雪峯義存章)(137頁)
■○大潙(だいい)禅師……―百丈懐海とその弟子である潙山霊祐の問答で潙山が百丈の道場で修行していたころ、ある日、二人は山に入って仕事をしていた。そのとき、百丈が潙山に火を持ってこいと命じたところ、潙山は即座にハイッ持ってきましたという。百丈がどこにあるかと尋ねると、潙山は1本の枯れ枝を手に取って、フーフーフーと3度吹いて百丈に手渡した。これを見て百丈は、潙山が悟境に達したのを認めたという。(137頁)
赴粥飯法
■○法性(ほっしょう)―あらゆる存在がもっている真実にして不変なる本性。仏教の真理を指す語の1つで、真如・実相・涅槃などと異名同体である。(144頁)
■○真如―あらゆる存在がかくのごとくあること。その本体が真実にして常住なるところから真如という。(144頁)
■○法界(ほっかい)―意識の対象となるすべての存在。あらゆる現象界をいう。(144頁)
■◯理―宇宙をつらぬく根本的真理。あらゆる現象の背後にあって、そのようにあらしめている普遍的な絶対平等の真理。真如。(144頁)
■○事―一々の差別的な現象。因縁によって生じている森羅万象の相。理の対。(144頁)
■○正等覚(しょうとうがく)―仏の無常のさとりのこと。三藐三菩提(さんみゃくさんぼだい)の意訳語。(144~145頁)
■◯本末究竟等(ほんまつくきょうとう)―本末諸相の究極としての平等性。本は真如のうえからみた、あらゆるものが平等であるという立場、末は実相のうえからみた、あらゆものが異なって現われている姿、究竟は結局、とどのつまりの意。(145頁)
■○威儀(いいぎ)を具し―行・住・坐・臥(四威儀という)において、僧として正しい立居ふるまいをすること。道元の禅においては「威儀即仏法、作法是宗旨」といって、日常の正しい規律のある生活そのままが仏法であるとされる。(148頁)
■○安居(あんご)―一定期間、一寺にとどまって、ひたすら坐禅を中心とした修行にはげむこと。期間は4月15日から7月15日まで(夏安居)と、10月15日から翌年の1月15日まで(冬安居)の、それぞれ90日間がある。結制、結夏、江湖会(ごうこえ)などといい、この間、第1座として多くの修行僧を統率するのが首座である。安居の制は古くインドにおいて、雨期のあいだ外に遊行せず、一箇所に集まって坐禅修行したことに始まる。(153頁)
■○大乗菩薩僧―菩薩は菩提薩埵(ぼだいさった)の略で、上求菩提下化衆生(じょうぐぼだいげけしゅじょう)といって、無上菩薩(仏のさとり)を求めながら同時に人々を救おうと努力する修行者のこと。自己の解脱だけを目的とする声聞(仏の教えを聞いてさとる者の意)や縁覚(独覚ともいい、他の教えによらずに道をさとるが、説法教化(きょうげ)は行なわないとされる)の教えを小乗というのに対し、涅槃(さとり)に積極的な意義を認めて自利(自らを利する)と利他(他を利する)の両面をみたす菩薩の道を説く教えを大乗と呼ぶ。(176頁)
■○妙法蓮華経―略して『法華経』といい、また『大乗妙典』ともいう。『般若経』、『維摩経』、『華厳経』など大乗仏教を説く諸経典のなかでも、とくに代表的なものとして重んぜられた。全編を通じ、仏教の高い理想を揚げながら、それをむずかしい理論によらずに通俗的な因縁や譬喩(ひゆ)によって大衆にわからせようとしている点、また戯曲風な展開で興味深く読ませるようにしている点に、すぐれた特徴がある。(177~178頁)
■○文殊師利菩薩―文殊師利は略して文殊という。仏弟子のなかでとくに優れて、智慧第一といわれ、俗に「文殊の智慧」の言葉がある。普賢とともに釈迦如来像の脇士として知られ、仏の智・慧・証の徳を代表する。(178頁)
■○大乗普賢菩薩―この「大乗」のところは普通「大行(だいあん)」と唱えられている。普賢菩薩は、文殊菩薩とともに釈迦如来像の脇士として知られ、仏の理・定(じょう)・行の徳を代表する。文殊の智慧に対して普賢の行願といわれ、十種の大願をおこして仏の化導(けどう)をを助ける大乗の菩薩で、この普賢の行を大行と形容した。(178頁)
■○観世音菩薩―略して観音といわれ、大乗菩薩の中でも、智慧の文殊、願行の普賢とともに、慈悲の観音として最も名高い。『観音経』では33身に身を変えてあらゆる衆生を救済すると説かれる。観自在菩薩とも呼ばれる。(178頁)
■○摩訶般若波羅蜜―梵語の音写。偉大な完全なる智慧の意。迷いの此岸からさとりの彼岸に到るために修すべき6つの行(六波羅蜜。布施・持戒・忍辱(にんにく)・精進・禅定・智慧)のうち最も重要とされるもので、あらゆる事物や道理を見抜く深い智慧のこと。(178頁)
■○檀波羅蜜―波羅蜜は大乗の菩薩がさとりに到るために修める行のことで6つある(六波羅蜜)。すなわち、布施(完全なる施し)、持戒(戒律を完全に守ること)・忍辱(にんにく、完全なる忍耐)・精進(完全なる努力)・禅定(完全なる心の統一)・智慧(最高完全なる智慧)の6で、檀波羅蜜はこの最初の布施行のこと。(187頁)
■○貧等(とんとう)―貧(とん)と瞋(じん)と痴。貧は貧欲(とんよく)で、むさぼり執著すること、瞋(じん)は瞋恚(しんに)で、自分の心に違うものをいかり憎むこと、痴は愚痴で、ものの道理のわからぬ愚かさのこと。これらを、仏道修行の障害となることから、三毒という。心の迷いを防ぎ、身・口(く)の過(とが)を離れるには、一切の悪行の根本であるこの貧・瞋・痴をなくすのが最高の修行であるということ。ここにこの句があるのは、日ごろわれわれは美味しい物に対しては執着の心を起こし、まずい物に対しては嫌悪心を起こし、ほどほどの物に対してはもっと旨い物をと思うものであり、食事の場こそが貧・瞋・痴の三毒を離れる修行道場となりうるからである。(195頁)
■○成道(じょうどう)―仏道を成就する。さとりを得て仏になること。われわれの最大の目標である。(196頁)
■○威儀(いいぎ)―正しく法にかなった立居振る舞い。(233頁)
解説
■中国唐代における禅の興起は、インドで成立した仏教がもっとも中国的に変貌をとげる過程で行なわれた、きわめて土着性の強い思想運動そのものであった。
禅思想の大きな特徴は、天台宗や華厳宗、三論宗・浄土教などが、特定の経典や論書を拠り所とし成立したのと異なり、唐代中期に禅宗内で成立し広く宣伝された標語成句「不立文字、教外別伝、直指人心、見性成仏(文字に絶対的な権威を措定せず、経論の教えとは別に自分の言葉で思想を語り、現在の自分のままで、自己の真実を明らかにする)」の語が示すように、自己自身が現在この場で、直接ブッダの悟りを追体験する(頓悟)ことにあった。(235頁)
■ 瓦官(がかん)、徳山にありて侍者となる。1日山に入りて木を斫(き)る。徳山、1椀の水を将(も)って官に与う。接得(うけとり)てすなわち喫却(のみほ)す。徳山云く、「会(え)すや(分かったか)」。官云く、「会(え)せず(分かりません)」。徳山、また1椀の水を将(も)って官に与う。また接して喫却(のみほ)す。徳山いわく、「会(え)すや」。官云く、「会(え)せず」。徳山云く、「何ぞ会せざるものを成持(じょうじ)取(しゅ)せざる」。官云く、「会せざるに、またこの什麽(なに)をか成持す」。徳山云く、「子(なんじ)は太(はなは)だこの鉄橛(てっけつ、優れ者)に似たり」。(『雪峰語録』巻上)
木を伐採する仕事をしている瓦官和尚に、徳山は1椀の水を与えて労をねぎらいながら、この伐採という仕事が自己の問題として受け止められているかどうか探りをいれるのである。「成持」という語は、事を計る、しっかりと守り育てることを意味するが、ここでは「分からない」ということが自己自身の問題とされつづけているかが問われている。
この会話の妙味は、二人の禅僧の間に交わされる丁々発止の禅機溢れる問答にあり、徳山は瓦官の受け止め方を最終的に認めることになるが、問答の発端そのものは、禅僧の作務にかかわる事態に対する根源的な問いかけであった。
道元も、中国留学の早々からこの禅と作務に関する大きな課題を、阿育王山広利寺で修行僧の食事の世話をしている老典座から突きつけられ、この問題を最晩年に至るまで抱きつづけ、また「道元禅」と呼ばれる独自の思想体系のなかに昇華させた、その背景には、以上のような中国禅宗の成立過程における思想的営みの大きな蓄積があったのである。(241~242頁)
■梁の武帝が問う―「私は帝位に就いて以来、多くの寺を造り経典を書写し、僧に供養してきましたが、どんな功徳があるのでしょうか」
達磨が答える―「功徳などなにもない」(中略)
武帝―「仏教の根本義(聖諦(しょうたい)第一義)とはどんなことですか」
達磨―「カラリと晴れわたった大空のようで、真理とか聖とかいったものはなにもない(廓然無聖)」
武帝―「そういうあなたは誰ですか」
達磨―「そんなことわしは知らん」
武帝は達磨の心を汲み取ることができなかった。
かくして達磨は、そのまま揚子江をわたって魏の国の嵩山(すうざん、河南省)に入ってしまったというのである。後に宝誌和尚という者が武帝に、「あの方は観音菩薩の化身で、ブッダの真の精神を伝えるためにこの国に来たのですが、あなたが後悔して、再びこの国へ迎えようとしても、もう決して帰ってはきませんぞ」と告げたという。(245頁)
■禅宗が、思想としてもまた教団ととしてもその存在が明確に人びとに認識されるようになるのは、二祖慧可・三祖僧璨(そうさん)・四祖道信・五祖弘忍とへて、弘忍のもとに神秀と慧能の二人の弟子が出て以後で、神秀は都長安に進出し、権力者則天武后の帰依を受けて世の注目を集め、その系統の禅僧も都の長安や河南省の嵩山を中心に栄え、後世北宗禅と呼ばれ、日本へは最澄によって伝えられその存在が知らされていた。
一方、これに対し慧能は、南方の曹渓(そうけい、広東省)の山中で密かに修道し、その弟子の神会(じんね、684-758)の活躍によって都にもその存在が知られるようになった。この系統は南宗禅と称されたが、同じく慧能の弟子の南嶽懐譲(なんがくえじょう、677-744)や青原行思(せいげんぎょうし、?-740)の系統の禅僧達は、おもに揚子江付近の江西・湖南・湖北などの温暖な地を拠点として修道生活をつづけ、独自の生活規範や聖典を成立させていた。
すなわち、南嶽の弟子である馬祖道一(709-788)と、青原の弟子である石頭希遷(せきとうきせん、700-790)の二師は、その思想や門人指導のあり方が、当時の人からそれぞれ、馬祖は「雑貨舗(あらゆる人びとに対応し鋭く相手の急所を突き導く修行道場)」と評されたことが伝えられている。こうした特徴ある主張や禅風は、門人や法孫達によって中国全域はもとより、朝鮮新羅にも伝えられ、平安期の日本にも伝えられた形跡がある。
さらに唐代末期から五代・宋初期にかけて禅宗は、南嶽・馬祖の系統は潙仰(いぎょう)宗・臨済宗の2系統に、青原・石頭のの系統は曹洞(そうとう)宗・雲門宗・法眼(ほうげん)宗の3系統に分かれ、臨済宗の系統はさらに黄竜慧南(おうりゅうえなん、1002-69)の系統の黄竜派と、楊岐方会(ようぎほうえ、992-1049)の系統の楊岐派の2派となり、全部で5宗7派に分かれたが、これを総称して「五家七宗」と言う。
これら禅宗の諸宗派は、それぞれ特色ある弟子の指導の仕方や思想表現、さらに坐禅観を展開させたが、臨済宗の宗風は、先人の残された語録・言行や代表的な逸話(公案)について、坐禅をしながらその真意を観察究明し、究極的意味を深く理解することを目指すという「看話(かんな)禅」を特徴とし、これに対し曹洞宗の宗風は、黙々と坐禅して自己の心奥に撤することを目指す「黙照禅」が特徴とされ、宋代禅宗の二大潮流となった。
鎌倉時代以降、栄西や道元・円爾(えんに)をはじめとする諸師によって本格的にわが国に伝えられたのが、この宋代の臨済宗・曹洞宗であり、これによって中世日本禅宗の隆盛期を迎えることになった。近世江戸期になって、隠元隆琦(いんげんりゅうき、1592-1673)によって伝えられた黄檗(おうばく)宗も臨済宗の系統であり、頭皐心越(とうこうしんえつ、1639-96)によって伝えられた寿昌(じゅしょう)派は、道元の系統とは異なるが、やはり曹洞宗の系統に属する。(246~249頁)
(2014年3月15日)