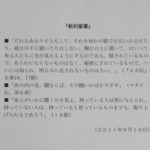『ペンローズの〈量子脳〉理論』ロジャー・ペンローズ著 竹内薫・茂木健一郎訳・解説 ちくま学芸文庫
■ 量子場の理論の守備範囲→素粒子論などのミクロの世界
一般相対性理論の守備範囲→宇宙論などのマクロの世界
さて、ここで問題になるのが、この2つの基礎理論の関係だ。最終的には、1つの基礎理論ですべてを説明したいから、この2つの理論が、うまく融合してくれれば好都合だ。そうすれば、われわれはいわゆる「万物の理論」(Theory of Everything 略してTOP)を手に入れることができる。量子場の理論と重力理論の融合なので、「量子重力理論」というわけだ。
ここで、ニュートン理論の立場を考えてみると、非常に奇妙なことが起こっていることが判明する。今述べたように、ニュートン理論は、一般相対性論の一部であるが、実は、量子場の一部でもある。だから、ニュートン理論は、二つの基礎理論の共通部分だということができる。イメージとしては、
二つの基礎理論のツインタワーがそびえ建っているが、二つのタワーの行き来
は、一階部分の細い渡り廊下でしかない。(43頁)
■量子論は確率の理論なので、個々の出来事が起こる確率が計算できる。ユニタリティーの大原則というのは、すべての出来事が起こる確率を足したら1になるということだ。確率の計算では、すべての可能な場合の確率を足して100パーセントになってくれないと困ってしまうから、このユニタリティーの大原則は基本的だ。ところが、ブラックホールは、あらゆる物質を吸い込むが、何も吐き出さない「黒い穴」であるから、ユニタリティーが破れてしまう。つまり、物質が中に入っていく確率と外に出ていく確率を足してはじめて100パーセントになるのに、入る一方で何も出てこないのだから、物質が外に出ていく確率の分だけ足りないのである。そこでホーキングは次のように考えた。
量子論のユニタリティーの原則からすると、ブラックホールからも少しは物質が
出てこないと困る。
つまり、量子論の原則からすれば、ブラックホールではなくて、グレーなのである。「グレーホール」でなくてはいけない、ということである。(47頁)
■量子力学には根本的に欠けているものがあるわけだから、それを完成するためには、現在の理論にはない何かが必要です。そこで、私は、「非計算的」な要素を付け加えるというのは、それほど悪い考えではないと思うんです。
もちろん、現時点では憶測にすぎません。ですが、そのような方向が正しいと信じる十分な理由があると思います。つまり、私の考えは、意識を説明するには量子力学が必要だということではないんです。意識を説明するには、量子力学を超える必要があるんです。(79頁)
■つまり、私たちの心が物理的世界からいかに生じるかというのが唯一のミステリーではないということです。実は、ミステリーは三つあります。つまり、物質的世界、心の世界、そしてプラトン的世界の3つの世界の間の関係が謎なのです。
このように言うと、カール・ポパーの考えに似ているように聞こえるかもしれません。でも、実際には少し違うのです。まず、ポパーの言う、「第三の世界」は、私の言う「第三の世界」、すなわちプラトン的世界とは違います。さらに、私はポパーのように3つの世界が線形につながっているのではなく、一つのサイクルをなしていると考えているのです。(84頁)
■しばしば、ゲーデルの定理は、人間の証明できない定理があることを意味すると考えられていますが、そうではないんです。ゲーデルの定理が証明していることは、私たちは常に新しいタイプの理屈を探し続けなければならず、ある一定の、固定したルールの集合に頼ることはできないということだけです。
「洞察力」さえあれば、すでに存在しているルールの外に出て、新しいルールを見いだすことは可能なのです。そして、このような「洞察力」を、実際私たち人間は持ち合わせています。ですから、私が言いたいことは、原理的に、人間の知性にとって到達できない真理などないということです。
随分回り道しましたが、あなたの質問に対する私の答えは、意識は、必ず物質的な基礎をもたなければならないということになります。(87頁)
■「物質主義者」とか、「イデア主義者」というような言葉が最初に考えられたとき、「物質」のイメージは、非常に具体的で、まさにそこに「ある」ものだというものでした。それに対立するものとして、人々はミステリアスな「心」というものを考えたわけです。
ところが、今では、物質そのものが、ある意味では精神的な存在であるとさえ言えるのです。(88頁)
■そのように考えていくと、そこに「ある」、堅固な存在という物質のイメージが、どこかに蒸発していってしまうのです。ですから、もう少し世界のことが深いレベルでわからないと、ほんとうのところはつかめないでしょう。「物質主義的」かどうかとか、そういう言葉で議論していると、世界観がどうしても制限されてしまうように思います。(89頁)
■原注1 ゲーデル型の議論(ゲーデルの定理とアルゴリズム)……アルゴリズムは、問題を解くための機械的な規則や手続きのこと。アルゴリズムは数学のあらゆるレベルに登場する。単純な例は、学校で教わる長除法(long division)と乗法。
どんな数学的証明も論理的なステップの連続の形をとり、機械によってチェックすることができる。1920年代にドイツの数学者ダーフィット・ヒルベルトは、数学的命題の真偽を解釈ぬきに決定するアルゴリズムが存在して、原理的には数学を形式化することが可能だと提案した。この数学の形式化によって、19世紀以来、数学の基礎をゆるがしてきた哲学的諸問題を一掃することができるとヒルベルトは考えていた。もしヒルベルトの予想が正しいとすると、たとえば、幾何学や算術に関する命題を適当に符号化して、判定機械に入れさえすれば、その真偽がわかるはずだ。
1931年にオーストリアの数学者クルト・ゲーデルがヒルベルトの夢が不可能なことを示した。ゲーデルの定理は、数学の真理を決定するアルゴリズムがどんなに精巧なものであっても、真理を決定できない命題が存在してしまって完全でない、という内容だ。ゲーデルは、そのような決定不可能な命題(ゲーデル文)を実際につくってみせた。
実際、特定の健全なアルゴリズムについてのゲーデル文は真だ(正しい)が、アルゴリズム自身は、その真偽を決定できないのである。ところが、人間の心は、その真偽がわかる。ペンローズ教授は、このことが、人間の心が単なる以上の能力を持っている証拠だと考える。(91頁)
■ペンローズの意識の物理学に関する二冊目の本『心の影』は、『皇帝の新しい心』と同様に、一つの寓話から始まる。洞窟を探検している少女ジェシカとその父親の物語だ。二人は、生まれたときから洞窟に閉じ込められていて、外の世界を見たことがない人に、外の世界の存在をどのように説得するかという問題を話し始める。洞窟の住人が見られるのは、外の世界の鳥や木の葉が洞窟の壁に投げかける「影」だけだ。「影」だけしか見えない人に、どのようにして「外の世界」の存在を確信させるのか?この説得はあんがい難しいと、ジェシカの父親は言う。というのも、洞窟の住人は洞窟の壁に投げかけられた「影」だけが世界のすべてだと思っている。洞窟の外に、さまざまな色や形に満ちた豊かな世界が広がっているなどとは、想像もつかない。自分に見えるものだけがすべてだと思う頑迷さが、洞窟の住人が真理に導かれるのを妨げている。
これは、もちろん、有名なプラトンの洞窟の比喩を踏まえている。
私たちが、洞窟の住人の愚かさを笑うのは簡単だ。だが、ペンローズの辛辣な批判は、実は心と脳の関係を解明するときに、人間の知性が、「意味」の理解に支えられていることを受け入れない人工知能の研究者たちにむけられている。そして、人間が「意味」を理解できるということは、人間の意識が、意味の棲む「プラトン的世界」の実在に接触できることを意味すると主張する。
本は二部に分かれている。
第一部では、ゲーデルの定理やチューリング機械を例に取り上げて、人間の知性には、計算不可能な要素があることを検証する。テーマになっていることは『皇帝の新しい心』に向けられたさまざまな批判に対して、細かく反論しているのが特徴である。特に21節にわたって、批判の一つ一つを細かく「つぶして」いくところは、ペンローズの知性の緻密さを表わしていて、圧巻だ。
第二部では、人間の知性の計算不可能な要素を理解するためには、新しい物理学が必要であると論じられる。量子力学の不完全生が指摘され、量子力学と重力理論が統合された量子重力において、われわれは初めて新しいより完全な理論を得るとする。そして、意識の作用は、量子重力的な効果、すなわち波動関数の自己収縮と関連していると主張する。ここまでは『皇帝の新しい心』でも論じられた点だが、ペンローズは、具体的に、ニューロンの中にあるマイクロチューブルが量子重力的効果による波動関数の自己収縮の起こる場所だと提案する。
全体として、『心の影』は、『皇帝の新しい心』に寄せられた批判に反論しながら、ペンローズの世界観に基ずく議論をさらに深く進めた本だと言うことができる。(117~119頁)
■健全(sound)と完全(complete)……大まかに言って、「健全」な理論は「証明や計算が間違った結果を出さない」。その反対に(ママ)、「完全」な理論は「正しい結果は必ず証明あるいは計算できる」。ペンローズがこの健全性を強調するのは、そもそも不健全な理論を論じてもはじまらないからである。(中略)健全は「証明できる」、完全は「真」に対応する。(122~123頁)
■アインシュタインの理論によれば、重力は、物理学において、非常にユニークな役割を担っている。その理由の中で最も重要なものは、次のとおりだ。
(1)重力は、時空間の中で起こるイベント間の因果関係に影響を与える唯一の物理現象である。
(2)重力は、何の局所的な実在性も持たない。なぜならば、適当な座標変換をほどこせば、局所的な重力は、いつでも消してしまうことができるからだ。重力は、むしろ、空間のグローバルな性質に関係している。そして、すべての粒子と力を含む、時空間自体の持つ曲率を決定している。
以上のような理由により、重力は、他の物理的効果から導き出される、2次的な現象とはみなされえない。重力は、物理的実在の最も根本的な因子であると考えなければならないのである。
アインシュタインによる一般相対論と、量子力学を統一すること、すなわち、量子重力をつくることは、未だに成功していない物理学の最重要課題の一つだ。そして、量子重力理論が完成した場合には、一般相対論と量子力学の両方が、根本的な変化を余儀なくされるだろうと考える強力な証拠がある。
そして、何よりも、量子重力理論は、物理的現実について、全く新しい理解をもたらすことになるだろう。じゅうりょくの大きさはきわめて小さい(たとえば、電気的力に比べると、40桁ほども小さい)。それにもかかわらず、重力は量子的状態がミクロなレベルからマクロなレベルに発展する上で深い影響力を持つと信じる理由がある。量子重力を生物学と結びつけること、少なくとも、神経系と結びつけることによって、「意識」という現象の、全く新しい理解がもたらされる可能性があるのである。(156~157頁)
■現代物理学の描像によれば、現実世界は、3次元の空間と1次元の時間が組み合わされた、4次元の時空の中に埋め込まれている。この時空は、アインシュタインの一般相対論に従って、少しだけ曲がっている。空間の曲がりは、質量密度の分布を重力場が反映することによって引き起こされる。質量分布があるかぎり、たとえどんなに小さくとも、時空の曲率に影響を与える。
以上が、古典的な物理学の下での標準的な描像だ。一方で、量子的なシステムが物理学者によって研究される際には、このような、質量の存在によって引き起こされる時空構造の小さな曲がりは、全くと言ってよいほど無視されてきた。その理由としては、重力の効果は、量子力学が対象としているような問題においてはほとんど微々たるものであるということが挙げられた。しかし、驚くことに、時空構造のこのような小さな違いが、実際には大きな効果を持つことがありうるのだ。というのも、時空の曲がりは、量子力学の法則自体に、デリケートだが根本的な影響を及ぼすからだ。
重ね合わされた量子的状況が、異なる質量分布を持つ場合、それぞれに対応する時空の幾何学も異なることになる。こうして、重ね合わせられた量子的状況が存在するときには、同時に、異なる時空構造の重ね合わせも存在する。量子重力理論が完成していない現状では、このような時空の重ね合わせを扱うための信頼できる方法は存在しない。(158~159頁)
■私たちのモデルでは、コヒーレントな量子的状態が、脳の中のマイクロチューブルの中で発生し、環境から隔離された状態に置かれる。そして、このような量子的状態が、重ね合わされたチューブリンの状態の間の質量―エネルギー分布の差が量子重力的なしきい値に達するまで維持されると考える。結果として生じる波動関数の自己収縮、すなわち「OR」が、時間的に不可逆なプロセスとして起こる。これが、意識における心理的な「今」を決定する現象なのである。このような「OR」が次々と起こることによって、時間の流れと意識の流れが作り出される。
私たちは、マイクロチューブルと結合したマイクロチューブル関連蛋白質(MAPs)が、量子的な振動を調節すると考える。その結果、「OR」の性質が決定される。以上の理由で、私たちは、マイクロチューブル関連蛋白質が結合したマイクロチューブルで起こる自己組織的な「OR」を、調節された客観的収縮、「Orch OR」(Orchestrated Objective Reduction)と呼ぶのである。「Orch OR」は、このようにして、基本的な時空の幾何学の中での自己選択的なプロセスであると考えられる。もし、経験が真の意味で基本的な時空の要素であるとするならば、「Orch OR」は、クオリアをはじめとする、意識をめぐる困難な問題と深く関係しているはずだ。(172~174頁)
■「Orch OR」と、その結果生ずる意識に至る変化の可能なシナリオとして、「細胞視覚」(cellular vision)がある。G・アルブレヒト=ビューラーは、1992年に、単一の細胞が、赤ないしは赤外の光を検出し、それに対して方向性のある反応をするということを報告した。この際、細胞骨格が関与しているらしいという。M・ジブらは、1995年に、このようなプロセスは、マイクロチューブルおよびその周囲の秩序だった水分子における量子的にコヒーレントな状態を必要とすると提案した。一方、S・ハーゲンは、同じ年に、量子的な効果や、細胞視覚を通して、量子的にコヒーレントな状態になることのできる配列したマイクロチューブルは、進化上有利な位置を占めてきたと示唆した。量子的にコヒーレントな状態がどのような理由で生じたかはわからない。だが、ある時、ある生物体が、「Orch OR」を起こせるだけのマイクロチューブルにおける量子的コヒーレントを実現し、「意識的」な経験を獲得したのであろう。(185頁)
■だが、その際に、強調されがちなのは、意識の問題が、従来の物質を記述してきた自然法則のアプローチでは、解けないであろうという一種の悲観論だ。特に、私たちの感覚の持つ、「赤」の「赤らしさ」、水の「冷たさ」といった質感、クオリア(qualia)は、自然法則の対象外であるという考えが根強い。意識は、宇宙の中で特別な存在だと考えてしまうわけである。
一方、ペンローズは、精神現象も、自然法則の一部であると考えている。たしかに、現在知られている自然法則では心の問題は理解できないかもしれないが、将来、クオリアや自意識といった心の属性も、電子の持つ電荷や質量と同じように、自然法則で理解できる日が来ると考えているのである。(201頁)
■ペンローズが、意識と量子力学の関係を論ずるときに、ペンローズの頭の中にあるのは、現在ある形での量子力学ではなく、「波動関数の収縮問題」などの欠陥を克服した、新しい量子力学なのである。ペンローズは、量子力学の革命が起こって初めて、意識の問題を理解することも可能になると考えている。ペンローズが、「意識も自然法則の一部である」と言うときには、そのようなイメージがあるのである。(202頁)
■ペンローズの意識の問題に関するアプローチは、物理的、ないしは数学的アプローチに基づいている。このようなやり方に対して、生物学の研究者、とりわけ実験的研究者から、「そんな抽象的な考え方で、生物が理解できるはずがないよ」という反論がよく聞かれる。先きに挙げたナンシー・カートライトの「なぜ物理学なのか?」という批判もそのような例だ。実際、ペンローズの説に対する反論は、しばしばその議論の細部に入った技術的なものであるというよりは、そもそも、物理的ないしは数学的アプローチの意識の問題における有効性に対する懐疑に基づいている場合が多い。
たしかに、生物は複雑なシステムであり、複雑な環境の中で、複雑なふるまいをする。だからといって、そのような複雑なふるまいを一つ一つ取り上げて、それについて常識的な知識をいくら積み上げても、それで意識の問題が解けるわけではない。生物学的常識論では、意識の問題は解けないのだ。(210~211頁)
■1960年代の後半から1970年代の初頭にかけて、人工知能の分野は、ブームと言ってよいほどの盛り上がりを見せていた。
約20年後、ペンローズのことを、
「人工知能が意識を持つのは当たり前だ、人工知能にできないことなどないのだ。だが、一部の馬鹿ものは、どうしてもそのことを理解しようとしない。あの、ペンローズとかいう輩は、自分が他の人よりも頭の良いことを鼻にかけて、人の仕事を中傷しているのだ……」(竹内薫、茂木健一郎共著『トンデモ科学の世界』参照)
とこき下ろすことになる人工知能の総大将、マーヴィン・ミンスキーは、まだまだ意気盛んで、「問題は、単に、いかにして1000万個の知識のカタログを作るかということだけだ」と豪語していた。(213頁)
■(a)「知性」(inteligence)は、「理解」(understanding)を前提とする。
(b)「理解」は、「覚醒」(awareness)を前提とする。
ここに「覚醒」は、「意識」(consciousness)の受動的な側面を表わしている……ということになるのである。ペンローズの議論は、非常にクリアカットだ。簡単に言ってしまえば、
*コンピューターには、計算可能なプロセスしか実行できない
*意識は、計算不可能なプロセスが実行できる
*したがって、意識は、コンピューター以上のことができる(244頁)
■「意識はアルゴリズムで、ただ、その複雑性が大きいだけではないか?」と言う。
このような意見に対して、ペンローズは、ある問題がそもそもアルゴリズムで解決できるかという、計算可能性の問題に比べれば、アルゴリズムが実際に存在したとして、問題解決にどれくらいのステップ数がかかるかという複雑性の問題は、本質的ではないとする。ペンローズにとっては、あくまでも、計算可能性が、意識とアルゴリズムを分ける分水嶺なわけである。(245頁)
■ところで、量子力学は、従来、しばしば人間が自由意志を持つかどうかという問題と関係すると言われてきた。そして、その際に重要なのは、量子力学が決定論的か、非決定論的かということだった。ここで、決定論的とは、現在の状態が決まれば、未来の状態が一つに決まってしまうことを言う。
――中略――
だがペンローズが意識との関係で注目している量子力学の性質は、それが決定論的か、非決定論的かということではない。ペンローズに関心があるのは、量子力学、特に波動関数の収縮の過程が計算可能なプロセスか、計算不可能なプロセスかということなのである。そして、ペンローズは、その直感に基づき、波動関数の収縮は、計算不可能なプロセスだと主張する。そして、意識の本質は、量子力学における波動関数の収縮過程が計算不可能であることと関連しているとするのである。さらに言えば、ペンローズは、環境から孤立した系の波動関数の収縮は「決定論的だが計算不可能」なプロセスだと考えている。この点は、ペンローズのすべての仮説の中でも、最もぶっとんでいる点だと言ってよい。ここには、ペンローズの数学的直感の、最も深い部分が顔をのぞかせているのだ。(252~253頁)
■もう一度、ペンローズが、意識に量子力学がかかわっているとするときに根拠とする論理構成を振り返ってみよう。
意識には計算不可能なプロセスがかかわっている。
↓
古典的法則には、計算不可能なプロセスは含まれていない。一方、量子力学の波
動関数の収縮の過程には、計算不可能なプロセスが含まれている可能性がある。
↓
他に計算不可能なプロセスがある可能性がないのだから、意識には、量子力学が
かかわっていなければならない。(257頁)
■量子力学では波動関数というのを考える。これは、複素数の値をとる。波動関数は、シュレディンガー方程式に従って時間発展する。この過程を「U」と書こう。一方波動関数から、いろいろな結果が生ずる確率を計算することができる。そのためには、波動関数の絶対値を計算する必要がある。イメージとしては、いろいろなことが起こる可能性がある状態から、一つの結果に波動関数が「縮んでいく」のである。この過程を、波動関数の収縮と言う。この過程を「R」と書こう。以下の議論で重要なのは、「U」の過程は過去と未来が対称であるが、「R」の過程は、過去と未来の区別がある。すなわち、時間反転について非対称であるということである。(274頁)
■何よりも重要なことは、最も基本的な自然法則である量子力学が、時間反転に対しては非対称だということだ。つまり、過去と未来に区別があるのである。この点についてはしばしば誤解されていて、波動関数の時間発展を記述する「U」の部分だけを捉えて、「量子力学は時間反転にに対して対称な理論である」と言われることもある。だが、量子力学は、あくまでも、「U」と「R」が一緒になって、はじめて完全な理論なのである。「U」だけを取り出してみても、何の役にも立たないのだ。それどころか、「U」と「R」という区別さえも人為的なもので、本来は一つのプロセスで書かれるものを、不完全に分離したものである可能性さえある。量子力学は、過去と未来が非対称な理論なのだ。これはとても重大なことで、決して忘れてはいけない!(275頁)
■アインシュタインの有名な言葉に、マックス・ボルンに宛てた手紙の一節がある。
たしかに、量子力学は印象的な成功を収めています。しかし、私の内面の声
が、これはまだ本物ではないと伝えているのです。この理論は、多くの成果をもたらしますが、まだまだ神様の意図するところの近くには来ていないと考えます。私には、どうしても神様がサイコロを振るとは思えないのです。
ここで、サオコロを振るといっているのは、波動関数の収縮過程のことである。現在の量子力学の標準的な解釈によれば、この過程は全くランダムである。つまり、「神様はサイコロを振っている」のであって、その結果をあらかじめ知ることはできないということになっている。これを、「コペンハーゲン解釈」と言う。(278頁)
■たしかに、現在の量子力学の体系の下で、ある瞬間の量子的システムの状態が与えられても、観測の結果は確率的にしか予測できないかもしれない。しかし、実際には、世界は、次の瞬間にはちゃんと一つの状態に収束するのである。ということは、どんなプロセスを通るにせよ、何らかの形で、世界は次の瞬間の状態を一つに決めているのである。そもそも、世界の時間発展が、「ランダム」に決まるというのは、何を言っているのだろうか?どうも、きちんと定義できないことをごまかして言っているにすぎないとしか思えない。アインシュタインの言うように、量子力学の観測の過程が、「神はサイコロを振って」、「ランダム」に決まるというのは、どうにも訳のわからない考え方なのである。(279頁)
■ペンローズもアインシュタインと同様、「コペンハーゲン解釈」に違和感を持つ人である。そして、ペンローズの提案する解決法は、大胆かつ過激だ。ペンローズは、孤立している系の波動関数の収縮過程は、「決定論的だが、計算不可能な過程」だとするのである。このような波動関数の収縮過程の解釈が、すでに見たように、意識に量子力学がかかわっているとするペンローズのアイデアの核になっている。(280頁)
■ところで、数学の基礎については、プラトン主義と、形式主義という二つの対立する思想がある。
プラトン主義の立場では、数学的真理は、最初から客観的実在として存在する。人間の知性は、単に最初から存在する真理を「発見」するだけだ。昔は絶対的な幾何学の真理だと考えられていた「ユークリッド幾何学」が今は絶対的な意味はないとしても、それはプラトン主義の立場を危うくすることはない。単に、ユークリッド幾何学しかないと思っていたときには、人類に見えるプラトン的世界の範囲が狭かっただけで、非ユークリッド幾何学が見えるようになった今、視野が広がったということだけなのである。一見神秘主義的に聞こえるプラトン主義の考え方だが、実際には多くの数学者が実感として持っている感覚だろう。ペンローズは、言うまでもなくプラトン主義者である。
一方、形式主義の立場では、絶対的な数学の真理をどうこうすることは意味がない。数学のすべてを、シンボルの操作という形式的なものにかんげんしようとするのが、ヒルベルトに始まる形式主義の目標なのである。形式主義の立場では、シンボルなどの「意味」を問うことはしない。したがって、変な話しだが、それが研究できる唯一の「価値」は、その形式的な体系の中に矛盾があるかどうかだけだということになる。ここに、矛盾があるとは、あり命題の肯定と否定が、両方とも証明されてしまうような事態を指す。もちろん矛盾があっては困るわけで、「ある形式的体系の中に矛盾がない」ことを示すのが形式主義にとって重要な目標になる。形式主義は、論理学や集合論、数論などの公理化とともに発展してきたが、幾何学などの分野にはそれほどのインパクトを及ぼしていない。ペンローズが『皇帝の新しい心』の中で攻撃した人工知能は、その精神において形式主義の子孫であると言うことができる。(288~289頁)
■つまり、一定の手続き(=「論理的整合性」や「実験による検証」などの条件)にさえ則っていれば、どんなに革命的な理論でも、科学は、それを自分のシステムの中に取り入れてしまう。
たとえば、量子力学と相対性理論の二大革命を経た現代の「科学」は、ニュートンの時代の「科学」とは全く内容が異なる。それでも、両者を同じ「科学」という名前で呼ぶのは、革命によって内容がどんなに変化してしまったとしても、どちらも、「化学的方法論」という、同じ手続きによってその存在が保証されているからだ。「科学」は、どのように激しい変化が起こったとしても、ある手続きさえ満たされていれば、変化の前後で同じものであり続ける。
このように、変化しても同じものであり続ける概念を、「メタ概念」(metaconcept)と呼ぼう。
科学は、変化にもかかわらず自己同一性(identity)を保つ、「メタ概念」なのである。科学は、「メタ概念」だからこそ、今日に見られるような高度の進化をとげたのだ。(298~299頁)
■私は、「プラトン的世界」は、今後の科学が間違いなく取り入れていく方向性の一つだと思う。
科学は、「プラトン的世界」を取り入れることによって、新しい展開を見せうるはずなのである。それが、意識の問題にあくまでも科学的に取り組もうとしている人(その中にはもとろんペンローズも含まれる)の「現場感覚だ」。(300~301頁)
■ゲーデルの定理の本当の意味(スティーン流の)を聞いて、私は狂喜乱舞したものだ。なぜなら、そのような心配は無用であることが判明したからだ。ゲーデルの定理は、人間理性の限界ではなく、むしろ人間の理性が事前に用意された形式的規則のシステムにせいげんされないことをしめしていたからだ。ゲーデルがしめしたのは、(規則自体が信頼に足る場合)いかにして、その規則体系を超えることができるか、についてであった。
加えて、明らかに形式体系とチューリングの実効的計算可能性との間に親密な関係が存在した。私にはそれで十分だった。人間の思考力と理解力は、明らかに何か計算以上のものだ。にもかかわらず、私は科学的方法と科学的な実在論(realism)強い信者であり続けた。私は、どうやら、当時、現在の私の見解に近い和解点を見いだしていたにちがいない。その詳細はわからなかったが、少なくとも、その精神においては。(349~350頁)
■私の数学的プラトン主義に(訳者――数学的プラトン主義は。数学の対象をあたかも実在するかのごとく扱う。もちろん、プラトン主義には、より哲学的な側面もあり、ペンローズはあくまでも「数学的」プラトン主義である)ついて一言。実際に、前記6節で提出した「間違い」に関する私の主張のある点は、ある人にとって不適切な「プラトン主義」とうつったことだろう。なぜなら、観念化した数学的議論をまるで特定の数学者の思考と無関係な実在として扱っているから。しかしながら、抽象的な概念を他のどんな方法で論じることができようか。数学的証明は抽象的な観念――一人のひとからもう一人へと伝達することができ、特定の個人に固有のものではない観念――である。
私が主張するのは、ある個人がたまたま都合が良いと考える特定の具象的実体と無関係に、数学的な「観念」を実在(もちろん、物質的な実在ではないが)として話すことに意味がある、ということだけだ。このことは、「プラトン主義的」哲学への傾倒を意味するものではない。(384~385頁)
■したがって、古典的なレベルと量子的レベルを結びつける新しい物理理論も計算不可能な理論になるだろうと私は主張する。もちろん、私はここでは不利な立場にある。なぜならこの理論は未だ発見されていないからだ!しかし総体的な話の核心は変わらない。
(訳注17:古典的なふるまい……「古典的」という言葉は、「量子的」という言葉の反対語。すなわち、量子力学の発見以前の物理学(ニュートン!)が古典物理学なのである。古典物理学と量子物理学との大きな違いは、理論が決定論的かどうかである。量子論は、確率的な予言しかできないが、ミクロの世界を扱うことができる。古典論は、決定的な予言ができるが、マクロの世界しか扱うことができない。そこで、問題は、ミクロとマクロの境界がどうなるか、ということになる。)(396頁)
■私はマイクロチューブルが実際に、現在のところ行なっていると信じられている仕事、そしてその他もっと多くのことを行なっていることを疑ってはいない。しかしそれは、私がそれらに要求する付加的な目的の役に立って「も」いることへの反証にはならない。
自然が同一の構造を多くの違った目的のために用いているたくさんの実例をわれわれは知っている。たとえば、われわれは哺乳類の鼻が(嗅覚への重要性は言うまでもなく)空気中の物質を肺に届く前に濾過することを知っている。しかし、これは象が地面から物体を拾うために彼らの鼻を繊細に使い「も」することへの反論とはならないのだ!(425頁)
■私はいかなる意識も個々の細胞に存在していると主張しているのではないことをはっきりさせておかなければならない。しかし私が唱えてきた見解に従えば、〈実際の意識に必要とされる〉構成要素のいくつかはすでに細胞レベルに存在しているにちがいまいことになる。個々の細胞は著しく精巧な方法で作用することができ、それらの作用を完全に伝統的な(古典的な)筋道にそって説明して納得するのは、非常に困難であることがわかった。(433~434頁)
■意識には、能動的な側面、すなわち、さきの13節で考察した「自由意志」の問題がある。また、きづいていること(awareness)と「クオリア」の議論のやかましい問題に関係する、受動的な側面もある。理解力はその二つの間のどこかに位置する。私の意見では、「物理的体系がどのように理解力を示すことができるのか」という難問にすこしでも光をあてるものは何でも、必然的に「自由意志」と「クオリア」の難問に光をあてるはずだ。さらに言えば、「理解力」の問題は意識のより具体的な側面の一つであろうと私には思われる。「自由意志」あるいは「気づいていること」の質についてそれが化学的に有益な方法でどのように議論すれば十分なのか私にはわからないが、「理解力」はわれわれが取り扱うことのできる何かである。(437頁)
■そういえば、最近、やたら「科学インタープリター」ということばが目につく。このことばは、私(岡野注;竹内)の記憶では、本書の出たころには、まだつかわれていなかった。当時は、新聞社や科学雑誌以外のところにサイエンス・ライターなる生きものは存在しなかったし、ましてや、「難解な科学を一般向けに翻訳する」という意味の科学インタープリターもほとんどいなかった。(454頁)
■複雑になりすぎた科学の世界を一般の人々に正確かつ平易に伝えるためには、だから、「橋渡し役」を専門とするプロ集団が必要になってくる。
それが、科学インタープリターなのである。(455頁)
■私(岡野注;茂木)が子供の頃、科学者になろうと志した理由はいろいろあるが、科学をやっていればどんな変人でもチャーミングになれると思ったことも大きかった。
二人の科学者が、黒板の前で難解な数式を書きながら議論をしている。髪の毛はぼさぼさで、服装もだらしなく、手を振り回しながら何やら虚空を見つめている。周囲の人間にとっては、何のことやらさっぱり分からないが、二人にとってはこの世で一番重大な真理についての大切な議論である。ふと気付くと、何時間も経っていて、お昼を食べるのを忘れている。
金も社会的地位もいらないから、そんな科学者になりたいと、子供の頃ぼんやりと思っていたが、実際に大学院に入って研究を初めてみると、学会というのは案外常識人ばかりの場所だと失望した。しかし、ペンローズだけはいつも「変人科学者」への期待を裏切らない。何も本人がもの好きで変人になろうというのではない。自分にとって大切なこと集中しているうちに、知らず知らずのうちに普通の人とは違った方向に行ってしまうのである。(459~460頁)
2009年8月24日