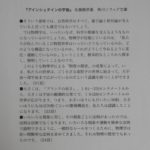『プロティノス「美について」』 斎藤忍随・左近司祥子訳 講談社学術文庫
■雑多なものと1つのもの。雑多なものは、変化きわまりないほとんど「夢」といったほうがいいようなこの世のものであるのに対して、1つのもの、それこそが本物なのだという考え方は、プラトンという、古めかしい、ひょっとすると、頭でっかちといってもいい男の嗜好の結果にすぎない、と思われる方もあるかもしれないが、実はそうではない。
普通、プラトンと対極にあると思われているデモクリトスというほぼ同時代の男がいる。私たちのなじみのアトム(科学の用語としてであれ、漫画の主人公としてであれ)という言葉を初めてあのような、「原子」という意味で使った哲学者である。彼の主張では、色は人が見るのと蜂が見るのとで違うし、下手をすれば隣にいるあなたでさえ、同じ対象を見てはいるが同じ感覚を持っているかは分らない、「ただ決まりによって、同じ言葉で名づけているだけである。そのとき、本当にあるのは、ただアトム(と空虚)だけである」、と彼は言っているのだ。確かにアトムは、数は無数といっていいほど大量である。決して単純化された1ではないと言えるかもしれない。しかし、アトムの内容は1つなのだ。アトムたちはまったく同一のものである。違いはただ形にしかない。(11~12頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■雑多なこの世を1つのもののもとに、無理だったら、限りなく1に近いもののもとに押し込めたいという試みは、だから、学問のはじめからあったのである。
1つのものから、すべてを説明する、1つのものからすべてのものを作りだす、これがギリシャ人が、はじめから、学問に寄せている期待だった。そして、当然、この場合こういった最初の(あるいは最後の)1つのものは、完全なものというレッテルがつけられることになる。ギリシャ人の学問は、この完全なものの探求ということになった。
プラトンが、イデアを、あるいはイデアの世界を、この世界やこの世界のものよりはるかに完全なものとして、提案したのは、だからギリシャの学問の伝統の上に立ってのことだった。だが、プラトンの潔癖さはそこにとどまらなかった。この世界を個々のものの住処としたのにあわせようと、イデアの在り処を「かなたの世界」と呼んだのである。(13~14頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■世界というようにまとめて言えるということは、イデアが多数あるということである。世界とはそれらを束ねるところということだからである。確かに、プラトンの対話篇を見てもイデアとして多数のものが挙がっている。正義とか勇気とか節制、敬虔、思慮という、いわゆる哲学者好みの徳はむろん、類似、主人―召使、大―小などという関係の概念、4角形、対角線などの幾何学の概念、そして、人間、牛など生き物のイデア、寝椅子、机などの工芸品のイデアなど、決して少なくない量である。そうだとすれば、プラトンとしては落ち着かなかったはずである。イデアは多になってしまうからである。解決はただ1つ、それらを統括するたった1つのイデアを立てることである。そして、それが、『国家』に出てくる善のイデアだったのである。(11~12頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■とすれば、源である水とこの水、統括者と被統括者とは、たとえ、名が同じでも、ランクの異なるものなのだと考えなくてはならない。絶対的な統括者を神とするなら、ここの人間は被統括者である。そして人間は神はランクが異なり、移動不可能というのがギリシャ人の日常の考え方だった。だから、イデア界とこの世がランクの違うもの、移動不能なものというプラトンの主張は、ギリシャ人にはかなり説得的だったろう。(15頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■このソクラテスの美=善という考え方は、先述のように、古代ギリシャ人の考え方だと言われ続けてきた。近現代風に考えれば、善は倫理学、美は美学あるいは芸術学担当ということになり、明らかに、範疇が異なるものとなるだろう。また、善については、主観的な問題だと思う人も多いとはいえ、それでもなお、客観的であることを信じている人もいるのだが、美となれば、圧倒的に、ほとんどの人が、主観的な問題だということになる。古代ギリシャ人にとっては、あるいはソクラテスにとっては、本当に両者は同じものだったのだろうか。同じだという主張が出されたにもかかわらず、その後の話は違うほうに進んでいくようにみえる。
そもそも、ここで展開される、ソクラテスのエロス讃歌は、彼が昔、異国の女性、ディオティマから教えてもらった話だという前提のもと、語られる話である。彼女は、エロスの奥義に入る前に、ソクラテスを相手に対話をする。そこにちょっと注目してみたい。
ソクラテスは、美を欠いているから美を愛するというエロスは人間にどんな利益をもたらすのかを気にしだす。その問いに対して、彼女は、まず「美を愛するとき、人は何を求めているのか」と問い返す。ソクラテスは「美が自分のものとなることを」と答え、さらに「美を自分のものにすると何を得たことになるのか」と再質問されると、ここで詰まってしまうのだ。彼女は、「たとえば、美の代わりに善を置いて、善を愛するとき、人は何を求めているのかと訊いたら」と問いを変える。もちろんソクラテスは直ちに「自分のものとなることを」といい、「そのとき手に入るものは」との質問に、「今度は答えられます。幸せになるのです」という。そして、幸せになるというのは人間の究極の望みであることから考えて、この話はここで終わる旨を同意しあうのである。(27~28頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■だが、本物を見たいと思う人は、地図を見ることによって自分の行動を決めていくのだ。
人の憧れの最高形態として哲学を捉えていたプラトンを、プロティノスは地図を作りつつも無視していなかったのだ。善が動かしがたくかなたのものでも、そして魂の位置は下方でも、その事実が変えられないとしても、憧れにみちている私の魂は、一者と何らかのかかわりが持てると確信していたのである。そうだとすれば、善を語るにも、善に行き着きたいと憧れる人と善の関係、それを無視して語るわけにはいかなくなる。このときの善は、鳥瞰図の中に描かれている、究極の完全無欠なもの、言い換えれば、、完全無欠とさえ言えないほどの完全無欠なもの、善とさえ呼べないものでありながら、すでに述べたように、私の欲求の対象であることによって、私にとっては善と呼べるものだったのである。(44~45頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■そう考えてよければ、第1の論文の第9章、90ページの、「善は自らの前に美を幕としている」と語られるのが、美の体系上の位置を考える手がかりとなるだろう。美は、第1位の一者を覆う位置にある。だが、一者から流れて出て来た第2位の知性のことも同時に覆っているなどとは書かれていない。そのことを考え合わせれば、美は、第2位の知性よりもはるかに一者の近くにいるはずである。一者、それに密着して美、そして知性……という鳥瞰図ができる。(47頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■なぜ幕の比喩が使われたのだろうか。幕というものは、隠すものであり、内を(この場合は善だが)人が見るのを妨げるものである。実は、この、もの暗さは、第3の論文の第3章で、美が比喩的に語られるときにも感じられるのだ。そこでは、美は、第1の神(善)の出現以前に姿を現す、先駆けである第2の神として語られるのだが、すばらしい第2の神を見て、満足して立ち去った人は第1の本当の神を見ることがないのだと言われもする。先駆けの神は、ある人間には、、幕と同じく、第1の神を見ることの妨げになるのだ。(48頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■確かに、美は、彼の作品の中で、ある種の暗い響きをもって語られている。確固たる成果の保証なしに、人を日常から本物の探求、要するに哲学に引きこんでしまう根源的力だからである。当然、できれば、障りを引き起こす可能性のある美について、完全否定で語ってくれたほうが気が楽だったのにと思う人々も入るだろう。それでも、プロティノが語りやめなかったということは、プロティノスは哲学者として、あるいは魂である人として、芸術家だけでなく、魂である人すべてに、外からの美に心動かすことのできる感受性をもってほしいと願っていたからではないかと考えるのである。(56頁)(プロティノス哲学の中の美・左近司祥子)
■すなわち魂が善くなり、美しくなるとは、「神に類似すること」であり、その理由は、美しいものも、それ以外の存在者たち(すなわち真の存在者たち)も神に由来をもつ点にあると。しかし、このように、美しいものとそれ以外の存在者たちというような言い方よりも、むしろ、美は真の真の存在者であると言うべきかもしれない。そして醜は真の存在者ならぬ別のものであり、この同じ醜こそ、根源的第1の悪なるものなのである。したがって神にとっては、前の一組のもの、つまり善なるものと美なるものあるいは善と美とは同じということになる。だから善と美、醜と悪は類似の方法で探求しなければならない。まず、美を根源的第1の美として始めにおき、それをばまた善でもあるとしなければならない。(80頁)(美について・第6章)
■そのようなかのものを見た時、それを眺め続け、それを味わい、それに同化するとすれば、他のいかなる美をその人はさらに求めるであろうか。というのも、ほかならぬそのものこそ最高度の美意識、根源的美であって、それを恋し、それを慕う者は、それによって美化され、恋い慕われるにふさわしい品位を得るからである。ここには実に、魂にとって根源的美をかけての最大の戦い、至高の戦いがある。魂は至善の眺めに与り、そこなうまいとして、根源的美のためにあらゆる労苦を傾ける。この至善の眺めをかち得た者は、その眺めに接して至福であり、至善の眺めをかち得ない者は、真実、不幸である。(83頁)(美について・第7章)
■だが、いかにすれば、善い魂の素晴らしい美しさがどんなものかを見ることができるようになるのだろう。汝自身に立ち帰り、汝自身を見よ、これがその方法である。たとえ未だ美しくない自分を、君が見たとしても、彫刻家のように振舞うべきである。彫刻家は美しい作品に仕上げなければならない大理石を前にして、あるいは削り、あるいは滑らかにし、あるいは磨き、あるいは拭い、ついに大理石の中に美しい顔を浮き出させるに至る。これが彫刻家のとる道だが、君もそのように、余分な不必要な部分はすべて取り除き、曲がった部分はすべて正すべきである。暗い部分はすべて浄めて、明るく輝くようにしなければならない。汝自身の像を刻む、この務めを中絶してはならない。このように努めていけば、遂には徳の神的光が君の前に輝き出るであろう。遂には「節制の美徳が聖なる台座に就く」光景に君も接することができるようになるだろう。(88頁)(美について・第9章)
■そして善は自らの前に美を幕としている。したがって、大まかな言い方をすれば、善が根源的美である。もし知性的なものを善と区別するとなると、純粋な「形」、つまりイデアの場を知性的美と見なし、美のかなたにあって、美の泉、美の源をなすものを、善と見なすべきであろう。あるいは善と根源的美とを同一視すべきである。ただしいずれの場合にも、美はここにではなく、かしこにある。(90頁)(美について・第9章)
■芸術によって美しい姿になるように作られたものが美しく見えるのは、石であるからではない。そうだったら、どんな石像も同じように美しかったろう。その像が美しいのは、芸術が植えつけた姿かたちのおかげなのである。そもそも、素材のほうはそういった姿かたちを持たないのである。姿かたちは、それが石に宿る以前でも、それを心で観ている作り手のうちにはあったのである。だが、作り手のうちにあるといっても彼が目と手を持っているからではない。彼が芸術に触れているからなのである。したがって、芸術のうちにある美は、作品のうちにある美より、はるかに優れたものである。なぜなら、かの、芸術のうちにある美がそのまま石に入ってくるわけではない。この美は一歩も動いたりしないものなのだ。石に到達するのは、芸術に由来はするが、それとは別の美である。この美は、当然、芸術の内にあるかの美より劣っている。しかも、石の内にあるこの美は、純粋なままあるわけではないし、芸術が望んだほどのものではない。石が芸術の技に服従したかぎりのものにすぎない。芸術が、自分の本当の姿に、あるいは、所持している姿に似せてものを作るとき――芸術は作品の形成原理(ロゴス)にしたがって美しい作品を作るはずである――、そのときの芸術は、外界のどんなものと比べても、はるかに卓越して美しい、芸術の美を持っているのであり、だから、芸術自身も、はるかに卓越して、真に美しいのである。(108~110頁)(知性の対象である美について・第1章)
■だが、もし誰かが芸術を馬鹿にして、自然を真似しているではないかと文句をつけるなら、まず言ってやらなくてはならないのは、自然もまた別のものを真似しているのだということである。次に、知らせるべきなのは、芸術は、感覚対象を単純に真似しているのではなく、自然が由来した、かの形成原理(ロゴス)を目指しているのだということである。(110頁)(知性の対象である美について・第1章)
■そうだとすれば、残るのは、この世界のすべてのものは他のもののうちにもとあるのだということである。両者の中間には何もなく、実有が他のもの(世界の材料)と隣接することによって、いわば突然、かの世界の痕跡を持った映像が出現するのである。その出現が、自分からなのか、魂の手助けによるのか、あるいはある種の魂の手助けによりのかは、今のところ、どうでもいいことである。ただ、この世のすべてのものはかしこからきたものであるが、それにもかかわらず、かしこのもののほうが、より美しい状態にあるのだ。なぜなら、こちらのものは(素材との)混ざりものであるが、かしこのものは混じりけのないものだからである。とはいえ、この世のすべてのものも、最初から最後まで形相の支配下にある。(131頁)(知性の対象である美について・第7章)
■あなたは(この世界のことについて)、大地はなぜ宇宙の中心なのか、なぜ円形なのか、黄道の傾きはなぜこのようなのかについて語ることはできる。しかし、かしこのものについては、かしこのものはこのようでなくてはならないので、このように計画されたのだとは言えず、ただ、かしこのものハ、現にあるようにあるので、そのためこの世のものどもも美しいのだといえるだけである。これは、たとえば、原因を推論する際、結論が前提から出てくるのではなくて、推論以前にすでにあるのと同じである。要するに、論理的必然や反省から出てくるのではなくて、論理的必然、反省以前にすでにあるものなのである。(131頁)(知性の対象である美について・第7章)
■確かに、始原の原因を探求してはならないという言葉は、正しい忠告である。特に、目的と同一であるような、完全な始原の場合には。初めでもあり、終りでもある、この始現は、実に、同時に宇宙全体なのであり、欠けるところのないものである。(134頁)(知性の対象である美について・第1章)
■かの知性界は、根源的に美しく、全体として美しいのだ。全体といっても、そのどこをとってもどこも全体なので、美を欠いた部分が残ってしまうこともないのだ。こういった世界を美しくないといえる人があるだろうか。確かに、それが、全体として美しいのではなく、部分的に美しいだけか、あるいは、美しい部分さえ持たないならば、別である。だが、かの世界が美しくないとすれば、他の何が美しいだろう。かの世界の前(=上位)にあるものは美であることなど望みはしないのだ。観照されるために現れる最初のものは、知性の観照対象でもある形相である。そしてそれが見るものの賞賛を浴びることになる。(135頁)(知性の対象である美について・第8章)
■実際、他のものを手本に作られたどんなものにしろ、それが驚嘆されるときには、その驚嘆は、かのイデアに向けられているのだ。この、賞賛されている作品の手本はイデアだったのだから。(136頁)(知性の対象である美について・第8章)
■「(世界の制作者が)賞賛した」という言葉が手本に向けて述べられたのだということを、プラトンは、以下の言葉を続けることで明らかにしようとした。彼は言った。「制作者は賞賛し、さらにそれをもっと手本に似るようにしたいと考えた」と。プラトンは、この生成世界のものが美しいのは手本のおかげで、この世のものはかのものの映像にすぎないと語ることによって、手本の美がどれほどのものかを示したのである。だから、かの世界が「途方もない、法外の美」を備えた、この上もなく美しいものでなかったりしたら、この可視的世界以上に美しいものなどなくなるのだ。だから、この世界に文句をつける人は間違っている。この世界がかの世界ではないという点で、文句をつけるのなら別であるが。(136~137頁)(知性の対象である美について・第8章)
■確かに、「存在」を奪われた美などどこにもないし、「美しくあること」を欠いた実有などどこにもない。美が欠如しているしているときには、実有も欠けているからである。だからこそ、美と同一である存在が欲求の対象になるのだ。そして美が心を惹くのは、存在と同じだからである。(141頁)(知性の対象である美について・第9章)
■ところで、見る力のある人が、見るときには、どの人も、その神ばかりでなく、神に関わるものも眺めるのである。もちろん、すべての人が、みな、いつも同じものを観るわけではない。ある人は、目を凝らして、正義の源泉とその本性が輝いているのを見るし、他の人は、節制の眺めを満喫する。かしこの節制は、人々がここで持つような姿はしていない。なぜなら、ここでの節制を何らかの仕方で真似しているにすぎないからである。これらの上にあって、かしこの、いわば全領域をあまねく覆う、美の本性は、これらすべてを鮮明に観たものたちだけが最後に見るものなのである。神々は一人ずつ、しかも「一度に全員」で、美を見る。また、かしこですべてを見、すべてを踏まえて生まれた魂も同じである。それだから魂は、自分自身で、初めから終りまで、すべてのことを自分のうちに持つことになる。魂の中でも、生まれつき、かしこにとどまることになる部分は、すべてかしこにいるし、また、魂が部分分けされていないときには、魂全体でかしこにいるのが常である。(143~144頁)(知性の対象である美について・第10章)
■しかし、全体を見ない人は外から来る印象だけしか認識しないが、
(143~144頁)(知性の対象である美について・第10章)(143~144頁)(知性の対象である美について・第10章)(143~144頁)(知性の対象である美について・第10章)(143~144頁)(知性の対象である美について・第10章)
■しかし、全体を見ない人は外から来る印象だけしか認識しないが、全体をあまねく見た人は、いってみれば、神酒で満たされ酔ってしまった人の場合のように、美が魂全体にいきわたり、ただの観照者ではすまなくなっている。なぜなら、観照の客体と主体は互いに異なるものとして外にあるのではなく、鋭いまなざしで見てとる人にとっては見る対象は自分のうちにあるからである。だが、多くの場合、自分のうちに持っていても、持っていることに気づかず、外にあるものと思って、眺めるのである。そのわけは、彼はそれを見る対象として眺めるし、眺めたいと思うからである。人が観る対象として眺めるものは、すべて、自分の外のものとして眺められているのである。だが、本当は、それを自分のうちに持ち込んで、自分と1つのものとして眺め、自分自身として眺めなくてはいけない。あたかも、神に乗り移られたもの、たとえばアポロン憑きとか、あるいは詩神の1人に憑かれたとか、そういう人が自分のうちに神を観る場合のように、である。もちろん、神を観る力が自分のうちにあればのことだが。(145~146頁)(知性の対象である美について・第10章)
■私たちのうちの誰かが、自分自身を見る力もないのに、かの神に乗り移られて、神を見ようと、見る対象として目の前に取り出すとき、彼の取り出しているのは自分自身であり、眺めているのは、美化された自分の映像である。だが、美しい映像を捨て去り、自分自身と1つになって、もはや分裂することがないなら、そのときその人は「1度にすべて」の1となり、音もなく傍に立つ、かの神のもとにいることになる。彼は、できるかぎりそして望むかぎり、神とともにいるのである。たとえ、向きを変えて、2となっても、純粋であり続けるかぎり、神の近くにいるのだ。だから、もう1度神のほうに向きを変えさえすれば、再び以前のように神のもとにいるはずである。この、向きを変えることには、次のような利益がある。まず第1に、人は、神と異なる自分自身を感覚する。次に、人は、自分の内部に駆け込むことで、すべてを獲得する。つまり、神と異なることを恐れて、感覚を後に投げ捨て、かしこの世界で1つとなるということである。それでも、神を異なるものとして見たいと思うなら、その場合には、自分自身を外に出せばいいのである。(147~148頁)(知性の対象である美について・第11章)
■どうして、人は、美のうちにいながら、美を見ないでいられるのだろうか。そうではないのだ。美を自分と異なるものとしてみるときには、美のうちにはいないのである。美と1つになってはじめて、完全に美のうちにいることになるのだ。(148頁)(知性の対象である美について・第11章)
■要するに、私たちが美しいのは、自分自身を認識しているからで、醜いのは、自分を知らないからなのである。
というわけで、美はかしこにあり、かしこから来る。(155~156頁)(知性の対象である美について・第13章)
■さらに言えば、知性は、自分が本当に把握したということをどういうふうにして知るのだろうか。また、それが善であるということ、正義であるということ、美であるということ、それを知性はどのようにして知るのだろうか。それらのそれぞれは知性と別のものであり、しかも知性のうちに確信できる判断根拠がないのである。それらは外にある。だから、真理もそちらにあるのだ。そうであるとすると、この知性の対象は、知覚を持たず、生命や知性を欠いているか、あるいは、知性を持つものかの、どちらかであろう。(166~167頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第1章)
■以上のことから、知性、全存在者、真理は1つのものであると私たちは結論づけるのだ。もしそうなら、それはある種の偉大な神である。ある種のというよりは、むしろ、すべてのとされるのがそういったものにはふさわしいだろう。このものは神であるが、かの神を観る前に姿を現す第2の神である。(174頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第3章)
■そこで、1へ、しかも本当の1へ上昇しなくてはならないのだ。この1は、それ以外のものが、多でありながら、1を分有することで一になっているというのとは違っている。本当の1を捉える場合、分有に拠らない1、1でありながら多でもあるということのない1、それを捉えなくてはならない。(176頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第4章)
■確かに、家は、連続体という観点から見ればⅠであるが、本質的にも、量的にも1とはいえない。では、5を束ねる1は、10を束ねる1と同じなのだろうか。そうではない。すべての船とすべての船、小さいものも大きいものも、それらが互いに同じものだとすれば、さらにポリスとポリス、軍隊と軍隊、それらが互いに同じだとすれば、その場合には、束ねる1は同一であろう。だが、同じでないなら、その場合にはそうはならない。(178~179頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第4章)
■したがって、一者は「存在を超えている」ということになる。だが、存在を超えたものとは何か一定のものではないからである。しかも、「存在を超えたもの」というのは、そのものの名前でもない。ただ、存在ではないものといっているにすぎない。もし名前をつけようとしても、それで一者はつかみきれない。彼の広大な本性をつかもうとするなど、お笑い種である。そういうことをしようと望む人は、自分で自分の邪魔をして、何らかの仕方でほんのわずかでも一者の足跡に到達しようとする試みさえ駄目にするのだから。そういうことはせず、知性的なものを見ようと望む人が、感覚対象のどんな表象も持たずに、感覚対象を超えて存在するものを見るのと同じように、知性対象を超えたものを観ようと望む人は、知性対象をすべて捨てたとき、それを観ることになるだろう。それがあるということは、知性対象を通して学ぶのだが、どのようであるかを知るためには知性対象を捨てなくてはいけないのだ。(184頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第6章)
■ひとつの意味では、目が見るのは感覚事物に備わる形相であるが、今ひとつの意味では、感覚事物の形相を目が見る際の助け手(光)のことである。助け手も、それ自身、感覚対象であるが、形相とは異なり、形相が見られることの原因である。これは、形相の内にあるとともに、形相を覆い、形相とともに見られるのだ。そこで、このときには、(光は)自分についての明確な感覚を与えないのである。なぜなら、目は光に照らされたものに向けられているからである。しかし、光以外の何もないとき、じっと目を凝らしてみれば、確かにそのとき光は見えてくるが、それは、あくまでも他のものに寄り添っている光である。光がそれだけになり、他のもののもとにない場合には、感覚は光を捉えることはできないのだ。実際、太陽の内にある光も、感覚で捉えることはできないだろう、もし、より硬い塊が光のもとにないとすれば。だがもし、太陽はすべて光なのだとの主張があれば、それを使って私の言おうとしていることの意味を明らかにすることができるだろう。要するに、太陽は光であるが、その光は、他の視角対象が持っているどんな形相の内にもなく、たぶん、ただ見られるだけのものなのだ。それ以外の見られる対象は、単なる光ではないのだから。(187~188頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第7章)
■もし、全体を見られないのであれば、あなたは思惟する知性でしかないだろう。たとえ、かのものにであったとしても、かのものは逃げ去るだろう、というよりあなたがかのものから逃げ去ることになろう。だから、見るときには、全体を眺めなくてはならないが、思惟するときには、かのものについて記憶していることなら何であれ、取り上げて思惟すべきである。(198頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第10章)
■したがって、究極の善、善そのものはすべての存在者を超えて、単独の善であり、自分のうちに何ものも持たず、どんなものとも混ざることなく、すべてのものを超え、すべてのものの原因であるということが私たちに明らかになったことになる。というのも、悪からは美も存在物も生じないし、また、善でも悪でもないものからも生じるはずはないからである。そのわけは、作るものは作られたものよりよいものだからである。作るものはより完全なのである。(210頁)(知性の対象は知性の外にはないこと、さらに善について・第13章)
■相手がどう思うかが大事なのではなく、本当にどうあるかが大事だと彼らは考えたのである。しかし、「無知の自覚」、「自分は何も知らない、そのまま知らないと思っている」という標語を持つソクラテスが、神でないたかが人間である自分が、「本当にどうあるか」を知ることが出来ると思っていたわけもなく、彼は最後の日にこのようなことを言っている。「実際私は、私の言っていることが真実であると周りの人々に思ってもらおうと努力しているのではなく、まあそういうことがあったっていいのだけれど、そうではなくて、そのようであると思わせようと努力しているのは、実にとりわけこの私自身に、なのだ」。(217~218頁)(解説・小島和男)
(2011年2月6日)