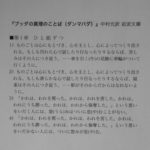『ブッダのことば(スッダニバータ)』中村 元訳 岩波文庫
■第1 蛇 の 章
1、蛇
13)走っても疾過ぎることなく、また遅れることもなく、「一切のものは虚妄である」と知って迷妄を離れた修行者は(注1)、この世とかの世とをともに捨て去る。――蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである。
注1;迷妄を離れた修行者は――貪りまたは愛欲、憎悪、迷妄という3つの煩悩は、人間にとって根本的なものであるから、古来の仏教の学問では「貧・瞋・癡の3毒」という。
2、ダ ニ ヤ
22)牛飼いダニヤがいった、
「わが牧婦(=妻)は従順であり、貪ることがない(注1)。久しくともに住んできたが、わが意(こころ)に適っている。かの女にいかなる悪のあるのをも聞いたことがない。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨をふらせよ。」
23)師は答えた、
「わが心は従順であり、解脱している。永いあいだ修養したので、よくととのえられている。わたしにはいかなる悪も存在しない。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨をふらせよ。」
25)師は答えた、
「わたしは何びとの傭い人でもない。。みずから得たものによって全世界を歩む。他人に雇われる必要はない(注2)。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨をふらせよ。」
23)師は答えた、
「未だ馴らされていない牛もいないし、乳を飲む仔牛もいない。孕んだ牝牛もいないし、交尾を欲する牝牛もいない。牝牛どもの主である牡牛もここにはいない。神よ、もしも雨を降らそうと望むなら、雨をふらせよ。」
33)悪魔パーピマンがいった、
「子のある者は子について喜び、また牛のある者は牛について喜ぶ。人間の執著(しゅうじゃく)するもとのものは喜びである。執著するもとのもののない人は、喜ぶことがない。」
34)師は答えた。
「子のある者は子について憂い、また牛のある者は牛について憂う。実に人間の憂いは執著(しゅうじゃく)するもとのものである。執著するもとのもののない人は、憂うることがない。」
注1;貪ることがない――食物、装飾品、男、財を貪ることがないのである。
この詩句は当時のインド人のあいだでの理想的な妻のすがた――夫に対して従順であるのみならず、婚化先の人々すべてに対しても従順でなければならぬ――を描いている。これに対して、対をなす文句で釈尊は自分の立場を宣言するのである。
注2)他人に雇われる必要はない ――多人に傭われることなく、精神的には全く独立して生きてゆくという強い確信をもっていた。そうしてそれが高らかな誇りを成立させるのである。
3、犀 の 角(注1)
38)子や妻に対する愛著(あいじゃく)は、たしかに枝の広く茂った竹が相(あい)絡むようなものである。筍(たけのこ)が他のものにまつわりつくことのないように、犀の角のようにただ独り歩め。
39)林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところの赴くように、聡明な人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
40)仲間の中におれば、休むにも、立つにも、行くにも、旅するにも、つねにひとに呼びかけられる。他人に従属しない独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
41)仲間の中におれば、遊戯と歓楽とがある。また子らに対する情愛は甚だ大である。愛しき者と別れることを厭いながらも、犀の角のようにただ独り歩め。
42)四方のどこでも赴き、害心あることなく、何でも得たもので満足し、諸々の苦難に堪えて、恐れることなく、犀の角のようにただ独り歩め。
47)われらは実に朋友を得る幸を讃(ほ)め称(たた)える。自分より勝(すぐ)れあるいは等しい朋友には、親しみ近づくべきである。このような朋友を得ることができなければ、罪過(とが)のない生活を楽しんで、犀の角のようにただ独り歩め。
50)実に欲望は色とりどりで甘美であり、心に楽しく、種々のかたちで、心を攪乱する。欲望の対象にはこの患(うれ)いのあることを見て、犀の角のようにただ独り歩め。
53)肩がしっかりと発育し蓮華のようにみごとな巨大な象は、その群を離れて、欲するがままに森の中を散歩する。そのように、犀の角のようにただ独り歩め。
55)相争う哲学的見解を超え、(さとりに到る)決定に達し、道を得ている人は、「われは智慧が生じた。もはや他の人に指導される要がない」と知って、犀の角のようにただ独り歩め。
57)義ならざるものを見て邪曲にとらわれている悪い朋友を避けよ。貪りに耽(ふけ)り怠っている人に、みずから親しむな。犀の角のようにただ独り歩め。
58)学識ゆたかで真理をわきまえ、高邁・明敏な友と交われ。いろいろと為になることがらを知り、疑惑を除き去って、犀の角のようにただ独り歩め。
70)妄執の消滅を求めて、怠らず、明敏であって、学ぶこと深く、こころをとどめ、理法をあきらかに知り、自制し、努力して、犀の角のようにただ独り歩め。
75)今のひとびとは自分の利益のために交わりを結び、また他人に奉仕する。今日、利益をめざさない友は、得がたい。自分の利益のみを知る人間は、きたならしい。犀の角のようにただ独り歩め。
注1;犀の角――仏教では、後世になると、3つの実践法(3乗)があるという。「声門(しょうもん)」(釈尊の教えを聞いて忠実に実践する人)。「独覚」(山にこもって一人でさとりを開く人)。「菩薩」(人々を救おうという誓願を起して実践する人)。
そのうちで、「独覚」には2種類ある。1、部行独覚(仲間を組んで修行する独覚。「部行」とは、仲間をつくって修行することである)。2、麟角喩(ゆ)独覚(常にひとりでいて伴侶のいない独覚。麟が1つの角のみをもっていることに譬えていう)。「麟角喩」とは「麟の角(1本しかない)に喩えられる」の意。この場合麟とは犀のことを言ったのだと考えられる。角が1本しかないからである。
さて、犀のことを、なぜ漢訳者は「麒麟」と訳したのか?想像が許されるならば、シナ人には犀はあまり知られておらず、むしろキリンのほうがなじみがおおかったからではなかろうか。
ところで、いま第35詩以下説かれているのは、『独りで覚る人」の実践である、とパーリ文の注釈は解する。
ここで「独りで覚った人」というのは、最初期の仏教の理想である。後代の仏教数学で考えた「独覚」とは必ずしも一致しない。
4、田 を 耕 す バ ー ラ ド ヴ ァ ー ジ ャ
76)「あなたは農夫であるとみずから称しておられますが、われらはあなたが耕作するのを見たことがない。おたずねします、――あなたが耕作するということを、われらが了解し得るように話してください。」
77)(師は答えた)、「わたしにとっては、信仰が種子(たね)である。苦行が雨である。智慧がわが軛(くびき)と鋤(すき)とである。慚(はじること)が鋤棒である。心が縛る縄である。気を落ちつけることがわが鋤先と突棒とである。
78)身をつつしみ、ことばをつつしみ、食物を節して過食しない。わたくしは真実をまもることを草刈りとしている。柔和がわたくしにとって〔牛の〕軛を離すことである。
79)努力がわが〈軛をかけた牛〉であり、安穏の境地に運んでくれる。退くことなく進み、そこに至ったならば、憂えることがない。
80)この耕作はこのようになされ、甘露の果実(みのり)をもたらす。この耕作を行なったならば、あらゆる苦悩から解き放たれる。」
5、チ ュ ン ダ
85)鍛冶工チェンダはいった、「目ざめた人々は誰を〈道による勝者(注1)〉と呼ばれるのですか?また〈道を習い覚える人〉はどうして無比なのですか?またおたずねしますが、〈道によって生きる〉ということを説いてください。また〈道を汚す者〉をわたくしに説き明かしてください。」
86)「疑いを超え、苦悩を離れ、安らぎ(ニルヴァーナ)を楽しみ、貪る執念をもたず、神々と世間とを導く人、――そのような人を〈道による勝者〉であると目ざめた人々は説く。
87)この世で最高のものであると知り、ここで法を説き判別する人、疑いを絶ち欲念に動かされない聖者を、修行者たちのうちで第2の〈道を説く者〉と呼ぶ。
88)みごとに説かれた〈理法にかなったことば〉である〈道〉に生き、みずから制し、落ち着いて気をつけていて、とがのないことばを奉じている人を、修行者たちのうちで第3の〈道によって生きる者〉と呼ぶ。
89)善く誓戒を守っているふりをして、ずうずうしくて、家門を汚し、傲慢で、いつわりをたくらみ、自制心なく、おしゃべりで、しかも、まじめそうにふるまう者、――かれは〈道を汚す者〉である。
90)(かれらの特徴を)聞いて、明らかに見抜いて知った在家の立派な信徒は、『かれら(4種の修行者)はすべてこのとおりである』と知って、かれらを洞察し、このように見ても、その信徒の信仰はなくならない(注2)。かれはどうして、汚れた者と汚れていない者と、清らかな者と清らかでない者とを同一視してよいであろうか。」
注1;道による勝者――道による勝者とはブッダサマーナのことである。これを逆に解すると、ブッダとは、世の中に多数いる修行者のうちの1種類にほかならないのである。
注2;信仰はなくならない――当時、「世の中には〈道の人〉(修行者)と称する人々が多数いるなあ」という感情をこめて、ゴータマ・ブッダが4種の修行者の区別を説いたのであるとすると、われわれはその情景を思い浮べることができる。有力な金属工は最新の技術を獲得し、また製品を売却するために種々の種類の人々と接触したであろうし、またかれが富裕であるならば多くの宗教者が近づいてきたにちがいない。だからこそブッダは真偽の見定めを説いて教えたのである。
ところでゴータマ・ブッダがどの生き方を最上と見なしたかは不明であるが、文脈から見ると〈道による勝者〉または〈道に生きる者〉を特に尊んでいたようである。かれは特殊な哲学説や形而上学説を唱導したのではない。人間としての真の道を自覚して生きることをめざし、生を終わるまで実践していたのである。
6、破 滅
92)(師は答えた)、「栄える人を識別することは易く、破滅を識別することも易い。理法を愛する人は栄え、理法を嫌う人は敗れる。」
94)「悪い人々を愛し、善い人々を愛することなく、悪人のならいを楽しむ。これは破滅への門である。」
96)「睡眠の癖あり、集会の癖あり、奮励することなく、怠りなまけ、怒りっぽいので名だたるひとがいる、――これは破滅への門である。」
98)「みずからは豊かで楽に暮しているのに、年老いて衰えた母や父を養わない人がいる、――これは破滅への門である。」
100)「バラモンまたは〈道の人〉(注1)または他の〈もの乞う人〉を、嘘をついてだますならば、これは破滅への門である。」
102)「おびただしい富あり、黄金あり、食物ある人が、ひとりおいしいものを食べるならば、これは破滅への門である。」
104)「血統を誇り、財産を誇り、また氏姓を誇っていて、しかも己(おの)が親戚を軽蔑する人がいる、――これは破滅への門である。」
106)(注2)「女に溺れ、酒にひたり、賭博に耽(ふけ)り、得(う)るにしたがって得(え)たものをその度ごとに失う人がいる、――これは破滅への門である。」
112)「酒肉に荒み、財を浪費する女(注3)、またはこのような男に、実権を托すならば、これは破滅への門である。」
114)「クシャトリヤ(王族)の家に生まれた人が、財力が少いのに(注4)欲望が大きくて、この世で王位を獲ようと欲するならば、これは破滅への門である。
115)世の中にはこのような破滅のあることを考察して、賢者・すぐれた人は真理を見て、幸せな世界を体得する(注5)。」
注1;バラモンまたは道の人――漢訳では「沙門」と訳す。
注2;俗な表現であるが、世間でよく「飲む、打つ、買う」が身を滅ぼすもとであると言うように、それと同じことが説かれている。人間というものは、何千年たっても変わらないものだということが解る。
注3;財を浪費する女――パーリ文注釈には「魚・肉・酒などに耽溺している女」の意に解している。「浪費する」とは「魚・肉・酒に耽溺するために財を塵芥のごとくに散じ尽して消費する」ということである。
注4;財力が少ないのに――これは権勢欲を戒めているのである。
注5;幸せな世界を体得する――幸せな世界を体得すると気づいた境地が〈幸せな世界〉である、というのであろう。(中略)「天」という別の場所に到達することを意味しているのではない。いま生きているこの場所に〈幸せな世界〉が存在するのである。
7、賤 し い 人(注1)
116)「怒りやすくて怨みをいだき、邪悪にして、見せかけであざむき、誤った見解を奉じ、たくらみのある人、――かれを賤しい人であると知れ。
118)村や町を破壊し、包囲し、制圧者として一般に知られる人、――かれを賤しい人であると知れ。
119)村にあっても、林にあっても、他人の所有物をば、与えられないのに盗み心をもって取る人、――かれを賤しい人であると知れ。(注2)
120)実際には負債があるのに、返済するように督促されると、『あなたからの負債はない』といって言い逃れる人、――かれを賤しい人であると知れ。
121)実に僅かの物が欲しくて路行く人を殺害して(注3)、僅かの物を奪い取る人、――かれを賤しい人であると知れ。
(岡野注:仏教は全元論である。世界存在は法〈プラトン的イデア界=真・善・美〉によって、今、今、今と現成公按している。偽・醜・悪は存在の法に反しているから、所詮、滅する)
122)証人として尋ねられたときに、自分のため、他人のため、また財のために、偽りを語る人(注4)、――かれを賤しい人であると知れ。
(岡野注;そもそも、「真・善・美」という法(ダルマ)が、この世界に存在しないと思って生きている人には、嘘をついたら恥ずかしいという良心を持ち合せていないので、平気で嘘をつく)
124)己は財豊かであるのに、年老いて衰えた母や父を養わない人、――かれを賤しい人であると知れ。
126)相手の利益となることを問われたのに不利益を教え、隠し事をして語る人、――かれを賤しい人であると知れ。
127)悪事を行っておきながら、『誰もわたしのしたことを知らないように』と望み、隠し事をする人(注5)、――かれを賤しい人であると知れ。
128)他人の家に行っては美食をもてなされながら、客として来た時には、返礼としてもてなさない人、――かれを賤しい人であると知れ。
131)この世で迷妄に覆われ、僅かの物が欲しくて、事実でないことを語る人、――かれを賤しい人であると知れ。
133)ひとを悩まし、欲深く、悪いことを欲し、ものあしみをし、あざむいて(徳がないのに敬われようと欲し)、恥じ入る心のない人、――かれを賤しい人であると知れ。
(岡野注;仏教は全元論である。一元論は他の一元論と争いが絶えないし、無神論者は自己の欲望の追求以外に生きる意味はない。だから仏教では、「かれを賤しい人であると知れ」と軽蔑するだけで、争わない。自分の賤しい行為は恥じ入るし、賤しい人とは、付き合わなければいいのだ)
135)実際は尊敬さるべき人ではないのに尊敬さるべき人(聖者)であると自称し、梵天を含む世界の盗賊(注7)である人、――かれこそ実に最下の賤しい人である。
142)生まれによって賤しい人となるのではない。生まれによってバラモンとなるのでもない。行為によって賤しい人ともなり、行為によってバラモンともなる。」
(岡野注;仏陀の有名な言葉。2000年以上前の時代に言った言葉が、正法である証拠で今だに、生き続けている。「生まれ」の単語を、別の言葉(例えば、性別、人種、才能、財産等々)に置き換えてみると、仏陀及び道元の仏教的世界観=全元論の正しさが、今、ここ日本に現成している)
注1;賤しい人――インドのどの階級にも属さない最も卑しい人々をいう。。
注2;仏教では国王と盗賊とは本質的に区別のないものであると考えていた(この点ではシナも墨子と共通である)。だから、第118詩で国王を非難し、つづけて第119詩で盗賊を非難しているのである。国王と盗賊とは、いつも並んで出てくる。
注3;盗む為に人を殺すなどというのはもってのほかである。インドでは旅人を襲って殺す山賊は、他国にくらべて比較的に少かった。山賊は現代に至るまで存在したが、人を殺す割合は低かった。しかし山賊がいたことは事実であるから、それがここに反映しているのである。現代インドでも若干の峠は盗賊の出る名所として知られている。古代インドにおいてはなおさらであったであろうから、それを戒めているのである。
注4;インドでは、日常生活のうちに法律の果たす役割は少かった。西アジアやヨーロッパに比べて法廷はさほど大きな意義をもっていなかった。そこで「偽証をなすなかれ」という教えの説かれることは少かった、その稀な事例の1つがここに見られる。
注5;嘘をつくのが何故いけないのかというと、他人の利益をそこなうからである。その急所をついているのである。ここでは良心の問題が出てきているわけであるが、インドでは「アートマンが見ている」ということを説く。たとい他人が見ていなくても、〈本来の自己〉が見ているというのである。
注6;人は何故嘘をつくのか?それは何ものかを貪ろうという執着があるからである。人間が嘘をつくのは、特に利益に迷わされた場合が多い。保守的仏教では10の完全な徳を説くが、そのうちの第7として真実を立てる。「たとい雷が頭上に落ちようとも、財宝などのために、利欲心などのために、知りつつも虚言をのべることをしてはならない。あたかも暁の明星が、あらゆる時節を通じて、自分の行くべき路を捨てて他の路を行くことがなく、必ず自分の路をとって進むように、汝もまた真実を捨てて虚言を述べることがないならば、ブッダとなることができるであろう」。事実を知らなかったために、偶然虚偽の申し立てとなったのは仕方がない。しかし意識して虚偽を述べてはならぬというのである。
注7;盗賊――尊敬されるに値しない人が尊敬を受けているのは、盗人だというのである。実に厳しい教えである。
8、慈 し み
142)究極の理想に通じた人が、この平安の境地に達してなすべきことは、次のとおりである。能力あり、直く、正しく、ことばやさしく、柔和で、思い上ることのない者であらねばならぬ。
144)足りることを知り(注1)、わずかの食物で暮し、雑務少く、生活もまた簡素であり、諸々の感官が静まり、聡明で、高ぶることなく、諸々の(ひとの)家で貪ることがない。
145)他の識者の非難を受けるような下劣な行いを、決してしてはならない。一切の生きとし生けるものは、幸福であれ、安穏であれ、安楽であれ。
146)いかなる生物(いきもの)生類であっても、怯えているものでも強剛なものでも、悉(ことごと)く、長いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、粗大なものでも、
147)目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。
148)何びとも他人を欺いてはならない。たといどこにあっても他人を軽んじてはならない。悩まそうとして怒りの想いをいだいて互いに他人に苦痛を与えることを望んではならない。
149)あたかも、母が己が独り子を命を賭けても護るように、そのように一切の生きとし生けるものどもに対しても、無量の(慈しみの)こころを起すべし。
150)また全世界に対して無量の慈しみの意(こころ)を起すべし。上に、下に、また横に、障害なく怨みなく敵意なき(慈しみを行うべし)。
151)立ちつつも、歩みつつも、坐しつつも、臥しつつも、眠らないでいる限りは、この(慈しみの)心づかいをしっかりとたもて。この世では、この状態を崇高な境地と呼ぶ。
注1;足ることを知り――僅かのもので満足することを足るを知る(「知足」)という。
これはまたストアの哲人の目ざす人生の理想でもあった。清沢満之が人生の師と仰いだエピクテートスは、「満足」という1章で次のように言う。
君は苦労もしないし、また満足もしていない。そしてもし君が独りぼっちならば、君は孤独だというし、またもし人々と一緒ならば、君は彼らを騙り屋だとか、泥棒だとかいう、また君自身の両親や、子供たちや、兄弟たちや、隣人たちをも非難するのである。だが君はただ独りいる時には、それを平和とか自由とか呼び、自分を神的なものに似ていると思うべきであったし、また多くの人々と一緒の時には、俗衆とか喧騒とか不愉快とか呼ばないで、お祭りとか集会とかいって、そしてそのようにしてすべてを満足して受けるべきであったのだ。そうするとそういうふうに受けとらぬ人々には、どういう罰があるか。彼らが持ってるようなそういう気持にあることがそれだ。或る人は独りでいることに不満だって。彼は孤独であるがいい。或る人は両親に不満だって。その人は悪い息子として、悲しんでいるがいい。或る人は子供に不満だって。その人は悪い父親でいるがいい。
「彼を牢獄に入れるがいい。」
どんな牢獄にか。彼が今いる処がそれだよ。というのは彼がいやいやながらいるからだ。人がいやいやながらいる処は、彼にとっては牢獄である。ちょうどソークラテースが、喜んでいたために牢獄にいなかったように。
「それでわたしの脚が跛になったのです。」
つまらんことをいうね君は、すると君は小っぽけな1本の脚のために、宇宙に対して不平なのか。それを全体のために、君は捧げないのだろうか。君は退かないだろうか。君はその授けてくれた者に、喜んで従わないのだろうか。君はゼウスによって配置されたもの、つまりゼウスが彼のところにいて、君の誕生を紡ぎ出した運命の女神と一緒に、定めたり、秩序づけたりしたものに対して不平で不満なのだろうか。君は全体に較べれば、どれほど小さい部分であるかを知らないのか。だがこれは肉体の点においてだ、というのは少なくとも理性の点では、神々に何ら劣りもしなければ、より小さくもないからである。なぜなら理性の大きさは、長さや高さによってではなく、その考えによって判定されるからだ。(エピクテートス『人生談義』上、岩波文庫、61~64頁)
哲人の帝王マルクス・アウレーリウスは、『自省録』のなかで次のような反省を述べている。
16 尊ぶべきは植物のように発散による呼吸を営むことでもなく、家畜や野獣等のように呼吸することでもなく、感覚を通して印象を受けることでもなく、衝動のまにまにあやつられることでもなく、群をなして集うことでもなく、食物を摂ることでもない。それは食物の残滓を排泄するのと同じたぐいのことだ。
では何を尊ぶべきか。拍手喝采されることか、否。また舌の拍手でもない。というのは、大衆から受ける賞讃は舌の拍手に過ぎないからだ。また君はつまらぬ名誉もおはらい箱にした。では何が尊ぶべきものとして残るか。私の考えでは、自己の(人格の)構成に従ってあるいは活動し、あるいは活動を控えることである。あらゆる職業や技術の目的となすところもそこにある。なぜならばあらゆる技術の目標は、すべて作られたものが、その作られた目的である仕事に適応することにある。葡萄の世話をする葡萄栽培者、子馬を仕込む者、犬を馴らす者、みなこれをめざしているのである。また子供の教育法や教授法もこれに向って努力する。これこそ尊ぶべきものなのである。このことをしっかりと身につけたならば、君は自分のために何もほかにかちえようとしないであろう。それとも君は自由の身にもならず、自足した人間にもならず、また激情にうごかされぬ者ともならないであろう。なぜならばその場合、君が羨んだりねたんだり、そういうほかのものを君から奪い取りうる人びとを疑ったり、君の大切に思うものを持っている人びとにたいして陰謀を企てたりするのは必定である。つまり、そういうもののいずれかを必要とする人間は、必然的に混乱の中にあらざるをえず、その上神々にたいしてもさまざまの非難を口にせずにいられないものである。ところが自分自身の精神を敬い尊ぶならば、それによって君は自己の意にかなう人間となり、人びとと和合し神々と調和する者、すなわちすべて神々の配し定めるところに喜んで服する者となるであろう。(岩波文庫、85~86頁)
考えて見れば、足るを知ること、すなはち自分の持ち分に満足して喜びを見出すということは、だれにでも可能な〈幸せへの道〉であると言えよう。
9、雪 山 に 住 む 者
171)「世間には5種の欲望の対象があり、意(の対象)が第6であると説き示されている。それらに対する貪欲(とんよく)を離れたならば、すなわち苦しみから解き放たれる。
173)「この世において誰が激流を渡るのでしょうか?この世において誰が大海を渡るのでしょうか?支えなくよるべのない深い海に入って、誰が沈まないのでしょうか?」
174)「常に戒(いましめ)を身にたもち、智慧あり、よく心を統一し、内省し、よく気をつけている人こそが、渡りがたい激流を渡り得る。
175)愛欲の想いを離れ、一切の結び目(束縛)を超え、歓楽による生存を滅しつくした人――かれは深海のうちに沈むことがない。」
10、ア ー ラ ヴ ァ カ と い う 神 霊
182)「この世では信仰が人間の最上の富である。徳行に篤(あつ)いことは安楽をもたらす。実に真実が味の中での美味である。智慧によって生きるのが最高の生活であるという。」
184)「ひとは信仰によって激流を渡り、精励によって海を渡る。勤勉によって苦しみを超え、智慧によって全く清らかとなる。」
187)適宜に事をなし、忍耐づよく努力する者は財を得る。誠実をつくして名声を得、何ものかを与えて交友を結ぶ。
188)信仰あり在家の生活を営む人に、誠実、真理、堅固、施与というこれらの4種の徳があれば、かれは来世に至って憂えることがない。
11、勝 利
203)〈かの死んだ身も、この生きた身のごとくであった。この生きた身も、かの死んだ身のごとくになるであろう〉と、内面的にも外面的にも身体に対する欲を離れるべきである。
204)この世において愛欲を離れ、智慧ある修行者は、不死・平安・不滅なるニルヴァーナの境地に達した。
12、聖 者
207)親しみ慣れることから恐れが生じ、家の生活から汚れた塵が生ずる。親しみ慣れることもなく家の生活もないならば、これが実に聖者のさとりである。
208)すでに生じた(煩悩の芽を)断ち切って、新たに植えることなく、現に生ずる(煩悩)を長ぜしめることがないならば、この独り歩む人を〈聖者〉と名づける。かの大仙人は平安の境地を見たのである。
209)平安の境地、(煩悩の起る)基礎を考究して、そのたねを弁(わきま)え知って、それを愛執(あいしゅう)する心を長ぜしめないならば、かれは、実に生を滅ぼしつくした終極を見る聖者であり、妄想をすてて(迷える者の)部類に赴(おもむ)かない。
210)あらゆる執著(しゅうじゃく)の場所を知りおわって、そのいずれをも欲することなく、貪りを離れ、欲のない聖者は、作為によって求めることがない(注1)。かれは彼岸に達しているからである。
211)あらゆるものにうち勝ち、あらゆるものを知り、いとも聡明で、あらゆる事物に汚されることなく、あらゆるものを捨て、妄執が滅びて解脱した人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
212)智慧の力あり、戒めと誓いをよく守り、心がよく統一し、瞑想(禅定)を楽しみ、落ち着いて気をつけていて、執著から脱して、荒れたところなく、煩悩の汚れのない人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
213)独り歩み、怠ることのない聖者、非難と賞讃とに心を動かさず、音声に驚かない獅子(しし)のように、網にとらえられない風のように、水に汚されない蓮のように、他人に導かれることなく、他人を導く人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
214)他人がことばを極めてほめたりそしったりしても、水浴場における柱のように泰然とそびえ立ち、欲情を離れ、諸々の感官をよく静めている人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
215)梭(ひ)のように真直ぐににみずから安立し、諸々の悪い行為を嫌い、正と不正とを(注2)つまびらかに考察している人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
216)自己を制して悪をなさず、若いときでも、中年でも、聖者は自己を制している。かれは他人に悩まされることなく、また何びとをも悩まさない。諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
219)世間をよく理解して、最高の真理を見、激流を超え海をわたったこのような人、束縛を破って、依存することなく、煩悩の汚れのない人、――諸々の賢者は、かれを〈聖者〉であると知る。
220)両者は住所も生活も隔っていて、等しくない。在家者は妻を養うが、善く誓戒を守る者(出家者)は何ものをもわがものとみなす執著がない。在家者は、他のものの生命を害って、節制することがないが、聖者は自制していて、常に生命ある者をまもる。
221)譬えば青頸(あおくび)の孔雀が、空を飛ぶときには、どうしても白鳥の速さに及ばないように、在家者は、世に遠ざかって林の中で瞑想する聖者・修行者に及ばない。
注1;作為によって求めることがない――「あれこれの執著を生ずる、善または悪をなさない。」だから、この解釈によると、善をも悪をもなさず、善悪を超越するのが聖者(ムニ)の理想であった。善だけをなすというのではないのである。
注2)正と不正とを――原語から見ると、すべて他のものに対して「平らか」であるのが正であり、「平らかでない」のが不正なのである。西洋人の考える〈正〉〈不正〉とは、少しく食い違うところもあると考えられる。
■第2 小 な る 章
1、宝
224(注1))この世また来世におけるいかなる富であろうとも、天界における勝れた宝であろうとも、われらの全き人(如来)に等しいものは存在しない。この勝れた宝は、目ざめた人(仏)のうちに存する。この真理によって幸せであれ。
226)最も勝れた仏が讃嘆したもうた清らかな心の安定(注2)を、ひとびとは「〔さとりに向って〕間をおかぬ心の安定(注3)」と呼ぶ。この〈心の安定〉と等しいものはほかに存在しない。このすぐれた宝は理法の(教え)のうちに存する。この真理によって幸せであれ。
231)〔1〕自身を実在とみなす見解と〔2〕疑いと〔3〕外面的な戒律・誓いという3つのことがら(注3)が少しでも存在するならば、かれが知見を成就するとともに、それらは捨てられてしまう。かれは4つの悪い場所(注4)から離れ、また6つの重罪(注5)をつくるものとはなり得ない。このすぐれた宝が〈つどい〉のうちに存する。この真理によって幸せであれ。
注1;「この真理にによって幸せであれ」という句が繰り返されるが、古代インドにおいては、真理、真実であることばは、必ずそのとおり実現されると考えていた。このことばが真実であるならば、必ずそのとおり実現されるはずだ、というのである。
注2;心の安定――原語は「三昧」と音訳される。心を統一して思うこと。漢訳仏典では「禅定」ということばで訳されるが、禅はジァーナの音写で「心に思うこと」、「定」は精神を統一安定する意味。
間をおかぬ心の安定――この禅定を得た直後に、間をおかずに、なんらの障礙(しょうがい)なくして聖果を得るので、このようにいう。
注3;3つのことがら――ここに挙げられた3つは十結のうちの最初の3つである。それらは聖者(預流向以上)では消え失せる。
4つの悪い場所――原語は「四悪趣」と漢訳される。地獄、餓鬼、畜生、阿修羅をいう。普通は「地獄・餓鬼・畜生」を三悪道という。ただし注釈から見ると、ここでは四悪道を認めていたのではなくて、三悪道という境地と、そのほかに阿修羅という特殊な生存者の身体を認めていたのである。
6つの重罪――母を殺し、父を殺し、阿修羅を殺し、仏の身体から血を出し、僧団の和合を破り、異教徒の教えに従うことをいう。第6のものは、原語から見ると、「他の師の教示を実行すること」である。だからゴータマ・ブッダ以外の師につくことを戒めているのである。
2、な ま ぐ さ
241)梵天(注1)の親族(注2)(バラモン)であるあなたは、おいしく料理された鶏肉とともに米飯を味わって食べながらしかも〈わたしはなまぐさものを許さない〉と称している。カッサパ(注3)よ、わたくしはあなたにこの意味を尋ねます。あなたの言う〈なまぐさ〉とはどんなものなのですか。」(ティッサの言葉)
242)「生物(いきもの)を殺すこと、打ち、切断し、縛ること、盗むこと、嘘をつくこと、詐欺、だますこと、邪曲を学習すること、他人の妻に親近すること、――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
243)この世において欲望を制することなく、美味を貪り、不浄の(邪悪な)生活をまじえ、虚無論をいだき、不正の行いをなし、頑迷な人々、――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
244)粗暴・残酷であって、陰口を言い、友を裏切り、無慈悲で、極めて傲慢であり、ものおしみする性(たち)で、なんびとにも与えない人々、――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
245)怒り、驕り、強情、反抗心、偽り、嫉妬、ほら吹くこと、極端の高慢、不良の徒と交わること、――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
246)この世で、性質が悪く、借金を踏み倒し、密告をし、法廷で偽証し、正義を装い、邪悪を犯す最も劣等な人々、――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
247)この世でほしいままに生きものを殺し、他人のものを奪って、かえってかれらを害しようと努め、たちが悪く、残酷で、粗暴で無礼な人々――これがなまぐさである。肉食することが〈なまぐさい〉のではない。
249)魚肉・獣肉(を食わないこと)も、断食も、裸体も、剃髪も、結髪も、塵垢にまみれることも、粗い鹿の皮(を着ること)も、粗い鹿の皮(を着ること)も、花神への献供(けんく)につとめることも、あるいはまた世の中でなされるような、不死を得るための苦行も、(ヴェーダの)呪文も、供犠(くぎ)も、祭祀も、季節の荒行も、それらは、疑念を超えていなければ、その人を清めることができない。
250)通路(6つの機官)を(注4)まもり、機官にうち勝って行動せよ。理法のうちに安立し、まっすぐで柔和なことを楽しみみ、執著を去り、あらゆる苦しみを捨てた賢者は、見聞きしたことに汚されない。」
251)以上のことがらを尊き師(ブッダ)はくりかえし説きたもうた。ヴェーダの呪文に通じた人(バラモン)はそれを知った。なまぐさを離れて、何ものにもこだわることのない、跡を追いがたい聖者(ブッダ)は、種々の詩句を以てそれを説きたもうた。(岡野注;編者の言葉)
252)目ざめた人(ブッダ)のみごとに説きたもうた――なまぐさを離れ一切の苦しみを除き去る――ことばを聞いて、(そのバラモンは)、謙虚なこころで、全き人(ブッダ)を礼拝し、即座に出家することをねがった。(岡野注;編者の言葉)
注1;梵天――ブラーフマン、世界を創造した主神として当時の人々から尊崇されていた。
注2;梵天の親族――「梵天の親族」といったわけは、「汝はバラモンとしての徳を欠いていて、ただ生まれのみのバラモンである」といって嘲っているのである。
注3;カッサパ――過去世においてカッサパ仏が求道者であったときのことをいう。
注4;6つの機官を――6つの機官とは眼、耳、鼻、舌、身、意をいう。
3、恥(注1)
253)恥じることを忘れ、また嫌って、「われは(汝の)友である」と言いながら、しかし為し得る仕事を引き受けない人、――かれを「この人は(わが)友に非ず」と知るべきである。
254)諸々の友人に対して、実行がともなわないのに、ことばだけ気に入ることを言う人は、「言うだけで実行しない人」であると、賢者たちは知りぬいている。
255)つねに注意して友誼(ゆうぎ)の破れることを懸念して(甘(うま)いことを言い)、ただ友の欠点のみ見る人は、友ではない。子が母の胸にたよるように、その人にたよっても、他人のためにその間を裂かれることのない人こそ、友である。
256)成果を望む人は、人間に相応した重荷を背負い、喜びを生ずる境地と賞讃を博する楽しみを修める。
257)遠ざかり離れる味と平安となる味とを味わって、法の喜びの味を味わっている人は、苦悩を離れ、悪を離れている。
注1;恥――註によるとバラモンの子である苦行者にこの教えを説いたという。この5つの詩句は殆んど同じかたちで、「恥の過去世物語」に出ている。また漢訳『雑阿含経』のも相似た内容が伝えられている。こういう一連の詩句としてまとまって伝えられたものに、後世の人が種々の因縁物語を付して、現在ののような種々の経典となったのであろう。
4、こ よ な き 幸 せ(注1)
259)諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に親しみ(註2)、尊敬すべき人々を尊敬すること、――これがこよなき幸せである。
260)適当な場所に住み(註3)、あらかじめ功徳を積んでいて、みずからは正しい誓願を起していること、――これがこよなき幸せである。
261)深い学識があり、技術を身につけ、身をつつしむことをよく学び、ことばがみごとであること(注4)――これがこよなき幸せである。
266)耐え忍ぶこと、ことばのやさしいこと、諸々の〈道の人〉に会うこと、適当な時に理法についての教えを聞くこと、――これがこよなき幸せである。
267)修養と、清らかな行いと、聖なる真理を見ること、安らぎ(ニルヴァーナ)を体得すること(注5)、――これがこよなき幸せである。
268)世俗のことがら(注6)に触れても、その人の心が動揺せず、憂いなく、汚(けが)れを離れ、安穏であること、――これがこよなき幸せである。
269)これらのことを行うならば、いかなることに関しても敗れることがない。あらゆることについて幸福(注7)に達する。――これがかれらにとってこよなき幸せである。
注1;私たちはどのように生きたらいいのか、ということを教えてくれるものが仏教であるが、では仏教は私たちにとって〈幸福〉とはどんなものだと教えているのだろうか。この短い一節は、〈人生の幸福とは何か〉をまとめて述べている。いわば釈尊の幸福論である。
注2;愚者に親しまないで賢者に親しむ――人間の理に気づかない人が愚者なのであり、理を知って体得している人が賢者なのである。金儲けだけうまくても、自分のもっている財産をふやすことに汲々として夜も安眠できないというような人は、いくら頭がよくても愚者であるといわねばならぬ。また、知識に乏しく、計算や才覚が下手でも、心の安住している人は賢者なのである。
注3;適当な場所に住む――工場で始終機械の運転を耳に聞き、あるいは鉄道のそばで列車の音を聞きつけている人には、騒音がそれほど気にならない。どの駅の近くにも飲み屋やパチンコ屋があるが、それらに、気づかなければ、そんなものはないのと同じである。
注4;ことばがみごとであること――立て板に水というようにしゃべりまくることではなくて、相手をおそれないで、思っていることが自由に口をついて出てくることである。この態度は仏教では常に尊ばれた。
現実に社会人として生きていくためには、ぼんやり暮しているのであってはならない。つねに新しい知識を得るように心がけ、日進月歩の技術を体得し、みずから自己を訓練し、向上につとめなければならない。そこで〈深い学識あり,技術と訓練をよく学び受ける〉ということが尊ばれるのである(のちの大乗仏教になると、「六度」という徳目を説くが、その最後の「智慧」とは、世俗の技術や学問に通じていることをも意味するのである)。
注5;安らぎを体得すること――世俗の生活をしている人が、そのままでニルヴァーナを体得できるかどうかということは、原始仏教においての大きな問題であったが、『スッタニバータ』のこの一連の詩句からみると、世俗の人が出家してニルヴァーナに達しうると考えていたことがわかる(しかし、のちに教団が発達すると、このような見解は教団一般には採用されなかった)。
注6;世俗のことがら――世俗のことがらとは、利得、不利得、名声、不名声、賞讃、譏(そし)り、楽、苦の8つをいう。「世俗のことがらに触れてもその人の心が動揺せず」ということは、志を固くもって誘惑に負けないことである。
注7;幸福――ここに述べられている幸福論は、必ずしも体系的とはいえない。原文は詩句のため韻律の関係もあり、論理的に筋道たてて述べられているわけではない。ただ、幸福に喜び満ちあふれている心境がつぎからつぎへとほとばしっている。その喜びの気持――それは現在の私たちのものでもあるといえる。
5、ス ー チ ロ ー マ
そこでスーチローマという神霊は、次の詩を以て、師に呼びかけた。――
270)貪欲(とんよく)と嫌悪とはいかなる原因から生ずるのであるか。好きと嫌いと身の毛のよだつこと(戦慄)とはどこから生ずるのであるか。諸々の妄想はどこから起って、心を投げうつのであるか?――あたかもこどもらが鳥を投げすてるように。
271)貪欲と嫌悪とは自分から生ずる。好きと嫌いと身の毛のよだつことは、自分から生ずる。諸々の妄想は、自分から生じて心を投げうつ、――あたかもこどもらが鳥を投げすてるように。
272)それらは愛執から起り、自身から現れる。あたかも榕樹(バニヤン)の新しい若木が枝から生ずるようなものである。それらが、ひろく諸々の欲望に執著していることは、譬えば、蔓草が林の中にはびこっているようなものである。
273)神霊よ、聞け。それらの煩悩がいかなる原因にもとづいて起るかを知る人々は,煩悩を除きさる。かれらは、渡りがたく,未だかつて渡った人のいないこの激流を渡り、もはや再び生存を受けることがない。
6、理 法 に か な っ た 行 い
274)理法にかなった行い、清らかな行い、これが最上の宝であると言う。たとい在家から出て家なきに入り、出家の身になったとしても、
275)もしもかれが荒々しいことばを語り、他人を苦しめ悩ますことを好み、獣(のごとく)であるならば、その人の生活はさらに悪いものとなり、自分の塵汚(ちりけが)れを増す。
276)論争を楽しみ、迷妄の性質に蔽(おお)われている修行僧は、目ざめた人(ブッダ)の説きたもうた理法を、説明されても理解しない。
277)かれは無明に誘われて、修養をつんだ他の人を苦しめ悩まし、煩悩が地獄に赴(おもむ)く道であることを知らない。
281)汝らはすべて一致協力して、かれを斥(しりぞ)けよ。籾殻(もみがら)を吹き払え。屑を取り除け。
282)次いで、実は〈道の人〉ではないのに〈道の人〉であると思いなしている籾殻どもを除き去れ。――悪を欲し、悪い行いをなし、悪いところにいるかれらを吹き払って。
283)みずからは清き者となり、互いに思いやりをもって、清らかな人々と共に住むようにせよ。そこで、聡明な者どもが、ともに仲よくして、苦悩を終滅せしめるであろう。
7、バ ラ モ ン に ふ さ わ し い こ と
298)バラモンたちは、手足が優美で、身体が大きく、容色端麗で、名声あり、自分のつとめに従って、為すべきことを為し、為してはならぬことは為さないということに熱心に努力した。かれらが世の中にいた間は、この世の人々は栄えて幸福であった。
299)しかるにかれらに誤った見解が起った。次第に王者の栄華と化粧盛装した女人を見るにしたがって、
300)また駿馬に牽(ひ)かせた立派な車、美しく彩られた縫物、種々に区画され部分ごとにほど良くつくられた邸宅や住居を見て、
301)バラモンたちは、牛の群が栄え、美女の群を擁するすばらしい人間の享楽を得たいと熱望した。
302)そこでかれらはヴェーダの呪文を編纂(へんさん)して、かの甘蔗王のもとに赴いていった、「あなたは財宝も穀物も豊かである。祭祀(さいし)を行いなさい。あなたの富は多い。祭祀を行いなさい。あなたの財産は多い。」
311)昔は、欲と飢えと老いという3つの病いがあっただけであった。ところが諸々の家畜を祀りのために殺したので、98種の病いが起った。
314)このように法が廃(すた)れたときに、隷民(れいみん、シュードラ)と庶民(ヴァイシャ)との両者が分裂し、また諸々の王族がひろく分裂して仲たがいし、妻はその夫を蔑むようになった。
315)王族も、梵天の親族(バラモン)も、並びに種姓(の制度)によって守られている他の人々も、生れを誇る論議を捨てて、欲望に支配されるに至った、と。
8、舟
318)未だことがらを理解せず、嫉妬心のある(注1)、くだらぬ人・愚者に親しみつかえるならば、ここで真理(理法)を弁(わきま)え知ることなく、疑いを超えないで、死に至る。
321)堅牢な船に乗って、橈(かい)と舵とを具えているならば、操縦法を知った巧みな経験者は、他の多くの人々をそれに乗せて渡すように、
322)それと同じく、ヴェーダ(真理の知識)に通じ、自己を修養し、多く学び、動揺しない(師)は、実に(みずから)知っているので、傾聴し侍坐しようという気持を起した他の人々の心を動かす。
323)それ故に、実に聡明にして学識の深い立派な人に親しめ。ものごとを知って実践しつつ、真理(注2)を理解した人は、安楽を得るであろう。
注1;嫉妬心のある――師が弟子に対して嫉妬心があり、弟子の成長発展に堪えられないことをいう。
この点では、原始仏教が主知主義的または貴族主義的表現を愛好していたことが知られる。そうしてこの点では、原始仏教は。ストアの哲人を思わせる。
注2)真理――この場合、真理とは人間の真理である。
9、い か な る 戒 め を
327)真理を楽しみ、真理を喜び、真理に安住し、真理の定めを知り、真理をそこなうことばを口にするな。みごとに説かれた真実にもとづいて暮せ。
328)笑い、だじゃれ、悲泣(ひきゅう)、嫌悪、いつわり、詐欺、貪欲(とんよく)、高慢、激昂、粗暴なことば、汚濁、耽溺をすてて、驕りを除去し、しっかりとした態度で行え。
329)みごとに説かれたことばは、聞いてそれを理解すれば、精となる。聞きかつ知ったことは、精神の安定を修すると、精になる。人が性急であってふらついているならば、かれには智慧も学識も増大することがない。
330)聖者の説きたもうた真理を喜んでいる人々は、ことばでも、行いでも、最上である。かれらは平安と柔和と瞑想とのうちに安立し、学識と智慧との真髄に達したのである。
10、精 励
331)起てよ、坐れ(注1)。眠って汝らになんの益があろう。矢に射られて苦しみ悩んでいる者どもは、どうして眠られようか。
332)起てよ、坐れ。平安を得るために、ひたすら修行せよ。汝らが怠惰でありその〔死王の〕力に服したことを死王が知って、汝らを迷わしめることなかれ。
333)神々も人間も、ものを欲しがり、執著にとらわれている。この執著を超えよ。わずかの時をも空しく過すことなかれ。時を空しく過した人は地獄に墜ちて悲しむからである。
334)怠りは塵垢(ちりあか)である。怠りに従って塵垢がつもる。つとめはげむことによって、また明知によって、自分にささった矢を抜け。
注1;坐れ――足を組んで禅定を修せよ、の意。
人間にはいろいろの欲望があるが、強い意志があれば、それを制御することができる。しかし、いかんとも超克し難いのは、睡眠したいと言う欲望である。だから、それを制御せよ、というのである。
11、ラ ー フ ラ(注1)
注1;ラーフラ――伝説によると、釈尊が故郷カピラヴァットゥへ帰ったときに一子ラーフラを出家せしめ、成年に達したときにサーリプッタ(岡野注;舎利子)がかれに完備した戒律を授けたという。ところでラーフラは生れが良かったことなどの故に、サーリプッタを軽蔑する傾きがあったという。開祖の実子であるという気持が、かれをしてつけ上がらせたのであろう。そこで次の対話が伝えられている。
12、ヴ ァ ン ギ ー サ
わたくしがこのように聞いたところによると、――あるとき尊き師(ブッダ)はアーラヴィーにおけるアッガーラヴァ霊樹のもとにおられた。そのとき、ヴァンギーサさんの師でニグローダ・カッパという名の長老が、アッガーラヴァ霊樹のもとで亡くなってから、間がなかった。そのときヴァンギーサさんはひとり閉じこもって沈思していたが、このような思念が心に起った、――「わが師は実際に亡くなったのだろうか、あるいはまだ亡くなっていないのだろうか?」と。
そこでヴァンギーサさんは、夕方に沈思から起き出て、師のいますところに赴いた。そこで師に挨拶して、傍に坐った。傍に坐ったヴァンギーサさんは師にいった、「尊いお方さま。わたくしがひとり閉じこもって沈思していたとき、このような思念が心に起りました。――〈わが師は実際に亡くなったのだろうか、或はまだ亡くなっていないのだろうか?〉」と。そこでヴァンギーサさんは坐から立上がって、衣を左の肩にかけて右肩をあらわし、師に向って合掌し、師にこの詩を以て呼びかけた。
348)風が密雲を払いのけるように、〔この人(注1)〕(ブッダ)が煩悩の汚れを払うのでなければ、全世界は覆われて、暗黒となるでありましょう。光輝ある人々(注2)も輝かないでありましょう。
注1;人――ブッダのこと。ブッダは原則的に人なのである。
注2;光輝ある人々――サーリプッタ(岡野注;舎利子)など智慧の光のある人々。
13、正 し い 遍 歴(注1)
360)師はいわれた、「瑞兆の占い、天変地異の占い、夢占い、相の占いを完全にやめ、吉凶の判断をともにすてた修行者は、正しく世の中を遍歴するであろう。
361)修行者が、迷いの生存を超越し、理法をさとって、人間及び天界の諸々の享楽に対する貪欲(とんよく)を慎しむならば、かれは正しく世の中を遍歴するであろう。
368)修行者が、自分に適当なことを知り、世の中で何ものをも害(そこな)うことなく、如実に理法を知っているのであるならば、かれは正しく世の中を遍歴するであろう。
369)かれにとっては、いかなる潜在的妄執も存ぜず、悪の根が根こそぎにされ、ねがうこともなく、求めることもないならば、かれは正しく世の中を遍歴するであろう。
370)煩悩の汚(けが)れはすでに尽き、高慢を断ち、あらゆる貪りの路を超え、みずから制し、安らぎを帰し、こころが安立しているならば、かれは正しく世の中を遍歴するであろう。
374)究極の境地を知り、理法をさとり、煩悩の汚れを断ずることを明らかに見て、あらゆる(生存を構成する要素)を滅しつくすが故に、かれは正しく世の中を遍歴するであろう。」
注1;正しい遍歴――古代インドのバラモン教の法典によると、バラモンは人生の4時期の慣習を実行すべきであるとされている。それは実際問題として制度化されている。ところでこの4つの時期のうちで、最後の第4の時期、すなわち遍歴修行の時期が最も尊いとされていた。そこでゴーダマ・ブッダはこの「遍歴」とは何であるか、ということをここで論議して、その内容を倫理的なものに改めているのである。
14、ダ ン ミ カ
390)実に或る人々は(誹謗の)ことばに反撥する。かれら浅はかな小賢しい人々をわれらは賞讃しない。(論争の)執著があちこちから生じて、かれらを束縛し、かれらはそこでおのが心を遠くへ放ってしまう。
393)次に在家の者の行うつとめを汝らに語ろう。このように実行する人は善い〈教えを聞く人〉(仏弟子)である。純然たる出家修行者に関する規定は、所有のわずらいある人(在家者)がこれを達成するのは実に容易ではない。
404)正しい法(に従って得た)財を以て母と父とを養え。正しい商売を行え。つとめ励んでこのように怠ることなく暮している在家者は、(死後に)〈みずから光を放つ〉という名の神々のもとに赴く。」
■第3 大 い な る 章
2、つ と め は げ む こ と(注1)
426)(悪魔)ナムチはいたわりのことばを発しつつ近づいてきて、言った、「あなたは瘠せていて、顔色も悪い。あなたの死が近づいた。
427)あなたが死なないで生きられる見込みは、千に1つの割合だ。きみよ、生きよ。生きたほうがよい。命があってこそ諸々の善行をなすこともできるのだ。
428)あなたがヴェーダ学生としての清らかな行いをなし(注2)、聖火に供物(そなえもの)をささげてこそ、多くの功徳を積むことができる。(苦行に)つとめはげんだところで、何になろうか。
429)つとめはげむ道は、行きがたく、行いがたく、達しがたい。」
この詩を唱(とな)えて、悪魔は目ざめた人(ブッダ)の側に立っていた。
430)かの悪魔がこのように語ったときに、尊師(ブッダ)は次のように告げた。――「怠け者の親族よ、悪しき者よ。汝は(世間の)善業を求めてここに来たのだが、
431)わたくしにはその(世間の)善業を求める必要は微塵もない。悪魔は善業の功徳を求める人々にこそ語るがよい。
432)わたくしには信念があり、努力があり、また智慧がある。このように専心しているわたくしに、汝はどうして生命(いのち)をたもつことを尋ねるのか?
433)(はげみから起る)この風は、河水の流れをも涸らすであろう。ひたすら専心しているわが身の血がどうして涸渇しないであろうか。
434)(身体の)血が涸れたならば、胆汁も痰も涸れるであろう。肉が落ちると、心はますます澄んでくる。わが念(おも)いと智慧と統一した心とはますます安立するに至る。
435)わたくしはこのように安住し、最大の苦痛を受けているのであるから、わが心は諸々も欲望にひかれることがない。見よ、心身の清らかなことを。
436)汝の第1の軍隊は欲望であり、第2の軍隊は嫌悪であり、第3の軍隊は飢渇(きかつ)であり、第4の軍隊は妄執といわれる。
437)汝の第5の軍隊はものうさ、睡眠であり、第6の軍隊は恐怖といわれる。汝の第7の軍隊は疑惑であり、汝の第8の軍隊はみせかけ(注3)と強情と、
438)誤って得られた利得と名声と尊敬と名誉と、また自己をほめたたえて他人を軽蔑することである。
439)ナムチよ、これらは汝の軍勢である。黒き魔の攻撃軍である。勇者でなければ、かれにうち勝つことができない。(勇者は)うち勝って楽しみを得る。
440)このわたしがムンジャ草を取り去るだろうか?(敵に降参してしまうだろうか?)この場合、命はどうでもよい。わたくしは、敗れて生きながらえるよりは、戦って死ぬほうがましだ。
441)或る修行者たち・バラモンどもは、この(汝の軍隊)のうちに埋没してしまって、姿が見えない。そうして徳行ある人々の行く道をも知っていない。
442)軍勢が4方を包囲し、悪魔が象に乗ったのを見たからには、わたくしは立ち迎えてかれらと戦おう。わたくしはこの場所から退けることなかれ。
443)神々も世間の人々も汝の軍勢を破り得ないが、わたくしは知慧の力で汝の軍勢をうち破る。――焼いてない生の土鉢を石で砕くように。
444)みずから思いを制し、よく念い(注意)を確立し、国から国へと遍歴しよう。――教えを聞く人々をひろく導きながら。
445(注4))かれらは、無欲となったわたくしの教えを実行しつつ、怠ることなく、専心している。そこに行けば憂えることのない境地に、かれらは赴くであろう。」
446)(悪魔はいった)、
「われは7年間も尊師(ブッダ)に、一歩一歩ごとにつきまとうていた。しかもよく気をつけている正覚者には、つけこむ隙をみつけることができなかった。」
447)烏(からす)が脂肪の色をした岩石の周囲をめぐって『ここに柔らかいものが見つかるだろうか?味のよいものがあるだろうか?』といって飛び廻ったようなものである。
448)そこに美味が見つからなかったので、烏はそこから飛び去った。岩石に近づいたその烏のように、われらは厭(あ)いてゴーダマ(ブッダ)を捨て去る。」
449)悲しみにうちしおれた悪魔の脇から、琵琶がパタッと落ちた。ついで、かの夜叉は意気銷沈してそこに消え失せた。
注1;つとめはげむこと――主として精神的な努力精励をいう。ここにえがかれていることは、諸伝説と対照して考えると、成道以前のブッダが悪魔と戦ったことをいう。
注2;あなたがヴェーダ学生として清らかな行いをなし――ここでは独身の学生として師のもとでヴェーダ聖典を学習する第1の時期と、次に家に帰ってから結婚して家長となり祭祀を司る第2の時期とに言及している。いずれもバラモン教の律法書に規定されていることであり、その規定を守るべきことを、ここで悪魔が勧めているのである。
注3;みせかけ――偽善に通ずるものである。
注4;(444)-(445) この2つの詩句から見ると、人々に対して教えを説くことが、義務とされているのである。
3、み ご と に 説 か れ た こ と
わたくしが聞いたところによると、――或るとき尊き師ブッダはサーヴァッティー市のジュータ林、〈孤独な人々に食を給する長者の園〉におられた。そのとき師は諸々の〈道の人〉に呼びかけられた、「修行僧たちよ」と。「尊き師よ」と、〈道の人〉たちは師に答えた。師は告げていわれた、「修行僧たちよ。4つの特徴を具えたことばは、みごとに説かれたのである。悪しく説かれたのではない。諸々の智者が見ても欠点なく、非難されないものである。その4つとは何であるか?道の人たちよ、ここで修行僧が、⑴みごとに説かれたことばのみを語り、悪しく説かれたことばを語らず、⑵理法のみを語って理にかなわぬことを語らず、⑶好ましいことのみを語って、このましからぬことを語らず、⑷真実のみを語って、虚妄を語らないならば、この4つの特徴を具えていることばは、みごとに説かれたのであって、悪しく説かれたのではない。諸々の智者が見ても欠点なく、非難されないものである。」尊き師はこのことを告げた。そのあとでまた、〈幸せな人〉である師は、次のことを説いた。
450)立派な人々は説いた――⑴最上の善いことばを語れ。(これが第1である。)⑵正しい理(ことわり)を語れ、理に反することを語るな。これが第2である。⑶好ましい言葉を語れ。このましからぬことばを語るな。これが第3である。⑷真実を語れ。偽りを語るな。これが第4である。
そこでヴァンギーサ長老は師の面前で、ふさわしい詩を以て師をほめ称えた。
451)自分を苦しめず、また他人を害しないことばのみを語れ。これこそ実に善く説かれたことばなのである。
452)好ましいことば(注1)のみを語れ。そのことばは人々に歓び迎えられることばである。感じの悪いことばを避けて、他人の気に入ることばのみを語るのである。
453)真実は実に不滅のことばである。これは永遠の理法である。立派な人々は、真実の上に、ためになることの上に、また理法の上に安立しているといわれる。
454)安らぎに達するために、苦しみを終滅させるために、仏の説きたもうおだやかなことばは、実に諸々のことばのうちで最上のものである。
注1;好ましいことば――漢訳仏典ではしばしば「愛語」と訳すが、愛情のこもったことばである。
4、ス ン ダ リ カ ・ バ ー ラ ド ヴ ァ ー ジ ャ
わたくしが聞いたところによると、――或るとき尊き師(ブッダ)はコーサラ国のスンダリカー河の岸に滞在しておられた。ちょうどその時に、バラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャ(注1)はスンダリカー河の岸辺で聖火をまつり、火の祀りを行った。バラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャは、聖火をまつり、火の祀りを行ったあとで、座から立ち、あまねく4方を眺めていった、――「この供物(そなえもの)のおさがりを誰に食べさせようか。」
バラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャは、遠からぬところで尊き師(ブッダ)が或る樹の根もとで頭まで衣をまとって坐っているのを見た。見おわってから、左手で供物のおさがりをもち、右手で水瓶をもって師のおられるところに近づいた。そこで師はかれの足音を聞いて、頭の覆いをとり去った。そのときバラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャは「この方は頭を剃っておられる。この方は剃髪者である」といって、そこから戻ろうとした。そうしてかれはこのように思った、「この世では、或るバラモンたちは、頭を剃っているということもある。さあ、わたしはかれに近づいてその生れ(素性)を聞いてみよう」と。
そこでバラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャは師のおられるところに近づいた。それから師にいった、「あなたの生れは何ですか?」と。
そこで師は、バラモンであるスンダリカ・バーラドヴァージャに詩を以て呼びかけた。
462)生れを問うことなかれ。行いを問え。火は実にあらゆる薪から生ずる。賤しい家に生まれた人でも、聖者として道心堅固であり、恥を知って慎しむならば、高貴の人となる。
463)真実をもてみずから制し、(諸々の感官を)慎しみ、ヴェーダの奥義(おくぎ)に達し、清らかな行いを修めた人――そのような人こそ適当な時に供物(そなえもの)をささげよ。――バラモンが功徳を求めて祀りを行うのであるならば。
464)諸々の欲望を捨てて、家なくして歩み、よくみずから慎しんで、梭(ひ)のように真直ぐな人々、――そのような人こそ適当な時に供物(そなえもの)をささげよ。――バラモンが功徳を求めて祀りを行うのであるならば。
465)貪欲(とんよく)を離れ、諸々の感官を静かにたもち、月がラーフの捕われから脱したように(捕われることのない)人々――そのような人こそ適当な時に供物(そなえもの)をささげよ。――バラモンが功徳を求めて祀りを行うのであるならば。
466)執著(しゅうじゃく)することなくして、常に心をとどめ、わがものと執(しゅう)したものを(すべて)捨て去って、世の中を歩き廻る人々、――そのような人こそ適当な時に供物(そなえもの)をささげよ。――バラモンが功徳を求めて祀りを行うのであるならば。
467)諸々の欲望を捨て、欲にうち勝ってふるまい、生死のはてを知り、平安に帰し、清涼なること湖水のような〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
468)全き人(如来)は、平等なるもの(過去の目ざめた人々、諸仏)と等しくして、平等ならざる者どもから遙かに遠ざかっている。かれは無限の智慧あり。この世でもかの世でも汚(けが)れに染まることがない。〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
469)偽りもなく、慢心もなく、貧欲を離れ、わがものとして執著することなく、欲望をもたず、怒りを除き、こころ静まり、憂いの垢を捨て去ったバラモンである〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
470)こころの執著をすでに断って、何らとらわれるところがなく、この世についてもかの世についてもとらわれることがない〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
471)こころをひとしく静かにして激流をわたり、最上の知見によって理法を知り、煩悩の汚(けが)れを滅しつくして、最後の身体をたもっている(注2)〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
472)かれは、生存の汚れも、荒々しいことばも、除き去られ滅びてしまって、存在しない。かれはヴェーダに通じた人であり、あらゆることがらに関して解脱している〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
473)執著を超えていて、執著をもたず、慢心にとらわれている者どものうちにあって慢心にとらわれることなく、畑及び地所(苦しみの起る因縁)とともに苦しみを知りつくしている〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
474)欲望にもとづくことなく、遠ざかり離れることを見、他人の教える異った見解を超越して、何らこだわってとらわれることのない〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
475)あれこれ一切の事物をさとって、それらが除き去られ滅びてしまって存在しないで、平安に帰し、執著を滅ぼしつくして解脱している〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
476)煩悩の束縛と迷いの生存への生れかわりとが滅び去った究極の境地を見、愛欲の道を断って余すところなく、清らかにして、過ちなく、汚れなく、透明である〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
477)自己によって自己を観じて(それを)認めることなく、こころが等しくしずまり、身体が真直ぐで、みずから安立し、動揺することなく、心の荒(すさ)みなく、疑惑のない〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
478)迷妄にもとづいて起る障りは何ら存在せず、あらゆることがらについて智見あり、最後の身体をたもち、めでたい無上のさとりを得、――これだけでも人の霊(たましい)は清らかとなる。――〈全き人〉(如来)は、お供えの菓子を受けるにふさわしい。
479)「あなたのようなヴェーダの達人にお会いできたのですから、わが供物は真実の供物であれかし。梵天こそ証人としてみそなわせ。先生!ねがわくはわたくしから受けてください。先生!ねがわくはわがお供えの菓子を召し上ってください。」
480)「詩を唱(とな)えて得たものを、わたくしは食うてはならない。バラモンよ、これは正しく見る人々(目ざめた人々、諸仏)のなすきまりではない。詩を唱(とな)えて得たものを目ざめた人々(諸仏)は斥(しりぞ)けたもう。バラモンよ。このきまりが存するのであるから、これが(目ざめた人々、諸仏の)行いのしかた(実践法(注3))である。
481)全き者である大仙人、煩悩の汚れをほろぼし尽し悪行による悔恨の消滅した人に対しては、他の飲食をささげよ(注4)。けだしそれは功徳を積もうと望む者の(福)田であるからである。」
482)「先生!わたくしのような者の施しを受け得る人、祭詞の時に探しもとめて供養すべき人、をわたくしは――あなたの教えを受けて――どうか知りたいのです。」
483)「争いを離れ、心に濁りなく、諸々の欲望を離脱し、ものうさを除き去った人、
484)限界を超えたもの(煩悩)を制し、生死を究め、聖者の徳性を身に具えたそのような聖者が祭詞のために来たとき、
485)かれに対して眉をひそめて見下すことをやめ、合掌してかれを礼拝せよ。飲食物をささげて、かれを供養せよ。このような施しは、成就して果報をもたらす。」
486)「目ざめた人(ブッダ)であるあなたさまは、お供えの菓子を受けるにふさわしい。あなたは最上の福田(ふくでん)であり、全世界の布施を受ける人であります。あなたにさし上げた物は、果報が大きいです。」
注1;スンダリカ・バーラドヴァージャ――最後の散文の部分は「蛇の章」の第4「田を耕すバーラドヴァージャ」の終わりの一部に同じ
インド人は大きな衣で身を包むことがあるが、寒いよきには頭までもその衣ですっぽりとかぶってしまう。釈尊もそのような恰好で樹の下に坐していたことがあるのであろう。また釈尊は剃髪していて、いわゆる坊主頭であった。仏像に見られるような髪を整えていたのではないのである。
注2;最後の身体をたもっている――もはや生まれかわってさらに新たな身体を受けることがない、との意。ニルヴァーナに達した人のことをいう。ニルヴァーナに入ると、もはや身体をたもつことがない、と考えていたのである。
注3;実践法――「詩を唱えて得たもの」というのは、恐らく仏教が興起した時代に、バラモンたちがヴェーダの呪句を唱えてそれに対する布施として種々の物品を得ていたが、真の求道者はそのようなことをしてはならない、ということを述べたのであると考えられる〔一般民衆のために祭詞を実行したり呪句を唱えることを、当時バラモンたちが実行し、それによって得る収入がかれらの生活源であった〕。
その裏面に内含されている趣意をいうと、バラモンたちが呪句を唱えたのに対して、物品の謝礼を与えることは無意味であるということを言おうとしているのである。
すると、バラモンたちは生活に困るわけであるが、当時は農耕、労働などに従事するバラモンたちも次第に現れてきた。そのことは、殊にジャータカ物語の中に顕著である(かれらの転職についての補償などはどこからも来なかった)。
最初期の仏教の修行者たちは、合理的な確信をもって行動していた求道者であった。だからこのようなことをキッパリと断言したのである。ところが仏教教団が発展して民衆の間に根を下ろすと、「お経を唱えて布施を受ける」という習俗が成立した。
注4;他の飲食をささげよ――呪句を唱えたことに対する布施としての飲食物ではなくて、他の性質の飲食物を真の求道者に(=仏教の修行者に)ささげよ、というのである。
6、サ ビ ヤ
わたくしが聞いたところによると、――或るとき尊き師(ブッダ)は王舎城の竹園林にある栗鼠飼養の所に住んでおられた。そのとき遍歴の行者サビヤに、昔の血縁者であるが(今は神となっている)一人の神が質問を発した、――「サビヤよ。〈道の人〉であろうとも、バラモンであろうとも、汝が質問したときに明確に答えることのできる人がいるならば、汝はその人のもとで清らかな行いを修めなさい」と。そこで遍歴の行者サビヤは、その神からそれらの質問を受けて、次の〔6師〕のもとに至って質問を発した。すなわちブーラナ・カッサパ、マッカリ・ゴーサーラ、アジタ・ケーサンバリ、パクダ・カッチャーヤナ、ベッラーッティ族の子であるサンジャヤ、ナータ族の子であるニガンタとであるが、かれらは〈道の人〉あるいはバラモンであり、衆徒をひきい、団体の師であり、有名で名声あり、教派の開祖であり、多くの人々から立派な人として崇(あが)められていた。〔しかるに〕かれらは、遍歴の行者サビヤに質問されても、満足に答えることができなかった。そうして、怒りと嫌悪と憂いの色をあらわしたのみならず、かえって遍歴の行者サビヤに反問した。そこで遍歴の行者サビヤはこのように考えた、「これらの〈道の人〉またはバラモンであられる方々は衆徒をひきい、団体の師であり、有名で名声あり、教派の開祖であり、多くの人々から立派な人として崇められている。かれら、すなわちブーラナ・カッサパからさらについにナータ族の子であるニガンタに至るまでの人々は、わたしに質問されても、満足に答えることができなかった。満足に答えることができなないで、怒りと嫌悪と憂いの色をあらわしたのみならず、わたしに反問した。さあ、わたくしは低く劣った状態(在俗の状態)に戻って諸々の欲望を享楽することにしよう」と。
そのとき遍歴の行者サビヤはまたこのように考えた、「ここにおられる〈道の人〉ゴータマもまた衆徒をひきい、団体の師であり、有名で名声あり、教派の開祖であり、多くの人々から立派な人として崇(あが)められている。さあ、わたしは〈道の人〉ゴータマに近づいて、これらの質問を発することにしよう」と。
ー中略ー〈道の人〉ゴータマはわたくしの発したこれらの質問に明確に答え得るであろうか。〈道の人〉ゴータマは生年も若いし、出家したのも新しいことだからである」と。
次いで遍歴の行者サビヤはこのように考えた、「〈道の人〉は若いからといって侮ってはならない。軽蔑してはならない。たといかれが若い〈道の人〉であっても、かれは大神通(だいじんづう)があり、大威力がある。さあ、わたしは〈道の人〉ゴータマのもとに赴(おもむ)いて、この質問を発してみよう」と。
そこで遍歴の行者サビヤは王舎城に向って順次に歩みを進め、王舎城の竹園林にある栗鼠飼養所におられる尊き師(ブッダ)のもとに赴いた。そうして、師に挨拶した。喜ばしい、思い出の挨拶のことばを交したのち、かれは傍に坐した。それから遍歴の行者サビヤは師に詩を以て呼びかけた。――
523)サビヤがいった、「諸々の目ざめた人(ブッダ)は誰を〈田の勝者〉と呼ぶのですか?何によって巧みなのですか?どうして〈賢者〉なのですか?どうして〈聖者〉と呼ばれるのですか?先生!おたずねしますが、わたくしに説明してください。」
524)師が答えた、「サビヤよ天の田・人の田・梵天の田という一切の田を弁別して、一切の田の根本の束縛から離脱した人、――このような人がまさにその故に〈田の勝者〉とよばれるのである。
525)天の蔵(くら)・人の蔵・梵天の蔵なる一切の蔵を弁別して、一切の蔵の根本の束縛から離脱した人、――このような人がまさにその故に〈巧みな人〉とよばれるのである。
526)内面的にも外面的にも2つながらの白く浄らかなものを弁別して、清らかな智慧あり、黒と白(善悪業)を超越した人、――このような人はまさにその故に〈賢者〉とよばれる。
527)全世界のうちで内面的にも外面的にも正邪の道理を知っていて、人間と神々の崇敬を受け、執著(しゅうじゃく)の網を超えた人――かれは〈聖者〉である。」
そこで、遍歴の行者サビヤは尊き師(ブッダ)の両足に頭をつけて礼して、言った、――「すばらしいことです、尊いお方さま。すばらしいことです、譬えば倒れた者を起すように、覆われたものを開くように、方角に迷った者に道を示すように、あるいは『眼ある人々は色やかたちを見るであろう』といって暗闇の中で灯火をかかげるように、ゴーダマさまは種々のしかたで理法を明らかにされました。ここでわたくしはゴーダマ(ブッダ)さまに帰依したてまつる。また真理と修行僧のつどいに帰依したてまつる。わたくしは師のもとで出家したいのです。完全な戒律を受けたいのです。」
(師はいわれた)、「サビヤよ。かつて異説の徒であった者が、この教えと戒律とにおいて出家しようと望み、完全な戒律を受けようと望むならば、かれは4カ月の間別に住む。4カ月たってから、もういいな、と思ったならば、諸々の修行僧はかれを出家させ、完全な戒律を受けさせて、修行僧となるようにさせる。しかしこの場合は、人によって(期間の)差異のあることが認められる。」
「尊いお方さま。もしもかつて異説の徒であった者が、この教えと戒律とにおいて出家しようと望み、完全な戒律を受けようと望むならば、かれは4カ月の間別に住み、4カ月たってから、もういいな、と思ったならば、諸々の修行僧はかれを出家させ、完全な戒律を受けさせて、修行僧となるようにさせるのであるならば、わたくしは(4カ月ではなくて)、4年間別に住みましょう。そうして4年たってから、もういいな、と思ったならば、諸々の修行僧はわたくしを出家させ、完全な戒律を受けさせて、修行僧となるようにさせてください。」
さて遍歴の行者サビヤは(直ちに)師のもとで出家し、完全な戒律を受けた。それからまもなく、この長老サビヤは独りで他人から遠ざかり、怠ることなく精励し専心していたが、やがて無上の清らかな行いの究極――諸々の立派な人々はそれを得るために正しく家を出て家なき状態に赴いたのであるが――を現世においてみずからさとり、証し、具現して日を送った。「生まれることは尽きた。清らかな行いはすでに完成した。なすべきことをなしおえた。もはや再びこのような生存を受けることはない」とさとった。そうしてサビヤ長老は聖者の一人となった。
8、矢(注1)
582)汝は、来た人の道を知らず、また去った人の道を知らない。汝は(生と死の)両極を見きわめないで、いたずらに泣き悲しむ。
583)迷妄にとらわれ自己を害っている人が、もしも泣き悲しんでなんらかの利を得ることがあるならば、賢者もそうするがよかろう。
588)ひとびとがいろいろと考えてみても、結果は意図とは異なったものとなる。壊(やぶ)れて消え去るのは、このとおりである。世の成りゆくさまを見よ。
589)たとい人が百年生きようとも、あるいはそれ以上生きようとも、終には親族の人々から離れて、この世の生命を捨てるに至る。
590)だから〈尊敬さるべき人(注2)〉の教えを聞いて、人が死んで亡くなったのを見ては、「かれはもうわたしの力の及ばぬものだ」とさとって、嘆き悲しみを去れ。
592)己が悲嘆と愛執と憂いとを除け。己が楽しみを求める人は、己が(煩悩の)矢を抜くべし。
593)(煩悩の)矢を抜き去って、こだわることなく、心の安らぎを得たならば、あらゆる悲しみを超越して、悲しみなき者となり、安らぎに帰する。
注1;矢――〈近親が亡くなった悲しみに打ちひしがれるな〉という教えを述べている一節である。或る在俗信者が子を失って、悲嘆のあまり、7日間食をとらなかったのを、ブッダが同情して、かれの家に赴いて、かれの、悲しみを除くために、この教えを説いたと、パーリ文註解には説明されている。
注2;尊敬さるべき人――この場合には、ブッダのことをいう。或いは諸宗教を通じての聖者と解してもよい。
9、ヴ ァ ー セ ッ タ
601)草や木にも(種類の区別のあることを)知れ。しかしかれらは(『われらは草である』とか、『われらは木である』とか)言い張ることはない。かれらの特徴は生れにもとづいている。かれらの生れはいろいろと異なっているからである。
607)これらの生類には生れにもとづく特徴はいろいろと異っているが、人類にはそのように生れにもとづく特徴がいろいろと異っているということはない。
610)手についても、足についても、指についても、爪についても、脛(すね)についても、腿(もも)についても、容色についても、音声についても、他の生類の中にあるような、生れにもとづく特徴(の区別)は(人類のうちには)決して存在しない。
611)身を稟(う)けた生きものの間ではそれぞれ区別があるが、人間のあいだではこの区別は存在しない。人間のあいだで区別表示が説かれるのは、ただ名称によるのみ。
620)われは、(バラモン女の)胎(はら)から生れ(バラモンの)母から生まれた人をバラモンと呼ぶのではない。かれは〈きみよ、といって呼びかける者〉といわれる。かれは何か所有物の思いにとらわれている。無一物であって執著にない人、――かれをわたくしは〈バラモン〉と呼ぶ。
648)世の中で名とし姓として付けられているものは、名称にすぎない。(人の生まれた)その時その時に付けられて、約束の取り決めによってかりに設けられて伝えられているのである。
650)生れによって〈バラモン〉となるのではない。生れによって〈バラモンならざる者〉となるのでもない。行為によって〈バラモン〉なのである。行為によって〈バラモンならざる者〉なのである。
652)行為によって盗賊ともなり、行為によって武士ともなるのである。行為によって司祭者となり、行為によって王ともなる。
653)賢者はこのようにこの行為を、あるがままに見る。かれらは縁起を見る者であり、行為(業)とその報いとを熟知している。
654)世の中は行為によって成り立ち、人々は行為によって成り立つ。生きとし生ける者は業(行為)に束縛されている。――進み行く車が轄(くさび)に結ばれているように。
655)熱心な修行と清らかな行いと感官の制御と自制と、――これによって〈バラモン〉となる。これが最上のバラモンの境地である。
10、コ ー カ ー リ ヤ(注1)
661)嘘を言う人は地獄に堕ちる。また実際にしておきながら「わたしはしませんでした」と言う人もまた同じ。両者ともに行為の卑劣な人々であり、死後にはあの世で同じような運命を受ける(地獄に堕ちる)。
663)種々なる貪欲(とんよく)に耽(ふけ)る者は、ことばで他人をそしる。――かれ自身は、信仰心なく、ものおしみして、不親切で、けちで、やたらにかげ口を言うのだが。
664)口穢(くちぎたな)く、不実で、卑しい者よ。生きものを殺し、邪悪で、悪業をなす者よ。下劣を極め、不吉な、でき損(そこな)いよ。この世であまりおしゃべりするな。お前は地獄に堕ちる者だぞ。
678)ここに説かれた地獄の苦しみがどれほど永く続こうとも、その間は地獄にとどまらねばならない。それ故に、ひとは清く、温良で、立派な美徳をめざして、常にことばとこころをつつしむべきである。
注1;しかし、ここでブッダは、コーカーりやに対して、むしろサーリプッタとモッガラーナをかばっている。そこから解ることは、⑴ブッダは、教団内の異なった意見に対して寛容であった。⑵かれは他人を非難することを好まなかった。
12、二 種 の 観 察
■「修行僧たちよ。善にして、尊く、出離を得させ、さとりにみちびく諸々の真理がある。そなたたちが、『善にして、尊く、出離を得させ、さとりにみちびく諸々の真理を聞くのは、何故であるか』と、もしだれかに問われたならば、かれらに対しては次のように答えねばならぬ。――『2種ずつの真理を如実に知るためである』と。しからば、そなたたちのいう2種とは何であるか、というならば、『これは苦しみである。これは苦しみの原因である』というのが、1つの観察〔法〕である。『これは苦しみの消滅である。これは苦しみの消滅に至る道である』というのが、第2の観察〔法〕である。修行僧たちよ。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちのいずれか1つの果報が期待され得る。
――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないこと(不還(ふげん))である。――
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて素因に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら素因が残りなく消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。」――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師(ブッダ)は、さらにまた次のように説かれた。
728)世間には種々なる苦しみがあるが、それらは生存の素因にもとづいて生起する。実に愚者は知らないで生存の素因をつくり、くり返し苦しみを受ける。それ故に、知り明らめて、苦しみの生ずる原因を観察し、再生の素因をつくるな。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『どんな苦しみが生ずるのでも、すべて無明に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら無明が残りなく離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。」――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師(ブッダ)は、さらにまた次のように説かれた。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて潜在的形成力に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら潜在的形成力が残りなく離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。」――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師(ブッダ)は、さらにまた次のように説かれた。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて識別作用(識)に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら識別作用が残りなく離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。」――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
735)およそ苦しみが生ずるのは、すべて識別作用に縁(よ)って起るのである。識別作用が消滅するならば、もはや苦しみの生ずることは有りえない。
736)「苦しみは識別作用にに縁って起るのである」と、この禍を知って、識別作用を静まらせたならば、修行者は、快をむさぼることなく、安らぎに帰しているのである。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて妄執(愛執)に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら妄執が残りなく離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師(ブッダ)は、さらにまた次のように説かれた。
740)妄執を友としている人は、この状態からかの状態へと永い間流転して、輪廻を超えることができない。
741)妄執は苦しみの起る原因である、とこの禍いを知って、妄執を離れて、執著することなく、よく気をつけて、修行僧は遍歴すべきである。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて執著に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら諸々の執著が残りなく消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
742)執著に縁って生存が起る。生存せる者は苦しみを受ける。生まれた者は死ぬ。これが苦しみの起る原因である。
743)それ故に諸々の賢者は、執著が消滅するが故に、正しく知って、生れの消滅したことを熟知して、再び迷いの生存にもどることがない。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて起動に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら諸々の起動が残りなく離れ消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『およそ苦しみが生ずるのは、すべて動揺に縁(よ)って起るのである』というのが、1つの観察〔法〕である。『しかしながら諸々の動揺が残りなく消滅するならば、苦しみの生ずることがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
750)およそ苦しみが起るのは、すべて動揺を縁(として起る諸々の動揺が消滅するならば、もはや苦しみの生ずることもない。
751)「苦しみは動揺の縁から起る」と、この禍いを知って、それ故に修行僧は(妄執の)動揺を捨て去って、諸々の潜在的形成力を制止して、無動揺・無執著で、よく気をつけて、遍歴すべきである。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『従属する者は、たじろぐ』というのが、1つの観察〔法〕である。『従属することのない者は、たじろがない』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
752)従属することのない人は、たじろがない。しかし従属することのある人は、この状態からあの状態へと執著していて、輪廻を超えることがない。
753)「諸々の従属の中に大きな危険がある」と、この禍いを知って、修行僧は、従属することなく、執著することなく、よく気をつけて、遍歴すべきである。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『物質的領域よりも非物質的領域のほうが、よりいっそう静まっている』というのが、1つの観察〔法〕である。『非物質的領域よりも消滅のほうが、よりいっそう静まっている』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
754)物質的領域(注1)に生まれる諸々の生存者と非物質的領域(注2)に住む諸々の生存者とは、消滅を知らないので、再びこの世の生存に戻ってくる。
755)しかし物質的領域を熟知し、非物質的領域に安住し、消滅において解脱する人々は、死を捨て去ったのである。
■「修行僧たちよ。『また他の方法によっても2種のことがらを正しく観察することができるのか?』と、もしだれかに問われたならば、『できる』と答えなければならない。どうしてであるか?『神々と悪魔とともなる世界、道の人(沙門)・バラモン・神々・人間を含む諸々の生存者が〈これは真理である〉と考えたものを、諸々の聖者は〈これは虚妄である〉と如実に正しい智慧をもってよく観ずる』――これが1つの観察〔法〕である。『神々と悪魔とともなる世界、道の人(沙門)・バラモン・神々・人間を含む諸々の生存者が〈これは虚妄である〉と考えたものを、諸々の聖者は〈これは真理である〉と如実に正しい智慧をもってよく観ずる』というのが第2の観察〔法〕である。このように2種〔の観察法〕を正しく観察して、怠らず、つとめ励んで、専心している修行僧にとっては、2つの果報のうちいずれか1つの果報が期待され得る。――すなわち現世における〈さとり〉か、あるいは煩悩の残りがあるならば、この迷いの生存に戻らないことである。――
師(ブッダ)はこのように告げられた。そうして、幸せな師は、さらにまた次のように説かれた。
756)見よ、神々並びに世人は、非我なるものを我と思いなし、〈名称と形態〉(個体)に執著(しゅうじゃく)している。「これこそ真理である」と考えている。
757)あるものを、ああだろう、こうだろう、と考えても、そのものはそれとは異なったものとなる。何となれば、その(愚者の)その(考え)は虚妄なのである。過ぎ去るものは虚妄なるものであるから。
758)安らぎは虚妄ならざるものである。諸々の聖者はそれを真理であると知る。かれらは実に真理をさとるが故に、快を貪ることなく平安に帰しているのである。
762)他の人々が「安楽」であると称するものを、諸々の聖者は「苦しみ」であると言う。他の人々が「苦しみ」であると称するものを、諸々の聖者は「安楽」であると知る。解し難き真理を見よ。無智なる人々はここに迷っている。
763)覆われた人々には闇がある。(正しく)見ない人々には暗黒がある。善良なる人々には開顕(かいけん)される。あたかも見る人々に光明のあるようなものである。理法が何であるかを知らない獣(のような愚人)は、(安らぎの)近くにあっても、それを知らない。
764)生存の貪欲にとらわれ、生存の流れにおし流され、悪魔の領土に入っている人々には、この真理は実に覚りがたい。
765)諸々の聖者以外には、そもそも誰がこの境地を覚り得るのであろうか。この境地を正しく知ったならば、煩悩の汚れのない者となって、まどかな平安に入るであろう。
注1;物質的領域――色界をいう。
注2;非物質的領域――無色界をいう。
■第4 八 つ の 詩 句 の 章
1、欲 望
766)欲望をかなえたいと望んでいる人が、もしもうまくゆくならば、かれは実に人間の欲するものを得て、心に喜ぶ。
767)欲望をかなえたいと望み貪欲(とんよく)の生じた人が、もしも欲望をはたすことができなくなるならば、かれは、矢に射られたかのように、悩み苦しむ。
768)足で蛇の頭を踏まないようにするのと同様に、よく気をつけて諸々の欲望を回避する人は、この世でこの執著をのり超える。
769)ひとが、田畑・宅地・黄金・牛馬・奴婢・傭人・婦女・親族、その他いろいろの欲望を貪りもとめると、
770)無力のように見えるもの(諸々の煩悩)がかれにうち勝ち、危い災難がかれをふみにじる。それ故に苦しみがかれにつき従う。あたかも壊(やぶ)れた舟に水に浸入するように。
771)それ故に、人は常によく気をつけていて、諸々の欲望を回避せよ。船のたまり水を汲み出すように、それらの欲望を捨て去って、激しい流れを渡り、彼岸に到達せよ。
2、洞 窟 に つ い て の 八 つ の 詩 句
772)窟(いわや)(身体)のうちにとどまり、執著し、多くの(煩悩)に覆われ、迷妄のうちに沈没すている人――このような人は、実に〈遠ざかり離れること〉(厭離)から遠く隔っている。実に世の中にありながら欲望を捨て去ることは、容易ではないからだ。
773)欲求にもとづいて生存の快楽にとらわれている人々は、解脱しがたい。他人が解脱くれるのではないからである。かれらは未来をも過去をも顧慮しながら、これらの(目の前の)欲望または過去の欲望を貪る。
774)かれらは欲望を貪り、熱中し、溺れて、吝嗇で、不正になずんでいるが、(死時には)苦しみにおそわれて悲嘆する、――「ここで死んでから、われらはどうなるのだろうか」と。
775)だから人はここにおいて学ぶべきである。世間で「不正」であると知られているどんなことであろうとも、それのために不正を行ってはならない。「ひとの命は短いものだ」と賢者たちは説いているのだ。
776)この世の人々が、諸々の生存に対する妄執を離れないで、死に直面して泣く。
3、悪 意 に つ い て の 八 つ の 詩 句
785)諸々の事物に関する固執(はこれこれのものであると)確かに知って、自己の見解に対する執著を超越することは、容易ではない。故に人はそれらの(偏執の)住居(すまい)のうちにあって、ものごとを斥け、またはこれを執(と)る。
786)邪悪を掃(はら)い除いた人は、世の中のどこにいっても、さまざまな生存に対してあらかじめいだいた偏見が存在しない。邪悪を掃(はら)い除いた人は、いつわりと驕慢とを捨て去っているが、どうして(輪廻に)赴くであろうか?かれはもはやたより近づくものがないのである。
4、清浄についての八つの詩句
788)「最上で無病の、清らかな人をわたくしは見る。人が全く清らかになるのは見解(注1)による」と、このように考えることを最上であると知って、清らかなことを観ずる人は、(見解を、最上の境地に達し得る)智慧であると理解する。
789)もしも人が見解によって清らかになり得るのであるならば、あるいはまた人が知識によって苦しみを捨て得るのであるならば、それでは煩悩にとらわれている人が(正しい道以外の)他の方法によっても清められることになるであろう。このように語る人を「偏見ある人」と呼ぶ。
790)(真の)バラモンは、(正しい道の)ほかには、見解・伝承の学問・戒律・思想のうちのどれによっても清らかになるとは説かない。かれは禍福に汚(けが)されることなく、自我を捨て、この世において(禍福の因を)つくることがない。
791)前の(師など)を捨てて後の(師など)にたより、煩悩の動揺に従っている人々は、執著をのり超えることがない。かれらは、とらえては、また捨てる。猿が枝をとらえて、また放つようなものである。
792)みずから誓戒をたもつ人は、想いに耽って、種々雑多なことをしようとする。しかし智慧ゆたかな人は、ヴェーダによって知り、真理を理解して、種々雑多なことをしようとしない。
795)(真の)バラモンは、(煩悩の)範囲をのり超えている。かれが何ものかを知りあるいは見ても、執著することがない。かれは欲を貪ることなく、また離欲を貪ることもない(注2)。かれは〈この世ではこれが最上のものである〉と固執することもない。
注1;見解――諸宗教や哲学の「教義」を意味する。
注2;欲を貪ることなく、また離欲を貪ることもない――ブッダゴーサは、前者は欲界の貪りに執することなく、の意で、後者は、色界、無色界を貪ることに執することなく、の意に解する。しかし『スッタニパータ』の最古層においては、まだ三界説は成立していなかったから、後代の思想にもとづいたこの解釈は無理である。恐らく、「欲望にとらわれることなく、また無理に欲望をなくそうと思ってその願望にとらわれることもなく」というのが、原意であったのであろう。
理想の修行者は、欲望を離れているのみならず、〈欲望を離れている〉ということをも離れているのである。こういう表現は、後代の空観、または禅僧のさとりを思わせるものがある。
5、最 上 に つ い て の 八 つ の 詩 句
796)世間では、人は諸々の見解のうちで勝れているものとみなす見解を「最上のもの」であると考えて、それよりも他の見解はすべて「つまらないものである」と説く。それ故にかれは諸々の論争を超えることがない。
797)かれ(=世間の思想家)は、見たこと・学んだこと・戒律や道徳・思索したことについて、自分の奉じていることのうちにのみすぐれた実りを見、そこで、それだけに執著して、それ以外の他のものをすべてつまらぬものであると見なす。
798)ひとが何か或るものに依拠して「その他のものはつまらぬものである」と見なすならば、それは実にこだわりである、と〈真理に達した人々〉は語る。それ故に修行者は、見たこと・学んだこと・思索したこと、または戒律や道徳にこだわってはならない。
799)智慧に関しても、戒律や道徳に関しても、世間において偏見をかまえてはならない。自分を他人と「等しい」と示すことなく、他人よりも「劣っている」とか、或いは「勝れている」とか考えてはならない。
800)かれは、すでに得た(見解)〔先入見〕を捨て去って執著することなく、学識に関しても特に依拠することをしない。人々は(種々異なった見解に)分れているが、かれは実に党派に盲従せず、いかなる見解をもそのまま信ずることがない。
801)かれはここで、両極端に対し、種々の生存に対し、この世についても、来世についても、願うことがない。諸々の事物に関して断定を下して得た固執の住居(すまい)は、かれには何も存在しない。
802)かれはこの世において、見たこと、学んだこと、あるいは思索したことに関して、微塵ほどの妄想をも構えていない。いかなる偏見をも執することのないそのバラモンを、この世においてどうして妄想分別させることができるであろうか?
803)かれらは、妄想分別をなくすことなく、(いずれか1つの偏見を)特に重んずるということもない。かれらは、諸々の教義のいずれかをも受け入れることもない。バラモンは戒律や道徳によって導かれることもない。このような人は、彼岸に達して、もはや還(かえ)ってこない。
6、老 い
804)ああ短いかな、人の生命よ。百歳に達せずして死す。たといそれよりも長く生きたとしても、また老衰のために死ぬ。
805)人々は「わがものである」と執著(しゅうじゃく)した物のために悲しむ。(自己の)所有しているものは常住ではないからである。この世のものはただ変滅するものである、と見て、在家にとどまっていてはならない。
806)人が「これはわがものである」と考える物、――それは(その人の)死によって失われる。われに従う人は、賢明にこの理を知って、わがものという観念に屈してはならない。
809)わがものとして執著したものを貪り求める人々は、憂いと悲しみと慳(ものおし)みとを捨てることがない。それ故に諸々の聖者は、所有を捨てて行なって安穏を見たのである。
811)聖者はなにものにもとどこおることなく、愛することもなく、憎むこともない。悲しみも慳(ものおし)みもかれを汚すことがない。譬えば(蓮の)葉の上の水が汚されないようなものである。
812)たとえば蓮の葉の上の水滴、あるいは蓮葉の上の水が汚されないように、それと同じく聖者は、見たり学んだり思索したどんなことについても、汚されることがない。
813)邪悪を掃(はら)い除いた人は、見たり学んだり思索したどんなことでも特に執著して考えることがない。かれは他のものによって清らかになろうとは望まない。かれは貧らず、また嫌うこともない。
7、テ ィ ッ サ ・ メ ッ テ イ ヤ
822)(俗事から)離れて独り住むことを学べ。これは諸々の聖者にとって最上のことがらである。(しかし)これだけで『自分が最上の者だ』と考えてはならない。――かれは安らぎに近づいているのだが。
9、マ ー ガ ン デ ィ ヤ
839)師は答えた、「マーガンディヤよ。『教義によって、学問によって、知識によって、戒律や道徳によって清らかになることができる』とは、わたくしは説かない。『教義がなくても、学問がなくても、知識がなくても、戒律や道徳を守らないでも、清らかになることができる』、とも説かない。それらを捨て去って、固執することなく、こだわることなく、平安であって、迷いの生存を願ってはならぬ。(これが内心の平安である。)」
842)『等しい』とか『すぐれている』とか、あるいは『劣っている』とか考える人、――かれはその思いによって論争するであろう。しかしそれらの3種に関して動揺しない人、――かれは『等しい』とか『すぐれている』とか、(あるいは『劣っている』とか)いう思いは存在しない。
843)そのバラモンはどうして『(わが説は)真実である』と論ずるであろうか。またかれは『(汝の説は)虚偽である』といって誰と論争するであろうか?『等しい』とか『等しくない』とかとかいうことのなくなった人は、誰に論争を挑むであろうか。
10、死ぬよりも前に
848)「どのように見、どのような戒律をたもつ人が『安らかである』と言われるのか?ゴータマ(ブッダ)よ。おたずめしますが、その最上の人のことをわたくしに説いてください。」
849)師は答えた、「死ぬよりも前に、妄執を離れ、過去に(注1)こだわることなく、現在においてもくよくよと思いめぐらすことがないならば、かれは(未来に関しても)特に思いわずらうことがない。
850)かの聖者は、怒らず、おののかず、誇らず、あとで後悔するような悪い行いをなさず、よく思慮して語り、そわそわすることなく、ことばを慎しむ。
851)未来を願い求めることなく、過去を思い出して憂えることもない。〔現在〕感官で触れる諸々の対象について遠ざかり離れることを観じ、諸々の偏見に誘われれることがない。
852)(貪欲などから)遠ざかり、偽ることなく、貪り求めることなく、慳(ものおし)みせず、傲慢にならず、嫌われず(注2)、両舌(かげぐち)を事としない(注3)。
853)快いものに耽溺せず、また高慢にならず、柔和で、弁舌さわやかに、信ずることなく(注4)、なにかを嫌うこともない(注5)。
854)利益を欲して学ぶのではない。利益がなかったとしても、怒ることがない。妄執のために他人に逆うことがなく、美味に耽溺することもない。
855)平静であって、常によく気をつけていて、世間において(他人を自分と)等しいとは思わない。また自分が勝れているとは思わないし、また劣っているとも思わない。かれには煩悩の燃え盛ることがない。
856)依りかかることのない人は、理法を知ってこだわることがないのである。かれには、生存のための妄執も、生存の断滅のための妄執も存在しない。
857)諸々の欲望を顧慮することのない人、――かれこそ〈平安なる者〉である、とわたくしは説く。かれには縛(いまし)めの結び目は存在しない。かれはすでに執著を渡り了(お)えた。
858)かれには、子も、家畜も、田畑も、地所も存在しない。すでに得たものも、捨て去ったものも、かれのうちには認められない。
859)世俗の人々、または道の人・バラモンどもがかれを非難して(貪りなどの過(とが))があるというであろうが、かれはその(非難)を特に気にかけることはない。それ故に、かれは論議されても、動揺することがない。
860)聖者は貪りを離れ、慳(ものおし)みすることなく、『自分は勝れたものである』とも、『自分は等しいものである』とも、『自分は劣ったものである』とも論ずることことがない。かれは分別を受けることのないものであって、妄想分別におもむかない。
861)かれは世間において〈わがもの〉という所有がない。また無所有を歎くこともない。かれは〔欲望に促されて〕諸々の事物に赴くこともない。かれは実に〈平安なる者〉と呼ばれる。」
注1;過去に――過去の生存、前世という意味ではなくて、瞬間瞬間に推移してゆく時間のうちの過去の時間をいうのである。
注2;嫌われず――人々から嫌悪されるような下劣な行動をしない、という意味である。人々の嫌がるようなことはしないようにしよう、という意味である。
注3;信ずることなく――西洋の訳者は「軽々しく信じない」「自信をもって厚かましくならない」と訳している。しかしブッダゴーサによると、もっと徹底した合理主義の立場をとっている。自分の確かめたことだけを信ずるのである。いかなる権威者をも信ぜず、神々をさえも信じない。
注4;なにかを嫌うこともない――すでに欲情がなくなっているのだから、欲情がなくなるということもないのだと解する。
もう1つの可能な解釈は、「特に欲情を去るということもない。欲情をそのままにしておく」ということである。今は解り易い解釈に従った。
11、争 闘
865)「世の中で愛し好むもの及び世の中にはびこる貪り(注1)は、欲望にもとづいて起る。また人が来世に関していだく希望とその成就とは、それにもとづいて起る。」
866)「さて世の中で欲望は何にもとづいて起るのですか?また(形而上学的な)断定は何から起るのですか?怒りと虚言と疑惑と及び〈道の人〉(沙門)の説いた諸々のことがらは、何から起るのですか?」
867)「世の中で〈快〉(不快)と称するものに依って、欲望が起る。諸々の物質的存在には生起と消滅とのあることを見て、世の中の人は(外的な事物にとらわれた)断定(注2)を下す。
868)怒りと虚言と疑惑、――これらのことがらも、(快と不快との)2つがあるときに現れる。疑惑ある人は知識の道に学べ。〈道の人〉は、知って、諸々のことがらを説いたのである。」
870)「快と不快とは、感官による接触にもとづいて起る。感官による接触が存在しないときには、これらのものも起らない。生起と消滅ということの意義と、それの起るもととなっているもの(感官による接触)を、われは汝に告げる。」
872)「名称と形態とに依って感官による接触が起る。諸々の所有欲は欲求を縁として起る。欲求がないときには、〈わがもの〉という我執も存在しない。形態が消滅したときには〈感官による接触〉ははたらかない。」
876)「この世において或る賢者たちは、『霊の最上の清浄の境地はこれだけのものである』と語る。さらにかれらのうちの或る人々は断滅を説き、(精神も肉体も)残りなく消滅することのうちに(最上の清浄の境地がある)と、巧みに(注4)かたっている。
877)かの聖者は、『これらの偏見はこだわりがある』と知って、諸々のこだわりを熟考し、知った上で、解脱せる人は論争におもむかない。思慮ある賢者は種々なる変化的生存を受けることがない。」
注1;世の中にはびこる貪り――迷いのなくなった人には苦は消滅している。欲望のなくなった人には、迷いは消滅している。貪りのなくなった人には、欲望が消滅している。何ものも所有しない人には、貪りが消滅している。
注2;断定――愛執にもとづく断定と誤った見解、すなわちアートマンがあると思う見解にもとづく断定と、2種あるという。
注3;名称と形態――これはウバニシャッドに説かれている2つの概念であって、現象界の事物の2つの側面を示す。
注4;巧みに――仏教、特にいわゆる小乗仏教の伝統説によると、無余涅槃にに入ることが修行の目標であった。ところが、ここでは、そういう見解は偏見であるとして、それを排斥しているのである。
12、並 ぶ 応 答――小 篇
884)真理は1つであって、第2のものは存在しない。その(真理)を知った人は、争うことがない。かれらはめいめい異なった真理をほめたたえている。それ故に諸々の〈道の人〉は同一の事を語らないのである。
893)自分の道を堅くたもって論じているが、ここに他の何びとを愚者であると見ることができようぞ。他(の説)を、「愚かである」、「不浄の教えである」、と説くならば、かれはみずから確執をもたらすであろう。
894)一方的に決定した立場に立ってみずから考えを量りつつ、さらにかれは世の中で論争をなすに至る。一切の(哲学的)断定を捨てたならば、人は世の中で確執を起すことがない。
13、並 ぶ 応 答――長 篇
900)一切の戒律や誓いをも捨て、(世間の)罪過あり或いは罪過なきこの(宗教的)行為をも捨て、「清浄である」とか「不浄である」とかいってねがい求めることもなく、それらにとらわれずに行え。――安らぎを固執することもなく。
903)ねがい求める者には欲念がある。また、はからいのあるときには、おののきがある。この世において死も生も存しない者、――かれは何を怖れよう、何を欲しよう。
907)(真の)バラモンは、他人に導かれるということがない。また諸々のことがらについて断定をして固執することもない。それ故に、諸々の論争を超越している。他の教えを最も勝れたものだと見なすこともないからである。
911)バラモンは正しく知って、妄想分別におもむかない。見解に流されず、知識にもなずまない。かれは凡俗の立てる諸々の見解を知って、心にとどめない。――他の人々はそれに執著しているのだが。――
912)聖者はこの世で諸々の束縛を捨て去って、論争が起ったときにも、党派にくみすることがない。かれは不安な人々のうちにあっても安らけく、泰然として、執することがない。――他の人々はそれに執著しているのだが。――
913)過去の汚れを捨てて、新しい汚れをつくることなく、欲におもむかず、執著して論ずることもない。賢者は諸々の偏見を離脱して、世の中に汚されることなく、自分を責めることもない。
914)見たり、学んだり、考えたりしたどんなことについてでも、賢者は一切の事物に対して敵対することがない。かれは負担をはなれて解放されている。かれははからいをなすことなく、快楽に耽ることなく、求めることもない。
――師はこのように言われた。
14、迅 速
916)師(ブッダ)は答えた、「〈われは考えて、有る〉という〈迷わせる不当な思惟〉の根本をすべて制止せよ。内に存するいかなる妄執をもよく導くために、常に心して学べ。
918)これ(慢心)によって『時分は勝れている』と思ってはならない。『自分は劣っている』とか、また『自分は等しい』とか思ってはならない。いろいろの質問を受けても、自己を妄想せずにおれ。
922)〔師いわく〕、「眼で視ることを貪ってはならない。卑俗な話から耳を遠ざけよ。味に耽溺してはならない。世間における何ものをも、わがものであるとみなして固執してはならない。
923)苦痛を感じることがあっても、修行者は決して悲嘆してはならない。生存を貪り求めてはならない。恐ろしいものに出会っても、慄(ふる)えてはならない。
924)食物や飲料や硬い食べものや衣服を得ても、貯蔵してはならない。またそれらが得られないからとて心配してはならない。
925)こころを安定させよ。うろついてはならない。あとで後悔するようなことをやめよ。怠けてはならぬ。そうして修行者は閑静な座所・臥所(がしょ)に住まうべきである。
926)多く眠ってはならぬ。熱心に努め、目ざめているべきである。ものぐさと偽りと談笑と遊戯と淫欲の交わりと装飾とをすてよ。
927)わが徒は、アタルヴァ・ヴェーダの呪法と夢占いと相の占いと星占いとを行なってはならない。鳥獣の声を占ったり、懐妊術や医術を行なったりしてはならぬ。
15、武 器 を 執 る こ と
941)聖者は誠実であれ。傲慢でなく、詐りなく、悪口を言わず、怒ることなく、邪な貪りと慳(ものおし)みとを超えよ。
942)安らぎを心がける人は、眠りとものぐさとふさぎこむ心とにうち勝て。怠惰を宿らせてはならぬ。高慢な態度をとるな。
943)虚言(うそ)をつくように誘(ひ)き込まれるな。美しいすがたに愛著を起すな。また慢心を知りつくしてなくすようにせよ。粗暴になることなく、ふるまえ。
944)古いものを喜んではならない。また新しいものに魅惑されてはならない。滅びゆくものを悲しんではならない。牽引する者(妄執)(注1)にとらわれてはならない。
950)名称と形態について、〈わがものという思い〉の全く存在しない人、また(何ものかが)ないからといって悲しむことのない人、――かれは実に世の中にあっても老いることがない。
951)「これはわがものである」また「もれは他人のものである」というような思いが何も存在しない人、――かれは(このような)〈わがものという観念〉が存しないから、「われになし」といって悲しむことがない。
952)動揺して煩悩に悩まされることなく、叡智ある人にとっては、いかなる作為も存在しない。かれはあくせくした営みから離れて、至るところに安穏(あんのん)を見る。
注1;索引する者――すべては移り行くということの認識にもとづいて、現実に即した柔軟性に富んだ実践原理が成立するのである。人生の指針として、こんなすばらしいことばがまたあるだろうか!
総じて人間の習性であろうが、年老いた者は昔を懐しみ、昔あったものを何でも良いものだと思う。他方若い人は何でも新奇なものにひきつけられ、古いものを破戒しようとする。この2つの傾向は互いに矛盾し抗争する。これは、いつの時代でも同じことである。最初期の仏教における右の詩句は、明言しているわけではないが、恐らくこういうことに言及しているのであろう。
しかしどちらの傾向も偏っていて、一面的であると言わねばならぬ。もしも昔のもの、古いものをことごとく是認するならば、進歩や発展はあり得ないであろう。またもしもすべて過去のものも否定するならば、人間の文化そのものが有り得ないであろう。またもしもすべて過去のものを否認するならば、人間の文化そのものが有り得ないであろう。文明は過去からの人間の努力の蓄積の上に成立するものであるからである。だから、新しいというだけで跳びついてはならぬ。
人間はどうかすると、人間の根底にひそむ、眼に見えぬ、ごす黒いものに動かされて衝動的に行動することがある。だが、それは、進路をあやまり、破滅のもととなるから、「索引する者(妄執)」に、とらわれていてはならない。
では、過去に対して、「どちらでもない中道をとるのだ」といって、両者の中間をとるならば、それは単に両者を合して稀薄にしただけにすぎないのであって、力のないものになってしまう。
転換期に当って、或る点に関して古いものを残すか、或いはそれを廃止して新しいものを採用するか、という決断に迫られるのではあるが、その際には、その決断は一定の原理に従ってなされねばならぬ。
その原理は、人間のためをはかり、人間を高貴ならしめるものでなければならぬ。それをサンスクリット語でarthaと呼び、漢訳では「義」とか「利」とか訳しているが、邦語でいえば「ため」とでも言い得るであろう。それは「ひとのため」であり、それが同時に高い意味で「わがため」になるのである。
人間のよりどころであり、人間を人間のあるべきすがたにたもつものであるという意味で、原始仏教ではそれを「法」(ダルマ)と呼んだ。仏はその〈法〉を見た人であり、仏教はその〈法〉を明らかにするものである(だから「仏法」ともいう)。その法は、民族や時代の差を超え、さらに諸宗教の区別をも超えて、実現さるべきものなのである。
16、サ ー リ プ ッ タ
964)しっかりと気をつけ分限を守る聡明な修行者は、5種の恐怖にあじけてはならない。すなわち襲いかかる虻と蚊と爬虫類と4足獣と人間(盗賊など)に触れることである。
965)異った他の教えを奉ずる輩(ともがら)(注1)をも恐れてはならない。――たといかれらが多くの恐ろしい危害を加えるのを見ても。――また善を追究して、他の危難にうち勝て。
966)病いにかかり、饑(う)えに襲われても、また寒冷や酷暑をも耐え忍ぶべきである。かの〈家なき人〉は、たといそれらに襲われることがいろいろ多くても、勇気をたもって、堅固に努力をなすべきである。
971)適当な時に食物と衣服とを得て、ここで(少量に)満足するために、(衣食の)量を知れ。かれは衣食に関しては恣(ほしい)ままならず、慎しんで村を歩み、罵られてもあらあらしいことばを発してはならない。
972)眼を下に向けて、うろつき廻ることなく、瞑想に専念して、大いにめざめておれ。心を平静にして、精神の安定をたもち、思いわずらいと欲のねがいと悔恨とを断ち切れ。
974)またさらに、世間には5つの塵垢がある。よく気をつけて、それらを制するためにつとめよ。すなわち色かたちと音声と味と香りと触れられるものに対する貧欲を抑制せよ。
975)修行僧は、よく気をつけて、心もすっかり解脱して、これらのものに対する欲望を抑制せよ。かれは適当な時に理法を正しく考察し、心を統一して。暗黒を滅ぼせ。」
――と師(ブッダは)はいわれた。
注1;異なった他の教えを奉ずる輩――場合によっては、仏教外の人々を外道と呼ぶが、ここではまだ「外道」というはっきりした観念が成立していなかったのである。
■第5 彼 岸 に 至 る 道 の 章
1、序
995)かのバーヴァリはこころ喜び、歓喜し、感動して、熱心に、かの女神に問うた。
「世間の主は、どの村に、またどの町に、あるいはどの地方にいらっしゃるのですか?そこへ行って最上の人である正覚者をわれは礼拝しましょう。」
997)そこでかれは(ヴェーダの)神呪(じんじゅ)に通達した諸々の弟子・バラモンたちに告げていった、
「着たれ、学生どもよ。われは、そなたらに告げよう。わがことばを聞け。
998)世間に出現すること常に希有であるところの、かの〈目ざめた人〉(ブッダ)として令名ある方が、いま世の中に現われたもうた。そなたらは急いでサーヴァッティーに赴いて、かの最上の人に見(まみ)えよ。」
2、学 生 ア ジ タ の 質 問
1033)師(ブッダ)が答えた、
「アジタよ。世間は無明によって覆われている。世間は貪りと怠惰のゆえに輝かない。欲心が世間の汚れである。苦悩が世間の大きな恐怖である、とわたしは説く。」
1036)アジタさんがいった、「わが友よ。智慧と気をつけることと名称と形態とは、いかなる場合に消滅するのですか?おたずねしますが、このことをわたしに説いてください。」
1037)「アジタよ。そなたが質問したことを、わたしはそなたに語ろう。識別作用が止滅することによって、名称と形態とが残りなく滅びた場合に、この名称と形態とが滅びる。」
6、学 生 ド ー タ カ の 質 問
1061)ドータカさんがたずねた、「先生!わたくしはあなたにおたずねします。このことをわたくしに説いてください。偉大な仙人さま。わたくしはあなたのおことばを頂きたいのです。あなたのお声を聞いて、自分の安らぎ(ニルヴァーナ)を学びましょう(注1)。」
1064)「ドータカよ。わたくしは世間におけるいかなる疑惑者をも解脱させ得ないであろう。ただそなたが最上の真理(注2)を知るならば、それによって、そなたはこの煩悩の激流を渡るであろう。」
注1;ここでは、「自分の安らぎ(ニルヴァーナ)を学びましょう」という。この文章から見るかぎり、安らぎを実現するために学ぶことがニルヴァーナであり、ニルヴァーナとは学びつつ(実践しつつ)あることにほかならない。ブッダゴーサの注によると、「貧欲などをなくすために(ニルヴァーナのために)戒などを実践をするのだ」と言い、ニルヴァーナを目的と見なし、戒などの実践を手段と見なしている。後代の教義学はみなこういう見解をとっている。しかしこういう見解によるならば、人間はいつになっても、戒律の完全な実践は不可能であるから、ニルヴァーナはついに実現されないであろう。この詩の原文によって見る限り、学び実践することがニルヴァーナであると漠然と考えていたのである、と解することができよう。
注2;最上の真理――ニルヴァーナ、をいう。
ここでは、、徹底した〈自力〉の立場が表明されている。仏は、人々を救うことができないのである。
7、学 生 ウ パ シ ー ヴ ァ の 質 問
1069)ウパシーヴァさんがたずねた、
「シャカ族の方よ。わたくしは、独りで他のものにたよることなく(注1)して大きな煩悩の激流をわたることはできません。わたくしがたよってこの激流をわたり得る(よりどころ)をお説きください。あまねく見る方よ。」
1070)師(ブッダ)は言われた、「ウパシーヴァよ。よく気をつけて、無所有をめざしつつ、『何も存在しない』と思うことによって、煩悩の激流を渡れ。諸々の欲望を捨てて、諸々の疑惑を離れ、妄執の消滅(注2)を昼夜に観ぜよ。」
1074)師が答えた、「ウパシーヴァよ。たとえば強風に吹き飛ばされた火炎は滅びてしまって(火としては)数えられないように、そのように聖者は名称と身体(注3)から解脱して滅びてしまって、(存在する者としては)数えられないのである。」
注1;他のものにたよることなく――ブッダゴーサによると、「〔他の〕人にたよることもなく、教義にたよることもなく」というのである。
〈宗教〉とは、普通は他のなにものかにたより帰依することだ、と考えられ、またそのように勧められている。ところが、ここでは、他人の権威にたよったり、教義にたよったりすることを否定しているのである。これは偶像破戒の精神に通ずる。
注2:妄執の消滅――ニルヴァーナというものは、固定した境地ではなくて、〈動くもの〉である。前掲の「妄執の消滅を昼夜に観ぜよ」という文章を解釈して、ブッダゴーサは「昼夜にニルヴァーナを盛んならしめて、観ぜよ」という(あるいは「ニルヴァーナを消滅せるものとなして」とも訳し得る)。われわれが、ホッとくつろいだときにには、その安らぎの境地を増大させることができる。それと同様にニルヴァーナを栄えさせ、増大させるか、あるいは少なくとも作り出すことのできるものだと解していたのである。
注3;名称と身体――他の箇所で「名称と形態」と呼んでいるものに同じ。結局、精神と身体とを意味する。
8、学 生 ナ ン ダ の 質 問
1077)ナンダさんがたずねた、
「世間には諸々の聖者がいる、と世人は語る。それはどうしてですか?世人は知識をもっている人を聖者と呼ぶのですか?あるいは〔簡素な〕生活を送る人を聖者と呼ぶのですか?」
1078)(ブッダが答えた)、
「ナンダよ。世のなかで、真理に達した人たちは、(哲学的)見解によっても、伝承の学問によっても、知識によっても聖者だとは言わない。(煩悩の魔)軍を撃破して、苦悩なく、望むことなく行う人々、――かれらこそ聖者である、とわたしは言う。」
1082)師(ブッダ)は答えた、
「ナンダよ。わたしは『すべての道の人・バラモンたちが生と老衰とに覆われている』と説くのではない。この世において見解や伝承の学問や想定や戒律や誓いをすっかり捨て、また種々のしかたをもすっかり捨てて、妄執をよく究め明かして、心に汚れのない人々――かれらは実に『煩悩の激流を乗り超えた人々である』と、わたしは説くのである。」
9、学 生 ヘ ー マ カ の 質 問
1086)(ブッダが答えた)、「ヘーマカよ。この世において見たり聞いたり考えたり識別した快美な事物に対する欲望や貪りを除き去ることが、不滅のニルヴァーナの境地である。
1087)このことをよく知って、よく気をつけ、現世において全く煩(わずら)いを離れた人々は、常に安らぎに帰している。世間の執著を乗り超えているのである。」と。
10、学 生 ト ー デ イ ヤ の 質 問
1089)師(ブッダ)は答えた、
「トーデイヤよ。諸々の欲望のとどまることなく、もはや妄執が存在せず、疑惑を超えた人、――かれには別に解脱は存在しない。」
1090)「かれは願いのない人なのでしょうか?あるいは智慧を得ようとはからいをする人なのでしょうか?シャカ族の方よ。かれが聖者であることをわたくしが知り得るように、そのことをわたくしに説明してください。あまねく見る方よ。」
1091)〔師いわく〕、「かれは願いのない人である。かれはなにものをも希望していない。かれは智慧のある人であるが、しかし智慧を得ようとはからいをする人ではない。トーデイヤよ。聖者はこのような人であると知れ。かれは何ものをも所有せず、欲望の生存に(注1)執著していない。」
注1;欲望の生存に――註解は(欲望の迷いと生存とに)と解する。
12、学 生 ジ ャ ト ゥ カ ン ニ ン の 質 問
1098)師(ブッダ)は答えた、
「ジャトゥカンニンよ。諸々の欲望に対する貪りを制せよ。――出離を安穏であると見て。取り上げるべきものも、捨て去るべきものも、なにものも、そなたにとって存在してはならない。
1099)過去にあったもの(煩悩)を涸渇せしめよ。未来にはそなたに何ものもないようにせよ。中間においても、そなたが何ものにも執著しないならば、そなたはやすらかにふるまう人となるであろう。
1100)バラモンよ。名称と形態とに対する貪りを全く離れた人には、諸々の煩悩は存在しない。だから、かれは死に支配されるおそれがない。」
14、学 生 ウ ダ ヤ の 質 問
1106)師(ブッダ)は答えた、
「ウダヤよ。愛欲と憂いとの両者を捨て去ること、沈んだ気持を除くこと、悔恨をやめること、
1107)平静な心がまえと念(おも)いの清らかさ、――それらは真理に関する思索にもとづいて起るものであるが、――これが、無明を破ること、正しい理解による解脱、であると、わたくしは説く。」
1109)「世人は歓喜に束縛されている。思わくが世人をあれこれ行動させるものである。妄執を断ずることによって安らぎがあると言われる。」
1111)「内面的にも外面的にも感覚的感受を喜ばない人、このようによく気をつけて行っている人、の識別作用が止滅するのである。」
16、学 生 モ ー ガ ラ ー ジ ャ の 質 問
1119)(ブッダは答えた)、
「つねによく気をつけ、自我に固執する見解をうち破って、世界を空なりと観ぜよ。そうすれば死を乗り超えることができるであろう。このように世界を観ずる人を、〈死の王〉は見ることがない。」
17、学 生 ピ ン ギ ヤ の 質 問
1121)師(ブッダ)は答えた、
「ピンギヤよ。物質的な形態があるが故に、人々が害われるのを見るし、物質的な形態があるが故に、怠る人々は(病いなどに)悩まされる。それ故に、そなたは怠ることなく、物質的形態を捨てて、再び生存状態にもどらないようにせよ。」
1123)師は答えた、
「ピンギヤよ。ひとびとは妄執に陥って苦悩を生じ、老いに襲われているのを、そなたは見ているのだから、それ故に、ピンギヤよ、そなたは怠ることなくはげみ、妄執を捨てて、再び迷いの生存にもどらないようにせよ。」
18、16 学 生 の 質 問 の 結 語
1137)即時に効果の見られる、時を要しない法(注1)、すなわち煩悩なき〈妄執の消滅〉、をわたくしに説示しました。かれに比すべき人はどこにも存在しません。」
1146)(師ブッダが現われていった)、「ヴァッカリやバドラーヴダやアーラヴィ・ゴータマが信仰を捨て去ったように、そのように汝もまた信仰を捨て去れ(注2)。そなたは死の領域の彼岸に至るであろう。ピンギヤよ。」
1147)(ピンギヤはいった)、「わたくしは聖者のおことばを聞いて、ますます心が澄む(=信ずる)ようになりました。さとった人は、煩悩の覆いを開き、心の荒みなく、明察のあられる方です。(注3)
1149)どこにも譬(たと)うべきものなく、奪い去られず、動揺することのない境地に、わたくしは確かにおもむくことでしょう。このことについて、わたくしには疑惑がありません。わたくしの心がこのように確信していること(注4)を、お認めください。」
注1;時を要しない法――この文から見ると、ニルヴァーナは即時に体得されると考えていたのである。
注2;信仰を捨て去れ――直訳すれば「信仰を解き放つ」であって、多くの訳者のように「信仰によって解脱する」と解することは、語法上困難である。
「信仰を捨て去れ」という表現はパーリ仏典のうちにしばしば散見する。釈尊がさとりを開いたあとで梵天が説法を勧めるが、そのときに釈尊が梵天に向って説いた詩のうちに「不死の門は開かれた」といって、「信仰を捨てよ」という。この同じ文句は、成道後の経過を述べるところに出てくる。恐らくヴェーダの宗教や民間の諸宗教の教条(ドグマ)に対する信仰を捨てよ、という意味なのであろう。最初期の仏教は〈信仰〉なるものを説かなかった。何となれば、信ずべき教義もなかったし、信ずべき相手の人格もなかったからである。『スッタニバータ』の中でも、遅い僧になって、仏の説いた理法に対する「信仰」を説くようになった。
注3;この詩および前の詩から見ると、最初期の仏教では、或る場合には、教義を信ずるという意味の信仰は説かなかったが、教えを聞いて心が澄むという意味の信は、これを説いていたのである。
注4;最初期の仏教のめざすことは、このように確信を得ることであった。
解 説
■それと同時にこの書は、現代のアジア仏教圏にとっても非常に重要な意義をもっている。例えば、スリランカでは、結婚式の前日に、僧侶を幾人も招待して、祝福の儀式を行う。その場合に僧侶は、この『スッタニバータ』のうちの「悲しみ」の一節、または「宝」の一節、または「こよなき幸せ」の一節、を唱え、つづいて説教を行い、若い二人が新たな人生の旅に出で立つに当っての心得をさとし、祝福を述べる。そのほか人心教化のために非常に重んぜられている聖典である。したがって多分に現代的意義をもっているのである。(439頁)
(2013年4月14日)