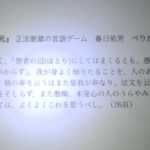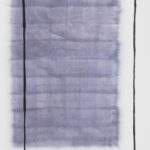『カント』 坂部恵著 講談社学術文庫
■クヌツェンの論理学提要には、まったく経験論的な、(ロックをおもわせると同時に)すでに後年のカントをおもわせもするつぎのような章句がみられる。
「知性のなか、さらには一般的にいって人間のすべての認識のなかで、すでにある意味からして感覚のなかになかったものは1つとしてない。……われわれのすべての認識の源泉は、内的なまた外的な経験である。」
クヌツェンはなかんずく、ニュートンの物理学に関心をよせており、その世界にカントを導いたことによって、これ以後のカントの思考の展開にたいして、決定的な影響をおよぼすことになった。ボロフスキは、つぎのように述べている。
「人の賢愚を見分けることに敏であったクヌツェンは、カントがすぐれた素質を有することに気づき、個人的な談話の機会にカントを激励し――のちにはカントにたいして特別にニュートンの書物を貸し与え、そうしてカントがこうした方面に興味をもつようになると、彼の立派な、豊富に備えられたなかからカントの望むものは何によらず皆貸し与えた。こうしてカントは研究に着手し、研究においてすぐに師をもしのぐようになった。クヌツェンはさらに、自分が植えつけ、なにくれとなく世話をしてきた若樹がひとを驚嘆させる果実をつけるのを見た。と言うのは、大学入学後4年にしてカントはすでに活力の測定に関する著作に手をつけはじめたからである。』(61~62頁)
■カッシラーは『啓蒙主義の哲学』(中野好之訳)のなかで、ニュートンについて、つぎのようにいっている。「――中略――。ニュートンの業績が比較を絶するほど偉大であるといわれたのは、単にその研究成果やそれの目指す目標によってばかりではない。この目標に到達するまでの手続きこそ真に偉大なものであった。ニュートンこそはじめて自然科学にたいして、恣意的・幻想的な仮定から明晰な概念への、闇から光への道を示した人物なのである。
『自然と自然法則は夜のうちに埋もれていた。神が言った〝ニュートンよ生まれよ〟と。――そうしたらすべてが明るくなった。』
このポウプの詩のなかにはニュートンにたいして啓蒙思想が捧げた尊敬の特質が最も簡潔に表現されている。」(62~63頁)
■この著作からほぼ40年ののち、思想的に成熟をとげたカントは、有名な「啓蒙とは何か」(1784)という論文の冒頭で、啓蒙をつぎのように定義する。
「啓蒙とは、人間が自分自身に責任のある未成年の状態から抜け出ることである。未成年の状態とは、他人の指導を受けずに自己の悟性〔知性〕を使用する能力のないことである。自己に責任があるとは、未成年状態の原因が悟性の欠乏にあるのではなく、他人の指導を受けずに悟性を使用する決断と勇気の欠乏にある場合のことである。知ルコトヲ敢テセヨ!自己自身の悟性を使用する勇気をもて!というのが、したがって、啓蒙の標語なのである。」(65~66頁)
■「……晴れわたった夜、星しげき空をながめるとき、ひとはただ高貴な魂のみが感ずる一種の満足を与えられる。自然の一葉な静けさと耳目の安らいのなかに、不滅な精神の隠された認識能力は、言いえざる言葉を語り、感受されはするが記述することのできない解きほぐされていない概念を与える。」(『天界の一般自然史と理論』1755)(76頁)
■と同時に、また一面で、このことばは、これから30年あまりのち『実践理性批判』(1788)のおなじく「結語」で、老境に入り成熟したカントが書きしるすことになるつぎの有名な一句とはるかにこだまし合うものでもある。
「それを考えることしばしばであり、かつ長きにおよぶにしたがい、つねに新たなるいやます感嘆と畏敬とをもって心を充たすものが2つある。わが上なる星しげき空とわが内なる道徳法則がそれである。」(77頁)
■「私はありていに告白する――デヴィド・ヒュームのうながしこそが、はるか過ぐる年にはじめて私の独断のまどろみを破り、思弁哲学の分野における私の研究に、まったく別の方向を与えてくれたものであった。ヒュームの諸帰結に聴従することからは、私ははるかに遠ざかっていたが、それというのも、それらの諸帰結は、彼が彼の課題を全体において考えず、全体を考えに入れなければなんの収穫も得られないのに、その一部分だけを思いついたために生じたものだからである。もしわれわれが、他人ののこした、十分展開されてはいないけれども、基礎づけをもった思想から出発する場合には、考えをさらに先へと進めることによって、この光明の最初の火花をその人に負わねばならぬこの聡明な人の到達したよりも、はるかに成功を収めることを期待することができるのだろう。」
後年『プロレゴーメナ(学として現われうるあらゆる将来の形而上学のための序説)』の序言の有名な箇所で、カントはこのようにいう。(106頁)
■詳しい話は追い追いすることにして、ヒュームのいわゆる懐疑論哲学による因果律批判は、カントが奉じていたライプニッツ=ヴォルフ流の形而上学の構築の要を危くするものであり、その意味で、われわれがすでにみた1750年代おわりのカントの心という重層的な織り物の表面に決定的といってもよい亀裂を入れるものにほかならなかったのである。(107頁)
■「私は気立てからしても学者だ。知ることを渇望し、また、ものを知りたいという貧欲な不安にとらわれ、あるいは、一歩進むごとに満足をおぼえもする。一時期、私はこのことのみが人間の名誉を形づくると信じ、無知な賤民を軽蔑した。ルソーがこの私を正道にもたらしてくれた。目のくらんだおごりは消え失せ、私は人間を尊敬することを学んだ。もし、その尊敬が、他のすべての研究に、人間の諸権利を顕揚するという価値をあたえうると信じなかったならば、私は私自身をありきたりの労働者よりずっと無用な者と考えるだろう。」
すでにわれわれが第1部でもみたこの断章は、1764年初頭カントが公にした『美と崇高の感情に関する観察』という小さな書物の手沢本に、心おぼえのために記された、今日「覚え書き」として知られる断片の集成ののうちに含まれるものであり、カントに対するルソーの影響のあり方をカント自身の口からあかしすることばとして有名なものである。
この断章によってみれば、1750年代のカントの心の宇宙の構築を、いわば上方から打ちくだいたのがヒュームであるのに対して、ルソーはむしろそれを下方から、いわば決定的に風通しのよいものとしたことがあきらかだろう。ルソーは、1750年代のカントに見られた知的貴族主義ないしは学問至上主義とでもいうべき傾向を打ち破り、学者の看板をはずした人間としての人間の広く自由な世界へとカントをつれだしたのである。(107~108頁)
■「青年の教育ということは、本質的に次のような困難をもっている。すなわち、自然的な順序からいえば、訓練と経験を積んだ理性によってはじめて理解されるはずの知識を、悟性の成熟を待つことなく、年月の先を越して与えることを、承知の上で余儀なくされる、ということである。」
カントは、「講義計画公告」をこのようなことばで説き起す。
「〔大学以前の〕学校教育から解放された若者は、学ぶことに慣れていた。いまや彼は考える。彼は、哲学を学ぶであろう、と。だがこれは不可能なことだ。というのは、彼は、いまや、哲学することを学ばなければならないからである。」
「哲学ではなくて哲学することを学ぶ」というこの表現は、のちに『純粋理性批判』にもとり入れられて、今日では大変よく知られているものだが、では、哲学することを学ぶとはどういうことか。
人間の認識は、普通まず、経験から直観的判断へ、そこから概念へと達することによって理性が形作られ、次に、この概念がその根拠と帰結との関係において、理性によって、最後に秩序づけられた全体において、学問によって認識される、と言う段階をたどって発展する。教育も、また、この自然の順序をたどらねばならない。
「まず、経験的判断を訓練し、諸感覚の印象を相互に比較することから知られるものに注意を向けさせることによって、悟性を熟させ、その成長を促進する。この判断あるいは概念から、学生は、より高くへだたった判断あるいは概念へと一気に飛躍してはならず、彼を一歩一歩と導くより低い概念の、自然な踏みならされた道を通って、そこに達しなければならない。しかも、これらすべてのことは、先行する訓練が充分に準備した理解力に応じてなされねばならず、教師が認めあるいは認めたと信じて、誤って聴講者に前提した理解力をあてにしてなされてはならない。」(121~122頁)
■ヘルダーの回想「私は、私の師でもある一人の哲学者を識るという幸運に恵まれました。彼は生涯の最も輝かしい時代において、若々しく、はつらつとした生気に満ちていましたが、それは、私のみるところでは、老年になるまで衰えることがありませんでした。彼の広く考え深げな額は、尽きることのない快活さと歓びをたたえており、口からは、含蓄に富んだ言葉があふれ出し、諧謔や機知やユーモアはたちどころに口をついて出ました。彼の講義は、最も楽しい談話の時でもあったのです。ライプニッツ、ヴォルフ、バウムガルデン、クルジウス、ヒュームの思想を吟味し、ケプラー、ニュートンをはじめとする物理学者たちの自然法則につき従う、それと同じ精神をもって、彼は当時世に出たばかりのルソーの著作、つまり『エミール』と『新エロイーズ』を、また彼の知るところとなったすべての自然科学上の発見を受容し、その価値を認め、そして、つねに、自然についてのとらわれのない知識と、また人間の道徳的価値とにたち返ってきました。人間、民族、自然の歴史、自然科学、数学、そして彼自身の経験が、彼の講義と談話に活気を与える素材であり、およそ知るに価するもので彼の関心を逃れるものはなく、どんなたくらみも、どんな党派も、どんな利益も、どんな名誉欲も、真理の拡大と解明にくらべれば、彼には無に等しかったのです。彼は学生たちに、みずから考えることをうながし、勧めました。独裁主義は、およそ彼の気質とうらはらでした。この人物は、私はその人を最大の感謝と尊敬をもって名指すのですが、イマヌエル・カントにほかなりません。彼の姿を、私はよろこびをもって思い浮かべるのです。」
1762年から2年間、若い学生としてカントの講義を聴き、個人的にも、その詩的才能によって師に深い印象を与え、何かと世話になったヘルダ-(1744-1803)は、後年このようにカントのことを回想している。(125~126頁)
■「……真の徳はただ原則の上にのみ、接がれうるもので、この原則が普遍的であればあるほど、徳はますます崇高にもなり、高貴にもなる。この原則は、思弁的な規則というようなものではなくて、すべての人の胸中に生き、同情とか厚意とかの特定の支えとなるものの範囲をはるかに越えて、広くにまで及んでいる感情の意識である。人間性の美と尊厳との感情であるといえば、すべてを集約したものだとわたしは思う。前者は普遍的な厚情の根底であり、後者は、普遍的尊敬の根底である。そして、この感情がある一人の人の心において最高の完全性を獲得したと仮定すれば、この人は自分自身をも愛しまた尊ぶであろうが、それはただ、彼が彼の広くに及びまた高貴な感情のひろがる範囲の全人類の一人であるというかぎりにおいてのみなのである。」
『美と崇高の感情に関する観察』のよく知られた箇所で、カントはこのようにいっている。(130~131頁)
■この小論のおわり近くで、カントが「私は、人が意志の堕落を心情の病気と呼ぶように、認識能力の疾患を頭脳の病気と呼んだ。また私は心における病気の現象面に対してだけ注意をはらい、その根拠をさぐろうとしなかった」と述べていることから、この著作のもつ性格と位置がほぼあきらかとなる。
すなわち、この著作は、あい前後して書かれた『美と崇高の感情に関する観察』が、「心情」のむしろ価値高い道徳的な側面をあつかうのに対し、「頭脳」ないし認識能力の病的ないしは異常な諸相を叙述する点で、ちょうど表裏の関係、あるいは対極の関係にある。と同時に、それは、「心における病気の現象面に対してだけ注意をはらい、その根拠をさぐろうとしない」という行き方、今日のことばでいえば、因果的説明を排して現象的記述だけにみずからの考察を意識的に限定するという行き方においては、『美と崇高の感情に関する観察』とまったく軌を一にする。(137~138頁)
■実際のカントの講義のあり方についても、伝記者のヤハマンは、つぎのように伝えている。
「形而上学の授業もまた、その対象が哲学の初心者にとって難しいものであったということを別にすれば、明快で魅力的なものでした。カントは形而上学的概念を提示し定義するにあたって一種特別の伎倆を示しました。というのは、カントは、あたかも自分自身がこの対象について考察をはじめ、しだいに新しい規定的な概念を付け加え、すでに試みた説明を段々に修正してゆき、最後に十全な、あらゆる側面から仔細に吟味された概念にたどりついたかのように、聴講者の前でいわば実験をやって見せましたので、真面目で注意深い聴講者はその対象に関して教えられるばかりでなく、さらにそれについて方法的に思索することをも学ぶようになったからです。カントの講義の進めかたを心得ず、最初の説明をすぐさま正しい説明だと思い込んで、注意を弛めずにカントの後についてゆかなかった人は、たった半分の真理をしか刈り入れなかったのした。」(141頁)
■「啓蒙とは、人間が自分自身に責任のある未成年の状態から抜け出ることである。未成年の状態とは、他人の指導を受けずに自己の悟性〔知性〕を使用する能力のないことである。自己に責任があるとは、未成年状態の原因が悟性の欠乏にあるのではなく、他人の指導を受けずに悟性を使用する決断と勇気の欠乏にある場合のことである。知ルコトヲ敢テセヨ!自己自身の悟性を使用する勇気をもて!というのが、したがって、啓蒙の標語なのである。」
1784年12月、既述のピースターの「ベルリン月報」に発表された「啓蒙とは何か」という論文の冒頭で、カントは、啓蒙をこのように規定する。啓蒙が要求するのは自由以外の何物でもなく、ここにいう自由とは、sらゆる事柄において、なかんずく宗教にかかわる事柄において、みずからの理聖を公的に行使する自由にほかならないのだが、現在のフリードリヒ大王の時代は、啓蒙された時代とは呼べなくと啓蒙の時代と呼ぶにはふさわしいだろう。(175~176頁)
■「世界市民的な意味における哲学の領域は、つぎのような問いに総括することができる。
⑴私は何を知りうるか。⑵私は何をなすべきか。⑶私は何を希望してよいか。⑷人間とは何か。
第1の問いは形而上学が、第2のものには道徳が、第3のものには宗教が、第4のものには人間学が、それぞれ答える。根底において、これらすべては、人間学に数えられることができるだろう。なぜなら、はじめの3つの問いは、最後の問いに関連をもつからである。」
カントは、『論理学』の序論で、彼の考える哲学のあらましの枠組をこのように述べている。(191頁)
■さて、われわれの認識の起源と根拠はどうなっているかといえば、認識は、すべて、純粋理性か、もしくはさらに理聖自身によって整序される経験から得られる。
純粋な理性的認識は、われわれの理性によって与えられる。一方、経験的認識は、感覚を通じて獲得される。しかし、われわれの感覚は、世界の彼方にまで及ぶということはありえないものであるから、われわれの経験認識もまた、ただ現在目前の世界のみをその範囲とするものにほかならない。
ところで、われわれは2重の感覚、すなわち外的感覚と内的なそれとをもつゆえに、経験的認識をとりまとめて、世界をやはりこの2つにしたがって観察するのが理にかなってる。すなわち、外的感覚の対象としての世界は自然であり、他方、内的感覚の対象としての世界は、心ないし人間である。
自然と人間とに関する経験は、あわせて世界認識となる。われわれは、人間の知識を人間学によって学び、自然の知識は自然地理学に負っている。いうまでもなく、もっとも厳密な意味でいうならば、じつは、経験というものは存在せず、たんにもろもろの知覚が存在するだけでであり、それらがより集まって経験になるというべきだろう(岡野注;身体の経験、記憶というものがあるのではないか)。とはいえ、ここでも実際には、その経験ということばを、たんにありふれた表現として、知覚の意味で使っていくことにする。(204~205頁)
■今日の教育になおいちじるしく欠けているのは、すでに獲得された認識をいかに使用すべきか、そして自分の置かれた状況のなかで、その知識に見合った役に立つ用途を、いかにしてみずからつくりだすべきか、ないし、われわれの認識に対して実践的なものを、いかにして与えるべきか、ということである。そしてこれこそが、世界の知識にほかならないのである。(206頁)
■世界は、われわれの運命という芝居の演じられる基盤であり、舞台である。世界は、また、われわれの認識が決定され、使用される基礎である。しかし、そこに生ずべきであると悟性の語るものが、実際に実現されうるためには、不可欠の前提として当の世界とという主題の性格が、知られなければならない。
ただし、その場合さらに、われわれの諸認識がけっしてたんなるよせ集めでなくて、1つの体系をなすように、経験の対象が1つの全体としてとらえられていなければならない。なぜなら、体系においてこそ、全体が部分よりも先にあるからであり、これにたいしてたんなるよせ集めにおいては、あらかじめあるのは部分部分にすぎないからである。
この事情は、われわれにおいて1つの連関を生み出すすべての学問、たとえば諸学汎論〔百科全書〕において、あてはまるものであって、そこでは、その全体が連関においてはじめてあらわれるのである。この観念は、建築術的であって、それが学問をして1つの学問たらしめる。たとえば、1軒の家を建てようと思うものは、最初に全体に対する1つのアイディアをいだき、そこからすべての部分のあり方が導かれてくる。というわけで、われわれが現在準備しようというのも、また世界の知識の1つの全体的な観念にほかならない。ここではまた、同時に、建築術的な概念、すなわち多様なものが1つの全体から導かれるような概念を、みずから作り出してゆくのである。(206~207頁)
■しかし、われわれは、自然の経験的法則、すなわち、つねに特殊な知覚を前提する法則と、純粋な、ないしは普遍的な自然法則、すなわち、特殊な知覚にもとづくことなく、たんに、1つの経験における知覚の必然的合一の制約のみを含む法則とを、区別しなければならない。そして、後者に関しては、自然と可能的経験とは、まったく同一である。この場合には、自然の合法則性は、1つの経験における現象の必然的結合(この結合なしには、われわれは、感性界の対象をまったく認識することができない)、すなわち悟性の根源的法則にもとづくものだからである。したがって、私がこの悟性の法則に関して、つぎのように言えば、たしかにはじめは奇妙にきこえるかもしれないが、それでも間違いなく確かなことなのである――悟性は、その法則(ア・プリオリな)を自然から組みとるのではなく、反対にこれを自然にたいして規定するのである。(岡野の考え;しかし、反対に身体はその法則を自然から組みとる)
〔以上の部分は、『純粋理性批判』の「概念の分析論」と「原則の分析論」を含む「超越論的分析論」に対応する〕(268頁)
■さて、勝手に考えだされたものなどではなく、人間理性の本性に根ざしており、それゆえに避けるべくもなく、またけっして終結することもない、この2律背反は、つぎの4つの相互に矛盾する命題からなっている。
1、定立 世界は、時間および空間に関して、始まり(限界)をもつ。
反定立 世界は、時間および空間に関して無限である。
2、定立 世界におけるすべては、単一なるものから成り立つ。
反定立 単一のものは何もなく、すべては複合されている。
3、定立 世界にはに自由よる原因がある。
反定立 何の自由もなく、一切は自然である。
4、定立 世界原因の系列のうちに、何かある必然的存在がある。
反定立 この系列のうちでは、何ものも必然的ではなく、すべてが偶然的である。(274~275頁)
■最初の2つの2律背反は――これは、同種のものの付加、あるいは分割に関するものであるから、私は、これを数学的2律背反と名づけるが――〔自己自身のうちに〕自己矛盾を含む概念にもとづいている。そのことからして、この2つの2律背反における定立も反定立も、ともに偽であることがどうして起るかを説明することにしよう。
私が、時間および空間のうちにある対象について述べる場合には、それは物自体そのものに関していうのではなく――というのは、私は物自体について何も知っていないから――、ただ、現象における物について、いいかえれば、それだけが人間に許されているところの、客観の特別な認識様式としての経験について、述べているにすぎない。それゆえ、私が空間または時間のうちで考えるものについて、それがそれ自体において、私のこの思考を離れても、空間および時間のうちに存在する、などと言ってはならない。なぜなら、もしそう言えば、自己矛盾をおかすことになるだろうからである。というのは、空間および時間は、それらのうちにある現象とともに、なんらそれ自体において私の表象の外に存在するものではなく、それ自身表象様式にすぎず、それゆえ、たんなる表象様式が、われわれの表象の外にも存在するなどと言うのは、矛盾以外の何ものでもないからである。ようするに、感官の対象は、ただ、経験においてのみ存在する。しかるに、経験を離れても、あるいは経験に先立って、感官の対象にそれ自体で成り立つ固有の存在を与えるのは、経験が、経験を離れても、あるいは経験に先立って実際に存在する、と想像するに等しいのである。(岡野の考え;客観世界と、主観世界が境界のないマンデルブロー集合のような形態、構造であるとしたら、上記の論旨の矛盾はなくなる)(276~277頁)
■これだけは確実なことであるが、ひとたび『批判』を味わった者は、すべての独断的なおしゃべりを永久に嫌悪する。かって彼がこのおしゃべりにやむをえず甘んじていたのは、彼の理性が、みずからを支えるために何ものかを必要としたのに、よりよいものを何も見いだすことができなかったからにすぎない。『批判』が通常の学派的形而上学にたいしてもつ関係は、ちょうど化学が錬金術にたいして、あるいはまた、天文学が予言的な占星術にたいしてもつ関係に等しい。私はうけあっていうが、たとえこの『プロレゴーメナ』においてであろうと、『批判』の諸原則を熟考し理解した者は、だれもいつか2度と、あの古い、詭弁的な偽学問にまいもどることはないであろう。むしろ彼は、ある種の喜びをもって、1個の形而上学を目ざすであろう。(281頁)
■すでに『人間学』の解説のところでもみたように、カントは、
哲学《⑴純粋哲学⑵応用哲学》 純粋哲学《⑴予備学――批判⑵体系――形而上学》 形而上学《⑴自然の形而上学⑵人倫の形而上学》
というヴィジョンをもっていたが、(284頁)
■そこで、定言命法はただ1つだけであり、つぎのようなものである。「それが不変的法則となることを、それによって君が同時に欲しうるような準則に従ってのみ行為しなさい。」(312頁)
■さて、結果がそれにしたがって生起するところの法則がもつ普遍性は、本来もっとも一般的な意味における(形式からみての)自然、いいかえれば、それが普遍的諸法則にしたがって規定されているかぎりでの、諸事物の存在を形づくるゆえに、義務の普遍的命法は、またつぎのように言い表わすこともできよう。「君の行為の準則が君の意志によって、あたかも普遍的自然法則となるであろうように行為しなさい。」………
あるものが存在し、そのものの存在がそれ自身において絶対的な価値を持ち、それがそれ自身における目的として一定の法則の根拠でありうるとしてみれば、このもののなかに、ただこのもののなかにのみ、可能な定言的命法、すなわち実践的法則の根拠が存しうるということになろう。
さて、そこで、私は言う。人間および一般にあらゆる理性的存在者は、それ自身における目的として存在する。すなわち、それは、たんにあれやこれやの意志にとっての、任意の使用のための手段としてではなく、自分自身および他の理性的存在者に向けられた彼のすべての行為において、つねに同時に目的とみなされなければならないのである。……
というわけで、もし最上の実践的原理が、ということは、人間の意志に関しては定言的命法が存在すべきであるならば、それは、そのものがそれ自身における目的であるがゆえに、必然的にあらゆる人間にとって目的であるものの表象にもとづいて、意志の客観的原理を形づくるような原理でなくてはならない。すなわち、この原理の根拠は、理性的存在者はそれ自身における目的として存在するということにほかならない。(312~313頁)
■………このようにして道徳法則は、純粋実践理性の客体であり究極目的である最高善の概念を通じて宗教へと、すなわちあらゆる義務を神の命令として認定することへと導く。神の命令とは、この際、聖断、すなわちある〔絶待〕、他者の意志がほしいままにくだすそれ自身偶然的な指令ではなく、むしろおのおの自由な意志それ自身の本質からする法則であり、しかし、それが、それにもかかわらずなお最高の存在者の命令と見なさなければならない類のものをいう。というのも、道徳法則は最高善をわれわれの努力の対象とすることを義務づけるが、われわれがこの最高善を希望できるのは、道徳的に完全で(神聖で慈悲深い)しかも同時に全能な意志によってのみであり、それゆえにこの意志と一致することによってそれに到達することを希望できるからである。それゆえ、ここでもすべては非利己的であり、もっぱら義務にのみもとづくのであって、恐れや希望が動機として根底に置かれることがあってはならない。もしそれらが原理とされるなら、行為の道徳的価値は総じて無に帰するからである。道徳法則は、世界における最高の可能な善を私のすべてのふるまいの究極の対象とせよと命ずる。私が最高善の実現を希望できるのは、しかし、私の意志が神聖で慈悲深い世界創始者の意志と一致することによるほかにはない。そして最高善においては、最大の幸福と最大量の道徳的な(被造物において可能な)完全性とがもっともふさわしく厳密な割合で結合して1つの全体をなしていると考えられるが、この最高善の全体の概念のうちに、たとえ私自身の幸福がともに含みこまれているとしても、意志に最高善を促進するよう指示する決定根拠は、それでも私自身の幸福ではなく、道徳法則(それは、むしろ、幸福への私の無際限な要求をさまざまな制約のもとに厳しく制限する)にほかならないのである。(330~331頁)
■それを考えることしばしばであり、かつ長きにおよぶにしたがい、つねに新たなるいやます感嘆と畏敬をもって心を充たすものが2つある。わが上なる星しげき空とわが内なる道徳法則がそれである。2つながら、私はそれらを、暗黒あるいははるか境を絶したところに閉ざされたものとして、私の視界の外にもとめたり、たんに推し測ったりするにはおよばない。それらのものは私の眼前に見え、私の存在の意識とじかにつながっている。(332頁)
■「今や早速『人倫の形而上学』の完成にとりかかります。でしから、しばらくの間は「一般文芸誌」に何もお渡しできないとしても、どうか今後ともお許し下さい。私はもうかなりの年齢ですし、以前とおなじように種々の仕事へと素早く調子を変えるような敏捷さをもはや持ち合せていません。体系全体を結びつける糸を失うまいとすれば、自分の思索を絶えず凝集していなければなりません。」(シュッツ宛の手紙、1785年)(334~335頁)
■趣味とは、あらゆる利害関心ぬきの愉悦ないしは不愉快による対象ないしは表象様式の判定能力のことである。そのような愉悦の対象が美しいと呼ばれる。(368頁)
■美しいのは、概念なしで普遍的に意にかなうものである。(368頁)
■ある一定の概念の制約のもとに対象を美しいと言明する趣味判断は純粋ではない。(370頁)
■美は、合目的性が目的の表象なしである対象で知覚されるかぎりにおいて、その対象の合目的性の形式である。(371頁)
■ところで、自然の本来の不変の根本尺度は1つの自己矛盾する概念であるから(終りのない前進の絶対的総体などというものは不可能であるがゆえ)、構想力がみずからの総括する全能力をそこでは無益に浪費するような、自然の対象の大きさは、自然の概念を1つの超感性的基体(この基体は、自然の根底に、同時にまた思考するわれわれの能力の根底になければならない)へと導くにちがいないが、この基体は、感官のあらゆる尺度を超えて大であり、したがって、、対象というよりも、むしろ対象を評価するときの心の調和的気分を崇高として判定させるものなのです。(379~380頁)
■ところで、われわれはその対象を恐怖することなしに、恐ろしいものとみなすことができる。つまり、それは、われわれがその対象になんらかの抵抗をしようとする場合をたんに思い浮かべてはみるが、そのときにはすべての抵抗がまったく空しいものにおわるにちがいないと、その対象を判定するような場合である。そこで、有徳なひとは、神を恐怖することなしに、神を恐るべきものとみなすが、それは、神とその命令とに抵抗しようと欲するのは、彼にはおこる気づかいのない場合であると、彼がかんがえているからである。しかし、彼がそれ自体として不可能ではないと考えるそのようなあらゆる場合に、彼は恐るべきものと認めるのである。
恐怖をいだくひとが自然の崇高なものについてまったく判断することができないのは、欲求や嗜好にとらわれているひとが美しいものについて判断しえないのと同様である。(381~382頁)
■切り立ち、突出した、いわば脅かすような岩石、電光と雷鳴をともないつつ天に重なる雷雲、破壊的威力のかぎりをつくしてみせる火山、荒廃をあとに残して行く台風、怒濤さかまくはてしない大洋、力強く流れる高い瀑布などは、われわれの抵抗能力をこれらのものの力と比較して取るに足りないほど小さなものにしてしまう。とはいえ、これらのものの眺めは、われわれの身が安全であれば、それが恐るべきものであればあるだけ、ますます心をひきつけるものとなるのみであり、しかもわれわれはこれらの対象を好んで崇高と名づけるが、それは、これらの対象が、精神力を常ならず高揚せしめ、まったく別種の抵抗能力がわれわれのうちにあることを発見せしめて、この抵抗能力が、自然の見かけの全能と匹敵するという気力をわれわれにあたえるからである。
なぜかというに、たしかに、われわれは、自然の領域の大きさの審美的評価に釣り合った尺度を立てるには、自然は測りがたく、われわれの能力は不十分であるがゆえに、われわれ自身の制限を見いだしはしたが、それにもかかわらず、同時に、われわれの理聖能力においても、ある非感性的な別の尺度を見いだしたのであって、この尺度は、あの無限性自身を単位としてそのもとにもち、それにくらべれば自然におけるすべてのものが小であるようなものであり、こうして、われわれは、われわれの心のうちに、自然が測りがたいものであるときですら自然にたいする卓越をあらわにするのであり、この卓越は、われわれの外なる自然によって脅かされ、危険におとしいれられることのありうる自己保有とはまったく別種の1つの自己保存の基礎となっているのであるが、そこにおいては、たとえ人間はあの威力に敗北せざるをえないとしても、われわれの人格における人間性はあくまでおとしめられることがないからである。こうして、自然がわれわれの審美的判断において崇高と判定されるのは、それが恐怖を喚起するものであるかぎりにおいてではなく、それがわれわれの力(この力は自然ではない)をわれわれの内に呼びおこし、こうして、われわれが気づかうもの(財産、健康、生命)を小なるものと見なし、したがって自然の力(われわれは、財産、健康、生命などに関しては、いうまでもなく自然の力に屈服している)をも、われわれとその人格性にとっては、それにもかかわらずやはり、われわれの最高の諸原則とそれらの遵守ないしは放棄が問題であるかぎり、われわれがそのもとに屈服しなければならないような威力とはみなさないからである。こうして、自然がここで崇高と呼ばれるのは、それが、自然にすらまさる心の使命そのものに固有な崇高さを心に感じうるようにさせる場合を描出するよう、構想力を高揚するという、たんにその理由からしてにほかならないのである。 (382~384頁)
■さて、その現存ないしは形式をわれわれが目的という制約のもとで可能なものとしてみなすようなものの概念は、その物の偶然性(自然法則にしたがう)の概念と分かちがたく結びついている。というわけで、われわれが目的としてのみ可能であるとみとめる自然の諸事物もまた、世界全体の偶然性にとって最大の証明となり、世界全体が、世界の外に存在していて、しかも(あの合目的形式のために)知性をもっているある存在者に依存しており、そうした存在者を根源としているということの、常識にとっても、おなじくまた哲学者にとっても、等しく妥当する唯一の証明根拠である。こうして、目的論はその諸探求の解明のいかなる完結をも、神学において以外には見いだせないのである。
ところで、しかし、このうえなく完璧な目的論といえども、一体何を証明するというのだろうか?それは、たとえば、そうした知性的存在者が現に存在することを証明するのだろうか?そうではない。それは、われわれがそうした世界のある意図的に作用する至高の原因を考えることなしには、われわれの認識諸能力の性質にしたがって、ということは、理性の至高の諸原理との経験の結合において、われわれはそうした世界の可能性をおよそ理解することができないということ以上の何ものをもしょうめいしはしない。それゆえ、われわれは、ある知性的な根源的存在者が存在するという命題を客観的に立証しうるのではなく、ただ、自然における目的について、それをある最高の原因の意図的因果性という原理以外のいかなる原理にしたがっても思考されえないものとして反省するときの、われわれの判断力の使用にとって主観的にのみ立証しうるにすぎないのである。(389~390頁)
■すなわち、それは、自然のすべての産物と出来事を、もっとも合目的なものですら、われわれの能力(その限界をわれわれはこの探求様式の内側に指示することはできない)がつねになしうるかぎりにおいて、機械的に説明すべきではあるが、しかし、そのさい、われわれが理性の目的についての概念のもとでのみまさに探求のために提示しうる産物と出来事を、われわれの理性の本質的性質にかなって、あの機械的な諸原因にもかかわらず、われわれはやはり最終的には目的にしたがう因果性に従属させざるをえないことを、けっして見失ってはならないということである。(393頁)
■【論理哲学論考】における主体
「5・631 思考し表象する主体なるものは存在しない。
〈私の見出した世界について〉という表題のもとに、私が1冊の書物を書いたとしよう。その書物は、私の肉体について報告するであろうし、さらに肉体のどの部分が自分の意志に従い、どの部分が従わないかについても語るであろう。すなわち、これは、主体を孤立化させる方法、というより、ある重要な意味においていかなる主体も存在せぬことを教える方法なのである。つまり、この書物のなかで話題にすることができぬ唯一のもの、それが主体なのである。
5・632 主体は世界に属さない。それは世界の限界だ。
5・633 世界のどこに、形而上学的な主体がみとめられるのか。
君は、眼と視野との関係とまったくおなじ関係が、ここになりたつという。しかしきみは、自分の眼を実際に見ているわけではない。
そして視野のうちにあるいかなるものからも、それが眼によって見られていることは推論されない。……
5・634 これは、われわれの経験のいかなる部分もア・プリオリでないことと関係している。
われわれが見るすべてのものは、それとは別の仕方であってもよかった。
およそわれわれが記述しうるすべてのものは、それとは別の仕方であってもよかった。
事物には、ア・プリオリな秩序は存在しない。
5・64 ここにおいて、独我論を徹底すれば、純粋の実在論に合致することがわかる。独我論の自我は延長をもたぬ点へと萎縮し、残るものはそれに対応していた実在のみとなる。
5・641 したがって、心理学とは異なる方法で哲学が問題とすることができる、自我の意味はたしかにある。
〈世界とは私の世界にほかならぬ〉という宣言を通じて、自我は哲学に入りこんでくる。
哲学的な自我。それは人間ではなく、人間の肉体でもなく、心理学のあつかう人間の心でもない。それは形而上学てきな主体であり、世界の部分ではなくて、世界の限界である。」
認識の主体について、『論理哲学論考』のよく知られた箇所で、ヴィトゲンシュタインは、このように述べる。(447~449頁)
■カント哲学の陰画
「6・52 科学上のありとあらゆる問題に解決が与えられたとしてもなお、人生の問題はいささかも片付かないことをわれわれは感じている。もちろんそのとき、すでにいかなる問いも残っていない。まさにこれこそが解答なのだ。
6・521 ひとは人生の問題が消滅したとき、その問題が解決されたことに気づく。
(まさにこのゆえに、長い懐疑のはてに人生の意味を悟ったひとびとが、その意味が奈辺に在るかを語りえないのではないか。)
6・522 いい表わせぬものが存在することは確かである。それはおのずと現われ出る。それは神秘である。」(449~450頁)
(2011年10月3日)