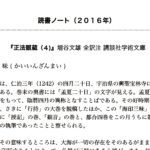読書ノート(2012年)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
『坂本繁二郎文集』 昭和31年 中央公論社刊
■藝術は藝術家の感能性を感得すること能わずして其あつかわれた材料の目を奪はるゝならば敢えて藝術家の感能性を待つ必要はない。之れ等を指して自分は形骸観者と名付ける。情熱的藝術家が一個の石を描いたのを見て彼れ等は冷やかな情熱に乏しい作物だと思ふだらう。多くの画がしかも努力されて並んで居るのに情緒感能の動いて居るのがないとは情ない様な気のするものだ。若し自分の要求が充たさるゝ程の作品が見付かつたならば其前に跪拜する事を辭さない。實に藝術の天地は六ケ敷い事で藝術の天地に動いた作物は滅多にない。世間は藝術を求めて居る。希望はさうなつて居るのに藝術はあべこべに實世間によりていがめられ侮辱せられて居る形なきや。批判と云ふ事を全く去つてしまつた藝術感の貴さは却つて何んにも知らぬ只の素人(かりに名付ける)の間に却つて多く見られる。彼等は幾何(いか)にも奇麗と思つたもの丈けを奇麗とするのだ。此點生なかな藝術社會者(之れもかりに名付ける)の一顧を要するところだらう。或は自分等も藝術の堕落を自覺出來ずに居るのかもしれぬ。(方寸 第4卷第8號〈明治43、12、昭和30訂正〉)(55頁)
■物の存在を認むる事に依つて、自分も始めて存在する。
存在によりて存在する意識は、自分の外には何物もないけれども、物の存在を認むる事は、自他同存でありながら意識には物なる只其事のみである。自分なる者があつては、それ丈け認識の限度が狭くなる。自分を虚にして始めて物の存在をよりよく認め、認めて自己の擴大となる。
此存在の心は、自然力その脈動する意識であるかも知れない。刹那々々のみを、自分たり得る心である。強ひて説明すれば消滅する心だらう。假に一元と名付けるが、茲(ここ)に云う一元は物の力の根原が、自然力と云ふ一原に起因したと云ふ理論の一元ではない。意識の同化である。理論には其意識をも一元と名付くるかもしれぬが、しかし理屈其儘を意識たり得る事の出來ない様に、意識其儘を理屈する事も出來ない。只假定は出來ても、直ちに其れが其事にはならない。眞に其れで理屈するならば、理屈を放れて意識の内に入つて來ねばならぬだろうが、さう云ふ事は理屈の表現では際限が付かなくなる。……只一點の立脚地により、只一方の見得る心は、心愕する程の存在境を意識するだらう。虚は實に逆に一大存在の意識である。此存在は石礫や、虫類、人、或は自分其事に歸するのである。自分なる五體の上にも、適切なる虚其事が脈動して居るのである。或は之れを現存の通り約束せられて居る理とでも云ふ可きか。燃ゆる火が熱いと云ふ約束は、現存の約束に相違ないのである。しかし此約束も現存こそすれ、或る時期に達したときに變化する事なしとは云はれず、現に其れが認めらるゝ意識に相違ないのであるにも係はらず、吾等は其絶對を保證する事は出來ない。斯(しばら)く進行して吾人は現存理外の想定可能に逢着する。一口に云へば自然の力の有を認める故に、之は恐ろしい事だがその無が匂ふ事である。さうして現有の姿が實に確實となつて來る。自分の五體の現肉欲に依りて見たるものは、たつた皮肌的神經の力の範圍である。音も、色も、熱も確かに認め得るには相違ない、けれども自分丈けの事、例へば不透明の物のあちらは見えない丈けの認め方である。それで此神經が動いて居る間は、其れ以外の脈動と云ふ様な意識は隠れてしまつて居る。虚の意識は我利と相容れない。我利も極度に達すれば又別であるが、要するに文字は只假示である。(虚或は一元等假に此の名稱を借る迄である)人體には、自分の肉丈けの慾を充たす丈の神經と共に、意識の慾望と其の可能性が存して居る。若し之がないならば、哲學など云ふ意識探求の喜悦があるわけがない。哲學的進路に眼を圓くして心を引かるゝものがあるだろうか。直接衣食住其事でない、此の道に人が興味を持つ筈がない。或は哲學に無感興の人もあるには相違ないが、其等は根本的に意識力が少いか無いかで、其無い意識を辿る事ならば、無論馬鹿氣た無用事に相違ないから、感興もないだろう。此種の人はそれ丈け狭い範圍に存在して居るので、其人の叫ぶ權限は隨つて狭い範圍しか力が及ばない。怒りと笑ひと泣くのと而して相論ずるときは、必ず喧嘩である。火に手をあてゝ熱いと云ふ意識を、馬鹿として笑ふ事の出來ない様に、哲學の意義は理屈でなく本能意識に於てである。狂とは違ふのである。それが一見非實際なるかの如き形なるが故に、狭い實際場裏に稍(やや)ともすれば無視せられる。しかし哲學意識程、實際界に密接して離るゝ事の出來ぬ意味のものはない。
藝術が、自己の慾望希望に一致するものを得しとき喜悦さるゝならば、虚の現した藝術は總べての人の意識に關係を持って居る何物かの伏在があるに相違ない。所謂達人の藝術が人心と深き交渉を持つところは、虚の意識或は一元の意識に接觸の境地、又は其れに近い或るものゝ存在であると思ふ。一元意識の上に認められた藝術は、(藝術と云つても之れは必ずしも作品の事ではない)其の喜びは衣食住の嬉しさの如くに、限内の喜びではなく、大きな世界に大きな自分を發見した喜びである。之は良心と言つてもいゝかも知れぬ。しかし其神經の發原地は、脈動こそは廣義に通じて居るのであるが、五體の盛衰と共に盛衰せらるゝ位置に在るので、衣食住を無視しては存在されないものである。衣食住の満足が足りた上に、其後に表はれて來る意識界である。此意識に依つて衣食住を超越した境地に入る事は出來るだらう。しかし意識の働きは何處迄も生肉でなければなるまい。
一元意識に住する間は、其脈動の通じ得る總べては自分たり得る境地である。他人は勿論木片草蟲其事の存在を認め、眞に此れを意識し其處に自己を認めたものである。脈動界の其總べては之れ自分の生存である、頭である、血である。其時肉の五體に起る憎悪好醜しないのである。此形を、單に五體主觀以内に住するところから見たならば、何か却つて不足した行動に見えるかも知れない。其形は或る不足があるに相違ないと共に、また只肉の範圍の存在者は只其れ丈けの存在にて、意識の存在なきものは其物の存在も其處にはないのであるから、矢張り狭い半面のみである。かわるがわる此兩面に出入りすることは出來るかもしれないが、同時に住する事は恐らく出來ない事だらう。
一元意識の如く、虚のところに立脚すれば、之れを説明すればする程非虚となつて、立脚地を遠ざからねばなるまい。虚なる事は虚其事で、言ふ事も示す事も出來ない、おのづから會得するところに出現する脈動である。其脈動なる事も存すれば即ち非虚である。而して虚なる事は非情に行渡りたる切實なる存在感に同居する。脊中の痒さを掻いて貰ふとき、も少し上の方下の方とは云へても、直ちに其當體を指す事の出來ぬ様に、偶然に痒いところに手が届いたとき、其處だ其處だとは云はるゝだらう。
藝術品もこの消息が自づから深さ大きさに關連するものと思ふ。哲學に渉つた藝術は、必ずしも人間と關係を保たない方面と、又最も適切な關係の方面とあるだらう。無論人的立場より求むる心の要求には、關係の適切なる方面が交渉するに相違ない。肉的範圍の藝術は、其れ丈け一元的の藝術意識にないところも存在して居るには相違ないが、一元的藝術には、又肉的局限立脚の藝術には及ばないものが宿る。そして之れが世間と云ふところに用事を持つとき、肉的立場のものは狭い近い周圍にのみ關係を持つもので、時代でも過ぎれば直ちに忘却さるゝ藝術であるが、一元的のものは總べて脈動して時代を經た世界に迄、何處迄も関係を持つだらう。斯くして却つてつ尤(もっと)も世間的用事を發揮して來る。之は人間向上慾の大なる一つの方向でこの立場より見れば、人肉限内的慾望は狭い消極の満足にしか見えないだらう。(『存在』方寸 第5卷第3號〈明治44、7、昭和30訂正〉)(56~60頁)
■相逢うてより相別れる迄特別なる印象を以つて自分に現はれて居た其君の顔が、大きな口を開けて無遠慮に笑った、其の吝でなかった心持ちのいゝ気魄、ハッハッハッと笑つた其の意味深き聲は忘れられない。大いに食った揚句、大いに描いた揚句、君は手を敲いて踊つた。『ポゝンのポン、ポポンポポンポポン』之れはいつも直ぐやり出す君の得意の調子である。それを繰り返して足拍子を合する、自分は之れを見るときに、君を尊敬せずには居られなかつた。妙義に登山したとき、夕日に染まつた錦鶏山の頭を望んで、君が大聲に『エヒヨウ』を叫んだのが木魂に響いたとき、自分は寫生の手を止めて只わけもなく胸を躍らした。社務所の2階にⅠケ月餘り丸野君と3人で宿つたとき、山中のシーンとした夜に只藝術の事許り話した事、幾夜さか夜撤(よあか)しした事、曙町の事や、房州に旅行した事など、皆新しい渦巻として頭の内に響いて居る。少年の折の君の優しかりし顔が、僅かの間に鋭く進んで、惣ちに又消えた。其一々の移り行きがありありとして、君が30年の生涯は、態々悲惨なる運命を求めて流星の如く現はれたものゝ様に許り思はれてならぬ。(『逝ける青木君』)(61~62頁)
■時勢や知識は何處迄も横には擴がる。しかし、それは必ずしも感能の深さではない。作品の上では之が屢々混同されて、唯時勢に依って作られた形式の變化に過ぎないものでも、直ちに感能の深さであるかの様に間違へられる事がある。
平面的進行は左程の骨は折れずに、時勢や流行の力で以て、無性者でも働き者でも差別なしにどんどん押しやって仕舞ふ。今日の小學生徒は遊び半分に、14,5年前の大家の苦心惨憺で以つてやつと仕上げた様な事を、御茶の子で仕て退ける。但し多くは平面的丈けの意味での事で、深さの方は時勢や流行と必ずしも倶(ともな)はないから、各自の先天的器量の馬力に依る外仕方がない。だから此方面にレコードを破る程の進行をする人は容易に出てない。(『寸感』)(81頁)
■畫の出來るのは元より物が是認されたときに限られて居る。若し否定するならば繪畫などとは無論縁が切れる。
しかし是認と云ふ事には自づから否定が裏付いても居る。其れは丁度否定の心理が即是認である様に、吾人の心は在るとか無いとか云ふものが常に遠心力と中心力との様に連絡を保つて居る、それで心の働らきと共に物の見え方なども餘程位置が違つて來る。例へば麥の生えて居るのを見ても、只麥が生えて居ると見た丈けでは其れ丈けで終へる。麥は麥吾は吾で明々白々ではあるが、只其れ丈けである。けれど1度麥なるものが否定され出すと、其次に麥は確かに麥に相違なき働きが一層感ぜられて來る。此否定は自づから心に迫って來るもので、理由は何う云ふものか分からない。例えば或る物を敲く場合に、只當てた斗りでは其れに障る丈けで打當る迄にはならないけれど1度他の一方に振り上げて打下ろすと強く打當り得る様な工合である。屢々(しばしば)人が善を善と知って、しかも之れ丈けが自己の行の總べてだと極めて満足して居る様な場合に起る反感の如きもので、之れは一寸事は違ふけれど要するに同じ意味になると思ふ。吾等は善人に反感を持つ事を普通の心では不条理とも見えねばならぬが、一面に此の動かす可からざる或る物は根強くより眞
實を求めんとする心に陰(かく)れて居るから仕方がない。(『思って居る事共』)(84~95頁)
■畫をかくからには誰れでも何かつかむところがあるには相違ない、しかしつかむと云ふ事は其處に悲哀がある。畫を描くからには何か機縁がなければならぬだらうけれ共、希望より云へば、つかむと云ふ事は仕度(したく)ないものである。つかまずして現はれたものならば、まだまだ自己の信(ママ)實の形を見得る丈け我慢も出來る。自己に意識しない進行には、詭(いつは)りのあり得様がないからである、意識して歩を進めると云ふところには、多く或る不滿が倶なひ勝である。意識は智的になり易い、知らず知らずにも本能感得の純を妨ぐる事があるからである。其かと云つて意識なしに進む事は事實される事ではない。偶然の結果以外に其れは期待する事は出來ない位置である。それでさうなると進路は只一筋の羽目から羽目を進まぬわけに行かない事になる。今羽目から羽目に行かねばならなくなつて居ると思つたら其處にはもう其羽目の信實は消失するわけである。此處に羽目から羽目の道がいや應なしに開けて居ると思はぬわけに行かなくなる。此の心も亦直ちに捨てられねばならない。
要するに新鮮と知とが相容れない形を持って居る間、吾等の進路は是が非でも此の無理な形に居ねばならぬ。此處に不斷足の裏に火の燃えて居る悶々が起る。知は何處迄行ったところで盲に追ひ及ぶ事が出來ない、盲は又知に従はねばならぬ、困った形なのである。吾等は批判の心を要すると共に、愈々(いよいよ)歩を進める時は盲に就かぬわけにはいかぬ。盲智に依って新鮮の世界に接する以上のいゝ道を、今の處思ふ事が出來ない。若し一を知って其儘一に居たならば、其處にはもう堕落の第一歩が芽ぐむであらう。知って其儘居るのは安逸である、其うして安逸に居るには此の世界は餘りに勿體ない。進む可き唯一の信實の道は、かくて盲に就いて得る捨身本能覺の道しか開けては居ない、止むを得ず吾等の最上の難有い位置は只默々の裏に迎合するのみにならぬわけに行かないのである。
批判の上からは色々と價値の上下も出來得るけれども、創作進行者には實際難有いものゝ外に難有(ありがた)いものゝ有り得様はない。(『進路』みづえ〈大正3、1、昭和30訂正〉)(100~101頁)
■中毒と云つても、一度作品となつたものが他に與へるところには大した事はない様なれど、作する事、筆を握る事には努力の結果などに中毒が起る。
画家は却つて畫の見え方が片寄り易い、正當な觀察は局外者の方が却って確かだ、などゝ云ふ空気を或る一方に作つたのなども、畫家の内にさう云はれても仕方のない事實があつたからに相違ない、現在にもある様だ。畫家なるが故に却って他のいゝものが見えないとは馬鹿らしい話しである。此んな矛盾した事が當り前にあるわけがない、之れは畫家自らの畫に對する考への至らない結果としか思はれない。枝葉事などに捉はれて畫の根本義を忘れたり、多年の間に自ら第二の天性などが出來たりした結果だらうと思ふ。此れを目して、畫家自身の境地に忠實なるものゝ必然に起る不可避のものだとされて居る向もあるが、自分はそれを認める事はない。不可避のものがあるなら、云ふ迄もなくそれは其畫家の至らぬ事を意味するに過ぎない。
一寸(ちよ)い一寸いした枝葉や、好き嫌ひの相違は無論ながら、いゝと云ふ事は例へそれが形式的に遠く東西に相分れて居るやうなものでも、火と水の様に根本的に迄相扞格するものでないのは云ふ迄もない事である。宗教が宗旨の是非を取つてこそ一歩も相下らずとも、其眞理の向ふ希望に於て相一致する如く、畫の力も形こそ多様なれ、いゝと云ふ事には自づから共通に近接すると思ふ。いゝ事をいゝとなし得ない不明なる自己の偏した歩調から、畫も中毒に足踏み入れた事になる。
努力とか硏究とかは半面常に却つて危險が倶(ともな)ひ易い、強く進めば進む程一度誤つた場合となると其中毒も一層となる。個性の發揮なども云はばただ中毒の有るなしに歸すると云つてもいゝ位だらう、つまり中毒がなければ個性も出る。畫が正常に身について育つ人ならば、進めば進む程個性は延び、明瞭となり、又其正當の當然の結果として、他に對する理解も開らけて來るのが當り前であると思ふ。此の行處は『だから』とか『でなければならぬ』とかを外から強ひるよりも、自己の歩調が自づから自己に道を開らく、行く可きところに自づから自信が現はれる。何よりも自己を欺かざる事が其道を得る尤賢なる態度だらうと思ふ。眞理を蹈む事は只自己を欺かざる事丈ではなからうか、そして其道を蹈み得しものは、いゝ事をいゝと自づからなし得る様になると思ふ、畫は覺(さと)る外ない。
大抵の人が畫の稽古を始むると一先ず下手になる。下手になる斗りでなく以前よりは下等な状態をすら呈する。あれなども云はば中毒の一つであらう。一度下等になつても一時丈ならばいゝが、それが一生其人から離れないで、畫をやる様になつたが故に却つて本來の自己自然の心をいがませ妙なものにしたらしい人も居るのを、感ぜしめらるゝのはなぜだらうか。畫作と云ふ事の困難、自己意志の發現不充分等が形式的に此現象を呈して居るのならば、實に愚も及ばざるわけである。努力や硏究やは危險が付随し易い、畫は描けば描く程、愈々(いよいよ)素躶であればある程にいゝ畫も近づくのだと思ふ、正直以外に道なし。
又吾々は畫筆を握る故に一面畫から面を背けても居ねばならぬ、繪畫以外の世界は却って密接に繪畫のあり方を暗示又一致共動もして居る、物事の眞實大切なのはその知覺、其處に生まれて來る繪畫が何よりも動かす事の出來ない眞(ほん)ものとして自己にも生きて働いて呉れるのだと思ふ。(『畫の中毒』みづえ〈大正4、4、昭和30訂正〉)(121~123頁)
■感激、總べての事は只この此一事に盡きる、理屈はない、感激が事實であるならばそれはそれで眞であらねばならぬ、感激は要するに事實の眞であらねばならぬ。
優れた位置と云ふ様な形式に知らず知らず進む事がある、さう進む事に或る嬉びがうつかりすると働くけれども對自然の生活味は位置の様な形式ではない、只感激丈である、其證明丈である、それ故に無智の幼年も感激に於いて老年者の上に立つ事が出來る、生活味が強いのだ、それ丈高價と云つていゝ、複雜とか廣さとかの價値は横に擴がる計りである。
感激を有する者は感激故に進む、此行處は只其れ丈け故の其れ丈けである外に何物もありはしない、世の中が轉がらうと破れ様と此心を何うする事も出來はしない、それ故に段々一方的に深入りもして行く。
微妙と熟練は加はりしもそれは必ずしも感激の高潮ではあらざりし故に思った程向上の結果を現はさなかつたのだ――但し珍又は新故の高潮なるものがある、それと自己本能と自然との動かす可からざる關係の高潮とがよく混同され易い、旅行でもすると見るものが珍らしく高潮をなす、しかし其高潮は只場合の高潮のみに過ぎないのが大分ある、珍らしさ新らしさ故の高潮は只面白さや或る別な快感の心等只の動感で此の意味でならばおどろかされて喫驚したのも感激になる、しかしそれ等の感激は感激の内容が違って居る。
尤も高潮適歸せる自己と自然との力の交渉は常に只一線の上にある。例へ複雑にても眞實に於て一線の上にある、そしてその意味では益々クラシカルに又宗教的に共鳴ともなる、所謂正直の頭に神宿るもの、此一線の進行はそれ丈深き意味を生ずる。深遠の境地の如きはさうなつた上からでなければ開けはしない様に思へる、一國一民族が段々築き上げた藝術が容易に一個人力の及び難き大きな境地を現出する如く、即ち必然性の發見。
此根本の何物であるかが意識に入らぬ人が感激の行處に迷ひ屢々(しばしば)中途より忘れた様に力點のきまらない敢果(はか)ない藝術の衰に入るのではなからうか、要するに彼は血気一つの馬力で兎も角は持つて居たのだから血気のなくなると共に消えるのだらう、本來必然の線に立てる者ならば中途からさうぼけはしなからう様に思へる、自己によく結合を有するならば世の中のすべてとも自づから結合すべきものに相違ない。
感激とそれに倶(ともな)ふ誠實良心何れも兄弟分である、人の顔に露骨に現はれるものは誠實の有無である、そして彼は其處に彼の感激の有無を語つて居る、専門家の相貌には従つて藝術の有無も大抵顔に示されて居る、誠實なくして藝術の事を云々する者に對する程心持のわるいものはない。
要するに感激の有無は直ちに善心の有無と云つてもいゝ様である。
感激の事實を有する者からその誠實を引きのける事が無理である如く、感激なきものに誠實を求むる事も無理である、誠實は何處迄も内容の事實に倶ふものであつて誠實の外形のみを装ふ事は許されない。
感激の消滅する事は人世から存在を辭する事である、あらゆるつまらない堕落の情念は感激のなくなるところに住家を有して居る、感激と云ふ事のいかに貴きものであるかを思はざるを得ない。
作品の消えざる意味なるものは此の感激の働ける故に外ならぬ、感激を作品にする以外に藝術の作品はない筈だ、其の感激を無理した努力感激のない只の馬力で出來た作品之等は皆折角出來ても反古になる作品である、感激は何うしても事實の眞に相違ない、感激の何物であるかを味得された者ならば情理共に味得されたものとしてもいゝ筈だ、貴といものは實に感激である。(『感激』みづえ〈大正4、9、昭和30訂正〉)(126~128頁)
■斯う云ふ企は面白い事だと思つて見ました。茲(ここ)に集められてある作品は代表的作品許るではない様ですが、兎に角古るいものから順々に並べて一處に見る事になると、色々の意味で反省を與へられます。殊にはつきり示されて居るのは今更でもないが、畫中の眞實性丈けが時代を超越して力である事で、其當座丈の豪さうな作品や、實在と交渉のうすい畫は、時代の前には頭の上らない事が暗示されて居る。それから眞(ほん)とな意味の永遠性の外に、單に風俗畫報的又は寫眞的に骨董的に交渉して來る永遠性に似て非なるものもあるのなどを面白く見ました。沿革と云つてもさう大した時代の相違ではないから、變遷と云つても僅かに未だ畫の解釋や技術上の事が少し斗る推移して居るのが示されて居る丈けで、非情な變化は見る事は出來ないけれど、兎に角推移の跡は見えて居る。しかし集まれる作品が代表的なもの斗りでないから、其點望蜀のこころから遺憾でありました。(『日本水彩畫會の沿革陳列を見て』)(137頁)
■村山君の畫を最初に見たのは、まだ同君の12か3位の頃山本鼎君のところに送られた繪葉書を見せられたときで、其れは一見尋常ならざる英気芽生のはみ出して居る、之は只者ではないと云ふ心持に打たれたるものでした。其時驚歎した事を覺えて居ます。其後數年にして君の畫は東京の展覧會に見らるゝ様になり、前の記憶があるので自然君の畫には注意を引かるゝ様な事になつて居ました。そして段々見て居ると君の畫は益々赤爛れのした様な色彩、血の流れ落さうな花の色、思切つて奔放な構圖、中には畫がうまからうが拙からうが其んな事にはさまで頓着されて居ないかの様になへ思はるるものもあるのを見て、之は少し期待と反した、何だ之は單に元気に淫して居るのみではないかと云ふ少し気乗りの抜けた心持ちになりました。そして其元気には感心しつゝも餘り其等の畫を好みませんでした。之等の奔放さは熱烈的ではあるかも知れない。然し私自身とは少し他處になつて居る熱烈で、刃物を直ちに向けらるゝ様な怖れの來ない、何だか對岸の火災の如きものに思はれました。之れは私自身の或る曲がつた感情がなす業かも知れないが、私には或る種の聰明さ、強さ、それが只體力的處産に屬するものであるとき、直接生々と嬉しさを受付けられません。其等に自づから倶(ともな)ふ快濶率直元気等を無論嫌ひではありませんが其れは間接的に私の心を嬉ばせる程度で、私の性分として尤も直接的に親しみを感ずるのは、熱烈を包んだ冷静にある様です。其んな方面を見出すと私の心も握手を求め度(たく)なるのですが、君の作品には此冷静が足りないと思はれて居ました。其れは寧ろ君の方が自然であり、率直であるかもしれませんが。それで君の作品の中でも人物よりも風景に、又作の態度でも君が思ふ儘に描き荒れたものよりも、單にモデルを追究し、率直に風景の如き無情物に對して其其奔放性が手放しにならずに居るところに、私の同感は動きます。其等の作品は熱烈が祈願を示して居るからです。畫以外の君の平常に就ては嘗(かつ)て只1度或る用件で遇つた斗るで何にも知りませんでしたが、先日の兜屋に展覧會で其目録にある諸氏の文章や話しを聞き、始めて君の他方面の事をも少し知つたのですが、兎に角君は畫を愛しては居たに違ひないが、畫以外に尚幅廣きものがあり、畫の中に全心が入つて仕舞ふと云ふよりも、君の或る行程から畫は放射されて居たものではないでせうか。君と畫との關係は恰(あたか)も排泄物が排泄さるゝ様に、君は畫慾を掃き捨てつゝあつたかの如き傾向ではないでせうか。只現在丈けのあるがまゝであつたらしいその色彩も形も自然の中に自己の投影を凝視したと云ふよりも、只見えた儘に興じた儘に描き捨てたところがあり、其畫は随分皮肉らしい圖柄もあつても少しも其處に批評は見えない。2人の男が片手を各々擧げて居る畫の如き、一見ムンクの畫などを連想されるものであるが、其持つ感じは自然の剔抉(てきけつ)と云ふ風ではない。君に自然があゝ見えたとは受取れるが自然があゝであると云ふ威壓は來ない。此畫に限らず他の乞食と女の畫其の他此感じは同様のやうです。君は又一二の展覧會に出品して居るが、其れは君の我儘の發揮さrた方のを多く撰ばれてある様ですが、先日の遺作展覧會で見ると却つて其等のものよりも出品されないである方により同感を持たるゝものがあつた様です。君としては冷静よりも奔放が自然であつたからでせうか。(『村山槐多君の藝術に就いて』みづえ〈大正9、2〉)(146~148頁)
■美術院の佛國の作品紹介は難有(ありがた)い事であつた。天覽會場に入る前から心が緊張する。よい藝術に對する止み難い憧憬である。恐ろしさに體を固くしながら場内を一巡二巡三巡と繰返へす。更に四巡五巡としかし最後に残った心持ちは何だか淋しかつた。此淋しさは何處から來るか。其等の作品がつまらないのか、其うではない。然らば何處から來る淋しさか。一方に頭の中では斯んな事を考へ始める、藝術の行付く最後の事など浮んで來たりして。
ルノアの前に立つ。大家の投げて呉れる恩惠のあり丈けは一滴ものがすまいと子供が母親の乳にしやぶり付く様な心持、しかし乳は澤山出て來なかつた。呑み方が惡るいのか口が届かないか。セザンの前に立つ、矢張り物足りない。ドガの前に立つ、矢張り物足りない。全部幾度繰返しても矢張り物足りない。此んな筈ではないがと自分の頭を疑つたりして更に考へねばならなかつた。
ロダンとルノアの作品に何となく慣用的表現を感ずる。始めて知るマチスの一々の自然に絶對的交渉が目立つ。マネエの流石に旨い美しい色。其等の中にピサロは一番親しく握手が出來さうな日本語を發して居る事。
要するに此淋しさは餘りに過大な期待を持つた反動なのか、其れとも國民性的相違からか。山本君の云ふところを聞けば巴里當りに往つた當座一寸其んな気がするが段々數多く見て居る内に奥の知れない味が分つて來るのだと。して見ると矢張りまだ自分がわからないのだらうか、願わくばそれであつて欲しい。其れでないなら餘りに藝術の淋しさがなさけなくなる、しかし一方之は國民性的相違もあるに相違ないと思ふ。そして改めて周圍の友人達の畫を考へる。そして其處に一層親し味の深い事に改めて気が付く。誠に日本の畫だと云ふ感じである。復製で見ると連想なども手傳ふのだらう、西洋の作品とて其れ程違つては思へなかつた様だつたが實物を見ると其點が目立つ様である。尤もルノアの作品などは一二前に見た。しかし要するにそれ等は片鱗隻影で迚(とて)も作家を充分知らるゝものでないとして居たが、今度のルノアは揃つても居るし其作中でも悪るくないものと云はれる。何だか淋しい気がする。更に気が付く事は何うも根本的に藝術の要求に幾分の違ひがある様である。早く云つて見れば吾々の心持ちよりも科學的行動がより多く容(ゆ)るされて居る。ルノアにしろロダンにしろ又セザンにしろ仕事臭いと云ふ事を其れ程気にしては居ない様である。道を藝術の上に取つた者としては其うなるのが當然ではあるが、しかし自分の心持から云はせて貰ふならばそれは理屈で、願(ねがは)くならば慣習的自然にはなりたくない。比較的マチスかピサロの方により同感が動く。自分の心には何うしても作品には一々新たなる詩を要求される。詩と云ふと少し語弊があるが文字の詩ではない。對自然の新鮮な最初の心である。自然に對して可成(なるべく)習慣的行動をきらふ筆触でもさうである。所謂惡るい意味の畫かきになり度くはない。科學的筆觸、頭のよい事に於て西洋人から教へられては居るが其れは嬉しさの最上のものではない。兎に角豪らいものには引かれろけれ共同じ引付けらるゝ内にも心から難有(ありがたく)引付けらるゝのとそれ程でなく引付けられるのとある。今自分の心は之等大家の作品に接して却つて或る淋しさ不安さと云ふやうな疑問が殘つて居る。(『佛國の作品を見る』みづえ〈大正9、10〉)(149~151頁)
■西洋人の作品は畫面の大小に不係(かかはらず)精神的に根本が社會意識衆意識になって居る。日本人の畫はまだ過去の習慣現在の生活感から家庭的個人的味がつきまとつて居る。大味と小味の原因がここにもあるようだ。日本人の畫は展覽會場に置くと少し落付き惡(にく)いのもある位。西洋人の畫は最初から會場的意識である。
日本の畫でも昔から、襖や、屏風の畫はやゝ衆的で大味だ、掛物も大幅になるとやゝ大味だが、多くは個人的生活感に立脚され又鋭さ純一さも、其處に嚴敷(きびしく)要求されて來て居る、匠気とか下品とか云ふ點に潔癖である事恐らく日本程嚴敷(きびしい)ところは他にあるまい。此の目で睨まれたら西洋の畫で助かる作品は少ないだらう、吾々には無意識の裏に此個人自分の心、云ひかへれば既に一種宗教意識化した希望が潜んで居る。その要求が充たされない作品には、容易に頭は下がらない。サロンドウトンヌの會場を歩いても、斯う云ふ自我から眺めて廻はるならば、下品でいやな畫、第一畫作の態度が根本に卑しいのが鼻につく。生存競爭などの結果もあらう、下品なものが大聲で廣告して居るやうなのが實に多い。信念の主張でなくして、商賣兢爭の浅間しさになつて居る、しかし濁流の中に揉まれても大水の中に自づから大魚居る如く、巴里の畫界には何としても日本よりは大物が居る事は事實である。色々の點で之ぞと取立てられないにしても、暗示は受けられる、表面あまりに多き藝術に神經麻痺の形がないでもないが、矢張骨は大きい。(『雑感』みづえ〈大正4、10〉)(180~181頁)
■新藝術の魅惑はしきりに吾人をそゝる、現代思潮の流れは何物も同様に押流そうとする。若し理解すると云ふ事が直ちに向上を意味し得るものならば現今の状態は何と解したらよいか、時代思潮は何物も押流す力はあつてもそれは必ずよいものとは極つて居ない。場合によつては時代に逆行する覺悟もなければならぬ、しかし此事は難事だ、時代に乗つて之にこびて居るものは兎も角も時代と共にあり得る、ピカソの如きは此點に於ける親玉だ、だが時代にのらぬものは大凡つぶされる、現代は特に時代の力の暴威が見える、そして此アンデパンダン(先年巴里に開かれたアンデパンダンの展覧會)の如きもそれに引ずられて居るのではないか、之れはアンデパンダンに限った事ではないが會の性質と國別陳列によつて特に此會の主義其ものと反對のものが皮肉にも最顯著に語られて居るのを見て改めて反省させられたのである、恐ろしき時代風潮の感化力。(『境遇の感化』みづえ〈大正15、1〉)(186頁)
■之迄西洋美術には色々とよい事を教へられ今後とも尚教へられるゝところは多いでせうが大凡西洋美術の、殊に繪畫の輸入時代はもう仕舞へました、最早吾々は自己の力によつて立上がる可きときになつて居ますが西洋の畫――と云つても佛國を中心として云ふのですが印象派以後根本的な大事な人間を忘れた禍根が未だに惰力的に進行を續けて居り此情勢を助長させたのは實に彼セザンヌであり次でピカソなどと思ひますが、現代佛國畫界の常に歸趨(きすう)するところのないたうなちからの据わらぬ原因は茲(ここ)に眼の届かぬ苦しみを意味して居ると思ひます。徒らに主義方法が重視され過ぎて居る。若し未來派式の見地からすれば、人間などゝ云ふような意識其事も既によくない保守の塔とさるゝかもしれませんが、吾々の生活は保守と生長との結合に力ある建設は見らるゝ筈です。嚴敷(きびしき)意味から云へばいくら保守して見たところで吾々の生活は刻々に新陳して居る、人間の一生はいやでも新陳し又いやでも保守である、根本的に新たなるものを求むるならば別人の次の時代でなければあり得ない、一個人の生活を無理に新しく刻々に押進むるのだつたら單なる分裂に過ぎぬ、自個と云ふ一固形の運命は其當然の保守が根とならねばならぬ、新しさはただ後天的の努力にしか容るされない、そこに建設も可能であり人間の深さも有意義となる、人間相互の補助ともなり得る、徒らに根據なき浮草の生活に建設は豫期されない。一と頃ピカソは現代のミケランゼロと云はれた事がある、又マチスはさながらビンチの描法を取り入れた、立體派となり未來派となり新古典とかはつてもそれが根本的の意義を外れて居ては遂に方法的の循環にしかならぬ。之が大凡現代佛國の状態と思ひます。(『之からの道』アトリエ〈大正15、2〉)(189~190頁)
■陰鬱な巴里の冬もやつと通過ぎてやゝ寒さもくつろぎ、鼠色の佛國は佛蘭西と一變して、長い籠居から郊外へ郊外へと人は飛出す。自分もやつと獨で汽車にもどうやら乗れるやうになつたので、もう矢も楯もたまらず巴里から逃るやうに佛國の西海岸クロアジックに向つたときは全く久々振りに蘇生するやうな心持がしたが、生憎にも夜汽車の空が次第に明けはなるゝのを見ると、あやしげな天候で車窓の硝子のは雨つぶがぽちぽちとかゝつて居る。窓から見らるゝ珍しき田舎の光景も陰うつにして折角の旅行も前途不安、愈々(いよいよ)クロアジックに着いて汽車から下りると、細雨霏ゝ(ひひ)と云ふ有様、兎も角も村の中央にある小さい宿屋には入つて天候恢復を待つ事にしたが、中々雨が止まぬ、翌日も翌々日も降りつづく眞に寂寞の雨が霧の如く只一つしかない窓の先を斜に流れる。來る日も來る日も四日目になつても晴れそうにない、折角の林檎の花も之では雨に散仕舞(ちりしまひ)になりそう、氣は氣でない、殊に旅先で降りこめられのやり切れなさにとうとうたまりかねて、雨中ながら外に出る。
雨傘で景色の見物である、海岸に足を向けると遠淺になつた海上には遠くの方迄岩の頭が點々と並ぶ、陸地一帶小山續きの平野で、雨の海は糢糊として淋しい。漁村の人々も雨籠りで外は人影も稀である、其翌日も雨に加へて風迄更に加はつて來たがもう絃を放れた矢のやうになる、觀念して風雨の中に七つ道具かついで飛出す。窓際に編物などして居る村の娘や、お婆様たちが此變な雨中の黄色のエトランゼーをけげんな目付で眺める、泥路を雨風と戰ひながらあちこちする、ひゆうひゆうと雨雜りの風が横なぐりに顔を打つ、しかし特別な場合の光景は苦しい中にも又快感がないでもない。海は暴れ雲行いよいよあやしくなる、天候をしきりに警戒して居る係員らしい男が、小高い物見の岡の上から沖の方を見て居る、沖には一隻の船影もない、たまたま景あるも風曝しでは畫架が立たぬ、物蔭を利用さるゝところではさう旨くは景がない、だが何うしても此まゝ引返へす気にもならぬ。矢張り珍らしさに引ずられて先から先をうろうろと雨をよけて立てば風に、風をよけると雨に木の下蔭は雫され人には見られ疲れ亡者のやうな姿を運ぶ。或廢屋の片蔭に風をよけてぬれながら辮當の牛鑵を開く、ぬれパンを嚙る、雨のしづくが襟首に鑵の中に、憂き事の尚此上につもれがし、戰へ戰はと自らはげましては一と口、はげましては一と口、吾ながら悲惨だが止むに止まれぬ意志だ、雨中にさまよふ鬼のやう、宿の主婦は恰もマリー・ローランサンの畫が抜け出したやうな風貌の持主、悄然とぬれて歸つた自分を見てムッシュウ此天氣に何處へ仕事に往つたか、海岸へ、オーと眼を見張つて肩を寒いと云ふようにすぼめる。此村は避暑地で宿も夏季の客を主に待つて居る、今はまだ其時期でないので空き部屋斗りが並ぶ。吹きすさぶ雨風の音も窓を〆ると陰陰として物音がない、静かさはよいが蜘蛛の巣のsりさうな部屋、主屋とは中庭一つ隔つた自分の一室に引取て夜は豆ランプ一つ、幽靈のやうに吾只獨灰色の壁に對す、達磨になつたつもりで瞑目しても追付かぬ、獄中生活が想像される、色々の事が徒らに頭の中を往來する、襲ひ來る憂鬱に壓倒されまいと反抗する斗り。翌日も雨の音、窓を明けて見ると向ふの屋根には朝日が光つて居るのに軒先をかすめて雨雜りの汐風が矢張りひゆうひゆうと悲鳴を擧げて居る、顔を洗はんとして水盤の前にかがむと鼻から鮮血がさらさらと滴り落ち盤中眞赤となる。血の止まるのを待つて又外出、もう度胸は据つて仕舞つた、強行軍が何處迄遂げらるるか天気と根比べだ、強風中の寫生のとほらぬ無理にこりて、今度は剥らの家に風をよけ、道路の片蔭に畫架を立てる、冷たい雨の雫と時々は霰も雜じる、全く氣違日よりだ。雨合羽の漁師が木靴でがぽがぽと通る自分の姿を見付けてムッシュウと云つて天を指して驚いたと云ふ顔を見せたりする、何でもかまはない、やうやう畫の具を半分塗りかけたとき、砂をつんだ牛車を追つてやつて來た一人の男、場處もあらうに今冩して居る直前にがつちと立ち止まり、さらさらと其處に砂山を築いて仕舞つた。眞に天無情、惨として云ひやうもない心持、すごすご中止、ぬれたトワル(キャンバス)を提げて再び宿に歸る。
入口の盤臺にいつも鎭座するローランサン夫人、ムッシュウ御覽なさい、まあ大變にぬれた肩を、あまりに無理をすると病氣する、休めやすめと云ふ、無理とは知つても外に仕様も無い田舎の旅の空、止むに止まれぬ衝動だ、室内に居ても心は矢張り死んで居る、まだ雨曝らしでも外に立つ方が心やりになる。
トワルを改めて更に出なほす、海邊には無人の別莊が幾つも立並ぶ、一つ一つ個性を見せた家が暴れ狂ふ海に對して居る、空き家は却つて家其物に不思議に生氣あるものゝやう、轟々と遠淺の岩共に押寄する浪の音が暗たんとして壯大なり自然其物の合奏曲を作つて居る。磯には浪に打揚げられた烏賊を拾ひ歩く子供の姿がうろつく、吹きつのる風と止んだり降つたりの雨、斯う云ふ場合でなければ見られない壯觀である、遮二無二又も風中に畫架を立てる、トワルは帆布の如くあをり立られ沖の方からは更に黒雲が雨を垂らして襲ひかゝる、斯うなると一種悲壯な氣持になつて仕舞ひ何處迄無理がとほるかとほらぬか、もう畫作よりも試練である。トワルの耳にはひゆうひゆうと風が鳴る。だがいくら踏張つて見ても風は無際限に吹いて來る、いつの間にか心身底冷が喰入つて來る、氣分は次第に變になる、醉つたやうになつて居た氣持もさめて漸く不安になる、何としても無理はとほらないのだ、千載一遇の光景も遂に見捨て止むなく畫架をたゝむ。せめて手帳を擴げると萬年筆のインクは雨に打たれて紙面怱絞り模様とかはる、最早云ふ事はない。頭斗りは火のやうになつて體は氷のやうに冷え切つて疲勞と冴えと憂鬱との混亂、宿に歸ると食事の時間はとうに過ぎて居る。腹の底にこたへるみじめさ、サーバントに食事を頼むとムッシュウあまりに時間が過ぎた、もう用意がない、オムレッ位ならばと云ふ、それで澤山だ、がらんとした食堂の片隅に自分獨りの食事、之でも特別の御なさけである。オムレッの一皿に申わけ丈けの腹をやつと濟す。深閑として居る牢屋のやうな一室の扉の前に立つと、吾部屋ながら中にはお化が待つて居さう、かちやかちやと云ふぁ手先の鍵の音が氣味悪るく響く、失敗のみじめなトワルは首くゝりのやうに恨みを呑んで壁にぶら下がる、豆ランプの覺朿ない光に自分の顔を鏡に映し出すと之が自分かと思はるゝ憔悴と角立つた意志の醜悪さ、翌日もしよぼしよぼと呪はれ切つた雨の音、愈々(いよいよ)無理が崇つて其朝はやゝ熱を帶た頭がふらふらとする、もう何としても斷念の外はない。折角意氣込んだ荷物を片付けるのも力なくとうとう悄然パリーに歸る。毎年此天候は此地方での例になつて居ると後で知つたが異境不案内の悲哀だ。アトリエでモデルを充分吾物につかひこなすのも一と骨だが旅行先の仕事は一層天祐なしには旨く行かぬ。
日本に歸つて二科會に自分の畫を並べたとき何だか詩のやうなものが胸裏に往來した。『私のタブローが並ぶ、泣きもせず笑ひもせず死人の眼玉のやうに眺むる人々に對して居る。私獨の胸の裏にはタブロー一つ一つの思出が悲痛、夢、自嘲、泣笑ひ、墓地の死骸の如くくらすみに折重なる。だがタブロー共の表情は泣きもせず笑ひもせず喜怒なきマスクの如く静寂の世界にある』。(『畫作難』マロニエ〈大正15、2〉)(192~197頁)
■今度二科出品の多くの畫に接して、全體に旨い畫が多くなつて居ると思ひました。色々の方向に色々な努力がされて居る。只しかし大體に於て、其旨さの割合に、やゝ必然性の缺けて居るのは物足らぬ思ひです。しかし此事は、二科斗りでなく現代的一面の傾向と思はれます。明治大正の名畫展を私は見ませんでしたが、人の噂によると、昔の作品の方がよかつたなどゝ云ふ人が多い。美術が發達して居る筈の時勢と矛盾したこんな現象は、つまり必然性の有無から来たものと察せられます。いくら上手に旨くなつたところで、必然性のないのは根本的に力はない、必然は人間本然の希望だから、之は如何なる場合もそれがないと云ふのは卽ち嘘である。必然性の稀薄な、上づつた社會の潮流の中などに居ると、作家もつい其勢ひに押流されたりするのであらう。凡そ作家自身は一生懸命で必然を追つて居るに違ひないのであるが、それでもいつの間にか社會の潮流には流されるのであらう。だからいやしくも作家たるものは、超時勢的達眼がなければならぬ。今日では水彩畫も技法の進歩から他の畫法との間にはつきりした境界がなくなつた程だが、水彩のやうに筆觸に一層其成立が托されて居るやうなものが、今日の如き旨さの發達と共に發達するのは當然でもあるが、一面又時勢の弊を受けて居る事も爭はれぬやうである。必然さと云ふ事は直ちに社會との交渉を意味される筈だ、道樂の如きものでもそれが必然性の上に立脚されたものである程、意義がある筈だ。必然性のないと云ふ事は作家としての耻辱であり、社會から見れば餘計な仕事にしか過ぎないのであらう、つまりカンバスや畫の具や努力の浪費に過ぎないのだ。(『必然性が割合に缺けて居る』みづえ〈昭和2、10〉)(200~201頁)
■寫實も色々であるが君の寫實は實相的であり寫實である、其物感にしんとした味野あるところ餘程クールベーを思はせられる、其色彩にありても何處か相通じたものがあるやうに思はれる、日本人の寫實には大凡寫實が寫實になつて居ないで何處かに一幕かゝつたものが多い、此點で硲君のは珍しく其鏡面はよく拭はれて隅々迄はつきりと澄んで居る、君は嘗て君自身の視覺について疑ひを抱き、永い畫人生活を一擲して彫刻に移り度いと云ふやうな希望を漏らされた事があるが、君の色覺がそれ程異狀であるとは私には思へない、尤もずつと以前の深川あたりの寫景時代にありては、墨つぽい色や青黒い色が慣用された事もあつた様に思うふが、滯佛當時のものにありては、見える可き色はちやんと描かれて居たと思ふ、クールベーにしても同様實相的な作家にありては、單に色彩計りが實相から離れて飛躍されないのは當然で、其色彩には常に物感が裏付いて居り、其邊の制限からたとへ色の見える人にありても色彩の跳躍が出來ないと云ふ點も考へらるゝところである、繪畫に於ける物感は凡そ畫である限り何程かは必らず裏付いて居るに相違ないが、人によりて物感の厚薄は甚しい相違がある、中には殆んど物感など無視されたものもある、しかし其いかによき色彩の趣味性であり明確らしい線條が引かれてあるとしても、それに物感の裏付いて居るものがないならば、それ丈け物足らぬものであり作家の趣味又は主觀的意志以上の生活感は稀薄となる、物感は特に作家の本能的個人的なもので、形や色の如く人間相互の感化傅習が容易でない、趣味色彩も勿論個人的なものではあるが、物感に比すれば遙かに共通消長のものである、物感はそれだけ畫者個人的生活感の實證が裏付いて居る、時代思潮や趣味やを超越して、尚且つ今日の人にも働きかゝるものをもつ、古代作品の如きは作家の偉かつた本能物感の働いて居る力に因るところが深いのである、永遠性の如きは物感の裏にあるとも云へるのであらう、物感もしかし色々で單に物感が濃厚と云ふ丈けでは寧ろ醜悪を催す、鋭どく優秀に咀嚼されたる本能が藝術に化合した物感でなければいけない、露國や獨逸あたりの畫によく見らるゝやうな咀嚼されない惡寫實はたまらない、つまり低能なる本能物感は論外である、物感があるとそれ丈け畫面も重々しくなり易い、上品なさつぱりした作品には物感のない、つまり消極的に上品なものも多い事である、日本人の作品には之が多い、つまり畫よりも字を喜び描いたものよりも布地の染模様を喜ぶ心である、畫家のそしつによつて物感にあまり要がなく、描寫の問題にしても色や形其物技術其ものにのみ關心してあつさり片付いて居る人は多い、畫から文學を撥無する事を早解して畫を單に畫模様的範圍に止めて居るやうな人も或はあるであらう、近代佛國畫壇の行づまりの如きも、要するにタブロー上の技巧的思索關心に過ぎて、物感的本能のほうが營養不良になつたのではあるまいか、勃興時代の作品は物感の脈搏が凡そ盛んだが、世紀末的になる程技巧が之と入りかはる、技巧の練達思想の新奇を誇られても、物質的實質が之に裏付いて居ないのでは、遂に問題が問題ともならないのである、東洋畫の如く氣韻墨色精神に重きを置かれ、一見物感と云ふ如き實形を超越された如きものでも、其事實は矢張り畫面の墨色に裏付く物感なくして何の表現でもあり得ないのである、氣韻も精神も物感に確實性があつての上の事で、よい作品になればなる程此事は明らかに實證されて居ると思ふ、紙本に於ける墨色床の間との調和等の上から、表現の約束が自づから東西洋の畫風を甚敷(はなはだしく)別趣にして居るけれ共、繪畫成立の歸するところにかはりはないであらう。寫實の力強さは直ちに筆触色調と共に物感に作家のメスの刃先が触れるところにある、之迄に冩實以上に出ようとする各種の運動は方々に飛躍を試みられはしたが、今のところ此本格さを壓倒する如き本道が外に現はれたのをまだ見る事が出來ない、繪畫の約束が視覺をとほして現はるゝ本能にある限り、此眞理を跳躍して百尺竿頭更に歩を進めるのは至難であるらしい、遂に之に満足し切れない者は、繪の具以外の物質迄を利用して畫の領域外に走つて行つた、豫覺は色々とつい其處にちらついて居ながらも中々到達する事が出來ない、丁度瀧の下迄寄せて來た魚群が尚上流に水の暗示を受けながらも瀧にせかれて混沌として居る形で、新しい運動が色々と動いては立消えて、矢張り寫實の本道に立かへるやうな有様である、寫實と云ふ事も單に理論にのみ考へると結局妙な事に歸着しなければならぬけれ共、之が畫人の本能に依つて解釋さるゝとき始めて意義が光つて來るのである、だから寫實の味覺なき人が單に理論的に寫實を形通り進めたとしても、それは結局よく徃つて寫眞機械位のところであらう。
硲君にありては此實相が本能的であるところに生命がある、多くの人は寫實に徃かんとして寫實以外に到りついて仕舞つた、君にありては落付くところが實相になつて居る、君は情に厚く友に優しき人であるが其道念に就ては犯す可からざる意氣を藏す、必然的に本格的である君の歩みは恐らく將來とも益々發揮さるゝであらう。
そして如何なる方向に更に進展さるゝとしても此寫實がそれに裏付く事によつて眞實の力を強めるであらう。(『硲(はざま)君について』アトリエ〈昭和5、6〉)(214~218頁)
■繪畫の健全性と云ふ問題が、改めて日本の畫界に起つたのはつい最近時局下に入つてからの事で、最近『或る種の不健全な傾向は遠慮せねばならぬ』と云ふことが云はれるやうになつて、一部の作家を間誤つかせたものである。
ではその禁制の『不健全』と云ふ意味を作家としての良心にどう解釋したらよいものか、これが作家の間には今も漠としたまゝになつて居るやうである、これは又反射的に『健全性を如何にすれば進め得らるるか』の意味にもなるのである、近代繪畫が個性を尊重するやうになつて以来、繪畫は畫面の獨立した美の問題を問題とひたすらするやうになり、色々な傾向の違つたものが簇簇と現はれて來た、畫面の美である限り、如何なるものをも美としての有用性を主張出來るわけともなつて『われ斯く感じ表現せり、それが人に解されようと又解されまいと、それは人各々各自生活の相違から來る事で仕方ないのである』とかいふ論理も一面成立分にである。
しかし、其結果作家自身以外の人には了解出來ないやうなものも當然視さるる形となつて居るのである。このやうな態度は、作家としての良心に一應撤したものではあるかも知れないが、これは近代佛國畫弾に現はれて居る思想外形的匂ひでもある。
畫壇の間にありては、健全性と云ふ如きことは餘りに分り切つた事であつて、且また、これはたヾ或る感じの上の事で抽象的なものであるからであるが、この健全性と云ふ感じは一個の作品だけを見る場合にはあまり目立たぬもので、或る數以上の作品、一團體、一畫壇、または一國の傾向と云ふやうに擴大さるゝ程この様相は顕著になるものである。
近代佛國畫壇の様相の如きは健全性の寧ろ反對でどうも不健全性と思はれるやうなものが多分に見られ『こんな事でよいか』とさへ思はれる程であつた、もつとも、これは二十年も前の私の體驗であるが、その當時色々と顯はれていた『立體派』とか『未來派』とか『野獸派』などと外形だけは色々華やかで、日進月歩の形であつても向上の實質は、必ずしもそれと添はないやうで、つまりあまりに方法的變化のみであつて眞實の響きが足らぬ思をされていた。
それらの主張も事實その後大した結實もなく、改めて古典に取りすがるやうな形が顯はれたりして、それ等佛國畫壇の狀勢はやがて來る可き佛國の運命を暗示して居るものとすると誠にこれは恐ろしい事である。
健全性には『眞實』『愛念』『熱意』等云ふやうな向上性が自然に附随せる現象であつて、單に上手下手と云ふやうなものとは違つた性格、興国的なものを暗示したものである。
健全性はか様に性質として重大な意味を持つものであるが、個人作家心理にあつては自覺され惡(にく)いものであるらしいのである、意識せざる裏に過誤をも犯す事になるのであらう、これは誠に機微なる魂の含みの問題であつて、出發點は殆んど同位置に見えたものでも此の僅かな性格の相違から來る進行結果の相違は甚だしい隔りともなるものであつて、前に述べた思想『わからぬののは仕方がない』として分かり惡い畫も當然として描くのと『是非分からせねばならぬ』と云ふ意志、何れも理路は殆んど同出發點であるが、意志の含みの僅かの相違から結果に於いて雲泥の差ともなるのである。
作家としては此邊よくよく考えねばならぬ大切なところと思ふのである。前者は或る程度以上周圍と無縁のままともなるが、後者は全人類への結合を指向する。自然に表現法も内容意義もそれに相應して發展し、大きい線となつて伸展するのであらう。
内容自體は勿論個性の上に立つものでも表現様相はここでは必然エスペラントに重點が進むであらう、前者にあつては個性特長等矢張りそれ相應の形に止まり、發展性は人に解され悪い範圍丈け狭い事にならねばならぬ道理である。
この創作眞理が何れにあるかは俄かに斷定されないが、これが單に一個人の上の事に止まるのであれば問題は小さいのであるが、全畫壇ひいては一國家の情勢にも連なる事になると問題は重大である。
日本畫壇の現在は、誠に見様によつては人類始つて以来の藝術上えらい機會に抱かれて居つて、西洋美術を吸収した東洋美術の生ひ立ち、過去及び將來の世紀を通じ再びこのやうな情勢はあり得ないだらう世紀の山を辿りつゝあるのである。
昭和16年12月8日、この偉大なる世紀の日以來、日本の國勢は計り知られぬ雄大な相貌を呈して來た、國勢と藝術が一致するものであるならば天平、桃山、の過去日本藝術の最高峰を更に遥かに抜くものとならねばならぬわけである。
今日の日本の作家はこの偉大なる情勢に壓倒されないためには餘程の逞しき輪廓、骨格、足踏を必要とされるのである。そして表現意志の如きも『わからぬものは仕方がない』と云ふ理窟に安居せず『何處々々までも徹底明瞭にわからせる』藝術を押し進め、世界人類の隅々まで意志は通ずるものと豫期してさしつかへない筈と思ふのである。
ここに健全性の如き性格も顯現されて來るのであらう。世界的藝術を目指すものであつたならば、かういふのが當然の性格、姿だらうと思ふのである。以上只アトリエ内にての一畫人としての考へで私の自戒とも致し度いところである。(『繪畫の健全性』福岡日日〈昭和17、3、17ー21、昭和30訂正〉)(249~253頁)
■此頃ダヴィンシの書いた芥子園畫傅的な著書の譯本を讀んで居るが聽く可き事を色々云つてある。「根源を究めずして學技を弄するものは梶なくして羅針盤なき航海に等しく、何處に着く可きやを知らず、實技は常に深き自然探究の上に建てざる可からず』『書物を一瞥して、其全體細部迄究め盡す能はず、例へば本を開きて紙上に視線を投ずるとき、最初様々の活字の充満せるを知るのみ、その内容は一字々々を辿つて後判斷する事を得、山の頂きに到るには一歩々々を重ねて後に達する事が出來る。畫に於て物の眞髄を知り、個性を知り、その特徴を充分頭脳に収めて、そらんずるに到る迄は、第2の仕事に着く可からず。然らざれば徒らに時間の空費多かるべし。畫は第1に常住勤勉急ぐ可からず』『自然のうちには原因なき結果なし。原因を究めよ、筆技の事自づから法あらん』『理論は實驗なき科學』『畫は大なる鏡にうつる自然の如くならざる可からず。名匠たらんには、自然の與ふる美を殘る隈なく描き盡し得る技術を知らざる可からず。汝の心に先ず自然の美を深く刻むに非ざれば此一事なり難し。』『何人も作畫の當初にありては、誤りあるを免れず、此時にあたり自然の妙諦を會得するに非ざれば、その誤謬を斧正する事も叶はず、先づ眞體に徹して過誤を批判せよ。最初より準備規矩を以て臨む如き安易なる態度は、一作遂にまとまる事なく支離滅裂に終る可し。』『よき解釋は、自然の原理、不變の法則を捉へる。之は一りつの準縄規矩とは以て非なるもので、眞の法則は各自實驗が生み出す愛嬢であり、また繪畫の母である。』こんは風だ。此本にはペラダンと云ふ仏文學者の讀後感も所々に入れてある。それには『ジョコンダは生けるが如しと雖も、生きたる肉體の再現ではない、此畫のモデルになつたモナリザは、疑ひなく美人であつたに違ひないが、セリメータの如く、崇高幽玄なるルーヴルのジョコンダではなかった。』などゝ書いてある。現本はヴァチカンに在るさうだ。ヴィンシがフローレンスのアカデミーで生徒に教へた講義録ださうだが、今日の畫論としても結構だね。
今春ポチパレーでは、プーサンからコロー迄の風景畫が展覽された、プーサンもクロードローレーンも實に澤山の鉛筆畫を勉強して居るのに驚く。その外にコロー以後現代迄のものがルウヴルの工藝美術館で催された。又ベルネイムジョンでも之に似た催しをしたが、之は寄せ集めたもので、シャンとしたものではなかつた。チェイルリーの現代展はまだ見ない。畫かき仲間、批評家仲間、美術雑誌新聞等々、現在も全く迫力なし。庭の草花の方が確かに養ひになる。どうも近代のだれ方は世界的ぢやないかな。何か暗然たるものを感ぜざるを得ない。つまりダヴィンシの云ふ根本の勘所があやしく徒らに方法許り氾濫の形だ。凡そ一國の文化が一たん向上しながらそれを次期時代に持ち越して進む事も出來ず、下向して仕舞ふ如きは理屈にあはぬ話だが、此の根本狀態は云つて見れば良知の消長で、良知の根本なくしては科學も衆の力も無意義となり充分に生きないので、止むなく下向線となるのであらう。
日本の場合にして見ても、能樂にしても、藝道にしても、足利時代からずつと下り坂で、只光悦等の後を追ふ許りとは寧ろ不思議な位、能樂興隆の恩人世阿彌は、作曲も脚本もそして出演も、自らの一手によくし、全組織の立體的成就者であり、見物群集心理迄、つまり自他一如の總合藝術を成し遂げて居る。その美貌であつたと云ふ事迄何だか日本の小ダヴィンシを思はす。天才と云へば何だか特別に平凡人の近づき難い位置にある人のやうだが、要するに之も眞髄知覺の有無に過ぎないのだらう。世阿彌も云つて居るやうに、遠く高く、及び難く見える彼岸でも覺つて見ればほんの一寸した違ひだと、その一寸した違ひがしかし、一國文化の高下を因し、時代の大衆と相關しつゝ文化を押し進めるのだらう。徒らに賑やかであつても其實質之に倶はなければ矛盾の現象も出て來るのだね。(『友人よりの古い書面』西部美術〈昭和21、5・6月合併號〉)(263~266頁)
■此の畫を描いた頃の思出としては現在の事情とは随分違ふものであつた。特に地方田舎のそれ等の狀態が頭に浮ぶ。藝術等と云ふ如き改つた觀念は普通一般人間には縁なきものゝやうに見えたものである。畫作も當時は寫生其場仕上げが唯一の方法になつて居た私は此百號のカンバスを現場にかつぎ出して寫生したものである。農家の軒下にカンバスを立てかけて寫生を始めたところ、經師屋と間違へられて襖の張りかへを頼まれて面喰つた。此村は附近に皿山の窯業地をひかへ、焼物類が色色村中に轉がつて居て興味を引かれた。木賃宿が村の出外れの往還端に一軒在つたのを幸に其家に一週間程滞在して出來たものである。畫中の人物は、同じ宿に滞在して居た盲目の女按摩を頼んでモデルになつて貰つたものだが、下を向いて居るので盲目の顔は見えない。此畫の外に百五十號のカンバスも用意して櫨畑の寫生を別に取りかゝつたが、第一日はどうやら描けたが二日目から少し風が出て宿から寫生場所迄カンバスを運ぶ事が出來ず、非力の私はカンバスに當る風に引摺られて動けず馬鹿を見た斗りで此方は遂に止めて仕舞つた。盲目蛇で只矢たらに描き度い斗りであつたものだ。私の行動は此村では不思議なものが降つて湧いたやうに見られたらしく警官の注意迄引く事になり、私の宿の居間に不意に警官に立入られたり、寫生中に話しかけられ調査を受けたりしたものである。その頃の気持には生きて居る内には現在の如き藝術認識時代が日本に來ようとは全く豫期の外であつた。それ丈けに今日になつて思ふと當時の二十代頃の畫學生氣心が思出の中に目立つのである。つまり洋畫では衣食出來ない事が今日とは比較にならなぬはつ切りして居る時代、それを承知で各地から出京して來た學生である。私のお世話になつた小山先生の不同舎の畫友も、それだのに何れも申合わせたやうに貧乏者が揃つて居たのは何か皮肉な感じさへある位、各思々のアルバイトでさゝへて居た。少し遠出の寫生には無錢旅行や野宿もする行者にも似た精進が競はれたものである。其等の人々は今日畫人としては消えて多くは行衞も不明である。明治時代頃は周圍が周圍であつたので畫人は畫人同志でないと分らぬものがあり、畫學生同志の人間的意志の共鳴は切實なものがあつて、以前は知らなかつた人間らしいものを此間に教へられた悦は今も忘れられない。(『「北茂安村の一部」につき』國立近代美術館ニュース〈昭和30、7〉)(291~292頁)
■もともとただ一人の兄が京都の第三高を出るのが小生一家の唯一の期待で、卒業すれば兄が私を何とかしてくれるというようなことでしたが、その兄が中途で病死しましたので、小生も一時は途方に暮れ、學校も當時の高等小學校を出るのがやつとでありました。このような狀態で繪の研究に上京するのは、どだい不合理滅法で明かに冒險で、ただ行けるところまで行つてみるばかりで、ただもう畫を描くこと以外は一切の希望を自然に捨ててしまいました。しかし何と云うても母が小生一人を頼りにしているという矛盾は自分に迫つていますから、絶體絶命でありました。自分一人なら橋の下や立ん坊にもなれるが、そんなわけで全く捨身でした。自分のような者が他にあるのだろうかと思いおりました。しかし不同舎に入つてみると、友人はそれぞれ似たり寄つたりの人々だつたので、自分のことなど當り前とわかり、妙な安心をしたものです。
こんなふうで東京へ一人出ても、母が田舎でひとり寂しく待つているということで絶對的に尻を叩かれ通しで、貧乏に對して臆病だつた私は、却つて捨身になつて消極的に我慢をする習性がついたようです。ですから、その頃私は、生きるということはどこまで行けるか行けるところまで行つてみる試しだ、というふうに思いおりました。(『幼少時代の囘想』〈昭和30、12、18談〉)(303~304頁)
■時代の先頭が決して追ふ者に期待さるゝ筈なく自ら往く者の力にのみ待つ可き筈なのに兎角批評家などが一般的に早分かりさす為か新しい表現の外形式を問題にする傾があるので輕薄な畫家は誘惑されたりする事になるらしい。
時流を追ふなどは自ら世間より後れて居る事を自白するものです。尤も時代の空氣を呼吸する事は必要に相違ないが此ところの微妙な相違は自ら進む者にはよくわかる筈でしょう。――中略――抑々作家でありながら時代と共に行く事を喜ぶなどは云ひかへれば意氣地のないわけで作家は宜敷(よろしく)いつも背後に時代は持つ可きです。つい氣焔になつて來ましたが此位の抱負は持つて居て然る可きと思います。(井上三綱氏宛書簡〈昭和4、9、9〉)(318頁)
■小生はセザンを認めないのではありません。只セザンのように一切が見へるのならセザンにはなり度くないと云ふのです。セザン位徹底した行き方には小生も賛美を惜しみません。又あのつめたい美しさも認めます。しかしセザンの如く自然を無機的に見做さずともまだとり當然なそして高い世界はある筈と思ふ心持です。セザンが若しアングルとかルーベンス位でも其畫境が吾々より遠い位置でしたらそう迄批難を投げる氣も却つてないでしようがつまりそれ程セザンは近々と働きかゝるところがある故にまだまだと押しのけずに居られぬわけです。少し無理な例へですが強いて云へばセザンは法律の眼でものを見てゞも居るようでそれよりは佛心で見た方がより當然さと大きさ深さがあるように思はるゝ心持です。没我的な人が應物の自在性を有する事は御説通りと思ひます。之について丁度よい例があります。或る學者が大人物を分類して『英雄型と偉人型の二つに區別し英雄型は自己本位で敵手は勿論自己の好まぬものはじゆうりんして仕舞ふ。身邊は好きにまかせて金殿玉樓をつくり其周圍は常にさんらんとして居る。ナポレオンや秀吉の如きがそれでつまり何處迄も自己肯定である。然るに偉人型は自己否定である。常に自己の缺點をのみ反省し之でもいかぬまだまだとして進む。一見平凡である。其實質が天下の大學者であつても尚及ばざらん事を恐れて行く。身を持するにも草屋布衣に甘んじ愛他は益々擴大する』と云ふのです。右の事は丁度畫家の自然に對した態度にあてはまると思います。英雄的な天才で自然を見た畫家の内尤其一長一短を露骨にして居るのはクールベでしよう。つまり彼の天才は自然の實相をあれ程捉へて居る程であるのに其才を自由自在にのばした半面には途方もないうそを無邪氣に曝露しても居る。つまり自然に對していつの間にか不遜となり忽ちにして實相力があべこべに裏切られる事になつて居る。彼の畫集を開くならば到るところに其破たんは見出されるでしよう。岸田君などはやゝ之に似たところがあると思ひます。岸田君と云へばつい最近なくなられた新聞を見ました。何とか云つても惜しい人でありました――
ミレとかピサロとか云ふ人々は偉人型の方でしよう。つまり没我的に應物されて其裏に一層の生(ママ)きが得られてある。之をセザンの場合にあてはめるならば英雄型と偉人型と半々に備へて居るとでも云ふ可きか。セザンの自然に喰付いたところは謙虚さがたしかにあるが他面彼は頑固に自然を型にはめて押しても居る。或はセザンに云わすれば此押しの信念はセザンを生かしたところかもしれないが第三者として見るときセザンに對する不滿のところもその邊に根源がある氣がされます。
つまり主觀的な押しも客觀的な没我もそれは何れにしても作家其者の性情本能の如何によつて是非の歸着は決せらるゝ事でそれを外にして單に此兩態度の是非は云へないでしよう。貴兄の云わるゝやうに「セザンの如きは何物も同じように描きはせぬかと小生の迷いに候」とありますのも若しセザンと同じ態度を持する人が外にあるととして其人の性格本能次第では或は其態度がよい結果をもたらすかもしれないし又人によつてはわるいでしよう。つまり筆者の本能の問題で態度丈けでは是非されないでしよう。
自然に對して謙虚でないと自然は決して見へないのは凡そたしからしいですがそうかと云つて全く没我になつて仕舞つては之も仕方のない事になる筈でよい自我は押して行く可きであるがそれを押し過ぎると罰が當るのでしよう。客觀主觀と云ふ事は容易に外からは云へない事で作家の本性生れつきを解ぼうでもして見ない限りわからない事で例へセザンにしても客觀的とも云へるし又主觀的とも云へましよう。ビンチにしてもそうです。つまり作品に現われた形について實相的とか想像的とか云ふ事は云へましようが主觀か客觀的かとは簡單には云へない事でしよう。ミケランゼロとダビンチの仲の悪るかつたと云ふのはつまりどちらからでも近々と働らきかゝるものがあり合つて却つて反撥したのではないかと想像します。つまり兄弟喧嘩に類するものです。ミレーとコローの如くです。――よい作家は一切をよく知り又容れ得る。しかしながら愈々(いよいよ)自己燃焼の場合となると當然一路(3字削)境地となる。此消息でしよう。御手紙の最後にある『自己に歸着する慾を出してはいけないと云ふのか』の御質問もつまりは前述の如く作家の生まれつきによる事でしよう。――しかし理想的な狀態なるものを假想するならば自己慾を充分に發揮してもそれが立派であると云ふならば之に越した事はないわけでつまり英雄的に進んでしかも英雄的缺點がないならばそれは自然人的神人的狀態と云ふ可く大乗でありそして小乗であり得て居るものでしよう。畫を描くにも出來る丈け自分に歸着する慾望がよい意味に生きるのならば大に自欲を進む可きではないでしようか。問題は此よい意味かそうでないかを判別さする知慧にありましよう。(井上三綱氏宛書簡〈昭和4、12、24〉)(320~324頁)
■つまり小生は時勢的と云ふよりも常に根本的を土臺として行き度いのです。例へば構成と云ふ如き事も勿論考へて居るつもりですがつまり小生がやゝ保守と見られ易いと思はるゝ點をかりに云つて見ますれば小生は何處迄も實體を解決し度いのが目的です。勿論實體と云つても比較的に過ぎぬのでありますが例へば線を入れて描けば割合に一見さし當りはよく解決され感じも出出來上りもきびきびして行くやうな場合でも線と云ふものは可なり主觀的なもので後日になつて見ると案外それが畫をうすつぺらにして居る場合が多い。つまり實體的追究より外れて早く畫になり過ぎる恐れがある故小生は畫面構成等の事についてもすべる事を要心し度いのです。勿論線を絶對に捨てるのではありません。しかし又一面美術的繪畫的興味的又藝術的とも云ふかしいて云へば畫面的の面白ささう云ふものの存在もあるのだから(勿論切り離して考へられない事ですが比較的です)大にそう云ふ意味の造形趣味に筆を雄健に揮ふのもよいに違いないのだから特にそう云ふ方面に才を持つて居る人が適者適處に筆をふるふのは當然でよいと思います。しかし小生自身としては實體に届くメスを常に問題とし度いので思想も描寫も之から外れたものには單に參考以上に深く引かれるわけには行きません。更に云へば見方はあまり問題にして居ないのです。見へ方を問題とし度いのです。現今の仕事は多く見方斗りの變化で其實大して變つたものが見へて居ないので外形程に働らきの事實は平凡であるのが物足らぬのです。しかし勿論見方も一つの方便だから實質が實際見へて來たら問題とし度いと思います。(井上三綱氏宛〈昭和5、9、19〉)(326~327頁)
■藝術の世界は誠に何と云つたらよいか只妙とでも云ふ外はない。此世界のみは無限の魅力と希望の奥が擴がつて居る。どうして斯う云ふものを人間に與へられて居るか其是非などは考へられぬ以上のものである。如何なる此道念の本には堪へ得られるのが不思議と云ふ外はない。吾々は只自然の命のまゝにわけはわからず歩ませられる斗り。匆々(井上三綱氏宛〈昭和6、11、2〉)(331頁)
■東洋は自然の中に解け入る大乗覺知に謎の鍵があり西洋は何處迄も自然を對照解釋して居る。西洋でも自然を見ない作家はないでしようが之は微妙な本能性の中の動き方を指す意味ですが東洋は宗教的で西洋は科學的とも云へさうです。何れにしても風土的地方的趣味的装飾感等の如きは各人の居所によりてそれぞれの必然性があり彼は彼之は之である外ないでしようが超國土的藝術は之れより以上の人間性が實證されたものでなければならないように思われ之の意味に於て小生は未だ表面化に至つて居ないものもあるらしい東洋の潜在力を期待されるように思います。更に云へば風土の力とも云へさうです。西洋は兎角作家の指向方向や態度其ものが割合問題となる多元的要求から來る平面的消長にも心引かれ易い傾向あり尤も日本でも之の傅染は流行して居るのですが問題の鍵はより高度の人間性に潜む筈で之が實證されない程度のものにありては只局部的變化平面現象に止まるのでしよう。(黒田重太郎氏宛〈昭和25、2、24〉)(362頁)
■自分の描画上の氣持丈けを云いますと一切は只作家の冩實々證に過ぎない。それ丈けで其人はまざまざと姿を現わして居る。只消極的と積極的の表現相違はある。それ故自己に既存せる内容ならばコローの言葉のように只正直に自然を描く事によつて自づから積極的でなくとも超現實もアプレゲールも出て來る筈である。自らにないより以上のものを取り入れる積極的歩みを行くには色々の思想や方法が其人に或る程度は役に立つ事にもなるのでしよう。しかし何れにしても作品の結果は常に正直であるものが現わるゝ外どうにも仕方はないものである。時代性が如何にあらふ共自らにないものはそれを追つても外形の無意味な姿以上に在り得る筈がない。要するに問題は自己にありての足の蹈みようを誤らぬ事。積極的と云ふ事も消極的と云ふ事も自己への適否できまる事でありませう。此のかね合いを尤も適當に自覺出來るのは其人の天才による外ない。更に云いかへればクラシックにありて如何なる未知の前途を加ふるか保守と進化向上の結合を實現するのが作家の姿でしようからこのかね合いは微妙な本能の作用が大に其消長を握つて居り新らたなる前途を偉(おほ)いなる結果をも作り出す。(黒田重太郎氏宛〈昭和25、2、24〉)(364頁)
■小生の抱いて居る油彩についての考へを云つて見ますと油彩表現の長處が實相表現に便宜であるところにあるのですが――繪畫表現に就いて現在考へられる理想的狀態は實相具象つまり作家の姿が出來る丈けそのまゝの眞相を現わす事例へ表現法其形式の如何にかゝわらず抽象となりシュールとなりキュービックとなつても此實相具象を帯同せる範圍にある事が必要と思われる事。
若し此根本性が他に外れて抽象が勝手な形の抽象化となれば其造形が如何に明確愉快に繪畫的構成色調の美しさ等が發揮されたとしても結局は繪畫としての目標よりも工藝美の方へ近づく事となり作品として面白くとも人間表現としての力が稀薄に傾く。
近代抽象作品に共通する一長一短がこゝにあり。あらゆる方面に自由明せき多様性の装飾性構成表現に於て魅力的であり會場効果的である事は結構ですが繪畫が單に面白く又美しい装飾的魅力に留つてよろしいものならば特に繪畫としての獨立した境地もなくなり他の工藝品とかわらぬ存在でしかない事になります。繪畫は繪畫の長處であり得る人間表現でならねばならぬと思ふのです。(井上三綱氏宛〈昭和25、8、29〉)(370~371頁)
■ピカソマチス展は小生も大阪迄往つて見ました。以前の彼よりも彼は彼なりの世界を今度見直されましたがしかし彼の一長一短は現代的思想一面の大勢を象徴した標本見たようなものでいやでも人の目を引く會場効果をつくるその意味での天才と思います。之は丁度新聞雑誌の編輯心理を思われまた作家と大衆關係が益々世知辛く密接せねばならなぬ職人としての合理性社會理念現實は否應ない此大勢にあるようで之は一面矛盾を内藏するものと思いますが事實ルオーやブラックの(彼等に限らないが)仕事を見ると其努力は貴とい事ながら何だか半面氣の毒の感じさへ起ります。畫面表現効果についてのやつ氣な姿、日本の大衆が最近畫を見る目に進歩があらわれて居るのは確かと見られるのですが要するに大衆は表面的空氣に導かれてあとからついて來る丈けであるようです。専門畫家も大體此姿が多いと思います。小生最近相當な作家として見て居た某君の口から「青木繁の作品が此頃よき見へるのに考へさせられる」と云ふ言葉を聞かされ青木は四十年も前に仕事して居るのに(4字削)尚斯の如きかと寧ろ(3字削)現代心理の面に考へさせられた事です。案外作家についての人の是非心理のどこかに他あいもないものゝひそんで居る事を思わされた事です。
兎に角畫面表現効果の近代は進みました。特に抽象的主觀方面の擴大を認められるのですが之は又半面遊戯自己に傾き易い危險性ありて作家としては此事要心せねばならぬかと思います。小生最近馬遠の大作を見ましたがそのスケールの大きさまざまざと來ろ人間の迫力。此頃の新しいとか舊るいとか云われる空氣が井戸端會議か何かのようにけちけちな哀れさに見へてなりませんでした。(井上三綱氏宛〈昭和28、3、31〉)(384~385頁)
■畫作についての小生の今の考へを言つて見ますと近代の抽象的思想は一面にの表現力を擴げ高めた事で結構ですが要は作品の到達點如何にある事勿論で作家としては象徴でも自然派でも各自の當を得たものに立場を取ればよいのですがそれぞれに一長一短もあるように抽象思想の半面に見出され易い冩實性の不足云いかへれば冩實が一層成就される範圍に於ては抽象も結構であると云ふ意味に歸着します。つまり抽象も象徴も廣い意味の眞實こそ冩實と解されるので畫面にありては抽象と冩實は矛盾しないものと解しての言い分です。繪畫と彫刻が特に單なる装飾美以上の表現に適して居るのは此冩實力であり折角の兒童自由畫の殆んどが面白さはあつても足りないのは此冩實の不足から來るもの足りなさで大人の畫でも冩實のないものは面白いものでも兒童畫に近似する冩實の眞實(廣い意味の)こそ人類的エスペラントの大道のあるところで大事な問題のあるところと思います。しかし抽象とか冩實とか名づけても明瞭な境界線があるわけではないので此要點を把握するのが天才の仕事でしよう。(井上三綱氏宛〈昭和29、5、26〉)(389~390頁)
(2012年1月29日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ボナール展』カタログ 1968年 毎日新聞社発行
■ボナールが20歳ごろに絵を描き始めたとき,印象主義者たちが,光線を目指して絵画の革命を行なっていた。セザンヌ,ゴーガン,ドガ,はヴォリュームや線や動感に対する新しい関心のもとに,すでに彼らの作品に,異なった方法を示していた。初期の小品ではコローを想わせるような明確で繊細な画風を示したボナールも,彼の友人のモーリス・ドニ,ポール・セリュジェ,ヴュイヤール,ルーセルたちとともに,印象主義に方向を転じた。彼ら若い芸術家たちの集団的な熱情的デビューはほとんど区別しがたいほどである。とりわけ彼らを瞠目させたのはゴーガンである。〝だがゴーガンは,それにもかかわらず,疑うべからざる巨匠であり,人びとは,彼の奇妙な言行を寄せ集め,ばらまき,その才能,饒舌,風采,肉体の頑健さ,下劣さ,湧き出す想像力,酒の飲みっぷり,ロマンティックな振舞いなどをほめそやしたのだ。彼の神秘な影響力は,ちょうど私たちがまったく教訓的な先例を見出しえなかったときに,非常に明快な一,二の理念をあたえてくれた。彼は,従来の模倣の理念が私たちを解放してくれたのである。彼は,私たちに抒情の権利をあたえたのだ〟とモーリス・ドニは書いている。そしてゴーガン自身も,〝すべてを敢えてなしうる権利〟を,あらゆる画家たちのために確立しようと望んだということを語っている。ボナールの場合,このような影響に加えて,さらにもうひとつの決定的な影響があった。当時,人びとは百貨店で,日本の風俗版画を手に入れることができた。〝私が,縮み紙やもみ紙に驚くべき色彩で描かれた作品を,2スーか3スーで手に入れたのは百貨店でだった。私は,この素朴で色調の甲高い版画で私の部屋の壁を埋めた。ゴーガン,セリュジェは,過去の事実に教訓を求めた。しかし,私の前にあったものは,今でも生きているもの,そして非常に教訓にみちたものであった〟日本の浮世絵版画は,ボナールにとって一つの啓示であった。〝私は,これらの擦りきれた版画によって,肉づけなしに,色彩だけですべてを表現しうることを学んだ。色価の助けを借りなくてもただ色彩のみで,ヴォリュームや光や性格を表現することが可能だと私は思ったのである〟。西欧の絵画が,事実,明暗のたわむれによって肉づけや凸凹の感覚―色価―をあたえようと試みるのに対して,日本の美術は,ヴォリュームの肉づけを,線の指示と,色彩の面によってのみ表出しているのである。それは,凹凸を表現しようともしないし,奥行にも結びつかない。それは,空間の第3次元を再現するのではなく,暗示する。もみ絵の〝素晴しい雑色〟が,もしボナールに,表現の手段としての色彩から描きだしえたものを啓示したとき,この私たちの観念とは全く異なった絵画的表現の観念,ボナールが日本の浮世絵画家に見出した観念は,彼に,ゴーガンに次いで,表現の自由ということをも啓示したのである。人間の才能が,これほどの巧みさをもって表現されたということは,芸術には絶対的な法則が存在せず,芸術家はどのような手段を用いることも自由だということの証明であるのだ。(『ボナール展に寄せて』 アントワーヌ・テラス)
(weblio辞書より:ナビ派;ポン=タヴェン派の一人ポール・セリュジェが中心となって、ゴーギャンの様式を基礎にパリで結成したグループ。ナビという語はヘブライ語の「予言者」を意味する言葉である。理論的リーダーはモーリス・ドニは、主観的状態と客観的形態の交感、すなわち感情の等価物、一種の心理的事実のあらわれとして芸術作品をとらえている。それに加えて、ナビという語に端的にみられるように、彼らはゴーギャンのやり方を一種の宗教的啓示として受けとめており、彼らの作品はいきおい象徴的な要素を秘めている。上記の2人の他ボナール、ヴュイヤールなどが参加し、トゥールーズ・ロートレックやマイヨールも一時期彼らと関係があった。また作曲家ドビュッシーや小説家プルーストらもかかわりをもっていた。彼らの間には、印象主義への反動や、色彩と歪曲した線の装飾的な使用など、共通点があるものの、強いまとまりはなく、1899年のデュラン・リュエル画廊での展覧会以降は、ばらばらに活動した。)
(岡野注;セザンヌとポン=タヴェン派の一人であったエミール・ベルナールの絵画観の分岐から、ベルナールの方向が現代美術の流れになり、その後のアメリカの現代美術に突き進む。このあたりの時代の画家の蹉跌が、今の美術の痩せた魅力のなさの元凶である。セザンヌや坂本繁二郎などのイーゼル絵画による「裸眼のリアリズム」こそがいつの時代にも画家が習熟せねばならないスキルであると私は考える。)
(2012年2月4日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『南北朝』日本歴史シリーズ7 世界文化社
■世阿弥は「諸道諸事において、幽玄なるをもて上果とせり。殊更、当芸において、幽玄の風体第一とせり。……何の物まねにしなを変へてなりとも、幽玄をば離るべからず」と、幽玄を能楽の最高の理念としている。しかしそれにしても、彼のいう幽玄とは、どのような美なのであろうか。
世阿弥の属した大和猿楽は、元来「遊楽の道は一切物まねなり」というように、物まね換言すれば写実的表現を特色としたものであった。しかし彼は余りにも写実的な表現は「俗にいやしく」なり、能楽の保護者である将軍義満ら「上つ方」「貴人高位」の好みに合わぬことを察知し、近江猿楽や田楽の特色である歌舞重視の芸風をとりいれ、芸風の革新をはかった。すなわち、せりふを歌謡化し、所作を舞踏化して表現をロマン的で非限定的なものとし、それだけ写実的表現を抑制し、幽思微情のただよう表現を主とするように改めた。そして彼は、このように歌舞を物まねに優越させることで成立する、余剰的表現様式を幽玄と称したのである。しかし彼においては、幽玄は表現の様式概念であると同時に、美の質にかかわる概念でもあった。
表現様式としての幽玄は余剰的表現のことであるが、その余剰の質は閑寂なもの、悲壮なもの、優艶なものなど、いろいろなものでありうる。ところで世阿弥の重んじた余剰の質はどのようなものであったろうか。それについて詳述している余裕はないが、彼が「何と見るも花やかなる為手(して)、是れ幽玄なり」「人の品々をみるに、公家の御たたずまひの位高く、人望余に変れる御有様、是幽玄なる位と申すべきやらん。然らば、ただ美しく柔和なる体、幽玄の本体なり」と説き、また「人においては女御(じょうご)、更衣(こうい)又は遊女、好色、美男、草木には花のたぐひ、かやうの数々は、その形、幽玄のものなり」「幽玄みやびたるふし、かかりは女体の用風より出づ」といっていることに、注意を喚起しておきたい。
それは今日人びとが一般に、この語において連想するような寂静、枯淡、冷厳の美ではなく、花やか・美し・柔和・みやび・やさしさなどの語で説明される貴族的・女性的な美、王朝貴族のあこがれた優艶の美に近いものであった。
世阿弥が能楽の理念とした幽玄は、このようにして、歌舞を物まねに優越させて余剰あふれる表現様式をとり、しかも情緒的・ロマン的・唯美的な王朝文学と緊密に結合した貴族的・女性的な優雅艶麗の美を、その余剰としてただよわせることであった。世阿弥の能楽が、将軍義満を中心とする公武の社会に大きな人気をえたのは、それがこのような意味での幽玄を理念とした歌舞劇であり、それが王朝文化憧憬の時代の好みによく投じたからにほかならない。能楽の興隆は、その意味で、北山文化の基本的性格を示すよい例証である。
しかし世阿弥は、以上のような幽玄の美を能の基本的な美とはしたが、これを究極至高の美としたのではなかった。彼が花の否定である「しほれ」の美を高く評価し、ことに『花鏡(かきょう)』の「批判之事」の一段で、はなやかな美しさを否定的に超越した「無文(むもん)の能」を至高のものとしていることを忘れてはならない。
けだし彼はここにおいて能を、「見(けん)より出でくる能、聞(もん)より出でくる能、心(しん)より出でくる能」の3段階にわけて、それぞれ説明している。ちなみに、見より出でくる能とは視覚に訴えて面白い「はではでしい能」で、「目ききは申すに及ばず、さほどに能を知らぬ人までも、みな同心に面白やと思ふ」大衆うけのする能のことであり、聞より出でくる能とは「さしより、しみじみとして、やがて音曲調子に合せて、しとやかに面白」いが、凡庸な「田舎目ききなどは、さほどとも思はぬ」向上した能のことである。
最後の心より出でくる能とは「無上の上手」名人が、すべての曲を習得した後に演ずる淡々とした能、「歌舞の二曲も物まねも儀理(戯曲の筋の面白さ)もさしてなき能」ではあるが、その『さびさびとしたる中に、何とやらん感心のある所ある」能のことで、これを「冷えたる曲」「無心の能とも、又無文の能」ともいうのである。これは「よき程の目ききも見知らぬなり、まして田舎目ききなどは思ひも寄るまじき」能で、これこそ究極至高の能だと、世阿弥はいうのである。
このようにして、はではでしく表現の多彩な能を基本としながらも、しみじみとしとやかに面白い能にいたり、さらに表現を極度におさえた象徴的な表現様式と、簡素枯淡・寡黙寂静の美、無一物の美を実現しようというのが、世阿弥の理想であった。
そして世阿弥の能のこの3段階論の構造が、公家的・浄土教的なものを基層とし、観音殿を中層とし、禅宗的なものを最上層とした金閣の構造と、きわめて類似しているのは単なる偶然であろうか。いや偶然ではなく、同じ北山時代の好みの異なる分野における表現だから類似しているのだ、と解釈すべきであろう。(『北山文化』世阿弥の幽玄 芳賀幸四郎)(146~148頁)
■四書中心と形而上学的学風とを特色とした宋学は、鎌倉中期に禅僧によって伝えられ、禅宗の布教と世俗教化の一方便として、もっぱら禅僧によって講究され、南北朝末期に義堂周信(ぎどうしゅうしん)らが出てからしだいに普及した。ついで、この時代には三教一致の思想――儒・仏・道の三教はその根本の理は一であるという思想にささえられて、岐陽方秀(ぎようほうしゅう)・大椿周亨(だいちんしゅうこう)らのように禅僧でありながら宋学の研究に専念するものが輩出し、宋学が大いに興隆した。そしてついに、漢唐訓詁(くんこ)の学の系統をひく清原家などの儒学にも、深く浸透するようになった。近世における朱子学興隆の基盤はこの時代に確立したのである。
禅宗が学問・文学の教養ゆたかな士大夫(したいふ)以上の知識階層を主たる支持者として発展した関係上、中国においてすで偈頌(げじゅ)とよばれる宗教的な詩や法語を述作する風が盛んであったが、この風潮も鎌倉末期以来、帰化僧や留学僧らによって輸入され、南北朝時代になって一段と盛んになり、その末期から北山時代にかけて、世にいう五山文学の黄金時代を現出した。(『北山文化』宋学と五山文学の興隆 芳賀幸四郎)(150頁)
■北宋から南宋をへて元にいたる時代には、北宋(ほくしゅう)画と南宋画・院体派と在野派それに非職業画人の一派などがきそいおこり、山水画・花鳥画・道釈画などが、それぞれ多彩な発展をとげ、ことに墨線と墨色とをもって対象の本質をきわめて主観的に表現する水墨画が発達した。
この水墨画は、禅の精神と深く相通ずるものがあったため、鎌倉の円覚寺蔵の『仏日庵公物目録』でその一端が察せられるように、鎌倉末期からすでに、禅僧らによって多数わが国に請来され、鑑賞されていた。ついで南北朝時代にはいるにおよんで、これら舶載の水墨画を鑑賞する趣味は、禅僧社会から上層武家社会にまで拡大するにいたった。そしてそれにともない、我が国人の間に、これらを模倣して描くものがあらわれるようになった。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(150頁)
■しかし、ここで注目すべきことは『御物御画目録』のうちで幅数の最も多いのが、103幅の牧溪の作品で、27幅の梁楷(りょうかい)をはるかに引きはなしていることである。牧溪の絵画は、元代の絵画批評家として名高い夏文彦(かぶんげん)の『図絵宝鑑』巻4に「粗悪にして古法無く、誠に雅玩に非ず」とあるように、中国では低く評価されていたのであった。
ところで、この『図絵宝鑑』は北山時代にすでにわが国に輸入されており、したがって、この牧溪評はわが国の知識人の間に知られていたはずである。しかもそれにもかかわらず、義満らが牧溪の画をきわめて高く評価していたことは、まことに興味深く、かつ示唆ゆたかな現象といわねばならない。
なぜなら、それは一つには義満らの鑑賞眼が必ずしも中国の評価にとらわれず自由独創的なものであったことを示し、二つには彼らが一方では伝統的な公家文化や優艶華麗を意味する幽玄美に心ひかれながらも、他方では禅宗的な簡素枯淡の美・清貧無一物の美に魅力を感じていたことを、よく語るものだからである。
ともあれ、この北山時代には一方では「融通念仏縁起絵巻」の筆者の一人として知られる土佐行広らによって、大和絵が復活した半面、このように宋元風水墨画が禅僧画家らの活躍で発達し、禅僧画家牧溪の作品が極度に尊重されたのであった。このことは、金閣の構造や世阿弥の美の理念の構造と一脈相通ずるもので、北山文化の性格を知る上のよい手がかりである。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(152~154頁)
■公家社会に荷担された伝統的な古典文化と、禅僧社会に荷担された新しい舶載文化とが、それぞれに独自に栄えながらも、将軍義満・義持を棟梁とする武家社会を媒介として接触し、しだいに融合の度を進めたこと、これが北山文化の基本的性格であり、またそこに日本文化史上における北山文化の歴史的意義があるのである。(『北山文化』水墨画の発達 芳賀幸四郎)(154頁)
(2012年2月15日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ジョルジョ・モランディ』 (有)フォイル社
■その生と芸術はそれゆえ、20世紀美術の大スター、パブロ・ピカソと好対照をなすとすらいってもけっして過言ではないだろう。(『喪としての絵画、あるいは幻の展覧会のために』岡田 温司)(4頁)
■20世紀の最初の20年間には、セザンヌ、モネ、スーラの仕事にわたしほど関心をもっているイタリアの画家は、ほとんどいませんでした(モランディ)。(『喪としての絵画、あるいは幻の展覧会のために』岡田 温司)(5頁)
■アトリエに残されたテーブルの表面には、鉛筆による無数の線の跡が残されていて、画家が壜や壷の配置具合をいつも工夫していたことがうかがわれる。また、中庭に面した窓から射す光の量を調節するために、白いパネルを利用していたことも知られている。(『喪としての絵画、あるいは幻の展覧会のために』岡田 温司)(6頁)
■「何かがうまくいっていない、それが何であるかわからないけれども、たしかに何かがうまくいっていないと感じるのだ」、制作中の画家があるとき友人の音楽学者(『我がモランディ』の著者でもあるルイジ・マニヤーニ)に漏らしたというつぶやきである。(『喪としての絵画、あるいは幻の展覧会のために』岡田 温司)(6頁)
■モランディはいちど父親が経営する商社に勤めるものの、絵画への思いは断ちがたく、1907年に当地の美術アカデミーへと進む。非凡な才能を見せながらも、そこでの19世紀的な教育に反発し、むしろ、1909年にはヴィットリオ・ピーカの著作やアルゴンソ・ソッフィチによる記事を通してのポール・セザンヌに、その翌年にはヴェネツィア・ビエンナーレでのピエール=オーギュスト・ルノアールに衝撃を受けた。おそらくこの頃にはすでに、パブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックがパリで起した革命についても十分に知識を得ていただろう。(11頁)
■しかしながら、モランディが本当の意味で自己の絵画を獲得するのは20年代に入ってからである。1920年、第12回ヴェネツィア・ビエンナーレのフランス館でのセザンヌの回顧展にて、モランディはこのエクスの巨匠の作品をまとめて実見することとなる。10年前にルノアールと同じくモランディをとらえたセザンヌが、連作的展開と総合的な作画をもって、再び彼をゆさぶるのである。(12頁)
■これらの作家評が伝えられる中、モランディ自身は、抽象絵画との関連性を指摘する論調に対しては否定的だったことが知られている。1955年と1958年には自らの制作信条を語る重要なインタビューが行なわれているが、その中で、モランディは「眼に見えているもの以上に抽象的なものは何もない」という趣旨の有名な発言をしている。これは、自らの制作は現実の世界を対象として出発するものであり、抽象的な形象の描出を目的としてはいないという態度を示したものと読み取れる。(66頁)
■1920年代前半では、わたしほどにセザンヌの作品に関心を抱いていたイタリア人はわずかだったのです。(モランディ)(124頁)
■ロンギは、モランディの歩んだ道のりは「きれいな放物線」からは程遠いものであったが、むしろ「しっかりと伸びた軌跡であり、長い道」であったと確信していた。そして美術史家は、自身に対して画家が死の間際に托すことを望んだ、「仕事」に関わる言葉を伝えている。ほとんど遺言というべきその言葉は、彼らの長きにわたる連帯感とともにあった豊かな友情のおかげで得られたものであった。それはまたモランディの活発な精神と情熱的で、粘り強い探求心を証明している。
親愛なるロンギ、わたしがどれほど仕事をしたく思っているか、あなたはご存じかと思います。
さらに
わたしはまた、新しい想を得ました。それを解きほぐし展開したいものです。(『友情について』ジョルジョ・モランディとロベルト・ロンギ マリア・クリスティーナ・バンデーラ)(128頁)
■モランディのことを思い出して美術史家は、自身の初期の著作群を特徴づけていた論争的な力(ヴィス・ポレミカ)を放棄してはいない。強調していわく、「気まぐれに満ちているとはいえ、決して無意味ではない因果応報という魔物」が望んだのは、ヴェネツィア「ポップアート」の製品が展示されるまさにその日に、モランディがこの世の舞台から退場することをだったのだ、と。(『友情について』ジョルジョ・モランディとロベルト・ロンギ マリア・クリスティーナ・バンデーラ)(128~129頁)
■一方、近代の芸術家としては郡を抜いてセザンヌであり、モランディ自身、1912年から1916年にかけての自作に、セザンヌの影響がみえることを公言して憚らない。(『モランディと同時代の画家たち』金井 直)(130頁)
■いずれの側にも「主義」なき静物の画家、モランディの居場所はないだろう。(『モランディと同時代の画家たち』金井 直)(131頁)
■「眼に見えているもの以上に抽象的なるものは何もない」というモランディーの名言も、この時期に語られたものである。「眼に見えているもの」が抽象的である以上、特段、純粋な、あるいは幾何学的な抽象に向き合う必要はない、という訳である。(『モランディと同時代の画家たち』金井 直)(132頁)
■そうした関係性を振り返るとき、モランディの没年が1964年であったことが、いかにも象徴的に思えてくる。この年のヴェネツィア・ビエンナーレ大賞受賞者はロバート・ラウシェンバーグ(1925-2008年)。つまり、アメリカのポップ・アートが最も伝統ある現代美術展を制覇し、ヨーロッパ近代絵画の終焉(少なくとも引き続き絵画を描き続けることの困難)を印象づけたその年に、壜を並べ替え、描き続けることで抽象との駆け引きを繰り広げた具象画家が世を去ったのである。この偶然の一致、二重の喪もまた、モランディの同時代性を、我々にひそやかにほのめかすことだろう。(『モランディと同時代の画家たち』金井 直)(133頁)
■モランディは時にアンフォルメルと関連づけられるアメリカの抽象表現主義の代表的な画家ポロックについて「彼は泳ぎ方を知る前に水の中に飛び込んでいる」と評したという。(『モランディとミニマル・アート』尾崎 信一朗)(137頁)
(2012年2月16日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ジョルジョ・モランディ展』 神奈川県立美術館カタログ(1989年)
■最後のモランディ,彼の制作の宿命(ヴィターリ)は,存在の探究が極限にまで達した後,非存在や無の表現にかくも近づいたのである。今やモランディは,存在と非在の対立物として現れない対立を通して,この哲学的叡智に到達し,そしてあらゆる物について,一時的な違いよりもその等しさに気づくのである。
存在することも存在しないことも,もはや同一であるように思われる。今では,もはや「トゥ・ビー」か「ノット・トゥ・ビー」の間の根本的な選択という,西洋文明がいつも新たにしてきた,シェイクスピアの問いの問題ではないのだ。今問題なのは,二つの対立物をともに結びつけることであり,存在するものと存在しないものを分けるものはほとんどない,ということを(柔順な紙や水彩を通して,油彩とカンヴァスを通して,そしていつも知性と視覚の叡智を通して)発見することなのである。(『ジョルジュ・モランディ――抽象と実在』メルチェデス・ガルベーリ)(17頁)
■「モランディは画布の塵をはらう。『死ぬ前に2点の絵を完成させたい。重要なことは,根底に,事物の本質にふれることである』。本質といっているが存在を意味しているように感ぜられる。見え方ではなく存在。われわれは,本質を,古典主義者の声高な宣言にむなしく追究されるあの客観主義の告白となる」。
このインタヴューそのものをジュゼッペ・メルシカはヴェネツィアのアルコバレーノ画廊でおこなわれたモランディ展の評(「エンポリウム」,1938年7月)に借用しているようで,芸術家のモノグラフがないことを嘆いたあと,モランディは「事物の本質に倦むことなく触れようとしている」と再言。(『言葉と視覚 バッケッリからアルカンジェリにいたる主要なモランディ解釈のテーマと方向(1918-64年)』エレーナ・ポンティッジャ)(179頁)
(2012年3月5日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『生命の光』 712号
■私たちは、果してモーセやキリストが祈られたほどに、祈っているかどうか。神の子イエスすらも、かく祈られた以上、生来の鈍根な私たちが、祈らずに霊性が向上したりするものですか。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(4頁)
■人間が言葉というものを最高度において語るのは、人に対してではなくして神に対して語っている時であろうとおもいます。「人がその友と語るようにも、主はモーセと顔を合わせて語られた」(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(4頁)
■私は自分の机の前に、「人に語らずして、神に語れ!神学者に聴くことせずして、神に聴けよ!」と書いて座右の銘にしています。今年こそは、もっと徹底して神に聴いて生きたい、主の膝下にて祈りたいと願っています。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(5頁)
■私はスンダル・シングやアウグスチヌスのように、独創的な、人真似でない宗教思想を得たい。そのために、いかにしても神に深く祈るのでなければと、常々努めてきたことです。実にこと信仰に関する限り、他人の信仰論の借り物では役に立たぬ。神にじかに聴いた知恵でなければならぬと思います。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(6頁)
■神に聴く者は実に独創的な知恵をもつ者であります。人間のもつ言葉というものは、人間同士で語るためにしか使わないものだと思われるかもしれませんが、もし「人間の言葉は、神と対座して、神に語るためにも持ちいうるものだ」と悟られたら、これは皆さんにとって大発見だと思うのであります。いつも言葉が神に語るものとして、「内的言語」の習慣がつくまでに、常に祈り心地で生きてゆきたいものです。祈りとは、神と語ることにほかなりません。神に語ることが、私たちに第二の天性になるようにと願います。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(6頁)
■悪魔は上手に人を惑わすことを通して、恐れさせます。イエス・キリストが十字架を前にしてゲッセマネで祈られた時に、弟子たちに「汝ら誘惑(まどわし)に陥らぬように眼を覚まし、かつ祈れ」(マルコ伝14章)と言われたのは、このためです。常に霊を目覚ませて、今年は恐れなき歩みをしよう。いつも祈って神的自覚をもち、霊的な武装をしたい。
「悪魔の策略に対抗して立ちうるために、神の武具で身を固めよ」(エペソ書6章)。神のご保護があり、神による使命感がある限り、私たちは怖さも忘れます。祈ることが習慣になるほどでありたい。祈らぬから、惑わされて真理を見失うのです。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(8頁)
■神に深く祈るのには、どうすればよいか。結論として、これは神と私たちの心とが正しい関係にあることがいちばん大事です。神様にやましい心で祈っても、祈りは叶えられません。
それから、我意を張るのではなく、神意に従うことを誓いつつ祈るとき、それが栄光の道であり、勝利の力を与えられます。(『主イエスの祈り方』手島郁郎)(15頁)
(2012年3月10日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『モランディとその時代』 岡田温司著 人文書院
■アルカンジェリのこの「辛口採点」は、ロンギの目にとまり、ロンギが主幹する雑誌『プロポルツィオーネ』(1943年)に「イタリアの若い絵画とその病根について」と改題され、増補されて再録される。なぜアルカンジェリは、同じ抵抗の世代として共鳴し期待もしていた、「若い絵画」に苦言を呈することになってしまったのだろうか。それはなによりも、ビロッリがファン・ゴッホに、グットゥーゾがピカソにあまりにもやすやすと飛びついてしまったからにほかならない。そこに認められる、歴史的な動機づけの欠如と皮相な新ロマン主義を、アルカンジェリは鋭く批判するのである。
「時代の苦悩」、「反発の運動」、「論争の行動」といった表現によって、これら「新ロマン主義者たち」の存在は正当化されることになるかもしれない。もちろん、どんな世代も、どんな芸術の時期も、先行する世代や時期にたいして不満や不安を抱く権利は認められている。だが、傑作にたいして駄作で論争を仕掛けるということが、ほんとうに可能なのだろうか。この場合、カッラやモランディにたいするビロッリやグットゥーゾの論争は、適切なものなのだろうか。(148頁)
■かってアカデミー教官時代のモランディの学生だった画家マンデッリもまた、興味深い回想を残している。マンデッリはあるとき、すでに流布していた例の「モンドリアンのようなモランディ」という評価について、画家本人に問いただしてみたらしい。すると、大先輩の画家からは、「そんなことを言うのは、何も知らない輩だ。言っておくが、わたしは、算術的な計算はいっさいしないし、定規やその他のばかげたものもいっさい使わない。すべてを眼でおこなって、本能に導かれるにまかせているだけのことだ」という返事がかえったらしい。モランディが、いかにモンドリアンの作品と、それに比較しようとする批評の言説を意識していたかを示すエピソードである。
第1章で見たように、アルカンジェリは、この時期のモランディに特徴的な中心性と幾何学性を、抽象表現主義のオールオーヴァーな画面にたいする「論争」であると解釈したが、むしろ、モンドリアン風の幾何学的抽象にたいする一種の挑戦であり、モランディ=モンドリアン説を唱える一部の批評にたいする挑発であったとも言えるのではないだろうか。モランディは、おそらくこう主張しようとしているように思われる。自分はあくまでも眼に見えるものから出発する。自分は、タブローを数的次元へと還元することはしない。自分は、光やタッチやマチュエールの感触をあくまでも重要視する、と。そのためには、敵陣にできるだけ近づいて、相手の戦術の裏をかく必要がある。モランディが1950年代、「抽象的」とも形容された画面構成にもっとも接近したとすれば、それはおそらく意識的な選択によるものであったと、わたしは考える。くり返すが、「眼に見えるものより抽象的なものは何もない」という有名なせりふは、このような文脈のなかで理解することができるだろう。すでに60歳を超えても、モランディの歩みはとどまることを知らない。(189頁)
■これらの論文において、ロンギは、見たものをことばに置き換えるその独特の才能を駆使して、作品の主題や内容とはほとんどかかわりなく、純粋に造形的な観点から作品を記述し、再評価しようと試みる。すると、過去の画家たちの遺産も、まるで現代の画家たちの作品と同じように、色彩や光、フォルムやヴォリューム、線や面、構図や空間といった造形的な諸問題をめぐる探究の産物として立ちあらわれてくるのである。ロンギにおいて、過去の芸術を見る眼差しとのあいだに本質的な差はない。あるいは、現代美術の経験と過去の美術の評価とのあいだに、実り豊かな相互作用が成立していると言うべきであろうか。そこにこそ、ロンギの「純粋造形批評」の真骨頂がある。それゆえ、後年になってロンギ自身も認めているように、彼のクールベ体験がカラヴァッジョを、セザンヌ体験がピエロを再発見させる原動力となっていたとしても、おそらく偶然ではない。(257頁)
■これにたいして、デ・キリコは、ロンギの批評にそれはど関心を示さなかったようである。それどころか、ロンギのほうから、デ・キリコにいわば決闘状が突きつけられているのである。1919年、『イル・テンポ』にロンギが発表した辛辣な評論「整形術の神様へ」がそれである。未来主義への共感から出発した、論争好きで戦闘的な若いフォルマリストにとって、謎めいた内容をこれ見よがしに暗示させようとするデ・キリコの形而上絵画は、あまりにも文学的で観念的、ロマン主義的で北欧的なもの(ニーチェ、ベックリンなどに啓示を受けた)に映ったのだった。その意味ではモランディも、密かにロンギに賛同していたかもしれない。もちろん、モランディがデ・キリコを批判した形跡は、わたしの知るかぎりいちどもないが、ふたりの差異は、それぞれの形而上絵画のなかにはっきりとあらわれている。(258~259頁)
■ 描くべき現実、いまこそ私はそれを悟ったのだが、それは主題の外観にあるのではなくて、その印象の深く浸透する度合いにあった。その深みにあっては、いかほど多くの人道主義、愛国主義、国際主義のお談義よりも貴かったあの皿の上のスプーンの音やナプキンの糊づけの固さが象徴しているように、どのような外観も問題ではなかった。〔「見出された時」井上究一郎訳〕
大戦の直後にプルーストが著したこの一節は、モランディの絵画へのこのうえなく適切な導入であり続けている。フォルムを介して、フォルムの奥を掘り下げることによってのみ、また色調の「追憶」を積み重ねることによってのみ、純粋で無欠の感情の光へと行き着くことができる。実際、ここにこそ、モランディの内奥の教訓があり、最小限に遍歴する彼の主題の還元の意味がある。いずれにしても、全速力で疾走して作品と鑑賞者をむさぼり食うような図々しい主題の撤廃である。無用の対象物、見捨てられた風景、季節の花たち、これらは「フォルムで」表現されるに充分であるというよりも、そのための口実なのである。なるほど印象主義やポスト印象主義においても、すでに静物や風景や花が支配的であったが、それはなお好ましい契機であり、強く望まれた「モティーフ」の企てであった。これに対して、モランディでは、絶対的な抽象主義の暗礁を避けるために充分な語彙であり、必要なシンボルであるにすぎない。まさしく彼は、同じ素材の口実のうえで、さまざまな感情の機微を表現し、その端正で澄みきった挽歌をさまざまに奏でることができたのである。(314~315頁)
(2012年3月12日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『風姿花伝』 世阿弥著 岩波文庫
■されば、古きを學び、新しきを賞する中にも、全く、風流を邪にすることなかれ。ただ、言葉賤しからずして、姿幽玄ならんを、(承けたる)〔正しく傅統をうけついでいる〕とは申すべきか。先ず、(この)道に至らんと思はん者は、非道〔専門外のこと。能藝以外の道〕行ずべからず。ただし、歌道は風月延年(ふげつえんねん)の飾り〔風月の景をかりた延年の舞である申樂に美を加えるもの〕なれば、もつともこれを用ふべし。およそ、若年より以來(このかた)、見聞き及ぶところの稽古の條々、大概注(しる)し置くところなり。
1、好色・博奕(ばくえき)、大酒、三重戒、これ古人〔世阿弥の父、観阿弥清次。〕の掟なり。
1、稽古は強かれ、諍識〔情識のあて字。自分勝手な慢心から生ずる争い心〕はなかれとなり。(10~11頁)
■(五十有餘)この比(ころ)よりは、大方、せぬならでは、手立あるまじ〔「せぬ」という方法より外に方法はあるまい〕。「麒麟も老いては駑馬(とば)に劣る」と申す事あり。さりながら、誠に得たらん能者ならば、物數はみなみな失せて、善悪見所は少(すくな)しとも、花は殘るべし。
亡父〔観阿弥。至徳元年(1384)歿〕にて候ひし者は、五十二と(申しし)五月(十九日)に死去せしが、その月の四日の日、駿河の國淺間〔静岡にある浅間神社であろう〕の御前(おんまえ)にて法樂〔神社に奉納し、神慮・仏意を慰め奉る能〕仕り、その日の申樂、殊に花やかにて、見物の上下、一同に褒美せしなり。およそ、その比(ころ)、物數をば早や初心に譲りて〔年若いシテにさせて〕、やすき所を少な少なと色へて〔色どって〕せしかども、花はいや増しに見えしなり。これ、誠に得たりし〔体得した〕花なるが故に、能は枝葉も(少く)、老木(おいき)になるまで、花は散らで殘りしなり。これ、目(ま)のあたり、老骨に殘りし花の證據なり。(21~22頁)
■老人の物まね、この道の奥儀なり。能の位、やがて外目に現はるる〔演者の藝位が(老人に扮すると)すぐ見物人に見えてしまう〕事なれば、これ、第一の大事なり。
およそ、能をよきほど〔相当に〕極めたる爲手(して)も、老いたる姿は得ぬ人〔手に入っていない人〕多し。例へば、木樵、鹽汲(しほくみ)の態(わざ)(物)などの翁形(おきなかたち)をし寄せぬれば、やがて上手と申す事、これ、誤りたる批判なり。冠(かぶり)・直衣(なほし)、烏帽子・狩衣の老人の姿、得たらん人ならでは、似合ふべからず。稽古の劫(こふ)入りて〔年功を積んで〕、位上(のぼ)らでは、似合ふべからず。
また、花なくば、面白き所あるまじ。およそ、老人の立ち振舞、老いぬればとて、腰・膝(を)屈め、身を詰むれば〔體をちぢめるようにすると〕、花失せて、古様(こやう)に〔古くさく〕見ゆるるなり。さるほどに、面白き所稀なり。ただ、大方、いかにもいかにも、そぞろかで〔はしたなくならないようにつつしんで〕、しとやかに立ち振舞ふべし。殊さら、老人の舞かかり、無上の大事なり。花ありて年寄と見ゆるる公案〔工夫すべき課題〕、委(くは)しく口傅あり。習ふべし。ただ、老木に花の咲かんが如し。(26~27頁)
■(直面(ひためん)〔シテが面をつけないで、素顔のままでする能〕)これまた、大事なり。およそ、もとより俗の身なれば、やすかりぬべき事なれども〔一體(直面物は対象が大てい)俗人であるから、(俗人である役者にとって)やさしいはずであるが〕、不思議に、能の位上らねば、直面は見られぬものなり。
先ず、これは、假令(けりょう)〔大體〕、その物その物によりて學ばん事、是非なし〔勿論である〕。面色をば似すべき道理もなきを、常の顔に變へて、顔氣色(かおけしき)を繕ふ事あり。さらに見られぬものなり。振舞・風情をば、その物に似すべし。顔氣色をば、いかにもいかにも、己(おの)れなりに、繕はで直(すぐ)に持つ〔あるがままに、あたり前にしている〕べし。(28頁)
■親に別れ、子を尋ね、夫に捨てられ、(妻)に後(おく)るる、かようの思ひに狂亂しる物狂ひ、一大事なり。よきほどの爲手(して)〔相当にできる役者〕も、(ここを)心に分けずして、ただ一偏に〔どれもこれも同じように〕狂ひ働くほどに、見る人の感もなし。思ひ故の物狂ひをば、いかにも、物思ふ氣色を本意に當てて、狂ふ所を花に當てて、心を入れて狂へば、感も、面白き見所も、定めてあるべし。かやうなる手柄〔手ぎわ〕にて、人を泣かする所あらば、無上の上手と知るべし。これを、心底に、よくよく思ひ分くべし。(29頁)
■また、直面(ひためん)の物狂ひ、能を極めてならでは、十分にはあるまじきなり。顔氣色をそれになさねば、物狂ひに似ず。得たる所なくて、顔氣色を變ゆれば、見られぬ所あり。物まねの(奥義)とも申しつべし。大事の申樂などには、初心の人、斟酌すべし。直面の一大事、二色(ふたいろ)を一心になして、面白き所を花に當てん事、いかほどの大事ぞや。よくよく稽古あるべし。(30~31頁)
■問。ここに大(おおい)なる不審あり。早や劫(こう)入りたる爲手(して)の〔(相手が)年功を積んだシテで〕、しかも名人なるに、ただ今の若き爲手の立合に、(勝つ)事あり。これ、不審なり。
答。これこそ、先に申しつる、三十以前の時分の花なれ。古き爲手は早や花失せて、古様なる時分に、珍しき花にて勝つ事あり。眞實の目利きは見分くべし。さあらば、目利き・目利かず、批判の勝負〔見物人の批判力の優劣を争う勝負〕になるべきか。
さりながら、様(やう)あり〔仔細がある〕。五十以來まで花の失せざらんほどの爲手には、いかなる若き花なりとも、勝つ事はあるまじ。ただ、これ、よきほどの上手の、花の失せたる故に、負くる事あり。いかなる名木なりとも、花の咲かぬ時の木をや見ん〔木を見ようか、それとも〕、犬桜の一重なりとも、初花色々と咲けるをや見ん〔咲いているのを見るだろうか、勿論後者である〕。かやうの譬(たと)へを思ふ時は、一旦の花〔一時的な花。時分の花〕なりとも、立合に勝つは理(ことわり)なり。
されば、肝要、この道は、ただ、花が能の命なるを、花の失するをもしらず、本(もと)の名望ばかりを頼む事、古き爲手(して)の、返す返(がえ)す誤りなり。物數をば似せたりとも〔數々の物まねに通じても〕、花のあるやうを知らざらんは、花咲かぬ時の草木を集めて見んが如し。萬木千草において、花の色も皆々異なれども、面白しと見る心は、同じ花なり。物數は少くとも、一方(ひとむき)の花を取り極めたらん爲手は一體(てい)の名望〔その一體についての名望〕は久しかるべし。されば、主(ぬし)の心には、随分花ありと思へども、人の目に見ゆるる公案なからんは、田舎の花・藪梅などの、徒らに咲き匂はんが如し。
また、同じ上手なりとも、その内にて重々あるべし〔段階段階があるであろう〕。たとひ、随分極めたる上手・名人なりとも、この花の公案なからんは、上手にて(は)通るとも、花は後まではあるまじきなり。公案を極めたらん上手は、たとへ、能は下るとも、花は殘るべし。花だに殘らば、面白さは一期(ご)あるべし。されば、誠の花の殘りたる爲手には、いかなる若き爲手なりとも、勝つ事はあるまじきなり。(46~47頁)
■そもそも、風姿花傅の條々、大方。外見の憚(はばか)り、庭訓(ていきん)のため注(しる)すといへども、ただ望む所の本意とは、當世、この道の輩(ともがら)を見るに、藝の嗜(たしな)みは疎(おろそか)かにて、非道〔能藝以外の道〕のみ行じ、たまたま當藝に至る時も、ただ一夕の見證(けしょう)〔藝道上の一時的な悟り〕、一旦の名利に染みて、源を忘れて流れを失ふ事、道すでに廢(すた)る時節かと、これを歎くのみなり。しかれば、道を嗜(たしな)み、藝を重んずる所、私なくば〔私心を去ったならば〕、などかその徳〔能藝にはげむことによって得られるよい結果〕を得ざらん。殊さら、この藝、その風を継ぐ〔古来の遺風伝統を継承する〕といへども、自力より出づる振舞あれば、語にも及び難し。その風を得て、心より心に傅はる花なれば、風姿花傅と名附く。(69頁)
■およそ、能の名望を得る事、品々(しなじな)多し〔いろいろな場合がある〕。上手は、目利(き)かず〔鑑賞眼の低い人〕の心に相叶(かな)ふ事難(かた)し。下手は、目利きの眼(まなこ)に合う事なし。下手にて目利きの眼に叶はぬは、不審あるべからず。上手の、目利かずの心に合わぬ事、これは、目利かずの眼の及ばぬ所なれども、得たる上手にて、工夫あらん爲手(して)ならば、また、目利かずの眼にも面白しと見るやうに、能をすべし。この工夫と達者とを極めたらん爲手をば、花を極めたるとや申すべき。されば、この位に至りたらん爲手は、いかに年寄りたりとも、若き花〔年若いシテの持つ時分の花〕に劣る事あるべからず。されば、この位を得たらん上手こそ天下にも許され、また、遠國(おんごく)・田舎の人までも、遍(あまね)く、面白しとは見るべけれ。この工夫を得たらん爲手は、和州へも、江州へも、もしくは田樂の風體(ふうてい)までも、人の好み・望みによりて、いずれにも亙(わた)る上手なるべし。この嗜みの本意を顯(あら)はさんがため、風姿花傅を作するなり。
かやうに申せばとて、我が風體の形木(かたぎ)の疎(おろそ)かならんは、殊(こと)殊に、能の命あるべからず。これ、弱き爲手(して)なるべし。我が風體の形木を極めてこそ、遍(あまね)き風體をも知りたるにてはあるべけれ。遍き風體を心にかけんとて、我が形木に入らざらん爲手は、我風體を知らぬのみならず、他所(よそ)の風體をも、確かにはまして知るまじきなり。されば、能弱くて、久しく花はあるべからず。久しく花のなからんは、いづれの風體をも知らぬに同じかるべし。しかれば、花傅の花の段に、「物數を盡(つく)し、工夫を極めて後、花の失せぬ所をば知るべし」と云へり。(73~74頁)
■(秘)儀に云はく、「そもそも、藝能とは、諸人(しょにん)の心を和げて、上下の感をなさん事〔上下の人々を一様に感動させること〕、壽福増長〔壽命福徳を増すこと〕の基(もとい)、遐齢(かれい)・延年〔どちらも壽命をのばすこと〕の法なるべし。極め極めては、諸道悉く、壽福延長ならん」となり。殊さら、この藝、位を極めて、佳名を殘す事、これ、天下の許されなり。これ、壽福増長なり。
しかれども、この故實〔心得べきこと〕あり。上根・上智〔根機も智慧もすぐれていること〕の眼(まなこ)に見ゆるる所、長(たけ)・位の極まりたる爲手(して)におきては、相應至極なれば、是非なし。およそ、愚かなる輩(ともがら)、遠國(をんごく)・田舎の賤しき眼には、この長(たけ)・位の上れる風體、及び難し〔鑑賞することができない〕。これをいかがすべき。
この藝とは、衆人愛敬(しゆにんあいぎやう)〔見物人からあまねく愛敬されること〕をもて、一座建立〔一座が繁榮していくための〕の壽福とせり。故に、餘(あま)り及ばぬ風體のみなれば、また、諸人の褒美缺(か)けたり。このために、能に初心を忘れずして、時に應じ、所によりて、愚かなる眼にもげにもと思ふやうに能をせん事、これ、壽福なり。よくよく、この風俗の極めを見るに〔世の習わしの根本に照らして考えてみると〕、貴所・山寺・田舎・遠國・諸社の祭禮に至るまで、おしなべて、譏(そし)りを得ざらんを、壽福の達人の爲手(して)とは申すべきか。されば、いかなる上手なりとも衆人愛敬(しゆにんあいぎやう)缺けたる所あらんを、壽福増長の爲手とは申し難し。しかれば、亡父は、いかなる田舎・山里の片邊(かたほとり)にても、その心を受けて、所の風儀を一大事にかけて、藝をせしなり。(75~76頁)
■およそ、花傅の中、年來稽古より始めて、この條々を注(しる)す所、全く、自力より出づる才覺ならず。幼少より以來(このかた)、亡父の力を得て人と成りしより二十餘年が間、目に觸(ふ)れ、耳に聞き置きしまま、その風を承(う)けて、道のため、家のため、これを作する所、私あらんものか。(78~79頁)
■一、作者の思ひ分くべき事あり。ひたすら静かな本木(もとき)の音曲ばかりなると、また、舞・働きのみなるとは、一向きなれば、書きよきものなり。音曲にて働く能〔謡をもとにして所作をする能〕あるべし。これ、一大事なり。眞實面白しと感をなすは、これなり。聞く所は、耳近かに、面白き言葉にて、節のかかりよくて、文字移りの美しく續きたらんが、殊さら、風情を持ちたる詰め〔演技の面白さを伴う一曲のやま〕を嗜(たしなみ)みて書くべし。この數々相應する所にて、諸人(しょにん)一同に感するなり。
さるほどに、細かに知るべき事あり。風情を博士(はかせ)にて〔所作を基準として〕音曲をする爲手(して)は、初心の所なり。音曲より働きの生ずるは、劫(こふ)入りたる故〔年功を積んだため〕なり。音曲は聞く所、風體は見る所なり。一切の事は、謂はれを道にしてこそ、萬(よろず)の風情にはなるべき理(ことわり)なれ。謂はれを現はすは、言葉なり。さるほどに、音曲は體(たい)なり、風情は用なり〔耳に入る音曲は體で、それから生ずる、眼に見える姿は用である〕。しかれば、音曲より働きの生ずるは、順なり。働きにて音曲するは、逆なり。諸道・諸事において、順・逆とこそ下(くだ)るべけれ。逆・順とはあるべからず。返す返(がえ)す、音曲の言葉の便りをもて、風體を彩り給ふべきなり。これ、音曲・働き、一心になる稽古なり。
さるほどに、能を書く所に、また工夫あり。音曲より働きを生じさせんがため、書くところをば、風情を本(ほん)に書くべし。風情を本に書きて、さて、その言葉を謡ふ時には、風情おのづから生ずべし。しかれば、書く所をば、風情を先立てて、しかも、謡ひの節かかりよきやうに嗜むべし。さて、當座の藝能に至る時は、また、音曲を先とすべし。かように嗜みて、劫入(こふい)りぬれば、謡ふも風情、舞ふも音曲なりて、萬曲一心たる達者〔あらゆる能を、音曲・風體一心に演じ得る達者〕となるべし。これまた、作者の高名なり。(83~84頁)
■一、能に、強き・幽玄・弱き・荒きを知る事、大方は見えたる事なれば、たやすきやうなれども、眞實これを知らぬによりて、弱く、荒き爲手(して)多し。先ず、一切の物まねに、偽(いつは)る所〔眞實でない所。ほんとうの物眞似になっていない所〕にて、荒くも弱くもなると知るべし。この境、よきほどの〔いいかげんな〕工夫にては、紛(まぎ)るべし。よくよく、心底を分けて案じ納むべき事なり。
先ず、弱かるべき事を強くするは、偽りなれば、これ、荒きなり。強かるべき事に強きは、これ、強きなり。荒きにはあらず。もし、強かるべき事を、幽玄にせんとて、物まね似たらずば、幽玄にはなくて、これ、弱きなり。さるほどに、ただ、物まねに任せて、その物に成り入りて、偽りなくば、荒くも弱くもあるまじきなり。また、強かるべき理(ことわり)過ぎて強きは、殊さら荒きなり。幽玄の風體よりなほ優しくせんとせば、これ、殊さら弱きなり。
この分け目をよくよく見るに、幽玄と強きは別(べち)にあるものと心得る故に、迷うなり。この二つは、その物の體にあり。例えば、人においては、女御(にようご)・更衣、または、遊女・好色〔美女〕・美男・草木には花の類(たぐ)ひ、かやうの數々は、その形、幽玄の物なり。また、あるいは武士(もののふ)・荒夷(あらえびす)、あるいは鬼・神、草木にも松・杉、かやうの數々の類ひは、強き物と申すべきか。かやうの萬物の品々を、よくし似せたらんは、幽玄の物まねは幽玄になり、強きはおのづから強かるべし。この分け目をばあてがはずして〔考慮しないで〕、ただ幽玄にせんとばかり心得て、物まねおろそかなれば、それに似ず。似ぬをば知らで幽玄にするぞと思ふ心、これ、弱きなり。されば遊女・美男などの物まねをよく似せたらば、おのづから幽玄なるべし。ただ、似せんとばかり思ふべし。また、強き事をも、よく似せたらんは、おのづから強かるべし。(85~86頁)
■そもそも、花と云ふに、萬木千草において、四季(折節)に咲く物なれば、その時を得て珍しき故に、翫(もてあそ)ぶなり。申樂も、人の心に珍しきと知るところ、卽(すなは)ち面白き心なり。花と、面白きと、珍しきと、これ三つは、同じ心なり。いづれの花か散らで殘るべき。散る故によりて、咲く比(ころ)あれば、珍しきなり。能も住(ぢゆう)する所なきを、先ず、花と知るべし。住せずして、餘(よ)の風體(ふうてい)に移れば、珍しきなり。
ただし、様(やう)あり。珍しきといへばとて、世になき風體をし出(い)だすにてはあるべからず。花傅に出だす所の條々悉(ことごと)く稽古し終りて、さて、申樂をせん時に、その物數を用々に従ひて、取り出だすべし。花と申すも、萬(よろず)の草木において、いづれか、四季(折節)の、時の花の外に、珍しき花のあるべき。その如くに、習ひ覺えつる品々を極めぬれば、時・折節の當世を心得て、時の人の好みの品によりて、その風體を取り出だす、これ、時の花の咲くを見んが如し。花と申すも、去年(こぞ)咲きし種なり。能も、もと見し風體なれども、物數を極めぬれば、その數を盡(つく)す(ほど)久しし。久しくて見れば、また珍しきなり。(92~93頁)
■物まねの鬼の段に、「鬼ばかりをよくせん者は、鬼の面白き所をも知るまじき」と申したるも、物數を盡(つく)して、鬼を珍しくし出だしたらんは、珍しき所花なるべきほどに、面白かるべし。餘の風體はなくて、鬼ばかりを(をする)上手と思はば〔(見物人が)あのシテは鬼ばかりを演ずる上手だと思っていたのでは〕、よくしたりとは見ゆるるとも、珍しき心あるまじければ、見所に花はあるべからず。「巌(いはほ)に花の咲かんが如し」と申したるも、鬼をば強く、恐ろしく、肝を消すやうにするならでは、およその風體なし。これ、巌なり。花といふは、餘の風體を残さずして、幽玄至極の上手と人の思ひ慣れたる所に、思ひの外に鬼をすれば、珍しく見ゆるる所、これ、花なり。しかれば、鬼ばかりをせんずる爲手(して)は、巌ばかりにて、花はあるべからず。(94~95頁)
■一、能に十體(じつてい)〔物まねのあらゆる風體〕を心得べき事。十體を得たらん爲手は、同じ事を、一廻り一廻りづつするとも、その一通りの間久しかるべければ、珍しかるべし。十體を得たらん人は、その内の故實・工夫にては、百色(ももいろ)にも亙(わた)るべし。先づ、五年・三年の中(うち)に一遍づつも、珍しくし替ふるやうならんずるあてがひ〔とりはからい。計畫〕を持つべし。これは、大きなる安立(あんりふ)〔安心立命の略。心頼み〕なり。または、一年の中(うち)、四季折節をも心に掛くべし。また、日を重ねたる申樂、一日の中(うち)は申すに及ばず、風體の品々を彩るべし。かやうに大がう〔大庭の晴れの演能〕より初めて、ちちとある事までも自然々々に心に掛くれば、一期、花は失せまじきなり。
また云はく、十體を知らんよりは、年々去來の花を忘るべからず。年々去來の花とは、例へば、十體とは物まねの品々なり。年々去來とは、幼かりし時の粧ひ、初心の時分の態(わざ)、手盛(てざか)り〔わざに油ののった30前後の頃〕の振舞、年寄りての風體、この時分々々の、おのれと身にありし風體を〔しぜんと身に備わっていた風體〕、皆、當藝に一度に持つ事なり。ある時は兒(ちご)、若族(にゃくぞく)の能(か)と見え、ある時は年盛りの爲手(して)かと覺え、または、いかほども臈たけて〔年劫を經て〕、劫入りたるやうに見えて、同じ主とも見えぬやうに能をすべし。これ、卽(すなは)ち、幼少の時より老後までの藝を一度に持つ理(ことわり)なり。さるほどに、(年々(としどし))去り來る花〔年齢に應じて、過去に身につけた花と、將來身にそなわるべき花〕とは云へり。(99~100頁)
■されば、初心よりの以來(このかた)の、藝能の品々を忘れずして、その時々、用々に従ひて取り出だすべし。若くては年寄の風體、年寄りては盛りの風體を殘す事、珍しきにあらずや。しかれば、藝能の位上れば、過ぎし風體をし捨てし捨て忘るる事、ひたすら、花の種を失ふなるべし。その時々にありし花のままにて、種なければ、手(た)折れる(枝の花)の如し。種あらば、年々時々の比(ころ)に、などか逢はざらん。ただ、返す返す、初心を忘るべからず。されば、常の批判〔常々聞かれる批評のことば〕にも、若き爲手(して)をば、「早く上(あが)りたる」、「劫(こふ)入りたる」なと譽め、年寄りたるをば、「若やぎたる」など、批判するなり。これ、珍しき理(ことわり)ならずや。十體の内を彩らば、百色(ももいろ)にもなるべし。その上に、年々去來の品々を、一心當藝(いつしんたうげい)に〔一身に當座の藝として〕持ちたらんは、いかほどの花ぞや。(101頁)
■一、因果の花を知る事、極め〔究極。極意〕なるべし。一切、みな因果なり。初心よりの藝能の數々は、因なり。能を極め、名を得る事は、果なり。しかれば、稽古するところの因おろそかなれば、果を果すことも(難し)。これをよくよく知るべし。また、時分〔時の運〕にも恐るべし。去年盛りあらば、今年は花なかるべき事を知るべし。時の間(ま)にも、男時(おどき)・女時(めどき)とてあるべし。いかにすれども、能にも、よき時あれば、必ず、また、わろきことあり。これ、力なき因果〔人力ではどうすることもできない因果〕なり。これを心得て、さのみ(に)大事になからん時の申樂には、立合い勝負に、それほどに我意執(がいしふ)〔我意を張ること〕を起さず、骨をも折らで、勝負に負くるとも心に懸けず、手を貯(たば)いて〔わざに餘裕を殘しておいて〕、少な少なと〔控え目に〕能をすれば、見物衆も、これはいかやうなるぞと思ひ醒めたる〔感興がうすらいでいる。興ざめしている〕所に、大事の申樂の日、手立てを變へて、得手の能をして、精勵(せいれい)を出だせば、これまた、見る人の思ひの外なる心出で來れば、肝要の立合、大事の勝負に、定めて勝つ事あり。これ珍しき大用〔珍しさの大きなはたらき〕なり。これほどわかりつる因果に、またよきなり。(106頁)
(2012年4月7日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上)』 杉浦明平訳 岩波文庫
■失われうるものを富と呼んではならない。徳こそ本当のわれわれの財産で、それを所有する人の本当の褒美なのである。徳は失われえない、まず生命がわれわれをはなれぬかぎり、われわれを見捨てない。財貨や外面的な富はいつもこれをびくびくしながら保っているが、一旦所有財産をうしなうと、しばしばその所有者を侮辱のうちに見捨て嘲弄の的にする。(33頁)
■経験のうちに存しないものを経験から期待するものは道理にはずれている。(33頁)
■食欲なくして食べることが健康に害あるごとく、欲望を伴わぬ勉強は記憶をそこない、記憶したことを保存しない。(35頁)
■鉄が使用せずして錆び、水がくさりまたは寒中に凍るように、才能も用いずしてはそこなわれる。(35頁)
■同じ眼でながめた対象があるときは大きく、あるときは小さく見える。(36頁)
■どのようなものであれ認識するということは常に知識に有益である。けだし無用なものを自分から追い放ってよきものを保存することができるであろうから。それゆえ、まず第一にその物の認識を有たないならば、いかなるものを愛することも憎むこともできぬ。(37頁)
■十分に終わりのことを考えよ。
まず最初に終わりを考慮せよ。(33頁)
■「幸福」が来たら、躊らわず前髪をつかめ、うしろは禿げているからね。(40頁)
■穴は掘るもののうえに、穴は崩れる。(41頁)
■壁を崩すもののうえに、壁は崩れる。(41頁)
■木は自分の破滅をもって木を伐るものに復讐する。(41頁)
■こわがればこわがるほど、逃げれば逃げるほど、近くによってくるものがある。それは貧窮だ、逃げれば逃げるほど、君は悲惨になり安らぎをうしなう。(41頁)
■堅忍不抜(コンスタンツィア)、はじめる人は必ずしも守る人ではない。(42頁)
■鋳物は型次第。(43頁)
■生のわれ甕は作り直せるが、焼いたのはだめ。(45頁)
■自由のあるところに秩序(レゴラ)はない。(45頁)
■孤りなればおとなしく虫も殺さざるもの、悪しき仲間ゆえに戦慄すべき獰猛なるものとなり、残酷極まりなくも多数の人々の生命をうばわん。洞窟より現るる霊魂なき物にしてかれらを防がずんば、さらに数多の人をも殺すべし。――自分一人では決して誰にも害をはたらかぬ刀や槍について。(164頁)
■「絵画」は「彫刻」よりも大きな知的論究を要し、より偉大なる技術的至驚異に属する。というわけは、必要に従って画家の知性(メンテ)は自然の知性そのものに変らざるをえず、かつ自然法則によって必然的に生せしめられたもろもろの現象の原因を芸術を以て解釈することによって、その自然と芸術との間の通訳者たらざるをえないからである。また眼を取り囲む対象の映像がどのように本当の相似光素(シムラクリ)となって瞳に集るか、大きさの等しい諸対象のうちいずれがより明るく、又はより暗く見えるか、等しい低さのもののうちいずれが多少とも低く見えるか、等しい高さにおかれたもののうち、いずれが多少とも高く見えるか、相異る距離におかれた等しい対象のうち何故甲は乙よりはっきり見えないのかということをも通訳するのである。かかる芸術は自己のうちにありとあらゆる可視物を包みとらえている。しかるに「彫刻」の貧困、すなわちあらゆる物象の色彩とその縮小〔の欠除〕はそうすることをゆるさない。この〔縮小法〕が透明な物象を形象化すのだが、彫刻家は細工をせずに自然のものを君に見せるだろう。画家は対象と眼との間に介在する空気の色合いの変化によってさまざまな距離を君に示すだろう、かれは霧を〔描く〕、対象の光素は辛うじてその霧を透過する。かれは雨を〔描く〕、そのうしろには山や谷とともに、雲があらわされる。かれは埃を〔描く〕、埃のなかに、またそのうしろに埃をおこしたものらの戦闘があらわされる。かれは多少とも濁った河〔を描く〕、この中でかれは水面と水底との中ほどであそびたわむれるうろくずを見せてくれるだろう。かれは、水面の底、緑なす草にかこまれた川底の洗われた砂のうえに色とりどりのきれいな甕がおかれているのを〔描く〕し、かれはわれわれの頭上さまざまな高みにある星辰その他同様に無数の現象を〔描く〕が、「彫刻」はそういう現象に及びえないのである。(206~207頁)
■私は「絵画」に劣らず「彫刻」に骨折り、どちらをも同じ程度に作るのであるが、両者いずれがより大きな天才と困難と完璧とを要するか、たいした非難もうけずに、宣告を与えることができるようにおもう。第一に、「彫刻」は一定の、すなわち上からの光に左右されるが、「絵画」はいたるところに光と影とをたずさえてゆく。しかも光と影は「彫刻」に大切なものなのである。彫刻家はこの場合、おのずからそれを生む盛上げ(リレーヴォ)の性質(ナトウラ)に援助してもらうが、画家は人為的な技術によって、自然が理屈に合ったようにつけるのと同じ場所に光と影とをつける。彫刻家は物体の色彩の相異なる性質に応じて変化を与えるわけにゆかない、が「絵画」はいかなる点にも欠けるところがない。彫刻家の遠近法〔浅浮彫〕は全然本当らしく見えない、が画家のそれは作品から何百マイルかなたのように見える。空気遠近法はかれら〔彫刻家〕の作品とは縁遠い。かれらは透明な物体を形象化しえず、発光するものを形象化することができぬ、反射光線もだめ、鏡のような光る物体や同じく艶のあるものもだめ、霧もだめ、曇った天気もだめ、限りないものがだめなのだが、退屈を慮って言わないでおく。(207~208頁)
■画家は万能でなければ賞讃に値しない――画家の心は鏡に似ることをねがわねばならぬ。鏡はつねに自分が対象としてもつものの色に変わり、自分の前におかれるものそのままの映像によって自己を満たすものである。従って、画家よ、君は自分の芸術をもって「自然」の産み出すあらゆる種類の形態を模造する万能な先生にならぬかぎりは、立派な画家たりえぬと知らなければならぬ。しかるに君はそれ〔あらゆる種類の形態〕を見てこれを頭に写しておかぬかぎり、これをなしがたいにちがいない。それゆえ君は野辺をゆくときには、種々の対象に判断力を向け、次々にこのものあのものと目を配りつつ、余り上等でないものの中から選択された各種の事物を一まとめにしなくてはならない。そして、自己の空想に倦み疲れると、仕事をやめて、散歩によって運動をとるけれど、頭には疲労を持ちつづける、そこらの画家たちのようにしてはならぬ。連中は種々の物象に気をとめようともしないどころか、しばしば、友人や親戚に出会って挨拶されても、これを見もせず聞きもせず、まるで何処を風が吹いていると思ってるのに異ならない。(211~212頁)
■画家は「自然」を師としなければならぬ――画家が手本として他人の絵を択ぶならば、かれは取柄の少い絵をつくるようになるだろう。然るに自然の対象をまなぶならば、立派な成果をあげるであろう、われわれがローマ以後の画家においてみとめるように。――中略――
私はこれらの数学的な仕事について、もっぱら粉本のみを学んで自然の作品を学ぶことをしない人々は、立派な作家の先生たるあの自然の嫡子ではなく、人工による甥〔即ち私生児〕にすぎないと言いたい。その自然の弟子にすぎぬ作家たちを放擲して、自然から習う人々を非難する者が愚の骨頂であることをよくきいておきたまえ。(214頁)
■顔を自然そのままに写すのを専門の業とするあらゆる人々は、一般に、よく似た顔をかく人ほど、他のどの画家よりも歴史画構成に拙劣なのをわたしは見てきた。こういうことが生じる所以は、一つの対象だけをより巧みに描くということは、自然がその人をば他の対象よりそういう対象にそれだけ適するように作ったこと、明瞭であり、このゆえにかれはそれだけ多くの愛情をもち、その大きな愛情がかれをそれだけ勤勉にしたわけだが、一部分にそそがれた分の愛情が全体には欠けているからである。何故ならかれは個のために普遍を捨てて、自分の好みのすべてをもっぱらその対象に集注するからである。――中略――
上に述べたような画家たちも、画のうちただ人間の顔だけしか好まないのだから、如上の働きをする。しかももっとわるいことには、かれらは芸術でも自分の好みに合った部分、または自分の判断できる部分しか認めない。そしてかれらの懶惰(らんだ)とものぐさ両方のために、その作品に全然動きがないものだから、かれらは、自分のかいた画より大きな迅速な動きをもっている作品をば、狐憑きやモール踊りの教師みたいだと言って、非難するのである。(215~216頁)
■つまり銭をふんだんに有っていても、君はそれを使いつくすわけにはゆかず、従って君のものではない、使えない財産はすべて一様にわれわれのものなのであって、君が自分の生活の役に立たないほど儲けてもそれは悉(ことごと)く君の意のままにならぬ他人の掌に握られている〔も同様な〕のである。しかし2つの遠近法の理論によって研究しよく推敲するならば、きみは銭よりも偉大な名誉を賦与する作品を残すことになるだろう。けだしそれのみがひとり名誉なのであって、銭を有っている人はそうではない。そういう人はしょっちゅう嫉妬羨望の的、泥棒のねらいの的となり、その生命といっしょに富豪の名声も消え去り、財宝の名はのこるが、財をためた人の名はのこらない。人間の技倆の名誉はかれらの財宝のそれよりはるかに偉大な光栄である。いかに数多の王侯が何の記憶ものこさずに過ぎさったことだろう!かれらは自己の名を残さんがために、一途に豪壮な生活と富とを求めたのである。技倆をゆたかならしめんがために銭の足りない生活をおくった人がいかにたくさん居ったことであろう!技倆がかの富にまさればまさるほどかかる願望は、金持よりも芸術の名人(ヴィルトオーソ)名を遂げるところとなるものだ。君は財宝というものが科学のようにそれ自身で金をためた人の名を死後まで揚げるものでないことを知らないのか。科学こそ永遠にそれを創った人の證據となりラッパとなる、けだしそれは、銭のように、継子ではなくて、それを生んだ人の娘だからである。
もた、もし君がその財貨によれば貧欲や色欲をよりよく満足さすことができるが、技倆ではだめだというなら、他の畜生同然、もっぱら汚らわしい肉体的欲望に仕えてきた他人のことをつくづく考えてみたまえ。一体かれらのどんな名が残るだろうか?もし君が生活の必要とたたかわねばならぬために研究したり自分を本当に立派な人間にする余裕がないと弁解するならば、それは君自身に罪を着せることにほかならない。けだし技倆の研究のみが霊肉の栄養だからだ。富豪に生まれながら、財宝によって汚されないため、自ら財宝と縁を断った哲学者がどんなに多いことであろう!
またもしも子供を扶養する必要があるからと弁解するなら、子供たちにはわずかなもので十分なのだから、忠実なる富である技倆を滋養となるようにするがいい。何故かなら技倆は、死なないかぎり、われわれを見捨て去ることがないのである。そしてもしも君が老後の年金(ドーテ)にするよう、予め一定の貨幣資本をこしらえておきたいというなら、この研究は絶対に著手されないだろうし、君を老熟させることもなく、技倆の容器〔たる頭〕は夢とむなしい希望でいっぱいになってしまうであろう。(217~218頁)
■絵画はまずそれを思索する人の脳裡に存在するが、手の操作をまたずには完全なものになりえない。この絵画の科学的で真の原理は第1に、陰翳のある物体とは何か、根源的な影および派生的な影とは何か、明暗すなわち、闇、光、色彩、形態、情景、遠近、運動および静止とは何かを定めることであるが、以上のものは手の労働を経ずもっぱら頭脳によってのみ把握せられる。これこそ絵画の科学〔たる所以〕であろう。すなわち絵画は観照者の脳裡に存し、しかるのち上述の観照または科学よりはるかに立派な制作活動が生れるのである。(224頁)
(2012年4月20日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『100年の難問はなぜ解けたのか』 春日真人著 新潮文庫
■しかし、だからといって、ペレリマン博士が金銭的に余裕のある生活をしていたわけではない。当時は自分と母親の二人の暮しを月々5000ルーブル(約2万2000円)の給料で支えていた。給料の振り込みが少しでも遅れると深刻な顔でタマーラさんのもとにやってきて、今月はまだ給料が入っていないのだが、と訴えたという。
「つまりペレリマンは、自分の決めた行動原理を守っているだけなのです。このことは私の知る限り、多くの数学者に共通した特徴と言えます。彼らの多くは自分が決めた原則に忠実で、他人との人間関係のためにその原則を曲げることは稀です。ですから、ペレリマンの行動を社会一般の基準と比べることにまったく意味はありません。そういう意味では、私はペレリマンの取った行動を理解できないというより、むしろもっともなことだと思っています」(30~31頁)
■ボエナル博士は授業の最後、地球儀にアリの絵を描いてこう説明した。
「地球の表面にいるアリが地球の『形』を知るのは、とても難しいことです。地球の外には出られませんからね。同じように、人間は宇宙の外に出ることはできません。ポアンカレは、宇宙の外に出なくても、宇宙の形を知る手がかりがあるはずだと予想したのです」(58頁)
■数学の命題であるはずのポアンカレ予想が、なぜ宇宙の形にかかわるのだろうか?
不思議に思っている方のために、なるべく数学的な表現から逃げないようにしてポアンカレ予想をひもといてみよう。
本来の記述は、「単連結な3次元閉多様体は、3次元球面に同相である」。聞き慣れない単語を、それぞれすこしずつ言い換えてみる。
・単連結=その表面にロープをかけたときに必ず回収できる
・3次元閉多様体=4次元空間の表面
・3次元球面=丸い4次元空間(4次元球)の表面
・同相=同じ
全部合わせると、こう読み換えられる。
「ロープをかけたとき必ず回収できる4次元空間の表面は、4次元球の表面と同じである」(62頁)
■ハーケン博士が初めてポアンカレ予想に出会ったのは大学生のときだ。最初はやさしい問題だと思ったのだが、やがて、一度入り込んだら決して抜け出すことのできない底なし沼のような存在となってゆく。
「ポアンカレ予想を初めて目にしたとき、ひどく簡単そうに見えました。『証明が見つからないのは、私がバカなのか、十分に努力していないのか、のどちらかだ』と思ったほどです。若かったから……としか言いようがありません。
思えば4色問題も、似たような歴史を辿りました。1900年代初め、ドイツの有名な数学者ヘルマン・ミンコフスキーが4色問題の噂を聞き、『そんな簡単な問題が証明されていないのは、一級の数学者が取り組んでいないからに違いない』と考え、自ら4色問題に取り組んだのです。
当時はまだ『ゲーデルの不完全性定理』もなかった時代ですから、数学には解決できない問題があるという考え方すら存在しません。ミンコフスキーは『解決は簡単だ。単に思考が妨害され、どうやるか明確な方法が見えないだけだ』と思ったのです。しかし挑戦を1年続けたあと、彼は認めました。『神は我々に研究を続けてほしくないのであろう』と。
数学者として成功するためには、ある意味で非常に楽観的でなければならないし。しかし優れた楽観主義者も、ときには大きな間違いに陥るのです」(93~94頁)
■この頃、ハーケン博士やパパ(岡野注;パパキリアコプロス)を悩ませていたのは、宇宙空間でできるロープの結び目だった。宇宙を一回りさせたロープを回収しようとすると、いわばロープが複雑に絡まり、結び目ができてしまうのだ。結び目の問題を解決しなければポアンカレ予想の証明には辿り着けない。ふたりには、どうしてもその方法がわからなかった。
「いつも証明の98パーセントまでは簡単に辿り着くのですが、あと一歩で失敗しました。でもそのうちに解決策が見つかり、しばらくはそれに夢中になる。それがダメだとわかる頃、また他にアイデアがでてくる。そうやって精神的に振り回され、ドンドンはまりこんでいきました。最初持っていた希望はやがて絶望に代わり、最後には自分の怒りをコントロールできなくなる。それが、ポアンカレ予想の罠なのです」(ハーケン博士)(95頁)
■「私はこう思いました。自分はポアンカレ予想の証明に98パーセント近づいているどころか、遙か遠くにいるのではないかと。なにしろ、非常にシンプルな特別な例だけを取り上げても正しいと証明できないのですから。そこで私は、反例を見つける試みをシステマティックにやってみようと思いついたのです」
つまり、たとえ宇宙にまわしたロープが回収できたとしても、その宇宙が丸いとは限らないのではないか?というのである。ハーケン博士は、当時まだ珍しかった電子計算機を使って「ロープが回収できる、丸くない宇宙の例」を探し始めた。
そしてある日、ハーケン博士はパパに自分のアイデアを打ち明けた。
「ポアンカレ予想は間違っているかもしれない、と私が言った途端、パパはこの上なく不愉快だという顔をしました。それはいわば、この世はパパにとって意味がないというのに等しいものだったからです。彼がポアンカレ予想に対して抱く宗教のような信念を打ち砕く、恐ろしい一言だったのかも知れません」――中略――
次の週、コモン・ルームのいつもの場所で平穏に座っているパパを見つけました。もう苛立ってはいませんでした。私が『誰かがポアンカレ予想をコンピューターで解くのを心配していないのですか』と聞くと、彼は落ち着いて答えました。『心配したよ。でも、この週末考えたんだ。そして数学は自己防御するはずだと決めたんだ』。
パパは数学の深さを信じていました。数学は長年培われた人類の知恵の集合体で、いわばそれ自体に生命が宿っていると考えていたのです」(98~100頁)
■そしてハーケン博士はついに「ポアンカレ病」からの脱出に成功する。なんとその研究を中断し、代わりの難問を解決したのだ。
「長い間、ポアンカレ予想でひとつのアプローチにこだわりましたが、それはどうやらうまくいかないことがわかりました。ちょうどそのころ、4色問題に挑戦してみないかと数学者のハインリヒ・ヘーシュから連絡があったのです。彼が言うには、私が以前彼にアドバイスした計算機の設定の小さな変更によって、突然効率が20倍も良くなったとのことでした。私は思いました。『すごい。ポアンカレ予想に1年かけるより、4色問題ではⅠ日、それも午後楽しく過ごすだけで、こんなに進展できる』。そこで、鞍替えしたらどうだろうという誘惑を感じたのです。
結局、私はポアンカレ予想では絶望のどん底に落ち込みましたが、4色問題ではどんどん成功し、ポアンカレ予想から抜け出すことができました。ポアンカレ病を重度にすることなく、回復することができたのです」
ハーケン博士が4色問題の証明に成功したのは、パパが亡くなってからわずかひと月後のことだった。
ポアンカレ病から抜け出すために、新たな難問を必要とした博士。数学者とは結局、「難問に挑み続ける」という病から逃れられない生きものなのだろうか。(103~104頁)
■ふたりの数学者の物語を取材した最後、私たちはプリンストン大学の共同墓地を訪ねた。パパキリアコプーロス博士が葬られている可能性があると聞いたからだ。
だが、この共同墓地に葬られているという記録は存在しなかった。アメリカに身寄りのなかったパパは、葬式すらおこなわれなかったという。生前に親しかった数学者の中にも、彼の墓の場所を正確に知る人はいない。
パパは不幸な人生を送ったのだろうか。そうではないとカペル博士は言う。
「パパはよく私に言ったものです。自分の人生を他人に勧めようとは思わないが、自分はこれで良かったんだと。その気持はわかります。数学者が難問に惹かれる気持ちは、皆同じですから。
数学者は常に、楽しみと苦痛とが織りなす日常、そして『特別な数学の世界』とのあいだを往き来しています。数学の世界への扉を開けられる者は限られていますが、そこには永遠の真理があり、すべてを理解できる者だけが、その世界で完璧な美を目撃することができるのです。まるで迷宮に迷い込んでしまったかのように、クリスタルの壁に乱反射する美しい光に数学者は思わず取り憑かれてしまうのです。
多くの数学者を凌駕する存在だったパパは、自分の人生のほとんどを、その『もうひとつの世界』で過ごすことに決めました。ときどき、食事とお茶のために日常の世界に出てきましたが……。彼がその世界で見つけた最後の宝物が『ポアンカレ予想』でした。最終的にはその世界から舞い戻って、究極の美しさを見つけたよと報告したかったはずです。さぞ無念だったでしょう。しかしこれは、科学の世界ではよくある話です」(105~106頁)
■「間違っているのは明らかなのに、証明の中の欠陥に気づかない。原因は自信過剰や興奮状態、あるいは過ちを犯すことへの恐怖により、正常な思考が邪魔されることである。こうした落とし穴に陥らない方法を、若い数学者が見つけてくれることを祈る」(ジョン・ストーリング博士)(109頁)
■クルト・ゲーデル(1906~1978)が1931年に発表した数学基礎論および論理学における重要な定理。数学は自己の無矛盾性を証明できないことを示したもので、正確にはふたつの定理からなる。
・第1不完全性定理
「いかなる論理体系においても、その論理体系によって作られる論理式の中に、証明することも反証することもできないものが存在する」
・第2不完全性定理
「いかなる論理体系でも、それが無矛盾であるとき、その無矛盾性をその体系の中だけでは証明できない」
「数学には、証明できない命題が存在する」ことを初めて示したこの定理は、数学界に計り知れない衝撃を与えた。「無矛盾性、完全性などが有限の立場で遠からず証明できるであろう」と宣言したドイツの大数学者ダフィット・ヒルベルト(1862~1943)の楽観的な期待を裏切り、多くの数学者を夜も眠れぬほどの不安に陥れた。
■サーストン博士の専門は双曲幾何学である。双曲幾何学とはユークリッド空間のような「まっすぐな空間」(曲率が0の空間)ではなく、負の曲率を持つ曲がった空間「双曲空間」の中で定義される幾何学だ。馬の鞍のような形がその典型である。ちなみに「丸い空間」(曲率が正の空間)で成り立つ幾何学を「球面幾何学」と呼び、ポアンカレ予想に出てくる「丸い宇宙」も、この幾何学が成立する空間である。
「双曲幾何の世界というのは、モノを見失いやすい世界です。理由をご説明しましょう。あなたは今、私から3メートル離れた距離にいます。その地点から歩いて私から離れて行けば、当然あなたの姿は小さくなっていきます。私たちが暮らすユークリッド空間では、3メートルの距離にいたあなたの大きさが半分になるには倍の6メートル離れれば良い。12メートル離れれば4分の1、24メートルで8分の1の大きさになります。2倍の距離を離れれば、サイズは半分になるのです。(岡野注;遠近法と、実際の眼球の見えとは違っている。網膜の面は球面なので写真や遠近法では、肉眼より近景が大きく遠景が小さく透写される)
ところが双曲空間の中では、もっと急激にサイズが小さくなります。3メートルから6メートルに離れれば半分のサイズになりますが、9メートルで4分の1、12メートルで8分の1、24メートルでは1000分の1、60メートルでは100万分の1のサイズになります。
もしあなたが私の子どもだったら、すぐ迷子になって私は大パニックです。もし飛行機のパイロットが双曲空間の中を飛び回ったら、簡單に軌道を見失って、2度と地球への帰り道を見つけることはできないでしょう」(岡野注;老人は大変だろうが、その空間で生活すれば若い人はすぐに慣れるだろう。つまり、世界認識を組み替え直せばよいのだから。もちろん、その空間に生まれ育てばなんの問題もない。例、逆さ眼鏡の実験)(147~148頁)
■ポアンカレ予想は、こう言っている。
「宇宙にロープを1周させて、その輪が回収できれば宇宙は丸いと言えるはずだ」
しかし気を付けて見てみると、この問いかけは「もしロープが回収できなかった場合、宇宙はどんな形をしているのか」については、まったく触れていないことがわかる。
サーストン博士が目をつけたのは、そこだった。
「宇宙が丸くないとすると、他にどんな形があり得るのだろう」
これが革命的なアプローチへの入り口だった。
「私は夢見たんです。宇宙が取り得る形を全部調べあげることはできないかと。無茶な挑戦だとおもったけれど、やってやろうと決心しました。もちろん最初は、考えられる宇宙のパターンをおぼろげに分類するのが精一杯でしたがね」
丸い形以外に、宇宙の形にはどんなものがあり得るのか。サーストン博士は身のまわりにある形をヒントに、その分類を始めたのだ。(152~153頁)
■博士は切り取った葉の「輪郭」をスケッチブックの上に乗せ、テープで固定した。すると、切り取る前にはくっついていた端と端が、交差したのだ!私とカメラマンは思わず声を上げてしまった。先ほどリンゴで見た「開いてしまった」状態とはまったく逆である。博士は、端と端が交差した(行き過ぎた)部分の「角度」を測った。
「角度は90°以上ですね……約100°だ。リンゴの場合とは反対に端と端が交差してしまったので、リンゴの曲率につけた+ではなく-を付けます。曲率は-100°です。曲率をπ(=180°)で表すと、-100π/180つまり-5π/9です。この測定値の意味がわかりますか。
例えば2つ穴のトーラスは、表面の曲率の合計が必ず-4πになることがわかっています。-5π/9の7・2倍です。ということは、この葉っぱを8枚集めてくっつければ、2つ穴のトーラスを作るのに十分だということなのです。いま手軽に測った曲率ですが、その背景には非常に美しく厳密な理論が隠れているのです」(156~157頁)
■――この葉っぱのように、幾何学やトポロジーの原則を美しく示す例は、日常生活や自然の中で簡單に探せるものですか。
「今の質問はとても重要です。あなたは『幾何やトポロジーは日常生活の中にあるのか』と聞いたのではなく、『日常生活の中に探せるか』と聞きましたね。幾何やトポロジーを探す視点がすでにあるなら、生活のあらゆるところに見つかるはずです。
数学の本質とは、世界をどういう視点で見るかということに尽きます。数学的な考え方を学べば、日常はまったく違って見えてきます。文字どおりの『見る』、つまり網膜に映るという意味ではありません。学ぶことによって見えてくるという意味です。
新しい言葉を学ぶと、それまでその言葉にまったく出会ったことがないのに、次の日に出会ったりして不思議に感じます。それと同じことです。物事を習うことは、物事を見ることです。あなたにとっては、もう幾何やトポロジーは生活の至るところにあるはずです」(157~159頁)
■様々なモノの形を通して、サーストン博士はこう確信した。世の中には、丸いモノよりむしろ、そうでない形が多い。
だが、手にとって見ることができる形を分類するのはまだ簡單だ。かってポアンカレがやったように、リンゴは丸い形の代表。それ以外は穴の数で分類することができた。
問題は、宇宙のように「決して外から眺めることができない」形を、どうやって分類すればいいのか……。
10年以上にわたる試行錯誤の末、サーストン博士は驚くべき結論に達した。
1982年に発表された論文 ‘ Three dimensional Manifolds, Kleinian Groups and Hyperbolic Geometry ’(「3次元多様体、クライン群、そして双曲幾何」)の中で、博士はあるひとつの壮大な予想を述べている。
「宇宙がたとえどんな形であろうとも、それは必ず最大で8種類の異なる断片から成り立っているはずだ」
この大胆な予想は、サーストンの「幾何化予想」と名付けられた。
サーストン博士は幾何化予想を、よくオモチャの万華鏡にたとえて説明するという。
万華鏡を回したときに見える模様は実に変幻自在で、同じ模様は2度と現れない。しかしもとを辿れば、いくつかの形の決まったビーズがその複雑な模様を作っているに過ぎない。
サーストン博士によれば、宇宙の形もまた同じ。宇宙がたとえどんなに複雑な形であったとしてもいわば8種類のビーズが絡み合ってできているはずだというのである。
つまり有限な数のビーズが、無限に複雑な図形を生み出す。同じように、宇宙が丸い以外のどんな形であったとしても、最大で8つの種類の断片がつながり合ってできているはずなのだ。
サーストン博士が提唱したこの「幾何化予想」は評価され、フィールズ賞に輝いた。それは数学者たちが、幾何化予想は、実はその一部にポアンカレ予想をも含む、壮大なる問いかけであると気づいたからだった。
もしサーストン博士の予想どおり、宇宙が最大8種類の断片の組み合わせでできていたとしよう。博士によると、その8つの断片とは、ひとつは丸い形で、それ以外は、ドーナツ形などの「丸くない」形である。
ここで、ポアンカレのロープを思い出してほしい。宇宙の断片の中に、ひとつでも「丸くない」形が含まれていた場合、ロープが引っかかって回収できないことに、数学者たちは気づいたのである。つまり、幾何化予想が正しいならば、ロープが回収できる宇宙はただひとつ、ポアンカレの予想どおり丸い形のみで作られている宇宙だけなのだ。(160~162頁)
■多くの数学者が長年、丸い宇宙(3次元球面)を念頭においてポアンカレ予想に取り組んできた。サーストン博士はなぜ、丸い宇宙にロープを巡らせるという発想から離れ、3次元の宇宙の形を全部リストアップしてみるという着想を得ることができたのだろうか。
「私は当たり前の考え方をしただけです。例えば1000ピースのジグソーパズルがあったとします。あなたが1000ピースのうち100ピースだけを渡されて、それを正しい位置に置こうとしても、まず無理でしょう。でも1000ピース全部を床に並べてみて、全体を眺めると、どう組み立てるべきかが簡單に見えてくるはずです」(163~164頁)
■博士は幾何化予想の証明をあきらめたのか、それとも敢えて続けなかったのだろうか。サーストン博士の真意を確かめるため、取材の終盤、思い切って聞いてみた。
――多くの数学者が、幾何化予想を提唱したあなたが、なぜそれを自分で根気良く追究しなかったのかと考えているようです。
「証明しようと努力はしたのです。でも私の考えたいくつかの方法は枯れてしまいました。追究しても可能性が見えない場合は、引き下がるのが賢明です。人生の目的はたったひとつではありません」
――あなたは自分ひとりで証明するというこだわりを捨て、敢えて周囲の数学者とのコミニケーションを大切にする道を選んだのではないですか。
「今では多くの数学者が、かって私がひとりで考えていたことを学んでいます。素晴らしいではないですか。多くの人が、幾何化や双曲幾何学など、私が背負ってきた研究分野に貢献してくれているのです。理解してくれる人が多くなって、昔のように寂しくなくなりました。私は身に沁みて知っています。最初に何かを考え出すとき、そこには孤独がつきものなのです」
博士はこの話題に関して、それ以上語ろうとはしなかった。(169~170頁)
■アンリ・ポアンカレはその著書「科学と方法」にこう書いている。
「数学とは、異なった事柄に同一の名称を与える技術である。言葉を適当に選べば、或る既知の対象について行なわれたすべての証明が直ちに多くの新しい対象についてもそのまま通用するのを見れば、まったく驚嘆に値するほどである」
ある一面では数学者とは、世の中に存在する無数の事柄のあいだに共通点を見出し、それに名称を与えて巧みに分類する仕事だ、と言えなくもない。(172頁)
■つまりポアンカレは「穴の数」を数えているように見せかけて、実は「表面の形」を見ていたわけである。これを数学的には「2次元多様体の分類」と呼び、この分類は20世紀初めにはすでに完成していた。(岡野注;双曲面、平面、2次元球面)
ポアンカレ予想「単連結な3次元多様体は、3次元球面に同相である」は、実はこの「2次元多様体の分類」を1次元上の3次元に置き換えた「3次元多様体の分類」にかかわるものだった。そしてその「3次元多様体の分類」を鮮やかに予想したのがサーストン、それを証明したのがペレリマンなのである。(173頁)
■双曲幾何学;19世紀前半にニコライ・ロバチェフスキー(ロシア)、ヤーノシュ・ボヤイ(ハンガリー)、フリードリッヒ・ガウス(ドイツ)らがそれぞれ独立に提唱した幾何学で、ボヤイ・ロバチェフスキー幾何学とも呼ばれる。非ユークリッド幾何学のひとつ。双曲幾何学が成り立っている空間を双曲空間と呼び、馬の鞍のような形がその典型とされる。ちなみに正の曲率をもつ「丸い空間」(曲率が正の空間)で成り立つ幾何学を「球面幾何学」と呼ぶ。(175頁)
■葉層構造論;自然界や身のまわりにある様々な模様のうちで層状に積み重なっているもの、例えば崖の断面に見える地層の模様、葉っぱの葉脈、木材の表面に現れる木目模様などを、葉層構造(foliation)という。サーストン博士によれば、葉層構造論とは3次元宇宙の表面に描かれたストライプ模様の研究のことだそうである。(176~177頁)
■世界の第一線の数学者たちが集い、しかも高収入が保証されるアメリカでの研究生活を捨て、故郷で難問に挑むというのは、数学者として大きな決断だったはずだ。
ペレリマン博士と同郷の先輩数学者ミハイル・グロモフ博士は、ペレリマン博士がふと漏らした言葉を覚えている。
「いつだったか私が、大きな難問に挑むのは魅力的だが大きければ大きいほど失敗したときのダメージは計り知れないと言ったのです。するとペレリマンは真面目な顔でこう答えました。『私には、何も起きない場合の覚悟がある』と」(191~192頁)
■イギリスの数学者G・H・ハーディーは、かってこう言った。
「物理学や化学における『真理』は時代によって移り変わる。しかし数学的真実は、1000年前も、そして1000年後も真実であり続ける」
実用的であることより、むしろ普遍的な真実であり続けることを望んできた数学者たち。だが数学を見つめる社会の目は、確実に変りつつあった。(193頁)
■――では100万ドルの賞金は、数学者が難問に取り組む一番の動機になるのでしょうか。
「それはあり得ません。この質問には、ひとりの数学者として答えさせてください。数学者が問題に挑む動機、それは未知なるものへの憧れです。数学者に意欲を起させるものは、子どもたちに意欲をおこさせるものとまったく同じです。ただ、知らないことを知りたいのです。
子どもは自分の周りの世界を理解したい生きものです。生まれついての科学者なのです。私たち数学者はいわば、大人になってもその好奇心を持ち続けているだけなのです。数学者の好奇心は、南極や北極やアマゾンを発見した探検家たちとも変わりません。いまやこの地球上では、まったく未開拓だと思われる場所はだいぶ少なくなってきました。でも頭の中の知的世界には、何の制限もありません。未知なるものは無限にあるのです」〔岡野注;「ミレニアム懸賞問題」と名付け、1問につき100万ドルを賞金として支払うと発表した、クレイ数学研究所(1998年設立、私設)の所長で数学者でもあるジム・カールソン博士の発言〕(199~200頁)
■数学者たちを苦しめていたのは、ペレリマン博士の証明の進め方だった。それはトポロジーの研究者たちが100年ものあいだ慣れ親しんで使ってきた手法とは、似ても似つかぬものだったのだ。
100年にわたるポアンカレ予想の研究について知り抜いているポエナル博士でさえ、圧倒されていた。
「トポロジーの専門家たちは、ペレリマンの話をまったく理解できませんでした。話の内容は確かにポアンカレ予想を扱っていたのですが、ついて行けなかったのです」
そして、トポロジーこそが数学の王者だと信じて研究を続けてきたジョン・モーガン博士は、とんでもないことに気づいていた。
「皮肉なことにその証明には、、トポロジーではない、あの『微分幾何学』が使われていたのです」
なんとペレリマン博士は、トポロジーの象徴と見なされてきた世紀の難問を、かつてトポロジーがふるくさいものとして退けた、「微分幾何学」の最新知識を駆使して解き明かしていったのである。
さらに証明には、「エネルギー」、「エントロピー」、「温度」などの言葉が頻繁に登場した。ペレリマン博士は、高校時代に育んだ物理学の延長線上にある熱力学の世界にまで立ち入って、難問に挑んでいたのである。
それはトポロジーこそが数学の王者であると信じてきた研究者にとって、とてつもない衝撃だった。
「まさに悪夢でした。私の知らない方法でポアンカレ予想が証明されてしまう瞬間を、ずっと恐れていたのです」(ヴァレンティン・ポエナル博士)
「そてまでポアンカレ予想に取り組んできた数学者は、証明が終わってしまったと落胆し、トポロジートの手法が使われなかったことに落胆し、さらに証明が理解できないと落胆しました。トポロジーの専門家たちは、『ああ、ついにが証明されてしまった。でも、自分にはその証明がまったく理解できない。誰か助けてくれ』という感じだったのです」(ジョン・モーガン博士)(207~209頁)
■短い散歩の間に、ペレリマン博士は驚くべき事実を次々と打ち明けた。
博士によればロシアに帰国して間もなく、1996年の2月には問題の突破口が見つかり、本格的な研究に取り組む決心をしたという。さらに驚いたことには、論文を発表する2年も前に既に問題を解決していたというのだ。2000年には問題を解いていたことになる。万が一ミスがあってはいけないと考え、証明が正しいと確信できるまで発表しなかったのだという。(211頁)
■だが、ペレリマン博士の証明を読み進めるのは至難の業だった。言葉遣いは極めて簡潔なのだが、博士が「自明」と考えている部分が省略されているため、初めて見る者には証明が飛び飛びに見えてしまうのだ。
「たとえば本文に、『単純な議論によって…AはBになる…』という言葉が頻繁に出てきます。しかしAとBは、普通すぐにはつながらない話なのです。ペレリマンは何を根拠にAとBをつなげたのか……。私たちはひたすら、彼の思考の道筋を追いかけて行ったのです」
ペレリマン博士の言う「AからB」をつなぐ道は、既存の論理の組み立てでは理解できない斬新なものばかりだった。しかしひとたび理解すると、その道以外には考えられないというほど単純な道だと気づいたという。そう気づいたときペレリマン博士は議論を省略したのではなく、確かに一度この道を歩いたのだと確信させられた、とジョン・モーガン博士は言う。
「数学でもっとも特別な瞬間は、問題を違った角度から眺めたとき、以前見えていなかったものが突然明確になったと気づく瞬間です。鬱蒼とした森だと思っていたのに、適切な場所に自分が立つと、木が整然と並んでいるのが見えるのです。他の角度から見るとその構造は見えずに、混沌とした木だけが見えます。でも、適切な方向に自分が向くと、突然、この構造が見えます。数学とはこのようなものです。私にとってペレリマンの論文はその連続でした。私は何度も『美しい』と思いました」(213~214頁)
■部屋の中でストーブに火をつけると、最初はその周りだけ暖かくなって、離れたところは寒いままだ。だが時間の経過とともに部屋全体が暖かくなり、そこで火を消すと、部屋の温度はだんだん均一になってゆく。つまり、最初は部屋の温度に凹凸があっても、それがだんだん均質になってゆくという現象である。
この熱方程式で扱っている「熱」を、「形(曲率)」に置き換えたのが、リッチフローなのである。いわば、「凹凸な形」を時間とともに「スムーズな形」に変化させる方程式なのだ。例えば、ギザギザな形をしたハンダにコテで熱を加えたとき、たとえ最初はどんな複雑な形でも、時間とともに丸い形に変化する……というようなイメージだ。
またはストローでシャボン玉を吹いたときのことを考えてみる。ストローから出たシャボン玉は、最初は凸凹を持ったグニャグニャな形だ。だが一定の時間を経れば必ず「きれいな球」になる。
形の凹凸をならしてスムーズにする。大ざっぱにいえば、それがリッチフロー方程式の役割なのだ。
このアイデアによってハミルトン博士は、切り分けた宇宙のピースの「形」を整えることに成功した……かに思えた。しかしこのアイデアには、やっかいな欠点があった。
宇宙の形を「シャボン玉」のように変化させるとき、その形はコントロールが難しく、ときに割れてしまう。ちょうどシャボン玉の膜が薄くなり、割れてしまうときのように。割れると宇宙の形そのものが消えてなくなり、計算が続けられなくなってしまうのだ。このような現象を数学的に「特異点が生じてしまう」と呼ぶのだが、ハミルトン博士はそこから先にどうしても進めなかった。(216~217頁)
■ブルース・クライナー博士は、難問が解決した背景は「ポアンカレ予想に応用できる数学のテクニックがようやく生まれたから」だという。だが同時に、ペレリマン博士が数学の幅広い分野にわたる知識を身につけることができる、極めて稀な「万能選手」であることを認める。
「数学において、ほとんどの人はふたつ以上の分野で重要な貢献をすることはできません。時間がかかるだけでなく、ふたつ以上の分野を習得するには、新しい考え方を一から再構築する必要があるからです。
ペレリマンはいわば、棒高跳びと100メートル競走、走り幅跳びと砲丸投げ、それらすべての種目で金メダルを取る能力を持った陸上選手のようなものです。これらの競技には違った筋力や精神力、違った訓練が必要です。重量挙げの選手はバーベルを持ち上げるために筋力を鍛える必要がありますが、それはマラソン走者の筋肉とは違います。ペレリマンのようにかけ離れたことを同時におこなう能力を持ち、かつそれが非常に高いレベルであることは、とても稀なことなのです」(223~224頁)
■「100年に1度の奇跡を説明するのは、実に困難です。しかし、ペレリマンが孤独に耐えたことが成功の理由かも知れません。孤独の中の研究とは、日常の世界で生きると同時に、めくるめく数学の世界に没入するということです。人間性をまっ二つに引き裂かれるような厳しい闘いだったにちがいありません。ペレリマンはそれに最後まで耐えたのです」
グロモフ博士は、世紀の難問を解決したこととフィールズ賞の拒否が、裏表の関係にあると考えている。
「彼は必要でないものを徹底的にそぎ落とし、社会から自分を遮断させて問題だけに集中しました。その純粋性が7年間もの孤独な研究を可能にし、同時にフィールズ賞を辞退させたのです。人間の業績を評価する場合、純粋性は大切です。なぜなら、数学、芸術、科学、何においても、堕落が生じれば消滅の途をたどってしまうからです。私たちの社会も、倫理の純粋性が一定のレベルで存在しなければ崩壊するでしょう。意識する、しないに関係なく、数学は何よりも純粋性に依存する学問です。自己の内面が崩れては、数学はできません」(224~225頁)
■特異点
数学において、与えられた数学的な対象が定義されない点、または微分可能性のように、ある性質がたもたれなくなるような例外的な集合に属する点をいう。
例えば、1/Xの値はX=1なら1、X=2ならば1/2、3なら1/3……等と定義できるが、X=0の場合だけは無限大になってしまって定義することができない。このとき、X=0は特異点であるという。
日常生活の例で言うと、例えば鉛筆の先、物体の輪郭のような、特別な点は「特異点」的な性格を持っていると言える。(227頁)
■・宇宙の年齢は、およそ137億歳である。
・宇宙の大きさは少なくとも780億光年以上である。
・宇宙の組成はおよそ5パーセントが通常の物質、23パーセントが正体不明の ダークマター、72パーセントがダークエネルギーだと考えられる。
・WMAPのデータに現在の宇宙モデルの理論を適用すると、宇宙は永遠に膨張を続けるという結果になる。
そして問題の「宇宙の形」である。
宇宙の形は通常、時空の曲率(曲がり具合)で表現される。宇宙に存在する物質の平均密度が臨界質量(10-29g /cm3)より上なら曲率がプラス、同じなら0、下ならばマイナスとなり、それぞれ「閉じた宇宙」、「平坦な宇宙」、「開いた宇宙」に対応する。現在、宇宙論の主流となる「インフレーション理論」は、宇宙の曲率は0だと予測していた。
そしてWMAPの観測結果は、理論を裏付けるものだった。宇宙の曲率は0、つまり平らだというのである。
だが、この結果は「宇宙の全体の形」を示しているわけではない。あくまでも部分的、局所的な宇宙の「曲がり具合」が平らだと言っているに過ぎないのだ。現在の最新技術をもってしても、広大な宇宙のほんの一部しか見られていない可能性が高いのだという。(229~230頁)
■かって人類は、地球をひたすら平らな平面だと信じていた。それと同じように、いま私たちは、ようやく大宇宙の渚に立ち、見える範囲の中だけで、宇宙の形の手がかりを摑もうとしているのだ。(231頁)
■若い頃、数学と同じくらい命がけの登山に魅せられたというヴァレンティン・ポエナル博士。
「例えば登山家は、普通の人とは違い、山で命を落とすことを恐れません。数学も同じなのです。たとえ命と引き替えでも構わない、世の中の他のことなど、愛する数学に比べれば、取るに足らないものだ。数学の真の喜びを1度でも味わうと、それを忘れることはできなくなるのです」
迷路のようなパリの地下鉄をぐるぐる回るのが今でも好きだというミハエル・グロモフ博士。
「数学の魅力は、謎を解くときの興奮そのものです。例えば、子どもにとっては世界のすべてが謎に映ります。手足を動かしては、不思議なことを体験し、食事をすれば、味とはいったいなんだろうかと考えます。普通の人は大人になるに連れ、そうした好奇心を失いますが、謎への興味を絶やさなければ、その人は、宗教家になるかもしれませんし、芸術家になるかも知れません。難問に挑む数学者も、そういう人たちの中から生まれるのです」
そして、数学者になって初めてありのままの自分でいられるようになったというサーストン博士。
「数学は旅に似ています。見たことのないものを、何とか見ようとする努力なのです。数学は不思議な力で私たちの目の前の世界を彩り、徐々にその神秘を明らかにしてくれるのです」(239~240頁)
■――解決された柏原予想とは、どんな問題なんですか?
「専門的になってしまいますが〝射影多様体上の半単純な正則ホロミックD-加群の圏が種々の関手によって保存される〟というものです」(京都大学数理解析研究所の望月拓郎准教授)
――論文が1000頁とはかなりの分量ですが、なぜそんなに長い論文になるんでしょうか?
「本質的な証明の部分はかなり短いはずですが、言葉が未発達だったので、一つ一つ定義していったら長くなってしまいました」
――言葉が未発達、という意味は?
「つまり、予想を証明する過程では〝新しい道具〟をいくつか使わないといけないんですが、それは初めて見る人には新しい概念なので、その意味を定義しておかないと混乱の元になって証明を読み進められないんです。例えば〝ツイスター構造〟という概念をこの証明ではよく使うので、論文のチャプタ-ひとつをまるまるその言葉の準備にあてました」
ここまで聞いて、私は「1000ページの論文」の意味をようやく理解した。〝数学は1つの言語だ〟という考え方をスティーブン・スメール博士の取材の際に知ったが、その〝言語〟は数学研究の最前線で望月氏のような開拓者によって日々更新され、今この瞬間も語彙を増やし続けているのだ。日本数学会による解説で、望月氏の仕事が〝解析的にはまったく未開拓の状況で、道具から作る必要があった〟と評価されていたのを思い出した。
4畳半あるかないかの狭く薄暗い部屋の中、細長いテーブルをはさんで望月さんと向い合いながら、私は考え始めていた。「もしペレリマン博士に直接質問が出来たとしたら、こんな風だったろうか?」(251~252頁)
(2012年5月4日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『芭蕉庵桃青』 中山義秀著 中公文庫
■芭蕉はこういう杜甫の生涯と自分の境涯をひきくらべ、考えなければならないのは、詩作にたいする杜甫の態度だということに気づきはじめていた。
およそ九百年前の遠い昔にうまれた杜甫の詩画、今なおいきいきと作者の面影をつたえ、読者に深い感銘をあたえるのは、いったいどうした理由からであろう。新奇さをてらう思いつきや頭だけの拵(こしら)えごとで、このように人の心をうごかせるはずはない。彼の生活現実と、それに交流する彼の生命との間に、なにか解かれぬ秘密がひそんでいるのではなかろうか。
杜甫も若い頃は当時の流行をまねて、言葉たくみに操(あやつ)り玩(もてあそ)ぶことから詩作をはじめている。しかし齢をかさね、生活のきびしい現実に直面してくるにつれ、物の実体をさぐろうとする、写実風の態度にかわってきている。さらに試練がくわえられてくると、外界の事象から内部の心に重点をおくようになった。そして内心の感動から生まれるものが、まことの詩だと実感するにいたったらしい。(33頁)
■其角にとって俳諧が、みじめな人間生活やみみっちい人生をよそにした、伊達と華麗とをきそう錦繍のせかいであり、荘子の夢の無何有(むかう)郷(岡野注;自然のままで、何の作為もない理想郷)とするならば、芭蕉にとってはおのれの生活と人生を賭けた、実有(じつう)のものとなっている。
其角の句は人目を驚かし喜ばせるが、芭蕉のそれは人々の心の奥にひそむ、寂寥と悲哀の永遠なるものへと誘いこんでゆく。それぞれの特色であり、他人に真似のできないものである。それ等をそなえた彼等は、言葉使いの巧みな、一種の魔術師にたとえられるべき人達なのか。(38~39頁)
■芭蕉の考えるところでは、松永貞徳以来の俳諧は、2変し3変しようとしていた。貞門時代の俳諧連句は、前の句の詞(ことば)や事柄をとって、後の句をつける「物付け」であった。
西山宗因はその「物付け」をあらためて、前の句の意(こころ)をとって後の句をつける「心付け」とした。前の句の意から聯想して、後の句に新しい意をもたせてゆくやり方だから、想像力が強く働き、連句は趣向をこらした物語風のものに発展してゆく。そのため形式も表現も自由、大胆となって、末は奇抜さをさそい奇矯をてらう放埒(ほうらつ)なものに堕落してしまった。(45頁)
■それというのも段倫風の「心付」にたいして、前駆の漠とした気分や味いをくんで、後の句をつけるといったやりかたをとり、聯想による前後の句のつながりを、一切廃してしまったので、連絡をたどるのに骨が折れ、前後まちまちの句、難解な連句となった。そのため一巻の連句をつらぬき流れる、快い階調がうしなわれ、イメージのうすいものとなった。それでは俳諧の木乃伊(みいら)でしかありえまい。(45~46頁)
■夜になって風がやみ、火事の延焼する心配はなくなった。ふだんならば肌もこおるような寒夜なのだが、火事の余焔と熱気で冷えは感じられない。川水すらなまぬるく思われるほどである。それほど地上といわず水上といわず、風に狂いはしった火勢は猛烈であった。
水中から匍(は)いあがった芭蕉は、草むらにまだ余燼のくすぼっている草庵に行ってみた。旧廬はおとかたもなく焼失してしまったけれども、生け簀の古池はのこっている。枯れた藻草におおわれた青みどろの水面は、なにごともなかったように静かだ。
古 池 や ……
芭蕉はそう口ずさみかけ、自分の宗匠気質(かたぎ)にきづいて、おもわず苦笑をもらした。一切が失われてみると、彼に残されているものは、自然にわきいでくる俳諧の形のない、無限の天地しかなかった。(53~54頁)
■初老にはいった芭蕉にも、俳諧の上で独自の風体をもたなければならない時期が、せまってきている。初期の貞徳流から談林調へ、談林調から新風をめざしての漢詩体へと、すでに3変してきているものの、まだ適切な風体をつかんでいなかった。漢詩体の表現は、理窟ばっていかめしげであるが、俳諧にふさわしい風体とはいえない。
俳諧の源は詩歌の気晴らしとされた、滑稽体からはじまったといわれている。その滑稽を俳味とする、俳諧の風体は、いかにあるべきものなのか。和歌や連歌界の先達者たちは、風雅のまことをば、ものの哀れを情趣とする幽玄体においた。
宗祇とともに時雨の句をよんだ心敬法師は、この幽玄体を、「冷え寂びたるあり方」と定義した。心敬は歌道の修行をもって、心の修行とした人である。彼は宗匠を業としないで、出家の心をもって生涯を終始した。芭蕉もまた、おなじ道をあゆもうとしている。心敬は風雅のまことを、「冷えさび」だとしたが、冨士のふところに入って芭蕉は、はたして何を感得するところがあったであろう。(60頁)
■「夏馬遅行(かばちこう)」の漢詩体は、推敲をかさなて後にこうあらためられる。〔岡野注;夏馬遅行我を絵に見る心かな〕
馬 ぽ く ぽ く 我 を 絵 に 見 る 夏 野 哉
そしてこれを主題にして、彼の像を描いた杉風の画に、芭蕉は次のような讃をした。
かさ着て馬に乗る坊主は、いづれの境より出て何をむさぼりありくにや。このぬしのいへる、是は予の旅のすがたを写せりとかや。さればこそ三界流浪のもゝ尻、おちてあやまちすることなかれ
もゝ尻とは鞍に尻の安定しない、下手な馬乗をさす。又いずれの境から迷いでて、何をきょろきょろ貧り歩くのかとは、この谷村時代の苦しかった心境を回想して、反語の諧謔を弄したものであろう。それだけ余裕をもったしるしである。
麋塒(びじ)と一晶は、この発句に感心して、
「『我を絵にみる』とは、面白いですな。唐土の高士の姿を、偲ばせる趣がある」
「何処でこの句を、えられましたな」
一晶が芭蕉にたずねると、
「吉田あたりの裾野を、農馬にまたがって旅しているうち、ふと思い浮んだものです」
「なるほど」
宗匠として一家をなしている一晶は、しきりと考えこみ、
「『夏馬遅行、我を絵に見る心かな』――広い夏の裾野を、独りゆっくりと馬でゆく姿、侘びてますね。漢詩体からして今、唐土風のものをよむのがはやっているが、この趣向は新しい。何か拠るところ御座いますか」
「拠るところがあるといえば、富士山です。崇高な霊峰にしても、山が山ならば、自分も自分だと思うより仕方がない」
一晶は膝をうって、
「翁はこの谷間から、広野へ匍いだされた。豁然として悟るところが、あったのではありませんか」
「さア、どうでしょう」
芭蕉は麋塒にも眼をうつして、
「一掬の水でも澄んでおれば、天心の月を我が物とすることができる。寒山がいう、心灑洒(さいしゃ)たれば、属目するところみな佳思あり、とはこの事かもしれません。お蔭でこの句を獲たことばかりでも、お世話になった甲斐がありました」
句がよいというのではなかった。冨士の雄大な山容にたいして、卑小な自分を救うことの出来た悦びである。そしてその事はまた、平談俗語をもって、卑俗なことがらを美化する、俳諧の精神につうじるものでもある。一晶が指摘したように、芭蕉はようやく俳境についての混迷からぬけだすことができたようだ――我を絵とみる心によって。(73~75頁)
■富士川のほとりを行に、3つばかりなる捨子の哀げに泣くあり、この川の早瀬にかけて浮世の波をしのぐにたへず、露ばかりの命まつ間と捨置けむ、小萩がもとの秋の風、こよひや散るらん、あすやしをれんと、袂より喰物なげてとほるに、
猿 を き く 人 捨 児 に 秋 の 風 い か に
いかにぞや、汝父に憎まれたるか、母にうとまれたるか。父は汝を惡(にく)むにあらじ、母は汝をうとむにあらじ。唯これ天にして、汝が性(さが)のつたなさを泣け。(96頁)
■芭蕉がつけた脇の両句は、とりたてて云うほどのものではないが、その調に独特の風格と重みがかんじられる。彼は2ケ月にわたるこの旅の間に、「笠は長途の雨にほころび、帋衣(かみこ)は泊りとまりの嵐にもめた」かわり、俳諧の道について、ゆるぎのない自覚と信念をえた。その精神をいえば、方外境に逍遙する風狂の心、その体をもうせば、景情一味の写実である。
たとい虚構とみなされたにせよ、富士川のほとりの憐な棄児にたいして、「汝が性(さが)のつたなさを泣け」と云いきる非情、客観の態度は、自然の景観や人事現象に活眼をひらかせた。もはや芭蕉にとって、貞徳流の古風はもとより、宋因の談林調も、天和期における漢詩文体もない。
長かった模索と低迷からぬけだしてみれば、天地の間に磅礴(ほうはく)して、四季の運行に変幻自在の妙をつくす、造化の自然があるばかり、無心にその機微と冥合するところに、風雅の誠がある。杜甫や西行などの詩歌の秘密も、結局はそこに帰せられるのではなかろうか。(101~102頁)
■たとえば620余年前の前9年役の際、八幡太郎義家と安倍貞任との間に、とり交されたという応答歌……戦にやぶれて衣川の館を落ちゆく貞任を、義家を追いかけて呼止め、
衣 の た て は 綻 び に け り
貞任はこの下の句に、上の句をつけて答え、
年 を 経 し 糸 の み だ れ の 苦 し さ に
「衣のたて」は糸のたて糸を館(たて)に通わしたもの、この形式を「短連歌」といい、単連歌から更に「鎖連歌」とよばれ「長連歌」が誕生してくる。単連歌の句形五七五、七七をつぎつぎと繰返しながら、鎖のようにつないでゆく方法で、一種の尻取り遊びのようなものだから、多人数がこれに参加して句作を楽むことができ、その連句の数も五十韻百韻、千句万句におよんだ。(116~117頁)
■宗因はこのような心境からして、謡曲、小唄、浄瑠璃、地口などに題材をとり、新しい詞を自由につかって、格式ばった貞徳流の俳諧を一変させた。それで芭蕉も、「上に宗因なくんば、われわれの俳諧は今もって、貞徳老人の涎を甜ぶるべし。宗因はこの道の中興開山なり」と推称している。(129頁)
■芭蕉がねらっているのも、いわば「匂(におい)付」ともよぶべきこの付筋にあった。連歌はこの付筋によって、鑑賞にたえる詩歌の1つとなった。おなじ母胎からでた俳諧もまた、かくあるべきではないか。(141頁)
■俳諧は形の上からいえば、平談俗語をとりいれた俳諧の使用で、連歌から差別されている。しかし実体は、幽玄を主調とする連歌の風体と、「侘び」、「寂び」に撤しようとする俳諧境との相違にある。(147頁)
■「春雨の柳はぜんたい連歌なり。田螺(たにし)とる鴉は、まったく俳諧なり」と、この間の差別をはっきりさせている。また続いて、これまた後年の物である、「五月雨に鳰(にほ)の浮巣を見にゆかん」という自作の句をひき、五月雨や鳰の浮巣は、素材としては俳諧ではないが、それをわざわざ見にゆく風狂に俳諧があるとする。
芭蕉はこの俳境をさぐり、身をもって俳情に生きるために、深川の隠士となり旅をゆく風狂の人となった。そういう彼にとって、心魂のあてどもない行方を辿るように、筋もテーマもなく象(かたど)られてゆく俳諧の様式は、飛花落葉の風情をそのまま、彼の心情に似つかわしい風姿だったのかもしれない。現世を常ならぬものとする、虚心、虚無の世界である。(148頁)
■千那と尚白は三井秋風と同様、田中常矩や惣本寺高政の談林派についていたが、「冬の日」を読んでその風体につよく関心をよせるようになった。奇抜な見立や珍しい趣向、変風などに憑かれている、空疎な談林俳諧にくらべ、それとは似もつかぬ「冬の日」の清澄高雅で、余韻のふかい俳諧境地に驚かされたためである。それで芭蕉の在京を知ると、さっそく彼を招いて話を聞き指導をうけることになった。(155頁)
■春光のうちに駘蕩として、いぶし銀のゆたかな広がりをもつ琵琶湖風景は、芭蕉の詩情をよび美しい吟調を生んだ。
湖水眺望
辛 崎 の 松 は 花 よ り 朧 に て
芭蕉の門弟達の間で後に、「にて」留めのこの句の仕立が問題になった際、芭蕉はこれは理窟ではない、「只、眼前なるは」と言ったそうだが、なるほど眼前の属目として、これ以上適切な表現はない。
この句も推敲をかさねた末定着したもので、初案の句は、
辛 崎 の 松 は 小 町 の 身 の 朧
であったという。雨にけむる孤松の姿を、美女の小町と対照させたわけだが、句意はともかく表現は改案されたほうが、段違いにまさっている。しかし美女を聯想するところに、彼の俳諧をつやめかせる、心情の秘密が隠されてあるようだ。(155~156頁)
■ 古 池 や 蛙 飛 こ む 水 の 音
一見してやすやすと詠みだされた、写実の1句にすぎないようだけれども、繰りかえして読みあじわってみると、深遠閑寂な響が余韻をひいて心につたわり、想いをはるか無何有の彼方へいざなってゆく。このような働きをする不思議な力は、いったい17字の何処にひそんでいるのか、神韻縹渺の趣とは、まさにこうした境地をさしていうことに相違ない。
蟇の青蟾(せいせん)堂を菴号としている仙化は、おもわず昂奮して、
「翁、でかされましたな。一言もございません」
しかし若い其角は、性来のはなやか好みからして、なお句の出来ばえを思案しながら、玉川の蛙をひきあいに、
「山吹やとおいても、面白いでしょうな」
「それはよくあるまい」
素堂は彼の言葉をおさえて、
「これには釈迦の出山に通じる、意味合いがある。冬の長い眠りから目ざめて、わが古巣の世界へ飛び入る蛙の無心欣求(ごんぐ)の姿は、山吹では出てこない、のう、翁」
芭蕉より2つ年上で、儒学者でもある素堂は、さすがに芭蕉の胸中を、推察しているような理窟をはく。6年の苦行をへた35歳の釈迦牟尼は、破衣蓬髪、おとろえた姿で雪山をさるにあたり、冬空にかがやく暁の明星をみて、「大地有情、同時成道」の悟りをえたとある。
これは道釈画にこのんで描かれる釈迦出山の図で、芭蕉の庵にもその木像が安置されている。素堂はそれから思いついて、こうした解釈をくだしたものであろう。またそれだけこの句を、高く評価したわけであるが、芭蕉はさりげなく、
「いや、枯草のうちからのそのそと匍いだした蛙が、萌えでる若草をわけて、古池へ飛びこむ水音に、俳諧を見つけたばかりのことでした」
たしかに芭蕉のいうとおりだったにちがいない。景物にたいして一念一動するところに理窟はなく、ただ詩魂のひらめきがあるばかりだ。(169~170頁)
■なお其角は、その後も芭蕉の句に心をとられていたのか、これに脇をつけたと伝えられている。
古 池 や 蛙 飛 こ む 水 の お と 芭蕉
蘆 の 若 葉 に か か る 蜘 の 巣 其角
もしこの句が其角の作だとすれば、其角は結局芭蕉の句を、叙景のものとしてしか受取っていなかったことになろう。昨年の秋、芭蕉は門弟の大垣藩士、中川濁子(じょくし)の筆写した、「野ざらし紀行」に奥書して1句をそえている。
た び 寝 し て 我 句 を 知 れ や 秋 の 風
芭蕉のこうした考えによると、彼の詩魂にひらめいて生みだされた蛙の句は、至れる者だけが知る境地なのかもしれない。(173~174頁)
■芭蕉が仏頂を徳としているのは、彼の勇猛心とその実行力である。仏頂が老中酒井忠国から、引退後の生活はどうすると問われた際、山になりとも里になりとも心まかせにするつもりだ、と答えた一言は、ながく芭蕉の心のささえとなった。
むしろ仏頂の行きかたを手本に、その後を生きつづけてきたとも言える。風雅のために最低の生活を決意して、貰うてくらい乞うてくらうことを恥とせず、飢(かつ)え死にすることすら辞さないよいう心底には、仏頂に劣らぬ勇猛進が、なくて叶わぬはずだ。その意味で仏頂は、国学における北村季吟、儒学における山口素堂と同様、禅学の上で芭蕉の育成に、無視できない役割をはたしている。(188頁)
■「笈の小文」の初で、芭蕉みずから記しているところを、次に意訳すると、
「旧友、親しい者、知りあい、門人等、あるいは詩歌文章をはなむけにして、訪れてくるかと思えば、あるいはまた草鞋銭をもって、志をあらわす者がある。おかげで旅費の苦労もいらないほどだ。ほかに紙衣、綿入れ、頭巾、足袋、といった物をくれる人々もあって、防寒の心配もない。ある者は小船の上で別宴をはり、ある者は別荘に招待して饗応する。草庵に酒肴を携えてきて、旅の前途を祝し名残を惜む者もあり、身分ある人の門出するみたいで、ひどく仰山な思いがした」(191~192頁)
■しかし「笈の小文」も書出しも、それに劣らずものものしい。当時はやりの漢詩文体調で、響高くつづられている。
「百骸九竅(けう)の中に物有り。かりに名付けて風羅坊といふ。誠にうすものの風に破れやすからむ事といふにあらむ。かれ狂句を好こと久し。終(つひ)に生涯のはかりごととなす。ある時は倦(うみ)て放擲せん事をおもひ、ある時はすゝむで人にかたむ事をほこり、是非胸中にたゝかうて、是が為に身安からず。しばらく身を立む事をねがへども、これが為にさへられ、暫く学んで愚を暁(さと)らん事をおもへども、是が為に破られ、つひに無能無芸にして、只この一筋に繋がる」
100の骨9つの穴から成る人体には、風羅坊とも名づくべき精霊がいる。薄くて風に破れやすい、芭蕉葉のごときものだ。この風羅坊は俳諧が好きで、とうとう一生の仕事とするようになった。ある時は倦きて棄てようかと思ったり、逆に進んで人に勝誇ろうとしたり、あれこれと迷いぬいて、心の安まることがない。一旦は立身出世を願っても、これにさまたげられ、学問してその愚さに覚めようとしても、この為に思いを破られ、とうとう無能、無芸の身をもって、俳諧一筋に生きることになった。
これを過去の述懐として、次は彼の美意識と信念を吐露した、有名な文章となる。
「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其貫通する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時(しいじ)を友とす。見る処、花にあらずといふ事なし、おもふ所、月にあらずといふ事なし。像花(かたち)にあらざる時は夷狄(いてき)にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類す。夷狄を出(いで)、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり」
和歌、連歌、点茶と、達人達の志した道は、それぞれ異っていても、帰するところは風雅の精神1つである。この風雅の情(こころ)は、自然の運行にしたがって、四季の眺めを友とするものだ。見るところ花でないものはなく、思うところ月でないものはない。像(かたち)に花を見ない者は蛮人とおなじく、心に月を思うことない者は、鳥獣に類している。蛮夷、鳥獣の境涯からぬけだして、造化の自然に眼をひらくべきだ。
つまり芭蕉の風雅の哲理は、自然との一体化を説くところにある。森羅万象、すべて自然の恵みによって在る、というその観想は、汎神論と原理をともにする、東洋の美学であろう。(195~196頁)
■芭蕉は昨年の4月末、杜国と連名で京都から、郷里上野の窪田猿雖(えんすい)にあて、「笈の小文」の旅程をくわしく報告しているように、こんどの旅の計画についても、この親友にむかって自分の意中を包まず述べている。
「去年の秋より心にかゝりて思ふことのみ多きゆえ、かへつて御無沙汰に成行き候。(中略)去秋は越人といふしれ者木曽路をともなひ、桟(かけはし)のあやふき命、姨捨のなぐさみがたき折、砧(きぬた)、引板(ひきた)(鳴子)の音、鹿(しし)を追う姿、哀れも見つくして、(中略)年明けても猶旅の心地やまず、(中略)弥生(3月)にいたり、待ちわび候塩釜の桜、松島の朧月、浅香(安積)の沼のかつみ(真菰(まこも))ふく頃より、北の国にめぐり、秋の初、冬までには美濃、尾張へ出で候。露命つゝがなく候はば、又(ま)みえ候て立ちながらにも立寄り申すべきかなど、たのもしく思ひこめ候。南都(奈良)の別れ一昔の心地して、一夜の無常、一庵の涙も忘れがたう覚え、猶(旅の)観念やまず、水上の泡消えん日までの命も心せはしく、去年(の)旅より魚類肴味(こうみ)口にはらひ捨て、一鉢(の)境界(涯)、乞食の身こそ尊けれ、とうたひに侘びし貴僧のの跡もなつかしく、猶ことしの旅は窶(やつ)し俏(やつ)して、菰かぶるべき心がけにて御座候。その上よき道づれ、堅固の修行、道の風雅の乞食尋ねだし、鄰庵に朝夕かたり候て、この僧にさそはれ、今年も草鞋にて年を暮らし申すべくと、嬉しく頼母しく、暖になるを待ちわびて居り申し候」
この手紙は2月初旬に書かれたものであるから、旅の企図はそれ以前になされていたことがわかる。「木曾の痩もまだなほらぬうちに」、はやくも此の大旅行を思いたつようになったとすれば、旅に憑かれたとしてもおかしくはあるまい。(254~255頁)
■そして草庵を表徴する愛翫の芭蕉も、近くの地に移植して、その世話を隣人達にたのんだ。
こ ゝ を ま た 我 が 住 憂 く て 浮 か れ な ば
松 は 独 り と な ら ん と す ら ん(「山家集」)
その西行の憐れみ心を、芭蕉のうえにくみとっての処置だ。「羇旅辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、これ天命なり」(「奥のほそ道」)と覚悟した、命懸けの旅の門出にあたり、心にかかる一切の物事を始末して、身も気持も軽くいで立とうという肚であろうが、それにしても定まった住居まで、人手に渡してしまうとは思いきっている。(259頁)
■「弥生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光をさまれる物から、不二の峯幽にみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心ぼそし。(中略)前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。
行 春 や 鳥 啼 魚 の 目 は 泪
これを矢立の初として、行道なほすゝまず。人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄は見送るなるべし」(「奥のほそ道」)
これが3月27日の早朝、千住を出発する時の情景だ。一蓋の菅笠、一条の杖、墨染の衣に頭陀と背負袋、脚絆、わらじの道心者姿で、「前途3千里」の旅におもむく2人にたいし、見送りの人々は声をあげて泣き、見おくられる芭蕉達もともに、涙を落とさずにはおられなかった。(262~263頁)
■修験道は山嶽信仰の交霊術(シャマニズム)が、道教や真言天台の両密教とむすびついて、盛んになったものである。病気をなおし災害をのぞき悪霊をはらう、加持祈祷の呪力をやしなうため、深山幽谷にわけ入り、諸国を遍歴して、困苦にうちかつ荒行を修めるが、これは仏道修行とおなじく、印度婆羅門の頭陀行にならうものだ。
頭陀行は婆羅門の修行形式で、衣食住の貪着(どんちゃく)から離脱して、身心の解放をはかり、自由をうるための行法である。
その段階として、一切の所有物をすてて山林に幽居し、思索の功をかさねる。ついで頭を剃り薄衣をつけ、首に頭陀袋、手に杖、といった物のほかは何ももたずに、身を雲水にまかせて、廻国遍路の旅にでる。「奥のほそ道」の冒頭にいう、「日々旅にして旅を栖(すみか)」とする、無所在の生活である。(276~277頁)
■その時弁慶以下の家士十余人は、館の大手、搦(からめ)手の防戦にはせむかい、数百の寄せ手を相手に死闘してはてた。後に一人のこった63歳の増尾十郎兼房は、義経夫妻が自裁した後、館に火をはなち、中庭にのりこんできた寄せ手の大将、長崎太郎を乗馬もろとも斬仆(ふ)すと、つづく弟の次郎を小脇にかかえこみ、火中に飛入って勇壮な死をとげた、と「義経記」にしるされている。
芭蕉も曾良も武家あがりなので、こういう話にはつよく感動しがちだ。「さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の叢(くさむら)となる。『国破れて山河在り、城春にして草青みたり』と笠打敷きて、時うつるまで泪を落し侍りぬ」(「奥のほそ道」)
夏 草 や 兵 ど も が 夢 の 跡
卯 の 花 に 兼 房 み ゆ る 白 毛 か な 曾良
「国破れて山河在り」は杜甫の有名な「春望」の詩、「『国破れて山河在り、城春にして草木深し」をとったもの、それにつづいて、「時に感じては花に涙を濺(そそ)ぎ、別を恨んでは鳥に心を驚かす」とある。
芭蕉の夏草の発句にも、時におどろく痛歎の響がある。曾良の句には、老いに寄せる悲哀がこめられている。両人それぞれの感銘のありかただが、ともに単純な写景ではなく、観念のうえの細工物でもなく、この場、この時、の実感だったことに相違はない。(206~207頁)
■五百有余年の風雨にさらされてくれば、どのような建物も頽廃はまぬかれず、さながら絶世の美女の老いた姿を目にするような思いだが、しかも堂宇はなお眼前にあって微ながら、燦然とした当時の余影をのこしている。
そして又その須弥壇の下には、奥の王者とよばれた藤原3代の主、清衡、基衡、秀衡が、生ける姿をそのまま木乃伊となった、黄金の柩の中によこたえられてあるという。
これより南東へ8町あまりを隔てた、山下高館の義経は、むなしく荒草の下に朽ちはててしまっているのに、庇護者の秀衡は、今に生前の姿をとどめている。どうした因縁によるものか、あまりにも対照の差が甚しい。
しかし、無為自然の世界では、万物斉同、人間の運命や因縁に、かかわりはなかった。ただまぎれもない現実として、古色に燻(くすぼ)んだ金色堂が、眼前に残存しているばかり、そこで、
五 月 雨 の 降 り の こ し て や 光 堂
すべてが滅びさった後に、光堂1つ残っているのは、一切無差別の自然界でも、美しいものだけはとっておくかとみえる。芭蕉は心にそう信じているかのよう、この佳句をなした。(298~297頁)
■「奥のほそ道」によると、市振の1つ宿にとまった2人の若い女は、伊勢参宮こころざす、新潟の遊女達であった。此処まで2人をおくってきた老爺が、新潟へひっかえすことになったので、未知の前途を心ぼそく思うあまり、芭蕉等の衣の袖にすがって、見え隠れにでも後を慕ってゆきたいという。
しかし芭蕉は、道中たちよる所がおおいので、気の毒ながら同行はできないと断り、ただおなじ方角へゆく人の後に跟いてゆけば、大神宮のお加護でかならず到着できる、と言い捨て別れたが、さすがにあわれでならなかったとある。
同様に芭蕉は、5年前の「野ざらし」の旅の折にも、富士川のほとりで哀げに泣いている、3つばかりの捨て子にたいし、捨てた親を恨むなよ、唯これ天命にして、汝の不運な生まれつきを泣け、といって通りすぎている。
ともに、芭蕉の持論とする、捨身無常の運命観を披瀝するものだ。1面には、世俗の生活をみかぎって、俳諧の風雅に身をささげた、芭蕉の非情の精神と覚悟を、しめしたものともされよう。(317頁)
■千三百石取の藩の名門戸田権太夫如水は、当時の芭蕉と路通の風采を日記にしるして、9月4日の昼、如行の手引で芭蕉と路通の2人を、下屋敷の別邸にまねき、俳席を設けて初対面した。両人よりいろいろと話があったが、主として風雅にかかわることが多かった。
その折芭蕉は、夏の単衣に裏をつけて綿入れとした、墨染の木綿着物に細帯をしめ、うえに十徳を羽織り、路通は木綿の白衣姿で、手に数珠をかけていた。近日伊勢神宮の遷宮式があるので、それを拝むため一両日中に出立するとのことである。両人の心底のほどはわからないが、その態度は俗事をよそに「浮世を安くみなし」て、人に諂(へつら)うことなく奢るところもない、といっている。(328~329頁)
■芭蕉はみちのくの旅の途中、出羽の羽黒山で土地の俳人呂丸に、発句は俳諧の主人公であり、それにつづく連句の流の水源になるものだ、と教えている。それ故発句を練りまわして、むずかしく凝り固めると、座の風情も締りわたって、1巻の句がみな面白くなくなってしまう。反対に百句にもおよぶ広やかな、「姿情」で、発句をおかしく詠みだすと、「一座同心の花」がひらけて、面白い俳諧ができる、というのである。(「聞書七日草」)
「ひさご」の3吟歌仙は、芭蕉のこうした主張を、はっきりとうちだしている。花見の景を軽くよみすてたかに見える、芭蕉の発句を源にして、脇も第3もかろやかにはこばれ、付合に苦渋のあとがなく、俳諧独特の可笑味をくわえて、面白い俳諧を展開している。曾てなかった新境地だといえよう。(332~333頁)
■ 草 庵 に 暫 く 居 て は 打 や ぶ り 芭蕉
い の ち 嬉 し き 撰 集 の さ た 去來
さ ま ざ ま に 品 か は り た る 恋 を し て 凡兆
浮 世 の 果 は 皆 小 町 な り 芭蕉
名残り29から、裏の32句。草庵をむすんでは又所をかえる風狂の歌人は、撰集がおこなわれると聞いて、命ながらえた甲斐あったと喜んでいる。反対に若い頃品かわった恋をしたところで、末はみな小町のなれのはてだ。(345頁)
■みちのくの旅を終えたあと、上方の自然や風物にたいする、芭蕉の見る目がかわってきている。都ととおく地をへだてた奥路の世界は、清冽できびしく山河の姿もうつくしいが、人煙にとぼしく寂寥(りょう)と沈黙の気配が色濃い。
芭蕉は歌枕をたずねまわって、歌人が昔みたところと今見るところと変りなく、太古の俤をさながらにとどめていることを知った。その不変の姿と天地の静寂は、詩情をそそるに適してはいても、生活する悦びはえられない。(348頁)
■ 薦(こも) を き て 誰 人 い ま す 花 の 春
この発句が去来の歳旦帳の引付(付録)にのせられて、諸方に配布されると、芭蕉外の京の俳人等は、菰かぶりの乞食を歳旦帳にだすとは何事だ、といって非難した。それにたいして芭蕉は、大垣藩士此筋(しきん)兄弟あての手紙で、次のように述べている。
別段のことでもないが、5百年昔の西行の「撰集抄」には、乞食となった多くの聖(ひじり)があげられている。眼識があきらかでないため、そうした尊い聖を発見できない悲しさに、ふたたび西行を思いかえして、この発句をよんだまでにすぎない。京の俳人達がかれこれと非難するのは、見識が浅いからである。(353頁)
■「蕉門に千歳不易の句、一時流行の句と云ふあり。其元は1つなり。不易を知らざれば風新ならず。不易は古(いにしえ)によろしく、後に叶ふ句なる故、千歳不易といふ。流行は一時々々の変にして、昨日の風今日宜しからず、今日の風明日に用ひがたき故、一時流行とはいふ」(「去来抄」)
そして去来は、ここに初めて芭蕉は、俳諧の本体をみつけたと言っている。また土芳の「三冊子」では、芭蕉の風雅は万代不易と一時の変化、この2つにきわまるもので、共通するところは風雅の誠1つである。代々の歌には代々の変化があるが、今日読んでも昔にかわらぬ哀れを感じさせる。これを不易という。
しかし、千変万化するものは自然の理であって、その変化にうつらなければ風はあらたまらない。風のあらたまるところが、流行の新しみだ。新しみは俳諧の花である。古びた俳諧は、花のない木立をみるに似ている。芭蕉はこの新しみの匂をもとめて、つねに痩せる思をした。(362~363頁)
■「倩(つらつら)年月の移こし拙き身の科(とが)をおもふに、ある時は仕官懸命の地をうらやみ、一たびは仏籬祖室の扉(とぼそ)に入らむとせしも、たどりなき風雲に身をせめ、花鳥に情を労して、暫く生涯のはかり事とさへなれば、終(つひ)に無能無才にして此一筋につながる。楽天は五臓の神をやぶり、老杜は痩せたり。賢愚分質のひとしからざるも、いづれか幻の栖(すみか)ならずやと、おもひ捨てふしぬ」
先 た の む 椎 の 木 も 有 夏 木 立
年月をへてきた自分のふつつかな人生を、つくづくふりかえって見ると、ある時期には一生の養いとなる領地をもった武士を羨み、またある時期には仏門、禅室へはいろうと考えたこともあった。
しかし、さすらいの旅に身をさらし、花鳥に情をささいで、ひとまず俳諧を一生の仕事ときめてしまった後は、無能無才ながらこの道一筋につながれている。白楽天は詩作のために五臓の精気をやぶり、杜甫は苦吟して痩せた。
人に賢愚の別があり、文章に平凡非凡の差はあっても、所詮は幻の世をすみかとする上で、誰もみな変わるところはない。そこで夏の陽をさけ、実は糧となる椎の木を、まず頼むという発句となる。
これが風雅人芭蕉の心境であり、47歳になった彼の述懐である。芭蕉は長明の「方丈記」の形式にならって、「幻住庵記」を書いたとしているが、「方丈記」の終は以下のように結ばれている。
「そもそも一期の月影かたぶきて、余算、山の端にちかし。たちまち三途の闇にむかはんとす。何のわざをか喞(かこ)たむとする。仏の教え給ふ趣きは、事にふれて執心なかれとなり。今、草庵を愛するも科とす。閑寂に着するも障りなるべし。いかゞ要なき楽しみをのべてあたら時をすごさむ。
静なる暁、このことわりを思ひつゞけて、みづから心に問ひていはく、(中略)若しこれ、貴賤の報のみづから悩ますか、はたまた、妄心のいたりて狂せるか、その時、心さらに答ふる事なし。只、かたはらに舌根をやとひて、不請(ふしょう)の阿弥陀仏、両三遍申してやみぬ」
わが一代もはや余命すくなく、冥府におもむく時がちかづいてきている。わが身の上について、今更愚痴をいったところではじまらない。仏は何事にも執着するな、と教えている。さすれば、方丈の草庵を愛し、閑寂を好むのもまた、罪障とならう。いたずらにその楽しみを語って、無駄に時間をおくるべきではない。しずかな春の明けがた此の道理に思をめぐらせて、山林に世をのがれ方丈の幽居に住んでも、なお迷蒙から脱却できないのは、貴賤といった過去の宿業にまだ囚われているためか、あるいは迷いのはて本心が狂ったのかと、自分の心に問うてみたが、何の答もえられない。よぎなく空念仏を2、3べん唱えて、考えることをやめてしまった、というのである。(367~369頁)
■土芳「三冊子」中の「黒双紙」に、芭蕉の言葉として、「発句というものは、行って帰る心の味だ。山里は万歳遅しというばかりでは、平句の位にすぎないが、梅が咲いている山里、と元にかえる心で発句となる。つまり発句は、取合せ物と心得るがよい」とある。(379頁)
■昨年の3月に亡くなった杜国を夢にみて、涙をながした。夢は心気によるとされているが、杜国の夢は、いわゆる念夢というものであろう。思うこと深ければ、それが夢となって現れる。杜国は自分に厚く志をよせ、3年前の伊賀の里まで慕ってきて、およそ百日ばかりの間、夜は臥床(ふしど)をともにし、昼は疲れをいたわりあって、影の形に添うように旅をつづけた。ある時は戯れあい、又ある時は互いに悲みをわかちあったその思い出は、心にきざまれて忘れることがない。目覚めて後も、流れる涙を抑え得なかった。(381頁)
(2012年6月1日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『生命の光』 714号
■キリストは、「不信仰な曲がった世の中は神のしるしを求めるが、ヨナのしるし以外は与えられない。信じやすい心の人には与えられるけれども、信じにくい、曲がってひねくれた心の人間には、神のしるしを悟りえない」と言われるのです。「しるし」とはセーメイオンというギリシア語です。目に見えない神様は、見えるしるしや奇跡をもってご自分の存在を示しなさる。神は目に見えないが、見えないから無いのではない。しるしとしてシンボルを通してでも、このように存在しているじゃないか、ということを示されているわけです。神が信ぜられる人には、何を見てもしるしです。空飛ぶ鳥を指してでも、野の百合を示してでも、イエス・キリストは神を説くことができました。
だが、多くの場合、しるしと言えば奇跡のことです。この29節は、「人々がイエスを試みようとして、天からのしるしを求めた」という同じ章の16節の言葉を受けております。だから、人々はイエスの説く福音を信じえず、「天からの素晴らしい奇跡が見たい、そうしたらあなたを信じよう」と言ったわけです。
それに対してキリストが言われるのは、小さなしるしにも驚かない者に、大きなしるしを見せたって、ただ奇跡を見たと思うだけで、信仰にはならない、ということです。不思議な救い、運命の変化、それがたとえ何かちょっとした良いことでも、信ずる心のある人には神のご愛がわかるものです。けれども、わからない人にどれだけ大きなしるしを見せたって信仰にはなりません。(『愛と最善の神を信ぜよ』手島郁郎)(3~4頁)
(2012年6月8日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ブッダの真理のことば(ダンマパダ)』中村元訳 岩波文庫
■第1章 ひ と 組 ず つ
1)ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも汚れた心で話したり行なったりするならば、苦しみはその人につき従う。――車を引く(牛)の足跡に車輪がついて行くように。
2)ものごとは心にもとづき、心を主とし、心によってつくり出される。もしも清らかな心で話したり行なったりするならば、福楽はその人につき従う。――影がそのからだからはなれないように。
3)「かれは、われを罵った。かれは、われを害した。かれは、われにうち勝った。かれは、われから強奪した。」という思いをいだく人には、怨(うら)みはついに息(や)むことがない。
4)「かれは、われを罵った。かれは、われを害した。かれは、われにうち勝った。かれは、われから強奪した。」という思いをいだかない人には、ついに怨みが息(や)む。
6)「われらは、ここにあって死ぬはずのものである」と覚悟をしよう。――このことわりを他の人々は知っていないし。しかし、このことわり知る人々があれば、争いはしずまる。
11)まことでないものを、まことであると見なし、まことであるものを、まことではないと見なす人々は、あやまった思いにとらわれて、ついに真実(まこと)に達しない。
12)まことであるものを、まことであると知り、まことではないものを、まことではないと見なす人は、正しき思いにしたがって、ついに真実(まこと)に達する。
16)善いことをした人は、この世で喜び、来世でも喜び、ふたつのところで共に喜ぶ。かれは、自分の行為が淨(きよ)らかなのを見て、喜び、楽しむ。
19)たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているのである。――牛飼いが他人の牛を数えているように。かれは修行者の部類には入らない。
■第2章 は げ み
21)つとめ励むのは不死の境地である。怠りなまけるのは死の境涯である。つとめ励む人々は死ぬことが無い。怠りなまける人々は、死者のごとくである。
22)このことをはっきりと知って、つとめはげみを能(よ)く知る人々は、つとめはげみを喜び、聖者たちの境地をたのしむ。
23)(道に)思いをこらし、堪え忍ぶことつよく、つねに健(たけ)く奮励する、思慮ある人々は、安らぎ(注1)に達する。これは無上の幸せである。
24)こころはふるい立ち、思いつつましく、行ないは清く、気をつけて行動し、みずから制し、法(のり)にしたがって生き、つとめはげむ人は、名声が高まる。
28)賢者が精励修行によって怠惰をしりぞけるときには、知慧の高閣(たかどの)に登り、自からは憂い無くして(他の)憂いある愚人どもを見下(おろ)す。――山上にいる人が地上の人々を見下ろすように。
30)マガヴァー(注2)(インドラ神)は、つとめはげんだので、神々のなかでの最高の者となった。つとめはげむことを人々はほめたたえる。放逸なることはつねに非難される。
32)いそしむことを楽しみ、放逸におそれをいだく修行僧は、堕落するはずはなく、すでにニルヴァーナの近くにいる。
注1;安らぎ――サンスクリット語でニルヴァーナという。「涅槃」と音写する。最高の理想の境地であり、仏道修行の最後の目的せある。そこで人間の煩悩や穢れがすべて消滅している。
注2;マガヴァー――「寛仁なる者」「恵みを垂れる者」の意で、インドラ神の別名である。空界を支配する最高神。『リグ・ヴェーダ』において最も有力な神であったが、仏教にとり入れられて「帝釈天」となった。『出曜経』第9巻戒品の相当漢訳では「摩喝人」と訳している。つまりシナ人は最も力強い神をもなお「人」だと考えていたのである。
■第3章 心
33)心は、動揺し、ざわめき、護り難く、制し難い。英知ある人はこれを直(なお)くする。――弓矢職人が矢柄を直くするように。
35)心は、捉え難く、軽々とざわめき、欲するがままにおもむく。その心をおさめることは善いことである。心をおさめたならば、安楽をもたらす。
36)心は、極めて見難く、極めて微妙であり、欲するがままにおもむく。英知ある人は心を守れかし。心を守ったならば、安楽をもたらす。
37)心は遠くに行き、独り動き、形体なく、胸の奥の洞窟(注1)にひそんでいる。この心を制する人々は、死の束縛からのがれるであろう。
38)心が安住することなく、正しい真理を知らず、信念が汚されたならば(注2)、さとりの知慧は全からず。
39)心が煩悩に汚されることなく、おもいが乱れることなく、善悪のはからいを捨てて、目ざめている人には、何も恐れることが無い。
40)この身体は水瓶のように脆いものだと知って、この心を城郭のように(賢固に)安立して、知慧の武器をもって、悪魔と戦え。克ち得たものを守れ。――しかもそれに執著することなく。
41)ああ、この身はまもなく地上によこたわるであろう、――意識を失い、無用の木片(きぎれ)のように、投げ棄てられて。
42)憎む人が憎む人にたいし、怨む人が怨む人にたいして、どのようなことをしようとも、邪なことをめざしている心はそれよりもひどいことをする。
43)母も父もそのほか親族がしてくれるよりもさらにすぐれたことを、正しく向けられた心がしてくれる。
注1;胸の奥の洞窟――古ウパニシャッド以来、アートマンは心臓の内にある空処に住すると考えられていた。それを受けているのである。
注2;信念が汚されたならば――漢訳『法句経』には「迷於世事」と訳している。つまり、世の中俗な事がらに迷って純粋の信念が汚される、という意味である。
■第4章 花 に ち な ん で
45)学びつとめる人こそ、この大地を征服し、閻魔の世界と神々とともなるこの世界とを征服するであろう。わざに巧みな人が花を摘むように、学びにつとめる人々こそ善く説かれた真理のことばを摘み集めるであろう。
46)この身は泡沫(うたかた)のごとくであると知り、かげろうのようなはかない本性のものであると、さとったならば、悪魔の花の矢(注1)を断ち切って、死王に見られないところ(注2)へ行くであろう。
47)花を摘むのに夢中になっている人を、死がさらって行くように、眠っている村を、洪水が押し流して行くように、――
48)花を摘む(注3)のに夢中になっている人を、未だ望みを果さないうちに、死神がかれを征服する。
49)蜜蜂は(花の)色香を害(そこな)わずに、汁をとって、花から飛び去る。聖者が、村に行くときは、そのようにせよ。
50)他人の過失を見るなかれ。他人のしたこととしなかったことを見るな。ただ自分のしたこととしなかったこととだけを見よ。
51)うるわしく、あでやかに咲く花でも、香りの無いものがあるように、善く説かれたことばでも、それを実行しない人には実りがない。
52)うるわしく、あでやかに咲く花で、しかも香りのあるものがあるように、善く説かれたことばも、それを実行する人には、実りが有る。
53)うず高い花を集めて多くの華鬘(はなかざり)(注4)をつくるように、人として生まれまた死ぬべきであるならば、多くの善いことをなせ。
54)花の香りは風に逆らっては進んで行かない。栴檀もタガラの花もジャスミンもみなそうである。しかし徳のある人々の香りは、風に逆らっても進んで行く。徳のある人はすべての方向に薫る。
56)タガラ、栴檀の香りは微かであって、大したことはない。しかし徳行ある人々の香りは最上であって、天の神々にもとどく。
57)徳行を完成し、つとめはげんで生活し、正しい知慧によって解脱した人々には、悪魔も近づくによし無し。
58)大道に棄てられた塵芥(ちりあくた)の山堆(やまずみ)の中から香しく麗しい蓮華が生ずるように。
59)塵芥(ちりあくた)にも似た盲(めしい)た凡夫のあいだにあって、正しくめざめた人(ブッダ)の弟子は知慧もて輝く。
注1;悪魔の花の矢――三界の生存をいう。
注2;死王に見られないところ――不死なる大ニルヴァーナ。
注3;花を摘む――5欲の対象をさしていう。
注4;花鬘――愛人が花嫁の上に投げかける花かざりであると解する。ここでは「多くの善」を花かざりに譬えていう。
■第5章 愚 か な 人(注1)
60)眠れない人には夜は長く、疲れた人には1里の道は遠い。正しい真理を知らない愚かな者どもには、生死の道のりは長い。
61)旅に出て、もしも自分よりもすぐれた者か、または自分にひとしい者に出会わなかったら、むしろきっぱりと独りで行け。愚かな者を道伴れにしてはならぬ。
62)「わたしには子がある。わたしには財がある」と思って愚かな者は悩む。しかしすでに自己が自分のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか。どうして財が自分のものであろうか。
63)もしも愚者がみずから愚であるとかんがえれば、すなわち賢者である。愚者でありながら、しかもみずから賢者だと思う者こそ、「愚者」だと言われる。
64)愚かな者は生涯賢者に仕えても、真理を知ることが無い。匙がが汁の味を知ることができないように。
65)聡明な人は瞬時(またたき)のあいだ賢者に仕えても、ただちに真理を知る。――舌が汁の味をただちに知るように。
67)もしも或る行為をしたのちに、それを後悔して、顔に涙を流して泣きながら、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善くない。
68)もしも或る行為をしたのちに、それを後悔しないで、嬉しく喜んで、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善い。
69)愚かな者は、悪いことを行なっても、その報いの現われないあいだは、それを蜜のように思いなす。しかしその罪の報いの現われたときには、苦悩を受ける。
73)愚かな者は、実にそぐわぬ虚しい尊敬を得ようと願うであろう。修行僧らのあいだでは上位を得ようとし、僧房にあっては権勢を得ようとし、他人の家に行っては供養を得ようと願うであろう。
74)「これは、わたしたちのしたことである。在家の人々も出家した修行者たちも、ともにこのことを知れよ。およそなすべきこととなすべからざることとについては、わたしの意に従え」――愚かな者はこのように思う。こうして欲求と高慢(たかぶり)とがたかまる。
75)1つは利得に達する道であり、他の1つは安らぎ(注2)にいたる道である。ブッダの弟子である修行僧はこのことわりを知って、栄誉を喜ぶな。孤独の境地にはげめ。
注1;愚かな人――この章は愚かな凡夫に関する詩を集めてある。
注2;安らぎ――ニルヴァーナ。
■第6章 賢 い 人
78)悪い友と交わるな。卑しい人と交わるな。善い友と交われ。尊い人と交われ。
79)真理を喜ぶ人は、心きよらかに澄んで、安らかに臥す。聖者の説きたまうた真理を、賢者はつねに楽しむ。
81)1つの岩の塊りが風に揺るがないように、賢者は非難と賞讃とに動じない。
82)深い湖が、澄んで、清らかであるように、賢者は真理を聞いて、こころ清らかである。
83)高尚な人々は、どこにいても、執着することが無い。快楽を欲してしゃべることが無い。楽しいことに遭っても、苦しいことに遭っても、賢者は動ずる色がない。
84)自分のためにも、他人のためにも、子を望んではならぬ。財をも国をも望んではならぬ。邪(よこしま)なしかたによって自己の繁栄を願うてはならぬ。(道にかなった)行ないあり、明らかな知慧あり、真理にしたがっておれ。
85)人々は多いが、彼岸(かなたのきし)(注1)に達する人々は少い。他の(多くの)人々はこなたの岸(注2)の上でさまよっている。
86)真理が正しく説かれたときに、真理にしたがう人々は、渡りがたい死の領域を超えて、彼岸(かなたのきし)に至るであろう。
87)賢者は、悪いことがらを捨てて、善いことがらを行なえ。家から出て、家の無い生活に入り、楽しみ難いことではあるが、孤独(ひとりい)のうちに、喜びを求めよ。
88)賢者は欲楽をすてて、無一物となり、心の汚(けが)れを去って、おのれを浄めよ。
89)覚(さと)りのよすがに心を正しくおさめ、執着なく貪りをすてるのを喜び、煩悩を滅ぼし尽くして(注4)輝く人は、現世において全く束縛から解きほごされている。
注1;彼岸――ニルヴァーナのことをいう。
注2;こなたの岸――自分の身体を真実の自己だと見なす見解をいう。つまり生死流転のありさまをいう。
注3;覚りのよすが――さとりを得るために役立つ7つの事がらの意。それは(1)択法。教えの中から真実なるものを選びとり、偽りのものを捨てること。(2)精進。一心に努力すること。(3)喜。真実の教えを実行する喜びに住すること。(4)軽安(きょうあん)。身心をかろやかに快適にすること。(5)捨。対象へのとらわれを捨てること。(6)定。心を集中して乱さないこと。(7)念。おもいを平らかにすること。
注4;煩悩を滅ぼし尽くして――阿羅漢のことをいう。たたし『ダンマパダ』では修行者の階位はまだ考えていない。
■第7章 真 人 (注1)
90)すでに(人生の)旅路を終え、憂いをはなれ、あらゆることがらにくつろいで、あらゆる束縛の絆をのがれた人には、悩みは存在しない。
91)こころをとどめている人々は努めはげむ。かれらは住居(注2)を楽しまない。白鳥が池を立ち去る(注3)ように、かれらはあの家、この家を捨てる。
92)財を蓄えることなく、食物についてその本性を知り、その人々の解脱(注4)の境地は空(注5)にして無相(注6)であるならば(注7)、かれらの行く路(=足跡)は知り難い(注8)。――空飛ぶ鳥の迹の知りがたいように。
93)その人の汚(けが)れは消え失せ、食物をむさぼらず、その人の解脱の境地は空にして無相であるならば、かれの足跡は知り難い。――空飛ぶ鳥の迹の知りがたいように。
94)御者が馬をよく馴らしたように、おのが感官を静め、高ぶりをすて、汚れのなくなった(注9)人――このような境地にある人を神々でさえも羨む。
95)大地のように逆らうことなく、門のしまりのように慎しみ深く、(深い)湖は汚れた泥がないように――そのような(注10)境地にある人には、もはや生死の世は絶たれている。
96)正しい知慧によって、やすらいに帰した人――そのような人の心は静かである。ことばも静かである。行ないも静かである。
97)何ものかを信ずることなく(注12)、作られざるもの(=ニルヴァーナ)(注13)を知り、生死の絆を断ち、(善悪をなすに)よしなく、欲求を捨て去った人、――かれこそ実に最上の人である。
98)村でも、林にせよ、低地にせよ、平地にせよ、聖者の住む土地は楽しい。
99)人のいない林は楽しい。世人の楽しまないところにおいて、愛着なき人々は楽しむであろう。かれらは快楽を求めないからである。
注1;真人――尊敬さるべき人、拝まるべき人、尊敬供養を受けるべき人の意。修行を完成した人。漢訳では「阿羅漢」「羅漢」などと音写する。「応供」「応真」とも訳し、意訳して「真人」ともいう。もとは修行を完成した人のことをいい、この点ではジャイナ教などと共通であったし、またブッダの称号の1つとされ、もとはアルハトとはブッダの同義語であったが、後世になると両者は区別され、ブッダは超人的な仏として尊崇され、アルハトは小乗仏教での修行完成者をいうようになった。五百羅漢の彫刻には小乗仏教のアルハトの像がよく表現されている。しかしジャイナ教では今日に至るまでアルハトはジナ(――最高の崇拝対象――)と同義である。
注2;住居――「住居」であるとともに「執着」を意味する。
注3;白鳥が池を立ち去る――白鳥が「これはわが水である」とか「これはわが蓮である」とかこれはわが果皮である」とか、いかなる場所にも執著しないように、修行僧は「これはわが寺院である」とか「これはわが邸である」とか「これはわが檀家である」とか執著することが無い。(ブッダゴーサ)
注4;解脱――束縛を離れた自主の境地である。
注5;空――「情欲、怒り、迷妄が存在しないから空なのである。」(パーリ文注解)
注6;無相――その境地においては情欲などの相が存在しないから無相なのである。(パーリ文注解)
注7;解脱の境地は……無相であるならば;「空と無相と無願解脱とはニルヴァーナの3つのなである。」(パーリ文注解)
注8;かれらの行く路は知り難い――人格を完成した人の生活の道は、凡夫のうかがい知り得ざるものがあるという趣意である。
注9;汚れのなくなった――「汚れ」の原語はジャイナ教では汚れが迫って来て霊魂にまといつくことをいう。字義に即する限りは、この見解のほうが原義である。文字に即している。ところが仏教ではこのアーサヴァを「漏」と訳し、「漏泄(ろぜつ)」の義と解した。漏れ出ること。人間は肉体的には外に漏れるいろいろの不浄物があり、また精神的には煩悩の穢れが外に洩れる。その煩悩を無くし、人格を完成することを「無漏」とか漏尽という。
注10;そのような――人々が尊んでくれても尊んでくれなくても、それに喜びしたがうのでもなく、さからうのでもない。(ブッダゴーサ)
注11;そのような境地にある人――「そのような人」という字義で、ブッダのことをいう。漢訳『法句経』では真人と訳している。ジャイナ教では修行完成者、ジナのことをいう。ところが後代の仏教者はこの語の意味が解らなくなってしまったので、「救う人、救世主」と訳している。自力的修行者的立場から信仰的他力的立場への転換がなされたのである。
注12;信ずることなく:従来の諸訳では「軽信することなく」と訳されている。しかし文字どおりの意味は「信仰すること無く」である。バラモン教や当時の諸宗教に対する信仰を捨てるのは当然のことであったであろう。ところが仏教が大きくなって、教団の権威が確立すると、信仰を説くようになった。
注13;作られざるもの――作られたもの(有為)は転変し、生起消滅するが、「作られざるもの」すなわちニルヴァーナは永遠不変のものである。有為は迷い、無為はさとりの境地である。
■第8章 千 と い う 数 に に ち な ん で
100)無益な語句を千たびかたるよりも、聞いて心の静まる有益な語句を1つ聞くほうがすぐれている。
101)無益な語句を千たびかたるよりも、聞いて心の静まる有益な語句を1つ聞くほうがすぐれている。
102)無益な語句よりなる詩を百もとなえるよりも、聞いて心の静まる詩を1つ聞くほうがすぐれている。
104、105)自己にうち克つことは、他の人々に勝つことよりもすぐれている。つねに行ないをつつしみ、自己をととのえている人、――このような人の克ち得た勝利を敗北に転ずることは、神も、ガンダルヴァ(天の伎楽神)も、悪魔も、梵天(注1)もなすことができない。
109)つねに敬礼を守り、年長者を敬う人には、4種のことがらが増大する。――すなわち、寿命と美しさと楽しみと力とである。
110)素行が悪く、心が乱れていて百年生きるよりは、徳行あり思い静かな人が1日生きるほうがすぐれている。
111)愚かに迷い、心が乱れていて百年生きるよりは、知慧あり思い静かな人が1日生きるほうがすぐれている。
112)怠りなまけて、気力も無く百年生きるよりは、堅固につとめ励んで1日生きるほうがすぐれている。
113)物事が興りまた消え失せることわりを見ないで百年生きるよりも、事物が興りまた消え失せることわりを見て1日生きることのほうがすぐれている。
114)不死(しなない)の境地を見ないで百年生きるよりは、不死の境地を見て1日生きることのほうがすぐれている。
115)最上の真理を見ないで百年生きるよりは、最上の真理を見て1日生きることのほうがすぐれている。
注1;梵天――ブラーフマン、世界を創造した主神として当時の人々から尊崇されていた。
■第9章 悪
116)善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなすのにのろのろしたら、心は悪事をたのしむ。
117)人がもしも悪いことをしたならば、それを繰り返すな。悪事を心がけるな。悪がつみ重なるのは苦しみである。
118)人がもしも善いことをしたならば、それを繰り返せ。善いことを心がけよ。善いことがつみ重なるのは楽しみである。
119)まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある。しかし悪の報いが熟したときには、悪人はわざわいに遇う。
120)まだ善の報いが熟しないあいだは、善人でもわざわいに遇うことがある。しかし善の果報が熟したときには、善人は幸福(さいわい)に遇う。
121)「その報いはわたしには来ないだろう」とおもって、悪を軽んずるな。水が1滴ずつ滴りおちるならば、水瓶でもみたされるのである。愚かな者は、水を少しずつでも集めるように悪を積むならば、やがてわざわいにみたされる。
122)「その報いはわたしには来ないだろう」とおもって、善を軽んずるな。水が1滴ずつ滴りおちるならば、水瓶でもみたされる。気をつけている人は、水を少しずつでも集めるように善を積むならば、やがて福徳にみたされる。
123)同行する仲間が少ないのに多くの財を運ばねばならぬ商人が、危険な道を避けるように、また生きたいとねがう人が毒を避けるように、ひとはもろもろの悪を避けよ。
124)もしも手に傷が無いならば、その人は手で毒をとり去ることもできるであろう。傷の無い人に、毒は及ばない。悪をなさない人には、悪の及ぶことがない。
125)汚(けが)れの無い人、清くて咎(とが)のない人をそこなう者がいるならば、そのわざわいは、かえってその浅はかな人に至る。風にさからって細かい塵を投げると、(その人にもどって来る)ように。
126)或る人々は〔人の〕胎に宿り、悪をなした者どもは地獄に堕ち、行ないの良い人々は天におもむき、汚(けが)れのない人々は全き安らぎ(注1)に入る。
127)大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の奥深いところに入っても、およそ世界のどこにいても、悪業から脱れることのできる場所は無い。
128)大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の洞窟に入っても、およそ世界のどこにいても、死の脅威のない場所は無い。
注1;安らぎ――ニルヴァーナ=涅槃。
■第10章 暴 力
133)荒々しいことばを言うな。言われた人々は汝に言い返すであろう。怒りを含んだことばは苦痛である。報復が汝の身に至るであろう。
134)こわれた鐘のように、声をあらげないならば、汝は安らぎに達している。汝はもはや怒り罵(ののし)ることがないからである。
135)牛飼いが棒をもって牛どもを牧場に駆り立てるように、老いと死とは行きとし生けるものどもの寿命を駆り立てる。
136)しかし愚かな者は、悪い行ないをしておきながら、気がつかない。浅はかな愚者は自分自身のしたことによって悩まされる。――火に焼きこがされた人のように。
141)裸の行も、髷(まげ)に結うのも、身が泥にまみれるのも、断食も、露地に臥すのも、塵や泥を身に塗るのも、蹲(うずくま)って動かないのも、――疑いを離れていない人を浄めることはできない。
142)身の装いはどうあろうとも、行ない静かに、心おさまり、身をととのえて、慎みぶかく、行ない正しく、生きとし生けるものに対して暴力を用いない人こそ、〈バラモン〉とも、〈道の人〉とも、また〈托鉢遍歴僧〉ともいうべきである。
143)みずから恥じて自己を制し、良い馬が鞭を気にかけないように、世の非難を気にかけない人が、この世に誰か居るだろうか?
144)鞭をあてられた良い馬のように勢いよく努め励めよ。信仰により、戒めにより、はげみにより、精神統一により、真理を確かに知ることにより、知慧と行ないを完成した人々は、思念をこらし、この少なからぬ苦しみを除けよ。
145)水道をつくる人は水をみちびき、矢をつくる人は矢を矯め、慎み深い人々は自己をととのえる。
■第11章 老 い る こ と
146)何の笑いがあろうか。何の歓びがあろうか?――世間は常に燃え立っているのに――。汝らは暗黒に覆われている。どうして燈明を求めないのか(注1)?
147)見よ、粉飾された形体を(注2)!(それは)傷だらけの身体であって、いろいろのものが集っただけである。病いに悩み、意欲ばかり多くて、堅固でなく、安住していない。
148)この容色は衰えはてた。病の巣であり、脆くも滅びる。腐敗のかたまりで、やぶれてしまう。生命は死に帰着する。
151)いとも麗しき国王の車も朽ちてしまう。身体もまた老いに近づく。しかし善い立派な人々は互いにことわりを説き聞かせる。
152)学ぶことの少ない人は、牛のように老いる。かれの肉は増えるが、かれの知慧は増えない。
153)わたくしは幾多の生涯にわたって生死の流れを無益に経めぐって来た、――家屋の作者(つくりて)(注3)をさがしもとめて――。あの生涯、この生涯とくりかえすのは苦しいことである。
154)家屋の作者(つくりて)よ!汝の正体は見られてしまった。汝はもはや家屋を作ることはないであろう。汝の梁(はり)はすべて折れ、家の屋根は壊れてしまった。心は形成作用を離れて、妄執を滅ぼし尽くした。
155)若い時に、財を獲ることなく、清らかな行ないをまもらないならば、魚のいなくなった池にいる白鷺のように、痩せて滅びてしまう。
156)若い時に、財を獲ることなく、清らかな行ないをまもらないならば、壊れた弓のようによこたわる。――昔のことばかり思い出してかこちながら。
注1;燈明を求めないのか――世の中が無常であり、万物が消滅することを、燃えさかる火に譬えていうのである。
注2;粉飾された形体――パーリ仏典では人間の身体あるいは個体のことをいう。
注3;家屋の作者――ここでは人間の個体を家屋にたとえ、妄執(愛執)を大工すなわち家屋の造り者(て)にたとえているのである。
■第12章 自 己
157)もしひとが自己を愛しいものと知るならば、自己をよく守れ。賢い人は、夜の3つの区分のうちの1つ(注1)だけでも、つつしんで目ざめておれ。
158)先ず自分を正しくととのえ、次いで他人を教えよ。そうすれば賢明な人は、煩わされて悩むことが無いであろう。
159)他人に教えるとおりに、自分でも行なえ――。自分をよくととのえた人こそ、他人をととのえるであろう。自己は実に制し難い。
160)自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?自己をよくととのえたならば、得難き主を得る。
161)自分がつくり、自分から生じ、自分から起った悪が知慧悪しき人を打ちくだく。――金剛石が宝石を打ちくだくように。
162)極めて性(たち)の悪い人は、仇敵がかれの不幸を望むとおりのことを、自分に対してなす。――蔓草が沙羅(しゃら)の木にまといつくように。
163)善からぬこと、己れのためにならぬことは、なし易い。ためになること、善いことは、実に極めてなし難い。
165)みずから悪をなすならば、みずから汚れ、みずから悪をなさないならば、みずから淨(きよ)まる。淨いのも淨くないのも、各自のことがらである。人は他人を淨めることができない。
166)たとい他人にとっていかに大事であろうとも、(自分ではない)他人の目的のために自分のつとめをすて去ってはならぬ。自分の目的を熟知して、自分のつとめに専念せよ。
注1;夜の3つの区分のうちの1つ――古代インドでは夜に3つの時分があると考えていた。それと同様に人生にも3つの時期がある。第1の時期では遊戯に夢中になっている。第2の中間の時期には妻子を養っている。第3の最後の時期だけは少なくとも善をなすべきであるというのである。この3つはほぼ少年期、壮年期、老年期に相当するといえようか。ブッダゴーサによると、人生の3つの時期のうち少なくとも1つの時期はめざめて修行につとめよ、という。在俗信者が第1の時期に善をなすことができなくても、第2の時期に行なうべきである。。第2の時期に妻子を養っているために善をなすことができなければ最後の時期に行なうべきである。第1の時期に出家したがなまけた場合には、第2の時期に沙門の法を行なうべきである。第2の時期に怠ったときには最後の時期に沙門の法を実行すべきであるという。
■第13章 世 の 中
167)下劣なしかたになじむな。怠けてふわふわと暮すな。邪な見解をいだくな。世俗のわずらいをふやすな。
168)奮起(ふるいた)てよ。怠けてはならぬ。善い行ないのことわりを実行せよ。ことわりに従って行なう人は、この世でも、あの世でも、安楽に臥す。
169)善い行ないのことわりを実行せよ。悪い行ないのことわりを実行するな。ことわりに従って行なう人は、この世でも、あの世でも、安楽に臥す。
170)世の中は泡沫(うたかた)のごとしと見よ。世の中はかげろうのごとしと見よ。世の中をこのように観ずる人は、死王もかれを見ることがない。
171)さあ、この世の中を見よ。王者の車のように美麗である。愚者はそこに耽溺するが、心ある人はそれに執著しない。
172)また以前には怠りなまけていた人でも、のちに怠りなまけることが無いなら、その人はこの世の中を照らす。――あたかも雲を離れた月のように。
173)以前には悪い行ないをした人でも、のちに善によってつぐなうならば、その人はこの世の中を照らす。――雲を離れた月のように。
174)この世の中は暗黒である。ここではっきりと(ことわりを)見分ける人は少ない。網から脱れた鳥のように、天に至る人は少ない。
175)白鳥は太陽の道を行き、神通力による者は虚空(そら)を行き、心ある人々は、悪魔とその軍勢にうち勝って世界から連れ去られる。
176)唯一なることわりを逸脱し、偽りを語り、彼岸の世界を無視している人は、どんな悪でもなさないものは無い。
177)物惜しみする人々は天の神々の世界におもむかない。愚かな人々は分ちあうことをたたえない。しかし心ある人は分ちあうことを喜んで、そのゆえに来世には幸せとなる。
178)大地の唯一の支配者となるよりも、天に至るよりも、全世界の主権者となるよりも、聖者の第1段階(預流果(よるか))のほうがすぐれている。
■第14章 ブ ッ ダ
179)ブッダの勝利は敗れることがない。この世においては何人(なんびと)も、かれの勝利には達し得ない。ブッダの境地はひろくて涯(はて)しがない。足跡をもたない(注1)かれを、いかなる道によって誘い得るであろうか?
180)誘(いざ)なうために網のようにからみつき執著をなす妄執は、かれにはどこにも存在しない。ブッダの境地は、ひろくて涯(はて)しがない。足跡をもたないかれを、いかなる道によって誘い得るであろうか?
181)正しいさとりを開き、念(おも)いに耽り、瞑想に専中している心ある人々は世間から離れた静けさを楽しむ。神々さえもかれらを羨む。
182)人間の身を受けることは難しい。死すべき人々に寿命があるのも難しい。正しい教えを聞くのも難しい。もろもろのみ仏の出現したもうことも難しい。
183)すべて悪しきことをなさず、善いことを行ない、自己の心を淨めること(注2)、――これが諸の仏の教えである。
184)忍耐・堪忍は最上の苦行である。ニルヴァーナは最高のものであると、もろもろのブッダは説きたまう。他人を害する人は出家者ではない。他人を悩ます人は〈道の人〉ではない。
185)罵(ののし)らず、害わず、戒律に関しておのれを守り、食事に関して(適当な)量を知り、淋しいところにひとり臥し、坐し、心に関することにつとめはげむ。――これがもろもろのブッダの教えである。
186)たとえ貨幣の雨を降らすとも、欲望の満足されることはない。「快楽の味は短くて苦痛である」と知るのが賢者である。
187)天上の快楽にさえもこころ楽しまない。正しく覚った人(=仏)の弟子は妄執の消滅を楽しむ。
190,191)さとれる者(=仏)と真理のことわり(=法)と聖者の集い(=僧)(注3)とに帰依する人は、正しい知慧をもって、四つの尊い真理(注4)を見る(注5)。――すなわち(1)苦しみと、(2)苦しみの成り立ちと、⑶苦しみの超克と、(4)苦しみの終滅(おわり)におもむく8つの尊い道(八聖道(はっしょうどう)(注6))とを(見る)。
192)これは安らかなよりどころである。これは最上のよりどころである。このよりどころにたよってあらゆる苦悩から免れる。
193)尊い人(=ブッダ)(注7)は得がたい。かれはどこにでも生れるのではない。思慮深い人(=ブッダ)の生れる家は、幸福に栄える。
194)もろもろのみ仏の現われたまうのは楽しい。正しい教えを説くのは楽しい。つどいが和合(注8)しているのは楽しい。和合している人々がいそしむのは楽しい。
195,196)すでに虚妄な論議をのりこえ、憂いと苦しみをわたり、なにものをも恐れず、安らぎに帰した。拝むにふさわしいそのような人々、もろもろのブッダまたはその弟子たちを供養するならば、この功徳はいかなる人でもそてを計ることができない。
注1;足跡をもたない――仏の活動は自在無礙であり、凡夫がうかがい知ることができない、との意。後代の禅でも「大用現前して規則を存せず」という。
注2;すべて……浄めること――これを昔から「七仏通誡偈」という。過去七仏がみなこの詩を教えたもうたというのである。その漢訳文である「諸悪莫作、諸善奉行、自浄其意、是諸仏教」は東アジア諸国にあまねく知られている。
注3;聖者の集い(=僧)――原語を音写して「僧」、「僧伽」という。5人もしくは5人以上の組織のある団体をいう。わが国では「1人の僧」などといって個々の僧侶をさしていうのは原義からの転用であって、この場合には適合しない。
注4;四つの尊い真理――漢訳では「四諦(したい)」とか「四聖諦(ししょうだい)」という。普通、「苦、集、滅、道」でしめされる。「諦」とは真理のことである。
注5;帰依する人は……見る――この詩句から見ると、三宝に対する帰依は、真理を知るための準備段階、入口と考えられていたことが解る。
注6;八聖道――八正道ともいう。正しい見解(正見)、正しい思い(正思)、正しいことば(正語)、正しい行為(正業)、正しい生活(正命)、正しい努力(正精進)、正しい気づかい(正念)、正しい心の落ちつき(正定)をいう。
注7;尊い人――明人と訳している。
注8;つどいが和合――サンガとは実際にはこの場合には出家修行僧のつどいを意味していたのであろう。
■第15章 楽 し み
197)怨みをいだいている人々のあいだにあって怨むこと無く、われらは大いに楽しく生きよう。怨みをもっている人々のあいだにあって怨むこと無く、われらは暮していこう。
198)悩める人々のあいだにあって、悩み無く、大いに楽しく生きよう。悩める人々のあいだにあって、悩み無く暮そう。
199)貪っている人々のあいだにあって、患い無く、大いに楽しく生きよう。貪っている人々のあいだにあって、貪らないで暮そう。
200)われわれは一物をも所有していない。大いに楽しく生きて行こう。光り輝く神々(注1)のように、喜びを食(は)む者(注2)となろう。
201)勝利からは怨みが起る。敗れた人は苦しんで臥す。勝敗をすてて、やすらぎに帰した人は、安らかに臥す。
202)愛欲にひとしい火は存在しない。ばくちに負ける(注3)としても、憎悪にひとしい不運は存在しない。
このかりそめの身(注4)にひとしい苦しみは存在しない。やすらぎ(注5)にまさる楽しみは存在しない。
203)飢えは最大の病であり、形成せられた存在(=わが身)は最もひどい苦しみである。このことわりをあるがままに知ったならば、ニルヴァーナという最上の楽しみがある。
204)健康は最高の利得であり、満足は最上の宝であり、信頼は最高の知己であり、ニルヴァーナは最上の楽しみである。
205)孤独(ひとり)の味、心の安らいの味をあじわったならば、恐れも無く、罪過(つみとが)も無くなる、――真理の味をあじわいながら。
206)もろもろの聖者に会うのは善いことである。かれらと共に住むのはつねに楽しい。愚かなる者どもに会わないならば、心はつねに楽しいであろう。
207)愚人とともに歩む人は長い道のりにわたって憂いがある。愚人と共に住むのは、つねにつらいことである。――仇敵とともに住むように。
208)よく気をつけていて、明らかな知慧あり、学ぶところ多く、忍耐づよく、戒めをまもり、そのような立派な聖者・善き人、英知ある人に親しめよ。――月がもろもろの星の進む道にしたがうように。
注1)神々――漢訳『法句経』安寧品には「光音天」と訳す。この天神は漢訳仏典では「極光淨天」「光曜天」とも訳される。この天神が語る時、口から清らかな光を放ち、その光がことばになるといわれる。のちのアビダルマ教義学においては、色界第2禅のうちの第3位に住する天とされた。色界16天の1つである。
注2)喜びを食む者――この一群の神々は「よろこび」を食物とすると信じられていた。『愚者常歓喜、如光音天』(増壱阿含経』24、36)
注3)ばくちに負ける――ばくち(賭博)における不運な骰の目をいう。
注4)かりそめの身――「蘊」と漢訳され、われわれの変化する生存の諸要素の集合、個人存在をいう。
注5)やすらぎ――漢訳『法句経』には「滅』と訳している。静まること。
■第16章 愛 す る も の
209)道に違うたことになじみ、道に順(したが)ったことにいそしまず(注1)、目的を捨てて快いことだけを取る人は、みずからの道に沿って進む者を羨むに至るであろう。
210)愛する人と会うな。愛しない人とも会うな。愛する人に会わないのは苦しい。また愛しない人に会うのも苦しい。
211)それ故に愛する人をつくるな。愛する人を失うのはわざわいである。愛する人も憎む人もいない人々には、わずらいの絆が存在しない。
212)愛するものから憂いが生じ、愛するものから恐れが生ずる、愛するものを離れたならば、憂いは存在しない。どうして恐れることがあろうか?
213)愛情から憂いが生じ、愛情から恐れが生ずる。愛情を離れたならば、憂いが存在しない。どうして恐れることがあろうか?
214)快楽から憂いが生じ、快楽から恐れが生ずる。快楽を離れたならば、憂いが存在しない。どうして恐れることがあろうか?
215)欲情から憂いが生じ、欲情から恐れが生ずる。欲情を離れたならば、憂いは存在しない。どうして恐れることがあろうか。
216)妄執から憂いが生じ、妄執から恐れが生ずる。妄執を離れたならば、憂いは存在しない。どうして恐れることがあろうか。
217)徳行と見識とをそなえ、法(のり)にしたがって生き、真実を語り、自分のなすべきことを行なう人は、人々から愛される。
218)ことばで説き得ないもの(=ニルヴァーナ)に達しようとする志を起し、意(おもい)はみたされ、諸の愛欲に心の礙(さまた)げられることのない人は、〈流れを上(のぼ)る者〉(注2)とよばれる。
219)久しく旅に出ていた人が遠方から無事に帰って来たならば、親戚・友人・親友たちはかれが帰ってきたのを祝う。
220)そのように善いことをしてこの世からあの世に行った人を善業が迎え受ける。――親族が愛する人が帰って来たのを迎え受けるように。
注1)道に違うた……いそしまず――以上は漢訳『法句経』にしたがって訳した。パーリ文註解によると「道に違うたことになじみ」とは遊女など、心を向けてはならぬものに耽ることであるという。
注2)流れを上る者――パーリ文註解によると「無煩天」に生れて、そこから出発して、転生して、アカニタ天に行く人」であるというし、またこの語は説一切有部のアビダルマ教義学ではいわゆる「上流般涅槃」であり不還(ふげん)の1つである。しかし『ダンマパダ』のこの詩句ではそのような複雑なことは考えていなかったであろう。
■第17章 怒 り
221)怒りを捨てよ。慢心を除き去れ。いかなる束縛(注1)をも超越せよ。名称と形態(注2)とにこだわらず、無一物となった者は、苦悩に追われることがない。
222)走る車をおさえるようにむらむらと起る怒りをおさえる人――かれをわれは〈御者〉とよぶ。他の人はただ手綱(たづな)を手にしているだけである。(〈御者〉とよぶにはふさわしくない。)
223)怒らないことによって怒りにうち勝て。善いことによって悪いことにうち勝て。わかち合うことによって物惜しみにうち勝て。真実によって虚言の人にうち勝て。
224)真実を語れ。怒るな。請われたならば、乏しいなかから与えよ。これらの3つの事によって(死後には天の)神々のもとに至り得るであろう。
226)ひとがつねに目ざめていて、昼も夜もつとめ学び、ニルヴァーナを得ようとめざしているならば、もろもろの汚れは消え失せる。
227)アトゥラ(注3)よ。これは昔にも言うことであり、いまに始まることでもない。沈黙している者も非難され、多く語る者も非難され、すこしく語る者も非難される。世に非難されない者はいない。
228)ただ誹(そし)られるだけの人、またただ褒められるだけの人は、過去にもいなかったし、未来にもいないであろう、現在にもいない。
229)もし心ある人が日に日に考察して「この人は賢明であり、行ないに欠点が無く、知慧と徳行とを身にそなえている」といって称讃するならば、
230)その人を誰が非難し得るだろうか?かれはジャンブーナダ河から得られる黄金でつくった金貨(注4)のようなものである。神々もかれを称讃する。梵天でさえもかれを称讃する。
231)身体がむらむらするのを、まもり落ち着けよ。身体について慎んでおれ。身体による悪い行ないを捨てて、身体によって善行を行なえ。
232)ことばがむらむらするのを、まもり落ち着けよ。ことばについて慎んでおれ。語(ことば)による悪い行ないを捨てて、語(ことば)によって善行を行なえ。
233)心がむらむらするのを、まもり落ち着けよ。心について慎んでおれ。心による悪い行ないを捨てて、心によって善行を行なえ。
234)落ち着いて思慮ある人は身をつつしみ、ことばをつつしみ、心をつつしむ。このようにかれらは実によく己をまもっている。
注1)束縛――語義は「結びつけるもの」、つまり人を結びつけ縛る煩悩をいう。
注2)名称と形態――この語は古ウパニシャッドにおいては「名称と形態」すなわち現象界のすべてを意味する。この語は仏教にも継承されて「名称」とは人間の精神的方向、形態とは人間の物質的側面を意味すると解釈されているが、教義学者たちが無理にこじつけた解釈であろう。インド思想一般の用例としては「名称」を精神と解することは無理である。
注3)アトゥラ――北方インドのサーヴァッティー市の在俗信者であったが、5百人の信者に囲まれて、レーヴァタ長老のところに行って教えを聞こうとしたが、この長老はひとり静かに瞑想に耽っていたために、何も説いてくれなかった。そこでかれは憤ってサーリブッタ長老のところへ行ったら、アビダルマに関する論議をやたらに聞かされた。「こんな難解な話を聞いて何の役に立つか?」と憤って、アトゥラは次にアーナンダ長老のところへ行ったところが、ほんの少しばかり教えを説いてくれた。そこでやはり憤って、最後に祇園精舎にまします釈尊のところへ行ったところが、釈尊はこの詩を語ったのだという。
注4)金貨――漢訳では「閻浮檀金(えんぶだんごん,えんぶだごん)」という。ジャンブー樹の大森林を流れる河の底に産する砂金で、金のうちでは最も高貴なものとされた。その金によってつくった良質の金貨をいう。
■第18章 汚 れ
240)鉄から起った錆びが、それから起ったのに、鉄自身を損なうように、悪をなしたならば、自分の業が罪を犯した人を悪いところ(地獄)にみちびく。
241)読誦しなければ聖典(注1)が汚(けが)れ(注2)、修理しなければ家屋(いえ)が汚れ、身なりを怠るならば容色が汚れ、なおざりになるならば、つとめ慎しむ人が汚れる。
242)不品行は婦女の汚(けが)れである。もの惜しみは、恵み与える人の汚れである。悪事は、この世においてもかの世においても(つねに)汚れである。
243)この汚(けが)れよりもさらに甚だしい汚れがある。無明(注3)こそ最大の汚れである。修行僧らよ。この汚れを捨てて、汚れ無き者となれ。
244)恥を知らず、烏のように厚かましく、図々しく、ひとを責め、大胆で、心のよごれた者(ひと)は、生活し易い。
245)恥を知り、常に清きをもとめ、執著をはなれ、つつしみ深く、真理を見て清く暮す者(ひと)は、生活し難い。
249)ひとは、信ずるところにしたがって、きよき喜びにしたがって、ほどこしをなす。だから、他人のくれた食物や飲料に満足しない人は、昼も夜も心のやすらぎを得ない。
250)もしもひとがこの(不満の思い)を絶ち、根だやしにしたならば、かれは昼も夜も心のやすらぎを得る。
251)情欲にひとしい火は存在しない。不利な骰(さい)の目を投げたとしても、怒りにひとしい不運は存在しない。迷妄にひとしい網は存在しない。妄執にひとしい河は存在しない。
252)他人の過失は見やすいけれども、自己の過失は見がたい。ひとは他人の過失を籾殻のように吹き散らす。しかし自分の過失は、隠してしまう。――狡猾な賭博師が不利な骰(さい)の目をかくしてしまうように。
253)他人の過失を探し求め、つねに怒りたける人は、煩悩の汚れが増大する。かれは煩悩の汚れの消滅(注4)から遠く隔っている。
254)虚空には足跡が無く、外面的なことを気にかけるならば、〈道の人〉ではない。ひとびとは汚れのあらわれをたのしむが、修行完成者は汚れのあらわれるをたのしまない。
255)虚空には足跡が無く、外面的なことを気にかけるならば、〈道の人〉ではない(注5)。造り出された現象(注6)が常住であることは有り得ない(注7)。真理をさとった人々(ブッダ)は、動揺することがない。
注1)聖典――ヴェーダ聖典の本文のことである。バラモンたちは朝夕これをとなえる。
注2)独誦しなければ……汚れ――パーリ文註解によると「聖典であろうとも、あるいは技術であろうとも、読誦しない人、すなわち努めはげまない人にとっては滅びてしまうか、あるいは不断に現れることが無いから、〈読誦しなければ聖典が汚れる〉というのである。」当時は聖典は暗誦によって伝えられ、技術は口伝によって伝えられていたから、人が暗誦をやめてしまったら、聖典は消え失せてしまうのである。紙や樹葉に書かれた聖典の読誦を想像してはならない。書かれた聖典の読誦は西暦紀元後に一般に行なわれるようになった。
注3)無明――われわれの生存の根本にある無智のこと。これがわれわれの迷いの根本原因となっている。
注4)煩悩の汚れの消滅――普通「漏尽(ろじん)」と漢訳されるが、煩悩を尽すことで、修行者としての最終段階(阿羅漢果)に達することをいう。
注5)外面的な……〈道の人〉ではない――殆んどすべての翻訳者はブッダゴーサの註解にしたがって「仏教の外なる外道(げどう)には真の修行者はいない」と解する。《中略》ブッダゴーサの解釈は後世にになって教団意識が高まってから、それに影響されたのであろう。
注6)造り出された現象――「有為」と呼ばれるものと同じである。
注7)有り得ない――漢訳『法句経』塵垢品には「世間皆無常」と訳している。
■第19章 道 を 実 践 す る 人
260)頭髪が白くなったとて〈長老〉なのではない。ただ年をとっただけならば「空(むな)しく老いぼれた人」と言われる。
261)誠あり、徳あり、慈しみがあって、傷(そこな)わず、つつしみあり、みずからととのえ、汚れを除き、気をつけている人こそ「長老」と呼ばれる。
262)嫉(ねた)みぶかく、吝嗇(けち)で、偽る人は、ただ口先だけでも、美しい容貌によっても、「端正な人」とはならない。
263)これを断ち、根絶やしにし、憎しみをのぞき、聡明である人、――かれこそ「端正な人』とよばれる。
264)頭を剃ったからとて、いましめをまもらず、偽りを語る人は、〈道の人〉ではない。欲望と貪りにみちている人が、どうして〈道の人〉であろうか?
265)大きかろうとも小さかろうとも悪をすべてとどめた人は、もろもろの悪を静め滅ぼしたのであるから、〈道の人〉とよばれる。
267)この世の福楽も罪悪も捨て去って、清らかな行ないを修め、よく思慮して世に処しているならば、かれこそ〈托鉢僧〉と呼ばれる。
271,272)わたくしは、出離の楽しみを得た。それは凡夫の味わい得ないものである。それは、戒律や誓いだけによっても、また博学によっても、また瞑想を体現しても、またひとり離れて臥すことによっても、得られないものである。修行僧よ。汚れが消え失せない限りは、油断するな。
■第20章 道
273)もろもろの道のうちでは〈八つの部分よりなる正しい道(注1)〉が最もすぐれている。もろもろの真理のうちでは〈四つの句(注2)〉(=四諦)が最もすぐれている。もろもろの徳のうちでは〈情欲を離れること〉が最もすぐれている。人々のうちでは〈眼(まなこ)ある人〉(=ブッダ)が最もすぐれている。
275)汝らがこの道を行くならば、苦しみをなくすことができるであろう。(棘が肉に刺さったので)矢を抜いて癒す方法を知って、わたくしは汝らにこの道を説いたのだ。
276)汝らは(みずから)つとめよ。もろもろの如来(=修行を完成した人)は(ただ)教えを説くだけである。心をおさめて、この道を歩む者どもは、悪魔の束縛から脱れるであろう。
277)「一切の形成されたものは無常である」(諸行無常)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
278)「一切の形成されたものは苦しみである」(一切皆苦)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
279)「一切の事物は我ならざるものである(注3)」(諸法非我)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
280)起きるべき時に起きないで、若くて力があるのに怠りなまけていて、意志も思考も薄弱で、怠惰でものうい人は、明らかな知慧によって道を見出すことがない。
281)ことばを慎しみ、心を落ち着けて慎しみ、身に悪を為してはならない。これらの3つの行ないの路を淨くたもつならば、仙人(=仏)の説きたもうた道を克ち得るであろう。
282)実に心が統一されたならば、豊かな知慧が生じる。心が統一され(注4)ないならば、豊かな知慧がほろびる。生ずることとほろびることとのこの2種の道を知って、豊かな知慧が生ずるように自己をととのえよ。
283)1つの樹を伐るのではなくて、(煩悩の)林を伐れ。危険は林から生じる(注5)。(煩悩の)林とその下生えとを切って、林(=煩悩)から脱れた者となれ。修行僧らよ。
284)たとい僅かであろうとも、男の女に対する欲望が断たれないあいだは、その男の心は束縛されている。――乳を吸う子牛が母牛を恋い慕うように。
285)自己の愛執を断ち切れ、――池の水の上に出て来た秋の蓮を手で断ち切るように。静やかなやすらぎに至る道を養え。めでたく行きし人(=仏)は安らぎを説きたもうた。
286)「わたしは雨期にはここに住もう。冬と夏とにはここに住もう」と愚者はこのようにくよくよと慮(おもんばか)って、死が迫って来るのに気がつかない。
287)子どもや家畜のことに気を奪われて心がそれに執著している人を、死はさらって行く。――眠っている村を大洪水が押し流すように。
288)子も救うことができない。父も親戚もまた救うことができない。死に捉えられた者を、親族も救い得る能力がない。
注1)8つの部分よりなる正しい道――漢訳では普通「八正道」という。正しい見解(正見)、正しいおもい(正思)、正しいことば(正語)、正しいおこない(正業)、正しい生活(正命)、正しい努力(正精進)、正しい注意(正念)、正しい精神統一(正定)の8つである。この8つが人を解脱(ニルヴァーナ)にみちびく正しい道であるという。
注2)4つの句――4つの真理。⑴苦しみの真理。この世は苦しみであるということ〔=苦諦〕。⑵苦しみのなりたちの真理。その苦しみの成立する原因は煩悩・妄執であるということ〔=集諦〕。⑶苦しみの原因の終滅という真理。すなわち無常の世を超え、執着を断つことが苦しみを滅したさとりの境地であるということ〔滅諦〕。⑷さとりに導く実践と言う真理。すなわち理想の境地に至るためには、八正道の正しい修行方法によるべきであるということ〔=道諦〕。
注3)一切の事物は我ならざるものである――これがパーリ聖典にあらわれる古い思想である。ところがのちには「一切の事物は恒存する実体をもたない(無我)」と解釈するようになった。
注4)心が統一され――原始仏教もヨーガを認めていたのである。ヨーガとは「結びつける」という意味で、心を散乱させないように1つの対象に結びつけることである。しかしそれは後代の曲芸のようなハタ・ヨーガとは異なっていた。
注5)危険は林から生じる――林のなかには猛獣や毒蛇がうろついていて危険であるように、人間の貪ぼり、怒りなどの煩悩は危険なものであるということを言おうとするものであろう。
■第21章 さ ま ざ ま な こ と
290)つまらぬ快楽を捨てることによって、広大なる楽しみを見ることができるのであるなら、心ある人は広大な楽しみをのぞんで、つまらぬ快楽をすてよ。
291)他人を苦しめることによって自分の快楽を求める人は、怨みの絆にまつわられて、怨みから免れることができない。
292)なすべきことを、なおざりにし、なすべからざることをなす、遊びたわむれ放逸なる者どもには、汚(けが)れが増す。
293)常に身体(の本性)を思いつづけて、為すべからざることを為さず、為すべきことを常に為して、心がけて、みずから気をつけている人々には、もろもろの汚れがなくなる。
294)(「盲愛」という)母と(「われありという慢心(注1)」である)父とをほろぼし、(永久に存在するという見解と滅びて無くなるという見解という)2人の武家の王をほろぼし、〔主観的機官と客観的対象とあわせて12の領域(注2)である〕国土と(「喜び貪り」という)従臣とをほろぼして、バラモンは汚れなしにおもむく。
295)(「盲愛」という)母と(「われありという慢心」である)父とをほろぼし、(永久に存在するという見解と滅びて無くなるという見解という)2人の、学問を誇るバラモン王をほろぼし、第5には(「疑い」という)虎(注3)をほろぼして、バラモンは汚れなしにおもむく。
302)出家の生活は困難であり、それを楽しむことは難しい。在家の生活も困難でであり、家に住むのも難しい。心を同じくしない人々と共に住むのも難しい。(修行僧が何かを求めて)旅に出て行くと、苦しみに遇う。だから旅に出るな。また苦しみに遇うな。
303)信仰あり、徳行そなわり、名声と繁栄を受けている人は、いかなる地方におもむこうとも、そこで尊ばれる。
304)善き人々は遠くにいても輝く、――雪を頂く高山のように。
善からぬ人々は近くにいても見えない、――夜陰に放たれた矢のように。
305)ひとり坐し、ひとり臥し、ひとり歩み、なおざりになることなく、わが身をととのえて、林のなかでひとり楽しめ。
注1)「われ有りという慢心」――「われはこれこれという名の王の子である」「われわれはこれこれという大臣の子である」といって、父に依存して「われ有りという慢心」が起るので、これを父に譬(たと)えていう。(ブッダゴーサ)
注2)12の領域――すなわち眼・鼻・舌・身・意という6つの主観的機能(六根)と色(=かたち)・声(音声)・香・味・触(=触れられるもの)・思考されるもの(法)という客観的な対象領域(六境)とをいう。
注3)虎――他の解釈によると、「虎」とは「瞋纏」すなわち怒りという煩悩である。また第5というのは、「5蓋のうちの第5の蓋」を喩えていうとか、あるいは「5順下分結のうちの第5の結」を喩えていうと解している。ところで5蓋とは、心を覆う5種の煩悩、5つの障害のこと(1)むさぼり(貧欲、情欲)(2)いかり(瞋恚)(3)心くらく身も重く、眠りこんだようなものうい状態(惛沈睡眠)、(4)心がざわざわして高ぶるはたらきと心を悩ませる後悔(掉挙悪作または悪悔)(5)疑いためらうこと(疑)をいう。これらは心を覆って善を生ぜしめない。これらの5つの心作用は心の明らかなはたらきを覆いかくして蓋(かさ)のごとくであるから、蓋という。
■第22章 地 獄
313)もしも為すべきことであるならば,それを為すべきである。それを断乎として実行せよ。行ないの乱れた修行者は、いっそう多く塵をまき散らす。
314)悪いことをするよりは、何もしないほうがよい。悪いことをすれば、後で悔いる。単に何かの行為をするよりは、善いことをするほうがよい。なしおわって、後で悔いがない。
315)辺境にある、城壁に囲まれた都市が内も外も守られているように、そのように自己を守れ。瞬時も空しく過すな。時を空しく過した人々は地獄に堕ちて、苦しみ悩む。
316)恥じなくてよいことを恥じ、恥ずべきことを恥じない人々は、邪な見解をいだいて、悪いところ(=地獄)におもむく。
317)恐れなくてよいことに恐れをいだき、恐れねばならぬことに恐れをいだかない人々は、邪な見解をいだいて、悪いところ(=地獄)におもむく。
318)避けねばならぬなことを避けなくともよいと思い、避けてはならぬ(=必らず為さねばならぬ)ことを避けてもよいと考える人々は、邪な見解をいだいて、悪いところ(=地獄)におもむく。
319)遠ざけるべきこと(=罪)を遠ざけるべきであると知り、遠ざけてはならぬ(=必らず為さねばならぬ)ことを遠ざけてはならぬと考える人々は、正しい見解をいだいて、善いところ(=天上)におもむく。
■第23章 象
320)戦場の象が、射られた矢にあたっても堪え忍ぶように、われはひとのそしりを忍ぼう。多くの人は実に性質(たち)(注1)が悪いからである。
321)馴らされた象は、戦場にも連れて行かれ、王の乗りものともなる。世のそしりを忍び、自らをおさめた者は、人々の中にあっても最上の者である。
322)馴らされた騾馬(らば)は良い。インダス河のほとりの血統よき馬も良い。クンジャラという名の大きな象も良い。しかし自己(おのれ)をととのえた人はそれらよりもすぐれている。
323)なんとなれば、これらの乗物によっては未到の地(=ニルヴァーナ)に行くことはできない。そこへは、慎みある人が、おのれ自らをよくととのえておもむく。
324)「財を守る者」(注2)という名の象は、発情期にこめかみから液汁をしたたらせて凶暴になっているときには、いかんとも制し難い。捕えられると、1口の食物も食べない。象は象の林を慕っている。
325)大食らいをして、眠りをこのみ、ころげまわって寝て、まどろんでいる愚鈍な人は、大きな豚のように糧(かて)を食べて肥り、くりかえし母胎に入って迷いの生存をつづける。
326)この心は、以前には、望むがままに、欲するがままに、さすらっていた。今やわたくしはその心をすっかり抑制しよう、――象使いが鉤(かぎ)をもって、発情期に狂う象(注3)を全くおさえつけるように。
327)つとめはげむのを楽しめ。おのれの心を護れ。自己を難処から救い出せ。――泥沼に落ちこんだ象のように。
328)もしも思慮深く聡明でまじめな生活をしている人を伴侶として共に歩むことができるならば、あらゆる危険困難に打ち克って、こころ喜び、念(おも)いをおちつけて、ともに歩め。
329)しかし、もしも思慮深く聡明でまじめな生活をしている人を伴侶として共に歩むことができないならば、国を捨てた国王のように、また林の中の象のように、ひとり歩め。
330)愚かな者を道伴れとするな。独りで行くほうがよい。孤独(ひとり)で歩め。悪いことをするな。求めるところは少なくあれ。――林の中にいる象のように。
331)事がおこったときに、友だちのあるのは楽しい。(大きかろうとも、小さかろうとも)、どんなことにでも満足するのは楽しい。善いことをしておけば、命の終わるときに楽しい。(悪いことをしなかったので)、あらゆる苦しみ(の報い)を除くことは楽しい。
332)世に母を敬うことは楽しい。また父を敬うことは楽しい。世に修行者を敬うことは楽しい。世にバラモンを敬うことは楽しい。
333)老いた日に至るまで戒しめをたもつことは楽しい。信仰が確立していることは楽しい。明らかな知慧を体得することは楽しい。もろもろの悪事をなさないことは楽しい。
注1)性質が悪い――この語の漢訳では「犯戒」などと訳し、「破戒」の意味にとっているが、シーラとはもともと人間の性質、性向、たち、という意味でインドの古典では用いられている。人間が何か戒律を守ると、おのずからその人の性向を形成するので、「戒」がまたシーラという語で表示されるようになったのである。
注2)「財を守る者」――パーリ文注釈に出ている物語によると、カーシー(=ベナレス)の王が象師を送って美しい〈象の林〉で捕えた象の名である。
注3)発情期に狂う象――象は交尾期になると性質が凶暴になり、あたかも酔っているがのごとくなるから、この時期における象を「酔象」と名づける。
■第24章 愛 執
334)恣(ほしいまま)のふるまいをする人には愛執が蔓草のようにはびこる。林のなかで猿が果実(このみ)を探し求めるように、(この世からかの世へと)あちこちにさまよう。
335)この世において執著のもとであるこのうずく愛欲のなすがままである人は、もろもろの憂いが増大する。――雨が降ったあとにはピーラナ草がはびこるように。
336)この世において如何ともし難いこのうずく愛欲を断ったならば、憂いはその人から消え失せる。――水の滴が蓮華から落ちるように。
338)たとえ樹を切っても、もしも頑強な根を断たなければ、樹が再び成長するように、妄執(渇愛)の根源となる潜勢力をほろぼさないならば、この苦しみはくりかえし現われ出る。
343)愛欲に駆り立てられた人々は、わなにかかった兎のように、ばたばたする。それ故に修行僧は、自己の離欲を望んで、愛欲を除き去れ。
344)愛欲の林から出ていながら、また愛欲の林に身をゆだね、愛欲の林から免(のが)れていながら、また愛欲の林に向って走る。その人を見よ!束縛から脱しているのに、また束縛に向って走る。
345,346)鉄や木材や麻紐でつくられた枷(かせ)を、思慮ある人々は堅固な縛(いまし)めとは呼ばない。宝石や耳環・腕輪をやたらに欲しがること、妻や子にひかれること、――それが堅固な縛めである、と思慮ある人々は呼ぶ。それは低く垂れ、緩く見えるけれども、脱れ難い。
かれらはこれをさえも断ち切って、顧みること無く、欲楽をすてて、遍歴修行する。
348)前を捨てよ。後を捨てよ。中間を捨てよ(注1)。生存の彼岸に達した人は、あらゆることがらについて心が解脱していて、もはや生れと老いとを受けることが無いであろう。
349)あれこれ考えて心が乱れ、愛欲がはげしくうずくのに、愛欲を淨らかだと見なす人には、愛執がますます増大する。この人は実に束縛の絆を堅固たらしめる。
350)あれこれの考えをしずめるのを楽しみ、つねに心にかけて、(身体などを)不浄(きよからぬもの)であると観じて修する人は、実に悪魔の束縛の絆をとりのぞき、断ち切るであろう。
351)さとりの究極に達し、恐れること無く、無欲で、わずらいの無い人は、生存の矢を断ち切った。これが最後の身体である。
352)愛欲を離れ、執著なく、諸の語義に通じ諸の文章とその脈絡を知るならば、その人は最後の身体をたもつものであり、「大いなる智慧ある人」と呼ばれる。
353)われはすべてに打ち勝ち、すべてを知り、あらゆることがらに関して汚されていない。すべてを捨てて、愛欲は尽きたので、こころは解脱している。みずからさとったのであって、誰を〔師と〕呼ぼうか。
354)教えを説いて与えることはすべての贈与にまさり、教えの妙味はすべての味にまさり、教えを受ける楽しみはすべての楽しみにまさる。妄執をほろぼすことはすべての味にまさり、教えを受ける楽しみはすべての楽しみにまさる。妄執をほろぼすことはすべての苦しみにうち勝つ。
355)彼岸にわたることを求める人々は享楽に害われることがない。愚人は享楽のために害われるが、享楽を妄執するがうえに、愚者は他人を害うように自分を害う。
356)田畑は雑草によって害(そこな)われ、この世の人々は愛欲によって害われる。それ故に愛欲を離れた人々に供養して与えるならば、大いなる果報を受ける。
357)田畑は雑草によって害(そこな)われ、この世の人々は怒りによって害われる。それ故に怒りを離れた人々に供養して与えるならば、大いなる果報を受ける。
358)田畑は雑草によって害(そこな)われ、この世の人々は迷妄によって害われる。それ故に迷妄を離れた人々に供養して与えるならば、大いなる果報を受ける。
359)田畑は雑草によって害(そこな)われ、この世の人々は欲求によって害われる。それ故に欲求を離れた人々に供養して与えるならば、大いなる果報を受ける。
注1)前を捨てよ……中間をすてよ――パーリ文註解によると、「前」とは過去の生存に対する執著、「後」とは未来の生存に対する執著、「中間」とは現在の生存に対する執著をいう。両極端にも中間にも汚されないという思想は『スッタニパータ』に出ている。さらに同様の思想はジャイナ教の最古の聖典にも出ている。『2つの極端によって見ることなく、聖者はそれを知って世界を克ち得た。』
■第25章 修 行 僧
360)眼(まなこ)について慎しむのは善い。耳について慎しむのは善い。鼻について慎しむのは善い。舌について慎しむのは善い。
361)身について慎しむのは善い。ことばについて慎しむのは善い。心について慎しむのは善い。あらゆることにについて慎しむのは善いことである。修行僧はあらゆることがらについて慎しみ、すべての苦しみから脱れる。
362)手をつつしみ、足をつつしみ、ことばをつつしみ、最高につつしみ、内心に楽しみ、心を安定統一し、ひとりで居て、満足している、――その人を〈修行僧〉と呼ぶ。
363)口をつつしみ、思慮して語り、心が浮わつくことなく、事がらと真理とを明らかにする修行僧――かれの説くところはやさしく甘美である。
364)真理を喜び、真理を楽しみ、真理をよく知り分けて、真理にしたがっている修行僧は、正しいことわりから堕落することがない。
365)(托鉢によって)自分の得たものを軽んじてはならない。他人の得たものを羨むな。他人を羨む修行僧は心の安定を得ることができない。
366)たとい得たものは少なくても、修行僧が自分の得たものを軽んずることが無いならば、怠ることなく清く生きるその人を、神々も称讃する。
367)名称とかたちについて(注1)「わがもの」という思いが全く存在しないで、何ものも無いからとて憂えることの無い人、――かれこそ(修行僧)とよばれる。
368)仏の教えを喜び、慈しみに住する修行僧は、動く形成作用の静まった、安楽な、静けさの境地に到達するであろう。
369)修行僧よ。この舟(注2)から水(注3)を汲み出せ。汝が水を汲み出したならば、舟は軽やかにやすやすと進むであろう。貪りと怒りとを断ったならば、汝はニルヴァーナにおもむくであろう。
370)5つ(の束縛)(注4)を断て。5つ(の束縛)を捨てよ。さらに5つ(のはたらき)(注5)を修めよ。5つの執著(注6)を超えた修行僧は、〈激流を渡った者〉とよばれる。
371)修行僧よ。瞑想せよ。なおざりになるな。汝の心を欲情の対象に向けるな。なおざりのゆえに鉄丸を呑むな。(灼熱した鉄丸で)焼かれるときに、「これは苦しい!」といって泣き叫ぶな。
372)明らかな知慧の無い人には精神の安定統一が無い。精神の安定統一していない人には明らかな知慧が無い。精神の安定統一と明らかな知慧とがそなわっている人こそ、すでにニルヴァーナの近くにいる。
373)修行僧が人のいない空家に入って心を静め真理を正しく観ずるならば、人間を超えた楽しみがおこる。
374)個人存在を構成している諸要素の生起と消滅とを正しく理解するのに従って、その不死のことわりを知り得た人々にとっての喜びと悦楽なるものを、かれは体得する。
375)これは、この世において明らかな知慧のある修行僧の初めのつとめである。――感官に気をくばり、満足し、戒律をつつしみ行ない、怠らないで、淨らかに生きる善い友とつき合え。
376)その行ないが親切であれ。(何ものでも)わかち合え。善いことを実行せよ。そうすれば、喜びにみち、苦悩を滅すであろう。
377)修行僧らよ。ジャスミンの花が萎れた花びらを捨て落すように、貪りと怒りを捨て去れよ。
378)修行僧は、身も静か、語(ことば)も静か、心も静かで、よく精神統一をなし、世俗の享楽物を吐きすてたならば、〈やすらぎに帰した人〉とよばれる。
379)みずから自分を励ませ。みずから自分を反省せよ。修行僧よ。自分を護り、正しい念(おも)いをたもてば、汝は安楽に住するであろう。
380)実に自己は自分の主(あるじ)である。自己は自分の帰趨(よるべ)である。故に自分をととのえよ。――商人が良い馬を調教するように。
381)喜びにみちて仏の教えを喜ぶ修行僧は、動く形成作用の静まった、幸いな、やすらぎの境地に達するであろう。
382)たとい年の若い修行僧でも、仏の道にいそしむならば、雲を離れた月のように、この世を照す。
注1)名称とかたちについて――このナーマルーパとは古ウパニシャッドに出て来る語で、「名称とかたち」という意味である。現象界の事物はそれぞれ名称をもっているし、またかたち(形態)をもっている。この観念が仏教にとりいれられたが、ナーパという語は「色」という意味もあるので、漢訳仏典では「ナーマルーパ」を「名色」(みょうしき)と訳す。それはあらゆる事象について言えるので、仏教では全現象の総括としての個人存在と同一視され、その構成要素としての五蘊とも同一視され、「色」は色蘊で物質面を、「名」は受・想・行・識の4つの蘊で精神面を意味すると解釈された。
注2)この舟――「舟」とは個人的存在のことをいう。
注3)水――「水」とは誤った思考をいう。
注4)5つ(の束縛)――五下分結をいう。欲界に属する5つの煩悩。結は束縛のことで、煩悩の異名。下分は欲界のこと。三界のうち最下の欲界(感覚で知ることのできる下界)に衆生を結びつけ、束縛している5種の煩悩、すなわち欲界における貧・瞋恚・有身見・戒禁取見・疑のこと。この五下分結のあるかぎり、衆生は欲界に生をうけ、これらを断滅すると、欲界に帰らぬ不還果を得るというのが、説一切有部などの伝統的見解であった。ところが前掲のパーリ文註解は、死後に四悪道のいずれかにおもむかせる5つの束縛と解していたようである。
注5)5つ(のはたらき)――五根。さとりを得させるための5つの力または可能力をいう。すなわち信と精進(勤)と念と定と慧とである。これらは諸の善いことを生ぜしめる根本であるから「五根」と名づける。
注6)5つの執著――貪りと怒りと迷妄と高慢と誤った見解とである。これらは執著を起させるもとであるから「五著」という。
■第26章 バ ラ モ ン
382)バラモン(注1)よ。流れ(注2)を断て。勇敢であれ。諸の欲望を去れ。諸の現象の消滅を知って、作られざるもの(=ニルヴァーナ)を知る者であれ。
384)バラモンが2つのことがら(=止と観)(注3)について彼岸に達した(=完全になった)ならば、かれはよく知る人であるので、かれの束縛はすべて消え失せるであろう。
385)彼岸(かなたのきし)もなく、此岸(こなたのきし)もなく(注4)、彼岸(かなたのきし)・此岸(こなたのきし)(注5)なるものもなく、怖れもなく、束縛もない人、――かれをわれはバラモンと呼ぶ。
386)静かに思い、塵垢(ちりけがれ)なく、おちついて、為すべきことをなしとげ、煩悩を去り、最高の目的を達した人(注6)、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
387)(注7)太陽は昼にかがやき、月は夜に照し、武士は鎧を着てかがやき、バラモンは瞑想に専念してかがやく。しかしブッダはつねに威力もて昼夜に輝く。
388)悪を取り除いたので〈バラモン〉(婆羅門)と呼ばれ、行ないが静かにやすまっているので〈道の人〉(沙門)と呼ばれる。おのれの汚れ(注8)を除いたので、それゆえに〈出家者〉と呼ばれる(注9)。
389)バラモンを打つな。バラモンはかれ(=打つ人)にたいして怒りを放つな(注10)。バラモンを打つものには禍がある。しかし(打たれて)怒る者にはさらに禍がある。
390)愛好するものから心を遠ざけるならば、このことはバラモンにとって少なからずすぐれたことである。害する意(おもい)がやむにつれて、苦悩が静まる。
391)身にも、ことばにも、心にも、悪い事を為さず、3つのところ(注11)についてつつしんでいる人――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
392)正しく覚った人(=ブッダ)の説かれた教えを、はっきりといかなる人から学び得たのであろうとも、その人を恭しく敬礼せよ、――が祭の火を恭しく尊ぶように。
393)螺髪(注12)を結っているからバラモンなのではない。氏姓によってバラモンなのでもない。生れによってバラモンなのでもない。真実と理法とをまもる人は、安楽である。かれこそ(真の)バラモンなのである(注13)。
394)(注14)愚者よ。螺髪を結うて何になるのだ。かもしかの皮(注15)をまとって何になるのだ。汝は内に密林(=汚れ)(注16)を蔵して、外側だけを飾る(注17)。
395)糞掃衣(ふんぞうえ)をまとい、瘠せて、血管があらわれ、ひとり林の中にあって瞑想する人――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
396)われは、(バラモン女の)胎から生れ(バラモンの)母から生れた人をバラモンと呼ぶのではない。かれは「〈きみよ〉といって呼びかける者(注19)」といはれる。かれは何か所有物の思いにとらわれている(注20)。無一物であって執著のない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
397)すべての束縛を断ち切り、怖れることなく、執著を超越して、とらわれることの無い人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
398)紐(注21)と革帯(注22)と綱(注23)とを、手綱(注24)ともども断ち切り、門をとざす閂(かんぬき)(注25)を滅ぼして、めざめた人(注26)、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
399)罪がないのに罵られ、なぐられて、拘禁されるのを堪え忍び、忍耐の力あり、心の猛き人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
400)怒ることなく、つつしみあり、戒律を奉じ(注27)、欲を増すことなく、身をととのえ(注28)、最後の身体に達した人(注29)――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
401)蓮葉(はちすば)の上に露(注30)のように、錐の尖の芥子(注31)のように、諸の欲情に汚されない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
402)すでにこの世において自分の苦しみの滅びたことを知り、重荷をおろし、とらわれの無い人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
403)明らかな知慧が深くて、聡明で、種々の道に通達し、最高の目的(注32)を達した人――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
404)在家者・出家者のいずれとも交わらず(注33)、住家(すみか)がなくて遍歴し、欲の少ない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
405)強くあるいは弱い(注34)生きものに対して暴力を加えることなく、殺さずまた殺させることのない人――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
406)敵意ある者どもの間にあって敵意なく、暴力を用いる者どもの間にあって心おだやかに、執著する者ども(注35)の間にあって執著しない人――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
407)芥子粒が錐の尖端から落ちたように、愛著と憎悪と高ぶりと隠し立て(注36)とが脱落した人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
408)粗野ならず、ことがらをはっきりと云える真実のことばを発し(注37)、ことばによって何人の感情をも害することのない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
409)この世において、長かろうと短かろうと、微細であろうとも粗大であろうとも、淨かろうとも不浄であろうとも、すべて与えられていない物を取らない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
410)現世を望まず、来世をも望まず、欲求がなくて、とらわれの無い人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
411)こだわりあることなく、さとりおわって、疑惑なく、不死(注38)の底に達した人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
412)この世の禍福いずれにも執著することなく、憂いなく、汚れなく、清らかな人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
413)曇りのない月のように、清く、澄み、濁りがなく、歓楽の生活の尽きた人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
414)この障害・険道(注39)・輪廻(さまよい)・迷妄を超えて、渡りおわって彼岸に達し、瞑想し、興奮することなく(注40)、疑惑なく、執著することがなくて、心安らかな人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
415)この世の欲望を断ち切り、出家して遍歴し、欲望の生活の尽きた人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
416)この世の愛執を断ち切り、出家して遍歴し、愛執の生活の尽きた人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
417)人間の絆(注41)を捨て、天界の絆(注42)を越え、すべての絆をはなれた人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
418)〈快楽〉と〈不快〉(注43)とを捨て、清らかに涼しく、とらわれることなく、全世界にうち勝った英雄、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
419)生きとし生ける者の死生をすべて知り、執著なく、よく行きし人、覚った人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
420)神々も天の伎楽神(ガンダルヴァ)たちも人間もその行方を知り得ない人、煩悩の汚れを滅ぼしつくした真人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
421)前にも、後にも、中間にも、一物をも所有せず、無一物で、何ものをも執著して取りおさえることの無い人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
422)牡牛のように雄々しく、気高く、英雄・大仙人・勝利者・欲望の無い人・沐浴者・覚った人(ブッダ)――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
423)前世の生涯を知り、また天上と地獄を見、生存を滅ぼしつくすに至って、直感智を完成した聖者、完成すべきことをすべて完成した人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
注1)バラモン――漢訳仏典では「婆羅門」「梵志」などと音写される。ヴェーダの宗教における司祭者のことで、バラモンはインドのカースト制においては最高のカーストであると考えられていた。原始仏教は表面的にはインド伝統のこの観念を継承したが、その意義内容を改めて、〈真のバラモン〉は祭祀を行なう人ではなくて、徳を身に具現した人のことであると主張した。この章に説かれる「バラモン」とは煩悩を去り罪悪をなさぬ人である。最初期のジャイナ教聖典でも理想の修行者をバラモンと呼んでいる。また開祖マハーヴィーラをバラモンと呼んでいる。
注2)流れ――愛執を流れに喩えていう。
注3)2つのことがら(=止と観)――こころを練って一切の外境や乱想にうごかされず、心を特定の対象にそそいで心のはたらきを静めるのを「止」といい、それによって正しい智慧を起こし、対象を如実に観るのを「観」という。止めて観るのである。互いに他を成立させ、仏道を全うさせる不離の関係にある。
注4)彼岸もなく、此岸もなく――「彼岸」とは完全な理想の境地であり、「此岸」とは迷いの状態であろう。さとりも迷いも超越しているというのであるから、大乗仏教や禅をさえも思わせる表現であるが、初期の仏典やジャイナ教聖典にはこのような表現を時々見かける。パーリ文註解には「彼岸」とは内の六処(眼・意・鼻・舌・身・意)であり、「此岸」とは外の六処(色・声・香・時・触・法)であると解するが、これは教義学の述語をもちこんだものである。
注5)彼岸・此岸――アンデルセンは「彼岸」とは来世、「此岸」とは現世、「彼岸・此岸」とは流転輪廻する人の全生存を意味するのではないかという。
注6)最高の目的を達した人――パーリ文註解にはアラハンに達した人と解するが、最初のじきにはそれほど明確に考えていなかったのであろう。
注7)『ウダーナヴァルガ』を月と結びつけて考えることはヴェーダ以来行なわれている。また月とブラフマンとを結びつけて考えることもあった。これに対してクシャトリヤを太陽と結びつける例があるかどうかというに、釈迦族はその姓を「太陽」と称すると言う。(例えば『スッタニバータ』423)太陽の裔と考えられていたらしい。
注8)汚れ――情欲などをいう。
注9)それゆえに〈出家者〉と呼ばれる――賢者は心の垢を去って自己を淨めよ、というのである。
注10)バラモンを……怒りを放つな――いまはパーリ仏教の伝統的解釈にしたがった。しかし『出曜経』梵志品第30巻によると、「在家の人が修行僧を世話しないで追放してはならぬ」という意味に解している。
注11)3つのところ――身とことばと心とを指していう。身・口・意。
注12)螺髪――当時のバラモンが螺貝のように髪を結うていたことを指していう。
注13)真実と理法をまもる人は……バラモンなのである――これはウパニシャッドにおけるサティヤカーマの物語と同趣意である。この精神は仏教においては特に強調された。『生れによってバラモンなのではない。生れによって非バラモンなのでもない。行為によってバラモンなのである。行為によって非バラモンなのである。』(『スッタニバータ』650)『ひとは行為によってバラモンとなり、行為によって王族となり、行為によって庶民となり、行為によって隷民となる。』『シュードラであっても、柔善・真実・徳のうちに常につとめている人を、バラモンだとわたくしはかんがえます。その人は行為(業)によって再生族となるでしょう。』
注14)この詩は仏教外の諸宗教における当時の修行者たちのすがたに言及しているのである。外形だけでは内心は淨まらないと説く。
注15)かもしかの皮――羚羊(かもしか)の皮の衣。今日でもインドの行者はかもしかの皮をまとって、うずくまっている。
注16)密林――貪欲などの煩悩のことを密林に譬えていう。
注17)外側だけを飾る――「外を磨き立てる」「光沢(つや)を出す」の意。
注18)糞掃衣――パンスクーラ、パンス(「糞掃」と音写する)とは「塵埃」のことで、その中から集めたボロ切れを洗い、縫い合せた衣をパンスクーラという。もとは出家者はこのようなものを身につけていた。
注19)「〈きみよ〉といって呼びかける者」――原始仏典を見ると、バラモンはゴータマ・ブッダに向って「きみよ!」といって呼びかけている。ゴータマ・ブッダに対して特別の尊敬を払っていないのである。
注20)何か所有物の思いにとらわれている――情欲などを所有していることであるとパーリ文註解は解するが、しかし原義は、自分が財産や名声など何ものかを所有していると思いなすことを言うのであろう。
注21)紐――結ぶ性質があるので、怒りを紐にたとえていう。
注22)革帯――縛る性質があるので、愛執を革帯にたとえていう。
注23)綱――62の誤った見解を綱に譬えていう。
注24)手綱――ひそんでいる煩悩を手綱にたとえていう。
注25)門をとざす門――無明のことをいう。
注26)めざめた人――パーリ文註解には四諦の理をさとった人と解しているから、崇拝対象としての仏ではなくて、真理をさとった人というほどの意味で、用法としてはジャイナ教など他の諸宗教と共通である。また後代の仏教教学によると、四諦の理をさとるのは小乗の声聞の道であるにすぎないとされていたのに、ここのパーリ文註解には、四諦の理をさとることによってブッダとなり得ると説いているから、初期の仏教思想がまだ注釈のうちにも保存されていたのだと解し得るであろう。
注27)戒律を奉じ――パーリ文註解によると、四清淨戒をたもつことであるという。⑴「別解脱律儀」、身と語とに悪をなさないことを誓うこと。⑵「根律儀」、感官を制しととのえること、⑶「正命清浄律儀」、生活を正しくすること、⑷「縁に関する律儀」、生活必需品を節制することである。清浄戒とは、説一切有部のほうでは四種持戒のうちの第4であり、煩悩の汚れを離れた無漏清浄を守ることであって、パーリ仏教で意味するところとは異る。
注28)身をととのえ――眼・耳・鼻・舌・身・意という6つの器官を制しととのえること。
注29)最後の身体に達した人――もはや生れ変って次の身体を受けることが無い、との意。
注30)蓮華の上の露――下の汚水に交らないから清らかである。『水の中に生じた蓮が水に汚されないように、そのような諸々の慾情に汚されない人――われはかれをバラモンと呼ぶ。』
注31)錐の尖の芥子――粘着してとどまることが無いから、執著の無いことにたとえている。
注32)最高の目的――パーリ文註解によると、真人の境地(阿羅漢果)であるという。
注33)在家者・出家者のいずれとも交わらず――『貧欲なることなく、人に知られずに生き、家なく、所有なく、在家者どもと交際しない人、――われらはかれをバラモンと呼ぶ。』『(両親など及び)親戚・縁者との以前からの結びつきを捨て、快楽に耽らない人、――われらはかれをバラモンと呼ぶ。』
注34)強く或いは弱い――『動く生きものでも動かない生きものでも悉く知って、3つのしかた(心とことばと身体)のいずれによっても(いきものを)害しない人――かれをわれらは〈バラモン〉と呼ぶ。』
注35)執著する者ども――パーリ文註解によると、精神と肉体(五蘊)について「われ」とか「わがもの」とかいって執著することである。
注36)隠し立て――パーリ文註解には他人の美徳を隠すことと解している。しかし仏教一般では自分のあやまちを隠蔽することをいう。漢訳では「覆」という。
注37)真実のことばを発し――『正直をたもっている人には、バラモンたる性質も現われる。』『バラモンでない者はこのことを明言しえないはずである。若き児よ。……わたしはきみを弟子入りさせてやろう。何となればきみは真実からはずれなかったからである。』『怒りの故にも、戯笑の故にも、貧欲の故にも、恐怖の故にも、決して偽りを語らない人――――われらはかれを〈バラモン〉と呼ぶ。』『怒りと迷いを捨てた人が〈バラモン〉であると神々は知りたまう。この世で真実を語り、師を満足せしめ、害せられても害しない人が〈バラモン〉である、と神々は知りたまう。諸々の感官にうち克ち、徳に専念し、清浄であって、(ヴェーダの)学習を楽しみ、愛欲と憤怒を伏する者が〈バラモン〉である。と神々は知りたまう。』
注38)不死――パーリ文註解は、これをニルヴァーナと解する。また甘露を意味する。
注39)険道――煩悩のことをいう。
注40)興奮することなく――興奮し、情欲に激することが無いの意。
注41)人間の絆――パーリ文註解によると、身体と五官による欲楽の対象とをいう。
注42)天界の絆――天の世界に住む神々といえども束縛の絆を受けていることをいう。神々といっても、人間よりはすぐれた存在であるというだけで、やはり、変化や苦悩を受ける存在なのである。神々はまだ解脱していない。
注43)〈快楽〉と〈不快〉――註によると、快楽とは五欲の対象を享楽することであり、不快とは林の中に住もうと熱望することである。
(2012年8月24日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ブッダの感興のことば(ウダーナヴァルガ)』中村元訳 岩波文庫
〈ウダーナは日本の学者は「感興後」と訳すことが多いが、ブッダが感興を催した結果、おのずから表明されたことばであるとされている。「無問自説」と訳す学者もある。(問われないのにブッダが自ら説いた、という意味である。)漢字にはなかなか訳しにくいので、難しい漢字で音写されていることが多い。ヴァルガとは「集り」を意味する。(389頁)〉
■第1章 無 常
3)諸のつくられた事物は実に無常である。生じ滅びる性質のものである。それらは生じては滅びるからである。それらのしずまるのが、安泰である。
4)何の喜びがあろうか。何の喜びがあろうか?――(世間は)このように燃え立っているのに。汝らは暗黒に陥っていて、燈明を求めようとしない。
5)あちこちの方向に投げ捨てられまき散らされたこの鳩色のような白い骨を見ては、この世になんの快(こころよさ)があろうか?
8)「わたしは若い」と思っていても、死すべきはずの人間は、誰が(自分の)生命をあてにしていてよいだろうか?若い人々でも死んで行くのだ。――男でも女でも次から次へと――。
18)昼夜は過ぎ行き、生命はそこなわれ、人間の寿命は尽きる。――小川の水のように。
19)眠れない人には夜は長く、疲れた人には1里の道は遠い。正しい真理を知らない愚かな者にとっては、生死の道のりは長い。
20)「わたしには子がいる。わたしには財がある」と思って愚かな者は悩む。しかし、すでに自分が自分のものではない。ましてどうして子が自分のものであろうか。どうして財が自分のものであろうか。
21)男も女も幾百万人と数多くいるが、財産を貯えたあげくには、死の力に屈服する。
25)大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の奥深いところに入っても、およそ世界のどこにいても、死の脅威のない場所は無い。
26)この世においては、過去にいた者どもでも、未来にあらわれる者どもでも、一切の生き者は身体を捨てて逝くであろう。智ある人は、一切を捨て去ることを知って、真理に安住して、清らかな行ないをなすべきである。
38)「わたしは雨期にはここに住もう。冬と夏にはここに住もう」と、愚者はこのようにくよくよと慮(おもんばか)って、死が迫ってくるのに気がつかない。
39)子どもや家畜のことに気を奪われて心が執著している人を、死は捉えてさらって行く。――眠っている村を大洪水が押し流すように。
40)子も救うことができない。父も親戚もまた救うことができない。死におそわれた者にとっては、かれらも救済者とはならない。
41)「わたしはこれをなしとげた。これをしたならばこれをしなければならないであろう。」というふうに、あくせくしている人々を、老いと死が粉砕する。
42)それ故に、修行僧らは、つねに瞑想を楽しみ、心を安定統一して、つとめはげみ、生と老いとの究極を見きわめ、悪魔とその軍勢に打ち克って、生死の彼岸に達する者となれ。
■第2章 愛 欲
1)愛欲よ。わたしは汝の本(もと)を知っている。愛欲よ。汝は思いから生じる。わたしは汝のことを思わないであろう。そうすれば、わたしにとって汝はもはや現われないであろう。
2)欲情から憂いが生じ、欲情から恐れが生じる。欲情を離れたならば、憂いは存しない。どうして恐れることがあろうか。
3)快楽から憂いが生じ、快楽から恐れが生じる。快楽を離れたならば、憂いが存在しない。どうして恐れることがあろうか?
4)果実が熟したならば、尖端は甘美であるが、喜んで味わってみると辛い。愛欲は愚かなる者どもを焼きつくす。――たいまつを放さない人の手を、たいまつが焼くように。
5,6)鉄や木材や麻紐でつくられた枷を聖者たちは堅固な縛(いましめ)とは呼ばない。心が愛欲に染まり愚鈍な人が、妻や子にひかれること、――これが堅固な縛(いましめ)であると、聖者たちは呼ぶ。それはあらゆる点で極めて堅固であって、脱れ難い。かれらはこれをさえも断ち切って、顧みること無く、欲楽をすてて、遍歴修行する。
7)世間における種々の美麗なるものが欲望なのではない。欲望は、人間の思いと欲情なのである。世間における種々の美麗なるものはそのままいつも存続している。しかし思慮ある人々はそれらに対する欲望を制してみちびくのである。
8)人間のうちにある諸の欲望は、常住に存在しているのではない。欲望の主体は無常なるものとして存在している。束縛されているところのものを捨て去ったならば、死の領域は迫って来ないし、さらに次の迷いの生存を受けることもない、と、われは説く。
13)諸の欲望にしたがっているあいだは、心が満足を得ることが無かった。しかし欲望から退き休止することを反省して見て、明らかな知慧によってよく満足した人々は、実に満足しているのである。
14)欲望によって満足することがないから、明らかな知慧をもって満足するほうが勝れている。明らかな知慧をもって満足した人を、愛執が支配することはできない。
17)たとえ貨幣の雨を降らすとも、欲望の満足されることはない。賢者は、「欲望は快楽の味が短い」と知って、
18)たとい天上の快楽にもこころが喜ばない。正しく覚った人(=仏)の弟子はつねに妄執の消滅を喜ぶ。
19)たといヒマーラヤ山にひとしい黄金の山があったとしても、その富も一人の人を満足させるのに足りない。このことを知って、平らかな心でおこなうべきである。
20)苦しみと苦しみの起る本(もと)を知る人は、どうして愛欲を楽しむであろうか?思慮ある人は、世間における絆を棘であると考えて、それを制しみちびくために修学すべし。
■第3章 愛 執
3)人々は盲目なる欲望の網のうちに投げ込まれ、愛執に蔽われて、放逸(わがまま)であり、獄舎にとじこめられている。――魚が魚獲(すなどり)の網の目にかかったように。かれらは老いと死とに向う。――乳を吸いたがる犢(こうし)が母牛に向うように。
4)恣(ほしいまま)のふるまいをする人には、愛執が蔓草のようにはびこる。林のなかで猿が果実(このみ)を探し求めるように、かれは(この世からかの世へと)あちこちにさまよう。
9)この世において極めて断ち難いこのうずく愛欲のなすがままである人は、諸の憂いが増大する。――雨が降ったあとにはピーナラ草がはびこるように。
10)この世において極めて断ち難いこのうずく愛欲を断ったならば、憂いはその人から消え失せる。――水の滴が蓮葉(はちすば)から落ちるように。
13)しかしこの世でその愛執を捨てて、移りかわる生存に対する愛執を離れたならば、その人はもはや輪廻しない。その人には愛執が存在しないからである。
15)実に愛執が原因であり、執著は(それに縁って)流れている川である。この世では(欲の)網が茎をつねに覆うている。蔓草である餓えを全く除去したならば、この苦しみはくり返し退く。
16)たとえ樹を伐っても、もしも頑強な根を断たなければ、樹がつねに再び成長するように、妄執(渇愛)の根源となる潜勢力を摘出しないならば、この苦しみはくりかえし現われ出る。
18)愛執は苦しみの起る根源であるとこの危ない患らいを知って、愛欲を離れ、執著して取ることなく、修行僧は気をつけながら遍歴すべきである。
■第4章 は げ み
1)つとめ励むのは不死の境地である。怠りなまけるのは死の足跡である。つとめ励む人々は死ぬことが無い。怠りなまける人々は、つねに死んでいる。
2)つとめはげむことについてこの区別のあることを知って、賢い人、聖者は、自分の境地であるつとめはげむことをいつも喜ぶがよい。
3)たえず(道に)思いをこらし、つねに健(たけ)く奮励する、思慮ある人々はニルヴァーナに達する。これは無上の幸せである。
4)賢明なる人がつとめはげみによって放逸(わがまま)をたち切るときには、知慧の高閣(たかどの)に登り、憂いを去って、憂いある人びとを見下(おろ)す。山の上にいる人が地上の人々を見下すように。
6)ふるい立ち、思いつつましくこころは清く、気をつけて行動し、みずから制し、法(のり)にしたがって生き、つとめはげむ人は、名声が高まる。
8)下劣なしかたになじむな。怠けて人々とともにふわふわと暮すな。邪な見解をいだくな。世俗のわずらいをふやすな。
11)叡智の無い愚かな人々は放逸の状態をつづけている。つとめはげむ人は、つねに瞑想し、汚(けが)れの消滅を達成する。
12)放逸(なおざり)に耽るな。愛欲と歓楽に親しむな。おこたることなく思念をこらす者は、不動の楽しみを得る。
16)自分の益になるものであると知り得ることを、あらかじめ為すべきである。(無暴な)車夫のような思いによらないで、賢者はゆっくりと邁進すべきである。
17)譬えば車夫が平坦な大道を捨てて、凸凹ある道をやって来て、車軸を毀してはげしく悲しむように、
18)愚かな者は、法から逸脱して、なしてはならぬことを実行して、死魔の支配に屈し、車軸を毀したように、悲しむ。
19)なすべきことを、なおざりにし、なすべからざることをなす、高ぶって放逸(わがまま)なる者どもには、汚れが増す。かれらには汚れが増大する。かれらは汚れの消滅からは遠く隔っている。
20)よく修行を始めて、常に身体(の本性)を思いつづけて、為すべからざることを為さず、為すべきことを常に為して、心がけて、みずから気をつけている人々には、諸の汚れがなくなる。
22)たといためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているのである。牛飼いが他人の牛を数えているようなものである。かれは修行者の部類には入らない。
27)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ、放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見る。自己を難処から救い出す。――泥沼に落ちこんだ象のように。
28)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ、放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見、悪いことがらを吹き払う。――風が木の葉を吹き落とすように。
29)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見、微細なものでも粗大なものでもすべて心の纏(わずらい)を、焼きつくしながら歩む。――燃える火のように。
30)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ、放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見、一切の束縛の絆の消滅し尽くすことを次第に体得する。
31)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ、放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見、やすらぎの境地を体得する。それはつくり出すはたらきの静まった安らかさである。
32)修行僧は、つとめはげむのを楽しみ、放逸(なおざり)のうちに恐ろしさを見、堕落するはずはなく、すでにニルヴァーナの近くにいる。
34)睡眠、倦怠、怠惰――これらは修行の妨げである。そのよすがを知り究めよ。――心の落ち着きが妨げられることの無いように。
35)奮起(ふるいたて)よ。怠けてはならぬ。善き行ないのことわりを実行せよ。ことわりに従って行なう人は、この世でも、あの世でも、安楽に臥す。
36)修行僧らは、つとめはげむのを楽しめ。よく戒めをたもて。その思いをよく定め統一して、自分の心をまもれかし。
38)この教説と戒律とにつとめはげむ人は、生れをくりかえす輪廻を捨てて、苦しみを終滅するであろう。
■第5章 愛 す る も の
1)愛するものから憂いが生じ、愛するものから恐れが生ずる。愛するものを離れたならば憂いは存在しない。どうして恐れることがあろうか?
2)愛するものから憂いが生じ、愛するものから恐れが生ずる。愛するものは変滅してしまうから、ついには狂乱に帰す。
3)世間の憂いと悲しみ、また苦しみはいろいろである。愛するものに由って。ここにこの一切が存在しているのである。愛するものが存在しないならば、このようなことは決して有り得ないであろう。
4)それ故に、愛するものがいかなるかたちでも決して存在しない人々は、憂いを離れていて、楽しい。それ故に、憂いの無い境地を求めるならば、命あるものどもの世に、愛するものをつくるな。
5)愛するものと会うな。愛していないものとも会うな。愛するものを見ないのは苦しい。愛しないものを見るのも苦しい。
6)愛する人々と離れるが故に、また愛しない人々に会うが故に、はげしく憂いが起る。それによって人々は老いやつれてゆく。
7)時が来て、愛する人が死ぬと、親族知人が集まって来て、長い夜を徹して悲しむ。実に愛する者と会うことは苦しい。
8)それ故に、愛するものをつくってはならぬ。愛するものであるということはわざわいである。愛するものも憎むものも存在しない人々には、わざわいの絆は存在しない。
9)つねに道に違うたことになじみ、道に順ったことにいそしまず、目的を捨てて、快いことだけを取る人は、みずからの目的につとめる者を憧れるに至るであろう。
12)悪いものは善いすがたをもって、憎らしいものは愛しきもののすがたをもって、苦しみは安楽のすがたをもって、放逸(なおざり)なる者どもを粉砕してしまう。
13)もしも自分を愛しいものだと知るならば、自分を悪と結びつけてはならない。悪いことを実行する人が楽しみを得るということは容易ではないからである。
14)もしも自分を愛しいものだと知るならば、自分を悪と結びつけてはならない。善いことを実行する人が、楽しみを得るということは、いともたやすいからである。
15)もしも自分を愛しいものだと知るならば、よく心がけて自己をまもるべきである。――辺境に有る、城壁に囲まれた都市が堅固に奥深く濠をめぐらされているように。賢い人は、夜の3つの区分のうちの1つだけでも、つつしんで目ざめておるべきである。
16)もしも自分を愛しいものだと知るならば、よく心がけて自己をまもるべきである。――辺境に有る城壁に囲まれた都市が内も外も堅固に守られているように、
17)そのように自己を守れ、汝らは瞬時も空しく過すな。時を空しく過した人々は、地獄に堕ちて悲しむ。
18)どの方向に心でさがし求めてみても、自分よりもさらに愛しいものをどこにも見出さなかった。そのように、他人にとってもそれぞれの自己がいとしいのである。それ故に、自分のために他人を害してはならない。
19)すべての者は暴力におびえている。すべての(生きもの)にとって生命が愛しい。己(おの)が身にひきくらべて、殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ。
24)徳行をそなえ、法(のり)にしたがって生き、恥を知り、真実を語り、自分のなすべきことを行なう人を、世人は好ましいと見なす。
■第6章 戒 し め
1)聡明なひとは、3つの宝をもとめるならば、戒しめをまもれ。――その3つとは、世の人々の称讃(=名誉)と、財の獲得と、死後に天上に楽しむことである。
2)この3つのことがらをはっきりと見て、賢者は戒しめを守れ。尊い人は正しい見解を具現して、世の中で幸せを得る。
3)戒しめを受けたもつことは楽しい。身体が悩まされることがない。夜は安らかに眠る。目が覚めたならば心に喜ぶ。
4)老いに至るまで戒しめをたもつのは、善いことである。明らかな知慧は、実に人々の宝である。福徳は盗賊も奪い去るのが難しい。
5)明らかな知慧があり、戒しめをたもつ人は福徳をつくり、ものをわかちあって、この世でもかの世でも、安楽を達成する。
6)修行僧は堅く戒しめをたもって、諸の感官をよくつつしみ、食事についてもほどよい量を知り、めざめているときには心を統一し、気をつけている。
7)このように、昼夜に熱心につとめはげみ、倦むことなく暮しているならば、その人は堕落するはずはなく、すでにニルヴァーナの近くにいる。
8)修行僧は堅く戒めをたもち、心の念(おも)いと明らかな知慧とを修養すべきである。つねに熱心に、つつしみ深くつとめはげむならば、苦しみを消滅し尽すに至るであろう。
9)それ故に、つねに戒しめを守り、精神の統一をまもる者であれ。真理を観ずることを学び、しっかりと気をつけて落ち着いておれ。
10)かれは束縛の絆が消え失せて、慢心もなくなり、煩悩のさまたげもなく、身体が壊(やぶ)れて死んだあとでも明らかな知慧をたもち、ときほごされて、(迷える人の)部類に入らない。
11)戒しめと精神統一と明らかな知慧とのある人は、これらをよく修養している。かれは究極の境地に安住し、汚れが無く、憂いが無く、迷いの生存を滅ぼし尽くしている。
12)執著から解放されて、こだわりなく、完き知慧あり、煩悩のさまたげなく、悪魔の領域を超えて、太陽のように輝く。
13)修行僧が、心が高ぶりざわざわして、恣(ほしいまま)に怠りなまけて、外のことがらに心を向けているならば、戒しめと精神統一と知慧とは完成しない。
14)覆われたものに、雨が降り注ぐ。開きあらわされたものには、雨は降らない。それ故に、覆われたものを開けよ。そうしたならば、それに雨は降り注がない。
15)心ある緋とはこの道理を見て、つねに戒しめをまもり、すみやかにニルヴァーナに至る道を清くせよ。
16)花の香りは風に逆らっては薫らない。――昼間に咲くタガラの花からも、栴檀(せんだん)からも――。しかし徳のある人々の香りは、風に逆らっても薫る。徳のある人は、すべての方向に薫るのである。
18)タガラ、栴檀の香りは、微かであって、大したことはない。しかし徳行ある人々の香りは、天の神々にもとどき、この世でも薫る。
19)清らかに戒しめをたもち、つとめはげんで生活し、正しい知慧によって解脱した人々には、悪魔も近づくによし無し。
20)これは安穏に達する道である。これは清浄に向う道である。心をおさめて、この道を歩む者どもは悪魔の束縛を捨て去るであろう。
■第7章 善 い 行 な い
1)身体に過ちを犯さないように、まもり落ち着けよ。身体について、慎んでおれ。身体による悪い行ないを捨てて、身体によって善行を行なえ。
2)ことばで過ちを犯さないように、まもり落ち着けよ。ことばについて、慎んでおれ。語(ことば)による悪い行ないを捨てて、語(ことば)によって善行を行なえ。
3)心で過ちを犯さないように、まもり落ち着けよ。心について、慎んでおれ。心による悪い行ないを捨てて、心によって善行を行なえ。
4)身体による悪い行ないを捨て、ことばによる悪い行ないを捨て、心による悪い行ないを捨て、そのほか汚れのつきまとうことを捨てて、
5)身体によって善いことをせよ。ことばによって大いに善いことをせよ。心によって善いことをせよ。――汚れのさまたげの無い、無量の善いことを。
6)身体によって善いこと為し、ことばによっても心によっても善いことをするならば、その人はこの世でも、またかの世でも幸せを得るであろう。
10)落ち着いて思慮ある人々は身をつつしみ、ことばをつつしみ、心をつつしむ。かれらはあらゆることに慎しんでいる。かれらは不死の境地におもむく。そこに達したならば、悩むことがない。
11)身について慎しむのは善い。ことばについて慎しむのは善い。心について慎しむのは善い。あらゆることについて慎しむのは善いことである。あらゆることがらについて慎しむ修行僧はすべての苦しみから脱(のが)れる。
12)(悪いことを言わぬように)ことばを護り、心でよく慎しみ、身体で悪いことをするな。この善き行為の道を浄めて、聖者の説きたまうた道を体得せよ。
■第8章 こ と ば
2)人が生まれたときには、実に口の中に斧が生じている。ひとは悪口を語って、その斧によって自分自身をきるのである。
3)毀(そし)るべき人々を誉め、また誉むべき人々を毀(そし)る者――かれは口によって悪運をかさね、その悪運ゆえに幸せを受けることができない。
6)悪い心のある人々は実に嘘を言う。つねに地獄(の苦しみ)を増して、おのれを傷つける。欠点の無い力のある人は、心の混濁を除いて、(すべてを)忍ぶ。
7)愚かにも、悪しき見解にしたがって、真理に従って生きる真人・聖者たちの教を罵(ののし)るならば、その人には悪い報いが熟する。――棘のある芦(あし)はのびて節が熟すると自分自身が滅びてしまうようなものである。
8)善いことばを口に出せ。悪いことばを口に出すな。善いことばを口に出したほうが良い。悪いことばを口に出すと、悩みをもたらす。
9)すでに(他人が)悪いことばを発したならば、(言い返すために)それをさらに口にするな。(同じような悪口を)口にするならば悩まされる。聖者はこのように悪いことばを発することはない。愚かな者どもが(悪いことばを)発するからである。
10)口をつつしみ、ゆっくりと語り、心が浮つかないで、事がらと真理とを説く修行僧――かれの説くところはやさしく甘美である。
11)善い教えは最上のものである、と聖者は説く。(これが第1である)。理法を語れ。理法にかなわぬことを語るな。これが第2である。好ましいことばを語れ。好ましからぬことばを語るな。これが第3である。真実を語れ、虚偽を語るな。これが第4である。
12)自分を苦しめず、また他人を害しないようなことばのみを語れ。これこそ実に善く説かれたことばなのです。
13)好ましいことばのみを語れ。そのことばは人々に歓び迎えられる。つねに好ましいことばのみを語っているならば、それによって(ひとの)悪(意)を身に受けることがない。
14)真実のことばは不滅であるはずである。実に真実のことばは最上である。かれらは、真実すなわちことがらと理法の上に安立したことばを語る。
15)安らぎに達するために、苦しみを終滅させるために、仏の説きたまうおだやかなことばは、実に善く説かれたことばである。
■第9章 行 な い
1)唯一なることわりを逸脱し、偽りを語り、彼岸の世界を拒んでいる人は、どんな悪でもなさないものは無い。
4)もし汝が悪い行ないをなすならば、あるいはいつかなすであろうならば、汝は苦しみから離脱することはない、――たとい汝が(空中に)浮び上って逃げ去ろうとしても。
5)大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の深いところに入っても、およそ世界のどこでも悪業の制圧しない場所はしない。
6)この世で他人のした悪い行ないを見ては、ひとは非難するであろうが、その悪い行ないを自からしてはならない。悪人は実に(自分の)業に束縛されている。
7)詐欺や慢心をともない、正しくない行ないにより、あるいは他人から企(たくら)まれて、人々を傷けるならば、その人々は深い坑(あな)の中に堕ちる。人々は実に(各自の)業に縛せられている。
8)人がもしも善または惡の行ないをなすならば、かれは自分のした1つ1つの業の相続者となる。実に業は滅びないからである。
9)或る物が人に役立つあいだは、その人は(他人から)掠奪する。次いで他の人々がかれから掠め取る。(他人から)掠め取った人が、掠奪されるのである。
11)愚かな者は(悪い事を)しながら「この報いはわれには来ないであろう」と考える。しかし、のちに報いを受けるときに、苦痛が起る。
12)もしも愚かな者が、悪い行ないをしておきながら、気がつかないならば、浅はかな愚者は自分自身のした行ないによって悩まされる。――火に焼きこがされてやけどした人が苦しむように。
14)もしも或る行為をしたのちに、それを後悔して、顔に涙を流して泣きながら、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善くない。
15)もしも或る行為をしたのちに、それを後悔しないで、嬉しく喜んで、その報いを受けるならば、その行為をしたことは善いのである。
16)自分の幸せだけをもとめる人々は、笑いながら悪いことをする。しかし、かれらはのちに苦しんで、泣きながらその報いを受ける。
17)悪い事をしても、その業(カルマ)は、しぼり立ての牛乳のように、すぐに固まることはない。(徐々に固まって熟するのである。)その業は、灰に覆われた火のように、(徐々に)燃えて悩ましながら、愚者につきまとう。
19)鉄から起った錆が、それから起ったのに、鉄自身を食いつくすように、悪をなしたならば、自分の業が、静かに気をつけて行動しない人を悪いところ(地獄)にみちびく。
■第10章 信 仰
1)信ずる心あり、恥を知り、戒しめをたもち、また財をわかち与える――これらの徳行は、尊い人々のほめたたえることがらである。「この道は崇高なものである」とかれらは説く。これによって、この人は天の神々の世界におもむく。
3)信(まこと)の人は最高の財である。徳を良く実行したならば、幸せを受ける。真実は、実に諸の飲料のうちでも最も甘美なものである。明らかな知慧によって生きる人は、生きている人々のうちで最もすぐれた人であると言われる。
4)尊敬さるべき真人たちに対する信仰を財とし、安らぎに至るための教えを聞こうと願うならば、聡明な人は(ついには)いろいろのことについて明らかな知慧を得る。
5)ひとは、信仰によって激流を渡り、つとめはげむによって海を渡る。勤勉によって苦しみを捨て、明らかな知慧によって全く清らかとなる。
6)信(まこと)は男に伴(つ)れそう妻である。知慧がかれを教えさとす。修行僧は安らぎ(ニルヴァーナ)を楽しみ、迷いの生存の束縛を断ち切る。
7)信仰と戒しめとをたもち、生きものを傷けず、つつしみあり、みずからととのえている人は、汚れを去った賢者であり、「端正な人」と呼ばれる。
8)信仰あり、徳行そなわり、ものを執著しないで与え、物惜しみしない人は、どこへ行こうとも、そこで尊ばれる。
9)生きとし生ける者どものあいだにあって、信仰と知慧とを得た賢い人にとっては、それが実に最上の宝である。そのほかの宝はつまらぬものである。
10)諸の聖者に見(まみ)えようと願い、正しい教えを聞くことを楽しみ、もの惜しみの汚れを去った人、――かれこそ(信仰心ある人)と呼ばれる。
11)信仰心の深い人は、人生の旅路の糧(かて)を手に入れる。それは盗賊も奪うことのできない福徳である。盗賊が奪い去るのを防ぐ。功徳をともなう修行僧らは、人々に愛される。修行僧らが来たのを見ては、賢い人々は歓び迎える。
12)或るひとびとは、信ずるところにしたがって、また財力に応じて、ほどこしをなす。だから、他人のくれた食物や飲料に満足しない人は、昼も夜も心のやすらぎを得ない。
13)もしもひとがこれらの悪徳、飽かざる思いを絶ち、ターラ樹の尖端のように根だやしにしたならば、その人は昼も夜も心のやすらぎを得る。
14)信仰の無い人とつき合うな。水の乾からびた池のようなものである。もしもそこを掘るならば、泥くさい臭いのする水が出て来るだろう。
15)しかし、信仰心あり明らかな知慧ある人とつき合え。――水をもとめている人が湖に近づくように、そこには、透明で清く澄み、冷やかで、濁りの無い水がある。
16)好きな人だからといってなじんではならない。ひとはそこで砕かれてしまう。清い信仰心の無い人を遠ざけて、清い信仰心のある人に近づく。
まとめの句
(1)無常と(2)愛欲と(3)愛執と(4)はげみと(5)愛するものと(6)戒しめと(7)善い行ないと(8)ことばと(9)行ないと(10)信仰とで、10になる。
■第11章 道 の 人
1)勇敢に流れを断て。諸の欲望をきっぱりと去れ。諸の欲望を捨てなければ、聖者は一体に達することができない。
2)知慧ある人は、(なすべきことを)いつも為しつつ、それを断乎として実行せよ。行ないのだらけた出家修行は、多く塵を受ける。
3)その行ないがだらしなく、その修行が汚れていて、清らかな行ないなるものも完全に清らかでないならば、大きな果報はやって来ない。
4)矢でも、とらえ方を誤ると、手のひらを切るように、修行者の行も、誤っておこなうと、地獄にひきずりおろす。
5)矢でも正しく捉えると、手のひらを切ることがないように、修行者の行も正しくおこなうと、。ニルヴァーナの近くにある。
6)修行者の行ないは、知能の鈍い人間の為し難く忍び難いことである。愚鈍なる者の気落ちするような苦悩は多いのである。
7)修行者の行をおこなう人は、自分の心を退けるべきではない。(そうでないならば)くりかえし心が沈んでしまって、諸の(乱れた)思いのままになってしまうであろう。
8)出家の生活は、困難であり、それを楽しむことは難しい。(世俗の)家に住むのも堪え難いことである。心を同じくしない人々と共に住むのも、苦しいことである。迷いの生存を重ねることは、苦しみである。
9)袈裟を頸から纏っていても、性質(たち)が悪く、つつしみのない者が多い。かれら悪人は悪いふるまいによって死後には悪いところ(地獄)に生れる。
10)この極めて性(たち)の悪い人は、仇敵がかれの不幸を望むとおりのことを、自分に対してなす。あたかも蔓草が紗羅の木にまといつくようなものである。
11)頭髪が白くなったからとて〈長老〉なのではない。ただ年をとっただけならば「ばかになって老いぼれた人」と言われる。
12)しかし福徳と罪悪とを捨て、清らかな行ないをなし、ひととの交りを捨てて行じている人、――かれこそ〈長老〉とよばれる。
13)頭を剃ったからとて、身をつつしまず、偽りを語る人は、〈道の人〉ではない。欲望と貪りにみちている人が、どうして〈道の人〉であろうか?
14)頭を剃ったからとて、身をつつしまず、偽りを語る人は、〈道の人〉ではない。大きかろうとも小さかろうとも悪をすべてとどめた人は、諸の悪を静め滅ぼしたのであるから、〈道の人〉と呼ばれる。
15)この世では悪を取り除いたので〈バラモン〉(婆羅門)と呼ばれ、不吉なことが静かにやすまっているので〈道の人〉(シャマナ、沙門)と呼ばれ、おのれの汚れを除いたので〈出家者〉と呼ばれる。
■第12章 道
1)明らかな知慧によって4つの尊い真理を見るときに、この人は迷える生存の妄執を破り摧(くだ)く道を明らかに知る。
2)風によって吹き上げられた塵が雨によって静まるように、ひとが明らかな知慧によって見るときに、諸の欲望の思いが静まる。
3)この世においては、実相を洞察するに至るこの知慧が、最もすぐれている。それによってひとは、生れと死の尽きてなくなることを正しく明らかに知る。
4)諸の道のうちでは〈8つの部分よりなる正しい道〉が最もすぐれている。真理について言えば〈4つの尊い真理〉(=四諦)が最もすぐれている。諸の徳のうちでは〈情欲を離れること〉が最もすぐれている。諸の人々のうちでは〈眼(まなこ)ある人〉(=ブッダ)が最もすぐれている。
5)「一切の形成されたものは無常である」(諸行無常)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
6)「一切の形成されたものは苦しみである」(一切皆苦)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
7)「一切の形成されたものは空である」と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
8)「一切の事物は我ならざるものである」(諸法非我)と明らかな知慧をもって観るときに、ひとは苦しみから遠ざかり離れる。これこそ人が清らかになる道である。
17)つねに善き思考をはたらかせよ。しかしつねに悪を避けよ。そうすれば、吹き上げられた塵を雨がしずめるように、諸の思考と思索とを捨て去るであろう。
19)明らかな知慧を武器とし、瞑想による力をそなえ、心が統一し、瞑想を楽しみ、気をつけている人は、世の中の興亡盛衰をさとって、智を具現した人として、あらゆることがらから解脱する。
20)不死に到達するために、めでたい真直(まっすぐ)な、8つのしかたより成る尊い道(八正道)を修する人は、安楽をもとめて正しく行なうので、幸せを得、またどこでも名誉と名声とを得る。
■第13章 尊 敬
1)芭蕉は実が生(な)ると滅びてしまう。竹や蘆は実が生ると滅びてしまう。牝の驢馬は自分の胎児のために滅びてしまう。そのように、悪人は尊敬を受けると滅びてしまう。
3)善くない人々は、利益を得ようと願い、修行僧らのあいだでは尊敬を得ようとし、僧房にあっては物惜しみの気持を得ようとし、他人の家に行っては供養を得ようとする。
4)「在家の人々も出家した修行者たちも、つねにわたくしのことを知れ。およそなすべきこととなすべからざることについては、わたしの意に従え」――
5)愚かな者はこのように思う。こうして欲求と高慢(たかぶり)とがたかまるのである。利益を得るよすがは、ニルヴァーナにいたる道とは異なっている。
6)ブッダの弟子は、つねにこのことわりを如実に知って、栄誉を喜ぶな。孤独の境地にはげめ。
7)いかなることにもあくせくするな。他人の従者となるな。他人に依存して生活するな。法による商人として暮すな。
8)(托鉢によって)自分の得たものを軽んじてはならない。他人の得たものを羨むな。他人を羨む修行僧は、心の統一安定を得ることができない。
13)たといその修行僧が三種の明知を体現して、死を打ちのめした者であり、汚れが無いとしても、無智なるものどもは、「かれは人に知られていることが少ない」といって、かれを見下す。
14)ところで、この世で食物や飲料を(多く)所有している人は、たとい悪いことを行なっていても、かれは(愚かな)人々から尊敬される。
17)この(体)は、食べなければ生きてゆくことができない。食物は心胸(むね)を静かならしめるものではない。食物は身体を存続させるためのものである。そのことを知って、托鉢の行をおこなえ。
■第14章 憎 し み
1)悪い行ないをなさず怒ってもいない人に対して怒るならば、この世においても、かの世においても、その人は苦しみを受ける。
2)かれは以前には自己を害(そこ)ない、後には外のものを傷ける。(自分が)害されると、他の人を害する。――鷹が鳥どもを害なうように。
3)殺す人は殺され、怨む人は怨みを買う。また罵りわめく人は他の人から罵られ、怒りたける人は他の人から怒りを受ける。
4)この正しい教えを聞くのでなければ、真理を識ることができない人々は、誰か他人に対して怨みを結ぶ。――人生はこのように短いのに。
9)「かれは、われを罵(ののし)った。かれは、われにこんなことを言った。かれは、われにうち勝った。人をしてわれに打ち勝たしめた。」という思いをいだく人々には、怨みはついに息むことがない。
10)「かれは、われを罵(ののし)った。かれは、われにこんなことを言った。かれは、われにうち勝った。人をしてわれに打ち勝たしめた。」という思いをいだかない人々には、ついに怨みは息む。
11)実にこの世においては、およそ怨みに報いるに怨みを以てせば、ついに怨みの息むことがない。堪え忍ぶことによって、怨みは息む。これは永遠のしんりである。
12)怨みは怨みによっては決して静まらないであろう。怨みの状態は、怨みの無いことによって静まるであろう。怨みにつれて次々と現われることは、ためにならぬということがみとめられる。それ故にことわりを知る人は、怨みをつくらない。
13)もしもつねに正しくこの世を歩んで行くときに、明敏な同伴者を得ることができたならば、あらゆる危険困難に打ち克って、こころ喜び、念(おも)いをおちつけて、かれとともに歩め。
14)しかし、もしもつねに正しくこの世を歩んで行くときに、明敏な同伴者を得ることができなかったならば、(戦いに負けて)広大な国を捨てた国王のように、唯ひとりで歩め。悪いことをしてはならぬ。
15)旅に出て、もしも自分にひとしい者に出会わなかったら、むしろきっぱりと独りで行け。愚かな者を道伴れにしてはならぬ。
16)愚かな者を道伴れにすることなかれ。独りで行くほうがよい。孤独で歩め。悪いことをするな。求めるところは少なくあれ。――林の中にいる象のように。
■第15章 念(おも) い を お ち つ け て
2)身をまっ直ぐに立て、心もそのようにして、立っても、坐しても、臥しても、つねに念いをおちつけととのえている修行僧は、過去についても未来についても、勝れた境地を得るであろう。過去についても未来についても勝れた境地を得たならば、死王も見(まみ)えないことになるであろう。
3)身体についてつねに真相を念い、つねに諸の感官を慎しみ、心を安定させている者は、それによって自己の安らぎを知るであろう。
4)もしも或る人にとって身体について真相を念うことがつねに完全に確立したならば、その(「アートマン」という迷い)は存在しないであろう。「わがもの」という迷いも存在しないであろう。その(「アートマン」という迷い)はあらわれないであろう。「わがもの」という迷いも起らないであろう。この人は種々の念いに順次に住するから、やがて適当な時が来れば、執著(の流れ)を超えるであろう。
5)目ざめていて、念いを落ちつけ、正気でいて、心を統一安定させ、喜んで、心もちが明らかに澄んでいる者は、適当な時々に正しい教えを熟考して、生れて老い、ならびに憂いをのり超えよ。
6)それゆえに、つねに目ざめておれ。念いを落ち着けて、怠ることなく、勇を鼓して、生れと老いという束縛の絆をすてて、この世にありながら苦しみを終滅させる。
7)目ざめている者どもは、わがことばを聞け。眠っている者どもは、めざめよ。眠っている者どもよりは目ざめている者がすぐれている。目ざめている者には恐れがないからである。
9)ブッダに帰依した人々は得るところがある。――かれらは昼も夜もつねに仏を念じているので。
10)法に帰依した人々は得るところがある。――かれらは昼も夜もつねに法を念じているので。
12)ガウタマ(=ゴータマ)のこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜もつねに仏を念じている。
13)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜もつねに法を念じている。
15)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜もつねに身体(の真相)を念じている。
15A)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜も心の安定統一を念じている。
16)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜も戒めを念じている。
16A)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜も捨て去ることを念じている。
16B)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜も神々を念じている。
17)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、昼も夜もその心は不傷害を楽しんでいる。
18)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は怒り害しないことを楽しんでいる。
19)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は昼も夜も(俗世からの)出離を楽しんでいる。
20)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は瞑想(禅定)を楽しんでいる。
21)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は遠ざかり離れる孤独(ひとりい)を楽しんでいる。
22)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は空を楽しんでいる。
23)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は無相を楽しんでいる。
24)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は無所有を楽しんでいる。
25)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は瞑想を楽しんでいる。
26)ガウタマのこの弟子たちは、よく覚醒していて、その心は安らぎを楽しんでいる。
■第16章 さ ま ざ ま な こ と
1)未来になすべきことをあらかじめ心がけておるべきである。――なすべき時に、わがなすべき仕事をそこなうことのないように。準備している人を、なすべき時になすべき仕事が害うことはない。
2)目的が達成されるまで、人は努めなければならぬ。自分の立てた目的がそのとおりに実現されるのを見よ。――希望したとおりになるであろうと。
3)起て、つとめよ。自分のよりどころをつくれ。鍛冶工が銀の汚れをとり去るように、自分の汚れをとり去れ。汚れをはらい、罪過(つみとが)がなければ、汝らはもはや生と老いとを受けないであろう。
5)ところで、以前には怠りなまけていた人でも、のちには怠り怠けることが無いなら、その人はこの世の中を照らす。――雲を離れた月のように。
6)以前には怠りなまけていた人でも、のちには怠り怠けることが無いなら、その人は念いを落ちつけていて、この世でこの執著をのり超える。
14)修行僧らよ。汝らは悪いことがらを捨てて、善いことがらを行なえ。家から出て、家の無い生活に入り、孤独(ひとり)に専念せよ。すぐれた人は欲楽をすてて、無一物となり、その境地を楽しめ。
16)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れは情欲である。それ故に、情欲を離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
17)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れは怒りである。それ故に、怒りを離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
18)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れは迷妄である。それ故に、迷妄を離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
19)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れはおごり高ぶりである。それ故に、おごり高ぶりを離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
20)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れは貪りである。それ故に、貪りを離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
21)田畑の汚れは雑草であり、この人々の汚れは愛執である。それ故に、愛執を離れた人々に供養して与えたものは、大きな果報をもたらす。
22)第6の機能(=五官につづく心)が、支配者である王である。それが情欲に染まっているときには情欲のままになり、染まっていないときには「汚れを離れた者」となるが、染まっているときには「凡夫」とよばれる。
24)苦しみはつねに因縁からおこる。そのことわりを観ないものだから、それによってひとは苦しみに縛られている。しかし、そのことを理解するならば、執著を捨て去る。けだし外の人々はその大きな激流を捨てないのである。
■第17章 水
1)心をとどめている人々は努めはげむ。かれらは住居を楽しまない。白鳥が池を立ち去るように、かれらはあの家、この家を(つぎつぎと)捨てる。
2)白鳥は太陽の道を行き、感官を制御した人々は虚空(そら)を行き、心ある人々は、悪魔の軍勢にうち勝って世界から去って行く。
5)「その報いはわたしには来ないだろう」とおもって、悪を軽んずるな。水が1滴ずつ滴りおちるならば、大きな水瓶でもみたされるのである。愚かな人々は、少しずつでも悪をなすならば、やがてわざわいにみたされるのである。
6)「その果報はわたしには来ないだろう」とおもって、善を軽んずるな。水が1滴ずつ滴りおちるならば、大きな水瓶でもみたされるのである。気をつけている人々は、少しずつでも善をなすならば、やがて福徳にみたされるのである。
8)バラモンである尊師ブッダは、(大河を)渡りおわって陸地に立っている。或る修行僧らはここで水浴をしている。他の修行僧らは筏をつくっている。
9)もしも水がどこにでもあるのであるならば、どうして泉をつくる必要があろうか?妄執の根を取り除いたならば、さらに何を求める要があろうか?
11)深い湖が、澄んで、清らかであるように、賢者たちは正しい教えを聞いて、こころ清らかである。
■第18章 花
2)学びにつとめる人こそ、この大地を征服し、神々とともなる閻魔の世界を征服するであろう。わざに巧みな人が花を摘むように、学びにつとめる人こそ、善く説かれた真理のことばを摘みあつめるのであろう。
3)(単に)1つの樹を切るのではなくて、(煩悩)の林を切れ。危険は林から生じる。(煩悩)の林とその根とを断ち切って、林(=煩悩)から脱れた者となれ。修行僧らよ。
4)たとい僅かであろうとも、親族に対する人の欲望が断たれないあいだは、その人の心はそこに束縛されている。――乳を吸う子牛が恋い慕うようなものである。
6)うるわしく、あでやかに咲く花でも、香りの無いものがあるように、善く説かれたことばでも、それを実行しない人には実のりがない。
7)うるわしく、あでやかに咲く花で、しかも良い香りのあるものがあるように、善く説かれたことばも、それを実行する人には、実のりが有る。
8)蜜蜂は(花の)色香を害わずに、汁をとって、花から飛び去る。聖者が、村のなかを行くときは、そのようにせよ。
9)他人の過去を見るなかれ。他人のなしたこととなさなかったことを見るなかれ。ただ自分の(なしたこととなさなかったこととについて)それが正しかったか正しくなかったかを、よく反省せよ。
■第19章 馬
1)良い馬が鞭をあてられると、勢いよく熱気をこめて走るように、勢いよく努め励め。信仰あり、また徳行をそなえ、精神を安定統一して、真理を確かに知って、感官を制御し、忍耐の力をそなえた人は、迷いの生存をすべて残りなく捨て去る。
2)良い馬が鞭をあてられると、勢いよく熱気をこめて走るように、勢いよく努め励め。信仰あり、また徳行をそなえ、精神を安定統一して、真理を確かに知って、知慧と行ないを完成し、思念をこらして、このような境地に達した人は、すべての苦しみを捨て去る。
3)御者が馬をよく馴らしたように、おのが感官を静め、欠点を捨て、汚れのなくなった人――その人を神がみでさえもつねに羨む。
5)恥を知り、明らかな知慧あり、よく心を統一安定しているこの人は、一切の悪を捨て去る。――良い馬が鞭を受けたときのように。
6)馴らされた馬は、戦場にも連れて行かれ、王の乗りものともなる。自らをおさめた者は、人々の中にあっても最上の者である。かれは世のそしりを忍ぶ。
14)実に自己は自分の主(あるじ)である。自己は自分の帰趣(よるべ)である。故に自分を制御せよ。――御者が良い馬を調練するように。
■第20章 怒 り
1)怒りを捨てよ。慢心を除き去れ。いかなる束縛をも超越せよ。名称と形態とに執著せず、無一物となった者は、苦悩に追われることがない。
2)怒りが起ったならば、それを捨て去れ。情欲が起ったならば、それを防げ。思慮ある人は無明を捨て去れ。真理を体得することから幸せが起る。
4)怒りたけった人は、善いことでも悪いことだと言い立てるが、のちに怒りがおさまったときには、火に触れたように苦しむ。
5)かれは、恥じることもなく、愧じることもなく、誓戒をまもることもなく、怒りたける。怒りに襲われた者には、たよりとすべきいかなる帰趣(よるべ)もこの世に存在しない。
13)愚者は、荒々しいことばを語りながら、「自分が勝っているのだ」と考える。しかし謗(そし)りを忍ぶ人にこそ、常に勝利があるのだ、と言えよう。
17)心が静まり、身がととのえられ、正しく生活し、正しく知って解脱している人に、どうして怒りがあろうか?はっきりと知っている人に、怒りは存在しない。
19)怒らないことによって怒りにうち勝て。善いことによって悪いことにうち勝て。わかち合うことによって物惜しみにうち勝て。真実によって虚言にうち勝て。
20)怒ることなく、身がととのえられ、正しく生活し、正しく知って解脱している人に、どうして怒りがあろうか?かれには怒りは存在しない。
22)走る車をおさえるように、ここでむらむらと起る怒りをおさえる人――かれをわれは〈御者〉とよぶ。そうでなければ、この人はただ手綱を手にしているだけである。(〈御者〉とよぶにはふさわしくない。)
まとめの句
(1)修行者と(2)道と(3)尊敬と(4)恐れと(5)念いと(6)さまざまと(7)水と(8)花と(9)馬と(10)怒りとで、10になる。
■第21章 如 来
1)われはすべてに打ち勝ち、すべてを知り、あらゆることがらに関してつねに汚されていない。すべてを捨てて、一切の恐怖から解脱している。みずからをさとったのであって、誰を〔師と〕呼ぶであろうか。
2)等しき者もなく、比べるべき者もない人は、誰を〔師と〕呼ぶのであろうか。自からさとりを得て自から教えを説く人なのであるから。如来は神々と人間の師であり、すべてを知る者(=一切智者)となって、(知慧の)力をそなえている。
9)正しいさとりを開き、つねに幸(さち)あり、瞑想に専念している思慮ある人々は、世間から離れた静けさを楽しむ。神々でさえも、かれらを羨む。
10)正しくさとりを開いた人々、誉れあり、速やかに知能がはたらき、最後の身体をたもっている人々を、神々も人間たちも羨むのである。
17)その聖者は完全な自在を得、一切のものにまさり、すべての恐怖から解脱し、愛執を捨て、汚れ無く、望むこと無く、生きとし生ける者どもを観じて、世のためを念うている。
18)山の頂にある岩の上に立っている人があまねく四方に人々を見下すように、あらゆる方向に眼をもっているこの賢明なる人は、真理の高閣(たかどの)に登って、(自分は)憂いはなくして、生れと老いとに打ち克たれ、憂いに悩まされている人々を見た。
■第22章 学 問
1)聞いて学ぶことは善い。正しく行なうことも善い。また住むべき家の無いことも善い。正しいことわりにしたがって出家して遍歴することも善い。――以上のことは修行者の境地にふさわしいことである。
2)この世でことわりをはっきりと知らない愚かな者どもは、自分たちが不死であるかのごとくに振舞う。しかし正しい真理をはっきりと知っている人々にとっては、(この世の生存は)病める者にとっての夜のごとくである。
3)よく密閉してあって暗闇にみたされた家に入ると、そこにある諸の見事な物を、眼のある人でも見ることができないようなものである。
4)この世では人間もまた、つねにそのようなものである。知識はもっているかもしれないが、教えを聞くことが無ければ善悪のことがらを識別することができない。
5)眼のある人は燈火によって種々の色かたちを見るように、ひとは教えを聞いて、善悪のことがらを識別する。
7)或る人が、たとい博学であっても、徳行に専念していないならば、世の人々はかれを徳行の点で非難する。その人の学問は完全に身に具わっているのではない。
8)或る人が、たとい学問が僅かであっても、徳行によく専念しているならば、世の人々、徳行についてかれを称讃する。その人の学問は完全に身に具わっているのである。
9)もしも或る人が学問も少なく、また徳行にも専念していないならば、世の人々は(学問と徳行と)両方の点でかれを非難する。その人の誓戒は完全に身に具わっているのではない。
10)もしも或る人が博学であって、また徳行にもよく専念しているならば、世の人々は(学問と徳行と)両方の点でかれを称讃する。その人の誓戒は完全に身に具わっているのである。
12)色かたちによって、わたしを測り、また音声によって、わたしを尋ねもとめた人々は、貧欲や情欲に支配されているのであって、(実は)わたしのことを知らない。
13)内を知らないが、外をはっきりと見て、外のほうの結果ばかりを見ている人は、実に音声に誘われる。
14)内を明らかに見ているが、外を見ないで、内のほうの結果ばかりを見ている人は、実に音声に誘われる。
15)内を知らないが外をも見ないで、(内と外と)両方について結果を見ない人は、実に音声に誘われる。
16)内をも明らかに知り、外をもはっきりと見て、よりどころにとらわれないで明らかに知る人は、実に音声に誘われることがない。
17)耳で多くのことを聞き、眼で多くのことを見る。思慮ある人は、見たこと、聞いたことをすべて信じてはならない。
18)みごとに説かれたことばは、それを聞いて理解すれば精となる。聞いたこと、識(し)ったことは、心にじっととどめておくと精となる。しかし人が性急であって怠けているならば、かれの知識も学問も大きな目的を達成することはできない。
19)聖者の説きたもうた真理を喜んでいる人々は、そのとき、かれらの説くことをことばでも実行する。かれらは忍耐と柔和と瞑想のうちに安定し、学問と知能との真髄にも達したのである。
■第23章 自 己
2)ひとり坐し、ひとり臥し、ひとり歩み、なおざりになることなく、自分ひとりを楽しめ。つねにひとりで林の中に住め。
4,5)自己にうち克つことは、他の人々に克つことよりもすぐれている。つねに行ないをつつしみ、自己をととのえている人、――このように明らかな知慧ある修行僧の克ち得た勝利を敗北に転ずることは、神々も、なし得ない。ガンダルヴァ(天の音楽神)たちも、悪魔も、梵天もなし得ない。
6)先ず自分の身を正しくせよ。次いで他人に教えよ。
8)自分が他人に教えるとおりに自分でも行なえ。わたしは常にわが身をよくととのえている。自分というものは、まことに制し難いものである。
10)たとい他人にとっていかに大事であろうとも、(自分ではない)他人の目的のために自分のつとめをすて去ってはならぬ。自分の最高の目的を知って、自分のつとめに専念せよ。
11)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、(自分の)主となり得る。
12)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、(自分の)目的を達成する。
13)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、徳行を達成する。
14)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、名声を得る。
15)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、名誉を得る。
16)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、いろいろの幸せを得る。
20)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、明らかな知慧を穫得する。
22)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、悩みのうちにあって悩まない。
23)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、いかなる束縛をも断ち切る。
24)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、すべての悪い生存領域(註1)を捨て去る。
25)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、すべての苦しみから脱れる。
26)この世では自己こそ自分の主(あるじ)である。他人がどうして(自分の)主であろうか?賢者は、自分の身をよくととのえて、ニルヴァーナの近くにある。
注1)生存領域――『法集要頌経』には「悪趣」と訳している。畜生、修羅、餓鬼、地獄をいう。
■第24章 広 く 説 く
1)無益な語句よりなる詩を百もとなえるよりも、聞いて心の静まる有益なことばを一つ聞くほうがすぐれている。
2)ことわりにかなわぬ語句よりなる詩を百もとなえるよりも、聞いて心の静まることわりにかなったことばを一つ聞くほうがすぐれている。
3)素行が悪く、心が乱れていて百年生きるよりは、つねに清らかで徳行のある人が一日生きるほうがすぐれている。
4)愚かに迷い、心の乱れている人が百年生きるよりは、つねに明らかな知慧あり思い静かな人が一日生きるほうがすぐれている。
5)怠りなまけて、気力もなく百年生きるよりは、しっかりとつとめ励む人が一日生きるほうがすぐれている。
6)事物(ものごと)が起りまた消え失せることわりを見ないで百年生きるよりは、事物(ものごと)が起りまた消え失せることわりを見て一日生きるほうがすぐれている。
7)苦痛が尽きてなくなるのを見ないで百年生きるよりは、苦痛が尽きてなくなるのを見て一日生きるほうがすぐれている。
8)汚れが尽きてなくなるのを見ないで百年生きるよりは、汚れが尽きてなくなるのを見て一日生きるほうがすぐれている。
9)不動の境地を見ないで百年生きるよりは、不動の境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
10)没落することのない境地を見ないで百年生きるよりは、没落することのない境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
11)塵汚れのない(無垢の)境地を見ないで百年生きるよりは、塵汚のない(無垢の)境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
12)塵汚れを離れた境地を見ないで百年生きるよりは、塵汚れを離れた境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
13)見難い境地を見ないで百年生きるよりは、見難い境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
14)最上の境地を見ないで百年生きるよりは、最上の境地を見て一日生きるほうがすぐれている。
21)たとい百年のあいだ毎日千回ずつ祭祀(まつり)を営む人がいても、その功徳は、仏を信ずる(功徳)の16分の1にも及ばない。
22)たとい百年のあいだ毎日千回ずつ祭祀(まつり)を営む人がいても、その功徳は、ダルマ(法、真理)を信ずる(功徳)の16分の1にも及ばない。
29)たとい百年のあいだ毎日千回ずつ祭祀(まつり)を営む人がいても、その功徳は、真理をよく説いた人(の功徳)の16分の1にも及ばない。
30)功徳を得ようとして、ひとがこの世で1年間神をまつり犠牲(いけにえ)をささげ、あるいは火にささげ物をしても、その全部をあわせても、(真正なる祭りの功徳の)4分の1にも及ばない。行ないの正しい人々を尊ぶことのほうがすぐれている。
■第25章 友
1)明らかな知慧のある人が友達としてつき合ってならないのは、信仰心なく、ものおしみして、二枚舌をつかい、他人の破滅を喜ぶ人々である。悪人たちと交わるのは悪いことである。
2)明らかな知慧のある人が友達としてつき合うべき人々は、信仰心があり、気持のよい、素行のよい、学識ゆたかな人々である。けだし立派な人々と交わるのは善いことである。
3)悪い友と交わるな。卑しい人と交わるな。善い友と交われ。尊い人と交れ。
5)劣った卑しい者になじむ人は堕落してしまう。しかし等しい者につき合う人は実に堕落することはないであろう。すぐれた者に近づく人はすぐれた状態に達する。それ故にこの世では自分よりもすぐれた人とつき合え。
6)知慧についても、徳行についても、心の静まりについても、最上のすぐれた人々に近づき仕える人は、つねにすぐれた境地に達する。
10)つき合っている悪人は、悪に触れられているが、また他人に触れて、悪をうつすであろう。毒を塗られた矢は、箭筒(やづつ)の束のなかにある、毒を塗られていない矢をも汚す。悪に汚れることを恐れて、思慮ある人は、悪人を友とするな。
11)どのような友をつくろうとも、どのような人につき合おうとも、やがて人はその友のような人になる。人とともにつき合うというのは、そのようなことなのである。
12)それ故に、賢者は、自分は、果物籠が(中にいれる果物に)影響されるようなものであるいうことわりを見て、悪人と交わるな。善人と交われ。
13)愚かな者は、生涯賢者たちに仕えても、真理をはっきりと知ることが無い。――匙が汁の味を知ることができないように。
14)聡明な人は、瞬時(またたき)のあいだ賢者たちに仕えても、ただちに真理をはっきりと知る。――舌が汁の味をはっきりと知るように。
15)愚かな者は、生涯賢者たちに仕えても、真理をはっきりと知ることが無い。かれには明らかな知慧がないからである。
16)聡明な人は、瞬時(またたき)のあいだ賢者たちに仕えても、ただちに真理をはっきりと知る。かれには明らかな知慧が存するからである。
17)愚かな者は、生涯賢者たちに仕えても、正しくさとりを開いた人(=仏)の説かれた真理をはっきりと知ることがない。
18)聡明な人は、瞬時(またたき)のあいだ賢者たちに仕えても、正しくさとりを開いた人(=仏)の説かれた真理をはっきりと知る。
20)愚者は、千の句をとなえても、1の句さえも理解しない。聡明な人は。1つの句をとなえても、百の句の意義を理解する。
24)愚かな者を見るな。そのことばを聞くな。またかれとともに住むな。愚人らとともに住むのは、全くつらいことである。仇敵とともに住むようなものだからである。思慮ある人々と共に住むのは楽しい。――親族と出会うようなものである。
25)よく気をつけていて、明らかな知慧あり、徳行をたもち、学ぶところ多く、しっかりしていて、敏捷な人に親しめよ。――諸の星が月にしたがうように。
■第26章 安 ら ぎ(ニ ル ヴ ァ ー ナ)
2)忍耐、堪忍は最上の苦行である。安らぎ(ニルヴァーナ)は最高のものであると、諸のブッダは説きたまう。他人を害する人は、他人を悩ますのだから、しゅっけした〈道の人〉ではない。
3)だれに対しても荒々しいことばを言うな。言われた人々はその人に言い返すであろう。怒りを含んだことばは苦痛である。報復が(その人の)身に迫る。
4)こわれた鐘のように、汝がいつも自分を動揺させ(煩悩をおこす)ならば、汝は生まれては死ぬ流転の迷いをながく受けるであろう。
5)しかし、こわれた鐘が音を出さないように、汝が自分を動揺させ(煩悩をおこす)ことが無いならば、汝はすでに安らぎ(ニルヴァーナ)に達している。汝はもはや怒り罵ることがない。
6)健康は最高の利得であり、満足は最上の宝であり、信頼は最高の友であり、安らぎ(ニルヴァーナ)は最上の楽しみである。
7)飢は最大の病であり、形成された存在(=わが身)は苦しみである。このことわりをあるがままに知ったならば、安らぎ(ニルヴァーナ)に専念するものとなるであろう。
8)善い領域(=天)におもむく人々は少ない。悪い領域(=地獄など)におもむく人々は多い。このことわりをあるがままに知ったならば、安らぎ(ニルヴァーナ)に専念するものとなるであろう。
9)ひとびとは因縁があって善い領域(=天)におもむくのである。ひとびとは因縁があって悪い領域(=地獄など)におもむくのである。人びとは因縁があって完き安らぎ(ニルヴァーナ)に入るのである。このように、このことは因縁にもとづいているのである。
10)鹿の帰るところは原野の奥であり、鳥の帰るところは虚空であり、分別ある人々の帰するところはことわり(=義)であり、もろもろの真人の帰するところは安らぎ(ニルヴァーナ)である。
11)気力無くなまけている人も、遅鈍な人も、はっきりと知ることの無い人も、あらゆる絆を破りくだく安らぎ(ニルヴァーナ)に達することはできない。
13)(注1)前にはあったが、そのときには無かった。前には無かったが、そのときはあった。前にも無かったし、のちにも無いであろう。また今も存在しない。
14)不動の真理は見難い。見易いものの真相を洞察して、妄執の消滅を見る人にとっては、苦しみが終滅すると説かれる。
15)この世で妄執を断ち切って、静かならしめ、すべての塵汚れをおさめて、河の水を乾かしてしまったならば、苦しみが終滅すると説かれる。
16)(注2)身体を壊(やぶ)り、表象作用と感受作用とを静めて、識別作用を滅ぼすことができたならば、苦しみが終滅すると説かれる。
17)見られたことは見られただけのものであると知り、聞かれたことは聞かれただけのものであると知り、考えられたことはまた同様に考えられただけのものであると知り、また識別されたことは識別されただけのものであると知ったならば、苦しみが終滅すると説かれる。
18)⑴苦しみと⑵苦しみの原因と⑶苦しみの止滅と⑷それに至る道とをさとった人は、一切の悪から離脱する。それが苦しみの終滅であると説かれる。
20)何ものかに依ることが無ければ、動揺することが無い。そこには身心の軽やかな柔軟性がある。行くこともなく、没することもない。それが苦しみが終滅であると説かれる。
21)不生なるものが有るからこそ、生じたものの出離をつねに語るべきであろう。作られざるもの(=無為)を観じるならば、作られたもの(=有為)から解脱する。
22)生じたもの、有ったもの、起ったもの、作られたもの、形成されたもの、常住ならざるもの、老いと死との集積、虚妄なるもので壊れるもの、食物の原因から生じたもの、――それは喜ぶに足りない。
23)それは出離であって、思考の及ばない静かな境地は、苦しみのことがらの止滅であり、つくるはたらきの静まった安楽である。
24)そこには、すでに有ったものが存在せず、虚空も無く、太陽も存在せず、月も存在しないところのその境地を、わたくしはよく知っている。
25)来ることも無く、行くことも無く、生ずることも無く、没することも無い。住してとどまることも無く、依拠することも無い。――それが苦しみの終滅であると説かれる。
26)水も無く、地も無く、火も風も侵入しないところ――、そこには白い光も輝かず、暗黒も存在しない。
27)そこでは月も照らさず、太陽も輝やかない。聖者はその境地についての自己の沈黙をみずから知るがままに、かたちからも、かたち無きものからも、一切の苦しみから全く解脱する。
28)さとりの究極に達し、恐れること無く、疑いが無く、後悔のわずらいの無い人は生存の矢を断ち切った人である。これがかれの最後の身体である。
29)これは最上の究極であり、無上の静けさの境地である。一切の相が滅びてなくなり、没することなき解脱の境地である。
30)(自分に)ひとしい、あるいはひとしくない生れ、生存をつくり出す諸の形成力を聖者は捨て去った。内的に瞑想を楽しみ、心を安定統一して、(自分の)覆いを破ってしまった。――卵の幕を破るように。
31)教えを説いて与えることはすべての贈与にまさり、教えを味わう楽しみはすべての楽しみにまさり、忍耐の力はすべての力にまさり、妄執をすべてほろぼすことは(すべての)快楽にうち勝つ。
注1)これは古い詩であり、聖典自体のなかでいろいろに解釈されている。『テーラーガーター』180によって、かっては生存の貪りがあったが、今は無い云々という意味であり、『ウダーナ』6・3ではいろいろの悪について言うのであると解していたようであり、『出曜経』によると、我が有るとか、無いとかいう外道の論議についていうと解している。
注2)ここでは五蘊のうちの色・受・想・識に言及しているが、行に言及していないから、五蘊の説の確立する以前の段階の思想を示している。
■第27章 観 察
1)他人の過失は見やすいけれども、自分の過失は見がたい。ひとは他人の過失を籾殻のように吹き散らす。しかしこの人も自分の過失は隠してしまう。――狡猾な賭博師が不利な骰子(さい)の目をかくしてしまうように。
2)他人の過失を探し求め、つねに他人を見下して思う人は、卑しい性質が増大する。かれは実に真理を見ることから遠く隔っている。
3)恥を知らず、鳥の首魁のようにがやがや叫び、厚かましく、図々しい人は、生活し易い。この世では、心が汚れたまま生きて行く。
4)恥を知り、常に清きをもとめ、よく仕事に専念していて、つつしみ深く、真理を見て、清く暮す人は、生活し難い。
5)この世は暗黒である。ここではっきりと(ことわりを)見分ける人は稀である。網から脱れた鳥のように、天に至って楽しむ人は少ない。
6)この世は虚妄の束縛を受けていて、未来に変化する可能性のあるもののごとく見られる。愚者らは煩悩に束縛されていて、暗黒に覆われている。(かれらには)無が有であるかのごとくに見られている。真理を見る人には何ものも存在しない。
7)人々は自我観念にたより、また他人という観念にとらわれている。このことわりを或る人々は知らない。実にかれらはそれを(身に刺さった)矢であるあるとは見なさない。
8)ところがこれを、人々が執著しこだわっている矢であるとあらかじめ見た人は、「われが為す」という観念に害されることもないし、「他人が為す」という観念に害されることもないであろう。
9)この世の中の人々は慢心をもっていて、つねに慢心にへばりつかれている。悪い見解にとりつかれていては、努力しても生死流転を超えることはできない。
10)すでに得たものと、これから得られるはずのものと――この2つは塵ほこりであり、病いであると知って、心を安定統一した智者は、それを捨てよ。
15)世の中は泡沫(うたかた)のごとしと見よ。身体はかげろうのごとしと見よ。世の中をこのように観ずる人は、死王もかれを見ることがない。
16)世の中は泡沫(うたかた)のごとしと見よ。身体はかげろうのごとしと見よ。身体をこのように観ずる人は、死王もかれを見ることがない。
19)つねにこの身体を見よ。王車の車のように美麗である。愚者たちはそこに迷うが、賢者はそれに対する執著をはなれる。
20)見よ、粉飾された形体を!(それは)傷だらけの身体という名のものであって、病いに悩み、虚妄の意欲ばかりで、堅固に安住することがない。
21)見よ、あのように宝石や腕輪で粉飾された形体を!それは愚人を迷わすには足るが、彼岸を求める人々を迷わすことはできない。
22)見よ、あのように宝石や腕輪で粉飾された形体を!(それは愚人を迷わすには足るが、賢者はそれに対する執著を離れる。
27)諸の欲望に執著し、つねに迷っている者どもは、束縛のうちに過ちを見ることが無い。束縛の執著にとらわれている者どもは、広くひろがった大きな流れを、決して渡ることがないであろう。
28)上にも下にも全く情欲を離れた人は、「われはこれである」と観ずることが無いので、このように解脱して、未だ渡ったことのない流れを、この世で渡り、再び(迷いのうちに)生れることがないであろう。
29)愛欲の園からも離れ、愛欲の林から脱している人々からも離れているのに、また愛欲の林に向って走る。――この人を見よ!束縛から脱しているのに、また束縛に向って走るのである。
31)多くの人々は恐怖にかられて山々、林、園、樹木、霊樹などをたよろうとする。
32)しかしこれは安らかなよりどころではない。これは最上のよりどころではない。それらのよりどころよっては、あらゆる苦悩から免れることはできない。
33)さとれる者(=仏陀)と真理のことわり(=法)と聖者の集い(=僧)とに帰依する人は、明らかな知慧をもって、4つの尊い真理を見るときに、――
34)すなわち⑴苦しみと、⑵苦しみの成り立ちと、⑶苦しみの超克と、⑷苦しみの終滅(おわり)におもむく8つの部分よりなる尊い道(八聖道)とを(見るときに)、
35)これは安らかなよりどころである。これは最上のよりどころである。このよりどころにたよって、あらゆる苦悩から免れる。
36)見る人は、(他の)見る人々を見、また(他の)見ない人々をも見る。(しかし)見ない人は、(他の)見る人々をも、また見ない人々をも見ない。
37)すがたを見ることは、すがたをさらに吟味して見ることとは異なっている。ここに両者の異なっていることが説かれる。昼が夜と異なっているようなものである。両者が合することは有り得ない。
38)もしもすがたをさらに吟味して見るのであるならば、単にすがたを見るということは無い。またもしも単にすがたを見るのであるならば、すがたをさらに吟味して見るということは無い。ここの人は、単にすがたを見るだけであって、すがたをらに吟味して見るということが無い。しかしすがたをさらに吟味して見る人は、つねにすがたを見るということがない。
39)単にすがたを見る人は、どうしてすがたをさらに吟味して見ることが無いのであろうか?すがたを見ない人がつねにすがたをさらに吟味して見ることが無いのは、どうしてであろうか?何があるときに、すがたをさらに吟味して見ることがあるのだろうか?何が無いときに、すがたをさらに吟味して見ることが無いのであろうか?
40)ここなる人が苦しみを見ないというのは、見ない人が(個人存在の諸要素の集合が)アートマンであると見ることなのである。しかし(すべてが)苦しみであると明らかに見るときに、ここなる人は「(何ものかが)アートマンである」ということを、つねにさらに吟味して見るのである。
41)(無明に)覆われて凡夫は、諸のつくり出されたものを苦しみであるとは見ないのであるが、その(無明が)あるが故に、すがたをさらに吟味して見るということが起るのである。この(無明が)消失したときには、すがたをさらに吟味して見るということも消滅するのである。
■第28章 悪
1)すべて悪しきことをなさず、善いことを行ない、自己の心を浄めること、――これが仏の教えである。
2)わかち与える人には功徳が増大する。みずからを制するならば、ひとが怨みをいだくことは無い。善い人は悪を捨てる。情欲と怒りと迷妄とを捨てるが故に、煩悩の覆いをのがれる。
4)世間のうちにある思いを見て、汚れの無いことわりを知って、聖者は悪を楽しまない。悪人は淨らかなことを楽しまない。
5)孤独(ひとり)の味、心の安らいの味をあじわったならば、熱のような悩みも無く、罪過(つみとが)も無くなる、――真理の喜びの味をあじわいながら。
9)汚れの無い人、つねに清くして咎のない人、を汚す者がいるならば、そのわざわいは、かえってその浅はかな人に戻って来る。風にさからって細い塵を投げると、(その人にもどって来る)ようなものである。
10)人が何をしようとも、その報いが自分に起るのを見る。善いことを行なった人は良い報いを見、悪いことを行なった人は悪い報いを見る。
11)みずから悪をなすならば、つねに自分が汚れる。みずから悪をなさないならば、自分が浄まる。
12)人は他人を淨めることができない、――もしもその他人が内的に心のはたらきが浄らかでないならば。金剛石が宝石を磨くように悪人を錬磨すること〔はできない。〕
15)もし掌(てのひら)に傷が無いならば、その人は掌で毒をもっていることもできるであろう。傷の無い人に、毒は及ばない。悪をなさない人には、悪の及ぶことがない。
16)善からぬこと、己れのためにならぬことはなし易い。ためになることで、しかも健全なことは、実に極めてなし難い。
17)善人は善をなし易い。悪人は善をなし難い。惡人は悪をなし易い。聖者は惡をなし難い。
18)愚かな者は、悪いことを行なっても、その報いの現われないあいだは、それを蜜のように思いなす。しかしその罪の報いの現われたときには、苦悩を受ける。
19)まだ悪の報いが熟しないあいだは、悪人でも幸運に遇うことがある。しかし悪の報いが熟したときには、悪人はわざわいに遇うのである。
20)まだ善の果報が熟しないあいだは、善人でもわざわいに遇うことがある。しかし善の果報が熟したときには、善人は幸福(さいわい)に遇うこのである。
21)人がもしも悪いことをしたならば、それを繰り返すな。悪事を心がけるな。悪がつみ重なるのは苦しみである。
22)人がもしも善いことをしたならば、それを繰り返せ。善いことを心がけよ。善いことがつみ重なるのは楽しみである。
23)善をなすのを急げ。悪から心を退けよ。善をなすのにのろのろしたら、心は悪事をたのしむ。
26-29)手むかうことなく罪咎の無い人々に害を加えるならば、次に挙げる十種の場合のうちのどれかに速かに陥るであろう、――⑴親族の滅亡(ほろび)、⑵財産の消滅、⑶国王からの侵略、⑷恐ろしい告げ口、⑤激しい痛み、⑹身体の傷害、⑺重い病い、また⑻乱心、また⑼その人の家を火がすっかり焼いてしまう、⑽第十として、聡明な知力がなくなって(老いぼれて)、身やぶれてのちに、悪いところ(=地獄)に生れる。
30)悪いことをしたときには気をゆるすな。その悪いことが、ずっと昔にしたことだとか、遠いところでしたことであっても、気をゆるすな。秘密のうちにしたことであっても、気をゆるすな。それの報いがあるのだから、気をゆるすな。
31)この世で善いことをしたとならば、安心しておれ。その善いことが、ずっと昔にしたことだとか、遠いところでしたことであっても、安心するがよい。人に知られずにしたことであっても、安心しておれ。それの果報があるのだから、安心しておれ。
32)悪いことをしたならば、ひとは憂える。ずっと昔にしたことだとか、遠いところでしたことであっても、ひとは憂える。秘密のうちにしたことであっても、ひとは憂える。それの報いがあるのだから、ひとは憂える。
33)膳いことをしたならば、ひとは喜ぶ。ずっと昔にしたことだとか、遠いところでしたことであっても、ひとは喜ぶ。人に知られずにしたことであっても、ひとは喜ぶ。それの果報があるのだから、ひとは喜ぶ。
39)また悪いことをして、善いことをしないならば、悪い行ないをした人は、禍のもとを身に受けて、福徳を捨てて、この世で死を恐れる。――大水のさ中に難破した舟に乗っている人のように。
40)善いことをして、悪いことをしないならば、善い人々が福徳のもとを昔行なったのであっても、決して死を恐れない。――堅固な舟で河を渡る人々のように。
■第29章 ひ と 組 み ず つ
1)太陽が昇らないあいだは蛍が輝いている。しかし太陽が昇ると、にわかに暗黒色となり、輝かない。
2)そのように、如来が世に現われ出ないあいだは、(仏教外の)思索者たちが照らしていた。しかし世の中が仏によって照されると、思索者は輝かないし、その人の弟子も輝かない。
3)まことでないものを、まことであると見なし、まことであるものを、まことではないと見なす人々は、あやまった思いにとらわれて、ついに真実(まこと)に達しない。
4)まことであるものを、まことであると知り、まことでないものを、まことではないと知る人は、正しき思いにしたがって、ついに真実(まこと)に達する。
5)(経験するものを)実質のある物だと思って、走り近づいて行くが、ただそのたびごとに新しい束縛を身に受けるだけである。暗黒のなかから出て来た蛾が(火の中に)落ちるようなものである。かれらは、見たり聞いたりしたことに心が執著しているのである。
6)思念して熱心に清らかな修行を行なっている人々は、ここで(自分が)いだき、あるいは別々の人がいだき、この世でいだかれ、またかの世についていだかれる一切の疑いをすべて捨ててしまう。
10)欺いて、吝嗇(けち)で、偽る人は、ただ名前とかたちだけでも、美しい容貌によっても、「端正な人」とはならない。
11)端麗な容貌によっても、動作を見ることによっても、いかなる人(の心)も知り得ない。この世ではよく身を慎んでいる人のように見せかけて、(その実は)慎みの無い人々が、この世を闊歩している。
24)(「盲愛」という)母と(「われありという想い」である)父とをほろぼし、(永久に存在するという見解と滅びて無くなるという見解という)2人の武家の王と(戒律と邪まな見解という)2人の博学なパラモンとをほろぼし、(主観的機官と客観的対象とあわせて12の領域である)国土と(「喜び貪り」という)従臣とをほろぼして、バラモンは汚れなくしておもむく。
33)人々は多いが、彼岸(かなたのきし)に達する人々は少ない。他の(多くの)人々はこなたの岸に沿ってさまよっているだけである。
41)悪いことをするよりは、何もしないほうがよい。悪いことをすれば、後に悔いる。悪いことをしたならば、(のちに)憂える。悪いところ(=地獄)に行って憂える。
42)善いことをするほうがよい。なして、後に悔いがない。善いことをしたならば(のちに)喜ぶ。善いところ(天上)に行って喜ぶ。
51)妄想して考え出された現象界もなく、個人存在の連続もなく、障害もなくなって、はたらきのなくなった人、愛執を離れて行じている聖者を、神々も世人も、それだと識ることがない。
57)前でも捨てよ。後でも捨てよ。中間でも棄てよ。生存の彼岸に達した人はあらゆることがらについて心が解脱していて、もはや生れと老いとを受けることが無いであろう。
■第30章 楽 し み
2)他人を苦しめることによって自分の快楽を求める人は、怨みの絆にまつわられて、苦しみから脱れることができない。
5)よい果報を生ずるもととして善い行ないを実行せよ。報いを生ずるもととして悪い行ないを実行するな。ことわりに従って行なう人は、この世でも、あの世でも、安楽に臥す。
6)道理を実践する人を、つねに道理が守る。大雨が降るときに傘が守ってくれるようなものである。道理をよく実践すると、このすぐれた利益がある。道理を実践する人は悪いところ(=地獄)におもむかない。
7)道理を実践する人を、つねに道理が守る。道理をよく実践すると、幸せを受ける。道理をよく実践すると、このすぐれた利益がある。道理を実践する人は悪いところ(=地獄)におもむかない。
10)執著する心がなくて施し与える人は、幾百の障害にうち勝って、敵である物惜しみを圧倒して、勇士よりもさらに勇士であると、われは語る。
11)福徳の果報が熟するのは楽しい。希望することが成就する。そうしてその人は速やかに最高のやすらぎ、覆いの解きほぐされた(解脱の)状態におもむく。
19)世にあって、情欲を離れ、諸の欲望を超えているのは、楽しい。「おれがいるのだ」という慢心をおさえよ。これこそ最上の安楽である。
25)諸の聖者に会うのは楽しい。かれらと共に住むのも、つねに楽しい。愚かな者どもに会わないならば、心はつねに楽しいであろう。
26)愚人とともに歩む人は長い道のりにわたって憂いがある。愚人と共に住むのは、つらいことである。――まるで仇敵とともに住むように。心ある人々と共に住むのは楽しい。――親族と共に住むように。
32)重い荷物を捨てたあとには、荷物をさらに引き受けるな。荷物を引き受けることは最上の苦しみである。荷物を投げすてることは楽しい。
38)この世で教えをよく説き、多く学んで、何物ももたない人は、楽しい。見よ!人々は人々に対して心が縛られ、何物かをもっているために(かえって)悩んでいるのを。
42)他人に従属することはすべて苦しみである。自分が思うがままになし得る主であることはすべて楽しみである。他人と共通のものがあれば、悩まされる。束縛は超え難いものだからである。
43)貪る人々のあいだにあって、われらは貪らないでいとも楽しく生きて行こう。貪っている人々のあいだにあって、われらは貪らないで暮そう。
52)立派な人々は、いかなるところにあっても、快楽のゆえにしゃべることが無い。楽しいことに遭っても、苦しいことに遭っても、立派な人々は動ずる色がない。
■第31章 心
1)こころは、捉え難く、軽々とざわめき、欲するがままにおもむく。その心をおさめることは善いことである。心をおさめたならば、安楽をもたらす。
6)汝は、幾多の生涯にわたって、生死の流れをくりかえし経めぐって来た、――家屋の作者(つくりて)をさがしもとめて。あの生涯、この生涯とくりかえすのは、苦しいことである。
7)家屋の作者(つくりて)よ!汝の正体は見られてしまった。汝はもはや家屋を作ることはないであろう。汝の梁(はり)はすべて折れ、家の屋根は壊れてしまった。心は形成作用を離れて、汝はこの世で滅びてしまった。
23)ものごとは心にもとづき、心を主とし、心のように疾く動く。もしも汚れた心で話したり行動したりするならば、苦しみはその人につき従う。車をひく牛の足跡に車輪がついて行くようなものである。
24)ものごとは心にもとづき、心を主とし、心のように疾く動く。もしも清らかな心で話したり行動したりするならば、福楽はその人につき従う。影がそのからだにつき従って離れないようなものである。
32)起つべき時に気力がなく、ことばでは力んだことを言うのに怠りなまけていて、希望もなく、つねに意欲が害われ、怠惰でものうい人は、知慧の道をつねに知らない。
33)心を揺れさせるために現われ出たこれらの粗大な思考および微細な思考を絶えまなく思いつつ、心の乱れた人はつねに走る。
35)この身体は水瓶のように脆いものだと知って、この心を城のように安立させて、明らかな知慧の武器をもって、悪魔と戦え。克ち得たものを守れ。しかもそれに執著するな。
49)心が岩山のように確立していて動揺しないで、心が染まり執著するはずのものから離れ、怒りをさそうものについても怒らず、このように心を修練した人に、どこから苦しみが来るのだろうか?
50)罵らず、害わず、戒律に関してつつしみ、食事に関して(適当な)量を知り、淋しいところにひとり臥し、坐し、心に関することにつとめはげむ。――これが仏の教えである。
58)心を制することは楽しい。汝らは心を守れ。怠るな。心がよく守られているならば、或る生けるものどもは人間のあいだにあって喜ぶ。
59)心を制することは楽しい。汝らは心を守れ。怠るな。心がよく守られているならば、或る生けるものどもは天上にあって喜ぶ。
58)心を制することは楽しい。汝らは心を守れ。怠るな。心がよく守られているならば、或る生けるものどもは、やすらぎ(ニルヴァーナ)に達する。
■第32章 修 行 僧
17)財を蓄積することなく、わがものという思いが存在せず、また(何ものかが)ないからといって憂えることのない人、――かれこそ「修行僧」(托鉢僧)とよばれる。
25)明らかな知慧の無い人には、禅定が無い。禅定を修行しない人には、明らかな知慧が無い。禅定と知慧とがそなわっている人こそ、すでにニルヴァーナの近くにいる。
26)それ故に賢者は禅定と知慧とにつとめはげめ。これは、そのように明らかな知慧ある修行僧の初めのつとめである。
27)満足し、感官に気をくばり、戒律をつつしみ行ない、食事について節度を知り、人々を離れたところで臥し坐し、心について専念する、――この人は〈修行僧〉とよばれる。
33)この世は熱のような苦しみが生じている。個体を構成する(5つの)要素(=五蘊)はアートマンではない、と考える。ひとは「われはこれこれのものである」と考えるそのとおりのものとなる。それと異なったものになることは、あり得ない。
■第33章 バ ラ モ ン
7)螺髪を結っているからバラモンなのではない。氏姓によってバラモンなのではない。生れによってバラモンなのではない、と伝えられている。大きかろうとも小さかろうとも悪をすべて除いた人は、諸の悪を除いたのであるから、〈バラモン〉と呼ばれる。
30)蓮葉(はちすば)の上の露のように、錐の先の芥子のように、諸の欲情に汚されない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
31A)曇りのない月のように、清く、澄み、濁りがなく、諸の欲情に汚れていない人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
37)虚空が泥に汚されることが無く、また月が塵に汚されることが無いように、諸の欲望に汚されることの無い人、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
50)牡牛のごとく雄々しく、気高く、竜・大仙人・勝利者・欲望の無い人・沐浴者・覚った人(ブッダ)、――かれをわれは〈バラモン〉と呼ぶ。
61)(「妄愛」という)母と(「われありという想い」である)父とをほろぼし、国王(「われ」という慢心)と(永久に存在するという見解と滅びて無くなるという見解という)2人の博学なバラモンとを滅ぼし、(主観的機官と客観的対象とあわせて12の領域である)国土と(「喜び貪り」という)従臣とを滅ぼして、バラモンは汚れなくしておもむく。
62)(「妄愛」という)母と(「われありという想い」である)父とをほろぼし、国王(「われ」という慢心)と(永久に存在するという見解と滅びて無くなるという見解という)2人の博学なバラモンとを滅ぼし、第5には(「疑い」という)虎をほろぼして、人は〈浄められた〉と言われる。
(2012年10月28日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『臨済録』入矢義高注 岩波文庫
上 堂
■僧「仏法のぎりぎり肝要の処をお伺いします。師はすかさず一喝を浴びせた。僧は礼拝した。師「この坊さん、結構わしの相手になれるわい。」
僧「師は一体だれの宗旨を受け、また、だれの法を継がれましたか。」師「わしは黄檗禅師の処で、3度質問して3度打たれた。」僧はここでもたついた。すかさず師は一喝し、追い打ちの1棒をくらわして言った、「虚空に釘を打つような真似はするな。」
示 衆(じしゅう)
■「諸君、三界(凡夫の迷いの世界)は安きことなく、火事に会った家のようなところだ。ここは君たちが久しく留まるところではない。死という殺人鬼は、一刻の絶え間もなく貴賤老若を選ばず、その生命を奪いつつあるのだ。君たちが祖仏と同じでありたいならば、決して外に向けて求めてはならぬ。君たちの〔本来の〕心に具わった清浄の光が、君たち自身の法身仏なのだ。君たちの〔本来の〕心に具わった、思慮分別を超えた光が、君たち自身の法身仏なのだ。また、君たちの〔本来の〕心に具わった、差別を超えた光が、君たち自身の法身仏なのだ。この三種の仏身とは、今わしの面前で説法を聴いている君たちそのものなのだ。外に探し求めないからこそ、このような〔すばらしい〕はたらきを具えているわけだ。経論の専門化は、この仏の三身を仏法の究極としている。しかし、わしの見地からすれば、そうではない。この三身は仮の名前であり、また三種の借り物なのである。古人も、『仏身の区別は仏法の教理によって立てたもの、また仏の国土はその理体によって設定したものだ』と言っている。法性の仏身とか、法性の仏国土と言っても、それは明らかにちらつきなのだ。諸君、君たちはそれをちらつかせている当体を見て取らねばならない。それこそが諸仏の出どころであり、あらゆる修行者の終着点なのだ。君たちの生ま身の肉体は説法も聴法もできない。君たちの五臓六腑は説法も聴法もできない。では、いったい何が説法聴法できるのか。今わしの面前にはっきりと在り、肉身の形体なしに独自の輝きを発している君たちそのもの、それこそが説法聴法できるのだ。こう見て取ったならば、君たちは祖仏と同じで、朝から晩までとぎれることなく、見るものすべてがピタリと決まる。ただ想念が起ると知慧は遠ざかり、思念が変移すれば本体は様がわりするから、迷いの世界に輪廻して、さまざまの苦を受けることになる。しかし、わしの見地に立ったなら、〔このままで〕極まりなく深遠、どこででもスパリと解脱だ。」(38~39頁)
■三、師は皆に説いて言った、「諸君、正しい見地をつかんで天下をのし歩き、そこいらの狐つき禅坊主どもに惑わされぬことが絶対肝要だ。なにごともしない人こそが高貴の人だ。絶対に計らいをしてはならぬ。ただあるがままであればよい。君たちは、わき道の方へ探して行って手助けを得ようとする。大まちがいだ。君たちは仏を求めようとするが、仏とはただの名前である。君たちはいったいその求め廻っている当人〔が誰であるか〕を知っているか。三世十方の仏や祖師が世に出られたのも、やはり法を求めんがためであった。今の修行者諸君も、やはり法を求めんがためだ。法を得たら、それで終りだ。得られねば、今まで通り五道の輪廻を繰り返す。いったい法とは何か。法とは心である。心は形なくして十方世界を貫き、目の前に生き生きとはたらいている。ところが人びとはこのことを信じ切れぬため、〔菩提だの涅槃だのという〕文句を目当てにして、言葉の中に仏法を推し量ろうとする。天と地の取りちがえだ。」(47~48頁)
■いやしくも出家ととあれば、ふだんのままな正しい見地をものにして、仏を見分け魔を見分け、真を見分け偽を見分け、凡を見分け聖を見分けねばならぬ。こうした力があってこそ、真の出家と言える。魔と仏との見分けもつかぬようなら、それこそ一つの家を出てまた別の家に入ったも同然で、そんなのを〈地獄の業を造る衆生〉というのだ。とても真の出家者とは呼べぬ。たとえばここに仏と魔が一体不分の姿で出てきて、水と乳とが混ぜ合わさったようだとする。そのとき鵝王は乳だけ飲む。しかし眼力を具えた修行者なら、魔と仏とをひとまとめに片付ける。君たちがもし聖を愛し凡を憎むようなことなら、生死の苦界に浮き沈みすることになろう。(53頁)
■五、問い、「仏と魔とはどんなものですか。」
師は言った、「お前に一念の疑いが起れば、それが魔である。もしお前が一切のものは生起することなく、心も幻のように空であり、この世界には魔ひとかけらのものもなく、どこもかしこも清浄であると悟ったなら、それが仏である。ところで仏と魔とは、純と不純の相対関係に過ぎぬ。わしの見地からすれば、仏もなければ衆生もなく、古人もなければ今人ももない。得たものはもともと得ていたのであり、時を重ねての所得ではない。もはや修得の要も証明の要もない。得たということもなく、失うということもない。いかなる時においても、わしにはこれ以外の法はない。たとい、なにかこれに勝る法があるとしても、そんなものは夢か幻のようなものだと断言する。わしの説くところは以上に尽きる。諸君、現に今わしの面前で独自の輝きを発しつつはっきりと〔説法を〕聴いているもの、その君たちこそが、あらゆる場に臨んで滞(とどこお)らず、十方世界を貫いて三界に自由なのだ。一切の個別の世界に入りつつ、少しの影響も受けぬ。一刹那の間に、あらゆる世界に入り、仏に逢えば仏に説き、祖師に逢えば祖師に説き、羅漢に逢えば羅漢に説き、餓鬼に逢えば餓鬼に説き、あらゆる場所で、さまざまの世界に遊行して、衆生を教化(きょうげ)しながら、当初の一念を離れない。いたるところが清らかであり、光明は十方にあまねく、一切のものは一つとなる。(56~57頁)
■六、問い、「正しい見地とはどういうものですか。」
師は言った、「君たちはそのままでともかく凡俗の世界にも入り、高貴の世界にも入り、不浄界にも入り、浄界にも入り、諸仏の国土にも入り、弥勒の殿堂にも入り、毘盧遮那法界にも入るなど、至るところにそれぞれの国土を現じて、成住壊空することだ。釈尊は世に出られ、大法輪を転じて、そのあと涅槃に入られたが、そこには出入去来の姿はなく、生まれたの死んだのという沙汰は全くない。そのままに無生滅の世界に入り、種々の国土に遊行し、蓮華蔵世界に入って、すべてのものは仮の姿で、実体はないのだと見究めた。ほかでもない〔今そこで〕この説法を聴いている無依独立の君たち道人こそが諸仏の母なのだ。だから、仏はその無依から生まれる。もしもこの無依に達したならば、仏そのものも無存在なのである。こう会得したならば、それが正しい見地というものである。(60頁)
■八、師は皆に説いて言った、「今、仏道を学ぼうとする人たちは、ともかく自らを信じなくてはならぬ。決して自己の外に求めるな。そんなことをしても、あのくだらぬ型に乗っかるだけで、邪正を見分けることは全然できぬ。祖師がどうの、仏がどうのというのは、すべて経典の文句の上だけのことだ。もし人が一句もち出して、明暗の両様をあやつって見せたりすると、とたんに君たちはもたついて、ばたばたとうろたえ、わき道の方へ尋ねまわって、ひどいあわてようだ。いっぱしの男子たるものが、やたら政治むきのことをあげつらったり、世間の是非善悪を論じたり、女や金の話しなど、むだ話しなど、むだ話ばかりして日を過してはならぬ。
わしのところでは、出家であろうと在家であろうと、どんな修行者が現れても、一目でその内実を見抜いてしまう。たとえ彼がどんな境界から出できても、彼が持ちだすお題目はすべて夢か幻にすぎない。逆に境を使いこなす者こそが三世諸仏の奥義を体した人である。仏の境界は自ら私は仏の境界ですなどとは言い得ない。この無依の道人こそが境をあやつって立ちあらわれるのだ。もしたれかがわしに仏を求めたならば、わしは清浄の境として現れる。もし菩薩を求めたならば、わしは慈悲の境として現れる。もし菩提を求めたならば、わしは清浄微妙の境として現れる。もし涅槃を求めたならば、わしは寂静の境として現れる。その境は千差万別であるが、こちらは同一人だ。それだからこそ『相手に応じて形を現すこと、あたかも水に映る月のごとし』というわけだ。(69~70頁)
■師子一吼(いっく)すれば、野干脳裂(やかんのうれつ)す。(78頁)
注1)ジャッカルに似た狼。それが獅子の一吼えで脳が割れるという話は『五文律』三に見える。
■平常心(びようじようしん)是れ道(どう)(80頁)
■一〇、問い、「その心と心とが異らぬところとはどういうところですか。」
師は言った、「君がそれを問おうとしたとたんに、もう異ってしまい、根本とその現れとが分裂してしまった。諸君、勘ちがいしてはいけない。世間のものも超世間のものも、すべて実体はなく、また生起するはずのものでもない。ただ仮の名があるだけだ。しかもその仮の名も空である。ところで君たちはひたすらその無意味な空名を実在と思いこむ。大間違いだ。たといそんなものがあっても、すべて相手次第で変わる境に過ぎない。それ、菩提という境、涅槃という境、解脱という境、三身という境、境智という境、菩薩という境、仏という境があるが、君たちはこういう相手次第の変幻世界に何を求めようというのか。そればかりではない、一切の仏典はすべて不浄を拭う反古紙だ。仏とはわれわれと同じ空蝉(うつせみ)であり、祖師とは年老いた僧侶にすぎない。君たちこそはちゃんと母から生まれた男ではないのか。君たちがもし仏を求めたら、仏という魔のとりこになり、もし祖を求めたら、祖という魔に縛られる。君たちが何か求めるものがあれば苦しみになるばかりだ。あるがままに何もしないでいるのが最もよい。(84~85頁)
■頭を丸めただけの坊主のなかには、修行者に向って、仏陀は完成の極致である。三大阿僧祇劫という長い長い間、修行し徳を積んで、始めて成道されたのだと言う連中がいる。諸君、もし仏陀がそんな極致の人だというのなら、ではどうして〔たったの〕80年でクシナガラ城の沙羅双樹の間で横になって死んだのだ。仏は今どこにいるのか。明らかにわれわれの生死と違ってはいないのだ。
君たちは、32相・80種好の瑞相を持つ者が仏であると言うが、それなら同じくそれらの相をそなえている転輪聖王は如来なのか。これで分かる、仏は空蝉の身であることが。だから古人も言った、『如来の全身にそなわる瑞相は、人びとの思い入れに応えようとしてのもの。人びとが断見を起こさぬようにと、方便のために付けた空な名。仮に32相と呼び、80種好と言うのもただの空名。釈尊の肉身は仏ではない、姿かたちなきものこそ真の姿』と。(86~87頁)
■諸君、出家者はともかく修行が肝要である。わしなども当初は戒律の研究をし、また経論を勉強したが、後に、これらは世間の病気を治す薬か、看板の文句みたいなものだと知ったので、そこでいっぺんにその勉強を打ち切って、道を求め禅に参じた。その後、大善知識に逢って、始めて真正の悟りを
得、かくて天下の和尚たちの悟りの邪正を見分け得るようになった。これは母から生まれたままで会得したのではない。体究錬磨を重ねた末に、はたと悟ったのだ。
諸君、まともな見地を得ようと思うならば、人に惑わされてはならぬ。内においても外においても、逢ったものはすぐ殺せ。仏に逢えば仏を殺し、祖師に逢えば祖師を殺し、羅漢に逢ったら羅漢を殺し、父母に逢ったら父母を殺し、親類に逢ったら親類を殺し、そうして始めて解脱することができ、なにものにも束縛されず、自在に突き抜けた行き方ができるのだ。(97頁)
■諸君、ほかならぬ君自身が現にいま見たり聞いたりしているはたらきが、そのまま祖仏なのだ。それを信じきれぬために、外に向って求めまわる。勘ちがいしてはならぬ。外に法はなく、内にも見付からぬ。しかし、こう言うわしのその言葉に飛びつくよりは、先ず何よりも、静かに安らいで、のほほんとしていることが一番だ。すでに起こった念慮は継続させぬこと、また起こらぬ念慮は起こさせぬことだ。そういけたら、君らが十年も行脚修行するよりもずっとましなのだ。(100~101頁)
■諸君、わしの仏法はきちんと受け伝えて来たもので、麻谷和尚・丹霞和尚・道一和尚・盧山和尚・石鞏和尚いらい、同じ道を天下に行じてきたのだ。しかしその道をたれも信ずるものはなく、一斉に誹謗したものだ。例えば道一和尚の宗風は純一そのもので雜りけがなく、修行者は4、5百人もいたが、たれもその真意を見ることができなかった。また盧山和尚は転変自在なまともさ、順逆縦横のはたらきに、修行者はその世界を測ることができず、みな茫然とさせられた。丹霞和尚の如きは、掌に珠を翫(もてあそ)んで隠したり顕したりして、やって来る修行者はみな頭から罵られた。また麻谷和尚の宗風は黄蘖(きはだ)のように苦み走っていて、たれも近寄れなかった。また石鞏和尚のやり方は、弓につがえた矢で修行者を試みたので、来る者はみな恐れた。(117頁)
■仰山「それ、楞厳の法会で阿難が仏を讃嘆して、『この深心を無数の国土に捧げまつる、これぞ真実に仏恩に報謝するもの』と言っております。これこそ真に師の報恩に報いるものではありますまいか。」潙山「いかにもそうだ。弟子の見識が師と同等では、師の徳を半減することになる。見識が師以上であってこそ、法を伝授される資格がある。」(199頁)
解 説
■その毒舌の切っ先が向けられるのは、自らを信じ切れぬ(「自信不及」な)修行者達の、自らの外に仏を求め法を求めようとする在り方であった。ほんものの修行者(真正の道人)はそんなことはせぬ。仏はこちらがわに奪い取って己れに主体化するのだ。なにものにも依存せぬその「無依(むえ)の道人」こそが仏法を創出するのだ。この人こそは「諸仏の母」にほかならぬ。その「この人」とは、実はお前たちそのものなのだと知れ。こう臨済は叱咤する。
臨済は「お前たちは無依(むえ)の道人であるはずだ」という言い方は絶対しない。一貫して「まさにお前達こそがそのままで無依の道人なのだ」と直示しつづける。(220~221頁)
■「仏もなく、法もない」となれば、では求道者はどうすればよいのか。外にも求めるな、内にも求めるな。「「平常(びょうじょう)無事」でよいであればよい。「ほかでもない〔今そこで〕この説法を聴いている無依(むえ)独立の君たち道人こそが諸仏の母なのである。だから、仏はその無依から生まれる。もしこの無依に達したならば、仏そのものも無存在なのである。こう会得したならば、それが〔平常の〕正しい見地というものである」(60頁)
なんという恐ろしい言葉であろう。自らがもともと無依の道人であることを信じ得るには一体どうすればよいのか、それは説かれていない。信じ得るか否かは、本人の意志と力量にかかわることだからである。(223頁)
■唐代の禅では、8世紀ごろから「自己」という用語が愛用され始める。それは、一者・絶対者としての仏と対決する気概を籠めた言葉であり、聖なるものへの反措定であった。臨済の師であった黄檗は、「三千世界(全宇宙)はすべて汝という自己にほかならぬ」と教えたし、また「学人(わたくし)の自己とは一体なんでしょうか」という一見奇妙な問い方が、9世紀になると定型化するに至った。「自己本来の面目」「自己本来の主人公」もそうである。さらには「超仏越祖」(仏祖をも越え出たところ)とか、「仏向上事」(仏の上へ踏み出た世界)という新用語が、臨済の時代には特に南方で流行した。つまり一種の超越志向の氾濫である。臨済の有名な「仏を殺し祖を殺す」という発言も、一見この志向につながるかと見える。しかし彼には、上述のようなギラリとした「自己」(Self)の措定は全くない。せいぜいのところ、「一箇の父母」とか、「自家屋裏」(自分の家のなか)という、おとなしやかな言い方だけである。おそらく彼は黄檗の師だった百丈(749-814)の次の戒めを知っていたに違いない、
本来、自知自覚の是れ自己仏なることを認めず。(私はもともと、自らの認識のはたらきは自己という仏のそれであるとは認めない)
如今の鑑覚は是れ自己仏なりと説くは、是れ初善なるのみ。(「現在の我が認識のはたらきは自己という仏のそれなのだ」という言い方は、初歩のテーゼに過ぎぬ)
百丈が否定するそのテーゼは、実は彼の師の馬祖のかつての教えそのものなのであるが、この教えが実は求道者を「解脱の深坑」に誘いこみかねないものであることを百丈を強く自戒している。臨済も、このような短絡した「自己」信仰が自らを陥れる穽に転化しかねないことを心得ていたに違いない。彼はやはり「脚(あし)は実地を踏む」――大地にしっかりと足を下ろす――ことを忘れない人だったのである。(225~226頁)
(2012年11月12日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『山猫』トマージ・ランペドゥーサ作 岩波文庫
■「ですが公爵、どうしてお受けなれないのでしょうか」
「まあそう慌てないでください、シュヴァレイ殿。いま御説明いたしましょう。われわれシチリア人はじつに長い間、われわれとは別な宗教をもち、われわれの言葉を話さない統治者のもとにあって、むやみに細かいことを穿鑿する癖がついてしまいました。そうでもしなかったら、ビザンチン政府(東ローマ帝国)の収税吏、ベルベル人(アラブ)の首長、スペインの副王らの魔手を逃れることはできなかったのです。こうして習いは性となり、現在のわれわれがつくられました。私は〈同意〉とは言いましたが、〈参加〉とは言いませんでした。この6カ月の間、皆さまのガリバルディがマルサーラに上陸して以来、あまりにも多くのことが、われわれにはいっさい相談もなく行なわれました。いまさら古い指導階層の人間に対し、そうしたことをさらに発展させ、完成させるために手を藉(か)して欲しいと頼んだところで、所詮それは無理というものです。私はいまここで、すでに行なわれたことが悪かったのか、よかったのかという議論をするつもりはありません。私の立場からは、かなり多くのことが悪い方策だったと思っております。しかし急いでつけ加えたいのですが、1年もこの地でお暮らしになれば、貴下御自身がおのずとそのことを御納得になりましょう。われわれシチリア人がけっして許容することのできない過失、それは端的にいって〈何かをする〉ということなのです。われわれはすでに齢をとっております、シュヴァレイ殿。非常な高齢なのです。少なくとも2千5百年の間私どもは、種々雑多、さまざまな輝かしい文明の重荷に耐えてまいりました。すべて外来の文明ですが、やってきたときにはすでに完成品でした。どれ1つとして、この地で芽生えたものはありません。どれに対しても、われわれ自身がその普及の先頭に立つ、ということもいたしませんでした。貴下や、そして英国の女王もそうであるように、私どもも白色人種です。しかし2千年前から、ここは植民地なのです。それもほとんど私たち自身のせいですよ。どのみち私どもは疲れ果て、完全に気力を削がれてしまいました」(258~259頁)
■「意図されるところは結構ですが、シュヴァレイ殿、しかしもう遅すぎます。それにいまも申しあげたとおり、このあやまちの責任は、大部分われわれ自身にあります。貴下は先ほど、驚異に満ちた近代世界を目指している若いシチリアというような形容をなされましたが、私に言わせれば、この土地はむしろ、手押し車に乗せられて、ロンドンの世界大博覧会の見物にやってきた、百歳の老婆のようなものです。なにがなにやら訳がわからず、シェフィールドの製鋼所にも、マンチェスターの紡績工場にも少しも心動かされず、ベッドの下におまるを置き、枕に涎をたらしながら、ただひたすら願うのは、少しでも居眠りを楽しむことでしかないのです」
それは穏やかな話し方だったが、その手は、サン・ピエトロ寺院の模型をしっかりと握っていた。翌朝、その丸屋根の頂上を飾っていた小さな十字架が、こなごなになっているのが見つかった。「眠りなんです、親愛なるシュヴァレイ殿。眠りこそ、シチリア人が望んでいるものなのです。そして彼らは、自分たちの眼を覚まそうとやってくる連中を憎むことになりましょう。たとえ最高の贈り物を携えてやってこようとも。それにここだけの話ですが、新王国イタリアがわれわれのために沢山の贈り物を用意しているとは、とうてい思えません。シチリア的特徴を備えた出来事や現象はすべて、夢の実現なのです。もっとも狂暴なものでさえも。いうところの色好みは忘却への願い、鉄砲をぶっぱなし、ナイフを振りまわすのは死の願望、じっと動かずに官能の歓びを味わおうとするのも、これまた死を願う気持です。その具体的な現れが、われわれの怠惰であり、バラモンジンやシナモン入りのシャーベットなのです。そうしてわれわれ特有の瞑想的表情なるものは、涅槃(ニルヴァーナ)の謎を探ろうとする虚無が示す表情なのです。こうしたところから、ある種の人間、つまりは半睡半醒の輩が振う狂暴な権力が発生し、シチリアの芸術的そして知的現象に、広く知られた、1世紀の時間の遅れが生じました。新しいものは、すでに生を終えたとき、もはや新たな生命(いのち)の流れをつくり出すことはできないと感じたとき、はじめてわれわれを魅了するのです。だからこそこの現代にあっても、神話がつくり出されるという、信じがたいような現象が生じることになります。本当に古いものでしたら、当然尊崇に値するはずですが、じつのところそれは、まさに死に絶えているが故に私どもを惹きつける過去、そうした過去への退行をそそのかす、不吉な誘惑にほかなりません」(260~261頁)
■「われわれも例外がないほど、数が少ないわけではありません。それに私は先ほど、半分だけ目覚めた人間という言い方をしました。その若いクリスピのことを申しあげたわけではありません。おそらく貴下も歳を重ねられて、われわれ同様甘美な夢想に耽るようなことになれば、経験なさることなのです。その点は誰も同じです。どうやら私の説明の仕方がまずかったようです。私はシチリア人と言いましたが、シチリアという土地柄、その自然環境、気候、風景をつけ加えるべきでした。こうしたものの総体こそ、この地の精神を形成するにあたって、おそらく外国勢力による支配や、でたらめな暴力行為以上に大きな影響力を振ったのです。これは、締まりのない色好みと、呪われた厳しさの、その中間の道を知らない風景です。したがって、理性的な人間が住む土地に相応しいような、みみっちさや月並さは微塵もなく、ゆるやかでも人間的でもけっしてありません。ほんの数マイル離れた場所に、ランダッツォの地獄と、タオルミーナの美しい入江という、両者ともに並外れた、危険な両極が共存する土地なのです。この気候は6ケ月もの間、40度という灼熱をもたらします。数えてみてください、シュヴァレイ殿。5月、6月、7月、8月、9月、10月という、30日の6倍もの間、頭上から垂直に直射日光を浴びせられるのですから。これこそがロシアの冬に匹敵する、長くて憂鬱なシチリアの夏というものの正体なのです。逆らってみたところで、そのロシアほどの成功すら覚束ないでしょう。貴下はまだ御承知ではないが、われらが土地にあっては、聖書の呪われた都市のように、頭から火が降ってくるのです。この6ケ付のどの月にあっても、シチリア人はもし真面目に働いたならば、通常は3ケ月間はもつはずのエネルギーを、ほんの1ケ月間で使い果すということになります。そして水はつねに欠乏していて、ときにずっと遠くのほうから運んでくる必要のある場合には、その1滴の水の運搬のために、i滴の汗を流すという有様です。そのあと雨がやってきても、決まってそれは豪雨で、いつもは乾ききっている水路に、突如猛り狂ったような急流が逆巻き、なんと1週間前までは乾きのために喘いでいた、動物や人間どもを溺死させてしまうのです。この風景の暴力、気候の酷さ、人や事物の絶えず緊張した表情、さらには壮麗な、とはいえわれわれ自身が建設したものではないために不可解で、このうえもなく美しい沈黙した亡霊ののように、われわれを取り巻いている過去の記念建造物。そしてどこからともなくやってきて島に上陸した武装した支配者たち、直ちに土着民を服従させることはできても、たちまち疎まれ、憎まれて、けっして理解されることはなく、われわれには謎そのもののような芸術作品だけで自己表現を行い、どこか別な場所の費用に当てるために、抜かりなく税金を取りたててきたそれら代々の政府、こうしたものすべてが、われわれの性格を形づくったのです。こうしてこの性格は、おぞましいほどのこの地の精神の狭隘(きょうあい)さ以上に、こうした外的な宿命によって左右されているのです」(262~264頁)
■「貴下は貴族階級の人間でいらっしゃる、シュヴァレイ殿。そういう貴下とお知り合いになれたのは幸運でした。おっしゃることはすべて正しい。ただ、シチリア人は自分たちの向上を願うだろうと言われたが、そのことだけは間違っています。私の経験をお話ししましょう。ガルバルディがパレルモの街へ入る2、3日前のこと、事件の真相を知ろうと、港に停泊中の軍艦に乗ってやってきた、数人のイギリス海軍の将校に紹介されました。たまたま連中は、屋根の上のテラスから、街を取り囲む山並が一望でき、しかも海が眼の前に見える海浜地区に私が家を構えている、という情報を手に入れたのです。そうしてわが家への訪問と、ガルバルディ軍がうろついているという噂の場所を展望したい、という申し出を受けました。船の上からでは状況がはっきり掴めないというのです。拙宅にやってきた彼らを伴ってテラスに登りました。赤味がかった頬ひげをたくわえながらも、まだ純情で元気のいい若者たちでした。彼らは見事な風景と光の強烈さに陶然としていました。しかし近くの街路の荒廃と老朽化と、すざまじい汚れを目のあたりにしたときは、身がすくんでしまったと、打ち明けてくれました。私は貴下に対してしたような、1つの出来事はもう1つ別な出来事から生じたというような説明はしませんでした。そのあと1人が、あの志願兵たちはなにしにきたのかと質問したので、答えました。「彼らはわれわれに礼儀作法を教えにやってきたのです。しかし成功は覚束ないでしょう。なぜならわれわれは神だからです」。なんのことやら彼らにはわからなかったと思います。連中は笑って立ち去りました。シュヴァレイ殿、貴下にも私はこうお答えします。シチリア人は、自分が完璧だと信じこんでいるという、このたった1つのことのために、自分を向上させようなどとは絶対に思わないでしょう。彼らの自惚れは、その悲惨な現実よりもはるかに強い。外国勢力の侵入は、基本的に、完璧さ獲得の妄想を覆し、虚無への心浮き立つ期待を妨害する危險性をもっています。シチリア人の場合,精神の独立性からいってもなおさらです。10いくつにも及ぶ、異なる人間たちに踏みつけにされながらも、自分たちこそそこの栄光ある歴史の担い手であって、その盛大な葬儀を営む資格を与えられている、と信じこんでいるのです。シュヴァレイ殿、貴下御自身が、始てシチリア人を、世界史の流れへと導くことを夢見た人間だと、本当に思いこんでいらっしゃるのですか?いったい何人の人が、貴下と同じような、美しくも儚(はかな)い夢想を胸に抱いたことでしょう?イスラムの宗教指導者、ルッジェーロ王配下の騎士、アンジュー家のシャルルの配下、シュタウフェン朝の書記、さらにはスペインの副王カルロス3世の革新官僚、いったい彼らは、どんな人間だったのでしょうか。そうした人々の切なる願いにも拘らず、シチリアは眠りを望んだのです。もしもシチリアが豊かで、思慮深く正直で、誰からも称えられ、羨まれ、一言でいえば、完璧そのものだとしたら、どうしてそんな連中の言葉に耳を傾けなければならないのでしょうか?」(268~270頁)
■「いまではわれわれの土地でも、ブルードンや名前は忘れましたが、さるユダヤ系ドイツ人が書いたことに敬意を払い、ここでも別なところでも、物事の悪しき状態の責任は、封建制にあるという議論がなされています。いうなれば、この私に責任があるわけです。そうかもしれません。しかし封建制はどこにもあったし、外国の侵略とて同様なのです。シュヴァレイ殿、私には、あなたの御先祖や、イギリスの地主、あるいはフランスの領主たちが、サリーナ家の先祖以上に巧妙な統治行ったとは思えません。それでいて違っています。その違いの理由は、どのシチリア人の眼からも光を放っている、優越感の意味にあります。私たちはそれを自尊心と呼んでいますが、実際はものが見えないだけの話です。いまのところ、いやさらにこれからも長い期間にわたって、なすすべはありません。嘆かわしいとは思いますが、政治という方法では、私は指一本動かすこともできないのです。これは、シチリア人に聞かせられるような話ではありません。私だってもし聞かされたら、気を悪くすることでありましょう」(270~271頁)
■「だけんどあっしらは、下剤のセンナにしろ、朝鮮アサガオにしろ、神様がお創りになられたこうした大切な草を、この自分の手で摘みに山へ出かけておるわけでやす。昼も夜も、雨だろうと晴れていようとも、前もってお上がお決めなすったとおりにしておりやす。その草を、誰のものでもねえ、みんなのものであるお日様に当てて乾かしてから、祖父(じい)さんが残してくれた乳鉢に入れて粉にいたしやす。それがお偉い皆さん方とどんな関係があるでござんしょう?なぜ20リラもはらわなけりゃならんのですかい?お手前どもの顔を立てるためでやすかい?」〔ドン・ピエトリーノがピッローネ神父に対して言った言葉〕(281~282頁)
■「いいかね、ドン・ピエトリーノ。あんたの言う旦那方(シニョーリ)というのは、ひどくわかりにくい人たちだ。神様が直接その手でお創りになったというのとは違う、あの人たち自身が何百年もの間、苦しみと喜びの、独特の経験を重ねたあげくにつくり出した、特別な世界に生きておいでなのだ。彼らはとっても頑丈な、集団の記憶をもっていて、そのために、あんたや私だったら取るに足らない、だけどあの人たちにとってはごく大切ななにかのことで、あたふたしたり、喜んだりする。なぜならそれが、あの人たち階級の記憶、希望、そして不安という共通の財産と関係があるからなんだよ。神の御意志のお蔭で私は、究極的勝利が約束された、不滅の生をもつ教会の中の、もっとも栄光ある教団のごくささやかな分子になったのです。あんたは階段の別な端に立っておいでだ。といっていちばん低いということではない。いちばん特殊な場所にいらっしゃる。あんたがオレガノの元気のある株や斑猫(はんみょう)がいっぱいいる巣(それも探しておいでだってことは知っていたんですよ)を見つけたときは、人間が自由に選択できるように神様が善悪の区別をつけないでお創りになった自然と、直接かかわることになる。ところが邪(よこしま)なことを考えている老婆や、物欲しげな娘どもから相談を受けたときには、ゴルゴダ(キリスト処刑の丘)に光明がともされるまでの、何百年もの暗黒の時代の奈落に落ちこむことになるんですよ」〔ピッローネ神父がドン・ピエトリーノに対して言った言葉〕(284~285頁)
■ピッローネ神父は考えた。数学も神学も知らない人にとっては、世界は大きな謎でしかあるまい。〈主よ、全知全能の主なればこそ、かかる難問を思いつくことがおできになるのです〉(293頁)
■ドン・ファブリーツィオは、その感じとはもうずっと前からなじみになっていた。すでに10年ほどにもなろうか、生命という名の流体、生存の能力、つまりは生そのものが、そしておそらくは生き続けようとする意志もまた、自分からゆっくりと、絶えず流れ出していくことを感じていた。それはまるで砂粒が、1粒また1粒と、砂時計の狭い口目指して急ぐでもなく休むでもなく、押し寄せては滑り落ちる感じに似ていた。精力的に活動したり、注意力を傾けたりしているときは、この絶えることなき喪失感は消えていたが、ほんのわずかでも静寂や内省の刻(とき)が訪れると、平然たる態度でふたたび姿を現すのだった。ちょうどいつも鳴っている耳鳴りや振り子の音のように、あたりが静まりかえっているときに、決まってその存在を明らかにし、そうすることによって、こちらが聞いていないときでも、いつもそこで見張っていることをあらためて確信させるのだった。
そのほかどんなときでも、そっと滑り落ち、自分の生命から逃げ出していく砂粒の、つまりは永久に戻ってくることのない刻々の時間の物音を感じとるためには、ほんのちょっとの間注意を向けるだけで、いつも充分だった。そのうえこの感覚は、最初から少しも不快な感じを伴ってはいなかった。この生命力の、気づかないほどの些細な観察ばかりか、自分の内なる広大な深遠の探索にも慣れ親しんだ彼にとって、それは少しも嫌なことではなかった。それは、人格が絶えず、ごく僅かずつ解体するという感じであって、いまほど自覚的ではないものの、もっと囚われない個性(神のお慈悲による、グラーツィエ・ア・ディオ)が、どこか別の場所に再生される、という漠とした予感と結びついていた。その砂粒はなくなってしまうのではなく、一時姿を消すだけ、そう、いずことも知れぬ場所に溜まって、もっと耐久性のある建物として固まることになる。建物というのはしかし、と彼はじっくり考えてみた。重量がある以上正確な言い方ではない、それに砂粒も適切ではない。というよりもっと、狭い沼地から立ち昇る水蒸気の小さな粒のようなものだろう。それが大空へと昇っていって、軽やかで自由闊達な巨大な雲になるのだ。生命を貯蔵したタンクが、長年続いた流出のあとでも、なおなにがしかの中身を残していることに、彼はしばしば驚いた。〈ピラミッドほどの大きさもないというのに〉。同時にそうした場合には何回となく、この生命の流出に気づいているのは、おそらく自分独りだけで、どうやらまわりの誰もそれを感じてはいないらしいことを見てとって、誇らしいような気持を抱いた。そして自分のまわりを唸りをあげて飛ぶ弾丸を、無害な蒼蝿と錯覚している新兵を軽蔑する古参兵のように、そこに他人軽視の理由を見つけだした。こうしたことは、なぜか自分から口にすることではなく、他人が感づくままにしておくものであるが、周囲の誰もが少しもそれに気づいていなかった。裁判所、料理人、修道院、そして時計屋その他すべてのもが存在する、この世とまったく同じ来世を夢見ている娘たちも、糖尿病による壊疽に蝕まれ、この苦しみ多い人生にみじめったらしくしがみついていたステッラも同様であった。おそらくタンクレーディだけが、控え目な皮肉をこめて、「伯父さま、死神(ラ・モルテ)を口説いているんですか」と言った瞬間だけ、そのことに気づいたにすぎなかった。いま、求愛は聞き届けられたのであって、美しい彼女が、はっきりと承諾してくれて、駆け落ちの手筈も決まり、出発の列車のコンパートメントも予約された。
なぜならいまや状況は変わり、まったく別な様相を見せていたのである。ホテル《トリナークリア》(3つの岬、つまり3角形を意味するイタリアの古名。3本足をもつ象徴的な図形も多々ある。)のバルコニーで、安楽椅子に腰を下ろし、ひどく長い両脚を毛布でくるんだ彼は、ライン川の滝の音にも喩えられるような轟音をとどろかせつつ、生命が次々と大きくうねりながら、自分の身から脱け出ていくのを感じていた。7月の終りの、ある月曜日の正午であった。油の表面のように密度が高く、まったくうごきのないパレルモの海が、飼主に威嚇されて身を隠そうとする犬のように這いつくばり、身じろぎもせずに眼前に広がっていた。しかし太陽は、両脚を広げ、仁王立ちになってじっと動かず、容赦することなく彼を鞭打っていた。あたりは完全に静まりかえっている。空高い太陽の光のもと、ドン・ファブリーツィオには、自分の体内から噴出していく生命の音しか聞えなかった。(349~352頁)
(2012年12月3日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――