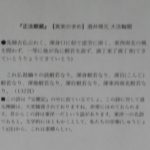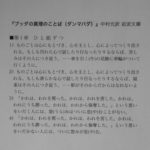読書ノート(2018年)
―――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵(1)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
摩訶般若波羅蜜(まかはんにゃはらみつ)
■〈原文〉
観自在菩薩の行深(じん)般若波羅蜜多時は、渾(うん)身の照見五蘊(うん)皆空なり。五蘊は色・受・行・想・識なり、五枚の般若なり。照見これ般若なり。この宗旨(そうし)の開演現成するにいはく、色即是空なり、空即是色なり。色是色なり、空即空なり。百草なり、万象(ばんぞう)なり。
般若波羅蜜十二枚、これ十二入(にゅう)なり。また十八枚の般若あり、眼(げん)耳鼻舌身意(い)、色声(しょう)香味触(そく)法、および眼耳鼻舌身意識等なり。また四枚の般若あり、苦集(じゅ)滅道なり。また六枚の般若あり、布施・淨戒・安忍・精進・静慮(じょうりょ)・般若なり。また一枚の般若波羅蜜、而今(にこん)現成なり、阿耨(のく)多羅三藐(みゃく)三菩提なり。また般若波羅蜜三枚あり、過去・現在・未来なり。また般若六枚あり、地・水・火・風・空・識なり。また四枚の般若、よのつねにおこなはる行・住・坐・臥なり。
〈現代語訳〉
〔大いなる智慧の成就〕
観自在菩薩が甚深(じんじん)の智慧を修行したもうた時には、全身をあげて五蘊のみな空なることを明らかに観じたもうた。五蘊というは、色(現象)・受(感覚)・想(表象)・行(感情と意志)・識(意識)である。かくて五つの智慧がある。明らかにみることがすなわち智慧である。その主旨とするところを説いたのが、色即是空であり、空即是色である。色とは現象であり、空とは変化し移ろうのである。百草がそうであり、よろずの現象がそうである。
あるいは、智慧の成就に十二の名目がある。六根(六つの感覚)と六境(六つの対象)がそれである。また、十八の智慧がある。眼・耳・鼻・舌・身・意の六根、色・声・香・味・触(そく)・法の六境、および、それぞれの交渉によってなる眼(げん)識・耳(じ)識・鼻識・舌識・身識・意識がそれである。また、四つの智慧がある。苦・集(じゅ)・滅・道の四諦(たい)がそれである。また、六つの智慧がある。布施・持戒・忍辱(にく)・精進・静慮(じょうりょ)・智慧の六波羅蜜がそれである。また、ただ一つの智慧の成就があって、いま現に成就しておる。比すべきものもなき等正覚(がく)がそれである。また、智慧の成立に三つがある。過去・現在・未来がそれである。また、六つの智慧がある。地・水・火・風・空・識がそれである。さらに四つの智慧がある。世の常に行われる行・住・坐・臥がそれである。
〈注解〉
※この一段は、まず、摩訶般若波羅蜜すなわち大いなる智慧の成就について解説するのである。それが『般若心経』の第一段である。
◯観自在菩薩 旧(く)訳においては、観音または観世音と訳し、新訳においては、観自在もしくは観世自在と訳する。もろもろの菩薩のなかでも、もっともよく知られ、ひろく帰依せられている菩薩である。
◯五蘊 人間を構成する物質的・精神的要素を五つのグループにわかって観察するのである。色(現象するもの)と、受(感覚作用)・想(表象作用)・行(意志作用)・識(意識作用)・の四つの精神的要素がそれである。それらの要素のそれぞれを観察して、そこには、いずれも、なんらの変化せざる固定的なもの、本質的なものは存しないことを知るとき、それを「皆空」となすのである。
◯色即是空、空即是色 色すなわちこの世の現象するものは、ことごとく変化し移ろわざるものはない。そのゆえにこれを空なりとなす。それを翻(ひるがえ)していえば、そこにはただ変化する現象的存在が存するのみである。空即是色とはそのことである。
◯般若波羅蜜十二枚 六根すなはち六つの感官(眼・耳・鼻・舌・身・意)と、六境すなわち六つの感官の対象(色・声・香・味・触・法)とが、それぞれ相関わることによって人間の認識作用が成立する。その真相を明らかにすれば、一切の存在とはその他(ほか)の何物でもないことが知られる。そのことを明らかに把握することもまた智慧の成就であるが、それには十二の名目がある。なお、それにつづいて「十二入」とあるのは、それらの相関わりを「渉入」と称するがゆえである。
◯十八枚の般若 前項の十二の項目の相関わりによって成立する六つの種類の認識、すなわち、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識を、さきの十二項に加えて十八項となすのである。
◯四枚の般若 四つの聖諦(しょうたい)、すなわち、苦諦(現状認識の真理)・集諦(じつたい、原因追及の真理)・滅諦(苦竟克服の真理)・道諦(克服実践の真理)をいう。それが仏陀の最初の説法の内容であったことは、人のよく知るところである。
◯六枚の般若 いわゆる六波羅蜜である。布施・持戒・忍辱・精進・静慮・智慧の六つがそれである。そのいずれかを修するもまた、大いなる智慧の成就にいたることができるとするのである。波羅蜜、新訳では波羅蜜多とは、成就・完成・到達・建立等の意のことばである。
◯阿耨多羅三藐三菩提 “anuttara-samyak-sambodhi”の音写であって、意訳すれば、無上等正覚(がく)となる。仏陀の正覚(さとり)の内容をなすものである。最高(阿耨多羅=無上)なる、普遍(三藐=等)にして妥当(三=正)なる智慧(菩提=覚)というほどのことばである。(22~24頁)
■〈注解〉
◯預流果・一来果・不還果・阿羅漢果 総じて四果という。(27頁)
■よって知るべきである。受持し、読誦(しょう)し、理(ことわり)のままに思惟することが、とりもなおさず智慧を守護することである。守護しようと欲するならば、それを受持し、読誦するがよいのである。わが先師・古仏如浄は詠じていった。
「全身を口として虚空にかかり
東西南北の風を問うことなし
ひとしく他のために般若を談ず
ちりん、ちりん、また、ちりん」
それが仏祖正伝の智慧を談ずるものである。身をこぞっての智慧であり、他者をこぞっての智慧であり、自己をこぞっての他者であり、東西南北をこぞってことごとく智慧である。(30~31頁)
■〈注解〉
◯天帝釈 また帝釈天といい、あるいは釈提桓因(しゃくだいかんいん)という。“Sakra devanam Indra”を音写して「釈迦提桓因陀羅(しゃかだいかんいんだら)」となし、それを略して釈提桓因となし、また意訳を加えて帝釈天または天帝釈となす。もとインドの神々のなかの主神インドラであるが、仏教でもそれを仏法守護の神として崇敬するのである。
◯憍尸迦(きょうしか) “Kausuka”の音写である。帝釈天の姓であるという。呼びかけには、その姓を用いるのである。
◯先師古仏 先師とは、すでに亡き師をいうことば。道元にとって先師とは、如浄にほかならない。しかるに、道元は、如浄を語るにあたっては、古仏の称をもってすることを常とした。
◯渾身似口掛虚空…… 如浄の頌(じゅ)であって、題して風鈴(ふうれい)という。結句に「滴丁東了滴丁東」とあるのは、風鈴の風に鳴る音を表示したものと知られる。(31~32頁)
■〈現代語訳〉
〔智慧は仏世尊にことならず〕
釈迦牟尼仏はいった。
「舎利弗よ、もろもろの衆生は、この智慧にたいして、まさに仏のましますがごとくにするがよい。この智慧を供養し、敬礼(きょうらい)し、思惟すること、まさに仏世尊を供養し、敬礼するがごとくにするがよい。その故はなんであるか。この智慧は仏世尊にことならず、仏世尊はこの智慧にことならず、智慧はすなわち仏世尊であるからである。なぜであろうか。舎利弗よ、すべてもろもろの菩薩・独覚・阿羅漢、もしくは、不還果(ふげんか)・一来果・預流果の境涯にあるものなど、みなこの智慧によって出現しうるからである。舎利弗よ、およそこの世間の十善業の実践も、四静(じょう)慮も、四無色定(じょう)も、五神通(じんずう)も、みなこの智慧によって実現されうるからである」
かくて、仏世尊は智慧である。智慧はすなわち諸法である。その諸法のありようは空のすがたである。不生不滅であり、不垢不浄であり、不増不減である。その智慧の実現がそのまま仏世尊である。問いきたり、学びいたるがよい。その智慧を供養し、敬礼することが、そのまま仏世尊にまみえ奉り、つかえ奉ることである。まみえ奉る仏世尊とはそのことである。(33~34頁)
■〈注解〉
◯舎利子 者利弗のことである。舎利弗とは“Sariputra”の音写であるが、その“putra”は子の意であるので、また舎利子となすのである。智慧第一の称あり、仏十大弟子のなかの第一人者である。
◯十善業道 十善業に同じ。また十善戒ともいう。不殺生・不偷盗、乃至不邪見の十善を行ずることである。
◯四静慮 また、四禅定ともいう。初禅より第四禅にいたる禅定の四つの段階をいう。
◯四無色定 また、四空定という。順次に、空無辺処(じょ)・無所有所(むしょうしょ)・非想非々想処にいたる定だるという。
◯五神通 また、五通という。天眼通・天耳通・他心通・宿命(みょう)通・如意通がそれである。(34頁)
現成公案(げんじょうこうあん)
■〈原文〉
諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟あり修行あり、生(しょう)あり死あり、諸仏あり衆生あり。万法(ばんぽう)ともにわれにあらざる時節、まどひなくさとりなく、諸仏なく衆生なく、生なく滅なし。仏道もとより豊倹(ほうけん)より跳出せるゆゑに、生滅あり、迷悟あり、生(しょう)仏あり。しかもかくのごとくなりといへども、華は愛惜(じゃく)にちり、草は棄嫌(きけん)におふるのみなり。
■〈現代語訳〉
〔存在と仏教〕
もろもろのことどもを仏法にあてていうとき、迷悟あり、修行あり、生(しょう)あり死があり、諸仏があり衆生がある。よろずのことどものいまだ我にかかわらぬ時には、迷いもなく悟りもなく、諸仏もなく衆生もなく、生もなく滅もない。だが、仏道はもとより世間の常軌をはるかに超えたものであるから、生滅があり、また衆生・諸仏があっても、なおかつ、花は惜しんでも散りゆき、草は嫌でも繁りはびこるものと知る。
■〈注解〉
◯諸法 法は「ダルマ」(darma)の訳語。それを仏教者は多様の意義をもって用いる。それを大別していえば、一には、存在そのもの、二には、存在の法則、三には、存在の法則にもとづいて説かれた教えの三つの意味がある。いま諸仏というときには、その第一のそれであって、「もろもろの存在」というほどの意である。
◯万法 この法もまた存在そのものであって、一切の存在というほどの意である。
◯豊倹 豊はゆたか、倹はまずしい。貧富・貴賤・智愚など、この世のつねなる規準を指すことばであると知られる。したがって、「豊倹より跳出」するとは、世間の常軌を超えることに他ならぬ。(41~42頁)
■〈原文〉
自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり。迷を大(だい)悟するは諸仏なり、悟に大迷なるは衆生なり。さらに悟上に得悟する漢あり、迷中又迷(うめい)の漢あり。
諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず。しかあれども証仏なり、仏を証しもてゆく。身心を挙(こ)して色を見取し、身心を挙して声(しょう)を聴取するに、したしく会取すれども、かがみに影をやどすがごとくにあらず、水と月とのごとくにあらず。一方を証するときは一方はくらし。
■〈現代語訳〉
〔迷いと悟り〕
自己をおしてよろずのことどもを計らうのは迷いである。よろずのことどもの来って自己を証(あか)しするのが悟りである。迷いを転じて大悟するのが諸仏であり、悟りに執して迷いに迷うのが衆生である。さらにいえば、悟りのうえに悟りをかさねる者があり、迷いのなかにあってまた迷う者もある。
しょぶつがまさしく諸仏となるときには、かならずしも自己は仏であると自覚するの必要はない。それでも仏を証するのである。仏とはこれかと悟りつつゆくのである。身心を傾けて物を見る。あるいは身心をそばだてて声を聞く。それが自分ではよく解るのであるが、鏡に物を映すようにはまいらぬ。水に映る月のようにはゆかない。一方がわかれば他方はわからないのである。
■〈注解〉
◯修証 修はおさめる、証はさとる。修行と証悟である。ただし、修と証の関係については、道元は、いささか世の常の仏教者をぬきん出た卓抜の見解を有し、修のほかに証なしとする。よって修証の二字は、修と証の二事を語っているのではなく、まさに修証一枚の境を指さしているものと知らねばならぬ。
◯色 “rupa”の訳語。もと「形あるもの」の意であって、眼識によってそれと認識することのできる物的存在(色法という)をいうことばである。ただし、それはまた「壊(え)するもの」すなわち「変化するもの」の意があるので、現代の用語をもってするならば、「物質」ではなくて、「物象』または「現象」が適当である。(41~43頁)
■〈原文〉
仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己をわするるといふは、万法(ばんぽう)に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごせき)の休歇(きゅうかつ)なるあり、休歇なる悟迹を長長出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ。
人はじめて法をもとむるとき、はるかに法の辺際を離却(りきゃく)せり。法すでにおのれに正伝するとき、すみやかに本分人なり。
人、舟にのりてゆくに、めをめぐらして岸を見れば、きしのうつるとあやまる、目をしたしく舟につくれば、ふねのすすむをしるがごとく、身心を乱想して万法を弁肯(べんこう)するには、自心自性(しょう)は常住なるかとあやまる。もし行李(あんり)をしたしくして箇裏に帰すれば、万法のわれにあらぬ道理あきらけし。
■〈現代語訳〉
〔仏道をならうというは〕
仏道をならうとは、自己をならうことである。自己をならうとは、自己を忘れることである。自己を忘れるとは、よろずのことどもに教えられることである。よろずのことどもに教えられるとは、自己の身心をも他己の身心をも脱ぎ捨てることである。悟りにいたったならば、そこでしばらく休むもよい。だが、やがてまたそこを大きく脱け出てゆかねばならない。
人がはじめて法を求める頃には、はるかに法のありかを離れている。すでに法がまさしく伝えられた時には、たちまち本来の人となる。
人が舟に乗って行くとき、眼をめぐらして岸をみれば、岸が移りゆくかにみえる。目を親しく舟につければ、はじめて舟の進むのがわかる。それと同じく、わが身心をあれこれと思いめぐらしてよろずのことどもを計らう時には、わが心、わが本性は変わらぬものかと思い誤る。もし仏祖先徳の足跡をつぶさに踏んでそこに到れば、よろずのことの我にあらぬ道理が明らかとなる。
■〈注解〉
◯他己 自己に対することばであるが、また、真の自己というものは、この箇体の身心だけで成っているものではなく、むしろ、他とのさまざまの関わりのなかに成立しているのである。そこには、他における自己ともいうべきものがあろう。かくて、自己の身心の脱落のみならず、また他己の身心なるものの脱落が語られねばならないのである。
◯悟迹 迹(せき)はあと。悟りのあとである。
◯休歇(かつ) 休はやむ、やすむ。歇はやむ。
◯長長出 ぐんと抜け出るというほどの意であろう。
◯本文人 自己の本来の面目に出会える人というほどの意であろう。「弁道話」の巻に、「この法は人々(にんにん)の分上にゆたかにそなはれりといへども、いまだ修せざるにはあらはれず、証せざるにはうることなし」とあるを参照せられたい。
◯弁肯 弁はわきまえる。肯はがえんずる。思弁首肯である。ただし、上に「乱想して」とあるから、「思い誤る」となる。
◯行李 行履である。仏祖たちの踏みきたった跡というほどの意である。道元はよく、おのれの計らいをすてて、ただ仏祖の行履をふむがよいと語っている。(44~46頁)
■〈原文〉
たき木はひとなる、さらにかへりてたき木となるべきにあらず。しかあるを、灰はのち、薪(たきぎ)はさきと見取すべからず。しるべし、薪は薪の法位に住して、さきありのちあり。前後ありといへども、前後際断せり。灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるがごとく、人のしぬるのち、さらに生とならず。
しかあるを、生(しょう)の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり、このゆゑに不生といふ。死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転なり、このゆゑに不滅といふ。
生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。たとへば冬と春とのごとし。冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。
■〈現代語訳〉
〔不生不滅ということ〕
薪(たきぎ)は灰となる。だが、灰はもう一度もとに戻って薪とはなれぬ。それなのに、灰はのち、薪はさきと見るべきではなかろう。知るがよい、薪は薪として先(さき)があり後(あと)がある。前後はあるけれども、その前後は断ち切れている。灰もまた灰としてあり、後があり先がある。だが、かの薪は灰となったのち、もう一度薪とはならない。
それと同じく、人は死せるのち、もう一度生きることはできぬ。だからして、生が死になるといわないのが、仏法のさだまれる習いである。このゆえに不生という.死が生にならないとするのも、仏の説法のさだまれる説き方である。このゆえに不滅という。
生は一時のありようであり、死もまた一時のありようである。たとえば、冬と春とのごとくである。冬が春となるとも思わず、春が夏となるともいわないのである。
■〈注解〉
◯法位 物のありよういうほどの意である。ここの法は存在そのものの意である。「薪の法位」という所以(ゆえん)である。
◯法輪のさだまれる仏転 法輪とは、説法をいう。その法は教法を意味する。仏がその教法を人間界に説き弘めるさまを、車がその輪を転じてゆくに喩えるのである。かくて、「仏転法輪」(仏が法輪を転ずる)の句が成り、それを駆使して「法輪のさだまれる仏転」とはいったのである。仏転法輪のさだまれるところというほどの意である。(46~48頁)
■〈原文〉
人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。月にぬれず、水にやぶれず。ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸の水にやどり、全月も弥天(みてん)も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。さとりの人をやぶらざること、月の水をうがたざるがごとし。人のさとりを眭礙(けいげ)せざること、滴露の天月を眭礙せざるがごとし。ふかきことはたかき分量なるべし。時節の長短は、大水小水を撿(けん)点し、天月の広狹を弁取すべし。
■〈現代語訳〉
〔悟りの風景〕
人が悟りを得るのは、水に月の映るようなものである。月も濡れない、水も割れない.月は広大な光であるが、盆ほどの水にやどり、月天のことごとくが、草の露にもやどり、一滴の水にもやどる。悟りが人をそこなうことなきさまも、月が水を穿(うが)たざるに同じである。人が悟りをはばむことなきさまは、一滴の露が月天をこばまぬにひとしい。深きは高さの尺度であろう。だが、年月の長短などのことは、水の大小により、映る月天の広狭はないことを考えてみるがよかろう。
■〈注解〉
◯弥天 弥はあまねし。全天というほどの意である。
◯眭礙(けいげ) 眭はひっかかる、礙(げ)はさまたげる。障碍(がい)をなすという意である。(48~49頁)
■〈原文〉
身心に法いまだ参飽さざるには、法すでにたれりとおぼゆ。法もし身心に充足すれば、ひとかたはたらずとおぼゆるなり。
たとへば舟にのりて、山なき海中にいでて四方をみるに、ただまろにのみみゆ、さらにことなる相みゆることなし。しかあれど、この大海、まろなるにあらず、方なるにあらず。のこれる海徳、つくすべからざるなり。宮殿のごとし、瓔珞(ようらく)のごとし。ただわがまなこのおよぶところ、しばらくまろにみゆるのみなり。かれがごとく、万法もまたしかあり。塵中(じんちゅう)格外、おはく様子を帯せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを、見取会取するなり。万法の家風をきかんには、方円とみゆるほかに、のこりの海徳山徳おほくこはまりなく、よもの世界あることをしるべし。かたはらのみかくのごとくあるにあらず、直下も一滴もしかあるとしるべし。
■〈現代語訳〉
〔悟りの境地〕
いまだ身心に。法のゆきわたらぬ時には、すでに法は満てりと思う。もし法が身心に満ちた時には、どこかまだ足りないように思われる。
たとえば、船に乗って、陸のみえない海にいで四方を眺めると、ただ円いばかりで、どこにも違った景色はみえない。だが、大海は円いわけでもなく、四角いわけでもない。それ以上の海のさまは見えないだけのことである。海の徳は宮殿のごとく、瓔珞のごとしという。ただ、わが視界のおよぶところが、いちおう円く見えるのみである。
よろずのことどももまた同じである。それはこの世の内外にわたり、さまざまの様相をなしているが、人はその力量・眼力のおよぶかぎりをもって見かつ解するのである。よくよろずのことどものさまを学ぶには、ただ円い四角いと見えるところのみでなく、見えざる山海のありようのなお際限なく、さまざまの世界のあることを知らねばならぬ。自己のまわりがそうというのみではない。脚下も、一滴の水も、またそうだと知らねばならぬ。
■〈注解〉
◯参飽 腹いっぱいになるというところであろう。
◯海徳 海のさま、海のありよう。徳は得であり、そのありようをいう。
◯瓔珞 “keyura”の音写である。珠玉・金銀などを編んで作った装身の具である。経の説くところによれば、龍魚は水をみること、瓔珞のごとしとなし、また宮殿のごとしという。いま、海をそのようにみるものもあるというのである。
◯塵中格外 塵中おは、この世の俗なるありようの中にあること。格外とは、その枠の外、すなわち出世間のありようをいう。
◯方円 方は四角、円はまるい。(49~51頁)
■〈原文〉
うお水をゆくに、ゆけども水のひはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれども、うおとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。只用大ののときは使大なり、要小のときは使小なり。かくのごとくして、頭頭(ずず)に辺際をつくさずといふことなく、処処に蹈翻(とうほん)せずといふことなしといへども、鳥もしそらをいづれば、たちまちに死す、魚もし水をいづれば、たちまちに死す。以水為命(いすいいみょう)しりぬべし、以空為命しりぬべし。以鳥為命あり、以魚為命あり。以命為鳥なるべし、以命為魚なるべし。このほかさらに進歩あるべし。修(しゅ)証あり、その寿者命(みょう)者あることかくのごとき。
しかあるを、水をきはめ、そらをきはめてのち、水そらをゆかんと擬する鳥魚あらんは、水にもそらにも、みちをうべからず、ところをうべからず。このところをうれば、この行李(あんり)したがひて現成公案す。このみちをうれば、この行李したがひて現成公案なり。このみち、このところ、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、さきよりあるにあらず、いま現ずるにあらざるがゆゑに、かくのごとくあるなり。
しかあるがごとく、人もし仏道を修証するに、得一法通一法なり、遇一行修(しゅ)一行なり。これにところあり、みち通達(だつ)せるによりて、しらるるきはのしるからざるは、このしることの、仏法の究尽(ぐうじん)と同生し同参するゆゑにしかあるなり。
得処かならず自己の知見となりて、慮知にしられんずるとならふことなかれ。証究すみやかに現成すといへども、密有かならずしも見成(じょう)にあらず。見成これ何必(かひつ)なり。
■〈現代語訳〉
〔魚と水・鳥と空にたとえて〕
魚が水のなかをゆく。どこまで行っても水の際限はない。鳥が空を飛ぶ。どこまで飛んでも空に限りはない。だが、魚も鳥も、いまだかって水を離れず、空を出ない。ただ大を用うるときは大を使い、小を要するときは小を使う。そのようにして、それぞれどこまでも水をゆき、ところとして飛ばざるはない。鳥がもし空を出ずればたちまちに死に、魚がもし水を出でなばたちどころに死ぬ。水をもって命となし、魚をもって命となすのである。いや、命をもって鳥となし、命をもって魚となすのであろう。そのはか、さらにいろいろといえようが、われらの修証といい、寿命というのも、またそのようなのである。
それなのに、水を究めてのち水を行かんとする魚があり、空をきわめてのち空をゆかんとする鳥があらば、彼らは水にも空にもその道を得ず、その処を得ることはできまい。その処を得れば、その行くところにしたがってさとりは実現し、その道を得れば、その履(ふ)むところおのずからにさとりは顕現する。その道、その処は、大にあらず小にあらず、自にあらず他にあらず、前よりあるにあらず、いま新たに現ずるにもあらず、おのずからにしてかくのごとくになるのである。
それと同じく、人の仏道をおさめんとするにも、一法を得れば一法に通ずるのであり、一行(いちぎょう)にあえば一行を修するのである。そこにもまた処があり、道が通じているのであるが、それがはっきりとは判らない。それは、仏法を究めるとともに生じ、ともに関わるからなのである。
自己の得たるところは、必ずしも、自己の知見となって自覚せられるものと思ってはならぬ。悟りはすみやかに実現しても、わが内なる処有(しょう)はかならずしも明らかではない。それを明らかにすることはかならずしも必要ではないのである。
■〈注解〉
◯密有 密には、精密の意と内容の意の両方の意味がある。ここでは、内証すなわちわが証し得たる内なる所有というほどの意であろう。
◯何必 なんぞ必ずしも必要ならんや、というほどの意である。(51~55頁)
■〈原文〉
麻谷(よく)山(ざん)宝徹禅師、あふぎをつかふちなみに、僧きたりてとふ、
「風性(しょう)常住、無処不周なり、なにをもてかさらに和尚あふぎをつかふ」
師いはく、
「なんぢただ風性常住をしれとも、いまだところとしていたらずといふことなき道理をしらず」
と。僧いはく、
「いかならんかこれ無処不周底の道理」
ときに師、あふぎをつかうのみなり。僧礼拝す。
仏法の証験、正伝の活路、それかくのごとし。常住なればあふぎをつかうべからず、つかはぬをちもはぜをきくべきといふは、常住をもしらず、風性をもしらぬなり。風性は常住なるがゆゑに、仏家の風は大地の黄金なるを現成せしめ、長河の蘇酪(そらく)を参熟せり。
■〈現代語訳〉
〔風性常住ということ〕
麻谷山の宝徹禅師が扇を使っていた。そこに一人の僧が来って問うていった。
「風性は常住にして、処として周(あまね)からぬはないという。それなのに、和尚はなぜまた扇を使うのであるか」
師はいった。
「なんじはただ風性は常住であるということを知っているが、まだ、処として周(あまね)からぬはないという道理はわかっていないらしい」
僧がいった。
「では、処として周からぬはないというのは、どういうことでありましょうか」
その時、師はただ扇を使うのみであった。それを見て、僧は礼拝した。
仏法のあかし、正伝の自由自在なることは、かくのごとくである。つねにあるから扇を使うべきではない、扇を用いぬ時にも風はあるのだというのは、常住ということも知らず、風性というものも解っていないのである。風性は常住であるからこそ、仏教の風は、大地の黄金なることをも顕現し、長河の水を乳酪たらしめる妙用をも実現することを得るのである。
■〈注解〉
◯麻谷山宝徹禅師 麻谷(よく)宝徹(生没年不詳)は馬祖道一の法嗣(ほっす)。
◯蘇酪 酥酪(からく)に同じ。バター、ミルクの類をいうことばである。ちなみに、諸経のうち、しばしば、大地を変じて黄金となすとか、海水を変じて酥酪となすなどの句がみえる。それらによって、「仏家の風は……」の一節をなし、よってもって仏教が、常情の思いのよらぬことを実現するものなることを語るのである。(55~57頁)
一顆明珠(いっかみょうじゅ)
■〈現代語訳〉
〔尽十方世界ということ〕
この「尽十方世界は、これ一顆の明珠である」という表現は、玄沙(げんしゃ)が始めて吐いたことばである。その大旨をいわば、尽十方世界とは、広大というにもあらず、微小というにもあらず、まるい四角いというにもあらず、中正なりというにもあらず、活撥撥地(かっぱつはつち)というにもあらず、炯々(けいけい)として明らかというにもあらず。あるいは、生死(しょうじ)にもあらず去来(こらい)にもあらぬがゆえに、生死・去来である。そのゆえに、昨日は去り、今日は来る。つまるところ、あれだこれだと見ることもできないし、これだあれだと挙げていうこともできない。
つまるところ、尽十方というは、客体を追うて主体となし、主体を追うて客体となし、その尽くるところを知らぬのである。情が生じれば智は遠ざかる。これを「隔(かく)」と表現する.頭を(こうべ)をめぐらして面をかえる。その時、事を展(の)べ、機に投ずるのである。主体を追うて客体となすがゆえに、尽くるところを知らぬ尽十方なのである。いまだ機の発せざる前(さき)の道理を得れば、機のかなめを支配するにあまりあるのである。(68~69頁)
■〈現代語訳〉
〔われもなんじも〕
すでにかくの如くであるのに、なお、われは明珠ではるまいと思い迷うのは、けっして珠ではないからではない。思い迷い、疑いをいだき、取捨にとまどうのも、ただしばらくの小さな計らいというもの。それは心せまきに似ているけれども、また愛すべきものである。明珠とは、そのように光彩きわまりないものである。その彩(いろ)と光の一片一片がすべて尽十方界の功徳であって、何びともこれを奪うことはできない。市場で瓦石を投ずる人はない.六道の因果に落ちるか落ちないかと思い煩う必要はない。因果はもともと徹頭徹尾明らかである。それが明珠の面目であり、それが明珠の眼睛(がんぜい)である。
そうではあっても、われもなんじも、いかなるが明珠であるか、いかなるが明珠であらぬかは知らない。それをあれこれと思い煩うのは、草を結んで罠をかけるようなもの。そこを玄沙の教えにより、この身心の明珠なるありようを、聞き知って明らかにしたうえは、もはやこの心はわがものではあるまい。とすれば、事の起こりまた滅するは誰のことであるか。いまや、明珠であるか明珠でないかと思い煩う要はないはず。たとい思い煩ったとて、明珠でないわけではない。また、たとい明珠ならぬものがあって、それでなにか事が起こったとしても、それはわが心の関わるところではあるまい。それはまさに黒山(こくざん)愧窟の関わるところ。それもまた一顆の明珠なるのみである。(78頁)
即心是仏(そくしんぜぶつ)
■〈原文〉
ー前略ー。仏祖の保(ほう)任する即心是仏は、外道二乗ゆめにもみるところにあらず。唯仏祖与仏祖のみ即心是仏しきたり、究尽(ぐうじん)しきたる。聞著(もんじゃく)あり、行(ぎょう)取あり、証著(じゃく)あり。仏百草を拈却(ねんぎゃく)しきたる。しかあれども、丈六の金身(こんじん)に説似(じ)せず。即公案あり、見成を相待せず、敗壊(え)を廻避せず。是三界(がい)あり、退出にあらず、唯心にあらず。心牆壁(しょうへき)あり、いまだ泥水せず、いまだ造作せず。あるいは即心是仏を参究し、心即是仏を参究し、仏即是心を参究し、即心仏是を参究し、是仏心即を参究す。かくのごとくの参究まさしく即心是仏、これを挙(こ)して即心是仏に正伝するなり。かくのごとく正伝して今日にいたれり。(94頁)
■〈現代語訳〉
いうところの仏祖の保ちきたれる即心是仏は、外道や小乗の徒の夢にも知らざるところである。ただ仏祖と仏祖のみ、即心是仏と正伝しきたり、聞ききたり、行じきたり、証しきたって究め尽くすところである。
仏は百草である。それを摘みきたり、また捨て去る。だが、それが丈六の金身(じん)だというのではない。即は公案である。だが、その理解をもまたず、その失敗をも避けない。是は三界(がい)である。だが、そこを出ずるにもあらず、唯心というにもあらぬ。心は牆(しょう)壁である。だが、土を捏ねるにもあらず、形を造るでもない。ただ即心是仏と究明し、あるいは心即仏是と究めいたり、あるいは仏即是心と訊ねいたり、即心仏是と問いいたり、また是仏心即と参究するのである。
かくのごとく究め到るのが、まさしく即心是仏であって、そのことごとくを挙げ、それを即心是仏の句にこめて正伝するのであり、そのように正伝して今日にいたっておる。(95頁)
■〈注解〉
◯曹谿古仏 六祖慧能のこと。彼は広東省韶(しょう)州府の双峰山下、曹候谿なる流のほとりに曹叔良なるものが建立した宝林寺に住し、そこにあって南宗禅を弘め、中国禅を大成した。よって六祖をまた曹谿をもって呼ぶのである。また、古仏とは、道元がまことの師家を称するに好んで用いた最高の尊称である。
◯仏百草…… 道元はそこにはなはだ特色のある行文をもって、即・心・是・仏の四つの文字の説明を試ている。すなわち、仏を語るに百草をもってし、即を語るに公案をもってし、是を説くに三界をもってし、そして、心を説くに牆壁をもってしている。それをさきのセーニャ外道の霊知の独存をとく所説と比べてみるがよい。ここでは、物を離れ対象を離れて、仏もなく心もないのである。詮ずるところは、一切の法(存在)に即して一心があるのであり、一心に即して一切の法があるのである。かくて、この説示を背景として、やがて「いはゆる正伝しきたれる心といふは、一心一切法、一切法一心なり」と説かれる。そこにこの巻の圧巻の文字があるといってよろしい。(95~96頁)
■〈原文〉
いはゆる正伝しきたれる心(しん)といふは、一心一切法、一切法一心なり。このゆゑに古人いはく、
「若人識得心大地無寸土」
しるべし、心を識得するとき、蓋(がい)天撲(ぼく)落し、匝(そう)地裂破す。あるいは心を識得すれば、大地さらにあつさ三寸をます。
古徳云、
「作麼生(そもさんか)是(これ)妙淨明心、山(せん)河大地・日月星辰(しん)」
あきらかにしりぬ、心とは山河大地なり、日月星辰なり。しかあれども、この道取するところ、すすめば不足あり、しりぞくればあまれり。山河大地心は、山河大地のみなり。さらに波浪なし、風煙なし。日月星辰は、日月星辰のみなり。さらにきりなし、かすみなし。生死去(こ)来心は、生死去来のみなり。さらに迷なし悟なし。牆(しょう)壁瓦礫(がりゃく)心は、牆壁瓦礫のみなり。さらに泥なし、水なし。四大五蘊心は、四大五蘊のみなり。さらに馬(むま)なし、猿(さる)なし、椅子払子(ほっす)のみなり。さらに竹なし、水なし。
かくのごとくなるがゆゑに、即心是仏不染汗(ふぜんま)即心是仏なり。諸仏、不染汗諸仏なり。しかあればすなはち、即心是仏とは、発心・修行・菩提・涅槃の諸仏なり。いまだ発心・修行・菩提・涅槃せざるは、即心是仏にあらず。たとひ一刹那に発心修(しゅ)証するも即心是仏なり、たとひ一極微(ごくみ)中に発心修証するも即心是仏なり、たとひ無量劫に発心修証するも即心是仏なり、たとひ一念中に発心修証するも即心是仏なり、たとひ半拳裏(けんり)に発心修証するも即心是仏なり。しかあるを、長劫(じょうごう)に修行作仏するは即心是仏にあらずといふは、即心是仏をいまだ見ざるなり、いまだしらざるなり、いまだ学せざるなり。即心是仏を開演する正師を見ざるなり。
いはゆる諸仏とは、釈迦牟尼仏なり。釈迦牟尼仏、これ即心是仏なり。過去・現在・未来の諸仏、ともにほとけとなるときは、かならず釈迦牟尼仏となるなり。これ即心是仏なり。(97~98頁)
■〈現代語訳〉
〔一心一切法、一切法一心〕
そこにいうところの正伝しきたれる心とは、一心一切法、一切法一心である。だから、古人はいっておる。
「もし人が心を識りうれば、大地には寸土もない」
つまり、心のなんたるかを知りえた時には、この世を覆う天も落ち、大地もことごとく裂け破れる.あるいは、その時、大地はさらに厚さ三寸を増すといってもよい。また古徳はいう。
「妙淨明心とはいったい何か。山(せん)河大地であり、日月星辰である」
それによっても、心とは、山河大地であり、日月星辰であると、明らかに知られる。だが、その表現は、一歩を進むれば不足があり、一歩を退けば余りがあろう。山河大地なりという心は、ただ山河大地なるのみである。別に波浪もなく、風煙もないのである。日月星辰であるという心は、ただ日月星辰なるのみである。さらに霧があるでもなく、霞がかかっているでもない。生死去来(しょうじこらい)の心はただ生死去来のみであって、別に迷いもなく悟りもない。牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)の心はただ牆壁瓦礫であって、さらに泥もなければ水もない。四大・五蘊の心はただ四大・五蘊にして、ほかに意馬(ば)も心猿もあるわけではない。あるいは椅子払子の心は椅子払子のみであって、ほかに竹があり木があるわけでもない。
かくのごとくである故に、即心是仏とは世の常情に染まぬ即心是仏であり、諸仏とは人の煩悩に汚れぬ諸仏である。詮ずるところ、即心是仏とは、発心・修行・正覚・涅槃の諸仏にほかならない。いまだ発心・修行・正覚・涅槃せざるには、即心是仏ではない。たとい一瞬といえども発心・修行すれば、それが即心是仏である。たとい一微塵のなかに発心・修行しても、それが即心是仏である。たとい無量の年月にわたって発心・修行しても、されが即心是仏である。たといただ一度でも発心・修行すれば、それも即心是仏である。あるいは、たとい片手ほどでも発心・修行すれば、それも即心是仏である。だからといって、長い長い間にわたって修行して仏となるのは即心是仏ではないなどというのは、いまだ即心是仏を見ざるものであり、知らざるものであり、学ばざるものである。即心是仏を説く正師にめぐり遇うことをえないのである。
いうところの諸仏とは、釈迦牟尼仏である。釈迦牟尼仏はまさに即心是仏である。過去と現在と未来の諸仏はすべて、その仏となりたまう時には、かならず釈迦牟尼仏となるのである。それが即心是仏である。(98~100頁)
法というは存在である。物であり、対象である。それを離れて別に独存する一心が存するわけではない。それをかく表現するのである。
◯不染汗 「ふぜんま」と読む。「ふぜんな」ともいう。清浄の意。
◯刹那 ksanaの音写。きわめて短い時間の単位である。
◯極微 paramanuの意訳。分割しつくされた最小の物質をいう。(100~101頁)
洗浄(せんじょう)
■水はかならずしももと浄なるにあらず、また、もと不浄なるにもあらず。この身もかならずしももと浄なのではなく、またもと不浄なのでもない。もろもろの事どももまた同じである。水に情(こころ)があるわけでもなく、また情がないわけでもない。この身が有(う)情なわけでもなく、非情なわけでもない。よろずの事もまた同じである。それが仏世尊の説きたまうところである。そうであるから、水をもって身を浄めるわけではなく、ただ、仏法によって仏法を保つためにこのことがある。それを洗浄という。それは、仏祖がしたしくその身心をもってまた、仏祖がその光明をもって明らかに示したまうところである。すべて無量無辺の功徳を実現したまうところであって、身心にその作法がぴたりと具(そな)わるその瞬間に、たちまちにして久遠の修行が完全に成るのであり、そのゆえに修行の身心が現ずるのである。(109頁)
礼拝得髄(らいはいとくずい)
■〈原文〉
修行阿耨多羅三脈三菩提の時節には、導師をうることもともとかたし。その導師は、男女等の相にあらず、大丈夫なるべし、恁麼人(にん)なるべし。古今人にあらず、野狐精(ぜい)にして善知識ならん。これ得髄の面目なり、導利なるべし。不眛因果なり、爾(に)我渠(こ)なるべし。
すでに導師に相逢(そうほう)せんよりここかたは、万(ばん)縁をなげすてて、寸陰をすごさず、精進弁道すべし。有(う)心にても修行し、無心にても修行し、半心にても修行すべし。しかあれば、頭然をはらひ、翹足(ぎょうそく)を学すべし。かくのごとくすれば、訕謗(せんぼう)の魔党におかされず、断臂(だんぴ)得髄の祖、さらに他にあらず。脱落身心の師、すでに自なりき。
髄をうること、法をつたふること、必定して至誠(しじょう)により、信心によるなり。誠(じょう)信ほかよりきたるあとなし、内よりいづる方なし。ただまさに法をおもくし、身をかろくするなり。世をのがれ、道をすみかとするなり。いささかも身をかへりみること法よりもおもきには、法つたはれず、道うることなし。その法をおもくする志気(しいき)ひとつにあらず、他の教訓をまたずといへども、しばらく一二を挙拈(こねん)すべし。
いはく、法をおもくするは、たとひ露柱なりとも、たとひ燈籠なりとも、たとひ諸仏なりとも、たとひ野干(やかん)なりとも、鬼神なりとも、男女なりとも、大法を保(ほう)任し、吾髄を汝得(にょとく)せるあらば、身心を(爿ニ木)座(じょうざ)にして、無量劫にも奉事(ぶじ)するなり。身心はうることやすし、世界に稲麻竹葦(とうまちくい)のごとし。法はあふことまれなり。
釈迦牟尼仏のいはく、無上菩提を演説する師にあはんには、種姓(しょう)を観ずることなかれ、容顔をみることなかれ、非をさらふことなかれ、行ないをおかんがふることなかれ。ただ般若を尊重するがゆゑに、日日(にちにち)に百千両の金(こがね)を食(じき)せしむべし。天食(じき)をおくりて供養すべし。天華(げ)を散じて供養すべし。日日三時に礼拝して恭敬(くぎょう)して、さらに患(げん)悩の心(しん)を生(しょう)ぜしむることなかれ。かくのごとくすれば、菩提の道かならずところあり。われ発心よりこのかた、かくのごとく修行して、今日は阿耨多羅三藐三菩提をえたるなり。
しかあれば、若(にゃく)樹若(にゃく)石もとかましとねがひ、若田若里もとかましともとむべし。露柱に間取し、牆壁をしても参究すべし。むかし野干を師として礼拝問法する天帝釈あり、大菩薩の称つたはれり。依業(えごう)の尊卑によらず。
しかあるに、不聞仏法の愚癡(ち)のたぐひおもはくは、われは大比丘なり、年少の得法を拝すべからず。われは久修(くしゅ)練業なり、得法の晩学を拝すべからず。われは師号に署せり、師号なきを拝すべからず。われは法務司なり、得法の余僧を拝すべからず。われは僧正司(そうじょうし)なり、得法の俗男俗女を拝すべからず。われは三賢十聖(さんけんじっしょう)なり、得法せりとも比丘尼等を礼拝すべからず。われは帝胤(いん)なり、得法なりとも臣家相門を拝すべからずといふ。かくのごとくの痴人(にん)、いたづらに父国をはなれて、他国の道路に(足ヘンニ令)跰(れいへい)するによりて、仏道を見聞せざるなり。(138~140頁)
■〈現代語訳〉
〔ただ法を重くすべし〕
最高の智慧を修するの時にあたっては、よき導師を得ることがもっとも難(かた)い。その導師は、男女等のすがたによるにあらず、ただ大丈夫でなければならぬ。恁麼の人でなければならない。古人でもなく今人でももなく、ただ変幻自在にして善き知識でなければならない。それが仏祖の骨髄を得たものの面目であり、よき指導者であろう。因果に眛(くら)からず、彼我の思いがないからである。
すでに導師にめぐり遇うことを得たならば、万事をなげすて、寸陰を惜しんで、ひたぶるに修行するがよい。心を用いて修行し、心を用いずして修行し、また心なかばにしても修行するがよい。そうすれば、頭然の燃えるを払い、足をつまだてて待つの思いで学ぶことを得るであろう。そのようになれば、もはや謗(そし)る悪魔どもにも煩(わずら)わされず、断臂得髄のことも他人(ひと)ごとではなくなって、いつしか自分が身心脱落の師となっているのである。
得髄も、嗣(し)法も、ひとえに至誠(じょう)により、信心によるものである。誠(まこと)の心、信ずる心は外からくるものでもなく、わが内から出てくるものでもない。ただ、まさしく法を重んじ、身を軽くするのみである。世をのがれて、道を棲家(すみか)とするのである。いささかでも法よりも身を顧みる心のあるものには、法は伝わらず、道を得ることは難しい。その法を重んずる志にもいろいろとあり、また他人の教えによるものでもないが、いま差しあたり一、二の例をあげてみよう。
まず、法を重んずるには、たとい法堂(はっとう)の円柱であろうと燈籠であろうと、たとい諸仏であろうと野牛であろうと、あるいは鬼神であろうと人間であろうと、もし大法を保持し、仏祖の骨髄を得たものがあれば、わが身心の床座(しょうざ)として、どこまでも事(つか)えまつるがよいのである。身心を得たることはやすい。この世のどこにも見るところである。方にめぐり遇うことはまれである。
釈尊のおおせには、――最高の智慧を説く師にめぐり遇うには、その血統をたずねてはならぬ、その顔容(かおかたち)をみてはならぬ、その欠点をきらうてはならぬ、またその行為を案じてはならない。ただ智慧を尊重するのゆえをもって、日々に百千両の金(こがね)をたてまつるがよく、最上の食をもって供養するがよく、天より花をふらせて尊重するがよく、日々朝・昼・夕に礼拝し恭敬(くぎょう)して、いささかも憂悩の心をあらしめてはならない。そのようにすれば、智慧の道はかならず開けてくるものである。われもまた、発心よりこのかた、そのように修行して、いまは最高の智慧を得ることができたのである――とある。
されば、樹も石もわがために説き、田も里もわがために説かんことを願うがよい。円柱にも法を問うてみるがよく、牆壁にも真理を聞いてみるがよい。むかし帝釈天は、野狐を師として礼拝し、法を問うたことがあるという。よって、大菩薩の称が伝わっているが、それはその手段の尊卑によるものではない。
それなのに、世のなかの仏法を知らざる愚か者たちは、われは大比丘であるから、年少の得法者を拝するわけにはゆかぬと思う。われは久しく修行してきたのだから、後進の得法者を拝することはできないという。あるいは、われはすでに師号をもっているのだから、師号なきものを拝するわけにはゆかぬといい、われは法務を司(つかさど)るものであるから、ほかの得法の僧を拝してはならぬといい、われは三賢である十聖であるから、たとい得法したからとて比丘尼などを拝するわけにはゆかないといい、あるいはまた、われは皇族の血統をひくものであるから、たとい得法者であっても臣下の僧を拝することはできないという。そのような愚か者たちは、いたずらに父の許(もと)を離れて他国に流浪し、ついに仏道を見ることはできないであろう。(140~142頁)
■〈注解〉
◯趙州真際大師…… 趙州従諗(じょうしゅうじゅうしん、897寂、寿120)は馬祖道一に学び、南嶽(がく)普願の法を嗣ぎ、趙州の観音院に住す。諡(おくりな)してして真際大師と証す。(149頁)
■〈注解〉
◯曹谿高祖 六祖慧能を曹谿大師という。曹谿の宝林寺に住していたからである。曹谿とは、広東省韶(しょう)州府雙峰山下にあり、そこに曹叔良(そうしゅくりょう)なるものが宝林寺をたてて慧能を住せしめたので、曹候谿といい、また略して曹谿というのである。
◯風幡の話 『景徳伝燈録』巻五、慧能伝に、「不是風動、不是幡動、仁者心動耳](これ風の動くにあらず、これ幡の動くにあらず、仁者の心動くのみ」と語った慧能のことばが見えている。よく知られた禅話である。
◯行者 「あんじゃ」と読む。禅院にありて、いまだ得度せず、寺中の諸役のもとにあって雑務の下働きをしている者をいう。
◯四果 仏教を修する者の四つの段階をいう。預流果、一来果、不還(げん)果、無学果とたてる。預流果とは、はじめて聖者の流れにあずかれる者、一来果とは、なお天界と人間界を徃来する段階、不還果とは、ふたたび人間の欲界に帰りきたることのない段階、そして、無学果とは、煩悩を断じつくして、もはや学ぶべきもののない聖者の段階である。ひっくるめて、小乗の行者・聖者というほどの意である。
◯四大 地・水・火・風をいう。万物の構成要素である。
◯五蘊 色・受・想・行・識をいう。人間の肉体および精神を構成する諸要素である。(155~156頁)
■〈注解〉
◯四衆 仏教教団を形成する四種の人々。比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷がそれである。
◯三界 欲界・色界・無色界の三つの世界をいう。欲界とは、人間欲望の世界であり、色界とは、現象の世界である。そして、無色界とは、叡智の世界と考えてよいであろう。(161頁)
■〈注解〉
◯波羅夷 “parajika”の音写。棄(き)または断頭(だんず)などと意訳する。戒を犯した罪に対する罰の名称の一つである。その罪を犯せば、もはや懺悔(さんげ)の余地もなく、教団より擯出(ひんずい)せられる。「不共住(ふぐじゅう)」とあるのはその意である。淫・盗・殺・妄語をもって四波羅夷罪とする。
◯付法蔵 法蔵とは、教法を記した経典の総称である。付とは付属、その伝持と弘法を委ね嘱(しょく)すること。付法蔵の祖師とは迦葉(かしょう)を指さす。彼は第一結集(じゅう)すなわちブッダの教法と戒律を編集した会議の中心人物であった。(167頁)
■〈注解〉
◯頌 “gatha”を音写して偈(げ)となし、意訳して頌(じゅ)となす。あるいは、それを重ねて偈頌という。頌には讃える意がある。(176頁)
谿声山色(けいせいさんしょく)
■〈現代語訳〉
〔竹の声に悟りをひらく〕
また、香(きょう)厳智(し)閑禅師が大洟(サンズイに為の旧字)大円禅師の門に学んだころのこと、大洟(サンズイに為の旧字)がいった。
「なんじは聡明にして博学であるが、ひとつ、注釈のなかから憶(おぼ)えたものでなく、父母のまだ生まれぬ以前(さき)から得きたった一句をわがために語ってみるがよい」
そこで香厳は、いくたびもそれを試みたが、どうしてもできなかった。彼は深くわが身を恨み、年来たくわえる書籍を披見してみたが、なお見当もつかない。かくて彼はついに年頃集めきたった書籍を焚(や)いていった。
「画に描いた餅は飢えをいやすに足りぬ。われは誓う。この生涯において仏法を理解することは望むまい。ただ行粥飯僧(ぎょうしゅくはんそう)となろう」
かくて、粥飯を行じて幾年も経(た)った。行粥飯僧とは、衆(しゅ)僧のために飯焚きをして奉仕する僧のことであって、わが国でいう台所方のようなものである。かくして彼は大洟にいった。
「わたしは身も心も昏(くら)く、なお、道(い)うことができません。願わくは和尚、わがために教えたまえ」
だが、大洟(サンズイに為の旧字)はいった。
「わたしは汝のために説くことを辞するものではない。しかし、そうしたならば、きっと汝はのちになってわたしを恨むこととなるであろう」
そのようにして年月を経るうち、やがて彼は大証国師の跡を訪ね、武当山(さん)に入って、国師のいおりのあとに草庵をむすんで住んだ。そこには竹を植えて友としていたが、ある日のこと、路を掃いているとき、石が跳んで竹に当たり、かっと音を立てた。それを聞いたとき、彼は豁然(かつぜん)として大悟(だいご)した。そこで、沐浴斎戒し、大洟(サンズイに為の旧字)山に向かって焼香礼拝して、はるかに大洟に向かっていった。
「大洟(サンズイに為の旧字)大和尚、かってあなたがわたしのために説いたならば、どうしてこのことがありえましょう。和尚の恩の深きことは、父母よりもすぐれております」
そして最後に、一偈を賦(ぶ)した。いわく。
「一撃所知を亡ず
さらに自ら修治(ち)せず
動容を古路(ころ)に揚(あ)ぐ
悄然の機に堕せず
処々に蹤跡(しょうせき)なし
声(しょう)色のほかの威儀なり
諸方の達道の者
みな上々の機といわん」
その偈を大洟(サンズイに為の旧字)に呈した時、大洟(サンズイに為の旧字)はいった。「こやつ徹底しよったわい」と。
〈注解〉
◯一撃亡所知…… 漢詩であるから一応訓読しておいたが、さらに意訳を試ておく。
「あの音ひとつで知識はふっとんだ
もはやあれこれ思い煩うことはない
ありのままの姿で仏道をあゆみ
行ないすました者にはなり申さぬ
ただ自由自在にこそ振る舞いたい
言語文字のほかに当為はある
無礙自在の道に達する者こそ
まさに上々の機というべきなり」
■〈現代語訳〉
〔桃花を眺めて眼(まなこ)を開く〕
また、霊雲志勤(きん)禅師は、三十年このかた修行してきた人であるが、ある時、山に遊び、山麓に休息して、はるかに人里を眺めた。時春にして桃花の盛りなるを見て、忽然として悟った。そこで一詩を賦(ぶ)して、大洟に呈していった。
「三十年このかた知識を訪ねて
葉落ち芽を生ずることすでに幾回ぞ
ひとたび桃花を見てよりのちは
たちまち疑いを超えて今にいたる」
大洟(サンズイに為の旧字)は、「縁より入る者は、長く退失せず」といって、ただちに印可を与えたという。だが、誰か縁より入らぬ者があろうか。また入りてはまた退失する者があろうか。それはひとり志勤のことのみではないが、彼はやがて大洟(サンズイに為の旧字)の法を嗣いだ。もしも山色が清浄(しょうじょう)身でなかったならば、どうしてこのようなことがありえようか。(194頁)
〈注解〉
◯霊雲志勤 福州志勤の人。年齢不詳。洟(サンズイに為の旧字)山の法を嗣いだ。(194頁)
■〈現代語訳〉
〔山(せん)河大地とはなにか〕
長沙景岑(しん)禅師にひとりの僧が問うていった。
「いかがしたならば、山河大地を転じて自己に帰することができましょうか」
師はいった。
「どうしたならば、自己を転じて山河大地に帰することができるだろうか」
この表現は、自己はおのずから自己であるから、たとい自己は山河大地だといっても、帰するところはいっこうに差し支えるところはないのである。
瑯揶(ろうや)の広照大師慧覚(えがく)和尚は、遠く南嶽の流れを汲むものであるが、ある時、教家(け)の学者である子璿(しせん)なるものが、和尚に問うていった。
「本来清浄なるに、どうしてたちまち山河大地を生ずるのであろうか」
その問いに答えて、和尚は示していった。
「本来清浄なるに、どうしてたちまち山河大地を生ずるのであろうか」
それで解ることは、本来清浄なる山河大地を、ただの山河大地と思い誤ってはならぬということ。しかるに、経のみを学ぶ学者は、そんなことは夢にも聞かないから、山河大地をそうとは知らないのである。(196頁)
〈注解〉
◯長沙岑禅師 長沙景岑である。年寿不詳、湖南の人。南泉普願の法嗣(ほっす)。
◯教家 禅家に対することば。仏法を語るに、教相を判断し、言句によりて説く者というほどの意。(196~197頁)
■〈現代語訳〉
〔菩提心のすすめ〕
かくて知らねばならぬ。山色谿声によらずんば、拈華微笑(ねんげみしょう)の舞台も開かれず、二祖が得髄もありえないであろう。渓声山色の功徳によって、大地と人間が同時に成道(じょうどう)するのであり、明星のきらめくを見て悟る仏たちもありうるのである。求(ぐ)法の志の深かった先哲たちも、われらと同じ人間であった。その先例をいまの人はかならず参考とするがよい。今日でも、名利を離れて真実に学ばんとする者は、そのような志を立てるがよい。
しかるに、近来のわが国においては、ほんとうに仏法を求める人は稀である。ないわけではないが、その縁に遇いがたいのである。たまたま僧となって俗を離れたようでも、仏道をもって名利の手段とするもののみが多い。気の毒なことであり、口惜しいことである。この月日を惜しまず、むなしく暗闇のわざに偓促(あくせく)として、いつになったらこの俗世をはなれ、そのような人を「かわいそうな者だ」といった。さきの世の悪因によってそうなのだからである。この世に生を受けても、法のために法を求める志がないから、本物をみても本物を疑い、正法(しょうぼう)に遇うても正法に嫌われるのである。この身心骨肉が、かって法によって生じたものでないから、法と相応しないのであり、法を受用することができないのである。その由は、仏祖よりこのかた師資相承(じょう)してすでに久しい。いまや菩提心は昔の夢を説くに等しいものとなった。かわいそうに、宝の山に生まれながら、宝をしらず、宝を見ず、いわんや法の宝を得ることをやである。
もしも菩提心を発(おこ)しさえすれば、そののちなお六道・四生(ししょう)を経(へ)めぐろうとも、その輪廻のえにしがすべて菩提のいとなみとなる。であるから、たといこれまでの年月はむなしく過ごしても、今生の間には急ぎ願を発(おこ)すがよい。その願のありようは、われも衆生もみなともに、今生よりこのかた生々(しょうじょう)を尽くして、正法を聞くことができますようにということ。また、聞くことを得たならば、正法を疑わず、不信の念を抱かじということ。まさに正法に遇うことを得たときには、世法を疑てて仏法をたもち、ついに大地有(う)情とともに成道することを得るようにということ。そのように発(ほつ)願すれば、おのずから正しい発心の条件がととのうのである。この心映えをおろそかにしてはならぬ。(198~200頁)
〈注解〉
◯拈華 世尊が拈華微笑し、迦葉がそれに相応じて、その時両者の間に以心伝心のことが成ったという有名な故事をいう。
◯得髄 二祖慧可が初祖達磨の骨髄を得てその法嗣(ほっす)となった故事を指さす。(200頁)
■〈現代語訳〉
いったい、菩提心を行ずるには、その発心や実戦を世の人々に知られたいと思ってはならない。むしろ知られまいとするがよい。ましてや、みずから口に称(とな)えるようなことは不可である。いまの人は実をもとめることが稀であるから、身に行ずることもなく、心に悟るところもなくとも、ただ他人がほめたりすると、それが学解(がくげ)・実践の具足した人だと思う。迷いの中に迷いを重ねるとはそのことである。そのような間違った考えはすみやかに捨てるがよい。
仏法を学ぶにあたり、もっとも見聞(けんもん)しがたいのは正法の心術というmのである。その心術は仏より仏へと相伝してきたもので、これを仏の光明といい、また仏心ともいい伝えておる。世尊在世の時から今日までには、名利をもとめることを学道の目的とするかに思われる人も少なくなかったが、それでもなお、正師の教えにめぐり遇うて、心を翻して正法を求むれば、おのずからに道を得ることができる。(202~203頁)
■〈注解〉
◯何必不必 「なんぞ必ずしも必せんや」というほどの句である。(211頁)
諸悪莫作(しょあくまくさ)
■〈原文〉
古仏云、諸悪莫作、衆善奉行、自浄其意、是諸仏教。
これ七仏祖宗の通戒つぃて、前仏より後仏に正伝す、後仏は全仏に相嗣(そうし)せり。ただ七仏のみにあらず、是諸仏教なり。この道理を功夫(くふう)参究すべし。いはゆる、七仏の法道、かならず七仏の法道のごとし。相伝相嗣、なほ箇裏の通消息なり。すでに是諸仏教なり、百千万仏の教行証なり。
いまいふところの諸悪は、善性・悪性・無記性のなかに悪性あり。その性これ無生(しょう)なり。善性・無記性等もまた無生なり、無漏(ろ)なり、実相なりといふとも、この三性の箇裏に、許多般(きょたはん)の法あり。
諸悪は、此界(しかい)の悪と他界の悪と同不同あり、先時と後時と同不同あり、天上の悪と人間の悪と同不同なり.いはんや仏道と世間と、道悪・道善・道無記、はるかに殊異あり。善悪は時なり、時は善悪にあらず。善悪は法なり、法は善悪にあらず。法等・悪等なり、法等・善等なり。
しかあるに、阿耨多羅三藐三菩提を学するに、聞教し、修行し、証課するに、深(じん)なり、遠(おん)なり、妙なり。この無上菩提を或従(わくじゅう)知識してきき、或従経巻してきく。はじめは、諸悪莫作ときこゆるなり。諸悪莫作ときこえざるは、仏正法にあらず、魔説なるべし。しるべし、諸悪莫作ときこゆる、これ仏正法なり。
この諸悪つくることなかれといふ、凡夫のはじめて造作してかくのごとくあらしむるにあらず。菩提の説となれるを聞教するに、しかのごとくにきこゆるなり。しかのごとくきこゆるは、無上菩提のことばにてある道著(じゃく)なり。すでに菩提語なり、ゆゑみ語菩提なり。無上菩提の説著となりて問著せらるるに転ぜられて、諸悪莫作とねがひ、諸悪莫作とおこなひもてゆく。諸悪すでにつくられずなりゆくところに、修行力たちまちに現成す。この現成は、尽地・尽界・尽時・尽法を量として現成するなり。その量は、莫作を量とせり。
正当恁麼時(しょうとういんもじ)の正当恁麼人は、諸悪のつくりぬべきところに住し、徃来し、諸悪つくりぬべき縁に対し、諸悪つくる友にまじはるににたりといへども、諸悪さらにつくられざるなり。莫作の力量見成するゆゑに、諸悪みづから諸悪と道著せず。諸悪にさだまれる調度なきなり。一拈一法の道理あり。正当恁麼時、すなはち悪の人ををかさざる道理しられ、人の悪をやぶらざる道理あきらめらる。(220~221頁)
〈現代語訳〉
〔諸悪莫作と聞こえるが仏正法である〕
古仏いわく、「諸悪莫作、衆(しゅ)善奉行、自浄其意、是諸仏教」(もろもろの悪を作(な)すことなく、もろもろの善を奉行して、みずからその意を浄む、これもろもろの仏の教えなり)と。
これは七仏に通ずる教誡として、前仏より後仏へと正伝し、後仏は前仏より相嗣ぎきたったものである。だが、それは、ひとり七仏のみならず、また、もろもろの仏の教えである。その道理をよく思い究めるがよい。いうところの七仏の教えは、かならずそれぞれの七仏のそれと同じである。相伝し相嗣するがゆえにかくなるのである。だが、すでに「これもろもろの仏の教えなり」とある。また百千万の仏たちの教(きょう)であり、行であり、証なのである。
さて、ここにいうところの諸悪とは、善・悪・無記の三つの性のなかの悪性である。だが、その性にはなんの実体もない。善性・無記性もまた同じであって、また無漏(ろ)である、実相であるともいうが、この三性については、なおいろいろのことがある。
いまはまず諸悪についていえば、この世界の悪とか世界の悪とはかならずしも同じではない。さきの時とあとの時でも違うことがある。また、天上界の悪と人間界の悪も同じからず、いわんや仏道と世間とでは、悪といい、善といい、無記というも、はるかに異なるのである。つまり、善悪は時によるが、時が善悪なのではない。善悪は事によるが、事が善悪なのでもない。事がひとしければ、善がひとしく、事がひとしければ、悪がひとしいだけである。
しかるに、仏の最高の智慧を学ぼうとして、教えを聞き、修行を重ね、証(さとり)にいたることは、まことに深(じん)にして遠(おん)、かつ妙である。その最高の智慧を、あるいは善知識にしたがって聞き、あるいは経巻によって学ぶに、はじめはただ諸悪莫作、つまり、もろもろの悪を作(な)すことなかれとのみ聞こえるものである。そう聞こえないのは、仏の正法ではなく、魔説なのである。されば、諸悪莫作と聞こえるのが、それが仏の正法であると知るがよいのである。
その諸悪を作すことなかれというのは、凡夫がみずから思いめぐらして、そのように思うのではない。仏の智慧の説かれるのを聞いていると、自然にそのように聞こえるのである。そのように聞こえるのが、最高の智慧をことばにいいあらわした表現である。すでに智慧のことばであるから、智慧を語っているのである.最高の智慧が説かれ、それが聞かれて、その力にひかれて諸悪莫作と願い、諸悪莫作とおこなっているうちに、いつしか諸悪が作られないようになる。それが修行の力の実現というものである。その力の実現は、あらゆる処、あらゆる世界、あらゆる時、あらゆる事にわたって成るのであるが、その基本はいつも莫作である。
その時その人は、たとい諸悪をつくるべきところに住し、あるいは到り、あるいは諸悪をつくる条件の下におかれ、あるいは諸悪をつくる友に交わっているように見えても、けっして諸悪をつくることがないのである。莫作の力が現れるが故に、諸悪が諸悪とならないのである。諸悪には一定の道具立てというものはない。自由自在なのである。まさにそこに到れば、悪が来って人を犯すのではない道理が解り、また人が悪を破るわけでもないことが解ってくる。(222~224頁)
〈注解〉
◯諸悪莫作…… いわゆる七仏通戒偈。しばしば経に見えているが、その初出は、『増一阿含経(ぎょう)』、四四、十不善品(ぼん)にみえているものであろうか。ただし、そこでは、「一切悪莫作、当奉行其善、自浄其志意、是則諸仏教」とある。むろん、それは翻訳の異なりにすぎない。
◯経行証 これを三法という。仏教の全道程をいうことばである。教は教法すなわち仏の教え、行は修行すなわち教法による実践、証は証果すなわち修行によって証(さとり)を得るのである。
◯無漏 漏(asrava)とは漏中の意。なにものかが人の感官などを通して沁み込んでくることをいう。特に、煩悩を指さしていうことが多い。ただ、いまここでは、前悪のことを語って、それらはそのように外より漏れ注いでくるものではないとするのである。けだし、それらはなんの実体もないものであるからである。
◯実相 諸法実相とて存在の真相をいうことばである。しかるに、仏教の説くところによれば、一切の存在は縁起すなわち関係性のものであって、なんら固定的な実体あるものでないとする。いまその実相のことばをもって、前悪の真相を語ることもできるとするのである。(224頁)
■しかるに、もろもろの仏祖はいまだかって教をも行をも証をも汚すことがないのであるから、教・行・証はまたもろもろの仏祖をはばむことがない。そのゆえ、仏祖の修行においては、過去・現在・未来を通じて、後にも先にも、その教・行・証・を避けて通る仏もなく祖もない。また、衆生が仏となり祖となる時には、これまでの仏祖が邪魔になるわけではないのであるから、いまの人もよく仏となり祖となりうる道理を、四六時中の行住坐臥のうちにもよくよく考えてみるがよい。衆生が仏となり、祖となる時には、衆生を破るのでもなく、奪うのでもなく、また失うわけでもない。ただ身心を脱落するのみである。
つまり、前悪の因果をそのままに修行するのであって、なにも因果を動かすでもなく、なんぞ手段を講ずるでもない。かえって因果が時に及んでわれらを修行せしめるのである。かくして、その因果の真相が明らかとなってみると、それはただ莫作である、無生(しょう)であり、無常である。また不眛であり、不落である。ただ身心脱落であるからである。(228頁)
■詮ずるところ、諸悪莫作は、驢馬(ろば)が井戸をのぞけば、井戸が驢馬をみるというのみではなく、井戸が井戸をみ、驢馬が驢馬をみるのである。人が人を見るのであり、山が山を見るのである。その相対的関係をつき破った道理を説くところが諸悪莫作なのである。
「仏のまことの法身(ほっしん)は、なお虚空のごとし。物に応じて形を現ずること、水中の月のごとし」
という。物に応じての莫作であるから、さまざまの形を現ずる莫作であって、その無礙自在なることは、なお虚空のごとくであるが、また水中の月のごとく、疑いもなく水が月を宿しているのである。そこまでゆけば、もはや莫作のありようは疑いもなく明らかであろう。(230頁)
■〈注解〉
◯四大五蘊 人間のすべてを、四大および五蘊の語句をもってか語っているのである。四大とは地・水・火・風の四の原素であって、人間の肉体を構成するものもまたその他ではない。五蘊(うん)とは、その肉体的部分としての色、および、その精神的部分としての受(感覚)・想(表象)・行(感情と意志)・識(意識)の五つの部分である。
◯不眛 不眛因果の句がある。因果の昭々として明らかなるをいう。不眛とは眛(くら)からずである。
◯井の驢をみる…… 曹山本寂の語録(「会元録]巻13)に、「驢が井をのぞけば、井が驢をみる」という句がある。それもまた主客転換の論理を語ったものであるが、それを道元はさらに、「井の井をみるなり、驢の驢をみるなり。人の人をみるなり、山の山をみるなり」と転じておる。それはもはや相対的関係ではないのである。
◯如水中月、被水月礙 「水中の月の如く、水中の礙をこうむる」とでも読むべきか。水中の月は、疑いもなく水が月を宿しているという制限のなかにある、というほどの意であろう。(230~231頁)
■〈原文〉
衆(しゅ)善奉行。こ衆善は、三性のなかの善性なり。善性のなかに衆善ありといへども、さきより現成して行人をまつ衆善いまだあらず。作(さ)善の正当恁麼時、きたらざる衆善なし。万善は無象なりといへども、作善のところに計会(けいえ)すること、磁鉄よりも速疾なり。そのちから、毘嵐風(びらんぷう)よりもつよきなり。大地山(せん)河・世界国土・業(ごう)増(ぞう)上力(じょうりき)、なほ善の計会を罣礙(けいげ)することあたはざるなり。
しかあるに、世界によりて善を認ずることおなじからざる道理おなじ。認得を善とせるがゆゑに。如(二、シ)三世諸仏説法之儀式(一、ノ)。おなじといふは、在世説法、ただ時なり。寿命身量またときに一任しきたれるがゆゑに、説(二、ク)無分別法(一、ヲ)なり。しかあらざればすなはち、信行の機の善と、法行の機の善と、はるかにことなり、別法にあらざるがごとし。たとへば、声聞(しょうもん)の持戒は菩薩の破戒なるがごとし。
衆善これ因縁生(しょう)・因縁滅にあらず。衆善は諸法なりといふとも、諸法は衆善にあらず。因縁と生滅と衆善と、おなじく頭正(ずしん)あれば尾正(びしん)あり。
衆善は奉行なりといへども、自にあらず、自にしられず、他にあらず、他にしられず。自他の知見は、知に自あり、他あり、見の自あり、他あるがゆゑに、各各の活眼睛(ぜい)、それ日にもあり、月にもあり。これ奉行なり。奉行の正当恁麼時に、現成の公案ありとも、公案の始成(しじょう)にあらず、公案の久住(くじゅう)にあらず。さらにこれを本行といはんや。
作善の奉行なるといへども、測(しき)度すべきにはあらざるなり。いまの奉行、これ活眼睛なりといへども、測度にはあらず。法を測(しき)度せんために現成せるにあらず。活眼睛の測度は、余法の測度とおなじかるべからず。
衆善、有・無・色・空等にあらず、ただ奉行なるのみなり。いづれのところの現成、いづれの時の現成も、かならず奉行なり。この奉行に、かならず衆善の現成あり、奉行の現成、これ公案なりといふとも、生滅にあらず、因縁にあらず。奉行の入・住・出等もまたかくのごとし。衆善のなかの一善、すでに奉行するところに、尽法・全身・真実地等、ともに奉行せらるるなり。
この善の因果、おなじく奉行の現成公案なり。因はさき、果はのちなるにあらざれども、因円満し、果円満す。因等法等、果等法等なり。因にまたれて果感ずといへども、前後にあらず。前後等の道あるがゆゑに。(232~233頁)
〈現代語訳〉
〔衆善奉行について〕
衆善奉行。この衆善というのは、三性のなかの善性である。善性のなかにはいろいろの善性があるけれども、すでに実現して修行者を待っているような善はどこにもなく、また、善をなすまさにその時には、きたらぬ善もないのである。すべての善は象(かたち)なきものではあるが、善のなされるところに集まること、磁石のもとに集まる鉄よりも速やかである。またその、力は劫初(ごうしょ)の旋風よりも強く、大地も山(せん)河も、世界も国土も、また業の増上力(りき)も、けっして善の集まることを碍(さまた)げることはできない。
しかるに、世界によって善を認めることが同じでないことが多い。認定をもって善としているからである。その消息は三世諸仏の説法のことによく似ている。三世諸仏の説法はすべて同じであるというが、釈尊在世のころの説法は時によって異なった。また、諸仏は寿命や身量はその時にまかせて、ただ無分別の法を説きたもうた。だから、信によって仏道に入った者の善と、法を理解して実践する者の善とは、はるかに相異なっているが、またけっして別の事ではない。たとえば、声聞の持戒と菩薩の破戒は別のことではないといった具合である。
さて、もろもろの善は、なにか条件があって生ずるというものでもなく、またなにか条件があって滅するというものでもない。
また、もろもろの善はもろもろの事ではあるけれども、もろもろの事がもろもろの善なのではない。条件と生滅ともろもろの善とは、それぞれ初めがあり終わりがある。
そのもろもろの善を奉行するというが、ここでもそれは、自にあらず他にあらず、また自他のしるところでもない。自他の知見といえば、知に自があり他があり、また見に自があり他があるのであるから、おのおのの開かれた眼が、ここにあり、またかしこにある。それが奉行である。だが、そのときの奉行は、たとい悟りが実現したとしても、その悟りはその時はじめて成るのでもなく、また、それがいつまで続くものでもない。ましてやそれを根本の行ということはできまい。
善を作(な)すことは奉行であるからとて、人の測り知るところではない。いまの奉行は、たとい開かれたる眼があってのこととしても、測らうべきことではない。事を測ろうがために眼を開いたのではない。開かれたる眼の測(しき)度は、余の事の測度と同じであってはならない。
つまるところ、もろもろの善は、有(う)でも無でもない、空でも色でもない。ただ奉行である。その奉行にはかならず衆善の実現がある。その奉行の実現こそが仏者の課題であるが、だからとて、それもまた生滅のことではなく、なにかの条件によることでもない。奉行のはじめも、中ごろも、終わりもまた同じである。すでに処善のなかの一善が奉行せられるところには、一切世界の善がことごとく奉行せられる。
この善の因果の道理もまた、奉行においてさとらるるべき課題である。因は前(さき)、果は後(あと)というではないが、因が円満して果が円満するのである。因がひとしければ事がひとしく、果がひとしければ事がひとしいのである。因があってはじめて果があるのだが、それもけっして前後ではないのである。前後などというものがあるので、念のためにいっておく。(233~235頁)
■〈注解〉
◯驢事未去、馬事到来 「驢事いまだ去らず、馬事到来す」と読む。前者の事のいまだ終わらないうちに、すでに後者の事がはじまっているというほどの意の句である。それを莫作と奉行とにあてていえば、莫作のことが完了してから、それから奉行のことが始まるのではないといっておるのである。(238頁)
■〈原文〉
たとひいくかさなりの尽界に弥綸(みりん)し、いくかさなりの尽法(じんぽう)を呑却(どんきゃく)せりとも、これ莫作の解脱なり。衆善すでに初中後善にてあれば、奉行の性相体力(しょうそうたいりき)等を如是せるなり。居易(きょい)かってこの蹤跡(しょうせき)をふまざるによりて、三歳の孩児(がいじ)も道得ならんとはいふなり。道得をまさしく道得するちからなくて、かくのごとくいふなり。
あはれむべし居易、なんじ道(どう)恁麼なるぞ。仏風いまだきかざるがゆゑに。三歳の孩児をしれるやいなや、孩児の才生(さいしょう)せる道理をしれりやいなや。もし三歳の孩児をしらんものは、三世諸仏をもしるべし。いまだ三世諸仏をしらざらんもの、いかでか三歳の孩児をしらん。対面せるはしれりとおもふことなかれ、対面せざればしらざるとおもふことなかれ。
一塵をしるものは尽界をしり、一法を通ずるものは万法(ばんぽう)を通ず。万法に通ぜざるもの、一法に通ぜず。通を学せるもの通徹のとき、万法をもみる、一ほうをもみるがゆゑに、一塵を学するもの、のがれず尽界を学するなり。三歳の孩児は仏法をいふべからずとおもひ、三歳の孩児のいはんことは容易ならんとおもふは至愚(しいぐ)なり。そのゆゑは、生をあきらめ死をあきらむるは、仏家一大事の因縁なり。(240~241頁)
■〈現代語訳〉
たとい諸悪が幾重にも全世界を覆い、一切を呑みつくしていようとも、それは莫作で解脱できる。衆善はもともと初・中・終の善であるから、それは奉行でその性も相も体も力もそのまま実現される。居易はまだその境地を踏んだことがないから、三歳の童子もいいうるであろうなどといった。いうべきことをいう力がないのに、そういったのである。
かわいそうに居易よ、なんじは何をいうぞ。まだ仏家の風情をきかないからなのであろう。いったい、なんじは三歳の童子を知っているか。童子が先天的にもっている道理を知っているか。もしよく三歳の童子を知るものは、三世の諸仏をも知っているはずだ。いまだ三世の諸仏を知らないものが、どうして三歳の童子を知っていようぞ。人は対面したから知っていると思ってはならない。また、対面しなければ知らないと思ってはならないのだ。
一塵を知るものは全世界を知り、一事を知るものは全存在を知る。だから、全存在に通じないものは一事にも通じないのである。この道理をよく学びいたる時、人は全存在をもみる。一事をみるがゆえに、一塵を学するものが、かならず全世界を学するのである。三歳の童子は仏法を語ることはできないと思い、あるいは、三歳の童子のいうことはやさしいことと思うのは、愚かさのいたりである。そのゆえは、生をあきらめ死をあきらめるのが、仏教のもっとも大事とするところだからである。(244~245頁)
■〈注解〉
◯江西大寂禅師 馬祖道一(786寂、寿80)、南嶽懐譲の法嗣。
◯頭正尾正 「ずしんびしん」と読む。頭と尾は始と終である。終始一貫、あるいは徹頭徹尾正しいというほどの意である。
◯性・相・体・力 この四つの語は、仏教においてよく用いられる述語であるので、ならべて注しておきたい。性は不易の義にして、変化することのない本質をいう。相は存在の相状であって、その本質のあらわれた姿である。また、体は本体というほどの義であって、力はその顕現した力用(はたらき)をいう。(246~247頁)
有時(うじ)
■〈現代語訳〉
いったい、この世界は、自己をおしひろげて全世界となすのである。その全世界の人々(にんにん)物々をかりに時々であると考えてみるがよい。すると、物と物とがたがいに相(あい)礙(さまた)げることがないように、時と時とが相ぶつかることもない。だから、同じ時に別の発心があることもあれば、同じ発心が別の時にあるということもある。そして、修行や成道についてもまた同じである。自己をおし並べて自己がそれを見るのであるから、自己もまた時だというのは、このような道理をいうのである。
そのような道理であるから、大地のいたるところに、さまざまの現象があり、いろいろの草木があるが、その現象や草木の一つ一つがそれぞれ全世界をもっていることを学ばねばならない。そのように思いめぐらしてみるのが、修行の第一歩である。そして、かの境地に到達してみると、そこにもまたさまざまの現象があり、いろいろの草木がある。そのなかには、わかる現象もわからぬ現象もあるし、また、わからぬ草木もわかる草木もある。だが、どこまでいっても、そのような時ばかりであるのだから、ある時はまたすべての時である。ある草木も、ある現象も、みな時である。そして、それぞれの時に、すべての存在、すべての世界がこめられているのである。ときには、いまの時にもれる存在や世界があるかないかと考えてみるのもよかろう。(254~255頁)
■〈注解〉
◯有 仏教において有というのは“bhava”(=beinng)の訳語であって、今日いうところの存在というほどの意である。その有を時に冠して有時というがゆえに、あるいは「時すでに有なり」と説き、あるいは「有みな時なり」と語って、そこから、存在と時間の問題を語りいでる。その導入のおもしろさを思うべきである。(256頁)
■〈現代語訳〉
いまもいうとおり、山を登り、河を渡った時に、われがあったのである。そのわれには時があるであろう。そのわれはすでにここに存する。とするならば、その時は去ることはできない。もしも時に去来(こらい)する作用がなかったならば、山に登った時のある時は「いま」であろう。もしも時が去来する作用を保っているとしても、なおわれにある時の「いま」がある。それが有時というものである。かの山を登り河を渡った時は、この玉殿朱楼の時を呑み去り、また吐き出すのであろうか。
三面・八臂はきのうの時であった。丈六・八尺は今日の時であった。だが、その昨日のことも今日のことも、真一文字に山のなかに入りきたって、いま千峰万峰を見渡している。その時はすでに去ったわけではないのである。三面・八臂もわがある時として過ぎ去った。だが、それは彼方にあるようであるが、また「いま」なのである。丈六・八尺もまたわがある時として経過した。だが、それも彼方に過ぎ去ったようであるが、また「いま」なのである。
とするなれば、松も時であり、竹も時である.時は飛び去るとのみ心得てはならない。飛び去るのが時の性質とのみ学んではならない。もし時が飛び去るものとのみすれば、そこに隙間が出てくるであろう。「ある時」ということばの道理にまだめぐり遇えないのは、時なただ過ぎゆくものとのみ学んでいるからである。(258頁)
■〈注解〉
◯而今 いま。今という今というほどの意であろう。したがって、「有時の而今」といえば、ある時にしてしかも「いま」なる時というほどの意であって、いま道元がここに語りいでる時間論の最大の急処がそこにあるといってよいであろう。(259頁)
■〈現代語訳〉
これを要約していえば、あらゆる世界のあらゆる存在は、連続する時々(じじ)である。だが、それはまたある時であるから、またわがある時である。そのある時に経(へ)めぐる作用がある。いうところの今日から明日に経めぐる。今日から昨日に経めぐる。昨日から今日に経めぐる。また、今日から今日に経めぐり、明日から明日に経めぐる。その経めぐることは時のはたらきであるから、古今の時が相重なることもなく、積もるわけでもなく、ただ、青原も時であり、黄檗(おうばく)も時であり、江西(こうぜい)も石頭も時である。自他それぞれがすでに時であるから、また修行も時、証得も時であり、泥に入り水をわたって人々のために法を説くのも、また同じく時である。(261頁)
■〈現代語訳〉
また、時はただ一向に過ぎゆくものとのみ考えて、そのいまだ到らざるを理解しないものがある。理解もまた時ではあるけれども、時を待てば理解が生れてくるわけでもない。そこで、時はただ去来(こらい)するものとのみ心得て、ある時とは物のありよう事のありようだと見透(みとお)す人はない。それではとても悟りの難関を突破する時はありえない。(262頁)
■〈注解〉
◯青原 青原行思(740寂、寿不詳)、六祖慧能の門下。南嶽とともにその法を嗣ぐ。それより南宗禅に、青原下と南嶽下の二つの流れがあることとなった。吉州青原山に住し、青原の名をもって呼ぶ。諡(おくりな)して弘済禅師と称する。
◯黄檗 黄檗希運(850寂、寿不詳)、百丈懐海の法嗣。黄檗山に住し、その名をもって知られる。諡(おくりな)して断際禅師と称する。
◯江西 馬祖道一(785寂、寿80)、南嶽の流れをくむ。世に江西(ぜい)の馬祖と呼ばれた。大寂禅師と諡(おくりな)する。
◯石頭 無際希遷(790寂、寿91)、青原の流れをくむ。衝山南寺の石上に庵をむすび、時の人が石頭和尚と呼んだ。江西の馬祖、湖南の石頭とならび称された。
◯究尽 『法華経』巻一、方便品に、「唯仏与仏、乃能究尽、諸法実相」(ただ仏と仏、すなわち能く諸法の実相を究尽す)というよく知られた一句がある。それを踏まえて、諸法の実相を究尽するというのは、「全世界をもって全世界を究め尽くすことだ」といい、それが仏にほかならないと語るのである。(263~264頁)
■〈現代語訳〉
思うに、経めぐり来るといえば、風の吹き来り、雨の降り去るように思うであろうが、そんなふうに考えるべきではない。この世界はすべて、変転せぬものはなく、去来せざるものはなく、みな経めぐり来るのである。そのありようは、たとえば春のようなものである。春にはいろいろの様相がある。それを経めぐるというのである。春のほかには何物もないのに、ただ春がめぐり来るというのである。たとえていえば、春の推移はかならず春を経きたるのである。春の移りゆきが春ではないが、それは春の推移であるから、経めぐり来って、いま春の時にあたって、春が実現するのである。つまびらかに思いいたり、思い去るがよい。その推移経過を語るにあたって、外界の対象はこれを外にして、別になにか経めぐるものがあり、それが幾世界を過ぎゆき、幾歳月を経めぐり渡るように思うには、なお仏道をまなぶに専一ならぬからである。(265~266頁)
■〈現代語訳〉
山も時である.海も時である。時にあらざれば、山も海もあることはできない。山や海の「いま」に時はないと思ってはならぬ。時がもしなくなれば、山海もなくなる.時が壊(え)せざるものであれば、山海も不壊(ふえ)なのである。この道理があって、はじめて明星が出現するのであり、如来の出世(せ)あるのであり、また開眼(げん)のことがあり、拈華(ねんげ)のことがあり得るのである。それが時というものであり、時にあらざれば、そのようなことはとてもあり得ないのである。(268~269頁)
■〈注解〉
◯薬山弘道大師 薬山惟儼(834寂、寿84)は石頭希遷(無際大師)の法嗣(ほっす)。諡(おくりな)して弘道大師と称する。
◯無際大師 石頭希遷、青原行思の法嗣(ほっす)。江西(ぜい)の馬祖とならんで湖南の石頭と称せられた。諡(おくりな)して無際大師と称する。
◯江西大寂禅師 馬祖道一、南嶽懐譲の法嗣(ほっす)。ここでは、湖南の石頭がその弟子を江西の馬祖にいたって問わしめておる。(269頁)
袈裟功徳(けさくどく)
■〈注解〉
◯正法像法 正法は正しい仏法。像法はそのすがたのみ似ている仏法。(282頁)
■〈原文〉
まことにわれら辺地にうまれて末法にあふ。うらむべしといへども、仏仏嫡嫡(ちゃくちゃく)相承(じょう)の衣法(えほう)にあふたてまつる、いくそばくのよろこびとかせん。いづれの家門にかわが正伝のごとく、釈尊の衣法とともに正伝せる。これにあふたてまつりて、たれか恭敬(くぎょう)供養せざらん。たとひ一日に無量恆(ごう)河沙(がしゃ)の身命をすてても、供養したてまつるべし。(282~283頁)
■〈注解〉
◯摩訶迦葉 仏十大弟子の一人。仏滅後の第一結集(じゅう)の主宰者として有名である。禅家においては、付法の第一祖として、特に尊崇せられる。
◯青原・南嶽 六祖慧能のもとに、青原行思(740寂、寿不詳)と南嶽懐譲(744寂、寿68)の二人の法嗣があり、それより禅門の南宗に二つの教系があり、それぞれ青原下・南嶽下と名のるにいたる。(287~288頁)
■〈注解〉
◯教・行・人・理 教は仏の教法、行はそれによる修行、人はその主体たる人であり、理はその人によりて悟られるまことの理である。
◯作・無作 作(さ)は自作、自然のままならず、人為の加われるをいう。有為ともいう。それに対して、無作は、無為にして自然のままなることをいう。(297~298頁)
■〈注解〉
◯鮮白比丘尼 また蓮華色比丘尼という。(305頁)
■〈注解〉
◯三乗 声聞乗・縁覚乗(以上は小乗)・菩薩乗(大乗)をいう。それが仏教のすべてであるがゆえに、三乗の語をもってすべての仏教をいうのである。(313頁)
■〈注解〉
◯欲色 欲界(人間のすむ欲望の世界)と色界(物象の世界)の意。人天の住むところであるとする。
◯盧行者 六祖慧能のことである。慧能はその姓を盧氏といった。はじめ五祖弘忍のもとにあって行者であった。行者とは、禅院にあって、いまだ出家得度せず、寺中の諸役の僧のもとにあって、雑役に従事する者をいう。しかるに、その慧能がやがて五祖を嗣いで六祖となり、仏祖の袈裟を正伝することとなった。(334頁)
■〈注解〉
◯慚愧 心に恥じ、人に恥じる心である。
◯良田 福田に同じ。そこに種蒔けば稔り多い田である。(340頁)
伝衣(でんえ)
■〈注解〉
◯卞璧 また、卞和璧(べんかへき)(べんかのたま)という。卞和なる者があり、名玉を得て楚王に献じたが、王は信ぜずして、彼を処した。のち、、玉人をして磨かせてみると、まさしく名玉であって、これを国璽(こくじ)としたという。その故事によって、卞璧の語をもって、最高の名玉をいうのである。
◯道士の教に…… 中国の国主のなかには、幾人かの仏教を排斥したものがあった。北魏の太武帝、北周の高祖武帝、唐の武帝、および後周の世宗が、その代表的な存在であった。これを山武一宗という。その廃仏の理由にはいろいろとあったが、なかでも道教を崇敬するの故をもって、仏教を斥けたものが多かったのである。(361頁)
■〈原文〉
わが大師釈迦牟尼如来は、正法の眼睛たる無上の悟りを摩訶迦葉に授けるにあたり、仏衣とともにそれを伝授した。それより仏々祖々に相伝して、曹谿山(ざん)の大鑑禅師にいたるまで、実に三十三代である。その布も色も寸法も、直々に見、直々に頂いて、その家門に伝えてきたり、いまなお受持されているのである。詮ずるところ、五家(け)の祖師がたそれぞれに受持するところはその正伝である。あるいは五十余代、あるいは四十余代と、それぞれ師から弟子へと乱るるところなく、先仏の法にしたがって製作する。それもまた、仏と仏の間のぴたりとした相伝であって、代に代を重ねて依然として新たである。(371頁)
■〈注解〉
◯三蔵の学者 三蔵とは、経(教法)・律(戒律)・論(注釈と理論)の各蔵をいう。それらに通じている学僧を、また「三蔵」という。
◯五宗 また五家(け)という。禅の五つの流派すなわち臨済宗・溈仰宗・曹洞宗・雲門宗・法眼宗をいったものである。
◯百丈大智禅師 百丈懐海(814寂、寿95)、馬祖道一によって得法。百丈山に住し、はじめて禅院の規範をつくった。世にこれを百丈清規(しんぎ)という。
◯授記 成仏の予言を与えること。
◯不退不転 また不退あるいは不退転という。“avinivartaniya”(音写して阿毘跋致)の意訳であって、仏道修行の道程においてもはや退転することなきをいう。
■〈現代語訳〉
また、仏衣のありようを明らかに知るのも、ただ仏祖の万にあるもののみである。他門のものは知らない。それを知らない者が、おのれを恨まなかったならば、それは愚かというものである。なんとなれば、たとい三昧に通じ、陀羅尼を知っていようとも、仏祖の衣法を正伝せず、袈裟のいわれを知らなかったならば、それは諸仏の正しい法嗣(ほっす)ではありえないのである。
他の国々の人は、仏衣が中国のように、自分の国にも正伝されることを、どんなにか願っていることであろう。自国に正伝がないことには、恥ずかしい思いをし、悲しむ心も深いであろう。まことに、如来世尊の衣法の正伝に遇うなどとは、宿世に植えた仏智の大いなる功徳の種子(しゅうじ)によるものに他ならないからである。しかるに、いま末法の悪世にして、おのれに正伝なきことを恥じず、かえって正伝をそねむ輩のみが多い。自己のいま有するところも住(とど)まるところも、それは真実のおのれというものではない。ただ、正伝を正しく伝え受けるならば、それが仏法を学ぶ直道(じきどう)というものである。(382頁)
■〈注解〉
◯十聖・三賢 十聖とは、菩薩行の十地(じゅうじ)にまでいたった者、それ以前の三十位までいたれる者を三賢という。ここでは、まだ究極の仏位にいたらぬ者という点に重点が置かれている。
◯三昧・陀羅尼 三昧は“samadhi”の音写。意訳して定(じょう)という。心を一処に定めて動ぜざらしめる行法である。陀羅尼は、“dharani”の音写。意訳して持(じ)もしくは能持となす。善法を散ぜしめず、悪法を起こらしめないとの意である。特に聞くところの文句を憶持(おくじ)して忘れず、それを陀羅尼とすることが広く行われている。(383~384頁)
■〈現代語訳〉
そのむかし、かの黄梅山(おうばいざん)の夜半にあって、六祖慧能は仏の衣法をいただうて正伝した。それこそ、まことに正法と仏衣の正伝であった。五祖がよく人物をみる目があったからである。小乗の聖者や、三賢・十聖(じっしょう)のたぐい、あるいは、教家の論師(じ)・経師(きょうじ)のやからであったならば、おそらく神(じん)秀に授けて、慧能には伝えなかったであろう。だが、仏祖を選ぶ時には、おのれを知っている趣は、いい加減に推し測りうるところではないのである。(392頁)
■〈注解〉
◯神秀 慧能と同じく五祖弘忍の弟子であり、その首座(そ)であったが、五祖の衣法は慧能に授けられた。そのために、傍出の法嗣となり、いでて北宗禅の祖となった。(394頁)
■〈現代語訳〉
この糞掃衣を用いるのは、ただいたずらに弊衣(へいい)を着て、みすぼらしいさまをするためと思うのは、愚かのいたりともいうものである。むしろ荘厳(しょうごん)にして整々たるために、仏道にこれを用いて来たのである.仏道においてやつれた服装というのは、錦や綾や、金銀や珠玉をちりばめた衣服が、不浄の動機に由来しているのをこそ、みすぼらしいとはいうのである。おおよそ、この世界とかの世界をとわず、仏道において清浄にして整々たるものを用いようとするならば、まさにこの十種がそれであろう。それは、浄・不浄の常識を超えているのみではなく、また、煩悩のありなしを超え、形と心とを問わず、得と失とを超越しているのである。ただこれを正伝し受持するものはすなわち仏祖である。仏祖となる時にはかならずこれを伝え受けるのだからである。仏祖としてこれを受持するとは、これをわが身に現ずるかどうかでもなく、また心にこれを挙げるかいなかでもなく、ただ正伝せられてそうなるのである。(398頁)
■〈現代語訳〉
宋国の嘉定(かてい)十七年(1224)の冬十月中のこと、朝鮮の僧二人が慶元府にやってきた。一人は智玄、一人は景雲(きょううん)といった。その二人とも、しきりに経典の文意などを語っていたが、そのうえ彼らはまた文章の人であった。だがしかし、袈裟もなく、鉢ももたず、俗人のようであった。かわいそうに、比丘の形はしていても、比丘の法がととのっていなかった。辺地の小国から来たからなのだろう。わが国の比丘の姿をしている人々も、他国にゆけば、またかの二人にひとしいであろう。
釈迦牟尼仏は、その修行の十二年の間、瞬時も袈裟をはなされたことはなかった。いまわたしどもは、その遠き弟子として、それを学ばねばなるまい。いたずらに、名利のために、天を拝し、王を拝し、臣を拝しているその頭をめぐらして、よく仏衣をおし頂くこととなるならば、それはまことに喜ぶべきことなのである。(404頁)
道元を見つめて(私の道元研究史)
■わたしは、もともと宗教学を専攻してきた人間であるから、ひろくもろもろの宗教を検討する機会をもってきたのであるが、いずれの宗教を調べてみても、結局、「人は二人の主に兼ね仕えることはできない」ことを教えている。キリスト教のことばをもっていうなれば、「神とマンモンには兼ね仕えることができない」のである。道をもとめることと富を求めることとは、詮ずるところにおいて両立しない。そのことを道元禅師もまた、口を酸ぱくしていっておられるのだということに気がついて、やっとほっとしているところである。
まず衣食の心配がないようにしておいて、それから心おきなく勉強しようなどというものがあれば、いまのわたしは、はっきり、「君は学問をする資格がない」ということができる。それは道元禅師のそれらのことばに教えられてのことである。「貧なるが道に親しきなり」その意味がやっと朗然として解ってきた。だが、そこまでくるのにわたしはどうやら三十年かかった。その間ずっと、わたしは道元禅師のそれらのことばを抱きつづけていた。この禅師のことばは、そのような重さをもっている。そのような堅確なものを蔵している。そのことを、わたしは、それらのことばによって思い知らされたのである。(410頁)
■「いまこの坐禅の坐禅の功徳、高大なることをききをはりぬ。おろかなる人うたがふていかん。仏教におほくの門あり。なにをもてかひよへに坐禅すすむるや。
しめしていはく、これ仏教の正門なるをもてなり。
とふていはく、なんぞひとり正門とする。
しめしていはく、大師釈尊、まさしく得道の妙術を正伝し、また三世の如来、ともに坐禅より得道せり。このゆゑに、正門なることをあひつたへるなり。しかのみにあらず、西天東地の諸祖、みな坐禅より得道せるなり。ゆゑにいま正門を人天(にんでん)にしめす」(418頁)
■たとえば、「弁道話」の巻のよく知られた問答の一節には「修証一等」なることを語って、「すでに修の証なれば証にきはなく」と示している。それは、平たくいえば一修すれば一証ありということである。『正法眼蔵』の巻々のなかでも、人間には生涯一度の証があるのではなくて、十度の証があり、百度の証があり、千度万度の証があるべきだというようなこともしばしば説いておられる。それを裏返していえば、さらに「道(どう)は無窮なり」ということともなる。(420頁
(2018年2月2日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『正法眼蔵(2)』増谷文雄 全訳注 講談社学術文庫
山水経(さんすいきょう)
■〈開題〉
この「山水経」の巻は、仁治元年(1240)の冬十月十八日、例によって興聖宝林寺にあって衆に示されたものである。その真蹟(せき)の草稿は、今日なお愛知県豊橋市の全久院に蔵せられて存している。
この巻題は、珍しいことに、「山水経」と経の一字が付されている。そのような例は、『正法眼蔵』の巻々はいうまでもなく、道元のその他の制作にも見ざるところである。では、「山水経」というこの巻題はなにを意味するか。それは、山水を経とする、もしくは、山水こそ経であるということでなくてはならない。その由(よし)は、まず冒頭の、
「而今(にこん)の山水は、古仏の道現成なり.ともに法位に住して、究尽(ぐうじん)の功徳を成ぜり」
の一句に遺憾なく吐露せられてある。そこには、「古仏の道現成なり」という。その「道」の一字は、わたしがこの巻の現代語訳においてもっとも苦慮したところであることを告白しなければならない。
「道」とは、「みち」であり、「条理」であるとともに、また「いう」であり、「ことば」である。かって中国人が『新約聖書』の「ヨハネ伝福音書」を訳するにあたって、その冒頭の一句を、「元始有道」(日本語訳では「太初(はじめ)に言(ことば)あり」である)と訳したことを、わたしは印象ぶかく憶えている。その「道」とは「ロゴス」を訳したものである。「ロゴス」にもまた、「条理」の意とともに、「ことば」の意がふくまれている。しかるに、日本語には、悲しいかな、そのふたつの意を併せふくんだことばがない。わたしは熟慮の結果、その「道」を「ことば」と訳して、「いまの山水は、古仏のことばの顕現である」とした。だが、その「ことば」はまた「条理」によって貫かれたものと承知していただかねばならぬ。それでこそ、はじめて「いずれも法に即して、その功徳を究め尽したものである」と続くことができるのであり、また、それでこそ、はじめて山水が経であるとの意が生きてくるのである。
もう一つ、この巻において特に注目していただきたいことがある。それは、この巻の前半、雲門のことばの「東山水上行(とうざんすいじょうこう)」なる句を釈する条(くだり)において、禅話の理会(りえ)・不理会について論じていることである。理会とは、今日のことばをもってすれば、おおよそ理解というにあたる。しかるところ、今日もなおしばしば聞き及ぶところであるが、仏祖の禅話はもともと判らないものであるという。それが禅家の常套語である。それに対して、道元は、そのような言説は「杜撰(ずさん)のやから」どものいうところであって、「禿子(とくし)がいふ無理会話、なんぢのみ無理会なり、仏祖はしかあらず。なんぢに理会せられざればとて、仏祖の理会路(ろ)を参学せざるべからず」という。そこには、世のつねの禅家とは、まったく異なれる道元の立場があることがしられる。
なるほど、道元の文章はむつかしい。特にこの『正法眼蔵』は難解至極である。わたしもその現代語訳をはじめて、日々悪戦苦闘の連続である。だが、わたしどもは決して、ついに理解しがたいものを読んでいるのでも、訳しているのでもない。道元その人もまた、なにとぞして理解させようとして、語をかさね句をつらねているのである。繰り返し繰り返ししてよんでいると、その気持ちが判るのである。それにも拘らず、それがなお鮮明ならぬのは、ひとえに、わたしどもの教養のせまさ、心境のひくさによるもの。さらに、年をかさねて「仏祖の理会路を参学す」るならば、この天下第一の難解の書にも、ついによく「山に梯(はしご)し、海を航する」の日を期することもできようというものである。なんとなれば、それは畢竟して「理会およびがたい」ものではないからである。そのことを、道元その人がその一節において保証しているのである。
さて、この一巻のいわんとするところは、きわめて明快である。まず、さきにいうがごとく、山水は「古仏の道現成」なることが、その冒頭に打ち出される。それは法に即したものだからである。
ついで、そのような仏教の見地から、凡情をとおく越えた山の見方、水の考え方が、つぶさに解説される。山が歩くといい、水は流れるとのみ見るべきではないと語るのは、そのような見地からの見方、考え方なのである。
さらに、山水が大聖の居(いま)すところであることが、事例をもって語られたのち、「かくのごとくの山水、おのづから賢をなし聖(しょう)をなすなり」と結語せられる。それがすなわち、山水こそ経であるとするこの一巻の趣としられるのである。(14~18頁)
■〈原文〉
而今(にこん)の山水は、古仏の道現成なり。ともに法位に住して、究尽(ぐうじん)の功徳を成ぜり。空劫已然(くうごういぜん)の消息なるがゆゑに、而今の活計なり。朕兆未萌(ちんちょうみぼう)の自己なるがゆゑに、現成の透脱(とうだつ)なり。山の諸功徳高広なるをもて、乗雲の道徳、かならず山より通達す。順風の妙功、さだめて山より透脱するなり。(17頁)
〈現代語訳〉
〔山水の功徳〕
いまの山水は、古仏のことばの顕現である。いずれも法に即して、その功徳を究め尽したものである。それはこの世界の成立の以前の消息であって、いまもなお活きているのであり、万物のきざしもない古(いにしえ)からのことであるから、その顕現は古今をつらぬくものである。かくて、山のもろもろの功徳は高大かつ無辺であるから、あるいは雲に乗って到り、あるいは風に順(したが)ってはたらき、自由自在にして到らざるはないのである。(17頁)
■〈注解〉
◯空劫 仏教の世界観は、連続の世界観であって、成(じょう)・住・壊(え)・空の四劫の繰り返しである。とするならば、いまの世界の成立のまえは空劫であって、万物は滅して何ものも存しなかったはずである。つまり、空劫已然とは、この世界の成立以前ということである。(18頁)
■〈現代語訳〉
〔山の運歩を疑うなかれ〕
太陽山の道楷和尚は衆に示していった。
「青山はつねに運歩し、石女はよる児を生む」と。
山はつねにあらゆる功徳をそなえている。そのゆえに、つねに安住し、またつねに歩くのである。その運歩もいとなみをつまびらかにまなぶがよい。山が歩くといっても、それは人間が歩くのとはちがう。だが、人間が歩くのとおなじでないからとて、山の歩くことを疑ってはならない。いま仏祖の説くところも、すでに山の歩くことを語っている。それは物の根本を抑えているからである。「つねに運歩す」とこの垂示をよくよく思いめぐらしてみるがよい。歩くがゆえに常なのである。青山の運歩はその疾(はや)きこと風よりも速やかであるが、山中の人は気づかず知らづである。山中とは、この世界の中の森羅万象である。山外の人もまた知らず気づかない。山を見るまなこのない人は、気づかず、知らづ、見ず、聞かざるが道理というものである。
もし山の運歩を疑うならば、それは自己の運歩をもまだ知らないのである。自己にも運歩がないわけではない。まだ運歩を知らないだけである。それを明らかにしないだけである.自己の運歩を知っているなら、きっと青山の運歩を疑うなどとはありえないことである。いろいろの世界を基準として青山を考えてみることを知らないからである。よくよく青山の運歩、ならびに自己の運歩をしらべてみるがよい。進歩のみならず、退歩をもしらべてみるがよい。この世界のはじめのかの時から、乃至は、まだ万物のなかったかの時から、あるいは進歩し、あるいは退歩して、その運歩のしばらくも休(や)む時のないことを点検してみるがよいのである。(21~22頁)
■〈注解〉
◯有情・非情 有情は“sattva”(=the living beinng)の訳。また衆生である。生類の意。生き物は情識を有するがゆえに有情と訳するのである。無情もしくは非情はその対である。いま道元は、青山をもって「有情にあらず、非情にあらず」といい、また自己もしかるという。その凡慮を超えた所見を学びいたらねば、山の運歩などのことは理解できないであろう。
◯量局 量は“pramana”(=standard,scale)の訳。尺度、基準の意。局はちぢこまるの意。(24頁)
■彼らは、いまの「東山水上行」の話や、南泉の「鎌子」の話などは、無理会話(えわ)というものだという。その意味は、もろもろの思惟にかかわれる語話は、仏祖の禅話というものではなく、理解のできない話こそ仏祖の語話だというのである。さればこそ、黄檗の棒や、臨済の喝などは、理解のおよびがたく、思惟のかかわるところでないが、これこそ無始以前の大悟というものである。先徳の手段がたいてい、煩わしき言辞を離れて、ずばりとした句をもってするのは、それが無理会だからであるというのである。
そのようなことをいう輩どもは、いまだかって正師にまみえたこともなく、仏法をまなぶ眼もまく、いうに足りない小さな愚か者である。宋国では、この二、三百年このかた、そのような不埒(ふらち)なにせものの仏教者がおおい。こんなことでは仏祖の大道はすたれてしまうと思うと悲しくなる。彼らの解するところは、小乗の徒にもなお及ばず、外道よりも愚かである。俗にもあらず、僧にもあらず、人間でもなく、天上の者でもなく、仏道をまなぶ畜生よりも愚かである。汝らがいうところの無理会話とは、汝らにのみ理解できないのであって、仏祖はけっしてそうではない。汝らに理解できないからとて、仏祖の理路はまなねばならないのである。もしも畢竟するところ理解できないものならば、汝がいうところの「理会」ということもありえないのである。
そのようなたぐいの輩が、いまの宋土の諸方におおく、わたしも目(ま)のあたりに見聞したことがある。かわいそうに彼らは、思惟は言語であることを知らないのであり、言語が思惟をつらぬいていることを知らないのである。わたしはかって宋にあったころ、彼らを嘲笑(あざわら)ったことがあるが、彼らはなにごともいうことができず、ただ黙っているだけであった。彼らがいう「無理会」とは、一つの邪計にすぎないのである。誰がそんなことを彼らにおしえたのか。本物の師がなかったから、おのずからにして外道の見解におちたのであろう。(28~29頁)
■〈注解〉
◯杜撰 疏漏(そろう)にして誤りのおおいことをいうことば。もと杜黙(ともく)なるものの作詩がよく韻をまちがえていたという故事による。道元は宗の禅僧たちの綿密ならぬ考え方を評して、しばしばこのことばを用いている。
◯魔子・六群・禿子 魔子は悪魔のやから、六群は六群比丘とて、しばしば戒を破った比丘たち、禿子は外形のみ僧形にして、その心事のしからざる者をいうことば。それらのことばを連ねて、仏法を毒するにせものの仏教者というほどの意を表している。(30~31頁)
■〈現代語訳〉
〔水は流れるとのみ見るべからず〕
およそ山水をみるにも、類(たぐい)にしたがってさまざまである。たとえば、水を瓔珞(ようらく)と見るものもある。だが、瓔珞が水であるとするのではない。わたしどもがああと思いこうと見るところを、彼らは水と見るのであり、彼らが瓔珞と見るところを、わたしどもは水と見るのである。(35頁)
■仏いわく、
「一切の諸法は、畢竟して解脱にして、住するところあること無し」
それによっても知られるように、自由にして繋縛(けばく)されることなくとも、もろもろの物は存在している。それなのに人が水を見る時には、ただ流れて止まらずとのみみる一途である。その流れ方にもさまざまあって、人の見るところはその一端のみである。すなわち、地を流れ、空を流れ、上にむかって流れ、下にむかって流れる。里にも流れ、淵にも流れる。昇っては雲を為し、下っては淵をなす。(37頁)
■水のいたらぬところがあるというのは、小乗のやからのいうところであり、あるいは外道のまちがった教えである。水は火焔のなかにも存し、思惟・思索・分析のなかにもあり、覚知する仏性のなかにもいたるのである。(37~38頁)
■かくて、仏祖のいたるところところには、かならず水がいたり、水のいたるところには、かならず仏祖が現われる。それによって、仏祖はかならず水をとりあげて、これを身心となし、これを思索の糧(かて)とする。だから、水は上にのぼらないなどとは、内外の文献にも見えない。水の道は上下に通じ、縦横に通ずるのである。
それなのに、仏教の経典には、時に、火と風は上にのぼり、地と水は下にくだるという。その上下について研究してみると、それは仏道の上り下りをいうのである。つまり、地と水のゆくところを下とするのであって、下を地と水のゆくところとするのではない。また、火と風のゆくところを上であるとするのみである。この世界のありようは、かならずしも上・下・四方の基準によるものではなくて、かりに、四大・五大・六大などの行くところによって、その方角を定めているだけである。無想天は上にあり、阿鼻獄は下にあるとするのではない。阿鼻獄はどこにもある。無想天はどこにもある。
それだから、龍魚が水を宮殿と見るのは、人が宮殿を見るようなものであろう。けっして流れ行くものとは思えないであろう。もし傍(かたわら)にあって観る者が、汝の宮殿は流れる水ではないかといったとしても、それはわたしどもが「山は流れる」ということばを聞くとおなじであって、竜魚はただびっくりして目を疑うのみであろう。あるいは、さらに宮殿楼閣の欄干はこう、円柱はこうといい張るかもしれない。そこの道理をよくよく思い来り、思い去ってみるがよい。(38~39頁)
■いま仏教をまなぶ人々は、水を考える場合にも、ひたぶるに人間の立場に固執(しゅう)してはならない。すすんで仏教の水の考え方をまなぶがよい。仏祖がもちいるところの水を、自分はどう考えているのか。また、仏祖の家においては、水があるかないか。そのようなことをまなびいたるがよろしい。(39~40頁)
■〈注解〉
◯地・水・火・風・空・識 これを六大という。大とは“mahabhuta”の訳語であって、この世界を構成する原素をいう。それに四大(地・水・火・風)を立てるもの、五大(地・水・火・風・空)を立てるもの、六大を立てるものがある。
◯色・声・香・味・触・法 六境すなわち眼・耳などの六つの感官の対象をあげたものである。(40頁)
■〈現代語訳〉
〔山は大聖(だいしょう)の居(いま)すところ〕
山ははるかなる古より大聖の居すところである。賢人・聖(しょう)者はともに山を住いとし、山を身心となした。賢人・聖者によって山はその意味を実現したのである。いったい、山にはどれほどの大聖・大賢が入ったことであろうかと思うのであるが、山に入ってからは、誰もたがいに相逢うようなことはなかった。ただ山のはたらきが現れるのみである。山に入った跡さえものこってはいないのである。
さて、世間にあって山を眺める時と、山中にあって山と相逢う時とでは、その顔つきも眼つきもはるかにちがっている。人は山は流れぬという。その憶測・知見は、すでに龍魚のそれと同じではない。人間が自分の世界にあって考えていることは、他類のものの疑うところ、あるいは疑ってもみないところであろう。だから「山はながれる」という仏祖のことばをまなぶがよいのである。ただ驚き疑うにまかせておいてはならぬ。その一つをとれば「流れる」であり、他の一つをあぐれば「流れぬ」である。ある時は「流」であり、またある時は「下流」である。そこをまなび究めなくては、如来のおしえは判らないのである。古仏はいう、「無間業(むげんごう)を招かざることを得んと欲せば、如来の正法輪(しょうぼうりん)を謗ずることなかれ」と。このことばをふかく骨髄に銘ずるがよい。身心に銘ずるがよい。空に銘ずるがよく、地に銘ずるがよい。それはすでに、樹に刻み石に刻み、あるいは野に説き里に説いて経としてのこされてある。(43~44頁)
■とするならば、水はすなわち真龍の住むところであって、それはただ流れ落ちるのみではない。流れるのみだというのは、そのことばがすでに水を謗(そし)っているのである。だから、たとえば、水は流るるにあらずと無理にもいわねばならぬのである。水は水のあるがままの姿でよいのである。水は水そのものであって、流れではないのである。一つの水の流るるを究わめ、流れざるを究むれば、あらゆる存在を究め尽くすことも、またたちまちにして成るのである。(48頁)
仏祖(ぶっそ)
■〈現代語訳〉
〔歴代の仏祖〕
毘婆尸(びばし)仏大和尚 訳して広説となす。
尸棄(しき)仏大和尚 訳して火なす。
毘舎浮(びしゃぶ)仏大和尚 訳して一切慈となす。
拘留孫(くるそん)仏大和尚 訳して金仙人となす。
拘那含牟尼(くなごんむに)仏大和尚 訳して金色仙となす。
迦葉(かしょう)仏大和尚 訳して飲光(おんこう)となす。
釈迦牟尼(しゃかむに)仏大和尚 訳して能忍・寂黙となす。
摩訶迦葉(まかかしょう)大和尚
阿難陀(あなんだ)大和尚
商那和修(しょうなわしゅ)大和尚
優婆(毛ヘンに菊)多(うばきくた)大和尚
提多迦(だいたか)大和尚
弥遮迦(みしゃか)大和尚
婆須密多(ばしゅみった)大和尚
仏陀難提(ぶっだなんだい)大和尚
伏駄密多(ふだみった)大和尚
波栗湿縛(はりしば)大和尚
富那夜奢(ぶなやしゃ)大和尚
馬鳴(めみょう)大和尚
迦毘摩羅(かびまら)大和尚
那伽閼刺樹那(ながありじゅな)大和尚 また龍樹あるいは龍勝、龍猛となす。
伽那提婆(かなだいば)大和尚
羅睺羅多(らごらた)大和尚
僧伽難提(そうぎゃなんだい)大和尚
伽耶舎多(がやしゃた)大和尚
鳩摩羅多(くまらた)大和尚
闍夜多(じゃやた)大和尚
婆修盤頭(ばしゅばんず)大和尚
摩拏羅(まぬら)大和尚
鶴勒那(かくろくな)大和尚
獅子(しし)大和尚
婆舎斯多(ばしゃした)大和尚
不如蜜多(ふにょみった)大和尚
般若多羅(はんにゃたら)大和尚
菩提達磨(ぼだいだるま)大和尚
慧可(えか)大和尚
僧璨(そうさん)大和尚
道信(どうしん)大和尚
弘忍(こうにん)大和尚
慧能(えのう)大和尚
行思(ぎょうし)大和尚
希遷(きせん)大和尚
惟儼(いげん)大和尚
曇晟(どんじょう)大和尚
良价(りょうかい)大和尚
道膺(どうよう)大和尚
道丕(どうひ)大和尚
観志(かんし)大和尚
縁観(えんかん)大和尚
警玄(けいげん)大和尚
義青(ぎせい)大和尚
道楷(どうかい)大和尚
子淳(しじゅん)大和尚
清了(せいりょう)大和尚
宋玨(そうかく)大和尚
智鑑(ちかん)大和尚
如浄(にょじょう)大和尚
わたし道元は、大宋国の宝慶(ほうきょう)元年(1225)の夏安居の時、先師なる天童古仏大和尚に参じて侍し、この仏祖を礼拝し頂載することを究めつくした。まさに、ただ仏と仏とのあいだの相承(じょう)である。
正法眼蔵 仏祖
この時、仁治二年正月三日、日本国雍(よう)州(京都)宇治県観音導利興聖宝林寺に書して、衆に示した。(58~61頁)
■〈注解〉
※歴代の仏祖を語って、わが相承を示すのである。
◯先師天童古仏 天童如浄(1228寂、寿66)のことである。先師とは、すでになくなった師をいうことばであり、天童とは、如浄が住持として住していた天童山景徳寺に由来する称であり、古仏というは、道元がもっとも敬重する仏祖に対して用いる敬称であると知られる。道元は、いうまでもなく、天童如浄の法嗣(ほうし)であって、いま先師天童古仏大和尚の一句には、最高の敬慕の念がこめられている。(62頁)
嗣書(ししょ)
■証するところがぴたりと相契(かな)う仏祖でなかったならば、仏の智慧とはいえない。祖師の究めるところとはいえない。仏の智慧でなかったならば、仏を信受するものではなく、祖師の究めるところでなかったならば、祖師の証するところと相契(あいかな)うはずはない。(70頁)
■釈迦牟尼仏は、ある時、阿難陀をして問わしめたことがある。
「過去の諸仏は、いったい、誰の弟子でありましょうか」
釈迦牟尼仏は答えていった。
「過去の諸仏は、みなわが釈迦牟尼仏の弟子である」
諸仏の仏なる所以(ゆえん)はかくのごとくであるのである。(71頁)
■〈注解〉
※この一段は、嗣法(しほう)ということの何たるかを語っている。その要点は、例によって、最初の一節に打ち出されているが、なかでも、単伝といい、証契(かい)という二句が、もっとも重要である。単伝とは、一人から一人へと仏心印が伝えられることをいう。仏心印とは、悟りの当体をいうことばであり、それが決定的にして不変であることを印の一字をもって示している。したがって、いずれの仏、いずれの祖のさとりも、ぴたりと相契(あいかな)えるものでなくてはならぬ。証契(しょうかい)とはそのことをいう句である。この一段に力説するところは、畢竟するにその一点に帰する。(71頁)
■〈注解〉
◯天然外道 また自然外道という。すべては自然にして成るものとの主張を有する思想家の一群である。(74頁)
■〈現代語訳〉
〔嗣書を見る〕
わたしは、宋にあったころ、嗣書(ししょ)を拝すことができたが、いろいろの嗣書があった。そのなかでも、惟一西堂(いいちせいどう)とて天童山に掛錫(かしゃく)していたが僧が見せてくれたものが、まず思い出される。かの僧が天童山に掛錫していたのは破格の人時であった。以前は広福寺の住持であって、先師如浄と同郷の人であったから、先師はよく、「わしの国のことは西堂に聞くがよい」といっておった。
その西堂が、あるとき、わたしに語りかけて、「古い筆跡のよいものは人間の宝じゃ。いろいろと見たことがあるか」といった。わたしは「あまり見たことがない」旨を答えた。すると、西堂は、「わしのところに一軸の古蹟がある。どんなものともいいにくいが、老兄に見せてあげよう」といって、持ってきたものを見ると嗣書であった。法眼(げん)の門流の嗣書であったのを、その長老の遺品のなかからえたということで、惟一(いいち)長老のものではなかった。そこには、
「初祖摩訶迦葉(かしょう)は、釈迦牟尼仏に悟り、釈迦牟尼仏は、迦葉仏に悟る」
と書かれてあった。わたしはそれを見て、正しい嗣ぎ手から正しい嗣ぎ手に嗣法するということを、はっきりと信受するkとができた。いまだかってないことである。仏祖が冥々のうちに遠き弟子を譲りたもうたというものであって、感激の思いしとどに勝(た)えざるものがあった。(79頁)
■そのころの万年寺の住持は元鼒(げんし)和尚であった。宗鑑長老が退いたのちに鼒(し)和尚が住持となり、法席を盛んにしていた。
人物の話のついでに、むかしからの仏祖の家風をいろいろと語り、大溈(爲)と仰山(きょうざん)の嗣法のことに及んだ時、和尚は「わしのところの嗣書を見たことがあるか」といった。わたしは、「どうして見たことがありましょうや」といった。すると、和尚は、自分で起って行って、嗣書を捧げてきていった。
「これは、たとい親しい人でも、たとい永年侍僧をつとめる者でもみせない。それが仏祖の訓戒である。しかるに、わたしは時々都城にでて知府(ちふ)にお目にかかるのだが、そのように都城にあった時、一夜夢をみたことがある。大梅山(だいばいざん)の法常禅師と思われる高僧が、一枝の梅花をかざしていった。〈もし海を渡ってくる本物があったならば、花を与えることを惜しんではならぬ〉と、そういって、わしに梅花を手渡した。わしは夢のなかで、思わず〈いまだ船舷(ふなばた)を跨(また)がざるに、好し、与うるに三十棒をもってせん〉と吟じた。しかるに、それからいまだ五日を経(へ)ざるに、いまそなたと相見えることをえた。しかも、そなたは海を渡って来たのである。梅花の綾もおそらくこの嗣にかけたのであろう。それを大梅が教えてくれたのにとがいあるまい。ぴたりと夢に符合するので、これを取り出して来たのである。もしもそなたが、わしの法を嗣ぎたいと思うならば、それを惜しみはしない」
わたしは感きわまって措(お)くところをしらず、嗣書をお願いするところであっただろうが、ただ焼香し、礼拝して、その嗣書を敬重し供養するのみであった。その時、焼香の侍者に法寧(ほうねい)というものがいたが、彼もこの嗣書をはじめて見るのだといった。
わたしはひそかに思った。この一段のことは、まったく仏祖の冥々のたすけなくてはあり得ないことであって、辺地日本の愚か者が、なんの幸いがあってか、この事に遇うことができたのであろう。そう思うと、感涙しきりに落ちて袖をぬらしたことであった。その時、天台山の維摩堂や大(だい)舎堂などは、まったく人無うして静まりかえっていた。その嗣書は、地(じ)に梅をしいた白綾に書したもので、長さ九寸余、幅一丈余であった。軸は黄玉にして、表紙は錦であった。
天台山から天童山にかえる途中、わたしは、大梅山の護聖寺(ごしょうじ)の宿舎に泊まったが、その夜は大梅祖師がきたって、花咲ける梅花一枝をさずける夢をみた。仏祖のみそなわすところは、まことにしるしありというべきである。その一枝はおよそ縦横一尺ばかりのものであった。その梅花はまさに優曇華(うどんげ)ともいうべきであろうか。夢もうつつも、おなじく真実であろう。このことを、わたしは、宋にあったころも、また故国に帰ってからも、まだ人に話したことはない。(90~91頁)
■〈注解〉
◯芙蓉山の道楷禅師 芙蓉道楷(1118寂、寿76)曹洞門の第八祖である。庵を芙蓉山の湖上に結んでいた。如浄は雪寶(せっちょう)智鑑の法嗣であるので、筋をまもって道楷の袈裟は着けなかったのである。
◯宝慶 中国の年号(1225-28)であって、南宋の理宗の治下である。道元が如浄によって大事を了ったのは、その元年(1225)の九月十八日である。(92頁)
■〈注解〉
◯青原 青原行思(740寂、寿不詳)。六祖慧能の法嗣である。青原山の静居寺に住してこの称がある。
◯阿笈摩教 阿笈摩(あぎゅうま)は“agama”の音写。また阿含と音写する。ただし、道元が「阿含」ではなくて、「阿笈摩」をもちいる時には、むしろ貶称としての小乗教を指しているようである。「阿含」の音写は主として「阿含経」を語る場合にもちい、その経にたいしては、つねに尊重の意をもってしておる。(97頁)
法華転法華(ほっけてんほっけ)
■〈開題〉
この一巻の制作の動機は、巻末にしるされている。時は仁治二年(1241)夏案居日、その時、慧達(えだつ)禅人なるものが、興聖(こうしょう)宝林寺にある道元のもとに来り投じて、出家し修道をはじめた。その志を感喜して書いて与えたのがこの一巻であると知られる。
慧達禅人なるものについては、別に知らるるところはないが、その巻末の記によれば、どうやら彼は、すでに出家していたのを、心をあらたにして道元のもとに来り投じたのでもあろうか。「ただ鬢髪(びんぱつ)をそる、なほ好事なり。かみをそりまたかみをそる、これ真出家児なり」とあるその巻末の一節が、そのことを示唆しておる。さらにいえば、つづく一節に、「今日の出家は、従来の転法華のおのずから然らしむる果報であるという。とするならば、この慧達ぜんじんはもと『法華経』を学びきたった人であったにちがいないのであった。
かくて道元は、かれ慧達禅人にちなんで、かの『法宝壇教(ほうぼうだんきょう)』がしめすところの、六祖慧能が法達(ほうたつ)なるもののために説いた有名な教誡、「心迷えば法華に転ぜられ、心悟れば法華を転ず、云々」なる一節を思いいいで、それを主題として、かれ慧達禅人のためにこの一巻を制作して与えたのである。けだし、かの法達もまた、もと、みずから称して「われ法華経を読誦することすでに三千部なり」と自負していた人物であったからである。その人物が、六祖慧能のもとに投じた経緯は、この一巻のなかにつまみらかである。
したがって、この一巻に題する「法華転法華」なる巻題が意味するところも、おのずからにして知られるであろう。それは、「法華転」と「転法華」をつらねたものである。だが、その二つの命題について展開せられる道元の思索は、また、遥かに世の仏教者の常識を超えるものであったことを思わねばならない。
いったい、道元という人は、『法華経』にたいして、ふかい造詣とふかい興味をもっていた方であった。その印象は、この『正法眼蔵』を繰り返し繰り返し味読しておると、しだいに鮮かさを増してくる。到るところにおいて、かの経からの文言が引用せられ、また、その美しい譬喩が援用せられている。さらにいうなれば、その詠草のなかには、「法華経に題す」る詠歌五首もみえているし、また『建撕(ぜい)記』の記するところによれば、その終焉にちかいある日のこと、道元はその病軀をもって室内を経行し、低声に「若於園中、若於樹中、若於僧房、若白衣舎、……諸仏於此、得阿耨多羅三藐三菩提、諸仏若於、転於法輪、諸仏若於、而般涅槃」という、あの『法華経』第二一「如来神力品」の一節を誦(じゅ)しおわると、それを面前の柱に記し、かつ、妙法蓮華経菴と書きとどめたという。道元がそこで病を養っていた高辻西洞(にしのとう)院なる俗弟子覚念(かくねん)の館においてのことである、あれを思い、これを思えば、『法華経』という経は、道元にとってもまた、並々ならぬ重さをもって経であったと申さねばなるまい。
しかるに、いま、これもまたその経に因縁あさからぬ慧達禅人のために、かの六祖慧能がいうところの「法華転」と「転法華」の二つの命題を主題としてこの一巻を制作した。そこには、むろん、かの経の要文が縦横無尽に引用されている。だが、そこに語られているものは、在来のかの経の解釈の埒をとおく越えたものと申さねばなるまい。たとえば、この一巻においても、道元はそのいわんとするところを、その冒頭において端的に打ち出して語っている。
「十方仏中者(は)、法華の唯有なり。これに十方三世一切諸仏、得阿耨多羅三藐三菩提衆は、転法華、法華転あり。これすなはち、本行菩薩道の不退不転なり」
そのいうところは、十方の仏土はただ法の花ひらくところであるというのである。そこには、十方三世の諸仏・諸菩薩があって、あるいは法華を転じ、あるいは法華に転ぜられているのであるが、それがそのまま菩薩のかぎりもない修行の不退転のあゆみであるという。
わたしどもは、心迷えば法華に転ぜられるといえば、それを恨むべきこととなし、心悟れば法華を転ずといえば、それを歓ぶべきことなりと受領してきた。だが、それは、どうやら、おろかな凡情の差別であったらしい。心迷えば法華に転ぜられるという。だが、それも法華のいとなみであるならば、結構なことではないか、と道元はいう。心悟れば法華を転ずるという。だが、それもまた、突きつめて考えてみると、法華のわれらを転じてそこにいたらしめるのではないかという。かくて結語がある。
「広大深遠(じんえん)なり、深大(じんだい)久遠(くおん)なり。心迷法華転なり、心悟転法華なる、実にこれ法華転法華なり」
かくして、「法華転」と「転法華」も二つの命題は、さらに広大なるところにおいて、みごとに「法華転法華」なる一つの命題に帰しているのである。そして、それこそ、道元が指さして、この一巻において開示しようとするところであったとしられる。(100~103頁)
■〈注解〉
※道元は、まずこの一段において、雄大荘厳なる法華の世界観を打ち出して語っておる。法華の世界とは、つまり、法の花ひらく諸仏の世界であり、それを端的にいえば、「十方仏土中は、法華の唯有なり」という冒頭の一句となるのである。
◯阿耨多羅三藐三菩提衆 得阿耨多羅三藐三菩提とは“anutara-samyak-sambodhi”の音写。無上等正覚と訳する。仏の最高の智慧をいうことばである。衆とは“samgha”の訳であって、その智慧を追求する人々である。ここには、その意をもって諸菩薩を指さしていうのである。
◯文殊師利仏云々 文殊師利は“Manjusri”の音写。智慧を代表する仏である。
◯普賢云々 普賢とは“Samantabhadra”の訳。文殊の智に対して行(ぎょう)を代表する菩薩である。
◯弥勒 弥勒は“Maitreya”の音写。未来仏としてよく知られている。
◯一乗・一仏乗 一切衆生をしてことごとく成仏せしめる教法というほどの意。(107~108頁)
■〈注解〉
◯三乗人 三乗とは、声聞乗・縁覚乗・菩薩乗をいう。そのような差別観にとらわれて仏教を修する人々を三乗人とする。(116頁)
■まことにこの土(ど)は「天人つねに充満」するところ、すなわち、釈迦牟尼仏・毘盧遮那仏の国土にして、常(じょう)寂光土にほかならない。われらはおのずから四土を具するというが、詮ずるところは、生仏一如の仏土に住するのである。
微塵を知るものは法界(ほっかい)を知り、法界を証するものは微塵を証する。諸仏はみずから法界を証して、われらには証を与えないわけではない。その説法は「初めも中も終わりも善き」がゆえである。したがって、いまもその証はあるがままの相である。驚き怖るるもまたあるがままならぬはない。ただ異なるところは、仏はその知見をもって微塵を見、微塵に安住するのである。法界に坐しても広きにあらず、微塵に坐しても狭いとはしないのである。その故は、安住せずしては坐すことがないからである。安住すれば広き狭きに驚くことがないのである。それは法華の実体とそのはたらきを究め尽しているからである。
とするならば、われらがいま具するこの相と性は、この法界における修行であろうか、微塵における修行であろうか。ともあれ、驚くことはない、怖るることはない、ただ法華の転ずるながいながい菩薩の修行にちがいないのである。それを微塵の小とみるも、法界の大とみるも、おのが作意でも計らいでもない。計ろうにも、法華の計らいをならうがよく、法華の思うところを思うがよいのである。
もし開示悟入ときくならば、それを「衆生をして開示悟入せしめんと欲す」と受けとるがよい。もし法華が「仏の知見を聞く」と転じたならば、それを「仏の知見を示す」と受けとるがよく、もし法華が「仏の知見を悟る」と転じたならば、それは「仏の知見に入る」とならうがよく、あるいは法華が「仏の知見を示す」と転ずるならば、「仏の知見を悟る」と受領するがよい。そのように法華の転ずる開示悟入にもいろいろの考え方があろう。すべて諸仏如来の実現したまえる知見も、この広大無辺なる法華の転ずるところ。あるいは、成仏の予言もまた自己が仏の知見を開くことに他ならず、けっして他人の与えるものではないのである。それがとりも直さず、心迷えば法華に転ぜられるということである。(122~123頁)
■〈注解〉
◯常寂光土 四土の一つ。生滅なく(常)、煩悩なく(寂)、智慧の光のみみちあふれている国土という。それは法身の仏たる毘盧遮那の国土であるとする。ただし、ここに釈迦牟尼仏と毘盧遮那仏の二仏をあげているのは、現身の仏にとっても、法身の仏にとっても、このあるがままの世界が常寂光土であるとするのであろう。
◯微塵・法界 微塵はこの世界の最小の単位をゆびさし、法界はこの世界のもろもろの存在を総じていうことばにして、この世界の最大の単位である。ここでは、その二つの語彙をしばらく相対化して語る。その間に、一即多、生仏不二のおもむきがおのずからに存することが汲みとられねばなるまい。
◯相・性 相はその現われたるすがたであり、性はその本性として内に蔵するところである。(124頁)
■たとい自ら心を強くしても弱くしても、すべてそれが法華である。すべてあるがままなるが珍宝であり、光明であり、仏智の行ぜられるところである。まことに広大にして深遠である。心迷えば法華が転ずるのであり、心悟れば法華を転ずるのである。さらにいえば、これこそ法華が法華を転ずるのである。
「心迷えば法華を転じ、心悟れば法華を転ず。究尽することよくかくのごとくなれば、法華法華を転ず」
そのように供養し、恭敬し、尊重し、讃歎するならば、それがまさしく法華これ法華というところであろう。(132~133頁)
■〈注解〉
◯色即是空 「般若心経」のよく知られた句であるが、いま道元はその句をもって娑婆即寂光土となることを語っているようである。
◯法華是法華 道元がこの巻において、法華ということばに込める意味はまことに広大無辺である。それはただかの『法華経』のことのみではない。この世界のおのずからの展開がそれであり、また仏の教化のいとなみのことがとくがそれである。その意味のことがとくをこめて、ここに「法華これ法華なるべし」の結語が語られているのだと知られる。(134~135頁)
心不可得(しんふかとく)(前)
■老婆はいった。
「わたしはある時「金剛経」を聴いたことがあるが、そのなかに過去心不可得、現在心不可得、未来心不可得とありました。いま和尚は餅を買うて、いずれの心に点じようとなさるのか。和尚がもし見事に答えたら餅を売りましょう。答えができなければ売るわけにはゆきません」
徳山は、その問いをまえにしてただ茫然、答うるすべを知らなかった。そこで老婆は袖を払って去り、ついに徳山は餅をえることができなかった。(145頁)
■では試みに、徳山にかわっていってみようか。かの老婆があのように問うたならば、そこで徳山は老婆にむかってこういうべきである。
「しからば、汝わがために餅を売ることなかれ」
もし徳山がそんなふうにいい得たならば、聡明な学者でもあろう。そこで、徳山がかえって老婆に問う。
「現在心不可得、過去心不可得、未来心不可得、いったいこの餅をもっていずれの心を点ずればよいのだ」
そう問われたならば、そこで老婆は徳山にむかっていうべきである。
「和尚はただ、餅をもって心を点ずべからざることのみを知って、心が餅を点ずることを知らず。また、心が心を点ずることをも知らず」
そういったならば、徳山はきっとそこで考えるだろう。その時にあたって、餅三つをとりあげて徳山に与えるがよい。それを徳山が受け取ろうとした時、そこで老婆はいうべきである。
「現在心不可得、過去心不可得、未来心不可得」
と。もしまた、徳山が手をさしのべて受け取ろうとしなかったならば、餅一つをにぎって、徳山を打っていうがよい。
「この魂のぬけた屍(しかばね)めが、なにをぼんやりしているのだ」
そこで徳山がなにかをいうならばよし。もしなんにもいわなかったならば、老婆はさらに徳山のために説くべきである。
だが、老婆はただ袖を払って去った。その袖のなかにもなにか刺すものがあったとは思われない。徳山もまた、
「われはいうことあたわず。老婆わがために説け」
ともいわなかった。いうべきをいわなかったのみではなく、問うべきこともとわなかったのである。かわいそうに、老婆も徳山も、ただ過去心の、未来心のと、問うたり答えたりしたのみであった。
いったい、徳山は、それから以後もたいして勝れたところがあったとは思われない。ただあらあらしいかりそめの行動のみである。ながいあいだ龍潭にいたことだから、師匠の角(つの)を挫くことだってあり得ただろうし、顋(あざと、(サイ、あご))の珠を頂戴する時だってあったはずだが、わずかに紙燭(しそく)を吹き消しただけのことで、燈を伝えるには足りなかった。
されば、学道の雲水はかならず力を尽くしてまなぶがよい。やすやすと思っては駄目である。力を尽くしたのが仏祖である。そもそも心不可得とは、画餅一枚を買いきたって、それを一口に咬み砕き、かつ、よくよく味わうことなのである。(151~152頁)
心不可得(しんふかとく)(後)
■〈注解〉
※道元は、まず「心不可得は、諸仏なり」と語りいでる。その一見唐突な表現も、よくよく味わい到れば、この心不可得なることを会得するものが諸仏にほかならないのであるから、まことに然りと頷かれるであろう。
◯三界 欲界(欲望に駆使される人間の世界)、色界(現象そのものの世界)、無色界(叡智による抽象の世界)。
◯諸法 もろもろの存在。(160~161頁)
■いわゆる仏心とはとは三世である。心と三世とは禹の毛ほどのへだたりもないのであるが、また、相去り相離るることを論ずるならば、十万八千里なりといってもなお及ばないであろう。過去心とはなにかと問うものがあらば、彼にむかっていうがよい、「これ不可得」と。また、未来心とは何ぞと問うものがあったならば、また「これ不可得」と答えるがよい。そのいうところの意味は、心をかりに不可得と名づける、そのような心があるというのではない。ただ不可得というのである。また、心は得られないというのでもなく、ただ不可得というのである。あるいは、心は得ることができるというのでもなく、ただ一途に不可得というのである。また、過去心不可得とはどういうことかと問うものがあらば、生死去来(しょうじこらい)と答えるがよい。現在心不可得とはどんなことかといわば、生死去来というがよい。あるいは、未来心不可得とはいかにといわば、また生死去来というがよい。いったい、牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)にほかならぬのが仏心であって、三世の諸仏はいずれもそれを不可得であると証(さと)っている。また、仏心にほかならぬ牆壁瓦礫があれば、三世の諸仏はそれをも不可得であると証している。ましてや、山河大地にほかならないものは、不可得そのものである。草木風水にして不可得なるもの、それが心であるといってもよい。あるいは、「まさに住する所なくしてその心生ず」という。それもまた不可得でる。あるいは、また、十方の諸仏は一代にして八万の法門を説くという。不可得の心(しん)とはかかるものなのである。(170頁)
■〈注解〉
◯生死去来 圜悟克勤のことばに「生死去来、真実人体」(『圜悟禅師語録』巻六)の句がある。道元はその句をしばしば引用している。生死はすなわち去来である。それが人間の究極的な事実であるというほどの意である。
◯牆壁瓦礫にてある仏心 『景徳伝燈録』巻二八、慧忠の語に、「僧又問、阿那箇是仏心、師曰、牆壁瓦礫」と見える。この句はおそらくその語によって成れるものであろう。道元はまたしばしば「牆壁瓦礫これ心なり」(「身心学道」の巻)などの句をなしている。(171頁)
■仏道において心(しん)をまなぶには、よろずの存在がそのまま心である。三界はただ心である。ただ心のみであるから唯心なのであろう。仏もまたそのまま心といってよい。いや仏のみではない。自己も他人もすべてひとしくそうなのである。だからして、いたずらに西川(せいせん)までも下ってゆく必要はなく、あるいは天津橋(てんしんきょう)まで飛んでいって心をさがす必要はない。仏道の身心を会得したいならば、仏道の智慧をまなぶがよい。さすれば、仏道ではすべての大地がみな心である。生ずると滅するとにかかわらず、すべての存在がみな心である。すべての心がみな智慧だと学んでもよい。(176頁)
■〈注解〉
※しかるに、世には、心といえば、なにか個体的なものがあるように思う者がすくなからず、なかには、他人の心を知るふしぎな通力をもつなどという者すらある。ここには、大証国師が他心通を得たという大耳三蔵なるものを看破した故事をあげて、その蒙を啓(ひら)こうとするのである。
◯大証国師 慧中(775寂、寿不詳)。「唯仏是心」の巻を参照。
◯野狐精 野狐のたましいに魅入られて、人をたぶらかす者というほどの意である。(177~178頁)
■〔長老たちの見解を評する〕
わが大師釈尊の法は、小乗・外道などの野狐精(やこぜい)の輩(やから)には思いも及ばぬとおろである。だから、この一段の物語も、ふるくから徳高い長老たちによって検討され、いろいろとその話がのこっている。
ひとりの僧があって、趙州(じょうしゅう)に問うていった。
「三蔵はどうして、第三度目のときには、国師の所在が判らなかったのでありましょうか」
趙州はいった。
「国師は三蔵の鼻のうえにあった。それで見えなかったのだ」
また、ひとりの僧があって、玄沙に問うていった。
「鼻の孔のうえにあったというのに、なぜ見えなかったのでありましょうか」
幻沙はいった。
「あんなり近かったからだなあ」
すると、海会守端(かいえしゅたん)はいった。
「もし国師が三蔵の鼻の孔のうえにいたならば、なんの見えないことがあろうか。それは、きっと、国師が三蔵の眼のなかにあったことをしらなかったからでしょう」
また幻沙は、三蔵をなじっていった。
「では汝は、はじめの二度は見たというのか」
雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)はそれを評して、「負けじゃ、負けじゃ」といっておる。
またひとりの僧があって、仰山(きょうざん)に問うていった。
「三蔵がどうしても三度目には国師のありかが判らなかったというのは、いったい、どうしてでありましょうか」
仰山はいった。
「はじめの二度は、あれはただ対象にかかわる心のうごきだったが、あとでは自受用三昧に入ってしまった。それで判らなかったのだ」
この五人の長老がたは、それぞれ甲乙はないが、やはり、国師の言行をうまく捉えているとはいい難い。つまり、第三問に答えなかったことのみを論じているのは、はじめの二度はうまく答えたとするに似ている。それは長老がたの取りそこねたところであって、のちにいたるわれらの考えねばならぬところである。
わたしがいま、この五人の長老たちをどうかと思う点は二つある。その一つは、国師が三蔵を試みる意味をしらないこと、その二つには、国師の身心をしらないことである。
まず、国師が三蔵を試みる意味をしらぬというのはこうである。最初に国師は、「わたしはいま何処におるか、いってみるがよい」といった。その意味は、いったいこの三蔵は仏法を知っているか、もしくは知らないかを試問しているのであるから、もし三蔵が仏法を聞いたことがあるならば、「わたしはいま何処におるか」と問るれば、それを仏法にならって受け取らねばならぬ。仏法にならって受け取るというのは、国師が自分はいまどこにおるかというのを、この辺りか、どの辺りか、あるいは、最高のさとりか、大いなる智慧か、あるいはまた、空にかかっているか、地に立っているか、草庵にあるのか、涅槃にあるのかと問うているのである。三蔵はその意味を知らないから、いたずらに凡夫・小乗の見解をもって答えた。国師はかさねて、「いってみるがよい。いまわたしは何処におるか」と問うた。だが、三蔵はまたもや無駄な返答をした。そこで国師が、三度かさねておなじ問いを繰り返した時、今度は三蔵もしばらく考えていたが、なんのいうところをも知らず、ただ茫然たるのみであった。そこで国師は叱咤して、「この野狐精(やこぜい)めが、なんじの他心通はいったい何処にあるのじゃ」といった。それでも三蔵はなんのいうところもなかった。
つくづくこの物語を考えてみると、長老たちはみな、いま国師が三蔵を叱ったのは、まえの二度は国師の所在を知ることができたが、三度目には知りえなかったので叱ったのだと思っておる。だが、そうではない。およそ三蔵の野狐にも似たる考えでは、仏法はまったく判っていないことを叱ったのである。まえの二度は知り得たが、三度目は知り得なかったというのではない。叱ったのは、三蔵のすべてを叱ったのである。国師の考えるところは、まず仏法に他心通ということがあるかないかということであった。また、たとい他心通ということがあっても、その「他」は仏道における他でなくてはならぬ。その「心(しん)」は仏道における心でなくてはならぬ。その「通」も仏道でいうところの通でなくてはならないのに、いま三蔵のいうところは、まったく仏道によるところのものではない。それをどうして仏法ということができようぞと国師は思ったのである。この試験は、たとい三度目にも答え得たからとて、まえの二度のようであったならば、それも仏法の道理にあわず、国師の本意にかなうものではないから、やはり叱すべきものであった。三度も問うたのは、もしや三蔵が国師のことばの意味を解することもあろうかと、重ねて問うたのである。
その第二に、国師の身心をしらずというのは、その国師の身心は三蔵の知り得るところではなく、理解知り得るところではないということである。それは十聖(じっしょう)・三賢(さんげん)もおよばぬところであり、補処(ふしょ)の菩薩も知り得るところではないのであって、どうして凡夫の三蔵が知ることができようかと、そこの道理をはっきりと思い定めねばならなぬ。それを、国師の身心は三蔵も知り得るところ、及びえざるところではないと思うのは、自分自身がすでに国師の知らないからである。他心通を得た者には、国師を知ることもできようというならば、小乗の者はもっとよく国師を知ることができるか。そんなことはあろうはずはない。小乗の聖者では、とても国師のほとりにも及びがたいのである。いまの小乗の人には大乗の経典を読むものもすくなくないが、彼らとても国師の身心を知ることはできない。また仏法のしんじんは、夢にも見ないところである。たとい大乗の経典は読んでいるようであっても、彼らはまったく小乗の人であると、はっきり知らねばならない。詮ずるところ、国師の身心は神通を修するような徒輩の知り得るところではないのである。国師の身心は、国師自身にもなお測りがたいであろう。その故はいかにとならば、その足跡はどこまでいっても仏となることを意図しないから、したがって、仏眼(ぶつげん)もこれを窺い見ることができず、その進退ははるかに所在をこえて、文字や表現のとらえ得るところではないからである。
しかるを、いまの五人の長老たちの所見は、いずれも批判さるべきものであった。
趙州は、「国師は三蔵の鼻の孔(あな)のうえにいたから見えなかったのだ」といった。それはなんというか、本(もと)を明らかにせず、末ばかりをいおうとするから、こんな誤りをするのである。国師がどうして三蔵の鼻の孔のうえにいようか。三蔵にはまだ鼻の孔などありはしない。国師と三蔵とはそこで会見したのだから、会ったようにみえるけれども、二人が相近づく道はなかった。明眼(げん)をもってそこをよくよく弁(わきま)えねばならぬ。
幻沙は「あんまり近かったからだ」といった。たいへん近かったことはそうだとしても、それが的(まと)に中(あた)っているわけではない。いったい、どういうことを近いというのか。なにが近いというのであるか。幻沙はまだ近いということを知らず、近いということをまなばず、仏法にはなおはなはだ遠いのである。
また仰山(きょうざん)が、はじめの二度は、あれはただ外境に関わる心のことであったが、そのあとは自受用三昧に入ったから、今度は判らなかったのだという。この人は、小釈迦のほまれが西の方までもひびいているが、これはどうも頂けない。もし相見(そうけん)すべきところはないであろう。あるいは、成仏の予言なども判ってはいないように思われる。はじめの二度は、三蔵にもよく国師の所在を知り得たという。それでは国師の徳がすこしも判ってはいないといわねばならない。
幻沙は、三蔵をなじって、「はじめの二度はほんとうに見たというのか」といった。その一句は、いうべきことをいっておるようであるが、それはどうやら「見れども見ざるがごとし」といおうとしているようである。だから、それも充分ではない。それを聞いて、雪竇明覚(せっちょうみょうかく)禅師は「敗けじゃ、敗けじゃ」と評している。それは玄沙のことばを道理とする時、そういうべきであって、道理にあらずとする時には、そういうわけにはいかない。
また海会守端(かいえしゅたん)は、「もし国師が三蔵の鼻の孔のうえにいたならば、なんの見えないことがあろうか。それは、国師が三蔵の眼の中にいたことをしらないからだ」といった。それもまた三度目だけを論じているのである。はじめの二度も見ることはできなかった。その呵(か)すべきことを呵していない。いったい、国師が鼻の孔のうえにいたのか、眼のなかにいたのか、どうして判るものか。
五人の長老たちは、いずれも国師のことを知らず、仏法をまなんだ力がまるでないようにみえる。しるがよい、国師はまさしく一世にひいでる仏祖である。あきらかに仏の正法の眼目を伝えている。小乗の三蔵や論師などが国師の境地がわからないのはその証拠である。小乗でいうところの他心通とは、むしろ他念通といったがよかろう。小乗の他心通の力で、国師の一本の毛のさく、いや半本の毛のさきでも知り得ると思うのは、とんでもない誤りなのである。いま小乗の三蔵はまったく国師の功徳の所在をみることができなかったのだと、そうまなばねばならない。もしも、さきの両度は国師の所在が判ったが、三度目には判らなかったのだとするならば、それは三つに二つの能力があったのであって、すべて叱すべきではあるまい。たとい叱られても、すべて失敗したわけではない。それを叱ったのでは、誰も国師を信じないであろう。それを叱ったのは、三蔵がまだまったく仏法の身心を得ていないことを叱ったのである。五人の長老たちは、みな国師の履(ふ)みきたれるところを知らなかったから、こんな失敗をしたのである。
だからして、いま仏道における心不可得について語るのである。この一つのことに通じないでは、他のことに通じたとは思えないのであるが、いま長老たちにも、うっかりしてこんな誤りがあったということを知るがよろしい。(184~191頁)
■〈注解〉
◯二乗 声聞乗と縁覚乗をいう。声聞とは、仏の言葉を聞きて悟る人、縁覚とは、縁を観じて証悟する人の意。いずれも小乗の道をゆくものであるとする。
◯趙州 趙州従諗(908寂、寿74)。雪峰義存の法を嗣ぎ、福州の玄沙山に住した。諡(おくりな)してと真際大師称する。
◯玄沙 玄沙師備(897寂、寿120)。南泉普願の法嗣、諡(おくりな)して宗一大師と称する。
◯雪竇 雪竇重顕(1052寂、寿73)。智門光祚(そ)の法嗣、雪竇山資聖寺に住し、雲門宗の中興の祖と称せられる。明覚大師と号する。
◯仰山 仰(きょう)山慧寂(916寂、寿77)。潙山霊祐の法を嗣ぎ、潙仰宗(いぎょうしゅう)の祖とせられる。智通禅師と諡せられた。潙
◯自受用三昧 自受用とは、他受用の対。自己の功徳をみずから受用して、その楽しみを味わうことをいう。そのような境地にひたり切っているのを而受用三昧というのである。
◯授記作仏 授記は仏が予言を与えることをいい、作仏とは仏になることである。つまり、仏がその弟子に成仏の予言を与えることである。(190~192頁)
■〈現代語訳〉
〔心不可得を参究すべし〕
ある時、ひとりの僧が国師に問うていった。
「古仏心とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「牆壁瓦礫じゃ」
これも心不可得である。
またある時、ひとりの僧が国師に問うていった。
「諸仏のつねなる心とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「幸いに、わしの参内(さんだい)に出遇ったなあ」
これも不可得の心を究明しているのである。
またある時、天帝釈(てんたいしゃく)が国師に問うていったことがある。
「どのようにしたならば、この無常の世界を解脱することができましょうか」
国師はいった。
「天神は道を修めて、この無常の世界を解脱するがよろしい」
天帝釈はかさねて問うていった。
「その道とは、どのようなものでありましょうか」
国師はいった。
「つかのまの心、それが道である」
天帝釈がいった。
「つかのまの心とは、どのようなものでありましょうか」
国師は手をあげて指さしていった。
「これが般若の台(うてな)である。あれが真珠の網でござる」
天帝釈は頭をさげて礼拝した。
およそ仏道にあっては、仏祖たちの会座(えざ)において身心を談ずることが多い。いずれもそれをまなぶことは、凡情の思量をもってしては及ばないところである。心不可得ということを思いめぐらしてみるがよいのである。(194~195頁)
■〈注解〉
※もう一度、仏心とは牆壁瓦礫なることを繰り返して、心不可得の道理を思いめぐらすことをすすめて結びとする。
◯般若台 般若は智慧である。この身心こそ智慧のやどるところというほどの意であろう。『法宝(ぼう)壇経』にみえる神秀の句に「心如明鏡台」とある。推して知られたい。
◯真珠網 この世界を指さして真珠をちりばめた網というのであろう。『華厳経』に因陀羅網(いんだらもう)とて、この世界の構造を語るに宝石をちりばめた宝網のたとえがある。推して知るべきである。(195~196頁)
古鏡(こきょう)
■〈現代語訳〉
〔仏祖の古鏡〕
もろもろの仏祖が伝え受け、保持し、また伝えいたるものは古鏡である。それはいつでも、同じ面(おもて)をうつし、同じ姿をうつし、同じ証(さとり)をうつし出す。胡人がきたれば胡人をうつし出すこと、その数かぎりなく、漢人がきたれば漢人をうつし出すこと、その時をえらぶことがない。古人がくれば古人を現じ、今人ががくれば今人を現じ、仏がくれば仏を現じ、また祖が来れば祖を現ずるのである。
〈注解〉
※こに一段は、仏祖の一人より一人へと仏心を単伝するありようを語るに、古鏡をもって象徴するのである。古鏡とは、智慧をたとえていうのが、古来からのならいである。
◯胡人 胡は北方のえびす。それによって、すべての異邦人をいうのである。(200~201頁)
■〈注解〉
◯性・相 性は本質であって、変わらないものであり、相はその現われであって、さまざまの相状を呈する。本質と現象である。
◯大円鏡(智) 一切種智ともいう。方法の空なるとともに、またもろもろの差別相があることを知る最高度の智慧である。だが、道元はそれをも、なお修行の段階とみているのである。
◯道眼被眼礙 「道眼は眼に礙(さ)えられる」と読む。道眼とは、仏道によってうる眼であり、法をみる眼である。その眼が開けないのは何故か。それもまた眼がさまたげているのだという。(209~210頁)
■〈注解〉
◯第三十三祖大鑑禅師 大鑑禅師は曹谿慧能の諡号。六祖である。ここに第三十三祖というは、西天二十八祖よりつづいて数えたのである。
◯菩提本無樹云々 『法宝壇経』によれば、五祖弘忍のもとに神秀と慧能のあったころのこと神秀が宝林寺の南廊壁間に、その心所見を呈して、「身是菩提樹、心如明鏡台、時時勤払拭、勿使惹塵埃」と書した。それに対して、慧能もまた所見を呈して、壁間にこの偈を書したという。ただし、古来その結句は「何処惹塵埃」(いずれの処にか塵埃を惹かん)と伝えられている。
◯園悟禅師 無着克勤(むちゃくこくごん、1135寂、寿73)の諡号。『碧巌録』の著者であり、また『園悟広録』がある。(212頁)
■〈注解〉
◯雪峰真覚大師 雪峰義存(908寂、寿87)。徳山の法を嗣ぎ、福州の雪峰山に住した。真覚大師はその諡号である。
◯玄沙 玄沙師備(908寂、寿74)。雪峰義存の法を嗣ぎ福州の雪峰山に住した。(219~220頁)
■〈現代語訳〉
人を鏡とするというのは、鏡を鏡とすることであり、自己を鏡とすることであり、天地のうごきを鏡とするのであり、人の道のありようを鏡とするのである。人間の去来するさまをみると、まさに「来るに迹(あと)なく、去るに方(かた)なし」である。それが人を鏡とする道理というものである。(224~225頁)
■〈注解〉
◯五行 中国古来の説である。天地に流行し万物を形成するに五つの元素(木・火・土・金・水)があり、一切の現象をその調和と相剋によって説明する。
◯五常 人のつねに守るべき五つの道として、儒教の語るところである。あるいは仁・義・礼・智・信をあげ、あるいは、父・母・兄・弟・子のそれぞれに守るべきものとして、義・慈・友・恭・孝をあげる。
◯去来(こらい) 生と死。(225~226頁)
■〈現代語訳〉
いったい、いまもいう古鏡に胡人・漢人が来り現ずるというのは、古鏡のうえに来り現ずるというのでもなく、古鏡のうちに来りげんずるというのでもない。また、古鏡のほかに来現するとも、古鏡とともに来現するともいうのではない。そのいい方をよく聴くがよいのである。もしも、胡人・漢人が来り現われる時には、古鏡が胡人・漢人を来現せしめるのだといったり、あるいは、胡人・漢人がともに隠れた時にも、古鏡はなお存在しているのだといったりしたのでは、まったく来の現も判ってはいないのであって、錯乱というもなお及ばざるところである。
さて、そこで玄沙は、「わたしはそうは思わない」といった。雪峰は、「しからば、そなたはどう思うか」といった。すると、玄沙は、「では、和尚の方から問うていただきたい」といった。その幻沙のことばを取り間違えてはならない。いま和尚が問い、幻沙が問うてくださいという。それは、師と弟子の呼吸がぴたりと合っていなくては、とてもそうはまいらぬところである。
すでに和尚に請うて問いたまえという。その時、その人はすでにその問題を解しているはずである。ひとたび和尚から問いが打ち出されれば、もはや逃げ隠れることはできない。
雪峰はいった。
「では、にわかに明鏡の来るに遇った時にはいかに」
この問いは、いま師と弟子とが相ともにまなびいたる一つの古鏡について問うのである。
幻沙は答えていった。
「木端微塵でござる」
そのいうところは、千々(ちぢ)に砕けるというところである。つまり、にわかに明鏡が現われてきた時には、それは木端微塵となるのである。千々に砕けることを会得するのが明鏡であろう。その明鏡を表現するとなれば、千々に砕けるとなるのであるから、砕けるところに明鏡があるのである。
それを、さきにはなお砕けない時があり、また、のちにも砕けない時があるのだろうと思ってはならない。ただ、「千々に砕ける」のである。その千々に砕ける真相に対面することは、まことに難事である。
しからば、いまもいう「千々に砕ける」とは、古鏡をいうのであるか、明鏡をいうのであるか。さらに一転して、そのような問い方もあろう。だが、その時は、もはや古鏡をいうのでもない。明鏡をいうのでもない。古鏡か明鏡かと問うことはできても、玄沙のことばをとりあげて論ずるときにも、その舌端はただ紗礫(しゃりゃく)・牆壁(しょうへき)となって砕け散るばかりであろう。その砕け散ったさまはいかにというなれば、まさに「万古の碧潭(へきたん)、空界の月」というところであろうか。(232~233頁)
〈注解〉
※こに一段の要をとって説くことは、まことにむつかしい。だが、あえて説くなれば、さきに冒頭の一句は、仏祖の単伝するは古鏡であると語った。雪峰はそのわが内なる古鏡を語って、「古来胡現、漢来漢現」と説いた。あるがままをうつし出すのが古鏡であるというのである。しかるに、いま幻沙は、忽然として明鏡の来る時いかんと問う。それは、要するところ、師資相承の古鏡のなる決定的瞬間である。その瞬間を語っていかに表現するかである。かって六祖慧能ははじめて南嶽を接得した時、「汝既如是、吾亦如是」と語った。そして、いま幻沙は、みずからその瞬間を表現して、「百雑砕(ひゃくざつさい)」と語ることを得たのである。その指さすところを、道元もまた肝胆を砕いて説明しているのである。
◯吾亦如是云々 『景徳伝燈録」巻五、南嶽伝に、「汝既如是、吾亦如是」とみえる。それは、南嶽がはじめて六祖慧能にまみえた時の、六祖のことばであった。そこには、いまの古鏡と明鏡についての消息が含意されている。「宗旨は吾亦如是なり云々」という所以である。
◯万古碧潭空界月 『景徳伝燈録」巻二九、同安禅師の十玄談のうち、「廻機」と題せられる偈にみえる一句である。(234頁)
■〈現代語訳〉
〔雪峰と三聖(さんしょう)の問答〕
雪峰山の真覚(がく)大師と三聖院の慧然(えねん)禅師とが歩いているとき、一群の猿どもを見た。そこで雪峰がいった。
「あの獮猴(みこう)どもは、それぞれ一面の古鏡を背負うている」
そのことばを、よくよく思いめぐらしてみるがよい。獮猴というは猿のことであるが、雪峰の見た猿はどんな猿であったかと、そんな具合に問いを立てて、さらに研究してみるがよい。時の経つのを気にしてはならぬ。
まず、猿がそれぞれに一面の古鏡を背負うているということであるが、古鏡といえば、もろもろの仏祖のそれを思うであろうけれども、それはまた、これからその境地にいたる者にもいいうる。その猿がそれぞれに古鏡を背負うているとは、それぞれにさまざまの古鏡をというのではなく、ただ一面の古鏡をである。また、背負うというのは、いうなれば仏の絵像を裏打ちするようなものである。猿の裏打ちに古鏡をもってするのである。では、どんな糊(のり)で裏打ちするのか。ともあれ、こころみにいうなれば、猿のうらは古鏡で裏打ちするがよい。では、古鏡の裏打ちは猿でするのか。いや、古鏡のうらは古鏡で裏打ちする。猿のうらは猿で裏打ちする。
また、おのおの一面の古鏡を背負うというのは、けっして虚(むな)しい喩(たと)えではない。まさにいい得たるところであろう。とするならば、それは猿か古鏡か、いったいどういったらよいのか。あるいは、われもまた猿なのか、猿ではないのか、誰に問えばよいのか。自分が猿であるかどうかは、自分の知るところでもないし、また他人の知るところでもない。自己が自己であるかどうかは、誰も覗(うかが)い知り得るところではないからである。
三聖(さんしょう)はいった。
「暦劫(りゃくこう)の昔から無名のものを、なにをもっていま古鏡というのであるか」
それは、三聖が、古鏡の古鏡たる所以を説いたことばである。
暦劫というのは、いまだ一心も一念も萠(もよお)さざる以前である。ながい月日のほかなにもなく、古鏡・明鏡のほかなにものもないことである。無名がほんとうに無名であるならば、暦劫もいまだ暦劫ではあるまい。暦劫が暦劫でないならば、三聖のことばもまたことばではあるまい。
だが、しかし、一念のいまだ萠(きざ)さざる以前とは、つまり、今日のことにほかならない。その今日を取り間違えないで錬磨しなければならない。暦劫無名などといえば、そのことばはまことに厳(いか)めしいが、いったい、何を指さして古鏡とはいうのであるか。といってしまえば、まったく尻つぼみのことである。
そこで、雪峰は三聖にむかって、ただ「古鏡、古鏡」といえばよいところである。だが、彼はそうはいわないで、「瑕(きず)生ず」といった。それで瑕ができたというのである。どうして瑕ができたのだろうか。暦劫無名といったのが瑕であるというのであろう。だが、瑕ができても古鏡は古鏡である。三聖はまだ古鏡の瑕の窟(あな)にこだわっていたから、そのようないい方もしたのであろう。それはまったく古鏡の瑕であった。だから、古鏡にも瑕ができる、瑕ができても古鏡であると、そのようにまなびいたるのが、古鏡のまなび方というものである。
そこで三聖がいった。
「什麼(しも)の死急ありてか、話頭(わとう)もまた識(し)らざる」
そのいう意味は、まず、「どうしてこんなに急ぐのでありましょうか」ということである。いうところの「死急」とは、今日か明日か、自分のことか他人のことか、あるいは、全世界のことか、中国のなかのことか、つぶさに思いめぐらしてみるがよい。
つづいて、「話もよく判りません」というのである。話というものは、いま語られている話もあり、まだ語られない話もあり、すでに語りおわった話もあるが、いまは話の道理を会得することをいっておるのである。たとえば、同じ話でも、「大地有情、同時成道」といったたぐいの話は、ただ言辞をつなぎ合せただけで理解できるものではない。だから「識らず」というのである。たとえば、「朕(ちん)に対する者は識らず」というがそれである。対面しても識らないのである。その時、対話がなかったわけではない。ただ理解できないのである。三聖が「識らず」といったのは、まったく赤心を打ち出していったのである。さらにいうなれば、それが明々白々にして、なお判らないというのである。
そこで、雪峰がいった。
「老僧がわるかったのだ」
そのことばは、いい方がわるかったという時にも、そういういい方をするけれども、ここではそう心得てはならない。老僧というのは寺のあるじである。その門下には、他の事をまなぶのではなく、ひとえに老僧をまなぶのである。いろいろの事があり、さまざまの人があるが、到ってまなぶのはただ老僧一人である、幾久しい間には、もろもろの仏祖がましますなかでも、参じて学ぶのはただ老僧一位である。「老僧がわるかったのだ」というのは、住持の仕事が繁多(はんた)であったというのである。
思えば、雪峰は徳山(さん)門下の俊秀であった。三聖は臨済門下の高弟であった。二人の長老はいずれも系譜はすばらしい。一人は青原のとおい法脈につながり、一人は南嶽のとおい流れを汲む。いま、ともに古鏡を保ちきたってかくのごとくであった。ひとしく後進の鑑(かんが)みるべき鏡であろう。(238~241頁)
〈注解〉
※この一段は、『碧巌録』第六八則がつたえる雪峰と三聖の問答をあげて、それに精細な説明を加えたものである。
◯三聖院慧然禅師 臨済の下に学び、のち辞して雪峰にまなび、また仰山にまなんだ。『碧巌録』第六八則を、「三聖金鱗」と題する。
◯老僧罪過云々 『碧巌録』第六八則には、「峰云、罪過、老僧住持事繁」と見えている。雪峰が、「わるかったなあ、わしは住職の仕事が忙しいものだから」といったのである。その意味を、道元はつぶさに説明しておる。なお、『碧巌録』の文は、つづけて、三聖が雪峰山をさって、「後至仰山」すなわち、仰山に参学したことを記している。(241~242頁)
■〈現代語訳〉
雪峰は衆に示していった。
「世界のひろきこと一丈であれば、古鏡のひろきことまた一丈である。世界のひろきこと一尺なれば、古鏡のひろきことまた一尺である」
その時、幻沙が囲炉裏を指さして問うていった。
「では、火炉(かろ)のひろさはどのくらいでありましょう」
雪峰はいった。
「古鏡のひろさに似ているよ」
幻沙はいった。
「老和尚の足のかかとは、まだ地についておりませんなあ」(246頁)
■だが、幻沙はそれを評して、「老和尚の足のかかとは、まだ地についていない」といった。
そのいうところは、老漢といい、老和尚といっても、必ずしも雪峰のことではあるまい。だが、雪峰もまた老漢であろうから、足のかかとというは、いったい、どこのことだと問うべきところである。
では、まず、足のかかととは、何をいっておるのかを究明してみるがよい。究明してみるというのは、正法(しょうぼう)の眼目をいうのか、虚空をいうのか、大地をいうのか、生命をいうのであるか。また、足のかかとは幾箇あるのか、一箇であるか、半箇であるか、それとも百千万箇あるものか。そんなふうに努めてまなぶがよいのである。
また、その足のかかとは、まだ地についていないという。その地というのは、いったいどんなものか。いまの大地というのは、一般の人々の所見にしたがって、いちおう地といっておるだけのことで、さらに所見を異にすれば、あるいは不可思議な解脱の境地とみるものもあり、あるいは三世諸仏の行ずるこころとみるものもあろう。
とするならば、足のかかとを印すべき地とは、なにをいうのであるか。いったい、地とは実在するものであるか、実在しないものであるか。あるいは、いったい地というものは、仏道においてはまったく無かるべきものであるか。問い来り、問い去り、あるいは、他に語り、自己に語ってみるがよい。
あるいは、また、足のかかとは、地につけるのがよいか、つけないのがよいか。また、どうしてまだ地についていないというのか。もしも大地に寸土もない時もあらば、地につけるというのも不十分であり、地につけないというのもおかしい。とするならば、老和尚の足のかかとが、まだ地についていないらしいというのは、老師の心境をいうに、しばらく足のかかとをもって語ったものであろう。(249~250頁)
〈注解〉
◯什麼物恁麼来 『景徳伝燈録』巻五、南嶽伝にみえる一句であって、南嶽がはじめて慧能にまみえた時、慧能が語ったことばである。「こんな者が、どこから来たのか」というほどの意であった。その類例をみない器であることを語ったことばである。
◯大道 すぐれた大いなる道というほどの意であるが、仏教をいっておることは間違いない。たとえば、「大道無門」などというのもそれである。(251頁)
■〈現代語訳〉
〔古鏡のまだ磨かない時〕
金華山の国泰院弘とう(王ヘンに舀)禅師に、ひとりの僧が問うていった。
「古鏡のまだ磨かない時は、どんなでありましょうか」
師はいった。
「古鏡」
僧がまた問うていった。
「では、磨いてからは、どうなるのでありましょうか」
師はいった。
「古鏡」
それでも判るように、いまいうところの古鏡には、磨く時があり、まだ磨かぬ時があり、また、磨いたあとの時があるけれども、いずれも同じく古鏡である。
したがって、また、古鏡を磨く時には、古鏡そのものを磨くのである。古鏡ではない水銀などを混ぜて磨くのではない。また、自己を磨くでも、自己が磨くでもない。ただ古鏡を磨くである。また、磨かない時にも、それは眛(くら)いわけではない。よく眛いとはいうけれども、眛いわけではあるまい。もともと古鏡は活(い)きているのである。
これを要すれば、鏡を磨いて鏡となすのであり、瓦を磨いて鏡となすのであり、さらにいえば、瓦を磨いて瓦となすのであり、鏡を磨いて瓦となすのである。世には、磨いても鏡とならないものもあれば、鏡となることができるのに磨かないものもある。それがすべて仏教というものである。
かって、江西(せい)の馬祖が南嶽に師事していたころ、南嶽は、ふしぎな仕方でさとりを得しめた。それが瓦を磨くということばのはじめであった。
そのころ、馬祖は伝法(ぽう)院に住して、世のつねのように坐禅を行ずること、ほぼ十余年のことのことであった。雨夜(あまよ)の草庵のただずまいを思いやるがよい。雪にとざされて寒々とした坐ショウ(爿ヘンに木)にも怠ることがなかった。その草庵を、ある時、南嶽が訪れたのである。
馬祖がかたわらに侍立(じりつ)していると、南嶽が問うていった。
「そなたは、この頃なにをしておるか」
馬祖はいった。
「この頃わたしは、ただ坐っておるだけでございます」
南嶽がいった。
「坐禅をして、どうしようというのか」
馬祖がいった。
「坐禅をして仏になろうとするのでございます」
すると、南嶽は、一片の瓦をひろってきて、草庵のほとりの石にあてて磨きはじめた。それを見て、馬祖は、問うていった。
「和尚は、なにをなさるのですか」
南嶽がいった。
「瓦を磨くのじゃ」
馬祖はいった。
「瓦を磨いて、それをどうなさるのですか」
南嶽がいった。
「磨いて鏡にしようというのじゃ」
馬祖はいった。
「瓦を磨いて、どうして鏡となすことができましょうぞ」
南嶽がいった。
「坐禅をしたからとて、どうして仏になることができようか」
この一段の対話は、昔から何百年ものあいだ、人々はたいてい、ただ南嶽が馬祖を激励したとのみ思っている。けっして、そうとのみは限らないのである。すぐれた聖者の言行は、はるかに凡人の境地をぬきん出ているのである。
いかにすぐれた聖者であろうとも、もし瓦を磨く手立てがなかったならば、どうして人のために方便をたてえようか。人のためにするというのは仏祖の本質というもの。そのために手段を講ずるのは、いうなれば手なれた家具というものである。家具であり、調度であるから、それが仏の家につたえられるのである。ましてや、いま南嶽は、それをもって、みごとに馬祖をみちびきたもうた。その指導のありようは、仏祖正伝とは直指(じきし)であることをよく示している。
まことに知る。磨いた瓦が鏡となった時、馬祖が仏となったのである。また、馬祖が仏となった時、馬祖はたちまち馬祖その人となったのである。そして、馬祖が馬祖となったその時、坐禅がたちまち坐禅となった。
もしも、磨いた瓦が鏡とならないならば、鏡を磨いても鏡となすことはできまい。誰が考えたことでもあるまいが、おなじ「作」の一字を冠(かん)して、作仏といい、また作鏡というではないか。
また、古鏡を磨くにあたり、あやまって瓦としてしまうことはないかと心配する者もあろうか。だが、この磨く時の消息は、他の場合をもって推し測るべきものではない。ともあれ、南嶽のことばは、まさにいうべきことをいいえているのであって、結局するところ、かならず瓦を磨いて鏡となすことをうるのである。では、いまの人もまた、その瓦をとって試みに磨いてみるがよい。きっと鏡となすことをうるであろう。
もしも、瓦が鏡とならないものならば、人が仏となろうはずはない。もしも、瓦は泥のかたまりだと軽んずならば、人もまた泥のかたまりと軽んじねばなるまい。人にもし心があるなとならば、瓦にもまた心があるかずである。誰が知ろうぞ、瓦を磨ききたって瓦を現ずる鏡のあろうことを。また、誰ぞ知らん、鏡を磨ききたって鏡をなせる鏡の存することを。(255~259頁)
〈注解〉
※この一段には、国泰院弘とう(王ヘンに舀)禅師の問答、ならびに、南嶽・馬祖の問答の二つの問答が取り上げられている。いずれも『景徳伝燈録』によるものであるとともに、また、ともに古鏡を論じたものである。しかも、その古鏡への言及は、いずれも鏡を磨くという問題に関連している。それは、詮ずるところ、修行と作仏の問題にほかならないと知られる。その問題に論じいたって、この「古鏡」の巻の結びとするのである。
◯塼 瓦である。
◯江西馬祖 馬祖道一(786寂、寿80)である。南嶽懐譲の法嗣、江西鎮陵の開元寺に住し、江西の馬祖として知られた。ここに記す南嶽との問答は、『景徳伝燈録』巻六、南嶽伝にみえる。この問答には、つづいて南嶽の教誡として、「汝学坐禅、為(これ)学坐禅、若(もし)学坐禅、禅非坐禅、禅非坐臥、若学坐仏、仏非定相」の句がみえておる。よってもって、南嶽が馬祖を接得した消息をうかがうことができるであろう。(260頁)
看経(かんきん)
■〈原文〉
阿耨多羅三藐三菩提の修証(しゅしょう)、あるいは知識をもちゐ、あるいは経巻をもちゐる。知識といふは、全自己の仏祖なり。全仏祖の自己、全経巻の自己なるがゆゑにかくのごとくなり。自己と称すといへども、我ニ(人べんに爾)の拘牽(こうけん)にあらず。これ活眼睛(かつがんぜい)なり、活拳頭なり。しかあれども、念経(きん)・看経・誦経(ずきょう)・書経・受経・持経あり、ともに仏祖の修(しゅ)証なり。(263~264頁)
■〈現代語訳〉
〔経巻とはなにか〕
最高の智慧を修するには、あるいは善知識にしたがい、あるいは善知識にしたがい、あるいは経巻をもちいる。善知識というのは全自己の仏祖であり、経巻というのは全自己の経巻である。これをひるがえしていうならば、全仏祖の自己であり、全経巻の自己であるがゆえに、かくはいうのである。自己とはいうけれども、それは、もはや我と汝の関係ではなく、そこにはただ活(い)ける拳頭(こぶし)があるのみである。それでもなお念経(ねんきん)があり、看経(かんきん)があり、誦経(ずきょう)があり、書経があり、受経があり、また持経ということがある。すべて仏祖のなしきたれるところである。
しかるに、仏の経巻に遇うということは、けっしてたやすいことではない。数かぎりない国々にあっても、その名すらも聞くことは稀である。仏祖のほとりにありながらも、その名を聞くことさえもえない者もある。あるいは、その生けるかぎりにおいて、その名さえ聞くことをえない者もすくなくない。仏祖によらざれば経巻を見聞することも、読誦(どくじゅ)することも、その意を解することもえないからである。かくて、仏祖にまみえて、やっと経巻を学びはじめる。その時はじめて、耳・眼・舌・鼻もしくは身心をあげて、到るところ、聞くところ、語るところにおいて、経の聞(もん)・持(じ)・受・説等のことが成就するのである。名聞(みょうもん)をもとめようがために外道の所説を語るような輩は、とても仏の経巻を知ることはできない。けだし、経巻は、かつて菩薩たちが、樹や石に書きつけて伝持したものであり、田や里にいたって流布したものであり、あるいは、如来が諸国に姿を現わして語り、あるいは虚空にあって説きいでたものであるからである。(264~265頁)
〈注解〉
※道元は、まず冒頭において、経巻とは何かを語り、この格調たかい一段をなしている。
◯受経 経をさずかって受けるのである。
◯持経 経をつねに持して忘失しないこと。(265~266頁)
■〈注解〉
◯転経 「てんぎょう」または「てんぎん」と読む。また転読という。経典を読誦することにほかならない。
◯五蘊 人間の身心をいう。
◯有漏・無漏 漏は煩悩。それのある智は俗智。それのないのが聖智。それを有漏・無漏法の界といえば、俗界と聖界であろう。(280頁)
■〈注解〉
◯知客 「しか」と読む。また転読という。禅林にて賓客のことを掌(つかさど)る役名。接待役である。
◯清規 禅林にて、大衆の日常における進退について定めた規則である。(297~298頁)
仏性(ぶっしょう)
■〈現代語訳〉
「一切衆生、悉有仏性、如来常住、無有変易(むうへんえき)」
それは、われらの大師釈尊のとかれた大説法であるが、また、すべての仏たち、すべての祖たちの頭頂(ずちょう)となし、眼目となすところである。仏教者はこれをまなびきたること、すでに二千百九十年(日本の仁治二年にあたる)、その間、正嫡(しょうちゃく)をかぞうればおおよそ五十代(先師天童如浄禅師に至る)、西のかた天竺において代々伝持すること二十八代、東のかた中国において世々相承(そうじょう)すること二十三世、みなよく保ちつづけて今日にいたる。
釈尊がいうところの「一切衆生、悉有仏性」とは、その意味するところはいかに。それは、「こんな物がどうして来たのだ」といっておられるのである。あるいは衆生といい、あるいは有情(うじょう)といい、あるいは群生(しょう)といい、あるいは群類という。悉有というのは、その群生のことであり、その群有(う)のことである。つまり、悉有は仏性であって、その悉有の一つのありようを衆生というのである。そさにその時にいたれば、衆生はその内も外もそのまま仏性の悉有である。それは仏祖の伝える皮肉骨髄のみではない。「汝はわが皮肉骨髄を得たり」であるからである。
それによっても判るように、いま仏性に悉有せられる「有(う)」は、有りや無しやの有ではない。悉有は仏のことばであり、仏の舌であり、したがって、また仏祖の眼目であり、仏者の鼻孔である。それはけっして始有(しう)でもなく、本有(ぬ)でもなく、また妙有(う)などというものでもない。ましてや、縁有(う)や妄有(う)であろうはずはない。心・境・性・相などに関わるものでもない。だからして、衆生悉有の身心と世界とは、すべて、業の力をもって変えうるものでもなく、妄情を縁として齎(もたら)されるものでもなく、あるいは自然にしてかくあるものでもなく、神通の力によって証得せられるものでもない。もしも衆生の悉有なる仏性が、業によるもの、縁によるもの、あるいは自然にしてかくあるものとするならば、もろもろの聖者のさとりも、もろもろの仏の智慧も、あるいはもろもろの祖の眼目も、また業や縁や自然にしてしかるものであろう。だが、そうではないのである。すべてこの世界にはまったく外より来るものはない。ずばりといえば、べつに第二の人があるわけではない。ただ、「直(ただ)ちに根源を切断することを知らず、あれこれと妄想を逞(たくま)しゅうして休(や)む」の時がないのである。「偏界かつて蔵(かく)さず」という。妄情によってなる存在などあろうはずもないのである。
だが、「偏界かって蔵(かく)さず」というのは、かならずしも「一切世界はわが有(う)」ということではない。それは外道のまちがった所見である。だからといって、また本有(ぬ)の有ではない。それは古今にわたっての存在であるからである。また、はじめて起これる有でもない。「一塵をも受けず」であるからである。また、突如として出現する有でもない。だから、「こんな物がどうして来たのだ」という。あるいは、ある時はじめて存する有でもない。だから「平常心これ道」というのである。つまるところ、悉有というは、快(こころ)よき便の捉えどころがないようなものであって、そのように会得すれば、悉有は気持ちよく身体を通りぬけて脱落してゆくのである。(304~306頁)
〈注解〉
※まず『涅槃経』のよく知られた「一切衆生、悉有仏性」の句をあげて解説する。しかるに、その解説はまったく卓抜にして、目を見張らしめる。特に「悉有」の解釈がそうである。それは「悉く有す」ではなくて、むしろ、全存在を意味することばとして解されている。はなはだ解しがたい一段であるが、よくよく心して味われたい。
◯什麼物恁麼来 『景徳伝燈録』巻五、南嶽伝にみえる一句。南嶽懐譲がはじめて六祖慧能に見参したときの問答であって、そこには、「乃直詣曹谿六祖、祖問、什麼処来。曰、嵩山(すうざん)来。祖曰、什麼物恁麼来」とある。「こんな物がどうして来たのだ」というほどの意であろう。
◯始有・本有・妙有・縁有・妄有 有という仏教の述語は、もと“bhava”(=beinng)の訳語である。音写して烏波(うは)ともいう。あることであり、存在である。そのありようにさまざまある。ある時より始めてあるを始有(しう)という。もとよりあるを本有(ぬ)という。空にして有なるを真空妙有という。また、縁(条件)あるによりてあるを縁有といい、迷妄によりてあるを妄有という。そして、仏性の悉有はそのいずれでもないとするのである。
◯心・境・性・相 心は内なる心、境は外なる対象、事物の本質として易(かわ)らざるは性であり、その性のあらわれとしてのすがた・はたらきは相である。
◯偏(ギョウニンベン)界不曾蔵 「偏界曾って蔵(かく)さず」である。『碧巌録』巻五三則に、「偏界不蔵、全機独露」の句もみえる。一切の諸法はいささかもその秘密をかくし蔵することなく、その実相をそのままに露呈しているというほどの意である。
◯平常心是道 『無門関』の「平常是道」のくだりに、南泉と趙州の問答がある。「趙州問、如何是道、泉曰、平常心是道」と。
◯快便難逢 『渉典続貂(しょうてんぞくちょう)』によれば、『談藪(だんそう)』なる文献に「下坡不走、快便難逢」の句があるという。坡(どて)でここちよく小便をする。小便はさらさらと流れてゆく。それはもう逢えない。そんな意味であろう。その句をもって、道元は、つぎの透体脱落の句にかけているのである。(306~308頁)
■〈現代語訳〉
〔仏性の誤れる解釈を批判する〕
その仏性ということばを、学者のなかには、先尼外道のいう「我(が)」のように思い誤っているものがすくなくない。それは、然るべき人にあわず、自己にもあわず、師にもまなばないからである。ただいたずらに、わが内に風のそよぎ火のもゆるようにゆれ動く心識をもて、それが覚知のはたらきだと思っているのである。いったい、仏性に覚知のはたらきがあるなどと、誰がいったのであろうか。なるほど、諸仏のことを覚者といい知者とはいうけれども、仏性はけっして覚知でも覚了でもない。ましてや、諸仏を覚者・知者というときの覚と知よは、なんじらが云々する誤れる考えをいうのではない。風・火の二大(にだい)のうごきを覚知とするのではない。ただ、一箇両箇の仏の面目、祖の面目のなるを覚知とするのである。
漢より宋にいたるまでの間にも、あるいは西の天竺にまで往復し、あるいは人々の教化に力をつくした古老先徳はすくなくなかったが、そのなかにも、風大(ふうだい)・火大(かだい)の動きをもって仏性のはたらきと思っていたものはすくなくなかった。あわれむべきことである。仏性のまなびかたが疎漏であったためにこの誤りをおかしたのである。いま仏教をまなぼうとする後学初心のものはそうではいけない。
たとい覚知をまなんでも、覚知とはそんな心の動きではない。たとい心の動きをまなんでも、心のはたらきはそんなものではない。もし本当の心のはたらきを会得できれば、本当の覚知もわかるはずである。「仏と性とは、かれに達しこれに達す」という。仏性はかならず悉有である。悉有が仏性であるからである。悉有とはばらばらになったものではなく、また鉄のかたまりのようなものでもない。あるいは、雲水が拳(げん)骨を突きだすあれであって、大でもなく小でもない。また、すでに仏性というからには、もろもろの聖者とならべていうべきでもない。それは仏性と比すべきものではない。
ある一部の人々は、仏性は草木の種子のようなものだという。それは、法雨のきたって、しきりと潤すとき、芽を出し、茎を生じ、枝や葉をひろげ、花をひらき果(み)をむすぶにいたり、さらにその果は種子をはらむ。だが、そのように考えるのは凡夫の計らいというものである。たといそのような見方をしても、その種子とその花と果は、それぞれ別々の心のすがたと考えてみるがよい。果のなかに種子があったり、種子のなかには見えないけれど根や茎があったり、あるいは、どこから集めてくるわけでもないが、そこばくの枝や葉をだして繁りはびこる。そんな内か外かの問題でもなく、生ずる生じないの問題でもない。これは古今にわたって空しからぬものである。だから、たとい一応は凡夫の見解にまかせるとしても、ここでは根も茎も枝も葉も、すべてが同時に生じ同時に滅するものと知らねばならない。同じく悉有なる仏性だからである。(310~311頁)
■〈注解〉
◯先尼外道 先尼は“Seniya”の音写であって外道の姓である。その外道の説くところは、さきの「即心是仏」の巻にくわしく紹介され、かつ、大証国師慧忠の語をもって、それに批判が加えられている。参照されたい。(312頁)
■〈現代語訳〉
〔仏性の義をたずねる〕
仏いわく、
「仏性の義を知らんと欲(おも)わば、当(まさ)に時節の因縁を観ずべし。時節もし至れば、仏性現前す」
いま仏性の義を知りたいと思うならばという。それはただ知るのみのことではない。また行じようと思うならばであり、証ししようとするならばであり、あるいは、説こうとするならばであり、忘れようとするならばである。その説も、行も証も、忘も、あるいは錯(たが)うも、錯わざるも、すべては時の関係である。その時の関係を観察するには、時の関係をもって観ずるのである。払子(ほっす)・拄杖(しゅじょう)などをもって観ずるのである。けっして、有漏智・無漏智、もしくは本覚(がく)・始覚(しかく)・無覚(かく)・正覚(しょうがく)の智をもってしては観察しがたいのである。当(まさ)に観ずべしというは、観るか観られるかにかかわらず、また正しく観るか誤って観るかなどということでもなく、まさに当に観ずるである。当に観ずるのであるから、自己が観るのでもなく、他が観るのでもない。時の関係そのままにして、時の関係を超絶するのである。仏性そのままにして、仏性を脱却するのである。仏は仏そのままに、性は性そのままに観ずるのである。
時節もし至ればという。その句を、昔の人も今の人も、往々にして、いつか仏性が現われる時があるだろうから、その時を待つのだと思っている。このように修行してゆけば、自然に仏性の現われる時期もsるだろう。時期が来なければ、いくら師を訪(おとな)うて法を問おうとも、分別して思いめぐらしても、なかなか現れてくるものではあるまいと、そのように考えて、なすこともなく俗塵に沈み、むなしく阿呆(ほう)な面(つら)をさらしている。そんな徒輩はおそらく自然(じねん)外道の仲間なのであろう。
いまいうところの「仏性の義を知らんと欲(おも)わば」とは、いいかえれば、また「当(まさ)に仏性の義を知るべし」ということである。また「当に時節の因縁を観ずべし」というは、「当に時節の因縁を知るべし」ということである。いわゆる仏性を知ろうと思うならば、時節の因縁がそれであると知らねばならない。時節もし至ればというのは、すでに時節がいたっておるのだ、なんの躊躇(ため)らうことやあらんというのである。疑うならば疑ってみるもよい。仏性はいつか我に還って来ているのである。
まさに知るがよい。時節もし至らばとは、寸分の時も空しく過ごしてはならぬということであり、もし至らばとは、すでに至るというに同じである。もしも時いたらばと待つならば、仏性はついに至らぬであろう。かくして、時すでに至れりとあらば、それこそ仏性の現われである。あるいは、その理(ことわり)もおのずから明らかなのである。およそ、時いたらぬ時というものはなく、仏性の現前せざる仏性というものはないのである。
第十二祖馬鳴(めみょう)尊者は、第十三祖のために、仏性海のことわりを説いていった。
「山(せん)河大地は、みな依りて建立し、三昧・六通は、これによって発現す」
とするならば、山河・大地はすべて仏性の海である。みな依りて建立すというのは、いま現に建立せられて、山河・大地はすべて仏性の海である。みな依りて建立とある。さすれば、仏性海のすがたはかかるものと知られるのである。それはけっして、内の、外の、中間のという問題ではない。そうだとすれば、山河を見るというのは、そのまま仏性を見ることであり、仏性を見るというは、驢馬(ろば)の腮(えら)を見、馬の觜(くちばし)を見ることである。みな依る(皆依)というは、全てが依る(全依)であり、また全てに依る(依全)であると、会得し、また会得せぬのである。
また、三昧・六通はここによりて発現すという。しるがよい。もろもろの三昧の発(おこ)り来るも、みな仏性によるのであり、六神通(じんずう)のなるもならぬも、ともに仏性によるのである。ここに六神通というは、ただ小乗教においていう六つの神通のみではない。六というのは、前後さまざまなるを六神通の成就とはいうのである。だからとて、六神通とは、きそい茂る百草をすべて、明々たる仏祖のこころであるといった工合に考えてはならぬ。六神通にこだわり滞(とどこお)るのもまた、仏性の海にそそぐ流れを阻害することとなるのである。(314~317頁)
〈注解〉
◯有漏智・無漏智 漏とは煩悩のはたらきをいうことば。有漏智とは、いまだ煩悩を断たざる世俗智をいい、それに対して、無漏智とは、一切の煩悩をはなれた清浄な智慧をいう。
◯本覚・始覚 本覚とは、本有(ぬ)の覚性というほどの意である。それに対して、始覚とは、教えを聞いてはじめて覚(めざ)めることである。だが、そのような覚める性は、突きつめてみると、もともとわが内に存するものであったはずである。それが本有の覚性である。(後略)
◯天然外道 また自然外道、もしくは自然見外道という。十種外道の一つである。一切の存在は因によりて生起することを認めず、自然にしてかくあるものとなすが故に、なんの人力の加うるところなしとする見解に立つのである。
◯三昧 “samadhi”の音写である。また、三摩提(さんまでい)と写す。定と訳す。心を一処に集中して動せしめざるをいう。
◯六通 六神通である。定・慧等の力によってうる六種の自在なる力をいう。神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏尽通(ろうじんつう)をいうのが常である。
◯神通波羅蜜 波羅蜜は“paranita”の音写であって、到達、完成、成就を意味する。(318~319頁)
■〈現代語訳〉
〔衆生無仏性ということ〕
中国の第六祖曹谿山(さん)大鑑禅師が、そのむかしはじめて黄梅山(おうばいざん)に詣(いた)ったとき、五祖は問うていった。
「汝はいずれの処よりきたのか」
彼はいった。
「嶺南人でございます。
五祖はいった。
「来ってなにを求めんとするか」
彼はいった。
「ただ仏となることを求めるのでがざいます」
五祖はいった。
「嶺南人は無仏性である。どうして仏となれようぞ」
この「嶺南人は無仏性」というのは、嶺南人には仏性がないというのでもなく、嶺南人は仏性があるというのでもない。ただ「嶺南人は無仏性」というのである。
いったい、仏性の道理は、これを明確につかんだ先達(だち)はすくない。それはも、もろもろの小乗の徒輩や、経師(じ)や論師の知りうるところではない。ただ仏祖の流れを汲むもののみがそれを伝え来っておる。(岡野;『)仏性というものは、成仏以前に身に具(そな)わっているものではなく、仏となってはじめて具わる。仏性はかならず成仏にともなう。その道理をよくまなびよく究めるがよい。(岡野;』)二十年も三十年もかけて工夫しかつまなぶがよい。修行の途中にあるものが知りうるところではない。いま衆生に仏性ありといい、また衆生に仏性なしというは、この道理によるのであり、それは成仏以来はじめて具足するのだとまなぶのが正しいのである。そのようにまなばないのは仏法ではあるまい。でなかったならば、仏法はとうてい今日に到りえなかったであろう。もしこの道理をしらなかったならば、成仏も判るまい、聞くことも見ることもないのである。
かかるがゆえに、五祖は、彼に向かって語るに、嶺南人は無仏性だといったのである。仏法をまなぶにあたって、まず聞きうることの難きは、衆生無仏性ということである。あるいは善知識にしたがい、あるいは経巻によって、聞いてよろこぶべきことは、衆生無仏性ということでなくてはならぬ。一切衆生に仏性なしと、いやというほど聞かされ思いしらされるのでなかったならば、まだ仏性のことを聞いた判ったとはいえない。六祖はひたすらに仏とならんことをねがう。五祖は彼をしてよく作仏せしめようとする。それには他にいい方はない。ただ「嶺南人は無仏性」だというのみである。かくて、無仏性と語り、無仏性と聞く。それがまっ直ぐに作仏にいたる道だと知られるのである。とするならば、まさに無仏性のその時こそが、とりも直さず仏となるの時である。いまだ無仏性と聞かず、語らざるの時には、まだまだ仏にはなれないのである。
すると、六祖はいった。
「人に南北はあっても、仏性には南北はありません」
そのことばを取りあげて、その句のこころを思いめぐらしてみるがよい。とくに南北ということばは、心にあてて照らしてみるがよいのである。この六祖のことばには大事な意味がある。それは、人は仏となりえても、仏性は仏となりえないという一つの構えである。六祖はそれに気がついていたかどうか。
思うに、四祖・五祖の語った無仏性という表現は、まことに注目をうながすに足るものであった。はるかにそれに相対して、迦葉仏や釈迦牟尼仏などの仏たちは、仏となり法を説くにあたって、悉有仏性と表現する力をもっておられた。その悉有の有から無仏性の無へと法が嗣がれてきたもすこしも不思議ではない。かくして、無仏性の語は四祖・五祖の室内より聞こえきたって、はるかに今日におよんでおる。だが、この時、六祖ほどの人であったならば、この無仏性の語をもう一歩ふみ込んだ工夫があってしかるべきであったと思う。有りや無しやはしばらく措(お)いて、いったい仏性とはいかにと問うてみるべきであった。仏性とはそもそもどのようなものかと訪ねるべきではなかったか。今の人々も、仏性と聞けば、さらに仏性とはなんぞと問うこともせず、ただ仏性の有りや無しやなどとのみ論ずる。それと同じである。迂闊というものである。
とするならば、しばらくいろいろの場合の無をとりあげて、無仏性の無にあてて考えてみるがよい。六祖は「人に南北あり、仏性に南北なし」といった。その表現を再三再四、ふかく沈潜して掬うてみるがよい。蝦(えび)をとるには撈波子(ろうはし)という竹具をもってすくう。まさにそのようにして掬ってみるがよい。あるいはそれをしずかに捏(こ)ねまわしてみるもよい。しかるるを愚かななる輩は、人間には物のひっかかりがあるから南北があるが、仏性は虚にして無礙なるがゆえに南北の論におよばずと、六祖のことばをそんな工合に推し測る。それはわけもない愚蒙の沙汰というもの。そんな愚かな考え方はなげすてて、まっ直ぐにまなびいたらねばならぬ。(330~333頁)
■〈現代語訳〉
〔無常とはすなはち仏性である〕
六祖が門人の行昌(ぎょうしょう)にしめしていった。
「無常とはすなはち仏性である。有情はすなはち善悪の一切諸法を分別する心である』
ここに六祖がいうところの無常は、外道や小乗などの測り知るところではない。小乗や外道のやからどもも、また無常というけれども、彼らはその意を汲みつくすことはできないのである。
つまり、無常なるものがみずから無常を説きいで、行じきたり、証し去るならば、すべては無常であろう。「いま現在の自身をもって得度すべき者には、すなわち自身を現じてために法を説く」という。それが仏性である。さらにある時には、大いなる法身(ほっしん)を現ずることがあり、またある時には、小さなる法身を現ずることもあるであろう。常なる聖者も無常である。常なる凡夫も無常である。凡夫と聖者がきまっているとしたら、それは仏性ではありえない。それは見解のせまい愚か者の見るところであり、凡俗の推測していうところであって、その仏は小さなる仏であり、その性はつまらぬ作用(はたらき)しかできない。その故をもって六祖は「無常は仏性なり」といった。
常(じょう)は未転であるという。未転とは、たとい煩悩を断つ、煩悩が断たれたという変化はあっても、かならずしも今までの自己が去って新しい自己が来ったわけではない。だから常である。むしろ、草木叢(そう)林の無常なるすがた、それが仏性である。あるいは、人間の身心の無常なるありよう、それが仏性である。国土山河の無常なること、それも仏性だからである。仏の無上の智慧、それも仏性であるから無常である。あるいはまた、仏が大いなる死をとりたまえること、それも無常であるから仏性である。もろもろの小見をいだく小乗のやから、あるいは経や論のみをあげつらう学者どむは、この仏祖をことがを聞いたならば、驚いてその耳をうたがい、震えあがって怖れるであろう。悪魔・外道のたぐいだからである。(335~336頁)
■そこにはまず、「汝仏性を見んと欲せば、先ず須(すべか)らく我慢を除くべし」とある。その説く意味を、素通りせずに考えてみるがよい。それは見ることができないわけではない。だが、見るためには我慢を除かねばならぬ。我もひとつではない、慢もさまざまである。それを除くにもまたさまざまの方法があろう。だが、いずれにしても、かくすれば仏性を見ることをうるのである。この眼で見るように見えるのである。
また、「仏性は大にあらず小にあらず」という。それも世のつねの凡夫や小乗のやからの例にならってはならぬ。かたくなに仏性は広大なものとのみ思うのは、かえって誤解を重ねることとなろう。もしも大にあらず小にあらずというその表現にひっかかるようならば、いままさに龍樹の前にあってそれを聴くような思いをもって思いめぐらしてみるがよい。そう思って聴いておると、尊者はやがて偈を説いて申される。「身に円月の相を現じ、もって諸仏の体を表わす」と。それは、もろもろの仏の実体を身をもって表現するのであるから、とうぜん円月の相でなくてはならない。そこでは、長いの短いの、四角いの円いのというは、すべてその実体ではない。その身相における表現が判らなければ、円月の相が判らないばかりでなく、また諸仏の実体も判らないであろう。(346頁)
■さて、迦那提婆(かなだいば)はその時、龍樹菩薩のその姿を指さして、一座の人々に告げていった。「これは尊者が仏性の姿を現じて、われわれに示しておられるのである。どうしてそれが判るかといえば、無相三昧(ざんまい)はその姿満月のごとくにして、仏性は廓然(かくねん)として虚明(こめい)なものであるからである」と。いまこの世界にくまもなく流布する仏法をまなび来れる古今の人々にして、この姿をもって仏性なりといったものが誰があろうか。その余の人々はただ、仏性とは眼に身、耳に聴き、心に識(し)るなどのものではないと表現するのみである。この姿が仏性とは知らないからいい得ないのである。祖師が惜しむわけではないが、ただ眼も耳もふさがっているから見聞することができないのである。あるいは、それをそうと識るべき境地にいたらないから了別することができないのである。無相三昧の姿の満月のごとくなるを望見し礼拝しながらも、なお眼はそれと見ることができないのである。(348~349頁)
■識(し)るがよい。かの円月の相を現じたるをえがかんとならば、その法坐にその姿が現われねばならない。眉を揚げ目をまたたく端正な姿がそこになくてはならない。正法眼蔵そのものの姿が、そこに高々として坐しているのでなくてはならぬ。あるいは、にっこりと微笑する顔がそこになくてはならない。けだし、その時こそ、仏が成り祖が成るのときだからである。その画がそのまま月の姿でなかったならば、それはいまだ到らず、説法もせず、声(しょう)色もなく、なんの用もなさぬのである。もしその姿をえがこうとならば、円月相をえがけば、円月の姿がえがかれるであろう。その姿が円月相であるから、円月相をえがけば満月の相がえがかれ、満月の姿が現ずるであろう。しかるに、その姿をえがかず、円月をえがかず、満月の相をえががず、したがって、諸法の実体を表わすことをえず、説法もせず、ただいたずらに画餅一枚をえがく。それがなんの用をなそう。いそぎ見たからとて、誰も飢えを充たすことはできまい。なるほど月は円い。円きは仏の姿である。その円きをまなぶに一枚の銭のように思ってはならぬ。一枚の餅に似ているとしてはならぬ。その姿は円月の姿である。「その形満月のごとし」である。一枚の銭、一枚の餅は、その円きをまなぶがよいのである。(350~351頁)
■〈注解〉
◯我慢 我をたのんで心おごれるをいう。(351頁)
■〈注解〉
◯知客 「しか」と読む。禅林にあって賓客の接待をつかさどる僧の役名である。
◯堂頭 「どうちょう」と読む。禅林にて、一寺の頭すなはち住持をいう。(350頁)
■〈現代語訳〉
〔有仏性ということ、無仏性ということ〕
杭州塩官(がん)県の斉(せい)安国師は、馬祖門下の長老である。ある時、衆(しゅ)に示していった。
「一切衆生有仏性」
いうところの一切衆生ということばを、まず検討してみなければならない。一切衆生は、その所業(ごう)、身心、住む世界においてひとつではなく、したがってその考え方もまちまちである。あるいは凡夫や外道の考え方があり、あるいは三乗・五乗の考え方など、それぞれに相異なる。いま仏教でいう一切衆生は、心ある者はみな衆生である。心がすなわち衆生であるからである。だが、心なき者も同じく衆生であろう。衆生がすなわち心であるからである。とするならば、心はみな衆生であり、衆生はみな有仏性である。草木国土は心である。心であるから衆生であり、衆生であるから有仏性である。日月星辰は心である。心であるから衆生であり、衆生であるから有仏性である。いま国師がいうところの有仏性とは、そのようなことなのである。もしそうでなかったならば、仏教でいうところの有仏性ではあるまい。
しかるに、いま国師がいうところは、一切衆生有仏性とのみである。とすると、衆生でないものは、有仏性ではないであろうか。そこで国師に問うてみるがよい。「一切の諸仏は有仏性なりやいなや」と。そのような問いをたてて吟味してみるもよいのである。
そこではまた、一切衆生即仏性とはいわず、一切衆生有仏性という。それも究明してみなければならぬ。いま国師はたといその理解するところを、ぴたりとそのことばに表現し得なかったとしても、またぴたりと表現し得るときがないでもあるまい。いまの表現とてまったく意味がないわけでもない。いったい人は、自己にそなわる道理をかならずしも気が付かなくとも、四大・五蘊があり、また皮肉骨髄がある。それと同じく、ことばにもまた一生をかけていい得ることばがあり、あるいは生々世々(しょうじょうぜぜ)をかけてのことばというものもあるのである。
大潙山の大円禅師は、ある時、衆に示していった。
「一切衆生無仏性」
それを聞く人々のなかには聞いてよろこぶすぐれた機根の人もあろう、また驚いてわが耳を疑うものもあろう。釈尊の説いたことばは「一切衆生悉有仏性」である。大洟の語るところは「一切衆生無仏性」である。有と無のことばの道理ははるかにことなる。そのことばの当否を疑うのも尤(もっと)もなことである。だが、「一切衆生無仏性」の表現こそもっとも勝れている。
斉(せい)安国師の「有仏性」の句は、古仏のそれとともに双手をなしているようであるが、それはいわば、一本の杖を二人で舁(かつ)いでいるようなもの。いまの大潙はそうではない。一本の杖が二人を呑んでいるともいえよう。さらにいえば、斉安国師は馬祖の直弟子、大洟は馬祖の孫弟子である。だがしかし、孫弟子は師の道においてむしろ年少である。いま大潙のいう趣は、一切衆生無仏性をもって理のきわまるところとなす。それはけっして、いい加減にして桁(けた)をはずれたことばではない。仏教のなかの経典もまた、そのように受けとっているのである。
では、さらに思いめぐらしてみるがよい。いったい、どうして一切衆生がそのまま仏性であろうか、あるいは、仏性をもっていようか。もし仏性をもっているならば、それは魔の徒党である。魔の子一匹をもたらして、それを一切衆生に重ねるようなものである。仏性は仏性であり、衆生は衆生である。衆生がもともと仏性を具えているわけではない。たとい身に具えようと思っても、仏性があたらしく何処かからか来るわけではない。張(ちょう)さんが酒を飲んで李さんが酔うようなものではない。だが、もしおのずからにして仏性があるのだったら、それはけっして衆生ではない。すでに衆生であるならば、つまり仏性ではない。その故に百丈はいった。
「衆生に仏性ありと説くも、また仏法僧を謗(ぼう)ずるなり。衆生に仏性なしと説くも、また仏法僧を謗ずるなり」
とするならば、有仏性といい、無仏性というは、ともに仏法僧を謗ずることとなる。謗ずることとなっても、やはりいわないわけにはゆかない。では、かりに大洟と百丈に問おう。
まず百丈に聞こう。謗のそしりはあたらないではない。だが、それで仏性は説き得たというのかどうか。もし説き得たとするならば、そのことばが邪魔になる。そして、聞く者にもまた同じではないか。
つぎに大洟(サンズイに爲)にむかっていいたい。たとい一切衆生無仏性とはいい得ても、なお一切仏性無衆生とはいい得まい。また一切仏性無仏性とはいうまい。ましてや、一切諸仏無仏性とは夢にもいまだ見ざるところであろう。試みにいってみるならば拝見したいものである。(360~362頁)
〈注解〉
◯三乗・五乗 三乗とは、声聞乗、縁覚乗、菩薩乗をいい、五乗とは、それに人(じん)乗、天乗の二乗を加えたもの。それらを並記して、仏教にも衆生についていろいろの見解のあることを示す。
◯大潙山大円禅師 前出。潙山霊祐(853寂、寿83)であり、諡(おくりな)して大円禅師という。(363頁)
■そこで南泉が、「誰ぞ長老の所見ではあるまいなあ」といった。それは、これを自分の所見とはよもやいうまいなあ、というほどのことばである。そなたの所見かときかれても、それを自分のですと頷(うなず)いてはならない。自分の考え方にぴったりだからとて、それは黄檗のものではない。黄檗の所見はかならずしも自己の所見ではない。長老たちの見るところはどこまでも露(あら)わなるものだからである。
そこで黄檗は「不敢(ふかん)」つまり「いえ、けっして」といった。このことばは、宋土において、おのが能について問われたとき、できることをできるという場合でも「不敢」というのである。だから、「敢(あ)えてせず」ということばは、かならずしも敢えてしないのではない。そのことばのままとはかぎらないのである。長老の所見は、たとい長老であっても、たとい黄檗であっても、それをいうには「不敢」であろう。一頭の水牛がでて来て「もう、もう」というの類である。そういうのが物のいい方というもの。その物いう意味は、ひとつみずから試みにいうてみるがよろしい。(369~370頁)
■そこでは、半分も全部も依(よ)らずである。百物も千物も依らずであり、百時千時もまた不依椅(ふえい)である。かくていう。籠は一枚、時は十二時、依るも依らざるも、葛藤(かつとう)の樹によるがごとし。全天全地、畢竟にしていまだ語(ことば)あらず。(371頁)
■〈注解〉
◯百丈山大智禅師 百丈懐海(814寂、寿95)。諡して大智禅師と称す。
◯無所礙風 なにものにも礙(さまた)げられずして自由なる仏教の家風をいうのである。
◯所留 生への執着をいう。
◯五陰 五蘊に同じ。五陰は旧訳、五蘊は新訳、ともに“skandha”の訳である。
◯定慧等学 定と慧をひとしく学す。そうでなくては仏性を明らかに見ることを得ずとする一節が『大般涅槃経』にある。(372頁)
■風化いまだ散ぜずとは、仏が法を説くのであり、いまだ散ぜぬ風火とは、法が仏を説くのである。ことばをかえていえば、一音(いっとん)の法を説く時機が到来したのであり、法を説く一音が到来する時機である。法は一音である。一音の法だからである。(385頁)
■また、仏性は生きている時のみのことで、死んだときにはないと思うのは、とんだ不勉強のあさはかな考えである。生の時にも有仏性であり無仏性である。死の時にも有仏性であり無仏性である。風火の散る散らぬをもっていうなれば、そのいずれの時にもまた然るのである。たとい風火の散る時にも、仏性は有であり、また無である。またいまだ散らない時にも、有仏性であり、また無仏性である。それなのに、その仏性を、動と不動とによって在りもしくは在らずとなし、また、識(しき)と不識とによってその霊妙なはたらきをありとしらずとする。あるいは、知るか知らざるかによって、仏性の具すると具せざるを分かたんとする者もあるが、そのような考え方はすべて誤った外道の考え方である。ふるい昔から、おろか者たちはたいてい、意識のふしぎなはたらきをもって仏性となし、それが本来の人間だとしているが、まことに笑止千万のことである。
もはや仏性を語るにこれ以上ことばを重ねるべきではないが、ずばりというならば、それは牆壁瓦礫(しょうへきがりゃく)である。では、それを仏の境地に向かっていうならば、そも仏性はいかに。それはもう、すべて三面八臂(はっぴ)の仏におまかせしよう。(385~386頁)
〈注解〉
◯三面八臂 仏のすがたをいうことばである。三面八臂である。
(2018年4月17日)
――――――――――――――――――――――――――――――
『ブッダ最後の旅(大パリニッバーナ経)』中村元訳 岩波文庫
第1章
〔1、鷲の峰にて〕
1)わたしはこのように聞いた。
あるとき尊師は王舎城の〈鷲の峰〉におられた。
そのときマガダ国王アジャータサットゥ、すなわちヴィデーハ国王の女(むすめ)の子、は、ヴァッジ族を征服しようと欲していた。かれはこのように告げた。
「このヴァッジ族は、このように大いに繁栄し、このように大いに精力があるけれども、わたしは、かれらを征服しよう。ヴァッジ族を根絶しよう。ヴァッジ族を滅ぼそう。ヴァッジ族を無理にでも破滅に陥れよう」と。
2)そこでマガダ国王アジャータサットゥ、すなわちヴィデーハ国王の女(むすめ)の子、は、マガダの大臣であるヴァッサカーラというバラモンに告げていった。「さあ、バラモンよ、尊師のいますところへ行け。そこの行って、尊師の両足に頭を礼せよ。そうしてわがことばとして、尊師が健勝であられ、障りなく、軽快で気力あり、ご機嫌がよいかどうかを問え。そうして、このように言え、――尊い方よ。マガダ国王アジャータサットゥは、ヴァッジ族を征服しようとしています。かれはこのように申しました。――〈このヴァッジ族はこのように繁栄し、このように勢力があるけれども、わたしは、かれらを征服しよう。ヴァッジ族を根絶しよう。ヴァッジ族を滅ぼそう。ヴァッジ族を無理にでも破滅に陥れよう〉――と。そうして尊師が断定せられたとおりに、よくそれをおぼえて、わたしに告げよ。けだし完全な人(如来)は虚言を語られないからである」と。(9~10頁)
■「アーナンダよ。〔1〕ヴァッジ人は、しばしば会議を開き、会議には多くの人々が参集する、ということをお前は聞いたか?」
「尊い方よ。〔1〕ヴァッジ人は、しばしば会議を開き、会議には多くの人々が参集する、ということをわたしは聞きました。」
「それでは、アーナンダよ。ヴァッジ人が、しばしば会議を開き、会議には多くの人々が参集する間は、ヴァッジ人には繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
ー中略ー
「〔2〕ヴァッジ人は、協同して集合し、協同して行動し、ヴァッジ族として為すべきことを為す、ということをお前は聞いたか?」
「〔3〕ヴァッジ人は、未だ定められていないことを定めず、すでに定められたことを破らず、徃昔に定められたヴァッジ人の旧来の法に従って行動しようとする、ということをお前は聞いたか?」
「〔4〕ヴァッジ人は、ヴァッジ族のうちの古老を敬い、尊び、崇め、もてなし、そうして彼らの言を聴くべきものと思う、ということを、お前は聞いたか?」
「〔5〕ヴァッジ人は、良家の婦女・童女をば暴力で連れ出し拘(とら)え留める(=同棲する)ことを為さない、ということを、お前は聞いたか?」
「〔6〕ヴァッジ人は(都市の)内外の、ヴァッジ人のヴァッジ霊域を敬い、尊び、崇め、支持し、そうして以前に与えられ、以前に為されたる、法に適ったかれらの供物を廃することがない、ということをお前は聞いたか?」
「〔7〕ヴァッジ人が真人(尊敬さるべき修行者)たちに、正当の保護と防禦と支持とを与えてよく備え、未だ来たらざる真人たちが、この領土に到来するであろうことを、またすでに来た真人たちが、領土のうちに安らかに住まうであろうことをねがう、ということを、お前は聞いたか?」
■そこで尊師はマガダの大臣であるヴァッサカーラというバラモンに答えた。――「バラモンよ。かって或るときわたしが、ヴェーサーリーのサーランダダ霊域に住んでいた。そこで、わたくしはヴァッジ人に衰亡を来たさないための法を説いた。このヴァッジ人の間に存し、またヴァッジ人がこの七つをまもっているのがみたれる限りは、ヴァッジ人に繁栄が期待せられ、衰亡は無いであろう。」
そのように教えられて、マガダ国の大臣・バラモンであるヴァッサカーラは、尊師に次のように言った。――
「きみ、ゴータマよ。衰亡を来たさないための法の一つを具えているだけでも、ヴァッジ人に繁栄が期待せられ、衰亡は無いであろう。況(いわ)んや七つすべてを具えているなら、なおさらです。きみ、ゴータマよ。マガダ国王アジャータサトゥ――ヴィデーハ国王の女(むすめ)の子――は、戦争でヴァッジ族をやっつけるわけには行きません。――外交手段だの、離間策によるのでない限り――。きみ、ゴータマよ。さあ、出かけましょう。われわれは忙しくて為すべきことが多いのです。」
〔ゴータマは答えた〕「バラモンよ。ではどうぞご随意に、(お出かけなさい。)」
そこでヴァッサカーラ、マガダ国の大臣・バラモンであるヴァッサカーラは尊師の説かれたことを歓び、喜んで、座を起(た)って去った。(15~16頁)
訳注
◯わたしはこのように聞いた――evam me sutam これは一般に仏教経典の最初に出て来る文句で、漢訳では「如是我聞」という。サンスクリットの経典の場合も同様にevam maya srtam という。従来の伝統的解釈によると、パーリ語の経典は、ブッダ(釈尊)の入滅後に最初の雨期にマガダ国の王舎城という名の首都のまわりの山の中にある七葉窟という大きな洞窟の中で第一結集(sangiti)が行われたときに、釈尊の愛弟子であったアーナンダ(Ananda 阿難)によって誦(とな)えられ、そこに出席していた長者たちによって承認され、それが順次にのちの世代に語り伝えられたということになっているので、どの経典でも最初には必ず「わたしはこのように聞いた」よいう文句が出て来るのである。ここで「わたし」というのは、「アーナンダ」のことである。こういう形式は大乗仏教のも継承された。(195頁)
◯王舎城――Rajagaha 王舎城は、中インドにあったマガダ国の首都であった。Raja は「王」、gaha は「舎(いえ)」という意味である。まわりは、中インドには珍しく連山に囲まれ、連山の頂に城壁を築いていた。敵を防ぐには屈強の土地であった。現在この首都のあとは無人の廃墟となり、灌木の藪が茂っている。稀に虎が出没することがあるという。城壁の残骸は現在なお残存している。(198頁)
◯鷲の峰――王舎城の周囲の東北方にある嶮しい一つの峰が〈鷲の峰〉なのである。そのように名づけられた理由としては、その頂きに鷲が住んでいたからであるともいい、あるいはまたその峰には鷲に似たかたちの頂きがあったからであるともいい、ブッダゴーサは両説を挙げている。現在〈鷲の峰〉の頂上には、いかにも鷲の翼を思わせる、層をなした巨岩石が存在する。(198頁)
◯マガダ国王アジャータサットゥー――マガダ国(Magadha)は中インドにあった強国で、今日はほぼビハール(Bihar)州を占めていた。マガダ国は当時インド最大の強国であったが、この国では農業の生産性が高く、また西北インドから学問を導入して、戦車などの武器が優秀であったからであった。
アジャータサットゥー(Ajatasattu=Sanskrit: Ajatasatru)は「敵の生じていない人」「敵として比肩し得る人のいないほどの武勇の士」「打ち勝つほどの敵のいない人」という意味。これはすでに『リグ・ヴェーダ』においてインドラ神の呼称とされている。マガダ国王の場合には、これは個人名ではなくて、かれの称号であったらしい。ジャイナ教徒はかれの名をKunika またはKonika として伝えているが、これはインドの伝統的な命名式のときにつけられた名ではなくて、のちに世人のつけたあだ名であろう。(198~199頁)
◯ヴィデーハ国王の女(むすめ)の子――パーリ本、サンスクリット本などには、アジャータサットゥ王のことを、「ヴィデーハ国の女(むすめ)の子」(Vedehiputta. Vaidehiputta つまりヴィデーハ国から来た妃の子)と呼んでいる。かれの母は「ヴィデーハ国の女」(韋提希夫人)(いだいけぶにん)であったのである。男の名を挙げる場合に、母の名を挙げ、しかも母のことを「……家の女」という言い方をするのは古代インドにおける通習であり、古碑文の中にも多数の実例が存する。これは、インド原住民の間の母系家族制の影響であり、純アーリヤ人のつくったヴェーダ聖典のうちには認められない。アジャータサットゥ王の母の個人名は、Vasavi であったというチベット所伝の伝説があるというが、詳細は不明である。かれの母はヴィデーハ国王の女(むすめ)ではなくて、コーサラ国王の女であったという説もある。すぐれた偉い人の胡人名を明示しないのがインドの通習であり、国王の場合にはなおさらである。(199~200頁)
◯バラモン――アジャータサットゥ王の大臣はバラモンであった。仏教以前にも国王の宮廷にバラモンがいて帝師(purohita)として祭儀を司っていたが、ヴェーダ聖典によると、政治の実権者ではなかった。ところがこの時代になると、四姓(バラモン、王族、庶民、隷民)の職務の区別を無視してバラモンが大臣となることもあり得た。そうしてバラモンたちよりもさらに偉大な指導者として釈尊を尊崇し、たよりにしていたのである。(201頁)
◯以下にも見られるように、この経典には繰返しの文句が非常に多い。そのわけは、仏教聖典は、最初の時期においては、口から口へ暗誦によって伝えられたので、暗誦し易いように繰り返したのである。文句を縮約するならばその場合ごとに考えねばならないが、考えないで暗誦するだけなら繰返しのほうがはるかに容易である。(201頁)
◯乗物で行き――いまの〈鷲の峰〉の山には良い登山道路ができているので途中までは自動車で行くことができるが、やはりその終点から先は歩かなければならない。昔も事情は同様だったのである。(206頁)
◯ゴータマよ――Gotama. 「ゴータマ」は「最もよき牛」という意味であり、ブッダ(釈尊)の姓(gotta)の名である。釈尊は王族(クシャトリヤ)の出身であり、ヴァッサカーラはバラモンであったから、いくらかさげすんで、このように呼んだのである。
◯アーナンダ――Ananda.「アーナンダ」とは「歓喜」「よろこび」を意味する語である。釈尊族の王子で、ブッダ(釈尊)の従弟であった。ブッダが故郷カピラ城に帰ったときに、釈尊族の他の王子たちとともに出家して、ブッダの弟子となった。ブッダの晩年に二十五年間ブッダの常侍の弟子として秘書のような役をつとめた。性格は温和、従順、賢明であった。ブッダの愛(まな)弟子として諸経典に登場する。(206頁)
◯nyagrodhaとはバニヤン樹のことをいう。いまゴータマ・ブッダの時代には、神聖だとみなされた大きな樹木がヴェーサーリーの郊外にあって、その樹陰で釈尊とアーナンダとは、暑い日光の直射を避けて休息していたのである。(210頁)
◯ところで死者を葬った塚のあるところで休むというのは、日本人には異様に思われるかもしれないが、ヒンズー教の行者は死者を葬ってある墓地で瞑想を修することを好む習俗がある。その習俗がここにも露呈しているのである。原始仏教では修行者が「塚間(ちょうげん)」にとどまることを勧めているのは、そのためである。(210頁)
〔2、修行僧たちに教える〕
■「汝ら修行僧たちよ。衰亡を来たさないための七つの法を、わたしはこれから説くであろう。それをよく聞け。心にとどめなさい。わたしは説くであろう」と。
「かしこまりました」と、その修行たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「〔1〕修行僧たちよ。修行僧たちがしばしば会議を開き、会議には多くの人が参集する間は、修行僧らには繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔2〕修行僧たちよ。修行僧たちが未来の世に、協同して集合し、協同して行動し、協同して教団の為すべきことを為す間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔3〕修行僧たちよ。修行僧たちが、未来の世に、未だ定められていないことを定めず、すでに定められたことを破らず、すでにさだめられたとおりの戒律をたもって実践するならば、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔4〕修行僧たちよ。修行僧たちが、未来の世に、経験ゆたかな、出家して久しい長老たち、教団の父、教団の導き者(て)を敬い、尊び、崇め、もてなし、そうしてかれらの言は聴くべきであると思う間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔5〕修行僧たちよ。修行僧たちが、のちの迷いの生存をひき起こす愛執が起っても、それに支配されない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔6〕修行僧たちよ。修行僧たちが、林間の住処に住むのを望んでいる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔7〕修行僧たちよ。修行僧たちが、みずから心のおもいを安定し〈いまだ来ない良き修行者なる友が来るように、また、すでに来た良き修行者なる友が快適にくらせるように〉とねがっている間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この七つの〈衰亡を来たさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちが、この七つの〈衰亡を来さざる法〉をまもっているのが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
「修行僧たちよ、さらに他の七つの〈衰亡を来たさざる法〉を、わたしは説くであろう。それを聞け。よく心にとどめよ。わたしは説くであろう。」
「かしこまりました」と、かれら修行僧たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「〔1〕修行僧たちよ。修行僧たちが、未来の世に、修行僧たちが動作を喜ばず、動作を楽しまず、好んで動作に従事しない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔2〕また修行僧たちよ。未来の世に、修行僧たちが談話を喜ばず、談話を楽しまず、好んで談話に耽(ふけ)らない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔3〕また修行僧たちよ。未来の世に、修行僧たちが睡眠を喜ばず、睡眠を楽しまず、好んで睡眠に耽らない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔4〕また修行僧たちよ。未来の世に、修行僧たちが社交を喜ばず、社交を楽しまず、好んで社交に耽らない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔5〕また修行僧たちよ。修行僧たちが未来の世に、修行僧たちが悪い欲望をいだかず、諸々の悪い欲望に支配されない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔6〕また修行僧たちよ。未来の世に、修行僧たちが悪友をもたず、悪い仲間をもたず、悪い同輩をもたない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
「〔7〕また修行僧たちよ。未来の世に、修行僧たちが少しばかり勝れた境地に到達したことによって中途で(ニルヴァーナへの到達の)中止に陥ることがない間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この七つの〈衰亡を来らさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちたちが、この七つの〈衰亡を来らさざる法〉をまもっていることが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
「かしこまりました」と、かれら修行僧たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「修行僧たちよ。また修行僧たちが、未来の世に、信があり、慚(は)じ心があり、愧(は)じ、博学であり、努力し励み、心の念(おも)いが安定していて、知識をもったものであるならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この七つの〈衰亡を来らさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちたちが、この七つの〈衰亡を来らさざる法〉をまもっていることが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
「修行僧たちよ、さらに他の七つの〈衰亡を来たさざる法〉を、わたしは説くであろう。それを聞け。よく心にとどめよ。わたしは説くであろう。」
「かしこまりました」と、かれら修行僧たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「修行僧たちよ。また修行僧たちが、未来の世に、〈よく思いをこらす〉さとりのことがらを修し、〈よく法をえらび分ける〉さとりのことがらを修し、〈よく努力する〉さとりのことがらを修し、〈よく喜びに満ち足りる〉さとりのことがらを修し、〈心身が軽やかになる〉さとりのことがらを修し、〈精神統一〉というさとりのことがらを修し、〈心の平静安定〉というさとりのことがらを修するならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この七つの〈衰亡を来たさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちが、この七つの〈衰亡を来さざる法〉をまもっているのが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
「修行僧たちよ、さらに他の七つの〈衰亡を来たさざる法〉を、わたしは説くであろう。それを聞け。よく心にとどめよ。わたしは説くであろう。」
「かしこまりました」と、かれら修行僧たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「修行僧たちよ。修行僧たちが、〔1〕未来の世にあらゆるものは無常であるという想(おも)いを修すならば、、〔2〕また、あらゆるものは我(が、アートマン)ならざるものであるという想いを修すならば、〔3〕またあらゆるものは不浄であるという想いを修すならば、〔4〕またあらゆるものは厭わしいものであるという想いを修すならば、〔5〕またあらゆるものを捨て去る想いを修すならば、〔6〕またあらゆる欲情から離れる想いを修すならば、〔7〕また止滅の想いを修すならば、その間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この七つの〈衰亡を来らさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちたちが、この七つの〈衰亡を来らさざる法〉をまもっていることが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
「修行僧たちよ、さらにこの六つの〈衰亡を来たさざる法〉を、わたしは説くであろう。それを聞け。よく心にとどめよ。わたしは説くであろう。」
「かしこまりました」と、かれら修行僧たちは尊師に答えた。尊師は次のように説かれた。――
「〔1〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、慈しみのある〈身体での行動〉を、共に修行する人々に対して、公けにも秘密のうちにも確かに実行しているならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔2〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、慈しみのある〈ことばでの行動〉を、共に修行する人々に対して、公けにも秘密のうちにも確かに実行しているならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔3〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、慈しみのある〈心での行動〉を、共に修行する人々に対して、公けにも秘密のうちにも確かに実行しているならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔4〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、未来の世に、修行僧のための規定にかなって得られたものを、単に鉢に入れられて得たものに至るまでも、分配することなしに食することがなく、戒しめをたもつ共同修行僧たちたちと仲よく分け合って食するならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔5〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、切れ切れではなくて、瑕(きず)の無い、斑点(まじり)の無い、汚れの無い、精神統一をあらわし出すような戒律に関して、共同修行者たちと、公けにも秘密のうちにも戒律をまもる修行者の境地を実践しているならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
〔6〕修行僧たちよ。また修行僧たちが、迷いの領域から離脱し得るような、それを実践する人をして完全に苦しみをなくさせるような、そのような立派な(正しい)見解によって、共同修行者たちと、公けにも秘密のうちにも(正しい)見解の究極の境地を実践しているならば、その間は、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。
修行僧たちよ。この六つの〈衰亡を来らさざる法〉が修行僧たちのうちに存在し、また修行僧たちたちが、この六つの〈衰亡を来らさざる法〉をまもっていることが見られる間は、修行僧らよ、修行僧たちに繁栄が期待され、衰亡は無いであろう。」
尊師はかの王舎城の〈鷲の峰〉なる山に住して、修行僧たちのために、このように数多くの、(法に関する講話)をなさった。――「戒律とはこのようなものである。精神統一とはこのようなものである。知慧とはこのようなものである。戒律とともに修行して完成された精神統一は大いなる果報をもたらし、大いなる功徳がある。精神統一とともに修養された知慧は偉大な果報をもたらし、大いなる功徳がある。知慧とともに修養された心は、諸々の汚れ、すなわち欲望の汚れ、生存の汚れ、見解の汚れ、無明の汚れから全く解脱する」と。(18~26頁)
訳注
◯真人たち――arahanto. arahannt(Sanskrit:arahat) は「尊敬・供養を受けるにふさわしい人」「立派な修行者」という意味であり、最初期の仏教やジャイナ教では「ブッダ」と同義であった。釈尊もこのようなarahatの一人にすぎなかった。ところが後代の仏教ではarahatは「阿羅漢」と音写され、小乗のさとりを極めた人のことになった。他方ジャイナ教ではarahatが神のように見なされるに至った。(211頁)
◯修行僧――bhikku.サンスクリットではbhiksuというが、それはバラモン教のほうでは、托鉢によって生きている遍歴の修行者である。かれらは組織された教団をつくっていなかった。しかしこの語が仏教で用いられると、「教団に属している者」という意味を内含している。そこで、その意味をあらわすために、これを「修行僧」と訳すことにした。(最初期の仏教の詩句では、仏教の修行者を「仙人」(isi)と呼んでいるが、その詩句を説明する、やや後代の散文ではisiをbhikkhuと書き換えている。)(214頁)
◯悪い欲望をいだかず――この文章からみると、仏教は欲望または欲求(iccha)を抑圧することを説いたのではなくて、「悪い欲望」(papiccha)を制することを教えたのである。(216頁)
◯ニルヴァーナ――サンスクリット語でnirvana,パーリ語でnibbana漢字で音写して「涅槃」という。煩悩の火を吹き消した状態。いかなる迷いも無くなった理想の境地をいう。(216頁)
◯慚じる心があり、愧じ――〈慚〉と〈愧〉とがどう異なるかということは伝統的教義学において古来しばしば論議されたが、ブッダゴーサは〈慚〉とは「悪を嫌悪すること」であり〈愧〉は「悪をなすと自分に悪いことが起こるのではないかと恐れること」と解していたようである。(216頁)
◯心の念い――sati(Sannskrit: smrti)は「心にとどめる」「よく気をつける」「心が落ち着いている」というほどの意味である。例えば、セイロンで小僧が心をとり乱して、あわてて茶碗をわったりすると、師僧は“sati! sati!”(落ち着いて!)といって戒める。リューダースはこの語を“vollbewusst”と訳している。この語を漢訳では伝統的に「念」と訳し、日本の仏教学界はそれに従っているが、いまの日本語で「念じて」というのとは少しく意味合いを異にする。(217頁)
◯他の七つ――この七つを漢訳の述語では「七覚支」「七覚分」「七菩提分」「七等覚支」などという。その七つを「念」「択法」「精進」「喜」「軽安」「三昧」「行捨」という。
◯身体での行動――漢訳では「身業」という。(217頁)
◯自在であって――妄執愛欲の奴隷たる状態から脱して自在となることができる。(217頁)
◯汚れ――漢訳では「漏」と訳す。(219頁)
◯アーナンダよ――釈尊が実際には身のまわりに侍る人としては殆んどアーナンダ一人をつれて遍歴していたという事実は重要である。また亡くなったときにはアルヌッダも来合わせていた。そのほかどれだけの弟子が同行していたか、よく解らぬが、ともかく、かれは仏教の開創者として権威はもっていたけれども、実際は引退して隠居のような恰好であったのであろう。(219頁)
◯四念処――玄奘以前の旧訳では「四念処」といい、玄奘にはじまる新訳では「四念住」という。「四念処観」に同じ。さとりを得るための四種の修行方法。⑴この身(kaya)は不浄である、⑵感受するもの(vedana)は苦である、⑶心(cita)は無常である、⑷すべての事物(dhamma)は無我であるという四つのことを心に思い浮べる修行。(223頁)
〔4、パータリ村にて〕
■そこで尊師はパータリ村の在俗信者たちに告げて言った。――
「資産者たちよ。戒しめを犯したために、行ないの悪い人にはこの五つの禍いがある。その五つとは何であるか?
ここで、資産者たちよ。行ないが悪く、戒しめを犯した人は、なおざりの故に、大いに財産を失うにいたる。これが、戒しめを犯したために行ないの悪い人に起る第一の禍いである。
また次ぎに、資産者たちよ。戒しめを犯した、行ないの悪い人には、悪い評判が近づいて来る。これが、戒しめを犯したために行ないの悪い人に起る第二の禍いである。また次ぎに、資産者たちよ。戒しめを犯した、行ないの悪い人は、いかなる集会におもむいても、すなわち、王族の集会でも、バラモンたちの集会でも、資産者たちの集会でも、修行者たちの集会でも、どこに行っても、不安で、おじけている。これが、戒しめを犯したために行ないの悪い人に起る第三の禍いである。
また次ぎに、資産者たちよ。戒しめを犯した、行ないの悪い人は、死ぬ時に精神が錯乱している。これが、戒しめを犯したために行ないの悪い人に起る第四の禍いである。
次ぎに、資産者たちよ。戒しめを犯した、行ないの悪い人は、身体が敗れて死んだのちに、悪いところ、苦しいところ、堕(お)ちるところ、地獄に生まれる。これが、戒しめを犯したために行ないの悪い人に起る第五の禍いである。(34~36頁)
■資産者たちよ。戒しめをたもっていることによって、品性ある人には、この五つのすぐれた利点がある。その五つとは何であるか?
ここで、資産者たちよ。戒しめをたもち、品性ある人は、なおざりにしないことによって、財産が大いにを豊かとなる。これが、戒しめをたもっていることによって、品性ある人の受ける第一のすぐれた利点である。
ここで、資産者たちよ。戒しめをたもち、品性ある人は、良い評判が起る。これが、戒しめをたもっていることによって、品性ある人の受ける第二のすぐれた利点である。
また次に、資産者たちよ。戒しめをたもち、品性ある人は、いかなる集会におもむいても、すなわち、王族の集会でも、バラモンたちの集会でも、資産者たちの集会でも、修行者たちの集会でも、どこに行っても、泰然としていて、おじけることがない。これが、戒しめをたもっていることによって、品性ある人の受ける第三のすぐれた利点である。
また次に、資産者たちよ。戒しめをたもち、品性ある人は、死ぬときに精神錯乱することがない。これが、戒しめをたもっていることによって、品性ある人の受ける第四のすぐれた利点である。
また次に、資産者たちよ。戒しめをたもち、品性ある人は、身体がやぶれて死んだのちに、善いところ、天の世界に生まれる。これが、戒しめをたもっていることによって、品性ある人の受ける第五のすぐれた利点である。(36~37頁)
■アーナンダよ、ここでわたしは、清らかな超人間的な千もの多くの神霊たちがパータリ村に敷地を構えているのを見た。優勢な神霊たちが敷地を構えようとする地方には、優勢な国王または大臣が住居を建築しようと心を傾ける。中位の神霊たちが敷地を構えようとする地方には、中位の国王または大臣が住居を建築しようと心を傾ける。低位の神霊たちが敷地を構えようとする地方には、低位の国王または大臣が住居を建築しようと心を傾ける。
アーナンダよ。パータリプッタが立派な場所である限り、商業の中心地である限り、ここは首都であり、物資の集散地であるであろう。しかしパータリプッタには三種の災難があるであろう。すなわち火と水と内部からの分裂とによるものである。」(39頁)
訳注
◯死ぬ時に精神錯乱することがない――これが後代に、殊に浄土教において重要視される「臨終正念」である。(225頁)
◯パータリプッタ――Pataliputta(Sanskrit:Pataliputra).このパータリプトラ市もアショーカ王以後、あるいはマウリヤ王朝以後には衰微したらしい。この事情がこの『大パリニッパーナ経』の中で、釈尊の予言のかたちでこのように示されているのである。(228頁)
◯パータリプッタには三種の災難があるであろう――ここでは歴史的事実が、ブッダの予言の中に反映しているのである。当時の仏教徒は、「仏さまがこのように予言なさった」といって、ますます信仰の念を固めたことであろう。しかし原典批判的立場から見ると、マウリヤ王朝の首都パータリプトラの衰亡はアショーカ王以後に現われたことであろうから、『大パリニッバーナ経』の原型がつくられたのは、西紀前二世紀あるいはそれ以後ということになる。パータリプトラ市が後世に水害に遭ったことは、考古学的発掘の結果の示しているところである。パータリプトラ市は八世紀の半ばには洪水のために亡びてしまった。次に外敵の侵略としては、マガダ国はのちにカリンガ国のカーラヴェーラ王に征服せられたらしいし(カーラヴェーラ王碑文)、またギリシャ人の軍隊もパータリプトラ市を征服したことがある。こういう歴史的事実が右の文章に反映しているのであろう。だから『大パリニッバーナ経』のこの一節がつくられたのは、アショーカ王以後、あるいはマウリヤ王朝以後のことであろう。(229~230頁)
◯渡し場―― tittha(Sannskrit: tirtha). 渡河場。河岸の階段を下りて行って舟に乗りまた水浴するところである。さらに tirtha とは『巡礼地」「霊場」をいう。(232頁)
◯聡明な人々は、すでに渡り終わっている――パーリ本によると、この詩句はゴータマ・ブッダが唱えたことになっているが、しかしサンスクリット本、チベット本有部本では、この詩句を「或る修行僧(ビク)」が語ったとなっている。古くからこの詩句が言い伝えられていたので、右のような相異が起ったのであろう。この詩句は、恐らくパーリ文以外の諸本がつづいて引用する他の詩句が示すように、苦しみの生存を渡り終わった聖者をたたえたのであろうただその趣意については四種類の解釈が可能である。⑴何らかの手段を講じて川や沼を渡ることをたたえているのだ、と解することができる。つまり方便思想を見出すのである。もしもそうだとすると、交通が不便であった時代に、橋や筏をつくって、実際に交通の便を開いてくれる人々に対する称讃の気持が含められている、と見てよいであろう。仏教は、ジャイナ教と非常に良く似ているにもかかわらず、ジャイナ教と非常に良く似ているにもかかわらず、ジャイナ教と異なって、ものをつくる道徳が称賛され、大乗仏教になるといよいよ強調されるが、その萌芽がここに見られると解し得ることになる。⑵凡愚の者どもは何らかの手段を講じて川や沼を渡ろうとするが、「聡明な人々」すなわちブッダや仏弟子たちは、筏がなくてもすでに渡りおわっている、というのである(ブッダゴーサの解釈)。これは、ブッダや仏弟子をたたえる宗教的な解釈である。⑶凡愚の者どもは、宗教儀式にたよったり神々に対して祈るというような〈筏〉に譬うべきことを行っているが、賢者は愛欲の大海をわたりおわったと解する(リス・デヴィッズの解釈)。⑷迷いの存在の洪水にうち克つために、賢者は速やかに橋をかける。凡愚の者どもが筏を求めてあくせくしているのに、その橋は賢者をして速やかに彼岸に至る道を見出させる(フランケの解釈)。現在のところどれが正しいとも断定できないので、いちおう文字どおり訳しておいた。(233~234頁)
第2章
〔5、コーティ村にて〕
■そこで尊師は修行僧たちに告げて言った。――
「修行僧たちよ。四つの真理をさとらず、通達しないが故に、この長い時間にわたって、わたしもお前たちも、このように流転し、輪廻したのである。その四つとはどれどれであるのか?
修行僧たちよ。(苦しみ)という尊い真理をさとらず、通達しないが故に、この長い時間にわたって、わたしもお前たちも、このように流転し、輪廻したのである。
修行僧たちよ。(苦しみの起るもと)という尊い真理をさとらず、通達しないが故に、この長い時間にわたって、わたしもお前たちも、このように流転し、輪廻したのである。
修行僧たちよ。(苦しみの止滅)という尊い真理をさとらず、通達しないが故に、この長い時間にわたって、わたしもお前たちも、このように流転し、輪廻したのである。
修行僧たちよ。(苦しみの止滅にみちびく道)という尊い真理をさとらず、通達しないが故に、この長い時間にわたって、わたしもお前たちも、このように流転し、輪廻したのである。
しかし、修行僧たちたちよ。(苦しみ)というすぐれた真理がさとられ、通達された。(苦しみの起るもと)というすぐれた真理がさとられ、通達された。(苦しみの止滅)というすぐれた真理がさとられ、通達された。(苦しみの止滅にみちびく道)というすぐれた真理がさとられ、通達された。生存に対する妄執はすでに断たれた。生存にみちびく(妄執)はすでに滅びてしまった。もはや再び迷いの生存を受けるということはない」と。
■尊師はこのことを説いた。幸いな人はこのことを説いたあとで、師(=ブッダ)はこのことを説いた。――
「四つの尊い真理を如実に見ないが故に長いあいだ幾多の生涯にわたって、とらわれこだわっていたのである。
それらの(尊い真理)はすでに見られた。生存にみちびく(妄執)はすでに根絶された。苦しみの根は断たれた。もはや再び迷いの生存を受けるということはない」と。
ついで尊師はそのコーティ村にとどまって、多くの修行僧たちにこのように数多くの〈法に関する講話〉をなされた。――「戒律とはこのようなものである。精神統一とはこのようなものである。知慧とはこのようなものである。戒律とともに修養された精神統一は、偉大な果報をもたらし、大いなる功徳がある。精神統一とともに修養された知慧は、偉大な果報をもたらし、大いなる功徳がある。知慧とともに修養された心は、諸々の汚れ、すなわち欲望の汚れ、生存の汚れ、見解の汚れ、無明の汚れから完全に解脱する。」(45頁)
訳注
◯四つのすぐれた真理――漢訳仏典では「四諦(したい)」「四聖諦(ししょうたい)」などという。「聖」(ariya)とは「聖なる状態をつくり出すところの真理」という意味である。
◯幸いな人――Sugata. 直訳すると「ヨク行った」の意。漢訳では「善逝」などという。仏の十号の一つ。(235頁)
〔6、ナーディカ村にて〕
■さて尊師はそのナーディカで〈煉瓦堂〉のうちにとどまって、修行僧たちのために、このように数多くの〈法に関する講話〉をなされた。――「戒律とはこのようなものである。精神統一とはこのようなものである。知慧とはこのようなものである。……乃至……欲望の汚れ、生存の汚れ、見解の汚れ、無明の汚れから完全に解脱する。」と。(52頁)
訳注
◯在俗信者――upasaka. 漢訳では「優婆塞」と音写する。(237頁)
◯在俗信女――upasika. 漢訳では「優婆夷」と音写する。「善信女」と訳すことがある。(237頁)
◯ひとを下界(=欲界)に結びつける五つの束縛――ブッダゴーサによると、生存者を欲界の生存のうちに転生させるものであるという。小乗仏教のアビダルマの教学においては、これを「五下分結(ごけぶんけつ)」という。「下分」とは下位の領域のことで、欲界をいう。「結」は束縛のことで、煩悩の異名である。その五つとは、欲貧、嗔恚(しんい)、有身見(〈われ〉とか〈わがもの〉とかいう観念を離れぬ我執)、戒禁取見(誤った戒律や禁制を正しい修養方法であるとして執着すること)、疑をいう。(237頁)
◯三つの束縛――漢訳では「三結」と訳す。預流果を得る人の断ずべき三種の煩悩。「結」は煩悩の異名。⑴「見結」(我見。われ有りと見なす見解)、⑵「戒取見」(あやまったことを解脱の因と見なすこと)、⑶「疑結」(正しい道理を疑うこと)。(237~238頁)
◯清らかな信仰を起している――「ブッダの諸々の美徳を如実に知るが故に、不動不滅の(確固たる)清らかな信仰を起している」。ここではブッダコーサは「知る」ことから信仰が起ると考えているのである。(239頁)
〔8、遊女アンバパーリー〕
■さて尊師はそのヴェーサーリーのうちのアンバパーリー女の林にとどまっておられたあいだに、この数多くの〈法に関する講話〉をなされた。すなわち「戒律とはこのようなものである。精神統一とはこのようなものである。知慧とはこのようなものである。戒律とともに修行して完成された精神統一は大いなる果報をもたらし、大いなる功徳がある。精神統一とともに修養された知慧は、大いなる果報をもたらし、大いなる功徳がある。知慧とともに修養された心は、もろもろの汚れ、すなわち欲望の汚れ、生存の汚れ、見解の汚れ、無明の汚れから全く解脱する。」と。(61頁)
訳注
◯遊女――当時、高等の娼婦は、かなり富裕であって、このような園林を所有していたのである。娼婦が富裕であって、ジャイナ教の寺院に立派な寄進をしたことは、マトゥラーから発見された銘文(西紀前1-2世紀)からも知られている。アンバパーリーは容姿美しく、財産もあり、物質的に豊かであった。のみならず、商業都市ヴェーサーリーの繁栄はこの娼婦に負うところが多かったとさえ言われている。『ヴェーサーリーは富み栄え、人民多く、人間が集まり、物資豊かであり、七千七百七の宮殿、七千七百七の重閣、七千七百七の遊園、七千七百七の蓮池があった。遊女アンバパーリーがいたが、容色端麗で、見めよく、美貌すぐれ、蓮華のような容色あり、舞踊・歌謡・音楽を能くし、求愛する人々に言い寄られ、一夜に五十金を受けた。かの女によってヴェーサーリーはますます繁栄した。』
かの女はかねてから釈尊に帰依していた、といわれている。そのありさまを聞いて、王舎城の人々も、負けてなるものか、と思って、サーラヴァティーという少女を、かの女に対抗し得るような遊女にしたて、『一夜に百金を受け』させた。有名な医師ジーヴァカはかの女の生んだ、父無し児である。一夜に「五十金」や「百金」を受ける遊女によって代表されるような都市の文化、――それは、進展しつつあった貨幣経済の所産であって、ヴェーダの祭りに代表されるような農村共同体の文化とは本質的に異なったものである。そうしてこのような爛熟した、頽廃的な雰囲気の中から、それに対する解決、それからの離脱として、仏教などの新宗教が現われ出たのであった。(ペリクレース時代のアテーナイがしばしば引合いに出される。)(245~246頁)
〔9、旅に病む――ペールヴァ村にて〕
■そこで尊師は、アンバパーリー女の林に心つくまでとどまったのちに、――若き人アーナンダに告げた。――
「さあ、アーナンダよ。〈ペールヴァ村〉に行こう」と。
「かしこまりました」と若き人アーナンダは尊師に答えた。
そこで尊師は多くの修行僧の群れとともに〈ペールヴァ村〉に赴いた。そこで尊師は〈ペールヴァ村〉に住された。
そこで尊師は修行僧たちに告げられた。――
「さあ、お前たち修行僧よ。ヴェーサーリーのあたりで、友人を頼り、知人を頼り、親友を頼って、雨期の定住(雨安居)に入れ。わたしもまたここのペールヴァ村で雨期の定住に入ろう」と。
「かしこまりました」とその修行僧たちは尊師に答えて、ヴェーサーリーのあたりで、友人を頼り、知人を頼り、親友を頼って、雨期の定住に入った。尊師もまたそこの〈ペールヴァ村〉で雨期の定住に入られた。
さて尊師が雨期の定住に入られたとき、恐ろしい病いが生じ、死ぬほどの激痛が起った。しかし尊師は、心に念じて、よく気をつけて、悩まされることなく、苦痛を堪え忍んだ。
そのとき尊師は次のように思った、――「わたしが侍者たちに告げないで、修行僧たちに別れを告げないで、ニルヴァーナに入ることは、わたしにはふさわしくない。さあ、わたしは元気をだしてこの病苦をこらえて、寿命のもとを留めて住することにしよう」と。
そこで尊師は、元気をだしてその病苦をこらえて、寿命のもとを留めて住していた。すると、尊師のその病苦はしずまった。(62~63頁)
■「アーナンダよ。修行僧たちはわたくしに何を期待するのであるか?わたくしは内外の隔てなしに(ことごとく)理法を説いた。完(まった)き人の教えには、何ものかを弟子に隠すような経師の握拳(にぎりこぶし)は、存在しない。『わたくしは修行僧のなかまを導くであろう』とか、あるいは『修行僧のなかまはわたくしに頼っている』とこのように思う者こそ、修行僧のつどいに関して何ごとかを語るであろう。しかし向上につとめた人は『わたくしは修行僧のなかまを導くであろう』とか、あるいは『修行僧のなかまはわたくしに頼っている』とか思うことがない。向上につとめた人は修行僧のつどいに関して何を語るであろうか。
アーナンダよ。わたしはもう老い朽ち、齢をかさね老衰し、人生の旅路を通り過ぎ、老齢に達した。わが齢は八十となった。譬えば古ぼけた車が革紐の助けによってもっているのだ。
しかし、向上につとめた人が、一切の相をこころにとどめることなく一部の感受を滅ぼしたことによって、相の無い心の統一に入ってとどまるとき、そのとき、かれの身体は健全(快適)なのである。
それ故に、この世で自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころをせずにあれ。では、修行僧が自らを島とし、他のものをよりどころとしないでいるということは、どうして起るのであるか?
アーナンダよ。ここに修行僧は身体について身体を観じ、熱心に、よく気をつけて、念じていて、世間における貧欲と憂いとを除くべきである。
感受について感受を観察し、熱心に、よく気をつけて、念じていて、世間における貧欲と憂いとを除くべきである。
心について心を観察し、熱心に、よく気をつけて、念じていて、世間における貧欲と憂いとを除くべきである。
諸々の事象について諸々の事象を観察し、熱心に、よく気をつけて、念じていて、世間における貧欲と憂いとを除くべきである。
アーナッンダよ、このようにして、修行僧は自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとしないでいるのである。
アーナンダよ。今でも、またわたしの死後にでも、誰でも自らを島とし、自らをたよりとして、他人をたよりとせず、法を島とし、法をよりどころとして、他のものをよりどころとしないでいる人々がいるならば、かれらはわが修行僧として最高の境地にあるのであろう、――誰でも学ぼうと望む人々は――。(64~66頁)
訳注
◯教師の握拳は――『(仏教外の)外の人々には〈教師の握拳〉なるものがあって、若い時には何人にも話さないでおいて、後の時に死の床に就いたときに、気に入った弟子に語ることがある。それと同様に如来には「わたしは、これを年老いてから、後の機会に話すことにしよう」といって、握拳をつくって、取り除いて置かれた何ごとも存在しない。』バラモンはこっそりと秘密のうちに弟子に伝授する。しかし仏教には秘密は無いというのである。(252頁)
◯向上につとめた人―― tathagata. 漢訳では「如来」という。(253頁)
◯誰でも学ぼうと望む人々は――「学ぶ」というのは〈修行する〉ことをいう。〈絶えず学ぼうと努めること〉〈不断の精進〉が最初期の仏教徒の理想であると解するならば、それが最高の境地であるという思想は充分に筋が立つことになる。(「最高の境地」ということを四向四果の最後の到達点と解する必要がないことになる。)(255頁)
第3章
〔10、命を捨てる決意〕
■「アーナンダよ、ヴェーサーリーは楽しい。ウデーナ霊樹の地は楽しい。ゴータマカ霊樹の地は楽しい。七つのマンゴーの霊樹の地は楽しい。パラプッタの霊樹の地は楽しい。サーランダ霊樹の地は楽しい。チャーパーラ霊樹の地は楽しい。
アーナンダよ。いかなる人であろうとも、四つの不思議な霊力(四神足)を修し、大いに修し、(軛を結びつけられた)車のように修し、家の礎(いしずえ)のようにしっかりと堅固にし、実行し、完全に積み重ね、みごとになしとげた人は、もしも望むならば、寿命のある限りこの世に留まるであろうし、あるいはそれよりも長いあいだでも留まることができるであろう。
アーナンダよ。修行を完成した人(如来)は、四つの不思議な霊力(四神足)を修し、大いに修し、(軛を結びつけられた)車のように修し、家の礎(いしずえ)のように堅固にし、実行し、完全に積み重ね、みごとになしとげた。かれは、もしも望むならば、寿命のある限りこの世に留まるであろうし、あるいはそれよりも長いあいだでも留まることができるであろう」と。
こういうわけであったけれども、若き人アーナンダは、尊師がこのようにあらわにほのめかされ、あらわに明示されたのに、洞察することができなくて、尊師に対して、「尊い方よ、尊師はどうか寿命のある限り、この世に留まってください。幸いな方(=ブッダ)は、どうか寿命のある限り、この世に留まってください。――多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々を憐れむために、神々と人々との利益のために、幸福のために」といって尊師に懇請することをしなかった。
それは、かれの心が悪魔にとりつかれていたからである。(68~69頁)
訳注
◯四足神――四つの自在力を得る根拠。超自然の神通力を得るための四種の基。つまり不思議に境界を変現する通力である。それらはさとりを得るための実践修行法の一つである。⑴欲神足。すぐれた瞑想を得ようと願うこと。⑵勤(ごん)神足。すぐれた瞑想を得ようと努力すること。⑶心神足。心をおさめてすぐれた瞑想を得ようとすること。⑷観神足。智慧をもって思惟観察してすぐれた瞑想を得ること。「神」とは神通のこと。妙用のはかりがたいことを「神」という。「足」とは因(よりどころ)のこと、すなわち禅定をさす。神通を起こす因であるから「神足」と名づける。ここでいう超自然の神通力は西洋でいう奇蹟(miracle)ではない。そこにはやはり一種の法則がある、と考えられていたのである。以上の四つは、それぞれ目的のための⑴意欲、⑵努力、⑶思念、⑷考察を示すといえよう。(257~258頁)
〔11、悪魔との対話〕
■このように言われたので、尊師は悪魔に次のように言われた、「悪しき者よ。汝は心あせるな。久からずして修行完成者のニルヴァーナが起るであろう。いまから三ヵ月過ぎて後に修行完成者は亡くなるであろう」と。(74頁)
訳注
◯いまから三ヵ月過ぎて後に……亡くなるであろう――この場合、釈尊がこの世になお永く留まるようにアーナンダが釈尊に懇請すべきであるというヒントを、釈尊がアーナンダに与えるのであるが、アーナンダは悪魔にとりつかれていたために、そのように懇請しなかった。そこで釈尊はみずからの意志で、残りの寿命をすててしまうのである。釈尊は、三ヵ月後にはみずから入滅すると悪魔に告げる。
古代インドでは英雄ビーシマのような人は「決意によって死ぬ」ことのできる人であると考えられていた。この観念が偉人と仰がれた釈尊に移されたのである。釈尊は永く生きようと思えば、できるのであるが、決意によって入滅するということは何を意味するかについて、後代の仏教徒の学者の間では盛んに論議されるのである。良く考えてみると、このようなテーマのとりあげかたは『法華経』の場合と本質的に異なっていない。この意味において『法華経』の精神は原始仏教に由来しているということができる。またこの観念は浄土経典にも継承されている。『アーナンダよ、如来は、もしそうしようと思えば、一食分の施された食物で、一劫のあいだ住することができるであろう。あるいは百劫も、あるいは千劫、あるいは百千劫に至るまでも、あるいはそれを過ぎても、なお住することができるであろう。』しかしいま伝説や神話の釈尊ではなく、歴史的人物としてのゴータマ・ブッダの実際の生涯を明らかにするという立場に立つならば、右の神話は、排除して考えなければならない。ただ次に出て来る詩句は右の伝説が出来上がるためのものとなったものであり、臨終にあたってのゴータマの心境をよく表明している。(264~265頁)
〔12、大地震に関連して〕
■アーナンダよ。これらの八つの解脱がある。その八つとは、どれどれであるか?(内心において)〈物質的なるもの〉という想いをいだいている者が(外において)(物質的なもの)を見る。これが第一の解脱である。
内心に(物質的なるざるもの)という想いをいだく者が外において〈物質的なもの〉を見る。これが第二の解脱である。
(すべてのものを)〈浄らかである〉と認めていること、――これが第三の解脱である。
〈物質的なもの〉という想いを全く超越して、抵抗感を消滅し、〈別のもの〉という想いを起こさないことによって、〈(すべては)無辺なる虚空である〉と観じて、〈空無辺処〉に達して住する。これが第四の解脱である。
〈空無辺処〉を全く超越して、〈(すべては)無辺なる虚空である〉と観じて、〈識無辺処〉に達して住する。これが第五の解脱である。
〈識無辺処〉を全く超越して、〈何ものも存在しない〉と観じて、〈無所有処〉(=何も無いという境地)に達して住する。これが第六の解脱である。
〈無所有処〉を全く超越して、〈何ものも存在しない〉〈非想非非想処〉(想いがあるのでもなく、思いが無いのでもないという境地)に達して住する。これが第七の解脱である。
〈非想非非想処〉を全く超越して、〈想受滅〉(表象も感受も消滅する境地)に達して住する。これが第八の解脱である。
アーナンダよ。これらが八つの解脱である。(84~85頁)
■若き人アーナンダは再び尊師に言った。――
「尊い方よ。尊師はどうか寿命のある限りこの世に留まってください。幸いな方(=ブッダ)は寿命のある限りこの世に留まってください。――多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々をあわれむために、神々と人間との利益のため、幸福のために」と。
「アーナンダよ。いまはお止めなさい。修行完成者に懇請してはいけない。いまは修行完成者に懇請すべき時ではない。」
若き人アーナンダは三度(みたび)尊師に言った。――
「尊い方よ。尊師はどうか寿命のある限りこの世に留まってください。幸いな方(=ブッダ)は寿命のある限りこの世に留まってください。――多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々をあわれむために、神々と人間との利益のため、幸福のために」と。
「アーナンダよ。お前は修行完成者の達成した(さとり)を信じますか?」
「はい。尊い方よ。」
「それでは、アーナンダよ、お前は何故、三度までも、修行完成者を悩ませたのですか?」(90~91頁)
■アーナンダよ。かって或るときわたしは王舎城のうちの〈鷲の峰〉に住していた。アーナンダよ。そこでもわたしはお前に告げていった。(92頁)
■アーナンダよ。かって或るときわたしは同じ王舎城のうちで、〈バニヤンの樹木の園〉に住していた。(94頁)
■アーナンダよ。かって或る時、わたしはヴェーサーリーにおいてウデーナ霊樹のもとにとどまっていた。(96頁)
■アーナンダよ。かって或るとき、わたしはヴェーサーリー(市)においてゴータマ霊樹のもとに住していた。(97頁)
■アーナンダよ。わたしはいま今日、王舎城のうちの〈鷲の峰〉に住していた。アーナンダよ。そこでもわたしはお前に告げていった。『「アーナンダよ、ヴェーサーリー(市)は楽しい。ウデーナ霊樹は楽しい。ゴータマカ霊樹は楽しい。サッタンバ霊樹は楽しい。バフプッタ霊樹は楽しい。サーランダ霊樹の地は楽しい。チャーパーラ霊樹の地は楽しい。
アーナンダよ。いかなる人であろうとも、四つの不思議な霊力(四神足)を修し、大いに修し、(軛を結びつけられた)車のように修し、家の礎(いしずえ)のようにしっかりと堅固にし、実行し、完全に積み重ね、みごとになしとげた人は、もしも望むならば、寿命のある限りこの世に留まるであろうし、あるいはそれよりも長いあいだでも留まることができるであろう』と。
アーナンダよ。修行完成者がこのようにあらわにほのめかされ、あらわに明示されたけれども、お前は洞察することができなくて、『尊師はどうか寿命のある限り、この世に留まってください。幸いな方(=ブッダ)は、どうか寿命のある限り、この世に留まってください。――多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々を憐れむために、神々と人々との利益のために、幸福のために』といって修行完成者(=ブッダ)に懇請することをしなかった。アーナンダよ。もしもお前が修行完成者に懇請したならば、修行完成者はお前の二度にわたる(懇請の)ことばを退けたかもしれないが、しかし三度まで言ったならばそれを承認したであろう。それだから、アーナンダよ、これはお前の過失である。」(97~98頁)
訳注
◯寿命の素因――「いのちのもと」である。ブッダはすでにニルヴァーナに達しているので、死後に生れかわることはない。しかし過去の業の余力があるので、それがこの世で生命をたもつ素因となって、ブッダはなおこの世で生きているのである。インド哲学一般では潜勢力のことをいうが、それと共通の観念である。ところがここでは寿命の潜在性(可能性)を放棄したのである。ここではブッダを神格化して、やがて大乗仏教の仏心観に向う第一歩が認められる。(75頁)
◯バラモン――brahmana.「婆羅門」と音写する。ヴェーダ聖典にしたがって祭祀を実行する司祭者。インドでは最高のカーストである。(267~268頁)
〔13、死別の運命〕
■「しかし、アーナンダよ。わたしはあらかじめこのように告げておかなかったか?――
「愛(いと)しく気に入っているすべての人々とも、やがては、生別し、死別し、(死後には生存の場所を)異にするに至る』と。アーナンダよ。生じ、存在し、つくられ、壊滅する性質のものが、(実は)壊滅しないように、ということが、この世でどうして有り得ようか?このような道理は存在しない。それは修行完成者によって棄てられ、吐きすてられ、放され、捨てられ、投げ捨てられたものである。寿命の素因は捨てられた。修行完成者は断定的にこのことばを説かれた、――『久しからずして修行完成者は亡くなるであろう。これから三ヵ月過ぎたのちに、修行完成者は亡くなるであろう』と。修行完成者が、生きのびたいために、このことばを取り消す、とうようなことは有り得ない。
さあアーナンダよ。〈大きな林〉にある重閣講堂に行こう。
「かしこまりました」と、若き人アーナンダは尊師に答えた。(99~100頁)
■そこで尊師は講堂に近づいた。近づいて、設けてあった席に坐した。坐して、尊師は修行僧たちに告げた。――
「修行僧たちよ。それでは、ここでわたしは法を知って説示したが、お前たちは、それを良くたもって、実践し、実習し、盛んにしなさい。それは、清浄な行ないが長くつづき、久しく存続するように、ということをめざすのであって、そのことが多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々を憐れむために、神々と人間との利益・幸福になるためである。そうして、修行僧たちよ。わたしが、それを知ってお前たちにために説示したが、お前たちがそれを良くたもって、実践し、実習し、盛んにすべきであり、そうしてそれは、清浄な行ないが長くつづき、久しく存続するように、ということをめざすのであって、そのことが、多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々を憐れむために、神々と人間との利益・幸福になるためであるところの、その〈法〉とは何であるか? それはすなわち、四つの念ずることがら(四念処)と四つの努力(四正勤)と四つの不思議な霊力(四神足)と五つの勢力(五根)と五つの力(五力)と七つのさとりのことがら(七覚支)と八種よりなるすぐれた道(八聖道)とである。修行僧たちよ。これらの法を、わたしは知って説いたが、お前たちは、それを良くたもって、実践し、実習し、盛んにしなさい。それは、清浄な行ないが長くつづき、久しく存続するように、ということをめざすのであって、そのことが多くの人々の利益のために、多くの人々の幸福のために、世間の人々を憐れむために、神々と人々との利益・幸福になるためである」と。(100~102頁)
■そこで尊師は修行僧たちに告げられた、「さあ、修行僧たちよ。わたしはいまお前たちに告げよう、――もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠けることなく修行を完成なさい。久しからずして、修行完成者は亡くなるだろう。これから三ヵ月過ぎたのちに、修行完成者は亡くなるだろう」と。
尊師、幸いな人、師はこのように説かれた。このように説いたあとで、さらに次のように言われた。――
「わが歳は熟した。
わが余命はいくばくもない。
汝らを捨てて、わたしは行くであろう。
わたしは自己に帰依することをなしとげた。
汝ら修行僧たちは、怠ることなく、よく気をつけて、
よく戒しめをたもて。
その思いをよく定め統一して、おのが心をしっかりとまもれかし
この教説と戒律とにつとめはげむ人は、生れをくりかえす輪廻をすてて、苦しみも終滅するであろう」と。(102~103頁)
訳注
◯四つの念ずることがら――旧い漢訳では「四念処」といい、玄奘以後の新しい漢訳では「四念住」という。「四念処観」に同じ。さとりを得るための四種の観想法。⑴この身は不浄なり、⑵受は苦なり、⑶心は無常なり、⑷法は無我なりと観ずること。すなわち、身体は不浄である。感受は苦である、心は無常である、すべての事物は無我である、という四つを心に思い浮べる修行。(276頁)
◯四つの努力――漢訳では「四正勤(ししょうごん)」、「四精勤(ししょうごん)」と訳す。四種の正しい努力。さとりを得るための実践修行法の一つ。⑴すでに生じた悪を除こうと勤めること。⑵悪を生じないように勤めること。⑶善を生ずるように勤めること。⑷すでに生じた善を増すように勤めること。(276頁)
◯四つの不思議な霊力――漢訳では「四神足」という。四つの自在力を得る根拠。超自然的な神通力を得るための四種の基。さとりを得るための実践修行法の一つである。⑴欲神足。すぐれた瞑想を得ようと願うこと。⑵勤神足。すぐれた瞑想を得ようと努力すること。⑶心神足。心をおさめて、すぐれた瞑想を得ようとすること。⑷観神足。智慧をもって思惟観察して、すぐれた瞑想を得ること。「神」とは「神通」のこと。妙用のはかりがたいことを「神」という。「足」とは因(よりどころ)のこと。すなはち禅定をさす。神通を起こす因であるから神足と名づける。(276~277頁)
◯五つの勢力――漢訳では「五根」と訳す。解脱に至るための五つの力、また能力。さとりを得るための五つの機根。可能力ある五つの美徳。信(sraddha)、精進(virya)、念(smrti)、定(samadhi)、慧(prajina)をいう。(277頁)
◯五つの力――漢訳では「五力」という。さとりに至らしめる五つの力。五つのすぐれたはたらき。信(信仰)、精進(努力)、念(憶念)、定(禅定)、慧(知慧)の五つををいう。(277頁)
◯七つのさとりのことがら――漢訳では「七覚支」「七菩提分」という。さとりを得るために役立つ七つのことがらの意。心の状態に応じて、存在を観察する上での注意・方法を七種にまとめたもの。⑴択法(ちゃくほう)。教えの中から真実なるものを選びとり、偽りのものを捨てる。⑵精進。一心に努力すること。⑶喜。真実の教えを実行する喜びに住すること。⑷軽安(きょうあん)。身心をかろやかに快適にすること。⑸捨。対象へのとらわれを捨てること。⑹定。心を集中して乱さないこと。⑺念。おもいを平らかにすること。(277頁)
◯八種よりなるすぐれた道――漢訳では「八正道」「八聖道」と訳す。理想の境地に達するための八つの道。八種の正しい生活態度。⑴正見(しょうけん)。正しく四つの真理(四諦)の道理を見ること。⑵正思惟(しょうしゆい)。正しく四つの真理の道理をよく考えること。⑶正語(しょうご)。正しいことば。⑷正業(しょうごう)。正しい行動をすること。⑸正命(しょうみょう)。身と口(ことば)と意(こころ)とにおける三種の行動を清らかにして、正しい理法にしたがって生活すること。⑹正精進。正しく道に努め励むこと。⑺正念。正しい道をこころにおもいつづけて、邪念の無いこと。⑻正定(しょうじょう)。正しく精神統一をして迷いのない清らかなさとりの境地に入ること。以上の八つをいう。簡単にいうと、⑴正しい見解、⑵正しい思い、⑶正しいことば、⑷正しい行為、⑸正しい生活、⑹正しい努力、⑺正しい気づかい、⑻正しい精神統一のこと。(277~278頁)
◯次のように言われた――すなわち釈尊が亡くなるともう指導者としての師はいなくなるのであるが、その代わりに真理の教えととしての〈法〉と実践のきまりとしての〈律〉とが規準となり、師とも見なさるべきものであるというのである。この、最後の教えから見ると、絶えず、まじめに自己の修養につとめる、ということが、最初期の仏教の中心の思想であったということができるであろう。(278頁)
第4章
〔14、一生の回顧――バンダ村へ〕
■そこで尊師は修行僧たちに説いた。――
「修行僧たちよ。四つのことわりをさとらず、また通達しなかったから、わたしもお前たちも、このように、この長い時間のあいだ、流転し、輪廻したのである。その四つとはどれどれであるか?〔1〕修行僧たちよ。尊い戒律をさとらず、通達しなかったから、わたしもお前たちも、このように、この長い時間のあいだ、流転し、輪廻したのである。〔2〕修行僧たちよ。尊い精神統一をさとらず、通達しなかったから、わたしもお前たちも、このように、この長い時間のあいだ、流転し、輪廻したのである。〔3〕修行僧たちよ。尊い智慧をさとらず、通達しなかったから、わたしもお前たちも、このように、この長い時間のあいだ、流転し、輪廻したのである。〔4〕修行僧たちよ。尊い解脱をさとらず、通達しなかったから、わたしもお前たちも、このように、この長い時間のあいだ、流転し、輪廻したのである。修行僧たちよ。しかし(いまは)もの尊い戒律がさとられ、、通達され、尊い解脱がさとられ、通達された。生存に対する妄執はすでに断たれた。生存にみちびく(妄執)はすでに滅びてしまった。もはや再び迷いの生存を受けるということはない。」(106~107頁)
■尊師はこのことを説いた。このことを説いたあとで、幸いな人・師はまた次のことを説いた。――
「戒しめと精神統一と無上の解脱と、
これらの(四つの)法を、誉れ高きドータマは、覚った。
ブッダは、このようによく知って、修行僧たちに法を説かれた。
苦しみを滅した人、眼(まなこ)ある師は、すでに束縛をときほごされた」と。(107頁)
■そこで、尊師はバンダ村に住しながら、修行僧たちのために、このように数多くの〈法に関する講話〉をなされた。――すなわち、戒律とはこれこれである。精神統一とはこれこれである。智慧とはこれこれである。戒律とともに修養された精神統一は、大いなる果報をもたらし、大いなる功徳がある。精神統一とともに修養された智慧は、大いなる果報をもたらし、大いなる功徳がある。智慧とともに修養された心は、諸々の汚れ、すなわち欲望の汚れ、生存の汚れ、見解の汚れ、無明の汚れから完全に解脱する、と。(107頁)
〔16、鍛冶工チュンダ〕
訳注
◯チュンダ――(前略)普通「鍛冶工」と解せられるが、インドでは金細工人、銀細工人、鉄や銅の鍛冶工が特に区別されることはなかった。従って「金属細工人」と訳した方がよいかもしれない。
チュンダは釈尊並びに弟子たちを招待し得たのであるから富裕な人であったにちがいない。しかしインドのカースト社会においては、鍛冶工や金属細工人は賤しい職業と見なされ、蔑視されていた。その招待を釈尊は受けいれたのである。ここにわれわれは二つの注目すべき歴史的特徴を認めることができる。⑴当時漸く富裕となりつつあったが、社会的に蔑視されていた人々は、新しい精神的な指導者を求めていた。⑵ゴータマ・ブッダの動きは当時のこの階級的差別打破の要求に応えたものであった。(岡野注;この説はこじつけだとおもう)(286頁)
〔17、臨終の地をめざして――ブックサとの邂逅(かいこう)〕
■そこで尊師は、マッラ族の子ブックサを〈法に関する講話〉によって、教え、諭し、励まし、喜ばせて、座席から起って、尊師に敬礼して、右肩を向けて(三たび)廻って、出て行った。
次いで若き人アーナンダは、マッラ族の子ブックサが去って間もなく、その柔らかいつやつやした金色の一対の衣を、尊師のからだに着せてあげた。尊師のからだに着せられたその衣は、輝きを失ったように見えた。(127頁)
■さてアーナンダよ。今夜最後の更にクシナーラーのウバヴァッタナにあるマッラ族の紗羅林の中で二本並んだ樹(沙羅双樹)の間で修行完成者の完全な死が起るであろう。(128頁)
■そこで尊師は若き人アーナンダに告げられた。
「誰かが、鍛冶工の子チュンダに後悔の念を起こさせるかもしれない、――〈友、チュンダよ。修行完成者はお前の差し上げた最後のお供養の食物を食べてお亡くなりになったのだから、お前には利益(りやく)がなく、お前には功徳が無い〉と言って。
アーナンダよ。鍛冶工の子チュンダの後悔の念は、このように言ってとりのぞかれねばならぬ。
〈友よ。修行完成者は最後のお供養の食物を食べてお亡くなりになったのだから、お前には利益(りやく)があり、大いに功徳がある。友、チュンダよ。このことを、わたしは尊師からまのあたり聞き、うけたまわった、――この二つの供養の食物は、まさにひとしいみのり、まさにひとしい果報があり、他の供養の食物よりもはるかにすぐれた大いなる果報があり、はるかにすぐれた大いなる功徳がある。その二つとは何であるか?修行完成者が供養の食物を食べて無上の完全なさとりを達成したのと、および、(このたびの)供養の食物を食べて、煩悩の残りの無いニルヴァーナの境地に入られたのとである。この二つの供養の食物は、まさにひとしいみのり、まさにひとしい果報があり、他の供養の食物よりもはるかにすぐれた大いなる果報があり、はるかにすぐれた大いなる功徳がある。鍛冶工の子である若き人チュンダは寿命をのばす業を積んだ。鍛冶工の子である若き人チュンダは容色をますを業を積んだ。鍛冶工の子である若き人チュンダは幸福をます業を積んだ。鍛冶工の子である若き人チュンダは名声を増す業を積んだ。鍛冶工の子である若き人チュンダは天に生まれる業を積んだ。鍛冶工の子である若き人チュンダは支配権を獲得する業を積んだ〉と。
アーナンダよ。鍛冶工の子チュンダの後悔の念は、このように言ってとり除かれねばならぬ」と。(130~131頁)
■そこで尊師は、その趣意を知って、そのときこの感興のことばを述べられた。――
「与える者には、功徳が増す。
身心を制する者には、怨みのつもることがない。
善き人は悪寺を捨てる。
その人は、情欲と怒りを迷妄とを滅して、束縛が解きほごされた」と。(132頁)
訳注
◯〈友よ。……業を積んだ〉――以上のことばは、チュンダが「自分の供養した食物で釈尊は亡くなった」と思って悲しんだり、また他の人々がそのように言ってチュンダを非難するかもしれないので、それを防いで、このように言ったのである。ここに人間ゴータマの温かい思いやりが見られる。すなはち、チュンダのささげた食物によって釈尊は中毒したのであるから、『誰かが鍛冶工の子チュンダに後悔の念を起こさせるかもしれない。』と思って、かれに心配させないように次のように言え、と伝えさせた。――「二つの供養の食物に最上の功徳がある。それは、さとりを開いた直後に供養された食物と、チュンダが供養した食物とである。」と。みずからは苦痛に悩みながらも、チュンダのことを気づかっていたのである。チュンダをかばう思いやりが見られる。ゴータマ・ブッダは思いやりの深い人であった。(304頁)
第5章
〔18、病い重し〕
■「さあ、アーナンダよ。ヒラニヤヴァティー河の彼岸にあるクシナーラーのマッラ族のウパヴァッタナに赴こう」と。(133頁)
■「さあ、アーナンダよ。わたしのために、二本並んだサーラ樹(沙羅双樹)の間に、頭を北に向けて床を用意してくれ。アーナンダよ。わたしは疲れた。横になりたい」と。(133~134頁)
■「アーナンダよ。信仰心のあるまじめな人が実際に訪ねて見て感激する場所は、この四つである。その四つとはどれどれであるか?
〈修行完成者はここでお生れになった〉といって、信仰心ある良家の子が実際に訪ねて見て感激する場所がある。
〈修行完成者はここで無上のさとりを開かれた〉といって、信仰心ある良家の子が実際に訪ねて見て感激する場所がある。
〈修行完成者はここで教えを説き始められた〉といって、信仰心ある良家の子が実際に訪ねて見て感激する場所がある。
〈修行完成者はここで煩悩の残りの無いニルヴァーナの境地に入られた〉といって、信仰心あるまじめな人が実際に訪ねて見て感激する場所がある。
アーナンダよ。これらの四つの場所が、信仰心ある修行僧・尼僧たち、在俗信者・在俗信女たちが、〈修行完成者はここでお生れになった〉、〈修行完成者はここで無上のさとりを開かれた〉、〈修行完成者はここで教えを説き始められた〉、〈修行完成者はここで煩悩の残りの無いニルヴァーナの境地に入られた〉といって(これらの場所に)集まって来るであろう。(138~139頁)
〔19、アーナンダの号泣〕
■若き人アーナンダが一方に坐したときに、尊師は次のように説いた。
「やめよ、アーナンダよ。悲しむな。歎くな。アーナンダよ。わたしは、あらかじめこのように説いたではないか、――すべての愛するもの・好むものからも別れ、離れ、異なるに至るということを。およそ生じ、存在し、つくられ、破壊さるべきものであるのに、それが破滅しないように、ということが、どうしてありえようか。アーナンダよ。そのようなことわりは存在しない。アーナンダよ。長い間、お前は、慈愛ある、ためをはかる、安楽な、純一なる、無量の、身とことばとこころとの行為によって、向上し来れる人(=ゴータマ)に仕えてくれた。アーナンダよ。お前は善いことをしてくれた。努めはげんで修行せよ。速やかに汚れのないものになるであろう。」(146~147頁)
■このように言われて、若き人アーナンダは尊師にこのように言った。
「尊い方よ。尊師は、この小さな町、竹薮の町、場末の町でお亡くなりになりますな。尊い方よ。ほかに大都市があります。例えば、チャンパー、王舎城、サーヴァッティー、サーケータ、コーサンビー、バーラーナシー(ベナレス)があります。こういうところで尊師はお亡くなりになってください。そこには富裕な王族たち、富裕なバラモンたち、富裕な資産者たちがいて、修行完成者(ブッダ)を信仰しています。かれらは修行完成者の遺骨の崇拝をするでしょう。」
「アーナンダよ。そんなことを言うな。アーナンダよ。(小さな町、竹薮の町、場末の町)と言ってはいけない。」(149~150頁)
〔22、スバッダの帰依〕
■そこで遍歴行者スバッダは尊師のもとに赴いた。赴いて、相い喜んで、挨拶のことばを交わし、ご機嫌伺いをして、一方に坐した。一方に坐した遍歴行者スバッダは、尊師にこのことを尋ねた。
「ゴータマさんよ。この諸々の修行者やバラモンたち、つどいをもち徒衆をもち徒衆の師で、世に知られ、名声あり、宗派の開祖として多くの人々に崇敬されている人々、例えば、プーラナ・カッサパ、マッカリ・ゴーサーラ、アジラ・ケーサカンバリン、バクダ・カッチャーヤナ、サンジャヤ・ペーラッティプッタ、ニガンタ・ナータプッタ――かれらはすべて自分の智をもって知ったのですか?あるいは、かれらはすべて知っていないのですか?そのうちの或る人々は知っていて、或る人々は知らないのですか?」
「やめなさい。スバッダよ。(かれらはすべて自分の智をもって知ったのですか?あるいは、かれらはすべて知っていないのですか?そのうちの或る人々は知っていて、或る人々は知らないのですか?)ということは、ほっておけ。スバッタよ。わたしはあなたに理法を説くことにしよう。それを聞きなさい。よく注意なさいよ。わたしは説くことにしよう。」
「かしこまりました」と、遍歴行者スバッダは尊師に答えた。尊師は次のことを説いた。――(159~160頁)
■「スバッタよ。いかなる教えと戒律とにおいてでも、〈尊い八支よりなる道〉が存在すると認められないところには、(第一の)〈道の人〉は認められないし、そこには第二の〈道の人〉も認められないし、そこには第三の〈道の人〉も認められないし、そこには第四の〈道の人〉も認められない。しかしいかなる教えと戒律とにおいてでも、〈尊い八支よりなる道〉が認められるところには、第一の〈道の人〉が認められ、そこには第二の〈道の人〉も認められ、そこには第三の〈道の人〉も認められ、そこには第四の〈道の人〉も認められる。この(わが)教えと戒律とにおいては〈尊い八支よりなる道〉が認められる。ここに第一の〈道の人〉がいるし、ここに〈道の人〉がいるし、ここに第三の〈道の人〉がいるし、ここに第四の〈道の人〉がいる。他のもろもろの論議の道は空虚である。――〈道の人〉を欠いている。スバッタよ。修行僧らはここに正しく住しなさい。そうすれば、世の中は真人たちを欠くことの無いものとなるであろう(=真人たちがつづいて出て来るはずだ)。
スバッタよ。わたしは二十九歳で、何かしら善を求めて出家した。
スバッタよ。わたしは出家してから五十年余となった。
正理と法の領域のみを歩んで来た。
これ以外には〈道の人〉なるものも存在しない。
第二の〈道の人〉なるものも存在しない。第三の〈道の人〉なるものも存在しない。第四の〈道の人〉なるものも存在しない。他の論議の道(=他派)は空虚である。――〈道の人〉を欠いている。スバッタよ。この修行僧たちは、正しく住すべきである。そうすれば、世の中は、真人たちを欠くことの無いものとなるであろう。」(160~161頁)
訳注
◯マンダーラヴァ華――「曼陀羅華」と書かれ、天の華としてたたえられている。極楽浄土でもマンダーラヴァの華の雨を降らせる。その木は現実の植物界にあてはめると、デイコという木で、『樹高十五ー十八メートルに達するマメ科の落葉喬木で、葉は広卵形の三出複葉、樹幹にはかたい棘がある。初夏にあざやかな深紅色から紫紅色の花が三十ー四十センチの総状花序に咲き、実にきれいである。』(満久崇麿『仏典の植物』前掲、40-42ページ)。仏典の中ではデイコの花を弔花として引用している。しかしブッダの誕生を祝する場合にも、天からマンダーラヴァの華が降って来た。(309頁)
◯つつしんでおれ――『修行僧らよ。お前たちは、母のような女に対しては、母だと思う心を起せ。姉妹のような女に対しては、姉妹だと思う心を起せ。娘のような女に対しては、娘だと思う心を起せ。』(314頁)
◯正しい目的のために努力せよ――仏教の修行僧は、自分の修養につとめることだけをせよ。葬儀などよるな、という思想は原始仏教聖典にまま散見するが、ここにも現われているのである。まだブッダの遺骨崇拝も世俗人のやることであり、出家修行僧のかかずらうことではないと考えていたことが、ここでも知られる。(309頁)
第六章
〔23、臨終のことば〕
■そこで尊師は若き人アーナンダに告げられた。――
「アーナンダよ。あるいは後にお前たちはこのように思うかもしれない、『教えを説かれた師はましまさぬ、もはやわれらの師はおられないのだ』と。しかしそのように見なしてはならない。お前たちのためにわたしが説いた教えとわたしの制した戒律とが、わたしの死後にお前たちの師となるのである。
また、アーナンダよ。いま修行者たちは、互いに『友よ!』と呼びかけて、つき合っている。しかし、わたしが亡くなったのちには、お前たちはこのようにいってつき合ってはならない。アーナンダよ。年長である修行僧は、新参の修行僧を、名を呼んで、または姓を呼んで、または『友よ!』と呼びかけてつき合うべきである。新参の修行僧は、年長の修行僧を『尊い方よ!』とか『尊者よ!』と呼んでつき合うべきである。
アーナンダよ。修行僧の集いは、わたしが亡くなったのちには、もしも欲するならば、瑣細(ささい)な、小さな戒律箇条は、これを廃止してもよい。
アーナンダよ。わたしが亡くなったのちには、修行僧チャンナには、〈清浄な罰〉(ブラフマ・ダンダ)を加えなさい。」
「尊い方よ。〈清浄な罰〉というのは、そもそも何ですか?」
「アーナンダよ。修行僧チャンナは、自分の欲することを何でも言ってよい。しかし修行僧たちはかれに話しかけてはならないし、訓戒してはならないし、教えさとしてはならない。」
そこで尊師は、修行僧たちに告げられた。――
「また、修行僧たちよ。ブッダに関し、あるいは法に関し、あるいは集いに関し、あるいは道に関し、あるいは実践に関し、一人の修行僧に、疑い、疑惑が起るかもしれない。修行僧たちよ。(そのときには)問いなさい。あとになって、〈わたしたちは師に目のあたりお目にかかっていた。それなのにわたしたちは尊師に目のあたりおたずねすることができなかった〉と言って後悔することの無いように」と。
このように言われたときに、かの修行僧たちは黙っていた。(165~167頁)
■再び尊師は……乃至……三たびも尊師は告げられた。
「また、……中略……後悔することの無いように」
(このように言われたときに)かの修行僧たちは三たびも黙っていた。(167頁)
■そこで尊師は、修行僧たちに告げられた。
「修行僧たちよ。お前たちは師を尊崇するが故にたずねないということがあるかもしれない。修行僧たちよ。仲間が仲間に(たずねるように)たずねなさい。」
このように言われても、かの修行僧たちは黙っていた。(167頁)
■そこで若き人アーナンダは尊師にこのように言った。
「尊い方よ。不思議であります。珍しいことであります。わたくしは、この修行僧の集いをこのように喜んで信じています。ブッダに関し、あるいは法に関し、あるいは集いに関し、あるいは道に関し、あるいは実践に関し、一人の修行僧たちにも、疑い、疑惑が起っていません。」(167~168頁)
■「アーナンダよ。お前は浄らかな信仰からそのように語る。ところが、修行完成者には、こういう智がある、〈この修行僧の集いにおいては、ブッダに関し、あるいは法に関し、あるいは集いに関し、あるいは道に関し、あるいは実践に関して、一人の修行僧たちにも、疑い、疑惑が起っていない。この五百人の修行僧のうちの最後の修行僧でも、聖者の流れに入り、退堕しないはずのものであり、必ず正しいさとりに達する〉と。」(168頁)
■そこで尊師は修行僧たちに告げた。――
「さあ、修行僧たちよ。お前たちに告げよう、『もろもろの事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成なさい』と。」
これが修行をつづけて来た者の最後のことばであった。(168頁)
訳注
◯チャンナ――かれは気むずかしく、かたくなで、教団の内部にあっても他人と協力せず、とかく摩擦・抗争を起した。しかしここで述べられたいる罰を受けてのちには、人格も円熟したと言われている。(331頁)
◯最後の修行僧――『徳の力に関して最も劣っている者のことで、アーナンダを意味しているのである。』アーナンダは若くて修行においても未熟であったが、しかしいつかは修行が完成するぞ、といって、かれに期待し、かれを激励しているのである。(331頁)
◯怠ることなく修行を完成なさい――仏教の要決は、無常をさとることと、修行に精励することの二つに尽きることになる。(332頁)
◯神々の主であるサッカ(=帝釈天)――インドラ神のことをいう。『リグ・ヴェーダ』においては最も強い。また最も多く崇拝された神で、もとは暴風神であった。かれの名をSakkaというので、漢字の「釈」で音写し、神々の王であるから「帝……天」という字を付加して「帝釈天」という。(337頁)
〔補遺〕
「つくられたものは実に無常であり、生じては滅びるきまりのものである。生じては滅びる。これら(つくられたもの)のやすらいが安楽である。」
というこの詩は、日本の「いろは歌」の原文であるが、この書『ブッダ最後の旅』では、釈尊の亡くなったときに唱えられた詩である。そこでスリランカでは、葬式のときに僧侶(ビク)がこの詩をとなえ、そのあとで説教を述べ、無常の理を教える。日本のようにお経をながながと唱えることはしない。(354~355頁)
〔24、死を悼む〕
■そこで尊師は初禅(第一段階の瞑想)に入られた。初禅から起(た)って、第二禅に入られた。第二禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第四禅に入られた。第四禅から起って、空無辺処定に入られた。空無辺処定から起って、非想非非想定に入られた。非想非非想定から起って、滅想受定に入られた。
そのとき若き人アーナンダは尊者アヌルッダにこう言った。
「尊い方、アヌルッダよ。尊師はニルヴァーナに入られました。」
「友、アーナンダよ。尊師はニルヴァーナに入られたのではありません。感受想定に入られたのです。」
■そこで尊師は滅想受定から起って、非想非非想定に入られた。非想非非想定から起って、無所有処定に入られた。無所有処定から起って、識無辺処定に入られた。識無辺処定から起って、空無辺処定に入られた。空無辺処定から起(た)って、第四禅に入られた。第四禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第二禅に入られた。第二禅から起って、初禅に入られた。初禅から起って、第二禅に入られた。第二禅から起って、第三禅に入られた。第三禅から起って、第四禅に入られた。第四禅から起って、尊師はただちに完きニルヴァーナに入られた。(169~170頁)
〔25、遺体の火葬〕
■そのとき、年老いて出家したスバッダという修行僧がかの会衆のうちに坐っていた。さて年老いて出家したスバッダはそれらの修行僧にこのように言った。
「やめなさい、友よ。悲しむな。嘆くな。われらほかの偉大な偉大な修行者からうまく解放された。〈このことはしてもよい。このことはしてはならない〉といって、われわれは悩まされていたが、今これからは、われわれは何でもやりたいことをしよう。またやりたくないことをしないようにしよう」と。(162頁)
■そこで尊者大カッサパは修行僧らに告げた。
「やめよ、友よ。悲しむな。嘆くな。友よ。まことに尊師はかって、あらかじめこのように説かれたではないか?『すべての愛しき好む者どもとも、生別し、死別し、死後には境界を異にする。どうしてこのことがあり得ようか。――かの生じた、存在せる、つくられた、壊滅する性質のものが、壊滅しないような、このような道理は存在しないのである』と。」(182頁)
〔26、遺骨の分配と崇拝〕
■そこで、マガダ国王であるアジャータサットゥ、ヴィデーハ国王の女(むすめ)の子、は、王舎城に、尊師の遺骨のためにストゥーパをつくり、また祭りを行った。
ヴェーサーリーに住むリッチャヴィ族はヴェーサーリーに、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
カピラ城に住むサーキャ(釈迦)族も、カピラ城に、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
アッラカッパに住むブリ族も、アッカラパに、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
ラーマ村に住むコーリア族も、ラーマー村に、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
ヴェータディーバに住むバラモンたちも、ヴェータディーバに、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
ラーマ村に住コーリヤ族も、ラーマ村に、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
パーヴァーに住むマッラ族も、パーヴァーに、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
クシナーラーに住むマッラ族も、クシナーラー村に、尊師の遺骨のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
ドーナ・バラモンも、瓶のストゥーパをつくり、祭りを行った。
ピッパリ林に住むモーリヤ族も、ピッパリ林に、(尊師の)灰のために、ストゥーパをつくり、また祭りを行った。
こういうわけで、八つの遺骨のストゥーパと、第九に瓶のストゥーパと、第十に灰の塔とがある。
以上のように、これはかって起った(昔の)できごとなのである。(191~192頁)
■眼(まなこ)ある人の遺骨は八斛(こく)ある。
七斛はインドで供養される。
最上の人(=ブッダ)の他の一斛(の遺骨)は、ラーマ村で諸々の竜王が供養する。
一つの歯はガンダーラ市で供養される。
また一つの歯は諸々の竜王が供養している。
その威光によってこの豊かな大地は、
最上の供養物をもって飾られているのである。
このように、この眼ある人(=ブッダ)の遺骨は、
よく崇敬され、種々にいともよく崇敬されている。
天王(=神々の王)・諸々の竜王・人王に供養され、
最上の人々によってこのように供養されている。
合掌して、かれを礼拝せよ。
げにブッダは百劫にも会うこと難し。(192~193頁)
(2018年7月17日)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ブッダが説いたこと』ワールポラ・ラーフラ 著 今枝由郎 訳 岩波文庫
第1章 仏教的な心のあり方
■「カーラーマたちよ、あなたたちが疑い、戸惑うのは当然である。なぜなら、あなたたちは疑わしい事柄に疑いを抱いたのであるから、カーラーマたちよ、伝聞、伝統、風雪に惑わされてはならない。聖典の権威、単なる論理や推理、外観、思弁、うわべ上の可能性、「これが私たちの師である」といった考えに惑わされてはならない。そうではなく、カーラーマたちよ、あなたたちが自分自身で、忌まわしく、間違っており、悪いと判断したならば、それを棄てなさい。あなたたちが自分自身で、正しく、よいと判断したならば、それに従いなさい」
ブッダはさらに、修行者は、自らが師事する人の真価を十分に得心するために、ブッダ自身のことさえも吟味すべきである、と言っている。(29頁)
■すべての悪の根源は無知であり、誤解である。疑問、戸惑い、ためらいがある限り、進歩できないのは否定できない事実である。そしてまた、ものごとが理解できず、明晰に見えない限り、疑問が残るのは当然である。それゆえに本当に進歩するためには、疑問をなくすことが絶対に不可欠である。そして疑問をなくすためには、ものごとを明晰に見ることが必要である。(30頁)
■ブッダはたえず疑問をなくすことを心がけた。死の直前になっても、ブッダは弟子たちに向かって、あとになって疑問が晴らせなかったことを悔いることがないように、今まで自分が教えたことに関して何か疑問があるかどうかを質(ただ)した。しかし、弟子たちは黙して答えなかった。そのときのブッダのことばは感動的である。
「弟子たちよ、そなたたちはもしかしたら、師への敬意ゆえに質問しないのかもしれない。もしそうなら、それはよくないことだ。友人に問いかけるように質問するがいい」(31頁)
■ニガンタ・ナータプッタ(ジャイナ・マハーヴィーラ)はブッダと同時代の人であったが、カルマに関してブッダと意見を異にしていた。あるとき彼は、弟子の一人で裕福な在家信者であったウパーリをナーランダにいたブッダの許に使わし、論戦を挑ませた。ところがまったく予想に反して、論戦の末にウパーリはブッダの意見が正しく、自分の師の説が間違っていることを確信した。そこで彼は、ブッダに弟子入りを願い出た。ところがブッダは「あなたのように知られた人にとって、慎重に検討することはいいことだから」と言って、急いで決断せず、もう一度考え直すように促した。ウパーリが再度弟子入りを乞うと、ブッダは彼に、今まで師事した先生たちを従来通り尊敬し、支持するように促した。(31~32頁)
■彼は真実を見たのである。薬が良ければ、病は治る。薬を調合した人が誰であるか、薬がどこからもたらされたかを知る必要はないのである。(40頁)
■信仰は、ものごとが見えていない――「見える」ということばのすべての意味において――場合に生じるものである。ものごとが見えた瞬間、信仰はなくなる。もし私が「私は掌の中に宝石を隠しもっている」と言ったら、あなたはそれが見えない以上、私が言ったことが本当かどうか、私のことばを信じるかどうか、という問題が生じる。しかし、私が掌を開き宝石を見せれば、あなたはそれを自分で見ることになり、信じるかどうかという問題は起こらない。それゆえに、古い経典には、こう記してある。
「掌の中の宝石(あるいはミロバラン〔訶梨勒、かりろく〕の果実)を見るように、真実を見よ」(41~42頁)
■ 訳注(10)
◯アラハント――欲望、憎しみ、悪意、無知、傲慢、うぬぼれといった汚れや不純さから解放された人。ニルヴァーナに至る第四段階すなわち最終段階に達した人で、叡智、慈悲といった高貴な資質に満ちたひと。〔訳注。漢訳仏典では阿羅漢〕ブックサーティは、アナガーミ(後戻りしない人)と呼ばれる第三段階に達した人であった。第二段階はサカダーガーミ(一度後戻りする人)、第一段階はソーターバンナ(修行の過程に入った人)と呼ばれる。(41頁)
■「汚れと不純さの消滅は、ものごとを知り、ものごとが見える人にとってのみ可能なことであり、ものごとを知らず、ものごとが見えない人には不可能である」
常に問題なのは、知ることと見ることであり、信じることではない。ブッダの教えは、「エーヒ・バッシカ」、すなわち「来て、見るように」という誘いであり、「来て、信じるように」ということではない。
経典のいたるところで、真理の実現は「汚れることなく、錆びることがないダルマの日が生じた」、「彼はダルマを見、ダルマに到達し、疑念を乗り超え、ためらうことがない」、「彼は正しい叡智でもって、ものごとをありのままに見る」などと表現されている。ブッダは自らの「目覚め」に関して、「目が生まれ、知識が生まれ、叡智が生まれ、知性が生まれた」と述べている。肝心なのは、知識あるいは叡智を通じて見ることであり、信心を通じて信じることではない。(42~43頁)
■「信仰のある人が、〈これは私の信仰です〉と述べる限りにおいて、彼は真実を保持している。しかし、そこから一歩進んで〈これのみが真実であり、他はすべて偽りである〉と断言することはできない。
言い換えれば、人は自分の好きなことを信じる権利があり、〈私はこう信じます〉と述べて差しさわりはない。その限りにおいて、彼は真実を尊重している。しかし自らの信仰から、自分が信じていることのみが真実で、他のすべては偽りであると主張することは許されない。
ある一つの見解に固執し、他の見解を見下すこと、賢者はそれを囚われと呼ぶ」(岡野注;全元論では当然)(45頁)
■「弟子たちよ、この見解は純粋で明晰である。しかしあなたたちがそれに固執し、思い入れ、尊び、拘(こだわ)るならば、教えは流れを渡るために乗る筏(いかだ)に似たものであり、保有するものではない、ということを理解していない」
教えは流れを渡るために必要な筏のようなものであり、保持して背中に負い運ぶものではない、というこの有名な譬えを、ブッダはいたるところで説明している。(46頁)
■弟子たちよ、私の教えは筏と同じである。それは、流れを渡るためのもので、持ち歩くためのものではない。あなたがたは、私の教えは筏に似たものであると理解したならば、よき教えすら棄てなければならない。ましてや悪しき教えを棄てるのは、言うまでもないことである」(47頁)
■ブッダは智的好奇心を満足させるために説いたのではない。ブッダは実践を教える師であり、人を平安と幸福に導く上で役立つ教えのみを説いた。(48頁)
■ブッダは、単なる推測にしか過ぎない想像上の不毛な形而上学的問題を論議する気はなかった。ブッダはそうしたテーマを「思想の荒野」と見なした。弟子の中には、ブッダのこうした態度を喜ばなかった者たちもいた。その一人であるマールンキャプッタ(岡野注:マールンクヤ)は、よく知られた古典的形而上学的問題に質問し、回答を求めた。
「ある日、午後の瞑想を終えてから、マールンキャプッタはブッダの許へ行き、師に挨拶をして、その傍に坐り尋ねた。
「師よ、私は瞑想中に、以下の疑問を抱きました。
⑴宇宙は永遠か、⑵否か、
⑶宇宙は有限か、⑷無限か、
⑸魂と肉体は同一か、⑹否か、
⑺ブッダは死後、存在するか、⑻否か、
⑼ブッダは死後、(同時に)存在もし、存在もしないか、
⑽それともブッダは死後、(同時に)存在もせず、存在しないことこともしないか。
◯訳注(12)
⑼、⑽は肯定・否定が同時に成立する、一般の論理上は有り得ない事であり、インド的な思弁法。(岡野注;アンティノミー)
しかしブッダは、私の疑問に答えて下さらず、なおざりにされます。私は、師の態度が意に満ちませんし、よいとは思いません。ブッダがこれらの問題を説明して下さるのなら、私は師の許で修行を続けます。説明していただけないのなら、私は別な師を求めて去ります。もし師が、宇宙は永遠である、とご存じなら、私にそう説明して下さい。もし師が、宇宙は永遠ではない、とご存じなら、私にそうおっしゃって下さい。もし師が、宇宙は永遠なのかそうでないのかをご存じないのなら、〈私は知らない、私にはわからない〉とはっきりとおっしゃって下さい」」
マールンキャプッタに対して、ブッダは以下のように答えたが、この答えは形而上学的問題を前に、貴重な時間を無駄に費やし、不必要に心の静逸を乱している何百万という現代人にとってきわめて有益である。
「マールンキャプッタよ、私は今までに「私の許で修行をしなさい。こうした問題を説明してあげよう」と言ったことがあるか」
「師よ、ありません」
「ではマールンキャプッタよ、そなたは今までに「ブッダよ、私は師の許で修行をします。師よ、こうした問題を説明して下さい」と言ったことがあるか」
「師よ、ありません」
「マールンキャプッタよ、今でも私は「私の許で修行をしなさい。こうした問題を説明してあげよう」とは言わない。そなたも「ブッダよ、私は師の許で修行をします。師よ、こうした問題を説明して下さい」と私には言っていない。だとすれば、誰が誰を拒否するのか。
マールンキャプッタよ、もし誰かが「私は、ブッダがこうした問題を説明して下さらなければ、ブッダの許で修行しません」と言うならば、彼は問題を説明してもらえずに死ぬことになるだろう」
毒矢の譬え
「マールンキャプッタよ、ここに毒矢に射られた一人の人がいるとしよう。そのとき、彼の友だちや親族が彼を医者の許に連れて行った。ところが彼が「私を射ったのは誰か? カーストは何で、どんな家系で、身長はどれくらいか? どんな弓と弦で射ったのか、矢羽根、矢尻はどんなものか? それがわからない間は、この矢を抜いてはならない」と言い張ったら、どうなるだろう。彼はその答えを得る前に死んでしまうだろう。
マールンキャプッタよ、それと同じく、もしある人が「私は、ブッダが宇宙は永遠か否か、といった問題を説明して下さるまでは、ブッダの許で修行しません」と言ったら、彼は問題の解決を得る前に死ぬであろう」
そこでブッダはマールンキャプッタに、そうした問題は修行とは無関係であることを説明した。
「宇宙が有限であるか無限であるかという問題にかかわらず、人生には病、老い、死、悲しみ、愁い、痛み、失望といった苦しみがある。私が教えているのは、この生におけるそうした苦しみの「消滅」である。
それゆえにマールンキャプッタよ、私が説明したことは説明されたこととして、説明しなかったことは説明されなかったこととして受け止めるがよい。
マールンキャプッタよ、私は、宇宙が有限か無限か、といった問題は説明しなかった。マールンキャプッタよ、私がなぜ説明しなかったのかというと、それは無益であり、修行に関わる本質的問題ではなく、人生における苦しみの消滅に繫がらないからである。それゆえに私は説明しなかったのである」
四聖諦
「ではマールンキャプッタよ、私は何を説明したのか。私は、
⑴ドゥッカの本質
⑵ドゥッカの生起
⑶ドゥッカの消滅
⑷ドゥッカの消滅に至る道
を説明した。マールンキャプッタよ、私がなぜ説明したのかというと、それは有益であり、修行に本質的に関わる問題であり、人生における苦しみの消滅に繫がるからである。私はそれゆえに説明したのである」(49~54頁)
第2章 第一聖諦 ドゥッカの本質
■四つの真理(四聖諦、ししょうたい)(55頁)
■四つの真理とは、
⑴ドゥッカの本質
⑵ドゥッカの生起
⑶ドゥッカの消滅
⑷ドゥッカの消滅に至る道
である。(55~56頁)
■ブッダは、人類の病いに対する賢明にして科学的な医者である。(57頁)
■確かに第一の真理のドゥッカには、普通の意味での苦しみも含まれているが、それに加えて不完全さ、無常、空しさ、実質のなさといったさらに深い意味がある。(58頁)
■同じく五部経典の一つである中部経典の一つのスッタ〔経〕では、瞑想の精神的幸せを賞賛したあと、ブッダは、
「それらは無常で、ドゥッカで、移ろうものである」
と述べている。ここで注意しなければならないのは、ことさらドゥッカという用語が使われていることである。普通の意味での苦しみがあるからドゥッカなのではなく、「無常なるものはすべてドゥッカである」からドゥッカなのである。(59頁)
■ドゥッカの三面
ドゥッカの概念は、
⑴普通の意味での苦しみ
⑵ものごとの移ろいによる苦しみ
⑶条件付けられた生起としての苦しみ
の三面から考察することができる。
老い、病い、死、嫌な人やものごとの出会い、愛しい人や楽しいこととの別れ、欲しい物が入手できないこと、悲痛、悲嘆、心痛といった、人生におけるあらゆる種類の苦しみは、普通の意味での苦しみである。
人生における幸福観、幸せな境遇は、永遠ではなく、永続しない。それらは、遅かれ早かれ移ろう。そしてものごとが移ろうときに、痛み、苦しみ、不幸が生じる。この浮き沈みは、移ろいによって生じる苦しみとしてドゥッカに含まれる。
以上の二種類の苦しみは容易に理解でき、誰にも異論がないだろう。第一の真理である「ドゥッカの本質」のこの点は容易に理解できるので、一般によく知られている。それは、誰しもが日常生活で体験することである。(62頁)
■「条件付けられた生起(2)」としての苦しみ
しかし、第三の「条件付けられた生起」としての苦しみという面こそが、「ドゥッカの本質」のもっとも重要な哲学的側面であり、それを理解するのには、一般に存在、個人あるいは「私」とされているものを分析してみる必要がある。
仏教的観点からすれば、私たちが一般に存在、個人あるいは「私」と見なしているものは、たえず移ろい変化する肉体的、精神的エネルギーの結合にしか過ぎず、それらは五集合要素から構成されている。そしてブッダは、
「これら執着の五集合要素はドゥッカである」
と述べている。また他の箇所では、「ドゥッカとは五集合要素はである」とはっきりと定義している。
「弟子たちよ、ドゥッカとは何か。それは執着の五集合要素はである」
ドゥッカと五集合要素は二つの異なるものでなく、五集合要素そのものがドゥッカである、とはっきり理解する必要がある。
◯訳注(2)
漢訳仏典では「縁起」。本訳書では、現在の日本語の縁起ということばに付随している概念を抜きに、著者の論考を明らかにするために、あえてこのことばを用いなかった。(63~64頁)
■意識は対象を認知しない、という点をはっきり理解せねばならない。それは、対象が存在するということに気付く、感知の一種に過ぎない。目が色――たとえば青――と接触すると、視覚意識が生じるが、それは単に色がそこに存在するということに気付くだけで、青であるとは認知しない。それが青であると認知するのは、識別作用(三番目の集合要素)である。「視覚意識」は、一般にいう「見る」ということを意味する哲学用語である。「見る」ことは、識別することではない。他(聴覚、嗅覚、味覚、触覚)の意識に関しても同様である。(68~69頁)
■ブッダは、意識は物質、感覚、識別、意志に依存しているのであって、それらから独立しては存在しえない、と明白に述べている。
「意識は、物質を手段とし、物質を対象とし、物質に依拠して生起し、喜びを求めて成長し、増大し、発展する。物質の代わりに、感覚、認識、意志に関しても同様である。
ある人が、「物質、感覚、識別、意志と無関係に、意識が生起し、去来し、成長し、増大し、発展するのをお見せしよう」と言ったとしたら、彼は何か実在しないもののことを語っているのである」(72頁)
■すべては移ろう
要するに、存在するのは五つの集合要素である。私たちが存在、個人あるいは「私」と呼んであるのは、この五つの集合要素の結合に対する便宜上の名称に過ぎない。それらはすべて無常であり、絶えず移ろうものである。「無常なものはすべてドゥッカである」というのが、「要するに、執着の五集合要素はドゥッカである」というブッダのことばの真意である。二つの連続する瞬間を通じて、同一であり続けるものは何一つとしてない。すべては、一瞬ごとに生起し、一瞬ごとに消滅し、流転を続けている。ブッダはラッタオア=ラにこう言っている。
「バラモンよ、それはあたかも、すべてを流し去り、遠くまで流れゆく山間の急流のようなものである。流れが止むことは、一瞬、一時、一秒たりともない。流れ続けるだけである。
バラモンよ、人の命はこの山間の流れのようなものである。世間は絶えず流動し、無常である(注6)」
因果律に従って、一つのものが消滅し、それが次のものの生起を条件付ける。その過程で、変わらないものは何一つとしてない。そのなかで、持続的「自己」、「個人」、あるいは「私」と呼べるようなものは存在しない。物質、感覚、識別、意志、意識の中で、一つとして本当に「私」と呼びうるものがないというのは、誰もが合意するであろう。ところが、相互に依存し合うこれら五つの肉体的、心的集合要素が、肉体的、心的機械として結合して機能するとき、「私」という概念が生まれる。しかし、それは間違った考えであり、四番目の集合要素の意志の項で言及した五二の意図的行為の一つに過ぎない。(72~74頁)
◯訳注(6)
ブッダは、この見解をアラカという名の、欲望から解放された古(いにしえ)の師に帰している。〔ギリシャの思想家〕ヘラクレイトス(紀元前五世紀)〔訳注。最新の研究では、紀元前540年頃ー480年頃とされる〕は、万物は流転すると考え、「人は同じ河に二度と入ることはできない。なぜなら、その水はたえず新しいから」という有名なことばを残しているが、両者を比較してみるのは興味深いことである(73頁)
■一般に「存在」と呼ばれる、この五つの集合要素の全体はドゥッカそのものである。ドゥッカを体験するするこれら五集合要素の背後には、「存在」も「私」もない。ブッダゴーサはこう述べている。
「苦しみは存在するが、苦しむ主体は存在しない。
行為は存在するが、行為主体は存在しない」
移ろいの背後には、自らは移ろうことがない移ろいの主体はいない。ただ単に移ろいがあるだけである。人生は移ろうというのは間違っていて、人生は移ろいそのものである。人生と移ろいは二つの異なったものではない。言い換えれば、思考の背後に思考者はいない。思考そのものが思考者である。仮に思考を取り除いてみても、その背後に思考者は見出せない。仏教的思考は、デカルトの「われ思う。ゆえにわれあり」という立場とはまっこうから対立するものであることがわかる。(74~75頁)
■生命には始まりも終わりもない
さてここで、生命には始まりがあるかどうかという問題を検討してみよう。ブッダの教えによれば、生きものの生命の始まりは考えられない。「神」による生命の創造を信じる人たちにとって、この考えは信じられないであろう。しかしもし「神の信者」に「神の始まりは何か?」と尋ねたら、彼はためらうことなく「神に始まりはない」と答え、自分の答えに驚きはしない。
ブッダはこう言っている。
「弟子たちよ、この輪廻の周期には目に見える終わりがない。そして、この無知に包まれ、渇望の足枷に束縛された彷徨も、いつから始まったのかわからない」
輪廻の最大の原因である無知に関して、ブッダはさらにこう述べている。
「無知の始まりは、この時点以前には無知はなかったというように理解されるものではない」
そうしてみると、この時点以前には生命はなかったということは不可能である。
突き詰めると、これがドゥッカと、これがの真理の意味である。この第一の真理を明確に理解することは、非常に大切である。なぜなら、ブッダが言っているように、
「ドゥッカ「を見るものは、ドゥッカの生起を見、ドゥッカの消滅を見、ドゥッカの消滅に至る道を見る」
からである。(74~76頁)
■仏教徒は幸せ
ここから言えることは、仏教徒にとっては人生はけっして憂鬱なものでも、悲痛なものでもない。ある人たちがそう思っているのは、誤解である。実際はその逆で、本当の仏教徒ほど幸せな存在はない。仏教徒には、恐れも不安もない。仏教徒は、ものごとをあるがままに見るがゆえに、どんなときでも穏やかで、安らかで、変化や災害によって動揺し、うろたえることがない。ブッダが、憂鬱、あるいは沈鬱だったことはけっしてない。同時代人も「ブッダはたえず微笑みを湛えていた」と伝えている。仏教絵画や彫刻でも、ブッダはいつも幸せで、静逸で、充足し、慈しみ深く表現されており、苦しみ、不安、苦痛の片鱗さえも窺えない(注10)。仏教芸術、建築、寺院には、陰鬱、悲嘆といった趣がなく、いつも平安で静逸な雰囲気が醸し出されている。
◯訳注(10)
ガンダーラおよび中国の福建でつくられた各々一体の仏像では、ゴータマは肋骨が露わになり憔悴した苦行者の姿をしている。これは、彼が「目覚め」に至る前に、激しい苦行を行っていたときのものであり、ブッダとなってからの彼はこうした苦行を弾劾した。
確かに人生には苦しみがあるが、仏教徒はそれに対して陰鬱になったり、立腹したり、いらだってはならない。仏教的観点からして、人生における主要な悪の一つは、嫌悪あるいは憎しみである。嫌悪は「他の生きものに対する悪意、苦しみおよび苦しみに対する邪な気持であり、不幸および悪事を生む原因になる」と定義されている。それゆえに、苦しみに対していらだつことは間違っている。苦しみに対していらだったり、立腹しても、苦しみはなくならない。その逆に、さらに問題をふやし、すでに不愉快な状況をいっそう深刻なものにし、悪化させる。必要なのは、怒ったりいらだったりすることではなく、苦しみという問題を正しく理解することである。苦しみがいかに生起し、それをいかにして取り除くかを見極め、心棒強く、賢く、決意をもって、努力することである。
初期の仏教経典に『テーラーガーター〔仏弟子の告白〕』と『テーリーガーター〔尼僧の告白〕』という二つの作品があるが、それらはブッダの教えによって人生に平安と幸福を見出した男性・女性の弟子たちによる、その喜びの表現をまとめたものである。コーサラ国王はかってブッダに向かって、他の教師の弟子たちが憔悴し、粗野で、血の気がなく、やせ細り、魅力がないのとは違い、ブッダの弟子たちは「楽しく元気で喜びに沸き、意気揚々として精神生活を喜び、健やかで、不安がなく、落ち着き、心安らかで、「鹿の心」で生きている、すなわち心軽やかである」と述べた。王はさらに、「こうした尊敬すべき弟子たちが心健やかにいるのは、必ずやブッダの偉大なる教えの精髄を理解したがゆえであると思う」と述べている。
仏教は、心が陰鬱で、沈痛で、後悔しているような重苦しい態度は真理の実現にとっての障害と見なし、その対極の立場を採る。仏教では、喜びはニルヴァーナの実現のために養育すべき必須な七つの資質、すなわち「目覚めの七要素」の一つと見なされているが、これはけっして偶然ではなく興味深い。(76~79頁)
第3章 第二聖諦 ドゥッカの生起
■それゆえに、渇望はドゥッカの生起の第一の、あるいは惟一の原因ではない。しかしそれはもっとも明白な直接的原因であり、主因あるいは支配的要因である。それゆえに、いくつかのパーリ語原典におけるドゥッカの生起の定義には、渇望が第一に挙げられているが、それ以外の汚れたもの、不浄なものも記されている。ここでは紙幅の制約から、この渇望は、主として無知から来る誤った自己の考えに起因していると述べるだけで十分である。(82頁)
■ここでいう渇望は、単に感覚的喜び、富、権力に対する欲望、あるいは執着を指すだけでなく、アイデア、考え、意見、理論、概念、信仰に対する欲望、あるいは執着を意味する。ブッダの分析によれば、この世における問題や係争は、家庭内の小さな個人的喧嘩から、国家間の大戦争に至るまで、すべては利己的な渇望から生じる。この観点からすれば、経済的、政治的、社会的問題はすべて、この利己的な渇望に根付いている。国際間の係争の解決や戦争と平和に関して、経済的、政治的な事柄だけを問題にする政治家は、表面的であり、問題の核心に深く踏み込めない。ブッダはラッタパーラにこう説いている。
「世界は物質に欠乏し、物質を欲しがり、渇望の奴隷と化している」(82~83頁)
■生存および生存の継続
生存および生存の継続には、原因あるいは条件という意味で四つの「栄養素」がある。
⑴普通の物質的な食べ物
⑵(心を含めた)感覚器官と外的世界との接触
⑶意識
⑷心的意図あるいは意志
である。
このうちの最後の心的意図が、生き、存在し、再存在し、継続し、増大しようとする意志である。それが、善悪の行為を行なうことにより、存在、継続の根源を生み出す。それが意図である。先に見たように、ブッダ自身『意図はカルマである」と定義している。今しがた触れた心的意図に関して、ブッダは「心的意図の栄養素を理解すれば、渇望の三つのかたちが理解できる」と述べている。こうして、渇望、意図、心的意図、カルマは同一のものを指している。それは、欲望であり、生存し、存在し、再存在し、増大し、一層蓄積しようという意志である。これが、ドゥッカの生起の原因であり、存在を構成する五集合要素の一つである意志のうちに含まれる。(83~84頁)
■それゆえに、ドゥッカの原因、芽は、ドゥッカ自身の中にあり、外にあるのではないということを、はっきりと、注意深く理解し、認識しなければならない。同様に、ドゥッカの消滅、破壊の原因、芽も同じくドゥッカのうちにあり、外にあるのではない、ということをよく認識する必要がある。これが「生起する性質のものは、消滅する性質のものである」という、有名なパーリ語定言の意味である。存在、ものごと、システムは、うちに生起の性質をもっていれば、同様にそのうちに消滅、破壊の原因、芽をもっている。こうしてドゥッカ(すなわち五集合要素)は、自らのうちに生起の性質をもっており、同じく自らのうちに消滅の性質をもっている。(84~85頁)
■カルマは、行為行ないを意味する。しかし仏教のカルマの理論では、カルマには特別の意味がある。それは、すべての行為を指すものではなく、意図的行為のみを指す。また多くの人は、カルマをその結果を意味することばとして用いているが、それは誤りである。仏教ではカルマは、けっしてその結果を意味しない。カルマの結果は、カルマの果実あるいは結実として〔カルマそのものとは区別して〕認識される。(85~86頁)
■私たちが生と呼ぶものは、繰り返し述べてきたように、肉体的、心的エネルギーのコンビネーション、五集合要素のコンビネーションである。これらは絶えず変化しており、連続する二つの瞬間において同一のままであることはない。毎瞬間、生まれ、死ぬ。
「弟子たちよ、集合要素が生起し、朽ち、死ぬとき、あなたがたは生まれ、朽ち、死ぬ」
こうして、この今の生においても、各瞬間ごとに私たちは生まれ死んでいるが、それでも私たちは継続する。自己とか魂といった永続的、不変的実体なしで、私たちが今この生を継続しているということが理解できたなら、こうした力が、身体の機能が停止したあとも、あとに残された自己や魂なしで継続できる、ということが理解できるだろう。(88頁)
■死後のエネルギーの継続
この肉体的身体が機能しなくなっても、それとともにエネルギーは死なない。それは何か別なかたち、姿をとって継続するが、それが再生と呼ばれる。子供の肉体的、心的、知的能力は幼くて弱いが、成人となる可能性を秘めている。存在を継続する肉体的、心的エネルギーは、自らのうちに新たなかたちをとり、次第に成長し、成熟する力を内在している。
永続的、不変的実体が存在しない以上、ある瞬間から次の瞬間に継続するものは何もない。それゆえに、ある生から次の生へと生まれまわる永続的、不変的なものは何もないことは明らかかである。途切れなく継続するのは連鎖であるが、それは一瞬一瞬変化する。連鎖とは、実際のところ運動に他ならない。それは夜通し燃え続ける炎のようなものである。それは、夜を通して同じものでもなく、また別なものでもない。子供は六〇歳にまで成長する。六〇歳の大人は、六〇年前の子供と同じではないが、かといって別人でもない。同様に、ここで死に、別なところに生まれかわった人の場合、同一人でもなければ、別人でもない。それは、同じ連鎖の継続である。死と生の区別は、思考瞬間の違いだけである。この生の最後の思考瞬間が、いわゆる次の生の最初の思考瞬間を条件付ける。この生においても、ある思考瞬間が次の思考瞬間を条件付ける。それゆえに、仏教的観点からすれば、死後の生は、神秘でもなんでもない。仏教徒はこの問題にけっして煩わされることがない。
この存在しよう、生成しようという渇望がある限り、継続の輪(すなわち輪廻)は続く、それが止むのは、現実、真理、ニルヴァーナを見る叡智によって、その原動力である渇望が断たれるときである。((89~90頁)
第4章 第三聖諦 ドゥッカの消滅
■第三の聖諦は、ドゥッカの継続から解放され、自由になることができる、という真理である。これは「ドゥッカの消滅すなわちニルヴァーナの真理」として知られる。
ドゥッカを完全に消滅させるには、その主な根源――すなわち、先に見られたように渇望――を消滅させねばならない。それゆえに、ニルヴァーナはまた「渇望の消滅」とも呼ばれる。(91頁)
■「それは、かの渇望の完全な消滅である。それを諦め、放棄し、それから解放され、それに囚われないことである」
「あらゆる条件付けられたものの沈静、あらゆる不浄の放棄、渇望の消滅、無執着、停止、ニルヴァーナ」
「ビックたちよ、絶対とは何か。ビックたちよ、それは欲望の消滅、憎しみの消滅、幻惑の消滅である。ビックよ、これが絶対と呼ばれるものである」
「ラーダよ、渇望の消滅がニルヴァーナである」
「ビックたちよ、条件付けられたものであれ、条件付けられていないものであれ、すべてのなかで最高なのは、無執著である。すなわち、うぬぼれからの自由、渇望の破壊、執着の根絶、継続の切断、渇望の消滅、無執著、停止、それがである」
ある修行者からの「ニルヴァーナとは何か」という単刀直入な質問に対し、ブッダの一番弟子であるシャーリプトラは、先に見た絶対に関するブッダの答えと同じく「欲望の消滅、憎しみの消滅、幻惑の消滅である」と答えている。(94頁)
■このように、ニルヴァーナは否定的なことばで表現されるので、多くの人はは否定的なものであり、自己否定だと誤解している。しかし、そもそも否定すべき自己そのものがないのであるから、はけっして自己否定ではない。否定すべきものがあるとすれば、それは自己に関する誤った概念、幻覚である。
ニルヴァーナが肯定的であるとか、否定的であるとか言うのは正しくない。肯定的、否定的というのは相対的なものであり、二元論の世界での話である。こうした用語は、二元論、相対性を超えたニルヴァーナ、絶対真理には適用できない。(96頁)
■自由が否定的だと言う者は、一人もいないだろう。しかし自由にも否定的側面がある。自由はたえず何か邪魔なもの、悪魔的なもの、否定的なものからの解放である。しかし自由は否定的ではない。それゆえに、ニルヴァーナ、絶対自由を意味するムッティあるいはヴィムッティは、悪からの自由であり、渇望、憎しみ、無知からの自由、二元性、相対性、時間、空間からの自由である。(97頁)
■他の箇所では、ブッダはニルヴァーナの代りにまぎれもなく真理ということばを用いている。
「私はあなたたちに真理および真理に至る道を教えよう」
この場合、真理とは確実にニルヴァーナを指している(岡野注;真・善・美、全存在)。
では、絶対真理とは何か? 仏教でいう絶対真理とは、世界には絶対的なものはなく、変わることなく、永続する絶対的な自己、魂、あるいはアートマンといったものは内にも外にもない、ということである。これが絶対真理である。否定的真理といった一般的表現があるが、真理はけっして否定的ではない。ものごとをあるがままに見る、というこの真理は、渇望の消滅であり、ドゥッカの消滅であり、ニルヴァーナである。(99~100頁)
■ニルヴァーナは結果ではない
渇望の消滅の自然な結果がニルヴァーナだと考えるのは間違っている。ニルヴァーナは、何かの消滅の結果ではない。もし結果であるとすれば、何らかの原因によって生み出されたものである。そうならば、それは「創造されたもの」であり「条件付けられたもの」である。ニルヴァーナは原因でも結果でもなく、それを超えたものである。真理は原因でも結果でもない。それは、瞑想のような創造された神秘的、精神的、心的な状態ではない。真実は実在し、ニルヴァーナは実在する。人ができる惟一のことは、それを見、それを体現することである。ニルヴァーナの達成に至る道がある。しかし、ニルヴァーナはこの道の結果ではない。道を辿って山頂にたどり着けるが、山頂は道の結果ではない。光を見ることはできるが、光は視覚の結果ではない。(100~101頁)
■ニルヴァーナの先には何もない
しばしば、こう質問される。ニルヴァーナの先には何があるのか? この質問はありえない。というのはニルヴァーナは究極真理だから。究極である以上、その先には何もない。もしの先になにかがあるとすれば、ニルヴァーナは究極真理ではない。ラーダという弟子が、別なかたちでブッダに質問した。「な何のためのものですか?」この質問は、ニルヴァーナの目的を問題にしている以上、ニルヴァーナの先に何かがあることを前提にしている。それゆえにブッダはこう答えた。「ラーダよ、この質問は的外れである。人は聖なる生を、ニルヴァーナを最終ゴール、目標、究極終着点として生きる」(101~102頁)
■ニルヴァーナは死ではない
一般に「ブッダは死後(あるいはパリニルヴァーナ)に入った」といわれるが、それは誤りである。しかしこの誤りから、ニルヴァーナに関して多くの想像的な推測がなされるようになった。「ブッダはニルヴァーナ(あるいはパリニルヴァーナ)に入った」という表現を耳にすると、ニルヴァーナは一般的存在の一つの形態と理解される。一般的に「ニルヴァーナに入る」といわれるが、この表現は原典には見当たらない。「死後ニルヴァーナに入る」ということはない。パリニルヴァーナということばは、ブッダあるいはニルヴァーナを体現したアラハントの死を指すが、「ニルヴァーナに入る」という意味ではない。パリニルヴァーナは、文字通りには「完全に逝った」「完全に消された」「完全に消滅した」を意味するが、それはブッダあるいはアラハントは死後存在することがないからである。(102~103頁)
■死後のアラハントは、薪がなくなった火、芯と油がなくなった炎に譬えられる。ここではっきりとさせておかねばならないのは、火あるいは炎に譬えられるのは、ニルヴァーナではなく、ニルヴァーナを体現した、五集合要素から構成された存在(アラハント)である。このことは強調しておかねばならない。なぜなら、多くの人たち――大学者でも――は、この譬えを誤ってニルヴァーナに当てはめているからである。ニルヴァーナは、けっして消えた火、あるいは炎に譬えられることはない。(104頁)
■ニルヴァーナを体現する主体
それゆえに、生起の芽も、消滅の芽も、共に五集合要素のうちに含まれている。「この背丈大の身体に、世界、世界の生起、世界の消滅、世界の消滅に至る道のすべてがある」というブッダの有名なことばの真意はこれである。ということは、四聖諦のすべては五集合要素、すなわち私たちの内にある、ということである。(105頁)
■ニルヴァーナは今の生で体現するもの
ほとんどのすべての宗教においては、最高善は死後にしか到達できない。しかしかこの今の生で実現することができ、到達するのに死を待つ必要はない。
真実、ニルヴァーナを体現した人は、世界でもっとも幸せな人である。その人は、他の人たちを悩ませている、あらゆる煩わしさ、強迫観念、心配、問題から解放される。彼は心的に完全に健康である。過去を悔やまず、未来を思い悩まない。彼は、今というときを全力で生きる。それゆえに、彼は肩肘張ることなく、もっとも純粋な意味でものごとを味わい、享受する。彼は喜びに溢れ、意気揚々とし、純粋な生を楽しみ、五感は心地よく、不安がなく、晴朗で安らかである。あらゆる利己的な欲望、憎しみ、無知、うぬぼれ、奢り、汚れから解放され、純粋で、やさしく、博愛、慈しみ、正直さ、同情、理解、寛容に富んでいる。彼は自己という概念をもっていないので、他人への奉仕はまさに純粋である。彼は自己という幻想、生成の渇望から解放されているがゆえに、精神的なことも含め、何一つ得ないし、集積しない。(106頁)
■ニルヴァーナは、二元論、相対的なことばを超えたものである。私たちの一般的な善悪、正邪、存在と非存在という概念を超えている。(107頁)
■シャーリプトラが言った。「友よ!ニルヴァーナは幸せなり、ニルヴァーナは幸せなり」
ウダーイが尋ねた。「友シャーリプトラよ、感覚がないのなら、幸せとはどんなものですか」
この問いに対するシャーリプトラの答えは、非常に哲学的で、普通の理解領域を超えている。
「感覚がないということ自体が幸せである」(107頁)
■ニルヴァーナは「賢者が自らの内に体現すべきものである」。もし私たちが、八正道を根気よく熱心に歩み、自らを修練し、浄化し、必要な精神的発展を遂げれば、高尚な、わけのわからないことばを操ることなく、ある日ニルヴァーナを内に体現できるであろう。(107~108頁)
第5章 第四聖諦 ドゥッカの消滅に至る道
■第四の聖諦は、「ドゥッカの消滅に至る道」であるが、このこの道は二つの極端な道を避けるがゆえに、「中道」と呼ばれる。二つの極端な道の一方は、感覚的な快楽を通じて幸福を求める道で、それは「低俗で、通俗的で、無益な、凡人の道」である。もう一方は、さまざまな禁欲的行為によって自らを苦しめることにより幸福を求める道で、「苦痛を伴い、無価値で、無益である」。自らこの二つの極端な道を経験し、それらがともに無益であることを理解した上で、ブッダは自らの経験から静逸、洞察、目覚め、ニルヴァーナに至る「中道」を見出した。(109頁)
■八正道
それは八項目から構成されているので、一般的に「八正道」と呼ばれる。すなわち、
⑴正しい理解
⑵正しい思考
⑶正しいことば
⑷正しい行ない
⑸正しい生活
⑹正しい努力
⑺正しい注意
⑻正しい精神統一
ブッダが四五年間にわたって説いた教えは、実質的にはこの八正道に凝縮される。ブッダは、弟子の発展段階、理解能力、実践能力に応じて、さまざまな場所で、さまざまなかたちでこれを説明した。ブッダの何千という教えのエッセンスは、この八正道に集約されている。(109~110頁)
■この八項目(正道)は、右に列挙した順に一つずつ実践していくものと思ってはならない。それらは、各人の能力に応じて、すべてを同時に実践しなくてはならない。八つは各々繫がっており、一つの実践が他の実践に役立つ。(110頁)
■これらの八項目は、仏教的修練と規律における三つの基本を増進し完成することを目的としている。三つとは、
•倫理的行動
•心的規律
•叡智(岡野注;貪・瞋・癡の対極)
である。それゆえに、これら八項目は三つの部類に分けて考察するのが妥当である。(110~111頁)
■倫理的行動
「正しいことば」とは、①嘘をつかない、②人びとや集団の間に憎悪や敵意、不一致や不調和をもたらすような蔭口、中傷、噂話を慎む、③荒々しく、粗暴で、無作法なことばや悪意を含むことば、罵(ののし)りのことばを慎む、そして④無用で役にたたない馬鹿げたおしゃべりや雑談をやめることである。
これらの誤った有害なことばをやめると、人は自然に真実をかたり、友好的で慈悲深いことば、快く優しいことば、そして意味深い、役に立つことばを使うようになる。軽率に話してはならず、発言は正しいときと場を心得たものでなければならない。もし、何か有益なことが言えない場合は「尊い沈黙」を守るべきである。(112頁)
■「正しい行ない」とは、道徳的で、尊敬に値し、安らかな行動を促進することを指す。命を傷つけたり、盗みを働いたり、不誠実であったり、邪(よこしま)な性的関係をもったりすることを慎むと同時に、他の人たちが正しく、安らかで、尊敬に値する生活を送るのを助けなくてはならない。(113頁)
■「正しい生活」とは、武器や兵器、酒、毒物の取引、屠殺、詐欺といった、他者を害することで生計を立てることを慎み、他者を傷つけることがなく、他者から批難されることがなく、尊敬される職業に就くことである。仏教は、武器や兵器の取引は邪悪で正しくない生計であると見なしていることから、仏教はいかなるかたちの戦争にも強く反対していることが明らかである。(113頁)
■八正道のこの三つの項目(「正しいことば」「正しい行ない」「正しい生活」)が倫理的行動を形成する。仏教の倫理的、道徳的行動は、個人および社会にとっての幸せで調和のとれた生活を促進することを目的としている。道徳的行動は、すべての高度な精神的達成にとって不可欠な基礎と見なされている。この道徳的基盤をなくして、いかなる精神的発達も不可欠である。(113頁)
■心的規律
次の「心的規律」には、八正道のうちの三つの項目が含まれる。すなわち、正しい努力、正しい注意、そして正しい精神統一である。
「正しい努力」とは、①邪で不健全な気持が起きるのを防ぎ、②すでに起きた邪で不健全な気持を取り除き、③正しく健全な心を起こし、④すでに起きた正しく健全な心を完成に導くことである。
「正しい注意」とは、①身体の活動、②感覚や感じ、③心の動き、④考え、思考、概念とものごとに関しては、はっきり意識し、気を遣い、注意することである。
身体に関しては、呼吸に注意することは精神的発達のためのよく知られた訓練の一つである。同じく身体に関連した事柄では、瞑想など他にも精神的発達を促す方法がある。(114頁)
■心的規律の三番目で最後の項目が、一般にトランスあるいは瞑想と訳されるジャーナ(注)で、四段階の「正しい精神統一」である。
◯訳注
漢訳仏典では「禅那」と音写され、現在日本語で、一般に用いられている「禅」の訳語。(115頁)
■ジャーナの第一段階では、感覚的欲望、悪意、物憂さ、不安、落ち着きのなさ、猜疑心といった情欲と不健全な考えが取り除かれ、ある種の心的活動に際して喜びと幸せの感情が伴う。
第二段階では、すべての知的活動は抑圧され、平静と心の「一点集中」状態が発達し、喜びと幸せの感情が保たれる。
第三段階では、アクティブな感覚である喜びの感情はなくなり、幸せの感情は残り、心の平静が加わる。
第四段階では、幸・不幸・喜び・悲しみといったすべての感覚がなくなり、ただ純粋な、平静と自覚だけが残る。
こうして、正しい努力、正しい注意、正しい精神統一によって心は訓練され、律せられ、啓発される。(115~116頁)
■叡智
残りの二つの項目、すなはち正しい理解と正しい思考が「叡智」を構成する。
「正しい思考」とは、すべての生きものに対する無私無欲な放棄あるいは無執着、愛の思い、非暴力の思いである。この無私無欲な無執着、愛、非暴力が叡智と併記されるのは興味深く重要である。このことからはっきりわかるのは、叡智にはこうした高貴な要素が具わっているということである。個人的であれ、社会的、政治的であれ、人生における利己主義的な欲望、悪意、憎しみ、暴力といった考えは、叡智に欠けていることの結果に他ならない。(116~117頁)
■仏教では、二種類の理解がある。私たちが一般に理解と呼んでいるのは、知識、すなわちある種のデータに基づいた、ある事柄の知的把握である。これは、「ものごとに准じた知識」と呼ばれるが、深いものではない。本当の深い理解は「透視」と呼ばれ、ものごとの本質を、名前や名称なしで見抜くことである。この「透視」は、心に一切の汚れがなくなり、心が瞑想によって完全に啓発されたときに初めて可能である。(117頁)
■以上ざっと見てきたところからわかるように、八正道とは、一人ひとりが、自らの人生において、歩み、実践し、開発する道である。それは、身口意の自己規律であり、自己啓発であり、自己浄化である。それは、信仰、崇拝、儀礼とは無関係である。この意味において、それは一般的に「宗教的」といわれるものとは無縁である。それは道徳的、精神的、知的完成を通じての究極の実存、完全な自由、幸せ、平和に至る道である。
■まとめ
四聖諦に関連して、われわれがなすべきことは以下のとおりである。
第一聖諦はドゥッカの本質で、人生の本質は苦しみ、悲しみ、楽しさ、不完全さ、不本意さ、無常さである、ということである。これに関連してわれわれがすべきことは、それを事実として明瞭に、完全に理解することである。
第二聖諦はドゥッカの生起である。すなわちもろもろの欲情、汚れ、不純さを伴った渇望、欲望の生起である。このことをただ理解するだけでは不十分であり、われわれがすべきことは、この渇望を退け、除き、破壊し、根絶することである。
第三聖諦はドゥッカの消滅、すなわちニルヴァーナ、絶対真理、究極実存である。われわれがすべきことは、それを体現することである。
第四聖諦はドゥッカの消滅に至る道、すなわちニルヴァーナの実現に至る道である。どれだけ完璧にこの道を知ろうと、単なる知識では不十分である。この場合われわれがすべきことは、それを辿り、歩むことである。(118~119頁)
第六章 無 我(アナッタ)
■我の概念の否定
この魂、自己、アートマンの 存在を否定するという点で、仏教は人類の思想史の中でユニークである。ブッダの教えによれば、自己という概念は実体に該当しない想像上の誤った考えである。それは、「私」、「私の物」、利己主義的欲望、渇望、執着、憎しみ、悪意、うぬぼれ、傲慢、エゴイズム、不純さ、その他、さまざまな問題を生み出す、それは、個人的いざこざから国家間の戦争に至るまで、世界のあらゆる問題の源である。突き詰めていえば、世界における諸悪の根源はこの誤った考えに辿り着く。(122頁)
■ブッダには、このことがよくわかっていた。彼は、自分の教えは「世の潮流に逆らう」、人間の利己主義的な欲望に逆らうものだと言っている。「目覚め」の四週間後、菩提樹の下に坐って、ブッダはこうつぶやいた。
「私が体現したこの真実は、見がたく、理解しがたく、賢者にしか把握されない。潮流に逆らい、高遠で、深く、微妙で、難解なこの真理は、欲情に打ち負かされ、闇に包まれた者たちにには見えない」(123頁)
■「条件付けられた生起」
アートマンのことを論じる前に、「条件付けられた生起」に関して見てみることが有益である。この教えの要点は、次の四行詩で明らかである。
「これが存在するとき、あれが存在する。
これが生起するとき、あれが生起する。
これが存在しないとき、あれが存在しない。
これが消滅するとき、あれが消滅する」(124~125頁)
■十二項目〔因縁〕
この条件性、相対性、相互依存性の原理に基づいて、すべての生の存在、継続そして消滅が、十二項目からなる「Aを条件として、Bが生起する」という定式によって説明される。
⑴無知を条件として、意図的行為あるいはカルマが生起する。
⑵意図的行為あるいはカルマ条件として、意識が生起する。
⑷精神的、肉体的現象を条件として、六器官が生起する。
⑸六器官を条件として、接触が生起する。
⑹接触条件として、感知が生起する。
⑺感知を条件として、渇望が生起する。
⑻渇望を条件として、執着が生起する。
⑼執着を条件として、生成が生起する。
⑽生成を条件として、誕生が生起する。
⑾誕生を条件として、⑿老い、死、悲嘆、痛みなどが生起する。
こうして生が生起し、存在し、継続する。
これを逆の順序でたどれば、消滅の過程となる。無知の完全な消滅から、意図的行為あるいはカルマが消滅し、意図的行為あるいはカルマの消滅から、意識が消滅し、……、誕生の消滅から、老い、死、悲嘆、痛みなどが消滅する。
はっきりと理解しなくてはならないのは、これらの一つひとつの要素は、〔他を〕条件付けると同時に、〔他により〕条件付けられているという点である。それゆえに、すべては相対的であり、相互に関連しており、何一つとして絶対ではなく、独立していない。それゆえに、先に述べたように、仏教では何かが絶対的主因であるとは見なさない。条件生起は、〔完結する閉じた〕輪と見なすべきであり、〔完結しない単なる〕連鎖とみなすべきではない(注)。
◯注
紙幅の制約から、この最も重要な教義をここでは精細に論じられない。仏教哲学に関する別の本でこのテーマに関する批判的比較研究を行なう予定である。〔訳注。この本は、訳者の知る限り刊行されていない〕〔岡野注;存在の中に、完結する閉じた輪の存在を認めるならば、禅宗の空の理論とは矛盾する。特異点があることになる。弦理論や数字、素数の存在とも関係ありそうだ〕(125~126頁)
■自由意志も条件付けられている
西洋思想・哲学では、自由意志の問題が重要な位置を占めてきた。しかし「条件付けられた生起」を現則とする仏教では、この問題は存在しないし、存在しようがない。すべてが相対的で、条件付けられて、相互依存してる以上、どうして意志だけが自由でありえようか。他のあらゆる思いと同じく、意志も条件付けられている。いわゆる「自由」自体も条件付けられており、相対的である。条件付けられてなかで相対的〔傍点は訳者による。次も同じ〕に自由な意志は否定されないが、すべてが相互依存的であり、相対的である以上、絶対的に自由なものは、肉体的なものであれ、心的なものであれ、何も散在しない。もしも自由意志を条件から、あるいは因果律から独立したものとするなら、そのようなものは存在しない。すべての存在が、条件付けられ、相対的であり、因果律に律せられている以上、意志が、あるいは別の何かが、条件なしに、因果律から独立して生起することはありえない。ここでまたしても、自由意志とという概念は、神、魂、正義、報賞、罰則という概念と結びついている。いわゆる自由意志そのものばかりか、自由意志という考え自体が、条件から解放されたものではない。
「条件付けられた生起」の理論、および存在の五集合要素の分析から、人間の内あるいは外に、アートマン、「我」、魂、自己、あるいはエゴといった不変、不死なるものを想定するのは、誤っており、単なる心的投射に過ぎない。これが、仏教のアナッタ、無魂、無我の教理である。(127~128頁)
■アートマン
―前略ー
人びとは、アートマンに関するブッダの教えによって、彼らが想像していた自己が破壊されることになると思い、神経質になった。ブッダにはそれがわかっていた。
あるとき弟子が尋ねた。
「師よ! 内なる永遠のものが見つからないとき、人は苛(さいな)まれるということがありますか?」
「弟子よ、それはある。ある人がこう考えたとしよう。
「宇宙はかのアートマンであり、私は死後、永遠で、不変で、永続的で、不易なそれとなろう。そして私は永遠にそのようにあろう」
その彼が、ブッダあるいはその弟子が、渇望の消滅を目指して、また執着を離れたを目指して、〔自分の〕推測的な見解を完全に打破する教えを説くのを聞いたとしよう。彼は、
「私は無に帰される。私は破壊される。もはや私は存在しない」
と思うだろう。そして彼は嘆き、心配し、泣き、胸を叩き、打ちのめされるだろう。こうして、内なる永遠のものが見つからないと、人はさいなまれることがある」
また他の箇所で、ブッダはこういっている。
「弟子たちよ、私は存在しないかもしれない、私は所有しないかもしれない、と思うと、一般の人は恐怖心に襲われる」(130~131頁)
■第一に、ブッダは、人間の内であれ外であれ、あるいは宇宙のどこであれ、アートマン、魂、エゴの存在については断固として、明瞭に、一度ならず否定している。いくつかの例を検証してみよう。(132頁)
■最初の二句は、
「条件付けられたものはすべて無常である」
「条件付けられたものはすべてドゥッカである」
第三の句は、
「すべてのものごと(ダルマ)は、無我である」
ここで注意しなくてはならないのは、最初の二句では「条件付けられたもの」ということばが用いられ、第三句では、その代わりに「ものごと(ダルマ)」ということばが使われていることである。どうして第三句では、最初の二句と同じように、「条件付けられたもの」ということばがもちいられずに、その代わりに、「ものごと」ということばが使われているのだろうか。すべての鍵はここにある。
「条件付けられたもの」ということばは、物質的であれ心的であれ、すべて条件付けられ、相互依存し、相対的な五集合要素およびその状態のすべてを指す。第三句が「すべての条件付けられたものは、無我である」であったなら、人は、条件つけられたものは無我であるが、条件つけられていないもの、すなわち五集合要素以外のものには我がある、と思うであろう。こうした誤解が生じないために、第三句では「ものごと」ということばが用いられているのである。
仏教用語としての「ものごと」ということばは、「条件付けられたもの」ということばよりもずっと広い意味をもっている。「ものごと」は、ただ単に条件付けられたものとその状態を指すだけはでなく、絶対とかニルヴァーナといった条件つけられていないものをも含む。宇宙の内であれ外であれ、善悪を問わず、条件付けられている・いないを問わず、相対的・絶対的を問わず、このことばにふくまれないものは何もない、それゆえに、「すべてのものごと(ダルマ)は、無我である」という句によれば、五集合要素の内に限らず、その外であれ、どこであれ、自己はなく、アートマンはない、ということは明らかである。(132~134頁)
■中部経典の「アラガッドゥパナ・スッタ」の中で、ブッダは弟子たちにこう言っている。
「弟子たちよ! 嘆き、悲しみ、心痛、辛苦のない魂理論があれば、それを受け入れよ。しかし弟子たちよ、嘆き、悲しみ、心痛、辛苦のない魂理論が、どこにあるのか?」
「師よ、どこにも見当たりません」
「弟子たちよ、その通りである、私自身も、嘆き、悲しみ、苦しみ、心痛、辛苦のない魂理論は、どこにも見出せない」
もしブッダが受け入れた魂理論があったのなら、ブッダはここでそれを説明したであろう。なぜなら、ブッダは弟子たちに、苦しみを生起しない魂理論を受け入れるようにと言っているのだから。しかしブッダからすれば、そんな魂理論はなく、いかに緻密で優れたものであれ、すべての魂理論は誤っており、想像的なものにしか過ぎず、嘆き、悲しみ、苦しみ、心痛、辛苦を生起するものである。
同じ経の中で、ブッダは続けてこうも言っている。
「弟子たちよ、自己も、自己に関連する何ものも本当の意味で、実際に見出せないなら、「宇宙はかのアートマン(魂)であり、私は死後、永遠で、不変で、永続的で、不易なそれとなろう。そして私は永遠にそのようにあろう」という考えは、完全に、完璧に愚かではなかろうか?」
ここでブッダは、アートマン、魂、自己は、実際にはどこにも見当たらず、そんなものがあると信じることは愚かしい、とはっきり断定している。(134~135頁)
■アートマンに関する誤解(一)
ブッダの教えの中に自己を見出そうとする人たちは、いくつかのことばを引用するが、実際にはそれらを誤解し、語訳している。その一つが『ダンマパダ』の「アッター・ヒ・アッタノ・ナート」という有明な一句である。それは、「自己は、自分の主である」という句で、偉大なる「自己」は、小さな「自分」の主であると解釈される。
まず、この解釈は間違っている。「アッター」は、魂の意味での自己を意味しない。パーリ語のアッターは、ことに哲学的に魂理論に言及する限られた場合を除き、一般的には再帰代名詞、あるいは不定代名詞である。『ダンマパダ』のこの句の場合もそうで、「自分自身」「あなた自身」「彼自身」「人」「人自身」を指す。
次に、「ナート」は「主」ではなく、「避難所」「よりどころ」「支援」の意味である。それゆえに「アッター・ヒ・アッタノ・ナート」は、「自分自身が、自分のよりどころである」あるいは「自分自身が、自分の避難所である」という意味である。この句は、形而上学的魂あるいは自己とは何の関係もない。意味するところは単に、他人ではなく、自分自身を頼りにしなくてはならない、ということである。(135~136頁)
■アートマンに関する誤解(二)
ブッダの教えに自己の考えを導入しようとしてよく引用されるもう一つの句は、『マハーパリニッパーナ・スッタ〔大般涅槃経〕』中の有名な「アッタディーバ・ヴィハラタ・アッタサラナー・アナッニャサラナー」である。この句は、「自分自身をよりどころとし、自分自身を避難所とし、他の誰をも避難所とすることなかれ」という意味である。仏教の中に自己という概念を導入しようとする人たちは、この句のアッタディーバとアッタサラナーを、「自己をよりどころとみなす」「自己を避難所と見なす」と解釈している。この句は、ブッダがアーナンダに授けた助言であるが、その背景を理解しない限り、その本当の意味は完全にはわからない。
ブッダはこのときベルヴァという村に滞在していた。死の三カ月前のことであった。ブッダは八〇歳で、重い病いに苦しんでおり、瀕死状態であった。しかしブッダは、親しい弟子たちに別れを告げずに死ぬことはできないと思った。それで勇気と決断をもって痛みをこらえ、病気を克服し、立ち上がった。しかし、体は弱っていた。回復してから、ある日住いの外の木陰に坐っていた。もっとも親しかった弟子のアーナンダがブッダの近くに行き、傍らに坐って言った。
「師よ、私は師の健康を管理し、看病してきました。しかし、師の病いを見るにつけ、世が暗くなり、気分がふさぎます。しかし、一つ気が安らぐことがあります。師はサンガに関する指示を与えないではお亡くなりにならないでしょう」
そこでブッダは、慈悲からそして人情から、もっとも愛しい弟子であるアーナンダに語った。
「サンガは私に何を望むことがあるのか。私は、内外のいかなる区別をすることもなく真理を教えた。教師としてブッダは掌のうちに隠すことは何一つない。「私がサンガを導き、サンガは私の指導を仰がねばならない」と思うものがいたら、彼に彼自身の指示を記させよ。ブッダにはそうした意図はない。それゆえに、どうしてサンガに関する指示を残す必要があろうか。アーナンダよ、私は年老いて、齢八〇である。使い古された車が修理によって動き続けるように、ブッダの身体は修理によって動き続ける。それゆえに、アーナンダよ、
自分自身をよりどころとし、
自分自身を避難所とし、
他の誰をも避難所とすることなかれ
ダルマをよりどころとし、
ダルマを避難所とし、
他の何ものをも避難所とすることなかれ」
ブッダがアーナンダに伝えようとしたことはきわめて明らかである。アーナンダは悲しくて、気落ちしていた。アーナンダは、偉大な師が亡くなったあとは、彼らは全員避難所もなく、師もなく、ひとりぼっちで、途方に暮れると思っていた。そこでブッダは、彼を慰め、勇気づけ、自信をもたせるために、自分自身とブッダの教えを頼りとし、他の誰にも、他の何ものにも頼ってはいけないと言った。この文脈に、形而上学的アートマンを見出すのはまったく場違いである。
さらにブッダはアーナンダに、身体、感覚、心、心の対象に対する正しい思いによって、いかにして自分自身をよりどころあるいは避難所とし、ダルマをよりどころあるいは避難所とするかを説明した。ここではアートマンあるいは自己は一切話題となっていない。(136~139頁)
■アートマンに関する誤解(三)
ブッダの教えの中にアートマンを見出そうとする人たちがよく引用するのが次のレファレンスである。あるときブッダはベナレスからウルヴェーラーに向かう途中の森の中で一本の木の下にいた、その日、三〇人の若い王子たちが若い妃たちを伴って、その森にピクニックに出かけた。そのうちの一人の王子は未婚だったので、娼婦を伴っていた。皆が浮かれている間に、娼婦はいくつかの貴重品を盗み、いなくなった。彼らは森の中で女を捜し回っている間に、木の下に坐っているブッダに出くわしたので、女を見なかったかと訊ねた。ブッダは何が起きたのかと訊ねた。彼らが説明すると、ブッダは言った。「若者たちよ、どう思うか?女を捜すのと、自分を捜すのと、どちらが大切か?」
これも単純で自然な質問であり、ここに形而上学的なアートマンとか自己といったアイデアを導入する正当性はない。若者たちは、自分を探す方が大切であると答えた。
これも単純で自然な質問であり、ここに形而上学的なアートマンとか自己といったアイデアを導入する正当性はない。若者たちは、自分を捜す方が大切であると答えた。そこでブッダは彼らに坐るように促し、ダルマを説明した。知られている原典では、アートマンには一言も触れられていない。(139~140頁)
■ブッダの沈黙
修行者ヴァッチャゴッタに、アートマンは存在するか否かを尋ねたときの、ブッダの沈黙に関して、今までさまざまに論議されてきた。その話は、次のとおりである。
ヴァッチャゴッタがブッダの許にやってきて訊ねた。
「師ゴータマよ、アートマンは存在しますか?」
ブッダは黙していた。
「では、師ゴータマよ、アートマンは存在しないのですか?」
またしてもブッダは黙していた。
ヴァッチャゴッタは立ち上がって、去っていった。
修行者が去ったあと、アーナンダがブッダにどうしてヴァッチャゴッタの質問に答えなかったのかと尋ねた。ブッダは自分の立場をこう説明した。
「アーナンダよ、ヴァッチャゴッタは「自己は存在しますか?」と尋ねた。もし私が「自己は存在する」と答えたなら、私は永遠主義のバラモンの側についたことになる。
またアーナンダよ、ヴァッチャゴッタが「自己は存在しないのですか?」と尋ねたとき、もし私が「自己は存在しない?」と答えたなら、私は虚無主義の修行者やバラモンの側についたことになる。
またアーナンダよ、ヴァッチャゴッタが「自己は存在しますか?」と尋ねたとき、もし私が「自己は存在する」と答えたなら、「もろもろのものごとには自己がない」という私の考えと一致するだろうか」
「師よ、一致しません」
「またアーナンダよ、ヴァッチャゴッタが「自己は存在しないのですか?」と尋ねたとき、もし私が「自己は存在しない?」と答えたなら、すでに(先の問答で)混乱していたヴァッチャゴッタをいっそう困惑させることになっただろう。というのは、彼は、「私は今まで、たしかにアートマンをもっていたのに、もはやもっていない」と思うからである」
なぜブッダが沈黙を保ったかは、今や明らかであろう。しかしその背景およびブッダの質問および質問者への対処の仕方――このことは従来無視されてきた点である――を考慮に入れたら、いっそう明瞭になるであろう。(140~142頁)
■ブッダの対応
(前略)
ある人たちは、「自己」を一般に「心」「意識」と言われているものだと考える。しかしブッダは、普通の人にとっては、心、考え、意識よりは、むしろ自分の身体を「自己」と見なした方がいい、と言っている。なぜなら、心、考え、意識は日夜たえず身体よりも速く変化するもので、身体の方が堅固だからである。
「私は存在する」という曖昧な感覚が、該当する実体がない「自己」という考えを生み出す。この事実がわかることがニルヴァーナを体現することであるが、それは容易なことではない。(144~145頁)
■ケーマカ
(前略)
「ケーマカは、「私は存在する」というのは、物質でも、識別でも、意志でも、意識でもなく、それを離れたものでもないと、と説明した。しかし彼は、五集合要素に関して「私は存在する」という感覚があるが、はっきりと「これが私の存在である」とはわからない、と言う。
かれは、それは花の匂いのようなものであると言う。それは、花弁の匂いでも、色の匂いでも、花粉の匂いでもなく、花の匂いである。
ケーカマは、さらにこう説明した。ある程度の修行レベルに達した人でも、未だに「私は存在する」という感覚をもっている。しかし、修行が進むにつれてこの感覚はすっかりなくなる。あたかも、衣類を洗濯した直後には洗剤の匂いが残るが、収納されている間に消えていくかのように。
この対話は非常に有益であったため、ついにケーカマを含めた全員がアラハントとなり、あらゆる汚れから解放され、「私は存在する」という感覚がなくなった。(145~146頁)
■まとめ
ブッダの教えによれば、「私には自己がない」という考えも、「私は自己をもっている」という考えも、ともに間違っている。なぜなら、両者ともに「私は存在する」という誤った感覚から生起する足枷だからである。アナッタ(無我)の問題に対する正しい見解は、いかなる見解にも見方にも固執せず、心的な投射を行なわずにものごとをありのままに見ようとすることである。私たちが「私」「存在」と呼んでいるものは、各々が独立に、因果律に従い刻一刻と変化する物質的、心的要素の結合に過ぎない。そうした存在には、恒久で、永続し、不易で、永遠なものは何もない。
ここで必然的に一つの質問が出てくる。もしアートマンあるいは自己がないのなら、カルマ(行ない)の結果を享受するのは何なのか? この質問にも、ブッダが誰よりも的確に答えている。一人の修行者がこの質問をしたとき、ブッダはこう答えた。「弟子たちよ、私はあなたがたにすべてのものごとに条件性を見るように教えた」
アナッタ、無魂、無自我の教えは、否定的、あるいは虚無的に理解すべきではない。ニルヴァーナと同じく、それは真理、実体であり、実体は否定的ではありえない。否定的なのは、本来存在しない自我を想像上存在すると信じることについてである。アナッタの教えは、誤った信念の闇を除き、叡智の光を生み出す。それは否定的ではない。アサンガの次のことばは的を射ている。
「無自我という真実が存在する」(146~147頁)
第7章 心の修養(バーヴァナ)
■ブッガが言った。
「弟子たちよ、病いには二種類ある。肉体的な病いと心的な病いである。
肉体的な病いは、一年、二年、……100年さらにはそれ以上にわたって、かからない幸せな人がある。
しかし弟子たちよ、心的な汚れから解放された者(すなわちアラハント)たちを除いて、この世の中で心的な病いのない状態を一瞬たりとも享受できる人は稀である」(149頁)
■ブッダの瞑想法
(前略)
瞑想ということばは「修養」「啓発」すなはち心的修養、心的啓発を意味する原語バーヴァナーの訳ではあるが、けっして適切ではない。仏教のバーヴァナーは心の修養である。それは心の肉欲、憎しみ、悪意、怠惰、心配、落ち着きのなさ、疑いといった汚れや動揺から浄化し、集中力、気付き、知性、意志、エネルギー、分析力、自信、喜び、静けさといった資質を啓発し、最終的にはものごとをありのままに見、究極の真理、ニルヴァーナを実現する叡智に到達させるものである。(150~151頁)
■2種類の瞑想
集中力 瞑想には2種類ある。一つは心の一点集中の啓発のためのものである。経典にはさまざまな方法が記してあるが、「無の領域」や「感受でもなく、無感受でもない領域」といった高度な神秘的段階に至る。ブッダによれば、こうした神秘的段階は、すべて心によって生起し、心によって生み出され、条件付けられたものである。それらは、実存、真理、ニルヴァーナとは何の関係もない。この種類の瞑想は、ブッダ以前に存在した。それゆえに、これは純粋には仏教的ではないが、仏教から除外されはしなかった。しかし、これはニルヴァーナの実現にとっては本質的なものではない。ブッダ自身「目覚め」に至る前に、さまざまな師についてこうしたヨーガを行ない、最高の神秘的境地に達した。しかし、彼は満足できなかった。なぜなら、それらによって完全な解放が得られず、究極実存の透視は得られなかったからである。ブッダは、こうした神秘的境地を「この生における幸せなせいかつ」「平安な生活」とみなしたが、それ以上のものではなかった。(151頁)
■ヴィバーヴァナー それゆえに、ブッダはヴィバーヴァナーと呼ばれるもう一つの瞑想、すなはちものごとの本質の「透視」を発見した。これは、究極の真理、ニルヴァーナの実現、心の完全な解放へと導くものである。これこそが、仏教の本質的な瞑想で、仏教の心的修養である。これは、気付き、自覚、注視、観察に基づく分析的な方法である。
■身体的活動に関する心的修養の、重要で、実践的で、有益なもう一つのかたちは、公私を問わず、仕事中であるかどうかを問わず、日常生活ですること、話すことを問わず、日常生活ですること、話すことを十分に意識し注意することである。歩く、立つ、坐る、横たわる、眠る、身体を曲げる、伸ばす、周りを見る、服を着る、話す、沈黙する、食べる、飲む、トイレに行くなど、すべての行ないに対して、それをする瞬間にそれを意識することである。すなわち、今この時点で、今行なうことに集中する、ということである。(155~156頁)
■弟子たちが、一日一食のシンプルで静かな生活を送っていながら、顔色が輝いているのはどうしてかと尋ねられ、ブッダはこう答えた。
「かれらは過去を悔やまず、未来のことを気に病まない。彼らは現在を生きている。だから彼らの顔色は輝いている。愚かな者たちは、未来のことを気に病み、過去を悔やんで、それはまるで青々とした葦が刈り取られ、陽に当たって枯れてしまうようである」(155~156頁)
■気付きあるいは自覚といっても、「私はこれをしている」「私はあれをしている」といつも思い、意識することではない。その逆である。「私はこれをしている」と思う瞬間、あなたには自意識が生まれ、行なっていることにではなく、「私は存在する」という考えに生きている。その結果、行ないはだめになる。あなたは自分を完全に忘れ、今行なっていることに自分を没入しなければならない。たとえば講師に「私はこの聴衆に話している」という自意識が生まれた瞬間、講演は乱れ、思考の流れが途切れる。しかし講演に、そしてテーマに没入しているとき、講師の能力は最大限に発揮され、話もスムーズで、説明もうまく行く。芸術的、詩的、知的、精神的分野における偉大な仕事は、本人が制作に没入し、自分を完全に忘れ、自意識から解放されたときになされる。(158頁)
■私たちの活動に関する気付きあるいは自覚に関してブッダが教えたことは、今の瞬間、今していることに生きることである(これはまた、本質的にはこの教えに基づいた「禅」の教えでもある)。この瞑想法では、気付きあるいは自覚を発達させるのに、ことさら何かを行なう必要はなく、自分が行なうことに絶えず気を遣い、自覚するだけで十分である。「瞑想」に、あなたの貴重な時間を一瞬たりとも費やす必要はない。あなたは、自分の日常生活におけるあらゆる行ないに関して、昼夜たえず気付きあるいは自覚を修養しなければならない。今まで述べた二種類の瞑想は、身体(的活動)に関するものである。(158~159頁)
■⑵感覚、感情に関する心的修養
次には、幸せ、不幸せ、そのどちらでもないといった感覚、感情に関する心的修養がある。その一例だけを挙げるとしよう。不幸な、悲しい感覚を経験したとしよう。こうした状況では、あなたの心には雲が立ちこめ、すっきりとせず、気落ちしている。場合によっては、あなたはどうして不幸せなのかがはっきりわからない。まずは不幸せと観じたとき、そのことでさらに不幸せになったり、心配事があるとき、そのことでさらに心配したりすることがないようにすべきである。そして、どうして不幸せ、心配、悲しみという感覚、感情が生まれるのかをはっきりと観察する必要がある。それがどのようにして生起するのか、何が原因なのか、どのようにして消滅するのか、どのようにして止むのかを検討する。科学者が対象を観察するように、外側に立ち、主観的反応を交えずに状況を吟味する。ここでも、主観的に「私の感覚」「私の感情」としてではなく、客観的に「一つの感覚」「一つの感情」として眺める必要がある。そして「私」という誤った概念を棄てなければならない。感覚や感情の本質、それがどのように生起し、消滅するかがわかると、心がそれに左右されなくなり、執着がなくなり、自由になる。これはすべての感覚、感情について当てはまる。(159~160頁)
■⑶心に関する心的修養
次には、心を検討しよう。心は、情熱的であったり、超然としていたり、あるいは憎しみ、悪意、嫉妬に打ち負かされていたり、その逆に感情、慈しみに溢れていたり、曇っていたり、あるいは明晰であったり、実にさまざまに変化するが、そのすべてを完全に意識しなければならない。往々にして、私たちは自分の心を直視するのを恐がったり、恥ずかしがったりし、それを避けたがるということを認めなくてはならない。しかし鏡で自分の顔を見るように、勇気をもって、真険に自分の心を直視しなければならない。
正邪、善悪の批判、判断、区別、といった問題ではない。単純に観察し、眺め、検討するだけである。あなたは裁判官ではなく、科学者である。自分の心を観察し、その本当の性質が明らかになると、あなたは情熱、感情、ストレスに対して冷静になれる。そうすると執着がなくなり、自由になり、ものごとがありのままに見えてくる。
一例を挙げてみよう。あなたは本当に立腹しており、怒り、悪意、憎しみが煮えたぎっているとしよう。不思議にも、そして逆説的に、立腹している当人は、自分が立腹していることを本当に意識せず、それに気が付いていない。自分の心の状態に気付き、それを意識し、自分の怒りが見えると、自分が恥ずかしくなり、怒りが静まり始める。怒りの本質、その生起、消滅を吟味しなければならない。ここでも「私は怒っている」とか「私の怒り」ということを思ってはいけない。怒っている状態に気付き、意識するに留めなくてはならない。怒った心をただ客観的に観察し、吟味するだけである。これが、すべての感覚、感情、心の状態に対してとるべき態度である。(160~161頁)
■⑷倫理的、精神的、知的事柄に関する心的修養
最後に、倫理的、精神的、知的事柄に関する心的修養がある。私たちの学習、読書、討論、会話、論議はすべて、この心的修養に含まれる。この本を読み、そこで扱われているテーマを深く検討することは、一種の瞑想である。先にニルヴァーナの実現に至った心的修養についてのケーマカと僧侶たちとの会話をみた。
この種類な心的修養では、五つの障害について学習し、考え、討議する必要がある。五つの障害とは①色欲、②悪意、憎しみ、怒り、③もの憂さと無感覚、④落ち着きのなさ、心配、⑤懐疑的な疑いである。この五つは、いかなる明晰な理解、実質的進歩にとっても障害となると見なされる。こうした感情に打ち負かされ、それを取り除くことができないときには、人はものごとの正邪、善悪が判断できない。(161~162頁)
■また「目覚めの七要素」を瞑想することもできる。
⑴気付き。今まで見てきたような、心的および肉体的すべての活動、動きに対する自覚。
⑵教えのさまざまな問題に対する検討と研究。宗教的、倫理的、哲学的学習、読書、研究、討議、対話、そしてこうした事柄に関する講演を聴くこと。
⑶熱意をもって仕事をやり遂げるエネルギー。
⑷喜び。すなわち悲観的、沈鬱でふさぎ込んだ心的態度の正反対の資質。
⑸肉体と心のくつろぎ。肉体的にも心的にも、硬直していてはいけない。
⑹今までみてきたような、集中。
⑺平静。冷静に、落ち着いて、心が乱れることなく、人生の浮き沈みを直視できること。
こうした資質を修養するのに、もっとも本質的なのは、願望、意志、あるいは意向である。テクストの中には、先の七資質の各々を発達させるための物質的・心的条件が説明されている。
また、「存在とは何か」とか「「私」と呼ばれるものは何か」ということを探究するために五集合要素を瞑想したり、四聖諦を瞑想することもできる。こうしたテーマを学習し、探究することは、究極の真理の実現に至る四番目の瞑想にあたる。(162~163頁)
■今まで述べてきたこと以外に、伝統的には四〇に分類されるテーマに関する瞑想がある。その内で特筆すべきは、
⑴「母親が自分の一人子を愛する」ように、すべての生きものに対していっさいの区別なく、無限の普遍的愛と善意を向けること
⑵苦しみや問題を抱え、苛まれているすべての生きものを悲しむこと
⑶他人の成功、安楽、幸せを共に喜ぶこと
⑷人生の浮き沈みに平静であること
である。(163~164頁)
第8章 ブッダの教えと現代
■誰にでも開かれた教え
ブッダのおしえは、僧院の僧侶たちだけでなく、家族と一緒に家庭生活を営む普通の男女にも向けられたものである。八正道という仏教の生活規範は、いっさいの区別なく、すべての人に向けられたものである。(165~166頁)
■一般に、ブッダの教えを実践するには実生活から隠遁しなければならない、と思われているが、それは誤解である。それは実践したくない人が、無意識に口にする言い逃れである。仏教経典の中には、普通の生活を送り、家族生活を営みつつも、ブッダの教えをしっかりと実践し、ニルヴァーナを実現した男女への言及が数多くある。修行者ヴァッチャゴッタはブッダに、普通の生活を営む男女で、ブッダの教えを実践して高度な精神的境地に達した者がいるかどうか、単刀直入に尋ねた。ブッダは、一人や二人ではなく、数百人でもなく、さらに多くの男女が、普通の生活を営みながら高度な精神的境地に達した、と答えた。(166~167頁)
■騒音や煩わしさから遠ざかった静な場所での生活を楽しむ人たちもいる。しかし、普通の人たちに交じって、彼らを助けつつ、彼らに役立つかたちで仏教を実践する方が、より価値があり勇敢である。ある人たちにとっては、自らの心と性格を向上させるための予備的な道徳的、精神的、知的訓練として、ある期間引きこもって生活するのは有益で、その後に強くなって普通の生活に戻り、他人を助けることができる。しかし、自らの幸せと解脱のことだけを考え、他の人のことを顧みずに、孤高の生活を営むのは、愛、慈悲、他人への奉仕を基本とするブッダの教えに沿わないものである。(167頁)
■こう質問するひとがあるだろう。普通の生活を営みつつ仏教を実践できるのなら、ブッダはどうしてサンガ、すなわち出家者の集団を設立したのか。サンガは、自分の人生を、ただ自分の精神的、知的成長のためだけではなく、他人への奉仕のために捧げたい人にそうする機会を提供するものである。普通の人は、人生を他人への奉仕にだけ捧げるわけにはいかない。ところが、家族的責任がなく、世間的絆をもたない僧侶は、「多くの人びとのために、多くの人びとの幸福のために」全人生を捧げる立場にある。こうして、仏教寺院は、歴史の歩みとともに、単に精神的中心となったばかりでなく、教育、文化の中心となっていった。(168頁)
■仏教徒
(前略)
仏教徒になるのには、入門儀礼(洗礼)は必要ない(しかしサンガの一員となるのには、長期にわたる規律的訓練と教育課程を経なければならない)。ブッダの教えを理解し、その教えが正しい道だと確信し、それに従おうとするなら、その人は仏教徒である。しかし、仏教国での伝統的な慣習では、ブッダ、ダルマ、サンガの三宝をよりどころとし、五戒(バンチャシーラ)――①殺生をしない、②盗まない、③不倫をしない、④嘘をつかない、⑤酒を飲まない――を守ることを、定形句を唱えて誓う者が仏教徒である。(172頁)
■経済的基盤――貧困は諸悪の源
『チャッカヴァッティシーハナーダ・スッタ』(長部経典26番)には、貧困は不道徳、盗み、虚言、暴力、憎しみ、残虐行為といった犯罪の原因である、とはっきりと述べられている。
(後略)(174頁)
■今生の幸福の四因
かってディーガジャーヌという男が