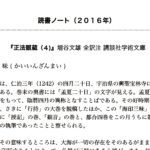読書ノート(2022年)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
『仏教の根底にあるもの』玉城 康四郎著 講談社学術文庫
■ このように、親鸞の救いは、弥陀の願力が衆生を救うことであり、道元の悟りは、三昧に端坐して自己を修証することである。そこでは宗教的世界の構造が違っている。親鸞は救いに至る道すじを説いているのであり、道元は悟りそのものの在り方を語っている。しかし親鸞の場合も、救われている状態を突きつめると、
「無明法性(むみょうほっしょう)ことなれど、心はすなわちひとつなり、この心すなわち涅槃なり、この心すなわち如来なり」
「弥陀の本願信ずべし、本願信ずるひとはみな、摂取不捨の利益(りやく)にて、無上覚をばさとるなり」
ということになって、救いと悟りとはもはや区別できなくなるであろう。
悟りという宗教的世界の構造もさることながら、むしろ、救われていることの目覚めの外にはあり得ない、という視点から、仏教の原点まで遡(さかのぼ)ってみると、ゴータマ・ブッダの菩提樹下における悟りは、まさしく人生の苦悩から救われたことであったとおもわれる。」(16~17頁)
■ゴータマにおける「……からの解脱」「……からの救い」という場合、その問題の生・老・病・死であったことは、一般にみとめられている。したがってゴータマにとってはその目標は明白であった。
「わたしもまた、以前に目覚めていない菩薩であったとき、自ら生でありつつ生そのものを求め、自ら老でありつつ老そのものを求め、自ら死ぬものでありつつ死そのものを求め、自ら憂いでありつつ憂いそのものを求め、自ら汚れでありつつ汚れそのものを求めていた。そのようなわたしに、つぎのことが思い浮かんだ。なぜにわたしは、自ら生でありつつ生そのものを求め、自ら老でありつつ老そのものを求め、ないし自ら汚れでありつつ汚れそのものを求めるのか。さあ、わたしは、自ら生でありつつ生そのもののなかの患(わずら)いを知って、不生なる無上安穏(むじょうあんのん)の涅槃を求めよう。同じように、自ら老・病・死・憂い・汚れ・でありつつ、それぞれのなかの患いを知って、不老・不病・不死・不優・不汚なる無上安穏の涅槃を求めよう」
これで見ると、ゴータマにおける人生の根本問題は、生・老・病・死・憂・汚そのもののなかで、これにかかずらっている自己自身であり、当然ながらそれからの脱却、それからの救いが目標であるあることは明白である。すなわち、不生・不老・不病・不死・不憂・不汚なる究極の涅槃である。
ところでゴータマは、まだ解脱を得られないときでさえ、究極の涅槃がどのような状態であるかをすでに推定し得ていたと考えられる。というのは、涅槃を求めて宮殿を出た後に、アーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタの二人の仙人をそれぞれたずねて修行にはげみ、師と同じ境地に達したのに、それはまだ涅槃ではないと判定しているからである。そしてひとり菩提樹の下に坐って禅定(ぜんじょう)に入り、やがて解脱して涅槃に達することができた。それが果たして真の涅槃であるかどうかは、誰からも証明されたわけではない。すなわち、自ら求める涅槃と、自ら解脱して得た境地とが完全に合致して、自ら満足することができたのである。(18~19頁)
■では、ゴータマをしていったい何が充足せしめ、かつそれを涅槃として確認せしめたのであろうか。この問題を、ゴータマの解脱の際の経典『ウダーナ』によって確かめてみよう。
菩提樹の下で解脱を得てブッダとなったとき、ゴータマ・ブッダは、結跏趺坐のまま七日のあいだ解脱の境地を深め、そのあとウダーナ(即興の詩)を述べている。日没時と真夜中と夜明けにわたって、それぞれ1つずつ、3つの詩がブッダの口から発せられている。
日没時の詩。
「実にダンマ(dhamma)が、熱心に瞑想しつつある修行者に顕になるとき、そのとき、かれの一切の疑惑は消失する。というのは、かれの縁起の法を知っているから」
夜明けの詩、
「実にダンマが、熱心に瞑想しつつある修行者に顕になるとき、かれは悪魔の軍隊を粉砕して、安立(あんりゅう)している。あたかも太陽が虚空を輝かすがごとくである」
右の3つの詩は、ゴータマが目覚めてブッダとなった状況を見事に表している。その目覚めの原型とは何か。それは3つの詩に共通している所の、「ダンマが瞑想しつつある修行者に顕になる」というそのことである。すなわち、「ダンマが主体者に顕になる」、まさにその時に一切の疑惑が消失したのである。(22~23頁)
■ブッダは弟子たちに次のように説いている。
「比丘(びく)たちよ、世に現れるところの一人(いちにん)は、多くの衆生の利益のために、多くの衆生の楽のために、世に対する慈悲のためにうまれる。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である。……
比丘(びく)たちよ、世に現れるところの一人(いちにん)は、多くの衆生の利益のために、多くの衆生の楽のために、世に対する慈悲のためにうまれる。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である。……
比丘たちよ、一人の顕わになることから、大いなる眼の顕わになることがあり、大いなる光明の顕わになることがあり、大いなる光照の顕わになることがある。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である」
如来・阿羅漢・正等覚者とは、如来の上にさらに尊称を加えたものである。阿羅漢は能力あるもの、正等覚者は正しく悟れるものの意味である。いいかえれば、如来の趣旨をいっそう強調したものである。しかも、その如来が、現実のゴータマ・ブッダによって第三者として弟子たちに語られているところから見て、現実のブッダをも超える、超越的なもの、絶対的なものであることが知られよう。
その如来が、ここでは、無二のもの、伴(つれ)なきもの、無比のもの、対比なきもの、比類なきもの……といわれているのであり、その如来が顕わになることによって、われわれには大いなる眼となり、大いなる光明となり、大いなる光照となる、と説かれているのである。すなわち先に「ダンマが顕わになること」が目覚めの原点であるといった、その形なき純粋生命たるダンマと、如来とはまったく同質であることがここに明瞭になったということができよう。(26~27頁)
■先に引用したように、ブッダは、
「わたしによって体得されたこのダンマは、甚だ深くて、理解しがたく、悟りがたく、寂静であり、分別を超えて微妙であり、賢者によって知られるべきものである」
と述べて、形なき純粋生命の体得された状況を伝えているが、それにつづいて、
「しかし、この世の人々は、アーラヤ(alaya執著しゅうじゃく)を好み、アーラヤを喜んでいる。そのような人々にとっては、この道理はとても理解できない。……たといわたしがダンマを説いても、人々は理解できないから、わたしはただ疲労して悩むだけであろう」
と語っている。
ここで道理といっているのは、ダンマがゴータマに顕わになって、すべての疑惑やぼんのうから解放され、もっとも平和な涅槃の境地に達した、その転換的な状況を指している。こうした道理は、世の人々には理解できないというのである。なぜなら人々は深い我執(がしゅう)に捕われており、本能的にアーラヤ(我執)を喜び、アーラヤ(我執)を楽しんでいるからである。
ここに、ダンマが顕わになって涅槃に達したブッダの境地と、本能的に我執を楽しんでいる世の人々との間に、まさしく対立的に逆行する、くっきりとした境界線が引かれてしまったのである。ブッダは、「たといダンマを説いても、ただ疲労困憊(こんぱい)するだけであらう」と、絶望の声を放っている。ブッダはついにそのまま沈黙に入ろうとした。
ブッダの境地と世の人々の実態、いいかえれば悟りと迷い、この二つの逆行的な対立は、決定的に重要な注目点である。簡単に妥協さるべき問題ではない。人間の生存が続くかぎり、永遠に解消しない対立である。この底知れない裂け目に慎重に留意しないでは、転迷開悟の機会は永久に訪れてこないであろう。後代に発達した大乗仏教の唯識思想では、原始経典のアーラヤがアーラヤ識として掘り下げられている。
これについては後に論じたいと思うが、人間の我執の根源を徹底的に究明して、ついにアーラヤ識に達したのである。それは、人間の個体における我執の根源であると同時に、世界そのものの我執の起源であるといってよいであろう。(28~30頁)
■ 「第一に、すべての世界の海は、かぎりない因縁によって成り立っている。すべては因縁によってすでに成立しおわっており、現在成立しつつあり、また未来も成立するであろう。
ここにいう因縁とは、つぎのことを指している。すなわちそれは、仏の神通力(じんずうりき)である。また、ものごとはすべてありのままであるということである。また、衆生の行為や宿業である。また、すべての菩薩は、究極の悟りを得る可能性を有しているということである。また、菩薩が仏の国土をきよめるのに自由自在であるということである。これが世界海(せかいかい)の因縁である。
毘盧遮那仏の境界は、とうてい思い測ることはできないが、われわれが経験しているとおりにすべてが安定している。なぜなら毘盧遮那仏は、無量無辺のすべての世界海をきよめたもうているからである」(『華厳教』「盧舎那品」における一文)(31~32頁)
■この主題に関する論点からいえば、迷いの世界にさまよっているわれわれ人間の宿業が、実はそのまま仏の因縁界の一景であるということができよう。そうしてみると、迷いと苦悩に充ち満ちてている人間の世界は、宇宙そのものが仏であるという仏国土と別でないことはいうまでもなく、そのような仏の世界に包括されており、ついにはそのままが仏そのものの世界であるということに気づかれるであろう。しかしそこまで至るのには、『華厳経』全体の長広舌(ちょうこうぜつ)が必要であったのである。(32~33頁)
■コーサラの国にアングリマーラという盗賊がいて、しきりに悪事を働いていたが、ついにブッダに帰依して悟りを開くことができた。仏道の究極目的を自ら証拠立てたのである。ある日、アングリマーラは托鉢に出たが、かつてかれが盗賊であったころ、種々のうらみをうけた人々がそのすがたを見つけて、棒や石や土くれを投げつけたので、かれは傷つけられ、血を流し、鉢はこわれ、衣は破れて、這々(ほうほう)のていでブッダのもとに帰ってきた。ブッダはアングリマーラに向って、次のように説いている。
「忍受せよ、汝修行者よ、忍受せよ、汝修行者よ、汝が幾年・幾百年・幾千年のあいだ、地獄において受くべき、その業の果報を、汝は現実において受けているのである」
そのときアングリマーラは、ひとり坐して冥想に入り、ブッダの説法に聞き入った。かれは今まで気づかなかった、自らの業の果報に触れたのである。そうすると、「あたかも雲をはなれた月のように、かれはこの世を照らし出した」といわれている。
アングリマーラは、すでに仏弟子となって修行し、解脱に達していたのである。それにもかかわらず、かれはかつて行為した業の果報のなかにおり、その果報のために苦悩せねばならなかった。それは、アングリマーラの意識的領域だけではなく、それを包む深い無意識的な領域である。いいかえれば、かれの自己は、限りなく深い業の果報、意識されざる領域にまで拡充しているのである。そしてかかる業の果報に気づくときに、アングリマーラ自身が果てしなき解脱へと開かれていくのである。
以上のアングリマーラと同室の問題が、禅宗の開祖と仰がれている菩提達磨の二入四行説(ににゅうしぎょうせつ)のなかに指摘することができる。二入とは理入(りにゅう)と行入(ぎょうにゅう)であり、四行とは、その行入のなかの、報怨行(ほうおんぎょう)・随縁行・無所求行(むしょぐぎょう)称法行である。問題の箇所は、この四行のうちの報怨行と随縁行に示されている。しかし、一先ず理入から見ておかねばならない。
理入の理とは真理である。
達磨は、
「……壁観(へきかん)に凝住(ぎょうじゅう)し、自も無く他も無く、凡聖(ぼんしょう)等一にして、堅住して移らず、更に文教に随(したが)わず、此れ即ち真理と冥苻(みょうふ)す。分別あることなく、寂然(じゃくねん)無為なるを、之(これ)を理入と名づく」
という。
壁が突き立っているように、身も心も一つになって禅定(ぜんじょう)に入るときに、やがて我もなく他もなく、衆生(しゅじょう)も仏も一如になる。このようにして不動のまま持続していけば、ついには真理と合一する、というのである。
ここにいう真理とは、もはや言葉や教えではない。また形に現れた道理や理法というべきものでもない。「自も無く他も無く、凡聖(ぼんしょう)等一にして、堅住して移らざる」ことにおいて、おのずから冥合(めいごう)して頷(うなず)く所のものである。したがって、無分別であり、寂然無為といわれる。
このような真理とは、もはや疑うべくもなく、先に挙げた原始経典における根源的意味のダンマ、それがゴータマに顕話になることによって、ブッダとして目覚めた所の、形なき純粋生命とまったく同質であるというべきであろう。
理入は、このように「堅住して移らず」して直接に真理と冥合することである。これに対して行人は、四つのそれぞれの行を通じて真理と冥合することである。真理と冥合することにおいては、理入も行人も異なることはない。
さて、行入の第一は報怨行(ほうおんぎょう)である。
「云何(いか)んが報怨行なる。修道の行人(ぎょうにん)、若(も)し苦を受くる時、当(まさ)に自ら念じて言うべし、我、往昔(おうしゃく)より無数劫中(むしゅごうちゅう)、本(もと)を棄てて末を逐(お)い、諸有(しょう)に流浪して、多くの怨憎(おんぞう)を起し、違害(いがい)すること限り無し。今は犯すこと無しと雖(いえど)も、是れ我が宿殃(しゅくおう)・悪業の巣の熟するものにして、天・非人の能(よ)く見与する所に非ず。甘心忍受(かんしんにんじゅ)して、都(す)べて怨訴(おんそ)すること無し、と。経に云わく、苦に逢うも憂えず、何を以(もつ)ての故に、識、本に達するが故に、と。此の心生ずる時、理と相応し、怨(おん)を体して道に進む。是の故に説いて報怨行と言う」
現在、悪事をしていないのに苦痛を受けることがある。そのとき、どう対処すればよいか、というのがこの報怨行である。実は、自分の意識にのぼってこない限りない昔から、根本の道を忘れて、さまざまな世界を流浪してきた。その間には多くの怨憎や障害を重ねてきたが、その数知れぬ悪業の結果が今ここに熟して、苦痛を受けている。いかなるものもこの業力を解消することはできない。そこで自ら甘んじてこれを忍受し、けっして他を怨(うら)みに思うことはしない。これが報怨行の要点である。そして、この心が起るときに真理と合一するというのである。
これは、ブッダに業の果報を教えられた先述のアングリマーラの場合と、まったく同様であるといえよう。
さて、次の第二の随縁行は、報怨行と逆の場合である。
「随縁行とは、衆生は無我にして、並びに業に縁(よ)りて転ずる所なれば、苦楽斉(ひと)しく受くること、皆、縁より生ず。若し勝報・栄誉等の事を得るも、是れ我が過去の宿因の感ずる所にして、今方(まさ)に之(これ)を得るのみ。縁尽くされば無に還(かえ)る。何の喜びか之れ有らん。得失は縁に従い、心は増滅無く、喜風動かざれば、道に冥順(みょうじゅん)す。是の故に、説いて随縁行と言う」
われわれ衆生は、もともと無我であって、ただ過去の業縁(ごうえん)によって動いており、そのために種々の苦楽を受けている。もしすぐれた果報や栄誉などのことを得ても、すべて過去の業報のもたらす所である。縁が尽されば無に帰する。別に喜びとするには当らない。このように得失は業縁に従うと諦観(たいかん)して心が動かされることなければ、そのままで仏道に冥合するというのである。この随縁行は、先の報怨行が苦を受けるのに対して、その逆に楽を受ける場合である。
以上のように、報怨行・随縁行は、苦楽の相違はあっても、いずれも過去の業縁にさかのぼって、量り知れない自分の姿がとらえられているといえよう。アングリマーラの場合もまったく同様である。しかも、過去の業縁が現在の自己として頷かれるときに、過去から現在にわたる自己の全体が解き放たれていくのである。
苦楽を受けているのは現在の自己である。その苦楽が過去の業縁へ伸びていく、現在から過去へである。しかもその業縁を現在の自己として受容する、過去から現在へである。そして業縁の事故が、そのまま形なき純粋生命のなかで果てしなく目覚めていく、いいかえれば、業縁の自己の外に目覚むべき自己はない、ただ業縁の自己のみである、現在から現在へである。
最初に述べた、菩提樹の下で悟りを開いたブッダが理入であるとすれば、ブッダに業の果報を教えられてさらに解脱を深めていったアングリマーラは行入(ぎょうにゅう)であるといえよう。理入も行入も、真理に冥合し証入することにおいて異なることはない。(34~38頁)
■アーラヤ識のアーラヤは、「蔵」の意味であり。それゆえに象識ともいわれている。英語では store consciousness と訳されている。その理由は、現実経験の世界が、ことごとくその中に貯蔵されているからである。あるいは、現実経験のすべての種子(しゅうじ)を貯えているから、一切種子識ともいわれている。これは、アーラヤ識自身が貯えているのであるから、能蔵の意味である。ところが、逆に所蔵ともいわれている。それは、アーラヤ識から現出した現実経験の世界は、同時にアーラヤ識を包むものとなっているからである。いいかえれば、アーラヤ識の現実経験に対する関係は、現実経験を包むものとしては能蔵であり、逆にそれに包まれるものとしては所蔵である。そしてアーラヤ識自体は、執著(しゅうじゃく)の源泉として執蔵(しゅうぞう)といわれている。(40~41頁)
■厄介なことには、マナ識たる自我意識は、底知れない無意識のなかに根ざしている。それは、日常生活のなかではほとんど意識されることはない。もとより意識される自我意識も存在していることは、日常経験のとおりである。それは、マナ識よりも表面的な意識、いわゆる心といわれるもののなかで起っている。その場合の自我意識は、起ることもあれば起こらないこともある。しかし無意識のなかの、マナ識たる自我意識は、寝ても覚めても、二六時中、起っており、中止することがない。その我執を『成(じょう)唯識論』では、倶生(くしょう)の我執といい、次のように述べている。
「無始時来(むしじらい)、虚妄薫習(こもうくんじゅう)の因の力の故に、常に身と倶(とも)なり、邪教及び邪分別を待たず、任運(にんぬん)して転ずるが故に、倶生と名づく」
倶生の我執とは、いわば生まれながらの、先天的な我執であり、始まりのない無限の過去から、迷いに迷いを重ねて流浪し、この身に付着している自我意識である。それは、意識上の分別を待たずに、元来、自然に生じている、といわれる。
通常の、心の中で起っている我執を意識的自我意識であるとすれば、マナ識の我執は無意識的自我意識であるといえよう。しかもそれは、無限の過去から断絶することなく、二六時中起っているということが特徴的である。
さて、これまで追求してきた主体の根源の実情が、ようやくここに浮かんできたのである。それは、マナ識とアーラヤ識との根本関係に存する我執であり、無始以来、中断することなく持続している所の自我意識である。しかもマナ識の我執は、深い無意識のなかに在り、そのマナ識さえも、われわれはほとんど意識することができないのであるが、その我執の源泉は、マナ識のいっそう根底的な、執蔵としてのアーラヤ識に在るといえよう。
では、仏教の究極の目当てである解脱はいかにして実現できるであろうか。それは、我執の根本転換の外にはあり得ないであろう。そのアーラヤ識の転換はどうしたらできるのであろうか。
アーラヤ識は、すでに述べた如く、人間存在の意識の源泉であり、さらに経験世界そのものの根拠でもある。人間存在そのもの、あるいは世界の存在そのものが、アーラヤ識として、根源的ミステークに陥っている。そうだとすれば、われわれがいかに努力を重ねても、もはやアーラヤ識そのものに転換の力がないことは明白である。
ヴァスバンドゥの兄であるアサンガ(Asanga 無著むじゃく、310-390頃)は『摂大乗論(しょうだいじょうろん)』の中で、全人格的思惟(瞑想、禅定)を行じつつ、慎重にアーラヤ識の所在を究明している。つまり、いかに瞑想、禅定を深めても、ついにはアーラヤ識に帰着する外はない。いいかえれば、ただ禅定を深めるのみでは、アーラヤ識の転換、すなわち解脱は実現してこないのである。
では、いかにしてその転換は達成されるのであろうか。アサンガは、次のようなただ一つ解答を提示するのである。
「最清浄法界(さいしょうじょうほっかい)より流るる所の正聞薫習(しょうもんくんじゅう)、種子(しゅうじ)となるが故に、出世心、生ずることを得」
チベット語訳では、
「最清浄法界が顕話になる所の聞薫習の種子から、それ(出世心)は生ずる」
となっている。
最清浄法界とは、まったく形を離れた純粋生命たる真実の世界である。その最清浄法界が、主体者に顕わになってくる。そのことは、主体者からいえば、全人格が耳となって、最清浄法界に聞きほれる。そうすると、その純粋生命が全人格に染みついて(すなわち薫習)、そこから初めて、人間の基盤(アーラヤ識)を超出する目覚めの心(出世心)が生ずる、というのである。
これは、唯識思想における主体の根源たるアーラヤ識の転換の状況である。
ここにおいて、われわれは直ちに思い浮かべるであろう、あの菩提樹下におけるゴータマ・ブッダの目覚めの実景を。まったく形を超えた純粋生命たるダンマが、ゴータマに顕わになったとき、一切の疑惑が消失して、目覚めが実現したのである。そしてダンマはその全人格に滲透して、ついに貫徹したのである。ブッダとアサンガにおける目覚めの構造が、軌を一していることはいうまでもないであろう。(43~46頁)
■しかし、空海が恵果の許(もと)にあったのは、わずか七、八ヶ月の短期間であった。しかも両者が出会って3ヶ月も経たぬうちに、空海は、胎蔵界・金剛界の伝法灌頂(でんぽうかんじょう)を受けたのである。いかに空海がすぐれた人物であったにせよ、インド正統の密教を継いだ恵果の、最内奥(ないおう)の教えを受けるには、すでに空海に相応の準備ができていたことは想像にかたくない。二十四歳の著作である『三教指帰(さんごうしいき)』に示されているとおり、空海は、ひとりの沙門に虚空蔵聞持(こくうぞうもんじ)の法をさずけられ、時には阿波の国の大滝岳によじのぼり、また時には、土佐の室戸岬で想念を凝らすなど、青年時代の苦行は、かれの深層領域を深く耕していたにちがいない。それが、桂花とのわずかの期間の接触によって、密教の大法(たいほう)を受けつぐことを可能ならしめたのであろう。
そればかりでなく、この著作の構造は、儒・仏・道の3教にわたっている。いわば、青年空海が触れ得る代表的な世界観のすべてを網羅している。このようなかれの見解の普遍性・世界性が、後年の教相判釈である『十住心論』『秘蔵宝鑰』『弁顕密二教論』などの著作となって実を結んだといえよう。かれは入唐(にっとう)して、仏教各派の教義を学び、またインド哲学や、さらに深く中国固有の思想に触れることができたのであろう。それらのすべてを包括して教相判釈の対象としたのである。いいかえれば、仏教の範囲に限るのではなく、人間であるかぎは、当時の普遍的な人間論であったということができる。
さて、このような事態のなかで、空海思想のもっとも大きな特徴は何であろうか。ここにゆっくり論ずるゆとりはないが、一語にして尽せば、弁別と包括であるといえよう。弁別とは、真実と非真実とをきびしく篩(ふる)い分けることである。仏教の根本は何か、真実の仏教とは何か、ということを、空海は徹底的に追求した。そしてその根本問題が恵果との出会いによって満足したのである。すなわち顕教(けんぎょう)からまったく峻別される密教の真実性である。しかし、包括とは何か。それは、密教以外の、一見真実ならざるように見える一切の教え・思想を包括することである。このように、真・非真をきびしく篩い分ける弁別と、非真なるものをも包みこもうとする包括とは、いかにも矛盾しているように見える。
しかし実は、この両者は物の表裏であって、根源において一体であるという点にこそ、かれの仏教観のすぐれた風格を見ることができる。つまり、顕教から弁別された密教とは、宇宙的絶対者である毘盧遮那仏のそれ自身の自覚内容であり、それは、そのまま法身(ほっしん)説法という形において現実に顕にわになっている。いいかえれば、色も形もない法身仏が、われわれの感覚するとおりに現れている、それがすなわち法身説法である。したがって、あらゆる教え・思想ばかりではなく、すべての現象が本質において密教ならざるを得ない。このように、顕教から区別された密教とは、実は存在の根源体であり、それは必然的に一切の存在者を包括しているのである。弁別と包括とが一体たつ所以(ゆえん)である。
空海の法身説法は、密教の秘中の特徴を表示するものである。空海は、中国華厳宗の世界観、すなはち重重無尽の無碍法界観(むげほっかいかん)を直接のパターンとして六大無碍の世界観を展開しているのであるが、華厳宗においては、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、ヴェールにおおわれた秘仏であった。すなわち、色も形もない法身仏のゆえに、自ら説法し得ないものと見なされている。説法し得るものは、毘盧遮那仏にもとづく諸菩薩であり、その説法が『華厳経』となっている。したがって華厳宗の教理において、毘盧遮那仏の活動する余地はほとんど認められていない。
しかるに、真言密教においては、毘盧遮那仏の活動のポジションが逆転するのである。説法するはずのない法身仏が説法を始めるのである。それこそ密教の密たる所以であり、秘秘中の最秘である。毘盧遮那仏とは、それとして心に浮ぶ仏のイメージをいっているのではない。それは、実は宇宙そのものであり、もっとも根源的な意味における自己そのものである。その毘盧遮那仏が法身説法するということは、宇宙のもっとも深き根源が、そのまま顕(あら)わになることである。実存の究極な神秘にきわまるという外はない。(53~55頁)
■自受用三昧
まず第一に、空海における毘盧遮那仏の自受用三昧(じじゅようざんまい)である。毘盧遮那仏(光の仏)は宇宙そのものの仏であり、自受用三昧は自ら体験しつつある三昧である。いいかえれば、宇宙そのものが三昧に入っている。この毘盧遮那仏の自受用三昧が密教の根本的立場であるということができよう。空海は、顕密二教の区別を仏の三身(さんしん)になぞらえて、応身・化身の説法が顕教で、法身の説法が密教であると述べ、さらに『金剛頂経』にしたがって、如来の変化身が三乗、他受用身が一乗で、併せて顕教であり、これに対して自受用仏の内証智の境を説くのが密教ということになる。自受用法性仏が、すなわち自受用三昧の毘盧遮那仏なのである。いいかえれば、まったく形を超えた宇宙そのものの絶対仏が、そのまま果てしなき瞑想を享受しているというのが、毘盧遮那仏の自受用三昧に外ならない。これが密教の根本三昧であり、この三昧に没同することによって、われわれ自身もまた仏そのものを受用することができるのである。
さて、道元の根本的立場もまた、このような密教の三昧とまったく同質であるということができる。
道元は、『正法眼蔵』「弁道話」の最初で、
「諸仏如来、ともに妙法を単伝して、阿耨菩提(あのくぼだい)を証するに、最上無為の妙術あり。これただ、ほとけ仏にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧、その標準なり」
と述べている。
阿耨菩提とはとは究極の悟りであり、それを体得するにすぐれた方法がある。それは、仏から仏へと正伝(しょうでん)されていくところの自受用三昧であり、それこそ、根本の基準であるというのである。この仏の三昧に自らも参与することによって、仏祖単伝の打坐(たざ)を成就することができる。道元は、その光景をつぎのように述べている。文章がむずかしいので意訳してかかげてみよう。
「たといひとときの坐禅であっても、自分の身・口・意(しんくい)の三つの働きに、そのまま仏の印をつけて三昧に端坐するとき、全世界がみな仏の印しとなり、全虚空がことごとく悟りとなる。諸仏如来はそのためにますます法楽を増し、迷界の衆生も十方世界の万物も、大解脱を実現し、すぐれた法輪を転ずる。これらの悟りが、さらに、自分に帰ってきて互いに通じ合うから、ついに坐禅人は身心(しんじん)脱落して、天真の仏法に証入することができる」
道元によれば、自分が坐禅し、その力によって悟りを開くのではない。坐禅に入るとき、すでに自分自身が仏に印(しるし)どけられることによって、全世界が悟りとなり、その力が自分に帰ってきて身心脱落することになる、――というのである。仏の本地(ほんじ)の大三昧にみずから加入することが、道元のいう、正伝の打坐なのである。それは、仏の三昧力に裏づけられてはじめて実現する、ともいうことができよう。(57~59頁)
■自然
第三に、自然の(じねん)の立場である。親鸞に「自然法爾(じねんほうに)」の一文があることは周知のとおりであるが、自然の見解は親鸞に限られているわけではない。とおく老荘(ろうそう)にさかのぼり、それに関連して中国において発展しており、やがてそれが仏教にも入ってきた。空海は、法然(ほうねん)という語によってその意味を表そうとしている。『即身成仏義』のなかでは、「法然、薩般若(さつぱにゃ)を具す」といい、『声字実相義』では、「法然・随縁の有(う)」という。前者では、法然を、「諸法の自然、是くの如し」と解し、後者では、法然を法爾と置きかえてている。すなわち、言葉の上からいっても、空海にはすでに親鸞の自然法爾の語が綴られ得るわけである。
このようにして空海は、「法然、薩般若(さつぱにゃ)を具す」という一文を、ありとあらゆる存在は、おのずからにして一切智智を成就する、というように解しており、「法然・随縁の有(う)」の箇所で、さらにそれを構造的に開示している。その構造というのは、仏の側と衆生の側とに分け、仏の側を、法身(ほっしん)・報身・応化身・等流身(とうるじん)の四種となしているが、ここでとくに留意したいのは、これを二方面から考察して、一つは法仏・法爾、二つは随縁顕現で、菩薩の随福所感と如来の信解願力の所生(しょじょう)となしている点である。しかも空海はさらに衆生の側からみて、衆生にも本覚法身があって仏と平等なすのである。いいかえれば、仏の側からは法身仏と仏の信解願力の所生、衆生の側からは仏と平等一体であるというのである。(62~63頁)
■このように見てくると、以上の点において空海と親鸞とはまったく構造をおなじくしているといわねばならない。しかも、親鸞の自然法爾は、形を越えた無上仏、いいかえれば法性法身にならしめることである。その形のない所を自然(じねん)というのである。念仏の行者からいえば「よからんとも、あしからんともおもはぬ」所が自然なのである。親鸞は、ながい苦闘のすえに、こうした自然の境地に達したのである。この点からいえば、右に論じた空海の凡仏一体の構造を、親鸞は、みずからの信心成塾の過程において実現したといえよう。(63頁)
■ さて道元においてはいかがであろうか。道元は、自然の見解を『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』「空華」のなかで展開している。かれは、『景徳伝燈録』に見える達磨の言葉を引き、「一華開五葉、結果自然成」という。一華(いちげ)はおのずから五枚の花びらとなって開き、果を結ぶことに自然(じねん)に成る、というのである。この自然についての道元の解釈が意味深い。自とは、己(おのれ)であり、それはかならず汝である。つまり、仏とも凡夫とも位のつけようもない真人を自由に使いこなしているもの、それが自である。然とは、聴許(ちょうきょ)、すなわち許すことである。このような自然成(じねんじょう)が、「華開き果を結ぶ時節」である、という。このように見てくると、道元の自然は、親鸞の自然を自らの主体そのものに集注して理解されているといえよう。空海・親鸞・道元、三者それぞれ視点を異にしながら、構造の本質においては同質的なものが指摘され得るのである。(63~64頁)
■ 道元についても、同じ趣旨の道元的な特徴を指摘することができよう。仏の自受用三昧において坐禅人(にん)が端坐するとき、万物が仏身となって、「無等等の大宝輪を転じ、究竟無為(くきょうむい)の深(じん)般若を開演す」るのである。端坐参禅における、仏の法身説法である。また道元は、「自己をはこびて万法(まんぽう)を修証するするを迷とす、万法すすみて自己を修証するするはさとりなり」という。自己から万法へ向うのではなく、万法が自己に顕わになるのである。同じように「自己をわするるといふは、万法に証さるるなり。万法に証さるるといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごしゃく)の休歇(きゅうけつ)なるあり、休歇なる悟迹を長長出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ」という。ここでも、万法が自己に顕わになり、自己を動かして、脱落せしめ長長出ならしめて、どこまでも果てしなく展開せしめるのである。これまた法心説法の実現であるといえよう。(65頁)
■ 法然がたぐいまれな秀才であったことはよく知られている。法相・三論・天台・華厳・真言・律、なんでも自家薬籠中のものにした。たとえば、こういうことがある。醍醐に三論の学者がいた。寛雅(かんが)という人である。寛雅は俊寛の父である。俊寛は、謡曲でも知られているように、平家倒滅のクーデターを主謀し、鹿(しし)ケ谷で密議したが、事が発覚して薩摩の鬼界島に流され、そこで歿した人である。法然がこの寛雅に、三論について意見を述べると、寛雅は沈黙したまま十台の文箱(ふばこ)を持ってきて、それを法然に授けたという。法然以上に三論を理解したものが寛雅には見当らなかったからである。
また、法然の師である叡空(えいくう)と天台の円頓一実(えんどんいちじつ)の戒体(受戒したときに、円満成就の真言すなわち仏心が身体に染みついたもの)について対談したことがある。叡空は、心が戒体である、と主張したのに対して、法然はそれに反対して、性無作の仮(け)色(ありのままの本性の無表色、無表色とは形に表われない潜勢力の如きもの)が戒体であると論じた。互いに負けずに議論すること再三に及んだが、叡空はついに腹を立てて木枕で法然を打った。しかしあとで反省してみると、どうも法然の説が正しいということに落着し、法然の部屋へやってきて、「お前の見解は、天台の本意一実円戒の至極である」とほめている。
また、仁和寺(にんなじ)に華厳宗の名匠、大納言法橋慶雅(だいなごんほっきょうけいが)という人がいた。慶雅は、弘法大師の『十住心論』は華厳宗の基づいて作られた、というのに対して、法然は、そうではなくて、『大日経』の十心品(じゅうしんぼん)で作られた、といい、第六住心(法相)、第七住心(三論)、第八住心(天台)、第九住心(華厳)、第十住心(真言)、について、一々道理を述べ、ことに天台・華厳についてことこまかに説いた。法橋は、自分はこれほどまでに明瞭ではなかった、あなたのために不審がはれた、と喜んで、法然に授戒している。
また法然は、興福寺の蔵俊僧都(ぞうしゅんそうず)の所に行って、法相宗の法門を談じた。蔵俊は、「これは直人(ただびと)ではない」と感歎して、毎年法然に供物を送っている。
このように法然は、仏教各派の学問に習熟していたことが分る。大変な勉強家で、十五歳で叡山に登って以来、十七歳の時には天台三大部六十巻を学び始め、十八歳で遁世して名利を絶ち、ただひたすらに仏法を学んだ。一切経を五遍も読んだといい、老後になって、往時を述懐していうに、聖教(しょうぎょう)を読まない日はなかったが、木曾義仲が京都に乱入した一日だけ見なかった、という。(68~69頁)
■ 第一に、法然の発見した念仏とは人々にとって何を意味しているのであろうか。まず法念が念仏に生かされてことは事実である。それはみずから告白しているとおりである。ここに法然の個人解脱は終わったと見て良い。しかし、法然自身は念仏によって救われたが、果たして人々もまたこれによって救われ得るであろうか。これが、つぎに法然を襲った大問題であった。自分は救われたが、人々は救われ得るか否かは法然には分からない。実は、法念が救われたということも、かれ自身左右できることではなかった。念仏の光は突如としてかれを照らしたのである。まして同じ光が人々を照らすかどうかはかれの知るところではない。しかし法然にとって、人々の救われるということが大問題であった。いいかえれば、自利行が実現するや否や、利他行の問題がかれの心を捕えたのである。(26頁)
親鸞の宗教的世界
■ 親鸞の世界は容易ならざるものである。その容易ならざる所以を辿っていくと、所謂(いわゆる)機法(浄土真宗などで、信心と救い)二種の深心にきわまるが如くである。
機とは、人間の掩(おお)うべくもない実相である。それは、人間における実存そのものの無智と、その惑乱とに帰するであろう。しかも人生の経験において、無智はそのまま惑乱と同体でありといわねばならない。無智はすなわち惑乱であり、惑乱がそのまま無智であるという実存の根本様態が、果てしなき宿世(すくせ)より流れ来れる自己存在の実相である。
法とは、このような機に顕わになるものである。法が顕わになるということは、実存を包越する根源的神秘であり、そしてただ法のみが、実存にとって根源の真実を表明するものである。根源の真実は、実存の無智と惑乱とに真っ向から対決し、かつ無智と惑乱とを貫きとおすのである。
親鸞は、このような実存の粉(まご)うことなき実相を究明しとおし、実存に顕わになる根源的神秘と根源的真実とを浮き彫りにして止まなかった。それは、仏教思想発展のもっとも深い意味において、はるかかなたの原始経典「自己にたよれ、法にたよれ」というブッダの本旨につらなるものである。歴史的世界に共住し、それを究明し究尽(ぐうじん)し、そしてついに歴史的世界を越える実存の神秘というべきであろうか。(86~87頁)
■ 現代人が親鸞に近づきがたく思う、もう一つの理由は、親鸞の経典絶対主義である。親鸞にとって真実の教えは『無量寿経』である。この経典は釈迦の真説であり、その内容は弥陀の本願を説き明かしたという。親鸞はそれを確信し、それにもとづいて信心が確かめられるに至った。しかし、経典史論の発達した現在の時点において、そのような親鸞の確信を承認することは不可能である。しかし、親鸞の宗教的生命は、このような根本条件の変化のためにくつがえるのであろうか。それとも、その難問の壁を破ってまでも、その生命は生きのびていくのであろうか。これは大きな課題であり、ひとり親鸞だけの問題ではない。(87頁)
■ 善鸞(ぜんらん、親鸞の子)の異議によってたじろぐような信心は、本来まことの信心ではなかった証拠である。これに対して親鸞の信心はいかがであろうか。
さきに挙げた善鸞義絶の手紙のなかで、
「光明寺の和尚(善導)の、信の様ををしえさせたまひさふらふには、まことの信をさだめられてのちにには、弥陀のごとくの仏、釈迦のごとくの仏、そらにみちみちて、釈迦のをしへ、弥陀の本願はひがごとなりとおほせらるとも、一念もうたがひあるべからずとこそうけたまはりてさふらへば、……」
という。
親鸞は、善導の教えによってみずからの信心を訴えている。まことの信心というのは、たとい弥陀や釈迦のような仏が空に充ち満ちて、釈迦の教えや弥陀の本願はいつわりであると説いたとしても、一念の疑いもあってはならない、というのである。これは、親鸞のおどろくべき発言であり、もはや一念のたじろぎをも見せぬ頑強な大信を表明している。(91~92頁)
■そこで親鸞は、深智博覧の点で等しいというのならば見当ちがいである、といい、
「往生の信心にいたりては、ひとたび他力信心のことはりを承(うけたまわり)しよりこのかた、またくわたくしなし。しかれば聖人の御信心も他力よりたまわらせたまふ。善信が信心も他力なり。故にひとしくしてかはるところなし」
と論じている。
法然は、この評論を裁断していうに、自力の信の場合には、智慧各別なるゆえに信もまた各別であるが、
「他力の信心は、善悪の凡夫ともに仏のかたよりたまわる信心なれば、源空(法然)が信心も善信房の信心も、さらにかわるべからず、ただひとつなり」
と判定している。
右の信心評論は、親鸞の宗教的な生涯のなかで、決定的に明白な信心の在り方を表明している。それは、その後の親鸞の生涯を貫いて変わることなき信心の礎であったということができる。晩年の法然が一つの信心を裁断したように、晩年の親鸞もまた、すでに述べたように、一つの信心を強調して止まなかった。それは法然の教える、浄土に往生することを信じて念仏するという行の、もっとも確かな、ゆるぎのない結果となった証拠である。
このように、「仏のかたよりたまわる信心」(如来よりたまわる信心)は、三十代初年の親鸞にすでに結定(けつじょう)している。それこそ他力信心のことわりであり、まったくわたくしなき、仏のかたよりもよおされる信心である。(100~101頁)
■ 親鸞はみずから釈して、
「尓(しか)れば、真実の行信(ぎょうしん)を護るものは心に歓喜多きが故に、是れを歓喜地と名づく。……十方の郡生海(ぐんじょうかい)、斯(こ)の行信に帰命(きみょう)すれば、摂取して捨てざるが故に、阿弥陀仏と名づく。是れを他力と曰(い)う。是を以て、龍樹大師は即時入必定(そくじにゅうひつじょう)と曰い、曇鸞大師は入正定聚之数(にゅうしょうじょうじゅししゅ)と云えり。仰いで斯れを憑(たの)むべく、専(もっぱ)ら斯を行ずべきなり」
と述べている。(113頁)
■ 親鸞はこのような念仏の特徴を、「化身土巻」の自釈において、つぎのようにまとめている。
「善本とは如来の嘉名(かみょう)なり。此の嘉名は万善円備せり。一切善法の本なり。故に善本というなり。徳本とは如来の徳号なり。此の徳号は、一声称念するに、至徳成満し、衆禍(しゅか)みな転ず。十方三世の徳号之本なり。故に徳本というなり」
すなわち名号は、あらゆる善なるものを円備しながら、しかもあらゆる善なるものの根本である。したがって、名号を称念することによって、善の根本が成就すると同時に、あらゆる不善なるものが転換するのである。親鸞はさらに「十方三世の徳号之本なり」といっているが、これについては後に論ずるように、念仏は時間・空間の普遍的世界を濾過し浄化する根本にまで徹底するということができよう。(114頁)
■ 「仏と仏と斉(ひと)しく証して、形、二の別なし。縦使(たと)い一を念じて多を見るとも、何の大道理にかそむかんや」
これによると、一仏の称名によって阿弥陀仏や一切仏を見ることは、仏仏相証の世界であって、いかなる仏も、自証の世界に相はないということになる。つまり阿弥陀仏も諸仏もまったく同一の世界を証しているのである。
『末燈鈔』に、
「釈迦・弥陀・十方の諸仏、みなおなじ御こころにて、本願念仏の衆生には、かげのかたちにそへるがごとくしてはなれたまはずとあかせり」
という。
本願念仏の衆生には、釈迦も弥陀も十方の諸仏も、同じ心でつきしたがうという。いいかえれば、阿弥陀仏も十方諸仏も、念仏の衆生に対してまったく同じ心であるというのである。(122~123頁)
真理の体現者 道元
■ このように見てくると、当時の情勢は、権謀術数と権力闘争との間断なき明け暮れであるといわなければならない。旧い体制が崩れ、新しい体制が興ってくる時には、民族の凝集したエネルギーが傾けられるが、そのエネルギーの移り行きは、ことに封建的世界が形成されつつある時代においては、権力者の戦意を中核として行われている。そして権力者の力と力とが衝突し合い、闘争が繰り返されつつ、唯一の権力者へと統合されていく。しかしその権力者もまた、いつ相対化されて次代のそれに取って代られるか分からない。しかしこのような権力の精神的核心は、全く我執に外ならないといえよう。そこから権謀と闘争とが間断なく生れてくるのである。
道元が古今を貫く真理の追求のために、このような世相に背を向けたことはまことに当然であった。同じいのちをかけるにしても、権力者は、権力獲得、いいかえれば我執拡大のためであり、道元は、まさにその我執を切り捨てることによって、決して相対化されることのない絶対不変の道を踏まえるためである。そしてこの着眼の基本的な相違にもとづいて、武士階級に現われた主従のうるわしい人倫関係も、道元の眼には弊履(へいり)のごときものであった。道元は、みずから解脱を求めるためには、師への奉仕さえ投げ捨てることを容認したのである。世の一般の、義理・人情、恩愛の絆、師弟の道は、大道の前には泡沫にひとしい。道元は徹底的に世界超越への路線を歩み続けたのである。(148~149頁)
■ 十五歳のとき、かれは宗教の根本問題につき当たっている。つまりわれわれは本来仏性をそなえ、その本性は清浄であるのに、なにゆえ三世(さんぜ)の諸仏は発心(ほっしん)して悟りを求める必要があるかというのである。これは、仏道を歩もうとするものの最初に逢着する問題である。不生禅(ふしょうぜん)で有名な盤珪(ばんけい、1622-93)も、少年のころ『大学』のなかの「明徳を明らかにす」という語を見て、もともと明らかな徳をなぜ明らかにする必要があるかという疑問をいだき、ついに禅門に入っている。道元と同質の根本問題といえよう。
道元はこの疑問をもって三井寺の公胤(こういん)をたずねたところ、この問いはたやすく答えることはできない、建仁寺の栄西(ようさい、1141~1215)に参禅せよ、といわれて栄西の門をたたき、臨済の宗風に接した。栄西の答えは、三世の諸仏などはいない。ただ狸や狐がいるだけだ、というのである。栄西は観念と現実のくいちがいを道元の前にはっきり示した。ここに道元の参禅が始まる。しかし栄西は翌年なくなり、道元はその弟子明全(みょうぜん)に師事することになった。(149~150頁)
■ 道元が如浄(にょじょう)に会見した刹那に、如浄は、「仏仏祖祖面授の法門現成せり」といっている。目的の大半はこのときすでに成就したというべきであろう。案に相違せず道元は、その後数ヵ月にして「参学の大事を了畢(りょうひつ)する」(悟りが徹底すること)のである。
その模様がつぎのように伝えられている。
ひとりの禅僧が坐禅しながら眠っているのを、如浄が叱りつけて、「参禅は身心脱落なるべきである。ただ眠るだけで何ができるか」と声をあらげた。傍らで参禅していた道元は、如浄のことばに豁然(かつねん)と大悟したのである。かれはただちに方丈にいたって焼香礼拝した。「如浄何のための焼香か」。道元「身心脱落し来(きた)る」。如浄「身心脱落、脱落身心」。道元「これはしばらくの力量である。どうかみだりに印可を授けたもうな」。如浄「みだりに印可を授けるのではない」。道元「みだりに印可を授けない。その当体は」。如浄「脱落脱落」。このとき道元は礼拝したという。
道元が如浄を古仏として崇拝し、いかに如浄に傾倒していたかは、その後の道元の言行からもうかがえるのであるが、右の身心脱落の刹那が、かれの究極目的の貫徹を物語るものである。道元はそれまでに悟りに類したことはいくたびか経験したであろうし、無際了派は印可まで与えようとしたが、かれ自らは満足しなかった。このことは「みだりに印可を授けたもうな」という右のことばにも現われているのであるが、そのことから同時にかれの徹底した批判精神もうかがうことができる。(151~152頁)
■ 如浄のもとの留まること二年あまり、道元は嘉禄(かろく)三年(1227)の秋、帰国する。はじめ京都の建仁寺におり、三十一歳のとき宇治深草の安養院に移り、翌年「弁道話」の説法、三十四歳のとき、近くの極楽寺の旧址に移り、観音導利院と称する。翌年第二祖の懐奘(えじょう)が弟子入りし、その翌年、僧堂の建立を発願し、さらにその翌年竣工、観音導利院興聖(こうしょう)宝林寺と命名する。いわゆる興聖寺である。道元が興聖寺に在住するのは前後十一年にわたり、この間に『正法願蔵』の「摩訶般若波羅蜜」「現成公案」をはじめ、多くの諸巻や、『典座(ぞ)教訓』『学道用心集』が述べられている。道元の名はようやくひろまり、弟子の礼をとって参禅するもの多く、また興聖寺の作法はきわめて厳格であった。日本における純粋の善はこの時に始まるといってよい。(152頁)
■ 遺偈(いげ)としてつぎの句が残っている。
「五十四年、第一天を照らす、箇の〔足ヘンに孛〕跳(ぼっちょう)を打して大千を触破す。咦(い)、渾身著する処なく、活(い)きながら黄泉(こうせん)に陥いる(注)」
(注)「五十四年の生涯の間、絶対界を照らしつづけてきた。どこまでも超越し抜いていく般若(智慧)を打って一丸となして三千大千世界(果てしなく広大な世界)を踏み破ってきた。ウン、そうだ。全身どこにも執著(しゅうじゃく)する所がない、活きながらあの世におちいる」(154頁)
■ 解脱を達成するための不可欠の要件は、いうまでもなく発(ほつ)菩提心である。発菩提心とは、解脱し、目覚めようとする心をおこすことである。(155頁)
■ ところで道元の発心は、通常のそれと趣きを異にしている。通常には、菩提心とは無上正等覚心(この上もない目覚めの心)である、あるいは一念三千(天台の教理。一念のなかに地獄から仏までの無数のすがたをそなえること)の理解である、あるいは入仏界心(仏の世界に入る心)である、などと解されている。ところが道元は、それらは菩提心を知らないばかりでなく、むしろ菩提心を誹謗するものであるときめつける。
それはなぜであるか。道元の趣旨を推察してみると、およそつぎのように考えられよう。つまり、右に挙げた菩提心は、たんに菩提心の定義であり、説明であり、観念にすぎない。それは物の役には立たない。道元は、観念ではなく、具体的な事実の問題に着眼している。試みに、われわれの当面の心を反省してみよ。果たして一念三千の心や入仏界心になっているであろうか。決してそうではない。実際は愛欲・貪欲・名誉欲・利害関係などの妄想だけである。これがわれわれの現実の心である。発心は、このような現実の心に対応するものでなければならない。
右のような種々の欲望の根本は何であろうか。それは一語でいえば我執(がしゅう)であり、道元のいう呉我の心である。道元はしきりに、呉我を離れよ、我見を離れよと強調する。(156頁)
■ 迷いの側から見れば、吾我の心は、我あると執著するこころである。そうだとすれば、解脱を得るためには、この心を除かねばならない。それと同時に自己意識としての人格や知性の基盤(人間的分別の立場)をも離れなければならない。われわれが真に絶対自由の世界に解放されるためには、人間のあらゆる立場を抜本的に離脱せねばならないのである。
ここに道元の徹底的な世界超越の路線が敷かれている。かれは真っ向から世界全体を否定する。そしてそれこそが、かれのいわゆる発心である。道元のことばにしたがえば、無常を観ずることである。この世界には何ものも常住不変のものはない。自己そのものが無常である。(157頁)
■ では無常に徹し吾我を離れて、どうなるのであろうか。どうなるものでもない。吾我を離れたそのままが仏を受けとることである。無常に徹することが、仏道のはじまりであるとすれば、仏を受けとることは目標の達成であるといってよい。このように見ると、仏道の道程はきわめて簡単である。吾我を離れて仏を受けとることで万事終了であり、その他の複雑な理論は一切無用である。
こういってしまえば簡単であるが、実際は必ずしもそうはいかない。吾我を離れることは、自分自身を捨てることであり、身心を放下(ほうげ)することである。仏道は、身心を放下して、ひたすら仏の大海に入ることである。百尺の竿頭一歩を進めよ、という語があるが、一歩を進めたら落ちて死んでしまう。そこで竿頭に強く執著しようとする心が残る。その心を放ち捨てて一歩を進めよ、というのである。それが身心放下である。このように捨て身にならねば、いかに懸命に学道に励んでも、悟りを得ることは不可能である。だから思い切って放下してしまえという。(『随聞記』四ノ一)(158頁)
■ では実際にはどのような方法があるというのか。その方法はまたきわめて簡単である。道元は只管打坐(しかんたざ)という。ただひたすら坐禅して、自己の全体を打って一丸となすことである。その間に、吾我を離れ、身心を放下して仏の大海に入る。道はただ坐禅より外にはない。坐禅を通じてのみ解脱は得られる。それがすなわち只管打坐である。
われわれはただひたすら坐禅し抜いていかねばならない。座禅はただそれを行なうことによってのみ、会得される。それはたとえば善人と交わるごときものである。善人と交わっておれば、知らず識らずのうちに、われわれ自身もまた善人となる。坐禅も同様で、久しい間続けていくうちに、いつとはなしに身心脱落し、解脱を得ることができるという。(『随聞記』五ノ三)(159頁)
■ 「学道の人は吾我のために仏法を学する事なかれ。ただ仏法のために仏法を学すべきなり。その故実は、我が身心を一物ものこさず放下して、仏法の大海に廻向(えこう)すべきなり。その後は一切の是非を管ずる事なく我が心を存ずる事なく、成し難き事なりとも、仏法につかはれて強いて是れをなし、我が心になしたき事なりとも、仏法の道理になすべからざる事ならば放下すべきなり。……ただ一たび仏道に廻向しつる上は、二たび自己をかへりみず、仏法のおきてに任せて行じゆきて、私曲を存ずる事なかれ。先証皆是(かく)のごとし。心にねがひてもとむる事無ければ即ち大安楽なり」(『随聞記』六ノ二)
学道の目的は、ただ仏法のために仏法を学ぶことである。わが身心の一切を抛(なげう)って仏法の大海に進入いた後は、私心を存することなく、全生活はただ仏法のために使われるべきである。それが大安楽であるという。
以上の道元の言葉から、一切の心構えを振り捨てた只管打坐の態度が了解できよう。それは、この身この心のままで、ただひたすら坐禅することである。そうすることによってこの身この心のままで、ただひたすら坐禅することである。そうすることによってこの身この心がそのままで仏を受け入れ、仏法の大海に浮び出る。そして一度その大海に浮び出れば、後は仏法のおきてにしたがって生きるのみである。(160~161頁)
■ 道元においては、解脱を得るためのただ一つの道は、これまで述べたように、ひたすら坐禅することであるが、それと併せて、正しい師につくことが必須の条件であると強調している。正しい師ということを道元はつぎのように定義している。それは、年齢の多少を問わず、正しい仏法を究明してその証拠を得ているものであるという。この定義はいかにも簡潔であるが、道元の批判は非常にきびしい、かれ自身が正師をたずねて中国にわたり、やっと如浄(にょじょう)に遭遇したほどであり、またわが国ではこれまで大師といわれている人々は出ているが、正師は一人もいないと名言している。その理由は、著作を見れば分かるのであり、ただ文字を伝えているだけで、悟道に達している面影は見られないというのである。
正師との出会いは、道元にとっては決定的な運命を意味するものであった。それは、正師によって正しい方を伝えるとともに、正師はそのまま仏祖であり、仏から仏へのつながりを表示するものである。だから道元が正師について正法を伝えたということは、その正法はただちに釈尊にさかのぼり、さらに過去七仏にまで遡源(そげん)する。過去七仏というのは、釈尊以前の諸仏であって、いわゆる歴史上の人物ではない。しかし七仏のつながりという歴史性は有している。それは、いわゆる歴史上の人物ではない。それは、いわば形而下の歴史に対する形而上の歴史ともいうべきものである。こうしてみると、道元の体得した正法は、永遠の仏から永遠の仏への伝法であったということができる。しかもかれにとって、それは観念上の事柄ではなく、もっとも実感的に仏の法を受けついでいる。過去七仏から釈尊へ、さらに次から次へと伝わって道元にいたっている。いわば歴史性と永遠性とが、道元が身をもって確かめた悟りのなかに一体になっているといえよう。(161~162頁)
■ では、仏から仏へと伝わる法とはいかなるものであろうか、それはいうまでもなく究極のさとりではあるが、そのさとりはどのように経験されるのであろうか。その悟りが事実上経験されて、仏祖正伝の道がわれわれの上に伝わらなくては、意味がないのである。
道元はそれを、単座参禅を入口とする所の自受用三昧(じじゅようざんまい)と名づけている。端座は正しく坐ることであり、参禅は禅の世界に参入することである。そして端座参禅には、前に述べたように、正師につくという条件が附されている。しかし要領としては、ただひたすら坐るという只管打坐が基本である。ただひたすら坐ることによって自受用三昧が得られるのである。
自受用三昧とは、「弁道話」に、
「ほとけ仏にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧、その標準なり」
といわれている。
この三昧は、永遠の仏から仏へと正伝してきた所の、いわば宇宙仏の三昧である。只管打坐は、この宇宙仏の三昧に与ることである。すべての作為を離れた只管打坐でなければ、自受用三昧に与ることはできない。逆にいえば只管打坐は、永遠の仏の顕わになっている三昧である。この点に、ブッダ以来の仏道の原型を道元のなかに明瞭に読みとることができるのであろう。(162~163頁)
■ ただ端座参禅することによって、三昧が感得されてくるのである。だから端座参禅の目的は、ここに明瞭となる。それは、一つには、この三昧によって限りなく自己を超えていくことであり、二つには、この三昧はあまねく人々・事物の上にそなわっているから、三昧のなかにありとあらゆるものを具現していくことである。
この二つの目標は、仏祖正伝の道における車の両輪のごときものであろう。一方では、どこまでも自己を超脱し、世界を超脱していく。同時に他方では、その超脱し切っていく三昧のなかにかえって森羅万象が実現する。むしろ超脱すればこそ、万象が顕にわになる、あたかも鏡が透明であり、無心であればあるほど、万象をうつして止まないがごとくである。このように見ると、この二つは、車の両輪のごとくでありながら実は一つである。その一つの所が自受用三昧といい、その三昧のなかに万法が具現しているのである。(164頁)
■ この自受用三昧は、道元によって種々の別名で呼ばれている。すなわち、三昧王三昧、自証三昧、海印三昧などである。
三昧王三昧は、三昧のなかの王三昧といういみである。三昧には多くの三昧がある。たとえば、空三昧・無相三昧・無願三昧の3三昧があり、また、大乗仏典には、般舟(はんじゅ)三昧・首楞厳(しゅりょうごん)三昧・慧印(えいん)三昧・法華三昧・如幻(にょげん)三昧・観仏三昧・月燈(がっとう)三昧・獅子奮迅三昧など、無数にある。また、三昧は身心がそれになり切っていることであるから、世俗においても、たとえば、読書三昧・勉強三昧・釣三昧(岡野注;描画三昧)など、多くの三昧が数えられよう。
しかし道元のいう三昧のなかの王三昧は、ただ結跏趺坐の三昧をいうのである。結跏趺坐とは、両足を組み、印を結ぶ坐禅の姿であり、端坐参禅である。正しい姿勢、正しい手足の結印や組み方によって、ただ坐るだけである。ではこのような簡単な坐禅が、なぜ王三昧になるのであろうか。それは一つには、この三昧こそ、過去七仏以来、諸仏諸祖が伝えてきた方法であり、また二つには、この三昧のなかに、すべての三昧が収められて、天地・万物と我と一体なる世界が開示されるからである。(164~165頁)
■ 道元によれば、このような結跏趺坐の三昧に徹底している禅者は滅多になく、
「仏祖の眼睛裏(がんせいり)に打坐すること、四五百年よりこのかたは、ただ先師(如浄)ひとりなり」(『正法眼蔵』「三昧王三昧」)
といっている。
仏祖の眼のたまのなかで坐禅しているもの、つまり仏祖正伝の坐禅に徹しているものは、四五百年来、如浄禅師ひとりだけであるという。では坐禅に徹しているというのはどういう意味か。仏法はすなわち打坐であり、打坐はすなわち仏法であると体得していること、さらに進んで、打坐を打坐と知り、仏法を仏法と知ることであるという。打坐を仏法であると知ることとりも、打坐を打坐と知ることの方が一そう徹底しているというのである。打坐を打坐と知ることは、打坐を仏法と置きかえなくても、打坐だけで十分充ち足りているのであり、打坐の外にも何物も望む要のないことを指している。このような結跏趺坐こそ、仏祖の命脈であり、三昧王三昧である。(166頁)
■ したがって結跏趺坐は、自証三昧ともいわれるのである。過去七仏から仏仏祖祖正伝し、ついに我において証明される所の三昧である。何が証明されるかといえば、十方世界を尽くして、山川草木がことごとく仏法であり、さらに、食事や衣服を整える日常の作法から、一挙手・一投足にいたる刹那刹那の挙動まで、すべてこれ仏法であることを親しくうなずくことに外ならない。
このうなずくということは、心をもってうなずき、身をもってうなずき、あるいはまた全身心をなげうって仏法をうけ入れることである。それが仏祖の眼の玉であるというのである。このような眼の玉は、過去七仏から釈尊を経て、次第に受け継いで道元にいたっているという、もっともリアルな、しかも一種歴史的な、あるいはむしろ形而上ー歴史的な伝法である。いわばそれは、時間的に縦に貫いた伝法のリアリティであるとともに、前に述べた十方世界、挙手投足がことごとく仏法であるという空間のリアリティが二重の意味を担っている。すなわち、仏仏祖祖正伝し来たった伝法が道元にとってリアルであればこそ、実はそれが、いつでも、どこでも、しかも何物によっても伝法し得る、いなむしろそのままが伝法であるという、時間的・空間的に普遍的な〔うなずき〕のリアリティが実現しているのである。(166~167頁)
■ 海印三昧というのは、もともと『華厳経』に述べられ、さらに中国の華厳宗で強調されてきたものである。(167頁)
■ 通常、思索し認識するという過程は、認識の主体と認識の対象との相対関係によって成り立っている。(168頁)
■ 道元は通常の意味の認識関係をどこまでもしりぞけて、主体と対象との相関性を超えた、あるいはそれを離れた世界、いいかえれば現在即今に開示されている世界――道元のいう恁麼(いんも)――を究明して止まない。したがって究明している道元の主体そのものは、即今に開示されている世界のなかに解消し、あるいはそれに埋没し、いいかえれば主体は世界そのものとなって、その世界を究明するのである。ここに道元の独特の思索が展開する。(168頁)
■ 道元はこのことを、
「海上行(こう)の功徳、その徹底行あり、これを深深海底行なりと海上行するなり」(『正法眼蔵』「海印三昧」)
といっている。
これは異様な表現であるが、その意味はつぎのごとくなるであろう。すなわち、海面を泳ぎながら、しかもその足は海底に徹しているのである。あるいは、深々と海底を行くままで海面を泳いでいるのである。普通に大海を遊泳しているといえば、魚や浮草を思い浮べるであろう。しかし魚や浮草の譬(たと)えには三昧の実態とは根本的に違っている所がある。魚は海中を泳いでいるだけであり、浮草は海面に浮遊しているだけである。しかるに海印三昧における万物は、海面を泳ぎながら、足が底についているという、つまりこの世に活動しながら悟りに徹底しているのである。これはたしかに自覚の世界であるが、しかし自覚によって始めてそうなっているのではない。意識しようとしまいと、それは自覚以前の海印三昧の実情である。このことは、きわめて重要な視点であり、そしてこの点にこそ、道元にまで正伝し来たった仏祖のいのち、永遠の仏の世界がかかっている。それは要するに、意識を離れて、いかなる一物も、何物にも疎外されることなく、徹底的に、あるいは底抜けて自由に活動している三昧の事情を表わしているのであろう。(169~170頁)
■ では、この場合における〈此の身〉とは何を指すのであろうか。それはもとより自我ではない。そうではなく、それこそまさに法なのである。法とは、たんなる〈もの〉ではなく、また〈心〉でもない。それは、海印三昧、すなはち宇宙そのものの仏の世界に〈あり〉、かつその世界から見られている〈もの〉である。だから、心的なものであれ、物的なものであれ、また事象であれ、ことごとく海印三昧にあり、何一つ法でないものはない。そのような無数の法が集中して〈此の身〉が成立しており、そしてそれもまた法である。
道元は『維摩経』の文を引きながらつぎのように述べている。
「但(ただ)、衆法(しゅぼう)をもって此の身を合成(ごうじょう)す。起る時は唯(ただ)法の起るなり。滅する時は唯法の滅するなり。此の法の起る時は、我起ると言はず。此の法の滅する時、我滅すと言はず。前念後念、念念相対せず。前法後法、法法相対せず。是(これ)を即ち名づけて海印三昧となす」(「海印三昧」)
此の身は多くの法によって合成されており、此の身が起るのは法の起るのであり、此の身が滅するのは法の滅するのである。それを自我が起ったり滅したりとはいわない、という。つまり自我という別人がいて、法の起滅を見聞しているのではない。そうではなく、無数の法によって合成されている〈此の身〉が起滅しているだけである。それは自我ではなく、無数の法の集中している〈全体の法〉が起滅している。起っている時は起っているだけ、滅する時は滅するだけである。たとえば春になった〈時〉は、春の全体が〈起って〉おり、夏になった〈時〉は、夏の全体が〈起って〉おり、そしてただ〈起っている〉のみである。
道元はこれを、
「起はかならず時節到来なり、〈時は起〉なるがゆゑに。いかならんかこれ起なる、〈起也〉なるべし」(「海印三昧」)
という。
したがって、起っている時はただ起っているだけであるから、何一つ隠されているものはない。「皮肉骨髄を独露さしめずといふことなし」という。皮も肉も骨も髄も、そして臓物(ぞうもつ)までもさらけ出している。一物も隠すことのない全露のすがたである。そして滅する時も同じように、このような全露の法が滅するのである。
ところで、この滅ということについて、仏教者は特別の感懐(かんかい)を伴うているのである。滅はすなわち、苦・集・滅・道の四諦のなかの滅諦であり、あらゆる煩悩の消滅を意味している。ここに、全露の法が滅するという時、それは、〈此の身〉にかかわっている全問題あるいは全煩悩が瞬時に滅することであり、道元はそれこそ無上大涅槃であるという。それは海印三昧における滅の功徳であるというのである。
このようにして、〈此の身〉すなわち全体の法は、瞬時の間断もなく停まる所をしらない。起っている時は起っているだけで絶対であり、滅する時は滅するだけで絶対である。起滅はただそれのみであるから、相対・対峙の関係を離れ切っている。この起滅停まることなき全露の、〈此の身〉の法こそ、仏祖の命脈であり、海印三昧である。(171~172頁)
■ これまで論じてきたような王三昧、あるいは海印三昧の世界を、自覚の核心から見ればどうなるのであろうか。そこには底抜けの希望と明るさと、永遠の解脱が息づいている。微塵(みじん)の暗さもペシミズムもない。道元は、それを、明珠とも光明とも、あるいは仏性とも表現している。
『正法眼蔵』には「一顆明珠」という巻がある。このなかに、「尽十方世界、是れ一顆の明珠」という一文がある。全宇宙が一つの明るい珠(たま)である、という。宇宙が一つの珠であるというのは、いったい何を意味しているのであろう。宇宙といえば、数かぎりのない日月星辰を思い浮べるであろうが、ここでは、外に見られた日月星辰を指すのではない。前の海印三昧においても触れたように、主体の自覚からみているのである。主体における執著(しゅうじゃく)の絆が断たれて、内から外に向かって門戸が開かれたときに、主体は宇宙と吹き通しになる。主体は宇宙と本質的に一体となるのである。その際の主体の自覚は、もはや自我意識にかこまれた個別的なものではない。〈此の身〉に生じている点ではまさに己の自覚であるが、自我意識の柵がはずされて宇宙意識となっている点では普遍的である。いわば、自己と普遍、主体と宇宙とが一つらなりとなっているといえよう。そのような自覚の世界が一個の明珠というのである。
このように見てくると、この珠は、現在一刹那の自覚に成立していると同時に、無限の過去にも遡(さかのぼ)り、尽未来際にもつながる。刹那的であると同時に永遠である。あるいはむしろ刹那のなかに永遠が展開していると見ることができよう。そしてこの珠こそ、仏祖の眼の玉(眼睛がんぜい)であり、それはただ仏から仏へと伝わるものである。(172~173頁)
■ 同じようなことではあるが、明珠や光明を、道元は仏性とも呼んでいる。『涅槃経』には、「一切衆生は悉(ことごと)く仏性を有す。如来は常住にして変易あることなし」という有名な言葉があるが、道元は『正法眼蔵』の「仏性」の最初にこれを提示している。
しかし仏性といえば、普通には、煩悩の身のなかに隠されている仏の本性というように解されやすい。ぶってんでは、仏性を如来蔵ともいうのであるが、たとえば『如来蔵経』では、右のような理解の仕方を示している。後の『宝性論』になってくると、このような実体的・対象的な解釈が消えて、作用的なものという見方が強くなってくる。道元は、仏性に関する実体性・対象性の見解を徹底的に排除し、そのような見解は外道(仏教以外の立場)であるとまで極言する。そして仏性の現実態を究明して止まないのである。したがって、道元の仏性論には、きわめてユニークな思索の跡をたどることができよう。(175頁)
■ そうだとすれば、全存在そのものは、一物も隠すことなく、〈むき出しのまま〉(徧界不會蔵へんかいかってかくさず)というほかない。そしてこの〈むき出し〉の存在そのものには、もはや主客の対立は解消してしまっている。つまり、存在そのものとの相関性は消失している。見ているものも見られているものもなくて、全存在が同一の〈むき出し〉である。だから強いていえば、この〈むき出し〉の存在は、存在がそのまま自覚であり、自覚がそのまま存在であるという、存在と自覚の二重性が、同一的に拡充し尽くされている。
このような性格を道元の表現に即していうと、存在そのものの〈むき出し〉は、永遠の過去から現在刹那に貫通しており(亙古亙今こうここうこん)、これに一物も加える余地がなく(不受一塵)、かつその全体が完結しており(合取)、そして真理の当体であり(是什麼物恁麼来ぜいんもぶついんもらい)、しかも日常生活そのままの心(平常心是道びょうじょうしんぜどう)である。したがって、あらゆる存在はそのまま、透明であり解脱している(透体脱落)、というのである。(176頁)
(岡野注;世界存在はこのようになっているのであり、画家はその世界を〈描写〉するだけである。私はイーゼル画(対象の直接描画)でそれを理解したのです。2021-12-5)
■ 道元はふたたび『涅槃経』の文を引き、
「仏性の義を知らんと欲せば、当(まさ)に時節の因縁を観ずべし。時節もし至れば、仏性現前す」
という。
ここで〈知る〉というのは、もとより認知だけでなく、行ずることも証することも含まれている。さらにいえば、忘れることさえも含まれているという。仏性の義を知ることは、すなわち忘れることであるというのである。われわれはここで、『正法眼蔵』の「現成公案」に述べられている有名な一文、
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわすれるるなり。自己をわするるといふは、万法に証せるるなり」
に思い到るであろう。
仏道をならうというのは自己をならうことであるが、それは自己を忘れるほかない。同じように仏性を知るためには、仏性を忘れるほかはない。仏性に関する分別・知見・智慧などがすべて除かれねばならない。仏性を忘れるとは、仏性の観念が消えることである。それが仏性そのもの(仏性聻ぶっしょうにい)であり、仏そのもの(仏仏聻)であり、性そのもの(性性聻)であるという。また、「時節もし至れば」というのを、「やがて時節が来た場合に」と解するのは外道の見解であるという。そうではなく、すでに時節は至っている、したがって仏性は現前しているのである。(177~178頁)
■ 以上述べてきた所から見ると、仏の世界は三昧であり、光明であり、そしてそれがそのまま現実のありとあらゆるものとなっており、自己の世界にまでいたっているということができる。そうしてみると、仏の世界は、われわれが見聞している自然ともなって現れている。むしろ自然そのものがすなわち仏の世界なのである。(178頁)
■ ところが道元のいう自然は、そうした見られている物ではない。道元の場合の自然は、〈物〉に力点が置かれているのではなく、字義通りに、〈おのずからそうなっている〉という所に視点が向けられている。同様に人間もまた、もともと〈おのずからそうなっている〉自然である、しかるに事実は、執心(しゅうしん)に障(さ)えられて本来の自然からつねにはみ出ている。その点に、われわれが自然を素直に、ありのままに見聞するという訓練(行)が要求されるのである。
(岡野注;画家の行はイーゼル画(対象の直接描画)である。既製品のソフトや、自我の欲望のオファーを解脱して、目を独立させ、裸眼で対象を見ると、ランダムドットステレオグラムのランダムなドットの中から、縦・横・奥行き・時間の構造が浮かび上がってくる。しかしそれを描写、顕現させるには、本(もと)に戻ってイーゼル画でスキルを磨くしかない。つまり修証一等(これも道元)なのですね。2021-12-8)
この訓練が熟して、要求が充されると、自然とわれわれとの間に、何物の介在物もなくなり、自然と人間とは同質化する。つまりわれわれもまた自然であり、自然もまたわれわれである。いいかえれば、宇宙は自然もわれわれも包んで一体であり、そのまま仏である。したがって自然を見聞せることは、すなわち仏を見聞していることとなるのである。(178~179頁)
(岡野注;スキルを磨いた画家のイーゼル画と同じでしょう。2021-12-9)
■ 生活がそのまま仏道であるということは、大乗仏教の原則であるが、道元は、とくにこの点に視聴を集めて強調している。かれが仏道の根本的解決をたずねて中国にわたり、ついに如浄の下で、身心脱落の体験を得て、究極の目的を達成し得た。しかしそれが神秘的な霊感にとどまるのか、またそれ以上の意味を持つのかということは、その体験以後のかれの思索と行動と生活とがこれを物語るのである。
けれども道元は、生活即仏道ということを軽快な心境でいっているのではない。とかく禅者ののなかには、さらりとした気持ちでこのことを受けとめ、軽快な行動がいかにも悟りの生活的な表現のように心得ている人があるが、およそ道元の場合は、それとは対照的なのである。かれが生活即仏道を唱える根底には、仏祖正伝の道の、大山にまさる重さがのしかかっており、したがってその重さの実感からにじみ出てくるきびしさによって、生活のひだひだを埋めつくしていこうとする気魄(きはく)がみなぎっている。
生活即仏道を、かれは行持というのであるが、それは、行を続けることによって生活のなかに仏道の真実を保持していくことを指していると思われる。したがって行持は、生活者における仏道の持続的な展開であり、行持によって仏道は、初めて生活のなかに具現していくということができる。
道元は、
「諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成(けんじょう)し、われらが大道通達するなり。われらが行持によりて、諸仏の行持見成(けんじょう)し、諸仏の大道通達するなり」(『正法眼蔵』「行持」)
と述べている。
われわれの行持が実現するのは仏祖の行持によるのであり、仏祖の行持が実現するのはわれわれの行持による、という。仏祖とわれわれとは、行持によってつながっており、行持によって、仏祖正伝の大道が顕(あら)わになるのである。とすれば、行持はまさに仏祖のいのちであるということができよう。
しかもかれは、
「無上の行持あり。道環して断絶せず、発心・修行・菩薩・涅槃、しばらくの間隙(けんぎゃく)あらず、行持道環なり」(「行持」)
と述べている。
行持は、どこで断絶するということはない。切れ目なく続いている。それはまさに生活が間断なく持続しているのと同様である。たとえば、菩提心をおこし、それにもとづいて修行し、ついには悟りを開き、涅槃に達し、そしてまた、菩提心・修行へと端(はし)なく連続している。したがって涅槃に達することが終局の到達点ではない。そこからまた、菩提心をおこし、修行へと続くのである。こうしてみると、われわれの生活は、いわば行持という太い軸がドーナツ型に円環的に結ばれており、われわれは綿密細心にこの軸を、仏祖の大道によって充たし続けていくべきである。ここでは、行持の円環的であることは、時の流れがまたそうであることを意味している。光陰むなしく過してはならない。時の一瞬一瞬が、仏のいのちであり、仏祖の大道である。その一瞬一瞬が綿密な行持によって充たされていかねばならない。
道元は、『正法眼蔵』の「洗面」という巻のなかで、ことこまかにそのやり方を述べている。洗面は面(かお)を洗うことであるが、もとより面だけではない。手を洗い、足を洗い、目を洗い、口を洗い、頭を洗い、体を洗い、心を洗い、生活を洗うことである。われわれの体も心も法界につながっており、その量は測り知れない無尽の意味をたたえている。そうだとすると、洗面は、この法界を洗うことであり、仏祖の大道を洗うこととなる。
道元は、たとえば楊枝を使う場合につぎのようにいう。
「歯のうえ、歯のうらをみがくように、とぎあらい、それを再三くりかえし、また、歯の根下の肉の上もよくみがき、歯の間をかきそろえて、よく洗え。たびたびうがいをして、すすぎきよめよ。また、面を洗う場合には、両手に桶の湯をすくい、額から眉毛、目、鼻のあな、耳のなか、耳のうら、頬など、あまねく洗え、その際よくよく湯をすくいかけて、摩擦するようにきよめよ、鼻しるや痰を桶のなかにおとしてはならぬ。むやみに湯をつかって、桶の外にもらし、早く湯を失ってはならぬ。あかおち、あぶらのぞかれるまで丁寧に洗え」
これが古仏の正法であり、仏祖の大道であるというのである。このようにして道元では、生活即仏道がすきまなく充たされているといえよう。(182~184頁)
■「生死」の巻には、
「この生死は、すなはち仏の御いのちなり、これをいとひ捨てんとすれば、すなはち仏の御いのちをうしなはんとするなり。……いとふことなく、したふことなき、このときはじめて、仏のこころにいる。……ただわが身をも心をも、はなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ仏となる」
という。
ここには、道元が生死をどのようにとらえ、どのようにそれを解脱しようとしたかが説かれている。生死は、生まれかわり死にかわりという輪廻を指しているが、もっと直接的に主体に引き入れて見れば、われわれの現実の生のことである。しかも、自分の生でありながら、根本的にこれを打開するすべもなく、ただあてもなくさまよう外はない生の根源状態である。それは、主体の自己把捉としては迷いであり、したがってこれを破って解脱へ向おうと決意する発菩提心が、求道(ぐどう)の第一要件として要請される。
ところが道元はここで、生死を捨てる、破る、という否定的態度を拒否している。それはかえって仏のいのちを失うことだという。なぜかといえば、捨てるべき生死こそ実は仏のいのちだからである。では、どうして生死が仏の命といえるのであろうか。道元はこれについては何も触れていない。しかしその意味をよくよく考えてみると、捨てるべき、いとうべき現実の生の根源態の外に、どこにわれわれ自身の生があるか、いとうべき現実の生こそ、まさにわれわれ自身ではないか。生死をはなれて仏になるのは、まさにこの生死そのものである。この生死そのものにこそ、道元は仏を仰いだのである。
しかし生死が、そのままで仏のいのちではない。もしそうだとすれば、初めから問題はなく、発菩提心の要もない。そうかといって、仏は生死の別にあるのではない。道元は、生死とは全く次元の異なった仏を、生死の只中に仰いだのである。わが身も心もはなち忘れて投げ入れる仏は、実は生死と一体になっている仏である。だからこそ、生死をいとうことなく、したうことなく、ただ仏の家に投げ入れて、それにしたがっていくとき、はじめていとうべき生死をはなれて仏となるのである。この意味において「生死」の巻は、道元の宗教性の結びともいうべきものであると考えられる。(188~190頁)
■ 鎌倉時代には、周知のように、法然・親鸞・一遍・道元・日蓮などのすぐれた仏教者が輩出しており、この時代の仏教の精華であるといわれている。これはどのような意味であるかということを考えてみたいと思う。この問題を考察するについては、少なくとも二つの視点が挙げられよう。一つは、鎌倉時代に至るまでの社会的・歴史的な背景の変遷であり、もう一つは、日本仏教思想史上における鎌倉仏教の意味である。この二つの視点は、内容的には互いにつながりを持っている。
第一の視点は、一語でいえば、摂関政治から武家社会への移り変りであるといえよう。それは大局的に見れば、古代世界から中世的世界への転換であるということができる。古代国家は、四、五世紀ごろに出立し、七世紀になって律令体制として成立し、それが、十二、三世紀の動乱を通じて崩壊し、そして武士の支配による国家体制が形成されていくのである。
このような中世的世界への転換を、他の時代の転換と比べてみたらいかがであろうか。たとえば、古代国家の形成の場合は、隋唐や朝鮮三国(高句麗・新羅・百済)の制度的・文化的な影響を受けながら遂行されていった。また、明治維新を通じて幕藩体制から近代国家への変遷も、欧米の武力や文化に刺戟された傾向が著しい。さらに外に眼を転ずれば、古代ローマ帝国の崩壊もゲルマン民族の侵入によるし、中国や朝鮮における諸おうちょうの交替も、北方異民族の攻勢と無関係ではない。これに対して、平安から鎌倉への転換は、ほとんど外国との交渉関係はなく、全く日本内部の民族の力によっておこなわれたのである。これはきわめて特徴的であり、他に類例を見ることができない。このような民族の自主的な力の転換は、民族の思想の上にも、したがって日本仏教思想の流れにも現れずにおかないであろう。
第二の視点は、まさにその鎌倉仏教の日本仏教思想史における意味である。わたしはこれについて、いくつかの特徴を考えてみたいのであるが、この視点を念願におきながら、同時に道元の思想に焦点を合わせてみよう。(190~191頁)
■ たとえばつぎの一文を引いてみよう。
「尽十方といふは、遂物為己、遂己為物の未休なり。情生智隔を隔と道取する。これ回頭換面なり、展事投機なり、遂己為物のゆゑに未休なる尽十方なり。機先の道理なるゆゑに、機要の管得にあまねることあり」
これは『眼蔵』の「一顆明珠」の中の一文である。つまり、全世界は一つの透明な〈たま〉であるというのが、その全世界についての説明である。道元は、世をたんなる空間と見て、それを一つの〈たま〉といっているのではない。そうではなく、どこまでも自己の活動の持続として全世界をとらえ、しかもそのなかに超越的なものを体認しようとしている。右の文に即していうと、全世界というのは、間断なくつづく遂物為己・遂己為物であるという。つまり、物を追求しても結局は己(おのれ)以外のものではなく、逆に、己を追求してもそれは物に外ならぬ、物と己とが対立的にあるのではなく、たがいに全面的であるというのである。
しかもこのような実態の体認をさまたげているものは、分別の情感である。いわば認識の対象性ともいうべきものであろう。その分別が生ずると、真実の智慧が〈隔たる〉のである。(195~196頁)
■ 道元の思索は、いかなる場合にも平板ではない。平板は分別の対象性を意味するにすぎない。だからかれは、たとい仏教の伝統的な原理であっても、それが平板なる場合には敢然とそれに立ち向かうのである。(196頁)
■ 道元の『正法眼蔵』は決して体系的ではない。それぞれの任意の主題について書きつらねたものに過ぎない。また理論という点から見ると、それは倶舎・法相(ほっそう)のようなものではない。倶舎や法相では、主題を追って一節からつぎの節へと、客観的にまちまって理論が展開する。したがって理性によってわれわれは、その理論を追求していくことができる。その意味では思惟の対象性をふくんでいるといえよう。しかるに道元の場合はそうではない。一節から、その節を掘り下げつつあるいは否認しつつ、つぎの節へ移る。それは理性的思惟によって理解することはとうてい不可能である。思惟するもの自身が同時に思惟の対象であるという、いわば主体的思惟の自己展開であるといわねばならない。この思惟は、道元のきわめて得意とする所であり、道元的思惟の特徴が全巻にみなぎっている。このような思惟の主体性が、現代人の心を打つことは否(いな)み得ないであろう。
第二に、したがってその思惟は実存的であるといえよう。ヤスパースは、西洋の過去の哲学史に実存の照明を当てると、そこに実存が浮び上ってくるという趣旨を述べているが、道元の場合にこの照明は、道元独特の世界を浮び上らせるのである。
たとえば、『正法眼蔵』「有時(うじ)」では、存在(有)と時間(時)の関係が論ぜられている。道元によれば、存在はそのまま時間であり、時間はそのまま存在であるという。ハイデガーの場合には、その名著『存在と時間』のなかで、この主題について長広舌の論陣を張っているのであるが、道元はいとも淡泊に右のようにいうのである。ハイデガーも道元も、思索が主体的であるという点では類似しているが、前者は、ニーチェ、キルケゴールを継いで従来の哲学の道を踏み破るような非哲学性を有しているとはいえ、やはり西欧の土壌に培われた論理の上にたっている。その主体性の表明は依然として論理的である。それに比べると後者は、まさに直覚的であるといえよう。論理は、表に現れずに直覚の中に包まれて、直覚から直覚へと飛躍する。そのギャップは、道元を学ぼうとするもの自身が埋めなければならないのである。この埋める行為は、前にも触れたようにもはや理論的理性では十分でない。あたかもニーチェやキルケゴールが従来の理性的立場に反旗をひるがえして、みずからの哲学的道路を開鑿(かいさく)した例にも比せられよう。(202~203頁)
■ 第三に、近世から現代にかけて実証性という態度・方法・結果が強調されている。それは、自然科学から社会科学・人文科学にわたっている。さまざまの領域はちがっていても、一語でいえば、その性格は科学的・対象的であるといえよう。
これに対して道元の実証性とは何であろうか。前に述べたように、道元の特徴は、たんに理性的・実存的な思惟ではなく。身体的・全人格的な思惟(行)である。それは思惟という抽象的な作用に終るのではなく、そのような思惟を通じて、あるいはそのような思惟作用のままが、身体的・全人格的に〈見る〉・〈うなずく〉・〈実証する〉という働きを伴うている。これが道元の実証性であり、現代のそれが科学的・対象的であるのに対して、自覚的・主体的であるといえよう。
道元がこのような実証性に到達するまでには、修行の紆余曲折があったことはいうまでもない。その果てに生じた、如浄のもとにおける身心脱落の自覚は、実証性の確かな証拠であり、道元の生涯における最高度の実証体験である。しかしその後の道元の生活では、実証性の確度が薄れたのではなく、むしろその体験を転機として、実証性の意味が新しい段階に展開していく。それが「弁道話」に示される修証一等の見解である。
「仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆゑに、初心の弁道すなはち本証の全体なり。かるがゆゑに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指(じきし)の本証なるがゆゑなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし」
修証一等というのは、修行と悟りとが同一であり、修行がすなわち悟りであるということを指している。悟りは、ここでは最高度の実証体験である。常識では、修行の後に悟りがあると解されやすいが、道元は明白にこれを否定する。そうではなく、悟りの上の修行であるから、最初の弁道がそのまま本来の悟りの全体である。したがって修行の後に悟りを期待する心はしりぞけられねばならぬ。修行のままが悟りであるから、悟りに終着点はなく、悟りのままが修行であるから、修行に出発点はないという。
修行は、道元において結局は生活そのものである。とすれば、生活がいわゆる本証の全体であり、直ちに実証そのものである。道元の実証性はここに窮まるといってよい。(204~205頁)
(岡野注;世界存在の個別の形態はフラクタルで、全体はマンデルブロー集合で、現実の実体はテンセグリティー構造で存在している。道元の『正法眼蔵』の「現成公案」も「修証一等」もこの存在の幾何学的な形態をイメージすれば理解しやすい。もちろん、この世界観は、私の描写絵画の画面にも反映される)
■ 道元が表明しようとしている仏は、そのような神ではない。それは、わが背後に、わが頭上に想定される神ではなく、脚下に照顧して、わが坐上に実現する仏である。ここにも主体性と実証性とが折り重なって、仏の世界が道元のそれとして顕わになっている。仏の世界は、すでに論じたように、大自然として、またわれわれの生活そのものとして感知されている。
(岡野注;この宇宙は、神も仏も、イデア界も、我も、物も、全ての存在が、全体としてマンデルブロー集合の形態で存在している。そうだとしたら、この宇宙も高次の次元から見ればたった一つではないであろう。その時空全体を通貫している軌持(レール)が法(ダルマ)である)
仏教の無
■ また、‘無’常、‘無’我というばあいには、aという接頭語が附けられて否定の意味を表わしている。すなわち、無常は常住の否定、無我は自我の否定として示されている。
部派仏教(小乗)になると、説一切有部と称される学派が現れている。普通には有部といっている。ありとあらゆるものの実在を主張する学派である。したがってここでもまた、無は否定されている。
その有名な典籍の『大毘婆沙論(だいびばしゃろん)』のなかで、三世(過・現・未)実有論に関して、
「もし過去・未来、実有に非ざれば、現在もまた、これ無なるべし。過去・未来を観じて現在を施設するがゆえに。もし三世なくんば、すなわち有為なからん。もし有為なくんば、また無為なからん。……もし有為・無為なくんば、まさに一切法なかるべし。もし一切法なくんば、まさに解脱・涅槃なかるべし。これすなわち大邪見なり」(「大正」27.393中)
という。
ここに挙げている無の思想も徹底的な虚無論であり、有部は真っ向からこれを否定している。(212頁)
■ このような無と関連して考えられるべきものは空である。無と空はきわめて類似しておりながら、無は否定性を示しておるのに対して、空はむしろ空という一つの主張を表わしている。
空の思想は、すでに原始経典のなかに、しかも最古層と考えられている『スッタニバータ』のなかに現れている。
「モッガラージャよ、つねに念じて、自我の見解を打ち破って、世間は空なりと観ぜよ。そうすれば死を越えることができよう。このように世間を観ずるものを死王は見ることがない」(1119)
ここでは、世間は空なりということは、一つの基本的な世界観であり、積極的な主張である。無がたんに否定性を表わすものとは異なっている。そして空の世界観は、自我の見解を打ち破ることによって開かれてくるのである。
その外、原始経典においてはさまざまな形で空が示されている。一、二の例を挙げよう。たとえば、『マッジマ・ニカーヤ』(MN.vol.1.p.485)のなかには、一切の存在を無常・苦・無我などと並んで空として観ずれば、一切の存在から心は解放される、と説かれている。
また同じく『マッジマ・ニカーヤ』のなかで釈尊は、
「わたしは、以前も今も、空性に安らうものとして安定している。たとえばこの鹿母(ろくも)講堂は、象・牛・馬・牝馬について空であり、金・銀について空であり、男・女の集まりについて空である」(MN.vol.111.p.104)
と述べている。
さらに『テーラ・ガーター』には、
「その煩悩は断じ尽くされ、食に執著することなく、その行いは空・無相・解脱である。虚空を行く鳥の跡のようにその跡を測ることはむずかしい」(92)
という。(214~215頁)
■ ナーガールジュナの次の一文は、まさにそのことを示している。
「空性の成立している人には、一切が成立し、空性の成立していない人には、一切が成立しない」(『中論頌』観四諦品集24・第14偈)(216頁)
■ クラマジーヴァ(羅什。らじゅう。344-413)は、中国仏教の初期における大翻訳家であるが、その『大乗大義章』に、
「もし法身、無来にして無去(むこ)なりといえば、すなわちこれ法身の実相にして涅槃に同じ。無為にして無作なり。法身、また久しく住すといえども、有為の法、ついに無に帰す。その性、空寂なり」(「大正」45・123上)
という。
法身というのは、仏の究極の身体であり、色も形もなきものである。それは自己そのものであるととも、宇宙そのものであるともいうことができる。そのような法身は目覚めることが、仏に成ることであり、涅槃に達することである。それは、形なきものであるから無為であり、作用として捕らえられるものがないから無作である。したがって来ることもなく、去ることもない。このような法身においては、形あるもの(有為)はすべて〈無〉に帰し、その本性は〈空寂〉である、という。ここでは、無と空とは一つであり、しかもそれは、色も形もなき法身であり、涅槃であるとなすのである。(216~217頁)
■ 無を宗教的体験として体得するか、あるいは現実生活の事実上の経験のなかで無を追求するか、いずれかに依らねばならぬであろう。従来の仏教では、現実生活の経験のなかで無を追求するということは、まだ十分に発達していない。したがって、その方面の思想や哲学も展開しなかった。このことは、今後の課題となるであろう。(220頁)
■『金剛般若経』のなかで、究極の目覚めについて釈尊とスプーティ(須菩提)との間で問答が交されている。
釈尊がスプーティに向かって、
「如来によって、これが究極の目覚めであると、まのあたり自覚した所のなにらかの法があるとお前は考えるか」
と問うと、スプーティは、
「わたしが世尊の説かれた意味を知る限りでは、如来によって、これが究極の目覚めであると、まのあたり自覚した所のなんらの法も存在しません。なぜなら如来のまのあたり自覚した所の法は、不可取(ふかしゅ)であり、不可説であります。というのは、聖人(しょうにん)は、無為から現れたものであるから」
と答えている。
すなわち究極の目覚めに達してみると、これがまさにそうであるというごときものは全く存在しない。という。それでは何を自覚するかといえば、それは不可取であり、不可説であるという。不可取や不可説は、認知不可能として先へ押しやるのではなく、実はそれこそが自覚の当体なのである。ここで聖人というのは、そのような自覚の主体を表わしているのであろう。すなわち、自覚の主体は、無為から、いいかえれば全く形なき世界から現われているというのである。
不可取や不可説がまさに自覚の当体であり、全く形なき無為が自覚の主体であるとすれば、これもまた無の体得というほかないであろう。このように見てくると、無の体得の資料は限りなく見出される。(222頁)
■ 天台宗の確立に与(あずか)って力のあったのは、慧思(えし、515-577)と智顗(ちぎ、538-597)である。二人ともきわめて実践的・体験的な人で、つねに道を追求して止まなかった。したがってその態度は、当然ながら、なにものにも捕われない般若(智慧)の探求であり、それゆえに無への徹底である。慧思は、体系をつくる暇もないほどに、道を求むること急であったが、智顗はその実践的態度を承けつつ、さまざまな体系を構成したのである。(224頁)
■ そのなかでも特に無の思想に関するものとして、空仮中(くうげちゅう)の三諦円融(さんたいえんにゅう)を挙げることができる。これはもともと、ナーガールジュナの『中論頌(じゅ)』の、「縁起なるものを、われわれは空と説く。それは相対的な施設(せせつ)であり、また実に中道である」という偈にかかわっている。空とは、ありとあらゆる存在・事柄は、ことごとく実体のないものであり、したがって空である。しかしその空のままが、あらゆる存在・事柄として現われている。それが仮(け)である。それゆえ空即仮、仮即空である。このように体得してみると、いかなる存在・事柄も、中心的な道を踏みはずすことがない。すなわち中である。したがって空即仮、仮即空となって、空仮中の三つの真理は円(まど)かに融合しているとなすのである。この点を具体的には、「一色一香、中道に非ざるはなし」とも、「資生産業、ことごとく中道に違背せず」ともいう。いかなる存在もことごとく中道であり、また、われわれの生活のそのままが中道であるというのである。このような三諦円融(さんたいえんにゅう)は、もとよりたんなる理論ではなく、生活の実践を導くものであるから、無(空)への徹底、無(空)の体験が、つねにその根底をなしていることはいうまでもないであろう。(224~225頁)
■ 華厳宗の大成者は法蔵(643-712)である。その根本思想は重重無尽の法界縁起である。あるいは、事事無碍法界ともいわれる。すなわち全宇宙のあるとあらゆる存在・事柄が、互いに果てしなく関係し合っているということを、究極の世界観となしている。そしてこれにもとづいて、十玄門・六相のごとき体系が構成された。
ところで、事事無碍法界を基礎づけるものは、理事無碍法界である。それは、すべての存在・事柄と真理とが互いに無障碍であるという世界である。この真理とは何を指すのか。それは結局、無への徹底、空の体得の外にはない。この体得の強力な裏づけがあってこそ、理事無碍、事事無碍の華厳独自の世界観が構成されたのである。(225頁)
■ 無の追求の純粋な実践は、何といっても禅宗に極まるといって過言ではない。禅宗は、坐禅というもっとも単純な修行法を通じて、ひたすら無の体得に専念し来たったのである。禅宗の全思想史は、無の追求によって貫かれているといえよう。したがって禅宗の文献のなかから、無の体得に関するものを拾い出せば、枚挙に遑(いとま)がない。(226頁)
■ ここで説いているのは、無の解釈ではない。無の体得へのすじ道を述べている。それにはまず、坐禅を通じて無になり切ることを学ばねばならぬ。ここには、言葉の説明や心の働きの立ち入る余地はない。坐禅のなかで、ただひたすら自己の全人格が無と一つになっていくことである。やがて自己もなく、無もなく、ただ打成一片(だじょういっぺん)となる。すなわち、全自己が、体も心も打って一丸となるのである。しかしこの状態もまだ不徹底である。さらに、打成一片をひたすら爆進するうちに、戛念(かつねん)として全自己が爆発し、無そのものに帰する。同時にそれは有そのものへの蘇(よみがえ)りである。絶対無がそのまま絶対有である。あるいは、無もなく有もなく、自己もなく世界もなく、しかも歴然(れきねん)として一切が現成している。これこそまさに無の体得であり、体得そのものである。しかし、求道(ぐどう)の過程は、これで終わったのではない。むしろこれが始まりであり、出立点である。そして長い時間を要して、生活と仏道とが融合し、生活のままが仏道となっていく。それは、仏道の無限の過程である。(227~228頁)
■ 空海は、『即身成仏義』のなかで、
「法身は大虚に同じうして無碍なり。衆象を含んで常恒(じょうごう)なり」(高野山大学『十巻章』14頁)
と述べている。
法身は、もとより色も形もなく、大虚に同じきものである。そのような絶対無の法身であればこそ、そのままが六大無碍となっている。すなわち、地・水・火・風・空・識の六つの要素が、互いに隔てなく融け合いながら活動しており、それがさのままヴィルシャナ仏の働きである。それは、唯物論でもなく、唯心論でもない。むしろ唯物のままが唯心であり、唯心のままが唯物である。世界の成り立ちのままが自覚の成り立ちであり、自覚の成り立ちのままが世界の成り立ちである。物も心も、世界も自覚も、たがいに無障碍である。絶対無の発展は、ついにここまで達したといえよう。(230頁)
■ 同じ鎌倉時代に道元(1200-1253)が現われた。禅宗のなかの曹洞(そうとう)宗の系統にありながら、その思想は独自のものである。
『正法眼蔵』「弁道話」のなかで、
「打坐して身心脱落することをえよ。もし人一時なりといふとも、三業に仏印を標し、三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる。ゆゑに諸仏如来をしては、本地の法楽をまし、覚道の荘厳をあらたにす。……万物ともに仏身を使用して、すみやかに証会の辺際を一超して、……究竟無為の深般若を開演す。……わづかに一人一時の坐禅なりといへども、諸法とあひ冥(みょう)し、諸時とまどかに通ずるがゆゑに、無尽法界のなかに、去来現に、常恒(じょうごう)の仏化(ぶつげ)道事をなすなり。……空をうちてひびきをなすこと、撞(とう)の前後に妙声綿綿たるものなり」(岩波文庫本・上、57-59頁)
とある。(232~233頁)
このように道元においてもまた、絶対無が深般若の説法を開演し、妙声(みょうしょう)のひびきをたてるのである。ただ、親鸞においては信心であり、道元においては坐禅である。いずれも人間の主体的態度において異なることはないが、同じ主体性のなかに微妙に相違する所がある。その相違の振幅を究めていくことは、きわめて興味ある問題であり、今後の大きな課題となるであろう。
以上、これまで発展してきた仏教思想の上で、無の問題を考えてみたのである。たんに無という言葉だけに捕われないで、無の意味を考察してみると、それは全仏教のもっとも基本的な立場を表わしていることが知られる。時には、空となり、無所有となり、不可説となり、またときに、実相となり、法性となり、真如となり、またあるときは、法身となり、ヴィルシャナ仏となり、尽十方無碍光如来となっている。それはすべて絶対無であることにおいて異なることはないが、名目の変るにしたがって、その性格や方向も微妙に変容してくるのである。(232~234頁)
■ われわれは、右の名目による特徴の区別に、それぞれ名前を附してみよう。第一の空・無所有・不可説には、無執(しゅう)への無限前進、第二の実相・法性・真如には、実相への果てしなき追求、そして第三の法身・ヴィルシャナ仏・尽十方無碍光如来には、法身の無尽説法、という類である。このような第一・第二・第三の特徴は、実は絶対無そのもののさまざまな現われ方である。これらの諸特徴は、インドの原始仏教以来、日本の大乗仏教に至るまで、たがいにあざなえる縄のごとくになって発展し来たったものである。しかしきわめて大まかに区別するとすれば、無執への無限前進はインド的であり、実相への果てしなき追求は中国的あり、法身の無限説法は日本的であるといえるかもしれない。そしてその特徴の変容の間に、インドから中国へ、中国から日本への仏教の歩みのすがたをおぼろげながら辿ることができるであろう。(235~236頁)
仏教の時間論
■ 原始仏教のなかで、ブッダが七法について教えている所がある。すなわち、出家者は七法を知らねばならぬという。七法とは、知法・知義・知己・知節・知時・知衆・知人である。このなかに知時というのがある。時を知ることである。これは何を意味するのであろうか。
ブッダによれば、
「これが説示の時である、これが質問の時である、これが修行の時である、これが独坐の時である、と、このように出家者は時を知る」
とある。
ここで知時といっているのは哲学的な論究の時間論ではない。出家者として定められた行動の適切な時を知るというのが、その主題である。いいかえれば、出家者の行動が時宣に適するという実践的な意味が強調されている。(238頁)
■ 部派仏教は多くの学派に分れているが、そのなかで説一切有部がもっとも有力である。有部を中心に時間論を考察してみたい。その考え方を一語にして表わせば、「三世実有(さんぜじつう)、法体恒有(ほうたいごうう)」といわれるものである。すなわち、過去・未来・現在の三世は実在的であるから、存在の自体は恒常的である、という見解である。(240~241頁)
■ このように見てくると、先の『婆沙論』でも世友説を採用しているように、この『倶舎論』においても、世友の見解を有部の正当な説と見ている点で、両者は一致している。しかし、その他の法救・妙音・覚天の諸説が、有部として不適当であるかどうか、これだけの解説では判断dきない。ことに肝心の実体とは何を指しているか、という問題になると、何れの説においても明らかでない。世友説でも、作用の存否によって過去・未来・現在の境位が変るだけであって、実体については何事も触れていない。
そもそも最初に述べたように、世と行とは同一と見られている。過去・未来・現在の時間がすなわち物の働きであり、働きがそのまま時間である。こうしたなかで、実体とは何か、という問題を追求しても不明に終らざるを得ない。しかし、過去・未来・現在の存在を主張した根拠は、すでに触れたように、きわめて実際的な感覚から出ていると思われる。すなわち、過去を否定すれば、それから影響を受けている現在もなくなり、さらに未来の結果も成立しない、というたぐいである。つまり、現在時点という否定できない存在感覚に出立して、現在と関係している過去も未来もまた必然的に存在せざるを得ない、という立場をとっていることは明らかであろう。(246~247頁)
ナーガールジュナの時間論
■ ナーガールジュナ(龍樹)は『倶舎論(くしゃろん)』の作者ヴァスバンドゥよりも百年以上古い人であるが、かれはそれまで展開してきた有部の見解をとり上げ、かえってこれを基礎づけることによってその立場を逆転した。すなわち、有部が実在論をとっているとすれば、ナーガールジュナは絶対空の立場に立っている。しかし、それは有部の立場を基礎づけることによってそうなったのであり、したがって、一切は空であればこそ一切は成立し得るということを主張している。
かれの時間論は、端的には『中論』観時品(ぼん)第十九に現われている。観時というのは、kala-pariksa すなわち、「時間の考察」という意味である。ナーガールジュナの作は実は『中論』のなかの偈(げ)のみであるから、まず第一偈を見てみよう。
「もし現在と未来とが、実に過去に関係してあるならば、現在と未来とは過去時のなかにあるであろう」
この偈の起ってきた背景を考えてみると、チベット訳『無畏論(むいろん)』によれば、現在と未来は過去に関係し、過去と未来は現在に関係し、現在と過去は未来に関係する、ということが前提となっている。漢訳の青目(しょうもく)釈も同様である。チャンドラキールティも、過去・未来・現在の三時は、存在自体の関係であるといっており、同様の意味である。つまり、過去・未来・現在はたがいに関係し合って成立しているという見解である。これは前に論じた有部の立場に外ならない。ナーガールジュナはこの立場を引き受けて論法を進めていく。それが、まずこの第一偈となって現われている。
しかし考えてみると、この第一偈には問題がある。すなわち、現在と未来とが過去に関係しているということから、どうして現在と未来とが過去のなかに存在しなければならないという結論が出てくるのか。その論法は曖昧であり、観念的であって、なんら具体的な根拠は示されてもいないし、考えられもしない。
けれどもこの問題は別として、ナーガールジュナ自身は第一偈は成り立つと考えているのであろうか。かれはこれに対して直接には答えていないが、第二偈以下の内容から見て否定的であることは明らかである。この点について、『ブラサンナバダー』、青目釈、『般若灯論』などは、同様の理由を挙げている。すなわち、現在と未来とが過去時のなかにあるとすれば、現在も未来も過去時になってしまって、そうなれば過去もなくなる、なぜなら現在・未来にあっての過去だからである。という。
この論法も奇妙だと思うが、それも暫く措(お)くとして、つぎの第二偈は、その逆をいっている。
「もし現在と未来とが過去時中にないとすれば、現在と未来とはいかにして過去時に関係して存在しようか」
この論理も第一偈と同じようにすっきりとうなずけない。『ブラサンナバダー』は、虚空の青蓮華のように関係は存在しない、というだけであるし、青目釈は、三時それぞれ異相であるから関係は成立しない、という。ともかくナーガールジュナは、第一偈の主張とは反対に、現在と未来とが過去時にない場合には過去時に対する関係が成立しないことをいおうとしている。そしてその理由から第三偈、
「過去に関係せずして、両者(現在と未来)の成立はない。それゆえ現在時と未来時は存在しない」
という内容が必然的に主張される。
しかもさらに、その点から第四偈の、三時相互の関係、上中下、一異などの全関係が問われ、それらのものはすべて存在しない、という結論に至る。
このようにして、第五偈では、時はまったく不可得となり、最後の第六偈では、
「もし存在に依って時があるとすれば、存在を離れてどうして時があろう。しかるにいかなる存在もない。まして時があろうか」(岡野注;私の『全元論』では、存在全体は在る。個別の実体は無い。法は在って、常恒に存在を貫いている。実体は諸行無常である)
といわれる。
すなわち、存在が否定されているのに、存在にもとづいている時は、いうまでもなくあり得ない。という主張に終わるのである。(248~254頁)
華厳宗の時間論
■ 中国における、華厳宗の時間論は、華厳宗の独特の立場である重重無尽事事無碍法界にもとづいて立てられている。これは、宇宙のありとあらゆる事象はたがいにさまたげることなく影響し合い、しかもその作用はかさなり合って尽きることがない、という世界観である。(252頁)
道元の時間論
■ 道元の時間論は、『正法眼蔵』「有時」のなかで展開している。それは、今日の感覚から見ても、きわめて実存的性格の強いものであるということができる。しかも仏教思想一般については、哲学的思索を期待することはできないにもかかわらず、道元の論述には、ある意味のそうした傾向さえ追跡することも可能である。
かれの時間論には、つぎのような要素が組みこまれている、その要素というのは、時間・存在・光明・自己であり、これらの四要素が実は別々のものではなくて、一体をなしている。そしてこの点に、かれの時間論のきわめて独自的な性格を有する所以(ゆえん)が存すると思う。
「いはゆる有時は、時すでにこれ有なり。有はみな時なり、丈六金身(こんじん)これ時なり。時なるがゆえに、時の荘厳(しょうごん)光明あり」
という。
時間がすなわち存在であり、存在がそのまま時間である。一丈六尺の黄金の仏身がすなわち時である。時であるから時そのものが光明を放っている、というのである。
しかし道元のこれだけの文章からは、その真意を汲みとるわけにはいかない。もう少しかれのいうことを聞いてみよう。
「われを排列しおきて尽界とせり。この尽界の頭頭物物を時時なりと覰見(しょけん)すべし。物物の相礙(そうげ)せざるは、時時の相礙せざるがごとし。……われを排列して、われこれを見るなり、自己の時なる道理、それかくのごとし」
世界全体というのは、実は〈われ〉がすきまなく配列されたものである。その世界の事事物物を時そのものと見るべきである。事事物物がさまたげ合わないのは、それぞれの時がさまたげ合わないのと同じである。そのことは、いいかえれば、〈われ〉を配列しておいて、〈われ〉がこれを見ているのである。自己はすなはち時であるという道理は、まさにこのようなものである、という。
ここでは、存在と時間に対して、さらに〈われ〉が登場している。世界の事事物物がここにあるということは、いいかえれば、〈われ〉が持続的に配列されていることである。その〈われ〉の配列を〈われ〉が見ているのである。
このように、〈われ〉なる世界が登場していることは、存在と時間の一体的関係を〈われ〉なる自覚において基礎づけていると見てよいであろう。なぜなら、たんに存在がすなわち時間、時間がそのまま存在であることを強調するのみでは無意味と考えられるからである。〈われ〉の配列が〈われ〉が見ているという根本状況において、存在がすなわち時間、時間がそのまま存在となるのである。いいかえれば、一世界全体の事事物物がすなわち時そのものであるということ、また、事事物物がさまたげ合わないことは時がさまたげ合わないことであるということ、こうしたことは、すきまのない〈われ〉の配列が〈われ〉が見ていることにおいて成り立つのである
ところで、右のような存在・時間・自己の関係は、われわれの反省において推論された構造であって、道元自身は、このような反省を抜きにして、存在・時間・自己の一体性を強調している。ただかれの主張の文脈をたどっていくと、こうした構造が考えられ得るというにすぎない。しかもさらに立ち入っていくと、このような自覚の構造において、はじめて、道元の「時なるがゆゑに、時の荘厳光明あり」という主張もうなずかれ得ると思う。なぜなら、〈われ〉における自覚のなかで、時の光明は実現されるからであり、道元においては、存在・時間のたんなる形而上学的関係ではなく、有を尽し時を尽していく参学が最大の関心事だからである。
かくして道元では、時間・存在・光明・自己が一体となって見られている。しかしかれは、これらの相互の関係については、これ以上立ち入ろうとはしない。道元は、西洋の哲学的意味においては、けっして哲学的追求者であるとはいえない。その点で、『存在と時間』のなかで究明していくハイデカーの哲学的態度とは比較され得ないであろう。ただここで留意すべきことは、ハイデカーが「時間性」の過去・現在・未来の分析によって人間存在が根源的に「照らされている」ことを論証しているのに対して、道元は、時間・存在・光明・自己の一体性をゆるがすことはないという点で、両者は基本的に相違しているということである。(256~259頁)
■ 「仏法をならはざる凡夫の時節に、あらゆる見解(けんげ)は、有時のことばをきくにおもはく、あるときは三頭八臂(さんちょうはっぴ)となれき、あるときは丈六八尺られりき、たとへば河をすぎ、山をすぎしがごとくなりと。いまは、その山河たとひあるらめども、われすぎきたりて、いまは玉殿朱楼に処せり、山河われと天と地となりとおもふ」
常人の時間観念について、道元はまず右のように考えている。すなわち、あるときは三頭八臂となり、あるときは丈六八尺となるという。いいかえれば、常人は、その時時の現象を想い浮べている。あるいはまた、河をすぎ、山をすぎて、いまは玉殿朱楼にいる、という。山や河、玉殿朱楼や〈われ〉が互いに相対している。いわば、過去の経験にもとづく想起から、現在刹那の状況に至るまでの諸現象の対照が、すなわち時間である、と考えられている。
これに対して、常人の立場を破る、根源的経験の時間とはどういうものであろうか。
「いはゆる山をのぼり河をわたりし時に、われありき。われに時あるべし。われすでにあり、時さるべからず。時もし去来(こらい)の相にあらずば、上山(じょうざん)の時は有時の而今(しきん)なり。時もし去来の相を保任(ほうにん)せば、われに有時の而近あるこれ有時なり。かの上山渡河の時、この玉殿朱楼の時を呑却(たんきゃく)せざらんや」
常人の立場では、山河や玉殿朱楼あるいはわれがその時時の現象として対照されていた。しかるにここでは、そのその現象の一つ一つにわれが充足している。山にのぼり河をわたったときに、すでにわれがあった。このわれこそ、前に論じた、存在・時間・光明・自己の一体なるわれに外ならないであろう。したがってその時時が、たんなる現象の対照ではなくて、光明であり、絶対である。あるいは、もし時に去来の特徴があるとすれば、われが絶対で、永遠の今である。このような点から見ると、「山にのぼったとき、河を渡ったとき、その〈時〉が玉殿朱楼の現在の〈時〉を呑み尽さないことがあろうか」となるのである。
かくして、常人の立場では時間経過における相対観念であったものが、根源的人間の立場では、時間経過における時時が絶対であり、永遠の今であると、ということができるであろう。しかも面白いことに、道元は、山にのぼり河を渡った過去の時が玉殿朱楼の現在時を呑み尽くす、といっている。いわば、現在時が過去時になってしまうことである。これは、ナーガールジュナでは誤った論証として用いられ、華厳宗では相即相入の論理として提示されたものが、道元では、かれ自身の根源的体験のなかで独自の思索として表明されているのである。
常人の立場の第二は、時間経過における飛去(ひこ)観念とも名づけられるべきものである。
これは第一の相対観念と事実上は密着している。しかし、これまた常人の特徴を示すものとして取り上げてみよう。
道元はこれについて、
「時は飛去するものとのみ解会(げえ)すべからず、飛去は時の能とのみは学すべからず。時もし飛去に一任せば、間隙(けんぎゃく)ありぬべし。有時の道を経聞(きょうもん)せざるは、すぎぬるとのみ学するによりてなり」
という。
常人では、時は飛び去っていくとばかり理解している。飛び去るとは、主体者のその時時の観念である。つまり主体者の心には、飛び去るといういくつかの諸観念が浮かんでいる。その観念ではとうてい全空間をうずめることはできない。ここでも第一の場合と同じように、諸観念とわれとの相対性・対照性が指摘できるであろう。
これに対して道元は、
「要をとりていはば、尽界にあらゆる尽有(じんぬ)はつらなりながら時時なり、有時なるによりて吾有時なり。有時に経歴(きょうりゃく)の功徳あり、いはゆる今日より明日へ経歴す、今日より昨日に経歴す、昨日より今日へ経歴す、今日より今日に経歴す、明日より明日に経歴す。経歴はそれ時の功徳なるがゆゑに、古今の時かさなれるにあらず、ならびつもれるにあらざれども、青原(せいげん)も時なり、黄檗(おうばく)も時なり、黄西(こうぜい)も石頭も時なり。自他すでに時なるがゆゑに、修証は諸時なり」
と述べている。
宇宙に存在するありとあらゆるものは、一つにつらなりながら、その時事の絶対生命である。ここで、時の流れに関して、常人と根源的人間との見方がくっきりと区別される。すなわち、常人では飛去であるが、根源的人間では経歴である。飛去は、飛び去るという、主体者の観念であり、イメージにすぎない。したがって観念とわれとがばらばらであり、相対的である。経歴はそうではない。宇宙全体の一つらなりが動いていくことである。明日へも動き、今日へも動き、昨日へも動いていく、自由自在である。したがって、経歴は有時の功徳であるといわれる。この世界に立てば、青原(青原行思、740年歿。六祖慧能の弟子)も黄檗(黄檗希運、生歿年不詳。弟子に臨済義玄がある)も、自も他も修証も、鳥のさえずりも陽のかげりも、その一つ一つが絶対生命である。(260~263頁)
■ 最後に、どうしても一言附け加えておかねばならぬことは、これまで論じてきた時間論では、まだ道元は満足していないということである。道元の体験と思索とは、果てしなき彼方まで果てしなく伸びていく。
前項で、常人と根源的人間の立場とを区別した。常人は、いわば踏みちがえている人であり、根源的人間は正道を踏み歩く人である。しかし道元は、踏みちがえているという、そのことも見逃さない。
「たとひ半究尽(ぐうじん)の有時も、半有時の究尽なり。たとひ蹉過(しゃか)すとみゆる形段(いんとん)も有なり。さらにかれにまかすれば、蹉過の現成する前後ながら、有時の住位なり。住法位の活發發地(かつはつはつち)なる、これ有時なり」
たとい究尽(究明し尽くすこと)が不徹底の場合でも、それは半有時の究尽である。有時の究尽には変りない。またたとい、踏みちがえた場合でも、その踏みちがえた形態のままが有時である。さらに進んで、それ自体の立場に立ってしまうと、踏みちがえるということの実現している状態のままが、有時の在り方である。それ自体の在り方において、魚が飛びはねるように活き活きとしていることが、絶対の生命である、というのである。道元は、踏みちがえている、そのことの絶対性をも見透かしているといえよう。
しかし、かれの見透しはさらにその奥を開こうとする。奥には奥の体験へ向おうとするのである。
「去来(こらい)を認じて、住位の有時と見徹せる皮岱(ひたい)なし、いはんや透関(ちょうかん)の時あらんや。たひ住位を認ずとも、たれか既得(きて)恁麼(いんも)の保任を道得(どうて)せん。たとひ恁麼と道得せることひさしさを、いまだ面目現前を模索せざるなし」
時は去来するものであるとのみ認知して、永遠の今を徹見(てっけん)している人はまれである、ましてその永遠の今をも解脱している人があろうか、というのである。これは常人の立場にひとたび戻って反省したものであろう。つぎに、たとい永遠の今を認知しても、それを持ち続けるといい得るものが果たしてあろうか、という。認知から、さらにその持続へ進むことである。そして最後に、たとい持ち続けるといい得ること久しきにわたっても、本来のめんもくの実現を模索している程度である、というのである。
われわれは、思索をつくし体験を深めて存在と時間を究尽していっても、なお道元の右の意味深い指標から、さらにその究尽を踏み破っていく七花八裂(こなごなに砕けること、自由自在)の全体体験へ向かうべきことをきびしく教えられるのである。(264~266頁)
仏教の未来
■ 日本仏教が日本文化のなかに深く染みこんでおりながら、現代人にとって思想的にも言語的にもつながりのないことが、大きな特色となっている〔しかし、五十年百年先には、この問題は大きく変っていくにちがいないし、むしろそのことを期待する〕。これを西洋哲学の発展の仕方にくらべると、著しい相違が見られる。西洋では、ギリシャ思想とキリスト教とが入り組みながら、ルネッサンスとなり、ヨーロッパ大陸に合理主義、イギリスに経験論が発展して、カント哲学となり、そこからさまざまに発展して、現代の実存哲学やマルクス主義ともなっている。
西洋思想にはつねに発展があり、言語でも種々の国語が共存しながら、思想的にも言語的にも現代とつながっている。たとえば、ドイツ哲学を見ると、カント(1724-1804)のドイツ語がわかれば、現代のハイデガーのドイツ語もわかる。しかも思想的にも、ハイデガーはカント哲学につながっている。これをわが国でいえばどうか。
カントと同時代に活躍した日本の思想家は、本居宣長(1730-1801)である。しかし宣長の『玉勝間』は現代の日本語ではない。その間には二転三転している。まして、日本人には珍しく独創的な道元(1200-1253)の思想になると、専門の研究者でもその言語や思想をもてあましている。道元の思想は、現代人の一部には強い魅力となっているが、道元と現代との間の思想的なつながりは皆無である。(273~274頁)
■ もともとインド思想と仏教とは、同じインドに発生しながら、歴史的にはかなり違った様相を呈している。たとえば、インド思想では世界の創造神を立て、自我を主張するのに対して、仏教では創造神を認めず、自我を否定して無我を説くにである。自我説と無我説を廻って両者の間には論争も行なわれてきた。
しかしインド思想の場合、創造神や自我説をもっと深く考えてみると、必ずしも仏教と対立すべきものではないようである。創造神はヴェーダやウパニシャッドの神話に由来しているのであるが、その後思想が発達するにつれて、それは必ずしもキリスト教のような明白な人格神ではなく、時には人格的な神、時には非人格的な原理として理解されている。そうなると大乗仏教の仏でも、ある場合には人格的な仏として、またある場合には、色も形もない、世界に遍満する法身仏として現われているのであるから、両者の間にはとくに対立すべきものは存しないことになるであろう。また自我説と無我説についても、ことばの観念としてはいかにも対立するようであっても、インド思想のアートマン(真実の自我)の意味をウパニシャッドのなかでただしてみると、それは決して実体としてのアートマンではない。むしろ正しい智慧における主体的な自覚を指している。そうだとすれば、仏教において無我たることを主体的に自覚することと異なることはないであろう。(281頁)
■ 前に挙げた三種の慈悲の方式にも見られるが、原始仏教や部派仏教では、生活を律していく具体的な多くの戒律が成立しており、後の大乗仏教になって、宇宙的なブッダの無縁の大悲が強調されるようになった。時として、小乗の破戒こそ大乗の戒律であるとも主張された。
これは、仏教のおおらかさを特徴づけるものであることは論を待たない。しかし同時に、ブッダのはてしのない無縁の大悲が、現実社会の実践の上に、何か具体的な旗印となって凝結するものがほしい。初期仏教の戒律は、きわめて具体的であるが、その都度その都度決められた雑多なものである。それが願わくは、大乗仏教の宇宙的なブッダのなかに融けこんで、そこから基本的な一つの、しかも具体的、現代的な戒律の顕現が望ましいのである。その戒律は、ブッダの無縁の大悲と虚空のような大智とが凝結して、われわれの社会生活を律し、かつ推進していくような一つの根本限定でありたい。したがってもはやそれは戒律という名目から離れたものとなるであろう。(289頁)
■ 未来社会の理念は、仏典のどこに求められるであろうか。わたしは、これまで折に触れて主張してきたごとく、それは仏教を貫いている「帰依三宝」であり、ことに『華厳経』浄行品(ぼん)に示されているものである。
自ら仏に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、大道を対解(たいげ)して無上意を発(おこ)さん。
自ら法に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、深く経蔵に入りて智慧海のごとくならん。
自ら僧に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、大衆を統理して一切無碍(むげ)ならん。
これは菩薩の願いであるが、まず重要なことは、菩薩ひとりではなく、つねに大衆と共に行動しようとしていることである。大衆の道こそ仏道であり、それは日本仏教の直接目標である。そして第一には、帰依仏であり、無上の菩提心(究極の目覚めへ向おうとする心)をおこすことである。これは仏道の根幹である。第二は帰依法である。真理への果てしなき追求心と恭敬(くぎょう)心であり、深く経蔵に入って海のような智慧を保有することである。ここで経蔵というのは『華厳経』における善財童子の求道の精神からいえば、仏教の経典に限定さるべきものではない。ヒンズー教もキリスト教も、西洋哲学も自然科学も、あるいは無宗教と思われる人々の思想も、それが一道に達してさえおれば、深くそこに分け入って、海のような智慧を汲みとるべきである。第三は帰依僧である。僧はもともとサンガであり、道を中心として集まりである。ここでは、一般大衆のサンガにまで拡がっており、ついには世界全体の共同体にまで至る。観念論者も唯物論者も、もろもろの宗教人も無宗教の人も、そしてあらゆる階級、あらゆる国籍の人々がいる。それらの大衆が、いかに見解が違うとも、たがいにさまたげあうことなく、統理されたいという願いである。
以上のような帰依三宝は、もはや仏教だけのものではない。それは人類の未来社会に普遍的な理法となるべきものである。(297~298頁)
あとがき
■ 禅のいわゆる見性は、むしろ性見、性が見(あら)われる、ということであった。これを仏教の原点まで遡っていくと、ブッダの言葉で「ダンマが顕(あら)になる」ということに帰着する。このことを自分の禅定(ぜんじょう)で繰りかえし繰りかえし、日に日に試みていると、いつのまにかブッダや経典のイメージが消えていくと同時に、ブッダ以外の、ソクラテス、エムペドクレス、ヘラクレイトスも、中国の古典に散見される部分も、そしてイエスやパウロも、それぞれ表示は異なっていても、その裏にある本質は同じではないか、ということに気づいてくる。つまり禅定は、自分という人間の普遍的な形で自覚されるものであり、この点から、禅定という仏教語は、全人格的思惟、推理、あるいは全人格的営みという一般的な語に置きかえられることになる。
さらに踏みこんでいえば、人類に普遍的な、いわゆる対象的思惟、推理に対して、もうひとつ、同じく普遍的な、全人格的思惟、推理が、少なくとも古代の東西において働いていたことが知られる。それが、インド思想のヨーガや仏教の禅定という、確立された方法によって、細々ながらも伝わってきたのである。それを今日的な形で、人類共通の資産にまで実現していくことが、これからの課題となろう。(301~302頁)
■ ところで、仏教の内側で、禅定を重ねながら調べていくと、ブッダから大乗の諸経典へのつながりが次第に明らかになってくる。原始経典から『般若経』へ、原始経典から『法華経』への、必然的に展開してくる基幹線である。この基幹線が資料のなかで覗かれてくることは、この上もない興味深いことである。そしてこの基幹線を支えている禅定こそ、あらゆる学派を包蔵している仏教の原型であると思われる。(302頁)
■ それぬつけて、もうひとつ決定的に重要なことは、「ダンマが主体的に顕になる」というが、主体者のどこに顕わになるか、という問題である。数年前、仙台で原始経典を調べているうち、ブッダにとって説かれている業異熟(ごういじゅく、kamma-vipaka、カンマ・ヴィパーカ)という想念に出会ったとき、長いあいだ悶え煩っていたさがしものものが不意に目の前に現れた思いで、私は小躍りして歓喜した。ただちに一つの拙論を試みた。ダンマはまさに、この業異熟にこそ顕わになりつづけるのである。
業異熟とは、業体(ごったい)であり、私は人格的身体と名づけた。果てしない過去から、ありとあらゆるもの、生きとし生けるものと交わりながら営みつづけてきた行為の結果が、今ここに私の全存在の基体として現われていることである。それは、私という存在の、したがって私性の窮まりであると同時に、ありとあらゆるものとの絡まり合いの、最高度に実質的なものとして、公性の窮まりである。いいかえれば、個性的な人格的身体でありながら、共同体的な人格的身体である。
そうした業異熟の実質はなにであろうか。それは、まさしく我執と煩悩の底知れない渦である。固体的であるばかりでなく、共同体そのもの、世界そのものの、絶えることなく噴き出てくる我執である。いわば、密林の山中深い地の底より、掘りあげたばかりの、みずみずしいどす黒い鉱物である。
ブッダによってそれは無明と呼ばれた。しかるに、その後の仏教思想史は、この無明の課題に徹底して立ち向かわなかった。ただアビダルマの随眠(ずいみん、煩悩のこと)、唯識説のアーラヤ識、浄土教の煩悩具足が、わずかにこれに応じようとした。その他の大乗各派は、まともにこれを受けとめていないといわねばならない。
全人格的思惟における人格的身体は、これからの課題である。それは仏教学だけのことではない。未来の存在を問われている、われわれ人類のもんだいである。昭和五十七年初秋(303~304頁)
学術文庫あとがき
■ 私はただちに全人格的思惟の実行に移る。同時に研究者として、対照的思惟による学問的論究も積まねばならぬ。いわばこの相反する二つの訓練を同時に重ねてきた。何十年という時間の経過のあいだにはさまざまなことがおこる。二つの訓練の絡まりあう複雑な状況のなかで、時として全人格が爆発して一切が雲散霧消する。気づいてみれば、果てしなき宇宙それ自体となっている、形なきままの〈いのち〉そのものである。しかし、やがてそれも消えて、元の木阿弥の煩悩具足にもどる。こうしたことを性懲りもなくくりかえすこと数知れない。
あるいはまた、仏教の根底はなにか、と問うこと自体、すでに潜在意識のなかに答えが芽生えている。それが形なき〈いのち〉そのものであることは、山人格的に気づかれている。形がなければ、仏教の枠組みを超える、枠組みを超えれば、当然ながら、他の宗教、哲学にも同一の根底のあることが知られる。
このようにして長い時間踏みわたってきた自分の足跡を、本書とならんで、『東西思想の根底にあるもの』(講談社、昭和58年)、『比較思想論究』(講談社、昭和60年)にまとめてみた。ふりかえってみれば、茫々幾星霜、夢のごとく、幻のごとし。その夢幻のただなかにあって、次の命題がくっきりと浮びあがっている。
「形なき純粋生命が、全人格的思惟を営みつつある主体者に顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換、すなわち目覚めが実現する」
このなかで、主体者とはなにか、さらに具体的には何を指すのか。それがブッダのいう業熟体(前には業異熟という漢訳を用いたが、このほうに訂正する)でありいわゆる人格的身体である。唯識思想のアーラヤ識もこれにつながるが、単に識というのみでは不徹底である。識も何もかも呑みこんでいる身体がここに問われている。それは、無限の彼方から営みつづけて、今、ここに現われている自己自体である。そこで、次の命題へと発展する。
「無限の過去から、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものと交わりつつ、生まれかわり死にかわり、死にかわり生れかわりして輪廻転生しながら、今、ここに現われている存在の統括体にこそ、形なき純粋生命が顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換、すなわち目覚めが実現する」
存在の統括体が、業熟体であり、人格的身体である。それは、自己意識も、無意識も一切が融けこんでいる、自己存在の根源体であり、自己の自己なるものである。同時に、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものとの交わりにおいてこそ現われているものなるがゆえに、宇宙共同体の結節点である。私性中の私性と、公性中の公性との、二つの同時的極点である。
われわれは、全人格的思惟において初めて、その極点になり果て得る。いいかえれば、思惟体そのものがすなわち極点である。それは、宇宙における唯一存在体なるがゆえに、〈唯体〉という名称によっても呼び得るであろう。譬えていえば、母親の胎内に宿った第一週の状態をカララム(kalalam、凝結)と名づけるが、全人格的思惟は、そのような状態に果てしなく近づく、その極まりが唯体であり、人格的身体である。私自身が全人格一体になりつぶれて、ありありとリアリティの感触体となる。まったくの無意識であり、無智であり、黒闇であり、黒々と、果てしなくつらなっていく盲目の生命体である。このような黒闇の生命体にこそ形なき〈いのち〉は顕わになり、闇の扉はじりじりと開かれていく。(305~308頁)
■ こうしたことを総合してみると、もとよりまだ的確なことは明らかではないが、意識・経験の統一性は、大脳新皮質のさらに奥まった領域に指摘されることは間違いないようである。そしてこのことは、全人格的思惟による経験と合致している。すなわち連日の全人格的思惟において、その度毎に自己意識がその箇所と思われる所に集約されてくるのであり、この実感は何十年のあいだ変らないからである。
しかし、問題はそこからである。大脳の奥まった箇所に意識の統一性が働いているとして、その箇所をとり除いた残りの肢体には、その人の生命、人間性、いいかえればその人自身を見ることはできないであろう。だからといって、その箇所だけを抽出して、果たしてその人自身を認知することができるであろうか。思うに、全人格的思惟の経験によれば、意識の統一性はたしかにその箇所に集約されてくるが、それはただこの思惟のなかでそう意識されてくるだけである。いいかえれば、自己意識や人格性の統一体がそこにあるというのではなく、単に統一の機能の現象としてその箇所に現われてくるというにすぎない。
それゆえに、意識・経験の統一体、あるいはその人自身は、脳の一部にあるというのではなく、身体全体に関わっていると見られる。そうしてみると、どうしても全人格的思惟による全人格の統一体、すなわち業熟体、いいかえれば、受胎時の一体の如きものに限りなく近づいていく唯体にこそ、それを求めなければならないであろう。このような業熟体、唯体というごときものを、科学的にどう証明するのか。もともと対象的思惟に属する科学が、いかにして全人格的思惟の領域に踏みこむのか。問題はここから始まるといってよいであろう。
二つには、右のことに関わって次の問題が生じてくる。命題にもあるように、業熟体、唯体は、生まれかわり死にかわり、死にかわり生まれかわりして輪廻転生しつつ、今、ここに現われている存在の統括体である。それがその人の人格体であり、その人自身である。そうしてみると、この唯体は、死とともに絶滅するのではなく、死後もまた存続する。つまり輪廻転生の実態がこの唯体であるということになる。(310~311頁)
■ 三つには、ニュー・サイエンスの一つであるホログラフィック・パラダイムである。これは、レーザー光線によって知覚される物の実相が、レンズの原理によって知覚される物の在り方とはまったく異なっているということである。われわれのこれまでの物の認識は、感官を先端とするものであるが、感覚的にはレンズの原理によって存在の形態を理解している。それに対して、レーザー光線を当てると、そこに復元してくるものは、被写体の一部ではなくて、その立体的な全体像である。
このことから、ホログラムにもとづく物の実相は、一部のなかに全体を含み、全体のなかに一部が偏在しているという。いわゆる華厳の一即一切、一切即一の実相に類似しているといわれる。つまり、これまでの認識による物の在り方、ここに机があり、コップがあるという在り方の、いっそう根底には、一のなかに一切を包み、一切のなかに一が遍満しているという実相が見られ、さらにその奥は宗教の世界につながるであろうといわれている。このパラダイムの提唱者の一人である物理学者デヴィッド・ボームは、インドのクリシュナムルティと交流して、科学と宗教の領域を究明しようとしているから、さらにこの研究の進展が期待されよう。
ところで、もう一人の提唱者である脳神経学者カール・プリプラムは、記憶の研究からこのパラダイムに到達したというが、かれの心を悩ましつづけたのは、ホムンクルス(homunculus、こびと)の幻影である、という。つまり、そのホログラムの「一即一切、一切即一」の実相を、いったい「誰が」見ているのかという問題である。要するに、ホルンクルスとは、認識する主体者それ自身、自我そのものである。そしてプリプラムとは別に、DNAの発見者ワトソン=クリックの中のクリックもまた、1979年「脳を考える」という論文のなかで、知覚の背景にはホムンクルスの問題のあることを指摘している。このように若干の科学者が、研究の只中で自我の問題に逢着してきたことは驚くべき状況であるといわねばならない。それはまさしく全人格的思惟の課題である。
以上、将来立ち向うべきいくつかの視点を挙げてきたのであるが、いずれも全人格的思惟における業熟体(人格的身体、唯体)、並にその目覚めの基本線にかかわっていることはいうまでもない。そして最後に私は、私自身のこの思惟のこれからの展望に触れて筆をおきたい。
それは、先の命題であるところの、
「形なき純粋生命が、主体者、すなわちに業熟体(人格的身体、唯体)に顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換たる目覚めが実現する」
に関わるものである。
この命題自体は変わることはない、不変である。しかし、かくのごとく目覚めていく主体者の態度が変容していく。その変容の典型的な例を、ブッダの第一の弟子サーリプッタ(舎利弗)のなかに見る。サーリプッタの変容は、同時に私自身の問題である。サーリプッタは、ブッダに導かれて、もっとすぐれたダンマ(形なきいのち)を示され、ついに一切の教えを貫ぬく唯一のダンマの究極に至る。それによって初めてサーリプッタは、
「世尊は究極の覚者であり、ダンマは世尊によってよく説かれ、サンガ(共同体)はよく仏道を行(ぎょう)ぜるものである」
ということを体得する。
これはそのとおりであり、一見問題はなさそうである。しかし、ダンマの究極に達したと思っているサーリプッタの意識の裏が問われる。そこには、なおダンマに絡まっているかれ自身の主体性が見えるからである。なぜなら、次に出てくるかれの言葉「世尊は究極の覚者であり、……」には、自分は唯一のダンマによって初めてこのことが体得されたという、微妙な自負が潜んでおり、そのような自己のすがたは、ここではまったく顧みられていないといえるであろう。
そのようなサーリプッタが、『法華経』「譬喩品」に至って根本転換する。かれは今や不可思議な気持で満され、歓喜にあふれている。そしてこれまでの自分の過失を反省し、
「今日、私は世尊自身の子であり、ダルマ(パーリ語のダンマ)から生まれたもの、ダルマから現れたものである」
ということを告白する。
ここにはもはや、かれ自身の主体性は消滅して、その全人格はダルマによって通徹され充足されていることが知られる。しかし実は、まったく同じこと「世尊自身の子であり、ダンマから生まれたもの、ダンマから現われたもの」であるということが、大乗経典の『法華経』に先んじて、原始経典の『アッガンニャ・スッタンタ』(『ディーガニカヤ』第27経)に説かれていた。過失は、まさにサーリプッタ自身(実は私自身)にあったのである。私はサーリプッタと同様、今や不可思議な気持ちに満されている。
改めて私は命題を凝視する。
「形なき純粋生命が、私自身たる業熟体(唯体)に顕わになるとき、初めて目覚めが実現する」
まったく形なき太虚から、今まさに生れでようとする初発の根源的限定(根本戒)、この不変なる〈いのち〉の言葉は、未来の生きとし生けるもののすべてに照応してやまないであろう。(313~317頁)
(2022年2月16日、了)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
『ブッダの世界』玉城 康四郎 NHKBOOKS
■ さて、われわれにもっとも親しい日本仏教ではどうなっているのであろうか。日本仏教の始まりである聖徳太子の仏教を見てみよう。太子は日本仏教の礎を築いたひとであり、『十七条憲法』を制定し、三経義疏(さんぎょうぎしょ)(大乗経典『勝鬘経』『維摩経』『法華経』についての注釈)を著したといわれる。その三経義疏の中で経という言葉を注釈して、
聖人の教は、時移り、俗を易(か)うといえども、先聖後賢(せんしょうごけん)、その是非を改むること能わず。故に常と称す。また物の規則となる。故に法と称す。
――三経義疏
と述べている。「聖人の教」というのは、仏の教えのことである。その教えはたとえ時代が移り、風俗慣がかわっても、先輩の聖人や後輩の賢人といえども、その是非を改めることはできない。それは永遠のものである。だから常という。また、物の規則となる。物というのは衆生のことを指している。われわれ衆生にとって、仏の教えは実践のよりどころとなる。だから、それを法と称するというのである。ここには、どんな人でも永遠の真理をかえることはできないという太子自身の確信が示されている。(28~29頁)
■ 帰依三宝ということを巧みに一つの形にまとめあげたものとして、『三帰依文(きえもん)』がある。これは、もともと『華厳経』の中の「浄行品(じょうぎょうぼん)」という章にある偈文の中から抜き出して、独立して仏教の基本を示すものとして流布したという経緯をもっているが、はじめに、
自ら仏に帰依たてまつる。まさに願わくは衆生とともに、大道を体解(たいげ)して無上意をおこさん。
――華厳経
とある。まず冒頭の「仏に帰依たてまつる」というのは、いうまでもなくひたすらな仏への信順を表明するものである。次に「まさに願わくは衆生とともに」からあとの文章は(原義的には別の読み方をすべきであるが、ここでは伝統の読み方に従っておく)、かっして自分一人だけが仏に帰依して誓うのではなくて、衆生と一緒になって仏に帰依し、そしておおいなる仏の道を体得し、究極の悟り、本当のこれ以上のものはないという究極の悟りに目覚めようという心をおこしていこうというのである。これは、個人にとって、また個人だけでなくすべての生きとし生けるものにとっての最高の目標を明らかにしたものである。(31頁)
■ 三期絵の第二は法に対する帰依である。
自ら仏に帰依たてまつる。まさに願わくは衆生とともに、深く経蔵に入りて智慧海の如くならん。
――華厳経
仏は真理を体得した人、体現した人である。その真理が法である。その法に信順し、帰依するというのである。
しかも「深く経蔵に入りて智慧海の如くならん」という。これはどういうことかというと、『華厳経』の最後の章に「入法界品(にゅうほっかいぼん)」というのがある。ここに善財童子(善財という少年)があらわれて、53人の先生をたずねて教えを請うのである。その先生の中には仏教以外の人も多く含まれており、在家者もいる。またさまざまな身分や職業の人もまじっている。それらの先生たちに善財少年はただひとえに少年の純粋な気持ちから真理を問うていくのである。そうしてみると、『華厳経』はすでに仏教の枠組みを越え、在家・出家の区別もなく、身分・職業の上下も離れている。
これを現代的に解したらどうであろうか。われわれはキリスト教もイスラム教も、西洋哲学も自然科学も儒教も老荘も、採るべきものはすべて受け入れていく。その受け入れる基準は何か。それこそ形なきいのちがわれわれ自身に顕わになるところのわれわれ自身の基盤である。その基盤から摂取すべきものはことごとく採り入れていく。その間には誤解もおこり、受けとり方の過ちもあろう。そのときには訂正すればよい。かくして海のように広く、深く、智慧の経蔵が膨らんでいくのである。(32~33頁)
■ さて、弟子たちの側からいえば、まずブッダの人格に対する信頼に始まるということができる。そしてブッダのもとで修行しているうちにブッダの人格に盛られている真理、すなわちダンマに対する信頼へと深まっていく。これについてついに仏に帰依したピンギヤの話を例に引いてみよう。ピンギヤはもともとバーヴァリンというバラモンの弟子であった。バーヴァリンが世俗の欲望から離脱したいと願っているときに、たまたまブッダのことを耳にした。そこでバーヴァリンは十六人の自分の弟子をブッダのもとにつかわしてブッダの教えを請うた。その十六人の弟子の中でピンギヤは最長老である。やがてピンギヤはとうとうブッダに帰してその弟子となるのである。年老いて、目も見えず、耳も聞こえなくなっているピンギヤは、それでもブッダの教えを懸命に学んだ。そしてブッダに向かって次のように訴えている。
私は聖者(ブッダ)のことばを聞いてますます信ずるようになりました。目覚めた方(ブッダ)は、心のおおいが開かれ、煩悩から解放され、しかも説法の智慧をそなえておられます……。私はたしかに次のような境地におもむくでしょう。すなわちよく落着いて、けっして動かされず、またなにものにも譬えようもない境地です。これについてまったく疑いがありません。このように私は、信じて傾倒していることを御承認ください。
――スッタ・ニパータ
目も耳も不自由になっている老人でさえも、ブッダの教えを学んでいるうちに、これほどまでに信心が深まっていることをあらわしている。このことは、仏道に専念しているわれわれを勇気づけるものであるといえよう。
ここで信ずるという語は、三人称単数ではpasidatiである。これにはいろいろな意味がある。信ずるという外に「浄まる」「澄みとおる」「満足する」「喜ぶ」「転換する」などである。むしろ信ずるということが、こうしたさまざまな意味を含んでいるといえよう。
信が深くなれば、心は自然に浄まり、そして澄み透ってくる。それは、ダンマが人格的に滲透してくるからである。中国でも「信とは澄浄の義なり」といわれているとおりである。そして何ともいえない喜びが湧いてきて心は満ち足りる。ついには真実の智慧が開かれて解脱する。すなわち人格体が転換されるのである。
右の一文の最後に「信じて傾倒している」という原語はadhimutta-cittaである。これは勝解心と訳されている。adhimuttaの名刺形であるadhimuttiは信解と訳す。muttiは解脱であり、adhiは「……の方へ指向する」意味であるから、adhimutta-cittaは、心が単に信ずるだけでなく、その信が解脱へと指向しており、解脱が開きかけている状態を指している。このようにみてくると、何もかも不自由になった老人のピンギヤでさえもブッダの教えを学んでいるうちに、これほどまでの心境にすすむのかと驚かされるであろう。(30~32頁)
■ さて、念仏と禅定がもともと一つであることというブッダの説法の一例を挙げてみよう。
如来を念じなさい。すなわち、「世尊は阿羅漢であり、正等覚者であり、(中略)人天師であり仏である」と。如来を憶念するとき、貪り、怒り、愚痴の煩悩から解放されて、如来に対して正直となる。正直となれば、おのずからダンマが受け入れられ、ダンマに伴なわれた悦びを覚える。やがて喜となり、体が軽やかに安らいだものとなる。さらに深まって楽となり、ついに三昧に入り、ダンマの流れに投入したものとなる。
これがすなわち念仏である。
――増支部経典
これは五比丘の一人であるマハーナーマンに対するブッダの説法である。ここで注意すべきことは、如来がブッダにとって第三者の位置にあることである。ダンマと同じであり、形なき永遠のいのちをあらわしている。(57~58頁)
■ そしてついに「ダンマの流れに投入したもの」となる、という。「ダンマの流れの中に入ってしまったもの」という意味がある。
いいかえれば、形なきいのちそのものの流れの中に全人格体がすっぽりと入ってしまうのである。あるいはいのちそのものが私の全人格体を包徹してしまったといってよう。これが念仏の成就したすがたである。このように如来を憶念することは、やがて喜となり楽となり、ついに三昧に入るのであって、念仏のままが禅定であり、禅定のままが念仏であって本来一つのものであることが知られる。(59頁)
■ 念仏・念法・念僧は、原始仏教から大乗仏教にかけて仏道者の根本態度である。その根本態度の成就・完了が「ダンマの流れに投入したものとなる」ということである。全人格体が如来のいのちの中にすっぽりと入ってしまうことである。これを不退転の境地という。
不退転の境地とはどういうことか。今日、日常語としては不退転の決意ということがいわれている。
しかし不退転の境地は、けっして単なる決意ではない。そうではなく、退転しないという確定した境地をいうのである。その境地は必ず涅槃に至るということが決定している。ここではもはや退くことはなく、ただ進むだけである。それゆえに仏道者はこの不退転の境地を目指してきた。(60頁)
■ インドに『大智度論』という著作がある。これは大乗仏教の先覚者ナーガールジュナ(竜樹)自身の書いたものではないが、かれにかかわるものである。したがって、のちの機会に述べる般若空(どこまでいってもとらわれない真実の智慧)の立場に立つものである。その中で次のようにいわれている。
菩薩、般若を行ずれば、一切法において所得なし。所得なきが故に、法として取るべき相あることなし。……菩薩かくの如く学べば、当に知るべし。これ不退転なり。
――大智度論
ここで般若(智慧)といっているのは、ブッダのダンマに相当する。ダンマが形なきいのちであるように、般若もまた形なきいのちである。その般若を行じていくうちに、なにものにもとらわれなくなる。形のないいのちを学んでいくのであるから、そうなるのは当然である。それゆえに、どういう場合に出会っても、その形にとらわれなくなる。形にとらわれないということは、全人格体がいのちそのものによって充足しているということである。いのちに充足しているからには、もはやあと戻りすることはない。すなわち不退転である。
先のブッダの説法にあったように、ダンマの流れの中にすっぽりと全人格体が入ってしまうことである。
つづいて道元の『正法眼蔵』から引いてみよう。
無上菩薩は出家授戒のとき満足するなり。出家の日にあらざれば成満せず。……この出家、すなわち無数の有生をして、無上ぼさつを不退転ならしめるなり。しるべし、自利利他ここに満足して、阿耨菩提(あのくぼだい)不退不転なるは、出家授戒なり。
――正法眼蔵・出家巻
無上菩薩とは究極の悟りである。究極の悟りは出家して戒の規則を受けたときに成就するという。それがすなわち不退転の境地である。しかしこの不退転は、自分の悟りだけでなく、ありとあらゆる生きとし生けるものをして不退転ならしめ、究極の悟りを得せしめるのである。このように自利利他満足して不退転ならしめるのは出家授戒の外はないという。阿耨菩提とは、anuttara-samyak-sambodhi(阿耨多羅三藐三菩提)の音訳語を省略したもので、無上菩薩と同じ意味である(岡野注;無上正等覚)。(61~62頁)
■ さきの『大智度論』にしても、道元の場合でもその至難なことは同じである。では、どうすれば不退転に至ることができるのであろうか。不退転に達するいちばんの近道は、自分に縁の深い、親しみのある、しかも毎日行うことのできる方法を選べばよい。念仏でも坐禅でも唱題でも、また経典の読誦や写経もある。あるいは仏道とは別のさまざまなやり方もあろう。ともかく気長に日々を怠ることなく勤めていけば満足する日が必ず到来するであろう。ひとたび不退転に至れば、もはや何の案ずることもなく、安んじて先に進むのみである。
世俗的な例であるが、野球のホームランに譬えられると思う。2塁打、3塁打であれば懸命に走っていかねばならない。さもないとアウトになって失敗する。しかしホームランはそうではない。安心して1塁、2塁、3塁のベースを回っていく。いわば人生のベース、生活の節目節目である。そしてホームに帰ってくる。真実のふるさとであり、仏国土であり、極楽浄土である。法然は、いよいよ臨終の際に、「師は極楽に往生なさるのですか」という弟子の問いに、「われはもと極楽にありし身なればさこそあらんずらめ」とおだやかに答えている。法然にとって極楽が真のふるさとである。しかしよく思案を巡らせてみると、法然だけではない、われわれ一人一人が実は極楽をふるさとにして、そのふるさとからこの世に出てきて活動しているのではあるまいか。ただそのことに気づかぬだけである。宿縁熟してふるさとに目覚めてみれば、おのずから不退転の位に安らっているといえよう。(63~64頁)
■ 禅定と念仏との二つは、東アジアの仏教においてはある時期まで分かれる方向で展開し、それが日本の仏教に及び、際立ってくる。しかし、釈尊の仏教に還って見ると、念仏がそのまま禅定、禅定がそのまま念仏であり、念仏と禅定の二つが一つになったのではなく、もともと一つである。ここがブッダの教えの基本となっており、そのブッダの教えを実践し、学んでいくことによって、やがて如来のいのちに育てられるようになり、ついにはいのちそのものの中に包まれてしまう。こうなれば、もうその境地からけっして退くことがない。そういうブッダの教えがインド、中国、韓国、そして日本へ伝わり、ついには鎌倉の祖師たちが、形は違うけれども、その根本のブッダの教えにまで踏み込み、それに基づいて不退転の境地に至る道を教えてきた。(66頁)
■ 人間のさがは非常に深い。我執は地球よりもなお深いとまでいわれている。したがって、法悦の瞬間を経験することがあっても長くはつづかない。ここに、業熟体としての自己がどこまでも深く反省されねばならない理由が存する。
業熟体について、ブッダは懇切丁寧にいろいろなところで説法している。それらをあわせて考えていくと、まずその把握の出発点は、自分がこうしてここにいるという、その現実にあることが分かる。その現実たらしめているものは何か。自己の背後には、これまで歩いてきた長い道筋がある。自己は広大な背景をもっている。無限の歴史を抱えている。限りなき過去から、生まれかわり死にかわり、死にかわり生まれかわりして、その間にさまざまな人と出会い、さまざまな生物たち、ありとあらゆるものと出会いながら、いま、ここに自分はこうしている。その全体がすなわち業熟体にほかならない。それはもっとも私的なものである。同時に、無限に長い間、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものと交わりつつあらわれているがゆえに、宇宙共同体の結び目である。したがってもっとも公的なものである。私的なるものの極まりであると同時に、公的なるものの極限である。
しかも業熟体は限りなく深く、暗い闇に包まれている。まったく無意識であり、無智であり、暗闇である。無限の過去からさまざまな問題が噴き出てきたのであり、今もなお、飢餓、貧困、環境破壊がおこっており、闘争、殺戮、戦争が繰り返されている。
このような業熟体にこそ、形なきいのち(ダンマ・如来)は、顕わになり、滲透し通徹しつづけているのであり、闇の扉はじりじりと開かれていく。ブッダの教えを聞いて忠実にしたがっていけば、必ず道が開けてくる。そこには、賢者、愚者の区別はない。ブッダは無理のない自然の生き方を教えている。(68~70頁)
■ ここで、釈尊の弟子の一人であったゴーディカの場合を考えてみよう。彼は熱心に禅定の修行をつづけ、ついに目覚めに至った。解脱を体得することができたのである。解脱というのは、またのちにも触れるが、根こそぎに迷いやこだわりが消滅してしまう、なにものにもとらわれない境地に至ることである。しかし、解脱の境地はやがて消えて、もとの木阿弥に戻った。これではいけないと思い。さらに禅定に励んでいるうちに、また解脱を得た。しかし、やがてまたもとへ戻る。いわゆる退転である。
このようにしてゴーディカは、3度、4度、5度、6度、解脱に至り、そして退転した。7度目に解脱したときに、もう退転することはないようにと、剣をとって自殺したという。仏道修行のきびしさを物語っている。ところで、ある人が、「ゴーディカはいまどこにいるか。息を引き取って、彼の魂はどこをさまよっているか」とブッダに訊ねた。すると、ブッダはたちどころに「いや、ゴーディカは完全に涅槃した、安らぎに入った」と答えたという。もともと自殺は教団においてきびしく禁ぜられている。それにもかかわらずブッダはゴーディカが解脱に達して究極の安らぎに入ったことを賞讃している。解脱ということが人生の最高の目的であることをブッダは教えている。
しかしながら、ブッダはその後、ダンマに養われ、培われ、熟して八十年の生涯を閉じた。さらに涅槃に入った後も、千年ににわたって大乗経典を説きつづけ、その後も各宗派に分かれて今日に至った。このように熟した仏道に教えられている私は、ゴーディカの最後の態度を断固として拒否する。いかなる理由があるにせよ、みずから命を絶つとはもっての外である。どれだけ元の木阿弥なろうとも、性懲りもなく励んで息(や)むことはない。必ず道が開けてくることを承知しているからである。
たとえば、『テーラー・ガーター』の中に出てくるサッパダーサ比丘は出家してから二十五年もの間、愛欲のために悩みつづけ、一瞬の間も心の平静を得ることができなかった。そういう自分に絶望し、剣をとって自殺しようとした。しかし、その瞬間、彼は正しい思惟を得て、解脱に達したという。いわば、ぎりぎりの限界状況において道が開けたのである。(70~71頁)
■ ブッダ自身においては、仏道の探究はどのような形で展開していったのであろうか。
この問題に関して、いくつかの物語や説法が伝えられている。その一つを紹介すると、マガダ国もゴーシンガ・サーラという森にブッダや弟子たちが滞在していたときのこと、ある月明かりの晩、やっと涼しさが戻り、沙羅の花が満開になって、あたりには何ともいえない香りが漂っていた。ブッダに身近な弟子たち、サーリプッタ(舎利弗)、アーナンダ(阿難)、モッガラーナ(目連)、カッサパ(迦葉)、アルヌッダ(阿那律)など、五、六人の者が集まって、お互いに法について話題になった。いうなれば、仏道の根本は何か、どういう行いをすることが仏道の基本であるかというテーマである。
弟子たちは思い思いに、自分の見解を語る。アーナンダは、常にブッダに寄り添ってその説法を聞いていたので、「釈尊の説法をよく聞いて、それを心にとどめ、その説法の主旨を洞察していく、そういう比丘こそが本当に森を輝かすものである」という。モッガラーナは「ダンマについてお互いによく質疑応答して、そのダンマを明らかにしていく、これこそが本当の比丘である」と主張する。サーリプッタは「午前中でも、お昼時でも、夕暮れでも、自分が禅定に入ろうと思ったらいつでも禅定に入ることのできる比丘、こういう比丘こそが本当の比丘だ」と述べる。ブッダはじっと聞いていたが、やがて「それぞれの見解はまことに結構である」といって賞讃したのち、「では自分の考えを述べよう」といって次のように語った。
食事のあとで、行骨から帰って、結跏趺坐し、姿勢を調え、念いを集中して次のように決意する。執着を離れ、煩悩から解脱しないかぎり、けっしてこの結跏趺坐をやめない、と。このような比丘こそこのゴーシンガ・サーラの森を輝かすものである。
――中部経典
結跏趺坐は両足を組んで行う正しい坐禅のことである。ここにブッダは比丘に託して述べているが、おそらく自身の考えを語ったにちがいない。すなわち、行乞から帰って、結跏趺坐して禅定に入る。姿勢を正し、心を集中する。そうして解脱しない限りは結跏趺坐をやめない、と。
つまり、ブッダは菩提樹下で禅定に入ったとき、ダンマが露わになって悟りが開かれたのであるが、その悟りの境地がそのまま持続していなかったことが知られる。いいかえれば、ゴーディカだけではなく、ブッダ自身も同じ問題を抱えていたのである。なぜそうなのか、ということについてブッダはみずからの禅定を深めながら説いている。そのことを次に述べてみよう。
禅定の深まりを示す九段階
この説法は、「中部経典」の中の『小空経』である。ここで禅定が深まっていく九つの段階が示されている。
初禅
第二禅
第三禅
第四禅
空無辺如
識無辺如
無所有如(むしょうしょ)
空想非非想如
夢相心三昧(むそうじんざんまい)
初禅から第四禅までの四禅については第Ⅲ講で説明したので、それにつづく禅定について簡単に述べてみよう。ブッダは空住に安らいながら禅定を深めていく。空住とは、空に住すること、すなわちなにものにもとたわれなくなることである。まず、空無辺処の空というのは虚空のことで、あたかも虚空のように果てしがないという境地である。それがさらに深まると識無辺処になる。識とは心と同じで、この心もまた辺(ほと)りがないという境地。さらに深まると無所有処で、なにものも存在しないという境地。次の非想非非想処は、想うのでもなく、想わないのでもないという境地である。
このように、空無辺処から非想非非想処までは、次第に深まっていく段階を示しているが、しかしながら、その境地にはまだ微妙な対象性が残っている。ところが次の無相心三昧になると、まったく対象性がなくなって、全人格体がひとかたまりになってしまうという境地である。ブッダはこのように、みずからの禅定を深めながら丁寧に説法している。
無想心三昧の境地
ところで、ここで注意しなければならないことは、このような禅定の段階は、たとえていえば、船が港に正しく入るときの水先案内、あるいは山道を歩いていく場合の道しるべということである。したがって、これにこだわっていると禅定はできない。禅定に入ったら、もう何もかもうち忘れ、ひたすら三昧に入るだけである。それでは、この水先案内、または道しるべは必要ないのかというと、けっしてそうではない。われわれが勝手に禅定に入ると、自己の主体がどちらの方へ向いていくか、その結果がどうなるか、はかりしれないものがある。大変な方向へ踏み迷ってしまうこともある。どうしても、指標が必要になってくる。
さて、ブッダの説法に戻ってみよう。たとえば識無辺処についてブッダは次のように説いている。
アーナンダよ、もはや空無辺処を思わず、ただ識無辺処に専心し、浄まり、確率している。それゆえに、ここには空無辺処はなく、その悩みもない。すなわち空である。
しかし、いま専心している識無辺処は空ではなく、残りものであり、それについて不安である。
――中部経典・小空経
これは前述のように、ブッダが空住という、何もかもなくなってしまった解脱に安らいながら、しかも禅定を深めている一つのプロセスである。この識無辺処に専心している際には、その前の空無辺処、あるいは初禅から空無辺処までは、すっかりなくなっている。その点では解脱である。しかし、いま専念している識無辺処は空ではない。まだ空になっていない。識無辺処は、いわば残りものになっている。したがって不安である。
しかしブッダは、その識無辺処に専念しているうちに、やがて脱却する。つまり空になる。それが識無辺処の解脱である。このようにして識無辺処から無所有処に入ると、識無辺如までは解脱したけれども、無所有処に専念しているときには、無所有処はまだ空ではない。どうしても不安である。こうして、さらに無所有処を解脱して非想非非想処に入り、非想非非想処に入り、非想非非想処も解脱して、最後の無相心三昧にはいる。そのときの状況を、
アーナンダよ、もはや無所有処も非相非非想処も思わず、ただ無相心三昧に専心し、浄まり、確立している。それゆえにここには無所有処も非想非非想処もなく、その悩みもない。すなわち空である。しかし、いま専心している無相心三昧は空ではなく、残りものであり、それについて不安である。(中略)
しかし、それもまた無常であり、滅びゆくものであると知ることによって、おのずから解脱する。そして解脱してもなお解脱しつづける。
しかしながら、ついには生命を縁としているこの身体にきわまる。それは空ではなく、不安であり、残りものである。
――中部経典・小空経
と説いている。これが禅定のいちばんきわまったところ、無相心三昧に入ったときのブッダの告白である。
ダンマの発展するところ
無相心三昧に専念していると、それまでの三昧の世界はすべて絶滅して空になる。しかし、いま専念している無相心三昧は空ではない。どうしても残りものとして不安がつきまとう。けれども、その無相心三昧も結局は無常であり、滅びていくものであると知ってそこからも解脱する。しかもなお、業熟体は、底なく深いものであるから、解脱しつづけることになる。
こうして、ついにはどうなるか。それを示すのが、最後の言葉である。「ついには生命を縁としているこの身体にきわまる」と。この生命のよりどころ、それは身体である。身体といっても、精神に対する肉体とか、心に対する身体とか、そういう身体ではないことはいうまでもない。意識も無意識も、あらゆる煩悩、業がすべてここに集約されているところの身体、これこそが業熟体のきわまるところである。その身体が最後にどうしても残ってしまう。不安である、空にならない、とこの説法はここで終わる。
しかし、ブッダの教説をさらに学んでいくと、そのきわまったところの業熟体にこそダンマは顕わになり、滲透し、そして通徹しつづけていくということが知られてくる。(72~79頁)
■ブッダの亡きあとにアビダルマ仏教がおこってきた。いわゆる小乗仏教といわれるものであるが、今日ではこの名称は用いない。さげすまれた名前だからである。アビダルマ仏教、あるいは部派仏教と称している。この中には、ダンマが体得されている証拠が明らかに見える。しかし、ブッダの深い教えまではとどかずに、細かな研究や議論の方へ走ってしまい、仏道の基本に復帰することができなかった。そこで大乗仏教があらわれてブッダの精神に帰れ、という運動がおこってきた。それが大乗諸経典や、それに基づく大乗諸学派の出現である。いわゆる大乗仏教である。
では、帰るべきブッダの精神とは何か。これについては、これまでしばしば述べてきたように、「ダンマ・如来が業熟体に顕わになり、滲透し、通徹しつづけていく」ことがブッダの原始経典について明らかにしたとおりであり、全仏道の基本である。ここにはもはや大乗もアビダルマ仏教も区別はない。ただ問題になるのは主体者の受けとり方である。その受けとり方について三段階に分けて考えてみたい。すなわち、初地(しょぢ)・中地(ちゅうぢ)・終地(しゅうぢ)である。地というのは境地であり、どういう境地を辿(たど)るかというのがこの三段階である。
これについては、これまで部分的には述べてきたのであるが、実はブッダ自身が自分の行動においてこの三段階を示している。(84~85頁)
■さて、第三段階の終地を端的に示しているブッダの教えを挙げてみよう。
信が如来において確立し、根ざし、堅固となって、沙門によってもバラモンによっても天によっても悪魔によっても、その他いかなるものによっても動揺しない、そのような人は次のように語る――。
「わたしは世尊自身の子であり、ダンマより生まれたもの、ダンマよりあらわれたものであり、ダンマの相続者である」と。
それはどういうわけであるか。実にこれは如来の同義語だからである。
すなわち、法身とも法体ともいう。
――長部経典
これは第三弾階としてとくに重要なブッダの言葉である。われわれはこの説法を、よく心にとどめて誤りのないように学んでいかなければならない。まず第一に、実は原始経典の中にすでにいわゆる大乗を先取りするような教えがはっきりと示されているということである。いいかえれば、のちにおこってくる大乗仏教の礎がブッダの原始経典において築かれているということである。
第二に、「信が如来において確立し……いかなるものによっても動揺しない」ということはどういうことであろうか。信というのは、第Ⅲ講で説明したように、はじめはブッダに対する信頼に始まり、やがてブッダとともに学んでいるうちにブッダの人格に盛られているダンマ、いのちそのものへの信頼となり、それが自分の身に沁み込んできて、ついには心の眼が開き、解脱となり、智慧となる。つまり、信はそのまま深まって解脱にまでつながっている。
先の中地において述べたように、自分が努力して獲得した解脱や信心ではなくて、ダンマが顕わになり、如来から恵まれた信心、如来によって与えられ回(めぐ)らし施された信心であるからこそ、確固不動である。いかなるものによっても動かされないのである。そういう人は、「私は世尊自身の子である」という。世尊の本当の子、すなわち如来の子、仏の子であるという確信の表明である。そしてさらに「ダンマより生まれたもの、ダンマよりあらわれたものであり、ダンマの相続者である」という。
このことはとくに注目すべきである。ダンマから生まれかわったものとなり、ダンマの相続者となって、現在から未来に向かって進んでいくのである。さきの中地において戒(いまし)めたように、煩悩が根絶し絶無にとどまるのではなく、ダンマを受けつぐ人となって、未来に向かって第一歩を踏み出していくのである。この点において、中地から終地への必然的な転換を確認することができる。それゆえに終地は、ここで終わるのではなく、真の仏道がここから始まるのである。(91~92頁)
■ ブッダの弟子の中で代表的な弟子を十大弟子というが、サーリプッタは、その中でもいちばん優れた弟子であったといわれる。ところが、残念なことにブッダよりも早く亡くなった。ブッダの歎きはいかばかりであったろうか。その智慧第一といわれたサーリプッタが、はじめてダンマに目覚めて、そのダンマの体験に歓喜しているすがたが一つの経典になって残っている。
ダンマは形がないいのちそのものであるから、捉えようとしても捉えることはできない。ダンマが顕わになる外はない。そのダンマに目覚めたサーリプッタが、ダンマとはいったい何かということを、一つの譬えで説明している。
城壁に囲まれた一つの都市がある。そこに門番がいて、彼はその都市を護衛しなくてはいけない。ところが城壁を全部見回ったら大変である。城壁とは、実はいろいろな仏の教えを、また見回るとは、たくさんの教えを一つ一つ学ぶことを譬えているのであるが、その城壁にはたった一つだけ門がある。門番はその一つの門だけを護衛すればいい。この一つの門というのがダンマの譬えである。すなわち、ダンマとはたくさんの教えの中の教え、根本のいのちをいう、次のサーリプッタの釈尊に対する告白は、その形のないいのち、ダンマに目覚めて喜んでいる彼のすがたをよくあらわしている。
わたしは聞法のために世尊のもとに参りました。世尊はそのわたしにすぐれたダンマを黒白を分けて示して下さいました。そのためにわたしはダンマの究極に達しました。このダンマこそもろもろの教えの中の無上のものであります。
――長部経典
いろいろな教えが説かれてはいるが、結局は根本の形なきいのちであるダンマに目覚めてもらいたいということがブッダの願いである。その願いが通じて、とうとうサーリプッタはダンマに目覚めた。嬉しくてしかたがない。彼がその喜びに踊っているすがたが目に見えるようである。
ところがサーリプッタは、ただこの目覚めということだけにとどまっていることはできない。さらに転換するのである。その大きな転換の姿が、『法華経』の中に描き出されている。
世尊よ、わたしはいま喜びに満ちております。
それはなぜでしょうか。わたしどもは世尊から小乗を教えられたと思っておりました。しかし、それはわたしどもの間違いでありました。……しかるに世尊よ、いまや(一仏乗の教えをきいて)完全に涅槃に達しました。世尊よ、いまやわたしは、世尊自身の子であり、ダルマから生まれたもの、ダルマからあらわれたもの、ダルマの相続者であります。
――サンスクリット本・法華経
サーリプッタははじめ、ブッダの真実の悟り、つまり如来から回らし施された悟りについての教えを聞き、やがて目覚めることができた。ダンマが顕わになったのである。しかし、まだ十分に機が熟していないために、その入口にとどまっていた。そのサーリプッタが、いまや『法華経』において、一仏乗の教えを聞いて転換した。すなわち「世尊自身の子であり、ダルマ(原始経典のパーリ語ではダンマ)から生まれ、ダルマからあらわれ、ダルマの相続者」となって、完全に涅槃に達したのである。
先に述べたように、「ダルマから生まれて、ダルマの相続者」になるという教えは、すでに原始仏典に説かれていたのであり、しかも第三段階である終地をあらわしていた。いいかえれば、原始経典の中に大乗仏教の礎が築かれているのであり、それこそ原始仏典から大乗経典を貫く仏道の基幹線であることが知られる。(93~96頁)
■ 信は種子である。行は雨である。智慧は軛(くびき)や鋤(すき)である。
――スッタ・ニパータ
これは、農業に譬えて仏教の基本にについてブッダが語った言葉である。信とは、すでに述べたように、最初はブッダに対する信頼である。ブッダに出会うとブッダの人格に触れて信頼感が出てくる。ブッダの教えを学んでいくうちに、ブッダの人格体に込められているダンマ、形のないいのちそのものに、共感するようになる。しかし、まだブッダほどに熟してはいないが、そのダンマの種子のようなものがおのずから弟子たちの心の中にも植えつけられる。この教えは、はじめにダンマの種子が植えつけられるということを、農業に譬えたものである。ダンマの種子がないと、いくら雨が降っても、鍬や鋤で耕しても、何も出てこない。ダンマの種子があってはじめて行という雨によって培(つちか)われる。それから、智慧の鋤や鍬で、その種子がうまく育つように耕していく。こうして、信心の種子は次第に大きくなっていくのである。
このことに関連して、同じ『スッタ・ニパータ』の中に味わいの深い教説がある。
人間の最高の富は何か。
何を行ずることが安らぎとなるか。
味わいのなかで何がいちばんおいしいか。
どのように生きることが最高の生き方か。
信が人間の最高の富である。
だんまが行ぜられることが安らぎとなる。
真実が味わいのなかでいちばんおいしい。
智慧によって生きることが最高の生き方である。
――スッタ・ニパータ
これは、「いのちの種子」が大きく成長して、最高の財産になってきた様子をあらわしている。「信が人間の最高の富である」という言葉からわれわれは、弟子たちの気持ちの中にブッダに対する信頼感が成長して揺るぎのない信心にまで発展していることを窺うことができる。当然、弟子たちには、ダンマ、いのちそのものが、禅定の中で、あるいは日常生活の中で実感されているのであろう。そのいのちが実践され、行ぜられて、本当の安らぎとなっていく。「ダンマが行ぜられることが安らぎとなる」のである。これほどの安らぎはないだろう。そのいのちを行ずる。いのちを実践することの中で、はじめて真実なるものが味わえるのである。(102~104頁)
■真実という言葉だけでは、単に観念的に理解するほかない。しかし、われわれの間の交際でも、友人関係、職場の同僚の関係に、いつの頃からか信頼感が定着してくる。お互いのまことを感じ、親身を覚えあうようになる。つまり、真実を分かちあうところまでくる。この場合も、やはり真実なるものが基本になっているのではないだろうか。
ブッダもそこを捉えて、真実の味わいほどおいしいものはない、と述懐したのである。われわれは日々の生活の中でいろいろな不安を抱き、また戸惑う。その繰り返しの中で生活が営まれているといえる。けれども、その不安感や戸惑いの中に感じられる真実の味わい、いのちそのものに透徹していくときに味わえる真実の味わいほどおいしいものはないというのである。
その真実を味わいつつ何の不安もなく生き通していくということが智慧に外ならない。おのずからなる生きざまの中で開かれてくる生き通し、あるいは見通し、それが智慧である。
その智慧が完成したものを般若波羅蜜多という。サンスクリット語の「プラジュニャーパーラミター」である。その般若波羅蜜多を行じていくことが大事なことであるが、この問題はまた別の機会に譲ろう。
ともあれ、さきの教説からも、信が、信ずるということでとどまるものではなく、そこにおのずから求めていく、行じていくということが含まれることが明らかとなった。のちの大乗の『涅槃経』でも、「信に二種がある。二種とは信(信じること)と求(求めること)である」といっている。これは、その点を端的にあらわしたものであると考えられる。(104~105頁)
■信は、さまざまな方向において追求されていく。われわれは、その一つの展開を示す代表的な教説を、大乗の『涅槃経』の中に見ることができる。
大信心は仏性なり。仏性は即ち如来なり。仏性とは一子地(いっしじ)と名づく。
(中略)
一切衆生、必ず当(まさ)に定(さだ)んで一子地を得べきが故に、一切衆生、ことごとく仏性ありと説く。一子地は仏性なり。仏性即ち如来なり。
――涅槃経
とあるのがそれである。
大信心というのは、自分の中に植えつけられ、自分自身が喜び保っている信心でありながら、ダンマ・如来から恵まれたものであり、けっして小さな信心ではない。それで大信心という。その大信心は仏性である。仏性とは仏としての本性である。いいかえれば、仏性はそのまま仏そのもの、如来である。
次に一子地という言葉が出てくるが、一子地とは、『法華経』の中で如来が、「衆生は我が子である。一切衆生はすべて自分の子である」といっていることに結びついている。このことを衆生の側から表現したもので、「如来ひとり子の境地」を意味する。大信心を恵まれた、その私は必ず如来ひとり子となって如来と同じ世界に住する。このことを示しているのが、「一切衆生、必ず当に定(さだ)んで一子地を得べきが故に、この故に、一切衆生、ことごとく仏性ありと説く。一子地は仏性なり。仏性すなわち如来なり」である。われわれは誰でも、知らないままに、この身に如来のいのち、如来のたからを保持しているが、仏道を学んでいくうちにやがて如来のひとり子の境地に気づくことができる。そのことが『涅槃経』に説かれているのである。
仏性というものも、ややもすれば、何か固定的で実体的な、仏となる種子のようなものを考えがちである。しかし、このような教えを学んでみれば、仏性は生き生きとした実践の中でこそはたらくものであるということが理解されよう。(105~107頁)
■別の和讃には、信心のいのちが親鸞の体の中でどのように発現したか、あるいはどういうふうにそれを親鸞自身が喜んでいたかということが出ている。
康元二歳、二月九日の夜
寅の時、夢の告げにいわく
弥陀の本願、信ずべし
本願信ずる人はみな
摂取不捨の利益(りやく)にて
無上覚をばさとるなり
この和讃をゆめにおおせをこうむりて、うれしきにかきつけてまいら
せたるなり。
正嘉元年三月一日
愚禿親鸞
八十五歳
――正像末和讃
これは親鸞の最晩年の和讃である。康元二年は年改まって正嘉元年となっているから同じ年である。これがもし昼間できた歌であるならば、ほかの和讃と別にかわるないであろう。しかるに、二月九日の夜中の四時ごろ夢告によって生まれてきた歌である。親鸞自身よほど嬉しかったと見えて、それから約二十日たった三月一日に「うれしさにかきつけてまいらせたるなり」といってわざわざこの歌を記している。ここにこの歌の格別に重要な意味が含まれている。
本願というのは、仏・菩薩によって立てられる根本の誓願である。それは、つきつめていえば、生きとし生けるものの本当の願いのことである。その本願を成就したものが、すなわち阿弥陀如来である。如来の本願を信ずることが、そのまま如来のいのちにつかまれて、もう離れないということになる。すなわち摂取不捨である。いくら日常生活に悩んでも、苦しんでも、如来に摂取されて離れないものになっている。この摂取不捨のままが、無上覚、すなわちこの上ない究極の悟りであるという。
この歌が夢の中で生まれていることに注目すべきである。親鸞の意識も潜在意識も無意識も包んで、身体全体で歌っている。いいかえれば、本願を信ずることと摂取不捨と無上覚とがひとつらなりになって親鸞の人格体に熟しているということができよう。(108~110頁)
■ 親鸞に一つの典型を見ることができるように、いのちそのものは、年数がたてばたつほど人格体に熟していく。このごろ熟年という言葉が使われるが、その意味は、ただ年をとっていくということではなく、年をとればとるほどいのちが熟してきて、以前には味わえなかったものが身体にしみ通ってくるということでなければならない。古人の言葉に、「もしきのう息を引き取ったら、けさ発見したことはわからなかったろう」というのがある。いのちの味わいもまさにそうである。年々歳々、われわれの身体は法によって熟していくのである。(110頁)
■ 親鸞と同じ鎌倉時代の道元も、
髄をうること、法をつたうること、必定して至誠により。信心によるなり。
――正法眼蔵・礼拝得髄
と説き、さらに、
信現成のところは、仏祖現成のところなり。
――正法眼蔵・三十七菩提文法
と示している。必ずまことの心により、信心によってダンマは体得、伝持される。したがって、信が実現するところ、そのままが仏祖のあらわれるところであるという。親鸞の「如来とひとし」といい、あるいは「無上覚をばさとる」という感懐と同じものであろう。只管打坐、すなわち、ただひたすらなる坐禅を唱道した道元の行の根幹に、同じように信が根づいている。歩いた道は互いに違っても、その根本は同じであるといわねばならない。(110~111頁)
■ 親鸞については、もう一つここで味わっておきたい言葉がある。それは『正信念仏偈』の中の次の文である。
煩悩、眼(まなこ)を障(さ)えて見たてまつらずと雖(いえど)も、大悲、倦(ものう)きことなくして、常に我を照らしたもう。
――正信念仏偈
(中略)
「煩悩、眼を障えて見たてまつらずと雖も」、つまり生活の戸惑いや悩みのために心の眼がさえぎられて、如来をじかに感得することができない。これがわれわれの日常のすがたである。しかしながら、それにもかかわらず「大悲倦きことなくして常に我を照らしたもう」如来の大悲は倦(あ)くことなく、私を照らしたもうている。
ブッダの言葉でいえば、「ダンマ・如来は業塾体に通徹しつづけている」のである。これこそ全仏道の息(や)むことなき根源のはたらきである。
われわれはこの如来の恒常のはたらきを聞法しつづけていくうちに、かならずやなるほどとそれに気づく機会に恵まれるであろう。(111~112頁)
■ このような安らぎの種子としての信心は、もう少し卑近な譬えでいえば、手持ちの傘に当たるのではなかろうか。外出しようとするときに、きょうは雨が降るのか降らないのか、傘は持って行った方がいいのか、どうか、迷うときがある。めんどうだから傘は置いていこうといって出掛けたあと、途中で雨に降られると途方にくれる。雨は降らなくても、だんだん曇ってくると不安にもなる。けれども、用心のために傘を持って外出すれば、雨が降った場合にはそれで間に合って、濡れずにすむ。降りそうなときにも、傘があるから安心である。降りそうなために不安がるのと、降っても降らなくても傘があるために安心しているのとでは大違いである。信心はいわば傘に譬えることができよう。
また、よく仏典に用いられる比喩でいえば、人生は海に、信心はおおきな船に譬えられる。
信心の大きな船に乗れば、如来という船長にすべてを任せ、安心して人生の大海をわたっていけるというものである。その際には、どのような煩悩も何の妨げにもならない。それが信心の世界なのである。(113~114頁)
■ 空は、日本の文化の基礎をつくり上げているといえる。その基(もと)をなすのが、般若経典あるいは『般若経』と総称されている一群の大乗経典である。さきほど触れた『般若心経』もその一つである。では『般若心経』を含め、般若経典と総称されているものはどのように捉えたらいいのであろうか。般若経典としては、『般若心経』というわずか二百五十字あまりのものから『大般若経』という全六百巻のものまであり、その間にさまざまな種類の『般若経』がある。それらに一貫している教えが般若波羅蜜多(あるいは般若波羅蜜)の行である。
般若波羅蜜多とはどういうことか。もとの言葉はサンスクリット語のブラジュニャーパーラミターで、その音写語がこれである。意味は「智慧の完成」ということである。また漢訳では「到彼岸」と訳している。「彼岸」というのは「彼(か)の岸」、すなわち輪廻している「こちら側の岸」に対して、それを超えている「向う側の岸」いいかえれば涅槃である。その涅槃に至った状態というのがすなわち「到彼岸」である。(119頁)
しかしながら通常は般若波羅蜜多というのが一般的である。なぜなら語の意味をとって「智慧の完成」と現代語訳すれば、経典の意味がまったく分からなくなってしまうからである。さすがに古人はそのことを心得ていたと思われる。
では経典の中の般若波羅蜜多とは、どういう意味であるか。まず、ブッダの解説の原点に戻ってみると、「ダンマが顕わになる」というのがそれであった。ダンマとは、いのちの中のいのち、形なきいのちそのものであった。そのダンマが『般若経』においては般若波羅蜜多となっているのである。(119~120頁)
■ まず、サンスクリット本の『八千偈般若経』の中から、般若波羅蜜多についての説法をとり上げてみよう。
声聞、縁覚、菩薩、仏を学ぼうと思う人は、般若波羅蜜多を聞くべきであり、奉持すべきであり、唱えるべきであり、熟達すべきであり、発現すべきである。また般若波羅蜜多において身心の統一に入るべきである。
――八千偈般若経
声聞、縁覚というのは、アビダルマ仏教の人たちであり、いわゆる小乗仏教徒である。菩薩は大乗の修行者たちのことである。仏はアビダルマ仏教も大乗仏教も包み込んだ修行の完成者である。そうしてみると、アビダルマも大乗も、また仏を目指す人も、ひとしく般若波羅蜜多を学ばなければならないということである。
般若波羅蜜多は、いわば言葉として結晶した形なきいのちであるので、ちょうど日本の言霊(ことだま)に当たるだろうか。その般若波羅蜜多を聞かなくてはいけない。この奉持というのは、真言宗でいう陀羅尼(だらに)と同じ語源の言葉で、般若波羅蜜多のいのちを身体で、あるいは心で常に保っていくということである。
次に、「唱えるべきであり」とは、今日の日本仏教で念仏を唱えるとか、題目を唱えるとか、あるいは大日如来の名を唱えるということが教えられるが、それと同じである。単なる言葉ではなく、そのいのちを唱えていくのである。聞いたり、保ったり、唱えたりしていくうちに、般若波羅蜜多といういのちがわれわれの身体に熟して、だんだん深まってくる。これが熟達である。そしていのちが私の全人格体と一つになって発現するのである。以上のことから明らかなように、この簡潔な句は、般若波羅蜜多の行道のプロセスを非常によくあらわしているといえよう。
さらに、われわれの全人格体、身心全体を般若波羅蜜多において統一していくべきことを述べている。これは禅定であるが、けっして自分の力で統一するのではない。般若波羅蜜多という如来の智慧に基づいてはじめて全人格体が禅定に入ることができる。ふつう仏教の実践については、禅定の実践を通して智慧が発現すると考え、禅定から智慧へという方向だけでそれをおさえている。しかし、そのおさえ方が一面的なものであることは、この『八千偈般若経』の言葉から十分に知られよう。より根底的には、まさに禅定そのものを支えるものとして般若波羅蜜多があるのである。(120~123頁)
■ 般若波羅蜜多が前述のようなプロセスを経て発現してくるときに、その状況はどうなるのであろうか。同じ『八千偈般若経』にはこの点に関して、
世尊よ、般若波羅蜜多において行じつつある菩薩は、つぎのように学ぶべきである。すなわち菩提心によってさえ行じつつあると思ってはならない。
なぜならその心は無心であり、心の本性は浄く輝いているからである。
――八千偈般若経
と説いている。冒頭の「般若波羅蜜多において行ずる」とは、菩薩の実践が般若波羅蜜多に支えられて成り立っていることをいう。般若波羅蜜多において行じつつある菩薩の全人格体に、般若波羅蜜多それ自体が発現してくる。如来の智慧そのものが行者の全人格体と一つに融けあってあらわれてくるのである。
その場合、「菩提心によってさえも行じつつあると思ってはならない」という。菩提心とは悟りを実現しようと願う心であり、もっとも大事な仏道の根幹である。「目覚めよう」と立ち上がることがなければ、悟りはありえない。それは基本の教えである。ところが、般若波羅蜜多が発現してくる場合には、そういう大切な教えも不要になっている。菩薩の心は、ただひとえに無心になって、その心の本性は般若波羅蜜多のいのちに輝いているばかりである。
なお、仏教思想の一つとして、心性本浄説、すなわち人間の心の本性はもともと清浄であるという説がある。この説が、とかく「こころの本性は浄く輝いている」というこの個所をよりどころとする場合があるが、それは、「般若波羅蜜多において行ずる」ということを無視した誤った見解である。
以上、『般若経』の教えについて述べたのであるが、しかし、学派・宗派の違う仏教の流れのなかにも同じ教説がでてくる。たとえば法然は般若波羅蜜多のかわりに、南無阿弥陀仏の念仏を唱えることを説いている。その法然自身の仏道の果てはどうなったかというと、念仏が独り立ちをするというのである。そうしてみると、般若波羅蜜多を学んでいるうちに、般若波羅蜜多そのものが人格体に発現してくるのとまったく同じである。
一遍も同様のことを説いている。「念仏は安心して申すも、安心せずして申すも、他力超世の本願にたがう事なし」(『消息法語』)と述べ、「となふれば仏もわれもなかりけり南無阿弥陀仏なむあみだ仏」と詠っているところから、それは明らかであろう。宗派の相違を超えて、仏道の到達する目的というのはきちんと決まっているわけである。だからわれわれは、安心して自分に適切なそれぞれの修錬を積んでいくことができるのである。(122~124頁)
■ ところで、『般若心経』とともに東アジアにおいても大変親しまれてきた『金剛般若経』では、次のように説いている。
如来によってこれこそ究極の悟りであると、まのあたり目覚めた所の、何らかのダルマが存在すると、お前は考えるか。
世尊よ、そうではありません。……なぜなら如来がまのあたり目覚めた所のダルマは、触れることもできず、説くこともできないからであります。
聖なる主体はまさしく無為から現れたものだからであります。
――サンスクリット本・金剛般若経
これは『金剛般若経』の中でもきわめて大事な個所である。ブッダが弟子のスプーティ(須菩提)に向かって問いかける。「本当に究極の悟りに目覚めた場合に、何か、目覚めたという形にあらわれたものがあるとおまえは思うか」と。スプーティは、「そうではありません」と答える。なぜかというと、如来が現実に目覚めたところのそのダルマ(パーリ語ではダンマ)、いのちそのものは、触れることもできないし、言葉で説明することもできないからであるという。「触れることもできない」というのは、何か形のあるものとして感触されるようなものではない、という意味である。悟りは、形のないいのちそのものが顕わになるのであるから、全人格体で感得する外はないのである。「聖なる主体」というのは、サンスクリット語ではアーリヤブドゥガラという。アーリヤは「聖なる」ということ、「聖なる」というのは、世間を超えたものという意味である。宗教学でも「聖と俗」といっているが、その聖である。ブドゥガラとは人、あるいは人を人たらしめるものを指す。それゆえに「聖なる主体」とは、如来であり、いのちそのものである。
「無為」とはどういうことか。「いろは歌」に「色はにほえどちりぬるを我が世誰ぞ常ならむ有為の奥山けふ越えて」という、このこの「有為の奥山を超えた」ところが無為である。「有為の奥山」というのは、一切合切の地上の生活の形あるものの奥深い山、という意味である。いくら奥の山を踏み分けて入っても形ある世界にすぎない。その奥山を越え出たところが無為という形なき世界であり、彼岸であり、涅槃である。この「いろは歌」はこちらから向こうへ越えるとなっている。ところが『金剛般若経』はちょうどその逆である。いのちそのもの、形なき世界から、聖なる主体、如来があらわれてくるのである。どこにあらわれてくるか。もとより私自身である。それゆえに如来を感得した私自身も如来とひとしくなるのである。
■ 同じ『金剛般若経』には、
何ものにも依りかからない心が生ずべきである。
――サンスクリット本・金剛般若経
という言葉もある。これは「応無所住、而生其心」と漢訳されて、東アジアの仏教において大変有名な一句となった。漢訳の方は訓読では「まさに住するところなくして、しかもその心を生ずべし」と読むが、要するに何ものにも依存しない心の確立を勧めるものである。言葉をかえていえば、如来のいのちそのものが心の奥から自然に吹き上げてくるということである。
仏教では、正しい生活の基盤として戒律を重視する。いわば生活の規範であるが、われわれが自らの生きざまを律していく場合、いちばんの根拠は内から吹き上げてくる、いのちそのものである。これが根本の戒である。
■ これは仏教だけのことではない。さきに触れた孔子の『論語』は道徳が中心になっており、仁、忠、孝などが説かれている。こうした道徳の基本は、孔子によれば天命を聞くということである。天命は道となって、一瞬もこの身から離れられない。寝ても醒めても離れられないものが道であり、それが天の声となる。その天の声を聞きながら、それが仁となり忠となっている。だから、仏教も儒教もキリスト教も、あらわれている形(教えや習慣)はそれぞれ違っていても、その舞台裏になっている眼に見えないいのちはまったく一つである。これが何百万年来生きつづけてきたヒトの当然のすがたである。(127~128頁)
■ 慧能は、子供の頃から大変苦労した人である。伝記によれば、家が貧しく、父を早く亡くし、薪を売って母との生活を支えていた。ある日、町に薪を売りに出たときに、一人の客が宿舎で『金剛般若経』を読誦するのを聞いて悟るところがあり、五祖弘忍の門に投じた。それから、八か月間、寺の片隅でひたすら石臼をつく仕事に専念したという。文字も知らなかったという話もあるが、いわゆる知識人からはほど遠い経歴の持主でであった。そういう人が六祖となり、摩訶般若波羅蜜多をねんずるという深い境地を得たのである。
では、六祖慧能はどういうところを説いているのであろうか。
善知識よ、惣じて自体を須(もち)いて与(とも)に無相戒を受けよ。一時に慧能の口に従って道(い)え。善知識をして自らの三身仏に見(まみ)えん。
自らの色身において清浄法身仏に帰依したてまつる。自らの色身において千百億の化身仏に帰依したてまつる。自らの色身において当来円満報身仏に帰依したてまつる。
已上(いじょう)三唱す。
――六祖壇経
この部分の漢文はむずかしく、ここではその一つの読み方を紹介したわけであるが、六祖慧能には、ほとんど修行の積み重ねというものがなく、五祖弘忍のもとで突然に大悟している。この点から考えると、慧能は、生まれながらにしてダイヤモンドを口にくわえて生まれてきた人のように思われる。つまり、ダンマが熟しかかったままでこの世に生まれて、一気に大悟徹底した。そういう慧能の教えであるから、非常に明白である。
まず慧能は、善知識よ、弟子たちよ、と呼びかける。「惣じて自体を須(もち)いて」というのは、弟子たちみずからの身体で、ということであり、「無相戒を受けよ」というのは形のないいのちに目覚めて、それによって律していけ、という勧めである。慧能はこのいのちを無相戒と呼んでいる。そして「みんな一緒になって自分とともに次の言葉を唱えなさい」といってその言葉がつづいている。すなわち、「自らの色身において清浄法身仏に帰依したてまつる」というのは、自分の身体に顕わになっている法身仏に帰依し、合掌礼拝していく。また、自分の身体に顕わになっている千百億の無数の化身仏に帰依していく。この自分はいろいろな人々とまじわり、さまざまな生きざまをあらわしている。そして、その中で出会う人びとがそれぞれ無数の仏となって説法してくれる。こちら側からいえば、そうした教えや経験を通じて修練を積ませてもらう。そこから千百億の化身仏(現実に仮りの身をあらわす仏)という表現が出ている。
今日の科学によれば、われわれの身体には約六十兆の細胞がはたらいている。それらの細胞が骨や血液をつくり上げ、自分の知らないうちにはたらいて私を生かしてうれる。だから、それら一つ一つが化身の仏だということもできる。さらには、自分の身体においてやがては功徳を完成するであろう報身仏に帰依していくという。この言葉を三たび唱え、みんな一緒に合掌し、般若波羅密多の行を続けていくのである(130~131頁)
■ 慧能は、三身は一身だともいっている。三身とは、法身仏・報身仏・化身仏である。その三身は一身たる法身仏に帰着する。法身仏は形のいのちそのものである。たとえば私は知らなくても、法身仏は私自身に顕わになっているのであり、その法身仏に合掌し、礼拝していくうちに、さきほどの『金剛般若経』のように法身仏が自分の全人格体に発現してくる。自己がいのちそのものとなる。これが見性である。このことを、「もし塵労(迷いの心)無ければ、般若は常に在りて、見性を離れず」などと表現している。ふつう見性というと、とかく自分の本性を見るという文字通りの意味に受け取りがちである。だが、本性を見るというのでは、どうしても見る主体が微妙に残る。そうではなく、すでに顕わになっているいのちそのものに見(まみ)えるときにはじめて自分そのものが空になる。何ものにもとらわれない、いのちそのものに充足されるからである。これを慧能は見性というのである。(131~132頁)
■ 後世、見性を揚げる禅宗の立場を厳しく批判した道元は、
仏法は人の知るべきにはあらず。このゆえにむかしより凡夫として仏法をさとるなし。ひとり仏にさとらるるゆえに、唯仏与仏(ゆいぶつよぶつ)、乃能究尽(ないのうぐうじん)という。……尽大地のことばは、ときにも、としにも、こころにもしたしくして、ひまなく親密なり。
――正法眼蔵・唯仏与仏
と説いている。これは、一面において慧能の見性を別の形で開示したものといってよいだろう。道元のこの一文はきわめて重要である。結局、われわれ人間は、仏法を悟ることは不可能だというのである。悟りとは、ただ仏に悟られるのみというのである。仏と仏とのみが、一切を究め尽くしているのである。道元はそれを「尽大地」という。尽大地とは、味わいの深い言葉である。大地全体であるから、おっこちようがない。ゆったりと安らうことができる。その尽大地が、年々歳々、年を経れば経るほど親しまれてならない、と道元は感嘆している。尽大地とは、要するに仏であり、法身仏に外ならないが、このことをよくよく味わってみるべきである。そしてはからずも、慧能と道元とが人間の深い根底においてぴったりと合致している。
ともあれ、慧能のいう見性のあり方は、帰依を通じていのちそのものに見(まみ)えることであって、「自己の本性を見る」という悟り方でないことは明らかである。今日の仏教にかかわりをもつ誰もが再三再四反省してみるべきことではだろうか。(132~133頁)
■ 帰依の実践ということで思い出されるのは、禅宗の開祖とされる達磨、菩提達磨の話である。『洛陽伽藍記』によれば、達磨は百五十歳を超えて、口に「南無」と唱え、日々合掌した、と伝えられている。ところで、達磨の真説といわれているものに「二入四行(ににゅうしぎょう)説」というのがある。この中で達磨は、自分の宿業の深さを深刻に反省している。ブッダのいわゆる業熟体である。そしてみずからの宿業を知らされたとき、おのずから解脱に達している、という。この宿業感が、そのまま最晩年の達磨の念仏につながっている。おそらく、100年以上もただひたすら坐りぬいてきた達磨の最後の姿が、みずからの宿業の身のままで南無仏、南無仏と毎日唱えつづけているのである。この行道の中に、如来のいのちあるいは般若波羅蜜多が発現していることはいうまでもないであろう。仏のいのちの発現は、もとより古代の聖者たちだけのことではない。実はわれわれ一人一人の生命も、宇宙を貫いている如来のいのちにつながっているのである。(133~134頁)
■ 釈尊はさまざまな瞑想の修行や苦行ののち、さらに菩提樹の下で禅定に入り、やがて目覚めを体得した。その目覚めの体験は、われわれがその教えにしたがって学んでいくうちに自然に気づくことはあるが、とうてい言葉に表現することはできなかった。その体験のありようをはじめて言葉としていいあらわしたのが「ダンマが顕わになる」ということである。
釈尊は目覚めてブッダとなったときに、「私は悟りを開いた」といわず、「ダンマが顕わになった」といった。これが仏道の根本なのである。「私は悟りを開いた」となると、無意識的な「私」が微妙にはたらいて消滅しない。これでは、安らぎにならない。そこで「形のないいのちであるダンマが顕わのなる」といった。では、どこに顕わになるのか。いうまでまなく業熟体である。すなわち「ダンマ・如来は業熟体に顕わになる」。ここに、仏道の本質がいい尽くされているといってよい。(138~139頁)
■ 目覚めるということは、ブッダの教えを学んでいくうちに、自分の意識の底が抜けてしまうことである。いいかえれば、自己そのものがあらゆる束縛から解放されることである。これが目覚めの体験である。しかし、この体験はなかなか持続しない。せっかく目覚めても、またもとの木阿弥に戻ってしまう。ゴーディカという弟子は、悟りを開きながら後戻りすることを繰り返し、七度目に目覚めたとき、後戻りをしないようにとみずからいのちを断ってしまった。こういう深刻なことさえおこってくるのである。しかも、これはけっして弟子たちだけのことではない。ブッダ自身がそのことを経験している。(139頁)
■ せっかく開いた目覚めがまた閉じてしまうことを、ブッダは禅定を深めながら懇々と説法している。それは、私というものが、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものと交わりながら、生まれかわり死にかわり、死にかわり生まれかわりして、いまここに現存している業熟体だからである。すなわち、はるかな過去から積み重ねてきた業が成熟して、いまここにこの身をもって生きている存在だからである。それゆえ、業熟体は、私という単独のそんざいではなく、共同体の結び目であるから、それは底がなく深い。われわれが思い描いている自分はごく浅いところで意識されたものにすぎない。底のない自分というものは、とうてい意識にはのぼってこない。
そのために、ある時点では目覚めても、もっと深まるとそれは閉じられてしまう。いくら目覚めても、業はさらに深いものであるから、やがて閉じられてしまう。結局は袋小路に入ってしまうことは分かっていても、この道をわれわれは避けることができない。繰り返し、何とかして目覚めたいという思いがおこってくる。このことはブッダみずからが認めているところである。
では、その袋小路からわれわれを抜け出させてくれるものは何であろうか。それが、繰り返し言及している形なきいのち、ダンマ・如来の間断なき通徹に外ならない。われわれが意識すると意識せざるとを問わず、生きとし生けるものに向かって常に顕わになりつづけ、はたらきつづけているのである。したがって、深い業をもつ私であっても、自ら修行僧となって禅定をつづけていくうちに、そのダンマ・如来、いのちそのもののはたらきが、ついには私自身を包み込み、滲透し、通徹する。一語にしていえば、包徹するのである。如来が私の全人格体を包徹する。包み込んで透徹する。こうして実現される境地が如来住である。如来が私に融け込んで、私は如来に安らうのである。こうなれば、私という業熟体は如来から包徹された如来の子となり、ダンマの相続者であるということになる。(139~140頁)
■ さて、ブッダの教えの原型は「ダンマ・如来が業熟体に顕わになる」ということであるが、代表的な大乗経典である『華厳経』ではどのように説かれているのであろうか。『華厳経』の仏は毘盧遮那仏といわれる。サンスクリット語ではヴァイローチャナ・ブッダで「光の仏」という意味である。この毘盧遮那仏は、法身仏であり、形なきいのちそのものである。その毘盧遮那仏が宇宙共同体たる業熟体に顕わになり、通徹していくすがたを説いたものが『華厳経』に外ならない。
それは、ブッダの原始経典の説法とは比較にならないほどの広大なスケールでiるが、仏道の基底である「形なきいのちそのものが業熟体に顕わになり、通徹する」という点ではいささかも異なることはない。まったく同一であることを、かたく牢記しておきたい。
目覚めたブッダを象徴する「光の仏」は、『華厳経』によれば、全世界を包みきっているといわれている。さらにいえば、全宇宙そのものがヴァイローチャナ・ブッダである。われわれは、宇宙そのものとしての仏の中でさまざまな生きざまをしているのである。
『華厳経』は、仏の悟りの世界をそのまま説いた経典であるといわれているが、毘盧遮那仏自身は、法身仏であるから、ひと言も説いていない。その仏にかわって、さまざまな菩薩や神々が登場して、仏の世界のあり方を説き明かしていくのである。(141~142頁)
■ 普賢菩薩は説法に先立って、まず三昧に入る。その際、毘盧遮那仏の本願力に催されて三昧に入るという。本願力というのは、文字どおり根本の願いから生まれてくる力である。根本の願いというのは毘盧遮那仏のそれであり、毘盧遮那仏は先にも触れたように、全宇宙そのものであるから、当然ながら一切衆生を包摂している。それゆえに毘盧遮那仏の願いは、そのまま一切衆生の願いである。毘盧遮那仏と一切衆生と一体となった本願である。その本願力に催されて三昧に入るというのが、入定(三昧にはいること)の大事な要(かなめ)である。けっして自分の力で入るのではなく、必ず仏の力に動かされて入定する。そこではじめて仏そのものに触れることができる。(143頁)
■ かくして普賢は三昧から出て、毘盧遮那仏の世界を説き始める。
すべての世界海は限りない因縁によって成り立っている。
すべては因縁によって、すでに成立しおわっており、現在成立しつつあり、また未来も成立するであろう。では、因縁とは何か。
仏の威神力(いじんりき)である。ものごとはすべてありのままということである。衆生の業を導くことである。すべての菩薩は究極の悟りを得る可能性を有していることである。仏の究極の悟りを完成しながら、神変を生ずることである。
これが世界海の因縁である。
――華厳経
ここに揚げたのは仏の世界の総論であって、これにつづいて各論が詳細に説かれている。ここでは総論だけを見てみよう。
「すべての世界海」というのは、仏の世界を縹渺(ひょうびょう)とした大海に譬えて海といっている。すべての世界は限りない因縁によって成り立っているが、すでに成立し終わったものもあり、現在成立しつつあるものもあり、将来成立するであろうものもある。これが仏の世界であるというのである。
では、因縁とは何か。この因縁ということが、およそわれわれが心に描いているような種類の因縁ではない。仏の世界の因縁であるから、まことに意表を突くような、しかもさまざまな因縁が説かれている。(143~145頁)
■ 次の因縁の説明には、「ものごとはすべてありのままということである」とある。これは法爾(ほうに)とか自爾(じに)といわれるもので、おのずからそうなっているということである。ただし、この「ありのまま」は、われわれがありのままというのではない。仏の目から見たありのままである。この世界は、どこまでも深く底の知れないものであり、思いを尽くせば尽くすほど、未知の領域は広がる。それなればこそどこまでも学んでいかなければならない。
次に、「衆生の業を導くことである」とあるが、仏の世界というと、われわれ苦悩している人間・衆生の世界とは別の、特別の世界かと思いがちである。しかしそれは間違いであって、実は苦悩しているわれわれ自身の世界が同時に仏の世界である。われわれは、ただ業のままに苦悩しているだけではない。常に仏に包まれ、仏の化身である菩薩に導かれつつあるのである。つづいて、「すべての菩薩は究極の悟りを得る可能性を有している」と示している。仏道修行に励んでいる人びとには、必ず究極の悟りが得られる。いつかはそこに達することができるという保証が与えられている。(146頁)
■「浄行品」には菩薩の具体的な生活を通しての願いが語られているが、次の「賢首菩薩品(げんじゅぼさつぼん)」ではさまざまな三昧が説かれている。
東方にて三昧に入り、西方にて三昧よりたち、あるいは西方にて三昧に入り、東方にて三昧よりたつ。
聴覚にて三昧に入り、音声において三昧よりたち、もろもろの音声をききわける。
――華厳経
前述のように、われわれの日常生活のひと駒は仏道につながっており、そのひと駒ひと駒の中で、三昧に入っていることになる。二人で語りあっているときは、語りあいということに専念している。それは一つの三昧のすがたである。ー中略ー。
また職場の中で三昧に入って家庭の中で三昧からたつ。両者はつながりあっている。また、「聴覚において三昧に入り……」というのは、うっとりと音楽に聞き惚れている音楽三昧のすがたであろう。このように、日常生活のすべてが三昧としてつながりあっているのである。むしろ三昧の世界から出ることができない。出るも入るも三昧の世界というのが実相――-真実のすがたである。(152~153頁)
■ 海印というは、真如本覚なり。妄尽き心澄み、万象ひとしく現ず。なお大海の風によりて浪をおこすも、もし風止息すれば海水澄清(ちょうしょう)にして象として現ぜざるものなきが如し。
――妄尽還源観
これは仏の世界を海に譬えたものである。波が静まるとあらゆるものが海面にすがたを映すように、毘盧遮那仏という広大な仏の世界に、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものが姿を宿しているというのである。たとえば、二人が語りあっているときには、語りあっているそのままが毘盧遮那仏の世界に映っているのである。
とかく生活の中ではいろいろな問題がおくってくる。人間関係がまずくなって憎しみあうこともあるし、仕事につまづいてにっちもさっちも動きがとれないこともある。そのことを心に思いつめてくると、自分はますます孤立して閉塞してしまう。そのとき海印三昧を思い浮かべてみる。いま苦しみ悩んでいるすがたが、そのまま仏の心に映っていることに気づく。すると悩みの根っこがほどけて、別の新しい道が開けてくる。(154頁)
■ 日本仏教の流れの中で、「仏のお見通し」という言葉が生まれているが、この簡単な言葉が出てくるまでに、どれほどのダンマの営みがつづけられてきたことであろうか、はかり知れないものがある。仏に見通されて、お見通しであるということに気づくと、悩みがこれまで望んだこともない安心にかわる。つまり不可思議な仏の力、仏の威神力が出てくる。このような海印三昧のはたらきを、深く追求し、的確に表現した一人が道元である。
諸仏諸祖とあるに、かならず海印三昧なり。この三昧の遊泳に説時あり、証時あり。行時あり。海上行の功徳、その徹底行あり。これを深深海底行となりと海上行するなり。
――正法眼蔵・海印三昧
中国の華厳宗における海印三昧も大変貴重な教えである。しかし道元は、さらに一歩を進めて、日常生活の活動そのものを海印三昧と見る。諸仏諸祖、すなわち、もろもろの仏祖には必ず海印三昧がある。その三昧の大海をわれわれは泳いでいるのであるが、その泳ぎの中に、説法のときもあれば悟りを開くときもあり、修行のときもある。それだけではなく、毎日毎日のわれわれの生きざま一つ一つが海印三昧である。そして「海上行の功徳、その徹底行あり」とあるとおり、そのような生きざまは徹底している。ということは、仏の威神力に動かされているから徹底しているのである。そのことを示したのが、最後の言葉の「深深海底行なりと海上行するなり」である。非常に面白い表現であるが、両足が海の底に根差したまま海の上を泳ぎ抜き生き抜いていく、というのである。
われわれは、一瞬も仏祖の海印三昧の世界を離れることはない。この事実を深く自覚し、ぴたりとその世界に足をつけて生き通していきたいものである。(154~156頁)
■ この現前地ではじめて我執が見えてきて、いま自分が見ている世界、経験している世界がそのままこの心であることに目覚める。これを漢訳では「三界は虚妄(こもう)、ただこれ一心の作(さ)」といい、簡単に三界唯心と表現している。三界とは、欲界(欲望の世界)・色界(物質の世界)・無色界(無物質の世界)の三つの世界で、要するにわれわれが生きている惑いの世界、悩みの世界の全体をいう。「虚妄」とは、むなしいいつわり、「一心の作」とは、虚妄がそのまま心の作用、はたらきだということ。もしこれを、惑い・悩みの世界が、実はそのまま自分の心だというように解釈すると、まったく違ってくる。なぜなら、この解釈では第三者の立場につれ戻されており、したがって自分という意識が残っている。そうではなく、世界のあらゆる虚妄はただ心だと気づく。これは驚くべき目覚めであり、解脱である。現前地なればこその目覚めである。というのは、その途端に、虚妄は消えており、心は真実心、如来心に転換しているからである。しかしながら、この現前地にもとどまらない。解脱してもなお解脱する、とブッダが言明しているとおりである。(161~162頁)
■ 第八の不動地は、菩薩の十地全体の中で最後の転換がなされる境地である。それは、仏の家に生まれたという全体から出発し、一切衆生とともに行じながら、仏のいのちが菩薩の人格体に次第に熟してきて、熟しきったところがこの境地だからである。いいかえれば、仏のいのちが菩薩に融け込み、菩薩はみずから意図することもなく、心構えることもなくおのずから仏に動かされて生き通していく境地、それが第八不動地なのである。
それゆえに、ここでは無功用(むくゆう)ということをいっている。無功用とは、こうしよう、ああしようという自分の意図なしに、自然にはたらいていくという意味である。サンスクリット語ではアナーボーガであるが、無功用の外に自然(じねん)とも訳されている。いずれにせよ、おのずからそうなっている、あるいはおのずからそうなっていくということである。親鸞の「自然法爾(じねんほうに)」とか、孔子の「心の欲するところに従って矩(のり)を踰(こ)えず」というような意味で、孔子も親鸞も晩年に到達した心境である。第八不動地もまた、菩薩の行道の中で最後の大きな転換だといえる。
中国の曇鸞(どんらん)という浄土教の祖師は第八地を目指し、たぶん実現したものと思われるが、わが国では聖徳太子が『勝鬘経義疏(しょうまんぎょうぎしょ)」の中で、第八地の菩薩に注目して、各地で強調しており、いかに太子が第八地を目指して仏道を行じていたかが知られる。(162~163頁)
■ 第九善慧地(ぜんねじ)では、たとえば「一毛端処(一本の毛の端)に無数の如来がいて、それぞれの如来が無数の衆生にダルマを説く。このような広大な心を成就すべきである」という。これはもはや一個の菩薩のはたらきを離れて、その活動が全法界へ移っていることが知られる。そして第十法雲地では、ダルマで、すなわちいのちそのものが雨霰(あめあられ)のように菩薩にふりそそぎ、菩薩は漏れなく受けとめる。これは法雲地にしてはじめてできることであるという。このような境地になってくると、われわれにしては推察はつくが、それを実現することは至難の業(わざ)である。
かくして十地(じっち、じゅうじ)の結びは法雲地であるが、それで終わるのではない。第十法雲地がまた出発点になって、限りなく仏道を行じていくということが「十地品」の教えである。
しかし、この十地は、あくまでも道しるべであり、水先案内である。菩薩、つまりわれわれ一人一人のいのちに支えられつつ踏み歩いていく道は、人によってそれぞれ違う。こうした道しるべ、水先案内に正しく導かれながら、一人一人が具体的に自分の生き方として学んでいくことが大事なのである。(163~164頁)
■ 一一(いちいち)の毛端の処、念念の中において無数の如来、未来際を尽くして常に法輪を転ず。
――探玄記
『探玄記』というのは、法蔵が『華厳経』六十巻本を注釈したもので、そのはじめには、当時の仏教全体を総括的に考察した仏教概論が示されている。中国仏教の無数の典籍の中でもっとも代表的なものの一つである。
ところで右の文は大変むずかしそうに見える。しかし、要点ははっきりしている。「一一の毛端の処」とは、われわれの体には無数の毛が生えている、その一つ一つの毛の端のところ、非常に小さいところをいう。念念というのは、われわれは生活の中でいつも何かを心に描いているが、その一瞬一瞬を意味する。つまり一本一本の毛の端のところ、われわれの生の一瞬一瞬の中で、数限りない如来が未来永遠にいつまでも説法しつづけていくというのである。
今日、人間の体は、六十兆の細胞で構成されているという。その細胞の中には、自他の区別をするものがあって、異物が入ってくると適切におさえこんでしまうともいわれている。そうしてみると、六十兆の一つ一つの生命のはたらきが、私自身を支えていることになる。私がまったく知らないうちに、私の体の無数の細胞がいのちのおのずからなるあり方を教えてくれているのである。生活経験のひと駒ひと駒の中で、天地の説法、仏の説法を聞き取っていくことを『華厳経』は教えているのであろう。紙に書いた経典は省略されたものであり、本当の経典は、いま現にわれわれが生きつづけている、そのただ中で聞き取っていくべきものである。(166~167頁)
■ 江戸時代の末期に、二宮金次郎、のちに号して二宮尊徳という人が出ている。いろいろな活動をした人で、七十歳で亡くなっているが、ことに農業をみずから実践しながら人生の教えを説いた。その翁の生活の中から出た歌に、「音もなく香もなく常に天地(あまつち)は書かざる経を繰り返しつつ」とある。本当の経典は、紙や書物にあるのではない。天地の中で教えられるものこそ本当の経典だというのである。(167頁)
■ この法身説法ということに、われわれはよくよく留意してみるべきである。法身とは、色も形もない如来である。それこそ原始仏教におけるダンマ・如来である。その法身が説法するとは、色も形もない如来が、われわれ衆生に法を説くことである。これはまさしく、ブッダにおける解脱の原型たる「ダンマ・如来が業熟体に顕わになる」ことではないか。ただ『大日経』は宇宙的なスケールで法身説法を実現しているに外ならない。いいかえれば『大日経』は、解脱の原型と合致しているのであり、見事にその原型に復帰したということができるであろう。(170頁)
■ では、どのように法身説法しているのであろうか。まず、『大日経』という経典の名前について見てみよう。前にも触れたが、『大毘盧遮那成仏神変加持経』というのが『大日経』の新しい名前である。空海の教えを学んでいくと、この経典の名前から、『大日経』がどういうことを説いているかを知ることができる。たとえば、神変加持という語である。神変とは、サンスクリット語ではヴィクルヴィタといい、いろいろな形をとっているという意味である。つまり、われわれ衆生は、さまざまな形をとっている。顔やすがたも違い、体質や環境も異なる。さらに気質、能力も多種多様である。しかも、互いにつながりあっており、大小さまざまな共同体を営んでいる。まさに千変万化である。そのような衆生の形にぴったりと密着して法身仏そのものがはたらいてくるのである。それが神変である。
では、それはどこからおこるのであろうか。まさに如来大悲の願力からおこるのである。大悲の願力がアディシュターナ、すなわち加持である。アディシュターナについては、第Ⅷ講で詳しくのべたので、それをよく参照してもらいたい。それは、よりどころであり、念力であり、力そのものである。われわれは意識すると、しないとにかかわりなく、仏に念ぜられ、動かされている。しかも、大日如来は宇宙全体である。宇宙におけるすべての動き、すべての音声、すべての思念は、そのまま如来のふるまい、如来の声、如来の思いであり、さらにそのままわれわれ自身の、身の動きであり、語らいであり、思念である。これこそ大日如来の法身説法に外ならない。(170~171頁)
■ 六大無碍(むげ)にして、常に瑜伽(ゆが)なり。三密加持すれば速疾(そくしつ)にあらわる。
――即身成仏義
これはよく知られた空海の言葉である。六大とは地大・水大・火大・風大・空大・識大の六つをいう。大とは要素の意味である。すなわち六大とは、すべての存在を作り上げている要素を六種と見たものに外ならない。このうちはじめの四大、すなわち地・水・火・風はインド以来のものであり、古代のギリシャにも共通している。次の空大というのは空間、虚空である。最後の識大というのはわれわれの意識的なはたらきをいう。すると、これは全宇宙の存在を成り立たせている要素をこの六つで代表させているということができる。物的なものも心的なものも、六大に収まる。これら六つの要素が互いにさわりなくはたらきあうのが無碍、しまもぴったりと相応しているというのが瑜伽である。これが大日如来の世界であり、密教の観点から見たコスモスとしての大宇宙である。いわば宇宙を構成する諸要素が互いに妨げあうことなくはたらき、宇宙そのものが大三昧に入っているという。
大日如来は、そのまま全宇宙であり、その全宇宙は三昧に入っている。そうしてみると、こうしている私自身は、このまま大日如来の三昧に参加しているのであり、さらに突きつめると、大日如来の三昧そのものであるということができる。
では、どうすればそうしたことをこの身には体得することができるのであろうか。それが「三密加持すれば速疾にあらわる」ということである。三密とは、三つのはたらき、すなわち、ふるまい・語らい・こころであり、この三つのはたらきがそのまま大日如来のはたらきとなっているから三密という。要するに三つのはたらきとは、私の全人格体に外ならない。それゆえに私は、この身をこのまま大日如来に任せ切って入定(禅定に入る)すれば、直ちに大日如来が私自身に顕わになってくる。如来のいのちそのものが私の全人格体に噴き出てくる。空海は加持について「如来はそのまま私の心にあらわれ。私の心はそのまま如来を感得する」と説いているから、大日如来にまかせて入定するだけでよい。そうすれば、如来がそのまま私の全人格体に顕わになってくるのである。いいかえれば、即身のままで成仏する。これが空海の大事な教えの一つである即身成仏である。(172~173頁)
■「風来たって門開く」――これは古人の言葉であるが、私のいのちが風になって吹いてくると、自然に心の扉が開かれてくる。実際、調息をやっていくと、最後には頭も心も身体もひとかたまりになった息づかいになる。それがそのまま天地の息づかいにつながってくる。そういうことをブッダも覚鑁(かくばん)も教えているのである。(175~176頁)
■ 釈尊が菩提樹の下で目覚め、ブッダとなったところから仏教は始まっている。ブッダが解脱し、八十年の生涯、説法をつづけたが、その間にブッダ自身もだんだん熟していった。それは、ダンマ・如来が業熟体に顕わになり、滲透し、通徹しつづけていくという、仏道の永遠のはたらきに包まれていたからである。
業熟体というのは、限りない昔から生まれかわり死にかわり、死にかわり生まれかわりして輪廻転生しつづけている私自身、同時にその私自身が、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものとまじわっている宇宙共同体である。その私自身ならびに共同体に、ダンマ・如来、いいかえれば形のないいのちそのものが顕わになって、滲透し通徹しつづけていく。それは現在もはたらきつづけ、未来永劫にはたらいて息(や)まないものである。
業熟体というのは、底の知れぬ深いものであるから、一度や二度の解脱で徹底することは不可能である。ブッダ自身も菩提樹の下で解脱に達したあとも、そのままその状態がつづいたのではない。解脱を回復しようと努めているうちに、こちらから目覚めようとしていた方向が逆転して、ダンマ・如来から通徹してくる境地に至る。それがすなわち如来住である。これは原始経典の中での最高の禅定である。
その如來住からさらに転換して、ダンマに目覚めようとしていた自分は、実はダンマから生まれたもの、如来から生まれたものとなり、ダンマ・如来の相続者となって、現在から未来に向かって歩きつづけるのである。
これが仏道の基幹線であり、原始仏教から大乗仏教を貫いて発展している。(198~199頁)
■ ブッダは八十年の生涯の間に、さまざまなことを教えている。そのすべてについては、凡慮のはかりしれないことであるが、ひたすらにブッダの教えにしたがって学んでいくうちに、仏道者としての根本態度はどういうことであるかということが知られてくる。それは帰依三宝である。三宝とは仏・法・僧である。
この中で法とはダンマであり、形なきいのち、いのちの中のいのちである。このダンマが如来と呼ばれるようになり、人格的な意味を帯びてくる。それがすなわち仏である。そしてダンマ・如来を中心とした共同体が僧に外ならない。この仏・法・僧を生活のとりどころとして尊敬し帰投していくことが帰依三宝である。帰依三宝は仏教の創始以来今日まで、仏道者の根本態度として一貫してきたものである。
さらには、帰依三宝の実践の道が念仏・念法・念僧である。ブッダはこれについて懇切に説法している。まず、念仏である。念仏は、仏の名を心に唱えて仏(如來)を憶念することである。そうすると全人格体が静まって禅定に入る。やがて貪ぼり・怒り・愚痴の根本煩悩から開放され、何ともいえない喜びが心の底からおこってくる。次第に深まってくると身も心も軽やかになり、さらに深まると喜びも身心もすべて忘れ果てて全人格体がすっぽりとダンマ(いのちそのもの)の流れの中に入ってしまう。これが念仏であると説いている。すなわち、念仏がそのまま禅定であり、禅定がそのまま念仏である。
しかるにのちの中国仏教では念仏は浄土宗、禅定(坐禅)は禅宗に分かれる動きがあらわれ、日本仏教もそれを受けて今日に至っている。ここで十分反省すべきことは、念仏と禅定はもともと一つであるということである。これが仏道の原型である。(200~201頁)
■ ブッダの教える学は、近代仏教学とは基本的に違っている。その学は戒・定・慧の三学といわれるものである。戒学は日常生活を統制することであり、そうすれば身心はおのずから静まる。それが定学のはじまりである。身心が静まる果てには、頭も心も魂も、そして体も、全人格体が一つになって作用する思惟が発現する。それが定学にほかならない。近代の諸科学(近代仏教学も含めて)の思惟が対象的思惟であるのに対して、全人格的思惟と呼ぶことができる。この思惟が持続していくうちに、やがて真実の智慧が開かれてくる。すなわち慧学であち、解脱の実現である。これがブッダの本来の学たる戒・定・慧の三学であり、ことにその基本は定・慧の二学に集約される。
そうしてみると、近代仏教学が開かれてくると同時に、われわれ学界人は、ブッダ本来の学を放棄してしまったことになる。その点から見て、本来の学に踏み込むことは、近代仏教学の館べにおいては不可能であるといわねばならない。
本編は、対象的思惟ではなく全人格的思惟のたちば、すなわちブッダ本来の学に立ち戻ることから出発する。そのためには本来の学をこの身に実現していかねばならない。その実現には私は五十年あまりの時間を要した。いわば生涯を賭けたことになる。この過程を述べることは私自身の個人的な課題であると同時に、公の意味を含むものである。というのは、ひとりの平凡な人間がブッダの説法のとおりに学んでいくことによって、自然に道が開けてきたからである。それはおのずからそうなっていく必然の結果であり、仏教の枠組みを超えた人間普遍の道である。(216頁)
(2022年5月18日、了)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
『宗教と人生』玉城 康四郎 春秋社
■ 仏教では、釈尊以来、そうした転換の機縁になるものを、信という言葉であらわしております。釈尊の最も古い経典といわれております『スッタニパータ』にも、この信がわれわれの世界における最上の富であるといっておりますが、釈尊の原始仏教以来、この信が大乗仏教を通じて、非常に大きな宗教の世界への入口、あるいは宗教の世界に対してわれわれの全人格が門戸を開くそのモメント、機縁になっておるのであります。
この信は、信ずるということなのでありますけれども、いろいろの意味があります。だいたい、仏教でいっておるところの信とは、次の三つの意味を含んでおるようです。一つはいわゆる信ずる、英語で申しますとビリーフ、ドイツ語ではグラウベン、これは仏教の場合にもシュラッダーとかサッダーとかいう言葉を使っておりますが、信頼するという意味であります。
私どものヒューマン・リレーション、人間関係におきましても、相手を信ずるということの基盤には、やはり真実というか、誠実というか、そういうことがあり、それが基盤になってはじめて信用関係ができるのじゃないかと思います。仏教でも、仏は真実であり、仏は誠実であるといわれますが、その仏はしんじつであり、誠実であることから、おのずから信ずるという仏と人間の関係が起きてくるように思われるのであります。
ところが、仏教の信はそうした意味ももちろんありますが、それだけではなくて、この信は、池の水がずっと底の底まで澄みとおっておるように、徹頭徹尾、底の底まで澄浄である、澄みとおって清らかである、という意味をもっておるのであります。
つまり、仏の世界は最澄浄法界といわれておりますが、少しもにごりのない、混じりけのない、ずっと底の底まで――私どもの知性や、私どもの心は、すぐ途中でつきあたりますが――仏の知性、心はずっと果てしなく、底の底まで澄みとおっている。そうした仏の心が自分の上に流れてきて、かすかなながらも、そういう澄みとおっておる世界が感じられてくる。そういうことが、第二の信の特徴としてあげられると思うのであります。
それからもう一つは、これはアディムッティとかアディムクティという言葉で、信をあらわしておるのでありますが、それを信解というふうに申しております。信とは、なにがなんでも、わけのわからぬことでも、なんでも頭から信ずることではありませんが、最初はやはり、どうもそういうふうなところから、われわれは歩きだすわけでしょう。
わけはわからぬが、とにかく、ひとつ信じてみようじゃないかというところから、私どもは出発するわけであります。だが、ほんとうの信の味わいは、なにがなんでもじゃなくて、ちょうど反対に自分の心の中からひらけてくるものがある、だからおのずから信ぜざるをえない、こういう意味のことを信と申しておるのであります。(12~13頁)
■キリスト教の信仰は、たとえばテルトリアヌスという中世の著名な護教家がおりましたが、その人は「不合理だから信ずる」と言っています。これは、合理的に理解できるものは信ずる必要は。神さまはわれわれの頭にものらない、われわれの言葉にも、考えにも、心にも、なんにものってこない。合理性を全く越えておるからこそ神を信ずるのだ。不合理だからこそ信ずる、というのであります。
これはキリスト教全体の信仰ではもちろんありませんけれども、少なくとも、仏教のアディムクティー、信解という意味とは根本的に違ってくるのであります。ほんとうの合理性、ほんとうのラチオ、ほんとうの道理を仏教はこれまで追求してきたし、また私どもも、そういう真実の道理をどこまでも徹底的に明らかにしていかねばならないと思うのです。そこに、一つの自然の道理によって、おのずからひらけてくる性格を信が持っておるわけであります。
こういうふうに、いろいろの意味あいの信が渾然と一つになっていて、信とはかくかくのものであると、きれいさっぱりと理屈であらわしてしまえるものじゃなく、やはりわれわれの宗教の世界において生きたものです。だから、そういったいろいろの意味が渾然と一つになって、信が今日まで動いてきたのであります。私どもは、仏教の真清水の流れの中で、そうした意味あいの信の真清水を汲み取っていきたいと思うのであります。(13~14頁)
■インドでは、古い時代から責任を果たすという教えがたいへん強調されております。自分に与えられた責任を果たすという、そのことによって、悟りの世界に至るというのです。『バガヴァット・ギータ』というインドの古典がありまして、そこにカルマ・ヨーガ(実践のヨーガ)ということが説かれております。それは、自分のつとめを果たすことによって宇宙の大きな生命に目覚めるというのであります。人によっては神も仏も信ずることのできない人がおります。どうしても信じられない人は信じなくてもよろしい、ただ自分に与えられた仕事を、全身全霊それに打ち込んでいく、たといそのために自分に何の報いが得られなくても少しも意に介しない、貪著しないで、ひたすら自分の責任を果たしていくという、そのことだけによって、おのずから悟りが開けてくる、目が覚めてくる、宇宙の大生命と一体になるというのであります。これがすなわち大きな報いであります。(22頁)
■そのとき釈尊の心の中に浮かんできたかと申しますと、「自分が目覚めた真理は非常に深くて、とても一般の人々には理解することはむずかしい。それは寂静微妙な世界であって、分別の境地を越えておる。ところが世間の人々は、アーラヤを喜び、アーラヤをたのしんでいる。(このアーラヤということは、ここでは簡単に自我の根源というふうに解していいかと思うのであります。)そのアーラヤを喜び、アーラヤをたのしんでいる、こういう衆生にとっては、自我の目覚めた縁起の道理はなかなか理解することが困難であり、たとい自分が説法しても人々は理解してくれないから、私はただ疲労困憊するにすぎないであろう」――そういう感懐が釈尊の胸に浮かんでまいります。そして釈尊は、このまま沈黙の世界に入ろうとされるのであります。もし釈尊がそのまま沈黙してしまわれたら、仏教というものは、われわれには伝わってこない。いかに釈尊の悟りが深くて大きいものであっても、それはわれわれにとっては全く無関係なものになってしまったはずであります。ところがその時、梵天が現われて、どうかひとつその真理をお説きくださいと懇願し、釈尊は、その願いをいれて山を降りて行かれるのであります。この「出山の釈迦」というのは、皆さんもよくご承知と思います。昔からこれが、一つのモチーフになって、盛んに「出山の釈迦」がいろいろな画家によって描かれてきておるのであります。
ここで申し上げたいのは、目覚めた釈尊の心に映じた私どものすがたであります。私どもがアーラヤを喜び、アーラヤを楽しんでおるという点であります。釈尊の悟りの胸に描き出された私どもの心の実景というものは、自我を楽しみ、自我に執着し、自我にとらわれているという点であります。これがわれわれの偽らない心の姿であろうと思うのであります。
釈尊の言葉の中では、このアーラヤという言葉には別に説明がつけられていないのでありますが、釈尊がなくなられてのちに、この問題がいろいろにその後の仏教者によって展開されてまいります。そして、釈尊の滅後七百年ばかりたった時に、そのような人間の心の世界が徹底的に究明されてきたのであります。それは、三世紀から五世紀にかけてインドの仏教者、無著、世親の兄弟によって明らかにされたのであります。いまはどうか知りませんが、前には上野の博物館に運慶作の無著と世親の等身大よりも大きい説法の像が陳列してありました。片手に経典を持って説法しておられる像であります。
この無著と世親は、インドの多くの仏教者の中で非常にすぐれた、非常に内面的に問題を追求した人であります。無著によって『摂大乗論』という書物が出ております。それを弟の世親が注釈しておりますし、また世親は『唯識三十頌』という心の世界に関する短い頌を作っておりますが、その頌に対してインドの安慧という人が注釈し、また護法という人が有名な『成(じょう)唯識論』という書物を作っています。この『成唯識論』が中国に翻訳されて法相宗となり、それが日本にも伝わってきたのであります。そして、大和の法隆寺などで盛んに研究されたのであります。(32~34頁)
■この無著、世親によって究明されました心の世界というものを、ここで、ご一緒に考えてみたいと思うのであります。この心の世界をこの兄弟が明らかにしたということは、ただ研究したとか、あるいは観察したということではないのであって、深い禅定に入って、その禅定の世界の中で自分の心がどういうふうに映ってくるか、どういう姿をしているかということをそのまま記述していくのであります。インド、中国、日本では、西洋のいわゆる科学的な考え方の芽ばえはありましたけれども、とうとう結果としては科学の世界は展開しなかったのであります。しかし、この無著、世親のやり遂げた仕事の根本は、実に科学的精神に貫かれているのであります。禅定に映っている心の姿をそのまま記述しているのであります。
まず私どもの心について考えられますことは、心の一番先端にあるものは、いうまでもなく感覚の世界であります。これは東洋でも西洋でも同様でありますが、眼、耳、鼻、舌、皮膚感覚。それに相い対するものが、色、声、香、味、それから皮膚感覚の対象になるもの、これを蝕と言っております。目とか鼻とかに対応して、色とか声とかがその対象となって、それをわれわれは感覚の世界で受け取っておるわけであります。たとえば赤を赤として感覚するのは、もちろん目に映っているわけですが、赤を赤として気づくのは、もう一つ感覚の世界の奥にこれを統一している心によって感知されているのであります。つまり、五つの感官を統一している心があります。ここまでは私どもにもよくわかります。
フランスの感覚論者にコンディヤックという人がおりまして、この人は徹底的な感覚論者でありました。たとえば、デクノボウの人間をまず想定してみる。目も口も鼻も何も持っていない。ただ頭と体と手足だけがついているデクノボウです。このデクノボウに、まず目という感覚を与える。そうすると、このデクノボウは視覚の世界だけが与えられている。さらにそれに鼻をつけてやると、視覚プラス嗅覚で、においの世界がそれに加わる。これに口をつけてやると、味わいの世界がそれに加わる。それから耳をつけてやると、さらに音の世界がこれに加わる。最後に皮膚感覚をつけてやる。それで感覚の世界の全部がそなわったことになる。そしてこれ以上加えるものはない、と考えるのが感覚論の主張であります。つまり、芸術的な感情も、宗教的な感情も、哲学的な推理も、全部感覚で解釈できるという非常に徹底した感覚論であります。これがフランスでルネッサンス以後おこっておるのでありますが、よく考えてみると、なるほど、非常におもしろい見解であると思います。
ところが、この観念が心の一番究極のものであるかというと、そうではない。自我の観念というものをよく考えてみるというと、別に自我というものはどこにもないのです。自我というものはどこにもないにもかかわらず、必ずこの観念が起こっておるのであります。私どもは、それをよく自分で気づくわけであります。そうすると、この自我の観念が起こってくる、その容れものがなくてはならない。そういう容れものを、自我観念の奥に考えているのであります。それを無著、世親の言葉でもうしますとアラヤ識というのであります。
さきほど、釈尊が悟りを開かれた時に、私どもの心の姿を見抜いて、人々はみなアーラヤに執着し、アーラヤを楽しんでおるといわれた、そのアーラヤであります。これを縮めてアラヤ識と申すのであります。つまり心の問題は、自我観念と、その自我観念の起こっている容れもののアラヤ識との関係に根本の問題が伏在しているように思われるのであります。(34~37頁)
■少し話がむずかしくなりますが、このアラヤ識ということを、ひとつ一緒に考えてまいりましょう。アラヤ識という言葉ですが、ヒマラヤ山のことはヒマアラーヤというのでありますが、ヒマというのは雪という意味であり、アーラヤというのは貯蔵の意味であります。つまり年がら年じゅう雪を蓄えているという意味がこのヒマラヤであります。このアラヤ識というのは、そういうふうに、まず貯蔵ということ、それを漢字では蔵と訳しております。ヨーロッパの学者は、ストア・オブ・コンシャスネス、意識の蔵、すべての人間の意識が蔵の中に蓄えられている、そういう意味でこのように訳しております。
このアラヤ識には、いろいろな意味、いろいろな性格が説かれておるのであります。まず第一が、いま申しましたアラヤ識、つまり、すべてのものをその蔵の中にいれて待っている容れものということであります。
この蔵の意味について、三つの方向が考えられております。その一つは能蔵、つまりそのアラヤ識が一切を蓄えている。現実経験の私どもの世界は、すべてこのアラヤ識の中に蓄えられている。
ところが、第二の意味はそれと逆の所蔵といういうのであります。これはちょっとわかりにくいかと思うのですが、ちょうどその反対で、現実経験の世界の中にアラヤ識が逆に蓄えられている、つまり所蔵であります。いいかえれば、私どもが経験している世界は、すべて自分のアラヤ識のあらわれである。苦しもうと、楽しもうと、どんな目に会おうと、それは全部自分のアラヤ識、いいかえれば自分自身の責任である。つまり自分のアラヤ識は経験している世界の中に蓄えられている、そういう意味をあらわしているのであります。
それから第三番目には、こんどは執蔵と申すのであります。この執蔵というのが、要するに執着の源泉を蓄えているところの蔵であります。つまり一切の自分の執着が、このアラヤ識から発生している。いいかえれば、執着の源であります。
このように、能蔵と所蔵と執蔵の三つが蔵の意味だというのであります。これがまずアラヤ識の第一の意味であります。
第二には、同じアラヤ識を根本蔵と申しております。これはわかりやすい名前であります。根本蔵というのは、人間の意識の中で最も根源的な意識、これは当然であります。
第三には、一切種子識つまり現実経験の世界の種をここに含んでいるところの意識、これがアラヤ識の第三のいみであります。ここには非常に大切なことが説かれているのであります。それはどういうことかと申しますと、アラヤ識というものは、私どもの経験の世界を起こすところの種を持っている。だから、私どもがいろいろな経験をする。たとえば、こういう場所でこういうことを話している。これは私の現実の世界でもありますが、それはことごとく自分自身のアラヤ識から発生している。これを種子生現行(しゅじしょうげんぎょう)といいます。現行というのは、今日の言葉でいえば、現実経験の世界ということであります。だから、種子が常に現行を生じている、現実経験の世界を生じている。私がこういうことを話している、こういう場所にいるということは、自分のアラヤ識が常にそういうふうに繰り出していることである。ところが世界の実相は、この一面と同時にもう一つの面があります。それはちょうどその逆で、現行薫種子であります。線香の入っている箱は、線香を除いて空箱になっても、それをかぐと線香のにおいがする。これを仏教では薫習(くんじゅう)と申しております。それぞれの人間にはその人のにおいがある。薫ずるものがる。現行薫種子というのは、これは現実経験の世界が同時に自分のアラヤ識、つまり自分の人格の根源に影響を与えている、しかもこれが同時だというのです。ということは、私は自分のアラヤ識に基づいて、こういうふうに経験しながら、しかもその経験の世界が自分のアラヤ識に、いいかえれば自分の人格の根源に常に影響を与えている。これが世界の実相であるというのであります。
最後の第四に、アラヤ識は異熟識と申します。お米に水を入れて火にかけるとご飯になる、あるいはまた青い果物が赤く熟れる、それを熟といっております。ではこの異熟識という言葉はどういう意味かというと、異というのは「いろいろさまざまな」ということであります。つまり異熟識というのは、いろいろさまざまな因縁によって、このアラヤ識、この人格の根源は熟しているということであります。自分の人格の根源でありながら、実は自分で始末がつかないのであります。というのは、ずっと無限の過去から年々歳々また一刹那一刹那に働き続けてきたその結果が、現在のアラヤ識として熟している。それが良かろうと悪かろうと、拙劣であろうと、どうであろうと、楽しかろうと醜かろうと、こういうぐあいに熟しておるわけであります。
では、どういう原因・事柄によってこれが熟しているかというと、これは無数の原因・事柄によって、つまり異、ほんとうにさまざまな因縁によって、無限の過去から現在のこの一刹那のこういう私として塾しているのであります。これをかりに私のアラヤ識といたしますと、この中にはこういうふうに――といっても、私にもまだ自分のことがどこまでわかっているかわかりませんけれども、しかも事実はこういう私として熟しているわけでありますが、これがずっと無限の過去から、決して同じものではなくて、年々歳々中身は変わりつつ熟して、現在にまできているわけであります。この無限のかこのどの刹那をとってみても、第三に申しましたように種子生現行、現行薫種子でありまして、その刹那のアラヤ識からその刹那の現実経験の世界が醸し出されて、しかも同時に、その世界がこのアラヤ識に影響を与えていく。つまり、醸し出すことと影響を与えることが同時で、それがずっと今日に来たって、いまもなお種子生現行、現行薫種子という働きを続けているのであります。ここが、いわゆる宿命論とか運命論とかいう問題と比較される点でありますが、現在の光景を過去のほうからながめて見た場合には徹底的な宿命論で、これはどうにもならないのであります。私の現在の人格というものの熟し方はずっと無限の過去から続いて今日に至っているのですから、自分の手先ではどうにもならない。この方面から見れば、徹底的な運命論であります。
しかし、いわゆる運命論と根本的に違うのは、無限の過去を全部ひき受けて立っている現在の自分が、現在の刹那もなお働いて、未来の熟にあずかっているということであります。その点では絶対自由であります。つまり、絶対必然を全部背負って、しかも絶対自由であります。迷いに向かおうが、解脱に向かおうが絶対自由なので、しかも現在私が働いている。これを仏教ではカルマ(業)といいます。現在もなお絶対必然の運命を背負って、その必然の中で絶対自由に働いている。この絶対自由の働きが、無限の過去から必然せしめられたそのアラヤ識をひき受けて、次の将来の自分の人格を必然ならしめ、結果していくものであります。だから、絶対必然を全部背負って絶対自由に働いている。これが、仏教のカルマであります。
インドにおいては、釈尊以前の非常に古い時代から、こうしたカルマには注目しておりました。古いじだいの『ウパニシャッド』に、この問題が当時の哲人たちによって論議されているのであります。このカルマの、そういう非常に奥の深い問題は、公の場で講義しておったのではなくて、先生と弟子との対坐の形で、この秘説が伝えられておったという記録が残っております。(39~43頁)
■ところで、親鸞は、このようなアラヤ識という奥の深い容れものの中で起こっている私どもの自我観念というものを、どのようにしてコントロールし、調伏し、解脱のほうへ向かわしめるか、であります。アラヤ識と自我観念の関係が存続する限りは、われわれはやはり迷わなくてはならない。苦悩から脱却することができない。ではどうしたらこの関係を転回して、ほんとうの目覚めの世界に達することができるか、これが、究極の問題になるのであります。
ここまで申しあげますと、もうお気づきかと思うのでありますが、結局のところは、自分の力ではどうにもならないということであります。というのは自分の力は、いま申しましたアラヤ識と自我観念の関係において発生しているからであります。ところが問題は、その関係を転回せしめねばならない。無著、世親は、さきほど申しましたように禅定をずっと深めて、禅定の世界に映じてくる自分の心の姿を記述してまいりました。ではいったい、どうしたら最後のアラヤ識を方向転回させることができるか。という最後の問題に突き当たって、いくら禅定を深めていっても、このアラヤ識はどうにもならない。ここでは、自分の小さな禅定から、その自分をも限りなく包むところの大禅定への転換が必要になってくる。それは何かというと、最清浄法界より流れてくるところの響きに触れなければならない。そうすることによって、自分の人格の根源を貫いているところの、その〈いのち〉に直接触れなければならない。そうすることによって、自分の人格の根源を貫いているところの大禅定の世界が存すると思うのであります。
この最清浄法界につきましては、何も説明されていないのでありますが、これはおすらくどこか天空の一角であるとか、あるいは、われわれ人間の世界とは別のところの、全然独立した世界であるとかいうことではないのであります。実は、われわれの心の世界の裏と表の関係のように思われるのであります。つまり、アラヤ識と自我観念の方向からいえば、そうではない最清浄の世界というものがあるわけでありますけれども、アラヤ識と自我観念の動いているままが、実はそういう実体はどこにもないのであって、ただわれわれの固執観念にすぎないのであるから、そのままで、最清浄世界の響きがそこに充ちわたっているのであります。ですから、私どもは気がつけば、いつでも、どこでも、その〈いのち〉に触れることができるのであります。
以上申し上げましたように、はじめは五つの感官、それから心、次に自我観念、最後にアラヤ識、こういう心の系列が、最清浄法界の〈いのち〉に触れることによって、われわれの人格的世界は根本的に転回して真実の智慧を獲得することができる。これを転識得智というのであります。識を転じて智を得る、というのであります。では、どのような智慧が得られるか。
まず五つの感官は、成所作智という智慧を得ることができる。つまり、目とか耳とかいうものが完全にその役目を果たす、その働きを完成することができる。
それから、その五官を統一している心は、妙観察智を得ることができる。妙観察智というのは、ものを観察する心の働きがきわめて微妙であるという智である。そういう妙観察智を得ることができる。それから、もう一つ奥にあるマナ識、つまり自我観念の意識は、その自我という観念が解消して自他平等の智慧、すなわち平等性智を獲得することができる。
最後のアラヤ識、これは、その転回にによって大円鏡智を獲得することができる。大いなる円かな鏡のような智慧、ちょうど大海原がしずまって一つの大きな鏡のようになる、そのような大円鏡智を獲得することができるというふうに説かれているのであります。
私どもがそこまで至るということは、現実の問題としては、なかなかたいへんなことでありましょうが、このように心の底の底まで見抜かれているわれわれの心の世界というものを、よく反省し、よく観察して、そしていいかげんなところで――ああ、これで悟りはひらかれた、というふうな慢心を起こさないで、どこまでも正直に自分の心の姿を反省し観察して、最清浄法界の〈いのち〉に直接触れていきたいと思うのであります。(43~46頁)
■【2『華厳経』とビルシャナ仏】ところで『華厳経』の精神、その世界観、人生観とはどういうことなのでしょうか。それは、いうまでもなく釈尊の悟りの内容になるのですが、この経典における表現が、多くの大乗経典の中で最も雄大なスケールを持っているものであります。『華厳経』における根本のブッダはビルシャナ仏です。ビルシャナというのは、原語でヴァイローチャナであり、光を意味しています。このビルシャナ仏はこの経典の根本仏でありながら、実は一度も説法しておりません。ただ黙然としているだけであります。あるいはむしろ、根本仏それ自体は説き得ないというのが適切でありましょう。
そして、このブッダをとりまく多くのボサツたちが、入れかわりたちかえり説法を行なっております。これらのボサツたちの説法をとりまとめたものが『華厳経』にほかなりません。ボサツは説法を始めるに当たって、まず禅定に入ります。禅定とは、姿勢を正し、足を組んで、身心を統一することです。この禅定に入ることによって、ボサツは深い宗教の世界に融没することができるのであります。
ところがボサツの入定(禅定に入ること)は、ボサツ一人で、自分の力でそうしているかというと決してそうではありません。彼の入定は、全くビルシャナ仏の意志力に基づくのであります。だから、ボサツの方からいうと、彼は入定によってビルシャナ仏の無限の力に触れているということができます。
かくして始められた説法は、ビルシャナ仏自体は一度も口を開くことはないのに、ビルシャナ仏が多くのボサツたちの口を借りて法を説いたともいえますし、あるいは、ボサツたちがビルシャナ仏の無限の力に動かされて口を開いたともいえます。『華厳経』の世界観・人生観を論ずるに当たっては、このような仕組みが考えられるのです。
ところでビルシャナ仏とは、いったい何でありましょうか。それは前に述べた如く光を意味しており、太陽の如く赫赫(かくかく)として照り輝いているものです。そしてその光は、この空間に行きわたらない所はありません。ビルシャナ仏の内容は、実はこの宇宙そのものなのです。われわれの肉眼に見え、われわれの意識に描けるところの宇宙ではなく、宇宙そのもの、宇宙の本体であります。宇宙の本体は、いかなる意味においても知ることも描くこともできません。だから、ビルシャナ仏は最後まで黙然としているだけなのです。一語も口を開くことはないのであります。
では、遂にそれはわれわれにとっては知り得ない、無縁のものになり終わるのでしょうか。否、否、決してそうではありません。それどころか、ビルシャナ仏は最もわれわれに近いもの、あらゆる近いもの以上に近いものなのです。なぜならそれは、宇宙の本体であると同時に、またそれなればこそ、われわれの本体であるからなのです。われわれ自身だからです。ビルシャナ仏は、まさにわれわれ自身なのです。
しかし、それはもとよりわれわれが意識しているところの自己ではありません。そのような自己はビルシャナ仏どころか、単なる煩悩の影にすぎません。自己の中の煩悩の影をすべて払い落としてみれば、自己意識というものがなくなって、自己と宇宙とがそのまま通じあっているのを感知することができます。いったい、自己そのもの、宇宙そのものとは何か、いいかえればビルシャナ仏とは何か。それについては、永遠にわれわれは知ることができません。しかし自己意識が消えて、自己がそのまま宇宙と通ずる時に、われわれはビルシャナ仏をうなずくことができるのであります。
このように、ビルシャナ仏はわれわれ自身の本体であり、また本来の故郷であり、実は本質的にわれわれ自身なのです。このビルシャナ仏に坐りを置いて世界の情景を描いたものが『華厳経』の世界観であり、われわれ自身の生きるべき道を説いたのがその人生観であります。(48~50頁)
■3『華厳経』の世界観
まず世界観はどうでしょうか。世界はどのような光景を呈しているのでしょうか。すでに明らかにした点からいえば、世界のあらゆる事象はビルシャナ仏の顕現であり、その働きであるということができます。ここに、ビルシャナ仏の智慧の眼に映ずる世界の光景と、われわれの凡眼にうつる光景とが全く相違していることが知られます。われわれの眼には万象が互いに差別しており、対立しているように見えます。しかし私の慧眼(けいがん)には、その差別しているままが互いに通じあっており、対立しているままが実は一つなのです。なぜなら、万象はことごとく仏のあらわれだからです。それが実相です。ここでは、万象は互いに何の障りや隔てもなく、自由に交流し、流通しあっているのです。この光景について『華厳経』は、いろいろな角度から説き明かそうとします。その一、二の例をここに述べてみましょう。
ビルシャナ仏は、いま大三昧に入っておられます。あたかも大海原が静まりかえっているが如くであります。それは限りない静寂の中にあります。同時に大海原には、ありとあらゆるものが姿を宿しています。一事も一物も、ここに映じていないものはありません。つまり、海原に映じているものが現実世界の事象なのです。現実世界の事象は、各個ばらばらぼように見えていて、実はビルシャナ仏の大三昧の海原の中に親しく映りあっているわけです。これは『華厳経』の世界観の一つの譬えであります。
ところで、この譬えをさらに身近につきつめて見るとどうなるでしょうか。世界の事象が海原に映じているということは、逆にいえば、この自分がいま経験していること、たとえば仕事の計画が思うようにすらすらとはかどっていること、あるいは病気がなかなか直らずに心あせっていること、等々、このように現実を経験しているということが、海原に映じているいることを意味するのです。ここから、『華厳経』における人生観の一つの深い意味が発生してきます。その点については後に触れましょう。
世界における一つの事象は、他の事象と交流しております。交流しあったものが、また他の事象と交流します。かくして無限であります。しかもそれは、順序を追って交流するのではなく、あちらからもこちらからも同時に行われますから、その様相の複雑さは想像を絶しています。静かな池の面に一つの小石を投ずるとします。始めは小さな波紋が、次第に大きく広がっていきます。別の石を投じます。前の波紋の広がりと新しい広がりとがぶつかりあい、かみあいして、いろいろ異なった波の形を示していきます。さらに次から次へと小石を投じていくと、無数の波紋が無数の異様な波の光景を呈します。一人一人が水に投じた小石なのです。しかもそれは絶えず波紋を起こしています。また逆に、一人一人が水に投じた小石なのです。しかもそれは絶えず波紋を起こしています。また逆に、一人一人は無数の波紋のぶつかりあいから生じた一波形にすぎないともいえます。そしてその一波形が、また波紋を呼び起こしていくのです。
一人の人間は無数の波紋のぶつかり合いから生じた一波形にすぎない、という点を考察してみましょう。たとえば、自分の一存在を中心に考えてみますと、自分には父母があります。その父母にはそれぞれの父母があります。またその父母には同じように父母があって、このようにして自分から逆に何代かをさかのぼって父母の総数を数えてみると、実に予想外の多きに達します。つまり、自分の現実の活動を少しく内面からながめてみると、このような無数の父母の血液がここに動いているということができるのです。しかしこれは、自分の存在をただ父母という角度から見たものにすぎません。実際は、そのほかの無数の角度が一つにみられて、自分の存在は活動しているに違いありません。
また、自分の投ずる波紋が他に無限の影響を与える光景は、次のような譬でも示されます。鏡の間があるとします。四方八方鏡で出来た部屋です。部屋の中心に立って右手を挙げます。しかしよく見ると、四方八方だけではありません。互いに他を無限に映し合っており、したがって無数の右手が同時に挙がっております。こんどはニッと笑ってみます。すると、無数の自己の影が同時にニッと笑います。間一髪を容れません。このように、自己の投じた一石の波紋が、限りなく宇宙にその影響を広げていくのです。
右に述べたいくつかの説喩からも推察できるように、『華厳経』に描かれている世界像は、一即一切、一切即一、互いに相い交じり、貫きあい、融けあいして尽きるところがありません。しかもこのような貫きあい、融けあいは、まさにビルシャナ仏そのものに基づいているのです。しかもビルシャナ仏は、われわれの本来の故郷であり、まさにわれわれ自身であるとしますと、融合無尽のこの華厳経的世界像は、実はわれわれ自身の内包する世界像にほかなりません。この点に、『華厳経』における世界観と人生観との最も深い帰一処が存するのであります。(50~53頁)
■4『華厳経』の精神
人生いかに生くべきか、ということは宗教の最大問題であります。『華厳経』が最も深い意味において宗教的であるとすれば、この経典は、当然、いかに生くべきかということを問題にしているはずです。
人生いかに生くべきかということは、生き方であり、生きる方法であります。方法は目的から生まれてこなければなりません。目的が明確であってこそ、方法はそこから考察されてくるものです。『華厳経』における目的はビルシャナ仏であり、ビルシャナ仏としてすでに実現されているものであります。一般には、目的をめざして方法に従って進む、その結果、目的は達成されるものです。しかるに、『華厳経』においては、目的はビルシャナ仏としてすでに実現され終わっています。その実現され終わっている中で、われわれは、最も的確な方法を究めようとするのです。
しかし一方から考えると、すでに目的は達成されているのにいまさら方法でもない、ともいえるでしょう。にもかかわらず方法を検討するのは、いかなる意味を認めようとするのか。この点に、実は『華厳経』における人生観の意味の深さを汲みとることができるのであります。すなわちそれは、華厳という文字そのものが如実に表示しているところのものであります。華厳とは「華(はな)をもって厳(かざ)る」ということです。華とはわれわれ一人一人のことであり、一人一人がビルシャナ仏の大法界をかざるのです。われもまた、この悟りの大殿堂に金の一鋲を打ちこむのです。その打ち込み方、かざり方が、すなわち『華厳経』における人生観にほかなりません。
ところで、この人生観を考察するには、まずその最も基本的な性格を明示しておく必要があります。それは、前に示した大海原に映ずる万象の譬えであります。これは世界観の根基でもあり、同時にまた人生観の根基ともなるものです。人生観からいえば、自分の現実経験はまさにこの大海原、すなわちビルシャナ仏の大三昧に映ずる影にほかなりません。いかに激しい喜びに満ちていようとも、また逆に、苦悩そのもののような経験でも、そのままがビルシャナ仏に映ずる影にすぎないとすれば、喜びも悲しみも全くわれ一個のものではないということが納得されるでしょう。喜びも喜びに執せず、悲しみも悲しみに執せず、われなる固執の源泉が打ちくだかれて、ビルシャナ仏の大三昧に融け入るのです。喜びは喜びのままで無住であり、悲しみは悲しみのままで無住であり、その無住のままがビルシャナ仏における大安住なのです。これが無住の住といわれるものであります。
『華厳経』における人生観は、まさにこの無住の住たるの根本性格から出発します。これは華厳経だけではなく、大乗経典の全体を貫く空観の思想につらなるものでありましょう。
さて、この無住の住に基づきながら、どのような人生観が描き出されるのでしょうか。これについてもいろいろな視点からの展望が許されると思います。たとえば、ビルシャナ仏を人生の根基として、その代表的な二つの性格を具現せしめたものに文殊と普賢(ふげん)とがあります。文殊は大智であり、普賢は大悲である、文殊は大解(だいげ)であり、普賢は大行(だいぎょう)であるといわれます。つまり、大智と大悲、大解と大行が、ビルシャナ仏が人生に顕現する際の根本性格なのです。したがって、われわれがビルシャナ仏の法界の進運に参加するところの人生観の根基は、大智と大悲、大解と大行ということになるでしょう。大智とは、世界の深い道理に限りなく透徹することであり、大悲とは、道理に透徹した純粋な心が間清水のようなヒューマニズムを漲(みなぎ)らせることであり、大解とは、世界の事象を誤りなく判断し判別することであり、大行とは、判断も判別も乗り越えて働きから働きへと出ることであります。しかもそのいずれもが、ビルシャナ仏の大法界に帰入し、またそこから発出していく意味において、これらの諸性格は根源的に一体です。
『華厳経』の終末、入法界品には善財という一少年の求道の姿が描かれています。少年は、智慧の代表者である文殊に励まされ、五十三人の人々を訪れて、いっそう深く真実の法を体現しようと努めるのです。そして最後に訪れたのが普賢でした。経典はなぜ、求道者として少年をここに登場させたのでしょうか大人でなく少年をです。思うに、世智にたけた大人は、出世間の道を尋ねるのに適しないのでしょうか。大人の思慮分別は、かえって真実の法を求める能力を欠いているのでしょうか。少年のように純粋な心でなければ大法を求めることは不可能でしょう。われわれ大人もまた、方に向かうためには少年の心に帰らなければならないのです。
少年の心は純粋なだけではありません。それは、一途に求めてやまない激しさを包んでおります。五十三人の人々を訪ね終わり、普賢に至って少年の求道はやんだかというと、決してそうではありません。普賢は少年に向かって、汝の純粋な心を持って弛みなく法を求め続けよ、といい放っているのです。すなわち、少年は求道の無限精神をあらわしているといえるのです。このように、一途に限りなく求めてやまないものが少年の心で、大人は右顧左眄(うこさべん)とつまづきとが多いのでありましょう。
ところで、少年が教えを乞うた五十三人の中には、いろいろな階級の人間が含めれています。ボサツや僧侶や尼僧はいうまでもなく、王、王子、商人、長者、婦人、大工などもあり、また、バラモン、賎業の婦人も含まれています。仏教の中で当然師とすべき人々ばかりではなく、仏教以外の宗教人にも、また卑しまれている人々にまでも教えを受けております。これは何を意味しているのか。それはつまり、求道の前には、道に達している人か否かということだけが問題であり、宗教の相違、貴賤の差別は全く問うに足らないということです。このことは当然であり、至極あたりまえのことでしょう。しかし、この当然なことを平気で敢行しうるのは、やはり少年の心なのでしょう。
かくしてビルシャナ仏は善財という一少年に具現して、求道の永遠の旅に出るのであります。それが永遠であればこそ、豊かな希望の光りに胸がふくらむのです。われわれは少年の心に帰ろうではありませんか。そこからは、法の限りない宝の山を展望することができるのであります。(53~57頁)
■原始経典を見ますと、ご承知のように釈尊が菩提樹のもとに坐禅を組まれ、それまでのすべての苦行を捨ててひたすら禅定に入られた。そして、十二月八日のあけぼのに豁然として大悟されたのであります。大悟された釈尊は、そのまま立ちあがって説法のためにでかけられたかというとそうではなくて、その菩提樹のもとで坐禅を組んだまま、静かにいま自分が開いた悟りを観察しておられます。その時間が一週間、一週間といえばずいぶん長い時間でありますが、その一週間の間、じっと坐ったままでその悟りを深めておられるのであります。一週間たちますと、その菩提樹のもとを立ちあがって、こんどは別の木のもとでさらにまた一週間、静かにその悟りを味わっておられます。それがすむと、その木のもとを立ちあがってまた別のところへ行ってさらに一週間、こういうぐあいにして数週間、釈尊は雨が降ろうが、風が吹こうが、その悟りを静かに観察しておられます。その間に、経典の描くところによりますと、いろいろな魔軍、悪魔の軍隊があらわれては釈尊を苦しめる。しかし釈尊は、微動だもしないでその魔軍を静かに撃退しておられます。そうして、あたかも太陽が虚空にのぼるがごとくに釈尊の精神がすっきりと確立してしまって、もはや何も疑うところのないというところまで、釈尊の悟りが深められてきているのであります。
別の経典によりますと、釈尊がいったい何をそこで観察しておられたかが問題になってまいります。経典では、釈尊がその数週間、何をみておられたかと申しますと、いわゆる十二因縁といわれているものであります。われわれ人間の現実の世界が、根本の無智に始まって、いろいろの働きを起こして、その働きにわれわれは執着してついには死んでいかなければならない、そういう私たちの現実の姿を、釈尊が静かに観察されているのであります。
さらにはかの経典によりますと、釈尊はその禅定に入っておられる間に人間の無限の過去の世界、私たちが生まれたり死んだり、無限の生死を続けてきた過去の世界に思いを馳せておられます。それからまた、現在の人間の、しあわせに暮らしているもの、不幸なもの、顔の醜いもの、端正なもの、そういう苦しみや楽しみというものを限りなく観察しておられます。それが釈尊の悟りの内容であると、これらの経典が伝えているのであります。
別の経典によりますと、釈尊がいったい何をそこで観察しておられたかが問題になってまいります。経典では、釈尊がその数週間、何をみておられたかと申しますと、いわゆる十二因縁といわれているものであります。われわれ人間の現実の世界が、根本の無智に始まって、いろいろの働きを起こして、その働きにわれわれは執着してついに死んでいかねばならない、そういう私たちの現実の姿を、釈尊が静かに観察されているのであります。
ところが、釈尊が悟りを開かれたということは、歴史的に釈迦牟尼世尊が初めてそういう大悟をなされたかというとそうではないので、釈尊の生まれる以前においてすでにある。経典では七人の仏さまが、別の経典では二十五人の仏さまがそれぞれ大悟徹底されて、当時の衆生に対して教えを説いていることが見えているのであります。つまり、釈迦牟尼世尊は最初の悟った人ではなくて、それ以前にたくさんの先輩である仏さまがおられる。そういたしますと、釈尊の悟った世界は、釈尊が、初めて発見した真理ではなくて、すでにもろもろの先輩諸仏によって発見されてあった真理を、同じように釈尊が見いだされたということになるのであります。これらの仏さまは、あるいは九十一劫前の仏であるといったり、あるいは四阿僧祇劫、十万劫といったり、ともかく、とほうもない昔に、こういう仏さまたちが出て大悟し、かつ衆生に説いたということになっているのであります。さらに大乗経典の『法華経』によりますと、ここではもはや数としては数えることのできない久遠の昔、無限の過去に大通智勝如来という仏さまが出られ、すでに大悟徹底され、しかもこの久遠の仏は、いまもなお衆生に向かって休みなく教えを説いている、というふうなことが見えているのであります。(59~60頁)
■ このように見てまいりますと、仏の悟りそのものは、私たちには窺い知ることはできませんけれどもだいたい次のような、三つの悟りの方面を考えてみることができると思うのであります。この仏の悟りの三つの方面が、二千何百年の間展開してまいりました仏教という大きな教えの世界観の基礎になっているように思えるのであります。
第一に、仏の悟りは、仏さまが何かインスピレーションをうけて、この世界を超越して、別の世界を悟られたというようなことではなくして、もとよりこのわれらわれの世間を全くとびぬけられたのではありますが、同時にわれわれ一切衆生にに、そのままかかわりを持っているのであります。つまり、現実の自己の姿、われわれ一人一人の現実のありのままの姿が、実は仏の悟りの内容であり、その一部であるということができるのであります。
仏の悟りに映されている自分の姿はどういうものであるか。これは、私がいま自分の目で自分の姿を見ている、その自分ではなくて、どこまでも仏の智慧の眼、慧眼(けいがん)に映しだされている私の姿なのであります。経典の説いているところに耳をかたむけてみますと、われわれは、いまこうしていろいろな環境に育ち、いろいろな能力を持ち、いろいろな社会的なポストについて、それぞれ働いているけれども、これが息をひきとってしまえばそれきりだと思っているのが、われわれ凡眼の自分の姿であります。あらためて人に聞かれると、いやそうじゃない、死んでからなんとかほかの世界に行くだろうとか、あるいは仏さまに救われるだろうとか、そういう理屈は申します。けれども、われわれの現在働いている生活態度を見ますと、いろいろな欲望に走ったり、自分のためになることだけを考えようとしたり、そういう自分の現在の態度を見ますと、ともかく、死んだら野となれ山となれ、というのがどうもわれわれの本音のようであります。ところが、釈尊の慧眼に映し出されている自分の姿は、実は無始劫以来、無限の過去から迷いに迷い、生まれかわり死にかわり、おそらく未来永劫にその輪廻を続けてであろう姿なのであります。
無始劫と申しますと、始めがない、いつ始まったかというその限界がない、無限の過去といっては漠としておりますから、少し注釈を加えますと、劫というのは梵語では kalpa ともうします。kalpa というのは、いろいろに計算されておりますが、たとえば一つの譬えとして、縦、横、高さ八十里の立方体の岩石に、三年に一度天女が現れて、天女の衣の裾でサッと一回なでる。そうしてその八十里の立方体の岩石が全部摩滅してしまう、これを一劫と数えます。それが無始劫、無限の劫でありますから、ともかくある程度の想像がついて、その想像を絶する計算であります。その一つの kalpa の時間のなかで、われわれが生まれかわり死にかわりして、おかあさんの乳を飲んだその乳の量が四大海水よりもなお多し。これは人間のおかあさんばかりじゃありませんでしょう。犬にも猫にも経めぐってきたわけではありましょうから。ともかくその飲んだ乳の量が四大海水よりもなお多し、また一劫の中で、われわれの築きあげた白骨が毘富羅山―王舎城の近傍にある山――よりもなお高しと申してあります。これは昔の話ではなくて、いまこうしてしゃべっている私自身がそういう無始劫を経てこの演壇に立っているわけなんで、考えてみると、一個の人間も実に雄大な背景を持っているのであります。迷うということも、これほど雄大な迷いであったならば痛快というほかないと思うのであります。短期を起こして、よく二十歳前後の人が自殺をしますけれども、そういうことに思いをいたせば、もっと別の世界観が生まれてくるに違いないと思います。(61~62頁)
■ 第二の悟りの方面は、われわれ衆生は、一人残らず仏さまになりうる可能性をもっているという点であります。釈尊の在世当時、アングリマーラというたいへん残忍な凶賊が悪事を働いておりました。そのアングリマーラはただの追剝ではなくて、人を殺してその着物をはぎとるという悪事をさんざん続けておった凶悪な賊であります。しゃくそんとの間に、いろいろないきさつがありますが、結局最後に、このアングリマーラが釈尊に帰依して、その弟子となっております。
悪事に強いものは善事にも強いと申しますが、ひとたびこのアングリマーラが弟子になりますと、一所懸命修行を積み、とうとう最後には、釈尊と同じ悟りに達したのであります。「わが生はすでに尽き、なすべきことはすでになされ、もはや後有を受けない」。これは釈尊について語られている悟りでありますが、同じ言葉がアングリマーラの口をついて出ているのであります。「わが生はすでに尽き、なすべきことはすでになされ、もはや後有を受けない」。このアングリマーラがあるとき行乞に出かけまして、町々を歩いておりますと――この人はむかし盗人でしたから、いろいろな人々からたいへん恨みをうけている――かつて怨みをうけた人々が石を投げつけたり棒を投げつけたりして、この賊であったものをさかんに懲らしめる。とうとう、彼は自分の持っている鉢はこわされ、また、着ている衣は破られ、身体からは血をふいて、さんざんな目に会って釈尊のもとに帰ってきたのであります。そのとき釈尊はなんと仰られたか。「汝静かに忍従せよ。汝の受けた罪業は地獄の中で報われなければならないのに、その汝の大きな罪行がいまここで報われている。汝静かに忍従せよ」、そう釈尊はおっしゃっております。アングリマーラは、釈尊の言葉をただ頭をさげて聞いているだけであります。その時の彼の心境を、経典は、「ちょうど雲を離れた十五夜の月のごとく、アングリマーラの心が世界を照らした」と描いているのであります。つまり、たといアングリマーラといえども、釈尊に帰依し、釈尊の弟子となり、遂に悟りを開いてみると、もはや釈尊のつっかい棒はいらなくて、釈尊と全く同格の世界に生きぬいているのであります。(62~63頁)
■ 第三に、仏教の世界の根拠は、光明に始まって遂に一切衆生はその光明に包まれる、これが、仏教世界観の源泉であると思います。『大無量寿経』にある法蔵菩薩の修行はご承知のとおりでありますが、法蔵菩薩の修行の前に、五十三の先輩の仏が出ておられます。その五十三の先輩の一番まっ先の仏さまを錠光如来、あるいは燃燈仏と申します。これは、もとの言葉ではともしびです。Kara というのは、それをつくりだす――ともしびを、光をつくりだす仏さま、これは『大無量寿経』に限ったことではなく、すでに原始経典のなかに Dipamikara の仏さまは、第一等にあらわれております。つまり、久遠の過去に生まれ出た仏の最初の姿は、光明であります。『大無量寿経』では、五十三の仏を経て本願の教えが説かれているのでありますが、最後のくだりになって、仏の智慧の眼に映じているわれわれ人間の姿のあくたもくた、すざましい凡夫の姿が描き出されております。これを説き終わった世尊は、静かに禅定に入られて、遂に三千大千世界が光明の渦に巻き込まれてしまっております。
『華厳経』や『大日経』の本尊はビルシャナ仏と申します。ビルシャナとは、もとの言葉では Vairocana というので、これも光の仏であります。『華厳経』では、この微盧遮那仏、光の仏さまが3千大千世界、宇宙の中心の仏になるのでありまして、仏の真体というものは、いったい何かというと、宇宙そのものが仏の真体なのであります。それが仏の光なのであります。この経典では、いろいろの菩薩が現われ、いろいろの天人が現われて、仏の悟りの世界を讃嘆しておりますけれども、その本尊である大毘盧遮那仏はついに一言も発しない、最後まで沈黙を守ったままであります。それはわれわれの目にも見えず、また耳にも聞こえず、形もない法身であり、宇宙そのものがこの大毘盧遮那仏でありますが、よく考えてみますと、私もまたこの大宇宙の一片なのであります。つまり、大毘盧遮那仏はみずからは一言も説かれませんけれども、私が知ると知らざるとを問わず、私の背後にあり、根底にあって、常にこの私を育てている大宇宙の法身が毘盧遮那仏なのであります。(63~65頁)
■『華厳経』では、多くの菩薩があらわれますが、この大毘盧遮那仏を代表している二人の菩薩があげられます。一人は文殊菩薩、もう一人は普賢菩薩であります。文殊は、文殊の智慧として親しまれておりますが、これは智慧の代表者、毘盧遮那仏を智慧として代表する菩薩であります。これに対して、普賢菩薩は慈悲を代表する菩薩であります。また、普賢菩薩は大行の菩薩であるとも申されております。
まず、文殊の智慧によって映されているこの世界の姿はどうであるか。これはわれわれの凡眼に映っている世界の姿とは違っております。われわれの凡眼には、われはわれ、おまえはおまえ、それぞれ別々であります。これはこれ、あれはあれ、これも別々であります。ところが、文殊の智慧に映されているこの世界の姿は、われとなんじとが別々のものでありながら、そのまま一つになっているのであります。この世界における対立のままが、根本において融合しているのであります。これを物にたとえてみますと、広い水の面に小石を投げると、その小石の波紋がずっと遠くまで続いてまいります。別の小石を投げると、また別の波紋が起こってまいります。そうして前の波紋とぶつかりあい、また交流しあって複雑な姿を呈します。次々に小石を投げこみますと、次々に複雑な様相を呈します。その小石というのが、われわれ一人一人なのであり、その波紋が生活の動きをあらわしているのでありまして、われわれが互いに小石となって水に投じて波紋を描きながら融合しているのが、この世界の実相なのであります。大毘盧遮那仏はこの宇宙そのものとして、常に大三昧、大禅定に入っておられるのであります。つまり、われわれが現実の社会でいろいろに対立したり、いさかいあったり、あるいは泣いたり笑ったりしている姿は、そのまま大毘盧遮那仏の大禅定の中で起こっているそれぞれの影にすぎないのであります。坐禅をして仏の世界に触れると申しますが、それは、自分が自分の力で禅定に入っているように思っていても、実は大宇宙の毘盧遮那仏が大三昧に入っておられるその力によって、われわれがそれぞれ三昧に入っているのであって、そこではじめて自分を越えた大きな仏の力を、その禅定の中で感得することができるわけであります。
もう一人の普賢菩薩は、文殊の大きな智慧に対して大行と申してあります。これは言葉をかえて申しますと、大いなる人生であります。つまり、人生はいかに生くべきであるかをこの普賢菩薩が教えているのであります。人生はいかに生くべきであるかということは、けだし、宗教の最大の問題であると思います。華厳という言葉がその人生の生き方ということを教えていることばであり、華厳は花でかざると書いてありますが、われわれ一人一人がその花で、われわれ一人一人が毘盧遮那仏の真理の世界をかざっていくのであります。(66頁)
■ 我と無我
無我は仏教のたてまえですが、実は仏教よりもずっと古い時代に、インドにおいてアートマンという思想が起こっており、「真実の我」あるいは「我の本性」といわれているのであります。このアートマンに目覚めることがインド思想の目的になっています。これに対して、仏教は無我を主張します。無我をわきまえ、無我になっていくことが仏教の最後の目標になるのであります。
日常生活でよく、自分は我が強すぎて人づきあいがうまくいかないというようにいったりします。ところが、一方では逆に、我がなくなったら何もできないではないか、自分というものがあればこそわれわれの生活をよくしていこうという努力も起こってくるわけだ、第一、生きていくことがすでに我がある証拠ではないか、という主張もありうるわけです。こういう問題を念頭において、無我が仏教の思想史の中でどんな形であらわれているかを考えてみたいと思います。
仏教の古い経典には、『スッタニバータ』とか『ダンマパダ』というものがありますが、こういう古い経典では無我という言葉はなく、ただ、執着を離れるということが強調されています。たとえば『スッタニパータ』には、「常によく自分に執着する見解をうち破り、世界を空であると観ぜよ。そうすれば、迷いの海を渡ることができるであろう」とか、あるいは「いかなる執着も離れているということがともしびであり、涅槃である」とあります。涅槃は、仏教の最後の悟りの境地ですが、むしろ執着を離れるというのは自分がそうするのであり、したがって、自分ということがたいへん強調されます。
『ダンマパダ』には、自分に関する一章が設けられていて、その章の中に「自分こそ自分のよりどころである。自分のほかにいったい誰がよりどころになろうか。すなわち、自分がよく調えられることによって、そのよりどころを獲得することができる」とあります。よく調えられるということは、私どもも道理はよくわかっていても実行はなかなかできない。自分というものがなかなかいうことを聞かない。それが次第に訓練を積むことによって、いうことを聞くようになる。これが調えられるという意味なのであります。要するに自分こそが真理をわきまえていくよりどころである。そのためには自分がよく訓練され、よくいうことを聞くようになることによって、自分のよりどころを獲得することができるというのであります。
釈尊の言葉として、「自分をともしびとし、自分をよりどころとしてその他のものをよりどころとするな。また真理をよりどころとしてその他のものをよりどころとするな」というのはよく知られております。真理が現れてくるのは自分よりほかにないということで、現代の言葉では、主体性を持つ、あるいは自主性を持つということになろうかと思います。キェルケゴールが「主体性こそ真理であり、主体性こそ真実である」といっていますが、この経典の気持ちもそれに通ずるかと思います。要するに釈尊の教えは、執着を離れるように自分が努力をする、ただ耳に聞くだけではなしに、みずからそれを実践していくことであって、自分がなくなってしまうどころか、実は自分こそが実践の主体であることを教えておられるのであります。
そこで執着の中心になるものは、結局は自分に対する執着、我執に帰すると思われますが、しかし自分をよく観察してみると、その執着すべき我のかたまり、自我のかたまりはどこにも見あたりません。これが経典の中に無我として用いられ、定まった形になっています。たとえば色・受・想・行・識の五蘊(ごうん)が無我であるという。色というのは私どもの肉体、それから受・想・行・識というのは、その肉体に対して、さまざまな心の働き、あるいは心の主体を指しています。つまり自分の肉体をいろいろ観察してみても、あるいは、感覚とか心の働きについて詳細に観察してみても、どこにも我のかたまりは存在しない。いいかえれば、執着すべき我はどこにもない、そのことが、この経典の中で無我という定まった言葉でいわれているのであります。
ここで、無我について二つの方向が出てきました。一つは執着を離れること、もう一つは執着すべき我のかたまりがないということであります。この二つの方向が、大乗仏教ではどのように動いてきたでしょうか。(68~71頁)
■ 無我の二面
執着を離れるということは、有名なあの『般若経』の中によく説かれています。般若は智慧のことであります。つまり、執着を離れることがわれわれの最も尊い智慧、人生の智慧を獲得することになるのであります。そして、私どものさまざまな生き方、あるいは人生観、世界観が説かれます。宗教的、道徳的な生き方として、これはもう、誰もが守らなければならない生き方として、生きものを殺さない、盗みをしない、嘘をつかない、腹をたてない、怠惰な心を離れる、乱れた心をしずめる、というふうに、そこからあらゆる真理を究めつくそうとする生き方が説かれます。
それから、貧しい人に富を与える、裸の人には着物を与える、餓えている人、渇いている人には飲食物を与える、病気の人を癒してやる、心に煩悶のある人を安らかにしてやる、というようにして、人のためにつくし、お互いに助け合っていかなくてはならないことも説かれます。
そのほか世界観としては、先の五蘊と十二処・十八界ということがいわれており、十二処・十八界は世界の組み立て、構造を明らかにしたものであります。
このようにいろいろ説かれていますが、最も大切なことは、私どもがどんな生き方をするにしても、また、どんな世界観を持つにしても、少しもそれに執着をしないことであります。執着をしないから、私どもの生命は限りなく発展していくことができる。無執着に基づく生命の無限の発展、それが『般若経』でいう人生の最も大切な智慧なのであります。すなわち、無我とは、自分がなにもかもなくなってしまうこととは反対に、自分の人生が限りなく発展していくということであり、それはもっぱら無執着によることになるのであります。
次に、無我は執着すべき我のかたまりがないということが問題であります。
いったい我のかたまりとは何かと考えてみると、これはもともとないのですから、結局そのかたまりは、私どもが執着しているところの我という観念、自我観念なのであります。
では、その自我観念がどうして起こってきたかを徹底的に明らかにしたのが、唯識という学問であります。この唯識は、私どもの意識の世界を深く掘りさげていったもので、私どもが外界に触れていく場合に一番先端にあるものは、いうまでもなく目・耳・鼻などの五つの感覚器官であり、この感覚器官のもう一つ奥にあって感覚を統一しているのが私どもの心であります。赤いものが目の感覚として赤く映っているが、それを赤いと知るのは感覚のもう一つ奥にあって感覚を統一している心によるのですが、その心のもう一つ奥に、実は自我観念の起こってくるもとがあります。それをマナ識といいます。マナとは考えるという意味ですが、このマナ識が、二六時中たえまなく自我観念の働きをしているものであります。心は誰でも経験で知っているように、熟睡の時とか、なにかの病気で気を失った時には働かない。ところが、このマナ識という自我観念の働きは、たとい熟睡の時でも、気を失った時でもなお働いています。これは唯識学派の人々が禅定に入って深く体験をしながら、人間の意識の状態を観察しているであります。現代の深層心理学でも、こういう自我の深い姿、日常の意識ではそれを知ることのできない潜在的な自我の深い姿を観察しています。
こういうマナ識、自我の働きがなくなってしまうのはどういう時か。それは」滅尽定であります。身も心も滅しつくしてしまうという禅定で、この滅尽定では働かない。しかし、その滅尽定から出ると、また自我の働きが起こってくるわけであります。
それから、悟りの究極に達した人(阿羅漢)では、もはやこのマナ識は働かないといわれております。
その自我観念をさらに探求していくと、実はマナ識のもう一つの奥のところにアラヤ識というものがあり、これが私どもの最後の意識であります。また意識というだけではなしに、外界の世界の起こってくる根本でもあるわけですが、このアラヤ識に基づいてマナ識が起こっていながら、しかもこのマナ識は、自分の起こってきているもとのアラヤ識を自分だとまちがえて認識している。これはたいへん微妙な心の奥の奥の働きになってくるのですが、とにかく非常に深いマナ識と、それよりもなお深いアラヤ識との相互の関係から、われわれの自我という観念が起こってきているのであります。だから、一口に執着を離れるといっても容易なことではなく、長い間の仏教の修行、訓練が必要になってきます。
先にいったように、自分は我が強くて困ると思っている人だけが我執があるのではなしに、そう思っていない人も、生きとし生けるものみな我執にとらわれているのであって、むしろ我が強いと困っている人のほうが実は宗教の問題に一歩近づいているともいえるのであります。
唯識の学問は、私どもの世界を私どもの迷いのほうからながめたものであり、アラヤ識といっても、マナ識といっても、そういうものの実物、実体というものはもともとないのであります。(71~74頁)
■ 無我の実現
そこでもう一歩すすんで、最後の涅槃に達した仏のほうからながめてみると、もう悟りとか迷いとかいう区別はなくなってしまい、全世界がそのまま仏の世界であるのです。仏といっては漠然としているかと思いますが、限りのない〈いのちの世界〉といってもいいかと思います。全世界がそのまま、そうである。『華厳経』とか『法華経』とか『無量寿経』に説かれてあるのがそういう世界なのであります。だから、私どもが迷ったり執着したりしているのは、実はそうした仏の世界の中で迷ったり執着したりしておることになるのであります。もっとつきつめていうならば、仏の性質、仏性というものが迷って私どもとなっているともいわれております。迷っているそのもとが、実は仏の世界であるということになるのであります。
こういう大乗仏教の世界の中で、私どもがどういう態度をとるべきであるか、無我をわきまえていくには、どういう態度をとるべきであるか、その最も代表的な問題について二、三申し上げてみたいと思います。
まず第一に、私どもは仏の世界にいるということに自分の心を安定させ、そこに心を安んずる。これが仏教でいうところの信であります。小さな我執の自分を離れて、大きな仏の生命を受け入れるのが信でありますから、この信がすなわち無我なのであります。
信にはいろいろな意味があります。それから、なんでもかんでも盲滅法に信ずるのとはちょうど反対に、実は自分の心の内から心の扉が開かれてくるという意味もあります。こういういろいろな意味が渾然として一つになっているのが仏教の信なのであります。西洋中世にテルトリアヌスという人がいて、その人の言葉として、不合理だからこそ神を信ずる、ということがいわれております。もちろん、キリスト教の信仰が全部そうであるといういうわけではないが、仏教の信はそういう信ではなくして、小さな我執がなくなって、ほんとうの道理が自分の内から開かれてくる、智慧の泉が湧いてくるのが仏教の信の特色であります。
次には禅定であります。禅定は、自分の身体も心も統一し、しずめていって、限りない大きな生命に合致していく。この禅定は仏教のすべてのものの基本になっているもので、禅定からほんとうの智慧が生まれてくるのであります。禅定三昧を実践することによって、私どもの乱れた心をしずめ、その心の本性、ついには仏のほんとうの精神を体現していくことができるのです。
それから慈悲の問題があります。私どもが我執にとらわれている限りは、慈悲は決して現れてこない。もともと、生きとし生けるものすべてが大きな生命の流れに包まれているのだし、その生命を一つにしているのですから、私どもの現実の世界ではお互いに相い別れて生きてはいても、同じ生命がそこに通じあっているというのが慈悲なのであります。ちょうど、水がすべての物にしみわたって、一つの水の流れとなっていくように、慈悲は一切のものを一つにしようとする働きです。だから、限りない大きな生命は、無我の大慈悲といわれるのです。こういう大きな生命に私どもが基づきながら、無我の大慈悲に参加しつつ、それぞれの慈悲を実現していきたいと思うのであります。
このようにみていくと、信も、智慧も、それから禅定も、慈悲も、実は一つの限りない生命のそれぞれ異なった方面なのであって、その実体は一つなのです。そして、いずれも方面も無我という点で共通の性格を持っています。その中で、信を強調したのがわが国の浄土教であり、また禅定を純粋化して、禅定一本に決定したのが禅宗であります。浄土教と禅宗では両極端のように思われたり、時に相い反するかのように考えられているむきもあるけれども、決してそうではなく、いずれも同じ一つの生命の中のそれぞれのほうめんであり、結局は無我の実現をめざしていることになるのであります。(74~76頁)
■ 仏教と倫理
仏教と倫理という問題につきまして、私はこれを三つの方面から考えることができるのではないかと思います、第一には、宗教<倫理<法律。宗教と倫理と法律というふうに三つ並べて考えてみますというと、これは一般に申されておることでありますが、法律的には何も罪を犯さない立派な人であっても、道徳的な鏡に照らしてみるとなかなかそうはいかない。常に完全であるとはいえない。したがって精神的には、道徳的世界のほうが法律的な世界よりもいっそう高い段階にあるということができるかと思います。さらに、道徳的には立派な人であっても、宗教的な眼をもってこれを観察してみると、道徳的には必ずしも悪い悪いことではないという場合でもなおこれは不完全である、あるいは罪悪であるというふうに見られる場合も起きてくるのであります。この点から考えてみますと、宗教の世界の方が道徳的な世界よりもさらに高い境地であるということができるとおもいます。これはやはり、仏教の場合にもそういう面があるのであります。仏教は宗教として、道徳的な世界よりも、もた法律の世界よりも、最も深い世界をめざしておるというふうに考えることができるのであります。
第二番目の見方といたしまして、仏教と倫理もしくは道徳という関係を考えていきます場合に、仏教の中に、実は道徳的な生活、倫理的な生活が仕組まれておるのであります。仏教の中で宗教もあれば、あるいは道徳や倫理も行なわれておるという場合がございます。この第二の見方をもう少し分けて考えていきますと、なおいろいろな場合が起こるかと思います。たとえば道徳的な生活は、仏教の目的を達成していくための準備的な段階、方便としての段階、その道徳生活を完成していくことによってついには仏教のめざすところの悟り、あるいは涅槃というものを完成していくことによってついには仏教のめざすところの悟り、あるいは涅槃というものを完成することができると、こういうふうに倫理と仏教の目的というものを段階的に考えていく場合もありましょうし、あるいはまた、仏教の中でどうとくせいかつと宗教生活とが並行して、相い伴って、ついには仏教の目標を成し遂げていくという場合も起こってくるのであり、いろいろな場合がありますので、これを後にもう少し組織だてて考えてみたいと思っています。
第三番目には、倫理という言葉を考えてみますと、われわれ人間仲間の生活を規定しているところの道理、根本の道ということになります。ところが、仏教も結局は、人間生活の根本の道理を実現していくことをめざしているのでありますから、その点からいえば、倫理のままが仏教である、こういう見方も成立するのであります。いまここに三つの方面から、この問題を少しく立ち入って考察してみたいと思います。(77~79頁)
■ 仏教の超越性
まず第一に、仏教は倫理や法律というような、ごくわれわれの一般的な人間生活よりも一段とすぐれたものである、という考え方から述べていきたいと思います。このことは、実は仏教の一番根幹になる立場でありまして、ある面からいえば最も重要な問題であろうかと思います。それは、仏教の目的としておりますところの涅槃、あるいは迷いから目覚めるという目的のためには、この究極の問題のためには、一切の人間生活を切り捨てて少しもいとわない、こういう最もきびしい面が仏教には厳然として存在しておりましても、もうその生命は消滅しておる、死んでおる、と申しても過言ではないのであります。その点からややもすれば、仏教には人生否定的な面がうかがえてくるのでありますが、実は最も重要な仏教の生命でありまして、ここから、はじめて人生を肯定し、人生を絶対に受け入れていく力が生まれてくるのであります。
釈尊の説法の中には、人生を切り捨てて顧みないという釈尊の言葉は、至るところにあらわれているのでありますが、その一つの例として、『スッタニパータ』というたいへん古い文献の中に、次のようにいわれております。「世の栄枯盛衰を超越したところの修行者は、この世とあの世とをともに捨てる。ちょうど蛇が古い皮をぬぎ捨てるようなものである」。あの世というのは来世のことでありますが、当時のインドの考え方として、この世でよいことをすれば、次の来世にはいいところへ生まれていく。したがってわれわれはこの世でよいことをしよう、というのでありますが、そういうこの世も捨て、あの世も捨てる、つまり人生のすべてを切り捨ててしまうというのであります。あるいは「一切のものは虚妄であると知ってむさぼりを離れた修行者は、この世と、かの世とをともに捨てる。あたかも蛇が古い皮をぬいで捨てるようなものである」。したがってそこには、究極の目的である涅槃のためには何もかも捨てていとはないというようなきびしい精神がみなぎっておるのであります。これは釈尊以来、インドにおきましても、また中国におきましても、ずっとこの伝統は守り通されてきておるのでありまして(岡野注;世界中で日本だけがこの伝統を現代にまで守り通している)、わが日本仏教の先覚者であられる聖徳太子のお言葉として、これはよく皆さんもご承知かと思いますが、おそらく太子がへいぜい仏教に帰依しながら、日常の間でつぶやかれたのではないかと思われるお言葉として、「世間虚仮、唯仏是真」というのがあります。世間のことはみな虚仮である、かりのものであり、むなしいものである、ただ仏だけが真実である。太子は、この人生の全体を捨てて、その一番確かな仏の世界に眼を向けていかれたのであります。
これは聖徳太子にはじまって、わが国の仏教の伝統的な精神になってきておるのでありますが、人生を捨てて顧みないということは、単なる人生否定ではなくして、人生全体を一まるめににして、なおそれよりも確かなもの、真実なものをはっきりとつかもうとした、これが仏教者の伝統的精神であります。釈尊の言葉の中に「いかなる所有もなく執着もないこと、これが人間のともしびであり、それが涅槃である。このことをよくわきまえて、現世においてわずらいを離れた人々は、悪魔に克服されることがない」ということを申しておられます。執着のないということは、一見、人生を放棄してしまったように思われるのでありますけれども、実はそうではなく、その心の底には悪魔にも克服されない、いかなるものによっても打ち負かされないだけの確固とした悟りの世界というものが開かれておるためであります。
釈尊と同じような意味の言葉が、日本の仏教者の中からも窺えるのでありまして、たとえば親鸞聖人の言葉の中に「信心の行者には天神地祇(てんじんちぎ)も敬伏し、魔界外道も障礙(しょうげ、しょうがい)することなし」というのは、非常に放胆な言い方のようでありますが、やはり行者の奥底には、何ものによっても打ち負かされることのない、いかなる境遇にも動じないところの仏教の目的が実現されておるためであります。その同じ親鸞聖人に、自分は善も悪も二つともわからない。何が本当の善なのか、また、本当の悪なのか、要するにわからない。「煩悩具足の凡夫、火宅無常の世界は、よろずのこと、みなもてそらごとたはごとまことにあることなきに、ただ念仏のみぞまことにておはします」という言葉も見えております。これも先ほど申しました太子の「世間虚仮(こけ)、唯仏是真」に通ずるものでありまして、その奥には何ものにもかえられらい確固とした世界が裏づけられておるためであります。こういうところから考えてみますと、仏教の根本には法律であろうと、道徳であろうと、いかなる世界にも立ちまさったところの、究極の涅槃ということが最後の目的になるわけであります。(79~81頁)
■ 仏教と倫理の共存
次に第二の問題は、仏教の中に宗教も倫理も並び行われておる、倫理がその中に含まれておるという見方であります。これは私の考察するところによりますと、だいたい四つの場合が考えられるのではないかと思います。
1倫理から宗教へ
まず一つは、「倫理→宗教」。道徳的、倫理的な生活の仕方が宗教の目的、仏教の目的を貫徹していくための準備の段階であるという立場であります。これにつきましては、いろいろな釈尊の教えや大衆の仏教が示しておるのでありますが、たとえば原始仏教の中で八正道、八つの正しい道ということがいわれております。これは、もうあるいは皆さんご存じかと思いますが、正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定、この八つの道を踏み行なっていくことによりまして、最後に涅槃に達する。われわれの身体からも精神からも火のように吹き出ておる煩悩が、プッと吹き消されて、安らかな境地に達するのであります。ニルヴァーナ(涅槃)とは、そういうように、煩悩の火の吹き消された安穏の世界をいうのであります。そういう涅槃に達するために、八つの道が説かれているのであります。
正見とは、正しい見解、正思惟は正しい考え方、正語は正しい言葉を語ること、正業は正しい活動、正命は正しい生活、正精進は正しい努力、正念は正しい思い、正定は正しい禅定であります。これらがみなわれわれの生き方を規定しているのでありまして、そこに八つの道が述べられているのでありますが、問題は、いったい正しさということがどういう意味か、ただ自分勝手に正しい言葉をはき、正しい生活をやっておると思うだけでは、ほんとうの正しさというものはわからないのでありまして、どこにその正しさの根拠があるかという点であります。
釈尊、すなわちブッダは、迷いから目覚めた人であります。目覚めた人の教えはもとより正しいといえるでありましょう。したがってまず第一に、目覚めた人の教えをよく聞くことであります。しかし、ただ聞くだけではだめなんでありまして、それを自分の心でよく味わってよく思う。ただしかし、思うだけではまだ不徹底でありまして、聞いて味わって、心によく思ったことを自分の身体の上に実現していくのであります。それを修(しゅ)と申します。聞いて、思って、修する、この聞思修(もんししゅ)ということが仏道の正しさ、確かさを身につけていく基本的な方法になっているのであります。
それから、この聞思修(もんししゅ)という訓練の仕方とあわせて、仏教ではこの八正道が示しておりますように最初に正見、正しい見解、これは智慧をあらわす。最後に正しい禅定、これは禅定三昧をあらわす。最初と最後が智慧と禅定になっているのでありますが、智慧と禅定が、離れることのできない密接な関係にあることは、原始仏教以来、仏道の大切な伝統になっているのであります。智慧はともしび、禅定は油にたとえられますように、必ず禅定(岡野注;画家はイーゼル画)に伴われて、光を放つのであります。この点が、西洋哲学における理性と、性格を異にしているのであろうとおもわれます。この智慧と禅定を互いに深めていくことによって、そこにおのずから出てくるところの人生の智慧、人生の分別というものが規範になって、それに基づいて、これは正しい、これは間違っておるということが、おのずから明らかになってくるのであります。この八正道を踏み行うことによりまして、やがては、その目的である涅槃に達することができる。すなわち、この道徳的な生活が準備となって、目的を貫徹していくという仕方になっておるのであります。(82~84頁)
■ 2 倫理と宗教との相補性
次は、倫理と宗教とが互いに補足しあう、相い補いあっていく行き方であります。これにもいろいろな例をあげることができると思いますが、たとえばその一例といたしまして、原始仏教の経典の長阿含の中に、『ソーナダンダ・スッタ』というのがあります。これはソーナダンダという波羅門に向かって、釈尊がいろいろのことを説法されておる経典であります。その中で、戒と慧の関係を釈尊が説いておられます。戒というのは戒律、慧というのは智慧であります。この智慧というのは、さきほど申しましたように、禅定がその基盤になっておるのであります。したがって仏教全体を大別する場合に、戒定慧の三学と申します。これは伝統的な分け方になっておるのでありますが、戒律の方面からと、禅定、智慧のこの三つの方面から分けまして、これを戒定慧の三学と申すのであります。
戒というのは、仏教生活、ことに原始仏教の場合には、僧侶の共同生活を規定した規則が戒律であります。したがって、狭い意味においてはこれが道徳的生活、倫理的生活といえるわけであります。この戒定慧の三学が互いに並び行なわれて、最後の目的を達成していくということになるのであります。戒は智慧によって清められ、また智慧は戒によって清められる、道徳は人生の智慧によって清められ、また人生の智慧は道徳によって清められる、こういうことを釈尊は説いておられます。つまり、宗教的な智慧と道徳的な実践とは、互いに働きあい、補いあって目的に向かって進んでいくのであります。
話が少しく横道にそれますが、これについて昔からたいへん有名な言葉が『涅槃経』の中に見えております。忍耐というのは、じっと耐え忍ぶという一つの道徳的な規範でありますが、この忍耐によって最後に人生の智慧、いいかえますと仏教の涅槃が得られるという意味の言葉を伝えております。『雪山(せつせん)に草あり、名づけて忍辱(にんにく)となす。牛もし之(これ)を食めば、即ち醍醐を生ず」。雪山というのはヒマラヤ山のことであります。ヒマは雪、アーラヤはそれをたくわえておること、つまり雪の蔵というのがヒマラヤの意味であります。昔の人は雪山と申しております。雪山に草がはえておる。どういう草かというと忍辱という草である。これは臭いニンニクのことではない。これは忍耐であります。これに近いように思われる言葉で、実は全く意味の違った言葉に我慢というのがあります。我慢するというのは、非常に近いようで、実は反対の概念であります。我慢というのは、自我意識が強くて、何くそと思いながらも、じっとそれをおさえるのでありますが、この忍辱というのは、そうじゃなくて、忍ぶ、じっとそれに耐える、これが忍辱の行であります。忍辱というのは、六波羅蜜の一つであります。
雪山に忍辱という草が草がはえておる。その草を牛がムシャムシャ食べるとついには醍醐を生じた。醍醐というのは皆さんご承知と思いますが、牛からまず乳を出す、乳から酪ができる、酪から生酥(しょうそ)ができる、生酥から熟酥ができる、最後に醍醐を生ずる。これは譬え話でありまして、実は仏教全体を低い教えから高い教えへと五つに分けて、この譬えをあてはめているのでありまして、その最も高い教えが、すなわち醍醐であり、究極の涅槃であります。
日本人の名前にも醍醐という人があり、また五つありますから五つの味、五味、これも日本人の名前になっておるほどに、醍醐や五味は私どもに親しまれております。このように、醍醐というのは究極の悟りの境地、究極の教えをいうのであります。私どもの日常の諺に、「石の上にも三年」といことがいわれます。この世の中で、苦しい目にあい痛い目にあって、それを避けないで、じっとそれに耐え忍んでおるうちに、いつの間にか、自分の腹の底から開けてくるものがある。それを大事に育てていくと、それがほんとうの智慧に変わってくる。ここで牛というのは、われわれのことでありますが、ちょうど牛が忍辱という草をムシャムシャ食っていくうちに、それがだんだん牛の血となり、肉となって、ついに、ほんとうのおいしい醍醐の味が出てくるように、石の上にも三年、五年、十年と、じっとわが人生に耐えていくうちに、何か知らぬが自分の心の底から明るいものが開けてくる。何か言葉では言えないけれども、内から放たれていく気持ちというか、開かれていくものがにじみ出てくる。それを一所懸命、大切に育てていくわけであります。それがやがては人生の大道に達する、ほんとうに公明な開かれた世界、自由な世界に生まれていくことができる、こういう意味のことを表しているのであります。
では、もとへ帰りまして、『ソーナダンダ・スッタ』の中で釈尊が説かれておりますところの戒とは何か。これは初歩的と申しますか、最も原本的な道徳の規範であります。たとい仏教者であろうと、キリスト者であろうと、儒教のひとであろうと、老荘の人であろうと、あるいはまた宗教に全く関係のない人であろうとも、誰でもがこれを守らなくてはならぬ、人間にとって最も基本的な道徳、これを釈尊は説いておられます。
たとえば次のように禅定の四つの段階が説かれているのであります。すなわち、われわれの心は平常たいへん乱れておる。水にたとえますと、ちょうど水面に波が立っておるように絶えず動いておる。自分では静かだと思っておっても、よく観察してみると、われわれの心の面がいつも波立っておるのでありますが、まずいろいろな欲望を離れ、またいろいろな不善を離れる、そうするとわれわれの心は分別はまだ残っておるけれども、なんともいえない喜び、なんともいえない楽しみが起こってくる。これがまず第一の禅定であります。それから次に、その禅定をだんだん深めていきますと、今度は分別もなくなってくる。そうして心は静かにやすらかなものとなって、その境地から生まれてくる喜びあるいは楽しみ、それをわれわれは味わうことができます。これが第二の禅定であります。それからその禅定を深めてまいりますと、次に喜びもなくなってくる。そうして楽しみだけが残ってくる。そうしてわれわれの思いは正しいものとなる。これを正念、さきほど八正道に出てまいりました正念、これが第三禅定であります。さらにこの禅定をいよいよ最後までおし進めていきますと、もはや苦しみもなく楽しみもなく、ただ心は清浄となり、この清浄となった心の中に真実の智慧が生まれてくるのであります。心の騒ぎや心の波立ちが全く静まり果てた心の中に、ほんとうの智慧のともしびがともってくる、これが第四禅定であります。
このように、戒定慧の三学が並び行なわれていくのであります。つまり、道徳生活を訓練していくことによって宗教生活が浄(きよ)められ、また反対に、われわれの心を深めていくことによって道徳的生活が完成していく、このように宗教と道徳が、互いに働きあい、補いあっていく行き方であります。(84~87頁)
■ それから第三には、いままでは宗教、道徳というものを段階的にかんがえたり、あるいは並び行なわれておるように見たりしてきたのでありますが、ここには、われわれの人間生活の中に一本はっきりした筋が通っておる。その筋というのは智慧であります。これにつきまして、釈尊がこういうことを申しておられます。「この世の中で人間の最高の富は何であるか」。この問題に対して釈尊は、「この世の中では信仰が最高の富である」といわれております。信仰については、また後に触れるかと思います。
それから次の問題は、「どのように生きることが最高の生活であるか」ということでありますが、これに対して釈尊は「智慧によって生きるのが最高の生活である」と答えておられるのであります。
ところで、智慧によって生きるということが、もう少し大衆仏教の中で味わってみたいと思います。『般若経』という経典があります。これは「智慧という経典」の意味であります。これにはいろいろの系統の経典が存在しており、大きいのでは、『大品般若経』六〇〇巻、小さいのでは私どもが常に親しんでおる、わずか二百何十字というごく短な『般若波羅蜜多心経』に至るまで、さまざまの『般若経』があります。般若というのはご承知かと思いますが、サンスクリットでは prajna 、パーリ語では panna と申します。これが智慧の意味でありまして、般若という漢文の音訳になったのであります。その『大品般若経』の一節に、智慧を中心にしていろいろな倫理生活が描かれておるのであります。そのいろいろな倫理生活の中枢を貫いて、一本筋金が通っておるのが、この智慧、般若なのであります。
たとえば次のようなことが説かれております。まず、自利と利他に分けて、その自利についてであります。自利というのは、自分の利益だけを考えるという意味でがないのでありまして、自分がまず個人的に道徳を守り、宗教の目的を貫徹するように努力する、これを仏教では自利と申しておるのであります。その自利的なものといたしまして、たとえば、瞋(いか)りの心を離れる、怠惰な心を離れる、それから散乱心を静める。そこから煩悩とか業障を離れて、われわれの心が障りのないものになる。業障というのは、働いても働いてもわが暮らしが豊かにならない。努力しても努力しても、人づきあいがうまくいかないこれをわれわれは宿業として感じてきたのでありますが、そういう業の障りや煩悩を離れて、心が自由になる。あるいはまた過去、現在、未来の無数の真理をきわめていく。あるいはまた六波羅蜜、すなわち布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧などを行じていく。この六波羅蜜は、仏教における大切な徳目になっております。まだそのほかにいろいろな徳目が説かれております。
以上は自利行でありますが、これに対して利他行、すなわち他人のためにつくすことが説かれています。たとえば、盲の人を見えるようにしてあげる、つんぼの人を聞こえるようにしてあげる、口のきけない人をきけるようにしてあげる。それから、狂者、精神に異常のある人を平静にしてあげる、心の乱れておる人を静めてあげる。貧しい人には施しものをする、裸の人には着物を与える、飢えておる人には食事を与える、のどの渇いておる人には水を与える。病んでおる人には病気を治療してあげる、迷悶者には心の迷いを解いてあげる。そうしてわれわれは、一切の悪をやめて一切の善を行じていく。このようにして、あたかも互いに父母、兄弟、姉妹のように助けあっていく。これが利他的な方面の徳目であります。ここでは、倫理的な問題に関するものだけをあげてみたのでありますが、そのほかにいろいろな世界観や人生観が説かれております。
つまり、ここには人間のいろいろな道徳的な生き方、あるいは人生観や世界観が述べられているが、結局、その根本は般若であり、真実の智慧であることを強調するのであります。その智慧から、さまざまな倫理的、個人的あるいは社会的な道徳生活や人生観が建設されていく、ということを説いているのであります。これは、いったいどういうことであるかと申しますと、どんな世界観、人生観を持つにしても、またどんな道徳的な生き方を実行するにしても、その人生観や生き方に全く執着しない、それに少しもとらわれない。これが『般若経』が求めてやまなかった、また説いてやまなかった人生の智慧なのであります。そしてこれが、さきほど述べました釈尊の精神にただちに通じていくのであります。
インドの大乗仏教の先覚者として有名な人に、竜樹菩薩、ナーガールジュナがおります。この人は西暦一五〇年から二五〇年ごろの間にインドに出た大乗仏教の先覚者で、その後、インド、中国、日本に発達した大乗仏教の源泉になる人でありますから、その思想は、非常に広い範囲にわたっておりますけれども、その基づくところは、般若の空にきわまるということができましょう。その竜樹の弟子にダイバという人がある。このダイバがどれだけ空の教えを体得しておるかということをテストするために、鉢にいっぱい水を張って、竜樹は木陰に隠れて見ておったのであります。そこへダイバがつかつかとやってきました。ものかげから竜樹は、いったいどういう動作をするだろうかと、それを見つめておったのでありますが、ダイバがその水を張ってあります鉢のところへやってきて、いきなり一本の針を取り出して、スッとこの水のなかに投げ入れ、そのまま立ち去っていったのであります。それを見ておった竜樹が非常に感嘆しまして、「ダイバはこれほどまでに空を体得しているか」といって喜んだというのであります。
つまりその針というのは、実はこの自分のことでありまして、いま自分は、いっぱい張ってある人生という水の中を懸命に泳いでおるのでありますが、どんな境遇に出会っても、ちょうど針が水の中をスッと通っていくように、ちっともベタつかない、とりもちのようにくっつかない。スッとどこまでも限りなく智慧が展開していく。それは、その根本の動力が執着を離れている智慧の力に存するからであります。その智慧の力というものが一本スッと通っておりまして、それを中心にわれわれの人間生活、あるいは、さまざまの世界観、唯物論にせよ、唯心論にせよ、観念論にせよ、論となったらそこに執着しておることになるかもしれませんが、ともかく、われわれの生活や世界観が無限に展開していく、そういうふうな積極的な力の展開ということを、この『般若経』は教えておるのであります。(91~91頁)
■ 4 倫理と宗教との一体性
それから次に、第四の見方といたしまして、宗教と倫理とというものが一つの全体性、あるいは一つの社会性となって働いてくるという場合であります。これにつきまして、多少話がむずかしくなってくるかと思いますが、大乗の戒律に三聚浄戒(さんじゅじょうかい)ということがいわれております。一つには摂律儀戒(しょうりつぎかい)、二つには摂衆生戒(しょうしゅじょうかい)、三つには摂善法戒(しょうぜんほうかい)。摂律儀戒は一切の戒律を守っていくこと、これは従来の戒律であります。摂衆生戒は衆生のために尽くすという戒律、摂善法戒は、一切の善を実現していくという戒律で、最後には仏教の根本の目的であるところの真理を実現していくのであります。(92頁)
この三つの方向から人間生活を規定しておるのでありまして、この三つで人間生活の全体性、あるいは社会性という問題を考えていくことができると思うのであります。この三聚浄戒(さんじゅじょうかい)につきましては、いろいろな経典や論の中に見えておるのでありますが、ここでは聖徳太子に親しみのある『勝鬘経(しょうまんぎょう)』から拝見してみたいと思うのであります。その中で、勝鬘夫人が仏に対して自分のわきまえておりますところの三聚浄戒を申し上げておる箇所があるのであります。それをちょっとここで御披露しましょう。
勝鬘夫人が、まず摂律儀戒(しょうりつぎかい)につきまして、たいへん幽遠な人生観を述べているのであります。すなわち、今日ただいまから悟りを開くまで、戒律をおかそうという心を起こさない、あるいは他の人々の環境や持ち物に対して慢心を起こさない、あるいは衆生に対して腹を立てない、あるいは他の人々の環境や持ち物に対して嫉妬心を起こさない、こういうことを夫人が語っております。これは主として自分の個人生活に関係のある事柄であります。したがって、これは自利、太子のお言葉では自行であります。
次の摂衆生戒(しょうしゅじょうかい)、これは大志のお言葉では化他、他の人々を教え導く、すなわち利他であります。これにつきまして勝鬘(しょうまん)夫人は次のように申します。私は今日から悟りを開くまで、自分のために財物をたくわえることをしない。貧しく苦しんでおる衆生を救うために財物を用いる。また、今日から悟りを開くまで、自分のために四摂法(ししょうぼう)、これは布施、施しものをする。愛語、穏和な言葉を語る。利行、他人のために利益になることを行なう。同事、他人のやっているおることに同化して、それと一つになる。これが四摂法でありますが、この四摂法を自分のために行ずることをしない。必ず一切衆生のために、むさぼり、はらだち、愚痴の心を離れて、衆生を受け入れる。あるいは、一切の衆生が孤独でさびしがっておったり、病気で苦しんでおったり、その他さまざまな困難や苦痛を受けておる場合には、しばらくも捨てないで必ずこの人々を安らかにしてあげる、これが摂衆生戒(しょうしゅじょうかい)であります。
最後に摂善法戒(しょうぜんぼうかい)と申しますのは、これは太子のお言葉にもありますように、正法を摂受(しょうじゅ)する、正しい道を受け取っていくことであります。すなわち、今日から悟りを開くまで、正しい道を受け取って、ついに忘失しない。正法を忘れないで大切に育てていくうちに、ついに永久に凡夫地を超えることができる。凡夫地というのは、われわれの現在の状況のように心の迷っておる境地であります。その心の惑うておる境地を、永遠にスパッと超えていくことができる。ただ忘失するようではだめ、またときどき思い出すようでもだめでありまして、毎日毎日この正法を受け取ってこれを大事に育てていく。そうすれば必ず凡夫地を超えることができる。このような三聚浄戒によって仏教全体の行き方というものをまとめておるのでありまして、ここに、自分も他人も、あるいは個人も社会も、その全体がこの倫理、宗教によって規定されていくのであります。
以上、この項目で四つの場合を考えてみたのであります(92~94頁)
■ 四 倫理すなわち仏教
最後に、人倫のおのずからなる道理を実現していくことが、そのまま宗教であり、そのまま仏教であるという見方であります。いいかえれば、倫理がすなわち仏教であるという立場であります。これは、実はいままでお話ししてきました釈尊の仏教や、あるいは大乗仏教が、根本からいえばそうなっておるのでありまして、人間として踏み行なうべき道がそのまま仏教である、あるいは、私どもの社会生活の中に、本来のものとしてあらわになってくる道理が、実は仏教であるといえるのであります。
たとえば、中国の大乗仏教として独自の立場を開きましたものに天台宗、華厳宗がありますが、その天台宗では、私どもの生活の真実の姿を追求していくことが、その根本の目的になっております。そして、その真実の姿を十分に明らかにしてみれば、目に触れるもの、耳に聞こえるもの、これすべて中道でないものはない。中道というものは、根本中心の大道であり、仏の道であります。また、資生産業ことごとく仏道でないものはない、といわれております。つまり、私どもが、毎日毎日、電車にゆられて会社にゆく、会社で仕事をする、家に帰ってみんなと楽しむ、それが一つ一つみな中道であるということに徹していくのであります。
また、もう一つの華厳宗では、事事無碍法界(じじむげほっかい)ということを申します。事というのは、これも私どもの生活経験の一つ一つ、あるいは、いろいろな事柄の一つ一つのことで、その一つ一つが互いに無限に関係しあって、世界全体が流動していく、これが事事無碍法界であります。この道理を生活経験の一つ一つに照らしてよくのみこみ、心の底から納得していくのであります。そして、わが生活の全生命を限りなく展開していくのであります。これが華厳における仏道であります。したがって、いま申しました天台や華厳という立場から見ますと、人間相互の生活の道理、すなわち倫理が、そのまま仏教であるということができるのであります。
では、この人倫の道を実現していくことが、このまま仏教であるという場合に、どこにわれわれの心のすわりを置いたらいいのであるか、これもいままで述べてまいりました。
たとえば『般若経』におけるところの般若波羅蜜、人生の智慧、あるいはまた、いまお話いたしました『勝鬘経(しょうまんきょう)』におけるところの摂受正法(しょうじゅしょうぼう)、正しい真理を受け取っていく、その般若とか摂受正法ということで十分なのであります。それで十分なのでありますが、ただ私は、ここにあらためてわれわれの心のすわりとして「信」と「行」ということを立ててみたいのであります。
さきほど申しましたように、釈尊が『スッタニバータ』の中で、人生の最上の富は信仰である、信であるということを申しておられるのでありますが、信ということは原始仏教以来大乗仏教に至るまで、たいへん重要な仏教の根本になっておる問題であります。しかしまたそれだけに、信よいうことはいろいろな意味を含んでおるのであります。けれども、よく用いられておる信の意味を一応区別してみますと、だいたい次のような三つの意味にまとめられると思います。
その一つは、パーリではサッダー、サンスクリットではシュラッダー。これが、普通われわれが言っております信頼、英語でいいますと faith とか belief とかいう言葉になるかと思います。私どもの人間関係で申しましても、信頼ということがヒューマン・リレーションの根本になっておることに気づくのであります。私どもの経験から申しますと、この信頼の基本には誠実ということがあるのではないかと思います。人間の誠実がお互いに通じあって、そこに信頼という関係が生まれてくるのであろうと思います。人間の誠実がお互いに通じあって、そこに信頼という関係が生まれてくるのであろうと思います。それに比類して考えてみましても、仏は真実であり、仏法は真実であるから、その真実の上に立って、われわれはおのずからそれに信頼するということになるのではないかと思います。これはやはり、一般の宗教で申しますところのいわゆる信仰、信ずるという意味に近いのであろうと思います。ところが仏教の信の意味は、決してこれだけに限るのではないのであります。
第二は、パーリでがパサーダ、サンスクリットではプラサーダ。これは古来、伝統になっている信のいみであります。すなわち「信トハ澄浄ノ義ナリ」といわれております。信とは、底の底までスッと澄みとおり、澄みきっている。この境地が、伝統的に伝えてきた信の性格であります。その性格は原始仏教の中にも生まれておるのであります。どこまでも澄みきって、裏表なしに澄みとおっておる、それは、無我の心であるからそうなっているのであります。純粋無垢というか、清浄第一というか、これが信の第二の意味であります。
そこで信の第三の意味は、これがたいへん重要な仏教の信の特徴をあらわしておるものでありまして、パーリではアディムッティ、サンスクリットでは、アディムクティであります。これは、内から開かれてくる心の智慧でありまして、それがそのまま信なのであります。したがって、信が必ず智慧につながっております。これも原始仏教以来、信をあげる場合には必ず智慧がそれにくっついて出てくるのでありまして、信と智とは離れえないものになっています。なにがなんでも信ずる、とにかく自分ではわからぬが盲目的に信ずるというのとは、根本的に性質を異にするのであります。そうではなくて、そうならずにはおれずに、自分の心の内側からその世界がひらけてきて、おのずからそうなってしまった、こういう性格が信に存しているのであります。これは仏教の心の底からの合理性ともいえるもので、今後、仏教思想が世界的に発展していく場合のエネルギーは、この辺から生まれてくるのではないかと思います。普通いうところの合理主義も、ここまで徹することによって、はじめて生きてくると思われます。自分の心の世界におけるおのずからうなずいてくるところのラチオ、道理、いわば合理性のこんかんというものが、仏教の基本に流れておるのであります。そこから信が生まれてくる。
これは少し極端な比較かもしれませんが、中世初期のキリスト教の護教家に、テリトリアヌスという人がおりましたが、その人の見解として「不合理であるからこそ私は信ずる」ということがいわれております。合理的なものは信ずる必要はない。合理は合理のままだから信ずることはいらない。神は、われわれの道理にはのらない。不合理そのものであるからこそ、私は神を信ずる、というのであります。これは、もとよりキリスト教全体の信を代表しているとはいえませんけれども、少なくとも仏教の信は、そういう性質のものとは根本的に異なっているのであります。仏教の信は、そうではなくて、おのずから自分がうなずいてくる、いいかえれば、内から開かれてくる智慧、という意味を持っているのであります。(94~98頁)
■ ちなみに、ここに信につきまして、『華厳経』の賢首品(げんじゅぼん)という一章がありますが、この一章は、ほとんどを全編にわたって信について語っておるのであります。要点は、信ということにわれわれの人生態度が始まって、その信を育て、信を養い、信によって貫いていくことによって、とうとうその究極の大目的までそのまま行きつくことができるということを、この賢首品の一章は強調しておるのであります。
ここに現代語訳でご紹介いたしますのは、そのほんの一節であります。
「菩薩が菩提心を起こすには、次のようなもろもろの理由がある。仏法僧の三宝に対して深い清浄の信心を有するがゆえに、菩提心を起こす。仏の正法を打ち立て、無上の悟りを得ようと思い、すべての智慧を修するために、菩提心を起こす。深い清浄の信心は、堅固にしてこわれることがない。すべての仏を敬い、正法および聖僧を尊ぶがゆえに、菩提心を起こす。信心は仏道の根本で、功徳の母である。すべての善を増進し、すべての疑いを除いて、無上の仏の道を開き示す。信心は、垢も濁りもなく、たかぶりの心を除き、敬いとつつしみの根本である。信心は第一の宝の蔵であり、清浄な手となって――この手がなければ、せっかく宝の山に入っても、また手ぶらで帰ってこなくちゃならない。竜樹も、信ということを手にたとえております。両手があればこそ、真理の山へ入って十分にその真理を自分のものにつかんでくることができるというわけでありますが――もろもろの行を受ける。信心の人は、すべての執着を離れ、深くて妙なる仏の法を悟り、ありとあらゆる善を行ない、ついには仏の国に至るであろう。もし、信心堅固にして動ずることなければ、身心ともに明るく、ことごとく清浄となるであろう。ことごとく清浄となれば、すべての悪友を離れて善友と親しむであろう。善友に親しめば、はかり知れない多くの功徳をおさめるであろう。功徳をおさめれば、もろもろの因果を学び、その道理を悟るであろう。その道理を悟れば、一切の諸仏に守られ、無上の菩提心を生ずるであろう。無上の菩提心を生ずれば、諸仏の家に生まれ、一切の執着を離れるであろう。一切の執着を離れれば、深い清浄の心が得られ、すべての菩薩行を実践し、大乗の法をそなえるに至るであろう。大乗の法をそなえれば、すべての諸仏に供養し、念仏三昧が絶えないであろう――」
まだずっと続いて、この経典は、信心の力を説いてやまないのであります。ともかく、これだけここに経典を引用いたしますと、皆さま方には、何か信心というものの力がお感じになれたかと思うのであります。
これに対し、行というのは、これはもう引用するにいとまのないほどに、いろいろな方面から仏教は説いておるのでありますが、押しつめていえば結局、生活、生きるということがそのまま仏教の行でありたいと思うのであります。この信と行とは、ちょうど、ものの表と裏の関係でありまして、信を育てていくことによって、われわれの心がますます仏の道に親しいものとなり、それによって、行、つまり生活が導かれて自分の身体にそなわったものとなり、身についたものとなってくると思うのであります。信と行は、ちょうど裏と表で、どっちを離すわけにもいかないのであります。
ところで、日本の仏教には、私どもの生活を統一しているところの根本の大行が伝えられておるのであります。たとえば、念仏あるいは坐禅であります。これは、非常に簡素な、最も単純な形で、われわれの全生活をまとめていくところの行の中の行、大行というものであります。これは、簡素で単純ではありますけれども、われわれの全生活をまとめていく無限の力が宿っているのであります。簡素で単純というもは、東洋人の生活の特徴でもあり、また芸術にも窺えるのではありますまいか。お茶の一服をたてる、謡曲の仕舞、そういうものは非常に簡素ではありますが、むしろ簡素でありますだけに、無限の力、はてしない世界を包んでいるように思われるのであります。このような、簡素にして単純な念仏や坐禅を、毎日毎日繰り返す、この繰り返しが大切なのであります。簡素であるからこそ、繰り返しができるのです。この繰り返しが行の〈かなめ〉なのであります。毎日毎日繰り返すことによって、その行が、自分の身についたものとなってくるのであります。
最後に、現代仏教的倫理の構えというものを、ちょっと申し上げてみたいと思います。つまり、仏教者としてどういう人倫の道理を実現していくべきであるかという問題であります。私はこの原理を同じく『華厳経』の浄行品の中から選びだしてみたいのであります。ところが実は、これは皆様がよくご存知の経典の言葉であります。「みずから仏に帰依したてまつる、まさに願わくは衆生ととまに大道を体解して無上意をおこさん。みずから法に帰依したてまつる、まさに願わくは衆生とともに深く経蔵に入りて智慧、海のごとくならん。みずから僧に帰依したてまつる、まさに願わくは衆生とともに大衆を統理して一切無碍ならん」。これが、現代における仏教的人倫の道理を実現していくための根本の原理になろうかと思うのであります。
つまり衆生とともに、これは聖徳太子の大精神でありますが、衆生とともにまず仏に帰依して、人生の大道を明らかにし、無上の悟りを実現していく、第二には、衆生とともに深く経蔵に入って智慧、海のごとくなる。仏は決して量見の狭いものではございません。自分の経典だけをわがものとする考え方ではありません。それについて申し上げる時間がありませんけれども、仏教の経典はいうに及ばず、キリスト教であろうが、論語であろうが、老荘であろうが、あるいは今日は科学をおいてわれわれの生活は成り立たないので、その科学であろうが、あるいは広く西洋の思想であろうが、そういう経蔵に深く入って、海のような智慧をたくわえていこう。この海のような智慧というのが大切であります。第三には、みずから僧に帰依したてまつる、この僧はサンガ(団体)でありまして、今日の観念でいえば、生きとし生けるものの団体ということになりましょう。原始教団ではお坊さんの集まりをサンガと申しましたが、サンガというのは結び、集まりなのですから、生きとし生けるもの、しばらくネコとか犬もわれわれの仲間でありますが、せいぜい人間だけはこの大サンガに参加して、そうして互いに一切無碍となっていこう。唯仏論者であろうが、精神主義者であろうが、それぞれ人間の生き方であり、考え方であり、そういうものが互いに障りなく融通しあって、この大道を実現していこうではないかというのが、この三帰依文の現代的な根本精神であろうと思います。そしてこれが、将来の仏教的倫理の社会を打ち立てていく根本原理になろうかと思うのであります。(98~102頁)
■ 第五章 インドの宗教と思想
2 インドの伝統
インドの思想の根本問題と申しますと、一口にいえばアートマンの自覚ということに帰するかと思うのであります。アートマンということは、自我の本性、ほんとうの自己という意味でありますが、インドでは、紀元前数世紀からすでにほんとうの自我に目覚めていくという思想が起こっておるのであります。かりにヨーロッパ、あるいはまた同じいんどにおきましても。われわれに関係の深い仏教、ことに大衆仏教の場合と比較して考えてみますと、ヨーロッパにおいてはご承知のように一五、六世紀から、中世の神中心の思想にプロテストしてルネッサンスが起こってきたのでありますが、その中心思想には、自我の発見ということがあります。
それから仏教の場合を考えてみますと、仏教では自我というよりはむしろ無我ということがたてまえになっておるのでありますが、紀元後三、四世紀ごろになりますと、インドにおいて自我の意識、自己意識の問題について、大乗仏教が非常に深い考察をやっております。それは、すなわち唯識思想であります。これは、現代の深層心理学がめざしておる同じ問題領域を、インドでは三、四世紀ごろから世親とか無著(むじゃく)とかいうようなすぐれた思想家たちが追求したものであります。
ところで、ルネッサンス以来起こってまいりましたこういう自我とか、あるいは仏教の唯識において明らかになっておりますところの自己意識を。アートマンと比較してみますと、そこには大きな違いがあることを知るのであります。この問題は、たいへんむずかしい問題になってきますが、自己の本性、自我の本性というこのアートマンは、たとえばデカルトにおける自己意識とか、あるいは仏教の唯識で唱えられましたマナ識、つまり自我意識というものとは根本的に違うのでありまして、少なくとも自己あるいは自我という意識がある限りにおいて、それはアートマンとは全く違うものである。つまりアートマンというものは、いかなる意味においても、自我とか自己とかいうような意識ではないのであります。
紀元前数世紀に、すでにインドにおいて瞑想的な文献としてあらわれておりますところの『ウパニシャッド』の中で、アートマンはそれ自身全く純粋無垢である。またアートマンそれ自身、決して死ぬことまなく、また生まれたこともない、不生不滅である。これがアートマンの本性であるということを、種々の形で『ウパニシャッド』は主張しておるのであります。決して自己意識ではなくて、目覚めており、純粋無垢であり、不生不滅であり、そのままがすなわち自分である。ここに目覚めるということが、古代以来現代に至るまで、インド人が追求してきたところの窮極の目標でありまして、そういうアートマンに目覚め、自分に気がついてみれば、そのままが絶対者ブラフマンであります。いいかえれば宇宙全体である。ラーマクリシュナも、ヴィヴェーカーナンダも、オーロビンドも、血みどろになってそれを真実の上において、ガンジーは自分の活動している社会において、実現しようと努力してきたのであります。
たくさんの『ウパニシャッド』の文献の中でも。ウッダーラカとヤージニャヴァルキヤはすぐれた誓人といわれておりますが、その一人のウッダーラカが自分の子供のシュヴェータケートに向かって、アートマンを一つの譬えによって説明しております。ニヤグローダというのは亭々としてそびえ立つ非常に大きな樹木の名前でありますが、そのニヤグローダの小さな実をシュヴェータケートに持ってこさせまして、「おまえその実を割ってみろ」と申します。シュヴェータケートは、お父さんの前でニヤグローダの実を割ってみますと、中から小さな実が出てきたのであります。お父さんはさらに、「もう一つそれを割ってみよ」といいますので、子供がまた小さな実を割ってみますと、さらに中から目に見えるか見えないほどの芽が出てきたのであります。そこでお父さんの(ウッダーラカは、それがアートマンである、汝がそれである、といってアートマンを説明しておるのであります。つまり、亭々として天を摩するような大木になるニヤグローダも、そのもとはといえば、目に見えるか見えないほどの小さな芽でありまして、それがやがて大きな樹木になるのでありますが、その小さな芽こそ実はアートマンである。しかもそれが汝それ自身である。先生と弟子とひざづめで真理の説明を伝えておる光景を、このように描写しておるのであります。
このような、自己の本性であるアートマンをほんとうに自分が自覚し、ほんとうに自分がそれによって生活していくということが実現いたしますと、そのままがすなわちブラフマンであり、絶対者であり、世界全体である。ありとあらゆるものがアートマンでないものはない。見たり聞いたり、また経験したりすることすべてがアートマンであり、またブラフマンである。そういう自覚に達することを述べておるのであります。
また別の『ウパニシャッド』では、アートマンを五つの段階に分けて、第一の段階から第二の段階、第二の段階から第三、第四、第五の段階というふうに次第にアートマンの意味が深まっていく、そのプロセスを述べておるのであります。
まず最初の段階のアートマンは、食事から成り立っているアートマンであります。われわれは、生きている限りにおいて食事をとらなくてはならない。われわれは霞を食ったり露を吸ったりする仙人ではなくて、具体的に生きておる人間である以上、われわれの身体も、あるいはその精神も食事によって養われておる。つまり食事から成り立っておるところのアートマンが、最初の段階のアートマンなのであります。
それから少し意味が深まってまいりまして、次は、呼吸から成り立っているアートマンであります。呼吸ということは、インドにおいては非常に古くから注目されておるところの重要な人格訓練の方法になるものでありまして、これは仏教においても受け継がれ、中国でも、わが国でも、禅定の作法において、呼吸を統制していくことは非常に重要な要目になっておるのであります。また中国では、インドとは別に古くから呼吸法が行われております。
呼吸をととのえることによって、われわれの人格を訓練し、向上させていくという方法は、インド、中国、日本において発達しました独特なものでありまして、おそらく西洋には見られないものではないかと思います。有名なドイツの実存哲学者であるカール・ヤスパースが、第二次大戦後、『真理について』という大部な書物を書きまして、その中で東洋人の呼吸というものに注目いたしまして、これは東洋独特なものであると賞讃しております。
このような呼吸は、実際にはわれわれが吸ったり吐いたりしている呼吸でありますが、これが深められてきて、生理的、物理的な呼吸から次第に内面的な生命というほうにまで、つながっていくのであります。
第三のアートマンは、心から成り立っておるところのアートマンであります。これは第一、第二の段階のアートマンに比べてみますと、第一の段階のアートマンはわれわれの身心を養っておるところの食事に着目しており、第二の段階のアートマンでは、呼吸はついには命につながるわけでありますから、第一よりもさらに内面的になっており、それから第三の心から成り立ってアートマンは、さらに内面化して、われわれの精神自体、心自体というものに目をつけて、そこにアートマンの実体を見ているのであります。
ところで、第一、第二、第三のアートマンは、われわれがアートマンを自覚しようと、自覚しまいと、これは誰しもそういう生き方をしておるわけでありまして、食事をとっており、呼吸をしており、そしてまた、われわれは心を持って活動しております。これは、悟ろうと迷っていとうと、等しくこのアートマンはそういう形で動いておるわけであります。ところが、第四の段階になりましてはじめてアートマン自体を自覚していく。もともとアートマンは目覚めており、解脱しているのであるが、しかしそれをわれわれは知らない。第四の段階において、はじめて自己自身に目覚めて、気がつくのであります。これは、智慧から成り立っているアートマンといわれるものでありまして、智慧とは、人生いかにして生くべきか、という智慧であり、結局は、アートマンの自覚であります。
その真実の自己に目覚めてみれば、われわれはただ歓喜だけである、ただ喜びだけであるということに気がつくのでありまして、これが第五の段階の歓喜から成り立っているアートマンであります。
こういうふうに『ウパニシャッド』では五つの段階のアートマンを描いておるのであります。最初は物質的、外形的、具体的なアートマンから、次第に精神的、内面的、無形的なアートマンのほうへ深まって、最後には真実の智慧、真実の歓喜のアートマンに達しておるのであります。
ここでわれわれが気をつけておかなけければならないことは、いま申しましたように物質的なものから精神的なものへ、外形的なものから内面的なものへと次第に深まっていくのではありますけれども、実は食事から成り立っておるアートマンについても『ウパニシャッド』の哲人たちは、食事というものを単に物質的なものというだけではなくて、絶対者ブラフマンとしてこれを礼讃しそれにぬかずいているのであります。また呼吸についても、その呼吸を絶対者として、ブラフマンとして讃えているのであります。ということは、一面からみれば、物的・外的なものから内的なほうへアートマンが次第に深まってはいきますけれども、また他面からみれば、実は食事は食事で絶対である、呼吸は呼吸で絶対である、われわれの心は心で絶対である、また目覚めた智慧、目覚めた喜びはそれ自身としてぜったいである、ということを『ウパニシャッド』の哲人たちは主張しております。しかも食事をとる時に、食事は単に物質ではなくて、絶対者として讃えてこれをいただく、という態度に、彼らの深い宗教性が見られるのであります。
われわれの人生の航路を振り返ってみますと、二十代のわれというものは、三十代のわれに向かって次第に前進していく。また四十代のわれは五十代のわれに向かってさらに人格が向上し、われわれの精神が深まっていくわけでありますが、しかしまた一面からみれば、二十代の現在は二十代として絶対であり、三十代の現在は三十代として絶対である。四十代のわれまた、四十代われとして絶対であります。また小学生は、単に中学生の予備段階ではない。中学生は、高等学校、大学の予備校ではない。それぞれの時代は、それぞれとしてかけがえのないものであり、われわれは、現在、現在を絶対的なものとして大切にしていかねばならない、ということを教えているようであります。(113頁)(2 インドの伝統、おわり)
■ 3 近代インドの復活
こういうふうなアートマンを具体的に実現していく方法が、古代インドから行われてきましたヨーガであります。ヨーガという言葉はいろいろな意味を持っておるのでありまして、実践、実修、修練、あるいはその方法、あるいはその道、あるいはまた精神統一、というように、多義にわたっているのでありますが、もともと結合、ユニオンの意味を持っております。ヴィヴェーカーナンダは、このヨーガの問題を四つに分けて述べております。第一はカルマ・ヨーガ、第二はバクティ・ヨーガ、第三はラージャ・ヨーガであります。
簡単に申し上げますと、第一のカルマ・ヨーガ(行為のヨーガ)は、筋骨たくましい体力的な人、あるいは、自分の立てた理論をすぐ実践に移していく活動的な人にふさわしいヨーガである。そのたてまえは、たとい結果がどうなろうと、成功しようと失敗しようと、そういうことには全く無頓着に自分に与えられた義務を全身全霊をもって遂行していく。その遂行していくという実践の中で、おのずから自分の精神が内から開けてくる、解脱に達する。たとえば、肉体労働にたずさわる人であるとか、会社の仕事に明け暮れしている人などは、ゆっくり思索し、瞑想するひまがない。農夫は大地を耕していく一鍬一鍬のうちに、会社の経営に当たるひとは、その経営に専心していくうちに、おのずから自分の心が開けてくる。これが、カルマ・ヨーガのめざす方法であります。
第二のパクティ・ヨーガ、これは信愛のヨーガ、信仰のヨーガといわれているものでありますが、この方法にふさわしい人は感情が豊かで、美しいもの、崇高なものに対して大きなあこがれを持っている。たとえばすぐれた音楽に自分を忘れて聞きほれるとか、自然の絶景にわれを忘れて陶酔するとか、情緒の豊かな人がパクティ・ヨーガを遂行していくというのであります。これは理屈もなにもない。とにかく、ブラフマン、すなわち絶対者に対して全身全霊を捧げて、その絶対者にまかせ、信頼しきっていく。絶対者にただまかせきっていくことによっておのずから自分の道が開けてくる、解脱の道がうなずかれてくるというのであります。
第三がラージャ・ヨーガ、ラージャというのは王さまという意味でありまして、ヨーガの中心的な構成をなすという意味でラージャ・ヨーガと申しておりますが、これは精神統一の方法であります。呼吸を調節したり、感情や心を統制していく方法を明らかにしております。このラージャ・ヨーガは、人間のタイプとしては自分の精神を分析し、自分の心理状態に深く注意していくような傾向の人がこのヨーガを遂行することによって、やはり同じ最後の解脱に達するというのであります。
第四のジニャーナ・ヨーガ、これは智慧のヨーガといわれているものでありまして、この類型に属する人間は、哲学的、瞑想的で人生の根本問題を深く思索していく人であります。
こういうぐあいに、それぞれの人々の性格、環境、あるいは好みによりまして、自分に最も適切なヨーガを選んでこれを実行していく。たといその方法は違いましても、結局は最後の目覚め、最後の悟りの世界に達することがヨーガの目的であります。ヴィヴェーカーナンダは、きわめて天才的な人物でありまして、この四つのヨーガを自分一人でほとんど理想的な形において実現した人のように思うのであります。(113~115)
■この教えが次第に大きくなり、真実の智慧となってあらわれてくるのであって、彼(岡野注;オーロビンド)はこれを蓮華の花にたとえておるのであります。大きく開いた蓮華の姿、これが完全な真実の智慧であるというのでありますが、現在われわれの心の中にあるものは、開いた蓮華ではなくて、まだつぼんだままの、まだ芽のままの蓮華である。それがヨーガの訓練によって、ある人はすみやかに、またある人はゆっくりと、蓮華が一ひら一ひらと花を咲かせて、ついにいっぱい開ききったのが智慧の完全な姿であります。つまり、アートマンが完全な姿で実現しておる状態であります。そういう教えの原型は、たとえていえば蓮華の芽のようなもので、その芽がわれわれの心の中にしまい込まれておるのであって、決して外から教えをもち込むのではない。その蓮華の芽をできるだけ丁寧に、できるだけ完全に、一ひら一ひらと花を咲かせていく、これが教育の根本であると申しておるのであります。(117頁)
■ 一つにはティーチング(Teaching)、すなわち教導でありますが、これが第一の資格である。これはどういうことかというと、先生が相手に向かって教え込むということではない。むしろ相手を目覚めさせる、これが教導の根本趣旨であります。教師は相手の内部にあるところの真理の芽を萌え出さしめるに必要なものだけを相手の中に投げ入れて、その神聖な光に目覚めさせるのであります。ギリシャのソクラテスは、産婆術ということを教育の根本と考えております。先生は産婆のようなもので、すべての人々は自分のおなかの中に真理の子供を宿している、産婆は真理をつくり出すものではなくて、手がもげたり、足がきれたりしては、産婆の役はつとまらない。それが教育の根本であるということをソクラテスは申しておりますが、ちょうどそれに似たようなことがここで考えられておるのであります。
二つにはエグザンプル(Example)、すなわち模範でありますが、これはティーチングよりもさらに重要な教師の資格であるということであります。このエグザンプルというのは、教師が自分の弟子に向かって模範を示すということではなくて、教師が生活しているそのまま、あるいは教師の全生活を支配している真理の活動が、そのまま人々に対してエグザンプルとなる、そういう意味をあらわしているのであります。これはティーチングよりもいっそう内的な、いっそう人格と人格との交流しあう教師の資格であります。
三つにはインフルエンス(Influence)、すなわち感化であります。これは第二のエグザンプルよりもさらに重要な教師の資格であると申しております。ここになりますと、教師が一人の人格としてそこに現在していること、ただそれだけで、おのずから人々を感化するというのであります。つまり、その人と接していること、自分の魂がその人の魂と隣接しておるという感じだけで、そこにおのずからわれわれの人格というものが変質してくる、感化を受けてくる。これが教師の最後の、しかも最も重要な資格であるというのであります。
以上は、教師の資格でありますが、しかし問題は、そのような理想的な先生はなかなか得られない、また、かりに得られたとしても、結局は、先生は目的実現のための手段であり、補助であり、水路であるにすぎない。したがって重要なことは、自分の内なる教師を発見して、その偉大な力に従っていくことであります。
第三のヨーガの要素はウトサーハ(Utsaha)、専心であります。これはわれわれがヨーガを実修していく場合にきわめて重要な要素でありまして、絶対者を求めていくことに専心し熱中する、そして全身全霊の努力を傾けるということであります。
このウトサーハに関連して、一つには必須の信仰、二つにはゆるぎのない忍耐、この二項目が特に強調されるのであります。この二つを欠いたならば、結局ヨーガの目的は実現することはできない。かなり長い間ヨーガを実修したひとでも、時によると、われわれの人生行路にはいろいろな出来事が起こってきて、われわれの心は曇ることもあるし、よろめくこともある、たといいかなる曇りやよろめきが起こってきても、それを乗り越えていくところの信仰と忍耐、この二つがことに強調されるのであります。オーロビンドは、この信仰ということにつきまして、ともかく最初は、盲目的でもいいから信仰を堅持せよ、いかなることがあっても信仰につまずくな、ということをいうのであります。そのような信仰の堅持が、たがては盲目のヴェールをほどき、真実の智慧を開かしめるのであります。
最後に第四の要素として、カーラ(Kala)、これは時、時間であります。これまでのヨーガの構成要素、シャーストラ、グル、ウトサーハは、実践の問題では非常に深い意味を持っておりますけれども、一応われわれが説明を聞くと納得することができる。ところが、この第四の構成要素であるカーラに対しては、オーロビンドは非常に深い思索を集中しておるのでありまして、なかなかわかりにくいのでありますが、その深い思索を踏み分けてこれを味わっていきますと、いろいろな問題がそれぞれの人生経験の中であじわわれてくるのではないかと思います。
このカーラ、時というのは、一番最初の問題はわれわれの人格の内容であります。われわれは人によりまして環境も違い、性格も違い、能力も違い、社会的な地位も違い、それぞれ異なっておりますが、とにかく自分というものには、無限の過去から行ない続けてきましたところの現在の人格の内容というものをそれぞれ包んでおります。それを彼はフィールド(field)、人格の場と申しております。これがカーラの第一に着目される要点でありまして、この人格内容のフィールドが進行していく、つまり時間的に進んでいく、これが第二のカーラの要素になるのであります。いいかえれば、われわれはいま人生を経験している、この経験の進行が第二の要素であります。
そうしてカーラの第三の、しかも最後の要素は、この全人格をもって我々が経験し、動いておるうちに、おのずから人格の全体の流れを則定するものが感ぜられてくる。それが神聖なるものに、いいかえれば絶対者である。神聖なるもの、すなわち、絶対者というものがカーラの本性であります。
ところが、時とすると、神聖なるものの代わりに、エーゴ、自我がわれわれの人生の測定者としてあらわれてくることがある。このエーゴが、神聖なるものをのけものにして人生の測定者となる時に、われわれの人生経験は常に反撥しあい、融合することができない。これに対して、エーゴではなくて、人生全体を見通し、人生全体を測定するものが神聖なるものである時に、われわれの人生経験はおのずから融合し、おのずから偉大なものに目が向けられその偉大な世界というものを、われわれの人生の中に実現していくということが望まれるのであります。(121~122頁)
■ ⑶ 不二一元論
不二一元論の立場は、人間の思索が最も深い境地に達したものであり、最も高い表現に至ったものであります。それは、哲学と宗教の世界の最も美しい花であります。したがって、ヴェーダンタ哲学の精髄であるといえます。しかしそれはあまりにも深遠であり、高度であるために、大衆の立場とはなりえません。彼によれば、不二一元論は、制限不二論と同じように、神は宇宙の動力因でもあり、質量因でもでもあります。神は創造者であるばかりではなく、創造されたものであります。ここまでは、制限不二論も不二一元論も同じ見解に立つのですが、不二一元論はさらに、この宇宙の神なる唯一の実在である、という考え方に全力を傾けていきます。
この立場では、全宇宙は唯一のじつざいであり、無限なものであり、常に祝福された一者であります。この実在の中で、われわれは種々の夢をみていますが、その夢みている主体こそ、実はこの実在なのであり、無限なのであり、いわゆるアートマン(真の自己)であります。それはあらゆるものを超え、知られるもの、知り得べきものの一切を超えており、われわれはその中で、またそれを通して宇宙を見ているのです。
このような不二一元論は、思想としてきわめてむずかしいものであります。なぜかというと、われわれの理解が、どこまでも主体そのものに立たねばならないからです。その主体がいかなる意味においても対象化できないという点に、そのむずかしさがあります。たとえば、ここにテーブルがある、壁がある、眼の前に群衆があるとします。実はそれらがすべてアートマンであり、唯一の実在なのです。なぜかというと、そのテーブルからその形態と名目をとり去る、また、壁や群衆から同じようにその形態と名目をとり去る、そして残ったものが「それ」(tat)であり、アートマンだからです。ヴェーダーンダではこれを、かれとか、かの女とかは呼ばない。アートマンにはいかなる性もなく、アートマンは純粋であり、常に祝福されたものだからです。したがって、ここでは「あなた」と「わたし」とは一つです。神に対する自然もなく、自然に対する神もなく、また宇宙もなく、唯一の無限な実在が存するのみです。そしてその実在から、形態と名目によって、すべてのものが顕現しているのです。
このように考えてくると、ヴィヴェーカーナンダの思想の中心的な主題は、アートマンの自覚にあるということができます。そして、これが、ヴェーダーンダ哲学の伝統的な課題であります。この目的のために、ヴィヴェーカーナンダはまず自己自身の生命に信頼を持つことを教えます。従来の宗教において無神論とは神を信じないことでしたが、彼は、自己の魂の光景を信じないのを無神論と呼ぶのです。この自己信頼こそ、全宇宙は一体であるという理想を実現するための最大の手助けとなるのです。
ヴィヴェーカーナンダの宗教と思想とについては、なお多くのことを語るべきですが、制限の枚数に達したので、すべてを割愛します。最後に、自己信頼の実践的意味について、彼の言葉を聞きたいと思います。
「まず、このアートマンが聞かるべきである。あなたは、その大霊であるということを、昼も夜も聞け。それがあなたの脈の中に、そして血液の一滴に浸透するまで、またあなたの肉となり、骨となるまで、昼も夜もあなた自身にそれをくりかえせ。《わたしは大霊である。生もなく死もなく、常に祝福され、全智全能にして、しかも栄光にみちている》と。
わたしは、自分の生涯でこのような経験を続けてきた。そしていまもなお経験しつつある。わたしが年をとればとるほど、その信頼はますます強くなってくる。」(138~140頁)
■ それから仏教においても同様で、『大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)』の中の釈尊の遺言として、「真理をともしびとし、よりどころとして他をよりどころとするな。自己をともしびとし、よりどころとして他をよりどころとするな」といわれている。つまり、真理が開かれるのは、結局、自己自信をよりどころとすることである。私(釈尊)のようなものをよりどころとしたらお前たちはだめだぞ、そうではなくて真理をよりどころとし、自己をよりどころとして、その他のものをよりどころとするな、ということである。ここに、非常にはっきりした釈尊の態度があらわれている。
その後、部派仏教においてはこの観点があまり表面に出ていまくて、大乗仏教になって強く押し出されてくるのである。特にその唯識、これは人間の根本意識、これを強く追求している。また、如来蔵思想、これは人間の中に包まれている仏の性格とというものを追求している。そういうインド仏教、いんどの大乗仏教の展開が、中国にきて華厳、天台、真言という大乗仏教としてあらわれてきて、いちいちはここで触れないが、やはりそこに共通的に見られる態度であるところの主体性の問題がある。(180頁)
第八章 鈴木大拙論
■ 大拙(岡野注;鈴木大拙)はまた、『華厳経』全体に流れているところの根本思想に深い思いをよせている。その思想とは、宇宙におけるあらゆる現象が互いに限りなく関係しあっているということであり、しかもいかなる一つの現象をとりあげても、たといそれが心の小さな動きであっても、また一つのかすかな塵であっても、その中に宇宙全体の影像が宿っている、ということである。「絶対の一点に三千大世界界を含み、絶対の現在に永遠の過去と永遠の未来を含む」(「選集」第8巻)のである。そして「いちいちの塵の中へ、仏はみなことごとく入っていって、あまねく衆生のために不思議をおこす」(同上)のである」(226頁)
■ 2 日本文化・禅・浄土
鈴木大拙は世界人であるとともに、根っからの日本人である。日本の文化を心から愛好し、日本人の精神的能力を深く讃美している。ところで彼は、どういう方面から日本の文化に興味を持ちはじめたのであろうか。前にに下手ように、西洋の思想の中にも禅と同類の世界があらわれているのを、彼は情熱をもって感じとっていた。
その同じ目を日本に向けたとき、大拙のいわゆる禅が日本人の伝統的な文化の中に、思想・芸術・生活のあらゆる方面にわたって、広く深く浸透しているのに気づいた。
この問題を、彼は『禅と日本文化』(正・続)の中にまとめている。この書はもともと英文で書かれたもので、後に邦訳(第九巻)されたが、内外に大きな反響を及ぼしている。ここでは種々の問題が取り扱われているが、ことに禅に関係の深いものとして、美術、武士道、剣道、儒教、茶道、俳句、能などを取りあげており、日本人の自然観を、西行、道灌、良寛などに託して述べている。こうしてみると、禅が日本文化の中にしみこんでいる状況には驚くべきものがある。
ところが大拙は、さらに一歩を進めて、右の考え方を裏返しにしてみようとするのである。それが日本的霊性の問題である。つまり、「禅が日本的霊性をあらわしているというのは、禅が日本人の生活の中に根深くくいこんでいるという意味ではない。それよりもむしろ、日本人の生活そのものが禅的である」(第一巻)というのである。霊性は、心霊の本性が目覚めることによって気づかれるのであるから、日本的な霊性は、日本民族の中に培(つちか)われてきている能力が個人の超越的経験を通してあらわれるのをさしている。
それがすなわち禅の体験に通ずるのであるが、大拙は、そうした能力が日本民族には豊かに恵まれている、と考えている。大拙は、この中で最も純粋に霊性の発現しているものを禅と浄土思想において見ている。
禅と浄土信仰とは、もともと同じ仏教でありながら、これまでの実情は互いに相い反目し、あるいはまた無関心の態度であった。他力信仰を主張する浄土系からいえば、禅は自分の力を頼みとしており、とうてい成仏の可能性はない、また禅から見ると、浄土信仰は、自分の外にアミダという宝を求めるだけで主体性を持っていない、というのである。互いに自分の立場から相手にそう決めているだけで、相手の真相を知ろうとしないのである。
このような事情の中で大拙は、一見対立しあっているように見える禅と浄土の、その内面に活動している日本的霊性を発見し、日本仏教における両者の同一の根源を明らかにしようとした。これによって禅宗の人も浄土に関心を持ち、浄土の人も禅を無視しえないことになって、両者の接近する傾向が生じている。このような着想は大拙自身の大きな開眼であり、実践的仏教の双璧である禅と浄土を内面的に結びつけたという意味で、これを大拙流にみれば、そのこと自体が日本的霊性のきわだった展開であるといいうるであろう。
大拙は、日本浄土教における霊性の完全な発現者を親鸞に見るのである。親鸞の根本思想は、大拙によれば、絶対他力であり、ただひたすら仏の無辺の大慈悲に身をまかせ、その光につつまれていることである、という。
だから、この世の苦しみを厭うて、あの世の浄土に生まれることを願う平安朝の浄土教とは全く質が違う。浄土往生ということは、親鸞にとって単なる方便にすぎない。目的は、無辺の光に包まれているという自覚であり、悟りである。
「つぎの世は極楽でも地獄でもよいのである。親鸞は、歎異鈔でそういっている。これが本当の宗教である。」(第一巻)大拙のいわゆる大地性の宗教である。自分自身は大地から出ており、大地の中にしっかりと根をおろしている、という自覚である。ものの感じ方、考え方が大地的であり、大地そのものが感じ、かつ考える。そこに大悲の光がひらめく、というのである。人間の宗教思想、ことに仏教が親鸞の世界にまで達するには、長い間の道中が必要であった。その親鸞を右のような形で掘り起こしたのは大地の卓見であり、彼の強靭な霊性にまつといってよい。
ここで大拙の仏教観に、ちょっと触れておかねばならない。仏教は、時代的には原始仏教、小乗、大乗となっており、その大乗が各派に分かれていて、互いに全く違った教義を持っている。きわめて複雑である。過去にも仏教統一論が叫ばれたが、事実上それは不可能であった。このような仏教をひとまとめにして大拙はどうみているか。
一九四六年(昭和二十一年)四月二十三日と二十四日の両日に、大拙は『仏教の大意』(第十一巻)と題して、宮中で進講の役をつとめている。そのときの内容が、大智と大悲である。これは、複雑きわまりない仏教の、そのものずばりの裁断である。しかもその裁断の仕方がいかにも大拙らしい。いやむしろ、いかにも日本人的であるといったほうがよい。なぜなら、大智は禅によって代表され、大悲は日本浄土教においてその絶頂に達したからである。彼は、さきに述べた華厳哲学における無限相関の思想にもとづいて、大智と大悲の根源的に一体となることを説きつつ、この二方面から仏教全体をつかまえた。(228~231頁)
■ 3 禅と無心
ここで、大智を代表する禅の思想に触れてみよう。禅は、いうまでもなく大拙の中心思想である。『選集』二十六巻が、ことごとく彼の禅思想のあらわれであるといえる。わけても禅の専門に関する論争が、その中でも十五巻以上はある。これについて詳説することはとうていできないが、彼の禅思想のいくつかの特徴を考えてみよう。
第一に、根本的に重要なことは、これまでも触れたように、禅体験がなければならない、悟りが経験されていなければならない、ということである。われわれの分別的な意識が破れて、超越的な智慧が明らかに獲得されることである。彼自身は二十五歳のときに見性しているが、悟りの要請は、彼の禅思想の大前提であり、終始一貫して変わらない。しかしこのことが、後に述べるように外国人からの批判を生ぜしめるのである。
それでは、悟り(禅)の事実とはどういうことであろうか。彼によれば、禅の事実と禅の哲学とは厳しく区別されている。世の多くの禅学者は、この二つを混同しており、そのために禅の生命を見失っている、という(第二十五巻)。
この点から第二に、禅の事実というのは、生活そのものをさしている。日々の経験そのものである。手を動かし、足を運ぶ、そのことである(第二巻、第二十五巻)。これに対して、手を動かすのは自分である、足を運ぶのは自分である、という意識が出てくると、たちどころに禅の事実は消える。それは分別の世界にすぎないからである。禅の事実は、分別のかかわらない行為そのものである。だから、感覚の世界のほかに超感覚の領域があるといっても、また、相対我を超えて絶対我が存在すると説いても、それはすべて哲学にすぎない、禅の事実ではないことになる。
しかるに、われわれの日常生活は、常に分別にとらわれているから、その分別を突き破るところの禅体験が要請されたのであった。
ところで第三に、このような禅の事実をわれわれの心構えから押していくと、無心という態度が出てくる。彼はこの無心ということに異常な情熱をよせ、常にこの無心の世界にあることにたゆみない精進を重ねていったと思われる。無心の代表的な表現として、彼は好んで次の句を引く。
「竹影、階(きざはし)を払って塵動かず、月、潭底(たんてい)をうがって水に痕(あと)なし」(第十巻)。竹の葉がそよいで、その影を石段の上にゆるがすが、段の上の塵は少しも動かない。また、月がふちの底をうがって影を落としているが、水にはそのあとかたもない。これはいかにも詩的であるが、そのまま無心の世界をあらわしている、そしてこの無心こそ宗教の極致である、というのである。
ここには、もはや無心という態度さえもない。われわれのいかなる態度も消滅してしまって、あたかも木石のごとき観がある。第三者から見れば、とりとめなく茫漠としているが、その人自身にとっては、これ以上確かな世界はなく、これ以上安全の世界はない。それは自分のいかなる態度でもないから、ただ絶対受動的であり、すべてのことがそのまま受け入れられるところの、最もやわらかい心である。道元のいわゆる柔軟心である。
第四に、そのような無心が最も端的に、最も具体的に自覚されるものは、人格そのものである。人格といえば哲学的・倫理学的な観念のように聞こえるが、禅においてはそうではなく、現在、刹那刹那の端的な自己である。禅ではこれを人(にん)という。大拙はこの人(にん)を『臨済録』の中に、まざまざと看取することができた。
たとえば、「赤肉団(しゃくにくだん)上に一無位の真人(しんにん)あり。常に汝等諸人の面門より出入す」。われわれの肉体の上に一無位の真人があって、われわれの五官から自由自在に出入している。というのである。このような人(にん)が明白に認得さるべきである。臨済にいたって、はじめて明らかにこの人(にん)が強調されたのは、さすがであるといえるが、同時に臨済の中にこの人(にん)を発見したのもまた、さすがに大拙の卓見であると考えられる。
彼はまた、徳川時代の禅僧盤珪(ばんけい)の不生禅に深いあこがれをいだいている。盤珪はこれまで一部の人には気づかれていたが、一般に知られるようになったのは彼の紹介による。誰にでもわかる話で不生の仏心を説いたところに盤珪の特徴があり、最も日本人的な禅僧の一人である。
スズメがチュウと鳴けばチュウと聞き、カラスがカーと鳴けばカーと聞く、それが不生の仏心であり、生まれついたままの不生であれば万事解決する、という。ここにもまた、最も端的な現在刹那の人が踊っている。
第五に、これまで述べたような禅の事実を大拙は、どのような形において論理化しようとしているのか。論理は事実をいかに的確にあらわしていても、要するにそれは分別の世界からながめたものにすぎないのであるが、分別の世界にあるわれわれにとっては、論理もまた必要となってくる。無知の知、無分別の分別、無行の行という表現(第二巻)も、知的であり、一つの論理であるが、もう少しまとまった形として、加rのいう論理(第七巻)がある。
これは、いわゆる神秘主義から区別されtるものである。神秘主義は、ごく一般的には、相対的な現実の自己と絶対者(神)に融合するという体験上の思想をさしている。ところが、禅はそうではない。相対的な自己と絶対的な神とが二つあって、それが一つになるというのではなく、相対的な自己のままが絶対的であり、絶対者のままが相対的な自己である。彼は、相対的な現実の自己を個一者と言い、絶対的なものを超個者という。すなわち、個一者のままで超個者が自覚されている。個一者と超個者との二つのままで一つであり、一つのままで二つである。一つのところが即、二つのところが非である。即のままで非、非のままで即、これが即非の論理である。
西田幾多郎は、ただ禅の趣旨だけを論じていく大拙に向かって「もっと論理的に、もっと論理的に」と注意していたが、そうした忠告も手伝って、彼の論理がここまで発展してきたのだろう。後期の西田哲学における絶対矛盾的自己同一の思想に通ずるものがある。(234頁)
(2022年11月22日、了)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
『風者小屋だより』ドーデ 作 桜田 佐 訳 岩波文庫
老人
――私に手紙かい、アザンじいや!
――へえ……パリから参りましたんで。
人の良いアザンじいさんは、パリから手紙が来たというので得意だった…… 私は違う。早朝不意に私の机を驚かした、ジャン・ジャック街からの手紙は、私の一日をつぶしてしまうんじゃないかしら。はたして誤らなかった。次のとおり。
「君に一つ用事がしてもらいたい。一日留守にするともりで風車小屋を閉めて、エイギエールは君のところから三、四里ばかりの田舎町だから一散歩(ひとあるき)だ。着いたら孤児修道院と尋ねてくれたまえ。修道院のすぐ次ぎの家は屋根が低く、戸が灰色で、裏手に小さな庭がある。たたかずに入るんだ――戸はいつも開(あ)いている――入ったら、大きな声で、『皆さん今日は、私はモーリスの友人です……』と叫んでくれたまえ。そしたら二人の背の低い老人、老人も老人、非常な老人が大きなひじかけいすの奥から両腕を差し出すだろう。君は僕に変わって、君のおじいさん、おばあさんに対するように、心から抱いてやってくれたまえ。それから話だ。彼らは僕のこと、僕のことばかり口にするだろう。くだらない話ばかりするだろうけれど、笑わないで聞いてくれたまえ…… 笑うんじゃないよ、いいかい! この二人は僕の祖父母で、僕がいるからこそ生きているんだ。しかも十年以来(このかた)僕に合わないんだ…… 十年は長い! だがしかたないよ! パリが僕を離さないし、あっちは高齢でね…… 何しろひどい老体で、もし僕に会いに来ようものなら、途中で骨がバラバラになってしまう…… 幸い君は近くにいる。ねえ粉ひき君、気の毒な老人たちは君を抱いて少しはこの僕を抱いた心地(ここち)がするだろう…… 僕は彼らになん度も話したんだ、僕たちのこと、僕たちの間のあたたかい友情……」
とんだ友情だ! ちょうどその朝はすばらしい天気だったが、出歩くには適しなかった。ミストラルが烈(はげ)しく、日光が強くて、全くプロヴァンス独特の日和(ひより)だった。このしゃくにさわる手紙が来た時、私は既に「避難所(カニヤール)」を二つの岩の間に選んで、松風に耳を傾け、とかげのように日向(ひなた)ぼっこをしながら一日過ごそうと考えていた…… が、今更どうもしかたがない。愚痴をこぼしながら風車小屋を閉めて、ねこの通る穴(シャチェール)にかぎを置いた。つえにパイプと。いよいよお出かけだ。
二時ごろエイギニエールに着く。皆野良に出ているし、教会の泉水の上にははとがとんではいたけれど、私に孤児院を教えてくれる者はだれもいなかった。と、突然一人のふしぎな女が目の前に現れた。戸口にうずくまって糸を紡(つむ)いでいる。尋ねる先をいうと、よほど魔力のある女と見え、その紡(つむ)ざおをさしあげただけで、ふしぎや孤児院はたちまち眼前にそびえ立った…… 陰気な、黒い大きな建物で、ゴシック式の戸口の上に、周囲に少しばかりのラテン語を刻んだ赤い砂岩の古い十字架を得意げに見せている。この家の並びに一軒、もっと小さいのが目についた。灰色の戸、裏手の庭…… 私はすぐにここだと思った。たたかずに入る。
あの涼しい静かな長廊下、ばら色の壁、明るい色のすだれを透かして奥に震える小園(こにわ)、どの鏡板(パネル)にも描かれた、色のあせた花とヴァイオリンの模様を、私は一生涯思い浮かべるだろう。スデーヌ(注;フランスの作家、1719-1797)の時代の、ある老いた大法官のうちに来たように思われた…… 廊下の尽きる左に、細く開かれた戸口から、大時計のカッチン、カッチンと刻む響きと、子ども、といっても学校に通う子の、一音節ごとに句切る読み声が聞こえる。『と、き、に、せ、い、じゃ、イ、レ、ネ、さ、け、び、い、い、け、る、は、わ、れ、は、しゅ、の、こ、む、ぎ、な、り、か、の、け、も、の、の、き、ば、に、く、だ、か、れ、ん…… 』私はそっと戸に近づいてのぞいた……
小さな部屋の静けさと薄明かりとの中に、ほお骨をばら色に染めて、指の先までしわのよった、人の良さそうな老人が、ひじかけいすに深く腰を下ろして、口を開いたまま、両手をひざに置いて眠っていた。その足下(あしもと)で、青い衣服(きもの)――大きな肩掛け、小さな帽子、修道孤児の服装――をした少女が、自分のからだよりも大きな本で、聖者イレーネの伝を読んでいた…… この霊妙な読者に家じゅうのものが感応していた。老人はひじかけいすに眠り、はえは天井に、カナリヤはあの窓の上のかごの中に、大きな柱時計は、カーッチン、カーッチンといびきを立てて。部屋の中で目ざめているものは、ただ閉ざされた戸のすきまから真直(まっすぐ)に射し込む日光の白く広い帯、その中でピチピチ跳ねる火花、こまかな踊り、すべてのものが仮寝の夢円(まど)かなうちに、少女は重々しく読書を続けた。『た、だ、ち、に、に、ひ、き、の、し、し、せ、い、じゃ、に、と、び、か、か、り、て、ひ、き、さ、き、く、ら、い、ぬ……』この時だ、私が入ったのは…… 聖者イレーネのししがこの部屋へ飛び込んでも、私が入ったほどのおどろきをひき起こしはしなかったろう。まさしく舞台の急変(クー・ド・テアートル)だ! 少女が叫び声をあげる。大きな本が落ちる。カナリヤもはえも目を覚ます。時計が鳴る。老人はびっくり仰天、ハッと立ち上がる。私もいささか当惑して、しきいに立ちどまり、大きな声で叫んだ。
――皆さん今日は! 私はモーリスの友だちです。
ああ、その時、諸君がこのあわれな老人を見たら…… 腕を差し出して私の方へ近づき、私を抱き、両手を握り、部屋の中を気の狂ったように歩きまわりながら、
――おお! まあ!…… という老人を。
顔のしわというしわが笑いくずれ、紅(くれない)の潮が差していた。どもりながら、
――ああ、あなた! ああ、あなた!
そして奥の方へ向かって、
――マメットや! と叫んだ。
戸の開(あ)く音がして、廊下にはつかねずみほどの足音がコトコト…… と聞こえ、現れたのはマメットさんであった。飾り帽子を載せ、薄茶色(カルメリト)の衣服(ローブ)を着け、私に敬意を表して古風に縫いのあるハンケチを手にした、この背の低い老婆は例えようもなく美しかった…… ほろりとさせられたのは二人が似ていることだった。髪を束ねて黄色いリボンを花結びにしたら、おじいさんもまたマメットと呼ぶことができたろう。ただ、本当のマメットさんはこれまでにだいぶ涙を流したとみえて、一層しわが多かった。おじいさんのように、そばに孤児院の少女を置いていた。青い肩掛けの護衛(おつき)は決してそのそばを離れなかった。二人の孤児に守られたこの老人(としより)たち、これほど胸を打つ光景があるだろうか。
部屋に入るとマメットさんは非常に丁寧なあいさつをしようとした。しかしおじいさんの一言は、そのお辞儀を途中で止(や)めさせてしまった。
――モーリスのお友達じゃ……
たちまち彼女は身を震わし、泣き出し、ハンケチを落とし、赤く、真赤に、おじいさんよりも赤くなった…… あわれこの老人たち! 脈管に残る血はわずか一滴なのに、少しでも心を動かすとたちまち顔にのぼる……
――さ、いすを早く…… おばあさんが自分の女の子に言う。
――窓をお開け…… おじいさんも自分の護衛(おつき)に叫ぶ。
そうして両方から私の手を取って、もっとよく顔を見ようと開(あ)け放した窓の方へよちよちと連れて行った。ひじかけいすが寄せられて、私は二人の間のたたみいすに腰を下(お)ろした。青い着物の子どもたちが私たちの後(うしろ)に控えて、尋問が始まった。
――孫は達者でおりますかい。あの子は何をしていますのじゃ。どうして来ませんのじゃろ。不足なく仕合わせでおりますかな……
それからこれは、そしてあれは、と、何時間でもこの調子だ。
私はあらゆる質問にできるかぎり答えた。友だちについて知っているだけの詳しい話をした。知らないことは大胆にこしらえて言った。そして、窓がちゃんと閉まるかどうか知らない、部屋の壁紙はどんな色か注意したことがない、などと白状するのは特に慎んだ。
――部屋の紙ですか?…… 青でしたよ、奥さん、薄青色に花飾り(ガーランド)の……
――まあ、そうですか?と、あわれ、おばあさんはほろりとなった。そして夫の方を振りむいてこう言った。
――ほんとうにいい子ですからね!
――そうとも本当にいい子だ! おじいさんは力を入れて答えた。
こうして私の話の初めからおしまいまで、二人は互いにうなずきあい、可愛らしく微笑(ほほえみ)み、目を細くし、すっかり分かったという様子をする。時には、おじいさんが私に近寄ってこう言った。
――もっと大きな声で話してくださらんか…… あれは少し耳が遠いでな。
また、おばあさんはおばあさんで、
――どうぞ、もちっとおお声を高く!…… おじいさんははっきり聞こえませんので……
そこで私は声を高める。すると二人ともうれしそうに微笑んで見せる。そして、私は孫のモーリスの姿を目の奥に探そうと私に向かって身を屈(かが)める二人の、このしなびはてた笑顔の中に、あたかも遠く霧の中に微笑んでいるような、ほのかに、ヴェールをかぶった、ほとんど捕え難い友の面影を見つけて、すっかり心を打たれたのであった。
――――――――――――――――
突然、おじいさんはひじかけいすの上に身を起こした。
――おお、そうじゃ、マメット…… 多分昼飯(おひる)がまだじゃろ!
するとマメットさんはびっくりして、腕を高くあげ、
――昼飯(おひる)がまだ!…… まあ!
私はこれもモーリスのことだと思ったから、この善良な子どもは、昼の食事を十二時より遅れてすることは決してありません、と答えようとようとした。ところがそうではなくて、話の本人は正に私であった。私が、まだです、と言った時の騒ぎは見ものだった。
――おまえたち、急いで食事の用意を! 食卓(テーブル)を部屋の真中(まんなか)に出して、日曜日の食布(ナップ)と花模様のおさらを。どうかそんなに笑っていないで! さ、大急ぎ……
子どもたちは確かに急いだのだろう。さらを二、三枚割るよりも早く、食事は整った。
――ごちそうはありませんがおいしい昼飯(おひる)で! 食卓に案内しながらマメットさんは私にこう言った。ただ、あなた様お一人でして…… 私どもはもう今朝がたいただきました。
かわいそうな老人たち! いつ訪ねて行っても、彼らは常に、朝いただきました、と言うのだ。
マメットさんお、ごちそうはないがおいしい昼飯(おひる)、というのは、わずかの牛乳と、なつめやしの実と、「バルケット」という軽い焼菓子とであった。これだけあれば、おばあさんとカナリヤとを少なくとも一週間養うことができる…… しかも私一人でこの貯えを平らげたんだ…… 無理もない、食卓のまわりにいかに激しい憤慨が起こったか! ひじを付き合いながら青い娘たちがささやくし、向こうのかごの中ではカナリヤが『おいおい、あのだんなを見ろ、バルケットを皆たべちまうよ!』と言っているようだった!
私は本当に皆平らげてしまった。それも、昔のものの香りでも漂っているような、明るい静かな部屋の中で、自分のまわりをながめるのに夢中だったので、ほとんどそうとは気がつかずに…… 特に目が離すことができない二つの小さな寝台があった。まるで揺かごを二つ並べたようなこの寝台を見ると、私は朝、明けがたに、総(ふさ)のついた大きな帳(とばり)のかげに、まだ夜具に埋(うずま)っている二人を思い浮かべた。三時が鳴る。どの老人も目覚める時だ。
――マメットや、眠っているかい?
――いいえ、おじいさん。
――モーリスは良い子じゃのう。
――ええ、全くねえ、ほんとうに良い子ですよ。
こうして、並べられた二つの小さな寝床を見ただけで、私はこんなふうに一(ひと)くさりの会話(はなし)を胸にえがいていた……
この間に部屋の片隅の戸だなのの前では、恐ろしい劇が演ぜられていた。一番上のたなにある、ブランデーづけのさくらんぼうのびんをとろうというのだ。十年も前からモーリスの来るのを待っていて、私にお初を振舞おうというわけだ。マメットさんの懇願には耳を借さず、おじいさんは自分でさくらんぼうを取り出すのだと言い張った。そしておばあさんに気をもませながら、いすの上に乗り、たなに届こうとしていた…… 今でもありありと見えるようだ。震えながら背のびするおじいさん、そのいすにしっかりくっついている青い着物の子どもたち、後で両手を伸ばし、息をはずませているおばあさん、そして開いた戸だなと、高く積まれた茶色のリンネルから流れ出る芳香みかん(ベルガモット)の淡い香りがすべてのものの上に漂っている…… 愛すべき情景だ。
とうとう非常な努力の後で、この由緒あるガラスびんは、モーリスが幼いころ用いたとというすっかりいびつになった古い銀の杯と一しょに、ようやくたなから引きおろすことができた。その盃に縁までたっぷりさくらんぼうが盛られた。モーリスはさくらんぼうがだいすきだったのだ! 私にすすめながら、おじいさんはさも食べたそうな様子でこうささやいた。
――あなたはほんとうにお仕合わせじゃ! これが召しあがれるなんて…… これは家内の手造りでな…… おいしゅうございますて。
残念! お手造りはありがたいが、奥様砂糖を入れるのをお忘れなされた。どうもしかたがない! 年をとればぼやけるものだ。マメットさん、せっかくのさくらんぼうはひどい味でしたよ…… しかし最後までまゆをしかめずにちょうだいした。
――――――――――――――――
食事が終わると、私は老人夫婦に暇(いとま)を告げようと立ち上がった。二人はなお私を引きとめてうちの良い子の話をしたかったろうが、日は西に傾き、風車小屋は遠いので、出かけなければならなかった。
おじいさんは私と同時に立ち上がった。
――マメット、着物だ!…… 広場まで案内してあげたいから。
マメットさんはもちろん内心では、私を広場までつれて行くには、もはや少し寒くなっていると思ったに違いないが、しかしそんな様子は少しも見せなかった。ただ着物のそでを通すのを手伝いながら、それは真珠母(しんじゅぼ)のボタンの、スペインたばこの色をしたきれいな着物であったが、夫思いのおばあさんが、優しくこう言っているのが聞こえた。
――あまりおそくお帰りになってはいけませんよ。
するとおじいさんは少し意地悪そうに、
――フーム、さあ!…… どうだかね…… もしかすると……
そして二人は顔をあわせて笑った。彼らが笑うのを見て、青い着物の子どもたちも笑った。かごの隅で、カナリヤもカナリヤらしく笑った……
内緒の話だが、さくらんぼうの香りで皆が少し酔っていたのだと思う。
……おじいさんと私とが表へ出た時、日は暮れかけていた。青い着物の少女がおじいさんを連れ帰るために遠くから従(つ)いてきた。しかしおじいさんには彼女が見えなかった。私の腕につかまって若い者のように歩きながら、おじいさんは非常に得意であった。マメットさんはそれを晴れやかな顔で入口の踏段(ふみだん)から見ていた。こちらをながめながらうれしそうにうなずいているのは、こう言っているようでもあった。『やっぱりおじいさん!……まだ足が達者だこと。』(100~110頁)(おわり)
(2022年12月13日、了)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
『風者小屋だより』ドーデ 作 桜田 佐 訳 岩波文庫