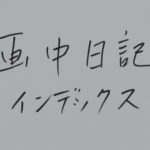読書ノート(2007年)全
■そしてこれをシュベングは、「なによりもまず素材としての物質からではなく、運動の相互作用から形態形成がなされるという可能性を理解すべきである」という。「素材を利用してこれを鋳造するものこそ、運動に他ならない」。すなわち作品をそうぞうするのも、まずはじめに素材を主体にして何かを形成するのではなく、運動ー〈精神・美〉が存在し、それが素材を周囲に呼び寄せ、秩序と律動があたえられるということである。くわえて、「こうした事実を正しく観察してはじめて、胚中にーあるいはさくひんにも、またたとえ細胞分裂をけんきゅうしても、それは理解することができないのである」と。成立させている素材や手法をいくら分析し研究してみても〈精神・美〉による形態創造の秘密を解き明かしたり、理解したりすることはできない。(149㌻)
■「われわれの肉体が形態化された流体であることには疑問の余地がない」:ノヴァーリス『断章』(赤井敏夫訳)(150㌻)
■ユイグはー原子からレンブラントへーとサブタイトルのある『かたちと力』で、古今東西の造形芸術に視線を向けながらも、つねに自然現象…原子から星の宇宙までを視野に入れ、とかく現代芸術の陥りやすい〈表現〉の短絡や廃棄、そして自然との乘離に注意をうながしながら綿密な造形論を展開している。この本を書くにあたってユイグは「わたしが知りたいと思っていたことは、芸術の研究から引き出した結論がいっそう広い射程を持つものではないかということ。つまり、芸術以外の領域においても同じように見いだされ、確認され得るものではないかということである」と。つまり「芸術すなわち、人間が創造し、仕上げ、洗練していったかたちと、もっとも奥深い有機的な現実とをふたたび結びつけなければという思い」であったと述べている。(163㌻)
■ゲーテは古典的なものを健康としてとらえ、ローマン的なものを病的なものとしてとらえていた。そして同時にシュベングの『カオスの自然学』のなかにでてくる〈炎のかたち〉に音響の与える影響を思い出す。つまり、よく調弦されたヴァイオリンの響きは火炎に均整のとれた古典的なかたちを与え、調弦の悪いヴァイオリンの響きは火炎のかたちにゆがみをみせ、なにか病的なおもむきを与えているのだ。(172㌻)
■あらためて注視すると、自然界における結晶への志向には驚異的なものがある。なにか物質のもつ根源的な意志を感じてしまう。スピノザは石が「衝撃によって空中を飛ぶとき、石に意識があれば、自分の意志で飛んでいるのだと考えるだろう」といった。ショーペンハウアーはその「石の考えていることは正しい」。そして「石において、仮定された状況のなかで、凝集力、重力、持続力として現象するものは内的本質の点から言えば、わたしがわたしのうちに意志として認識するものと同じである」といった。(176,177㌻)
■「マンダラとは[ミグパdmigs–pa]、すなわち精神の像(imago mentalis)であって、深い学識を備えたラマ僧のみが創造の力によってこれを形成することができる。マンダラには一つとして同じものはなく、個々人によって異なる。また僧院や寺院に揚げられているようなマンダラは大した意味をもたない。なぜならそれは、外的な表現にすぎないからだ。真のマンダラは常に内的な像である。それは心の平均が失われている場合とか、ある思想がどうしても心に浮かんでこず、経典をひもといてもそれを見出すことができないので、みずからそれを探し出さなければならない場合などに(能動的な)想像力によって徐々に心のうちに形作られるものである」(ユング『心理学と錬金術』池田紘一・鎌田道生訳)。(182㌻)
■タージリンの僧院長リンダム・ゴームチェーン師が語っていたではないか。「マンダラとは内的な像である」。そして、それは「ある思想がどうしても心に浮かんでこず、経典をひもといてもそれを見出すことができないので」、各人が「みずからそれを探し出さなければならない場合などに、(能動的な)想像力によって徐々に心のうちに形づくられる」ものであるのだ、と。そしてそれは、とくに「宗教ではない」(ムケルジー)。(188㌻)
『抽象絵画の世界』薗部雄作著 六花社 2007年2月8日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■姉ヘルミーネはL・ヘンゼルに向かって次のようにいわざるをえない、「不幸な聖人よりも幸福な俗人を弟に持ちたい!と何遍思ったことか。聖人の場合にはこの先どうなるか、全くわからないからです。わたしも家族も単なる人間にすぎず、ものごとを人間的にしか把えられません。他の者が明るく幸せなのを知ることは、まさに人間的な喜びなのに、残念ながらそのような願望さえ、ルートウィヒのことを考えると、放棄せざるをえません」(1920年12月13日付書翰)と。
さらに、彼女は、父の遺産をすべて他人に譲与して修道僧のように生きようとしている弟の「気が変わったら、財産を取り戻せるようにしておいてやれ」という亡き伯父パウルの意見を容れて、遺産をすべて自分たち(妹ヘレーネ、弟パウルと三人)で分有し、第二次世界大戦が近づいてナチによる財産没収が危惧されると、他の親族(主としてウィトゲンシュタインの甥や姪)に分配してしまう。兄弟縁者といえども他人に仕送りや経済上の援助をしてもらうことをいさぎよしとしなかったウィトゲンシュタインが、その後しばしば最低水準の生活水準に甘んじていたのは、それがかれの生活信条であった以上に、事実お金をもっていなかったためなのである。(84㌻)
■カルナップの「自伝」によると、「哲学的な問題に対する態度は、科学者が自分たちの問題に対する態度とあまり違わなかった」のに対し、「人々や諸処の問題に対するかれの視点や態度は、科学者よりも創造芸術家のそれのほうに遥かに類似していて、宗教的予言者の態度といえるほどだった」。(111㌻)
■かれは戦争が常に無条件に悪いなどと杓子定規には考えていない。だから、海軍に入りながら戦闘に参加した経験のないマルコムが「戦争は退屈だ」と述べると、ウィトゲンシュタインが「もし少年が学校はひどくつまらないといったら、まわりのひとはそれに答えて、もしお前が学校で本当に学べることを学ぶようになれさえしたら、学校をそれほど退屈だとは感じなくなるだろう、というでしょう。だから、わたしが、この戦争でも――眼を見ひらいていさえすれば――人間存在について実に多くのことが学べると信じざるをえない、といっても赦していただきたい……」(1945年6月、マルコム宛て書翰)と返事しているのも、同じ精神の境位を示していることになろう。(133㌻)
■ふつうなら教授として働き盛りのウィトゲンシュタインが、五十八歳で世界に冠たるケンブリッジ大学を辞職するのは、哲学すること、おるいは哲学の仕事を、大学教師としての生活と混同していなかったからである。しばらくあとになって、余りの孤独に仕事がうまくいかず、多少いらだって、「自分は大学を離れてしまうべきだったろうか、結局は教職を続けているべきではなかったろうか、と自問してみました。わたしは直ちに、自分にはあのまま教えていくことなどできなかったと感じて、もっと早く辞職すべきだったかもしれないと自分にいいきかせさえしました。……わたしの哲学的才能がいま涸渇したとすれば、それは不運というべきでしょうが、それも止むをえません」(1948年7月、マルコム宛て書翰)と述べてはいるけれども。(142㌻)
■夫人ジョーンは、はじめてウィトゲンシュタインが家にやって来たときの模様を、次のように日記にしたためている。
「わたしはかれに対して大変な畏敬の念を抱いていたから、何もいわずにパンと
バターだけを出し、あとからお茶を差し上げた。しばらくすると、ウィトゲンシ
ュタインがアメリカについて話しをしたので、わたしは〈アメリカへいらしたな
んて、何て幸福なことでしたでしょう〉と合いの手をさしはさんだ。すると、か
れは、かれだけにできる目付きでわたしをじっと見つめ、〈幸福とはどういうこ
とですか〉と訊ねたのである。わたしはこのときはじめて、ことばの正しい使い
かたがいかに大切であるかを理解しはじめた。」(150㌻)
■「およそ言い得ることは明瞭に言い得、語り得ざることについては沈黙しなくてはならない」(162㌻)
■「……わたしの著作は二つの部分から成る、一つはここに提示されているもの、もう一つはわたしの書かなかったことのすべて、である。そして重要なのは、まさにこの第二の部分なのです。わたしの本は倫理的なものごとの領域をいわば内側から限界づけているのであり、それこそかような限界づけの唯一の正しい方法であると確信しています……」(163㌻)
■……わたしに考えられるどのような記述も、わたしのいう絶対的な価値の記述に役立たないのみならず、かりに誰かが有意味な記述と称するものを提案できたとしても、わたしはそのような記述のいずれをも、その有意味性を根拠としてはじめから拒否するでしょう。すなわち、このような無意味な表現〔あるいは絶対に神秘的なことについて語ることの無意味さ〕は、わたしがいまだ正しい表現を発見していないから無意味なのではなく、そうした無意味さこそがほかならぬそれらの表現の本質だからなのです。なぜなら、そうした表現を使ってわたしのしたいことは、世界を超えていくこと、有意味な言語を超えていくことにほかならないからです。……倫理学が人生の究極の意味、絶対的な善、絶対に価値あるものごとについて何ごとかを語ろうとする欲求から生まれるものであるかぎり、それは科学ではありえません。その語るところは、いかなる意味においてもわれわれの知識を増やすものではありえません。その語るところは、いかなる意味においてもわれわれの知識を増やすものではありません。しかし、それは人間の精神に潜む傾向を記した文書であって、わたしは個人的にこの傾向に対し深い敬意を払わざるをえないし、それを生涯あざけったりしないでしょう。(166㌻)
■四・一一六 およそ考えうるものごとは、すべて明晰に考えうる。いい表しうるものごとは、すべて明晰にいい表わしうる。(218㌻)
■五・六 わたしの言語の限界はわたくしの世界の限界を意味する。
五・六一 論理は世界に充満する。世界の限界は論理のげんかいでもある。
それゆえ、われわれは論理の内部で、かくかくのものは世界の中に存在するが、あれは存在しない、などということができない。……なぜなら、論理が世界の限界を跳び越えていたはずだからである。思考できないことを思考することはできない。それゆえ、思考できないことを言うこともできない。
五・六二 ……世界がわたくしの世界であるということは、この言語(わたくしの理解している唯一の言語)がわたくしの世界の限界を意味するということのうちに示されている。
五・六二一 世界と生は一つである。
五・六三 わたくしとは、わたくしの世界のことである。(小宇宙)(223㌻)
■六・三七三 世界はわたくしの意志から独立している。(228㌻)
■六・四二一 倫理をいい表わすことができないのは明白である。
倫理は超越的である。(倫理と美学は一つである。)(229㌻)
■六・四四 世界がいかにあるかではなく、世界があるということが神秘的なことなのである。(230㌻)
■六・五 いい表わすことのできない答えに対しては、問いをいい表わすこともできない。
謎といったものは存在しない。
そもそも問いが立てられるなら、それに答えることもできる。
六・五二二 いい表わせぬものごとがたしかに存在する。それはみずからを示す。それは神秘的なものごとである。
六・五三 哲学の正しい方法とは、本来次のようなものであろう。いいうること以外、それゆえ自然科学の命題以外――それゆえ哲学に関係のないこと以外――、何ごともいわないこと。そして、誰かが何か形而上学的なことをいおうとしたときには、いつも、その人が自分の命題の中のある種の符号に全く意味(ベドイトウング)を与えていないことを指摘してやること。このような方法は余人を満足させないだろうし――その人はわれわれから哲学を学んだという感じをもたないであろう――けれども、しかし、これこそ厳正な唯一の方法であろう。(231㌻)
■わたしの書く命題は、どれも常に全体を意味しており、それゆえいつも同じことを意味しているが、それはいわば異なった角度から観察される一つの対象の〔異なった〕見えかたなのである。(253㌻)
■ひとは明証の可能性〔の限界〕を言語によって踏み越えることができない。(2
57㌻)
■言語はそれ自身で語るのではなくてはならない。(262㌻)
■三七一 本質は文法の中に表明されている。
三八四 〈痛み〉という概念を、きみは言語とともに学んだのである。(310㌻)
■ひとは、ある動物が怒り、恐れ、悲しみ、喜び、驚いているのを想像することができる。だが、望んでいるのは?では、なぜできないのか。
イヌは、自分の主人が戸口にいると信じている。だが、イヌは、自分の主人が明後日やってくると信ずることもできるのか。――では、イヌは何をすることができないのか。――わたしはそれをどのようにしているか。――わたしはこれにどう答えるべきか。(312㌻)
■「いいうること、すなわち自然科学の諸命題――それゆえまた哲学に関わりのないものごと――以外には何ごともいわぬこと」(六・五三)といった警句や、「真なる命題の総体が全自然科学(あるいは自然諸科学の全体)である」(四・一一)といった断定に接して、我が意を得た感じがしたことであろう。有意味な命題はすべて要素命題の真理関数であり、その要素命題はすべて世界内の諸事実によって真とされなくてはならない(検証理論)、はずであった。(333㌻)
■ウィトゲンシュタインもまた、「世界は事実の総体であって、物の総体ではない」(一・一)と述べて「物的世界像」に反対しているけれども、他方要素命題に対応すべき事実の基本単位「事態」が「対象(物)」の結合したものだという考えかたも温存していて(二・〇一)、一種中途半端な二元説をとっている。そして、その中途半端さかげんが、論理学的ものの考えかたにとってはきわめて好都合なのである。なぜなら、「対象」ないし「もの」とは述語論理学における「個体定項」ないし「個体変項」によって表記されるもの、、「事態」ないし「こと」とは命題論理学における「命題常項」ないし「命題変項』によって表記されるものごと、とそれぞれ解釈しておけば、現在すでに一体となって無矛盾的に併立している述語論理学と命題論理学の双方を意味論的に救うことができるからである。(335、336㌻)
『ウィトゲンシュタイン』藤本隆志著、講談社学術文庫 2007年2月14日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「抽象芸術という言葉は意味がない。いつでも何ものかから出発し、その後に現実的な外観をとり去るだけなのだ。しかし心配無用だ。実体のイデーは絶対に消すことの出来ない痕跡を残すから。それは芸術家を示唆して彼のイデーを覚醒させ、エモーションを活動させるのだ。イデーとエモーションは決定的に作品におしこめられて、どんなことをしても絶対に画面から脱れることは出来ない。それらは全面的に場所を占めているのである。たとえまったく判断出来ないほど、表面に現れていなくとも。
好むと好まざるとにかかわらず、人間は自然の道具である。自然の性質と相貌を強要されている。(ピカソ)」(39㌻)
■「私はものと同じように 絵画を扱う。私は窓から外を見るように窓を描く。もし開いているのが気に食わなかったら、実際に部屋でやるようにカーテンを引いてしめてしまうのだ。
実生活のように、じかに絵に処すべきである。もちろん絵には致し方のない絵そのものの約束があり、それを織らなければならないが。(ピカソ)」(40㌻)
■「私はペシミストではない。私は芸術を嫌っていない。なぜなら私は自分の全部の時間をそれにさかないでは生きていられないからである。私は生命の目的のすべてとしてそれを愛する。芸術に関して私のするすべては大きな歓びである。(ピカソ)」(47㌻)
■十九世紀芸術は素朴な科学主義に影響されて、外的世界のみを現実だと思い込み、内的現実の表現を抹殺した。印象派でさえこの観念の虜であった。(78㌻)
■セザンヌがいかに画面を合理化し、フォーヴィストたちが自由な表現を試みたとしても、彼らは結局、対象である自然の約束からは逃れ得なかった。何らかの形において客体を再現し、造形的な立場から自然をぎりぎりのところまで歪曲する、つまりデフォルマシオン(セザンヌ自身の言葉で言えばレアリザシオン)を試みたにとどまる。ところで、一見それと混同されるピカソの立体派芸術は、デフォルマシオンではなく、実はフォルマシオン(成形)なのである。(88㌻)
『青春ピカソ』岡本太郎著、新潮文庫 2007年3月9日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■個々の定理の証明などは一つ一つわかっても、全体系を作り上げるのに、なぜその一つ一つの定理がそういう順序でつみ上げられねばならないか、そういう点までわからないと、その勉強は結局ものにならないようである。数学者にきくと、数学の仕事は、一つ一つの定理の証明などはむしろあとからでっち上げるもので、実際は結論がまっさきに直感的にかぎつけられ、次にそこへ至るいくつかの飛び石が心に浮かんできて、最後にそれを論理的につなぐ作業が行われるということである。数学を勉強してほんとにわかったという気もちは、おそらくその数学が作られたときの数学者の心理に少しでも近づかないと起り得ないのであろうか、一つ一つの証明がわかったということは、ちょうど映画のフィルムの一こま一こまを一つずつ見るようなもので、それでは映画のすじは何もわからない、そんなものではなかろうか。
そうなると、数学がわかるというのは、数学者のもっているような見通しの力がないとだめだということになる。しかし、小学生は小学生なりに算術ができ、中学生がいつの間にか負に負を乗じて正になることを不思議に思わなくなるのは、凡人でも時間をかけて数学をいじくっているうちに、無自覚のうちに全体の未通しが脳のどこかに形づくられるのであろうか。(138㌻)
■原子物理学者の行き方に三つの方法がある。第一は現在の事実には一切眼をつぶって、千年先のことを考えて純粋な研究をすること。第二は千年先の研究は抛って、現在のことに捲込まれ、正しいと考える主張を実現すべく己を無にして努力すること。第三はどっちつかずの立場で、適当に研究もし、現実の問題にも捲込まれない程度にタッチする。(中略)
泥まみれになって戦う意義は認めるけれど、近頃の不愉快な実例を見ていると、やはり先の第一の行き方が一番純粋で力強い気持ちがする。そうは思っても非人情になり切れない僕の弱さがある。本当の人情は、ある面からいえば、非人情に徹するところから産まれると思う。ゴーギャンがタヒチ島は行っての仕事が多くの人に喜びを与えたように、自分自身の喜びが他の人を喜ばせる仕事が一番理想的なものであると思うだが……。(151㌻)
『鏡のなかの世界』朝永振一郎著 みすず書房 2007年3月15日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「去リシ日ノ薔薇ハ名バカリニテ、虚シキ名ノミ残レリ」
ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』は、この老修道士アドソの諦念に満ちた言葉で終わっている。彼のモデルが十世紀に『アンチキリストの出現と時代』を記した終末論者アドソ・モンティエル=アン=デルであるとするなら、感傷的なエンディングにもうなざける。若い修練師として遭遇したミステリアスな事件から数年を経て、今は廃墟になったかっての修道院を訪れたアドソは、図書館跡に焼け残ったいくつかの写本の断片を見つける。しかしそれはいかにうまく再構成されてもただの「記号のつぎはぎ細工」以上のものではない。図書館も修道院も、そして敬愛した師も、彼が戒めを破って愛した「少女」も、彼女の村ももはや存在しない。それらはすべて虚シキ名となって残ったにすぎない。「薔薇」とは彼が名も知らず愛した少女に与えた記号でであった。しかし《nomina nuda tenemus》と語るアヂソは薔薇の名前が虚しくなったと嘆いているだけなのであろうか。筆者にはそれが別の意味のように思えてならない。
彼の師パスカヴィルのウィリアムのモデルは中世の論理学者オッカムのウィリアムだとされる。事実、作中には普遍論争を思わせる機知に富んだ師弟の会話が随所に挿入されている。ウィリアムは徹底した論理学者である。「私は記号の真実を疑
ったことはない。アドソよ、記号とは人間がこの世と折り合いをつけるために手にしている唯一のものだからだ。私が理解できなかったのは記号と記号の間の相互関係だ」(第七日夜)。彼は記号(殺人現場)をたどることで、真犯人に行く着くことができると信じて行動するが、同時に記号の分析がそのまま事件の解明につながるとは考えていない。なぜなら記号とは複合的に結びつけば、まったく予測不可能な意味をつくりはじめるからだ。記号間の規則性を解明できると考えることは、ウィリアムにはこの上ない思い上がりのように思えた。なぜならそうすることは、人知のおよばない神の全能に制限を加え、神を人間の虜囚にしてしまうからである。たとえば書物に書かれた一角獣はそのままで一角獣の実在を保証するものではない。それでは実在しない一角獣を記した写本は嘘をいっているのかというアドソの問いに師は次のように答える。「われわれは神の全能に制限を加えてはならない。神が望めば、一角獣だって存在するかもしれないではないか。がっかりするな。それはともかくも書物の中には存在するのだから。たとえ現実ではなくとも、可能な存在としてわれわれには知らされているのだから」(第四日終課後)。
『冬の薔薇』香田芳樹 創文No.495(2007.03)2007年4月11日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■沖の小島(国木田独歩)
沖の小島に雲雀があがる
雲雀すむなら畑がある
畑があるなら人がすむ
人がすむなら恋がある(24㌻)
■希望(土井晩翠)
・・・略
港入江の春告げて
流るる川に言葉あり、
燃ゆる焔に思想(おもひ)あり、
空行く雲に啓示(さとし)あり、
夜半の嵐に諫誡(いさめ)あり、
人の心に希望(のぞみ)あり。(26/27㌻)
■街頭初夏(木下杢太郎)
紺の背広の初燕
地をするように飛びゆけり。
まづはいよいよ夏の曲、
西(ざい)―東西の簾(みす)巻けば、
濃いお納戸の肩衣の、
花の「昇菊,昇之助」
義太夫節のびら札の
藍の匹田(しつた)もすずしげに
街は五月に入りにけり
赤の襟飾(ねくたい)、初燕
心も軽くまひ行けり。(150㌻)
■塩鮭(中勘助)
ああこよひわ我は富みたり
五勺の酒あり
塩鮭は皿のうへに高き薫りをあげ
湯気たつ麦飯はわが飢えをみたすにたる
思えば昔
家を棄て
世を棄て
人を棄て
親はらからを棄て
瞋恚(しんい)や
狂乱や
懐疑や
絶望や
骨を噛む心身の病苦に悩み
生死の境をさまよひつつ
慰むる者とてもなく息づきくらし
または薬買ふ場末の町の魚屋の店にならぶ
塩鮭のこのひときれにかつえしこともありしかな
見よや珊瑚の色美しく
脂にぬめるあま塩の鮭のきれは
われにその遠き昔をしのばせ
しぞろに箸をおきて涙ぐましむ(176、177㌻)
■負数(川路柳虹)
零(ゼロ)よ。おまえは何もないのか。
いや、いや、おまえは虚無の扉にすぎぬ。
おまえを一つおすと、そこから
冷たい道がひらける。マイナスよ、-1-2-3…
ああ限りもない富よ、失恋の歌反古(ほご)よ。
何にもならぬが、もしか、
「生活」を拒否して生きるとしたら、
おまへのやうな性質のものが
吾らの友とならう。(209㌻)
■鳥影(生田春月)
晴れた空のもと、
光る風の中を、
瞬間の鳥が過ぎる
ただ一列なして。
とらへたや、とらへたや、
あれはみなわがもの、
わが身の後光、
美しく失はれて……
身にひそむもの
身を編むもの、
あまりに早く放ち、
悔いてみる、鳥影。
とまれ、とまれ、鳥よ、
わたしの生の水晶を
切り出して生んだ鳥、
飛び去るな、今より。
わが裡(うち)なる谷窪、
晶石のうつろに
一体の光としづめ、
永遠の相(そう)を現じて。(256、257㌻)
■エレオノーレ(尾崎喜八)
椋鳥がどんなお饒舌(しゃべり)をするか、あんた知ってる?
寒い夜ぢゆう凍った地面へ立つたまゝ、
朝を待つ雪割草のくるしみをしってる?
それから、今、
三月の昼間の空へ出ている星があんたに見えて?
天ノ河の岸でWになってるカシオペイヤの星座が。
神様のおぼしめしが無くつては
一羽の小鳥だつて死にはしないわ。
だけど、今朝、あたし
市場で死んでる鳥を見つけたわ。
あんたはなんにも知らないのね。
それでもどこか善いところがあるわ。
あたしなんでも知っているの。
何かを知るといふ事は、
生まれる前から知ってる事を思い出すことなのよ。
大人は思慮が無くつて残酷なものね。
互いに憎み合つてる内にだんだん自分を磨り減らしてしまふんだわ。
ほら、そとで電線が鳴つてるでしよ。
ほそい、柔らかい、きれいな銅(あかがね)。
人間が電話で蔭口や悪口を云ひ合ふと、
美しい銅がなくわ……
*
ありがたう、エレオノーレ、
氷を溶かす春風のやうな
するどくて温かなお前の叡智(えいち)は
僕の心から人間の銹(さび)を落としてくれた。
ありがたう、悲しく賢いインドラの娘、
「復活祭」のエレオノーレ!(275、276,277㌻)
■雨(三野混沌)
むぎのくろはな
ひらけてとじない
そのまま雨にぬれた
暗闇にふる雨
しかたのない雨だから
ないもののように
ただいきるばかりだ
むぎのくろはなないように
ないもののようおれににて
雨にぬれ
ひばりよそうではないか(336,337㌻)
■夕暮れに(片山敏彦)
雨がやんで
ぬれた樹々は夕暮れの蒼ざめた光の中で
身ぶるひしている。
霧と灯とを持つ秋の夜の影は
それらの樹々を包まうとしている。
不思議な時間よ。
紙を照らす灯(ひ)の黄色さは
親しさを以つて私のこころを呼んでいる。
遠い者が近くなり
過ぎ去った日々の明るさが心によみがへる
静かな時よ。
私は君の中で自身を一つの中心と感じる。
はるかなところで生まれた波が
私をつらぬいて、はるかなところへ行こうとするのだ。
私は潮の先端に立っている。
私はどこへ行くのか?いつかは行くところへ――大きな海の中へ行くのだ。
私は消え去った日々を悲しんで見ている。
然し、決して亡びない日を
私は歓喜して見ている。(377,378㌻)
■新しい空間(片山敏彦)
ものの内部に沈み込んで
暗がりに黙ってすわって
君はあたりを見まはした。
君は自分の、いひがたい苦しみを畳んでつかんで
その手の平から新しい空間を投げた。
そこで、冬のあかつきの
ほのぼの白い光のやうに
ものが、君の前でひろがつた。
お父さんから、おぢいさんから、
いや、もつともつと前のお父さんから
君が最後に今、受ついだばかりの
古い親しい物たちのやうに
雑然と匂はしくならんで、
ものが君の前でひろがつた。
そこで、君が事物に与へた
その新しい空間が、
君をふかぶかと事物につなぐ。
さうしてそのつながりの血が
世界へ今生まれたばかりの光なのだ。(378,379,380㌻)
■一九三九年の詩(片山敏彦)
父よ ひとびとが大事(だいじ)と呼ぶものも
その殆んどが むなしい灰のやうに
あなたを隠して立ち迷ひ
或る晴れた夕ぐれに あなたの岸辺で
音もなく沈んで 跡かたが無い。
父よ ともすれば忘れがちな
遥かな日の空の奥に
名の無い喜びのなかに浮んでいた
ささやかな ほのかな薫りに似た
あのものを 心のすべてで今宵呼びます。
今はまだ無いものが、この夕暮れの
夢の思ひのなかに 確かに生きて
それが 心に充ちて息づくと
まだ知らないものの大きな横顔を
わたしは見ます。
不安な手で 習はしのやうに
握りつづけていたもの達を
わたしはそのとき手ばなすのです
弱っている蛍を放すときのように。
すると 心に新しく生まれ出た 呼吸するひろがりを
渡り鳥のやうに 充たしに来るものがある。
眠っていた遠い日の空の にはかに見ひらいた眼ざしや
麓の路の まがり角で あのときのわたしのために
歌ふ啓示だった 一本の明るい樫の木や
そして わたしが死に近づいていたときに
心を照らした白い花や
そして 明けがたに書いた手紙の中に
羽ばたいていた 自分の心のわななきや
そんなものらが 時の奥から渡つて来て
この心に 新しい巣をかけます。
すると 父よ、あの大きなものの遥かな横顔は
青い海です。歌っている 深い海です。
それで わが心の渡り鳥らは羽ばたいて
わたしの鈍い現実をかいくぐり
屈折する弧を描いて飛んで
あの海の きらめく波の穂を慕って行く……
おお 渡り鳥、あの波の穂の兄弟たち……(380,381,382,383㌻)
■詩の心(片山敏彦)
われわれ人間は神の眠りである――リルケ
どこから来てどこへ行くかを
知ることのできない人生の
短くて長く 長くて短い道程で
人間の詩の心は
或る一つの純粋さの重みを
不思議な預りものとして荷ひ
この重さを
めぐまれたことばによつて
美の炎の
軽さに変へる。
その炎の中から 新しい
不死鳥が飛び立つと
その鳥のつばさのそよぎが
永くこだまして
そのこだまから 星々の
円天井が生れ出る。(388,389㌻)
『明治 大正の詩』日本の詩 ほるぷ出版 2007年5月27日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「私が愛するレオニイ(註,彼の愛人,老寡婦)寝ようとする前に,ヴァンサンヌで電車を待つ間に,共同椅子(バンク)にかけながらお前が言った意見に就いて一言書こうと思う.お前は私が何事にも價しない様に言ったけれども,然し少なく共滑稽な人間(ブーフオン)として用立っている筈である.―(中略)―クリストも『総ての草木その他のものは無用として創造されず』と云っています.私達は生み殖えさねばならないのですが,お互いの年齢ではモウその事は考えなくてもいいでしょう.―(中略)―あなたとしても今少し私を冷酷に扱わないで下さい,私があなたを愛撫せんとする時に不愉快らしくして,私の申出に対しては厭々か,でなくば苦情の他は答えないで,私の心を裂く様な思いをさせない様にして下さい.―(後略)
愛情に充ちたる千の接吻を.
アンリイはお前の事で一ぱいだ. ア・ルッソオ」(足立源一郎氏訳による)
『みずえ』1952年3月号10頁 2007年6月2日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■再三,僕が人に話すのは,芸術は活写なりというふるいことばである。あらゆる知性的な奇工は淪(ほろ)びても、活写だけは,芸術の力としてのこりうるのだ。トルストイの倫理的な苦悩よりも,『アンナ・カレーニナ』のなかの溌剌とした競馬場の馬の活写はのこるのだし、やはり、馬だが、ベラスケスの「ブレダ城の降伏」の馬の,尻の毛並みにうけている光線の活写は、アバンギャルドをしのぐ、時間を超えて人の心を感動させるものを持っている。(123㌻)
『金子光晴詩集』金子光晴 思潮社 現代詩文庫 2007年6月3日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■一般に俗受けするもの、わいわい騒がれるようなものは最初から読まないことである。もっとあっさり言えば、出版された最初の年が、その存在の最後の年となるようないっさいの出版社を唾棄することである。(ショーペンハウレル)(19㌻)
■あらゆる宗教の本質は,私はなんのために生きるのか,私を取り囲む無限の世界に対する私の関係は何かという問いに対する答えにのみ存する。きわめて高尚な宗教から,最も野蛮な宗教に至るまで,およそいかなる宗教も,その根底にそのような,己れを囲繞(いにょう)する世界と〝我〟との関係の樹立というものを持たぬものはない。(モリス・フリューゲル)(21㌻)
■われに向かいて〝主よ主よ〟と言う者、ことごとく天国に入るにはあらず、天に在(ま)しますわが父の御旨(むね)を行う者のみ入るべし。(「マタイ伝」第七章二一節)(22㌻)
■燃える力、光を放つ力がないならば、せめて光を消さぬようにするがよい。(23㌻)
■智慧の掟を知る者も、これを愛する者に劣る。これを愛する者も、これを実践する者に劣る。(中国の智慧)(23㌻)
■善き人々は、あえてそのことを意識せぬまま互いに助け合っている。しかしながら悪しき人々は、意識的に互いに敵対行動をとるものである。(中国の俚諺)(25㌻)
■ある事柄について自分であらかじめ思索しないうちに、それについて書かれたものを読むのも、有害と言わねばならない。なぜなら新しい材料と一緒に、それに対する他人の見方,他人の態度がその人の頭のなかにまぎれ込むからである。もともと人間には怠惰と無関心から,自ら努力して思索するよりも、できあいの思想を受け入れて用をすませようという習性があるから、ますますその確率が大きい。この習性がやがて根を張ると、もはや思想は溝に注ぐ小川のように、ただ一定の通路を進む。そうなると、自分自身の新しい思想を発見することは二重に困難になる。独自性のある思想を持つ学者がめったにいないゆえんもそこにあるのである。(ショーペンハウエル)(44㌻)
■教育の基礎は,万有の本源に対する関係の樹立と、その関係から生ずる行動の規範の樹立である。(46㌻)
■われわれは一人一人自分自身で、自分と世界および神との関係を樹立しなければならない。(53㌻)
■なくてかなわぬ唯一のこと、それはすべてを神に委ねることである。自らの姿勢を正し,この世の絆、わが身の運命(さだめ)を解きほぐすことは、神に任せることである。消滅であろうと、不滅であろうと、かまわぬではないか。いずれにせよ来るべきものが来るのだ。そして来るものは、必ず善であろう。人生を生き抜くためには、善に対する信仰以外なに一つ必要ではない。(アミエル)(54㌻)
■天と地は永遠である.なぜ永遠かと言えば、それはもともと自分のため存在しはじめたものではないからである。だからその存在は永遠なのだ。そのように聖人も己を脱却することによって永遠となる。彼は永遠となることで強力無比となり、己に必要ないっさいのことをなしとげる。(『老子』)(74㌻)
■もしある人が、自分の家に屋根を葺いたり、窓を取りつけたりせずに、雨風のたびに外へ飛びだして、風に吹かれ雨に濡れながら、雨風に向かってお前は右に行け、お前は左に行けとどなっているのを見たら、われわれはその人のことを、あれは気が狂っているのだと言うにちがいない。しかしながら人々が悪を行うのを見て、腹を立てて彼らを罵り、自分の内の悪を根絶する努力をいっさいしないならば、われわれもその狂人と同じことをしているわけである。自分の内の悪を避けること、つまり屋根を葺き、窓を取りつけることは、われわれにもできることだけど、世のなかの悪を根絶することは、雨雲に命令することと同様、困難なのである。もしも人々が人を教える代わりに、ほんの稀にでも自分自身を教えるようにすれば、世の中の悪は次第に少なくなり、人々の暮らしは次第によくなるであろう。(78,79㌻)
■小さな悪事を行っても、これぐらい大したことではないなどと絶対に考えてはいけない。「今日はしたけれど、もうこれからしない」と言う。そんなことは嘘である。一度やったことをもう二度とやらないというのは、なかなかできることではない.善事の場合にも「別に努力する必要はない。これくらいへちゃらで、やろうと思えばいつでもやれる」などと言ってはいけない。そんなことは思ってもいけないし、言ってもいけない。ほんの小さな善事でも、必ず善き生活を築くための力を与えてくれる。悪事が必ずその力を減殺するように。(80㌻)
■自愛からは、傲慢と貧欲と淫欲と妬みと瞋恚と怨恨とかが生じ、神に基づく万人の生の一体感からは、温柔、自己棄却、および内的平安――すなわち地上の苦しみを何者によっても破壊されない至福へと昇華せしめる、純粋な法悦が生ずるのである。(83㌻)
■憤怒がどんなに他人にとって有害であろうと、それは何にもまして憤怒する当人にとって有害である。憤怒は必ずそれを呼び起こした相手の行為以上に有害なのだ。(89㌻)
■生命に導く道は狭く、これに入る者は少ない。なぜ少ないかと言えば、大多数の者は、みんなが歩く広い道へ入るからである。本当の道は狭くて、一人ずつしか入れない。それに入るためには、群衆と一緒に歩くのでなくて、仏陀とか孔子とかソクラテスとかキリストとかといった孤独な人のあとについてゆかなければならない。彼らこそ自分自身のために、そしてまたわれわれみんなのために、次々と同じ狭い道を開いていった人々なのである。(リュシー・マローリーによる)(91㌻)
■大事なのはわれわれが占めている場所ではなくて、われわれが進んでいる方向である。(ホルムス)(92㌻)
■三つの道によってわれわれは、叡智に達することができる。第一は思索の道で、これは最も高尚な道である。第二は模倣の道で、これは最も安易な道である。第三は経験の道で、これは最も苦しい道である。(孔子)(112㌻)
■われわれの住む大地全体が地主たちの私有財産で、彼らが地上権を持つものとすれば、すべて、それに対するなんらの権利を持たないことになる。したがって土地の非所有者は、地主たちの承諾を得てはじめて地上に住むことができるわけである。彼らは地面に両足で立つ権利さえ、地主たちの承諾を受けてはじめて獲得することになる。それゆえ、もしも地主らが彼らに足を置く場所を与えようとしなかったら、彼らは地球から放りだされねばならないであろう。(ハーバート・スペンサー)(115㌻)
■もしも君が、自分の外被である肉体を放棄しなくてはならないときが、つまり死ななければならないときがいつやって来るかわからないということに深く思いを馳せ、胆に銘じて忘れないならば、君にとって公正を守り、正義に生きることがより容易になり、己の運命を甘受することもとり容易になるであろう。それゆえ君はただ、その日そのときのすべての行為において、正義を逸脱しないように、その日そのとき君の上にふりかかる運命を穏やかに受け止めるように努めるがよい。
そのように生きれば――君は世界の人々のいかなる蔭口にも、誹謗にも、誘惑にも泰然たる態度で臨みうるし、彼らのことなど考えもしなくなるであろう。そしてまた、君を襲うかもしれないいろんな不幸など物の数でもなくなるであろう。なぜならそのような行き方においては、君のあらゆる願望は、神の御旨を遂行しようという願望に融合統一されるからである。神の御旨の遂行は、君にとって常に可能なのだ。(マルクス・アウレリウスによる)(127,128㌻)
■善良であることが習慣になってしまった状態ほど、自分の生活や人々の生活を美しく飾るものはない。(132㌻)
■何を考えなくてもいいかをしることは、何を考えなければならないかを知ることよりも、むしろ大事なくらいである。(140㌻)
■われわれの習慣になった思想は、われわれの脳裏でわれわれの接触するすべてのものに、その思想特有の色彩を与えるものである。だからそれらの思想が間違っていれば、それは最も崇高な真理さえ引き歪めてしまう。習慣的な思想によって周囲に形成された雰囲気というものは、われわれ一人一人にとって、いわばわれわれの住む家よりも根強い。それはちょうど、蝸牛がどこへ行くにも自分の身につけている殻のようなものである。(リュシー・マローリ)(141㌻)
■三つの誘惑が人々を苦しめる。肉欲と傲慢心と富への愛着とである。そこから――人々の苦しみがうまれる。肉欲や傲慢心や富への愛着がなければ、すべての人々は幸福になれるであろう。どうしたらそのような恐ろしい病気を免れることができるだろうか? それらを免れることは大変難しい。というのは、何よりもまずその病根が、われわれの本性のなかに潜んでいるからである。
ただ一つ、それらを免れる方法がある。それは一人一人が自分自身に働きかけることである。人々は往々にして、法律とか政府とかいった代物が力を藉(か)してくれると思いがちであるが、そんなことはけっしてない。なぜなら、法律を起草したり民衆を支配したりする連中もまた、われわれと同じように肉欲や傲慢心や物欲の誘惑に苦しんでいるだからである。だからして、法律とか政治家とかをあてにするわけにはゆかない。それゆえ、人々が幸福のためになしうるただ一つのことは、自分のなかの肉欲や傲慢心や物欲をなくすことである。一人一人がそうした自己改革を始めないかぎり、いっさいの改革は不可能である。(ラムネによる)(146㌻)
■奇妙な話しではないか! われわれは外部からの悪には、換言すれば、他人から蒙る悪、どうにも排除できない惡には憤慨するけれども、いつも自分の支配下にある自分自身の惡とは、いっこう闘おうとはしない。(マルクス・アウレリウス)(147㌻)
■人を裁くことなかれ、されば汝も裁かれじ。人を裁きしごとく己れも裁かれん。人を量りたる秤にて己れも量られん。なにゆえ兄弟の目にある塵を見て、己が目にある梁木を認めざるや。あるいは己が目に梁木あるのに、なにゆえ兄弟に向かい手「汝の目より塵を取り除かしめよ」と言うや。偽善者よ、まず己が目より梁木を除け。されば兄弟の目よりいかにして塵を除きうるかを悟らん。(「マタイ伝」第七章一~五節)(150㌻)
■最も偉大な真理は――最も簡潔である。(174㌻)
■ひたすらに神を愛し、ひたすらに己れの我を憎むべきである。(パスカル)(181㌻)
■われわれは自分のことを思い煩い、自分のことにかまけることが多ければ多いほど、そして自分の生命を守ろうとあくせくすればするほど、ますます弱くなり、まします不自由になる。反対に自分のことを思い煩うことや、自分にことにかまけることや、自分の生命を守ることにあくせくすることが少なければ少ないほど、ますます強く、ますます自由になる。(182㌻)
■情け深い人は金持にはならないし、金持は情け深くはない。(満州の諺)(228㌻)
■往来に追い剥ぎが出没するようなとき、旅人は一人では旅をしなくなる。彼は誰か護衛の付いた人が通るのを待ってその人と一緒になり、それではじめて追い剥ぎたちを恐れなくなる。
賢い人は自分の人生行路においても、そのように振る舞う。彼は自分に向かって言う。
「人生にはいろんな災害がある。その災害からの防衛者をどこで探したらいいだろう。どんなふうにしてその災害から免れたらいいだろう? 安全に旅行するためには、どんな道連れを待ったらいいだろう? 誰のあとについていったらいいだろう? この男だろうか、それともあの男だろうか? 金持についてゆこうか? 位の高い人についてゆこうか? それともいっそ皇帝についてゆこうか? でも彼らは私を保護するだろうか? 彼ら自身も略奪されたり、殺されたりして、ほかの人たちと同じように災害に陥るではないか? それにまた、ひょっとしたら私の道連れ自身が、私に襲いかかって私から略奪するかもしれない。私を保護してくれ、けっして私を襲ったりしない強力で信頼のおける道連れを、どんなふうにして探したらいいのだろう?」
そうした信頼のおける道連れが一人だけいる――それは神である。災害に陥らないためには、神についてゆかねばならない。では、神についてゆくというのはどういうことか? それは神の欲したまうものを欲し、神の欲したまわぬものを欲しないことである。ではどうすればそれができるか? 神の律法を理解し、それに従うことによってである。(エピクテトスによる)(240,241㌻)
■われわれはみんな野獣を馴らす獣使いのようなものである。そして野獣とは、一人一人のなかにある欲情である。野獣たちの牙や爪を抜き取り、轡をはめ、訓練を続けて、たとえ咆えはしても従順な家畜に、人間の召使いにすること――そこに自己教育の課題があるのである。(アミエル)(252㌻)
■君が自分の知る真理を遵奉(じゅんぽう)してはじめて、新たな真理が啓示されるであろう。(リュシー・マローリ)(281㌻)
■善き人は、自分の身に何が起きるかということよりも、自分のなすべきことをなすことに、より心を配る。「なすべきことをなすのは自分の業で、わが身に何が起きるかは、神の業である。たとえ私に何が起きようとも、私がなすべきことをけなすのを妨げうるものは何もない」とその人は言うであろう。(282㌻)
■失うべき何物も持たない人こそ、最も富める人である。(中国の諺)(284㌻)
■もしもある人が、そもそもどんな質問をしたらいいかをわきまえているならば、もうそれだけでその人が聡明な人であるという紛れもない証拠となる。なぜなら、もしも質問自体が愚劣で無益な答えを求めるなら、それは、その質問をした人自身の恥であるばかりでなく、質問された相手もうっかり愚劣な答えをすることになるからである。そしてその結果、昔の話にあるように、一人が牡山羊の乳を搾れば、一人が篩(ふるい)を当てがうという滑稽な場面が生ずるのである。(カント)(293㌻)
■人を恐れる者は神を恐れない。神を恐れる者は人を恐れない。(337㌻)
■われわれはみんな、他人のなかに、自分自身の罪悪や欠点をいろんな悪癖やをはっきり写しだす鏡を持っている。しかしその場合、われわれのほとんどが、自分が写っている鏡を見て、ほかの犬だと思って吠える犬のように振る舞うものである。(ショーペンハウエル)(340㌻)
■学問の数は無数であり、またどの学問にも限界というものがなくて、どこまで行っても究めつくすということはない。それゆえ、あらゆる学問において一番大事なことは、どんな事柄が一番大事で、どんな事柄がそれほど大事ではないか、さらにどんな事柄がそれほど大事でなく、どんな事柄がもっと大事でなく、どんな事柄がもっともっと大事でないかを知ることである。それを知ることがなぜ大事かと言えば、どうせ何もかもを学ぶことはできないのだから、一番大事なことを学ぶ必要があるからである。(382㌻)
■習慣はけっして善とは言われない。たとえそれが善き行為の習慣であっても、そうである。善き行為も、習慣となってしまえばもう徳行とは言えない。ただ努力によって得られたものだけが徳なのである。(カント)(386㌻)
■他人に対する悪意は本人を不幸にし、相手の人々に対する善意は、車輪に差された油のように、その人の生活や相手の人々の生活を軽やかな、快いものとする。(390㌻)
■日々よりよき人間になろうと精進する行き方よりもよい行き方はなく、実際に自分がよりよき人間になりつつあることを感ずることよりも大きな喜びはない、と私は思う。これこそ私が今日まで絶えず味わってきた幸福であり、私の良心が私に向かって、これこそ真正の幸福であると語っている。(ソクラテス)(396㌻)
■汝の心に教えよ、心に学ぶな。(仏陀の箴言)(399㌻ )
■自然界の植物や動物には、善も悪もない。また生きてはいても、思想のない人間の肉体のなかにもそれはない。善と悪との差別(けじめ)が人間の心のなかに生ずるのは、その人の意識する能力によってである。人間の心には、若いころから悪との絶えざる闘争が行なわれている。そしてまた、悪との闘争の場所として人間にとって最もふさわしく、かつ、実り多いのは、まさにその場所、すなわち自分の心のなかである。そのほかの場所での闘争は人間にとってふさわしくなく、また実りも少ない。悪をもって悪に抗するなというキリストの誡めは、まさにそのことを言っているのである。その誡めは、悪との闘争の場を明瞭的確に指定している。その場所は――自分の心のなかなのだ。―後略ー(ブーカ)(400㌻)
■真に神を愛する者は、自分も神に愛されようと躍起になったりはしない。彼にとっては、自分が神を愛するだけで充分である。(スピノザ)(409㌻)
■われわれが存在する以上、神もまた存在する。それを神と呼ぼうとなんと呼ぼうと、とにかくわれわれの内にわれわれが創造したものでなくて、われわれに与えられた生命があることには論争の余地がなく、その生命の源泉を神と呼ぼうとなんと呼ぼうと、それはどうでもいいことである。(ヨセフ・マッジニ)(416㌻)
■己れの責務を果たせ。しかしてその結果は、汝にその責務を課した者に任せよ。(『タムルード』)(447㌻)
■人間の仕事に伴う決定的な条件の一つは、努力目標が遠ければ遠いほど、そしてまた自分の仕事の結果を見たがる気持が少なければ少ないほど、仕事の成功度は大きくかつ広いということである。(ジョン・ラスキン)(448㌻)
■われよりも父もしくは母を愛する者は、われにふさわしからず。われよりも息子もしくは娘を愛する者も、われにふさわしからず。また己(おの)が十字架を取りてわれに従わざる者は、われにふさわしからず。己が命を見出せし者は、これを失い、わがためにその命を失う者は、これを見出すなり。(「マタイ伝」第10章37~39節)
■我執――それは霊にとっての牢獄である。牢獄がわれわれの肉体的自由を奪うように、我執は間違いなくわれわれの幸福を奪う。(リュシー・マローリ)(466㌻)
■人を裁くことなかれ、さらば汝も裁かれじ。人を裁きしごとくに己れも裁かれん、人を量りたる秤にて己れも量られん。なにゆえ兄弟の目にある塵を見て,己が目にある梁木(はりぎ)を認めざるや。あるいは己が目に梁木あるに、なにゆえ兄弟に向かいて「汝の目より塵を取り除かしめよ」と言うや。偽善者よ、まず己が目より梁木を除け。さらば兄弟の目よりいかにして塵を除きうるかを悟らん。(「マタイ伝」第七章一~五節)(488,489㌻)
■運命に偶然というものはない。人は運命に出会うのではなく、運命を創造するのである。(ウィルメン)(533㌻)
■何よりも、天がそのうちにわれわれの過ちを正してくれるだろう、などといった馬鹿な考えを棄てることが大切である。ぞんざいな料理の作り方をしながら、神様がおいしくしてくださるだろうなどとあてにするわけにはゆかないではないか。それと同じように、もし諸君が長い年月にわったて愚劣な日々を送って、自分の生活を誤った方向へ導いてしまったならば、そのうち神様が手を伸べて、何もかもいい方向に向けてうまくお膳立てをして下さるだろうなどと期待すべくもないではないか!(ジョン・ラスキン)(540㌻)
■岸に近いところを泳いでいる者には、あの丘、あの岬、あの岸等々を目指して泳げ、と言っていい。しかし岸からはるかに遠くを航海している者には、方向を示すはるかな星や羅針盤だけが頼りである。その双方ともわれわれに与えられているのだ。(547㌻)
■〝この息子たちは私のもの、この財産は私のもの〟と、こんなふうに愚者は思う。彼自身がすでに彼のものでないのに、どうして息子たちや財産が彼のものであろう?(仏陀の教え)(550㌻)
■万人に向かって、この私のように振る舞え、と言えるように行動せよ。(カントによる)[訳注―「汝の行為の格率が、同時に万人にとっての行為の格率でありうるごとく行為せよ」―カント]
■人間は何もかもできるものではない。しかし何もかもはできないからといって、悪いことをしなければならないことにはならない。(ソロー)(601㌻)
『文読む月日(上)』トルストイ 北御門二郎訳 ちくま文庫2007年6月24日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■クリフォード様
私の展覧会の件では大変なご苦労をおかけしており、深く感謝しております。あなたのご努力にふさわしい展覧会となってくれるように心から願っております。
しかし、これだけ大がかりな準備をして開かれるこの展覧会ですので、大きな反響をよびおこすことも考えられ、そのために私としては、それが若い画家たちに、多かれ少なかれ、好ましくない影響を与えるかもしれないことを恐れております。私の絵やデッサンの全貌を、ごく短時間に、上っ面だけで見た場合、私の作品が一見きわめて容易そうな外観をもっているだけに、彼らはそれをどんなふうに解釈することでしょうか。
私はつねに自分の苦心を隠そうとしてきました。私がどれだけきびしい労働を費やさねばならなかったなどということはだれ一人考えもしないように、作品が春の軽やかさと歓びをもつよう願ってきました。それゆえ、若い画家たちが私の作品の中に単に表面的な容易さ、デッサンの手軽さだけを見てとり、これを必要不可欠なある種の努力をおこたる口実に使うようになりはしないかと恐れるのです。
最近、2、3年のあいだに私が見る機会のあったいくつかの展覧会の印象からすると、若い画家たちは、色彩だけで構成すると称する現代画家の教育にとっては不可欠の、ゆっくりした,苦しみ多い修行というものを、避けているのではないでしょうか。
この、ゆっくりした苦しみ多い仕事は、避けて通るわけにはいかないものです。実際、正しい時季に耕しかえさなかったら、庭はたちまちひからびてしまいます。季節ごとに、土地は除草し、耕さねばならないはずです。
最後に出来上がった作品とはほとんど似ても似つかないような出発点の作品、そういう作品によって、のびざかりの時期に修行することを知らないような画家は、先の見込みはありません。また、「出来あがった」画家でも、時々地面にじかにたちかえる必要を感じなくなった場合には、自己模倣におちいってどうどうめぐりをはじめ、このくりかえしそのものによって、新鮮な好奇心をすっかり失ってしまうのです。
画家は「自然」を所有しなければなりません。彼は自然のリズムと一体にならねばなりません。そこで費やされる努力によって、技術が習得され、やがてそれが、自分自身の言葉で自己を表現することを可能にしてくれるのです。
未来の画家は、自分の発展にとって何が有益なのか―デッサンであれ、彫刻でさえもーを感じとらねばなりません。彼の感情をふるいたたせる事物ーつまり、私のいう「自然」ーの中に突きすすむことによって、彼を「自然」と合一させ一体にさせるあらゆるものを感じとるのです。私はデッサンによる勉強が最も肝要だと思います。デッサンが「精神」,色彩が「感覚」からくるものならば、まずデッサンすること、精神を耕すことによって、色彩を精神の小径にまで導き入れることが必要でしょう。私は声を大にしてこのことを叫びたいのです。わけても、若者にとって、絵画はもはや冒険ではなく、名声の道への第一歩である個展をしゃにむに開こうとするのが目標であるような事態を見るだけに、そのことを強調したいのです。
若い画家は、長い修業の期間を経たのち、色彩に手をつけるべきだすー単なる描写の色彩のことではありません。そうではなくて、内的表現の手段としての色彩のことです。それをやれば、彼は自分の描くあらゆる影像、いや、あらゆる象徴さえも、事物に対する彼の愛の反映となることを期待できるでしょう。彼が純粋に、自己をいつわることなく修業してきたならば、彼はこのことについて自信をもっていいのです。そのときには、彼ははっきりした認識をもって色彩を用いるでしょう。彼は色彩を、彼の感情から直接溢れ出る、未分化の、完全に隠されていた、自然の意図に沿って、画面に配置するでしょう。これこそトゥールーズ=ロートレックをして、その生涯の終わりにのぞんで「とうとう、私はこれ以上どうデッサンしたらいいかわからなくなってしまった。」と叫ばせたののなのです。
かけだしのがかは、自分がハートで描いていると思います。完成の域に達した画家も、同様、自分がハートで描くと思います。正しいのは後者だけです。というのも、彼は訓練と規律によって、衝動を受けとめ、それを、少なくとも部分的には、隠すことができるからです。
私はえらそうなことを言うつもりはありません。私の展覧会が、これから始めようとしている人々にまちがった解釈を与えないよう願っているだけです。私は人々に、色彩に近づくのは納屋の戸口から入るのとわけがちがうということを知ってもらいたいのです。それはそれにふさわしいきびしい準備が必要だと言いたいのです。しかし、何よりもまず明らかなことは、歌い手がいい声を、必要とするように、画家は色に対する素質をもたねばなりません。この素質なしには、どうにもならないのです。だれでもがコレッジオのように「吾もまた画家」と宣言するわけにはいかないのです。色彩画家(コロリスト)というものは単なる木炭デッサンでも、はっきりとその姿をあらわすのです。
クリフォードさん、これで手紙を終えます。あなたがしてくださっているご努力に対する謝意を述べつつ、筆のおもむくままに、デッサン、色彩、ならびに画家の修業における規律の重要性についての私の考えを開陳いたしました。もしこれらの考えがだれかにとって有益であるとお思いでしたら、この手紙をご自由に利用くださって結構です。
敬具
『アンリ・マティス(ヘンリ・クリフォードへの手紙、1948年2月14日ヴァンス)』大岡 信 訳 2007年7月18日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■―― 物の存在を認むる事に依って、自分も始めて存在する。
存在によりて存在する意識の心は、只自分の外には何物もないけれども、物の存在を認むる事は、自分なる事ではない、物なる只其事のみである。自分なる者があっては、眞の物は未だ認められない。物認められねば、自分の存在がない。自分を虚にして始めて物の存在を認め、認めて始めて眞の自分が存在して来る。
眞存在の心は、一元と脈動した意識である。刹那々々のみを、自分たり得る心である、強ひて説明すれば消滅する心だろう。(以下略)――坂本繁二郎
まるで禅問答のような文章をまだ二十九歳の若者が理路整然と述べているので、本当に恐れ入ってしまうが、ここにはそれ以後の坂本繁二郎の制作思想が集約されている。つまり、自己の意識を滅却して〝事物の存在〟をはっきりと認識することにより、己の存在も見えてくる、物の存在と己とを、一元化すること、それが自分がめざしている芸術の道である、と彼は説いているのだ。(175㌻)
『海を見つめる画家たち』 大久保守著 鳥影社 2007年7月22日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■「貴方の詩集『防風林』を送っていただきました。有難く御礼申上げます。未だよく読みませんが夜の静かな折読ませていただきます。孤独ななかでこんなに気取らないで極めて平易でそれでいてするどいまた骨節のあるものをボクに見せてくれようとしています。最初のものでしたでしょうがそうでない感じがしてボクはおずおずします。親しく、貴方の手をとるように思います」(三野混沌の斉藤庸一の詩集への礼状のはがきの文面)(29㌻)
■二つのうち一つを断ち切って喋らずに進むことの出来なかった者であります(草野天平)
おうい雲よ ゆうゆうと 馬鹿にのんきさうぢゃないか(山村暮鳥)(29㌻)
■ おなじく(山村暮鳥)
おうい雲よ
ゆうゆうと
馬鹿にのんきそうじゃないか
どこまでゆくんだ
ずっと磐城平(いわきたいら)の方までゆくんか
ある時
雲もまた自分のやうだ
自分のやうに
すっかり途方にくれているのだ
あまりにあまりにひろすぎる
涯のない蒼穹なので
おう老子よ
こんなときだ
にこにことして
ひょっこりでてきませんか(64㌻)
■ 地の果 (三野混沌)
みんなめいめいのみちをいく
たれもいなくなった
たれもいなくなったところに
ひろびろと土地が拡がっていて
果ての方に荒地さえ黄色に見える
ことりの巣立ったあとの空しいとこのように
私もまたいつかここを離れていく
けれどもここで死ぬ
ここで仕事をし さようならする
クサや木や それらの果実に別れて
私はもう何もしなくなる
何も考えたりもしない
語ることもしない
そしてより一層 ここは寂しくなろう
ウツギが小さく立っている
エダ葉の先に丸い花咲くだろう(106㌻)
■ 詩(遺稿) 三野混沌
たいそうのろのろにみえるぎちぎちだ
死んでしまえといえば死んでもいいほど
そうして どういうものか分からなくなる
そのふあんが口をあけてあるいている
おおいくさはらの中のま白い尾花が
ふらふら動くのとかはりはない
雷雲のしたではなおさらだった
自分のかんがえを歌うべきでない
自分はいつでも客だ
つくりごとでもねたみでもない
かたらない おもしろくない
ま夏のあつい野中のことだ
そこを いつも もっている
どんなことがあっても ぽかんとする
そこが血をふきだした
牛蠅がさした
シャツのやぶけたところからだ(112㌻)
■ 柱時計 (淵上毛銭)
ぼくが
死んでからでも
十二時になったら 十二
鳴るのかなあ
まあいいや
しっかり鳴って
おくれ
死算
じつは
大きな声では言えないが
過去の長さと
未来の長さとは
同じなんだ
死んでごらん
よくわかる(130㌻)
■「しばしば、自殺をおもい立つのであったが、そのたびに詩人は未練がましく、もう少し書きたいという気持をどうすることも出来ないで、とうとう自殺したつもりで生きることに決めたのである。この決心は、ぼくから、見栄も外聞も剥ぎとってしまって、色色なことを僕にさせることができたのである。それは職歴にも反映しているようだ」(山之口貘 現代詩人全集より)(141㌻)
■静かな、こころよいブルタイニュの薄明りの中に、
僕らは口数もきかず、黙々と坐っていた、あんたのおっ母さんが叱口をいひに
やってくるまで、
でも、もう草には露が下りていたものね。でも僕は知っていた、あんたの心臓
が、おどろかされて、まごついている鳩のやうに波うっているのを。
あんたは憶えているかね、イヴォンヌ!
この恋のはじめの弱いはにかみを。
アーネスト・ダウスン 火野葦平訳(151㌻)
■ 秋の夜の会話 (草野心平)
さむいね。
ああさむいね。
虫がないているね。
ああ虫がないているね。
もうすぐ土の中だね。
土の中はいやだね。
痩せたね。
君もずいぶん痩せたね。
どこがこんなに切ないんだろうね。
腹だろうかね。
腹とったら死ぬだらうね。
死にたかあないね。
さむいね。
ああ虫がないてるね。(234㌻)
■『(略)これがですね、すでに芭蕉が日本では、奥の細道という言葉によって象徴している。それは、
この道や 行く人なしに 秋の暮
この有名な文句は、これは芸術の極地を、誰も行かない道、今の、
われのゆく道もありなむ、
たぐいなく軽ろく巧みなる道、
われらともどもにうけがうべきそこはかの道、
あるかないかの細道です。しかしそれが非常に大事なんです。つまり、
ほほえみの……
ほほえみはすぐ消えるもの、つまりさっき言ったように非常にtransientなもの、早く、すぐ消えて行くもの、
ほほえみのごと、さりげなき、不実なる道。
これは芸術の、あるいは芸術家のみち、非常にむつかしい。芭蕉も「軽み」「細み」ということをいいました。俳句は軽く細く、重かったら俳句にならない。その「軽み」ということは、非常に大事なことなんでありますが、これは芸道の極地だと思うんであります。これは現代的エリオットも、芭蕉的な境地をこういう言葉で表していると思うのであります。』(深瀬基寛 昭和三十四年十月「歴程」十月号の「悦しき知識」―停年講義より)(350、351㌻)
■『―芸術とは或る意味で芸術家の宗教であり、……。詩人が在るところのもの、いな、いつの時代にもかって在りしところのもので、どこまでも在ろうとするためにのみ、彼がみずからをまもらざるを得ないという時、詩人のヴァニティを以てどうして詩人を責めることができよう。――人間を裏切った罪を問うべきは芸術にではない。人間にこそ、芸術を裏切った罪が問われるべきである。』(深瀬基寛 昭和三十三年十一月十五日発行、筑摩書房刊「現代の詩心」の中の「詩の道と宗教の道より)(354,355㌻)
■「岡倉天心の先生でね、アメリカの人でフェノロサという人がいる。この人が明治の美術を批評しているんだ。詩もやった人だよ。この人が言ってるんだが、すべては『見る』ことから始まっているというんだ。そして私たちはすでに漢字のセンスを失ってしまったのだが、彼は『見る』の『見』という字は、上は目で、下は人間の足だというのだ。右足は跳ねている、左足は蹴っている、土を蹴って跳ねている二本の足の上に目があるというのだ。走りつつある目、活動しつつある目、人間が動いている作用を見ている目だというのだ。見るという動作は、象形文字で、どう表わしているかというのだ。日は太陽で、木は樹木だという、単なる伝統の約束、言葉だけではなくて、漢字の形、フォルムを、見るわけだ。何千年前の誰かが考えて作ったんだけれども、漢字の形はそのまま詩になっているのだ。死んだ目、魚の目で見ることは、見るではない。土を蹴って飛んでいる二本の足の上に目があるというのだ。直覚的体験、感じられたそのままの内面の流れが一じ一句になって詩になるのでなければいけないのでないかね」(深瀬基寛)(358㌻)
■『―略―。追憶がおほくなれば、つぎにはそれを忘却することが出来ねばならぬだろう。そして、ふたたび想ひ出だけは何のたしにもならぬ。追憶が僕らの血となり、眼となり、表情となり、名まへのわからぬものとなり、もはや僕ら自身と、区別することが出来なくなって、初めて、ふとした偶然に、一篇の詩の最後の言葉はそれら想ひ出のまんなかに想ひ出のかげからぽっかりうまれて来るのだ』(昭和十六年十一月一日発行、白水社刊「マルテの手記」大山定一訳より)(360㌻)
■家はもらぬほど、食事は飢ぬほどにてたる事也,是仏の教、茶の湯の本意也,水を運び、薪をとり、湯をわかし、茶を立てて、仏にそなえ、人にもほどこし、吾ものむ,花をたて香たく、みなみな仏祖の行ひのあとを学ぶ也。(利休居士)(372㌻)
■茶は服のよきように点て、炭は湯の沸くように置き、花はその花のように活け、さて夏は涼しく、冬は暖かに、降らぬとも傘の用意、相客に心せよ。(利休居士)(372㌻)
■深瀬さんが何度もいったり、書いたりしているエリオットの「たぐひなく軽ろく巧みなる道、われらともどもうけがふべきそこはかの道、ほほえむごと、手を振るがごと、さりげなき、不実なる道」と、「この道や行く人なしに秋の暮れ」の芭蕉の「奥の細道」が、同じ「軽み」「細み」の芸術の道だという意味が、見えはじめてくる。唐木順三氏の『千利休』によって、「能」の世阿弥の「姿を善く見するは心なり」の「さび」から、「茶」の利休の「夏ハいかにも涼しきやう、冬ハいかにも暖かなるやうに、炭ハ湯のわくやうに茶ハ服のよきやうに、これにて秘事ハすみ候」の「わび」へ。そして芭蕉の「物の見へたるひかり、いまだ心にきえざる中にいひとむべし」「命ふたつ中に活けたる桜かな」の「さび」へ至る、日本の芸の「こころ」の伝承を知って、私は、深瀬さんの長い談話を貫いていた「そこはかの道」への考え方がわかりかけてくる。(374㌻)
■ 桜 (岡本弥太)
おたっしゃでいてください
そんな風にしか言へないことばが
さくらのちるみちの
親しい人たちと私の間にあった
そのことばに
ありあまる人の世の大きな夕日や涙がわいてきた
私は
いまその日の深閑と照るさくらの花のちる岐路に立っている
おたっしゃでいて下さい
私はその路端のさくらの花に話かける
さくらは
日の光に美しくそよいでいる(398㌻)
■ われもゆく道もありなむ、
たぐいなく軽ろく巧みなる道、
われらともどもにうけがうべきそこはかの道、
ほほえみのごと、手を振るがごと、さりげなき、不実なる道。
(T・S・エリオット 「なげく少女」より)(424㌻)
■「…俗人のなりわいの、普通の人間のくらしの損得の毎日を渡ってゆく道ではない。俗人でもない。かといって仙人でもない。悟りきった道でもない。その仙俗ふたつにわたってしまって、詩というものは、ごくふつうの人の使う言葉を使うんだが、俗にいて俗でないところ、悟れなくて迷っていて、なお悟れない。その世界に入ってしまって、わかりきってしまえば仙だけれども、それでもない、俗の範疇の言葉でもないし仏教やキリスト教の言葉でも語れない。不実なる道というのはね、信仰なきというのかね。帰依していない、帰依なんかかんたんにできない。実にすっとあらわれて、ふっと消えてしまう刹那的なものを追っていて、追いつめようとしていて、その一瞬のものをかたちにしようとしている。何ものにもしばられない道だ。その見えてくる淡い光の線のようなものが見えるという、一心不乱のこころは信仰や観念に偏ったら見えないものだ。どうも私も、よくわからんけれども、どうもこのへんでないかと思うのだよ」(深瀬基寛)(425㌻)
『詩に架ける橋』 斎藤庸一著 五月書房 2007年9月1日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■己れのために、宝を地上に積むことなかれ。ここにては虫と錆とに損なわれ、盗人に押し入られ盗まるるなり。汝ら己れのために、宝を天に蓄えよ。かしこにては虫と錆とに損なわれず、盗人に押し入れられず、盗まれざるなり。汝の宝のあるところに、汝の心もまたあらん。(「マタイ伝」第六章十九~二一節)(14㌻)
■貧乏に苦しまぬようにするには、二つの方法がある。一つは自分の富を増大させることであり、もう一つは欲望を減らすことである。前者はわれわれの支配圏外であるが、後者はわれわれの支配下にある。(15㌻)
■肉体は、絶えず自己を主張してやまないものであるから、それだけ精神的努力が必要である。自分の精神を鍛錬することをやめたが最後、汝は肉体の虜囚となってしまう。(18㌻)
■病人がまるで生きることをやめて、病気治療だけに専念したりするよりも、むしろ不治の病の場合にしろ、治療可能な病気の場合にしろ、病気なんか無視して普通の生活をするほうが、たとえそのために生命(いのち)が縮まっても(縮まるかどうか大いに疑問だけど)、そのほうがまともに生きることであって、絶えず自分の肉体のことを恐れ思い煩うこととは違うだけに、ずっと有利と言えるであろう。(21㌻)
■病気を恐れず、治療を恐れるがよい。有毒な薬を飲んだりするという点で治療を恐れるというのではなくて、病気の結果、自分は道徳的要求から解放されていると考えがちだという点で、治療をおそれるがよい。(22㌻)
■神とは何ぞや?と尋ねられるならば、私は答えよう。神とは―私が自分をその一部として意識する無限者であり、全体者である、と。(44㌻)
■どんなものでも顕微鏡や望遠鏡で見ると、ごくつまらないものになってしまう。(ソロー)(51㌻)
■天与の資質を与えられた人々は、それを、肉体的な幸福や、世俗的な幸福や、人を支配し人より上に立つことと交換しはしない。(ピョートル・ヘリチーツキー)(71㌻)
■五歳の子供から私までは、ほんの一歩である。生まれたばかりの赤ん坊から五歳の子供までの距離は、恐ろしく遠い。胚児と生まれ立ての赤ん坊のあいだには―深淵がある。未存在と胚児とのあいだには深淵どころではなく、そこには人智の捕捉できない謎がある。(84㌻)
■君が十日間寝たっきりでいて、その後立って歩こうとすれば、君の足がすっかり弱くなっているのに気づくであろう。つまり、君が何かの習慣で獲得しようと思えば、それを大いに、そして頻繁に実行しなければならないし、反対に何かの習慣から離れたいと思えば、それを行わないようにしなければならない。(エピクテトス)(90㌻)
■自分の仕事を発見した人は幸福なるかな。彼にはもうほかの幸福を探す必要はない。彼には仕事があり、人生の目的があるのだ。(カーライル)(93㌻)
■死がわれわれを待ちかまえている―このことだけはわれわれは確実に知っている。〝人の一生は、部屋のなかを掠めて飛び去る燕のようなもの〟。われわれはどこからともなくやって来て、どこえともなく去ってゆく。見透しがたい暗さが後方にあり、濃い闇が前方にある。いよいよわれわれの時が来たとき、われわれが、うまいものを食べたとか食べなかったとか、柔らかい着物を着たとか着なかったとか、大きな財産を残したとか何一つ残さなかったとか、栄誉に輝いて暮らしたとか蔑まれたとか、学者と思われたとか無学者と思われたとかいったことが―われわれが神に委託された才能をいかに活用したか、ということに比べてどれほどの意味を持つのであろう。(ヘンリー・ジョージ)(95㌻)
■時は過ぎても、言葉は残る。(109㌻)
■自分の使命を認識する人は、そのこと自体によって自分の人間的価値をも認識する。ところで、自分の使命を認識するのは、ただ宗教的な人間のみである。(115㌻)
■君は仕事を完成させる義務はないけれども、それを回避してもいけない。君に仕事を託した神は、君の仕事を期待しているのだから。(『タムルード』)(118㌻)
■嵐に遭って初めて航海士の腕は発揮され、実戦の場で初めて軍人の勇気が試されるように、人間の男らしさというものは、彼が人生における最も困難で危険な状況に直面したとき初めてわかるのである。(ダニエル)(133㌻)
■人々は、自己棄却が自由を破壊すると思っている。彼らは、実は自己棄却のみがわれわれをわれわれ自身から、われわれの堕落した奴隷状態から解放することによって、真の自由をわれわれに与えてくれるものであることを知らない。われわれの欲悪煩悩こそ―最も残酷な暴君である。それに屈したが最後、われわれはその無残な奴隷となって、自由に呼吸をすることもできなくなるであろう。ただ自己棄却のみが、われわれを奴隷状態から救ってくれるのであろう。(フェヌロン)(137㌻)
■享楽的で自己満足的な思想家とか芸術家とかは、いるものではない。真にその人には使命があるかどうかに対するただ一つの疑うべからざる証拠は、自己棄却、すなわち他人に奉仕するためにその人に与えられた力を発揮することである。苦しみなくして霊の果実は生じない。
この世界に幾種類の甲虫がいるかを数えたり、太陽の黒点を調べたり、小説やオペラを書いたりするのは、個人的目的によっても可能であるが、人々に、もっぱら自己棄却と他者への奉仕のなかにのみ存在する彼らの幸福を教え、それを強く表現するためには、自己犠牲なしにはすまされない。
キリストが十字架で死んだのも宜なるかな。自己犠牲の苦悩がすべてを克服するのも宜なるかな。(138㌻)
■真理に鋭敏な人々は、自分たちに見える至高の光に一致した理解の仕方をし、その光にふさわしい生活を築こうとするが、真理に鈍感な人々は、従来の人生観、従来の生活体制に固執し、これを擁護しようとする。(140㌻)
■俺の生活は俺のものと考えている人は、謙虚ではない。なぜならその人は、誰に対しても何一つ責任はないと思っているからである。自分の使命は神に仕えることだと思っている人は、謙虚にならざるをえない。なぜなら彼は、絶えず自分はまだ充分責任を果たしていないと感ずるからである。(144㌻)
■キリストの教えを信ずる者には、一定の完成度に達するごとに、さらにより高き段階を目指す欲求が生まれ、その段階からさらにより高き段階が望まれる、といったふうに、どこまで行っても限界がない。キリストの教えを奉ずる者には、自分のうしろの、これまで通ってきた道は見えないで、いつも前方のまだ通ったことのない道だけが見えるので、常に自分をまだまだ未完成だと感ずるものである。(146㌻)
■己れの外に向かって権利を主張するよりも、己れの内に向かって義務を思うがよい。(147㌻)
■誠に誠に汝らに告ぐ、一粒の麦地に落ちてもし死なずば、ただ一つにしてとどまる。もし死すれば多くの実を結ぶ。(「ヨハネ伝」第十二章二四節)(179㌻)
■大木も初めはかよわい幼木にすぎない。九階の塔も、小さな煉瓦の積み重ねより始まる。千里の旅も一歩より始まる。自分の思想に注意せよ―思想こそ、行為の始まりである。(老子による)(220㌻)
■この世の喧噪のなか、誘惑の渦巻くなかにあっては、われわれの欲望に対する対抗手段を探求する暇はない。
君がただ一人ののとき、誘惑が存在しないときに君の目的を定めるがよい。そのとき初めて君は、君を襲う誘惑と闘うことができるであろう。(ベンサム)(222㌻)
■また他の一人言いけるは、「主よ、われ汝に従わん、されどまず家の者に別れを告げしめたまえ」と。これにイエス言えり、「鋤に手をかけて、なおうしろを顧みる者は、神の国にふさわしからず」(「ルカ伝」第九章六一、六二節)(257㌻)
■自分の生涯を自己完成のために献げてきた人は、いつも前方を見ている。立ち止まっている人だけが、自分のしてきたことを振り返って眺めるものである。(257㌻)
■己のために、宝を地上に積むことなかれ。ここにては虫と錆とに損なわれ、盗人に押し入れられ盗まるるなり。汝ら己のために、宝を天に蓄えよ。彼処にては虫と錆とに損なわれず、盗人に押し入れられず、盗まざるなり。汝の宝のあるところに、汝の心もまたあらん。(「マタイ伝」第6章十九~二一節)(261㌻)
■死すら、全力をあげて正義のために闘う人の勝利を阻むことはできない。さらば闘え、不屈の正しき心よ。幸不幸に右顧左眄することなく前進せよ。そして汝がそのために闘う正義の勝利を信ずるがよい。滅びるものはただ不正なもののみであり、正しきものの負ける道理はない。なぜならそれは汝の意思によってでなく、永遠なる神の掟によって行われるものであるからである。(カーライル)(286㌻)
■一人の人間が大勢の人々を支配する権利がないばかりでなく、大勢の人々が一人の人間を支配する権利もない。(ウラジミール・チェルトコフ)(292㌻)
■人間が死ぬことも、お金や財産を失うことも別に悲しむべきことではない。それらはもともと人間に属しているものではない。人間が自分の真の財産、すなわち人間的尊厳を失うこと、これこそ悲しむべきことなのである。(エピクテトス)(356㌻)
■受け取るときには手を伸ばすな。与えるときには手を縮めるな。汝が自らの手で稼いだものを、自分の罪の償いとして人に与えよ。与えるときは躊躇せず、与えたあとは惜しがるな。なぜなら、汝は汝のなした善に対して、何がそのよき報酬であるかを知るであろうから。(377㌻)
■ところがわれわれは世の中が悪い、世の中がよくできていないと苦情を言い、実は世の中がよくできていないのではなくて、われわれがなすべきことをなしていないのだ、ということを考えようとしません。ちょうど酔っぱらいが、あんまり酒場や居酒屋がたくさんあるから、こんなに酔っぱらったのだ、と苦情を言うようなもので、実は彼のような酒飲みが大勢いるようになったからこそ、酒場や居酒屋がふえた、というのが真相なのです。(382㌻)
■人々の生活がよくなるための方法はただ一つ、人々自身がよくなることです。もし人々がよくなれば、おのずからよき人々のよき社会が現出するでしょう。(383㌻)
■諸君およびすべての人々の救いは、罪深い、暴力的な社会革命のなかにはなく、精神革命のなかにこそあるのです。そうした精神革命によってのみ、われわれ一人ひとりは、自分のため、また人々のために人々の望みうるかぎりの最大の幸福、最良の社会を築くことができます。人間の心が求めてやまぬ真の幸福は、なんらかの将来の、暴力によって維持される社会体制のなかに与えられるものではなく、現在、われわれがどこでも、また生死いずれの瞬間でも、愛を通じて手に入れることができるものなのです。(385㌻)
■君は生きる、つまり生まれて、成長して、大人になって、老人になって、とうとう死んでしまう。はたして君の一生の目的が君自身のなかにあるでしょうか?そんなはずはありません。そこで人間は、一体なんだろう、この私は?と自問します。
答えはただ一つ、私は愛する何物かであるということです。そして最初は自分だけを愛しているように見えるけれども、しばらく生き、しばらく考えさえすれば、過ぎ去ってゆく生命、死んでゆく存在である自分を愛することは不可能であり、無益であることがわかります。私は自分を愛すべきだし、また愛していると感ずる。しかし自分を愛してみて、私は私の愛の対象が実は愛するに値しないことを感ぜざるをえません。それでも私は愛せずにはいられない。愛こそ――生命ですから。
ではどうしたらいいでしょう?他人を、隣人を、友だちを、自分を愛してくれる人を愛したらいいでしょうか?最初それは、愛の要求を満足させてくれるように思われます。しかしながらそれらの人々も、まず第一に不完全な存在であり、第二に刻々変化する存在であり、何よりも――死んでしまう存在です。一体何を愛したらいいのでしょう?
答えはただ一つ、万人を愛すること、愛の根源を愛すること、愛を愛すること、神を愛することです。愛する相手のためにでも、自分のためにでもなく、愛そのもののために愛するのです。そのことさえ悟れば、人生における悪はたちまち消滅し、人生の意味が明瞭な、悦ばしいものとなるのです。(388,389㌻)
■親愛なる諸君、われわれの生活をわれわれの内なる愛の強化に置き、世間は世間の欲するままに、つまり天が命ずるままにその道を歩くに任せようではありませんか。そうすることによってわれわれは、自分自身にも最大の幸福を受け、人々にも己れにあたうかぎりの善を行なうことを信じてください。(391㌻)
■もしも人がその真の本性を失ったなら――どんなものを持ってきても、それが彼の本性ということになる。ちょうどそれと同じように、もしも真の幸福を失ったら、どんなものを持ってきてもそれが彼の幸福ということになってしまう。(パスカル)(395㌻)
■何かいいことをしようとするたびに邪魔をするのは、「われわれはわれわれの置かれた社会的地位というものを考えないわけにゆかない」という思いである。
そうした逃げ口上を言う人の大多数にとって、自分らが実生活上、あるいは〝天の摂理によって〟置かれた地位を保持するということは、つまり彼らが自分らの財力の許すかぎり、たくさんの馬車や下僕たちや広大な家を持ちつづけるということなのである。ところが私としては、もし天が彼らをそうした地位に置いたとしたら(実際にそうであるか、はなはだ疑わしいけれど)、天はまた、彼らにその地位を放棄することを求めていると思うのである。
レヴィの地位は税金を集めることだったし、ペテロはガリレア湖畔の漁師だったし、パウロは司祭長の玄関番だった。そして三人ともその身分を放棄した。放棄すべきだと思ったからである。(ジョン・ラスキン)(398㌻)
■何人も新布を古き衣に接ぐことはせじ、補いたる布、古き衣を破りて、破れさらにははなはだしかるべし。また新しき酒を古き皮袋に入るることはせじ、しかせば袋裂け、酒流れでて、袋もまた廃らん。新しき酒は新しき皮袋に盛るなり、かくて二つながら保つなり。(「マタイ伝」第九章一六、一七節)(398㌻)
■宗教が第二義的な場所にしか占めていない人は、全然宗教を持たぬ人である。神は人間の心のなかでいろんなものと共存しうるけれども、自分が第二義的な場所を占めることには、堪えうるものではない。神に第二義的な場所を当てがう者は――全然場所を与えていないのである。〈宗教=芸術〉(ジョン・ラスキン)(408㌻)
■自分は善を行なうのだけれど不幸を感ずると言う人は、神を信じていないのか、その人が善と思っているものが実は善でないかのどちらかである。(437㌻)
■精神的生活を送る人は、年齢が増すにつれてその精神的視野が広くなり、その意識は鮮明になるが、世俗的生活を送る人は、年とともにますます愚鈍になってゆく。(『タムルード』)(470㌻)
■「それは私がまだ五十歳に充たぬ頃である。私には善良な、愛し愛される妻や、立派な子供や、私が別に骨を折らなくとも、自然に生じ、また増大して行く莫大な財産があった。私はそれ以前のどの頃よりも身内の者や友人達に尊敬され、他人に賞めそやされ、殊更うぬぼれなくとも、自分の名声が輝かしいものであると考えることが出来た。しかも私は、自分の同年輩の人々の間にめったに見かけないほどの、精神的肉体的力を持ち合わせていた。肉体的には、草刈りで農夫達におくれをとらずに働くことが出来た。智的労働では、八時間から十時間ぶっつづけに仕事が出来、その無理があとに尾を引くということもなかった」。
そんな健康で幸福であるはずのトルストイの中にきみょうにも「どう生きたらいいのか、何をしたらいいのか分からなくなるといった、生命力の停滞ともいう疑問が起きはじめた」。
〈一体なぜ、私は生きて行くのか?なぜ何かを望むのか?なぜ何かをなすのか〉もっと別な言い方をすれば〈私の生に、どうにものがれようのなく迫ってくる死によっても滅ぼされない、何らかの意味があるのだろうか?〉という疑問が現れ、疑問はますます頻繁に繰り返され、ますますしつこく解答を迫り始めたのだ。
〈よろしい、お前は、ますます増加する莫大な財産を手にするだろう。――でも、それがどうだというのだ?〉
〈よろしい、お前はゴーゴリ、プーシュキン、シェークスピア、モリエール、その他世界のすべての作家以上に名声に輝くかもしれない――でも、それがどうだというのだ〉
〈私の業績が、よしどんなものにせよ、早晩すっかり忘れ去られ、そしてなによりも今日、――でないならば明日、死がこの私をおそい、私は、元も子もなくなってしまうではないか。なのに、一体何のためにあくせくせねばならないのか?〉
〈私は何故生きているのか?〉
〈私はいったい何者か?〉
それはまさに、「この年まで成熟して心身共に発達し、人生の全展望が開ける生の頂点に達して、――さてそこで、見渡してみれば、人生には何もないし、過去にもなかったし、未来にもないであろうことがはっきりと分かって、馬鹿みたいにぼんやりとその頂点に立っている」といった心の状態であった。
だからといって、「お前は生の意義を悟りっこない。考えるな、ただ生きよ、と言っても、そんな訳には行かない。私は以前から、あまりに永い間そんな風に暮らして来すぎた」のだから。
トルストイは「自然科学から哲学まで、人間が獲得したあらゆる学問の中から、その疑問に対する説明を探した。それでもなんにもみつからなかった」。
その間、自殺の想念がごく自然に生じてきた。
「この想念が、すごく魅惑的なので、私はあわててそれを実行に移すことがないように、自分自身に対してからくりをしなければならない。私があまりに事を急ぐのを欲しなかったのは、ただ、何とかこの窮状を打開するためにやれるだけやってみたいと思ったからだ。もし打開ができなくても、死ぬのはいつでも死ねると思われたのだ」。
やがて、トルストイは茨の道を通って、その解答が、自ら不合理と考えていた、「神えの信仰」の中にあることを、それも、無学で、貧しい、素朴な、額に汗して働く、農民や労働者の信仰の中にこそあることを悟る。
しかし、「この大転換は、ある日突然に私の内部に生じたのではない。何十回なん百回と、喜びと生気、それにつづく絶望と生存不可能の意識を繰り返して、いつのまにか徐々に生の力が私に帰ってきたのである」。
「私は、神を感じ神を求めるとき、そんな時だけよみがえり、まぎれもなく生きていることに気づく」。
「かくて私の内部および周辺において、全てが未だかってなかったほど明るく輝き、そしてその光はもう決して私を離れなかった」。
「神を求めつつ生きよう」。
こうして生きる光を得たトルストイは、さらに信仰の問題を掘り下げながら、今まで書いてきた『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』などの大作を否定し、これからは「民衆とともに生き、人生のために有益な、しかも一般の民衆に理解されるものを、民衆自身の言葉で、民衆自身の表現で、単純に、簡素に、わかり易く」書こうと決意するのである。
そのようななかから次々と民話が誕生した。(507,508,509,510㌻)
『文読む月日(下)』トルストイ 北御門二郎訳 ちくま文庫2007年10月3日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■こうした色の違いが実生活で重要になることはほとんどないが、画家にとってはなによりも重要である。常識的に物の「本当の」色だと言われる色を、物は持つように見える、そう考える習慣を私たちは持っている。しかし画家はこの習慣を脱ぎ捨て、見えるがままに物を見る習慣を身につけなければならない。ここで私たちは、最大の哲学的問題の一つの原因になる、ある区別をし始めている。「現象 appearance」と「実在 reality」の区別、つまり物がどのように見えるかと、どのようであるかの区別である。画家が知りたいのは物がどのように見えるかだが、いわゆる現実的な人や哲学者は、物がどのようであるかを知りたいと思う。(11㌻)
■つまり色は、テーブルそのものに属するのではなく、テーブルと観察者、そしてテーブルへの光の当たり方に依存するのである。テーブルのその色についてふだん話しているときには、正常な観察者が普通の視点から、通常の光の条件下で見る色を意味しているにすぎない。しかし他の条件下で見える色にも何もおかしいところはなく、本当だとみなされる資格がある。それゆえ、えこひいきを避けるためには、テーブルが、それ自体としてある特定の色をしていることを否定しなければならなくなる。(12㌻)
■もし本当にテーブルが存在するのだとしても、それは直接経験されるものと同じではなく、見たり聞いたりできないことが明らかになる。実在のテーブルが存在したとしたとしても、それはけっして直接には知られず、直接知られるものから推論されなければならないのだ。ここから、非常に難しい二つの問題が同時に生じてくる。(1)そもそも実在のテーブルはあるか。(2)もしあるなら、それはどんな対象でありうるか。(14㌻)
■実在のテーブルが存在するとして、それを「物的対象」と呼ぼう。よって考察すべきなのは、物的対象とセンスデーターとの関係である。すべての物的対象をひとくくりにして「物質」と呼ぼう。それゆえ先ほどの二つの問題は、次のように言いなおせる。(1)そもそも物質のようなものがあるか。(2)もしあるのだとしたら、その本性は何か。(15㌻)
■かなり多くの哲学者たち―恐らくは多数派といえるだろう―が、心と観念以外には何も実在しないと主張してきた。このような哲学者たちは「観念論者」と呼ばれている。彼らの物質を説明する段になると、バークリーのように、物質は実は観念の集まりにほかならないと言ったり、ライプニッツ(1646-1716)のように、物質のように見えるものも、実は多少発達していないところのある心の集まりだとしたりする。(18㌻)
■事実ほとんどすべての哲学者が、実在のテーブルがあることに同意するように思われる。つまり「色、形、なめらかさなど、どれほど多くのセンスデーターが私たちに依存するとしても、それらが生じていることは、私たちから独立な何かが存在するとしても、それらが生じていることは、私たちから独立な何かが存在するしるしである。そしてそれはセンスデーターとはまったく異なるのだが、しかし実在のテーブルと私たちが適切な関係にあるときには、いつでもセンスデーターの原因になると見なされているものである」ということは同意されるのである。(19㌻)
■ある内在的な本性を持ったテーブルが存在し、見ていないときにも存在し続けているのか。それとも想像の産物にすぎず、長い夢のテーブルでしかないのか。これはとてつもなく重要な問題である。なぜなら、対象が[私たちが知覚することから]独立して存在すると確信できないなら、他者の身体についても確信できなくなる。さらには、その身体を観察する以外に、他者に心があると信じる理由はまったくないため、他者の心についてはなおさら確信できなくなるからだ。(22㌻)
■センスデーターに対応する対象があるという本能的信念は一向に弱まりはしない。この信念は何の問題ももたらさないばかりか、かえって経験の説明を単純かつ体系的にするので、それを拒否すべきだとするまともな理由はないと思われる。それゆえ、わずかに夢に基づく疑いが残るものの、外界は本当に存在し、知覚され続けることにはまったく依存せず存在し続けると認めてよいのである。(31㌻)
■哲学は、最も強く抱かれている本能的信念から初め、ひとつひとつ取り出してそこから余計な交ざりものをそぎ落としながら、本能的信念の階層構造を示さなければならない。そして最終的に提示される形式では、本能的信念は衝突しあわず、調和した体系をなすことを示さなければならない。他と衝突するということ以外に本能的信念を退ける理由はないのだから。調和した体系をなすことが分かれば、本能的信念の全体は受け入れるに値するものとなる。(32㌻)
■特定の道を何度も通った馬は、別の方向に進ませようとすると抵抗する。いつも餌をくれる人を見ると、家畜は餌がもらえるものと期待する。「いつもと同様のことが起るだろう」と期待しているわけだが、知ってのとおり、こうした幼稚な期待が裏切られる可能性は、非常に高い。ひよこのときから毎日欠かさず餌を与えてきた人も、最後にはかわりにニワトリの首をしめてしまう。ここから分かるように、「自然の斉一性 the uniformity of nature」についてもっと洗練された考えを持っていれば、それはこのニワトリの役に立ったことだろう。
しかし裏切られやすいにもかかわらず、それでも現にこうした期待は抱かれる。あることが何回も生じたという、ただそれだけのことが原因となって、動物も人間も、また同じことが生じるだろうと期待するようになる。このように、私たちは本能を原因として「太陽は明日もまた昇る」と信じるようになるのだが、だからといって、思いがけなくも首をしめられてしまったニワトリよりも私たちがましな立場にあることにはならないのである。それゆえ、「過去の斉一性が未来についての期待の原因である」という事実と、「そのように期待することが妥当かどうかが問われたときに、それを信頼する合理的な根拠があるか」という問題を区別しなければならないのである。(78㌻)
■科学は作業仮説として、「一般的規則のうち、例外がありうる規則は例外のない規則に置きかえることができる」と仮定することを習慣としている。「空中にある支えられていない物体は落下する」という一般的規則には、風船や飛行機など例外がある。しかし運動法則や重力法則は、たいていの物体が落下することだけでなく、風船や飛行機が空を飛べることも説明するので、これらを例外とせずにすむ。
太陽は明日も昇るだろうという信念は、地球が自転を止めてしまうほど巨大な物体と衝突してしまった場合、その間違いが立証される。だがその出来事によっても、運動法則と重力法則が破られることはない。これらの法則のような、私たちの経験のおよぶ限り例外がまったくない斉一性を発見することが科学の仕事なのである。科学はこの探求において、目覚ましい成功をおさめてきた。今までのところは、科学が発見した斉一性は成立していると認めてよい。しかし、私たちはここでまたもや、「それらの斉一性がこれまでいつも成り立っていたことを受け入れるとき、今後とも成り立つと考える理由があるだろうか」という問題へと連れ戻されるのである。(79㌻)
■帰納原理は、経験に基ずくすべての論証が妥当であるために欠かせないものなのだが、しかし帰納原理そのものは経験によって証明できない。にもかかわらず私たちはみな帰納原理を、少なくともそれが具体的に適用される場面では信じている。(87㌻)
■「真なる命題によって含意されることは、すべて真である」または「真なる命題からどのようなことが帰結しようと、それは真である」ということだ。
実は、この原理は――少なくともその具体例は――すべての論証に含まれている。私たちが自分の信念を用いてほかの何かを証明するとき、そして結果として証明されたことを信じるときには、この原理がつねに一役かったいる。「真なる前提に基づき妥当に議論をして得られた帰結をなぜ受け入れなければならないのか」とたずねられたなら、この原理に訴えるよりほかに答えるすべはない。(89㌻)
■(1)同一律「何であろうと、あるものはある」
(2)矛盾律「いかなるものも、ありかつあらぬことはありえない」
(3)排中律『すべてのものは、あるかあらぬかのどちらかでなければならな
い」(90㌻)
■哲学における大論争の一つに、「経験論者」と「合理論者」と呼ばれる二つの学派の間の論争がある。経験論者たち――ロック、バークリ、ヒュームといったイギリスの哲学者によってもっともよく代表される――一七世紀のヨーロッパ大陸の哲学者たち、特にデカルトとライプニッツがその代表である――は経験によって知られることに加え、何らかの「生得観念」や「生得原理」が存在し、これは経験とは独立に知られると主張した。いまや、これら対立する両学派のそれぞれどこが正しく、どこが間違っていたのかを、ある程度自身を持って決定できる。まず認めておくべきなのは、私たちは論理的原理を知っているが、それを経験によって証明することはできない、ということだ。なぜならこの原理は、いかなる証明にも前提されるからである。それゆえこの、論争において最も重要な争点にかんしては合理論者が正しかったのである。(92㌻)
■論理学と同じく、純粋数学もすべてアプリオリである。経験論者たちはこれを熱心に否定し、「地理学の知識と同じように、算術の知識もまた経験からうまれる」と主張した。(95㌻)〈私の意見:この意見には、両論納得がいかない。自己の内部世界は自己意識の外側にあらかじめ写りこんでいる。つまり人間(生物も)は,外側の世界に対して世界=内=存在であるが、内部でも自己意識は世界=内=存在であるのだ。世界の存在の形態は、内部と外部の境界が無いマンデルブロー集合のように自己相似形なのだ。そう考えるとアプリオリの問題は、あらかじめそうなっている世界(時間、空間)がすでに自分の内部に写し込まれていてその内部に自己意識(知性)が生まれ育つと考えれば説明できる〉
■カントは物的対象――彼はこれを「物自体」と呼ぶ――を本質的に知りえないものとみなす。知りうるのは経験に現れる対象だけで、カントはそれを「現象phenomenon」と呼ぶ。現象は知覚者と物自体の共同の産物だから、知覚者に由来する特性を確かにもち、それゆえ確かにアプリオリな知識と一致する。よってアプリオリな知識は現実的・可能的な経験のすべてに関して真であるが、しかし経験の外部にも適用されると考えてはならない。したがってアプリオリな知識があるにもかかわらず、物自体について、あるいは現実的・可能的な経験の対象ではないものについては、何も知ることができない。このようにしてカントは合理論者の言い分を経験論者の議論と和解させ、調和させようとした。〈私の意見:自分の内部の自己意識が知りえないのであって、物自体は自己意識に関係なく勝手に写り込んでいる〉
■「関係は心が作る。物自体はまったく関係を持たず、心が考える時にそれらを引き合わせ関係させるのである。そうして心は、物自体がそうした関係を持つと判断するのだ」と主張した。
しかしこの見解に対しては、先にカントに反対したのと同様の反論ができるだろう。思考が「私は自分の部屋の中にいる」という命題を真にするのではないことは、明らかではないだろうか。私の部屋にハサミムシがいることは、たとえ私やハサミムシ、あるいは他の誰もこの真理に気づかなかったとしても、真でありうる。この真理はハサミムシと部屋にだけ関わり、それ以外の何にも左右されないからである。よって関係は、次の章でいっそう十分に確認するように、心的でも物理的でもない世界にあるにちがいない。この世界は哲学にとって――とくにアプリオリな知識の問題にとっては――大変重要だ。(111㌻)
■この意味での記憶という事実がなければ、そもそも過去があったことすら分からず、「過去」という言葉も理解できないにちがいない。それは、生まれつき目の見えない人には「光」という言葉を理解できないのと同じことだ。(142㌻)〈私の意見:ここまで読んできてこれ以上読み続けるのを断念した。この文章には全く同意できない。参照:『芸術の杣径』の中の「夢の中の空間」〉
『哲学入門』 バートランド・ラッセル(高村夏輝訳)ちくま学芸文庫
2007年11月14日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――