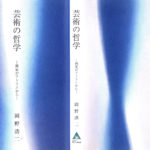『芭蕉庵桃青』 中山義秀著 中公文庫
■芭蕉はこういう杜甫の生涯と自分の境涯をひきくらべ、考えなければならないのは、詩作にたいする杜甫の態度だということに気づきはじめていた。
およそ九百年前の遠い昔にうまれた杜甫の詩画、今なおいきいきと作者の面影をつたえ、読者に深い感銘をあたえるのは、いったいどうした理由からであろう。新奇さをてらう思いつきや頭だけの拵(こしら)えごとで、このように人の心をうごかせるはずはない。彼の生活現実と、それに交流する彼の生命との間に、なにか解かれぬ秘密がひそんでいるのではなかろうか。
杜甫も若い頃は当時の流行をまねて、言葉たくみに操(あやつ)り玩(もてあそ)ぶことから詩作をはじめている。しかし齢をかさね、生活のきびしい現実に直面してくるにつれ、物の実体をさぐろうとする、写実風の態度にかわってきている。さらに試練がくわえられてくると、外界の事象から内部の心に重点をおくようになった。そして内心の感動から生まれるものが、まことの詩だと実感するにいたったらしい。(33頁)
■其角にとって俳諧が、みじめな人間生活やみみっちい人生をよそにした、伊達と華麗とをきそう錦繍のせかいであり、荘子の夢の無何有(むかう)郷(岡野注;自然のままで、何の作為もない理想郷)とするならば、芭蕉にとってはおのれの生活と人生を賭けた、実有(じつう)のものとなっている。
其角の句は人目を驚かし喜ばせるが、芭蕉のそれは人々の心の奥にひそむ、寂寥と悲哀の永遠なるものへと誘いこんでゆく。それぞれの特色であり、他人に真似のできないものである。それ等をそなえた彼等は、言葉使いの巧みな、一種の魔術師にたとえられるべき人達なのか。(38~39頁)
■芭蕉の考えるところでは、松永貞徳以来の俳諧は、2変し3変しようとしていた。貞門時代の俳諧連句は、前の句の詞(ことば)や事柄をとって、後の句をつける「物付け」であった。
西山宗因はその「物付け」をあらためて、前の句の意(こころ)をとって後の句をつける「心付け」とした。前の句の意から聯想して、後の句に新しい意をもたせてゆくやり方だから、想像力が強く働き、連句は趣向をこらした物語風のものに発展してゆく。そのため形式も表現も自由、大胆となって、末は奇抜さをさそい奇矯をてらう放埒(ほうらつ)なものに堕落してしまった。(45頁)
■それというのも段倫風の「心付」にたいして、前駆の漠とした気分や味いをくんで、後の句をつけるといったやりかたをとり、聯想による前後の句のつながりを、一切廃してしまったので、連絡をたどるのに骨が折れ、前後まちまちの句、難解な連句となった。そのため一巻の連句をつらぬき流れる、快い階調がうしなわれ、イメージのうすいものとなった。それでは俳諧の木乃伊(みいら)でしかありえまい。(45~46頁)
■夜になって風がやみ、火事の延焼する心配はなくなった。ふだんならば肌もこおるような寒夜なのだが、火事の余焔と熱気で冷えは感じられない。川水すらなまぬるく思われるほどである。それほど地上といわず水上といわず、風に狂いはしった火勢は猛烈であった。
水中から匍(は)いあがった芭蕉は、草むらにまだ余燼のくすぼっている草庵に行ってみた。旧廬はおとかたもなく焼失してしまったけれども、生け簀の古池はのこっている。枯れた藻草におおわれた青みどろの水面は、なにごともなかったように静かだ。
古 池 や ……
芭蕉はそう口ずさみかけ、自分の宗匠気質(かたぎ)にきづいて、おもわず苦笑をもらした。一切が失われてみると、彼に残されているものは、自然にわきいでくる俳諧の形のない、無限の天地しかなかった。(53~54頁)
■初老にはいった芭蕉にも、俳諧の上で独自の風体をもたなければならない時期が、せまってきている。初期の貞徳流から談林調へ、談林調から新風をめざしての漢詩体へと、すでに3変してきているものの、まだ適切な風体をつかんでいなかった。漢詩体の表現は、理窟ばっていかめしげであるが、俳諧にふさわしい風体とはいえない。
俳諧の源は詩歌の気晴らしとされた、滑稽体からはじまったといわれている。その滑稽を俳味とする、俳諧の風体は、いかにあるべきものなのか。和歌や連歌界の先達者たちは、風雅のまことをば、ものの哀れを情趣とする幽玄体においた。
宗祇とともに時雨の句をよんだ心敬法師は、この幽玄体を、「冷え寂びたるあり方」と定義した。心敬は歌道の修行をもって、心の修行とした人である。彼は宗匠を業としないで、出家の心をもって生涯を終始した。芭蕉もまた、おなじ道をあゆもうとしている。心敬は風雅のまことを、「冷えさび」だとしたが、冨士のふところに入って芭蕉は、はたして何を感得するところがあったであろう。(60頁)
■「夏馬遅行(かばちこう)」の漢詩体は、推敲をかさなて後にこうあらためられる。〔岡野注;夏馬遅行我を絵に見る心かな〕
馬 ぽ く ぽ く 我 を 絵 に 見 る 夏 野 哉
そしてこれを主題にして、彼の像を描いた杉風の画に、芭蕉は次のような讃をした。
かさ着て馬に乗る坊主は、いづれの境より出て何をむさぼりありくにや。このぬしのいへる、是は予の旅のすがたを写せりとかや。さればこそ三界流浪のもゝ尻、おちてあやまちすることなかれ
もゝ尻とは鞍に尻の安定しない、下手な馬乗をさす。又いずれの境から迷いでて、何をきょろきょろ貧り歩くのかとは、この谷村時代の苦しかった心境を回想して、反語の諧謔を弄したものであろう。それだけ余裕をもったしるしである。
麋塒(びじ)と一晶は、この発句に感心して、
「『我を絵にみる』とは、面白いですな。唐土の高士の姿を、偲ばせる趣がある」
「何処でこの句を、えられましたな」
一晶が芭蕉にたずねると、
「吉田あたりの裾野を、農馬にまたがって旅しているうち、ふと思い浮んだものです」
「なるほど」
宗匠として一家をなしている一晶は、しきりと考えこみ、
「『夏馬遅行、我を絵に見る心かな』――広い夏の裾野を、独りゆっくりと馬でゆく姿、侘びてますね。漢詩体からして今、唐土風のものをよむのがはやっているが、この趣向は新しい。何か拠るところ御座いますか」
「拠るところがあるといえば、富士山です。崇高な霊峰にしても、山が山ならば、自分も自分だと思うより仕方がない」
一晶は膝をうって、
「翁はこの谷間から、広野へ匍いだされた。豁然として悟るところが、あったのではありませんか」
「さア、どうでしょう」
芭蕉は麋塒にも眼をうつして、
「一掬の水でも澄んでおれば、天心の月を我が物とすることができる。寒山がいう、心灑洒(さいしゃ)たれば、属目するところみな佳思あり、とはこの事かもしれません。お蔭でこの句を獲たことばかりでも、お世話になった甲斐がありました」
句がよいというのではなかった。冨士の雄大な山容にたいして、卑小な自分を救うことの出来た悦びである。そしてその事はまた、平談俗語をもって、卑俗なことがらを美化する、俳諧の精神につうじるものでもある。一晶が指摘したように、芭蕉はようやく俳境についての混迷からぬけだすことができたようだ――我を絵とみる心によって。(73~75頁)
■富士川のほとりを行に、3つばかりなる捨子の哀げに泣くあり、この川の早瀬にかけて浮世の波をしのぐにたへず、露ばかりの命まつ間と捨置けむ、小萩がもとの秋の風、こよひや散るらん、あすやしをれんと、袂より喰物なげてとほるに、
猿 を き く 人 捨 児 に 秋 の 風 い か に
いかにぞや、汝父に憎まれたるか、母にうとまれたるか。父は汝を惡(にく)むにあらじ、母は汝をうとむにあらじ。唯これ天にして、汝が性(さが)のつたなさを泣け。(96頁)
■芭蕉がつけた脇の両句は、とりたてて云うほどのものではないが、その調に独特の風格と重みがかんじられる。彼は2ケ月にわたるこの旅の間に、「笠は長途の雨にほころび、帋衣(かみこ)は泊りとまりの嵐にもめた」かわり、俳諧の道について、ゆるぎのない自覚と信念をえた。その精神をいえば、方外境に逍遙する風狂の心、その体をもうせば、景情一味の写実である。
たとい虚構とみなされたにせよ、富士川のほとりの憐な棄児にたいして、「汝が性(さが)のつたなさを泣け」と云いきる非情、客観の態度は、自然の景観や人事現象に活眼をひらかせた。もはや芭蕉にとって、貞徳流の古風はもとより、宋因の談林調も、天和期における漢詩文体もない。
長かった模索と低迷からぬけだしてみれば、天地の間に磅礴(ほうはく)して、四季の運行に変幻自在の妙をつくす、造化の自然があるばかり、無心にその機微と冥合するところに、風雅の誠がある。杜甫や西行などの詩歌の秘密も、結局はそこに帰せられるのではなかろうか。(101~102頁)
■たとえば620余年前の前9年役の際、八幡太郎義家と安倍貞任との間に、とり交されたという応答歌……戦にやぶれて衣川の館を落ちゆく貞任を、義家を追いかけて呼止め、
衣 の た て は 綻 び に け り
貞任はこの下の句に、上の句をつけて答え、
年 を 経 し 糸 の み だ れ の 苦 し さ に
「衣のたて」は糸のたて糸を館(たて)に通わしたもの、この形式を「短連歌」といい、単連歌から更に「鎖連歌」とよばれ「長連歌」が誕生してくる。単連歌の句形五七五、七七をつぎつぎと繰返しながら、鎖のようにつないでゆく方法で、一種の尻取り遊びのようなものだから、多人数がこれに参加して句作を楽むことができ、その連句の数も五十韻百韻、千句万句におよんだ。(116~117頁)
■宗因はこのような心境からして、謡曲、小唄、浄瑠璃、地口などに題材をとり、新しい詞を自由につかって、格式ばった貞徳流の俳諧を一変させた。それで芭蕉も、「上に宗因なくんば、われわれの俳諧は今もって、貞徳老人の涎を甜ぶるべし。宗因はこの道の中興開山なり」と推称している。(129頁)
■芭蕉がねらっているのも、いわば「匂(におい)付」ともよぶべきこの付筋にあった。連歌はこの付筋によって、鑑賞にたえる詩歌の1つとなった。おなじ母胎からでた俳諧もまた、かくあるべきではないか。(141頁)
■俳諧は形の上からいえば、平談俗語をとりいれた俳諧の使用で、連歌から差別されている。しかし実体は、幽玄を主調とする連歌の風体と、「侘び」、「寂び」に撤しようとする俳諧境との相違にある。(147頁)
■「春雨の柳はぜんたい連歌なり。田螺(たにし)とる鴉は、まったく俳諧なり」と、この間の差別をはっきりさせている。また続いて、これまた後年の物である、「五月雨に鳰(にほ)の浮巣を見にゆかん」という自作の句をひき、五月雨や鳰の浮巣は、素材としては俳諧ではないが、それをわざわざ見にゆく風狂に俳諧があるとする。
芭蕉はこの俳境をさぐり、身をもって俳情に生きるために、深川の隠士となり旅をゆく風狂の人となった。そういう彼にとって、心魂のあてどもない行方を辿るように、筋もテーマもなく象(かたど)られてゆく俳諧の様式は、飛花落葉の風情をそのまま、彼の心情に似つかわしい風姿だったのかもしれない。現世を常ならぬものとする、虚心、虚無の世界である。(148頁)
■千那と尚白は三井秋風と同様、田中常矩や惣本寺高政の談林派についていたが、「冬の日」を読んでその風体につよく関心をよせるようになった。奇抜な見立や珍しい趣向、変風などに憑かれている、空疎な談林俳諧にくらべ、それとは似もつかぬ「冬の日」の清澄高雅で、余韻のふかい俳諧境地に驚かされたためである。それで芭蕉の在京を知ると、さっそく彼を招いて話を聞き指導をうけることになった。(155頁)
■春光のうちに駘蕩として、いぶし銀のゆたかな広がりをもつ琵琶湖風景は、芭蕉の詩情をよび美しい吟調を生んだ。
湖水眺望
辛 崎 の 松 は 花 よ り 朧 に て
芭蕉の門弟達の間で後に、「にて」留めのこの句の仕立が問題になった際、芭蕉はこれは理窟ではない、「只、眼前なるは」と言ったそうだが、なるほど眼前の属目として、これ以上適切な表現はない。
この句も推敲をかさねた末定着したもので、初案の句は、
辛 崎 の 松 は 小 町 の 身 の 朧
であったという。雨にけむる孤松の姿を、美女の小町と対照させたわけだが、句意はともかく表現は改案されたほうが、段違いにまさっている。しかし美女を聯想するところに、彼の俳諧をつやめかせる、心情の秘密が隠されてあるようだ。(155~156頁)
■ 古 池 や 蛙 飛 こ む 水 の 音
一見してやすやすと詠みだされた、写実の1句にすぎないようだけれども、繰りかえして読みあじわってみると、深遠閑寂な響が余韻をひいて心につたわり、想いをはるか無何有の彼方へいざなってゆく。このような働きをする不思議な力は、いったい17字の何処にひそんでいるのか、神韻縹渺の趣とは、まさにこうした境地をさしていうことに相違ない。
蟇の青蟾(せいせん)堂を菴号としている仙化は、おもわず昂奮して、
「翁、でかされましたな。一言もございません」
しかし若い其角は、性来のはなやか好みからして、なお句の出来ばえを思案しながら、玉川の蛙をひきあいに、
「山吹やとおいても、面白いでしょうな」
「それはよくあるまい」
素堂は彼の言葉をおさえて、
「これには釈迦の出山に通じる、意味合いがある。冬の長い眠りから目ざめて、わが古巣の世界へ飛び入る蛙の無心欣求(ごんぐ)の姿は、山吹では出てこない、のう、翁」
芭蕉より2つ年上で、儒学者でもある素堂は、さすがに芭蕉の胸中を、推察しているような理窟をはく。6年の苦行をへた35歳の釈迦牟尼は、破衣蓬髪、おとろえた姿で雪山をさるにあたり、冬空にかがやく暁の明星をみて、「大地有情、同時成道」の悟りをえたとある。
これは道釈画にこのんで描かれる釈迦出山の図で、芭蕉の庵にもその木像が安置されている。素堂はそれから思いついて、こうした解釈をくだしたものであろう。またそれだけこの句を、高く評価したわけであるが、芭蕉はさりげなく、
「いや、枯草のうちからのそのそと匍いだした蛙が、萌えでる若草をわけて、古池へ飛びこむ水音に、俳諧を見つけたばかりのことでした」
たしかに芭蕉のいうとおりだったにちがいない。景物にたいして一念一動するところに理窟はなく、ただ詩魂のひらめきがあるばかりだ。(169~170頁)
■なお其角は、その後も芭蕉の句に心をとられていたのか、これに脇をつけたと伝えられている。
古 池 や 蛙 飛 こ む 水 の お と 芭蕉
蘆 の 若 葉 に か か る 蜘 の 巣 其角
もしこの句が其角の作だとすれば、其角は結局芭蕉の句を、叙景のものとしてしか受取っていなかったことになろう。昨年の秋、芭蕉は門弟の大垣藩士、中川濁子(じょくし)の筆写した、「野ざらし紀行」に奥書して1句をそえている。
た び 寝 し て 我 句 を 知 れ や 秋 の 風
芭蕉のこうした考えによると、彼の詩魂にひらめいて生みだされた蛙の句は、至れる者だけが知る境地なのかもしれない。(173~174頁)
■芭蕉が仏頂を徳としているのは、彼の勇猛心とその実行力である。仏頂が老中酒井忠国から、引退後の生活はどうすると問われた際、山になりとも里になりとも心まかせにするつもりだ、と答えた一言は、ながく芭蕉の心のささえとなった。
むしろ仏頂の行きかたを手本に、その後を生きつづけてきたとも言える。風雅のために最低の生活を決意して、貰うてくらい乞うてくらうことを恥とせず、飢(かつ)え死にすることすら辞さないよいう心底には、仏頂に劣らぬ勇猛進が、なくて叶わぬはずだ。その意味で仏頂は、国学における北村季吟、儒学における山口素堂と同様、禅学の上で芭蕉の育成に、無視できない役割をはたしている。(188頁)
■「笈の小文」の初で、芭蕉みずから記しているところを、次に意訳すると、
「旧友、親しい者、知りあい、門人等、あるいは詩歌文章をはなむけにして、訪れてくるかと思えば、あるいはまた草鞋銭をもって、志をあらわす者がある。おかげで旅費の苦労もいらないほどだ。ほかに紙衣、綿入れ、頭巾、足袋、といった物をくれる人々もあって、防寒の心配もない。ある者は小船の上で別宴をはり、ある者は別荘に招待して饗応する。草庵に酒肴を携えてきて、旅の前途を祝し名残を惜む者もあり、身分ある人の門出するみたいで、ひどく仰山な思いがした」(191~192頁)
■しかし「笈の小文」も書出しも、それに劣らずものものしい。当時はやりの漢詩文体調で、響高くつづられている。
「百骸九竅(けう)の中に物有り。かりに名付けて風羅坊といふ。誠にうすものの風に破れやすからむ事といふにあらむ。かれ狂句を好こと久し。終(つひ)に生涯のはかりごととなす。ある時は倦(うみ)て放擲せん事をおもひ、ある時はすゝむで人にかたむ事をほこり、是非胸中にたゝかうて、是が為に身安からず。しばらく身を立む事をねがへども、これが為にさへられ、暫く学んで愚を暁(さと)らん事をおもへども、是が為に破られ、つひに無能無芸にして、只この一筋に繋がる」
100の骨9つの穴から成る人体には、風羅坊とも名づくべき精霊がいる。薄くて風に破れやすい、芭蕉葉のごときものだ。この風羅坊は俳諧が好きで、とうとう一生の仕事とするようになった。ある時は倦きて棄てようかと思ったり、逆に進んで人に勝誇ろうとしたり、あれこれと迷いぬいて、心の安まることがない。一旦は立身出世を願っても、これにさまたげられ、学問してその愚さに覚めようとしても、この為に思いを破られ、とうとう無能、無芸の身をもって、俳諧一筋に生きることになった。
これを過去の述懐として、次は彼の美意識と信念を吐露した、有名な文章となる。
「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其貫通する物は一なり。しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて四時(しいじ)を友とす。見る処、花にあらずといふ事なし、おもふ所、月にあらずといふ事なし。像花(かたち)にあらざる時は夷狄(いてき)にひとし。心花にあらざる時は鳥獣に類す。夷狄を出(いで)、鳥獣を離れて、造化にしたがひ、造化にかへれとなり」
和歌、連歌、点茶と、達人達の志した道は、それぞれ異っていても、帰するところは風雅の精神1つである。この風雅の情(こころ)は、自然の運行にしたがって、四季の眺めを友とするものだ。見るところ花でないものはなく、思うところ月でないものはない。像(かたち)に花を見ない者は蛮人とおなじく、心に月を思うことない者は、鳥獣に類している。蛮夷、鳥獣の境涯からぬけだして、造化の自然に眼をひらくべきだ。
つまり芭蕉の風雅の哲理は、自然との一体化を説くところにある。森羅万象、すべて自然の恵みによって在る、というその観想は、汎神論と原理をともにする、東洋の美学であろう。(195~196頁)
■芭蕉は昨年の4月末、杜国と連名で京都から、郷里上野の窪田猿雖(えんすい)にあて、「笈の小文」の旅程をくわしく報告しているように、こんどの旅の計画についても、この親友にむかって自分の意中を包まず述べている。
「去年の秋より心にかゝりて思ふことのみ多きゆえ、かへつて御無沙汰に成行き候。(中略)去秋は越人といふしれ者木曽路をともなひ、桟(かけはし)のあやふき命、姨捨のなぐさみがたき折、砧(きぬた)、引板(ひきた)(鳴子)の音、鹿(しし)を追う姿、哀れも見つくして、(中略)年明けても猶旅の心地やまず、(中略)弥生(3月)にいたり、待ちわび候塩釜の桜、松島の朧月、浅香(安積)の沼のかつみ(真菰(まこも))ふく頃より、北の国にめぐり、秋の初、冬までには美濃、尾張へ出で候。露命つゝがなく候はば、又(ま)みえ候て立ちながらにも立寄り申すべきかなど、たのもしく思ひこめ候。南都(奈良)の別れ一昔の心地して、一夜の無常、一庵の涙も忘れがたう覚え、猶(旅の)観念やまず、水上の泡消えん日までの命も心せはしく、去年(の)旅より魚類肴味(こうみ)口にはらひ捨て、一鉢(の)境界(涯)、乞食の身こそ尊けれ、とうたひに侘びし貴僧のの跡もなつかしく、猶ことしの旅は窶(やつ)し俏(やつ)して、菰かぶるべき心がけにて御座候。その上よき道づれ、堅固の修行、道の風雅の乞食尋ねだし、鄰庵に朝夕かたり候て、この僧にさそはれ、今年も草鞋にて年を暮らし申すべくと、嬉しく頼母しく、暖になるを待ちわびて居り申し候」
この手紙は2月初旬に書かれたものであるから、旅の企図はそれ以前になされていたことがわかる。「木曾の痩もまだなほらぬうちに」、はやくも此の大旅行を思いたつようになったとすれば、旅に憑かれたとしてもおかしくはあるまい。(254~255頁)
■そして草庵を表徴する愛翫の芭蕉も、近くの地に移植して、その世話を隣人達にたのんだ。
こ ゝ を ま た 我 が 住 憂 く て 浮 か れ な ば
松 は 独 り と な ら ん と す ら ん(「山家集」)
その西行の憐れみ心を、芭蕉のうえにくみとっての処置だ。「羇旅辺土の行脚、捨身無常の観念、道路に死なん、これ天命なり」(「奥のほそ道」)と覚悟した、命懸けの旅の門出にあたり、心にかかる一切の物事を始末して、身も気持も軽くいで立とうという肚であろうが、それにしても定まった住居まで、人手に渡してしまうとは思いきっている。(259頁)
■「弥生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光をさまれる物から、不二の峯幽にみえて、上野谷中の花の梢又いつかはと心ぼそし。(中略)前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。
行 春 や 鳥 啼 魚 の 目 は 泪
これを矢立の初として、行道なほすゝまず。人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄は見送るなるべし」(「奥のほそ道」)
これが3月27日の早朝、千住を出発する時の情景だ。一蓋の菅笠、一条の杖、墨染の衣に頭陀と背負袋、脚絆、わらじの道心者姿で、「前途3千里」の旅におもむく2人にたいし、見送りの人々は声をあげて泣き、見おくられる芭蕉達もともに、涙を落とさずにはおられなかった。(262~263頁)
■修験道は山嶽信仰の交霊術(シャマニズム)が、道教や真言天台の両密教とむすびついて、盛んになったものである。病気をなおし災害をのぞき悪霊をはらう、加持祈祷の呪力をやしなうため、深山幽谷にわけ入り、諸国を遍歴して、困苦にうちかつ荒行を修めるが、これは仏道修行とおなじく、印度婆羅門の頭陀行にならうものだ。
頭陀行は婆羅門の修行形式で、衣食住の貪着(どんちゃく)から離脱して、身心の解放をはかり、自由をうるための行法である。
その段階として、一切の所有物をすてて山林に幽居し、思索の功をかさねる。ついで頭を剃り薄衣をつけ、首に頭陀袋、手に杖、といった物のほかは何ももたずに、身を雲水にまかせて、廻国遍路の旅にでる。「奥のほそ道」の冒頭にいう、「日々旅にして旅を栖(すみか)」とする、無所在の生活である。(276~277頁)
■その時弁慶以下の家士十余人は、館の大手、搦(からめ)手の防戦にはせむかい、数百の寄せ手を相手に死闘してはてた。後に一人のこった63歳の増尾十郎兼房は、義経夫妻が自裁した後、館に火をはなち、中庭にのりこんできた寄せ手の大将、長崎太郎を乗馬もろとも斬仆(ふ)すと、つづく弟の次郎を小脇にかかえこみ、火中に飛入って勇壮な死をとげた、と「義経記」にしるされている。
芭蕉も曾良も武家あがりなので、こういう話にはつよく感動しがちだ。「さても義臣すぐつてこの城にこもり、功名一時の叢(くさむら)となる。『国破れて山河在り、城春にして草青みたり』と笠打敷きて、時うつるまで泪を落し侍りぬ」(「奥のほそ道」)
夏 草 や 兵 ど も が 夢 の 跡
卯 の 花 に 兼 房 み ゆ る 白 毛 か な 曾良
「国破れて山河在り」は杜甫の有名な「春望」の詩、「『国破れて山河在り、城春にして草木深し」をとったもの、それにつづいて、「時に感じては花に涙を濺(そそ)ぎ、別を恨んでは鳥に心を驚かす」とある。
芭蕉の夏草の発句にも、時におどろく痛歎の響がある。曾良の句には、老いに寄せる悲哀がこめられている。両人それぞれの感銘のありかただが、ともに単純な写景ではなく、観念のうえの細工物でもなく、この場、この時、の実感だったことに相違はない。(206~207頁)
■五百有余年の風雨にさらされてくれば、どのような建物も頽廃はまぬかれず、さながら絶世の美女の老いた姿を目にするような思いだが、しかも堂宇はなお眼前にあって微ながら、燦然とした当時の余影をのこしている。
そして又その須弥壇の下には、奥の王者とよばれた藤原3代の主、清衡、基衡、秀衡が、生ける姿をそのまま木乃伊となった、黄金の柩の中によこたえられてあるという。
これより南東へ8町あまりを隔てた、山下高館の義経は、むなしく荒草の下に朽ちはててしまっているのに、庇護者の秀衡は、今に生前の姿をとどめている。どうした因縁によるものか、あまりにも対照の差が甚しい。
しかし、無為自然の世界では、万物斉同、人間の運命や因縁に、かかわりはなかった。ただまぎれもない現実として、古色に燻(くすぼ)んだ金色堂が、眼前に残存しているばかり、そこで、
五 月 雨 の 降 り の こ し て や 光 堂
すべてが滅びさった後に、光堂1つ残っているのは、一切無差別の自然界でも、美しいものだけはとっておくかとみえる。芭蕉は心にそう信じているかのよう、この佳句をなした。(298~297頁)
■「奥のほそ道」によると、市振の1つ宿にとまった2人の若い女は、伊勢参宮こころざす、新潟の遊女達であった。此処まで2人をおくってきた老爺が、新潟へひっかえすことになったので、未知の前途を心ぼそく思うあまり、芭蕉等の衣の袖にすがって、見え隠れにでも後を慕ってゆきたいという。
しかし芭蕉は、道中たちよる所がおおいので、気の毒ながら同行はできないと断り、ただおなじ方角へゆく人の後に跟いてゆけば、大神宮のお加護でかならず到着できる、と言い捨て別れたが、さすがにあわれでならなかったとある。
同様に芭蕉は、5年前の「野ざらし」の旅の折にも、富士川のほとりで哀げに泣いている、3つばかりの捨て子にたいし、捨てた親を恨むなよ、唯これ天命にして、汝の不運な生まれつきを泣け、といって通りすぎている。
ともに、芭蕉の持論とする、捨身無常の運命観を披瀝するものだ。1面には、世俗の生活をみかぎって、俳諧の風雅に身をささげた、芭蕉の非情の精神と覚悟を、しめしたものともされよう。(317頁)
■千三百石取の藩の名門戸田権太夫如水は、当時の芭蕉と路通の風采を日記にしるして、9月4日の昼、如行の手引で芭蕉と路通の2人を、下屋敷の別邸にまねき、俳席を設けて初対面した。両人よりいろいろと話があったが、主として風雅にかかわることが多かった。
その折芭蕉は、夏の単衣に裏をつけて綿入れとした、墨染の木綿着物に細帯をしめ、うえに十徳を羽織り、路通は木綿の白衣姿で、手に数珠をかけていた。近日伊勢神宮の遷宮式があるので、それを拝むため一両日中に出立するとのことである。両人の心底のほどはわからないが、その態度は俗事をよそに「浮世を安くみなし」て、人に諂(へつら)うことなく奢るところもない、といっている。(328~329頁)
■芭蕉はみちのくの旅の途中、出羽の羽黒山で土地の俳人呂丸に、発句は俳諧の主人公であり、それにつづく連句の流の水源になるものだ、と教えている。それ故発句を練りまわして、むずかしく凝り固めると、座の風情も締りわたって、1巻の句がみな面白くなくなってしまう。反対に百句にもおよぶ広やかな、「姿情」で、発句をおかしく詠みだすと、「一座同心の花」がひらけて、面白い俳諧ができる、というのである。(「聞書七日草」)
「ひさご」の3吟歌仙は、芭蕉のこうした主張を、はっきりとうちだしている。花見の景を軽くよみすてたかに見える、芭蕉の発句を源にして、脇も第3もかろやかにはこばれ、付合に苦渋のあとがなく、俳諧独特の可笑味をくわえて、面白い俳諧を展開している。曾てなかった新境地だといえよう。(332~333頁)
■ 草 庵 に 暫 く 居 て は 打 や ぶ り 芭蕉
い の ち 嬉 し き 撰 集 の さ た 去來
さ ま ざ ま に 品 か は り た る 恋 を し て 凡兆
浮 世 の 果 は 皆 小 町 な り 芭蕉
名残り29から、裏の32句。草庵をむすんでは又所をかえる風狂の歌人は、撰集がおこなわれると聞いて、命ながらえた甲斐あったと喜んでいる。反対に若い頃品かわった恋をしたところで、末はみな小町のなれのはてだ。(345頁)
■みちのくの旅を終えたあと、上方の自然や風物にたいする、芭蕉の見る目がかわってきている。都ととおく地をへだてた奥路の世界は、清冽できびしく山河の姿もうつくしいが、人煙にとぼしく寂寥(りょう)と沈黙の気配が色濃い。
芭蕉は歌枕をたずねまわって、歌人が昔みたところと今見るところと変りなく、太古の俤をさながらにとどめていることを知った。その不変の姿と天地の静寂は、詩情をそそるに適してはいても、生活する悦びはえられない。(348頁)
■ 薦(こも) を き て 誰 人 い ま す 花 の 春
この発句が去来の歳旦帳の引付(付録)にのせられて、諸方に配布されると、芭蕉外の京の俳人等は、菰かぶりの乞食を歳旦帳にだすとは何事だ、といって非難した。それにたいして芭蕉は、大垣藩士此筋(しきん)兄弟あての手紙で、次のように述べている。
別段のことでもないが、5百年昔の西行の「撰集抄」には、乞食となった多くの聖(ひじり)があげられている。眼識があきらかでないため、そうした尊い聖を発見できない悲しさに、ふたたび西行を思いかえして、この発句をよんだまでにすぎない。京の俳人達がかれこれと非難するのは、見識が浅いからである。(353頁)
■「蕉門に千歳不易の句、一時流行の句と云ふあり。其元は1つなり。不易を知らざれば風新ならず。不易は古(いにしえ)によろしく、後に叶ふ句なる故、千歳不易といふ。流行は一時々々の変にして、昨日の風今日宜しからず、今日の風明日に用ひがたき故、一時流行とはいふ」(「去来抄」)
そして去来は、ここに初めて芭蕉は、俳諧の本体をみつけたと言っている。また土芳の「三冊子」では、芭蕉の風雅は万代不易と一時の変化、この2つにきわまるもので、共通するところは風雅の誠1つである。代々の歌には代々の変化があるが、今日読んでも昔にかわらぬ哀れを感じさせる。これを不易という。
しかし、千変万化するものは自然の理であって、その変化にうつらなければ風はあらたまらない。風のあらたまるところが、流行の新しみだ。新しみは俳諧の花である。古びた俳諧は、花のない木立をみるに似ている。芭蕉はこの新しみの匂をもとめて、つねに痩せる思をした。(362~363頁)
■「倩(つらつら)年月の移こし拙き身の科(とが)をおもふに、ある時は仕官懸命の地をうらやみ、一たびは仏籬祖室の扉(とぼそ)に入らむとせしも、たどりなき風雲に身をせめ、花鳥に情を労して、暫く生涯のはかり事とさへなれば、終(つひ)に無能無才にして此一筋につながる。楽天は五臓の神をやぶり、老杜は痩せたり。賢愚分質のひとしからざるも、いづれか幻の栖(すみか)ならずやと、おもひ捨てふしぬ」
先 た の む 椎 の 木 も 有 夏 木 立
年月をへてきた自分のふつつかな人生を、つくづくふりかえって見ると、ある時期には一生の養いとなる領地をもった武士を羨み、またある時期には仏門、禅室へはいろうと考えたこともあった。
しかし、さすらいの旅に身をさらし、花鳥に情をささいで、ひとまず俳諧を一生の仕事ときめてしまった後は、無能無才ながらこの道一筋につながれている。白楽天は詩作のために五臓の精気をやぶり、杜甫は苦吟して痩せた。
人に賢愚の別があり、文章に平凡非凡の差はあっても、所詮は幻の世をすみかとする上で、誰もみな変わるところはない。そこで夏の陽をさけ、実は糧となる椎の木を、まず頼むという発句となる。
これが風雅人芭蕉の心境であり、47歳になった彼の述懐である。芭蕉は長明の「方丈記」の形式にならって、「幻住庵記」を書いたとしているが、「方丈記」の終は以下のように結ばれている。
「そもそも一期の月影かたぶきて、余算、山の端にちかし。たちまち三途の闇にむかはんとす。何のわざをか喞(かこ)たむとする。仏の教え給ふ趣きは、事にふれて執心なかれとなり。今、草庵を愛するも科とす。閑寂に着するも障りなるべし。いかゞ要なき楽しみをのべてあたら時をすごさむ。
静なる暁、このことわりを思ひつゞけて、みづから心に問ひていはく、(中略)若しこれ、貴賤の報のみづから悩ますか、はたまた、妄心のいたりて狂せるか、その時、心さらに答ふる事なし。只、かたはらに舌根をやとひて、不請(ふしょう)の阿弥陀仏、両三遍申してやみぬ」
わが一代もはや余命すくなく、冥府におもむく時がちかづいてきている。わが身の上について、今更愚痴をいったところではじまらない。仏は何事にも執着するな、と教えている。さすれば、方丈の草庵を愛し、閑寂を好むのもまた、罪障とならう。いたずらにその楽しみを語って、無駄に時間をおくるべきではない。しずかな春の明けがた此の道理に思をめぐらせて、山林に世をのがれ方丈の幽居に住んでも、なお迷蒙から脱却できないのは、貴賤といった過去の宿業にまだ囚われているためか、あるいは迷いのはて本心が狂ったのかと、自分の心に問うてみたが、何の答もえられない。よぎなく空念仏を2、3べん唱えて、考えることをやめてしまった、というのである。(367~369頁)
■土芳「三冊子」中の「黒双紙」に、芭蕉の言葉として、「発句というものは、行って帰る心の味だ。山里は万歳遅しというばかりでは、平句の位にすぎないが、梅が咲いている山里、と元にかえる心で発句となる。つまり発句は、取合せ物と心得るがよい」とある。(379頁)
■昨年の3月に亡くなった杜国を夢にみて、涙をながした。夢は心気によるとされているが、杜国の夢は、いわゆる念夢というものであろう。思うこと深ければ、それが夢となって現れる。杜国は自分に厚く志をよせ、3年前の伊賀の里まで慕ってきて、およそ百日ばかりの間、夜は臥床(ふしど)をともにし、昼は疲れをいたわりあって、影の形に添うように旅をつづけた。ある時は戯れあい、又ある時は互いに悲みをわかちあったその思い出は、心にきざまれて忘れることがない。目覚めて後も、流れる涙を抑え得なかった。(381頁)
(2012年6月1日)