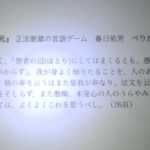| 『仏陀』増谷文雄 著 角川選書ー18 |
| 第1章 この人を見よ
■1898年、プッペが、ネパールの南境ピプラーバーにおいて舎利瓶(へい)を発掘した。その瓶(つぼ)の側にはインド古代文字をもって、「この世尊なる仏陀の舎利瓶は、サキャ族が兄弟姉妹妻子とともに、信の心をもって安置したてまつる所である」と刻みつけられてあった。『遊行経』そのほかに記し伝えるところの仏骨八分の記においては、サキャ族の人々もまたその一分をえて、これをカピラヴァッツに安置したてまつったとある。その古き経典の記し伝えるところは、いま仏証をもって実証せられた。されば、今後もはや、この人がかってわたしどもと同じくこの地上に生をいとなんだことを疑うものはないであろう。(10頁) ■『仏所行讃』も、『仏本業集経』も、わたしどものいわゆる「大蔵経」の中にその位置をしめている。経はわたしどもにとってもまた、最高の信のよりどころでなければならぬ。釈尊は、その死に際して、比丘たちのために説いて、「われによりて説かれ教えられたる教法と戒律とは、わが亡き後になんじの師である」と、教えられたという。それは、この師の最後の教えとしてまことにふさわしく、この教えのもつ意味はまことに重い。したがって、その教法と戒律とを記しつたえる経は、滅後の弟子たらんとするわたしどもにとっては、師その人として仰ぎ尊ばれなければならぬ。だが、それにもかかわらず、いずれの経が、かの教法もしくは戒律をより正しく記し伝えるものであるかについては、わたしどもの批判的精神は、するどくはたらくことを許されねばならないであろう。(12頁) ■釈尊の十大弟子の一人に、カッサパ(迦葉)という人があった。師の釈尊とは別に、多くの比丘たちとともに遊行していたが、途中で遇った一人の波羅門によって師の入滅せられたことを知った。その時、なげき悲しむ比丘たちの中にあって、ただ一人「友よ、悲しむなかれ。われらは今や自由になったのである」と暴言を吐くものがあった。それを耳にして、正しい教法と戒律とがやがて乱れ汚されるであろうことを憂えたカッサパは、主なる長老たちを集めて、いわゆる「結集」の仕事にとりかかった。結集とは、簡単に言えば、経典編集の事業であるが、まだ文字の常用せられていなかった当時においては、これを各人の記憶の中において、確立するよりほかはなかった。その結集の方法は、つぎのようであったと記されている。 アーナンダ(阿難)は、師の侍者であったので、師がどこでいかなる教えを説かれたかを、もっともよく知っていた。したがって、教法については彼が中心になった。ウパーリ(優波離)は、戒を持することもっとも厳であって、持戒において弟子中の第一とされていた。戒律については彼が誦出者(じゅしゅつしゃ)となった。そして、誦出者を中心として、師がどこで、何びとにたいして、いかなる教えを説かれたか、また師は、いずこにおいて、いかなる因縁によっていかなる戒律をさだめられたかを検討した。検討の結集、それが正しいとされると、列座の比丘たちは、それを同声に誦(じゅ)した。 それゆえに、結集はまた「等誦」と称せされる。この等誦によって、比丘たちはみな、確認せられたる教法または戒律を、おなじ文言によって、おのれの記憶の中に確立した。そこに、教法と戒律とは、整理と統一とを与えられ、異端邪義の侵入に対してみずからを守る用意をととのえることを得た。その精神を、経典は、カッサパの結集提唱のことばとして、「友よ、われらは、よろしく法と律とを結集し、非法おこりて法おとろえ、非律おこりて律おとろえ、非法を説く者つよく正法を説く者よわく、非律を説く者つよく正律(しょうりつ)を説くよわくならんことに先んぜん」と伝えている。(13~14頁) ■清沢満之は、『阿含経』を自己の「三部経」の一つに数えて、「別けて『阿含経』は、釈尊が諄々(じゅんじゅん)としてお弟子を教訓したもう様子が、眼に見えるようでありがたい」と語ったことがあるが、この経の価値の最大なるものは、まさにそこに存するのである。なにほど表現を巧(たくら)んでみようとも、いかほど荘厳なことばをつみ重ねようとも、とうていおよぶことのできない素朴なる真実のもつ強さというものが、つくづくと、そこに感じられる。「かようにわたしは聞いた」という冒頭のことばが、そのままなんの掛け値もなくうけとれる経文がそこにあるのである。したがって、そこにある釈尊のすがたは、わたしどもに身近に感ぜられ、そこに語られる釈尊のことばは、人間的な親しみにあふれている。それはもはや、天界の神話などとはまったく関係なく、わたしどもとおなじようにこの地上に生をいとなみ、しかも人間としてきわめうる最高のあり方を実現した人の言行思想そのものである。その人はもはや、わたしどもにとっては、壇上の礼拝の対象ではなくして、わたしどもを励ましみちびく文字どおりの導師であられる。(17頁) 第2章 比類(たぐい)なき人うまるー降誕 ■「生まれによりて聖者となるのではない。生まれによりて非聖者となるではない。人はその行為によりて聖者となるのであり、その行為によりて非聖者となるのである」 それは、この師によって人類の中にもたらされた教え、すなわち仏教の根本原理の一つに直結する考え方である。身・口・意一切の人間の所作は、結局するところ、その業報(ごっぽう)を、その人のうえに結ぶ。自業自得果である。「自ら悪を作(な)して自ら汚(けが)れ、自ら悪を作さずして自ら浄(きよ)い。おのおの自ら浄(じょう)となり、自ら不浄となるのである。人は他を浄(きよ)めることはできぬ」と、かの『法句経』の一句が語っているのも、そのことのほかでではない。 このことを裏がえして言うと、いかなる人の生涯も、その生まれによって決定されるのではないということであらねばならぬ。その生まれによって、賤しき人としての生涯を決定せられるのでもない。素質や環境やが、各人の人生行路を、左右する要因でないわけでもないけれども、もっと重要な条件は、彼が自己の所作として何をえらぶかということであらねばならぬ。何を意志し、何を語り、何をなすか。そのことが結局、彼の人間としてのあり方を決定するのである。釈尊のよりてたつ立場は、予定説でも、また宿命論でもなかった。それはあくまでも業(ごう)の立場であった。みずから悪をなさずしてみずから浄(きよ)きひととなり、みずから善き行為をつんで聖者となるのであって、人はその生まれによって聖者となるのでもなく、またその生まれによって非聖者となるのでもなかった。 しかるとすれば、釈尊がその弟子たちに語って、彼らの人生向上の一路に資すべきものは、自己の出生や自分の家柄のことではなかったはずである。語るべきことは、生まれに関してではなくして、行為にかんしてでなくてはならなかった。わたしはかく思い、かく行じ、かのごとくわが人生を建立したということであらねばならなかった。(21~22頁) ■「智慧ふかく、賢慮ありて、道と非道とをわきまえ、最上の義に到達せる人。わたしはかかる人を聖者とよぶ」 「蓮の葉にやどる水のごとく、錐の先端におけるけし粒のごとく、もろもろの欲に染著(せんじゃく)せざる人。わたしはかかる人を聖者とよぶ」 「粗暴なることばをもちいず、つねに教訓にみてる真実のことばを語り、ことばにおいて何者をも怒らしむることなき人。わたしはかかる人を聖者とよぶ」 「悪意ある人々の中にありて悪意なく、刀杖(とうじょう)を手にする人々の中にありて温柔に、執著おおき人々の中にありて執著なき人。わたしはかかる人を聖者とよぶ」 「人はその風姿と姓名にとによって聖者たるのではない。真実と正法とを具え有するもの、彼は幸福なるかな、彼こそはまことの聖者である」 釈尊はかくのごとく考え、かくのごとく行じ、みずからかくのごとき聖者となって、「なんじらもまたこの、道をきたれ」と、その弟子たちにおしえ、またわたしどもをさし招いているのである。そして、かの阿含部の諸経の記すところは、かかる聖者たりし釈尊が、その道によって彼にしたがわんとする人々のために、その奉ずべき教えを説き、その践(ふ)むべき道を示し、その仰ぐべき範を垂れたもうた、その思い出をかりそめにも違えじと結集して伝え来たったものであった。(22~23頁) ■それは、彼が菩提樹のもとを辞してバーラーナシーの鹿野苑(ろくやおん)にむかう途中のことであった。ふと道で出会った外道のウパカなる者が「なんじは誰の弟子であるか、誰の教法を信奉する者であるか」とたずねたとき、それに答えて釈尊は、毅然として偈をもってかように言った。 「われは一切勝者である。一切智者である。 一切を捨離し、渇愛つきて解脱した。 みずから認知したのであるがゆえに、誰をかわが師といおうか。 われには師もなく、われに等しき者もない。 人天の世間にわれにたぐうものはない。 われは世間の応具であり、無上の師である。 われひとり正覚者にして、清涼寂静である。 いま法輪を転ぜんとてカーシーの都にゆく。 盲闇(もうあん)の世間に甘露の法鼓をうたんとするのである」(27~28頁) ■それは、初転法輪に先立ってなされたるブッダの自覚の宣言であった。その自覚の内容をなすところのものは、一切智者、一切勝者にして、人天の世間に比類(たぐい)もなき正覚者であるということに外ならなかった。言いかえると、「天井天下、唯我独尊」とは、人間としての最高のあり方たる仏陀の自覚の表白に外ならない。したがって、その後、この師を仰ぎたたえた人々は、つねに語ってこの人を、「無等、無比」であるとたたえ、また「人中の最勝」であると称した。ふるき経の一句は、かようにも語っている。 「一人あり。その世に生るるや、無等、無比にして、人中の最勝者として生まる。その一人とは、誰であるか。そは如来、応供、正覚者である」 それをわたしどもは、この人が生まれながらにして仏陀であり、人中の最勝者であったと解する必要はない。彼がかかる最高の存在となりえたのは、ながき求道の精進のすえ、ついにかの菩提樹下に大悟せられてからのことであった。それが信憑すべき資料のわたしどもに語るところである。とまれ、この人は、無等、無比にして、天上天下、唯我独尊なる存在となったのであり、人天の世間に比類(たぐい)なき人間のあり方にまで高まることを得た。その比類なき人は、今をさる二千有余年のむかし、わたしどもとおなじく、人間として、この地上に生をうけられた。そのことこそが、一切の伝説と空想とを超えて、「いくたび思いおこしても、なお足らぬ」ほどの意義を、わたしどものうえにもつのである。(28頁) 第3章 大いなる放棄ー出家 ■このように、釈尊はまず、その出家まえの生活が、世の通念にしたがって言えば、きわめて幸福であったことを、淡々と、しかも具体的に語ったのち、さてしかし、ふと翻って考えてみると、それはけっしてほんとうの幸福、「究竟して苦無き」ものではないことを知ったと語りついでゆくのであった。 「比丘たちよ、わたしは、かように幸福であって、まったく苦を知らなかったにもかかわらず、わたしは考えたのである。ー愚かなる凡夫(無聞の異生)は、みずから老いるものにして、いまだ老いをまぬがれることを知らないのに、他人の老い衰えたるを見ると、おのれのことは打ちわすれて恥じ嫌う。わたしもまた、老ゆべきものである。いまだ老いを免れることを知らぬ。わたしもまた老ゆべきものにして、いまだ老いを免れることを知らないのに、他人の老い衰えたるをみて、厭い嫌ってよいものであろうか。これはわたしにふさわしいことではない。ー比丘たちよ、わたしは、かように考えたとき、わたしの青春の憍逸(たかぶり)はことごとく断たれてしまった」 つづいて釈尊は、病について、死について、おなじような思惟をいとなんだことを語る。病まねばならぬ身でありながら、また、死なねばならぬ身でありながら、そのおのれのことは忘れ果てて、他人の病めるを見ては眉をひそめ、他人の死をみては眼をそらせる。それはけっしてふさわしいことではないのだと気づいた時、釈尊は、「わたしの健康の憍逸(たかぶり)はことごとく断たれ、わたしの生の憍逸はみじんに砕けちった」と述懷しているのである。(30~31頁) ■「比丘たちよ、それらは3つの憍逸(たかぶり)である。3つとは何か。壮年憍(きょう)、無病憍、活命憍がそれである。比丘たちよ、あるいは壮年憍におごる者は、あるいは無病憍におごる者は、また、あるいは活命憍におごる者は、学を棄捨し、下劣に生きるであろう」と、戒め教えることが、この経の主題であったのであって、ここに釈尊がその出家前の生活を語り、また出家の動機について語りいでたのは、かかる憍逸の克服のための一つの思惟の過程として、おのが体験を例示したのであった。(32頁) ■「刹帝利(クシャトリア)種の家に生まれたる者が、 資力小にして、欲望のみ大きく、 この世において王位を希求する。 それは破滅(敗亡)にいたる門である」(36頁) ■釈尊はある時、出家してなお日浅き比丘たちのために、かように説いて教えられたことがあった。 「比丘たちよ、出家行乞の生活は、もろもろの生活の中の下端の生活である。だが、比丘たちよ、善き人々があえてこの生活にいたるのは、勝れたる義(わけ)があるからである。それは、王に強いられたからでなく、賊に強いられたからでなく、負債のゆえからでもなく、怖畏(おそれ)のゆえからでもなく、生計(なりわい)の苦しみからでもない。われらは、生・老・病・死・愁・悲・憂・悩の中に沈んでいる。苦に沈淪し、苦に包囲せられている。その苦の積集を滅しつくさんがためにこそ、われらはここにいたったのである」 そして釈尊は、出家しながらもなお俗世の欲望に心ひかれがちな若き比丘たちに、決然たる放棄を要求しているのであるが、わたしどももまた、大いなる放棄なくしては大いなる獲得のないであろうことを知らねばならない。右顧左眄する者は、とうてい真の宗教的生活を味わうことはできない。放棄においてやぶさかなるものは、畢竟するに、釈尊の道をゆくことは許されぬであろう。かつてイエスもその弟子たちに言ったことがあった。「なんじら神と富とに兼ね事(つか)うること能わず。このゆえに、われなんじらに告ぐ、何を食い、何を飲まんと生命(いのち)のことを思いわずらい、何を着んと体のことを思いわずろうな」と。その道は異なるといえども、その救うるところの心組みは異ならない。最高のものを求めんとするものは、つねに一切をすててそれに向かわねばならぬ。それが真に宗教と呼ばれうる道の歩み方である。そのことを釈尊はまず、この「大いなる放棄」において、身をもって垂範している。(40~41頁) 第4章 大いなる道生ずー成道 ■「仏陀はいかにして出家したもうたか。 彼はいかに観察したまいしがゆえに、 出家を大いに喜びたもうたのであるか。 仏陀の出家についてわたし(阿難)は語ろう。 『家居は狭隘(きょうあい)にして煩わしく、 塵垢(じんこう)の発(おこ)り生るるところ。 しかるに、出家は広寛にして煩いなし』 かく観察して、仏陀は出家したもうた。 ぶっだは出家したまいてより、 身による悪しき業を避けたまい、 語による悪しき業を捨てたまい、 あまねく生活を浄めたもうた」(42頁) ■つかわされた使者は、釈尊のあとに随(つ)いて行った。釈尊は托鉢をおえると、ラージャガハの郊外なるパンダヴァ山の洞窟へと帰りゆいた。「大王よ、かの比丘は、パンダヴァの前面なる山窟の中に、虎のごとく、牛のごとく、獅子のごとく坐している」。帰り報じた使者の言をきいて、ビンビサーラ王は、かの山窟に釈尊を訪れた。対坐して、喜ばしい挨拶のことばをかわしたのち、王は釈尊に言った。 「なんじはいまだ若く、年すくなく、 人生の第一期に達したばかりである。 なお豊かなる青春を保持して、 しかも由緒ただしき刹帝利(クシャトリヤ)なるがごとし。 われはなんじの欲する禄を与えよう。 光輝あるなんじは、わが精鋭なる軍に加わり、 戦士の栄誉を享受するがよい。 われは問う。なんじの生まれを語れ」 それに対する釈尊の答えもまた、偈文(げもん)をもって、かように記されている。 「王よ、かの大雪山(ヒマーラヤ)の山のふもとに、 いにしえよりコーサラ国に属し、 財宝と勇気を兼ね備えたる、 端正なるなる一つの部族がある。 その部族を「太陽の裔」(日種)といい、 わが生族をサキャ(釈迦)となす。 王よ、その家よりわれは出家した。 もろもろの欲を冀求(ききゅう)せんがためではない。 もろもろの欲の災いを見おわって、 迷いをいで欲を離るるこそ安穏なりとするがゆえに、 その道に精勤せんと、われは思う。 緒欲にあらず、精勤をこそ、わが心は喜ぶ」(46頁) ■たとえば、六師外道はそのころの沙門たちの学派の六つの代表的なものであったが、彼らが主として論陣を張ったのも、このマガダにおいてであった。また、釈尊がその出家後師事ことがあったというアーラーラ・カーマーラおよびウッダカ・ラーマプッタの二人も、マガダにあった沙門団の統率者であった。されば、さきに述べたように、出家して沙門となった釈尊が、まず南行してラージャガハ(王舎城、マガダの都)の方面にその姿をあらわしたこともまた、かかる時代の雰囲気を知るとき、その当然しかるべかりしゆえんのあったことが理解せられるのである。(49頁) ■さらに、わたしどもは、中部経典のうちの『聖求経(しょうぐきょう)』とよばれる一経をひもとく時、そこに出家後の釈尊が、どのような考え方をもって、求道の一途を邁進せられたかを、釈尊自身の述懐の形式において見いだすことができる。 「かようにわたしは聞いた」と語りいずるこの経は、例によって、この教法の語られた因縁を、このように伝えている。その時、釈尊は、サーパッティー(舎衛城)の郊外なる祇園精舎にあった。比丘たちは、ここしばらくの間、釈尊の説法に接しなかったので、アーナンダに請うて、「われらは、世尊の説法をききてよりすでに久しい。願わくば、世尊の放談を聴くを得ば幸いである」と言った。その願いは早速に容れられて、その夕頃(ゆうけい)、彼らが、波羅門ランマカ(羅摩)の庵(いおり)にいると、釈尊はそこを訪れて、彼らのために説法した。 「比丘たちよ、人の求むるものに、二種の求めがある。すなわち、聖なる求めがあり、聖ならざる求めがある」 かく説きいでて、釈尊は、まず、何が聖ならざる求めであり、何が聖なる求めであるかを語った。ー人は生老病死の法(ありかた)の中にあり、また愁(なげ)きの法、穢(けが)れの法の中にある。かかる者が、依然としてかかるあり方、かかる生き方をのみ追い求めていたならば、いずれの時にか解脱、向上の時があろうか。それが聖ならざる求めというものである。それに対して、もし人が、生老病死の法の中にありながらもその患(わざわ)いなることを知り、愁きの法、穢れの法の中にありながらも、その然るべからざるゆえんを知って、より高きあり方、より優れた生き方、無上安穏の涅槃の境地をあこがれ求むるならば、それが聖なる求めというものである。ーそして釈尊は、そのことを、みずからたどって来た道をふり返り、しみじみと身の体験するところに当てて、説きすすめる。その中に、わたしどもは、釈尊のあるいた求道のあとを、かなり詳細に知ることができるのである。(49~50頁) ■かくて出家の修行者となった釈尊は、いかなる困難をもおかして、すべて善なるものを求めよう、無上の寂静を求めよう、最上の道を追求しようと決意して、まずアーラーラ・カーラーマなる沙門を訪うて、彼に師事した。そして、精進刻苦の結果、久しからずして、その師の説く境地を到りきわめることを得た。経典はその境地を、「無所有処」と語っている。だが釈尊は、かかる境地にきわめ到った結果、その教えがなんら「智にみちびかず、覚にみちびかず、寂静涅槃にみちびかざるもの」であることを知って、この師のもとを去って行った。(50~51頁) ■ついで釈尊は、ウッダカ・ラーマプッタなる沙門を訪うて、彼に師事したが、そこでも結局、おなじような結果をくりかえしたにすぎなかった。この師の語る最高の境地は「非想非非想処」と呼ばれている。その境地を釈尊は、非常なる精進努力をもって、久しからずして、きわめ到ることを得た。だが、きわめ到ってみると、その道もまた、「智にみちびかず、覚にみちびかず、寂静涅槃にみちびき到るものではない」ことを知って、またこの師のもとを去って行った。(51頁) ■菩提樹の下に坐した釈尊は「われよく煩悩を滅し尽くすことをうるまでは、要(かな)らずこの坐を解かじ」と念じて、懸命の思索精進をつづけた。その間、釈尊の心裏に去来したものが何であったかを、わたしどもはつぶさに知ることはできないが、なお、いささかその心のうごきをうかがうべき手がかりを、ふるき経典は記しとどめている。 相応部経典の第四に『悪魔相応』と名づけられる一群の短い経が存する。そこには、釈尊がさまざまの悪魔の試みにあい、しかもそれらによく打ち克ったことが語られてある。それは、かのイエスが荒野にみちびかれ、悪魔の試みにあったという、かの「福音書」の記事を思いおこさしめる。だが、ここ釈尊の場合は、イエスのそれに比して、悪魔なるものの考え方が、きわめて高い意識の中に受けとられていることが知られねばならない。それは悪魔とよばれ、悪魔波旬と語られている。だが、わたしどもはまた、ある経において、「悪魔、悪魔と語られるが、それは心のあしき動きに外ならない、煩悩のわざの外ではない」と語られていることをも思いだすことができる。しかるとすれば、いま菩提樹下の金剛不動の坐にあって、悪魔にこころみられ、かつこれに打ちかったという、ふるき経典のしるすところは、とりもなおさず、そのとき、釈尊が、煩悩との戦いをいかに戦ったか、聖なる求めをいかに精進したかを、いささかうかがい知るべき手がかりをあたえるものなのである。 その一つの場合は、このように記されている。ーそのとき、釈尊は独坐静観のうちに、このような思いをした。「ああ、わたしはかの苦行より離れた。なんの利をもたらすことなき、苦行を離れたことは善いことであった」。すると、その時、悪魔波旬は、世尊の心に思うところを知って、世尊の前にあらわれ、偈をもって語って言った。 「苦行を修しつづければこそ、 若き人々は清められるのである。 浄き道をさまよい離れて、 浄からずして、なんじは清しと思う」 だが釈尊は、それを悪魔のわざであると知って、偈をもって答えて言った。 「陸にあげられし船の艣舵(ろだ)は、 何の利ももたらすことがない。 不死を願うに苦行をもってするも、 また何らの利あることなしと知る。 われは、戒と定と慧とをもて、 この菩提(自覚)の道をおさめ、 上なき清浄にいたりついた。 破壊者よ、なんじは敗れたのである」 かくて、悪魔は、「世尊はすでにわれを知りたもう」とて、苦しみしおれて、その姿を没したという。(53~54頁) ■その苦行のために、釈尊は、髪はよもぎのようになり、眼はくぼみ落ち、骨はあらわれて、腹の皮と背の皮とがくっつきそうになった。だが、それにもかかわらず、真のさとりは一向に彼を訪れなかった。その時、付近のネーランジャラー河の堤のうえを、民謡をうたって通る農夫の声がきこえてくる。耳をかたむけるともなく聴けば、 「絃(いと)がつよすぎると切れる。 弱いとよわいでまた鳴らぬ。 程ほどの調子にしめて、 上手にかきならすがよい」 という意味のことであった。その時、釈尊の心の中に霊感がひらめき、そこで彼はすっぱりと苦行をやめた、というのである。(54~55頁) ■そのほかにも、彼がたたかわなければならぬ悪魔は、けっしてすくなくなかった。愛欲もそれであった。貪欲(とんよく)もそれであった。権勢もそれであった。青春なお豊かなることに名残りおしいと思うこともあった。樹下のねむりを、高牀(こうしょう)のやすき眠りにかえたいと思うこともあった。だが彼はそれらのことごとくに、よく打ち勝つことを得た。聖なる求道を妨害せんとする破壊者は、ことごとく敗れしりぞいた。そのさまを経の一偈は「膏石(あぶらいし)を襲いし鳥のごとく、気くじけてゴータマより去れり」とて、かく述べ記している。 「あぶらにも似たる石をみて、 ここに軟(やわらか)き、甘きを得むと、 鳥は空より舞い来たりしが、 そこに甘き、軟きを得ずして、 空のかなたにとび去れり」 そして、ついに大覚は成就した。かの菩提樹の蔭涼やかなるところ、サキャ族より出家した聖者によって、「いまだ起こされざりし道は起こされ、いまだ生ぜざりし道は生じ、いまだ知られざりし道は知られた」のである。(56頁) 第5章 汝らも見よー正法 ■たとえば、かのよく知られた梵天勧請の説話を、熟考検討してみるがよい。それは、梵天の勧請に仮托して、釈尊がその内証を世間の人々にむかって伝達すべきやいなや、その可能性をみずから検討して、ついに伝道の決意をした心境のいきさつを語れるものであるが、そのとき、釈尊のまず考えたことは、「欲望のむさぼりや瞋(いか)りの心にまどわされた人々にとっては、この法は悟ることはやすからぬものである」ということであった。「それは世の流に逆らい、はなはだ微妙であって、甚深(じんじん)・難見であるがゆえに、欲に著(じゃく)し、暗黒におおわれた者は、とうてい見ることを得ぬであろう。いまわが刻苦して証得せるところを説くといえども、結局むだであろう」。かく考えた時に、釈尊の心は黙止すべき方(かた)に傾いていた。その釈尊の心がやがて伝道に傾き、この法を説かんことを決意するにいたった理由は、詮ずるところ、この法はなるほどはなはだしく深くして、見がたく、知りがたいものであろうけれども、なおよくこの法を聞いて悟りうる者の存することを、観察しかつ確信し得たからにほかならなかった。その観察したところを、経典のことばは、紅白の蓮の咲ききそえる蓮池に引例して、美しい譬喩をもって語っている。「たとえば、蓮池において、青き紅きまた白き蓮の生い繁れるさまを見るに、あるものは、水中に生じ、水中に長じ、水中に沈みてある。また、あるものは、水中に生じ、水中に長じ、水面にいたってある。またあるものは、水中に生じ、水中に長じながらも、水面を抜いて、水に染まらずしてあるものもある」。それとおなじように、世間の人々のあり方もまた、さまざまであって、一方においては、欲に著(じゃく)し、暗黒におおわれて、とうていこの法を理解しうるとは思われぬ人々もあるが、その他面においては、かかる塵垢(じんく)のすくなくして、よくこの法を理解しうると思われる人々も存する。そのことを釈尊は、観察しかつかくしんすることを得たのであり、かくて、「甘露の門は開かれたり。耳ある者は聞け」と、この法を説かんことを決意したのであった。それが、梵天勧請の説話がわたしどもに語り示すところの釈尊の心境の展開であった。(57~58頁) ■「如来はこれをさとり、これを知りて、教え示し、宣(の)べ弘め、詳説し、開顕し、分別し、明らかにして、しかして『汝らも見よ』というのである」 と語られたこともあった。ではわたしどもは、釈尊の教え示されるところについて、釈尊の言うところの「この法」とは何であるかを、まず問い入り、尋ね入ってみなければならぬ。けだし、菩提樹下の大覚成就以後の45年にわたる釈尊の生涯は、ただこの自内証の法の宣説と、その実践とであったと信ぜられるがゆえに、まずこの法の真相に近づきうかがうことなくしては、わたしどもは、一歩といえども大覚成就以後の釈尊の生涯に、立ち入ることはできないのである。(59頁) ■「比丘たちよ、わたしはまだ正覚(さとり)を得なかったころのこと、かように考えた。ーーまことに、この世間は苦の中にある。生まれ、老い、衰え、死し、また生まれ、しかも、この苦を出離することを知らず、この老死を出離することを知らぬ。いったい、いかにしたならば、この苦なる老死からの出離を知ることができようか」(59頁) ■「比丘たちよ、その時、わたしはかように考えた。ーー何があるがゆえに、老死があるのであろうか。何に縁(よ)って、老死があるのであろうか」 また、 「比丘たちよ、その時、またわたしはかように考えた。ーー何がなければ、老死がないのであろうか。何を滅すれば、老死を滅することをうるであろうか」 そのように考えることによって、釈尊はついに、「いまだかつて聞きしこともなき法において、眼(まなこ)生じ、智を生じ、明(さとり)をうることを得た」と語っているのであるが、しかし、この法なるものは、いまだかつて、なかりしものを、いまここに新たに生み出したものではなくして、いわば、古くから存していたものを、いま見いだしたにすぎないのであるとて、このような譬喩を、そこに語りいでているのである。 「比丘たちよ、たとえば、ここに人ありて、林の中をさまよい、ふと古人のたどった古い道を発見したとするがよい。またその人は、その道にしたがい、すすみ行いて、古人の住んだ古い城、園林があり、岸もうるわしい蓮池のある古城を発見したとするがよい。 比丘たちよ、その時、その人は、王または王の大臣に報じて言うであろう。ーーわたしは、林の中をさまよって、ふと古人のたどった古道を発見した。その道によって進みゆいてみると、古人の住んだ古城がある。園林があり、岸もうるわしい蓮池もある古城である。願わくは、かしこに城邑(まち)を築かしめたまえ。 比丘たちよ、そこで王または王の大臣は、そこに城邑を築かせたところ、その城邑はさかえ、人あまた集まり来たって、殷盛をきわめるにいたった。比丘たちよ、それと同じく、わたしは過去の正覚者たちのたどった古道、古径を発見したのである」 釈尊がしばしばこのような説き方を、この法について試みられていることは、何を意味するものであろうか。わたしどもは、まずその意味するところを、とくと考えてみなければならない。そして、その意味をよく掬(きく)することを得たならば、その時、わたしどもは、この法なるものの性格の一片を、まずうかがうことができたと称することをうるであろう。 では、釈尊はいかなる意味をもって、この法を古道、古径ににたとえて語ったであろうか。それは古今と東西とを問うことなく、時間と空間とを貫いて、この法は常恒(じょうごう)に存しているものであることを言わんとするのほかではなかった。それは、釈尊がこの世にいでて、釈尊が考え出したというがごときものではなかった。あるいはまた、わたしどもが釈尊の教え示すところによって、新たに体系づけるとき、その時はじめて生まれて来るがごときものでもなかった。さらにまた、それは仏教の世界に存し、他の思想に存しないというがごときものでもない。そのことを、釈尊はまたある時、 「如来のこの世にいずるも、もしくは如来のこの世にいでざるも、このことは定まり、法として定まり、法として確立している。すなわち相依性である。如来はこれを証(さと)り、これを知る」 と語ったこともあった。それは、釈尊がこの世に出ようと出まいと、元来厳として存し、厳として確立しているものである。ただ、釈尊のいでて、これを証得し、これを教示するまでは、わたしどもにはそれが知られていなかった。この法はそのようなものであるがゆえに、それを釈尊は、譬喩をもって、「わたしは古道を発見した」と説いているのであるそのことを、わたしどもは、まずはっきりと承知しておきたいのである。(61~62頁) ■「これあるに縁(よ)りてかれあり。これ生ずるに縁りてかれ生ず。これなきに 縁りてかれなし。これ滅するに縁りてかれ滅す」(67頁) 第6章 真理の王国なるー伝道の決意 ■その頃、世尊は、ひとり坐し、静かに観じて、かくの如く考えたもうた。『尊敬するところのものなく、恭敬するところのものなき生活は苦しい。われは如何なる沙門もしくは波羅門を敬い、尊び、近づきて住すべきであろうか』と。(71頁) ■ーーもしわたしが、いまだ戒について満たされぬものがあり、定(じょう)について満たされぬものがあり、また、智慧について満たされざるものがあり、それらについて、依ってもって学ぶに足るほどの沙門もしくは婆羅門がありとするならば、その人を敬い尊び、近侍して学ぶという理由はある。だが、わたしはいま、戒にちうても、定についても、解脱のための智慧についても、尊敬し近侍して、依りて学ぶべき人物をどこにも見いだすことはできない。それについて、わたしよりも優ったものを、遺愾(けいけ、リッシンベンに感)ながら、わたしはどこにも見いだすことはできない。ーーかように考えて、結局、釈尊が到達したところのものは、「われはむしろ、わが悟りし法、この法をこそ、尊び敬い、近づきて住すべきである」との結論であった。(72頁) ■世の多くの宗教においては、「依人(えにん)」すなわち人に依ってその信仰を樹立することが説かれている。わたしどももまた、ともすれば、ひとによってその信を樹(た)つることに心やすきをおぼゆる。だが、釈尊の道は、明々白々に「応(まさ)に法によるべく、人に依らざるべき」ことを教える道であった。そのことのもっとも堅確なる表現は、この師が入滅を前にして弟子たちのために垂れたもうた訓誡の中にある。 「ここにみずからを燈明とし、みずからを依所(よりどころ)として、他人を依りところとせずして住せよ」 それは、わたしどもが「自帰依、法帰依」の教えとして、もっとも感銘ふかく記憶するところのものであって、そこに正法中心の宗教である仏教の立場がもっとも明白に、かつ厳粛に宣言せられているのであるが、かかる仏教の基本的な立場は、そのはじめ、いかにして自覚され、確立されたものであるかといわば、わたしどもはこの樹下(じゅげ)の瞑想の間に去来せし釈尊胸中の思念を指して、ここに正法中心の立場は確立したのであるとすることができる。(72~73頁) ■ひるがえって考えてみると、釈尊は、そのはじめ出家して行乞の沙門となった時には、ただ自己の苦悩の解決を得んがためであった。したがって、その苦悩の解決を求めて、ついに最高の智慧に到達した時、彼の目的は一応達せられたのである。静かにこの最高の智慧を味わい、それに随い順じて、不死安穏の生涯をうることを得ば、そのほかに何の求むるところもないはずであると思われる。しかるとすれば、大悟まもなき釈尊が、沈黙にかたむいて、説法を思わなかったとしても、一応それは当然であると言うことができる。いなむしろ、彼が本来の目的よりいわば、説法すべきか沈黙すべきかというがごとき問題はないはずであるとも言うこともできる。(77頁) ■かく言うのは、けっして、単なる推測でもなく、また単なる理窟でもない。相応部経典の『七年』と題される1経は、これまでの仏伝研究者によってまったく看過されているが、そこには釈尊もまた、かく思われたことがあったであろうことを、うかがい知るべき手がかりが存している。そのとき、釈尊はネーランジャラー河のほとりの一樹のもとに止まっていた。すると、出家以来7年の間、たえず彼につきまとっていた悪魔が、彼の前に姿を現わして、偈文をもって語りかけた。その一節はかようであった。 「もしなんじの言うがごとく、 安穏不死にいたる道を知らば、 行けよ、なんじ独りゆけよ。 何のために他に教えんとするか」 ここに悪魔の呼びかけとして記されているものは、既に言うがごとく、釈尊の心中に去来せし疑念であったにちがいない。そのとき釈尊もまた、最高の智慧を得、安穏の生涯を成じたるうえは、また何の他に求むるところがあろうかと考えたに相違ない。さらにはまた、何のために自分は、他の人々にこの法を説かんとするのであるか、と自問したに違いあるまい。(77~78頁) ■鹿野苑(ミガダーヤ)に到着した釈尊は、そこでもまた抵抗を見いださねばならなかった。5人の修行者たちは、必ずしも快く彼の説法に耳を傾けようとはしなかった。彼らは、釈尊の来るのをはるかに見て、互いに約して、「彼に礼をなすなからん、起ちて迎うることなからん、彼の衣鉢(えはつ)をとるなからん」と云い合わせた。釈尊が彼らのもとに到り彼らとともに坐した時、彼らは釈尊を呼ぶにその名をもってし、また同輩をよぶ呼称をもってした、と経典はしるしている。彼らのかかる態度の理由は、さきに釈尊が苦行をすてたことをもって、努力をすて快楽に堕したものと解したからであり、かの「精勤(しょうごん)を捨て、奢侈(しゃし)に堕し」た沙門が、大いなる悟りを獲得しえようとは思えなかったからであった。 「比丘たちよ、善く聴け、われはすでに不死を証得せり。われ教うべし。法を説くべし」 かように、釈尊は彼らに語りかけたが、彼らは聞こうとはしなかった。3たび重ねて呼びかけたが、彼らは3たび聴くことを拒んだ。そこで釈尊は、あらためて彼らにいった。「比丘たちよ、わたしはこれまで、なんじらに対してこのような言い方をしたことがあったであろうか」そういわれてみると、今日のこの沙門は、かの時の沙門とはちがっていると、彼らも思わずにはいられなかった。そして、では、そのいうところを聴いてみようとの心が、やっと彼らにきざしてきた。 かくして、釈尊がこの5人の修行者を前にして説きいでたものは、中道の宣言であり、4つの真理であり、8つの実践の項目であった。ふるき経典は、そのとき諸天は声を発して、この初転法輪を賛嘆し、大千世界はために動きふるい無量の光明は世間に充満したと記している。その荘厳の描写は古典的であるが、その意味するところは何であったかを、わたしどもはふかく潜り入って理解しなければならぬ。(82~83頁) 第7章 鹿のすむ園にてー最初の説法 ■その根本的立場は何であったか。「比丘たちよ、世に2つの辺(極端)があるが、出家の者はそれらに親近(しんごん)すべきではない。その2つとは何であるか」そして釈尊は、1つの極端として快楽主義をあげ、他の極端として快楽主義を指し、そのおのおのを批判して、それらは無義相応である。道理にふそうものにあらず、聖賢の道にあらずとしてしりぞけ、「比丘たちよ、如来はこれら2辺を捨てて中道を現等覚せり」と宣言する。これが最初の説法の冒頭におかれる「中道の宣言」であった。 では、この中道とは何であるか。それを、人々の生活実践のうえに当てて言わば、いかに考え、いかに語り、いかに行為することが中道にかなうものであろうか。 「比丘たちよ、では何をか中道となすか。それは、すなわち8つの正道である。いわく、正見・正思・正語・正業・正命・ならびに正精進・正念・正定である。比丘たちよ、これらが如来の悟得せるところの中道であって、これは眼を開き、智を発し、寂静を得しめ、涅槃におもむかしむるであろう」(84~85頁) ■「比丘たちよ、苦の聖諦とはかくのごとくである。いわく、生は苦である。老は苦である。病は苦である。死は苦である。怨み憎む者に会うは苦である。愛する者に別れるは苦である。求めて得ること能わざるは苦である。略説すればこの五蘊(身心)はすべて苦である」(85頁) ■それとともに釈尊はまた、この人生観察の結論「一切皆苦」の前に心くじけて、厭世の囚虜(とりこ)となりおわった人ではなかった。中道の立場は、そのこともまた許さない。むしろ彼は、毅然として、この人生苦の解決の道をたずねた。すなわち、その原因をたずね得て、これを第2諦において宣明し、さらにその対治の処方をもとめて、これを第3諦において説き、またその対治の実践の体系をたてて、これを第4諦に述べているのである。(86~87頁) ■「比丘たちよ苦の集(生起の因)に関する聖諦(しょうたい)はこれである。いわく、後(ご)有をもたらし、喜貧(きとん)倶(とも)におこり、随処に歓喜する渇愛である。それに欲愛と友愛と無友愛とがある」 では渇愛とは何であろうか。 仏教において語られる愛ということばは、必ずしも常に美しい印象をまとえるものではない。それは、もっと厳粛に「一切」をあらしめる根源的な力を指している。ある時、釈尊は、このように説いたこともあった。 「比丘たちよ、わたしはいまなんじらのために〈一切〉なるものを説こう。よく聞くがよい。比丘たちよ、何をか〈一切〉というのであろうか。眼と色、耳と声、鼻と香、舌と味、身体と感触、心と法、比丘たちよ、これを〈一切〉というのである」(87頁) ■私を衝きうごかしてくる力がある。その現れたものが、わたしども人間のさまざまの欲望であって、それに欲愛(自己延長の欲求として性欲を代表とする欲望)と友愛(自己保存の欲求として食欲を代表とする欲望)と無有愛(名誉権勢の欲求にあらわれる欲望)とがあると、釈尊は分析を試みている。(88頁) ■かく知ることを得れば、「一切皆苦」の人生にたいする対治の処方は、縁生縁滅の法則によって、おのずからにしてうまれる。すなわち、「これなきに縁りてかれなし。これ滅するに縁りてかれ滅す」この公式に当てて、「何がなかったならば、かかる人生はないのであろうか」と問えば、そこに、第3の聖諦が生まれてくるのである。いわく、 「比丘たちよ、苦の滅に関する聖諦はこれである。いわく、この渇愛をあますところなく離れ滅すれば、解脱して執著なきにいたる」(89頁) ■そしてさらに、そのことは、如何にして生活実践の中に実現せらるべきかとなれば、そこに第4の聖諦、苦の滅にいたる道(実践)に関する聖諦が、さきに述べた8つの正道をその内容としてかたられるのであった 「比丘たちよ、苦の滅にいたる道に関する聖諦はこれである。8つの正道がそれである。いわく、正見・正思・正語・正業・正命ならびに正精進・正念・正定である」(89頁) ■そのことを解いてゆくためには、苦行をすてたことは1つの極端を去って中道の立場をとったことを意味すると納得せしめねばならぬ。「世には2つの極端があり、それらは道理にかなわぬ道である。わたしはそれらの2つの極端をすてて中道をとった」その冒頭のことばは、釈尊にとって自己の道の根本的立場の宣明であるとともに、この5人の修行者に対する自己弁明でもあった。 ともあれ、ここに、仏教の基本構造は語り明かされた。5人の修行者はその所説と熱心に取組んで、それを理解しようとした。ふるき経典によると、「3人の比丘乞食にゆき、その得たる所によりて6人住せり」とも記されておる。(91~92頁) ■そして、ついにまず、5人のうちの1人、コンダンニャが悟ることを得た。「コンダンニャは悟った。コンダンニャは悟った」と釈尊は歓喜した。(92頁) ■「その時、この世間に阿羅漢は6人となれり」と、ふるき経典は記している。(92頁) ■ともあれ、かくしてヤサの父は、釈尊の在俗の信者の最初の人となった。そのことを経典は「彼は世間に初めて三帰依を唱えた優婆塞なりき」と記している。そして、ヤサもまた、出家して釈尊の弟子となることを許された。そのことは、バーラーナシーの町の人々に大きな影響をもたらした。「長者の子ヤサは、鬚髪(しゅはつ)を剃り、袈裟衣をつけ、家を捨てて出家した。それはきっと優れた教法にちがいあるまい」そのように聞き、そのように考えた良家の若者たちが、はじめは4人、のちには50人、ミガダーヤの園に釈尊を訪れ、その教えを聞いて、相ついで出家して沙門となった。かくて「その時、この世間に阿羅漢は61人となった」と経典はしるしている。 だが、ミガダーヤにおける釈尊の教化の活動はやがて終り、彼はまた、新興の国の都ラージャガハ(王舎城)を指さして、伝道教化のさすらいの旅にのぼるのである。(96頁) 第8章 世の幸福のためにー伝道の宣言 ■釈尊はかって、いまだ聖者にはあらぬ者が、聖者のごとくふるまうことほど賤しいことはないと語ったこともあった。(100頁) ■そしていまや、この人間自覚の道をひっさげて、ひろく人々の間に宣べ伝えんとするにあたっても、われら(釈尊ならびに弟子たち)はすべてすでにふさわしきものである、阿羅漢(arlat=deservinng 応供)であることを宣明することが必要であったのである。(100~101頁) ■「盲人が盲人の手引きして、ともに堕獄に陥ちる」がごときことをしてはならぬ。(101頁) ■「世間をあわれむがゆえに、彼らの幸福と利益とを念ずるがゆえに、わたしどもは人人の間にこの自覚の道をもたらさんとするのである」そのことを釈尊はついで語っている。そして、「1つの道を2人してゆかぬがよい」と語り加える。そのことばは、わたしどもにとって、はなはだ感銘のふかいものであった。(101頁) ■わたしどもはイエス・キリストが、その12人の弟子をはじめて福音伝道に送り出すとき、彼らにあたえたことばを知っている。そこでは、「2人ずつ遣わされ」「人々に心すべき」ことが、ことばをきわめて語られてある。「視よ、我なんじらを遣わすは、羊を豺狼(さいろう、山犬と狼)の中に入るるが如し」とも語られ、「このゆえに、蛇のごとく慧(さと)くあれ」とも教えられてある。それらのことばに比するとき、わたしどもは、釈尊の伝道の宣言が、いかに平和と良識とに充ちていたか、いかに人々にたいする純粋の愛情にあふれていたかについて、ふかい感銘をもたざるを得ないのであるが、かかる平和と良識と愛情とは、さらにこの「1つの道を2人して行かぬがよい」という1句の中に結晶しているのである。(101~102頁) ■さらにわたしは、「世間われとあらそう。されどわれは世間とあらそわず」といった釈尊のことばを思い出す。釈尊の理解するところによれば、この世界の存在の仕方は、対立性のものではなくして、むしろ、相依(そうえ)性のものであった。相依性こそが縁起の本質であった。そして、かかる人生の態度に徹せるがゆえに、仏者にとっては、「人々に心する」用もなく、「蛇のごとく慧(さと)く」ある用もなかった。とすれば、豺狼(さいろう)の中におもむく者は2人して行かねばならぬであろうが、仏者は「1つの道を2人して行かぬがよい」と教えられねばならぬ。なんとなれば、恐怖をもって警戒すべき何者もなく、ただ念ずるところは、1人でも多くのものが、法を聞き、法に眼を開かんことであったからである。(102頁) ■ギリシャ人は、こよなく雄弁を愛したことがよく知られておる。また、その雄弁は、合理的精神と芸術的精神との所産であったと語られている。さらにまた、その聴衆はすぐれた素質ある人々であったがゆえに、弁者は充分の敬意を彼らにたいしてはらわねばならなかったのであって、そのことは特に、アテナイの雄弁家たちの演説が、その結語を興奮なき静けさもて述べたことにおいて示されているという。聴く者にたいして権威ある者のごとくふるまうものは、単にその結論を力強きことばをもって押しつけるであろう。また、聴衆の感情に訴えをなさんとする者は、高まりゆく興奮の中においてその結語を述べんとするであろう。しかるに、その結論を興奮なき静けさの中において述べたアテナイの雄弁は、弁者が聴く者の理性にたいして敬意を表しつつ、もう1度最後の説得をなすものであった。(102~103頁) ■しかるに今、釈尊の語る説法の理想も、またかかるものであった。それは「義(ただ)しき道理と表現とをそなえねばならぬ」と、語られている。そのことは、ギリシャの雄弁が、合理的精神と芸術的精神との要求に応えるものであらねばならぬとされたことに平行する。また、その説き方は、「初めも善く、中ごろも善く、終りも善く」と語られていた。そのことは、終始一貫して、理論的に、かつよき表現をもって、聴く者の理性に訴うべきことを意味していたのである。それは無論、結語を感情をゆりうごかす行き方でもなかった。初・中・終を一貫して、理路と表現とを兼ねそなえて、静かに理性が理性にむかって語りかける。それが、釈尊のみずから行ない、かつその弟子たちに求めた説法の理想であった。(101頁) ■そして、かかる説法の理想はイエスのそれとはまったく対照的であったことも、また、興味ふかく思われる。イエスがその弟子たちに教え、彼らを伝道に送り出したとき、彼らはただ「往きて宣べつたえ、〈天国は近づけり〉と言え」と、その語るべきことの内容を指示されたのみであった。また、もしも、司たち王たちの前に曳かれるようなことがあっても、「如何になにを言わんと思いわずらうな、言うべきことは、その時さずけられるべし、これ言うものはなんじらにあらず、その中にありて言うものはなんじらの父の霊なり」と教えられた。そこには、理性が理性にからりかけるがごとき説教は、まったく求められてはいない。語るものはただ霊にみたされて、「舌語りに」語ればよかったのであり、人々はただその福音をうけ容れるべきか否か、いきなりその選択の前におかれるのであった。したがって、福音書の記者たちも、イエスの説法に接した人々の感想を書きとどめて、「それは学者のごとくあらず、権威あるもののごとく説きたもうた」としるし、また人々はその説法におどろき合って、「こは如何なる人ぞ」「こは如何なる言(ことば)ぞ」と語ったという。それは、釈尊が理想としたものとまったく別の世界のものであった。(103~104頁) ■あるとき、釈尊は、そのことを3つの田の譬喩をもって、このように語ったこともあった。それは、ある部落の長が、「世尊は、すべての人にたいして慈悲の心をもち、すべての人を利益せんとの心であられるのに、ある人のためには詳しく法を説き、ある人々のためには、さほど詳しく説かれないのは、何故であろうか」と問うたことに対する答えであった。 「部落の長よ、なんじは、かかる場合にはいかに思うか。ここに一人の農夫があって、彼に3つの田があるとするがよい。その1つは中等の田であり、いま1つの田は、悪質の砂地であって、塩分をふくんでいるとする。それらの田にたいして、彼が種子を蒔かんとするには、まずいずれの田からはじめるであろうか」 かく言われて、部落の長はむろん、「その農夫はまずもっともすぐれた美田に種子をおろすであろう」と答えるのほかはなかった。 いま釈尊は、その弟子たちを伝道に派するにあたっても、この法の種子のまず播(ま)かるべき美田は、いかなる人々であるかを、ここに語り教えている。それは「汚れすくなき生を受けた人々」であった。若くして、いまだ世間の汚れになじむこと少なく、教養にも知性にもすぐれた人々。やがて釈尊の教団に相ついで来り投じた人々は、かかる人々であったのである。(104~105頁) 第9章 すべては燃ゆるー山上の説法 ■「比丘たちよ、すべては燃えている。熾燃として燃えさかっている。なんじらは先ずこのことを知らねばならぬ」 それは、これまでの釈尊の説法と、その概念をはなはだ異にしていた。理路整然として、人生のあるがままの観察より出発して、その原因の追求、その処理の原理、そしてその実践の方法ーーそれの典型的な説き方が四諦説法であったーーへと説きおよんで行った釈尊の説法は、いまや焔という1つの譬喩をもって装われ、かつ簡明にされようとしているのである。 「比丘たちよ、すべては燃えているというのは、いかなることであろうか。比丘たちよ、人々の眼は燃え、また眼の対象は燃えている。人々の耳は燃えまた耳の対象は燃えている。人々の鼻は燃え、鼻の対象は燃えている。人々の舌は燃え、また舌の対象は燃えている。身体は燃え、身体の対象は燃えている。さらに、人々の意(こころ)もまた燃えており、その対象もまた燃えているのである。 比丘たちよ、それらは何によって燃えているのであろうか。それは、貪欲(むさぼり)の焰によって燃えており、愚痴(おろかさ)の焔によって燃えているのであり、また生・老・病・死のほのおとなって燃え愁(うれい)・苦(くるしみ)・悩(なやみ)・悶(もだえ)のほのおとなって燃えているのである」 いま釈尊の前にあって、この新しき師のことばに耳をかたむけている人々は、思えば数日の前では事火外道として事火法を修する人々であった。火は一切のものを清浄にするものとして、火を尊び、これに供養して福を求めんとする人々であった。しかるに今や彼らにとって、世界は一変した。この世のすべては、火によってさいなまれていると、このあたらしき師は説く。なんじの眼も、鼻も、舌も、耳も、身も意(こころ)も燃えていると語られる。煩悩のほのおが一切をもやしているのが、すべての人々と世界とのあり方であると指摘せられる。この一変した世界と人生の観方は、彼らにとって、際だってつよい印象をもって迫ってきたに相違あるまい。そこで、釈尊は、さらに語りつづける。 「比丘たちよ、そのように観察する者は、よろしく一切をおいて、厭(いと)いの心を生ぜねばならぬ。眼において厭い、耳において厭い、鼻において厭い、舌において厭い、身において厭い、また意(こころ)において厭わねばならぬ。しかして、一切において厭いの心を生ずれば、すなわち、解脱することを得るのである」(112~113頁) ■だが、いずれにしても、この「涅槃」なることばは「煩悩のほのお」という譬喩に関連するものであったことは、確信してさしつかえない。すなわち、このことばは「吹き消される」という動詞を語源としてつくられた「火の(吹き)消されたる状態」という意味のものであったことは疑いを容れない。(114頁) ■かくのごとく、彼岸の境地が「涅槃」すなわち「煩悩の火の消えたる状態」をもって示すべきものであったとするならば、それに対して此岸の状態が「煩悩の火の燃えさかる状態」として考えられることは、むしろ単なる譬喩以上のものと言わなければならぬ。(115頁) ■それは、われらを縛して甲斐なき生死をくりまえさしめるがゆえに「爆」ーー縛するものとも呼ばれる。それはまた、われらの善根を毒するものであるがゆえに「毒」ーー毒するものとも称される。またそれは、われらの智明を蓋うものであるがゆえに「蓋」ーーおおうものとも名づけられる。そのほか、さまざまの語法があるが、なかんずくこれを「煩悩の焔」として考える考え方は、何よりも、人々の体験に即して、訴える力をもっている。(115頁) ■いま釈尊がラージャガハの都に入ったころ、その六師の一人なるサンジャヤという者もまた、この都のあたりに止住していた。 その主張するところは、真理なるものには一定の動かすべからざる常規はないのであって、自己にとって善と思われるものが善であり、自己にとって真と思われるものが真であるとするのであった。その所説は、あたかも古代ギリシャのソフィストたち、特にゴルギアスの虚無的な言説を彷彿たらしめる。経典はこれを呼んで「鰻論」と称する。かの二人もまたこの徒の中にあって、その高足として学修につとめていた。そして、この二人は親交を結んで、「もしいずれかさきに不死の道をえたならば、かならず教えるであろう」と相約していた。(119~120頁) ■だが、アッサジは、出家して日なお浅く、その師の教えを深く説くことも、またその要領を略説することもできぬ由を答えた。サーリプッタはそれでもあきらめなかった。「では、たとい深からずとも、また要領をつくさずとも、多少なりとも、片鱗なりとも、その師の教えについて語らんことを」と、彼に請うた。そのとき、アッサジが彼のために、その師の教えについて語ったことばは、ふるき経典につぎのごとく記しとどめられてある。 「諸々の法は因によりて生ずる。 如来はその因を説きたもう。 諸々の法の滅についても、 如来はまたかくのごとく説きたもう」 それはなるほど釈尊の教えの片鱗にすぎなかった。だが、サーリプッタは、それによって釈尊の教えるところがいかなるものであるかを洞見し得た。「生ずるものはみな必ず滅する。もしそれだけであるとしても、これは正しい教えである。この師の弟子たちは、すでに、愁(うれい)なき境地をさとっているにちがいない」それは、サンジャヤの徒にとっては、大きな驚きであったに相違ない。彼らは、その師によって、真理の客観的基準はあることなしと教えられた。(120~121頁) ■この二人(岡野注;サーリプッタとモッガラーナ)と、そしてその他のサンジャヤの弟子たちー経典はその数を250人としるしているーは、やがて竹林の園へと向かった。(122頁) ■「マガダの国の山の都(王舎城)に、 大いなる沙門は現れたり。 さきにはサンジャヤの徒を誘い入れ、 つぎには誰を誘わんとするか」 比丘たちは、人々の難詰することばをきいて、帰り来たって、釈尊につげた。それに対して釈尊は、かように教えて言った。「比丘たちよ、かかる非難のことばは、ながくつづかないであろう。おそらく7日をすぐれば消え去るであろう。もし人々が、行乞するなんじらを難じたならば、なんじらは偈をもって、かように答えるがよい」そして、ふるき経典は、その答えをもまた、偈文をもってかように記しとどめている。 「如来は法をもって誘いたまえり。 法に来たるをう嫉むものは誰ぞ」(122~123頁) 第10章 祇園精舎 ■釈尊の伝道の生涯は45年のながきにわたるものであった。それはほとんど半世紀にわたるものであって、世の教祖と称される人々に、かくも長い伝道の生活を有したものを、わたしどもは知らない。しかも釈尊は、かくも長きにわたる教化説法の間においても、なんらの基本的な変化をその教説の中に示していない。のみならず、その説法の態度や語調についても、わたしどもは、伝道の時期によっての変化をほとんど指摘することができない。いつも静かに、そして懇切に、彼は語った。その語るところは、つねに不動の道理と整然たる表現をたもっていた。(124頁) ■あるいはまた、ある経においては、ビンビサーラがなおマガダの国に君臨していることが知られる。またある経においては、すでにアジャータサッツ(阿闍世)王父にかわってその国を統べていた時代のものであることを知りうる。(125頁) ■そこで、その長者(岡野注;スダッダの妹の嫁ぎ先)はかの仏陀がこの都の郊外なるヴェルーヴァナ(竹林)という園林にとどまり住しておられること、そこはこの国の王によってこの仏陀に寄進せられた園林であることなどを語り、さらに、彼がその園林に多くの房舎をたてて寄進したことを物語った。この長者がその園林に房舎をたてた顛末は、律蔵正品(ほん)の一節によって、つぎのように伝えられている。 ある朝のこと、この長者は竹林を訪れた。まだ房舎のなかった竹林では、比丘たちは樹下や洞窟や藁堆(わらづみ)のうえにいね、早朝におきて威儀をととのえていた。長者はその様をみて、心に清浄を感じ、歓喜を感じた。出家の比丘の生活は、行雲流水の生活を建前とする。樹下に住み、石上に坐して、それをいささかも苦痛と思ってはならない。洞窟に住み、藁堆にいねて、なお厳然たる威儀を持せねばならぬ。いまこの師の比丘たちは、この出家の生活の建前を立派に実現している。そのことには自然に頭の下がる思いがする。だが頭がさがればさがるほど、尊敬すればするほど、比丘たちの樹下石上の生活が相すまないと思う。 「もしわたしが、あなた方のために房舎を造ったならば、住んでいただけるでいただけるであろうか」 「では、お許し願えないかどうか、ひとつ、世尊におたずね下さるまいか」 長者の熱心なことばにうごかせれて、比丘はこのことを世尊に報じた。するとはからずも、一定の制限のもとに比丘のために房舎をたててもよいということであった。そこで、かの長者は、よろこびいさんで、その園林に60の房舎をたてはじめた。それがすでに落成して、明日は、釈尊とその弟子衆を請じて、かの房舎を献ずるのだという。 「兄さん、そのような聖者があらわれるならば、わたしも行ってその方を拝したい」 「だが、釈尊とその弟子衆は、規律ただしい生活をしておられる。今日はもうかの仏陀を拝する時間ではない。明朝はやく行かれるがよい」 その夜、寝についたスダッタは、仏陀を拝したい思いにかられ、暁をまちかねて夜半三たびまで眼をさましたと、経典のことばはしるしとどめている。(131~132頁) ■ともあれ、歓喜と緊張に心はずませつつ、かの園林に近づいた彼は、思いもかけず、林間を遊歩するかなたの人から声をかけられた。それは、早朝のそぞろ歩きをしていた釈尊その人であった。それが仏陀なるかの人と知らされたとき、恐怖にも似た緊張は霧のごとく消えさって、ただ歓喜のみが彼の心をふくらませていた。「世尊よ、昨夜はやすらかに眠らせたもうか」近づいて釈尊の足を拝したとき、彼の口からはそのような心やすいことばが自然にでた。そのとき、釈尊が彼に答えたことばを、経典は偈をもってかように伝えている。 「貪りを離れ、清らかにして、心にけがれがなければ、 さとりに入れる者は、いずこにありても安らかに眠る。 すべての執著をたちきり、悩みを調伏したるがゆえに、 心は静寂に入りて、しずけくもまた安らかにねむるなり」(133頁) ■まもなくスダッタは、車に積んで黄金をはこばせ、それをもってジェータ(祗陀)王子の林に布かせはじめた。だが最初に運んだ黄金でしきつめた土地の広さでは、彼はまだ満足できなかった。 「もっと黄金を運んで来い。わたしは、この土地を全部しきめぐらさねばならぬ」 そして、黄金をつんだ車がまた、後から後からとつづいた。そのさまをみたジュータ(祗陀)王子は、さすがに心おどろき、胸をうたれた。 「長者よ、どうか一部分の土地を私のために残していただきたい。わたしもまた、あなたがかくまでも尊ばれる方に、布施したいと思う」 その申し出を、長者はこころよく受けた。この賢明な王子の胸にも、釈尊の教法への信の燈火がともりはじめたと思うと、彼はうれしくてたまらなかった。 やがて林の中に、精舎が建ち、講堂が建ち、厨屋・浴室・厠屋。阿屋(あずまや)がたち、経行堂がたった。王子のために残された土地には、王子によって門が建てられた。その規模と景観とは、今世紀になって発掘せられた遺蹟によっても、そぞろしのぶことができる。時の人々は呼んで、この精舎を「祗陀林なる給孤独の園の精舎(祗樹給孤独園精舎)と、この二人の名を冠して称した。給孤独とは、親なき子、子なき老人など、憐れな人々に施すの意であった。この富める商人は、以前から、心やさしく、数々の善行のあった人であって、かかる名をもって呼ばれていた。 程へて、釈尊は、サーヴァッティー(舎営城)に到着し、スダッタの供養をうけ、かつ、この新たに成れる精舎を献ぜられた。そのとき釈尊が、彼のために、謝意をこめて説いた偈を、経典はこのように記しとどめている。 「林苑を施し、果樹を植え、 橋を架し、船もて人を渡し、 曠野に泉水、井戸をひらき、 あるいは精舎を建立する。 かかる人々に於ては さいわい日夜に加わり、 戒をたもち、法を楽しみて、 後生に善道を得るであろう」 そして釈尊は、当来四方の僧伽(サンガ)の名において、この精舎を心よく受けさせ給うたという。 これが、いうところの祇園精舎の成立の因縁であった。(137~138頁) 第11章 人は何を願うべきかー涅槃寂静 ■「比丘たちよ。なんじら出家たる者は、髪を剃り、鉢を持して、家々に乞食(こつじき)して生を支える。乞食とは、世のもろもろの活命(かつみょう、生活の仕方)のなかの下端である。だが比丘たちよ、もろもろの秀抜なる人々が、かくのごとき生活に就くゆえんのものは、義(ただ)しき目的の存するによりてである。王に強いられたるにあらず、賊にしいられたるにあらず、負債のゆえにあらず、活命に窮したるにあらず。われらは苦に陥り、苦に沈み、苦に囲まれてある。されば、われらはこの苦の集積をのぞきつくさんとて此処にいたれるのである」(139頁) ■その理由とは、何であろうか。その目的とは何であろうか。それをさきの引用区の中では、「義(ただ)しき目的の存するによりてである」と意訳しておいたが、それをある経においては「意趣あるに縁(よ)る」としるしている。「意趣」(attha)とは、われらの認識ならびに判断の対象を指すことば、すなわち、人の願うところのものであり、人の求むるところのものであり、われらの善(よし)として追求するところのものである。したがって、「意趣あるに縁りて」この乞食沙門の生活に入ったというのは、然るべき目的が存して、みずからこの道を選んだというものである。さらに他の経は、その目的なるものを、もっと明白に「勝義を求むるためのゆえに」と言いあらわしている。「勝義」(paramattha)とは、人の願うところの最上のものであり、人間にして思念し能うかぎりの最高善であり、人間の生活の終極の標的である。そして出家の生活とは、この最高なる善の実現のために、他の一切を賭するものに外ならなかった。(141~142頁) ■「比丘たちよ、もしも、かくのごとくして出家せる者が、なお世間的な欲のむさぼりを抱き、もろもろの欲望において執著を生じ、瞋(いか)りの心を生じ、邪(よこし)まの思いにとらわれ、放逸にして専念することを得なかったならばいかがであろうか。それはたとえば、両端は燃えて中間は糞(ふん)をぬりたる炬火(たいまつ)のごときものである。それは、薪の用もなさず、木材の用もなさぬ。それとおなじく、かかる比丘は、在家人の生活をすてたるがゆえに在家人にもあらず、しかも沙門の勝義(最高善)を成満せざるがゆえに、出家の沙門でもない」 と。この譬喩は、釈尊の好んで用いられたもののごとく、他の経にもしばしば見られる。その言わんとするところは、無論、出家たりしうえは、断じて中途半端な存在であってはならぬとするのである。人生最高の善を追求せんとするからには、決然として一切を賭してこの道をゆかねばならぬとするのである。(142~143頁) ■「世間のあらゆる力のうち、 天にありても人中にあっても、 福(さいわ)いの力をもっとも勝れりとなす。 福いによって仏の道をなすなり」(145頁) ■それもまた、かの祇園精舎においてのことであった。 「世の人々はことごとく、 さまざまの福祉(さいわい)をねがい さまざまの吉祥を念ずる。 願わくは、わがために最上の吉祥を語りたまえ」 かように問える者があったとき、釈尊はそれに答えて、つぎのように語り教えた。その全文を、この経典は、すべて偈文をもって記しとどめている。 「愚かなる者に親しみ近づかぬがよい。 賢き人々に近づき親しむがよい。 また仕(つこ)うるに値する者に仕うるがよい。 これが人間最上の幸福である。 よき環境に住うがよい。 つねに功徳をつまんことを思うがよい。 またみずから正しい誓願(ちかい)を立つるがよい。 これが人間最上の幸福である。 ひろく学び、技芸を身につけるはよく、 規律ある生活を習うはよく、 よきことばになじむはよい。 これが人間最上の幸福である。 よく父と母とに仕うるはよく、 妻や子を慈しみ養うはよく、 ただしき生業(なりわい)にはげむはよい。 これが人間最上の幸福である。 布施をなし、戒律をたもち、 血縁の人々をめぐみたすけ、 恥ずべきことを行わざるはよい。 これが人間最上の幸福である。 悪しき業を楽しみとしてはならぬ。 酒を飲まば程をすごしてはならぬ。 もろもろの事に於て放逸であってはならぬ。 これが人間最上の幸福である。 他人(ひと)を敬い、みずからへりくだるはよく、 足るを知って、恩をおもうはよく、 時ありて教法(おしえ)を聞くはよい。 これが人間最上の幸福である。 事忍び、柔和なるはよく、 しばしば沙門を訪れまみえて、 時ありて法を語り談ずるはよい。 これが人間最上の幸福である。 よく自己(おのれ)を制し、清浄なる行ないをおさめ、 4つのまことの道理を証(さと)りて、 ついに涅槃を実現することを得なば、 人間の幸福はこれに勝るものはない。 その時人は、毀誉と褒貶とによって心を擾(みだ)されることもなく、 得ると得ざるとによりて心を動かさるることもなく、 愁いもなく、瞋(いか)りもなく、ただこの上もなき安穏(やすらぎ)の中にある。 人間の幸福はこれに勝るものはない。 人よくかくの如きを行ないおわらば、 いずこにあるも打ち勝たるることなく、 いずこにゆくも幸いゆたかならん。 かかる人々にこそ最上の幸福はあるであろう」(148~152頁) 第12章 常恒(つね)なるもの無しー諸行無常 ■「比丘よ、この世のものには、常恒にして永住するもの、いつでも変易しないというものはまったくない」 そう答えてから、釈尊は、そのあたりの土をすこしつまんで、爪のうえにのせて比丘のまえに示しながら、さらに語っていった。 「比丘よ、たったこれったけの物といえども、常恒永住にして、変易せざるものとては、この世に存しないのである。もし比丘よ、この爪のうえの土ほどのものでも、永住常恒にして変易せざるものが存するならば、わたしの教える情浄の行によって、よく苦を滅しつくすことはできないであろう。だが比丘よ、この世には、この土ほどのものといえども、常恒にして変わることのないものはないからして、わたしの教えるこの道によって、よく苦を滅しつくすことができるのである」 そして釈尊は、さらに受(感受)についても、想(表象)についても、行(意志)についても、識(意識)についても、おなじ趣旨のことをくりかえしした。すなわち、この世界におけるあらゆる物質(色)もまた精神(受・想・行・識)も、すべて常恒ならぬものであり、移ろうものであるとの見解を、ここに釈尊は披歴せられ、そうであるがゆえにこそ、わが説き教えるこの道が、はじめて可能となるのだと語っているのである。 この短い経は、なにげなく読み去りゆけば、なんの変哲もないように思われる。そこには、例によって、仏教の無常感が語られているにすぎないと思われるのみであろう。だが、心して再読すれば、そこには釈尊が、自己の教法のよってたつ根本的立場を、さらりと打ち出して語っていることが知られるであろう。「もしもこの世に、この爪のうえの土ほどの物でも、永住常恒にして移ろわざるものがありとするならば、わたしの教えるこの道はなることを得ないであろう」と釈尊は語っている。そのことは、仏教というこの宗教が、まったく「常恒なるもの無し」とする世界解釈のうえに立っていることを語っている。もしも、一毫(ごう)といえども常恒なるものがありとするならば、この宗教はそのよりて立つところを失うのだ、と言っているのである。(153~154頁) ■「善い哉、世尊よ、願わくばわがために、略して法を説きたまえ。わたしは世尊より法を聞きて、ひとり静かなる処におもむき、放逸ならずして、精進し努力したいと思います」 「阿難よ、では、なんじは、如何に思うか。物象(もの、色)は、常恒であると思うか。無常であると思うか」 「大徳よ、それは無常であります」 「では、無常であるならば、苦であろうか、楽であろうか」 「大徳よ、それは苦であります」 「ではさらに、無常にして苦なる、それらの変易するものは、これを観察して、これはわが物(mama 我所)である。これはわがわれ(me atta 我体)であるとなすことを得るであろうか」 「大徳よ、それはできませぬ」 さらに釈尊は、受(感受)についても、想(表象)についても、行(意志)についても、識(意識)についても、おなじようにたずねる。それに対して、アーナンダの答えもまた、そのいずれについてもおなじであった。 そこで釈尊は、彼のために教えて言った。 「そのゆえに、阿難よ、われらは一切を厭い離れねばならぬ。一切を厭い離るれば、欲を離れることができる。欲を離るれば、解脱することができる。すでに解脱するに至れば、ーーわれは解脱したのである。ーーとの智が生ずる。かくてーーわが迷妄の生涯はすでに終わった。わが清浄の行はすでになった。わが作(な)すべきことはすでになされた。このうえは、さらにかくのごとき生涯をくりかえすことはないであろう。ーーと証知することができるのである」 それでこの短い経は終わっているのであるが、この問答と教示とは、その中にほとんど基本的な構造の全体をふくんでいる。すなわち、無常と苦と無我と、そして厭離と解脱とに言及しているのである。しこうして、その問答の部分すなわち無常観と苦観と無我観とについては、釈尊の弟子の比丘たちは、問われればいつでも、この問答とおなじ型で、すらすらと答えることができた。したがって、ふるい経典の中には、いくたびとなく、型もことばもおなじ問答がくりかえし記されている。(157~158頁) ■さて、この世に常恒なるもの一もあることなし、物質(色)も精神(受・想・行・識)もすべて変転するもの、無常なるものであるとして、では、いかにして、さきの問答における、 「では、無常であるならば、苦であろうか、楽であろうか」 「大徳よ、それは苦であります」 という公式は成立するのであろうか。さらに釈尊は、多くの説法の中において、そのことをもっと簡勁(けい、つよい)に、 「およそ無常なるもの、そは苦なり」 と説いているが、かかる命題はいかなる推理によって成立しているのであろうか。おそらく、そのことは、初期の教団の比丘たちにとっては、ほとんど自明の理にひとしいものであったであろう。(159頁) ■「ここに大徳よ、わたしは独り坐し静かに思索しているとき、心のなかにかような疑問が起こりました。それは、ーー世尊は3つの種類の感受を説きたもうた。それは楽受(楽しとする感情を生ずること)と苦受(苦しとする感情を生ずること)と非楽非苦受とであって、世尊はこの3種の受を説きたもうた。しかるに、世尊はまた、およそいかなる感受も、それは結局苦であると、かく説きたもうた。いったいそれは、いかなる意味をふくんでいるのであろうか。ーーということであります」 その比丘の名は知られていないが、この疑問の趣旨は、今日のわたしどもにも身近な親しみを感ずることができる。彼は「世尊は3種の受を説きたもうたのに」と語っている。今日のわたしどもには、「世の中には苦しいこともあれば、また楽しいこともあるのに、何をすれば釈尊は『すべては苦である』と説きたもうのであるか」と疑われる。その疑いは、彼においても、またわたしどもにおいても、詮ずるところ、おなじ筋のものということができよう。それに対して、釈尊はかように答えている。 「善い哉、比丘よ。善い哉、比丘よ。なるほど、わたしは3つの種類の受があると説いた。それは楽受と苦受と非苦非楽受とであって、わたしはその3種の感受があると説いた。しかるに、わたしはまた、およそいかなる感受も、所詮ことごとく苦であると説いた。それは何故であるかというに、比丘よ、わたしはこれを諸行の無常なることについて語ったのである。比丘よ、一切の諸行は変易するものであるがゆえに、わたしは、およそいかなる感受も、つまるところみなことごとく苦に帰すると説くのである」 そして、漢訳においては、さらに偈を説いて、 「諸行は無常にして、 皆これ変易の法なることを知る。 ゆえに受はことごとく苦なりと説く。 さとれるもの(正覚)の知るところなり」 と教えたもうたという。(160~161頁) ■だが、諸行は無常にして、常恒なるものは一つもありうることを得ない。愛する者とはいつかは別離しなければならぬ。美しい物は美しいほど、移ろうこともまた速やかである。そのときには人はまた涙さんぜんと悲しまねばならぬ。では、楽受もまたやがて苦受となって、彼を裏切るのではないか。なんとなれば、諸行は無常であるからである。常恒なるものは一つもありえないからである。そのことを釈尊は、しばしば「受の縁より愛生ず。これ苦の生起なり」と、簡明率直に語っておられる。かくて諸行無常の理のうえに立ってみると、いかなる受もすべて、所詮は苦に帰するのだと言わねばならぬのである。(162頁) ■それは、かれサーリプッタが、マガダ国のとある村にいたときのことであった。そのとき、一人の外道の修行者のジャンブカーダカなるものが彼を訪ねきたって、このような会話を交したことがあった。 「友サーリプッタよ、〈苦、苦〉というが、いったい苦というものは何であるか」 「友よ、これらの3つのものが苦である。それは苦々性のもの、壊苦性のもの、行苦性のものである。友よ、この3つのものが苦であると称せられる」 苦(dukkah)ということばは1つであっても、人々がそれによって意味するものは必ずしも同一ではあるまい。ある人はその貧しくして苦しいことを苦とするであろう。それは貧苦を苦といっているのである。またある人はその罪ふかきことを自覚して思い悩んでいることもあろう。それは罪苦と呼ばれたこともあった。あるいは愛児をうしなった人は、そのことを悲しむであろう。事業に失敗した者は、そのことに苦しみ悩むであろう。さらに、病の床に呻吟している人々は、それを苦しんでいるにちがいない。 ことばはおなじく苦であっても、それによりて意味し、そのために苦しみ悲しみ悩んでいるものは、人それぞれによってさまざまに異なっている。しかるとすれば、釈尊がそれによって意味せられた「苦」というのは、いったい何であったのだろう。そのことを的確に知っておかなかったならば、わたしどもはあるいは、釈尊の真に与えんとするものを取りちがえ、期待すべからざるものを仏教に期待するのおそれなしとなし得ない。(163~164頁) ■さていまサーリプッタは、外道の修行者の問いに答えて、いうところの苦なるものを、3つの性格に分類して語っている。それは苦々性と壊苦性と行苦性とであって、「この3つのものが苦であると称せられる」と言い切っている。苦々性とは、苦事の成るによって苦悩を生ずるもの、たとえば寒さ暑さのごとき、あるいは飢え渇きのごとき、これが生ずれば、これを受くるものは当然苦しまねばならぬ。かかるものを苦々性の苦というのであって、それはもっとも素朴にして直接的な苦と言ってよいであろう。つぎに、壊苦性とは、おのれの愛楽するものの壊するによって苦悩を生ずるがごときもの、たとえば、愛する妻や子が死んだという場合、あるいは美しいと思う花が散ってゆくとき、そこには当然悲しみが湧き、憂いが生ずる。かくて、「楽境の壊するとき壊苦を生ず」という命題がそこにある。さらに、行苦性とは、「一切法の遷流し無常なるによりて苦悩を生ずる」ものと注されることができるであろう。たとえば、いつまでも若くありたいとねがっているのに、わたしどもはいつの間にか老いゆかねばならぬ。いつまでも生きていたいと思われるのに、わたしどもはやがて死んでゆかねばならぬ、それらは何よりもまず生老病死の四苦にとって代表せられる。(164頁) ■いうまでもなく、それらのことはすべて、万象ことごとく変易せざるはないという事実のうえになるものにほかならなかった。そこに、「およそ無常なるもの、そは苦なり(岡野注;その苦も無常である)」と簡明に説き給うた釈尊のことばが、寸毫のあますところなく、このことを言いつくしていることが知られるであろう。(165頁) ■「比丘たちよ、よく聞き、よく思ってみるがよい。未だ正法を聞かざる凡夫は2種の受を感ずる。それは身における受と心における受とである。それはたとうれば、第一の箭(や)をもって刺され、さらに第二の箭をもって刺されるに似ている。彼はいまだ正法を了知せざるがゆえに、もし五欲において楽受をうければ、それに愛執するがゆえに、さらにたちまち浴貧の煩悩の縛するところとなる。またもし苦受をうくることあれば、それに対して瞋恚(いかり)を生ずるがゆえに、また瞋恚のとらうるところとなる。 それに反して、すでに教法を聞くことを得たる聖弟子は、ただ一つの受を感ずるのみである。すなわち彼は、身における受は感ずるけれども、心における受を感ずることはないであろう。これをたとうれば、第一の箭をもって刺され、されど第二の箭を受くることなきに似ている。なんとなれば、彼はすでに正法を知るがゆえに、もし五欲において楽受を受けても、彼はこれを愛執することなきがゆえに、その心をさわがしその意を乱すにいたらず。またもし苦受を味わうことがあっても、彼はそれに対して瞋恚を生ずることなきがゆえに、また煩悩の擾乱(じょうらん)するところがない。これを第二の箭を受くることなしというのである」 わたしどもは、ともすれば、仏陀もしくは阿羅漢といえば、苦楽ともに滅しつくして、寒厳枯木のごとき存在となりきっているかに考えがちである。だが、釈尊のこの説法は、明らかに、そのような考え方は間違いであることを語っている。聖者といえども、聖弟子といえども、凡俗の人々とおなじように、「楽受をも感じ、苦受をも感じ、非苦非楽受をも感ずる」のである。美しいものを見ては美しいと感じ、愛(いと)しいものを見ては愛しいと感ずる。また、醜いものをみれば醜いと感じ、憎いものをみれば憎いと感ずる。そのことは少しも異なるところがない。だが、彼らはけっして「第二の箭」をうけないのである。「第二の箭」を受けざるがゆえに、苦受もまた楽受も、さらに彼らの心の平和をかき乱すにいたらないと釈尊は説いている。(166~167頁) 第13章 自己についてー諸法無我 ■「われというものはない。 また、わがものというものもない。 すでにわれなしと知らば、 何によってか、わがものがあろうか。 もし、このように解することを得れば、 よく煩悩を断つことを得るであろう」(168頁) ■「無知にして愚かなる者は、 おのれに対して仇敵のごとくふるまう。 なんとなれば、彼は悪しき業をおこない、 おのがうえに苦果をもたらすがゆえに」(174頁) ■「おのれを愛すべきものと知らば、 おのれを悪に結びつくるなかれ。 けだし、悪しき業をなす人々には、 安楽は得がたきものなればなり」(174~175頁) ■人々はたいてい、その肉体をゆびさして、それが「われ」であると思っている。そのことをゆびさして、釈尊は、「彼らは、色(もの)がわれである、われは色を有す、われの中に色がある、色の中にわれがある、と見ているであろう。それが迷いのもとである」と教えている。 だが、よく考えてみると、わたしどもにも、そのことが間違いであることがわからぬでもなかろう。わたしどもはけっして、わが手をゆびさして、われであるとはいわない。わが足がわれであるともいわない。わが胃がわれであるともいえない。釈尊はそういうときに、よく芭蕉のたとえを説かれている。芭蕉というものは、そのどこにひそんでいるのであろうかと、いくら皮をむいてみても、何にも出て来はしないであろう。それとおなじように、肉体(色)のどこをさがしてみても、これが「われ」であるといえるものは、何処にもみつかりはしない。そのことを、釈尊は、「色はわれなり」とみるのは、正しい見方ではないと教えている。(岡野注;ミリンダ王の問い)(177頁) 第14章 わが衷(うち)なる悪しきものー悪魔物語 ■「たとい雪山を化して黄金となし、 さらにこれを2倍すといえども、 よく一人の欲をみたすに足らず。 かく知りて、人は正しく行わねばならぬ。 人間の苦しみとその原因をさとる者は いかでか、かかる欲貧(よくとん)に傾こうぞ。 物欲に依る者は物欲に縛せられる。 人はよくその縛を解くことを学ばねがならぬ」(184頁) 第16章 庶民とともにー対機説法(2) ■「たとえば、もろもろの大河あり。いわくガンガー、ヤムナー、アチラヴァテー、サラブー、マヒーなり。これらは大海にいたらば、さきの名姓(なまえ)をすててただ大海とのみ号す。かくのごとく、刹帝利(クシャトリヤ、王族武人)波羅門(司祭者)吠舎(ヴァイシャ、庶民)首陀羅(シュードラ、奴隷)の4姓あり。されど彼らは、如来所説の法と律とに於て出家せば、さきの姓名をすてて、ただ沙門釈氏とのみ号する」(209頁) ■ある役者のために またある時のこと、釈尊がかの王舎城の郊外なる竹林の園にあった頃、タラプタというある村の長がたずねてきたことがあった。彼の村は、代々芝居の役者を業とするものの村であったらしく、経のことばは彼のことを歌舞伎聚落の主であると記している。 さて、彼が釈尊を訪れて問うたことは、その村の代々の言い伝えについてのことであった。 「大徳よ、わたしは、昔から代々の歌舞伎者の言いつたえとして、かように聞いております。すなわち、すべてこの歌舞伎者は、舞台において真実と偽装とをもって人々を笑い楽しましむるがゆえに、身壊(こわ)れ命終りし後には、喜笑天に生まれることができると、かように聞いておりますが、世尊はこれについて如何にお考えでありましょうか」 だが釈尊は、このように問われても、すぐには答えようとしなかった。 「村の長よ、そんなことを問うのは、止めたがよいであろう。わたしにそんなことを聞くのは措(お)いたがよい」 それでも彼は、問うことをやめなかった。経のことばはそれについて何ごとも記していないが、おそらく彼は、この言いつたえについて、何か疑いをもち始めていたのではなかったであろうか。そのゆえにこそ、彼はわざわざ釈尊を訪れて、このことについて教えを乞わんとするのではなかったか。釈尊は2度までも、問うことを止めよ、とすすめた。彼はそれを押し切って、3度びおなじ質問をもって釈尊の教えを乞うた。そこで釈尊は、それほどまでに問うならばと、大体つぎのように説いたのであった。 「村の長よ、昔から歌舞伎者は、よく真実と偽装とをもって人々を笑い楽しまましめるがゆえに、死しての後は喜笑天に生まれる、と言い伝えているというが、それは邪(よこし)まの見解であると申さねばならぬ。なんとなれば、昔から歌舞伎者のしていることを考えてみるがよい。歌舞伎を見ようとして集まってくる人々は、まだけっして貪欲をはなれてはいない。その人々のまえに役者たちは、あらゆる貪欲の対象をあつめ展じ、かつそれを強調して人々の心をかきたてる。また彼らは、いまだ瞋恚(しんい)をぬけきらぬ人々のまえに、あらゆる瞋恚のさまを演じ示して、人々の激情をかきたてる。さらにまた、彼らはいまだ愚痴を脱しきれぬ人々をまえにして、さまざまの愚痴のすがたを演出して、いよいよ人々の愚痴をふかからしめる。かくのごとく、村の長よ、歌舞伎者はみずから貪欲に、瞋恚に、愚痴に陶酔して、それによってまた他の人々をも貪欲に、瞋恚に、愚痴に陶酔せしめるのである。されば彼らは、死して後には、喜笑と名づくる地獄におちるであろう」 それを聞いて、タラブタなる歌舞伎聚落の主は、涙をながして泣き悲しんだ。その姿をみて、釈尊は、しずかに慈眼を彼にそそぎ、 「だからこそ、村の長よ、そのようなことはわたしに聞かぬがよいと言ったではないか」 となぐさめ給うた。すると、かのタラブタは、やがて涙にぬれた顔をあげていった。 「大徳よ、わたしは世尊の教えたもうたことを悲しんで泣いているのではありません。わたしが悲しいのは、これまで歌舞伎役者の言い伝えに、ながい間だまされていたことであります。だが、いま世尊のおしえは、蔽(おお)われしものを啓(ひら)くがごとく、迷える者に道を示すがごとく、暗中に燈火をもたらして、眼のあるものは見よと仰せらるるがように、わたしのひさしい蒙を啓いて下さいました。わたしはいまや、世尊と世尊の教法と比丘衆に帰依いたします。大徳よ、願わくは、このわたしが世尊のもとに出家を許され、修行することを許したまえ」 かくて彼は、出家を許され、修行をかさねて、やがて阿羅漢の一人となることを得たという。この経は、南伝においては相応部教典(42、2、布吒)に、また漢訳においては僧阿含経(32、2、動揺)の中にみえている。(213~215頁) ■もう一つは、ここに釈尊は、ほんの片鱗だけではあるが、その芸術論を語っておられることである。そのような見解は、経の他の処では殆んどみることがないのではあるが、ここでは、はからずも、歌舞伎者の問いに際会して、歌舞伎なるものを演ずる人生における役割について、釈尊らしい見解を説いていられる。それは、今日の芸術にたずさわる人々からみれば、やや一面的であって、容易に承服しがたいものであろうと思われる。しかし、今日の文学や演劇や音楽もまた、そのあまりに人々の官能に訴え、人々の衝動をかきたてようとしていることにおいて、真面目によき人生の建立を考える人々の納得しがたいものが多いことを、誰も否定することはできないのであるまいか。(216頁) 第17章 譬喩(たとえ)をもって ■「比丘たちよ、ここに一枚の布があって、それは穢(よご)れ垢づいているとするがよい。それを染物工が、藍色なり、黄色なり、あるいは茜色なりに、染めようとて、染色の壺のなかに浸したとしたならば、いかがであろうか。その時、この布は染色もあざやかに染め上がるであろうか。そうはゆくまい。何故かというと、それはいうまでもなく、布が清浄でないからである。それとおなじように、比丘たちよ、なんじらの心が穢れていたならば、悪しき結果が予期せられねばならぬのである」(221頁) ■「比丘たちよ、では心のけがれとは何であろうか。欲のむさぼり、邪(よこしま)の貧欲は心のかがれである。喩(いか)りは心のけがれであり、恨みは心のけがれであり、過ちをかくすは心のけがれであり、吝(おし)んで施さぬは心のけがれであり、偽り瞞(だま)すことも心のけがれである。また、心の頑(かたく)ななるも心の汚れであり、性急なるも心の汚れであり、慢(おご)り憍(たか)ぶるも心の汚れであり、放逸なるもまた心のけがれである」(223頁) ■それは、世尊が、比丘たちをつれて、ヴァッジーの国をあちこちと遊行せられて、ウッカチューラーという土地で、かのガンガーの河岸に達した時のことであった。その時、釈尊は、比丘たちとともにガンガーの河の岸にたって、その状景にふさわしい譬喩を説いた。 「比丘たちよ、むかしマガダの国に、ひとりの愚かしい牛飼いがあった。雨期の最後の月をすぎて、彼は、牛の群れをつれて、このガンガーの彼(か)の岸に渡ろうとした。しかるに彼は、この岸をもよく観察せず、適当な渡場でないところを、牛を駆って流れに入ったために、牛の群は河流の中程にいたって立往生し、密集して溺死するという災厄にあってしまったという。それは何のゆえであったかというと、よく観察しなかったからに外ならなかったのである」 そのような喩(たと)え話をして、そこで釈尊は、比丘たちをかえりみて言った。 「それとおなじく、比丘たちよ、いかなる沙門にあれ、また波羅門にあれ、もし彼らがこの世界をよく知らず、また、かの世界をもよく知らず、観察のいたらぬものがあったならば、彼らにしたがって聴いて信ぜんとするする人々は、ながき不幸を見なければならぬであろう」(222~223頁) ■「比丘たちよ、むかし、またマガダの国に、ひとりの智慧ある牛飼いがあった。彼もまた、雨期の最後の月をすぎて、牛の群をひきいて、ガンガーの彼の岸に渡ろうとした。そのとき彼は、この岸をよく観察し、またかの岸をよく観察して、しかるべき渡場によって、牛どもを対岸に渡そうとした。すなわち、彼はまず、牛どもの中でもっともつよいものを選んで、それらを流れに入れ、よく流れを横切って、安全にかの岸に到らしめた。つぎに彼は、牛の群の中で比較的につよいもの、よく飼いならされたものを流れに入れて、またよく河の流れをこえて、無事にかの岸にいたらしめた。そして最後には、まだ力の弱い犢(こうし)たちや、乳ばなれしたばかりの牛どもを流れに入れたのであるが、彼らもまた、すでにかの岸にわたった親牛たちの吼える声にひかれ励まされて、無事に河の流れをよぎって、かの岸に到り着くことを得しめたという。それは何のゆえであったかというに、彼がよく観察しよく導くことを得たからに外ならないのである」(228~229頁) ■「比丘たちよ、それとおなじく、いかなる沙門にあれ、また波羅門にあれ、彼らがもし、この世界をよく知りつくし、またかの世界をもよく知りつくし、観察充分にして、導くことをうるならば、彼らについて、聴いて信ぜんとする人々は、ながき幸福をみることをうるであろう。 比丘たちよ、牛の群の中で、最初にガンガーの流れを渡った力づよい牛たちのごとく、比丘たちのなかでも、すでに煩悩を断ち、修行をみたし、所作すでに弁じおわった者もある。彼らはすでに魔の流れをよぎって、安穏に彼岸にある。また比丘たちよ、かの牛の群の中で、よく馴らされ、比較的つよい牛たちが、ついで流れをこえることを得たように、比丘たちの中でも、すでに三結を断ち、貪瞋痴もうすく、正覚決定せる者もある。彼らもまた、やがて魔の流れをよぎって、無事に彼岸に到るであろう。さらにまた、比丘たちよ、乳離れしたばかりの牛や、いまだ力かよわい犢たちも、すでに彼の岸にある母牛たちの呼び吼える声に惹かれ励まされて、ついに流れを渡りえたように、比丘たちの中にあっても、いまだ煩悩つよく、修行の力よわき者もあれど、彼らも、また、よく法に随い、信に依らば、やがては魔の流れをこえて、彼の岸にいたることができよう。 比丘たちよ、わたしはよくこの世界を観察した。またよくかの世界を観察した。すべての世界を知りつくして、わたしは正覚者、一切知者となった。されば比丘たちよ、このわたしについて聴いて信ぜんとする者は、ながく利益と幸福とを見ることができるであろう」(229~230頁) ■釈尊の譬喩をかたる場合に、わたしどもは、かの「毒箭(や)の譬喩を語りおとすことはできない。それはこの仏の道においては、何ごとに努力を集中すべきであるか、何ごとに心をうばわれてはならないかについて、はなはだ適切な教誡を垂れさせ給うたものである。その説法の因縁をつくったのは、マールンクヤという哲学ずきの比丘であった。 それは、例のごとく、釈尊が祇園精舎にあらわれた時であった。その時、かの比丘は、一つの不満をもって、師を訪れ、師の前に坐して言った。 「世尊よ、わたしは、ひとり空閑処(くううかんじょ)に坐しているとき、心の中でかように思った。世尊は、このような問題については一向に説かれない。すなわち、この世界は常住であるか無常であるか。この世界には辺際ありやなしや。霊魂と身体とは同じであるか別なるか。あるいは、人は死後もなお存するか存せざるか。このような問題について、世尊は何ごとも説いて下さらない。問えば答えることを拒みたもう。わたしはそれが不満であって、堪えられない。いまわたしは、かさねて世尊に問い申す。それでも答えたまわずば、わたしはこの道をすてて俗に還るのほかはない」 ここでマールンクヤが言うところの問題なるものは、その頃の思想家たちの、いわば流行の課題であった。この哲学ずきの比丘は、それらの問題についてすぐれた解答をこの師に期待していたのであろう。だが、他の経においてもしばしばみられるように、それらの問題にたいして、釈尊はいつも黙念として答えなかった。この比丘はそのことを不服として、今日はどうしても答えを得ようと、意気ごんでやって来たのである。 「マールンクヤよ、わたしはかってなんじに、このような問題について教えるがゆえ、わたしの許に来るがよいと言ったことでもあったであろうか」 そう言われてみると、別にそのような約束で出家したわけではなかった。だから、「そうではなかった」と答えはしたものの、彼は不服そうな顔をふくらませていたに違いない。そのとき、静かに、そして懇切に語りいでた譬喩が、「毒箭の喩」としてひろく知られているのである。 「マールンクヤよ、ここに人があって、毒矢に射られたとするがよい。その時、彼の親友たちは、彼のために医者を迎えるであろう。だが彼は、この毒矢を射た者は何びとであるか、また、この矢を射た弓はいかなる弓であるか。あるいはまた、この矢は、その矢柄はいかがであり、その羽は何でできており、その尖端はいかなる形をしているか。それらのことが知られざるうちは、この矢を抜いてはならぬと言ったとするならば、いかがであろうか。マールンクヤよ、もしそうすると、彼は、それらのことを知りうるまえに、命終わらねばならぬであろう。 マールンクヤよ、それとおなじく、もし人あって、かかる問題について説かれざる問は、わたしの許(もと)で清浄の行を修しないと主張したならば、いかがであろうか。彼もまた、ついに浄行を脩する機会なくして、命終わらねばならぬのである」(230~233頁) ■「マールンクヤよ、世界は常住であるとかという見解を立てても、それによって清浄の行が成る道理はない。むしろそれらの見解の存するところには、依然として、生老病死、愁悲苦悩がとどまり存するであろう。わたしはただ、この現在の生存において、それらを克服することを教えるのである。 そのゆえに、マールンクヤよ。わたしの説かないことは、説かないままに受持するがよい。わたしの説いたことは、説かれたままに受持するがよい。マールンクヤよ、世界の常住・無常・有辺・無辺などのことは、わたしはこれを説かない。何故に説かないのであるか。それは道理の把握に役立たず、正道の実践に役立たず、正覚・涅槃に資することなきがゆえである。そのゆえに、わたしはそれらのことを説かないのである。 それでは、マールンクヤよ、わたしの説いたものとは何であろうか。マールンクヤよ、『これは苦である』とわたしは説いた。『これは苦の集起(じっき、原因)である』とわたしは説いた。『これは苦の滅である』とわたしは説いた。また『これは苦の滅にいたる道である』とわたしは説いた。何故にわたしはそれらのことを説いたのであろうか。それは、道理の把握をもたらし、正道の実践に基礎をあたえ、正覚、涅槃に資するがゆえである そのゆえに、マールンクヤよ、わたしの説かないことは、説かないままに受持するがよく、わたしの説いたことは、説かれたままに受持するがよいというのである」 かの比丘は、この譬喩説法によって、それまでの迷妄をはなれ、歓喜して釈尊の教えを信受したという。わたしどももまた、この説法を深く味わうことによって、よく釈尊の教えのまことに指すところを見いだすべきであると思うのである。(232~233頁) 第18章 善き友とともにー僧伽の精神 ■「比丘たちよ、朝な朝な太陽が東にのぼるときには、その先駆として、またその前相として、東の空に明るい相が出るであろう。比丘たちよ、それとおなじく、比丘たちが八つの聖道をおこすときにも、その先駆たり、その前相たるものが存する。それは善き友のあることである。 比丘たちよ、善き友をもてる比丘においては、八つの聖道を修習し、八つの聖道を多修するであろうことを、期して待つことができる」(237頁) ■「比丘たちよ、ここに一つの法があり、それは八つの聖道をおこすに利益が多い。その一つの法とは何であろうか。それは謂(い)わく、善き友のあることである。 比丘たちよ、善き友をもてる比丘においては、八つの聖道を修習し、八つの聖道を多修するであろうことを、期して待つことができるのである」(238頁) ■「比丘たちよ、わたしは、未だ生ぜざる八つの聖道を生ぜしめ、すでに生ぜる八つの聖道を修習し円満ならしめるものとして、他にこれにすぐる一つの法をも知らない。比丘たちよ、それはすなわち善き友のあることである。 比丘たちよ、善き友をもてる比丘においては、八つの聖道を修習し、八つの聖道を多修するであろうことを、期して俟(ま)つことができるであろう」(238~239頁) ■それは、釈尊が釈迦族のすむサッカラという村にとどまり住しておられた時のことであった。その時、かの常随の弟子アーナンダは、ふと師の釈尊を拝して、このようにたずねて言った。 「大徳よ、善き師匠(善知識)善き友輩(善伴党)善き弟子(善随徒)を有するということは、これは、この聖なる道の修行(梵行)のなかばをなすものであると思われますが、いかがでありましょうか」(239頁) ■「アーナンダよ、この言をなすなかれ。アーナンダよ、この言をなすなかれ。アーナンダよ、善き師、善き友、善き弟子をもつということは、これこの道の聖なる修行のことごとくである。アーナンダよ、善き師、善き友、善き弟子をもてる比丘は、八つの聖道を修習し、八つの聖道を多修するであろうことは、期して俟(ま)つことをうるのである」(240頁) ■「アーナンダよ、この理によっても知るがごとく、善き先達、善き朋輩、善き後輩をもつということは、これこの聖なる道の修行のことごとくである。アーナンダよ、なんじらは、わたしを善き友となすことによって、生・老・病・死の法の中にあるものにして、しかも、その法より解脱することを得・愁・悲・苦・悩の法のなかにあるものにして、しかも、それらの得・愁・悲・苦・悩を解脱しうるのである。このことによってもまた、アーナンダよ、善き先達、善き朋輩、善き後輩をもつということは、この道のすべてであると知るべきである」(240~241頁) ■釈尊を拝し、釈尊に対坐したサーリプッタは、白(もう)して言った。 「大徳よ、善き師(善知識)、善き友(善伴党)、善き後輩(善随従)をもつことは、これ聖なる修行のすべてであると思われるが、このことはいかがでありましょうか」(241~242頁) ■「善いかな、善いかな、サーリプッタよ、善き師、善き友、善き後輩をもつことは、この道の修行のすべてである」(242頁) ■「大王よ、ある時、わたしは釈迦族のすむある村にいた。その時、大王よ、アーナンダはわたしに問うて、善き友、善き仲間をもつことは、この道の半ばであると思ってよいかと言った」 ーー中略ーー 「大王よ、かかるがゆえに、王は、かくのごとく学ばれるがよい。ーーわたしは善き友、善き朋輩、善き仲間をもつものとなろう。ーーと、かく王は努めて学ばれるがよい。大王よ、善き友、善き朋輩、善き仲間をもつものとなるには、この一法に住せなければならぬ。それは即ち、善をなすことにおいて放逸ならざることである。 大王よ、王がよく不法逸に住し、怠ることがなかったならば、王の後宮はみな、かく思うであろう。ーー王は不放逸に住したまい、怠ることあらせられぬ。われらもまた、不放逸に住し、怠ることがあってはならぬ。ーーと。 大王よ、また、王がよく、怠ることなく不法逸に住せられたならば、王の武臣たちもまた、かく考えるであろう。ーーわれらの王は怠ることなくよく不放逸に住したもうてあられる。われらもまた、怠るこをせず、不放逸に住せなければならぬ。ーーと。 さらに、また大王よ、王がよく不法逸にして、怠ることがなかったならば、王の国民たちもまた、かように思うであろう。ーーわれらの王は、よく不放逸にましまし、怠ることあらせられず。われらもまた、怠ることなく、よく勤めねばならぬ。ーーと。 大王よ、かくのごとく、王がよく不法逸に住し、懈怠することがなければ、自己もよく護られ、後宮もよく護られ、武臣も国民もまた護られることとなるのである」(243~244頁) 第19章 雑話すべからずー教誡説法 ■「激搖する馬車を抑止するがごとく、勃発したる忿怒をよく抑止する人。わたしはこれを真の御者とよぶ」(245頁) ■「比丘たちよ、かかる談義にふけることは、なんじら善き男子の、家よりいでて家なき出家沙門の身となった者にふさわしいことであろうか。比丘たちよ、なんじらが、つどい集まった時には、ただ二つのなすべきことがあるのである。その一つは、法に関する談義、いま一つは、聖なる沈黙である」(248頁) ■わたしはかつて、かの芭蕉翁の『行脚の掟』の一条に、「俳諧のほか雑話すべからず、雑話いでなば、居眠りして労をやしなうべし」とあるを見て、異常な感銘を感じたことがあった。一道に秀(ひい)ずる者の心底に存するものは、これなるかなと思ったことであった。しかるに、いまふとひるがえってみれば、それはすでに、遠き以前に釈尊の教えたところであったのである。(250頁) ■「アーナンダよ、あの漁師たちが魚を獲る時のような、あの声高な喧噪は、何ごとであるか」 「世尊よ、あれはサーリプッタ(舎利弗)とモッガラーナ(目犍連)のひきいる多勢の比丘たちが、世尊におめもじせんとて、いましがたこの樹園に到着いたしまして、旧住の比丘たちと挨拶を交わし、久々の歓談をたのしんでいるのであります」 アーナンダ(阿難)があるがままのことを答えると、釈尊は、その主だった者を呼んでくるようにと命じた。 召された比丘たちが、釈尊を拝して、その座についた時、釈尊は彼らにむかって言った。 「比丘たちよ、なんじらのあの声高な喧噪は何ごとであるか。まるで漁師たちが魚をとる時のようではないか」 比丘たちもまた、ありしがままをもって答えるの外はなかった。(251~252頁) ■「比丘たちよ、行け。わたしはなんじらをして去らしめる。なんじらは、わたしの前にあってはならぬ」 そのことばは、なお、声をはげましての叱咜ではなかったとおもわれる。それにしても、わたしどもは、このようなつよい叱責のことばを、その弟子たちにむかって語った釈尊を、他のどの経にもたずねることはできない。わたしどもはこの師にしてなおかつ、かかる叱咜のことばを吐くかと、この経をひもといて、わが眼をうたがわんばかりである。 この叱責のことばに遇って、かえすことばももたぬ比丘たちは、ただ「畏まれり」とのみ答えて、師のまえに深く伏しぬかずき、やがて、しおしおと起って、床座をたたみ、衣鉢をととのえて、またこの樹園を去って行った。 ちょうどその時分、この聚落の釈迦族の人々は、何かの用事で会議所にあつまっていた。見ると、さきほど到着したばかりの比丘たちが、また、とぼとぼと、かの樹園から去ってゆく。何ゆえならんと、いそぎ出て問うてみると、師の叱責を受けて、去らしめられるのだという。 「しからば、尊者たちは、しばらくここに坐して待っておられるがよい。わたしどもが行ってお詫びしたならば、あるいは大徳のお心を和げることができるかも知れぬ」 そして、この聚落の釈迦族の人々は、釈尊を訪れて、かの比丘たちのために、このように申しあげた。 「世尊よ、願わくは、かの比丘たちを歓び迎えられたい。世尊はいつも比丘たちを、快く摂せられたもう。そのごとく、今日もまたかの比丘たちを、許し摂せられたまえ。世尊よ、かの比丘たちの中には、出家してまだ久しからぬ新入の比丘たちも見受けられる。彼らはもしいま世尊を見ることを得なかったならば、あるいは異心を生ぜんやもはかりがたい。 世尊よ、たとえば、若い種子が水を得なかったならば、その発育は異変を生ずるであろう。そのごとく、出家していまだ久しからぬ比丘たちは、もし世尊を見奉(たてまつ)ることができなかったならば、あるいは変心の生ぜんことも保しがたい。 世尊よ、また譬えば、幼き子牛が、母牛を見ることができなかったならば、いかがであろうか。それと同じく、もしこの法と律とに入りてなお日浅き比丘たちが、いま世尊を見奉り、世尊の教えに接することができなかったならば、いかがであろうか。 世尊よ、願わくは、今日の不束(ふつつか)を許したまい、かの比丘たちを、いつものごとく、歓び摂したまえ」 この釈迦族の人々のことばは、まことに条理をつくしていた。釈迦はじっとそのことばを聞いていたが、やがて心を和らげ、彼らを許し迎えて、さらに一場の説法を彼らのために行なった、という。(252~253頁) ■一つの経によれば、コーサンビーの国ゴーシタ園にあった比丘たちが、何かの問題について、はげしい論諍を行ない、激語を交えて、果つるところを知らなかったとき、釈尊は彼らを召して、問うて言った。 「比丘たちよ、なんじらは、議論にふけり、たがいに激しいことばを相手になげて、いつまでも和するにいたらずという。それに相違ないか」 「世尊よ、そうであります」 「比丘たちよ、それでは、このことをなんじらはいかに思うか。なんじらがたがいに論じ諍(あらそ)い、激しいことばを相手にむかって語るとき、その時、なんじらは、陰にも陽にも、身における慈悲を行ない、口における慈悲をいとなみ、意において慈悲をいただいているであろうか」 「世尊よ、そうではありません」 「比丘たちよ、もし然るのでなかったならば、なんじらはそこに何を求めて、たがいに諍い論ずるのであるか。愚かなる者よ、かくのごときはただ、ながき不利と不幸とを招くにいたるであろう」(253~254頁) ■それもおなじコーサンビーの国ゴーシタ園の比丘たちのことであった。彼らの中に、またもや、紛諍をおこし、激越の語をもって相争うものがあった。そのことを、一人の比丘が釈尊に報じ、釈尊に乞うて言った。 「世尊よ、願わくは、慈愍(びん、あわれみ)をたれたまい、彼らの許にいたって、教えをたまわらんことを」 そこで釈尊は彼らの許にいたり、彼らに呼びかけて言った。 その時、その坐にあった一人の比丘は、釈尊のことばをおさえとどめて釈尊に申して言った。 「あわれ比丘たちよ、諍論することなかれ、異論することなかれ……」 「世尊よ、われらの法の主にまします世尊は待たらせられよ。世尊はかかることにギョウ(女へんに堯)乱せられてはならぬ。われらは応(まさ)にみずからこの紛諍を鎮めるであろう」 かの比丘は、釈尊がかかることに心労されるのを見るに忍びず、断じて自分たちだけで、この事を処理せねばならぬと思ったのである。それは釈尊にとっても、うれしい比丘たちの心づかいであった。 ではと、釈尊は、その場を去って、やがて衣鉢をととのえ、コーサンピーの町に托鉢におもむきたもうた。その途すがらこの師はつぎのような偈を誦(しょう)したもうたという。その偈の一部は、いまかの『法句経』の第三偈と第四偈にも、記しとどめられていることを知るものもあろう。(255頁) ■「ひとわれを罵(ののし)れり、われをうてり、 われに打ち勝てり、われを笑えりと、 およそかくのごとく怨み思う者には、 いつまでも敵意の鎮まることなし。 ひとわれを罵(ののし)れり、われを擲(う)てり、 われは打ち勝たれ、われは笑われたりと、 およそかかる怨念あることなき者には、 いつか敵意は鎮まるであろう。 他人の牛馬、財産をかすめる者、 他の国土を掠奪する人々にも、 なお和するということがある。 いかでかなんじらに和することなかるべき。 もしなんじら、よき友をもつことを得、 賢にして慧ある同行者を得なば、 一切の艱難(かんなん)にうちかちて、 ともに歓喜し、ともに行ずるがよい。 もしなんじら、よき友をもつことを得ず、 賢にして慧ある同行者を得ずんば、 林中をゆくかの大象のごとく、 ただ一人にして、独り往くがよい」(256~257頁) 第20章 貴賎と吉凶 ■それらの経の一つ、『賎民経』と称する経においては、釈尊もまた、「似而非(えせ)沙門」となじられ、「賤しき者」と呼ばれたことがあった。それは、例によって、釈尊がサーヴァッティー(舎衛城)の郊外なる祗陀林の精舎にあらわれたことであった。ある朝のこと、釈尊がサーヴァッティーの町に托鉢におもむき、たまたまある波羅門の住居に近づくと、いきなり、罵(ののし)る声があびせかけられた。 「坊主よ、そこにとどまれ。えせ沙門よ、そこにとどまれ。賤しき者は、そこにとどまって、この神聖なる場所に近づいてはならぬ」 その波羅門は、事火(じか)すなわち火をたっとび、火をまつることを業とするものであって、いまや、その住居において、神火を点じ、供物をそなえて、事火の祭式をいとなもうとするところであった。そこに、行乞する釈尊が近づいて来たので、「賤しき者よ、この神聖な場所に近づいてはならぬ」と罵り叫んだのであった。だが、その時、釈尊は、静かにかの波羅門に問うていった。 「波羅門よ、しからばなんじは、賎しい者とは何であるか、また人はいかなることをなせば、賤しき者であるか、知っているか」 そう問われてみると、彼は、すぐに答えることはできなかった。そのような問題について深く考えてみたこともなかった。急所をつかれて、たじたじとしたのである。 「沙門よ、わたしは何が賤しいか、どうすれば賎しい人になるか、答えることができない。沙門よ、それについて、なんじの考えを教えて下さるまいか」(258頁) ■「村に於て、あるいは林園に於て、 他の人の所有に属する物を、 与えられざるに、盗心をもて盗る者、 かかる人は賤しいと知るべきである。 他人に負債をもてる者が、 返済を迫られ、遁辞をかまえて、 なんじに負債あることなしと言う、 かかる人は賤しいと知らねばならぬ。 証人として問われたる時に、 自己のために、また他人のために、 また財のために虚偽を語る人、 かかる人は賤しいと知るがよい。 まことに些少なる欲のために、 道ゆく人々を殺害して、 些少の金品を奪うがごとき者、 かかる者は賤しい人と知るがよい」(259~260頁) ■「年老いて人生のさかりを過ぎし 母たる人、もしくは父たる人を、 みずからは富裕に暮らしながら扶養せぬ者、 かかる人は賤しいと言わねばならぬ。 母や父や、また兄弟姉妹を あるいはことばをもって悩まし、 あるいは手をもって打擲する、 かかる人は賤しいと言わねばならぬ。 みずから悪しき行為をなしながら、 このこと知らざれと願い、 隠匿せんことに心をくだく人、 かかる人は賤しいと言わねばならぬ」(261~262頁) ■「おのれを高くほめそやし、 たにんをけなし軽んずる者は、 自慢のためにかえって卑賎に堕す。 かかる人もまた賤しいと言わねばならぬ。 まことは聖者にあらずして、 みずから聖者なりと公言する者は、 一切世間をあざむく賊であって、 かかる者は実に最下の賎民である」(262頁) ■「人は、生まれによって賎民たるにあらず、 生まれによって波羅門たるのではない。 人は、行為によって賎民となり、 行為によって波羅門となるのである」(263頁) ■「人は、生まれによりて聖者たるにあらず、 生まれによって非聖者たるにあらず。 人は、行為によりて聖者となり、 行為によて非聖者となるのである」(264頁) ■「これら生物がその生まれによって、 相形の別さまざまなるがごとき、 生まれによる相形の別なるものは、 人間においては見ることを得ぬ」(265頁) ■「蓮の葉が水に染まることなきがごとく、 芥子粒が錐(きり)の尖にとどまらぬがごとく、 もろもろの欲に染著せざる者、 かかる人をわたしは波羅門という」(266頁) ■「違背(いはい)する人々の中にて違背せず 笞(むち)を執(と)れる人々の中にて笞をとらず、 取著をいだく人々の中にて取著なき、 かかる人をわたしは波羅門という」(266~267頁) ■彼らはそれによって、聖者とは、波羅門とは、まことに尊貴なる人間とは何であるかを、「暗(やみ)の中に燈火をもたらして『眼ある者はこれを見よ』というがごとく」に教え示されて、彼らもまた、生涯を在俗の信者として、釈尊にしたがうものとなったと、経のことばは結ばれている。(267頁) ■「カチて存(のこ)る者を知るは易い。 敗れ亡ぶる者を知ることも易しい。 法を欲する者が勝ち存(のこ)る者となり、 法を欲せぬ者が亡ぶる者となる」(268頁) ■「睡眠を事とし、集会を好み、 懶惰(らんだ)にして奮起することなく、 しかも亊々に忿(いかり)をなす人、 これが敗れ亡ぶる者の門である」(269頁) ■「多くの財を擁し、金銀をたくわえ、 ゆたかな飲食をほしいままにし、 しかも、ひとり美味をむさぼる、 これが敗亡にいたる門である。 年老いて人生の盛時(さかり)をすぎし、 母たる人、また父たる人を、 みずからは富裕に暮しながら扶養せぬ者、 これが敗亡にいたる門である」(270頁) ■「おのが妻をもって満足せず、 もろもろの遊女にまみえ、 また他人の妻女にゆく者、 これは敗亡への門であると知るがよい。 青春をすぎたる人が、 テインパル果のごとき乳房の女をもち、 彼女への嫉妬のため夜も眠らず、 これは敗亡への門であると知るがよい」(270~271頁) ■「刹帝利(武族)の家に生まれたる者が、 財は小に、渇愛は大に、 この世に不可能なる王位を希う。 これは敗亡への門と知らねばならぬ」(271頁) 第21章 法を見るものはわれを見る ■「比丘たちよ、なんじらは、わたしの法の相続者とならねばならぬ。財の相続者となってはならぬ。わたしはなんじらを憐愍(れんみん)して、わが弟子たちは法の相続者たれかし、財の相続者たることなかれかし、と願っているのである。 比丘たちよ、もしなんじらが、わたしの財の相続者となり、法の相続者とならなかったならば、なんじらはそれによって、他人より指さされ、かの師の弟子たちは、財の相続者にして法の相続者にあらず、と批評せられるであろう。わたしもまたそれによって、他人に指さされ、かの師の弟子たちは、財の相続者であって法の相続者にはあらず、と評されるであろう。 比丘たちよ、さればなんじらは、心してわたしの法の相続者とならねばならぬ。財の相続者となってはならない。さすれば、なんじらも、またわたしも、他人の指弾を受け、かの師の弟子たちは財の相続者であって、法の相続者ではないなどと、非難せられることはないであろう。そのゆえに、わたしはここに、なんじらはわたしの法の相続者たれ、財の相続者たるなかれ、と説くのである」(272~273頁) ■「また比丘たちよ、たとい比丘が、わたしを去ること百由旬(距離の単位、40里または30里、あるいは16里にあたるという)のかなたに住すとも、もし彼が、はげしい欲望をいだかず、欲望のために激情をいだくこともなく、瞋恚をいだくこともなく、よこしまの思惟にかられることもなく、不放逸にしてよく知解し、道心堅固にして、よく一境に心をとどむることをうるならば、則ち彼は、わたしの近くにあるのであり、またわたしは、彼の近くにいるのである。そのゆえんは何であろうか。比丘たちよ、かの比丘は法を見るものであり、法を見るものはわたしを見るからである」(276~277頁) ■「ソーナよ、では、その糸があまりに強くなく、ゆるくもなく、程よく張られてあったならば、いかがであろうか。なんじはこれをかなでて、よき音を生ずることをうるであろう」 ソーナが、「しかり」と答えたとき、釈尊は、その問答の結論を、つぎのように説き教えた。 「ソーナよ、まさにそれと同じであると承知するがよい。刻苦精進にすぎれば心高ぶって静かならず、精進緩やかにすぎれば懈怠(けたい)にかたむく。そのゆえに、ソーナよ、なんじは平等の精進に住し、また諸根の平等を守り、かの中(ちゅう)における相をとるがよい」 その教誠によって、ソーナは、これまでの極端におもむく態度をやめ、やがて、出家の究極の目標を、実現することを得た。そのことを、彼はみずから『長者偈経』の中に、つぎのように語りのこしている。 「直ぐき道を説き示されたならば、往きて還ることなかれ。みずからおのれを励まして、究竟の境地を成就せよ。 われ極端の努力をなせしとき、世間無上のわが師には弾琴の例えを以て、法を説き示したもうた。 われはその言を聴きて、教えを楽しみて住し、涅槃に達せんがために止観を行じ、三明を逮得して、仏陀の教えを成就した」(279~280頁) 第22章 自燈明、法燈明ー最後の説法 ■「世の人々が籠筏を結ぶ間に、 深所をすて、橋を架して、 河の流れを渡る者をこそ、 よく渡りたる者、賢者という」(285頁) ■「ではアーナンダよ、比丘僧伽はわたしに何を待望するというのであるか。わたしはすでに内外の区別もなく、ことごとく法を説いたではないか。アーナンダよ、如来の説法にはあるものを、弟子に隠すというような、教師の握りしめた秘密の奥義はないのである。またアーナンダよ、もしわたしが、『われは比丘たちの指導者である』とか、『比丘たちはわれに頼っている』とか思ったならば、わが亡きのちの比丘たちについて何かを語らねばならぬであろう。だが、わたしは、比丘僧伽に関して何をか語ろうか。 さればアーナンダよ、なんじらはただみずからを燈明とし、みずからを依処ととして、他人を依処とせず、法を燈明とし、法を依処として、他を依処とすることなくして住するがよい。 まことにアーナンダよ、今に於ても、またわれ死して後においても、自らを依処として、他人を依処とせず、法を燈明とし、法を依処として、他を依処とすることなくして、修行せんと欲するものこそ、アーナンダよ、かかる者こそ、わが比丘たちの中において最高処にあるのである」(287頁) ■「アーナンダよ、樹々は時ならぬ花をひらき、虚空よりは香華ふりそそぎ、微妙の音楽は天の方よりおころうとも、かかる手段をもって、如来は崇め羅れ、尊ばれ、供養せらるべきものではない。アーナンダよ、比丘もしくは比丘尼、優婆塞もしくは優婆夷にして、よく法と随法とによって住する者こそ、如来をこの上もなく崇め、尊び、供養する者であると知らねばならぬ。されば、アーナンダよ、なんじらは、いま、法と随法とによりて住し、法によりて行ずべきであると、かように学ぶべきである」(289頁) ■「アーナンダよ、悲しむな。慟(なげ)くことをやめよ。わたしはいつも、教えていたではないか。すべて愛する者とはついに別れねばならぬ。生じたるものはすべて壊せずということはできない。 アーナンダよ、なんじは長い間にわたって、わたしの侍者としてまことによく世話をしてくれた。それは立派なことであった。このうえは、さらに精進して、すみやかに究極の目標を実現するがよい。 アーナンダよ、あるいはなんじらは、かく思うかもしれない。ーー師のことばはおわった。われらの師はすでにないーーと。だがアーナンダよ、そのように思うべきでない。アーナンダよ、わたしによって説かれ教えられた教法と戒律とは、わが亡きのちに、なんじらの師として存するであろう」(290~291頁) ■「では、比丘たちよ、わたしはなんじらに告げよう。ーー諸行は懐法(えほう)である。放逸なることなくして精進するがよい。ーーこれがわたしの最後のことばである」(292頁) ■それらの中にあって、アルヌッダの説いた偈が、そぞろわたしどもの心に染み入ってくる。 「心安らけき救済者は、 いまや入る息も出る息もない。 欲なき者は寂静に達し、 聖者はいま滅したもうた。 ゆるぎなき心をもて、 よく苦にたえたまい、 燈火の消ゆるがごとく、 心の解脱をとげたもうた」(293頁) (2020年3月9日、了) |
『仏陀』増谷文雄 著 角川選書ー18
投稿日:
執筆者:okanokouseki