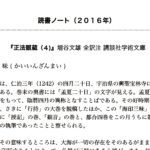『仏教の根底にあるもの』玉城 康四郎著 講談社学術文庫
■ このように、親鸞の救いは、弥陀の願力が衆生を救うことであり、道元の悟りは、三昧に端坐して自己を修証することである。そこでは宗教的世界の構造が違っている。親鸞は救いに至る道すじを説いているのであり、道元は悟りそのものの在り方を語っている。しかし親鸞の場合も、救われている状態を突きつめると、
「無明法性(むみょうほっしょう)ことなれど、心はすなわちひとつなり、この心すなわち涅槃なり、この心すなわち如来なり」
「弥陀の本願信ずべし、本願信ずるひとはみな、摂取不捨の利益(りやく)にて、無上覚をばさとるなり」
ということになって、救いと悟りとはもはや区別できなくなるであろう。
悟りという宗教的世界の構造もさることながら、むしろ、救われていることの目覚めの外にはあり得ない、という視点から、仏教の原点まで遡(さかのぼ)ってみると、ゴータマ・ブッダの菩提樹下における悟りは、まさしく人生の苦悩から救われたことであったとおもわれる。」(16~17頁)
■ゴータマにおける「……からの解脱」「……からの救い」という場合、その問題の生・老・病・死であったことは、一般にみとめられている。したがってゴータマにとってはその目標は明白であった。
「わたしもまた、以前に目覚めていない菩薩であったとき、自ら生でありつつ生そのものを求め、自ら老でありつつ老そのものを求め、自ら死ぬものでありつつ死そのものを求め、自ら憂いでありつつ憂いそのものを求め、自ら汚れでありつつ汚れそのものを求めていた。そのようなわたしに、つぎのことが思い浮かんだ。なぜにわたしは、自ら生でありつつ生そのものを求め、自ら老でありつつ老そのものを求め、ないし自ら汚れでありつつ汚れそのものを求めるのか。さあ、わたしは、自ら生でありつつ生そのもののなかの患(わずら)いを知って、不生なる無上安穏(むじょうあんのん)の涅槃を求めよう。同じように、自ら老・病・死・憂い・汚れ・でありつつ、それぞれのなかの患いを知って、不老・不病・不死・不優・不汚なる無上安穏の涅槃を求めよう」
これで見ると、ゴータマにおける人生の根本問題は、生・老・病・死・憂・汚そのもののなかで、これにかかずらっている自己自身であり、当然ながらそれからの脱却、それからの救いが目標であるあることは明白である。すなわち、不生・不老・不病・不死・不憂・不汚なる究極の涅槃である。
ところでゴータマは、まだ解脱を得られないときでさえ、究極の涅槃がどのような状態であるかをすでに推定し得ていたと考えられる。というのは、涅槃を求めて宮殿を出た後に、アーラーラ・カーラーマとウッダカ・ラーマプッタの二人の仙人をそれぞれたずねて修行にはげみ、師と同じ境地に達したのに、それはまだ涅槃ではないと判定しているからである。そしてひとり菩提樹の下に坐って禅定(ぜんじょう)に入り、やがて解脱して涅槃に達することができた。それが果たして真の涅槃であるかどうかは、誰からも証明されたわけではない。すなわち、自ら求める涅槃と、自ら解脱して得た境地とが完全に合致して、自ら満足することができたのである。(18~19頁)
■では、ゴータマをしていったい何が充足せしめ、かつそれを涅槃として確認せしめたのであろうか。この問題を、ゴータマの解脱の際の経典『ウダーナ』によって確かめてみよう。
菩提樹の下で解脱を得てブッダとなったとき、ゴータマ・ブッダは、結跏趺坐のまま七日のあいだ解脱の境地を深め、そのあとウダーナ(即興の詩)を述べている。日没時と真夜中と夜明けにわたって、それぞれ1つずつ、3つの詩がブッダの口から発せられている。
日没時の詩。
「実にダンマ(dhamma)が、熱心に瞑想しつつある修行者に顕になるとき、そのとき、かれの一切の疑惑は消失する。というのは、かれの縁起の法を知っているから」
夜明けの詩、
「実にダンマが、熱心に瞑想しつつある修行者に顕になるとき、かれは悪魔の軍隊を粉砕して、安立(あんりゅう)している。あたかも太陽が虚空を輝かすがごとくである」
右の3つの詩は、ゴータマが目覚めてブッダとなった状況を見事に表している。その目覚めの原型とは何か。それは3つの詩に共通している所の、「ダンマが瞑想しつつある修行者に顕になる」というそのことである。すなわち、「ダンマが主体者に顕になる」、まさにその時に一切の疑惑が消失したのである。(22~23頁)
■ブッダは弟子たちに次のように説いている。
「比丘(びく)たちよ、世に現れるところの一人(いちにん)は、多くの衆生の利益のために、多くの衆生の楽のために、世に対する慈悲のためにうまれる。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である。……
比丘(びく)たちよ、世に現れるところの一人(いちにん)は、多くの衆生の利益のために、多くの衆生の楽のために、世に対する慈悲のためにうまれる。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である。……
比丘たちよ、一人の顕わになることから、大いなる眼の顕わになることがあり、大いなる光明の顕わになることがあり、大いなる光照の顕わになることがある。一人とは誰であるか。如来・阿羅漢・正等覚者である」
如来・阿羅漢・正等覚者とは、如来の上にさらに尊称を加えたものである。阿羅漢は能力あるもの、正等覚者は正しく悟れるものの意味である。いいかえれば、如来の趣旨をいっそう強調したものである。しかも、その如来が、現実のゴータマ・ブッダによって第三者として弟子たちに語られているところから見て、現実のブッダをも超える、超越的なもの、絶対的なものであることが知られよう。
その如来が、ここでは、無二のもの、伴(つれ)なきもの、無比のもの、対比なきもの、比類なきもの……といわれているのであり、その如来が顕わになることによって、われわれには大いなる眼となり、大いなる光明となり、大いなる光照となる、と説かれているのである。すなわち先に「ダンマが顕わになること」が目覚めの原点であるといった、その形なき純粋生命たるダンマと、如来とはまったく同質であることがここに明瞭になったということができよう。(26~27頁)
■先に引用したように、ブッダは、
「わたしによって体得されたこのダンマは、甚だ深くて、理解しがたく、悟りがたく、寂静であり、分別を超えて微妙であり、賢者によって知られるべきものである」
と述べて、形なき純粋生命の体得された状況を伝えているが、それにつづいて、
「しかし、この世の人々は、アーラヤ(alaya執著しゅうじゃく)を好み、アーラヤを喜んでいる。そのような人々にとっては、この道理はとても理解できない。……たといわたしがダンマを説いても、人々は理解できないから、わたしはただ疲労して悩むだけであろう」
と語っている。
ここで道理といっているのは、ダンマがゴータマに顕わになって、すべての疑惑やぼんのうから解放され、もっとも平和な涅槃の境地に達した、その転換的な状況を指している。こうした道理は、世の人々には理解できないというのである。なぜなら人々は深い我執(がしゅう)に捕われており、本能的にアーラヤ(我執)を喜び、アーラヤ(我執)を楽しんでいるからである。
ここに、ダンマが顕わになって涅槃に達したブッダの境地と、本能的に我執を楽しんでいる世の人々との間に、まさしく対立的に逆行する、くっきりとした境界線が引かれてしまったのである。ブッダは、「たといダンマを説いても、ただ疲労困憊(こんぱい)するだけであらう」と、絶望の声を放っている。ブッダはついにそのまま沈黙に入ろうとした。
ブッダの境地と世の人々の実態、いいかえれば悟りと迷い、この二つの逆行的な対立は、決定的に重要な注目点である。簡単に妥協さるべき問題ではない。人間の生存が続くかぎり、永遠に解消しない対立である。この底知れない裂け目に慎重に留意しないでは、転迷開悟の機会は永久に訪れてこないであろう。後代に発達した大乗仏教の唯識思想では、原始経典のアーラヤがアーラヤ識として掘り下げられている。
これについては後に論じたいと思うが、人間の我執の根源を徹底的に究明して、ついにアーラヤ識に達したのである。それは、人間の個体における我執の根源であると同時に、世界そのものの我執の起源であるといってよいであろう。(28~30頁)
■ 「第一に、すべての世界の海は、かぎりない因縁によって成り立っている。すべては因縁によってすでに成立しおわっており、現在成立しつつあり、また未来も成立するであろう。
ここにいう因縁とは、つぎのことを指している。すなわちそれは、仏の神通力(じんずうりき)である。また、ものごとはすべてありのままであるということである。また、衆生の行為や宿業である。また、すべての菩薩は、究極の悟りを得る可能性を有しているということである。また、菩薩が仏の国土をきよめるのに自由自在であるということである。これが世界海(せかいかい)の因縁である。
毘盧遮那仏の境界は、とうてい思い測ることはできないが、われわれが経験しているとおりにすべてが安定している。なぜなら毘盧遮那仏は、無量無辺のすべての世界海をきよめたもうているからである」(『華厳教』「盧舎那品」における一文)(31~32頁)
■この主題に関する論点からいえば、迷いの世界にさまよっているわれわれ人間の宿業が、実はそのまま仏の因縁界の一景であるということができよう。そうしてみると、迷いと苦悩に充ち満ちてている人間の世界は、宇宙そのものが仏であるという仏国土と別でないことはいうまでもなく、そのような仏の世界に包括されており、ついにはそのままが仏そのものの世界であるということに気づかれるであろう。しかしそこまで至るのには、『華厳経』全体の長広舌(ちょうこうぜつ)が必要であったのである。(32~33頁)
■コーサラの国にアングリマーラという盗賊がいて、しきりに悪事を働いていたが、ついにブッダに帰依して悟りを開くことができた。仏道の究極目的を自ら証拠立てたのである。ある日、アングリマーラは托鉢に出たが、かつてかれが盗賊であったころ、種々のうらみをうけた人々がそのすがたを見つけて、棒や石や土くれを投げつけたので、かれは傷つけられ、血を流し、鉢はこわれ、衣は破れて、這々(ほうほう)のていでブッダのもとに帰ってきた。ブッダはアングリマーラに向って、次のように説いている。
「忍受せよ、汝修行者よ、忍受せよ、汝修行者よ、汝が幾年・幾百年・幾千年のあいだ、地獄において受くべき、その業の果報を、汝は現実において受けているのである」
そのときアングリマーラは、ひとり坐して冥想に入り、ブッダの説法に聞き入った。かれは今まで気づかなかった、自らの業の果報に触れたのである。そうすると、「あたかも雲をはなれた月のように、かれはこの世を照らし出した」といわれている。
アングリマーラは、すでに仏弟子となって修行し、解脱に達していたのである。それにもかかわらず、かれはかつて行為した業の果報のなかにおり、その果報のために苦悩せねばならなかった。それは、アングリマーラの意識的領域だけではなく、それを包む深い無意識的な領域である。いいかえれば、かれの自己は、限りなく深い業の果報、意識されざる領域にまで拡充しているのである。そしてかかる業の果報に気づくときに、アングリマーラ自身が果てしなき解脱へと開かれていくのである。
以上のアングリマーラと同室の問題が、禅宗の開祖と仰がれている菩提達磨の二入四行説(ににゅうしぎょうせつ)のなかに指摘することができる。二入とは理入(りにゅう)と行入(ぎょうにゅう)であり、四行とは、その行入のなかの、報怨行(ほうおんぎょう)・随縁行・無所求行(むしょぐぎょう)称法行である。問題の箇所は、この四行のうちの報怨行と随縁行に示されている。しかし、一先ず理入から見ておかねばならない。
理入の理とは真理である。
達磨は、
「……壁観(へきかん)に凝住(ぎょうじゅう)し、自も無く他も無く、凡聖(ぼんしょう)等一にして、堅住して移らず、更に文教に随(したが)わず、此れ即ち真理と冥苻(みょうふ)す。分別あることなく、寂然(じゃくねん)無為なるを、之(これ)を理入と名づく」
という。
壁が突き立っているように、身も心も一つになって禅定(ぜんじょう)に入るときに、やがて我もなく他もなく、衆生(しゅじょう)も仏も一如になる。このようにして不動のまま持続していけば、ついには真理と合一する、というのである。
ここにいう真理とは、もはや言葉や教えではない。また形に現れた道理や理法というべきものでもない。「自も無く他も無く、凡聖(ぼんしょう)等一にして、堅住して移らざる」ことにおいて、おのずから冥合(めいごう)して頷(うなず)く所のものである。したがって、無分別であり、寂然無為といわれる。
このような真理とは、もはや疑うべくもなく、先に挙げた原始経典における根源的意味のダンマ、それがゴータマに顕話になることによって、ブッダとして目覚めた所の、形なき純粋生命とまったく同質であるというべきであろう。
理入は、このように「堅住して移らず」して直接に真理と冥合することである。これに対して行人は、四つのそれぞれの行を通じて真理と冥合することである。真理と冥合することにおいては、理入も行人も異なることはない。
さて、行入の第一は報怨行(ほうおんぎょう)である。
「云何(いか)んが報怨行なる。修道の行人(ぎょうにん)、若(も)し苦を受くる時、当(まさ)に自ら念じて言うべし、我、往昔(おうしゃく)より無数劫中(むしゅごうちゅう)、本(もと)を棄てて末を逐(お)い、諸有(しょう)に流浪して、多くの怨憎(おんぞう)を起し、違害(いがい)すること限り無し。今は犯すこと無しと雖(いえど)も、是れ我が宿殃(しゅくおう)・悪業の巣の熟するものにして、天・非人の能(よ)く見与する所に非ず。甘心忍受(かんしんにんじゅ)して、都(す)べて怨訴(おんそ)すること無し、と。経に云わく、苦に逢うも憂えず、何を以(もつ)ての故に、識、本に達するが故に、と。此の心生ずる時、理と相応し、怨(おん)を体して道に進む。是の故に説いて報怨行と言う」
現在、悪事をしていないのに苦痛を受けることがある。そのとき、どう対処すればよいか、というのがこの報怨行である。実は、自分の意識にのぼってこない限りない昔から、根本の道を忘れて、さまざまな世界を流浪してきた。その間には多くの怨憎や障害を重ねてきたが、その数知れぬ悪業の結果が今ここに熟して、苦痛を受けている。いかなるものもこの業力を解消することはできない。そこで自ら甘んじてこれを忍受し、けっして他を怨(うら)みに思うことはしない。これが報怨行の要点である。そして、この心が起るときに真理と合一するというのである。
これは、ブッダに業の果報を教えられた先述のアングリマーラの場合と、まったく同様であるといえよう。
さて、次の第二の随縁行は、報怨行と逆の場合である。
「随縁行とは、衆生は無我にして、並びに業に縁(よ)りて転ずる所なれば、苦楽斉(ひと)しく受くること、皆、縁より生ず。若し勝報・栄誉等の事を得るも、是れ我が過去の宿因の感ずる所にして、今方(まさ)に之(これ)を得るのみ。縁尽くされば無に還(かえ)る。何の喜びか之れ有らん。得失は縁に従い、心は増滅無く、喜風動かざれば、道に冥順(みょうじゅん)す。是の故に、説いて随縁行と言う」
われわれ衆生は、もともと無我であって、ただ過去の業縁(ごうえん)によって動いており、そのために種々の苦楽を受けている。もしすぐれた果報や栄誉などのことを得ても、すべて過去の業報のもたらす所である。縁が尽されば無に帰する。別に喜びとするには当らない。このように得失は業縁に従うと諦観(たいかん)して心が動かされることなければ、そのままで仏道に冥合するというのである。この随縁行は、先の報怨行が苦を受けるのに対して、その逆に楽を受ける場合である。
以上のように、報怨行・随縁行は、苦楽の相違はあっても、いずれも過去の業縁にさかのぼって、量り知れない自分の姿がとらえられているといえよう。アングリマーラの場合もまったく同様である。しかも、過去の業縁が現在の自己として頷かれるときに、過去から現在にわたる自己の全体が解き放たれていくのである。
苦楽を受けているのは現在の自己である。その苦楽が過去の業縁へ伸びていく、現在から過去へである。しかもその業縁を現在の自己として受容する、過去から現在へである。そして業縁の事故が、そのまま形なき純粋生命のなかで果てしなく目覚めていく、いいかえれば、業縁の自己の外に目覚むべき自己はない、ただ業縁の自己のみである、現在から現在へである。
最初に述べた、菩提樹の下で悟りを開いたブッダが理入であるとすれば、ブッダに業の果報を教えられてさらに解脱を深めていったアングリマーラは行入(ぎょうにゅう)であるといえよう。理入も行入も、真理に冥合し証入することにおいて異なることはない。(34~38頁)
■アーラヤ識のアーラヤは、「蔵」の意味であり。それゆえに象識ともいわれている。英語では store consciousness と訳されている。その理由は、現実経験の世界が、ことごとくその中に貯蔵されているからである。あるいは、現実経験のすべての種子(しゅうじ)を貯えているから、一切種子識ともいわれている。これは、アーラヤ識自身が貯えているのであるから、能蔵の意味である。ところが、逆に所蔵ともいわれている。それは、アーラヤ識から現出した現実経験の世界は、同時にアーラヤ識を包むものとなっているからである。いいかえれば、アーラヤ識の現実経験に対する関係は、現実経験を包むものとしては能蔵であり、逆にそれに包まれるものとしては所蔵である。そしてアーラヤ識自体は、執著(しゅうじゃく)の源泉として執蔵(しゅうぞう)といわれている。(40~41頁)
■厄介なことには、マナ識たる自我意識は、底知れない無意識のなかに根ざしている。それは、日常生活のなかではほとんど意識されることはない。もとより意識される自我意識も存在していることは、日常経験のとおりである。それは、マナ識よりも表面的な意識、いわゆる心といわれるもののなかで起っている。その場合の自我意識は、起ることもあれば起こらないこともある。しかし無意識のなかの、マナ識たる自我意識は、寝ても覚めても、二六時中、起っており、中止することがない。その我執を『成(じょう)唯識論』では、倶生(くしょう)の我執といい、次のように述べている。
「無始時来(むしじらい)、虚妄薫習(こもうくんじゅう)の因の力の故に、常に身と倶(とも)なり、邪教及び邪分別を待たず、任運(にんぬん)して転ずるが故に、倶生と名づく」
倶生の我執とは、いわば生まれながらの、先天的な我執であり、始まりのない無限の過去から、迷いに迷いを重ねて流浪し、この身に付着している自我意識である。それは、意識上の分別を待たずに、元来、自然に生じている、といわれる。
通常の、心の中で起っている我執を意識的自我意識であるとすれば、マナ識の我執は無意識的自我意識であるといえよう。しかもそれは、無限の過去から断絶することなく、二六時中起っているということが特徴的である。
さて、これまで追求してきた主体の根源の実情が、ようやくここに浮かんできたのである。それは、マナ識とアーラヤ識との根本関係に存する我執であり、無始以来、中断することなく持続している所の自我意識である。しかもマナ識の我執は、深い無意識のなかに在り、そのマナ識さえも、われわれはほとんど意識することができないのであるが、その我執の源泉は、マナ識のいっそう根底的な、執蔵としてのアーラヤ識に在るといえよう。
では、仏教の究極の目当てである解脱はいかにして実現できるであろうか。それは、我執の根本転換の外にはあり得ないであろう。そのアーラヤ識の転換はどうしたらできるのであろうか。
アーラヤ識は、すでに述べた如く、人間存在の意識の源泉であり、さらに経験世界そのものの根拠でもある。人間存在そのもの、あるいは世界の存在そのものが、アーラヤ識として、根源的ミステークに陥っている。そうだとすれば、われわれがいかに努力を重ねても、もはやアーラヤ識そのものに転換の力がないことは明白である。
ヴァスバンドゥの兄であるアサンガ(Asanga 無著むじゃく、310-390頃)は『摂大乗論(しょうだいじょうろん)』の中で、全人格的思惟(瞑想、禅定)を行じつつ、慎重にアーラヤ識の所在を究明している。つまり、いかに瞑想、禅定を深めても、ついにはアーラヤ識に帰着する外はない。いいかえれば、ただ禅定を深めるのみでは、アーラヤ識の転換、すなわち解脱は実現してこないのである。
では、いかにしてその転換は達成されるのであろうか。アサンガは、次のようなただ一つ解答を提示するのである。
「最清浄法界(さいしょうじょうほっかい)より流るる所の正聞薫習(しょうもんくんじゅう)、種子(しゅうじ)となるが故に、出世心、生ずることを得」
チベット語訳では、
「最清浄法界が顕話になる所の聞薫習の種子から、それ(出世心)は生ずる」
となっている。
最清浄法界とは、まったく形を離れた純粋生命たる真実の世界である。その最清浄法界が、主体者に顕わになってくる。そのことは、主体者からいえば、全人格が耳となって、最清浄法界に聞きほれる。そうすると、その純粋生命が全人格に染みついて(すなわち薫習)、そこから初めて、人間の基盤(アーラヤ識)を超出する目覚めの心(出世心)が生ずる、というのである。
これは、唯識思想における主体の根源たるアーラヤ識の転換の状況である。
ここにおいて、われわれは直ちに思い浮かべるであろう、あの菩提樹下におけるゴータマ・ブッダの目覚めの実景を。まったく形を超えた純粋生命たるダンマが、ゴータマに顕わになったとき、一切の疑惑が消失して、目覚めが実現したのである。そしてダンマはその全人格に滲透して、ついに貫徹したのである。ブッダとアサンガにおける目覚めの構造が、軌を一していることはいうまでもないであろう。(43~46頁)
■しかし、空海が恵果の許(もと)にあったのは、わずか七、八ヶ月の短期間であった。しかも両者が出会って3ヶ月も経たぬうちに、空海は、胎蔵界・金剛界の伝法灌頂(でんぽうかんじょう)を受けたのである。いかに空海がすぐれた人物であったにせよ、インド正統の密教を継いだ恵果の、最内奥(ないおう)の教えを受けるには、すでに空海に相応の準備ができていたことは想像にかたくない。二十四歳の著作である『三教指帰(さんごうしいき)』に示されているとおり、空海は、ひとりの沙門に虚空蔵聞持(こくうぞうもんじ)の法をさずけられ、時には阿波の国の大滝岳によじのぼり、また時には、土佐の室戸岬で想念を凝らすなど、青年時代の苦行は、かれの深層領域を深く耕していたにちがいない。それが、桂花とのわずかの期間の接触によって、密教の大法(たいほう)を受けつぐことを可能ならしめたのであろう。
そればかりでなく、この著作の構造は、儒・仏・道の3教にわたっている。いわば、青年空海が触れ得る代表的な世界観のすべてを網羅している。このようなかれの見解の普遍性・世界性が、後年の教相判釈である『十住心論』『秘蔵宝鑰』『弁顕密二教論』などの著作となって実を結んだといえよう。かれは入唐(にっとう)して、仏教各派の教義を学び、またインド哲学や、さらに深く中国固有の思想に触れることができたのであろう。それらのすべてを包括して教相判釈の対象としたのである。いいかえれば、仏教の範囲に限るのではなく、人間であるかぎは、当時の普遍的な人間論であったということができる。
さて、このような事態のなかで、空海思想のもっとも大きな特徴は何であろうか。ここにゆっくり論ずるゆとりはないが、一語にして尽せば、弁別と包括であるといえよう。弁別とは、真実と非真実とをきびしく篩(ふる)い分けることである。仏教の根本は何か、真実の仏教とは何か、ということを、空海は徹底的に追求した。そしてその根本問題が恵果との出会いによって満足したのである。すなわち顕教(けんぎょう)からまったく峻別される密教の真実性である。しかし、包括とは何か。それは、密教以外の、一見真実ならざるように見える一切の教え・思想を包括することである。このように、真・非真をきびしく篩い分ける弁別と、非真なるものをも包みこもうとする包括とは、いかにも矛盾しているように見える。
しかし実は、この両者は物の表裏であって、根源において一体であるという点にこそ、かれの仏教観のすぐれた風格を見ることができる。つまり、顕教から弁別された密教とは、宇宙的絶対者である毘盧遮那仏のそれ自身の自覚内容であり、それは、そのまま法身(ほっしん)説法という形において現実に顕にわになっている。いいかえれば、色も形もない法身仏が、われわれの感覚するとおりに現れている、それがすなわち法身説法である。したがって、あらゆる教え・思想ばかりではなく、すべての現象が本質において密教ならざるを得ない。このように、顕教から区別された密教とは、実は存在の根源体であり、それは必然的に一切の存在者を包括しているのである。弁別と包括とが一体たつ所以(ゆえん)である。
空海の法身説法は、密教の秘中の特徴を表示するものである。空海は、中国華厳宗の世界観、すなはち重重無尽の無碍法界観(むげほっかいかん)を直接のパターンとして六大無碍の世界観を展開しているのであるが、華厳宗においては、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、ヴェールにおおわれた秘仏であった。すなわち、色も形もない法身仏のゆえに、自ら説法し得ないものと見なされている。説法し得るものは、毘盧遮那仏にもとづく諸菩薩であり、その説法が『華厳経』となっている。したがって華厳宗の教理において、毘盧遮那仏の活動する余地はほとんど認められていない。
しかるに、真言密教においては、毘盧遮那仏の活動のポジションが逆転するのである。説法するはずのない法身仏が説法を始めるのである。それこそ密教の密たる所以であり、秘秘中の最秘である。毘盧遮那仏とは、それとして心に浮ぶ仏のイメージをいっているのではない。それは、実は宇宙そのものであり、もっとも根源的な意味における自己そのものである。その毘盧遮那仏が法身説法するということは、宇宙のもっとも深き根源が、そのまま顕(あら)わになることである。実存の究極な神秘にきわまるという外はない。(53~55頁)
■自受用三昧
まず第一に、空海における毘盧遮那仏の自受用三昧(じじゅようざんまい)である。毘盧遮那仏(光の仏)は宇宙そのものの仏であり、自受用三昧は自ら体験しつつある三昧である。いいかえれば、宇宙そのものが三昧に入っている。この毘盧遮那仏の自受用三昧が密教の根本的立場であるということができよう。空海は、顕密二教の区別を仏の三身(さんしん)になぞらえて、応身・化身の説法が顕教で、法身の説法が密教であると述べ、さらに『金剛頂経』にしたがって、如来の変化身が三乗、他受用身が一乗で、併せて顕教であり、これに対して自受用仏の内証智の境を説くのが密教ということになる。自受用法性仏が、すなわち自受用三昧の毘盧遮那仏なのである。いいかえれば、まったく形を超えた宇宙そのものの絶対仏が、そのまま果てしなき瞑想を享受しているというのが、毘盧遮那仏の自受用三昧に外ならない。これが密教の根本三昧であり、この三昧に没同することによって、われわれ自身もまた仏そのものを受用することができるのである。
さて、道元の根本的立場もまた、このような密教の三昧とまったく同質であるということができる。
道元は、『正法眼蔵』「弁道話」の最初で、
「諸仏如来、ともに妙法を単伝して、阿耨菩提(あのくぼだい)を証するに、最上無為の妙術あり。これただ、ほとけ仏にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧、その標準なり」
と述べている。
阿耨菩提とはとは究極の悟りであり、それを体得するにすぐれた方法がある。それは、仏から仏へと正伝(しょうでん)されていくところの自受用三昧であり、それこそ、根本の基準であるというのである。この仏の三昧に自らも参与することによって、仏祖単伝の打坐(たざ)を成就することができる。道元は、その光景をつぎのように述べている。文章がむずかしいので意訳してかかげてみよう。
「たといひとときの坐禅であっても、自分の身・口・意(しんくい)の三つの働きに、そのまま仏の印をつけて三昧に端坐するとき、全世界がみな仏の印しとなり、全虚空がことごとく悟りとなる。諸仏如来はそのためにますます法楽を増し、迷界の衆生も十方世界の万物も、大解脱を実現し、すぐれた法輪を転ずる。これらの悟りが、さらに、自分に帰ってきて互いに通じ合うから、ついに坐禅人は身心(しんじん)脱落して、天真の仏法に証入することができる」
道元によれば、自分が坐禅し、その力によって悟りを開くのではない。坐禅に入るとき、すでに自分自身が仏に印(しるし)どけられることによって、全世界が悟りとなり、その力が自分に帰ってきて身心脱落することになる、――というのである。仏の本地(ほんじ)の大三昧にみずから加入することが、道元のいう、正伝の打坐なのである。それは、仏の三昧力に裏づけられてはじめて実現する、ともいうことができよう。(57~59頁)
■自然
第三に、自然の(じねん)の立場である。親鸞に「自然法爾(じねんほうに)」の一文があることは周知のとおりであるが、自然の見解は親鸞に限られているわけではない。とおく老荘(ろうそう)にさかのぼり、それに関連して中国において発展しており、やがてそれが仏教にも入ってきた。空海は、法然(ほうねん)という語によってその意味を表そうとしている。『即身成仏義』のなかでは、「法然、薩般若(さつぱにゃ)を具す」といい、『声字実相義』では、「法然・随縁の有(う)」という。前者では、法然を、「諸法の自然、是くの如し」と解し、後者では、法然を法爾と置きかえてている。すなわち、言葉の上からいっても、空海にはすでに親鸞の自然法爾の語が綴られ得るわけである。
このようにして空海は、「法然、薩般若(さつぱにゃ)を具す」という一文を、ありとあらゆる存在は、おのずからにして一切智智を成就する、というように解しており、「法然・随縁の有(う)」の箇所で、さらにそれを構造的に開示している。その構造というのは、仏の側と衆生の側とに分け、仏の側を、法身(ほっしん)・報身・応化身・等流身(とうるじん)の四種となしているが、ここでとくに留意したいのは、これを二方面から考察して、一つは法仏・法爾、二つは随縁顕現で、菩薩の随福所感と如来の信解願力の所生(しょじょう)となしている点である。しかも空海はさらに衆生の側からみて、衆生にも本覚法身があって仏と平等なすのである。いいかえれば、仏の側からは法身仏と仏の信解願力の所生、衆生の側からは仏と平等一体であるというのである。(62~63頁)
■このように見てくると、以上の点において空海と親鸞とはまったく構造をおなじくしているといわねばならない。しかも、親鸞の自然法爾は、形を越えた無上仏、いいかえれば法性法身にならしめることである。その形のない所を自然(じねん)というのである。念仏の行者からいえば「よからんとも、あしからんともおもはぬ」所が自然なのである。親鸞は、ながい苦闘のすえに、こうした自然の境地に達したのである。この点からいえば、右に論じた空海の凡仏一体の構造を、親鸞は、みずからの信心成塾の過程において実現したといえよう。(63頁)
■ さて道元においてはいかがであろうか。道元は、自然の見解を『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』「空華」のなかで展開している。かれは、『景徳伝燈録』に見える達磨の言葉を引き、「一華開五葉、結果自然成」という。一華(いちげ)はおのずから五枚の花びらとなって開き、果を結ぶことに自然(じねん)に成る、というのである。この自然についての道元の解釈が意味深い。自とは、己(おのれ)であり、それはかならず汝である。つまり、仏とも凡夫とも位のつけようもない真人を自由に使いこなしているもの、それが自である。然とは、聴許(ちょうきょ)、すなわち許すことである。このような自然成(じねんじょう)が、「華開き果を結ぶ時節」である、という。このように見てくると、道元の自然は、親鸞の自然を自らの主体そのものに集注して理解されているといえよう。空海・親鸞・道元、三者それぞれ視点を異にしながら、構造の本質においては同質的なものが指摘され得るのである。(63~64頁)
■ 道元についても、同じ趣旨の道元的な特徴を指摘することができよう。仏の自受用三昧において坐禅人(にん)が端坐するとき、万物が仏身となって、「無等等の大宝輪を転じ、究竟無為(くきょうむい)の深(じん)般若を開演す」るのである。端坐参禅における、仏の法身説法である。また道元は、「自己をはこびて万法(まんぽう)を修証するするを迷とす、万法すすみて自己を修証するするはさとりなり」という。自己から万法へ向うのではなく、万法が自己に顕わになるのである。同じように「自己をわするるといふは、万法に証さるるなり。万法に証さるるといふは、自己の身心、および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹(ごしゃく)の休歇(きゅうけつ)なるあり、休歇なる悟迹を長長出(ちょうちょうしゅつ)ならしむ」という。ここでも、万法が自己に顕わになり、自己を動かして、脱落せしめ長長出ならしめて、どこまでも果てしなく展開せしめるのである。これまた法心説法の実現であるといえよう。(65頁)
■ 法然がたぐいまれな秀才であったことはよく知られている。法相・三論・天台・華厳・真言・律、なんでも自家薬籠中のものにした。たとえば、こういうことがある。醍醐に三論の学者がいた。寛雅(かんが)という人である。寛雅は俊寛の父である。俊寛は、謡曲でも知られているように、平家倒滅のクーデターを主謀し、鹿(しし)ケ谷で密議したが、事が発覚して薩摩の鬼界島に流され、そこで歿した人である。法然がこの寛雅に、三論について意見を述べると、寛雅は沈黙したまま十台の文箱(ふばこ)を持ってきて、それを法然に授けたという。法然以上に三論を理解したものが寛雅には見当らなかったからである。
また、法然の師である叡空(えいくう)と天台の円頓一実(えんどんいちじつ)の戒体(受戒したときに、円満成就の真言すなわち仏心が身体に染みついたもの)について対談したことがある。叡空は、心が戒体である、と主張したのに対して、法然はそれに反対して、性無作の仮(け)色(ありのままの本性の無表色、無表色とは形に表われない潜勢力の如きもの)が戒体であると論じた。互いに負けずに議論すること再三に及んだが、叡空はついに腹を立てて木枕で法然を打った。しかしあとで反省してみると、どうも法然の説が正しいということに落着し、法然の部屋へやってきて、「お前の見解は、天台の本意一実円戒の至極である」とほめている。
また、仁和寺(にんなじ)に華厳宗の名匠、大納言法橋慶雅(だいなごんほっきょうけいが)という人がいた。慶雅は、弘法大師の『十住心論』は華厳宗の基づいて作られた、というのに対して、法然は、そうではなくて、『大日経』の十心品(じゅうしんぼん)で作られた、といい、第六住心(法相)、第七住心(三論)、第八住心(天台)、第九住心(華厳)、第十住心(真言)、について、一々道理を述べ、ことに天台・華厳についてことこまかに説いた。法橋は、自分はこれほどまでに明瞭ではなかった、あなたのために不審がはれた、と喜んで、法然に授戒している。
また法然は、興福寺の蔵俊僧都(ぞうしゅんそうず)の所に行って、法相宗の法門を談じた。蔵俊は、「これは直人(ただびと)ではない」と感歎して、毎年法然に供物を送っている。
このように法然は、仏教各派の学問に習熟していたことが分る。大変な勉強家で、十五歳で叡山に登って以来、十七歳の時には天台三大部六十巻を学び始め、十八歳で遁世して名利を絶ち、ただひたすらに仏法を学んだ。一切経を五遍も読んだといい、老後になって、往時を述懐していうに、聖教(しょうぎょう)を読まない日はなかったが、木曾義仲が京都に乱入した一日だけ見なかった、という。(68~69頁)
■ 第一に、法然の発見した念仏とは人々にとって何を意味しているのであろうか。まず法念が念仏に生かされてことは事実である。それはみずから告白しているとおりである。ここに法然の個人解脱は終わったと見て良い。しかし、法然自身は念仏によって救われたが、果たして人々もまたこれによって救われ得るであろうか。これが、つぎに法然を襲った大問題であった。自分は救われたが、人々は救われ得るか否かは法然には分からない。実は、法念が救われたということも、かれ自身左右できることではなかった。念仏の光は突如としてかれを照らしたのである。まして同じ光が人々を照らすかどうかはかれの知るところではない。しかし法然にとって、人々の救われるということが大問題であった。いいかえれば、自利行が実現するや否や、利他行の問題がかれの心を捕えたのである。(26頁)
親鸞の宗教的世界
■ 親鸞の世界は容易ならざるものである。その容易ならざる所以を辿っていくと、所謂(いわゆる)機法(浄土真宗などで、信心と救い)二種の深心にきわまるが如くである。
機とは、人間の掩(おお)うべくもない実相である。それは、人間における実存そのものの無智と、その惑乱とに帰するであろう。しかも人生の経験において、無智はそのまま惑乱と同体でありといわねばならない。無智はすなわち惑乱であり、惑乱がそのまま無智であるという実存の根本様態が、果てしなき宿世(すくせ)より流れ来れる自己存在の実相である。
法とは、このような機に顕わになるものである。法が顕わになるということは、実存を包越する根源的神秘であり、そしてただ法のみが、実存にとって根源の真実を表明するものである。根源の真実は、実存の無智と惑乱とに真っ向から対決し、かつ無智と惑乱とを貫きとおすのである。
親鸞は、このような実存の粉(まご)うことなき実相を究明しとおし、実存に顕わになる根源的神秘と根源的真実とを浮き彫りにして止まなかった。それは、仏教思想発展のもっとも深い意味において、はるかかなたの原始経典「自己にたよれ、法にたよれ」というブッダの本旨につらなるものである。歴史的世界に共住し、それを究明し究尽(ぐうじん)し、そしてついに歴史的世界を越える実存の神秘というべきであろうか。(86~87頁)
■ 現代人が親鸞に近づきがたく思う、もう一つの理由は、親鸞の経典絶対主義である。親鸞にとって真実の教えは『無量寿経』である。この経典は釈迦の真説であり、その内容は弥陀の本願を説き明かしたという。親鸞はそれを確信し、それにもとづいて信心が確かめられるに至った。しかし、経典史論の発達した現在の時点において、そのような親鸞の確信を承認することは不可能である。しかし、親鸞の宗教的生命は、このような根本条件の変化のためにくつがえるのであろうか。それとも、その難問の壁を破ってまでも、その生命は生きのびていくのであろうか。これは大きな課題であり、ひとり親鸞だけの問題ではない。(87頁)
■ 善鸞(ぜんらん、親鸞の子)の異議によってたじろぐような信心は、本来まことの信心ではなかった証拠である。これに対して親鸞の信心はいかがであろうか。
さきに挙げた善鸞義絶の手紙のなかで、
「光明寺の和尚(善導)の、信の様ををしえさせたまひさふらふには、まことの信をさだめられてのちにには、弥陀のごとくの仏、釈迦のごとくの仏、そらにみちみちて、釈迦のをしへ、弥陀の本願はひがごとなりとおほせらるとも、一念もうたがひあるべからずとこそうけたまはりてさふらへば、……」
という。
親鸞は、善導の教えによってみずからの信心を訴えている。まことの信心というのは、たとい弥陀や釈迦のような仏が空に充ち満ちて、釈迦の教えや弥陀の本願はいつわりであると説いたとしても、一念の疑いもあってはならない、というのである。これは、親鸞のおどろくべき発言であり、もはや一念のたじろぎをも見せぬ頑強な大信を表明している。(91~92頁)
■そこで親鸞は、深智博覧の点で等しいというのならば見当ちがいである、といい、
「往生の信心にいたりては、ひとたび他力信心のことはりを承(うけたまわり)しよりこのかた、またくわたくしなし。しかれば聖人の御信心も他力よりたまわらせたまふ。善信が信心も他力なり。故にひとしくしてかはるところなし」
と論じている。
法然は、この評論を裁断していうに、自力の信の場合には、智慧各別なるゆえに信もまた各別であるが、
「他力の信心は、善悪の凡夫ともに仏のかたよりたまわる信心なれば、源空(法然)が信心も善信房の信心も、さらにかわるべからず、ただひとつなり」
と判定している。
右の信心評論は、親鸞の宗教的な生涯のなかで、決定的に明白な信心の在り方を表明している。それは、その後の親鸞の生涯を貫いて変わることなき信心の礎であったということができる。晩年の法然が一つの信心を裁断したように、晩年の親鸞もまた、すでに述べたように、一つの信心を強調して止まなかった。それは法然の教える、浄土に往生することを信じて念仏するという行の、もっとも確かな、ゆるぎのない結果となった証拠である。
このように、「仏のかたよりたまわる信心」(如来よりたまわる信心)は、三十代初年の親鸞にすでに結定(けつじょう)している。それこそ他力信心のことわりであり、まったくわたくしなき、仏のかたよりもよおされる信心である。(100~101頁)
■ 親鸞はみずから釈して、
「尓(しか)れば、真実の行信(ぎょうしん)を護るものは心に歓喜多きが故に、是れを歓喜地と名づく。……十方の郡生海(ぐんじょうかい)、斯(こ)の行信に帰命(きみょう)すれば、摂取して捨てざるが故に、阿弥陀仏と名づく。是れを他力と曰(い)う。是を以て、龍樹大師は即時入必定(そくじにゅうひつじょう)と曰い、曇鸞大師は入正定聚之数(にゅうしょうじょうじゅししゅ)と云えり。仰いで斯れを憑(たの)むべく、専(もっぱ)ら斯を行ずべきなり」
と述べている。(113頁)
■ 親鸞はこのような念仏の特徴を、「化身土巻」の自釈において、つぎのようにまとめている。
「善本とは如来の嘉名(かみょう)なり。此の嘉名は万善円備せり。一切善法の本なり。故に善本というなり。徳本とは如来の徳号なり。此の徳号は、一声称念するに、至徳成満し、衆禍(しゅか)みな転ず。十方三世の徳号之本なり。故に徳本というなり」
すなわち名号は、あらゆる善なるものを円備しながら、しかもあらゆる善なるものの根本である。したがって、名号を称念することによって、善の根本が成就すると同時に、あらゆる不善なるものが転換するのである。親鸞はさらに「十方三世の徳号之本なり」といっているが、これについては後に論ずるように、念仏は時間・空間の普遍的世界を濾過し浄化する根本にまで徹底するということができよう。(114頁)
■ 「仏と仏と斉(ひと)しく証して、形、二の別なし。縦使(たと)い一を念じて多を見るとも、何の大道理にかそむかんや」
これによると、一仏の称名によって阿弥陀仏や一切仏を見ることは、仏仏相証の世界であって、いかなる仏も、自証の世界に相はないということになる。つまり阿弥陀仏も諸仏もまったく同一の世界を証しているのである。
『末燈鈔』に、
「釈迦・弥陀・十方の諸仏、みなおなじ御こころにて、本願念仏の衆生には、かげのかたちにそへるがごとくしてはなれたまはずとあかせり」
という。
本願念仏の衆生には、釈迦も弥陀も十方の諸仏も、同じ心でつきしたがうという。いいかえれば、阿弥陀仏も十方諸仏も、念仏の衆生に対してまったく同じ心であるというのである。(122~123頁)
真理の体現者 道元
■ このように見てくると、当時の情勢は、権謀術数と権力闘争との間断なき明け暮れであるといわなければならない。旧い体制が崩れ、新しい体制が興ってくる時には、民族の凝集したエネルギーが傾けられるが、そのエネルギーの移り行きは、ことに封建的世界が形成されつつある時代においては、権力者の戦意を中核として行われている。そして権力者の力と力とが衝突し合い、闘争が繰り返されつつ、唯一の権力者へと統合されていく。しかしその権力者もまた、いつ相対化されて次代のそれに取って代られるか分からない。しかしこのような権力の精神的核心は、全く我執に外ならないといえよう。そこから権謀と闘争とが間断なく生れてくるのである。
道元が古今を貫く真理の追求のために、このような世相に背を向けたことはまことに当然であった。同じいのちをかけるにしても、権力者は、権力獲得、いいかえれば我執拡大のためであり、道元は、まさにその我執を切り捨てることによって、決して相対化されることのない絶対不変の道を踏まえるためである。そしてこの着眼の基本的な相違にもとづいて、武士階級に現われた主従のうるわしい人倫関係も、道元の眼には弊履(へいり)のごときものであった。道元は、みずから解脱を求めるためには、師への奉仕さえ投げ捨てることを容認したのである。世の一般の、義理・人情、恩愛の絆、師弟の道は、大道の前には泡沫にひとしい。道元は徹底的に世界超越への路線を歩み続けたのである。(148~149頁)
■ 十五歳のとき、かれは宗教の根本問題につき当たっている。つまりわれわれは本来仏性をそなえ、その本性は清浄であるのに、なにゆえ三世(さんぜ)の諸仏は発心(ほっしん)して悟りを求める必要があるかというのである。これは、仏道を歩もうとするものの最初に逢着する問題である。不生禅(ふしょうぜん)で有名な盤珪(ばんけい、1622-93)も、少年のころ『大学』のなかの「明徳を明らかにす」という語を見て、もともと明らかな徳をなぜ明らかにする必要があるかという疑問をいだき、ついに禅門に入っている。道元と同質の根本問題といえよう。
道元はこの疑問をもって三井寺の公胤(こういん)をたずねたところ、この問いはたやすく答えることはできない、建仁寺の栄西(ようさい、1141~1215)に参禅せよ、といわれて栄西の門をたたき、臨済の宗風に接した。栄西の答えは、三世の諸仏などはいない。ただ狸や狐がいるだけだ、というのである。栄西は観念と現実のくいちがいを道元の前にはっきり示した。ここに道元の参禅が始まる。しかし栄西は翌年なくなり、道元はその弟子明全(みょうぜん)に師事することになった。(149~150頁)
■ 道元が如浄(にょじょう)に会見した刹那に、如浄は、「仏仏祖祖面授の法門現成せり」といっている。目的の大半はこのときすでに成就したというべきであろう。案に相違せず道元は、その後数ヵ月にして「参学の大事を了畢(りょうひつ)する」(悟りが徹底すること)のである。
その模様がつぎのように伝えられている。
ひとりの禅僧が坐禅しながら眠っているのを、如浄が叱りつけて、「参禅は身心脱落なるべきである。ただ眠るだけで何ができるか」と声をあらげた。傍らで参禅していた道元は、如浄のことばに豁然(かつねん)と大悟したのである。かれはただちに方丈にいたって焼香礼拝した。「如浄何のための焼香か」。道元「身心脱落し来(きた)る」。如浄「身心脱落、脱落身心」。道元「これはしばらくの力量である。どうかみだりに印可を授けたもうな」。如浄「みだりに印可を授けるのではない」。道元「みだりに印可を授けない。その当体は」。如浄「脱落脱落」。このとき道元は礼拝したという。
道元が如浄を古仏として崇拝し、いかに如浄に傾倒していたかは、その後の道元の言行からもうかがえるのであるが、右の身心脱落の刹那が、かれの究極目的の貫徹を物語るものである。道元はそれまでに悟りに類したことはいくたびか経験したであろうし、無際了派は印可まで与えようとしたが、かれ自らは満足しなかった。このことは「みだりに印可を授けたもうな」という右のことばにも現われているのであるが、そのことから同時にかれの徹底した批判精神もうかがうことができる。(151~152頁)
■ 如浄のもとの留まること二年あまり、道元は嘉禄(かろく)三年(1227)の秋、帰国する。はじめ京都の建仁寺におり、三十一歳のとき宇治深草の安養院に移り、翌年「弁道話」の説法、三十四歳のとき、近くの極楽寺の旧址に移り、観音導利院と称する。翌年第二祖の懐奘(えじょう)が弟子入りし、その翌年、僧堂の建立を発願し、さらにその翌年竣工、観音導利院興聖(こうしょう)宝林寺と命名する。いわゆる興聖寺である。道元が興聖寺に在住するのは前後十一年にわたり、この間に『正法願蔵』の「摩訶般若波羅蜜」「現成公案」をはじめ、多くの諸巻や、『典座(ぞ)教訓』『学道用心集』が述べられている。道元の名はようやくひろまり、弟子の礼をとって参禅するもの多く、また興聖寺の作法はきわめて厳格であった。日本における純粋の善はこの時に始まるといってよい。(152頁)
■ 遺偈(いげ)としてつぎの句が残っている。
「五十四年、第一天を照らす、箇の〔足ヘンに孛〕跳(ぼっちょう)を打して大千を触破す。咦(い)、渾身著する処なく、活(い)きながら黄泉(こうせん)に陥いる(注)」
(注)「五十四年の生涯の間、絶対界を照らしつづけてきた。どこまでも超越し抜いていく般若(智慧)を打って一丸となして三千大千世界(果てしなく広大な世界)を踏み破ってきた。ウン、そうだ。全身どこにも執著(しゅうじゃく)する所がない、活きながらあの世におちいる」(154頁)
■ 解脱を達成するための不可欠の要件は、いうまでもなく発(ほつ)菩提心である。発菩提心とは、解脱し、目覚めようとする心をおこすことである。(155頁)
■ ところで道元の発心は、通常のそれと趣きを異にしている。通常には、菩提心とは無上正等覚心(この上もない目覚めの心)である、あるいは一念三千(天台の教理。一念のなかに地獄から仏までの無数のすがたをそなえること)の理解である、あるいは入仏界心(仏の世界に入る心)である、などと解されている。ところが道元は、それらは菩提心を知らないばかりでなく、むしろ菩提心を誹謗するものであるときめつける。
それはなぜであるか。道元の趣旨を推察してみると、およそつぎのように考えられよう。つまり、右に挙げた菩提心は、たんに菩提心の定義であり、説明であり、観念にすぎない。それは物の役には立たない。道元は、観念ではなく、具体的な事実の問題に着眼している。試みに、われわれの当面の心を反省してみよ。果たして一念三千の心や入仏界心になっているであろうか。決してそうではない。実際は愛欲・貪欲・名誉欲・利害関係などの妄想だけである。これがわれわれの現実の心である。発心は、このような現実の心に対応するものでなければならない。
右のような種々の欲望の根本は何であろうか。それは一語でいえば我執(がしゅう)であり、道元のいう呉我の心である。道元はしきりに、呉我を離れよ、我見を離れよと強調する。(156頁)
■ 迷いの側から見れば、吾我の心は、我あると執著するこころである。そうだとすれば、解脱を得るためには、この心を除かねばならない。それと同時に自己意識としての人格や知性の基盤(人間的分別の立場)をも離れなければならない。われわれが真に絶対自由の世界に解放されるためには、人間のあらゆる立場を抜本的に離脱せねばならないのである。
ここに道元の徹底的な世界超越の路線が敷かれている。かれは真っ向から世界全体を否定する。そしてそれこそが、かれのいわゆる発心である。道元のことばにしたがえば、無常を観ずることである。この世界には何ものも常住不変のものはない。自己そのものが無常である。(157頁)
■ では無常に徹し吾我を離れて、どうなるのであろうか。どうなるものでもない。吾我を離れたそのままが仏を受けとることである。無常に徹することが、仏道のはじまりであるとすれば、仏を受けとることは目標の達成であるといってよい。このように見ると、仏道の道程はきわめて簡単である。吾我を離れて仏を受けとることで万事終了であり、その他の複雑な理論は一切無用である。
こういってしまえば簡単であるが、実際は必ずしもそうはいかない。吾我を離れることは、自分自身を捨てることであり、身心を放下(ほうげ)することである。仏道は、身心を放下して、ひたすら仏の大海に入ることである。百尺の竿頭一歩を進めよ、という語があるが、一歩を進めたら落ちて死んでしまう。そこで竿頭に強く執著しようとする心が残る。その心を放ち捨てて一歩を進めよ、というのである。それが身心放下である。このように捨て身にならねば、いかに懸命に学道に励んでも、悟りを得ることは不可能である。だから思い切って放下してしまえという。(『随聞記』四ノ一)(158頁)
■ では実際にはどのような方法があるというのか。その方法はまたきわめて簡単である。道元は只管打坐(しかんたざ)という。ただひたすら坐禅して、自己の全体を打って一丸となすことである。その間に、吾我を離れ、身心を放下して仏の大海に入る。道はただ坐禅より外にはない。坐禅を通じてのみ解脱は得られる。それがすなわち只管打坐である。
われわれはただひたすら坐禅し抜いていかねばならない。座禅はただそれを行なうことによってのみ、会得される。それはたとえば善人と交わるごときものである。善人と交わっておれば、知らず識らずのうちに、われわれ自身もまた善人となる。坐禅も同様で、久しい間続けていくうちに、いつとはなしに身心脱落し、解脱を得ることができるという。(『随聞記』五ノ三)(159頁)
■ 「学道の人は吾我のために仏法を学する事なかれ。ただ仏法のために仏法を学すべきなり。その故実は、我が身心を一物ものこさず放下して、仏法の大海に廻向(えこう)すべきなり。その後は一切の是非を管ずる事なく我が心を存ずる事なく、成し難き事なりとも、仏法につかはれて強いて是れをなし、我が心になしたき事なりとも、仏法の道理になすべからざる事ならば放下すべきなり。……ただ一たび仏道に廻向しつる上は、二たび自己をかへりみず、仏法のおきてに任せて行じゆきて、私曲を存ずる事なかれ。先証皆是(かく)のごとし。心にねがひてもとむる事無ければ即ち大安楽なり」(『随聞記』六ノ二)
学道の目的は、ただ仏法のために仏法を学ぶことである。わが身心の一切を抛(なげう)って仏法の大海に進入いた後は、私心を存することなく、全生活はただ仏法のために使われるべきである。それが大安楽であるという。
以上の道元の言葉から、一切の心構えを振り捨てた只管打坐の態度が了解できよう。それは、この身この心のままで、ただひたすら坐禅することである。そうすることによってこの身この心のままで、ただひたすら坐禅することである。そうすることによってこの身この心がそのままで仏を受け入れ、仏法の大海に浮び出る。そして一度その大海に浮び出れば、後は仏法のおきてにしたがって生きるのみである。(160~161頁)
■ 道元においては、解脱を得るためのただ一つの道は、これまで述べたように、ひたすら坐禅することであるが、それと併せて、正しい師につくことが必須の条件であると強調している。正しい師ということを道元はつぎのように定義している。それは、年齢の多少を問わず、正しい仏法を究明してその証拠を得ているものであるという。この定義はいかにも簡潔であるが、道元の批判は非常にきびしい、かれ自身が正師をたずねて中国にわたり、やっと如浄(にょじょう)に遭遇したほどであり、またわが国ではこれまで大師といわれている人々は出ているが、正師は一人もいないと名言している。その理由は、著作を見れば分かるのであり、ただ文字を伝えているだけで、悟道に達している面影は見られないというのである。
正師との出会いは、道元にとっては決定的な運命を意味するものであった。それは、正師によって正しい方を伝えるとともに、正師はそのまま仏祖であり、仏から仏へのつながりを表示するものである。だから道元が正師について正法を伝えたということは、その正法はただちに釈尊にさかのぼり、さらに過去七仏にまで遡源(そげん)する。過去七仏というのは、釈尊以前の諸仏であって、いわゆる歴史上の人物ではない。しかし七仏のつながりという歴史性は有している。それは、いわゆる歴史上の人物ではない。それは、いわば形而下の歴史に対する形而上の歴史ともいうべきものである。こうしてみると、道元の体得した正法は、永遠の仏から永遠の仏への伝法であったということができる。しかもかれにとって、それは観念上の事柄ではなく、もっとも実感的に仏の法を受けついでいる。過去七仏から釈尊へ、さらに次から次へと伝わって道元にいたっている。いわば歴史性と永遠性とが、道元が身をもって確かめた悟りのなかに一体になっているといえよう。(161~162頁)
■ では、仏から仏へと伝わる法とはいかなるものであろうか、それはいうまでもなく究極のさとりではあるが、そのさとりはどのように経験されるのであろうか。その悟りが事実上経験されて、仏祖正伝の道がわれわれの上に伝わらなくては、意味がないのである。
道元はそれを、単座参禅を入口とする所の自受用三昧(じじゅようざんまい)と名づけている。端座は正しく坐ることであり、参禅は禅の世界に参入することである。そして端座参禅には、前に述べたように、正師につくという条件が附されている。しかし要領としては、ただひたすら坐るという只管打坐が基本である。ただひたすら坐ることによって自受用三昧が得られるのである。
自受用三昧とは、「弁道話」に、
「ほとけ仏にさづけてよこしまなることなきは、すなはち自受用三昧、その標準なり」
といわれている。
この三昧は、永遠の仏から仏へと正伝してきた所の、いわば宇宙仏の三昧である。只管打坐は、この宇宙仏の三昧に与ることである。すべての作為を離れた只管打坐でなければ、自受用三昧に与ることはできない。逆にいえば只管打坐は、永遠の仏の顕わになっている三昧である。この点に、ブッダ以来の仏道の原型を道元のなかに明瞭に読みとることができるのであろう。(162~163頁)
■ ただ端座参禅することによって、三昧が感得されてくるのである。だから端座参禅の目的は、ここに明瞭となる。それは、一つには、この三昧によって限りなく自己を超えていくことであり、二つには、この三昧はあまねく人々・事物の上にそなわっているから、三昧のなかにありとあらゆるものを具現していくことである。
この二つの目標は、仏祖正伝の道における車の両輪のごときものであろう。一方では、どこまでも自己を超脱し、世界を超脱していく。同時に他方では、その超脱し切っていく三昧のなかにかえって森羅万象が実現する。むしろ超脱すればこそ、万象が顕にわになる、あたかも鏡が透明であり、無心であればあるほど、万象をうつして止まないがごとくである。このように見ると、この二つは、車の両輪のごとくでありながら実は一つである。その一つの所が自受用三昧といい、その三昧のなかに万法が具現しているのである。(164頁)
■ この自受用三昧は、道元によって種々の別名で呼ばれている。すなわち、三昧王三昧、自証三昧、海印三昧などである。
三昧王三昧は、三昧のなかの王三昧といういみである。三昧には多くの三昧がある。たとえば、空三昧・無相三昧・無願三昧の3三昧があり、また、大乗仏典には、般舟(はんじゅ)三昧・首楞厳(しゅりょうごん)三昧・慧印(えいん)三昧・法華三昧・如幻(にょげん)三昧・観仏三昧・月燈(がっとう)三昧・獅子奮迅三昧など、無数にある。また、三昧は身心がそれになり切っていることであるから、世俗においても、たとえば、読書三昧・勉強三昧・釣三昧(岡野注;描画三昧)など、多くの三昧が数えられよう。
しかし道元のいう三昧のなかの王三昧は、ただ結跏趺坐の三昧をいうのである。結跏趺坐とは、両足を組み、印を結ぶ坐禅の姿であり、端坐参禅である。正しい姿勢、正しい手足の結印や組み方によって、ただ坐るだけである。ではこのような簡単な坐禅が、なぜ王三昧になるのであろうか。それは一つには、この三昧こそ、過去七仏以来、諸仏諸祖が伝えてきた方法であり、また二つには、この三昧のなかに、すべての三昧が収められて、天地・万物と我と一体なる世界が開示されるからである。(164~165頁)
■ 道元によれば、このような結跏趺坐の三昧に徹底している禅者は滅多になく、
「仏祖の眼睛裏(がんせいり)に打坐すること、四五百年よりこのかたは、ただ先師(如浄)ひとりなり」(『正法眼蔵』「三昧王三昧」)
といっている。
仏祖の眼のたまのなかで坐禅しているもの、つまり仏祖正伝の坐禅に徹しているものは、四五百年来、如浄禅師ひとりだけであるという。では坐禅に徹しているというのはどういう意味か。仏法はすなわち打坐であり、打坐はすなわち仏法であると体得していること、さらに進んで、打坐を打坐と知り、仏法を仏法と知ることであるという。打坐を仏法であると知ることとりも、打坐を打坐と知ることの方が一そう徹底しているというのである。打坐を打坐と知ることは、打坐を仏法と置きかえなくても、打坐だけで十分充ち足りているのであり、打坐の外にも何物も望む要のないことを指している。このような結跏趺坐こそ、仏祖の命脈であり、三昧王三昧である。(166頁)
■ したがって結跏趺坐は、自証三昧ともいわれるのである。過去七仏から仏仏祖祖正伝し、ついに我において証明される所の三昧である。何が証明されるかといえば、十方世界を尽くして、山川草木がことごとく仏法であり、さらに、食事や衣服を整える日常の作法から、一挙手・一投足にいたる刹那刹那の挙動まで、すべてこれ仏法であることを親しくうなずくことに外ならない。
このうなずくということは、心をもってうなずき、身をもってうなずき、あるいはまた全身心をなげうって仏法をうけ入れることである。それが仏祖の眼の玉であるというのである。このような眼の玉は、過去七仏から釈尊を経て、次第に受け継いで道元にいたっているという、もっともリアルな、しかも一種歴史的な、あるいはむしろ形而上ー歴史的な伝法である。いわばそれは、時間的に縦に貫いた伝法のリアリティであるとともに、前に述べた十方世界、挙手投足がことごとく仏法であるという空間のリアリティが二重の意味を担っている。すなわち、仏仏祖祖正伝し来たった伝法が道元にとってリアルであればこそ、実はそれが、いつでも、どこでも、しかも何物によっても伝法し得る、いなむしろそのままが伝法であるという、時間的・空間的に普遍的な〔うなずき〕のリアリティが実現しているのである。(166~167頁)
■ 海印三昧というのは、もともと『華厳経』に述べられ、さらに中国の華厳宗で強調されてきたものである。(167頁)
■ 通常、思索し認識するという過程は、認識の主体と認識の対象との相対関係によって成り立っている。(168頁)
■ 道元は通常の意味の認識関係をどこまでもしりぞけて、主体と対象との相関性を超えた、あるいはそれを離れた世界、いいかえれば現在即今に開示されている世界――道元のいう恁麼(いんも)――を究明して止まない。したがって究明している道元の主体そのものは、即今に開示されている世界のなかに解消し、あるいはそれに埋没し、いいかえれば主体は世界そのものとなって、その世界を究明するのである。ここに道元の独特の思索が展開する。(168頁)
■ 道元はこのことを、
「海上行(こう)の功徳、その徹底行あり、これを深深海底行なりと海上行するなり」(『正法眼蔵』「海印三昧」)
といっている。
これは異様な表現であるが、その意味はつぎのごとくなるであろう。すなわち、海面を泳ぎながら、しかもその足は海底に徹しているのである。あるいは、深々と海底を行くままで海面を泳いでいるのである。普通に大海を遊泳しているといえば、魚や浮草を思い浮べるであろう。しかし魚や浮草の譬(たと)えには三昧の実態とは根本的に違っている所がある。魚は海中を泳いでいるだけであり、浮草は海面に浮遊しているだけである。しかるに海印三昧における万物は、海面を泳ぎながら、足が底についているという、つまりこの世に活動しながら悟りに徹底しているのである。これはたしかに自覚の世界であるが、しかし自覚によって始めてそうなっているのではない。意識しようとしまいと、それは自覚以前の海印三昧の実情である。このことは、きわめて重要な視点であり、そしてこの点にこそ、道元にまで正伝し来たった仏祖のいのち、永遠の仏の世界がかかっている。それは要するに、意識を離れて、いかなる一物も、何物にも疎外されることなく、徹底的に、あるいは底抜けて自由に活動している三昧の事情を表わしているのであろう。(169~170頁)
■ では、この場合における〈此の身〉とは何を指すのであろうか。それはもとより自我ではない。そうではなく、それこそまさに法なのである。法とは、たんなる〈もの〉ではなく、また〈心〉でもない。それは、海印三昧、すなはち宇宙そのものの仏の世界に〈あり〉、かつその世界から見られている〈もの〉である。だから、心的なものであれ、物的なものであれ、また事象であれ、ことごとく海印三昧にあり、何一つ法でないものはない。そのような無数の法が集中して〈此の身〉が成立しており、そしてそれもまた法である。
道元は『維摩経』の文を引きながらつぎのように述べている。
「但(ただ)、衆法(しゅぼう)をもって此の身を合成(ごうじょう)す。起る時は唯(ただ)法の起るなり。滅する時は唯法の滅するなり。此の法の起る時は、我起ると言はず。此の法の滅する時、我滅すと言はず。前念後念、念念相対せず。前法後法、法法相対せず。是(これ)を即ち名づけて海印三昧となす」(「海印三昧」)
此の身は多くの法によって合成されており、此の身が起るのは法の起るのであり、此の身が滅するのは法の滅するのである。それを自我が起ったり滅したりとはいわない、という。つまり自我という別人がいて、法の起滅を見聞しているのではない。そうではなく、無数の法によって合成されている〈此の身〉が起滅しているだけである。それは自我ではなく、無数の法の集中している〈全体の法〉が起滅している。起っている時は起っているだけ、滅する時は滅するだけである。たとえば春になった〈時〉は、春の全体が〈起って〉おり、夏になった〈時〉は、夏の全体が〈起って〉おり、そしてただ〈起っている〉のみである。
道元はこれを、
「起はかならず時節到来なり、〈時は起〉なるがゆゑに。いかならんかこれ起なる、〈起也〉なるべし」(「海印三昧」)
という。
したがって、起っている時はただ起っているだけであるから、何一つ隠されているものはない。「皮肉骨髄を独露さしめずといふことなし」という。皮も肉も骨も髄も、そして臓物(ぞうもつ)までもさらけ出している。一物も隠すことのない全露のすがたである。そして滅する時も同じように、このような全露の法が滅するのである。
ところで、この滅ということについて、仏教者は特別の感懐(かんかい)を伴うているのである。滅はすなわち、苦・集・滅・道の四諦のなかの滅諦であり、あらゆる煩悩の消滅を意味している。ここに、全露の法が滅するという時、それは、〈此の身〉にかかわっている全問題あるいは全煩悩が瞬時に滅することであり、道元はそれこそ無上大涅槃であるという。それは海印三昧における滅の功徳であるというのである。
このようにして、〈此の身〉すなわち全体の法は、瞬時の間断もなく停まる所をしらない。起っている時は起っているだけで絶対であり、滅する時は滅するだけで絶対である。起滅はただそれのみであるから、相対・対峙の関係を離れ切っている。この起滅停まることなき全露の、〈此の身〉の法こそ、仏祖の命脈であり、海印三昧である。(171~172頁)
■ これまで論じてきたような王三昧、あるいは海印三昧の世界を、自覚の核心から見ればどうなるのであろうか。そこには底抜けの希望と明るさと、永遠の解脱が息づいている。微塵(みじん)の暗さもペシミズムもない。道元は、それを、明珠とも光明とも、あるいは仏性とも表現している。
『正法眼蔵』には「一顆明珠」という巻がある。このなかに、「尽十方世界、是れ一顆の明珠」という一文がある。全宇宙が一つの明るい珠(たま)である、という。宇宙が一つの珠であるというのは、いったい何を意味しているのであろう。宇宙といえば、数かぎりのない日月星辰を思い浮べるであろうが、ここでは、外に見られた日月星辰を指すのではない。前の海印三昧においても触れたように、主体の自覚からみているのである。主体における執著(しゅうじゃく)の絆が断たれて、内から外に向かって門戸が開かれたときに、主体は宇宙と吹き通しになる。主体は宇宙と本質的に一体となるのである。その際の主体の自覚は、もはや自我意識にかこまれた個別的なものではない。〈此の身〉に生じている点ではまさに己の自覚であるが、自我意識の柵がはずされて宇宙意識となっている点では普遍的である。いわば、自己と普遍、主体と宇宙とが一つらなりとなっているといえよう。そのような自覚の世界が一個の明珠というのである。
このように見てくると、この珠は、現在一刹那の自覚に成立していると同時に、無限の過去にも遡(さかのぼ)り、尽未来際にもつながる。刹那的であると同時に永遠である。あるいはむしろ刹那のなかに永遠が展開していると見ることができよう。そしてこの珠こそ、仏祖の眼の玉(眼睛がんぜい)であり、それはただ仏から仏へと伝わるものである。(172~173頁)
■ 同じようなことではあるが、明珠や光明を、道元は仏性とも呼んでいる。『涅槃経』には、「一切衆生は悉(ことごと)く仏性を有す。如来は常住にして変易あることなし」という有名な言葉があるが、道元は『正法眼蔵』の「仏性」の最初にこれを提示している。
しかし仏性といえば、普通には、煩悩の身のなかに隠されている仏の本性というように解されやすい。ぶってんでは、仏性を如来蔵ともいうのであるが、たとえば『如来蔵経』では、右のような理解の仕方を示している。後の『宝性論』になってくると、このような実体的・対象的な解釈が消えて、作用的なものという見方が強くなってくる。道元は、仏性に関する実体性・対象性の見解を徹底的に排除し、そのような見解は外道(仏教以外の立場)であるとまで極言する。そして仏性の現実態を究明して止まないのである。したがって、道元の仏性論には、きわめてユニークな思索の跡をたどることができよう。(175頁)
■ そうだとすれば、全存在そのものは、一物も隠すことなく、〈むき出しのまま〉(徧界不會蔵へんかいかってかくさず)というほかない。そしてこの〈むき出し〉の存在そのものには、もはや主客の対立は解消してしまっている。つまり、存在そのものとの相関性は消失している。見ているものも見られているものもなくて、全存在が同一の〈むき出し〉である。だから強いていえば、この〈むき出し〉の存在は、存在がそのまま自覚であり、自覚がそのまま存在であるという、存在と自覚の二重性が、同一的に拡充し尽くされている。
このような性格を道元の表現に即していうと、存在そのものの〈むき出し〉は、永遠の過去から現在刹那に貫通しており(亙古亙今こうここうこん)、これに一物も加える余地がなく(不受一塵)、かつその全体が完結しており(合取)、そして真理の当体であり(是什麼物恁麼来ぜいんもぶついんもらい)、しかも日常生活そのままの心(平常心是道びょうじょうしんぜどう)である。したがって、あらゆる存在はそのまま、透明であり解脱している(透体脱落)、というのである。(176頁)
(岡野注;世界存在はこのようになっているのであり、画家はその世界を〈描写〉するだけである。私はイーゼル画(対象の直接描画)でそれを理解したのです。2021-12-5)
■ 道元はふたたび『涅槃経』の文を引き、
「仏性の義を知らんと欲せば、当(まさ)に時節の因縁を観ずべし。時節もし至れば、仏性現前す」
という。
ここで〈知る〉というのは、もとより認知だけでなく、行ずることも証することも含まれている。さらにいえば、忘れることさえも含まれているという。仏性の義を知ることは、すなわち忘れることであるというのである。われわれはここで、『正法眼蔵』の「現成公案」に述べられている有名な一文、
「仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわすれるるなり。自己をわするるといふは、万法に証せるるなり」
に思い到るであろう。
仏道をならうというのは自己をならうことであるが、それは自己を忘れるほかない。同じように仏性を知るためには、仏性を忘れるほかはない。仏性に関する分別・知見・智慧などがすべて除かれねばならない。仏性を忘れるとは、仏性の観念が消えることである。それが仏性そのもの(仏性聻ぶっしょうにい)であり、仏そのもの(仏仏聻)であり、性そのもの(性性聻)であるという。また、「時節もし至れば」というのを、「やがて時節が来た場合に」と解するのは外道の見解であるという。そうではなく、すでに時節は至っている、したがって仏性は現前しているのである。(177~178頁)
■ 以上述べてきた所から見ると、仏の世界は三昧であり、光明であり、そしてそれがそのまま現実のありとあらゆるものとなっており、自己の世界にまでいたっているということができる。そうしてみると、仏の世界は、われわれが見聞している自然ともなって現れている。むしろ自然そのものがすなわち仏の世界なのである。(178頁)
■ ところが道元のいう自然は、そうした見られている物ではない。道元の場合の自然は、〈物〉に力点が置かれているのではなく、字義通りに、〈おのずからそうなっている〉という所に視点が向けられている。同様に人間もまた、もともと〈おのずからそうなっている〉自然である、しかるに事実は、執心(しゅうしん)に障(さ)えられて本来の自然からつねにはみ出ている。その点に、われわれが自然を素直に、ありのままに見聞するという訓練(行)が要求されるのである。
(岡野注;画家の行はイーゼル画(対象の直接描画)である。既製品のソフトや、自我の欲望のオファーを解脱して、目を独立させ、裸眼で対象を見ると、ランダムドットステレオグラムのランダムなドットの中から、縦・横・奥行き・時間の構造が浮かび上がってくる。しかしそれを描写、顕現させるには、本(もと)に戻ってイーゼル画でスキルを磨くしかない。つまり修証一等(これも道元)なのですね。2021-12-8)
この訓練が熟して、要求が充されると、自然とわれわれとの間に、何物の介在物もなくなり、自然と人間とは同質化する。つまりわれわれもまた自然であり、自然もまたわれわれである。いいかえれば、宇宙は自然もわれわれも包んで一体であり、そのまま仏である。したがって自然を見聞せることは、すなわち仏を見聞していることとなるのである。(178~179頁)
(岡野注;スキルを磨いた画家のイーゼル画と同じでしょう。2021-12-9)
■ 生活がそのまま仏道であるということは、大乗仏教の原則であるが、道元は、とくにこの点に視聴を集めて強調している。かれが仏道の根本的解決をたずねて中国にわたり、ついに如浄の下で、身心脱落の体験を得て、究極の目的を達成し得た。しかしそれが神秘的な霊感にとどまるのか、またそれ以上の意味を持つのかということは、その体験以後のかれの思索と行動と生活とがこれを物語るのである。
けれども道元は、生活即仏道ということを軽快な心境でいっているのではない。とかく禅者ののなかには、さらりとした気持ちでこのことを受けとめ、軽快な行動がいかにも悟りの生活的な表現のように心得ている人があるが、およそ道元の場合は、それとは対照的なのである。かれが生活即仏道を唱える根底には、仏祖正伝の道の、大山にまさる重さがのしかかっており、したがってその重さの実感からにじみ出てくるきびしさによって、生活のひだひだを埋めつくしていこうとする気魄(きはく)がみなぎっている。
生活即仏道を、かれは行持というのであるが、それは、行を続けることによって生活のなかに仏道の真実を保持していくことを指していると思われる。したがって行持は、生活者における仏道の持続的な展開であり、行持によって仏道は、初めて生活のなかに具現していくということができる。
道元は、
「諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成(けんじょう)し、われらが大道通達するなり。われらが行持によりて、諸仏の行持見成(けんじょう)し、諸仏の大道通達するなり」(『正法眼蔵』「行持」)
と述べている。
われわれの行持が実現するのは仏祖の行持によるのであり、仏祖の行持が実現するのはわれわれの行持による、という。仏祖とわれわれとは、行持によってつながっており、行持によって、仏祖正伝の大道が顕(あら)わになるのである。とすれば、行持はまさに仏祖のいのちであるということができよう。
しかもかれは、
「無上の行持あり。道環して断絶せず、発心・修行・菩薩・涅槃、しばらくの間隙(けんぎゃく)あらず、行持道環なり」(「行持」)
と述べている。
行持は、どこで断絶するということはない。切れ目なく続いている。それはまさに生活が間断なく持続しているのと同様である。たとえば、菩提心をおこし、それにもとづいて修行し、ついには悟りを開き、涅槃に達し、そしてまた、菩提心・修行へと端(はし)なく連続している。したがって涅槃に達することが終局の到達点ではない。そこからまた、菩提心をおこし、修行へと続くのである。こうしてみると、われわれの生活は、いわば行持という太い軸がドーナツ型に円環的に結ばれており、われわれは綿密細心にこの軸を、仏祖の大道によって充たし続けていくべきである。ここでは、行持の円環的であることは、時の流れがまたそうであることを意味している。光陰むなしく過してはならない。時の一瞬一瞬が、仏のいのちであり、仏祖の大道である。その一瞬一瞬が綿密な行持によって充たされていかねばならない。
道元は、『正法眼蔵』の「洗面」という巻のなかで、ことこまかにそのやり方を述べている。洗面は面(かお)を洗うことであるが、もとより面だけではない。手を洗い、足を洗い、目を洗い、口を洗い、頭を洗い、体を洗い、心を洗い、生活を洗うことである。われわれの体も心も法界につながっており、その量は測り知れない無尽の意味をたたえている。そうだとすると、洗面は、この法界を洗うことであり、仏祖の大道を洗うこととなる。
道元は、たとえば楊枝を使う場合につぎのようにいう。
「歯のうえ、歯のうらをみがくように、とぎあらい、それを再三くりかえし、また、歯の根下の肉の上もよくみがき、歯の間をかきそろえて、よく洗え。たびたびうがいをして、すすぎきよめよ。また、面を洗う場合には、両手に桶の湯をすくい、額から眉毛、目、鼻のあな、耳のなか、耳のうら、頬など、あまねく洗え、その際よくよく湯をすくいかけて、摩擦するようにきよめよ、鼻しるや痰を桶のなかにおとしてはならぬ。むやみに湯をつかって、桶の外にもらし、早く湯を失ってはならぬ。あかおち、あぶらのぞかれるまで丁寧に洗え」
これが古仏の正法であり、仏祖の大道であるというのである。このようにして道元では、生活即仏道がすきまなく充たされているといえよう。(182~184頁)
■「生死」の巻には、
「この生死は、すなはち仏の御いのちなり、これをいとひ捨てんとすれば、すなはち仏の御いのちをうしなはんとするなり。……いとふことなく、したふことなき、このときはじめて、仏のこころにいる。……ただわが身をも心をも、はなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆくとき、ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ仏となる」
という。
ここには、道元が生死をどのようにとらえ、どのようにそれを解脱しようとしたかが説かれている。生死は、生まれかわり死にかわりという輪廻を指しているが、もっと直接的に主体に引き入れて見れば、われわれの現実の生のことである。しかも、自分の生でありながら、根本的にこれを打開するすべもなく、ただあてもなくさまよう外はない生の根源状態である。それは、主体の自己把捉としては迷いであり、したがってこれを破って解脱へ向おうと決意する発菩提心が、求道(ぐどう)の第一要件として要請される。
ところが道元はここで、生死を捨てる、破る、という否定的態度を拒否している。それはかえって仏のいのちを失うことだという。なぜかといえば、捨てるべき生死こそ実は仏のいのちだからである。では、どうして生死が仏の命といえるのであろうか。道元はこれについては何も触れていない。しかしその意味をよくよく考えてみると、捨てるべき、いとうべき現実の生の根源態の外に、どこにわれわれ自身の生があるか、いとうべき現実の生こそ、まさにわれわれ自身ではないか。生死をはなれて仏になるのは、まさにこの生死そのものである。この生死そのものにこそ、道元は仏を仰いだのである。
しかし生死が、そのままで仏のいのちではない。もしそうだとすれば、初めから問題はなく、発菩提心の要もない。そうかといって、仏は生死の別にあるのではない。道元は、生死とは全く次元の異なった仏を、生死の只中に仰いだのである。わが身も心もはなち忘れて投げ入れる仏は、実は生死と一体になっている仏である。だからこそ、生死をいとうことなく、したうことなく、ただ仏の家に投げ入れて、それにしたがっていくとき、はじめていとうべき生死をはなれて仏となるのである。この意味において「生死」の巻は、道元の宗教性の結びともいうべきものであると考えられる。(188~190頁)
■ 鎌倉時代には、周知のように、法然・親鸞・一遍・道元・日蓮などのすぐれた仏教者が輩出しており、この時代の仏教の精華であるといわれている。これはどのような意味であるかということを考えてみたいと思う。この問題を考察するについては、少なくとも二つの視点が挙げられよう。一つは、鎌倉時代に至るまでの社会的・歴史的な背景の変遷であり、もう一つは、日本仏教思想史上における鎌倉仏教の意味である。この二つの視点は、内容的には互いにつながりを持っている。
第一の視点は、一語でいえば、摂関政治から武家社会への移り変りであるといえよう。それは大局的に見れば、古代世界から中世的世界への転換であるということができる。古代国家は、四、五世紀ごろに出立し、七世紀になって律令体制として成立し、それが、十二、三世紀の動乱を通じて崩壊し、そして武士の支配による国家体制が形成されていくのである。
このような中世的世界への転換を、他の時代の転換と比べてみたらいかがであろうか。たとえば、古代国家の形成の場合は、隋唐や朝鮮三国(高句麗・新羅・百済)の制度的・文化的な影響を受けながら遂行されていった。また、明治維新を通じて幕藩体制から近代国家への変遷も、欧米の武力や文化に刺戟された傾向が著しい。さらに外に眼を転ずれば、古代ローマ帝国の崩壊もゲルマン民族の侵入によるし、中国や朝鮮における諸おうちょうの交替も、北方異民族の攻勢と無関係ではない。これに対して、平安から鎌倉への転換は、ほとんど外国との交渉関係はなく、全く日本内部の民族の力によっておこなわれたのである。これはきわめて特徴的であり、他に類例を見ることができない。このような民族の自主的な力の転換は、民族の思想の上にも、したがって日本仏教思想の流れにも現れずにおかないであろう。
第二の視点は、まさにその鎌倉仏教の日本仏教思想史における意味である。わたしはこれについて、いくつかの特徴を考えてみたいのであるが、この視点を念願におきながら、同時に道元の思想に焦点を合わせてみよう。(190~191頁)
■ たとえばつぎの一文を引いてみよう。
「尽十方といふは、遂物為己、遂己為物の未休なり。情生智隔を隔と道取する。これ回頭換面なり、展事投機なり、遂己為物のゆゑに未休なる尽十方なり。機先の道理なるゆゑに、機要の管得にあまねることあり」
これは『眼蔵』の「一顆明珠」の中の一文である。つまり、全世界は一つの透明な〈たま〉であるというのが、その全世界についての説明である。道元は、世をたんなる空間と見て、それを一つの〈たま〉といっているのではない。そうではなく、どこまでも自己の活動の持続として全世界をとらえ、しかもそのなかに超越的なものを体認しようとしている。右の文に即していうと、全世界というのは、間断なくつづく遂物為己・遂己為物であるという。つまり、物を追求しても結局は己(おのれ)以外のものではなく、逆に、己を追求してもそれは物に外ならぬ、物と己とが対立的にあるのではなく、たがいに全面的であるというのである。
しかもこのような実態の体認をさまたげているものは、分別の情感である。いわば認識の対象性ともいうべきものであろう。その分別が生ずると、真実の智慧が〈隔たる〉のである。(195~196頁)
■ 道元の思索は、いかなる場合にも平板ではない。平板は分別の対象性を意味するにすぎない。だからかれは、たとい仏教の伝統的な原理であっても、それが平板なる場合には敢然とそれに立ち向かうのである。(196頁)
■ 道元の『正法眼蔵』は決して体系的ではない。それぞれの任意の主題について書きつらねたものに過ぎない。また理論という点から見ると、それは倶舎・法相(ほっそう)のようなものではない。倶舎や法相では、主題を追って一節からつぎの節へと、客観的にまちまって理論が展開する。したがって理性によってわれわれは、その理論を追求していくことができる。その意味では思惟の対象性をふくんでいるといえよう。しかるに道元の場合はそうではない。一節から、その節を掘り下げつつあるいは否認しつつ、つぎの節へ移る。それは理性的思惟によって理解することはとうてい不可能である。思惟するもの自身が同時に思惟の対象であるという、いわば主体的思惟の自己展開であるといわねばならない。この思惟は、道元のきわめて得意とする所であり、道元的思惟の特徴が全巻にみなぎっている。このような思惟の主体性が、現代人の心を打つことは否(いな)み得ないであろう。
第二に、したがってその思惟は実存的であるといえよう。ヤスパースは、西洋の過去の哲学史に実存の照明を当てると、そこに実存が浮び上ってくるという趣旨を述べているが、道元の場合にこの照明は、道元独特の世界を浮び上らせるのである。
たとえば、『正法眼蔵』「有時(うじ)」では、存在(有)と時間(時)の関係が論ぜられている。道元によれば、存在はそのまま時間であり、時間はそのまま存在であるという。ハイデガーの場合には、その名著『存在と時間』のなかで、この主題について長広舌の論陣を張っているのであるが、道元はいとも淡泊に右のようにいうのである。ハイデガーも道元も、思索が主体的であるという点では類似しているが、前者は、ニーチェ、キルケゴールを継いで従来の哲学の道を踏み破るような非哲学性を有しているとはいえ、やはり西欧の土壌に培われた論理の上にたっている。その主体性の表明は依然として論理的である。それに比べると後者は、まさに直覚的であるといえよう。論理は、表に現れずに直覚の中に包まれて、直覚から直覚へと飛躍する。そのギャップは、道元を学ぼうとするもの自身が埋めなければならないのである。この埋める行為は、前にも触れたようにもはや理論的理性では十分でない。あたかもニーチェやキルケゴールが従来の理性的立場に反旗をひるがえして、みずからの哲学的道路を開鑿(かいさく)した例にも比せられよう。(202~203頁)
■ 第三に、近世から現代にかけて実証性という態度・方法・結果が強調されている。それは、自然科学から社会科学・人文科学にわたっている。さまざまの領域はちがっていても、一語でいえば、その性格は科学的・対象的であるといえよう。
これに対して道元の実証性とは何であろうか。前に述べたように、道元の特徴は、たんに理性的・実存的な思惟ではなく。身体的・全人格的な思惟(行)である。それは思惟という抽象的な作用に終るのではなく、そのような思惟を通じて、あるいはそのような思惟作用のままが、身体的・全人格的に〈見る〉・〈うなずく〉・〈実証する〉という働きを伴うている。これが道元の実証性であり、現代のそれが科学的・対象的であるのに対して、自覚的・主体的であるといえよう。
道元がこのような実証性に到達するまでには、修行の紆余曲折があったことはいうまでもない。その果てに生じた、如浄のもとにおける身心脱落の自覚は、実証性の確かな証拠であり、道元の生涯における最高度の実証体験である。しかしその後の道元の生活では、実証性の確度が薄れたのではなく、むしろその体験を転機として、実証性の意味が新しい段階に展開していく。それが「弁道話」に示される修証一等の見解である。
「仏法には、修証これ一等なり。いまも証上の修なるゆゑに、初心の弁道すなはち本証の全体なり。かるがゆゑに、修行の用心をさづくるにも、修のほかに証をまつおもひなかれとをしふ。直指(じきし)の本証なるがゆゑなるべし。すでに修の証なれば、証にきはなく、証の修なれば、修にはじめなし」
修証一等というのは、修行と悟りとが同一であり、修行がすなわち悟りであるということを指している。悟りは、ここでは最高度の実証体験である。常識では、修行の後に悟りがあると解されやすいが、道元は明白にこれを否定する。そうではなく、悟りの上の修行であるから、最初の弁道がそのまま本来の悟りの全体である。したがって修行の後に悟りを期待する心はしりぞけられねばならぬ。修行のままが悟りであるから、悟りに終着点はなく、悟りのままが修行であるから、修行に出発点はないという。
修行は、道元において結局は生活そのものである。とすれば、生活がいわゆる本証の全体であり、直ちに実証そのものである。道元の実証性はここに窮まるといってよい。(204~205頁)
(岡野注;世界存在の個別の形態はフラクタルで、全体はマンデルブロー集合で、現実の実体はテンセグリティー構造で存在している。道元の『正法眼蔵』の「現成公案」も「修証一等」もこの存在の幾何学的な形態をイメージすれば理解しやすい。もちろん、この世界観は、私の描写絵画の画面にも反映される)
■ 道元が表明しようとしている仏は、そのような神ではない。それは、わが背後に、わが頭上に想定される神ではなく、脚下に照顧して、わが坐上に実現する仏である。ここにも主体性と実証性とが折り重なって、仏の世界が道元のそれとして顕わになっている。仏の世界は、すでに論じたように、大自然として、またわれわれの生活そのものとして感知されている。
(岡野注;この宇宙は、神も仏も、イデア界も、我も、物も、全ての存在が、全体としてマンデルブロー集合の形態で存在している。そうだとしたら、この宇宙も高次の次元から見ればたった一つではないであろう。その時空全体を通貫している軌持(レール)が法(ダルマ)である)
仏教の無
■ また、‘無’常、‘無’我というばあいには、aという接頭語が附けられて否定の意味を表わしている。すなわち、無常は常住の否定、無我は自我の否定として示されている。
部派仏教(小乗)になると、説一切有部と称される学派が現れている。普通には有部といっている。ありとあらゆるものの実在を主張する学派である。したがってここでもまた、無は否定されている。
その有名な典籍の『大毘婆沙論(だいびばしゃろん)』のなかで、三世(過・現・未)実有論に関して、
「もし過去・未来、実有に非ざれば、現在もまた、これ無なるべし。過去・未来を観じて現在を施設するがゆえに。もし三世なくんば、すなわち有為なからん。もし有為なくんば、また無為なからん。……もし有為・無為なくんば、まさに一切法なかるべし。もし一切法なくんば、まさに解脱・涅槃なかるべし。これすなわち大邪見なり」(「大正」27.393中)
という。
ここに挙げている無の思想も徹底的な虚無論であり、有部は真っ向からこれを否定している。(212頁)
■ このような無と関連して考えられるべきものは空である。無と空はきわめて類似しておりながら、無は否定性を示しておるのに対して、空はむしろ空という一つの主張を表わしている。
空の思想は、すでに原始経典のなかに、しかも最古層と考えられている『スッタニバータ』のなかに現れている。
「モッガラージャよ、つねに念じて、自我の見解を打ち破って、世間は空なりと観ぜよ。そうすれば死を越えることができよう。このように世間を観ずるものを死王は見ることがない」(1119)
ここでは、世間は空なりということは、一つの基本的な世界観であり、積極的な主張である。無がたんに否定性を表わすものとは異なっている。そして空の世界観は、自我の見解を打ち破ることによって開かれてくるのである。
その外、原始経典においてはさまざまな形で空が示されている。一、二の例を挙げよう。たとえば、『マッジマ・ニカーヤ』(MN.vol.1.p.485)のなかには、一切の存在を無常・苦・無我などと並んで空として観ずれば、一切の存在から心は解放される、と説かれている。
また同じく『マッジマ・ニカーヤ』のなかで釈尊は、
「わたしは、以前も今も、空性に安らうものとして安定している。たとえばこの鹿母(ろくも)講堂は、象・牛・馬・牝馬について空であり、金・銀について空であり、男・女の集まりについて空である」(MN.vol.111.p.104)
と述べている。
さらに『テーラ・ガーター』には、
「その煩悩は断じ尽くされ、食に執著することなく、その行いは空・無相・解脱である。虚空を行く鳥の跡のようにその跡を測ることはむずかしい」(92)
という。(214~215頁)
■ ナーガールジュナの次の一文は、まさにそのことを示している。
「空性の成立している人には、一切が成立し、空性の成立していない人には、一切が成立しない」(『中論頌』観四諦品集24・第14偈)(216頁)
■ クラマジーヴァ(羅什。らじゅう。344-413)は、中国仏教の初期における大翻訳家であるが、その『大乗大義章』に、
「もし法身、無来にして無去(むこ)なりといえば、すなわちこれ法身の実相にして涅槃に同じ。無為にして無作なり。法身、また久しく住すといえども、有為の法、ついに無に帰す。その性、空寂なり」(「大正」45・123上)
という。
法身というのは、仏の究極の身体であり、色も形もなきものである。それは自己そのものであるととも、宇宙そのものであるともいうことができる。そのような法身は目覚めることが、仏に成ることであり、涅槃に達することである。それは、形なきものであるから無為であり、作用として捕らえられるものがないから無作である。したがって来ることもなく、去ることもない。このような法身においては、形あるもの(有為)はすべて〈無〉に帰し、その本性は〈空寂〉である、という。ここでは、無と空とは一つであり、しかもそれは、色も形もなき法身であり、涅槃であるとなすのである。(216~217頁)
■ 無を宗教的体験として体得するか、あるいは現実生活の事実上の経験のなかで無を追求するか、いずれかに依らねばならぬであろう。従来の仏教では、現実生活の経験のなかで無を追求するということは、まだ十分に発達していない。したがって、その方面の思想や哲学も展開しなかった。このことは、今後の課題となるであろう。(220頁)
■『金剛般若経』のなかで、究極の目覚めについて釈尊とスプーティ(須菩提)との間で問答が交されている。
釈尊がスプーティに向かって、
「如来によって、これが究極の目覚めであると、まのあたり自覚した所のなにらかの法があるとお前は考えるか」
と問うと、スプーティは、
「わたしが世尊の説かれた意味を知る限りでは、如来によって、これが究極の目覚めであると、まのあたり自覚した所のなんらの法も存在しません。なぜなら如来のまのあたり自覚した所の法は、不可取(ふかしゅ)であり、不可説であります。というのは、聖人(しょうにん)は、無為から現れたものであるから」
と答えている。
すなわち究極の目覚めに達してみると、これがまさにそうであるというごときものは全く存在しない。という。それでは何を自覚するかといえば、それは不可取であり、不可説であるという。不可取や不可説は、認知不可能として先へ押しやるのではなく、実はそれこそが自覚の当体なのである。ここで聖人というのは、そのような自覚の主体を表わしているのであろう。すなわち、自覚の主体は、無為から、いいかえれば全く形なき世界から現われているというのである。
不可取や不可説がまさに自覚の当体であり、全く形なき無為が自覚の主体であるとすれば、これもまた無の体得というほかないであろう。このように見てくると、無の体得の資料は限りなく見出される。(222頁)
■ 天台宗の確立に与(あずか)って力のあったのは、慧思(えし、515-577)と智顗(ちぎ、538-597)である。二人ともきわめて実践的・体験的な人で、つねに道を追求して止まなかった。したがってその態度は、当然ながら、なにものにも捕われない般若(智慧)の探求であり、それゆえに無への徹底である。慧思は、体系をつくる暇もないほどに、道を求むること急であったが、智顗はその実践的態度を承けつつ、さまざまな体系を構成したのである。(224頁)
■ そのなかでも特に無の思想に関するものとして、空仮中(くうげちゅう)の三諦円融(さんたいえんにゅう)を挙げることができる。これはもともと、ナーガールジュナの『中論頌(じゅ)』の、「縁起なるものを、われわれは空と説く。それは相対的な施設(せせつ)であり、また実に中道である」という偈にかかわっている。空とは、ありとあらゆる存在・事柄は、ことごとく実体のないものであり、したがって空である。しかしその空のままが、あらゆる存在・事柄として現われている。それが仮(け)である。それゆえ空即仮、仮即空である。このように体得してみると、いかなる存在・事柄も、中心的な道を踏みはずすことがない。すなわち中である。したがって空即仮、仮即空となって、空仮中の三つの真理は円(まど)かに融合しているとなすのである。この点を具体的には、「一色一香、中道に非ざるはなし」とも、「資生産業、ことごとく中道に違背せず」ともいう。いかなる存在もことごとく中道であり、また、われわれの生活のそのままが中道であるというのである。このような三諦円融(さんたいえんにゅう)は、もとよりたんなる理論ではなく、生活の実践を導くものであるから、無(空)への徹底、無(空)の体験が、つねにその根底をなしていることはいうまでもないであろう。(224~225頁)
■ 華厳宗の大成者は法蔵(643-712)である。その根本思想は重重無尽の法界縁起である。あるいは、事事無碍法界ともいわれる。すなわち全宇宙のあるとあらゆる存在・事柄が、互いに果てしなく関係し合っているということを、究極の世界観となしている。そしてこれにもとづいて、十玄門・六相のごとき体系が構成された。
ところで、事事無碍法界を基礎づけるものは、理事無碍法界である。それは、すべての存在・事柄と真理とが互いに無障碍であるという世界である。この真理とは何を指すのか。それは結局、無への徹底、空の体得の外にはない。この体得の強力な裏づけがあってこそ、理事無碍、事事無碍の華厳独自の世界観が構成されたのである。(225頁)
■ 無の追求の純粋な実践は、何といっても禅宗に極まるといって過言ではない。禅宗は、坐禅というもっとも単純な修行法を通じて、ひたすら無の体得に専念し来たったのである。禅宗の全思想史は、無の追求によって貫かれているといえよう。したがって禅宗の文献のなかから、無の体得に関するものを拾い出せば、枚挙に遑(いとま)がない。(226頁)
■ ここで説いているのは、無の解釈ではない。無の体得へのすじ道を述べている。それにはまず、坐禅を通じて無になり切ることを学ばねばならぬ。ここには、言葉の説明や心の働きの立ち入る余地はない。坐禅のなかで、ただひたすら自己の全人格が無と一つになっていくことである。やがて自己もなく、無もなく、ただ打成一片(だじょういっぺん)となる。すなわち、全自己が、体も心も打って一丸となるのである。しかしこの状態もまだ不徹底である。さらに、打成一片をひたすら爆進するうちに、戛念(かつねん)として全自己が爆発し、無そのものに帰する。同時にそれは有そのものへの蘇(よみがえ)りである。絶対無がそのまま絶対有である。あるいは、無もなく有もなく、自己もなく世界もなく、しかも歴然(れきねん)として一切が現成している。これこそまさに無の体得であり、体得そのものである。しかし、求道(ぐどう)の過程は、これで終わったのではない。むしろこれが始まりであり、出立点である。そして長い時間を要して、生活と仏道とが融合し、生活のままが仏道となっていく。それは、仏道の無限の過程である。(227~228頁)
■ 空海は、『即身成仏義』のなかで、
「法身は大虚に同じうして無碍なり。衆象を含んで常恒(じょうごう)なり」(高野山大学『十巻章』14頁)
と述べている。
法身は、もとより色も形もなく、大虚に同じきものである。そのような絶対無の法身であればこそ、そのままが六大無碍となっている。すなわち、地・水・火・風・空・識の六つの要素が、互いに隔てなく融け合いながら活動しており、それがさのままヴィルシャナ仏の働きである。それは、唯物論でもなく、唯心論でもない。むしろ唯物のままが唯心であり、唯心のままが唯物である。世界の成り立ちのままが自覚の成り立ちであり、自覚の成り立ちのままが世界の成り立ちである。物も心も、世界も自覚も、たがいに無障碍である。絶対無の発展は、ついにここまで達したといえよう。(230頁)
■ 同じ鎌倉時代に道元(1200-1253)が現われた。禅宗のなかの曹洞(そうとう)宗の系統にありながら、その思想は独自のものである。
『正法眼蔵』「弁道話」のなかで、
「打坐して身心脱落することをえよ。もし人一時なりといふとも、三業に仏印を標し、三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる。ゆゑに諸仏如来をしては、本地の法楽をまし、覚道の荘厳をあらたにす。……万物ともに仏身を使用して、すみやかに証会の辺際を一超して、……究竟無為の深般若を開演す。……わづかに一人一時の坐禅なりといへども、諸法とあひ冥(みょう)し、諸時とまどかに通ずるがゆゑに、無尽法界のなかに、去来現に、常恒(じょうごう)の仏化(ぶつげ)道事をなすなり。……空をうちてひびきをなすこと、撞(とう)の前後に妙声綿綿たるものなり」(岩波文庫本・上、57-59頁)
とある。(232~233頁)
このように道元においてもまた、絶対無が深般若の説法を開演し、妙声(みょうしょう)のひびきをたてるのである。ただ、親鸞においては信心であり、道元においては坐禅である。いずれも人間の主体的態度において異なることはないが、同じ主体性のなかに微妙に相違する所がある。その相違の振幅を究めていくことは、きわめて興味ある問題であり、今後の大きな課題となるであろう。
以上、これまで発展してきた仏教思想の上で、無の問題を考えてみたのである。たんに無という言葉だけに捕われないで、無の意味を考察してみると、それは全仏教のもっとも基本的な立場を表わしていることが知られる。時には、空となり、無所有となり、不可説となり、またときに、実相となり、法性となり、真如となり、またあるときは、法身となり、ヴィルシャナ仏となり、尽十方無碍光如来となっている。それはすべて絶対無であることにおいて異なることはないが、名目の変るにしたがって、その性格や方向も微妙に変容してくるのである。(232~234頁)
■ われわれは、右の名目による特徴の区別に、それぞれ名前を附してみよう。第一の空・無所有・不可説には、無執(しゅう)への無限前進、第二の実相・法性・真如には、実相への果てしなき追求、そして第三の法身・ヴィルシャナ仏・尽十方無碍光如来には、法身の無尽説法、という類である。このような第一・第二・第三の特徴は、実は絶対無そのもののさまざまな現われ方である。これらの諸特徴は、インドの原始仏教以来、日本の大乗仏教に至るまで、たがいにあざなえる縄のごとくになって発展し来たったものである。しかしきわめて大まかに区別するとすれば、無執への無限前進はインド的であり、実相への果てしなき追求は中国的あり、法身の無限説法は日本的であるといえるかもしれない。そしてその特徴の変容の間に、インドから中国へ、中国から日本への仏教の歩みのすがたをおぼろげながら辿ることができるであろう。(235~236頁)
仏教の時間論
■ 原始仏教のなかで、ブッダが七法について教えている所がある。すなわち、出家者は七法を知らねばならぬという。七法とは、知法・知義・知己・知節・知時・知衆・知人である。このなかに知時というのがある。時を知ることである。これは何を意味するのであろうか。
ブッダによれば、
「これが説示の時である、これが質問の時である、これが修行の時である、これが独坐の時である、と、このように出家者は時を知る」
とある。
ここで知時といっているのは哲学的な論究の時間論ではない。出家者として定められた行動の適切な時を知るというのが、その主題である。いいかえれば、出家者の行動が時宣に適するという実践的な意味が強調されている。(238頁)
■ 部派仏教は多くの学派に分れているが、そのなかで説一切有部がもっとも有力である。有部を中心に時間論を考察してみたい。その考え方を一語にして表わせば、「三世実有(さんぜじつう)、法体恒有(ほうたいごうう)」といわれるものである。すなわち、過去・未来・現在の三世は実在的であるから、存在の自体は恒常的である、という見解である。(240~241頁)
■ このように見てくると、先の『婆沙論』でも世友説を採用しているように、この『倶舎論』においても、世友の見解を有部の正当な説と見ている点で、両者は一致している。しかし、その他の法救・妙音・覚天の諸説が、有部として不適当であるかどうか、これだけの解説では判断dきない。ことに肝心の実体とは何を指しているか、という問題になると、何れの説においても明らかでない。世友説でも、作用の存否によって過去・未来・現在の境位が変るだけであって、実体については何事も触れていない。
そもそも最初に述べたように、世と行とは同一と見られている。過去・未来・現在の時間がすなわち物の働きであり、働きがそのまま時間である。こうしたなかで、実体とは何か、という問題を追求しても不明に終らざるを得ない。しかし、過去・未来・現在の存在を主張した根拠は、すでに触れたように、きわめて実際的な感覚から出ていると思われる。すなわち、過去を否定すれば、それから影響を受けている現在もなくなり、さらに未来の結果も成立しない、というたぐいである。つまり、現在時点という否定できない存在感覚に出立して、現在と関係している過去も未来もまた必然的に存在せざるを得ない、という立場をとっていることは明らかであろう。(246~247頁)
ナーガールジュナの時間論
■ ナーガールジュナ(龍樹)は『倶舎論(くしゃろん)』の作者ヴァスバンドゥよりも百年以上古い人であるが、かれはそれまで展開してきた有部の見解をとり上げ、かえってこれを基礎づけることによってその立場を逆転した。すなわち、有部が実在論をとっているとすれば、ナーガールジュナは絶対空の立場に立っている。しかし、それは有部の立場を基礎づけることによってそうなったのであり、したがって、一切は空であればこそ一切は成立し得るということを主張している。
かれの時間論は、端的には『中論』観時品(ぼん)第十九に現われている。観時というのは、kala-pariksa すなわち、「時間の考察」という意味である。ナーガールジュナの作は実は『中論』のなかの偈(げ)のみであるから、まず第一偈を見てみよう。
「もし現在と未来とが、実に過去に関係してあるならば、現在と未来とは過去時のなかにあるであろう」
この偈の起ってきた背景を考えてみると、チベット訳『無畏論(むいろん)』によれば、現在と未来は過去に関係し、過去と未来は現在に関係し、現在と過去は未来に関係する、ということが前提となっている。漢訳の青目(しょうもく)釈も同様である。チャンドラキールティも、過去・未来・現在の三時は、存在自体の関係であるといっており、同様の意味である。つまり、過去・未来・現在はたがいに関係し合って成立しているという見解である。これは前に論じた有部の立場に外ならない。ナーガールジュナはこの立場を引き受けて論法を進めていく。それが、まずこの第一偈となって現われている。
しかし考えてみると、この第一偈には問題がある。すなわち、現在と未来とが過去に関係しているということから、どうして現在と未来とが過去のなかに存在しなければならないという結論が出てくるのか。その論法は曖昧であり、観念的であって、なんら具体的な根拠は示されてもいないし、考えられもしない。
けれどもこの問題は別として、ナーガールジュナ自身は第一偈は成り立つと考えているのであろうか。かれはこれに対して直接には答えていないが、第二偈以下の内容から見て否定的であることは明らかである。この点について、『ブラサンナバダー』、青目釈、『般若灯論』などは、同様の理由を挙げている。すなわち、現在と未来とが過去時のなかにあるとすれば、現在も未来も過去時になってしまって、そうなれば過去もなくなる、なぜなら現在・未来にあっての過去だからである。という。
この論法も奇妙だと思うが、それも暫く措(お)くとして、つぎの第二偈は、その逆をいっている。
「もし現在と未来とが過去時中にないとすれば、現在と未来とはいかにして過去時に関係して存在しようか」
この論理も第一偈と同じようにすっきりとうなずけない。『ブラサンナバダー』は、虚空の青蓮華のように関係は存在しない、というだけであるし、青目釈は、三時それぞれ異相であるから関係は成立しない、という。ともかくナーガールジュナは、第一偈の主張とは反対に、現在と未来とが過去時にない場合には過去時に対する関係が成立しないことをいおうとしている。そしてその理由から第三偈、
「過去に関係せずして、両者(現在と未来)の成立はない。それゆえ現在時と未来時は存在しない」
という内容が必然的に主張される。
しかもさらに、その点から第四偈の、三時相互の関係、上中下、一異などの全関係が問われ、それらのものはすべて存在しない、という結論に至る。
このようにして、第五偈では、時はまったく不可得となり、最後の第六偈では、
「もし存在に依って時があるとすれば、存在を離れてどうして時があろう。しかるにいかなる存在もない。まして時があろうか」(岡野注;私の『全元論』では、存在全体は在る。個別の実体は無い。法は在って、常恒に存在を貫いている。実体は諸行無常である)
といわれる。
すなわち、存在が否定されているのに、存在にもとづいている時は、いうまでもなくあり得ない。という主張に終わるのである。(248~254頁)
華厳宗の時間論
■ 中国における、華厳宗の時間論は、華厳宗の独特の立場である重重無尽事事無碍法界にもとづいて立てられている。これは、宇宙のありとあらゆる事象はたがいにさまたげることなく影響し合い、しかもその作用はかさなり合って尽きることがない、という世界観である。(252頁)
道元の時間論
■ 道元の時間論は、『正法眼蔵』「有時」のなかで展開している。それは、今日の感覚から見ても、きわめて実存的性格の強いものであるということができる。しかも仏教思想一般については、哲学的思索を期待することはできないにもかかわらず、道元の論述には、ある意味のそうした傾向さえ追跡することも可能である。
かれの時間論には、つぎのような要素が組みこまれている、その要素というのは、時間・存在・光明・自己であり、これらの四要素が実は別々のものではなくて、一体をなしている。そしてこの点に、かれの時間論のきわめて独自的な性格を有する所以(ゆえん)が存すると思う。
「いはゆる有時は、時すでにこれ有なり。有はみな時なり、丈六金身(こんじん)これ時なり。時なるがゆえに、時の荘厳(しょうごん)光明あり」
という。
時間がすなわち存在であり、存在がそのまま時間である。一丈六尺の黄金の仏身がすなわち時である。時であるから時そのものが光明を放っている、というのである。
しかし道元のこれだけの文章からは、その真意を汲みとるわけにはいかない。もう少しかれのいうことを聞いてみよう。
「われを排列しおきて尽界とせり。この尽界の頭頭物物を時時なりと覰見(しょけん)すべし。物物の相礙(そうげ)せざるは、時時の相礙せざるがごとし。……われを排列して、われこれを見るなり、自己の時なる道理、それかくのごとし」
世界全体というのは、実は〈われ〉がすきまなく配列されたものである。その世界の事事物物を時そのものと見るべきである。事事物物がさまたげ合わないのは、それぞれの時がさまたげ合わないのと同じである。そのことは、いいかえれば、〈われ〉を配列しておいて、〈われ〉がこれを見ているのである。自己はすなはち時であるという道理は、まさにこのようなものである、という。
ここでは、存在と時間に対して、さらに〈われ〉が登場している。世界の事事物物がここにあるということは、いいかえれば、〈われ〉が持続的に配列されていることである。その〈われ〉の配列を〈われ〉が見ているのである。
このように、〈われ〉なる世界が登場していることは、存在と時間の一体的関係を〈われ〉なる自覚において基礎づけていると見てよいであろう。なぜなら、たんに存在がすなわち時間、時間がそのまま存在であることを強調するのみでは無意味と考えられるからである。〈われ〉の配列が〈われ〉が見ているという根本状況において、存在がすなわち時間、時間がそのまま存在となるのである。いいかえれば、一世界全体の事事物物がすなわち時そのものであるということ、また、事事物物がさまたげ合わないことは時がさまたげ合わないことであるということ、こうしたことは、すきまのない〈われ〉の配列が〈われ〉が見ていることにおいて成り立つのである
ところで、右のような存在・時間・自己の関係は、われわれの反省において推論された構造であって、道元自身は、このような反省を抜きにして、存在・時間・自己の一体性を強調している。ただかれの主張の文脈をたどっていくと、こうした構造が考えられ得るというにすぎない。しかもさらに立ち入っていくと、このような自覚の構造において、はじめて、道元の「時なるがゆゑに、時の荘厳光明あり」という主張もうなずかれ得ると思う。なぜなら、〈われ〉における自覚のなかで、時の光明は実現されるからであり、道元においては、存在・時間のたんなる形而上学的関係ではなく、有を尽し時を尽していく参学が最大の関心事だからである。
かくして道元では、時間・存在・光明・自己が一体となって見られている。しかしかれは、これらの相互の関係については、これ以上立ち入ろうとはしない。道元は、西洋の哲学的意味においては、けっして哲学的追求者であるとはいえない。その点で、『存在と時間』のなかで究明していくハイデカーの哲学的態度とは比較され得ないであろう。ただここで留意すべきことは、ハイデカーが「時間性」の過去・現在・未来の分析によって人間存在が根源的に「照らされている」ことを論証しているのに対して、道元は、時間・存在・光明・自己の一体性をゆるがすことはないという点で、両者は基本的に相違しているということである。(256~259頁)
■ 「仏法をならはざる凡夫の時節に、あらゆる見解(けんげ)は、有時のことばをきくにおもはく、あるときは三頭八臂(さんちょうはっぴ)となれき、あるときは丈六八尺られりき、たとへば河をすぎ、山をすぎしがごとくなりと。いまは、その山河たとひあるらめども、われすぎきたりて、いまは玉殿朱楼に処せり、山河われと天と地となりとおもふ」
常人の時間観念について、道元はまず右のように考えている。すなわち、あるときは三頭八臂となり、あるときは丈六八尺となるという。いいかえれば、常人は、その時時の現象を想い浮べている。あるいはまた、河をすぎ、山をすぎて、いまは玉殿朱楼にいる、という。山や河、玉殿朱楼や〈われ〉が互いに相対している。いわば、過去の経験にもとづく想起から、現在刹那の状況に至るまでの諸現象の対照が、すなわち時間である、と考えられている。
これに対して、常人の立場を破る、根源的経験の時間とはどういうものであろうか。
「いはゆる山をのぼり河をわたりし時に、われありき。われに時あるべし。われすでにあり、時さるべからず。時もし去来(こらい)の相にあらずば、上山(じょうざん)の時は有時の而今(しきん)なり。時もし去来の相を保任(ほうにん)せば、われに有時の而近あるこれ有時なり。かの上山渡河の時、この玉殿朱楼の時を呑却(たんきゃく)せざらんや」
常人の立場では、山河や玉殿朱楼あるいはわれがその時時の現象として対照されていた。しかるにここでは、そのその現象の一つ一つにわれが充足している。山にのぼり河をわたったときに、すでにわれがあった。このわれこそ、前に論じた、存在・時間・光明・自己の一体なるわれに外ならないであろう。したがってその時時が、たんなる現象の対照ではなくて、光明であり、絶対である。あるいは、もし時に去来の特徴があるとすれば、われが絶対で、永遠の今である。このような点から見ると、「山にのぼったとき、河を渡ったとき、その〈時〉が玉殿朱楼の現在の〈時〉を呑み尽さないことがあろうか」となるのである。
かくして、常人の立場では時間経過における相対観念であったものが、根源的人間の立場では、時間経過における時時が絶対であり、永遠の今であると、ということができるであろう。しかも面白いことに、道元は、山にのぼり河を渡った過去の時が玉殿朱楼の現在時を呑み尽くす、といっている。いわば、現在時が過去時になってしまうことである。これは、ナーガールジュナでは誤った論証として用いられ、華厳宗では相即相入の論理として提示されたものが、道元では、かれ自身の根源的体験のなかで独自の思索として表明されているのである。
常人の立場の第二は、時間経過における飛去(ひこ)観念とも名づけられるべきものである。
これは第一の相対観念と事実上は密着している。しかし、これまた常人の特徴を示すものとして取り上げてみよう。
道元はこれについて、
「時は飛去するものとのみ解会(げえ)すべからず、飛去は時の能とのみは学すべからず。時もし飛去に一任せば、間隙(けんぎゃく)ありぬべし。有時の道を経聞(きょうもん)せざるは、すぎぬるとのみ学するによりてなり」
という。
常人では、時は飛び去っていくとばかり理解している。飛び去るとは、主体者のその時時の観念である。つまり主体者の心には、飛び去るといういくつかの諸観念が浮かんでいる。その観念ではとうてい全空間をうずめることはできない。ここでも第一の場合と同じように、諸観念とわれとの相対性・対照性が指摘できるであろう。
これに対して道元は、
「要をとりていはば、尽界にあらゆる尽有(じんぬ)はつらなりながら時時なり、有時なるによりて吾有時なり。有時に経歴(きょうりゃく)の功徳あり、いはゆる今日より明日へ経歴す、今日より昨日に経歴す、昨日より今日へ経歴す、今日より今日に経歴す、明日より明日に経歴す。経歴はそれ時の功徳なるがゆゑに、古今の時かさなれるにあらず、ならびつもれるにあらざれども、青原(せいげん)も時なり、黄檗(おうばく)も時なり、黄西(こうぜい)も石頭も時なり。自他すでに時なるがゆゑに、修証は諸時なり」
と述べている。
宇宙に存在するありとあらゆるものは、一つにつらなりながら、その時事の絶対生命である。ここで、時の流れに関して、常人と根源的人間との見方がくっきりと区別される。すなわち、常人では飛去であるが、根源的人間では経歴である。飛去は、飛び去るという、主体者の観念であり、イメージにすぎない。したがって観念とわれとがばらばらであり、相対的である。経歴はそうではない。宇宙全体の一つらなりが動いていくことである。明日へも動き、今日へも動き、昨日へも動いていく、自由自在である。したがって、経歴は有時の功徳であるといわれる。この世界に立てば、青原(青原行思、740年歿。六祖慧能の弟子)も黄檗(黄檗希運、生歿年不詳。弟子に臨済義玄がある)も、自も他も修証も、鳥のさえずりも陽のかげりも、その一つ一つが絶対生命である。(260~263頁)
■ 最後に、どうしても一言附け加えておかねばならぬことは、これまで論じてきた時間論では、まだ道元は満足していないということである。道元の体験と思索とは、果てしなき彼方まで果てしなく伸びていく。
前項で、常人と根源的人間の立場とを区別した。常人は、いわば踏みちがえている人であり、根源的人間は正道を踏み歩く人である。しかし道元は、踏みちがえているという、そのことも見逃さない。
「たとひ半究尽(ぐうじん)の有時も、半有時の究尽なり。たとひ蹉過(しゃか)すとみゆる形段(いんとん)も有なり。さらにかれにまかすれば、蹉過の現成する前後ながら、有時の住位なり。住法位の活發發地(かつはつはつち)なる、これ有時なり」
たとい究尽(究明し尽くすこと)が不徹底の場合でも、それは半有時の究尽である。有時の究尽には変りない。またたとい、踏みちがえた場合でも、その踏みちがえた形態のままが有時である。さらに進んで、それ自体の立場に立ってしまうと、踏みちがえるということの実現している状態のままが、有時の在り方である。それ自体の在り方において、魚が飛びはねるように活き活きとしていることが、絶対の生命である、というのである。道元は、踏みちがえている、そのことの絶対性をも見透かしているといえよう。
しかし、かれの見透しはさらにその奥を開こうとする。奥には奥の体験へ向おうとするのである。
「去来(こらい)を認じて、住位の有時と見徹せる皮岱(ひたい)なし、いはんや透関(ちょうかん)の時あらんや。たひ住位を認ずとも、たれか既得(きて)恁麼(いんも)の保任を道得(どうて)せん。たとひ恁麼と道得せることひさしさを、いまだ面目現前を模索せざるなし」
時は去来するものであるとのみ認知して、永遠の今を徹見(てっけん)している人はまれである、ましてその永遠の今をも解脱している人があろうか、というのである。これは常人の立場にひとたび戻って反省したものであろう。つぎに、たとい永遠の今を認知しても、それを持ち続けるといい得るものが果たしてあろうか、という。認知から、さらにその持続へ進むことである。そして最後に、たとい持ち続けるといい得ること久しきにわたっても、本来のめんもくの実現を模索している程度である、というのである。
われわれは、思索をつくし体験を深めて存在と時間を究尽していっても、なお道元の右の意味深い指標から、さらにその究尽を踏み破っていく七花八裂(こなごなに砕けること、自由自在)の全体体験へ向かうべきことをきびしく教えられるのである。(264~266頁)
仏教の未来
■ 日本仏教が日本文化のなかに深く染みこんでおりながら、現代人にとって思想的にも言語的にもつながりのないことが、大きな特色となっている〔しかし、五十年百年先には、この問題は大きく変っていくにちがいないし、むしろそのことを期待する〕。これを西洋哲学の発展の仕方にくらべると、著しい相違が見られる。西洋では、ギリシャ思想とキリスト教とが入り組みながら、ルネッサンスとなり、ヨーロッパ大陸に合理主義、イギリスに経験論が発展して、カント哲学となり、そこからさまざまに発展して、現代の実存哲学やマルクス主義ともなっている。
西洋思想にはつねに発展があり、言語でも種々の国語が共存しながら、思想的にも言語的にも現代とつながっている。たとえば、ドイツ哲学を見ると、カント(1724-1804)のドイツ語がわかれば、現代のハイデガーのドイツ語もわかる。しかも思想的にも、ハイデガーはカント哲学につながっている。これをわが国でいえばどうか。
カントと同時代に活躍した日本の思想家は、本居宣長(1730-1801)である。しかし宣長の『玉勝間』は現代の日本語ではない。その間には二転三転している。まして、日本人には珍しく独創的な道元(1200-1253)の思想になると、専門の研究者でもその言語や思想をもてあましている。道元の思想は、現代人の一部には強い魅力となっているが、道元と現代との間の思想的なつながりは皆無である。(273~274頁)
■ もともとインド思想と仏教とは、同じインドに発生しながら、歴史的にはかなり違った様相を呈している。たとえば、インド思想では世界の創造神を立て、自我を主張するのに対して、仏教では創造神を認めず、自我を否定して無我を説くにである。自我説と無我説を廻って両者の間には論争も行なわれてきた。
しかしインド思想の場合、創造神や自我説をもっと深く考えてみると、必ずしも仏教と対立すべきものではないようである。創造神はヴェーダやウパニシャッドの神話に由来しているのであるが、その後思想が発達するにつれて、それは必ずしもキリスト教のような明白な人格神ではなく、時には人格的な神、時には非人格的な原理として理解されている。そうなると大乗仏教の仏でも、ある場合には人格的な仏として、またある場合には、色も形もない、世界に遍満する法身仏として現われているのであるから、両者の間にはとくに対立すべきものは存しないことになるであろう。また自我説と無我説についても、ことばの観念としてはいかにも対立するようであっても、インド思想のアートマン(真実の自我)の意味をウパニシャッドのなかでただしてみると、それは決して実体としてのアートマンではない。むしろ正しい智慧における主体的な自覚を指している。そうだとすれば、仏教において無我たることを主体的に自覚することと異なることはないであろう。(281頁)
■ 前に挙げた三種の慈悲の方式にも見られるが、原始仏教や部派仏教では、生活を律していく具体的な多くの戒律が成立しており、後の大乗仏教になって、宇宙的なブッダの無縁の大悲が強調されるようになった。時として、小乗の破戒こそ大乗の戒律であるとも主張された。
これは、仏教のおおらかさを特徴づけるものであることは論を待たない。しかし同時に、ブッダのはてしのない無縁の大悲が、現実社会の実践の上に、何か具体的な旗印となって凝結するものがほしい。初期仏教の戒律は、きわめて具体的であるが、その都度その都度決められた雑多なものである。それが願わくは、大乗仏教の宇宙的なブッダのなかに融けこんで、そこから基本的な一つの、しかも具体的、現代的な戒律の顕現が望ましいのである。その戒律は、ブッダの無縁の大悲と虚空のような大智とが凝結して、われわれの社会生活を律し、かつ推進していくような一つの根本限定でありたい。したがってもはやそれは戒律という名目から離れたものとなるであろう。(289頁)
■ 未来社会の理念は、仏典のどこに求められるであろうか。わたしは、これまで折に触れて主張してきたごとく、それは仏教を貫いている「帰依三宝」であり、ことに『華厳経』浄行品(ぼん)に示されているものである。
自ら仏に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、大道を対解(たいげ)して無上意を発(おこ)さん。
自ら法に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、深く経蔵に入りて智慧海のごとくならん。
自ら僧に帰依したてまつる。当(まさ)に願わくば、衆生と共に、大衆を統理して一切無碍(むげ)ならん。
これは菩薩の願いであるが、まず重要なことは、菩薩ひとりではなく、つねに大衆と共に行動しようとしていることである。大衆の道こそ仏道であり、それは日本仏教の直接目標である。そして第一には、帰依仏であり、無上の菩提心(究極の目覚めへ向おうとする心)をおこすことである。これは仏道の根幹である。第二は帰依法である。真理への果てしなき追求心と恭敬(くぎょう)心であり、深く経蔵に入って海のような智慧を保有することである。ここで経蔵というのは『華厳経』における善財童子の求道の精神からいえば、仏教の経典に限定さるべきものではない。ヒンズー教もキリスト教も、西洋哲学も自然科学も、あるいは無宗教と思われる人々の思想も、それが一道に達してさえおれば、深くそこに分け入って、海のような智慧を汲みとるべきである。第三は帰依僧である。僧はもともとサンガであり、道を中心として集まりである。ここでは、一般大衆のサンガにまで拡がっており、ついには世界全体の共同体にまで至る。観念論者も唯物論者も、もろもろの宗教人も無宗教の人も、そしてあらゆる階級、あらゆる国籍の人々がいる。それらの大衆が、いかに見解が違うとも、たがいにさまたげあうことなく、統理されたいという願いである。
以上のような帰依三宝は、もはや仏教だけのものではない。それは人類の未来社会に普遍的な理法となるべきものである。(297~298頁)
あとがき
■ 禅のいわゆる見性は、むしろ性見、性が見(あら)われる、ということであった。これを仏教の原点まで遡っていくと、ブッダの言葉で「ダンマが顕(あら)になる」ということに帰着する。このことを自分の禅定(ぜんじょう)で繰りかえし繰りかえし、日に日に試みていると、いつのまにかブッダや経典のイメージが消えていくと同時に、ブッダ以外の、ソクラテス、エムペドクレス、ヘラクレイトスも、中国の古典に散見される部分も、そしてイエスやパウロも、それぞれ表示は異なっていても、その裏にある本質は同じではないか、ということに気づいてくる。つまり禅定は、自分という人間の普遍的な形で自覚されるものであり、この点から、禅定という仏教語は、全人格的思惟、推理、あるいは全人格的営みという一般的な語に置きかえられることになる。
さらに踏みこんでいえば、人類に普遍的な、いわゆる対象的思惟、推理に対して、もうひとつ、同じく普遍的な、全人格的思惟、推理が、少なくとも古代の東西において働いていたことが知られる。それが、インド思想のヨーガや仏教の禅定という、確立された方法によって、細々ながらも伝わってきたのである。それを今日的な形で、人類共通の資産にまで実現していくことが、これからの課題となろう。(301~302頁)
■ ところで、仏教の内側で、禅定を重ねながら調べていくと、ブッダから大乗の諸経典へのつながりが次第に明らかになってくる。原始経典から『般若経』へ、原始経典から『法華経』への、必然的に展開してくる基幹線である。この基幹線が資料のなかで覗かれてくることは、この上もない興味深いことである。そしてこの基幹線を支えている禅定こそ、あらゆる学派を包蔵している仏教の原型であると思われる。(302頁)
■ それぬつけて、もうひとつ決定的に重要なことは、「ダンマが主体的に顕になる」というが、主体者のどこに顕わになるか、という問題である。数年前、仙台で原始経典を調べているうち、ブッダにとって説かれている業異熟(ごういじゅく、kamma-vipaka、カンマ・ヴィパーカ)という想念に出会ったとき、長いあいだ悶え煩っていたさがしものものが不意に目の前に現れた思いで、私は小躍りして歓喜した。ただちに一つの拙論を試みた。ダンマはまさに、この業異熟にこそ顕わになりつづけるのである。
業異熟とは、業体(ごったい)であり、私は人格的身体と名づけた。果てしない過去から、ありとあらゆるもの、生きとし生けるものと交わりながら営みつづけてきた行為の結果が、今ここに私の全存在の基体として現われていることである。それは、私という存在の、したがって私性の窮まりであると同時に、ありとあらゆるものとの絡まり合いの、最高度に実質的なものとして、公性の窮まりである。いいかえれば、個性的な人格的身体でありながら、共同体的な人格的身体である。
そうした業異熟の実質はなにであろうか。それは、まさしく我執と煩悩の底知れない渦である。固体的であるばかりでなく、共同体そのもの、世界そのものの、絶えることなく噴き出てくる我執である。いわば、密林の山中深い地の底より、掘りあげたばかりの、みずみずしいどす黒い鉱物である。
ブッダによってそれは無明と呼ばれた。しかるに、その後の仏教思想史は、この無明の課題に徹底して立ち向かわなかった。ただアビダルマの随眠(ずいみん、煩悩のこと)、唯識説のアーラヤ識、浄土教の煩悩具足が、わずかにこれに応じようとした。その他の大乗各派は、まともにこれを受けとめていないといわねばならない。
全人格的思惟における人格的身体は、これからの課題である。それは仏教学だけのことではない。未来の存在を問われている、われわれ人類のもんだいである。昭和五十七年初秋(303~304頁)
学術文庫あとがき
■ 私はただちに全人格的思惟の実行に移る。同時に研究者として、対照的思惟による学問的論究も積まねばならぬ。いわばこの相反する二つの訓練を同時に重ねてきた。何十年という時間の経過のあいだにはさまざまなことがおこる。二つの訓練の絡まりあう複雑な状況のなかで、時として全人格が爆発して一切が雲散霧消する。気づいてみれば、果てしなき宇宙それ自体となっている、形なきままの〈いのち〉そのものである。しかし、やがてそれも消えて、元の木阿弥の煩悩具足にもどる。こうしたことを性懲りもなくくりかえすこと数知れない。
あるいはまた、仏教の根底はなにか、と問うこと自体、すでに潜在意識のなかに答えが芽生えている。それが形なき〈いのち〉そのものであることは、山人格的に気づかれている。形がなければ、仏教の枠組みを超える、枠組みを超えれば、当然ながら、他の宗教、哲学にも同一の根底のあることが知られる。
このようにして長い時間踏みわたってきた自分の足跡を、本書とならんで、『東西思想の根底にあるもの』(講談社、昭和58年)、『比較思想論究』(講談社、昭和60年)にまとめてみた。ふりかえってみれば、茫々幾星霜、夢のごとく、幻のごとし。その夢幻のただなかにあって、次の命題がくっきりと浮びあがっている。
「形なき純粋生命が、全人格的思惟を営みつつある主体者に顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換、すなわち目覚めが実現する」
このなかで、主体者とはなにか、さらに具体的には何を指すのか。それがブッダのいう業熟体(前には業異熟という漢訳を用いたが、このほうに訂正する)でありいわゆる人格的身体である。唯識思想のアーラヤ識もこれにつながるが、単に識というのみでは不徹底である。識も何もかも呑みこんでいる身体がここに問われている。それは、無限の彼方から営みつづけて、今、ここに現われている自己自体である。そこで、次の命題へと発展する。
「無限の過去から、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものと交わりつつ、生まれかわり死にかわり、死にかわり生れかわりして輪廻転生しながら、今、ここに現われている存在の統括体にこそ、形なき純粋生命が顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換、すなわち目覚めが実現する」
存在の統括体が、業熟体であり、人格的身体である。それは、自己意識も、無意識も一切が融けこんでいる、自己存在の根源体であり、自己の自己なるものである。同時に、生きとし生けるもの、ありとあらゆるものとの交わりにおいてこそ現われているものなるがゆえに、宇宙共同体の結節点である。私性中の私性と、公性中の公性との、二つの同時的極点である。
われわれは、全人格的思惟において初めて、その極点になり果て得る。いいかえれば、思惟体そのものがすなわち極点である。それは、宇宙における唯一存在体なるがゆえに、〈唯体〉という名称によっても呼び得るであろう。譬えていえば、母親の胎内に宿った第一週の状態をカララム(kalalam、凝結)と名づけるが、全人格的思惟は、そのような状態に果てしなく近づく、その極まりが唯体であり、人格的身体である。私自身が全人格一体になりつぶれて、ありありとリアリティの感触体となる。まったくの無意識であり、無智であり、黒闇であり、黒々と、果てしなくつらなっていく盲目の生命体である。このような黒闇の生命体にこそ形なき〈いのち〉は顕わになり、闇の扉はじりじりと開かれていく。(305~308頁)
■ こうしたことを総合してみると、もとよりまだ的確なことは明らかではないが、意識・経験の統一性は、大脳新皮質のさらに奥まった領域に指摘されることは間違いないようである。そしてこのことは、全人格的思惟による経験と合致している。すなわち連日の全人格的思惟において、その度毎に自己意識がその箇所と思われる所に集約されてくるのであり、この実感は何十年のあいだ変らないからである。
しかし、問題はそこからである。大脳の奥まった箇所に意識の統一性が働いているとして、その箇所をとり除いた残りの肢体には、その人の生命、人間性、いいかえればその人自身を見ることはできないであろう。だからといって、その箇所だけを抽出して、果たしてその人自身を認知することができるであろうか。思うに、全人格的思惟の経験によれば、意識の統一性はたしかにその箇所に集約されてくるが、それはただこの思惟のなかでそう意識されてくるだけである。いいかえれば、自己意識や人格性の統一体がそこにあるというのではなく、単に統一の機能の現象としてその箇所に現われてくるというにすぎない。
それゆえに、意識・経験の統一体、あるいはその人自身は、脳の一部にあるというのではなく、身体全体に関わっていると見られる。そうしてみると、どうしても全人格的思惟による全人格の統一体、すなわち業熟体、いいかえれば、受胎時の一体の如きものに限りなく近づいていく唯体にこそ、それを求めなければならないであろう。このような業熟体、唯体というごときものを、科学的にどう証明するのか。もともと対象的思惟に属する科学が、いかにして全人格的思惟の領域に踏みこむのか。問題はここから始まるといってよいであろう。
二つには、右のことに関わって次の問題が生じてくる。命題にもあるように、業熟体、唯体は、生まれかわり死にかわり、死にかわり生まれかわりして輪廻転生しつつ、今、ここに現われている存在の統括体である。それがその人の人格体であり、その人自身である。そうしてみると、この唯体は、死とともに絶滅するのではなく、死後もまた存続する。つまり輪廻転生の実態がこの唯体であるということになる。(310~311頁)
■ 三つには、ニュー・サイエンスの一つであるホログラフィック・パラダイムである。これは、レーザー光線によって知覚される物の実相が、レンズの原理によって知覚される物の在り方とはまったく異なっているということである。われわれのこれまでの物の認識は、感官を先端とするものであるが、感覚的にはレンズの原理によって存在の形態を理解している。それに対して、レーザー光線を当てると、そこに復元してくるものは、被写体の一部ではなくて、その立体的な全体像である。
このことから、ホログラムにもとづく物の実相は、一部のなかに全体を含み、全体のなかに一部が偏在しているという。いわゆる華厳の一即一切、一切即一の実相に類似しているといわれる。つまり、これまでの認識による物の在り方、ここに机があり、コップがあるという在り方の、いっそう根底には、一のなかに一切を包み、一切のなかに一が遍満しているという実相が見られ、さらにその奥は宗教の世界につながるであろうといわれている。このパラダイムの提唱者の一人である物理学者デヴィッド・ボームは、インドのクリシュナムルティと交流して、科学と宗教の領域を究明しようとしているから、さらにこの研究の進展が期待されよう。
ところで、もう一人の提唱者である脳神経学者カール・プリプラムは、記憶の研究からこのパラダイムに到達したというが、かれの心を悩ましつづけたのは、ホムンクルス(homunculus、こびと)の幻影である、という。つまり、そのホログラムの「一即一切、一切即一」の実相を、いったい「誰が」見ているのかという問題である。要するに、ホルンクルスとは、認識する主体者それ自身、自我そのものである。そしてプリプラムとは別に、DNAの発見者ワトソン=クリックの中のクリックもまた、1979年「脳を考える」という論文のなかで、知覚の背景にはホムンクルスの問題のあることを指摘している。このように若干の科学者が、研究の只中で自我の問題に逢着してきたことは驚くべき状況であるといわねばならない。それはまさしく全人格的思惟の課題である。
以上、将来立ち向うべきいくつかの視点を挙げてきたのであるが、いずれも全人格的思惟における業熟体(人格的身体、唯体)、並にその目覚めの基本線にかかわっていることはいうまでもない。そして最後に私は、私自身のこの思惟のこれからの展望に触れて筆をおきたい。
それは、先の命題であるところの、
「形なき純粋生命が、主体者、すなわちに業熟体(人格的身体、唯体)に顕わになるとき、初めて人間自体の根本転換たる目覚めが実現する」
に関わるものである。
この命題自体は変わることはない、不変である。しかし、かくのごとく目覚めていく主体者の態度が変容していく。その変容の典型的な例を、ブッダの第一の弟子サーリプッタ(舎利弗)のなかに見る。サーリプッタの変容は、同時に私自身の問題である。サーリプッタは、ブッダに導かれて、もっとすぐれたダンマ(形なきいのち)を示され、ついに一切の教えを貫ぬく唯一のダンマの究極に至る。それによって初めてサーリプッタは、
「世尊は究極の覚者であり、ダンマは世尊によってよく説かれ、サンガ(共同体)はよく仏道を行(ぎょう)ぜるものである」
ということを体得する。
これはそのとおりであり、一見問題はなさそうである。しかし、ダンマの究極に達したと思っているサーリプッタの意識の裏が問われる。そこには、なおダンマに絡まっているかれ自身の主体性が見えるからである。なぜなら、次に出てくるかれの言葉「世尊は究極の覚者であり、……」には、自分は唯一のダンマによって初めてこのことが体得されたという、微妙な自負が潜んでおり、そのような自己のすがたは、ここではまったく顧みられていないといえるであろう。
そのようなサーリプッタが、『法華経』「譬喩品」に至って根本転換する。かれは今や不可思議な気持で満され、歓喜にあふれている。そしてこれまでの自分の過失を反省し、
「今日、私は世尊自身の子であり、ダルマ(パーリ語のダンマ)から生まれたもの、ダルマから現れたものである」
ということを告白する。
ここにはもはや、かれ自身の主体性は消滅して、その全人格はダルマによって通徹され充足されていることが知られる。しかし実は、まったく同じこと「世尊自身の子であり、ダンマから生まれたもの、ダンマから現われたもの」であるということが、大乗経典の『法華経』に先んじて、原始経典の『アッガンニャ・スッタンタ』(『ディーガニカヤ』第27経)に説かれていた。過失は、まさにサーリプッタ自身(実は私自身)にあったのである。私はサーリプッタと同様、今や不可思議な気持ちに満されている。
改めて私は命題を凝視する。
「形なき純粋生命が、私自身たる業熟体(唯体)に顕わになるとき、初めて目覚めが実現する」
まったく形なき太虚から、今まさに生れでようとする初発の根源的限定(根本戒)、この不変なる〈いのち〉の言葉は、未来の生きとし生けるもののすべてに照応してやまないであろう。(313~317頁)
(2022年2月16日、了)